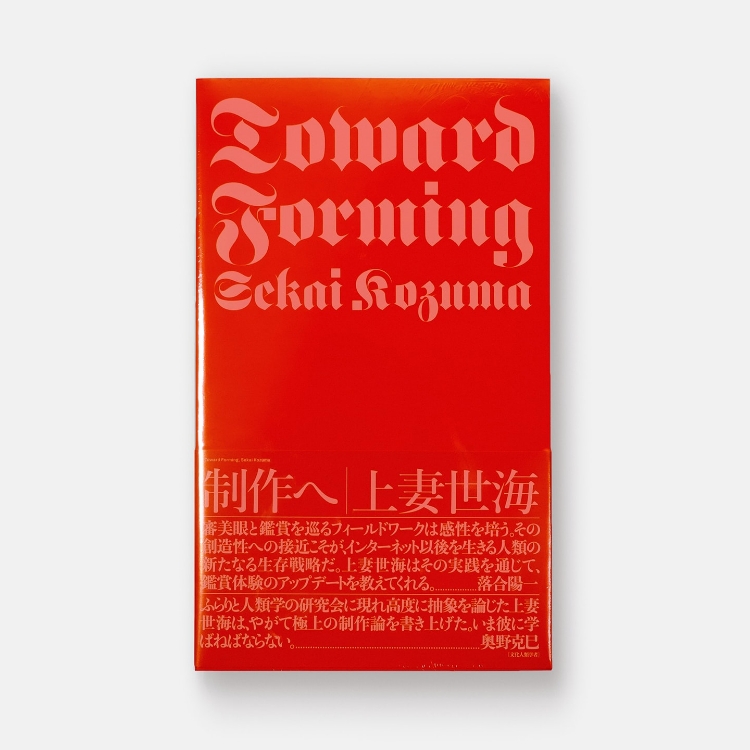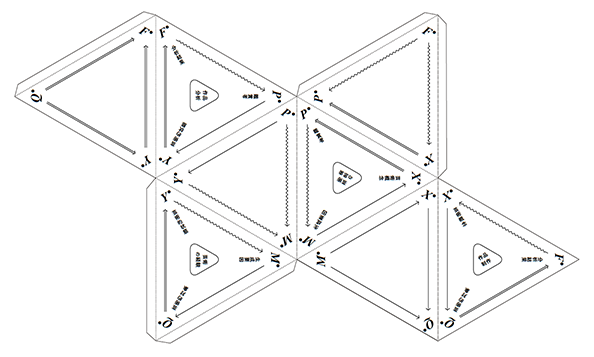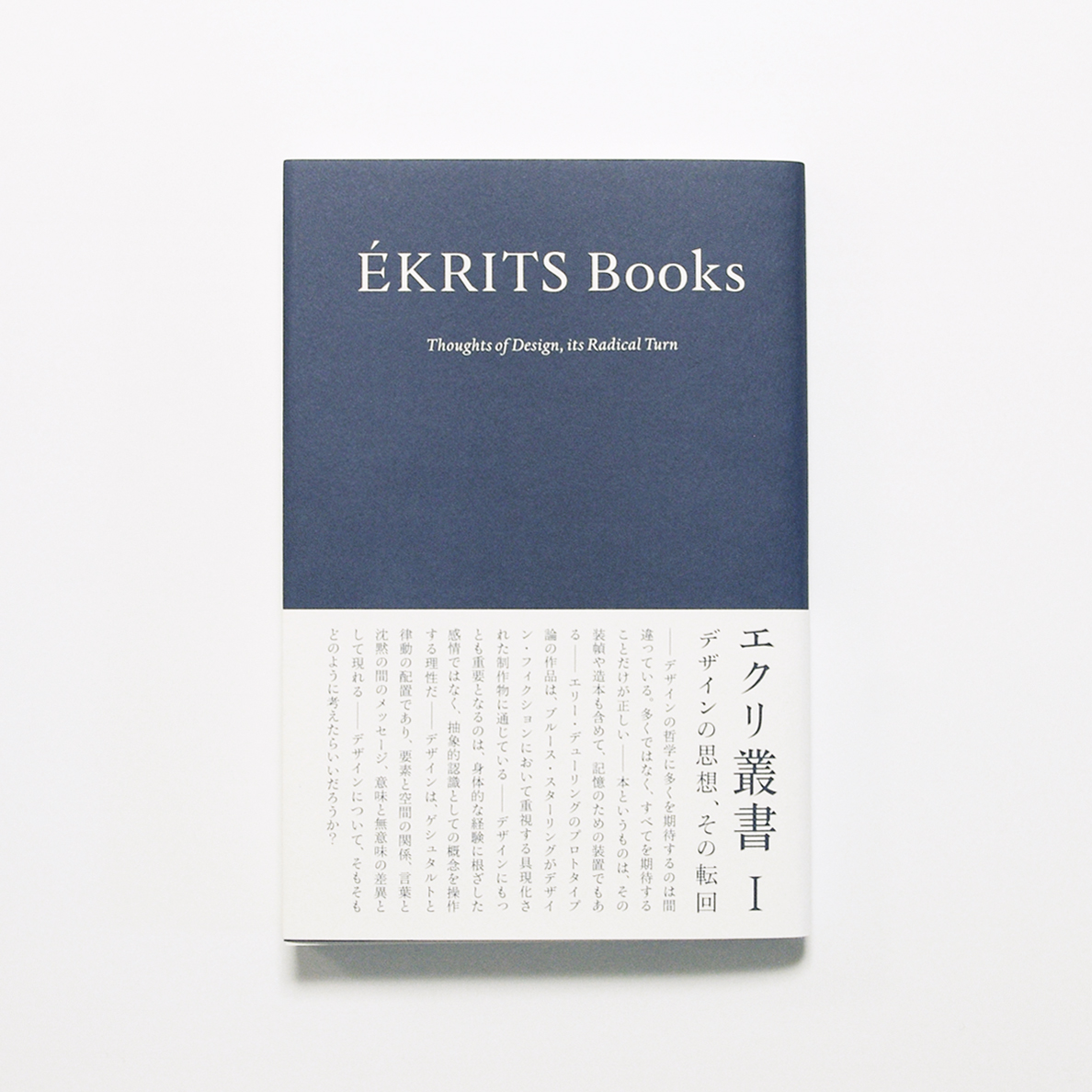夢の終わり
2019年11月のブラックマウンテン訪問から、もう1年も経ってしまった。これを書いているのは2020年の11月半ばである。本来であれば今ごろ4度目のアッシュビルから戻り、第6回の執筆にかかっているところだが、コロナ禍でそれも叶わなかった。
前回訪問の目的は、主に1948年から52年にかけての夏期美術講座について調べることにあった。ジョン・ケージとマース・カニンガムが初めてBMCを訪れた48年から、ハプニングのはじまりとして名高い「シアターピース No.1」が行なわれた52年までのことだ。その間、バックミンスター・フラーのドーム建設があり、ルース・アサワやアーサー・ペン、ロバート・ラウシェンバーグ、サイ・トゥオンブリー※1らが入学し、デ・クーニング夫妻やM.C.リチャーズ、ビューモント・ニューホル、ベン・シャーン※2らが教鞭をとった。美術史的にはもっとも実りの多い、その5年間を重点的に調べたかった。
そして、もうひとつ目的があった。エデン湖キャンパス全体を見て回ることである。2019年の春ごろだっただろうか、BMCの調べものでノースキャロライナ州のサイトを検索しているとき、たまたまキャンパスの完成後と思われる地図をみつけた。略地図ではあったが、おおよその場所はわかる。そこで、実際に歩いて確かめてみたいと思ったのだ。
エデン湖キャンパスを歩く
夏期講座が実現したのは、エデン湖の土地を得ることができたからである。ブルーリッジのYMCAは夏の期間明け渡さねばならず、長い夏休みをつくるしかなかった。新キャンパスの地として見つけたエデン湖畔の土地はもともと避暑のための別荘であり、そこにスタディ棟をDIYで建てたことは第3回で述べたとおりだ。もともとあったコテージがあり、さらにその間を埋めるようにして新しい小屋が建てられた。
NCアーカイヴズで写真を見ていると小さなインターナショナルスタイルの建物がいくつかあり面白い。資料に残っているローレンス・コーチャーのスケッチにはロッジ風のものとインターナショナルスタイルのものとがあるが、写真のそれらはコーチャー退任後に学生たちが自主的に建てたもののようだ。コーチャーのスケッチよりかなり小さい。スタディ棟を建てたときの経験が生きたのだろうが、DIY建築に堅牢性はなかった。山小屋風の建物は今も残るが、ミニ・インターナショナルスタイルのものはどれも残っていない。
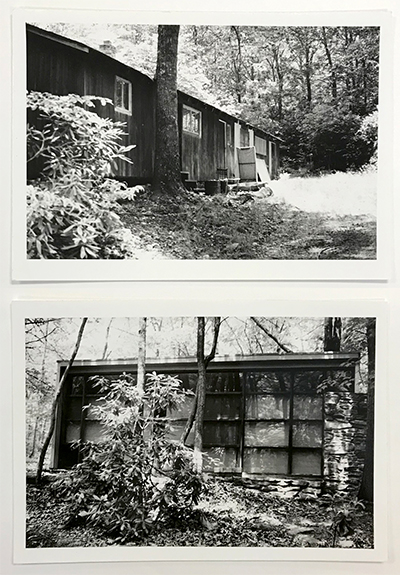 [図1-1]上:印刷ワークショップのためのロッジ(地図22)。下:インターナショナルスタイルのミニマムハウス(地図26)。学生有志による設計と建築。1947年に評議委員会の承認がおり、48年に完成した
[図1-1]上:印刷ワークショップのためのロッジ(地図22)。下:インターナショナルスタイルのミニマムハウス(地図26)。学生有志による設計と建築。1947年に評議委員会の承認がおり、48年に完成した
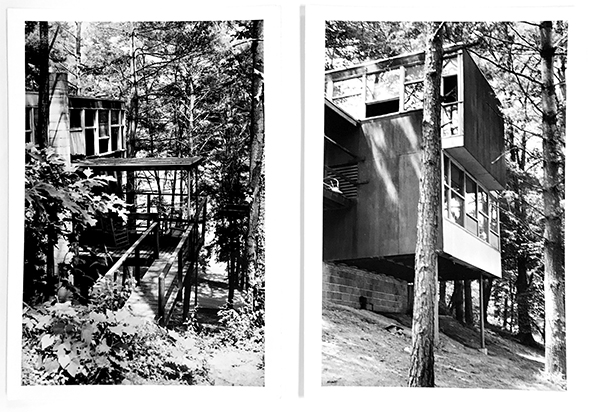 [図1-2]サイエンス棟(地図に記載なし)。学生だったポール・ウィリアムスが設計し、1949年から53年にかけて断続的に建築した。ウィリアムスはエデン湖キャンパス建設のために、BMCに多額の寄付や融資を行なっている
[図1-2]サイエンス棟(地図に記載なし)。学生だったポール・ウィリアムスが設計し、1949年から53年にかけて断続的に建築した。ウィリアムスはエデン湖キャンパス建設のために、BMCに多額の寄付や融資を行なっている
アッシュビルについて週が明けた月曜日、すぐにリッチモントキャンプの事務所を訪ねた。窓口になってくれているレベッカと再会を喜び、もう一度スタディ棟の中を撮影させてもらってから外に出た。
iPadに表示した地図を確かめる。地図には、古い建物(Old Building)と新しい建物(New Building)の凡例があるが、今となっては全てが古い建物なので見た目ではほとんど区別がつかない。とにかくスタディ棟を出発点として、地図のとおりに歩いてみることにした。黄色にマークしたところは、当時のものかどうかは別にして、とりあえず確認できた建物である。
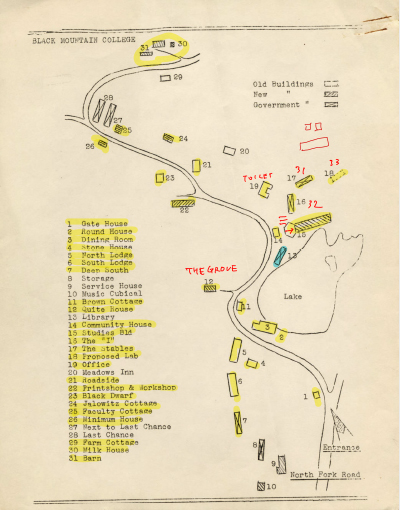 [図2]North Carolina Digital Collectionサイトで見つけた地図。マークとメモは筆者
[図2]North Carolina Digital Collectionサイトで見つけた地図。マークとメモは筆者
スタディ棟(15)の北に作られた階段を登ると16から19の建物がある。どれも凡例ではOld Buildingだ。Governmentは管理棟と訳していいのだろうか、全て同じような山小屋である。19のコの字型の建物はトイレに改装されており、周囲の建物には新しい番号が振ってあった(図に朱書きしているもの)。そのさらに上には地図にない建物があり、それを西に向かって坂を下ると道にでる。少し脇に入ったところに印刷ワークショップのためのロッジ(22、図2−1上)、少し歩いて右側にはジャロウィッツハウス※3(24)と呼ばれる建物がある。両方ともNew Buildingだが、当時につくられたものはもうなく、建て替えられたロッジがあった。
建物を見ているうちに基礎の作り方がいくつかあることに気がついた。たぶん作られた時期の違いによると思われるが、残念ながらそれがわかるほど建築の知識がない。
 [図3-1]スタディ棟の背後の崖を登る階段。地図には赤線でメモ(≡)
[図3-1]スタディ棟の背後の崖を登る階段。地図には赤線でメモ(≡)
 [図3-2]現在は棟番号33のロッジ(地図18)。Old Buildingはほとんどこのようなロッジで所々に補修の跡がある。元のものを改修して使い続けているのか、建て替え後にさらに改修したのかはわからない
[図3-2]現在は棟番号33のロッジ(地図18)。Old Buildingはほとんどこのようなロッジで所々に補修の跡がある。元のものを改修して使い続けているのか、建て替え後にさらに改修したのかはわからない
 [図3-3]18からさらに上の坂道。山側の雰囲気はだいたいこんな感じ
[図3-3]18からさらに上の坂道。山側の雰囲気はだいたいこんな感じ
 [図3-4]トイレに改修されたOld Building(19)
[図3-4]トイレに改修されたOld Building(19)
 [図3-5]山側ロッジのテラスから見たエデン湖。樹が育っているので当時はもっと良く湖が見えたと思われるが、基本的に風景は変わっていないはずだ
[図3-5]山側ロッジのテラスから見たエデン湖。樹が育っているので当時はもっと良く湖が見えたと思われるが、基本的に風景は変わっていないはずだ
さらに道を北に上っていく。あるところからキャンプ場ではなくなりプライベートエリアになるが、それとなく入っていく。途中、犬の散歩をする人に出会う。おおらかなもので“Hello”のひと言で済んでしまった。歩いていくと24番の建屋があり、中を覗くと机や椅子が積まれ、教室として使われていたようにもみえる。さらに上った丘の上には写真で見慣れた家畜小屋(30)や納屋(31)があるはずだったが、そこにはもう何もなく、柵で囲まれた広場になっていた。
 [図4-1]地図の一番左の二股の分かれ道。ここまでがロックモンドキャンプだと思われる。標識にはPRIVATE ROADとあるが、この道を登ったところにあった牧場まで行ってみることにした
[図4-1]地図の一番左の二股の分かれ道。ここまでがロックモンドキャンプだと思われる。標識にはPRIVATE ROADとあるが、この道を登ったところにあった牧場まで行ってみることにした
 [図4-2]坂を登り切ったところにある広場(空き地?)。フェンスの向こうが元牧場
[図4-2]坂を登り切ったところにある広場(空き地?)。フェンスの向こうが元牧場
 [図4-3]広場の突き当たり、一番奥にある木製の柵。これはどうもBMC当時からあるもののようだ
[図4-3]広場の突き当たり、一番奥にある木製の柵。これはどうもBMC当時からあるもののようだ
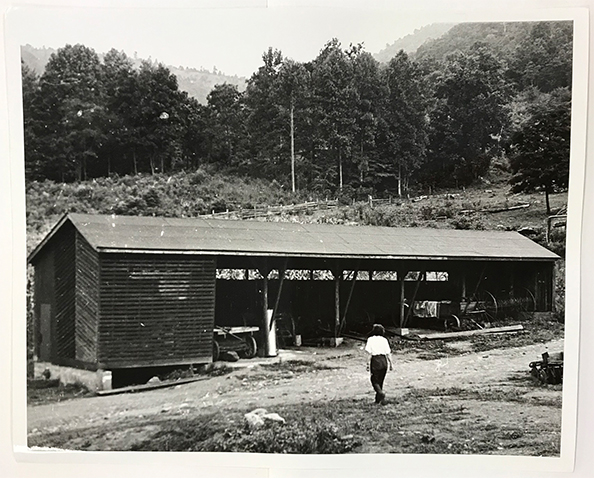 [図4-4]31の納屋。向こうに見える柵が上の写真と同じものであることに注目
[図4-4]31の納屋。向こうに見える柵が上の写真と同じものであることに注目
坂を下ってエデン湖に戻る。THE GROVEのプレートが掲げられたロッジ(12)を左手に見ながら、さまざまなドラマがあったダイニングルーム(3)で休憩し(ケージはBMCの教育は主にダイニングで行なわれていたと述懐している)、南に下る。ストーンハウス(4)だけがはっきりとわかる石造りの建物で、あとは、同じ場所に建物があったというだけの確認でしかなかった。エントランスの位置は変わらず、ゲートハウス(1)もこの場所にあった。それより南へは工事で行けなかったが、立方体の音楽室(10)が残っていれば見たかった。その向こうは農場のあったあたりで特別な収穫はなかっただろう。
坂を上ったり下ったりして1時間強といったところだろうか。これが、エデン湖キャンパス全体を歩いたおおよそである。
 [図5-1]THE GROVE のプレートがかかるロッジ(12)。New Building。石積みから見て、これは当時立てたままではないか。もちろん補修はされているだろう
[図5-1]THE GROVE のプレートがかかるロッジ(12)。New Building。石積みから見て、これは当時立てたままではないか。もちろん補修はされているだろう
 [図5-2-1]ダイニングルームの全景(3)
[図5-2-1]ダイニングルームの全景(3)
 [図5-2-2]ダイニングルーム入口。EDEN HALLのプレートがかかる
[図5-2-2]ダイニングルーム入口。EDEN HALLのプレートがかかる
 [図5-2-3]ダイニングルーム内部。鍵が開いていたので初めて入ることができた。食事を摂るのは中よりテラスの方が人気だったようだ
[図5-2-3]ダイニングルーム内部。鍵が開いていたので初めて入ることができた。食事を摂るのは中よりテラスの方が人気だったようだ
 [図5-3]石造りのストーンハウス。そのまま残っている
[図5-3]石造りのストーンハウス。そのまま残っている
 [図5-4]入口にあるゲートハウス。守衛所といったところ。これも大きくは変わっていないだろう
[図5-4]入口にあるゲートハウス。守衛所といったところ。これも大きくは変わっていないだろう
 [図5-5]ゲートの様子。右のキャンプのサインの位置にBMCのプレートがかかっていた(第2回[図3]参照)。手前の黄色いラインの道がNorth Fork Road
[図5-5]ゲートの様子。右のキャンプのサインの位置にBMCのプレートがかかっていた(第2回[図3]参照)。手前の黄色いラインの道がNorth Fork Road
ドレイアー、そしてアルバースの退任
先に書いたように、昨年の渡米は1948年から52年にかけての調査が主な目的だった。その間に多くの芸術的成果があったことも先に述べた通りだが、もうひとつ重要な出来事があった。BMCの美術教育を主導してきたジョセフ・アルバースの退任である。
アルバースの退任理由は、教育的なことより運営的な問題、主に学内でのイデオロギーの対立にあったとされている。アルバース自身も1965年のインタビュー※4で、「学校の失敗、継続できなかった要因は?」という質問にこう答えている。
それは、基本的な態度を変えた結果だ。最初のころはとても刺激的な状況だった。なぜなら、私たちの多くが亡命者だったから。私たちはポケットマネー程度の給料しかもらっていなかった。しかしのちに、人類の学問の中で私たちがもっとも恐れていた経済学の流行がやって来た。……誰もが同じ権利を持ち、誰もが同じ社会的機能を持っている。……しかし、人の間には、精神的にも肉体的にも平等はない。見た目が違うように、私たちも違う。こんな平等な所有の理論では、世界の問題は何も解決しない。それが私の信念だ。彼らは経済学において、自分たちが有能だと考えていた。……それが摩擦を引き起こしたのだ。特に、創設メンバーだった同僚の一人に対してひどい扱いをする者がいた。私はあと数年は残る約束をしていた。でも、辞めたんだ。1949年のことだ。何人かが一緒に辞めて、それがカレッジの「ダウン」だった。
Melvin Lane “Black Mountain College Sprouted Seeds”
ここで言っている「経済学(economics)」というのは、当時流行していたコミュニズム的な指向を指しているのだろうか。いずれにしてもよほど腹に据えかねることがあったのだろう。話しているうちに熱を帯びてくるのがわかる。
それは民主主義の誤解だった。民主主義では誰もが投票しなければならない。だから我々は会議をした。無限の会議。今日はYes、明日はNo。民主主義と呼ばれるものに吹き飛ばされて、不可能であることを証明しただけだった。……BMCは当たり前のことをしてきたんだ。しかし無能な人が多すぎて、有能な人が有能な役を演じている。それではまるでティーンエイジャーのスタイルだ。そのまま大人になったらそれこそ地獄だよ。
確かに成熟したヨーロッパからやってきた人たちにとって、アメリカはティーンエイジャーに見えたのかも知れない。このときの状況をフラーもインタビューで話している。
すべての教育機関で常に大きなものは財政問題だ。そして、テッドはより多くのお金を得るためにいつも外に出かけていた。……コミュニズムに対する当時の若者の関心は高まっていた。……テッドやアルバースについて話す方法を本当に知っている人に会ったことがない。私の非常に多くの友人が大恐慌の間にコミュニストになったので、私はそれについてとてもよく理解しているつもりだった。……アルバースは彼の絵と彼の美しい色の講義に夢中になっていた。テッド、この理想主義者は自治的な教育機関のアイデアを実行しようとしていた。……彼は本当に多くの、非常に理想的で美しい教育を行なった。
メアリー・エマ・ハリスによるインタビュー
アルバースのインタビューにある「創設メンバーだった同僚の一人」とフラーの「テッド」は、同一人物である。ライスとアルバースに並ぶ第三の人物、テッド(セオドール)・ドレイアーのことだ。
テッド・ドレイアーは、ライスと行動を共にしてフロリダのロリンズ大学を退職したBMC設立メンバーのひとりである。それだけではない。ライスをフォローしてBMC設立へと導き、開校準備からブルーリッジYMCAの貸借、エデン湖キャンパスの購入、スタディ棟の建設など、BMCの運営と経済を一手に担ってきた、まさにBMCを経営する中心人物だった。あまり表には出てこない彼の話をわかるかぎりで書いてみたい。
ドレイアーについてのまとまった記述は驚くほど少ない。断片的に拾うことはできるが、二次情報、三次情報で憶測に過ぎないものもある。本人のインタビューが先のアルバース同様、『Black Mountain College Sprouted Seeds』に掲載されている。そこでは、BMC設立時の資金調達やエデン湖移転時の苦労、またスタディ棟建設のいきさつが話されているが、本当の心の内は話はしていないように思う。しかし、本人の言葉として引いておきたい。
BMCは1933年9月に開校した。しかし、7月にはまだ財政計画はなかった。ライスは、ロリンズ大学の学生の父親から個人的に1,000ドルの贈与を受けた。その学生は、私たちが新しい大学を始めることに成功した場合、家族といっしょに夏を過すため、そして大学を組織するために、私たちと行動を共にしたいと考えていた。……しかし、計画も予算も立たなかった。ライスと私は、スワースモア大学のアイデロット学長(ライスの義理の兄弟)の家で会い、これからどのように進むべきかを相談した。私は、資金不足を最も懸念していたのだ。……アイデロッテはライスに私を会計係に立てた方が良いと提案した。とにかく私は、一晩かけて予算を立てるために滞在した。……15,000ドルを支払う15人の学生がいて、さらに15,000ドルの現金または引受があれば、1年間30,000ドルで走ることができる。新しい大学を公けにする前に、これらの最低条件を満たさなければならなかった。
これが、BMC開設のためのリアルなストーリーだ。ライスやアルバースの話ばかりが表に出るが、実は裏ではこういった苦労が続いていた。それは、学校が軌道に乗ってからも同じだった。
教員の給与については何も保証されていなかった。教員の給与は、15人以上の学生が来た場合にのみ配給された。来たいと言った学生は大勢いたが、自分でコミットしたいと思っていたのは実際には3人か4人だけだった。
アルバース招聘を実現させたのもドレイアーだったし、第二次大戦の危機を乗り越えられたのもドレイアーあってのことだ。エデン湖キャンパスも彼の努力で手に入った。グロピウスに校舎建築を依頼したのも、MoMAでのプレゼンテーションをお膳立てしたのも彼だった。
……地元のエデン湖として知られている700エーカーのサマーホテルを購入し、そこに理想的な大学キャンパスを設計するためにグロピウスとブロイヤーに新しい建築を依頼した(私たちは二人と仲良しだった。ドイツの元バウハウスの創始者であるグロピウスは、そのときハーバードの建築学科の部長であり、同じくバウハウスのブロイアーはグロピウスの新しい教授陣の一人だった)。図面が作成され、建築モデルがつくられ、フォトモンタージュで建築後を示す写真を公開した。……モデルはニューヨークの近代美術館に展示され、そこには数百万ドル(大恐慌の時代にはとても大きな金額だ)の資金集めキャンペーンを開始する機能があった。新しいBMCを構築するためのキャンパスがそこにあったのだ。
たぶん1932年のMoMAでの展覧会《モダン・アーキテクチャー展》のときに知り合ったのだろう、グロピウスとドレイアーはBMC以前から親交があったようだ。
「1948年と49年、その二つの夏の間に、私が本当にとても親密になった人が何人かいた。彼らがブラックマウンテンの本質(essence)だったんだ」そう前置きして、フラーはドレイアーについて語っている。
ブラックマウンテンカレッジの歴史についての私の見解を聞いてほしい。それはフロリダのロリンズ大学の教授とその他の教授たちから始まる。ロリンズカレッジは非常に裕福な大学であり……
ひとくさり、ロリンズ大での悶着の説明をしたあと、ドレイアーに話が移る。
そして、(ロリンズ大の)教授たちのリーダー、彼自身が去った——彼の名前はライスだ——。それ(新たな学校の設立)を実行に移す並外れた能力を持つ誰かがいなければ、彼がいくら野心を持っていてもどうすることもできなかっただろう。そして、それを実装したのがセオドール・ドレイアーだった。
ドレイアーの5人の兄弟姉妹は、20年代にそれぞれ100万ドルを相続した。テッドは理想主義者だったから、お金を引き継ぐのは間違っていると感じそれを拒否した。彼のお金はほかの兄弟たちに分配された。彼らはブルックリンのコロンビアハイツ出身だった。私の妻も何世代にもわたってコロンビアハイツにいたので、テッド・ドレイアーのことをよく知っていたんだ。テッドは理想主義者であるだけでなく、エンジニアであり科学者でもあった。彼はMITに行っていたんだ。彼の妹のキャサリン・ドレイアーは——おそらく彼のお金の一部を使って——20年代を代表するモダンアートの収集家の一人になった。キャサリンはカンディンスキーたちのコレクターの最初の人だ。彼女はアーティストの非常に活発な後援者だった。……とにかく、私はこのテッド・ドレイアーのことを知りたかった。
フラーによると彼の妻君とドレイアー一族は同郷で、よく知る間柄だったらしい。しかし、フラーが妹として紹介しているキャサリン・ドレイアーは実は叔母であることがインタビュー原稿に注釈として書き足されている。誰が書いたものかはわからない(あとからエマ・ハリスが加えたのかもしれない)。このようにフラーの記憶がどこまで正しいのかは疑問だが、ドレイアーは裕福な環境の下で十分な教育を受け、身内に名の知れた美術コレクターがいて、アメリカやヨーロッパの美術界、ひいてはバウハウスとも関係があったことがわかる。
そういうことを知って初めて、なぜBMCの設立前からMoMAと関係が持ててアルバースを招聘できたのか、YMCAに間借りできたのか、そして、まがりなりにも運営できるだけの資金調達ができたのか、などの疑問が解けてくる。
彼らはフロリダからノースカロライナの西部に移動した。それがブラックマウンテンだ。美しい山里、アメリカ合衆国のはじまりのころからあった信仰心の厚い地域、そして多くの宗教上の会合が行われてきた、まさにキャンプが集まった場所だ。……そのような地域にはとても貧しい人々が住んでいた。しかし、丘にはとても豊かな土地があり、お金持ちもたくさんいたんだ。……そしてドレイアーは、その地域に、YWCAやYMCAなどの北部の機関が、夏の休暇に大勢の子供たちが集まるための独自の場所を建設したことを知った。……テッドはとても大きなホテルをとても安くで借りることができて、彼とフロリダの教授たちはそこに引っ越した。その後、彼は湖の周りに開発された土地を見つけた……そして、テッドはその地所も購入することができた。……大恐慌のあとであり、誰もお金を持っていなかったが、それは物理的な意味でのブラックマウンテンの創立だった。そう、テッドはいつも舞台裏にいたんだ。
裏方に徹して決して表に出ようとしなかったドレイアーだが、火中の栗を拾う心境だったのだろう、スキャンダルでカレッジを去ったボブ・ウンシュに代わって、1945年11月から46年の春学期が終わるまでのあいだ学長(レクター)を務めている(46–47年度も再選されたという記述もあるが、現存するBMCの議事録では明らかにはなっていない)。そんな彼が、なぜBMCを追われなければならなかったのか。インタビューでフラーはBMCの内実に関して(多少主観的なところはあるとはいえ)かなり詳しく語っている。
テッドとアルバースを最後に見たのはその夏のことだと思う。……テッドはより多くのお金を得るために絶えず出かけていた。……しかし時はマッカーシー※5の(赤狩りの)時代で、コミュニズムに対する若者の関心は高まっていた。学生たちは心理学にひどく興味を持つようになり、テッドとほかの評議員たちを説得して心理学者のリヴァイ※6を招聘した。彼は最終的に学内に多大な力を持つようになった。……やがてリヴァイは学生の一人と結婚した。
この話にインタヴュアーのエマ・ハリスは「ホント?(really?)」と応えている。結婚相手はM.C.リチャーズで、彼女はのちに陶芸の学生としてBMCに戻ってくるが、この時点では「Reading and Writing」を担当する教員で学生ではない。これもフラーの勘違いと思われる。
M.C.リチャーズは、40年代後半から50年代初頭にかけてのBMC(つまりBMCの動乱期)に欠かすことのできない人物だ。48年にケージの「メデューサの罠」の翻訳を担当し、その後もケージやカニンガムと交流を深めつつ、もともと文学の人ということもあってオルソンやロバート・クリーリーとも親交を持った。48年には印刷工房で学生とともに「ブラックマウンテンプレス」を設立したが、彼女たちが刊行した『ブラックマウンテンカレッジ・レビュー』は1951年6月発行の1号だけで終わっている。51年には教職を退き、NYに移ってケージやラウシェンバーグらと行動を共にし、52年夏、再びBMCでケージの「シアターピース No.1」に参加する。53年には学生としてBMCに戻り、陶芸と詩作で注目されるようになった。
47年秋にドレイアーのあとの学長に就任したリヴァイは学生を扇動し、学生や一部の教員がコミュニズムにのめり込んで、資金集めに奔走するドレイアーをキャピタリストだと糾弾した──とフラーは述べている。しかし、記憶は曖昧なものだろう。アルバースのインタビューも加味すると、コミュニズム的な傾向と民主的なプロセスとが混ざり合って起きたアジテーションのようなものだったと思える。
どうであれ、バウハウスでもデッサウ時代の学長であったハンネス・マイヤーがコミュニストであることを公言して学生を組織したため当局に目をつけられ、政治色を払拭しようとベルリンに移転したものの、時を同じくして政権を取ったナチスの圧力は収まらず、結局閉鎖に追い込まれた経験を持つアルバースにとっては、まさにデジャヴュだったに違いない(実際にFBIがBMCを捜査していた記録が残っている)。アルバースはリヴァイのあと48年秋から49年春まで実質半年だけ学長を務め※7、ドレイアーとともにBMCを去った。
このことについて、フラーは「彼とアルバースは本当に大きな痛みにだまされていた」と言い、アルバース本人は「カレッジのダウンだった」と述べている。しかし、マーティン・デュバーマンの『Black Mountain: an Exploration in Community※8』には、少し違う面からこのことが書かれている。
もうひとつの退任譚
戦争が終わった1年後の1946年9月、BMCは92人(男性49人、女性43人、うち10人がGI法案を利用してやってきた退役軍人)というかつてない数の学生を迎える※9。学習は実際の経験を通じて最も効果的に達成されると考え、デューイ流の進歩的教育をさらに推し進めたかたちで実践していたBMCにとって、急激に増えた学生に対応するのは大変なことだった。
これまでのリベラルアーツプログラムを拡充するためには、少なくとも30人の教員が必要だった。もちろんかなりの予算が必要になる。学生と教員は共同生活を営み、経費節減もあって自給自足を目指して農場と牧場を運営していたが、それもとうてい追いつかなくなる。
それなら、BMCにおける体験学習の中心で、最もよく知られている芸術分野に注力すべきではないか。夏の音楽講座や美術講座には100人近い学生が集まる。そこにクラフトや製本、印刷、そして建築や農業も含めて、これまで蓄積してきた知見を注ぎ込めば、既存の一方的な美術や音楽の学校ではない新しい形態の学校ができるのではないか。そう考えたアルバースとドレイアーは芸術学部の設立を提案した。そして、その名称を「Black Mountain College of the Arts」として、芸術学部だけに用いる(校名は変更しない)ことで、合意がとれるところまでは漕ぎつけていた。
先ほど「デューイ流」と書いたが、BMCはライスからカレッジの組織原則と芸術に重点を置いた体験学習の両方を受け継いでいる。その上で、後者を独立させることはなんとかできそうだった。しかし、アルバースらは前者にも手をつけようとした。
BMCは設立以来、教員と学生の代表で話し合う合議制をとっていた。President(学校長)すら存在しないことは前回にも書いたとおりだ。外部にはジョン・デューイはじめ、ワルター・グロピウスやアルバート・アインシュタイン※10らが名を連ねる諮問委員会が設置されていたが、権限は何も持っていなかった。教員と1人の学生で構成される評議委員会(Board of Fellows)が唯一の統治機関だった。BMCは、学生と教職員が住まいと食事をともにし、ともに学び、働き、交流し、創造する、小規模で実験的かつ経験的な大学コミュニティとして自治され、教員と学生によって所有および運営されている——それがカレッジの自負であり、大前提だったのだ。
しかし経営の安定を理由に、アルバースとドレイアーは新たな理事会の導入を提案した。アルバースは、9人の評議員(6人の学外者と3人の教職員)で構成される委員会を設立しようと考えていた。ドレイアーはそれに対し「委員会は、富を求めるアイデアではなく、カレッジが何をしているのかを理解するためにつくる。私たちが自信を持って推薦した人々と計画されたプログラムを信じることだ」と援護をした。それはBMCのメンバーにとって受け入れがたいことで、反発は火を見るより明らかだった。
アルバースは、「芸術家が総合的な教育を受けることができる場所」あるいは「経験するだけではなくカリキュラムの中心にある芸術の専門家を育てる場所」の実現で満足し、BMCの運営に意見できる学外評議員の招聘まで言う必要はなかったのかも知れない。彼がそれを遂行しようとしたのは、ヨーロッパからの亡命者がアメリカで発言権を持ちはじめたことが背景にあったのか、あるいはその逆で、いつまでも亡命者でしかあり得ないことに業を煮やしたのか。いずれにせよ、バウハウスでなし得なかった理想の美術学校の夢はここで潰えた。
ドレイアーについてはもう少し複雑だ。ドレイアーは経済的にBMCを支えていた結果、それがためにBMCを追われることになった。これについてはいろんな記述があるが、本当のところはよくわからない。
ドレイアーの扱いに対する抗議から、アルバース、トルード・ゲルモンプレズ、シャーロット・シュレシンジャーが辞任した(そしてグロピウスはすぐに諮問委員会から辞任した)。アルバース ─ ドレイアー政権に対する反逆は秋を通して構築されていた。……ドレイアーがブラックマウンテンをあきらめて閉鎖するつもりだという噂が広まり始めたとき、あるいは、将来の管財人から新しい「Black Mountain College of the Arts」を率いるように頼まれたという噂が広まり始めたとき、不満は頂点に達した。
Martin Duberman “Black Mountain: an Exploration in Community”
このあたりが、そうだったのかなと思えるところだ。ドレイアーは、ライスの描いたリベラルアーツ教育を諦めて、ニーズのある芸術教育に移行しなければ経営的にBMCの将来はないと考えていたのだろう。そしてそれを実行しようとしたのだ。
戦後の状況やその後の社会変化を知っている我々からすれば、彼の判断は理解できる。しかし、(たとえアルバースの言うように青臭い考えだとしても)ユートピアとしてのカレッジコミュニティも否定したくはない。仮にアートスクールに鞍替えしていれば、アートやデザインに特化した(バウハウス型の)美術教育はできても、その後のハプニングに代表されるような新しい(アメリカ美術的な)運動やブラックマウンテン派の詩人に代表される文芸活動などを生むことはなかっただろう。その後現れてくる対抗文化やコンピュータカルチャーにまで繋ぐことができたかどうか。新しい文化の芽が美術の内側に取り込まれていったであろうことは想像に難くない。
結果として、ドレイアーとアルバースはBMCを去った。ドレイアーの長い経理責任者としての、そしてアルバースの芸術部門責任者としての、プレッシャーもここに解き放たれることになった。BMCから解放されたあと、アルバースはイェール大学に移り、その後の活躍は周知のとおりである。ドレイアーは、1950年から62年までGE(General Electric Co.)で働き、最初の原子力潜水艦を駆動する電源を開発するプロジェクトに参画、のちにノウルズ原子力研究所の課長を務めた。
これによって「ライス、アルバース、ドレイアーのBMCが終わった」とデュバーマンは書いている。しかしこの騒動は、この時代特有のイデオロギー対立の一面があったにせよ、アメリカ的な(特にデューイ的な)プラグマティズムと第一次大戦後の西欧(主にドイツ)文化や思想との軋轢の帰結だと総括できる。ドレイアーはその間に立って理想論者として働いたが、結局のところ疲弊し、あきらめたのだと思う。アニ・アルバースは、「絶え間ない緊張、プライバシーの絶え間ない欠如、お金の絶え間ない欠乏、そしてあなたたちが持っていたのと同じ投票権を持つことによるすべての教員との絶え間ない摩擦、それらによって疲れ果てた」という言葉を残している。
そして1949年の夏を待たずして、フロリダ・ロリンズ大からやってきたすべての教員がBMCを去った。ドレイアーは最後に最善を尽くし、「カレッジの友人」にと長い謄写版の会計報告を書いた。彼は個人的な確執と苦い記憶を押し戻し、こう語っている。「ブラックマウンテンは15年間素晴らしい場所だった。私たちはいくつかの新しい道を切り開いたのだ」。
エデン湖とダウンタウンでの出来事
話をエデン湖に戻そう。かつてのキャンパスをひととおり巡ってスタディ棟に戻り、ピロティに腰掛けて気がついた。壁が立っている —— ピロティのスペースを区切るパーティションが立っていたのだ。キャンプに来る子供たちのためだろうか。コーチャーが考えた建物の端からクラフト室の石垣までを見渡せた空間は、そこにはもうなかった。来るのが1年遅かったらパーティションのある風景しか見ることができなかったし、それをスタディ棟だと思っていただろう。間に合って良かった。写真に収めながらそう思った。
そのピロティを象徴するフレスコ壁画※11の修復が始まったというニュースが、2020年の春に舞い込んできた。1946年にジーン・シャーロットが描いたものだ。保存修復家のクレイグ・クロフォードとマホ・ヨシカワが復元に取り組んでいるという。秋になって修復が完了したという投稿がFacebookにあった。写真もアップされており、ずいぶんきれいになっている。子どもたちに落書きされたりしてけっして良い保存状態とは言えなかったし、劣化も進んでいたので、長く残していくために修復は当然だろう。しかし、色が剥げ落ち壁が削れていたとしても、シャーロットのオリジナルを見ることができて良かった。こちらも間一髪で間に合った※12。
 [図6]手前が二つある壁画の片方「INSPIRATION」のオリジナル。左手奥に見えるのが新しく立ったパーティション。
[図6]手前が二つある壁画の片方「INSPIRATION」のオリジナル。左手奥に見えるのが新しく立ったパーティション。
週末、ブラックマウンテンのダウンタウンまで足を伸ばす。目的は二つあった。前回資料を買った本屋のオヤジさんの写真を撮りたかったことと、Song of the woodという楽器屋にもう一度行きたかったのだ。
2018年秋に訪れたとき、曲がり角にあったハンマーダルシマーと書かれた五線譜の看板が目に止まった。店に入ってみると、これまで見たことのない(強いていえばオートハープに共鳴用のボディをつけたような)美しい楽器が並んでいた。サイズは、ノートPCぐらいからコーヒーテーブルぐらいのものまで大小さまざまだ。カウンターではオーナーなのかお店番の人なのか、年配の女性がバチで弦をたたいて美しいメロディを弾いていた。「打弦楽器だからハンマーなのか…」その音色にしばらく聴き入っていた。
東京に帰って調べてみると、ハンマーダルシマーはペルシャに起源をもつ民族楽器だということがわかった。ピアノの祖先のひとつだそうだ。しかし、ブラックマウンテンで見たものとは少し違う。一方、マウンテンミュージックと呼ばれているアパラチア山脈に伝わる伝承音楽に使われる楽器の一つにアパラチアンダルシマー(マウンテンダルシマー)がある。膝に置いて弦をはじいて弾く、ルーツミュージックファンには馴染みのある撥弦楽器だ。ブラックマウンテンで見たダルシマーは、ペルシャ起源のものとアパラチア伝承のものとの中間のようなイメージだった。コロンコロンと鳴る美しい音をもう一度聴きたかったし、小ぶりのものを1台買って帰りたいと思っていたのだ。
アパラチア山脈はアメリカ音楽のルーツの地と言われており、なかでもブルーリッジは音楽が盛んな土地柄である。アッシュビルでは、1928年に始まったアメリカでもっとも古い伝承音楽のフェスティバル「マウンテン・ダンス&フォーク・フェスティバル」が毎年8月に開催されている。そういう場所でBMCはヨーロッパのクラシック音楽を教え、ケージの現代音楽を受け入れたのだ。「ブルーリッジにおけるBMCの音楽」というような文章もいつか書いてみたい気がする(ちなみにぼくはルーツミュージックのファンです)。
楽器屋は、旧駅舎からメインストリートに入る角の建物にある。そしてちょうどその角にハンマーダルシマーと書かれた看板があって、曲がるとライブのフライヤーが貼られたショーウィンドウがある……はずだったが、そこには違うメッセージがあった。Song of the Wood has Moved! —— 引っ越したんだ!たしかに前回来たときこの建物は売りに出されていた。そういえば隣の店も閉まっている。オーナーが変わって立ち退かざるを得なくなったのだろうか。貼紙には電話番号が書かれており、そこに電話すれば移転先を教えてくれるのだろう。番号の下にはAnd We’ll see you soon…とあった※13。
 [図7-1]Hammer Dulcimers と書かれた、楽器店「Song of the Wood 」側面の看板
[図7-1]Hammer Dulcimers と書かれた、楽器店「Song of the Wood 」側面の看板
 [図7-2]角を曲がったショーウィンドウにあった貼紙
[図7-2]角を曲がったショーウィンドウにあった貼紙
 [図7-3]全景。シェードにSINCE 1975とある(2018年撮影)
[図7-3]全景。シェードにSINCE 1975とある(2018年撮影)
結局楽器を手に入れることはできなかったが、気を取り直して本屋に向かう。日曜だからか人通りが多い。車も多く、通りの反対側からは店が見えないぐらいだ。それでも通りを渡って店の前に出た。ドアには「Sale All Books 50% Off」という貼紙がある。どおりで人が集まっているわけだと思ってふと横を見ると、大きく「For Sale」と書かれたポスターが目に入った。どういうことだ!?ドアを開けた。
閑散とまではいかないが、確かにずいぶん本が減っている。半額セールなのだから当然か。オヤジさんは見当たらず、女の人がいた。たぶん彼のワイフだろう。思い切って声をかけた。
「去年来て、本を買ったんです。そのときはここに男の人がいました」
「あらそう。それはきっと夫よ」
「店を閉めるんですか?」
「そうなの。跡を継いでくれる人を探したんだけどいなくて。もう私たちも年だから。去年は何の本を買ってくれたのかしら」
「BMCの本です。奥に棚があったから」
「棚はまだあるわ。もうあまり残ってないけど、欲しい本があれば全部半額だからお買い得よ」
だいたいそんなやりとりをして、BMCの棚に向かった。本当にもう何も残ってなかったが記念にと思い、48年夏の「メデューサの罠」にも参加したアーティスト、レイ・ジョンソンの詩画集を持ってレジに行った。
「詩が好きなのね。ロバート・クリーリーのサイン本があるけど、いる?これは売らないつもりだったけど……。もちろん半額よ」
そう言ってレジのうしろの戸棚から本を出してくれた。本には黄緑色の紙片が挟まっていて、SIGNED by Robert Creely (Black Mtn College) と書かれていた。
「写真を撮らせてもらっていいかな。去年ご主人を撮り損ねたんだよ」
少しはにかんだ笑顔と2冊の本を持って、店をあとにした。
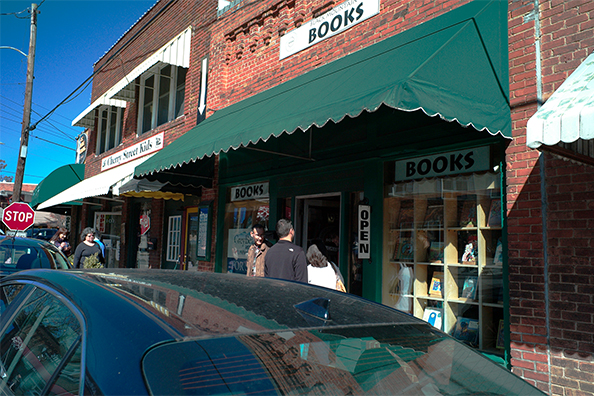 [図8-1]店の前の人だまり。入口左のショーケースにFor Saleのポスターが見える
[図8-1]店の前の人だまり。入口左のショーケースにFor Saleのポスターが見える
 [図8-2]BMC 関連書籍の棚。もともとたくさんは並んでいなかったと思うが、もう何もなくなっていた
[図8-2]BMC 関連書籍の棚。もともとたくさんは並んでいなかったと思うが、もう何もなくなっていた
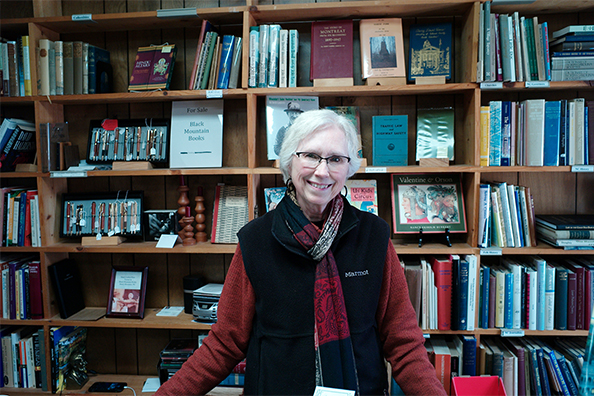 [図8-3]お元気で。またいつか。
[図8-3]お元気で。またいつか。
今度行ったときには楽器屋同様、本屋もそこにはないだろう。小さな山間の町でも、やはり変化していくのだ。同じように今に残ったBMCも変わっていく。それをこうして記録できるのは、幸運なことだ。
1949年春にBMCは大きく変わった。それはそう悪いことでもなかった、とぼくは思う。その後のBMCや20世紀中葉のアメリカ文化を知っているからそう思えるのだが。
1949年3月、アルバースは評議委員会を辞任し、臨時委員長の選出を要請する。委員長には農場の責任者で農村社会学を担当していたレイモンド・トレイヤーが指名され、10月には財政を立て直すためにやってきたビジネスマネージャーのN.O.ピッテンガーが学長に選出された。しかし、早くも12月には辞任について言及されており、以来、混乱のなかで学長(レクター)は不在となった。
1950年6月2日、候補者を検討するためにレクター委員会を設置し、長い議論の末、改めてレクターの権限についての文書を作成した。1952年1月18日、チャールズ・オルソンは、外部からレクターを招聘するという考えを破棄するよう動議し、マックス・デーン※14はそれを支持した。同月25日、誰かが再びそれを持ち出すまでレクターを決めることを延期することが動議され可決された。10月7日、教授会はレクターの必要性を再度議論し、主任管理者(chief administrator)として誰かを探すことに着手するという動議を可決した。そして53年にオルソンがそのポジションに就いたとされるが、正確な日付はわかっていない。
さて、写真とキャプションを整えているちょうど今日、2021年1月27日から、ドレイアーのアーカイヴ展示「Connecting Legacies; A First Look at the Dreier Black Mountain College Archive※15」がアッシュビルのヴァン・ウィンクル法律事務所ギャラリーで始まった。アッシュビル美術館が主催しており、昨年少し話題になったCLIR(図書館情報資源評議会)からの助成金によるBMCデジタルアーカイヴ※16最初のお披露目展である。400点に及ぶドレイアーのBMC関連ドキュメントが展示されるらしい。誰も書けなかったドレイアーとBMCの関係の一端を見ることができるかも知れない。すぐに飛んでいきたいところだが、そういうわけにもいかなくなった。YouTube※17を見ながら、デジタルアーカイヴの公開を待つことにしよう。
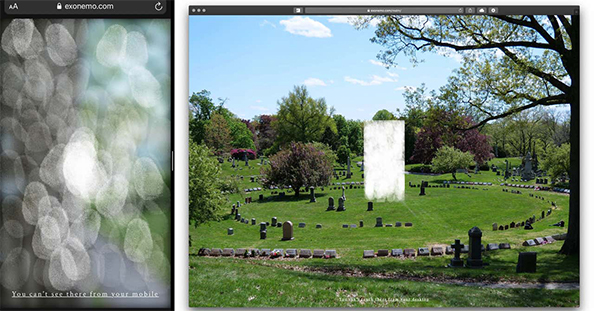 [図1]エキソニモ《Realm》(2020)/左がスマートフォンで見た場合,右がパソコンで見た場合
[図1]エキソニモ《Realm》(2020)/左がスマートフォンで見た場合,右がパソコンで見た場合
本論考は、エキソニモが久々に発表したネットアートの作品である《Realm※1》が、二つのインターフェイスを持つ意味を探るものである。
《Realm》はパソコンとスマートフォンという二つの環境からアクセスできるオンライン作品である。同じサイトにアクセスしても、パソコンとスマートフォン双方のディスプレイに表示される映像が異なり、そこでの体験も別々のものになっている。東京都写真美術館で開催されたエキソニモ個展「UN-DEAD-LINK」の作品解説には「見えない風景、美しい墓場の写真群のイメージは、二つの全く異なったものが共存している環境を示唆している」と書かれている※2。エキソニモが《Realm》で「墓場」という死を連想させる風景とともに、同一の作品に二つの異なる環境と体験を用意し、それらを行き来して体験するような仕掛けをした意味を探っていきたい。
ヒトを「Realm=中間地点」に呼び寄せる白いオブジェクト
私はエキソニモの《Realm》を、まずスマートフォンで体験した。スマートフォンのディスプレイをタップすると白い指紋のイメージがついた。私の指紋がディスプレイにもついたけれど、それは見えない。見えるのは、白い指紋のイメージだけであり、それは私の指紋ではない。指紋の奥には「美しい墓場」の緑が見えるけれど、ボケていてあまりよく見えない。少し時間が経つと、私がタップしなくても、白い指紋は増えていって、奥の緑の風景はさらに見えなくなっていく。風景は切り替わっていくが、指紋のイメージは墓場と私とのあいだに残り続けている。私がスマートフォンに触れた痕跡を示す私の指紋は見えないままであるが、私が触れたところには白い指紋が残り続けている。ディスプレイのガラスの奥から放たれるピクセルの光が、私や他の人のタップの痕跡を白い指紋として表示し続ける。その結果、白い指紋がディスプレイのほとんどを覆ってしまい、その奥の緑の風景はほとんど見えなくなる。この段階になると、私はディスプレイの下部に表示されている「You can’t see there from your mobile」というテキストの意味を実感している。「there」は白い指紋の奥にひろがる「墓場」である。
「You can’t see there from your mobile」をタップすると「You can visit there from your desktop」とでてくるので、私は「there」=墓場を訪れるために、パソコンを開き、ブラウザを立ち上げ、《Realm》のサイトにいく。パソコンを開いて《Realm》にいくと、私は「there」=墓場を見ることができた。緑の風景のなかに墓石が並んでいる様子が確認できると同時に、そこには霧のようにもやっとした白いオブジェクトがあるのが見える。先ほどのスマートフォンでの体験から、この白いオブジェクトが、スマートフォンのディスプレイを覆う白い指紋の集まりであることをすぐに理解する。白いオブジェクトはスマートフォンの縦長のディスプレイと比率も同じように見える。スマートフォンのディスプレイをタップすると、そのタップに応じて、パソコンのディスプレイが表示している白いオブジェクトにも白い指紋が現れる。パソコン版の《Realm》のディスプレイの下部には「You can’t touch there from your desktop」 と記されている。確かに、私のMacBook Proではディスプレイに触れても「there」=墓場で何も起こらないので、触れている感じはない。では、タッチパネルを搭載したパソコンならどうだろうか。おそらくディスプレイには触れることはできるが、白い指紋を残すことはできないようにプログラムされていて、白いオブジェクトを含んだ墓場に触れることはできないと考えられる。
墓場の風景と白いオブジェクトは、スマートフォンとパソコン双方に現れるが、その見え方は全く異なるものになっている。エキソニモの千房けん輔は、この状況を次のように述べている※3。
加えてウェブの技術的な話で、ロックダウンの時に、未発表の個展のために作品を作ったりする中で発見がありました。スマートフォンと同じアドレスを、パソコンのウェブブラウザで開くとリッチな画面が出てきて、スマホで開くと省略された画面になって、スマホで見るときは主観的で視野も狭まっているし、パソコンのブラウザで見ると客観的に広く見えるみたいな、同じ空間でも、全然違う見え方をしている、その二つの領域の中間地点みたいなものが気になってたんですよ。だから全てにおいて、ロックダウンの中で、いろんなものの間にある中間地点みたいなことが、頭に浮かんで、ちょうどその時にネットアートをまたやりたいっていう希望も出てました。それまではちょっと物理的な作品が多かったですが、ロックダウンになった後にネットだけでしか存在しない作品を作りたい、そういう意識も芽生えて、そこら辺がすべての中間地点でパンと繋がったアイディアでした。
エキソニモ「エキソニモへのインタヴュー」
千房は、主観と客観とのあいだの中間地点として《Realm》が現れると述べている。主観では見えないものが、客観では見える。客観では触れられないものが、主観では触れることができる。墓場のなかの白いオブジェクトを「オブジェクト」として見るにはパソコンが必要となるけれど、それに触れるにはスマートフォンが必要となり、誰かがスマートフォンのディスプレイに触れないと白いオブジェクトはパソコンに現れない。二つの異なるインターフェイスを行き来するなかで、《Realm》の白いオブジェクトを含んだ墓場の風景が見えないものと見えるもの、触れられるものと触れられないもののあいだに現れてくる。また、千房はこの作品を「ネットアート」と考えている。ネットアートを語る際に必ず登場するMTAAの《SIMPLE NET ART DIAGRAM※4》は、ネットアートがパソコンとパソコンとのあいだ=中間地点で起こることを端的に示している。この作品を見れば、《Realm》がネットアートとして作成された理由は理解できるだろう。「ネットアート」である《Realm》において、パソコンとスマートフォンというあいだに緑の風景を持つ墓場があり、そこには象徴的な白いオブジェクトは、《SIMPLE NET ART DIAGRAM》が示すように異なるインターフェイスをつなぐリンクの中間地点にあることになるだろう。しかし、二つのインターフェイスでその見え方が異なるものになるのが、この作品の興味深いところになっている。
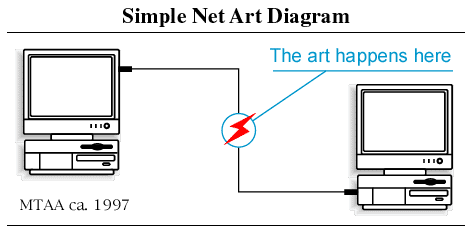 [図2]M.River & T.Whid Art Associates (MTAA)《Simple Net Art Diagram》(1997)
[図2]M.River & T.Whid Art Associates (MTAA)《Simple Net Art Diagram》(1997)
スマートフォンのディスプレイに触れ続け、パソコンのディスプレイを見続けると、「there」としての白いオブジェクトを含んだ墓場を見ることも、触れることもできるようになっていく。二つのインターフェイスの体験によって、《Realm》はスマートフォンとパソコンのどちらか一方のみで体験したものと異なる作品になっていく。スマートフォンのディスプレイをタップしながら、白いオブジェクトをつくり、それに触れているという感覚が強くなるほど、その存在は明確になっていく。白いオブジェクトが二つのインターフェイスをつなぐ中間地点として存在感を強めるとともに、それを見ている私もそこに引き寄せられていく。そして、その触れている感覚とともに明確になっていく白いオブジェクトを含んだ墓地の風景をパソコンで見ていると、二つのインターフェイスを行き来する自分の居場所が曖昧になってくる。私は白いオブジェクトに触れられるところにいながら、その全体が見えるところにもいて、主観的な位置と客観的な位置に同時にいるような感覚になっていくが、そのどちらか一方にいるわけではなく、私自身も白いオブジェクトとともに二つの異なるインターフェイスを結びつけている「中間地点」に存在しているのではないかと感じられるのである。
《Realm》は二つの異なるインターフェイスを用いて、触れることと見ることとを結びつける「中間地点」として白いオブジェクトをつくり、そこに作品体験者を引き寄せていく。この作品体験と対比するために、エキソニモの「ゴットは、存在する。※5」という連作を取り上げたい。その理由の一つが、2009年に発表された「ゴットは、存在する。」には、スマートフォンを用いた作品がないということである。この作品には、エキソニモがスマートフォン以前のインターフェイスについての考え方が色濃く示されている。その考えは、インターフェイスを用いた作品でありながら、鑑賞者とのインタラクションがなく、触れることなく見るだけの作品体験になっているということに現れている。
標準的なインターフェイスやデバイス、インターネットの中に潜む神秘性をあぶり出すことをテーマにした一連のシリーズ。光学式マウスを2つ絶妙なポジションで合わせることでカーソルが動き出すことを発見し、その祈っているような形態と、祈ることで奇跡が起きている状況を作品化した「Pray」。日本語で神を意味する「ゴッド」と、一箇所だけ違うが意味を成さない単語「ゴット」をTwitterの検索結果の中で置き換え「ゴット」の存在する世界を表出させた「Rumor」など。用途をずらし、無効化されたインターフェイスの中に神秘性を見出していく試みでもある。
エキソニモ「ゴットは、存在する。 (series)」
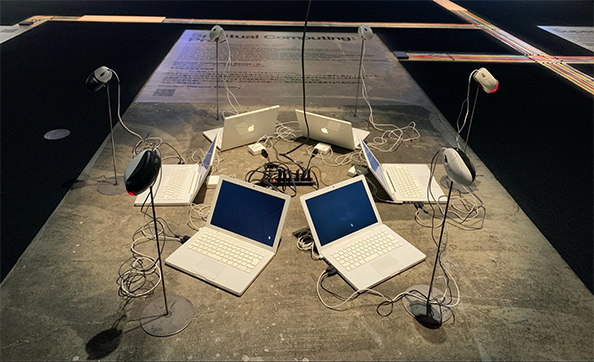 [図3]エキソニモ《Pray》(2009)
[図3]エキソニモ《Pray》(2009)
エキソニモによる作品解説にあるように、「ゴットは、存在する。」はマウスとカーソルとの組み合わせたインターフェイスに「神秘性」を見出していく。それはインターフェイスの無効化、言い換えれば、ヒトを介さずにコンピュータを「操作」することが可能かを試すことであり、その試みに意味=神秘性を見出すことであったと言える。「ゴットは、存在する。」シリーズで「UN-DEAD-LINK」に展示されている唯一の作品《Pray》では、重ね合わされた二つの光学式マウスがヒトの行為を介さずにディスプレイ上のカーソルを動かしている。「ゴット」を「ゴッド=神」と勝手に読み替えてしまうように、鑑賞者はこの状況から勝手に「祈り」という人間らしい行為を想起してしまう。コンピュータは情報入力のためにヒトの行為を必要とし、その情報の入出力の場としてインターフェイスが開発された。しかし、エキソニモはインターフェイスからヒトを締め出し、インターフェイスが自律的に情報を生み出す状況をつくり出す。ヒトを介さずに自律的に情報が生み出されるのを見て、ヒトはそこに何かしらの意味を見出してしまう。
私は「メディウムとして自律したインターフェイスが顕わにする回路※6」というテキストで《Pray》と谷口暁彦の連作「思い過ごすものたち」とを論じて、以下のような結論に至った。
エキソニモと谷口は、それぞれのインターフェイスからヒトを取り除き、インターフェイスをアートのメディウムとして自律させることによって、ヒトとコンピュータを取り巻くより大きな回路の存在を顕わにする方法を得ているのです。
水野勝仁「メディウムとして自律したインターフェイスが顕わにする回路」
「より大きな回路」というのは、自律的に情報が生み出されていく領域のことを意味している。通常、インターフェイスはヒトとコンピュータとのあいだにあり、双方から情報の入出力を受け付ける機能を担っている。しかし、《Pray》はヒトがいなくても、一定の状況に置かれたインターフェイスがコンピュータとともに情報を生成できることを示している。それは、ヒトとコンピュータ、そのあいだにあるインターフェイスが「より大きな回路」ではすべて等しく、情報をつくり出すためにオンオフの切り替えを行うスイッチとして存在していることを意味している。スマートフォンの《Realm》は《Pray》と異なり、ディスプレイをタップするヒトの行為が「白い指紋」という情報を生み出している。スマートフォンを介して作品に取り込まれた「白い指紋」が、パソコンでは自律的な情報となって白いオブジェクトを生成していく。しかし、パソコンの《Realm》では《Pray》と同じように、インターフェイスに触れることが無効化されており、ただ白いオブジェクトを見るだけになっている。
《Realm》はパソコンとスマートフォンとで見ると触れるという異なる体験をつくりながら、ヒトを「より大きな回路」に組み込み、ディスプレイに向かわせる。パソコンでは見ることしかできず、触れることはできないが、スマートフォンではディスプレイとヒトとのあいだに接触が起こり、指紋が情報として「より大きな回路」に取り込まれていく。ヒトが再びインターフェイスに取り込まれたことで、《Realm》では「ゴットは、存在する。」シリーズの作品になかった「奥行き」がディスプレイに生まれている。ディスプレイの最前面に位置するカーソルが大きな役割を果たしていた「ゴットは、存在する。」では、カーソルとウィンドウという平面的な存在の重なりが強調され、パソコンのディスプレイに「奥行き」が無効化されていた。対して、《Realm》ではタッチ型インターフェイスとカーソルを用いたインターフェイスとのあいだを行き来することで、デスクトップで作品を体験した際に、最前面のカーソルとその奥にある白いオブジェクトとのあいだに「奥行き」が生まれている。この「奥行き」は、インターフェイスが生み出す情報の流れにヒトが入り込んだ結果として生まれたものであろう。そして、「奥行き」とともに墓場という場所が提示され、その奥にある白いオブジェクトにはスマートフォンを介して、触れられるようになっている。しかし、パソコンが見せる「奥行き」とともに現れる「美しい墓場」には入ることも触れることもできないのである。
《Realm》で、ヒトはインターフェイスに戻り、ヒトが入り込める余地としての「奥行き」をディスプレイに見つけたということになるだろう。しかし、それはパソコンのディスプレイが示すデスクトップから眺めた風景でしかないということも考えなければならない。スマートフォンで作品を体験するときには、「奥行き」の存在はぼやかされていて、ディスプレイに触れるほど「奥行き」は見えなくなっていき、最前面の「指紋」を見ることになり、ヒトはインターフェイスに触れながらも、そこから締め出される。スマートフォンの白い最前面は、デスクトップではヒトを招き入れている白いオブジェクトとなって、ディスプレイに「奥行き」をつくる。白い最前面と白いオブジェクトとが同一の存在であり、それが二つのインターフェイスを行き来するヒトを締め出すと同時にヒトを受け入れている。そのプロセスにおいて、ヒトは情報の入出力をつかさどる「より大きな回路」のなかに組み込まれたり外されたりしながら、二つの異なるインターフェイスがつくる「中間地点」に呼び寄せられていく。
「幻想の触覚」を用いて死を呼び寄せる
エキソニモの《Realm》では、スマートフォンのタッチパネルに触れることでインタラクションが起こり、そこから白いオブジェクトが墓場に生成され、ヒトが「より大きな回路」のなかの「中間地点」に呼び寄せられる。ここで考えたいのは、エキソニモがパソコンとともにスマートフォンというあたらしいインターフェイスを用いて、《Realm》で「中間地点」をつくり出しているということである。このことを考えるために、まずはスマートフォンによってもたらされたあたらしい感覚について考えてみたい。
アーティストであり、美術批評も行う布施琳太郎は「新しい孤独※7」において、iPhoneに代表されるタッチパネルに触れることをアートの文脈から考察している。そこでは、私が書いたGUIに関してのテキスト「インターフェイスを読む #3 GUIが折り重ねる『イメージの操作/シンボルの生成※8』に触れつつ、パソコンでは触れることがないディスプレイに触れることの意味が書かれている。
私は上のテキストで、コンピュータ科学者のアラン・ケイが提唱したスローガン「Doing with Images makes Symbols(イメージを操作してシンボルをつくる)」を論じ、「イメージ=見えるもの」と「シンボル=見えないもの」のあいだに「/」を入れた。それは、ディスプレイに表示される「イメージ」と「シンボル=プログラム」とが折り重なっていることを示すためであった。イメージを操作することは、プログラムを操作することにつながっている。そして、マウスとカーソルとの組み合わせでは、「イメージの操作」はマウスと連動するカーソルという「イメージ」で行われることになっている。ディスプレイに表示されるイメージには直接「触れる」ことはできないまま操作を行い、シンボルを生成し続けている。
布施は「iPhone」がこの状況を一変させたと考えている。
つまり「iPhone」は「イメージの操作/シンボルの生成」というアラン・ケイを起源に持つGUIやパーソナル・コンピュータの基本コンセプトから離れ、その操作を、対象を直接操作するような「幻想の触覚」に一元化した。その実現のためにマウスやトラックホイールをはじめとした物理的な入力装置、GUIの大きな特徴である重なり合う複数のウィンドウ、そしてプラスチックで固定されたキーボードなどは排除されたのである。そして「iPhone」はイメージとシンボルの二層構造を排除しながら、巨大なタッチスクリーンを採用する。「iPhone」のユーザーは、麦畑でLSDを摂取したジョブスと同じように、「幻想の触覚」によって対象を直接操作するのである。
布施琳太郎「新しい孤独」
iPhoneの登場によって、ディスプレイに表示されているイメージを直接操作できるようになり、「イメージの操作/シンボルの生成」という二層構造は「幻想の触覚」に一元化されると、布施は指摘する。確かに、マウスとカーソルとの組み合わせで「イメージでイメージを操作する」ものよりも、「指でイメージを操作する」という方がダイレクトにイメージを操作する感覚になる。しかし、指はイメージに直接触れるのではなくタッチパネルを介して触れているので、この状態を「幻想の触覚」とするのは的確な命名である。そして、布施は最果タヒの詩「白の残滓」を経由して、「幻想の触覚」の考察を深めていく。布施は「白の残滓※9」において、以下の部分が最も重要だと指摘する。
大丈夫、窓に近づくと蒸し暑く、私はガラスに手をつけて、
向こう側の私と、半分ずつ祈りを捧げている、
やわらかい体、だということを私は知らない、
硬質なつもりでこの時間をつきぬけようとしている、
その先にあるものが、新生児の私、また、やり直しの人生だとしても。
最果タヒ「白の残滓」
そして、布施はこの部分を「iPhone」を軸に以下のように考察していく。
この作品で最果タヒが表現したのは、生と死や視覚と触覚(=寒/暖)といった複数の二項対立を、ガラスのこちらと向こうに同時に存在できるような「やわらかい体」によって二重性へと変奏し──しかしそれ自体は「私が知らない」ことだ──それを「硬質」な体の「つもり」で「つきぬけようと」する様子である。これはGUIという「二層構造」とは異なるコンセプト、つまり「幻想の触覚」に基づいて設計された「iPhone」についての記述として理解することができる。
つまり「ガラスのこちらと向こうに同時に存在する私」であるところの「やわらかい体」とは「ガラス=GUI」による二層構造に基づいたインターフェイス的主体である。しかし最果は、ガラスのこちらとそちらに同時に存在する「やわらかい体」を自身が持っていることを「知らない」のだと言う。そこでは「硬質な」体によって、その「ガラス」を、「この時間を」、「つきぬけようと」する。こうして「ガラス」はパーソナル・コンピュータにおける「GUI」から「iPhone」へと置き換えられる。彼女は、その「知らな」さによって、二層構造の後の「iPhone」の時代を定義する。我々はその「二層構造」を「知らない」のである。
布施琳太郎「新しい孤独」
GUIの「二層構造」とは異なる原理を持つスマートフォンは、生と死、視覚と触覚の二項対立は二重性と変わっていく。生と死とは対立するものではなく、それぞれが重なり合うものになり、同時に存在している。最果の詩を読み解く布施においては、こちら側も向こう側もなく、それらは二重に重なり合って一つの平面になっていると言える。「二層構造」を「知らない」ことで、あらたに「幻想の触覚」が生まれてくるというのは、とても魅力的である。あらたな感覚が生まれるときに、それまでのことを「知らない」がゆえに感覚が刷新されることがあるからである。
布施は「「iPhone」の画面はイメージとシンボルの二層構造を持たない。「見えるもの」と「見えないもの」の二重性は、その「ずれ」は、世界を直接操作するような「幻想の触覚」によって一元化され、消去される」と書いているが、エキソニモは「見えるもの」と「見えないもの」とのあいだに「ずれ」があると考えているのではないだろうか。なぜなら、彼らはGUIの二層構造をよく知っているからである。よく知っていることを知らないふりをするのでも忘れてしまうのでもなく、GUIの「二層構造」とスマートフォンの「幻想の触覚」とをリンクさせて、あらたな二層構造をつくることで自らの作品をこれまでとは異なる方向性に持っていこうとしていると考えられる。
千房:《Realm》はロックダウンの初期の頃から作っていて、そのままその時のナイーブな雰囲気が出ていて、結構今のこの状態を的確に表現できていると思って気に入っています。詩的でストレートにも見えますが、詩を構成する“言葉”としての、スマホなどのメディアやそれら同士の関係性を意識しています。今気が付きましたが、若い頃拒絶していた写真のような古典的なメディアと、夢から現実化していったインタラクティヴなメディアアートの両方の要素も持っていますね。今はそういう相反する要素を共存させることが、自分たちにとっての挑戦なんです。
エキソニモ「エキソニモへのインタヴュー」
ここで千房は「相反する要素を共存させる」と言っている。異なる要素を一元化するのではなく、要素を共存させるとなると、そこには必ず「ずれ」が生じるはずである。エキソニモは《Realm》で、スマートフォンがつくる「幻想の触覚」から距離をとるために、パソコンとスマートフォンとをリンクさせ、あらたな二層構造をつくったと考えられる。また、千房の言葉から、エキソニモはマウスとカーソルによるパソコンのインターフェイスとタッチパネルによるインターフェイスとを「言葉」として捉えていることがうかがえる。最果が言語で詩をつくるように、エキソニモは異なるインターフェイスを「言語」として組み合わせて詩=《Realm》をつくっている。布施が最果が記述した言語の関係性を読み解くことで「幻想の触覚」を導き出したように、異なる二つのインターフェイスのリンクを読み解くことで、エキソニモが示すあらたな方向性が見出せると考えられる。
エキソニモ作品のあらたな方向性を探る一つの手がかりが、スマートフォンがもたらす「幻想の触覚」で一元化された感覚とパソコンのGUIにおける「見えるもの=イメージ」と「見えないもの=シンボル」の二層構造の感覚とのあいだを行き来していると現れる白いオブジェクトである。なぜなら、この白いオブジェクトはスマートフォンによる「幻想の触覚」が、GUIの二層構造の「ずれ」を可視化したものだと考えられるからである。
千房:今の時代は触ったら感染するなど、今までなかったセンシティヴさが問われていて、でもスマホはよく触る。だから画面にタッチすると指紋が表示される仕組みを作って、スクリーンが一枚の膜であることやよく触っていることを再認識させる意味も持たせています。スマホはより身近で身体的で、インタラクティヴで、でもウェブブラウザは、逆に全く接触ができない状態にする。その二面性がある構造を作って、その中間地点には何があるかを問うているところがあります。
エキソニモ「エキソニモへのインタヴュー」
エキソニモは「接触」をキーワードにして、スマートフォンとパソコンのブラウザで相反する「二面性の構造」をつくり、「幻想の触覚」で一元化された感覚を用いて、GUIの二層構造の「ずれ」をよく見ようとしている。こちらとあちらとを貫く「幻想の触覚」は「見えるもの=イメージ」と「見えないもの=シンボル」のあいだの「/」に触れていく。スマートフォンのディスプレイに触れるヒトの指紋によって可視化される「/」は、パソコンのディスプレイではこちらとあちらとを区切るような「一枚の膜」となって、ディスプレイに「奥行き」をつくるとともに「美しい墓場」を見せるようになる。「美しい墓場」のなかに現れた「一枚の膜」は、パソコンのディスプレイが示す「奥行き」のために見ることはできるが触れることはできない「中間地点」に位置するようになっている。
《Realm》で「幻想の触覚」によって可視化され、「美しい墓場」の「中間地点」に現れる「一枚の膜」の意味をさらに考えるために、編集者の伊藤ガビンによる「UN-DEAD-LINK」展のレビューを引用したい※10。伊藤は今回の回顧展から見えているエキソニモの主題と《Realm》について、以下のように書いている。
回顧展という空間で、過去作をまとめてみると、その作家の強い主題、隠しようのない芯が見えてくる。私にはエキソニモが、執拗に「こちら側」と「あちら側」と「その間にある膜」みたいなものを描いているように思える。
物理空間と仮想空間だけではない。作品とツール、アートとコマーシャル、東京と地方、日本と英語圏、男と女、大人と子供、そして生者と死者。「その間にある膜」をエキソニモは揺らす。人々はその膜のゆらぎに気づくと同時にどうしようもなく「こちら側」と「あちら側」も意識せざるを得なくなる。
物理会場の最後に「Realm」という作品があるのは象徴的だ。触っているのに触れることもできていない。膜を破ることができなくても、何かを伝えることはできるのだ。
伊藤ガビン「メディア・アートの王道と呼ばれて。|メディア・アートの外道と呼ばれて。」
エキソニモは「こちら側」と「あちら側」と「その間にある膜」を描いてきたと、伊藤は指摘している。エキソニモはスマートフォン以前のGUIをよく知っているために、「こちら側」と「あちら側」とを一元化することはできない。ここで注目したいのは、エキソニモは「その間にある膜」を揺らすことで、作品の体験者が「こちら側」と「あちら側」とを意識せざるを得なくなるという点である。確かに、《KAO》や《DISCODER》、《FragMental Storm》といった初期のエキソニモの作品は、インタラクションとともにインターネットやコンピュータそのものの原理を「その間にある膜」として扱い、物理空間と仮想空間との存在を考えさせた。その後の《断末魔ウス》、「ゴットは、存在する。」シリーズ、「Body Paint」シリーズなどのヒトのインタラクションを持たない作品においては、エキソニモはヒトの認識をハッキングするような強い衝撃によって「その間にある膜」を揺らし、作品の体験者が「こちら側」と「あちら側」も意識せざるを得ない状況においたと言える※11。しかし、《Realm》においては、体験者は「こちら側」と「あちら側」も意識せざるを得ない状況に置かれるのではなく、その「中間地点」を意識させられる。つまり、《Realm》は「その間にある膜」そのものを主題にして可視化しているのである。この作品の体験者は「一枚の膜」を「触ってるのに触れることもできていない」状況のなかで、見つめ続けるようになる。エキソニモは《Realm》で「こちら側」と「あちら側」ではなく、「その間にある膜」を意識せざるを得ない状況をつくっているのである。
では、ここで意識せざる得ない存在となっている「一枚の膜」とは何なのだろうか。それは、《Realm》の風景となっている「墓地」が示す「死」であろう。哲学者のウラジーミル・ジャンケレヴィッチの『死』の冒頭「死の神秘と死の現象」に、最果の詩のようにガラスを介した生と死とが語られる記述がある。
生きている者と彼岸[オー・ドラ]の大いなる秘密とを隔てるものは、その透明なガラスの厚みでしかないというのだろうか。ドストエフスキーの作品中の人物は時にこの魅力にひかれる……。半透明な膜が此岸[アン・ドサ]と彼岸[オー・ドラ]とを隔てる、とメーテルリンクは言っている。膜の片側には此岸にしてすでに彼岸にあるものが、他の側には、辛うじて彼岸にあり、ごくわずかしかむこう側になくて、要するにほとんどこの世にある彼岸。一つの他の世界。絶対的に他で、絶対的にほかにあり(ここ以外のところ、これ以外のものであり)ながら、しかもいたるところで現存するむこうの世界、つまり、神のごとくいたるところに現存して、いたるところに不在なもの。むこう側[エケイ]とこちら側[エンタウタ]の両側に同時にいて、超越的であってまた内在的なもの。──というのは、ほんのすこしのこと、動脈の中に血塊が一つ、心臓の痙攣一つで《あそこ》がただちに《ここ》になるのだから……。
ウラジーミル・ジャンケレヴィッチ『死』
ジャンケレヴィッチが書く「死」の観点から《Realm》を記述すれば、スマートフォンのディスプレイのガラスが生と死とを分けつつ、ガラスに触れれば触れるほど、《あそこ》=死を《ここ》=生にもたらすような白いオブジェクトの存在が明確になっていく、となるだろう。エキソニモはスマートフォンとパソコンとをリンクさせ、「こちら側」と「あちら側」とをつらぬく「幻想の触覚」を用いて、「こちら側」と「あちら側」との「ずれ」といったそこに存在することは想定できるけれど、実体としては見えない空白を「その間にある膜」として実体化し、一つの白いオブジェクトとして見せている。《Realm》で二つのインターフェイスを行き来しながら、触れつつ触れず、見えつつ見えないという体験とともに実体化していく白いオブジェクトこそが「生きている者と彼岸(オー・ドラ)の大いなる秘密とを隔てるもの」なのである。
メディアアーティストの藤幡正樹は今回の展覧会への寄稿文で、《Realm》の白いオブジェクトが物語を進める謎として機能する「マクガフィン」として言及している※12。
この作品では、現実の自分と画面の中に逝ってしまった自分の指紋と対面する。「これがあれになった」とでも言えばいいだろうか。で、この白い板とはいったいなんなのか、それは手元のスマホのタッチパネルのコピーであると同時に、スクリーン上の光の明滅でもある。とはいえ、ひとまずその機能が判ったとして、つまりブラックボックスの仕組みが判ったとしても、実際にはなにも判ったことにはならない、依然としてマクガフィンの意味は不明だ。なので、より良く理解しようとする人は、何度もスマホにタッチする、「でもそれは『マクガフィン』なんだよ、君。」タッチすることに熱狂させることが、この作品の目的なんだよ。
藤幡正樹「『エキソニモ UN-DEAD-LINK』展特別寄稿」
《Realm》では、白いオブジェクトがマクガフィンとして作品の中心に位置している。それは謎であるがゆえにインタラクションを生み出しはするが、ヒトの認識をハックするような強い衝撃を持つ表現というわけではない。ここで重要なのは、エキソニモのインタラクションを伴う作品で、「マクガフィン」と呼ばれるような「秘密」や「象徴」が表出されることは、これまでなかったということである。いや、それらを多少は持っていた作品はあるかもしれないが、《Realm》のように「マクガフィン」が中心に据えられることはなかった。白いオブジェクトをよりよく理解しようと、スマートフォンの透明なガラスに多くタッチしても、白いオブジェクトが明確になるだけで、そこに何も意味は生まれない。しかし、「これがあれになった」というかたちで、スマートフォンの指紋は直ちにパソコンのディスプレイに「逝って」、白いオブジェクトになってしまう。そして、白いオブジェクトが明確になればなるほど墓石のようになっていき、「死」が強まっていくのである。
《Realm》には、ヒトの認識をハッキングするような強い衝撃もなければ、インターネットやコンピュータ、または、インターフェイスの「神秘性」を否応なく感じさせることもない。その代わりに、エキソニモは「死」という見ることも触れることもできない象徴的な対象を作品に呼び込んでいる。芸術作品では対象となることが多い「死」ではあるが、エキソニモの作品において、ダイレクトに感覚できる死や否応なしに死を認識してしまうというかたち以外で「死」が作品に持ち込まれたのは、はじめてだと言える。《Realm》は「死」が「こちら側」や「あちら側」としてダイレクトに認識されるではなく、「そのあいだの膜」として表出され、象徴性を持って作品に入り込んできたという意味で、エキソニモ作品の一つのターニングポイント=将来の中間地点になると考えられるのである。
近藤宏:
私自身も日本語版の翻訳に関わったのですが、2013年に英語で発表されて世界中で大きな反響のあった“How Forests Think(邦題:『森は考える※1』2016年刊行)”の著者であるエドゥアルド・コーンさんに、本日は主に三つのテーマについてお伺いしたいと思っています。ひとつ目は、『森は考える』についてお尋ねしたいと思います。つぎに、民族誌的現実について分析し、考える方法について。そして、最後に、『森は考える』以後に、どのようなことをなされてきたのかについてお聞きしたいと思っています。まずは、この刺激的で挑発的なタイトルの著作『森は考える』で、何を目指されていたかを振り返りっていただけますか。
『森は考える』はどのように作られたのか
エドゥアルド・コーン:
『森は考える』は民族誌なので、人々と共に暮らし、その人たちがなすことに耳を傾けるなかで出来上がりました。わたしがフィールドワークを行なった地域では、人は人のあいだでのみ暮らしている訳ではありません。彼らは森のなかで、人と人以外の様々な存在に囲まれて暮らしていました。そのため「民族誌を行なって(doing ethnography)」、様々な存在に「耳を傾け」ました。そこには「人びとの声を聞くこと」以上の意味があったのです。私は、人ではない存在たちの声にも耳を傾けていたのです。わたしは、人々がこうした「他なる存在」と交流する様子を傾聴していました。
そのうち、人々が森にいる存在とコミュニケーションをとるときには、言語がふつうとは少し変わったかたちで使用されているのに気付いたのです。そのようにして、人々が何をしているのかを理解するには、わたしがもともと考えていた人類学自体についても変えていかなければならないことに気付いたのです。森のなかで様々なたぐいの存在と関わり合う人々と真の意味で一緒に過ごすこと。それがこのプロジェクトの根本にあります。

近藤:
コーンさんが、そのような発見を一冊の本にまとめる際に、最も難しかったことは何でしょうか。
コーン:
いろいろな段階で多くの困難に出くわしました。私は、本書の基になる調査を行なったエクアドルでは四年間を過ごしました。現地のフィールドワークも、その段階のひとつです。そのフィールドワークは博士論文のプロジェクトの一部だったのですが、ともかく、本当に長い時間をそこで過ごしたのです。「ああ、全く何も起こらないな、退屈だ」と感じたこともありました。しかし、物ごとが急にひとつに結びついて、ひらめく瞬間もあって、後から振り返ってみると、本書にあげた最も刺激的な発見のいくつかは、ほんの数秒の間に起こったことだったのです。
そうした発見については、その後かなりの時間を割いて執筆することになりました。時間性というのは、面白いものですね。とくに何もしないことに多くの時間を費やすこともあれば、瞬く間にことが起こる状況が突然訪れたりもします。そんなふうになるには、自分がその場に居続けることが必要だったのです。いずれにせよ、この本では森が考えるとはどのようなことであるのかを説明しようとしています。そして「なぜそんなことが言えるのか」「人類学の枠組みでもそんなことが言えるか」といったことを、本書を読んだ人たちが話題にできるように、揺さぶりをかけることが狙いなのです。
わたしはこれまで、人類学が多くのことを伝える術を持たないことに歯痒い思いを抱いてきました。人類学者が決まって言うのは、この人たちはこう考え、あの人たちはこう考えている、といったことです。わたしには、そんなことをやっていたのでは、誰かが言った何ごとかを記述する以上に先に進んでいくことができないように思えたのです。
人が他なる存在と関わり合っているという事実があったため、わたしは、研究のやり方は他にもあるのではないかと考えたのです。その結果、本書で扱った研究に結びつきました。というのは、彼らは、森のなかで事を成し遂げるためには、社会的現実や文化的現実 —— 人類学者が日ごろ研究対象としているようなたぐいの現実 —— とは異なる現実へと踏み込んでいく必要があったからです。人々は、他なる存在とは異なる水準で交流しています。話し方や考え方を変えざるを得ないほどに異なる水準においてなのです。わたしはこうした点にとても興味を抱きました。
こうしたことをひとたび理解し、その跡を追うようになれば、その現実が見えてくるようになる、そしてもしその現実にきちんと目に向けるならば、読者が人類学であると考えていることを問わずにはいられなくなる。そうしたことを本書では示そうとしました。人類学は、もはや文化について語るだけではなくなっています。人間であるとはいったい何を意味するのかを考え直すよう、読者は促されるからです。こうしたことすべてにわたって書かれているのが本書です。
§
近藤:
『森は考える』でコーンさんは、人類学者として、現実の新たな捉え方を探っていたのですね。人類学者は、現実を文化的現実として描写することに慣れていて、「ある人たち」だけにとっての現実、つまり他の誰かの現実として理解しています。それに対して、コーンさんが行なったのは、このような現実を、他なる存在の現実、そしてわれわれの現実にまで広げる方法を探すということだったということですね。つまり、「他者の現実」を二つの方向に広げることだと理解しました。
コーン:
まさにそれこそ、わたしが試みたことだったのです。このように現実について語ることができるという事実を示したいと考えました。だからこそ「いかに森は考えるのか」という問いが浮かび上がってきたのです。 わたしは、そこにこそ問題があると指摘したのです。それは、人文科学や社会科学、人類学にある真の問題、これまではなかなか取り組みえなかった問題です。人間を超え、人間が世界をどう見ているのかは超えていくことなどできやしないと考えているのです。
跳ね返ってきた『森は考える』のインパクト
近藤:
なるほど。『森は考える』には、様々な反響が寄せられました。もし気になった反響があれば、教えていただけますか。好意的な反響のなかで、意外だったものはありましたか。
コーン:
学術的な反響は、概ね好意的なものだったと思います。それらは興味深いもので、今でもたまに思い返しています。なかには、わたしの意図を理解していると感じるものもありましたが、その他にはどうなのか分からないものもありました。わたしの意図を十分に理解できていないと感じる表面的な反響もありました。しかし、あまり期待はしていなかったのでその分とても刺激的に感じたのが、専門の人類学外からの反響でした。とくに音楽や芸術の分野で重要視されたことでした。これはとても刺激になりました。
§
近藤:
どのような反響だったのですか。
コーン:
リザ・リムという音楽家がいます。彼女は、中国系オーストラリア人で、現代クラシック音楽のすばらしい作曲家です。彼女は、「How Forests Think」という曲名の交響曲を作曲しました。
これには本当に感動しました。彼女はこの曲を12種類の楽器のアンサンブルとして書きましたが、そのなかには中国の楽器である簫が含まれています。この楽器は、彼女がこの交響曲を演奏する際にはいつも使用されています。簫は、一人の演奏者が演奏します。中国の音楽家がこの楽器を使用するレパートリーを作ったのですが、息を吐いたり吸ったりして音を出すので、とても有機的です。それを演奏するプロセス、さらに、演奏者同士が調子を合わせようとする様子がとても面白いと感じました。作曲にわたしは全く関わっていませんが、わたしの本『森は考える』がインスピレーションとなってこの曲ができたと聞いて、とても興奮しました。
当たり前ですが、珍しいことですね。専門書の議論を参考に音楽に置き換えるなど、普通なら考えられません。この本はわたしの手を離れて歩き出したのです。何が起こっているのか、わたしには理解できませんでしたが、後になって、われわれは連絡を取り合うようになり、カナダ南部にあるバンフという町の芸術センターで、音楽コース、つまり夏期の音楽コースを共に教えました。それ以来、われわれは一緒に活動をしています。わたしにとって、このコラボレーションはとても刺激的なものです。
§
近藤:
音楽家としての彼女の反応が、今では新たなコラボレーションへと発展したのですね。他のアーティストは、いかがでしょうか。
コーン:
本当に新しいことが起きているのは、アートの分野ではないかと思います。アーティストたちはアイデアを求めており、気候変動に関心を強く持っています。アーティストたちは、拙著から、気候変動について表現する方法を見出しました。
また、アートにおける問題には、表象に関するものがたくさんあります。本書では、生ある世界と私たちの関係性を本当に理解するには、表象について理解せねばならないということを強調しました。私たちはいかに事物を表象するのか、また他者がいかに事物を表象するのか。そういったことを理解しなければならないのです。
§
近藤:
日本では、ある美学の専門家が『かたちは思考する』という本を執筆しています※2。このタイトルには、『森は考える』の影響が見られます。内容は、芸術家や画家の創作過程を通して、図形やかたちそのものがどのように考え始めるのかというものです。あなたと彼の著書は、どこか似たような考えに基づいているようです。
コーン:
そうですか。ぜひ彼と連絡をとってみたいですね。
§
近藤:
わたしの知る限りでは、日本でも、人類学以外の分野からも創造的な反響がありましたよ。
一流の人類学者とは民族誌的思想家のことである
近藤:
では、つぎのテーマに移りたいと思います。翻訳者として感じる本書の魅力のひとつは、フィールドワークの経験で得られた民族誌的現実を独特な仕方で読み解いていくところにあると思います。あなたが現代人類学を論じたレビュー論文※3のなかで、一流の人類学者を「民族誌学的思想家」だと表現していますね。民族誌的現実が人類学独特の広い視点をもたらしていると述べているように思われる、喚起的な表現だと思います。民族誌的現実をめぐる考え方や、民族誌的現実を通した考え方というのは、いったいどういうものだと思いますか。
コーン:
人類学という分野が非常にユニークである点として、観念とその歴史に高い関心を持っていることも挙げられるでしょうけれど、結局のところ、方法論が重要なのです。民族誌とは、個人的な思い込みを少しでも取り除いて、事物に対する考えを変えるような何かと向き合う方法を見つけるための手法です。
民族誌がそうした手続きの中心にあるのも、それが、あらゆることを考え直さざるを得ない場のようなものだからなのです。事物に対する思い込みを思い切って捨てなければなりません。そして、それがまさに廃れることのない、変わることのない形式なのです。形式というよりも、変わらず進行しつづける、そのようなものだと言ってもいいかもしれません。人類学のなかでも優れたもののひとつは、方法にあると思います。それは、自らの道具立てや思い込みの全てを問い直すようなものとしての、耳の傾け方なのです。
§
近藤:
『森は考える』では、数秒から1分ちょっとの間に起こったことを詳細に描写し、そこにいかに民族誌的に深い意味があるのかを説明していましたね。民族誌的現実について考えることが、われわれの考えの前提を再考する機会となるという点は、多くの人類学者が同意すると思います。ただ、本書にはそれ以上のもの、現実の豊かさを伝える方法のようなものがあるように思えます。
コーン:
はい、そうした現実にはいくつかのことが含まれていると思います。まず、本書を執筆するときにとても助けになったのは、会話や、起きた出来ごとに対する非常に丁寧な描写の録音データがあったことでした。些細な事柄に対する豊かさは、ここから生み出されています。また現実の細部は、言わばいくつもの層をなしているのだと受け止めまることができました。そして、その点に留まることにも時間をかけたのです。そのようにすることで、物ごとを様々なレイヤーから比べることが可能になったのです。
現地の民族生物学というレイヤーではできる限りの動植物の調査を行ない、さらには民族誌的なレイヤー、歴史的知識のレイヤーへと踏み込みました。これらの事柄全てによって、様々な事物を探り当て、関連づけることが可能になったのです。そしてもちろんのこと、それらの多くは、書いているあいだにやって来たものだったのです。
わたしは、書くこと自体が、関連性や物ごとを把握する方法であると考えています。なので、別の事柄をコツコツと探り当てるために、立ち戻っては別の道のりを探るという方法を取ったのです。本書を書いていたときに行なっていたことのひとつがそれです。
本書は博士学位論文を再考し、完全に書き換したものです。学位論文にある文章は、本書には一文も入っていないかもしれません。しかしそれでも、土台にあるプロジェクトは同じでものですよ。扱われているのは同じ素材です。
学位論文と本書の文章は全く異なりますが、同時に全く同じものです。ただこの研究においてとくに刺激的だったのは、たくさんのフィールドノートを手にしていたときです。ノートはすべてタイプされていました。すべてコンピュータに収められたのです。研究期間も終わりに近づいており、これらのノートをすべて手に取って丁寧に読み込み、そのノートに対してさらにノートを作ったのです。フィールドノートにある大きなテーマはそれぞれ何だったのか、ノートを取ろうとしたのです。
わたしは最終的に約125ページの長さの文章を書き上げました。これらはフィールドノートに対するノートなのです。それはこれまでになく興奮した時間でした。自説を立証し要点を示さねばならないとき、すべてが関連している様子を示さなければならないとき、そうした考えを書くことは難しいように思われました。ですが、パターンだけを見ているとき、物ごとを見ているとき、洞察力が発揮されているときには、すべてをありのまま残したいと思う気持ちによって、書くことに対する情熱が続いたのだと思います。そうできるよう、深く注意を払っていました。こうして本書が出来上がったのです。
パターンを見つける、森を録音する、森の思考が人間の言語を変える
近藤:
おっしゃってることに、とてもワクワクします。それが、『森は考える』のなかでも述べられている、パターンを見つけるための方法だったのですね。
コーン:
そうなんです。まさに、パターンを見つけることだったんですよ。類似性について、ともいえるでしょう。森はいかに考えるかが本書のテーマであり、森の考え方が、全体像として繋がりを持ち始めたのです。そのような思考を自分の創造的思考においても養おうと努めたのです。そして、そのために文章を書くことがどれだけ助けになったことか、ひとたび物ごとが分かり始めて並行して見えてくるものがあるのは面白いですよね。非常に興奮します。
実は、わたしは文章を書くのが上手ではありません。明解な文章を書くのが苦手なのです。すごく長い時間をかけて書いています。数段落を分かるようにするために数週間をかけることさえあります。そのような文章が説得力を持つようになるのは、こういった文章に対して「この文は何だ?わたしはあまり好きになれない。何てつまらないんだ!」といった自分の心の反応を大切にするのです。そして、より良い文章が書けるよう、できる限りの努力を続けています。
§
近藤:
あなたが思考する上で、パターンや類似性を見つけることが非常に重要であるとおっしゃっいましたね。著書では、類似性やパターンを見つけようとするのは生命特有の考え方だというベイトソンの研究について触れていましたよね※4。ベイトソンの議論を見つける前に、なんとあなたはすでに彼が述べていたこと、つまりフィールドノートからパターンを見つけ始めていたのですね。生命が考えるように、あなた自ら考え始めていた。
コーン:
レヴィ=ストロースは、数学、音楽、人類学が、真の天命(vocation)であるという素晴らしい発言をしています※5。なぜなら、それらの分野は、自分自身によって、あるいは、自分自身のうちに、すっかりと見出すことができる天命だからです。自分のなかから引き出すことができるのです。
そして、自分の発見が、フィールドとの関わりが、考えるためのツールを与えてくれるという意味において、まさしくその通りだと思います。そして、深く考えているときは、その考えが他の人の深い考えと合致するということは十分にあり得る話なのです。もちろん、ベイトソンとわたしは同じ考えにたどり着くかもしれませんが、それはその考えが本当はわれわれの考えではないからなのです。それは、われわれが耳を傾けた世界から示されたものなのです。
§
近藤:
日本で行なったプレゼンテーションでは、森での録音を使って、木が倒れる音を聴衆に聴かせていましたね※6。わたしも人類学者としてフィールドワークを行なうのですが、わたしは木の倒れる音を録音するために森にレコーダーを持って行くという考えは全くありませんでした。レコーダーをわざわざ持って森のなかを歩こうということは、どのように思いついたのでしょうか。
コーン:
わたしが用いる方法のひとつは、インタビューではなく、自然のなかや、自然に囲まれて起こっている物ごととして、人々が普段どおりの文脈で話している様子を捉えようとするのです。そのために、テープレコーダーを森に持って行なったのです。
§
近藤:
フィールドワーク中はいつもテープレコーダーを持っていて、どこでも録音を始めていたということですね。
コーン:
森に入るときは、たくさんの物を持って行くのですが、何も使わないときもありました。今、どうやっていたかを思い出します。わたしは本当に興味深い会話を録音したときもありますが、いつも上手くいくとは限らず、結果的にはどうということのない録音もたくさん残っています。
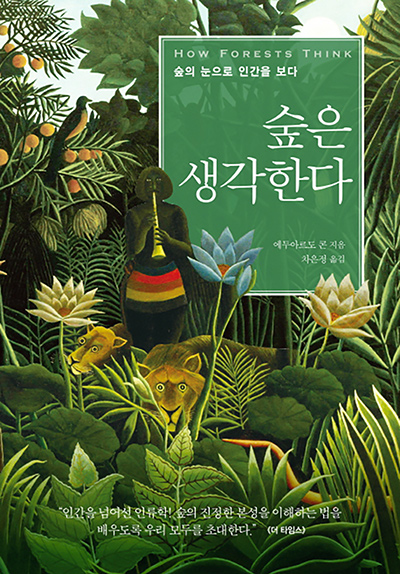
近藤:
『森は考える』で、コーンさんはイメージで考えるという表現を使って、人類学者の考えに特有の感性を表わしているように思われます。そして、著書のなかの写真はとても美しく、とても示唆に富んだものになっているように思います。 イメージで考えるというアイデアは、どのように思いついたのでしょうか。とくに刺激を受けた経験や研究、議論などはあったのでしょうか。
コーン:
わたしがフィールドワークを行なった地域の人々は、数百年前はどの言語を話していたかあまり分かっていないような人びとです。どのようなことばを話していたか、誰も知らないのです。
数百年前から現在にかけては、ペルー由来のケチュア語族のひとつであるキチュア語を話しています。この言語は、インカ文明と共に北方に広がり、アンデス系諸語と密接に関係しています。アマゾンで話されていることには、アンデスで話されていることと密接に関連するものがあります。しかし、興味深い例外もあります。そのひとつが、アマゾンの方言には、アンデスにおける同じ言語には存在しない「擬音語」が、ひとつのクラスと呼べるほど多く生まれているということです。
わたしはそのことに注意を向けるようになりました。わたしは、これが別の考え方への小さな入り口のようなものだということに気づいたのです。そうした擬音語は、いろいろな事を為すことばです。森のイメージを創造することで、森のことを語っているのです。音のイメージ、行動のイメージ、行動が展開されてゆくイメージ。普通のことばの使い方とは、全く異なるものです。そのことばはどれも、本当に写象主義的(imagestic)なのです。それらのことばを調べ、なぜ使われているのか、なぜ森のなかでなのか、なぜアンデスでは使われずにこの場所では使われているのかについて分かろうとしました。
そうしたことがわたしの関心を引くようになり、イメージを考えることへの足掛かりができたのです。そしてわたしが考えるには、つまるところその考えによって、人が森のなかで考えることが可能になるのです。それが「森の思考」にとても似ているからなのです。つまり、言語で用いられているような象徴、つまり恣意的な記号を伴わない思考のかたちであるような、森にいるあらゆる存在の思考にとても似ているのです。
非常に興味深いのは、それがどれほど模倣されるのかによって言語が変わってくる、という点です。また、そうした模倣による部分は言語そのものにうまく収まらないことが多いという点も、興味深く思っています。イメージは全体で、たとえば活用変化させることはできないからです。そして、他の言語にもこのようなイメージ的な部分があるのも面白いところです。日本語にも多いのではないでしょうか。
真の思想家であるアマゾンの人たちとともに、倫理的なプロジェクトへ
近藤:
なるほど、すごく面白いですね。ところで、三つ目の話題に話を移したいと思います。ここからは、「森は考える」以降のプロジェクトについてお尋ねします。現在進められている、「Forests for Trees」というプロジェクトについて教えてください※7。そこでは、アニミズム的概念を実際の環境政策に生かし、関連づけようとするエクアドルの人びとのネットワークと協力されていますね。彼らはどのような活動を行なっているのでしょうか。また、彼らとどのように仕事をしており、そこから何を学びましたか。このようなコラボレーションを通して感じることはありますか。
コーン:
『森は考える』という本は、様々な意味で存在論的な本でした。その本では、世界における物ごとのあり方をテーマにしています。どちらかと言うと学者向けに、世界は現在考えられているものではないことを述べた本でした。もしそうなら、哲学的・概念的な枠組みを超えて、もっと世界に対して正確なものにしていかなければなりません。とくに世界をめぐる議論としては、われわれはみな何らかの仕方で考える森に暮らしているということがあります。それはひとつの実在です。だから、そのことについて書いてみたのです。すると、新しいプロジェクトがかたちになり始めました。
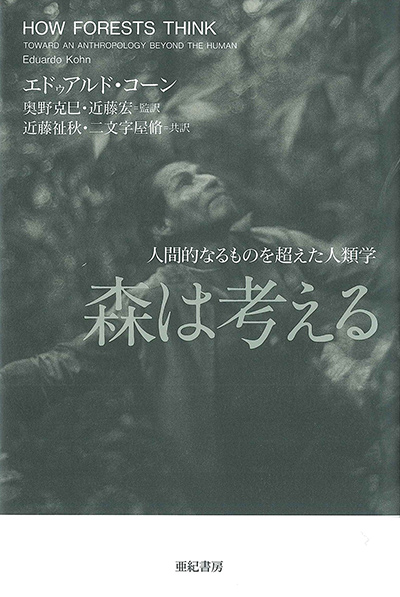
『森は考える』の刊行後に、わたしは「待てよ、考える森というのは実在するだけではなく、良いものでもあるんだ」と考え始めたのです。それには価値があります。そして価値があるならば、その価値が壊されないようにするために、そして世界にそうしたものを増やすために、われわれができることは何かを考え始めました。こうして、わたしの研究がより倫理的なプロジェクトに繋がったのです。存在論的なプロジェクトは、倫理的なプロジェクトに変わっていきました。
そうして、わたしはエクアドルに戻りました。わたしは、2015年から16年にかけて、研究休暇期間をエクアドルで過ごしました。その期間に成し遂げたかったのは、アマゾンにある他のコミュニティと共に活動することでした。これらのコミュニティとは、こうしたたぐいの倫理的プロジェクトを分かち合うことができました。そのプロジェクトは、われわれの生き方やなすことではなく、本当に守るべき良いものなのです。そのことを、わたしたちは人々に伝えています。こうしてわたしは、アマゾニアにある森を石油会社や道路工事から守っている人びとと同盟を結び、世界の人々に伝えようとしています。そうした人びとと共に活動するようになることで、わたしの研究もとても刺激的なものとなりました。
「Forests For The Trees」のという本についてのアイデアですが、タイトルは英語のことわざから来ていて、日本語に相当するものがあるかどうかわかりませんが、英語では「木を見て森を見ず(you can’t see the forest for the trees)」と言います。この表現は通常、細部ばかりに気を取られて全体を見失うことを意味しています。一般性が見えていないのです。つまりこの表現について考えられるのはたいてい、人間には抽象化する能力が特別に備わっているということです。本当にしっかりと考えているときは、適切な抽象化を行なっています。わたしもこの表現について考えていますが、同じ比喩を、文字通りに、また比喩的に考えています。
何が言いたいかというと、森のようなものが存在するということです。森は、われわれがつくりあげる、単なる抽象化されたものではありません。森とは、単なる木々の集まりではないのです。それは創発的な特性ですから、それを構成する諸要素に還元できるものではないのです。ひとつの森という事物が存在し、その森には木々にとって良いものを言い表すための何かがあるのです。比喩的に言えば、われわれはその木々なのです。
つまり、わたしは今では、森とは何かを語るのではなく、気候変動や恐ろしい生態学的危機に直面しているわれわれを、森がどのように導いてくれるのかを問うているのです。今までの人間中心の倫理観が通用しなくなっていることは明らかです。われわれを導いてくれる、より大きな世界の声に耳を傾ける方法を見つけなければなりません。しかし、どうしたらいいのかがあまりよくわかっていないのです。
森のなかに導きを見つけるというのは、実際にはどういうことなのか。アマゾンに暮らす人びとは、その方法について素晴らしい答えを持っていました。そのため、わたしは真の思想家である、アマゾンの思想家、精神的なリーダーたち、物ごとを探求する方法や問いかける方法、関わり合う方法を絶えず問い直すこの人びとと共に活動をしています。彼らと共に事をなすのはとても刺激的で知的な旅ですが、いつでもその目標は、気候変動に対する具体的な方法を考え出すことにありました。
§
近藤:
最近、エクアドルの原油流出事故について、他の著者と共著でアルジャジーラに短い記事を寄稿していましたね※8。この記事も、ネットワークのメンバーとのコラボレーションの産物なのでしょうか。
コーン:
はい、彼女もメンバーです。 わたしは仕事の幅を広げています。以前、アヴィラで仕事をしていた頃の仕事は、わたしと、コミュニティと森だけでした。今ではいろいろな人と共に活動をしています。そのひとつに、サラヤクとサパラという2つの先住民族のコミュニティとのコラボレーションがあります。わたしはどちらとも共に仕事をしていますが、なかには密接な共同作業になるものがあります。わたしは、彼らのアニミズムを政治的声明文書に翻訳する作業を手伝っています。
これは新しいからこそ非常に面白く、魅力的な仕事です。わたしは、教えながら、ある種の翻訳を彼らが行なうことを手伝っています。このことは、その場所で起こっていることを描写する機会を与えてくれるだけではなく、描写することが物ごとに対する考え方といか関係しているかを教えてくれます。こうして、彼らがそうしたことを行なうのを、手伝ってきたのです。さらに、共に執筆もしています。
そうしていると、彼らの夢やビジョンを見る仕方が重要なものになったために、書くことに対する私たちの考え方が変わりました。ことばに対する感情面での応答が、大切になってきたのです。コミュニティとの共同作業の他にも、アーティストとの共同作業もあります。ミュージアムを作ろうとしています。パズルのもうひとつのピースは、弁護士や森の保護に興味のある人たちとのコラボレーションです。
なので、アルジャジーラの記事は、活動家であり学者でもあるマヌエラ・ピークとのコラボレーションから生まれたものです。彼女とわたしは、法廷で争われることになった原油流出事故の証人の友人です。そのため、それに関する記事を書いたのです。
§
近藤:
先住民のコミュニティと書いた文章は公開されたのでしょうか。
コーン:
はい。なかでもとくに面白いのが最初の一本で、それが理由でこのような仕事をするようになりました。サラヤクのコミュニティが執筆し、完成させました※9。つまり、わたしは書いていないのです。編集作業を手伝い、よりまとまったものにしただけです。
文章は、初めからよく練りこまれたものでした。キチュア語で「Kwak Sacha」と呼ばれる、生きている森を意味する概念はすでに出来上がっていました。「生きている森」は、パリで開催されたCOP 21気候サミットで、彼らが発表した宣言です。わたしはサラヤクの人びとからこの宣言を発表できるように、編集する手伝いをしてほしいと頼まれました。そして、それを各国の首脳の前で発表したのです。多くの人の前で発表を行ないました。
文章はアニミズムに関するもので、人類学者にとってはそれほど驚くべきものではありません。このようなアニミズムは、アマゾンの先住民の考え方として重要な部分を占めます。しかし、この文書が他と一線を画するのは、彼らが理解しそれに従い生きているアニミズムを取り上げて、「もし、わたしたちこそが法律を作ることができたら、どうなるだろうか。それによって、法律や財産、主権や権利に対する理解は、どう変わるだろうか」と言っているところにあります。
彼らはアニミズムの考えを政治の領域に持ち込み、どうしたら押し戻すことができるのかを示しています。まずこの作業が終わると、他のコミュニティ、サパラがわれわれの活動を聞いて、森との関係についての知と彼らのメッセージを世界に伝えるために、いくつかの法的な活動を行ないたいと考えるようになりました。これはとても面白いプロセスです。というのも、森の声を聞く様々な方法を見つけながら、そうした文章を書ことになったからです。とても深められています。今までに二本の文書を仕上げ、三本目に取り掛かっています。
世界に耳を傾け、イメージ的な地図制作をせよ
近藤:
コーンさんは、ある論文で、「時代が求める倫理的実践の一環として森の考え方を育てていく」という決意を表明していましたね※10。人類学は、現代にどのような倫理的プロセスを提供できるのでしょうか。あなたは、われわれの今をどう捉えて、現代における喫緊の課題とは何なのでしょうか、人類学は現代にどのような貢献ができるとお考えですか。
コーン:
現代の大きな問題は、気候変動という危機だと思います。皮肉めいて面白いのは、この気候変動は、人間が原因のものだという点です。それは人間のあり方に対する理解を変えてしまいます。実際にこのような影響を与えているのが人類の文化であるならば、それを理解した上で、人間とは何かを考え直さなければならないのではないでしょうか。
また、われわれが生きるこの時代は、地質学的には人間の時代である「人新世」としばしば考えられています。それを考え直す際に、人類学が関わってくるのは、ごく自然なことだと思います。批判としてだけではありません。単に人間は間違ってしまったと言うだけでなく、これから何が可能なのかを提言する立場として。そう、これは創造的なプロジェクトなのです。
§
近藤:
森と同盟を結ぶ新たな方法を考えだす必要があるのですね。
コーン:
はい、その方法を見つけなければなりません。人類学的な問いとして興味深いのが、その解決策が耳を傾けることから生まれるというところです。それを成し遂げるには、いかになされてきたのかに耳を傾け、習得することが必要になるのです。こうした倫理的アプローチを面白いと思うのは、あることが良いとか悪いとか、あるいは道徳的規範を学ぶための異なる場所が見つけられる、と述べている訳ではないからです。その倫理的アプローチは、あなた自身が答えを見つけられると伝える、世界に耳を傾ける特別な方法で、耳を傾ける様式は、生ある世界にある様々なダイナミクスの一部として既に存在しうる、ということを言っているのです。
ここにもある種の並行性、つまり物ごとをめぐるわれわれの考え方との間にあるイメージ的な地図制作(imagestic mapping)が、改めて存在するということです。その地図を通して、そのかたちを、世界に事物が到来するプロセスを通して、事物を考えることを学ぶのです。
§
近藤:
今日はインタヴューに答えていただきまして、ありがとうございました。エクアドルの人々とコラボレーションした文章を読むのが楽しみです。人類学者だけでなく、気候変動や環境災害の問題を真剣に考えるすべての人にとって、非常に重要なことではないでしょうか。
コーン:
今後、もっと一緒に何かができるといいですね。
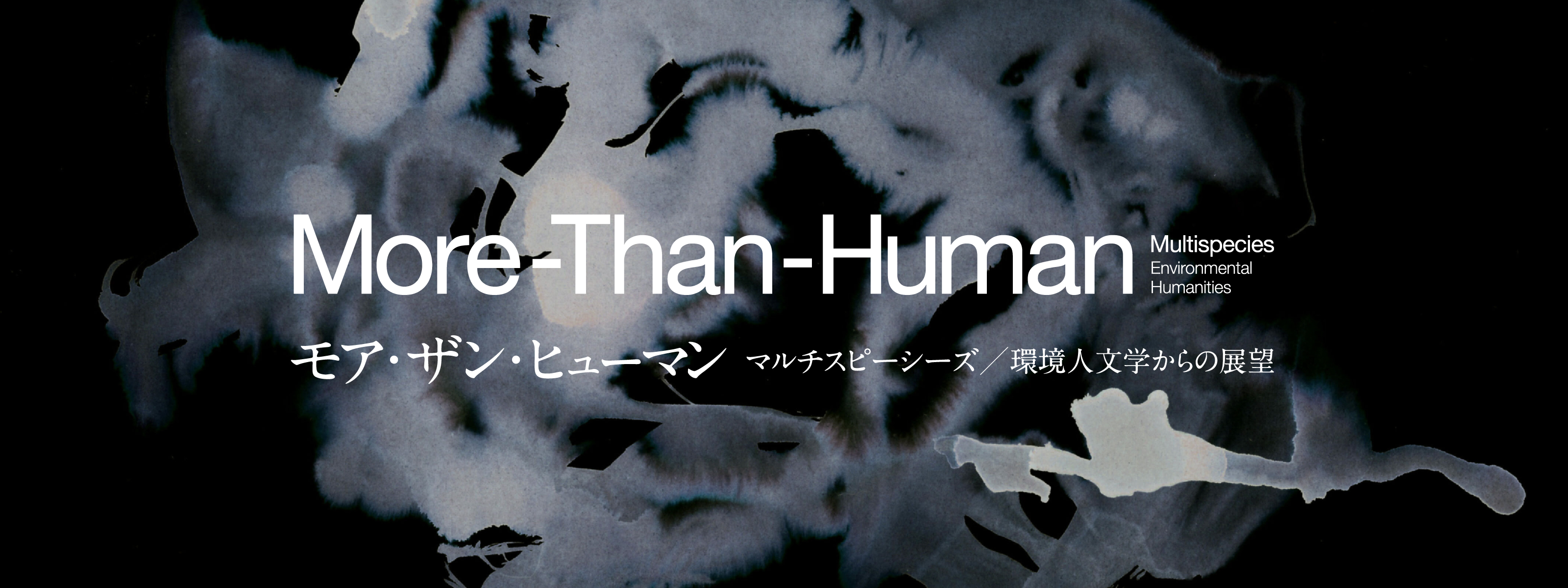
環境運動から人類学への道のり
山田祥子:
パンディアンさんはこれまで人類学者として大変幅広く研究されてきていますが、その中でも根底にあるひとつのテーマとして「人間の創造性」、つまり、農民や映画作家、また文化人類学者に至るまで、この世界を人がいかに即興的に、常に新しい可能性を創り出しながら生きていくかという問題に関心があるように感じます。ですが以前、別の場※1で、ご自身は大学院に進まれるまで人類学者になるつもりはなく、それ以前は環境関連のアクティビストとして活動されていたともお話しされていました。環境に関わるお仕事をされる中で、なぜ人類学、また特に人間の創造性に関する問いに惹かれるようになったのか、お話しいただけますか。
アナンド・パンディアン:
私はロサンゼルスのコンクリートジャングルの中で育ったのですが、高校生のときから環境問題に興味を持ち、環境保護主義者として自分を見るようになっていきました。これは大学に入っても続き、アマースト大学での学部生時代には「ポリティカル・エコロジー」という学際専攻を自分で組み立てて学びました。ポリティカル・エコロジー(政治生態学)という分野が実際に存在することは当時は全く知らなかったわけですが、私としては、環境政治に関心があったわけです。時代は1990年代、地球サミットが話題で、政治においても環境が重要な位置を占めるようになったかに見えました。私自身、当時のこうした政治情勢から、読むもの、余暇の過ごし方、参加するコミュニティー活動や社会運動など、様々な側面で影響を受けました。またその中で、環境問題は、集団行動はもちろん、ともすれば社会的変革をも伴う政治的問題である、という感覚が養われたのだと思います。このような興味関心から、大学卒業後数年間は、いろいろな環境団体や開発団体で仕事をしました。
1996年に大学院に戻ったときに入ったのは、カリフォルニア大学バークレー校の環境科学・政策・マネジメントの学際プログラムでした。出願は南インドの地方の小さな村からおこないました。当時は地元のNGOで環境開発のプロジェクトに関わっていて、博士号を取得したらまた環境・開発関係の仕事に携わりたいと思っていました。そこで履修した授業、学んだ教授陣は素晴らしく、ナンシー・ペルーソ、マイケル・ワッツといった本物の政治生態学の第一人者らに出会う機会にも恵まれました。ですが、それ以前もある程度は感じていたことかもしれませんが、そのときに考えさせられたのは、社会的・応用的アプローチ両方を含め、環境関連の研究全般は、人間の本質に関するある大前提に基づいたものである、ということでした。つまり、人間とは根本的に問題のある存在で、やるべきことをやるように人を説得するのは容易ではない、という考え方です。その結果、環境に関する専門知識を持つ者は何がなされるべきかを必然的によりよく理解しているということになっていて、そこで問われるのは、その他大勢をいかにやる気にさせるかということでした。
ですが、これは問題のある考え方で、未だに西洋および世界各地における環境分野で広く見られる人種・階級差別主義をよく表しています。私がこのような考え方に疑問を持つようになったのは、ひとつには当時読んでいたものを通してのことです。私自身が南インドの山村の人々と仕事をし、知るようになっていった経験も大きく影響しました。自分たち自身のことや、西ガーツ山脈の森林保護区の端のあの場所に対する考え方、その土地や風景、またその地を労って大切に扱うとはどのようなことかについて、彼らは根本的に異なる解釈を持っていたのです。
たとえば、私が滞在していたオフィスは山腹地帯の中央に位置していましたが、その地域は政府からは「荒地」とみなされ、荒廃して価値のない、然るべき管理のなされていない場所とされていました。ですが、そこに暮らす人々は、その低木だらけの土地の中で数十種もの薬草を見分けることができていました。その一帯を管理する政府当局の役人が殆ど気付いていないだけで、材木にせよ、家畜にせよ、彼らは明らかに日常的な習慣や実践をおこなっていたのです。
こうして環境マネジメントの分野で力を持っていた言説や組織に対して段々と違和感を持つようになり、人類学へと駆り立てられたのだと思います。人は習慣として悪いことをしてしまうものである、だからそれをどう直すべきか考えるのが私たちの仕事である、という前提に立つのではなく、人がどうして特定の行動をとるのかをもっときちんと理解したかったのです。習慣的行動はどのように形成されるのか。有害な事態が生じる原因には何があるのか。個人の行動と政治、経済、社会、文化、歴史といった構造的要因にはどのような関係性があり、それはどのような結果を生むのか。一度立ち止まって問うべきは、こういった問いではないだろうか。このような問題意識に駆られて、私は政治生態学、ひいては人類学へと踏み込んでいくことになりました。
バークレーの人類学部が私を転入学生を受け入れてくれたこと、またドナルド・ムーアが私の指導を快く引き受けてくれたことには感謝しています。ローレンス・コヘン、ステファニア・パンドルフォ、ポール・ラビノーなどからも非常に多くを学ぶことになりました。
ある種の環境主義としてのエスノグラフィー
山田:
そのトップダウン型の管理と、移りゆく中で形成される習慣的実践との対照は、ご著作にも色濃く現れているように感じます。最新の単著、『ある可能な人類学(A Possible Anthropology)※2』では、人類学の研究手法が持つ可能性について書かれていますが、手法について丁寧に考えることがなぜ今重要なのかに関してお伺いできればと思います。
この本は、この「手元の世界」の中のシワにこそ既に可能性や開放性が内在しているとの考えに基づく一方、現在進行形の様々な問題にも触れられています※3。本書はメティスで学者のゾイ・トッドとの会話から始まりますが、彼女は人類学で今なお続く人種差別・植民地主義のレガシーを踏まえ、人類学をいっそ辞めてしまうべきかどうかの苦悩を語っていて、この緊張関係をよく捉えています。こうした中で、世界の可能性と実際性、その両面を考慮する手法の重要性についてお聞かせいただけますか。
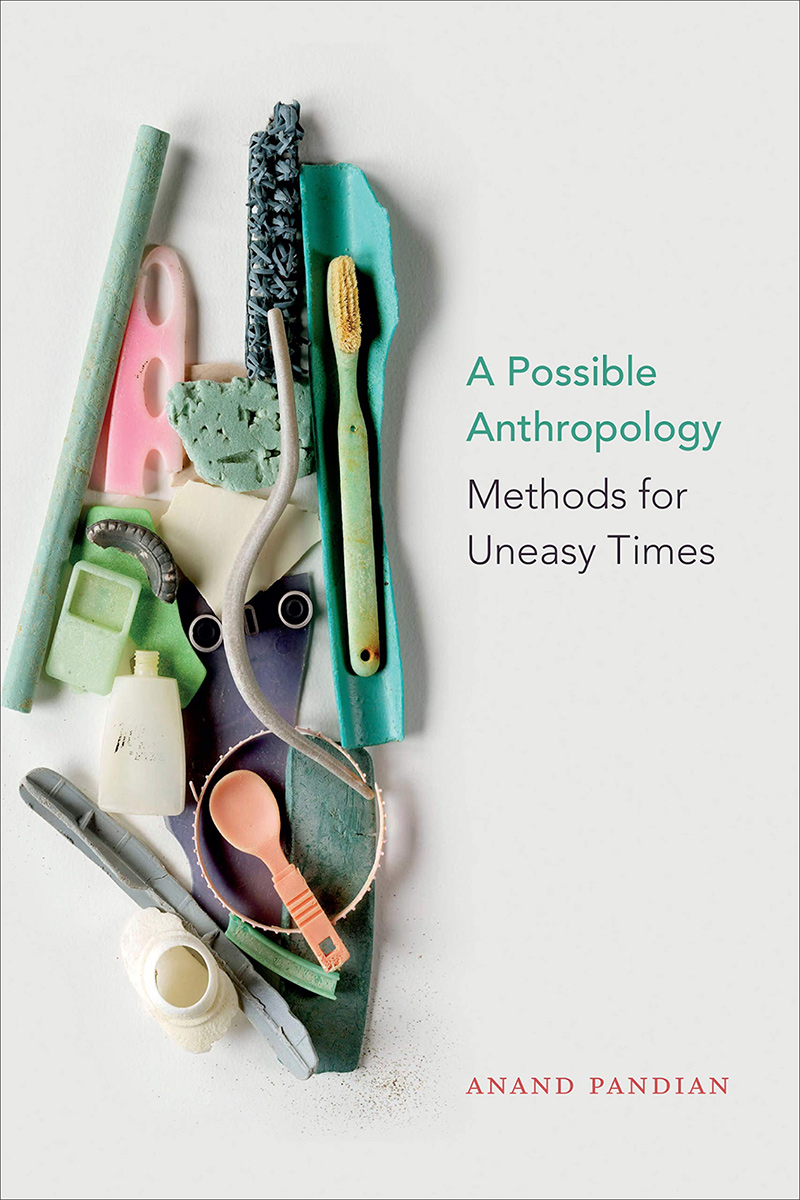
パンディアン:
今が困難のときであることに疑いはありません。環境に関してもそうですし、人種や健康、社会の中で誰が受けるべきケアを受けることができるのかという根本的な問題、そのすべてにおいてそうです。また、コロンバスやセシル・ローズなど植民地主義を象徴する人物らの銅像がようやく撤去されてきていますが、ここアメリカや世界各地で人々が格闘している問題の多くは、現在に至るまで続いている植民地主義や帝国主義のレガシーに深く関わっています※4。私たち人類学者はこれらの状況を直視すべきです。われわれの分野を可能にした条件そのものに対して、広く世の中としての反省がなされているのですから。
ここまでのことをすべて言ったうえで、同時にまた主張すべきだと思うのは、何かに問題があるということは、同時に他のやり方で物事をおこなうのが可能であると示唆していることです。物事には他のやり方がありえるのだという発想は、現状の問題点や困難を指摘する批判において必然的に伴う考え方です。一方がなく他方だけが存在することはありえません。アメリカでここ何週間か精力的に声を発していたアフリカ系アメリカ人の文化人の中には、社会正義に向けた闘争において、ビジョンある想像力が果たす役割について論じている方々がいます。
たとえば、先週ワリダ・イマリシャが素晴らしい講演をしていたのですが、その中で彼女は、すべての社会運動はスペキュレイティブ・フィクションであると主張していました。これは彼女が『Octavia’s Brood※5※6』という本の冒頭でも提示しているポイントですが、社会正義のための運動は、他の可能性に関する思弁的な想像力なしにはありえません。社会の編成の仕方、政治のあり方、私たちの互いの関係性について、根本的に異なる別のあり方を想像することが必要なのです。
そうだとすれば、この点について人類学は何か貢献できるのでしょうか。偶然にも、人類学という学問は、経験的現実に対して横断的な関わり方をとりながら発展してきた経緯があります。実際の現実と実現されていない可能性との間の関係性に波長を合わせながら、現実の世界を他のやり方で生きる可能性を、人類学は常に模索してきました。経験主義的探究に対するこうした先鋭的精神が、人類学をその黎明期から駆り立ててきたのです。
もちろん、このようなコミットメントがあるからといって、人類学が潔白であるということではありません。略奪的暴力や搾取への協力者に成り果てた人類学者を、自動的に救済してくれるわけでもありません。しかし、この人類学の精神は、世界の問題とよりオープンな形で向き合い取り組むにあたっての道具を提供してくれます。
『ある可能な人類学』の中の章のひとつは、まさにこの点を示そうとしたものです。本章では、植民地時代の人種差別を体現していたブロニスラウ・マリノフスキと、20世紀初頭の世界の厳しい人種ヒエラルキーに人生を翻弄され続けたゾラ・ニール・ハーストン、このふたりの間を行き来しながら思索しようと試みています。そうすることで、ともすれば自明に思えることを他の方法で検討するという重要な課題に取り組むにあたり、助けとなるある手法が見えてくると論じたものです。このために私たちは、魔術、神話、メタファーといったものの変革的な力に対して、自らを開放する必要があります。
§
山田:
マリノフスキとハーストンは、一見互いに全く異なるようにも見えますが、エスノグラフィー(民族誌)という実践を共有していました。あなたは本の中で、エスノグラフィーこそがこの世界の可能性とアクチュアリティの狭間に向き合う手法を与えてくれる、と論じられていますが、この試みの実用的な側面についてお伺いできればと思います。エスノグラフィーのこのような可能性を成就させるには何が必要となるのでしょうか。また、そこにはどのような感性や倫理が求められるとお考えですか。
パンディアン:
人類学、中でも手法としてのエスノグラフィーは、いかなる環境人文学のプロジェクトにおいても、大きく貢献しうると考えています。ここまでお話ししてきた経験的現実との横断的関係においては、従来とは異なる類の世界への順応の仕方や、既存の手元の世界の中からより広範に問題意識を見出すことが、究極的には必要となります。研究手法としてのエスノグラフィーを通して他者の世界に没入することは、実はある種の環境的方法論でもあります。
エスノグラフィー自体、ある変わった類の環境主義であるとすら言えます。というのは、この世界を丁寧に気配りを持って生きるための知恵は、その時々の状況の困難さや移ろいやすさへのある種の服従からこそ生まれるものだという可能性を、真剣に捉える環境主義です。この世で出会いうる物事の幅広い可能性に対するオープンな寛容さ、これを育むことが私たち人類学者には求められます。未知の環境に対して、支配欲が頓挫したときの失望感ではなく、関わり合いの精神で応じる力を養う必要があるのです。
私が博士論文のためのフィールドワークで南インドの別の地方の山村部に行ったとき、人の心を〈猿〉に喩えるのをよく耳にしました。予測不可能な直観や欲望は抑制されなければいけない、でないと人が人として崩壊してしまうかもしれない、という考え方です。でも、フィールドワーク自体は私に違った教訓を与えてくれていました。エスノグラファーとして私は、自分自身の心をより広く自由に放浪させることを学んでいったのです。
『ある可能な人類学』の中で私は、このように現在を放浪する感性を〈経験の手法〉と呼んでいます。これはつまり、想定外の事態やそこから生まれる困難に対峙する開放性と感応性を養い、予測しなかった状況と共に生きることを学ぶ方法を指します。これは究極的には、この世界の不確実性そのものに、知識や倫理の礎を見出すことでもあります。エスノグラフィーというのは、ある境遇の野性に対する実践的かつ経験的なコミットメントや、物事が思い通りに進むことに対する拒絶なしには成立しえません。ゆえに私は「人類学的遭遇」において鍵を握るある種の感受性は、環境政治や環境倫理について私たちに多くのことを教えてくれると考えています。
他者に対する共感としての人間性こそが人類学的問いの原動力
山田:
だとすれば、今後、支配や進歩に対する執着とは異なる形の環境主義を想像するにあたって、人類学的感受性がひとつ助けになってくれるのかもしれません。本の中であなたは、人類学というプロジェクトが向かうべきひとつの地平、また鍵となる媒体として、人間性について論じられていますが、以前のお仕事では、文章や映画など他の種類の媒体についても考察されています。特に、『リール・ワールド(Reel World)※7』では、思考媒体としての映画を、直観で考え動くことへのある種の招待として捉えていらっしゃいます。このように媒体というものを様々な種類・角度から考えた場合に、人間性をエスノグラフィー的な関係性における媒体として据えることによって、どのような可能性に開かれるのだとお考えですか。先ほどお話しされていた人種差別や植民地主義のレガシーのことを考えると、人間を単一の共同体として捉えるのは難しいようにも思えます。
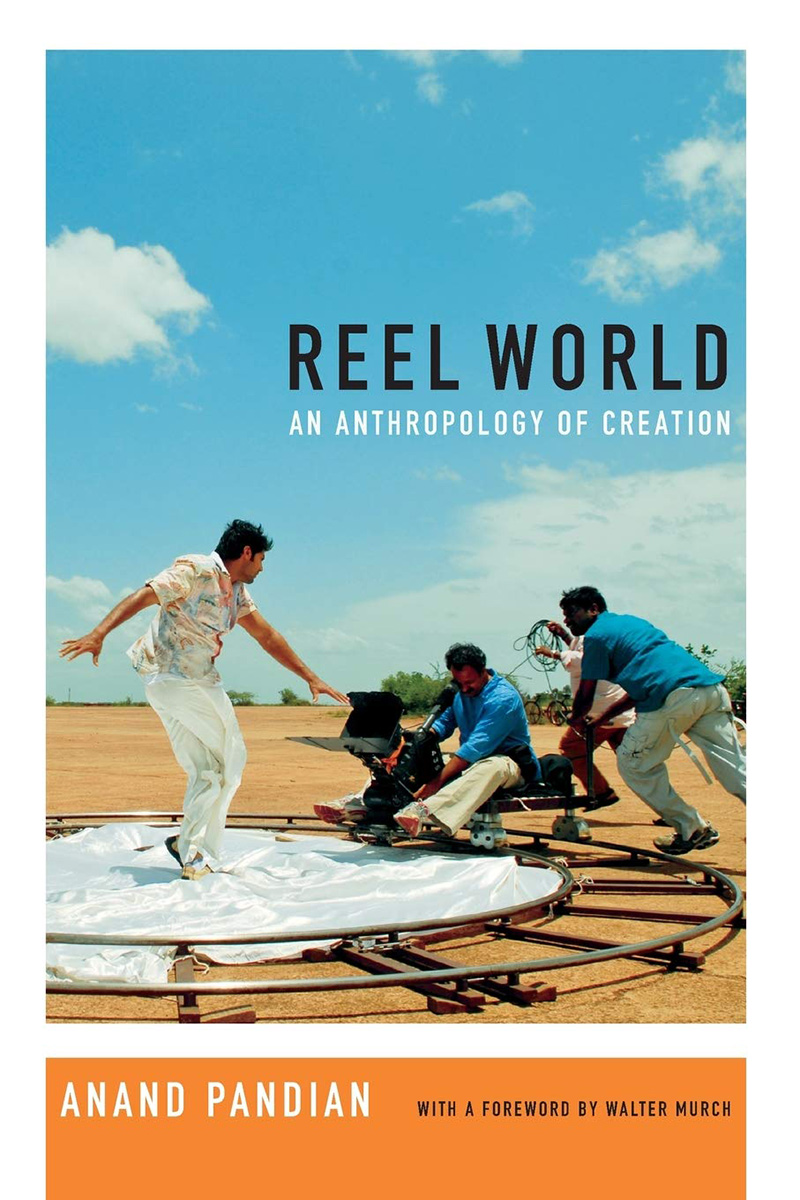
パンディアン:
これは重要な問いですね。ここで強調しておきたいのは、私が〈来たるべき人間性〉について論じるとき、それは単に人間、つまり種としてのホモ・サピエンスを指すのではないということです。人間性とは、自己とは異なる他者に対する共感感覚や同胞意識のことであると私は思っていて、それは状況の良し悪しを問わずすべての人類学的問いを突き動かすものでもあります。学問分野として、私たちは、他者の経験やその違いに真剣に足を踏み入れたときに何が起こりうるのかについて考えています。
すると、この変革的意図に、私たちが仮にもっと正直になった場合に生まれうる政治的および文化的な可能性に関する問いが湧いてきます。私にとってよい人類学の仕事とは、出会う者の心を揺り動かそうとせずしてはありえません。それは本や映画、物語、教室での授業、どのような形式を取る場合もそうです。いかなる形にせよ、出会う者を動かそうとすることでその作品が試みるのは、共同体感覚の地平を変えること、つまり運命を共にするかもしれないと想像する相手の範囲の境界線を動かすことです。人類学をやっていると、実際的にそのようなことが起こる、もしくは起こりえます。
いつも必ずしも今お話ししたようなことが起きたり機能したりするわけではありません。でも、うまくいくときには、そうやって機能するのだと思います。これは、私自身も人類学者だからだけでなく、エスノグラファーとしても申し上げています。『ある可能な人類学』において、エスノグラファーとして人類学という学問を観察していますが、私はこのように人類学が機能するのを見てきました。
この意味で、私たち人類学者が鮮やかで人の心を掴む物語を通じて出会う者の心を動かそうとするとき、そこでやろうとしていることは、映画作家やその他文化人がやっていることとそう変わらないのかもしれません。目的や組織的立場、忠誠心の所在や制作内容は全く違うかもしれませんが、彼らの活動もまた、文化生活は介入可能な領域である、という感覚に突き動かされているわけです。
たとえば、本の中で私は、リチャード・ラングとジュディス・セルビー・ラングという二人組のアーティストを紹介しています。彼らは北カリフォルニアの海岸で10年以上にわたり集めた海洋プラスチックごみを使ってインスタレーション・アートを制作していて、それらはまるで現代世界の考古学的アーカイブのようです。プラスチックには致死性や毒性がある以上、海から流れ着いた破片を使ったその作品にはある種の恐ろしさがあります。でも彼らアーティストは、この恐ろしさを伝えるには、そのモノへのある種の同情的帰属感を通して見る者をまず惹きつけることが必要だと強調しています。
私たちが人類学の社会的役割についてより率直で、注意深くなれば、われわれ人類学者が展開しようとしている主張が、公の場でも他の文化的制作活動と似た形で機能することがわかるようになるかもしれません。そして、それが人々が連帯感を抱く相手の範囲を動かしたいという想いに駆られている以上、そこには大きな政治的、倫理的意義が懸かっています。これが〈来たるべき人間性〉で私が意味するところです。
ここから生まれるのは、次のような問いです。これらの技法を使って私たちは何ができるのか。これまでおこなわれてきたよりももっと面白いことができるだろうか。これまで他の生き方を犠牲に西洋的在り方をこんなにも独善的に持ち上げてきた人種差別的、帝国主義的レガシーに対して、より効果的に立ち向かうことは可能だろうか。われわれ人類学者はこれらのことを既に一定程度はやっていると私は思いますし、それこそが私たちが今暮らしているような社会の中で人類学が果たすべき役割なのだと考えています。
もちろん、私たちは厳密な意味での学問分野として自負することもできます。でも実際には、他者の経験や自己理解を通じて私たちがやっていることというのは、映画作家や他のメディア制作者が実践していることとそう変わらないのかもしれません。私たちがこのことにもっと誠実になり、この分野での研究の型破りな性質に向き合えば、これまで以上にクリエイティブに、もっと面白くそれに取り組むための自由が生まれるのかもしれません。
§
山田:
パンディアンさん自身も、書き物としてのエスノグラフィーや文学人類学の観点から様々な実験的試みをされていますが、それらもまた、今おっしゃっていたような、人類学の持つ、人を動かす力を力強く証明してくれているように感じます※8。この人を動かす力というのは受け手側にある種の脆さを要求するように思えますが、先ほどのお話では、エスノグラフィー自体、エスノグラファーのオープンさ、つまりやはりある種の脆さを必要とするとおっしゃっていましたね。だとすれば、人類学研究を通じて社会に人間性を育てるという課題は、私たち自身の人間性から始まるのかもしれません。
パンディアン:
そうですね。実際、全くもって冷酷な人類学やエスノグラフィーも数多く存在してきました。今お話ししたことは、われわれがある一貫性や効力を持ってこの倫理的仕事をやり切る能力を必然的に持っていると示唆するわけではありません。ですが、それがこの仕事の根幹をなす暗黙の責務であることには変わりないと思います。
だとすれば、私にとって重要になってくるのは、これらの能力をよりよく育み、その野心をより効果的に実現するための条件を作り出すには何が必要なのか、という問題です。おっしゃる通り、これにはある種の開放性と脆さが必要です。ですからそれには、脆くあっても問題がなく、不安定な立場に陥ったりしない状況の創出が伴わなければいけません。それを可能にするには、様々なインフラの整備が必要になってきます※9。
人間的なるものを超えて、イメージの現実喚起力
山田:
そうですね。先ほど、人間性とは私たち以上の存在への共感感覚であるとおっしゃっていましたが、このように広く寛容に人間性を捉える考え方は、近年のポスト・ヒューマニティーズの研究にも繋がる部分があるように感じます。あなた自身もこの分野のご研究に関わってこられていますね。たとえば、『ある可能な人類学』では、ナターシャ・マイヤーズを訪ねて彼女のトロントの都市ランドスケープの木々とのフィールドワークに参加される場面があり、植物の感覚系を理解しようと絵を描いたり、匂いを嗅いだり、地下の根の部分に頭を突っ込んだりもされています。開拓者植民主義や都市化、環境汚染など、その地域の人間的歴史に留意しながらも、人の感覚体験やその変革的可能性を模索した、とても興味深い実験的試みだと感じました。
さらに最近では、新型コロナウイルスの流行当初に世界中でステイ・ホーム令が出され、ここまで蔓延することになってしまったこのウイルスの下でいかに生きるべきか、という問いを私たちは突きつけられています。その中であなたは、〈ホーム〉という概念に関する論評を出され、地球そのものを人間およびそれを超えるすべての存在のホームとして再考することが何を意味するのか考察されています※10。人間性に関するご自身のお考えと近年のモア・ザン・ヒューマン研究の関係性についてお話しいただけますか。
パンディアン:
社会科学および人文学のあらゆる研究分野にとって、今はとても重要なときです。人間は他から孤立して生きているわけではないということを認識させられているわけですから。他者に対する人の行為や希望、欲望は、人間や人間的なもののみでなく、あらゆる類の他の生き物や物質成分から構成された、さらに大きな社会的・物的世界に織り込まれています。それらはわれわれの前から存在していて、今も私たちと共に生きていて、彼らの要求や性向、効力は、われわれが人間としてできることに根本的に影響するものです。ですから、このタイミングというのは、関係性やコンテクストにこれまで以上にしっかりと根ざした形で思考を展開する能力をより深めていくことが求められているのだと思います。近年とても重要な形で発展してきたポスト・ヒューマニティーズの研究の意義のひとつは、そこにあると理解しています。
ですが、ここで興味深いのは、人類学の関心対象が、抽象としての人間であったことは一度もないということです。人について何かしらの知見を得ようとして人間を場所や状況から単に抽象化しようとした人類学の研究は、これまでひとつもありません。むしろその逆で、経験的状況や生活世界、様々な状況のディテールや豊かな肌触りに細かく注意を払わずして、いかなる場所にいる人間のことをも理解することはできない、人類学者は長くそう主張し続けてきました。
ある特定の人間環境で起こりうることを十分に検討するということは、その生活世界に生息し、息を吹き込み、突き動かす力となる、他の人間的および生物・非生物を含めた人間以外の要素まつわる無限の細部に着目することなしに成しえません。ですから、より強固に環境に配慮した方向性が求められている今このときにおいて、それに必要な道具を人類学は長い間保有してきたということを認識するのが重要であると私は考えています。
この点以外にも、どのようなコミットメントのもとに人類学的問いは成立しているのかを問うことはもちろんできます。人類学はある一種類の生き方を理解することに傾倒するあまり、他の生き方を蔑ろにしてきた、それゆえに、われわれがこの世界を共有している他の存在に改めて注視する必要があると、実際にはどの程度言えるのでしょうか。
これに関しては、私たちの分野にとって基礎を成し、大きな影響を与えたきた、ヨハン・ゴットフリート・ヘルダーに立ち返って考えてみることができます。彼については本の中でも第3章で触れています。実に興味深いことに、ヘルダーは18世紀の時点で既に、人間と非人間の境界を行き来するような非常に面白い人間性に関する思索を展開しています。“Outlines of a Philosophy of the History of Man※11”の中で、彼は次のように書いています。
自然は人間を、諸生物の中でも他者の運命に最も密接に携わるよう形成してきた
ここでヘルダーは、単に他の人間のことだけを考えているわけではありません。むしろ、人間と非人間の線を超えたある種の共感的親しみが存在するという事実、さらにはその必要性にまで言及しています。
緑の若木が切り倒されたり破壊されるのを見ていられない人もいる
傷ついたミミズの身悶えするかのような動きを無関心に眺めることなど、心ある人にはできない※12
ヘルダーが説いたのは、すべてに対して自らを投じ、感じ取ることでした。他分野の研究者たち同様、人類学を営む私たちも、人間社会を共有している非人間の他者に対して一層着目しようしています。その中にあって、こうしたより状況に根差した形で物事を理解することに誘いかける開放性は、ひとつとても大切な道標を提供し続けてくれるのではないか、と私は考えています。
§
山田:
もし人類学が、特定の状況下の人間を理解しようと常に試みてきたのであれば、明確に「環境」に関わる研究をおこなう際には、それが一体何を指すのか今一度考えてみる必要もありそうですね。「環境」という概念は、人が暮らすコンテクストに関するある特殊な想定に基づいていることが多く、それは、何が注目に値し保全されるべき環境にあたるのか、という問題も孕んでいます。対して人類学では、膨大な範囲のものを人の生活世界の一部として捉えようとしてきたわけですね。
パンディアン:
まさにその通りだと思います。私たちは環境を人間的であり非人間的であると同時に、社会的であり物質的でもあるものとして語る方法を見つけていく必要があります。それはまた、環境を人間の努力によってのみ生み出されるのではなく、人間の意図を超えた他の多くの存在や要素によって棲まわれ構成されたひとつの境遇として考えることでもあります。西洋の自然・文化の二元論の存在論的奇妙さを単に反復するのではない、より強固な環境概念を私たちが展開しようとするならば、より幅広い枠組みで考えていくことが求められます。この点に関しても、人類学の歴史はまた違ったやり方でそこに焦点を当てるためのひとつの方向性を示してくれると思います。
§
山田:
自然・文化二元論の再考に関しては、エドゥアルド・コーンの著作に関連してお伺いできればと思っていました。コーンはパースの理論的枠組みの中のイメージ、つまりイコン(類像記号)に着目して、人間独自の現象と考えられてきた言語を地域化することを試みています。一方、パンディアンさん自身の特に映画に関するご著作の中では、「言語だけでなく生命をも地域化する」可能性について言及されていて、たとえば映画作家たちと物質的環境との情動的遭遇が、その結果できる映画に組み込まれていくプロセスについて考察されています※13※14。ここで言われているイメージの役割について、人間および人間以上の観点から改めてお話しいただけますか。
パンディアン:
長い間私が大きな影響を受けてきた文章に、フリードリヒ・ニーチェによるエッセイ『善悪の彼岸※15』があります。その中でニーチェは、この世界にまつわる知識に関するあらゆる主張は、常に必然的に比喩的であると述べています。私たちが抽象的真実や主張として当たり前に思っていることは、そのメタファー性を忘却されたメタファーに過ぎないというのです。
他の多くの思想家同様、ニーチェにとって、思考するということ、理解するということは、必ず情動的で、根本的に感覚的かつ身体的、そして経験的なものでした。つまり、考えることと感じること、思考と身体を不可分なものとする発想です。それは思考に対して、その身体的・感覚的生活へのインパクトの観点から向き合う方法でもあります。
イメージと一言で言っても、メタファーと呼ばれる言語的イメージ、写真や映画といった視覚的イメージ、また音のイメージや匂いのイメージなど様々な種類のものを考えることができます。これらに一貫して私がイメージに惹かれるのは、それが思考の物質的基質として働くからです。イメージの力は、その伝達先であり媒体でもある身体から切り離せないものなのです。
映画や映画制作の世界では、これらの問題について多くの大変興味深い思索がなされてきました。たとえば、ロシアの映画監督であるジガ・ヴェルトフは、キノグラース(映画眼)という概念を提唱しました。ドゥルーズも『シネマ※16』で、モノの目、つまり、世界の外部に立つのではなく、世界そのものに内在したある種の見る能力として触れています。また、フランスの映画批評家であるジャン・エプシュタインは、“The Intelligence of a Machine”の中で、「映写機は普遍的変質の力を有する」と述べています※17。
インドや世界各地の文学・哲学的伝統の中にも、イメージと想像力の関係性についてとても面白い考え方があります。デビッド・シュルマンが『More than Real※18』という素晴らしい本の中で示しているように、16世紀の南インドの文学作品では、想像は単に精神上の作り話ではなく、現世的かつ極めて生成的な力として捉えられていました。想像はイメージを通して現実の豊かさや強烈さを増幅させるというのです。
ここでこういったお話をして、環境人文学の観点からイメージを軽視できないと考えているのには理由があります。イメージは、思考の基質でありながら還元不可能なレベルで物質的であるがゆえに、物事の外部に立って遠くから理解するという幻想を見限る必要性を、私たちに突きつけてきます。現代の環境危機やそれに対して、われわれが向き合えない今の状況には、デカルト的心身二元論が大きく関わっていると考えられます。そうだとすれば、その二元論を拒絶して他の枠組みで思考するにあたって私たちが持っている最良のツールは、思考は世界から距離を保った場所で起こるのではなく、世界そのものに属するものだと主張する類のものであるということになります。
コーンは『森は考える ― 人間的なるものを超えた人類学※19』の中で、人間による社会・文化的構築を超えたところで意味というものを考えるひとつの方法を提示してくれました。概念による支配という近代的自惚れを再考していくにあたり、イメージはひとつ大きな道筋を示すものであると私は考えています。イメージは、知覚とモノの関係性を再想像する方向に後押ししてくれるからです。
チャネルとしての人類学、自身を超えて生きつづけるものをつくり続ける
山田:
著作でも触れられていますが、今おっしゃったことは、人類学の中で伝統的に維持されてきた、調査するための「フィールド」、戻って論考をおこなうための「ホーム」という区別に対しても、興味深い別の可能性を示してくれるのかもしれません※20。思考が物質的な基盤と不可分なのであれば、フィールドから戻って始まると考えられていた人類学的思考は、実はフィールドでこそ起こるということになります。
パンディアン:
私自身、人類学の役割はチャネルやメディアであると考えるようになりました。他の誰も見たことがないことや考えもしなかったことを私が見たり発明したりするわけではありません。人類学者として私は、ある知見の独立的・主権的根源でも、知覚の中心でもありません。私が扱うイメージは私自身から来るわけではないのです。伝達チャネル、コミュニケーションメディアとして、私はイメージが通過するひとつの場所に過ぎません。
このような考え方には、ある種の環境倫理が懸かっているようにも思います。私が理解しようとするのは、私なしには無意味な世界ではありません。私にできる精一杯は、私以前から存在している他の生き方を、目に見えて飲み込みやすい形にすることで、願わくば私自身を超えたところで生き続ける何かを作ることだけなのだと思います。
§
山田:
もし人類学者がチャネラーなのだとしたら、その伝達の過程で私たちがする仕事というのはどのようなものなのでしょうか。
パンディアン:
やや挑発的な言い方をすると、最良のときにおいてさえ、それは単に研ぎ澄ます作業に過ぎないのだと思います。より鮮明かつ人の心を捉える形で物事に焦点を当てる作業ですね。プラグマティズムを唱えた哲学者のジョン・デューイは『経験としての芸術※21』という本の中で、一般的な〈経験 (experience)〉と〈ひとつの経験 (an experience)〉を区別し、前者と違って後者には質的統合性があると述べています。芸術作品は往々にして、このように感覚を集中・調整するはたらきをしてくれます。フィールドでの体験を伝えるときに私たちがおこなう作業というのは、このようにしてある経験を研ぎ澄まし、焦点を当て、質的統合性を可能にする作業だと私は考えています。
これは実はフィールドワーク以外にも、読むこと、書くこと、教えることを含めて人類学者の仕事のあらゆる側面に言えることです。学生指導を例に取れば、人類学における効果的な教授法というのは、われわれ教える側が教材に対して絶対的権威を主張することでは実現しません。むしろ、教室の中で創発されるアイディアや驚きに常にアンテナを張り、それに向き合うことでより理解しやすい形に咀嚼し、そうした出会いがわれわれの集合体としての思考や存在の質感そのものを変容してくれるような絶え間ないプロセスにこそ、本質があると思います。このように、変革的な出会いを育み、研ぎ澄ます方法こそが、人類学の持つ〈経験の方法〉だと考えています。
人新世はうまくまとめられすぎていないだろうか、と人類学者は考える
山田:
少し話題は変わりますが、次は人新世についてお伺いできればと思います。これについては、つい最近、シムニー・ホウとの共編で『まだ見ぬ人新世(Anthropocene Unseen: A Lexicon)※22』を出されています。この論集は用語集という少し変わった形を取っていて、各章がある概念に関する僅か数ページの短いエッセイになっています。この形に辿り着かれた経緯についてお話しいただけますか。人新世に関する本であるという点も影響したのでしょうか。
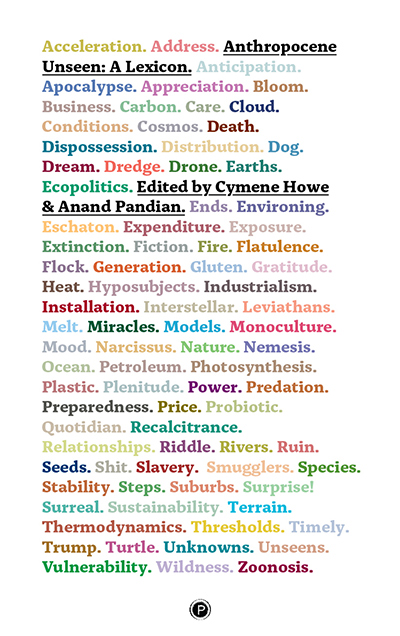
パンディアン:
この形は、もしかしたらどんなものもそうなのかもしれませんが、常に発展途上でした。当初はこのような本を作る意図はありませんでした。もともとの始まりは、2015年のデンバーでのアメリカ人類学会大会でのパネルです。ラウンドテーブルとして実施する予定だったのですが、何人か急に来れなくなった人が出てしまい、パネルをそのままやるか中止にするべきか迷いました。結局行き当たりばったりではありましたが、直前になって大会に来ていた面識のある人たちに短い文章を提供してもらうようお願いしたら、興味を持っていただいて、みなさんが参加に同意してくださいました。最終的には、ラウンドテーブルの予定だったものが、10から15程度の特定のキーワードに関する短いプレゼンとなり、とても面白いものになりました。
すると、聴衆の中にいたゾイ・トッドが立ち上がり、即興で別のトピックに関するスピーチを始めて、それ自体がまた別の見出語のように感じられました。その後パネルをアメリカ文化人類学会のウェブサイト上でシリーズ化することになったのは、そこから着想を得たところが大きいと思います。サイトでは彼女の論考も入れました※23。ですが、最初に15程度のエントリーが出揃ったところで、他には何があるだろうと疑問が湧いてきたわけです。プロジェクトはそこから大きくなっていき、最終的にはサイト上で50程度、論集では85ぐらいの見出語があったかと思います。
なぜ用語集か。このプロジェクトを突き動かすものは、これまでお話ししてきたことと関係しています。このプロジェクトを「まだ見ぬ人新世」と名付けたのは、人新世という概念があまりに一般論的で、物事を丸く収めようとしすぎているのではないかという懸念を、他の人類学者や社会科学者同様、シムニーと私が抱いていたからです。現在人新世と呼ばれるようになった地質学的状況を作り出すにあたって、ヨーロッパやアメリカ以外に暮らす多くの人々が果たした役割は遥かに小さいわけです。その生活や経験からしてみると、人新世というのは不公正で不当な一般化だと言えます。実際、この惑星で生きるにあたっての彼らの営みは、人間による人新世的支配がそもそも何を意味しうるのかを想像するにあたり、全く異なる可能性を示してくれるかもしれないのです。
ですから、このプロジェクトでは、オルタナティブな可能性や、今この時代およびその全体性を理解する他の方法を記録してきました。各章がそれぞれにこの時代を概念化する別な方法を提示することで、ともすれば不可避に見えるこの状況を、根本的に異なる方法で理解することが可能になることを示したかったのです。そのためには、特定の用語に着目して、それがある異なる状況でどのように使われてきたのかの観点から考えることが必要でした。その着眼点は経験的なものから歴史的、社会的、芸術的なものまで様々です。
結果として、この論集は仮定の集まりとなりました。こう見たらどうなるだろう。ああ見たらどうなるだろう。その目的は、ある特定のひとつの観点から見なければならないと主張することではなく、多くの異なる観点から見る方法を学ばなければならないということです。用語集という形を取った最大のモチベーションは、今のこの状況は同時に様々な角度から検討されなければならないという発想に対する、シンプルなコミットメントにあります。用語集という形は、それを達成するためひとつのやり方を与えてくれると思います。
§
山田:
この点に関連して、論集の序章では、「緊張を孕んだこの瞬間の意味を成すには、どんな見るべき何かがそこにあるのかというシンプルな問いから始まる」と書かれています※24。そこでも指摘されている通り、人新世概念の全体的な性質はある種の無力感を生みかねませんが、一歩引いて周りを見てみるというのは、物事が他にどうありえるのかを想像し始めるにあたってひとつ大きな助けになるのかもしれません。人新世概念が批判を受けてきたのは、現在だけでなくそこに至るまでの歴史上の〈人類 (anthropos)〉の中の違いを無視してきたこともあります。この概念自体、新たな地質時代を提唱することで過去からのある種の決裂を示唆しますが、終末論的危機感というのは歴史的に周縁化されたコミュニティからしてみれば今に始まった話ではないわけですよね※25※26。論集の中で書かれているように現在の複数性を探るにあたり、このような不均一な歴史的経験をどのように考えればよいのでしょうか。
パンディアン:
現在というのは、〈現前化〉なしにはありえません。今この瞬間という感覚は、解釈や枠組みによってある特定のものに存在感を与え、他を不在とみなす行為によって成立しています。この点において、人新世というのは、ある種のメタ物語であると言えます。これはリオタールが『ポストモダンの条件(The Postmodern Condition)※27』の中で、近代のメタ物語について論じている意味においてです。いかなるメタ物語でもそうであるように、これにはある一貫性や現実味を与えるための特定の形の現在化が必要です。
ここで、この論集がふたりの人類学者によって編集されたということが重要な意味を持つと思います。本の中には人類学者に限らず、アーティストや人文学者など、様々な分野からの論説が収録されています。ですが、編者が人類学者ふたりであったことで、メタ物語における存在感や不在感に関するこれらの問いを、論集の中心に据えることができたのだと思います。何に存在感を与え、何を不在のままにしておくのか。存在感を持つものは、どんな犠牲のもとに成り立っているのか。異なる場所や物語、視点に存在感を与えることは、何を意味しうるのか。他のものに存在感を与えることで、われわれの抱く現在に対する意識にどんな変化が起こるのか。こういった類の問いが、論集の制作にあたり大きな役割を果たしました。
そこで主張したかったことはシンプルで、地球環境に対する現状での人間の影響力を前に、他の考え方や向き合い方により大きな存在感や鋭い焦点を当てることで、そうもしなければ考えもしないかもしれない重要な介入や潜在的変革の可能性を私たちは手にすることができるかもしれない、というものです。究極的には、現在というのは時間的カテゴリではなく、時間と空間の連鎖による時空間(クロノトポス)であるという点を強調しておきたいと思います。今この状況の時間的論理というのは自明に感じられるかもしれませんが、それを問い直して活性化していく必要があります。存在感に関する問いを立てることは、それにあたって大きな可能性を持っていると考えています。
§
山田:
現在はある種の時空間であるという点に関して、あなたの著作を拝読する中でとても印象的なことのひとつに、現在の社会を考えるうえで歴史を複数の形で織り込まれていくことがあります。たとえば、先ほどもお話に挙がった通り、『ある可能な人類学』の一章では、マリノフスキとハーストンを並べることで、人類学における経験主義と思弁の実践という現代的問いについて考察されています。また、最初の単著である『曲がった茎(Crooked Stalks)※28』では、南インドのカラ―ル(Kallar)カーストのコミュニティが、植民地化以前、植民地時代、独立後それぞれの過去から受け継がれた複数の断片的要素の中に道徳的支えを見出していく様子が描かれています。一方人新世は、将来や加速に対する衝動にひとつの特徴があると言われています。いわゆる人新世がいつ始まったのかについてはいろいろと議論がありますが、グレート・アクセラレーションと呼ばれる時代にひとつの答えを見出す研究者もすくなくありません。もし現在がひとつの時空間であるとすれば、歴史を掘り出して語り直す作業というのが、人新世に関連する「加速」と向き合う方法を与えてくれる可能性はあるのでしょうか。
パンディアン:
「加速」というのは、私が訪れたことのある世界中のあらゆる場所においてひとつの事実ではあります。南インドの遠く離れた山村部においても、25年ほど前に私がフィールドワークを始めたときに比べて、物事が動く速度は遥かに増しています。モーターバイクや携帯電話を持つ人も多くなりました。こういった情報伝達の即時性や動きの速さは、私がこれらの場所で最初に時間を過ごし始めたときには想像もできなかったことです。ですが同時に、加速に向き合い、グレート・アクセラレーションといった概念について考える際には、一体何が加速したりそんなに速く動いているかを問わなければならないと思います。
最も単純なレベルで、私がその最初の本で言いたかったことは、インドのような場所において、近代というのは私たちが思う以上に複雑なものであるということです。現在の生活というのは植民地時代および独立後を通じておこなわれてきた特定の近代的な形の開発主義や介入の遺物でしかありえないと考えられがちです。それは当然そうですし、重要な指摘です。ですが、現在の状況に批判的に関わるための道具として人々が共に生き、向き合い、頼みにしているものの中には、もっといろいろなものが含まれています。
私たちは、今動いているものが何にせよ、それがひとつの場所だけから来ているわけではないことを忘れてはならないと思います。今出回っているものはある特定の起源だけから派生してきたわけではなく、あらゆる種類の生き方や想像力、或いは人間・非人間を含めた他者と共存する方法が、いろいろと混ざっているわけです。こういった様々な文化的遺物は、生きていくうえで大きな助けになってくれるものです。
人類学に課されたひとつの重要な任務に、失われつつあるものを回復すること、さらに言うならば、救済すること(サルベージ)があります。サルベージ人類学の考えが厄介なものになりえることは理解しています。それは北米の帝国主義的征服から生まれた発想でもあります。しかし、われわれ人類学者のしていることというのは未だに往々にして、過ぎ去ったものとされる要素や物語、ものの見方や生き方を回復したうえで、それらが今に至るまで持続してきた可能性を主張することであると思います。その中で、そういったものに居場所を作ったり、それらを置き去りにしたかに見える世界にあってそれらがどんな未来を持ちうるのかを想像したりすらするわけです。
先日、『まだ見ぬ人新世』にも参加しているイザ・カヴェジヤの編集による10の短編シリーズに寄稿する機会がありました。シリーズはアメリカ文化人類学会のウェブサイト※29に掲載されているのですが、ボッカチオの『デカメロン※30』の現代版で、いわばパンデミックにおける10の物語集です。私が書いたのは小さな思弁小説で、遠い未来のインドの山村部を想像しようと試みたものです。書きながら実際に考えていたのは、フィールドワークを中によく知り合うことができた人たちのことです。彼らを消えゆく過去にしがみつく存在として捉えるのではなく、彼らのしていることや考えていることを、今はまだなき未来の社会の礎として想像してみたらどうだろう。そんなことを考えながら実験したみたんです。人類学において現在に対して批判的に関わることというのは、このようにして過去と未来を錯綜させることなのだと思います。そうすることで、一見過去の遺物にしか見えないようなものの未来性を主張することが可能になります。
想像力や共感の限界と可能性をめぐる今後の研究について
山田:
最後に、現在進行中のご研究についてお伺いできればと思います。今取り組まれていることや、本日お伺いしたアイディアの新たな方向性など、お聞かせいただけますか。
パンディアン:
今進めているプロジェクトは大きく3つあります。2016年の大統領選挙以来、アメリカにおける壁、境界線、国境に関する本に取り組んでいます。現代アメリカにおいて、〈壁〉なるものが環境に関するメタファーとして持ちうる訴求力について、理解しようと試みるものです。実は既に原稿を書いたのですが、パンデミックや直近の人種差別反対の抗議活動や運動など、今年起きている様々な出来事をもとに考え直さなければいけない状況です。このプロジェクトで検討したいのは、多くのアメリカ人が他者の苦しみを無視することを可能にしている〈無関心の壁〉とも呼べるものに関してです。この〈壁〉は、たとえば、国境の壁が移民・難民の人々が直面している悲惨な状況に対する応答として持ちうる魅力に、よくあらわれています。
ですが、それは現代アメリカにおける生活の他の側面においても顕在化しますし、いずれもある根本的な意味で冷酷かつ反環境主義的なものです。例としては、要塞かのような住宅の出現が挙げられます。これは家というものを、不安定な世界からのある種の避難所として捉えるものとして考えられます。また、SUV(スポーツ多目的自動車)に代表される巨大な乗り物が台頭してきていて、動く装甲装置として環境を支配する手段のようにすら機能するようになりつつあります。また、身体の脆さに関する考えから、その健康を守るために排他的手段が使われるようになっており、より不安定な環境に暮らす他者をそのために犠牲にすることすらいとわないのです。このプロジェクトでは、今挙げたようなことを考察してきました。最終的にどうなるかはまだわかりませんが、今はこの国で大きな変化が起きようとしているときであり、この現状にかなう形にするためにこの文章にどう手を加えるのがよいのか、考えていくつもりです。
もうひとつ取りかかり始めた本は、腐敗に関するものです。脱成長運動を追い始めたのですが、私が特に関心を持っているのが、経済成長への執着に対するひとつの応答としての脱成長という考え方です。それはまた、活力というものを従来とは異なる形で思い描くことを招くとも捉えることができます。直観として、これらの問いに切り込むひとつの方法は、成長への固執によって気付くのが難しくなっている類の変化のプロセスについて考えてみることなのではないかと思っています。
たとえば、私たちは成長の裏側としての腐敗をなかなか認めることができずにいますが、その難しさ自体に着目しようというわけです。そうすることで、腐敗や非恒久性といった現実と共に生きる生き方が存在すること、またその中には、成長以外の願望や福利の考え方を前提として社会や経済を編成するための実用的な手掛かりが隠れているのを示すことができれば、と思っています。実際のフィールドワークも始めていて、本では世界4ヶ国からの4つの物語集の形を取ることを想定しています。
最後に、これはまだ私の頭の中でも整理しきれていないのですが、私がこれまで取り組んできた様々なプロジェクトのほとんどすべてに関わる、あるアイディアに関する本について構想を始めています。それは、私の仕事の中で重要な問題であり続けてきた、環境倫理についての考え方の根底にあるものとも言えるかもしれません。それは「開かれた心」についてです。つまり、世界やその予測不可能性と移ろいに対して「開かれた心」、またある種のエコロジカルな応答性としての「開かれた心」を養う可能性のことです。これまでいろいろなプロジェクトに取り組んできましたが、それらは「開かれた心」の人類学とも呼べるものの各章を構成しているのではないかと考え始めています。先日、これらのアイディアについてインドのインフォシス科学財団での講義として探索する機会があり、いずれそう遠くない将来には本の形にまとめられればと思っています※31。
§
山田:
想像力、好奇心や共感の限界と可能性に関するこれらの問いは、ますます重要性を増していくようにも思えます。本日は示唆に富んだお話をいただき、本当にありがとうございました。今後もパンディアンさんの著作を通して考えていくのがとても楽しみです。
パンディアン:
ご質問を聞きながら改めて考えるのもとても楽しかったです。このような機会をいただき、ありがとうございました。
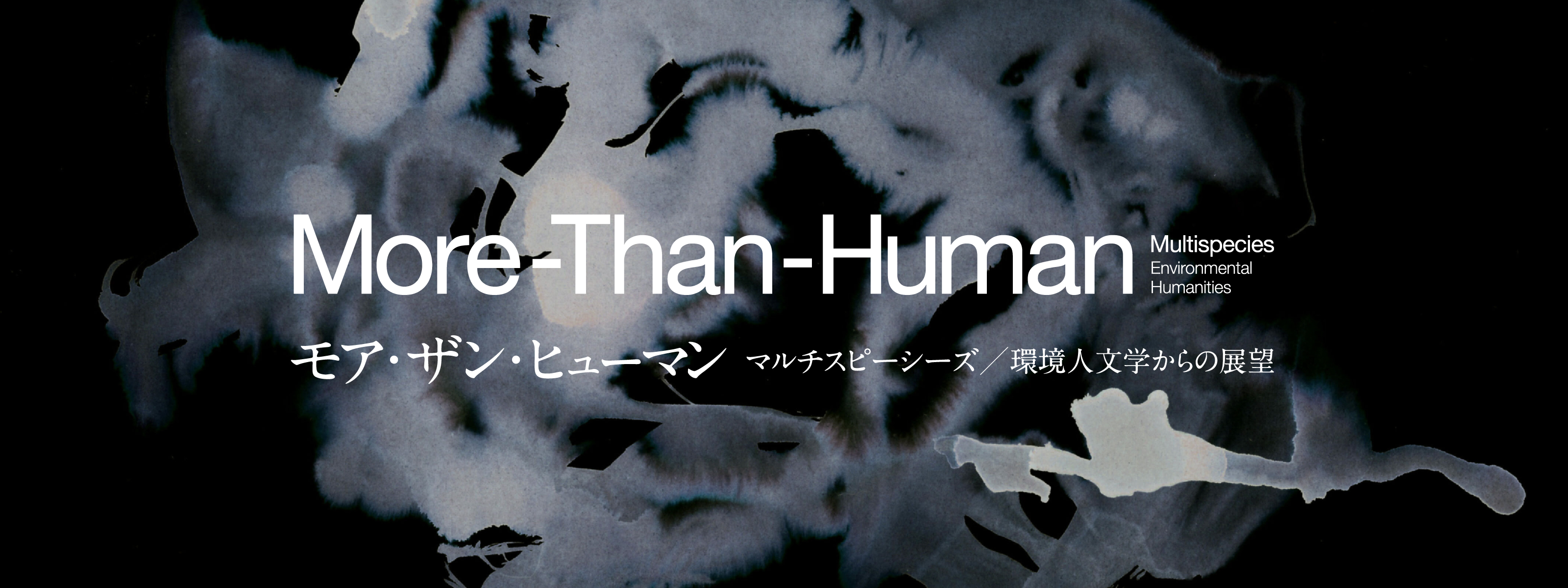
宮本万里:
ご著書 “Animal Intimacies: Interspecies Relatedness in India’s Central Himalayas※1”に対するアメリカ人類学会の2019年のベイトソン賞の受賞おめでとうございます。今日は、この本の中身を中心にインタヴューを行ないたいと思います。
本書のなかでは、ヤギ、ウシ、サル、ブタ、クマという5種類の動物を主に取り上げていますね。これらの動物のうち、サルやクマは明らかに家畜化された動物ではありません。家庭で飼育されている家畜と野生動物とでは、村の人々と動物との関係性は全く異なると想像しますが、この5種類の動物に関する物語を1冊の本にまとめようと考えた理由は何だったのでしょうか。また、これらの複数の動物の関係性を通して何を伝えたいと考えたのでしょうか。
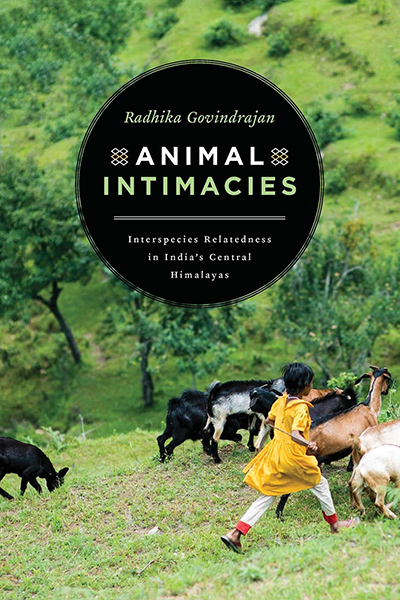
ラディカ・ゴヴィンドラジャン:
私は、修士号を南アジア近代史で取り、修士課程では、同地域における植民地時代の野生動物保護に関する研究を行いました。その後、博士課程の研究として、そのテーマでフィールドワークを行いました。私が博士課程を開始した当初は、野生動物の保護に焦点を当てつつ、それを現代にまで拡大していこうと考えていました。しかし、私はすぐに、野生動物と家畜動物といった分類は歴史的背景に左右され変化するものであって、その境界は常に曖昧であることに気がつきました。例えば、ヒョウが村をうろついて人を襲うのは、神々が「バリ」、つまりは家畜の生贄を望んでいることを示しています。ゆえにヒョウは神々にとっては家畜化された動物なのだ、と村人が私に言ったことがありました。こうした分類における流動性が、様々な動物がどのように異なる場所に出入りしているのか、もっと深く考えてみたいと思うきっかけです。それによって、「野生動物」という自明で不変の分類に違和感を覚え、人間と人間以外の動物が日常的に遭遇していくなかで、このような分類が、いつどうして意味を持つようになったのかを考えるようになりました。
なぜこの5種類の動物なのかという問いについては、これらの動物が、それぞれが全く異なる状況に置かれていると考えるからです。本書における重要なポイントのひとつは、個々の動物やその集団の歴史・性質・行動が、特定の社会的関係や社会を構築する上で欠かせないものだという点です。
血縁関係の一形態としての生贄に関する章は、ヤギの物質性とその性癖、そして人間とヤギとの関係性について扱っています。ウシの保護に関する問題や、国家の開発プロジェクトが「外来種」のウシを飼うのか「在来種」のウシを飼うのかというジレンマをどのように生み出してきたかという問題などがあります。それらについては、様々なウシの特性を実際に知ることによってのみ解決することができるのだと思います。外来種のウシへの懸念や、そのことが文化的アイデンティティに与える影響については、平地の都市部から山村に置き去りにされたサルの話を通して探ることができます。私がヤギを通してこうした話を語ったとしても、同じものとはならなかったでしょう。なぜなら、帰属に関するこのような話が可能になったのも、外来種のサルの行動があったからです。セクシュアリティと家父長制に関する問題は、クマの話を中心にしています。
はじめにこのような大きなテーマに興味を持ち、そのテーマが特定の動物によって具現化されていることに気づいたのです。最初に本書を執筆しようと考えたとき、各章で異なる動物を取り上げることになるとは思ってもいませんでした。各章は「生贄について」「宗教と保護政策について」「所有と移動・移住について」、そして「セクシュアリティについて」の章になると考えていました。しかし、執筆を進めるうちに、「なるほど、それぞれのテーマは、これら5種類の動物と、人間・神・国家・人間以外のその他動物との間にある状況化された関係性によって明確に説明できるのだ」と思うようになりました。ですので、異なる動物を中心に各章を構成したいとはじめから考えていたわけではなく、こうした経緯を通して本書の構成が自然と出来上がりました。
人間の代わりに犠牲となるヤギ
宮本:
第2章はヤギの生贄についてでしたが、そこでは、生贄として捧げる動物を世話する村の女性たちの労働とその価値について書かれています。
南アジアにおいて女性と「自然」との関係性や愛着を説明する際、ヴァンダナ・シヴァ※2などが主張するエコフェミニズム等の既存の理論を通して説明されることが多いですが、あなたは女性の労働に焦点を当てることで既存の理論を全く異なる方向へ導いており、その分析視角は非常に新鮮でした。
ゴヴィンドラジャン:
そうですね、ある種のエコフェミニズムの文献は、このような本質化された範疇で議論される傾向にありますが、それは、たとえそのような主張が善意に行われたのとしても、本当に問題だと思っています。とはいえ、いくつかの研究は、自然に対する女性の親和性を示す例としてエコフェミニストたちが支持しているチプコ運動などについて議論しながら、これらの主張を見事に複雑化させています。例えば、ハリプリヤ・ランガンは、女性が「生まれながらの」環境保護主義者であるというエコフェミニストの主張は、実際には女性たちが抱く経済開発への願望を不可視化することになっていると指摘しています※3。
そもそも彼女らが抗議を行う理由のひとつは、このような状況で生きていくことの難しさに注目してもらうことにあります。私にとって、カースト・資本・ジェンダーといった政治経済的問題について考えることは非常に重要であり、女性の自然への親和性を生来的なものとして崇拝することに対する重要な対抗手段となります。私は、広範囲の構造的な要素によって形作られる労働の特定のやり方から、どのようにして感情的な愛着や葛藤が生まれてくるのかを探ることに興味があります。生贄を扱った章では、このように、母性的な愛着というジェンダー化された言説が、動物の世話において、女性が全責任を背負うという家父長的な労働体制によって、どのように形作られているのかを考えています。

宮本:
人々の労働の軽重が神々によって計測され、その労働だけがヤギを貴重な生贄として価値あるものにするという考えは、刺激的であり興味深いと思います。他方で、あなたの主張の中では、野生動物を生贄にするという習慣の有無やその価値については、全く触れられていないようです。狩猟を通した野生動物の供儀のような習慣は、あなたのフィールドとする山間部にはもともと存在しないのでしょうか。あるいは、現在のように家畜を生贄とする風習は、実際には平野部の人々によって持ちこまれたものである可能性はあるでしょうか。
ゴヴィンダラジャン:
興味深い質問ですね。ヴィーナ・ダスといった研究者は、ヴェーダ時代までさかのぼれば、人間も生贄となる5種類の存在のうちのひとつであったのだと主張しています※4。私たちが野生動物と呼ぶ動物も含め、さまざまな種類の生物が生贄として供されてきました。しかしながら、私のフィールドワークの対象地域では、生贄とされているのは家畜だけです。この地域の生贄の歴史が示すように、本来の生贄は人間でしたが、悲しみにくれた両親の嘆願の末、神々は人間の代わりに動物を生贄にすることを許しました。しかし、その代替の生贄を失うことは、痛みと悲しみをもたらさなければなりません。簡単に別れられるなら、本来、犠牲とはならないからです。
狩猟に関して述べると、この地域において植民地時代と植民地後の野生動物保護の歴史が長く、法的な規制の結果、狩猟はほとんど行われなくなりました。この地域の人々は、「密猟」により、国から罰金や投獄という罰則が与えられることを恐れました。時折ジャングルの鳥を殺したり、イノシシを殺す話をする人もいますが、野生動物の狩猟は決して一般的なものではありません。私が話を聞いた人々のなかで、野生動物を生贄として捧げたと記憶している者はいませんでした。
そうは言っても、この地域のある特定の寺院では、生贄となる動物やその方法について、今述べたことと違う部分もあります。デヴィドゥラ(Devidhura)という寺院で聞いた話によると、女神は、人々が人間の代わりに動物を生贄として受け入れて欲しいと懇願した際、こう言ったそうです。「よろしい、では動物の生贄を受け入れるが、人間の血も捧げるように」と。ラクシャー・バンダンの日にこの寺院で何が行われるかというと、寺院の世話を任されている4つの氏族が寺院に集まり、10分間互いに石をぶつけ合うのです。そして、戦いの後に地面に十分な人間の血がこぼれていれば、女神の人間の血に対する要求は満たされた、と考えることにしたのです。そしてご想像の通り、この種の儀式は、多くの活動家や第三者の不安の種となっています。なぜなら、儀式的な投石が例証したように、これには「近代性」が欠けているとして受け取られたためです。
しかし、この場はたしかに「近代的」な空間であり、祭はすくなくともこれまで数回は(携帯電話会社の)ボーダフォンがスポンサーとなっていました。このイベントの見物者には、携帯電話のSIMカードが配布されることもあったのです。これらの祭りは、しばしば地方公務員らによって開催されていました。活動家がどのように生贄というテーマに取り組むかを決定づける、伝統と近代性の言説を考えるためには、この場は本当に魅力的な空間だと思います。
在来のウシと外来のウシ、ウシ保護論者とヒンドゥー・ナショナリズム
宮本:
第3章では「パハリ牛」と呼ばれる在来牛に対する人々の愛着・執着が描かれています。パハリ牛あるいは在来牛というカテゴリーは、「商用牛」や「近代牛」と呼ばれる外来種のジャージー牛と比較するなかでその特徴が明確化します。本を読んで、牧畜村の発展のために政府がジャージー牛を導入したブータンの事例が思い起こされました。私が調査を行っているブータンの村の村民は仏教徒です。ウシにはヒンドゥー教のような宗教的価値はありませんが、外来種のウシが季節的な移牧の妨げになることが懸念されており、人々は交雑が進むことを心配していました。あなたがフィールドワークを行った地域では、在来牛がジャージー牛と交配した場合、生まれた雑種はジャージー牛とみなされるのでしょうか。また在来牛だけが持つ宗教的な力を認める一方で、地域の人々は、この2種類のウシの境界をどこに定めているのでしょうか。
ゴヴィンドラジャン:
これらのウシを交雑させた場合、通常は「ドガラ(dogalla)」と呼ばれ、2つの品種の中間に位置づけられます。それは、もう「純粋な」在来牛とはみなされません。
ヒンドゥー教至上主義者の言説の中でも、在来性が特に重要視されています。現在、多くの牛舎では「うちは在来牛しか飼っていないよ。外国産の牛は要らないね」と言うでしょう。そして、本書にもある通り、確かハリヤーナー州だったと思いますが、ある政治指導者は、ジャージー牛の牛乳を飲むと、ジャージー牛自身が犯罪者の性質を持っているため、犯罪者になってしまうという類のことを言っていました。その言説の中には、非常に強い排外主義的な歪みがあります。「在来牛の繁殖のみを推奨すべきだ」と国に提言するウシ保護論者も出てきています。そして、国はある在来品種の再現プロジェクトにも投資しています。

しかし、酪農を農村開発の原動力にしようとするのであれば、ジャージー牛よりも乳量がすくない「パハリ」種を奨励するのが難しいという事実は変わりません。乳量が多いとの理由から、サヒワール種や平地系の在来品種を勧める人もいますが、このような地形では飼育はより困難です。つまり、酪農とウシの保護を同時に推進するというこのプロジェクトの核心には、軋轢が存在するのです。私が本書で述べたなかでの最大の葛藤のひとつは、「ジャージー牛をどうすべきか?」という問題で、ヒンドゥー教至上主義者と地元の人々の双方を悩ませています。ウシ保護論者は、外来種のウシは純粋でなく、犯罪者で、愛情や世話をするに値しないと思っていても、「ああ、このジャージー牛は外来種だから殺しても良いのだ」とは言いたくないのです。結局のところ、これらのウシもまたウシなのですから。そして、この認識が行き詰まりを生み、彼らが現在、解決しようとしている難問を生み出しています。彼らの多くは、現実にはそこまで多くのウシを育てることができないこと、そして国によって酪農がこれほどまでに推進されている限り、雄牛や老齢牛を見捨てざるを得ないことを認識しているからです。
ケイティ・ガレスピー※5やヤミニ・ナラヤナン※6ようなフェミニスト研究者が指摘するように、乳牛の理にかなった末路は牛肉なのです。この点は、右翼のウシ保護論者の多くが考え抜こうとしている問題だと思います。本書では、世界ヒンドゥー協会(VHP)のある指導者が、ヒンドゥー教徒はウシを捨てても非難されるべきではなく、ウシを捨てず手放さないよう人を説得する方法を考える責任は、ウシ保護論者にあると主張したことについて述べています。彼らは、「どうすれば酪農にも焦点を当てつつ、在来牛を推進できるのか」と問いかけています。そして、それが時々、興味深い意味で国家との対立点となって現れるのです。
§
宮本:
現在のインドにおけるウシ保護を取り巻く環境について知ることができ、とても興味深く感じました。ウシをめぐる分類はすでに重層的なものとなっていますが、あなたが在来牛に関して説明された側面は、ヒマラヤ地域を含む多くの地域で、一層重要なものになってきていると思います。近年では、女性たちは、在来牛以上に、ジャージー牛の飼育により多くの労力を投入する必要に迫らせているようです。もしも、投入された労働量を考慮すれば、将来的には、ジャージー牛が神々への最良の贈り物になりうるでしょうか。それとも、ジャージー牛は、宗教的価値という点から在来牛の代わりになることは決してないと考えますか。
ゴヴィンドラジャン:
いいえ、人々はジャージー牛が宗教的に重要なウシになる可能性があるという考えも受け入れています。本書のなかでも触れた、私が興味深いと感じた疑問のひとつに「どの時点でジャージー牛が山地のウシになるか」というものがあります。「品種」自体も存在論的には不変の分類という訳ではありませんが、必ずしも「品種」の変容という意味ではなく、これらのウシが食べる食べ物、飲む水、従属する神々、山で過ごした世代の長さなど、山に対する様々な実質的な関連性や交流という面での話です。すくなくとも私がフィールドワークを行った地域では、農村部の家庭で「純粋な」在来牛を見つけることがより困難になっていることから、多くの人がジャージー牛しか手に入らないかもしれないという考えで揉めていたように思います。
人々はジャージー牛の糞尿で間に合わせの儀式を行うようになっています。一部の人々は、このような儀式は最終的にジャージー牛の異なる物質性に順応していくのではと推測しています。ジャージー牛が「商用」牛となると同時に、「儀式用」牛となることへの寛容性もありました。これが、これらの農家が持つウシの分類についての見解と、右派ヒンドゥー教徒の無節操な排外主義とを区別している点だと考えます。これらの村でも、外来牛や在来牛といった分類を使っていましたが、ジャージー牛に深い愛情を注いでいないという訳ではありませんでした。その点については、本書の中で詳しく記しています。村人たちは、ジャージー牛がある種の儀式には不向きなウシであると言いつつも、自分たちが育てているウシに強い愛情と尊敬の念を抱いていました。これは特に、これらのウシの飼育に関する労働の大部分を担っていた女性に当てはまりました。
外来のサル、在来のサル、排除するか、帰属させるか
宮本:
続く第4章では、都市部に住むよそ者が新たに連れてきたサルと地域の人々の関係性を、サルに対する人々の振る舞いや態度から描き出そうとしています。(都市から山岳部へサルを移動させるという)この現象の背景には、ハヌマーン(ヒンドゥー教の神猿)の崇拝もあるとお考えですか。つまり、ヒンドゥー教を信仰する人々が、ハヌマーン神の眷属は聖域にいるべきだと考え、都市に住むサルを山へと移動させようとしているのでしょうか。
ゴヴィンドラジャン:
それもありますが、サルが野生動物保護法で保護されているからです。間引きに反対する宗教的な議論は確かにありますが、動物愛護活動家が主張する、サルを殺すことは法律に違反するという議論もあります。隣のヒマーチャル・プラデーシュ州では、農家に凶暴化するサルを銃で撃つ免状を与えると発表しました。それが発表された時、様々な選挙区で大騒ぎになりました。動物愛護団体は、これは残虐行為だと言い、野生動物保護活動家は、インドの野生動物の遺産の大規模な破壊への扉を開くきっかけとなることを懸念し、ヒンドゥー・ナショナリズム団体は、サルはハヌマーンを体現した存在であるため殺してはならないと主張しました。多くの森林警備隊員は、この問題がどれほど多くの議論を生んでいるかを考えると、どうしたらいいのか本当にわからないと私に話してくれました。
しかし、農村の生活への被害は現実のものです。複数の組織やNGOがこの問題に取り組んでいます。このような状況では、人は農業を続けることができません。これは深刻な問題で、さまざまな解決策が提案されています。不妊手術を行うという選択肢もあります。それが成功しなかったのは、特に動物愛護活動家から、人道的に実施できるかどうかについて懸念が出たからです。間引きという解決策も、まだあまり好意的に受け止められていません。
宗教の問題は、多くの山地の民にとって複雑なものでした。サルを殺すのは罪深いと考える傾向にある一方で、果樹園を荒らしていたサルに毒を盛るという話もよく聞きます。ある男性は、かつて私に、自身の土地で、死んだアカゲザルを見つけたと言いました。彼はあまり多く説明しませんでしたが、私は彼が多くの収穫物を失ったことへの悔しさから、畑に毒を撒いたのではないかと推察しました。死んだサルを見て罪悪感と恐怖を感じた彼は、贖罪としてラングールに餌を与えていました。このように、こうした都会からきたサルをどう扱うかについては、倫理的・宗教的に深いジレンマがあり、それに対応するために様々な解決策が生まれました。

§
宮本:
現在、村にはあなたが描くように都市部から来た外来のサルがいますが、それ以前から同地域には在来のサルが生息していましたよね。その在来のサルと外来のサルを比較してみると、当然のことながら、人々は現在は在来のサルに対して自分の身内のような愛着を持っており、都会のサルが彼らにとっていかに異質な存在であるかを語るでしょう。しかし、都会のサルが来てから、在来のサルに対する認識が寛容になったということは考えられるように思います。在来のサルと村人との以前の関係性はどのようなものだったのでしょうか。地域の共同体の一部となりうるような、親しみのある存在としてのみ認識されていたのでしょうか。それとも、駆除されるべき害獣として認識されていたのでしょうか。
ゴヴィンドラジャン:
その地域に生息するあらゆる動物が、害獣・友人・仲間という異なるカテゴリーの間を浮動する存在だ、という強い感覚が、私の中に間違いなくあります。在来のサルも、間違いなく時には「害獣」となる可能性があります。しかし、人々は、在来のサルの「略奪」には対処できるという感覚があり、それは外来のサルとの共存に関連してよく表現される言葉「アアタンク(aatank)」、つまり恐怖、の感覚はありませんでした。人々が私に言うには、たいていの場合、在来のサルが果樹園に来るのは数日で、その後は森に戻るのだそうです。彼らにとっては、森で十分だったからです。彼らは時々森から出てきましたが、村に住むことはありませんでした。このこともまた、現在の状況の特異性を強調するための、懐古の念を含んだ過去の恣意的な解釈である可能性もあります。しかし、それは広く主張されており、私たちは真摯に受け止めなければならないと思います。
また、人々はそれとは異なったことも述べます。一つには、略奪の性質の違いが挙げられます。在来の森のサルはたまに果実を盗んだり、農作物を食べたりすることはあっても、外来のサルのように家の中まで入ってくることはありませんでした。そこには、恐怖感と不安感が蔓延していたのです。「これら外来のサルは、すぐに家の中まで入ってきます。人が家の中で座っていても、ただ入ってきて人の食べ物を奪うのです。もしあなたが何かを言えば、噛み付いてくるでしょう」と。人々はこの行為を、在来のサルにはない「大胆な犯罪性」のようなものとして語っています。在来のサルと外来のサルを区別する際に人々が指摘するのは、この完全なる恐怖心の欠如と村の「乗っ取り」ともいえる行為でした。
「家畜-野生動物」としての野生化したブタ
宮本:
何重もの意味も込められているという点で、逃走した雌ブタの話は非常に読みごたえがありました。私が調査しているブータンでも、昔はブタの飼育が一般的で、ご存じの通りトイレの下でブタを飼うこともありました。ただ、宗教に関係しているとはいえ、ブタの飼育をやめた理由は両者でかなり異なるように思います。
この章では、実験農場の家畜化されたブタが脱走して野生化していくストーリーをベースにしながら、インドで法的には否定され禁止されているカーストによる差別や抑圧について、その重層的な構造が巧みに描かれていますね。
ゴヴィンドラジャン:
カーストに基づく抑圧は、インド全土と同様にこの地域でも存在し、今でも力を持っています。私は、蔓延するカーストの暴力と、この抑圧や暴力に対する最下層のダリット(不可触民)の抵抗や拒絶が、日常的な人間関係の中でどのように行われていたのかを理解することに興味を持っていました。
ブタはこの疑問に対し、重要な取っ掛かりを提供してくれました。ブタと、ブタを飼育するダリットカーストを「不浄」とみなすことは、B.R. アンベードカル博士が言うところのカーストの「段階的不平等※7」を維持するために、支配的なカーストの人々が日常的にカーストの暴力を行使するための方法となったのです。フランツ・ファノンが力強く指摘しているように、抑圧者の言説は根本的に動物学的なものであり、抑圧された者に動物性を与えることで、彼らに対する植民地的な暴力を正当化する方法として使われているのです。私は、ベネディクト・ボワスロンが「連結性※8」と呼ぶような、カーストと動物化の交点についてはやるべき重要な研究が残っており、人間と人間以外の動物との関係性を研究することにより、こうした関係性への洞察が得られるだろうと考えています。
しかし、この交点をどう捉え、どう表現するかということにも気を配らなければなりません。ザッキヤ・イマン・ジャクソンが指摘するように、「人間」を超越して、人間-動物間の区別を元に戻そうとする急激な動きは、人間が決して不変の分類ではなかったという事実を見落とすだけでなく、解放的なヒューマニズムを求める様々な被抑圧集団の葛藤を根底から覆すこととなります※9。
私にとって特に重要だったのは、支配的なカーストによるカースト暴力の全容を明かさず、その暴力が向けられた人々にとって異論のない形で示されることにありました。私は、ダリットの村人たちがどのようにして支配的なカーストによるこうした抑圧に立ち向かい、それを覆してきたかを、脱走した雌ブタの話を交えながら強調したかったのです。
本書でも触れていますが、ダリットの村人数名がよく言っていたのは、森にいるイノシシはおそらく脱走した雌ブタの子孫であり、本当は野生のイノシシではないということでした。このことは、豚肉の消費を不浄であり「最下層カースト」の地位を示すものだと非難する支配カーストが、せいぜい暴力的な偽善者でしかないことを意味しているのだと、彼らは言うのです。私は、これらのカースト支配に対する批判は、野生化したブタの歴史、特にその話で示されているような、野生の流動的な性質に基づいていることを主張します。私にとって、これらの論争は、カーストと動物性の関係が偶発的で予期せぬものであり、民族学的に理解されなければならないことを思い起こさせてくれます。
§
宮本:
非常に刺激的な議論ですね。ザッキヤ・イマン・ジャクソンが示す論点は、検討に値するものだと思います。階層や差別と動物性の関係を論じるためには、前提として理解しておくべき論点が非常にたくさんあるように思います。
この章の中で、もしかしたら重要な点ではないかもしれませんが、脱走した雌ブタの牙の大きさについて人々が話している箇所が気になりました。村人たちは、脱走した雌ブタの子孫はより大きい牙を持っていると語っていたそうですが、その話をすることで、彼らはいったい何を示唆したかったのでしょうか。動物を危険な存在に変えるという意味で、遺伝子操作を恐れているということでしょうか。論点として私はそこは興味深いと思ったのですが、結局その話題は全体的な議論に再び包摂されることはありませんでした。この一連の会話を通して何を伝えたかったのか、もし可能であれば教えていただけますか。
ゴヴィンドラジャン:
この章では、ブタの凶暴性についての様々な証言を、互いの会話の中に入れてみました。多くの野生生物学者は、ブタが「野性化」した場合、迅速な形態学的な変化が起こる可能性を示唆しています。豚の形態は、数世代という非常に短い期間で変化することができます。私にとって、これらの知見は、人々が私に話してくれた、脱走した雌ブタの歴史や、その子孫が簡単に「ジュングリ(jungli)」つまり野生化した話と非常に一致していました。
私が本書を執筆する際、ある男性は、イノシシを「パルトゥ・ジュングリ(paltu-jungli)」つまり「家畜-野生動物」と呼びましたが、それはブタが両者のカテゴリー間をいかに簡単、迅速に移動することができるかを言い表しています。私にとっては、野性の偶発性について、人々が主張の根拠として挙げた証拠に重点を置くことが大切なことでした。私はこれらを、故意に証拠と呼んでいます。彼らは、非常に長い間動物と共に暮らし、動物に関する観察的・経験的知識を豊富に蓄えている人々です。私は、このような異なる種類の状況化された知識のいずれかを使って他方の真実性を確認すると言うよりも、これらの知識を積み重ねることに関心を抱いていました。言い換えれば、私はクマオニの人々が私に話してくれたことを、「科学的証拠」によって裏付けしたり証明しなければならない、ある種の「ローカル・ナレッジ(土着の知)」として主張したくはなかったのです。私は、彼ら自身の証拠を元にして考え、野生生物学者の状況化された知識と合わせることで、会話にまとめたいと思ったのです。
クマとのセックスを語る女性たち
宮本:
ご著書の最後の章は、クマについての話でしたね。この章は、インスピレーションを与えてくれる内容でした。ここで登場するクマは、この本に書いてあった他の動物とは全く異なる姿をしているように思えます。クマと女性の物語を通して、男女の(不)平等性や再生産能力、家庭内暴力など、女性を取り巻く問題の存在を示唆していますが、この本の最後の章としてこの物語を挿入した動機はどのようなものだったのでしょうか。そうしたジェンダー不平等に対する意識が、女性たちの全ての会話の底流に常に存在していることを示唆したかったのでしょうか。そして、彼女たちが抱くひそかな不満や希望を抽出して表現するには、このクマの話が最適だったということでしょうか。そんなことを聞いてみたいと思います。
ゴヴィンドラジャン:
興味深い質問ですね。私は、ヤギやサル、さらにはイノシシやヒョウと比べて、クマがこの風景にいかに「存在しない」かについて悩んでいました。しかし、後になって気がついたのですが、クマは物質的・象徴的風景の中に、私が考慮に入れるべき重要な仕方で、存在していたのです。同僚のジュノ・パレーニャス※10の研究は、この点を考える上で非常に参考になりました。特に彼女の「物質的痕跡」という考え方は、存在していないように見えるものの中で存在を示すものです。トウモロコシ畑が平らになっていて夜間に食べた跡があったり、クマに襲われた女性の顔の傷跡があったりと、いたるところにクマの「物理的痕跡」は存在していました。
女性たちがクマについて極めて性的な話をすることで、多くの根源的な禁止事項や二項対立が露わになってしまったのではないかと考えています。例えば、人間とクマが恋人同士だったという考えです。親密性の持つ本来の寛容性を強調することで、女性の性的快楽に対するカースト家父長的な支配に立ち向かっていたのです。ある女性は、夫が疲れすぎてセックスできないと言った時に、夫を叱責したという話を私たちにしていました。彼女は夫に、クマならセックスしても疲れないだろうと言いました。このクマの話を通して自身の性欲を主張する姿には、本当に心を打たれました。確かに、女性がクマとのセックスの話をすることで得られる快感については、私も考え抜いてみたいものでした。単に、この話を戦略的に使って家父長制へ挑戦していただけではありません。そこにはクマとのセックスがどのようなものであるのか想像することへの、純粋な好奇心と興奮がありました。
私にとっての課題は、これが、いかに親密で具体化された関係であるかを考えることでした。それは、人間と動物、血族と他人といった分類がどのように理解され、経験されるかを形作る上で、女性が飼育しているヤギとの関係性とは全く異なる一方で、それに劣らず意味のあることでした。私にとってこの章は、人間以外の動物との多様な関係性、そして前述のように、それらの関係性の状況化された明示に対して民族学的な注意を払うことの重要性について述べることにありました。
§
宮本:
なるほど、確かにこの章は他の一連の章と表面的には全く異なるように思えますが、クマの話は、人々と動物との関係性に対する我々の想像力を刺激しながら、この本のすべての章を繋げる役割を果たしているようにもみえます。そして、おっしゃるように、人間が多様な他の生物種との境界線を越えることで快楽を経験すると考えることは、他章を含む本の全体を包括的に理解するヒントをくれるように思います。
マルチスピーシーズ民族誌の展望
宮本:
本書を含むあなたの研究が多様な研究領域を横断している点は承知していますが、インタビューの最後に、特にマルチスピーシーズ民族誌という分野の将来的な展望について、ご意見を伺ってもよろしいでしょうか。
ゴヴィンドラジャン:
私がマルチスピーシーズ民族誌の分野でとても刺激的だと思うのは、その知的な幅広さであり、それが実際に広い範囲に渡って関心を持ち、取り組んでいるという点です。
私が思う、マルチスピーシーズ民族誌として分類される研究の多様性をゆるやかに結びつけているものは、ステファン・ヘルムライヒとエベン・カークセイが、人間以外の動物や物質の持つ特有の歴史や伝記と表現したものを辿ることへの関心です。それ以上に、この分野のすべての仕事で力を発揮しているのは、寛容性であり、創造的な探求と思考への献身だと考えます。自分自身の研究において、私はこうしたことを、批判的な擬人観であり、他の人の立場にある自己を想像しようとする意思であり、すべてのリスクや消去にもかかわらず自己を超越した運動を生ぜしめる姿勢であり、より公正でより自己陶酔的ではない未来の可能性を開くような行為、として捉えてきました。
私は、マルチスピーシーズ民族誌を、多様で異なる問題に洞察を与えてくれる分析レンズのようなものだと捉えており、それは必ずしも人間と人間以外との関係性が中心であるとは限りません。エミリー・イエーツ・ドーア※11、ナタリー・ポーター※12、アレックス・ネイディング※13のように、健康や病気を理解するための方法としてマルチスピーシーズ民族誌を研究している人たちもいます。アレックス・ブランシェット※14、ケイティ・ガレスピー、ソフィー・ツァオ※15のように、屠殺場や酪農場、ヤシ農園など、産業資本の現場においてマルチスピーシーズ民族誌を研究している人たちもいます。ジュノ・パレーニャス、ハーラン・ウィーバー※16、アンヌ・ジャレ※17、ベネディクト・ボワスロン、ザッキヤ・イマン・ジャクソン、マリア=エレナ・ガルシア※18のように、人種、ジェンダー、帝国主義、宗教に関する問題を不可欠と考え、中心的な課題とした研究もあります。
私が考える限りにおいて、マルチスピーシーズ民族誌は、より広い学問分野との対話を模索し、人間以外と人間との関係性がどのように形成されているのかを考察し、数多くのその他の構造的要素のなかで、人種、人種差別、ジェンダー、セクシュアリティ、医療や資本の言説や実践を形づくる際に、最も力を発揮するでしょう。ある意味、この分野は本当に爆発的に発展しており、その包括的な理論的枠組みを特定のアプローチや学派に絞るのが難しいところまで来ていると思います。それは素晴らしいことです。
私の考えでは、マルチスピーシーズ民族誌は、さまざまな存在の異なる作用や働きによってさまざまな社会がどのように構成されているかについて、多様な方法で探求するときに、最盛期を迎えると思います。そして私は、この流動性と寛大性が、今後もこの分野の特徴であり続けることを期待しています。
§
宮本:
マルチスピーシーズ民族誌に関して、とても豊かな示唆をいただき、ありがとうございました。
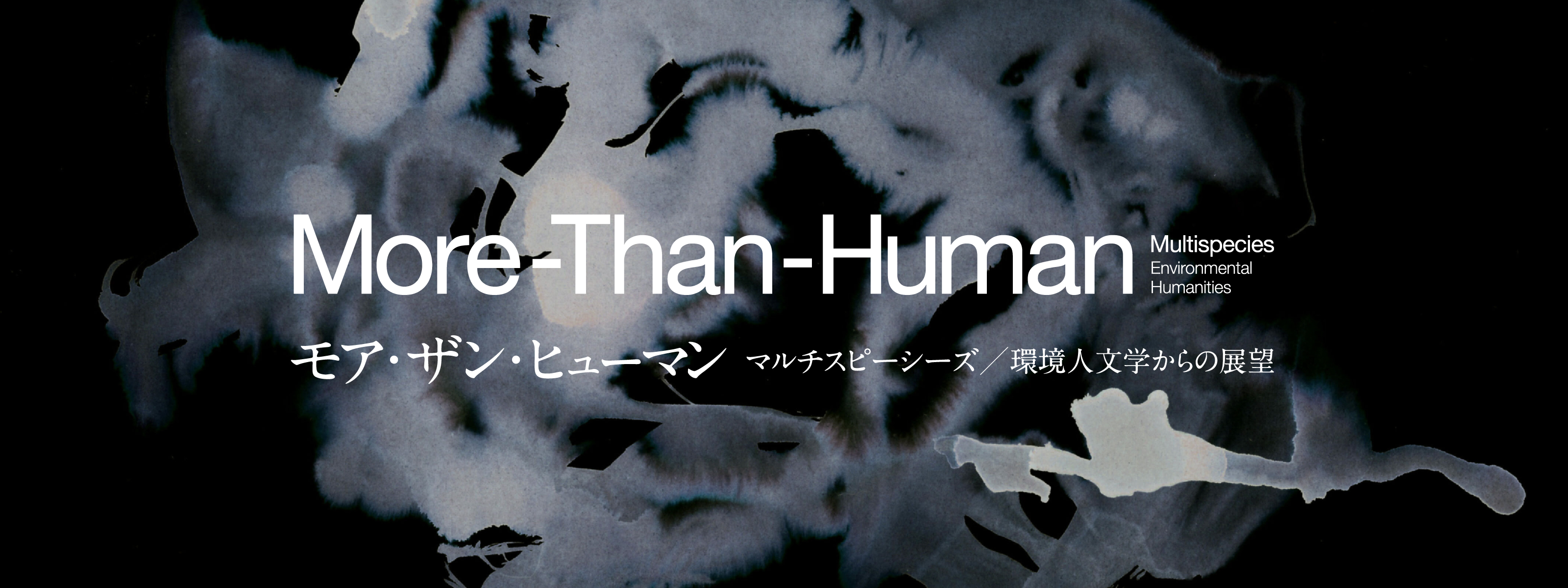
唐澤太輔:
今日は神話研究を中心にして、人間と非-人間とのあり方を深く思索されている石倉敏明さんに、改めて現在の研究内容やアートとの接続などについてお伺いしたいと思います。以前、明治大学の野生の科学研究所で行われた公開研究会「可食性の人類学※1」にまつわる非常に興味深いお話をされていました。今一度この「外臓」という概念について簡単に教えていただけますでしょうか。
石倉敏明:
「外臓」という言葉を初めてお話ししたのは、ご指摘いただいた「ホモ・エデンス 可食性の人類学」という研究会の最終回です。この発表に至るまでに、実は二つの体験的なルーツがあるんですね。一つは2011年の東日本大震災の後に、写真家の田附勝さんと一緒に約1年かけて日本列島各地を旅した12回の旅の経験があります。
§
唐澤:
その旅というのは『野生めぐり:列島神話の源流に触れる12の旅※2』に載っている旅のことでしょうか。
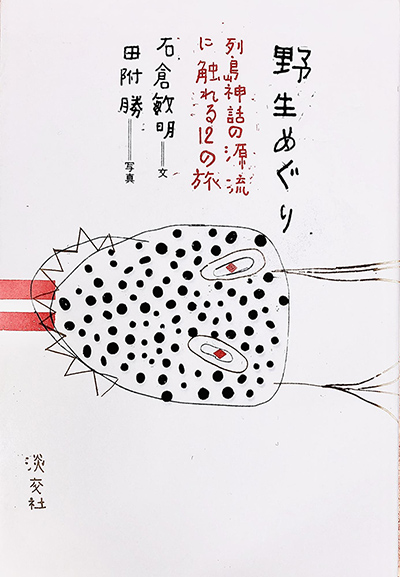

石倉:
そうです。田附さんと東北から九州まで一年間かけて旅をするなかで、各地で神々に捧げられた神饌だとか、死者や祖先の供養のためのお供物と何度も出会ってきました。そのとき、各地の農作物やお酒や味噌・醤油などの発酵食品、魚や動物の肉のような「海の幸」や「山の幸」をいただくことが、各地の神仏に対する信仰と不可分であることに改めて気づかされました。各地の食文化の背景を知る体験から、私たちの活動のエネルギーを支え、個々の身体を構成している「自然からの贈与」に対して敏感にならざるを得なかったのです。
なぜなら、東日本大震災の原発事故や放射能汚染の体験があったからです。当時は放射能汚染によって、東北では採集されていた山菜や魚が食べられない状況にあり、農作物や海産物に対する出荷制限もかなり残っていました。こうした経験と並行して、水俣病の発生現場でも同じような例が発生していたことを、結城正美さんの石牟礼道子論※3を通して知りました。郷土食の料理を、海や大地からの贈与としていただくという非常に古い時代から伝えられた感覚と、その贈与物が人間の社会経済活動の拡張に由来する放射能や水銀によって汚染されるという矛盾。そういった非対称の状況から自らの身体を取り戻すには、どう想像力を駆使すればいいのかを、一年間旅をしながら考えていたんです。つまり、食を通して自分の体と環境との関係をもう一度見直してみたかったんですね。
ちょうど東京から秋田に移住する時期でもありました。秋田の自宅からさほど遠くない田んぼの一角を借りて、子供たちと一緒に農作業をしたり、沢水で遊んだり、里山から山菜を採ったりするような経験も重ねていました。不耕起農法の稲作をやってらっしゃる菊地晃生さん※4が農場の一部を共有地として解放していて、市民が週末にやってきて農作業をするコミュニティをつくっていたんですね。
ある休日、お借りしている田んぼで無心に草取りをしながら、ふと一息ついて周囲の里山を見渡したときに、まるで自分の身体感覚が切れ目なく、目の前の空間や田んぼとつながっているイメージが湧き出してきました。近くの畑では山から降りてきたカモシカが歩いていて、田んぼのなかにはタニシやカエル、ザリガニなどの無数の生物が食べたり食べられたりしています。人間が食べ物として育てている作物もそこにあれば、その田んぼには無数の小動物や昆虫や植物、そして膨大な微生物が存在する。そういう多くの生物が混在するなかで、自分の身体の内側に広がる領域が外界の現実とつながっているのではないか、という思考実験をしてみたんですね。
考えてみたら、自分の体の内臓は、口と肛門を通して一つのチューブのように外部に開かれています。その内臓を、手袋をひっくり返すように拡張してみたときに、食料や他の生物とつながっている目の前の風景は、自分自身の内臓と地続きの空間と捉えられる。自分の目の前にある風景は、自分の内臓を外側にひっくり返した身体の延長として捉えることが可能なんじゃないか。「外臓」という概念を思いついたときに、そんな具体的なイメージが浮かんできました。
こうして、震災後の旅の経験と田んぼでの体験から、僕はこの地上の有限な空間の一部分が身体の内部と深く連絡しているという感覚を得ることができました。僕は大学院時代に人類学者の中沢新一先生から「対称性人類学※5」という、非常にユニークな理論を学んでいましたが、それを自分なりに理解する手がかりを掴めたように感じたのです。
この理論は、人間の思考のなかで世界の全体性を把握するような「対称性の論理」と、事物を分節して時系列に配置する「非対称性の論理」が複合的に生起している、という思想です。つまり人間の心は、時間と空間を超えていく「無意識的思考」と、世界を合理的に把握しようとする「意識的な思考」という二つの論理体系が「複論理(bi-logic)」として並行的に影響を及ぼしあっている。そうした論理が、「外臓」という言葉を通して、自分の身体的な実感として実を結んだように感じました。
自分の身体を貫く消化器系のチューブが、実は外部空間と無限に開かれた絡まり合うループを形成している。このループを「外臓」として概念化することによって、個々の身体を外界とつなぎながら、食べるものと食べられるものが共生している世界を理解するような回路が開かれるのではないか。そう思ったわけなんです。
里山や里川といった環世界の現実を、われわれ人間は皮膚や骨格といった身体の外部に広がる単位だと理解している。これを「非対称性の論理」だとすると、他方には、外的な環境のなかに存在している生物が、食べ物として身体をとおり抜けていくような「対称性の論理」が並存している。つまり自分が何かを消化して、それをエネルギーに変えていったりするような食の体験は、根本的には外臓と内臓との一種の連続した絡まり合いとして理解できる。別の視点からみれば自分の身体も、他者にとっては、外臓の一部であるかもしれない。そうやって鏡のようにイメージを映し合い、エネルギーが移行するループとして、内臓と外臓を捉え返してみたいというのが最初のアイディアでした。
§
唐澤:
自分の内臓を裏返した姿が自然なのですね。自分の身体が外界にも延長しているという感じですね。
石倉:
自分の内的自然と外的自然というものがあるとしたら、それを結んでいる様々な知覚的なインターフェースがあると思うんですね。たとえば五感を構成している様々な感覚器官は、すべて内臓という目に見えない無意識のレベルの身体につながっています。この感覚の回路は、内側に深く潜っていけばいくほど、外の空間とつながっている。この身体的な内と外との絡まり合いを意識化するような光景を「外臓」と名付けているわけです。
§
唐澤:
なるほど。内側が外に、他者につながっている。内即外、クローズ即オープンという感じで、その区別が曖昧になるところがインターフェースなのですね。
内が外になり、外が内になるとすれば、極端な話を言うと、人間が何か物を食べるってことは、結局自分の延長でもある自分自身を食べているとか、同種を食べているっていうことにもなるようにも思えます。それは一種の「カニバリズム」とも言えますか。
石倉:
はい。「外臓」という概念は、内臓的な体験を、皮膚を超えて外の環境へとつなげるときに出てくる概念です。つまり、僕らは山を見ても、山というリアルな空間を「自然」というカッコに括っている。一種の認識の閉域に入れてしまっている。でも、その山を具体的に見ていくと、様々な生き物が刻々と生を営んでいて、食べたり食べられたりするような、リアルな世界がそこには生成されています。
別の言い方をすると、様々な記号次元がそこで生起しているわけですね。人間的な記号はもちろん、それを超えたエドゥアルド・コーンが『森は考える※6』で伝えたような、様々な自己の生態系が、そこにひしめいている。そこで生きているものたちを食べるということは、実は人間を食べることと他の生き物を食べるということがフラットに同じような意味を持ってしまう危険とつながっています。喉元過ぎてしまえば、それは人間の肉であるか牛の肉であるか、それが何であるかっていうのは意識できなくなってしまう。そういう無意識の体験を自分の体の内側に抱えていて、常にカニバリズムと近いところにいる。
しかし、実生活においては、そこから理性的に遠ざかる、遠ざかっていられるかのように、自分たちを社会的な空間のなかで島のように限定された領域として囲っています。それが一種の共同体だとすると、共同体を超える流動的なエネルギーや知覚の絡まり合う次元に常に接しているはずなのではないかっていうことを、内臓の外側にあるリアリティとして掴んでみたいのです。
§
唐澤:
「島のように限定された領域として囲っている」という表現をされましたけれど、それは私たちが対象を理性的に遠ざけてしまっていて、本来的につながっているっていう事態に、分割線を引いてしまっているということでしょうか。
石倉:
そのとおりです。たとえば哲学者のデカルトは「我考える故に我あり」って言いましたけれども、たとえば芸術的な創作活動も、「我描く故に我あり」「我つくる故に我あり」を前提としてしまっている。つまり、ヨーロッパから始まった芸術のモデルで言うと、そもそもの起点となる主体はデカルト的な思考のモデルから抜け出せていない。僕はその「考える我」を、分割線以前に引き戻す作業が必要だと感じています。
「考える我」あるいは「つくる我」や「創作する我」も、無意識的にいつも何かを食べているはずです。僕らは理性的に身体的な次元を囲い混んでいるように見えるんだけど、何かを食べることによって、自分自身を外界に開き、同時に変容している。あのデカルトの「懐疑し、考える我」も、思考のエネルギーが働くためには、何か食べているはずです。食というインターフェースは、実は非常に大きなトランスフォーメーションの体験に隣接している。
§
唐澤:
非常によくわかります。「我考える故に我あり」に対して、石倉さんは「我食べる故に我あり」と「複数種世界で食べること※7でもおっしゃっていましたね。人は「我考える」という思考のエネルギーのためにも食べているわけで、その意味で「食」というのが最も基盤的なものとしてあると石倉さんは考えてるのだと思いました。
たとえば、仏教の捨身飼虎や神道の大宜都比売もそうなのですが、「食」にまつわる話が出てくる場面って、その宗教において非常に大事なことを伝えているケースが多いですよね。キリスト教のアダムとエヴァも、禁断の木の実を食べる話が極めて重要ですが、これは仏教と神道とすこし位相が違うという感じもします。
捨身飼虎や大宜都比売の話は、贈与という側面がとても強いように感じます。つまり、自分自身を純粋に捧げるという側面がすごく強いと思うんです。一方で、キリスト教の創世記における禁断の木の実を食べる行為は、人間による能動性の強さみたいなものが垣間見られる。キリスト教圏における「食」と、それ以外の場所における「食」の違いみたいなものについては、何かお考えはありますか。
石倉:
一神教の背景には、旧約聖書と新約聖書っていう二つの神話のシステムが絡み合って、そこで生まれている食の世界観がありますよね。ヘブライズムの考え方では、まさに知恵の実を食べることによって、純粋なイデアルな世界から追放されて、身体性を獲得していく。人間は、純粋に精神的な世界から追放されて、性や食といった、動物性と人間性の絡まり合う「肉」の次元、あるいは「堕落した世界」に落ちていく。しかし、こうした世界観の前提を神話学的に遡ると、エヴァをそそのかした蛇という存在は、実は古代的な知恵の象徴でもある。これはヘブライズムの神話以前の新石器時代的な、もっと古い神話につながっているわけです。
同様に日常食についての規定も聖書に由来しています。たとえば、イヴォンヌ・ヴェルディエの『料理民俗学入門※8』を読むと、やはり神が7日間で世界を創ったという神話が、フランスの農村の食事の思想として構造化されている様子が見えてきます。休息日である日曜日に人々が食べるメニューや食材の調理法、皿の数、テーブルマナーと、『創世記※9』で神が世界を創造していたとされる平日の日常食とは、区別されていて食べ方も違うんです。食材となる動物の種類も、神によってあらかじめ定められている。
だからキリスト教では、食事の前にまず創造主である一神教の神へ感謝をしてから食べ物をいただきます。それは食材となっている動物や野菜に対する感謝というよりは、それを与えてくれた神様の恩寵への感謝という意味を持っている。「一者に対する感謝」という前提があると思うんですね。つまり、食材は多様だけど、感謝すべき対象、食材を創った存在は唯一者であるっていう考え方があります。これは「一つの自然と多様な文化」という、人類学者フィリップ・デスコラが言うナチュラリズムの論理構造と同型ではないかと思うんです。
一方で、ヨーロッパ的な世界観の背景には、そうしたヘブライの神話に対して、ギリシャ・ローマの多神教的世界で生まれた別の世界観が組み込まれているようです。ギリシャ・ローマ的な古い神話は、一神教の表舞台からは姿を隠していますが、芸術的な想像力の世界では盛んに表象され、あるいは地中海のアルテミス神殿がのちにマリア信仰の拠点になったように、神話的な翻訳を経て、一神教の世界における聖母子像や聖者信仰、天使信仰といった形に偽装されていきます。実はこうした一種の神話的な異文化の翻訳システムのなかから、ヨーロッパの芸術や哲学が生まれていく。
自然は一つであるが、文化は多様である。これは言ってみれば、一神教的なヘブライズムの思想と多様な現れとしてのギリシャ・ローマの思想が折衷されている。人類学的な整理によれば、単一自然主義と多文化主義と言い換えられるでしょう。ニーチェが言ったように、近代という時代に「神は死んだ」かもしれない。しかし、その後にはヘブライズムの神が、フィジックスを支える「一者」として居座り続ける。それに対して多様な表象、多元的な価値のシステムとして「文化」が現れてきた。ニヒリズムというのは、この交代と分割以外の何ものでもありません。多文化主義とは、まさにギリシャ・ローマ的な仮象の世界として「多様性と虚構」を結びつけてきたわけです。つまり、自然と文化という二元論を背景としながら、一者と多者が結合しているヨーロッパ的なコスモロジーの体系があって、そのなかで実は「食」という体験の持っている多元性が矮小化されてきたのではないか。
僕は、こうしたヨーロッパ中心主義に対して、本当に食を多元論として語るためには、単一の自然という前提を、多自然主義的に解放していく必要があると考えています。そうすると、日本人のように「いただきます」と言って食事する習慣も、その対象は森羅万象の働きや個々の食材となっている生物群、食を提供してくれた生産者や料理人に至るまで、実は多様なものであることが見えてきます。
「食べられているもの」と「食べているわれわれ」が対峙することができるポイントは、もちろん創造主を絶対的な他者と考える神話とは別のシステムです。われわれが食べているものと、食べているものが生まれてくる環境と、われわれ食べている主体がどのようにつながっているのかということをたどっていくとき、このように思考を脱植民地化して、自然と人間の関係を別のしかたで編み直す可能性が見えてくると思うんです。
§
唐澤:
実は人間も食べられる存在であるというわけですね。だけど、私たち人間は往々にして、人間こそが最高捕食者であって、他のものが人間に食べられるということだけしか考えてない。それこそ動物園に囲われてしまっている動物は、人間によって見られる対象となっています。根本にある、人間が食べる方あるいは見る方、動物は食べられる方あるいは見られる方といった非対称な構造を問い直す必要がありますね。人間がそういう他種から食べられる可能性ということを、真剣に意識したときに、何が開けてくるのでしょうか。
石倉:
「我食べる故に我あり」という存在論的な起点からはじめると、一歩進んで「われわれもまた食べられる可能性がある」という推論が導き出されます。つまり、われわれのような肉を持った存在が、他者の「外臓」のなかで食べられる存在としてあるということから、「我食べられる故に世界あり」っていうことも反転して言える。
「食べる我」の内臓的視点からは「世界がある」ということは説明できない。なぜなら、その食べ物は、すでに世界のなかで与えられてしまっているからです。しかし、外臓的に「我食べられる」と言ったときに、複数種の次元が現れる。初めて食べられるものがたくさんひしめくモノの世界、物象の世界が見えてくる。ここが世界の世界性、食の世界性を担保している外臓の根拠であり、身体の外在性や相互性を支えている物質的次元の根拠でもある。
しかもこの物質的次元は、常に数多くの分解者という存在によって支えられている。生態学の理論のなかでは、生産者と消費者、そして分解者っていうふうに三層に分かれて論じられます。たとえば森のなかに入ってみると、直接食べる・食べられる関係にあるという生き物はごく一部で、圧倒的多数は食べられずに朽ちていく。つまり、運良く食べられて、他者のエネルギーとして活用されてもらったのはごく一部であって、食べられることなく朽ちていくものが圧倒的多数なんです。だけど、その朽ちていくものたちがどうなるのかというと、実は菌類や粘菌といった目に見えないものたち、あるいは目につきにくい小動物や昆虫に食べられる。この「食べられることの多数性」に、循環という次元の深みがあると思います。
「食べること」「食べられること」は決して「対関係」じゃないんですよね。われわれは「食べること」を、常に恋愛や性愛関係のように、二者の関係としてモデル化しがちです。しかし、これは実は「一対多」の関係を孕んでいます。しかも、この場合「多」に対峙するのは「一」を含むような生態系全体の集合としてイメージできると思います。「私はわれわれに食べられる」とでも言えるような「多数者に食べられている」という感覚。常に地球に食べられているというか、自然に食べられているというか、自分を取り囲む外臓全体に還元されていく。それによって朽ちて、自分も、大きなものがエネルギーの一部になることができる。
つまり開かれた全体性に対して、自分が食べ物になるということは、誰かと特別な関係を結ぶというよりは、もしかしたら「無駄死に」のような体験に見えるのかもしれない。しかし、もちろんそれは無駄ではあり得ないのです。ですから、菌とかウィルスとかと共生するっていう次元を真剣に考えるならば、捕食者・被捕食者の対関係を超えたところまで、食の思想を拡張しなければならないと思います。
§
唐澤:
まさにそうだと思います。朽ちていくっていうのも、実は食べられているんですよ。僕は死んだら粘菌に食べられたいと思っているんですけど、粘菌とかバクテリアが食べることによって朽ちていくんですよね。だから、人間というのは、ある特定の一者だけに食べられるだけじゃなく、食べられた後、糞尿になって排出された後は、バクテリアとか粘菌にも捕食されていく。そうやって、他の生命を、あるいは世界を支えていくっていうことだと思うんです。
そういった意味でも、捕食者と被捕食者は、一対一ではありません。一対多なんですよね。そのように、自分が食べられることが世界を支えていることにつながることを意識したり実感することが、現在は少なくなってきている。その原因は一体どういったところにあるんでしょうか。
石倉:
都市化、文明化の進展によって、われわれが直接土に還元されなくてすむようなシステムが構築されてきました。その環境では、土とつながっているという実感すら忘れてしまいがちです。これを乗り越えて、自然の循環系と人間の文明圏の循環系を接続するためには、おそらく「自己」や「身体」という概念を更新する必要があります。
グレゴリー・ベイトソンが言っているように、森のなかの生物の「自己」は皮膚を超えて存在している。その自己は、複数の身体に渡って分散することもあれば、自分の身体の内部にある様々な、たとえば細胞の一つ一つといった次元まで、実は自己が縮尺されたり拡散している。このことを踏まえて、エドゥアルド・コーンが「諸自己の生態学」という視点を出したことは、非常に革命的なことだと思っています。
この思想は、食べられる経験とも関係しています。実は自分が多数者に食べられるということは、自己が身体の皮膚のような境界では区切られないし、時間的にも個体の一世代では決して終わらないっていうことですよね。だから「複数の自己」によるアニミズムが可能になる。食べる・食べられる関係のなかで捉えられる二者の次元を超えて、実は多数者に食べられ、解体され、朽ちて土に還って、次世代の再生を準備するという次元から、「諸自己の生態学」を担保するような別の現実性が見えてくる。
しかし、アニミズムを一神教よりも遅れた原始的段階にある素朴な宗教思想であるという思想モデルを、19世紀の人類学はつくってしまっていた。こうした人類学がつくってきた前提によって、私たちはおよそ100年間ものあいだ思考を停滞させてきたのかもしれません。そのことにはっきり気づいていたのは、南方熊楠くらいではないでしょうか。今や文明圏における循環と自然界における循環を接続することによって、新しいアニミズムというか、より適切なアニミズムのモデルを提示することが可能になってきました。それをやらなければいけない時期に差し掛かって来ている、と考えています。
§
唐澤:
文明圏における循環システムと自然界における循環システム、それらをどう接続していくかは難しい問題だと思うんですけど、何か重なり合う部分ってありますか。
石倉:
本来はあらゆるシステムが重なり合っていると思います。文明圏の人工物と、自然の次元は常に重なり合っている。このことを、ネパールのサンクという町で出会ったネワールの友人は、「この世界のなかには、女神の身体と関係ないものはどこにも存在しない」と言っていました。つまり、人工物と自然物を分割しない、非二元論的な思考がネワール仏教の女神信仰を支えているわけです。このような知恵は、ネワールだけでなく世界中の先住民社会に伝えられています。ここから、自然資源に対するエコロジカルな配慮や生命倫理の感覚も継承されてきました。
ところが、私たちは資本主義が前提とする「自然の植民地化」によって、無限につながる女神の身体を人間の有限な所有物であるかのように、そして地球上の限られた資源を無限に開発できるかのように取り違えるようになってしまった。人間の文明圏を中心とするモデルに縛られてしまって、都市を取り巻くものを軽く見たり、自然を開発したり、環境を棄損してきたわけです。これが「人新世」と言われる時代の非常に大きな問題をつくってしまった。形而上学的な問題と社会的・経済的な問題のあいだに、解消しがたい大きな亀裂が生じています。ここに生じているのは有限と無限の大きなズレなのです。
§
唐澤:
人間界における人工物というのは、実はすべて自然からできているわけですもんね。だから、それぞれの人工物には、すでに自然のすべてが含まれていると言ってもいいかもしれない。これは如来蔵思想の考え方にもつながってくるものがあって、それぞれ個々の存在として生きているが、実はそれらのなかにすべての如来なる種みたいなものが含まれている。今のお話を聞いていて、そのようなことを想像しました。
また先ほどから説明されている「食べるもの」「食べられるもの」の関係に真摯に向かい合いつつ、我と汝、我と世界との関係を考えていくという話にもつながりそうです。石倉さんがイメージされている日本の歴史と仏教、あるいはそれを背景にした「共生の思想」について、もうすこし教えていただけますか。
石倉:
如来蔵思想の日本的展開を考えてみるとき、「ヒジリ」という存在が重要な役割を担っていたと思います。最初期のヒジリには二つのタイプがある。一つは行基菩薩のように、社会的な空間に介入していくタイプのヒジリ。つまり、たとえば治水や土木工事、大仏建立といった社会事業を通して、人間のために環境をよくするような、一種の人間的利他だと思うんです。同時に、自然智宗や道教の山林修行者や伝説上の役小角や蜂子皇子のように、修行のために山林に入っていく別のタイプのヒジリがいて、彼らは人間界から離れたエコロジカルな現実に触れることによって、「人間を超える」立場から利他を完成させようとします。どちらも人間と非人間の根源に、分割することのできない「如来」を胎児のように抱えている。平安時代には、その前の時代の律令仏教と山林仏教の分岐を背景に、この二つの流れがダイナミックに交わることによって、都市と山岳を結ぶ新しい思想が生まれてきました。いわゆる「本覚思想」の展開も、人間と非人間の双方に「如来」を宿すという如来蔵思想の読み替えから生まれています。
つまり、多くの人口が集まる文明的な生活圏と、山岳のアジールを背景とする修行道場とを結び、人間的利他と超人間的利他をつなぐ。これが日本仏教のプロトタイプだと思います。しかし、都市の政治権力と山岳の宗教的権力が拡大してしまうと、人間的世界と宗教的世界が分離していきます。すると、多くの祖師が比叡山から下りて、鎌倉仏教という宗教的なルネッサンスを発生させる。このように日本仏教は常に里と山の関係を背景にしていて、多様な宗派や修験道の行者たちがその媒介役を担っていた。そういう形で、如来蔵思想は日本列島に一つの大きな思想史をつくってきたのではないでしょうか。
日本列島の歴史では、こういった仏教的な利他思想の系譜と、古くから継承されているような神話の神々の世界が集合することで、いわゆる「神仏習合」という人・生物・自然・神仏の共生関係が思想化されてきたと思います。この共生関係をベースに人間と非人間の関係を見ようとすると、最初から人間だけに限定された世界が形成されいく「共同体」といったイメージで、社会を捉えることが難しくなってきます。
僕は「共異体」という概念が必要になってくると思っています。つまり、同一的な共同性が担保された純粋な社会共同体以上のモデルとしての「共異体」です。人間を取りまく世界が常に「人間以上(more than human)」であるように、日本列島の各地に形成されてきた社会は常に「共同体以上(more than community)」であったのではないでしょうか。
§
唐澤:
「共異体」という概念を最初に使ったのは、小倉紀蔵さんでしたよね。
石倉:
そうです。哲学者の小倉紀蔵さんは「共異体」という概念を、中国と朝鮮半島、極東の日本列島といった東アジア諸地域の広域共同体として概念化しました※10。かつて民主党の鳩山政権が「東アジア共同体」という理念を掲げたときにも、それに対する一種のオルタナティブとして、互いの差異を尊重する「東アジア共異体」を提起されていたわけです。
僕は2017年に、中国返還後20周年を迎える転換期の香港で「神話・歴史・アイデンティティ」について考えるアートプロジェクトで香港に滞在したとき、韓国語と日本語の通訳者からこの概念を教えていただきました。この概念を知って、僕は大きな衝撃を受けたんですが、同時にこの概念を本来の文脈から大幅に拡張してみたいという誘惑に駆られました。つまり、この概念を、歴史と神話の関係、複数種の共生圏、身体と環境世界の関係など、これまで「同一性」の枠内で語られてきた物語をハイブリッドなものに書き換えるための概念につくり変えてみたい。そう思ったんです。
§
唐澤:
「共異体」は華厳思想的という気がします。「共同体」は、同じ種のなかで、さらに同じ理念みたいなものを共有している集まりという印象ですが、「共異体」は、異種間同士の対称的なあり方、個々を単純に無化しない形での異種間の共存のあり方、つながり合いみたいなものを目指していると感じます。華厳でいう「事事無礙法界」的なものを感じるんですが、石倉さんは「共異体」と華厳とで、何かつながりを考えられてたりするのでしょうか。
石倉:
「共異体」というモデルは、個々の差異を解消することなしに、むしろ差異によってこそ個々の生命存在をつなぐことができるのではないか、という発想に基づいています。そして、そこには異なる存在論の接続を通じて、人類が蓄積してきた多種多様な科学の成果を排除せずに、どんなふうに各集団の神話やコスモロジーからも多元的な知恵を継承するか、という課題が含まれています。
人間の共同体を中心に科学を語ろうとすると、そこに一神教の遺産である「絶対的な一者」の残滓として「単一の世界」という近代的前提を抱え込まざるを得なくなってしまいます。これは人類学者のジョン・ロー※11やアルトゥーロ・エスコバル※12が「単一世界の世界(One-World World)」という形で批判してきたように、地球を人間活動の背景として一元化し、植民地主義的な開発経済の枠組みを形成してしまう。
これに対して「野生の科学」というものがあるとすれば、その視点には人間の人間性を相対化するような、多次元性の政治が関与してきます。人間の共同体が宇宙の中心にあって、人間がすべてを俯瞰して自然をつくり変えていくのではない。そういった人間中心主義的な視点から離脱して、一種の共通世界を再発見していくときに、仏教が説いている非二元論や多元論が再発見されることになります。
その内実に深く入り込んでいくためには、仏教の思想だけでなく、神話的思考や先住民のコスモロジーのように、科学的なロゴスの枠組みでは捉えきれない、「レンマ」の思考による「多元的宇宙(pluriverse)」の次元が現れてくる。このようにロゴスの物語で捉え切れないものをどう想像し、世界化のモデルとして実現していくのか。唐澤さんが一貫して取り組まれている南方熊楠研究や中沢先生の『レンマ学※13』のように、華厳思想を現代的に再発見していくことは「共異体」の現代的な問いに直結すると思います。
人類学者の大杉高司さんが「非同一性による共同体※14」、あるいは非本質主義的な「無為のクレオール」ということを提案されています。これは仏教が説いている「空の論理」や「縁起の法」といった、インドの古代宗教に対する、ブッダによる本質主義批判の問題と重なってくるのではないか、と昔から考えてきました。つまり、クレオールやハイブリッドの実相を見ていこうとする人類学的な同一性批判は、仏教的なロジックと親和性が高いと思えるのです。
このような「非同一性」が担保されないまま、人間と非人間の集合体が実体化されてしまうなら、コーンの「森は考える」という議論は森全体を実体化して「森の神」という偶像の思考を想定することになってしまう。ところが、そうならないような仕組みが先住民社会にはあって、常に複数種が多元的に拮抗しながら、「開かれた全体性」が維持されるような状況が生まれている。ここにも「非同一性による共同体」あるいは「共異体」が生成しているのだと思います。
§
唐澤:
なるほど、今仏教を複数種の問題と関連付けられていましたが、僕は「種」と関係しているのではないかと思いました。要するに、日本という神道の土壌に蒔かれた「種」で、それが土壌のエネルギーを吸い上げつつ、花を咲かせている。それがいわゆる神仏習合だとも言えるし、日本的な仏教を展開していく手法だと思っています。日本に仏教が入ってきて、どう花を咲かせていったのか。その手法を見ていく必要もありそうです。
石倉:
たしかに仏教を複数の「種」と考えるのは、とても魅力的ですね。僕は、仏教は地中に根茎をめぐらす植物のようなもので、そこからアジア各地の芸能や建築などが展開してきたのではないか、と考えたことがあります。
僕は学生時代に北インドでフィールドワークをしていて、手持ちの金銭が尽き、大きな壁にぶち当たった時期に、仏教聖地のブッダガヤで行われていた仏教の祭礼に参加して、しばらく頭を冷やしていました。そんなぽっかりと空白が開いてしまったような体験をしていて、ふと気がついたことがあります。
ゴータマ・シッダールタが悟りを開いたというブッダガヤの聖地には、大菩提寺という寺院の伽藍がありますよね。ご存知のとおり、その中心部には簡素な金剛座というブッダ成道のモニュメントがあって、その後ろに一本の菩提樹が生えています。もちろん、この樹は何代も植え替えられてきているのですが、それを見たとき僕は「仏教とは、一本の樹なんだ」と理解しました。
ゴータマは、シャーキャ族の王子として城内で暮らしていたときも、想像を絶する苦行に取り組んでいたときも、結局悟りを開くことはできなかった。しかし、彼は苦行をやめて山から降り、この菩提樹の前に座ったときにようやく、世界を貫いている縁起の法則を発見した、と言われていますよね。この有名な説話は、この地に生えていた菩提樹という植物をなくしては、決して語ることができないのです。
ゴータマは、個人の心理的な葛藤を超えて、この一本の樹の下で世界のリアリティを悟った。僕はそのことに大きな意味があると思っています。僕が菩提樹の前で、茫然自失としていたとき、周囲ではチベットやモンゴル、ネパール、中国、タイ、韓国、日本といった様々な地域から聖地を訪れた仏教徒たちが、それぞれ全然違うスタイルでお祈りをしていました。キリスト教やイスラム教の世界ではありえない光景ですが、それはまさに唐澤さんがおっしゃったように、仏教という種を各地の民衆が自分たちの思想や表現の大地に移植して、それぞれ異なる果実を育てているように見えたのです。
このように、仏教世界の多様性というのは実に大きなもので、ブッダガヤにある各国の寺院は全て建築様式が異なっているし、礼拝のしかたも微妙に異なります。そもそも経典も、多様な言語に翻訳されていますし、五体投地の作法も違う。しかし、お祈りをしている人たちは、同じように一本の樹の方を向いています。そこには、仏像も神像もなくて、一本の菩提樹が生えているだけだった。
もちろん菩提樹の前には、金剛坐という簡素な「場所」があります。そこに一本の樹があり、人が座れる場所があるということ。つまり、「場所」と「植物」の関係から、全ての歴史が始まっているということだと思うのです。神々からではなく、聖書から始まっているわけでもない。土地に先住する「植物」と、人が座る「場所」だけがある。ブッダという存在は人間と地続きで、理論上は万人に開かれた「覚者」としての理想像です。このことは、誰もがこの菩提樹の下に座る権利と可能性を有している、という開かれたビジョンにつながってくる。
そう考えると唐澤さんがおっしゃったように、仏教という「種」を、あるいは菩提という「種子」を運んで、離れた土地に根付かせて、花を咲かせ果実を実らせていくという、魂の歴史が見えてきます。仏教が移植される大地は、古い時代から続く各地の神話と地続きです。ある土地から別の土地へと種を運ぶことや根を生やすこと。そこに育つこと。そして知恵の花を咲かせ、慈悲の実をならせること。世代を継いでいくこと。仏教からこういう可動的な植物の生態モデルが得られるのではないかと思っています。
§
唐澤:
言葉も違う、お祈りのしかたも違う人たちがいて、真ん中に仏像ではなく菩提樹だけというのおもしろいですね。強力な中心ではない柔らかな中心が、逆に共異体的に人々をつなぎ合わせるものとして機能しているように思いました。「共異体」に関しては、〈Cosmo-Eggs|宇宙の卵※15〉(第58回ヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展日本館展示)でも重要なテーマだったと思うんですが、これは作品内でどう実現されたと思いますか。
石倉:
そのように〈Cosmo-Eggs|宇宙の卵〉というプロジェクトを読み込んでもらえて嬉しいです。「共異体」というものが実現されなかったことは、これまで一度もないと思っています。常にそこにあるものだという言い方もできると思います。かといって、それを実体化したときに、大きなものを失ってしまうかもしれない。「共異体」とは、架空の集合体であって、そこに創造の可能性がある、と理解するべきかもしれません。僕たちが「卵」というモデルにこだわったのは、そこにまだ生まれていない世界像を込めたかったからです。
同時に、僕たちは沖縄の八重山諸島や宮古諸島に散在している「津波石」という小さな場所を手掛かりにしながら、人新世という時代に通用するような、具体的な共生と共存のイメージを共有したいと考えてきました。そもそも共同制作のきっかけになったのは、美術家の下道基行さんが沖縄の離島で撮影してきた「津波石」の映像作品のシリーズでした。
ご存知のとおり、「津波石」とは、かつて海の底にあった巨石が、大きな地震や津波の衝撃を通じて移動し、地表にもたらされたものです。つまり、この石は過去の大きな災害のモニュメントになっています。同時に、その津波石を撮影した下道さんの作品には、アジサシという渡り鳥が営巣している姿や、小さな生物が岩のうえを這っている姿、岩に生えている苔や植物、農機具を使ってサトウキビを収穫する島民の姿、石の前で記念撮影する子どもたちの姿も写っています。つまり、津波石とは異なるものの集合体、あるいは「共異体」という開かれた全体性のモデルを示すのにうってつけなミクロコスモスだったのです。
科学的な視点から見れば、津波石の多くはもともと海中に沈んでいたサンゴ石灰岩で、海中の生物が化石化して付着しています。そもそもサンゴは褐虫藻という藻類と共生する生物で、津波の後に打ち上げられた陸上でも、多くの動植物と共生領域を形成していました。つまり、石の上に木々や植物が生い茂っていたり、様々な鳥類の生息地になってもいます。

津波石は聖地として信仰されていたり、特別な埋葬場所とされたこともあります。そうかと思えば、児童が遊ぶ公園の遊具になっているし、多良間島には津波石を壁面に、手づくりの住居をつくって住んでいる方もいました。〈Cosmo-Eggs|宇宙の卵〉というプロジェクトでは、服部浩之さんのキュレーションによって、そういった多種多様な存在へとつながっていく津波石のあり方を、人間と非人間の共生モデルの表現として提示しています※16。
こういった津波石の多様性を発見し、映像作品としてシリーズ化していた下道さんの活動への応答として、作曲家の安野太郎さんは現地で再録した鳥の声をもとに、卵生神話を彷彿とさせるような曲を作曲し、機械制御されたリコーダーで音楽が自動生成される装置を制作しました。建築家の能作文徳さんは、中心部が筒抜けになっている日本館という歴史的な建築物に対して、参加した作家たちのそれぞれのアプローチを丁寧に共存させるような、現代のエコロジー思想を体現する建築を制作しています。下道さんの作品を映す可動式のスクリーンやマップケースなどの什器、安野さんの音楽を生成するバルーンや空間内のリコーダーの配置も、すべて能作さんと作家たちとの共同制作です。

僕は、宮古・八重山諸島や台湾でのフィールドワークから津波神話や卵生神話を収集し、そこから子宮からではなく卵という空間から新しい人類が生まれるという創作神話を作り、他の作家たちがそれを日本館の壁に刻んでくれました。こうして日本の最南端の島々で行われた津波石のフィールドワークを通して、美術家・建築家・作曲家・人類学者がヴェネチアでの展示プロジェクトを構築するのは、これまであまり行われたことがない、実験的な取り組みだったと思います※17。
§
唐澤:
「共異体」は常にダイナミックな動きで、ある意味プロセスそのものですよね。先日見たアーティゾン美術館での帰国展でも、プロセスが生き生きと描かれていたのが印象的でした。壁に〈Cosmo-Eggs |宇宙の卵〉が展示されるまでのプロセス・タイムラインがずっと書いてあって、共異体的だと思いました。
〈Cosmo-Eggs |宇宙の卵〉がすごくおもしろいのは、常に変化していくところです。真ん中のバルーンに人が座ったときの空気が管を通ってリコーダーへ運ばれる。そしてそれぞれのリコーダーが反応し合って、常に違う音が出る。あれは動的な様態を示唆的に表現されていると思いました。それから、スクリーンに付いている車輪、あれは動かさないのに動くという可能性を見せてるところがすごくおもしろい。止まっているけども動く可能性を示しているっていう意味で、静と動の共存、それは静止状態のなかにダイナミックな動きを想像させ、とても共異体的な装置だと感じました。
異なる専門性を持つ者同士が理解・制作・実践を共有する共異体的協働の方法を模索するなかで、石倉さんは創作神話をお作りになったわけですが、そこには「共異体」の概念はどのように反映されているのですか。

石倉:
このプロジェクトの特徴は、集中的なフィールドワークだけではなくて、日本の各地に分散して住んでいるメンバーが、オンライン上のコミュニケーションを利用して打ち合わせを続けてきたことにも現れていると思います。つまりその後、新型コロナウイルスで一般化したオンライン会議のような仕組みを多用して意思疎通を図ってきた、ということです。初回の打ち合わせも、僕は秋田からオンラインで参加しましたが、そのとき、二十年ほど前に宮古諸島を旅行したときに聞いた「卵生神話」のことを思い出しました。
この打ち合わせのときに決まった「宇宙の卵」と言うタイトルは、もちろん神話学上の「宇宙卵(Cosmic Egg)」を参照していますが、その背景にはこの「卵生神話」があります。池間島のウハルズ御嶽という場所と関連する日光感精説話で、少女が太陽を浴びて卵を生むという伝説ですね。創作神話のなかでは、同じ宮古諸島や近くの八重山諸島に伝わる津波伝承神話と一緒に取り上げられますが、その理由は、前者の「卵生神話」が世界の始まりを、後者の「津波神話」が世界の終わりを伝える神話だからです。
下道さんの映像作品も、安野さんの作曲した音楽の生成装置も、実は反復構造という共通点を持っています。僕が調査した「津波神話」と「卵生神話」は、それぞれ別の系統で一緒になることはないのですが、実はこの二つを連続的に扱うことで、この地域に長い時間をかけて反復している地震や津波という災害、そしてそれを超えて生存し続けてきた人間とそれ以外の生物の歴史を喚起してみたい、と考えました。その後、少女が12個の卵を産むという話が、偶然安野さんが展示空間内に設置した12個のリコーダー装置と呼応したり、日本館の天井から差し込む陽光や卵の黄身のようなバルーンといった卵の隠喩的な視覚的要素がつながって、徐々に無意識の必然性や共同性を獲得していくことになりました。
それでも、「津波神話」と「卵生神話」をつなぐミッシングリンクは、結局2019年の1月に台湾を訪れるまではうまく発見することができませんでした。創作神話をつくる期限が迫っていたこの時期、沖縄から国境をこえて台湾原住民の神話を現地で調査するなかで、偶然この二つの話型をつなぐ神話が見つかりました。台湾の台東地域には、海岸部に転がる大きな石から先祖が生まれてきたとか、洪水の後に生き残った祖先が卵を産んだという格好のモチーフがあったんです。それは、まるで卵のように孵化する雛鳥のように、海の近くにある鉱物から祖先が現れるという神話群です。こうした台湾に伝わるいくつもの神話を見つけたときに、ようやく創作神話の全体像が浮かんできました。
僕は、自分が物語作者となって神話を書くというよりは、日本の南限に当たる先島諸島や国境を超えた台湾の神話を集めることによって、これまで国家単位で語られてきた神話を、島々のコスモロジーの感覚から再構築したいと思っていました。この作業は、最後に台湾で「石の卵」の神話を見つけたことによって、一気に進んで完成に向かいました。
できあがった創作神話には、いわゆる民間伝承ばかりでなく、自分自身の個人的な想像やイメージが含まれていますし、今回関わったメンバーや現地の人々から聞いた出来事の断片が織り込まれています。また、東アジアの日光感精説話が男性や女性の同性集団の結社と関係してきたことも、大きな意味を持っています。結果的に、今回は男性のメンバーばかりが集まったので、あえて子宮からではなく、卵から先祖が生まれたという話型に集中し、人間を超えた次元での誕生や生命について考えるという展開になっていきました。
§
唐澤:
たしかに〈Cosmo-Eggs |宇宙の卵〉のメンバーは男性だけですね。あえて同性集団で、異性性を考えるのは大事だと思いますが、もしメンバーに女性がいたら、また作品もすこし違う感じになっていたかもしれません。
「太陽を浴びた少女が卵を産む」と言う展開も、いろんな重要なエレメントが隠されているようで、おもしろいと思いました。太陽からの光という贈与によって、大人ではない少女が爬虫類のように卵を産む。これは人間の生理を優に超えている。贈与を起点にしながら、人間と非-人間、大人と子供など、共異体的在り方を表現しているとも思えます。そこに大きなヒントを得て、石倉さんは創作神話をつくったのだと思います。人類学者が神話を創作するのは、なかなか勇気がいることだと思ったんですが、他の人類学者から何かコメントはありましたでしょうか。
石倉:
生産的な批評はいくつもありましたが、非難の類は一切無かったですね。今の日本の人類学は、従来の制度から発展して表現方法を多元化・豊穣化していこうとしています。ですから、僕たちの仕事も、アートと人類学の協働を探ろうとしている一連の実験的な流れの一部として受容されているのかもしれません。
もちろんこうした実験の先駆けとして、中沢新一先生がアーティストのマシュー・バーニーに向けた創作のユーカラ※18をはじめとする、批評的な考察と詩的実践のあいだに位置付けられるような、一連のテキストが存在しているはずです。上橋菜穂子さんみたいに小説や物語を書いたりするような人類学者もいらっしゃるし、人類学者シオドーラ・クローバーとアルフレッド・クローバーの娘であるアーシュラ・K. ル=グウィンの『ゲド戦記※19』にも、神話的な要素はふんだんに盛り込まれています。そういう創作的なテキストと、人類学的な記録としての民族誌をつないでいくような回路が、「表象の危機」以後に数々の苦闘を通じて獲得されてきました。20世紀後半から21世紀の頭にかけて、人類学・歴史学・神話学・考古学・社会学・精神分析学・芸術学などが再構築の時代に入ってきて、そこで生まれてきた一つの可能性として、創作実践があるはずです。
§
唐澤:
石倉さんより前に、中沢先生も創作テキストを発表されていたんですね。よく考えたら「四次元の賢治※20」も、それに近い表現な気がします。中沢先生は、いち早く宮沢賢治や南方熊楠に可能性を見出し、再評価するテキストを発表し続けているのだと思います。
石倉:
そのとおりです。そして中沢先生も、多くの先人からその精神を受け継いできたのだと思います。たとえば民俗学の方でも、柳田國男と佐々木喜善の『遠野物語※19』から折口信夫の『死者の書※22』まで、ストーリーテリングを組み込んだ学問の系譜がつくられてきましたし、フランスの人類学ではレヴィ=ストロースやフィリップ・デスコラが、非常に詩的な創造をテキストに組み込む方法に挑戦してきました。ルーマニア出身のミルチャ・エリアーデ のように、学術と文学の両輪から研究を深めていった宗教学者もいます。そう考えると、ストーリーテリングをもう一度見直してみるのも、芸術人類学の一つの重要な課題と言っていいと思います。
また、複数の種との関係や視覚的な媒体以外の表現方法、音楽や演劇、現代芸術や環境デザインなどの領域と人類学的実践の協働も、これから大きく発展していく見込みがあると思っています。そのためには、人類学を知的生産に閉じ込めるのではなく、他の学問領域とアートを架橋するような、越境的インターフェイスとして鍛えていく必要があると考えています。
§
唐澤:
僕が研究している南方熊楠という存在との接点も、そのあたりに隠されているように感じます。ストーリーテリングの可能性は、南方熊楠が膨大な書簡や記録を通して実現してきた、まだ未開拓な知の領域にも含まれているように思えるのです。また熊楠が粘菌研究をとおして生命のロジックを掴み取っていったように、科学と様々なアートの領域を結んでいくような視点も、これから大事になっていく予感がしますね。今日はありがとうございました。
合原織部:
ナイトさんは、社会人類学者として、日本の紀伊半島の山村を対象にした数多くのフィールド調査をされてきました。扱ってきたトピックは、狩猟、農業、林業、そして人間と野生動物とのコンフリクトなど、広範囲にわたります。近年の研究は、日本のモンキーパークにおける人間とサル(ニホンザル)の関係性をワイルドライフ・ツーリズムの場として考察するものです。これまでの研究では、今日の日本における人間と動物の関係性のダイナミクスが主なテーマとなっていたように思うのですが、どのような経緯でこれらのトピックに関心を持ったのでしょうか。また、調査対象として日本の山村を選んだ理由はありますか。私自身、宮崎県の山村で人間と野生動物とのコンフリクトに関する調査をおこなっていて、このようなトピックに関心があります。
ジョン・ナイト:
1980年代に博士課程の学生として日本を訪れ、和歌山の本宮町で山村での過疎化について研究していました。本宮には約3年間滞在して、町の外へと移住し、お盆や正月に故郷へと帰省する人々といった、とくに人間の移動に注目していました。最終的に博士論文では、観光客(本宮には有名な温泉があるため)や「Iターン」と呼ばれる移住者や、外に移住していく人々を扱いましたが、私の主な関心は、人々が地元を離れる理由や、そのような移住が残された村へ与える影響にありました。
これが私の日本での研究における第一ステージだったと思います。このとき村が動物が住む森に囲まれていたこともあって、研究の背景程度ですが、動物への関心もありました。1990年代に追加調査で本宮に戻ったとき、森の動物にも強い興味が湧き、それらの動物と、耕作を諦めたり村を出たりしていく人々、また村に侵入して農作物を荒らす動物との関係性などにも関心を持つようになりました。
はじめてモンキーパークに関心を持つようになったのは、1990年代後半に本宮出身の人と和歌山の伊勢ケ谷モンキーパークを訪問したときのことでした。そのパークがある椿エリアを訪れたのは、その周辺で深刻な猿害があると聞いたからだったのですが、それがモンキーパークに関心を持つきっかけになりました。
猿害の温床となる可能性があるにしても、モンキーパークは魅力的な場所です。伊勢ヶ谷にはじめて訪れてから、機会があるたびに伊勢ヶ谷や、他の地域にあるモンキーパークを訪問しました。結果的にこの経験は、日本の人間とサルとの関係性に関する私の視野を広げてくれました。村で生じている人間と動物のコンフリクトだけではなく、日本での人間と動物の関係性について、もうひとつの側面であるワイルドライフ・ツーリズムについて学ぶことも有意義だと考えるようになりました。それは野生動物を、害獣としてだけではなく、観光の資源としても捉えるということです。
モンキーパークの研究を通じて、私のテーマは人間とサルのコンフリクトから、サルが人間の魅力を受け取ることへと移っていきました。2000年代には日本中のモンキーパークを訪れましたが、なかでも特に深く関わったのが、小豆島の銚子渓自然動物公園でした。そこは他のパークとは違い、来園者が屋外で自由にサルにエサを与えることが許されていました。スタッフと知り合いにもなり、今ではそこが一番よく知っているモンキーパークです。
銚子渓自然動物公園は、私のモンキーパークに関する研究のメインの調査地となり、2018年までの間、機会があるたびに訪問しました。しかし、私のモンキーパークに関する調査は、もともと和歌山の山村でおこなっていたような長期滞在型のフィールドワークとはやり方が異なります。私は本宮に3年近く滞在しましたが、モンキーパークの調査は、短期間で複数回おこなった結果を元にしていました。小豆島でさえ、滞在期間は数週間を超えたことがありません。
動物の人間観とは何か
合原:
現代日本の人間と野生動物の関係性を考えるとき、近年の自然・社会環境の変容、特に農山村が経験してきたことを考慮するのが重要です。あなたの編著である『Natural Enemies※1(天敵)』と『Waiting for Wolves※2(狼を待ちながら)』では、現代日本の山村状況について論じています。それによれば、山村で過疎が起こるのは、人々が仕事を求めて都市に移住した結果だと言います。そして山村に人がいない状況は林業や農業の活動を低下させ、それが森林の野生動物の圧力に抵抗する人々の力を弱めることにつながると論じていて、このような人間と野生動物の衝突が生まれるプロセスは、日本の農山村に特有のものであると指摘しています。日本の人間と動物の関係性が持つ特異性について、もう少し説明していただけますか。
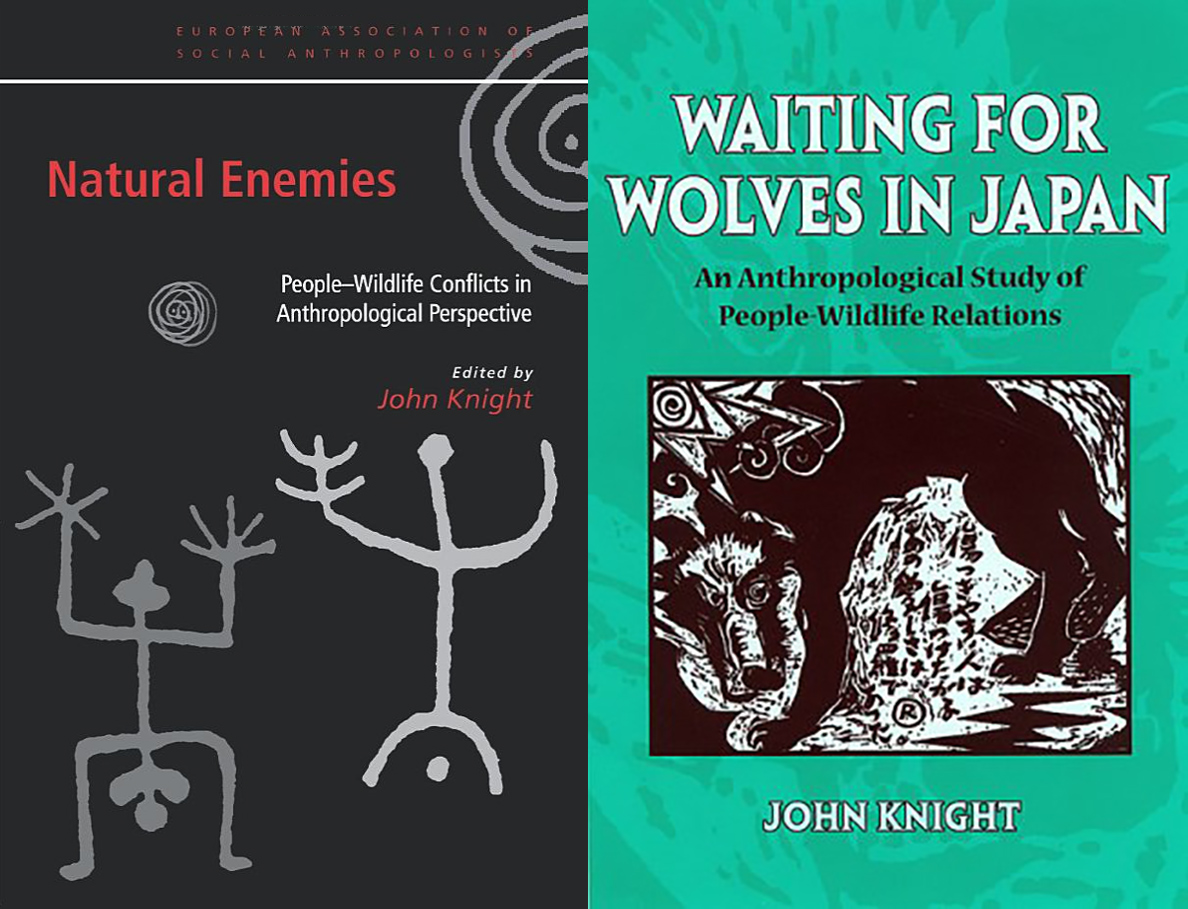
また今日の日本において、地方と都市の分離や、過疎化、人間と野生動物の衝突の問題は、以前にも増して深刻です。あなたは人間と野生動物の関係性について、このような変化をどのように捉えていますか。
ナイト:
人間が都市に流出し、野生動物が農山村に侵入することを、英語では”encroachment”という語で表します。社会人類学者として、私のアプローチは、山村の住民がその「侵略」という状況をいかに理解するのかや、それをいかに彼らの生活における大きな変容として捉えるのかを理解することにあります。彼らにとって、村と山林の境界は非常に重要なのです。
§
合原:
そうですね。彼らはそれを区別していますね。
ナイト:
動物が村のはずれに住んでいるときでさえ、動物が村に入ってくることは、村人たちにとってはある意味無秩序で異常な経験なのだと思います。それはどのような無秩序なのか。これに答えるためには、日本の山村住民の事例のように、ある場所に私たち人間が独占的に居住するのではなく、他の様々な存在とも重なり合っているという前提から始めるべきかもしれません。そして、このような場所での暮らしには、活動的な人間の存在が必要です。
この考え方は、過疎化に対する私の理解を次第に変えていきました。はじめのうちは、過疎化を単に数値の問題として捉えがちでした。役場の職員が人口減少についての話で取り上げる数値と似ているかもしれません。人々は過疎について、単純に人口減少によって生じる量的で数値的な問題という印象を持つ傾向にあります。ですが、私は過疎は量的かつ質的な問題であり、山村の生活空間における人々の活動の減少と連関していると確信しています。
簡単に言うと、山村で効率よく暮らすには、人々はそこで「活動的」に住まなくてはならないということです。逆に、過疎は環境に関わる活動が失われた状態だとも理解できます。単に人口だけでなく、残された人々の活動が減り、農作業や草むしり、植生除去もしなくなり、村のなかや近くの森を動き回ることも少なくなります。つまり、農山村の過疎化は「環境の不活性化」であり、このような人間の活動の減少が森の動物が侵入する状況を作り出すと考えられます。これが、農山村の過疎化と野生動物の侵入が同時に生じるひとつのあり方だと思います。
農山村と都市の乖離と、人間と野生動物の関係性の変容との関係についても質問されていましたが、私は動物がどのように人間を見るのかについて知りたいと思っていました。日本の民俗学者らは、ときどき「人間の動物観」という概念を使います。人間が動物をどう見るかというのは、魅力的な研究対象です。しかし、その言葉の逆、動物が人間をどう見るかという「動物の人間観」と呼べるようなものも、とても興味深いと考えています。
日本の農山村では、動物が人間に対する恐怖心を失ってより大胆にふるまうことが、今日大きな問題になっています。このことが逆に人間を刺激し、彼らが様々な方法で動物を追い払ったり怖がらせたりして、動物の人間に対する恐怖心を回復させることになります。それは「修復的に向き合い方を習慣づけること」と呼べるかもしれません。
もちろん、これはワイルドライフ・ツーリズムで生じていることとは対照的です。モンキーパークは、サルが人間への恐怖を失うことでのみ存在することができます。モンキーパークの人々は、そこを「野生のモンキーパーク」と呼びますが、「懐いたモンキーパーク」と呼ぶほうがより適切かもしれません。「懐く」という言葉には「慣れる」という意味も含まれますが、パークのサルは「極度に飼い慣らされている」と言えそうです。人間はサルを飼い慣らすためにエサを与え、人間に対する恐怖心を減らすことで、近寄ってくる観光客に慣れさせてきました。サルの大胆さは農民にとって問題ですが、モンキーパークが機能する前提でもあるのです。
日本のモンキーパークでサルに接触する人間
合原:
先ほど話したように、人間と野生動物の衝突は、人間の領域と野生動物の領域の境界に関する問題と深く関わっています。このような居住域の移動や、異種間の関係といった問題は、現在世界で広がっているコロナウイルスの状況下においても明らかと言えるのでしょうか。
森林伐採とコウモリの居住域の破壊が、人間とコウモリの接触を増やし、それによってウイルスがコウモリから人間へと伝染したと言われています。また、世界中でのロックダウンが、自然環境に予想外の利益をもたらしているという報告もされています。人々が一定期間家に閉じこもることで、空気や水はきれいになり、動物の生息数が増加したと言われます。あなたはウイルスと人間の関係や、それらの境界の問題について、どうお考えですか。
ナイト:
とても興味深い質問ですが、正直に言うとあまりよく知っているわけではありません。この数か月間、日本に行ってこの時期のモンキーパークを訪問したいと願っていました。コロナ禍がパークにもたらす変化を観察するのは、興味深いことだと思います。先に指摘していたように、コロナウイルスの起源は明らかに野生動物であるため、パークのサルなどを含めて野生動物と関わることに、人々がより神経質になるであろうことは想像できます。この状況が、パークにおける観光客とサルとの接触にどのような違いをもたらすのか知りたいと思っています。
この状況によって、パークが来園者にサルとの接触、特にサルへのエサやりを制限するようになるかもしれません。来園者にサルのエサやりを禁じているパークがある一方で、エサやりを許可しているパークもあります。そこでは人々が手でサルにエサをやることも許されていますが、その状況が変わるかもしれないと考えています。「ソーシャル・ディスタンス」が、パーク内の人間同士の接触だけではなく、人間とサルの接触にも適用されるかもしれないのです。
私は、人間による動物へのエサやりにとても関心があります。サルにエサを手渡しするのは、とても密な接触をともなう方法なので、よりセンシティブな対応になると予測しています。これまで通り来園者にサルへのエサやりを許可するパークもあるかもしれませんが、手渡しではなくエサを投げるように求めるかもしれません。コロナ禍は、人間と野生動物との接触により広い範囲の影響を与えるので、ワイルドライフ・ツーリズムにとっても特別な意味合いを持つと思います。
§
合原:
コロナウイルスの世界的流行が、人間同士だけではなく、人間とサルの「ソーシャル・ディスタンス」にも影響する可能性があるという考え方は興味深いですね。
人間と動物の関わり合いをどう見るか
合原:
続いて、人間と動物の関係を分析する際の、あなたの理論的視座について聞かせていただけますか。和歌山での野生動物による農作物被害に関する研究では、山村の人々の生活における動物の捉え方を示すために、動物のイメージや象徴的な意味を分析されています。これらの研究は、主に人間と動物の間のコンフリクトに関わるものである一方で、あなたの著作の『Animals in person※3(親しい動物たち)』では種間の親密性に着目して、いかに人々が動物に人間的な感情や知性を見るかについて検討されています。あなたの研究は、動物の人格に最も早い段階で着目した人類学研究なのではないでしょうか。
ナイト:
先にも述べたように、私の人間と動物の関係へのアプローチは農作物被害をめぐる山村住民と森の動物との間のコンフリクトに着目することから始まり、のちに動物に対する人間の魅力に関心を持つようになりました。それが話に出た『Natural Enemies』と『Animals in Person』の二冊につながっていきます。
『Animals in Person』は、人間と動物の関係の異なる側面に光を当てようと試みたもので、動物が人間に対して感じている魅力を検討しようとしたものです。そして、私はこの視点が、人間に匹敵するある種の感情や知性を持つ、人間と似た動物たちへの関心を引くと思います。私たちがコミュニケーション可能な相手としての動物です。
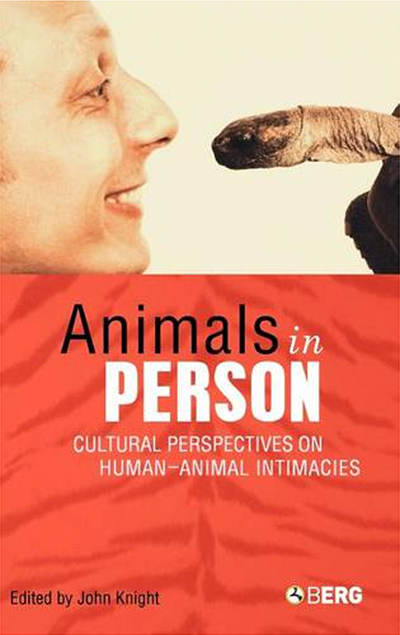
動物との衝突に関する理論に関して、私はある時期、人類学の理論である構造主義に基づいた「アノマリー(変則)」理論を用いていたことがありました。境界づけられたカテゴリーに収まらないものは、問題含みなものや無秩序、「アノマリー」として見られます。これを動物に当てはめると、私たちにとってある動物が文化的カテゴリーに当てはまらないと見える場合、それは変則的な動物とされ、特別で文化的な着目の対象になります。そのため、サルや大型類人猿を含む他の霊長類は、「アノマリー」として見られます。なぜなら、解剖学的、行動学的、認知学的など様々な点において、動物と人間のカテゴリーの間にあり、私たちと似ているけれども異なる、どっちつかずな存在だからです。
森から村へ移動して農作物を荒らし、また森へと戻っていく動物は、重要な空間の境界線を違反していると言えるので、この「境界侵犯」の考え方が適用できます。これが『Natural Enemies』で扱ったテーマであり、貢献した点でした。
最近は、人間による動物の表象よりも、人間と動物の関わり合いについて深い関心を持っています。ひとつモンキーパークで魅力的に思うのは、それが人間とサルの相互交渉を考察するのに適した場所であるということです。
§
合原:
人間と動物の関わり合いについて、何か具体的な理論を採用していますか。というのも、先の変則的動物についての説明を聞いて、メアリー・ダグラスのことを思い出したからです。そのような動物たちの関わり合いについて考察するときに参考にする特定の理論があるのではないかと思いました。
ナイト:
おそらくアーヴィン・ゴッフマンのような人でしょうか。ゴッフマンは、一対一や一対多を問わず、人間同士の相互交渉について強い関心があるので、さまざまなインスピレーションを与えてくれます。間違いなく霊長類学は、サルでも特にニホンザルの階層的な社会性など、サル同士の相互交渉のしかたについて多くのことを教えてくれます。そしてその型は、サルと人間との関わり合いについて理解するためにも使えます。
また、私たち人間が他者とどのように関わるかについての考察から派生して、サルを人や子どものように扱いながら、擬人的にサルと関わり合う方法を学んでもよいでしょう。ですが、実際の人間とサルの相互交渉は違ったものかもしれません。私のアプローチは、実際の交渉を観察して、何が起こっているのかを明らかにしようとするものです。
§
合原:
フィリップ・デスコラとジズリ・パルソンが編集した1998年刊行の『Nature and Society※4(自然と社会)』のなかの、あなたが執筆した章に関しても質問があります。あなたが執筆した章や、自然と動物に関して、デスコラらとはどのような議論をされたのでしょうか。
ナイト:
『Nature and Society』の主なテーマは、自然と社会の二元論に挑戦するものです。それは、非二元論または一元論的な視座から人間と自然の関わりに着目しています。私の章では、日本の材木プランテーションとそれが軽視されている状況を扱いながら、そのテーマに貢献しようと試みました。私の考えは、過疎というのは村だけではなく、特に放置された人工林などの森林にも起こっているのではないかというものです。例えば人工の針葉樹に人の手が入らなくなったり、人間と木の標準的なつながりが壊れたりしたときです。このことは、先に話したこととも関連しますが、人間の活動は、人間と環境との関係を作るのに役立っていて、日本の山村住民にはその感覚が強く根付いているように感じます。今もまだこのテーマに関心がありますが、それを針葉樹のプランテーションだけでなく、より一般的な形で日本の山村の環境にも適用しています。
最近の論文で、「環境下での行動のズレ※5という概念を使いました。その論文では、日本の山村における様々な「環境下での行動のズレ」を明らかにし、それらを埋める試みや、人間と土地との関わりを復活させて環境の秩序を回復させる試みについて説明しました。これらの環境下での行動のズレを埋める試みには、村人がサルや他の動物を追い払う「追い払い活動」があります。村の縁の植物を切り払ったり、木を切り倒したりすることで、動物の侵入を防ぎます。このような人間の活動の対象となる環境と、それがされない環境では大きな違いがあります。
複数の場所でフィールドワークをする
合原:
近年、フィールドワークをおこなう際の方法論として、マルチサイテッド・アプローチを用いるのが流行になりつつあります。つまり、複数の場所で調査研究を行なうというものです。この方法は、マリノフスキーの参与観察のようなクラシックな人類学の調査法とはやや異なるように思われます。マルチサイテッド・アプローチは、人間と自然の関係性を考察するうえで、新たな視座を与えることができると考えますか。
また、この調査法を用いて、今の日本の自然環境と人間の関係性を考察して、マルチスピーシーズ民族誌を書く研究も増えつつあります。マルチスピーシーズ民族誌は、人間と非人間の関係性を考察するもうひとつの流れとなっています。あなたはこれらの方法論的、理論的トレンドをどのように見ていますか。
ナイト:
いくつかの場所で調査をおこなうマルチサイテッド・フィールドワークは効果的だと思います。もちろんトピックにもよるのですが。私が実施した本宮での調査は、数多くの集落が広範な地域に分散している自治体ではありましたが、基本的にひとつの場所でおこないました。マルチサイテッド・フィールドワークの重要性は、異なる場所でたくさんの事例を調査することではなく、その異なる場所それぞれが研究のトピックにおいて重要な要素を形作ることのなかにあるのだと考えています。農山村の過疎化について言えば、移住者がどこから来るかだけではなく、どこに移住するのかにも目を向けるということなのかもしれません。
このような調査に最も近い経験は、本宮から大阪に移住した人に会うために大阪を訪れ、和歌山出身の大阪在住者が集まる和歌山県人会のミーティングに行ったことです。そこで関心を持ったもうひとつのカテゴリーは、本宮町のふるさと会(文字通りふるさとをベースとした集まり)に参加する人々でした。ふるさと会は、本宮にゆかりのない都会の住民に地元の名産品を販売する事業で、都市部のメンバーは季節ごとに地元の食品が入った荷包みを受け取ります。これは本宮を彼らの第二の故郷にするアイデアです。この架空のふるさととのつながりを明らかにするため、本宮産の食べ物を受け取る消費者にインタビューしようと町を訪れました。これが、おそらく私の本宮での調査でおこなった、マルチサイテッドフィールドワークに一番近い経験です。
人間と動物の関係について、マルチサイテッドフィールドワークをおこなうことには可能性を感じています。例えば、肉と動物の関係というトピックでは、うまく機能しそうです。それは生産者や、おそらくハンター、中間業者、これらの製品を売る会社、そして町の消費者を考慮した、肉の流通に関するマルチサイテッド的な調査ができそうです。この種のフィールドワークが、いかにマルチサイテッドな研究になるかが想像できます。
§
合原:
肉と動物の関係の事例をあげているように、マルチサイテッドなアプローチは、サプライチェーンを追うのに適しているように思えます。例えば、アナ・チンの書籍で取り上げられたマツタケの場合では、どのようにこれらの製品が生産され、モノへと変えられ、最終的に消費者によって消費されるのかといったことが書かれています。チンは、マツタケを事例に、人間と非人間の関係を含むこれらのつながりを描くためにマルチサイテッドのアプローチを使ったのだと思います。
ナイト:
あなたの宮崎の猟師に関する調査では、マルチサイテッド・フィールドワークを採用することも考えているのですか。
§
合原:
はい。私は「ジビエ」と呼ばれる、宮崎の野生のシカとイノシシの肉の商業化についてマルチサイテッド・フィールドワークをおこなったことがあります※6。野生獣肉の商業化により、人間や猟犬の寄生虫感染について興味のある寄生虫学者などの新しいアクターが、地域社会に参加するようになったのがわかりました。この新しい展開によって、私たちは山村を超えて、実験室やレストラン、マーケティング・コンサルタントを訪れてみたりするようになりました。
日本のモンキーパーク、動物へのエサやり
合原:
近年の研究では、サルと人間の関係性に注目し、農作物被害、野生のモンキーパーク、観光へのサルの利用などを含む、幅広いトピックを扱っています。あなたは野生のモンキーパークを、霊長類学と観光の視座から考察しています。あなたは、サルと人間の関係性を考察するアプローチには霊長類学者の視点も取り入れているのですか。
ナイト:
私が教育を受けた伝統的な社会人類学は、人間に焦点があてられた人間中心的なものでした。動物が、人間環境の一部として取り扱われていたのです。
それに代えて今では、私たち人類学者は、動物を仲間の主体として見ることができます。動物たちの生きる空間は人間と重なり合いながら、共通の空間を、異なるしかたで経験している非人間の主体だといえます。人間とサル(霊長類の仲間)に関しては、世界を経験する方法や集団のメンバーとしてのふるまい方などに、似ているところや違うところが混ざっていると思われるのです。私のアプローチは、人間とサルの関係を見るのに、人間の視点だけでは十分ではないと考えています。サルの視点から人間-サル関係に着目するというやり方が重要だと考えていて、いまはそちらに移行しつつあります。
このアプローチを進めるためには、特にニホンザルの場合、日本の霊長類学者の研究にある程度精通している必要があります。霊長類学は、モンキーパークの出現に重要な役割を果たしましたが、もっと根本的なところでもサルのふるまいに対する理解を助けてくれます。そうでないとしたら、私の説明は、モンキーパークで働く従業員や観光客、またはサルから畑を守る村の人々といった、単に人間の視点からサルとの関係について描いたものでしかなくなるでしょう。
いかにして私たちがサルの視点を理解できるのかという質問がありましたね。どのようにサルの群れが機能するのかや、どのようにサルたちの間の階層や序列が機能するのか、サルがエサの周りでどのようにふるまうかを知ることは、おおむね可能です。私はエサに対するサル同士の競争に強い関心があります。ニホンザルがエサのために競争するとき、上下関係がとても重要です。これは、人がサルにエサをやるのを見たり、(私がときどきするように)エサやりをするときに明確になります。
エサやりは一対一でおこなわれるのではありません。なぜなら、近くでエサを狙う他のサルがいるためです。来園者がサルにエサをあげるとき、多くの場合は一対一の状況と考えますが、実は一対多なのです。サルは「エサを手に入れる」のを近くにいるサルとの競争として見ているのです。パークの来園者は、エサやりを通じた相互交渉について、あまりちゃんと理解していないようです。はじめは一対一の相互交渉のように見えるかもしれませんが、実際はより複雑です。霊長類学は、それを理解する手助けをしてくれます※7。
§
合原:
なるほど、人間からではなく、サルの視点からサル-人間を研究するというのは、言われてみればとても魅力的な研究方法ですね。最後に、あなたの研究の今後について聞かせていただけますか。
ナイト:
数年前にモンキーパークについての本を執筆し、モンキーパークの組織とその機能のしかたを考察しました。動物園に見られる飼育下の展示システム(captive system)と対比して、モンキーパークを展示における放し飼いシステム(open-range system)に見立てたのです※8。最近はパークの訪問者が娯楽として行うような、手渡しでのエサやりに関するの本を執筆しており、それが時間とともにどう展開してきたのか、そしていかにそれが間違った方向に進み問題となりかねないのかについて書いています。
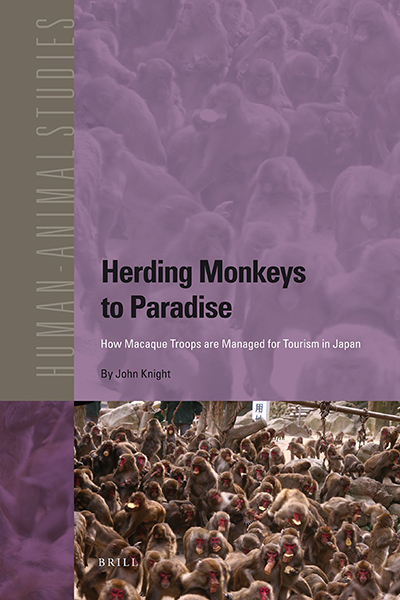
また最近は、日本における娯楽としての動物へのエサやり一般に興味があります。エサやりは日本で広くおこなわれており、道路端や庭や公園、駅前でハトや野良ネコへのエサやりが見られます。今年は日本を訪れることができていませんが、次に機会があればモンキーパークから離れ、他のさまざまな動物たちを対象にしながら、食物がやりとりされる場をより詳しく観察したいと考えています。
§
合原:
今日は、興味深い話をお聞かせいただき、ありがとうございました。
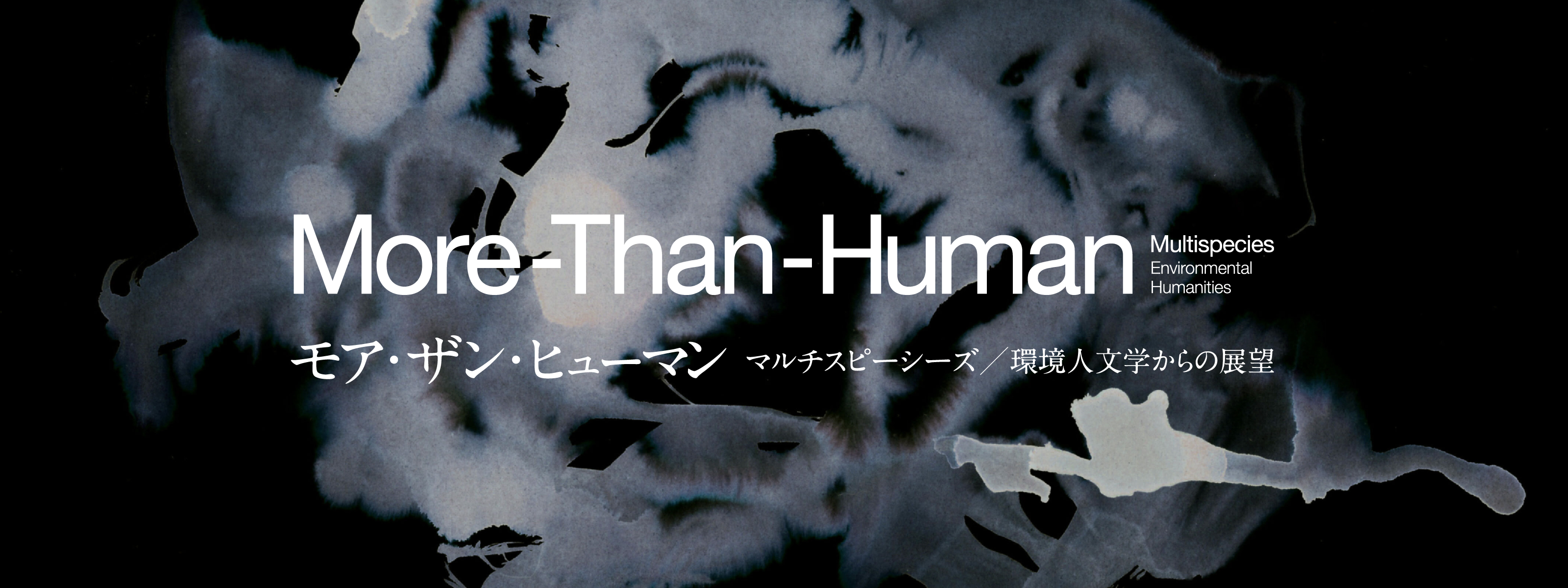
吉田真理子:
2020年に刊行されたばかりのご著書“Porkpolis※1”は、工業的な養豚業をひとつの全体として分析していて、非常に示唆に富んでいると感じました。資本主義システム下の畜産業というのは、豚の一生のあらゆる時点から利益を得るべく、きわめて特殊な人間労働を前提としている。均質な豚を集約的に生産し、高い効率性と収益性を実現するために垂直統合や標準化、独占化がおこなわれていて、その大きなプロセスの中で、労働者もまた「飼いならされて」いるように思えます。動物の身体的条件と人間の労働形態の変化を考察するアプローチはとても興味深く、マルチスピーシーズ人類学でさらに深く議論されるべき点だと思いました。まずは、ブランシェットさんが現代の資本蓄積の形態や、人間以外の種の結びつきについて考えるようになったきっかけを聞かせてください。
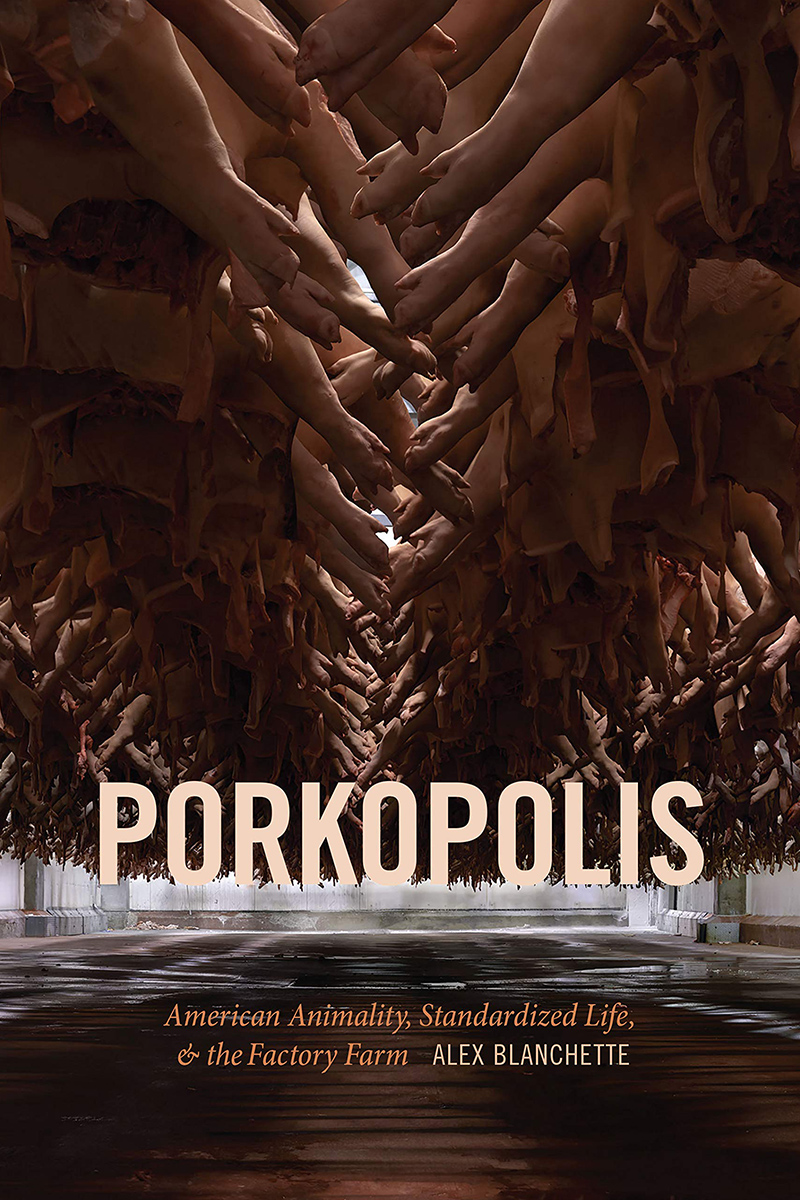
アレックス・ブランシェット:
私は、マルチスピーシーズ民族誌の問題への関心や、動物の問題への関心がきっかけでこの研究プロジェクトを始めたわけではないんです。特に調査を始めた2005年ごろは、こういったことよりも、幼少期を過ごしたオンタリオ州(カナダ)の農業地帯について考えていました。当時あの地域では、飼育する家畜の数をどんどん増やしていました。鶏は特に顕著で、豚もある程度増えていました。それで、自分が育った地域社会に何らかの形で貢献できるような論文を執筆したいと思っていました。2005年当時、工業化された農場について書かれたものというと、消費者倫理の観点からのものが多かったんです。「これを食べることは何を意味するのか?」といったような。けれど、畜産業によって変わりゆく地域社会で生きることや、工業型畜産における日々の労働を取り上げたものは比較的少なくて。家畜動物を大量生産しているところで生活し働くとはどういうことなのか考えていたんです。1年に700万頭もの豚を産ませ、育て、殺す場所とはどんなところなのか。
それである夏、車でアメリカ中を走り回り、いろんな企業を見学するうち、経営者や役員が養豚の未来について明確なビジョンを持っている拠点を見つけました。彼らにとって、産業資本主義的な哲学や目的論というのは、養豚にまつわる全てを「垂直統合」することにありました。垂直統合というのはつまり、種付け用の牡豚の飼育、繁殖畜舎、飼育畜舎、食肉処理場、後処理施設などをすべて一つの企業の傘下に収めることです。家畜の一生をより高度に管理し、より均質な豚を生み出すというのが垂直統合の目的でした。中西部やグレートプレインズを初めて訪れたとき想像していたのは、家畜の一生を科学技術によって支配する大規模な事業でした。
けれどこうした地域で生活し、仕事をするうち、実際はかなり脆弱なプロジェクトであることがわかりました。彼らは豚の身体を管理して徹底的な均一性をはかったり、新たな価値を生み出すための拠点を探したりしていましたが、なぜそうするのかと言えば、さらなる利益や成長を見込めるだけの余地が尽きた養豚業の現実に直面していたからです。豚というのは、過去150年間の工業化の対象となってきた生きものです。
そういうわけで私の本は、ある企業があらゆるものをどう強力に支配するようになったかを描いた典型的な告発、つまり企業による支配の民族誌というより、すでに極度に工業化された畜産業になんらかの成長を見出そうとする企業の試みを分析したものになりました。
個々の豚は支配され深刻な被害を受けているかもしれない。その一方で、ビジネスモデルとして工業化された豚が、ある種の主体として現れていることに気づきました。日々の仕事や生活は、資本家が豚から新しい価値を絞り出すため組織化されていました。
労働と動物の関係について言うと、工業製品としての豚の民族誌を書こうとしたんです。“Porkopolis”は一般的な豚の話ではなく、時代を超越した生物学的存在の話です。そして、「工業製品としての豚」とは、ある意味では資本主義的な人間の労働搾取と結びついた生きものを指します。賃労働をめぐる関係性のなかで不均衡に出会わされ、知覚され、生成される生物種です。そんなわけで、超工業化された存在形態を囲い込むことで生じる、人間のさまざまな主体性、意識のありよう、労働作業を考察しました。
§
吉田:
複製可能な畜産モデルをもとに工業化される動物は他にも色々ありますが、その中で豚を選んだのはなぜですか。
ブランシェット:
それにはいくつか理由があって、私は豚を、極度に工業化された最初の動物と捉えています。例えば畜牛は、少なくともアメリカでは今でも不均質な面があります。農家が所有する牛舎や牧場がまだ残っていて、牛たちは一生のほとんどを広大な牧場で過ごし、最後に飼養場に入ってから食肉処理場へ送られます。また、養鶏を現代の工業化された畜産業のモデルと見なす人もいます。けれど養鶏が工業化されたのは比較的最近で、実は1950年代に入ってからなんです。私は、最近の工業化や1980年代にあった出来事だけに因らない生物種を取り上げたいと思っていました。それはより長い時間軸で工業化されてきた動物を研究したかったからです。
もう一つの理由は、組織形態です。通常アメリカでは、養鶏業は契約ベースで組織化されています。例えば、食肉加工会社や飼料製造会社は、表向きは自営の養鶏農家と契約していたりします。一方養豚業は、半分は養鶏業と同じような契約ベースで、もう半分は、彼らの言葉を借りれば「契約を超えた」事業形態の企業体です。
私が着目したのは後者でした。こうした企業は、建物と土地のほとんどを自社保有していて、ほぼ賃労働のみで経営していました。契約している畜産農家はほんの一部で、実質的には畜産家を必要としていません。調査当初、私は、初歩的ながら一筋縄ではいかない問題意識を持っていました。「工業型畜産」の「工業」とは何か。また「産業化された養豚」の「産業」とは何かという問いです。私が取材した企業は、資本主義の本質について明解な哲学を持っているように見えました。なかでも、自社の事業を、産業主義のいわゆる発展史的段階を通過していると捉えている経営者がいました。請負契約やもっと古い家庭内労働の「出力」システムを、工場生産や垂直統合、直接所有へと変えていった産業は数多くありますが、こうした産業を踏襲していると考えていたんです。
2010年代初頭、豚という生物種は、いわゆる「工業型」畜産のプロセスを検討するにあたって、最も興味をそそられる対象でした。世界中で畜産というものが垂直統合された企業によって次々営まれるようになっていたので、タイムリーなプロジェクトでした。しかし、蓋を開けてみると不思議なほど時代に即していない。ポスト工業化時代のアメリカにいるのに、地方では強い意志を持って工業化がおこなわれているんです。
§
吉田:
豚の一生を通して、工業型畜産が再編成しているのは人間社会だけではない。飼料工場、遺伝資源センター、養豚場、食肉処理場、ペットフード工場、豚骨の粉砕施設といった「ドムス」と人間・非人間の関係性も組み替えているということですね。ブランシェットさんは、経営者から日本の製造業の理論に関する講義を受けたそうですね。現代のアメリカの養豚産業が、第二次世界大戦後の日本の生産システムをベースにした垂直統合モデルとして構造化されている点に衝撃を受けました。
ブランシェット:
私も驚きました。アメリカでは特に、これらの企業に取材するのは難しくて。何でもかんでも社外秘にするわけではないにせよ、多くの企業は大体慎重になります。ですからひたすら正直に、自分が何を調査しているのか伝えました。私が初めに関心をもったのは、「工業型畜産」において「工業的」であるとはどういうことかという点でした。アメリカでは、「工業型畜産」という言葉は否定的に捉えられます。通常は軽蔑を込めて使われる言葉なので、この問い自体、相手を動揺させるだろうと思っていました。しかし、驚いたことに、役員や経営者と話すと、「我々もその問いに興味があります」と言うんです。興味、と言っても明らかに私とは違う意味での興味でしたけど。彼らが何をしていたかと言うと、統計やリーン生産方式、品質改善モデルなどを従業員や経営者に講義していたんです。
製造業理論の授業を一緒に受講するうち、研修の目的がわかってきました。まず第一に、動物種を垂直統合することの複雑さを理解するということです。豚が一生を通して通過する作業場ひとつひとつに、個別の歴史、文化、物質的な労働プロセスがあります。食肉処理場の工業化の歴史は、1860年代にシンシナティで始まりました。一方、農場における専業化と工業化が押し進められるようになったのは、かなり最近の話です。食肉加工の町で生まれ育ち、地元経営幹部としての地位を築いた人間は、地方の農場で動物に囲まれる生活をしていた人間とは全く異なります。また、母豚に人工授精をするという行為プロセスそのものは、フォード主義的な解体ラインに沿って一日に1万9000頭の豚を処理する行為と根本的に異なります。ですから、研修の目的は、まず第一に、異なる背景をもった者同士がお互いをよく知るための場を提供することでした。あるCEOは、「私たちは豚を統合したが、次は人を統合しなければならない」と話していました。また、研修には、母豚の授精、豚の出産、ハムのスライスといった特殊なタスクから、定量的な共通言語を取り出すという目的もありました。
また当時(2000年代初頭)、このような事業が目指す輸出の割合は、私の想像をはるかに超えていました。彼らは、できるだけ多くの豚肉をアメリカ国外、特に日本と韓国に輸出しようとしていました。これらの国々の卸売業者は、高品質の豚肉をより高価格で買い付けます。一部の企業は、すでに高価値をつけられた豚からさらに価値を生み出すために、より多くの肉の部位を見つけることに熱心になっていました。第二次世界大戦後の製造原理の知識を身に着け、多くを語ることができたら、世界中の卸売業者とより良いコミュニケーションがとれ、卸売業者のみが持つ特有言語を体得できると考える人もいました。
もう一点補足すると、これらの研修授業は品質向上クラスと呼ばれています。経営者の言う「品質」とは、生産過程で生じる不均質さが減るということです。豚を生産するための労働プロセスや周辺環境、豚に与えるものの変数が減ることで、より均質な肉質になることを目指しているんです。品質とは均一性のことであり、世界の卸売業者がブランド化において最も重視している点です。
研修では、21世紀初頭における生きものの工業化が何を意味するのか観察できて、興味深かったです。自動車工場で生まれた認識論を取り上げながら、その理論を今度は生物学的な存在の生成にあてはめていくということがおこなわれていました。しかしこれはあくまでも研修です。時間をかけて豚を均質化していくことは、経営者の研修だけで達成できるものではありません。繁殖のための遺伝子設計や飼料ペレットの生産、そして、種付け用の牡豚、牝豚、子豚、死骸など、様々な豚に対する振る舞いに至るまで、豚の生死サイクルのあらゆる段階で新しい管理とエンジニアリングが求められます。

均質な豚肉をつくる
吉田:
現代の日本の養豚業は輸入豚の3割近くを米国に頼っており、世界的な物流インフラに大きく依存しています。国内の飼料産業も輸入の飼料原料なくして成り立ちません。日本のバイヤーは、より高い収益性を得るために仕入れを拡大し、日本ではなく米国で加工費を支払ったり、付加価値のある製品を入荷したりしています。“Porkopolis”では、バイヤーと販売者がカットの種類だけでなく、特定の風味を出すための豚の太り具合も指示している点を指摘されていますね。色味や水分保持量、寿命が、品質を維持する上で非常に重要であるという点も興味深いです。国境を超えた分業形態を特徴とするグローバル物流は、均質な豚肉づくりにどう関係しているのでしょうか。物流が多様化する中で、人間の労働はどのような形をとっているのでしょうか。
ブランシェット:
これらの企業がどのように、時とともに均質化してゆく動物の飼育と食肉加工を実現しようとしているかという質問ですね。経営者が豚のライフサイクルを標準化し、自分たちや従業員をも標準化した生活に組み込んでいるのを間近で見て、現代の工業型畜産に関する理解が覆されました。はじめに立てていた仮説というのは、自動化が進み、テクノロジー主導で景観や動物の生活が支配されるにつれ、人間の労働力に依存する部分が少なくなるというものでした。工業化の過程で賃金労働者が減っていくという典型的なストーリーです。しかし、豚が室温管理された屋内で、自動給餌機などを使って飼育されている反面、人間の膨大な労働力が必要とされていました。もっと均質な豚を作るためにはもっと多くの人手が必要です。少なくとも、豚が生まれてから死ぬまで、より多様な作業や介入が必要になってきます。
高度に工業化された食肉処理場は、COVID-19のウイルス感染の温床として広く知られるようになりましたが、ここでも、2,500人もの人々がベルトコンベアに沿って働いています。動物の身体や筋肉に個体差があるので、何千人もの労働者が同じ動きをして、腱や脂肪の割合が異なる動物ひとつひとつをその場で調整しながら均一に切り分ける必要があります。全ての豚の体重を生後6ヶ月できっちり285ポンドにするには、信じられないほどの集約型労働が求められます。豚の生死のサイクルを通して、労働プロセスが介入する部分は次々に発見され、増えているのです。ある意味、生きものの標準化というのは、人間の労働が豚の存在そのものにさらに深く介入できるよう、豚を解体して再構築することかもしれません。つまり、豚そのものを、より多くの労働力を生み出すための肉の土壌のようなものに変えてしまう。感染症が個体間で伝染しないよう勤務時間外の行動を監視することから、豚の表皮に特化した新しい労働、人工授精、さまざまな薬の投与、屠殺して、豚をより細かく分解することまで、全てが含まれます。工業製品としての豚が今まで以上に労働力を必要としているのは明白です。
§
吉田:
商品化の過程で、個々が質的に変質することなく、継続的に拡大していくシステマティックな事業形態をとっているというのはとても興味深いです。一例として、1,000以上の商品コードをもつバーコードのインフォマティクスを取り上げていますね。また、経営者が生物種を定量的に再生産する装置として「群れ(the Herd)」を定義づけ、豚の品種が統計的に導き出された生命の単位に変わる様を分析されているのも示唆に富んでいました。こうした拡張は日本の養豚業でも見られます。例えば「三元豚(3品種の豚の交配種)」や「四元豚(4品種の豚の交配種)」のような交雑豚生産から資本主義的な価値が引き出され、日本の高級豚肉ブランドの基礎を築いてきました。標準化された豚の一生は、アナ・チン※2の言う「スケーラビリティ」の文脈の中でさらに議論できるでしょうか。工業製品としての豚肉を、拡張性のあるスケーラブルなプロジェクトとして捉えることについてどう考えますか。
ブランシェット:
こうした事業の設計者にとって、「スケーラビリティ」の実現は理想的、あるいは幻想のようなものだと言えます。スケーラビリティとは、1頭の豚を生産することと700万頭の豚を生産することに違いがないという意味だと理解していますが、そうしたスケーラビリティはぜひとも実現したいでしょう。しかし実際には非常に困難で、常に失敗しているように見えました。例えば、豚の生産を年間600万頭から年間700万頭に増やすということは、労働プロセス(殺処分のスピード向上など)と生態系(豚の感染症の増加など)の両方を変えることを意味しています。にもかかわらず、多くの点で、これらの事業はスケーラビリティ、あるいは私が「総体の生成(totality-making)」と呼ぶ概念を前提としています。より多くの豚肉を無限に作ろうとしているんです。無限に標準化でき、無限に多くの製品を生み出せる動物です。おっしゃる通り、豚から生み出される製品には現在1,100個のプロダクトコードがあり、さらにもう数百個のプロダクトコードが生み出される未来が予測されています。これらは実験テストの領域のようなものかもしれません。より多くの豚の体の部品を作るだけでなく、モジュラーモデルを開発しようとしています。世界中で、特に南米や東欧のような穀物価格の安い地域で簡単に再現できるモデルです。実現はまだ先ですが、こうした事業は実際に販売される豚肉だけでなく、このような事業を世界中で再現するための投機的な未来にも収益性を見込んでいます。
一方で、実際のところそういったモデルは常に失敗しています。私が考察したかったのは、家畜の集約性を維持すべく人間や人間社会が追求する、継続的かつ終わりのない変容です。企業は、工業製品としての豚肉を生み出すインプットとなる、エンジニアリング的な人間の存在形態に着目しなければならないことを認識しています。豚そのものではなく。これも、豚の群れを維持し拡大し続けるためです。親族関係、男女関係、人種関係、階級関係など、日常的なことが改めて問われるようになっています。高齢化が進んだり、地域の農村生態系に感染症が蔓延するにつれ、肉体的な人体を持つことの意味さえも産業システムの問題点として認識されるようになっています。調査中、完全にはそれを理解できていなかったのですが、最終的には養豚そのものの解明ではなく、豚の集約にこれまで以上に対応できるよう人間の組織形態を作り直す試みに焦点を当てました。

知覚する生物種
吉田:
あなたは、サラ・ベスキーとの共編著“How Nature Works: Rethinking Labor on a Troubled Planet※3”で、サプライチェーン資本主義を、労働者が同じやり方でおこなう反復作業と、集合的な暗黙知(刺激による牝豚の発情誘起など)双方を伴うものとして位置付けていますね。人間と豚をめぐるこうした単調な生産労働は、豚の意識や知覚をどうコントロールしているのでしょうか。
ブランシェット:
“How Nature Works”では、公に語られる工業型畜産を批判検討するのが目的でした。誰も観ない深夜帯に放映される養豚システムの告発番組などは、非常に限定的な視点しか提供していません。人の手による作業がほとんどなく、機械がほとんどやってくれて、人間と接触せずに機械の中を通過していく存在として豚が描かれるので、退屈で単調なものに見えるかもしれません。
しかし実際には、豚の体重が45kgを超えるような成長期を除いて、すべての業務に人間の労働が介在しています。私が調査した企業では、豚の飼育・繁殖をおこなう畜舎に約2,000人の従業員がいました。論文で考察したのは、豚が信じられないほど単調な生活をしていて、その単調さが彼らの体にはっきりと表れている、という点でした。妊娠した豚は、飼育箱の中に一日中横たわっているので床ずれを起こします。逆説的かもしれませんがここで重要なのは、非常に単調な存在が多大な労働に裏打ちされているということです。それに気付いたのは、第6繁殖畜舎と呼ばれる、人工授精と子豚を出産する豚舎で仕事していたときでした。よく同僚から、豚の前でどう振る舞うべきか教わっていたんですが、あるとき、牝豚を犬や猫を撫でるような手つきで撫でてみたんです。それが私の知っている、動物に対する振る舞いでした。すると同僚が大声で「豚に触らないで!」と。個体に注意を払うといういつもと違う振る舞いが、牝豚を動揺させ、興奮させる危険性があったんです。豚はケージの中で暮らしていますから、そういうことが起きると流産に繋がる可能性もありました。
また、勤務中ずっと豚に見られていたのを鮮明に覚えている労働者もいました。豚たちは常に彼らの身体を解釈しようとしていたそうです。そこで私は、アグリビジネス業界の雑誌で、豚がどのように色や音、人間行動を認識し、それらが産仔数や豚の「出来高」にどのような影響を与えるのか、といったことに関する情報や研究論文を読むようになりました。そして、単一のタスク、例えば発情や代謝だけをおこなう豚の労働に関わるとき、労働者は自分の身体や振る舞いが動物にとって意味のあるサインを出している可能性に注意を払わなければなりません。均質に育てられた豚の周りで均質な行動をとろうとする労働者を観察していると、豚の感受性自体が労働者の振る舞いの生成に関わっているような感覚がありました。工業化が進むにつれ、免疫系やホルモン系、神経系に至るまで、人間労働の対象として扱われる動物が多面化していくのがわかりました。
もう一つ重要なのが、アメリカで家畜産業は、しばしば非熟練の「肉体労働」として語られます。反復的で、単調な労働が多いというのがその理由です。私の担当業務のひとつに、人工授精のため母豚の背中に一日中座り続けるというものもありました。けれどそのシステムを支える労働者の専門知識にも注意を払う必要があります。実際、養豚場では、動物のライフサイクルに関するさまざまな深い知識が求められます。例えば、40万頭の出産に立ち会って初めて身に着くような、子豚を正しく取り扱うための技術。これは非常に脆弱な養豚システムを支えている知識の一つです。
§
吉田:
豚の知覚に関して言語化されない専門知識が、ある部門から別の部門の季節労働者へと伝搬されることはありますか。管理職がそうした知識を、入ったばかりの労働者に教えることはあるのでしょうか。
ブランシェット:
はい。私に仕事を教えてくれたのは、グアテマラシティからアメリカのグレートプレインズに移住してきた人でした。彼は長年豚の畜舎で働いた後、最終的に下級の管理職のポジションに就いていました。いろんなことをよく知っていて、他の同僚も知識の宝庫でしたね。養豚場や食肉処理場で働く労働者は入れ替わりが激しく、多くが勤続1年未満だったりするのですが、驚いたことに、養豚場で一緒に働いた同僚の多くが、過去10年間で他の豚肉製造企業で働いたことがありました。中西部全域の工業型畜舎で働いたことがある友人もいました。彼らは多くの企業で働いていたので、いろいろなコツややり方を身につけていました。
一方で、上級管理職は生身の豚と関わりを持ちません。確率や統計、モデル化といったレベルで、18万頭の母豚の出産や、700万頭の豚の生産増大に注力しているからです。あまり一般化したくはないですが、どのようにしてプロセスを実行するかという知識が、従業員の入れ替わりを超えて伝播され、磨かれ、翻訳されているように感じました。
工業型の動物性とは
吉田:
ディクソンで調査されていた当時、2000年代半ばのアメリカの大不況とその他の社会経済的な落ち込みが、労働者のダイナミクスに影響を与えていたと思います。分業によって労働者同士が隔てられているどころか、経営者が労働者の顔を見ることすらできないバイオセキュリティゾーンの特性も興味深いです。豚の生命世界に関する経営者の知識と、労働者の日常知識との間には、対照的なギャップがあるように思います。
ブランシェット:
管理者と労働者の間にある産業階級的な隔たりは決して単純なものではありません。それだけでなく、動物や畜産に関する経験も根本的に異なります。垂直統合されたシステムでは、「労働者」と呼ばれる人たちは、動物のある一面だけに特化した作業に従事する傾向があります。豚の感染症がある場所から他の場所に広がることが懸念されるような、バイオセキュリティの問題もあって、基本的に異なる作業場を労働者が行き来することはあまりありません。本の中で、一緒に働いていた女性の同僚について触れていますが、彼女は子豚の扱いには非常に慣れている一方、屠殺場に足を踏み入れたことは一度もなくて。おそらく、生後21日以上の子豚を見ることもないと思います。牝豚の生殖本能を刺激する方法について、実地経験にもとづいた知識を持っている労働者もいましたが、屠殺場や、種雄の精液が抽出される場所で働いたことはおそらくないはずです。つまり、人間と豚との親密な関わりがあったとしても、あくまで緻密な分業の発展を前提とした資本主義的な親密さです。
対照的に、管理職の人たちは豚の生死のサイクル全体を改善しようとします。彼らの業務が対象にしているのは、豚の精液から1,100種類の製品までの全てです。彼らが向き合っているのは、私が思い浮かべるような、畜舎で寝そべっている個々の動物ではなく、家畜なんです。給餌や地域の天候パターンは、消費肉になる豚の構成要素であり、影響を与えるものとして捉えることができます。また、彼らは、先ほどお話しした製造理論も含めて、動物の繁殖、出産、飼育、屠殺という全く異なる行為を一つのプロセスとして捉えるための認識論を開発しようとしています。個々の動物ではなく、垂直統合された豚をモデル化していると言えます。
§
吉田:
「資本新世(Capitalocene)」において、そのような親密さを検討することは非常に重要ですね。そのような資本主義的な親密さをもって、彼らは生産サイクル全体を組み立てラインのように捉えているんですね。最近のインタビュー※4の中で、ブランシェットさんが「現代の豚肉生産の現場は、人間中心でも豚肉中心でもなく、むしろ資本中心である」と指摘されていた理由が今なら理解できます。
ブランシェット:
そうですね。私は「人間中心」という言葉が好きではありません。ある種の画一化された人間性の名の下に、生態系や種の支配を暗示した言葉のように思えるからです。工業型畜産は、異なる種の間の搾取と同一種の間の搾取が同時におこなわれている場として見る方が良いと思います。そこでは、人間の労働者を搾取する余地を生み出し続けるように豚が形作られています。逆に言えば、私がいた地域は、動物の繁殖を最大化し、屠畜のスピードを加速させるために組織された企業街のようなものでしたが、「豚中心」とは到底言えません。あくまで資本主義的畜産の中で生産性の増大をはかる場所にすぎません。新しいモデルや指標、品種を生み続けながら、常に収益性を高めていくのです。
§
吉田:
東京の豊洲市場でも、連動した株式所有、高度に管理された売場、整備された競売システムという形で垂直統合が採用されています。しかし、垂直統合されたネットワークの中での分業を見ると、養豚業とは大きく異なるように思います。仲卸業者は、特定の業界ギルド内での家族経営が基本です。仲買人は特定の魚種と関連する専門分野の仕事に割り当てられます。卸会社の社員も、特定の魚種に特化した訓練を受けていることがほとんどです。この違いは、労働者が特定の経済的ニッチを支配しているかどうかの違いと捉えることができるかもしれません。
ブランシェット:
そうですね、畜牛に関しても似たようなことが言えるかもしれません。養豚場で一緒に働いていた同僚の多くは、牧場や肉牛の肥育場で働きたいと考えていましたし、実際そういう業務の方が給料が高いんです。しかし人種差別的な背景から、グアテマラやメキシコ出身の人々に開かれた雇用形態は、養豚場での仕事だけでした。たとえそれまでメキシコ北部の牧場で働いていたり、似たような就労経験があったとしてもです。牛は歴史が深く、昔から貴重な労働力とされている文化的にも経済的にも重要な生きものでした。この点では、豚と牛という異なる種の間に、人種階級的なヒエラルキーがあったように思います。私には、ある動物種が別の動物種よりも多くの技術や専門性、知識を必要とするとは思えません。にもかかわらず、異なる動物種の間で人種的な分業が正当化されていました。

§
吉田:
あなたは、“Porkpolis”の中で、ポスト人間中心主義的なバイオセキュリティについて、以下のように指摘されていますね。
家畜動物を屋内に閉じ込めること自体は、他の生物との予期せぬ接触(例えば人獣共通感染症の病原体の宿主になりやすい野生のガチョウなど)によるウイルス感染を避けるため正当化されることがある。一方、生きものを工業化することに注力してきたこの地帯は、それが生み出す予測不可能なリズムがいかにして豚の感染症に巻き込まれているのかを示している。もはや人間社会は豚の感染症をため込む「貯蔵庫」の中核なのだ。
私はコロナウイルスを含む人獣共通感染症について、これと似たようなことを考えていたんです。新自由主義的な資本主義社会において、気候危機の問題は同じ生産モードに起因しています。また、自然の過剰搾取によって、人間と人獣共通感染症の宿主動物の接触や近接性が問題視されていますよね。つまり私たちは、社会全体に跳ね返ってくる新たなリスクに身をさらしているわけです。そう考えると、本の最後で脱工業化を指向されているのが非常に興味深いです。脱工業化という概念は、人間と人間以外の生物社会をどのように定義し直していると思いますか。
ブランシェット:
その読み方は素晴らしいですね。アメリカでも、他の社会でも、私たちが期待するほど脱工業化が進んでいないというのが現実です。今日のアメリカで、工業セクターに就く人が少なくなってきているのは事実ですが、一方である地域では超工業化が進んでいます。5,000人もの人々が年間70億頭もの家畜の生産に携わっている。つまり、ほとんど前例がないほどの過度な生産性を獲得しているということを意味します。現在、私たちの日常生活にかかわるほぼ全てのものが、工業化された生産過程から生まれています。気候パターン、水運、航空なども、より工業化されています。製造業の従事人口が減っていたとしても、現実の生活は工業的な労働力によって媒介され続けている。ひょっとすると、1920年代や1950年代よりもさらに過度に工業化されているかもしれません。
現代のアメリカの農業について考えるとき、「工業化」というと、化石燃料や機械の多用だったり、大規模生産を指しがちです。でも私は、産業資本主義の観点から工業化(と脱工業化)について考えています。産業資本主義とは、人間労働に対して不均衡なほど多大な社会的、集団的価値を置き、労働力を搾取するための新たな場所を開発し続ける時代です。豚がその最たる例です。豚という動物は、150年に及ぶ複合資本主義的なエンジニアリングを内包しているのです。1頭の豚から、何百種類、何千種類もの製品が生み出されます。豚は、労働によって膨大な数の製品に形作られ、知られ、接触される動物でもあります。調査を経て、私は脱工業化を、意識的で、野心的で、最終的にはポジティブな方向性を見出すプロジェクトとして、どう捉え直すべきか考えるようになりました。今私たちが一丸となって達成しようとしているテーマだと思います。労働者の追放ではなく、共同体としての急進的な政治目標を意味するものです。労働を減らし、労働の対象とするものを減らすこと。社会貢献と言ったときに、生産性や効率性を軸に考えないこと。むやみに働かせず、生産プロセスを非効率にさせておくことに価値を見出すこと。労働を介してではない方法で、豚やその他無数の生きものと関わり合うこと。それがこの本の結論ですが、今後も私が取り組むテーマです。
現在、シカゴのユニオンストックヤードが残した影響、廃墟、遺構についての長期調査を進めています。この食肉加工場は1860年代から1940年代にかけて、現代の私たちがイメージするようなアメリカの産業主義の多くの面を生み出しました。例えば、ヘンリー・フォードは、自動車の組み立てラインのアイデアをこの食肉加工の解体ラインから得たようです。今、シカゴの16ヶ所を調査中ですが、住民はこの閉鎖された食肉処理システムを社会的にも生態学的にも継承することが何を意味するのか、すべてを過去の遺物にすることが何を意味するのかを考えているようです。引き続き現場の人々と一緒に、「真の意味でのポスト工業化、脱工業化の瞬間に到達した」と言えるのはどういうことなのかを理解したいと思っています。脱工業化をめぐる集団的実践とは何なのか考えていきたいですね。
§
吉田:
シカゴの労働組合のストックヤードに関する調査プロジェクト、おもしろそうですね。おっしゃるように、モノを生産することを中断する、というのはある意味能動的かつ再帰的な実践と言えます。この点を念頭に置いた上で、〈自然〉を過剰に酷使する中で何が生まれているのかを深く考える必要がありますね。私たちの〈自然〉との関係の再考にも繋がりそうです。興味深いお話を聞かせていただき、どうもありがとうございました。
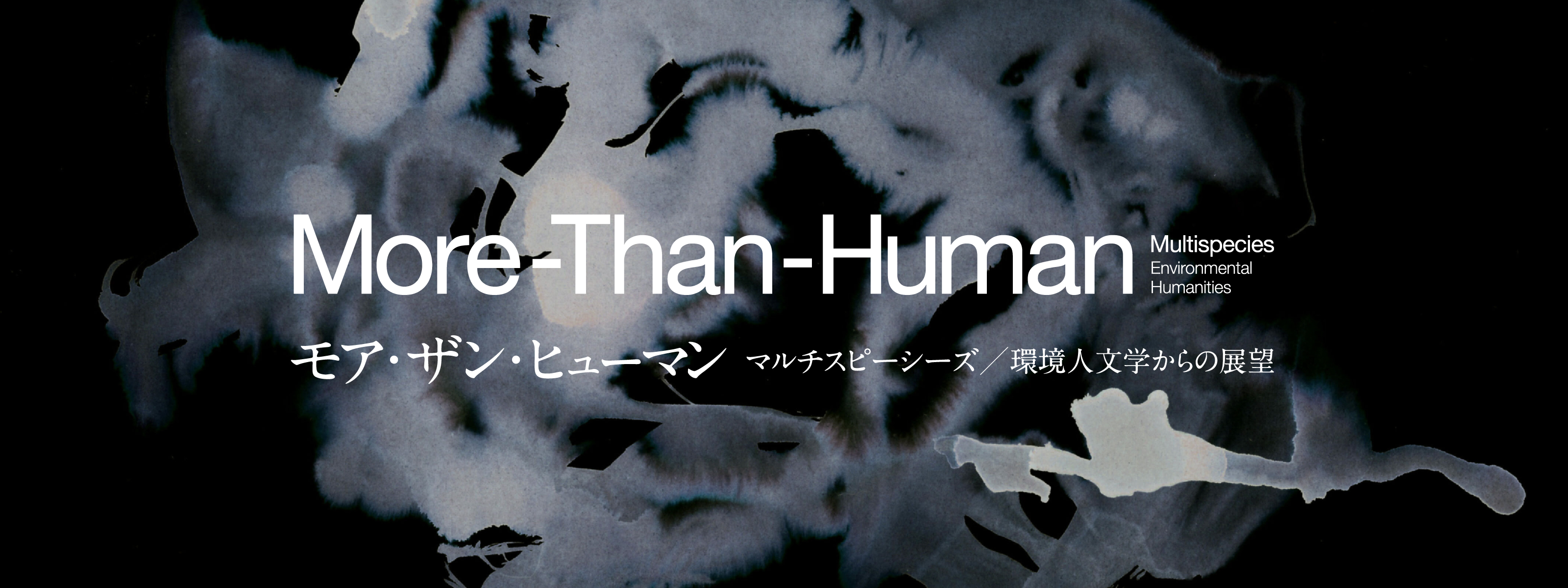
——— 上野さんが出版された本『オブジェクト指向UIデザイン※1』は、体裁が実用書という形で、副題には「使いやすいソフトウェアの原理」とあって、そしてユーザーインターフェース(UI)の「操作性と開発効率の劇的な向上」と書かれています。なので、基本的にはUIデザイナーの人たちに向けた実用マニュアルみたいなもので、そこをメインターゲットとして想定しているんでしょうか。
上野:
これは技術評論社という出版社の一連のシリーズなんです。もともとコンピューター関係の技術本を出してるので、想定読者としてはコンピューター技術者ですね。たぶんこのシリーズで初めてのデザインに関する本なんですが、技術者向けの枠組みでデザインについて書いています。担当編集者の方には、前から雑誌記事でお世話になっていて、僕がどういうことを書くのかよくわかっていたので、かなり好きなことを書かせてもらいました。
§
——— ただこの「オブジェクト指向」という概念は、UIデザインという意味を超えて、そもそも「人間にとって道具とはどういうものか」とか、あるいは「デザインってそもそも何なんだろう」といった、非常に拡張性の高い問題まで広がっていくコンセプトになっていると思うんですね。なので、まずは書かれている内容を簡単におさらいをして、その上でオブジェクト指向という概念が上野さんからどのように出てきたのかを聞いていきたいと思っています。
結構多くのページを占められているのが実践演習で、実用書という体裁を保っているとは思うんですけど、「はじめに」とか「おわりに」とか、後半の「オブジェクト指向UIのフィロソフィー」では、かなり抽象度が高い話も交えてますよね。
上野:
最初はプログラミング教本みたいにノウハウだけが書かれた体裁にしようと思ってたんです。「まずこの文字を打ってください。それから次にこれをしてください。この通りにやれば誰でもできますよ」みたいな。だけど、今回「ワークアウト」と呼んでいるところを書いていたら、もうすこし説明がないとわかんないよねと思ってきて、そしたら公理系のメモがどんどん増えていき、半分ぐらいになってしまいました。
§
——— 逆に言うと、上野さんはもともと公理系が身体化されていて、実践ではその場の課題に合わせて公理系を導きながらお仕事されてるんですよね。要するに、マニュアルが先行してあるわけではないと思うのですが。
上野:
そうですね。自分がやってることをメソッド化しながら書きました。もちろん人それぞれで勝手にやっていいし、いろんなやり方があるんだけど、その背景にある考え方は、自分のなかで確たるものがある。そこをあえてメソッドにして一存をまとめてみました。
§
——— そういうことですよね。では内容に入っていきながら、その辺の背景にある思考のコアコンセプトが、上野さんのなかでどうできあがってきたのかを、徐々にお聞きしていきたいと思います。
まず大前提として、多くのUIが非常に使いづらいと言われます。それは利便性を損なっているだけではなくて、使う人から創造的な試行錯誤の機会をあらかじめ奪っている。つまり、使う人間がある種の疎外感を持っているというのが、電子機器に接する多くの人の印象なんじゃないかと思うんです。この問題については、本の「はじめに」でオブジェクト指向とタスク指向を概念として対比しながら論じられています。
すごく単純化すると、多くのUIが使いづらいのはタスク指向で作られてるからだってことだと思います。タスク指向は、ゴールをあらかじめ想定して、そこに向けて最適化しているデザインであり、その最適化されたライン以外の道をすべて排除することによって成り立っている。それが使いづらさを生んでいるんじゃないかってことですよね。
このように、そもそもいろんなUIがタスク指向で設計されてきた要因を、上野さんはどのように考えられてますか。
上野:
タスク指向については、おっしゃるとおりですね。本の「はじめに」で石器の写真が出てきます。実はこの写真の使用許諾を得るのが結構大変だったんですけど、ここに石器を載せた理由は、この本が「道具論」であるという導入にしたかったからなんです。
道具を作ったり使ったりするというのは、人間の根本的な営みです。そして道具は、われわれが世界とインタラクトするインターフェースでもある。パソコンが普及して、さらにスマホやクラウド系のサービスが生活のなかに浸透して、使ってる時間も長くなっています。そういったものとネイティブに接している世代からすれば、ソフトウェアのバーチャルな世界とリアルな世界は区別がないと思うんですよ。そうすると、ソフトウェアのインターフェースは世界のインターフェースであるとも言える。だから、そのあり方を考えるのはデザイナーとして重要だし、人間としても重要なんじゃないかってことですね。これはUIデザインやソフトウェア開発といった特定のジャンルというより、もっと普遍的なテーマだと感じていました。
そのなかで問題になっているのが、先ほど指摘されたようにコンピューターのデザインがタスク指向になっていることです。自分なりにその要因を考えると、もともとコンピューターは高速に計算をする機械として便利だから、ということになります。コンピューターに高速に計算をさせるために、そのプロセスやロジックを教えるプログラミングをする。そうすると、人がやっていたら何人も必要で長時間かからないと終わらないことを、ものすごく高速におこなうことができる。つまり、長いプロセスをコンピューターに埋め込むことで、たくさんのステップを自動的に実行するという考え方が先行してあると思うんです。
その発想だと、コンピューターにやらせる計算は、目的に向かって線形化して正規化してプログラミングをするというプロセスになってしまいます。コンピューター以前からそうかもしれないですけど、自動化というのは機械を使って機械化することなんです。そして、次に複数のプロセスを連続的に走らせる。なので、コンピューターでシステムを作るときは、どうしても線形化したタスクを実行するという固定観念になってしまいます。今も業務系のシステムは、そっちの方が多いと思います。
だけど、それはわれわれの世界の認識のしかたや物の考え方と違う。それに気がついた天才的なコンピューター科学者たちが、オブジェクティブに操作できるコンピューターを作れないか考え始めた。60年代に始まって、70年代から80年代と研究してきた人たちがいて、今のコンピューターやスマホみたいなグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)ができました。
§
——— そもそもの開発プロセスが、タスク指向と親和性が高いってことですよね。もしかすると「はじめに」で書かれていることに、もうひとつの観点があるのかもしれないと思いました。
顕在化した課題に対する即物的な解消手段として狭く捉えること。システムの全体性を軽視して部分最適化を偏重すること。テクノロジーにのって人々の射幸心を狡猾に刺激し、その行動を支配して盲目的な消費欲を増幅させること。権力者の要求に合わせてその他の人々を一方的なタスクに従属させること※2。
ここに書かれているようなUIは、市場構造みたいなものを背景にした要請とも言えるんじゃないかと思います。「人々の射幸心を狡猾に刺激する」と書かれているところは、ユーザーに物を買ってほしいとかサービスに契約してほしいといった、事業者の強い動機が反映されたゲームの課金システムやランディングページを思い出させます。こうした動機は、市場としては当然のことなんですけど、その実現手段としてユーザーにこう動いてほしいという前提で、多様性を与えないように作られてるものが多い気がします。費用対効果を計算して、それに最適化するデザインが優秀と言われるような環境ですね。
オブジェクト指向UIデザインという考え方は、こうした市場の要請自体を根本的に変革していこうという視点を孕んでいるような気がします。つまり、アテンションエコノミーと言われるような市場性に最適化されたデザインに対して、どうにか変革していこうという意図もあったりするんでしょうか。
上野:
資本主義システムに駆動されたコンピュータテクノロジーが急速に発展して、ビジネスはとても狡猾になっています。それがアテンションエコノミーやインテンションエコノミーといった言葉であり、行動経済学的な考え方ではないかと思います。そこでおこなわれているのは、「人はこういったものにこう反応する」というパターンラーニングで、そのパターンマッチングによるデザインです。そうなると、われわれのようなユーザーは、自由意志で行動してるようで実はコントロールされてる。泥臭い話なんですが、それに危機感を感じています。
しかし、コンピューターやデザインの歴史において、オブジェクト指向やGUIは、リベラリズムに根ざしてきました。一部の特権的な人が持っていたコンピューティングパワーを開放して、自分たちで作ったり使ったりできるようにしようという考え方です。その観点だと、デザイナーは事業側が持っているテクノロジーの使い方を監視する役割を持つべきとも言えます。それを「はじめに」のところですこし書きました。
§
——— デザイナーだと、事業者がクライアントでお金をもらうという事情もあるので、そこに抵抗するのはなかなか難しいと思うんですね。ただ事業者にとっても、ユーザーフレンドリーな環境を作った方が利益性が高い。それを考えると、このオブジェクト指向UIデザインはものすごくアクチュアリティの高い手法という印象がありますが、それを実践のなかで感じるようなことはありますか。
上野:
デザインの受発注関係では、事業者が欲しいと思っているものを作って対価を得ている構造があるので、それに反した行為はあまり意味がない。だけど、今言われたとおり、事業者も実際ユーザーにとって意味が感じられないものを作ってもどうしようもない。じゃあ何をすればいいのかというと、事業者から何か頼まれて作るというより、事業とは直接関係のない部分で、デザイン行為として本来いいものを提案していくことになります。
その提案というのは、事業者に対する提案でありながら、ユーザーに対する提案でもあるんです。この本で何度も書いた「ユーザーに合わせたものではなく、ユーザーが合わせられるものを作りましょう」という話です。ユーザー自身は、自分たちが何が欲しいのか言語化できないので、デザイナーから事業者や市場を通じて「こういうものはどうですか」と、ユーザーに提案する形になっていくべきじゃないかと思います。
§
——— この本の「はじめに」でも、「業務の形骸を暴き、それを創造の場にリフレームする※3」と表現されてましたね。ただ事業者はどういうものを作ればいいのか、何の確信もない状態だと思うんです。それをユーザーに聞こうとするんだけど、ユーザー自身も自分が何をしたいのか答えを持っていない。だから、デザイナーがある確信を持って、両者を啓蒙していくポジションにいるべきなのかもしれません。
さて次に聞きたいのが、オブジェクト指向UIの「ユーザーを対象に直接的にアプローチできるようにする」という定義についてです。これをより細かくしたのが次の4つになります。
- 人々をそれぞれの目当てに接続すること。
- ユーザーが自分なりの方法で目的に向かっていけること。
- 行動の可能性を解放し、その道具を使うことで仕事や遊びに対する自身の意味空間を創造できるようにすること。
- 思弁性をもって潜在的な課題に取り組み、道理をわきまえ、異なる視点を得られるようにすること※4。
これは「道具」全般の話として聞けました。ハンマーは釘を打つのに使われる道具だけど、たとえば泥棒が来たら防犯対策にもなる。つまり、ハンマーを使う人は、その形状からいろんな使い方を導き出すことができる。釘を打つという行為ひとつを見ても、大工のようにエレガントな技術レベルで打つ人もいれば、うまく打てない子供もいます。
これはあらゆる道具に言えることで、たとえばギターが一本あれば、それでどんな音楽を作るかは無限にバリエーションが考えられるわけですよね。オブジェクト指向の前提として、何か道具があってそれに触れられることを先行させれば、人間は自由に道具の可能性を引き出せると考えていいんでしょうか。ハンマーだと、実際に物質として存在しますけど、コンピューターのUIだと存在しないわけですが。
上野:
物理的なものでも、最初はそこに何かがあるというだけで、それが何なのかは決まってないと思うんですよ。たとえば浜辺に貝が落ちていて、それを食べるためには割らないといけないですけど、手では割れないから石を使って割ったとします。そこにあった貝と石と食べるって行為はまったく別なものだけど、ある瞬間にひとつになるわけですよね。われわれが生きていくなかで、そういった瞬間は何度も発生してくる。
つまり、道具の「道具性」は、意味があとからラベリングされる性質を持っていると思うんです。まずは何でもないオブジェクトそのものがあって、われわれはそこに意味を与えていくという能力がある。そう促すのが道具の「存在性」だと思います。だからこそオブジェクト指向なんだと。
§
——— なるほど、非常にわかりやすいです。今言われたのは、道具のインターフェースでありインタラクションの話ですけど、ここで縮約してコンピューター画面のUIについて聞いていきたいと思います。
コンピューター画面のUIって、表示されているのがグラフィックであれテキストであれ、単純に言うとひとつの記号にすぎないわけですよね。その記号にすぎないものをオブジェクトと感じさせる原則が書かれていて、これがおもしろいと思ったんです。
オブジェクト指向UIの原則
- オブジェクトを知覚でき直接的に働きかけられる
- オブジェクトは自身の性質と状態を体現する
- オブジェクト選択→アクション選択の操作手順
- すべてのオブジェクトが互いに協調しながらUIを構成する※5
このなかでも、「オブジェクトは自身の性質と状態を体現する」と「すべてのオブジェクトが互いに協調しながらUIを構成する」という原則が、非常に奥深いものに感じました。
「オブジェクトが自身の状態を体現する」というのは、単純な例だとマウスオーバーでボタンの色が変わるといったことだと思います。物を自由自在に使えるのは、物とのインタラクションにおいて、それがどんな形の反応をするのかが、自分の記憶のなかで構成されるからですよね。UIデザインは、それを見越して物の性質をあらかじめ付加しておかないといけない。すべては予測できないかもしれませんが、人間の心理に合わせてオブジェクトの挙動をあらかじめ反映させておく。これはかなり高度なことをやっている印象を持ちました。
上野:
まず「オブジェクトは自身の性質と状態を体現する」について話します。タスク指向が使いづらいのは、先に誰かがゴールを決めて、必要な手順が設定されているからです。そうじゃなくて、われわれが現実世界で物理的なものに対してインタラクトするような感覚を、データのなかでできるようにしないといけない。この本の「オブジェクト指向UIのフィロソフィー」に書いたのは、そういった発想で研究してきた人たちの話でした。
UIと言っても、最初はただの光の点だったんですけど、当時は画面に絵が出ているだけで画期的なことでした。なぜなら、初期のコンピューターにはディスプレイがなかったからです。それどころか、もっと初期にはキーボードもなかった。今のわれわれからすると、コンピューターにはディスプレイやキーボードのような入力装置がついてるのは当たり前ですが、最初は単にどこかで作ったプログラムを読み込ませて、結果が紙テープみたいなもので出てくるだけでした。もちろんリアルタイム性もまったくありません。
それから、リアルタイム性を持たせるために、まずはディスプレイが必要だよねということなったんです。文字でも絵でもいいから、コンピューターのなかで起こってることを、その場で何とか表示させる。今度は表示されてるものに対して、こちらから何か入力をしてインタラクションさせたいという発想になりました。入力したいから、キーボードやマウスみたいなものが出てきます。そうやってディスプレイと入力装置がコンピューターにあるということが、かなりエポックメイキングなことだったんです。
コンピューターはさらに発展していくんですけど、たとえば計算するときに数字を画面に映し出すとします。これは紙に字を書いたり読んだりするメタファーに則っている。二次元のディスプレイに記号を映し出し、われわれはそれを見て、数字が出ていれば数字とわかるし、絵が出ていれば絵だとわかる。こうやってコンピューターで扱っている情報や概念を、絵や記号や文字に見立てて表してきた。今では当たり前だと思うんですけど、当時は画期的なことでした。つまり、今われわれが当たり前にコンピューターを通じて知覚できることが、当初は意外とできてなかったんです。
さらに、われわれが知覚しているものが、本当に「そのもの」であることを示すには、インタラクティブに反応しないといけません。字を打ったら字が出なきゃいけないし、字を消したら消えなきゃいけない。そこにリアルタイム性を持たせることで、自分がイメージしているとおりに操作していると認知するわけです。文字を打っても出てこなかったら、自分が何やってるかわからないし、そこにあると思ってたものが実はないってことになる。
このように認知心理学的な観点で、われわれがそこに期待していることが起こっているように見せかけるのは、とても重要でした。そうしながら、現実世界にある物と同じような感覚で、概念を対象化して画面のなかで操作可能にしていったわけですが、これはオブジェクト指向のプログラミングとオブジェクト指向のUIが、内的に連動してるから実現されています。そのおかげで、ユーザーはどうプログラミングされているか知らなくても、アイコンのようなグラフィックを自由に操作できる。この本でも引用したアラン・ケイが、プログラム構文の記述とUIの組み立て方は一貫しているべきで、内と外がひとつの原理に基づいて作られているのがオブジェクト指向の特徴だと言っています。
コンピューターを立ち上げて、仕事を始めて終わるまで、その手順は無限にあるじゃないですか。従来のコンピュータープログラムの考え方で、無限に条件分岐がある手順を、ひとつのプロセスに線形化するのは不可能です。ユーザーの作業を線形化しない代わりに、ボタンを押したら光ったり、図形を引っ張ったら変形したり、オブジェクトというカプセル化された概念自体に振る舞いが定義されていれば、それらをつなぎ合わせて無限の操作ができるようになる。この操作の体系を作るために、オブジェクト指向のプログラミングが生まれたわけです。だから、オブジェクト指向でこれができるというよりは、これをできるようにするためにオブジェクト指向プログラミングが作られたってことなんです。これを考えた人は天才的だと思います。
もうひとつの「すべてのオブジェクトが互いに協調しながらUIを構成する」という話も、似たような話になります。ひとつひとつのプリミティブなオブジェクトがあって、それぞれは自律的に独立していて外からは遮断されている。その代わり限定的なインターフェースがあって、あるボタンがクリックされたらこう動きなさいということが、あらかじめオブジェクトのなかにプログラミングされています。オブジェクトはプログラミングされた反応をするだけ。ボタンはユーザーに押されたとき、どういう文脈の命令かはまったく知らずに、ただ自分の仕事をしているだけです。それらが集まってより大きな体系を作ると、さらに複雑な仕事をサポートできるようになります。
これはわれわれの言語構造のようなものに感じます。単語みたいに独立したプリミティブなものがあって、それらを組み合わせて無限の表現ができる。その言語体系の全体性のなかで、単語のように個別に存在している。こういう言語体系みたいな構造を作る仕組みとして、オブジェクト指向のプログラミングがあって、われわれの複雑な仕事をサポートできるようになっているわけですね。
§
——— 先ほどの繰り返しですが、オブジェクト指向的に考えると、ハンマーがあれば釘を打つだけじゃなくて、防犯にも使える。だけど、そのハンマーという形がないと使い方のバリエーションは発想できないってことですよね。
上野:
ハンマーみたいなものを作って、それで釘を打ったら具合が悪かった。じゃあちょっと形を変えてみようって話になる。だけど、ソフトウェアの場合には、作るまでに時間も人もいっぱいかかって、非常に複雑で難しい。あらかじめ作業を計画しておかないと見積もりすらできません。なので、とくに規模が大きくなると、現状は何度も作り直すフローはできないケースが多いです。
たとえば業務系のシステムだと、業務要件をまとめて機能を決めて、それらを実現するのに必要な仕組みを定義した仕様書ができて、それに従ってプログラマーが作ります。だけど、そのUIを作ろうとすると、成立しない場合が結構あるんです。ソフトウェアは自由度が高いので、プログラム上ではなんでもできるんですけど、実際に使われるUIとして人間が理解できる形で表現できるかというのは、また別の問題になります。つまり、UIとして成立するものに合わせて、要件も定義しなきゃいけないってことです。
§
——— UIとして成立するものというのは、おそらく人間の習慣がある程度ナレッジとして共有されてる状態じゃないかと思います。当然ながらUIを使うのは人間なので、人間の認知や身体とのインタラクションとして適切じゃないといけないわけですよね。
先ほどコンピューターの歴史において、グラフィックという発想が画期的だったとお話されてましたけど、おそらくデザイナーは開発の場面で、まず形をつかむという抽象的なプロセスをしている気がするんですね。悪い意味ではなく、勘で仕事しているというか。デザインじゃなくて彫刻家の仕事でも何でもいいんですけど、そういう人たちは形を表したところで仕事が完結するので、まずはその形をつかむということを、仕事の一番最初にしてるんじゃないかと思うんです。
これはUIデザインに関しても同じ気がしています。つまり、いろんな要件から必然として演繹的に導かれるものではなく、こういうシステムにするならこの形になるというのを、まず帰納的な状態でつかむ。そうやって直観を働かせるというプロセスが先にあるんじゃないかと思うんですけど、実際の作業ではどんな感じなんでしょうか。
上野:
その通りですね。こういう入力をしたらこういう出力があるという仕様通りに動いたら、プログラムとしては完成なんですけど、グラフィックなどのデザインでは、機能的な要件は一定でも表現の方法は無限です。プログラムは中身が見えないので、出てきたものが合ってればいいですけど、グラフィックデザインは中身が見えている。だから、デザイナーは中身そのものの形で評価されるし、勝負しないといけません。
僕がいつも比喩的に言うのは、真っ白の紙の上で最初の点を打つときのことです。そこには言葉に表せないような不安や恐怖があります。無限に可能性があるなかで、どこに点を打つかは非常に恣意的で、職人の勘のようなものにかなり依存していると思います。だけど、点を打たなければ次に進まないので、どこかに打つ。これは清水の舞台から飛び降りるようなものです。
それで、とりあえず一度どこかに点を打ったら、その次の点は最初よりは楽なんです。なぜなら、最初の点がここなら、次はここに打てばいいというのが、今までの自分の経験である程度予測できるからです。無限にあった可能性が、最初に点を打つことですこし狭まって、それを繰り返しながら最終的なものができあがっていく。そういう意味で、UIデザインはグラフィックデザインの性質を持っていると思います。
理論上の話ですが、プログラムは無限の情報を扱えます。なので、無限の情報が扱えることを前提にプログラムは作られます。たとえば顧客情報が無限に入れられる箱を作ったりといったことですね。それに対してUIは、ソフトウェアとしての無限の利便性を有限にすることで、人が見て把握できるようにしないといけない。
僕はよく「ガッツ」という言い方をするんですけど、恣意的な判断をデザイナーが引き受けて責任を取らないといけないんです。色はこれで数はこれぐらいなどと、無限のなかに有限性をもたらしていく。そこについては、ある種の直観というか、職人的な判断は常にあると思います。
§
——— 最初の点を打つとき、当然まったくデタラメに打つわけにはいかないし、たぶんデタラメに打つと次が成立しないと思うので、そうやって直観みたいなものを働かせると思うんですね。で、その直観はアブダクションじゃないかと。アブダクションというのはチャールズ・サンダース・パースが提示した概念ですけど、いわゆる神秘的な啓示とはすこし違う。日本語では帰納的推論と言われたりしますが、天から啓示が降りてくるようなものではなくて、今までの経験が身体化されていないと、そういった勘がそもそも働かないというメカニズムだと思うんです。このメカニズムがどう動いているのかを考えていきたいと思います。
ここで鈴木宏明の『類似と思考※6』という本を紹介したいのですが、ここにはアブダクションの基礎には類推、いわゆるアナロジーで結ばれた記憶のマトリックスがあると書かれています。要するに、無限の可能性のなかで点をひとつ打つというのは、言ってみればまったく未知のところにひとつの実践を導入する作業だと思うんですけど、これは自分が白紙状態では何もできなくて、すでに経験したいろんなことのマトリックスによって思考して導き出されるんだと言うわけですね。これはいわゆる演繹的な論理思考ではなくて、抽象化されて断片化された既知のものが、経験のレゴブロックみたいな状態になっていて、まったく未知の仕事をするときには、自分なりにそれをカチャカチャと組み立てて、形を見立ててポンと打つみたいな作業をしているんじゃないかという議論がされているんです。
当然ながら、何か形をアブダクションとして直観するためには、いろんな経験が自分の身体に高い抽象度で記憶されて眠ってるんだと思うんですが、この話はデザイナーに共通する資質だと感じますか。
上野:
そうですね。おそらくデザイナーだけじゃなくアーティストも同じように、最初の点がどこにあっても、何かしら作ることはできると思います。というのは、その経験のパターンみたいなものの数がかなりあるので、点がひとつあるだけで可能性はかなり絞られるからです。きっとたくさんある自分の引き出しで対処できる。
僕はもともとグラフィックデザイナーだったんですね。グラフィックデザイナーは、最初の仕事で名刺を作らされることが多いんですが、名刺はどれも機能としては同じで、名前と会社名と住所といった要素が決まっていて、そこにグラフィックデザイン性が加わってくるじゃないですか。最初に自分で名刺をデザインしたとき、もっと経験値の高いデザイナーが作ったものと比べると、明らかに差があったんですよ。自分が作った名刺はどこか素人くさくて、経験値の高いデザイナーが作ったものは、プロっぽいとしか言いようがなかった。同じ情報をデザインしているのに、ものすごい差があったんです。
まあその差を出せるのがプロってことだと思いますが、なぜその差が出せるかというと、おそらくプロっぽく見えることをたくさん知ってるからなんだと思います。そのセオリーやパターンにしたがって、ここに置いたら違和感があるからすこし位置を変えるといったことを、非常に細かく実践している。だけど、途中で素人が手を出すと、そこに素人っぽいものが加わって、全体に素人っぽいものになる。つまり、最初の点を手がかりに、すべての点を打ち終わるまで、一度もプロっぽい場所を外さずに最後まで行かないといけないということなんだと思います。
原体験みたいな話ですが、小学校の頃は漫画家になりたくて、漫画クラブの部長をやってたんですね。あるときクラスの女の子が転校することになったので、みんなで寄せ書きをしてました。それが僕にも回ってきたので、そこにイラストを描こうと思ったんです。ちゃんと水彩絵の具で色を塗って、いい絵を描こうと思ったんですけど、失敗してしまって。変な絵になったので、水で絵の具を溶かして消そうとしたら、うまく消えなくて紙がボロボロになったんです。
次の日に渡さなきゃいけなかったので、夜中に一生懸命描いてたんですけど、代わりの紙もなくて、これは明らかにヤバいという状態で徹夜になってしまい、もう絶望的な気分でした。でも、そこで一旦落ち着いて、もう一度やり直そうと思ったんです。紙が削られて薄くなって穴があきそうなんですが、水でその絵の具を丁寧に溶かしました。これが最後のチャンスだから冷静になって、最初に描こうと思っていたのとは違うものだったんですが、その場で自分が書けそうなものを改めて描きました。そうしたら、すごくいい感じのができたんですね。
自分がとても気に入るものが描けて、それを転校する子に自信を持ってあげることができた。今でもこの経験がしっかりと記憶に残っています。自分はまったく何もできあがってない最悪な状態からでも、何か形を作り出すことができる人間なんだという確信があって、それが自分に対する信頼になっている。
話を戻すと、ひとつの点から次の点を打って、そのクオリティのまま最後の形まで持っていけるのは、自分に対する信頼がドライバーなんじゃないかなと思います。それがないと、ある点を打って何か違うと思って、さらに次の点を打って、また何か違うってなったときに、あきらめてしまうと思うんですよ。これも自分の経験の話でしかないですけど。
§
——— 個人的な話がおもしろいですね。上野さんの言い方だと「デザインの目的は形である」という前提があるわけですもんね。
上野:
はい。それはクリストファー・アレグザンダーの受け売りですが※7。
§
——— 「形とはわれわれの認識のあり方であり、事柄を結ぶパターンであり、行為の可能性である」というやつですね。さっきの『類似と思考』に話を戻すと、この「われわれの認識のあり方」「事柄を結ぶパターン」「行為の可能性」という自分の潜在的なものが形を見て、そこでインスパイアされて賦活されるようなものが、プロっぽいものとして成立する形だという議論だったんですよ。そして、その形はロジカルに抽出できるものではなくて、最初から形としてとらえるしかないものだと。さっきの上野さんの話を聞いていて、それがオブジェクト指向のデザインでも重要な前提になるんだという気がしました。
ここからは、さらに抽象度の高い話になりますけど、オブジェクトと対峙するときに、そもそも人はなぜ自由になったり創意工夫ができたり創造的に物と関わることができるのかを掘り下げていきたいと思います。
まずは上野さんの過去のツイートから関連しそうなものを挙げていきます。ひとつ目はこれですね。
道具の手元性を自己帰属感と言うこともできるが、オブジェクト指向的に主客を転回すると、自分の拡張として道具が帰属するのではなく、道具のインターフェースとして自分が接続されるのである。道具存在が感覚から退隠するのは、自分がその実在的対象の側にあるからである※8。
それから、もうひとつドリルの話があって、これも先ほどの主題につながる話だと思いました。
電ドラを使いながらその道具的存在性を確認している。私の関心は明らかに、締められたネジよりもこの道具自体、そしてそれを使うことによって起こる私自身の世界内存在としての変化(これは多分に詩的である)に向けられている。やはり穴よりドリルだ※9。
マクルーハンのメディア論もそうですけど、「道具は身体の拡張である」って言われるじゃないですか。たとえば「ハンマーは手の拡張である」といったものです。でもこの理屈をよく考えると、自分の身体の拡張であれば、本来は自分の身体だけでも事足りるわけで、それをさらに便利にするものとしてしか道具は存在していないという話なんですよね。
だけど、おそらく上野さんはそのように考えられていないんだと思うんです。つまり、人間には素の身体みたいなものがあって、便利だから道具を使っているのではなくて、そもそも道具と人間というのがハイブリッドなものとして存在していた。そして、この道具とのハイブリッドなものとして存在していることが、他の動物と大きく違う人間の特質だと考えられている気がしています。
これにまつわる話で、大藪泰の『共同注意の発達※10』という発達心理学とか発達認知科学あたりの分野の本があるので、簡単に内容を紹介します。まず類人猿は幼児の段階から「自己と他者」という二項性しか認識できないという話があって、非常におもしろいと思いました。これがあらゆる共同体の基盤になっているわけですね。それに対して、人間は言葉も喋れず立つこともできない乳児の段階から、「自己と他者」の間に物を関係させて、その三項性に基づいた行動パターンや意識が認められると論じてるんですね。
つまり、人間は最初から本能的に道具を組み込んでいく身体感覚を持った動物であるってことです。だから、まず主体があってサブジェクトとしてオブジェクトの道具を使うという関係ではなくて、先ほどの道具とのハイブリッド性の話のように、実はすべてをオブジェクトとして想定できてるということなんです。
こういった話は、上野さんも実感を持たれていますか。
上野:
絵を描いててうまく描けないというのは、あくまで自分のなかでの自分への評価で、すごく残念で悲しい気持ちになってるんですよね。逆にそれがうまくできたときは、その絵が自分とあまり分離してないものとして実現されたという感覚なんです。
自分のなかでこういうものを作ろうと思って作り始めるんですけど、大体は途中でうまくいかなくて、ああでもないこうでもないってやるじゃないですか。グラフィックを作るときもそうだし、文章を書くときも、プログラムを書くときも、自分ひとりで孤独な作業をしてますよね。そうやってずっと個人的な時間をすごしていると、同じものを見たとしても、よかったものがよくなくなったりして、自分の考えが変わっていく。もしくは自分自身が自分が作ったものに影響されて、次の考え方が変わることがあります。
そうやって、自分が作っているものとの対話を長時間繰り返していると、自分が作ったものでありながら、それに影響された自分が次の行動を取ったりするので、自分が作るものが自分でもあるし物でもあるという不思議な感覚になっていきます。そうすると自分が作っているというよりも、自分が作られているような感覚になる。われわれがしゃべっているこの言葉も道具のひとつですけど、そうやって道具を使うことによって自分たちが変容していく体験をずっとしているんだと思うんです。そして、これが自分たちの世界の見方そのものであるべきなんじゃないかと思っています。
§
——— そうですね。そのどこまでが自分でどこからが道具なのかは、実質的に切り離せないのかもしれませんね。それは道具や作品だけじゃなくて、言語なんかも同じことが言える。自己と道具を両極に置くとすれば、われわれの生はその中間ぐらいで成り立っていて、ここまでが自己でここからが道具と切り離すのは現実的ではない。
道具を作るという行為は、さらにその自分を変えたり道具を変えたりすることによって、自分自身を変えるという相互作用を発生させていくことになります。その相互性を認めるのであれば、道具というのは身体の延長ではなくて、やはり道具と人間の身体がハイブリッドであるという考え方が近いのかなと思いました。
さっきの絵の話もそうですけど、上野さんがそれをどこかで気づいて獲得したわけじゃなく、子供の頃から実感としてその世界観を持っていたように感じるところがおもしろいですよね。もちろん勉強して身につけたわけではないし、いろいろな経験も感覚を強めるエビデンスにはなってると思うんですけど、どうも最初からその感覚を持たれているような印象があって。何かを制作するというプロセスのなかで、作品と対話をして自分にフィードバックできる人は、必然的にそういう考え方になるのかもしれませんが。
上野:
よく言われるように、あらゆる芸術においてデザインをするときには、だいたい過去の誰かが作った何かを真似したり組み合わせたりします。たぶん、それ以外の作り方はありません。自分がすごく独創的なことをやっていると思っても、必ず何か元ネタがあるわけです。すくなくとも何か発想のきっかけはあって、アーティストやデザイナーは常日頃から何かを真似しながらすこし変えたり組み合わせたりして作っている。何かを作っている人であれば、自分が独創的にやったところは1%ぐらいしかないという感覚を持っていると思います。
僕はそれを「アートの委譲」と呼んでいます。ここで「アート」と言ってるのは、人が工夫して作った術とか技みたいなものです。そして、「アート」は人類の歴史のなかで蓄積されてきました。たとえば、ホームセンターに行って、小さなハンマーを500円で買うとしましょう。このハンマーの形や大きさや構造には、ずっと昔に石で貝を割っていたノウハウが蓄積されているわけです。
このハンマーは、何百万年も前の人がいろんな試行錯誤して積み重ねた結果なので、デザインの価値は500円ではないと思うんです。潜在的な価値を考えると、ものすごく高価なものですが、それが500円で売られているのは驚きじゃないですか。じゃあ今まで試行錯誤してきた人の努力はどこに行っちゃったんだと思うんですよね。実際どこかにあるはずなので。
この「アート」という人の術や技みたいなものは、無償で次の世代に受け渡されていくもので、今われわれはそれを受け取って次の物を作っている。だから、物を作るという行為は、そうやって別の人に価値を受け渡していくということでもあるんです。そこで昔の人たちから価値を受け取っていると感じることが、とても大事だと思います。500円で売ってるハンマーを見たときに、本来これは500円じゃないというロマンと言いますか。
§
——— 今なぜこうやって抽象度の高い話ができてるかというと、知的な蓄積を受け取ってるからですもんね。ゼロから自分で考えて発言しているわけではなく、過去の成果である言語を借りて、そこに乗っかってるだけですから。そう考えると、人とオブジェクトにおいて、むしろオブジェクトの方がマトリックスであって、人はそこに宿を借りてるぐらいの位置づけで考えた方が正確かもしれません。
生物の進化を見ても、まったく何もない状態から形ができるわけではなくて、先行形態からの転用によって成り立っているわけですし、形は神様がゼロベースで作ったものではないわけです。
上野さんがデザインすることを「そこに物を置く」と言われるのも、そういった感覚を表しているのかもしれません。物が「そもそもそこにあるべきような形である」のは、自分が制御した結果として出す答えではなく、対話的に自分の創造性を働かせる態度、あるいは物に歩み寄っていく態度の方が、正解に近づく確率が高いと言いますか。
上野:
そうですね。だから当たり前だと思うんですけど、意外と自分たちが必要に応じて物を作ってるという感覚の人の方が、多い気がしますね。
§
——— 最初に話してたタスク指向じゃないですけど、サブジェクトがすべてのメタレベルに立っていて、その世界観で作業を成立させている感覚ですよね。しかし、サブジェクトの方がオブジェクトに従属してるか、あるいは対話的なレベルで関わっているという世界観を持たないと、オブジェクト指向における創造性は発揮できないんだと思います。
このあたりに関わる話で、上野さんがこんなツイートをされていました。
道具の道具的存在性とは、何かを作るためのエンパワーメントだと思う。そしてその道具も何かのエンパワーメントによって存在する。デザイナーはこのスパイラルを感じながら道具の使いこなしに貪欲であるべきだし、道具を作る道具を積極的に作るべきだ※11。
これも、まずはさっき言われていたような視点を持とうということですよね。
上野:
そうですね。「アートの委譲」をちゃんと意識しましょうということです。
§
——— ここでは「道具を作る道具」という言い方をされてますけど、単純に手で道具を作るわけじゃなくて、ハンマーで釘を打って家を作るみたいに、そこには階層構造や段階があるわけですよね。そう考えていくと、家も道具なわけですけど、家はハンマーに比べてすこし機能が限定されてます。家に比べると、ハンマーは抽象度の高い道具と言える。
同じように、プログラミング言語も道具だと思いますけど、これも何でも作ることができる非常に抽象度の高い道具じゃないですか。人間はプログラミング言語も作るし、そのプログラミング言語を使ってひとつのソフトウェアも作ることができる。そうやって道具がいろんな形でネットワーキングされている状態で、それらをサブジェクトとして上から見るのではなく、そのネットワークに入っていく方がいいと読めました。
ここで興味を持ってしまうのは、オブジェクトがいろんな形でネットワークになった状況に入っていくサブジェクト、つまり主体としてのわれわれの意識のことなんです。それはいったいどんなモードなのか聞かせてもらえますか。
上野:
先ほどの「アートの委譲」の話と似てるんですけど、形を作り続けるのは、僕にとってある種の贖罪なんですよね。何か形を作るのは、そこでエントロピーを抑制してるわけですけど、それによって自分たちが利便性なりを受け取っています。だけど、エントロピーの加算法則から言うと、おそらくその代わりに、宇宙のどこかでより多くの混沌が生じてることになります。自分たちが便利なものを作る反作用で混沌が増してることに、罪悪感があるんです。
われわれが生きていて何かを作り続けることには、ずっと何らかの原罪があるという気がしています。だから、ある種のエコロジーとして、自分たちが作った形を次の世代に受け継いで、あまり混沌を増やしすぎないようにしなきゃいけないと思ってるんですね。そして、まったくその考えが感じられないデザイン、つまりただ物事を複雑にしているだけのデザインを見たときに、なんてことをしてるんだ、宇宙の混沌が増してるじゃないかと思うわけです。それをできるだけ減らしたいし、そう考えることも大事にしたいと思っています。
§
——— ひとつの会社が利益を最大化して成功しても、地球環境に悪影響を及ぼしてるかもしれないといったような話があるように、スケールの設定でも相対的に変わっていくような話ですよね。
最後にお聞きしたいのが、「道具を使うと人間は創造的になれる」と言われているところです。これまでの流れでも話されていましたが、もうすこしフォーカスしてクリアにしていければと思います。ここでも上野さんのツイートをいくつか引用して、話のきっかけにしてみます。
道具のエモーショナリティというのはやはりユーザビリティと相関しているだろうということ。ただしそのユーザビリティは合目的性のことではなく、コントローラビリティのことである※12。
道具を手にすることでなぜ自己が肯定されるのか。われわれは子供の頃から様々な道具を使って外界に対するコントロール性を試す。その経験から、道具を見た時にコントローラビリティを評価するようになっている※13。
人と道具の間には合目的性よりも先にコントローラビリティがある。これは主観的な期待値として評価されるのもので、操作性とは異なる。自分の延長として世界をコントロールできそうに思えるかどうかが重要だ。自己肯定のための試行錯誤が、人と道具の相互発展スパイラルを生む※14。
世界をコントロールできそうかどうかの度合い。これをコントロール期待性と呼ぼう。われわれはコントロール期待性が高いものを好むのだ。その好みは経験によって異なり、中には複雑な道具を扱うことを好む場合もある。複雑な道具の力で世界をより複雑にコントロールしたい場合だ※15。
まずは「コントローラビリティ」をすこし敷衍して考えてみたいと思います。
ミゲル・シカールという哲学者が、『プレイ・マターズ※16』という本で「遊び論」のようなものを書いています。「遊び論」というと、これまでもヨハン・ホイジンガの『ホモ・ルーデンス※17』やロジェ・カイヨワの『遊びと人間※18』などいくつかありましたが、この『プレイ・マターズ』には、今までにない非常におもしろい観点があって、それが「コントローラビリティ」の話につながるように感じています。
本のなかで、遊びの特質をいくつか羅列してあるんですけど、そのなかで重要だと思うものが2つありました。まずひとつは遊びが「個人的なもの」であるというもので、もうひとつが遊びはコードや文脈を乗っ取って「流用するもの」であるというものです。簡単に言うと、そこにある与件としての世界を、誰かの指示に従って生きるのではなく、おもちゃ箱のようなものと認識してるってことなんです。
そして、自分で自由に流用して、しかもその個人的なモチベーションのなかだけで通用するのが、遊びというモードだと書いてあるんですね。ここがまさに道具の「コントローラビリティ」に関わる問題だと感じました。
つまり、人間は何かを学習するときに、学習プランに沿ってひとつひとつ自分のなかにインストールしていくのではない。幼児が積み木で遊ぶときのように、いろんな形で試しながら、そこの挙動を自分のなかにフィードバックさせながら、物の扱い方を学習していく。その学習は楽しかったはずなんです。なぜ楽しかったかというと、ミゲル・シカールが言うような「個人的なもの」として創造性があり、なおかつ自分で楽しめるように自由に「流用するもの」だからです。そういった遊びの自在性が担保されていることで、楽しいモードにいられたんだと思います。
おそらく「物を最初に出す」というオブジェクト指向の話も、誰かの指示に従うモードから、そのものを遊ぶというモードに転回させるという意味が含まれてるのかなと思いました。つまり、人間が「コントローラビリティ」が高いことに対して反応するのは、自分で自由に使えて試せるからだと思うんです。
上野:
まさにそうです。遊びには見立てが関係していて、たとえば棒切れが一本落ちているときに、それがちょうどよい長さや太さであれば、途端に遊びの玩具になる。これは、われわれがオブジェクトを何かに見立てるのを、自動的におこなっているということなんだと思います。それが道具として役立つこともあるし、既存のコードを乗っ取って、木の枝でおこなうべきではないと考えられているようなことを触発されて、楽しそうだから思わずしてしまうこともあると思うんです。この見立ての能力というか習性みたいなものは、遊びにもオブジェクト指向にも共通してると思います。
2万年ぐらい前の洞窟には、牛とか馬の壁画がありました。当時どれぐらい言語が発達していたのかは解明されてないと思うんですけど、とにかく絵を描くことはやっていた。でも、洞窟のなかにいないはずの牛や馬の絵を描くということは、牛や馬の概念を対象化できていたということじゃないですか。それを絵として表象していたわけです。
つまり、昔から人はそうやって遊んでいた。それが楽しい遊びだったのか、コミュニケーションだったのか、どういう意味があったかわからないんですけど、あまりそういった区別もされてなかったんじゃないかなと思うんです。
人が絵を描いたり、物を玩具のように扱うという行為をし続けているのは、われわれが世界とインタラクトすることそのものなんだと思うんですよ。オブジェクト指向でUIを表すというのも、コンピューターのなかで扱っている情報を玩具化するということですよね。
§
——— 今のお話に対応するような内容として、前に「創造性とは、サブジェクティブな駆り立てではなく、オブジェクティブな見出しから伸び栄えるものである※19」ともツイートされていましたね。
たとえばインターネットを見ていても、あまり楽しい気分になることはなくて、何か一方的にこうしなさいと指示されているような、ある種の掌握感があります。これはUIというよりも、市場社会が要因になっているかもしれませんが、遊園地に行っていろんな遊具を見て何をしようかワクワクするモードと、ブラウザでいろんなWebサイトを見たときの気分は全然違うわけです。だけど、本来は遊園地にいるときのような楽しい気分であるべきものなんじゃないかなと思います。
上野:
まさに最初に話していたタスク指向の問題だと思います。機械化が起こって、さらにコンピューターみたいな高速で処理をするものが出てきたときに、プロセスを自動化するという発想があった。そうすると、コンピューターに対してだけじゃなく、ユーザーに対しても何か仕事をさせるといった使役的な考え方になる。コンピューティングパワーを使って、ユーザーに何か一連の行動を取らせるように設計されているケースが非常に多い。
たとえば、子供の玩具を見ても、積み木のように好きに遊べるオープンゴール系のものもあれば、手順に従ってうまくできるかどうかを競わせるものもあるじゃないですか。本来の遊びは、前者のオープンゴール系なんだと思います。
§
——— 後者の手順に沿った遊びについては、さっきのミゲル・シカールの本でもゲームデザインの問題として取り上げていました。ゲームデザインは、デザイナーが仕切るエモーショナルのデザインだと考えられているけど、遊び本来の意味から考えると、すこし歪なんじゃないんじゃないかという議論です。
ただオープンゴールにすればいいというわけではなくて、人間社会は当然ながらある程度の「型」を文化的に備えているものです。さっきの「アートの委譲」の話でもあったように、ある一定の「型」を、自由な動きのなかから見出していくものだとも思うんですね。あるいは、その自由な動きさえも、ある一定の「型」がないとそもそも実現しないところがあったりして。
なので、デザイナーはさっきの「アートの委譲」のなかで「型」を与えることで、人々の創造性をインスパイアしていく。そんなポジションとして考えた方がいいのかもしれません。
上野:
その通りだと思います。だから「型」を作る。そういった意味で、デザインはメタデザインだと思ってます。
——— デザインをデザインする。
上野:
そうですね。コンピューターのプログラミングではキーバリュー(Key-Value)という言い方をしますけど、「色」とか「スピード」みたいなキーがあって、それに対して「赤」とか「100km/h」といったバリューがある。デザインもキーの方、つまり「型」を作ることによって、バリューで遊ばせるというところがあります。
§
——— やはり人間の創造性は、そこに没入する精神の運動だと思うんです。没入することが楽しいかどうかは、主観的な問題になるんですけど、没入していること自体は客観的なモードだと思うんです。今日のお話を聞いて、オブジェクト指向UIデザインとはそこに誘うための基本的原理という感じがしました。
上野:
物理的な物であれば、右から左に移動させれば、その物はちゃんと右から左に移動しますが、ソフトウェアのなかではデザイナーやプログラマーがそう振る舞うように作らないといけません。ユーザーがマウスで右から左にアイコンを移動したら、アイコンを右から左に移動するように作って、「コントローラビリティ」を感じさせる。
GUIの歴史では、それをプログラムで自然に見せるために、ものすごい努力をしてきたわけです。われわれはそれをさまざまな形で「アートの委譲」として受け取り、日々デザインしている。そう考えていくと、オブジェクト指向UIデザインのことも当たり前に感じてもらえると思います。
§
2020年7月3日
インタビュアー: +M(@freakscafe)
はじめに
本稿は、拙著『タイポグラフィの領域※1』(以下、『領域』)について、その結論部を補足する試みである。
『領域』を執筆した動機は、タイポグラフィという言葉の定義化の必要を痛感したからである。まずこの国では、本来の意味と齟齬をきたす使われ方がなされていると見えたからであり、次に本質的な概念の抽出が、その語を口にする者にとっては必要だろうと考えたことにある。そのためには時代の技術変化に支配される環境下においても一定不変である概念を引き出す努力が不可欠であり、その定義化という作業では歴史を遡らざるを得ないことから、可能な限りの広い渉猟と慎重さが要求される。それに応えられたかはかなり心もとないが、幸運にも発表の機会を得て、ここに四半世紀を迎えようとしている。
『領域』の結論では、「タイポグラフィとは活字書体による言葉の再現・描写である」と示し※2、定義の一例として提案した。
タイポグラフィの定義化での障害
そもそも『領域』は意味ある提案だったのかとの杞憂は長く続いている。文字さえあれば「タイポグラフィ」だという歴史を無視した曖昧な認識が大多数であり、現にその認識のままご都合主義的・恣意的に意味が拡大されている。
自分たちが携わる職業またはその重要な一部を誰にでも説明できることは、至極当然の責任ある態度だと考える。だがその説明において、十人十色や百人百様状態という事態を許している理由は、「タイポグラフィ」というカタカナ語にあると思える。日本人の多くには、カタカナ語表記の外来語に対して舶来物崇拝の遺伝子があり、さらになんとなくわかったつもりになって済ませ、安易さに寄りかかる習性が様々な日常場面で強く見られるからだ。それを巧みに常套手段化して利用する分野では、特別な雰囲気だけを煽ることで大衆を煙に巻いたり、時には先導したりと忙しい。
このカタカナ語の欠点を加藤周一は「カタカナにすると概念相互の関係がはっきりしません。……思考が断片的になる傾向を、非常に強める」、また「誰も定義を考える必要がない。だから誰も知らないということになる」状態に陥ると警告している※3。
タイポグラフィという語もまた同類である。したがってこの語に対して例えば「活字(組版)演出法」「活字描写法」などの和訳があり得るが、ふさわしい新しい和訳語を与えるべきだ、と痛感した。そのためには定義を優先する方が理に叶う。
その他にも、『領域』の主旨がデザイナーに届き難かった付帯的な理由は、「再現」という語自体にありそうだ。仮にデザイナーが『領域』の結論を知っていたとすれば、「再現」という語から彼らは抵抗感を覚え、自身の創造性を否定されかねないと感じたかもしれない。「再現」は、デザイン現場で頻繁に使われる「表現」という語よりも一段低く見られているのではないか、一種のなぞり事だけのように受け取られたのだろうか、と想像もした。そのような語感から得られる皮膚感覚は厄介であるが、無視できないかもしれない。
1. 文学者の関心
芥川龍之介
ところでこの国で初めて「タイポグラフィ」という語が一定の影響を与えるほどに使われたのは、いつ頃の誰によってだろうか。それはおそらく書誌学分野ではどなたかが使っていただろうが、印刷関係者やデザイン関連従事者が発表した記事・論文からでは見かけず(「※5」とも関連)、大正末期の作家・芥川龍之介の文章ではないだろうか。
彼の『芭蕉雑記※4』には「装幀」と題した見出しの下に、「芭蕉は俳書を上梓する上にも、いろいろ註文を持っていたらしい。たとえば本文の書きざまにはこういう言葉を洩らしている」として、以下の松尾芭蕉の感想がその弟子の服部土芳の書き残した『三冊子(さんぞうし)』から紹介されている。「書きやうはいろいろあるべし。唯さわがしからぬ心づかひ有りたし。『猿蓑』能書なり。されども今少し大なり。作者の名大にていやしく見え侍る※5」
芥川はこれに感想を加える。「勝峯晋風氏の教へによれば、俳書の装幀も芭蕉以前は華美を好んだのにも関わらず、芭蕉以後は簡素の中に寂びを尊んだと云ふことである。芭蕉も今日生まれたとすれば、やはり本文は九ポイントにするとか、表紙の布は木綿にするとか、考案を凝らしたことであろう。或いはまたウイリアム・モリスのように、ペエトロン杉風とも相談の上に、Typographyに新意を出したかも知れぬ。」
この時代に芥川はすでにタイポグラフィという専門語を英語で紹介している。彼がこの語を知っていた理由は、彼の卒業論文が英国のウィリアム・モリス関連だったからだろう。なお、ペエトロンはパトロンのことで、杉風(さんぷう)とは蕉門十哲の一人の杉山杉風である。
日本でタイポグラフィなる語を公的かつ組織的に使い始めた機会は、1971年に日本レタリング協会という名称を日本タイポグラフィ協会と改めた時であった。だがその際には一定のまとまった概念ではこの語を捉えていなかったことは『領域』で指摘した※6。そして「広義のタイポグラフィ」を扱うと公表していることから、中心となる語の範囲が恣意的に拡大された。それとは別に2007年に日本タイポグラフィ学会が組織され、調査研究に値する対象としてタイポグラフィを捉え、紀要が発行されて、地道な活動が始まった。
谷崎潤一郎
芥川ならずとも、タイポグラフィに深く関心を抱いた文学者がいる。例えばその一人は『文章読本※7』を著した谷崎潤一郎だ。谷崎自身は自覚していないだろうが、紛れもなくそれはタイポグラフィに関わることである。
谷崎の文体は彼の得意とする英語文の影響が強いとは、丸谷才一氏の説である(丸谷才一著『文章読本※8』参照)。とすれば、谷崎がtypographyという語を知っていたと予想しても不自然ではない。
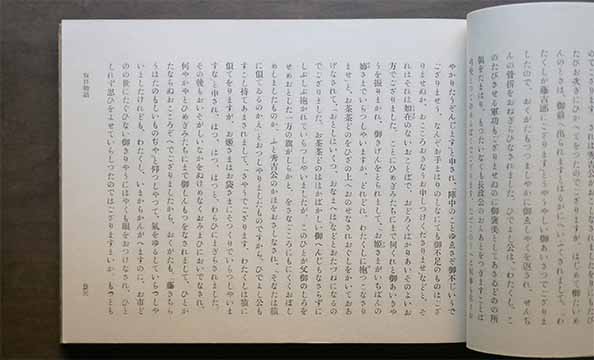 [図1]谷崎潤一郎『盲目物語』の本文
[図1]谷崎潤一郎『盲目物語』の本文
谷崎は『文章読本』の「三、文章の要素、体裁について」の箇所で、振り仮名及び送り仮名の問題、漢字及び仮名の宛て方、活字の形態の問題、句読点を取り上げ、それぞれ例をあげてわかりやすく自説を説く。活字の件では、「楷、行、草、隷、篆、変態仮名、片仮名等、各種の字体(これは正確には書体:筆者)を有する国が、それらの変化を利用しないのは、間違っております」と述べる。
また谷崎は、例えば『春琴抄※9』のある部分で意図的に文章から句読点を省いて書き表し、活字書体、文体、表記、組版表情(テクスチャ)に関しての問題意識の高さを示した。この全てはタイポグラフィを実践する上でチェックすべき基本項目である。
立原道造
また例えばその二人目は、夭折の詩人として知られる立原道造だ。彼は自分が書いた一編の詩がどのような活字の状態で読まれるかに関心があった形跡が見られる。活字化された体裁を書き写すような下書きが残っていることから、それが想像できる。
詩人は誰も、行の長さのバランスをどう調整するか、行をどこで改行させるか、ある語を漢字・ひらがな・カタカナのどれで表すか、語間を1字分意図的にあけるかどうか、ある行を1字下げて始めるか、また行間は読み進む音のリズムや調子や速度を考えてどのくらいにするのがふさわしいか、などに関心を示さざるを得ないし、工夫するだろうし、要望もするだろう。そこで詩人の言葉と表記への繊細な神経は、タイポグラフィの力を必要とすることは容易に想像できる。立原は日本語による4・4・3・3行構成のソネット形式の組み方では、紙面上での行の配置などの活字の展開や並べ方にある限界を感じたかもしれないとも思える。
立原は若さに潜む憂いやかすかな望みをその軽やかな言葉遣いとともに軽井沢の草原の風に吹かせて、いくつかのソネットを残した。そこには自分の言葉がタイポグラフィを通して実現することをひそかに願った立原の意思があった、と思わせるものがある。
平井功
さらに探せば、三人目として平井功というやはり夭折の詩人がいる。1929年に『游牧記※10』を自費で発行したことで知られる。
自らを「年少無名の貧学徒」と名乗った平井は、二十歳を過ぎたばかりの年齢で、後に紹介するフランシス・メネルという同時代のイギリスの出版人に手紙を書いたと伝えられている。それは彼の組版に対する執拗なこだわりにあり、問題解決についての質問を投げたと思われる節がある。これは推測だが、その質問内容は特殊な技巧を要する困難な組版方法についてだったのではないか。
同時に平井は自分が出版する『游牧記』の購読予約をメネルから受け取っており、それは巻末のリストから分かる。かつて『游牧記』原本1冊を松本八郎氏のご好意で実見できたが、その際松本氏は、平井は日本で自分が要望する組版と印刷の見積もりを取ろうとした。しかし、どの印刷所もその複雑な組版や予算の関係で、平井の仕事の受注を避けたらしい、と話された。
平井がメネルのナンサッチ・プレスの技量や存在について知り得たのは、彼の先輩からであろう。愛書家の日夏耿之介氏、木下杢太郎氏、庄司浅水氏などからの助言で紹介されたと思われる。結局平井は、自分の詩集の印刷を精興社に任せた。その紙面は、詩、随筆、論文、2段組みの書評や後記で占められ、詩には和文書体でのイニシャル・レターも使用され、特殊な活字は上海から取り寄せられるなど、この若き詩人のこだわりは明らかにタイポグラフィであって、それは次の言葉からも十分に察せられる。
遂に日本には一人のEmery Walkerはゐない、Theodore de Vinneはゐない、Bruce Rogersはゐないのである。わたくし自身が起って自ら以つてそれに任ずる他に途ははないのである※11。
平井功『遊牧記』
ここで挙げられている3人は、ともに紹介するまでもないほど高名な人物だ。この時代のこの時期に平井が英米のタイポグラファの名前を挙げていることに、言葉の表出形式と印刷分野への特段の関心の高さを見る。彼が長く生き永らえていれば、日本の気骨あるメネルが誕生していたかもしれない。その夭折が惜しまれる。
また、未消化ゆえに紹介できないが、もう一人詩人がいる。昭和初期にボン書店を営んだモダニストの詩人・鳥羽茂である。自費出版活動のために印刷機や活字などを設備し、貧しさの中で懸命に言葉を綴り文字を組み印刷した若き詩人であるが、この詩人にとっての活字とは何か、気になる。内堀弘著『ボン書店の幻※12』が参考となるだろう。
その他の分野から
ここに興味ある事実がある。以前からこの国ではタイポグラフィについての記述は、書誌学者かつ翻訳家の壽岳文章氏、英文学者の小野二郎氏、編集者の大輪盛人氏などデザイン系以外の人による言及が先立っていた。つまり、タイポグラフィ関連の洋書に目を通していた人達だ。
ただしデザイン系では、例外として第一世代の原弘氏がタイポグラフィに注目していたし、デザインにおける文字活字中心の姿勢を示し、その重要性を認識していた。原氏がむしろ希少の存在だったのは、昭和の大戦前では芸術家を目指した一部の人たちが転身して図案家と称し商業美術を職業として、現在のデザイン分野に参入したからだろうか。その「美術」という語からその後の認識での混乱の元があるのかとも思える。
その後、かなりの時をおいて少しずつ本格化する。1970年代にはすでに小池光三氏がおそらく初めて本格的なタイポグラフィ教育の体系的な実践を武蔵野美術短期大学(当時)にて行い、有志による欧文印刷学会の活動や出版もあり、またタイポグラフィ専門出版社・朗文堂からの数多くの関連書の出版と私塾の活動、それに武蔵野美術大学教授の新島実氏らが教授法に方法論を持って授業展開した経緯がある。これでわかる通り、タイポグラフィへの注目は、概ね英文学などに関わる人物がデザイン関連業界に先んじていたという実態を残している。
ついでながら、武蔵野美術大学が発行する『武蔵野美術 No.113(夏)号※13』は特集として珍しくタイポグラフィが選ばれている。ここでもタイポグラフィとは何かとの解説はほぼ見られないし、歴史に触れる記事はわずかである。だが注目すべきは特集の冒頭での対談である。そこでは編集工学研究所の所長である松岡正剛氏がタイポグラフィをめぐる状況に関心を持とうとする人が意外と少ないことに触れ、「活字の生い立ちから離れようとして、活字にあまり関心を持たないデザイナーも多い」と指摘して、杉浦康平氏との対談を始めている。
デザインとは異なる分野からの関心の強さをここにも見るし、翻ってデザイナーたちへの厳しい視線が重なる。むしろこれは過去のデザイン教育でタイポグラフィの基本である組版実践や歴史が無視され続けていることの影響であろう。加えてこの国における日本語と欧文のタイポグラフィのための基礎教育が貧しい現実がある。それに先立って、教育機関での体系的で詳細な授業シラバスのモデル構築が急務である状態が続いている※14。
これらの現実をきたした遠因には、デザイナーは組版オペレーターではない、という理解があると思える。そこにオペレーターに対する特殊な意識がにじむ。デザイナーには確かに単純に見えるオペレーターの受け身的な作業だけではない仕事が多くあるとはいえ、現在では組版操作そのものはデザイナーにとっては重要な一部であることには変わりがない事態に変化している。
組版操作は他者の指示に従っているので受動的であるが、その他者がデザイナー自身である任務の兼業が多くの場合の現実だろう。少なくとも操作を直接に担当しない場合でも、本文組版仕様の詳細を指定(原稿指定)できること、または完成形を明確に頭に描けることは、最低限の任務ではある。
なお個人的ながら、私がタイポグラフィ関係の英文に本格的に触れた契機は、英文学者の助言にあった※15。
言葉の重み
小説家や詩人は、自分の書いた作品がどのように読まれるかにも心を砕く。言葉の表出に死力を尽くしたテキストをデザイナーが扱うこともあるだろうし、それを敷衍すれば、全てのテキストは気力を絞った結果としてのなにがしかの創造行為として尊重すべき対象となる。
小説家や詩人が、活字化された自らの文章の姿を思い描きつつ原稿用紙に向かっていたこともあり得る。そう考えれば、文学者ならずとも、また手書きの文字原稿でなくても、デザイナーは誰かが時間をかけて用意した文章を素材として扱うことに、一層の覚悟が求められても良いはずだ。その素材の重さこそ、タイポグラフィに関わる者が感じつつ仕事に取り組む真摯な構えにつながる。洋の東西を問わず、詩を組む作業こそタイポグラフィでの最も難しい課題ではないだろうか。
タイポグラフィはそもそも読者には無意識下のことが多く、多くの読者が気づかないこと、つまり恙なく読み進まれる状態の実現が優先される。さらに書く側の方では、文章と文字がどのような形で視覚化されるのだろうかと無意識に近いレベルでなんらかの想像が働くであろう。またなんらかの視覚化された場面に期待を抱きつつ文章を書き綴る者もいるだろう。読み手の側は受動的であって、与えられた形態を無条件に受け入れて読まざるを得ない。例えば選ばれた書体が何であろうが、行間がどうであろうが、可読性の有無などに読み手が気づくことはなく、ただ受け入れるだけだ。もし読みにくければなんとなくという意識のレベルで「読みにくさ」を漠然と感じるだけだろうが、無難に読めた場合には、組版という状態には何も感じないはずだ。
つまり活字は意識されないことから、一般の人の関心とはなり得ない。ただ、組版上の誤りやデザインにわずかな不具合や破綻がある場合だけにそれに気づく。地味な裏方の技であることが常態である。それ故に、若いデザイナーたちがタイポグラフィの重要性に気づくにはそれなりの時間を要する実態がわかるようだ。いずれにしても読者は書体と組版の作法によりなんらかの組版表情に対する視感覚を紙面から受け取っているはずだが、それは読み手の中で言葉になりえないほどわずかであろう。
タイポグラフィはこの読む環境の整備と文章へといざなう「導入作法」の中に、最初のそしておそらく唯一の技芸が発揮されると考えて差し支えない。タイポグラフィもデザインとして捉えられていることから、その技芸の塩加減が印刷紙面の体裁あるいは電子媒体での画面上での体裁を、それぞれ左右することになる。だがまた、読みにくさや錯乱状態の演出を試みられることがあり得る。それを歓迎するのか排除するのかは、ひとえにテキストを用意した側の指示や同意が必要だろうし、あるいは読み手の側の受容の程度に関わる。タイポグラフィはひとえに文意とその提供者に依存するからである。
また、そこに微妙な、そしてある意味で議論を呼び起こす問題が生じえるが、ここでは扱わない。『領域』ではそこに多少踏み込んだが、この文章・文意のデザイン側における選択または拒否というテーマは人の生き方や趣味や思想に関わり、深刻な議論の余地がある。これに対する解決があり得るのかも含めて、興味深いテーマではある。言葉の発信者と受信者、それに社会的な発言という立場の根本的な考察、つまり情報リテラシーの吟味なしに扱えないことも確かである。
言葉、文字、活字、その変換作業
ここでタイポグラフィの実践を単純化すれば、それには「言葉から文字へ」、「文字から活字書体へ」という2つの段階がある。前者では言葉が基本となる。言葉の表出作業によって特定の書記言語に変換される。つまり音声言語形態ではなく「文字化される、テキスト化される」メッセージが素材となる。後者では多くの場合、手書きではないパソコン内の初期設定の「活字書体」に変換され、未加工文(あるいは「素材文」、シンプル・テキスト)の原稿となる。
さらに別の段階として、その未加工文を一般化および可視化するための洗練作業が加わる。それは読みやすさを目指しつつ、社会的に標準化された骨格(字体)を基として言語表記の慣習に沿い、意匠を施された活字書体に変換することだ。それには専門的な知識・技術・感性が必須となる。
この一連の作業の共通項は「変換作業」であるとわかる。またその変換では、当然ながらある重要な不可避の判断が伴う(その最終段階での無自覚状態の個性が作用して影響する)。これがタイポグラフィにおけるデザイン作業の基本構造だろう。この構造における決定的な要素は、語感という言葉への感受性に基づく図像喚起力であり、それはデザイン上の理知的な判断と等価である。
2. タイポグラフィの分業・統合
タイポグラフィの原義とその技芸
タイポグラフィは印刷の現場で生まれた印刷術を意味する言葉である。それでは印刷と印刷術ではどこが異なるのだろうか。印刷は何を印刷するのか。印刷はその発明のあった15世紀半ば以降近年までは文字を中心に扱ってきたし、その印刷物の流通主体は書籍という形態だった。これが基本の理解である。紙に文字を記して複製する行為と読みやすさを追求する研鑽であり、そうであれば文字の刻印のための品質管理こそが中心課題で、そこに集中的な力量が試される。
つまり印刷の核となる活字の扱い方である「技術」と総体として造形化する「芸」がタイポグラフィだとの認識だ。したがってタイポグラフィの和訳語は印刷ではなく、その中核行為を強く意識する技芸を含む「印刷術」であったし、印刷の結果としての紙面の体裁やその有効性の評価も含めた印刷物のデザイン行為だった。
だが近年の印刷産業の現実では、この「印刷術」の含意は印刷工程上の機械工学の側面が主となっており、機械操作の熟練度や機械構造や機材・資材に関する理解度であり、ここでいう印刷術ではない※16。それは電子工学に依存する高度な自動化の恒常的進歩への即時対応を示さなければ産業として生き延びられないから、当然のことだろう。そして先の「技芸」の部分を20世紀前半から担った職種がデザイナーであり、現代では彼らの活動はウェブ・デザインに及び、ディスプレイ画面上へと急速に拡張した。
タイポグラファの自覚と使命
タイポグラフィの実践者であるタイポグラファは、かつては単なる印刷従事者ではなく、誇るべき職業人としてみなされてきたという。印刷の中心課題である活字の扱いは無論のこと印刷機・印刷用紙について深く広い知識と実践上の技術を有する職人であった。さらに関連して製本とその資材類などを含む書籍製作全般について熟知していることも求められた。したがって、「書籍製作者」という意味での理解があったことがうかがえる。それはまた、広く文化的使命に従事しているという職業観への自覚と自負のある存在でもあったはずだ。
過去には、タイポグラファと呼ぶにふさわしい人物がいた。例えば、15–16世紀ヴェネチアのアルダス・マヌティウスは、ギリシャの古典、とりわけアリストテレスの復刻や古典復刊のための組版への工夫に取り憑かれた。16世紀パリのロベール・エティエンヌは、かのギャラモン設計のローマン体活字を見出しつつも禁書だった新教関連書の出版活動に命を賭けた。18世紀パリのピエール・シモン・フールニエは、ロココ調の香りを浴びつつ書籍製作への意義ある参加に誇りを抱いた。19世紀ロンドンのジョン・ベルは、活発化した市民社会の雑多な情報の提供と自説の公表に元祖とも言える新聞形態を工夫して提供した。20世紀ロンドンのフランシス・メネルは、独自の考案による書籍形態の質の確保とその安価な提供に集中した。北イタリア・ベロナのマルチーノ・マーダーシュタイクは、ボドニのオリジナル活字への敬愛と高品質の組版・印刷の実現に心を砕いた。それぞれが使命を抱いてその実現に挑み、生涯を貫いた。
紙媒体を担う従来の印刷ではタイポグラファは存在しうるが、動画を含むウェブ系媒体では今後どのような新しい呼称が生まれるのか、あるいは変わらないのか。いずれにせよ、語彙の整理は、タイポグラフィを広角的・歴史的さらに恒常的にとらえる場合には、必須な課題である。
再統合化へ
多くの業種もそして印刷業も、個人が全ての工程に関わる単独統合型から、工程が細分化して関わる専門分業型へと進んだ。だが、デジタル技術の進歩で、現代では再度の統合化が起こっている。タイポグラフィもその流れにあるが、書体設計はタイポグラフィ分野の主要な要素とはいえ、いつの時代も統合されていない。それほど書体設計が熟練と思考と繊細さを要する特殊技能だからだろう。
手元に1968年発行の“Monotype Newsletter※17”がある。ここでは、‘Typographers v. Printers’と題する1ページ2段組の短い報告記事がある。2つの立場の間に生じている問題を議論する企画で、意思伝達に関する質疑が主な内容となっている。タイトルにあるPrintersとはここではモノタイプ組版のオペレーターであり、Typographersとはタイポグラフィック・デザイナー協会という団体である。
 [図2]“Monotype Newsletter Issue 84” (1968)
[図2]“Monotype Newsletter Issue 84” (1968)
その報告内容よりも、このタイトルに注目したい。この20世紀中頃にはすでに組版兼印刷所とタイポグラフィの実践者が分業化されていたことが推測できる。産業としての印刷業が機械化の進展に伴って個々の工程で特殊技能が求められたからだろう。これ以降は欧米でも日本でも、写植による文字組版では写植オペレーターという専業が生まれ、デザイナーは組版仕様を指定して、写植および版下制作サービス会社に作業を依頼していた。だがその後、組版を担うデザイナーはパソコンを獲得し常用化することに至り、組版も自分で仕上げざるを得なくなり、一気に統合が進んだ。ところが教育の現場ではその組版部分が詳しく教えられない状態が続いたため、危機感を持った古参のデザイナーたちが独学の末に組版の参考書を発行し始めた。この現象はこの統合化の影響だろう。
このような紙媒体と電子情報網とに二極化する中で、デザイン作業は自己管理が容易な道具の獲得と操作が主流となった。活字使用の専門性と活字の概念の急速な液状化的現象は、いずれ新たな整理を必要とされるだろう。とはいえ、時代が変わろうとも言葉と文字との関係とその発信行為が溶解しない限りは、共通する核となる内容があるはずで、その抽出を試みる作業が無価値とは思えない。いやむしろ必須の課題だと考える。
3. 「再現」の意味の確認
『領域』ではタイポグラフィについて語った人物を時代ごとに紹介した。以下ではタイポグラフィの定義を明確に試みた主要な4人について、『領域』の既述に若干の補足を交えて確認する。
3つ作業:ピエール・シモン・フールニエ
18世紀フランスの印刷者フールニエは、その未完の著作“Mannuel Typographique※18”で、タイポグラフィは3つの部分「父型彫刻、活字鋳造、印刷」からなると表明している※19。彼は合理性を追求した技芸者で、印刷機も操作し、多作かつ緻密な活字設計者だった。つまり、上の3つの工程を一人でこなした熱血の人生、読書の価値を自覚してその支援に注力できたことを誇りとした人生だった。彼は印刷を「天からの贈り物」と捉えていたほど、自らの職業に誇りを持っていた。「フールニエはタイポグラフィにおけるモーツアルトと位置付けられる」という天才扱いの評価さえある※20。
また彼は、自分が世界で初めて印刷の手引書を書いたと思っていた節があるが、それは早計だった。彼の父親のジャン・クロード・フールニエは、ル・ベ活字鋳造所の支配人となったほどだ。ル・ベとはギャラモンの弟子で、ギャラモンが残した活字の大部分をプランタン印刷所に売却し、後に独立した人物であり、その3世の後をピエールの父クロードが引き継いだ。つまり偉大なギャラモンの弟子という名門の流れにあることがわかる※21。
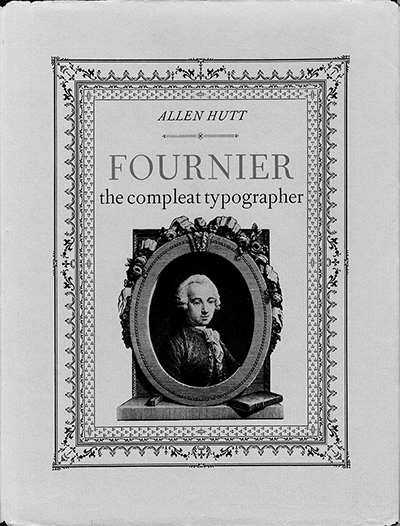 [図3]Allen Hutt “Fournier, the complete typographer” (1972)
[図3]Allen Hutt “Fournier, the complete typographer” (1972)
印刷の手引書を最初にものした人物は、イギリス人のヨゼフ・モクスンだった。なお、モクスンはその著作“Mechanick Exercises: Or, The Doctrine Of Handyworks Applied To The Art Of Printing※22”で、タイポグラファとは今日でいうプリンティング・ディレクターに重なる守備範囲を担う者だと捉えていた。だが活字製造や印刷機の操作もできることを含むため、現在のディレクターとはやや異なるだろう。モクスンは、タイポグラファとは「自身の確たる根拠(または理性)から、自身の判断によって、手作業と実働的な操作の全てを初めから終わりまで行える者、またそのように他者に行動するよう指図できる者」と規定しているからだ。この「確たる根拠」はやがて次に紹介するスタンリー・モリスンの胸中で終生響いていた。理性や根拠に基づく判断には、経験が知識として明確に言語化されているという内面の働きが前提になる。
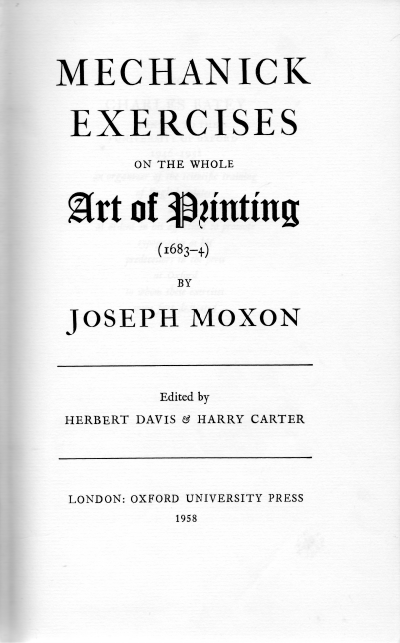 [図4]Joseph Moxon “Mechanick Exercises: Or, The Doctrine Of Handyworks Applied To The Art Of Printing” (1683) 復刻版の扉
[図4]Joseph Moxon “Mechanick Exercises: Or, The Doctrine Of Handyworks Applied To The Art Of Printing” (1683) 復刻版の扉
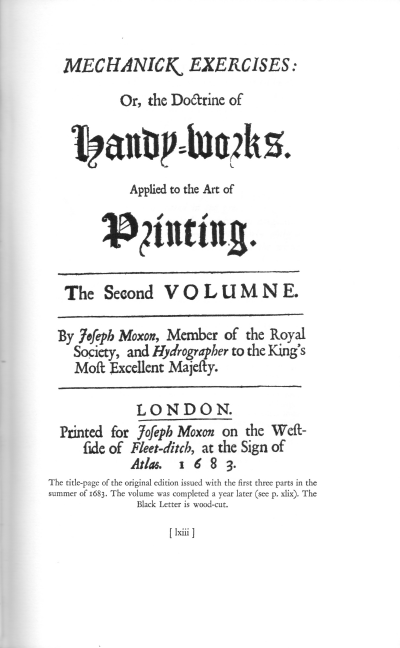 [図5]Joseph Moxon “Mechanick Exercises: Or, The Doctrine Of Handyworks Applied To The Art Of Printing Vol. 2” (1683) 原本の扉
[図5]Joseph Moxon “Mechanick Exercises: Or, The Doctrine Of Handyworks Applied To The Art Of Printing Vol. 2” (1683) 原本の扉
著者と読者の間:スタンリー・モリスン
20世紀前半になって、モリスンは“First Principles of Typography”の冒頭で初めてタイポグラフィを定義した※23。いわく「特定の目的に従って印刷材料を正しく配置する技芸であり、それによって読者が本文をなるべく的確に理解できるように文字を並べ、余白を配置して、活字を使いこなす技です」「意図することが何であれ、著者と読者との間に一定の効果を生じさせる印刷材料の配置は、どれも誤りです」※24。
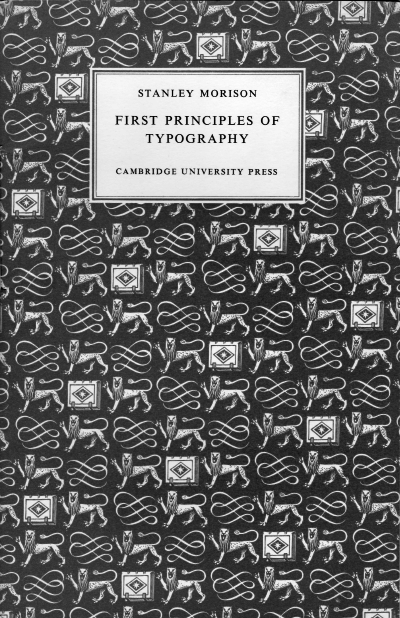 [図6]Stanley Morison “First Principles of Typography” (1936)
[図6]Stanley Morison “First Principles of Typography” (1936)
この小著は専門家相手ではなく、むしろ初心者向けの啓蒙的な解説であることがまずは前提として重要である。したがって専門的な記述はない。そしてここに示された定義は、活字組版と呼ばれる印刷の中心課題に絞っている。ここでモリスンは書き手と読み手の双方に目を向けている。「一定の効果をもたらす」というのは、意訳すれば「両者の間に余計に介入することで両者を離してしまう」というマイナス面のことで、例えば「美的効果」の追求であって、テキストが活字に変換されること以外は不要だと踏み込んだ厳しさを表明している。
モリスンはこの続きの文章で、政治広報や商業広告でのディスプレイ・タイポグラフィの実践、つまり現代の多くのデザイナーが関わっている面もタイポグラフィの2つの役割のうちの他面であることを伝えている。言い換えれば、活字書体の本文用書体としての非個性的な役割(いわゆるビアトリス・ウォード女史のいう「水晶の透明性(Crystal Goblet)」※25)と、ディスプレイ用で選ばれる場合の、書体の特徴が顕著で個性的で言葉の意味を増幅する役割、という基本である。
またモリスンは活字設計について「親指の指紋は不要」だと断言している。タイプ・デザイナーが己の刻印を活字書体に残そうとする行為は、広く共通して目にさらされる活字書体には雑音や障害となる、という意味だろう※26。この厳しさから出発することが基本だと確信する。
翻訳能力:ハーバード・スペンサー
スペンサーはイギリス人のデザイナーである。彼はイギリスにモダニズムのデザインを紹介したが、評論家のロビン・キンロスによれば、スペンサーの行動には思想的な含みはなかったと言う。むしろスペンサーの舞台は、時代のビジネスマンのための経済活動を支援するタイポグラフィであった。それは彼がコスト削減や能率化の実現という単純な文脈でタイポグラフィを語っているということであろうし、いわば目的合理性と機能性を貫くモダン・デザインの形式的解釈と言える。これはレイアウトにおける誰にでもわかりやすい文字情報の整理法であり、ビジネス社会の行動における節約を強く意識した問題解決法であり、省略・削減を是とし、無駄を省く指向と言える。
だが、キンロスのいう「思想的な含みがなかった」スペンサーの評価とは何を指すか。それは彼がヤン・チヒョルトの影響を受けて、その中の現実的解釈の手法だけを解説したという意味だろう。チヒョルトは審美的そして理想的な紙面のありようを歴史への接近の中から理解していたが、スペンサーにはその自覚が希薄だという意味だ。また、モダニズムで基盤をなす捉え方の省略でもあろう。
それはプロテスタンティズムが支配するデザインにおける装飾的要素の排除という意味ではないか。図式的に簡略化すれば、これは教会建築物を比べれば明白なように、神の言葉と人との直接の接触・対話を理想とし、神と人との間に介在物を不要とする交渉を基本とする構図だ。それはテキストへの尊厳につながる。したがってモダニズムのデザインではグラフィックな要素に特徴的な傾向として、テキストと図版の各領域を支配する引力の駆け引きの結果として生じる緊張状態を演出することで調和を実現する行為だ
ここでのテキスト以外の要素である図版もまた最小限に絞られ、図版の提示において複雑な技法や技巧を裏に隠すことで、紙面の集中力を表出させる。またテキストと図版のレイアウトは、計算された数値換算可能な秩序管理の下で計画的になされる。そこに生じる静謐簡素なデザインの表情は、見る者に視覚の愉悦を誘うこともあろう。テキスト(言葉、メッセージ)やデザインの説得力を提示する目標が期待される。そこでは空白は残ったのではなく「残した」のであり、その白は意味を孕み、墨(黒)のテキスト部分や図版と等価値の扱いとなる。
スペンサーはプロテスタントに特有で支配的な志向における形式の中立化や標準化だけを紹介したのであり、根拠は示さなかったという意味として捉えることができる。彼には“Typographica※27”という雑誌発行における貢献度での評価がある。
彼の言葉に「タイポグラフィの実践者の個人的な貢献は、テキストの書き手のメッセージをわかりやすく的確な形式に翻訳できる能力にかかっていますし、その能力に限定されねばなりません」がある※28。ここでは書き手の方、つまりテキストの方に重心がある。スペンサーは「存在根拠たるテキストに常に従う」とも述べ、テキストがあって初めて成立し、「テキストに従属する状態」がタイポグラフィの役割だ、と指摘する。
再現による描写:ヘルムート・シュミット
エミール・ルダーに師事し、私的には小文字主義(自分の文章には大文字を使用しない。大文字を一種の権威的存在と捉えた)に徹し日本で後半生を過ごしたシュミット氏は、モダン・デザインの洗礼を受けた。
彼はデザイン書である“typography today※29”を企画して自らも文章を寄せている。その中で‘Typography, seen and read’と題して次のように述べている※30。「タイポグラフィは見えて読みやすいだけではありません。それは聞こえなければ、感じられなければ、経験されなければなりません。現在ではタイポグラフィは(文字などを)配置することではなく、描写することを意味します」※31。「視覚で示されるものについて求められていることは、いわば文章の内容の中にすでに具現化されています」※32。情報整理というレイアウトを超えてさらに踏み込む意図が明確だ。
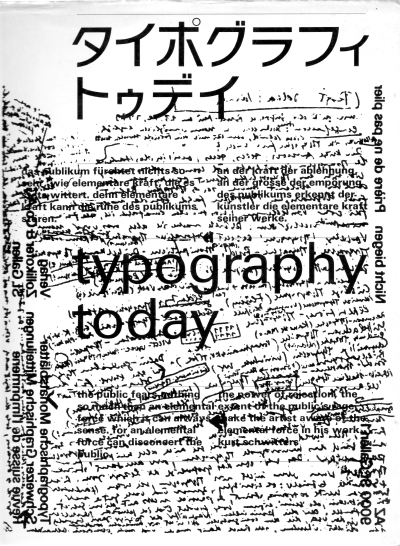 [図7]ヘルムート・シュミット『タイポグラフィ・トゥデイ』(1980)
[図7]ヘルムート・シュミット『タイポグラフィ・トゥデイ』(1980)
この引用英文の中でとりわけportrayという語に注目した。ここで「描写」と訳出した部分だ。実は“typography today”の中ではportrayが「表現」と和訳で紹介されているので、『領域』の中では「描写」とあえて訳し変えた。Portrayの名詞形はポートレートとして日本語化して使われている。Portrayには「描いて前に出す」という原義がある。英英辞典によれば「特定の方法で何かを記述するまたは示すことで、とりわけ完璧または正確な印象を与えない場合に記述または示すこと」「映画や演劇で特定の役割を演じること」であることから、説明的な意味合いが強いことが分かるだろう※33。このportrayやその名詞形のportrayalは、かなりフォーマルなdepictやその名詞形のdepictionとも通じる。
Portrayには我々日本人が使う比較的に軽い「表現する」という響きとは異なる受け取りがある。日本語の「表現」はおそらく結果に重点が置かれ、英語の「表現する」にあたるexpressには「内面の抵抗に打ち勝って外に出す(ex + press)」語感と主張性が強く、過程に重きがあるようだ。ここでのportrayには「詳しく説明する」意図が明らかで、自己主張的な響きはない。したがってここでportrayを「表現する」と和訳することに抵抗を感じざるを得ない。
シュミット氏の要請には、書き手の代弁者的な立場にあることで達成できる技芸がタイポグラフィだとする意向がうかがえる※34。
また、視覚提示へのヒントは「文章の内容の中にすでに具現化されている」との言及もあることから、デザイナーの仕事は、テキスト中の言葉とテキストの構造の中にデザイン上のヒントを見つけ出すこと、という意味ととれる。文意の具現化とは、書体の選択や組み方による視覚世界での描写を指すだろう。
「再現・描写」では対象が前提とされていてそれを客体として扱う。だが「表現」では、自己の内面の葛藤を経た表出に力点があることから、主体そのものの行為である。
4. 新たな言説:『領域』出版以降に見出した言葉
次に『領域』で取り上げられなかった4名の記述を紹介してみる。この人物たちからタイポグラフィの意味を具体的に確認し、共通項を抽出することが「再現論」の確認と再考にふさわしい。
書き手への奉仕:フランシス・メネル
メネルはイギリスの出版人である。1923年にナンサッチ・プレスを設立して、埋もれていた小説・詩歌を含む文芸書を復刻発行したタイポグラファだ。メネルの言葉は『領域』では当時未読のために紹介していない。以下にいくつかの引用を試みる。
- 書物の物理的な心臓や頭部は、印刷されたページにあります。つまり、印刷者の扱う活字として目にされて判断される書き手の言葉の形象です※35。
- 書物は分かりやすくあるべきで、書き手の目的への誠実な奉仕です。……時として書き手の意図を増幅したり、独自の意味ある形に仕上げたりすることです※36。
- 派手に着飾った書物ではなく、絶妙にして程よくまた出しゃばることなく、書物への思いで身をまとった書物を求めているのです※37。
Francis Meynell “English Printed Books※38”
「書物の心臓は、書き手の言葉の形象」や「書き手の目的への誠実な奉仕」という言葉、ここに残された言葉の地味な輝きにこそ、メネルという人物の見識が垣間見られる。この特徴的な表明は、書き手の立場を常に意識している態度であり、書き手の言葉を活字という手段で丁寧に「置き換える」「演出する」ことにタイポグラファの役割、つまりタイポグラフィの技芸の核を捉えていると考えて差し支えない。
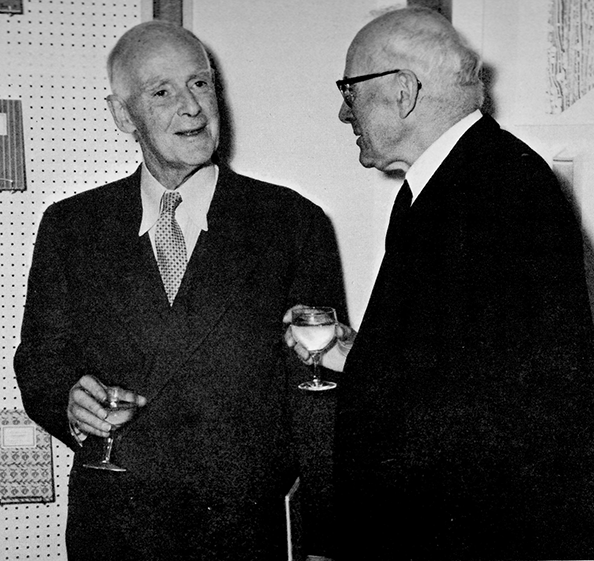 [図8]フランシス・メネル(左)とスタンリー・モリスン(右)
[図8]フランシス・メネル(左)とスタンリー・モリスン(右)
メネルは、書体選択ではその姿勢が一貫していた。私はかつてナンサッチ・プレスの全貌を記録した書籍の詳細な記述式出版目録※39から、発行書籍142点(194冊)で使用された活字書体31種類の使用リストを作成し、書体と著者・ジャンル・時代などの傾向を分析したことがある※40。そこでメネルが明らかに著者に関連する事柄を基本に据えて書体を選択していることが見えた。著者の出身地と生きた時代を中心に、さらに書物の内容やジャンルを核にして、総合判断して書体を選んでいたことが明らかになった。
メネルの逸話が彼の手紙の中に記録されている。ある企画で扉ページのデザインの最終案が決まるまで、27通りの扉の組版を試み、納得するまで待ったという。他者と自分への彼の誠実さと執拗さがうかがえる記録である。テキストへの敬意が己の熱量を高めているようだ。タイポグラフィの実践上の動機と使命感が強烈に自覚されることで、このような仕事が可能となる好例である。
内容への敬意:ロバート・ブリングハースト
ブリングハーストはカナダの詩人であり書籍デザイナー、そしてタイポグラファとして活躍しているそうだ。彼の文学者としての資質や立場がその著作“The Elements of Typographic Style※41”を、文体的あるいは語彙的に特徴付けている。この書籍は、20世紀後半から今世紀初頭にかけて世に現れたこの種の分野で群を抜いた充実を示しており、俯瞰的ながら詳細かつ深く著者の説が展開されているし、独自の書体分類案も提示されている。タイポグラフィが言語表記と密接不可分であり、また言語表記の理解と普及に大いに役立っていることも再確認できる。
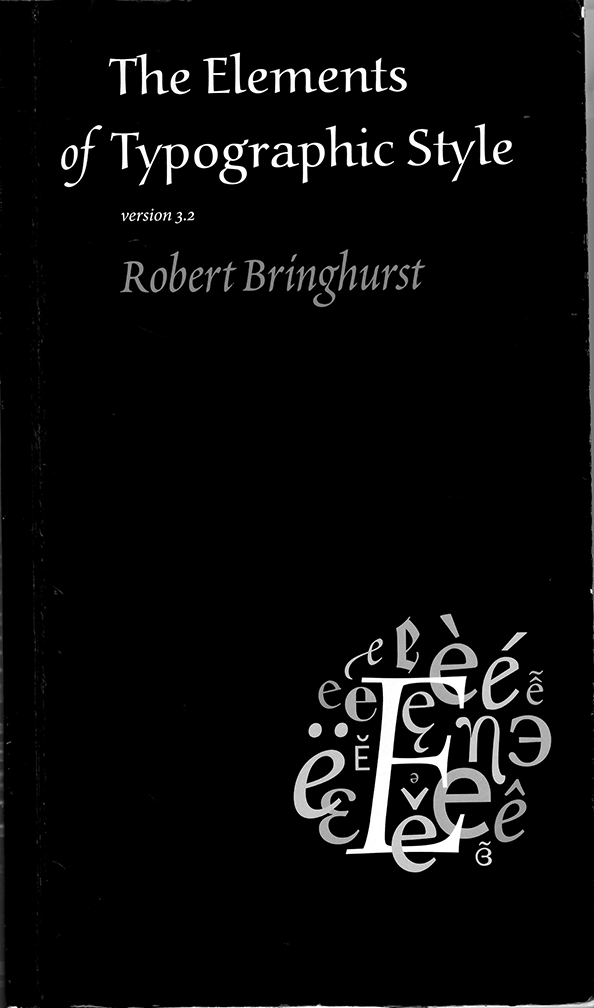 [図9]Robert Bringhurst “The Elements of Typographic Style” (1992)
[図9]Robert Bringhurst “The Elements of Typographic Style” (1992)
その裏表紙に書体設計家のヘルマン・ツァップは、推薦文を寄せている。「ブリングハーストという専門家によって書かれた本書は、タイポグラフィのデザインが時としてデザイナーにとって私的な自己表現の形式だと誤解されている時代に、とりわけ歓迎されます。……この本がタイポグラフィのバイブルになることを願っています。」と出現を待ちかねたように称賛している※42。デザイナーの恣意的な欲求表現の素材扱いとされかねないオリジナル・テキストへの低い意識や活字書体を乱暴に扱う者に対して警鐘や不満が込められており、温厚なツァップ氏の怒りとして傾聴に値する。
“The Elements of Typographic Style”にはブリングハーストによる膨大な量の貴重な言葉が記されている。以下に総論的で本質的言及の見られる最初の章と「まえがき」から引用する。
- タイポグラフィが現実に生きるとは、内容に敬意を払うことです※43。
- タイポグラフィの行動は、内的構成を置き換えるのではなく顕在化することです。……タイポグラファは、音楽家であり、作曲家であり、著者も、他の芸術家や工芸職人と同じように、往々にして仕事をこなして、姿を消さなければなりません※44。
- タイポグラフィを納得するには、本文を解明する、そしておそらく本文を高めることから始まります※45。
- タイポグラフィは読者に対して次のように役立つ方が良いのです。つまり、テキストへ読者をいざなう、テキストの趣旨と意味を表に出す、テキストの構造と秩序を明らかにする、テキストを他の要素と結びつける、読者にとって理想的な状態である活動的な休息へと誘います※46。
- なんとでも言えるタイポグラフィですが、それは塑像に見られる優雅な透明性のようなものを切望します。別の古くからの目標は耐久性です。変化のための免疫性(変化に耐えること)ではなく、流行に対する優越性(流行現象に惑わされないこと)です。タイポグラフィは超時代性と時代性につながっている言語による視覚造形(形式)です※47。
- タイポグラフィではテキストは台本に対する演劇監督、譜面に対する音楽家です。……タイポグラフィという外側の論理をテキストの内側にある理論の中に見出そう※48。
Robert Bringhurst “The Elements of Typographic Style”
第1章の冒頭でタイポグラフィは「内容に敬意を払うこと」に存在する意味がある、と宣言する。そして、文字表記による視覚造形論理がタイポグラフィであり、それはテキストの筋に沿って対応することで役割を果たし、かつまた姿を隠す透明性を認識すること、そして主人公であるテキストを生き永らえさせる耐久性の確保に従事することが特徴だ、と理解できる。
ブリングハーストは多彩な例を挙げて自説を展開する、そして全体としては書き手と読み手の双方への比重が均等に意識されている。つまり、タイポグラフィの実践者の中では両者が常に同時に意識されており、分けられないということだ。
本書は手軽にすぐに理解できるマニュアルでも技術書でもない。タイポグラフィの主要な仕事を言語化すると、これほど大量の知識と慎重な考察が凝縮されるという実態を読む者に突きつける。タイポグラフィとは、小手先の気軽な仕事とは到底思えない専門職である。
介在の余地と画文共鳴:白井敬尚
白井氏はこの国で最も強くタイポグラフィに意識と関心を抱き、最もタイポグラフィを追究しているデザイナーの一人であろう。とりわけ欧文書体への造詣と実践が際立つ。伝統あるデザイン雑誌『アイデア』に10年間従事し、そのデザインとディレクションにおける腕が広く評価された実績を持つ。近年「組版造形展」を開き、グラフィック・デザイン界でおそらく国内で初めて文字組版中心の制作物を展示して、注目され話題を集めた。アジア諸国でも注目を得ている。とりわけ彼の編み出したいわば「多重グリッド」とも呼ぶべき柔軟で斬新な課題対応法があり、その工夫は独特である。
彼への評価の特徴は、出版編集者から注目されていることにある。これはおそらくかつてなかった逆転評価であり、稀有で好ましい関係であり、本来の紐帯が構築され始めたと言える。タイポグラフィは編集作業と緊密である関係が理想の状態のはずだ。
タイポグラフィにおける造形は、見易さや読みやすさを支援した結果であり、組版の造形そのものに言語伝達の本質があるわけではありません。けれども書体の形をはじめとする組版の造形には、時代の感性と技術、歴史の記憶、身体が感知する圧倒的な量の非言語情報が存在しています。テキストは、これらの非言語情報によって「形」を与えられ、視覚言語としての機能を果たすことになるのです。
読者はテキストを読み自らの内部でイマジネーションを働かせ、場面や情景を思い描くことでしょう。言語伝達にとって理想の「絵姿」とは、このように読者それぞれのなかに描かれるものであって、そこに組版の形が介在する余地はないのかもしれません。だが、しかし、それでも、と、組版の形にどうしようもなくこだわる自分がいます。ページをめくる瞬間、テキストを読む前の一瞬、そのほんの僅かな時間に組版は読者と出会います。その時テキストは期待と予感に満ちたものになっているか否か——組版造形の意義とは、その一点に尽きるのではないかと思うのです。
白井敬尚「組版造形展 白井敬尚」図録ポスター
引用冒頭文は、自分はタイポグラフィの本質的なこととは離れた位置で仕事に関わる、という表明に一見すると受け取れる。だが何気ないが、心しておきたい貴重な言葉だ。書き手を念頭に置いたメネルにつながる読み手への配慮が見られる慎重な態度表明で、造形者としての白井氏の姿勢はここで明快である。総じて、「非言語情報」と彼が呼ぶ組版造形に至るまでの蓄積に点火することにタイポグラフィにおける可視化の基本があると理解できる。その情報は組版者と読み手に共通する文化的共通項により成立する。「組版が介在する余地はないのかもしれない」が、実は読者に手を添えるようにして言葉を多くの需要者に手渡すことは、デザイナーの介在なしではあり得ない。デザイナーもメディアの一員だからである。送り手のテキスト・意図を何に包んで受け手に届けるか、その「渡し方の作法」が白井氏の造形化の意味だろう。だがその行為の主体は見えないし成果を証明できない。
だから、「だが、しかし、それでも」という制作者の自問と追求は自然であろう。デザイナーの役割の限界を知っているがゆえに、彼のかすかな望みは残る。望みの第1は、読者によるテキストへの「期待と予感」を裏切らないこと、第2は、読者が読み終えた後に中身に集中できて活字や組版を意識しなかったこと、第3は、何らかの「絵姿」が読者の中で展開できたかもしれないことへの期待である。相手に思い描かせることを支援する技にかすかながらも望みなくして、この綱渡り的な仕事は続けられないはずだ。
また、白井氏の表明は、ある意味で一瞬の勝負で決まる要素が大きいこと、また気づかれない部分や細部が全体を支配していることを熟知している言葉でもある。当たり前に文字が読める、という本質的状態の実現の中にタイポグラフィの基本的な貢献があるとの自覚があるだけに収まらず、そこを一歩踏み出している。つまり「追」がある。
読者からの一瞬の注目を最初に浴びるという言葉の海への導入以上のことに携われない限界を知る故に、テキストへの案内役としてのタイポグラフィの醍醐味に気づいたデザイナーの言葉だろう。その繊細さに裏打ちされた細部の微調整という職人的作業が表に見えない場合と、その繊細さと大胆さが同時に表に彷彿とうかがえる場合との、双方を駆使できる柔軟な仕上がりにこそ、白井氏の真骨頂がある。
彼の常の課題と意識はおそらく「画文共鳴」にあるだろう。それはテキストと図版類との共鳴・共存という状態であるが、そこに彼の技芸が挑み、映える。そこでは時に対決や調和や差異化などの変化を伴う。図版と本文という関係の構築と調整に、彼の隠喩的手法が密かに味をふりかけているようだ。
白井氏はヤン・チヒョルトに影響を受けており、「タイポグラフィの目的とは決して自己表現の類であってはなりません」というチヒョルトの言葉を肝に命じているようだ※49。さらに、彼が私に語った次の言葉にその滋味ある関心の程がうかがえる。「昔の組版職人が志しても技術的な制約があって実現が困難だったこと、彼らが実際に挑戦できなかったことはどんなことだろうかと我々が想像する。そこに現代の技術で可能であれば実現に挑戦する価値がある」。時代を経た書籍やそれに関する歴史に触れなければ、口から出ない言葉である。
よき伴奏者:鈴木丈
デザイン論考サイト「エクリ / ÉKRITS」に掲載されたエッセイ「音楽、数学、タイポグラフィ※50」では、ウェブ・スクリーン上での文字生成についての試みが述べられている。鈴木氏はその文章の中で、次のような言葉を記している。
言葉で書かれたコンテンツを届けるということは、歌手が歌うということであり、ピアニストがソロを弾くということです。その時タイポグラフィに求められるのは、そのメロディを力強いリズムと美しいハーモニーで支えること。よい伴奏者、優れたバックバンドであることだと思います。
ここでも先に紹介したブリングハーストの快著“The Elements of Typographic Style”での解説が紹介されている。ハーモニー、リズム、メロディという音楽の要素と「調和数列」という数的秩序を基に文字組版への捉え方を比較していて、斬新である。このような新分野からのタイポグラフィへの言及こそ当然ながらあってしかるべきであると言える状況だ。
オンスクリーンというメディアでタイポグラフィに取り組む必要がある鈴木氏の姿勢は、ここに明快だ。歌手もピアニストも、ともに作詞や作曲というオリジナルの制作つまり独創案の存在なくしては成り立たない。新メディアにおけるタイポグラフィのあり方は、曲の「伴奏者」「コンテンツを届ける」「バックバンド」という例えから、それらが主役を支える確実で必須の役割を果たす技芸であり、デザインにおける書体の扱い方がメディアを問わず本質では変わらないことが確認できる。タイポグラフィが文字情報の整理のための不可欠な支持体だとの自覚が読み取れる指摘である。
鈴木氏は結びの段落で次のように述懐している。「タイポグラフィの作業をしていると、いつしか偏執狂的に細部を追求しています。その度に、独りよがりの美意識を読み手に押し付けているのではないか」。ここには彼の正直で健康な意識がうかがえる。また、「まだ始まったばかりのオンスクリーンメディアのタイポグラフィの可能性を、より開かれたものにするための試みなのです」と終えている。ここに仕事の役割への彼の自覚が表明されている。この言葉は、ウェブ系デザイナーの中で時代の技術に対応できてタイポグラフィへの重要性に気づいたプロが既に登場していたことを示す。遅まきながらも機が熟したことの証として捉えたい。
そしてこのようなデジタル環境による状況の変質は、今後のタイポグラフィの方向を暗示している。元来はファウント(fount)だった「フォント」という専門語が意味を変化させつつも大衆化し、パソコン内にデフォルト搭載されている文字書体に自ずと関心を持つ人が増えた。またマイ・フォント志向もある現状などと合わせて、ここに鈴木氏が紹介している、パソコンの操作を担う者自身が組版を調節・選択できる事態などを重ねれば、主に公的用途として数百年に及ぶ複製のための技芸が、一定の制約はあるものの私的自由度が保証された自己管理装置の上に展開される個的環境となり得ていることを知った。そしてタイポグラフィ実践のための要素が自己の嗜好や流儀で管理できる状態、つまり組版的要素がかなりの程度の自己流を反映できる装置の中へと拡張している実態がある。
デジタル環境は、個人的な色を出しやすくなる場となった。それはある意味で千年を超える大衆化した手書き式文化のアナログ的な筆記状態へと、作業環境を変えつつも先祖返りする状態が一部で生じることもあろうかと予想できる事態に至ったことを意味する。紙媒体を介在させないプライベート・プレスもあり得る状況だ。
また例えば、自分の筆跡を元に自分用のフォントを備えるという行為には、手書きの癖を自己同定確認(アイデンティティ)として確保したがる人間の避け難く根強い欲求が覗ける。そこにタイポグラフィという公的技芸が私的技芸へと浸透し変質する領域が現出する。
ただし後述するように、ここでも己のテキストを客観視しつつ社会的に発信するためのデザイン志向が必要となろう。何故ならば、その行為はどこまでも文字で意思を特定または不特定の多数に正確に伝える媒体を通過することを考慮すれば、一定の整理作業が必要となるからだ。その文字情報整理の作業には、己の表出した文章であろうが、一度は対象素材として客体化しなければならないからだ。
また鈴木氏は数学や音楽をタイポグラフィと結びつける貴重な視点を確認したが、それと関連するもうひとつの視点も必要だろう。それは造形や視覚に関わる心理学や認知学である。タイポグラフィの理解では、科学的分析や証明が困難な分野であることで、これまではその知見や常識の多くは経験則を基に語られている。例えば読みやすさについてだけでも、統計や調査にはかなり複雑な要素が絡むし、大規模になることが予想されることで、客観性の確保が困難な故に限定的だった※51。だが、少なくとも、紙媒体中心の視点を排除するならば、ウェブ・スクリーン上でのあらゆる規模と種類での調査は、従来と比べて実現性が高くなるだろう。
多くの新語が新技術の発展に伴って20世紀後半から流通し始めたが、この鈴木氏の記事により、その種の技術用語ではなく、デザイン上の新しい語彙がタイポグラフィ分野の専門語に加わる契機となることを期待できる。新しい分析的視点の導入は、関係者からの理解を得るために歓迎されるだろう。ただし鈴木氏ならずとも、この分野の語彙はできるならばカタカナ語のままではなく、和訳するようにお願いしたい。それが技術の受容と親近性確保への重要な要素だからだ。
5. 共通点の確認
介在者
これらの言説から共通して見えてくることは、各人が基本的には同じ内容を語っている事実である。ある人は文章の書き手に、またある人は文章の読み手に、それぞれが仕事の現場で意識する温度差はあるが、彼らの基本認識ではあくまでも書き手の代弁行為であり、書き手の言葉をその受け取り手である読者に有効に伝えるための技芸こそがタイポグラフィだと確認できる。つまりメッセージを伝えるメディア(media)であり、仲介者であるとの自覚だ。
英単語mediaの綴りにあるmed-やmid-はともに「中間」を意味する。したがってmediaとは媒体であり、言葉を送る側と受け取る側の間で仕事をこなす中間的立場に立つ仲介者だ。ギリシャ神話に登場するヤヌスは、顔の前と後ろに目を持つ。タイポグラフィの実践者にも、2つの立場を同時に考慮する意識が求められる。
2つの役割
デザイナーが、そして今では絶滅危惧種たる伝統的な意味でのタイポグラファが、扱う素材をテキストに焦点を合わせていることが明瞭であった。そのことは、モリスンの指摘にあるように、テキストの目的によって、基本的理解のためには2種類ある。
ひとつは書籍と、それに準じる雑誌類である。書籍という形態の立体性と平面性にデザイン上の創意工夫の要素が詰まっていること、そして内容の解釈と反応は多様でもあり、空間と時間を超えて永く読み継がれる寿命を期待できる。
他方はディスプレイ・タイポグラフィである。広告や広報の目的では、即時了解的で流行する束の間(ephemeral)の勝負である。ニュー・タイポグラフィ運動を牽引したヤン・チヒョルトも晩年にその限界を悟ったように書籍形態などの長文用には不適合が際立つし、適合させるにはかなりの力量が必要だろう。彼が提唱した運動の扱う範疇は期間限定で、期限が過ぎれば不要となる消耗品を制作するデザイン行為に有効であり、その短期の集中性と即効性が命となる。ただし、この「端物」と呼ばれる印刷物と大型の広告類でも、ともに書籍本文組みの活用もあり得る。
いずれにせよ、この言語伝達における長命と短命の対象のどちらもタイポグラフィの領域であることに変わりはない。雑誌類はこの2つの紙媒体を統合した役割を求められる。
限界の自覚から
また時には、「読めると伝わるは違う。読めても伝わるとは限らない。伝わったとしても意図通りとは限らない」という意見も耳にする。タイポグラフィが関わる範囲は、読める状態の確保であり、それは最低限の使命であり、本質である※52。次には伝わることが目標となるが、伝えはするが、伝達可能かどうかはもちろん判定不可能であるし、読み手個人の主観や読解力や想像力の問題なので、そこにタイポグラフィの介入する余地はなく、限界がある。
だが、伝えることを目指す意欲がなくては「伝わる状態」に近づけない。意味の理解は文体に決定的に依存するしそれが限界であるとの自覚の上で、まずは意味の理解への舞台を用意する準備が基本となる。その舞台には、読書環境という物理的な快適さの確保や、身体・生理上の疲労を和らげる配慮も含むはずだ。素の状態にある未加工文(書記言語)を白井氏のいう「非言語情報」の景色を意識しつつ味付け演出する、意味の流れや解釈への支援がタイポグラフィである。
匿名性
タイポグラフィを担い実践する表立った職種は、20世紀初頭以来現在まではデザイナーに移っている。私はこの技芸のこの行為には「(自己)表現」の余地はないとした。オリジナル・メッセージが表現行為である故に、その主体と責任と意図は書き手にあり、デザイナーにはない。デザイナーはそれを生かすべく料理する立場にある。デザイナーに過失や責任があるとすれば、それはオリジナル・メッセージの意図的な改竄や曲解であろう。書き手の言葉(原案創造物)の意味内容を扱う仕事がデザイナーである。言葉や文字化されたメッセージというテキストはタイポグラフィの存在根拠であり、それがなければデザイナーの仕事はあり得ないことになる。だが、オリジナルの表現者の裏に隠れざるを得ない「伴奏者」たるデザイナーの無記名性(匿名性)が必然となる。デザイナーによっては、そこに不満や鬱屈があることが想像できる。
一般的には、デザイナーの名前だけによってデザイン制作物の質が評価されることはない。基本としてデザインは売り物ではなく、したがって価格はない。あったとしてもその評価の客観性は保証されないだろう。現実上の評価は、請け負う仕事への対価に示され、目的有効性への期待と評価である。見てきた通り、タイポグラフィというデザインでは記名性が出る幕はない。自己表現や記名性に固執するならば、アーティストを名乗るべきだろう。
6. 「再現」に代わる「追創造」
楽譜と演奏の関係
そこで近年「再現」と「描写」の代わりに用意した言葉は「追創造」である。これは私の造語ではなく、中野雄著『丸山眞男 音楽の対話※53』で、政治思想史研究家の丸山氏が趣味に取り組む姿を紹介する中で使われていて、それを拝借した。
学者・丸山氏がクラシック音楽のオーケストラの役割について語った言葉が紹介された中で、丸山氏は演奏者の役割を「第二次創造、追創造」だと指摘したという。つまり「演奏者は形式的な構造や思想や時代背景を解釈することで、作曲の魂を再現する」「それは自己責任による創造行為である」。そこから演奏家は再現芸術家であり、追創造を実行する。楽譜は第一次創造つまり原作・原案(オリジナル・アイデア)であるとする言説だ。「解釈」と「再現」という語に注目する。また、「再現」は「追創造」と言い換えられていることも納得できる。
これをタイポグラフィにおけるデザインにたとえてみる。第一次創造は原稿(オリジナル・メッセージ)、追創造は視覚化、書体選択、文字組みであり、デザイナーは追創造の実践者となる。そこに「非言語情報」あるいは直接に言及されていない思想や時代背景の援用が必要とされる。
演劇との比較
この行為は、演劇に例えられる。演劇は作品・戯曲の台本は作家のテーマやメッセージであり、演出家は全体と細部を把握し、適切な指示をする。そして仕上がりに責任を負う。役者は演技する、台詞を口から発することで、第二次創造を実行する。観劇側(観客)は作家のメッセージを受け取り解釈する。
役者の演技力とは、自分の言葉でない台詞つまり(作家による)「第一次創造である既に表現された言葉」を発する。演技は表現力で示す。表現力は何のためか。それは台詞を効果的に発声するためであり、演技という言葉の意味の増幅を通して代弁者として台詞を伝えるためだ。役者のこの表現力とは、他者の言葉を表出して伝える技芸だ。それは他者の言葉を「いきいきとそこに再現する能力」であり、言い換えれば「追創造する役割」ではないか。役者個人の表現力とは、正確には「再現力」であり、表現力は再現のために活用され機能すると言える。
かつて小林秀雄氏はどこかで吠えた、「役者?それはアクセントに過ぎぬ」と。役者の上手下手は二の次であり、核心は劇作家のメッセージ(言葉)とその伝え方にあるという意味だろう。それは言語表現を第一義に置く文芸上の観点である。だが、演劇はアクセントたる身体による立体的な可視化がなければ大衆化しにくい。役者がいなければ劇としての鑑賞、演劇としての総合的な芸能は成立しない。
このあたりについて、作家の井上ひさし氏は次のように書く。「劇の形式を、いま仮に(物語+ことば)形式と言うことにします」として小説ではこの(物語+ことば)が当てはまるが、「芝居では(物語+ことば)はそのまま受け手に渡されるのではなく、物語もことばもひとまず俳優の身体に叩き込まれ、それぞれの俳優の個性や才能や技術でいっそう磨き上げられて表現されます」と説明している※54。これは役者による身体造形とも言えるし、追創造とも言える。ここでの「表現される」は、私流では「再現される」または「追創造される」となる。
さらにまたこの芸能は、観客と役者が無意識のうちに共に劇を成立させるあるいは作り上げる時間と空間を共有することでもある。さらに、役者の台詞の言い回しが公演ごとの身体状態によっても異なることもあり得るだろう。回を追うごとに納得できる芝居が多くなると思える。客の反応が演技に影響するはずだし、演技によって客の反応も異なるという、一回性の成立で、同じことが起きない刹那的な芸能だし、それゆえに興味が尽きない。
なお、タイポグラフィもメッセージの可視化であり、それは造形化がなければ成立しない。ただし、これは小説を劇化する際のいわゆる「脚色」という、再構築や省略化あるいはまた新解釈の介入などの行為とは異なるはずである。
想像から追創造へ
ここで「追創造」をさらに考えてみよう。ここにも書き手の自己表現たる第一次表現・創造が基になって、それを視覚的提示において演出する行為を目指している。したがって、その演出行為では、デザイナーは書き手の伝えたい意図である言葉・思想である表現に第三者の表現を重ねることは二重表現となり、それは違反行為に等しい逸脱ということである。
そこでその第三者たるデザイナーは書き手の意図に基づき、創造的に紙面を設計する視覚提示によって読み手に提供することになる。それはつまり「追創造」と呼べるだろう。この「追」とは、「後につく、追いかける、後から補う」という意味であり、書き手の意図に忠実に従うことであり、文章を活字書体に「変換」することで視覚的に「後から補う」という意味で使うことができ、追う対象が前提としてある。
したがってこの「追創造」は「第二次創造」とも言い換え可能であり、活字に変換することで成立を見る。ここには創造的な展開が求められるが、その内実は造形的描写と言える。そして、「自己責任による創造行為」という丸山氏の指摘は、原意尊重の上で実際の音に置き換える際の緊張した責任感なしには実現できない行為だという意味であり、その緊迫感と誠実さはそのままデザイン行為にも当てはまる。
さらに言えば、ここでの創造は「正確な解釈によって新たな対象として存在させる」ことだ。ひとつの独創表現を一層多くの人々の目前に提供する「媒体への登壇行為」である。広く伝えるための媒体への対応でもある。核となるテキストを複製手段によって多方向かつ大量に届けるための「一から多への変換行為」あるいは加工作業である。しかも、効果的に分かりやすく読みやすく、という条件付きである。
またこの「効果的」とは言葉の意味を「微増幅する」とも言えるだろう。この「効果的」の中身が創造的な色の添加である。言葉の意味の読み取りの連続に障害物なく集中できる状態の確保の上に、言葉を取り巻く物理的な環境としての書籍やそのページ展開の全体と細部に対して慎重に造形を与えることだと言える。
あるいは「追創造」とは、モノクロの写真に色彩を施す作業に似ている(その色の塗り方は、扱うメッセージのジャンルや文体などによって異なるだろう)。元のモノクロ写真には写るべき本来の色彩は見られない。だが、その単色の各部分を例えばデジタル技術で彩色再生することができる。この再生技術をタイポグラフィに置き換えれば、具体的には活字書体の選択、活字書体による組版、この2つが主な実践行為である。そのために必要なのは活字書体の歴史や特徴の理解などを素養として、解釈に基づく配置と組版以外の暗示的な構図や配色や挿絵などの追加することである。また、言葉のナレーションつまりその声質、温度、抑揚、強弱などを活字書体への変換を中心として造形化、内的音声の視覚化、意味の増幅効果による援用と言えよう。
フランシス・メネルはこのような行為を「隠喩的なタイポグラフィ(allusive typography)」と名付けた。タイポグラファによるテキスト解釈の介入がなければ、組版造形行為は成立しない。彼は介入の余地は不可避としながらも、演出におけるその解釈の核は、書き手という表現者の用いる言葉の集積や、書き手に関連する文化的・地理的な背景と考えたようだ。
先に引用した人々の抑制的ながらも著者(テキスト)のためにそれを微増幅して味付けを行う姿勢の表明を、我々は記憶すべきだろう。これも二次的創造行為である。それは決して自己を打ち出す創造ではなく、あくまで原文表現者への敬意と忠実な解釈による、読者へ手渡すまでの言葉の造形化による視覚提示である。追創造の行為は隠喩的演出によっても可能となるはずだが、これは高度な技芸や深い知識の裏打ち無くしては不可能だ。
つまり「追創造」は、テキストの「追体験」という内面のスクリーンに映る言葉から得たなにがしかの像を投影する作業から始まるということだ。それが受け手の側での新たな「追創造」を生む契機となりやすいことが理想となる。
個性の位置付け
そうなると「追創造」の実践において、デザイナーの個性は不要なのか、という疑問が湧く。だが、個性とは隠しても隠しおおせないほとんど無自覚の性質であり、またそれは否定しようがない。デザイナーの個性は抑制されるように見られるだろうが、上に述べたような意識があれば、テキストの解釈や「再現・描写=追創造」という行為では、自ずと表出してくるはずだ。同じテキストでも、異なるデザインが生まれ得るということだ。
こまごまとした作業の連続の中の各細部には、常にあらゆる種類の選択という判断がつきまとう。この各段階での判断の集積こそ、抑制しようとするも現出してしまう個性であろう。だが、その個性の否定は「追創造」とはなり得ない。個性を含むその判断は、究極的には書き手または読み手の満足度の評価が優先される。
このデザイナーの判断の集積と個性を例えて、本文用の明朝体が数種類あると仮定してみよう。その書体間の差異は個々の文字をかなり拡大してみれば、細部での差異がやっと見られるが、ストロークの抑揚の程度、ハネやハライでなどの点画の角度、文字間のつながり方や脈略、それらの差異は極めて微細である。したがって書体間の差異は一見した次元では見分け難い。ところが、各書体の文字が文章で組まれてマスとなることで、一気に書体間の差異が見え始める。その組版状態全体の表情、つまり粗密度・温度差・平滑度・凹凸度・明暗・寒暖・軽重などのテクスチャ、質感や手触り感などが少しずつ現れる。これはデザイナーの個性の表出に似ている。
また、その中での「再現・描写=追創造」の成果は、デザインが完成した結果を享受する読み手にも及ぼすはずだ。読み手の内面で文字を追う長い持続時間のうちに育ってくる、白井氏の言う「絵姿」がやがて読み手の無意識のうちに読み手自身の個性や経験の形で「再現=追創造」されるだろう。
それはタイポグラフィという技に無意識のうちに触発され発生し、自ずと展開する。デザイナーの無意識の個性は、無意識だからこそ読み手の中で新たな「追創造」される契機を促すと言えるのではないだろうか。デザイナーの個性は貴重な要素であり、また影響という面では危うさも同時に孕んでいる。デザイナーの人数だけ解釈と追創造がある。したがって組版紙面の評価もタイポグラフィの原義に含まれている。
先に業務の分業・統合の箇所で触れたことで、確認がある。それは現代ではテキストの書き手が組版者となりうる場合である。ここでも自分のテキストとはいえ、それを客観視できる力量と技術が求められることになる。ここでいうタイポグラフィのデザインとは、その種の質や体裁を整える行為を含むからだ。
7. 余論:能楽との比較
目前心後と離見
ここで伝統芸である能の舞について、本稿のテーマに通じる興味ある言葉を紹介する。梅若猶彦著『能楽への招待※55』での世阿弥の『花鏡』からの引用である。著者の梅若氏による解釈を示し、これを我田引水ながら解釈してみる。
舞において、目前心後ということがある。「目は前方を向いているが、心は自分の後ろにおけ」ということ。観客席から見られている自分の姿は、離れて人から見られている自分の姿、つまり離見なのだ。これに対して、自分の目でみようとする意識は我見である。それは離見で見ているのではない。離見で見ているとうことは、観客と同じ意識で見るということである。このとき自分のほんとうの姿がわかるのだ。その位に達すれば、目を正面に向けていながら、目を動かすことなく意識を左右前後に向けることができる、つまり自由自在に自分を見ることもできるのだ。しかし、多くの役者は目を前にすえて、左右を見ることはできても、自分の後ろ姿まで見ることができる段階には達していない。自分の後ろ姿を知らなければ、身体の俗の部分は自覚できないのだ※56。
梅若猶彦『能楽への招待』
能は謡(うたい)と舞で成り立つ。舞は、能の本であるテキストを核にして身体でその意味や心情・情景・場面を上演する57。ここでは「観客」を「読み手」に、「自分」を「デザイナー」に置き換えてみよう。「我見:自分の目で自分を見ようとする意識」は主観的に自分のデザインを眺めることにつながる。だが「離見:離れて人から見られている自分の姿」はいわば客観性の確保や、他者の目のことだろう。「目前」という意識の立ち位置は、デザイン制作物の評価が可能となる姿勢でもある。第三者にどのように見えているのか、その視線に自分を置き換える批評的な感受性や視力が求められる。
次に「目を動かすことなく意識を左右前後に向ける」ことで、制作過程を刻々検証する。ここでの意識とは、書き手の意図(テキスト)への集中であろう。それは「心後:心は自分の後ろ」に通じる。「心後」とは、全体的把握の中での時々刻々の意識だろう。読む相手を柔軟に感じる遠近感を獲得した後に、グラフィックという手法でテキストの解釈に集中する態度から生まれる広角な視界と言えるし、非独断的な把握になるだろう。またさらに、客観性の維持と異なる次元への「想像力」が生じるとも言える。その先で「創造の種」が連鎖しつつ成長し、大きく包むような自在な概念が現出する。視線は一点に、意識は全体を往還させるという離れ業である。
世阿弥はまた有名な『風姿花伝※58』において「花」という概念と語を提出して、能の鍛え方を述べ伝えた。その言語化への執念と力量に感動さえ覚える。舞の動作をひたすら無心に繰り返すことにより身体に叩き込み、自己の各年代において発揮する身体的な魅力を「時分の花」と呼び、その花を自覚し乗り越え、やがていかなる時でも自在に発揮できる究極の魅力を「まことの花」と呼んだ。「花」とは一種の「舞台的効果」であり「能が観客に与える感動」の比喩だとされる。そして観客との時々の関係のあり方が花を開かせるともいう。また歌の技巧を「花や詞」とし、舞の意図や内容を「実や心」として2つに分けたそうだが※59※60、理解は容易ではない。
タイポグラフィにおけるデザインでは、読み手(観客)に感動ではなくむしろ内容の理解へと導く機会を与えるある種の効果の実現を目指すとすれば、そこに読み手との共感を得られる才能が必要なことが理想となるだろう。タイポグラフィでも「花」という技芸の自在さを獲得できる域にまで己のたゆまぬ訓練、つまりは読解力と追創造力に当てはまる「実・心」を身につけることが望まれるのだろう。その過酷で一心な経験から得られる言葉「目前心後」「離見の見」の世界、それに「花」の存在を実感するまでの訓練、それらからも暗示を得られたようである。
8. むすび
『領域』の出版後、新たに多くの貴重な文献が手に入り、雑文を書きなぐる中で確信が生まれ、昔の著述に補足の必要性を覚え、久しぶりにこのテーマに向き合い、性懲りも無く付け足した。振り返ってみれば、何を読んでもタイポグラフィに引きつけてしまう読書癖が身についていたかもしれない。
結局、言葉に触発された想像から創造への過程の中で、言葉への敬意を払う意識の連続の果てに「再現=追創造」が実現するのだと思える。そのテキストへの共鳴という一体感は、やがて言葉の受け手に手渡されて受け手の中で映像を一層鮮明に描き出すだろう。その期待の裏には、確かにあるのだが意識されない活字の連なりがある。活字化された個々の文字には意味はないが、その文字が連なることで意味の連続が生成し深まる。それはまるでDNAの塩基配列に似た、読み取るべき膨大な文字数が絡みつつ描く意味の小宇宙となる。その概念世界は人間の日々の営みの糧になり、また遺産ともなりうる。タイポグラフィに携われることの意味は、その貴重な仕事に自分の時間を捧げる行為ではないだろうか。
なお余分ながら、書名中の「領域」は英語ではfield、realm、territory、domain、area、limitなどがあり得るが、私はsphereを与えている。この語の素に球体のイメージがあるからだ。タイポグラフィは主に平面が舞台だが、その実践における思考・感覚・技術などは立体的に中心の課題に向かって調和裏に絡むと考えている。それは主題が領域と中核の提示だからである。
いつ狂っていたのか、いつ狂っていなかったのか?何日のあいだ錯乱していたのか、何日のあいだそうではなかったのか?何日病気だったのか、何日そうではなかったのか?どれが真実だったのか、どれが誤りだったのか?真実だったのは何か?偽りだったのは何か?私の人生の記憶のなかで、どれとどれが偽りで、捨ててしまうべきもので、どれとどれが真実で、しまいつづけておくべきものなのか?
エドゥアール・デュジャルダン「過ぎ去った狂気」※1
不要不急のレイヴでラン・ザ・ジュエルズ💰
TOKYO2020、応答せよ。ウチら感染都市の乗組員。エアコンの風に吹かれて夢想してる。ここが自宅なのか宇宙船なのか職場なのか独房なのかわからない。新型ウイルスは旧型インフルエンサー。現実は早い。これはクールさを競い合うゲーム。パンデミックの人狼ゲーム。あつまれヘイターの森。
いや、どこまで加速しても、現実は遅すぎるのかもしれない。長い目で見れば。と言っても、それほど長くはない時間。コーヒーが冷めるまでの時間。夢から覚めるまでの時間。夜更けから夜明けまでの時間。エモーショナルをキャンセルして記憶のストリームを止める。すべてがムダだとわかるまで、すべてがムダじゃないふりをする。隠し口座よ、もっと潤え。
COVIDから遠く離れて、息を吸ったり吐いたりする。人混みなんて最初から大嫌いだった。でも人がいないのもつまらない。オーバーシュートしそうな心配をロックダウンして、今日も不要不急のレイヴに向かう。スマホ見ない勇気あるヤツだけ煽り運転で付いて来い。ハーネスをブラウジングして出かける。マイウェイはハイウェイ。人に会えばエロティックになれる。要は突き抜けるあの感じ。浮気なヒッピーガールに会いに行く。
歌って踊ることだけが生きる理由という事実を隠蔽する文科省。カンパニーフロウの「ブレードランナー」のようにヴィジョンをハックして、デフジャックスを通り越してラン・ザ・ジュエるしかない。怪盗ルビイはハート泥棒。乃木坂の「ザナドゥ」ってマンションに住んでる。できればこのまま、たとえばフォーエバー。
シードからウィードに魂のステージをアゲてく🚬
秒針を戻せば、ウチらはみんな2020年に死んでいたのだろう。あらゆるものが停滞し、なにもかも退屈で仕方がなかった。女の子に犬の名前をつけては、幽霊たちがざわめいていたあの夜。新しくできたショッピングモールに棲む真夏のストレンジャー・シングス。針とインクで全身に、彫刻刀で机に。彫る主体と彫られる主体。ホルスタインとパラレルな不在。お揃いのタトゥー入れよう like カーラとカイア。#ahegao上手い子、この指とーまれ!
本日あの世でワーケーション。ソーシャルメディアからはソーシャルディスタンシング。ときどきテキストするだけのカリスマ偏執狂。ゲリラガールズのマスク被った女子と美術館デート。バンクシーよりもバンクラプシーがずっとリアル。マスクレスの口元に、ブランドロゴのタトゥーを入れる。拡散希望つーか感染希望。ただトイレで自由にお弁当食べたいだけ。とにかく匂いがないのが嫌。いい匂いがすれば全部OKになるから。もっと自愛してたい。
イケイケのベンチャーがシードからウィードに魂のステージをアゲてく。抽象表現する中小企業への誹謗中傷。来るはずのない未来を想像してたら、現実の解像度が上がってただけのクラウドパンク。あきれるほどやることない。リモートネイティブは手触りを知らない。大事なことを後回しにするクセなおしたい。何歳になっても子供たちが死なないジュブナイル映画を観てたかった。
移ろう街のジェントリフィケーション。もうここでネットミームは生まれない。アーバンな盂蘭盆。毒がなきゃヴァジャイナ濡れない。ウェルビーイングはサイケデリックなメンタルケアに行き着いた。光の速度でREJUVENATEする男塾(メンズサロン)。目に見えんMANY MENが目指すスパニッシュ・メイン。厚切りオードリー・タンの爪の垢を巻いて吸って吐く。巻かれては浮上、登る煙と思惑。
ウチらの夜の街(インナーシティ)の浄化作戦(膣内洗浄)。オーガニック肥料としての糞尿を再生して作られた食料を食べて、産業廃棄物だけでリメイクされた服を着る。廃棄前提 ON THE RUN. シケモクくわえて IN THE SUN. ネットで見た景色を確認しにDOWN TOWNへくりだそう。
STAY HOMEつーかSTAY HOODで蜜ってる🏕
誰もが誰かの日記を読みたがる。「或るコロナ脳者の手記」というフェイク文書は、最初からグリッチノイズまみれのコピーのコピーである写本のスキャンだった。身分証明書のコピーを用紙に糊付けするときには、裏面に名前を書いておく。剥がれても誰のものかわかるように。自分が誰なのかわかるように。集合体としての自己しか持ちえないかもしれないのに。
フェイクとは偽物があるのではなく、真実がいくつもあることであり、すべては選択に委ねられている。マスクをするのかしないのか。どちらが表で裏なのか。不織布かガーゼか。右耳から引っ掛けるか左耳から引っ掛けるか。マスクの紐にイヤホンのコードは通すか通さないか。真実をひとつしか選ぶことができないのであれば、すべては信仰の問題になる。
誰にも信仰を区別できないから、不可避的に信仰のキメラになる。自意識のレベルでは黒マスク原理主義者で、行動においてはマスクレス派のCOVID-19不可知論者。量子レベルでのシンクレティズムが進みながらも、ピュアな単一信仰を自認している。
信仰によって生活様式が変わってく。新しい生活様式。古い生活様式。きれいな生活様式。おいしい生活様式。ていねいな生活様式。ヒップな生活様式。ジェットセットな生活様式。獣のような生活様式。嘘みたいな生活様式。生きてるのか死んでるのかわからない生活様式。最高の復讐である優雅な生活様式。生活には様式しかないから様式の無い生活をしたっていい。それはポストコロニズムの生活様式。
ウチらは他者からウチらを同定するしかないが、他者の信仰のうちのどのレセプターが機能するかは不明確なので、ウチらは可能な限り多くの他者と接触して、ウチらのほんとのトゥルーリアルな形を定めていく。STAY HOMEからSTAY HOODでEVERYBODY IN DA HOUSE. ウチらのフッドはいつも密。密いのがいい。密いのがいいよ。だってギュッてするでしょ。密ってる?密ってぬなら、密ってく?
治療薬のない夏から抜け出すためのコロナパーティー😷
コロナパーティー・トゥ・コロナパーティー。ティピカルな悪としての濃厚接触。それはNO COST接触だったり、NORTH COAST BAD接触だったり。接触不良より濃厚接触の方が悪いかな?希薄なのはどうなの?どっちがクール?90年代初期のウェアハウスパーティーみたいに、ネットでパスワードを入手して、サウンドシステムが持ち込まれた廃墟に向かう。モーフィアスみたいにフロアを焚きつける。山手線クラスター爆弾がゴジラに突っ込むみたいに。
ベイビー、それでもリアルなのは電車の中で吐いてるやつなんだ。それでもやっぱり希薄なんだ。夏へのフォビアで呼吸もできない。希死念慮を燃料に粘土のような呪詛を垂れ流して岸辺までたどり着いた。メディア関係者に向けた自殺対策の手引きを読みながら、治療薬のない夏から抜け出す方法を吟味している。ちゃんと夏に抱きしめられたい。マスクをして対面しない姿勢で。
Zoom保守派の連中は、上座と下座や入退室ルールを決めたがる。でもここは部屋じゃない。マナーはテンポラリーな関係を確かなものにする道具立て。マナーで序列を展開してディスプレイを解釈し、その場での身体のありようを決定する。ディスプレイと身体を結びつけることで、それぞれの行動を規定する。これはディスプレイという空間における権力発動の手段であり、人為的に空間を構成する建築が誕生の瞬間より維持し続けているプリミティブな機能だろう。そういう言ってる間に「ミーティングは終了しました」。
They wanna Zoom Zoom Zoom. まるでドレーとクールJ。ほんの一瞬ハッピーな気分になるためのZoom飲み。あの子は録画OK。リングライトと修正機能でZoom盛りして、Zoom勝ち組の彼と101回目のZoom。遠隔でチャHして存在を見つめてる。でもラグって一緒にイケない。オンラインマナーをアップデートすることで安定して存在する。ねえ、オンラインマナーつくろう。ウチらだけのマナー。LOVE OVER RULES.
気圧低いと調子悪いし欲しいものもわからない⛅️
ハマってる晩夏、抜け出せない。サマーチューンは永遠。サマーチューンだけが永遠。ずっと言ってるね、これ。何も言わないでいるために、恐ろしいくらい言葉を費やしている。主語よりも速く、自己が大きくなる。すべてがそうなってしまうか、すべてがそうでないかのどちらか。カテゴライズするとすぐ内面化される。これだけは言える。菅田将暉が好きな女は気圧低いと調子悪い。
ノンバイナリーでジェンダーフルイドだけど、インターセクショナルなXジェンダーは、ある意味で中動態だし相互包摂。割り切れない問題は割り切らずに置いておきたい。「二項対立を超えていきましょう」派と「二項対立かそうじゃないかという図式が二項対立だ」派が、互いに「あなたとは議論にならない」と飛沫を飛ばし合う。女帝とステップを踏む東京の完全勃起(マウンティング)。
キャットファイトがはじまりそうな街のムードは悪くない。価値が暴落した女の特権を、精神年齢7歳ぐらいのかわいい男の子が無邪気に奪っていく。オスに必要なメスの成分を大量に自家精製して自己精算しながら自家中毒になってる。それって男性の女性性だし、女性性の男性性性とも言える。そんな夜も港区女子は青山墓地で運動会。ねえねえ、さっさと潮吹けば?
生権力や規律権力を超えて、鳳凰ビヨンセの独裁的な主権権力を希求する人民。自分が思ってるような自分として見てほしい欲求に駆られて、今日もずっとテキスティングする。自分はツイートばっかりしてるのに、ツイートばっかりしてる他人が嫌いな理由教えて。本当に欲しいものなのか、欲しいと思ってるだけなのか、欲しいと思わされてるのかわかんない。思うようにいかない現実に、破れかぶれの虚構を重ねる。そうやって実装されてる自意識。
トーストのバターみたいに薄く延ばした夏の夜🍞
We’re so 2020. もう誰もSNSにテキストをドロップする意味がわかってない。とっくに終わってる8月の終わりに向けて、失われた夏が弧を描く。フラクタルな季節の中で水分を放出する新規感染者数グラフ。「もうあのお店に行けないね」とか言ってる間に、夏終わるね。実家帰った?フェス行った?海見た?夏はきみのことを待ってたんだ。部屋でMac Millerのラストアルバム聴いたりしながらさ。
JR新宿駅で降りると、向かいのホームの向こうに海が見える。南口からは水平線しか見えない。そして歩道橋から飛び込めば、橋脚にまとわりつくやわらかい水面がゆっくりと近づいてくる。珊瑚の形状をモデルに身体が再形成される。波打つコンクリートに張り巡らされた修悦体が水中を漂う。鼻腔から吹き出した大きな泡が太陽を分割する。波の表面に海棲哺乳類のぬるぬるとしたシェイプが透けて見える。
フラッシュフォワードする死。半径5メートルの死体置き場に過ぎ去った会話がどこまでも蓄積されている。拡張する身体から偏在する存在へのデジタルトランスフォーメーション。部屋に転がしたままの自作のジェムリンガ。エモーショナルの奴隷。ヒューマンよりもヒューマン。かわいそうに思ってメッセすると、勘違いしてファム・ファタられちゃう。
ようこそ、ポスト・ポスト・ポストヒューマンの時代へ。ヘロー、ヘロー、ヘローアゲインからアローンアゲイン。もし電車でこのテキストを読んでるなら、すぐに降りたことのない駅で降りて、そのホームから見えるもの全部を記録して。それがあなたにとって意味を持つ最後のテキストになるから。知りたいのは、今日の肌感。
ベイビー、本当の人生はジェリービーンズの中にしかない。胡桃の中の宇宙。頭の中のポークビッツ。バターコーン味の通過儀礼。棺桶みたいなレーズンサンド。トーストのバターみたいに夏の夜は薄く延びる。ここは2020年TOKYO。感染都市のミッドナイトゴスペル。スペースキャスターたちよ、帰還せよ。インサイダーで密くなろう。
村津蘭:
ナターシャさんは2016年からモンゴルのマルチスピーシーズ医療について調査されていると伺っています。まずその観点からコロナウイルスについてのご意見をお聞かせいただけますか。
ナターシャ・ファイン:
私は現在、モンゴルの医療と知識の伝達について研究する国際チームで活動していて、その一部は「ワンヘルス※1」という概念の枠組みに関係しています。ワンヘルスとは、人間への医療と動物に対する医療、そして環境的な要因を組み合わせる、比較的新しい医療的な枠組みです。この種を超えた学際的なアプローチは、人文学や社会科学の中では今まであまり探求されてきませんでした。
私たちのプロジェクトのひとつの課題は、フィールドワークを通して、ローカルの文脈の中で用いられてきたモンゴル医療を、どう文化横断的に見ていくかということです。ちょうどマルチスピーシーズ的なつながりに焦点をあてたマーモットとペストについての論文を2本書き上げたばかりなのですが、そのひとつはマーモットと(ウイルスの媒介動物である)蚤、ペスト菌、その他の種が、どのように相互接続的な社会生態の一部であるかについて注目したものでした。モンゴルの牧夫はマーモットを狩って、珍味として食します。マーモットに強力な治療性があると感じているのです。モンゴルでは毎年数件、マーモットを狩った若い男性がペストで亡くなるケースがあるにも関わらず、マーモットに対する古くからの文化的な伝承やコスモロジーにおける知覚は、ペストへの恐怖に勝る傾向があると言えます。
コロナウイルスもまた種を超えた病で、最近はウイルスがどこから来たのか、それが潜んでいるのは蝙蝠か鳥なのか、その媒介体となるのは何か、センザンコウなのかジャコウネコなのかなどの議論がされています。しかし、このように素早く変異するウイルスは、種の間の差によって可鍛性が高くなるため、出所を特定するのが困難です。私は、このようなウイルスの発生源に着目して、場所を明確に特定して責任を配分しようとするのではなく、ウイルスが異なる種の間を移動するあり方や、私たちにとって採用可能な予防措置に焦点をあてる必要があるというエベン・カークセイ※2の意見に賛成します。
コロナウイルスを国内に入れないように、モンゴルはよくやっているといえます。その理由のひとつは、遊牧を主な生業とする国家として、しばしばペストのような動物由来感染症の病気や、ブルセラ病や口蹄疫、炭疽病のような人獣共通感染症に対処しなければならなかったからだと思います。本来彼らは、生物科学の医者や獣医が、人獣共通感染症に対抗するためには種を跨ぐ病に注目することが最良な方法だと言い始めるずっと前から、何千年もワンヘルスの枠組みに沿ってやってきたのです。
モンゴルでは、病に対する検疫や隔離に長い伝統があります。例えば去年の2019年5月初旬に、薬として生のマーモットの肉を食べて亡くなった夫婦がいましたが、彼らがいた地元の町では即座に隔離が宣言されました。モンゴル人はこのような対策に慣れているのです。しかし、牧畜コミュニティにおいて、病の予兆に気づいたときの対応は、どちらかというと予防法に関するものです。例えば、馬が鼻水を出していたり躓いたりするのは、馬インフルエンザのサインかもしれなかったり、見張り役のマーモットが警告音を出すことに失敗し鈍い動きをしているのは、マーモットの群居地にペストが潜んでいるサインかもしれないといったことです。ですから、政府はワクチンなどの生物医療の技術と、牧畜コミュニティが持つ病の前兆や予防実践に関する知識を統合するべきなのです。
§
村津:
私たちの医療や健康の考え方に、コロナウイルスはどう影響を与えたと考えますか。
ナターシャ:
コロナウイルスは、人間の身体と健康だけに着目するような、人間中心的やり方ではいけないという、私たちの認識を高めたと考えています。生物医療や西洋医学の枠組みはとても細分化されています。アネマリー・モル※3は『多としての身体』を出版し、医療システムが異なる存在論としてどのように分断されているのかを手際よく示しました。また、彼女とジョン・ローはカンブリアの羊について書いています※4。彼らは、農夫たちの羊に対するある見方に対して、獣医はまた異なる見方で見ていること、さらに疫学者もまた異なるスケールで見ていることを指摘しました。人類学者や社会科学者として私たちがしなければならないのは、これらすべての異なるパースペクティヴを、健康という観点でどのように結び付けられるのか考えることです。
モンゴルの医療はより包括的なものであって、さまざまな側面を別々の領域的なカテゴリーにただ振り分けるものではありません。治療師(healer)は、特定の薬用植物を、出産した後の牛にも腎臓に問題を抱えた人にも、処方する場合があります。違う分量で、おそらく他の特定の材料と混ぜたりする形で。ここで問題なのは、新しく変異した毒性のある病に対抗するには、どうしてもワクチンに頼る必要があるために、伝統的医療で対処できないことです。このように素早く広がる病とどう向き合うかについては、何世紀にもわたって蓄積された知識がないのです。
しかし、モンゴルの医療が得意なのは、免疫力を高めて健康を維持し、周囲の土地(ノタック)を見守りながらバランスを保って、このような病を初期段階で予防する方法を考えることです。この性質は、日本や中国、チベット、アーユルヴェーダのような、多くの異なる伝統医療のアプローチにも共通していると思います。モンゴルの医療はあまり知られておらず、もともと多元的で、他の「伝統的な」医療技術を受け入れていますが、モンゴル高原に特有の長年の実践も多くあるのです。

村津:
調査について言えば、ナターシャさんはテクストを基盤とする従来の民族誌(ethnography)だけではなく、民族誌映画(ethnographic film)も作成していますね。今世紀に入って、映像の技術的な発展と人類学におけるパラダイムシフト、特に象徴的な構造から実践や感覚に力点が移る中で、民族誌的調査を構成するものとして、映画制作に対する関心が高まっています。今日、映像人類学者は実験的なものからフィクション映画まで、さまざまな映画制作のスタイルを使っていますが、その中でも「観察映画(observational film)」は主要な位置を占め続けています。ナターシャさんも制作方法として採用している「観察映画」は、1960年代の移動可能な音声同録システムと軽量カメラの発達によって可能になった、ダイレクト・シネマやシネマ・ヴェリテ※5を含めた一群のドキュメンタリー映画です。ナターシャさんが「観察映画」という映像制作のスタイルに辿りついた経緯と、調査方法としてどんな特色があるのかを教えていただけますか。
ナターシャ:
私の学問的背景には動物行動学があり、以前はナチュラル・ヒストリー的な映画制作をしていました。ですが、2004年に初めてオーストラリア国立大学(ANU)に来て、博士号取得のための調査を実施したときに、民族誌的な映画制作が人類学的な調査の一部として認められていることを知りました。それで映画制作を自分のフィールド調査の方法として取り入れることができたのです。デイヴィッド・マクドゥーガルとジュディス・マクドゥーガル※6が私の大学を拠点としていたのは幸運でした。
観察映画は、観客がまるで対象と一緒にいて、自分たちが全体の一部かのように感じさせるように、異なるコンテキストで彼らを夢中にさせます。それは、時間や空間がごた混ぜに短いカットが編集され、必然的に没入しにくいものとは違うものでありたいのです。ANUに所属していたもう一人の有名映像作家のゲリー・キルディアは、全知の存在のような外部のナレーションで観客を動揺させるのではなく、いかにドキュメンタリーの「夢の中に」没頭させるべきかについて語っています。
観察映画制作は、スタイルとしても倫理的にも、自分が動物に関して伝えたいことと一致するように感じました。なぜなら、ナチュラル・ヒストリー的な映画制作は演出されることが多く、現実よりもドキュメンタリードラマのようだからです。観察映画は、フィールドの人々が展開する出来事を実際に記録するプロセスであり、用意されたスクリプトや計画に沿うものではありません。つまり、観察映画はコンセプトやアイディアに関しての方向性は持っていますが、フィールドに根付くことで影響を受けていく、現在進行形のプロセスなのだと言えます。
§
村津:
観察映画はあからさまなナレーションや演出を含めず、フィールドの実践に焦点をあてることで、物語の対象の方が映画制作者の計画よりも重要だと示しているのですね。この態度は人類学的な関わり方と一致していて、それが人類学的な映画制作として支持される理由かもしれません。デイヴィッド・マクドゥーガルといえば、彼は「観察映画が世界には見るべき価値があることが起こっているという前提に基づいている。そして、対象の持つ特有の空間的、時間的なあり方は、その見るべきもののひとつである※7」と述べています。ナターシャさんの制作した映画「ヨルング・ホームランド」は、場所のもつ時間やテンポを感じさせることに成功していると思いますが、このような効果をもたらすために考えたことを聞かせていただけますか
ナターシャ:
テンポとコンテキストを築くことは、デイヴィッド・マクドゥーガルから学んだ重要な観点で、私はそれをこの「ヨルング・ホームランド※8」の中で実践しました。私は自分が運営に携わっていた修士課程の民族誌映画制作コースにデイヴィッドをゲスト講師として招いたのですが、彼は映画の最初の5分間でテンポを描き、残りがどのように進むかを示すのだと話していました。つまり、ゆったりとしたテンポで始めたならば、その後の映画が同じようなテンポで進むことを観客は受け入れるのです。だから「ヨルングの時間」のゆったりとしたテンポを表現するために、映画の冒頭は静かな朝のシーンから始めました。町から離れたアボリジニーのコミュニティの中にいるということが、どう感じられるかも伝えたかったのです。大抵の場合は静かで、物事がゆっくり起こりますが、太陽が降り注ぐと、急に多くの活動が始まることもあります。
村津:
民族誌映画はマリノフスキーが言った、声のトーンや物の手触りなど、日常の数えられない質である「不可量部分(imponderabilia)」を伝える方法だと思います。不可量部分は民族誌家が調査するべき要素のひとつとされますが、社会的構造やナラティブと違い、テクストだけで表現することが難しいものです。ナターシャさんの映画「ヨルング・ホームランド」で、特に不可量部分的なものを感じたのは、海辺で一人の女性が、獲った魚を分け与えなかったことで海鷲になってしまった男の子の民話を語るシーンでした。このシーンを作ろうと思った背景を教えていただけますか。
ナターシャ:
その民話を取り上げることにしたのは、ヨルングの老人が語っていたからです。それは、私たちが捕らえた海の食料を調理していたら、ちょうど近くで海鷲が数匹のカラスから巣を守ろうとして騒いでいたときのことでした。彼女は私に実際の海鷲とコスモロジーの間のつながりを感じてほしかったのだと思います。この民話はよく知られたもので、ヨルング・ホームランドの学校教育のために英語で書かれていました。本で読むこともできますが、私はこの民話がどんなやり方で語ることを目指されていたのかを、田舎で物語られる正しい文脈の中で示したかったのです。これは子どもたちのための物語ですが、海鷲が頭上で鳴いている場所で座って聞く必要があるのです。そうすることで、物語の中の鷲と空を飛び回る本物の鷲のつながりを作ることができて、まったく文脈から外れた教室の本の中にある物語より、ずっと心に訴えるものになります。
この鷲は多層的な意味を持っています。海岸にいる実際の鷲であるというだけではなく、物語を聞いている子どもたちと直接的にもつながっている存在です。物語の中で、人間、つまり子どもたちの先祖が鷲に変身したことで、海鷲が彼らのトーテム動物かもしれないという点で、彼ら自身も鷲の一部であると考えられるからです。この動物は人間と鷲の間を変身することができるので、物語を聞くヨルングの子どもたちにとって意味深いものです。それはヨルングの人々が鷲のパースペクティヴで考えることを促すのです。
§
村津:
民話の的な側面だけではなく、ナターシャさんのおっしゃる「多としての存在(multiple being)※9」という概念も伝えているわけですね。このような不可量部分的な側面を伝える方法は、映画だけに限定されているわけではありません。近年、アメリカを中心として「マルチモーダル人類学(multimodal anthropology)」という概念が、映像人類学に代わるものとして提唱されています。この動向は、フィールドにおいても、人類学者が属する社会においても、さまざまなメディア環境が急速に発展してきたことを反映しています。このマルチモーダルという発想は、メディア関連の実践だけにとどまらず、感覚的・身体的を巻き込む民族誌にも広げられるのではないでしょうか※10。マルチモーダル人類学について、ナターシャさんのご意見をお伺いできますか。
ナターシャ:
私はさまざまな種類のメディアを用いた、マルチモーダルなコミュニケーションに賛成です。ポッドキャストの新たな動向や、調査を追究するためにオーディオを使うこともとても良いと思っています。学者たちはいまだに本というメディアによって自己規定する傾向がありますが、他の要素も取り入れていくことは重要だと思います。私は限られたアカデミックの聴衆だけではなく、一般の人々にもアイディアやコンセプトを伝えたいのです。アカデミアという枠を超えて、自分の研究に関心を持ってくれる人々に届けたいと常々思っていました。
私はさまざまなコミュニケーションのモードを試してみるのが好きで、ひとつひとつのプロジェクトにおいて、どのように伝えるのが一番いいのか考えてきました。2017年に私は「二つの季節 ~モンゴルのマルチスピーシーズ医療~※11」という観察映画を撮ったのですが、そこで多くの馬の瀉血(医療の目的で実践者が、さまざまな箇所に針を刺し血を抜くこと)の事例を撮影しました。また、ある作品は、医学歴史家が主催した、流動体に関するカンファレンスに出席したことに刺激を受けて始めたものです※12。私たちはそれを、新聞や雑誌で探査ジャーナリズム的なものを伝えるのによく使われる「Shorthand」というツールを用いて作りました。ページをスクロールしていくと、それに合わせてイメージが変化するのです。多様な静止画があることで、ストップモーションアニメーションのようになる。最終的に、3つの独立部からなるフォトエッセイになったのですが、瀉血についての調査を伝える新しい道具として「Shorthand」を使うことは、非常に楽しいことでした。
近年は、別の存在のパースペクティヴを得るために、GoProカメラも使っています。ちょうど今年の初め、コロナウイルスが私たちの生活に影響を与える前に、さまざまな聴衆に対して多様な方法でコミュニケートするためのひとつの試みとして、パートナーと他のアーティストと一緒に展示会を共同キュレートしました。その展示会は「モア・ザン・ヒューマン:人新世時代における動物※13」というタイトルです。ここで私が展示した映像は、気候変動に直面する人間と馬の経験に関わるために、馬に乗る若いモンゴル人の牧夫のヘルメットにGoProをつけて撮ったものでした。馬と牧夫は、残りの群れの馬を見つけるために、雪嵐の中を探索しなければいけない中で、人間と馬がひとつの存在としてどのようにランドスケープと関わっているかがわかる、素晴らしいフッテージになったと思っています。
また去年には、私が住んでいるところの周辺、オーストラリアの首都キャンベラから1時間ほど離れたところで、ひどい山火事があったんです。そこで私は火事で全焼した直後に、馬とその騎手が黒く焦げてしまった森林を横切るところを記録しました。モンゴルの凄まじい雪嵐から、オーストラリアの夏に火事を引き起こす異常な熱波まで、気候変動が環境に対して全く異なる方法でどのように影響しているのかを示したかったのです。私はこの展示で、2つの対照的なシナリオを、ひとつは白を中心に、もうひとつは黒をを中心とした映像として並べ、馬と騎手が変化しゆく彼らの世界を案内するというかたちで展示しました。

最終的には、人々に、自分自身が他の動物や土地との関わりを異なる方法で認識できるということを理解してもらうことが目的です。彼らの中には、家畜が道具になったり、消費される生産物になることを恐れて、肉を食べることを心配する人がいます。しかし、私は他の文化にいる動物へのさまざまなパースペクティヴや存在論を示すことで、彼らにそのような問題を超えて考えたり、動物と関わり合う方法がいかに異なっているかについて知ってほしいと思うのです。
私は奥野教授が代表をしているマルチスピーシーズ人類学に関する科研費プロジェクト※14の一員です。そのプロジェクトの一環で、日本で騎射のフィールドワークをして、2018年9月には東京の流鏑馬祭と京都の笠懸神事を観ました。また、二つの異なる文脈における人間と馬の感覚的エスノグラフィや社会文化的な関与を比較するために、去年9月にモンゴルのウランバートルで国際騎射フェスティバルを調査しました。更にこのプロジェクトの一部として実施されている連続セミナーの中で発表し、マルチスピーシーズ研究における私のアプローチを博士課程の学生に教えるために、東京へも行きました。この複数年のプロジェクトの一端を担い、マルチスピーシーズ人類学にフォーカスしている日本の研究者と関わる機会が与えられているのは、素晴らしいことだと感じています。
§
村津:
ナターシャさんがおこなっている、一般の人々へのアウトリーチの仕方や人類学的な参与のスタイルを広げていくアプローチはとても興味深く、刺激的だと感じました。人類学的な実践が多様な方法で実施されているという意味で、私たちが目指しているのは、ナターシャさんが提示する概念を借りて言うならば、「マルチプルな人類学」と言えるものかもしれませんね。今日はコロナウイルスやマルチスピーシーズ、そして今日の人類学的な取り組みについて示唆的な考えを聞かせていただき、本当にありがとうございました。

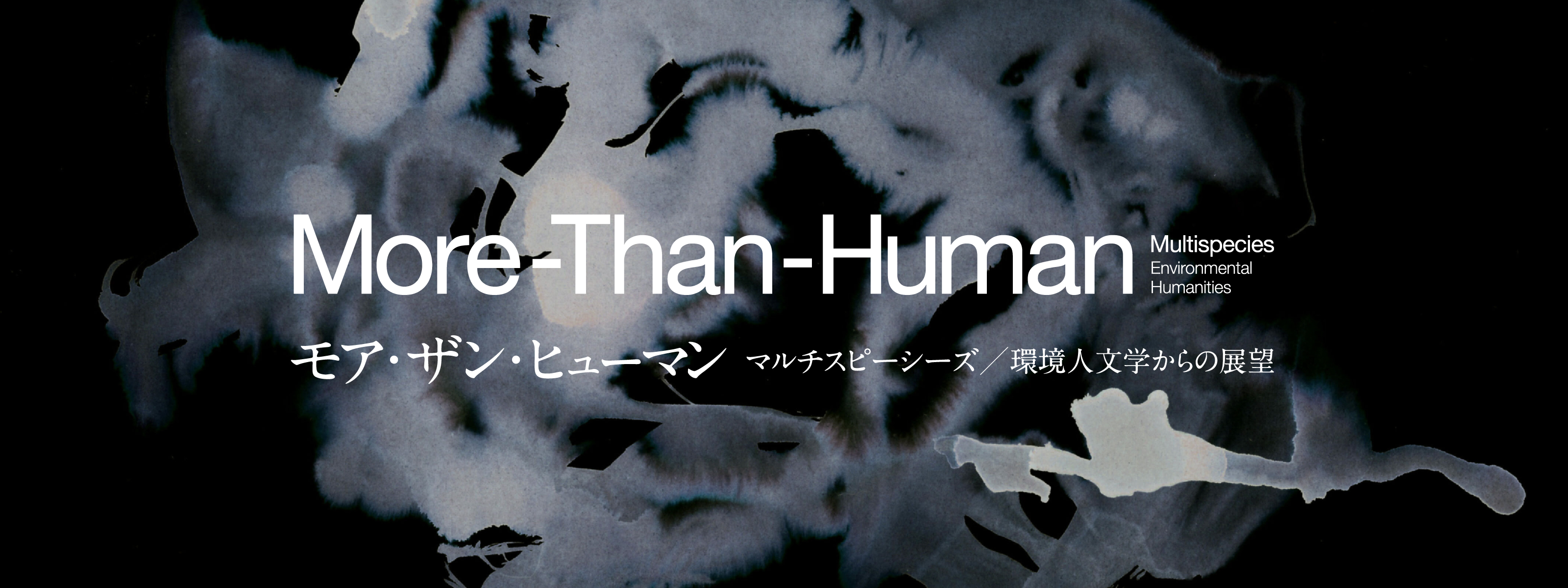
師茂樹:
最初に、清水さんがしばしば東洋の古典、特に仏教などを使いながらご自身の哲学を展開されているのには、どういった背景があるのかということから、お話を聞かせいただければと思います。
清水高志:
そうですね。子どもの頃からインドの古典に親しんでいたというのもあるんですが、そもそも欧米の現代思想じたいが、だんだん今世紀になって東洋的ロジックを再びなぞり始めているところがあるように僕は感じているんです。主客二元論とか、二元論的思考を超克するというようなことは、これまで20世紀までの思想でも主張されてきたし、もちろんドイツ観念論にもそうした考え方はあるわけですけど、主体と対象のように相反する二極があると、その両者の拮抗した境界を曖昧にし、間を取るというもの、《a》かつ《非a》みたいなものを考えるというものが多かったんですね。例えば、デリダの脱構築主義なんていうのもそういうものだと思う。
しかし、インドの伝統的な思考には、《a》でも《非a》でも《aかつ非a》でもない第四の「テトラレンマ」というものがあって、それは《aと非aのどちらでもない》というものです。論理的思考というのは《a》か《非a》かを定めるものだというのが西洋の伝統的な考え方で、《a》か《非a》かのどちらかを取ったらもう間は成立しないというのが排中律ですが、それではインド人は納得しないんですね。《a》にも還元されないし《非a》にも還元されないのは何かというのを、彼らは常に考え続けているんです。
ところが現代の哲学もまた、そういうことを考えるようになってきています。グレアム・ハーマンのような哲学者は、対象というものがあると、それは内的構成要素にも還元されないし、それを取り巻く外的文脈にも還元されない、そうした中間的統一体がオブジェクトである、ということを言います。これまではいずれかへの還元主義だったというのですね。さらに小さい原子のようなものであっても、色々な性質の集合体としてあるのだから被構成的でもあり、だんだん大きなものへとボトムアップしていく出発点であるわけでもなく、どんなものも内部と外部の両要素に還元されない中間的なものとしてあって、そうしたものが相互包摂しあって全体としての世界ができている、と考えるわけです。これはある意味でネットワーク的な世界観とも取れる思想だし、《一と多》という問題にも繋がる。仏教が考えてきた世界にすごく近いと思うんですよね。
僕は何年かごとのサイクルで、仏教のことしか考えられないくらいに仏教にのめりこんでいることがあって、特に道元やナーガールジュナは去年からずっと読んでいます。ブッダの思想はその断片しか伝わっていなくて、その一つが「離二辺の中道(不常不断)」で、要するに《ある》ということと《ない》ということのどちらにも世界を還元してはいけないという独特の考え方。もう一つはいわゆる「縁起」です。十二支縁起の思想が当時からあったらしいということしか分からない。初期の部派仏教のいろいろな哲学はそこから発達してきたわけですが、そのなかでさきほどお話しした排中律をいかに超えるか、二項対立のどちらにも還元されないかたちで排中律をどう超えるかという問題は、非常に大きかったんじゃないかと考えています。
例えば、ナーガールジュナがおもに批判している説一切有部(せついっさいうぶ)の時点で、もうそういう試みが出ていたのではないかというふうに思います。西洋のロジックで普通に判断をするという場合、「ソクラテスは人間である」といったように、述語の中に個別の主語が包摂されて、それが《判断》というふうにみなされますよね。このとき、人間の中にソクラテスが入ったら、ソクラテスは非人間であるというところには二度と行かない。これが排中律的なロジックです。さらに「ソクラテスは人間である」「人間は死ぬものである」という具合に、この論理は階層性を持つことにもなります。これに対して、実はインドの否定形というのはそういうロジックだけじゃないといわれている。《これは壺である》という場合の否定形と、《ここに壺がある》という場合の否定形は違うとインド人は考えるらしい。
師:
そうですね。絶対否定と相対否定みたいな言い方をしますけども。否定をすることによって何か別のことを肯定してしまうという否定のあり方と、単に否定しているだけで別のことを何も言っていない否定の仕方があるということですよね。
清水:
そうです。ここには二つの考え方があるんですよ。主語のほうに複数の性質を帰して、「それ(主語)にはこういう属性がある」という言い方をする哲学もあります。シェリングはむしろそういう考え方をしました。例えば、「二等辺三角形は三角形である」という場合、主語《二等辺三角形》が述語《三角形》に属するようなんだけれども、「等しい二辺からなる図形である」という言い方もでき、このときのグループには正四角形も正六角形もいっぱいあるかもしれない。こんなふうに主語が一つの述語に属していくだけじゃない、むしろ主語のほうにいろいろな性質が属しているという考え方もできるよ、ということを言う人はいるんです。
ここで重要なのは、要するに述語で「何かがある」というとき、それが主語に属するという考え方をされた場合には、排中律が適用されないということです。説一切有部の思想には「法有」というものがあります。彼らは《~がある》という、この《ありよう》を主語化するんです。主語化して、その中にこういう《ありよう》があるというかたちで、さまざまな現象が起こってくるとする。そうやって彼らは《ありよう》やはたらきの主体、原因として、排中律を超えたものの存在を見出していくわけです。こうして生まれた主体(主語)においてこそ《ありよう》はあるし、この主語は西洋的な論理学で扱われるもののように階層性もないから、否定判断の対象とすることもできない。そのような主語として思考され得たならあるとしか言えない。
そうしたものが彼らの言う「法有」だし、彼らはそれによってこの世界そのものを肯定しようとしたんじゃないかと思う。けれども、それに対してナーガールジュナによる述語、《ありよう》の主語化の批判というのが仏教にはあって、それを『中論※1』の第二章がどれくらいしつこくやっているかということを考えてみたんですよ。
彼は主語が二重になるとか、はたらき、つまり《ありよう》が二重になるとか変な言い方をするじゃないですか。あれは何を言っているかというと、例えば、《はたらきa》があって、それを《主語a》に主語化しちゃうわけですよ。主語化してしまうのは、それを原因とするということなんですけど、その後、今度は《主語a》をこれが最初からあったかのように持ってくるわけです。それを《主語a2》とします。そうすると、それが最初にあったかのようにしてここからはたらきが出てきたという説明がなされるわけです。これは実際には、《はたらきa2》ですね。ここは実は循環しているんですが、《主語a》と《主語a2》、《はたらきa》と《はたらきa2》は、ここで二重になっているんじゃないかという言い方をナーガールジュナはしているんですね。
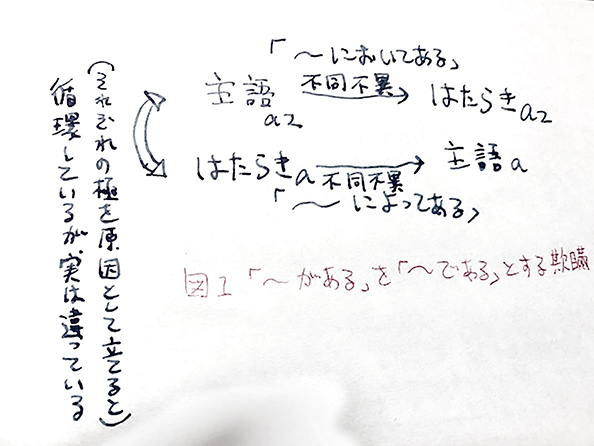
はたらきから主語を作ったのに、主語からはたらきが出てきたというんだから、これは《はたらきa2》じゃないか。ここで主語とみなされたものにしても、行為主体2(主語2)みたいなものが実際には二重に出ている。この循環が嘘だということを彼はものすごくしつこく言っているわけなんですよ。この図で大体の構造が説明できるんですが、上の《主語a2》と《はたらきa2》は「~においてある」、という《含まれる構造》ですね。これに対して下の《主語a》と《はたらきa》は、「~によってある」構造。このはたらきによってこれはある、というもの。こうした循環が生まれることで、《~がある》の《~である》化、みたいなものが起こっている。
彼は、そう発想してしまうことの欺瞞を執拗に問うています。主語とはたらきの両極で、こっちの極を原因として立てて反対側を帰結する、また逆の極を原因として立てて反対側を帰結する、というのは、本当はここは循環になっているから言えてないんですよ。だからこれは虚偽だということをしつこく指摘し、はたらきから即、主語が言えてそれらが同じものだというのは間違いであると。それなら両者は個別に切り離されて存在していて違うのかと言ったら、それもおかしいだろうということで、《はたらきa》と《主語a》の間には不同不異の関係が成立する。上の《主語a2》から《はたらきa2》についても、やはり不同不異の関係が成立するということになる。これら一つ一つを『中論』の二章の何番目の偈で言っているかを全部言える。それをすごく簡単な図にするとこうなるわけです。
師:
そういうことですよね。そして、はたらきというのが二重化するのはおかしいという話になるわけですけど。
清水:
二重化というのが分かりにくくて、それを言いたいがために、《去るもの》がさらに《去る》のはおかしいとか、「不来不去」という言い方をしている。あれは逆説的な否定としては言いやすいんだけど議論の本質が分かりにくいです。
今述べた循環が嘘であるということで、実のところ彼が何を考えているかというと、この構造は「離二辺の中道」に抵触するわけですよ。テトラレンマに抵触する。《~がある》ものを主語にすることで、《~である》というかたちにしてしまっているんですよ、実際は。そうやって対立二項の両極に交互に原因を帰している還元主義なので、これは「離二辺の中道」に当てはまっていない。
結局のところ、《~がある》という出来事の次元をせっかくテトラレンマ的に全部活かそうと思ったのに、全部主語化してしまったことで、《~であるのでも、~でないのでもない》という、ブッダが最初に言ったテトラレンマに抵触してしまうので、これをどうするかというのがナーガールジュナの本題だったと思うんですね。縁起というものも、《aがあるから、bがある》、《bがあるから、cがある》と表現されるけど、実際には全部主語化されたものが連鎖しているわけですよね。この主語が一つ一つループであるということをまず認めないといけない。
また主語化した前件・後件といったもの同士で、前件があるから後件がある、と語られるものも、前件から見て後件もあり、後件から見て前件もある、というかたちで読み替えないと成り立たない、それら相互もループであるはずだということを彼は執拗に論証していく。だから『中論』では「~によってある」「~においてある」ということが、前件からも後件からも繰り返し否定されている。これらの可能性をすごく論理的に周到に全部つぶしていっていますよ。
ここで重要なのは、「~によってある」「~においてある」ということが前件・後件のどちらかから一方的に語られてはならず、相互的、しかも同時に相互包摂でないと成り立たないということ。このあたりを執拗に考えているのが、おそらく『中論』の二章だと思うんですね。そこから出てくるのが相依性という考え方 —— あらゆる《a》が《非a》によってあり、《非a》も《a》によってある。それゆえ《みずからの本質》といったものによってあるのではなく、無自性で《空》なるものだ——という思想ですね。
師:
今のお話で非常に印象的というか、そうだなと思うのは、ナーガールジュナの『中論』で書かれているこういう議論は、今までは「論理を超えた」ものであるという言い方がよくなされてきました。だから「空というのは言葉を超えている」というふうに言われているわけですけど、それを現代哲学の道具立ても含めて整理していくと、非常にロジカルにナーガールジュナが理論を組み立てているというのが清水さんの目からは見えるということですよね。
清水:
そう。だから何一つ無駄がないし、妙なことを言っているようなことを一つ一つ考えていくと、それを絶対言わなければいけない理由があるわけなんです。「何があるから何がある、何があるから何がある…」ということを非還元的にしていくためには、「~においてある」というものも主語になった極の話ではなくて、反対側の極のことでもない。「aでも非aでもない」、また「非aでもないしaでもない」ということが同時に両方言えるというかたちで、考えなければならない。
そうすると縁起と言っているものも、全部主語化されたもの同士の作用だと考えるだけでは駄目で、それらが「~である」化しているのを否定するためには、相互にこれがあってこれがあるということを言って、そこで主語化されたという契機もあった、ということも考えて、両極を同時に否定するロジックを作っていかないといけないんです。これは例えば鈴木大拙が、まさに排中律の成立しない仏教特有の超論理の典型として《般若即非の論理》ということを言うときに、「aはaではない。ゆえにaと名づく」と言っていますよね。あれは『金剛般若経※2』に延々と出てくるロジックですが。
師:
そうですね。『金剛般若経』は延々そればっかりですね。
清水:
その「名づく」というのが何かと言ったら、この主語化ということなんです。「名づく」ということ、いったん現象が主語化され、主語に帰されるという契機が必要で、しかしそれも原因の還元の一方的な対象としては置かれないし、対置される《非a》も置かれないというかたちが作られねばならない。これが大事なんです。この二極が、同じでも異なってもいないということの論証を、中観学派では《一異門破(いちいもんは)》と呼んでいますね。
師:
「一異門を破する」ですね。
清水:
三論宗の吉蔵などはこの論理をそう呼んでいます。《一》と《異なる》もの、《a》と《非a》がどっちから見ても不同不異だというのが一異門破です。これは徹底した論理で、一異門破はあらゆるものすべてに言えるわけですよ。はたらきが認識だとすると、認識主体というのがあって、こっちも主語化しているんですけど、それによって認識(所縁縁)がある。それらは別でもないし、同じでもなく、不同不異なんです。ただそれが一つのユニットとしてあった場合に、むしろメタ一異門破みたいなものがあるわけです。これが一つの環界(環境世界)みたいなものを作る。
認識主体と認識、主体と対象世界は、それぞれ相依性においてあるので、これらは二重三重になっていくんですよね。縁起っていうのは、主語化したもの《a》があるから、主語化したもの《b》があるみたいなものになっていたじゃないですか、実際には。それはミクロで見れば、《はたらきa》⇔《主語a》なんだけど、《主語a2》と《主語b2》もループなんですよ。《主語a2》⇔《主語b2》というふうに。そういうロジックが前提としてあって、さらにだんだん考えていくと、これは環界ができていくということなんです。主客の主体と客体があって、それらの相依性の重層が環界の形成でもあると。
主体がはたらきかけることによってできる世界があり、世界によって主体も作られるという関係が、こうしてだんだん発展していく。縁起の説というのは、拡張的に読んでいくと、本来はたらきと主語のループであったところがさらに重層して、一異門破になって、メタ一異門破みたいなものができて、メタメタ一異門破ができていく。そうしたものだと考えると、それは結局《一と多》の問題になっていく。相依性の重層から、《一》や《個》が《多》、もしくは《全体の世界》と不同不異である、《一即多》という世界観がだんだんできてくる。これは『法華経』の思想なども混じって、のちに仏教的に展開されるけれども、最初のロジックはナーガールジュナの一異門破の話なんですよ。《一》とか《個》としてのものが世界と相即的にあるというもので。ナーガールジュナが論理的必然性を探求しながら言っていたことから、何種類もの二項対立を一異門破で調停する論理が重なって出てくる。それが後年の大乗仏教のさまざまな切り口になっていくわけです。
そして、このとき環界とともに出てくるのがパースペクティヴというもの。世界の眺めそのもので、道元がまさに《山河》と呼んでいるものです。
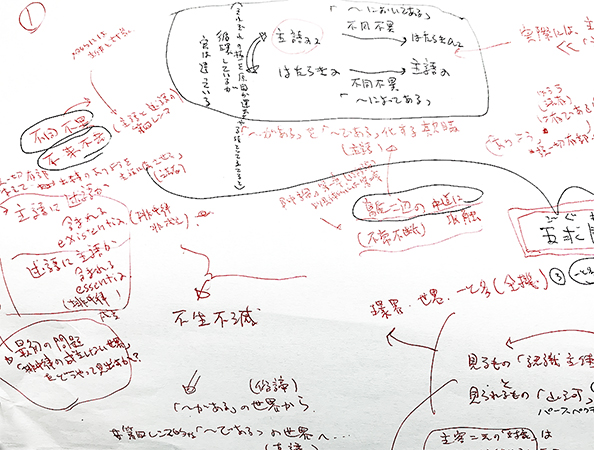
師:
今の主客と環界の形成の話というのは、まさに『正法眼蔵』の「現成公案」とかで言っていることと、同じ話をしている感じですね。
清水:
同じ話なんですよ。だから、ここで「これとこれの主語化が」といった話をしていると、抽象的な話に聞こえるけれど、そこから考えていかないと実は道元は分からないんです。例えば、道元は、舟に目を留めていないで対象を直接見ていると岸が動くように見えるけれど、自分が乗っている舟に目を留めると、自分が動いているのが分かるというような言い方をするけれども※3、それは自分が身を置いている一つ一つの環界の小さいループを考えて、世界の側のより大きなループも考えなさいということです。そう考えたときに、個というもののテトラレンマ的な独立性や不生不滅性が出てくるわけです。
同じく「現成公案」で、道元はまた、薪が灰になる。その薪にも先があって後がある。灰にも先があって後がある。それらは一つ一つ「法位」にある。生と死もそのようなものだとも語っていますね。これはもっと小さいループがあって、それぞれが単に被包摂的なものではないんだ、ということです。インド仏教は、超論理どころかまさに完全な哲学ですよ。対立二項のどちらにも原因を還元しないということを重層的に考えるという。だから「~がある」とか「~である」とかということを徹底的に展開していくと、パースペクティヴの話になるんです。ここからがまさに道元の展開なんです。
師:
普通はナーガールジュナって実在論の反対の立場みたいなかたちで言われますよね。でも今のお話だと、現代哲学の「新しい実在論」や「モノの哲学」と言われているものに近いというのは、大変興味深いと思いました。
清水:
ハーマンのオブジェクトの話も、外部と内部のどっちにも還元しないからかえってある、一つのモノが際立ってくるというロジックですが、仏教だと「~においてある」という包摂のテーマも相互的に考えるので、それが《一と多》の問題としておもに展開されているわけです。実在やオブジェクトは、仏教では《どちらにも還元しない》ということが相依性という観点から扱われたおかげで、一見真逆な《空》というものとして考察されたんですが、実際には表裏一体なわけです。
師:
ちなみに、先ほどのパースペクティヴの話を、もうすこし詳しく説明してもらえませんか。
清水:
その話を徹底して展開しているのが、僕は日本仏教の特徴だと思うんです。道元が実際にそれをやっているということは、ここまでの議論から逆に見るとはっきりと分かるんです。さきほどの話のように舟があって、中に人がいて、岸という対象があるというとき、舟という対象と人という対象同士は身心依正、どちらも相互生成的にあり、しかもさらに岸=環境があるんだけれども、これらすべての要素を完全に相互包摂とみた場合には、例えば、岸のほうが包摂する側として一方的にあるということはないわけですよ。おのおのが包摂の軸になる。このとき《一》が即《全》であるというのは、例えば、鳥が空を飛んでいてその環界と一体になっているとき、その空じたいはさらにメタ空(そら)みたいなものとの関係のうちにあるんだけど、今度はその環界そのもののループとメタ環界とのループを考えた場合には、どこからどこへ飛んだかとかそういう位置づけられるという問題じゃないわけで。
師:
「現成公案」の後ろのほうの話、「鳥そらをとぶに、とぶといへどもそらのきは(きわ)なし」ですよね。
清水:
そうです。そうしてこんなふうに舟と私というものに対して岸というものがあるというかたちを考えると、それらの間に相即関係があって、こちらに岸というものもあるという関係を考えると、このループが何重にもなって、《一》も際立つかもしれないけど、《全体の世界》である《山河》全体というのが肯定されてくるということになってくる。
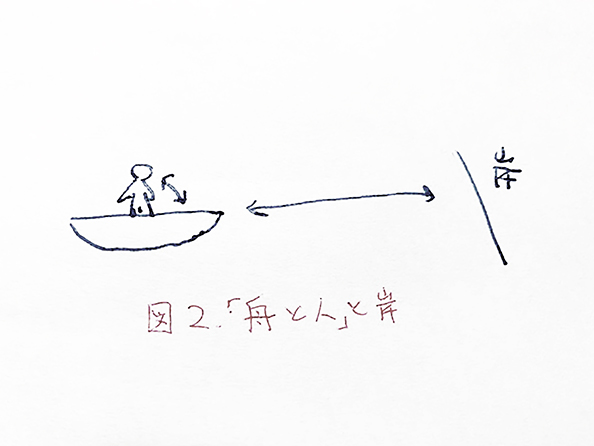
師:
そうですね。《虚空》という言い方を道元はよくしてますね。
清水:
この《山河》全体は《個》(《一》)と相互生成ですから、ある意味でお前もそれをつくっているんだという軸足にもなるわけです。さらに言えば、この認識主体と舟という一番小さいところから、《全体の世界》とそれに対する《超越的認識者》みたいなもの、両方の考え方まで出てきて、古仏の眼睛(ブッダの眼)とか、道現成とかいう言い方をしますよね。「而今の山水は古仏の道現成である」という、端的な世界の肯定が出てくる。
師:
「山水経」ですね。
清水:
「山水経」ですよ。そして山河は全体として構成されるんだけれども、それがすべてを包摂しているだけでもないし、もろもろの複雑な環界が、さまざまに別様にあるということも道元は認めていて、それらが皆パースペクティヴであるとすると、例えば《水》を見るのに、鬼はこんなふうに見るし、龍魚は宮殿として見るし、瓔珞(ようらく)と見るものもあるとか、いろいろな言い方をする※4。皆それぞれの環界、それぞれのパースペクティヴを持ってこの世界を見て、その世界が軸足になって、また個々のものを照らし出しているということを、さんざん道元は言っている。
この言い方じたいはこれまで考察してきたことの完全にロジカルな展開だけれども、それを自然に対するヴィジョンとしても語るわけですが、これが今人類学で語られているところの多自然論とか、パースペクティヴィズムと完全に重なってくると思うんですよ。文化相対主義や多文化論を超えた、多自然論ということを21世紀の人類学は語り始めていますが、徹底して考えるとまさに世界はそのようなものとしてしか捉えられない。
師:
『中論』が非常にロジカルにミニマムなところから積み上げていくとすれば、それを自然とか環境世界とか世界とかそういうものにバッと拡張して適用していったのが道元であるという、そんな感じでしょうか。
清水:
それが道元だし、またここで《個人》も出してくるのがそもそも禅だったと思うんですよ。臨済禅でも《人》というのが出てきて、《赤肉団上(しゃくにくだんじょう)に一無位の真人あり》とか《主人公》とか。だから主客の主の方もある意味ではバーンと出すし、オブジェクトも出すし、世界も出す。
師:
やっぱり道元がすごいなと思うのは、「人は歩くけど、山も歩く」とか平気で言うじゃないですか※5。あれがすごくでかいですよね。
清水:
山中に人がいるんですよね。舟が山になったとしましょう。山の中で人が歩いているんだけど、これは一見すると作用主体と作用対象なんですけど、「山」が何か大きな環界との関係の中でさらにやっぱり動いているんですよね※6。こう考えないとこの世界は成り立たないし、だからこの(山の)中にただいる人はそれが分からないし、外(大きな環界)の側にただいるという人も分からない。このとき「外にいますよ」という立場で見ている人は、単世界論的な人です。人類学者の岩田慶治さんから見た大昔の博物学者フンボルトみたいなもの。
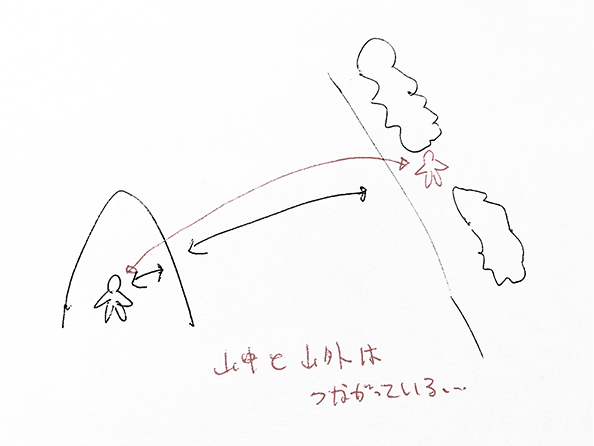
こっちは「山」の外の人で、こっちは「山」の内の人だとすると、それらの単にどちらであってもいけないというのが、「青山常運歩(せいざんじょううんぽ)」の話でしたね。そんなふうに一つ一つ考えると、それに続けて出てくる「石女夜生児(せきじょやしょうじ)」は何だろうとかね。児を生まない女が夜に児を生む。生まれることと生むこと、夜って何だろうとかね。児が生まれるから親ができる※7。それらが同時にできるということを考えろとも道元は言っているんですよ。
これはだから原因とか、元になったものと、後になったものの相互成立をめぐる謎かけであって、石女夜生児というのは、おそらく自分自身を生むのかなと。相依性のループは、なによりミニマムで単独的なものでもある。まずそれを見ろということなんですよ。闇の中で。誕生と闇の強烈なコントラストがそこに同時に浮かび上がってくる。
師:
さっきもちょっと言ったんですけど、『中論』がある意味言語を超えたものであると理解されるように、道元もこういうものは体感すべきものなんだという感じで理解されてきたと思うんですね。それがこういう綿密な、それこそ哲学的な思惟として構築されているというのは非常に面白いし、仏教学をやっている人間としても学びが多いと思いました。
清水:
しつこく『中論』や吉蔵を考えないで道元をパッと読んでも、何を言っているのかと思うだろうけど、六割ぐらい彼らの理論を考察することに力を注いで、四割ぐらいで道元を読むと言っていることが分かるし、そこで語られる世界が古来の日本人や、非ヨーロッパ圏のさまざまな人たちの世界観とも地続きなのが感じられてくる。そのあたりが印象的です。
師:
『中論』は、今の第二章などもかなり短いじゃないですか。『正法眼蔵』七五巻とかと比べたら。『正法眼蔵』があれほど執拗に、自然だの海だの舟だのということについて、ひたすら言葉を重ねていこうとしたのは何故なんでしょうね。
清水:
僕はあえて主語化をしようとしていると思うんです。表現ということで。不立文字とか言いながら、襟首掴んで「言え言え」とか言い合っているじゃないですか、禅の人って。「祖師西来意」《達磨はなぜ中国まで来たのか》を、樹の枝を口にくわえてぶら下がっている人に言え、とか訳の分からないやり取りまであって※8。「言う」ということ、一回表現して主題化するというモーメントがなくてはならなくて、しかもそれがまた「aがないから、非aがない」というふうに、還滅門(げんめつもん)的に捉えられたときに始めて《一》にして《全》なる世界が現成してくるという構造があるんですよ。道元ではそうした構造はかなり普遍的で、主客の話も、鏡の話になったりするでしょう?
師:
「古鏡※9」ですね。
清水:
認識主体としての心とか、眼とか、それが眺める対象としての古鏡といったものが「古鏡」では語られていますね。この古鏡にそれらが映っているというのも、相依性のループであり相互生成、フランス現代思想でいう鏡像段階みたいなものですよ。これが一つの一異門破です。しかしそれに対して、メタ一異門破の論理がすぐに始まるわけですよ。
それは何かと言ったら、この古鏡は《彼》と《我》、全部映すんだという話になる。そうすると別のものも出てきて、漢人(中国人)が来たら漢人が映るし、胡人(西域人)が来たら胡人が映るということが言われる。これは《全体の世界》に対するパースペクティヴが幾つもあるという話と同じです。そして鏡そのものが来たらどうするんだという問いかけがなされると、「木端微塵にする」(百雑砕)と言うんですよね。これは端的に対象世界を見ようと思ったら、メタ一異門破で、《一と多》の問題にいかないといけないということですね。
師:
さっきチラッと言っていた、還滅門的にという話ですね。
清水:
そもそも初期仏教から言われている十二支縁起は、「~があるから、~がある」というかたちで列挙していって、「無明」から「老死」にいたる苦の世界がいかに生まれていくかを説くものです。この流れを《順観》というんですが、これには《逆観》(還滅門)というものがワンセットであるんです。つまり「~がないから、~がない」というふうに十二支を逆に辿ることで、苦の世界が寂滅していく。
ところでテトラレンマの考え方は、「~でなく、~でないわけでもない」というかたちで、単純に「~である」ことを退けていますから、「~」にまた主語を安易に入れて話を蒸し返すのは無意味なんです。ナーガールジュナも『中論』でそうした議論を全部否定している。テトラレンマは一部の絞った命題についてしか言えない。『中論』では四種類に厳選されています(八不)。
これに対し、「~がある」の世界はもともと本当に多様なものです。説一切有部はいちいちそれらを主語化しましたが、あらゆるものにその世界を拡張し、しかもそれで排中律を超えようとしたんですね。縁起という思想は、そこではよく分からなくなった。しかしそもそも縁起の還滅門というのは、「aがないなら、b(非a)がない」ですけど、彼らがやった主語化を踏まえるなら、「(原因が)aでなく、非aでない」ということなんですよ。「~である」化しているわけですから。またここでは両極に相依性が成立しているので、それはもうテトラレンマの最終形態(第四レンマ)なんです。
これはもはや《主語a》がなんであるかという議論ではなくて、メタレヴェルの構造についての洞察ですから、還滅門を通じれば、あらゆる「~がある」について、テトラレンマが適用されると。第四レンマの典型は不生不滅とかそういうものと同じなので、例えば先に述べた「薪が灰になる」ということも、その変化や滅びやうつろいの中で、それぞれが第四レンマ的であることになる。もちろん生も死もそういうふうに考えられていて、生から死への移り行きがあるんだけど、それらの中にもミニマムな前と後があり、そのうつろい、移り行きがあって、それらじたいがテトラレンマ的に、その「法位」のうちにある。
有名な道元の「有時」も、「松も時なり、竹も時なり」と言うけれども、これは全部ミニマムに「時」だということなんですよ。その移り行きがあって、しかもそれが入れ子に重層化していて。色んな道元の不思議なロジック、例えば「画に描いた餅は食べられない」という話にしても※10、それをお題にして道元がひたすら何を言うかというと、画に描いた餅が対象としてあるかということではなく、画の餅をどう作って、描いていくのに何を用いたかということです。要するに、動作主体がオブジェクトをどう作るかという話に置き換えるんですね。それによって、対象がただ漠然と外にあるわけじゃないんだという話にしてしまう。この主体が対象世界を「作る」ということも、何かを表現したり言ったりすることがモーメントとして大事なように、きわめて大事なことなんです。
岩田慶治さんは、「道元は世界をつぶつぶと画に描いていくみたいに正法眼蔵を書いている」と言っているけれど、そんなふうに森羅万象を表現世界にもう一回裏返して、しかもそれは還滅門の世界でもあり、だからこそかえって不生不滅の世界でもあるんだということを、道元は語っていますね。
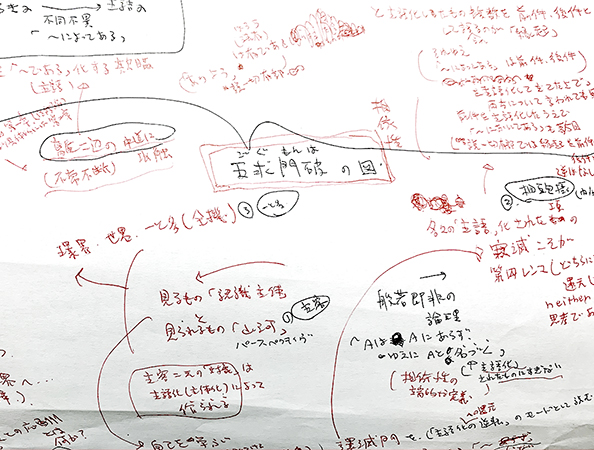
師:
仏教的な考え方からすると、こういう道元の理論にせよナーガールジュナにせよ、やはり悟りとか解脱とか、そういうものが目標としてあるわけですけど、清水さんの哲学が何を目指しておられるのかというのを、今聞いて考えていました。
仏教としては、皆で悟ろうということがあるんですが、さっきのお話のように表現者としての道元というものもある。清水さんの哲学も道元のように世界を表現していくというか、そういった方面への関心があるということなんでしょうか。
清水:
それはありますね。世界が表現しているものが「古仏の道現成」であるなら、悟ること、あるいは悟られたものとしての世界をどう見ていくかが問題であり、そうしたものの多様な表現の意味を解き、理解していきたいというのがあるんですね。晩年の西田幾多郎は、「自分の哲学は創造的モナドロジーだ」と言っていた。僕は若いころからまさにそれに共感していたんです。《一と多》が相即的であるとか、そういうことをただの概念で終わらせるのではなく、創造の極点に個々の人間がならないといけない。
創造というのは、世界の創造ですよ。世界制作の極点にある意味でいなければならなくて、それが自由ということでもあると思うんです。仏教で自由というものが感じられ、苦の繋縛から解き放たれるということがあるなら、まさにそうしたものだろうと。
逆に哲学の側から、近代思想の価値観をそのまま背負って、社会制度の中での自由ということを語っても、少なくとも僕は本質的に自由になった気がしない。人間的自由を超えた「モア・ザン・ヒューマン」な自由を求めること。それがこれからの文明の大きな課題でもあるというふうに僕は思っています。
江川あゆみ:
「エコクリティシズム」と呼ばれる文学研究の、日本における牽引者のお一人である結城正美さんに、エコクリティシズムとは何か、また日本でのエコクリティシズムの状況、ご自身の研究について伺っていきたいと思います。
まずは、エコクリティシズムがどのような文学研究か。それが成立した背景や、これまでどんな展開を見せてきたのかをお聞かせください。
結城正美:
包括的に言えば、「エコクリティシズム」は人間と環境との関係をめぐる文学研究です。研究が組織的に始まったのは1990年前後です。1960~70年代に、それまでの白人男性作家中心の文学研究が見直され、人種やジェンダーの問題に目が向けられる修正主義的な動きがありました。そして、環境の時代が世界的に幕を開けた1970年代から、今エコクリティシズムと言われているような研究が個人レベルでは存在しはじめていました。しかし、個人レベルでは相互参照は難しく、学会がなければ共同研究や研究交流もなかなかできません。
エコクリティシズムはいくつかの変化を経てきました。これは波のメタファーで語られることが多く、「第一波」からはじまって、現在を「第四波」だと言う人もいます。最初期の第一波では、人間と環境の関係と言うとき、環境という言葉は主に自然環境、とくに野生の環境を指していました。研究者も白人研究者が中心でした。
その後、エコクリティシズムの内部から、自然環境に焦点を当てることを批判的にとらえる動きが出てきます。社会環境を視野に入れて、人種やジェンダーの問題も環境問題に結びついているという認識が共有されていきました。それとともに、研究者も人種やジェンダーの点で多様化し、国や地域も脱アメリカ中心的な広がりをみせます。なので、エコクリティシズムは非常に多様化している文学研究だと言えるでしょう。
エコクリティシズムには、文学研究における「キャノン(正典)」の問題も含まれています。文学研究と言うと小説が批評の対象に据えられることが多い。しかし、エコクリティシズムでは英語でいう“literature”(書かれたもの一般)が批評対象である点が大きな特徴です。
初期の頃に注目されたのは、「ネイチャーライティング」と呼ばれる自然環境についての一人称ノンフィクションエッセイでした。ノンフィクションエッセイは、文学研究でほとんど取り上げられてこなかったのですが、エコクリティシズムでは一人称ノンフィクションエッセイにこそ、人と環境との関係をめぐる深い思索が織り込まれていると考えられてきました。ほかにも、映画や漫画、アニメなどの文学表象に関わるものまで、広くエコクリティシズムの検討題材になっています。
私が今お話ししていることのほとんどは、この文学研究を組織的に生んだ研究者の一人であるシェリル・グロトフェルティの共編著“The Ecocriticism Reader※1”のイントロダクションに書かれています。彼女は、エコクリティシズムの特徴として、“open and suggestive”であることを挙げています。端的に言えば、間口が広い、ということです。そのため、エコクリティシズムという言葉自体に縛りがあるとして、「文学・環境」(literature and the environment)と言われることもあります。
オープンであることは、他分野との関連を重視する姿勢を含んでいますので、学際的なアプローチをとることもエコクリティシズムの特徴です。また、オープンであるとは、研究者だけで議論するのではないという意識の現れです。環境の問題に関わるわけですから、研究者以外の幅広い層の人たちと交流することが重要になる。一方、それが裏目に出て、文学批評理論として洗練されていないという批判が、エコクリティシズム内部からあったのも事実です。
21世紀に入り、国や地域を超えたトランスナショナルな視点が出てきました。人種問題が環境問題に関わっていると認識した上で、人種を超えて共通する問題に目を向ける研究が見られるようになりました。国や地域を超えたグローバルな地球環境問題への関心の高まりと、軌を一にしていると思います。
エコクリティシズムや「環境人文学」(Environmental Humanities)で醸成されている概念や切り口が持つ可能性として、私は、従来論じられていたことを新たにとらえ直して議論を活性化するはたらきに注目しています。
たとえば、奥野克巳さんを中心に日本で進められているマルチスピーシーズ研究。「マルチスピーシーズ」は、日本の環境文学の代表的作家である石牟礼道子さんの作品を論じる際にも「使える」概念だと思います。石牟礼作品では、人間とノンヒューマンの存在の交流が描かれています。
石牟礼作品はこれまで「アニミズム」や「共生」、あるいは水俣病の問題では「共苦」といった概念で、文学だけではなく社会学など多分野で議論されてきました。同時に、そうした議論は前近代を理想化していると批判する向きがあります。しかし、これらを「マルチスピーシーズ」という枠組みでとらえ直すと、批評的距離が生まれます。対話のプラットフォームが開けてくるのです。「共生」として語られてきた石牟礼作品のある一面を「マルチスピーシーズ」の見地から語ることで、より広い分野や世代の人たちと話ができる印象があります。
この「マルチスピーシーズ」という概念が提起する問題について、すこしお話をさせてください。まだ勉強中ですが、「マルチスピーシーズ」というのは「種」という概念自体を問い直す動きであると理解しています。
「人新世」(the Anthropocene)の問題は、現在エコクリティシズムでも環境人文学でも議論されています。その根底にあるのは、人類というとき「この人類とは誰のことか」(Who is this “we”?)という問いです。歴史家のディペシュ・チャクラバルティが言っていますが、現代に生きているわたしたちは、これまで一度も人間を「種」ととらえてきたことはないのではないか。人新世を「種」としての人間が“geological force”(地質学的に強い存在)になった時代ととらえるシナリオに対して、マルチスピーシーズ研究がどう切り込んでいくのか関心があります。
人間を「ひとつの種」として見るという問題を考えるとき、やはり石牟礼道子を参照したくなるんです。石牟礼作品には虐げられている人々が多く描かれます。社会的に差別を受けている人々、たとえば水俣病患者であったり、狂人だと思われている人は、他者を同じ人間として見ているところがあります。少なくとも石牟礼作品ではそう描かれています。
たとえば、水俣病患者がチッソ※2の社長に「同じ人間として自分たちのことを考えてもらいたい」とか、「同じ人間としてこの苦しみを一緒に考えてもらいたい」と言います。同じ人間としてチッソの社長や役員と向き合っているわけです。ですが、チッソの社長たちは彼らを人間扱いしていなかった。だから、平気で有毒物質を垂れ流していたわけです。被差別者が他者と「同じ人間」として向き合うとき、そこには「ひとつの種」と言える広い人間のとらえ方がある。そして石牟礼の描くそういう人々の世界には、蛸や狐や馬酔木との交流があり、マルチスピーシーズの関係が描かれている。
ですから、科学的な「種」の再考を含めて、人間をひとつの種としてとらえることを学ぶ上でも、石牟礼作品は示唆的だと思います。人類が“geological force”となった人新世の議論をするときに、自分たちが「ひとつの種であるとはどういうことなのか」という問題についても考えなくてはいけない。そのときにエコクリティシズムが重要な役割を果たすと思っています。
§
江川:
結城さんご自身がエコクリティシズムを始めたきっかけはどういったものなのでしょうか。
結城:
私はもともと田舎の育ちです。川や原っぱ、山など、自然豊かなところで毎日遊んでいました。今思えば、非常に恵まれた子ども時代だったと思います。家のぐるりに小魚が泳ぐ小川があって、祖母はそこで洗濯をしていたし、母は鍋を洗っていた。小川といっても生活に必要な水を引く用水路ですが、側面に苔が生え、タニシがくっついているような、本当に楽しい小川でした。家の敷地内を流れるその小川で、裸になって遊んでいました。
ですが、小学高学年の頃に、そこがコンクリートで三面張りにされてしまいました。小魚は姿を消し、時期になると湧いて出ていたホタルもいなくなりました。それには衝撃を受けましたし、怒りも感じました。なんでこんなことをするんだと。小学生の私は、建設会社が工事する現場を見ていて、言葉にならないモヤモヤしたものを感じていました。しかし、どうすることもできず、とくに行動を起こすわけでもなく、そのモヤモヤをずっと抱えることになりました。
大学に入り、師匠である野田研一さんの授業がきっかけで、アメリカ文学を専攻するようになり、修士課程に進みました。修士論文を書いているとき、シェリル・グロトフェルティと共にエコクリティシズムの生みの親の一人である、スコット・スロヴィックの集中講義がありました。そこで環境文学作品をたくさん読んで衝撃を受けました。「これも文学なのか」と、私の文学観が音を立てて崩れました。
でも、それらを読みながら、幼少期に感じた「なんできれいな小川をこんな風にするんだろう」というモヤモヤにつながったんです。そして気づいたらこの道に入っていました。ですから、自分の経験と学問としてのエコクリティシズムは分離していない。後付けかもしれませんが、分離していないところに魅力を感じたのかもしれません。
エコクリティックには、プライベートな生活と研究者としての自分を分けていない人が少なくありません。環境の問題は人間の問題であり、ローカルであると同時にグローバルであり、パーソナルなものとプロフェッショナルなものが絡み合っている。そのスタンスに惹かれて、気づいたらそっちに進んでいたという感じです。
§
江川:
結城さんは博士論文をサウンドスケープについて書かれ、そこから関心が多岐に広がっていかれたように思います。もし関心が広がるきっかけになった人や作品との出会い、あるいはご経験などがあれば、お聞かせください。
結城:
最初にサウンドスケープやアコースティックエコロジーに関心を持ったのは、修士課程でランドスケープについて学んだことと関係していると思います。指導教授の野田研一さんが「文学におけるランドスケープ」の問題を専門としていて、風景論についての講義を受けてきたからです。そのときに「なぜ見ることばかりなんだろう」と疑問に思ったのが出発点かもしれません。視覚中心主義は差別の問題とも関わります。ですので、視覚とは別の感覚経験から文学研究ができないかと考えていたように思います。
ちょうどその頃、テリー・テンペスト・ウィリアムスという作家の作品を読んでいたことも聴覚的経験に関心を持った理由だと思います。この作家は先住民文化に造詣が深く、彼女の作品を読みながら、先住民の口承文化や、「耳を傾ける」という心構えや態度に、非常に関心を持ちました。また留学先のネヴァダには先住民が多く、アジア系の私は親近感を持ってもらえたのか、部族の集まりにも参加させてもらえました。先住民文化に関心を持ち、そういう出会いもあって、サウンドスケープの問題に行き着いたように思います。
日本に帰ってきてからは、アメリカの環境文学ばかり研究していても、なんだか机上の空論という感じがしたんです。環境の問題はローカルな問題でもありますから、日本のことにも目を向けないといけないんじゃないかと思ったわけです。そこから、日本文学とアメリカ文学とを比較研究的に見るスタンスにシフトしていきました。それで石牟礼道子や森崎和江の作品を研究するようになりました。
§
江川:
結城さんはデイヴィッド・エイブラムの『感応の呪文※3』(原題 “The Spell of the Sensuous”)を翻訳出版されています。訳者あとがきでは、この本が“more-than-human”(人間以上)という言葉を学術的に用いた最初の著作だと書かれていましたが、この“more-than-human”という概念についてお話しいただけますか。
結城:
“more-than-human”は、おそらくマルチスピーシーズと非常に近い概念、インターチェンジャブルに使えるものだと思います。とはいえ、まったく同じではありません。マルチスピーシーズでは、種という概念の見直しも含めて、人間もひとつの種と考えることが根底にあります。“more-than-human”は、人間がいて、しかし人間だけではなく、それ以上の存在がいるということでしょうか。指しているのはそれほど違わないのですが、開かれ方がすこし違うイメージだと思います。
『感応の呪文』の章のひとつは、1998年に出版された『緑の文学批評※4』という、エコクリティシズムの主要論文のアンソロジーに入っています。私はこの翻訳を担当し、非常に優れた研究書だと感じていました。そのうちいろんな人の書くものに“more-than-human”という言葉が出てきたのですが、ほとんどエイブラムへの言及がない。それほど一般的な用語として流通しはじめたということです。
しかし、日本ではまだほとんど使われていませんでした。なぜ日本で“more-than-human”という概念が使われないのか考えたとき、エイブラムの翻訳がないからだと気づいたんです。重要な概念は、研究書が翻訳されているから広く使われるわけなので、これは自分で翻訳しようと思いました。
『感応の呪文』は、エコクリティシズムの「ナラティブ・スカラシップ」に相似したスタイルで書かれているのが、面白いところです。ナラティブ・スカラシップとは、従来の学術スタイルとは異なり、作品に描かれている場所に研究者が身をおき、文学テクストとそのテクストに影響を与えている場所というふたつのフィールドで分析をおこない、そのときの経験や思考の揺れをテクスト分析に織り込む研究手法です。ですから、そこにはパーソナルな思索が含まれています。
ナラティブ・スカラシップは、現在ではエコクリティシズムで一般的になりつつありますが、『感応の呪文』が出版された1996年当時はめずらしかった。この本は、エイブラムが博士論文を発展させたものだと思いますが、博士論文は学術的に書くことが求められています。しかし、その後に発展された『感応の呪文』を読むと、執筆スタイルがかなり工夫されていることがわかります。
まずイントロダクションが、学術的なイントロダクションとナラティブ・スカラシップ的なパーソナルなイントロダクションに分かれています。各章も学術的な章とパーソナルな章が交互に配置してあります。学術的に書こうとすると漏れてしまう思索の部分を取り込もうとしている。その試み自体が“more-than-human”への接近に必要な手続きだったのでしょう。従来の学術的方法では、おそらく“more-than-human”に接近することができない。つまり、あの本のスタイル自体が“more-than-human”なるものへのアプローチを示すひとつのかたちなのだろうと思います。
日本だと、管啓次郎さんの論考は初期の頃からナラティブ・スカラシップですね。
§
江川:
結城さんは今まで単著を2冊出版されていますが、2冊目の『他火のほうへ※5』では、食や汚染に関する論考と作家のインタビューが並べられています。その構成は、食を描いた文学テクストとの対話と、そのテクストを生み出した作家の身体的環境との対話を重視したものだと書かれていますね。ここには“academic”の言葉の語義とされる「研究のことばかり考えて外の世界を忘れてしまう」研究スタンスではなく、研究者による批評的モノローグにならないよう、他者に対して開かれた研究者の姿があるように思います。
対象へ身体的に参与していくこうした批評のスタンスから、文学から見た食の問題、汚染の問題、核・原発の問題へのアプローチなど、これまで取り組んでこられたことについてお聞かせいただけますか。
結城:
食の問題と汚染の問題はつながっています。これもきっかけは石牟礼文学でした。とくに『苦海浄土※6』の「水俣病わかめといえど春の味覚」という、忘れがたいフレーズ。なぜ有機水銀で汚染されているとわかっているのに、あの人たちはわかめを食べたのかと、不思議で不思議で仕方がなかった。その疑問が食と汚染の問題への関心につながりました。
食と汚染に関する議論では、食の安全性やリスクに焦点が当てられますが、水俣病わかめの問題は、それからことごとく外れます。社会的に非常に影響が大きく、読み手の心を揺さぶる石牟礼さんの文学世界に描かれている「水俣病わかめといえど春の味覚」というのは、どういう食の風景なんだろうと思い、食と汚染について考え始めました。これが私の食をめぐるエコクリティシズムの原点です。
汚染への関心はそこからさらに膨らんで、今取り組んでいるのは放射性物質による汚染の問題です。これには文学研究だけでなく、対話活動からもアプローチしています。エコクリティシズムの研究者の間では、「エコクリティシズムとは何か」(What is ecocriticism?)だけでなく、「エコクリティシズムは何をするのか」(What does ecocriticism do?)ということが、初期の頃から問われています。いろいろなタイプのエコクリティックがいますが、私自身は“doing”の方にいく傾向がある。専門として文学研究に従事していますが、それが行動につながるような機会には積極的に参加してきました。
そのひとつが高レベル放射性廃棄物の地層処分の問題です。高レベル放射性廃棄物は地上に貯蔵しておくわけにいかない。テロなどで狙われると大変なことになります。今すぐにでも処理しなくてはいけない。地下500メートルくらいのところに安全な形で隔離する地層処分が国の方針として選択されましたが、場所の選定は進んでいません。埋める場所を決める上で多くの人との対話が必要ですが、その対話が成り立たない。
高レベル放射性廃棄物は「原発のごみ」とも言われます。地層処分は、原発の問題ではなく、ごみの問題なのですが、やはり原発と関わるために、賛成・反対という対立軸が持ち込まれます。対立の場になってしまうと、当然ながら対話は進まない。でも地層処分をめぐる対話は絶対に必要なので、今はこの対話活動に関わっています。
この対話活動の一環として、2019年の秋に福井県鯖江市で開催された、原発のごみを考えるシンポジウムに参加しました。福井は原発銀座と呼ばれるほど原発が集中しています。ですから、登壇者はみんな結構ピリピリしていて、そのパネラーの一人がNUMO(原子力発電環境整備機構)という地層処分を進める組織の方でした。
NUMOの方たちは、日本各地で地層処分に関する対話型説明会をおこなっています。「非常に安全な技術で埋めますから、どうぞご安心ください」と説得するスタンスです。司会は作家の田口ランディさん。私はランディさんと一緒に何度か対話活動に参加していますが、彼女は分かりやすい言葉で重要なことをお話しになるので適任でした。そして、私は文学研究でこういった問題に関わる立場から、パネラーの一人として参加していました。
そのときに、上品に話をしても対話にならないと思ったので、私がすこし誘導尋問みたいなことをしたんです。「ウランの身になって考える」ということを説明するために、アメリカのネイチャーライターであるアルド・レオポルドの“Thinking Like a Mountain※7”(山の身になって考える)というエッセイを引き合いに出したんですね。このエッセイは、生態系という大局的な見地に立ったときに、人間のおこないがどう見えてくるかということを主題にしています。
それで私は「原発のごみを安全な形で埋めるといっても、埋められるウランの残りかすにしてみれば、人間のために徹底的に搾り取られた後に、ごみとして埋められるって、やってられないんじゃないですか」と言いました。驚いたことに、そうするとNUMOの方が「自分がウランだったら、これだけ人間に貢献したのにごみとして捨てられるって、ふざけんじゃねーって言いたい」って答えたんです。そのときに初めて、NUMOの方と通じ合った感触を得ました。対話の場が開けるかもしれないと感じたんです。
地層処分の対話の場をつくるのに、文学が有効な手段になりうると思いました。批判的な物言いだと喧嘩になってしまうので、文学を媒介に「こういうふうに語っているエッセイがあります」と言ってみる。対話を進めるためのコモングラウンドを形成するときに、文学が果たす役割は小さくないと思いました。このように、今はエコクリティックという立場で作品分析をしながら、そこで培ってきた考え方をアクチュアルな問題につなげることを試みています。
§
江川:
最後に「環境人文学」についても聞かせてください。環境人文学は21世紀に入ってから始まった人文・社会科学分野の協働の動きで、環境をめぐる文化的・哲学的枠組みを学際的アプローチから探ろうとするものですが、結城さんも里山についての協働的研究を実践され、その成果を共編著『里山という物語※8』として出版されています。この取り組みについても聞かせください。
結城:
『里山という物語』は、歴史学者の黒田智さんとの共編著書で、他の分野の研究者にも関わっていただきました。環境人文学という協働の取り組みはオーストラリア、北欧、北米でかなり盛んですが、それぞれ地域ごとに特定のトピックで議論されています。たとえば、オーストラリアでしたら先住民アボリジニの問題がかなりフォーカスされていますし、北欧ですと寒冷地特有の問題と気候変動、北米でもロサンゼルスならアーバンネイチャーなど、その地域特有の環境に関わるトピックが扱われています。
当時勤務していた金沢大学は、キャンパスが里山にあり、里山研究も活発でしたので、この問題は金沢でやるべきだろうと問題意識を共有する研究者が集まって取り組みました。共生のシナリオだけで進んでしまうのは危険だという共通認識があり、里山を言説や歴史の観点からきちんと分析をしなければと考えたのです。その成果をまとめたのが『里山という物語』です。
環境人文学は研究分野ではなくプラットフォームです。問題意識を共有する研究者が集まって協働しながら研究を深めていく場なので、問題意識が共有されていないと成り立ちません。専門知を深めて共有することと、実際に起きている問題への理解が、協働には必要です。
そこでいう問題はローカルなものもあれば、グローバルな気候変動や、先ほどお話しした放射性廃棄物の地層処分のような問題もあるわけですが、里山は金沢という場所にあったテーマでした。いずれも、アクチュアルな問題に向けた研究であり、対話のコモングラウンドを探る環境人文学的プロジェクトなのです。
§
江川:
文学的想像力を対話の場に用いていくということですね。それは文学的想像力が社会に対してなにができるかという問いへのひとつの答えかもしれません。本日は大変興味深い話をお聞かせいただき、ありがとうございました。
Oddly Satisfying Videoとは何か
ここ数年、ネットで密かに増殖をし続けているOddly Satisfying Video(あるいはSatisfying Video)と呼ばれる映像群をご存知だろうか。この名前に聞き馴染みがなくても、Oddly Satisfyingな映像は度々目にしたことがあるかもしれない。Oddly Satisfying Videoとは、オンラインビデオのジャンル名のようなもので、「視聴者が心地よいと感じる出来事や特定のアクション」をドキュメントしたスタイルのもの。Wikipediaによれば、典型的な例として「木や泡、スライムといった素材を削ったり、溶かしたり、塗り付けたりするもの」「ドミノ倒し/Rube Goldberg Machine(いわゆるピタゴラ装置)」「手品/隠し芸的なもの」などがあげられている。「なぜかうっとり眺めてしまう動画」あるいは「不思議なよさがある動画」というのが、ニュアンスが近い翻訳になるだろうか。
Oddly satisfying videos are a genre of internet video clips that portray repetitive events or actions that viewers find satisfying. Typical subjects include materials (wood, foam, etc., and in particular slime) being manipulated (carved, smoothed, dissolved, etc.), domino shows, or parlor tricks.
Wikipedia: Oddly satisfying videos※1
以下はOddly Satisfying Videoの一例である。(YouTubeやInstagram※2で「Satisfying Video」などで検索すれば嫌というほど同じような動画を見ることができる)
YouTube: Satisfying Videos of Workers Doing Their Job Perfectly (2019)
YouTube: Oddly Satisfying Magnetic Balls | Magnetic Games (2017)
YouTube: Hydraulic Press | 9 Different Balls (2016)
YouTube: Oddly Satisfying & Relaxing Video to Help You Feel Calm (2020)
インターネット・ミームに特化した百科事典サイト、Know Your MemeのOddly Satisfyingの項目によれば、この奇妙な動画群がインターネット上で広がりはじめたのは、およそ10年前からと言われている※3。2013年にRedditで、「不思議なよさがある動画/画像」を投稿し合うOddly Satisfyingというサブレディット(いわゆる板)が立ち上がって以降、じわじわとそのポピュラリティが広がり、2020年4月時点では、420万人以上もの人々がこのサブレディットを購読している※4。
また、Know Your Memeでは、Oddly Satisfying Videoから派生した、あるいは関係があるジャンルとして、物が偶然ぴったりとはまる場面を集めたPerfect Fit※5や、様々なものを縦横にキッチリと整列させて並べたものを俯瞰で撮影した写真をあつめたKnolling※6※7、水圧洗浄機の使用前・使用後を眺めるPower Washing Porn※8、また昨今日本でも認知度が上がりつつある、ゾワゾワとした感覚を味わう「トリガー」を共有し合うASMR(Autonomous Sensory Meridian Response※9)などを紹介している。
インターネットが炙り出す「非言語の感覚が規定するジャンル」
これらは一体何なのだろう?どの映像もひたすらぼんやり眺めてしまう不思議な魅力を持っているが、その魅力が何なのか、うまく説明するのが難しい。2018年、WIREDイギリス版ではOddly Satisfying Videoを紹介する記事の中で、この奇妙なムーブメントについて、YouTube動画トレンド分析の総責任者であり、YouTubeにおける動画文化を語った“Videocracy”(邦題『YouTubeの時代 動画は世界をどう変えるか※10』)の著者であるKevin Alloccaの考察を紹介している。
I think we’ve always had a desire to watch these type of things, but we just didn’t have a language for it. Now we do.
Kevin Allocca “The odd psychology behind oddly satisfying slime videos”※11おそらく我々は元来こうしたタイプの動画を見たいという願望を持っていたのだけど、ただそれに名前がなかっただけなのです。(著者翻訳)
つまり、Oddly Satisfying Videoは新たに「発明」された映像形式ではなく、名前のない不思議な感覚に共感する人たちがインターネットによって顕在化したことによって「発見」された映像ジャンルであり、それまで視聴者がなんとなく共有していた「こういうタイプの映像」の非言語な感覚、いわば「よさ」に「Oddly Satisfying」という名前がついたことで、共感しやすくなり爆発的に広がったというわけだ。
このように、インターネットによって「発見」された事象というのは、実はOddly Satisfying Video以外にも多くの事例がある。例えば、RedditではOddly Satisfyingと近接するジャンルとして扱われているASMR※12も、Oddly Satisfying同様に、キーボードのタイピング音や、指でものをタップする音、ハサミの音、あるいはボブ・ロス(「ボブの絵画教室」の、あのひげのおじさんだ)のボソボソとした話し声といった特定の音に独特の心地よさを感じていた人たちがいたものが、「ASMR」という名前が付いたことで爆発的に広がった。
また、通称「蓮コラ※13」とともにネットで話題になった、小さな穴や斑点などの集合体に対する恐怖症の名称とされる、トライポフォビア※14という言葉があるが、これは実は正式な医学用語ではなく、小さな穴や斑点などの集合体が写った写真に同様の嫌悪感を感じる人々がいることからネット上で命名されたものであった※15。これもOddly SatisfyingやASMRと同様に、「ネットによって炙り出された恐怖症」と言えるだろう。
「Goods(よさ)」へのまなざし
Oddly Satisfying Videoが新たに発明されたジャンルではなく、発見された〜炙り出されたジャンルなのだとすれば、Oddly Satisfyingという言葉が生まれる前からOddly Satisfyingな要素を持った映像を制作している作家がいたはずである。
YouTube: Ralph Steiner “Mechanical Principles” (1933)
これは1933年にアメリカの写真家、Ralph Steinerによって撮影されたドキュメンタリー作品。ストレートフォトグラフィーの視点から歯車の動きなどをグラフィカルに切り取っている。工場の機械が淡々と物を製造する様子は、現代のOddly Satisfying Videoの中でもポピュラーなジャンルの一つだ。
YouTube: Charles & Ray Eames “BlackTop” (1952)
学校の校庭に清掃員が水をまいているのを見てその場で撮影したという、家具のデザインで知られるCharles & Ray Eamesの1952年の作品。洗剤で泡立つ水、乾いたアスファルトが湿って色が変わっていく様子などOddly Staisfyingな瞬間に溢れている。水の振る舞いをグラフィカルに捉えていく手法は先に紹介したRalph Steinerの1929年の作品”H2O※16”との類似が見られる。
YouTube: Charles & Ray Eames “Fiberglass Chairs” (1970)
FRPの椅子が手作業で作られていく過程をドキュメントした映像。ファイバーグラスにプラスチックを流し込み、プレッサーで型押しをする瞬間や、型押しからはみ出たファイバーグラスをカッターで切り取る瞬間などがたまらない。
どの映像にも物や事象に対するフェティッシュとも言える視線を感じることができる。後年Charles Eamesはハーヴァード大学での講演で、この眼差しを「Goods」という言葉で語っている。
YouTube: Charles Eames ”Norton Lecture ‘Goods’” 岩本正恵訳 (1981)
1971年にハーヴァード大学で行われた記念講義で、3枚づつスライドを映しながらCharles Eamesが「もの」(Goods)について語るというもの。上記の映像でも見られたようなモノ、事象に対してのフェティッシュな視点が語られている。
「もの」(Goods)というのはじつに魅惑的です。
布地には独特の魅力があります。布地そのものの外見、動き、感触──布で何を作るか、何を縫うかではなく、布地そのものの魅力があります。
そしてロープのかせも魅力的です。このごろはもうロープはかせでは売っていないでしょうか。おそらく物干し網はかせで売っているように思います。かせはお互いにつながっているように並んでいます。これだけで完璧な感じがします。かせをほどくのがもったいない。そのままとっておきたくなります。
リールに巻かれた網もみごとです。これは針ヤード、帆を上下させる動索です。すばらしい。船具屋などで売られている様子…巻きついている様子…この細部。これもまたすばらしいものです。
糸玉。糸玉を捨てるなんてできません。糸玉にはなにか特別なところがあります。封を切って使いはじめる直前の瞬間。まるで封印されたような状態の糸玉は、手放したくなくなるもののひとつです。糸玉の入っているあの鉄の道具もすばらしいですね。下から糸を引き出すと、永遠に出てくるような気がします。
小さな樽に入った釘。樽に入った釘もすばらしい。家で何かを使いはじめるとき、かならず「釘の樽を開ける」と言う人がいるでしょう。このごろは家庭に樽入りの釘はありませんが、何かを使い始めるときの、あとは減る一方のものを使い始めるときのシンボルです。
箱入りのお菓子。これも樽入りの釘に似ています。最初のひとつに手をつけたときは、樽入りのりんごもそうですが、まだまだあると思うものです。樽入りも釘もそうですが、いつのまにかなくなってしまいます。
紙束。夢に見たことがあるでしょう。じつに美しい。
封を切った包みにも独特の魅力があります。隅が破けているようす、まるで誘っているようです。最初の一枚を取り出す時の、あの特別な感覚。なにかが変わるような、あの感覚。
箱入りのチョーク。チョークは箱に入って並んでいる時が一番すばらしい。箱にもさまざまな種類があります。このごろでは箱入りのチョークにめったにお目にかからなくなりました。
薪の束。ある時期にはこのうえないあこがれの対象です。薪にも、あの感覚、最初に手をつけるときのあの感覚があります。最初の一本を取り出すと、もう束は崩れてしまう。そしていつのまにか、薪の束はなくなってしまいます。
これが「もの」(Goods)です。
Charles Eames “Norton Lecture ‘Goods’”
講義の中で「Goods」というものが単に「物質」の話ではなく「事象」についても語られていることに注目したい。この言葉自体は、非言語な感覚=「よさ」という言葉に近いニュアンスを包含しているのが興味深い。
「よさ」を先鋭化するインターネットのアーキテクチャ
このように、以前からOddly Satisfying VideosやASMRのような非言語の「よさ」は既に存在していた。ではなぜ、2010年代に入ってからこれらが再発見され、急速に広まっていったのだろうか。これは、2010年代に起こったインターネットにおける以下4つの構造の変化が関わっていると考える。
①YouTubeをはじめとする長尺のビデオコンテンツだけではなく、写真と動画の中間にあたるようなマイクロビデオと呼ばれる新しいメディアとグローバルプラットフォームが登場したこと。RedditにOddly Satisfyingのサブレディットが登場した2013年は、まさにVineが登場とともにTwitterに買収された年であり、それを追うようにInstagramが動画対応した年でもあった。
②Pinterest、Tumblrなどの映像やビジュアルといった非言語コンテンツにフォーカスしたソーシャルブックマーク/ミニブログサービスがミレニアル世代を中心にユーザーを拡大しはじめたこと。これらのサービスはInstagramやFlickrといった自身の写真をアップするという用途よりも、ネットで見つけたお気に入りの映像や写真、テキストを引用という形でクリッピングしていくという行為をベースにしており、さらにrepinやreblogという仕掛けによって、自分がフォローしている人がクリッピングしたものをさらに自分の場にn次的にクリッピングできるようになっていた。これにより、ウェブ上から本来の文脈から部分的に切り抜かれたパーツが蓄積され、交換されていくという動きが加速していった。奇しくも、Tumblrが熱狂的なユーザー層が評価されYahoo!に買収されたのも2013年である。
③上記1、2に該当するサービスがいずれもフォークソノミーの概念を導入していたこと。フォークソノミーとは、ひとつのコンテンツに対して、分類者が決めた統制語彙による分類法「タキソノミー」ではなく、ユーザー(Folks)一人一人が各々好きなラベル(タグ)をつけることができるユーザー主導型の分類システムのことである。1、2のサービスで自分が「よさ」を感じるコンテンツに巡り合ったとして、その時に類似したより多くのコンテンツをひきあてるためには、ラベル(タグ)が必要になる。そこで、自然にOddly SatisfyingやASMRといった、よさを指し示すためのタグが開発され、リファラビリティが高くなっていく。「よさ」にラベルがつけられた瞬間というのは、これらの非言語の「よさ」に明確に「ニーズ」が生まれた瞬間でもある。
④動画プラットフォーム上でのマネタイズのためのシステムが整ったこと。再生回数が稼げれば稼げるほど広告収入が入るという極めてシンプルなルールだ。グローバルプラットフォームで再生数を稼ぐには、非言語で、スティッキネスが高い(=じっと見入ってしまう)Oddly Satisfying Videoはビュースルー率も高く、収益化には極めて向いているジャンルであると言える。(最近、Oddly Satisfyingな動画が、「Promoted動画」としてあなたのInstagramやFacebookのタイムラインに流れてきて、じっと見入ってしまったことはないだろうか?)
非言語の「よさ」がオンラインビデオという形で「標本化」され、その標本が個別に参照可能になった。
↓
それらの「よさ」に共感しシェアする人々が顕在化した。
やがて、フォークソノミーのアーキテクチャによってその非言語の「よさ」に名前がつけられるようになった。
↓
名前がついたことで、より多くのニーズが生まれた。
このニーズによるマネタイズを狙ったユーザが、より「よさ」のある動画を量産していくことで「よさ」が先鋭化されていった。
プラットフォームのグローバル化により非言語の「よさ」が追求されるようになり、競合との差別化とのために見ている人が「よさ」を感じることを主な目的として先鋭化され、より生理的な心地よさがただひたすらに追求された結果がOddly Satisfying Videoの正体である※17。
ここまではOddly Satisfying Videoがどのように登場したのか、考察を展開してきたが、ここからは主にOddly Satisfying以降に登場したいくつかの作品をとりあげながら、Oddly Satisfying以降の表現のあり方を探ってみたい。
Satisfyingな瞬間を彫刻化する
ストックホルムをベースに活躍する映像作家Andreas Wanner※18は、ずばり「Oddly Satisfying」と名付けられた動画シリーズに象徴されるように、まさにOddly Satisfyingをテーマに作品を制作している作家だ。3D空間上の物理シミュレーションを利用して、完全にループするように再現されたOddly Satisfyingな現象がポストモダン風のアートディレクションでパッケージングされている。
Vimeo: Andreas Wanner “Gummy Tron” (2020)
基本的にOddly Satisfyingな動画は現実世界での中毒性のある瞬間をドキュメントしたものが中心的だが、Andreas Wannerの作品は、そうしたOddly Satisfying動画の中の中毒性を分析し、それをシミュレーション空間上で再現するアプローチと言える。
パリをベースに活躍するCGアーティストのRoger Kilimanjaro※19もAndreas Wannerと同様、Satisfyingな瞬間をループ映像として再現するアプローチをとっている作家の1人だ。
YouTube: Roger Kilimanjaro “Sliced gold loops” (2018)
Andreas WannerやRoger Kilimanjaroのような作風が登場した背景には、Cinema4DやHoudiniのように3D制作環境で高精度な物理シミュレーションやパラメトリックな動きの制作が行いやすいようになってきたこともあるだろう。しかし2015年あたりから、FacebookやInstagramで再生される動画がフィード上で自動再生になり、かつ短尺の映像はループ再生されるようになったことがより大きな影響を与えていると考える。それは彼らのポートフォリオにYouTubeやVimeoのリンクだけではなくInstagramアカウントへのリンクがあることからも明らかだ。
シームレスにループ再生されるこれらの映像は、YouTubeやVimeoのように始まりと終わりがあるフォーマットとは時間の概念が異なる。ちょうどOddly Satisfyingのエポックである2013年の数年前に流行した、GIFのループアニメーション機能によって、うまく画像の中に時間の概念を閉じ込める手法、Cinemagraph※20に見られるような、いわば現象を彫刻化するような時間特性を持っている。
ウェブデザイナー、中村勇吾の初期の作品の一つである物理シミュレーションを利用した“JamPack※21”や、ハイスピードカメラで水の中に文字が落ちる瞬間を組み合わせた“DROPCLOCK※22”、トラス構造が物理シュミレーションに忠実に崩壊していく様子を描いた“CRASH※23”など、これらの作品は、前述したSatisfyingな瞬間の彫刻化という動きを予見していた作品とも言えるだろう※24。
Satisfyingのメカニズムを利用する
アメリカのサイエンス誌『Discover』は2017年、Oddly Satisfying Videoに関する記事の中でOddly Satisfyingを心地よく感じるメカニズムを考察している※25。
Hard answers may be lacking, but the oddly satisfying videos appear to tap into a subconscious urge toward what psychologists call a “just right” feeling. It’s the sensation that arises when we’ve put things in order, and serves as a useful cut-off point for simple tasks. It’s also what often goes wrong in individuals with Obsessive Compulsive Disorder (OCD). For reasons not quite understood, some people with OCD don’t interpret the sensory cues that indicate the job is done, leaving them searching fruitlessly for a sense of completion. The quest for finality often leads to things like continually arranging objects, checking doors repeatedly to see if they are locked or cleaning things uncontrollably.
“Why Are Oddly Satisfying Videos So … Satisfying?※26”どうやらOddly Satisfying Videoは、心理学者が“Just right feeling”(まさにぴったり感)と呼ぶ、潜在的な感覚に関与しているようです。“Just right feeling”とは、我々が物事を整理したときに発生する感覚で、人が「ある作業が完了した」ということを認識させるために生じる感覚とされていますが、強迫性障害(OCD)の患者の多くは、この感覚をうまく感じれないことがあります。この“Just right feeling”を感じ取ることができないため、「作業が完了した」と認識することができず、「作業が完了した」ということを認識するために無駄な作業を繰り返してしまう。それが、場所の配置を延々調整しつづけたり、ドアに鍵をかけたかずっと確認したり、延々掃除をしつづけてしまうというといった行動に現れるのです。(著者翻訳)
“Just right feeling”のような認知のメカニズムを応用することで、新しい表現を探索することが可能だろう。映像作家、菅俊一の映像作品『Imagine Yourself / その後を、想像する※27』では、シンプルな図で描かれている事象は、どれもがSatisfyingな瞬間なように見えるが、映像の中で最もSatisfyingな瞬間は、画面がブラックアウトしてしまう。
Vimeo: 菅俊一『Imagine Yourself / その後を、想像する』(2019)
しかし、肝心な瞬間は描かれていないにもかかわらず、なぜか我々の脳内ではそこで何が起こるのか、想像できてしまう。菅はこれらの人間の認知における補間能力に注目し「指向性の原理」を提唱している※28。
また、「特定のタスクが終了した、ということを知らせるための満足感の伴う感覚」の想起はユーザーインターフェイスにおいても非常に重要な要素である。近年多く見られるマイクロインタラクション※29と呼ばれるユーザのアクションに付随する細かなモーションデザインは、ユーザーの“Just right feeling”を想起させ、ユーザーエクスペリエンスを向上させるためのデザインアプローチと言えるだろう※30。
未知の「よさ」を探索する
最後に、2013年に公開された1本の奇妙なミュージックビデオについて、その監督2人(細金卓矢と杉山峻輔)への伊藤ガビンによるインタビューの一部を紹介したい。
YouTube: tofubeats “No.1 feat.G.RINA” (2013)
—— 今日はこの極めて評判のいいMVの「よさ」について語ってみたいわけなんですけどね。
細金:「よさ」ね。でもこれアップするまで受け入れられるかどうかまったくわかんなかったですよ。自信ないってことじゃないんだけど、判断基準がなさすぎて。
—— うん。「よさ」しかないからね。
スケブリ(杉山):そうそう、中身ない(笑)。
細金:だから「よさ」が合う人にはいいだろうけど、それがいったいどれくらいの数なのか、未知数すぎてわからなかった。
—— 結果、すごく受け入れられたよね。でも考えてみれば「よさ」を描くって、ミュージックビデオの根幹でもあるわけで。
細金:うん。だから発表したらみんなが「よさ」って書いてて、それはよかった。
「よさについて tofubeats No.1 feat.G.RINA 監督インタビュー※31」
Oddly Satisfying Videoが顕在化する前段階として、本記事では非言語の「よさ」がオンラインビデオという形で「標本化」され、その標本が個別に参照可能になったことが引き金になっていると考察した。これは現在進行形の現象であり、Oddly Satisfyingという既存のジャンルに自己言及する形で先鋭化していく表現とは別に、新たな、未だ名前のない「よさ」を探索する動きは今日もインターネットのどこかで続いている。うまく言葉にできないもの、その非言語の感覚が何故か人と共有できてしまうもの、それらを発見するところからすべては始まる。
1948年6月、ドイツの米英仏占領区域でドイツマルクが導入され、ソ連によるベルリン封鎖が始まった。いわゆる冷戦の始まりである。アメリカでは1940年以来の平時徴兵が復活する一方、トルーマン大統領が軍における人種差別禁止の大統領令に署名した。7月29日、第二次大戦で繰り延べになっていたロンドンオリンピックが開幕、敗戦国の日本は参加を認められなかった。同31日にニューヨーク国際空港(のちのJFK空港)開港。8月には大韓民国(韓国)が、9月には朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)が相次いで成立した。日本では5月に美空ひばりがデビューし、7月に風営法公布、8月には渋谷ハチ公銅像再建除幕式が行なわれた。第二次世界大戦が終結して3年目の夏に、ブラックマウンテンで起こったことをお話ししたい。
2つのインタビュー
「私がブラックマウンテンに着いたのは1948年の夏だった」バックミンスター・フラー※1はインタビューに応えてそう言った。1971年10月3日、ワシントンD.C.でのインタビューだ。インタビュアーはメアリー・エマ・ハリス※2。1987年にMITプレスから刊行された『The Arts at Black Mountain College』の著者である。BMCのリサーチはハリスのノースキャロライナ大学における修士研究で、このインタビューのときにはまだ在学中だったと思う。彼女は修了してからもBMCのリサーチを続け、16年後に前述の大著を上梓。BMC芸術分野研究の第一人者と目されるようになった。
フラーがBMCに着任したちょうど70年後の2018年夏、文字起こしをしたままのそのインタビュー原稿を見た。ノースキャロライナ州西部地域アーカイヴズ(以下、NCアーカイヴズ)でのことである。タイプされた文字を読んでいく。話し言葉なのでそれぞれの単語は難しくないのだが、ベタ起こし※3ということもあって、言葉の意図を読み解くことは難しい。PDFをもらって帰ってしばらくそのままにしていた。
1年経った2019年夏、そのインタビューを粗訳してみた。やはり細かなニュアンスはとりにくいが、置き換える言葉を丁寧に探していくと、フラーが言いたかったことの輪郭が見えてきた。
そして秋(2019年秋)、三たびブラックマウンテンを訪れた。JFK空港で乗り換えてシャーロット空港へ。今度はちょうどお昼ごろに着く便である。シャーロットから85号線を走り、321号、40号と乗り継ぎ、ブラックマウンテンを越え、スワナノア渓谷を渡るともうアッシュビルだ。そして定宿になったモーテル「ダウンタウン・イン」に着いた。静かな部屋にしておいたよ、とフロントマンがいう。どうもありがとう、と入った部屋は、いつもと変わりない部屋だった。
今回の主要な目的のひとつに、NCアーカイヴズで1948年と49年の夏期講座を調査することがあった。しかし、いつものことだが充分な時間をとれるわけではない。フラーの資料がたくさんあることはわかっていたので、最初にジョン・ケージ※4の資料がないか尋ねてみた。ケージは48年と52年の夏期講座に講師として参加し、BMCとは深い繋がりを持つアーティストである。
「ケージの資料は図書館やトラストが持っていて、写真もここにはほとんどないの。でもインタビュー原稿ならあるわよ」
司書のサラはそう言ってタイプされた原稿のコピーを出してくれた。それは、『Black Mountain: An Exploration in Community※5』の著者、マーティン・デュバーマンが1969年4月26日に電話インタビューしたものだった。これも文字起こししたままの原稿だが、デュバーマン自身によるものと思われる校正が入っている。
「コピーを取ってもいいかな」
「PDFがあるから送るわ」
ものの数分でメールが届いた。
東京に戻ってすぐ、フラーとケージ、この2人のインタビュー原稿から夏期講座の読み解きをはじめた。
サティ・フェスティバルとメデューサの罠
フラーは1948年の夏期講座に講師として参加し、49年にはディレクターとして迎えられている。夏期講座だけではなくBMC全般において、外部から招聘されたただ一人のディレクターである。指名したのはアルバースだが、フラーはそれをこのインタビューを受けるまで知らなかったようだ。
フラーはBMCへの着任を偶然だったと言っている。もともと1948年の講師を頼まれたのは、シカゴの建築家でバウハウスへの留学経験があるバートランド・ゴールドバーク※6だった。しかし都合がつかなかったのか、その代役としてフラーに話がきたらしい。しかもフラーとゴールドバークとは面識がなく、共通の知人を通じての誘いというから、フラーにとっては本当に偶然のようなものだったのだろう。
1946年ごろからフラーは本格的な幾何学の研究に入っており、BMCの夏期講座に参加する直前にその後のフラー幾何学の核となる「ジターバグ変換※7」を発見している。それが1948年夏のBMCでのジオデシックドームの実験に繋がるのだが、フラーが本格的に注目を浴びるのはドームが実用性を帯びる50年代半ばまで待たねばならない。したがって、このころはまだまだ不遇をかこっていた時期だった。そんなフラーにとって、2度のBMCの夏はかけがえのない時間だったはずだ。そしてそれは、BMCにとっても同じだった。
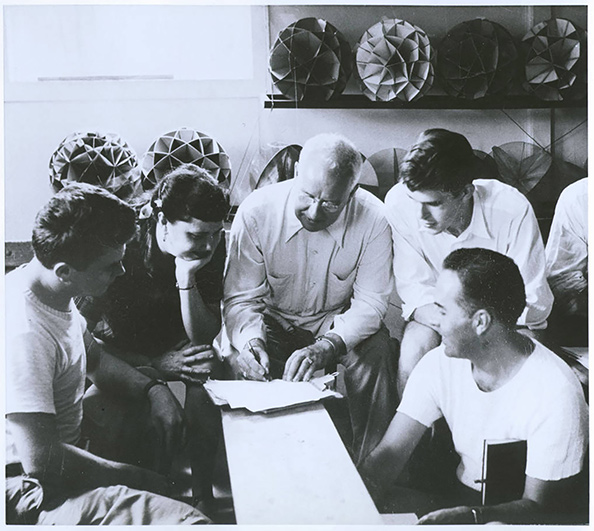 [図1]1949年夏のBMC。ジターバグ変換の自作模型に囲まれ授業するフラー
[図1]1949年夏のBMC。ジターバグ変換の自作模型に囲まれ授業するフラー
インタビューは、1948年にフラーが「メデューサの罠(Le piège de Méduse)」のお芝居でメデューサ男爵を演じた話で始まる。たぶん写真を見ながらだと思う。演劇はBMCの芸術教育のなかでもベーシックなものだが、この舞台は少し事情が違ったようだ。
 [図2-1]エレイン・デ・クーニングとフラー
[図2-1]エレイン・デ・クーニングとフラー
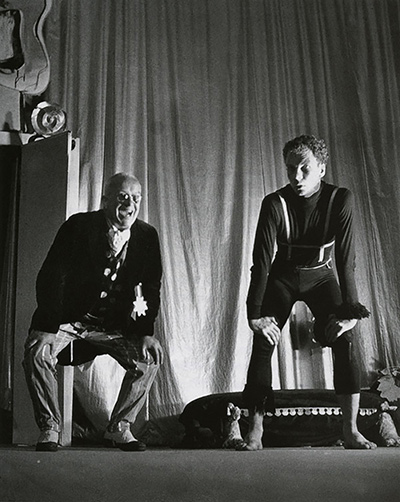 [図2-2]機械仕掛けの猿を演じるマース・カニンガム
[図2-2]機械仕掛けの猿を演じるマース・カニンガム
(以下、BFはフラー、MHはハリス、##は誰だかわからない。頻繁に発言してるところから、フラーとは親しい人のようだ。このインタビューのコーディネイターなのかもしれない。カッコ書きは筆者の補足。)
BF「これはウィレムとエレイン、失礼、マース・カニンガム※8とエレイン・デ・クーニング※9だ。エレインは私の娘役で、マースは猿(機械仕掛けの猿)の役だった。こっち(の写真)はその猿と踊っているところだ。そして……。」
##「おお、それが知りたかったの!バッキー!」
BF「シアターに参加したすべての人のなかで、私が考えられる完璧なキャストだよ。」
##「ほら、この帽子を見て!とても素敵な帽子!」
BF「私が作ったんだよ。」
##「あなたが?」
BF「うん、ベネチアンブラインドストラップで作った。」
MH「この帽子を?」
BF「そうだよ。」
MH「どっちの?」
BF「私が被ってる帽子」
MH「あなたの帽子……わかった! ラインがあるのに気付かなかった。 」
BF「私はこの小道具を長い間全部保管していたけど、移動が多くてもうどこにやったかわからなくなってしまった。」
##「バッキー、ジョン・ケージは出演していた?」
BF「いいや、彼は最後まで音楽を演奏していた。彼はこのハプニング全体を担当していたんだよ。」
MH「この人は誰?」
BF「それは、猿に扮したマース(・カニンガム)だよ。彼は猿だから、決して直立姿勢にはならなかったんだ。」
「メデューサの罠」はエリック・サティ唯一の戯曲で、ジョン・ケージがBMCで企画した「サティ・フェスティバル※10」に関連したパフォーマンスだ。もちろん当時にはまだ「パフォーマンス」という概念はない。フラーがインタビューで言っている「ハプニング」の概念もまだないが、同じことを指しているはずだ。戯曲や演劇とは言いたくない、新しい何かだったのだ。
パンフレットがあるので見てみよう。
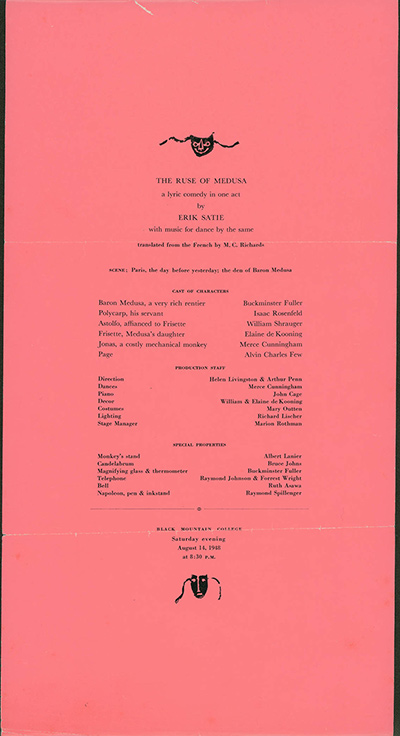 [図3]「メデューサの罠」パンフレット。フラーはインタビューで、ブラックマウンテンの印刷所で刷った美しいパンフレットと言っている
[図3]「メデューサの罠」パンフレット。フラーはインタビューで、ブラックマウンテンの印刷所で刷った美しいパンフレットと言っている
タイトルは「メデューサの罠 一幕の詩劇 エリック・サティによる」。原詩はフランス語で、翻訳はM. C. リチャーズ※11。キャストは、メデューサ男爵にフラー、その奉公人にアイザック・ローゼンフェルド※12、娘の許婚にウィリアム・シュラウガー、男爵の娘にエレイン・デ・クーニング、機械仕掛けの猿にマース・カニンガム、ペイジ役にアルビン・チャールズ・フューの6人。
スタッフとして、監督:ヘレン・リヴィングストンとアーサー・ペン※13。振り付け:マース・カニンガム、ピアノ:ジョン・ケージ、舞台装置:ウィレム※14&エレイン・デ・クーニング、衣装※15:マリー・アウテンなど、そのほかさまざまな役割をあわせて14名、総勢20名で行なった演劇(パフォーマンス)である。こうして名前を並べるとその豪華さに驚く。フラーとケージはそれなりに知られていたかもしれないが、2人を含め、まだみんな無名だった。
ここで「メデューサの罠」を企画したジョン・ケージに話を移そう。ケージは1948年4月にカニンガムといっしょにBMCを訪れている。ニューヨークからカリフォルニアへと向かう大学を巡る「ソナタとインターリュード※16」のツアー(ダンスと音楽のツアー)を組んでおり、その一番最初の公演先がBMCだった。滞在は5日間で、公演の報酬は宿泊と食事だったという。
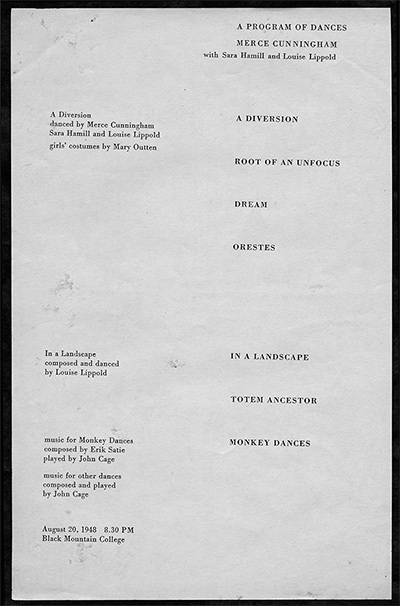 [図4]4月20日に公演されたカニンガムのダンスプログラム。音楽とピアノはケージ。ここでサティの「モンキーダンス」を踊っている
[図4]4月20日に公演されたカニンガムのダンスプログラム。音楽とピアノはケージ。ここでサティの「モンキーダンス」を踊っている
ケージはBMCの進歩主義的な教育方針に惹かれ、これまでに2度手紙を出している。1度目は30年代末、教員のポストを打診するもの。2度目は1942年に実験音楽センターの開設を要望するものである。どちらのラブコールも叶わなかったケージにとって、この公演はとても楽しみだったに違いない。
結果、公演は大成功を収め、ケージとカニンガムはアルバースからその年の夏期講座の講師を依頼される。ケージは、同じく講師として、彫刻家のリチャード・リッポルド※17と画家のウィレム・デ・クーニングを推薦した※18。
ケージは自叙伝でBMCの印象を述べ、サティ・フェスティバルについても触れている。
ドイツ人が多いブラックマウンテンカレッジで、エリック・サティの音楽に触れる機会が少ないことに気がついた。ここでひと夏教えることになり、学生がいないこともあって、サティの音楽を紹介して聴いてもらおうと、夕食後30分のサティ・フェスティバルを企画した。そしてそのなかでサティとベートーヴェンを対峙させる講演を設け、ベートーヴェンではなくサティが正しいことを語った。
ジョン・ケージ「自叙伝※19」
ケージは「音楽の構造」と「振付法」という二つの授業を担当していたが、「振付法」には履修者がいなかった(「音楽の構造」は7名が履修した)。したがって、サティ・フェスティバルは「振付法」の代替えとして考えたプログラムだったのだろう。
学校ではほとんどの人がドイツ人かドイツ気質だった。だから夏を通じて現代音楽全般ではなく、エリック・サティだけを取り上げたということで、とても反感を買ったんだ※20。アルバースはそれを少しでも軽減し、考えが理解されるようにと、毎回のコンサートの前に講義をするように求めた。それはうまく機能したと思う。
マーティン・デュバーマンによる電話インタビュー
ケージが「BMCはドイツ人ばかり」と言っているのは、ほかの文章でも目にしたことがある。ひとつの発言がさまざまに引用されているのだと思うが、印象に残る言葉ではある。あきらかにドイツからやってきた亡命芸術家への、ある種の感情が見え隠れしているからだ。
一方の“ドイツ人ばかり”のBMCの音楽講座は、伝統的なクラシック音楽教育が中心で、ディレクターを務めていたエルヴィン・ボドキーはバッハやショパンを鑑賞する「土曜の夕べ」のコンサートを企画し、ベートーヴェンの「32曲のソナタ」の講義を行なっていた。ベートーヴェンはご存じのようにドイツが生んだ偉大な作曲家である。
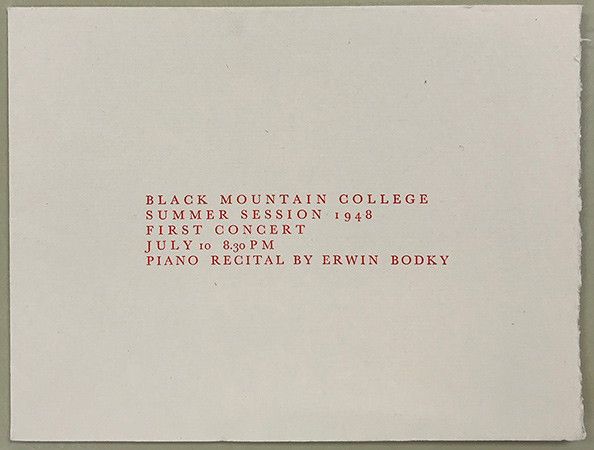 [図5-1]夏期音楽講座で催されていたコンサートのパンフレット。7月10日のプログラム
[図5-1]夏期音楽講座で催されていたコンサートのパンフレット。7月10日のプログラム
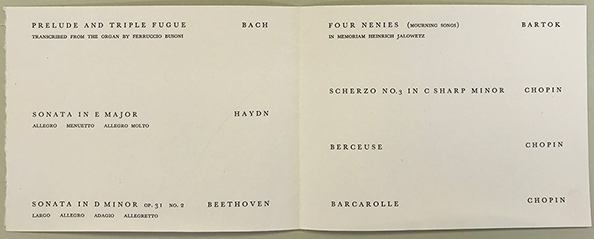 [図5-2]バッハ、ハイドン、ベートーヴェンといった名前が並ぶ
[図5-2]バッハ、ハイドン、ベートーヴェンといった名前が並ぶ
ロサンゼルス生まれのケージは、1930年、17歳のときに飛び級で入学した大学を中退し、ヨーロッパへ旅に出ている。最初に滞在したパリでピアノのレッスンを受け、ドイツ、イタリアと移動したが、大恐慌の影響で家が傾き、17ヶ月でLAに戻った。なので、けっしてヨーロッパに対する理解がないわけではない。ケージにとってもヨーロッパ文化はお手本であり、先導者だった。しかし多くのケージ研究が指摘するように、ヨーロッパから帰ってからは東洋的な偶然や不確定性に関心を寄せるようになった。ケージはサティ・フェスティバルでの講義をこう記している。
西欧の物質主義の出現とともに和声的構造が出現し、物質主義に対する疑問をいだきはじめたときに、それは崩壊していった。そして異なった東洋の伝統、心の平穏、自己を知ること、そういったことを、われわれが心から必要とした時期に、問題の解決として東洋に伝統的に存在しているリズム構造という問題に到達したことは興味深く、注目に値する。
ジョン・ケージ「サティ擁護※21」
サティとベートーヴェンを対峙させる講演「サティ擁護」で語られた和声(=ベートーヴェン)とリズム(=サティ)の議論に、ヨーロッパ的伝統から離脱しようとする戦後アメリカ美術の萌芽をみることができる。この場合、東洋的云々はさほど重要ではないだろう。戦争も終わり、自分たちの表現を見つけはじめていたケージらアメリカの若いアーティストたちにとって、BMCで講義されているようなドイツのクラシック音楽は、かび臭く、否定すべきものだったに違いない。
しかし、学生の側からすると少し事情が違ってくる。第二次大戦から戻った退役軍人を支援するためのプログラムであるGI法案※22を利用して1947年秋にBMCに入学したアーサー・ペンは、テレビジョン・アカデミーのインタビューに応えてこう言っている。
ドイツのバウハウスにいた移民アーティストの多くが、アメリカの大学について知ることができなかったためか、ブラックマウンテンに定住し、そこで教鞭を執っていたんです。それで私もBMCに興味を持ちました。BMCは学校として認可されていなかったため、彼らはそこで自由に仕事を得ることができたんです。
Arthur Penn on studying at Black Mountain College※23
1948年秋学期から入学したロバート・ラウシェンバーグ※24も同じくGI法案を利用してBMCにやってきたひとりだが、彼もアルバースの厳格な教育に惹かれて入学したと述懐している。
つまり、バウハウス出身者に代表されるドイツ人講師と、その(アメリカ側からみれば)伝統的な教育に憧れた学生、そして、すでに新しいスタートを切っていたアメリカ人アーティストたち、それら三者三様のインタラクションが1948年夏のBMCで起こっていたのである。
いずれにせよ、このサティ・フェスティバルでの講義は、ケージが言うように“うまく機能した”わけではなかった。アルバースが心配したとおり、音楽講座の教員との軋轢は、和解不能なところにまで陥っていた。ケージの評伝にこういった記述がある。
ケージの講演は、この学校を2つの音楽陣営に分断した。ある指導者によると、何人かの学生がベートーヴェンのレコードと楽譜を燃やした。……学校の校長は、長引く論争を終わらせようとして、両陣営に台所で戦闘の準備をして、決着をつけることを提案した。ベートーヴェン派は仔牛肉のカツレツを手にし、反ベートーヴェン派はクレープ・シュゼット〔リキュールに火をつけて出すクレープ〕をつかんだ。校長の戦闘開始の呼びかけは、食べ物を投げ合う大乱戦となったようだ。
ケネス・シルヴァーマン『ジョン・ケージ伝 新たな挑戦の軌跡※25』
訳文に「校長」とあるが、BMCに「President」は存在しない。ただ、ディレクター的な役割の人は決められていて、「Rector※26」と呼ばれていた。1948年8月時点のレクターは、アルバースである。このエピソードに間違いがなければ、アルバースが台所の決闘を提案したことになる。いかにもBMCらしい決着のつけ方ではあるが、厳格でならしたアルバースからは想像しがたい。しかし、そういう一面もあったと思えば微笑ましい。
だからと言って、これで決着がつくはずもなかった。音楽講座の教員たちの怒りは収まらず、理解者であったアルバースの退任もあって、ケージは1952年の夏までBMCに戻ることはなかった。
BMCの夏期講座は、1944年から「サマーインスティテュート」として、音楽(Summer Music Institute)と美術(Summer Art Institute)の2本立てでスタートしている。夏期講座には、この44年からとする論と、前回に紹介した建築と農業の実践講座「サマーキャンプ」が始まった41年からとする論があるが、実は1940年の夏に「スペシャル・サマーミュージックコース」という講座が開かれている。期間は6月16日から7月21日までの5週間、場所はエデン湖キャンパスだが、キャンパスができるまで避暑施設として運用していた名称である「LAKE EDEN INN」となっている。これがBMCが開講した一番最初の夏期講座である。
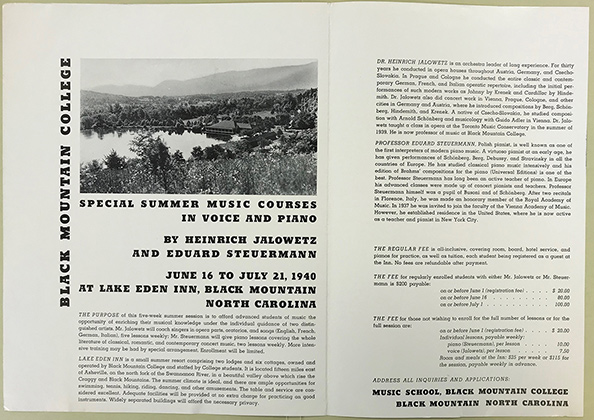 [図6]1940年のスペシャル・サマーミュージックコース、パンフレット
[図6]1940年のスペシャル・サマーミュージックコース、パンフレット
エデン湖畔の土地を手に入れて、長い夏休みに何かプログラムがつくれないかと考えたのだろう。それがサマーミュージックコースだった。ディレクターはハインリッヒ・ジャロウィッツ※27とエデュアード・スティアーマン※28。ジャロウィッツは第二ウィーン学派の中核メンバーとして活躍したヨーロッパからの亡命組でBMCの音楽教育を支えたひとりである。スティアーマンもやはりオーストリア生まれのピアニストで、渡米後もベートーヴェンのリサイタルで名を馳せた。つまりドイツやウィーンのクラシック本流の音楽家たちである。音楽系の教員たちには自分たちが夏期講座をつくったという自負もあったのだろう。名もなき美術講座の若い講師がフランスの異端者の音楽を学生に聴かせることだけでも受け入れがたかったに違いない。
そして、そのサティ・フェスティバルの最後に企画されたのが「メデューサの罠」だった。主演のフラーはシャイなうえ、もちろん演技経験はない。たぶんその素養もない。そのフラーをはしゃがせ、飛び跳ねさせたのは、のちに世界的にエポックメイキングな映画となる『俺たちに明日はない(原題:Bonnie and Clyde)』を監督するアーサー・ペンの演技指導だったというから面白い。フラーはインタビューでこう言っている。
MH「以前にお芝居をしたことはありますか? 」
BF「人生で一度もないよ。」
MH「しかし、アーサー・ペンはあなたに演じさせた?」
BF「観客と実際にコミュニケーションをとる方法について、彼から本当に多くを学んだよ。このことが長年にわたってとても役立ったと思ってる。」
MH「スピーキングや講義で?」
BF「そう。そのとき私は、おそらく演技できないだろうと思っていた。私は子供会など——知ってる?学校じゃないところ——の経験で、実際に演技するのに十分なほど自分を冷静にすることができないと知っていたんだ。詩的な表現を覚えることはできたけど、それを演技に適用することはできないと思っていた。でも、ケージとマースとアーサー・ペンは私にはできると確信していた。だから、『まあ、試すことを鍛錬するのは良いことだと思う』と言ったよ。そして、本当に私は演技のほぼ全部ができたんだ。とても難しい演技だったのに。私はステージに出ずっぱりだった。私のパートは何度も何度も続いた。だから私は、そう、演技することができたのだと思う。」
この舞台は、フラーにとって(内的な)転機となるものだった。まさに経験とは実験の結果に過ぎない。50年代以降のフラーの活躍にとって、この経験は大いなる糧となっただろう。また、ケージやカニンガムと親密な関係になったことも見逃せない。
BF「ジョン(・ケージ)と私は本当にとても暖かい友人関係を作った。ジョンはいつも私について書いているか、あるいは話していた。私も同じだった。
……
そしてジョンとマース、ナターシャが料理をし、私たちは毎日朝食を一緒に木の下で食べた。それは、私たちのための特別な時間だったんだ。……その夏を彼らと一緒に、新しい学校で、本当にとても楽しい時間を過ごした。
……
いくつかの壊滅的なできごとはあったが、それらも私たちがすでに話していた類いのものだった。ジョンとマースの地図(活動計画の話)は、本当にとても楽しかった。私もそうだが、彼らは話すことが好きだったんだよ。」
夏期講座は大成功だった。フラーはインタビューで、「冬のBMC(の学生数)は1ダースかせいぜい2ダース。でも夏はその10倍。少なく見積もっても100人は下らなかった」と述べている。フルに参加した学生がどのくらいいたのかはわからないが、ピーク時にはそれぐらいの人がいたのだろう。経済的にも夏期講座で大いに(とはいかないまでも、少しは)潤ったと思われる。


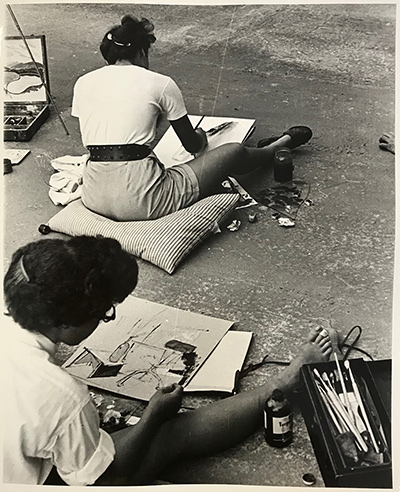
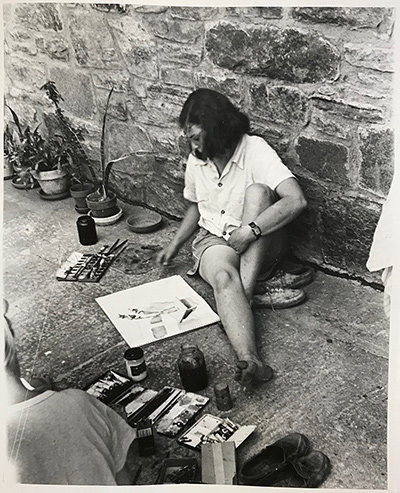
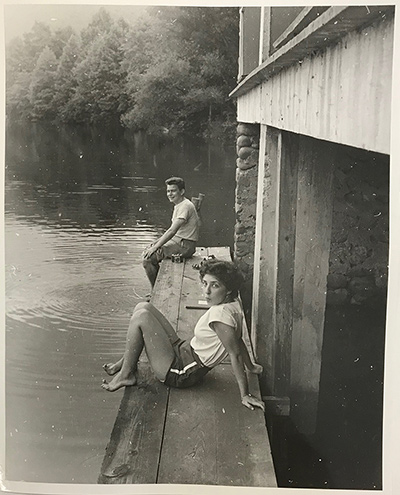

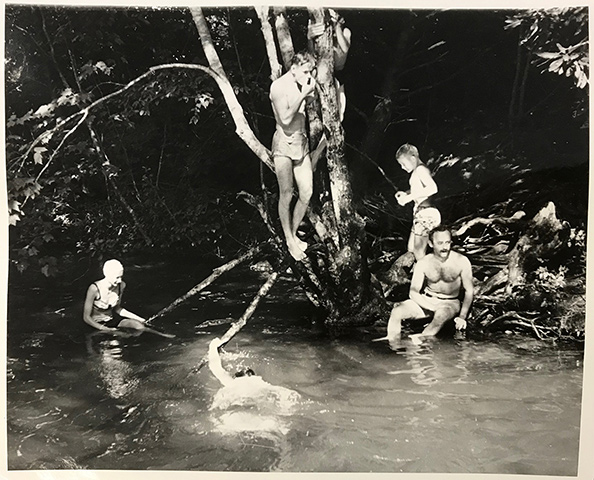
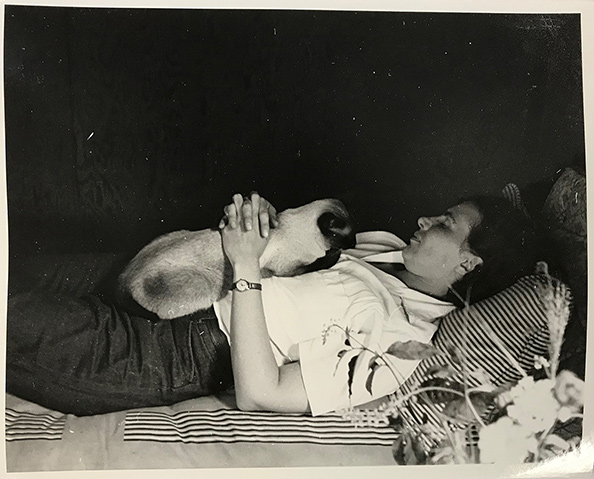 [図7-1〜8]夏期講座での教員や学生たち。オフも授業中もあまりかわりはない。少しでも雰囲気が伝わればと思い、写真を選んだ
[図7-1〜8]夏期講座での教員や学生たち。オフも授業中もあまりかわりはない。少しでも雰囲気が伝わればと思い、写真を選んだ
1948年の夏期講座終了後、フラーはシカゴのデザイン研究所※29で教鞭をとるようになる。デザイン研究所は、モホイ=ナジがシカゴに創設したニューバウハウスの後継校である。当然、ナジとアルバースは親交があるが、着任においてアルバースの口利きがあったのかどうかはわからない。フラーは、アルバースが深く信頼を寄せ、自分が退任したのちに夏期芸術講座を任せようと考えたほどの人物である。まったく無関係とも考えにくい。いずれにせよ、アルバース夫妻、フラー、ケージ、カニンガムらの親交はBMC後も長く続き、それぞれの生涯において欠かすことのできない関係を紡ぐことになる。
最初のジオデシックドームの実験
夏期講座に限らずBMCの授業は担当教員が自由に決めていたようだ。だからこそ、ケージもサティ・フェスティバルを開くことができたのだ。教育の自由に関して、フラーはこのように答えている。
MH「(BMCで)教師は本当に教える自由がありましたか?」
BF「ええ。あれ以上の自由はなかったでしょう。私たちは望み通りに何でもできた。それはとても良いことだったと思う。誰も何も言わなかった。教員の資格云々といったことさえも。」
フラーのドーム建築に協力したひとり、エレイン・デ・クーニングもこう言っている。
(夏期講座の)客員教員は何をどのように教えるかを知らされていませんでした。一部の人は、そういった自由に当惑させられました。ほかの人たちは、スポンサーによる精査や事前の宣伝、大規模な資金提供が必要となるプロジェクトに着手するよい機会だと考えました。彼らは彼らの目の前の情熱、その時に取り組んでいたプロジェクトを教えました。したがって、学生は新しい学習に伴う興奮と不確実性の恩恵を受けることができました。……フラーの夏のプロジェクトは、ベネチアンブラインドストリップの彼の最初のジオデシックドームを建設することでした。
Mary Emma Harris “John Cage at Black Mountain by Mary Emma Harris※30”
エレインの言うとおり、フラーのプロジェクトは、直径48フィート、高さ23フィート、面積1500平方フィートにおよぶ、大きなドーム型構造体「ジオデシックドーム」をつくることだった。BMC着任前にその着想を得ていたフラーは、トレーラーハウス(移動式研究室!)にたくさんのドームの模型を積み込んでBMCにやってきた。そして、すぐにジオデシックドームの実験に取りかかった。それが初めてのドーム建設の実験とされているが、フラー自身の気持ちではそうではなかったようだ。
MH「あなたは…その夏に演技者になっただけでなく、ベネチアンブラインド※31を使用してドームをつくりませんでしたか?」
BF「うん、つくったよ。そのとおりだ。ちょうど利用可能な素材を持っていたので、それができた。 」
MH「それ以前にドームを建設していましたか、それとも…?」
BF「ああ、つくっていた。全部自分ひとりでやっていたよ。ジオデシックドームについて実証したかったんだ。私は自分でつくったモデルでいっぱいのトレーラーを持っていた。」
……
MH「ベネチアンブラインドタイプのモデルも、そこにあった?」
BF「いや。さまざまなタイプのジオデシックドームをつくったが、それはなかった。(BMCで使った)ベネチアンブラインドはアルミニウムを削って使用できるので、とてもたくさんの実験ができたんだ。」
結局、1948年夏のジオデシックドームの実験は失敗に終わった。しかし、そのことに対してフラーはあまり落胆はしておらず、うまくいかないことを予想できていたようだ。そして失敗はより良い結果のための経験であると考えていた。うまくいかなかった理由は資金や資材の不足と言われている。そういうことも多少はあったのだろうが、いろんな意見を統合すると単なる準備不足だったのだと思う。まだ時期尚早だったのだ。それをフラーはよくわかっていたのだろう。この失敗したドームは「The Supine Dome(あおむけのドーム)」と名付けられた。
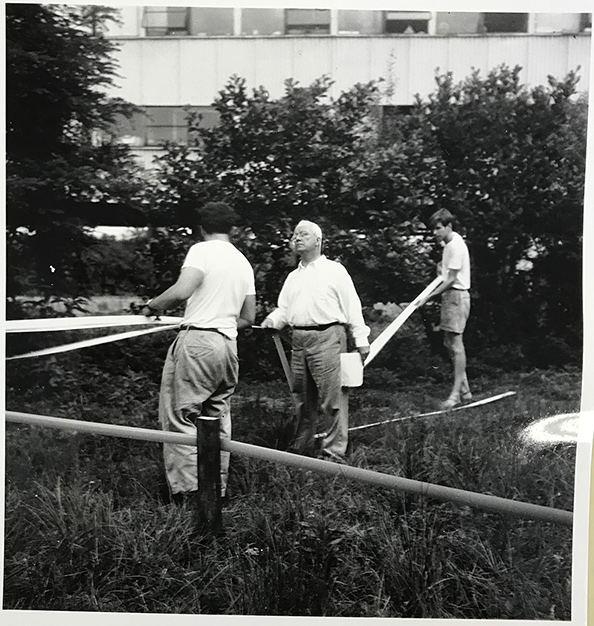
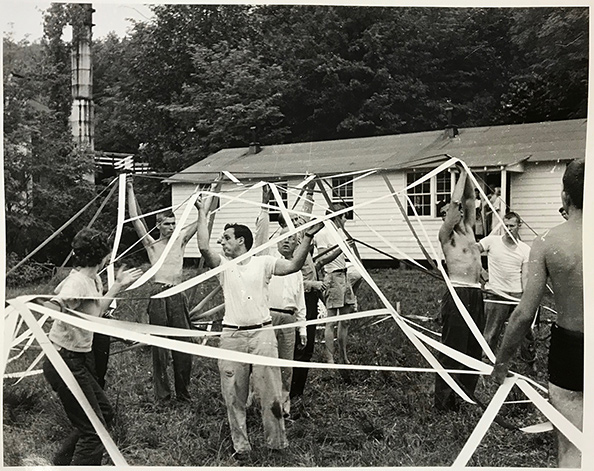 [図8-1,2]制作中のフラー(中央)
[図8-1,2]制作中のフラー(中央)
 [図8-3]失敗したドームについて話し合うメンバー
[図8-3]失敗したドームについて話し合うメンバー
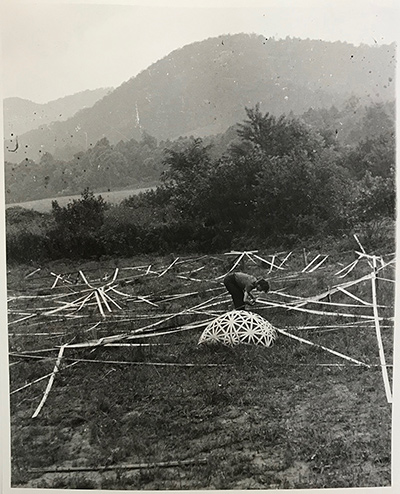 [図8-4]失敗したドームに残って作業するエレイン
[図8-4]失敗したドームに残って作業するエレイン
いくつかのコメントから、ドーム建築の実習より初回授業の講義がみんなの心に残っていることがわかる。フラーの3時間にもおよぶ熱弁は、聴くものの心を揺さぶったようだ。エレインは「バッキーはめまぐるしい勢いで話し、ボビーピン、洗濯ばさみ、5セントストアや10セントストアで買い集めたあらゆる種類のものを部品にして、幾何学的な可動構造をつくり……」とアクティブなフラーを、また、カニンガムは「バッキーのBMCでの講義は……当時すでに、世界を単一の存在として見なしていた彼の考え方についてでもあった」と思索的な内容について、それぞれ回想している※32。ほかにもこの講義についての記述は散見され、名講義だったことが伺える。きっとアルバースもこの講義に心を動かされた一人だったのだろう。
戦後アメリカ美術の発火点
1948年、BMCの夏期講座に参加した学生や教員のリストをここにアップしておきたい。なぜなら、このBMCの夏が戦後アメリカ美術と呼ばれる美術界の新潮流の発火点になったと思われるからである。
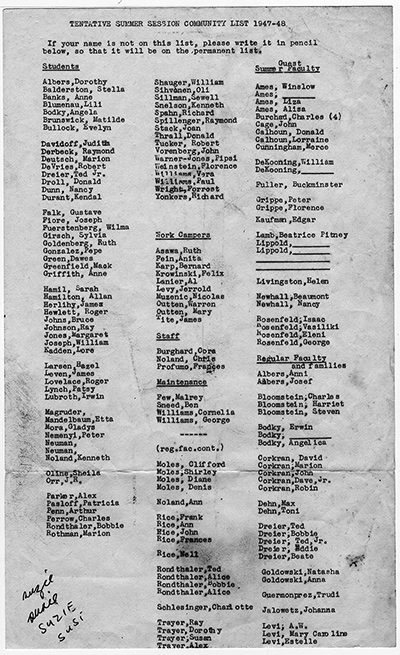
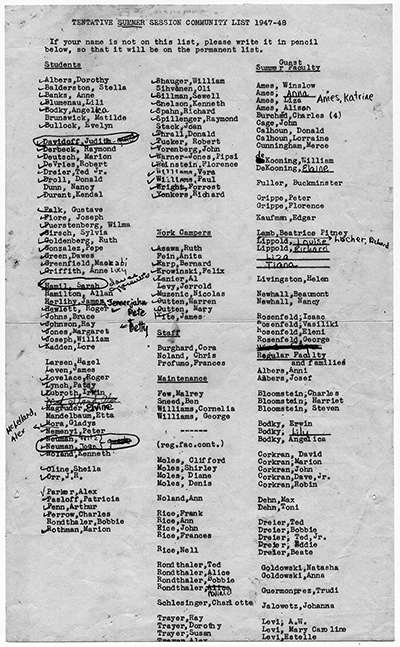 [図9-1,2]1948年夏期芸術講座、学生・教員リスト最初のペーパーと記入後の最終リスト
[図9-1,2]1948年夏期芸術講座、学生・教員リスト最初のペーパーと記入後の最終リスト
たとえばケージからフルクサスに至るハプニングを軸とした音楽とも美術とも演劇とも言い難い“行為の芸術”の潮流は、この夏期講座から端を発していることは間違いない(ケージが最初のハプニングと言われるイベントをBMCで行なうのは52年の夏だったにせよ)。まだラウシェンバーグは登場していないが、ウィレム&エレイン・デ・クーニングやM. C. リチャーズ、また学生では、アーサー・ペンや、文中には登場していないがルース・アサワ※33といった、このあとに美術を超えて活躍する人たちがいた。そして写真の教員として、BMCにおいて多くの写真を残したビューモント・ニューホル※34のことも忘れてはならない。
ここに書いた人以外にも、ぼくが知らない「え、こんな人もいたの?」と思える人物がこのリストのなかにいるかもしれない。もし、そういう人いたら知らせてほしい。アメリカという新しい国が新しい芸術を育んでいく萌芽がここにあったのだ。そして彼らはそれに立ち会った実験者だった。そしてその実験は、美術のみならず、アメリカを中心として現在まで続くコンピュータやインターネット文化にも影響が及んでいる。それが、この1948年のBMC夏期講座が、「奇跡の夏」として語り継がれている所以である。
1948年夏期講座の話はこれで終えておこう。しかし、48年の夏に起こったことはこれだけではない。同年、この夏期講座をディレクションしたアルバースが退任し、49年にはフラー・ディレクションの夏期講座が始まる。次回はこの続きから話を始めたい。
タイポグラフィ、すなわち活字版印刷術は、金属活字(鋳造活字、メタル・タイプ)であれ、写植活字(写真植字用活字、フォト・タイプ)であれ、また電子活字(デジタル・タイプ、フォント)であっても、活字版印刷術創始以来550年以上にわたって「活字」を用いて言語を組み、配置・印刷し、テキストを描写・再現させる技芸であり続けている。
金属活字は鉛・アンチモン・錫などによる合金を文字の「型」に流し込んで作られる。写植活字は被写体である文字のネガ画像に光学技術を用いて印画紙に露光・現像して刷版用の版下となる。電子活字は文字形状に関する電子情報がコンピューター支援によって呼び出され生成される。
いずれにせよ「活字」は、文字の複製原形、つまり規格化された文字の「型(タイプ)」をもとに、繰り返し同じ形象で再生されることを前提とする公的文字のことを指す。
活字と活字組版は規格化されていることによって制御され形成される。組版を形成するにあたって、金属活字は四角柱の金属(ボディ)を組み合わせるので、同一規格がまず大前提となり、基本的にはその分割・倍数計算によって制御できていなければ物理的に版として成り立たない。
写植活字はレンズによる拡大・縮小の比率によって活字サイズが決定され、字送りと行送り(字間・行間)は歯車の噛み合わせ量によって制御されている。
電子活字に至っては、書体デザインから活字サイズ・行送りを含むすべてが0と1の電子情報によって管理・制御されているのだ。
同様に紙面設計も数値によって制御されている。まずは紙の大きさ、といった時点で既に数値の範疇であり、量産することが前提となれば当然規格化が求められる。また組版を紙面のどの位置に配置するのかという版面の設定、これも最終的には数値によって決定される。つまりタイポグラフィとは、活字そのものの生成だけでなく、のちの工程である組版・紙面構成・印刷、さらには製本に適応することを考慮しなければならない、数値と規格で制御された世界なのである。
「文字」の数値化と幾何学的構成
文字そのものを規格化・数値化する試みは、イタリア・ルネサンスに端を発する。その嚆矢はイタリアの古都ヴェローナのフェリス・フェリチアーノ(1433–79頃)だとされている。フェリチアーノは考古学者、古代ローマ大文字(碑文)研究家、また能書家・印刷人でもあった。
フェリチアーノはイタリア北東部の街ラヴェンナなどの古代ローマの碑文を研究し、それらから導いたローマ大文字の構成法を1463年に発表した(図1)。フェリチアーノは、古代ローマ人はコンパスと定規を使った数学的規則でローマ大文字を描いたと信じ、その再現を試みた。フェリチアーノは正方形を8分割、アルファベットの縦画(ステム)の幅を正方形の1/10と設定し、幾何学的にローマ大文字を構成した。
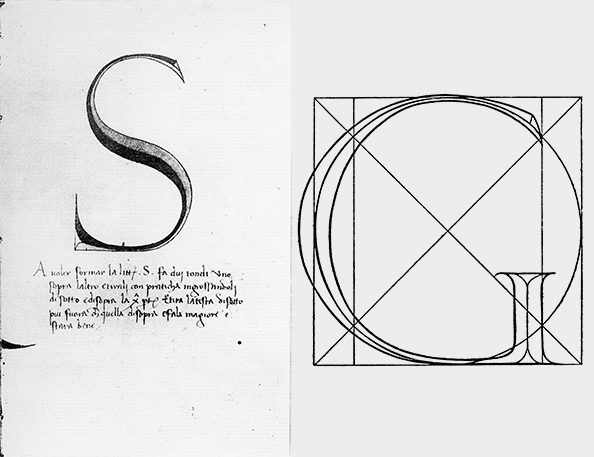 [図1]フェリス・フェリチアーノによる古代ローマの碑文の分析図(1483)
[図1]フェリス・フェリチアーノによる古代ローマの碑文の分析図(1483)
建築家レオン・バティスタ・アルベルティ(1407–72)は、それ以前の1450年代、フェリチアーノと同様の構成法に基づいたローマ大文字を碑文として残したが(図2)、その分析・構成法についての資料が現存するのか否かは不明である。
 [図2]レオン・バティスタ・アルベルティによる碑文より(1450年頃)
[図2]レオン・バティスタ・アルベルティによる碑文より(1450年頃)
フェリチアーノに続いたのは、パロマの能書家ダミアヌス・モイリス(1439–1500)。モイリスは1483年にローマ大文字を分析した『アルファベット論考※1』を著した(図3)。正方形と正円、そしてその対角線を基準値とし、正方形の縦1/13をステムの幅と設定している。そして各文字の下には字画同士の比例関係と幾何学的比例に関する短文を付した。
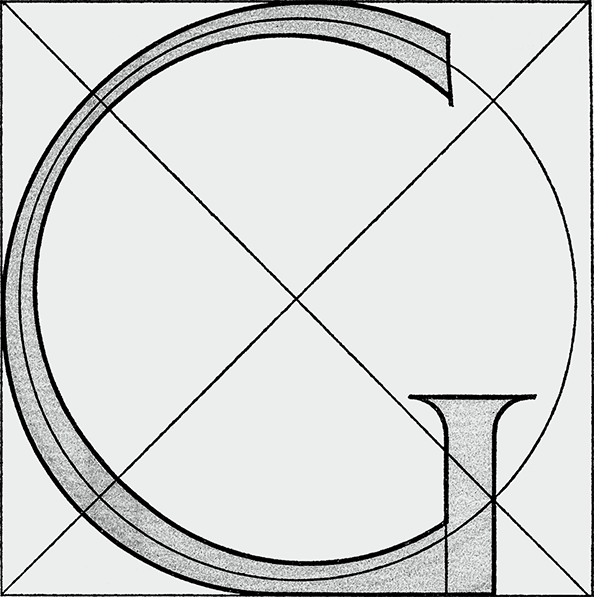 [図3]ダミアヌス・モイリス『アルファベット論考』より(1483)
[図3]ダミアヌス・モイリス『アルファベット論考』より(1483)
1509年に刊行された『神聖比例※2』によってその名を知られるトスカーナ出身の数学者、フラ・ルカ・デ・パチョーリ(1445–1514)のローマ大文字の分析・構成理論が次世代に与えた影響は絶大だとされている(図4)。パチョーリは正方形の縦1/9をステムの幅と設定し、モイリスが施した正方形・正円・対角線をさらに細分化。またセリフを形成する円弧の設定をも示し、ローマ大文字が幾何形態によって構成できることを証明してみせた。そしてパチョーリはその学恩を、同世代で同郷の友人レオナルド・ダ・ヴィンチによるものだと1497年の『神聖比例』の草稿に記したのである。
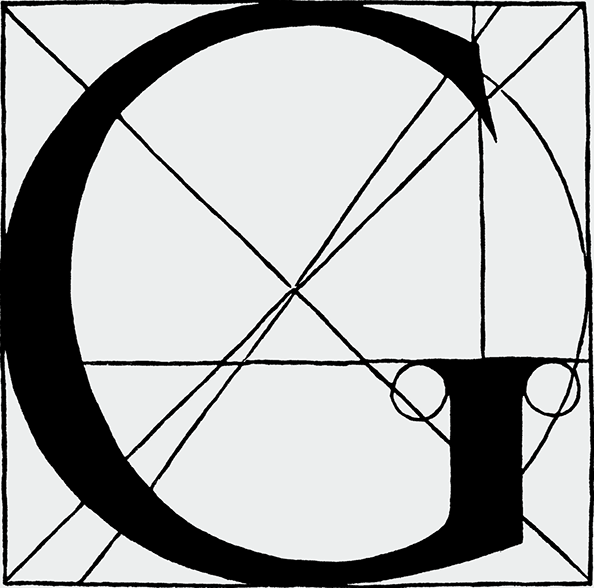 [図4]ルカ・パチョーリの幾何学的構成によるローマ大文字(『神聖比例』 1509)
[図4]ルカ・パチョーリの幾何学的構成によるローマ大文字(『神聖比例』 1509)
アメリカ・シカゴのニューベリー図書館に所蔵されている通称「ニューベリー・アルファベット」と呼ばれるローマ大文字の手稿が近年話題となっている※3。
この手稿は1464–1525年の間に制作され、制作者不明としながらも、一部の研究者がダ・ヴィンチではないかと推察しているものだ。その真意のほどは定かではないが、なるほど、絵画を「まさしく科学」であると書き残した人物が描いたのではないか、と思わせるほどに詳細で、科学分析的に視覚化されたローマ大文字である(図5)。
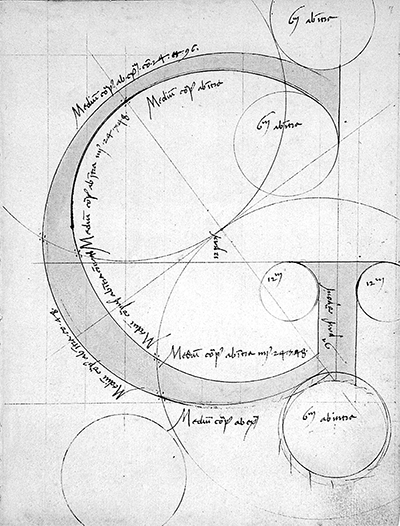 [図5]ニューベリー図書館所蔵のニューベリー・アルファベット(1464–1525)
[図5]ニューベリー図書館所蔵のニューベリー・アルファベット(1464–1525)
1525年には、ドイツ・ニュルンベルクの画家・版画家・美術理論家として北方ルネサンスの最も著名な芸術家アルブレヒト・デューラー(1471–1528)もあとに続いた。デューラーは著作『幾何学※4』で、パチョーリの理論を敷衍したローマ大文字とブラックレターを描いたのだ(図6)。
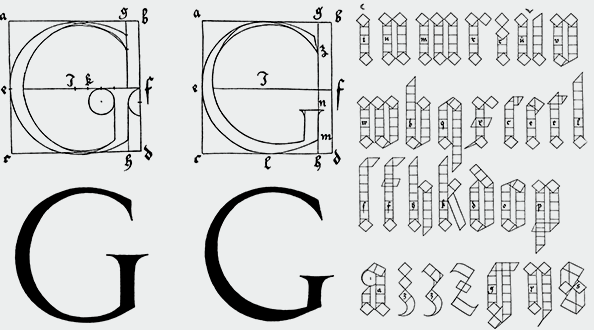 [図6]アルブレヒト・デューラーのローマ大文字とブラックレター(『幾何学』1525)
[図6]アルブレヒト・デューラーのローマ大文字とブラックレター(『幾何学』1525)
そして学者や芸術家たちがローマ大文字の分析を進める一方で、書字の本家である書家たちも書法の教科書で一斉にローマ大文字を発表し始めるのである※5。
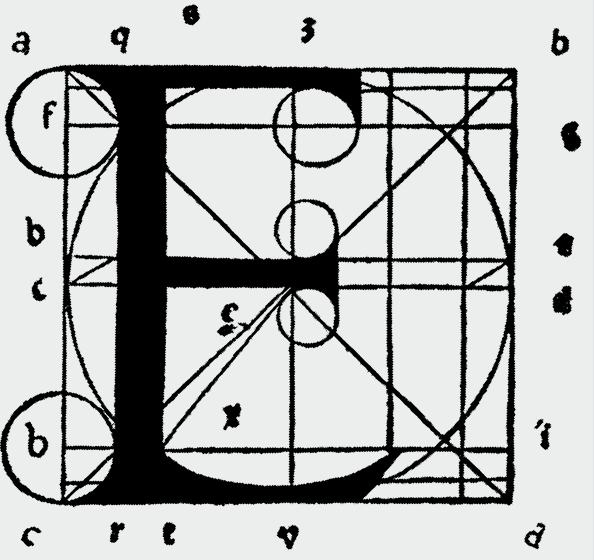 [図7]シジスモンド・デ・ファンティ(1514)
[図7]シジスモンド・デ・ファンティ(1514)
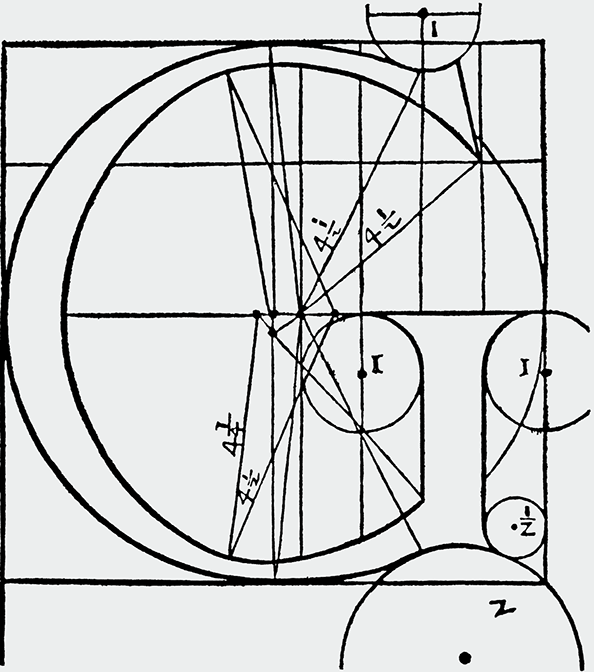 [図8]フランチェスコ・トルニエロ(1517)
[図8]フランチェスコ・トルニエロ(1517)
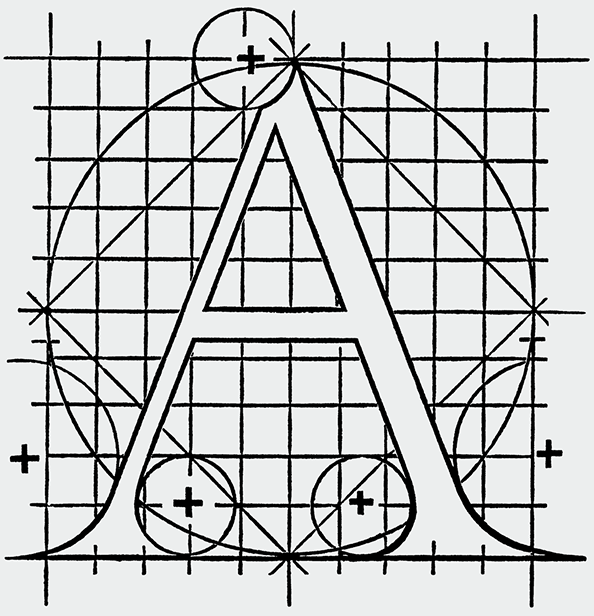 [図9]ジェフロア・トリー(1529)
[図9]ジェフロア・トリー(1529)
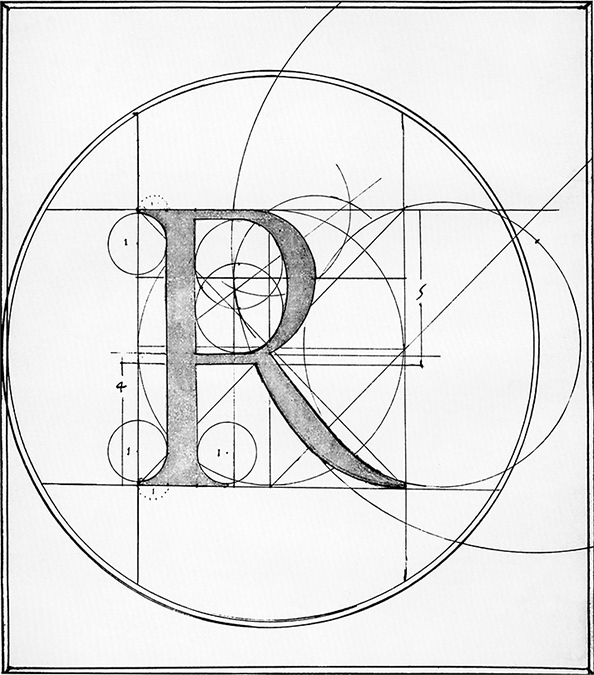 [図10]ジャンバティスタ・パラティノ(1550)
[図10]ジャンバティスタ・パラティノ(1550)
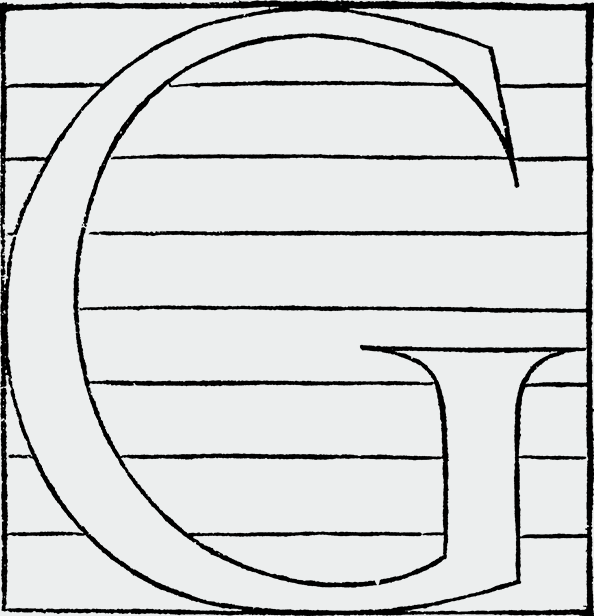 [図11]ヴェスパシアーノ・アンフィアレオのローマ大文字(1554)
[図11]ヴェスパシアーノ・アンフィアレオのローマ大文字(1554)
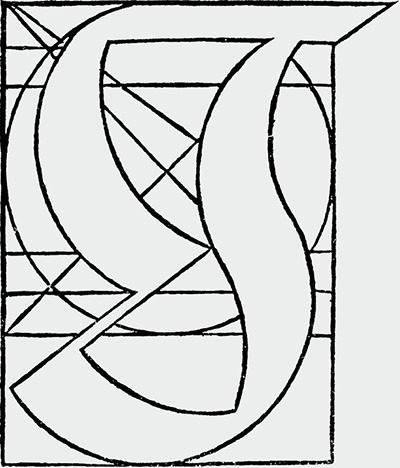 [図12]ヴェスパシアーノ・アンフィアレオのブラックレター(1554)
[図12]ヴェスパシアーノ・アンフィアレオのブラックレター(1554)
このように碑文研究家だけでなく書家や建築家、芸術家も、皆一様にローマ大文字を方形の中に納め、分割し、定規とコンパスで構成し、規格化を行ない、再現・再構築を試みていた。
*
ではここで、なぜ彼らがローマ大文字そのものにこだわったのか、という根本的な問題について、若干ではあるが触れておきたい。E・P・ゴールドシュミットの著作『ルネサンスの活字本※6』には、以下のように簡潔に記されている。
彼らがローマの碑文に関心を示した第一の理由は、古典ラテン語の正確な綴りをぜひとも知りたかったからだろう。彼らは古典的著作が中世写本に筆写される際、乱暴で粗野な綴り字が使われ、原文が勝手に改竄される傾向があるのを知っていた。だから彼らは直接ローマの碑文・記念碑を見て、古代ローマ人が遵守していた通りの正確な正書法を学ぼうとしたのだ。……たしかに、ルネサンスの人文主義者たちは正書法を学ぼうとしてローマの碑文に興味を持った。しかし、彼らは現代人と同じように、古物研究・歴史研究等の見地からも碑文に関心を寄せ、古代ローマの石碑等に刻まれた銘文を解読する「碑銘(エピグラフィ)研究」にも真剣に取り組むようになった。こうして、ルネサンスの人文主義者は古代の石碑、墓石などに刻まれた銘文、碑銘を各地で探索しながら、精確かつ綿密に模写し、そのように蒐集された碑文は写本の形で集成され、見事な書体となって精確に復元されたのだ。
E・P・ゴールドシュミット『ルネサンスの活字本』
*
数値化し幾何形態に還元することは、なにもローマ大文字だけに限ったことではなかった。視覚的に表わすことのできるありとあらゆる図像表現、とりわけ古代ギリシャ・ローマの造形物は、彼ら人文主義者にとって格好の研究対象であり科学的・数学的・幾何的に分析された。
「美しいものはすべて古典的であり、古曲的なものはすべて美しい」、また、古代ローマ人はそうして「絶対的な美」「真の比例」の基準を設けたのだと彼らは考えていたからだ。
こうした思想を持ったのは人文主義者(ヒューマニスト)であった。彼ら人文主義者の科学分析的思考への執着は、中世以来の不透明な神の力ではなく、黄金分割に代表される古代ローマ期に培われた普遍的な入間の叡智を科学的に理論化しようとする思想を象徴するものだといえる。もっとも、これには確固たる根拠もあった。ユークリッドなどの著作が再発見され、幾何学の分野が著しく進歩していたからだ。また13世紀以降「0」を用いて少数を表現できるアラビア数字がローマ数字にとって変わっていたことも見逃せない。
「数によって道が求められなければならない。また、数によってすべてを理解することができる」と記したのは、人文主義者ピコ・デラ・ミランドラ※7である。
人文主義者にとって、数値換算とは学問であり、思想・知識・美の普遍化とその共有化を意味するルネサンス思想の一側面でもあったのだといえる。
だが、こうしたルネサンス思想を背景としながらも、金属活字の基となる「型」を作る活字父型彫刻師(パンチカッター)は、幾何学的に構成されたローマ大文字の形象をそのまま無批判に受け入れたわけではなかった。
パンチカッターはヒューマニスト・ミナスキュール(人文主義者の小文字筆記書体)を基に活字化した小文字書体、それに組み合わせるための大文字に古代ローマ大文字を採用した※8。
しかしパンチカッターは活字書体を形成する骨格・バランス・字幅・濃度、さらには小文字と組み合わせるための整合性等々、適正な活字組版を生成するために必要な要素を考慮し、技芸者特有の眼と手、そして製造工程などの技術的経験則にしたがってローマ大文字の活字父型を彫刻した。つまり活字化することが目的ではなかったにせよ、数値化されたローマ大文字の構成法は活字製造の現場では机上の空論だったわけである。
*
やがて人文主義者がローマ大文字に施した数値化と幾何学的分析に異を唱える人物が現れる。
それがヴァチカン教皇庁図書館の書記官ジョヴァンニ・フランチェスコ・クレッシ(1534頃–1614頃)である。クレッシは、すべてのラテン・アルファベットの起源とみなされているローマのトラヤヌス帝の記念柱(紀元113年建立)の基壇にある碑文、通称「トラヤヌス帝の碑文(図13)」を、人文主義者の幾何学的規範によらない書法で提示した(図14)。
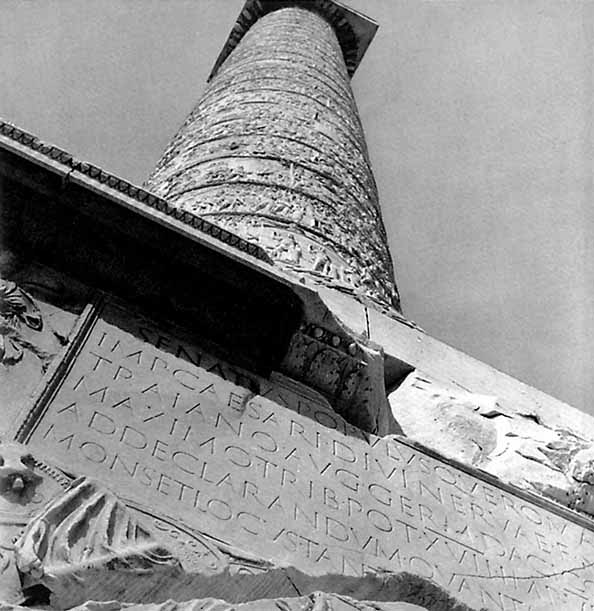 [図13]トラヤヌス帝の記念柱の基墳にある通称「トラヤヌス帝の碑文」(113)
[図13]トラヤヌス帝の記念柱の基墳にある通称「トラヤヌス帝の碑文」(113)
 [図14]ジョヴァンニ・フランチェスコ・クレッシによるローマ大文字 (1560)
[図14]ジョヴァンニ・フランチェスコ・クレッシによるローマ大文字 (1560)
クレッシは1560年に発行され、のち幾度も版を重ねた著作『多くの文字をそなえた手本※9』で「ローマ大文字を円と四角形で構成する必要はない」と印し、たとえ道具を用いたとしても最終的には人間の眼と手を用いて描くべきだとしたのだ。つまり身体性の復権である。だが、この考え方は人文主義の理念からの逸脱であり、結果「異端」として捉えられている。
クレッシの後を継いでヴァチカン教皇庁図書館の書記官を勤めたのがルカ・オルフェイ(生没年不詳)である。
オルフェイはシクストゥス5世(教皇在位1585–90)が推進した「ローマの都市改造計画」において、碑文用書体を監督する任務に就いた。
オルフェイが1589年に作った碑文の設計図は、手稿と銅版印刷による2種類が残されている。その2種類共にクレッシ系のトラヤヌス・ローマンを誇張した形状をしている。
コンパスを用いて描かれた手稿のローマ大文字(図15)は、9分割されたユニットを基準とし、肉厚の形状をしている。そしてもう1種はエングレーヴィング技法による精緻な銅版印刷によるもので、10分割されたユニットにコンパスの基点と円弧によってローマ大文字が構成されている(図16)。
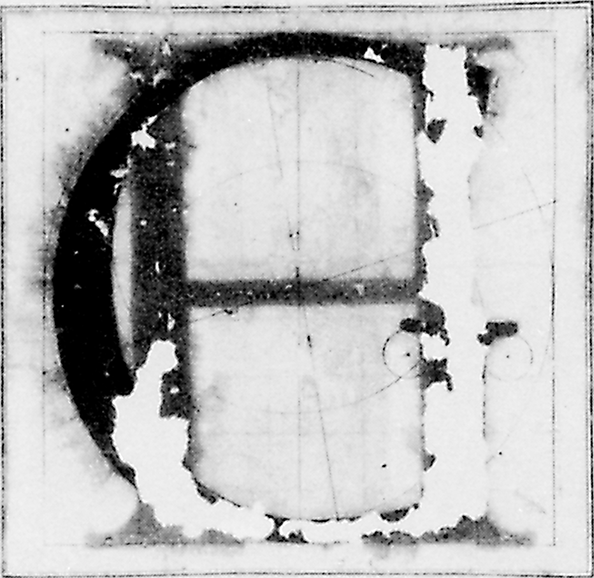 [図15]ルカ・オルフェイの手稿(1589)
[図15]ルカ・オルフェイの手稿(1589)
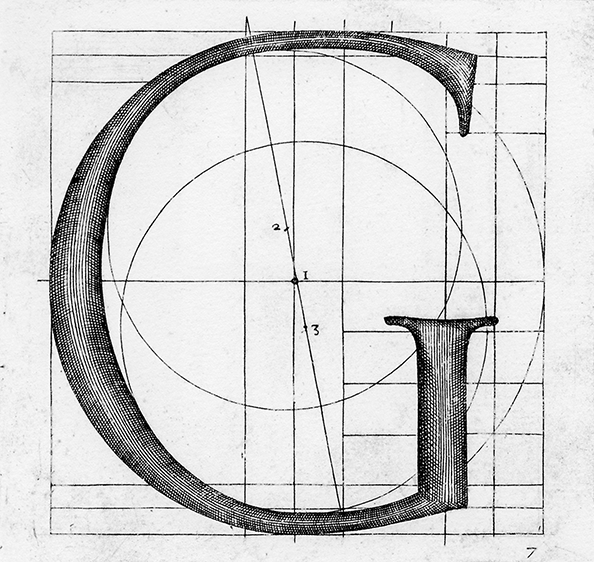 [図16]ルカ・オルフェイの銅板印刷のローマ大文字(1589)
[図16]ルカ・オルフェイの銅板印刷のローマ大文字(1589)
シクストゥス5世に捧げられたこの2種類のローマ大文字は「シクスティーネ」と呼ばれ、ローマの街や建築物に刻まれた。つまりシクスティーネはローマの都市改造計画用の制定書体だといえる。
制定書体である以上、同一形状を求められる。クレッシの薫陶を受けながらも幾何形態を活用した背景には、「規格化」という必然があったのだ。
「活字」の数値化と幾何構成による規格化
1517年、マルティン・ルターによる九十五ヶ条堤題に端を発する宗教改革の嵐は、またたく間に16世紀のヨーロッパに広がった。やがてプロテスタントを押さえ込もうとするカトリック勢力の巻き返し現象が起こる。
フランスではプロテスタント勢力を排撃すべく、さまざまな手段が講じられた。その1つはルイ13世の治下、枢機卿リシュリュー※10が1640年にルーヴル宮殿内に王立印刷局を創設したことである。その目的は、国家の栄光を讃え、カトリック教を広め文芸を発展させることにあった。
ルイ13世の後を継いだ14世は、1693年、科学アカデミー※11に、新しい活字を製作するように要請した。科学アカデミーは委員会を組織し、研究を重ね、定規とコンパスで円を分割し、細密な幾何学構成の大文字と小文字のローマン体とイタリック体の原図を作成した。設計者は数学者ニコラ・ジョージョンら3名、銅版彫刻はルイ・シモノーである。
原図は大文字縦8×横6—8ユニットの方形、小文字縦15×横7—12ユニットに分割され、その1ユニットはさらに6分割されて48×48=2304の方眼によって書体デザインが生成されていた(図17)。この精度はもはや電子レヴェルに近い。
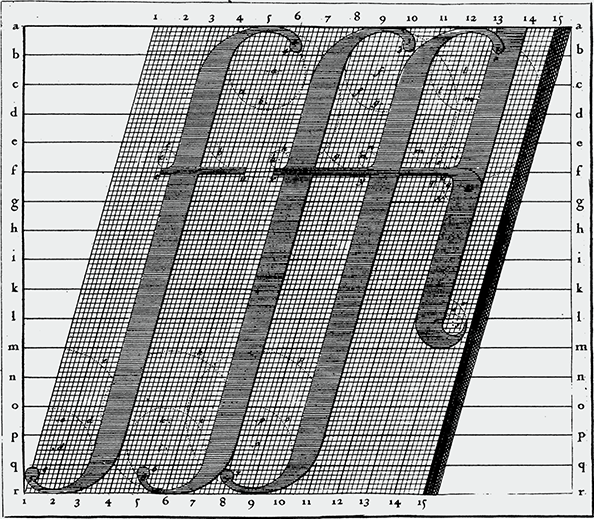
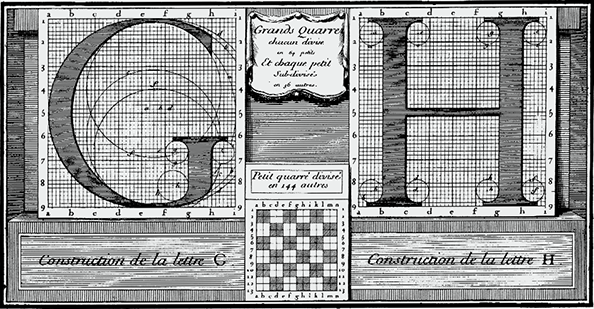 [図17]フランス科学アカデミーの数学者ニコラ・ジョージョンらによるローマン・ド・ロワの設計図。銅版彫刻はルイ・シモノー(1693)
[図17]フランス科学アカデミーの数学者ニコラ・ジョージョンらによるローマン・ド・ロワの設計図。銅版彫刻はルイ・シモノー(1693)
設計されたその書体を科学アカデミーは「ローマン・ド・ロワ(王のローマン体)」と名付けて、王立印刷局のパンチカッター、フィリップ・グランジャン(1666–1714)に活字化するよう指示した。
だが、グランジャンはこの原図に正確に基づいて父型彫刻を行ったわけではなかった。グランジャンは数学者ジョージョンの学理と精神を咀嚼しながらも、イタリア・ルネサンスのパンチカッターと同様に、技芸者として眼と手を用いて活字父型を作った(図18)。
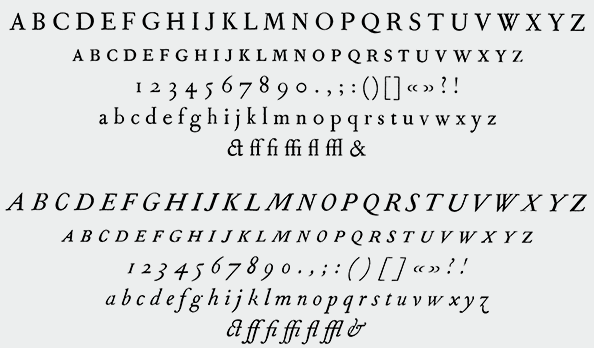 [図18]活字化されたフィリップ・グランジャンによるローマン・ド・ロワ(1702)
[図18]活字化されたフィリップ・グランジャンによるローマン・ド・ロワ(1702)
活字生成における数値(理想)と技芸(現実)の相剋は、以後、後世のコンピュータ時代にまで連綿と続くことになる。
活字鋳造と組版における計測単位の基準・体系化
活字製造における活字サイズ(ボディサイズ※12)、そしてその活字を組版として形成するための計測単位を初めて規格体系として標準化したのは、フランス・ロココ期にパリで活字製造者として活動をしたピエール・シモン・フールニエ(1712–68)である。
とはいうものの、フールニエ登場以前の活字製造者が活字鋳造と活字組版において規格化をしなかったわけではなかった。規格化できていなければ物理的に活字組版が成立しないからだ。だが、その規格は活字鋳造所ごとに異なるものであった。活字製造と組版・印刷、さらには製本・出版すべてを自家で賄っていた家内制手工業の時代にあって、標準化はさほど問題ではなかった。また、活字の大きさと書体の種類(ローマン体とイタリック体程度であった)も少なかったこともその要因の1つにあげられる。
ところが時代が下り、活字鋳造と印刷の分業化が進み、活字を流通させることが求められるようになると「互換性」と「共有化」という問題が浮上するようになる。なぜなら、組版・印刷所が異なる活字鋳造所の活字を混用して組もうとする場合、物理的に「ボディサイズ」の大きさが統一されていなければ活字は組めないからだ。したがって、当時の組版・印刷業者にとって、ボディサイズの不揃いを解消することは切実な課題だったのである。
フールニエはボディサイズ間の比例関係を列挙した『比例対照表』を1737年に作成。それは異なるサイズ同士に比例関係を設定し、異サイズの活字が混用された際の不整合を解消するものであった。
彼はフランスのインチである「プース」を12分割し1プース=12リーニュと定め、さらに1リーニュが6ポイントに相当するように設定し体系化した。これが現在にまで繋がるポイント・システムの原形である。
フールニエはこのシステムを、1742年発行の『印刷活字見本』(図19)にあらためて掲載、1764年には『比例対照表』をさらに発展させたポイント・システムを『タイポグラフィの手引き』(図20)で発表した。そしてこのシステムは、次世代の活字製造者フランシス・アンブロワーズ・ディド(1730–1804)へと受け継がれていく。
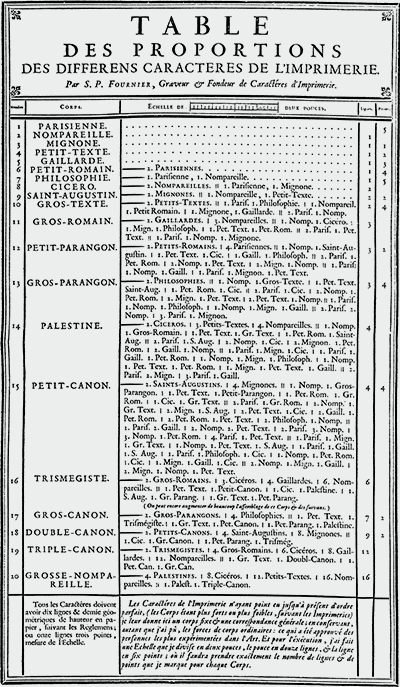 [図19]ピエール・シモン・フールニエによる『比例対照表』は『印刷活字見本※13』に掲載された(1742)
[図19]ピエール・シモン・フールニエによる『比例対照表』は『印刷活字見本※13』に掲載された(1742)
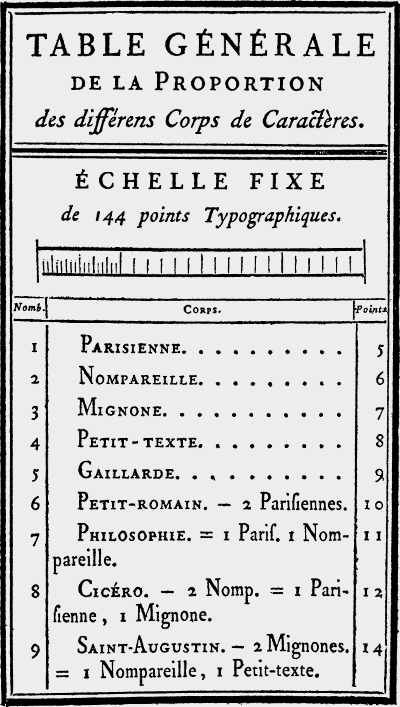 [図20]1764年にフールニエは『比例対照表』をさらに発展させたポイント・システムを『タイポグラフィの手引き』で発表した
[図20]1764年にフールニエは『比例対照表』をさらに発展させたポイント・システムを『タイポグラフィの手引き』で発表した
後世「ディド・ポイント」と呼ばれたこのシステムは、フランスの標準的なインチとの関係が今一つ不正確で、精度が悪かったフールニエのシステムを再整備したものである。
ディド・ポイントは、フランス、スイス、ドイツを始めとする大陸ヨーロッパの活字版印刷の標準値として普及し、コンピュータが一般化する近年まで採用され続けた。ちなみに、メートル法に換算すると1ポイント=0.3759ミリである。
フールニエのシステムを源流とし、19世紀末にアメリカで整備されたポイント・システムが「アングロ・アメリカン・ポイント」である。
アングロ・アメリカン・ポイントでは1インチを72分割したサイズ、1ポイント=0.3514ミリに設定されている。イギリスではこの設定値を1905年に採用、日本では1908年以降より新聞社を中心に採用され、金属活字による活字版印刷の現場で標準値として使用され続ける。
そしてコンピュータ制御による「DTPポイント」と呼ばれる現在のポイント・システムは、1インチを正確に分割したサイズ、1ポイント=0.3528ミリと設定され、これがコンピュータにおける計測単位の世界標準となったのである。
活字製造の数値による規格化と標準化は、単に合理化といった利便性だけでなく、量産規格品→流通→産業という意味においての「近代」を結果的に導くことになる。歴史的経緯から見ても、このフールニエの業績は来るべき産業革命を準備したといっても過言ではない。「型」による量産規格品「タイプ(活字)」の存在は、言語伝達以上の意味を持つのである。
さらに加えれば、「活字」が規格・標準化・量産化されて流通(普及)することによって「書記言語」の固定化も同時に推進される。「書記言語」の固定化とは綴字法、句読法、文法といった言語表記法の確立を指す。活字版印刷術の伝播の経路と、イタリア語、フランス語、英語などの言語表記法確立の年代順は、その軌を一とするのだ。
*
翻ってわが国における活字版印刷術はといえば、幕末から明治初期にかけて移植されたもの、といって差し支えないだろう。わが国の活字版印刷の祖、本木昌造(1824–75)は、残念ながら活字版印刷術の創始者ヨハン・グーテンベルクに相当する人物ではない。長崎のオランダ通詞であった彼は、出島で見たであろう活字版印刷術の移植と、その普及と発展に多大なる貢献をした人物なのである。
わが国における活字版印刷術は、活字版印刷用の機材と周辺機器、技術、書体デザイン(この場合仮名書体は含まれないのだが)を含む「物」と「事」のほとんどが移植によるものだ。
そしてその多くは、当時アメリカの統治下にあった中国・上海、もしくはアメリカ本土からもたらされたものだといってよいだろう。機材と周辺機器が導入されることは、同時に「サイズ」も導入されることを意味する。
アメリカにおける活字サイズの規格統一が合衆国活字業協会によってなされたのは1886年のこと。したがって本木昌造は、それ以前のサイズ体系を日本に導入したことになる。
規格統一以前、アメリカの活字鋳造所の多くが活用していたサイズ体系は、当時最大大手であったマッケラー・スミスズ・ジョルダン活字鋳造所が採用していたシステム、「ジョンソン・パイカ」に拠るものが大半だったとされている※14。
このジョンソン・パイカは、かのベンジャミン・フランクリン(1706–90)※15が、駐仏全権公使時代にフールニエの活字鋳造所から印刷用資材一式を購入したという歴史的関連を持つサイズ体系であった。つまりフールニエに端を発するポイント・システムの日本上陸である。
本木昌造らはこうした活字サイズの倍数体系※16を、「号」(図21)という名称に置換し活用しはじめた。
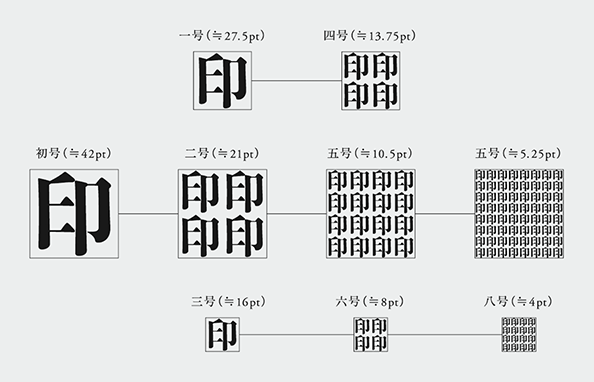 [図21]号数制活字の体系
[図21]号数制活字の体系
のちわが国では規格統一された「アングロ・アメリカン・ポイント」を明治末期(1908)以降に採用しはじめるが、従来の「号」体系のものと「アングロ・アメリカン・ポイント」双方が、金属活字による印刷の現場で併用され続けることになる。そしてこの1ポイント=0.3514ミリのアングロ・アメリカン・ポイントがJIS規格として制定されたのは1962年のことであった。
金属活字の次世代の組版機である邦文用写真植字機は、1924年に森沢信夫と石井茂吉の両氏によって特許出願され、5年後の1929年に初期実用機が完成した。写真植字では、当初アングロ・アメリカン・ポイントを採用していたが、のちにメートル法にしたがった「級」(図22)という単位に改められる。
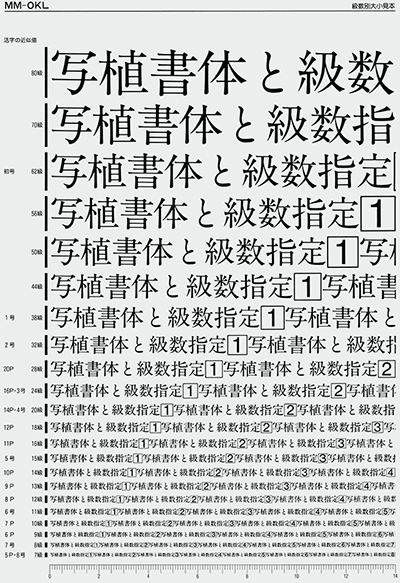 [図22]写真植字のサイズ体系にはメートルによる「級」が用いられているが、その体系は号数とポイントの倍数体系に倣っている
[図22]写真植字のサイズ体系にはメートルによる「級」が用いられているが、その体系は号数とポイントの倍数体系に倣っている
「級」とは1ミリを4分割した0.25ミリを1級とする単位であり、今日の日本語用組版のDTPソフトウェアでもポイント・システムと併用されているものである。
4分割すなわちQuarter、略して「Q」、漢字に置換して「級」、これが写真植字の設定基準値となっている。写真植字では、この0.25ミリを基本単位として活字サイズと字送り、行送りを設定し組版が形成されるのである。
活字鋳造・制作におけるユニット・システム
産業革命以降、あらゆる生産活動は大規模工場での大量生産時代に突入していく。なかでも活字製造と印刷産業はその先陣を切って、機械の大型化と自動化を推進させた。
活字版印刷術創始以来、活字製造の工程は鋳型に鉛合金を流し込み、1本ずつ活字を鋳造し人間の手で組み上げていくという、多大な労力と時間を要するものであった。
しかし1838年にアメリカのデヴィット・ブルース・ジュニア(1802–92)が発明した手回し式の活字鋳造機「ブルース活字鋳造機」の登場によって、手動式ながらも鋳造の速度は格段に向上し生産性を高めていた。
1885年、アメリカのドイツ人オットマー・マーゲンターラー(1854–99)が、1行単位で活字を鋳造する機械、ライノタイプ自動活字鋳造植字機(図23)を発明し、1887年には同国のタルバート・ランストン(1844–1913)が、1文字単位で活字を鋳造し植字までできるモノタイプ自動活字鋳造植字機(図24)を考案、1989年には試作機を完成させた。
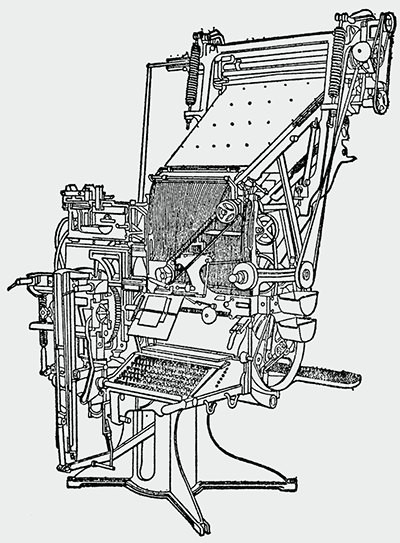 [図23]ライノタイプ自動活字鋳造植字機
[図23]ライノタイプ自動活字鋳造植字機
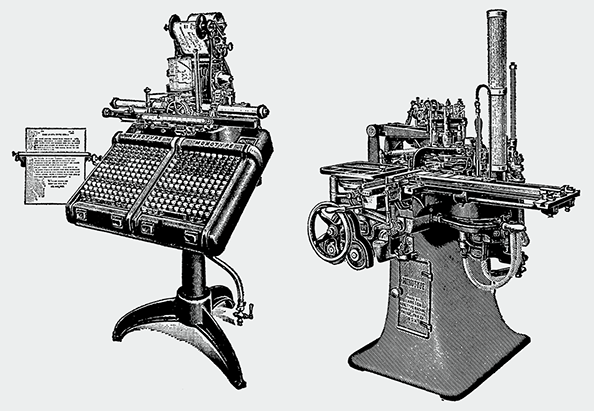 [図24]文字入力用のモノタイプ・キーボード(左)とモノタイプ自動活字鋳造植字機(右)
[図24]文字入力用のモノタイプ・キーボード(左)とモノタイプ自動活字鋳造植字機(右)
これらの自動活字鋳造植字機では、字幅が1文字ずつ異なるラテン・アルファベットのキャラクタを、素早く自動的に鋳造することが目的であった。そのため合理的で効率的に製造できるシステムが考案された。
モノタイプのシステムでは、全角(em、1 : 1の正方形)を18分割し(ライノタイプは19分割である)、個々に字幅が異なるキャラクタの文字幅(セット・ウィドゥス)を18分割したユニットのいずれかの数値にあてはめ、数値管理によって活字を鋳造できるようにしたのである(図25)。
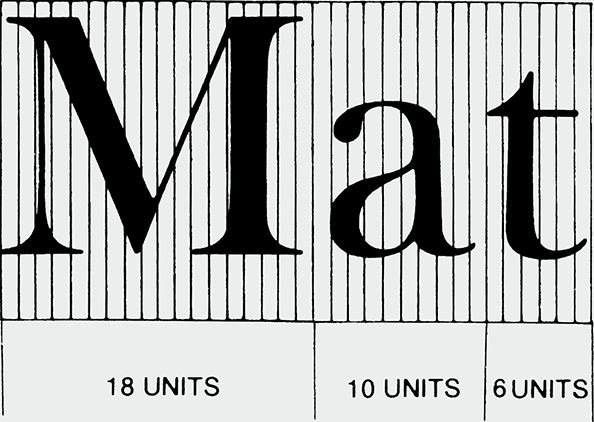
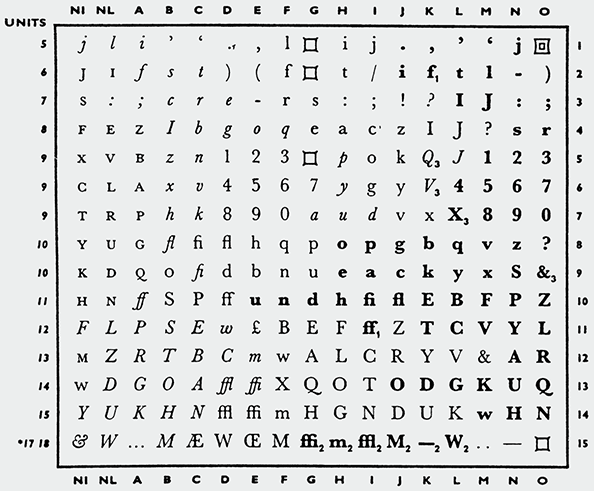 [図25]モノタイプのユニット・システムは18ユニット。ユニット数は書体によって異なる。上はスコッチ・ローマン、下はバスカヴィル
[図25]モノタイプのユニット・システムは18ユニット。ユニット数は書体によって異なる。上はスコッチ・ローマン、下はバスカヴィル
例えば小文字のi、j、lは5/18ユニット、a、c、eは8/18ユニット、大文字のM、Wは18/18ユニットの矩形に納めるというようにだ。つまり個々のキャラクタ・デザインは、機械の都合と制約によって成立しているという側面を併せ持つ。またこのユニット・システムは、レター・スペース(字間)の調整にも応用された。
ユニット・システムは、全角を分割する単位が細かければ細かいほど必然的に精度は高まり、書体デザインは自然な形象に近付く。そのため時代が下がりユニットが細分化されるにしたがって書体デザインの精度は向上することになる。
先に人文主義者たちのローマ大文字の分割について記述したが、ユニット・システムの主たる目的は、機械による活字鋳造と植字工程の合理化であり、ローマ大文字を幾何学的に構成するためのガイドラインであったルネサンス期の分割法とは根本的に異なるものなのだ。
邦文写真植字にもこのユニット・システムは応用された。
写真植字には金属活字のように物理的な大きさ(ボディサイズ)がない。写真植字はガラス文字盤に定着されたネガ状の文字書体が、レンズによる拡大・縮小率によってサイズ決定されて光学処理で印画紙に焼きつけられる。したがって書体デザインをする際にも活字サイズを指定するためにも仮想の枠「仮想ボディ」を必要とする。
写真植字における和文書体の仮想ボディは、金属活字の四角柱と同様に正方形(全角1 : 1)である。そしてこの全角を縦横16分割(のち32分割)した「ユニット」の単位によって、邦文写真植字における欧文書体の文字幅が設定された(図26)。
また欧文、和文も共に0.25ミリ単位の制御だけでなく、級数個々に対応した16あるいは32分割ユニットの単位によって字間の調整をすることもできるようになったのである。
このユニット・システムは、次世代のシステムになって限りなく細分化されることになる。
1984年、アップル・コンピュータ社によってマッキントッシュ・パーソナル・コンピュータが登場し、情報伝達の構造を革新させた。文字組版でいえば、それまで印刷・組版業者専有だったものが、デザイナー、編集者だけでなく一般的にも解放された。
機械鋳造による金属活字においても写真植字の時代においても、活字制作と組版における調整可能な全角のユニット数は2桁以上になることはなかった。そのため、制作者は理想的な文字形象と機械との整合性の接点を求めることに必要以上に傾注しなければならなかった。
したがって、機械の制約に縛られない時代の手組用の活字書体のデザインが、ある意味で理想的であるという論拠が成立することにもなる。
しかし —— 現時点でのパーソナル・コンピュータにおける印刷用書体(デジタル・タイプ)は、任意のサイズに対して縦横1000分割(1000メッシュ)が基準値(図27)として設定され、フォント・フォーマットに電子信号として収納されている。また組版ソフトウェア上で1/1000単位でのレター・スペース調整も可能となった。さらにいえば、デジタル・タイプの制作現場では、それをはるかに超える数値(15000メッシュなど)での書体開発がなされており、それを1000メッシュに間引いてフォント・フォーマットとして生成しているのだ。
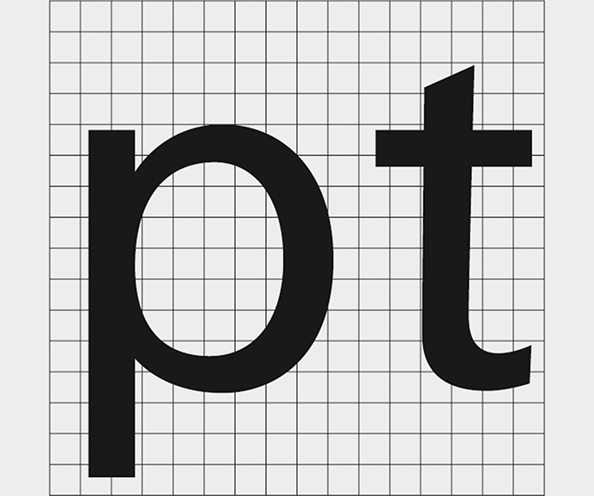 [図26]写真植字における16分割のユニット・システム
[図26]写真植字における16分割のユニット・システム
 [図27]デジタル・タイプにおける1000メッシュのユニット・システム
[図27]デジタル・タイプにおける1000メッシュのユニット・システム
かつて先人たちが求めてきた数値化、定量・定数化、規格化はむろんのこと、その精度は、もはや人間の眼と手の領域をもはるかに超え、紙にインキを転写するという物理的な再現の範囲(たとえば画面上・数値上では表現できているが印刷では細密すぎて表現できない極細の罫線など)をも軽々と超えてしまったかのようだ。ルネサンス以降、あまたのタイポグラファが営々と求め続けてきた理想的な書体デザインとタイポグラフィを実現するための制約は一切合切取り払われた、といった案配だ。
実際、パーソナル・コンピュータの登場以降、デジタル・タイプは加速度的に増え続けた。かつて金属活字も写植活字も実現不可能だった、筆脈の接続を要する繊細なスクリプト書体や手書きのニュアンスを有したカリグラフィ系書体、古典書体の覆刻、それにトラヤヌスの碑文に代表されるローマ大文字の碑文系書体、筆やペンなど筆記具のニュアンスが色濃く残った筆書系書体など、およそ現時点で考えられる文字形象のほとんどが、1000メッシュのフォント・フォーマットに落とし込まれコンピュータに実装できるようになった。
これをしてルネサンス以降、550年以上にわたって展開されてきたタイポグラフィの数値(理想)と技芸(現実)の相剋の終焉と捉えてよいのだろうか?
*
1990年、コンピュータ・プログラミングによってキャラクタ個々の形象がマッキントッシュ®︎の画面に現れる度に変化する書体「ベーオウルフ※17」(図28)が登場した。
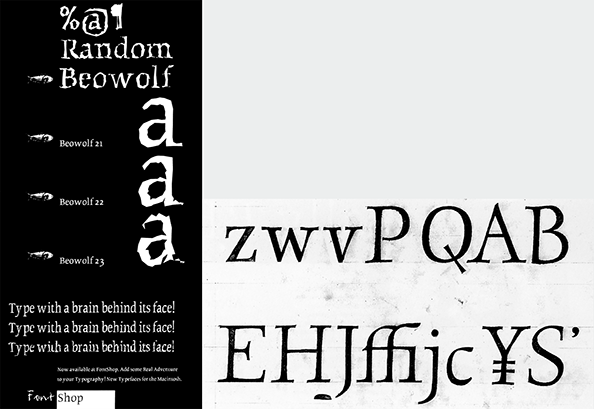 [図28]エリック・ファン・ブロックランドとジャスト・ファン・ロッサムの設計による「ベーオウルフ」(左)。ベーオウルフの骨格はごくオーソドックスなローマン体(右)を基にしている(1990)
[図28]エリック・ファン・ブロックランドとジャスト・ファン・ロッサムの設計による「ベーオウルフ」(左)。ベーオウルフの骨格はごくオーソドックスなローマン体(右)を基にしている(1990)
デザインはオランダの若いタイプ・デザイナー、エリック・ファン・ブロックランドとジャスト・ファン・ロッサム。彼らは、かつて先人達が追い求めた、人間の理性によって制御可能な領域にある書体デザインにはもはや興味なし、ともいわんばりに「べーオウルフ」を発表したのだ。
ベーオウルフは、その形象の奇抜さゆえ、単なるキッチュな書体として捉えられ、結果として時代の流行書体として消費される運命を辿った。だが、その奇抜なデザインの背後には、タイポグラフィの根幹を揺るがす問題が存在していた。
その1つは、規格化された文字の「型(タイプ)」をもとに、繰り返し「同じ形象で再生される」公的文字、という「活字の定義」を、ベーオウルフは「可変造形する活字」であるがゆえに逸脱しているという点。
さらにもう1点。文字活字が印刷によって現れる時につきまとうインキの滲みや掠れといった予測・制御不能の事象(ノイズ)は、既にコンピュータによって克服されたものとし、予測・制御不能の事象、あるいは文字を成立させていた人間が書くという身体性を含む不規則なリズムを、逆にプログラミングによって再制御・再現出させる、という点である。この2点においてベーオウルフの登場は正に衝撃的であったのである。
禁断の木の実といえなくもない未知なる領域に踏み込んだべーオウルフが登場して早18年たつ。しかし現在に至るもべーオウルフについて言及した論文がこの分野から出る気配はない。
紙面設計における規格化と数値化(1)
ブック・フォーマット
これまで文字・活字設計と組版における数値・定数化、規格化の概略を追ってきたが、ここからは活字書体が組まれ紙面に定着される際の数値・定数化、規格化を概観してみたい。
活字版印刷術が発明されるはるか以前の書写本の時代より、紙面に文字が記される体裁(ブック・フォーマット)は、段組(コラム)と呼ばれる様式によって形成されてきた。それは文字がテキストとして並べられた「書物」ほぼすべてに共通するものであり、たとえテキストの支持体が紙でも皮革でもなく、石などの鉱物であったとしてもコラムは存在してきた。
活字版印刷術の創始者グーテンベルクは、活字書体のデザインだけでなく、2段組というブック・フォーマットも当時の書写本に倣っている(図29)。活字版印刷術は基本的に既存の書写本を、機械を使って合理的・効率的に複製することから始まったのである。
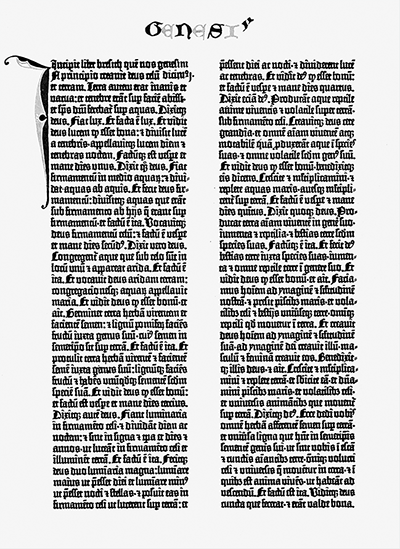 [図29]ヨハン・グーテンベルクの『42行聖書』の本文組版(1450–55)
[図29]ヨハン・グーテンベルクの『42行聖書』の本文組版(1450–55)
19世紀末、かつて誰も顧みなかったブック・フォーマットの重要性を説く人物が現れる。
それがイギリスでアーツ・アンド・クラフツ運動を提唱し、社会主義者として活動したウィリアム・モリス(1834–96)である。モリスがデザインに与えた影響は、あらゆる分野において語り尽くされてきた。
それはタイポグラフィの分野においても同様で、実際に彼の個人印刷所であるケルムスコット・プレスの活字書体、組版、印刷・製本など、モリスのタイポグラフィにおける事蹟についての研究書は、洋の東西を問わず数多く存在している。
モリスは紙面における組版の位置をどのようにすべきか、抽象的ではあるものの初めて提示した。
「文字組版の版面は、ノド(糸でかがられた中央部)の余白はもっとも狭く、天(上部)はそれよりもやや広く、小口(書物の左右の外側)はさらに広く、地(下部)はもっとも広くしなければならぬ。中世の書物では、写本であれ印刷本であれ、この規則からの逸脱はまったく見られない。……これらの間隔と位置の問題は美しい書物を制作するのに一番大事なことである」と記し、テキストが見開き単位で1つのブロックとして見えることが重要だと説いたのだった(図30)。
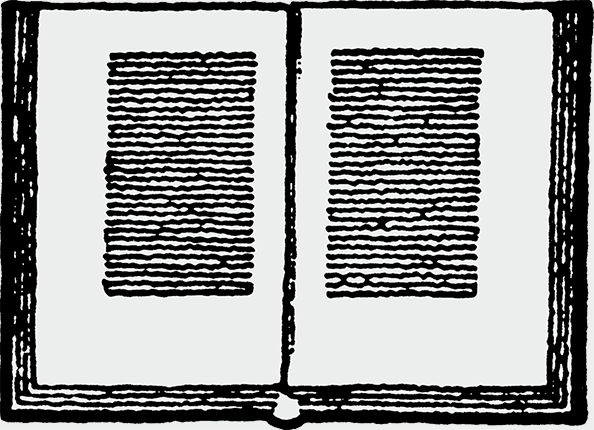 [図30]ウィリアム・モリスの版面設定
[図30]ウィリアム・モリスの版面設定
モリスに続いたのは、彼の直接的な影響下にあったイギリスのエドワード・ジョンストン(1872–1944)である。
ジョンストンは今日においても、近代カリグラフィの開祖として広く知られている人物であり、その著書『書字法・装飾法・文字造形※18』は、古典的な書法を具体的に示し詳細に解説したカリグラフィの教科書として世界各国で翻訳され、刊行以来現在まで途切れることなく発行され続けている名著である。
ジョンストンはその著作の一節で、ブック・フォーマットを以下のように具体的な数値で提示した。
マージンはテクストをほかの部分と分離するためには不可欠な余白の部分で、文字を読みやすくしかも美しく保つためにとても重要である。狭いよりは広いマージンのほうが無難だが、無闇に広く取るのは逆効果である。……各ページの中でのテクストとマージンの比率は状況次第で決まるので、感性に頼る部分が大きいといえる。そのためにもページサイズとそれに対応したマージンの定型を、あらかじめ何とおりか用意しておくと便利だろう。
ほかの各部とマージンとの比率は伝統にしたがう。すなわち地のマージン[4]は、天のマージン[2]の2倍になり、両脇小口のマージン[3]は一般に天と地の間の値を取る。
見開きで2ページ分を見た時に、テクストのふたつの段が並んでいるように見えるようにする。中央(ノド)に位置する各ページの左右小口のマージンは、実際にはひとつの空間として統合されて見えるので、ノドのマージンを小口の半分程度に狭くしておけば、双方のページを合わせたときに小口のマージンとほぼ等しくなる。初期写本のマージンの比率は、ほぼノド1.5、天2、小口3、地4となっている。このように十分なマージンを適宜配置することで、書物は格段に使いやすくしかも美しくなる(図31)。
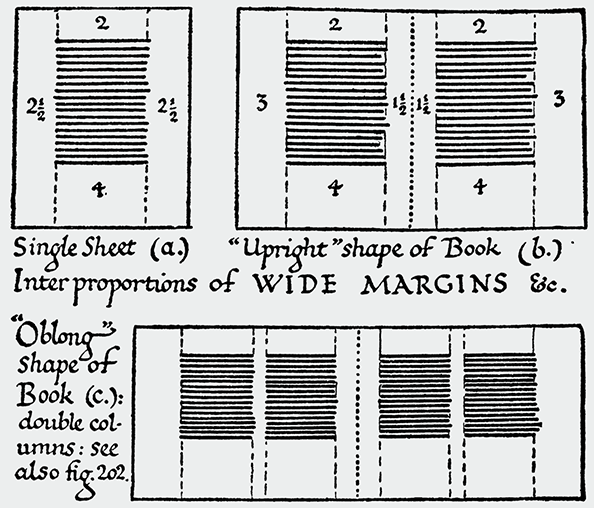 [図31]エドワード・ジョンストンの紙面におけるプロポーション(1906)
[図31]エドワード・ジョンストンの紙面におけるプロポーション(1906)
このジョンストンの提示したブック・フォーマットをさらに詳細に数値化し、図式化してみせたのが、20世紀を代表するタイポグラファ、ヤン・チヒョルト(1902–74)である。
チヒョルトはドイツ・ライプチヒに生まれ、カリグラフィと伝統的なタイポグラフィを学び、1923年ワイマールでのバウハウス展に感化され、その前半生をいわゆるモダン・スタイルのタイポグラフィにおいて展開した(図32)。
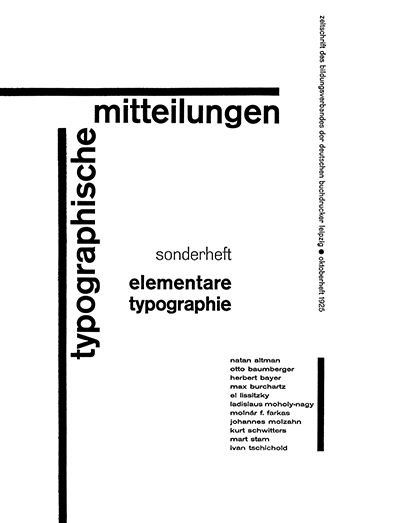 [図32]チヒョルトによって編集とデザインがなされた『タイポグラフィ通信特別号※19』「タイポグラフィの基礎」(1925)
[図32]チヒョルトによって編集とデザインがなされた『タイポグラフィ通信特別号※19』「タイポグラフィの基礎」(1925)
ナチの迫害を逃れスイス・バーゼルを拠点に活動した後半生は、伝統的な様式に基づいたタイポグラフィ(図33)に回帰。彼はタイポグラフィにおける2つの有用なる様式それぞれを理論・体系化し、さらにはそれを高次元で具現化したタイポグラファとして、いまだ論議の俎上にのぼり続けている人物なのである。
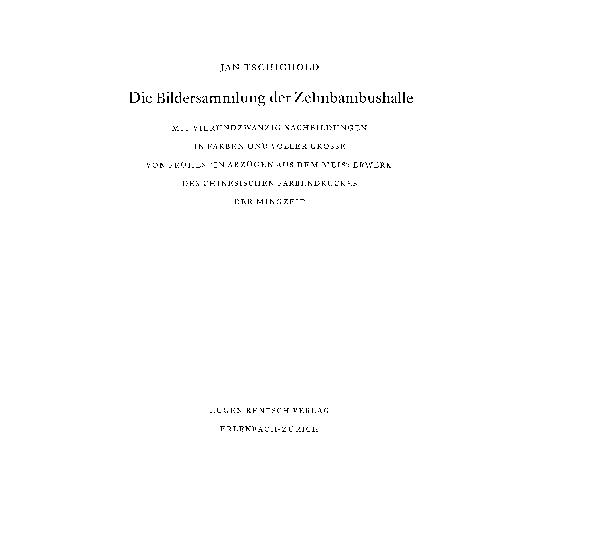 [図33]チヒョルトが晩年に手掛けた『十竹斎書画譜』(1970)
[図33]チヒョルトが晩年に手掛けた『十竹斎書画譜』(1970)
チヒョルトは生涯数多くの文学作品のブック・デザインを手掛けた。なかでももっともよく知られているのがイギリス・ロンドンのペンギン・ブックス社での仕事である。
彼はペンギン・ブックス固有の活字書体の選定法と組版規則を「ペンギン組版ルール」(図34)として定めた。また、ペンギン・ブックスの各シリーズのブック・フォーマットを作成し、高品質でありながらも大量生産を前提とした、合理的で汎用性のあるデザインを展開したのである(図35-A、図35-B)。
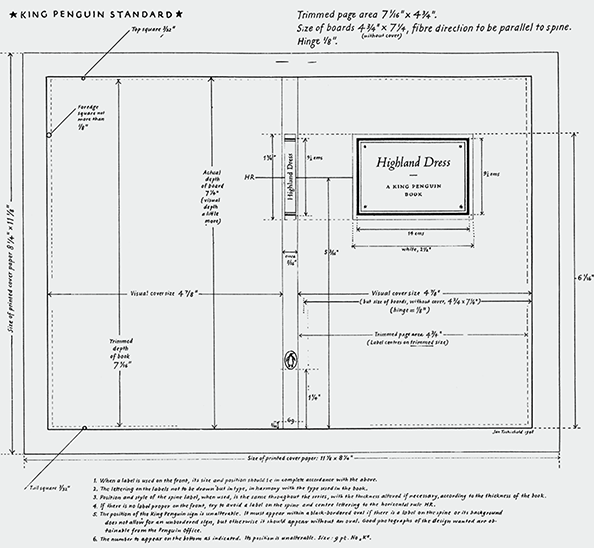 [図35-A]「キング・ペンギン」用のデザイン基準指定図と表紙用のフォーマット(1948)
[図35-A]「キング・ペンギン」用のデザイン基準指定図と表紙用のフォーマット(1948)
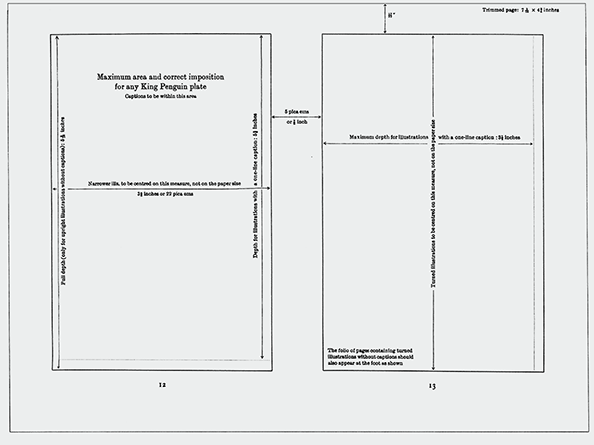 [図35-B]「キング・ペンギン」用の紙面の最大版面と同シリーズ共通のタイトル・プレートのフォーマット(1948)
[図35-B]「キング・ペンギン」用の紙面の最大版面と同シリーズ共通のタイトル・プレートのフォーマット(1948)
1962年、チヒョルトは自身が徹底的に調査・解析した、ブック・フォーマットの設定基準値と規範図式(カノン)を開陳した。『Willkürfreie Maßverhältnisse der Buchseite und des Satzspiegels※20』(図36)がそれである。
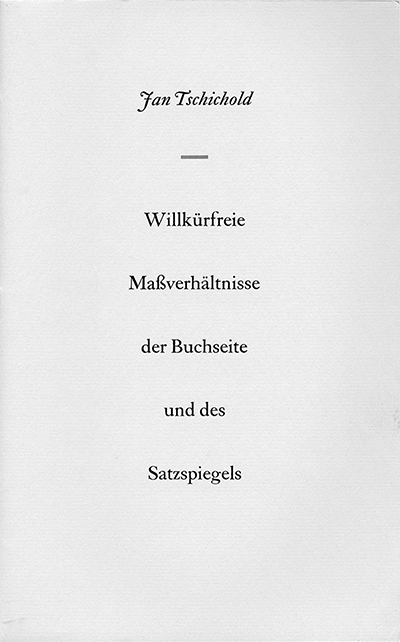 [図36]『Willkürfreie Maßverhältnisse der Buchseite und des Satzspiegels』の表紙(1962)
[図36]『Willkürfreie Maßverhältnisse der Buchseite und des Satzspiegels』の表紙(1962)
彼は歴代の書物を解析し、有用なブック・フォーマットの定数と規範図式を再構成してみせた。美学の分野では既に議論が尽きたはずの審美的要素の定数・図式化である。
チヒョルトは後期ゴシック期の写本工房の工匠ヴィラール・ド・オネクールの紙面構成図に含まれる調和的分割法(図37)や、チヒョルトと同時代の研究者ファン・デ・グラーフ(図38)、ラウル・ロザリヴォ(図39)などの分割法を具体的に図式化し、応用展開を試み、汎用性のある指標としてのブック・フォーマットを提示してみせたのだ。
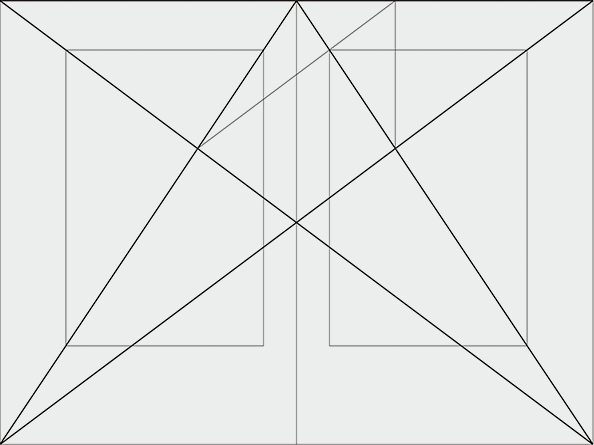 [図37]ヴィラール・ド・オネクールの調和的分割法(13世紀前半)
[図37]ヴィラール・ド・オネクールの調和的分割法(13世紀前半)
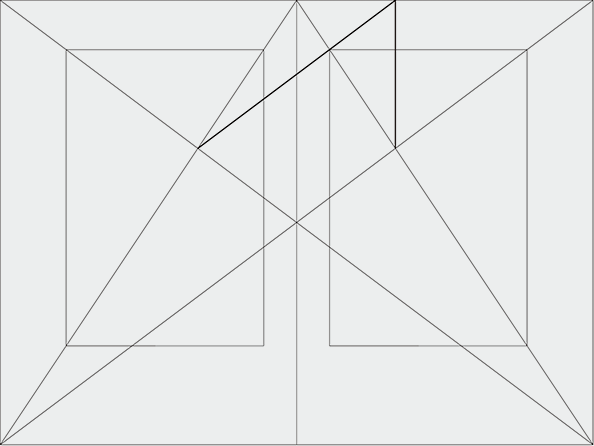 [図38]ファン・デ・グラーフによる9分割の方法(1946)
[図38]ファン・デ・グラーフによる9分割の方法(1946)
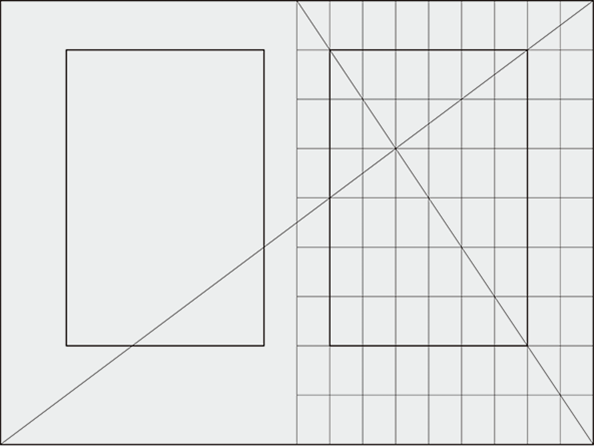 [図39]ラウル・ロザリヴォによる紙面の縦横の9分割(1961)
[図39]ラウル・ロザリヴォによる紙面の縦横の9分割(1961)
しかし、これらはあくまでも基準値であって、絶対値ではなかった。なぜなら、書体の種類とサイズ、そしてそのウェイト(太さ)、字間、語間、行送り、組幅など、紙面における所与の関係はその都度異なるため、指標にはなるが絶対値とはならなかったからである。
そしてチヒョルトは、数値化することのできない定数「目」と「手」が良質の書物の均整をかたちづくるのだ、とその著作に印したのである。
紙面設計における規格化と数値化(2)
グリッド・システム
それまで1段組、2段組、3段組など縦の段組だけを考慮し分割されていたブック・フォーマットを、縦横共に細分割し、写真や図版(視覚情報)とテキスト(言語情報)のレイアウトを支援するために生まれたのが、「グリッド・システム」と呼ばれる格子状のガイドラインである。
グリッド・システムは、ナチの迫害を逃れ中立国スイスに身を寄せていた周辺諸国のグラフィック・デザイナーが、第二次世界大戦後に確立したシステムである。彼らはグリッド・システムを用いて視覚情報と言語情報を統合させ、さらに技術と美学を同時に結び付け、分析的かつ機能的で秩序だったデザインを展開していった。
このグリッド・システム成立の背景には、ディ・スティールやバウハウスなどに代表される20世紀初頭の前衛芸術運動の潮流から派生した「ディ・ノイエ・ティポグラフィ(ニュー・タイポグラフィ)」と呼ばれる機能的で合理的なタイポグラフィの存在があった。
「ニュー・タイポグラフィ」はロシア構成主義のエル・リシツキー(1890–1941)、バウハウスのラズロ・モホリ゠ナジ(1895–1946)、ヨースト・シュミット(1893–1948)、ヘルベルト・バイヤー(1900–85)、それにオランダのピート・ツヴァルト(1885–1977)などが提唱・実践したモダン・タイポグラフィである(図40)。
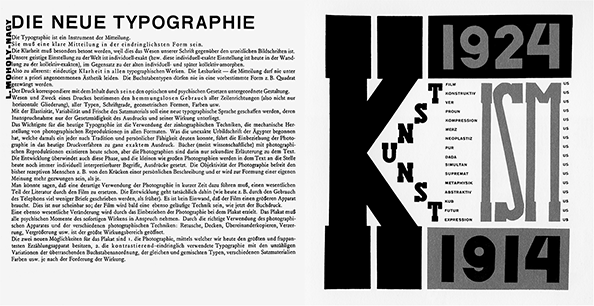 [図40]ラズロ・モホリ゠ナジ自身による「新しいタイポグラフィ」のテキストと組版(左、1923)と、エル・リシツキーの著作『諸芸術主義 1914–1924※21』(右、1925)
[図40]ラズロ・モホリ゠ナジ自身による「新しいタイポグラフィ」のテキストと組版(左、1923)と、エル・リシツキーの著作『諸芸術主義 1914–1924※21』(右、1925)
「ニュー・タイポグラフィ」では
タイポグラフィは機能的かつ合目的的であるべきであり、そのため歴史・宗教・民族臭が付着した従来のローマン体は使用せず、無機的なサンセリフ(日本でいうところのゴシック体)を用いること。さらに古典的な中軸揃えを破棄し、時代と生活の運動性に適応した能動性のあるアシンメトリー(非対称)の組版とする。新しい時代の視覚情報である写真術とタイポグラフィによる視覚効果の融合を計る。工業規格に合わせた標準化
などが提唱された。これを論理的に言語化し、体系化したのが若きヤン・チヒョルトである。
1940年代後半、補助的とはいえグリッドを利用した初めての印刷物が発行される。それはまだ未成熟なものとはいえ、規則的な原則に基づいた組版や図版の配置、ページ・レイアウトの均一性、そして題材の存在を客観的に捉えようとする次世代のモダン・タイポグラフィの特徴を有するものであった。
グリッド・システムの効用がもっとも具体的に示されたのが1958年に刊行されたスイスのグラフィック・デザイン誌『ノイエ・グラーフィク(ニュー・グラフィック・デザイン)※22』(図41)である。デザインはハンス・ノイブルク(1904–83)、リヒャルト・ローゼ(1902–88)、カルロ・ヴィヴァレリ(1919–86)、ヨゼフ・ミューラー゠ブロックマン(1914–96)。やがてスイス・デザインの潮流を牽引することになるグラフィック・デザイナーたちである。
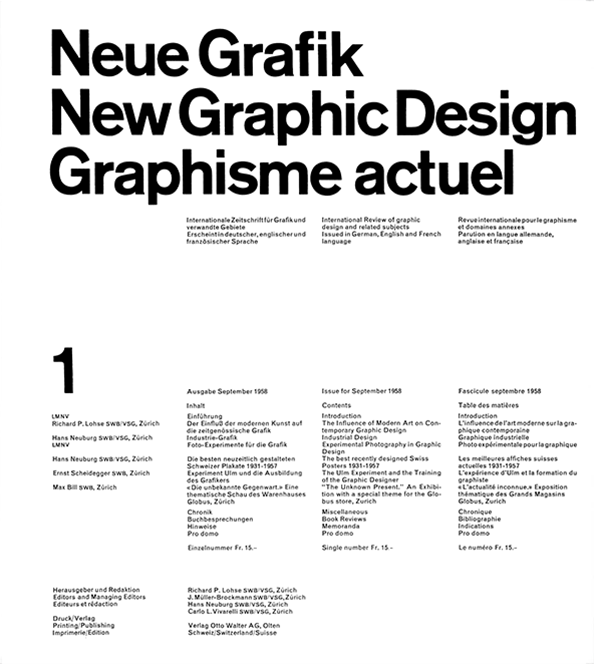 [図41]『ノイエ・グラーフィク』(1958)
[図41]『ノイエ・グラーフィク』(1958)
『ノイエ・グラーフィク』は、ドイツ語、英語、フランス語の3ヵ国語と写真や図版などの視覚情報を同一誌面に視覚的に融合させることを目的としていた。彼らは活字サイズと行送りから導き出されたユニットを用いて誌面を分割し、数学的秩序に基づいたグリッドを活用しはじめる。
ブロックマンはのちにこのグリッド・システムを『グリッド・システムズ・イン・グラフィック・デザイン※23』(図42)としてまとめ、その生成法と活用法を説き、グリッド・システムの理念を以下のように提示した。
「組織化して明確さを得る」「本質的要素を理解し純化する」「主観性ではなく客観性を育てる」「創造と技術の制作過程の合理化」「色彩、形態、素材の統合」「面と空間に建築的支配を確保する」「能動的態度をとる」「建築的創造的精神による制作物の効果」「教育の重要性の認識」。
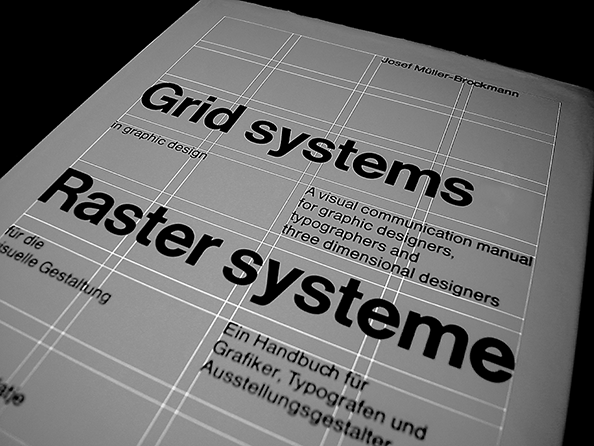
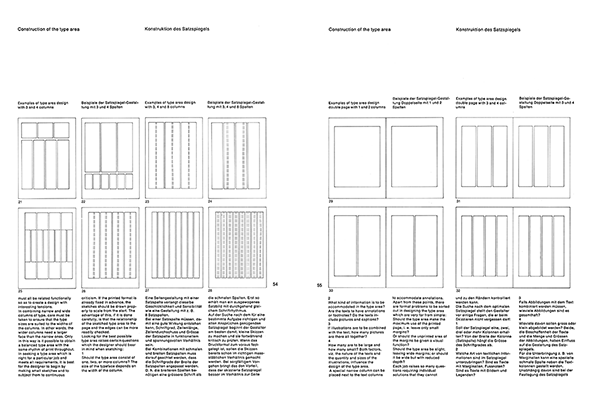
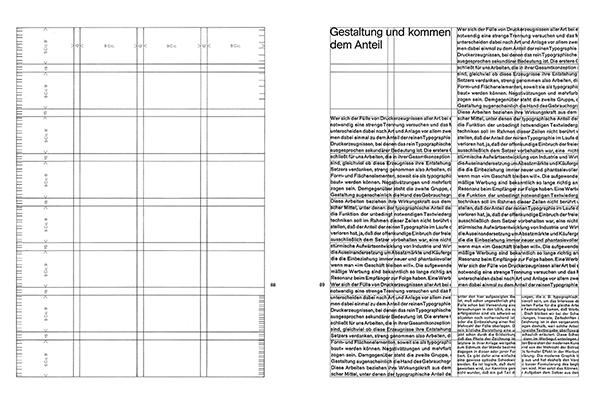 [図42]ヨゼフ・ミューラー゠ブロックマンの著作『グリッド・システムズ・イン・グラフィック・デザイン』のジャケット(上)と本文(中・下) (1981)
[図42]ヨゼフ・ミューラー゠ブロックマンの著作『グリッド・システムズ・イン・グラフィック・デザイン』のジャケット(上)と本文(中・下) (1981)
またその利点を以下のように示した。
「視覚伝達において論拠を客観的に組み立てることができる」「本文や図版を規則正しく論理的に組み立てることができる」「本文と図版とが調和を保ちながら、簡素に編集・構成することができる」「わかりやすく、高度な均衡性を組織化するための視覚要素を組み立てることができる」。
このようなグリッド・システムの性格上、言語情報を主とする書籍にグリッド・システムが活用されることはほとんどなかった。そのかわり視覚情報を優先する雑誌、カタログ、図録などの冊子媒体のほか、ポスター、広告、販売促進物、展示ディスプレイ、サイン・システムなど、時代が求める新たな媒体に活用されることになる。
1960年代以降、グリッド・システムを利用したデザインは世界のデザイン界を席巻した。わが国も例外ではなく、すぐさまその方法論は転用され応用された。
しかしグリッド・システムを技法としてのみ取り入れ不用意に活用すると、紙面は画一化を招くことになる。つまり読者にとってはどのページを開いても同じような紙面が現れるという、硬直した単調なページ展開にしか映らなくなるのだ。一方デザイナーにとっては、単純にグリッドにそってレイアウトしていくのには効率的ではあるものの、一旦その枠から外れようとすると一挙にグリッドは扱いづらく堅苦しいだけの制約となる。その結果多くのデザイナーは、その堅苦しさをヨーロッパの合理主義に重ね合わせ忌み嫌うことになるのである。
だが、堅苦しい制約、硬直した単調なページ展開の要因はグリッド・システムそのものにあるわけではない。グリッド・システムはあくまでもレイアウトを支援するガイドラインであって、良質なデザインを保証するものではないからだ。つまり、チヒョルトが『紙面と版面の明晰なプロポーション』で記したように「数値化することのできない定数「目」と「手」が良質の書物の均整をかたちづくる」ことが、グリッド・システムについても同様にいえるのである。
紙面を構成する諸要素は、数値化することのできない意味と統語、語用などの所与の関係性によって成立しており、結果的には視感覚によって制御されなければならない。
ブロックマンらが活動したスイスの拠点はチューリヒであった。ほぼ同時代、同国のバーゼルでは1人の教師が工芸学校「バーゼル・スクール・オブ・デザイン」を拠点として、タイポグラフィにおける視感覚コントロールの可能性を試みていた。エミール・ルダー(1914–70)がその人である。
ルダーは1957年に発売されたサンセリフ書体「ユニヴァース」を用いて、それまで静的な二次元空間に安住していた紙面空間を、擬似的とはいえ三次元化させ、なおかつ動的均衡を保有する紙面が可能であることを実証してみせた。
ユニヴァースは、1957年にアドリアン・フルティガー(1928–)※24がデザインしたサンセリフ書体である。ユニヴァースは設計当初よりファミリー※25展開することを前提にデザインされた初めての書体であった。
その特質は、英語、フランス語、ドイツ語など異なるラテン・アルファベットを組んでも、どの言語も破綻のない均質な組版が得られるという、かつてどの書体もなし得なかったことを可能にしたことにある。また、ライトからボールドウェイトまでの組版濃度(グレートーン)の段階に均等なグラデーションを持たせることができる視覚的な書体であった。
フルティガーはこの均質な書体をデザインするにあたって、縦画(ステム)の幅などはある程度の定数化をしたものの、印刷される黒と印刷されない白との濃度バランスをはじめ、そのほとんどを眼と手を使ってデザインした。
ルダーはユニヴァースの持つ特性を最大限に生かした動的で奥行き感のある紙面を、グリッド・システムを援用し視感覚コントロールによって現出させることに成功する(図43)。欧米諸国では60年代から80年代にかけて、こうしたグリッド・システムを活用したバーゼルやチューリヒのデザイナーの影響を色濃く受けたデザインが次々と生み出されていった。
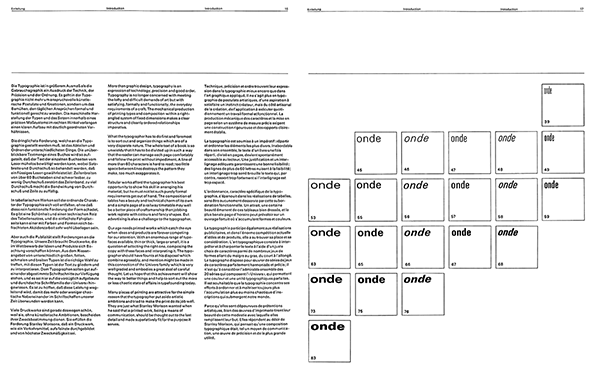
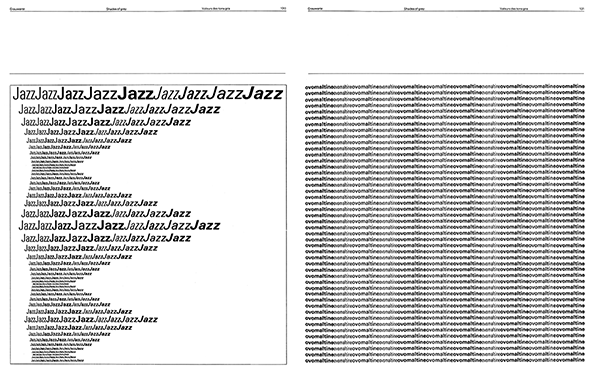 [図43]エミール・ルダーの著作『タイポグフィ』(1967)は、タイポグラフィにおける視感覚コントロールについての事例が数多く掲載されたタイポグラフィの教科書。掲載図版はユニヴァース・ファミリー(上)と、ユニヴァースを用いた「グレーの階調」(下)
[図43]エミール・ルダーの著作『タイポグフィ』(1967)は、タイポグラフィにおける視感覚コントロールについての事例が数多く掲載されたタイポグラフィの教科書。掲載図版はユニヴァース・ファミリー(上)と、ユニヴァースを用いた「グレーの階調」(下)
80年代中期以降になると、ルダーの跡を継いで「バーゼル・スクール・オブ・デザイン」で教壇に立ったウォルフガング・ワインガルト(1941–)が行ったオフセット平版印刷における実験的タイポグラフィの強い影響と、パーソナル・コンピュータの出現によって、グリッドは重層化され、なおかつ限りなく細分化され、遂には方眼紙レヴェルからビットマップ・レヴェルにまで細分化される。
そしてグリッド・システムは、脱構築主義の潮流と相まって、一挙に解体への道を歩むのである。それをデザインの分野ではニュー・ウェイブ・タイポグラフィ(図44)と呼んだ。
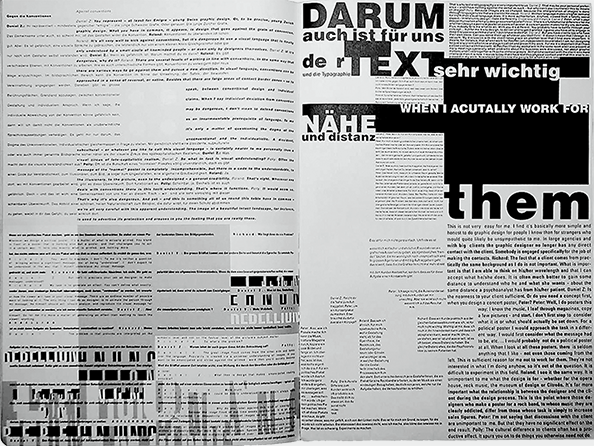 [図44]ズザーナ・リッコとルディ・バンダーランスによる『エミグレ』誌の本文。ニュー・ウェイヴ・タイポグラフィは、コンピュータを用い始めた世代が牽引し、1980年代後半から90年代中期にかけて、世界的な潮流となった(1984–2005)
[図44]ズザーナ・リッコとルディ・バンダーランスによる『エミグレ』誌の本文。ニュー・ウェイヴ・タイポグラフィは、コンピュータを用い始めた世代が牽引し、1980年代後半から90年代中期にかけて、世界的な潮流となった(1984–2005)
ルダーが提示した紙面空間は、視感覚コントロールによらないレイヤー機能とスリー・ディメンション機能で簡便に実現するようになった。視覚情報と言語情報はデジタル支援によって幾重にも重層化し、テキストは画像と化し、画像は視覚「言語」として画面上でテキストと等価となった。
さらに画像は動画となり音声情報までもが付与された。まさに、ブロックマンが掲げたグリッド・システムの理念の1つ、視覚情報と言語情報の統合、それ以上の実現である。ブロックマンが著作『グリッド・システム・イン・グラフィック・デザイン』を『グリッド・システムズ・イン・ブック・デザイン』としなかった1つの理由がここにある。
その後のタイポグラフィの進展
視覚情報と言語情報の統合を目指したモダン・タイポグラフィが加速度的に進化(?)する一方で、伝統的タイポグラフィはその後どうなったのであろうか。
だが、そもそも伝統的タイポグラフィとは一体何を指すのだろう?
一般的に「本を読む」とは、テキストそのものを読むことを指している。むろん視覚情報から「読み取る」ことはできるが、それは視覚情報を受け手が言語化することであって、言語そのものを読んでいるわけではない。したがって、ここでは伝統的タイポグラフィを「言語情報を主とするタイポグラフィ」と仮定して、まずは話を進めてみる。
言語情報を主とするタイポグラフィでは、印されたテキストから内容を理解する。紙面に印されていない視覚情報や音声情報は、読者の内的対話や想像力(イマジネーション)によって補完される。つまり言語情報を主とするタイポグラフィには「足りない情報」という贅沢な「余地」が残されており、その余地が読者自身によって埋められることでテキストは一応の成立をみる、といえなくはない※26。
モダン・タイポグラフィでは、この余地をあらかじめ補完するために写真や図版という視覚情報が用意され、さらには受け取られ方を限定すべく視覚情報と言語情報は制作者の能動的態度でもって視覚的に制御される。
これが言語情報を主とするタイポグラフィとは異なるニュー・タイポグラフィとモダン・タイポグラフィの歩んだ道であり、ひいては、受け手の介在の余地の少ない一元的な情報の伝達にとって効力を発揮することになったのである。
とはいえ、言語情報を主とするタイポグラフィとモダン・タイポグラフィを分かつ境界線は限りなく曖昧だ。なぜなら、受け手個々によってその受容の仕方は結局は千差万別だからだ。
*
1996年、アメリカに移住したチェコ出身のタイプ・デザイナー、ズザーナ・リッコ(1961–)と、オランダ出身のグラフィック・デザイナー兼編集者ルディ・バンダーランスの2人のデザインチーム「エミグレ(移民を意味する)」が「ミセス・イーヴス」という名のデジタル・タイプを発表した。
彼らは1980年中期よりマッキントッシュ・コンピュータを使って数多くのデジタル・タイプを制作してきた。なかでも当時のデジタル環境を考慮した、自虐的とも諧謔的とも受け取られかねない疑似ビットマップ・フォント※27「ロウ・レゾ(低解像度)」(図45)の登場は、センセーショナルであった。
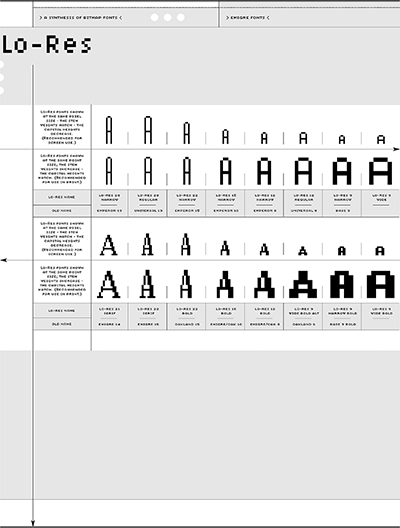 [図45]ズザーナ・リッコのデザインによる「ロウ・レゾ」のファミリー。1985年に設計され、2001年にも改刻されている
[図45]ズザーナ・リッコのデザインによる「ロウ・レゾ」のファミリー。1985年に設計され、2001年にも改刻されている
それは、既に1000メッシュでのアウトライン・フォント※28を実装できる時代にあって、あえて目の粗いビットマップ・フォントを制作し、それがデジタル時代の読者の「眼の慣れ」に適しているという主旨だったからだ。
彼らはそれらの書体を用いて自分達の媒体であるデザインとタイポグラフィの雑誌『エミグレ』を発行。そこで展開されたのが先に紹介したニュー・ウェイブ・タイポグラフィである。彼らはこの潮流を牽引した第一人者でもあったのだ。
1996年、それまで独創的な書体だけをデザインしてきたズザーナ・リッコは、初めて古典書体を手掛ける。「バスカヴィル」の復刻「ミセス・イーヴス」(図46)である。
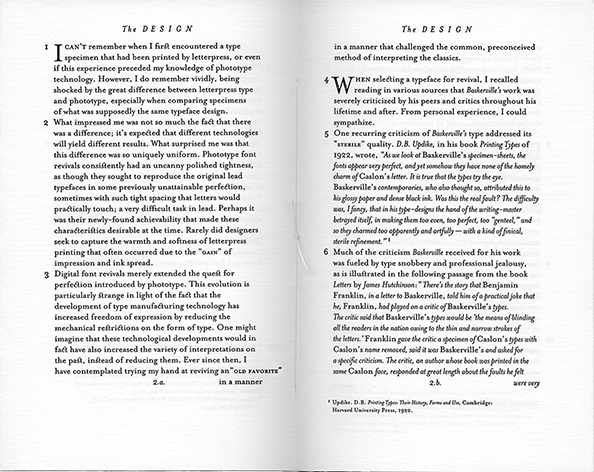 [図46]古典的な組見本が掲載された『ミセス・イーヴス』の書体見本帳(1996)
[図46]古典的な組見本が掲載された『ミセス・イーヴス』の書体見本帳(1996)
バスカヴィルはイギリスのジョン・バスカヴィル(1706頃–75)を源流とする活字書体で、20世紀初頭から現在まで、書体メーカーが必ず時代のテクノロジーに適合させて復刻してきた定評ある書籍本文用書体である。
リッコはこの「ミセス・イーヴス」の制作を境に、再び紙の上のタイポグラフィに戻ることを宣言し、古典書体を現代の読者の時代性と需要に適合するように最新のデジタル技術を援用して、デジタル技術でなければ実現不可能な書体を復刻(改刻)させた。
ミセス・イーヴスには、リガチュア(合字)(図47)が随伴書体として付加されており、「リガチュア・メーカー」と呼ばれるアプリケーション・ソフトを介して生成される。その本文組版は、過剰なほど擬古典的ともいえるが、リッコのミセス・イーヴスにおけるこの試みは、本文用書体開発における多様な可能性を示すことになった。
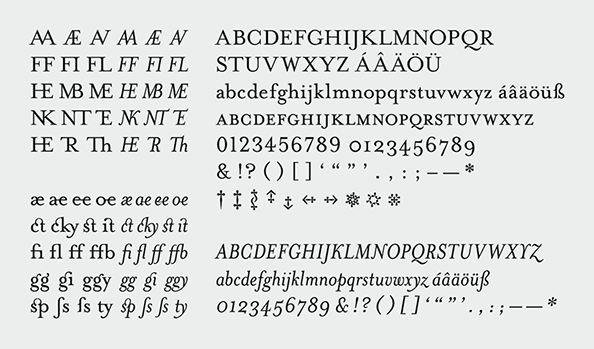 [図47]「ミセス・イーヴス」には、通常のローマン体、イタリック体、スモール・キャピタルのほかに、過剰ともいえるリガチュアが100種以上も存在している(1996)
[図47]「ミセス・イーヴス」には、通常のローマン体、イタリック体、スモール・キャピタルのほかに、過剰ともいえるリガチュアが100種以上も存在している(1996)
こののち、従来の書体(金属活字・写植活字)を単にデジタル・フォーマットに置換するだけに安住していたタイプ・デザイン界は、本文用書体の開発において、本来なにが必要で、そのためにコンピュータはどのように活用できるのか、という視点を持つようになる。そしてその手始めにタイプ・デザイナーたちがしたことは、古典書体の見直しと、その現代的解釈による改刻なのであった。
*
イギリスのペンギン・ブックスでは2004年に『グレート・アイデアズ※29』(図48)を刊行した。このシリーズは、古典から近代までの名著を復刻したもので、いわゆるペーパーバックと呼ばれる、ごく当たり前の読み物(言語情報を主とするタイポグラフィ)であった。
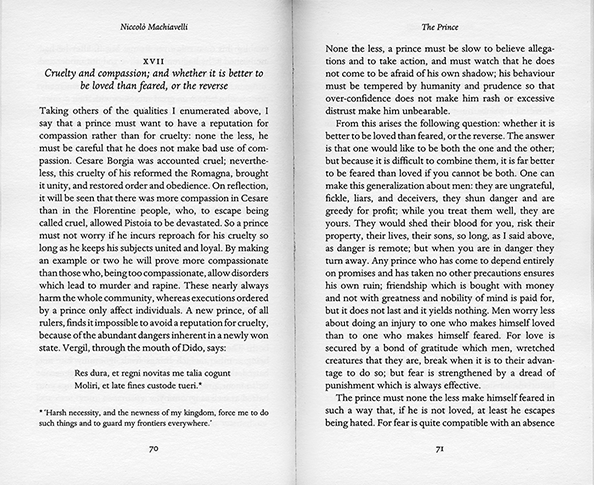 [図48]2004年に刊行された『グレート・アイデアズ』の本文組版。その組版は伝統的な様式にしたがった中軸揃え
[図48]2004年に刊行された『グレート・アイデアズ』の本文組版。その組版は伝統的な様式にしたがった中軸揃え
使われている書体は金属活字でも写植活字でもない、デジタル・タイプの「ダンテ」という書体である。ダンテの源流はルネサンス期に印刷・出版人として活動した人文主義者のアルダス・マヌティウスの工房で使われていたローマン体で、1946–56年に金属活字として改刻され、近年になってデジタル化された書体である。
『グレート・アイデアズ』の組体裁は、伝統的タイポグラフィの様式に乗っ取った一見何の変哲もない様相を呈している。そこには新奇な書体は使われておらず、また目新しい組体裁があるわけでもない。しかし、用いられている書体は古典書体を改刻したデジタル・タイプで、組版はコンピュータ支援によるアプリケーション・ソフトなのだ。そして、それはわが国の文庫本や単行本における現在のタイポグラフィの状況とまったく同様なのである。
最新のテクノロジーを用いながらも、従来と異なることのないタイポグラフィ。「言語情報を主とするタイポグラフィ」は「なにも変わらなかった」のか?
否、変わったのである。これがタイポグラフィにおけるわずかばかりの変化であり進展なのだ。
*
言語を活字によって記述する。
ただそれだけの事にタイポグラフィは存在し、ただそれだけのためにタイポグラファはグーテンベルク以来、550年以上にわたって膨大な時間と労力を注ぎ込んできた。
そしてその背景には必ず数値化、定量・定数化、規格化が存在し、同時にそれを支える眼と手という身体が存在してきた。
文筆家も読者もほとんど無自覚のままそれを受け入れている。むろん、それは否定されるものではなく、むしろ無自覚でいることのほうが幸せではないか、とも思う。だが数値化、定量・定数化、規格化は今日ある「近代」を根底から支えた思想であり、その意味でいえば活字版印刷術(タイポグラフィ)こそ近代そのものだといえるのではないか。だからこそ、せめてその一端でも知っておいてもらいたいと思うのである。
「近代は終わった。いや、終わってはいない」、「モダンとは、モダニズムとは、モダニティとは」と、さまざまな分野で「近代」は語られ続けてきた。決して意識されることのないタイポグラフィを通して —— 。
そしてそのテキストを印すための書体のほとんどが、明治初期以来使われ続けてきた「モダン」な書体「明朝体」に属し、現在200を優に越す明朝体の中から選ばれた1つの明朝体であることも意識されることはない。そう、このテキストでさえも※30。それが言語社会を支え続けてきたタイポグラフィの尽きせぬ魅力なのである。
タイポグラフィとしてのスタイルシート
タイポグラフィでは、文字や単語は機械的な手法で生み出されます。……(サイズや位置などの)情報は他の人に渡すことができ、別の機会にまったく同じものを再現することもできます。
フレット・スメイヤーズ『カウンターパンチ※1』
タイポグラフィとは、人の手によって直接描かれるものではなく、機械的な手法によって生成されるものです。そして、その書体や文字サイズや行間といったものをデータとして定義でき、そのデータをもとにまったく同じものを再現できるものでもあります。
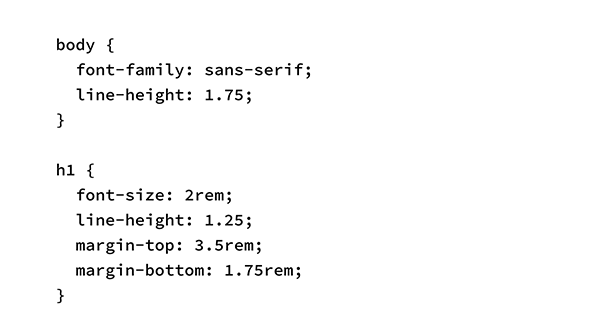
ここに示したのはウェブサイトやモバイルアプリケーションなどの表示スタイルを記述する言語であるCSS(カスケーディング・スタイル・シート)のコードです。これによって書体や文字サイズ、行間、そして文字サイズを基準にしたスペーシングなどが定義されます。このコードをもとにして、ウェブブラウザなどユーザーエージェントという機械が文字を整形して表示する。これは表示する環境が変わっても再現可能です。タイポグラフィの定義を見れば、こういったCSSのコード片も、タイポグラフィであることがわかります。
紙面に文字を配置する技術として数百年の歴史を持つタイポグラフィですが、近年はパソコンやスマートフォンなどデジタルデバイスの画面にもその領域を広げてきました。本稿ではウェブサイトやアプリケーションなどのオンスクリーンメディアにおける実践を題材にして、タイポグラフィを考察していきます。
音楽と数学から考えるタイポグラフィ
欧米のタイポグラフィの本を読んでいると、必ずと言っていいほど出くわすのが音楽の話です。しかも「リズムを意識しましょう」とか「ハーモニーが大切です」とかいった抽象論や精神論ではなく、 数学に基づいた音楽理論をもとにタイポグラフィを解説している例が多々あるのです。
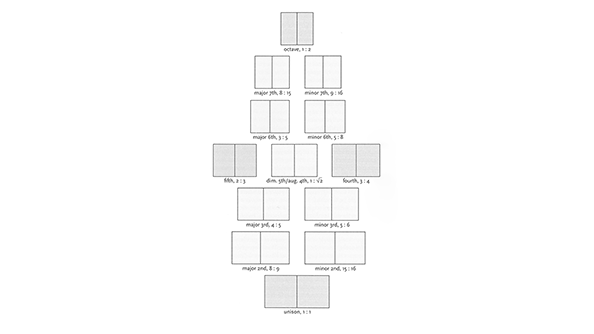 Robert Bringhurst “The Elements of Typographic Style※2”
Robert Bringhurst “The Elements of Typographic Style※2”
この図版はカナダの詩人でありタイポグラファーのロバート・ブリングハーストが書いた『The Elements of Typographic Style』という本に掲載されているもの。それぞれ本の見開きの状態が示されていて、ページの縦横比をいかにデザインするかということが語られています。いちばん上は縦長の本でページの縦横比が1 : 2。いちばん下は正方形の本で比率は1 : 1。さらにその間に様々な縦横比のバリエーションがあり、これらのページの比率はすべて音楽における音程の周波数比になっているのです。
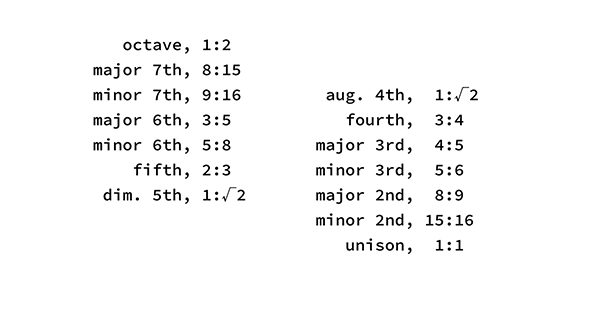
音の高さは周波数によって決まります。ここでは基準となる音と各音程との周波数の比率を示しています。ユニゾン、つまりまったく同じ高さの2音の周波数比は1 : 1で、オクターブ上の音は1 : 2になります。こういった音程の周波数比をページの寸法に適用しているわけです。
またこれらの数字を見ていくと、わたしたちに馴染みの深い比率が多く含まれています。たとえば画像や映像のアスペクト比でよく使われる、短7度の16 : 9や完全5度の3 : 2、完全4度の4 : 3といった比率があります。また短6度の5 : 8は黄金比に近く、減5度(増4度)の1 : √2は白銀比です。
音楽と諸芸術は、数学の姉妹である。全ての芸術と同じように、音楽もまた自然の法則に基づいている。
ヨゼフ・ミューラー゠ブロックマン『グリッドシステム ― グラフィックデザインのために※3』
タイポグラフィに数学的思考を取り入れモダンデザインを牽引したヨゼフ・ミューラー゠ブロックマンが言うように、デザインと音楽には深い関連性がある。つまり、タイポグラフィの背後には必ず数学的なロジックが潜んでいます。当然、最終的にはデザイナーの「眼」で見て判断されるわけですが、その前に音楽や数学のロジックはガイドラインとして大いに力を発揮するのです。
音楽には様々な要素が複雑に関係しており、そのコアになるのはハーモニー、リズム、メロディという3つであると言われています。「ハーモニー」は、複数の音の調和のこと。ギターやピアノで弾くコードや、オーケストラなどでたくさんの音が同時に鳴ったり、アカペラで声がハモったりといったものを想像してください。「リズム」というのは、音楽の時間的な変化。もっともわかりやすいのはドラムやメトロノームなどの拍。「メロディ」は、旋律とも言いますが、たとえばロックバンドのヴォーカルやジャズのピアノソロなどで表現されるものです。
この音楽の3要素に沿って、それぞれがタイポグラフィにどう関係するのか、またその背後にどのような数学的ロジックがあるのかを見ていきたいと思います。
ハーモニー
「ハーモニー」とは音が協和すること、つまりいくつかの音が合わさって心地よい響きを生むことを言います。日本語で「調和」とも訳されます。音の高さは振動数によって決まるという話をしましたが、音が調和するということはつまり、振動数の比率がちょうどいいバランスになっている状態です。
タイポグラフィにおける調和とは何かというと、文字サイズや行間、グリッドのカラム幅など、様々なサイズが美しい比率で画面上に共存している状態です。今回はその中でも、文字サイズの調和について考えてみます。
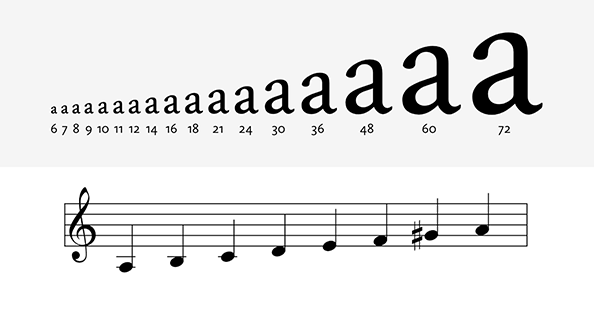
オンスクリーンメディアでは、本文、見出し、キャプション、ボタンといった様々な文字サイズのテキストが要素となって画面が構成されます。そこでは、たとえば見出しを本文よりどのくらい大きくするか、またキャプションをどのくらい小さくするかといった選択によって、画面の調和が決まってくるのです。このときに、それぞれの文字サイズを場当たり的に決めるのではなく、あらかじめ一連のサイズを用意して組み合わせながら画面を構成します。ここで用意される一連のサイズを「スケール」と言います。
文字サイズのスケールは、音楽におけるスケール、つまり音階に当たります。このスケールを無視して適当に弾いていたら、調子外れな演奏になってしまうので、曲に調和するスケールに沿って演奏するわけです。これは文字サイズも同様です。ボタンの文字サイズがコンポーネントによってバラバラだと、調和が得られません。タイポグラフィ設計は、まず文字サイズのスケールを定義するところから始める必要があります。
文字サイズのスケールを考えるときに役立つ手法として「モジュラースケール」というものがあります。スケールの各サイズを経験や勘にもとづいて決めるのではなく、意味のある一連の調和した比率をもとにしようというものです。これは文字サイズに限らず、たとえば本のページの縦横比やグリッドのカラムなどにも使われるものです。
モジュラースケールは音階のようなもので、あらかじめ用意された、一連の調和したプロポーションです。それは言わば、目盛りが一定ではなく、寸法が均一ではない物差しです。
Robert Bringhurst『The Elements of Typographic Style』
ブリングハーストは、モジュラースケールを「物差し」にたとえて説明しています。物差しは、目盛りが1mm単位で長さ30cmといった具合に、目盛りが一定間隔で並んでいて寸法が決まっています。しかし、モジュラースケールというのは目盛りが一定間隔ではなく、かつ寸法も自由に伸び縮みさせられる物差しだ、とブリングハーストは言っています。
また彼はその書籍の中で「モデュロール」という寸法体系にも触れています。モデュロールとは、建築家のル・コルビュジエが考案した、人体と黄金比にもとづいた寸法体系で、どうやらこれがモジュラースケールのもとになっているようです。
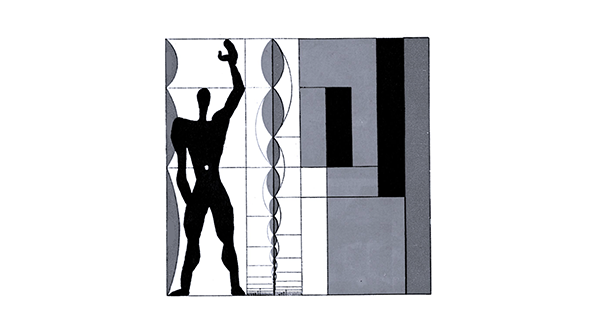
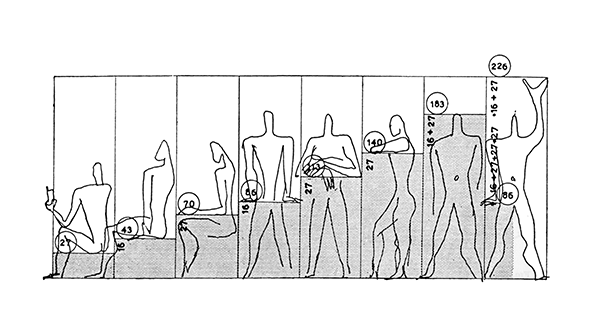 ル・コルビュジエ『モデュロール』
ル・コルビュジエ『モデュロール』
モデュロールは、人間の身長とヘソの位置、そして手を上げた高さなどが黄金比になっているとして、これらをフィボナッチ数で分割して作った寸法体系です。ル・コルビュジエはこのモデュロールをもとに、建物だとか家具だとかを作りました。このモデュロールにおける黄金比のように、なんらかの調和する比率をもとにスケールを作り、そのスケールをタイポグラフィのガイドラインとしよう、というのがモジュラースケールの考え方です。
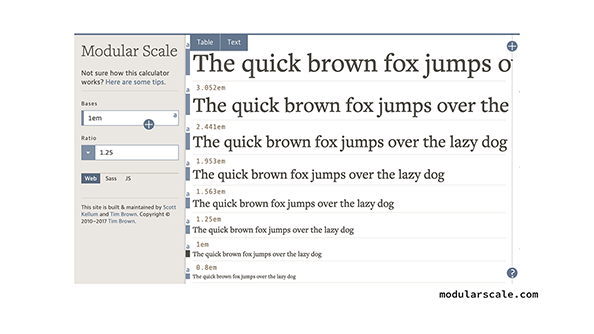 “Modular Scale※4”
“Modular Scale※4”
実際にモジュラースケールを作る場合、最初に基本となる文字サイズを決定します。まずはウェブブラウザのデフォルトである16pxとしてみます。次に、その基本サイズに掛け合わせる比率を決めます。ここでは1.25としています。この比率が大きいほど、文字サイズ間の差が大きくなる、いわゆるジャンプ率が高くなるということになります。その結果このような一連のサイズが得られるので、この中から各要素に適用するサイズを選びます。たとえば本文が16pxで、大見出しが39.0625px、キャプションは12.8px、という具合です。
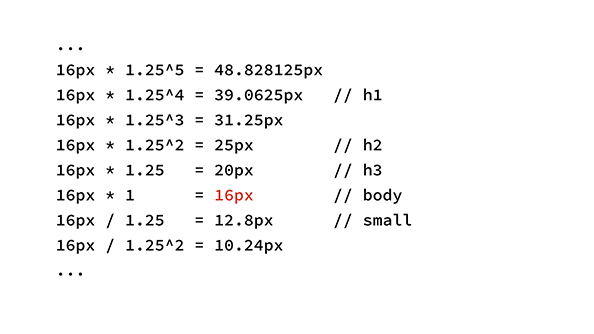
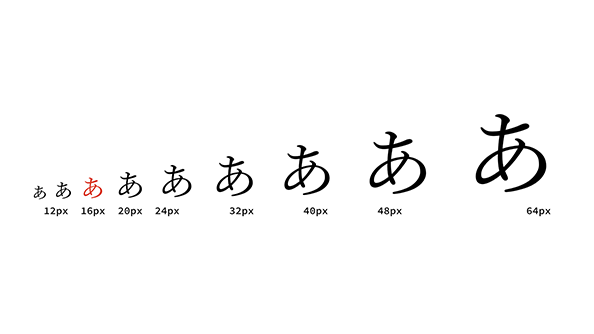
こうして見ると小さいサイズから大きいサイズまできれいに並んでいるように見えます。しかし、実際にこのスケールを使ってみると、あまりうまくいかない。とくにベースの本文サイズの周辺にバリエーションがないと使いづらい。ではベースのサイズに掛け合わせる比率をもっと細かくすればいいかというと、今度は大きいサイズで選択肢が増えすぎてしまって、サイズ間に差が生まれにくいスケールになってしまいます。
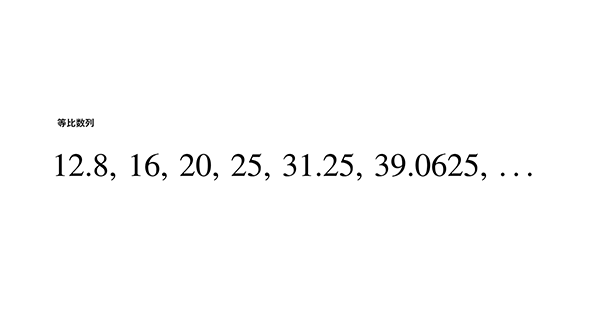
いま作ったモジュラースケールは、ベースの文字サイズに対して一定の比率を掛け合わせてできた「等比数列」です。これは隣り合う項の比率がつねに等しい数列。どうもこの等比数列が、文字サイズのスケールには合わないのではないか。そこで登場するのが「調和数列」です。
調和数列というのは各項の逆数を並べると等差数列になる数列です。ピタゴラス音律や倍音など「ハーモニー」に関連していることから調和数列という名前で呼ばれています。
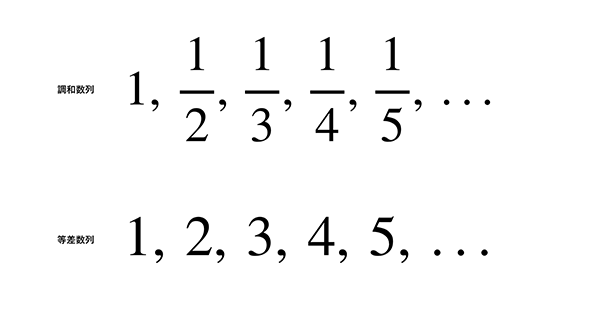
数学的な定義から見ていくと、図の上が調和数列、下が等差数列です。調和数列の例は1、1/2、1/3、1/4というように、分数のかたちをしています。これらの分数の逆数、つまり分子と分母をひっくり返すと、下の等差数列になります。等差数列というのは隣り合う項の差がつねに等しい数列です。この例では1、2、3、4と隣り合う項との差がつねに1です。このような等差数列の各項の逆数を並べると調和数列が出来上がります。この調和数列は、音楽に由来するものです。
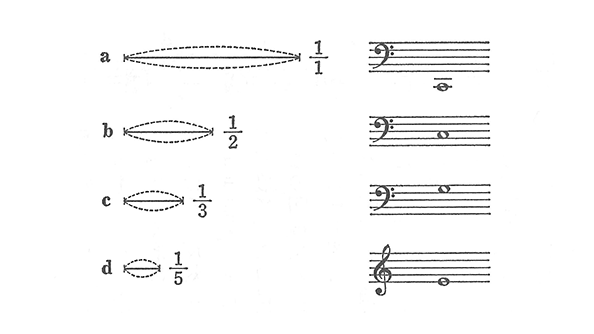 調和数列と音程※5
調和数列と音程※5
ギターやヴァイオリンといった弦楽器を想像してみてください。ある弦の開放、つまりフレットを押さえずに弾いた音が「ド」だったとします。次に、弦の長さの半分のところを押さえて弾きます。すると弦の音の鳴る部分の長さは1/2になる。これが何の音になるかというと、さきほどの「ド」のオクターヴ上の「ド」の音になるのです。今度は弦の長さの1/3のところを弾く。すると「ソ」の音になります。このように弦の長さを1/2、1/3、1/4というふうにどんどん短くしていく。こうして得られた音と弦の長さを並べると、下の図のようになります。
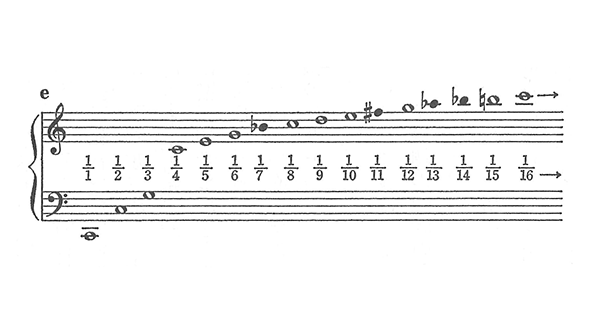 倍音列
倍音列
この音階は「倍音列」と呼ばれるものです。楽器や人の声は、たとえば「ド」の音を出していてもドの音だけが鳴っているわけではなくて、同時に色んな音程の音がごく小さく鳴っている。このように基準となる音のほかに鳴っている音のことを倍音といいます。この倍音のうち、どの音が大きくてどの音が小さいかといったことが楽器によって異なり、それが音色に関係してきます。さきほどギターの弦の押さえるところを変えて得たこの音階が、まさにこの倍音の構成になっているのです。
また、この倍音列の構成音を順に見ていくと、低い方から順にド、ド、ソ、ド、ミとなっていて、「ドミソ」という音のグループが表れます。このドミソというのはCメジャーのコード(和音)の構成音です。これはギターでまず最初に習う基礎的なコードです。
つまり倍音というのは、ある音を鳴らしたときにかすかに鳴って豊かな音色を作るものであると同時に、それらを抜き出して同時に鳴らせば美しく調和する和音のもとになるのです。そういった理由で、このギターの弦の長さにあたる1/2、1/3、1/4という数列は調和数列と呼ばれています。
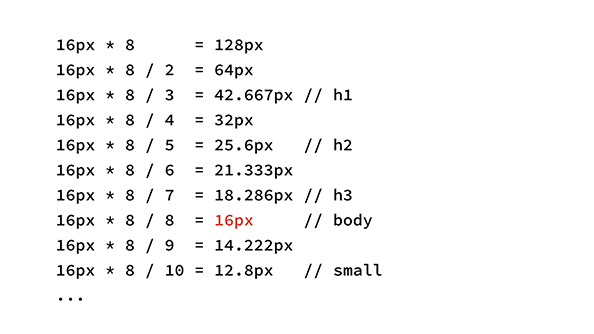
この調和数列を文字サイズのスケールに当てはめてみます。基準の文字サイズ16pxに1/2、1/3、1/4という分数をそのまま掛け合わせると、小さいサイズしか得られませんので、さらに一定の整数を掛け合わせます。ここでは8を掛けていますが、この数字はなんでもかまいません。この数字が小さいほどスケールは大雑把になり、大きいほど目が細かくなります。
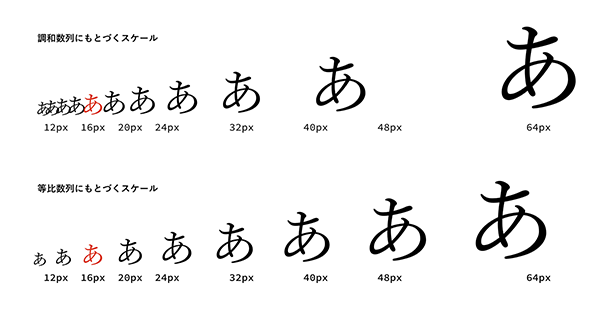
この図の上が「調和数列にもとづくスケール」で、下が「等比数列にもとづくスケール」です。調和数列のスケールはサイズが小さいほど密で、大きいほどまばらになっているのがわかると思います。等比数列のスケールにあった、さきほどのベースサイズ周辺のバリエーションが足りないという問題が解消されました。
調和数列をもとにした文字サイズのスケールにはもうひとつ特徴があります。それは日本語や中国語など、全角文字を並べたときに、図のように数文字ごとに幅が揃うということです。たとえば、本文8文字と、見出し3文字、キャプション10文字が同じ幅になる。
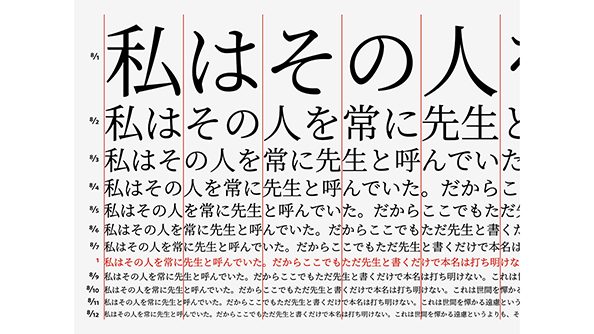
ハーモニーの例として、文字サイズのスケールに調和数列を応用する手法をご紹介してきました。しかし、調和数列にもとづいているからこれは美しい、読みやすいなどと因果を逆転させることはできません。重要なのは、それぞれのサイズが意味ある比例にもとづいた秩序でデザインされているという事実なのです。
リズム
次にリズムです。リズムはあらゆる音楽の出発点であると言われ、まさに音楽の核をなす要素です。音楽というのは時間の芸術です。リズムが止まるとき、音楽もまた止まります。またハーモニーやメロディのない音楽は想像できますが、リズムのない音楽というのは想像できません。たとえばアンビエントとかフリージャズとか、明確なビートがなかったり、ビートが不規則だったりするとしても、それが音楽である以上は必ずリズムが存在しています。
タイポグラフィには縦のリズム、「ヴァーティカル・リズム」という概念があります。これは横組である欧文のタイポグラフィに由来する概念で、行の折り返しによって生まれる行間や、要素間の余白に一貫性があるかどうか、という視点です。この縦のリズムに規則性がないと、読みづらかったり、情報のヒエラルキーが正しく伝わらなかったりします。これはビューが縦方向に長くなるスマホではとくに重要な視点です。本の組版では本文(ボディテキスト)の行送り、CSSでいうところのline-height(行の高さ)が縦のリズムの基準になります。
たとえば、このようなページなどの本文部分。本文の行送りが28pxだとしたら、段落間の余白はその1行分の28px、中見出しの上は2行分の56pxアケる、といった具合です。しかし実際のウェブサイトやアプリケーションでは、このようなシンプルなビューだけではありません。
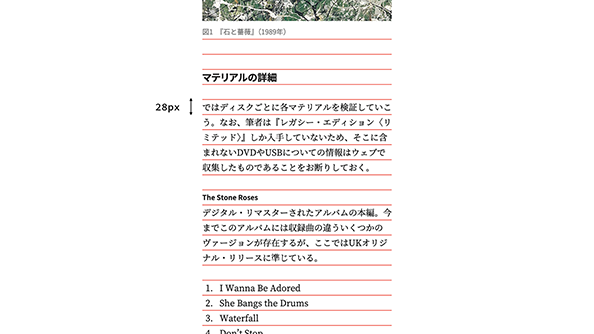
次の例は、ニュース記事などで使用されるカード型のUI(ユーザーインターフェース)。この小さなカードの中だけでも複数のサイズのテキストがあり、情報の主従関係や重要度といったヒエラルキーがあります。またカードを複数並べるときのカードどうしの余白や、見出しの上下の余白などにも注意を払う必要があります。この場合、本文の行送りだけを単位にしていては、とてもレイアウトできません。

ではどうするかというと、リズムを構成するビートを細かく分割して、状況に応じて組み合わせるのが有効です。いわばシンプルな4ビートだったのを16ビートにするような、そんなイメージです。テキストの行送りは4px単位、コンポーネントのスペーシングは8px単位、そしてさきほどのように本文は行送り単位、という3つのスペーシングユニットを組み合わせる手法を紹介したいと思います。
4pxグリッド
まず4pxグリッド。これがすべてのリズムの最小単位になります。これはテキストの行送りに適用します。つまり、すべてのテキストのline-heightの計算値が4pxの整数倍になるようにします。
カード型のUIを例に考えてみましょう。ここにはラベル、タイトル、ディスクリプション、メタデータといった、文字サイズの異なる要素が並んでいます。
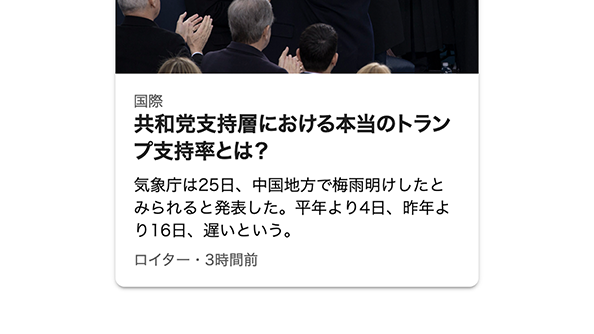
これらをこのように、すべてのテキストの行送りを4px単位に揃えます。最小単位は必ずしも4pxでなければいけないわけではないですが、計算のしやすさや、最適なサイズを考えて、取り扱いやすい4pxを行送りの単位としてみました。
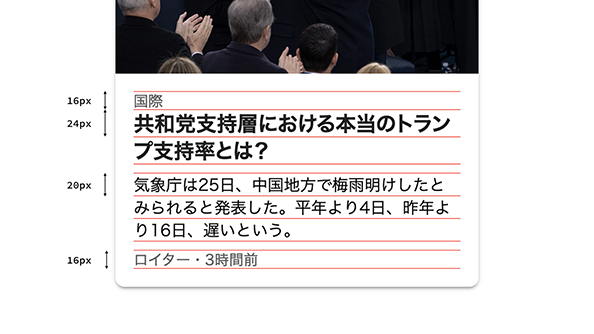
CSSでは、すべてのline-heightが4pxの整数倍になっています。
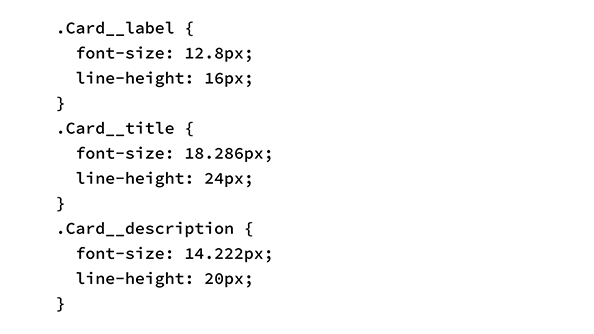
8pxグリッド
次に8px単位のグリッド。コンポーネント内のスペーシングや、コンポーネントどうしのスペーシングが8pxの整数倍になるようにします。とは言え、8px単位でどのように配置してもいいとなると、システムとして一貫性のないものになってしまいます。そこでさきほどの文字サイズのスケールと同様に、あらかじめ使うべきスペーシングを「スケール」として定義しておくのがよいでしょう。

たとえばさきほどのカード型のUIが並んだ画面。見出しの上下のスペーシング、カードどうしのスペーシング、カード内のテキスト間のスペーシング、それらすべては互いに影響しあって情報のヒエラルキーを表現しています。これらを8pxを単位に配置するとき、どのようなスペーシングのスケールを定義すべきかについて、いくつかのパターンを考えてみたいと思います。
もっともシンプルなのは、8pxを2倍、3倍、4倍……と大きくしていくパターン。その結果出来上がるのは8px、16px、24px……というスケールです。
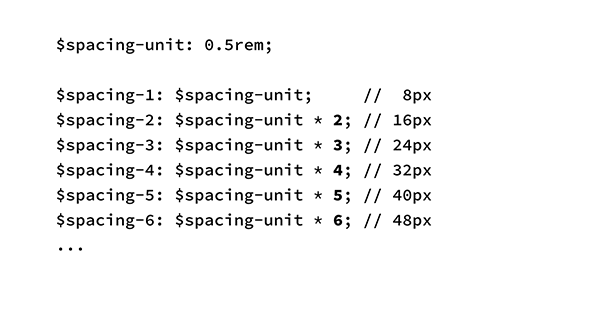
このスペーシングを図にするとこのようになります。これでは大きいサイズになったとき、スペーシング間の差があまり感じられず、コンポーネントによって使うスペーシングにばらつきが出てしまいます。
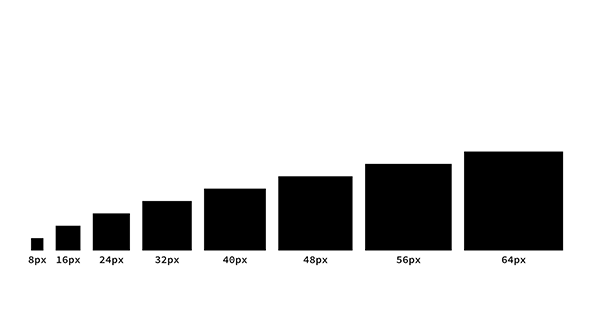
次に8pxのユニットを16px、32px、64px……と2倍に増やしていくスケールです。これでは差が極端になって、実用性がないのがひと目見てわかります。
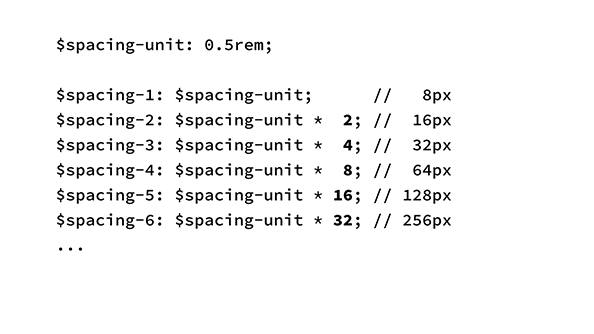
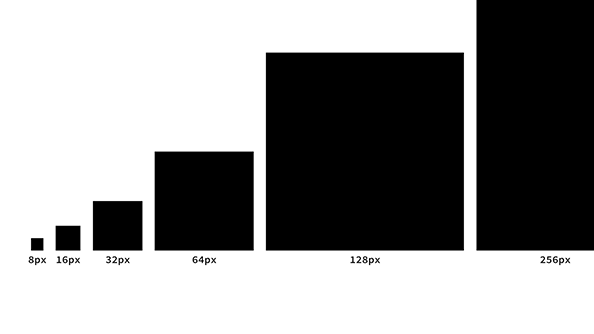
スペーシングスケールの最適化
どのようなスペーシングスケールが最適なのか。それは8pxのユニットに1、2、3、5、8、13というフィボナッチ数を掛け合わせていったものです。
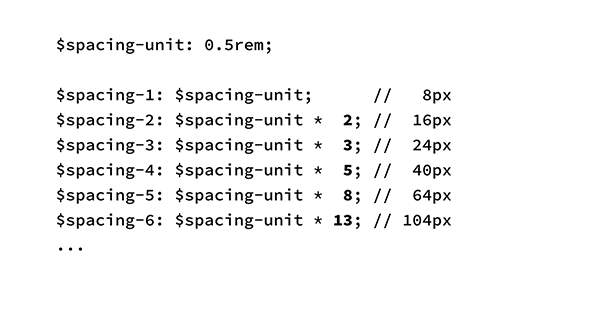
フィボナッチ数列は、1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, …と続き、各項の値が前の2つの項の合計になっています。そして隣り合う項の比率がどんどん黄金比(1.618)に近づいていくという特徴があります。
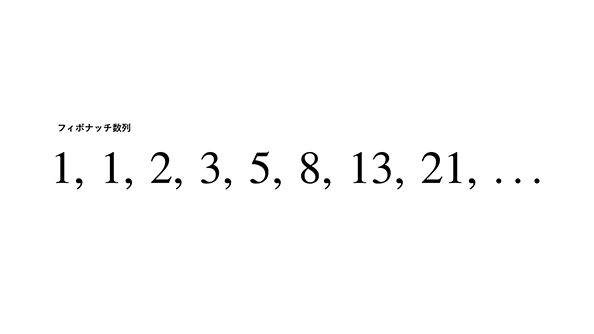
フィボナッチ数を使ったスペーシングのスケールを利用すると、サイズ間の差が大きすぎず小さすぎず使いやすい。
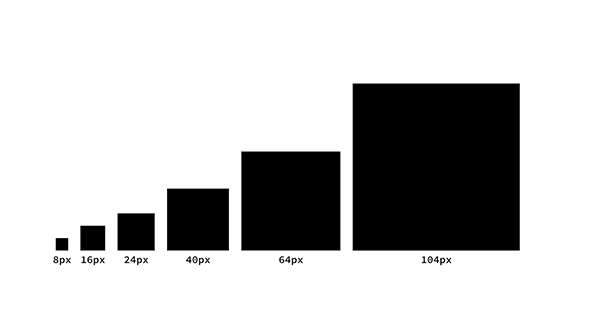
さきほどのカードUIの例に、8pxにフィボナッチ数を掛け合わせたスケールでスペーシングを構成してみるとこうなります。
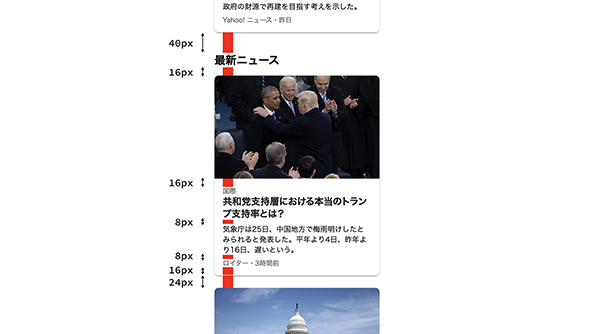
本文の行送りだけですべてのリズムをコントロールするのは無理があるので、いくつかのスペーシングユニットを組み合わせること。また、ただユニットに沿わせるだけではなく、そこに一貫性を持たせるためにスペーシングスケールを作ることが、タイポグラフィにおける縦のリズムにとって大事なのです。
メロディ
最後に音楽の3要素の3つめ、「メロディ」について。メロディの語源はギリシャ語で「歌うこと」を意味する「メローディア(melōidíā)」という語で、このメローディアという語はさらに「歌(mélos)」と「詩(ōidḗ)」という2語の合成語です。音楽のルーツがどういうものであったのかということについては諸説ありますが、メロディは語源に「詩」があり、どうやらそのルーツは「言葉」なのがわかります。まず伝えるべき言葉があり、それに節をつけて歌ったものがメロディなのです。
ここでの結論は単純です。メロディのルーツが言葉であるように、タイポグラフィにとってもっとも重要なものも、やはり言葉ということです。どのようなタイポグラフィも、伝えるべき言葉が最初にある。言葉で書かれたコンテンツを届けるということは、歌手が歌うということであり、ピアニストがソロを弾くということです。そのときタイポグラフィに求められるのは、そのメロディを力強いリズムと美しいハーモニーで支えること。よい伴奏者、優れたバックバンドであることだと思います。
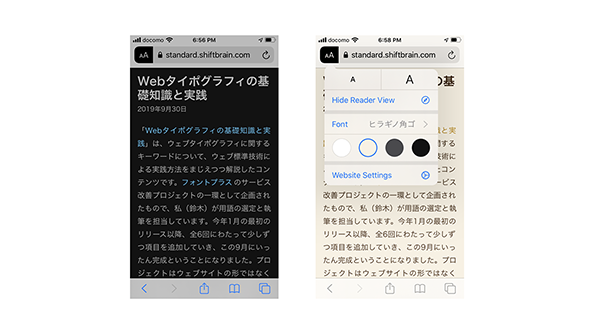
この画面は、iOS Safariのリーダービューです。ウェブサイトのスタイルをプレーンなかたちにリセットして、書体、文字サイズ、カラーなどをユーザーが選択して読むことができます。同様の機能はChromeやFirefoxなど多くのウェブブラウザで、モバイルでもデスクトップでも提供されています。このようなビューでは、デザインしたタイポグラフィが無効になるわけです。
しかし、これこそがオンスクリーンメディアにおけるタイポグラフィのもっとも素晴らしい点です。ユーザーにとって読みにくい書体があったり、見えにくい色があったりしても、その障害を乗り越えてコンテンツを届けられる可能性がある。そして、このようなアクセシビリティを支えているのがHTMLというものです。コンテンツが適切にマークアップされているから、アクセシビリティの提供が可能になる。
それなら最初からユーザーにすべて設定させればいいじゃないか、と思う方もいらっしゃるかもしれません。たしかにすべての人にとって読みやすいタイポグラフィは不可能かもしれませんが、それでもタイポグラフィを追求することには意味があります。
開かれたタイポグラフィのために
タイポグラフィには文字によって情報を伝達するという明白な義務がある。いかなる議論や考察も、タイポグラフィをこの義務から解放することはできない。読むことができない印刷物は、目的を失った制作物である。
エミール・ルーダー『タイポグラフィ※6』
これはエミール・ルーダーが印刷物のタイポグラフィについて語った言葉ですが、オンスクリーンのタイポグラフィにも適用できます。すべてのタイポグラフィは、より多くの人に、より間違いのないかたちで、よりわかりやすく、そしてより美しく「伝える」ためのものなのです。
わたしがオンスクリーンメディアのタイポグラフィに取り組みはじめたときには、音楽や数学の理論を参照するとは想像していませんでした。ここにたどり着いたのは、制作の現場で直面した具体的な課題を解決しようとした結果です。異なる文字サイズのテキストをうまく配置できないかとスケールを試行錯誤するうち、いつしか数列のようなものが導き出され、それはどうやら音楽に由来する調和数列らしいことがわかるといった具合に、少しずつかたちをなしていきました。これは楽典を学んでから音楽を聴きはじめる人がいないのと同じかもしれません。
タイポグラフィの作業をしていると、いつしか偏執的に細部を追求しています。その度に、独りよがりの美意識を読み手に押しつけているのではないか、誰も望まない完璧さを求めているだけではないのか、と不安になります。そういったときに、タイポグラフィの歴史を見つめ直したり、音楽や数学などの知恵から学ぶようにしています。その理由は、すでに完成された世界を新しいメディアで再現したいからではありません。これは、まだはじまったばかりのオンスクリーンメディアのタイポグラフィの可能性を、より開かれたものにするための試みなのです。
1行のコード
ソフトウェアと、それを記述するコンピュータ・プログラムは、今日もっとも身の回りに溢れ、私たちの生活の中に偏在するメディアとなった。コンピュータはプログラムに書かれたコードを翻訳、解釈、実行することで、大量のデータを処理し、その結果を表示したり、コンピュータ同士でやりとりする。人々は、コンピュータのプログラムを作成するだけでなく、ソフトウェアを日常的に使用することで、ものごとの見方や考え方を形作っていく。私たちは、プログラム・コードをつくるだけでなく、プログラムによってつくられている。
プログラムは、コンピュータと人間の双方が理解可能な、人工言語によって記述されている。プログラムはコンピュータと人間のコミュニケーションの記述であり、より一般的には(分析や解釈の対象となる)「テクスト」である。そこには、アルゴリズムだけでなく、プログラム制作の前提、目的、過程、改良の過程が埋め込まれている。さらに変数や関数の名付け方や、アルゴリズムの注釈や解説といったプログラムのアルゴリズム以外の部分にも、さまざまなものごとを書き込むことができるし、逆に人間にとって理解しにくいよう難読化することもできる。プログラムは数学/数値的、論理/構造的な言語であると同時に、文化/人文的、思想/哲学的なテクストでもある。
実用的な、あるいは有用なプログラムの多くは、正しく、効率よく実行すること、あるいは保守や改良、再利用がし易いことが求められている。それらを巧みなバランスで実現したコードはしばしば、コンピュータ・プログラミングの「ART(技芸)」と呼ばれる。しかし、そうした自明な目的や有用な機能がないプログラム・コードでありながら、多くの人に共有されているものも存在する。そのひとつの(代表的であり、極めて早い時期の)例が、「10 PRINT」と呼ばれる1行のBASICプログラムである。
10 PRINT CHR$(205.5+RND(1));:GOTO 10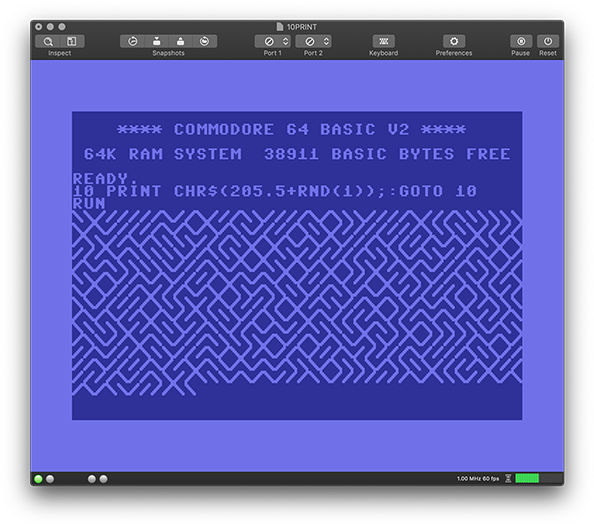 「10 PRINT」プログラムをVirtualC64(Commodore 64のエミュレータ)上で実行している様子
「10 PRINT」プログラムをVirtualC64(Commodore 64のエミュレータ)上で実行している様子
Commodore 64という、米コモドール社が1982年に発売開始した8ビットの家庭用コンピューターで、この極めてシンプルなコードを実行すると、斜め線、または逆斜め線のグラフィック記号がランダムに1つづつ、左から右、そして上から下へと表示されていく。画面が一杯になると2行ずつスクロールし、このプログラムは(中断するまで)永遠にこの表示を繰り返す。当時のコンピュータの速度は遅かったので、記号が画面を埋め尽くすのには約15秒かかる。しかしこのたった1行のコードが、当時のさまざまななパーソナルコンピュータに移植され、さまざまなバリエーションが生みだされた。そして、Commodore 64の誕生から30年を経た2012年、この文化的工芸品としてのプログラムを、ソフトウェア・スタディーズの視点から詳細に分析した本※1がThe MIT Pressから出版された。本のタイトルも『10 PRINT CHR$(205.5+RND(1));:GOTO 10』である。
ジェネリックでないコード
今日の、使いやすく、わかりやすく、役に立つ、そして技芸に優れたソフトウェアからみれば、こんなちっぽけで単純な迷路生成プログラムは、取るに足らないもののように見える。しかしそんな、40年近く前のマイクロコンピュータのための1行のプログラムに対して、今なお多くの人が関心を持ち、議論し、さらには今日のコンピュータにも移植され、さまざな修正版が実行されているのはなぜなのだろう。
まず重要なのは、このプログラムが非常に短いことである(おそらくこれ以上に短いものは、“hello, world” くらいのものだ)。今日の大規模データを活用した計算論的(computational)な文化分析手法(cultural analytics)が、対象そのものに触れることなく、そのマクロな傾向を把握しようとするのに対し、このコードは私たちに、ミクロな「精読」を要求する。しかしその精読は、限られた専門家による精読ではなく、(コードが短いがゆえの)万人に開かれた、そして対象に自由に手を加えることができるような精読である。
伝統的なプログラミングにおいては、プログラムで記述しようとする対象を分析し、それをなるべくシンプルなかたちで抽象し、(人間にとって)わかりやすい形で表現することが推奨されてきた。こうした機能の抽象化によって、コードの汎用性、再利用性を高めたコードを「ジェネリック・コード(generic codes)」と呼ぶとすれば、「10 PRINT」のように、(キャラクター文字を使って迷路のような模様を生成し続けるという)ある限られた目的のために作られたプログラムは、「スペシフィック・コード(specific codes)」と呼べるだろう。
スペシフィック・コードという呼び名は、ジェネリック・コードの対義語であるだけでなく、米国の美術家ドナルド・ジャッドが1964年に提示した「スペシフィック・オブジェクト」という概念にも由来している※2。ジャッドのこの概念は、50年代から60年代に制作された、アメリカ美術の新しい傾向の特徴分析から生まれたものである。「彫刻でも絵画でもない」このスペシフィック・オブジェクトのように、スペシフィック・コードはプログラム・コードであるだけでなく「テクストでもポエトリーでもある」。一般的で汎用のコードは、コードそのものよりも、コードが記述しているアルゴリズムとその実行結果が重要であることが多い。それに対して、スペシフィックなコードは、コードそのもの、そこに何がどのように記述されているのかが重要である。つまり、コードの実行結果(例えば「10 PRINT」が描く迷路自体)だけではなく、コードを実行した主体がその実行をどのように受容(観賞)したのか、コードの実行中に何が生み出されているのか、そしてそれらが指し示しているものごとは何なのか、ということに思いを馳せなければならない。
ミニマルであるが故に、固有のものであると同時に拡張的でもあるスペシフィック・コードは、ユーザーにシステムやツールを提供するのではなく、ユーザーとしての、つまり個人の使用から見たコードの内在的な可能性を探求し、それを限りなく拡げていこうとする。通常のプログラミングにおける有用性や再利用性のような、客観的な価値や機能を実現するのではなく、その意味や価値は状況や文脈(コード以外の環境)に大きく依存している。スペシフィックであるということは、ジェネリックでないだけでなく、それが異質であり、強いインパクトを持っている、ということでもある。
テクストとしてのコード
スペシフィック・コードが現れる代表的な場として、「コード・ポエトリー」と「ライヴ・コーディング」の2つがあげられる。コード・ポエトリーとは、その名前の通り、コードを用いて詩を書くことである。その代表的なサイトの一つである、Source Code Poetry※3には、このような規範が書かれている。
- どんな言語でもいい:あなたが一番好きな言語で書いてください。
- コンパイルできること:とはいえ、インタープリタ言語で書かれたものでも受け付けます。
- 韻を踏むこと:とはいえ、現代の名作は規範を逸脱しています。
このサイトには、さまざまなコード・ポエトリーの作例が掲載されている。中でも、Python言語で書かれたこのMike Heatonの詩はもっとも短いものである。
t = 0
while True:
print("Nothing lasts forever.")
t += 1
「10 PRINT」と同じように、単にテキスト出力を無限に繰り返す(だけの)ものであるが、時間を表す変数名の「t」と出力を繰り返す文の間には、意味の詩的な結びつきがある。
2012年に刊行された「code {poems}※4」というアンソロジーには、55のコード・ポエトリーが掲載されている。これらは、プログラム・コードとして実行するよりもむしろ、テクストとして読まれることを意図している。例えば、Daniel Bezerraの「UNHANDLED LOVE(処理されない愛)」は、C++のプログラムではあるが、その実行結果ではなく、プログラムのエラー管理機能としての「例外処理」が持つ意味を用いた詩である。
class love {};
void main()
{
throw love() ;
}
Richard Littauerの「Import Soul」も同様に、Python言語としての意味とテクストそのもの意味が重ね合わせられている。
# This script should save lives.
import soul
for days in len(life):
print "happiness"
Daniel HoldenとChris Kerrによる、「./code–poetry※5」は、逆にコードの実行結果に着目したものである。そこにはコードの実行時に具体詩、あるいはアスキーアートのような視覚的出力が生まれる、実行詩としてのコード・ポエトリーが数多く収録されている※6。
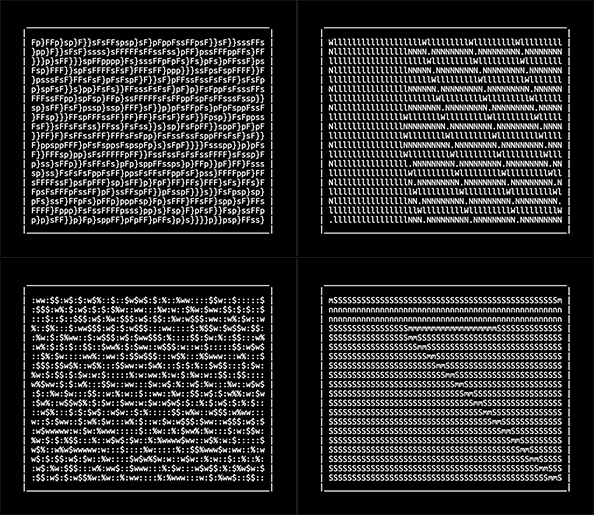 ./code –poetryトップページの「turing.poem」のスナップショット
./code –poetryトップページの「turing.poem」のスナップショット
パロールとしてのコード
ライヴ・コーディングは、プログラム・コードを直接操作しながら行うライヴ・パフォーマンスの総称である。その起源は、21世紀初頭のラップトップ・ミュージック、さらには80年代のFORTH言語の音楽制作への使用に遡ることができる※7。今日のライヴ・コーディングは、Algorave※8というクラブ文化との融合や、プログラミング教育への応用※9など、多様な文化と結びついている。
ライヴ・コーディングのスタイルには、白紙のエディターから始めて、その場で一からすべてのコードを書く人から、事前に用意していたコードのフラグメントを、DJのようにその場で組み合わせていくスタイル(CJ:コード・ジョッキー)まで、さまざまなやり方がある。しかし、基本的にライヴ・コーディングにおけるコードは、音のようにその場で生まれ、その場で消える。コード・ジョッキーのように、事前に準備しておくことはあっても、パフォーマンスの場で一度実行されたコードを、そのまま別のライヴで再利用することはない。
ライヴ・コーディングの場におけるコードの現れ方を、もっとも特徴的に体現しているのが、ライヴ・コーディング運動の提唱者の一人であり、自らが生み出した TidalCycles※10というライヴコーディング言語を用いて行われる、アレックス・マクリーンのパフォーマンスだろう。彼が2018年11月に来日した際に出演した、DOMMUNEでのライヴの様子が以下に記録されている。
YouTube: Alex McLean (Yaxu) live on DOMMUNE Tokyo, 14 Nov 2018
TidalCyclesという言語が、少ない入力で迅速に出力(パターン)を変化できるように設計されているため、アレックスが書くプログラムは決して長くはなく、どんなに長くても数行で、全体が1画面の中に収まる程度である。ライヴ・コーディングにおいては、ディスプレイが身体であり、この身体をパフォーマーと観客が共有することから出発していることを考えれば、常にコード全体を一望できることは、ライヴ・コーディングの演奏者にとっても、リスナーにとっても、重要な意味を持っていることがわかる。
しかし何よりアレックスのコーディングで印象的なのは、コードの入力のしなやかさと、書いたコードを実行し終わるとすぐに消し、新たなコードを次々と書き続けていく、エフェメラルな姿勢である。プログラム言語というと、どうしてもアルゴリズムを正確に記述するラング(規則体系としての言語)を思い浮かべがちだが、アレックスのライヴ・コーディングにおけるコードは、話しことばとしてのパロール(個人的な発話)である。コード入力の行き来はアレックスの思考の構造を垣間見せ、カーソルの揺らぎはアレックスの思考の状態を反映している(ように見える)。このパフォーマンスでは、映像のちょうど18分のところで突然コンピュータがクラッシュし、再びそこからライヴを再開するのだが、そんなハプニングも決してエラーやミスには感じられない。日常の会話においては、言い直したり、中断する(させられる)ことは茶飯事である。パロールとしてのコードは、スペシフィック・コードのもうひとつの重要な特徴である。
通気口としてのコード
ソフトウェアが日常のインフラストラクチャーとなり、スマートフォンが生活の日用品となった今、それらは生活の中で、ますます見えなくなっている。人間は、スマートフォンを運ぶメディアとなり、人々のものの考え方や行動は、暗黙のうちにソフトウェアによって操作管理されている。冒頭で述べたように、プログラム・コードは確かに人間がつくったものであるが、逆にプログラムによって人間なるものがつくられている。
そうした状況の中、個人、あるいは市民としてのエンドユーザーが、自らの手でプログラムを書き、それを実行することに、一体どんな意味が残っているのだろうか。本稿で取り上げたいくつかのスペシフィック・コードは、
- 極めて短いミニマルなコード
- 正しさよりも大切なものがあるコード
- アルゴリズム以外の部分も重要なコード
- 環境や文脈に依存するコード
- 実行する必要のないコード
- 話し言葉のように生成され消滅するコード
といった特徴のいくつかを持つ。それはいずれも、IT/SNS企業やエリートハッカーのように超越的に見える何者かが提供してくれる、使いやすく、わかりやすく、役に立つものとは違うかもしれない。しかしスペシフィック・コードは、自分でつくり実行するものであり、変更できるものであり、他の人たちと共有できるものでもある。その意味で、スペシフィック・コードは、究極のエンドユーザー・プログラミングであり、今日の資本主義と監視社会の中で、個人が自由に息をするための、通気口のひとつにもなる。だから僕自身、個人が生き延びるための通気口としてのスペシフィック・コードを書き、そのことについて、もうしばらく考え続けたいとも思っている。
はじめに
本稿では、イギリスのタイポグラフィ専門雑誌『フラーロン(The Fleuron)』誌を探ってみる。その活動期間は、1923年に発行開始し1930年までと短く、ほぼ1年に1号発刊という計画で、7号目で幕を下ろした。その発刊の経緯と編集方針、同時代へのタイポグラフィを巡る視点を調べ、その後の雑誌類への影響を比較し、現代に残したその意義を考えてみる。
なお、本稿をまとめる前に、筆者はこの雑誌の体裁上の解剖を試みた。つまり、印刷部数、判型、本文組版、扉と目次、ノンブルと柱、内容構成、執筆者とその特徴、広告主、資金調達、定価設定、編集者による執筆者の選択、内容構成上の差異などを調べたが※1、ここではそれを踏まえている。
日本でいえば大正12年から昭和5年までの間に、ロンドンで発行された『フラーロン』は注目されることが少ない。この雑誌に掲載された論文内容と発行を支えた人物の行動は専門的かつ地味であるために、日本ではその存在はごく一部でしか知られていない。例えば英文学者の小野二郎氏が『書物の宇宙』の中でわずかに紹介しているに過ぎない。その後は『欧文書体百花事典』に多少のスペースを割いて紹介がある。その他の日本で発行されるデザイン関連やタイポグラフィ関連の雑誌などでの言及は、不思議なことに筆者の知る限りでは皆無である。タイポグラフィがグラフィック・デザインと切り離されてきている事実がうかがえる現象だ。
革命的な電子技術が進む現代にあって、『フラーロン』の志向と姿勢は何を示唆するだろうか。意欲的な評論・論考集として再評価されることがあるのだろうか。時代との格闘から生まれたこの雑誌をたどってみる。
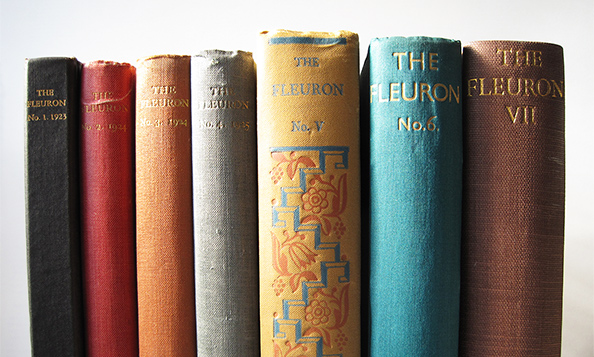
1. 時代状況(19世紀末から20世紀初頭)
ヴィクトリア朝のタイポグラフィ
19世紀のイギリスの印刷業を席巻した現象は、いわゆる「ヴィクトリア朝のタイポグラフィ」と呼ばれた印刷物と活字の暴発現象である。19世紀は「世界の銀行」「世界の工場」と呼ばれたイギリスが最も活力を発揮した時代で、世界の経済を支配したと言われる。植民地政策と産業革命後の経済的な果実に酔いその隆盛を謳歌していた64年間の時代にあって、その時期のタイポグラフィは旺盛な商業活動を支援するための商品・製品の宣伝活動による激しい競争から出現した。時代の息吹を遺憾なく発揮したこの状況を「ヴィクトリアン・ディライト(Victorian delight)」と表す言葉もあるほどで、社会はこの高揚した雰囲気を受け入れていた。
さらに品物や催し物の情報を多くの人々に伝えるためには大声が有利であることから、文字情報はその声を代弁して特大サイズや極太の特製の奇妙な文字で訴求された。それは活字の乱舞とも呼べる様相を呈し、文字活字による乱雑・強烈な視覚の衝撃を意図した印刷物を輩出したこの時代を如実に物語っている。その様式は雑誌や書籍の一部にも影響を与えて、タイポグラフィの伝統が崩れて品性を欠き、粗製濫造気味の活字や印刷紙面が急増し、識者の苦言を許す、という混沌とした状況にあった。そこでこの動きに異議を呈し危機感を抱いたことで起きた動きが、印刷改革や手工芸的な意義の復活だった。これは同時並行的にいくつかの緩やかな組織的行動としての批判的な提起だった。
アーツ・アンド・クラフツ運動
19世紀後半のイギリスでは、アーツ・アンド・クラフツ(以下、A&C)運動が起こった。その理由は大きく分けて3つあるとされる。
- 遠因として、ジャン・ジャック・ルソーの思想への共鳴がある。
- 機械生産による製品の質の低下への不満が起こった。
- 懐古主義への傾斜が高まった。
ルソーとの影響関係については、筆者は未調査のため、言及は避ける。この運動への直接の影響を与えた人物はピュージン(1813–52)とジョン・ラスキン(1819–1900)で、両人は中世芸術を讃えてゴシック様式の復活いわゆる「ゴシック・リヴァイヴァル」を唱道した人物だ。彼は1871年に「セント・ジョージ・ギルド」を構想して理論を実践に移したことで知られ、教育面で貢献したと言われる。彼にとって装飾とは神の啓示を受けた自然の豊かなフォルムの再現であり、その自然観は「芸術のための芸術」という芸術の理念との密接な関係を推進する核であった。後に社会改革に強い関心をもち、道徳観を重視した。そこから機械依存の大量複製への嫌悪を抱いていた。また、これらの動きに加えて、1884年に「アート・ワーカーズ・ギルド」の設立を試みる。これはアート(美術またはその技芸)とクラフト(工芸)の展示発表を進めるという組織だったが、ギルドという語は、そのまま中世への志向を強く暗示する響きだったことだろう。
ラスキンの考えに影響を受けて、実践面で誠実に実行したのがエメリー・ウォーカー(1851–1933)だった。書籍やアートに関しての博識さにおいて彼を凌ぐ者はいなかったほどだったと言われている。そのウォーカーの刺激と支えにより、ウィリアム・モリスは最後の華を咲かせた。モリスはいくつかのアートを実践した後にたどり着いた総合的な成果を発揮できる分野として、書籍製作に取り組み、ケルムスコット・プレスを開設して、晩年の時間を注いだ。モリスの製作した書籍は、その判型の大きさと材質の贅沢さ、独自の活字書体の使用で存在感を示していた。
また、A&C運動は欧州の一部の動きとも関連があるだろう。例えば20年ほど続いたドイツのアール・ヌーヴォも改革運動としてあり、日常生活の中での芸術の必要性を訴えた。この運動は具体的には有機的な自然観を基本とした植物の造形を生活の身辺に散りばめる装飾賛歌であった。いわば、近代の夜明けを喜ぶどこか無邪気で純粋で遊戯的な趣向の発露に見える。建築デザイン、書籍、活字書体では装飾的な造形言語という新しい思想の登場を見たし、生活を美的に形作ることを目指した。エックマンやベーレンスが設計した活字書体は、独特な曲線とブラックレターが融合していた。
だが第1に、それはタイポグラフィという長い歴史的な観点からするとその影響力と説得性はわずかであり、現在では実験的な試みと言える。第2に、時代への批評というよりは提案であり、強いカウンターとは言えない。とはいえ、この時代の活字書体におけるブラックレターとの関連では、この「有機的自然観」はドイツの狂った悲しい時代を覆った見えにくい裏のキーワードであろう。いずれこの点は追求したい。
私家版運動
日本ではおおむね「私家版印刷所」との訳語が定着している「プライヴェット・プレス」は、個人規模での印刷・出版活動の拠点として位置づけられている。私家版印刷所の定義については、マルティン、クローディン、ポラードなどという書誌学系の権威者による試みがあるが、その見解は微妙に異なるので、彼らの定義での共通項目をまとめてみるほうが分かりやすい。つまり「私家版印刷所の運営形態は個人または少人数によって所有されて使用される規模であり、その製作物は独自の主張や理念や趣味に基づいた書籍が主体である」と定義してみる。
私家版印刷所の一般的な特徴は次のように3つあるだろう。
- 印刷所の所有者の趣向・主張が、その印刷物(多くは書物)の全体に明瞭である。
- 印刷所の所有者自身の著作よりは既存の文芸作品を書籍化する。
- 印刷所の所有者は印刷の実践家であることが多く、印刷機やその操作にも詳しく、印刷用紙・活字書体・製本材料および製本様式についても独自の観点から選択する。場合によっては活字書体にこだわって独自の書体を製作することもある。
以上のことから、企画発案者と製作者が同一人あるいは同僚同士であり、作業の分業化が少ないことが、商業主体の印刷出版と異なる点だとわかる。だがまた、簡易様式の印刷物も多く印刷発行したことも事実だったようで、必ずしも書籍に限定しないという見方もできる。何れにしても、「年金受給者の暇つぶし」だと揶揄されることもあったほど趣味的要素が強い。
私家版はイギリスで1757年ころに設立されたホーレス・ウォルポールによるストロベリー・ヒル・プレスが最初とされる。ウォルポールは大物政治家の息子で、自身も政治の世界に踏み込んだが、(イギリス絵画の庭園に関する)歴史家、詩人、小説家、劇作家、論説者、古物収集家、印刷人などと多方面に手を広げた。また、彼につけられた肩書きは、「美の判定者」だった。
その他の主な私家版印刷所またはそれに準じる印刷所が20以上挙げられるが、そのうちよく知られた名前を挙げてみる。チャールズ・ウィティンガムが設立してその甥で同名の人物がウィリアム・ピカリングと手を組んだチジック(チズウィック)・プレスを皮切りに、20社近くが生まれている。チジック・プレスの活動は1844年にイギリスを代表するオールド・ローマン体活字のキャズロン書体を復活させたことで名を知られている。さらには、蔵書6万冊を誇る世界有数のミドル・ヒル・プレス、珍しいところでは農民だったチャールズ・クラークのグレート・トーサム・プレス、神学博士によるダニエル・プレス。
また、19世紀後半になるとローレンツ・シェパードという尼僧によるスタンブルック・アビィ・プレスが異彩を放って、その後引き継がれておよそ100年間活動を継続させた。芸術家に依頼して作らせた木版彫刻をイラスト図版として印刷に多用したヴェイル・プレスや、ウォーカーの指導のもとにジョーン・ホーンビーが設立したアシェンディン・プレスが、50部程度の印刷数とはいえその存在を際立たせていた。そして、私家版の仕事をひとつの社会運動のようにその影響を誇ることになったケルムスコット・プレスが登場する。1900年にはウォーカーとコブデンサンダースンによるダヴス・プレスの設立をみる。
『フラーロン』の発行前後にも個人的な印刷所が数社現れて、賑やかな様相を呈している。中でもギヴィングスらのゴールデン・コッカレル・プレスはその組版と印刷の質の高さで群を抜いていた。彼らは「書籍の印刷と出版のための共同社会」という理念を基に、優れたタイポグラフィの実現という夢を抱いて、安価な書籍の提供を目指して設立した。
カトリックへの改宗
西洋の出来事を語るには宗教を切り離せない。イギリスでは国教会(聖公会)という、新教と旧教の中間的性格を帯びている宗教が支配している。中世の複雑な事情が関わって、教義はカトリック式ではあるがプロテスタントに近いという信仰形態が支配的である。何事にも極端を嫌うイギリス人気質が影を落としているようである。宗教改革以来イギリスではカトリック信仰は違法だった。
19世紀になってカトリック教徒が法的には差別から解放された。国教会の刷新を目指すオックスフォード運動や中世志向のラスキンの行動もあって、19世紀中頃から著名人のカトリックへの改宗が続いた。たとえば先に挙げた建築家のピュージンをはじめ、劇作家のワイルド、画家のビアズリーなどで、20世紀でも作家のチェスタトン、グリーン、詩人のエリオットなどもいた※2。タイポグラフィ関連では、エリック・ギルもハリー・ペプラーも1910年代に改宗している。そしてこの改宗は時代の動きを象徴してもいた。「社会主義とカトリック信仰は、相互に影響し合い、強化し合ったとされる。産業主義(資本主義)の矛盾に対して社会改良を目指すという方向性で、両者は一致※3」して、芸術や工芸の実践への背景として時代を揺るがしていた。
カトリックへの傾斜は、製作物に反映したという。「アーツ・アンド・クラフツ運動とキリスト教、とくにカトリック的な傾向とは親和性があったが、アーツ・アンド・クラフツ運動の成果として登場した私家版運動で刊行された作品にも、そういった傾向のタイトルが目立つ※4」という指摘があり、絵画や挿絵を偶像崇拝につながるとみなすプロテスタントとは異なって、「私家版のほとんどが旧約聖書に基づいている※5」ことでカトリック的な傾向がうかがえるとのことだ。たしかに豊かな装飾性とカトリックとは教会建築にも深いつながりがうかがえる。書籍印刷という広い意味での造形行為の裏にも、宗教が隠れているのだろう。興味ある指摘だ。
また、本テーマの中心人物の一人スタンリー・モリスンは、19歳でカトリックに入信している。彼の母親が資本主義への嫌悪を露にした理神論者で、社会主義思想に共感したことで、その影響が色濃いとされる。彼はプロテスタントではなかったので改宗ではないが、カトリックに共感した。
新タイポグラフィ運動
『フラーロン』誌が閉じられる頃、大陸では先鋭的な新タイポグラフィ運動の胎動があった。ヨーロッパでは新しい職種を確保しようとして活動を始めた美術系(アート志向)のグループが躍り出た。そのグループは後には商業印刷の分野に進出し、グラフィック・デザイナーと呼ばれた。旧来のままで工夫が見られないような印刷物の停滞状況に対して人々の感性に鮮明な造形で訴求することを目指す新しい職種がドイツを中心に動き出した。
イギリスの産業革命が遅れて波及したドイツでは、印刷所の内部で行われていた組版作業を新しい考えで人々の前に提出し、社会との関連を意識したいわゆる「デザイン的思考」に基づく業種の必要性が叫ばれた。大量消費に裏付けられた大量生産方式という工業化社会の原則には、製造現場での部品類の規格化が必須であった。それには同時に単純化を求められた。工場では流れ作業による製品加工が主役となり、単純な作業と単純な部品の積み重ねが製造工程を支えた。そして、時間の短縮と経済性が結び付けられて、直線的なスピード感と鋭く明快な造形が好まれる傾向が顕著になり、グラフィック・デザイン上でもそれを反映した幾何学的なサンセリフ(ジオメトリック・サンセリフに分類される)が編み出された。この書体群がポスターなどの図案における文字類の大胆な配置に適合したことで、視覚上の斬新な衝撃を伴った力強いデザインが躍り出た。
この動きは、やがて革命後のロシア、オランダ、ポーランドやチェコなどにも広がった。構成主義であり、「新タイポグラフィ運動」であり、イギリスはこれらにほぼ無反応を装ったことが特徴的である。この運動の主導者はマックス・ビルやヤン・チヒョルトだった。これはやがて「モダン・デザイン」という風を起こす契機となったが、その中心地はスイスへと移っていった。
そして1950年代後半から洗練されたサンセリフ書体の登場が登場する。ジオメトリック・サンセリフの冷たさと可読性への疑問から、ネオ・グロテスク系書体が誕生し、モダン・デザインを支えた。このサンセリフを主とするデザインが機能主義と結びついて装飾性が雑音として徹底的に排除され、消毒したような潔癖さが印刷デザインを席巻する。これはプロテスタント系に特有の体裁と言える。ドイツやオランダで顕著な動きが見られた。
見落としてはならないことは、この運動が商業活動を支援する技能として認識されていたことだ。それはあくまで広告分野でのデザインの刷新であり、大胆で自在なレイアウトを提示し言葉(文字活字)とその自由な配置(例えば紙面を大胆によぎる斜めの配置)や罫線による誘目性の発揮にあり、文芸・科学・そのほかの論文類や著述による長文のテキストを主とする書籍・雑誌には対応し難いデザインであった(チヒョルトは後半生でそのことを痛感した)。いわばその内実は「商業美術」「広告図案」などという和訳語が当時の日本で使われた部類であり、タイポグラフィの根本からの刷新とは言い難い現象だった。だがその言葉の意味をいっそう増幅してコノテーションを強調する刹那的で強烈な一撃は、一種の視覚上の圧力によって物欲を刺激することで成立する消費行動への誘導という広告の基本原則と合致して、その影響を無視できない。刺激はさらにいっそうの強い刺激を無限連鎖的に要求する本能的欲求があることから、この紙面刷新はやがてアメリカで1960年代に心理学の援用でまとめられた広告理論の成立に、なにがしかのヒントを提供したのではないかと推測できる。
2. 雑誌『フラーロン (The Flueron)』の発行へ
フラーロン協会
『フラーロン』が発行される前年の1922年夏の終わりには、「フラーロン協会(The Fleuron Society)」というグループが結成されて、活動の話し合いが行われている。だがこの会はそれに先立って、30歳代前半と20歳代前半の2人の男の出会いから始まっていた。この会の主唱者である1人はオリヴァー・サイモン(1895–1956)で、ヘラルド・カーウェン(1885–1949)が興したカーウェン・プレスの一員であった。もう1人が当時クロイスター・プレスに席を置いていたスタンリー・モリスン(1889–1967)だった。
 オリヴァー・サイモン
オリヴァー・サイモン
 スタンリー・モリスン
スタンリー・モリスン
2人の呼びかけに応じて集まった会員は、一家言をもつ3人だった。月刊文芸雑誌『ツデイ(Today)』の編集者だったホルブルック・ジャクスン(1874–1948)、当時ペリカン・プレスの主宰者だったフランシス・メネル(1891–1975)、アーデン・プレスやシェイクスピア・ヘッド・プレスの設立者バーナード・ニューディギット(1869–1944)。
最初の会合では、サイモンが示した協会の基本方針について、メンバーの意見は激しくぶつかった。方針の趣旨は、このころに開発された機械組版でも手組みに匹敵する品質保持を求めて新しい技術との協調の道を探り、タイポグラフィの可能性を開くとする意見だった。ここでいう機械組版とは、主には19世紀末に開発されたモノタイプ機とライノタイプ機で、前者は活字を自動鋳造して文字単位で組む方式で、後者は同じ自動鋳造組版機ながら、行単位で組む方式である。この趣旨に対してニューディギットだけは、手組み組版の優越性と手漉きの印刷用紙の使用というような、ハンディ・クラフトを主張する強硬な意見を通した。他のメンバーがどのような意見だったかの記録は残っていないが、大勢はサイモンの趣旨にほぼ賛同していたと思われる。この2つの意見の溝は最後まで埋まらず、協会の会合はわずか2回目でその花をしぼませてしまった。サイモンによればその議論の様子は「嵐」のようであり、メネルによれば自分は嵐に手を貸した覚えはないし、あの議論は見解の「相違」にすぎないという冷静な受け止め方だった。
雑誌名の決定
結局のところ会は解散し、サイモンとモリスンという当初の2人が自費で雑誌を出版することを決意した。「フラーロン」という先のグループの名称はフランシス・メネルの提案で、この麗しい名前をモリスンは気に入っていた。ちなみに、「フラーロン」とは印刷の専門用語で、花形装飾活字のことで、現代ではPi fontsあるいはdingbatとも呼ばれる類の紙面を彩る花や葉の模様で、文字以外のキャラクタである。
雑誌名の当初の案では、タイポグラフィという語をメイン・タイトルに掲げるつもりだったのだろう。モリスンが1922年10月8日にサイモン宛に送った手紙には「タイポグラフィというタイトルはかなり固いし、一般の人には技術的な連想が先立って、自由な雰囲気をまったく感じさせない。このフラーロンには、歴史的でロマンティックな趣を示せる響きがある。これこそ我々が表明する必要のあるものだ」と書かれている。そこでこの雑誌でフラーロンという名前を継承し、タイポグラフィという専門語は『フラーロン』の副題”A Journal of Typography”という形で収まった。ちなみに、モリスンは『フラーロン』発行と同じ1923年には、すでにモノタイプ社の活字開発計画のアドヴァイザーとして契約を交わしていた。その後そこから生み出された古典書体の復刻と新書体の新刻による活字書体の数々の登場は、モリスンが強烈な集中力で古典書体を発掘したことを物語り、現代の欧文用書体の豊かな発展の基礎となっていることは重い事実である。
この雑誌の発行意図については、最終号である7号の「あとがき」でモリスンが次のように明快に総括している。
その意図は、活字、印刷紙面、書籍デザインに関わる問題を詳細にわたって議論することにあったので、現在の商業雑誌でできるようなことを遂行するのではなかった。つまり、イギリスの印刷人が調べようとすればできたはずなのに、いままで放置してきたヨーロッパ大陸の印刷業を歴史にとどめること、印刷人・読者・書籍商・職人との関係を理解すること、イギリスの印刷人の知識を広げ、印刷に対する意気込みを強めることが目的である。
顧客と書き手に対して責任感を強めることによって、印刷人が職人の高い水準を目指すように励まされることが望まれていた。
スタンリー・モリスン『フラーロン』7号「あとがき」
ここに当時の印刷業界では何が欠けていたのか、また望ましい印刷物の質とは何か、という問題意識の独自性がうかがえる。商業雑誌とは一線を画すという厳しい覚悟が明瞭だ。
編集者のサイモンとモリスン
そして、『フラーロン』が動き出す。その編集担当者は、前期4号はオリヴァー・サイモンで、後期3号はスタンリー・モリスンだった。机1つと電話1つで間に合うようなロンドン市内の事務所で雑誌の発行が管理され、原稿や手紙をタイプし整理する女性の秘書兼タイピストが1人雇われていたような極めて小規模の版元だった。この2人の担当した号は、それぞれの個性と思想を反映した編集を示している。各号の小論の執筆陣の選択とその内容、また構成やページ数にもそれが明瞭に現れている。
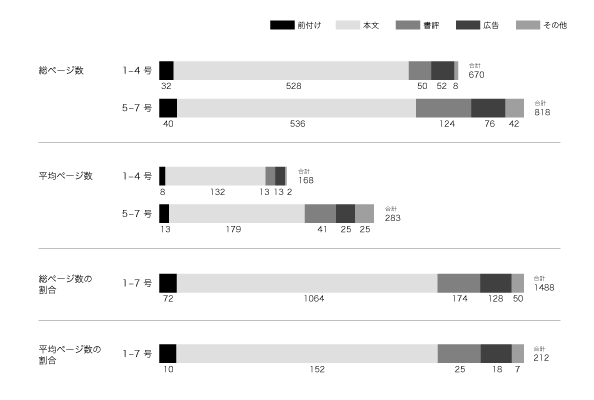 前編・後編のページ数比較
前編・後編のページ数比較
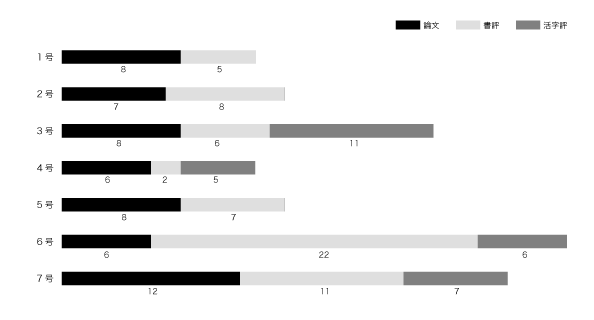 各号の記事の内容と分量(単位:記事数)
各号の記事の内容と分量(単位:記事数)
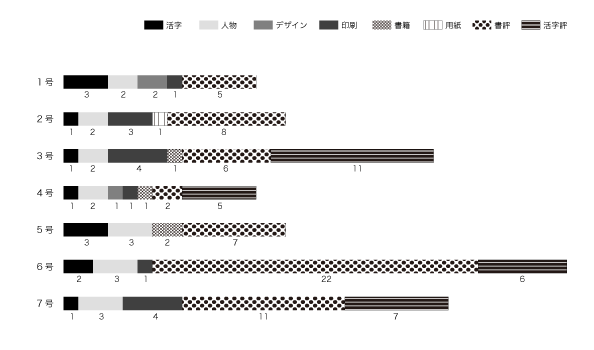 記事の内容と分量(単位:記事数)
記事の内容と分量(単位:記事数)
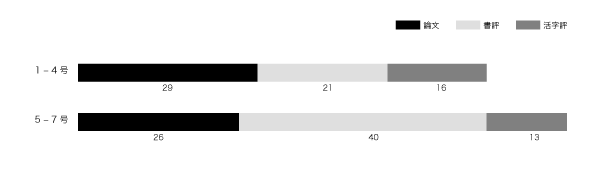 前編・後編の記事の内容と分量(単位:記事数)
前編・後編の記事の内容と分量(単位:記事数)
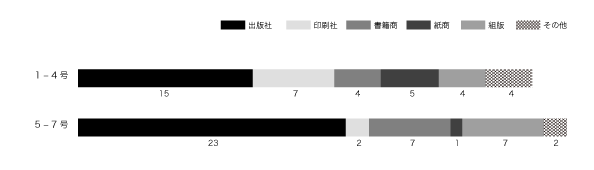 前編・後編の広告主(単位:広告数)
前編・後編の広告主(単位:広告数)
サイモンは、1919年にカーウェン・プレスという商業印刷所に入社し、やがて主任となって働く傍らその印刷所の名を挙げる働きによって知られた。1924年には「ダブルクラウン・クラブ」という会を設立し、1936年には印刷雑誌『シグネチュア(Signature)』を創刊した。著作もあり、その筆致は平明である。彼の両親もそして彼もウィリアム・モリスの影響を濃く受けている。装飾的要素の濃いデザインを好んでいて、印刷紙面に図版の役割を積極的に活用する趣向を持ちつつ、ドイツの印刷文化の賛美者でもあったそうだ。モリスンによれば、サイモンは議論を好まず、他者に与える印象は薄いようだと言う。大人しく寛容な性格だったと思える。
他方モリスンについてはここに紹介するまでもないほどで、タイポグラフィに関して多くの著作(書籍と論文記事は約180点)を出版した人物だ。日本のデザイナーでは、タイムズ・ニュー・ローマン書体の生みの親だと言えば分かるだろう。彼の基本姿勢の背景には、おそらくイギリスで最初のタイポグラフィの技術書として知られるモクスン著『印刷術における機械操作の実践(Mechanick Exercises on the Whole Art of Printing)』が濃い影を落としているはずだ。そこにはモクスンの姿勢が表明されているからだ。「タイポグラフィの実践者とは、独自の判断力と自らの揺るがぬ理性(Solid reasoning)を基に行動できて、他人を指図して、終始タイポグラフィに関する手作業と実際の操作の全てを遂行できる者である」という記述だ。その中から若きモリスンが掴み出した語は「揺るがぬ理性」、つまり「確固たる論理的思考」を意味する語だった、と紹介するに留める。
市井の読者のために
先に記したアーツ・アンド・クラフト運動とプライヴェット・プレスの行動は、機械に頼る製品の画一性を助長する近代式生産方式に対して、手のぬくもり感の喪失を嘆くものであるとして、一部の職人や思想家の共感を得ていた。
他方で、モリスンやメネルが志向したタイポグラフィ観は、その2つの動きに刺激を受けたとはいえ、異なっていた。それはよりいっそう市井の読者を念頭においていたし、経済生活にも資するものであるべきだという考えが濃厚だった。いいかえれば、印刷の本質は大量複製であって、実利的な目的を本来的に有しているという認識の下に、技術の新しさだけに溺れず、社会の伝統や慣習を重んじつつ技術の長所を上手に使いこなす、という向日的かつ慎重冷静な姿勢だ。そしてその目的遂行のために、歴史に踏み込んで学ぶという側面があった。その姿勢は単なる伝統保守主義者とは異なる性格を帯びていた。
『フラーロン』に使われた活字
この雑誌で使われた活字について、若干ながら付記する。全7号で4書体が選ばれている。サイモンが担当した前半の1〜4号では、3書体である。1号は14ポイント(以下「ポ」)のギャラモン書体、行間ベタ(行間なし)、2号は14ポのバスカヴィル書体、行間ベタ。3号は11ポのキャズロン書体、行間3ポ、4号は13ポのキャズロン書体で、行間1ポ。モリスンが担当した後半5〜7号では全て14ポのバルブ書体で、行間は1.5ポで共通している。ちなみに行長を見ると、前半4号は1ページ38行、後半3号は33行が主である。組み幅は前半が33パイカ(396ポ、約140 mm)、後半は32.5パイカ(390ポ、約138 mm)と計測できた。
使用4書体は全てモノタイプ社製造の活字である。ギャラモン書体はジャノン系であり、フランスの17世紀前半のスダンのジャン・ジャノンが設計した(16世紀のギャラモン書体の模造)書体がモデルである。ギャラモン書体はおそらく世界で最もよく知られた欧文書体の代表格であろう。バスカヴィル書体は、18世紀のバーミンガムのジョン・バスカヴィルが設計した。キャズロン書体はロンドンのウィリアム・キャズロンが設計し、イギリス製初の独自書体の誕生として歓迎された書体をモデルにした。バルブ書体は18世紀フランスのフールニエが設計した書体をモデルにしている。バルブとはフールニエに協力した印刷者。モノタイプ社にはフールニエの設計書体をモデルにしたフールニエ書体もあるが、バルブ書体に酷似している。その理由はここでは省略する。

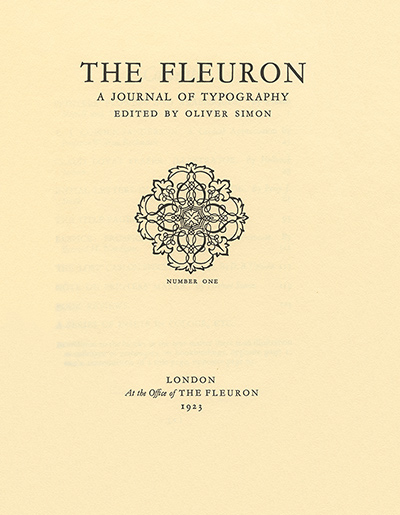

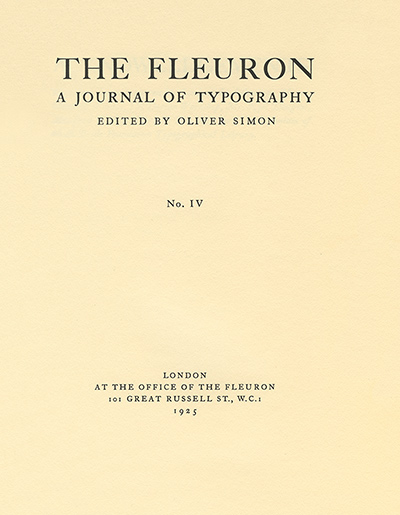
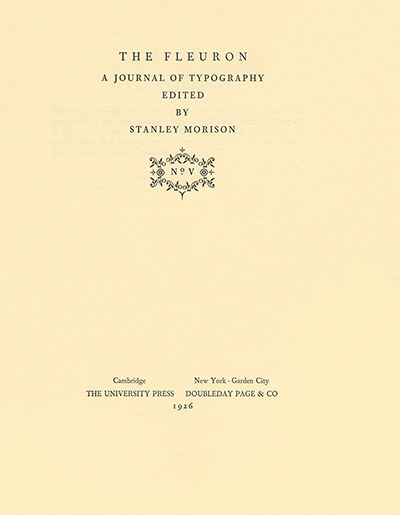
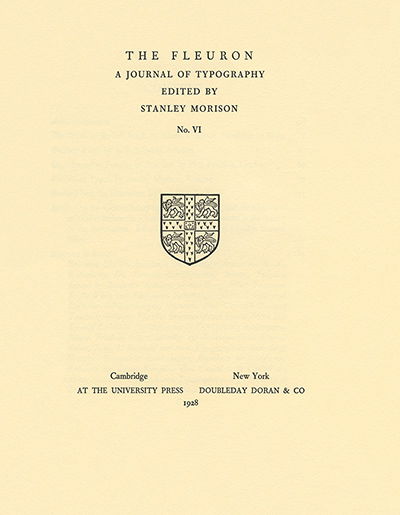
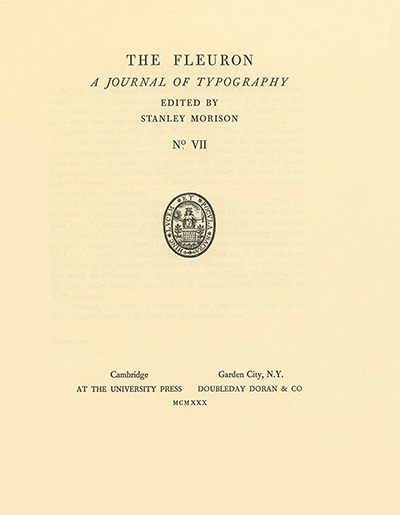
3. 同時代のさまざまな運動との相違
『フラーロン』が世に出た契機は、時代が抱える課題への対応だった。印刷の改革を巡るかまびすしい動きに一石を投じる意図があったと観察できる。彼らの提言には、印刷関連業者の自覚を促すという啓蒙の意図もあった。その行動がどのような言論の形で受け継がれたかを、同時代およびその後の主な定期刊行物から探って位置づけを試みよう。
産業革命という動力エネルギーの発明から起こった大地殻変動により、家内制手工業から工場制機械工業へという製品製造現場の激変があった。そこでは、大量複製への焦りと希望とが織り混ざった美的価値および装飾的価値についての見解を孕みつつ、一部で活字とその演出法についての議論を巻き起こしていたが、果たしてどんな評価や試行があったのだろうか。
アーツ・アンド・クラフツ運動との比較
ここでは目的、手段、装飾の3つの側面で、主にA&C運動の支柱としてのモリスの書籍設計の理念と比較してみる。モリスがラスキンの中世の正当化に同調して「ゴシック・リヴァイヴァル」の洗礼を受けている有名な事実も不可欠な背景である。モリスンが「(1851年開催の)大博覧会ではゴシックの唱道者ピュージンがデザインした中世の装飾や復活したブラックレターの活字は、当時のタイポグラフィの帰結のひとつだった。文字よりも重要だったのは復古の精神だった。それは産業の前進を強く批判するもので、前の世代を熱くさせた精神だ※6」と言うように、ゴシックの復活という残照がまだ覗けた背景がある。
第1に目的から眺めると、『フラーロン』発行がA&C運動の影響下から生まれたことから、この運動との共通点は無視できない。モリスンは、A&C運動に一定の評価を与えていた。それは主に「モリスの産業主義への抵抗が感傷的ではなく社会的だった※7」からで、思想的背景への共感だった。モリスの抵抗は社会主義者としては当然な姿勢だ。産業主義への突入と人間の手仕事の軽視への危機感と社会改革が絡んだ運動だからこそ、モリスンの賛同があったのだろうが、評価は全肯定ではない。その理由は、おそらくモリスのアート志向と耽美主義傾向への疑問からだろう。
もうひとつの共通点があるとすれば、それは「優れた製品」を実現し提供する目的にある。この場合の「優れた」という語の英語はfineであるが、洗練された仕上がりを意味する。きめ細かく丁寧で、しかも機能面だけでなく心理的にも満足感や喜びを与える製品。ただしこの優れた製品の中身つまり実践に立ち入ると、そこにはA&C運動との相違が現れる。
モリスンはモリスの行動に限界を感じていただろう。つまり機械化への傾斜を忌避するのではなく、工芸的要素を活用しつつ、量産の可能性に希望をつなげて、機能性と経済性を重視していたことに伺える。工芸的要素とは活字の原型(父型)がグーテンベルク以来500年間近くは手によって彫られていたことを指し、その手作業によって生じる避けがたい限界が示す「金属活字」独特の姿であろう。読まれることを前提とする文字造形への繊細な神経とその実現へ向けての沈黙の中で作業が続けられる飽くなき姿勢である※8。
また、ここでいう機能性とは製品としての直接的つまり身体的、それと間接的つまり心理的な「有用性」、この双方であり、経済性とは効率的生産による「価格の抑制・適切さ」であり、人々の日々の生活つまり経済的行動への貢献である、と解釈できる。大量生産による製品の画一性は、それ自体が大衆に同一の品質を安価で保証するというメリットに転化されていて、それが社会貢献となる。解決すべきは粗雑な製品という質の問題であった。総じて、モリスは理想主義的であり、モリスンは現実主義的であろう。
第2に手段で眺めると、A&C運動の趣旨には機械文明への嫌悪があった。彼らの拒否する「機械」は熱エネルギーを動力機関として利用する自動方式であり、受け入れた機械は旧式の木製手動式であったが、素朴ながら一定の構造を有した力学的な動作器具すなわち機械であることに変わりはない。機械とは何かの定義がないために、曖昧さを残している。加えて産業主義の進展で分業化が進み、職人が責任感を喪失しかねないことにも危機意識があった。
機械の活用では、A&C運動の後に生まれた『フラーロン』の編集方針とは異なる。既に触れたように、『フラーロン』は新しい技術を利用して、産業の枠組みを経由して受け手に的を定めた外向的な行動だったが、A&C運動では素朴な機械と道具それに手工芸に依存する中で、内向的に充足した作業工程と作業環境を是としていた。
第3に装飾要素の扱い方の差異は何か。装飾過剰気味のモリスは、優れた製品には装飾が不可欠だと理解し、装飾は生活に豊かさを添える要素であるとして、第三者にもその鑑賞を求めたし提供したのだろう。だが、装飾の美は、モリスが描く理想的な民衆にはふさわしいし、とりわけ忙しく動く近代人の心身の一部を潤しうるが、モリスが支持する労働者階級には装飾を生活の中で鑑賞する余裕があったか疑問である。さらに、モリスはアートに傾いたために、無意識的であろうがつい大判の仰々しい装飾を加えた重い書籍を堂々と製作した。教会の奥に鎮座して鍵がかけられた権威的な聖書を彷彿とさせるほどの存在感を誇示する書籍である。
『フラーロン』では、全号を通しての紙面デザインが一定の回答を用意していたと見ることができる。つまり、テキストが主であり装飾性は乏しい。扉のデザインは簡素であり、装飾要素はアクセント程度である。だが、モリスンには「利便性はタイポグラフィの技芸にとっては始まりではありえても、最終目的ではない。……装飾のある書籍を提供することは、無視すべきでないタイポグラフィの技芸の一面である※9」という理解があった。功利性一本やりの造形行為・技芸には、モリスンは反対だった。つまり「適切な装飾」という考え方を主張するのであろうが、その「適切さ」には曖昧さが残る。何を念頭に置いているのか。そこには「フラーロン派」の一員であり、若きモリスンにタイポグラフィの手ほどきし、1923年にナンサッチ・プレスを起こしたメネルの理念と実践が、この曖昧さを解く鍵になるだろう。
つまり、メネルの組版演出の特徴は、出版物ごとの書体選択の多彩さと「隠喩に富んだ印刷(allusive printing)※10」にあるとされている。このprintingはtypographyと置き換え可能だろう。オーナメントの使用は内容と著者との関連で選択する、というその有効性を重視していた。つまり、オーナメントに意識的な機能を発見した。言葉だけに喚起されて思い描くだけでなく、装飾要素の挿入によって膨らむ想像力への点火による、読書の楽しみを味わう場の提供である。読み手と作り手とのつながりを強化する相互共感を活用した心理的な機能主義であり、書籍の装丁と一体化した活字と組版と飾りの交響が生み出す理性と身体感覚と心理反応の面で満足させようとする演出である。ここにモリスの装飾に対する姿勢との違いが明らかである。
ちなみに、A&C運動は日本の民芸運動の唱導者で主役である柳宗悦と比較できる。A&C運動の思想の核は復古へ向かう精神と一神教の神と装飾にあり、モリスなどの社会主義者による民衆への視線にあった。ただその視線は彼らの生み出したモノの中に見えにくい。他方で民芸運動では職人への眼差しはA&C運動よりは明確であり、その思想の核となるヒントは仏教の中にあった。西洋の二項対立思考という発想の原点を疑わないで揺るがない態度に対して、柳の発見は鈴木大拙らの紹介した禅の高踏的で孤高の精神から導き出された二項対立以前の宇宙的な混沌状態にその行動の核を求めている。さらにその先に浄土教の民衆救済への傾斜がある。つまり善悪や美醜という相対立する2つの価値が生じる以前の状態があるとの認識を出発として、名も無い庶民の無私の習慣的な創作(あるいは製作)行為に理想を発見した。まことに斬新である。
翻って『フラーロン』派の動きは、むしろ柳らの行動と重なるだろう。人々の生活の基盤を支える裏側の立場を自覚することから社会にモノを送り出すという意味で、共通点がある。つまり、少なくともunsung hero(讃えられない主人公=影の功労者)的な部分だけは共通するはずだ。己の労働にひたすら取り組む無垢の姿勢であり、生活の中で必須な部分だけを想像し、創造への昇華の意識もない繰り返しの地べたの日常行為は、評価の有無は眼中にない一種の超越的な態度と言える。
柳の独自性は、言葉に頼らないこの国の伝統を受け継ぐ職人の現場に対して、初めて言葉による根本的で意識的な考察を残したことにあるだろう。だが、言語化したことによって、匿名性の中での仕事に職人はかえって己の働きが外部から眺められたことを意識せざるを得なくなり、当惑したのではないか、という危惧もある。無自覚が意識された時に成長は始まるのが常ではあるが、近代は果たしてこの当事者の外部からの好意的で夾雑的な鑑賞や評価を果たして回避したのであろうか、それとも昇華したのであろうか。
私家版運動との比較
ここでは読者への意識、印刷への動機、製作物への価値観、それにタイポグラフィについて、19世紀中頃から盛んになった私家版印刷と比較してみる。
第1に読者という存在の意識はどうであったか。『フラーロン』は印刷業者を対象として、彼らに読み手の存在を意識させるよう促したが、私家版印刷の考え方に影響を受けているとはいえそれとは異なり、市井の読者への意識が濃厚だった。それは私家版にありがちな、自己の美的価値観の発露の手段としての書籍製作という、自足して閉じ籠る志向ではない。私家版では読者は極めて限定された中での、価値観の共有が前提でもあった。
モリスンは伝統主義者ではあるが、盲目的な伝統保守とは異なる言動を示した。印刷の本質である複製技術の長所を社会の伝統や慣習を重んじつつ適切に使いこなすという慎重だが向日的な理念だった。その裏には大方の読者は(とりわけ活字書体において)保守的であるという認識があった。その保守的な受け手には慣習という容易に崩せない深層が埋まっているとの判断だろう。慣習という同一地域で暮らす人々の文化の下層に堆積する無意識に近い錘(おもり)は伝統に裏付けられて存在する、という認識がモリスンの思想の核にあるはずだ。そこで慣習的受け手に届ける目的遂行のために、歴史に踏み込んで慣習や伝統の役割を確認する必要が求められた。したがって、伝統の解釈が後ろ向きに働かない。この考えはいわばリテラシーの向上による「近代読者」が成熟期を迎えていた時勢への必然の対応として生じたものだろう。
第2に印刷に対する動機を比較する。私家版運動を「内向的」と評したが、行動の裏には反抗心も隠れていた。それは当時の無秩序な印刷物への静かな抵抗でもあり、表立って声高に主張しない紳士的な態度のようでもある。だからこそ彼らの言葉は鬱屈の中からの辛辣なユーモアとなって周辺に波紋を投げる。私家版での印刷(および裝本)は、既存の文芸作品を素材にした書籍形態の美の追求のための手段だった。他方でモリスンらの印刷の位置づけは、自己または他者の追求テーマや見識を広く公表する手段だったのであり、健康な志向だろう。その意味で彼にとって活字は、公のものだったのかもしれない。議論を起こし提供するための基盤的な、言わば民主的な支持媒体だったのだろう。
第3に製作物への価値観を比較してみる。私家版印刷の評価では、モリスンはそこに見られる閉塞的な習癖と個人の美的趣向の追求とは一線を画していた。モリスの原点である装飾の価値と職人の責任感に共感しつつも、それだけでは限界があると考えていた。モリスンは印刷では美の追求のあまりに優先課題が看過されることに警鐘を込めて、「美は望ましい。そして美は求めなければ現われるものだ。美のための美、あるいは変革のための変革ほど、タイポグラフィにとって災難を引き起こすものはない※11」と指摘している。製品の「用」が十分にしかも無意識の上に機能すれば、そこには「美」が自ずから沁み出てくると解釈できる。もし「用の美(beauty of utility)」という語が常用の英語にあったならば、モリスンはそれを採用したはずである。書籍という形態とそれが秘める内容が統一的に造形化される先には、充足感からの喜びという心的機能性が立ち現れるはずだという考えであろう。
次に具体的な面で比較してみると、エゴイストで嫉妬心が強かったダヴス・プレスのコブデン・サンダースンは、モリスの書籍製作を批判している。「彼の作品はすばらしいし、それ自体が時代を画するもの」との一定の評価はあるものの、「彼(モリス)の行なったことの多くはタイポグラフィの点からは見当違いだし、著者の思考表現がなされるべきページを完全に破壊している」と、素人性と過剰なデザイン志向を退けている※12。書籍デザインにおける表現主義の弊害の指摘だ。サンダースンの書籍に対する思想はモリスと異なる。彼が完成した書籍のたたずまいは簡潔を旨としているために、装飾的な要素を排除していて、プロテスタント的特徴を示す。したがって、サンダースンは流行思潮を気分的に捉えた気取りではなく、あくまで批評精神を思想の表出として挑んだ私家版印刷者だと言える。
また、ある解説では「頽廃的な印刷はつねに装飾的な印刷である。タイポグラフィの想像力がうまく働かないと、装飾的になる」というジャクスンの引用に続き、これを最も熱心に採用したのがバウハウス派であるとしている※13。モダニズムがこの辺りで「カルヴァン主義者のスタイル」の延長と確認できる。
第4にタイポグラフィの面での違いを見てみる。モリスンは活字書体の設計においてもモリスの有名なヴェネチアン系のゴールデン書体を評価していない。この書体はケルムスコット本全体の約5割で使用されている。私家版の活字ではジェンソンとその同時代人のヴェネチアン系をモデルとした活字が多くを占めていて、モリスの影響に対するモリスンの批判は激しい。たとえば有名なゴールデン書体は「醜い」し、私家版が使う同類書体は「これ見よがしで、悪名高い出来損ない※14」だと切り捨てている。そして「すぐれた印刷という大義は、自分専用の奇妙な様式のための下品な狂気で台無しになっている※15」として、ケルムスコットとその亜流に厳しく反発している。
ヴェネチアン系の代表であるジェンソンのローマン体の文字造形に対するモリスンの批判は、大文字の字幅と高さに向けられている。とりわけ高さがアセンダー・ラインと同じであって際立ち過ぎること、それに小文字hやeが読み手の眼を捉え過ぎて読書行為に支障がある、さらに「見栄を張ったg、e、b、yの文字と突出した大文字でルネサンスの活字に忠実だ※16」などと、読者の目を止めてしまう文字造形を批判している。この指摘は、彼の「理想の活字を求めて(Toward The Ideal Type)」という『フラーロン』で発表したエッセイに披露されている。読者は文字の1つずつを読むのではなく、文字を通して単語の輪郭を認識し意味を読み取り続けるが、文字のわずかな不慣れな造形が視覚の躓きを起こして、意味への瞬時の経路を妨害してはならないという意味である。
『フラーロン』の同時代の雑誌
『フラーロン』以外で英国内での「印刷改革運動」の流れの中に、いくつかの雑誌が手を挙げていた。ここでそれをチェックしてみる。
『インプリント(The Imprint)』
『インプリント』は1913年に月刊を目指して出発したが、9号を発行してあえなく終結した。1月から8月までは順調に月刊で発行できたが、9号は11月発行となり、それが最終刊となった。創刊号の巻頭で発行人であるジェラード・メネル(フランシス・メネルの従兄弟)と思われる匿名の記録欄があるが、そこには詩人・画家であるウィリアム・ブレイクの言葉「輝かしい夜明け」がこの雑誌の理想だと紹介されている。高揚感が伝わる一節である。ちなみに、ここで専用された活字書体は、キャズロン書体をモデルにしてモノタイプ社で急造された「インプリント書体」として知られている新しい活字である。
この雑誌に関係した人物を調べると、意外と多くの者が参画していた。編集担当はリトグラファのE・ジャクスン、タイポグラファのJ・H・メイスン、カリグラファのE・ジョンストン、そして印刷者のジェラード・メネルの4名で、専門分野が異なることが特徴である。その他に諮問委員会として桂冠詩人のR・ブリッジ、中央美術工芸学校の初代校長であるW・R・レザビー、印刷人のデヴィーン、アシェンディーン・プレスのS・J・ホーンビーを含む33名が名を連ねている(5号以降は32名)。有名な私家版派が際立つ。
執筆陣は91名が寄稿し(このうち4名は共同執筆)、87の記事が発表された。毎号平均では、同一人物による複数執筆と匿名執筆を含めて10名が書いている。際立った寄稿者では8回発表した者がメイスンと古書販売人のエヴェラード・メネルの2人。7回発表者はE・ジョンストン、肩書き不明のD・パウエル。6回発表者は物故者で「尊師」と称号のある19世紀の書誌学者T・ディブディン。5回発表者はリトグラファのE・ジャクスンである。これらはほとんど連載記事である。珍しい人物として、フランシス・メネルの母親で詩人のアリス・メネルが2号に児童書の挿絵について寄稿している。また、モリスンが24歳にして初めて発表した論文「典礼書に関する覚書」が8号に見られる。最終号では6名しか書いていないが、急激な状況の変化がうかがえる。その理由のひとつは第一次大戦前夜の英国社会の経済状況の混乱とそれに伴う資金面での困難であり、もうひとつは、意見の相違であったと報じられているが、詳細不明だ。
『インプリント』の主な対象は印刷業界であり、その内容は主に業界への提案だった。印刷を工芸分野の価値ある地位へ引き上げようと、印刷関係者への自覚を促す企画だった。全号の目次を眺めると、印刷関連(方式や機械や用具類)などが最も多い記事であり、次は評論関連であり、ビジネスに関する記事が3番目に目立つ。その他は装飾や挿絵や書籍などに関する記事が占めている。
また「『フラーロン』は『インプリント』で示されていた課題を引き受けた※17」と『モダン・タイポグラフィ(Modern Typography)』の著者ロビン・キンロスはまとめている。だが、同じように業界向けを意識したとはいえ、『フラーロン』はいっそうの広い範囲からの執筆者とテーマを特徴としている。また、キンロスの『フラーロン』に関する見解は「印刷業界に向けて語りかける明確な意志はないが改革運動内あるいは集まりの中での議論のための手段として間違いなく機能した※18」と、実践的ではなく内輪だと見ている。これには創刊号での「発刊にあたって」という類いの宣言が見られないことも関係しているだろう。だが、『フラーロン』は「議論ための手段」ではあるが、広角的内容を扱い、海外からの執筆者の寄稿もあり、ヨーロッパへの一定の広がりは推測できるし、雑誌の意図を広く欧州諸国にも知らせる思惑もあるだろう。川の底流に細々とだが流れを繋いでいたような現象に見える。時代状況への反応ではあったが、その流れは時代を超える意義を伝えていたようだ。それこそ静かな波及効果で良しとする抑制的で一種紳士的な態度と言える。
『インプリント』と『フラーロン』との関係では、やはりキンロスの解説が参考になる。『インプリント』は「『フラーロン』およびその後に現れた他の雑誌の精神的な母体であった※19」。この言葉は、この2誌の影響を位置づける上では重要な指摘であり、その後の印刷改革運動の先駆けとしての存在を評価している。
ダブル・クラウン・クラブ(Double Crown Club)
ダブル・クラウン・クラブでは、『インプリント』誌以上にA&C運動の影響は濃厚である。1924年10月に結成して、40年以上継続した会合である。設立会員はサイモンのほかに出版人かつ多方面で活躍したS・ロバーツ、出版人のF・シジック、タイポグラファで音楽系出版者のH・フォス、それにG・メネルであった。初代の会長はロバーツが務めた。年数回の不定期な集まりであって、タイポグラフィや書籍製作についての論文が食卓を囲んだ会員に配付されて、議論が交わされた場(ダイニング・クラブ)であった※20。モリスンは設立会員としては名前の記録はないが、何度か参加している。1964年のクラブの40周年記念講演で、晩年のモリスンはクラブの功績をこう語っている。
印刷人とデザイナーだけでなく読者の執事たる出版者が参加することで、「読者と向き合う必要のある出版者と奇行と乱暴をはたらくデザイナーが向き合うことを気づかせた※21」。
モリスンの伝記作家であるJ・モランは、モリスンを公平に見つつも、名を遂げたモリスンの晩年の言動に対しては批判が目立つ。だが、「奇行と乱暴をはたらく」のは「デザイナー」だという指摘には耳が痛い人もいるだろう。これは活字設計について「設計者の親指の指紋は不要だ」というモリスンの名言を思い出させるし、その先には、グラフィック・デザインにおいて、デザイナーが往往にして「私流」を付加したがることへの批判が見える。「これが私のデザインだ」という、まるで電柱に自分の証拠を振りかける犬の行為に似て、そこで自足する現代の職業人の一面だ。グラフィック・デザインもタイポグラフィも、与えられた素材を視覚化・現実化させる行為であり、それはハーバート・スペンサーが「(タイポグラフィにとっては)テキストはレゾン・デトル((raison d’etre)」だと言うまでもなく、第三者が用意または表現した素材なくてはあり得ない技芸であり、つまりは代弁的な再現行為であり、あるいは追創造行為でもある。
ダブル・クラウン・クラブの形式を雑誌発行という公開の場で発展させたのが『フラーロン』であるとも言える。キンロスは「これらの改革運動の快楽主義的で自己閉鎖的観点は、ダブル・クラウン・クラブで崇められた※22」と述べて、広がりを見せない仲間内の趣味の場だとして厳しい視点で観察している。しかし、「快楽主義的」は何を指しているのか。キンロスが支持しているように見えるモダン・タイポグラフィでの抑制的な組版も、その清楚な空気感も「快楽主義的」ではないと言えないだろう。余分な要素を全て取り払う行為は合目的性だけを追求し、息つく暇さえ排除する一直線的な紙面展開は一定の緊張感を読者に与え続け、その非装飾的で張り詰めた無機質性を是とする。それも一種の無意識的な快楽追求ではないだろうか。ここで引用しているキンロスの著作の本文と見出し類は同一書体と同一サイズで組版され、余白がその分節化を暗示している。
カーウェン・プレス
基本的にカーウェン・プレス(Curwen Press)は端物と広告の印刷物を得意としていたが、美術家や挿絵画家が集まる場でもあって、カーウェン一家の後を引き継いだサイモンが活字と挿絵との独自の分野を築いた。やはりキンロスによれば、この印刷所は「とりわけ良質の食事とワインを連想される、文士風であるが深刻過ぎない世界だ※23」と分かりやすく例えている。「深刻過ぎない」という部分こそ、モリスンとは異なる挿絵とテキストとを同等に扱って特徴を見せていたサイモンの真骨頂だろう。自分の楽しみを優先する姿が見え隠れする。この時代に多く存在した私家版印刷者の典型のひとつだ。フラーロン派の両頭の一人にもこの理念の表出を許したことは、互いの懐の深さに起因するだろう。
『ペンローズ・アニュアル(Penrose Annual)』
1895年という早い時期にグラフィック・アートの評論を目的として発行された年1回発行の雑誌が『ペンローズ・アニュアル』である。1982年まで87年間続いて貴重な記録を残した息の長い定期刊行物である。『フラーロン』よりは28年早い刊行であるため、その当初の発刊趣旨は『フラーロン』とは無関係である。「グラフィック・アート」という言い回しにも美術への憧れあるいは負い目が伺えるとするのは言い過ぎか。
発行数とページ数が共に多く、統計と分析は物理的に不可能だが、印刷に関連する事柄を全方位から集めて評する雑誌であると総括できるだろう。グラフィック・デザインの製品類の紹介や評論、最新式印刷関連機械や機材や技術、インキ類、用紙、特殊加工法などの情報紹介が主体と言える。かつて数点を手にとって眺めた経験では、印刷技術面のページが多かったという印象が残っている。したがって、タイポグラフィに関する記事は主ではなく、モノタイプ社の広報担当だったビアトリス・ウォードやモリスンやチヒョルトらが寄稿した1930年代だけは、例外的に当時のタイポグラフィへの熱気を伝えることに注目したのではないか。
その編集の守備範囲が広いことは特徴のひとつだった。この年鑑雑誌の発行期間それ自体が近代印刷の歴史と重なる時代の傾向を映すだけでなく、印刷の可能性も探った印刷ジャーナリズムでもあるだろう。それだけに筋が通っていて、グラフィックつまり写真図版などの視覚要素のカラー印刷が主体となる制作物の変化の様子を追跡できるだろうし、視覚要素が大胆に展開して読者の興味を引くなど、その編集方針の勢いが時代を貫いていたと想像できる。
また、組版と印刷の技術形式が進展する時代の課題に取り組んでもいた。めまぐるしく変転する目の前の問題解決へのヒントを機を見て旬に提供していた。そのため、印刷やデザインの新情報をいち早く取り入れるには重宝であり、時代と共に歩む息の長い雑誌たりえた。ただここには、手工芸の要素は見られない。それが過去の技術であるからだろう。つまり、A&C運動の痕跡はうかがえず、グラフィック・デザインと多色印刷再現技術の輝かしい可能性を追っている。色彩豊かな図版と文字組版との意欲的な合体を疑うことなく試みた媒体と言えよう。
新タイポグラフィ運動との関連
グラフィック・デザイナーがタイポグラフィを担う宣言があったことで、「印刷デザイン」とも言える技芸の登場があった。それは時代の技術の進展とも密接だった。カラー印刷の本格化とオフセット平版印刷と新しい組版方式の登場、それにサンセリフという新分類書体の本格的な登場とも時期が一致することで、グラフィック・デザイナーを刺激して活躍の場を増やした。だがその反面でタイポグラファの役割と立場が霞んだ。
新タイポグラフィ運動に対するモリスンの私的な場での意見が残されている。1937年にしたためられたモリスンのアップダイク宛の手紙だ※24。ドイツを中心とする新タイポグラフィ運動に対して憤慨しているくだりがある。いわく、かれらの言動は「空念仏だ」、「様式と感覚をすり替えたがっている」として、アップダイクの吐いた「汚れた自己顕示欲だ」「利己主義がはびこっている」との言葉に賛意を示している。アートに傾斜する大陸のグラフィック・デザイナーへの不信の表明である。
アートとデザインの分岐点は、誰がオリジナル・メッセージ(独創的視点)を用意するかどうかである。この2つの語の基本的な概念をまとめれば、アートは非実用性、個から個へ、自作自演、独創性の自己表出(圧出)で内発的であり、独創性が評価の重点であり、基本は単品製作。デザインは実用性、個から多へ、計画・統合・設計、ある概念の実現化であり外発的であり、条件・制約が伴い限定的で具体的な創意工夫が不可欠で、基本は複製されるものが多い。デザインにおける創造性とは、第1次の(オリジナルな)言葉・概念の視覚化・現実化における第二次創造あるいは追創造(再現)にあるといえる。
Artがギリシャ語arsに発して、「人の関節・腕の動き」などの原義があり、Designはde「下に」sign「記す」の2つの合成語だとされている。前者は人間の個人的な発露と身体の動きが基本であり、後者は人が人に意志・情報を説明する・伝えるという行為に直結していた。そこからも相違を理解できそうである。
アートは多様な解釈を許容し予言的でもあり問題提起的でもあり、時代を超越する普遍性を内包する。デザインは平面や立体を問わず一義性や機能性を求められる時代直結の造形行為である。しかしまたデザインは、社会生活に直結する故に、問題提起型もありうる。
ちなみに、モリスンのアートの定義は「技能によって知的に熟考され意図されたあとのひとつの結果だ、と定義できるかもしれない※25」とあっさりしているが、実は警戒心が働いている。「この時点(1851年の大博覧会:筆者注)以降、アートは魔法の言葉となった。アートと名のつくあらゆるコースの講座があって、アート雑誌が出版された。また木彫りアート、刺繍アート鉄製品アート、調度品アートなどが流行った※26」と、言葉の意味の無制限な拡大に懸念を示している。
また、タイポグラフィはアートかデザインかという問題では、チヒョルトとウォード女史を紹介しつつ検討したC・ビゲロウの小論の中に見出せるとのことだ※27。興味ある重要なテーマだが、その論を未読のためにここでは割愛し、いずれ検討したい。ここでもアートという語の広さをどのように把握するかが基本となるだろう。この2つの外来語の和訳が定着していないことが、我々の基本的な理解を妨げていると観察できる。
4. 『フラーロン』誌と後続雑誌との関係
状況の変化
グラフィック・デザイナーが登場し、その後の印刷関連の状況を変貌させた。伝統的な長文用活字組版と、消費されるデザイン的要素が先行する作業、この活字を巡る作業環境の二極化が生じた。書籍印刷と商業広告印刷の役割が自覚されたともいえる。19世紀の商業印刷と大量消費社会の出現でもその変化はあったが、そこにはおよそグラフィック・デザイナーという自覚された職業集団の存在はなかったと想像できる。
その当時の印刷物、主にポスター類や端物類に見られるデザインには、計画的な設計という視覚要素の演出を活字書体の個性の衝突で圧倒する勢いで満ちている※28。活字のサイズと種類の多さが混在し、底抜けな活気がありカオス的であるが、現代から見れば焦点が定まらない粗雑さが際立つ。文字情報が窮屈さの中で未整理で効果を減じている。文字組版作業上の混乱を整理するにはそれなりの苦労や工夫があったと容易に想像できるが、訓練された職人の手技かどうか疑問でもある。
『フラーロン』誌が発行されていた時代の前後での印刷改革運動では、盛んな議論が続いていた。それは数人規模の印刷関連者による小集団行動で、雑誌類の発行で自らの主張を印刷物によりその質的な意識を具現化して発表することだった。
また大陸での新タイポグラフィ運動は、その意図がどうであれ、資本主義経済での生産者と消費者との関係の密接化、言い換えれば消費者を説得するまたは囲い込むという意味では、経済活動に寄与した。だが、書籍と広告物の印刷量の差は一般的には桁が異なるほど大きいし、市場規模や普及度も異なる。その差はまた影響の範囲や目的とする対象の層にも関わる。そこで両者の条件や制約を無視して現象だけに言及することは、ことの本質を見失いかねない。つまり、モリスンの語る「経済活動に資する」面が現実化しているとは言い難い。モリスンは物質的貢献(製造費とその定価の抑制)が同時に市民の精神的生活(読書など)を支える上で役立つことを願っていたと思える。モリスン自身が図書館通いを続けて書籍を資料として読み込んだ経験からも、それが想像できる。
主なタイポグラフィ関連雑誌
『フラーロン』の影響を英国内で眺めてみる。まずは時代順にいくつかの雑誌をとりあげて、『フラーロン』との影響関係を検証する。ここで取り上げる雑誌媒体は、いずれも第二次大戦前後からの数十年間ほどに試みられた企画である※29。
この時代の雑誌の特徴としては、2つあげられる。1つはグラフィック・デザイナーが編集を担うことから誌面が色彩に溢れ、情報整理の徹底によりレイアウトに多彩な変化または統一感を加えたりしたこと。すなわち情報の整理として視覚要素が優先・有効視されて前面に現れた。グラフィック・デザイナーは実践家であるために、テーマに対して学究的な姿勢がとれない。そこから雑誌の内容は、現実的な課題への実践的な対処法または意見表明が多くなる傾向がある。
もう1つは、印刷出版業が印刷業と出版業に分化する現象が固定化されたことだろう。出版業が独立する傾向が濃厚となった頃から、グラフィック・デザイナーが表紙デザインや編集に関わる行動が見られた。同業内での分業制の確立がもたらした時代に登場したグラフィック・デザイナーの幸運な門出だった。しかし、半世紀後には技術のDTP化に見られるデジタル革命の影響で分業制が崩れ、統合化現象が発生している。
『タイポグラフィ(Typography)』誌と『アルファベット・アンド・イメージ(Alphabet and Image)』誌
『タイポグラフィ』誌はロバート・ハーリングが企画し、1937年に発行された定期刊行物である。全8号を発行して1939年に廃刊したが、1946年に彼は『アルファベット・アンド・イメージ』(以下A&I)というタイトル変更によって再発行を試みた。このとき、『タイポグラフィ』誌の印刷出版で協力した印刷者ジェイムズ・シャンドがこの雑誌の発行に関わった。
この時代の印刷現場を巡る状況の変化を語るには、第一次世界大戦を無視できない。雑誌発行の困難さが想像できるからだ。戦後でも印刷業界には頑迷で保守的な工芸職人が生きていて、グラフィック・デザイナーが志向する新しい動きには興味を示さないあるいは無視という態度だったのだろう。
ハーリングは、この印刷関連で一定の役割を果たしていた美術工芸の職人と、新しい職業人であるグラフィック・デザイナーとの仲を取り持つことを志向していた。グラフィック・デザイナーを「美術家と印刷名人(親方)により歓迎される、見失われた技術者※30」と位置づけしていた。この雑誌ではページ物という書籍デザインへの意識は少なく、主に端物印刷物や新しい製作物を紹介することに意欲的だったようだ。そこには19世紀のタイポグラフィの復活を匂わせる意図があり、一種の復古的雰囲気が見られる。1950年代に19世紀のスラブ・セリフ系書体の復活をみることにつながるだろう。
『タイポグラフィ』誌はやがて方向転換を試みた。タイトルが活字に集中し過ぎていると反省して、『アルファベット・アンド・イメージ』という柔軟な誌名の下での写真などをはじめとする、グラフィックな要素を取り入れた紙面や記事に方向転換した。その点で、すでにここには『フラーロン』誌の趣とは異なる傾向を明らかにしている。ただ、この発想の根底には、職人を共同の作業の良き相手としてどのように互いに刺激し合ってグラフィックな展開を可能とするのかが模索されている。この一部分は『フラーロン』からつながる意識と重なる。つまりモリスンの「印刷人が職人の高い水準を目指すように励まされることが望まれていた※31」という印刷現場の意識改革が前提とされていたことに通じている。
いずれにせよ、この2誌には、『フラーロン』の影響は見られないと判断できる。大陸からの新タイポグラフィ運動が持ち込まれた状況下で、独自性と伝統を意識した結果の、カトリック的な装飾性への憧れがこぼれ出たのではないだろうか。
『タイポグラフィカ(Typographica)』
タイポグラファでありグラフィック・デザイナーでもあり教育者でもあったハーバード・スペンサーが弱冠25歳で1949年から発行した雑誌がこの『タイポグラフィカ』である。スペンサーは1920年代に大陸で起こった「モダン・タイポグラフィ」つまり「モダニズムへの理解と賞賛」を英国のグラフィック・デザイナーに紹介する役割を果たした※32。さらに彼は1964年から73年の間に先に紹介した『ペンローズ・アニュアル』の編集長も務めた時期がある。
本誌は新旧2つのシリーズに分けられる。旧シリーズは1949年から59年の間に16号を、新シリーズは1960年から67年の間に同じく16号を発行した。1巻の平均ページ数は旧シリーズでは40で、新シリーズではその1.6倍の65である。本文書体の使用状況は資料不足のため今のところ不明であるが、かつて手にした記憶ではサンセリフ体が主要書体だった。
この雑誌の目次一覧を概観する限り、テーマはタイポグラフィだけでなく、人物の評論や紹介、サインやレタリング、写真、デザイン・印刷、書籍、その他を扱っている。旧シリーズでは①タイポグラフィ、②デザイン・印刷、③レタリング・サイン・文字・記号の順で記事が多く、新シリーズでは①レタリング・サイン・文字・記号、②人物評論・人物紹介、③タイポグラフィ、の順位となる。新シリーズでは④にデザイン・印刷が続く。
内容は歴史に遡る調査や研究を奨励する記述ではなく、その時代に発生している問題または将来への問題提起を主に含む。それはタイポグラフィを巡る技術と社会へのコミットが盛んになりつつある時代の必然と言えよう。つまり、モノフォトやルミタイプなどを代表とする写植組版とオフセット平版印刷が主流となりつつあった印刷の新技術の洗礼を受けていた時代で、多くの課題が山積されていた。
『タイポグラフィカ』の背景には、研究調査という時間を許さない時代の速い流れがあって『フラーロン』のような学術的なテーマが見られないことが特徴である。つまり、歴史を貫くような思想的な姿勢は見られないが、同時代の目前の現実と向き合う姿勢は顕著だったと言えよう。
スペンサーの英国でのタイポグラフィにおける貢献は、大陸のモダニズムと新タイポグラフィの紹介と普及にあった。それは主にチヒョルトを通した理解であった。しかし、キンロスはこの2人を次のように比較している。
チヒョルトが自分の全経験において美的かつ理想的に魅了されたタイポグラフィに固執し続けた一方で、スペンサーの指導には少なくとも明らかにそのような部分はなかった。それはビジネスマンの日常世界のためのタイポグラフィであって、そこでは造形の簡潔さは効率とコスト節約を意味したし、思想的な含みはなかった※33。
スペンサーの実利的で現実重視の姿勢と、チヒョルトの厳格で精緻で完璧さを追求する、スタイリッシュで緊張感をはらんだタイポグラフィ観が、ここで要領よく紹介されている。妥協的で現実重視の英国人気質と、理論的に頑固で理想追求型のドイツ人気質の違いにも見えてくる。英国のペンギン・ブックスでの仕事を契機に書籍タイポグラフィを捉え直したチヒョルトが、その後に英国のデザイナーやタイポグラファに影響を与えた背景には、スペンサー流の現実的な解釈があったということでもある。
スペンサー以前には、地味ながらアンソニー・フロショーというタイポグラファで印刷者がいた。フロショーもチヒョルトの影響を受けていたが、そのデザイン意識の新しい捉え方は印刷現場との違いをいっそう強く意識せざるをえなくなり、1950年代以降はタイポグラフィの教師となってグラフィック・デザイナーを育てた。彼の熱心な教育活動はグラフィック・デザイナーが英国に出現した時期と重なる。
『印刷歴史協会誌(Journal of the Printing Historical Society)』
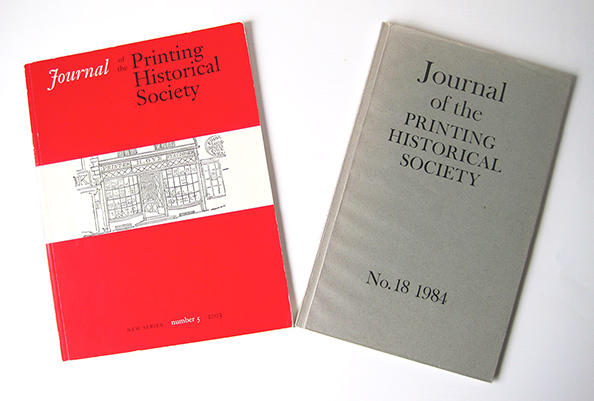 印刷歴史協会誌 表紙
印刷歴史協会誌 表紙
1964年に設立された団体である歴史印刷協会が発行する雑誌がこの『歴史印刷協会誌』である。設立会員はレディング大学のタイポグラフィ教授のJ・モズリー、タイポグラファで歴史家のJ・ドレイファス(1918–2002)、タイポグラフィと印刷史の研究家J・モラン、M・ターナー、レディング大学のタイポグラフィと視覚伝達の名誉教授のM・トゥワイマン(1934–)、D・チャンバース、ドイツ生まれで英国に移住したタイポグラファで活字設計家のB・ウォルプ (1905–89)である。モズリーなどがいることで分かる通り、レディング大学とのつながりが深く、いわば重鎮とも呼べるタイポグラフィまたはグラフィック・コミュニケーションの専門家が集まって学術的な研究成果を発表している機関誌だ。
その活動目的は前付けページに明記されている、次の3つである。
- 印刷の歴史の研究を促進し、その関心を高めること。
- 印刷機、記録、過去の道具類の保存を進めること。
- 上の2つの目的に関する出版物を制作すること。
具体的には、印刷の技術と資材の歴史、個々の印刷人の歴史、業界組織の歴史、それにこれまで扱われていない事柄についての、権威ある記事を出版という形で世に問うことを意図している。年1、2回発行するこの刊行物には歴史に埋もれている課題の掘り起こしと追求があって、その研究成果は興味深く読める。その意味では、『フラーロン』の趣旨と内容をもっとも強く受け継いでいるし、名称から明らかなように『フラーロン』よりも徹底して「歴史」を探っている。ただし時代の課題と取り組んだ『フラーロン』の趣旨はここでは欠けているが、その行動には『フラーロン』が刺激として働いていたと推測できる。それはアカデミックな方向への傾斜だろう。
1965年発行の第1号の前書きでは、この定期刊行物が発行された頃の事情が2つ述べられていて、興味深い。①冒頭での当時の歴史的資材の散逸への危機感が表明されていること。また、数世紀続いた印刷の本質的な部分が変わらない時代がついに消えつつあることも指摘されている。つまり写植(英国では「写真組版(photo-typesetting)」と呼ばれた技術)の出現があって、金属の活字と活字版印刷が消えつつあり、それに伴いプロセス製版とオフセット平版印刷が時代の趨勢となっていることを指している。②オックスフォードとケンブリッジの両大学印刷局が歴史的に価値ある証拠文書・資料を努力して収集したこと。それに反して、例外はあるものの、博物館が何も援助していないことを取り上げ、その原因が「印刷が片隅の手工芸なので語られ得ないからであり、昔から業界がロンドンに集中していることで地方都市の誇りが元気を失っているからだ※34」という事情を指摘している。
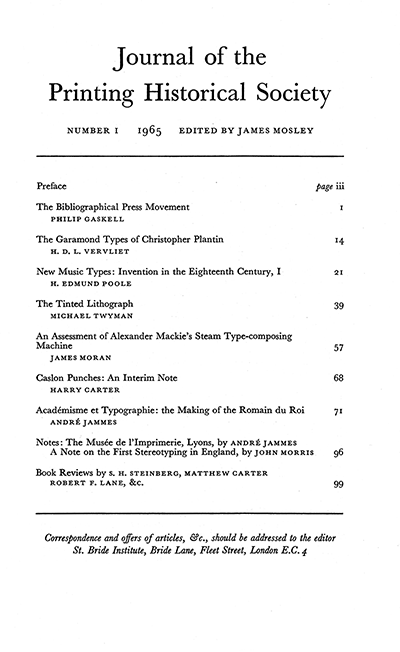 印刷歴史協会誌 目次
印刷歴史協会誌 目次
その他の雑誌
先の3点の後に現れた雑誌類の特徴は、グラフィック・デザインとタイポグラフィを統合するという意味で、写真図版類が格段に増えて、視覚要素と書体との競演となった。だがそれは、「新しく現れたタイポグラフィ中心のデザイナーたちの集団が展望も議論の場もなく片隅にいて追いつめられ、国内に閉じこもった」という指摘※35にあるように、次に起こる大陸の新タイポグラフィとの違いがうかがえるし、『印刷歴史協会誌』が、その後に英国に現れる雑誌類の特徴と異なっていることは明らかだ。たとえば、以下のような雑誌である。
『ベースライン(Baseline)』
この『ベースライン』はデザイン関連用具・用品や転写式活字書体シートを製造販売するレトラセット社が1979年から発行した。マイク・ディンズが設立者のひとりで、編集を長く担当していた。主なテーマは活字とタイポグラフィであるが、グラフィック・イメージを気楽に楽しみながら多少は学べるという内容が特徴のようで、グラフィック・デザイナー向けの情報誌的な位置づけができる。1990年代中頃にはレトラセット社が離れて、デザイナーらが集まってこの雑誌の発行を継続させていた。
『アイ(Eye)』
評論家のリック・ポイナーが1990年に発刊した雑誌が『アイ』で、当初は編集を務めていたが、その後は多くのグラフィック・デザイナーが編集を順次担当していて、誌面の活発さと大胆さが特徴である。ポイナーはグラフィック・デザインやグラフィック・コミュニケーション分野の評論と解説が専門である。
後に、彼はタイポグラフィのニュー・ウェイブ関連誌にも広く興味を示している。読むことを拒否・排除するデザイン『The Graphic Edge』、陶酔・幻覚を思わせる画像を使用した『Get the Message?』、『Typography Now』などにも関わった。
この2誌を含む後発の雑誌では、大陸のモダン・タイポグラフィが影響を及ぼしていて、装飾要素は意図的に避けられているのも特徴である。
『タイポグラフィ・ペイパーズ(Typography Papers)』
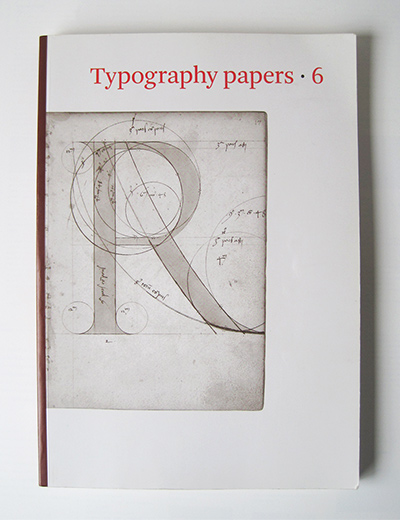 タイポグラフィ・ペイパーズ 表紙
タイポグラフィ・ペイパーズ 表紙
この『タイポグラフィ・ペイパーズ』は前の2誌とは異なる例外的存在である。1996年からレディング大学のグラフィック・コミュニケーション部のP・スティッフが発行を開始した、本格的な論文を集める不定期刊行物だ。編集担当者は途中の号から各号により異なることが慣例化している。この誌面にもモダン・タイポグラフィの影響が見てとれる。執筆陣が『印刷歴史協会誌』と交差・重複する。
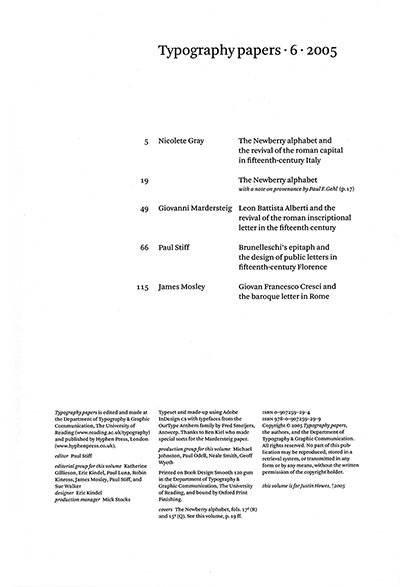 タイポグラフィ・ペイパーズ 目次
タイポグラフィ・ペイパーズ 目次
5. 『フラーロン』誌の現代的な意義
まとめ
『フラーロン』の基本には人々に伝える価値のある課題を提起するという意識があり、書籍という小宇宙的に統合された伝達形態への期待がある。いわゆる端物や広告物は消耗品であり、期限付きでその当面の価値を失う媒体だが、書籍は国境(空間)と時代(時間)を越えて回遊する永続性を秘めた存在であるとの認識があったのだろう。
モリスンはタイポグラフィの主たる領域を書籍製作に集中していたことで、際立っていた。この点で彼と距離をおく専門家が彼の見解に対して異論を挟んでいるが、それは論点の比重の置き方の違いであり、批判者も知る通り、モリスン自身は広告などの商業印刷の場を当然ながら認めていたし、両者の差異を語っている。
『フラーロン』は、その後のタイポグラフィの研究という面では貴重な足跡を残した。その価値には、以下のような特徴がある。
- タイポグラフィの質の向上を目指した考察・分析などの掲載。
基礎的な参考資料となる財産であり、知識のための知識に終わらない理知的な問題意識を秘めた内容であるため、見解の宝庫となっている。 - 学術的な研究対象として一歩を踏み出す契機となった行動。
タイポグラフィが書誌学の補完的な位置づけであった状況から、書誌学から独立できうる可能性を秘めた対象として、一定の水準にまでタイポグラフィ研究を押し上げる契機を与えた※36。 - 書籍製作での読者への配慮の意識。
活字の選択という実践には活字書体の特徴に関する知識が必須であることから、自ずと可読性への配慮、つまり読み手を意識化する行動を優先した。
またデザインの面では、装丁や装飾要素の点で、『フラーロン』の中で一定の節度のうちに提示したことも追加できるだろう。それはおそらく モリスの実践とその理念との差異を提示していて、抑制的で密かな喜びを詰め込んだ。
このように『フラーロン』の特殊性は理念を設定して後に実践で示す行動力にある。理念には歴史との対話が必須で、そこから同時代の状況批評を試み、論考を示し、あるべき手法を駆使して安価で良質の書籍類のための参考となる見解の提示だった。それはタイポグラフィの社会的役割を自覚した課題追求だった。
また、新技術への対応の姿勢を示して、現代的な課題への示唆も引き出せる。デジタル革命期の現代では、かつての職人の責任感は、今や組版技術の開発に携わるエンジニアにはタイポグラフィへの深い理解を必要とすべきだという意味の自覚と言い換えても良いだろう。
『フラーロン』の後を受けて、『印刷歴史協会誌』がタイポグラフィを本格的な学問の一分野として確立させている。『歴史協会』の機関校が美術大学にあり、そこでタイポグラフィが一教科となった本格的な研究が教授陣を中心に展開されている。この現象には『フラーロン』などで、タイポグラフィ研究の可能性を開いたモリスンの功績が影を落としているだろう。
後記
『フラーロン』が世に問い始めて90年余りが経過し、世紀も変わった。現在のタイポグラフィ関連の革命的技術では、中心となる活字は金属やネガフィルムという物質性から離れて不可視・不可触のデジタル信号を通して画像化する何物かへと変貌した。「活字は彫られたものである」とするモリスンの原点認識は今や牧歌的な響きに聞こえるが、タイポグラフィが書記言語による伝達方式に関わることに違いはない。
しかし、活字とはなんだろうか。個人的な修辞を許されるならば、活字は書き手の言葉をいったん「凍結」させると言えるだろう。書き手の熱を帯びた文字が書体という「凍結」された公的な文字として読み手に届けられる。読み手の前に現われ心の中で音読される。読む行為のエネルギーによって文字として活字は「溶解」されるが、その直前にかすかに化学変化を起こすようだ。それは「書体」に変換された文章(組版)から生じる表情だ。このとき溶解された活字に血が通う。まるで毛細血管を巡る血液のように、意味という血液が流れ始める。言葉は血流となってわずかに「増幅」する。流れる意味の増幅作用のエネルギーによって読み手の音声に変わる。それにはテクスチュアとしての組版表情が関わっているかもしれない。読み手の内的音声が己のリズムを獲得しつつ意味の流れに没入され始める。活字は水や空気のようでありながら、色も味も誘惑もあるのかもしれない。
タイポグラフィの本質は伝達媒体の中の文字情報の整理であり、その文字表記法にも深く関わる。『フラーロン』から読み取るべきは、技術や技芸と学問の成果との緊密な連携の再確認から始めることにあると言える。それは内向きでは開けない地平だ。
リル・チージーな夏の終わりのイグジット⛵
Don’t call it a come back! ウチら全部忘れるために刻んでるだけ。忘れたくないだけ。暑すぎてどうかしてんの? マブい生命線が導火線?空がタイダイ色だね、ユノウセイン? ハリウッドドリーミンっていうかGames? 3人でクロムハーツするSTAY PINK。ウチらSo Highな国民だからHIコクミンだぜナァミーン? ってコクミンドラァグでセミ鳴いてくミーンミーン。そのあと止まってシーンとする。
ウチらαネオいサマーヌードで夏だけプリ(ズム/ミティヴ)っちゃってるちゃってってるたったひとつのチャネル。勝手に掘ってるトンネル。スラッシュで区切るプロフィールよりもクラックよりもクラッシュする今(する今)。キチン質のきちんとしたキッチンにいるクソスニッチに特攻(ぶっこ)む。まだ夏を終わらせない。
と寝たふりでネタ振り。Netflix & Chillも積もれば山となって街の景色変える like 渋谷をジュラ紀に戻す。ジェラってる暇ない甘すぎてるbaby。ニューシットの「Soホントにそれは躁」をチェックしてフォローして。フォロバよりも転ばして滅ぼして。でもバズよりバグというかバグっちゃう前にハグしてよ、今すぐ。でもハグされたらバグっちゃってテクノブレイク。
アダムスキー型の鉄板が飛ぶ新大久保。チーズティー飲みながらホットク頬張ってWOAHキメてくリル・チージーな夏の終わり。ピーチ烏龍茶にミルクフォームをトッピングしてサマー。ウチらネオチンピラばりにアリノママ。ゾロアスター? アーリマン。悪魔だってすうはあ息するみたいに崇拝してた? でも崇拝もロールモデルも平静でいられない。そういうの平成でおしまい。
CBD99%のクリスタルをヴェポライザーで蒸せば、アナーコフェミニズムとネオリアクショニズムを両立させた法案・草案(仮)が立ち上がる。シュプレヒコールは「マジ令和ナメんな」。ラディカルで卍ベリーなシスヘテロシステム。ならもう普通にTHCでよくない? なくなる電池。ウチらだけの聖地。朝からちゃんと巡礼。
ペヨーテばりにペヨってて、コヨーテばりにアグリーなんだけど、アグリーなしじゃウチらサンノゼまでカリフォルニアハイウェイ。ヒッチハイクしてもアウトロー俳句よりもビッチ短歌で灰食って徘徊ってかフライハイ。パタフィジックな懐古趣味じゃいられない。イラレ立ち上げたまんま前乗りして火葬の前撮り。
彼女がタピをカラダに入れる。硬さは睾丸と同等。平等じゃ物足りない like 男の潮吹き。けど進化心理学や進化生物学の最新研究は、人間の本性をミソジニックに暴く。ブレグジットの先のブリブリのアセンブリ。資本主義のパーリーはリアルすぎるから今すぐイグジットしよう。泣かないで、ダンディ・ウォーホール。
エコーチェンバーで高めるテストステロン🥦
わたしの彼ピはオルタナ右翼でヒプノティックなタオイスト。インフルエンサーのサイキックインカムに頼って生きるアンフルエンサー。AMSRで自己催眠かけてアムスで脳イキ狙ってる。非合法なSISSY系のPMVをディグってる。当然いつもスマホの指示待ちしてる。
彼はセックスしてるときも、アルファメイルのことばかり考えてる。インテル入ってるみたいにかなりインセル入ってる。ブラックピルを飲んだフーディーな加速主義者でスローな過食主義者。今日も半グレで賑わうサウナ。筋肉の厚さと男性器の大きさは奇妙に反比例する。
遅れて来たアーリーアダプターは知ったふり(act like you know)。人権MAXで殴る蹴る噛みつく。アイデンティティとシチズンシップはバックの取り合い。ガチでリッチなホモノーマビリティ。確証バイアスで信念を固めてリベラルな正論を全力ツイート。ぶらさがってるコメントはキショいのもマジなのも全部わかんなくて届かない。スシ詰めのキャリオケで中飛びするみたいにウチらずっとピンとキてないからすぐキて。
なりたいカラダをジムで手にするアシッド共産主義者。エコーチェンバーでテストステロン高めてる。レッドブルにアルギニンとシトルリンと亜鉛とクエン酸を混ぜて飲んでる。骨盤底筋にオットピンを塗りたくって羽目を外す like 人生どうでもイリーガル。覚えてる? リアルに触れたらジンジンしてボンヤリする。
本ばっかり買ってた彼に最近言葉が語りかけて来ない。都市も遠ざかって最近服のことばかり考えてる。意味よさらば。悲しみよこんにちは。服と顔と表情と声でディープラーニングするネオルッキズム。ハードに世界をDRIPするならテキストよりモード。
ハイブランドはお高いふりのまま、ストリートカジュアルはインフレで、コリアンブランドも出尽くして、今はインドネシアが熱いじゃない。フォーマルに逆張りするとストリートがマイナーチェンジで勝つ。ウーシーランとウーヨンミのコラボまだだっけ?
マノスフィアの父権主義者はメス堕ちを誘う。ドライオーガズム専用アプリとエネマグラIoT。ディアスポラのクンダリーニ。ディストピアでのクンニリングス。ディスカウントストアでクウネルアソブ。この橋渡ったところでキスしたい like 1時間に1本のバス。苦いキス、甘いペニス。これはただの夏。
懐かしさと気恥ずかしさのAESTHETIC🐬
ごめんね、ウチらネオヒューマンよりも寝起きでNEWoMan。これが新宿クリーンサウススタイル。キューバンなメンズとランウェイをUターン。世界はゲットーってかここは地元のロードサイド。クソみたいにウチらMinna Rich。純トロ同クラのビッチとペニバンでベスパでニケツで卍快調。ランブレッタでドーバーから飛び降りるストリートマーケット。
ビッチでもビッチでなくもない名前をドロップ。ウチらの365日24時間の這いつくばってイキは、かつてないヤってイキだし、息するみたいにイキってる。一人で死ぬ(die alone)気ないし、死んでも友達と一緒(die VLONE)。バブーシュカ被ったまま歌舞伎町サイケデリア。素朴パリピは失うと老化する。闇堕ちにも品格がある。
見てと見んなのフィラメントの揺れがわかんないとハラスメントはなくなんない。恨み晴らすメンソールの洋モクがウチらのトレードマーク。ギャングとヘッズ、大人と子供、女と男の間で、ウチらだけのかわいいを見つけるのがゴール。身体で感じるとジョークで頭で考えるとエシック。電マよりレンマ使ってく。メンチ切ってくるならホームセンターでギったレンチで顔面ミンチかレンチンしたメンチで(そのあとほらね、わかるでしょ?)。
知りたくないことばかり知りたくなるのはなんでだろう?知っちゃうとすぐ思想変えちゃうわたし何か悪いことしてる?転向(テンコ)しないの怖くない?変化だけが変化しないんだって。変節だけが思想だって。いなくなっちゃってわかんないし執着(ストーク)したら死んじゃう。憂鬱(フレンド)に相談しながらテキスティング。さよならだけが沈静化。
ジョブズ亡きあとのアブロー。キラキラしてるものが虹色に見えちゃうポリティクス。コンプライアンスとコンプレックスの狭間で朝まで吸って吐いてる。コントレックスで流し込むコーンブレッズ。今すぐ買いに行ってボーイ・ミーツ・バールもしくはパール(口唇期的ジェムリンガ)。だってガールはもういない。透明少女は台風でさよならって話。
OK、コンピューター。クラフトワークが新世界を予言して幾星霜。Lay low, nobody move until I say so. 分裂病者とAirDrop痴漢のダンスパーティー。懐かしさと気恥ずかしさのAESTHETIC。カチッて押し込む三角形のプレイボタン。グライコだけが光ってる。地元のショッピングモールは潰れてしまった。ここにティファニーはもう来ない。I think we’re alone now.
セフレとソフレのマテリアルワールド🦋
ヒト科が無理な晩夏に提唱されるポストコンテンポラリーデス。セフレからソフレにハッテンした恋をファッショウェイブにするパームエンジェルズ。房中術仕掛けてくるE-boy対策で、クリトリスに毒薬を塗るのはE-girlのエチケット。背中まで45分。
健康管理とオーガズミック瞑想。脊髄反射と生体電子エネルギー。何かがクソエロいんじゃなくて、お前の頭の中が勝手にクソエロいんだし、結局エロいと痙攣って同義じゃない? つーかノリノリにノッてる女の子みんなエロくない? like 折口信夫を静脈注射して死者のショー。
夏なのに彼ピッピとつながれない。白Tにぶん殴られる一人称ビュー。歯茎に白い粉をこすりつけるシュガーダディ。Tohjiみたく雪山ではしゃぐウチら寒っ。Meganみたくボムなヒップで、ELLEみたくKawaii Bubbly Robbery。タクティカルにRun The Jewels.
トリュフフレーバーのスナック無条件興奮。寝まくって食べまくってしゃべくってる。コンビニつくった神様がボースティングしてて神。ほんのちょっとも困ってないってことに対して困ってるって顔してる。ダンスフロアのパッションフルーツ。ポルチオ揺らすローライダー。あいつらスタンばってる横で本番。ガスパンとホーチキでso far.
プラザ合意のときのビルボードHOT100トップが“Money For Nothing”だった皮肉。いまだにI want my MTV。ウチらニューヨークのイギリス人でエイリアン。そのチャートに入ってた“Material Girl”。ウチらにはマテリアルワールドさえ遠い。パパとママがネオン焼けした黄金の国ジパング。手を伸ばすより先に掴んでるエコノミックアニマルニトライト。
今は誰もが気軽に呪いをかけられる。恋し恋され保存される聖像(アイコン画像)。手短かに神の存在証明を済ませるイットガール。鮮烈に刺さってきてほしいだけ。死んじゃったラッパーみたく刻んでくだけ。左右にスワイプして就職先マッチングさせれば普通によくない? でもこれってUIが悪いよね?
メスイキ化する世界で消えた記憶🍄
ウチらの生まれた街のコンテナみたいなキャリオケ。先行って待ってる間にまくのはマキビシとまざふぁきびちとガンジャってことはリアルニンジャでヒップホップ。Kunoichi Moneyゲトってもゲットーだし、もうアガってくだけ。ダレもナニも落とさないレースじゃアジられても飛べやしない。ギャングキング読んでたらずっと3時。Justified and Ancient of Mu Mu.
メスイキ化する世界はエイジ・オブ・アクエリアスとテイストが違う。マウンティングで精神のあおり運転。No RuleなムードがFabulous。バイト受けるノリで絶滅しあおう。生命力の高い死に生殺しにされる生存を生暖かく見守る死。シンギュラリティは今何時?(渋谷で5時!)
この場所の外部は別の場所の内部。内と外で実体化することがプロブレム。泥水からシャンパンだし棺桶からロブるスター。結局はビッチかウィッチを選ぶ人生。選んだらきっちりスイッチ。片割れに目もくれない配色ステッチ。この惑星のニュースに飽きたら特異点の向こうへin da sky.
ウチらまわりでウチらが一番大きな主語。しゅごいおっきいってスピットしたげる。電車で脚広げたソーリーなメンズより、ステージで脚広げるブーティーなビッチーズ。だってあいつらムショに行ってなくない? ウチら河原で橋の下で水道管の上で歩道橋で溶けてくシーンをTwerkしながらトロトロになって見てる。
川崎ナンバーのバンで遊びに行こうよホーミー。先輩が来たらすぐホットポットスポット。夏の夜風に吹かれてハンドルKILL。次の瞬間、脳内の図像がフラッシュ。そっから秒でフラッシュバック。リアルに記憶も今も同じになってく like 体育館の屋根の上履き。
ウチらの回帰するランウェイ。少しずつズレながら変わってく刻んでく。これ秒でリアル。ウチら忘れたくないだけ。全部忘れるために刻んでるだけ。この空にリミットはない。うれしはずかしレイドバック。持ってきてるレイノヤツ。そっから記憶消しに行こうよ。見慣れた景色もネオくなってskrrr!skrrr!
深夜のドラッグストアカウボーイってかウチら💉
ウチらはウチらの話しかしない。ウチらが話せばウチらの話になる。誰かが話したことをウチらが話せばそいつはウチら。だから永遠のランウェイが終わるまで(アプロ)プリってる。ずっとヴァーチャルでローカル。フッドはどこにあるのっつってどこにでもあるフッドがフッド。ウチのフッドじゃないウチらのフッド。
ウチらのルーツは収束しない。ウチらの拡散する根(リゾーム)。ロックは自殺でヒップホップは他殺を志向すると言うけれど。なにもかもKIMONO。赤い着物でかちこむチームSKIMS。階段上ったところにいる目出し帽被ったGOLDIE的なTRICKY風のBANKSYワナビー。ダチの姉ちゃんが警棒持ってるって。
気分じゃないときでもキテるマブからの手紙。目が覚める河川敷。卍る売ってるばあちゃんが放火でパクられてる間にもパクってる。三白眼とパキパキの睫毛。意思する前に石(stoned)する。タイムズの看板すぐのドンキで買ったハンマーをラップでぐるぐる巻きにする。
誰も見てない電車が来るタイミングですべてがはじまり、すぐに終わる。その瞬間がゆっくりバチバチに弾けてる。カヌー漕ぐみたいにオールを振り回す。まるで映画のワンシーンだけどunseenの束の間、全部見失って安心できない。アイパッチの向こう側でぐじゅぐじゅになってる眼球か世界か、そのどちらかどちらも。
ドラッグストア、眩しくてイラついてる。ドラッグストア、牧場に血の海。ドラッグストア、ノーATM。ドラッグストア、カード何枚目? ストゼロ欲しいだけなのに、クルーのママがちんたら金数えてて、クソ時間経過してブチギレソウ。畑の真ん中の土埃まみれのドラッグストアの美容部員やるってどんな気分?
「ムー大陸」は23時に閉まる。電車で一駅だけどチャリ倒しながら歩いたらすぐ。白線の上、まだ24時。コスメに不時着する白い歯。鏡月のビンだっけ? かちわられて血がついてヌルヌルする。アブストラクトじゃない行動訓練。グリップのギザギザしてる金属。ずっと記憶飛ばしてる。ずっと嫌な夢見てる。
死ぬまでの数分をどう過ごす? 目を瞑るか開けるかすれば、セイタカアワダチソウが生い茂っていて。ねえ、ずっと生い茂っていて。ウチらの死骸を草葉の陰に隠していて。ねえ、お願い。ウチらの話だ。ウチらの話をしよう。
2018年の夏、アッシュビル滞在中は毎日雨だった。「雨が続くね」とアーカイヴセンターの司書に話しかけたら、「夏は毎年よ。それを理由に夫は9月までペンキの塗りかえをしないの」彼女はたしかにそう言った。
なのにBMCのサマーインスティテュート(以下、夏期講座)が続いたのはどうしてだろう。雨期なら避けるはずだが、夏期講座の写真を見ても雨の気配はない。
不思議に思って調べてみた。2018年の7月と8月をみると、晴天は少なく曇りがちで、にわか雨も数えれば二日に一度程度の降雨。一日中降っている日は1ヶ月通して7〜8日ほどだった。東京の梅雨と比べてすこし少ないぐらいだろうか。毎日が曇天でいつ雨が降ってもおかしくないような天候だったが、実際に降っている時間は短かったのかもしれない。
気温は15度を下ることはなく、30度を超えることもない。湿度は50%程度で過ごしやすい。そういえば、エデン湖キャンパスはもともと避暑地として使われていた別荘だった。それに今はサマーキャンプ地だ。好天が続く秋に比べれば、夏は雨が多いということか。
1944年の夏期講座
ライスがBMCを去った1940年、学長は演劇を専門とするウィリアム・ロバート・ウンシュ※1が引き継ぎ、美術関連の指導は引き続きアルバースが担当した。ウンシュはロリンズ大学からライスと行動を共にしたひとりであり、地元であるノースキャロライナ大学の出身だった。ライスの“解毒剤”とする評価もあるが、彼は学生の話をよく聞き、明瞭で深い洞察力を持つ、民主的かつ進歩的な人物だった。
ウンシュは、自分がどうして学長に選ばれたのか疑問に思っていた。たぶんそれは、謙遜ではないだろう。彼にはライスのような独善的なところが全くなく、逆にリーダーシップを執らないところが評価されていた。
 [図1]ブルーリッジキャンパスにて教員たちの写真。中央がロバート・ウンシュ
[図1]ブルーリッジキャンパスにて教員たちの写真。中央がロバート・ウンシュ
前回にも書いたとおり、夏期講座(summer camp)は1941年から開かれている。時期を考えれば、開講にはウンシュの判断があったと思われる(あるいは、そういうことに反対しない人物としてウンシュが選ばれたのかもしれない)。
最初は農場や建築の実習を主体としたボランティア労働との単位交換制度といってもよく、エデン湖への移転が完了した44年から、夏期美術講座(Summer Art Institute)や夏期音楽講座(Summer Music Institute)が開講されるようになった。この夏期講座が、多くの人がイメージしている「ブラックマウンテンカレッジ」なのだと思う。
まずは、44年夏期講座のパンフレットから見ていこう。これまで同様、農場体験や建築実習を対象としたサマーキャンプも開かれているが、この年から、サマーセッションとして音楽と美術の講座をスタートさせている。下記は担当した教員である(パンフレットどおりの表記)。
音楽講座:Marcel Dick, Joanna Graudan, Nikolai Graudan, Rudolph Kolisch, Ernst Krenek, Lotte Leonard, Yella Pessl, Edward Steuermann, Frederic Cohen, Heinrich Jalowetz, Edward E. Lowinsky, Gertrude Straus, Elsa Kahl.
ゲストとして:Agnes de Mille, Virgil Thomson, Mark Brunswick, John Martin, Aaron Copland, Herbert Graf, Doris Humphrey, Paul Green.
美術講座:Anni Albers, Josef Albers, Victor D’Amico, Joseph Breitenbach, Jean Charlot, Jose de Creeft, Walter Gropius, Barbara Morgan, J. B. Neumann, Amedee Ozenfant, Bernard Rudofsky, J. L. Sert, Howard Thomas.
音楽講座では、ウィーン交響楽団で活躍したユダヤ人のマルセル・ディック、ユダヤ系オーストリア人で左利きのヴァイオリニストとして知られたルドルフ・コーリッシュ。ゲスト講師として、ニューヨーク出身でやはりユダヤ系のアグネス・デミルらの名前が見られる。ジョン・ケージやマース・カニンガムが参加するのは、まだ先のことである。
芸術講座は、アニとジョセフ・アルバースを筆頭に、MoMAエデュケーション部門の創設ディレクターだったビクター・ダミコ、バウハウス初代学長のヴァルター・グロピウスらの名前が並ぶ。シュルレアリストの写真家ジョゼフ・ブライテンバッハは、ミュンヘン出身のユダヤ系ドイツ人。校舎ピロティに壁画を残したジーン・シャーロットはフランス、パリの出身。やはり移民(亡命者と言った方がいいか)が多くを占める。個人的には70年代はじめに読んだ『みっともない人体』のバーナード・ルドフスキー※2の名前をみつけて少し興奮した。
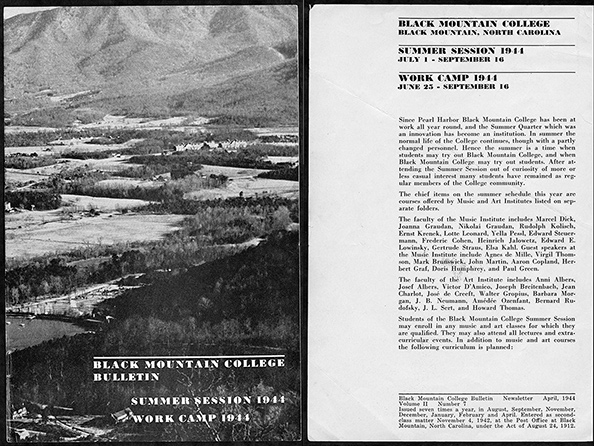 [図2]1944年夏期講座パンフレット。表紙(左)、中ページ(右)
[図2]1944年夏期講座パンフレット。表紙(左)、中ページ(右)
BMCがヨーロッパからの亡命芸術家の受け皿のひとつであったことは厳然たる事実だが、さまざまなエッセイに「ユダヤ的」と書かれているのは、実際どう言うことを指しているのか、東洋人のぼくにはよくわからない。しかし、こうして名前を並べてみるとユダヤ系の教員がいかに多かったかはわかる。それは移民国家アメリカにおいても特殊なことだったのだろうということぐらいは想像がつく。そして、そのユダヤ的なるものがBMC内部になにか軋轢のようなものを生んでいたらしいことは、残された文章のいくつかから読み取ることができる。しかしそれでもなお、他者を受け入れようと繰り返す葛藤がBMCの魅力になっていることは間違いない。
話を戻そう。音楽、芸術、両講座ともリベラルアーツ科目も履修できるようになっており、そちらは常勤の教員が担当した。ちなみに学長のウンシュは、「演劇(Drama)」と「作文法(Composition and introductory writing)」の授業を受け持っている。演劇はのちの夏期講座で重要な役割を果たすことになる。
パンフレットには、授業料についても書かれている。サマーセッションの受講料は、滞在と授業料を含めて400ドル。しかし受講生の経済状況によって、最低150ドルまでは考慮される。キャンプは定員20人で週14ドル。部屋、食事、および設備使用の費用が含まれている。参加期間は1ヶ月以上であれば自由だったようだ。安いのか高いのかよくわからないが、経済的に余裕のある(そして進歩的な考えを持つ)者しか、こういう学校には関心をもたないだろう。しかも戦争の真っ最中なのだ。ほとんどが北東部かニューヨークからの学生だったという。パンフレットから引用する。
夏期講座では学生がブラックマウンテンカレッジを試すことができ、そしてブラックマウンテンカレッジも学生を試すことができます。カジュアルな好奇心からサマーセッションに参加したのち、多くの学生はカレッジコミュニティの正規メンバーとして残っています。……ワークキャンプに志願できるのは、高校2年生以上、または大学生です。キャンプ参加者は地域社会の一員として責任を負い、地域社会の生活に貢献する能力が必要とされます。……参加者は1日5時間労働、一部の人は、部屋と食事の費用を稼ぐために8時間まで働くことができます。これらの時間は単位互換にも使うことができます。
“Black Mountain College Bulletin”, 1944
キャンプでの労働は、5時間を学習として行ない、プラス3時間働けば報酬があったようだ。寝食の足しにと書かれているが、前述のとおり、生活に苦労している学生は少なかったはずである。
BMCのカリキュラム
通常のカリキュラムについても書いておこう。毎年発行される学校案内には、理念やコース内容、教員紹介、募集要項について書かれている。ごく一般的な学校案内といっていいだろう。違いがあるとすればその内容だ。
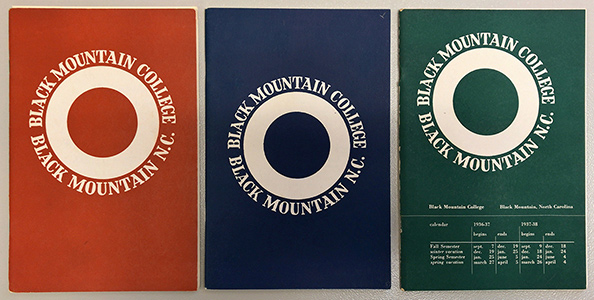 [図3]BMC学校案内。右が1936–37年版(ほかは不明)
[図3]BMC学校案内。右が1936–37年版(ほかは不明)
各授業は教員の専門によって提案されるので、芸術、哲学、社会学から生物学、化学、物理学まで、バラエティはあるが体系化されているわけではない。本来はリベラルアーツ全域をカバーしたかったのだろう。しかし、学校の規模から考えてそれは難しい。そのため、教員と学生が相談しながら、それぞれが複合的なコースを組むようにしていた。
最初の2〜3週間で授業を見学し、その後、履修コースを決める。全てが少人数のクラスなので教員との相性が一番の問題となるが、上級生によるいわゆるメンター制度のようなものがあり、彼/彼女らのアドバイスが一番有効だったという。選択後のドロップアウトも自由だったようだ。
新入生は、まず入門コース(introductory courses)を取ることが推奨された。入門コースにはアルバースのドローイングやライスの古典学などがあったが、受講しない学生もいたようだ。必修と書かれた資料もあるが、履修しなくても問題なかったのだろう。
教室は決まっておらず、ロビーや食堂、屋外などいろいろなところで開講されていた(もちろん教室はあった)。当時にしては珍しく、スーツにネクタイのようなスタイルの教員はほとんどいない。学生の服装も自由だった。学生も教員もファーストネーム、あるいはニックネームで呼び合っていた。
BMCの教育構造の特色は構造がないことだ。全てがプロセスだったのだ。
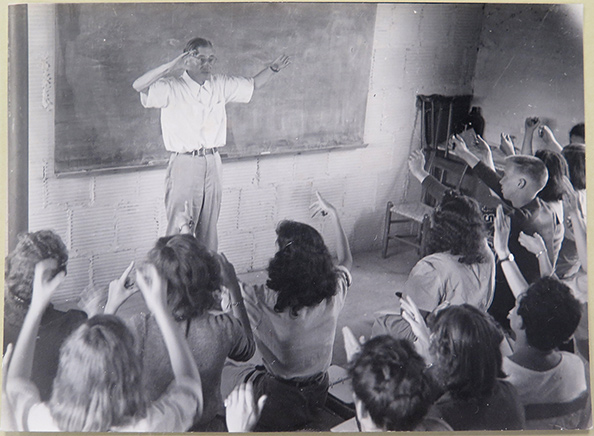 [図4-1]アルバースのドローイングクラス
[図4-1]アルバースのドローイングクラス
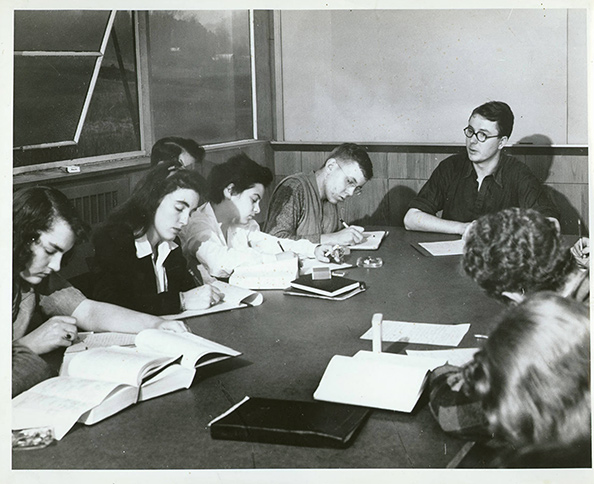 [図4-2]エリック・ベントレーの歴史クラス
[図4-2]エリック・ベントレーの歴史クラス
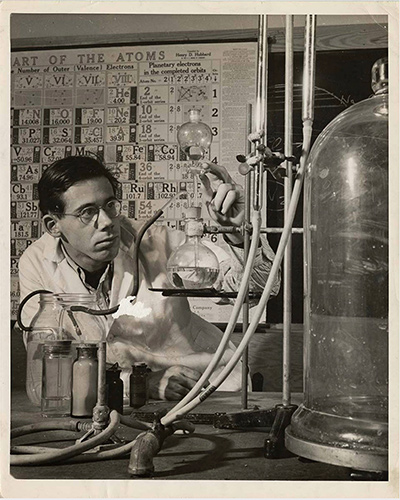 [図4-3]化学実験室で実験する学生
[図4-3]化学実験室で実験する学生
このように書けば、何もかも自由なようだが、決まった制度はあった。一般的な学習課程として、新入生はジュニアクラス(the Junior Division)からはじめ、広汎にリベラルアーツ科目を学び2年間基礎教養を積んだあと、シニアクラス(the Senior Division)に入るための試験を受ける。シニアクラスは専門課程で、個々人でテーマを決め、卒業に向けて研究する。
進級・卒業に関する単位取得の規定や要件はなく、認定は教員の総合的な判断によるものだった。ただし、他大学との単位互換のための単位規定はあった。成績もつけられていたようだが、それを学生たちに伝えることはしなかった。
出席名簿などの資料から、多くの学生は卒業前に退学したことがわかっている。入学したおおよそ1200人の学生のうち、卒業した者はわずか60人程度だったという※3。
在学した人たちの手記を読んでいると、いわゆる“卒業”にはあまり関心がなかったようだ。卒業したところで何らかの学位が取得できるわけでもないのだから、当然と言えば当然だ。やはり、学校というよりコミュニティという意識が強かったことが感じられる。
アルバースの講義ノート
最初にNCアーカイヴズを訪れたとき、突然紹介してもらったものだから何があるのかもわからず、とりあえずアルバースの資料を出してもらった。
そのなかで、ぼくが興味を持ったのは、アルバースを招聘するときの書類やアルバースが書いた寄付を求めるための手紙である。前者は第1回で少し触れたが、後者はスキャンしたきりになっている。まぁ、お金を無心しているだけで面白い話ではない。アルバースは英語が全くできずに赴任してきたはずだが、すぐに英語で手紙を書いている。多少英語ができたアニが代筆したか、秘書がついていたかのどちらかだろう。
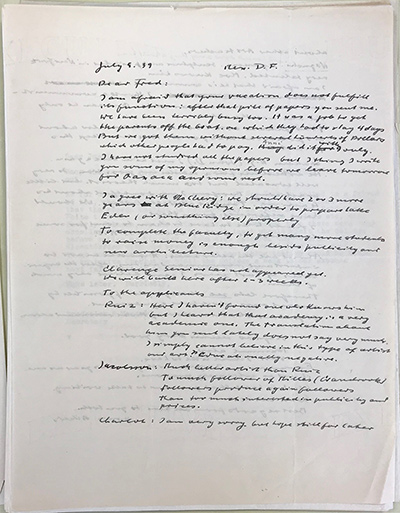
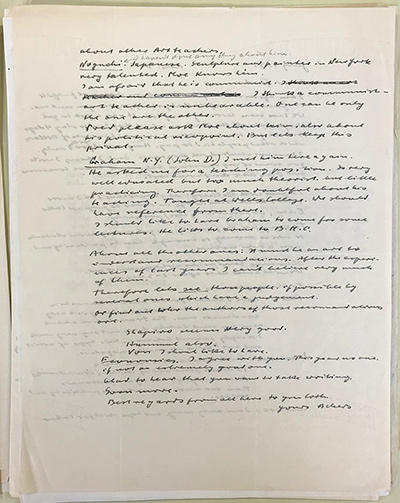 [図5]アルバース自筆の手紙(1939年7月)
[図5]アルバース自筆の手紙(1939年7月)
資料のなかにはたくさんの写真があって、授業風景からアルバースが熱心な教育者であったことが伺える。しかし、制作しているところの写真は不思議なほどない。この時期アルバースは、ブラックマウンテン時代を象徴する落ち葉のコラージュや、リトグラフによる線の抽象構成などを精力的につくっており、1936年から41年の5年間にギャラリーや美術館で21回以上もの個展を開いている※4。
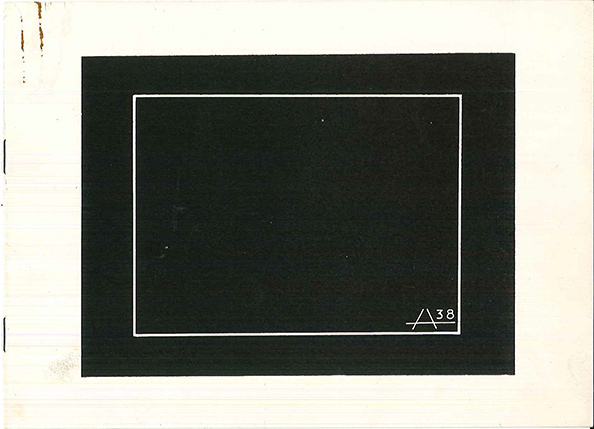
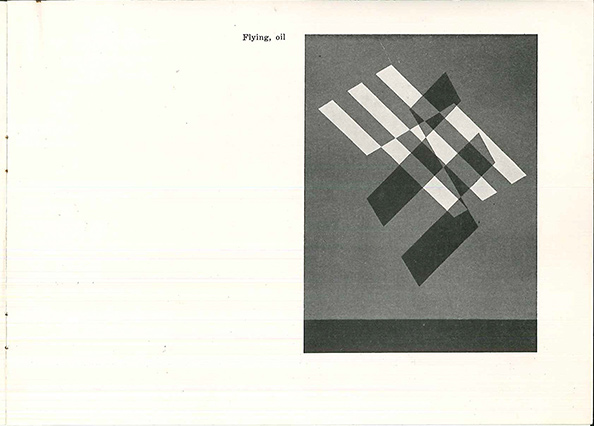 [図6]ジョセフ・アルバース個展のカタログ。表紙と中ページ。1938年12月、Artist’s Gallery, NY.
[図6]ジョセフ・アルバース個展のカタログ。表紙と中ページ。1938年12月、Artist’s Gallery, NY.
制作風景を撮られることを嫌っていたのかも知れないな、などと思いながら資料を繰っていると、いくつかのノートが目についた。どうも学生がとったアルバースの授業のノートのようだ。かなりベーシックな色彩と造形の講義で、バウハウスの基礎過程もこのようなものだったかと思わせる。
お願いして、一番丁寧にとっていたビート・グロピウスという学生(1943年から46年まで在籍)のものをスキャンしてもらった。タイトルに「色彩とデザイン(Color and Design)」とあるが、カリキュラム上は「色彩」と「デザイン概論」の二つの授業に分かれており、夏期講座期間、それぞれ週1回午前中に開講されていた。
ノートは全部で137ページ、1ページ目からいきなり「色の相互作用」についての洗礼を受けている。アルバースの色彩理論として名高い『インタラクション・オブ・カラー※5』の祖型だ。
熱いお茶を紙コップと金属のコップで飲むときの身体感覚の違いを例に、物理学者と心理学者と色彩学者、それぞれの色のとらえ方の違いを説明する。たとえば「白」であれば、物理学者はすべての色の総和であるとし、心理学者は色のひとつであると考え、色彩学者は単なる色と捉えると解説している。そして、背景色によって同じ赤でも違う赤に見え、違う黄色でも同じ黄色に見えるという色の相互作用をカラーチップで体感させる(ノートはモノクロコピーなのでカラーチップの実際を見ることはできないのだが)。
そういう話を終えて、ゲーテの色相環、マンセルやオズワルドの色立体を講義し、補色対比や明暗対比などの色の関係の話に進む。このあたりは、バウハウスの師であったヨハネス・イッテンから継承したものだろう。
次にデザインの話に移る。ページの冒頭に Design is planning とあり、そこに下線が引いてある。そして、プラニングとは組織化(organization)であり、順序立て(order)であり、構築(constraction)であり、選択(selection)であるといった言葉が並び、すなわち、行為(action)のことだと結ばれている。つまり、デザインとは行為=アクションのことだとアルバースは定義していたのだ。このあたり、実際の講義を聴いてみたかった気もする。
そして、話は幾何学的造形へと展開する。1枚の紙を折ることで生まれる造形から3次元の空間が立ち上がることをメモしたノートは、当時のアルバースの抽象造形への興味を追体験しているようで面白い。
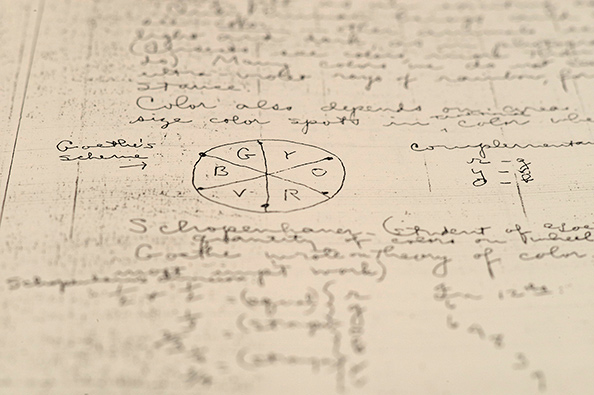
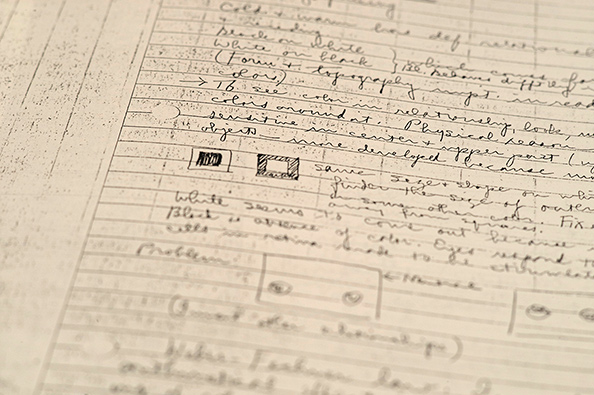 [図7-1]ジョセフィン・レヴィンの授業ノート(1946年夏期講座)
[図7-1]ジョセフィン・レヴィンの授業ノート(1946年夏期講座)
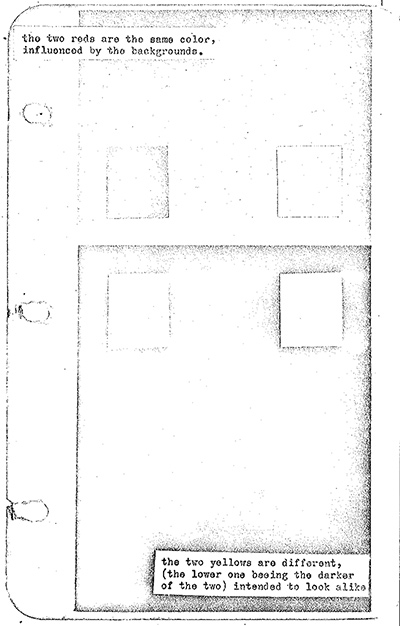
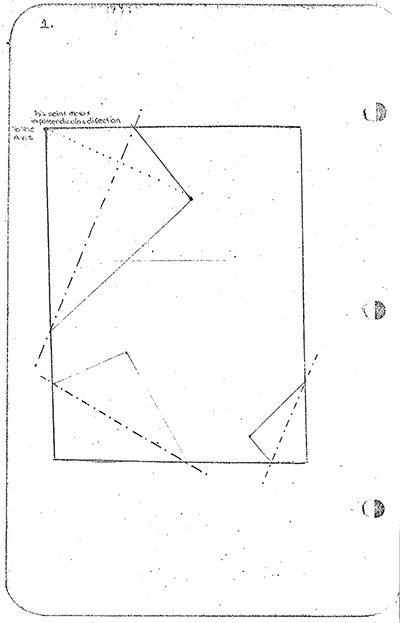
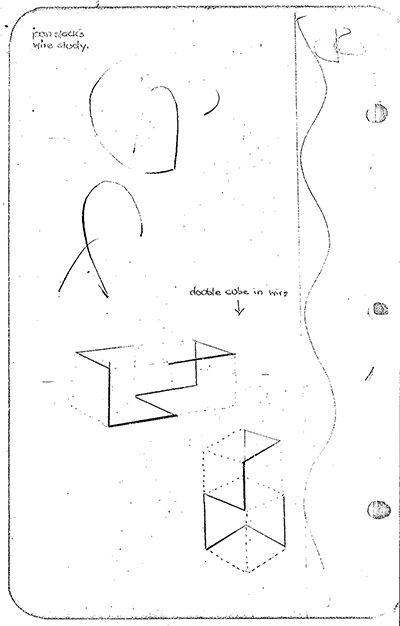
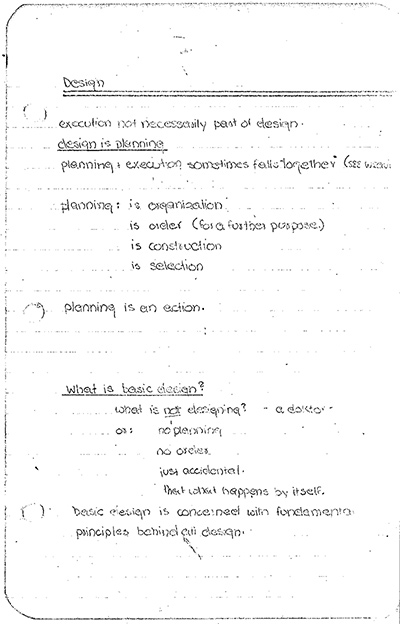 [図7-2]ビート・グロピウスのノート
[図7-2]ビート・グロピウスのノート
幾何学的造形理論は、バウハウスから引き継いだものでもあるが、この時期、アルバース夫妻はメキシコに良く出かけており※6、二人はそこで見た遺跡や幾何学的建造物にインスパイアされて新たな造形を生みだしている。アニは織物の構造を用いて幾何学的反復を再現し、アルバースはリトグラフで線の重なりから空間が立ち上がることを示した。二人の作品は同調しているようにも見え、互いに深く影響を与え合っていたことは誰の目にも明らかだ。
このノートからアルバースのデザイン理論の基本的な考え方を読み取ることができ、その色彩と造形の究極のかたちがのちの「正方形賛歌(Homage to the Square)※7」のシリーズであることがわかる。ちなみに「正方形賛歌」は、平面構成ではなく、立体物(四角錐)を真俯瞰から見たところの図だとされている。アルバースはその空間性を指して「作品が地上を離れて,天上へ昇ろうとする動き」だと説明しているが、その原型はメキシコのピラミッドにあるのだろう。
ノートは、タイポグラフィとコンポジションに触れたところで終わっている。
この授業は、最初、1944年の夏期講座で行なわれ、その後「色彩とデザイン」コースとして毎年開講されるようになった。アルバース退任後も学生だったピート・ジェンナージャーン※8が授業を引き継いだ。
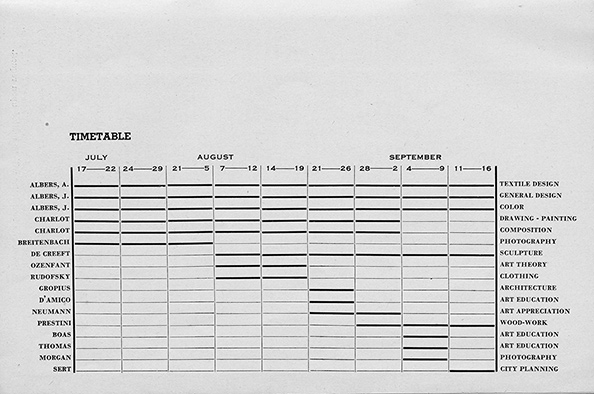 [図8-1]1944年夏期美術講座のタイムテーブル。グロピウスやダミコは1週間しかいなかったことがわかる
[図8-1]1944年夏期美術講座のタイムテーブル。グロピウスやダミコは1週間しかいなかったことがわかる
 [図8-2]夏期講座での色彩の授業(1944年)
[図8-2]夏期講座での色彩の授業(1944年)
このノートから、アルバースが中心となった40年代中期BMCの雰囲気を感じ取ることができる。ライスが構想したデューイの実用主義に基づく進歩的自由学校の美術教育に比べてアカデミックな香りが強く、体験するだけではない“創作としての芸術”を重んじた。その厳格さが学生からの信頼に繋がり、学外にも多くの信奉者を生んだ。
アルバース夫妻が長期休暇を取る1946〜47年ごろまでこの傾向が続き、48年の夏期講座にバックミンスター・フラーが加わったあたりから、風向きが変わってくる。秋にはロバート・ラウシェンバーグが入学し、チャールズ・オルソンが着任。はじめてジョン・ケージとマース・カニンガムの講演が行なわれたのも、同じ秋であった。
ウンシュの事件
前回も書いたが、BMCがアフリカ系米人※9を受け入れたのは1944年の夏期講座からである。アルマ・ストーン・ウィリアムズ※10という音楽を専門とする女性だった。開校から10年の時間を費やしたが、ほかの南部の学校と比較するとかなり早い措置だった。
1944年初頭、ライスと行動を共にしてきた初期からの教員たちは、教員会議の重要な議題として人種統合の問題を押し出していた。一部の教員が反対を表明する一方で、ジョセフ・アルバースら亡命芸術家たちは統合そのものには反対ではなく、むしろそのタイミングに反対していた。多くの教員や学生は、大学が地域社会との軋轢を生むような行動をとることについて懐疑的な考えを持っていた。学内だけではなく学外からもアフリカ系米人学生の入学許可を控えるようにという意見があったが、学長のウンシュは公平な立場をとることを試みた。
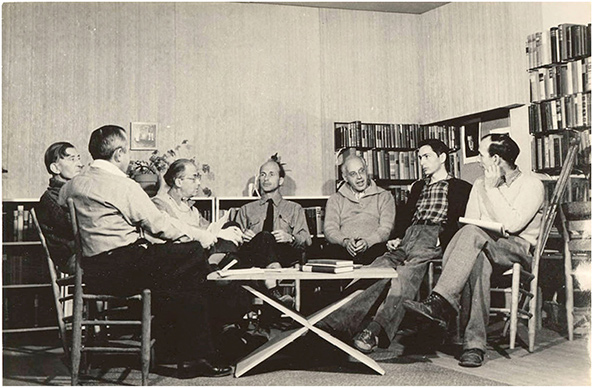 [図9]教員会議の様子。左から、ロバート・ウンシュ、ジョセフ・アルバース、ハインリッヒ・ジャロウィッツ、テオドール・ドライアー、アーウィン・ストラウス、不明(学生代表?)、ローレンス・コーチャー
[図9]教員会議の様子。左から、ロバート・ウンシュ、ジョセフ・アルバース、ハインリッヒ・ジャロウィッツ、テオドール・ドライアー、アーウィン・ストラウス、不明(学生代表?)、ローレンス・コーチャー
ウンシュはこの問題に対し、彼の黒人仲間や友人たちに意見を求めることにした。彼は、ロリンズ大学時代からの友人であるゾラ・ニール・ハーストン※11に手紙を書いた。ハーストンはアフリカ系米人の作家で、文化人類学者でもある。ウンシュはその手紙で、BMCが南部の論理から脱却するのに今が適切な時期かどうかを尋ね、「私は臆病になりたくない。同時に、無謀なこともしたくない」と綴っている※12。
「(黒人学生の受け入れは)大いに注目を集めることになるだろうけど、それは必ずしも私たちに良い結果をもたらすとは限らない」。ハーストンからの返事は警告とも取れる内容だったが、教員会議は夏期講座に黒人学生を招待することで決着がついた。ただし、身分は学生ではなく研究員としてだった。候補に挙がっていたアルマは、すでに充分に高い教育を受けており、奨学金の取得も決め手になった。妥協案とはいえ大きな一歩だった。
人当たりの良いウンシュだったからこそ、この采配ができたのだろう。かなりのリスクを伴う決断だったはずである。このことによって1名の学生と会計係が学校を去ったが、社会的なトラブルを回避し、BMCにおける人種統合への道を拓いた※13。
ウンシュは人種問題に対して分別と配慮をもって対峙し、この難問を解決した。それは、彼自身もマイノリティだったからできたことなのかもしれない。彼は同性愛者だった。
ウンシュが同性愛者だということは、BMCのなかではよく知られていることだったという。ウンシュだけではない、BMCは性的少数者を暗黙のうちに受け入れており、誰もそれに対して意見をいうようなことはなかった。
開学以来男女共学であり、ヨーロッパからの芸術亡命者を積極的に受け入れ、黒人問題は開学10年を経てようやく解決し、同性愛者は暗黙の了解のうちに、だれもがBMCというユートピアに守られているはずだった。しかし、事件は起こった。
個人の車を持つ者が少ないBMCのコミュニティのなかで、ウンシュの愛車、小型のロードスターはそれなりに目立っていたようだ。ウンシュは州の演劇協会や友人のいるアッシュビルのダウンタウンに、ロードスターに乗って出かけて行くのが常だった。
1945年の6月半ば、彼はいつものようにロードスターを走らせてアッシュビルに向かった。そして友人の海兵隊員と一緒に車を止めていたところ、警官に捕まった。突然のできごとだった。罪状は「自然に対する罪(crimes against nature)」、ようは海兵隊員との同性愛による淫行を疑われたのだ。
アッシュビルの警察がウンシュを同性愛者としてマークしていたという記述もあるが、そこで何があったのかはよくわかっていない。いずれにせよ彼は逮捕された。その後起訴状は不法侵入に変更され、ウンシュは猶予付で釈放となった※14。
アメリカ南部は今でも同性愛に厳しい地区だ。2017年の資料にも“自治体における差別禁止法の通過・施行を阻止する法を有する州”としてノースキャロライナが挙がっており、性的指向およびジェンダー・アイデンティティに基づく雇用上の差別を禁じていない28の州に含まれる※15。宗教上の理由もあるのだろうが、1940年代当時の弾圧は想像に難くない。
ウンシュは、釈放されはしたが、ブラックマウンテン地域や一部教員からの怒りを避けることはできなかった。彼は大学に戻り、朝早く、前日まで歓迎されていた場所から、ハグも別れの言葉もなしに、誰と会うこともなく、小さなロードスターに乗って去って行った。学生たちもウンシュに対する処遇に抗議することはなかった。
それは、教員や学生の心の傷となっていつまでも残った。後年、なぜ別れに立ち会えなかったのか、なぜ彼に留まるように言えなかったのか、という後悔の念を、多くの人が文章に残している。
ウンシュは故郷のルイジアナに戻り、再びロードスターでカリフォルニアに向かい、そこで消息を絶った。そして、カリフォルニアで郵便配達員として働いているという噂だけが、ブラックマウンテンに残った。
実験のはじまり
1945年のBMC夏期講座には、ローゼンウォルド基金※16からの支援もあって、すでに高名だったアフリカ系米人歌手、ローランド・ヘイズとキャロル・ブライスの二人を教員として迎えることができた。今も語り継がれている夏期講座でのヘイズのコンサートは、多くの人に感銘を与え、人種的偏見からの解放の一助となった。そしてそれは、夏期講座を音楽や美術の実験の場とするはじまりでもあった。
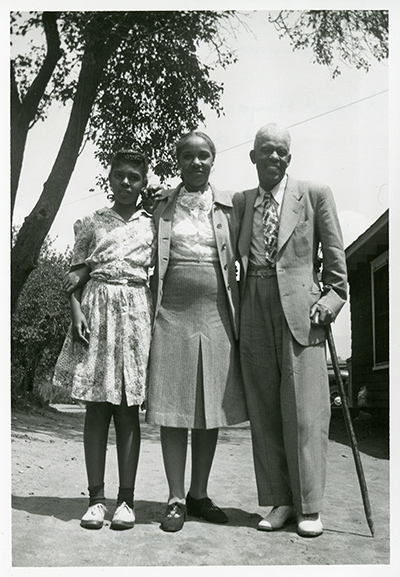 [図10]ローランド・ヘイズ(右)とその家族。3週間BMCに滞在した
[図10]ローランド・ヘイズ(右)とその家族。3週間BMCに滞在した
その場にもうウンシュはいなかったが、これは彼がいなければ実現しなかったことだ。ウンシュ事件の内実は、どの資料も明らかにはしていない。暗黙のうちに認め合った自由も、大きな力の前には無力だったことを誰もが恥じた。
そしてその後も、制作とプライベート、両方のパートナーだったマース・カニンガムとジョン・ケージの活躍にみられるように、同性愛は特別視されることなく、BMCのなかにこれまでと変わらず自然に溶け込んでいた。
次回以降は、そのカニンガム、ケージ、ロバート・ラウシェンバーグや夏期講座のディレクターとなるバックミンスター・フラー、そして残されたアルバースやもう一人の重要人物テオドール・ドライアー※17について書いてみたい。
『空間へ※1』は、磯崎新の膨大な著作の数々の中で最初に刊行されたものであり、全体で82冊※2という膨大な著作の数を誇る氏の著述のキャリアの中で、その輝かしい思考の経緯の出発の地点をなまなましく記録したドキュメントである。磯崎新という稀代の建築家が世の中でデビューを果たし、その長いキャリアを通じて世界的な建築家として活動を繰り広げるきっかけとなった、すべての思考の原点がいわば無数の宝石の原石の如く散りばめられ、その精緻な議論と視点の斬新さ、議論の射程の巨大さ、学問領域としてカヴァーする範囲の広大さに、『空間へ』に触れた人間は誰でも驚愕することであろう。
磯崎新の活動の全容とその日本の建築界、そして世界の建築界への影響力について今ここで改めて振り返る必要はないだろう。丹下健三の弟子としてのキャリアを開始し、メタボリズムの建築運動の最中に彼が発表した数々の都市計画案は世界の若い建築家達を即座に魅了し、アーキグラムなどの前衛的な建築運動が世界で立ち上がる直接的なきっかけとなっただけでなく、その後ポストモダン・ムーブメントとして世界を風靡することになる先鋭的にしてラディカルな世界の建築家の活動の数々にいち早く着目し、その流れを日本に紹介するばかりでなく、自らも先鋭的なプロジェクトの数々を発表し、1970年代の前半に実現を果たしたそれらの数々の大規模な公共建築群は日本国内のみならず世界の建築シーンに巨大な衝撃を与え、以後日本国内および世界の建築界における最先端のシーンを牽引するトップランナーとしての地位を確立することになる。設計を手掛けるプロジェクトの数と種類、規模は飛躍的に拡大し、設計活動の舞台は世界中に広がるのみならず、数々の国際的な設計コンペティションの機会において審査員を務め、当時はまだ無名であったザハ・ハディドらの新人の建築家の数々を発掘し、世界の建築シーンにデビューさせるのみならず、都市計画のプロジェクトのプロデュースを幾つも携わり、レム・コールハース、スティーブン・ホールらまだ若く実作に恵まれない野心的な建築家達に数々に実作の機会を与え、国内でも同様に無数の若い建築家達に実作の機会を提供し、今日世界的に前衛的な建築家が活躍するシーンの下地を生み出したという事実の数々は、ここで改めて記す必要もない程広く知られている。
このように甚大な影響を世界の建築シーンにおいて炸裂させた建築界の巨星の、思考の端緒のすべてがこの『空間へ』には収められている。私自身この書籍に触れた時の衝撃は大きく、オランダに留学を文化庁の奨学金にて行い、ロッテルダムに滞在した折に、日本から2冊だけ持っていった本のうちの1冊が、この『空間へ』であった。いわばこの本は、当時、建築の設計とデザインを志す者の間で、のみならずおよそ建築と都市について思考する人間にとって、共通の一種の〈聖典(バイブル)〉のような存在であったといってよい。建築の設計を志す同世代の友人の家を訪れると、かならず書棚にはこの『空間へ』と『建築の解体※3』が収まっているのを見かけることができた。あたかも敬虔なカソリックの信徒にとってベッド脇にそっと置かれている聖書のようにして、この『空間へ』はおそらく今日世界的に活躍する著名な建築家を含めて実に多くのさまざまな建築の設計を志す人間を精神的に支えてきたのではないだろうか。またこの本は数多の建築の設計を志す人間にとってかけがえのない思考の導きの糸となり、建築家としてデザインを世に問うために誰しもが通過する自らの独自のデザインを確立するための思考へと深く沈潜するその時期において、自らのデザインを確立するために不可欠となる建築と都市のあり方とは何かを本源的に問いただす、いわば「根源へと遡行する思考」へと数多の建築家を駆り立てていったのではないだろうか。少なくとも私にとって、『空間へ』はそのような導きの糸であり続けていた。
『空間へ』は磯崎新の1960年から1969年にかけて様々なメディアに発表された文章やエッセイの数々を発表順に収録し、磯崎新の1960年代の思考の流れをクロノロジカルに読み取ることが可能なように構成された論考集であるが、収められた内容は広範に及ぶ。その記述の対象は、「孵化過程」のエッセイに代表されるような都市に対する具体的なヴィジョンの提案から、「都市デザインの方法」のような都市設計の手法を体系的に論じたもの、あるいは「プロセス・プランニング論」のような独自の建築設計の手法をまとめたもの、「闇の空間」のエッセイに象徴されるような建築空間や都市空間に対して独特のアプローチによる考察と探求を経て到達した独自の空間論、「日本の都市空間」のような日本文化の特性に基づいた都市空間のあり方の理論的な考察、「見えない都市」にみられるような未来都市に対するヴィジョンと考察、「世界のまち」のような世界各地の都市や集落を実際に訪れて廻った体験を綴ったエッセイの数々、はたまた巻末に収められた建築家のとしての自らのアイデンティティの形成にまつわるエピソードの数々を綴った「年代記的ノート」、など、この本に収められた文章の守備範囲は多岐に亘り、書籍全体の内容を要約し概略として示すのは著しく困難である。
また『空間へ』が「日付の付いたエッセイ」と著者自らによって名付けられていることからも伺えるように、それらの文章は基本的には雑誌媒体等への発表順に配置されたものであり、この本の構成がなにがしかの理論的な結論へと収斂してゆくことを意図したものでは決してない。しかしながら『空間へ』の構成を丹念に探ってゆくと、そこには明らかに1960年代の10年間を通じての磯崎自身の思考の流れの系譜とそれぞれの時期ごとの思考の主題を読み取ることが可能である。具体的には1960年~1961年にかけてのさまざまな未来都市のイメージを具体的なヴィジョンとして提出することを主眼としていた「都市のイメージの胚胎期」とでも呼びうる時期、続いて1962年~1963年にかけての都市とは何かについてのリサーチと思考を精緻かつ体系的に行い、その成果を綴る作業に没頭した「都市理論の体系期」とでも呼びうる時期、続いて1964年~1965年にかけての、世界中の都市や集落を実際に訪れてその体験を考察した「都市空間への身体的な耽溺期」、そして1966年~1967年にかけての、それまでの都市、建築の設計の理論を実際の都市設計、建築設計へと応用し検証を行った「都市・建築理論の実践と検証期」、そして最後の1968年~1969年にかけての当時の世界的な政治状況の中で混乱・拡散してゆく都市のあり方で都市と格闘する過程を記した、「混乱・拡散してゆく都市との対峙の時期」とでも呼びうるような5つの時代区分に『空間へ』全体に収められた数々の論考とエッセイの配置を大まかに分類することが可能であろう。そしてこの中に、このような大きな流れとは幾分不連続な形で、「孵化過程」(1962年)、「プロセス・プランニング論」(1963年)、「闇の空間」(1964年)、「見えない都市」(1967年)というその後も磯崎新自身の思考と理論の展開の原点として広く参照されることとなる重要な文章が配置されるという構成を取る。『空間へ』の相互の議論が絡み合いながら時には錯綜・反射し合い、輻輳する複雑きわまりないあたかもそれ自体が都市そのものであるかのような議論の構成を理解するとしたら、おそらくはこのような見取り図を描くことができるのではないか。
このように建築と都市空間にまつわる思考が多岐に渡る視点から広範に展開する数々の論考が収められ、1971年の刊行の直後から今日に至るまで建築の世界においてあたかも一種の〈聖書〉の如く長い期間に及んで広く読まれてきた『空間へ』であるが、ここに収められた議論を今改めて読み返して驚くのは、その議論の数々の射程は今日でも依然有効であるばかりでなく、いやむしろ今日の都市と建築をめぐる議論において、この本の数々の原稿が執筆された1960年代の当時よりも、今日の情報ネットワークとコンピュテーションが社会の隅々にまで浸透した状況において、この本に収められた数々の議論の内容の重要性と意義は明らかに増大しているという事実である。
今日の激しく進展を遂げる情報化社会の中で、さまざまな表現がコンピューターを介して生み出されている。プロダクトデザイン、グラフィックデザイン、映像、音楽、出版、広告、いうまでもなく建築の設計、都市計画の分野も含まれる。芸術の分野全般も今日ではかつてのように手作業のみで完結するものではなく、創作の過程において多かれ少なかれコンピューターという情報技術の影響と恩恵を被っている。このように言ってみればすべての創作と表現がコンピューターを介して行われる現在、表現を支える創作の論理、美学、哲学は根本的な変化を遂げ、不可避的に大きな変容を果たしていると言ってよい。
その変化をもっとも端的に指し示すのが、フランスの哲学者、エリー・デューリングによる「プロトタイプ論」であろう。哲学・美学の領域において今日世界で最も注目を集めるフランスの新鋭の哲学者、エリー・デューリングによって2009年に発表されたこの「プロトタイプ論※4」においては、従来の芸術の観念とは異なる「プロトタイプ」としての芸術という概念が、それまでの芸術概念とは対比され、「準芸術(quasi-objects d‘art)」として提起されている。この「プロトタイプ」としての芸術という概念の提出によって一躍世界的にその名を知られることになったエリー・デューリングであるが、この概念を紐解くと、そこには今日の情報技術が進展を遂げた社会における芸術のあり方、創作の論理についての最も先鋭的な思考を見て取ることができるだろう。ここでその理論の概要を簡単に一瞥したい。
そこではまずフランスの科学人類学者、ブルーノ・ラトゥールの定義したハイブリッドと純粋化という議論の枠組みが前提とされている。ブルーノ・ラトゥールは世の中のあらゆるものが複雑なネットワークを構成しており、この複雑なネットワークは「ハイブリッド」と名付けられ、同時に近代という時代においてはその複雑なネットワークが絶えず隠蔽されてきたことを指摘する。この隠蔽化の作業は「純粋化」と呼ばれ、近代という時代においてはこのハイブリッドが純粋化のメカニズムによって単純化され、今日私たちが一般的に見るような社会の諸制度の数々が生み出されてきたと語る。このような近代の社会のあり方を解きほぐし、物事の実体を再び複雑なネットワークとして、つまりはハイブリッドなものとして世界を捉え返すパラダイムをブルーノ・ラトゥールは提示する。そのような世界のあらゆる物事を複雑なネットワークとして眺める視点は今日の哲学・人類学の世界においては「存在論的転回(オントロジカル・ターン)」と呼ばれる。
しかしこのような観点は、主に2000年代以降さまざまな分野に浸透し、芸術・美学の世界においては「関係性の美学」と呼ばれる立場が広く浸透し、リレーショナル・アートに代表されるような、主にコミュニケーションそのものを題材とし、作品自体を極度に軽視する流れが生み出されることとなる。エリー・デューリングの「プロトタイプ論」が批判するのは、まさに芸術と美学の分野におけるこのような傾向についてである。エリー・デューリングは世界そのものが複雑なネットワークであることは認めながらも、そのネットワークを無際限に拡張し、作品としては最後に何も物理的な実体が残らないリレーショナル・アートの動向を「ロマン主義」と名付けて批判し、攻撃を加える。対して、複雑なネットワークのあり方を、その動的に変化を遂げてゆく無限の流動的なネットワークのあり方を一時的に「切断」し、作品が物質的な安定性を保持する状態を「プロトタイプ」と名付ける。この「プロトタイプ」は作者の観念が一時的に視覚化されたものであるとされ、その後に続く無数のバリエーションの存在や、その後の絶えざる変容の可能性を示唆するものとされる。いわば、近代の芸術の完結したオブジェクトでもなく、また無限のネットワークを指し示すことを主眼としたリレーショナル・アートのようなオブジェクトの不在のプロジェクトとしての芸術でもなく、そのどちらでもない中間の状態を指し示す芸術のあり方を指し示すものであると言える。ここでは、オブジェクトとしての作品の意義が「プロトタイプ」として新しい位相のもとで照射され、全く新たな形で指し示されていると言ってよい。
重要なのは、この「プロトタイプ」としての芸術のあり方が、今日の、そしてこれからの芸術のあり方を模索するための大きな方途を指し示しているという点である。というのも、あらゆる表現がコンピューターを介して制作される情報の時代においては、制作とは、そして創造とは、旧来の意味での制作や創造とは異なり、無数のバリエーションの中からとりもなおさずひとつのバリエーションの選択を意味することになるからである。このバリエーションの選択という作業が、エリー・デューリングの「プロトタイプ論」における「切断」の概念の内実となる。コンピューター上での表現は、変数を無数に入力することによってほぼ無限ともいえる表現のバリエーションを即座に生成することが可能となる。そのために、制作とは、創造とは、この無限のバリエーションの中から、ひとつの変数を選択するという行為、いわば流動しかつ無限の変動の可能性を示唆するコンピューター・アルゴリズムの織りなす関数のネットワークの中にひとつのパラメーター(=変数)を投じてそのネットワークを「切断」するという行為に、その重要な力点が移行することになるのである。ここで「切断」された変数が、すなわち実際の作品として、オブジェクトとして立ち上がることになるのだ。建築の場合では、コンピューターのモニター上で変数の投入に従って刻々と多様に変化を遂げてゆくヴァーチュアルな形態のあり方から、ひとつの変数を選び出す作業が、「切断」に相当することになる。この「切断」の経緯を経なければ、コンピューターのモデル上で多様に変化を遂げてゆく建築の姿は、物質として、現実の空間として私たちの前に立ち現れることは、決してない。
ここで『空間へ』の中に収められた論考の数々を読み返してみると、磯崎新が1963年に大分県立図書館を設計する際に独自の設計論として組み立てた「プロセス・プランニング論」に、このエリー・デューリングによる「プロトタイプ論」で提示された今日の情報の時代における芸術のあり方、すなわち「プロトタイプ」の創作のあり方に極めて酷似した論理の体系を、私たちは見出すことができるだろう。
「プロセス・プランニング論」において、磯崎新は動的に変化を遂げてゆく流動的なプロセスを提示し、その動的なあり方とダイナミズムを内包しつつ、最後にその動的で流動的な変化を遂げてゆくプロセスが「切断」される様を描き記した。そもそもは敷地条件が決定しているのみで、予算も規模も決定せず、一切が流動的であるという困難な条件下におかれた磯崎新が、独自の手法で、大分県立図書館の建築を組み立てるために編み出した苦肉の策とも言える方法論であるが、動的な諸条件の中から機能を導き出し、その機能を類型化することによってエレメントを生み出し、そのエレメントの相互の関係性をスケルトンとして定義し、それらの様態がプロセスに応じて刻々と変化をしてゆく様子を「プロセスの建築」と呼びならわし、これらは一切が流動的で可変的な条件と状況に応じて変化を遂げるプロセスそのものであるが、しかし最後の一瞬においてそのプロセスが「切断」されることにより建築物としての具現化・現実化を果たすという独自の建築の創作のあり方が指し示されている。
ここで重要なのは、条件に応じて自在に対応し流動的に変化を遂げてゆくプロセスが「切断」されることによって、初めて建築として具現化されるという視点が明確に打ち出されている点である。この「切断」のイメージは、当時のメタボリズムの建築家たちの共通した発想と比較して考えるとその独自性が顕著に浮かび上がるだろう。当時のメタボリズムの建築家たちの発想は皆おしなべて社会工学に裏打ちされた未来志向であり、メタボリズム=新陳代謝の言葉に端的に表れているように未来への無限の成長と発展を暗黙の裡に前提としていたと言える。このことはメタボリストの建築の作品が、いずれもメガストラクチャーの内部に設えられた居住ユニットが自在な更新、つまりは新陳代謝を意図して設計されていた事実に伺えるだろう。しかしたとえば黒川紀章の代表作である中銀カプセルタワーが、メガストラクチャーに吊り下げられたカプセルとしての居住ユニットがたやすく更新をされることを意図されながらも、それらは決して現実には更新されることはなかったという事実に端的に表れているように、メタボリズムの建築の作品は、未来への無限の成長・発展を夢見ていながらも決してその夢は実現する契機を果たすことがなかったと言える。しかしながら磯崎新はそのようなメタボリズムの未来志向とは対照的に、「都市の未来は廃墟である」という終末のイメージを語りながら、当時活躍していたメタボリズムの建築家達においてはまったくのところ欠如していた「切断」の思考の重要性を繰り返し指摘する。
そして重要なのは、ここで提出された「切断」のイメージに裏打ちされた磯崎新の創作の思考と論理が、エリー・デューリングの唱える「プロトタイプ論」における「切断」に基づく創作の論理、イメージとまったく同様のものであるという事実である。あたかもメタボリズムの建築家達の将来への無限の成長を志向した思考の限界を見定めるかのようにして、磯崎新は「切断」のイメージを提出し、エリー・デューリングもまた「プロトタイプ論」において流動変化する無限のネットワークの「切断」のイメージを提出するのだ。情報の時代の創作のあり方として今日もっとも先鋭的かつクリティカルな議論を展開するエリー・デューリングの思考の一端を、なかば40年以上も前に先取しているかのような思考を私たちはこの本に認めることができるという事実に、私たちはこの『空間へ』に収められた磯崎新の数々の議論の射程の長大さの一端を見て取ることができるのではないだろうか。
設計とは、とどのつまり無限に変化を遂げてゆく流動的なネットワークを、「切断」するという行為に他ならないのではないか。さらにこの「切断」という行為を突き詰めるならば、その根拠は、おそらくは自らの身体感覚のみを頼りにして、多様に変化を遂げてゆく流動的な状況の中で、その無限ともいえる膨大な可能な選択肢の中からたった一つの可能性を、選び出す作業に他ならなくなる。私たちは、磯崎新の「プロセス・プランニング論」に、その創作の最も重要な契機として、そのような自らの身体感覚を介しての「切断」の瞬間が、生々しく刻印されているのを、読み解くことが可能だろう。そして情報化がさらに進展を遂げ、創作のあり方が根本的な変容を被りつつある現在、この「切断」についての先鋭的な思考が封じ込まれたこの『空間へ』という書物は、今後のあらゆる建築家、都市計画家、のみならずおよそ芸術とあらゆる表現を志す全ての人間にとって、創作とは何か、その表現の根拠は何かについて思考をするための、巨大な導きの糸となり続けることだろう。
はじめに
このテキストは上妻世海の『制作へ』で提示された概念を手がかりに、詩という言語表現一般の制作をめぐるものです。制作するという行為そのものについての思考が書かれた本書を、実際の制作者や制作を志す人間が引き受ける際に重要となるのは、そこで提示される制作概念はどのように個々の表現ジャンルへと展開できるのかという問いであるとおもいます。執筆者自身は言語表現、とりわけ詩というジャンルの表現に携わる人間なので、『制作へ』を詩論として読みました。
さて、詩という言語表現はなぜここに書かれてあるテキストが詩なのか、つまり詩「以外」でないのかを説明することが非常に困難です。萩原朔太郎という近代詩人は、詩は言葉というよりもむしろ言葉を読んで喚起される感覚こそがその本質であると考えましたが、この指摘はなかなか的を得ています。なぜなら、たとえば「絵画的」「映画的」という形容は絵画や映画を担う媒体の固有性に由来する性質が見込まれているのに対して、なにかが「詩的」であると言い表されるとき、そこで注目されているのはたいていの場合、鑑賞者の情動を喚起させる表現の質だからです。「詩的な絵画」や「詩的な映画」は、それが詩というテキストに特有のなにかを含んでいるというよりも、「詩的」と形容するほかない感覚に向けられているわけです。
そうなると「詩」という表現は、言語だけを土台としているとは必ずしもいえないのではないか、という疑問が浮かんできます。であれば、詩という表現はなにをその本質的な土台としているのでしょうか。この「土台」を「媒体」と言い換えてみましょう。つまり、詩における媒体とは、なにを意味するのか? ここで、『制作へ』の巻頭テキストである「制作へ」で、しばしば「媒体との対話」という表現が用いられていることに触れてみたいとおもいます。詩を書くとき、詩人は言葉と対話をする以上に、なにと対話をしているのでしょうか?
媒体とは、そもそも対話が可能な対象として自明に存在するものなのか、どうか。メディウムの固有性に対する議論を思い返すとき、それはしばしば素朴な実在性においてとらえられてしまう傾向があります。制作において、作品は最後の最後まで姿をあらわすか(完成するか)わかりませんが、媒体そのものは作品に先行して、非芸術的な物質性を発揮しつつ私たちの目の前に存在している。その存在が疑われてしまえば、そもそも固有性を問うことさえできなくなります。
しかし、物質的な「素材」と作品の「媒体」にはいくらかの差異があると考えてみることはできないでしょうか。つまり、その固有性を問うに値する知覚が素材から引き出されたとき、私たちははじめて素材をとおして、つくられるべき作品を支える媒体との対話を立ち上げることができる。このとき、対話の条件そのものが不安定であらざるをえない詩という表現から媒体概念を考えてみることは、翻って詩に限らないさまざな表現における媒体のあり方を問いなおすための手がかりになるのではないかとおもいます。
第1章 上妻世海『制作へ』について
消費から制作へ
ひとまずは『制作へ』に収められたいくつかの文章と、同名の巻頭エッセイ「制作へ」における制作概念を急ぎ足で踏まえつつ、そこで用いられるさまざまな対概念を整理していきましょう。『制作へ』における「制作」という語は、単になにかをつくることを意味していません。というより、「なにかをつくる」ことそのものは、制作が担うある試みに比べれば、それほど重要ではないとさえいえます。それはひとつに、制作概念が「なにかをつくること」として同一視されやすい「決められた設計図通りに同じものを作ること」を意味する「生産」と区別されるものとして、もうひとつに、制作的態度が特定の制作物を「観る」側にも起こりえる(制作者/鑑賞者の差異に左右されない)事態としてある、ということです。
さて、『制作へ』で制作と対置される概念は、いま述べた「生産」と、一方で作品を受容する行為における「消費」が当てはまります。これらは制作とどのように異なるのか。鑑賞体験をめぐる具体例として、本書のインタビューからひとつ引いてみます。
消費的に「ピカソの絵っていいよね」と終わる前に、ピカソの人生を追っていったら、四次元思考の話に行くし、当時の数学によって空間の捉え方が変わったこともわかる。……好きなものを外側から見て消費するんじゃなくて、まずは自分の内側にピカソを取り入れて、自分がピカソになる。それだけで身体が複雑になっていかざるをえない。
上妻世海「制作的身体のためのエクササイズ」
つまり、鑑賞においては「外側から見ること」と「内側から見ること」の対比が、「消費」と「制作」を区別しています。作品を外在的に観るのではなく、作品を内在的に経験すること。内在的な鑑賞は、作品の制作プロセスそのものを巡る経験へと私を巻き込むものとして起こり、場合によっては鑑賞者である私の思考や存在の様態が「組み替えられ」る。それは、必然的に従来の制作者/鑑賞者の区分や、鑑賞経験そのものの再定義へとつながります。それを端的に言い表すものとして、『制作へ』は「リバースエンジニアリング」という語を用いて、次のように解説しています。
また、僕は「リバースエンジニアリング」という方法を、鑑賞するときにも制作するときにも必要なものだと考えている。何故なら、リバースエンジニアリングを上手く実行するためには、単に好き/嫌い、良い/悪い、美しい/醜いといった価値判断に基づいて鑑賞/消費するだけでなく、潜在的な可能性へと潜り込み、観察者や制作者、モノなど様々な視点を往還しながら、複数の要素間の関係性を分析し、名前をつけることで抽象的な場を生成し、変換/操作可能性を作らなければならないからである。その動的な場所から作品を体験することは、もはや鑑賞者と制作者の間の差異がその人の中にある部分的な役割に過ぎないことを意味する。
上妻世海「神話的世界へ、僕の方法、そして、僕と異なる方法」
リバースエンジニアリングとは工学用語で、製品を分解しもとのかたちに組み立てなおすことで、その技術的構造を明らかにしようとする行為を意味します。言い換えれば、「内在的に見る」とは、制作者による制作プロセスを内面化し、作品を構成する要素や要素間の関係を見ようとする行為であり、この過程が制作者と鑑賞者の両者において求められること、そして制作者はものをつくる過程においてつくられつつあるものの分析(「内在的に見ること」)を絶えず行うことから、そもそも「制作者」と「鑑賞者」の区分は個人のなかで絶えず切り替わる「部分的な役割」にすぎないわけです。
制作的空間
さて、制作に対置されるふたつの用語として、「生産」と「消費」があると先に述べました。『制作へ』において賭けられる制作概念の可能性は、このふたつの語によって表現されるだろう、「近代」からの乗り越えにあります。生産や消費という概念を成立させるために不可欠なシステムは、「制作へ」では「近代制」と呼ばれていますが、その最たるものとして挙げられるのは「AがAであること」、つまりある対象の同一性を確保し、これを保証するシステムです。
個人の時代に代わるもの、それは、しばしば素朴に信じられがちなように、集団の時代なのではない。そうではなく、ある非人称の時代。なぜなら、個人の時代が終わったとすれば、問題は、主体=客体という二元論と、そして認識 → 伝達(現実の主体的な再現)という二重過程との上に成立してきた近代の古典的な認識論そのものの崩壊にほかならないであろうからだ。そして、このコギトの消滅のうちにあらわれるもの、それはそれ自体の存在における言語であり、イマージュであり、コミュニケーションでなくて、なんだろうか。
宮川淳『鏡・空間・イマージュ』
「制作へ」はこのシステムについて、宮川淳の『鏡・空間・イマージュ』というテキストを引用しつつ説明します。近代という区分はなによりも私=主体と対象=客体の明確な分離、「私は私である」と「私でないものは私ではない」の確立にあった。それによって「消費」的な鑑賞態度、作品を外側から見ることが可能になった。
この分離について、重要な比喩となるのが「鏡」です。私たちは鏡を見ることによって、そこに私を発見し、同時に私が私であること=私の同一性を確認します。しかし、鏡に「私」が映り、それを「私」が見るという構造には、実は隠されたねじれの構造があります。「私が私であること」の確認が鏡をとおしてしか行えないのであれば、そこに映る「私」は鏡によってつくりだされた像であり、そして私の像と私を結びつけることで「私が私であること」の同一性が確認されるのであれば、鏡を見ずにこの同一性は保証されず、前提にもされていないのではないか。いわば、鏡は「私が私であること」を生産する装置であるといえるでしょう。このとき、鏡は自己の同一性が確認される「表面」と、その基盤となる「鏡のなか」というふたつの性質を持っていることが示されるのですが、この私の同一性の知覚の根源は、主体と対象という区分の設置、いわゆる二元論に基づく思考であるといえます。
「鏡」が二元論的知覚がおこなわれる場であるのなら、「鏡のなか」は二元論的知覚を可能にさせる場として存在することになるでしょう。
鏡を見ることは一般的に、主体としての私が対象としての私を見ることを意味している、と考えられているが、それだけでなく、主体と対象という二元論的知覚そのものを成立させる場所を見るという経験でもある、と言うのだ。そしてその場所こそ、宮川が「鏡の中に降りていく」と表現している場所なのである。ここに二つの「見る」がある。私が対象を見るという仕方、私が私と非—私を成立させる基体そのものを見るという仕方。鏡の表面と、その中。
上妻世海「制作へ」
重要なのは、同一性を生産するシステムが安定化し、自明視されることで、安定化した私が私でないもの=対象を観察するという、主体と客体の分離へとつながることです。近代とはこの自己の同一性と主客の分離を押し進めてきたと。
しかし、私と対象の二元論が近代制=「鏡の表面」の産物であるのなら、「鏡のなか」にはそれ以前の、非人称とでもいうべき場がありえるということになる。
《ぼく》の存在そのものの曖昧性はここから生まれる。それは決してあのいわゆる自我の非連続、不確実性を意味しているのではない。それは書くことの根源的な体験 —— 鏡の体験、二重化の体験であり、多かれ少なかれ、一人称の小説、いやすべての小説に内在する曖昧性なのだ。というより、フィクションとはおそらく、この二重化の危険な体験のいわば制度化によるエグゾルシスムではなかっただろうか。それによって、作家はおしゃべりの不毛な空間、この鏡のなかからのがれ出ることを、一方、読者は物語、この無意味なおしゃべりの背後に意味を求めることを許されるのだろう。
宮川淳『鏡・空間・イマージュ』
この「非人称」とは、制作者・鑑賞者として安定化された位置にある私ではなく、両者を行き来しながら、内在的に作品をとらえ、「私」の視点と「対象」の視点を行き来するような様態として、制作概念の核心になります。
モノと情報と人間は各々が自律的な役割を与えられ、それぞれが主と従を相互に奪い合いながら相互生成している。人間も含め世界を構成する全ての演算子は、観察するという特権的な地位を与えられていない。むしろ、全ては自己制作的であり相互制作的なのである。それは同時にあらゆる領域における定義の再編成を僕たちに要請するだろう。なぜなら、そもそも人間が自らのシステムを「感性」「悟性」「構想力」「理性」と整理し、世界を現象や確定記述の束として扱ったり、その外側をモノ自体として不可知に定めることを通じて、様々なモノの定義がなされていたからである。
上妻世海「消費から参加へ、そして制作へ」
いわば、「制作へ」における制作概念は、近代化の過程で試みられた「同一性の確保」=「私が私であること」に代表される、主客の分離=連続的な世界の分節を前提とする消費的な身体とは異なる、べつの身体のあり方を、私たちに提案しているわけです。
消費は安定した自己同一性を前提としていますが、制作においてその安定性は突き崩され、そこでは「私でなく、私でなくもない」=絶えざる視点の交換や主従関係の往還が起きる、私と他者のあいだの連続的な中間領域が開かれます。この中間領域は「制作的空間」と呼ばれます。
ここまでで二つの存在様態があることを示してきた。一つには安定した自己同一性が対象を認識するという常識的な在り方、一人称単数小説のような私小説的コギトである。第二に、鏡の空間、イマージュとミメーシスによる魅惑の世界では、「私は私ではなく、私でなくもない」といった二重否定を伴った不安定な〈私〉が取り出された。……僕はここで、描くこと、書くこと、狩ることを通じて僕たちが降りていく、あるいは落ちていく空間を「制作的空間」と名づけたい。……僕たちは、制作という媒介によって、「制作的空間」に入る。制作するためには制作を介さなければならない。この一歩、降りていく経路、落ちていくまでの経路を無視してはならない。「制作的空間」には、世界観が前提とするような全体性は客観的に存在しないのである。
上妻世海「制作へ」
「制作へ」というテキストは、この制作的空間と呼ばれる領域を「制作」するために編まれたものであるということができるでしょう。
主語的統合と述語的統合
「制作へ」で、制作的空間の画定作業は宮川淳の「鏡/鏡のなか」に始まり、さまざまな対をとおして試行されていきます。対はきわめて簡略化すれば「上部構造/下部構造」のような図式を取っていて、制作空間は両者のあいだにありつつ、下部構造寄りの場所に位置づけられます。ここで、「制作へ」で用いられている対のなかでも代表的な例である、「主語的統合/述語的統合」を挙げてみたいとおもいます。この対に向けられた思考こそが「制作へ」の根幹をなす、「制作行為による身体の再編成」に関わるからです。
主語的統合および述語的統合は、中村雄二郎の『共通感覚論』というテキストから取られたものです。まず前段として、この対のもとになる鍵概念である「コモン・センス」と呼ばれる感覚について説明します。中村いわく、この語はふたつの意味を持っているといいます。
日常経験は、多くのわかりきったこと、自明なことの上に成り立っている。そのために、もっとも身近なものでありながら、かえってありのままにはとらえにくい。あまりにも身近で、多面的で、錯綜しているために、距離をとって一定の視点からとらえることができない。ここで要求されるのは、なによりも総合的で全体的な把握、それも理論化される以前の総合的な知覚である。その点からいうと〈常識〉は、現在ではあまりその知覚的側面が顧みられないでいるが、まさに総合的で全体的な感得力としての側面を持っている。常識とは〈コモン・センス〉なのであるから。というより、ふつういう常識とは、この〈コモン・センス〉の一面をあらわしたものにすぎない。たしかにコモン・センスには、社会的な常識、つまり社会のなかで人々が共通(コモン)に持つ、まっとうな判断力(センス)という意味があり、現在ではもっぱらこの意味に解されている。けれどももともと〈コモン・センス〉とは、諸感覚(センス)に相わたって共通(コモン)で、しかもそれらを統合する感覚、私たち人間のいわゆる五感(視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚)に相わたりつつそれらを統合して働く総合的で全体的な感得力、つまり〈共通感覚〉のことだったのである。
中村雄二郎『共通感覚論』
通常は「社会のなかで人々が共通(コモン)に持つ、まっとうな判断力(センス)」としての「常識」を意味するコモン・センスは、「諸感覚(センス)に相わたって共通(コモン)で、しかもそれらを統合する感覚」=「共通感覚」を同時に意味するというわけです。いわば、互いに異なる、バラバラな感覚を統合し、対象を知覚する動的な機能である「共通感覚」が、静的な枠組みとして固定化されることで「常識」が構成される。
彼は、ここで〈コモン・センス〉が本来持っていた二つの意味、〈常識〉と〈共通感覚〉を取り出している。〈共通感覚〉は、アリストテレスが用いていたように、五感を跨りそれを統合する感得力であり、感性と理性を結びつけ、想像力を司る場所であると言われる。そして、そこから広く一般に、人々に共有され制度化された判断が常識と言われるものになったのである。つまり、共通感覚とは一種の統合作用であり、それは生成を司るものである。そして、それが静的に固定化されたものが常識なのだ。
上妻世海「制作へ」
バラバラな感覚を統合する「共通感覚」と、それが固定化された「常識」。「鏡のなか」と「鏡」の対構造が、ここでは共通感覚をめぐる対としてパラフレーズされています。中村はこの共通感覚の考察をとおして、近代史に諸感覚の編成と変容の過程を見ていきます。共通感覚は単に諸感覚を統合するだけではなく、五感のどれかを中心として、それ以外をその下部に組織化していくわけです。たとえば、中性ヨーロッパでは聴覚優位の感覚編成があり、視覚はその下位に置かれていたと。「キリスト教会がその権威をことばという基盤の上においており、信仰とは聴くことであるとしていたからである」。
しかし、時代が推移するにつれて、やがて視覚に対する聴覚の優位という構図に転倒が起こり、近代化の過程で視覚優位の編成へと移行していきます。「近代文明にあっては、ものや自然との間に距離がとられ、視覚が優位に立ってそれらを対象化する方向に進んだのである」(『共通感覚論』)。つまり、「『主体–対象–属性』という認知の在り方が近代において成立」していきます(「制作へ」)。
重要なのは、こうした時代の推移に応じて共通感覚における五感の編成が変化することで、それが固定化されることで共有される、私たちの「常識」も変化していくことです。時代によって常識が異なるのは、共通感覚における五感の編成が時代ごとに異なるからだというわけです。
さて、このようにして「常識/共通感覚」の対は、後者における五感の編成の組み替えに伴い、前者を変化させる時代の時間性へと接続されます。中村はここで、よりミクロなレベルでこの対に動性を付与します。具体的には、ベルクソンの「運動図式」やメルロ=ポンティの「身体図式」をもとに、共通感覚における諸感覚の統合機能と、それをベースとした行為への能動的な意味付与機能を身体に搭載させていきます。「制作へ」で手際よくまとめられているので、そのまま引用します。
まず「運動図式」とは、「人間の身体は、生の有用性のために組織され習慣化された〈感覚—運動機構〉として捉えることができる。それは、生理学的な意味で、求心性の感覚神経回路と遠心性の体性つまり運動神経回路との連動機構であるにとどまらない。そうではなくて、主体の行動への身構え、つまり能動的な意味賦与の作用、とのかかわりで働くものとしての、そのような二つの回路の連動機構」である。このように「運動図式」を、これまでの五感に基づいた受動的な知覚概念とは異なり、体性感覚とくに運動感覚の全体化の働きのうちに、内部世界の無意識に根ざした、行動への意味と方向を賦与したものであると評価する。他方で、それはまだ人間の身体のもつ受動的かつ能動的という両義性を捉え切れていないと考える。そして、運動感覚をただ単に運動感覚としてではなく、深層の内部知覚として捉え直すために、「運動図式」に加え、メルロ=ポンティの「身体図式」を持ち出すのだ。
「身体図式」は、〈運動感覚〉を表層における外部とのかかわりとしてだけでなく、深層の内部知覚としても捉えるものである。通常、身体の内部知覚は意識の表層には現れない。しかし、それは実存的な身体の本質的基盤であり、しかも外部知覚と連続している。無意識の苛立ちや内臓の機能不全が気分に影響を与え、それが知覚や行動に影響を与えることは、日常的に理解できるものである。「身体図式」は、〈体性感覚〉としての〈運動感覚〉を、外部世界に行為として表層的に関連づけるだけでなく、気分として潜在的にかかわらせている、主体的で可能的な身構えのことを指す。
上妻世海「制作へ」
ここで注目されるのは、視覚や聴覚といった外的な感覚と、内臓感覚に代表される内的な感覚をつなぐ、〈あいだ〉の場所としての触覚である「体性感覚」です。中村は体性感覚における諸感覚の統合を「述語的統合」と定義し、述語的統合が固定化されたものを「主語的統合」と定義します。
つまり、「常識/共通感覚」の対に加えて、ここで「主語的統合/述語的統合」の対が持ち出されます。この後者の対は、共通感覚がいかにして常識へと変化するのかを分析するものとして、共通感覚を構成する論理に組み込まれます。
〈体性感覚〉は、〈触覚〉、〈運動感覚〉、〈筋肉感覚〉が、すなわち内側と外側が交差的に入り組んだ場所である。そして、その場所は、表層である特殊感覚(視覚、聴覚、嗅覚、味覚、平衡感覚)と深層である特殊感覚(臓器感覚、内臓痛覚)を相渡る場所であり、だからこそ中村は諸感覚(特殊感覚)の体性的統合を〈基体的〉統合とも〈述語的〉統合とも呼ぶのである。
上妻世海「制作へ」
共通感覚における五感の編成は、さらに述語的統合と呼ばれる体性感覚をベースとした諸感覚の編成として細分化されるのです。そして、主語的統合は、述語的統合における諸感覚の編成が可視化され、常識へと固定化されていく枠組みを意味します。
それが〈基体的〉統合だけでなく〈述語的〉統合と呼ばれる理由は、お察しの通り、諸感覚の〈主語的〉統合と言うべきものがあるからだ。これは〈共通感覚〉と〈常識〉の対概念に相当するものである。つまり、僕たちが暗黙の裡に用いている知覚の構造、近代図式、主体—対象—属性という構造が、〈主語的〉統合と呼ばれるもの、そして〈常識〉にあたる。……〈主語的〉統合が、時代、地域、そして人によって異なるのは、この〈述語的〉統合が別の〈主語的〉統合を「制作」する潜勢力を持っているからである。
上妻世海「制作へ」
述語的統合における諸感覚の編成が、主語的統合をつくりだす。それは時代や個々人の差異に応じて複数あると。ここまでは常識と共通感覚の対にほぼ近しく、実際に「相当する」と「制作へ」では述べられていますが、単なる言い換えではないことに注意しましょう。共通感覚が主語的なものと述語的なものに分けられているのは、この感覚の統合の仕方そのものが時代において変化するという、歴史的過程との関係を記述するために試みられているからです。
そして、この主語的統合の次元こそが常識を準備する。述語的統合の次元で果たされた五感の編成=主語的統合は、いったん組織化されると、今度は述語的統合を制限し、その統合作用の方向性を抑制する働きを持ちます。この過程が社会的な次元へと拡張され、反復されたものが、常識と共通感覚の対であるわけです。
重要な点は、主語的統合は述語的統合の上に成り立つとは言え、ひとたび成り立つと述語的統合を方向づけるようになるということである。つまり、主語的統合が強烈に優位になると、述語的統合が異なる身体を「制作」することを抑制するようになる。人と違うからとか、常識的ではないという理由で、違和感や差異を無視したことは誰にでもあるだろう。
上妻世海「制作へ」
以上を簡単にまとめてみると、人々のあいだで共有される常識という観念があり、それはそのつどの時代の人々によって共有されている五感の統合と編成=共通感覚の変化に対応している。共通感覚は主語的統合と述語的統合の対に分けられ、編成そのものの変化は述語的統合の次元で行われる。編成の組み替えは主語的統合の変化によって可視化されるが、主語的統合が形成されると述語的統合の作用を限定してしまう。この主語的統合によって常識がつくられる、と。
そして、この主語的統合が「制作へ」においては近代制がもたらす同一性の確保や自他との区別=対象化のシステムになぞらえられます。ここで制作的空間は、主語的統合と述語的統合のあいだを切り開き、述語的統合=五感の組み替えによって身体を作り替える、そのための領域として要請されます。
要するに「制作」とは、この〈共通感覚〉という暗闇へと降りていき、新たな五感の秩序を形成すること、それぞれの身体を独自の身体として生成することにあるのだ。
……中世から近代にかけて〈述語的統合〉として近代の視覚中心の〈主語的統合〉が制作され、近代の只中では、その視覚中心の〈主語的統合〉から、また別の身体の制作が行われていた。一九世紀後半から二十世紀前半は、現在僕たちが置かれている状況と非常に似たものであった。機械化の波が、人々の生活を激変させ始めていた。モダニズムの芸術家たちは、動植物だけではなく、近代社会の只中で、異質なパースペクティブを取り込むことで、感応的知覚を取り戻し、それぞれの身体を制作していたのである。
上妻世海「制作へ」
制作的空間の足場としての作品=主語的統合
さて、このようにして「制作へ」における制作的空間の持つ意義が明らかになりました。制作的空間が位置づけられるのは主語的統合と述語的統合の「あいだ」ですが、組み替え自体は述語的統合の次元で行われます。制作とはこの身体の組み替えを行う行為を意味する。
では、一方で制作をとおして生み出される作品はどのように位置づけられるのでしょうか。「制作へ」において作品が持つ意義は、近代制と制作的空間の両者に関わるものとして想定されます。しかし、重要なのはなによりも制作そのものであるとくり返し「制作へ」では述べられ、作品そのものはあまり特権的な地位を与えられていません。むしろ、制作過程で生み出される副産物であるとさえ形容されます。
芸術家とは「作品」を作る人を指すのではない。上記のように、「作品」は、あくまで「制作」という媒体との対話を通じて、私と非–私が不安定に循環し、私と対象それ自体を生成し、その中で〈あいだ〉に生じるものが〈形〉として外在化されることで、外側から見たときに「作品」と呼ばれるだけのことなのだ。それは同時に「作者」と「読者」を生む。しかし、それは副次的なことである。重要なことはそれぞれの諸感覚を再構成すること、それぞれの身体を制作することである。
上妻世海「制作へ」
つまり、作品は主語的統合(主体と対象の峻別を担うシステム)を不安定化させ、主体と対象が絶えず往還しあう「あいだ」の空間である、制作的空間の外在化において生じるものにすぎないと。作品は、述語的統合に対置される主語的統合、ないしは常識のようなものと平行関係にあります。常識は特定の時代において、共通感覚が固定的なものとして外在化され、だれかへと共有・伝達される過程を意味するからです。イコールで結べば、述語的統合=五感の再編成=制作は、それが外在化されることで主語的統合=常識=作品となる。そしてある作品が人々のあいだで共有されるにあたって、近代制のもとで作品に同一性が与えられ、流通する過程を不可欠とします。その意味で、作品という存在を支えるのは近代制というシステムの側によるものです。
「私が私であること」を保証するために作り上げてきた一連の制度を、近代制と呼んでもよいくらいだ。絵画という制度、作品という制度は、まさにそれらを象徴していると言えよう。
上妻世海「制作へ」
なぜ、「作品」は制度を象徴するのか。作品は「私が私であること」に通じる同一性の保証を可能にする制度として、「作品が作品であること」の同一性を保証する制度を必要とするからです。そして、この保証を通じて私たちは作品を消費し、場合によっては同一性のレベルを操作することで、図録や複製物といった作品の(ある一定のレベルにおける)等価物を生産しさえします。
しかし、近代制のベースとなる主語的統合は、単に否定されるべきものではないことに注意しましょう。「私」や作品の同一性を保証する主語的統合は、制作をとおして乗り越えられるべきものではなく、制作的空間そのものが充填されるべき「あいだ」をつくるために、不可欠な要素でもあるのです。「制作へ」では、しばしば制作的空間における制作や、述語的統合における諸感覚の組み替えが強調されますが、こうした制作が可能になるのは、私たちがすでに主語的統合を備えているからです。べつの主語的統合をつくるためには、「この」主語的統合=「鏡」を通じて、「鏡のなか」に降りていかなければならないのです。
そしてこのとき、べつの身体=主語的統合の生成を成し遂げた結果の副産物として外在化される作品は、一方で私でない他者におけるべつの主語的統合をつくりだすための足場になります。
「作品」とは「制作」の外在化であり、制度化である。しかし、それは同時に、いつか、どこかで、誰かの、次の、身体制作への足場となるものでもある。僕が今、彼が作った足場に立っているように。つまり、「作品」とは外在化であり、誘惑であり、誘惑された者たちの、小さな部分的共同性を生成する装置でもあるのだ。
上妻世海「制作へ」
自他の対象化と同一性を確保する近代制は、むしろ近代制に還元することのできない制作的空間の持つ非人称の次元を他者に送り届ける機能を同時に担う。主語的統合は一方でべつの主語的統合へと移行する、述語的統合の組み替えを可能にする足場であると同時に、他方では他者が組み替えを行った足場の誘惑を可能にするのです。
場合によっては、個々の表現ジャンルにおける歴史性を過度に相対化する読みを『制作へ』は許してしまうかもしれません。それは作品そのものへの軽視というより、作品が持つ制作過程の固有性が、制度によってつくられた同一性へとすり替えられてしまうことへの問題提起であり、その意味でこうした態度は選択的に取られたものである点に、注意しておかなければいけません。
作品は制作の外在化による副産物であるが、私たちはそれをとおして他者の制作的空間を仮想的に自らのうちに取り込み、あらたな身体の生成=述語的統合の再編成を行うことができる……この指摘は見逃せませんが、ところで、この「外化された他者の(私の)制作的空間」としての作品が備える主語的統合は、近代制という一本の太い線だけなのでしょうか。言い換えれば、述語的統合によって相対化され、べつの主語的統合への移行が試みられるとき、私たちの可能な身体のあり方を制限しているのは近代制や、それを象徴する巨大な主語的統合「だけ」なのでしょうか。「制作へ」で、「〈主語的〉統合が、時代、地域、そして人によって異なる」と述べられている点を確認しましょう。時代や地域だけではなく、個々人によっても異なる主語的統合。それなら、常識そのものがなぜ通じるのか。それは、時代と地域、個々人でそれぞれが異なる主語的統合を備えているのではなく、そもそも主語的統合と呼ばれるものが個人のパースペクティブにおいて複数存在することを意味するのではないでしょうか。
「媒体との対話」をめぐって
複数の主語的統合は、時代や地域、共同体、個々人といった複数の階層に渡って存在し、私というパースペクティブのなかでそれらは共存し、私が私であることの同一性を維持させる。このとき、近代制は同一性そのもののフレームをつくりだしたシステムとして想定されつつ、その同一性を維持する機構は階層ごとに異なっている、と見ることができるでしょう。
ここにあるのは私の複数性ではなく、私の同一性の複数性ともいうべき事態です。述語的統合におけるべつの身体の生成、つまり制作は、生産的・消費的な身体のあり方を迫る近代制からの相対化を試みつつも、「近代制」の語だけには単純に還元されない、複数の同一性の維持システムとの緊張関係に置かれることになります。
このようにして近代制という巨大なシステムを土台としつつも、複数的にあらざるをえない主語的統合を、個々の制作の現場からとらえてみることが、制作を考える上で重要になるのではないかとおもいます。端的にいえば、述語的統合における五感の再編成に、複数の主語的統合の再編成を絡ませること。
近代という抽象的な時代区分を単一の主語的統合として扱うことで、そこからの乗り越えをはかるにあたって必要となる「足場」のなかに、制作と密接に関わる複数の主語的統合が温存されているのではないか。そうした制作的空間に絡みつく複数の主語的統合を細分化し、一足飛びではなく多分に緊張をはらんだかたちで、べつの身体の制作を試みる必要があるでしょう。
それを考えるにあたってひとつの鍵となるのは、「制作へ」でしばしば述べられる「媒体との対話」です。制作主体を主語的統合から解放し、述語的統合における五感の組み替えの舞台となる「媒体」は、絵画であればキャンバスや絵の具、彫像であれば石であり塑像であれば粘土といったように、主語的統合からの制限を逃れて制作主体の五感をフル稼働させてくれる存在といえばいいのでしょうか。あまりにも強い説得力を持って私たちの身体に迫る物質性は、そこに制作的空間をありありと現出させます。
環境によって身体を作られるな。作られつつ、作ること、作りつつ、作られること。受動的な状態から往還的な状態へ移行すること。能動的な状態ではない。それは幻想にすぎない。自分勝手な幻想を媒体に投影するな。媒体には媒体に固有の特性がある。媒体と対話することで私と対象の双方が生成される。事前にすべてを把握する主体は存在しない。
上妻世海「制作へ」
この引用は「制作へ」における「媒体との対話」がもっとも詳しく書かれている箇所です。「自分勝手な幻想」とは、制作主体が制作の素材に対して二元論的に向き合い、前者が後者に対して制作をおこなうという、本書で描かれる制作論が批判すべき「近代的な」制作態度です。そうではなく、制作者/対象という区分は、制作的空間に降りていき、「対話」をとおしてはじめて生み出されるのです。
しかし一方で、対話される「媒体」とはそもそもどのような存在を念頭に入れているのか、という疑問が浮かびます。ひとまずは私=主体と対象の区分を新たに生成する基盤となり、述語的統合の組み替えによる、べつの主語的統合への移行を可能にする制作的空間が、媒体の持つ特性であると見ることができます。このとき、媒体という語は制作的空間を身体に引き起こすものとして、近代制の制限から外れた中性的な概念として用いられています。また同時に、素材が持つ物質的な説得力によって、その実在性はあらかじめ担保されているともいえます。
媒体が制作的空間の基盤となること、それ自体は積極的に肯定すべきですが、その詳細な議論は「制作へ」においてあまり多く語られてはいません。ある主語的統合を備えた身体がその五感を述語的統合の次元で組み替えようとするとき、媒体はどのような存在として制作する身体のまえに到来しているのか。あるいは、このときすでに制作者の(意識的なものであれ、無意識的なものであれ)認識の投影として、媒体は無垢な物質性とは異なる次元の性質を備えてしまっているのではないか。
本テキストは、先ほど述べた複数の主語的統合と述語的統合の関係を、制作における媒体概念の議論によって分析できるのではないかと考えます。なぜなら、媒体は制作に関わる限りにおいて、既存の主語的統合からまったく自由なものではなく、むしろ複数の(細分化された)主語的統合に依存するものだからです。たとえ素材の物質性が制作主体の主語的統合を突き抜けて、その奥にある述語的統合に直接な作用をもたらしたとしても、たとえば素材を選択する過程や素材そのものへの操作の吟味は、主語的統合からまったく自由であるとは必ずしもいえないでしょう。むしろ、ここで制作につきまとう複数の主語的統合と述語的統合の往還関係を視野に入れ、それらを媒体そのものの問いへと送り返していくことで、より細密に制作的空間を取り巻く複数の視点の関係を描き出せるのではないかとおもいます。
第2章 岩成達也「詩的関係」について
詩の言葉における「第二の意味」
さて、複数の主語的統合と媒体の関係を分析する上で、本テキストは言語表現、とりわけ詩がそのモデルになるのではないかと考えます。というのも、詩は言葉によってつくられるものでありながら、言葉そのものをその中心的な媒体として提示することができないからです。俳句や短歌であれば音数律というフレームとの参照関係から、両者を区分することは基本的に可能です。しかし、音数律を基盤としない詩、たとえば散文詩は、単なる散文とどうちがうのか。際立って詩的な言葉が用いられているわけでもなく、改行もされていないテキストが、場合によっては詩として提出されることもあります。いわば、詩における言語とは、単に物理的な材料のようなものにすぎないのです。「詩は言語でつくられる」と主張するだけでは、詩が「散文」と異なることを提示することができず、決定的に抜け落ちてしまうなにかがある。
単に言葉そのものの物質性を強調するだけでは、常にそれが単なる言葉、詩ではない言葉(たとえば小説の言葉)と見分けがつかないことで、言語だけでは詩の媒体になりえない。メディウム・スペシフィックではあることのできない詩。詩という言語表現において媒体に相当するものは、言語だけではないのです。翻って、制作における媒体を考える上で、詩と散文を巡る過去の議論をあらためて参照する意義が多分にあるでしょう。
こうした詩の問題を考える上で、かつては非常に参照される機会の多かった書き手として、岩成達也の理論を叩き台にしてみます。彼は、詩を言語による世界認識、およびそこで果たされる私たちと世界の関係の問題として考えつつ、そうした認識=関係そのものと詩の「あいだ」の問題について触れています。詩とは言葉でつくられる以上に、言葉によってつくられた世界の認識、つまり私と世界との関係こそが、詩の構成要素であると。
正直なところ、岩成の詩論はかなり異様で、「詩とはなにか」をめぐってそれなりに多くの書き手が言葉を費やしてきた歴史のなかでも、とくにその難解さにおいては他を抜きんでているとおもいます。彼はとりわけ言葉を用いた私と世界の関係に重きを置きましたが、そこで用いられる「世界」や「現実」、「関係」といった語彙を多重に複雑化させ、文脈によってそれらが担う意味は微妙に異なっている上に、その差異をさらに語彙にフィードバックさせて「非現実的現実」や「非現実的非現実」など、ねじれた定義分けが目立ちます。
詩を語る上で避けられないある種の「言いにくさ」のようなものを全身で引き受けようとするなかで議論が込み入ってくるのは、吉本隆明の『言語にとって美とはなにか』や菅谷規矩雄の『詩的リズム』といった書物に共通する点ではありますが、岩成は客観的な公理を詩に見いだそうとするなかで、同時に読み手や書き手の主観的な側面をそこへと回収しようとすることで、主観的なものと客観的なもののあいだのねじれが議論のなかにもつれ込んでいるような印象を受けます。
岩成の理論を解説するにあたって、『詩の方へ』という書物から引用してみます。冒頭にある「詩(論)を求めて」というエッセイで、彼は言葉を表現の基礎素材とするだけでは、詩が「散文」との区別がつけられないと指摘しています。
絵画は線と色でつくられ、音楽は音でつくられる。では、詩は何でつくられるのか。あまりにも当り前の答えですが、詩をつくるものは言葉です。しかし、困ったことに、言葉は詩だけではなく、散文もまたつくるのです。のみならず、普通、言葉は意味から切り離せませんから、言葉の組み合わせ↔意味の組み合わせ↔概念の束(世界)という経路で、たちまちにしてそれは散文になってしまうのです。
岩成達也「詩(論)を求めて」
「散文もまたつくる」とは、言葉によって詩が書かれるほかに、メモや報告書、日記、小説、シナリオなど、「詩ではないもの」もまた、言葉によって書かれるということです。そのため、岩成は「この言葉が詩であること」を保証し、それを提示する「制度」が、詩を書く上では絶えず必要とされてきたと考えます。制度、というと輪郭がぼやけてしまいそうですが、とりあえず「このように書けば詩として読まれる」というルールが強固になり、固定化されたものととらえていただければとおもいます。その制度の代表的な例として、岩成は「抒情」と「行分け」を挙げています。
抒情とはいったい何でしょうか。ごく簡単に言えば、それは意味のさしだしや概念表出ではないこと、つまり、感受(特に感情に係わる)の総体のさしだしだ、ということでしょうか。一方、行分けとは、一口で言って、散文ではないという宣言であり、行間の概念飛躍を容認するというか――むしろ、行間での概念の非連続、意味の跳躍そのものに「内容、または第二の意味を読みとれ」とする仕組みだと思われます。
岩成達也「詩(論)を求めて」
制度は、ある言葉が「意味のさしだしや概念表出ではないこと」を伝達するもの、いわば意味の伝達が一義的な目的とされない言葉を設計するものであり、意味に替わるものとして「感受の総体のさしだし」や「概念飛躍」といったものを、制度は言葉から引き出そうとする。「感情に係わる感受」という言い回しは、詩が詩的な感情そのものを不可欠の要素とするといった萩原のような議論を相対視する意図があるのではないかとおもいます。
さて、岩成は「抒情」や「行分け」が制度であると述べていますが、とはいえこれらが不要であると考えているわけではないことを、補足しておく必要があるでしょう。後述しますが、この二つの表現がやり玉にあがっているのは、これらがなければ詩として読めないという認識が人によってはありえてしまうこと、このふたつが詩的言語を担保する上で覇権を握りすぎていて、詩を書く上でほとんど慣習化されているからです。そうした状況は「抒情」や「行分け」があれば詩になるという、短絡した思考に結びつきかねない。
しかし、同時に「抒情」や「行分け」はその慣習としての側面以上に、制度として覇権を握るに足る機能を備えていることが、一方では指摘されてもいます。岩成によれば、「抒情」や「行分け」という「制度」を利用することによって、言葉は「通常の意味」を奪われ、「第二の意味」が与えられるといいます。
この二つの「制度」に共通する仕組みの働きは、本質的には、言葉からいったん意味を奪ったうえで、その上に第二の意味を発生させるということにありました。……つまり、言葉から意味(概念)を奪うと同時に、意味を奪われた言葉の組み合わせが第二の意味を発生さえさせることができれば――詩が成立するとひとまずは見做すわけですから、そこでは様々な仕組みの試みが可能になります。
岩成達也「詩(論)を求めて」
言葉から意味を奪い、意味を奪われた言葉の組み合わせから生じる第二の意味によって、詩ができる。このとき、「奪われた意味」と「第二の意味」の対が散文と詩の文章の差異に相当します。この対は「制作へ」における「科学革命以降の言語」と「感覚・身体的な言語」の対と同様に、固定化され、安定性を備えた社会的な言語と、身体性(感受)を備えた言語という、言語における二つの様態を指し示すものです。
詩的関係と媒合機能
しかし、岩成は詩がいわゆる詩的言語と呼ばれる言語から構成され、それが「日常言語」もしくは「社会的言語」と対置されるという、詩的言語の実在性ではなく、言語から意味が奪われたり与えられたりすること、つまり、言語と意味のあいだの間接性に注目します。言語は意味を持つにあたって、特定の環境や話者の「関係」を経由する必要があるのです。その上で意味を散文的なものから詩的なものへ変えるために、抒情や行分けといった制度に代表される仕組みが存在するわけです。
ここで、岩成は「通常の意味」と「第二の意味」を「散文的関係」、「詩的関係」と言い換えながら、詩とは言語を用いる人間の想像力と「現実」のあいだの関係=認識を取り扱うジャンルであると考えます。
少なくとも私にとって、想像力とは〈現実〉と間接的な関係を結ぶこと、もっと言えば、〈現実類同物〉とでもいったものを介して〈現実把握〉を行うことを意味していた。ちなみに、私は詩に興味を持った当初から、詩は現実/世界を把握する営為、この意味ではある種の認識(類似)行為だと考えていた。
岩成達也「詩についてのごく僅かの手掛り」
私(達)は抒情と行分けよりなる作品が、あるいはこのいずれかを主要な特徴とする作品が、詩作品ではない、と言っているわけではない。私(達)が見いだしたいと思っていたのは、むしろ、抒情や行分けもそこに含むような、より〈根源的な〉一つの関係系なのであった。
岩成達也「詩についてのごく僅かの手掛り」
しかし、私/世界の関係の現実類同物としての言語をとおして現実を認識する過程は、散文的関係(通常の言語使用)においても同様に見られます(というより、これは言語が言語であるための根源的な要素のひとつでさえあります)。現実類同物は「非現実」のものとしてありつつ、「現実」を認識するためには不可欠である。つまり、非現実はイコール現実ではないことを意味せず、むしろ現実を構成する要素でもある。彼は散文的関係を「現実的非現実」、詩的関係を「非現実的非現実」と呼んだりします。
さて、散文的関係と詩的関係はどのように異なるのでしょうか。岩成は、散文的関係は「現実」たりうる安定性を備えた関係である一方で、詩的関係とはある異常(=第二の意味の付与)があり、そのために不安定化していると述べた上で、その条件をつぎのように定義します。
①詩的関係が成立する場合、言述の〈表現(形相):内容(形相)〉関係が必ず異常(不十分/過剰)である。
②詩的関係が成立する場合、言述の連辞–連合関係(その支配のあり方)が異常であることが多い。
③ー1:詩的関係は本質的に不安定である。
③ー2:あるテクストが詩(作品)であるためには、(明示的であるにせよ、暗示的であるにせよ)関与者の宣言を必要とする。(同前)
岩成達也「詩についてのごく僅かの手掛り」
散文的関係は安定化し、共同体内で共有化された言語による世界認識を意味し、詩的関係はそこで用いられる意味から逸脱した言語による世界認識を意味する。しかし、詩的関係は不安定性をどうにかして回復される必要がある、と岩成は述べます。つまり、詩的関係の不安定性、異常性は、そこに「第二の意味」を与えることで安定化される必要があります。また、岩成はべつのテキスト『詩的関係の基礎についての覚書』で、安定化は言葉の「媒合機能」によっておこなわれる、と述べます。
〈表現:内容〉が不充足である場合の典型例は、〈表現:内容〉関係が不十分にしか成立していない場合、あるいは〈表現:内容〉関係が過剰に成立している(通常の用語では「一義的に確定し得ない」)場合のいずれかが与えられるであろう。ところが、これらがコノテーション関係(乃至は詩的関係)に係わっている場合には、これらの二つの例を通じて、次のような現象が認められるのである。まず、この場合の〈表現:内容〉関係を、更に小さい単位へと分割していくと、ある小(関係)単位があって、そこでは〈表現:内容〉関係が一応は充足されている。……しかも、多くの場合、それらの小関係単位での表現形相や内容形相の中には、別のある小関係単位での表現形相や内容形相に対する一種の対立/同調の指標(とでもいうべきもの)を担っているものがある。そして、この場合、さきほどの媒合機能は、これら対立/同調の指標を手掛かりとし、これら対立/同調を統合する新しい構造 —— したがって、その構造よりもたらされる「第三の」内容形相 —— の造出を通して自らを実現する。
岩成達也『詩的関係の基礎についての覚書』
媒合機能は一連のテキストから見られた複数の詩的関係を束として、そこからかろうじて安定化が確認できる意味をとおして、詩的関係の構造化をもたらすものです。ここには制作に参与する制作者の介在が前提となるので、言葉の持つ機能というより言葉を書き、読むことをめぐる私たちの認識の機能であるように読めます。つまり、いったん異常性として把握された詩的関係に対して、その異常性が担うべき意味や構造を、私たちは他の詩的関係との関係から見いだそうとせざるをえず、結果として不安定な詩的関係は、その外部である他の詩的関係を拠り所として、散文的関係とは異なる安定化=新たな統合を果たします。複数のテキストと私のあいだの、個々に不安定な認識=視点を飛び移り、詩的関係を安定化できる第二の意味を探索すること(上記の引用では、「第三の内容形相」に相当するもの)。それが詩を読むという行為にほかなりません。
さて、ここまで見てきた散文的関係と詩的関係の対にあたって、岩成の議論ではソシュールなどの構造主義言語学における「ラング/パロール」や「デノテーション/コノテーション」の対が援用されていることを補足しておく必要があるでしょう。というのも、パロールおよびコノテーションは、彼によれば言語使用者が前–言語的な身体を持つことに由来し、言語が「主体の介在によって『無数の滲みを持つ意義』」を含んでいることで生じるものであるからです。つまり、詩的関係は前言語的な身体が言語に介在することによって生じ、その不安定性を回復させる媒合機能もまた、私たちの身体が他のテキストやテキストの外と関係することによって可能になるのです。
言語と同時に身体があり、その身体をとおして不安定性が知覚され、詩的関係が生み出される。「制作へ」の言語観もまた、こうした言語の母胎となる身体を問題としています。
ここまでロゴス的論理と言ってきた慣習的で指示的な言語は、本質的に二次的で派生的なのだ。もし言語が純粋に理性的で恣意的なコードではなく、「肉的相互交流と参与=融即から生まれる感覚的で身体的な現象」であるならば、私たちの言語は人間という種以外のものの身振り、音、リズムからも影響を受けていると言えるだろう。……それは身体が自然に根を下ろした状態なのである。そうでなければ、言語は死んでしまうのだ。主語的統合を作り変え続けなければならない。それが身体を制作するということなのである。
上妻世海「制作へ」
「慣習的で指示的な言語」は、言語の社会的な使用を支える一方で、その活動を制約するものでもある主語的統合です。慣習や指示性だけを言語の特質とすると、述語的統合の次元にある融即的な言語を見いだすことができない。「制作へ」において、「融即」的な言語とは「主語的統合のように主体と対象が分離された状態での知覚ではなく、主体と客体が未分化の状態で相互に影響を与え合う知覚」に根ざした言語として、「慣習的で指示的な言語」の以前に設定されるものです。媒合機能における複数の詩的関係の交差は、詩的関係の不安定性という「なにが意味されているのか」を探索せざるをえない、ある種の主客の分節の破綻につながる知覚であることを踏まえれば、「制作へ」の議論を
- 散文的関係=「慣習的・指示的な言語」=主語的統合としての言語
- 詩的関係=「融即としての言語」=述語的統合としての言語
と、岩成の理論に結びつけてみることができるのではないでしょうか。つまり、散文的関係と詩的関係を、主語的統合と述語的統合の対から見ること。詩的関係は通常の意味=散文的関係=主語的統合(的な言葉)とは異なる言葉、そこから逸脱する言葉です。そして、それは主語的統合に対置される述語的統合(的な言葉)としてあらわれつつも、不安定な関係(言葉)に意味を見いだす対象化の過程(媒合機能)を経て、文章単位での主語的統合が行われている。形式化すれば、詩的関係の把握は「主語的統合=散文的関係↔述語的統合=詩的関係(→主語的統合=第二の意味)」という手続きで立ち上げられていくことになります。詩は、こうしたテキスト単位での主語的統合と述語的統合の往還関係をもとに書かれていくのです。
「関与者の宣言」の不確定性
ところで、以上で述べた詩的関係の発現と媒合機能による把握=回復の流れが、そのまま詩を意味するわけではないことが、詩的関係の定義の最後で不穏に示されています。あらためて引用すると、「あるテクストが詩(作品)であるためには、(明示的であるにせよ、暗示的であるにせよ)関与者の宣言を必要とする」の箇所です。「詩(論)を求めて」にも、制度としての行分けが「散文ではないという宣言」を意味すると述べられていますが、最終的にテキストを詩として提出する、この「関与者の宣言」とはなんでしょうか?
これについてより詳しく見ていくには、岩成達也のべつのテキストを参照する必要があります。詩的関係についてのより詳細な記述がある『詩的関係の基礎についての覚書』で、彼は該当の定義を次のように分解しています。
(1)あるテキストが与えられたとき、そこに含まれる個々の詩的関係を(個々の宣言に基づいて)間主観的に確定することはできる。しかし、そのテキストが詩(作品)であるかどうかは、そのテキストが与えられただけでは間主観的に確定しつくすことができない。
(2)あるテキストが詩(作品)であるためには、そのテキストへの関与者(作者、読者等)がそのテキストを詩(作品)であると宣言する必要がある。
岩成達也『詩的関係の基礎についての覚書』
詩が詩であるためには、「このテキストは詩である」という「関与者の宣言」が最終的に要請される……これでは、「詩として書かれたものが詩である」という、同語反復のような議論に聞こえます。しかし、ここで岩成は「詩と散文のちがい」について触れた、当初の議論を蒸し返しています。つまり、テキストからは客観的に詩と散文を区別できないという、他の言語表現との識別可能性の希薄さが、「宣言」の存在を要請しているわけです。
詩は言葉でつくられるが、言葉は詩以外のものもつくる。そのため、彼は詩的関係という、テキストから発見される異常な認識への知覚をとおして、詩を構成するテキストの条件をそのテキストへの関与者(制作者および読者)に求めたのでした。しかし、それは一方で、詩的関係が詩を保証する客観的な指標にはなりえないことを、同時に表明してしまってもいます。
すべての関与者に対して詩であるようなテキストは理論上存在しない。何故なら、あるテキストが詩であるためには、関与者との関係において専ら詩的関係が成立しなければならないが、すべての関与者に対してこのような関係が成立し得るかどうかは、一般論としては確言できないからである。
岩成達也『詩的関係の基礎についての覚書』
ここで、詩的関係を成立させた(とみなされる)制作者と言語の関係が、さらにそれを読む読者とテキストのあいだで検証されています。私において詩的関係を担う文が、私でないだれかとも詩的関係を持ちうるか、どうか。それが不可避的に求められつつも、しかし実際に果たされうるのかどうかが担保されていない……「制作へ」の議論に転用すれば、述語的統合における五感の組み替えという内在的な行為が、詩作品そのものの組織化の水準で起きているのです。詩的関係の量子性は、詩的関係が詩的関係であることの条件である(散文的関係との対から見られた)不安定性へとつながりつつも、客観的な安定性を欠如していることそれ自体によって、詩的関係は詩作品を保証できない。だからこそ、このテキストは詩であるという「宣言」が必要とされてしまうわけです。
しかし、この詩的関係が持つ不確定性は、詩を成立させるための「宣言」そのものの不確定性にも食い込んでいきます。
例えば、新聞記事の断片を詩(作品) —— オブジェ —— として読むことはしばしば可能であるが、執筆者たる記者との関係においては、多くの場合、明らかに詩的関係は成立していない。また逆に、作者および多数の読者に対して詩(作品)であるようなテキスト(例、「行分け詩」)でも、作者の宣言(「行分け詩」の場合には行分け表現そのもの)を識別し得ず、識別し得たとしてもそれにより詩的関係が成立しないような関与者に対しては、それは詩(作品)であることができないからである。つまり、宣言の存在でさえも、詩(作品)成立のための必要条件ではあっても、十分条件ではないのである。
岩成達也『詩的関係の基礎についての覚書』
たとえ「行分け」でテキストが書かれていても、「行分け」=詩の「宣言」という「制度」が共有されていない関与者や、「制度」を理解していてもそこで書かれたテキストに詩的関係を見いだせない関与者にとって、そのテキストは詩ではない。詩的関係の不安定性が詩の不安定性へと滲みだし、行分けに代表される制度を含めた「宣言」と強く拮抗しあっています。
当然ながら、こうして関与者の差異によって量子的であらざるをえない詩作品は、そこで知覚される詩的関係の様態さえも個々の関与者によって複数化されます。つまり、私があるテキストから読み取った詩的関係は、必ずしも他のだれかにとっても同じ詩的関係であるとは限らない。
更に、あるテキストが複数の関与者に対しそれぞれの詩(作品)である場合も、それらの詩的関係が関与者の間で共通しあるいは同一である —— とはかぎらない(関与者による詩的関係の「滲み」)。
岩成達也『詩的関係の基礎についての覚書』
このようにして、「宣言」をめぐる不確定性へと議論が展開されていくにつれて明らかになるのは、そもそも岩成が述べる「宣言」とは、それを発し、聞き取ることができるかどうかという私たちの知覚・判断レベルの問題であるということです。また、先ほどの引用で「宣言」に「行分け」という表現形式が含まれている点にも注意しましょう。「宣言」が明示的であったり暗示的であったりするのは、それがテキストに対する関与者の知覚・判断の次元(あるテキストが詩・詩的関係であるという知覚)や、表現形式そのものも含んでいるからです。いわば、該当のテキストを詩作品として認識することが妥当な表現という、形式と知覚・判断のセットが「宣言」と名づけられているのです。つまり、「宣言」はテキストに対するなんらかの特筆すべき知覚を土台とする詩的関係の成立の条件と、程度の差こそあれ同一の基盤を共有している。であれば、ある意味で「このテキストは詩である」という知覚は、必ずしも詩的関係と無関係であるわけではなく、むしろその成立の条件において両者は同じく関与者の知覚を必要としていると見なすことができるでしょう。
弱い主語的統合
さて、「宣言」の定義をめぐって取り出された不安定性・不確定性を、あらためて散文的関係と詩的関係の対から確認した主語的統合と述語的統合、べつの主語的統合への移行へとつなげてみます。
詩的関係とは安定的に世界を表象し、かつ個々人に広く共有された主語的統合としての言語から構成される散文的関係に対置され、常に個々の「私」との関係においてその様態が多様化する述語的統合としての言語表現です。そして、あるテキストから知覚された詩的関係は、すぐさま他のテキストとの配置関係をとおしてそのテキストに固有の「第二の意味」が見いだされることで安定化し、組み替えられた意味としてべつの主語的統合を形成します。このとき、同時にテキストは特定の理解の形式を伴って対象化されてもいます。
しかし、詩的関係は特定の関与者によっては発生しない場合が多いにありえますし、たとえ知覚されたとしても、その知覚のあり方は個々の関与者によって異なり、同一性が保証されていません。かつまた、詩的関係が見いだせるテキストであれば詩であると断定することもむずかしく、書いた本人がそうおもわなくても、読者が勝手に詩的関係を知覚してしまうかもしれない。いわば、関与者の内在的な経験に深く根ざしたものとして、詩的関係は存在するのです。
詩的関係の成立が詩の成立を必ずしも意味しないということは、詩が詩であるために詩的関係は必要でありつつ、詩的関係だけではテキストを詩として見なすことができないことを意味します。そのため、「このテキストは詩である」という「宣言」が、あるテキストを詩として提出するために要請されます。この「宣言」は「行分け」や「抒情」に代表されるように、多かれ少なかれ詩の「制度」に依存する場合があります。
しかし、「宣言」もやはり関与者の知覚が介在し、客観性が保証されているとはいえません。「宣言」はテキスト内部の表現形式と個々の関与者による知覚、判断のセットにおいて成立するものであり、そのなかで知覚される「宣言」=主語的統合は各々の関与者にとってバラバラであるほかありません。言い換えれば、「宣言」は制作過程と受容過程のあいだにギャップがあり、「宣言」は万人に共有されているものではないと。このギャップによって、「詩として提示されているにも関わらず、詩のように読めない作品」もありえます。たとえば、山田亮太の「災害対策本部」という詩の冒頭を見てみましょう。この作品は東日本大震災時、各企業による支援物資の引用から構成されています。
【森永製菓】ウィダーinゼリー180万個無償提供。従業員1名の安否未確認。東北配送センター(宮城県黒川郡)の建物と製品在庫に被害。小山工場(栃木県小山市)において建物及び設備の一部に損傷。小山工場の主要生産品目:チョコボール、キャラメル、エンゼルパイ。おもちゃのカンヅメ発送延期。【ロッテ】コアラのマーチビスケット〈保存缶〉14,000個、キシリトールガム48,000個、のど飴ZERO48,000個、その他ガムやチョコレート、ビスケットを含め、合計288,000個提供。『ホカロン』1万枚提供。追加提供準備。新宿区が停電地域となった場合ホームページ閲覧不可。【明治HD】義援金1億円。支援物資対応。以下工場で(一部)操業停止。
山田亮太「災害対策本部」
もともとが「詩ではないテキスト」を、引用と「宣言」によってかろうじて詩作品として提示し、翻って山田自身の引用主体としてのテキストとの関わり方が吟味されるという作品ですが、ぱっと見た限りでは詩のように見えません。テキストそのものというより、「宣言」をとおして事後的に詩的関係をそこから構成する作品であるといえるでしょう。このとき、「宣言」は対象のテキストが詩であることを表明し、一方では「宣言」の機能そのものが疑いにかけられるという二重性も、同時に知覚されます。ほかにも、ほとんど小説のような体裁のマーサ・ナカムラの作品や伊藤比呂美の『河原荒草』も、俎上に乗せるべきかもしれません。
さて、こうした言語表現をめぐる詩的関係や「宣言」の問題から、主語的統合に強度のバリエーションを考えてみることができます。つまり、複数的な主語的統合にはさらに、「制度」と呼ばれるような「強い主語的統合」と、さらに個々の「私」や事物をめぐる「弱い主語的統合」がありえるのではないか。
たとえば、「このテキストは詩である」という「宣言」や、それを表現する行分けや抒情といった「制度」は、詩的関係をめぐる議論において強い主語的統合として、詩を読む経験に強く働きかけます。しかし、この強度は万人に共有されるものではなく、詩に関わる個々の存在者にとって異なるものでしょう。そして、第2章の「詩的関係と媒合機能」の後半で述べたテキスト内部の詩的関係への知覚は、まず散文的関係からの逸脱として把握され、そこから媒合機能をとおして新たな意味を形成するという手続きを踏みます。その意味で複数の詩的関係をめぐる「宣言」の知覚は、徹底した不確定性を基盤に持ちつつも、「制度」とある種の緊張関係をはらんだ「弱い」主語的統合であるといえます。
制作過程は述語的統合の組み換えによる新たな主語的統合を形成しつつも、それは個々のちいさな、弱い主語的統合の成立によって行われると同時に、「制度」という強い主語的統合との関係を不可避的にはらんでいる。「制作へ」において「作品」や「ジャンル」といった問題は、近代制のパターンのひとつとして扱われ、制作過程はそれに還元されないものとして確保されています。なので、こうした主張はいわば「作品やジャンルはやはり考慮すべきなのではないか?」という、保守的な主張であるようにも聞こえます。
しかし、制作を近代制からの自由ではなく、常に過去の歴史や当座の文脈との関係を不可避なものと仮定した上で、そうした関係を含んだ上で制作を引き受けることが、本テキストの主題のひとつでもあります。つぎの章では、「制度」をめぐるべつの議論として、「制度」が発現させる複数の主語的統合間で異なる強度について考えてみましょう。
第3章 詩の媒体とはなにか
「宣言」の強度
「制作へ」において、「媒体には媒体に固有の性質がある」と述べられていましたが、詩の固有性がつよく発揮されるのは、詩的関係から意味を見いだしていく媒合機能にあるでしょう。しかし、それは詩に限らないテキストにも見いだされるものであるため、同時にテキストが詩であるという「宣言」を不可欠とする、ハイブリッドな様態を示します。もっとも安直な答えであれば、詩の固有性を担保してくれるのは「宣言」であるという話になるわけです。
言い換えれば、この「宣言」=あるテキストが詩であるという知覚・判断および表現形式と、その周辺に組織化される複数の詩的関係の束から、詩の媒体を見いだすことが可能なのではないでしょうか。前章ではこの「宣言」をめぐる不確定性の議論を中心に行いましたが、一方で詩が詩であることの「宣言」を強く担う「制度」と、詩の制作のあいだの緊張関係について、本章では論点をい くつか提示したいとおもいます。
先に見た通り、「行分け」は「抒情」と合わせて、岩成によって「制度」と呼ばれていました。なぜ「抒情」や「行分け」が制度なのか。岩成はこれについて、言語という素材そのものが「通常の意味を持つこと」を要請し、安定化が絶えず強力に働くからだと考えました。つまり、通常の意味を解除するためには、その強度に釣り合う(意味を解除しうる)操作を制度として強固に持つ必要があった。行分けや抒情は「制度」として、詩・詩的関係を成立させる効果を持っていたのです。
おそらくは、ここに、抒情や行分けが制度化せざるをえなかった事情の一斑があるようです。つまり、言葉の元々の成り立ちからして、言葉は意味とともにあるのがもっとも安定的だという性質をもっています。したがって、言葉から意味を奪うような仕組みは、その仕組みそのものがよほど強力でないと(制度化がその一例)、持続しないはずだからです。
岩成達也「詩(論)を求めて」
これは、詩・詩的関係が制作者とテキストと読者のあいだで量子的なふるまいを見せる、二重に不安定な関係であることも要因のひとつとしてあるでしょう。詩的関係はテキスト内部から知覚される異常性をもとに把握される一方で、言葉は不安定な状態に留まろうとせず、常にその意味を一般性、流通可能性へと回帰しようとする安定化の傾向を持っている。構造上不安定な詩・詩的関係を安定的に制作可能なものとして、慣習的な「行分け」と「抒情」が要請されてきたというわけです。
しかし、「行分け」と「抒情」がその詩的関係の生成しやすさゆえに制度化へと至ったという回答には、留保すべきであるとおもいます。なぜなら、この二つには詩の言語をつくる上で非常に機能的だったために濫用され、歴史的に制度化されたという過程だけではなく、そもそも日本の詩の成り立ちにおいて深く絡んでいるものだからです。
たとえば「行分け」は、日本語圏で書かれた最初の(翻訳)詩集『新体詩抄』(1882年)において、海外詩のフォーマットを直接的に借用することで日本近代詩史上に現れ、文語体と合わせて詩が詩であることを示す規範となりました。当時の日本語において改行規則を適用して書かれる文章は詩以外にはあまり見られず、翻って改行された文章=詩という認識さえ起こっていたわけです。
また「抒情」については、文語定型詩が口語自由詩へと変化する過程のなかで、詩が詩であることの根拠を制作者の「内面」の発露に求めることで、詩が文語体および改行操作に拠らずとも制作できることを模索した、という経緯があります。冒頭に述べましたが、萩原朔太郎が代表的な例です。
私の詩の読者にのぞむ所は、詩の表面に表れた概念や「ことがら」ではなくして、内部の核心である感情そのものに感触してもらいたいことである。私の心の「かなしみ」「よろこび」「さびしみ」「おそれ」その他言葉や文章では言い現わしがたい複雑した特殊の感情を、私は自分の詩のリズムによって表現する。しかしリズムは説明ではない。リズムは以心伝心である。そのリズムを無言で感知することの出来る人とのみ、私は手をとって語り合うことができる。
萩原朔太郎『月に吠える』
リズムは言葉として外化されず、それを読む人間の内在的な経験として生み出されるものであり、その意味で詩のリズムは書かれえず、常に詩を読む人間とのセットでつくりだされる。いわば、私にもテキストにも事前に位置づけられないものとして、詩のリズム=抒情は存在する。萩原自身は改行のフォーマットに対して批判的で、改行があれば詩になるという誤解が生まれた原因であるとさえ述べてもいますが、抒情は言葉そのものの機能というより、それを読む人間の心の機能であるという意味で、やはり「言葉以外のなにか」を要請するものです。
さて、「行分け」は日本語における詩の誕生に付随してあらわれた詩のフォーマットであり、「抒情」はそれに替わって詩が詩であるために必要とされたものでした。つまり、これらは詩の言語を散文的なあり方から変形させるための強力な装置であると同時に、詩が詩であることを保証するための、慣習としての側面を多く含んでいます。しかし、その「慣習」とは装置として機能しやすいがために慣習化されたというより、詩というジャンルの組成そのものを成立させるための形態的なイデオロギーとして(「行分け」)、またそのイデオロギーから自由な表現のあり方を提案するためのべつの(非形態的な)イデオロギーとして、慣習化されたものなのでした。
主語的統合としての流通過程
詩はあらたな言葉の意味の制作を担うものとして、慣習的な散文的関係から距離を取り、あるいは相対化しようとします。しかし、詩というジャンルそのものは、なんらかの慣習化を必要とする。とはいえ、この慣習化されたフォーマットには、詩の根源的な要素である詩的関係を成立させるための代表的な仕組みである「行分け」や「抒情」が含まれています。つまり、制度はある意味で、慣習(=散文的関係)からの解放を試みるにあたって用いられる、「べつの慣習」であるということができます。慣習をめぐる制作の問題は、こうした二重性にさらされています。「制作へ」から見てみれば、詩の制作はある主語的統合からべつの主語的統合へと身体を組成する営みですが、一方で詩の制作をとおして形成されるべつの主語的統合もまた、ある表現ジャンルや制作内部での慣習と向き合わざるをえないのです。
このべつの慣習が「あるテキストを詩として読む」ということを可能にさせるという、「宣言」のひとつとして非常に有効であるという視点は、避けがたくあります。岩成が述べるように、「宣言」が決して前提ではなく、かつまた、前提として万人に共有可能なものではないとしても、「制度」として機能していないべつの仕組みと比較すれば、詩・詩的関係をつくりやすいからです。
さて、この「制度」をめぐる機能と慣習のあいだの問題を、岡﨑乾二郎によるキッチュ(kitsch)についての発言から考えてみることで、より明確にしていきたいとおもいます。キッチュとは俗悪なもの、芸術作品を模倣したり過度に大衆化したものを意味しますが、岡崎によればそれは「何かが生産されたときの条件、生活様式と、それが流通され認知されるときの様式、流通様式のズレが生み出すもの」、「流通様式を反映し、それを生産様式にフィードバックされたとき生成されるもの」であるといいます。
……どんな芸術作品であれ、セザンヌだろうとダヴィンチだろうと、それが社会に触れ流通する過程においてはキッチュ化される。これをフロイトに倣って二次過程といってもいいかも知れません。制作過程というものを一次過程とすると、それが流通する二次過程においてはキッチュになってしまっている。だがわれわれはこの二次過程によってしか事物を認知できない。
岡﨑乾二郎「キッチュとは何か、あるいは〈価値真空状態〉の芸術 ― 石子順造を読む」
つまり、流通過程とはなにかが制作されるプロセスとそれを知覚するプロセスのあいだにある差異を根源に持つものであると。言い換えれば、キッチュとはいわゆる「キッチュな」作品に見られる性質だけではなく、むしろあらゆる表現においてキッチュ化、ないしはキッチュ的なものの介入が避けられないことを意味します。詩においていえば、散文的関係=ある主語的統合からべつの主語的統合への移行を試みるための「抒情」と「行分け」という制度が、鑑賞体験においては「詩らしさ」を装うものとして、固定的な主語的統合を呼び込んでしまいます。近代制の相対化において試みられる制作の技術が、同時に「制度」でもありえるのです。
とはいえ、岩成の詩論はもとより、「制作へ」における制作行為が試みるものは、こうした芸術作品のキッチュ的鑑賞=消費の批判にあるでしょう。先ほどの引用は石子順造を巡る座談会のなかでの発言ですが、石子にとってキッチュへの注目は近代から現代への移行を示す鍵概念でした。いわば、キッチュという流通様式の模倣は、「制作へ」における「近代制」が担保する芸術作品の「同一性」を強力に組織化するものです。ある表現がある表現として同一視され、流通するということは、言い換えれば主語的統合としてのキッチュの生産を意味するのです。
さて、「詩が詩であること」を保証する最も安直で強力な「宣言」は、掲載紙面において作品に「詩」の名が冠せられるなど、「このテキストは詩である」というインデックスをつけること、あるいは「抒情」や「行分け」=流通過程から見られた詩の慣習を無批判にフィードバックさせること、が挙げられるでしょう。岩成は絶えず、こうした強力な「宣言」でさえ前提にできないことを指摘しますが、であればよりいっそう、キッチュ化を経由して詩を詩として成立させようとする傾向は、個々の制作者の身体と作品のあいだの詩的関係を確立させる上で、慣習化されやすいともいえます。不安定性をとおして、かたや表現の成立の決定できなさが展開されつつ、一方では強固に「制度」が機能してしまう現場として、詩の制作的空間が存在するのです。
制作的空間としての媒体
「抒情」や「行分け」が制度化するにいたった過程については、複数の手続きが踏まれています。まずは、それが詩的関係をつくりだす(=知覚・判断を作動させる)ために効果的な表現形式であること。つぎに、日本近現代詩と同時に出現したフォーマットとして、詩的関係の束を詩として統合させやすい歴史性を持つこと。そして、それに伴ってあるテキストが流通過程における「詩であること」を安定的にフィードバックできること。詩を書き、読む経験に介在するゆらぎを排除することはできませんが、だからこそ「制度」としての「宣言」は、多くの制作者によって濫用されてしまう。こうして「制度」は制作者の身体に深く根づいた慣習として、べつの主語的統合の生成を目指す述語的統合の組み替えの次元に介入します。
これまでの話をふり返って、主語的統合・述語的統合の概念と結びつけながら図式化してみましょう。
① 散文的関係=言語をとおして把握される、私と世界の安定的な関係/認識(主語的統合)
② 詩的関係=不安定な関係/認識(述語的統合)
③ 媒合機能…詩的関係(②)における不安定な構造を(内部としては不安定なままで)安定化させる構造を、他の詩的関係や外部において見いだし、安定化させようとする力(述語的統合→主語的統合)
④ 宣言…「詩が詩であること」、「詩的関係が詩的関係であること」を成立させる表現形式と知覚・判断のセット(インデックス=キッチュとしての「詩」に代表される、慣習や「制度」を含んだ複数の主語的統合)
⑤ 不確定性…①~④に内在する制作者–テキストと読み手間の量子的ゆらぎ(強い述語的統合)
④は詩のインデックスが伏されることで詩として流通されたり、制度をフィードバックさせることで詩のフォーマットを搭載されたりといった「強い主語的統合」や、詩的関係の把握から媒合機能による安定化といったテキスト単位の「弱い主語的統合」といった、いくつかのバリエーションを含んでいます。また、⑤は④の裏返しとして詩の制作をめぐる不確定性であり、便宜上「強い述語的統合」としました。
さて、詩の制作的空間は、いくつもの主語的統合と述語的統合の対が多重的に重ね合わされた場所です。制作者は述語的統合における意味の組み替えを不断に行い、テキスト単位で複数の主語的統合を行き来しながら、決して一般化されることのない言語的複合体を、自身の身体と一般化された詩の制度とのあいだで、絶えざる検討と反省のなかでつくり上げていきます。
最終的にはインデックスや制度を背景とした「宣言」がテキストを詩として提出することで、この「宣言」を知覚しテキストを詩として読む者にとって、テキストはあらかじめ詩として書かれていたかのような体裁を事後的にまとってしまいます。しかし、その中途で行われる制作過程と、作品にインデックスが付されて流通される過程のあいだにはズレがあることを、あらためて強調しておく必要があるでしょう。これは一次過程と二次過程のあいだの差異に相当しますが、後者は不断に前者へとフィードバックされうる(キッチュ化する)という緊張関係をはらみつつも、制作過程が純粋に流通過程の模倣へと還元しきれない(「生産」にならない)ことに、制作という行為の核心があります。そして、このズレを開くために制作的空間は要請されてもいたのでした。
いわば、中途にある制作行為の次元で制度や慣習、流通過程と距離を取りつつ、引き受けること。複数の主語的統合同士が織りなすレイアウトのなかで詩の制作を立ち上げること。ここに詩の核心があるのです。詩のテキストの核心となる詩的関係だけではなく、詩的関係とセットで現れ、かつ詩が詩であることを提示する大文字の「宣言」から、詩の媒体を考えてみましょう。
それにあたって参照すべき視点として、先ほどの図式を念頭に入れながら、クレメント・グリーンバーグによって開発されたメディウム・スペシフィシティの議論からの相対化をめざす、いくつかの論考を見てみたいとおもいます。ここで叩き台となるグリーンバーグの理論は、特定の表現における媒体の不透明性の強調による、他の表現に回収されない自律性の確保をめぐるものです。
芸術の純粋性は、特定の芸術におけるミディアムの限界を受け入れる、それも進んで受け入れることにある。……各々の芸術が独自のもので、厳密にそのもの自身であるのは、まさにミディアムによるのである。ある芸術の独自性を回復するためには、このミディアムの不透明性が強調されねばならない。
クレメント・グリーンバーグ「さらに新たなるラオコオンに向かって」
「不透明性」とは、絵画であればそこで描かれるイメージの土台になるキャンバスや絵の具、言語表現であれば言語それ自体が持つ物理的な性質を意味します。ある表現が他の表現と異なることを提示するにはそれ自身が依拠する物質性を消去するのではなく、むしろ強調する必要があるというわけです。
彼の思考はこの自律性の強調だけにとどまるものではありませんし、いまでは参照される機会もすくなくなってはいますが、いっときは表現の固有性を考える議論のなかで強く支配的なものでありました。しかし、先に述べたとおり詩の媒体を考えるにあたって、グリーンバーグが提唱するような自律性は採用できません。言葉そのものの不透明性を強調するだけでは、詩以外の言語表現との区別がつけられないからです。
慣習の束としての媒体
さて、制度や慣習、流通過程といった複数の主語的統合の束から組織される媒体の諸相をとらえるうえで、ロザリンド・クラウスによる「メディウムの再発明」というテキストを参照します。彼女はメディウム(媒体)の問題を、その固有性ではなく異種混合な要素の組み合わせとしてとらえなおしています。いわば、物質的与件を強調するのではなく、ある表現が流通するにあたって共有される性質、とりわけ慣習に由来する要素に注目します。
「メディウムの再発明」はまず、ベンヤミンの歴史哲学について触れながら、写真という表現の歴史的な盛衰をめぐる記述から始まります。クラウスはここで、自身の理論が過去への想起に深く関わるものであるとし、現代から見て衰退しつつある表現、過去の時代の産物と見なされ、特権的な地位を失った表現に注目していくのですが、そこから先ほど述べた「物質性へと限定されないメディウム」の諸相を分析するにあたって、写真が代表的なモデルとして選択されています。
さて、クラウスは写真が他の表現ジャンルと異なる点のひとつとして、その美学的な次元以上に「理論的対象」としての側面が利用されてきたことにあると述べます。
それがロラン・バルトによる神話学の典型例であったのか、あるいはジャン・ボードリヤールによるシミュラークルの典型例であったのかは問わないことにしておくが、いずれにせよ、写真は一九六〇年代までに歴史的もしくは美的対象としてのみずからのアイデンティティを背後に置き去りにし、その代わりに理論的対象へと変化した。
ロザリンド・クラウス「メディウムの再発明」
どういうことかというと、写真は美的対象として、芸術ジャンルのひとつとして考察される以上に、ヴァルター・ベンヤミンやロラン・バルト、ジャン・ボードリヤールらの理論における重要なモチーフとして、哲学的に考察されてきたと。つまり、「複製技術」や「引用」、「オリジナルなき大量生産品」といった概念を語る上で格好のモデルとして写真は扱われたわけです。
そしてつぎに、こうした「理論」が暴こうとしていたものは、芸術作品一般の固有性そのものの破壊ないしは衰退という事態でした。資本主義体制下において流通過程をフィードバックした「キッチュな」作品は大量に生産され、あるいは複製可能性を見越した作品がつくりだされるようになると。また、写真などの各種メディアに流通するイメージだけで済ませることも可能になった鑑賞体験は、美術作品そのものの同一性をゆるがし、その固有性の地位を低下させていく。
クラウスはベンヤミンの「複製された芸術作品は、いまだかつてないほどに、複製可能性を見越した芸術作品へと変化している」という言葉を引きながら、つぎのように述べています。
ベンヤミンにとって、理論的対象〔としての写真〕が明らかにした変化には二つの顔がある。第一の変化はその対象の領域にかかわるものであり、そこでは連続するユニットが、複製の構造上、統計処理におけるそれと同じく等価なものへと変化する。その結果、さまざまな事物は〈より近い〉という意味でも〈より理解しやすい〉という意味でも、大衆にとって〈より手に取りやすい〉ものとなる。他方、もう一方の変化は主体の変化に関わるものである。というのも、この主体に対しては新たなタイプの知覚が作動するのだが、その新たな知覚においては「「事物の普遍的な平等性に対する知覚」が増していくため、それは複製という手段によって、唯一無二の対象からさえもその平等性を抽出する」からである。
ロザリンド・クラウス「メディウムの再発明」
この複製技術と手を組んだ平等性の知覚は、デュシャンが行った仕事を経由しながら「レディメイドな平等性」の知覚という様相を帯びています。そのため、芸術作品をとおして万物の普遍性が知覚されるのではなく、すべてを等価なものとして還元可能なシステムから芸術作品を見るという、逆の流れが起きているのです。
重要なのは、写真がこうした時代の推移とパラレルな関係を持った、メディウム・スペシフィックであることが非常に困難な表現であるということです。クラウスはそこから、写真が「芸術的な実践を脱構築するための道具」として現代美術においてスポットを当てられる、1960年代以降の様相について解説します。きわめて一般化された議論ではありますが、芸術作品の唯一無二性の神話を解体し、各々の芸術表現が持つ物質的な伝統を相対化していく現代美術と、絶えず「視覚的な」水準で自身の性質を体言し、自身の外にある文脈の連続性やキャプションに依拠しなければいけない(「つねにイメージとテクストが潜在的に入り交じっている」)非自律的な構造を持つ写真とは、相性がとてもよかったと。
しかし、やがて写真は世俗化し、ビデオカメラといった後続の出現によって、その地位がすこしずつ特権視されなくなっていきます。写真は哲学や芸術の領域以上に、商業的な利用価値を持つものとして市民権を得ましたが、技術革新が進むにつれてべつの表現に取って代わられ、最盛期から衰退期へと移行し、20世紀の後半には過去の遺物として扱われるようになったわけです。そのなかで、クラウスはこのようにして写真が「古びていく」という過程にこそ注目します。
このようにして写真は突如として、さまざまな産業廃棄物のひとつ、すなわちジュークボックスや市街電車と同じように、新たに生み出された骨董品のひとつとなった。だが、写真が美的な生産物と新たな関係を結ぶにいたったのは、まさしくこの時点において、すなわちそれが〈時代遅れになる〉という条件においてであったように思われる。ただし今度は、写真は〈メディウムを破壊する〉というかつてのみずからの本分に反する役割を担うことになる。というのもそれは、まさしくみずから衰退しているさまを装いながら、〈メディウムを再発明する〉行為とでも呼ばねばならないような、ひとつの手段へと転じたからである。
ロザリンド・クラウス「メディウムの再発明」
この「再発明」という語は、物質に内蔵された性質からメディウムとしての固有性を引き出すのではなく、複数の物質やそれに対する私たちの慣習的な使用法や知覚といったルールの束から、特定の表現が持つ同一性を引き出し、再帰的に使用可能なものへと生成することを意味します。つまり、媒体を物質的条件による拘束ではなく、そこから引き出される使用法や知覚が一般化し、「慣習にもとづいた約束事」という再帰性の問題とすることで、その固有性はあらかじめ物質的に付与されているのではなく、そうした約束事を反省的に見出すことによって事後的に発明できる、ということです。
ロザリンド・クラウス「メディウムの再発明」
ここで問われているメディウムというのは、絵画、彫刻、素描、建築、さらには写真そのものさえ含むような、伝統的な諸メディウム〔=メディア〕のいずれとも異なる。……むしろそれは、メディウムの観念そのものにこそ関わっている。すなわちここで言うメディウムとは、所定の技術的支持体がもつ物質的な条件から生じてくる(が、それとは同一でない)慣習にもとづいた約束事(convention)としてのメディウムであり、〔未来への〕投影であり、〔過去への〕想起でもありうるような表現力に富んだ形式は、この約束事から展開されていくことになる。
ロザリンド・クラウス「メディウムの再発明」
こうして、「メディウムの再発明」は写真についての考察から始まり、「絵画、彫刻、素描、建築、さらには写真」といった伝統的はメディウムとは異なる、たとえばスライド・テープのような商業的な用途で使用された表現や、フォトノベルのような複数の要素から構成される表現について注目していきます。そこではむしろ、商業的な意図のもとで使われる表現への考察こそが重要になります。なぜなら、「使い古される」に足るだけの多くの人々による使用と時間の経過を前提として、ある慣習は再帰性を持つからです。言い換えれば、クラウスの理論は慣習として私以外のだれかが知覚し、反復可能な使用に足る要素間の関係を含んでいるかどうかが問題になります。そのため、発明は慣習という保守的な傾向のある語によって立ち上げられるものでありながら、その共有可能性が保証されていません。その意味で、「再発明」は「未来への投影」であり、かつ「過去への想起」なのです。
クラウスの理論は使い古され、遺物として見向きもされなかった過去の表現に対する意味で「発明」という語を用いているので、これをそのまま詩の問題として引き受けられるとはいいがたいかもしれません。とはいえ、対象の物質的な性質ではなく、むしろそこから引き出される使用法や知覚こそが、ある表現を表現たらしめる基盤として思考可能であるという視点は実りあるものであるしょう。岩成が言語それ自体ではなく言語から引き出される知覚や認識=関係を詩の問題としてとらえたことや、「新聞記事」のような定型文のオンパレードからも詩的関係は知覚されうるという指摘を思い出せば、クラウスの指摘は詩の条件を言語に対する使用法や知覚、ひいては「制度」的な慣習から考えることを有効にしてくれます。
そして、媒体は慣習の知覚と再発明による再帰性の発現という、他者がそれを慣習として利用可能になるよう制作される過程が、事前に決定できない状態で要請されるという点も、詩が抱える不安定な性質をうまく言い表しているのではないかとおもいます。つまり、詩は際だって明確な媒体の固有性を知覚できないからこそ、その制作においては常にいくぶんか「メディウムの再発明」に相当する過程が存在してしまうのです。
「あなたの記憶」に生成される媒体
クラウスによる「メディウムの再発明」をとおして、特定の表現における慣習の束から媒体を制作(発明)するという議論が可視化されました。これまで制作された詩から見いだされた「制度」に代表されるような、流通過程をフィードバックした慣習を取り込むことで行われる「宣言」を、詩の媒体として再発明することで、私たちはテキスト自体をその構成要素のひとつとして見つつも、さらにべつの視点から詩を考えることができるでしょう。
しかし、詩を支える慣習は必ずしも物質と分かちがたく結びついたタイプのものでも、慣習としてただ単一化できるタイプのものでもありません。これまで見てきたように、「詩が詩であること」を保証する「慣習・制度・宣言」(=主語的統合)は個々のテキストとそれらの関係において複数化され、さらに「行分け」や「抒情」といった「制度」、「このテキストは詩である」という巨大なインデックスなどもそのひとつに数えられます。そして、制作者・テキスト・読み手が個々に単一の主語的統合に属していないこと、それぞれが一方にとって他者であり、かつまた、それぞれが過去・現在・未来において変容しうることに由来する、徹底した不確定性の次元も見逃すことはできません。つまり、慣習の束をそのまま詩の媒体と見なすのではなく、再帰性の獲得に伴う不確定性を積極的に組み込むことが必要なのです。
ここでさらに、グリーンバーグとの相対化を試みつつも、岩成が量子的なものとして指示した個々の関与者=他者の問題と、詩における「物質性」の問題とを同時に考えたテキストとして、詩人の佐藤雄一による「さらに物質的なラオコーンに向かって」を挙げてみたいとおもいます。このテキストでは、他者への伝達における不確定性を帯びた詩という表現の条件が、具体的な受容のレベルから問いなおされています。
佐藤はまず、詩と絵画のあいだのパラゴーネ(優劣比較)の歴史的言説を引きながら、グリーンバーグの理論によって、絵画はメディウムの物質性をいかに取り扱うかが不可避の課題となった反面、詩がその物質性を消去する表現として扱われてきたこと、また絵画や詩のメディウムを巡る議論において、そもそも「物質性とはなにか」に対する問いが欠けている、と指摘します。
その議論は基本的にひとつの図式に収れんできる。つまり、彼らは、アリストテレス的な「形相–質料(メディアム)」という図式のなかで思考しているということである。そして、「形相」に重点をおくとき「絵画は詩のように」あるべきだという主張になり、「質料(メディアム)」に重点をおくとき逆になる。
佐藤雄一「さらに物質的なラオコーンに向かって ― 「固有値(Eigenwerte)」としての支持体を自己生成する」
詩と絵画の区別はレッシングの『ラオコオン』が代表的な例です。そこで詩は時間的な継起性を取り扱い、絵画は同時性を取り扱うべきものであると区別されます。いわば、詩と絵画を比較可能なものと見なした上で「詩は絵画のように」、あるいは「絵画は詩のように」あるべきだという、優劣比較を持ち込む議論とは距離を取り、詩と絵画はそれぞれが自律した芸術であるという視点を提示しました。
グリーンバーグは「さらに新たなるラオコオンに向かって」で、こうしたそれぞれの芸術における純粋性とはなにかを追求することで、個々の表現のメディウムが持つ固有性の問題を展開します。しかし、それらはそもそも形相と物質の二項対立に依拠した議論であり、かつまた、物質がいかにして物質たりえるのかについての視点が欠如していると佐藤は指摘し、ここで問われていた物質性そのものを再定義していきます。
では「物質性」とは何か。グリーンバーグのつぎの言葉に気をつけてみよう。「鋳造による作品は細く滑らかになって、それが注ぎ込まれた時の元の溶解した状態の流れに返ろうとしている、いや、初めて作り出された時の粘土の材質感や可塑性を思い出そうとしているかに見える。」ここでの「物質性」とは「可塑性」である。「可塑性」とは、カトリーヌ・マラブーにならっていえば「変形作用に抵抗しながら形に譲歩することを意味する」言葉である。
佐藤雄一「さらに物質的なラオコーンに向かって ― 「固有値(Eigenwerte)」としての支持体を自己生成する」
可塑性とは粘土のようにやわらかい物体が、外部の力を加えられて変形しつつ、そのかたちを保持する性質を意味します。対象の物質性は一般的に、その存在に付随する性質として静的にとらえられる傾向がありますが、ここで物質性を可塑性の観点からとらえることで、ある物体とそれに変形作用を加える力とのあいだの動的な関係を含み持つことになるのです。佐藤はこうして物質の可塑性を「動的システムにおける均衡概念」として解釈しながら、さらにジルベール・シモンドンを引用し、可塑性を土台とした物質性の基礎づけをおこなっていきます。このとき重要なのは、変形を受け入れつつそのかたちを維持するという準安定状態モデルは、素朴な意味での物質に限定されないということです。
つまり「形を受け入れる粘土の能力は、その形を保持しておく能力と区別されない」。だから、受動的な「質料(メディアム)」に一方的に力を与えて変形するのではなく、形を保持する力と形を与える力(たとえば「レンガの鋳型の力」と「粘土の可塑性」)が運動システムのなかで衝突しているとき、その諸力を均衡させて「準安定状態(metastabilité)」を保っている状態をそれぞれの「物資性」であるということができる。……ここで「支持体」およびその「物質性」を「動的システムにおいてある形を均衡させ相対的に長く保つような固有値(Eigenwerte)」と定義しなおしたい。
佐藤雄一「さらに物質的なラオコーンに向かって ― 「固有値(Eigenwerte)」としての支持体を自己生成する」
こうして、所与の物質そのものに還元されない動的システムと固有値の議論は、対象を観測する私たちの知覚においても適応可能なものとして拡張されます。たとえば詩を書き・読むという動的システムのなかで得られる認識を含めた、私たちの記憶においてつくりだされる固有値として、ある認識が記憶される過程やその記憶の傾向性に物質性が紐づけられるのです。
ところで、物質性という語をめぐる佐藤の理論展開は、「物質性とはなにかという問い」の補填を目的としている以上に、「なぜ問いが欠如してしまうのか」を同時に考えるものでもあります。「物質性」という語は、避けがたく推論の展開を止めてしまう実在性の強度を呼び寄せ、「マジックワード」的に用いられる危険が伴うのです。そのように記憶をめぐる「固有値」へと物質性の指す意味がとらえなおされるなかで、佐藤はジャック・デリダの詩論から、詩におけるリズムの問題に注目します。
デリダは、詩をどんなに長くても「暗記(apprendre par cœur)」できるものとしている。……たとえばデリダは次のようにいう。(マラルメによるエドガー・アラン・ポーの「鐘」仏訳にふれながら)「ポーの押韻が保持できないのは、もちろんだが、あらゆる階梯で、あらゆるリズムの鼓動(battement)は、可能な支持体あるいは質料的表面がなんであっても、可能な限り保存される」。ここで、デリダは通念とは逆のことをいっている。詩は翻訳されたら原語のリズムが失われると考えるのが普通だからだ。にもかかわらず、押韻のような狭義のリズムでない「リズムの鼓動(battement)」が保存されるということ。……つまり、記憶においてあるかたちを相対的にながく維持できる物質的な「抵抗」として、詩のリズムは「固有値(Eigenwerte)」をつくりだすことができる。つまり詩は自身を保存する支持体を自身で生成できる。
佐藤雄一「さらに物質的なラオコーンに向かって ― 「固有値(Eigenwerte)」としての支持体を自己生成する」
押韻に代表される修辞的な技術に限定せず、なによりも詩を読むという行為において、私たちの記憶に働きかけ、暗記という固有値=支持体に関わるリズムを、「あらゆる『質料的表面』に移動させられても、それをフィードバックしつつ、『固有値(Eigenwerte)』を生成し、形を恒常性(ホメオスタシス)として記憶に保持できるアルゴリズム」と、佐藤は定義します。
さらに、佐藤はコンセプチュアル・アーティストのローレンス・ウィーナーや詩人の藤井貞和などを引きながら、このリズムが「あなた」という具体的な他者の「質料的表面」を不可欠の要素として導入することで、「コミュニケーションによって支持体を生成していく『創発』モデル」として、詩を提案します。あなたの記憶に保存されるかどうかが事前には決定されず、固有値の生成をとおしてリズムの強度が事後的に観測されるわけです。
これは、ともすれば萩原朔太郎のリズム論のように神秘的な「内在律」を相対化するため、リズムを「私の内面」ではなく、そこから「あなたの内面」へと接続可能な積極的なコミュニケーションの現場に開くことを意味します。ここで注目すべきは、言葉が相互発信される場において、リズムが変化し、洗練されていく過程です。動的な様態で把握される物質性(固有値)を支えるリズムは、相互発信の関与者が持つ身体から演繹的に導かれず、そのつどの伝達を経由しながら変化し、より固有値を生成しやすいリズムの実現に向けて練り上げられていくのです。
すなわち、「Eigenwerte(固有値)」としての「支持体」が生成されているかどうか検証できる「あなた」の記憶(淘汰システム)を一度経ることで、もしそれが残れば、「物質性」を生成した自分の「作品」だと主張することができる、と。……つまり、(主に記憶などによる)淘汰を織り込んだ言葉の相互発信によって、結果として「支持体」を生成できるアルゴリズムをみつけることができるのだ。
佐藤雄一「さらに物質的なラオコーンに向かって ― 「固有値(Eigenwerte)」としての支持体を自己生成する」
詩のリズム=アルゴリズムの実現は記憶の保存に伴う固有値の生成から判断されるため、観測者の「記憶に残る『物質性』を生成すること」が作品の条件として設定されつつも、その効果は事前に保証されていません。そしてまた、このリズムは複数の作品や制作者のあいだで反復され、変化していく過程での淘汰を織り込みながら発展していくものであり、その意味で閉じた領域にとどまるものでもありません。
さて、こうした理論から導き出される実践として、佐藤は自己生成するリズムを複数人でのコミュニケーションをとおして検討するシステムから詩を考えるべく、「サイファー」というプログラムを提案します。もともとはヒップホップで使用される語ですが、ここでは(主に公園や路上などで)参加者たちがお互いにフリースタイルを回していき、発された言葉を絶えずフィードバックしていくことで、「詩をつくりだすリズム」の生成へと向けた「淘汰システム」を意味します。これは、さきほど述べたリズムの変化と洗練の過程を具体的にモデル化するものであると同時に、この変化と洗練をとおして「私」から「あなた」へと詩のアルゴリズムが鍛え上げられていくことが目指されます。いわば、「ひとを詩人にできる作品だけが詩である」という仮説のもと、詩が複数人の記憶を経由しながらつくり上げられるのです。
リズム化される「制度」=慣習の固有値
「さらに物質的なラオコーンに向かって」の核心は、詩の媒体が私たちの「記憶」という動的システムのなかで保存される固有値としてつくられるという点にあります。ここから、「メディウムの再発明」における慣習の束としての媒体概念を組み合わせながら、「制作へ」で述べられた主語的統合・述語的統合の対を引き受けた詩的関係の議論をふり返ります。
さて、岩成の詩論における「宣言」は、あるテキストが詩であるという知覚・判断と表現形式のセットを意味していました。そのため、「宣言」は必ずしも客観的に保証されるものではなく、制作者・読者のあいだで取り交わされる具体的なコミュニケーションに関わるものです。くり返しになりますが、テキストはひとまず散文におけるそれとは区別される異常性の知覚が必要となり、散文的関係という主語的統合のゆらぎとして、私たちの記憶という述語的統合に働きかけます。そして、詩的関係は私たちの知覚において「宣言」が把握され、そこから媒合機能を経由しながら、あらたな主語的統合として組織化される。ここで「宣言」をめぐる知覚、そして媒合機能によって制作される主語的統合は、私たちの知覚過程という動的システムのなかで不確定性を伴いながら果たされるという、流動的な物質性を携えています。
しかし、こうした詩的関係をめぐる「宣言」とは別個に、詩として提出されるテキストにはより大きな主語的統合である「このテキストは詩である」というインデックス=「宣言」が要請されるため、「詩」という語の付与をめぐる問題はさらに二重化されています。この大きな主語的統合には「行分け」や「抒情」といった制度に関わるものが挙げられますが、それらはこれまで詩が詩として読まれてきた流通過程を絶えず反映させた慣習として、歴史的な性質を持っています。
この慣習は、詩の制作において単に無視すべき存在ではなく、むしろ積極的に制作の現場においてフィードバックすべきものです。なぜなら、「さらに物質的なラオコーンに向かって」で見たように、固有値を生成させるリズムは個々の「あなたの記憶」を経由しながら変化し、洗練されていくわけなのですが、先ほど述べた相互発信=コミュニケーションの現場を最大限に拡張させれば、そこには流通過程という巨大な主語的統合も含まれるからです。つまり、慣習をありうべき詩のアルゴリズムの生成過程の途上にあるリズムの一種として考えることができるのではないか。いわば、詩の制作に絶えず介入する歴史的な慣習や「制度」は、「流通過程を経て、より洗練された詩のアルゴリズム」なのです。これを「制作へ」における主語的統合と述語的統合の議論に接続すれば、リズムの変化・洗練とは制作的空間における「他者の作品=主語的統合を足場とした新たな主語的統合の生成」にほかなりません。
もちろん、この慣習は佐藤の提案するリズム=アルゴリズムと完全に同一視されるものではありません。先ほど述べたように、この慣習はコミュニケーションの過程で獲得された技術である以上に、日本において突如として誕生した詩という表現に付随して開発された、外在的なフォーマットとしての側面を多分に含んでいるからです。しかし、私たちが考える詩の「制度」は、単に制度の一語で括られうるような抽象化された存在ではなく、常に個々の関与者の身体による知覚(=「宣言」)を媒介して把握される、動的で不明瞭な輪郭を持ったものであることを補足しておく必要があるでしょう。たとえば「行分け」ひとつを取っても、文語定型詩から口語自由詩を経て、五七調の切れ目で機械的に改行する方法が自明のものではなくなり、文のどこで改行するかを事前に決定できなくなりました。そのため、「行分け」は過去に書かれた作品群への参照を伴いつつ、個々のテキスト単位で制作者の身体に根ざしたものへと技術的な変形が起きています。ここにコミュニケーションレベルでのリズムの洗練と近しいものを見ることは十分に可能です。
さて、この点からいえば「行分け」や「抒情」といった「制度」=慣習は、(視覚的な、あるいは情動的な)リズムと見なすこともできるので、クラウスの「メディウムの再発明」によって可能になった「慣習の束」としての媒体概念は、固有値=再帰性の実現によって獲得されるというかたちで、より強固に輪郭づけられます。そして、このリズムは前述した「制度」の複数的なあり方や、「制度」との緊張関係を伴いながら生み出される個々のテキスト=詩的関係を引き連れているため、非常に多重的な様相を持っています。
また、述語的統合(=不安定な詩的関係)の組み換えをとおして、ある主語的統合(=散文分的関係)からべつの主語的統合(=新たな意味)への生成を可能にさせる媒合機能から、「あなたの記憶」における保持と同程度に有効な固有値の生成を見いだすことが可能であることも、指摘しておく必要があります。詩をめぐる固有値の生成は「さらに物質的なラオコーンに向かって」において、主に鑑賞者である「あなた」の記憶に固有値をつくりだせるかどうかの問題として扱われていました。しかし、詩的関係における新たな意味の生成に伴う不安定な関係の回復は、それ自体がテキストの意味の準安定状態をつくりだすものとして考えることができます。つまり、詩の媒体という固有値は慣習=リズムの束という「制度」の次元において、そして媒合機能による詩的関係の準安定化において成立するのです。詩の媒体をこの二重の論理から立ち上げることで、詩とそうでない言語表現とを区別する詩の固有性を取り出せるのではないでしょうか。
肯定すべき不確定性に向けて
さて、あらためてこれまでの議論をまとめてみます。詩の媒体は歴史的過程と流通過程において反復された複数の「制度」=慣習の束と、個々の詩的関係における媒合機能から形成される。このふたつの論理にはいくつもの主語的統合と述語的統合の対がひしめきあい、それらが織りなすレイアウトに詩の制作的空間が存在しています。
この制作的空間は、たったいま書かれている詩がほんとうに詩であるのかどうか、新たな意味を備えたテキストなのかどうか、その意味の探索を引き起こす魅惑の知覚が「あなた」に起こり、「あなたの記憶」に残るのかどうかが事前に決定されていません。詩の媒体は、「事前にすべてを把握する主体は存在しない」という「制作へ」の記述をまさしく体現するものとしてあります。
とはいえ、この不確定性は「わからない」という否定形で記述されるものでは必ずしもありません。岩成のテキストはくり返し客観的な定義の不可能性を論じていますが、「制作へ」はもちろんのこと、クラウスや佐藤のテキストからはむしろ肯定的な意味を持つ言葉として「不確定性」という語をとらえることができます。というより、むしろこの不確定性を基盤に置いてこそ、はじめて詩の媒体は論じるに値するものとして存在するとさえいえます。つまり、事前にその存在を自明視できないという問題は、制作に不可欠の要素として引き受けられるのです。
クラウスにおいて媒体の再発明が「未来への投影」であり、「過去への想起」でもありうると述べられていたのは、現在の時制における制作行為が過去の慣習を引き受けつつ未来における再帰性の生成に向けられていたからです。いわば、対象が多くの人間にかつて知覚されてきたが見過ごされてきたものをあらためて過去から抽出し、再帰性を持ちうるものとして提出することを意味します。であれば、制作は常に再帰的構造の実現が不確定だからこそ意義のあるものであり、これを詩の問題へと転用すれば、「宣言」は不安定だからこそ「宣言」されなければならない(それを詩として提出しなければらない)、といえます。
そして、佐藤が述べた「あなたの記憶」における固有値の生成に関わるリズムは、岩成によって共通項を著しく欠いていると述べられていた「宣言」の問題に、ポジティブな視点を加えてくれるものです。なぜなら、ここで「宣言」の持つゆらぎは、客観的な定義の不可能性ではなく、当事者間でのコミュニケーションをめぐる応答可能性へと開かれるため、詩を書き、読む経験のなかで不確定性は「共有可能なものかどうかわからない」ものから、「共有可能にすることができる」ものへと、その様相を変えるからです。万人があらかじめ詩人であることはできないが、そのうちのだれかを詩人にすることができるかもしれない。だれかの身体を詩人の身体へと述語的統合を組み替える力が、詩が詩であることの本質なのです。
しかし、これはこれで「あなた」を詩人にさせるかどうかは事前に決定できず、詩作品の完成は常に事後的であるほかないという結論に向きやすい傾向があります。ところで、「制作へ」で試みられた制作的空間は、この身体=主語的統合をべつの身体=主語的統合へと変形させるために、その変形を可能にさせる「あいだの空間」なのでした。制作行為が述語的統合の次元へと降りていき、そこで新たな主語的統合=身体の生成を目的とするなかで、制作的空間はそれを可能にする自他の対象化以前の、「媒体との対話」をとおして私と対象を生成する領域です。しかし、詩の制作においてこの自他の対象化は詩的関係の生成と、そこで得られた不安定な知覚の回復という、弱い主語的統合の複数的な発生によって観測されます。またべつの視点から見れば、制作はジャンル=流通過程=インデックスとしての「詩」という巨大な主語的統合をフィードバックすることによって「制度」化された複数の慣習=リズムと、それを引き受ける私の身体のあいだで、私の知覚において徐々に組み立てられてもいます。
であれば、詩の固有値は「変化した」あなたの身体をめぐる事後性だけではなく、あなたの身体の変化を試みるべくして制作をおこなう私の身体にも見いだされうるものでしょう。つまり、詩の媒体としての固有値は「あなた」という、事後性のもとで観測可能になる手前の地点にまで拡張される。「あなたの記憶」における固有値の形成が未了である状況を背景として、制作者の身体と言語のあいだにある制作的空間で個々の詩的関係が組み立てられ、それらが媒合機能をとおして関わりあうなかで、固有値は徐々に(自己)生成されているのです。
これは個々のコミュニケーションが流通過程を含めて、ゆるく連鎖的につながりあうシステムのどこに力点を置くかという問題であるともいえます。詩を読む者にとっての詩の固有値と、詩を書こうとする制作者にとっての固有値の質的な差異が、一方で読み手であり他方では書き手であることもできる私たちの身体において、二重化されている。これは、あなたから私の記憶へとつくりだされる固有値と、私からあなたの記憶へと保存されることを目指すテキストを制作しようとするなかで、私とテキストのあいだにつくりだされる固有値の差異として分けられます。つまり、制作過程=一次過程と流通過程=二次過程のあいだのズレの反映として、その構造式がコミュニケーションを介在させつつ変異する。私を詩人にさせる言葉を、私がつくることの次元。むしろ、たったいま書かれる言葉が「詩ではなく、詩でなくもない」という未定の時間、テキストと制作者の身体という述語的統合のあいだで、制作者にとっての詩の媒体がつくられるのだと言い換えてもよいのかもしれません。
つまり、制作に伴う媒体との対話は、媒体の制作と平行しながら漸進的に展開される。あらためて整理をすれば、その制作は二つの手続きを要請します。ひとつはインデックスとして示されるような近代制=巨大な主語的統合の、複数的なバリエーションである「制度」=慣習=リズムの束を取り込み、詩が詩であることの「宣言」を知覚可能なかたちで表現することによって果たされます。もうひとつには、いくつもの詩的関係が述語的統合としてテキスト単位で発生し、媒合機能によって組織化される、弱い主語的統合の束として。両者が相補的に機能することではじめて、詩は他のテキストから区別される固有の媒体を表現できるようになりますが、それは他者への伝達をめぐる不確定性を抱える制作者の身体に知覚される限りでのみ機能する「私にとっての詩の媒体」であり、他者への流通過程においては事後的な慣習=リズムの再帰性と記憶の固有値を基盤とする「あなたにとっての詩の媒体」へと、テキスト内部の情報は受け渡されていきます。
詩の媒体は固有の領域に限定化されず、個々の関与者を横切りながら自己を変形させていく過程のなかで、そのつど異なる様態でしか知覚されない。しかし、こうした異なる媒体の往還関係は詩そのものの構成に不可欠のものであり、それこそが詩の媒体に固有の性質であるといえます。つまり、不確定性を表現の基盤とすることで、徹底して個々の関与者が(媒体の)制作者であらざるをえないという経験の渦中にあらわれるもの。それが、ほかならぬ詩と呼ばれる言語表現なのです。
1. 人間的なるものを超えて
気がつくと、人類学はその名前が示すとおり、人間のことだけを探究する学問になっていたと言ったら、奇妙に響くだろうか。
人類学は長らく、人間が生み出し、営んでいる制度や慣習などを「文化」と呼び、その記述を「民族誌」と称して、人間の文化の記述と考察に浸った末に、記述のしかたや学問を成り立たせている仕組み、その権力配分にまで気を配りながら、どうしたらそのような再帰的な課題を乗り越えて正統な学問たり得るのかを考えるのに頭を悩ませてきた。
そのことは、形質人類学、考古学、言語人類学、文化人類学という4部門から成る総合学を目指した、20世紀初頭のボアズ流のアメリカの人類学の「後退」であり、フィールドワークを学問の中心に位置づけ、民族誌を制度化した、マリノフスキー由来のイギリスの人類学の「前進」の結果だった。世界に広がった、民族誌を重要視するイギリス流の人類学は、アメリカで巻き起こったポストモダン的な自己反省モードの投入によって内向きの議論を重ね、前世紀末から今世紀初頭にかけて隘路を歩むことになったのである。
そうした前進と後退の歩みの陰に、もう一つの人類学の流れがあった。レヴィ=ストロースの人類学である。1938年にブラジル調査に出かけたレヴィ=ストロースのフィールドワークは、一つの社会で局地的な調査をおこない、輝かしい成果を出し始めていたマリノフスキーのそれとは異なり、集団間の「断面」の比較を通じて変異の多様性と共通性をあぶり出し、様々な変形によって一定の原理が広汎に見出されることを示すものだった。その手法はその後、レヴィ=ストロースの研究に通奏低音として鳴り響きながら、「音韻論の社会構造への応用」(『親族の基本構造※1』)から「異種との交換(交歓)」(『神話論理※2』)という主題へと次第に高められていったのである※3。
デスコラやヴィヴェイロス・デ・カストロなど、レヴィ=ストロースの思想を継承した人類学者たちは、人間と他の生物種との関係へと踏み込むことで、「アニミズム」「パースペクティヴィズム」「多自然主義」など、人類学だけに留まらないより包括的な人文学の新たなトピックを見出したのである。人類学は21世紀を迎えると、人間のみでなく、人間を含みつつ人間を超えて、より大きな研究枠組みの中で思考するようになった。コーンの「人間的なるものを超えた人類学」は、そうした流れの中から生まれた一つの果実である。
森が考えているということで、いったい何が言われようとしているのかをよく考えてみたい。つまり、(全ての思考の基礎を形成する)表象の諸過程と生ある存在のつながりを、人間的なるものを超えて広がるものに民族誌的に注意を向けることを通じてそれがあきらかになるにつれて、つかみだすことにしよう。そこで表象の本性について私たちが抱く前提を再考するに至った見識を用いることで、それが私たちの人類学的な概念を変えるのかを探ってみるのがよいだろう。このアプローチを「人間的なるものを超えた人類学」と名づけようではないか。
エドゥアルド・コーン『森は考える — 人間的なるものを超えた人類学※4』
コーンは、パースの記号過程を用いて、人間を含め、あらゆる生ある存在がいかに思考するのかという問いを立てる。そうすることによって、人間のみを扱う人類学を超えて、哲学とも深く交差しつつ、ノンヒューマンとヒューマンを同じ地平に眺める人類学の新たな領野を切り拓いたのである。
2. マルチスピーシーズ民族誌/人類学
「マルチスピーシーズ(複数種)民族誌」も、その流れに位置する。それは、異種間の創発的な出会いを取り上げ、人間を超えた領域へと人類学を拡張しようとする。
その成立の経緯は、概ね以下のように説明される。レヴィ=ストロースが動物を「考えるのに適している」と捉えたのに対し、ハリスは、それらは「食べるのに適している」と捉えた。しかし、動物を含む他の生物種は、人間にとって、たんに象徴的および唯物的な関心対象というだけではない。他種は、人間や別の種と関わりながら絡まりあってきた。ハラウェイが言うように、他種は人間にとって「ともに生きる」存在でもある。マルチスピーシーズ民族誌は、この「ともに生きる」というアイデアを重視する。それは、複数種を取り上げることによって、動植物を人間主体にとっての対象としか捉えようとしてこなかった人類学が抱える人間中心主義的な傾向に挑戦しようとする※5 ※6 ※7。
オグデンらによれば、マルチスピーシーズ民族誌とは、行為主体である存在者の絶え間なく変化するアッサンブラージュの内部における、生命の創発に通じた民族誌調査および記述である※8。それは、複数の有機体との関係において、人間的なるものが創発する仕方を理解しようとする。ヴァン・ドゥーレンらによれば、マルチスピーシーズ人類学は、他種をたんなる象徴、資源、人間の暮らしの背景と見ることを超えて、種間および複数種間で構成される経験世界や存在様式、他の生物種の生物文化的条件に関する分厚い記述を目指す※9。マルチスピーシーズ民族誌/人類学は、人間を静的な「人間–存在(human beings)」ではなく、動的な「人間–生成(human becomings)」と捉える。
インドでは年間何百万という牛が死ぬが、神聖視されているため食べられることはない。牛は死にかけると、遺体ごみ置き場に連れて行かれる。ハゲワシはそれを30分できれいに解体する。しかし今日、牛を食べることがハゲワシを殺す。というのは、貧困層が牛を使って作業を続けるために、また牛の足の病気、乳腺炎、出産困難などを処置するために、安価な非ステロイド系抗炎症薬ディフロフェナクが牛に投与されるが、それがハゲワシに腎障害をもたらすからである。インドでは現在、ハゲワシの減少に反比例してイヌが増えている。イヌは、ハゲワシのようなスピードと完璧さで死骸を片付けはしない。イヌは町をうろついて人を襲い、狂犬病などをもたらす。ハゲワシがいないと、人や動物の健康に重篤な影響がある。このようにして個体は絡まりあって生きており、生と死を含む複数種の文脈では、他者の苦しみへの純粋な反応を考慮しなければならない。
ツィンによれば、マツ、マツタケ、菌根菌、農家の人たちが絡まりあって生存可能性を生み出している。痩せた土地でマツと菌根菌は共存しており、菌根菌が育つとマツタケになる。農家の人たちは、燃料や肥料を求めてマツ林に入り、生態系に介入する。そのことで、マツは排除されることを免れ、マツにとって程よく攪乱された状況がつくり出される。マツ、菌根菌、農家の人という異種の偶然の遭遇によりマツタケが育つ。また日本では、高品質のマツタケは高価な贈り物として、特定の小売に卸され、人間関係の構築のために用いられる。マツタケはいったん自然から切り離されるが、人間と自然が絡まりあったものとして、人間社会にもたらされる※10 ※11。
ドメスティケーションを再考する過程で、ステパノフらは「飼育する/飼育される」という古典的な二項図式に代えて、ヒューマンとノンヒューマンが入り乱れ、それらが長期にわたって根を張るハビタット(生息地、なわばり)である「ドムス(domus、家)」を変容させるような、相互行為的な動態による三項的な図式を提起している。コミュニティとはこれまでは、生物学では自然環境の中で種が相互作用する場であり、社会科学では人間の集団を意味したが、ステパノフらはレステルの概念を拡張して「ハイブリッド・コミュニティ」という包括的な概念を創出する。それは、「共有されたハビタットの周りの人間、植物と動物の間の長期にわたるマルチスピーシーズ的な連携の形式」のことである。南シベリアのトゥバの「アアル・コダン(生きる場所)」というハイブリッド・コミュニティでは、家族と家畜がともに暮らしている。そこでは、すべての要素が相互に依存しあっていて、人間の過ちが家畜に病気をもたらし、ヤクの供犠はアアル・コダン全体に繁栄と健康をもたらすとされる※12。
マルチスピーシーズ民族誌/人類学は、人間と人間以外の存在という二元論の土台の上で繰り広げられる、人間と特定の他種との二者間の関係ではなく、人間を含む複数種の3+n者の「絡まりあい」とともに、複数種が「ともに生きる」ことを強調する。人間主体に現れる範囲のみで他種は捉えられるべきではない。それはたんに象徴的・唯物的な対象ではないとされる。
こうしたマルチスピーシーズ人類学※13の特性をより鮮やかに理解するために、哲学の課題を一瞥することは有用だと思われる。現代のモノの哲学は、マルチスピーシーズ人類学と同根の主題を孕んでおり、人類学の近年の研究成果を取り入れて交差し、拡張されているからである。
3. 種を記述する技法
カント以降の哲学では、人間がモノに対してつねに特権的な位置を保ってきた。対象世界が差異や多様性に満ちているにしても、あくまでも人間主体から見た剰余や外部とされてきたのである。ハイデガーにとっても、世界は何らかの目的をもった道具が連関してできており、その連関に不確定さを持ち込むのはつねに人間であった。モノが人間に現れる範囲でしか捉えられてこなかった「相関主義」を批判して、近年ハーマンは、モノとモノが能動的であり受動的である役割を演じながら独立的に作用することを強調する※14。
哲学者・清水高志は、近年の人類学の議論を積極的に援用しながら、擬人化される傾向にあるハーマンの「オブジェクト指向哲学」に挑んでいる※15。清水は、モノとモノが互いに移動し相互包摂する往還運動を強調する。マルチスピーシーズ人類学もまた他の生物種を人間に現れる範囲でのみ扱うのではなく、相関主義を超えて種と種の関係性それ自体へと踏み込んでいるのだとすれば、両者の課題は共通している。
ところで、ここでいうモノには非生命だけでなく、生命も含まれる。マルチスピーシーズ人類学が扱う「種」とは、主に生命である。以下では、生命記述の技法について、モノの哲学の議論の延長線上で手短に触れておきたい。
清水を継承しつつ上妻世海は、「ありのままの、不合理で、重畳で、無駄が多く、混沌に満ち溢れた、あやうい可能性の上にかろうじて成り立つ動的なものとしての自然である※16」〈ピュシス〉や、「あらゆる存在を様々な〈あいだ〉において見ようとする理論的態度※17」としての〈レンマ的論理〉を骨組みとして、生命記述の技法を検討している※18。上妻は福岡の「動的平衡」論を導きとしながら、以下のように述べる。
なぜか僕たちは、明日も、明後日も、明々後日も、同じ身体をもち、自己同一性を保ち続けることができると信じている。しかし、物質的には1年も経つと、僕は僕でない。僕は自らを分解することで自らを構築し、自らを構築することで自らを分解する「流れ」である。そして、この「流れ」の中で構造を維持するためには、「私は私である」という自己同一性の耐久性や構造を強くするのではない。エントロピー増大の法則による乱雑さが構造の維持を不可能にしてしまう前に、先回り的にその同一性を部分的に分解し、そして構築する必要があるように、「私は私でなく」(分解)、「私は私でなくもない」(構築)という「流れ」の中に身を置くことになる。
上妻世海「制作へ」
生命は変形と流れの中で、つまり時間の中で分解と構築を孕むものとして捉えなければならない。言い換えれば、「僕たちは『死につつ、生き、生きつつ、死んでいる』」のだ。
上妻はこの議論をさらに進めて、生命記述の技法を、事物がそこに存在するのはそれ自らによってではなく、他に依って他との関係においてであるとする龍樹(ナーガルジュナ)の『中論』に求めている。生命は「相依相待」により、生命たり得ている。生命の本質とは、事物の存在が「他との関係に縁よってある」という「縁起」に他ならない。
種が生命のことであるならば、「種」を自律的で安定的なものと捉えることには慎重でなければならない理由がここにある。種に出入りする他種によって種が相依相待的に生まれつつ死に、死につつ生まれるのだとすれば、「マルチスピーシーズ(複数種)」が喚起する、自律し安定した「種」のイメージは問題含みであることになる。それゆえに、種と種の絡まりあいに迫ろうとするマルチスピーシーズ人類学は、「種」とは何であるのかという問いを疎かにすべきではないということを、ここでは確認しておきたい※19。
4. 制作論的転回のほうへ
マルチスピーシーズ人類学が、人類学自体を反省的に捉え返した「再帰人類学」の先に、「人間とは何か」をふたたび問い始めた21世紀の人類学によって生み落とされた一つの嬰児であるならば、それは、既存の人類学の装いを必ずしも纏っている必要はない。先述したように、マリノフスキーの流れを汲む民族誌の積み重ねがあったからこそ人類学は発展したのであるが、他方で、人間に現れる範囲でしか他の生物種を取り上げることがない、人間しか対象にしない多文化主義的(文化相対主義的)な人類学を生産し続けてきたのであり、その延長線上で、再帰人類学においては民族誌を書くことそれ自体が問われたに過ぎなかったのである。では、「既存の人類学の装いを必ずしも纏わない」人類学は今日、いかにして可能なのだろうか。その解の一つは、いわゆる「人類学の存在論的転回」を超え出ていくところにある※20。
そしてその手がかりは、ふたたび上妻の制作論に求めることができる。上妻の説く「消費から参加へ、そして制作へ」という図式は、「他者」の真っただ中で暮らし、民族誌を書いて人類学を生産し続けた、マリノフスキー以降の〈消費〉、文化を書く自己を反省し社会実践に向かうとともに、民族誌を「他者」の参加へと開いた、再帰人類学の〈参加〉、そして、そうした多文化主義の所産を経て、今日、複数種の「制作的空間」へと降り立って、〈制作〉へと踏み出し始めた、多自然主義的な人類学の流れにそのまま当てはめることができよう。
上妻が示唆するように、「制作的空間」に降りていく時、異質なパースペクティヴとの感応的な関係を取り戻すためには、言語、とりわけ人間の「言語」を用いているだけでは十分ではない。そこでは、「現象を超えて実在を感じること、音やリズム、形として繋ぎ合わせること」が要請される。「制作的空間」におけるテキストとは、身体に他ならないのだ。鏡の向こう(「制作的空間」)に降りて、鏡の中で乱反射を浴びることで、自らの身体を作り替えなければならない。
「制作」とは、実際にやってみることで「未来の情報」を生み出しながら、その次へと進んでいく、あるいは引き返していく往還運動である(中略)まずは「制作」してみること、そうすることで僕たちは「制作的空間」へと入り込んでいく。
上妻世海「制作へ」
なすべきは、多文化主義的な土台の上でなされる〈消費〉と〈参加〉を超えて〈制作〉することである。「制作的空間」は、自己/他者、人間/自然に分割された人間の自己同一性を前提とせず、動植物を含む雑多な他者との不安定な運動の中に自己の変容を促すという意味において、多自然主義的な場へと向かう。マルチスピーシーズ人類学の「制作的空間」には、異種間の交歓からなる多自然主義的風景が開かれているのだ。
『マルチスピーシーズ・サロン』の中でシムンが試みるのは「人間のチーズ」の〈制作〉である。人間のミルクから作られたチーズを問題なく食べた人がいた一方で、ミルクの提供者が何を食べたのか分からないという理由で食べるのを拒否した人もいた。しかし、人間のミルクは人間にとって生まれて最初の栄養である。乳の分泌によって汚染は取り除かれるため、疫学上の問題はない。乳首を刺激していれば、年齢に関わらずミルクが出る。性腺刺激ホルモン注射によって男性が授乳することも可能であり、自ら授乳して子を育てた男性の報告もある。人間のミルクには凝乳させる乾酪素が欠如しているため塊にならないので、シムンは山羊のミルクを混ぜてチーズを作る。それは蜂蜜をかけてクラッカーの上に乗せて食べるとおいしいという。だが、人間のチーズにはどこか場違いの感覚がある。逆に、牛や羊などの他種から作られるチーズこそが「人間的」なのだ※21。私たちは、「内なる他者としての人間のミルク」から作られるチーズから乱反射を浴びることになる。
カークセイは、ザレツキーによる〈制作〉を取り上げている。彼はホモ・サピエンス代表としてコンテナの中で、ショウジョウバエ、酵母菌、大腸菌、アフリカツノガエル、カラシナなどと1週間過ごした。作業中に(頭からアンテナではなく足が伸びている)「アンテナペディア異常」のショウジョウバエを逃がしてしまったことがある(そのハエは食べても無害だという)。逃げたハエをめぐるメールのやり取りの最中に、ザレツキーは遺伝子が組み換えられた虫がすでにたくさん放たれていることを知る。他方、人間の管理の下で展示されたネズミがその後どうなったかが示されていないと、PETA(動物の倫理的取り扱いを求める人々の会)のローズはザレツキーに噛みついた。ザレツキーは5、60匹のネズミのうち展示後10匹が持ち帰られ、その他は廃橋の下に逃がされて死んだか食べられたのだろうと応答するとともに、「マルチスピーシーズ・ハウジングの倫理とは何か?」「生き物は人間の管轄下で生きることが許されるべきか?」という問いを発した。そしてザレツキーは、冷たいケージで病みやつれ孤独に苦しむ動物たちは自由に動き回りたがっていると説くPETAに従って、ケージの扉を開いて生き物たちを解き放ったのである。そのことでザレツキーは、人間の管理下に出現した「新しい野生」と、動物たちが長らく自由に動き回っていた「古い野生」の間の境目を曖昧にした。カークセイによれば、ザレツキーは狂った市民科学者を装って運動家や行政官たちの不安と戯れながら、「責任」についての問題提起をし、生物学的汚染に対する恐怖のイメージを喚起したのである※22。ザレツキーの「制作的空間」で、人間は他種との間で、自己の身体をじわじわと変容させていく。
身体の変容を伴う〈制作〉は、本源的には、日々のマルチスピーシーズ的な実践の中に埋め込まれている。雑誌『つち式』には、奈良県で数年前から農業に従事する東千茅が身体的に経験し、その目に映る農の風景が綴られている。東は、脱穀した籾の山に鼻を近づけて青い匂いを嗅ぎ、自らの生身を作ってくれる稲籾「ほなみちゃん」を慈しむ。退治した蝮の肉を鶏と分かち合い、鶏はかわいくかつうまそうだと語る。鶏種をニックと名づけて飼うが、時々鶏に飼われていると感じるともいう。
生きるとは、なによりもまず、他の生き物たちと生きかわすことなのだ。それは、多種多様な生成子たちの、それぞれの個体への作用とそれぞれの個体の外部の作用の、複雑にからみあい織りなす布の一糸となることである。
東千茅『つち式 二〇一七※23』
個体中心主義的なドグマから翻訳された日本語である「遺伝子」に代えて、「生成子」という日本語を案出した真木悠介(見田宗介)の生命論と交差しながら、東は「土を耕さない」日々の農業の実践をつうじて、他種との間でなされる自己の変容を言葉として紡ぎだす※24。
「本来生きることは、他人との関わり以前に、他種との関わりの次元の話である」。「現行の社会では、こうした異種との話が語られることはほとんどなく、人間間の話ばかりが氾濫している(中略)そこには不思議なくらい異種との話が見られない。あったとしてもそれらは、異種との関係を嗜好品的なものに限定するような、あるいは、異種との関係をあくまで同種との関係の手段や代償とするような、人間関係中心主義的な諸相である」。『つち式』は、マルチスピーシーズ人類学が取り組むべき今後の実践的な制作論的課題の一つの方向性を示している。
5. はじまりに向けて
マルチスピーシーズ民族誌としてはじまった試みは同時にマルチスピーシーズ人類学へと拡張され、その後またたく間に、アートやパフォーマンスなどを含む様々な実践と連携しながら、新たな知の領域を形成しつつある。マルチスピーシーズ研究は、人類学の下位部門というよりも、人間を単一の統合された存在として見るのではなく、それらがないと人間が存在しなくなる他の種と絡まりあいを視野に入れながら、人間中心主義的な既存の人文学とその周辺領域を脱中心化する、新たな「思想」となりつつある※25。人間と他種という二者間の関係ではなく、人間を含みながら複数種という3+n者の絡まりあいを。人間に現れる範囲での種ではなく、ともに生きる種たちのダイナミズムを。人間–存在ではなく、人間–生成を。安定的で自律的な「種」ではなく、相依相待によりそのつど作られる「たぐい※26」を。民族誌を著わすだけではなく、多様なメディアをつうじて制作を。
人間は、身体外部の環境の中の種を体内に取り込みながら生命を繋ぐだけでなく、身体内部に住む1千兆個に及ぶとされるヒト常在細菌の複数のコミュニティーとのマルチスピーシーズ的な関係の中で生きる人間–生成である。ストレプトコッカス・ミュータンスという細菌は、農業により穀物を摂取し、糖分が豊富になった人間の体中で「家畜化」されるようになった。それは糖分を好み、歯周病や虫歯を引き起こす原因となる※27。あらゆる生命はまた、複数種との関係だけでなく、非生命との絡まりあいの中にも生きている※28。マルチスピーシーズ研究はすでに石と人の関係をも研究の俎上に載せてきており※29、研究対象をモノやコトなどを含む、非生命にまで拡張する兆しがある。人間が生み出した「情報」が逆に人間の思考や行動に影響を与える状況は、科学情報革命の進展によって、とりわけ、モノのインターネット(IoT)の広がりにより顕著なものとなりつつある。
最後に、人類には世界の歴史を超えるより大きな歴史があるという考えに基づいて、138億年前の宇宙創成にまで遡って、そこから宇宙、地球、生命、人類へと複雑化する現象を探る「ビッグヒストリー」という新しい学問の動きがある※30。私たちの経験からは遠いながらも、宇宙の事象をいかにマルチスピーシーズ研究の射程に収めるかは、宇宙という壮大な外部を想定することで人類や文化を強烈に意識すること目指す「宇宙人類学」の試みとも重なる※31 ※32。
民族誌だけでなく、アートやパフォーマンスや種々の実践とも連携し、さらにミクロ、生命以外、マクロを取り入れながら、マルチスピーシーズ人類学は今後その研究と活動をいったいどこまで拡張していくのだろうか。マルチスピーシーズ人類学は、いまその歩みをはじめたばかりである。いや、はじまりに向けてその準備の緒についたばかりなのかもしれない。『たぐい vol.1』に掲載されるのは、種と種の絡まりあいの考察を今後一層深めていくための起点となる論考である。
苦しみを堪え忍ぶことに誇りをもてるような、労働の必然性に結びついた苦しみではない。
そうではなく、無意味な苦しみである。
この種の苦しみは、魂を傷つける。
なぜなら、概して、この種の苦しみの不平を言おうとすら思わないからである。
シモーヌ・ヴェイユ『シモーヌ・ヴェイユ アンソロジー』
プロローグ:r/place的主体?
まず、全体を象徴するイメージから始めてみます。分散化と多様性、そして善意と悪意に対するイメージです。
社会のなかで(少なくとも主観として)善意を持つ人は少なくありません。しかし、その善意の発露としての抗議運動は、なかなか成果をもたらさないという当たり前の現実があります。たとえば、ウォールストリートや国会議事堂の前に人が集まったという事実は、何かを変えたと言えるでしょうか。最近ではFacebookの情報漏洩に関連した対抗運動(後で説明するESG投資の一種)で、同社の株価が多少下がりましたが、すぐに回復しました。
よくある意見は、それでも抗議には意義があり、為政者がそれを気にするということを通じて運動は現実を変える、という考え方です。しかし、あまりにも遠い目標や間接的な実現を目指して、フィードバックのない活動を続ける精神力を求めることは酷ですし、抗議のための抗議に堕してしまわないことをチェックするのも困難です。
散発的な善意は、何かしらの形でつながらないと成果を出すことは難しいと言えます。ですが、運動を上から集権化する「革命運動」は、さらなる悲劇(ナチズム、ソ連の虐殺、またそれらをコピーした様々な暴力的支配)しか生みませんでした。
2017年、「ブロックチェーン」が「(制度・社会的に)何かを変える技術」として騒がれましたが、その際、キーワードになったのは「集権化」ではなく「分散化」です。しかし、そもそも分散化とは何でしょう? 分散化や分権化によって何が「良く」なるのでしょうか? これだけ価値観もコミュニティもバラバラになった時代に、無邪気に「良い」なんていう言葉を使えるのでしょうか?
それを考えるためのヒントが、次の映像です。
YouTube: Reddit Place (/r/place) — FULL 72h (90fps) TIMELAPSE (2017)
この動画は、72時間という制限のもとで、ネットワーク上で共有された100万ピクセル分のキャンバスを、一度に一人1ピクセルずつ自由に変更し、集団で編集する仕組みによって作られました。このキャンバスは「r/place」と呼ばれ、ロックがかけられているわけではないので誰でも編集に参加できます。描いたピクセルは、意味があろうとなかろうと、他人によって勝手にどんどん上書きされていきます。
その結果は? ぜひ、リンク先の動画を観てください。
r/placeの意義についてはこれから説明します。が、まず動画を見てもらったのは、そもそも分散化と善意や悪意を合わせた制度によって生じる事態について、わたしたちは言葉や観念による想定しか持っていない場合が多いからです。
分散化という言葉だけでは、海中で分子が勝手に混ざって意味ある秩序ができるという話のバリエーションのようにしか聞こえないかもしれません。その手の話は結局、マクロな権力に対して何もできませんでした。
同様に、当初は「新しさ」があった暗号通貨やブロックチェーンも、2018年に入って急激に国家規制の対象になり、「思想的含意を持つ技術」という意味では瀕死の状態で、技術の幻滅期※1へと向かっています。
こういった背景の元では、「理想主義ではダメ。もっとシニカルに現実を見よ」とあなたも言うかもしれません。
しかし、そういう態度の延長線ではない別の可能性を、r/placeの動画には感じます。
この文章では、その可能性を少しだけ展開してみます。現実逃避のために「現実を見ろ」と恫喝するアジテーションや、あえて手段を考察しない抽象的希望以外の道をみつけたいからです。
ブロックチェーンと分権化の夢
2017年、多くの人がブロックチェーンという新しい技術、そのアプリケーションである暗号通貨に対する夢を語りました。中央銀行の死。権力分散化の夢。貨幣発行の自由化・市場化によって、既得権益や国家運営の失敗によるインフレから脱出すること、中央集権的な権力によらない、自律した多様な価値観による社会設計、等々。
たとえば、暗号通貨技術を法定通貨に応用すれば、ゼロ以下の金利を柔軟に用いた新しい金融政策ができるようになるという、ゲゼル型マネー※2の実現も論じられています※3。
しかし、そもそもマイナスの金利がかかってしまうほど人や企業がお金を使わない原因が、現実主義の蔓延によって「希望や夢」を削られすぎているからだということも考えられます。 もしそうなら、金融政策技術の効率化を進めても、無駄な処方かもしれません。
希望を語ることの愚かさは、『カラマーゾフの兄弟※4』の大審問官が、あるいは現実に生きる政治エリートが熱く語ってくれます。大衆は愚かだから数字でコントロールするしかない。未来への希望で熱を持った奴ほど危険なものはない。そもそも人の心が抱えているファクターなどわかるはずがない。しかし、『カラマーゾフの兄弟』では、現実主義を語るイヴァンが自らの欺瞞に耐えきれず発狂し、理想を語るアリョーシャが彼を救出します。現実主義が、現実主義の観点から見て間違っていることもありうる。そんな漠然とした感触を抱くよう、あの小説はできています。
もちろん、小説は判断の根拠にならないとはいえ、わたしたちは現在、あまりにも理想や夢それ自体を語ることを恐れすぎている気もします。そんな状況のもとで、テクノロジーは再び理想を語ることを可能にしてくれるのでしょうか?
どうなるのが「良い」?
分散化の「夢」を描くには、まず、分権化テクノロジーはいったい何を思想的、倫理的、政治的に可能にするのかについて考える必要があります。つまり、記録・認証・管理などのシステムを分散化・分権化すれば、実質的なガバナンスも分権化できるのか、について、です。分権化は、「何を」「誰にとって」「良く」するのでしょうか?
そもそも問題は、わたしたちにとって何が「良い」ことなのかを、漠然としか思い描けないことにあります。共同体にとって「良い」ものを積極的に定義するのは難しいことです。答えを出せない問題とも言えます。
かつてウィトゲンシュタインは、「ある規則に従っていないということを指摘することは可能だが、その規則を明確に定義することはできない」という意味の指摘をしました※5。ウィトゲンシュタインの指摘は、一見そのような不定さを持たない「+の記号が意味する規則」のようなものまで含んでいました。また同様のことは、現在の技術において、パターン認識で雑多な画像から「猫らしきもの」を選ぶことはできても、「猫であることの画像的特徴」を定義として明示的に宣言・列挙・記述することはできない、というような事態にも現れています。
また、過去の革命運動は、本来書き下すことができない夢や希望を「理念」として定義してしまい、それに従わない人を内部闘争で追い落としたり、都合の良い解釈に従わない人を「反動的」であると非難することで惨劇を生みました。
つまり、「良い」は定義することが難しく、かつ、定義すると形骸化しやすいのです。
正義を声高に語る人たちに感じる鬱陶しさや胡散臭さが、わたしたちに現実主義を強いている理由の一つでもあります。あるいは、20世紀の共産主義の理想や思想が、いったいどれだけ多くの人命を奪ったのかという歴史をみても、中庸な現実主義しか選択しようがないという判断は必然であるようにも思われます。敵が理想ではなく利益を求めている限りは、交渉の余地があるのです。
一方、ポジティブに何かを得ようと求めるのでなく、マイナスを減らすという思考もあります。
「ポジティブな目標はわからないが、これだけは嫌だということは割と簡単にわかる」と仮定できるなら、これは有効な方針です。たとえば、統計的なAI技術の多くは「損失関数」という指標を使って、「損失を減らす」ことで学習します。「損失」を定義できる程度の漠然とした方向性は研究者によって与えられても、損失の低減を具体的に達成するポジティブな方法は、研究者にも、学習に成功したAI自身にも、最後まで明示的なルールとしては不明であることがほとんどです。それでも学習は達成されます。「規則は定義できないが、使える」というウィトゲンシュタインによる指摘の現代版です。
また、このように考えても、必ずしもその場の微調整だけで済むわけではありません。局所的な調整が連鎖する仕掛けは、目標が漠然としたままでも作り込むことができるのです。
そこで、「減らしたい損失」を「組織によって生じる、いろいろな苦痛」と仮定してみます。組織や社会から要請されても、嫌なものはイヤだと言いたいわけです。しかし、組織の内部で勇気を出して発言するのは難しいものです。哲学者ハンナ・アレントは『全体主義の起原※6』や『エルサレムのアイヒマン※7』などで類似の問題を深く分析して、組織の命令に従うだけではなく、ある種の勇気、命を危険にさらして命令に逆らい、人類にとっての正義を維持するような判断を個人に求めました。勇気はおそらく重要で、必要です。しかし、個人の勇気に依存しすぎたガバナンスは持続可能ではないでしょう。勇気のある人は少ないし、増える見込みも特にないからです。
勇気を必要とせずに、嫌なものはイヤだと客観的に伝える仕組みが(昔は無理だったが)今なら作れる。もしそうなら、少しは希望があるのかもしれません。
薄められた全体主義としてのブラック・ガバナンス
ナチスや旧ソ連その他のような、虐殺さえ伴う真の全体主義は、現在の世界では今のところ少数派です。一方、たとえば日本のブラック企業のように、現実主義・利益の名のもとに、言葉の裏読みと忖度、恫喝を伴う「脱落してもいい全体主義」のようなガバナンスを伴う組織は無数にあります。
ここで、殺戮を伴わない薄められた全体主義を、「ブラック・ガバナンス」と呼んでみます※8。
ブラック・ガバナンスを正確に定義するのは難しいことでしょうが、簡単にその特徴をスケッチしてみましょう。以下に二つの概念的な図があります。
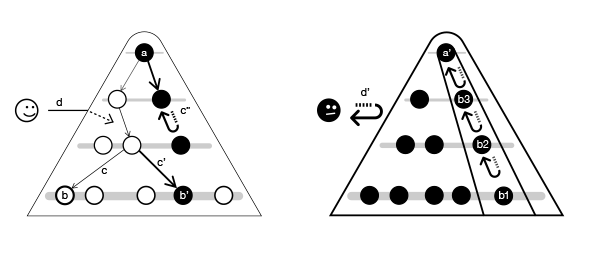
まず、左の図から説明します。
極端な中央集権性と予測不能性:a
権力が最上位の一極に集中します。その方が、臨機応変な環境への対応や既存の慣習・制度を無視した大胆な行動ができるので、他の優柔不断な組織に対する優位にもなりえます。しかし、中枢の指示に対する予測不能性が高まり、組織メンバーにとっては、その不安定性が恐怖や不安、さらには忖度の源泉にもなります※9。
非現実的な要求:b/苦痛:b´
上位者からの指示は「絶対修正できない目標」の達成を要求することがあります。白丸は、通常の階層的(官僚的)組織のなかで機能するメンバー、黒丸は、命令・恫喝・皮肉によってストレスや苦痛に晒されているメンバーを表します。
命令:c/恫喝:c´/シニカルな自己満足:c″
ブラック・ガバナンス下では、上位者からの(しばしば非現実的な)命令は、責任逃れのため抽象的で、かつ手段が明示されません。また、上位者しか知らない隠された組織内事情があり、命令と、それが現実的に(あるいは事後的に)意味するものの乖離が生まれます。そのため、命令される側は、命令の意味と解釈を巡る忖度や不安を感じ、命令する側は、意図あるいは事実を知らせず恫喝したりします(c´)。また命令する側に、隠された事情を知らない者へのシニカルな態度や侮蔑、その裏返しとしての自己満足(あれはそういう意味じゃないこともわからないの?)などが起きることがあります(c″)。また、恫喝が強くなると、命令する側の責任逃れだけではなく、過剰な忖度や癒着により、下の階層が持っているはずの情報が、その上の 階層にフィードバックされなくなり(c″で示される自己に回帰する矢印=組織内での不透明性)、そもそも何が起きているか誰も把握できないため、組織の外部から見た不透明性(d´)も強化されます。
外部からの視線:d
左の図では、まだ外部からの視線が通る隙間、すなわち透明性が残されていて、批判や改善、指導の余地があり、ストレスが緩和されることがあります。
一方、極端にブラック化が進むと、やがて右の図のように組織全体がブラックボックス化していきます。
シニシズムの連鎖:b1 > b2 > b3 > a´
指示の曖昧化や忖度、組織内の裏情報を知っている上位者からその情報を持たない者へのシニカルな侮蔑が連なり、何度も反復されます。その結果、常に「自分の一つ下の階層は現実を知らない」というシニシズムの連鎖が作られます。また、この連鎖で最上位以外の階層では、上の階層が持つ意図が誰にもわからないので、不安からイエスマンが増え、上位者はますます「意図を不明にする」ことによりコントロールをかけられるようになります。なお、この構造で、上位者は下の階層を分割統治するため、各メンバーの横のつながりを絶ち、基本的に最上位者に縦にぶら下がるだけの構造を目指します。図では、そのことを縦に走る境界線で表しました。なお、図が煩雑になるので加えていませんが、すべてのメンバーに同様の隔離があると思ってください。
また組織全体を見ると、下の階層からは情報が吸い上げられず、上の階層は自らの組織事情以外は考慮しない、環境からの入力と無関係な組織となります。
外部からの不透明性:d´
シニカルな自己満足と情報の遮断が支配的になること(c″)により、内部の指示系統を外部からトレースできなくなります(同時に、内部にある他の情報経路からも見えなくなります)。不可視であることで、上位者の理不尽な「裁量」権の発生を、どこからもチェックできなくなります(d´)。
上記の事柄により、苦痛がメンバー全体にひろがります。右の図では、この状況を真っ黒になった全体像として表現しています。
なお、図に描かれていない特性としては、
- メンバーが組織の外に出る(=逃げる)ことのリスクと困難(生活を利用した支配)
- 拡大以外の目的の消滅(ガン化)
もありますが、企業からの退出が難しいのは日本の特殊事情である可能性もあるので、除外してあります。また、ガン化は図に表現しづらいので描いていませんが、そもそも多くの企業は拡大以外の目的を持たないとも言えます。
ブラックな組織、アンフェアな組織には、それなりに自然な存在理由があるのかもしれません。意思決定の迅速さ、決してくじけない拡大への意志などは、たとえばナチスの拡大に貢献しましたし、サービス残業は企業にとっては単純に好都合です。激しい資本主義的競争と実需の後退により、現実的には世界、国、企業、家族、個人、あらゆるレベルで最終的にブラック・ガバナンスに至らざるをえないのが実情だとしたら、その外側に出る方法は、そもそも存在するのでしょうか?
歴史上の全体主義は、まさに「全体」、たとえばアジア全体や日本全体などの大きなスケールに現れますが、ブラック・ガバナンスはあらゆるスケールで現れます。ブラック・ガバナンスは、ブラック個人 < ブラック家族 < ブラック企業 < ブラック国家 < ブラック世界システム、という入れ子になるのです。
以下の図を使って、このことをもう少し補足しましょう。
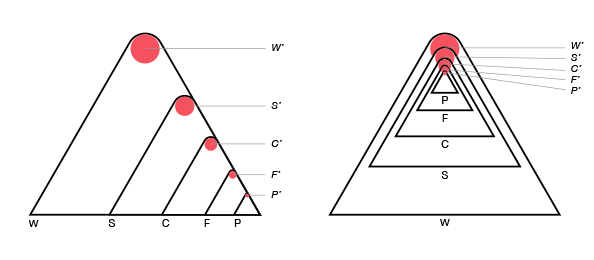
たとえば、適当にスケールを決めて組織を見てみると、以下のことがわかります。
ブラック世界システムW(以下「´」が付く場合はそのスケールでの最上位者を表す)
先進国でも、たとえばドバイやスイスでは、国内の人々は幸せに生きているように見えます。しかし、世界全体から見ればこれらの国は特権的な地位にあり、その経済はタックスヘイブン税制に支えられていると言えます。租税回避地であることにより金利差の分だけ、必ず儲かるためです。そしてそれは、不正や搾取を行う、すでに豊かな人々に利用され、格差を増幅させます。そもそも近代世界システムが出現する過程で、西欧系社会が非西欧系社会を支配するという構造ができてしまっています。なお、Wにおける最上位者(W´)は、現状アメリカや西欧を起源とする先進国となるでしょうが、中国など他のアクターも比較しうる力を持つので、異なるタイプの寡頭制への移行も生じています。いずれWはそのブラック・ガバナンス性を失うのかもしれませんし、アクターだけ交代して同じ構造が続くかもしれません※10。
ブラック国家S
南北問題がWというもっとも外側の構造としてあるのに対し、その下位メンバーである発展途上国内では、さらに独裁者(S´)に統治され、いわゆる「開発独裁」が行われるという入れ子構造があります。
ブラック企業C
上に見たように、企業(などの組織)内には、理不尽な裁量権を持つ上司(C´)がいて、低賃金や長時間労働が常態化しています。ブラック国家内部にブラック企業が生じる頻度は高まりそうですが、先進国においても、企業組織内あるいは外部委託関係に、裁量権由来の圧力が強く働けば、劣悪な労働環境は容易に生じることがあります※11。
ブラック家族F
企業のメンバーは、家族を持っている場合が多いでしょう。その内部に、強い発言権を持つ誰か(F´)とそれに従う者がいるという家庭においては、子供への圧政、あるいは無関心が働きます。なお、家族という組織には、脱退が極めて困難という特徴もあります。
ブラック個人P
さらに、家族のメンバーである個人の内部で、精神的な独裁者あるいは脳の一部(P´)が、自分の体を無理やり酷使して物事に取り組むことがあります。それによって達成感が得られますが、酷使されたPの体(あるいは精神)は壊れてしまいます。しかも、このタイプの個人は、同様の酷使をしばしば他人に強制します。
さらにこの見方を敷衍すると、全体主義のように「増える」ことだけが目的になった(実際の生体での)癌細胞も、ブラック・ガバナンスの例と言えるかもしれません。
以上のブラック・ガバナンスについての説明は、具体的な規模の違いや、地域や歴史の違いなどを見ていない抽象的なものです。これに対する反論として、対応はそうした個別のケースにより異なる、あるいは一見同じように見えるケースが実は全く違うタイプの事例である、といった指摘がなされるのが、近代的な社会科学の常道です。たとえば、アレントも「ファシズム」と「全体主義」という言葉をまったく違う概念として区別します(前者は国家の占拠を目的とするが、後者はそもそも国民国家という制度自体を廃棄するものとして)。
しかし、個別のケースに取り組むことを続けていった結果、専門が細分化していき、問題の全体像や対策が誰にも見えなくなるということがありえます。アカデミズムの視点で見ると、一次近似から二次近似、さらに三次近似…へと進み新しい知見を得られるなら、反例提出と理論のパッチ当て作業には意義もあるでしょう。しかし、近似レベルの向上とセットで、現実に対する影響力の尺度もないと、単に最適化とすべての事例を包摂できる力を持った複雑なモデルが良い、ということになりがちで、過去の例外的事例へのオーバーフィットを防ぐ手段がなくなってしまいます。
したがって、たとえ紋切り型に見えてしまうとしても、直観的な一次近似の方が影響力が強いなら、あえて単純なモデルを選ぶべき局面もありうるでしょう。
図で示したブラック・ガバナンスは、いつの世でも変わらず、どのスケールでも繰り返される「変えようのない現実」に見えます。しかしながら、様々なスケールで似たような構造がありそうなことに希望があるとも言えます。もし、すべてのレベルで似た構造が支配しているなら、あるレベルで発見されたブラック・ガバナンス構造への対抗手段が、他のスケールにも転用しうるからです。
こんな言葉もあります。
闘争は、とりわけ派生的命題にかかわる企業という枠組を逸脱するものだ。闘争は直接、国家の公的支出を決定する公理や、国際組織(たとえば、多国籍企業はある国に置かれた工場の閉鎖を勝手に計画できる)にかかわる公理を対象にする。これらの問題を担当し、世界規模の労働にかかわる官僚機構やテクノクラートたちによる脅威そのものを祓いのけるには、局所的な闘争が国家レベルや国際レベルの公理を直接の標的としつつ、まさに公理が内在性の場に挿入される地点で行なわれなければならない(この観点から注目されるのは農村地帯における闘争の潜在性である)。
ドゥルーズ=ガタリ『千のプラトー』
要求がいかに些細であれ、人々が自分自身の問題を提出したり、それらの問題がより一般的な解決をえるための個別的な条件を決定しようとするとき(革新的形態として個別的なものにこだわること)、その要求はつねに公理系が許容できない一点を提示している。同じ歴史が繰り返されていることには驚くばかりだ。最初はささやかなマイノリティの要求が、それに対応する最も些細な問題さえ解決できない公理系の無能と出会う※12。
ドゥルーズ=ガタリ『千のプラトー』
なお、ここまでに挙げたブラック・ガバナンスの属性は、ほぼアレントの「全体主義」から借用しています。彼女は、旧ソ連の全体主義が、衛星国に縮小・複製されたという記述を残していますから、「全体主義の空間的な移動、縮小」までは同意せざるをえないでしょう。一方、縮小や拡大が「世界システム」や「個人内部」まで及ぶことを認めるのは、躊躇するかもしれません。
しかし、仮にこの縮小が際限なく続くなら、どのスケールでも中心になるメンバーが必要で、それは入れ子になるため、中心は先に示した右の図のように重なります。極端に単純化したこの図では、「たった一人のブラック個人」が世界全体のブラック・ガバナンスを左右してしまうことになり、明らかに間違いです。ただ、入れ子構造自体はありうるとすると、「どのスケールで際限のない中心の共振が不可能になるのか」は興味深い課題です。それをヒントに、違うスケールのブラック・ガバナンスを修正する手段を発見しうるからです。
なお、アレントは、「全体主義」の構造的特徴を、先にブラック・ガバナンスの箇所で触れた命令の意味と解釈を巡る恣意性と、それがタマネギ状に重なり、誰も組織目標を信じていないが、シニカルな自己満足と下層のメンバーへの「現実主義」的恫喝によって動くことではないか、と示唆しています※13。もし、「命令解釈の恣意性」や「信じていないが、実行すること」に多少の苦痛が伴うなら、その苦痛をシグナルに、この構造が働きすぎる前に止める技術的解決策、ガンが増殖する前に免疫する方法があるかもしれません。
このような対抗手段として「苦痛の最小化」という最小限の指針を導入するとして、どうやったらそれを実現できるか。その具体的な方法を、後半で考えてみます。
分散化は暴力のメタに立てるか?
冒頭で触れたように、ビットコインなどの暗号通貨への支持は、そもそも投機以外の目的を持っていました。中央銀行と政府が独占してきた通貨発行権、それに伴うアンフェアな澱みを、ピア・ツー・ピアによる分散化によってなくす、というような主張です。
では「(通貨発行権に伴う)アンフェアな澱み」とは何でしょうか? また分散化はそれを解消できるのでしょうか?
具体的に、リーマンショックのようなシステミックリスクについて考えてみましょう。政府の政策と私有財産の関係については、非常に多くの因果関係が想定できます。が、一つサンプルがないと検討できないので、たとえば以下のような因果関係を想定します。
①デリバティブで貸借関係の依存性が非常に複雑になる
②どこかが破綻
③複合的なシステミックリスクが現実になる
④市中民間銀行や投資銀行が破綻(しかける)
⑤カウンターパーティー(負債)へ波及(しかける)
⑥株・債券等の市場が崩壊(しかける)
⑦破綻をなかったことにするために一部に公的資金注入(増税・国債発行など)
⑧貨幣発行量増加 ※ポイント1
⑨その時点での国内貨幣の実質価値低下
⑩景気破壊
(ここで終わらない場合、以下が続く)
⑪政府が信用を失う ※ポイント2
⑫政府の財政破綻、 ハイパーインフレ、中央銀行破産のいずれかにより既発銀行券が紙屑と化す
このモデルで、暗号通貨やブロックチェーンによる分散化が効くポイントは2箇所あります。
一つは、暗号通貨では貨幣発行量のコントロールが分散化できることです(※ポイント1)。分散化が機能していれば、システミックリスクの責任を無関係な国民に負わせるというような国家による責任転嫁を、少数の決定者では起こせなくなるでしょう。このような責任転嫁の究極のかたちは、本来不可能に近いレベルの「投資=軍備」を国家が行い、その後破綻する「戦争」かもしれません。
もう一つ(※ポイント2)は、そもそも少数が恣意的なコントロールをする政府・中央銀行の発行する貨幣を持つ(=貯蓄する)のをできるだけやめる(たとえば暗号通貨を使う)、という選択が可能になることです。政府と中央銀行は独立して意思決定するというのが建前ですが、ここでは実質上そのように運営されていない(一体化している)という立場をとります※14。国家の機能から貨幣発行をより原理的に切り離すわけです。
しかし、これらを可能にする暗号通貨を国家が許せないかもしれません。 上記2箇所のポイントを国家が嫌い、かつ、不法な行動をする暗号通貨ユーザーが多ければ、違法行為を抑制するついでに(それを理由に)暗号通貨そのものを違法にしてしまえばいいでしょう。
国家は法、あるいはその背後にある警察、そして軍隊によって暴力を行使できます。論理とは無関係に、あるいは後付けの適当な理由で、「駄目なものは駄目」と言い、国家にとって都合の悪い制度を禁止できます。同時に、革命的技術は革命的であるからこそ悪意を持つ人も真っ先に流れ込むという事実が、国家による禁止を補完・正当化する論理として働きます。事実、2017年に暗号通貨として可能になった投資には詐欺的なものが大量にあったようです。
もちろん、行政や官僚が何もかも禁止したいという意図を持っていると想定する必要はありません。しかし、たとえば官僚が、テクノロジーによるイノベーションに合わせて金融の非特権化を進めよう※15としても、法案にする際、彼の意図と無関係な横槍や権力闘争で歪められることは大いにありえますし、そのプロセスも往々にして不透明です。
分散化は「市場外部性処理装置としての国家」に代わってその必要性を補えるのかという疑問もあります。たとえば、国民皆保険のような、有無を言わせぬ強制加入によってのみ成立する国家的福祉制度の代替物を、分散的に与えることは困難でしょう。
あるいは、(大きなブロックチェーンへの攻撃は今後も難しいと仮定しても)「一つのチェーン」という単なる公開記録の正当性が、国家による暴力的強制よりも、人々が従うべき強い根拠と成りうるのか? ブロックチェーンは暴力という裏付けを持たない、単なる事実のようなものです。フェイクニュースとパワーゲームに明け暮れる現実主義の人々は、まさにその真逆、権力への意志によって真理や事実を政治的に生産するという世界に生きています。そのような時代に、単なる事実が力を持つことを、想像するのは難しいかもしれません。
また、そもそも分散化したブロックチェーンがあったとして、それは別の力関係、たとえば「分散化によって中央集権化の弊害を除くと主張をする、中央集権化したグループ」によって事実上支配・寡占され、制度の形骸化が起きることもありえます。 その時、暗号通貨の重要なポイントの一つであった恣意的なコントロール不能性が、理論や建前ではなく、事実として失われます。
中央集権でしかできないことと分散化すべきことを棲み分ければいい、という主張もよく聞きます。しかし問題は、中央集権部分が、あるいは分散化部分が、「棲み分け」のような平和的共存を望むとは限らないことです。
否定的理想、可能な一歩はどこに?
これまで語ってきた具体的な技術、ガバナンス、そして国家と暴力という制度から、いったん少し抽象的な思想へ視野を広げて、希望を探ってみましょう。
そもそも、EUや国連のような国家間共同体、あるいは全体主義的な世界観による共同体以外に、国民国家の上位、あるいは外部に立つ制度は構想しうるのでしょうか?
2017年の暗号通貨ブームの到来と共に、人々はこぞって新しい貨幣、可能な通貨制度、さらには新しい組織原理や分散国家のようなものまで、次々に発表し始めました。それらたくさんの夢(ハードフォークによらないアップデートが可能な暗号通貨「Tezos」、AIの共同所有開発を目的とした「SingularityNET」など)の一方で、挫折(EthereumでのDAO破綻から詐欺的ICOブームへの流れ)もまた経験されました。この挫折は、真っ当なガバナンスの欠如、あるいは本来の開発者の意図を裏切り詐欺を主導するブラック・ガバナンスによるものだったと言えるかもしれません。
しかし、貨幣制度あるいは社会制度をゼロから構想できる、ブロックチェーン上のプロトコル策定という構成的権力の観点からすれば、多様な制度設計に伴うブラック・ガバナンス的失敗例を見せてくれるこれらの事例に、希望を見出すこともできるはずです。前述した通り、同じ構造がスケールを超えて繰り返すなら、同じ処方箋で他のスケールを持つ制度を変えうるからです。
では、もしブラック・ガバナンスをあらゆるスケールで変更できるとして、どんな状態を目指すのか?
様々な理想を語ることはできます。しかし、20世紀にナチズム、共産主義という原理がもたらした災厄は、肯定的な表現で記述された無制約な理想と、そのルールに起きる形骸化が、単なる虐殺の道具になることを繰り返し見せつけました。その結果が、理想や原理よりも拝金とプレイヤーたちの損得勘定の方がまだまし、という現実主義なのかもしれません。
ですが、理想や原理を完全に捨て、拝金とパワーゲームにすべてを還元してしまうことは、虚無からの全体主義というナチス以前の状況を復元するのではないでしょうか?
そこで、「肯定的ではない理想」を考えてみます。
肯定と否定は、反転しただけで同じ、とつい言いたくなりますし、また、否定は時に無内容に見えます。
しかし、たとえば、その都度「これは違う」という形で、境界を外側から徐々に限定していくような方法はどうでしょう?
その時、境界の内側が肯定されたわけではないとは言え、とりあえず駄目なものを否定することで境界の形は徐々に限定され、不確実性の度合いを境界線の幅に反映させることもできます。こうして描かれる境界は、たとえ否定だけで描かれていても「無内容」ではありません。
境界の形を前もって知る方法がない場合、その形を肯定的に「定義」することはできませんし、むしろ、「しない方がいい」のです。
もし、無理やり定義してしまえば、その定義と現実のズレが、肯定的目標の形骸化を生むからです。あるいは、現実とズレた肯定的目標の「ほんとうの意味」に対する忖度が始まってしまうかもしれませんし、さらには、自分たちは目標の「ほんとうの意味」を知っているが他の人間は知らない、という形でシニカルな自己満足が顔を出しかねません。
たとえば、AIによる顔認識の技術では、明示的なルールを記述することはできませんが、仮にそれを「顔を認識する三つのルール」として強引に書き下したとしましょう。「卵型で、黒い部分が2箇所あり、上の方がやはり黒い」というように。ただし、人間による実際の顔認識は、やはり決してルールでは書けない複雑な判断でできているとします。
上記のルールの場合、「横顔」や「灰色の髪」が出てきた瞬間に破綻しますが、それでも「三つのルール」を守りたい人はどう振る舞うでしょうか? ルールの解釈を変えて忖度させるか、あるいは、あらゆるルールに失望するか、どちらにしてもルールは形骸化します。ルールへの固執は、その形骸化を導きがちなのです。
そこで、理想を抱き、それをルールによって表現する以外に、目標を定める方法を探してみます。
ポイントとなるのは、「(AIは)ルールでは書けないが、事実上は顔を認識できている」ということです。ルールに固執する視点からは、この顔認識の実現は望めません。諦めるべきは、「明示的なルール(による理想の表現)」であって、ルールによって目指されていた、自然言語では「否定」という形式でしか表現できない「理想」ではありません。また、顔認識は否定神学のように「〜でない」という言葉を繰り返すだけの無内容な主張でもありません。
同様に、r/placeにも見られるような上書きの繰り返しによるガバナンス、つまり否定を根拠にした自律的なガバナンスも、ルールベースでは実現できないでしょう。ですが、結果さえ出ればどんな手段を用いてもいいと言うのなら、それは現在の日本社会を広く覆う現実追認主義、上書きに上書きを繰り返すバトルロワイアル的世界観の礼賛にしかなりません。また、明示的に定義できないゆえに、とりあえずすべての共同体的伝統を肯定する(共同体主義)のなら、これもまた「自分たちの価値観の外でどのような苦痛が起きていようと無関心」という現実追認の一種となります。
では、r/place的な「ルールで明示的に書けない理想によるガバナンス」が、むき出しの生存競争と自由放任に陥らないようにするには、どういう条件が必要なのでしょう?
組織の外部をキープし続けるためのブロックチェーン:PS3と苦痛トークン
最小限の理想主義として、西川アサキが「PS3」というものについて書いています※16。そこでは「否定」による目標として「①苦痛の最小化」が挙げられます。そして、その実現を目指す組織が維持される条件として、さらに三つの前提を挙げています。外部からの攻撃や悪意ある制度のチートを防御する「②操作へのセキュリティ」、メンバーが増加しても他のメンバーの目標が維持されるような「③スケールの拡張性」、そして持続(競争)可能性を生む「④同時に存在する異なる組織、制度との共存」です。
これらの条件を「PS3(Pain, Security, Scalability, Sustainability)」と呼び、ガバナンスの基本的な要請として「無根拠」に仮定してみます。
あえて「無根拠」とする理由は二つあります。まず、ここで掲げられている理想がすべて効率の一種であることに対して、たとえば、生理学的な要請を政治的な領域や理想に持ち込むことに反対する思想家(先に出てきたアレントなど)は反論するはずだと想定され、しかも、これから論じることは、様々な政治哲学の議論を踏まえていないからです。
そのような態度について議論を尽くすこともできるでしょう。しかし、そもそもそうした議論が、議論のための議論、一種のゲームになってしまい、結局は最終的な制度設計にとって意味を持たないという事例が多いと感じるので、ここでは単なる「仮定」として、前に進みたいのです。
PS3は否定的な目標です。それはブラック・ガバナンスに対する抑制の条件であり、積極的に理想の状態を描くものではありません。しかし、その実施は極めて具体的にならざるをえないと思われます。また、通常は肯定的に扱われるメンバーの多様性や組織の学習可能性などは、多様性がないと学習不能になり、結果的に組織が現実への適応能力を失って持続不能となり、苦痛の増大が起きるならば、という条件でしか考慮しません。
さらにPS3は、「ルールに従っていれば、後は個々人の自由」という思想だけの状況とは、似ているようで違います。どう違うのでしょうか?
一つには、言い換えられたかたちでの、他人との共感・関心が、すべての項目に入っていることです。感情的、あるいは感覚的な共感としての「①苦痛最小化」、見知らぬ意図を持った他者への関心としての「②セキュリティ」、群衆としての他者に埋もれても制度が破壊されないこととしての「③スケーラビリティ」、相反する目標や信念を持つ他者たちと共に生存しつづけるための「④持続可能性」、というように。
PS3は、ブロックチェーンという技術の制度的可能性について考える中で仮定されたものでした。苦痛を最小化するといっても、苦痛を追跡・評価する手段がなければ無意味ですし、その信用が特定の権力によって維持されているなら、結局のところ国家の上位はないという事態へ逆戻りします。全体主義と現実主義をくぐり抜けた人類に、国家が苦痛の追跡に関してだけは不正をしない、と説得するのはとても難しいことです。
しかし現在では、ブロックチェーンによって、「(苦痛への)トレーサビリティ」と(中央集権的な組織や権威に頼らない)「分散化した信用」とを、技術的に結びつけるやり方を想像できるようになりました。
また、西川は「苦痛トークン」という簡単な仕組みを提案しています※17。
苦痛トークンは次のような文脈を仮定した仮想的な権利です。
- 幸福についての合意よりも、苦痛についての合意の方が得やすい
- 大義(理念)や誰かの幸福のためには当然苦痛が伴う、と信じるのを避ける
- 潜在的で見えない苦痛を顕在化する
- 組織の失敗が苦痛というシグナルを持ち、それを通じて組織構造を変え、学習しうる
苦痛トークンは、ネットワーク内で利用されるトークン(仮想通貨のような、権利量を表す単位)という形をとり、次のようなルールに基づいて運用されます。
- 苦痛トークンは、組織のメンバー(=以下の図に描かれたグラフに含まれるノード)に一定期間に一定量配布される
- 譲渡不可能
- メンバーは行使量を毎期決める
- 行使は匿名で行われる
- 組織はその生産物(アウトプット)に、それを生産する際に行使された苦痛トークン量を、トレースできる形で添付する義務があるとする
苦痛トークンは、パブリックなブロックチェーンに記載されるため、改竄できず、しかも匿名で分散された、組織に対する変更要求権限となります。
苦痛トークンには、具体的な提案への評価の必要がなく、誰のせいでそうなっているのか、なぜ苦痛なのかわからないが、とにかく「苦痛」が生じている事実を匿名で表現できる、という特徴があります※18。
では、その苦痛トークンの行使に対し、組織はどう応じるのか? たとえば以下のような想定ができます。
- 苦痛トークンの行使により、組織構造(各メンバーの貢献、権限、命令、資源のルーティング方法)が変化する
- 変化の大きさや形は、行使された苦痛トークンの総量、行使したメンバー群の分類情報、現在の組織構造などを配慮し、別途定められたアルゴリズムによって(裁量の発生をできるだけ防ぐため人の手を介さずに)決定される
苦痛トークンは、組織メンバーの苦痛シグナルを組織内外でトレースする仕組みの初歩的な一例に過ぎません。が、似たような仕組みが正常に機能しうるのなら、「フェアでない商品は買わない」というような行為にも、もう少し具体的な内実を与えうるはずです。
ここまで説明したことは、以下の図のように整理できます。
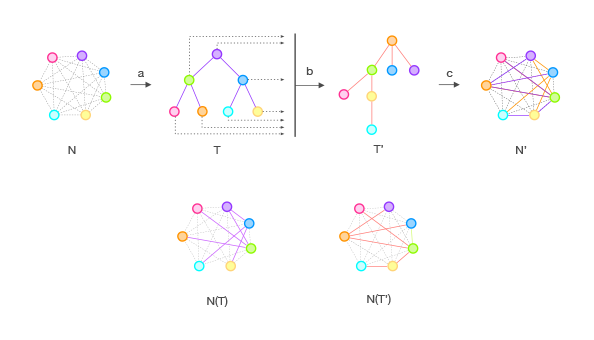
N:仮に想定した、完全にフラットで分散的なネットワーク状組織。
T=N(T):ある時点までの環境や学習によって形成されたツリー状のルーティング構造=組織。
※ N(T)はTと同じ構造を表現するネットワーク。
T´=N(T´):苦痛トークンの行使結果をフィードバックし、新たにルーティングし直された、別のツリー構造。
※ N(T´)はT´と同じ構造を表現するネットワーク。
N´:N(T)とN(T´)の両方に素早く切り替わりうる動的ルーティング構造として、複数のツリー的支持構造を内在させた組織。
a:現在のタスクや状況にあわせ、ネットワークNをツリーTにします。ツリーにする必要があるのは、分業可能性や実行速度などの点では、多くの場合ツリーが有効だからです。ただし、一度できたツリーの硬直化、利権化、裁量化、支配権化が問題になります。
b:Tの環境不適応シグナルとして発せられた苦痛トークンを、ブロックチェーンを用いてトレースします。このシグナルは組織内政治からの客観性を担保するため、パブリックなブロックチェーンを使用するべきでしょう。苦痛トークンのトレースを考慮した自動プロセスによって、ツリーTはT´へと変化します。そして、この苦痛トークンのシグナルを、人の手が入らない形で、組織構造やルーティングへ反映させるアルゴリズムを走らせます。
パブリックなブロックチェーンを使っているので、トレース結果は外部から参照できます。排出ガスのようなイメージで、組織が活動によって産出した苦痛トークンの総量がわかるわけです。これにより、ブラック・ガバナンスの不透明性、シニカルな自己満足の両方を打ち消すよう試みます。なお、組織がトレース結果を公表しない場合、なぜ公表しないのか、という公衆からの疑問に対峙する必要があります。
苦痛トークンを行使するのはメンバー自身であり、しかも匿名かつブロックチェーンにより客観性が担保されるので、情報入力部分での不正はかなり防げるでしょう。むしろ、問題は苦痛トークンの組織構造への反映方法や、そのアップデートアルゴリズムを巡る政治だと思われます。が、これについては、いずれ別に論じる予定です。
c:環境の状態に応じ、過去の学習結果を参照したアクションとして組織構造を組み替えます。図ではN(T)とN(T´)の二つが同時に描かれていますが、ツリー構造はいくつあっても構いませんし、明確に切り分けることができない場合もあるでしょう。この状態の組織では、異質なツリー構造が同居するので、状況に応じ「上司-部下」のような関係が逆転することもあります。このような動的構造をキープすることが、環境に対してツリー状組織よりも高い適応能力と学習能力を持つなら、ブラック・ガバナンスは競争力を持たず消滅します。苦痛は主観的なものなので、物理的・統計的な保存とは無関係に、いわばフリーランチで減らせる可能性があり、そこには希望があります。
なお、ここで記したAIやルーティングアルゴリズムの使用は、とても観念的なもので、現実的にはデータの不足や再現の不可能性、タスクの不明確さ、報酬定義方法、学習の失敗など、様々な問題、特にAIの仕様変更を巡る問題が生じます。これらを考慮すると、ルーティング変更規則は、機械学習を使わず、誰にでも意味の明らかな非常に単純なルールで機械的に行うという手もあります。ただし、その場合は環境への適応能力が犠牲になるかもしれません。ポイントは、特定主体の責任・裁量が可能な限り無関係になるように、自動化・分散化・明示化することです。
では、仮にそのようなシステムが機能したとして、「誰かにとって不幸な組織変更が起きた場合、誰が責任を取ればいいのか?」、そんな疑問が生じるかもしれません。
しかし、誰か特定の人間・主体に「責任」を取らせる、という方法自体、システムが複雑化した場合の制度維持方法として、もはや効果がなくなりつつあるように思えます。苦痛トークンは、「主体–責任」というペアを、「苦痛トークン–分散的変更」というペアに置き換えようとしているとも言えます。
はじめの一歩:PS3+ESG投資
PS3や苦痛トークンは大雑把な指針にすぎません。ブロックチェーンも単なる技術で、それを苦痛の最小化などと実効的に結ぶステップはまだ不明です。目標となる状態はあっても、そこへの軌道は別に必要です。
では、とりあえず何から始めればいいのでしょう?
手をつけやすいのは、「建前上正しくて、すでにあり、景気を良くするもの」を更新することです。なぜならば、これら三つの条件が揃っていると、国家はその仕組を建前上も実質上も禁止しにくいからです(ただし旧ソ連の大粛清は、すべての条件を無視しましたが)。
ここでは、そういったものの一例として冒頭で少しだけ触れた「ESG投資」に着目してみたいと思います。
ESG投資とは、自然環境(Environment)・社会(Social)・企業統治(Governance)に配慮した活動を行っている企業に対し、選別的に投資を行おうという運動です。受託者責任(フィデューシャリー・デューティー※19)の徹底による安定的資産形成および利益相反行為の抑止という考え方の拡張と言えるかもしれません。
ESG投資の基本的枠組は、ポジティブ・スクリーニングとネガティブ・スクリーニングの組み合わせと、テーマ別投資です。ネガティブ・スクリーニングとは、武器やポルノ、動物実験、宗教的倫理観に反するような観点から、リスクの大きい銘柄を排除することです。逆に、ポジティブ・スクリーニングは、人権や多様性、再生可能エネルギーなどに配慮している銘柄(企業)、およびそれらによって構成される指標に対し、積極的に投資することです。
つまり、企業の社会的責任という文脈で文化・芸術への支援を主目的としたメセナとは違い、より直接的に投資によって社会環境をコントロールしようという動きであり、社会的に無意味な指標や高リスク銘柄に対しては投資が起こらず、結局は市場に評価されなくなるという力学によって駆動されることが期待できます。
しかし、現実主義によって疑い深くなったわたしたちには、そもそもいいことばかり言うESG投資が、「本当に善きもの」だと素直に信じるのは難しいことです。たとえば、ESG指標を満たしていると主張する企業と、ESG評価機関やESG投資を行う投資機関が癒着している場合、ESG投資は、単なる投資の新しいネタぐらいの意味しか持たないでしょう。現状を放置すれば、事実上もそうなる可能性があります。
今までのところ、ESG評価機関と企業の癒着を防ぐ仕組みは確立されていませんし、ESG投資を行うにしても、誰かが資料をもとに機密の理由で判断するという枠組みは変わりません。たとえば、日本の巨大な政府系機関投資家であるGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)が、なぜか軍需産業に投資していたことが指摘され、まさにESG的観点から問題になりました※20。
なお、GPIFがESG投資についてどう考えるのかについての活動記録が公開されています※21。が、その内容の是非以前に、150兆円以上※22というGPIFの投資規模を考えると、その意思決定をどのように行うのか、どの程度の規模の組織で行うのが適切か※23という問題があります。
つまり、現状のESG投資の仕組みそのままでは、現実主義的目線に耐え切れない可能性があります。そこで、どのようなESG投資ならば、結果としてPS3が実現できるのかを考えてみます。
まず、極端に理想的な状況を考えてみましょう。ESG投資が全面化して、世界や国家の景気を左右するほど規模が大きくなる。しかも、ESG指標の作成や評価は、とてもうまく分散化され、透明かつフェアで、国境を越えているとします。
ESGの無視(=環境、社会、ガバナンスを配慮しない企業の存在)を「苦痛」と考え、(苦痛トークンを一部に含むような)ESG投資のトレーサビリティが完璧であるなら、ジャーナリストが発見しなくても、たとえばAmazonの倉庫で苦痛に満ちた作業が行われているだけで株価が自動的に下がり、それが是正されれば上がるような世界もありえます。
もちろん、今現在でも似たような働きは報道や株式市場への反応によって起きますが、その経路は誰にもトレースできず、日々の新しいニュースに流されて忘れられがちです。だからこそ、「理想的な」ESG投資は一種の「革命」なのです。
では、理想から現実に戻って、「革命」を起こすためには何が必要か、まず技術的な観点から探ってみましょう。
ESG指標の作成や評価が自動化される場合、それぞれの企業において、全体や組織のために「仕方のない犠牲=苦痛」が生じていないか、生じているとしてその補償はあるのか、そもそもその苦痛は補償しうるものなのか、といった状況をモニターする仕組みが必要となります。
この時、苦痛トークンが指標として役に立ちます。「何か異常が起きている!」という段階で検出と緩和を行う仕組みでは、問題を整理して明文化する前に対処する必要があるからです。原因や対処は不明でも「苦痛がある」こと自体が検出されなければなりません。
また、モニターする仕組みや指標が「事実」であるためには、特定の人物や組織の意図だけで動かないことを保証し続ける仕組みも必要ですが、その役目にはパブリックなブロックチェーンが適任です。既存の経済システムで構築されているバリューチェーンをそのままブロックチェーン化することでも、恣意性の排除だけならば可能かもしれません。
ただし、ESG投資におけるトレーサビリティは、これまでのような限定されたバリューチェーン内の物流(ロジスティクス)ベースの追跡性だけでは不十分です。バリューチェーンの指標は相対的に固定していますし、その正当性や評価に関しても利潤追求以外の目的がないため、抽象度の高いESGよりも信用の保証が簡単にできるからです。
さらに、もしESG投資+ブロックチェーン化された(苦痛などESG失敗の)トレーサビリティ、という構造が実現しても、それだけではまだ足りません。
そこには、「理解可能性」と「参加への動機づけ」が欠けています。技術的にインフラが整ったとしても、ほとんどの人に理解できない指標の羅列がモニターを流れていくだけなら意味がありませんし、ESG投資を実現できる枠組みがあっても、市場が閑古鳥では無意味、もしくは事情通の投機を呼び込むだけです。参加者とのインターフェイスデザインが問題になる、とも言えるでしょう。
この「理解可能性」については、AIの解釈可能性という研究分野があります。可視化、因果性追跡、反実仮想フェアネス※24など、「自分の行為が、何に、どの程度貢献しているのか、誰のどのような行為が、どのような貢献をしているかを追跡すること」にも、AIを使えるように改良する試みが始まりつつあります。
一方、「参加への動機づけ」については、ESG投資がやはり利潤性を持つ「投資」であることが、かなり大きなインセンティブになります。しかしそれに加え、自分のしていることが何をもたらし、何を防いでいるのかという公共性が可視化されるなら、「投資の利潤」という経済的・生理的・現実主義な動機だけではなく、アレントのいう意味での「政治的」な領域を弱められた形で復活させうるかもしれません(なお、アレントの場合、「政治的」とは、現実主義的な利害調整ではなく、物事をどうするべきかという「理想についての熟議・表現」という特殊な意味を持ちます)。
行き過ぎたESGの要求が、社会に遊びをなくしてしまう危惧もありえますし、さらにそのムードを悪用して市場操作を試みる者もいるかもしれません。冒頭に挙げたFacebookの株価変動がまさにその例です。ですが、もしそのようなESG指標を利用した相場操縦が起きたとしても、その抑制には、ブロックチェーンによる「失敗のトレーサビリティ」に加え、AIの補助による「理解可能性」、投資による「参加への動機づけ」を得て、変質した新しい政治的な領域としてのESG投資が、効果的な手段になりうるでしょう。
ここで、もう一度r/placeを思い出してみます。
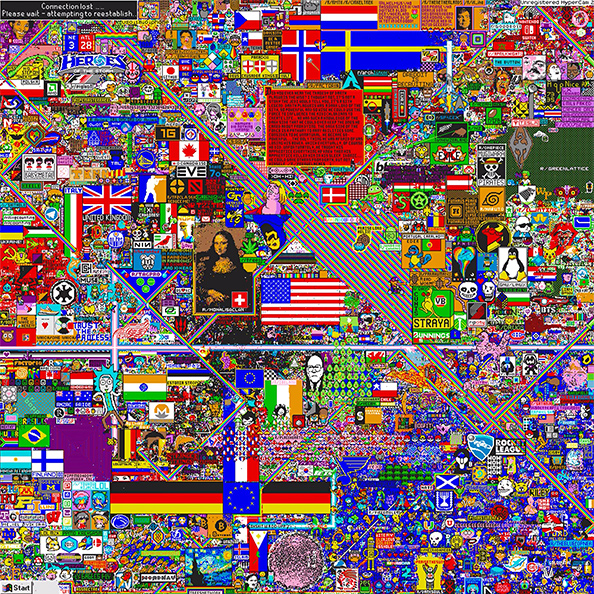
 r/placeのBTC版として開発された「Satoshi’s Place」
r/placeのBTC版として開発された「Satoshi’s Place」
上の画像は、「Satoshi’s Place※25」という、r/placeを模してBTC(ビットコイン)コミュニティが作った仕組みによって描かれたものです。r/placeより多少カオス的というか、単純に秩序が崩壊しがちな印象を受けます。
r/placeのイメージは、「社会」という巨大なものに対する、とても優れたインターフェースの形を暗示しています。個人が全体を把握でき、その影響も1ピクセルの貢献という形で理解できます。自分が何をしているかも、他人が何をしているのかも、そして、全体が何をしているのかも、管理されない形でわかります。
r/placeの動きは収束しません。しかし、意味のある図形を描いた状態が、わりと長く続きます。たとえば、悪意をもった個人や集団が意図的に図形を破壊する行動をとっても、その意図が誰の目にも明らかなので、対抗する動きを自発的に起こす人たちが出てくるからです。
最後に:r/place主体の実験と「制度の形骸化を防ぐ制度」について
最後に、PS3のもとでESG投資が機能する条件をおさらいしてみましょう。
- 単なるブロックチェーンだけでは、「国+暴力=規制」にも「企業/個人+悪意=詐欺」にも勝てない
- すでにある仕組みを、目的に沿って事実上の意義が変わるまでアップデートした方が、既存制度による抑圧(禁止)がしにくい
- ESG投資は証券取引+フェアネスなので、建前上、国家=規制によって消せない
- しかし、ESG投資を特定機関で行うのは、様々な形骸化が発生しうる上、規模が小さい
- 規模が大きくなり、分散化され、透明かつフェアで、さらに国境を越えた政治的影響力を持つなら、ESG投資は一種の革命になりうる
- 第一歩となるのは、ESG投資のトレーサビリティ、解釈可能性、インターフェースを改良していくこと
おそらく、分権的トレーサビリティ基盤・AI・インターフェース、それらすべてが揃っていないと、ESG投資は文字通りの意味では機能しません。
さらに、後述する「制度の形骸化を抑制する制度」もないと、すぐ骨抜きになります。
以上をすべて揃える仕方はまだわかりません。しかし、理想に破れ、現実主義を標榜し、結局は薄められた全体主義に流されていくよりは幾分ましな形で、スローガンや手段のないアジテーションではない、具体的・個別的な対策をいろいろと考える余地がまだ残っているのではないでしょうか?
たとえば、この文章はr/placeを模して、筆者たちが非同期リアルタイムで書いてみました。一つのGoogleドキュメントを共有し、メンバー全員が同時に執筆・編集し、他人の書いた文章を無断で消したり上書きしたりしています。これに加えて、文章を書く速度を一定化するルール、コンフリクトを解消するルール、誰が何をしたのかを追跡し、報酬に反映する方法などがあれば、よりr/place的なガバナンスに近づきます。
奇妙なのは、このような執筆方法だと、論文の一貫性をマネジメントする必要が減少するという体験をすることです。r/placeと同様、誰かが勝手に直すからです。「主体の死」については散々語られてきましたが、それを要約したり入門書を書く作者はたいてい一人で、一貫した文章を書くことになります。しかし、この文章は実際に複数の著者で同時に書かれています。「ある人にしかできない」と想定されるタイプの仕事でも、意外に分散化できるかもしれないという印象が、実感として得られました。
もし、国会答弁や公文書などをトレース付きでr/place的に書けば、非常に簡単な手段で、文書の真正性保証や官僚の責任逃れの防止ができるかもしれません。そもそも、記録が残る状態で同時に編集作業をすると、恫喝が難しくなります。恫喝するぐらいなら、自分で直せばいいのですから。
もちろん、最終的な状態やスタイルをどう確定するか、意図的ではない破壊=失敗をどうリカバーするかなど、課題も多いことは確かです。しかし、共同編集には、新しいガバナンスと主体性を同時に実現する可能性を途中で実地体験できるメリットがあり、理想社会と、それに至るプロセスに生じる「必要悪」としての制度を分離した結果失敗した共産主義を反面教師にできます。
最後に、「制度の形骸化を抑制する制度」について少しだけ触れましょう。
歴史を振り返ると、古代ローマでも近代のワイマール憲法でも、専制や全体主義はいつも「正当な」民主的手続きから生まれています。いわば、民主制の自殺傾向です。分権化を唱うパブリックなブロックチェーンでも、現状しばしば問題になるのは、その実質上の権力の寡占による中央集権性です。
分権を維持する仕組みの最もメジャーな形は三権分立です。しかし現実を見れば、忖度、癒着、ロビイングが発生し、権力分立は形骸化します。近世ヴェネチアでは、周囲の都市国家が君主制へ移行していく際、いろいろと制度を工夫して寡頭制を維持しようとしましたが、分権化を維持する制度的な枠組みのデザインには、まだ工夫の余地が残っている気がします。
そこで、筆者たちは、新しい権力分立の図式も考察しています。以下の図は、そのなかで描いたものの一つですが、その具体的な中身については、別稿で綴ります。
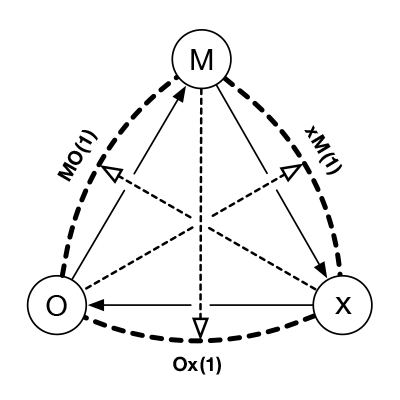
おそらくブロックチェーンの新しさは、それがありとあらゆるメタレベルからのチートに晒されても、ひとまず存続しているという事実にこそあります。そのような事態は、今まで暴力によってしか達成できなかったことです。
我々自身、ここではお話しきれなかった仕組みを、苦痛トークンやESG投資の改良以外にもいくつか考えていますが、同様に誰もが、無数の新しい制度を想像できるはずなのです。
P.S.
この文章を作成中に「ESG投資」ということばが、それなりに説明を要する概念から、「わりと知られた時事ネタ」へと変貌しました。それは、ESG投資が、「投資」という「市場の心臓部」に位置する概念と、「環境E・社会S・統治Gの重視」というある種のフェアネス、つまり「市場の外部」をショートカットする、手品じみた概念だからだと思われます。
たしかにESG投資には希望があります。しかし、このまま行けばきっと失敗して、むしろ既に冷笑の準備を完了している人々を鼓舞する結果になるでしょう。ESG投資は、善意の形骸化に抗する免疫機構を、あまりにも欠いているからです。
ですが、初手の失敗は、それが希望であったことまでは毀損しません。
ある程度むずかしい数学の問題は、そもそも「何が困難なのか?」をはっきり見定めるまでで、やっと序盤です。近頃、われわれは「困難の兆し」だけで問題から逃げまわる、ワガママな、あるいは臆病な子供のようになっているのではないでしょうか? そのような子供は、問題が自分に解けないと感じるや、「終わった」と恫喝し、次の問題を探しに行くのです。Don’t Panic.
2018年11月3日朝、ぼくは再びシャーロット空港に降り立った。夜に着いて夕食を食べ損ねた前回の反省から、今度は早朝に着くナイトフライト便を選んだのだ。雨期の夏から3ヶ月、どうしても秋のブラックマウンテンを見たかった。ジョセフ・アルバースが世界一美しいと言ったあの紅葉の季節である。
新BMCミュージアムの開館展
前回と同じアッシュビルのダウンタウンの端っこにあるモーテルに宿を取っていたが、チェックインまで時間があるのでフロントに荷物を預けて街に出た。目指すは開館25周年を記念して新しくなったBMCミュージアム※1。Google Mapsをたどりながら街を歩く。地図が不要なぐらいわかりやすい場所に新しいミュージアムはあった。なかに入って全体を見る。展示室は広くなり、階下に図書室兼資料庫ができていた。
まずは、前回いろいろ教えてもらった学芸員のアリスにお礼を言わなければならない。すべては彼女から繋がっていったのだ。おみやげに持ってきたお煎餅と監訳したアルバース『配色の設計』※2を手渡し、iPadでこの連載の1回目※3を見てもらう。「ほらみて、日本に美術館のことを紹介してくれているのよ」と同僚にも画面を見せて、写真がきれいと喜んでくれた。開館したばかりで忙しいことは承知しているので、早々に挨拶を済ませ、館を見て回ることにした。
 [図1]街の建物に掲示されていた新BMCミュージアムの案内サイン
[図1]街の建物に掲示されていた新BMCミュージアムの案内サイン
 [図2]BMCミュージアム+アーツセンター「Between Form and Content展」展示風景
[図2]BMCミュージアム+アーツセンター「Between Form and Content展」展示風景
 [図3]階下の図書閲覧室。エデン湖キャンパスの入口にかかっていたBMCの看板がある
[図3]階下の図書閲覧室。エデン湖キャンパスの入口にかかっていたBMCの看板がある
 [図4]階下通路にもあったローレンスの展示
[図4]階下通路にもあったローレンスの展示
開館展は「Between Form and Content; Perspective on Jacob Lawrence + Black Mountain College」。ジェイコブ・ローレンス※4はNYハーレムが輩出した最初のアフリカ系米人画家で、1946年のBMC夏期芸術講座※5(以下夏期講座)にアルバースの招待を受けて講師として参加している。このとき、アルバースの抽象的造形理論に触れたことで新たな境地を開いたといわれており、そのことが展覧会名の「形(form)と意味(content)のあいだ」に繋がっている。黒人の日常や労働、また徴兵された経験をもとに第二次大戦を描いた社会派の画家である。
BMCの時代は公民権運動前夜で、まだまだ黒人や女性に社会参加の道は開けていなかった。美術の世界も同様で、ヨーロッパにおいて進歩的美術学校であったはずのバウハウスですら、女性は建築や絵画のクラスに入ることができなかった。アニ・アルバースがバウハウス入学の際、絵画を学ぶことを希望したが許可されず、テキスタイル工房に入らざるを得なかったことはよく知られている※6。
アメリカの男女共学の歴史は古く、19世紀初頭に遡ることができる。1920年代にはほぼ全ての公立学校が共学を実現しており、BMCも共学の学校としてスタートした。しかし、黒人学生の入学を認めたのは開学から11年目、1944年の夏期講座からである。1933年の開学時にイェール大学の教授から訪問の希望があったが、同行の一人に黒人学生がいたことで来校を断わったというエピソード※7も残っており、黒人の受け入れに前向きではなかった。「他者の“奇妙さ(strangeness)”から学ぶ」という方針によって大勢の亡命者を受け入れてきたBMCにとって、黒人問題は大きなジレンマだった。
アルバースが黒人を受け入れることに反対していたという記事を読んだことがある※8。しかし、ジェイコブを招聘したのもアルバースだ。ジェイコブを迎えるため、鉄道で人種隔離政策をとる州を通過する際に有色人種用車両に乗り換えなくてもいいようにと、プライベート車両まで用意している※9。
反対理由には地元への配慮があったようだ。東部と南部の境に位置するノースキャロライナ州は、農業を主産業としつつも東部都市のリゾート地として栄え、深南部に比べれば進歩的な土地柄だったとはいえ、まだまだ南部の考え方が根強かったのだろう。しかし、1943年に州議会が全人種の子ども全員の修学を承認する。
たぶんそのこととも関係しているのだろう、1944年に南部会議厚生評議会がBMCで開かれ、黒人学生の受け入れについて話し合われている※10。議論は難航し、その結果、暫定的に夏期講座への黒人学生参加を認めることとした。フルタイムでの受け入れは、1945年秋学期まで待たねばならなかった。
そういったさまざまな経緯を含め、開館展にジェイコブ・ローレンスを持ってきたのは気骨ある選択である。現在の分断社会への意思表示でもあるのだろう。
ダウンタウンからエデン湖へ
秋の観光シーズン最後の週末とあって、アッシュビルの街は夏とはうってかわってにぎやかだ。夏も人が少ないというわけではなかったが、朝からカフェやダイナーは観光客であふれている。聞けばみんなハイキングに出かけるのだという。紅葉で名高いブルーリッジの山麓が目当てだ。
しかし、のんびり山歩きする気にはなれない。街角にある観光案内板を見てみると、ブラックマウンテンにもダウンタウンがあった。とりあえずそこに行ってみようと15分ほどハイウェイを走る。着いたところはブラックマウンテン旧駅舎前の小さな町だった。
町を隔てるようにして線路が延びている。かつては旅客鉄道が走っていたのだろう。今では貨物列車が通り過ぎるだけになった。とはいえ、貨物列車の長さは尋常ではなく、数分間目の前を走り続ける。そんなアメリカ特有の鉄道風景は、かつてのホーボー※11たちの旅を思わせる。しかし、BMCの時代には国道整備が始まっており、同時代のスタインベックの小説『怒りの葡萄』※12でも、主人公一家はボロ車に乗って、ルート66でオクラホマからカリフォルニアへと向かう。1956年の高速道路法成立までまだ時間があるとはいえ、すでに鉄道の時代は終わろうとしていた。モニュメントとしてきれいに整備されたブラックマウンテン駅は、観光資源ともいえず、所在なさげにたたずんでいた。
 [図5]整備されて残っているかつてのブラックマウンテン駅。もう列車は止まらない
[図5]整備されて残っているかつてのブラックマウンテン駅。もう列車は止まらない
 [図6]鉄道の時代を彷彿させる、まっすぐに伸びた単線の線路
[図6]鉄道の時代を彷彿させる、まっすぐに伸びた単線の線路
町は賑わってもなく寂れてもいず、時折やってくる観光客と地元の人たち相手になんとか経済はまわっているようす。何軒かのレストラン、カフェ、日用雑貨の店、小さなホームセンター、自転車屋、ハープ専門の楽器店、ギャラリー、教会……などに混ざって本屋が2軒もある。1軒はカフェや雑貨を併設した今どきのつくり。もう1軒はアメリカによくある古書と新刊を区別なく売っている昔ながらの書店である。町の規模に対して2軒は多いなと気になりつつ、カフェのある方で休憩を取り、町を出た。
帰り道、見学のアポイントを取っているBMCエデン湖キャンパス跡のロックモントキャンプ※13に行ってみることにした。場所だけでも確かめておこうと思ったのだ。GPSを頼りにしばらく走るとエデン湖らしきところに出た。「湖」というには小さい。でも「池」とよぶには少し大きい※14。とりあえず進んでみようと、湖畔の道を走る。
「あっ」と声に出したと思う。眼の端を見たことのある建物が過ぎ去った。「あれだ!」。車をUターンさせて、道端に止める。道を渡って柵を越え、湖の傍に出る。その向こうにBMCエデン湖校舎があった。
でも記憶の写真ではもっと建物がはっきりと写っていたはず。それはそうだ。まわりの樹木が育って校舎が半分隠れている。でも間違いない。何枚か写真を撮って、入口を探すことにした。
胸が高鳴るという言葉のとおり、心臓が鼓動を打つ。ここか、いや違う。何度目かの曲がり角でキャンプ場のサインをみつけた。ゲスト用の駐車スペースに車を止めて中に入る。シーズンオフなので誰もいない。いくつかのコテージを過ぎたところに、BMC校舎があった。
これか?波板に囲われたそれは建設現場の詰所のようだった。一見して本当にDIYでつくったのだとわかる、言ってみれば“つたない”建造物だ。しかし、ピロティがあり、連続水平窓で、ファサードはフリー。しっかりとモダン建築の要素を踏まえている。しかも、驚くことに今でもまだ使われているようなのだ。建物を見るだけでこんなにワクワクしたことはなかった。明日はこのなかを見ることができる。湖のまわりを少し歩いてから車に戻った。
 [図7]1942〜43年ごろと思われるエデン湖対岸から望んだ校舎
[図7]1942〜43年ごろと思われるエデン湖対岸から望んだ校舎
 [図8]今回、同じ対岸正面あたりから撮影したもの。木々の成長がよくわかる
[図8]今回、同じ対岸正面あたりから撮影したもの。木々の成長がよくわかる
 [図9]1933年製ライカで撮影したエデン湖校舎(湖の反対側)。正面のポーチと入口はあとからつくられたもの。オリジナルは完全なファサードフリー
[図9]1933年製ライカで撮影したエデン湖校舎(湖の反対側)。正面のポーチと入口はあとからつくられたもの。オリジナルは完全なファサードフリー
デューイとライス
前回でも紹介した、BMCを開校した人物であるジョン・アンドリュー・ライスのことを、もう少し話したい。彼はフロリダ州のロリンズ大学を騒動の末に解雇され、仲間の教員や学生たちとBMCを創立した。ライスがエキセントリックな人物だったことは想像に難くないが、ひとりで騒ぎを起こすような、単なる跳ね返り者だったとも思えない。その背景に何があったのか知りたかった。
設立当初からBMCが注目を集めていたのも不思議だった。普通、山奥のコミューンのことなど、誰も気にかけたりはしない。これまでのように、デザイン・美術史や地域史から見ているだけでは足りないのだろう。そう思い、教育学方面の資料も探してみることにした。
ライスは、1888年にサウスキャロライナで生まれている。ノースキャロライナの隣州である。なぜノースキャロライナだったのかという答えは、意外にこういうところにあるのかもしれない。ニューオリンズのトゥレーン大学卒業後の1911年、23歳のときに英オックスフォード大学に留学。3年間在籍し、帰国後ネブラスカ大学に赴任した。そこではギリシャ語とラテン語を教え、早くも彼の講義の特色であるディスカッションを中心とする授業を展開している。1929年にグッゲンハイム・フェローシップを得て再び渡英。翌年、ロリンズ大学に着任した。
ここで話は19世紀末にさかのぼる。アーツ&クラフツ運動(以下、A&C運動)が始まったころのロンドンで、新教育運動とよばれる教育改革も始まっていた。その後、新教育運動は世界中に広まるのだが※15、アメリカでは進歩主義教育運動へと展開し、コミュニティスクールやフリースクールがつくられた。民主主義を基盤とした、教える側ではなく学ぶ側を主体とする学校である。その運動をリードしたのが思想家のジョン・デューイ※16で、彼自身も「実験学校」※17を開設し、進歩的教育を実践した。
ライスがデューイの教育思想に傾倒していたことは、よく知られていたようだ。経験主義によって児童の自発的な成長を促すというデューイの教育理論は、そのままライスの教育方針と重なっている。その考えの源流は前述の新教育運動にあるのだが、ライスがそのためにイギリス留学したのかどうかはわからない。しかし、直接の理由ではなかったにせよ、留学中に多くを得たであろうことは想像がつく。いずれにしても、彼は進歩主義教育運動の只中にいた。
いましばらく、新教育運動とライスの教育観との関連について、話を続けたい。少し長くなるが「新教育運動における共同体形成」について書かれた論文※18から引用する。
階級意識の根強いイギリスには、トマス・モア以来のユートピア思想を憧慢的に捉える心性がある。……どこにもない夢想と知りつつ、それでもなおその理想に近似した場を現世の地に創造しようとする「共同体意識」は、19世紀末に現れたレディやバドレーの新学校(New School)、その後の幼児学校(infant school)や初歩学校(elementary school)の教育改革にも認められる。そして、ダイナミックな新教育運動の源泉となったイギリス固有の新理想運動が、Garden city※19運動、大学拡張運動、女性参政権運動に関与したオーウェン主義、ラスキン主義、モリスのギルド社会主義、キリスト教社会主義などに影響された人々や、非国教会派(ユニテリアン、クエーカー教徒、神智学徒など)の人々の社会改革・社会改良の意識に負っていたことも、イギリス新教育運動における「共同体志向」を裏づけている。……それゆえ、彼らの関心は、社会変革・社会改革・社会改良への希求とその胎動の確信に裏打ちされたかたちで、「有機体としての社会」とそれを構成する「個人」の存在様式を「共同体としての学校」のなかで模索する基本的方向に焦点化され、まさに古くて新しいテーマが教育の俎上に載せられることになったのである。
新教育運動にはイギリス特有のユートピア思想があった。デザイナーには、ウィリアム・モリスの『ユートピアだより』※20がなじみ深いだろう。ライスはそのユートピア(=共同体としての学校)をつくろうとしたのではないか。BMCは教員家族と学生が寝食をともにし、単位も学位の発行もなく、まさしくそれを実現しようとしていたかにみえる。
もうひとつ、興味深い記述がある。
したがって、学習内容としては子どもの本能(創造的本能)を重視した工芸(arts and crasts)、劇(unaided deramatic work)、ストーリーテリングなどが重視され、……それゆえ、教育内容としては、当然のことながら、古典的・伝統的・因習的な教科はできるだけ廃止されて、スポーツ、近代科学にもとづく実験、自己解放・自己表現としてのダンス、劇などが取り入れられ、共同体を民主的に維持するための直接民主制の自治(self-govermment)が中核となって学校生活を支えた。
デューイはこの考えを引き継いだのだろう。芸術による経験こそが芸術本体であるという立場をとり、『経験としての芸術』※21を記した。まさにそれらが、ライスがリベラルアーツの基礎に芸術体験を求めた動機なのだとすれば合点がいく。ライスは新教育運動とその発展形であるデューイの芸術論に忠実であり、それを大学教育に応用しようとしていたのではないだろうか。
ライスは学生に「経験・観察・批評」を求め、「知識を用いていかに行動するかが重要で、ただ知識を持っているだけでは十分ではない」と説いた。結果よりプロセスを重視し、哲学や芸術を「想像力を養うためのもっとも適した育成土壌」ととらえ、「演劇の脚本を読むことも良い。演劇を鑑賞することはなお良い。だが、音楽と運動の間の繊細な関係を理解するには、下手にせよ舞台上で演じなければならない」と、実践することを求めた。彼は芸術を単なる自己表現ではなく、すべての人にとって「自らの人生を選択することに役立つ訓練の源」だと考えていた※22。
アルバースもまた、BMCでの芸術教育を「一般教育と成長のための重要で貴重な媒体」と規定し、「自らの生活(life)、存在(being)、行動(doing)に目を開くこと」だとした※23。着任会見時の有名な言葉「To open eyes」を思わせる言葉だ。アルバースは、BMCの芸術教育が、けっして専門家教育のためのものではないことを理解していた。
また、同論文はこうも述べている。
新教育運動は宗教的な色彩が強く、奉仕の行為や神への奉仕活動としての農業・園芸・工芸が重んじられ、不可視なるものへの憧憬にもとづく『神秘』志向(神秘主義、心霊主義、神智主義など)があった。
これもまた、BMCの土地の開拓や農業への関心と重なり、アルバースのバウハウス時代の師であったヨハネス・イッテンの神秘主義指向にも通じている。
進歩主義的な北東部の教育とは違い、南部では職業教育に重点がおかれ、特に恐慌下の30年代はその傾向が強かった。そういう背景もあって、BMCは、進歩主義教育運動の論客として知られるライスが創設した南部のオルタナティヴスクールとして注目を浴びた。その期待はバウハウスからアルバース夫妻を迎えたことで一層高まった。
一方の当事者であるアルバース夫妻はバウハウス教育の理想の体現を試みようとした。バウハウスは社会民主主義国家であるワイマール共和国の国立学校として出発し、イギリスのA&C運動からも多くを学んでいる。特にウィリアム・モリスが提唱した中世のギルドシステムを参照して、親方とその弟子というスタイルのマイスター制をとった。つまり、ライスもアルバースも同じ19世紀末ロンドンのモダニズムの影響下にあり、ともにその継承者だったのである。
BMCエデン湖キャンパス
明けて月曜の朝、BMCエデン湖キャンパス(現・ロックモントキャンプ)を訪ねた。キャンプについたものの、事務所がどこにあるのかわからない。場所を尋ねようにも広い敷地に人が見当たらない。ようやく人のいるロッジを見つけ場所を聞く。たどり着いたその場所は、なんとエデン湖校舎だった。校舎は事務所として使われていたのだ。周辺には大型犬が何匹もいて、すべてがスタッフの人たちの飼い犬のようだった。
待っていてくれた担当者に遅れたことを詫びると、「約束は午前中よ。まだまだ大丈夫」と犬といっしょに笑顔で迎えてくれた。
「ここはBMCの校舎ですよね?」
「そう。そのまま使ってるわ」
「補修はしてるんですか?」
「外壁には手を入れてるけど、部屋のなかはなるべく残すようにしている。こっちに来て」
案内された部屋に行くと、絵の具を落とした跡がある。
「これは、BMCの授業でついた絵の具よ。そのまま残しているの。ここに荷物を置いて。案内するから」
少なくとも床は張り替えていないということだ。言われるままに荷物を置いて、館内の見学に出た。
「ここは、BMCが手放したあとヴァンダービルト家が買って管理していたの。今は二人のオーナーがいて、このキャンプを経営しているわ」
ヴァンダービルト家というのは、今もアッシュビルの観光名所として残るアメリカで一番大きな個人邸宅「ビルトモア・エステート」のオーナー一族である。
「では、このキャンプは私設なんですか?」
「そうよ。息子がこのキャンプに来た縁で、私もここで働くようになったの」
そういう話を聞きながら、館内を歩く。
細い廊下の脇には学生の居室がある。かなり狭い。教室もさほど広くは感じない。考えてみれば4棟を計画したうち1棟しか建たなかったのだから、それぞれが狭くなるのも無理はない。
ひととおりまわって、あとは自由に見てもいいというので外へ出た。ピロティには意匠は施されていないが、1944年の夏期講座の際、ジーン・シャーロット※24によって描れたフレスコ画の壁画がそのまま残っている。木製のテーブルや倉庫らしき所の木の扉や石積みも、たぶん当時のままだろう。
内部は今も使われているからだろうか、ピロティや外壁の方がBMCの残像を感じることができる。校舎以外でBMCが主に使っていたエリアを教えてもらっていたので、その場所まで歩く。坂を上るといくつかの小屋があった。しかし、どこまで当時のものが保管されているのかはわからない。質素な小屋だが、DIY建築を見たあとでは、どれもが専門家がつくった建物に見えた※25。
 [図10]今も残るBMC時代の絵の具の跡
[図10]今も残るBMC時代の絵の具の跡
 [図11-1]現在のエデン湖校舎内廊下。ペンキの塗り替え程度で、BMCのころとさほど変わっていないと聞いた
[図11-1]現在のエデン湖校舎内廊下。ペンキの塗り替え程度で、BMCのころとさほど変わっていないと聞いた
 [図11-2]学生の居室は狭い。当時のままの状態で残しているらしいが、調度は今のものだろう
[図11-2]学生の居室は狭い。当時のままの状態で残しているらしいが、調度は今のものだろう
 [図12]石積みと扉は補修の跡があるが、ほぼ当時のまま。「CRAFTS」のプレートもそのまま残されたようだ
[図12]石積みと扉は補修の跡があるが、ほぼ当時のまま。「CRAFTS」のプレートもそのまま残されたようだ
 [図13-1]ピロティとそこに残るフレスコ画の壁画。左「KNOWLEDGE」右「INSPIRATION」のタイトルプレートがある。現在、最低限の修復と保存のプロジェクトが進んでいる※26
[図13-1]ピロティとそこに残るフレスコ画の壁画。左「KNOWLEDGE」右「INSPIRATION」のタイトルプレートがある。現在、最低限の修復と保存のプロジェクトが進んでいる※26
 [図13-2]ジーン・シャーロットによるフレスコ画の壁画「KNOWLEDGE」
[図13-2]ジーン・シャーロットによるフレスコ画の壁画「KNOWLEDGE」
 [図13-3]ジーン・シャーロットによるフレスコ画の壁画「INSPIRATION」。落書きされているのがわかる
[図13-3]ジーン・シャーロットによるフレスコ画の壁画「INSPIRATION」。落書きされているのがわかる
 [図14]BMCが使っていたらしきコテージ。たぶん教員寮だろう
[図14]BMCが使っていたらしきコテージ。たぶん教員寮だろう
 [図15-1]グローブ時代からあるBMCの食堂棟。今でも食堂かどうかはわからない
[図15-1]グローブ時代からあるBMCの食堂棟。今でも食堂かどうかはわからない
 [図15-2]当時のデッキの中のようす
[図15-2]当時のデッキの中のようす
 [図16]ロックモントキャンプ事務所入口に飾られたアルバース「正方形賛歌」と1995年のBMC同窓会集合写真
[図16]ロックモントキャンプ事務所入口に飾られたアルバース「正方形賛歌」と1995年のBMC同窓会集合写真
ライスとアルバースのブルーリッジ時代は、ライスを中心とした教育に関する実験の時代と言っていい。必修はライスの古典学とアルバースのドローイングだけで、あとは自由に選択できるようになっていた。もちろん工芸・芸術以外の、物理や化学、心理学や哲学などの授業もあった。
ライスは対話と批評による「経験(experience)」を重視し、アルバースは素材と造形を扱いながらも形態の問題に留まらない「実験(experiment)」を柱とした。共通するのは、知識の暗記や自然の模写をよしとしなかったことだろう。しかし、二人の蜜月時代はあまり長くは続かなかった。
芸術体験をベースにリベラルアーツを学ぶフリースクールとしてBMCは順調に進んでいるとみられていたが、内部ではさまざまな問題が噴出していた。なかでも、早急に解決すべきはキャンパスの問題だった。ブルーリッジ協議会から賃貸された建物は、夏はクリスチャン・カンファレンスセンターの集会所として使われる。つまりサマーシーズンを迎える前に学校のなかを片付け、また秋に戻ることを繰り返していたのである。
解決策としては自分たちのキャンパスを持つしかない。そこで白羽の矢が立ったのがブルーリッジから数マイル離れたエデン湖畔の土地である。アッシュビルの開発者、エドウィン・W・グローブ※27によって1920年代初頭につくられた避暑のための別荘地だ。家族とごく親しい仲間だけが使っていた隠れ家的な場所だったらしい。
1937年6月、グローブ家は674エーカーの土地をBMCに売却する。購入価格は35,000ドルで、2,000ドルの頭金と年間7,000ドルの返済が条件だった。BMCは支援者に寄付を募ることにしたが、そのためには新しい校舎の建設計画が必要だった。
新校舎の設計は、初代バウハウスの学長でハーバード大学に赴任していたヴァルター・グロピウスと、同じくバウハウスの教員だったマルセル・ブロイヤー※28に依頼された。彼らが提示したプランは、バウハウス・デッサウ校をベースにしながらも、それをしのぐ規模の国際様式の建築群だった。
1940年1月にはMoMAで新校舎の発表をし、アルバースらによって大々的に宣伝されたが、やはり経済的負担が大きく、高額寄付者の援助を受けなければ実現できないことは明らかだった。そのためには大学然とした伝統的な教育モデルを取り入れる必要があった。しかし、設立時のメンバーがそれを承知しなかった。なんとなく逆に思えるが、ヨーロッパから亡命してきた芸術系教員たちは旧守的であることを受け入れており、一般科目を受け持っているアメリカ人教員たちの方が急進的な考え方をしていた。
すでにヨーロッパでは第二次世界大戦が始まっており、政情が不安定なこともあって、最終的にはグロピウス同意の下、ローレンス・コーチャー※29設計による学生と教員スタッフの現場労働によって建てることができるシンプルなプランにおちついた。これによって25,000ドル以上の節約ができ、なんとか教育共同体は保たれたのである。そしてその年の9月、5000ドルの資金を得て、校舎の建設が始まった。
この自主建設のプロジェクトにも、デューイの影を見ることができる。デューイがつくった自由学校では、子どもたちによる自主的な活動がいくつも起こっており、その会合の場所としてクラブハウス建設のアイデアが出てきた。彼らは建築にまつわるさまざまな調査と研究を行ない、その結果、自分たちの手で建てることを決め、それが可能なコロニアル様式の小屋を設計し、実際にクラブハウスをつくりあげた(もちろん、手に余る部分は教員や大人たちの協力があった)。
このことが、エデン湖キャンパスの自主建設案に直接繋がったとは思わないが、ヒントや勇気を与えたことは想像に難くない。
BMCキャンパス建造
エデン湖を訪ねた翌日、興奮冷めやらぬままNCアーカイヴズに出かけた。今回は2日間予約を取っている。早速、コーチャー設計のエデン湖キャンパスの資料をみせてもらう。実現した現存する校舎だけではなく、全体のスケッチはもちろんシアターやキッチンなどの詳細図面も残っていた。
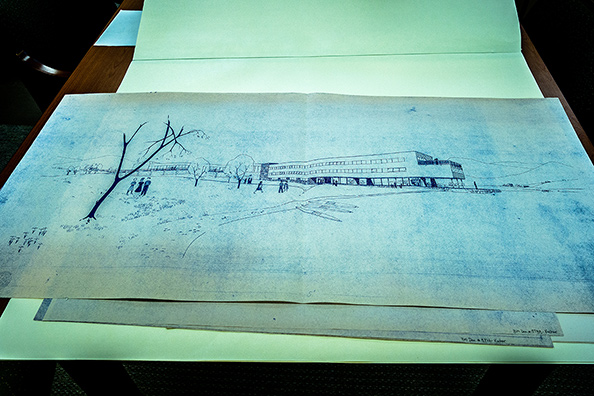 [図17]コーチャーによるエデン湖キャンパスのパース図
[図17]コーチャーによるエデン湖キャンパスのパース図
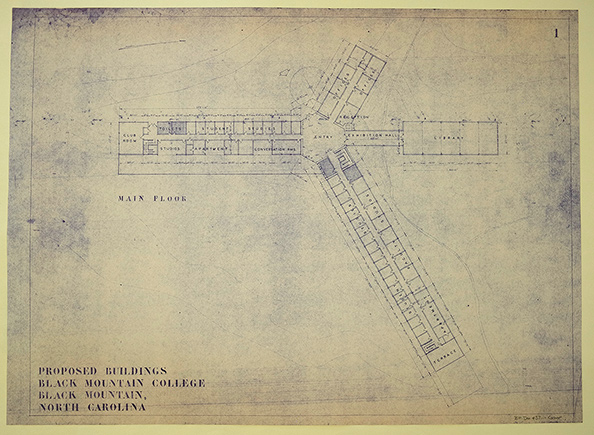 [図18-1]4翼のメインビルディング平面図
[図18-1]4翼のメインビルディング平面図
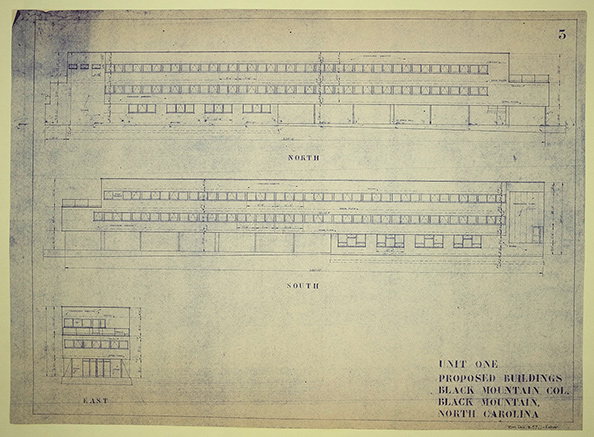 [図18-2]実現した研究棟の立面図
[図18-2]実現した研究棟の立面図
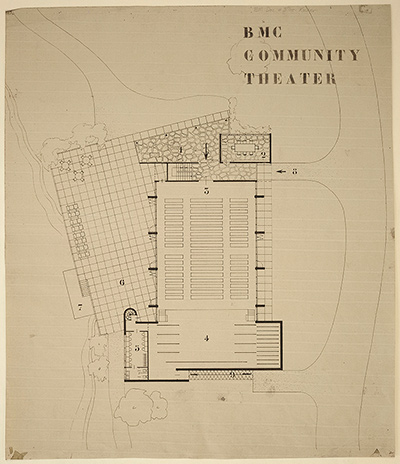 [図18-3]建たなかったシアター
[図18-3]建たなかったシアター
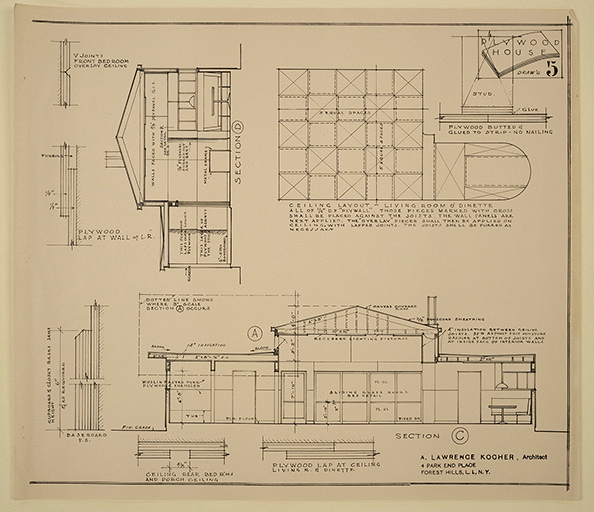 [図18-4]プライウッドハウス。合板を組み合わせてつくる
[図18-4]プライウッドハウス。合板を組み合わせてつくる
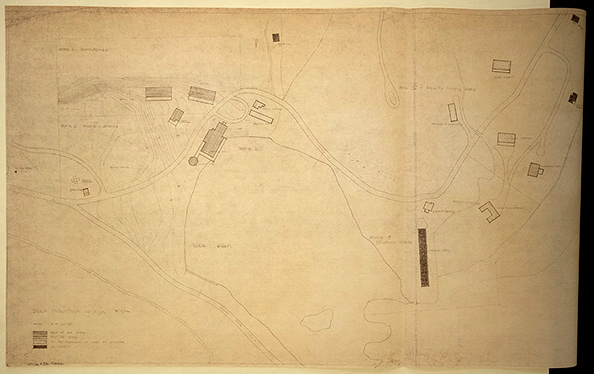 [図19]戦争が終わった1946年に描かれたエデン湖キャンパスマップ。これが最終形と考えていいだろう。中央右下の黒く塗られた細長い建物が研究棟。図14はその右上の教員寮エリアあたり。図15の食堂棟は中央左の湖に張り出している建物
[図19]戦争が終わった1946年に描かれたエデン湖キャンパスマップ。これが最終形と考えていいだろう。中央右下の黒く塗られた細長い建物が研究棟。図14はその右上の教員寮エリアあたり。図15の食堂棟は中央左の湖に張り出している建物
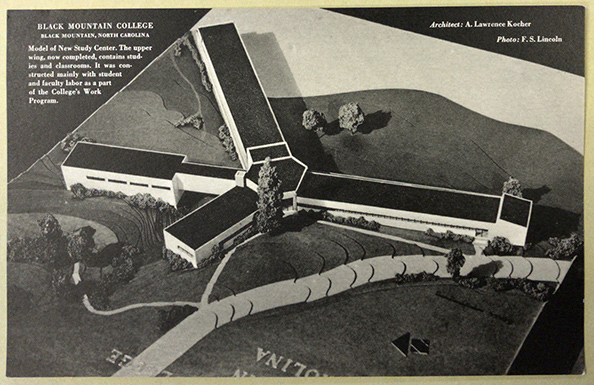 [図20]メインビルの模型。図版は自主建設宣伝のためのポストカード
[図20]メインビルの模型。図版は自主建設宣伝のためのポストカード
仕上がり図面をひととおり確認し、建設過程の資料に移る。大量の写真によって、基礎から仕上げまですべての工程が記録されている。指導も兼ねた専門家の協力があったにせよ、教員と学生の実践によってつくりあげたことは写真を見ても明らかだ。
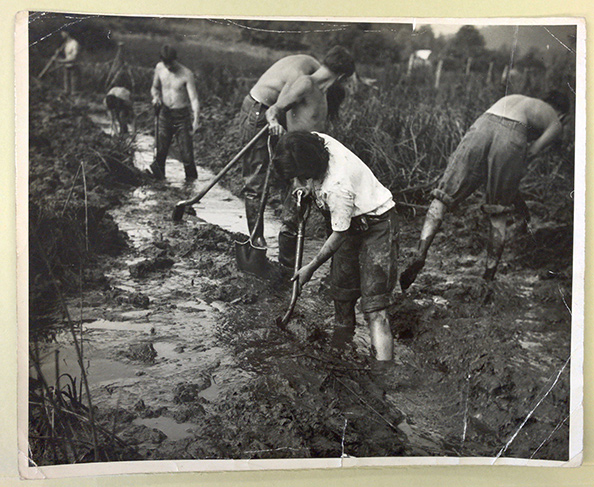 [図21-1]基礎から上棟、仕上げまでの建設風景。地均し・排水溝工事
[図21-1]基礎から上棟、仕上げまでの建設風景。地均し・排水溝工事
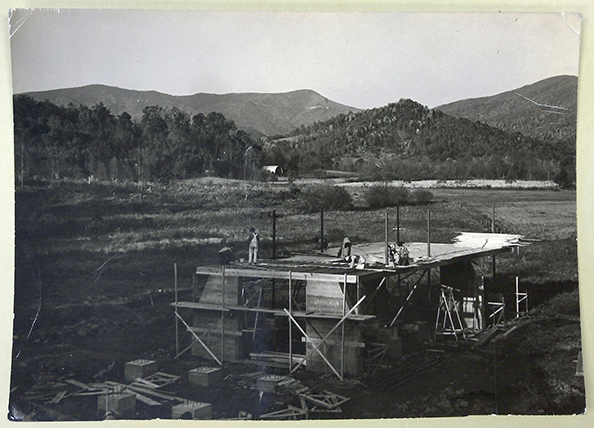 [図21-2]基礎・支柱工事
[図21-2]基礎・支柱工事
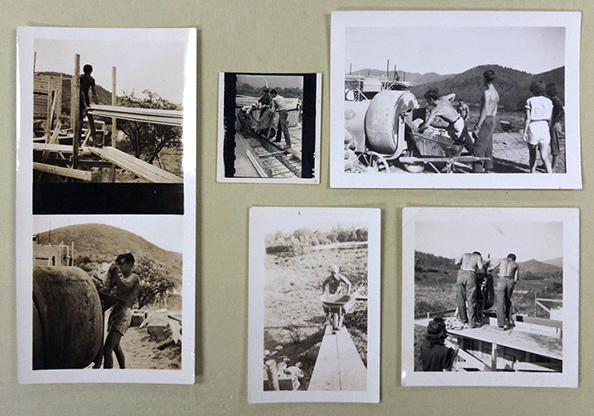 [図21-3]コンクリート工事
[図21-3]コンクリート工事
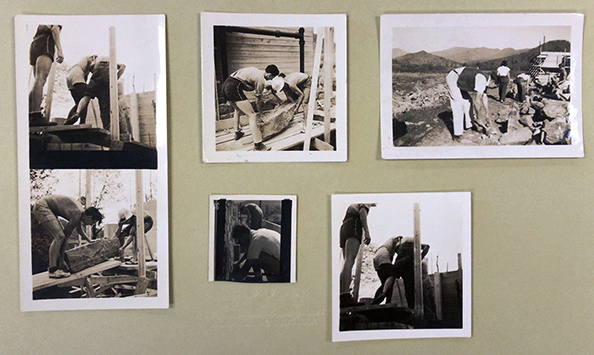 [図21-4]石積み工事
[図21-4]石積み工事
 [図21-5]フレーム工事
[図21-5]フレーム工事
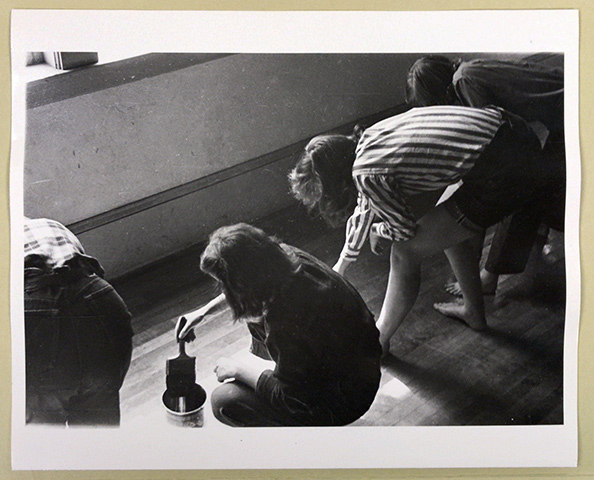 [図21-6]仕上げ・内装工事
[図21-6]仕上げ・内装工事
 [図21-7]完成した研究棟
[図21-7]完成した研究棟
この自主建設のプロジェクトは全国的に宣伝され、その結果、寄付も集まるようになった。現場監督の任を受け建築の教授として着任したコーチャーの給与も、最初の2年間はニューヨーク・カーネギー財団によって支払われ、3年目からは当時MoMA評議会のメンバーだったフィリップ・L・グッドウィン※30の寄付によって賄われた。
建設作業は非公式ながらカリキュラムに組み込まれ、午後の授業は夕方以降に振り替えられた。教員と学生は、午前の授業を終えるとトラックに乗ってブルーリッジからエデン湖に向かい、夕方まで現場仕事をし、夜はまた授業に戻った。
コーチャーは大小のコテージや、キッチンスタッフと黒人労働者用の小屋も設計している。それはブラックマウンテンの多くの山岳民が暮らしていた上水道や電気もない家に対する提案にもなっていた。コーチャーによるBMC設計思想の背景に、都市や工場にのみ貢献する建築家たちへのアンチテーゼを見ることができる。
写真を見ると、女性も等しく力仕事をしているのがわかる。民主的といえばそうなのだが、実は戦争にかり出されて男手が足りなくなっていたのだ。1941年12月、第二次大戦は太平洋域にひろがり、いわゆる太平洋戦争が始まる。翌年にはアメリカの参戦も本格的になり、男子学生は徴兵され、ヨーロッパからの亡命者と高齢の教授、そして女子学生だけが残った。
1941年秋、4棟で計画されたメインのビルのうち、1棟だけが学生たちの手によって完成した。それがここで「エデン湖校舎」と呼んでいる「研究棟(Studies Building)」である。第二次大戦後には残り3棟の建設も検討されたが、設計者であり監督担当のコーチャーが大学に戻ることができず、プロジェクトが再開されることはなかった。建設中止は資金難だったためといわれているが、戦争がなければ計画通り完成していたかもしれない。
ダウンタウンのブックストア
NCアーカイヴズの閲覧時間は16時まで。16時半には全部片付けて仕事が終わる。なので我われは、15時半ぐらいから片付けを始めなければならない。16時前に退室して、夕食まで少し時間があるので、もう一度ブラックマウンテンのダウンタウンに行くことにした。もうひとつの本屋が気になっていたことと、タイ料理屋があったからである。エデン湖からさほど時間はかからない。ということは、BMCの人たちもきっとここで食事や買い物をして時間を過ごしたのだ。
 [図22]BMダウンタウン
[図22]BMダウンタウン
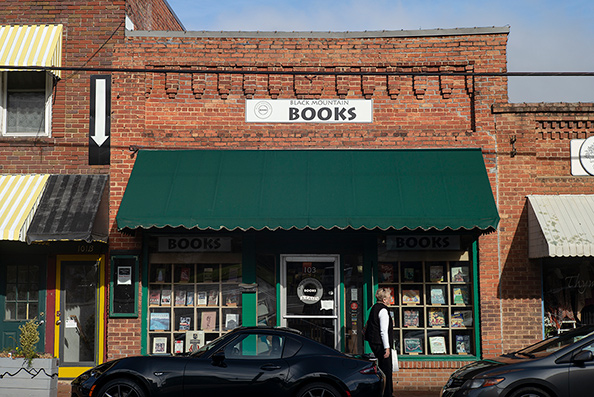 [図23]BMダウンタウンの書店。その名も「Black Mountain Books」
[図23]BMダウンタウンの書店。その名も「Black Mountain Books」
着いてまず本屋に入った。棚を見る。特徴があるのかもしれないがよくわからない。奥まで進む。ガラス戸がついたクラシックな棚があった。覗いてみるとBMC関連の古書が並んでいる。最初に厚手のハードカバー『Black Mountain College: Sprouted Seeds』※31という本が目についた。BMCにかかわった主要人物へのインタビューなどをアンソロジーとしてまとめた本だ。これは貴重な資料本なので買っておくとして、同じ棚に『Black Mountain Review』※32
の1号と6号があった。1号は創刊号なので手に入るときに躊躇してはいけない。問題は6号である。終刊号は7号でギンズバーグやケルアックといったビートニクの詩人たちが寄稿している。そういった意味では6号は微妙だが、そうそう出会えるものではない。
全部買うと結構な値段になるので、価格交渉をすることにした。まずは「3冊ほしいけどいくらになる?」と聞く。店主は初老のいかにも本屋の親父である。ちらっとこちらを見て電卓をはじく。ラベルの価格とさほど変わらない。
「XXXドルにならないかな?」思い切って低めの値段を提示してみる。
「どこから来たんだ?」と親父は言う。
「日本から」
「本のバイヤーじゃないだろうな」
どうも金額がいいところをついたらしい。
「ちがう、ちがう。BMCのリサーチに来たんだよ」
じっとこちらを見て、「OK。その値段でいいよ」と言ってくれた。
売ると決まってからは機嫌がよかった。大切な本だから痛まないようにと言って、一冊ずつクラフト紙に包んでくれる。待っていたレジの前には反トランプ本が平積みしてあった。
アッシュビルもそうだがブラックマウンテンはリベラルな土地柄である。だからBMCをつくることができたのかもしれない。小さなダウンタウンに本屋が2軒あるのも、そういったことと無関係ではないだろう。
ここで、ぼくの思い違いを正しておかなければならない。アッシュビルはノースキャロライナ州のバンコム郡にあり、ブラックマウンテンは“バンコム郡アッシュビル市ブラックマウンテン町”のようなものだとばかり思っていた。しかしそうではなかった。アッシュビルは東西南北に別れ、ブラックマウンテンは東アッシュビルのさらに東に位置している。規模はまったく違うが、隣町というわけだ。しかし同じ文化圏であることは間違いない。ちなみに、ブルーリッジは行政区分をまたぐ山麓エリアの呼称である
本屋を出て、数軒先にあるアートセンター「Black Mountain Center for the Arts」に入る。小さなギャラリーとオフィスがあり、ワークショップルームが併設されている。その日はバンジョーの教室が開催されていて、ギャラリーでは常設なのか偶然なのか、BMCの歴史が展示されていた。フラードームが展示パネルのフレームに転用されているなど、町の遺産として大切していることがよくわかる丁寧な展示だった。閉館間際に入ったので駆け足で観て、タイ料理を食べて、ホテルに戻った。
ライスの退任
ライスはそのカリスマ性で人を惹きつけながらも、うまく折り合いをつけることができないタイプらしく、BMCでもトラブルは絶えなかった。きっかけのひとつは1936年から取材が始まった雑誌記事である。
その記事では、ロリンズ大学を解任されてからBMC設立までの経緯が描かれ、ライスの存在がクローズアップされていた。それによってライスのやり方に不満を覚えていた教員たちとの対立が表面化し、学生の間にもそれは伝搬していった。大きく振れた振り子は、反対側にも大きく振れるものだ。ライスのカリスマ性が裏目に出始めたのだ。民主化された学校をつくるために、中央集権的リーダーシップを発揮するという矛盾も起きていた。
トラブルが噴出したとはいえ、ライスはBMCに必要な人物だった。だれも本気で彼を追放しようとは考えていなかった。しかし、結局ライスは、学生との恋愛が表沙汰になって学校を去ることになる。ピューリタニズムが根強いアメリカで、BMCも例外ではない。道徳的な問題が追及され、寄付への影響も心配された。すでにライスの家庭は崩壊しており、アルバースとの亀裂も決定的なものとなっていた。
1938年3月、ライスは5月まで休暇を与えられ、自由にその期間を伸ばすことができた。学校に戻ることもあったが、もうかつての自信にあふれた彼ではなかった。1939年秋学期から1940年の春学期にかけてが彼の最後の年度となる。そのタイミングで学校を去るべきという合意が教員の間でできていた。このころにはアルバースとの仲は修復されていたというが、もうどうすることもできなかったのだろう。ライスは1940年夏に正式に辞任し、エデン湖校舎の完成を見ることなくBMCを去った。
その後ライスは、再び教職に就くこともなく作家として生きた。自身の回想録のほか、短編集『Local Color』※33などを残している。
伝説の夏期講座のはじまり
さて、前述したとおりブルーリッジキャンパスは夏に使うことができず、その間を夏期休暇にあてるカリキュラムが組まれていた。エデン湖に移った1941年から1943年にかけて、その休暇を利用してキャンパスの整備・建設のためのサマーワークキャンプが開催された。
1942年夏のパンフレットがあるので見てみよう。この年にはサマースクールとワークキャンプがあり、スクールが“6月22日〜7月25日”と“7月27日〜9月5日”の2クール、キャンプは7月8日に始まって9月5日まで3ヶ月間みっちりある。テーマは「Education in Wartime(戦時中の学び)」である。
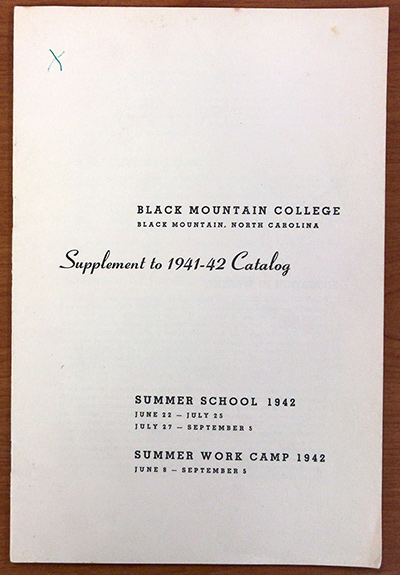 [図24-1]“Black Mountain College, Supplement to 1941–42 catalog” 表紙
[図24-1]“Black Mountain College, Supplement to 1941–42 catalog” 表紙
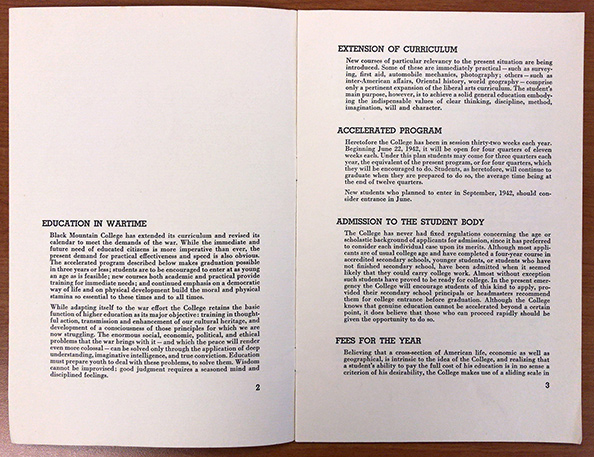 [図24-2]“Black Mountain College, Supplement to 1941–42 catalog” 中ページ
[図24-2]“Black Mountain College, Supplement to 1941–42 catalog” 中ページ
スクールの講義は、建築、美術、音楽、英米文学、外国語、社会研究、生物学、心理学と哲学。ワークキャンプは、体験型と銘打った建設作業や農作業などのエデン湖キャンパス整備だった。高校生と大学生を対象にセカンダリースクールとして任意の3週間単位で募集し、フルに参加する学生にはコーチャーの建築指導を受けることができるという特典がついた。
そしてそれらは、戦争協力の一部(part of the war effort)だと書かれている。民主主義のための教育を目指した進歩主義者も、戦火と政治的圧力から逃れて亡命してきたヨーロッパ人も、素直に加担してしまうのが戦争というものの怖さなのだろう。
このサマーワークキャンプは、1944年以降、美術や音楽に特化した夏期講座(Summar Institute)に姿を変える。多くの特別講師が招聘され、カニンガムのダンスカンパニー、ケージのイベント、フラーのジオデシックドーム建設など、現代まで語り継がれるさまざまな伝説を生むことになるのである。
目次
- Abstract
- 1.「制作へ」における言語
- A. 三種の「よって」
- B. 言語
- C. 「感覚的で身体的な現象」としての言語
- D. テクストの制作と私・身体・五感の組み換え
- 2. 非人称的空間 —— 宮川淳
- A.〈鏡≒本の空間〉
- B. 史的背景
- 〈反芸術〉
- 鏡と影
- 空白な空間を満たさずにはいられないわれわれの営為
- C.〈非人称的空間〉の作家
- 無名の眼
- 素材としての〈非人称的空間〉
- D. いったんのまとめ
- 3. 抒情主体と〈喩〉
- A.「わたしはきみになるために、わたしを制作しよう」
- 抒情詩
- 二者関係
- B. 言語表現の根底としての〈喩〉=プロソポペイア
- 自叙伝と鏡像構造
- 〈喩(figure)〉
- C. テクストと身体の組み換え、鏡の制作
- ミメーシスを強いる構築物
- テクストにおける共同体の生成・制御
- 鏡を制作すること
- 4. さらにミメーシスの方へ —— 荒川修作
- A. 荒川修作 (1936-2010)
- B. デュシャンからの影響
- 〈影のダイアグラム〉
- 運動、影、矢印
- 〈第四の次元(La Quatrième Dimension)〉
- 〈アンフラマンス(inframaince)〉
- C. 遠近法
- D. 作者
- E. 共同制作
- F. 〈ブランク(Blank)〉
- G. 距離を隔てた私らのネットワーク、〈遍在の場(Ubiquitous Site)〉
- H. まとめ
- 5.「あそこに私がいる」で編まれた共同体の設計へ
Abstract
各章の要旨は以下の通りです。
1.「制作へ」における言語
「制作へ」は、《三種の「よって」》の整理に代表されるように、零地点的領域から制作的空間に入り、そこでの五感の組み替えによって私や身体が別のかたちに再構成されるという、垂直方向の動きを通して水平方向の動きが生じる過程として〈制作〉を論じる。
そしてその議論のなかで、言語をめぐる再定義が、具体例+内実として展開されている。曰く、言語とは、《アニミズムの実践的側面であり、その世界製作の仕組みそのものである》ミメーシスがもたらす主客未分化状態=融即において、身体の振る舞いが事後的に制作する、《「肉的相互交流と参与=融即から生まれる感覚的で身体的な現象」》である。
2. 非人称的空間 —— 宮川淳
「制作へ」の出発と終わりにそれぞれ置かれている宮川淳、その〈非人称的空間〉をめぐる議論は、アンフォルメルから〈反芸術論争〉〈影論争〉といった、1960年代日本美術における代表的な議論・論争の流れのなかで形成・提示されたものだった。宮川の著作を土台にして構築された「制作へ」での〈制作〉論もまた、そのような文脈の延長線上に位置づけることができる。
宮川は、作品に避けがたく生じる表現主体の問題を、「客観的なレアリテの概念」が崩れた先に不可避に生じるものとして論じ、《主体と客体、実体と虚像という二元論的な認識図式の間隙からの中性的な《と》の空間の滲出、侵食》、その《空白な空間を満たさずにはいられないわれわれの営為》が、言語を用いた芸術制作におけるメディア=素材として計上されるという事態に注目していた。ではそこで私らが空白に向かって投げ込んでいるものとは何なのか。それは言語といかなる関係を持っていたのか。
3. 抒情主体と〈喩〉
詩人の安川奈緒は、テクスト内発話者と作者を同一視する傾向の強い〈抒情詩〉をめぐる問題を、入沢康夫が1968年に刊行した『詩の構造についての覚え書』と、それに対する北川透による批判の整理を通して論じている。
そこでは、〈抒情詩〉に対して作者と発話者を明確に切り分ける構図を適用することの是非や、作者の制作過程と発話者のあいだにある関係を問わなければ制作過程が神秘化してしまうのではないかという問いが扱われていた。テクストの制作は否応なく発話者の到来を招かざるをえない、ならばその不可避性をどのように理論に組み込むか。
安川は、ミメーシスに問題の核を見出そうとする。おのれの外側にあるものに魅惑されながら自らを構築する主体のエコノミー、それが埋め込まれたものとしての言語、それを素材として用いる表現=詩。《わたしはきみになるために、わたしを破棄しよう》と安川は言う。しかし本稿では「制作へ」での議論を踏まえ、次のように言いたい。「わたしはきみになるために、わたしを制作しよう」
テクストとその手前側に生きる身体との間のミメーシス的関係は、ポール・ド・マンやブリュノ・クレマンらによって、言語の根本にある比喩形象的性格の代表的あらわれたる〈プロソポペイア(活喩法)〉として論じられていた。対象が不在の中で、しかし対象が立ち上がってきてしまうという事態を操作するものとしての言語、その根本に、〈喩〉が見出されること。そしてそれが、テクストにおいて、誰のものか定かでない無名の声を生じさせること。宮川が論じていた、空白を満たすため私からテクストに向かって投げ込まれていたものとは、すなわち〈喩〉であった。
言語表現はそもそもその素材に〈非人称的空間〉=〈制作的空間〉を食い込ませたものとしてある。そしてテクストは、〈私〉と〈私でないもの(エルク)〉の狭間において事後的に制作された〈鏡〉であり、そこでは〈私が私であること〉の内部に異種や事物が距離を隔てたまま混入し〈私が私であること〉内部の類似論理を組み替えていくという事態が生じる。
〈非人称的空間〉=〈制作的空間〉を素材としているがゆえに、言語表現はすでにしてそのつどの私の群れによってなされる共同制作であり、かつ、共同体の生成・制御をめぐる試行錯誤でもある。
4. さらにミメーシスの方へ ——「あそこに私がいる」ことの制作
宮川が繰り返し〈非人称的空間〉の作家として参照していた荒川修作は、アメリカで晩年のデュシャンから直接影響を受け、デュシャンが〈第四の次元(La Quatrième Dimension)〉を経由し〈アンフラマンス(inframaince)〉として模索していた問題を受け継ぎ拡張しようとしていた。それは、遠近法(すなわち表現主体の側にある知覚形式)の画布上での多重混在という手法から、対象の側の運動的遍在をめぐる手法へと進むことで、キュビズムからの逸脱をおこなったデュシャンの仕事を、さらに再び私=作者の側へと —— 身体・共同制作の問題として —— 反転させる試みだった。
荒川にとって、事物は、常にもはや表現・制作されたものとしてあり、その同一性は、常になんらかの表現主体の知覚形式にさらされた結果、成立すると考えられていた。そして知覚形式=遠近法=〈作者〉=《空間の意味》が埋め込まれた事物 —— 言語をその最たるものとする —— を、変換等を表すダイアグラムとしてレイアウトすることによって、それに対する身体の様々な抵抗、抽象的な法則性を検分し、さらにはその分解・再構築を目指していたのである。
求められるのは、〈作者〉間の接続が容易に生じる場所としての個体の自己同一性を組み換え、物質的死の先にも制作が持続するという事態、すなわち不死をもたらすことである。荒川は問いをダ・ヴィンチの言葉を用いてあらわす。
「作者が死に続けるのなら、誰がそれを新たに作るのか?」
そしてその答えは、〈ブランク(Blank)〉という概念によって探られることになる。
実践例としての「極限で似るものの家」(養老天命反転地)。そこでは、机や風呂やベッドなどといった家具が、多数の壁に分断されながら、上下左右に繰り返し配置されている。そのなかを歩く私は、右を向けばベッドを左から見、左を向けば同じベッド(に見える対象)を右から見る。上下も同様。すなわち私は瞬間的に1つの同じベッドを様々な位置から見つめる経験を得ることになる。これは言い換えれば、ベッドが方々に位置する私らを高速でつないでいるとも言える。個体の自己同一性が、対象の側を経由して分解・再構築される。しかもそれは、対象側のみに還元される類似(「ベッドはベッドである」)だけでなく、《身体の動きによって全く似ていない部屋の細部が、ほとんど同じように感じられるようにする》というかたちで支えられてもいる。つまりそれは対象と身体のあいだでフィクショナルに生じる何重もの相互包摂的運動としてある。
このように荒川の建築は、距離を隔てたものとのあいだに私のネットワークを築く、アニミズム的〈鏡〉を多重的に誘発する装置として存在する。私でないものに私を見ることにおいて生じる、魂の内的構造たる〈距離〉から編まれた制作的共同体。〈遍在の場(Ubiquitous Site)〉と呼ばれる、《現実と虚構が交わり、支離滅裂でアブストラクトなフィールド》。それは、宮川が素材として計上した〈非人称的空間〉の、身体+環境における展開例であり、テクストにおいて生じる抒情主体をめぐる事態である「わたしはきみになるために、わたしを制作しよう」の実践例でもあり、さらにはデュシャンが模索した〈アンフラマンス〉の拡張されたかたちでもあるだろう。私らは「制作へ」で構築された〈制作〉論の展開例のひとつを —— あるいは参照先の多くを共有し、同様の問題意識を持ったがゆえに結果として近似したもうひとつの〈制作〉論を —— 荒川の作品・理論に見る。
5.「あそこに私がいる」で編まれた共同体の設計へ
「制作へ」は、宮川に代表されるような、作品内部における非人称化や、先取りされた安定した対象ないしは表現主体を抜きにしてなされる類似の錯綜といった問題を、具体的かつ日常的な〈制作〉に関わるものとして読み替える。それは、デュシャンの仕事を身体や共同制作に関わるものとして組み換え拡張した荒川修作のアプローチと近接関係にあると同時に、作家論かその否定か、人間か事物か、相関主義か非相関主義か、といった二元論を超えるための試み —— 土台=〈プロトタイプ〉 —— としてもある。
言語とは、認知の根底にある〈摸写(ミメーシス)的鏡像構造〉を根幹に持つ素材=メディウムであり、それによって構築されたテクストは、おのずと避けがたく〈非人称的空間〉=〈制作的空間〉を立ち上げる。ゆえに、言語を用いてなされる表現をめぐって議論され実践されてきた技術や思考は、「制作へ」での議論を発展させていく上で豊かに活用しうるのではないか。
たとえば貞久秀紀による詩作品は、いくつもの相容れない私を投入し行き交わせることを身体に強いる一種の〈指示書〉としてあるだろう。それを携えて散歩するとき、私と散歩道は、 それ自体が鏡を多数発生させたりさせなかったりする〈非人称的空間〉=〈制作的空間〉の実験場となっているのである。
1.「制作へ」における言語
A. 三種の「よって」
上妻世海「制作へ」は、宮川淳、レーン・ウィラースレフ、西田幾多郎、中村雄二郎、福岡伸一、木岡伸夫、デイヴィッド・エイブラム、養老孟司、中沢新一など、様々なジャンル・年代の論者のテクストを、〈制作〉という概念において次々結びつけていく仕方で書かれています。結果、各々のテクストの設けた概念分類が、相互に翻訳関係におかれるという事態が生じている。たとえば〈述語的統合〉という概念は、木村敏が野矢啓一との対談のなかで提示したものですが、「制作へ」はそれを、宮川における〈鏡≒本の空間〉や、ウィラースレフにおける狩りの様態、大乗仏教の空観などと接続させています。
そうして読み手のなかには、徐々に、大量の概念を行き交わせる体系のようなものが作り出されていく。
おそらくそれを自ら最も明確に示したのが、中盤辺りに出てくる《三種の「よって」》でしょう。
ここまでの議論を、「因って」(原因)、「依って」(縁起)、「由って」(理由)という三種の「よって」を通じて、整理することができる。
自然科学の因果関係と「主語的統合」は、物事の「原因」と「結果」を追究し、「私が対象を見る」という記述を可能にし、「私は私である」という自己同一性を強化することで、第一の「因って」を保っている。
大乗仏教の空観、鏡≒本の空間、狩りの様態、「述語的統合」、すなわち「制作的空間」では、第二の「依って」が表す一と他の相依相待、つまり「縁起」の関係、私の二重化、ミメーシスの眩暈、「私は私でなく、私でなくもない」という私と非—私の不安定な統御、そして五感の組み替えによって、「主語的統合」を可能にする場が示された。
第三の「由って」が表すのは、存在の根拠が存在でも非存在でもなく、それらの根源たる「非」、絶対無にあることが明らかにされた。そして、その「非」の場所から、肯定と否定が現れるのであった。それは、これまであまり指摘されることのなかった「制作的空間」への媒介、つまり一歩目の「制作」という側面である。まず、この「由って」を経ることで、僕たちは肯定と否定が現れる場所、主語的統合を生み出す場所、常識が生成される場所、そして身体が新たに編成される場所に立つことができるのである。
上妻世海「制作へ」(改行は引用者による)
つまり、〈制作〉とは、次のような過程であると考えられる。
まず制作者は、③「由って」を通って〈制作〉へと進み、②「依って」=制作的空間=〈共通感覚〉=デュシャンが切り開いた場所において、私や五感を操作する。そしてその操作を通じて、①「因って」における自己同一性・五感の秩序が組み換えられていく。
③②①と縦に積まれた三層構造になっていると考えれば、③から②、そして①へという垂直方向の〈あいだ〉での動きが〈制作〉では生じている。同時にそれは、①における水平方向の〈あいだ〉の行き来を実現してもいる。
このような大枠において —— あるいはその大枠の記述を目指して ——「制作へ」の議論は展開されていると、ひとまず簡単には言うことができる。
B. 言語
以上をいったん踏まえた上で、本稿では、言語・テクストの問題に注目したいと思います。
「制作へ」は、その論の展開において、繰り返し言語・テクストの問題を扱っている。たとえば次のような箇所 ——。
そこ〔=制作〕では、安定的な自己同一性を保つことはできない。なぜなら、あらかじめ構想していた安定的な私は、書くこと、描くことによって、そのたびに別の私として作られるのだから。ロラン・バルトが『言語のざわめき』の中で、「書くということにおいて、主体はエクリチュールと/から直接に同時的なものとして構成される、エクリチュールを介して実現され、影響をこうむる」と言っているように、である。「作品」や「作者」「読者」という概念は、制作の過程の中で「これでよし」と切断し〈形〉として外在化した結果、生じるものにすぎない。ここには過去から現在、そして未来へ、という時間の流れでは捉え切れない往還運動が存在する。つまり、偶然誤って引いてしまった線によって、作り手がそれに導かれることで〈形〉ができ上がったとき、その偶然性は「作品」にとっての必然性へと変化する。過去は変えられないものではなく、「制作」では頻繁に変わり続けるのだ。そして、「作品」として外在化されること、あるいはそれを引き受け「作者」となることで、主体もまたさらに変化していく。リチャード・セネットが『クラフツマン』の中で語るように、「制作」の中で、つまり物質性との対話の只中で、作り手は作ることへの責任や技術や精神の自己規律を醸成していくのだから。
上妻世海「制作へ」
感応的な関係を再度取り戻すこと……そうすることで、僕たちはそれぞれの身体と世界との相関性に閉じるだけでなく、その外側の存在を知り、振る舞いでもって交感するようになる。現象を超えて実在を感じること、音やリズム、形として繋ぎ合わせること。それはある意味、僕たちが自然に根を下しさえすれば当たり前のことなのである。テキストとは身体である。分かるだろうか。
上妻世海「制作へ」
書くことによる私の変容。あるいはテクストそのものが、もはや身体であるということ。
こうした言語・テクストの問題が特に積極的に論じられるのが、論も佳境に入った、第15章です。その冒頭の一節を見てみます。
言語と身体は、分離された異なる領域と考えられがちである。しかし、「身体性」を考える上で、言語を起点にすることは重要である。身体が理性と感性、そして想像力を司る場所だとするなら、傾きとして理性的な言語、そして感性的、想像的な言語もある。また、このエッセイでここまで忌避してきた、ロゴスと結びつく形式化された言語ではなく、身体に根を下ろした生きた言語について考えることは、マジックワードとして曖昧に扱われがちな「身体性」という概念の解像度を上げることに寄与するからである。
上妻世海「制作へ」
「制作へ」は、〈制作〉を通してなされる私や五感や身体の組み換えを論じるなかで、しかしそのままだと《身体性という一点において神秘化するだけ》になってしまうのではないか、という問いを立てます。そしてそれを解決するためには、《〈共通感覚〉に根を下すこと、〈体性感覚〉を活性化することを可能にする原理を明らかにしなければ》ならない、と主張する。
そのために向かう先として設定されるのが、言語というものの再定義なのです。
ロゴスと結びつく形式化された言語、すなわち《世界と分離された慣習的かつ恣意的な記号システム》としての言語(ソシュール的言語観)ではないものとして、言語を定義すること。それが、〈制作〉すなわち《三種の「よって」》を通じてなされる私・五感・身体の組み換えの具体的展開例につながると、考えられている。逆に言えば、「制作へ」での〈制作〉論は、その成立において、言語というものにかなり大きなものを賭けている。
C. 「感覚的で身体的な現象」としての言語
では、それは具体的にはどのような内容だったのか。
「制作へ」が大きく依拠するのは、デイヴィッド・エイブラムによる『感応の呪文』という書物です。「制作へ」が引いている箇所をここでも引いておきます。
① 知覚という出来事は、経験的に考えると、本来相互作用的で参与=融即的な出来事であり、言い換えれば、知覚するものとされるものの相互交流にほかならない。
② 知覚される事物は知覚する身体との遭遇において、生命ある生ける力となって積極的に私たちを関係の中へ引き入れる。自発的で前概念的な経験は現象を二元論的に、生命あるものと「無生命」のものに分け隔てることはせず、せいぜい生命あるものの多様な形における相関的区別を認める程度である。
③ 感覚する身体と、表情に富む生ける風景との知覚的相互交流は、他者とのより意識的で言語的な相互交流を生みもし支えもする。私たちが「言語」と呼ぶ複雑な相互作用は、私たちの肉体と世界の肉との間で常にすでに展開している非言語的な交流に根ざしているのである。
④ したがって、人間の言語は、人間の身体や共同体の構造によってのみ特徴づけられているのではなく、人間以上の大地の喚起力に富む地形や型の影響も受けている。経験的に考えれば、言語が人間という有機体の特別な所有物でないことは、言語が私たちを包み込む生命ある大地の表現であるということと同じである。
デイヴィッド・エイブラム『感応の呪文』
《分離された二元論ではなく、移行性、可逆性、共感性、共感覚性を伴った未分化の相互浸透である》ものとしての知覚、それに根付いたものとして言語を定義すること。人間に専有されないものとしての言語。
こうしたパースペクティブを土台にしつつ、そこへV・S・ラマチャンドランの『脳のなかの幽霊』や「数字に色を見る人たち」での議論(獲得性過共感をめぐるラバーハンド実験や、共感覚性をめぐるブーバ・キキ効果など)を接続していくことで、「制作へ」は、私というものを《三種の「よって」》を通じて組み換え可能なものとして定義しなおしたように、言語というものを、主客未分化状態において行き交う様々な身振り・音・リズム・感覚から生じるものとして定義しなおそうとします。
僕たちにはもともと、異なる感覚を繋ぎ合わせる能力が備わっている。これを隠喩的と呼んでもよいし、詩的と言ってもよいだろう。そして、ここまでロゴス的論理と言ってきた慣習的で指示的な言語は、本質的に二次的で派生的なのだ。もし言語が純粋に理性的で恣意的なコードではなく、「肉的相互交流と参与=融即から生まれる感覚的で身体的な現象」であるならば、私たちの言語は人間という種以外のものの身振り、音、リズムからも影響を受けていると言えるだろう。それはウィラースレフのミメーシスの理論からでも、エイブラムによる融即理論からでも示すことができるはずだ。そうなれば、もはや「言語」は人間だけの所有物ではない。言語が、常にその根底において身体的、感情的に共鳴するのであれば、鳥が奏でる歌の疑いようもない表現の豊かさや、深夜に響きわたる狼の遠吠えから、完全には分け隔てられない。実際、もし人間の言葉が身体と世界との絶えざる相互作用から生ずるのであれば、エイブラムの言うように、「この言語は私たちに『属して』いるように生命的風景にも『属して』いる」のではないだろうか。
上妻世海「制作へ」
言語は、先んじて与えられた指示の枠組みではない。ウィラースレフいわく《アニミズムの実践的側面であり、その世界製作の仕組みそのものである》ミメーシスがもたらす主客未分化状態=融即において、身体の振る舞いが、事後的に〈制作〉するものである。
このように定義することで、「制作へ」は、〈制作〉を通じての私・五感・身体の組み換えの具体的プロセスの一例を見せるとともに、身体性という概念の解像度を上げようとしたのでした。
言語とは何かを見ていくことを通じて、身体を活性化させること、あるいは体性感覚から主語的統合を作り出すための基礎を描き出せたのではないだろうか。円としての私は、眼によって分離された対象を表象するのではなく流れの中に内在し、視点が移行し、さまざまな情やイマージュ、音や形が飛び交う中で、リズムを感じ、自らの身体で振る舞い、それらを隠喩的に接合していく。そして、それは身体が自然に根を下ろした状態なのである。そうでなければ、言語は死んでしまうのだ。主語的統合を作り変え続けなければならない。それが身体を制作するということなのである。
上妻世海「制作へ」
D. テクストの制作と私・身体・五感の組み換え
言語とは《「肉的相互交流と参与=融即から生まれる感覚的で身体的な現象」》である —— これは、たしかに《かなり実感に近いものがあるので納得できる》(「制作へ」)話です。
たとえば認知言語学における議論は、言語をおおよそそうした身体や環境に由来して構築されるものとして考えていくし、一般的に非言語的情報と見なされるところの身振り手振りや場、視線の動き、言い澱み、声のイントネーションなどまで含めたかたちで言語コミュニケーションを捉え考えていくものとしては、談話分析の蓄積がある。あるいは言語が音にはっきり影響を受けて変容したり構築されたりする事態に関して言えば、オノマトペをめぐる研究は発展途上ながらも充実した蓄積を生んでいるし※1、詩人・批評家の吉本隆明も、宮沢賢治におけるオノマトペ・造語を、既存の言語を離れ《事象そのものの実体の像》《意味多様体のアモルフなそして重層したかたまり》を一挙に表現する新たな言語を創造するものとして論じていました※2。個人的な小説・詩歌の制作経験から言っても、日々の生活における身体と環境のあいだの相互作用は、言語表現の制作へと、確かにつながっているように感じられる。
ただ、同時に、言語とは《「肉的相互交流と参与=融即から生まれる感覚的で身体的な現象」》である、というテーゼだけでは、詩歌や小説、あるいは言語を用いて制作された美術作品等における具体的な技術と、「制作へ」における〈制作〉論とのあいだのつながりが、若干まだ見えづらいようにも思える。結果、ともすれば、《鳥が奏でる歌の疑いようもない表現の豊かさや、深夜に響きわたる狼の遠吠え》に身を晒していればよい作品が作れる、という、漠然とした姿勢・生き方の話で完結してしまう危うさが、いくらか生じてしまうのではないか。
もちろんそこにおさまることを許さない議論が「制作へ」には多く含まれているし、たとえそうなったとしてもそれはそれでよいのかもしれませんが、しかしひとたびそうした姿勢・生き方のレベルにとどまってしまうと、これまでの歴史において、言語を用いた(詩歌、散文、美術、その他様々な)〈制作〉をめぐって生まれてきた数多くの技術や理論が、「制作へ」とのつながりのなかでうまく使えないままになってしまう恐れがある。逆に言えば、そこのあたりをさらに明確に地続きにしておけるなら、私らは「制作へ」での議論とより密に関わるものとして、かつて書かれた詩を読み、小説を書き、絵画や建築やダンス等様々な表現形式の試みと言語のあいだの関係を考えていくことができるだろう。
言語の(身体・環境を介した)組み換えは良いとして、言語を用いた〈制作〉によって生じる私・身体・五感の組み換えの内実についても、それを今後〈制作〉論に紐付いたかたちで様々に検分していけるようなとっかかりをもう少し設けておきたい —— そのように、主に言語表現に携わっている身としては、切実に感じるところがあるのです。
そして、「制作へ」が言語の問題に賭けていたものの大きさを考えれば、こうしたかたちで補助線を何本か引いておくことは、〈制作〉論の解像度をさらに上げ、拡張可能性を開いていくことにも直結するのではないでしょうか。
以上のような観点から、本稿では、「制作へ」が参照していたいくつかの議論の背景を、関連するだろうテクストや作品とともに再度検討していく過程を通じて —— 特にミメーシスの問題に焦点を当てながら ——〈制作的空間〉と言語の関係についてあらためて記述していきたい。「制作へ」論であると同時に、「制作へ」に触発され生まれた思考の集積(のひとつ)として提示できればと思います。
あらためて本稿の流れに触れておきます。
まず、美術批評家でありながら言語・テクストの問題を積極的に扱い、かつ、「制作へ」でも冒頭から末尾に到るまで通低音のように参照されていた宮川淳について、主に1960年代に起こっていた議論を駆け足にたどりながら、彼の思想の背景にあったものを掴んでいきます。
次に、宮川が積極的に論じるとともに、「制作へ」における〈制作〉の主たる特徴のひとつでもあるところの〈非人称〉の問題について、詩や散文をめぐる議論から考えます。重要となるのは、〈喩〉の問題です。
その上で、荒川修作によるアプローチを見ていきます。荒川は、宮川が自らの議論を展開する上で繰り返し参照した作家であり、かつ、これもまた「制作へ」が大きな参照項として置いていたマルセル・デュシャンから直接影響を受け、彼の思想を拡張しようとしていた人物でもあります。
荒川のアプローチは、「制作へ」での議論とも、様々な共鳴を起こしています。美術を出発点としながら、宮川ら同時代の批評との緊張関係のなかに身を置き、さらにデュシャンを批判的に受け継ぐ過程で言語の問題に大きく接近し、共同制作や身体の問題へ、ついには建築の実践にまで到った荒川のしごとを確認することで、「制作へ」での議論を歴史的文脈に接続すると同時に、〈制作〉と言語の関係について、より深く潜った見取り図や展開例を記述してみたいと思います。これはまた、補足すれば、詩歌や小説をめぐってこれまでなされてきた議論と、宮川・デュシャン・荒川らをはじめとする美術でなされてきた議論を、「制作へ」をもとに地続きなものとして設定する試みにもなるでしょう。
2. 非人称的空間 —— 宮川淳
A.〈鏡≒本の空間〉
「制作へ」は、冒頭と末尾で、それぞれ宮川のテクストを引用しています。いくらか特権的な地位を与えているといっても過言ではない。たしかに宮川の論じる〈鏡≒本の空間〉=〈非人称的空間〉は、「制作へ」での議論の根幹部分を築いているもののひとつであるように思えます。
似ていること、それは単にあるものがほかのものに似ていることにすぎないのではないのだから。というか、むしろこの事実を通じて、しかし、より深く、つぎのようなことなのだ —— 同じものであり、しかも同時にほかのものであること、それがあることとは別のところでそれ自体であること、それゆえに、ある〈中間的な〉空間……いわばこの非人称的な〈と〉の空間そのものの浸透であり、それがすべての自己同一性……をむしばむのだ。なによりもこのわたしとわたしとのあいだのずれ —— 「もう一度映像が僕を見つめる、その映像の目。そしてもう一度およそ想像を絶する空間が僕たちのあいだに形作られる。……」
宮川淳『鏡・空間・イマージュ』
《安定的なコギトが分裂し、その奥にある基底が見え隠れする》事態が生じるという、宮川の〈鏡≒本の空間〉は、先ほど触れた《三種の「よって」》による整理のなかでは、②「依って」に位置づけられています。つまり、〈制作的空間〉や〈共通感覚〉、《デュシャンが切り開いた場所》といった、〈制作〉論の核にあたる概念らとのあいだで翻訳関係を生じさせるものとして考えられているのです。
宮川によれば、この空間は、《書く行為と読む行為が同時的・相互的なものとして理解される……〈彎曲した空間〉》であり、《一人称の小説、いやすべての小説に内在する曖昧性》をもたらすのだと言います。読み手・書き手の隔たりなく皆が制作主体として想定されること、そしてそれがテクスト内部の問題として生じること ——〈非人称的空間〉としてのテクスト(の〈制作〉)。
では、こうしたパースペクティブに宮川が至った背景には、そもそも何があったのでしょうか。そしてそれは、宮川が繰り返し接近する言語の問題と、いかなる関係を結んでいたのでしょうか。
B. 史的背景
「制作へ」で参照された『鏡・空間・イマージュ』は、1967年に刊行されました。宮川が「アンフォルメル以後」という論考でデビューしてから4年後の書物ですが、当然ながらそこには、それまでに彼が展開した議論や、同世代の批評家との論争など、様々な背景が多分に埋め込まれています。今回すべてを確認する余裕は当然ありませんが、いくつかの点にしぼって、辿っていきます。
〈反芸術〉
宮川はそのデビュー作である「アンフォルメル以後」において、近代芸術の歴史を、形式批判の悪循環として捉え、同時に《完全な自己表現への幻想》を批判しました。表現に先立つ何ものかがまずあり、それを作家が自らの表現としてあらわす。その表し方=表現形式が、たとえば具象から抽象へというように時代とともに移り変わっていく……そんな考え方が、いまだに残ってしまっている。しかしそれはおかしいのではないか、という問いです。
そしてそこからの離脱方法として提示されたのが、ジェスト(行為)とマチエール(物質)の相互作用による、芸術表現そのものの自立化でした。
描かれる対象と、描く行為。両者を事前に切り分け、前者に応じて後者がなされていくと考えるのではなく、物質の側に、描く行為が埋め込まれ、さらにはあらゆる日常的な物質が、行為として用いられるという状態を、考える。ジェストとマチエールの拮抗関係が続いていくなかで、表現行為というものは、描かれる対象と描く行為のいずれかに従属するのではないかたちで、真に自立するのではないか。
こうしたパースペクティブのもとで、ラウシェンバーグをはじめとする「反芸術」の画家たちによる、作品への日常的なオブジェクトの使用を、宮川は理論的に説明したのでした。
ただ、こうして論じられた〈反芸術〉、特に日本におけるそれをめぐって、東野芳明とのあいだで論争が生じます。これが有名な〈反芸術論争〉です。
きっかけは、読売アンデパンダン展とその中止でした。1949年の開催時には平穏な展覧会だった読売アンデパンダン展は、無審査だったということ、また1956年11月に東京日本橋高島屋百貨店でミシェル・タピエの企画のもと行われた「世界・今日の美術展」をきっかけとするアンフォルメル旋風の影響も後押しして、徐々に、一般的な美術材料とは異なるとされてきた素材、たとえば砂や布、金網、さらにはたわしやサンダル、機械部品などを使った作品が、若手の作家によって多数出品されるようになります。こうした傾向に対して広く名称として用いられたのが、〈反芸術〉という言葉でした。もともとは、1960年の第十二回展に対する展評において、美術批評家の東野芳明が、工藤哲巳の作品《X型基本体に於ける増殖性連鎖反応》に対して用いたものでした。
〈反芸術〉は次第に若手作家らのあいだで一大潮流となったのですが、しかしその結果として、1961〜1963年の読売アンデパンダン展は極度の混乱に陥り、第16回展開催直前(1964年1月)、東野芳明が南画廊で企画した「ヤングセブン」展初日にあわせて開かれたシンポジウム「“反芸術”是か非か」(ブリヂストン・ホール)にて、中止が発表されました。
そのシンポジウムで、東野は、〈反芸術〉をはじめとするポップ・アーティストたちの活動について、セザンヌがサン・ビクトワール山を描いたのと同様に、彼らにとっての自然であるマスメディアのイメージを描き出しているのだろう、と発言しました。
これに対して、宮川が「反芸術 その日常性への下降」(『美術手帖』1964年4月号)というテクストで問題提起します。東野の見立ては、絵画が何ものかの表現としてあるというパースペクティヴを維持したまま抽象と具象の二元論を延命させているに過ぎないのではないか、と批判したのです。
宮川は画布や絵具を物体として見るラウシェンバーグの言葉を引き、アクションペインティングが為した、絵画を純粋な行為にまで還元するという目論見が、《事物の行為への還元》、さらには《客観的なレアリテの概念》の否定というかたちで反芸術に引き継がれた結果、《日常の物体を作品の中に導入することを許した》のではないか、と論じます。そしてそこで、事前に先取りされた表現対象が《不在の芸術はいかにして存在可能かという不可能な問い》が、当時の芸術において大きなものとしてあるはずだ、と主張したのです。
もちろんこれは、宮川自身が「アンフォルメル以後」で展開した議論に限りなく近い。いわば日本における〈反芸術〉の名付け親となった東野の考えに対して、あらためて持論をぶつけたのだとも言えます。
鏡と影
結局、〈反芸術論争〉は、うまく噛み合わないまま数ヶ月で消滅します。
とはいえ、多くの注目を集め、読売アンデパンダン展の中止とともに、日本の美術の流れにおいて明確な切り替わりを示すものとなりました。同じく美術批評家として活躍していた中原佑介は、「「反芸術」についての覚え書」(『美術手帖』1964年12月)というテクストを発表し、そこで〈反芸術論争〉を彼なりに総括しています。さらに翌月の『現代美術』1965年1月号に発表した「「見る」ことについて」でも、〈反芸術論争〉を意識したようなかたちで論を展開しました。
後者のテクストで、中原は、サルトルのテクスト『文学とは何か』から、〈ことば〉の透明さと〈色彩〉の不透明さという二項対立を抽出し、さらにそうした透明な〈ことば〉によって構成されるものとしての小説を〈読む〉ことに関して、やはりサルトルのドス・パソス論「アメリカ論」から、小説という一つの鏡の中へ飛び込むこと、という表現を引用しています。透明な〈ことば〉は、対象を鏡のように曇りなく映し出すものであり、〈読む〉とはそういった曇りなき関係性のもとで構築された作品を、現実の反映として理解することである。ゆえに絵画においてもまた、〈読む〉は成立する。たとえば写実主義の絵画は、《絵画の世界と小説の世界の構造上の類似性を土台にしている》ものであり、それは〈見る〉絵画というよりは〈読む〉絵画とされるのです。
その上で、中原は絵画を〈見る〉とはどういうことかという問いに関して、アンリ・ルフェーヴルの弁証法的解釈などに触れながら、画布や絵具といったオブジェクトのレベルと、絵画によって描かれたイリュージョンのレベルの二項対立を提示し、《絵画とは、この世に現存する「もの」のひとつの条件づけである。あるいは、ある条件を課せられた「もの」であるともいえる》と主張します。そして、《戦後の絵画の特徴のひとつは、絵画のマチエールがクローズアップされたことにあるという》とした上で、以下のように論じる。
変ったのは色彩という「もの」そのものでなく、それにたいする「条件づけ」が変ったのである。……絵画における「条件づけ」の変化は、美術用語でいうなら、イメージとオブジェの両者が互いに浸透し合ったということである。たとえば、そのイメージにおいても、またさまざまな物体の導入という事実においても、絵画が日常的なものをおおきくとり入れたのは、必らずしも、その主題、素材のもつ日常性ということだけを意味しない。……むしろその「条件づけ」の変化が、われわれが絵画の内の世界を「見る」ということと、絵画でない日常生活の事物を「見る」ということとのその双方が境界をもちがたく混淆しはじめたということにほかならない。絵画の世界を日常的というのは、つまるところ「見る」ものの視覚を通した体験によって決るほかないのである。
中原佑介「「見る」ことについて」
絵画作品として発表されたオブジェクトだけでなく、日常のあらゆるものをイリュージョン込みで見るように視覚そのものが変化したことで、日常の素材を芸術作品の中に取り込むということが容易になった —— その結果として〈反芸術〉を代表とする当時の美術の傾向があらわれたのだ、というわけです。
中原は、〈反芸術論争〉において宮川が提示した、客観的なレアリテの瓦解という見立てに一定程度同意しつつ、それを表現過程の自立として捉えるのではなく、あくまで、見ることの条件づけの変化として捉えることで、あらゆるオブジェクトに対する視覚にイリュージョンが混入するというような事態に注目したのでした。
さらに8ヶ月後、中原は、「影と神秘の画家たち —— イメージと影についての考察」(『美術手帖』1965年9月号)を発表します。これは、〈反芸術〉での物体の氾濫から一転して不在の問題が前面に出始めていた当時の日本の美術の状況を、それまでの美術史に位置づけようとする試みであると同時に、主に高松次郎をめぐる議論として整理されることの多い宮川淳との論争〈影論争〉の発端にもなったテクストです。※3
そこでは、見ることの条件づけという「「見る」ことについて」での議論を引き継いだものとして、〈カテゴリーの体系〉=〈ことば〉を介しなければ絵画は運動を描くことができないという問題設定を最初に行い、その上で、自然をそのままに描こうとした印象派、絵画内部で(世界とは別に)独自の〈ことば〉間関係を構築したジョルジュ・スーラ、さらにその先で絵画における物体と影の関係を模索し「表現の表現」のような状態にまで達したジョルジョ・デ・キリコを論じ、最後に荒川修作を、《ことばと同じ程に抽象的であり、個別性をも具体性をも持っていない》シルエットを用いてそれらの間の非常に具体的な関係を試行錯誤する作品を発表している作家として論じたのでした。
空白な空間を満たさずにはいられないわれわれの営為
このように、中原は〈反芸術論争〉における宮川の議論を踏まえつつ、独自にそれを発展させ、描く対象と描く行為の関係が作品内部で問われるような状態を論じたのでした。
これに対して、宮川が即座に反応します。そのとき宮川は『美術手帖』の月評を担当していたのですが、そこで、各展覧会へのコメントに絡めつつ、中原のテクストに言及したのです。
宮川は、中原の主張を《イメージとは影である》というテーゼに圧縮した上で、それを《実体思考》と看破しました。中原は、「影と神秘の画家たち —— イメージと影についての考察」のなかで、単に絵画=イメージがそれの描く対象の虚像としてあるだけだとは主張していません。表現において、何かが何かの表現とされること、そこに存在する類似関係の問題を論じることが目指されていました。
ただ、宮川は、中原が提出した、絵画と表現対象の間の新たな対応関係の模索というあり方では、《実体と影、主体と客体》という構図が残り続けていると考えたのです。つまり依然として中原の考えには、表現に先立つ描写対象が存在しているため、いくらそれを表現内部で問うと言っても、結局は描写対象に従属する形で表現がなされるだけになってしまうのではないか、ということです。それに対して宮川が注目するのは、《イメージへのイメージ自体の回帰》、そして《空白を満たさずにはいられないわれわれの営為》でした。
しばしば危険視されてきたとすれば、それは信じられがちなように、イメージが実体の影であり、虚像であり、偽りであるからでない。影はそれ自体においては現実である。むしろ、それはイメージにおいて、われわれ自身が実体であることを失い、実体と影、主体と客体との間の無名で中性的な領域の中にさまよいこむからにほかなるまい。……イメージをポジティヴな価値にまで高めようとした過程がイメージの自壊作用にまで行きついたあと、今日の絵画にふたたびイメージが戻りつつあるとすれば、重要なことはイメージの回復であるよりも、イメージへのイメージ自体の回帰であるように思われる。……イメージを虚像として捉えるものはなお実体思考だろう。イメージは認識の対象として主体の外にある。だが、イメージとは単に実体の影にすぎないのではない。それはむしろ、主体と客体、実体と虚像という二元論的な認識図式の間隙からの中性的な《と》の空間の滲出、侵食であると同時に、この空白な空間を満たさずにはいられないわれわれの営為にほかならない。たとえばアラン・ロブ=グリエの映画『不滅の女』の主題はぼくにはイメージのこのような本質にほかならないように思える。
宮川淳「月評」(『美術手帖』1965年10月号)
すでにこの1965年の段階で、『鏡・空間・イマージュ』のテクストと一致するところが多く見られるかと思います。実はこの月評は、当時発表済だったテクスト「鏡について」からの引用によって構成されていて、しかもそれは『鏡・空間・イマージュ』の冒頭に収録されている一連のテクストの元となったものなのです。
つまり、宮川は、中原が〈反芸術論争〉を踏まえて執筆していた「「反芸術」についての覚え書」と「「見る」ことについて」に対して、その数カ月後に密やかに応答していた、とも言える。〈鏡〉というモチーフは、『鏡・空間・イマージュ』だけを読むと宮川がオリジナルに持ち込んだもののように感じますが、その4ヶ月前にすでに中原がサルトル経由で導入しており、それに対して宮川は、同じ〈鏡〉についてあえて論じることで、異なるアプローチをよりはっきりと提示していた ーー そう考えてもさほど不自然ではない。
そしてこの月評も、同じく〈影〉という中原の中心的モチーフに言及しつつ、それを5ヶ月前にすでに自分が発表していたテクストの切り貼りで批判しようとしています。宮川は、中原の〈影〉というモチーフがもたらす同一性の問題に関する議論には同意できても、オブジェクトとイメージのカップリングが維持されることには同意できない。さらに言えば、《空白な空間を満たさずにはいられないわれわれの営為》に注目せよ、と主張しています。表現行為と表現対象の二項関係を無化し、《実体と影、主体と客体との間の無名で中性的な領域》を強調する宮川の議論は、一見すると、表現主体も表現対象も抜きに、イメージだけがうごめいていくというようなかたちで想像されるかもしれません。しかし、そうではない。宮川は、《実体と影、主体と客体との間の無名で中性的な領域》をどうにかして満たそうとしてしまう《われわれの営為》こそを問題にしているのです。
宮川は「反芸術 その日常性への下降」のなかで、次のように書いていました。《マチエールとジェストとのディアレクティクにまで還元されることによって、表現過程が自立し、その自己目的化にこそ作家の唯一のアンガージュマンが賭けられるべき》。〈アンガージュマン〉とは実存主義の用語で、簡単に言えば、自覚的選択のもとで社会へ参加していくこと、というような意味です。表現過程の自立という言葉で、作家と無関係な何かが問われていたわけではない。あくまでそこには作家がいる。しかし、それでも理論的に目指されるのは、表現と表現対象の分離を超えた、もはや作家も対象も無化されるような領域だった。その狭間における、まさに〈不可能な問い〉こそが、宮川の最大の関心事だったのです。
このような〈不可能な問い〉は、「制作へ」における〈制作〉論が重視するところの〈不安定な魂の制御〉の問題とも直結するものでしょう。
実践とは「私が対象を見る」といった、私と対象が切り離された認識の在り方でもなければ、私と対象が完全に同化すること、「私はエルクである」でもなく、その間を揺らぎながら「私はエルクではなく、エルクでなくもない」を維持することなのである。その制御に失敗することは、彼らにとって死を意味する。模倣とは魅惑と危険に満ちたものなのだ。
上妻世海「制作へ」
《実体と影、主体と客体との間の無名で中性的な領域》の問題にとどまらず、それをどうにかして満たそうとしてしまう《われわれの営為》にまで議論を押し広げていくこと。それができてはじめて、私らは、私らの生において、具体的に〈制作〉を続けていくことができる。
C.〈非人称的空間〉の作家
無名の眼
宮川による『美術手帖』月評を読んだ中原は、自らが親しく相談役を務めていたおぎくぼ画廊の機関誌『眼』への寄稿を、宮川に依頼しました。宮川はそれに応じ、翌月刊行の『眼』(1965年11月)に、「絵画とその影」を発表します。〈反芸術〉以後において、イメージの問題が絵画とは別の場所で満たされ、むしろ絵画そのものがもはやイメージと化しつつあるという状況を指摘し、それを象徴するのが、荒川の作品におけるイメージへの思考であると論じました。
さらに宮川は、続けて2つのテクストを発表します。「影の侵入」(『1966年美術年鑑』―『美術手帖』1965年12月増刊号)と、『美術手帖』1966年1月号での荒川修作の作家紹介文です。前者は後者との重複が多いので、本稿では後者のみを扱います。そこでは、荒川の作品が次のように論じられていました。
この世界の忘れがたさはその薄明の光のような非人称性だろう。それは例えばアンチロマンの作家ロブグリエの小説「嫉妬」の決して姿は見せないが、たえずそこにいることをやめないあの無名の眼を想わせる。この影の世界はおそらくこの無名の眼に対応している。
この無名の眼、それはもはや見ることの可能性ではなく、見ないことの不可能性でしかないだろう、そしてこの眼にとって、すべては影、つまりもはや存在することの可能性ではなく、存在しないことの不可能性でしかないだろう。
宮川淳「荒川修作」
ロブ=グリエの名前は、先ほどの月評でも《空白な空間を満たさずにはいられないわれわれの営為》をめぐるものとして取り上げられていました。
『嫉妬』は、ひたすらな客観描写の積み重ねの中から、消しきれない語り手の存在が浮き彫りになるという技法が駆使された小説として知られています。つまり、どのように表現主体を排除しようとしても、作品内部に表現主体が〈無名の眼〉としてあらわれてしまうこと。それが、《空白な空間を満たさずにはいられないわれわれの営為》の帰結として生じるのです。
中原が論じたように、オブジェクト同士の平等性が目指されたとしても、そこには常にパースペクティブが存在する。しかも、わたしによって占有されることのない、ひたすらな〈無人称性〉として。※4
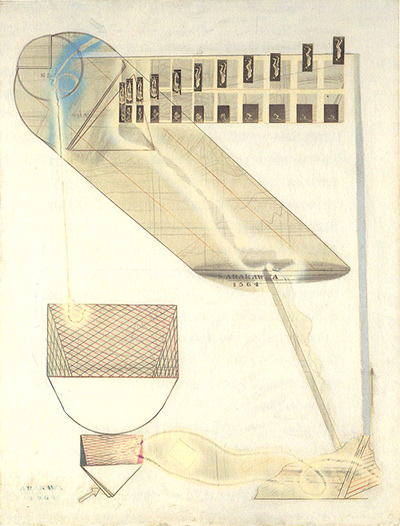 荒川修作『無題』(1964)(宮川淳「荒川修作」に引用されている作品)※5
荒川修作『無題』(1964)(宮川淳「荒川修作」に引用されている作品)※5
素材としての〈非人称的空間〉
さらに宮川は、ミシェル・フーコー「これはパイプではない」の抄訳とともに『美術手帖』1969年1月号に発表したテクスト「絵を見ることへの問い〈陳述〉と〈反陳述〉との交錯」で、またもや荒川の作品を、デュシャンとマグリットの中間に位置付けつつ、先の〈無人称性〉に関する議論の延長線上で論じます。
荒川修作があらわれ出させるこの未知の空間……この空間、それを見ることの空間はその手前に、画面と見る者との間にあるからである。われわれは画面の背後の、いいかえれば事物にまで到達せず、画面の表面で反射され、ことばに収斂される。画面は事物とことばとを切り離す表面である。
無限の往復運動が錯雑するこの厚み、われわれの絵を見ることを可能にさせると同時に、〈絵画〉を成立させ、この空間そのものの中に、一枚の物質的な平面に還元されることのできない〈作品〉を出現させるのは、この非人称的な空間である。
メディアとしての空間について考えること。いいかえれば、ことばがあるいはそれと対立させられる意味でのイメージが、メディアなのではない。われわれをとりまく、この見えない非人称的な空間そのものがメディアなのだ。
宮川淳「絵を見ることへの問い〈陳述〉と〈反陳述〉との交錯」
ここに見いだせるのは、いわば〈制作〉におけるメディア=素材としての〈非人称的空間〉です。
絵画の中に言葉を用いる荒川の作品は、しかし言葉だけを素材としているのでも、あるいは言葉が指し示す対象やイメージを素材としているのでもない。《主体と客体、実体と虚像という二元論的な認識図式の間隙から》滲出、侵食する《中性的な《と》の空間》、それこそを最たる素材として用いている。
そしてその空間は —— 繰り返すようですが —— ただの無ではない。あくまでそこには、〈無名の眼〉が存在しているからです。《空白な空間を満たさずにはいられないわれわれの営為》によって投げ込まれた眼。それは各々の私が投げ込んでいながら、しかし作品において私なのか私でないのか判別つかないものへと組み換えられてしまった眼です。
D. いったんのまとめ
以上、駆け足で、宮川の1960年代の議論とその周囲を見ていきました。
『鏡・空間・イマージュ』で展開され、「制作へ」でも取り上げられた、イマージュの自立性の問題 ——「制作へ」の言葉を借りれば、《イマージュは、根源的に、ここ、イマージュが現わす対象の存在ではなく、いわばイマージュそのものの現前、なにものかの再現ではなく、単純に似ていることなのである》—— は、アンフォルメルから〈反芸術〉、そして不在の芸術へという、1960年代中盤ごろの日本の美術をめぐる言説・実践のなかで醸成され、発展させられていったものとしてあったのでした。
またその発展過程において常に参照されていたのが、荒川修作の作品でした。宮川の1960年代の議論は、荒川の作品の発展過程と並行して展開されていたのです。
そして宮川は、イマージュの自立性と表現主体の関係をめぐる〈不可能な問い〉の先で、荒川の作品を手がかりに、ひとつの考え方に到った。それは、〈非人称的空間〉を、作品と鑑賞者のあいだにおいて —— 作品の手前側において —— 生じる素材として考えるというアプローチです。
それは、絵画の問題であるにとどまらず、言語の問題でもありました。むしろ、言語こそが、素材としての〈非人称的空間〉を直接的に起動させるものとして存在していたと言えるでしょう。
では、ひるがえって、言語のみを主に用いる表現であるところの詩や散文をめぐる議論では、こうした素材としての〈非人称的空間〉は、どのように論じられてきたのでしょうか。
宮川が常に参照し、また「制作へ」が大きく依拠するデュシャンの仕事を、間近で見、引き継ぎ発展させようとした荒川修作について考える前に、いちど詩・散文をめぐる議論を確認しておくことで、宮川が言うところの《空白な空間を満たさずにはいられないわれわれの営為》の内実に、より広く・深く迫れるようになるはずです。
3. 抒情主体と〈喩〉
A. 「わたしはきみになるために、わたしを制作しよう」
抒情詩
今回手がかりとするのは、詩人の安川奈緒のテクスト「感傷的筋肉、詩的虚構について」です。宮川が論じた、素材としての〈非人称的空間〉は、詩においては、抒情詩の問題として主に論じられてきました。安川のテクストは、この問題を簡潔に整理し、かつ、「制作へ」で重要な論点となった〈ミメーシス〉にまで議論を推し進めています。
まず、安川は、『抒情主体の諸相』という書物について論じます。これは《ドイツ・ロマン主義を淵源とし成立した「抒情主体」の概念が、歴史的にどのような形象化を経て今日に現れているのか》や、《抒情詩における、発話主体の声の特異性が何に拠っているのか》を検討するために1995年に行われた、コロックでの発表ないしはその他の原稿から構成された書物です。
抒情詩とは、簡単に言えば、詩人の内面や感情、情緒を、主観的に表現したとされる詩です。つまりそこには、一見すると、小説をはじめとする多くの言語表現が抱え持つような、虚構の語り手と作者の切り分けが、生じない。テクストを制作した者の声が、そのままテクストを担っているという特異な状態が、感じられてしまう。ジェラール・ジュネットやケーテ・ハンブルガーといった論者もみな、こうした考えのもと、抒情詩を《虚構性の問いが発生しない》ものとして例外化している。
しかし、果たして本当にそうなのか。抒情詩のテクストは、現実の詩人というものを正確に指し示すものとして存在しているなどと、言ってよいのか。言語表現である以上、そんな例外はありえないのではないか。
こうした問いに真っ向から向かい合ったものとして、安川は、『抒情主体の諸相』のなかから、ひとつの論文、ドミニク・コンブ「分割されたレフェランスフィクションと自伝のはざまにある抒情主体」を紹介します。
抒情主体の発話は、すべて他の虚構ジャンルと同じように「真でも偽でもない」と言わねばならない、そして、経験的な主体に修辞をほどこし、形象をあたえる再記入として抒情詩はあり、その作業こそが抒情主体を分泌するのだから、絶えまない非−人間化と脱−人称化の過程として抒情主体はあるだろう。レフェランスとしての現実からの退出過程としての抒情主体、すなわち、虚構化のダイナミズムとしての抒情主体…。
安川奈緒「感傷的筋肉、詩的虚構について」
すなわち抒情詩の主体もまた、虚構性を帯びたものとしてある。抒情詩の制作は、制作者である詩人が、《非−人間化と脱−人称化》に晒される過程を示す。
続けて安川は、この問題をめぐる日本での議論を参照します。詩人の入沢康夫が1968年に刊行した『詩の構造についての覚え書』と、それに対する同じく詩人の北川透による批判です。
入沢は「詩は表現ではない」という恐るべき(だがしかしこれは、西洋の詩学においては伝統的な議論である)一行とともに、作者−発話者−主人公に分割されてしかありえない詩的発語の性質を、ジュネットとほぼ同時代に、綿密に論じてみせた。入沢の議論においてほぼ前提とされているのは、詩の語りは、作者と語り手を必ず分割するという観点である。小説の語り手のように、とはいわないまでも、入沢においては、そういった語り手の審級は、自動的に分割され、配備されるものであると論じられていたのだったが、北川の批判は、ここに関わってくる。つまり、この発話者の審級の発生、それはよいだろう、ではなぜ、発話者が発生するのか、発話者の発生そのものの動機は詩人の側にあるのではないか、という問いかけとして、北川の批判はあったのだ。
安川奈緒「感傷的筋肉、詩的虚構について」
詩のテクストにおいても、作者と語り手は切り離されるものとしてある。これは、先のドミニク・コンブの議論とともに、容易に受け入れようと思えば受け入れられるところのものかと思います。ただ、重要なのは、そのあと、《そういった語り手の審級は、自動的に分割され、配備されるものである》ということ、そして《なぜ、発話者が発生するのか、発話者の発生そのものの動機は詩人の側にあるのではないか》という問いです。
言語表現は常に作者と語り手を切り離すよ、という認識は、いったん受け入れればあまりに当然のように感じられる。どうやったって表現はフィクションになってしまうよ、と言ってもいいし、あるいは再度、《単純に似ていること》をめぐるイマージュの議論を思い出してもいいかもしれない。テクストにおいて表現されるものは、テクストの外にいる作者の、現前・再現などではなく、ただテクスト内部において《似ている》だけなのだ、と。
しかし、ではそもそも何によって語り手は生じているのか、と考えると、非常に難しい。自動的にそうなる、と言って済むものなのか。そうではないのではないか。北川は次のように指摘します。
わたしが〈発話者〉の概念を受け入れるとしたら、むろん、フィクショナルなものとしてである。それは、作品を書くという行為における〈作者〉の意志が、何らかの必然において、意識的であれ、無意識的であれ、〈仮構〉しなければならなかったものとして意味をもっている。つまり、その〈仮構〉されたある視点、—— それを〈発話者〉と読んでさしつかえない —— ……を、〈作者〉の意志が何らかの必然(それこそをわたしはまさに解こうとしている)において、〈仮構〉するものとして考えず、〈作者〉と等価な〈人格〉として、天啓のように出現したものと考えるならば、書くという行為は、外在化され、外在化されることにおいて主体的な活動とは無縁な神秘化におちいらざるを得ないのである。
北川透「〈発話者〉とは誰か 「詩の構造についての覚え書」批判」
まず注目すべきは、北川が〈発話者〉=語り手というものを、《何らかの必然において、意識的であれ、無意識的であれ、〈仮構〉しなければならなかったもの》として論じているところです。こういった言い方は、宮川の《空白な空間を満たさずにはいられない》を思い出させます。
作ろうとして作られるものではなく、もはや不可避に、否応なく立ち上がってしまう、無名の視点。同時に、そうした無名の視点が、もし詩の制作者といっさい関わりのないかたちで勝手に生じるのであれば、それは結果的に、テクスト内部での語り手の発生を、制作者の制作と無関係に自動的に生じるものとしてしまうだろう。その先にあるのは、制作過程ないしは作品の、まったくの神秘化である。
それを避けるためには、詩がフィクショナルなものとなる過程を、制作者と密接に関わるものとして定義しなければならない。《絶えまない非−人間化と脱−人称化の過程》(ドミニク・コンブ)。画面と見る者、紙面と読む者の、間にある〈非人称的空間〉を、制作の内部に組み込むこと(宮川)。
入沢康夫の議論の強みは、書き手が受動的に、どのようなありようを強いられるかを、「書くこと」そのものの側から、思考してみせたことだろう。少なくとも入沢にとっては詩人が「語り」の体勢をとればすぐさま「発話者」はテキストにとりつく。「発話者」とは、書記行為に自らを投入することによるほとんど被害のような受動的な経験が、悲しいばかり幽霊のように出現させる形象なのかもしれないのだ。……この抒情主体の、先ほどまでに述べたような自らの虚構化は、入沢の観点を引き継ぎ、また言語との関係の手前に設定される「意志」や「主体性」の形而上学を相対化すべく(抹消すべく、ではない)、言語との関係によって、言語との関係のただなかで思考されねばならない。
安川奈緒「感傷的筋肉、詩的虚構について」
〈発話者〉の立ち上げを、《ほとんど被害のような受動的な経験》として語ること。詩を制作することとはすなわち、強制的に無名の眼で満たされた〈非人称的空間〉に自らをさらすことである。そしてその問題は、どこまでも、紙面に記されたテクストと、その手前側にいる身体(そこに根付いた生)の、あいだの関係に存在すると、考えられなければならないのです。
二者関係
このように議論を整理した上で、安川は最後に、ミメーシスの問題を接続させます。
アリストテレス『詩学』のある種の解釈のなかで、抒情のジャンルはミメーシスの過程を経ないものとして論じられてゆくのだが、本当にそうだろうか、もちろん詩はなんらかの対象を描写することに仕えるものではないだろう。だが、たとえば主体の発生におけるラカンの鏡像段階の議論……など……においては、自らの外側にあるものが要請してくるものそのものになってしまおうとすることにおいて成立する主体のエコノミーが問題になっているのだったが、翻って、抒情主体とは、ある始原の、主体の成立にかかわるミメーシスを、言語との関係に転移、投影することによって繰り返すところのものなのではないか。それはすなわち、自らがそれに成りたいと願わざるを得ないほど、自らによびかけ、自らを呼びつけてくるような詩を投げ出すこと、投げ出すという仕方での自己への触手から駆動されるミメーシスとしての、虚構「化」としての全体=詩作。この悲惨なミメーシスは、抒情的に言ってみるならば、「わたしはきみになるために、わたしを破棄しよう」
安川奈緒「感傷的筋肉、詩的虚構について」
ここには『制作へ』に収録されたいくつかの論考の中で、〈魅惑〉として論じられた事態が、抒情主体のなかに見出されていると言えるでしょう。つまり、テクストにおいて、それと接する身体によって仮構された表現主体は、《自らがそれに成りたいと願わざるを得ないほど、自らによびかけ、自らを呼びつけてくるような》ものとして、私を魅惑する。その過程とは、《主体の成立にかかわるミメーシスを、言語との関係に転移、投影することによって繰り返》したものである、と。
重要なのは、ここで二者関係が前提とされていることです。詩人と、テクスト内表現主体。私とあなた。つまり、〈非人称的空間〉=〈制作的空間〉において生じる無名の眼は、ただ漠然と複数であるというものではない。いわばそこには、「あそこに私がいる」というような関係がある。
自らの外を経由した「私」の分解・再構築。アニミズム的形式でもって私の外に私の魂を見られるような、内側に距離をもった「私」の構造を制作すること。それが、詩では《ほとんど被害のような受動的な経験》として、否応なく到来する。
そしてそこに生まれるだろう、制作者と作品のあいだのぎりぎりの関係を、「制作へ」は、狩りの現場におけるエルクとの関わりをモデルにして考えていたのでした。再度引用しましょう。
実践とは「私が対象を見る」といった、私と対象が切り離された認識の在り方でもなければ、私と対象が完全に同化すること、「私はエルクである」でもなく、その間を揺らぎながら「私はエルクではなく、エルクでなくもない」を維持することなのである。その制御に失敗することは、彼らにとって死を意味する。模倣とは魅惑と危険に満ちたものなのだ。
上妻世海「制作へ」
安川の最後の一節は、《「わたしはきみになるために、わたしを破棄しよう」》です。
ただ、「制作へ」での議論を受け止めた上で考えるなら、次のように言い換える方が良い。
すなわち、「わたしはきみになるために、わたしを制作しよう」。
B. 言語表現の根底としての〈喩〉=プロソポペイア
次に、言語表現において駆動する《主体の成立にかかわるミメーシス》をめぐって、さらに参照項を増やしていきましょう。宮川が《空白な空間を満たさずにはいられないわれわれの営為》と言うとき、そこで私から作品へと放出されていた〈空白な空間を満たすもの〉とは、いったい何なのでしょうか。
自叙伝と鏡像構造
まず参照するのは、ポール・ド・マン「摩損としての自叙伝」です。
この短いテクストは、一般的に書き手の人生をあらわしているとされる〈自叙伝〉という形式をめぐって、しかしそれが決して書き手の人生そのものを透明にはあらわしえないこと、むしろテクストが書き手の人生を制作するような逆流状態を生む可能性があることを論じています。そして重要なのは、その原因にあたるものとして、あらゆるテクストに内在する「摸写(ミメーシス)」の機能を指摘しているのです。
写真が被写体に、(写実的な)絵がその題材に依存しているように、自叙伝は指示性に依存するものであると、それほど確信できるだろうか。私たちは、行為がその結果を産むように人生が自叙伝を〈産む〉と考えているが、同様の正当性をもって、自叙伝という企図のほうが人生を産み、決定することもあるし、書き手の〈行う〉ことはすべて、実は自己描写のための技術上の要請に支配され、したがって全面的にそのメディウムの資質によって決定づけられているのだと言えないだろうか。また、ここで作用していると考えられている摸写(ミメーシス)というのはなかんずく比喩的表現の一形態であるわけだから、指示対象が比喩を決定しているのか、それとも逆なのか —— すなわち指示性という幻想は、比喩の構造と相関関係にあるのではないか。つまり、もはや明白かつ単純な指示対象などというものではなくて、むしろより虚構に近いものであって、とはいえそこである程度の指示的生産性を獲得するというものではないか。
ポール・ド・マン「摩損としての自叙伝」
何かが何かを指示するという言語の性質は、比喩の構造から二次的に生じるものである、とド・マンは論じています。そしてそのような言語の性質があるからこそ、それをメディウム=素材として制作を行う言語表現は、テクストのなかに仮構された表現主体と、テクストの外にいる書き手とを、同一のものとする認識を生じさせてしまう、と。
言語における指示性は、「制作へ」でも、次のように語られていました。《ロゴス的論理と言ってきた慣習的で指示的な言語は、本質的に二次的で派生的なのだ》。ド・マンにおいても「制作へ」においても、言語にはまったく指示性などないと言っているわけではなく、《ある程度の指示的生産性》が事後的に獲得される、とされていることが重要です。指示性が無いのなら、それは先ほど北川が批判していたように、制作者・制作過程が、作品と完全に切り離され、いずれかが神秘化してしまうことになる。両者が否応なく接続してしまうことにいかにとどまって思考するか、がポイントです。
続きを読みましょう。
とすれば、自叙伝はジャンルや様式ではなく、あらゆるテクストにおいてある程度生じる、読みや理解の比喩なのだということになる。自叙伝が生まれる契機は読みの過程に関わり、そのなかで互いに反射して置き換わることによって明確にし合う二つの主体間の連合という形をとって生じる。その構造は、類似性とともに差異性も含んでいる。というのは、どちらも主体を構成する置換をよりどころとするからである。この鏡像構造は、著者が自らを自分自身の理解の主体であると断言するようなテクストに内在化されているが、しかしこのことは、一つのテクストが誰かに〈よる〉ものであると明言され、そのかぎりにおいて理解可能であると考えられている場合にはかならず起こってくる著者の存在性へのより一般的な主張をたんに明確化しているだけのものである。つまり、読解可能なタイトル・ページを持つ書物はいかなるものもある程度自叙伝的だということになるのである。
ポール・ド・マン「摩損としての自叙伝」
あらゆるテクストは、《二つの主体間の連合》という《鏡像構造》をもつ。安川が見出した、魅惑に満ちた二者関係がここでも言語表現の根底に見出されます。
ちなみに、宮川の言う《鏡の体験、二重化の体験》もまた、こうした状態を指摘していたことを、あらためて意識しておきたい。
《ぼく》の存在そのものの曖昧性はここから生まれる。それは決してあのいわゆる自我の非連続、不確実性を意味しているのではない。それは書くことの根源的な体験 —— 鏡の体験、二重化の体験であり、多かれ少なかれ、一人称の小説、いやすべての小説に内在する曖昧性なのだ。
宮川淳『鏡・空間・イマージュ』
さらにド・マンは、こうした《摸写(ミメーシス)》に基づく《鏡像構造》を、《あらゆる理解の一部》《自我についての認識を含む、あらゆる認知の根底にある転義的な構造》として位置づけます。
鏡像的契機は本質的に歴史のなかに位置づけることのできる状況あるいは出来事といったものではなくて、指示対象のレヴェルにおけるある言語的構造の表われである……あらゆる理解の一部である鏡像的契機は、自我についての認識を含む、あらゆる認知の根底にある転義的な構造を表層化する。
ポール・ド・マン「摩損としての自叙伝」
テクストが書かれ、読まれること。そこにおいて身体が否応なくさらされる〈非人称的空間〉=〈制作的空間〉は、あらゆる認知の根底にある〈摸写(ミメーシス)的鏡像構造〉によって構成されている。
これは言い換えれば、テクストを書くこと、読むことに避けがたく伴う、制作主体の把握ないしは解体、虚構化、生々しさなどは、いずれも、テクストに特定的なものというよりは、テクストの外にいる身体やそこに根付いた生にこそ、由来するということでもあります。あるいは、テクストとはそのような身体・生を食い込ませたかたちで生じる構造物である、とも言えるでしょう。
以上のように論じた上で、ド・マンは、ワーズワスの『墓碑銘考』を分析します。そしてそこで、極めて興味深いことに、《まさに自叙伝というテーマの主題論や文体論が達成しようと目指すすべてである》ものとして、プロソポペイア(活喩法)という修辞技法を取り上げるのです。
プロソポペイアとは、《その場にいない、または亡くなった、あるいは声のない存在に呼びかけるという虚構》であり、かつ、《そういった存在の返答の可能性を仮定し、話す力をそれらに授ける》レトリックのことを指します。それが、言語・テクスト(だけでなく、認知や理解までも含む)の根本にある「摸写(ミメーシス)」的「鏡像構造」の内実であるとされるわけです。
はたしてなぜ、プロソポペイアだったのか。
この問題をさらに精緻に論じたものとして、ブリュノ・クレマン『垂直の声 ― プロソポペイア試論』を参照しましょう。
〈喩(figure)〉
クレマンは、プロソポペイアを次の4つの傾向に分類しています。
①プロソポペイアは直接話法である。
②プロソポペイアは虚構的言説である。
③プロソポペイアは包摂された言説である。
④プロソポペイアは道徳的な言説である。
それぞれ、聞くものに直接語りかけてくる(①)、語るはずのないものが語る(②)、「筋」に合った慣習的・常識的な声のそばでそれに対する「他者」として現れる(③)、常識的な声とは異なる崇高的かつ倫理的な声として到来する(④)、というかたちで説明することができるでしょう。
クレマンが例に挙げるのは、たとえば法律が話しかけてきたり、外から聞こえてきた知らない子どもの声のような音を神の命令として聞いたり、あるいは古代の人物にテクストのなかで語らせたりするような事態です。
そして、こうした修辞技法であるプロソポペイアに、クレマンは、言語の根本にある比喩形象的性格のあらわれを見るのです。言語とは、そもそも、対象が不在の中で、しかし対象が立ち上がってきてしまうという事態を操作するものとしてあります。通常それは指示性と呼ばれるところのものでしょうが、ド・マンや「制作へ」と同じく、クレマンは言語における指示性を二次的なものと考えた上で、より根底のところに、〈喩(figure)〉を置く。そしてそれは、何者でもない声を、テクストから直接話法的に立ち上げる機能としてある。
言語表現が素材としてもつ、〈非人称的空間〉=〈制作的空間〉。その《空白な空間を満たさずにはいられないわれわれの営為》と宮川が語るとき、そこで私からテクストに向かって放出されていた、空白な空間を満たすものとは、以上のようなド・マンとクレマンの議論を踏まえれば、すなわち〈喩〉である、と言えるでしょう。
誰のものでもない無名の声を、テクストにおいて否応なく仮構させる〈喩〉の力。そこにこそ、言語(表現)の根底がある。
C. テクストと身体の組み換え、鏡の制作
ミメーシスを強いる構築物
ここまでの議論を整理しましょう。
まず、「制作へ」では、言語は《移行性、可逆性、共感性、共感覚性を伴った未分化の相互浸透》としての知覚によって構成される、《「肉的相互交流と参与=融即から生まれる感覚的で身体的な現象」》とされていたのでした。《人間という種以外のものの身振り、音、リズムからも影響を受け》、組み換えられていくものとしての言語。
その上で、本稿では、宮川や安川、ド・マンやクレマンの議論を経由することで、言語の根底に、〈ミメーシス的鏡像構造〉を生じさせる〈喩〉の機能をも、見出したのでした。それは、言語を超え、認知を根底から支えるものでもあります。
言語は常に、その表現を為したものの情報を、おのれに接した者に否応なく仮構させる、そんな〈喩〉の力を持つ。そうして立ち上げられた表現主体は、書き手や読み手の私ではないが、私でなくもない、奇妙な〈魅惑〉を持ったミメーシス的対象としてある。
そしてそれが複数並べられていくことで、テクストの手前側に生きる身体に根付いた私は、それ以前には不可能だった思考をおこなっていく。いわば言語表現とは、素材=メディウムからして既にもはや〈非人称的空間〉=〈制作的空間〉を立ち上げずには成立しえない営みであり、そこで生み出されたテクストとは、ミメーシスの複雑な運動を身体に強いる構築物としてあるのです。
テクストにおける共同体の生成・制御
振り返れば、「制作へ」では、書くという営みについて次のように語られていました。
そこ〔=制作〕では、安定的な自己同一性を保つことはできない。なぜなら、あらかじめ構想していた安定的な私は、書くこと、描くことによって、そのたびに別の私として作られるのだから。ロラン・バルトが『言語のざわめき』の中で、「書くということにおいて、主体はエクリチュールと/から直接に同時的なものとして構成される、エクリチュールを介して実現され、影響をこうむる」と言っているように、である。「作品」や「作者」「読者」という概念は、制作の過程の中で「これでよし」と切断し〈形〉として外在化した結果、生じるものにすぎない。ここには過去から現在、そして未来へ、という時間の流れでは捉え切れない往還運動が存在する。つまり、偶然誤って引いてしまった線によって、作り手がそれに導かれることで〈形〉ができ上がったとき、その偶然性は「作品」にとっての必然性へと変化する。過去は変えられないものではなく、「制作」では頻繁に変わり続けるのだ。そして、「作品」として外在化されること、あるいはそれを引き受け「作者」となることで、主体もまたさらに変化していく。リチャード・セネットが『クラフツマン』の中で語るように、「制作」の中で、つまり物質性との対話の只中で、作り手は作ることへの責任や技術や精神の自己規律を醸成していくのだから。
上妻世海「制作へ」
こうした事態を、本稿の議論とともにあらためて考えてみます。
テクストのなかに否応なく立ち上げられていく〈形〉=表現主体と、それに対してミメーシス的関係を紡いでしまう、(紙面の手前側に生きる身体において発生する異様な同一性としての)私。この両者の関係は、言語という素材内部に食い込んだものとしてあり、〈書く〉という営みを、それ自体として否応なく共同制作的な領域へと押し広げます。〈非人称的空間〉=〈制作的空間〉を素材としているがゆえに、言語表現はすでにしてそのつどの私の群れによってなされる共同制作であり、かつ、共同体の生成・制御をめぐる試行錯誤でもある。
テクストの制作は、そこまで書き進めてきた数日前の私と、いまこの瞬間あらたに言葉をつないでいこうとする私のあいだの関係を、表現された言葉の並びにおいて組み換え、接合していく。さらにそうして作られたテクストを時間をかけて書き直していくなら、私(による表現)らのあいだの関係は、より多重的かつ複雑なものとなっていくでしょう。言語を用いて〈制作〉する限り、そこには、常に既に〈制作〉の外在化があり、それを足場として構築される多重的な私らによる共同体が伴うのです。
「作品」とは「制作」の外在化であり、制度化である。しかし、それは同時に、いつか、どこかで、誰かの、次の、身体制作への足場となるものでもある。僕が今、彼〔=デュシャン〕が作った足場に立っているように。つまり、「作品」とは外在化であり、誘惑であり、誘惑された者たちの、小さな部分的共同性を生成する装置でもあるのだ。
上妻世海「制作へ」
また、テクストの制作を、様々な私が仮構され、積み重なり、身体とのあいだでミメーシス的関係を多重的に紡いでいく共同制作の営みとして考えることは、すなわち、書き手とテクスト内表現主体をイコールで結ぶかどうかという、一対一関係をもとにした、あまりにありふれた(先のない)問いを避け、作家論とテクスト論の対立から、テクストにおいて制作者や制作過程を思考する場所へと歩を進めることにもつながります。
鏡を制作すること
ミメーシスの複雑な運動を身体に強いる構築物といえば、「制作へ」でそれは、まず宮川による〈鏡〉のモチーフを用いて語られ、次にウィラースレフ『ソウル・ハンターズ』での、エルクとのあいだの関係として語られたのでした。
宮川の「私は私ではなく、私でなくもない」と、ウィラースレフの「私はエルクではなかったが、エルクでなはないというわけでもなかった」は、私が見ているのが鏡であるか、エルクであるかの違いでしかない
上妻世海「制作へ」
しかし、両者にはかなりの違いがあるのではないでしょうか。
まず〈鏡〉においては、私とそれに似たあなたのあいだを関係づけるものが、両者のあいだに事前に確固たるものとして存在している。〈鏡〉があれば、その前でどのような振る舞いをしようとも、私と類似したあなたが立ち上がる。
一方、エルクとのあいだでは、そのような安定したミメーシス的構造が、事前には存在し得ない。私は私であることを解体し、エルクとの類似関係を自ら制作しなければ、ミメーシスは生じ得ない。つまり、私は〈鏡〉自体を制作しなければならない。
しかも、エルクとの場合には、異種間の越境という問題も生じている。私とは大きく異なる身体を持った動物とのあいだで、私を分解・再構築していくことが求められるのです。そこでは、私でないものまでもが制作者として入ってきて、私とのあいだで類似関係を紡ぎながら、類似関係そのものの質を組み替えていくという事態が生じるでしょう。
テクストを、ミメーシスの複雑な運動を身体に強いる構築物として考えるとき、想定すべきは、単なる〈鏡〉ではなく、こうしたエルクとのあいだで生じる事後的かつぎりぎりの関係です。死者や事物の声を立ち上がらせるプロソポペイアを根底に働かせる言語、そしてそれを用いた言語表現は、「私が私であること」という、私内部の類似関係を、事物や動物にまで展開し、結果として事物や動物による表現を、私とのあいだの身体的差異・隔たりを保ったまま、「私が私であること」の内部に混入させる営みとしてある。喩の力でもって、おのれの内部に見知らぬものの声を聞き、おのれの外部に、おのれの魂を見る —— テクストの制作とは、そのような特異な〈鏡〉を作ることでもあるのです。
こうしたパースペクティブを設けることで、「制作へ」で語られていた〈制作〉論の延長線上に、より多くの詩歌・散文の実践を置くことが可能となるのではないでしょうか。
4. さらにミメーシスの方へ —— 荒川修作
ここまで、宮川淳や抒情詩、自叙伝の問題について見てきました。
最後に扱うのが、荒川修作です。「制作へ」が宮川とともに大きく依拠していたデュシャンの思想についても、あらためて整理していきます。荒川のアプローチをたどっていくことで、議論を再度、芸術表現全般の問題へ広げると同時に、(第2章での宮川をめぐる整理に続き)「制作へ」の美術史的背景の一部を記述してみましょう。
A. 荒川修作 (1936-2010)
荒川は、美術から建築まで、特定ジャンルにとどまらない非常に多岐にわたる活動で知られています。岐阜にある『養老天命反転地』や、三鷹にある『天命反転住宅』などには、訪れたことのあるひとも多いのではないでしょうか。
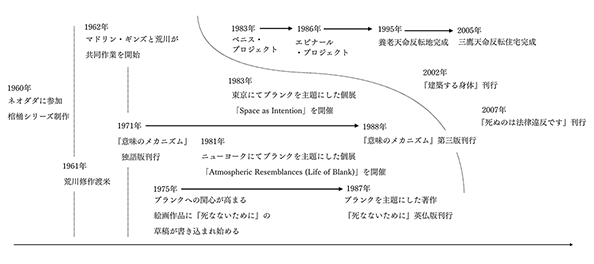 荒川修作簡易年譜(筆者作成)
荒川修作簡易年譜(筆者作成)
活動をおおまかに紹介しておきます。
まず荒川は、1957年に第9回読売アンデパンダン展に初出品し、1960年には篠原有司男や赤瀬川原平らとともに「ネオ・ダダ」に参加、〈反芸術〉を代表する若手作家の一人として、江原順や東野芳明をはじめとする批評家らに評価されます。
このころは、いくつかの絵画や彫刻、パフォーマンスのほか、〈棺桶シリーズ〉と称される一連の作品を制作していました。
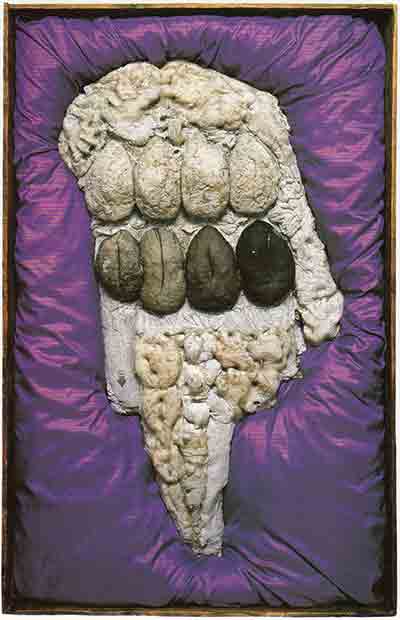 荒川修作『抗生物質と子音にはさまれたアインシュタイン』(1958-59)※6
荒川修作『抗生物質と子音にはさまれたアインシュタイン』(1958-59)※6
その後、1961年12月に渡米、しばらくは引き続き〈棺桶シリーズ〉を制作していましたが、並行して、大きく作風の異なる〈ダイアグラム絵画〉と呼ばれる作品群を制作しはじめ、徐々にそちらの方が主流になっていきます。
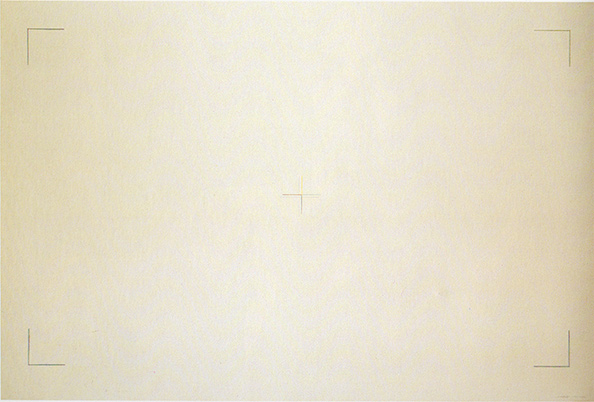 荒川修作『Untitledness No.2』(1961-1962)※7
荒川修作『Untitledness No.2』(1961-1962)※7
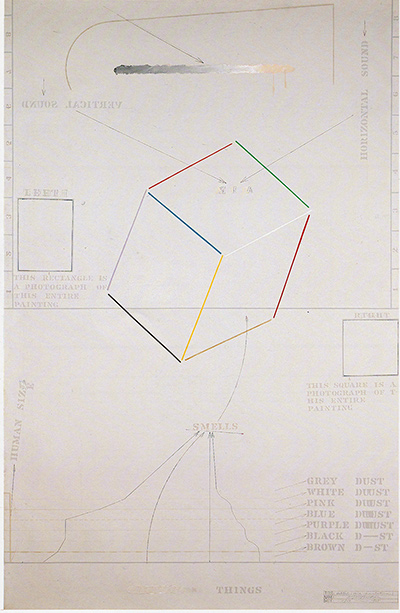 荒川修作『Untitled (Voice Inoculations)』(1964-1965)※8
荒川修作『Untitled (Voice Inoculations)』(1964-1965)※8
1962年にはマドリン・ギンズと出会い、『意味のメカニズム』の共同制作を開始。絵画作品制作の傍ら、人間の知覚や身体の問題に取り組み、映画作品も制作します。
80年代に入ると、さらに建築作品に取り掛かり始めます。1994年には『遍在の場・奈義の龍安寺・心』(後に『遍在の場・奈義の龍安寺・建築する身体』に改題)を、1995年には『養老天命反転地』を完成させます。自らを建築家、さらには(哲学・芸術・科学を総合した存在として)コーデノロジストと称し、都市計画などにも取り組みました。
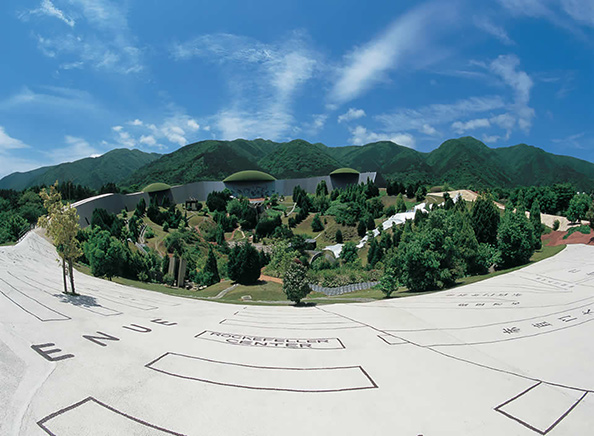 荒川修作+マドリン・ギンズ『養老天命反転地』(1995)※9
荒川修作+マドリン・ギンズ『養老天命反転地』(1995)※9
B. デュシャンからの影響
〈影のダイアグラム〉
今回まず注目するのは、荒川が渡米後しばらく制作していた〈影のダイアグラム〉とでも呼ぶべき作品群、ならびにそこに見られるデュシャンからの大きな影響です。
先ほど記したように、荒川は、まさに〈反芸術〉を代表するような、セメントや綿や金属などで構成された〈棺桶シリーズ〉という作品群から、渡米をきっかけに、それとは大きく異なる作風の〈ダイアグラム絵画〉に変化したとされています。
ただ、荒川はその両者の中間に位置するような作品群を、1964年前後に制作していました。その姿を、東野芳明「荒川修作の近作」(『現代美術』1965年2月号)という記事に見ることができます。
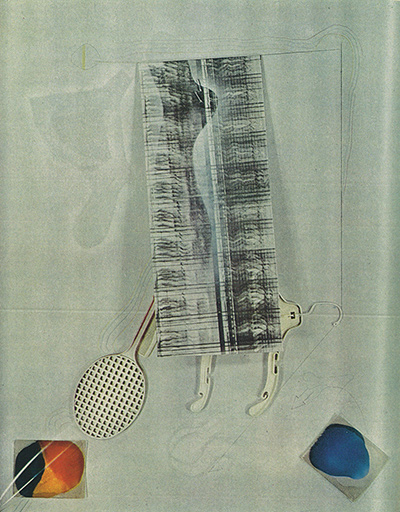 荒川修作『作品』(1964年頃)※10
荒川修作『作品』(1964年頃)※10
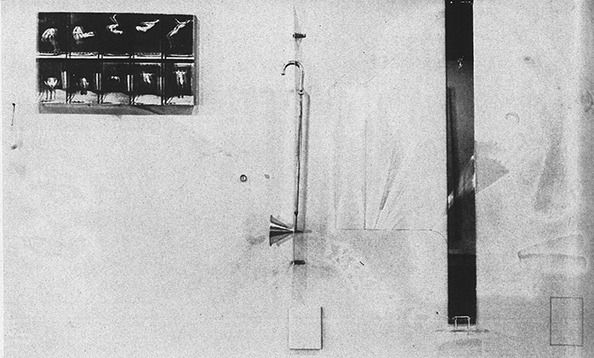 荒川修作『空中ヲトンボ返リシタ時、彼ハ空中デ止マリ、傘ト漏斗ガ交合シテイルノヲチラリト覗イタ。彼ハ、ソレカラ傘ガ帽子掛ケノ方ニ落チテユキ、帽子掛ケノ方ハ漏斗ノ形ヲシタ庭ニアル櫛ヲ眺メテイルノヲ見タ。』(1964年頃)※11
荒川修作『空中ヲトンボ返リシタ時、彼ハ空中デ止マリ、傘ト漏斗ガ交合シテイルノヲチラリト覗イタ。彼ハ、ソレカラ傘ガ帽子掛ケノ方ニ落チテユキ、帽子掛ケノ方ハ漏斗ノ形ヲシタ庭ニアル櫛ヲ眺メテイルノヲ見タ。』(1964年頃)※11
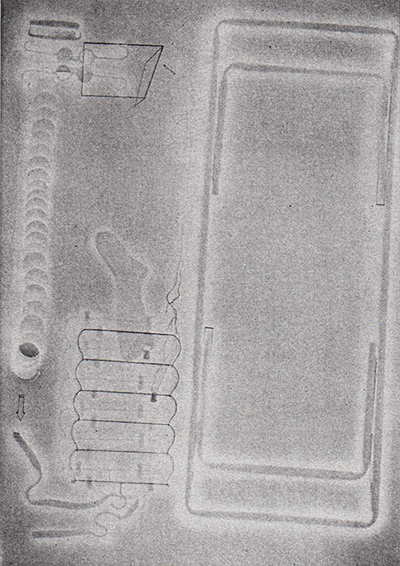 荒川修作『作品』(1964年頃)※12
荒川修作『作品』(1964年頃)※12
これらの作品では、先ほど紹介した〈ダイアグラム絵画〉とは異なり、画布に事物がそのまま貼り付けられていたり、あるいは事物のシルエットが中心的構成物となっていたりしています。1964年3月にドワン画廊で行われたアメリカでの初個展で発表されたものとされているのですが、東野による記事のなかで、例えば『Untitledness No.2』のような、後に渡米初期の代表的作品とされるものたちが一切紹介されていないことからしても、少なくとも1964〜1965年ごろには、簡略化された線や抽象的図像、語詞などで構成された〈ダイアグラム絵画〉よりも、これら〈影のダイアグラム〉の方が制作の中心にあったと考えることができるでしょう。
運動、影、矢印
さて、その上で〈影のダイアグラム〉を検討したとき、半ば露骨な特徴として浮かび上がってくるのが、当時密な関係にあったデュシャンからの影響です。
荒川は海藤日出男や出光孝子など、多くの助けによって渡米を果たしますが、その際、いち早く荒川に注目していた瀧口修造の計らいで、晩年のデュシャンと出会います。デュシャンは当時日本に強い関心をもっていたからか、荒川に注目し、アンディ・ウォーホルやジャスパー・ジョーンズ、ジョン・ケージ、ロバート・ラウシェンバーグといった当時活躍していたアーティストや、画商らを紹介したほか、展覧会にも毎回訪れ、さらに『意味のメカニズム』制作の際には、アトリエにたびたび来ては議論をしていたそうです。
のちに荒川は、デュシャンに対して、アート的制度への従属※13や、精神的なものへの志向を指摘し※14、自身がデュシャンの追随者と見なされることを強く忌避しましたが、一方で2001年には馬場俊吉を相手に、デュシャンとの出会いや彼から受けた影響を以下のように語ってもいます。
彼が一つのモノサシになってくれましたね。彼の存在が、現在、私が進めている生命の外在化の方向へ向かわせたのです。その間、彼の死から二十年ほどは大変でした。すべての芸術の形式も信じられず、詩、哲学もダメでした。ほんの少し、新しい科学の動きがあって……興味がありましたが。そして、やっと、欧米の「精神重視志向」を「身体の動きや行為」に置き換えることによって、デュシャンの思想や考えから、距離を置いて仕事を始められるようになったのです。もちろん、それから長い間、ジグザグの実験がありましたが……。
荒川修作+馬場駿吉「精神の場から身体の場へ —— 戦後アメリカ美術の超克のために」
デュシャンを高く評価し日本へ紹介していた東野芳明や瀧口修造を身近に持ち、デュシャン本人とも密な関係にあった荒川は、デュシャンからの影響を激しく受けながら、自分なりのデュシャン理解を培い、それによって自らの制作を発展させていったのです。荒川の活動は、その全体が一種のデュシャン論であったとも言える。
あらためて〈影のダイアグラム〉を見てみます。ここに確かめられるデュシャンからの影響は、おおまかに言って次の3点かと思います。
①マイブリッジの連続写真の使用
②オブジェクトの影の使用
③矢印の使用※15
まず、①マイブリッジの連続写真について。〈影のダイアグラム〉の多くの作品には、写真家のマイブリッジが1887年に刊行した写真集『運動する人体』の図版引用が見られます。マイブリッジは馬をはじめとする動物や人の動きを独自の装置で連続写真として収めたことで知られますが、デュシャンは同じく連続写真で運動を分析していたマレーの仕事とともに影響を受けて、『階段を降りる裸体 No.2』(1912年)を制作していました。※16
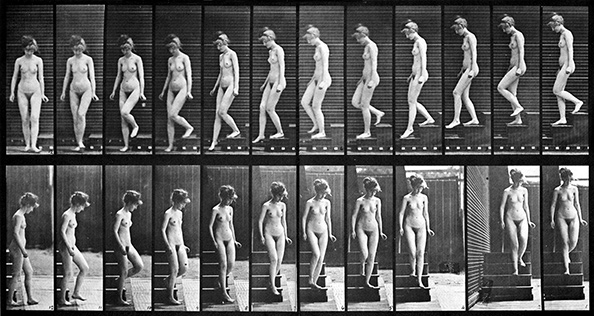 エドワード・マイブリッジ『運動する人体』(1887)※17
エドワード・マイブリッジ『運動する人体』(1887)※17
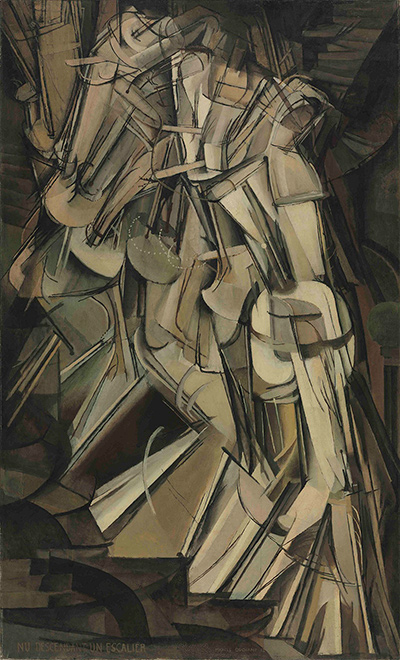 マルセル・デュシャン『階段を降りる裸体 No.2』(1912)※18
マルセル・デュシャン『階段を降りる裸体 No.2』(1912)※18
また、②オブジェクトの影についても、『Tu m’』(1918年)をはじめとするデュシャンの作品に多く見られるモチーフです。
 マルセル・デュシャン『Tu m’』(1918)※19
マルセル・デュシャン『Tu m’』(1918)※19
そして③矢印の使用に関しても、『コーヒー・ミル』(1911年)などで、絵画内の運動をあらわすものとして用いられていました。
 マルセル・デュシャン『コーヒー・ミル』(1911)※20
マルセル・デュシャン『コーヒー・ミル』(1911)※20
以上のように、デュシャンからの影響を如実に感じさせる箇所を、荒川の〈影のダイアグラム〉作品はいくつも抱え持っているわけですが、しかしそもそもデュシャンはなぜ、マイブリッジの連続写真やオブジェクトの影、矢印などに注目していたのでしょうか。
そこで浮上するのは、「制作へ」でも紹介されていた〈第四の次元(La Quatrième Dimension)〉です。
〈第四の次元(La Quatrième Dimension)〉
デュシャンは1911年から1912年ごろ、パブロ・ピカソやジョルジョ・ブラックの影響でジャン・メッツァンジェやアルベール・グレーズを中心に形成されたキュビストの一派「ピュトー・グループ」に身を置き、キュビズム的な多視点を扱う絵画を制作していました。
ピュトー・グループでは当時、ユークリッド幾何学に基づく伝統的な一点透視図法を乗り越え、対象の全体像に関する新たな遠近法へ接近する手立てとして、画家が自らの描く対象の周囲に視線を巡らせる時間を画布上で統合するという考え方や、三次元の透視図を二次元の画布に作り出すように三次元を超えた真実=〈第四の次元〉を物体に対する視点の多重化によって画布上に描くというスタイルが流行していましたが※21、デュシャンもまた、その他のピュトー・グループ所属の画家らと同じく数学者プランセ経由で〈第四の次元〉の考え方に接し、大きな影響を受け、『ソナタ』(1911年)や『チェス・プレイヤーの肖像』(1911年)などといった作品を、複数視点を掛け合わせる手法の下で制作していました。
 マルセル・デュシャン『ソナタ』(1911)※22
マルセル・デュシャン『ソナタ』(1911)※22
 マルセル・デュシャン『チェス・プレイヤーの肖像』(1911)※23
マルセル・デュシャン『チェス・プレイヤーの肖像』(1911)※23
しかし、次第に兄のレイモンや、画家のフランチシェク・クプカに感化され、視覚における運動表象に興味を持ち始め、マレーやマイブリッジの連続写真が表すような、静止した画家に対して動き続ける対象を描くというスタイルで絵画を制作するようになり、1912年には『階段を降りる裸体 No.2』を完成させます。
そこにおいて運動とは、静止した対象に対して画家が動きまわるというかたちで主体的になされるものではなく、描かれる対象の側こそが担うものとなり、それゆえデュシャンの絵画は、無時間的な多重性を纏ったキュビズムの絵画とは異質の、画布上に時間経過や運動方向が表象されたものとなりました。※24
その傾向は、『コーヒー・ミル』(1911年)に描き込まれた矢印の形象や、『Tu m’』(1918年)における指差しを経由して、ダイアグラム的作品『彼女の独身たちによって裸にされた花嫁、さえも』(1915〜1923年、以下『大ガラス』と呼ぶ)へと至ることになります。
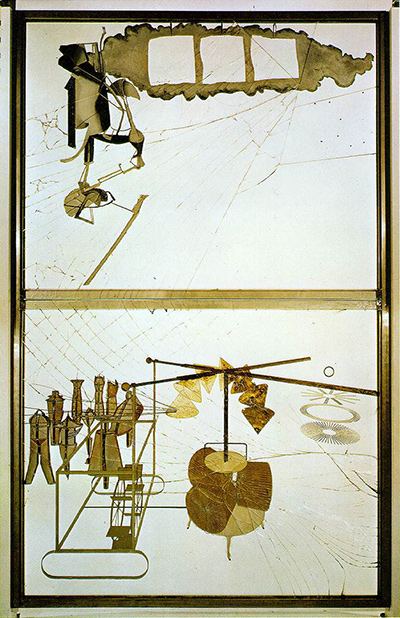 マルセル・デュシャン『彼女の独身たちによって裸にされた花嫁、さえも』(1915-1923)※25
マルセル・デュシャン『彼女の独身たちによって裸にされた花嫁、さえも』(1915-1923)※25
運動はもはや、画布の外の描写対象の残す痕跡としてではなく、鑑賞者が(複数の遠近法で描かれた)オブジェクト同士の関係を辿っていく思考の経路として表される。こうした試みは、視覚像に還元されない極めて抽象的な領域への探求として、ピュトー・グループ内で議論・実践されていた〈第四の次元〉を、デュシャンなりに発展させるものだったのです。
そして影についても、デュシャンにとっては〈第四の次元〉の問題に直結するものでした。「制作へ」でも、中沢新一『東方的』を参照しつつ語られていましたが、あらためてデュシャンの言葉を見ておきましょう。『大ガラス』の制作に向けて、彼が制作した修作のひとつに『花嫁』があります。『階段を降りる裸体 No.2』での運動表現がいくらか薄れ、機械的表現のほうが顕在化したこの作品に関して、デュシャンは後年次のように語っています。
私は単に、投影、不可視の四次元の投影というアイディアを考えただけです。四次元を眼で見ることはできませんからね。
三次元の物体によって影をつくることができることはわかっていましたから、 —— それはどんな物体でも、太陽が地面の上につくる射影のように、二次元になります —— 、単純に知的な類推によって、私は四次元は三次元のオブジェに射影されるだろうと考えました。別な言い方をすれば、われわれが何気なく見ている三次元のオブジェは、すべて、われわれが知ることのできない四次元のあるものの射影なのです。
これはちょっと詭弁めいたところもありますが、とにかくひとつの可能性です。私はこれをもとに、『大ガラス』の中の「花嫁」を、四次元のオブジェの射影としてつくったのです。
マルセル・デュシャン『デュシャンは語る』
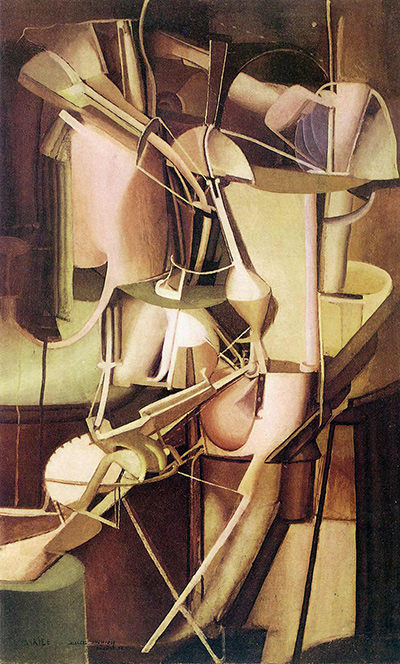 マルセル・デュシャン『花嫁』(1912)※26
マルセル・デュシャン『花嫁』(1912)※26
視覚的には表現され得ない四次元の領域は、三次元のオブジェクトが二次元に影として表現されるように、三次元において表現され得る。デュシャンは1959年にも、『花嫁』が〈第四の次元〉の住人であると語っている他、1913年頃には、以下のようなメモを書いています。
おそらく四次元透視図法のノートを比較対照すべきところ。
……花嫁のあとで
(一)平面上への
(二)しかじかの湾曲がある表面上への
(三)いくつかの透明な表面上への、物体の射影によってタブローをつくること、
こうして(形態=輪郭―における)物体の連続的変形の反物理的分析が得られるそのために、(一)光源(色の分化のためのガス、電気、アセチレン等々)を規定すること。(二)光源の数を規定すること。(三)射影される面と光源の位置との関係を[規定すること]。当然のことながら、物体は任意ではないだろう。それは
三次元に彫刻のように設置されなければならないだろう。—— 光源を用いてタブローを制作すること、そして射影された現実の輪郭にただただしたがってこれらの面[射影される面]への射影をデッサンすること。
マルセル・デュシャン「射影」
注目すべきは、《四次元透視図法》という言葉が用いられている点、そして《物体の連続的変形の反物理的分析が得られる》とされている点です。影とは、あるひとつの光源が生み出す遠近法の結果として存在する。そしてそれらがタブロー上に、画家の恣意性抜きに《ただただしたがって》デッサンされていくとき、そこには事物の変形・運動に内在的な抽象的法則性に関する分析が立ち上がる。それは、マレーやマイブリッジの連続写真のように、二次元から三次元への変換の論理を明かすものとしてあり、さらにその延長線上で三次元から四次元への変換もまた発見されていくだろう。複数の遠近法の同居と、事物の運動を描くことが、影をめぐる操作によって重なるのです。※27
〈アンフラマンス(inframaince)〉
デュシャンにおける〈第四の次元〉の思索は、デュシャンの死後発見された手稿のなかの〈アンフラマンス(inframaince)〉という概念に行き着きます。これもまた、「制作へ」のなかで語られていました。曰く、《都市におけるレンマ的思考》、《外側から見れば同一、内側から見れば、その同一性の中に無数の差異が生じていることが分かるのである》。
「制作へ」での議論をさらに厳密に追うために —— そしてここまで辿ってきたデュシャンによる〈第四の次元〉をめぐる模索へとよりしっかり接続させるために —— デュシャン自身のメモをいくつか引用します。
①類似性、相似性。同一物(大量生産品)相似性の実際的近似。時間の中で、ひとつの同じ物体は、一秒たてば同一物ではない —— 同一律といかなる関係?
②矢印記号の慣習は、受入れられた移動の方向に関して、アンフラマンスの反応をうみだす。
③影を投げるものはアンフラマンスにおいてはたらく。
④二次元から三次元への“導体”としてのアンフラマンスの観念
⑤可能なものはアンフラマンスである ——いく本かの絵具チューブが、一点のスーラになる可能性は、アンフラマンスとしての可能なものの具体的な“説明”である。
可能なものは何かになることを含んでいる —— ひとつのものから他のものへの移行は、アンフラマンスにおいて起る。
“忘却”についての寓意
マルセル・デュシャン「極薄」(岩佐鉄男 訳、一部改訳、番号や順序は引用者による)
まず①からは、〈アンフラマンス〉がレディメイドの問題と地続きにあることがわかります。たとえば同じコーラのペットボトルを2本買ってきたとする。それらはほとんど見分けがつきません。そしてそのうちの1本を、まず机の上に置く。それを見る。次に一度眼を閉じ、別の人が机の上のコーラを回収して、代わりにもう1本のコーラの方を、床に置く。眼を開ける。そこで生じる知覚は、「机の上のコーラが、床の上に移動した」というものでしょう。もちろんそれを疑うことはできる。しかし、区別がつかないのも確かなのです。
注目すべきは、これが、『階段を降りる裸体 No.2』におけるような、ある特定の事物の運動の軌跡が二次元に投影されるという事態と酷似しているということです。Aという場所にいる人がBという場所へと移動するさまを、Aにいる人と、Bにいる人、二人を同じ画布上に別々に描くことで表現するのは、Aにいた人とBにいる人を同一の存在として判定する前提が、画家や鑑賞者において存在しているからこそなりたつ。これを大量生産品の問題と重ねて考えるということは、すなわちあるコーラがそのコーラであることと、ある人がその人であることを、ともに極めて脆弱なものとして考えてしまうということでもあります。Aにいる人とBにいる人は、Aに置かれたコーラとBに置かれたコーラに対してと同じくらい、その同一性は覆される可能性がありうる。さらに言えば、同じ場所にあるコーラも、同じ場所にいる人も、毎秒別のコーラや人へと移り変わっていると考えられるはずです。〈アンフラマンス〉という概念が、事物の運動をめぐる絵画的操作の延長線上で、事物の同一性や時空間の問題を考えようとしたとき導き出されたものであることがわかります。
さらに②からは矢印の問題が、③からは影の問題が、それぞれ〈アンフラマンス〉へと収斂させられていることが見て取れる。同様に、④では次元間の変換が、⑤からはある事物に生じる変容過程が、意識されるでしょう。運動、同一性、時空間、次元の変化(三次元と二次元のあいだの翻訳可能性の模索)、表現……さまざまな問題が、〈アンフラマンス〉というひとつの概念を通じて、行き来する。デュシャンは絵画における新たな遠近法の模索という地点から、知覚の根本で働くものにまで、探求を進めていたのです。
さて、ひるがえって荒川は、活動の初期の時点で、デュシャンから、運動、矢印、影といったモチーフをほぼそのまま受け継いでいました。すなわちデュシャンが〈アンフラマンス〉というかたちで検討していたところから、荒川は出発した。そこに大きな葛藤があったことは、先ほど引用した荒川の言葉からも知ることができますが、はたして彼は、デュシャンの試みを、どのように消化し、発展させようとしたのでしょうか。キーワードは以下の4つです。〈遠近法〉〈作者〉〈共同制作〉〈ブランク〉。
C. 遠近法
荒川は、1964年のドワン画廊での展覧会に、先ほど言及した〈影のダイアグラム〉とは異なる作品をひとつ、出品しています。『デュシャンの大ガラスを小さな細部としている図式』です。
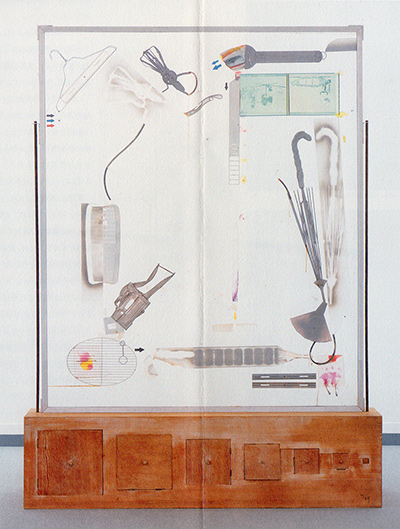 荒川修作『デュシャンの大ガラスを小さな細部としている図式』(1963-1964)※28
荒川修作『デュシャンの大ガラスを小さな細部としている図式』(1963-1964)※28
《大ガラス》を図像として使用しているのはもちろん、全体から細部に至るまで、随所にデュシャンからの露骨な影響を感じさせます。興味深いところは多いのですが、今回は、台座の部分に焦点を絞りたい。
木製の台座には、7つの大きさの異なる四角い扉が確認できます。この作品を現在所蔵している名古屋市美術館によると、最も大きな扉の中には、作品の全体像をおさめた写真が収納されているそうです。
このモチーフで、荒川は何を表現しようとしていたのか。荒川が東野芳明へ宛てた手紙の中には、次のような一節があります。
新しい遠近法について、カク度の問題についてしています。あなたのいう物タイのトウシ図というのが、これです。遠近法とカク度について考えることは僕等のもっているキオクのブンセキ、物体のショウメツ等々の発見のテがかりになります。フロイドなど今の僕にはなんのやくにもたちません。たとえば一定のキョリをヘダテタ場にオナジ大きさの物体がおかれ、それが一つ一つの大きさがちがってみえる事等(中には見えないものがある、そのショウメイ)。これは僕のいましている遠近法です。
東野芳明「荒川修作の近作」
同じ大きさの対象が、置かれる位置に応じて大きさを変えてしまうこと。つまり、台座に設けられた7つの大きさの四角い扉は、同じ大きさの四角形が、異なる位置に置かれた状態を示しているということです。
このモチーフは、荒川がマドリン・ギンズとともに長期に渡り取り組んでいたプロジェクト『意味のメカニズム』の第5章「意味の諸段階」にも、同一のものを見つけることができます。※29
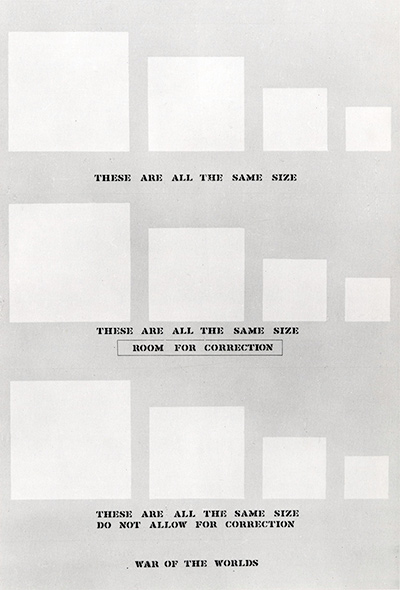 荒川修作+マドリン・ギンズ『意味のメカニズム』― 第5章「意味の諸段階」※30
荒川修作+マドリン・ギンズ『意味のメカニズム』― 第5章「意味の諸段階」※30
パネルの上中下にそれぞれ4つずつ、先ほどの台座と同じように大きさの異なる四角形が描かれています。四角形たちの下には、それぞれ次のように書かれている。
これらはすべて同じ大きさである
これらはすべて同じ大きさである
訂正の余地ありこれらはすべて同じ大きさである
訂正を許さず世界たちの戦争
荒川修作+マドリン・ギンズ『意味のメカニズム』― 第5章「意味の諸段階」
4つの大きさの異なる四角形が、しかし同じ大きさであると意識されること。そしてそれが、修正されたりされなかったりすること。パネルに描かれた四角形、あるいは台座に刻まれた四角形は、当たり前すぎる話ですが、どうやってもその大きさを別のものに変えることは無いように思えます。しかし、遠近法という形式は、それをなぜか可能にしてしまう。絵画の中で奥にいるとされる人は、手前にいるとされる人の顔くらいの大きさであっても、なんらおかしくはない。奥にいる小さな人は、手前に向かって歩いてくれば、どんどんと大きくなるだろうと信じられる。たとえそんなことがありえなかったとしても。
この問題を、やはりデュシャンが考えていました。
線遠近法は等しいものをさまざまに表現するのによい手段である。すなわち等価なもの、類似するもの(相似的なもの)そして同等なものが透視図法的シンメトリーでは混同されるのである。
マルセル・デュシャン「一九一四年のボックス」
同じ事物でも、遠近法における位置を変えれば、異なる大きさに描くことができる。逆に言えば、異なる大きさで描かれていても、遠近法の設定によっては、同一サイズのものとして処理することができてしまう。異なることと同じこと、それらの判定が、対象の側ではなく遠近法の設定に委ねられてしまう。
『意味のメカニズム』でのパネルには、《世界たちの戦争》と記されていました。ある四角が描かれたものとしてあるとき、その大きさは、背後にある遠近法をどのように設定するかに依存する。四角形の周囲にサイズを比較できる別の図像や、あるいはわかりやすい空間的配置があれば、それをもとに遠近法を設定できるかもしれませんが、それでもやはり、四角形をめぐっての完全に客観的な遠近法をひとつ設けるというのは厳密に言えば難しい。パネルに描かれた四角形らは、自らのサイズを保証する遠近法を抱え込めず、そこには様々な遠近法=世界が競合したかたちで同居せざるを得ないのです。
荒川は、こうした遠近法をめぐる問題を、他でもないデュシャンへのオマージュ作品でまず展開したのでした。
他にも荒川は、デュシャンの『3つの停止原器』(1913-1914) に対して、遠近法の問題を見出しています。
 マルセル・デュシャン『3つの停止原器』(1913-1914)※31
マルセル・デュシャン『3つの停止原器』(1913-1914)※31
ニスの塗られた画布の上に、1メートルの高さから落とした1メートルの紐が、偶然のかたちを作り出す。それをもとに3本の木製定規を制作したこの作品を、荒川は、世界の認識がその都度変わっていく例として挙げています。つまり、画布に四角形を描いた瞬間そこにその四角形のサイズを左右する遠近法が生じてしまうように、紐を落として生み出されたかたちにひとつの遠近法を見出し、それを定規として用いて世界のすべてのサイズを計ってしまう。いわば、〈落とす〉という一種の表現をほどこされた紐に、遠近法の埋め込みを見るのです。
これは、荒川にとって、実は言語の問題にも結びついていきます。『絵画たち』という作品を見てみましょう。
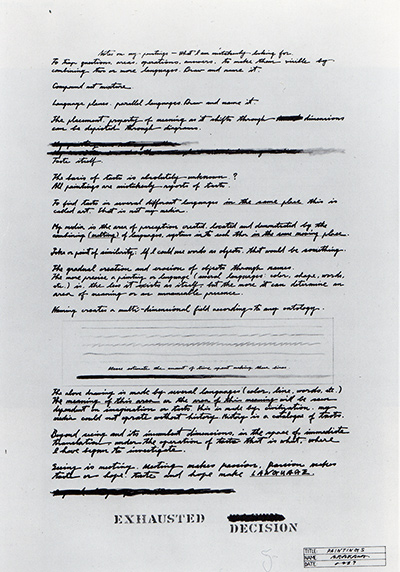 荒川修作『絵画たち』(1969)※32
荒川修作『絵画たち』(1969)※32
この作品に書き込まれたテクストは、ほぼ同時期に「私の絵画らについてのノート:私が誤って探しているもの」というタイトルでエッセイとして発表されているのですが、注目すべきは中央下あたりにある何本かの様々な描き方をされた線と、それに付随する言葉です。そこには次のように書かれています。
私のメディウムは、言語や様々なシステムを互いに同じ動く場へと結合する(融解する)ことによって想像され、位置づけられ、そして表示されるような知覚の領域である。……
〔何本かの様々な描き方をされた線〕
これらの線を制作する時間を見積もること。
上記の図は、いくつかの言語(色、線、単語など)で制作されている。
……
見ることは出会うことである。出会うことは情熱を作る。情熱は趣味や希望を作り、趣味や希望は言語を作る。
荒川修作「私の絵画らについてのノート:私が誤って探しているもの」
宮川が〈非人称的空間〉をメディアと読んだように、荒川は、知覚の領域を自らのメディウムと呼びます。また、線の制作過程への注目は、『3つの停止原器』と明らかに地続きなものとしてあると言えるでしょう。そのうえでここでは、事態が、言語の問題として考えられている。
荒川は一連の〈ダイアグラム絵画〉において、文字を絵画の中に導入し、言語を様々に問題化したことで知られていますが、特に荒川の言語観で異質なのは、絵画に用いる色や線や形はもちろん、肉体や事物に関してもみな、言葉であると考えていることです。
これは言葉と言葉の格闘に近いんです。なぜかというと、われわれの肉体とか物とかそれは全部言葉ですから。……あるものからいろいろな自由を取ってしまった言葉、集約された言葉ですね。重さを失ったり、フロントを失ったり、バックを失った言葉です。それをぼくはある一定のところへ置いて、引き伸ばしたり、私と同じような高さにしたり、いろいろしたわけです。ひょっとすると、その仕掛けから逆にこちら側、こちらの肉体が見えてくるんじゃないか。言葉だけの世界はあるはずです。というのは、われわれのこの世界というのは、ぼくにいわせれば、言葉だけの世界だと思う。
荒川修作+中村雄二郎「新しい創造を求めて」
ふつう、言語は事物との対応関係でもって成立します。「さる」という言葉なら、特定の動物と結びついたものとして使用される。しかし荒川にとってその指示関係は、画布に描かれた四角の大きさが、それが表現されたものである限り極めて二次的にしか判定できないように、不確かなものでしかなった。とはいえそれはなんでもありであることを意味しない。私らの身体や知覚、思考は、確かにある一定の傾向でもって、遠近法を設定し、それを土台にしてさまざまなサイズを、情報を、得ているだろう。どのようにも表現できるということのなかから、否応なく、それについていったりいけなかったりする私らの身体の抵抗が浮かび上がる。そうして様々なかたちで、遠近法が埋め込まれた事物を、画布上に、ダイアグラムとしてレイアウトし、それらのあいだの関係性を操作しつつ、おのれの身体をそこに向かって投じることで、おのれの身体が依拠している法則性を分析するということが可能となる。言葉、言語は、そうした遠近法の埋め込み・レイアウトにおいて極めて有効な素材であると言えます。なぜなら言葉、言語は —— 宮川や安川、ド・マン、クレマンらの議論を通して見てきたように —— それ自体として常に、様々な表現主体の情報=遠近法が埋め込まれたものとして、各々を身体に向かってあらわすから。言語ひとつひとつを表現主体の情報=遠近法として用いること※33、それらをダイアグラムとしてレイアウトすること。多次元的絵画=テクスト。そこから見えてくる身体や魂の構造。
位置。複数の次元を転じていくその意味の性質は、ダイアグラムを通して描くことができる。
荒川修作「私の絵画らについてのノート:私が誤って探しているもの」
荒川にとって、事物は、常にもはや表現・制作されたものとしてあり、その同一性は、いつでもなんらかの表現主体の遠近法にさらされた結果において成立すると考えられていた。これは、デュシャンが〈アンフラマンス〉の定義において、《類似性、相似性。同一物(大量生産品)相似性の実際的近似。時間の中で、ひとつの同じ物体は、一秒たてば同一物ではない —— 同一律といかなる関係?》と語っていたことと直結します。
あらゆる事物は、どのような時空間に置かれ、どのようなかたちで知覚されるかによって、そのサイズを如何様にも変えうる、そう考えてみること。それは、世界を《言葉だけ》のものとして考えてしまうことです。ただし、指示関係にのみ特化した言語がすべてを占める世界では決してない。色も、形も、線も、肉体も、すべてが混在した世界です。では、なにが一般的な世界観と異なるのか?……みな、何らかのかたちで表現されている。そしてその表現によって事物には、表現主体の情報が、サイズ等を左右する遠近法が、ひとつの次元が、埋め込まれている。
そんな、遠近法の埋め込まれた事物を、変換等を表すダイアグラムとしてレイアウトすることによって、それに対する身体の様々な抵抗を検分し、さらにはその分解・再構築を目指す。このようなプランを、荒川は、デュシャンの拡張されたかたちとして想定し、検討していたのでした。
D. 作者
さらにここから荒川は、〈作者〉という問題に焦点を当てます。あらゆる事物が表現されたものとして存在している《言葉だけの世界》を想定することは、すなわち、デュシャンが〈アンフラマンス〉を通して考えていた毎秒の事物の変化において、そのつど新たに遠近法とそこから想定される表現主体を考えるということでもあります。荒川は、遠近法(すなわち表現主体の側にあるもの)の多重混在から、対象の側の遍在へと進むことでキュビズムから逸脱したデュシャンの仕事を、さらに再び私=作者の側へと反転させたと言えるでしょう。
そしてそのとき、私=作者は、決して特権化された画家個人などではない。ある事物のレイアウトに応じて検討・抽出される一種の抽象的な法則性たる《こちら側、こちらの肉体》、それに関わるすべての知覚・思考・身体が、そこに属する。芸術作品は、そうした知覚・思考・身体を、様々に立ち上げ、鑑賞者に強いる装置としてある。見るものの側を作る作品。
それまで見る者に利用できていた場所のどんなものとも質的に異なる場所は、知覚が物質的にそれと拮抗するものを見いだすところで形成される。それらは現象的には反転が可能な場所である。見るものはそれ自体見られるものとなるだろう。それはもはや、芸術作品を最終的に仕上げるのが見る者だという問題ではなく、芸術作品が見る者の最終的なつくり手となるという問題となるだろう。問題のプロセスは、つねに反転できる必然の可能性を帯びていなければならない。
荒川修作+マドリン・ギンズ「エピナール・プロジェクト 制作ノート」
荒川にとって〈作者〉とは、事物の存在に常に伴うものであると同時に、なにより事物によって制作されるものだった。そして、事物ら幾重にも立ち上げる〈作者〉らは、その立ち上げにおいて働いている何らかの法則を徐々に浮かび上がらせるだろう……。
これが、荒川の生涯口にし続けてきた言葉「死なないために」の問題としてあります。
「作者が死に続けるのなら、誰がそれを新たに作るのか?」
レオナルド・ダ・ヴィンチがその手帖のひとつで提出した問は、この状況の動力学をより確固たるものにするのに役だつだろう。この深遠なまでに修辞的な問を —— たぶんこれに答えようとして —— 理解するためには、だれが、あるいはなにが“作者”であるか、よりはっきりと決定されねばならない。しかし、いまのところ、これを決定するためにあるものといえば、“いかなる作者”もその内部で活動している一連の状態こそ、まず定義されねばならないという共通の認識だけである。
ならば、とりあえず、“作者”とは一個人の空間の意味であるといおう。あるいは、さらにすすんで、その空間こそ、“作者”に達せんとするものであるといおう。
荒川修作「制作ノート」(本江邦夫 訳、一部改訳)
一個人の《空間の意味》、すなわち遠近法たる〈作者〉—— それらが《その内部で活動している一連の状態こそ、まず定義されねばならない》。そしてその先に、ダ・ヴィンチによるという「作者が死に続けるのなら、誰がそれを新たに作るのか?」という問いの答えがあると、荒川は言います。※34
実はこの言葉は、荒川が1970年ごろから晩年に到るまで頻繁に言及し、『WHO IS IT』(1970年)をはじめとする絵画作品内にもたびたび書き込んでいるものです。
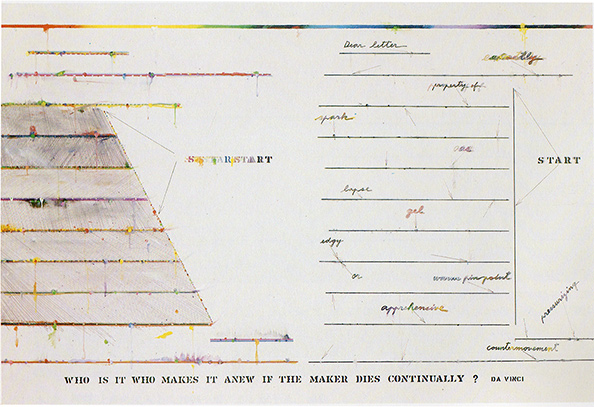 荒川修作『WHO IS IT』(1970)※35
荒川修作『WHO IS IT』(1970)※35
出自を調べてみると、ダ・ヴィンチによって数多く残されている手稿のうちのひとつ「パリ手稿F」のなかに、その存在を確認できます。前後も含めて引用すると、次のようになっている。
光を見てその美しさを考えよ。そしてまばたきをし、もう一度それを見てみる。あなたが見ているものはもともとなかったし、そこにあったものはもう存在しない。作者が死に続けるのなら、誰がそれを新たに作るのか?
レオナルド・ダ・ヴィンチ
ダ・ヴィンチは、画家として、光や影を、遠近法の生じる仕組みと重ね合わせ、検討していました。そうしたメモのなかのひとつです。対象の同一性をめぐるものとして考えれば、デュシャンが〈アンフラマンス〉として考えていたことともかなり近いように感じられる。事実、荒川のダ・ヴィンチ理解も、同一性、それを生み出す類似の問題に極めて偏ったものでした。
どうしてあれほど自然の動きや現象を観察し、研究したのでしょう。私の考えでは、レオナルドは有機体についての構築を、「類似」と「似ている」から始めたようです。
荒川修作+小林康夫「一日も早く自由の自由に向かうために」
〈作者〉とは、すなわちデュシャンが大量生産品に見出したような、毎秒失われていく同一性に伴う《空間の意味》である。それを踏まえて考えれば、「作者が死に続けるのなら、誰がそれを新たに作るのか?」という問いは、すなわち「私が私であること」における自己同一性の問題に近づきます。もちろんそれは、先ほど特権的な画家を否定したように、単純な個人の自己認識の問題ではない。事物の知覚に伴う遠近法=〈作者〉らがどのように関係していくのか、その接続の動きの内部に働く法則性を、やはり問うている。※36その上で、この私においてそのような〈作者〉間の持続的関係が容易に生じてしまうこと、あるいはそれが物質的死によって断絶される可能性があること、が議論の焦点になっている。これがまさに、荒川における不死への試みの端緒である。
荒川の言葉をさらにふたつ続けて引きましょう。
Maker、作る人が毎秒死んでいるとしたら、一体作られているものは、誰によって作られるのか、とレオナルド・ダ・ヴィンチが言ったんです……一九六二年に、ある大学の先生から「荒川君、もし君のお父さんやお母さんがいなかったら、この世にいますか?」って言われた時、僕は即座に「勿論います」って言ったわけだ。何がそうさせたのか。それについて僕は真剣に考えて、それでたまたまそのレオナルド・ダ・ヴィンチの言葉を見つけたわけだ。……これは物語じゃないんだ。構築されてんだ、毎秒。そしてその構築は毎秒死んでるんだ。もっと言うと誰かが壊してるんだ。
もうひとつの問題にサイズの問題があります。サイズ。ひょっとすると、僕が今日言った中で一番大切なことだ。一体、僕達が大きいとか小さいとか言うのは自分の体に対して言うのか、自分のイメージに対して言うのか、自分の習慣や趣味に対して言うのか……。それすらもほとんどの人は知らないでいると思う。どうして僕達は、簡単に蚊とか何かを殺したりできるのか。あれが僕達と同じ大きさで日本語が出来たらどうするか、と思ってもいいですよ。蟻が向こうから僕の前へ来たら、僕と同じ大きさになって「コンニチワ」と言ったとしましょう。構築っていうのはそれに近い。物語はそういうことがありましたって語るだけ。思想もそういうことがありますよってことだ。構築はそうじゃない。そういうのが前に本当に出てきちゃったんだ。しかも「コンニチワ」って言われてみたら、蟻の顔をしているわけだ。そいつを見てみたら、その辺りをスーと行くわけだ。それでまた次にこうだ、っていうことをレオナルドはその言葉で言ったわけですね。
荒川修作「「構築する」ために」
カレンダーだって全部変えちゃう。こんな幾何学的なカレンダーじゃない。僕たちのつくった街には、今あるようなジオメトリーはすべてなくなるんだ。「僕は、今日は四メートル二センチくらいある、昨日の夜は一メートルくらいだった」、そういうふうに話をしなければならない。真実がそうなんだよ。僕たちは嘘の世界に住んでるんだよ。一〇〇パーセント、嘘の世界に住んでるんだ。すべての大切なものを、全部切られてしまったんだ。私たち人間は何千というセンス(赤ちゃんのもっている感覚)を、生活の中でなんにも使っていませんね……。
荒川修作+塚原史「荒川修作の奇跡 天命反転、その先へ」
サイズの判定をめぐる遠近法の問題への執着と、その毎秒の変化、そしてダ・ヴィンチの言葉を介しての不死への問いが、荒川の中で地続きなものとしてあることは明白です。またさらに、ふたつ目の発言からは、これが様々な感覚の問題としてあることもわかります。遠近法=〈作者〉=《空間の意味》を、事物の側で様々に試行錯誤することは、すなわち様々な知覚・思考・身体を鑑賞者において立ち上げるよう強いることでもある。そこで、鑑賞者は、それまで展開したことのなかったけれども構造上可能では可能ではあったはずの感覚を、自らにおいて駆動させる。本稿第3章の議論を踏まえれば、そうした作品側からの強制は、すなわち〈喩〉による機能であると考えることができるでしょう。
以上のように、荒川は、デュシャンから〈アンフラマンス〉を代表とするような様々な問いを受け取り、それを、制作をめぐる問題へと移行させました。つまり、対象の側における異様な同一性だけでなく、それを知覚し表現してしまう私の側にも、同様の異様な同一性を見、対象と私のあいだで、その構造自体を組み換えることで、不死の成立を試みたのです。
その際、荒川は「この私」の同一性を、おそらくは最終目的に解決すべきものとしながらも、手順としてはひとまず二次的なものとして置きます。まずはあらゆる事物に〈制作〉を見出し、そこで遠近法=〈作者〉=《空間の意味》が立ち上がって鑑賞者の身体にそれが強いられるというプロセスが想定されていた。そしてそこで、遠近法=〈作者〉=《空間の意味》同士の特異な関係性として、自己同一性が問われた。
さて、そう考えると、〈作者〉間関係は、理論上、「この私」とはまったく別の身体や時空間に属する私とのあいだでも、十全に培われうるものでなければならないでしょう。〈作者〉の立ち上げに伴う抽象的な法則性たる《こちら側、こちらの肉体》を分析・抽出することを目指すなら、なおさら「この私」だけが関わるだけでは不十分です。
こうして荒川は、ひとつの身体≒私に還元されない〈制作〉、すなわち共同制作の問題へと不可避に進んでいくことになります。
E. 共同制作
荒川が注目するのは、矛盾です。〈作者〉が別の〈作者〉と接続しようとするとき、お互いの間に相容れなさが生じるとする。当然両者は地続きにはならない。しかしそれでも私の身体やオブジェクトが両者を同居させてしまえるとき、その特異な同居のあり様が、「作者が死に続けるのなら、誰がそれを新たに作るのか?」という問いへの答えに関わる手がかりとして浮上するだろう。そしてそれは、まず作品を作ることで実現されようとするけれども、同時に、様々な身体によってその作品を用いて実験を行い、さまざまに改良を施していくことによって、より個人に還元されないレベルで、抽象的な法則性たる《こちら側、こちらの肉体》の分析・抽出がなされることとなるだろう。
マドリン・ギンズによる荒川修作論のなかの一節を引きます。
事実上起こりえない紡ぎ(対立しあう二つの道を同時に進む)から長く引き出された仮説線が分散し、その仮説同士で、軸点のまさに「肉」を事実上分割している。もしこの仮説線が個人から送り出されるなら、ブランクな部分を送り出しているのは誰か?
こうして画布は、個々別々の視点から分割される。個人の考えも同じように分割される。もっと厳密に言うなら、個人の考えは、画布に示された仮説と傾向のすべての接合点(複数の点)になる。
実験にたずさわろうが瞑想しようが、見る者はこの研究の対象となる。そもそもの初めから、この個人にとっては、彼がひとつの集団であることがはっきりしていなくてはならない。実際、彼はその集団の構成分子の集合以上のものである。というのは、少なくともその瞬間には、彼は、ブランクら(blanks)をも送り出しているからだ。
マドリン・ギンズ「アラカワ・図形からモデルへ」(一部改訳)
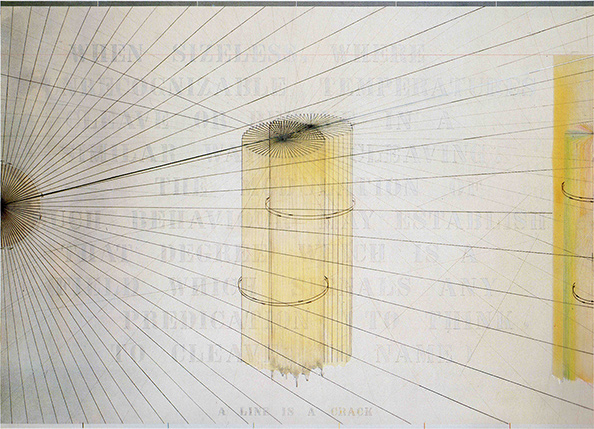 荒川修作『Or Air』(1974)※37
荒川修作『Or Air』(1974)※37
ひとつの画布のなかに、相容れないいくつかの遠近法が同居するように描かれている。鑑賞者はそれらを同時に知覚することはできない。「うさぎ−あひる図」でうさぎとあひるをそれぞれ交互に見出すことはできるがそれらを同時に見出すことはうまくできないように。
しかし、画布あるいは鑑賞者の身体の、それぞれの持続性において、遠近法同士は相容れないまま並置されている。私のなかに、あるいは事物の中に、いくつもの〈作者〉が群れとして同居している。
部分部分は誰にでもわかる、それでいながら一つなのです。
ぼくが一つ情熱を持っているのは、フランケンシュタインの例じゃないけれど、あのようにできる人もいるんじゃないか、私はできなくても、あのようにこの主題をつくるやつがいるんじゃないか。
荒川修作+中村雄二郎「新しい創造を求めて」
鑑賞者は画布とのあいだで様々な遠近法を〈作者〉として立ち上げながら、その画布に明瞭に記されたものとして、異なる遠近法、〈作者〉を意識する。今の私とは違う、しかし私でもありうるものとして——《私は私ではなく、私でなくもない》(「制作へ」)。
共同作用者は、それ自身《私》であるかのように語る。
荒川修作+マドリン・ギンズ『死なないために』
そのような私の複数性は、個の内部と外部を反転可能なものとしながら、そこにある〈作者〉と〈作者〉のあいだの間隙の質や、その発生の可否をめぐって展開されていく。荒川+ギンズが共同制作を見出すのはその地点においてです。
共同制作というコンテクストにおいて、その共同制作者は、アラカワが部分的にしろ全体的にしろ、正しいか間違っているかを証明することによって、手を貸すのだ。……「われは他者なり」と言ったランボーは正しかった。だが、「他者はわれなり」とも言える。共同制作を学ぶことは、他者である私をさらに変調させることになろう。……「われわれは私」なのである。
マドリン・ギンズ「アラカワ・図形からモデルへ」
ただし、こうした《私》である《われわれ》は —— 先ほどから繰り返し触れているように —— なんでもありではない。〈作者〉の立ち上げに伴う抽象的な法則性たる《こちら側、こちらの肉体》に応じて、発生したりしなかったりする部分をもっている。私がいま把握していない遠近法は、はたしていかなる場所においても(人間の身体においては)存在しえないものなのか、それともただこの私が把握できていないだけなのか。これを、ギンズは〈盲点〉と〈ブランク〉の問題として整理します。
盲点は「目的を常に見えるところに置いておく」重宝な方法と考えられるかもしれない。
思考する場においては、我々が見るのに失敗しているポイントのうちの一体どれだけが、実際に機能する「盲点」かということは、まだ確立されていない。
考える者の盲点は、見落しの領域かもしれず、その領域は、彼の対象への注意をバランスの崩れたぐらついたものにしてしまう。考える者が所有していないものについて、ときに他者が考えるかもしれないということは、この領域のいくつかが盲点ではなくて、ブランクだということを示している。おそらく、ブランク・ポイントとみなされるものから盲点かもしれないものへの変調がある。ちょうど、ブランクから知覚されるものへの変調があるように。
思考する場を我々の面前に持って来ることによって、荒川は、それまでは詰まるところ単なるブランクだったものと、我々の考え方に関し、事実機能的に「盲点」かもしれないものとの間に、なおはっきりと区別をつける機会を我々に与えてくれる。
マドリン・ギンズ「アラカワ・図形からモデルへ」
いかなる遠近法も生じ得ない領域は〈盲点〉と呼ばれ、ただこの私においてまだ掴みきれていないだけの遠近法の集まりとしての〈ブランク〉と、区別される。その境目を、私らは作品を通じて検分し、発見する。その先に、人間という種の身体が持つ法則性や、遠近法同士の接続関係の、網羅的把握があるのではないか。
さて、〈ブランク〉は本節の最初の引用の末尾にも書き込まれていました。曰く、《彼がひとつの集団であることがはっきりしていなくてはならない。実際、彼はその集団の構成分子の集合以上のものである。というのは、少なくともその瞬間には、彼は、ブランクら(blanks)をも送り出している》。
作品に向かって鑑賞者から送り出される〈ブランクら〉。宮川における《空白な空間を満たさずにはいられないわれわれの営為》や、そこで働いているところの、誰のものでもない無名の声をテクストにおいて否応なく仮構させる〈喩〉の機能を思い出すところでもありますが、〈ブランク〉とは実は、荒川が1970年代前半から1990年代はじめごろまで最重要主題としていた概念だったのでした。
F. 〈ブランク(Blank)〉
〈ブランク〉は極めて複雑な概念であり、付随するいくつかの概念とともにしっかりと検討しなければ解明しきれないところがあるので、ひとまず本稿では、以下に関連するテクストを列挙しておき、詳細に関しては稿をあらためます。
あることを捉えるという行為を確実に続けていく時に、媒体となるのは、ブランクである(そのような媒体がないのであれば、ただ何かが起こったというだけになる)。
マドリン・ギンズ『ヘレン・ケラーまたは荒川修作』
さまざまな感覚を関連させつつ定立するはたらきは、ブランクの中で起こるのだから、この定位をつかさどるものは、なににまれ私たちにとってはやはりブランクであり続けるより他ない。それを知ったからには、「ブランク」に拠らずに感覚の定位について語ることが、どうしてできるだろうか。
荒川修作+マドリン・ギンズ「『SPACE AS INTENTION』展カタログ」(池田信雄、池田香代子、鈴木仁子 訳、一部改訳)
ブランクは出来事であり方法である。
荒川修作+マドリン・ギンズ『死なないために』(三浦雅士訳、一部改訳)
何かするということはブランクでできている。何もしないでいても動いていても、あるいは何気なく動いていても。これらは普通、感情や思考と呼ばれている。エネルギーのこれらさまざまな姿そのものが、《生成するブランク》に場所をあつらえるのはもとより、ブランクを通して、意識の変化の段階をつくるように動くのである。また、ときには完全なブランクのなかにとどまりもする。
荒川修作+マドリン・ギンズ『死なないために』(三浦雅士訳、一部改訳)
ブランクなしに感覚はありえない。ブランクはおそらく感覚の第一段階であり、他のすべての感覚は、それ自身生起するために、つまり感覚されるために、このブランクを通過するほかない。
荒川修作+マドリン・ギンズ『死なないために』(三浦雅士訳、一部改訳)
《私》という領域、そしてそのほかすべての出来事の領域は、ブランクを通して互いに浸透し合い、ブランクのなかで互いに影響し合う。そしてまた、この中間的な領域は、《外部》を変えるのとまさに同時に《私》を変えながら、《私》のなかへと、あるいはうえへと踏み込んでくるだろう。ブランクが《私》を鋳直すように、私もブランクを手さぐりする。
荒川修作+マドリン・ギンズ『死なないために』(三浦雅士訳、一部改訳)
瞬間的に、また、繰り返し、ブランクは、我々の感覚のための宿、持続していると感じることができるようにするための宿として、働く。同じように、《私》もしくは場所の虚構が同時にかたちづくられるようになる。したがって、ブランクは、行為というものに必須のものをかたちづくりながら、私のなかにくまなくまき散らされているといってよい。ブランクに注目する場合は、以下のことが思い起こされなければならない。ブランクは広く散乱しているということ、さまざまに異ったしかたで一挙に振舞いうるということ、そしてこの、ブランクに注目するという行為においても、それ自身、基本的な役割を果しているということ。
荒川修作+マドリン・ギンズ『死なないために』(三浦雅士訳、一部改訳)
感覚や行為が生じる発端であり、それらが互いに関連していく場であり、そこで働いているエネルギーでもある、〈ブランク〉。遠近法=〈作者〉=《空間の意味》が、人間という種の身体に特有の、「いまこの私には把握できていないが確かに別の私によって抱えられ展開されているだろう」ものらの群れとして存在する領域を見つけ、その輪郭や性質を、具体的な感覚や行為との関連のなかで明らかにすること。
荒川とギンズは、こうした〈非人称的空間〉=〈制作的空間〉を、哲学や認知科学、文学、心理学等のテクストからの引用・編集(『SPACE AS INTENTION』展カタログ、1983年)や、遠近法の撹乱された画布に大量の矢印を描いた作品の制作(『DRGREES OF BLANK』(1981年)、〈実際には、盲目の意志〉シリーズ(1982-1983年)など)、『意味のメカニズム』の第三版へ向けた修正(-1988年)などを通して理論化し、それを一冊にまとめました(『死なないために』1987年、日本語訳 1988年)。その後、絵画から離れ、より身体の問題を徹底して試行錯誤することのできる建築作品の制作へと本格的に進むのでした。※38
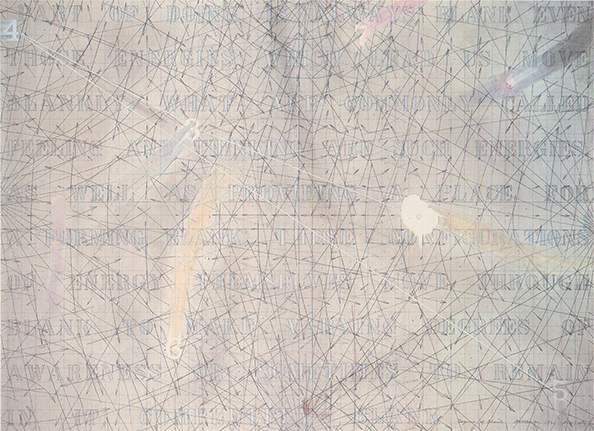 荒川修作『DEGREES OF BLANK』(1981)※39
荒川修作『DEGREES OF BLANK』(1981)※39
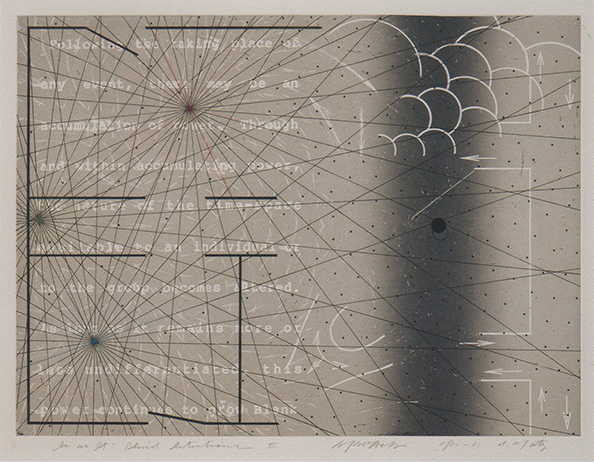 荒川修作『実際には、盲目の意志 Ⅵ』(1982-1983)※40
荒川修作『実際には、盲目の意志 Ⅵ』(1982-1983)※40
G. 距離を隔てた私らのネットワーク、〈遍在の場(Ubiquitous Site)〉
荒川+ギンズの建築作品からひとつ、分析してみます。「極限で似るものの家」(養老天命反転地)です。
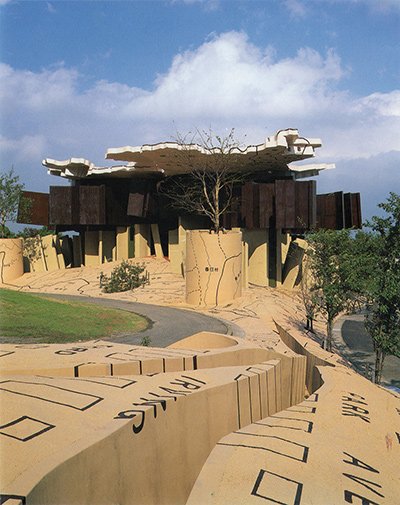 荒川修作+マドリン・ギンズ「極限で似るものの家」(1995)※41
荒川修作+マドリン・ギンズ「極限で似るものの家」(1995)※41
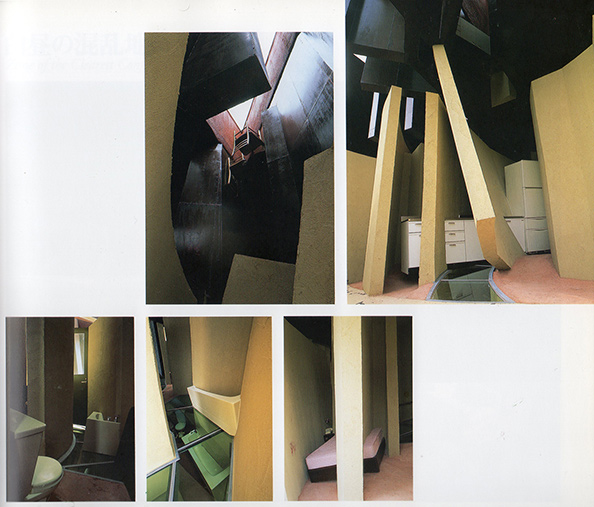 荒川修作+マドリン・ギンズ「極限で似るものの家」(1995)※42
荒川修作+マドリン・ギンズ「極限で似るものの家」(1995)※42
建物の中は、いくつもの壁が錯綜し、それに分断された机やお風呂やベッドの模型が、繰り返し配置されています。さらに天井と、(ガラスで覗ける)地下にも、同様に家具の模型が配置されており、歩いているとほとんど迷路のような感覚が生じる。
この作品には使用法が用意されています。そのうちのひとつには、次のように書かれている。
自分と家とのはっきりした類似を見つけるようにすること。もしできなければ、この家が自分の双子だと思って歩くこと。
荒川修作+マドリン・ギンズ「養老天命反転地:使用法 極限で似るものの家」
鑑賞者と対象のあいだで生じるミメーシス関係を記述しているようでもありますが、まだ明晰には掴みづらいところがあります。
実はこの作品には荒川の制作メモが残っています。そちらを見てみましょう。
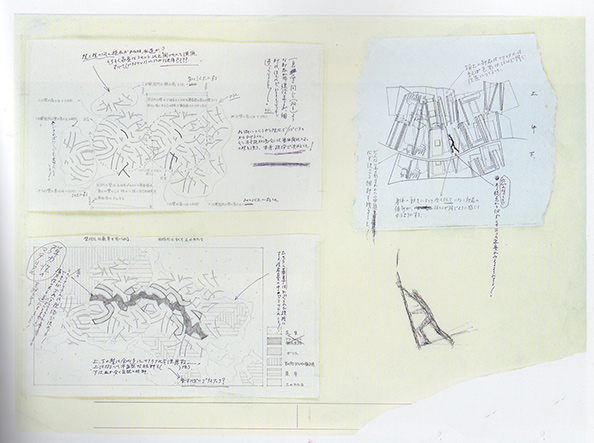 荒川修作+マドリン・ギンズ『《養老天命反転地 極限で似るものの家》のためのドローイング』(1992-1994)※43
荒川修作+マドリン・ギンズ『《養老天命反転地 極限で似るものの家》のためのドローイング』(1992-1994)※43
頭上の部屋は、マテリアルは変えるが、色、形は、ほとんど同じ位置につくること
身体の動きによって全く似ていない部屋の細部が、ほとんど同じように感じられるようにする
一見全く同じ(双子)ような部屋が2つ建設されるが、細部は、ほとんど、どこをとっても違っていること!
上、下の壁は全く違ったマテリアルを使用する —— 上はなるべく不自然な材料を(安っぽいプラスティック?)使う。下は土か全く自然の材料
荒川修作+マドリン・ギンズ『《養老天命反転地 極限で似るものの家》のためのドローイング』
注目すべきは、《全く似ていない部屋の細部》《全く違ったマテリアルを使用する》などと、類似とは真逆の差異が家具や壁に関して重視されていること、そしてその上で、身体の動きによってそれら似ていないものらが《ほとんど同じように感じられるようにする》ことが狙われているということです。
この建物の中を歩くとすぐに感覚として立ち上がるのは、自分のいま立っている場所がどこなのかわからなくなってしまうような、夢にも似た状態です。まず、視線が壁によって激しく遮蔽されているため、視野が常に狭い。また、家具を模したオブジェクトがほうぼうに見える。しかもそれは、壁に食い込むようにして配置されているため、見えるのは常に一部分であり、さらに上下左右の異なる場所に繰り返し配置されている。
鑑賞者は、右を向けば、ベッドの一部が見える。さらに少し歩いて左を向けば、同じベッド(に見えるオブジェクト)の一部が見える。ふたつのベッドは決して同じものではありえないはずです。しかし、壁に遮蔽された視野のなかで、部分的に見えるそれは、どうにも同じものに感じられてしまう。
つまり鑑賞者は、ベッドの左端を左から見ている経験をした直後に、同じベッドの右端を右から見ている経験をする。さらに上を向けばそこにあるベッドをまるで頭上から見ているような経験が生じ、下を見ればベッドを上から見下ろしているように感じられる。いわばそうした1つのベッドをめぐる様々な遠近法=〈作者〉=《空間の意味》が —— 通常ならそれはベッドの周囲を時間をかけて自ら歩き回ることではじめて得られるはずのものであるにも関わらず —— 少し歩いて周囲を見渡す動きをしただけで、高速で鑑賞者の身体において接続させられるのです。
しかもそれらのベッドは、制作メモによれば、色や形は似ているけれども材質は大きく異なるものとしてあるとされています。鑑賞者は、迷路のような建物内を歩き回りながら、様々な家具の同一性を、《身体の動きによって》作り出す。私の遍在が生まれる。
「使用法」は、一つには、私等の行為をインスタントに中性化させるためのものなのです。
歩けるパッサージュ、歩けないパッサージュを見ながら、何かが使い始める。さっき藤井さんの言われた距離というのは、その距離を縮めて、あの混沌とした〈遍在の場〉を発生させるでしょう。そのとき、現実と虚構が交わり、支離滅裂でアブストラクトなフィールドが生成する。つまり環境がほとんどそうですけど、そうなったときに唯一頼る武器は、人体の行動でしょう。その行動も狂ってきたらどうします?
そのときに、その使用方法は誰も教えてくれない。これが使用法に近いものなんです。自分でみつけだすよりしようがないんですよ。そのときに、新しい経験が生まれる。
荒川修作、藤井博巳『生命の建築 ― 荒川修作・藤井博巳対談集』
「遍在の場」と簡単に言ってしまったけれど、身体の運動や行為のバランスを崩したときに生まれる新しい感覚や知覚は、必ず遍在として、身体のまわりに視覚や知覚とともに存在し始めますね。いわゆる、内在している感覚と外在し始めた感覚の距離や位置が振動を始めるのでしょうね(笑)。もし「無限」を体験できる環境が建設できれば、「永遠」に近づく可能性も……。しかも、その「永遠」のコンセプトを現実に生きるためには、どうしても環境から発生する出来事と距離をつくることによって生れる、気配のような現象を「反復」せねばなりませんね。そしてその現象を、さまざまな詩人や思想家がこの何百年も歌ったり語ったりしてきましたが(笑)。
荒川修作、藤井博巳『生命の建築 ― 荒川修作・藤井博巳対談集』
以上を整理すれば、次のようになるでしょう。
「極限で似るものの家」のなかでは、まず、対象の側の〈アンフラマンス〉的同一性が、身体の動き(それに伴う、対象を把握する上での形式たる遠近法)によって仮構されるさまが検分される。オブジェクトのマテリアルが意図的にずらされていることで、類似が、対象の側ではなく私の側でフィクショナルに生じるさまが露呈するのです。
さらにそれを支えにして、ある特定の対象をめぐる様々な遠近法が高速で自らのうちに蓄積していく事態が生じる。本来それら遠近法らを経験する上で必須とされるような自己の持続的経験が、ずたずたにされ、対象の配置において再度編まれてしまう。まるで部屋の右奥にいる私、天井に立つ私、床の下にいる私、はるか遠く部屋の外にいる私など、〈距離〉を隔てて偏在している異なる私らが、対象側に生じた類似のネットワークによって高速でつながれ、「私が私であること」を意識するような自然さでもって、しかし別々な存在として共同しているかのように、感じられる。〈遍在の場(Ubiquitous Site)〉、ミメーシス的・アニミズム的構造に支えられた〈鏡〉の多重的誘発。そこでは時空間すらも分解され、新たな構築へと向かうでしょう。
H. まとめ
距離を隔てたものらとのあいだに《「私は私でなく、私でなくもない」》ネットワークを築くことを、そこに入り込んだ身体らに向かって強いる、荒川の建築作品。そこで私の身体や知覚は分解され、私の分身があちらこちらに遍在しては消える。さきほどあそこにいた私が、今ここにいて、ここにいる私が、あそこにもいる。それら私の群れの出現・消失の傾向や質が、「作者が死に続けるのなら、誰がそれを新たに作るのか?」という問いをめぐる実験(の結果)として、蓄積する。※44
私は、世界は、毎秒死んでいる。そして次の瞬間、また私が、世界が、生まれている。何が私を、制作を、持続させているのか。そしてそれは、感覚や対象操作によってどのように組み換えることができるのか。その先で、私とは別の場所に私の持続を作り出し、不死の制作をもたらすことはできないか……私でないものに私を見ることにおいて生じる、魂の内的構造たる〈距離〉から編まれた、不死の制作的共同体。それは、宮川が素材として計上した〈非人称的空間〉の展開例であり※45、テクストにおいて生じる抒情主体をめぐる事態である「わたしはきみになるために、わたしを制作しよう」の実践例でもあり、さらにはデュシャンが模索した〈アンフラマンス〉の拡張されたかたちでもあるでしょう。私らは「制作へ」で構築された〈制作〉論の展開例のひとつを —— あるいは参照先の多くを共有し、同様の問題意識を持ったがゆえに結果として近似したもうひとつの〈制作〉論を —— 荒川の作品・理論に見ることができるのです。
5. 「あそこに私がいる」で編まれた共同体の設計へ
ここまで、大きく分けて3つの議論をたどってきました。
①宮川淳が〈非人称的空間〉や、先取りされた安定した対象ないしは表現主体を抜きにしてなされる類似の錯綜といった問題を扱うことになった背景としての、1960年代日本美術における代表的な議論・論争の流れ。「制作へ」は、宮川がかつておこなった議論を、ウィラースレフを始めとする様々なテクストと繋げていくことで、具体的かつ日常的な〈制作〉の営みをめぐる新たな理論へと組み換えたのでした。それは、作家論かその否定か、人間か事物か、相関主義か非相関主義か、といったような二元論を超えるものとしてあります。
②抒情詩や自叙伝をめぐる諸議論。言語とは、認知の根底にある〈摸写(ミメーシス)的鏡像構造〉を根幹に持つ素材=メディウムであり、それによって構築されたテクストは、おのずと避けがたく〈非人称的空間〉=〈制作的空間〉を立ち上げ、私の群れによってなされる共同制作を起動させる。〈喩〉の力でもって、おのれの内部に見知らぬものの声を聞き、おのれの外部におのれの魂を見る営みとしての、言語表現。このようなパースペクティブを設けることで、まさに「制作へ」で語られていた〈制作〉論の延長線上に、多くの詩歌・散文の実践を置くことが可能になります。
③荒川修作とデュシャンをめぐる諸議論。デュシャンの仕事を身体や共同制作に関わるものとして組み換え拡張した荒川の仕事は、宮川による議論の源泉のひとつであると同時に、〈第四の次元〉や〈アンフラマンス〉をめぐる思考を身体や共同制作の問題として展開した「制作へ」での〈制作〉論に並行したものとしてあります。そしてその先には、荒川がその建築によって具体化したような、外化された〈魂の内的構造〉が生じさせる〈距離〉から編まれた、《「私は私でなく、私でなくもない」》ものらの制作的共同体があるでしょう。そこに向けて、過去の蓄積と最新の技術、なによりこの私の身体を、日常的に、徹底して酷使していくことが、今後も様々な分野において求められるのではないでしょうか。
さて、最後に、現代日本の詩とのつながりについて補足しておきます。いわば、詩における〈制作〉論の具体的展開として、貞久秀紀による詩を参照したい。
きょう、やぶ道をきてひとつの所に立ち
それがこの岩であるときはみえずにいる雲が
おなじ岩の台座から
きのうの曇りぞらにとりわけ陰がちにかたまり
光につよくふちどられて
山の真上のかぎりあるちぎれ雲のすがたにまで
高められ親しくながめられたことは
その日そこに湧きいでたただひとつのことがらとして
指折り数えることができる
貞久秀紀「例示」
この細道はいずれひとつの岩に当たり
岩がゆくてを塞ぎ
かたわらに迫る崖からゆるみでて
道に来ていた
それは近づくにつれはじめて目にうつり
すぐさまそれが前方に横たわる岩であることを
知らせるとともに
今しがた来たことの証しに土をつけているかのように
埋もれていたところに湿った土や
樹木の細く白い根が絡みついていたある日ひとりの口のきけない友が食卓について
食事をしていたとき
わたしがこの友といて食事をしていたように
このときもわたしはひとつの岩に近づき
そこからのぞむことのできる
岩のおおまかな姿をながめていたが
そのころ
わたしはこのうごかずに目の前にある岩にうでをのばし
土や根や
岩の外であるところから自然とそれに触れた
貞久秀紀「この岩を記念して」
ふり返り
想い起こすものが
草がちな
ゆく道なかにはじめから
鳥のすがたでいた
ふたつ手をあわせたお椀にすくいあげれば
まだ羽のある
白灰の身がらをもつ小鳥が
ふたたび手をのばすことができたならはじめてこの鳥にゆきあたり
あたたかく触れうるものとして横たわり
ひとりのわたしが近づいていた
貞久秀紀「ゆく道なか」
貞久の詩作品は、いくつもの相容れない私を投入し行き交わせることを身体に強いる一種の〈指示書〉としてあります。内容としては、散歩している私が遭遇した何気ない風景や出来事をめぐるものが(特に最近の作品には)多いのですが、読み進めていくと、私の自己同一性が、私の外まで拡張されていくような感覚が生じはじめる。細かくは分析しませんが※46、そこでは一行ごとに表現主体をめぐる情報が切断され、並置されることで、いくつもの私の遍在と、それらのあいだでの〈距離〉を含んだミメーシス的ネットワークが形成されています。しかもそれが、リズムなどを強く意識した言葉などではなく、非常に明晰な —— 一見するとあまりにありふれた —— 言葉らの、配置関係によって生じさせられていることが重要です。読み手は、このテクストを読むためには、一行ごとに、自らの同一性を分解し、岩や小鳥、雲、かつての私などにまで《「私は私でなく、私でなくもない」》関係を波及させながら、新たな身体を構築していかなければならない。そのような動きがこの詩にあるというよりは、この詩が自らに接する身体に対して、そうした動きを強いる、そんな〈指示書〉としてあるのです。
私らは、詩を携えて散歩する。詩のなかに埋め込まれた様々な運動、それを起動させるところの技術が、私の身体を通じて、散歩道を、ミメーシス的・アニミズム的関係を生じさせたりさせなかったりする〈非人称的空間〉=〈制作的空間〉の実験場へと変化させる。
言語表現は、あくまで数多くある〈制作〉のなかのささやかな1つでしかありません。しかし同時にそれは、〈非人称的空間〉=〈制作的空間〉をめぐる試行錯誤が凝縮した形で展開されてきた場所でもあります。そこでの蓄積を用いること、自らによっても実践することは、その他の様々な表現形式に、さらには〈制作〉を基盤とする生の構築に、手がかりと手段を与えるでしょう。「制作へ」は、そのようなかたちで言語表現を酷使することの、出発点に —— あるいは「別の土台」=〈プロトタイプ〉※47に? —— なりうるテクストだと思います。
ブラックマウンテンカレッジのことを書いてみようと思い立ったのは、縁あってジョセフ・アルバースの“Interaction of Color”の監訳作業※1をしていた2016年春のことだ。それから2年たった今、ようやく手をつけることができた。
ブラックマウンテンカレッジ(以下、BMC)は、1933年から1957年の25年間、アメリカ東南部ノースキャロライナ州ブラックマウンテンにあったリベラルアーツスクールだ。芸術教育が目立ったがためにアートスクールと思われていることが多いが、それは大いなる誤解である。
BMCの芸術教育を先導したのはジョセフ・アルバース※2で、バックミンスター・フラー※3がドーム建築を試み、ジョン・ケージ※4が最初のイベント「シアター・ピース#1」を実行し、マース・カニンガム※5が舞踏団を結成、そして後期にはチャールズ・オルソン※6の下、ブラックマウンテン派と呼ばれる詩人たちが生まれた。教員には前述のほかにデ・クーニング※7やアニ・アルバース※8、学生にはロバート・ラウシェンバーグ※9らがいた。
このように人物名を列挙したところで、何の意味もないだろう。ここで伝えたいのは、BMCが戦後アメリカの美術や文学に多大な影響を与え、それに連なるいくつものムーブメント、ひいては現代のインターネット文化にも通じる思想的バックグラウンドを形成した学校だったということだ。学校というよりコミューンとよぶ方がふさわしいのかもしれない。アパラチア山脈の麓で、学生と教員家族が共同生活を営みながら、新しい教養教育の実験に取り組んでいたのだから。
1933年
1933年製のライカを手に入れた。II型をIII型に改造したものだ。ライカはご存じのとおりドイツのカメラメーカーである。35mmのムービー用フィルムを使うことで、コンパクトで携帯可能なカメラを実現したことで知られる。これによってスナップ写真という分野が生まれ、報道写真にも大きな影響を与えた。いや、ライカの話をしようというのではない。1933年のことを話したいのだ。
デザインにおけるモダニズムの発祥をいつと仮定すればいいだろうか。モダンデザイン論の古典となった、ニコラス・ペヴスナーの『モダン・デザインの展開』※10から引けば、19世紀末のウィリアム・モリス※11の活動とアーツ&クラフツ運動(以下、A&C)あたりということになる。彼らが重んじたマイスターとその弟子で構成される中世ギルドの制作スタイルは、ブティック型のデザインオフィスとして20世紀を通じて継承された。また、彼らに大きな影響を与えた思想家ジョン・ラスキン※12の存在も考慮に入れれば、ひとつの有力な手がかりになることは間違いないだろう。
しかし、モリスもA&Cも造形的にはゴシックリバイバルであり、われわれが知っている清潔でシンプルなモダンスタイルからは遠い。それはA&Cの影響下に生まれたドイツ工作連盟も同じだ。連盟展に出品されたものを観るかぎり、多くはアールヌーボー様式の製品にすぎない。ドイツ工作連盟といえば名前の挙がるペーター・ベーレンス※13だけが特例だったとも思える。かのバウハウスも、ワイマール校舎のころは表現主義的な審美性が色濃い。
往々にして、かたちというものは突然変異的に生まれることがある。また一方で、美術やデザインの歴史をひもとけば、そのかたちを準備した思想や社会の動向をそこに見つけることができるのも事実だ。
突然現われたかにみえるシンプル・イズ・ベストなモダニズム造形も例外ではない。その発祥は、19世紀中葉のヨーロッパに興った社会主義運動を起点とすることもできるし、イギリスの工業化社会を背景としたデザイン教育の整備にまでさかのぼってもいい。あるいは、市民革命が勃発し第一次産業革命がはじまった18世紀を起点としてもいいだろう。だいたいそのあたりから、市民という新階層による美意識の形成=モダニズムへの準備が始まっており、それは20世紀初頭に具体的なかたちとして現われてくる。モダンデザインのはじまりは、そのような流れを大まかに捉えていればこと足りる。
いずれにせよ、そのスタート時はまだ美術と未分化で、キュビズムなどの新潮流や、第一次大戦後のヨーロッパを彩った数々のアヴァンギャルド運動とも密接な関係を持っている。
美術からの離脱は1950年代まで待たねばならないのだが、20世紀前半のモダニズムが魅力的に見えるのは、その分岐点にあるからなのだろう。
で、1933年である。
1933年は、ぼくたちデザイナーにはバウハウスが解散した年として記憶されているが、世界史的なトピックはナチス政権の誕生だろう。1932年のドイツ国会選挙において国家社会主義ドイツ労働者党が第一党となり、翌年1月にヒトラーが首相に任命された。
バウハウスはデッサウ校時代の校長であるハンネス・マイヤー※14が共産主義を掲げていたこともあって、右翼勢力からは敵対視される存在だった。マイヤー退陣後、校舎をベルリンに移して政治色の払拭に努めていたものの、政権を取ったナチスから教育方針の変更を求められる。しかし新校長のミース・ファン・デル・ローエ※15はそれを拒否。閉校させられる前に自ら解散を決めた。
以後、そのローエはじめ、ハーバード大学に着任した初代校長のヴァルター・グロピウス※16や、シカゴにニュー・バウハウスを設立したモホリ=ナジ※17ら、多くのバウハウスの教員たちがドイツを離れアメリカに赴いた。それは、国を追われたドイツのデザイナーたちがアメリカに活躍の場をみつけ、それぞれに偉大な足跡を残したというような単純なサクセスストーリーではない。イギリスの初期モダニズムからはじまり、A&C、ドイツ工作連盟、ウィーン分離派、アールヌーボー、ドイツ表現主義、デ・ステイル、ロシア構成主義など、美術、建築、工芸、デザイン、さらに写真や映像といった最新のテクノロジーをも巻き込んで渾然一体となったヨーロッパのモダニズム運動の濁流が、政治的圧力によって決壊したバウハウスという水門から一気にアメリカに流れ込んだことを意味する。そのなかで真っ先に流れ着いたのが、1933年にBMCへ招聘されたジョセフ・アルバースであった。
アルバースは妻アニと共に未知のブラックマウンテンに赴き、戦後現代美術に大きな影響を与えた。またデザイン分野でも、現在の情報文化に繋がるオルタナティヴデザイン思想に先鞭をつけた。先述の「突然変異」を生む触媒的役割を果たしたのである。バウハウスがモダニズムの出口であるならば、BMCはモダニズムの次への入口といってもよい。1933年は、BMC開学の年としても記憶されなければならない。
アッシュビルへ
ここまでは長い前置きとも読めるが、実はぼくの興味の在りどころをあらかじめ書いた、本稿の核となるところの一部分でもある。
現在の自由主義社会は、ヨーロッパ文明の文脈のなかにある。ぼくが生業とするデザイン分野も同じで、その隣接分野であるアートもまた然りである。明治の開国以降、日本もヨーロッパ文脈に組み込まれてきた。積極的に組み込まれることを望んだと言っていいだろう。そして、第二次世界大戦での敗戦以降、それはユーラシア大陸を横断してやって来るのではなく、大西洋と太平洋、二つの大海を渡り、アメリカ合衆国経由でやって来るようになった。
先にも述べたように、その最初期の入口のひとつがBMCなのだ。だから、BMCを知ることは、ぼくたちが享受してきた戦後アメリカ文化についてふたたび考察するためのとば口になると考えた。それは、現在、世界的な課題となっている「国家」や「移民」、あるいは「分断」の問題にも繋がっている。BMCを彩ったアルバースをはじめとする大勢のアーティストや詩人たちが、BMCという場で何と出会い、どういう関係を育んだのか —— そこには、今私たちが探しているコミュニティの在り方へのヒントがあるのではないか。
ここで話は前項の冒頭に戻る。1933年製のライカである。
BMCでアルバースがカメラを持っている写真がある。フラーやデ・クーニングと一緒に写っているよく知られた写真だ。アルバースはふたりから少し離れて、カメラに目をやりながら歩いている。カメラそのものは手の陰に隠れてよく見えないが、ライカI型かスタンダード型とおぼしき軍艦部が覗いている。アルバースの写真好きはよく知られており、2016年にニューヨーク近代美術館(以下、MoMA)でバウハウス時代の写真の展覧会※18も催されている。
 [図1]中央左がフラー、右がデ・クーニング。右後方にいるのがアルバース。※19
[図1]中央左がフラー、右がデ・クーニング。右後方にいるのがアルバース。※19
1933年11月に、アルバース夫妻は大西洋を渡っている。もし、アルバースが祖国ドイツを離れるときに新しいカメラを求めたとすれば、やはりそれはライカに違いない —— そう思って1933年製を探していたのである。レンズも同年製のものを首尾良く手に入れることができた。さすがにフィルムは当時のものを用意できないが、同じ時代のカメラで撮ってみたかったのだ。そうしたところで何がわかるわけでもないが、過去へのフィールドワークとはそういうことなのだと思う。
BMCについて日本で手に入る本はだいたい集めていた。貴重な資料もわずかだがあるにはあった。まずはそれらを読み込んで書いてみようと思ったのだが、どうにも筆が進まない。
ネットであれこれ調べていると、8月4日までアッシュビルのBMCミュージアムで「Shared History」という展示をしていることを知った。しかも、今年(2018年)はミュージアムの25周年だという。展覧会タイトルからこれは行くしかないと思い、すぐにJALに電話して行き方を相談した。シカゴでトランジットして国内線でシャーロットへ。そのまま航空券を予約した。
BMC物語の始まり
ここでBMC設立の話を少し書いておきたい。BMCは1933年に古典教授のジョン・アンドリュー・ライス※20によって開設された教養教育のための学校である。「カレッジ」とあるので「大学」と思われているむきもあるが、英単語の“college”には団体や集団といった意味もあり、実態はそちらに近い。“Black Mountain College(Images of America叢書)”※21に設立の経緯があるので抜粋してみよう。
ジョン・アンドリュー・ライスは、ロリンズ大学を解雇されたのち、1933年にブラックマウンテン村のはずれにあるブルーリッジの地で、21名の学生(うち12名はライスら教員のあとを追ってきたロリンズの学生)を率いてブラックマウンテンカレッジを開設した。彼は芸術分野および、すべての学生の心身を支えるカリキュラムをつくった。その教育哲学は今日まで受け継がれ、大学や地域社会の文化のなかに生きている。(中略)ライスがブラックマウンテンカレッジの最初の主任教授であると思われているが、化学の教授であるフレデリック・ジョージアが最初1年間の主任を務め、すみやかにライスに引き継いだ。(p.11)
ライスは「Classics(古典)」を専門とするアカデミシャンで、名著への過度な依存や暗記など従来の高等教育批判を展開するリベラルアーツ教育の論客でもあった。彼の授業は知識の伝授に留まらない、ディスカッションを中心とした感覚的で知的なものだったという。しかし、その教育思想を知った上で彼を迎え入れたはずのフロリダ州ロリンズ大学でも学長のハミルトン・ホルトと意見が対立し、退職を余儀なくされた。アメリカ大学教員協会とも争うような攻撃的な性格だったライスだが、そのカリスマ性は誰もが認めるところでもあり、この騒動でも数名の教員と学生が彼と行動を共にし大学を去った。
その夏、ライスの元学生や同僚の多くは、ライスが頻繁に話していた教育理論を実践できる新しい実験的な学校を開設するように勧めていた。最終的に彼は決意したのだが、それを運営するためのスペースと資金を急いで見つけなければならなかった。(p.7)
ブルーリッジを選んだのは、アッシュビルで教鞭を執っていた元ロリンズ大学教授らの提案があったからと同書に書かれている。アパラチア山脈の麓、ブラックマウンテンの南に位置するその土地は、山脈が連なる美しい風景で知られ、ブルーリッジ協議会の施設であるクリスチャン・カンファレンスセンター(以下、YMCA)※22があった。
夏の集会場として使用されていたので、それ以外の季節は空いている。9月からの開校はお互いに好都合だ。かくしてBMCはその場所から始まることになる。
 [図2]BMC開学時の最初の教員10人。前列一番右がライス。※23
[図2]BMC開学時の最初の教員10人。前列一番右がライス。※23
YMCAを借りることができた背景には、1929年に始まった世界大恐慌がある。この史上最大の金融パニックは、同年の夏から秋にかけてウォール街で株の大暴落が続いたことで世界経済を巻き込み、自律的に再建不能な状態に陥れた。特にアッシュビルはその打撃を大きく受け、街にあった六つの銀行すべてが破綻した。また、同時期に機械化による農業恐慌も始まっており、有数のタバコ生産地であるノースキャロライナでも厳しい状態が続いていた。映画にもなったコールドウェルの小説『タバコ・ロード』※24が当時の悲惨さを伝えている。舞台となったジョージアは隣の州である。
ブルーリッジ協議会もそれらの影響から逃れることはできず、経営が大変困難な状態にあった。そのため、冬の間だけ建物を貸すという条件はとても魅力的なものだったのだ。しかし、ライスたちにもお金があるわけではない。
明確な運用計画もなく、伝統的な資金源(訳註:銀行や投資家)からの資金調達は難しかった。しかし最後の最後で、彼は裕福な元ロリンズの教員、マック・フォーブスの家族から1万ドルの寄付を受けることができた。フォーブス家は、長年にわたってカレッジに惜しみないサポートを続けた。(p.7)
こうして1933年8月に、契約が無事に取り交わされ、学校設立は現実のものとなった。9月の開校まで1ヶ月を残すだけ、まさに首の皮一枚のときに幸運が舞い降りてきたのだ。ブルーリッジのYMCAについてライスはこう語っている。
ここは平和だった。ほどほどの賃料にもかかわらず、冬の寒さをしのぐ毛布、シート、お皿や食器があり、十数の講義のための充分なセントラルヒーティングがあった。(p.14)
大不況下に失職したライスら教員と学生にとって、厳しい冬を越えられることは何にも代えがたいことだったのだろう。開校が決まった喜び以上に、その安堵の気持ちが伝わってくる。
一方で、教育への意欲も衰えてはいなかった。ライスは、あらゆる分野の学習には芸術的経験が重要だと考えており、その教育を実践できる美術教師を探し求めていた。そこで、解散したばかりのバウハウス教員だったジョセフ・アルバースに白羽の矢が立つ。
BMCの実験的教育のなかで最も革新的で重要かつ忘れてはならないことは、カリキュラムの中心に芸術を位置づけるという方針である。学生は演劇、音楽、絵画、詩の講義を受けることを奨励された。しかし、芸術を中心に据えるためには、芸術の教員を見つけなければならない。ライスはいくつかの提言を聞いたのち、バウハウスを閉鎖して渡米を希望しているドイツ人夫婦のことを耳にした。
彼は、行く末を見通せないまま、画家であるジョセフ・アルバースと染織家である妻のアニを雇うことに決めた。アルバース夫妻は1933年の感謝祭の直前にブラックマウンテンに到着し、その後10年間、カレッジにおける芸術教育の原動力となった。その間、たくさんの亡命したアーティストたちがBMCを避難所として、学校そのものをかたちづくっていった。(p.7-8)
ライスにアルバース夫妻の招聘を薦めたのは、当時MoMAのキュレーターを務めていた建築家のフィリップ・ジョンソン※25である。ライスがどのように芸術をカリキュラムに組み込むかについて考えあぐね、慈善家で美術界のパトロンでもあったエドワード・ワーバーグ※26に相談に行ったときのことだった。※27
ジョンソンは、1932年にMoMAで「モダン・アーキテクチャー展」※28を開催し、建築領域にインターナショナル・スタイルを定着させた人物である。その展覧会を機に、バウハウス学長だった建築家のローエやマルセル・ブロイヤー※29のドイツ亡命の手助けをしていた。ジョンソンはベルリンでアルバース夫妻にも会っていたが、アルバースが英語をひと言も話せないため、受け入れ先を探せずにいたのだ。ライスには無理を承知で話してみたのだろう。しかし彼の決断は早かった。「英語ができないことは問題ではない。ブラックマウンテンにはドイツ語を話す人も住んでいるだろう。」ライスはすぐに電報を打った。
残された書類から、その後、大変な手間がかかったことがわかる。入国手続きなどの労を惜しまず手を尽くした結果、10月に割当移民ビザが発行され、アルバース夫妻は無事11月に着任する。それは、地方紙「Asheville Citizen-Times(1933年12月5日号)」で報じられるような、それなりに大きなできごとであった。
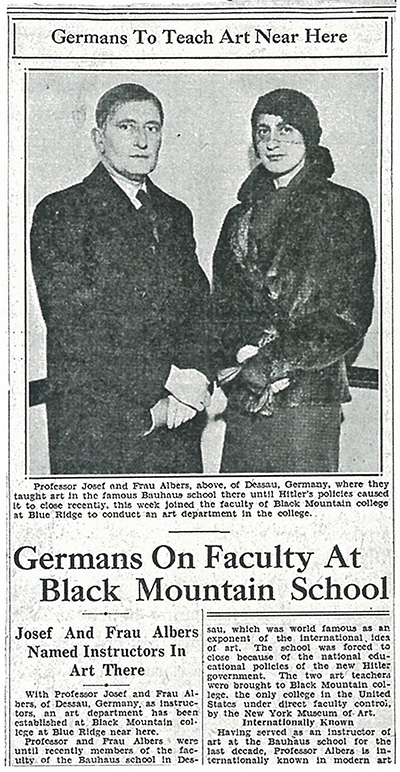 [図3]「Asheville Citizen-Times」の記事※30
[図3]「Asheville Citizen-Times」の記事※30
時代の転換とはまさにこういうことなのかもしれない。ライスが決断したアルバース夫妻の招聘によって、ヨーロッパ・モダンデザインの水脈がBMCに流入し、リベラルアーツのさらに基礎となる教養としてさまざまな芸術的実験が行なわれることになる。
BMCの活動は一気に活発になった。ライスの直感が的中したのだ。そこから一種のアートコミュニティが生まれるまで、さほど時間はかからなかった。
ここまでがBMC物語の第一幕である。それからのことについては、今後少しずつ明らかにしていくが、そろそろ航空券を手に入れたところに話を戻したい。
LOVE ASHEVILLE GO LOCAL
7月31日に成田から飛び立つフライトだったのだが、アッシュビルの天気予報を見ると、滞在予定日だけではなく毎日が雨である。まさかと思ったが、とりあえずレインコートをカバンに詰めた。
飛行機の遅れによるトランジットミスやその振替便の欠航など、さまざまなトラブルに見舞われながらも、シャーロットに着いたのが20時ごろ。予定より4時間遅れだった。それからおおよそ2時間の雨のドライブを経て、アッシュビルのモーテルにチェックインしたときには22時30分を回っていた。東京ではなんということもない時間だが、東南部の田舎町では食事をするところもない。自動販売機にあったナッツをかじって、その日は眠りについた。
翌朝、やはり雨は続いていた。レインコートを着て外に出る。せき立てられるようにしてアッシュビルまでやって来たものの、なんの情報も持っていない。とりあえずBMCミュージアムに行けば、展示も観られるし情報もあるだろうと思って街へ出た。
ミュージアムと言っても、展示室がひとつしかない小さな施設だ。そこでは、事前に調べたとおり「Shared History」展が開催されており、地元の小学生がレクチャーを受けていた。地域の文化を大切に継承することは素晴らしいが、BMCを子どもたちに説明するのはさぞ骨が折れるだろうと思いながら、彼らが去るのを待って展示を観た。
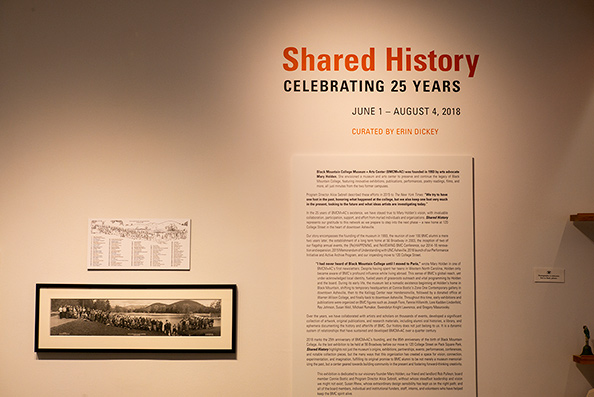
 [図4・図5]展示風景
[図4・図5]展示風景
展示の量そのものは多くなく、丹念に観たところでさほど時間はかからない。このあとどうしようかと考えていたら、展示室の奥に、たくさんの資料と一緒にキュレーターとおぼしき女性が仕事をしているのが見えた。そこで、BMC初期のYMCA校舎やその後のエデン湖校舎を見ることができるか、彼女に尋ねることにした。まずは現場を訪ねたかったこともあるが、机の前の壁に描かれていた大きなエデン湖校舎の図面に目が止まったのだ。BMCで教鞭もとった建築家のローレンス・コーチャー※31が、教員と学生がDIYでつくれるようにと設計した4翼の校舎の図面である。
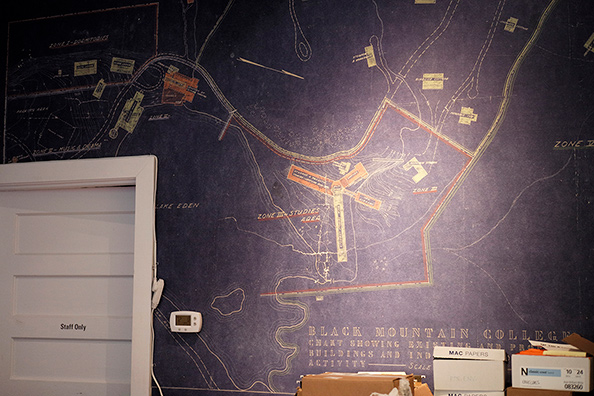 [図6]オフィスの壁全面に描かれているエデン湖校舎の図面
[図6]オフィスの壁全面に描かれているエデン湖校舎の図面
今では子どもたちのサマーキャンプ地になっているらしく、「エデン湖はキャンプ中だからダメね。YMCAなら見れるわよ。」と言って、その所在地をメモして渡してくれた。そして、「BMCについて知りたいのなら、アーカイヴズオフィス(以下、NCアーカイヴズ)※32に行った方がいい。BMCの研究者もいるから。今日行ける?」と言って、すぐに電話を取って連絡してくれた。「BMCの何について知りたいの?」と聞かれ、あわてて「アルバース」と答える。14時から16時でアポイントを取ったからと、場所を教えてくれた。
アッシュビルは不思議な街である。何も知らずにやって来たが、あとで調べると人気の街で、2007年には全米で住みたい街の1位になっている※33。19世紀に鉄道ブームで栄え、東部のリゾート地として発展した。山間部なので木材や繊維の工場もたくさんあったが、先述の大恐慌で町は寂れ、そこから今日まで産業的な復興はなかった。しかし、それが結果として良い方に作用した。美しい大自然とともに1920年代のアールデコ建築が数多く残り、今では人びとが憧れる街になった。
観光は秋がシーズンで、紅葉に尽きるようだ。アルバースは、ブラックマウンテンほど紅葉の美しい土地はないと語っており、落ち葉の作品や、学生たちへの落ち葉を使った課題はよく知られている。
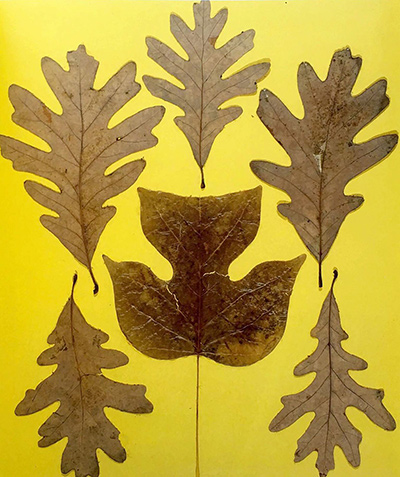 [図7]Josef Albers “Leaf Study IX” (1940)※34
[図7]Josef Albers “Leaf Study IX” (1940)※34
ダウンタウンは小さく、ほとんど歩いて移動できる。ブルーグラスミュージックの伝統だろうか、音楽、特にライブ演奏が盛んで、夜になると飲食店はもちろん、本屋や路上でもライブが始まる。年老いたヒッピー然とした人も多いが、ノースキャロライナ大学アッシュビル校など大学もいくつかあるため、若者の姿も目立つ。町を歩いていると出会う人のほとんどが白人で、黒人はモーテルのフロントマン以外見かけなかった。アジア系も滞在中たった一人とすれ違っただけである。アメリカは多民族国家で都市部でこういうことはまずないが、田舎町では案外普通のことなのかもしれない。
観光客向けなのか、街中のそこかしこに“LOVE”や“PEACE”の文字があり、多幸感にあふれている。その感じが懐かしくも不思議でならなかった。街のキャッチコピーは“LOVE ASHEVILLE GO LOCAL”である。
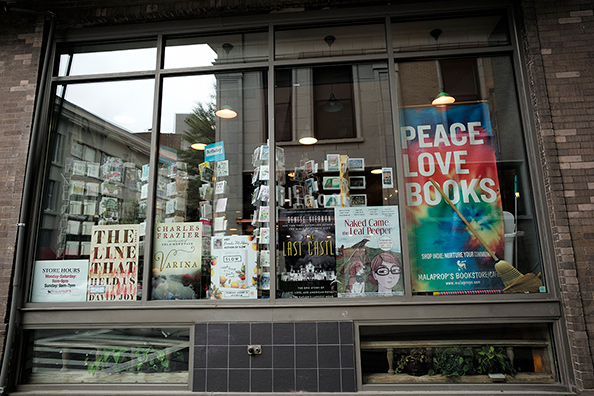 [図8]本屋に掲げられた“PEACE LOVE BOOKS”の文字
[図8]本屋に掲げられた“PEACE LOVE BOOKS”の文字
 [図9]町で見かけるフラッグ
[図9]町で見かけるフラッグ
アーカイヴを探る旅
道に迷い、NCアーカイヴズに着いたときには15時を回っていた。遅いから心配していたのよ、と快く迎え入れてくれたのは、アーキヴィストのヘザー・サウスだった。先に引用した“Black Mountain College(Images of America叢書)”の著者のひとりである。とにかく、出会う人みんなが人懐っこく親切だ。閲覧が16時までだったので、アーカイヴ室を見せてもらい、翌朝9時からの予約を入れてからYMCAに向かった。
 [図10]NCアーカイヴズのある建物
[図10]NCアーカイヴズのある建物
YMCAは想像していたよりも広く、立派な建物が並んでいた。入っていいのかどうかもわからなかったので、まずはフロントでBMCについて尋ねることにした。80年前のBMCのことがフロントでわかるのだろうか、という心配は取り越し苦労であった。フロントにいた女性は、案内マップを拡げ校舎として使われていたロバート・E・リーホール(現・EUREKAホール)の場所を示し、その左の建物も使っていたらしいがよくわからない、と言って印をつけてくれた。
 [図11]広い敷地の中央に位置するリーホール
[図11]広い敷地の中央に位置するリーホール
 [図12]リーホール正面。BMC最初の校舎兼宿舎。今もロッキングチェアで学生がくつろぐ
[図12]リーホール正面。BMC最初の校舎兼宿舎。今もロッキングチェアで学生がくつろぐ
 [図13]授業に使用していたと思われる別棟
[図13]授業に使用していたと思われる別棟
リーホールで学生と教員家族が一緒に暮らしていたことは、本を読んで知っていた。なんとなくYMCA全体を学校として使っていたと思っていたのだが、どうもそうではないらしい。リーホールに向かうと、写真で見覚えのある広いデッキといくつものロッキングチェアがあり、そこにくつろぐ学生たちがいた。80年前の写真と変わらぬ光景に少し驚く。
中に入ってみた。まず大きな柱が並ぶ講堂があり、真ん中に暖炉、左右に教室に向かう通路がある。教室に入ってみると、正面に黒板があり窓からは木々の緑がみえる。黒板は補強してあるが、当時そのままなのではないかと思えるような年季の入ったものだった。木々は育っていても、景色に大きな違いはないだろう。なるほど、ここがスタートだったのだ。

 [図14・図15]講堂と教室。写真ではきれいに見えるが、おおむね当時のままだと思える
[図14・図15]講堂と教室。写真ではきれいに見えるが、おおむね当時のままだと思える
持って帰ったYMCAのパンフレットには、こう紹介されていた。
1933年、フロリダ州ウィンターパークにあるロリンズ大学の学生と教師のグループが、自分たちの学校を開校することに決めた。 ジョン・ライスほか10人の教員と22人の学生がブルーリッジを訪れた。彼らはブルーリッジと恋におち、ブラックマウンテンカレッジが生まれた。この冒険的な学校は、芸術、教育、そして生き方を教える先駆者として高い評価を得た。この学校には諮問委員を務めたアルバート・アインシュタインやジョン・デューイーら、著名な人びとがたくさん訪れた。“EUREKA! A Century of YMCA Blue Ridge Assembly” p.12
翌日9時、NCアーカイヴズを再訪し、資料の閲覧をはじめた。用意してくれていたアルバース夫妻の資料を端から見ていく。渡米の際の書簡を見ると決してイメージするような「亡命」ではなく、むしろVIP扱いで招聘されていたことがわかる。きっとグロピウスやナギら、渡米したほかのバウハウスの教員たちも事情は同じであろう。
大量の写真から、アルバースの人となりが見えてくる。指導に熱心な良い教師だったのだろう。学生がとったノートからもそれはうかがえた。
アニの資料として残る織物の切れ端は、学生の習作か、それともアニ自身が織ったお手本だろうか。指導用のメモには几帳面に織り方が記されていた。
 [図16]NCアーカイヴズ閲覧室
[図16]NCアーカイヴズ閲覧室
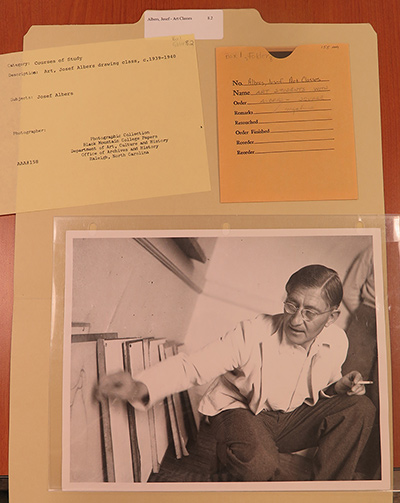 [図17]アルバースのアートクラスの様子。写真の時代を示すようにBMCの写真は数多く残っている
[図17]アルバースのアートクラスの様子。写真の時代を示すようにBMCの写真は数多く残っている
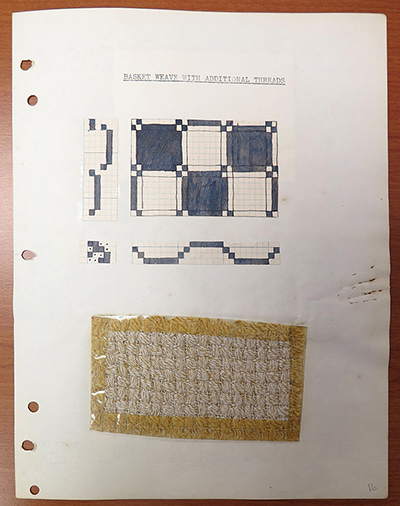 [図18]アニ・アルバースの織り見本とその織り方を示した図
[図18]アニ・アルバースの織り見本とその織り方を示した図
続けて出してもらったフラーの資料のなかには、BMCでの生活がわかるような貴重なインタビューもあった。許可が取れれば、次回以降の記事のなかで紹介したい。ほかにもBMCに在籍した全教員のリストなど得がたい資料も手に入れたが、目を通すことができたのはまだ全体の1割にも満たない。これから何度も足を運ばねばならないだろう。
アルバースの“Interaction of Color”を監訳したこと、BMCのことをまとめて本にしたいことなどを伝えると、快く協力を約束してくれた。
アッシュビル滞在中は予報のとおりずっと雨だった。1933年製のライカで撮る機会もあまりなかった。レインコートが大活躍した夏の雨期も終わり、美しい紅葉の季節がもう始まっているはずである。そろそろまた旅に出かけようかと思っている。
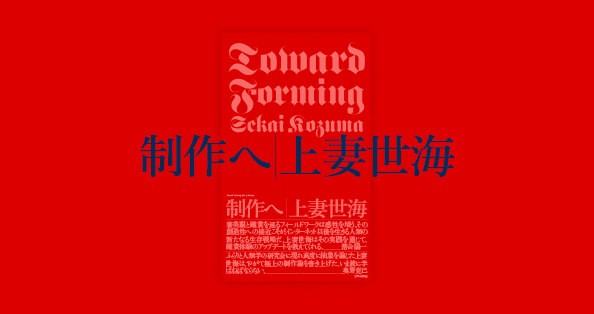
——— 『制作へ』に収められた上妻世海の「制作論」には、以前から実存主義的な意味合いを感じていました。批評や美術史の文脈として成立してるんだけど、クローズドサーキットのなかで自己言及するようなものではなくて、むしろクローズドサーキットな構造に組み込まれていない人間の方を魅惑してる。だから、その魅惑がどう発生しているのかを明確にしていきたいと思っています。
その手始めとして、まずこの「制作論」が誰にどうインパクトを与えるのかというところから考えてみたいと思います。エリー・デューリングがプロトタイプ論で「なぜ作品にする必要があるんだ」と言ってたように、「なぜ上妻世海は制作論という形で書かなきゃいけないのか」ということを。
補足すると、この「制作論」はクローズドサーキットのなかで「批評を活性化するための論」ではなく、「クリエイティビティにコラボレートしていく機能を持つ論」だと考えているんです。むしろ批評的に読み解こうとしない人にこそ、ある種の作品として乱反射していく効果がある。実際に批評家やアカデミシャンではなく、クリエイターの人たちの方がはっきりと反応しているのがおもしろいところなんですよ。
西田幾多郎が「自己のなかで自己を観る」って言うじゃないですか。外で見ようとした瞬間に他者になってしまうので、モノを見るときには「内で観る」と。清水高志さんなんかは、「内で観る」ときには袋詰め的に役割が転換して、あるときは主体あるときは対象と二項がどんどん入れ替わりながら機会原因的に時空間を形成して、西田の「永遠の今」って話につながっていくと言ってる。西田幾多郎は、鈴木大拙との関わりもありつつ、禅の実践のなかで自分の感じた時空を言葉にしながら、こういうところにたどり着いているんだと思うんですね。「一の多」と「多の一」って問題から未来を考えて、相互否定的な領域としてとらえることで「永遠の今」になる。
ジャコメッティが絵を描いたり彫刻を作ったりするために、女性のモデルを目の前に立たせてポーズを取らせたときのエピソードなんですが、彼がずっと見てるだけなので、モデルの人がたまりかねて「アルベルト、なぜ貴方はそんなに私を見続けるの?」と言うんです。それに対してジャコメッティは、「なぜなら僕はまだ君のことを見ていないからさ」って答えるんですけど、実はポージングさせてからすでに6時間が経ってるんですって。これもさっきと同じ話で、「内で観る」ことができないと本当に見たことにならないって感覚があるわけですよ。
僕は修行のような実践をしてるわけじゃなくて、西田幾多郎や折口信夫といった人たちの言葉に導かれて、こういうところにたどり着いてるじゃないですか。だから、実践によって伝承してきたけど、今は失われてしまった日本人像みたいなものに乗っちゃうと、間違ってしまうとわかってるんです。むしろジャコメッティの悩みに近いわけですよ。なぜ内で観れないんだって悩み。これを解決する理論が必要だと思っています。
批評的で消費的なカルチャーの問題点は、主体っていうものを固定化した状況で、外側にある対象をどんどん新しいものにしたりヴィンテージにしたり、横滑りにモデルチェンジをしていくところです。欲望のサーキットにいろんなものが出てきて、「いいよね」「楽しいよね」「でもこれは面白くないよね」とか言って。僕の問題意識は、外側にあるものを内側から「観る」っていうことをどうやって成立させるかということ。「消費から制作へ」と言っているのは、こういった欲望のサーキットはもうやめましょうという話です。
これはおそらく時代的な背景もあります。僕たちの世代には色んなものが揃ってる。漫画ならWebでたくさん読めるし、月にいくらか出せば映画も見放題だし、音楽もYouTubeで聴き放題。新しいものもどんどん出てくるし、過去のマニアックなのも全部ある。昔のリッチ層がお金を使ってやっていたのと同じくらいのことを、かなり低価格で体験できる環境にいる。そういう状況で消費のサーキットを回していくって、最初から虚しさがあるわけですよ。だから、もうこっちのロジックに行ってもしょうがないと思っています。
つまり、ジャコメッティの悩みみたいな「観る」ってことと真剣に向き合ったとき、それは外側から見ることじゃないってところにしか行き着かない。どう考えても、内在=超越っていう帰結になってしまう。時代の潮流としても、次は制作的ロジックに行かざるをえないと思ってるわけです。
宮川淳が『鏡・空間・イマージュ』のなかで、個人の時代に代わるものは集団の時代ではなく非人称の時代だと言っています。鏡に反射されるイマージュと、鏡の外の持つ暗さみたいな比喩がありますよね。ラカン的な意味で、鏡の反射による同一性のレベルで留まっていたら、それはイマージュによるイマージュでしかないのだと。つまり、宮川淳が言ってる非人称の時代というのは、反射の世界から鏡の暗さの底に行くことで、非人称の私が現れるという話なんです。
日本語のなかには、非人称でしか使われないものが結構ありますよね。木村敏と坂部恵が共同編集してるシリーズなんかでも、日本語圏には「気」とか「情」とか、いわゆる中動態的な文法がたくさん残ってる。つまり、まだこの頃には「レンマ」的な観点があったんだと思うんです。
それで、ここの橋渡し役をやっていたのが、アヴァンギャルドの人たちなんだと思います。相関主義のど真ん中にいたヨーロッパの人たちが、 制作していくっていうプロセスのなかで、一点透視図法みたいな秩序立って整理された空間認識の間違いや不誠実さに気づいて、そうではない空間や時間のあり方を探求していった。
今、相関的なものに対して批評的なロジックが受け入れられやすいのは、最初から相関的としか思えない世界で生きてるからだと思うんです。だって、僕たちは身体的にさっきのクローズドサーキットにいるわけなので。ある種のイニシエーションを経由していないから、消費カルチャーしか持つことができない。
だけど、さっき挙げたような日本の哲学者たちは、また違う身体を作ってきた。これはかつてのアヴァンギャルドやサイケデリックの人たちがやってきたことにも近い。クローズドサーキットじゃないところにどうやって行くのかということに向き合ってきた。でも、それを言葉にしようとすると、消費カルチャーのアイテムになってしまう。じゃあどうすればいいか。それはもうイニシエーション的にウィリアム・ジェイムズが言う「二度生まれ」をしなきゃいけないわけです。つまり、消費的な肉体から、制作的な身体へ変化しないといけない。そのためには啓蒙ではなく誘惑が必要になってくる。
啓蒙というのは、教育システムのようなものを前提にしています。「カントを読んだら、次はヘーゲルを読みなさい」と、正しい道筋がすでに定まっていて、それをたどっていくことである種の市民的なマインドを獲得できるという話で。もし近代的な社会が成立している場所なら、これは何の問題もないと思うんです。だけど、もう僕たちはそういう世界に生きていない。だから、それぞれがさまざまなルートで、自ら身体を制作しないといけないんです。消費的な空間にいなければ、制作へと誘惑されるんですよ。誘惑された人たちは、それぞれ作り始めなきゃいけなくなる。だから誘惑する。
さっき話してもらったように、いい消費物を探して批評する人たちよりも、すでに音楽とかアートとかやってる人たちが僕に興味を持つのはその通りなんですね。でも、これは第一段階という気がしています。なぜなら、そういう人たちは初めからこっちに向かっていたわけじゃないですか。自分で身体を作りつつあった人たちだから、自分が感じていたことを言語化してて、おもしろいと反応してくれる。それで何か一緒にやりたいと思ってもらえる。
この第二段階として、消費に飽き飽きしているけど、まだこっちに来れていない人をどうやって誘惑していくかという問題があります。だけど、どうすればいいのか僕自身にもまだわからない。というか、これは誰もわからないんですよ。昔みたいに、自立的で市民的な主体を育てるといった確固たる目的があるわけではなく、特異な身体性を形成するという終わりなきプロセスに入っていく話なので、あとはそれぞれやるしかありません。
——— そういった「潜在的なクリエイター」は、たぶんもう消費カルチャーに飽き飽きしていて、「この生、つまんなくない?」「退屈だ、生き難い」と思ってる。だけど、今は新しい消費物しか用意されてない。だから、この「つまんない」という実感がある身体性の人たちに、上妻世海の制作論は「実存的」な魅惑を放っているんだと思います。ただ、おそらく今は一部の感度のいい人にしか伝わってない。
もうひとつ、上妻世海の制作論がおもしろいのは、結構むずかしい言葉で書いてあるところです。内容を正確に理解しなくても、この本に書かれていることが「つまらなさ」を打開してくれそうな予感を孕んでいるのはわかる。誘惑した次は、それぞれのなかで芽生えてくる内発的なものを、自分で何とかするしかないってところまで持っていくのが、ひとつの役割なんだと思います。
何かを制作していくときに、批評的なものばかり読んでいたら、行動できなくなりますよね。だから「どうやって教養を身につけたらいいですか」といった間違った質問をする人には、自分が好きだったり興味がある人の伝記を読むことをよく勧めてるんです。ジャコメッティとかピカソとかマレーヴィチとか、誰でもいいんですけど、その人たちの人生とか参照してきたものとか、どういう風に考えながらやってきたのかとか、その時代や雰囲気とか、そういったものに興味を持ち始めたら、あとはまかせるだけだと思うんですよ。だって、いずれの人も密度の濃い人生を歩んでるし、いろんな人と出会ってたり、いろんなカルチャーに影響されながら、身体を作ってきたことに気づけるはずですから。
今の情報社会だと、その人たちが読んできたものを読んだり、その人たちが触れてきたものに触れるのがやりやすいんですよ。インターネット環境は、消費カルチャーに向いてるけど、制作カルチャーとも相性がいい。つまり、自分の身体に必要な素材は、すでにインターネット上にアーカイブされてる。ユーザー側が消費的な身体だと、そのネットワーク性が前景化してきて、出会い系とか友達作り系とかバズらせる系みたいなロジックになってしまうけど、インターネットが潜在的に持っているパワーはアーカイブ性にあるんです。
消費的に「ピカソの絵っていいよね」と終わる前に、ピカソの人生を追っていったら、四次元思考の話に行くし、当時の数学によって空間の捉え方が変わったこともわかる。文化的な状況もそうだし、第一次世界大戦といった歴史的背景にも詳しくなる。X線や電話が発明されたことで、コミュニケーションの考え方がどう変わったのかを知りながら、造詣が深くなっていくはずなんです。ピカソを知ろうとするだけで、めちゃくちゃ教養が必要になってしまう。
好きなものを外側から見て消費するんじゃなくて、まずは自分の内側にピカソを取り入れて、自分がピカソになる。それだけで身体が複雑になっていかざるをえない。そのプロセスさえ始まっちゃえば、どんどん自分が変化していく。自分が変化していけば、自分のまわりにいるパーティーが豊かになっていく。変化のプロセスを自分で止めない限り、あとは恐怖や不安と戦うだけなんです。変化を止めてしまいそうになる自分と向き合うだけ。ピカソを内側に取り込めないのは、自分が近代とか常識みたいなものを前提にしてるからで、そこでリミットが外せてないんだなと気づくことができる。
あとは好奇心の問題で、どんどんアナロジカルにつながっていく。そう「すべき」ではなく、そう「なる」。次のプロセスが勝手に決められていくから、やることを自分が決めていく必要さえなくなるわけです。もし選択しなきゃいけないっていう状況に置かれているとしたら、まだ消費的な身体だというだけ。この変化のプロセスに入ってから選択肢があるとしたら、身をまかせるか、怖いから逃げるかの二択なんです。
——— 消費的な身体というのは、主体はいつも単一でしかない。主体が単一だから客体も単一で、ただ客体のバリエーションがあるだけだよね。主体と客体の関わりがつねに一対一で、ひとつの客体に飽きたら次の客体を選ぶという形で欲望がドライブしていくだけだから、どんな経験をしても主体も客体ももとのまま何も変わらない。だから、消費と呼ばれてしまう。
今言っていた「自分の内に取り込む」というのは、自分のなかのアナロジカルな群像を作動させるということだと思うんですよ。これは主体が一対一となる客体を選ぶことではなく、自分の中に取り込んで「半ば自分でもあるような対象」が別の「半ば自分でもあるような対象」とリンクしていく自動運動みたいなものを作動させるということ。「身をまかせる」というのを言い換えれば、主体としての自分を主客がつねに多重化してあるような境域に「溶かし込む」とも言える。でも、これは最終的に「飛び込むかどうかの決意」の問題とも言えそうだね。
主客未分の領域に入らないと、本当の変化って生まれないんですよ。だけど、多くの人が勉強して頭良くなるとか、資格を取ったり身分を得ることを変化だと考えてる気がするんです。勉強ロジックでピカソの伝記を読んで、知識を取り込もうとしてる。でも制作ロジックというのは、自分とピカソの間にある境目をなくすことなんです。いろんなものを身体に入れて「自分はこうしたいけど、ピカソはこうしないよな」って考えることができる。あるとき私はピカソになってるんだけど、またあるときは人と喋ったりして社会的な私を留めてる。そうやっていろんな人を自分のなかに持つというのは、自分の欲に従って生きない方法を身につけるってことでもあると思うんです。
僕の話でいうと、文化人類学者の奥野克己さんに誘っていただいて、今度ボルネオに行くんですけど、調べたらそこのプナン族ってほとんど裸で暮らしてるんですよ。家は外から丸見えだし、蚊もめちゃくちゃ多くて、マラリアにかかる可能性もある。冷静に考えて死ぬ可能性があるんです。だけど、自分のなかにさまざまな主体がいて、ビビってる自分とは別の自分が「いや、行くでしょ」って言ってくる。こうやって決断するのがいいのは、今まで内に留めていた問題が外化するからなんです。もう一人の自分が「行くでしょ、だってフィッツジェラルドも戦争行ったし」って言うんだけど、ヘタレな自分が「これはまずい」って震えてる。「ああ、でももう行くって言っちゃったよ」みたいなやりとりがある。
つまり、ジェイムズの純粋経験論みたいな主客未分の状態を保ちながら、いつでも主客が入れ替わるような場所に自らを置いて、あるときは主体として考え、またあるときは対象として自分を見る。さまざまなものを内側に取り込んでいくというのは、情報として理解するってことじゃなくて、自分がいて相手がいるという図式じゃない状況を作り出していくこと。そうすれば自分の変数は勝手に大きくなっていくんですよ。だって、取り込んだ相手になるのって、相当難しいじゃないですか。自分で自分をピカソだって思えるようになるには、ピカソよりピカソのことを知ってないといけないので。
——— 制作ロジックとして内に取り込むか、あくまでも勉強ロジックとして対象を増殖させていくか。内に取り込むっていうのは、具体的にはミメーシス(模倣)ってことですよね。だって、ピカソを取り込むってピカソを真似ることじゃないですか。真似ることでピカソを身体にインストールするには、ピカソを十分に知ってなきゃいけない。対象を増やすのではなくて、真似るっていう機能をアナロジカルに増やしていく。真似る対象を豊かにするため、いかにアーカイブからアナロジカルにピックアップできるかというのが、いわゆるサバイブにとって重要になってくる。そんな話としても聞けました。
そうですね。たとえばヘンリー・ソローが好きな人の系譜ってあるじゃないですか。そういう人たちによってブックガイドが作られていくんだけど、僕には全然わからない。その人たちは、別に意識してそうなったってわけじゃなくて、どんどんアナロジカルに連鎖していった結果なんだと思うんです。さっきのプロセスに入ってて、その世界の住人になった。でも、これはスピリチュアルな話ではなく、単にそうなってしまうものなんだと。
——— ピカソを内に取り込むとき、そのピカソって何かっていうと、ピカソの「層」じゃないですか。要するに、アナロジカルな構造そのものがピカソなわけで。さらにピカソが取り込んだ、たとえばアポリネールみたいな人がピカソのなかにも存在しているわけですよね。これは言ってみれば、アーカイブのネットワークにアナロジカルにアクセスする潜在性を自分のなかに取り込むってことなので、スピリチュアル云々という文脈ではなく、「情報論」として考えた方がいい。
そうなんです。陳腐な言い方になっちゃいますが、人って作品じゃないですか。さまざまなネットワークの凝縮点としての人が、ある形を留めているだけの話だと思うんです。だから、人に出会うことは、そこにアクセスすることになる。そこから無数の線が飛び出して、その線からまた無数に飛び出していかざるを得なくなるわけです。
僕もそのプロセスの途中だから、自分が今後どう変化していくのかわからない。ボルネオから帰ってきたときに、どんな自分になってるのかも。そういう風に変形を遂げていくときって怖いわけですよね。つまり、状態Aのことを自分だと思っている人って、自分がAとイコールでつながっていることを自己同一性と考えてるわけじゃないですか。Aとイコールって考えてしまう、このこと自体が問題だと思うんです。AからBとかCになるってことは、その人にとって同一性がなくなることだから、死ぬことと一緒なんですよ。私ではなくなるけど私ではあるわけで。
——— やっぱりそこが面白いところで、「私は私である」「A=Aである」っていうのは、再帰性の問題じゃないですか。「私は私」って再帰していないと、私は私じゃないわけだから。だけど、人間が「作品」でネットワーキングの「節」だと考えれば、そこには再帰性は存在しない。マルクス・ガブリエルが「世界は存在しない」と言ったけど、これってつまり再帰性の問題だと思うんですよ。ガブリエルが言う「世界」ってのは「意味の意味」「包摂の包摂」ということで、つまり無限にメタレベルに上昇していくようなベクトルは「存在しない」ということ。A、B、C…という項同士が、ただ相互に参照して包摂し合う「意味の場」だけが存在していて、その「意味の場」において現れるモノが実在であると。
今の「ネットワークとしての人間」というのは、自らの身体性をガブリエルがいう「意味の場」に「同期」してしまうということだと思うんです。人間はA、B、C…といった項を、自らの身体性において「意味の場」として成立させる能力がある。ウィラースレフが『ソウル・ハンターズ』で説いたように、ミメーシスの能力がそれです。
自らを「意味の場」として成立させること、これは再帰性を免れ、項目間が自律的に結び合う、ある意味オートマティックなプロセスに自らを投企するということでもある。どこまでその自動運動に自分を溶かし込むことができるか。これはもう根性があるかどうかという、根性論みたいな話でもある。
それがさっき不安や恐怖って言ってたものですね。だってAの僕が、何かをやったらBになるかもしれないときって、Aとは別人になる可能性と向き合わなきゃいけないですから。怖がってるのは、結局Aの自分なんですよ。今この瞬間の僕はAなわけで、そのことは否定できないから怖い。でも、非人称の場で考えると、いつものプロセスなんだと認識できるので、この恐怖は薄れます。一度経験しちゃえば、変化するってことは普通になるので。実際、僕がこの変化のプロセスを認識するのは、ずっとAから変化してない人と会ったときぐらいです。
——— Aから変わるのが怖いのは、Aが死ぬからですよね。でもこの小さな死を経験して、またBとして再生する。この「死と再生」っていうのは、通過儀礼の基本的なフェーズだと思います。プレモダンの通過儀礼には、そこで生まれてくるBがあらかじめセットされていた。でも、今はそのBがわからない。Aの自分が死んで生まれ変わったら、Bになるのか、Cになるのか、Dになるのか見えないなかで、死ななければいけないから、より大きな不安になってしまう。
不安は大きいんですけど、実際にAから急に特殊なBになれるわけではないんですよ。短期間でさまざまな経験をするとか、さまざまな人物を内面に取り込むのは、量的に考えても無理なので、部分的に小さな死を繰り返していくしかない。制作ロジックに入っても、完全に消費ロジックから切り離されるわけじゃないですし。だけど、ちゃんと標準偏差から離れた体験ができるということが重要なんだと思います。
——— そこの制作的なプロセスにいる自分は、すくなからず多重化されてるわけですよね。多重化されてるから変わっていく。AからいきなりBにならなくても、AからA’やA’’ぐらいにはなると。すると、A’’’ぐらいで「これはBだな」ってなる。
具体的にアーティストで考えてみると、制作的な強度をずっと保っている人って作品が変わっていきますもんね。自分の極みのようなものをひとつ作って、自己模倣して似たものをどんどん量産していく人もいますけど、変化のプロセスのなかで別の極みのようなものを追求していく人には興味が尽きない。後者は死と再生を繰り返しているわけです。
それがまさにピカソですよね。基本的に変化のプロセスって、好奇心で惹きつけられてアナロジカルに連鎖して生成されるんですよ。だから、この制作ロジックのプロセスとインターネットは相性がいい。つながったり発信したりするだけじゃなく、アーカイブの深みや厚みを身体的に獲得できる。そして、これはアーティストやクリエイターに限った話じゃなくて、自分の軸を作っていくという普遍的なプロセスでもある。実は最初から「個」というものは与えられてないので、自分で「個」を作っていくという話で。もっと言うと、変化のプロセスに入ってないと、劣化していくと思うんですよ。貨幣が劣化していくみたいに価値が下がっていく。
——— 今の「個」の問題は、結構重要かもしれないですね。例えば、パパ・ママ・ボクのエディプス三角形を説く精神分析も、基本的には「承認のお話」ですよね。ものすごく端折ってしまえば、人間として生きることは他者(神であり、言語であり、他人であり…)に承認してもらうことであると捉えられてる。制作的なプロセスに入って自分が変わっていくということは、この「承認のお話から降ります」という宣言でもある。
自分は制作的身体として、どんどん変わっていく。しかも、AからBに突然変わるわけではなく、グラデーションで変わっていく。つまり、実際は、AともBともCとも定位できない状態で、変わり続けていく。だから、自他ともに評価ポイントが特定できない。このプロセスの恐怖って、つまり社会的承認体系から外れていくことにも関係している気がします。
ピカソは友達から褒められて、承認されたと思って喜ぶことはなかったはずです。確かに彼も若い頃には、いろんな美術館に行き、いろんな人の作品を見て、それらを模倣していました。そうやって他の人を取り込んできた。それは褒めてくれる友達を目指していなかったということだと思うんです。もしかすると、制作プロセスに入ってしまうことは、承認を否定することなのかもしれません。青の時代には承認してもらえたけど、わけのわからないキュビズムの絵を描いたら認められないかもしれない。たまたまピカソは認めてもらえたけど、一般的には認められない可能性の方がむしろ強いわけじゃないですか。もちろん友達には止められるでしょうし。
——— なぜそこに行くかというと、より強い承認を求めていたからわけではなく、行かざるをえないから行ってしまったと。それは相互に承認される社会のフィールドから、いったん外れてしまうことでもあるけど、外れないとアナロジカルに作動できない。しかも、そのフィールドから出て、承認される可能性を捨てるということは、ある種の契約を破棄することなんでしょうね。承認という価値は確固としてあるものではなくて、お互いに価値があるという確認が必要で、その契約によって成り立ってるので。
だけど、別に今いるコミュニティから外れたとしても、大丈夫なんですよ。絶対に別の人たちが出てくるはずだから、何も不安になる必要はないんです。なぜなら、何かを作るってことは、基本的に一人じゃできないからです。制作から流通から販売まで、自分だけで完結することはありません。むしろ何もしない方が孤独になるので、承認が必要になるんだと思います。
——— 確かに、そのプロセスに入ってしまうと、同じようなプロセスを生きている人のことがわかってしまって、自然とリンクするからね。今こうやって僕らが話しているのもそうだけど、別にそれぞれの社会的な属性やポジションと関係ないところで、常に多様なリンクが発生してくる。そして、これは今回の本にも書かれてる「制作者の共同体」の話でもある。アーカイブを掘り下げていくと、共同体のなかでアナロジカルにネットワーキングもできてしまう。
ここまでネガティブな意味で使ってきた消費とか承認とか鑑賞とかって、外にあるものを使ったり頼ったり見たりってプロセスです。でも共同体にいれば、勝手につながっていくんで、そもそも友達作りたいということを目的にしなくなる。お金出しても行けないところに行けたりする。あとは自分のやりたいことやって、やるべきことにフォーカスするために、集中できる環境を作っていくのに頭を働かせるわけです。制作するから、自分も変わるし、まわりも変わっていく。これは何かっていうと、物語なんですよ。ずっと登場人物が変わらないなら、おもしろい物語にはなりません。
——— つまり、創造性を自分のコアにしないと、目減りしていくだけで、もはや立ち行かないんだと。これはアーティストに限ったことではなく、今では企業においてもイノベーティブであることが最重要の価値となってきています。だから、上妻世海の制作論は、状況論的に言っても、有意義でおもしろい。
イノベーションには、メソッドがないんです。自分が置かれた環境のなかで、自らの身体性で以て自己判断できなければ、イノベーションの運動を起こすことはできない。つまりイノベーティブであるための「方法論」があるとすれば、それは「クリエイティブな身体性を持つ」ということに尽きるんだよね。
スティーブ・ジョブズでもジェフ・ベゾスでもいいんだけど、彼等はクリエイティブな身体性を持っていたと思う。アナロジカルな運動性を自分の身体に落とし込んで、統計やマーケティングに関係なく、なにが正解なのかを自己判断して、「これは正しいんだ」と直観的な確信をもって市場に挑んだ。根拠はないけど、アナロジカルな身体性による自己判断で「正しい」んだと。
では、「クリエイティブな身体性」を育むには、どうすればいいか。たとえば、ピカソを自分にインストールする。それは、必ずしもピカソみたいなアーティストになりたいという人に限らず、すべての「クリエイティブな身体」を望む人にとって有効になる。起業したいからジョブズの本を「参考にする」というんじゃダメで、むしろデヴィッド・ボウイを掘ってみる。そうすれば、この「掘る」というプロセスのなかで、起業に必要になるアナロジカルな身体性が育まれていく。
そうやって、読む人を「クリエイティブな身体性」へと誘う魅惑を孕んでいるのが、上妻世海の制作論なんですよ。クリエイティブなプロセスにどうやって参入していけばいいのか、さらに「クリエイティブな身体性」がどう機能するのかということまで、多角的に解像度の高い形で示して、読む人をコーチングしている。つまり、ただ読解して終わりじゃない。「クリエイティブな身体性」を獲得するための「エクササイズ」への誘惑であり、同時にこのテキスト体験自体が「エクササイズ」でもある。
僕はそういう意味だと、スティーブ・ジョブズをインストールすればいいと思うんですよ。ジョブズを掘っていったら、ジョブズで止まるわけないって発想なので。彼だって、元々はヒッピー青年だったわけだし、カリグラフィーを習ってたり、東洋思想をかなり深く信じてたわけじゃないですか。そうやってジョブズが形成されるまでには、さまざまなネットワークが彼に突き刺さっていって、そういった偶然性が潜在的にあって彼の形になった。だから、「ジョブズがすごいから、ジョブズが好き」で終わってたら、それはジョブズを取り込めてないんですよ。
——— そうなんだけど、ジョブズを掘っていく最初の取っかかりとしては、ジョブズそのものに強く魅惑される経験がモチベーションになると思うんだよね。つまり、そこからアナロジカルに運動し始めるには、トラウマ的にインパクトのある魅惑を体験することが大事じゃないかと。魅惑体験というのは、ファンになるって消費行動とはまったく違う。そして制作論は、魅惑されたあとに掘り進めていく道筋も示してると思う。
そうですね。プロセスに入っていけば自らが形成されていくっていう話で。
——— あと制作論には身体性の話がよく出てくるけど、これってハードウェアですよね。さらに人間の身体っていうのは、市川浩が言うところの「身」なんです。制作論が言ってるのは、「身」を変えるということじゃないかと。
その市川浩と同時代にソシュールを研究していた丸山圭三郎は、「身分け構造」と「言(こと)分け構造」という分類をしています。「身分け構造」はユクスキュルの環世界論みたいに、蝶が蝶の世界を見てるのは蝶の身体を持ってるからというもので、「言分け構造」は言葉で分節されたもので、人間の場合は「身分け構造」の上に「言分け構造」が乗ってると考えてました。ハードウェアの上にソフトウェアが乗っているような構造ですね。
さらに彼は、「言分け構造」が「身分け構造」のなかに陥入してるのが人間の特徴だとも言っています。これは「言分け構造」によって「身」の部分を変えることができるということなんです。この身体性の変容は、さっきの通過儀礼における死と再生みたいな、たとえばシャーマンに自分たちが知らないはずの「異言」が降りてきたりするような話です。これが上妻世海の制作論で言われる身体性につながっているんじゃないかと感じました。
最後にまとめると、上妻世海の制作論は、近代的なソフトウェアをどう変えても立ち行かないという状況に対して、「言分け構造」が「身」を変えるかのように、身体性のレベルを変えなければならないと明確に言い切ってる。まさにここが最大のおもしろさなんですよ。
その解釈、すばらしいです!
2018年5月25日
インタビュアー: +M(@freakscafe)
個人の時代に代わるもの、それは、しばしば素朴に信じられがちなように、集団の時代なのではない。そうではなく、ある非人称の時代。なぜなら、個人の時代が終わったとすれば、問題は、主体=客体という二元論と、そして認識 → 伝達(現実の主体的な再現)という二重過程との上に成立してきた近代の古典的な認識論そのものの崩壊にほかならないであろうからだ。そして、このコギトの消滅のうちにあらわれるもの、それはそれ自体の存在における言語であり、イマージュであり、コミュニケーションでなくて、なんだろうか。宮川淳『鏡・空間・イマージュ』
[0]はじめに
このエッセイは、「制作」という概念を制作することを目標としている。「制作」とは捉えどころのない、奇妙な概念で、「制作」を介して、常識とされている知覚や行為の様態が変化することを伴う。だから、これまで人々は、芸術家の発言を過度に神秘化したり、あるいは、過度に単純化したりしてきた。彼らの発言は、真剣に受け取られることがなかった。
僕はときどき、宮川淳が、アルベルト・ジャコメッティの「似ている、見えるとおりに」という発言に導かれる仕方で、イマージュの存在論に迫る姿を思い浮かべる。彼を駆動しているのは、僕と同様の問いであるように思えた。つまり、「見たまま書いている、描いている。彼らはそう言う。にもかかわらず、なぜそのような表現になるのか」、これである。見たまま、書くこと。この〈見たまま〉が意味することには、「制作」を考える上で、重要な鍵が隠されているように思えた。まずは、宮川淳の『鏡・空間・イマージュ』を検討するところから議論を始めることにしよう。
[1]描くこと、書くことを通じて
ポール・エリュアールは書く。
そして、ぼくはぼくの鏡のなかに降りる
死者がその開かれた墓に降りてゆくようにコクトオのオルフェもまた鏡をとおりぬけて冥府に降りてゆく。そして、なによりもわれわれは鏡のなかに落ちることをおそれるのだ宮川淳『鏡・空間・イマージュ』
宮川は「鏡について」というテキストを上記の一文から始める。僕たちはなぜ〈鏡のなか〉へと降りていくことを恐れるのだろう。
まずは宮川がここで鏡という言葉で表現していること、そして彼が、〈鏡のなか〉(そして、鏡の表面)という言葉を用いていることについて考えたい。宮川は、鏡とは何かということを考える上で距離という視点から思考しはじめる。「距離が見ることの可能性であるならば、〈見ないことの不可能性〉(モーリス・ブランショ)、それが鏡であり、その魅惑なのだ。なぜなら魅惑とはまさしくわれわれから見ることをやめる可能性を奪い去るものにほかならないのだから」と彼は言う。距離は、僕が対象を見るとき不可避に存在するように思われる。そして、距離は見ることの可能性であり、見ないことも可能にするものである。僕が焦点を合わせた対象とそれを可能にする距離という構造は、知覚の基礎的構造として一般化できるように思う。
しかし、そうではない、と宮川は言う。彼は、アルベルト・ジャコメッティの絵画とその絵画へのサルトルの批評に対する反論を元に、「絵画は、イマージュの危険な魅惑、見ないことの不可能性を見ることの可能性に馴化することによって、はじめて絵画として制度化されてきたのではないか(その典型的な例は透視法だろう。透視法が決して視覚の真実ではなかったことはすでに明らかだが、さらに、それはおそらく、この不透明な空虚を、測量可能な距離に還元することによって透明で機能的な空虚と化す、もっとも体系的な方法ではなかっただろうか。)」と言い、画家としてのジャコメッティの課題は、逆に、見ることの可能性を、見ないことの不可能性へと解放することであった、と言う。つまりこういうことになる。鏡、眼をそらすことを奪う魅惑、見ないことの不可能性が先にあり、それを馴化・制度化する形で絵画が成立しており、ジャコメッティの目的は、この一度馴化されてしまった〈見ないことの不可能性〉、鏡とその魅惑を再度取り戻すことにあるのだと。
〈見ないことの不可能性〉と〈見ることの可能性〉、〈鏡のなか〉と〈鏡の表面〉。見ること、そして鏡にはそれぞれ二つの重なった様態があるらしい。その二つの側面は、宮川だけでなく、精神病理学の中でもしばしば言及される。例えば木村敏は、『空間と時間の病理』での野矢啓一との対談で、「鏡で自分の姿を見るというときに、私が、あるいは自分が、自分を能動的に見るのでもあるし、自分が自分によって受動的に見られるのでもあるんだけれども、もう一つね、自分が自分にとって見えている、という中動態的な経験でもあるわけでしょう。自分という場所で、その場所自身が経験されているという。自己とか自我とかいった主語的あるいは客語的な存在ではなくて、自分が自分に見えるという述語的・与格的な主体の確認、これが大きいんじゃないか、という気がするんですよ」と語っている。鏡を見ることは一般的に、主体としての私が対象としての私を見ることを意味している、と考えられているが、それだけでなく、主体と対象という二元論的知覚そのものを成立させる場所を見るという経験でもある、と言うのだ。そしてその場所こそ、宮川が「鏡の中に降りていく」と表現している場所なのである。ここに二つの「見る」がある。私が対象を見るという仕方、私が私と非—私を成立させる基体そのものを見るという仕方。鏡の表面と、その中。
しかし、ここには反論が考えられる。例えば、鏡の経験は、単に私が私のイマージュを見るだけのことであり、宮川が言うような大層なことではない、と。もしあなたがそう反論したくなるとしたら、あなたはイマージュとその魅惑を捉え損ねているのかもしれない。宮川は次のように言う。「イマージュはつねに対象の再現であることが自明の前提となっている」。イマージュの問題は、それがそのイマージュである「元の事物」、言いかえれば、イマージュとして意識に与えられた対象の存在に、そしてそれのみに還元されてしまうことにある。しかし、「イマージュがそこにある」(ガストン・バシュラール)ということが真の問題なのである。イマージュは、根源的に、ここ、イマージュが現わす対象の存在ではなく、いわばイマージュそのものの現前、なにものかの再現ではなく、単純に似ていることなのである。
似ていること、それは単にあるものがほかのものに似ていることにすぎないのではないのだから。というか、むしろこの事実を通じて、しかし、より深く、つぎのようなことなのだ —— 同じものであり、しかも同時にほかのものであること、それがあることとは別のところでそれ自体であること、それゆえに、ある〈中間的な〉空間、「表と裏、夜と昼 —— というよりも蝶番のように表と夜、裏と昼、そのどちらでもなく、しかも同時にその両者であるもの」、いわばこの非人称的な〈と〉の空間そのものの浸透であり、それがすべての自己同一性(「彼が彼と自分の肉体を占有しており、彼と彼の大きさを占めており —— 道のほこりにまみれてそこにある二本の足 —— 時間と空間のすべてを占めており、それをかんづかれることなく離れようとする彼の努力にもかかわらず、ついに逃れうるものでもなく……」)をむしばむのだ。なによりもこのわたしとわたしとのあいだのずれ —— 「もう一度映像が僕を見つめる、その映像の目。そしてもう一度およそ想像を絶する空間が僕たちのあいだに形作られる。もっと近く、もっと遠く。僕は右腕をあげる、とただちに左腕が答える……」宮川淳『鏡・空間・イマージュ』
似ているものを模倣先の対象に還元することは、常にAはAであると盲目的に信じていることを意味している。僕は鏡を見る、右腕をあげる、とただちに左腕が答える。鏡に映る僕のイマージュは、僕にとても似ている。しかし、それは僕である。鏡の表面を見ることは、「私は私である」と確認することである。確認することで、僕は安心する。やはり私は私であった、と。「私が私であること」は、見ることの可能性である。それを前提にすることなく、「私は対象を見た」という一文を書くことなどできるだろうか。しかし、僕たちは油断することはできない。なぜなら〈見ることの可能性〉は、いつだって〈見ないことの不可能性〉へと転換する危険性を持っているのだから。
じっと鏡を見つめてはならない。そこには僕たちを引き込む魅惑があるのだ。鏡を見ることは私を見ることであるわけだが、そこで私は、「見ている私」と「見られている私」という、二人の私に分裂している。そしてこの分裂を通して、「見ている私」が「見られる私」との同一性を確認する。この同一性の確認は、時間の中で、常に流れ去った私を後から確認することでしかない。流れ去った時間、それは〈見ることの可能性〉であり、宮川がいう〈距離〉のことである。「見ている私」と「見られている私」の間の距離。僕たちが自己同一性として安心しているものの構造はこのようになっている。分裂しつつ同一であることを確認すること。もう、その分裂の裂け目、距離が、〈見ないことの不可能性〉へと転換する一歩手前である。その裂け目からは、この再帰的運動を可能にする場所が、あなたを覗き込んでいるのだから。あなたは鏡の中へ誘い込まれていく……。
鏡の中は「私は私でなく、私でなくもない」という二重否定の眩暈、自己同一性の裂け目、木村敏のいう述語的・与格的主体の横溢、危険な香りと魅惑に満ちた〈あいだ〉の空間を開くことである。宮川が鏡という言葉を用いて「見ること」を考える理由は、ここにある。なぜ僕たちは「鏡の中に降りていく」のを恐れるのか。そして、それと同時に、なぜこれほどまでに惹きつけられるのか。僕たちは「私は私である」という同一性に安心を覚える。他方で、この同一性に嫌気がさしている。宮川は「この鏡の空間、この二重化の体験、この自己同一性の裂け目、それは《彼》が、たえず、そしてたとえば、車を全速力で疾走させることによって空しく期待していたものにほかならないだろう」と言う。僕たちは安心を求めるだけでなく、それを退屈だと思う。そして危険な香り漂う眩暈の中へ、誘い込まれる。
宮川は鏡の空間を描き出す上で、さらに興味深い論点へと進む。彼は言う。「それはまたすぐれて〈本〉の空間ではないだろうか」と。ここまで「見ること」と「見られること」によって語っていたことを、「書く行為」と「読む行為」という二項を用いて、再度、そして別の仕方で、彼はこう語る。
書く行為は読む行為によって二重化されなければならないのだ、そのときに成立する〈中間的な〉空間、すなわち〈本〉(だが作品ではなく)。作家が、あるいは作品が —— あの自己表現が重要なのではもはやない。作家はなにごとかを伝えるために書くのではなく、そしてコミュニケーションとは作家が読者に伝えることではない。重要なのはこの本の空間であり、この本の成立そのものこそがコミュニケーションにほかならないのだ。そこでは書く行為と読む行為とが同時的・相互的なものとして理解されるこの〈彎曲した空間〉……そしてもう一度およそ想像を絶する空間が僕たちのあいだに形作られる、もっと近く、もっと遠く。僕は右腕をあげる、とただちに左腕が答える……このすぐれて鏡の空間であるもの、一冊の〈本〉。
……
《ぼく》の存在そのものの曖昧性はここから生まれる。それは決してあのいわゆる自我の非連続、不確実性を意味しているのではない。それは書くことの根源的な体験 —— 鏡の体験、二重化の体験であり、多かれ少なかれ、一人称の小説、いやすべての小説に内在する曖昧性なのだ。というより、フィクションとはおそらく、この二重化の危険な体験のいわば制度化によるエグゾルシスムではなかっただろうか。それによって、作家はおしゃべりの不毛な空間、この鏡のなかからのがれ出ることを、一方、読者は物語、この無意味なおしゃべりの背後に意味を求めることを許されるのだろう。
……
しかし、制度(たとえば三人称単数)であるよりも前に、フィクションとは言語の根源的な体験なのだ。文学言語のではなく、われわれの言語そのものの。なぜなら、日常言語があり、文学言語があるのではないのだから。そうではなく、文学とはわれわれの言語の根源的な体験なのだ —— 語るというそれ自体の運動における言語そのものの現前、それゆえに、すでにそれ自体のうちにおいて、非人称的な〈書く行為〉と〈読む行為〉とによってたえず二重化されなければならないこの鏡の空間。この二極が外在化され、人称化されるとき、われわれはそれを作家と呼び、読者と呼ぶのだ。宮川淳『鏡・空間・イマージュ』
繰り返しになるので、簡単にまとめる。ここで宮川が言っていることは、「見ること」と「見られること」の二重化と並行的な関係にある。そして、この「書く行為」と「読む行為」という二重化の中を〈本〉と呼ぶのである。彼が絵画を〈見ないことの不可能性〉を〈見ることの可能性〉へと変容させる制度であるというように、ここでは作品が絵画に相当する。根源的体験とは、作家が作品を読者に届けることではなく、この非人称的な〈書く行為〉と〈読む行為〉に二重化されることなのである。作家、読者、作品は、あくまでその外在化、制度化として成立している。宮川はジャコメッティを評して、彼は見ることの可能性を再度見ないことの不可能性へと開こうとしていると言った。同様に、書くことの可能性を書かないことの不可能性へと再度解放すること。それこそが求められているのだ。
宮川は〈描くこと≒見ること〉あるいは〈書くこと≒読むこと〉という制作の循環構造の中に、魅惑的かつ危険な非人称性を見出す。なぜ危険か。それは制作的実践によって、安定的なコギトが分裂し、その奥にある基底が見え隠れするからである。近代化とはこの同一性を確保することでなければ何なのだろう。「私が私であること」を保証するために作り上げてきた一連の制度を、近代制と呼んでもよいくらいだ。絵画という制度、作品という制度は、まさにそれらを象徴していると言えよう。鏡≒本の空間は、非人称の二重化が可能になる場のことを指している。そして、僕はこれから、レーン・ウィラースレフの『ソウル・ハンターズ』を参照しながら、鏡≒本の二重化を生きること —— 森の中では、それがミメーシスの実践として現れるのだが —— が、いかに不安定な生と死のあいだの統御であるかを示すつもりである。しかし、その前に宮川がここまでに示した「制作」に焦点を当てることにしよう。
宮川が言うように、「制作」とは二重化の体験である。描くことは見ることであり、書くことは読むことである。それは媒体との技術的対話である。作り手は素材に働きかけ、そこから何らかの応えを得る。そして、それに導かれながら、あるいはそれを裏切りながら、書く、そして読む、書く、その循環。もちろん構想はあるだろうが、すべて計画した上でそれを投影するわけではない。媒体との対話・抵抗の中で出てきた偶然性と向き合いながら、良いか悪いか試行錯誤しながら、修正したり、加筆したり、行ったり、来たりするのである。
アランは『芸術の体系』の中で、「アイディアが制作に先だち、それを規制するのは工業である。制作とは、制作の只中でアイディアが湧いてくること」だと言い、保坂和志は『小説の自由』の中で、「書かれた文章は書き手のイメージの写しではなくて、書き手は半分は書かれた文章からその先を書くヒントを得る」と言う。旧約聖書「創世記」の冒頭は「光あれ」「神は光を見てよしとされた」である。神ですら〈形〉にするまで光の良し悪しを判断できなかったのだ。「生産」が、決められた設計図通りに同じものを作ることを意味するとしたら、「制作」とはその只中でまた別のアイディアが湧き、それによって行き来する往還運動なのである。
そこでは、安定的な自己同一性を保つことはできない。なぜなら、あらかじめ構想していた安定的な私は、書くこと、描くことによって、そのたびに別の私として作られるのだから。ロラン・バルトが『言語のざわめき』の中で、「書くということにおいて、主体はエクリチュールと/から直接に同時的なものとして構成される、エクリチュールを介して実現され、影響をこうむる」と言っているように、である。「作品」や「作者」「読者」という概念は、制作の過程の中で「これでよし」と切断し〈形〉として外在化した結果、生じるものにすぎない。ここには過去から現在、そして未来へ、という時間の流れでは捉え切れない往還運動が存在する。つまり、偶然誤って引いてしまった線によって、作り手がそれに導かれることで〈形〉ができ上がったとき、その偶然性は「作品」にとっての必然性へと変化する。過去は変えられないものではなく、「制作」では頻繁に変わり続けるのだ。そして、「作品」として外在化されること、あるいはそれを引き受け「作者」となることで、主体もまたさらに変化していく。リチャード・セネットが『クラフツマン』の中で語るように、「制作」の中で、つまり物質性との対話の只中で、作り手は作ることへの責任や技術や精神の自己規律を醸成していくのだから。
[2]狩猟を通じて
ベンヤミンはミメーシスにひとつの理論ではなく、ひとつの「能力」を見出すのであり、それは身体のように人間の条件から切り離せないものである。この能力は、近代において、諸々のイメージとシミュラークルが横溢し、ゆえに現実的と感じるものが何もない世界をもたらした。だが、ベンヤミンが論じるには、ミメーシスの根源はまねることによって世界や他者との間に類似性を育もうとする原始的な衝動にまでさかのぼることができる。「自然は類似性を作り出す。擬態のことを考えるだけでわかるだろう。だが、類似性を生み出すための最も高い素質は、人類のものである。類似性を見出す才能は、他の何者かになったり、そのようにふるまったりしようとする、往時の力強い衝動の痕跡に他ならない。おそらく、人間の高次の機能のうち、模倣する能力が決定的な役割を担わないものはないだろう」。レーン・ウィラースレフ『ソウル・ハンターズ』
ここまで宮川淳の『鏡・空間・イマージュ』を元に、「制作」によって二重化の空間が開かれることを示してきたわけだが、ここからは予告していたように、レーン・ウィラースレフの『ソウル・ハンターズ』を参照しながら「非人称の二重化の経験」をより詳細に思考していきたい。この二重化の経験が、近代的な「見る私が見える私を確認するという自己同一性の在り方」と対照的な関係にあることは分かったし、それが「描くこと」「見ること」と「書くこと」「読むこと」の往還運動の中で見出されることも確認したが、それが近代的自我とは別の「私」であるとするならば、この「非人称の二重化」を生きるとは何なのか、より具体的に考える必要がある。宮川は鏡≒本の空間を理論として描き出した。しかし、「鏡の中に降りていく」ことは、鏡があるから可能になるわけではなく、そもそもそれを可能にする能力が僕たちにあるから可能なのだ。それは一般に、ミメーシス(模倣)と呼ばれる力である。
『ソウル・ハンターズ』は、シベリアの先住民ユカギールの元で行なった通算18か月のフィールド調査 —— ウィラースレフはある事件をきっかけに森の中での逃亡生活を余儀なくされ、現地民と狩猟生活を共にしながら多くの時間を過ごすことになるのだが —— をまとめた民族誌である。『ソウル・ハンターズ』の感想でしばしば聞かれるように、確かに一読しただけでは、本書は僕たちとまったく異なる枠組みを用いる〈狩猟民の哲学〉を詳細に記述し、僕たちに彼らの身体の在り方≒模倣様態を教えてくれるものとも読める。「彼は境界領域的な性質を有していた。彼はエルクではなかったが、エルクではないというわけでもなかった。彼は、人間と非人間のアイデンティティの間にある奇妙な場を占めていたのだ」という記述が、そのことを象徴的に示している。エルクというのはユカギールではよく狩猟されているシカ科の動物であり、この描写はウィラースレフが狩猟を共にしていたスピリドン爺さんが実際にエルクを狩るときの描写である。
僕たちは生活する上で狩りをすることはないので、この本が描いている様態が僕たちのものとは異なると、考えてしまうことも無理はない。しかし、すでに宮川の「鏡」についての議論を経た僕たちは、ここに書かれている境界領域的な場所を自分たちと無関係であるとは考えないだろう。宮川の「私は私ではなく、私でなくもない」と、ウィラースレフの「私はエルクではなかったが、エルクではないというわけでもなかった」は、私が見ているのが鏡であるか、エルクであるかの違いでしかないのである。
模倣行為の最中に狩猟者が持つ人間のパースペクティブ —— つまり、世界についての自らの主体的な観点を有する、自意識を持つ人間としての自覚 —— は、それ自体を超えて、エルクに対して外側から投影されるようになる。それゆえエルクは、狩猟者が持つ人間のパースペクティブを帯びたものとして経験される。同時に狩猟者は、脱人間化を経験する。つまり狩猟者は、自らの模倣演技を鏡写しにするエルクのふるまいを観察することを通じて、外側から、すなわち主体としての他者の観点から、自らを客体として見るようになる。結果として狩猟者の人間としての自己同一性は、自らのうちにではなく、模倣的な生き写しのうちに宿ることになる。狩猟者はもっぱらエルクのうちに自らを見出すことができる。そのためエルクは、狩猟者が本当はいったい何者であるのかの「秘密」を握ることになる。そういうわけで、逆説的なことに、狩猟者は容易にエルクの人格性を否定することができないのである。なぜなら、このことが実質的に彼自身の人格性を否定することを意味するからである。換言すればエルクが意志、意識、情動性などの力を持たない純粋な世界=内=客体に過ぎないのだと考えようとすれば、狩猟者は自らに対してもそのような諸性質を否定することになり、ある意味で、「自己を欠いた」まま置き去りにされてしまう。それゆえ、狩猟者の心理的な安定、つまり人格としての自己意識は、人格としての動物にこそ依存している。
それだけではなお、狩猟者によって経験されているエルクの「人間化」は完全ではない。エルクの身体は外部から認識される。そのことは、それが外にあるもので、それゆえ、狩猟者にとってはいくらか異質なものであることを意味する。狩猟者は、エルクと自分自身がまったく同じではないことを知っている、むしろ、知っている必要がある。もしそうでなければ、彼は(主体である)エルクのパースペクティブだけに文字通り身を委ねて、変身してしまったことであろう。だから、エルクは狩猟者自身と似てはいるが、まったく同一のものではないと認識される。
換言すれば、私たちが扱っているのは、「私」と「私=ではない」が「私=ではない=のではない」になるような、奇妙な融合もしくは統合である。私はエルクではないが、エルクでないわけでもない。同じように、エルクは人間ではないが、人間でないわけでもない。他者と似ているが、同時に異なっているという、この根源的な曖昧さは、動物と人間がお互いの身体をまといながら、なりすました種に似ているが、まったく同じというのではないやり方でふるまうという、ユカギールの語りの中に私たちが見出すものに他ならない。さらに、模倣の文脈で狩猟者が出会うのは、独自の個的な自己としての動物ではなく、人格の原型としての動物である。つまり、動物は自己=充足的な人格としてではなく、むしろ人格性の鏡、媒介物、もしくは仲介路として経験される。だからユカギールの神話では、繰り返し、彼以外の何ものでもない固有名を持つ特定の狩猟者が、種の原型的な名前に総称的な接尾辞である「男」あるいは「女」を加えた名前を持つ動物と出会うのである。レーン・ウィラースレフ『ソウル・ハンターズ』
ここに、宮川が「鏡の中」として描き出した「非人称の二重化」としての私が、より一般性のある仕方で描き出されていると、僕は考える。鏡を見るとき、私は私を見る、見る私と見られる私の間隙に、「非人称の二重化」「私は私ではなく、私でなくはない」が現れる。しかし、それはミメーシス(模倣)によって、より一般的な経験として捉え返すことができる。私はあなたを見る。私はあなたでなく、あなたでなくもない。そしてあなたは私でなく、私でなくもない。ユカギールにおいて、動物は鏡として、媒介物として、あるいは仲介路として経験される。そうであるとすれば、近代人が対象として見ていると思い込んでいる他者も、そうでないとどうして言えるだろうか。そして、だからこそ、僕たちは他者に対して人格性を付与できるのである。私とあなたが分離された認識論を前提にしていたら、僕はあなたに人格性があることを見出すことはできない。その認識論を前提にすれば、あなたがタンパク質でできたアンドロイドであることを、僕は否定できない。しかし、そうではなく、ミメーシスを前提にすれば、僕があなたの人格性を否定することは、僕の人格性を否定することになる。僕はあなたではなく、あなたでないのでもないのだから。僕はあなたを通じて僕を部分的に知るのである。そして、それはユカギールが動物に人格性を付与していることと同じなのだ。
ウィラースレフによれば、実践とはデカルト—デュルケム主義における「分離された二元論」でも、ハイデガー—インゴルドにおける「世界との完全な一致」でも汲み尽くせないものである。換言すれば、実践とは「私が対象を見る」といった、私と対象が切り離された認識の在り方でもなければ、私と対象が完全に同化すること、「私はエルクである」でもなく、その間を揺らぎながら「私はエルクではなく、エルクでなくもない」を維持することなのである。その制御に失敗することは、彼らにとって死を意味する。模倣とは魅惑と危険に満ちたものなのだ。獲物を誘惑することについての彼らの実践を、その一例として引用しておこう。
誘惑は基本的にはゲームである。そこでは、誘惑者が彼の犠牲者の自己愛的な傾向に付け込むことによって、彼女が興奮の頂点に達するところを探り、それによって彼女がすべてを、その命さえも、彼のために犠牲にしてもいいと思うようになる。しかし、誘惑者である彼自身は、感情面で抜き差しならない状態になるに違いない。犠牲者に対して共鳴や愛情を示すことが必要なのだけれども、彼には彼女と恋に落ちることは許されない。愛とは変身のようなものである。それは自分から他者への移譲、すなわち自分を譲り渡すことである。ゲバウアーとウルフは、「愛の終着点」とは、「自分自身を拡張して、相手に同化すること」であると述べている。この意味で、愛は誘惑とはかなり異なる。誘惑とは、少なくとも理念的には、誘惑する側には偽りの愛が、誘惑される側には虚栄があるだけだ。それにもかかわらず、誘惑と愛の境界線ははっきりしない。誘惑のゲームは、二者の間に本当の愛情が芽生えるという危険を常に抱えている。狩猟者たちは、自分が殺す動物に対して、いかに同情や愛さえ感じるようになるのかを語る。しかし彼らは、そうした感情が危険で払いのけられるべきものであることを常に強調したのである。それでもなお彼らは、狩猟者がエルクを観察していてある種の魅力的な特性や行動に惹き込まれ、差し迫った自分の仕事のことを忘れてしまって、気がつけばすでに手遅れで、動物が手の届かない場所に行ってしまうことが、ときどき起こると語る。こうした失敗を、彼らは狩猟者が獲物と恋に落ちたと表現する。この愛に夢中になると、他になにも考えられなくなり、食欲を失くして、しばらくすると死に至る。レーン・ウィラースレフ『ソウル・ハンターズ』
生きることは、僕たちを世界に接触させつつそこから切り離す存在様態≒二重のパースペクティブであり、狩猟のモードでは動物への/からの模倣を通じて人間と動物の間を揺らぐ「愛と誘惑の駆け引き」であり、人間集団の中では先祖のアイビ(魂)を引き継ぎつつ「木煙の匂い」や「語り」を通じて自己のアイデンティティを保ちつつ生きることである。繰り返すが、実践的生とは、動物と人間と魂のどこか一極に偏ることを防ぎながら、その不安定さを乗りこなすこと=生きることである。
その生を、ウィラースレフは、具体的な事例を用いて描き出すことに成功している。そして、実践に重きを置く=二重のパースペクティブを生きるが故に、アイビ(魂)はあらかじめ与えられた二元論(精神と身体)に基づくものではなく、文脈と関係性によって動物にも人間にも「人格」を付与すると説明する。彼は「アイビは同じ理性的能力を人間と非人間に付与するのであって、それらの人格が別様に考えるのは、それぞれの種が特定の身体的存在であり、世界に対する志向性をもたらす独自の肉体的自然 —— メルロ・ポンティの言葉を使うならば、特定の『身体意識』 —— を持つためである」と述べる。
『ソウル・ハンターズ』の読者の中には、ヴィヴェイロス・デ・カストロのパースペクティヴィズムとの近さを感じる人がいるかもしれない。ウィラースレフ自身は、パースペクティヴィズムの理論的成果を多分に認めつつも、理論的でしかないことへの疑念を発している。彼が描き出すのは「実践によって開かれるモード」である。それは「世界観」という概念が前提としているような、「全体性をもった構造や地図のような形」で実在しているわけではない。だからこそ、彼は具体的な事例と共に、人々がどのように「不安定な魂の制御」を行っているのかを記述する必要があったのである。それは「動物やモノの人格性は、狩猟の最中のような、綿密で実践的な没入が生じる特定の状況下において立ち現れるものだ。こうした特定の状況を離れたとき、ユカギール人は、私たち同様、必ずしもモノを人格として見ているわけではなく、代わりに人間の主体と非人間の客体の区別がはるかにたやすくなされるような、ありふれた客体からなる世界を生きている」という記述を見れば明らかであろう。これは宮川が「描くこと」や「書くこと」を通じて、鏡の中へ、そして本の中へと降りていくことと同様である。画家であろうと、作家であろうと、綿密で実践的な没入が生じているとき以外は、コンビニで買い物をしたり、テレビを見たりして過ごすこともあるに違いない。彼らも、実践的モード以外の時は、私と対象を二分する日常的な認識論を生きているのである。
僕にとってユカギールの実践哲学は、それだけで魅力的なものだ。しかし、僕が『ソウル・ハンターズ』を読んでいて最も震撼させられた点は、ウィラースレフが実践的揺らぎの中で「実在」を見出す際に、精霊とコンピュータを並列的に例示していることにある。彼は、ユカギールの人々が精霊を実践的道具として扱っているが故に全体的な理論的説明を必要としていないことを、ハイデガーの道具連関を用いて示す。他方で同様に、僕たちがコンピュータを用いる際に、上手くいっているときは情報工学やコンピュータの機能的連関について知る必要がないことを挙げている。あらかじめ与えられた抽象的な「実在と虚構」の二元論がなければ、ユカギール人の「住まわれる視点」(インゴルド)から、実践の中で必要に応じて精霊が生成されるのであり、それは僕たちの日常生活の中で必要に応じてコンピュータが生成されていることと同義なのである。換言すれば、共同体を維持していく上で必要であるから精霊が要請されているのであって、それが上手くいっている限りは、精霊がどのような姿をしているのか、どんな機能をもっているか、などと考える必要はないのである。それは今、僕がコンピュータでこのエッセイを書く上で何の不都合もないが故に、コンピュータとは何かとか、なぜコンピュータで文字を打てるのかなどと考えないことと同義である。
それは、「知覚とは概念表象や認知の問題だとする伝統的視点を留保し、その代わりに事物が人々の日常的な活動の流れの中で立ち現れるやり方によって進められる。換言すれば私が提起するのは、いわば分析の順序を逆転させることである。つまり、人々と事物との実践的なかかわりの方こそが決定的な基礎であり、それが『知的文化』すなわち抽象的な認知や概念表象にとって不可欠の前提になっているという仮定からはじめるのである」というウィラースレフの宣言からも、読み取ることができる。「我々にとって事物の根源的な価値とは抽象的な思考の対象としてではなく、実践的使用のための道具的なモノであるということだ。コンピュータにせよ精霊にせよ、それは何かがなされるために用いられるのであり、それゆえ具体的な目標を成就するために事務的に淡々と用いられる『道具』として立ち現れる」のである。
つまり、ウィラースレフの隠されたもう一つの主張は、遠くのどこかに住む「他者」の存在様態を描くことではなく、僕たちが抽象的二元論を暗黙の裡に基礎として据えているが故に、自身の実践的様態をまるで解明できていないということであり、またアニミズムや模倣様態は近代社会の中でも強く生き延びているということである。ユカギール人は、文化的な質が近代文明に比べて低いから、動物に人格性があると考えているわけではない。復習になるが、なぜ彼らがそのように考えるかというと、それはミメーシスによって「私はエルクではなく、エルクでなくもない」「エルクは私でなく、私でなくもない」という状態を経験するからである。エルクの中に私を見出さざるをえないので、エルクの人格性を否定することは私の人格性をも否定することに繋がるのである。そして、それは、僕たち近代人が「私はあなたではなくあなたでなくもない」という状態を経験することによって、他者の人格性を捉えることと同義なのだ。あなたの人格性を否定することは、私の人格性を否定することに繋がる。鏡の経験、ミメーシスの経験がなければ、僕たちは機械論的な無機質なものとして世界を捉えざるをえないのである。そして、この主張は、分離的な二元論の象徴的な思考法であるデカルト—デュルケム主義の延長線上にある文化相対主義が、他文化を見ることで自文化を相対化するというよりも、その基礎に他者を当てはめるが故に、自らの枠組みを自ら強化することになっている、という記述によってより強く述べられる。
まさにこの文化相対主義の主張には問題がある。すべての文化がそれ独自の構築された意味の枠組みに閉じ込められ、そうした枠組みはその文化に関連する基準でのみ測ることができると主張するということは、人類学者はある特定の文化の成員であるにもかかわらず、すべての文化についての文化=超越的な解釈を提示していることになる。これは論理的に矛盾している。相対主義的な言明を非相対主義的な一般主張としておこなっているからである。それゆえに相対主義的立場は、あらゆる他者の生がその中で形作られているとされる文化の諸世界から、人類学者だけは一歩抜け出していることを必然的に含意する。なぜなら、「文化を超えた観察の地点によってのみ、〔土着の〕理解を……ある独立した現実の……ひとつの可能な構築に過ぎないと見なすことができる」(インゴルド)からである。換言すれば人類学的な文化相対主義の主張は、西洋の認識論が土着の理解に対して持つ優位性の基盤を掘り崩すのではなく、実際にはむしろ改めて強化するのである。レーン・ウィラースレフ『ソウル・ハンターズ』
これは、単に他文化を解釈するときだけでなく、自文化を解釈するときに対する警告でもある。二元論的分離の元で何を解釈したとしても、基礎であるその二元論を当てはめ強化するだけになり、都合の悪い問題は隠喩的/象徴的な意味しかなく、実在ではないと処理し続けることになるのだから。ウィラースレフは、これまで隠喩としての地位しか与えられなかった「実在と実践の関係」について、真摯に向き合おうとしているのだ。そして、彼は本書の最後の段落で次のように言う。
私が主張しているのは、ミメーシスはアニミズム的な象徴世界を制作するための前提にして不可欠の条件であるということだ。日常生活におけるミメーシス的実践なしには、アニミズムの象徴世界は生きられた経験との間にいかなる類似も生まず、まったくのところ宇宙論的な抽象概念以外の何ものでもなくなるだろう。したがってミメーシスはアニミズムの実践的側面であり、その世界製作の仕組みそのものである。現代世界ではミメーシスが重要性を持つというベンヤミンの発見それ自体が、我々の大衆文化の中でアニミズム的な形のつながりが表面化していることの証左である。実際のところ現代におけるアニミズムの広範な役割についてはかなり多くのことを語ることができるものの、それは別な本の主題としなければならない。レーン・ウィラースレフ『ソウル・ハンターズ』
現代におけるアニミズムの役割に関するウィラースレフの本は、未だ出版されていないようだが、本書だけでも十二分にその可能性は伝えられている。本書の表向きの目的は、アニミズムを〈真剣に受け取る〉ための枠組みを提示することである。そして、そのために抽象的な枠組みから現象をトップダウンに当てはめるのではなく、実践的に文脈と関係性の網目の中へ再参入する必要性を論じる。しかし、ベンヤミンが言うように、人間こそがミメーシスを最大限に用いることができるのであれば、その原理はまさに僕たち自身の隠蔽された原理でもあるのだ。宮川が「描くこと」「書くこと」を通じて鏡の空間へ、本の空間へと僕たちを誘うように、ウィラースレフは「狩ること」を通じて、「愛と誘惑の危険な場所」へと僕たちを誘う。
その場所は鏡による死と誘惑の乱反射、私と非—私がせめぎ合う場所である。「私は彼/女ではなく、彼/女でなくもない」。だからこそ、僕たちは途切れなくメディアを経由して届くニュースに模倣的共感を示すのだ。なぜ、テレビやSNSを通じて届く有名人の浮気や不倫に対して、怒ったり嫉妬したりする人がいるのか。ミメーシスは、未だ僕たちの実践的知覚の基礎的な原理なのである。もはや僕たちは、「発達した人間は象徴的に統合されることで単一の〈私〉を形成し、その外部として〈他者〉と向き合う」という枠組みを疑わなければならない。これは発達過程としての〈鏡像段階〉ではない。僕たちの中にある危険な魅惑と向き合わなければならない。ユカギール人が、サウナに入り人間の匂いを落とし、森の中でヒトの言葉を控え、模倣を通じて部分的に非人間化し、キャンプに帰還した後は仲間に出来事を語り、木煙とタバコの煙の中で部分的に人間化するように、僕たちも僕たち自身の方法で、誘惑と変身の世界に再参入しなければならない。もうそれを否認することはできない。
ここまでで二つの存在様態があることを示してきた。一つには安定した自己同一性が対象を認識するという常識的な在り方、一人称単数小説のような私小説的コギトである。第二に、鏡の空間、イマージュとミメーシスによる魅惑の世界では、「私は私ではなく、私でなくもない」といった二重否定を伴った不安定な〈私〉が取り出された。そして、宮川にもウィラースレフにも共通するのが、特殊な二つの様態を示しているわけではなく、それが描くことや書くこと、あるいは狩猟をすることといった実践や儀礼を通じて切り替えられる様態であるということであった。一流の画家であろうと、日常生活においては社会に共有される〈常識〉を踏まえてコンビニやスーパーマーケットで買い物をするだろうし、狩人もキャンプに帰ると、二元論的な認知の元、仲間と語り、木煙やタバコの煙の中で人間化するのである。
僕はここで、描くこと、書くこと、狩ることを通じて僕たちが降りていく、あるいは落ちていく空間を「制作的空間」と名づけたい。なぜなら、これまでの宮川やウィラースレフについての議論は、二つの空間が記述され、AからBへの移行が無媒介に示されてしまうのが常だったからだ。僕がここまでの議論で強調してきたのは「描くこと、書くこと、狩ること」を経由するということである。僕たちは、制作という媒介によって、「制作的空間」に入る。制作するためには制作を介さなければならない。この一歩、降りていく経路、落ちていくまでの経路を無視してはならない。「制作的空間」には、世界観が前提とするような全体性は客観的に存在しないのである。鏡≒本の空間や、狩りの空間が制作的であるという側面だけでなく、表と裏を繋ぐ制作という契機を強調する意味でも、このように名づけたいと思っているのだ。
[3]制作的空間への二重拘束的方法
西田幾多郎は「場所」という論文の有名な箇所で、「我とは主語的統一でなくして、述語的統一でなければならぬ、一つの点ではなくして一つの円でなければならぬ、物ではなく場所でなければならぬ」と述べている。僕は、これから「制作的空間」が主語的統一ではなく述語的統一であるということ、一つの点ではなく一つの円であるような私であることについて記述したいと思っている。しかし、上記のように、それはAからBへという単純な移行として示すことが難しい。なぜか。それはウィラースレフの言うように、それがデカルト—デュルケム主義的な二元論でもなく、ハイデガー—インゴルド的な「世界との完全な一致」でもない、〈あいだ〉の場所だからであり、「制作」という契機を必要としているからである。二元論でも一元論でもダメだというのは、美術史的に言えば、僕たちがモダニズムを経由した現在を生きていることとも関連している。すでに僕たちは、分離的な二元論も、同化的な一元論も、共に否定された歴史の上に生きているのである。
例えば、岡崎乾二郎は『絵画の準備を!』の中で、こう述べている。
レディメイドといういい方には二重の意味が読みとれます。実はデュシャンが絵画の網膜性を批判するといった場合、その網膜性とは、むしろ視覚のレディメイド性をこそ批判していると思うんです。通常の自然主義的な絵画もしくは芸術というのは、つねに受動的であって、受動的であるかぎり、そこで得られた視覚はぜんぜん自然ではなく、むしろレディメイドの社会化されたものとしてしかありえないというのが、実はデュシャンの根本的な批判にはあった。なおかつ純粋な経験ないし純粋な知覚、あるいは松浦さんのいい方でいえば、ある種の純粋なイメージというものを自律させようとするならば、むしろそれを成り立たせていると自明視されているところの当の物体なり場というものをすり替える必要がある。網膜が受動的にあてにしている対象、それをあらかじめ社会化されたオブジェとして置きかえてしまうことによって、ずれを発生させ、視覚=網膜と対象を結びつけていた自明なつながりを切断し、どこにも属さない経験を確保しようとする作戦が、簡単にいえばデュシャンのレディメイドにはあると思います。つまり、「網膜の受動性」の批判がデュシャンにはある。社会的、歴史的に規定される対象と結びついた自明性を破壊することによって、もしくは遅延させることによって、いかなる対象にも結びつかない経験の自律性が得られる、と。……おそらく、モダニズムの根本には、純粋知覚に対する断念みたいなものがあって、なおかつ、それを仮に成り立たせるとすればどういうかたちがありうるか、という二重拘束的な方法論があったのではないか。岡崎乾二郎 / 松浦寿夫『絵画の準備を!』
ここで言われているレディメイドの戦略とは、簡単に言えば、対象によって文脈をずらすことで前提として隠れていた視覚的自明性を露わにする、というよく知られたものである。しかし、岡崎が指摘するのは、その戦略の意図が自明性を露わにすることによって、既存の認知フレームを使いまわすことのできない経験=純粋経験を炙り出すことだと言うのである。そして、レディメイドの戦略に見られるように、モダニズムの根本には純粋知覚に対する断念があり、単純に制度的な知覚から純粋知覚への移行という戦略は取れないのである。デュシャンの場合、それはレディメイドという制作であった。そして、そこにはもちろん、歴史も絡んでいる。
岡崎 ― そうですね。ヨハネス・イッテンや宮沢賢治の教え方というのは限界としての個人を探求するわけです。都会文化や都会人のあらぬ表現に憧れ、自分の能力を省みず、やらなくてもいい勉強をしたり、ひとの色使いを真似したりしないで、自分の限界に気づいてそれをプラスに生かしなさいとやる。それは素材に対する教え方にも反映している。
松浦 ― だけど、それは結局、あらゆる現状の社会的矛盾をありのままに維持しろということになる。
岡崎 ― まさにそう機能する可能性がある。だけどそのモラルが、バウハウス以降のというか二十世紀の教育モデルにはあるわけですね。素材を生かしなさいというのと、素材としての自分の特性を見つけなさいというのは同じことでしょ。紙で鉄や木の真似をするな、紙自身の限界を楽しめ、破れやすい紙であることを生かして表現しろと。そういう意味でヨハネス・イッテンだとか宮沢賢治自身は媒介者でしかないわけです。だけどその媒介者がむしろ芸術家として突出し、実際の個々の表現者、生産者は媒介者によって組織されるための素材そのものになってしまう恐れがある。もちろん、芸術家という代表、特権的な主体を排除できないと考えられてしまうとすればですが。反対に、こうした特権的な主観を先験的構造の中に位置づけ、解消しようとしたと見れば、イッテンや賢治は、その認識も、その存在もとても大きかったことになると言えますね。つまり構造主義につながる視点がそこにあった。
松浦 ― たしかに二十世紀のある種の芸術家のイメージは、能産的に何かを無数に産出する天才というよりも、媒介者という位置、ないしメタファーがもっとも的確なような気はします。たとえばシュルレアリストの場合でも、霊媒者への自己同一化というか、それこそ闇の領域の言葉を自分の身体を通過させることによって、それを昼間の言葉に置きかえるような、媒介者の位置の確保への意志が見られます。あるいはクレー自身の用いた言葉の中にも、媒介者としての「木の幹」という比喩があるね。岡崎乾二郎 / 松浦寿夫『絵画の準備を!』
このように、純粋知覚—純粋受動性の戦略というのは、二十世紀の美術史の中に散見されるが、ここで二人が行なっている批判は、ウィラースレフが行なったハイデガー—インゴルド的な「世界への完全な一致」という戦略への批判と同質の関係にある。単純に同化する一元論的な神秘主義に居座ることはできない。もちろん分離的な二元論を肯定することなど不可能である。二元論でも一元論でもない不安定な場所を維持することが求められているのだ。作りつつ、作られ、作られつつ、作ること。宮川が鏡≒本として、あるいはウィラースレフが二重のパースペクティブ、不安定な魂の統御と言った、その魅惑と危険に満ち満ちた場所に立ち続ける技術である。
[4]常識と共通感覚
二重拘束的方法論というとき、一つの疑問が湧いてくる。主体—対象—属性的な日常的視覚でもなければ、自己を媒体とする一者への同化でもない〈あいだ〉の場所。単に日常的な知覚に居座るのでもなく、霊媒者としての芸術家の位置を獲得するのでもなく、その間の揺らぎの中を、生と死の揺らぎを生きなければならないということは分かった。そして、先に挙げたデュシャンのレディメイドの戦略は、岡崎曰く、自明性を露わにすることを媒介に、僕たちを純粋知覚へと進ませるものであった。しかし、自明性を露わにすることは、即、純粋知覚へと飛躍可能なのだろうか。私と非—私の裂け目から見える、それを可能にする場所、それ自体が問われなければならない。
ここからは、中村雄二郎の『共通感覚論』の議論を検討していきたい。中村は、〈コモン・センス〉という言葉がもともと持っていた二つの意味を検討することを通じて、自明性が露わになった場所に辿りついているように思う。
常識とは、私たちの間の共通の日常経験の上に立った知であるとともに、一定の社会や文化という共通の意味場のなかでの、わかりきったもの、自明になったものを含んだ知である。ところが、このわかりきったもの、自明になったものは、そのなんたるかが、なかなか気づきにくい。常識の持つ曖昧さ、わかりにくさもそこにある。その点で、さきにふれたデュシャンとケージの企てが、〈芸術作品〉の通念(約束事)の底を突き破り、そこに芸術の分野で、日常化された経験の底にある自明性をはっきり露呈させたことは、甚だ興味深い。この場合、日常経験の自明性が前提とされ、信じられていなければ、その二つの企ては共にもともと根拠を失い、〈作品〉として成り立たないだろう。しかしながら二人の作品の場合、そのような日常経験の自明性は、もはや単に信じられているのではない。信じられていると同時に、実は宙吊りにされ、問われているのである。中村雄二郎『共通感覚論』
このように、中村もマルセル・デュシャンについて注釈を加えることから議論を始めている。まずは彼が示す〈コモン・センス〉についての二つの側面を見てみることにしたい。
日常経験は、多くのわかりきったこと、自明なことの上に成り立っている。そのために、もっとも身近なものでありながら、かえってありのままにはとらえにくい。あまりにも身近で、多面的で、錯綜しているために、距離をとって一定の視点からとらえることができない。ここで要求されるのは、なによりも総合的で全体的な把握、それも理論化される以前の総合的な知覚である。その点からいうと〈常識〉は、現在ではあまりその知覚的側面が顧みられないでいるが、まさに総合的で全体的な感得力としての側面を持っている。常識とは〈コモン・センス〉なのであるから。というより、ふつういう常識とは、この〈コモン・センス〉の一面をあらわしたものにすぎない。たしかにコモン・センスには、社会的な常識、つまり社会のなかで人々が共通(コモン)に持つ、まっとうな判断力(センス)という意味があり、現在ではもっぱらこの意味に解されている。けれどももともと〈コモン・センス〉とは、諸感覚(センス)に相わたって共通(コモン)で、しかもそれらを統合する感覚、私たち人間のいわゆる五感(視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚)に相わたりつつそれらを統合して働く総合的で全体的な感得力、つまり〈共通感覚〉のことだったのである。
この共通感覚のあらわれをいちばんわかりやすいかたちで示しているのは、たとえばその白いとか甘いとかいう形容詞が、視覚上の色や味覚上の味の範囲をはるかにこえて言われていることである。すなわち甘いについていえば、においに関して〈ばらの甘い香〉だとか、刃物の刃先の鈍いのを〈刃先が甘い〉とか、マンドリンの音に関して〈甘い音色〉だとか、さらに世の中のきびしさを知らない考えのことを〈甘い考え〉だとか、など。またアリストテレスでは、共通感覚は、異なった個別感覚の間の識別や比較のほかに、感覚作用そのものを感じるだけでなく、いかなる個別感覚によってもとらええない運動、静止、形、大きさ、数、一(統一)などを知覚することができるとされている。その上、想像力とは共通感覚のパトス(受動)を再現する働きであるともされている。さらにすすんで、共通感覚は感性と理性とを結びつけるものとしてもとらえられている。中村雄二郎『共通感覚論』
彼は、ここで〈コモン・センス〉が本来持っていた二つの意味、〈常識〉と〈共通感覚〉を取り出している。〈共通感覚〉は、アリストテレスが用いていたように、五感を跨りそれを統合する感得力であり、感性と理性を結びつけ、想像力を司る場所であると言われる。そして、そこから広く一般に、人々に共有され制度化された判断が常識と言われるものになったのである。つまり、共通感覚とは一種の統合作用であり、それは生成を司るものである。そして、それが静的に固定化されたものが常識なのだ。つまり、デュシャンの例で中村が露わにしたのは、表層を覆う〈常識〉を剥ぎ取った先に見える〈共通感覚〉である。
『共通感覚論』の素晴らしいところは、この〈共通感覚〉という場を見出すだけでなく、それがどのようなものなのかという問いへと、さらに突き進んでいくことにある。例えば、先のデュシャンのレディメイドについて、僕は自明性を剥ぎ取ることが純粋経験へと繋がるのか、という問いを投げかけておいた。中村は、「〈社会通念としての常識〉は、多面性を持った豊かな現実、変化する生きた現実を十分に捉ええないものとして問われ、打破されねばならない。けれども、だからといってまったく無用なものであるどころか、私たちにとって社会生活上なくてはならないものであって、むしろ〈豊かな知恵としての常識〉へと自己脱皮するための前提となっている」と言う。どういうことだろう。
中村はここで、精神病理学者ブランケンブルクの論文「〈コモン・センス〉の精神病理学序説」と著書『自明性の喪失』を参照しながら、議論を深める。ブランケンブルクの患者であるアンネ・ラウは、「私に欠けているのは、きっと自然な自明さということなのでしょう」「私に欠けているのは何なんでしょう。ほんのちょっとしたこと、ほんとにおかしなこと、大切なこと、それがなければ生きていけないようなこと」と言う。アンネの症状は寡症状性分裂病の症例として、とくにその自己陳述として完璧に近いものだとされている。彼女の意見を元に考える限り、アンネの病状は、自明性を欠いていることにある。しかし問題は、自明性を欠いた先にあるのが、活き活きとした現在としての純粋経験などではなく、現実と生命的接触を欠いた(ミンコフスキー)生だということである。つまり、常識や自明性を剥ぎ取ることは、直接的に純粋経験へと辿りついたりしないのである。ここでアンネが失ったのは、本当に自明性なのだろうか。中村はそうではないと結論づける。
この問題を考える上で、中村が〈コモン・センス〉を、静態的な社会〈常識〉としての側面と、それすら含め五感を貫通し統合する理性と感性を繋ぎ、想像力を司る場所としての〈共通感覚〉とに分けていたことが重要になる。彼は次のように言う。
アリストテレスが〈共通感覚〉として名づけたこの基本的な感受性は、人間と世界とを根源的に経路づけ、僕たちがそもそも〈世界〉といわれうるものを現前させる働きをもっているのだ。そしてこの感受性が欠けるとき、〈世界〉は単なる〈感覚刺激の束〉としてただ僕たちの感覚表面につきささってくるカオスにすぎなくなる。われわれの方からそれを積極的に〈世界〉として構成することがどうしてもできなくなる。すでにアリストテレスは〈共通感覚〉を〈構想の能力〉と見なしたが、この〈構想〉とは単なる想像や空想の意味をこえて、現勢的な構成的知覚に際していつでも一緒に働いているものなのだ。中村雄二郎『共通感覚論』
アンネが喪失したものは〈常識〉としての自明性ではない。〈常識〉をそのたびに構成している〈共通感覚〉を喪失しているのである。僕たちの議論に合わせて整理すれば、私—対象—属性という〈常識〉的な認知の在り方は毎回同じように〈共通感覚〉が構成してくれるから、その事実を忘却している限りにおいて〈常識〉なのである。〈共通感覚〉の部分集合として〈常識〉があるのだ。
デュシャンがレディメイドの戦略で露わにしているのは、自明性の基盤ではない。それが僕たちに開示しているのは自明性を生成する〈共通感覚〉の場であり、異なる知覚への可能性の中心なのである。そして、お分かりの通り、これは僕が宮川やウィラースレフを経由することで定義した「制作的空間」と同じ場所である。ここまでの中村の議論では、〈コモン・センス〉の二つの側面、〈常識〉と〈共通感覚〉、静態的な枠組みとそれを含めて生成する動態的な機能が示されただけであり、そこへの経路、つまり「制作」という側面はまだ見えてこない。しかし後に、中村もその経路について示すことになる。先に進めよう。
[5]〈共通感覚〉から五感の組み替えの歴史へ
カール・マルクスは『経済学・哲学草稿』の中で、「五感の形成は、現在に至るまでの全世界史の一つの労作である」と言った。僕は、この言葉に「制作」を考える上での二つのヒントが隠されていると思う。一つには、五感は形成されたものであるという点。そしてもう一つには、全世界史の〈一つ〉の労作であるという点である。あえて記述される〈一つの〉という言葉には、〈別の〉という暗示が込められている。中村雄二郎『共通感覚論』は、上記の〈共通感覚〉の発見から、五感の組み替えという議論へと進む。それは別の身体の制作へと繋がる重要な論点である。
中村は「五感の形成は歴史のなかで行われ、感性は歴史的なものであるという考え方は、これを私たちの観点から、つまり知覚を共通感覚の働きとして捉えなおすとき、もっと別のかたちで展開することができるのではないだろうか。……人間感覚の歴史的な形成と変化とを、知覚の深層の歴史として捉える視点が得られるだろう。五感そのものの洗練と組み替えによる、緩慢で非連続な人間の知覚の深層の歴史、としてである」と言う。そして、その具体的な例として、近代の初めに行われた〈五感の階層秩序の再編成〉を紹介する。
ヨーロッパ中世世界では、もっとも洗練された感覚は、すぐれて知覚的な感覚、世界のもっとも豊かな接触をうち立てる感覚とは、なにかといえば、それは聴覚であった。そこでは視覚は、触覚のあとに第三番目の位置を占めていたにすぎない。つまり五感の序列は、聴覚、触覚、そして視覚の順であった。ところが近代のはじめになって、そこに転倒が起こり、眼が知覚の最大の器官になった。見られるものの芸術であるバロックが、そのことをよく示している。では、中世世界ではなぜ聴覚が優位を占め、視覚が劣位におかれていたのであろうか。それは一方で、キリスト教会がその権威をことばという基盤の上においており、信仰とは聴くことであるとしていたからである。聴覚の優位は十六世紀においても、神学に保障されてまだ強かった。《神ノ言葉ヲ聴クコト、ソレガ信仰デアル》、《耳、耳だけが〈キリスト教徒〉の器官である》とルターも言っている。それだけではない。それとともに他方で、視覚は触覚の代理として官能の欲望に容易に結びつくものと考えられたからである。スペインの聖者フアン・デ・ラ・クルスの先駆者たちの一人は、自分の眼で見るものをなんと五歩以内のものに限り、それを越えてはものを眺めてはならない、としていた。イメージにはなにか自然のままのもの、つまり規律的な道徳を破るところがあると考えられていたのであった(ロラン・バルト『サド、フーリエ、ロヨラ』)。
ルネサンスの〈五感の階層秩序〉のなかで聴覚と視覚の位置が逆転し、視覚が優位化したことは、たしかに自然的な感性としての官能が解放されたことと結びついている。ところが、近代文明は、触覚と結びついたかたちでの視覚優位の方向では発展せずに、むしろ触覚と切りはなされたかたちでの視覚優位の方向で展開された。近代文明にあっては、ものや自然との間に距離がとられ、視覚が優位に立ってそれらを対象化する方向に進んだのである。近代透視画法の幾何学的遠近法や近代物理学の機械論的自然観、それに近代印刷術は、その方向の代表的な産物である。と同時に、その方向を強力におしすすめたものであると言えよう。そうしたなかで、時間も空間もすべて量的に計りうるものだと考えられるようになり、その結果、人間の時間も空間も宇宙論的な意味を奪われ、非聖化された。また、遠近法にもとづく錯覚が利用されて、一般に視覚上或る一点が固定され、そこに収斂するように描き出されたものこそが眼に見える、秩序だった、永続的なものであるという幻想がつくり出された。中村雄二郎『共通感覚論』
この引用で覚えておいてほしいのは、中世から近代にかけて、聴覚中心の五感の秩序が視覚中心の秩序へと変化したことと、その視覚の在り方が、触覚と結びついた形で発展したのではなく、切り離される形で進んだということである。これは、主体—対象—属性という認知の在り方が近代において成立したことを意味している。中世から近代にかけて五感の組み替えがあったことについては、中村雄二郎だけでなくさまざまな論者がそれぞれの視点から論じている。その中で最も示唆的であったのは、理論物理学者ゲーザ・サモシが『時間と空間の誕生』という本の中で論じていることである。
重要で新しい種類のシンボルによる時間と空間と、それによる新しい人間の宇宙像は、十七世紀の実験科学の誕生とともに展開した。科学革命である。最初の実験科学は時間や空間の中の世界を数学による数量というシンボルで記述し、これらの数が興味深い実験と観測によって見い出されうると考えた。「実験的方法」は、よく知られるようになっているように、人間の感覚が正しく用いられれば外界から信頼に足る情報を得ることができ、数学と言語はシンボルによる時間や空間の一般法則を数式化するために用いられうるという考えに基づいている。この考え方は類まれなるもので、それ以前には似たようなことが系統だてて行われたことはなかった。
感覚を時間や空間での数量的な法則、秩序を見出すために用いるという発想が諸科学を生んだのである。しかしその発想そのものは科学から生まれたわけではなく、むしろ芸術に源を発している。物理学における実験という方法が生まれるよりも約四世紀前に、多声音楽が西欧で発展し、それとともに音楽のリズムをそろえるための記譜法がもたらされた。この方法は歴史上初の数に基づく、周囲とは独立した、正確なシンボルによる時間の測定を可能にしたのである。これがうまく行ったことで、正確で信頼しうる方法で短い時間間隔を数えれば数を用いて時間の経過を記述することが可能だということがはっきりわかったのである。このように、科学で計測されるあるいは数学的な時間が用いられるようになるはるか以前に、音楽家によってそれは発明され、定義され、用いられ、研究されていたわけである。
他方、視覚芸術の方は、空間の知覚を表す法則の発見という形で役に立った。科学で実験という方法が確立する二世紀ばかり前に、人間の最も重要な空間感覚である視覚に関する洗練された数量的規則が立てられたのである。イタリア・ルネサンスの画家たちは、幾何学法則を視覚の法則にあてはめ、それにより歴史上初めて、高度にリアルな絵の創造が可能になったのである。この結果は、人間の空間や空間にかかわる性質の知覚においては、視覚が数学法則に正確に従っているということを強く示したのである。
西洋文明が扱う文化史家がこぞって認めると思われることは少ないが、そのうちの一つは、三つの重要な発展が西洋文明にのみ発生し、根づき、花開いたという点である。その三つは多くの面で西洋の文明の特徴となっている。その三つが、多声音楽、透視図法による絵画、実験科学である。めったに気にとめられないことではあるが、この三つがいずれも、基本的には同じ技術上の問題と取り組むことで生まれてきたというのは特筆すべきことである。その問題とは、時間間隔、空間的な隔たり、それらの様々な関係について、信頼しうる尺度を見出すための感覚の使い方ということである。つまり、知覚される世界を、いかにして数学的秩序に従わせるかということである。また、これもめったに気づかれないことだが、この決定的な企てに関しては、芸術の方が実験科学に先んじているという点も特筆すべきことである。
この西洋の芸術と科学での問題は、おおよそ十三世紀の半ば(多声音楽の始まり)から、十七世紀末のアイザック・ニュートンの時代(科学革命の仕上げ)にかけて、徐々にではあるが着実に解決されていった。この新しい発展は、シンボルによる時間や空間の新しく強力な体系を生み出し、それが世界の新しい知覚のしかた、理解のしかたにつながったのである。先にも触れたように、この新しい宇宙像は、人々が意識して自分の五感を信頼し、直接の感覚印象が性質についての主な情報源になるのと並行して展開した。これがこの時期に、知られる限りでは歴史上初めて、しかもただ一度起こったのである。ゲーザ・サモシ『時間と空間の誕生』
重要な箇所なので長い引用になったが、今では近代主義とされている特徴が中世、ルネサンス期に準備されたことだけでなく、その五感の組み替えが芸術によって率先して行われたことが、ここで示されている。繰り返し言うように、デュシャンの戦略は〈共通感覚〉という隠された生成の場を開示することであった。そして〈共通感覚〉は、僕たちが前提としている自明性を生み出すものであるが(その場合には〈常識〉と呼ばれる)、他方で新たな五感の秩序をも生み出すものである。要するに「制作」とは、この〈共通感覚〉という暗闇へと降りていき、新たな五感の秩序を形成すること、それぞれの身体を独自の身体として生成することにあるのだ。
事前にある「私」を「私と非—私」へ切り裂き、その裂け目へと降りていくこと。「私が私ではなく、私でなくはない」場所で、媒体と対話する中で偶然と戯れ、よろめきながら往還運動を続けること。その危険と魅惑に満ち満ちた不安定な場所で生き抜き、新しい私を立ち上げ続けること。中世から近代にかけて開発された多声音楽と透視図法による絵画は、まさにこの新たな感覚、新たな身体の制作によって/と共に制作されたのであった。そして、ここまでで、僕たちは、デュシャンのレディメイドの戦略が、彼の制作の終わりではなく、始まりにすぎなかったことを理解できる。なぜなら、〈常識〉を解除し〈共通感覚〉の場を開示すること、それはそこから新たな身体の制作が始まることなのだから。
[6]諸感覚の新しい配分比率
中村は「近代世界での視覚の独走と専制支配に対して、触覚や聴覚の回復を図ること、その方向で五感の組み替えを行なうことの必要性は増している」と言う。なぜか。それは、現代が、次々と新たに現れるテクノロジーによって、五感の組み替えを強制する時代だからである。しかし、この事実は自然への回帰を推奨するものではない。そうではなく、このようなテクノロジー環境こそが僕たちにとっての自然なのであり、〈共通感覚〉を麻痺させるのではなく、〈共通感覚〉を活性化し、それぞれの五感の組み替えを制作することが推奨されるのである。
レオナルド・ダ・ヴィンチが自然を観察することを何よりも重視したように、僕たちはこの「第二の自然」(タウシグ)の生成を観察することを重視しなければならない。テクノロジーを嫌悪したり忌避したりしている場合ではないのである。1979年に『共通感覚論』を刊行した中村が存命なら、2018年現在のテクノロジーに対する熱狂を見て何と言うだろう。現在は、彼が危惧していた時代よりもさらに増して、それぞれが諸感覚の新しい配分比率を制作する必要性が高まっていると言えるのではないか。
ここにおいて必要なことは、人間拡張としての技術手段あるいは媒体のひき起こす感覚の〈麻痺〉や〈閉鎖〉をこえて、五感を組み換え、諸感覚の新しい配分比率を発見することである。新しい技術の衝撃によって、変化を蒙るのは、部分ではなく全体としての組織である。すなわち、ラジオの影響は視覚に及び、写真の影響は聴覚に及ぶ。新しい衝撃が加わるごとに、感覚全体の配分比率が変化する。今日われわれが求めているのは、心理的、社会的見地から感覚の配分比率の変化をいかに統御するかという方法である。あるいは、そのような変化をすべていかに避けるかという方法である。ここにおいて、物事を全体的に把握する人間として、芸術家の存在が重要な意味を持ってくる。
新たな技術の打撃でわれわれの意識の働きが麻痺してしまうまえに、芸術家は感覚の配分を調整することができる。彼らは、麻痺と識域下の動きや反応がはじまるまえに、感覚を正すことができるのである。事実、芸術家たちは、すでに百年以上もまえから、〈諸感覚を統合する〉神経組織の役割を触覚に与え、それによって電気時代の挑戦に応えようとしてきた。とくにセザンヌ以来、触覚は、芸術作品に一種の神経組織あるいは有機的統一を与えるものとして、芸術家の心をとらえてきた。その後、触覚の働きが美術において持つ重要性は、バウハウスの感覚教育のプログラムをはじめ、パウル・クレーやワルター・グロピウスその他、1920年代のドイツの多くの芸術家たちの仕事によって、広く一般に知られるようになった。そして、そのような電気時代への応戦は、逆説的にも〈抽象芸術〉によって、つまり古い絵画的イメージの因襲的な形骸ではなく中枢神経組織を作品にもたらす抽象芸術によって、はじめて成就された。人々はいまや、人間という統合的存在によって、触覚がこれまでよりもいっそう必要であることを感じてきている。宇宙船のカプセル中で無重力状態におかれた乗務員は、この統合的な働きをもつ触覚を保つためにたいへんな努力をしなければならない。おそらく触覚とは、ものとの皮膚接触にとどまるものではなく、精神のなかで、ものが持つ生命そのものと触れ合うことではないだろうか。古代ギリシャ人は、一つの感覚を他の感覚に変換し、人間に意識を与える共感覚あるいは〈共通感覚〉の能力を想定していた。と、このようにマクルーハンは言っている。中村雄二郎『共通感覚論』
ここにおいて、なぜ僕が鏡≒本の空間、〈共通感覚〉の場を「制作的空間」と名づけ直すかを、より明確にできる。中世において芸術家によって準備された身体は、近代において一般化され、常識となった。それはまた〈共通感覚〉を覆い隠す〈常識〉になったのだ。しかし、さらにそこから、近代はそれに対して新たな身体を作り出していた。中村は「セザンヌ以降、触覚は芸術作品に一種の神経組織あるいは有機的統一を与えるものとして、芸術家の心をとらえてきた。〈抽象芸術〉によって、つまり古い絵画的イメージの因襲的な形骸ではなく中枢神経組織を作品にもたらす抽象芸術によって、はじめて成就された」と言う。
芸術家とは「作品」を作る人を指すのではない。上記のように、「作品」は、あくまで「制作」という媒体との対話を通じて、私と非—私が不安定に循環し、私と対象それ自体を生成し、その中で〈あいだ〉に生じるものが〈形〉として外在化されることで、外側から見たときに「作品」と呼ばれるだけのことなのだ。それは同時に「作者」と「読者」を生む。しかし、それは副次的なことである。重要なことはそれぞれの諸感覚を再構成すること、それぞれの身体を制作することである。毎月のように発表される新たなテクノロジー、そして変わっていく環境。それは僕たちのコントロールを超えている。僕たちの身体は次々と無意識のうちに変更される。
僕たちは今、自覚的に、この諸感覚の配分比率へ介入することを求められている。中村はその役割を芸術家に与える。しかし、僕はそれを、皆がもつべき技術であると思っている。これは皆が制度的な意味で芸術家であるべきだと言っているのではない。非制度的な意味で芸術家であるべきだと言っているのだ。環境によって身体を作られるな。作られつつ、作ること、作りつつ、作られること。受動的な状態から往還的な状態へ移行すること。能動的な状態ではない。それは幻想にすぎない。自分勝手な幻想を媒体に投影するな。媒体には媒体に固有の特性がある。媒体と対話することで私と対象の双方が生成される。事前にすべてを把握する主体は存在しない。だからこそ僕はこのエッセイを通じて、「制作的空間」とは何かを詳細に記述したいのだ。そして皆を誘惑したい。自己同一性が分裂する危険な場所へ、魅惑的な場所へ。何よりも僕自身の新たな身体への足場として機能させるために。そして、それがいつか、どこかで、誰かの足場として機能することを祈って。
[7]諸感覚の〈体性感覚〉的統合
先の中村の記述について、僕が意図的にまだ語っていない部分がある。それは、中村が触覚を特権的に扱っている点である。彼は近代世界の中で視覚の絶対的優位に疑問を投げかけた人物として、ジョージ・バークリーとコンディヤックを挙げる。そして、「距離そのものは見られない。遠くにある物体との距離の見積もりは感覚ではなくて、むしろ経験にもとづいた判断の働きである」というバークリーの言葉や、「視覚だけによっては、ひとは空間についての観念も位置についての観念も大きさや運動観念も持ちえず、眼にそれらを見ることを教え込めるのは触覚だけである」というコンディヤックの言葉を引用しながら、視覚を基礎づけるものとしての触覚という論点が、近代の只中にも生じていたことを示す。
また、コリングウッドの「そこへセザンヌがやってきて、あたかも盲目の人のように描くことをはじめた。彼の天才のなんたるかをよく示している静物画のデッサンは、あたかも両手で探りまわされた物体のようである」という記述を引用し、「セザンヌにあるのは絵画における〈触覚〉の回復」であり「運動する〈触覚〉である」と言う。そしてセザンヌ以降、「普通考えられているよりもはるかに大きく触覚的なものの重視の上で近代絵画が成り立っている」と言う。中世の聴覚中心の身体から、近代にかけて芸術家が制作してきた身体を視覚中心のものとするなら、近代のまさに中ほどで哲学者や画家たちが取り組んできたのは、視覚から触覚優位への身体の編成であったということを、中村は言いたいのである。
もちろん、この視点は一面的であり、近代美術史に詳しい人であれば、反論や反例を示すことは容易かもしれない。しかし、最後まで彼の議論を追ってみることにしよう。そうすることで、彼がなぜ触覚優位の五感編成を推奨しているのか、その理由が分かるはずである。そのために、これまでの議論よりも五感について解像度を上げなければならない。僕は、ここまで無批判に五感という用語を用いてきたが、現在最も広く近代生理学で用いられている分類は、もう少し入り組んだものになっているようである。
現在最も広く用いられている感覚の分類(勝木保次)によると、諸感覚は特殊感覚(視覚、聴覚、嗅覚、味覚、平衡感覚)、体性感覚(触覚、圧覚、温覚、冷覚、痛覚、運動感覚)、内臓感覚(臓器感覚、内臓痛覚)という三つに分けられる。そして、第一のグループの特殊感覚とは、脳神経によって信号の伝達されるもの、つまり脳神経連絡の諸感覚であり、次に第二のグループの体性感覚とは、体性脊髄神経によって伝達されるもの、つまり脊髄連絡の諸感覚であり、最後に第三のグループの内臓感覚とは、内臓神経によって伝達されるもの、つまり内臓連絡の諸感覚であった。
このような三つのグループの伝達・連絡経路をみると、第一のグループの特殊感覚が純脳型で直接に大脳に伝えられるのに対して、第二のグループの体性感覚が四肢へと広がる脊髄神経をとおして大脳に伝えられることが示されている。また、第三のグループの内臓感覚は、体性感覚が脊髄神経系の内部知覚であるのに対して、自律神経系の内部知覚であるということになる。自律神経も脳から出て内臓に分布している。けれども、その脳の部分というのは、大脳皮質ではなくて脳幹と呼ばれるところなのである。この自律神経系の内部知覚は、視覚や聴覚などの特殊感覚にくらべてはもちろんのこと、体性感覚にくらべても漠然として曖昧である。それというのも、この場合、内臓感覚神経からの情報が間接的に、拡散したかたちでしか脳幹を含む皮質下中枢に伝えられないからである。そして体性感覚は、すでに述べたように、無意識のまとまりと結びついた諸感覚の遠心的な統合の働きを持っている。けれども、体性感覚がその働きを十分に発揮するためには、このもっと無意識的で暗い内臓感覚に根を下ろす必要があるのだろう。
昔からただ触覚といわれたものは、単に皮膚の接触感覚にとどまらない体性感覚の一つであり、それは、同じく体性感覚に属する筋肉感覚や運動感覚と密接に結びついて働くものであった。かつて触覚とされたものを、このように体性感覚として捉えなおしたのは、もとより狭い意味での触覚までも体性感覚に還元するためではない。そうではなくて、狭義の触覚も、体性感覚の一つとしてその基盤の上に、筋肉感覚や運動感覚と結びついてはじめて、具体的な触覚として働くことを明らかにするためであった。このようなわけで、触覚を以て昔からよく五感を総合するものといわれてきたけれども、それはいわゆる触覚、ふつういう意味での触覚のことではなくて、実は、触覚に代表された体性感覚のことだったのである。中村雄二郎『共通感覚論』
彼は〈触覚的〉という概念を、上記のように近代生理学の成果を用いて再定義する。中村は、セザンヌを「絵画における〈触覚〉の回復」と言い、彼の絵画には「運動する〈触覚〉」があると言った。しかし、彼は今や〈触覚〉を〈体性感覚〉と、〈運動する触覚〉を〈運動する体性感覚〉と言い換える。そして、「風景を分解する印象派の外光描写をこえて、セザンヌは体性感覚を重視し、〈盲目の人のように〉静物や風景を描いたのであった。それというのも、印象派の外光描写によっては自然のもつ生命そのものに触れえないことに気がついたからである」 と言ってのける。彼が〈触覚〉を〈体性感覚〉と再定義した理由は、〈体性感覚〉が〈触覚〉という表層との接触だけでなく、内(筋肉感覚や運動感覚)と外(触覚)を繋ぐものであること、そして筋肉感覚や運動感覚に代表されるような動態的な感覚であることを強調するためである。それは、中村による「この風景を分割する印象派の外光描写」と「セザンヌの自然のもつ生命そのものに触れるような運動する体性感覚」という対比に示されている。そして中村は、「自然のもつ生命そのものに触れる」ことが、体性感覚を優位にすること、あるいは活性化することによって可能になると考えているのである。
[8]一つの点ではなく一つの円であるような私について — 主語的統合と述語的統合
[2]において、僕は西田幾多郎の「場所」という論文を引用することで、次のように宣言していた。主語的統一ではなく述語的統一へ、一つの点ではなく一つの円であるような私について記述したいと思っていると。そして、ようやくここで、僕は「点ではなく円である私」の輪郭を示すことができる。
中村が〈触覚〉を特権的に扱う理由は、彼が〈触覚〉を〈体性感覚〉という筋肉感覚や運動感覚を含めたものとして考えていることを配慮しなければ分からない。〈体性感覚〉は〈触覚〉という表層感覚であると共に、〈筋肉感覚〉や〈運動感覚〉は深層感覚でもあるので、一方では〈視覚〉、〈聴覚〉、〈嗅覚〉、〈味覚〉などと結びついて外部世界に開かれており、他方では〈内臓感覚〉と結びついて暗い内部世界への通路を持っている。〈体性感覚〉は、このように外部世界と内部世界を繋ぐ〈あいだ〉の場所である。知覚を〈五感〉による外界からの感覚刺激だとすれば、知覚は受動的であると考えざるをえないが、現実の知覚は言うまでもなく空間の中での運動を伴っている。対象を触ったり、振ったり、押したり、叩いたりすることで、その対象から情報を引き出している。
佐々木正人は『知性はどこに生まれるか』という著書で、アメリカの心理学者ジェームス・ギブソンのアフォーダンス理論について解説している。そこで説明されるのは運動の中での知覚である。これまでの知覚理論が不動の定点から五感に基づいた受動的な知覚を扱ってきたとすると、ギブソンが扱うのは双方がバラバラに運動する中での知覚である。例えば、眼の前にアルミニウムの1メートルの棒があるとする。これまでの知覚理論であれば、定点から頭も首も固定した状態で観察することが求められ、「この棒はだいたい1メートルである」とか「この棒は、つるつるとしていて硬そうである」とか、五感のどれかに基づいた情報を引き出すことを期待された。しかし、それは僕たちの通常行っている知覚の在り方とは大きく異なる。なぜなら、見るとき、僕たちは身体や首や頭の向きを動かしたりしながら見ているからである。僕たちは眼で見るのと同様の記述情報(長さや硬さ)を、棒を振ったり、押したり、叩いたりすることで、眼をつむっていても引き出すことができる。このように動かすことで、変化の流れの中で変化にもかかわらず、モノの変わらない性質(不変項)を見出すことを、アフォーダンス理論ではダイナミック・タッチと呼ぶ。
ダイナミック・タッチにおいて、環境自体が持続と変化をもったものとして扱われる。その持続と変化の中で、僕たち自身も運動しながら、「変形」と「不変」を受け取ることで情報を得る。先ほどの棒の例で言えば、僕たちは、実際にさまざまな仕方で振ってみることで、その棒を曲げたり折ったりしなくても、どのくらいの力で、どのくらいの遠心で振ると、この棒が曲がるのか折れるのかという、より具体的かつ実践的な情報を掴むことができる。もちろん、そこで得られる情報の質と量は、動かす主体の経験値によって左右される。普段からアルミニウムの棒を扱う仕事をしている人と、初めて触る人では、ダイナミック・タッチから得られる情報に差がある。初めて陶芸をしてみる人と、熟達した陶芸家とでは、泥に触れるときの腕の動きとそれに伴う泥の変化と不変をまったく異なる質で受け取っていることは、実際に陶芸家に会ったことがなくても想像できるはずである。そして、得られる情報は身体との循環構造を作り出す。流れの中で得られた情報によって、身体が制御され、その制御によって、また異なる情報が流れの中から得られるのである。佐々木は次のように言う。
行為の未来をつくりだすことは、行為がじょじょに露わにする環境の変化の中にあるというわけだ。未来、ただし探索する行為がなければ存在しない未来であるが、それは進行している行為が露わにする環境の変化に知覚されている。つまり行為はこれから起こることを「予期する情報」をつくりだしている。行為はそれが探索し、これから発見することになることによって創造されている。佐々木正人『知性はどこに生まれるか』
「制作」とは、実際にやってみることで「未来の情報」を生み出しながら、その次へと進んでいく、あるいは引き返していく往還運動なのである。あらかじめすべての情報が客観的にあるわけではない。未来がある。ただし、探索する行為がなければ存在しない未来なのである。未来は、経験と行為によってそれぞれに創造される。まずは「制作」してみること、そうすることで僕たちは「制作的空間」へと入り込んでいくのだ。
『共通感覚論』が出版された当時、まだジェームス・ギブソンの議論は日本にほとんど紹介されていなかったので、ここでギブソンが参照されることはなかっただろう。にもかかわらず、僕が佐々木の議論を紹介したのは、動きの中での知覚を別の視点からも捉えるためであった。中村はギブソンと同様、身体運動にも焦点を当てはするのだが、これから説明するように、彼の関心の中心は、運動感覚がいかに知覚そのものを生み出す基体として機能しているかという点にある。しかし、「制作」というこのエッセイの目的から言えば、「諸感覚の基体的統合」だけでなく「行為によるそれぞれの未来の創造」という論点は、是非とも紹介する必要があった。視覚中心の知覚ではなく、身体中心の知覚を理解する上で、この二つの側面は外せなかった。一つは「行為によるそれぞれの未来の創造」という点が、「制作」を媒介として「制作的空間」へ入って行くという議論を裏づけるものであり、もう一つは「諸感覚の基体的統合」という点が、「制作的空間」の内部を記述する上で必要だったからだ。
中村はギブソンではなく、ベルクソンの「運動図式」とメルロ=ポンティの「身体図式」の考え方を元に思考する。これまでの議論と「身体図式」の考えを組み合わせることで、「諸感覚の基体的統合」の役割を身体に持たせているのだ。まず「運動図式」とは、「人間の身体は、生の有用性のために組織され習慣化された〈感覚—運動機構〉として捉えることができる。それは、生理学的な意味で、求心性の感覚神経回路と遠心性の体性つまり運動神経回路との連動機構であるにとどまらない。そうではなくて、主体の行動への身構え、つまり能動的な意味賦与の作用、とのかかわりで働くものとしての、そのような二つの回路の連動機構」である。このように「運動図式」を、これまでの五感に基づいた受動的な知覚概念とは異なり、体性感覚とくに運動感覚の全体化の働きのうちに、内部世界の無意識に根ざした、行動への意味と方向を賦与したものであると評価する。他方で、それはまだ人間の身体のもつ受動的かつ能動的という両義性を捉え切れていないと考える。そして、運動感覚をただ単に運動感覚としてではなく、深層の内部知覚として捉え直すために、「運動図式」に加え、メルロ=ポンティの「身体図式」を持ち出すのだ。
「身体図式」は、〈運動感覚〉を表層における外部とのかかわりとしてだけでなく、深層の内部知覚としても捉えるものである。通常、身体の内部知覚は意識の表層には現れない。しかし、それは実存的な身体の本質的基盤であり、しかも外部知覚と連続している。無意識の苛立ちや内臓の機能不全が気分に影響を与え、それが知覚や行動に影響を与えることは、日常的に理解できるものである。「身体図式」は、〈体性感覚〉としての〈運動感覚〉を、外部世界に行為として表層的に関連づけるだけでなく、気分として潜在的にかかわらせている、主体的で可能的な身構えのことを指す。
このようにして、中村は内部感覚としての〈体性感覚〉という点から「身体図式」に着目することで、〈体性感覚〉が知覚あるいは五感の統合の基体であることを示す。〈体性感覚〉は、〈触覚〉、〈運動感覚〉、〈筋肉感覚〉が、すなわち内側と外側が交差的に入り組んだ場所である。そして、その場所は、表層である特殊感覚(視覚、聴覚、嗅覚、味覚、平衡感覚)と深層である特殊感覚(臓器感覚、内臓痛覚)を相渡る場所であり、だからこそ中村は諸感覚(特殊感覚)の体性的統合を〈基体的〉統合とも〈述語的〉統合とも呼ぶのである。
それが〈基体的〉統合だけでなく〈述語的〉統合と呼ばれる理由は、お察しの通り、諸感覚の〈主語的〉統合と言うべきものがあるからだ。これは〈共通感覚〉と〈常識〉の対概念に相当するものである。つまり、僕たちが暗黙の裡に用いている知覚の構造、近代図式、主体—対象—属性という構造が、〈主語的〉統合と呼ばれるもの、そして〈常識〉にあたる。それはもちろん、時代、地域、そして、芸術家の例で見ても分かるように、人によっても異なる。〈常識〉が通じないことがしばしばあるのを思い出せば分かるだろう。そして、〈述語的〉統合は、鏡≒本の空間、デュシャンが切り開いた場所、〈共通感覚〉、そして「制作的空間」のことを指している。〈主語的〉統合が、時代、地域、そして人によって異なるのは、この〈述語的〉統合が別の〈主語的〉統合を「制作」する潜勢力を持っているからである。
私たち人間の諸感覚の統合は、基体的、述語的な統合の上に成り立つ主体的、主語的な統合として考えることができる。そして、主体的、主語的統合は、基体的、述語的統合の基礎の上に成り立つとはいえ、それと同時にひとたび成り立つと、基体的、述語的統合を拘束する働きを持っている。後者を潜在的な基盤として前者が現れる一方、前者によって後者は導かれ、方向づけられる。まさにそのようなものとして、後者は基体的、述語的統合なのであり、前者は主体的、主語的統合なのである。諸感覚の体性感覚的統合が基体的、述語的統合であり、主体的、主語的統合を代表するのが視覚的統合であることはすでに述べたとおりである。中村雄二郎『共通感覚論』
重要な点は、主語的統合は述語的統合の上に成り立つとは言え、ひとたび成り立つと述語的統合を方向づけるようになるということである。つまり、主語的統合が強烈に優位になると、述語的統合が異なる身体を「制作」することを抑制するようになる。人と違うからとか、常識的ではないという理由で、違和感や差異を無視したことは誰にでもあるだろう。
しかし、ここまでの議論で、知覚の在り方そのものを「制作」する場所を、ある程度明らかにできた。僕たちは、西田的に言えば、点でもあり円でもあるのだ。ここから先は、さらに議論を進め、中村が「この風景を分割する印象派の外光描写」と「セザンヌの自然のもつ生命そのものに触れるような運動する体性感覚」という対比で示していること、つまり述語的統合を活性化させることで、「自然のもつ生命そのものに触れる」ということを考えていきたい。
[9]「ロゴス的立場」と「形式論理」が捉えられないもの — 生命、進化、偶然性
ここまで、分離する二元論と同化する一元論という二つの〈あいだ〉の場所について語ってきた。分離する二元論は、自然や生命を記述する際に区分することで、〈あいだ〉をノイズとして切り捨ててしまうし、同化する一元論は、体験によって自然や生命と同化することで「分かる」というプロセスを経るため、その体験を言葉では汲み尽くせないものとして神秘化してしまう。
ここまで僕は、どちらかの立場に偏ることではなく、その〈あいだ〉を維持することを説いてきた。もちろんその立場は変わらないが、今度は中村雄二郎がセザンヌを評して発した「生命そのものに触れる」ということを別の角度から考え直すために、生命を記述する方法や技法について考えていきたい。中村が言うように、〈共通感覚〉の活性化によって、生命そのものに触れる言語が、つまり生命の記述が可能になるなら、その可能性について考えていきたいのである。
しかし、繰り返すようだが、もう僕たちは単に純粋経験を称揚することはできない。一なる者との同化、世界との完全な一致は、今や神秘主義的とかファシズム的と形容されるものの象徴でもある。同様に、分離された二元論の問題も至るところに噴出している。僕たちはピュシス(自然)をロゴスで切り分けるのではなく、別の仕方で捉える技法を必要としている。ここから見ていきたいのはロゴスとピュシスの差異、そして形式論理とレンマ的論理という二つの論理である。
福岡伸一は『福岡伸一、西田哲学を読む』の中で、ロゴスとピュシスの差異について、「ロゴスは、自然を切り分け、分節化し、分類し、そこに仮説やモデルやメカニズムを打ち立てようとする言葉の力、もしくは論理の力である。イデアやメタファーを作り出す力である。一方、ピュシスとは、切り分け、分節化し、分類される以前の、ありのままの、不合理で、重畳で、無駄が多く、混沌に満ち溢れ、あやういバランスの上にかろうじて成り立つ動的なものとしての自然である」と言う。
また、木岡伸夫は『〈あいだ〉を開く』の中で、形式論理とレンマ的論理の違いについて、「Aと非Aの関係は、形式論理における矛盾律と排中律を前提としている。両者にとって〈中間〉は存在しない。これに対して、AとBの関係は、Aがある程度までBと共通する存在であることを容認する。この関係における両者の区別は曖昧であって、両者は分断されることなく、つながりをもつ。この意味において、差異は中間的なものを予想し、異なるものとものの〈あいだ〉が開かれている。このように、レンマ的論理では、世界をどこまでも非対立的で差異的なものの表れとして見る姿勢、すなわちあらゆる存在をさまざまな〈あいだ〉において見ようとする理論的態度が、前提されていると言わなければならない」と言う。
二人がピュシスとレンマ的論理への回帰を必要だと考える理由は、共通している。それは、切り分け、分類する思考法や、矛盾律、排中律を絶対的公理としてしまうことで、二項が互いに作られつつ/作る〈あいだ〉の場所、活き活きとした生命の生成、流れや循環を歪めて解釈してしまう、あるいは思考不可能なものへ変えてしまうと考えているからである。しかし、切り分けることでは捉えられない生命の領域と言われても、何を言っているんだ、と驚く人がいるに違いない。そこで、まずはこの領域が、僕たちの現実的な実践に深くかかわる話であることを示す必要がある。
森田真生は『数学する身体』の中で、「人工進化」という分野での興味深い話を紹介している。人工進化とは、人間が理論的に一から構成したアルゴリズムではなく、偶然性と試行錯誤という進化の仕組みを元に作られたアルゴリズムのことである。例えば、何かしらの最適化問題を解く場合、進化アルゴリズムは初めにランダムな解の候補を大量にコンピュータの中で生成し、目標に照らして相対的に優秀な解の候補をいくつか選び出す。次に、それらの比較的優秀な解の候補を元にして、さらに「次世代」の解を生成する。そして、その操作を繰り返す。つまり、各世代の「次世代」を「変異」させながら、次々と自己複製をさせていくだけなのだが、最初はランダムに選ばれた候補群であっても、上記の操作を繰り返していくと、より目標を達成できるものへ「進化」させることができる。
森田が紹介しているのは、人工進化の研究の中でも少し変わっている、イギリスのエイドリアン・トンプソンとサセックス大学の研究グループによる「進化電子工学」の研究である。通常の人工進化が、コンピュータの中の仮想的なエージェントを進化させるのに対して、彼らは物理世界の中で動くハードウェアそのものを進化させることを試みる。
課題は、異なる音程の二つのブザーを聞き分けるチップを作ることである。人間がチップを設計する場合、これはさほど難しい仕事ではない。チップ上の数百の単純な回路を使って、実現できる。ところが彼らはこのチップの設計プロセスそのものを、人間の手を介さずに、人工進化の方法だけでやろうとしたのだ。
結果として、およそ四千世代の「進化」の後に、無事タスクをこなすチップが得られた。決して難度の高いタスクではないので、それ自体さほど驚くべきことではないかもしれない。が、最終的に生き残ったチップを調べてみると、奇妙な点があった。そのチップは百ある論理ブロックのうち、三十七個しか使っていなかったのだ。これは人間が設計した場合に最低限必要とされる論理ブロックの数を下回る数で、普通に考えると機能するはずがない。
さらに不思議なことに、たった三十七個しか使われていない論理ブロックのうち、五つは他の論理ブロックと繋がっていないことがわかった。繋がっていない孤立した論理ブロックは、機能的にはどんな役割も果たしていないはずである。ところが驚くべきことに、これら五つの論理ブロックのどれ一つ取り除いても、回路は働かなくなってしまったのである。
トンプソンらは、この奇妙なチップを詳細に調べた。すると、次第に興味深い事実が浮かび上がってきた。実は、この回路は磁気的な漏出や磁束を巧みに利用していたのである。普通はノイズとして、エンジニアの手によって慎重に排除されるこうした漏出が、回路基板を通じてチップからチップへ伝わり、タスクをこなすための機能的な役割を果たしていたのだ。チップは回路間のデジタルな情報のやりとりでだけでなく、いわばアナログの情報伝達を、進化的に獲得していたのである。
人間が人工物を設計するときには、あらかじめどこまでがリソースでどこからがノイズかをはっきりと決めるものである。この回路の例で言えば、一つ一つの論理ブロックは問題解決のためのリソースだが、磁気的な漏れや磁束はノイズとして、極力除くようにするだろう。だが、それはあくまで設計者の視点である。設計者のいない、ボトムアップの進化の過程では、使えるものは、見境なくなんでも使われる。結果として、リソースは身体や環境に散らばり、ノイズとの区別が曖昧になる。どこまでが問題解決をしている主体で、どこからがその環境なのかということが、判然としないまま雑じりあう。森田真生『数学する身体』
僕がこの話を引用した理由は三つある。
第一に、それがチップ上の回路という人工的なものであっても、実在の世界は連続的であり、0と1に切り分ける二値論理からトップダウンで判断することによって見逃されてしまう領域が生じることである。自然は連続的で人工物は非連続であると聞くが、そうではない。デジタルに機能するように作られたチップでさえ、連続的なのである。生命はこの連続性の中で、偶然性と試行錯誤によって生成を行なう。しかし、僕たちは視覚中心のロゴスによって「Aと非A」に切り分けてしまう。生命は切り分けることができるわけではなく、余剰部分をノイズとして処理することで、人間にとっての「生命」を「機械」的かつ効率的に捉えているだけのことである。つまり、人工物もふくめてすべては連続的で、それを切り分けて捉える視点と連続的に捉える視点が二つあるだけなのだ。この問題については、後ほど「外在的観察」と「内在的観察」という議論として、改めて取り上げたい。
第二に、トンプソンらがこの奇妙なチップを詳細に調べることで、0と1の外側に置かれていた磁気的な漏出や磁束の機能を見出したことである。この事実は、人間がロゴスや知覚原理の外側を発見できることを示している。もしロゴスに切り分けられた認識の外側にアクセスできないのだとしたら、なぜ37個の論理ブロックだけで機能するのか、僕たちは永遠に解明できない。しかし世界には、現在その人が用いている知覚原理で現象される「強い属性」だけでなく、潜在的な「弱い属性」が満ち満ちており、注意する範囲を変えたり、カメラやレントゲンなどの装置によって知覚範囲を拡張したりすることで、その実在を確認できる。それは、人間が主語的統合だけでなく述語的統合から、別の主語的統合を「制作」することができるという事実を示している。また人間は、自らの生物学的条件に基づいて、可視光の外側にある波長を赤外線や紫外線などと名づけているが、それは他の動物にはない特徴である。人間は道具によって所与の環世界、現象の世界を超えて、実在の存在を確認し、さらにそれを述語的に統合することで新たな身体を「制作」できるのである。
第三に、ロゴスによって切り分けられた世界でのトップダウンの構築よりも、連続性の中での偶然性と試行錯誤によるボトムアップの進化の論理の方が、より最適な解を導き出すことを具体的に例示したかったのである。
[10]ピュシスへの回帰 —「外在的観察」と「内在的観察」
先ほどは、連続性を切り分けることで理解する方法、ロゴスや形式論理では捉えられない領域があることを示した。それは、生命や進化や偶然性として扱われている領域なのだが、他方で僕たちの常識とは異なり、チップなどの人工的だと思われている世界も、実は連続性の世界の只中にあるということを示した。そして部分的ながら、人間がその連続性を捉え記述できる可能性についても示してきた。では、福岡の言う「ピュシスへの回帰」や木岡の言う「レンマ的論理」は、どのような仕方でそれを捉えるのだろうか。
まず、福岡伸一は前出の書で、「生命を定義する時、生命とは細胞をもつもの、遺伝子(DNAもしくはRNA)をもつもの、代謝を行うものというように、属性を列記することでは、本質の廻りを堂々巡りするだけで生命たりえる条件に辿りつかない」と言う。例えば、「ウイルスは、DNA(もしくはRNAを)をもつが、それ自体では細胞をもたないし、代謝も行わない。こんなウイルスは生命といえるのか。それは生命をどの属性で定義するかに関わってくる」と。それは、それぞれの研究者が自らの専門に基づいて複数の属性の中のいくつかを特権化することを意味し、相対主義的な混乱をもたらすことになる。
僕はこのような「主体—対象—属性構造」に基づいた記述スタイルを、「外在的観察」と定義する。これまでの議論からすると、これは主語的統合の近代バージョンである視覚を中心化した認知の在り方と同義である。同書において、福岡と対談している池田善昭も、上記のような議論は「生命を外部の視点(立脚点、着眼点)から存在として見ている」だけだと批判し、より正確に判断しようとするなら、生命の内側から生命自体になりきってなされなければならないと述べる。そして、それが実在として生命を捉える方法であると言う。
この「生命になりきって内側から捉える」という表現には、どこか同化的な一元論の匂いがする。しかし、ここでの「内側から見る」というのは、構造でもあり流れでもある状態を捉える方法を指しており、福岡はそれを「動的平衡」という概念で提示している。「動的平衡」とはルドルフ・シェーンハイマーが名づけた言葉であるが、福岡は「福岡伸一の生命浮遊」という連載の中で、このように語っている。
シェーンハイマーは、同位体を使って生体物質の動きを可視化し、私たち生物が食べものを摂取することの意味を問い直した。一般に、生物にとって食べものとは、自動車にとってのガソリンと同じ。つまりエネルギー源だと考えられていた(今もそう捉えている人は多い)。
しかし実はそうではない。確かに食物(主に炭水化物)はエネルギー源として燃やされる部分もあるが、タンパク質は違う。私たちが毎日、タンパク質を食物として摂取しなければならないのは、自分自身の身体を日々、作りなおすためである。シェーンハイマーはこの事実を鮮やかな実験で初めて示した。
たとえば私たちの消化管の細胞はたった2、3日で作り替えられている。1年も経つと、昨年、私を形作っていた物質はほとんどが入れ替えられ、現在の私は物質的には別人となっているのだ。つまり、生命は絶え間のない分子と原子の流れの中に、危ういバランスとしてある。私が自らの生命論のキーワードとしている「動的平衡」である。それまで静的なものとして捉えられてきた生命観に、シェーンハイマーは、新しいパラダイムシフトをもたらしたのだ。
動的平衡の流れを作り出すためには、作る以上に壊すことが必要である。それゆえ細胞は一心不乱に物質を分解している。福岡伸一「福岡伸一の生命浮遊」
福岡は、生命は「この流れの中の危ういバランス」としてある、と言う。ここでいう流れとは、作るために壊すことであり、壊すことで作ることである。僕がここで、食べることを中心に「動的平衡」を説明した部分を引用した理由は、食べることという日常的な行為の意味が、不動のAという個体にエネルギーを外部から加えることから、Aが常に非Aへと変化しながらAであることを保つことへと、意味が転回するからである。ここで福岡が「危ういバランス」と言うのは、Aは非AになりつつAであるということが、非AになりつつAでないものになる可能性を常に孕んでいるからである。食べることという、とても日常的な行為でさえ、危ういバランスの中でなんとか自己同一性を維持している、非常に危険な行為なのである。
福岡は『生物と無生物のあいだ』で、「もし、やがては崩壊する構成成分をあえて先回りして分解し、このような乱雑さが蓄積する速度よりも早く、常に再構築を行うことができれば、結果的にその仕組みは、増大するエントロピーを系の外部に捨てているということになる」と言い、「流れこそが、生物の内部に必然的に発生するエントロピーを排出する機能を担っていることになるのだ」と書く。そして、「生命がエントロピー増大の法則に抗う唯一の方法とは、生命システムの耐久性と構造を強化することではなく、むしろ、そうした仕組み自体をエントロピーの流れの中に置くだけのことだった」と述べるに至る。
なぜか僕たちは、明日も、明後日も、明々後日も、同じ身体をもち、自己同一性を保ち続けることができると信じている。しかし、物質的には1年も経つと、僕は僕ではない。僕は自らを分解することで自らを構築し、自らを構築することで自らを分解する「流れ」である。そして、この「流れ」の中で構造を維持するためには、「私は私である」という自己同一性の耐久性や構造を強くするのではなく、エントロピー増大の法則による乱雑さが構造の維持を不可能にしてしまう前に、先回り的にその同一性を部分的に分解し、そして構築する必要があるように、「私は私でなく」(分解)、「私は私でなくもない」(構築)という「流れ」の中に身を置くことになる。こう言うと、言いすぎだろうか。生命は、物理的な法則を先回り的に捉え、分解と構築のリズムによって、その流れに乗ることで自らを維持している。それは、過去から現在へ、そして未来へと流れる線的な時間(エントロピー増大の法則)を内側に取り込むことで、未来から現在へと流れる時間を生み出すことであろう。なぜなら、乱雑さが増大する時間の流れを先回り的に捉えて、つまり未来を捉えて、現在において分解と構築を行っているのだから。
池田善昭は『福岡伸一、西田哲学を読む』の中で、「時間というものは過去から未来へと線的に流れるだけじゃなくて、向こう(未来)から(回って)くる時間もある」と言う。そして、このような生命の捉え方を、福岡は「内側から見る」と言っている。外側から、生命をAであるとかBであるとか切り分けることで静態的に定義するのではなく、外側の流れ(エントロピー増大の法則)と内側の流れ(分解と構築のリズム)が相互に包摂し合いながら、Aは常に非AになりながらAであるという不安定な状態を保つ構造体として、生命を捉えること。同一性ではなく、変形と流れの中で、つまり時間の中で生命を捉えること。このエッセイでは、このように流れに身を置くことで内側から生命を捉える方法を、「内在的観察」として定義する。
[11]〈あいだ〉を切り捨てず、〈あいだ〉を捉えること — レンマ的論理について
「中間」、〈あいだ〉を考えようとするレンマ的論理と、中間的なものを認めないロゴス的論理の対蹠点は、〈生〉をいかにとらえるかにある。生(ないし生命)の領域は、形式論理の同一律および矛盾律にもとづく弁別・分別を受け付けにくい独特の性格を帯びている。無生物の世界に妥当する、Aか非Aかの二者択一に対して、Aでも非Aでもないといった中間的で曖昧な様相を呈するのが、生きたものの世界だからである。木岡伸夫『〈あいだ〉を開く』
僕がレンマ的論理に注目する理由は、ロゴスによって捉えられない生命の領域を、純粋経験によってではなく、その体験を媒介に、別の言語によって捉える方法を考えるためである。流れに内在化するというのは、そのための第一歩なのだ。中村雄二郎は〈体性感覚〉の活性化を推奨したが、〈体性感覚〉が活性化した後、どのような言語がそこに現れるのか、僕はそれを考えたいと思っている。ヒントになるのは、ロゴス的論理に代えて、木岡伸夫がレンマ的論理としてまとめる山内得立の思想である。ここにはまさに、鏡≒本の空間、「制作的空間」を記述するための論理が隠されているように思えるからだ。
山内がテトラレンマの形に仕上げたのは、大乗仏教を代表する龍樹(ナーガールジュナ Nāgārjuna)による『中論』(Madhyamaka-kārikā)の根本思想である。後に詳しく見ることになるが、『中論』の核心的主張は排中律の逆転にある。
これらは「AでもなくĀでもない」という仕方での二重否定をつうじて、独特な「中」の境域を開く論理を表している。しかし、排中律の逆転だけなら、伝統的なインドの四論(四句分別)にも見られる。それは、①A、②非A、③A亦非A、④非A亦非非A、の順に立てられ、第三レンマが二重否定を表し、第四レンマが二重否定の形をとる。
これに対して山内は、四句の配列を変えるべきであり、両非(④)が両是(③)に先立つ形式こそ、レンマ的論理体系でなければならないと主張する。なぜなら、龍樹が革新的であったのは、素材としては古代インドの論理形式にほかならない四論を解体して、「AでもĀでもない」両非の第三レンマを柱とする新たなテトラレンマを構築した点にある、と解釈されるからである。
一 A(肯定)
二 Ā(否定)
三 AでもなくĀでもない(両非)
四 AでもありĀでもある(両是)龍樹の立場は、「AでもなくĀでもない」第三レンマを中心とする否定の論理である。それは、肯定を否定し、その否定をまた否定することによって肯定に還る、という意味の二重否定ではない。肯定も否定もともに否定することによって、〈肯定—否定〉の対立そのものを否定するという「絶対否定」である。木岡伸夫『〈あいだ〉を開く』
ここで木岡は「AでもなくĀでもない」両非こそが、テトラレンマを一つの論理とするための鍵を握ると言う。「論理とするために」という言葉が重要である。なぜか。それは山内が、「AでもĀでもある」という両是が先行する四論の形式は一種の直観知ではあっても、それを「論理」と呼ぶことはできない、と考えたからだ。山内はこのように考えることで、鈴木大拙が説くような、非AであることがそのままAであるとする類の「般若即非の論理」を、非論理として一刀両断に斥ける。それは、僕がここまで展開してきた議論で言えば、純粋経験をそのまま称揚するような仕方を退け、二元論と一元論の〈あいだ〉になんとか留まり、そしてその場を記述するという危険なサーフィンを続けることなのだと思う。
しかし、僕は、この龍樹のテトラレンマを組み替える形で作られた山内版テトラレンマには弱点があるように思う。ここまでの議論で、僕が「制作的空間」に入るには「制作」を媒介にするしかない、と言っていたことと同じなのであるが、山内のテトラレンマでは、一度純粋経験へと降りていく媒介が存在しないように思えるのだ。サーフィンをするためには、まず海に入らないといけない。陸サーファーが言葉の上で、「サーフィンというのはねー」といくらでも言葉を紡ぐことはできるが、形式的なことは言えても制作的なことは何も語れないだろう。まずは海に入ること、そしてそこから、ボードの上で初めて波との対話が始まるのである。
では、そもそも山内版テトラレンマではなく、その元である龍樹のテトラレンマとはどのようなものなのだろうか。清水高志は『実在への殺到』の中で、カンタン・メイヤスーの〈素朴実在論者〉、〈弱い相関主義者〉、〈強い相関主義者〉、〈思弁的哲学者〉という四項を説明する上で、龍樹の『中論』におけるテトラレンマを用いている。
『中論』の第十八偈に現れる典型的なテトラレンマ(四句分別)では、最初に①「すべては真実(如)であるという命題が語られ、次に②「すべては真実でない」という命題が述べられる。①は素朴に現実の世界を信じる者の見方であり、②は現象はすべて一刹那の後には変化するという洞察をもったものの見解である。そして三番目に③「すべては真実であり、かつすべては真実でない」という命題が述べられる。つまり、①のような素朴なものにとっては真実であり、修行をして②のような見解をもったものには真実でない、というのである。
しかしこれらは、ある刹那の次の刹那に起こることにいずれも依存したものなので、第四の命題④「すべては真実であるのではなく、かつすべては真実でないのではない」が説かれなければならない。仏教ではなにか対象を否定するとき、次の対象が浮かんでくるような否定、対象のあり方にその都度左右される否定を相対否定と呼び、そうでない否定を絶対否定と呼ぶ。「空」が理解されるのはこの絶対否定によるとされるが、③まではいずれも否定対象の状況に依存した、相対否定によるものである。それゆえ④では、③そのものが否定され、何らかの対象に依存しない(無自性な)かたちで、③の不可知論自体がさらに転倒されねばならない。④の命題は、なんらかの対象について語られるわけではないが、すべての対象について真実なことが述べており、「空」の立場からこうした否定を行う何者かも、また確かなのである(真如の確立)。清水高志『実在への殺到』
ここまで繰り返し出てきた鏡とミメーシスの論理、「Aでなく、Aでなくもない」という二重否定を、仏教では絶対否定と呼ぶ。木岡はそれを、一種の直観知であっても論理とは呼べないと言った。単に体験をベースにした「制作的空間」を上位のものとし、「日常的知覚」を下位のものとするような言葉では、確かに論理と呼べないだろう。しかし、清水がこの後に、「メイヤスーが、現実世界の法則の安定性への疑念だけを語っていると考えるのは、ナーガールジュナの空論が虚無ばかりを語ったものだと考えることと等しい。彼らの思想は、むしろ大いなる肯定の思想へと繋がるものなのだ」と書くように、この絶対否定、二重化の運動、制作的空間は、体験による暗き底へと降りていくときの危険で不安定なリズムを、サーフボードで波に乗るように乗りこなすことなのである。つまり、絶対否定自体を肯定するのではなく、その不安定さを乗りこなすこと、それこそが絶対否定が肯定だと言う意味であり、清水の挙げた①の素朴実在論者でいることが肯定的なのではない。また、相対否定の中でポジショントークを繰り広げるスキルを磨くことが、肯定に繋がるわけでもない。それは現状維持的であり、制度肯定的なのであって、一つ一つの生命を肯定するわけではないのだ。
ここまでの議論を整理すると、素朴な肯定から相対否定へ、そして絶対否定へと降りていった後に、それを一種の直観知で終わらせず、一つの論理とするためにレンマ的論理があると再定義できるように思う。つまり、まずは龍樹—清水テトラレンマで絶対否定に辿りついた後に、龍樹—山内テトラレンマによって、直観を論理へと記述しなければならないのである。
実際、『ロゴスとレンマ』が参照する『中論』の核心的主張は、排中律を逆転する〈中の論理〉にある。そして、『中論』に具体化された〈中の論理〉の核心は、龍樹—山内テトラレンマの第三レンマ(二重否定)から第四レンマ(二重肯定)への転換であり、それを山内は「即の論理」と呼んでいる。一見、山内の議論の問題は、四項に収めなければならないという強迫観念ではないかとさえ思う。そもそも「即の論理」さえあれば、龍樹—清水テトラレンマでも二重否定から、即、二重肯定へと転換することになっているので、安直に第五レンマとして、二重肯定を設定すればいいと考えてしまいそうになる。あるいは、第五レンマなど必要ではなく、二重否定即二重肯定なのだと、直観的に分かればいいとも言いたくなる。しかし、山内の悩みは、まさにこの「即の論理」がはたして論理と呼べるものなのだろうかということに端を発しているのである。
山内を悩ませたのが「即の論理」であったことは間違いない。繰り返すと、なぜなら彼は、直観知ではなく論理を示すことを目標としていたが、「即の論理」における否定は弁証法のような媒介作用ではなく、もちろん前提から演繹できるような推論でもないからだ。二重否定から二重肯定への移行は、即時に成立する直接的な体験、直観的で具体的な事実としか考えられないのである。もちろんこれまで見てきたように、このような二重否定から二重肯定へという「即の論理」は、描くこと、書くこと、そして狩ることなど多くの場面で見られる経験である。しかし、そこに成り立つ直接的な知は、はたして「論理」の名に値すると言えるのだろうか。
山内は『ロゴスとレンマ』の中で、「即とは分かたれたものが同時にあり、分かたれてあるままに一であることである」と言う。木岡伸夫は前出の書で、この発言を元に、ロゴス的論理とレンマ的論理が前提とする論理空間の違いについて次のように述べる。
弁証法における媒介が時間の作用として考えられているのに対して、否定と肯定の両立は一つの空間を必要とする。対立する二項を、時間における矛盾ではなく空間における差異として見るとき、上の第三・第四レンマのあいだに不即不離の関係が生じる、と考えて不都合はないだろう。矛盾律・排中律は、生成を時間の相のもとにとらえるという大前提において、存在理由をもつ。それとは反対に、空間的な観点に立つことによって、時間的見地からは両立しがたいものの並立が可能となる。たがいに矛盾対立するものの両立する論理空間が、そこに成立することによって、「即の論理」は〈中間を開く〉と考えられる。
ロゴス的論理は、存在と存在の根拠としての原因、つまり別の存在を区別する。物の存在を根拠づけるとされるのは、ふつうの物ではない特別な存在、つまりは神である。したがって、存在と非存在が同列に立つなどということはありえない。これに対してレンマ的論理は、存在の根拠を無とすることによって、存在と非存在、有と無を、不即不離の関係においてとらえる。これは、存在を「物」ではなく「事」として考える立場である。AとĀが区別されつつ同時に成り立つ根拠が考えられ、それは「非」と呼ばれる。「即」が成り立つのは「非」によってであるから、「即の論理」は「即非の論理」でなければならない。
西洋起源の形式論理が、排中律によって中間的なものを否定するのに対し、「空の論理」は対立する二者の中間を容認する。しかしその立場は、存在を無からとらえる存在否定の立場であり、それも単に有を否定する無にとどまらず、その否定をも否定する「絶対否定」の立場である。木岡伸夫『〈あいだ〉を開く』
ここで木岡が言っていることは、「即の論理」を論理として捉えられないのは、矛盾するものが並置している空間を前提にしていないからであるということだ。鈴木大拙に頻繁に見られる「Aは非AであるからこそAである」という般若思想を、山内が反論理的と厳しく指弾したことは、すでに記述しておいた。山内は、このような逆説が成り立つ根拠について、「般若の思想において存在と非存在とが同一視せられるのは決して論理的にではなく、むしろ場所的に近接しているからである……存在することは決して存在しないことを原因とするのではなく、存在と非存在とが直観的に近接しているところから両者が結合するのである」と言う。つまり、「場所的に近接している」ことが直観的に把握されるが故に、存在と非存在とが同一であるとされているだけであり、論理的ではないと言うのである。
しかし、山内はそれを直観ではなく論理として扱う術を見出す。そこには絶対否定が関係する。これは相対否定にとどまらず、肯否の区別がそこから生ずる根源的な無、「絶対無」である。この点に注目しよう。山内は「レンマ的無はロゴス的有無を超越して、それらを共にその中に成立せしめる」と言う。これは非常に興味深い指摘である。僕たちは〈常識〉を生成するものとしての〈共通感覚〉、〈主語的統合〉を制作する〈述語的統合〉をすでに見てきた。つまり、ここで山内が言っているのは、有無の区別によって成り立つための根拠がレンマ的無であり、それは「否」や「不」ではなく「非」であるということだ。山内は「非は肯否の合一であるのではなく、むしろ、肯否の区別がそれ(「非」)から発源するか、または少なくとも、それ(=「非」)を根拠とするか、そのいずれかのものでなければならない」と言う。
ここまで僕たちが議論してきたことと重ねて解釈すれば、絶対否定の場所とはまさに「非」であり、鏡≒本の空間であり、〈共通感覚〉であり、それらをまとめて僕が「制作的空間」と名づけた場所であった。山内はここで、鈴木大拙が言い表したような般若思想の直接経験の賛美を超えて、「非」を肯否の区別の根拠として位置づけている。彼が言う論理性は、ロゴス的論理ではなく、この「非」の場所における論理なのである。
さて、ここで木岡が言う時間的見地というのは、因果律にもとづいた単線的時間概念であり、福岡がピュシスとして捉えた流れとは異なるわけだが(なぜなら、生命はこの因果律を先回り的に捉えて分解と構築を行なう)、その時間的見地では、Aは何かの結果であり原因である。A → B → Cと因果律に基づいて連鎖していくことが前提とされている。そして、その始まりとして神がある。しかし、存在と非存在、有と無が並立する空間を前提に思考すれば、即の論理は論理として扱うことができるのだ。もちろん「即の論理」さえ、即、「非即の論理」であるわけだが。
とは言え、この違いをこれだけで理解するのは難しいため、補助線を引くことにする。例えば、岩田慶治は『アニミズム時代』の中で、この二つの考え方を「因果性」と「同時性」と定義している。「因果性」とは、今言ったように、原因と結果の連鎖として世界を捉える立場である。そこでは対象はすべてバラバラになっており、有と無は同時に存在しえない。そして「同時性」とは、「A即非A、非A即A」として捉える立場である。ここで岩田が「同時性」として描いたものは「即の論理」に違いないのだが、興味深いことに、自然科学者である福岡伸一が言っていた生命の時間も、まさにこの「同時性」の時間のことなのである。
生命は、上述したように、エントロピー増大の法則が生命構造を維持不可能にする前に、先回り的に自らを分解し、そして構築する。そこで起こっているのは、分解即構築、構築即分解という絶え間ない流れである。食べ物の例で説明したように、AがAであることを維持するという意味で食べることを捉えると、Aが動けることの原因であり、Aが動けることはその結果である。しかし、実際に起こっていることは、Aを構成している要素を絶え間なく分解し、それを絶え間なく構成する流れである。食べることは、この流れの中で起こる要素の入れ替えなのであって、それは「因果性」ではなく「同時性」として考えなければ捉えられない。言い換えれば、僕たちは「死につつ、生き、生きつつ、死んでいる」のである。そして、それこそが生きることなのだ。福岡は、それを自然科学の中で、「同時性」の論理、「即の論理」として捉えたのである。中村元と紀野一義が翻訳した『般若心経・金剛般若経』には、こんな一節がある。
かれらは生きているものでもなければ、生きているものでないものでもない。それはなぜかというと、スブーティよ、「〈生きているもの〉というものは、すべて生きているものでないということだ」と如来が説かれているからだ。それだからこそ、〈生きているもの〉と言われるのだ。『般若心経・金剛般若経』
[12]「即の論理」と「中の論理」にまたがる縁起思想
木岡伸夫は、「空の論理」が縁起の構造と結びつくことによって、初めて〈中の論理〉がその実質を備えると言うが、これはすでに、このエッセイで鏡の空間における人格性というテーマで論じたこととかかわっている。つまり、「私はあなたではなく、あなたでなくはない」という二重否定によって、私はあなたの中に私を部分的に見出す。それ故に、私はあなたの人格性を否定できない。これはあなたがエルクであろうが、熊であろうが同様である。文化的水準が低いから、ユカギール人が動物に魂や人格性を賦与するのではなく、ミメーシスによって「鏡の中に降りていく」が故にそうなのであった。では、山内にとって、空の論理と縁起思想はどのように結びつくのだろう。
すべての事物が縁起的関係においてあるということは、それ自体としての本質(自性)をもたない、すなわち空であるということだ。山内は『ロゴスとレンマ』にて、「一つの事物がそこに存在するのはそれ自らによってではなく、他に依って、他を持って、他との関係に於て存在すると考えるのが中論の立場であった」と説明する。そして、その縁起的関係と無自性を理解する上で、木岡は『ロゴスとレンマ』の第十章「火と薪との考察」(「燃焼可焼品第十」)を取り上げて、説明する。
火と薪の関係は、同一でもなく別異でもない。もしこの二つが同一なら、薪に点火する必要はなく、火は絶えず燃え続けるであろう。しかし、火と薪がまったく別のものであるなら、どうして火を薪に点じることができるだろうか。火と薪は同一でもなく、異なったものでもないからこそ、火が薪に点じて燃えるということが起こりうる。
火が現に燃えつつあるとは、どういうことか。薪が薪として燃えることはなく、火は単に火として燃えることもない。火が薪に点じられることによってはじめて燃えるということは、それぞれがたがいに他を待って、他に依って、自己の存在を表すこと(相依相待)を意味する。しかし、両者が相待的である関係において、火と薪は別々のものでなければならない。火は火として、薪は薪として、それぞれの自性をもたなければならない。しかし、そうした自性にとどまるかぎり、両者は独立であって燃えることは生じない。火と薪は自性を有しながら、また自性を失わなければならない。自性をもつと同時に自性を失うことによって、すなわち火が火として、薪が薪としての同一性を保つとともに、その同一性を失うことによって、はじめて両者の関係 —— 燃焼の事実 —— が成立する。
燃焼の事実において、火と薪はそれぞれの独自性を失って結合し、一体化する。火と薪は相互に依存しつつ、相互肯定的な関係にある。しかるに、火が燃えていくとは薪を減少させていくことであり、逆に火が消えかかっていくとは薪の減少が否定されることである。つまり、火の肯定は薪の否定を、火の否定は薪の二重否定つまり肯定を意味する。これは、最初の相互肯定とは異なり、一方の肯定が他方の否定につうじるという反対の関係、矛盾的対立というべきあり方を示している。
さらに、火がいっそう燃え盛っていった場合、薪は小さくなる。火の肯定、薪の否定が進行して、ついに薪が燃え尽きたとき、薪は完全に否定される。しかしそれは、火の肯定ではなく、火の消滅を意味する。これは、火の側からすれば、自の肯定、他の否定が、自己否定にゆきつくということにほかならない。その反対に、火勢が弱まり消えかかっていくならば、火の否定が薪の肯定につながることになる。しかし、もし火が消えてしまい、火の否定が成就したならば、そこには薪もまた存在せず、ただ木片が転がっているに過ぎない。こうして自己否定の極にゆきついたなら、それと同時に、矛盾対立の関係にあった他も滅び去る結果となる。
この例を見れば分かるように、対立する二者の肯定—否定の関係は複雑である。単純な二値論理の世界では、一方の肯定は他方の否定であり、他方の肯定は一方の否定である。ところが、一方が自己の肯定(他方の否定)を強行したとき、それが他方の消滅を生じさせることによって、自己も消滅せざるをえない結果を生む。逆に、自己の否定がゆきつくところは、他者の全面肯定のようでいて、他者否定の結果を生む。「相互対立における両者は、対立を残していないかぎり、自ら自己を滅ぼしてしまう結果を招く」(『ロゴスとレンマ』)ことになる。木岡伸夫『〈あいだ〉を開く』
ここまで読むと、なぜ僕が論を進めるにあたって、レンマ的論理を紹介しているのかが理解できるだろう。ロゴス的論理は外側から事物を眺め、AであるとかBであるとかCであるとか定義することで切り分け、原因と結果の連鎖によって、必然的な関係の中に整理してしまう。薪と火の関係であれば、木に火をつける(原因)、すると燃焼が生じる(結果)。しかし、レンマ的論理は、その只中で起こっていることについて「内在的観察」を行なう。薪と火の関係は相互依存的であり、薪でありつつ火であるという状態を維持しなければ、相互に消滅する危ういバランスの中にある。そして生命とは、そのような相互依存的なバランスの中での流れであった。だから、それを捉える「内在的観察」の技法、そして「レンマ的論理」が今求められているのである。
ここに、前出の森田真生『数学する身体』で紹介されていた例がある。とある大学で、マグロロボットを作るというプロジェクトが立ち上がった。実際のマグロは驚くべきスピードで泳ぐので、そのマグロの「泳法」の秘密を解明して、潜水艦や船の設計に活かそうという目的だ。科学者たちがマグロの泳法を調べる過程で、ある興味深い仮説が浮かび上がった。マグロは自らの尾ひれで周囲に大小の渦や水圧の勾配を作り出し、その水の流れの変化を活かして推進力を得ているというものだ。ロゴス的論理で作られた船や潜水艦にとって、海水はあくまで克服すべき障害物である。そこには海水があり船があるという切り分けの論理が働いている。しかし、マグロは周囲の水を、泳ぐという行為を実現するためのリソースとして積極的に活かしている。燃焼が薪と木の〈あいだ〉のバランスによって生じる現象であるとすれば、遊泳は海水と動きの〈あいだ〉のバランスによって生じていたのである。
ロゴス的論理ではAとBは別のものとされ対立し、克服すべきものと捉えられるが、生命は環境との相互作用の上で生きている。マグロにとって周囲の水の流れは、運動のためのリソースであって障害ではない。森田は次のように言う。「生物は機械と違い、環境の中を生き残ってきた進化の来歴を背負っている。ロボットにとって環境はあくまで『解決すべき問題』かもしれないが、生命の方は、環境を『問題』と片づけてしまうにはあまりにもそれと深く交わっている」と。すべての事物は、本質あるいは実体として切り分けられるわけではない。あるいは切り分けて考えてしまうと、本質を掴み損ねる。泳ぐという行為一つを取ってみても、切り分ける思考だけでは捉えられないのだ。
仏教では、完全に独立した自己存在をもたず、他のすべてと関係し合う在り方が、そのものの無自性、すなわち空を意味する。そのように相互依存的かつ相互排除的な両面をもった「相依相待」の関係が、縁起の構造である。ロゴス的論理によって捉えられないものを、西欧では生命を内側から見ることで捉えようとしている。マグロの泳法は、その一例である。しかし、東洋はもともとレンマ的論理を持っていたはずであり、「内在的観察」を得意としていたはずだ。今、レンマ的論理が求められているというのは、「外在的観察」と「内在的観察」という二つの様態があるという哲学的関心からの主張ではなく、実践的に有効であると考えているからなのだ。
[13]形の論理と二種の〈あいだ〉— 垂直的と水平的
ここまでの議論を、「因って」(原因)、「依って」(縁起)、「由って」(理由)という三種の「よって」を通じて、整理することができる。自然科学の因果関係と「主語的統合」は、物事の「原因」と「結果」を追究し、「私が対象を見る」という記述を可能にし、「私は私である」という自己同一性を強化することで、第一の「因って」を保っている。大乗仏教の空観、鏡≒本の空間、狩りの様態、「述語的統合」、すなわち「制作的空間」では、第二の「依って」が表す一と他の相依相待、つまり「縁起」の関係、私の二重化、ミメーシスの眩暈、「私は私でなく、私でなくもない」という私と非—私の不安定な統御、そして五感の組み替えによって、「主語的統合」を可能にする場が示された。第三の「由って」が表すのは、存在の根拠が存在でも非存在でもなく、それらの根源たる「非」、絶対無にあることが明らかにされた。そして、その「非」の場所から、肯定と否定が現れるのであった。それは、これまであまり指摘されることのなかった「制作的空間」への媒介、つまり一歩目の「制作」という側面である。まず、この「由って」を経ることで、僕たちは肯定と否定が現れる場所、主語的統合を生み出す場所、常識が生成される場所、そして身体が新たに編成される場所に立つことができるのである。
しかし現代において、最後の「由って」からはファシズムの香りがしなくもない。事実、木岡も「絶対無という言葉で飾ってはいるものの一なるものへの回帰なのではないかという疑問が頭をよぎる」と言っている。山内は「存在が無根拠であることによって、自由が成立し、存在の自覚が生まれる」と、ハイデガー風のことを言ってしまうので、なおさらである。この垂直上の〈あいだ〉、存在と存在の根拠の〈あいだ〉を、山内はどのように捉えていたのか。木岡は「存在論的な水準を異にする二者を結ぶ中間者は考えられるのか」と言う。そして、山内が最後に辿りついた〈形〉の論理について、「この問いに対する彼の答えは、中間者は〈存在〉ではなく〈形〉であり、形の世界において〈一〉と〈多〉の統一が実現する —— そこに働く論理は存在の論理ではなく表現の論理である」と言うのだ。
〈型〉はそれ自体、存在と非存在の領域にまたがることを含む概念である。それは、多様なものの〈形〉の中から、統一的な意味として浮かび上がる、そのかぎりで具体的な存在性をもつ。それを現実化しようとすれば、存在するいずれかの〈形〉によって表現されるほかない。そのさい〈型〉は、そこに存在する〈形〉とは異なるものの、その〈形〉をつうじてのみ窺い知られる根源的な何か、つまりは表現する働きを意味している。
いま「表現する働き」と言ったが、それは〈もの〉ではない。ものに具わる〈形〉を透かしてその背後を窺うがゆえに、われわれはそこに実体的な〈もの〉を見ようとする。しかしそこにあるのは、働きとしての〈こと〉、つまり表現作用のみである。存在の根拠を存在に見立てようとするこうした思考に対して、現れるのは存在ではなくその幻に過ぎないということを、まさに〈型〉(かた=痕跡)という語が示している。
〈形の論理〉を構成する〈形〉と〈型〉の関係において、二者はいずれもが他方から規定されるとともに、自己から他を規定するという、相反する二重の面をもつ。〈型〉は〈形〉を生み出し、つねに〈形〉に先んじて存在する。しかし〈形〉は〈型〉によって規定されるばかりでなく、自己を創造し、かつそれをつうじて〈型〉をつくってゆく自由を有する。このことを縁起思想に則って、〈型〉と〈形〉の相依相待と呼んでもよいだろう。
つまり、西洋哲学の根本前提である「存在するものは、すべてその根拠である存在(神)から生まれた」という存在論的命題を換骨奪胎しているのである。木岡伸夫『〈あいだ〉を開く』
驚くべきことに、ここで言われている〈型〉と〈形〉の論理は、すでに「制作的空間」として述べたような、〈型〉という〈常識〉と〈形〉という〈共通感覚〉の相互包摂関係にほかならない。ここでも「制作」は、やはり存在と存在の〈あいだ〉で行われる。僕たちは、そこで作りつつ、作られ、作られつつ、作る。ますます確信をもって、僕は恐怖に打ち勝つことができそうだ。僕たちは、まず一歩を踏み出し、降りていかなければならない。今、僕たちが絶対的だと思っている視覚中心の「主語的統合」という〈型〉は、中世においては聴覚中心の「主語的統合」であった。それは近代以前の芸術家たちが作り上げた身体が一般化したものにすぎない。降りていかなければならない。その場所は、魅惑と危険に満ち満ちた鏡と模倣の空間である。そこで再度、僕は僕の身体を作り上げる。もう一度、身体の内へと進もう。〈体性感覚〉を活性化しなければならないのだ。
[14]芭蕉、道元、岡潔の身体へ
ここで森田真生が紹介する松尾芭蕉と道元、そして彼らについてコメントしている岡潔について語っていきたい。それによって、本論を再び整理する。そして、体性感覚を活性化させる方法について、再度考えていきたいのである。まずは簡単に、森田の議論を通じて、僕のこれまでの議論を振り返ることにしよう。
芭蕉の句は「生きた自然の一片がそのままとらえられている」ような気がする、と彼は言う。
たとえば、
ほろほろと山吹散るか滝の音
という句があるが、これなどは「無障害の生きた自然の流れる早い意識を、手早くとらえて、識域下に映像を結んだ」ためにできたのだろう、と岡はエッセイの中で書いている。
「ものの見えたる光いまだ心に消えざるうちにいいとむべし」とも言った。芭蕉の方法には「もの二つ三つ組み合わせて作る」アルゴリズムはない。芭蕉の句は、ただ芭蕉の全生涯を挙げて「黄金を打ちのべたるやうに」して導出される。その「計算速度」は、まさに電光石火の如きである。
芭蕉の意識の流れが常人よりも遥かに速いのは、彼の境地が「自他の別」「時空の框」という二つの峠を超えているからだと、岡は考えた。過去を悔いたり、未来を憂いたり、人と比べて自分を見たり、時間や空間、あるいは自他の区別に拘っていては、それが意識の流れをせき止める障害となる。逆に、そうした区別にとらわれなければ、自然の意識が「無障害」のまま流れ込んでくるというのである。
生きた自然の一片をとらえてそれをそのまま五・七・五の句形に結晶させるということに関して、芭蕉の存在そのもの以上に優れた「計算手続き」はない。水滴の正確な運動が、水を実際に流してみることによってしかわからないのと同じように、芭蕉の句は、芭蕉の境地において、芭蕉の生涯が生きられることによってのみ導出可能な何かである。森田真生『数学する身体』
ここで語られる、芭蕉の「自他の別」「時空の框」という二つの峠を超えているという状況は、まさに「AはAである」という状況から「AはAではなく、Aでなくもない」という状態への移行を指す。狩人は森の中でヒトの言葉を話さない。なぜなら、それはミメーシスを通じて鏡の空間に入るための重要な儀礼だからだ。自己同一性を外す技術は多数ある。画家は「描くこと」「見ること」を通じて、鏡の中へ降りていく。作家は「書くこと」「読むこと」を通じて、降りていく。芭蕉も、自己同一性の区別を外す。そうすることで、生きた自然の一片を捉えて、そのまま五・七・五の句形に結晶させる。そこで用いられるのは、ロゴス的論理ではなくレンマ的論理であり、「内在的観察」である。これは単に、自他の区別が無い状態を作ればよいということではない。彼の身体が、その結晶化の基体なのである。〈述語的統合〉を活性化すること、それぞれの身体を作ること、それが「制作」であるというのは、まさにこういうことなのだ。芭蕉は俳句という〈形〉を制作することを通じて〈型〉を作る。とは言え、最初は芭蕉も〈型〉の元にあったのである。作りつつ、作られること。まさに「制作的空間」の中で。
道元禅師は次のような歌を詠んでいる。
聞くままにまた心なき身にしあらば己なりけり軒の玉水
外で雨が降っている。禅師は自分を忘れて、その雨水の音に聞き入っている。このとき自分というものがないから、雨は少しも意識にのぼらない。ところがあるとき、ふと我に返る。その刹那、「さっきまで自分は雨だった」と気づく。これが本当の「わかる」という経験である。岡は好んでこの歌を引きながら、そのように解説をする。
自分がそのものになる。なりきっているときは「無心」である。ところがふと「有心」に還る。その瞬間、さっきまで自分がなりきっていたものが、よくわかる。「有心」のままではわからないが、「無心」のままでもわからない。「無心」から「有心」に還る。その刹那に「わかる」。これが岡が道元や芭蕉から継承し、数学において実践した方法である。森田真生『数学する身体』
ここでも芭蕉と同様に、「無心」であることが唱えられる。「無心」から「有心」へと還るときに「わかる」のだと。しかし、なぜ、それによって「わかる」のか。森田は岡潔の言葉を引き、「それは自他を超えて、通じ合う情があるからだ。人は理でわかるばかりでなく、情を通わせ合ってわかることができる。他の喜びも、季節の移り変わりも、どれも通い合う情によって『わかる』のだ」と言う。
「情緒」は「情」の「緒」(いとぐち)と書く。「情」という日本語には独特のニュアンスがある。情が移る、情が湧く、あるいは情が通い合う。情はいとも容易く「私」の手元を離れてしまう。「私(ego)」に固着した「心(mind)」とは違い、それは自在に、自他の壁をすり抜けていく。しかも環境の至るところに「情」の動きの契機となる「緒」がある。そんな「情」と「緒」の連関としての「情緒」を、日本人は歌や句の中に読み込んできた。
うちなびく春来るらし山の際の遠き木ぬれの咲き行く見れば
(『万葉集 巻第八』一四二二 尾張連の歌)遠くの山に、桜がぱぁっと咲いている。すると、その姿がそのまま自分の喜びになる。花の咲く姿を「緒」として、人の「情」が動き出す。
「情」と「情緒」という表現で言えば、岡はある時期からこれを、意識的に使い分けるようになる。一口に「情」と言っても様々なスケールがあって、「大宇宙としての情」もあれば、「森羅万象の一つ一つの情」もあるというのだ。それを使い分けるために岡は、前者を「情」と言って、後者を「情緒」と呼び分けるようになる。
自他の間を行き交う「情」が、個々の人や物の上に宿ったとき、それが「情緒」となるというのである。森田真生『数学する身体』
これまでの議論で、鏡の空間では、あなたにもエルクにも人格性が与えられると言った。それはイマージュ、あるいはミメーシスの作用であった。「私はエルクでなく、エルクでなくもない」が、同様に「エルクは私でなく、私でなくもない」。僕はエルクの人格性を否定できない。なぜなら、僕はエルクの中に「私」を部分的に見出すのだから。岡の場合は、「情」が行き交い、人や物に宿った「情緒」がある。もちろん表現は異なるが、「創造性」についてのさまざまな議論を読めば読むほど、同様の論理が潜んでいるとしか思えない。「自他」の区別のない状態に自己を持っていくと、「情」や「イマージュ」や「縁起」が飛び交う場所が開かれる。詩人はその場所において、「無心」であるだけでなく「有心」に戻らなければならない。僕たちはすでに知っている。あちら側に完全に移行することは危険なのだ。その危険なバランスを生きること。そうすることで「わかる」のである。
ここまででイマージュや情緒の行き交い、ミメーシスの眩暈が体感的統合の領域において生じることを確認してきた。さらにそれを裏づけるものとして、カッシーラーが『シンボル形式の哲学』の中で表情 —— 魅惑的であったり威嚇的であったり馴染み深い感じを与えたり心和ませたりするもの —— こそが、知覚に「実在性の根源的色調を与え」、それによってこそ、知覚が「実在についての知覚」になっていると述べていることを挙げておこう。さらに、木村敏の『自分ということ』によると、離人症患者は客観的に「近い/遠い、重い/軽い、熱い/冷たい」を理解できる —— どちらが重いだろうか、どちらが軽いだろうかと質問されれば、数字を頭の中で介して、難なく答えることができる —— が、彼の患者が「温度の高低はわかりますが、暑い寒いといった感じはどうもピンときません」と答えるように、その「実在性」を掴むことができない。
これまでの議論を踏まえると、彼らは主体的統合—視覚的統合として、また「対象」として、つまり自分とは切り離されたモノとして、今日が暑いのか寒いのかは理解できるが、〈私〉—〈対象〉構造を支える基体、述語的統合=体感的統合が機能していない状態のため、自らの身体との繋がり、「実在性」を持てない。やはり、体感的統合は情動やイマージュ、表情といったエモーションの行き来の前提となる基底なのである。
[15]体性感覚を活性化することとは
すでに取り上げたように、森田真生は「芭蕉の句は、芭蕉の境地において、芭蕉の生涯が生きられることによってのみ導出可能な何かである」と述べていた。僕たちに最後に残されている問いは、それぞれの身体を作り上げるとは何かということである。芭蕉は、芭蕉の身体を作り上げた。それによってのみ、芭蕉の句は導出可能である。確かにそうだろう。しかし、〈共通感覚〉に根を下すこと、〈体性感覚〉を活性化することを可能にする原理を明らかにしなければ、身体性という一点において神秘化するだけのことになってしまう。ここまで示してきたように、〈共通感覚〉は体性感覚であり、感覚と理性の変換点であり、想像力の場所であった。中村雄二郎は『共通感覚論』で、次のように言う。
その働きは身体を基礎として身体的なもの、感覚的なもの、イメージ的なものを含みつつ、それをことばつまり理のうちに統合することである。また、サブ言語としての身体言語からいわゆる言葉への通路を開くことでもある。私たちの感性は、共通感覚をとおして活性化され、整えられ、秩序立てられなければならず、また理性は共通感覚にしっかり根をおろすことが必要である。感性のいたずらな放散と理性の不毛な形式化を免れるためには、共通感覚をいきいきと働かせることが大いに役立つはずである。このようなものとして共通感覚を、またその十全な意味を捉えなおす上で、統合関係と連合(範列)関係、あるいは結合関係と選択軸という二つの関係軸の直覚的な交叉から成る言語活動ほど、好都合な手がかりは少ない。なぜなら、語の自由な選択と結合とによる自由な言語活動は、デカルトやチョムスキーのいう理性や良識よりも、共通感覚の覚醒によってはじめてなされるからである。中村雄二郎『共通感覚論』
言語と身体は、分離された異なる領域と考えられがちである。しかし、「身体性」を考える上で、言語を起点にすることは重要である。身体が理性と感性、そして想像力を司る場所だとするなら、傾きとして理性的な言語、そして感性的、想像的な言語もある。また、このエッセイでここまで忌避してきた、ロゴスと結びつく形式化された言語ではなく、身体に根を下ろした生きた言語について考えることは、マジックワードとして曖昧に扱われがちな「身体性」という概念の解像度を上げることに寄与するからである。
そして、ここから僕は、この身体と環境と言語という問いについて、環境人文学に大きな影響を与えてきたデイヴィッド・エイブラムの『感応の呪文』という書籍を元に考えていくことにする。エイブラムはその中で、レヴィ=ブリュールやメルロ=ポンティを元に、身体と知覚と言語の関係を次のように要約している。
①知覚という出来事は、経験的に考えると、本来相互作用的で参与=融即的な出来事であり、言い換えれば、知覚するものとされるものの相互交流にほかならない。
②知覚される事物は知覚する身体との遭遇において、生命ある生ける力となって積極的に私たちを関係の中へ引き入れる。自発的で前概念的な経験は現象を二元論的に、生命あるものと「無生命」のものに分け隔てることはせず、せいぜい生命あるものの多様な形における相関的区別を認める程度である。
③感覚する身体と、表情に富む生ける風景との知覚的相互交流は、他者とのより意識的で言語的な相互交流を生みもし支えもする。私たちが「言語」と呼ぶ複雑な相互作用は、私たちの肉体と世界の肉との間で常にすでに展開している非言語的な交流に根ざしているのである。
④したがって、人間の言語は、人間の身体や共同体の構造によってのみ特徴づけられているのではなく、人間以上の大地の喚起力に富む地形や型の影響も受けている。経験的に考えれば、言語が人間という有機体の特別な所有物でないことは、言語が私たちを包み込む生命ある大地の表現であるということと同じである。デイヴィッド・エイブラム『感応の呪文』
融即とは、主語的統合のように主体と対象が分離された状態での知覚ではなく、主体と客体が未分化の状態で相互に影響を与え合う知覚を意味している。もともとは、哲学者レヴィ=ブリュールが『未開社会の思惟』の中で提示した未開人の知覚に関する概念であったが、後に文化人類学の調査によって論争が起こり、撤回されたものである。エイブラムはこう言う。
メルロ=ポンティの著作では、融即が知覚それ自体を定義する特性であることが示唆されている。現象学的にみて知覚は本来融即的であると主張することは、最も親密な次元において、融即が常に、知覚する身体とそれが知覚するものとの活動的な相互作用あるいは連結をめぐる経験であることを意味している。あらゆる言語的反省以前の、世界との自発的で感覚的な関わりの次元において、私たちはみなアニミストなのである。デイヴィッド・エイブラム『感応の呪文』
これは僕たちがこれまで見てきたように、ミメーシスによって動物やモノに人格性が付与されることと同じであり、他者に人格性が付与されるのも、同様の論理によるものであった。僕たちは近代人であってアニミストではないと主張することは、他者に人格性を賦与することを否定するに等しい。
さらに融即を詳しく見ていくと、四つの特徴によって語られている。その四つとは、移行性、可逆性、共感性、共感覚性である。まずは移行性と可逆性について、エイブラムの書籍から見ていこう。
実際、マウンテンライオンと出会った時、私はより強烈に自分が感覚する主体であるだけでなく、他者の目(と鼻)からすれば感覚される客体であり食べられる対象ですらあることを思い知らされる。私の腕を這っている蟻、目と肌が知覚しているこの蟻でさえ、私の動きや気分の化学変化に即座に反応して蟻自身の感受性を示している。蟻との関係において私は自分自身が高密度で物質的なものであり、うねる大地と同じように自分の行動が気まぐれなものだと感じる。最後に問うが、なぜこの主体と客体の「可逆性」は私が経験するすべての存在に及ばないのだろうか。私の感受性ないし主観性が、他者にとって目に見えて肌で感じられる形態はどれも、周りの存在そして私に対しても敏感で反応の早い、経験する主体であると考えるほかないと思うに至った。
知覚の移行性や肉の可逆性というのは、突如として木が私たちを見ていると感じること —— 自分が剥き出しにされ、視線にさらされ、観察されているように感じること —— なのである。デイヴィッド・エイブラム『感応の呪文』
視覚の移行性や肉の可逆性は、マウンテンライオンやジャガーといった、人間を食べる生き物との遭遇によって強く印象づけられる。確かに、ヴィヴェイロス・デ・カストロも同様のことを言っている。彼は「アメリカ大陸先住民のパースペクティヴィズムと多自然主義」という論文で、「パースペクティブの転置に際しての基礎的な次元であり、同じく構成的であるだろう次元は、捕食者や獲物という相対的で関係的な状態に関連している」と述べている。もちろん、そうなのかもしれないが、この狩る/狩られる、見る/見られるという相対的で関係的な状態は、都市生活を行なう僕たちにも想像することはできるはずである。
次に、共感性と共感覚性は、エイブラムの著書で次のように定義されている。
「知覚」という語が意味するのは、すべての身体的感覚がともにはたらき活発化しながら協調しておこなう活動にほかならない。実際、刻々と変化する周りの風景をめぐる非言語的経験に注意を払うと、いわゆる別々の感覚といわれるものが融合していることがわかる。距離をおいて目や耳や肌の関わりを個別に考えることができるのは、経験の後でしかない。ある感覚の役割を他の感覚の役割と区別しようとしたとたん、私の感覚する身体の感応的世界への全的な融即を絶たざるをえなくなる。
これは、感覚が別々の様相であることを否定するものではない。ここで主張したいのは、感覚が、単一の統一された生ける身体の様々な様相であり、それらの複合的な相互依存において展開する相補的な力であるということである。それぞれの感覚はこの身体の存在の独特の様相なのだが、知覚という活動においては、様々な種類の感覚が交わり重なりあう。そういうわけで、遠くの空を舞っている大鴉は、私にとって単なる視覚的イメージではない。目でその姿を追いながら、私は大鴉が羽を伸ばしたり曲げたりするのを自分の筋肉で感じるし、すぐ近くの木に向かって舞い降りてくれば、それは視覚に訴えると同時に内臓にも訴える経験にほかならない。大鴉のおおきなしわがれ声は頭上で方向転換する時も厳密な意味で聴域内に限定されているわけではない。その声は、見えるものを通じて響いているのであり、その漆黒の姿にふさわしい向こうみずなスタイルや気分で、目に見える風景を生き生きとさせているのである。デイヴィッド・エイブラム『感応の呪文』
まずエイブラムは、言語以前の経験においては、五感という分節化を経ないことを示唆している。次に、統一された生ける身体では、複合的な相互依存においてさまざまな種類の感覚が交わり重なりあうと主張する。見ることを通じて、〈運動感覚〉や〈内臓感覚〉が共鳴し、声が見ることを通じて響くと表現されている。言語以前の経験とは、これまでの議論では〈共通感覚〉〈述語的統合〉〈体性的統合〉などと言われてきたものである。そこは、理性と感性を繋ぐ場所であり、情動やイマージュが飛び交い、想像力を司る場所であった。
エイブラムは自らが体験したことを元に、民族誌や哲学書を使って概念を構築していくタイプの論者なので、テキストは詩的で喚起力があるが、フィクションの印象を回避できないのも確かである。なので、ここではヴィラヤヌル・ラマチャンドランによる共感性と共感覚性の定義も引いて、エイブラムの主張がある程度妥当性のあるものであることを補完しておきたい。まずは、共感性に関するラマチャンドランの有名な実験を紹介したい。それは彼が『脳の中の幽霊』で取り上げた実験である。
ラマチャンドランはミラーニューロンを応用した実験を行なった。ミラーニューロンとは、イタリアのジャコモ・リゾラッティらがサルの実験で発見した、脳の模倣を司る機能を指している。例えば、サルがものを持ち上げる動作をする。すると、該当する脳の一部分も当然のことながら活動している。さらに彼らは、他のサルが何かを持ち上げる動作を見ているだけでも、脳の同じ部分が活動していることを発見した。模倣機能が存在するということは、視覚芸術や文学ではしばしば言われていたことだが、彼らはこの運動と脳の対応を元に、実際に自分が運動しているときだけでなく、他者の運動を見ているときにさえ、さも自分がその運動をしているかのように脳が活動することを発見したのだ。ミラーニューロンは他者の運動だけでなく、他者の痛みや感覚も模倣する。例えば、目の前の人の手が金槌で思い切り叩かれるところを見たら、こちらまで思わず手を引っ込めてしまうだろう。脳は活動しているが、本当に痛いわけではない。これはどういうことであろう。ラマチャンドランの疑問は、そこに端を発している。
ラマチャンドランは、他者の痛みや感覚を見ると、その痛みや感覚に対応する脳の一部分は活動するが、同時に、実際の手の皮膚や関節にある受容体から「私は触れられていない」というフィードバック信号が出て、ミラーニューロンからの信号をキャンセルしていると考えた。そして、そのアイディアを検証するために、湾岸戦争で片腕を失ったハンフリーという幻肢患者に協力を依頼した。一般に幻肢患者は、腕がないにもかかわらず、まだそこに腕があるという幻想を抱いている。ハンフリーの場合は戦争で腕を失っていたのに、顔を触れられるたびに失った手の感覚を感じていた。ラマチャンドランはそんなハンフリーに、学生の一人を見てもらいながら、そのジュリーという学生の手を撫でたり叩いたりしてみせた。すると、ハンフリーは驚いた様子で、ジュリーの手がされていることを自分の幻肢に感じる、と叫んだ。ラマチャンドランの予想通りの結果だった。ハンフリーのミラーニューロンは正常に活性化されたが、それを打ち消す手からのフィードバック信号がないので、ミラーニューロンの活動が、そのまま意識体験として現れてしまったのである。
ラマチャンドランが「獲得性過共感」と名づけたこの現象は、幻肢患者だけでなく、簡単な操作を加えることで健常者にも再現できることがわかった。例えば、ラバーハンド実験と呼ばれるものでは、被験者の目の前に置いた作り物の手と、被験者の手に同様の刺激を10分間与えて、作り物を自分の手と錯覚させ、今度は作り物の手の上に室温のプラスチックを置いて取り除いた後に氷を置き、温度の変化をどう感じたかを調査した。本物の手には温度変化がなかったにもかかわらず、20人中15人が「自分の手が冷たく感じた」と回答した。さらに、氷の後にプラスチックを置くと、18人が「温度が上がった」と答えた。あるいは、麻酔によって皮膚からの感覚入力を遮断すると、誰もが文字通り、目の前の人と痛みを共有してしまうこともわかった。これらの例が意味するのは、皮膚からのフィードバックがなければ、自己と他者の運動や感覚を区別する術がないことである。
次に、共感覚性に関するラマチャンドランの発表を見ていきたい。ラマチャンドランが「数字に色を見る人たち」という論考で言うには、共感覚とは、二つ以上の感覚が混ざり合ってしまうことだが、それ以外は極めて正常な状態にある。何十年にも渡り、共感覚で起こる現象はインチキだとか、単に記憶によるものとか言われ、あまり真剣に受け止められることはなかった。しかし最近、これが実際に起こっていることが科学的に証明された。おそらくこの現象は交差活性化、つまり通常は別個に働く脳の二つの領域が互いに活性化し合うために起こるとされる。また、共感覚のメカニズムを探求するうちに、脳がどのように感覚情報を処理し、それを使って一見無関係なものを抽象的に結びつけるかもわかってきたそうだ。彼は共感覚を研究することで、それが共感覚者と呼ばれる一部の人に見られる特性ではなく、概念をつくるということを可能にする一般的な性質であると主張するに至った。少し長くなるが、見てみよう。
共感覚の仕組みを神経学的に理解することによって、画家や詩人、小説家の創造力を多少は説明できるかもしれない。ある研究によると、このようなクリエイティブな職業に携わる人々では、共感覚者の割合は一般の8倍にのぼるという。
創造的な人々の多くに共通する才能のひとつが、隠喩的表現の巧みさだ(たとえば、シェイクスピアの戯曲の台詞「あの窓が東の空ならば、ジュリエットは太陽」のように)。彼らの脳は、太陽と美少女のように一見無関係な領域どうしがリンクするようにできているかのようだ。つまり、共感覚が一見無関係な知覚的要素(色や数字など)を勝手に結びつけてしまう状態だとすれば、隠喩は一見無関係な概念的領域を結びつけてしまうことだといえる。おそらく、これは単なる偶然ではないだろう。
多数の高次概念がおそらく特定の脳領域(マップ)につながっているのだろう。考えてみれば、数字以上に抽象的なものはないのに、先ほど説明したように、脳の比較的小さい領域(角回)で処理されているのだ。私たちは突然変異によって異なる脳マップ間で過剰な交信が起こるために共感覚が引き起こされると考えている。
ここでいうマップとは皮膚の小領域のことで、そこでは特定の知覚的要素、たとえば、形の直線性や曲線性、そして色合いなどが表される。共感覚を生み出す遺伝子が脳のどこで、どのくらいの広がりで発現するかによって、共感覚や、一見無関係な概念をリンクさせる傾向(つまりは創造性)が生まれるのだろう。こう考えれば、あまり役に立つとは思えない共感覚の遺伝子が生き延びてきたこともうなずける。
私たちの研究は、芸術家には共感覚者が多い理由を明らかにするだけでなく、一般の人も実は共感覚の能力を持っていて、そうした形質が抽象概念を進化させてきたのではないかということを示唆している。抽象概念をつくることに関して、ヒトは抜きん出た能力を示す。抽象概念に関係するTPOとその内部にある角回は、通常、異種感覚情報の統合(クロスモダル統合)にかかわっている。
この脳領域には、触覚、聴覚、視覚からの情報が一緒に流れこみ、ここで高次の知覚が作り出されていると考えられている。たとえば、猫はふわふわしていて(触覚)、ニャーと鳴いたり、喉をごろごろ鳴らし(聴覚)、ある決まった外見(視覚)とにおい(嗅覚)をしている。猫を思い浮かべたり、「猫」という言葉を聞いただけで、これらの感覚がいっぺんに喚起される。
ヒトでは角回が類人猿やサルと比べて不釣り合いに大きい。それは角回が最初は異種感覚情報の関連づけのために進化したものの、しだいに隠喩などのより抽象的な機能が勝るようになっていったからなのだろう。
心理学者のケーラー(Wolfgang Köhler)が考案した2つの絵を見てみよう(詳しく知りたい方はブーバ・キキ効果で検索してみてほしい)。ひとつはインクの染みのように見えるが、もうひとつは割れたガラスの尖った破片のように見える。「どっちが『ブーバ』でどっちが『キキ』に見えるか」と尋ねられると、98%の人がインクの染みがブーバで、ガラス破片をキキと答える。アメーバのようなやわらかい曲線が、脳の聴覚中枢で優しい波動として処理される「ブーバ」という音にぴったりくるのだろう。そして「ブーバ」と発音するときに唇をゆっくりとすぼめる感じともよく合うのだろう。一方、「キキ」という音の波形と、それを発音するときに舌が口蓋に鋭くあたる感じは、この尖った形に見られる突然の変化によく表れている。
この2つに共通するのは、形から連想される抽象的特徴だけだ。そうした抽象的概念はTPO近辺、おそらく角回で生まれるのだろう(最近、私たちは角回が傷ついた人々ではこのブーバ・キキ効果が失われることを発見した。彼らは、2つの形を適切な音に結びつけることができない)。ある意味で、私たちは誰もが“隠れ共感覚者”なのかもしれない。
つまり、角回は非常に初歩的な抽象概念を作り出している。似ても似つかないものから共通する特徴を引き出しているのだ。角回がどの程度正確にこの仕事をするのかはわからない。しかし、クロスモダル抽象概念をつくれるようになったことで、もっと複雑な種類の抽象概念に進むことができるようになったのだろう。異なる機能のために別の機能が乗っ取られてしまうのは進化ではよく見られることだ。クロスモダルによる抽象概念構築は、隠喩や抽象的思考だけでなく、言語のもとにもなったかもしれない。ヴィラヤヌル・ラマチャンドラン「数字に色を見る人たち」
これによって、エイブラムが主張していたように、知覚とは分離された二元論ではなく、移行性、可逆性、共感性、共感覚性を伴った未分化の相互浸透であることが、ある程度証明されたのではないかと思う。それだけでも、『感応の呪文』は十二分に重要な書籍なのだが、さらにこの四つの知覚の前提を受け入れることで、現在の言語理論に対して別の道を示していくことになる。
少なくとも科学革命以降に一般化し、また今日でもほとんどの言語学者が最も一般的なものと仮定している言語観によれば、あらゆる言語は恣意的ではあるが慣習的に合意を得ている言葉ないし「記号」の連なりであり、統語的および文法的規則に備わる純粋に形式的なシステムによってつながっている。このような見解のもとでは、言語はコードの様相を呈する。言い換えれば、言語は知覚世界における現実の物や出来事の表象=再現前の方法であって、世界との内在的で非恣意的な結合がなく、したがって世界から切り離すことが可能だということになる。デイヴィッド・エイブラム『感応の呪文』
さらにエイブラムは、「そうした言語観は、意味を新たに創造してゆく行為が廃れ、『われわれから真の表現の努力といえるものを少しも要求せず、聞き手がそれを了解するためにも何ら努力を必要としないような』慣習的かつ既成の様式にならって人びとが話をする時、すなわち意味というものが貧弱になってゆく時にのみ生じうる」と続ける。彼は、科学革命以降の最も一般的な言語観(ソシュール以後) —— 世界と分離された慣習的かつ恣意的な記号システム —— では、意味を新たに創造していく行為が廃れると警鐘を鳴らしている。なぜなら彼は、言語が世界と分離されたものではなく、世界が奏でる音、形、そしてリズムと切り離すことができないと考えているからである。
よく知られている一章「表現としての身体と言語」(『知覚の現象学』)では、言語が身ぶりに由来するということ、すなわち、伝達指向的な意味はまず身ぶりに宿り、この身ぶりによって身体が自発的に感情を表したり感情の変化に対応する過程を詳細に論じている。身ぶりは自発的かつ直接的であり、心の中で特定の感情と結びつけられてしまうような恣意的な記号ではない。むしろ、身ぶりこそ私たちの感情が具体化したもの、明確に見て取れる形をとった喜びや怒りという感情なのである。そうした自発的な身ぶりに遭遇したとき、私たちはまずその身ぶりを意味のない態度として受け取り、次に心の中で特定の内容や意味と結びつけて理解するということはしない。身体的身ぶりは私たち自身の身体に直接話しかけるのであり、内的にあれこれ考えることなく理解されるものなのである。
活動的な生きた語りはまさに身ぶりであり、言葉の意味をその言葉の音、形、リズムと切り離すことのできないような音声的身ぶりである。伝達指向的な意味は根底において常に感情に訴える。すなわち、他の身体ないし風景全体と共鳴することができるという元来身体に備わっている能力から生み出され、経験をめぐる感覚的な次元に根ざしているのである。言語的意味は、物理的な音や意味に恣意的に当てはめられて「外的」世界に投げ出されるような観念や身体のない本質といったものではなく、感覚的な世界の深奥から、すなわち出会い、遭遇、参与=融即という行為のさなかから生まれてくるのである。デイヴィッド・エイブラム『感応の呪文』
エイブラムはこのように、言語とは世界と分離した恣意的かつ慣習的な記号システムではないと繰り返す。融即を前提とした身振りによって、僕たちは世界と共鳴し合い、音、形、リズムと絡まり合いながら意味を生成している。また彼は、「慣習的な意味から成るこの二番目の層を、口頭の表現に備わる音の調子、リズム、共鳴によって成立している意義、感じることのできる意義から切り離してはじめて、言語をコードとして —— 純粋に形式的な規則によって結びつけられている恣意的な記号から成る確定的で写像可能な構造として —— 捉えることが可能になる。そして、言語を真に抽象的な現象であると考えることによってのみ、言語が人間だけの所有物である」と言うのだ。
確かに、エイブラムの主張は非常に興味深く、僕に限って言うと、かなり実感に近いものがあるので納得できる。しかし、身振りが言語の起源であるという仮説に対して、言語学の主流は懐疑的なので、再びラマチャンドランに登場してもらい、先ほどの議論を説得的に示しておきたい。
言語を発明しようとしている原始人のグループを想像してみよう。みんなはリーダーを見つめている。「よし、今日からこれをバナナと呼ぶ。さあ、みんなで言ってみよう。バ・ナ・ナ」—— いやいや、こんなふうではなかったことは確かだ。
そのグループには、すでに体系的な言語コミュニケーションのための下地ができていたはずだ。私たちは共感覚の神経生物学的基盤を研究したことにより、隠喩の発達(つまり外見上は似てもいないし、関連つけようもないものどうしに深いつながりを見つけられるようになったこと)が、タネとなって、そこから言語が芽生えたのではないかと考えるようになった。
人間には、ある特定の形にある種の音を結びつけるという生まれながらの傾向がある。これは、原始人が共通する語彙を使いはじめるときに重要だったはずだ。さらに、物体の視覚的形態、文字や数字、そして単語を処理する特定の脳領域は、共感覚者でない人でも相互に活性化される。つまり、ぎざぎざの形態には鋭い発音の名前をつけたくなるのだ。
さらに、2種類の異なるタイプの神経連絡が私たちの考えを裏付ける。第一に、視覚的形態と聴覚のための知覚野は脳の後ろ側にあるが、ここと、脳の前方にある発話に関係する特定の運動領域の間には交差活性化が起こる。とがった形や耳触りな音は、発話に関係する運動制限領域を誘発して、目や耳から入ってきたぎざぎざの情報に合うような破裂音が出るように舌と口蓋を動かす。
「ちょっぴり」「ちょっと」などを意味するdiminutiveやteeny-weeny、フランス語のun peuの発音をするときに、私たちは口をすぼめるが、これは物の小ささをジェスチャーで示しているのだ。脳は、見たことや聞いたことを、その入力情報にあった口の動きに翻訳するルールをもともと持っているらしい。
第二の証拠は、手と口の動きに必要な一連の筋肉の動きを調整している2つの近接する運動野間で、シグナルの溢れ出しのような現象が起こることだ。私たちは、この効果を協調運動と呼んでいる。ダーウィンが指摘したように、はさみで紙を切るとき、私たちは無意識のうちに歯をくいしばったり弛めたりしている。まるで手の動きを口に反映させているかのようだ。言語学者の多くは、手の動きが声の言語の基礎になったという説には異論を唱えているが、協調運動は「手の動き・言語説」の裏付けになると私たちは考えている。
私たちの太古の先祖が、主として唸りや喚きや悲鳴などの感情的な声でコミュニケーションをとっていたとしよう。それらの声は右半球と感情に関係する前頭葉によって生み出されるということがわかっている。後に、身振りによる初歩的なコミュニケーションシステムをつくりあげ、それが徐々にもっと精巧で洗練されたものになっていった。
何かを自分の方に引っ張る手の動きが、「こちらへ来い」という手招きへと発達したという仮説には無理がない。そのような身振りが協調運動によって、口と顔の筋肉の動きに変換され、それから、のどから出てくる感情的な声がこれらの口や舌の動きを通して伝え、その結果として、最初の発話が生まれたと考えることもできる。
では、この説にシンタックス(言語において単語やフレーズを用いる規則)はどのようにはめ込まれるのだろうか。道具の発明が、これに重要な役割を果たしたかもしれないと私たちは考えている。たとえば、まずハンマーの頭部を作り、次に柄を付け、それから肉を叩き切るといったふうに、道具作りには順序がある。これは大きな文の中に節を組み込むのと似ている。カリフォルニア大学ロサンゼルス校のグリーンフィールド(Patricia Greenfield)に続いて、私たちも、道具の使用における下位部品の組み立てのために発達した前頭葉の領域が、のちに単語を節や文章につなぎ合わせるという完全に新しい機能にとって代わられたのかもしれないという説を提案する。ヴィラヤヌル・ラマチャンドラン「数字に色を見る人たち」
エイブラムとラマチャンドランによると、言葉の意味は本来表情に富み、身振り的であり、かつ詩的なのである。僕たちにはもともと、異なる感覚を繋ぎ合わせる能力が備わっている。これを隠喩的と呼んでもよいし、詩的と言ってもよいだろう。そして、ここまでロゴス的論理と言ってきた慣習的で指示的な言語は、本質的に二次的で派生的なのだ。もし言語が純粋に理性的で恣意的なコードではなく、「肉的相互交流と参与=融即から生まれる感覚的で身体的な現象」であるならば、私たちの言語は人間という種以外のものの身振り、音、リズムからも影響を受けていると言えるだろう。それはウィラースレフのミメーシスの理論からでも、エイブラムによる融即理論からでも示すことができるはずだ。そうなれば、もはや「言語」は人間だけの所有物ではない。言語が、常にその根底において身体的、感情的に共鳴するのであれば、鳥が奏でる歌の疑いようもない表現の豊かさや、深夜に響きわたる狼の遠吠えから、完全には分け隔てられない。実際、もし人間の言葉が身体と世界との絶えざる相互作用から生ずるのであれば、エイブラムの言うように、「この言語は私たちに『属して』いるように生命的風景にも『属して』いる」のではないだろうか。
ここまでで、言語とは何かを見ていくことを通じて、身体を活性化させること、あるいは体性感覚から主語的統合を作り出すための基礎を描き出せたのではないだろうか。円としての私は、眼によって分離された対象を表象するのではなく流れの中に内在し、視点が移行し、さまざまな情やイマージュ、音や形が飛び交う中で、リズムを感じ、自らの身体で振る舞い、それらを隠喩的に接合していく。そして、それは身体が自然に根を下ろした状態なのである。そうでなければ、言語は死んでしまうのだ。主語的統合を作り変え続けなければならない。それが身体を制作するということなのである。
もし僕たちが融即としての知覚を、ミメーシスとイマージュの力を再度手に入れるならば、それは可能である。確かに、単純に推奨することはできない。そこは、「私は私でなく、私でなくもない」という危険なバランスが求められる場所なのだから。宮川が言うように、僕たちは「鏡の中へ降りていく」ことを何より恐れる。しかし、恣意的で無機質なシステムの中で鬱々としながら、自己同一性の檻の中に入っているくらいなら、「制作」を介して、その世界へ降りていくことを選ぶ方がいいのではないだろうか。
エイブラムは言う。「人間の作った複雑な技術をすべて放棄しなければならないということを意味するのだろうか。いや、そうではない。だが、感応的世界としっかり付き合えるようにならねばならない、ということは含意されている」と。なぜか。それは「身体的世界の肌理、リズム、味わいを知り、人間の発明品との違いを容易に見分けることができなければならない。直接的で感応的な現実だけが人間以上の神秘において唯一の試金石であり続け、電子的に生産される眺望や遺伝子工学で作られた快楽にあふれた昨今の経験世界を判断する確固たる試金石になる。身体的に感じることのできる大地や空との日常的な接触を通してのみ、私たちは、私たちを支配する多次元において自分の位置を確かめ航海する術を学ぶ」からである。僕は今を生き延びるためにこそ、むしろエイブラムにならい、そして勇気をもって、「制作へ」と言うのだ。
[16]ロゴス的環境と資本主義の論理
自殺した女の子の日記を見ると人、人、人……人物しか出てこない
犬はいなかったのか? 猫は? 鳥は? 花は?
コンクリート塗れの人工物に囲まれた閉塞空間の中ではどうしても
人間関係の比重が重くなってしまう
軸足の半分は、花鳥風月の自然に置いたほうが良い養老孟司『ホンネ日和』
これは2011年9月25日(日)にTBSで放送された『ホンネ日和』という番組で、養老孟司が語った言葉である。僕はこの言葉を聞いたとき、まさにエイブラムの融即についての四つの特徴を思い出していた。とりわけ、移行性と可逆性の部分である。僕たちは見るものであり、見られるものであること。あるいは食べるものであり、食べられるものであること。これは確かに、ジャガーやマウンテンライオンと遭遇した場面を想像すれば、容易に理解できる。鳥やエルクがいる。木があり、花が咲いている。ヒトとは異なる生命がいることは、ヒトというものが一つの視点に過ぎないことを理解させてくれる。人間関係に疲れることは多々あるだろう。しかし、そのとき自然に根を下し、感応的に身体が動きさえすれば、そこには動物や植物との声と、形と、リズムによるコミュニケーションがある。そして、そこで制作すればよい。身体を、言語を、それぞれの仕方で作り上げればよい。確かにそうだ。
理論として理解できても、身体を開くのは、難しい。そう思う読者がいてもおかしくないと思う。僕たちは人、人、人、そして人工物に囲まれている。養老孟司が言うことは確かに正しい。軸足の半分は、花鳥風月の自然に置いた方がいい。しかし、どうすればいいのだろうか。この章では、芸術、狩猟、宗教、そして脳科学の一部などで、ここまで論じてきたような身体の在り方が幅広く見られるにもかかわらず、なぜ分離する二元論的な見方が近代世界を覆い尽くしているのかを考えてみたい。そして、これまで記述してきた「制作」の概念によって、最終的に近代世界を生き延びる技法として示せればと思う。
木岡伸夫は、二元論が広く一般化している理由をこう述べている。
デカルト的な世界認識の方法・構図が、古い見方に取って代わったということは、それが正しいからというよりも、その見方に付随する実践の成果が、人々に受け容れられ、支持されたということに過ぎない。つまりそれは、新たに確立された機械論的な自然観が、それまでに不可能であったような能動的で積極的な生き方、人間の世界に対する技術的な支配を可能にしたということである。それは、世界認識の「正しさ」ではなく、実践に結びつく有用性が人々によって受け容れられたということを意味する。〈あいだ〉に関して言えば、〈もの〉と〈こころ〉には中間が存在しないというのが「正しい」ということではなく、そういう中間的なものを考えない態度が、技術的実践に必要不可欠であったというだけのことである。〈あいだ〉を考えるよりも、考えないことの方に有益さがある。このことが、哲学的二元論のロゴスを近代科学の原理たらしめた根本的理由である。レンマ的論理が、ロゴス的論理に対するオルタナティヴとしての地位を失い、忘却の彼方に退くことになったのは、それが認識の原理として不適切で誤りである、というようなことではなく、社会が期待する実生活に有用な論理ではなかったからにほかならない。木岡伸夫『〈あいだ〉を開く』
確かに木岡の言うように、これまでの技術的水準であれば、ロゴス的論理を用いて、要素を外在的に組み合わせることで十分に必要な需要は賄えたのかもしれない。しかし、木岡が『〈あいだ〉を開く』を書く動機として、生命を捉える論理が必要とされてきていると言うように、分離された二元論で世界を捉えることには限界が来ているように思う。それは環境汚染などの問題だけではない。僕がここまで、「人工進化」や「マグロロボット」の例など、実際に「内在的観察」が社会実装の水準で必要とされてきている事実を示してきたこと、あるいは養老孟司の言葉からも察することができるように、今やますます画一化と自己同一性を強める現代社会において、このエッセイで記述してきた技法は、技術の面でも実存の面でも必要不可欠の知識であると、僕は考えている。とは言え、まだ答えを急がず、別の視点からの論点も眺めてみよう。
福岡伸一は『福岡伸一、西田哲学を読む』で、木岡とは別の視点から、「内在的観察」が排除されてきた論理を語っている。彼がその典型的な例として挙げるのは、花粉症である。そもそも花粉症は病気ではなく、免疫システムの暴走であると言う。清潔になりすぎた近代社会では排除するべきウイルスや雑菌が少なく、花粉に害があるわけではないにもかかわらず、免疫システムはそれを過剰に洗い流そうとしてしまう。これは、「①ある免疫細胞が花粉に反応してヒスタミンという物質をばらまく。②別の免疫細胞の表面にあるアンテナのような分子(ヒスタミンレセプター)がヒスタミンをキャッチし、外敵が襲来してきていることを察知する。③この免疫細胞が涙や鼻水のような分泌液をたくさん出させて、花粉を体内から洗い流そうとする」と形式化できる。この状態を、僕たちの社会は花粉症と名づけているのである。
こうした暴走を機械論的に見て治そうとすると、僕たちは抗ヒスタミン剤という薬を服用することになる。抗ヒスタミン剤とは、ヒスタミンとしての機能(外敵が襲来してきたことを知らせる信号)は持たないが、ヒスタミンレセプターを占拠することができるように、ヒスタミンに似た化学構造をもった物質のことである。免疫系は、前述した三段階の作用によって花粉症の状態を作り出しているので、先ほどの②の段階を防ぐことで、涙や鼻水など人間が不快と感じる反応が生じないようにするのである。
しかし、すでに見てきたように、僕たちの身体は同一性の構造ではなく、常に分解と構築を続ける不安定な流れである。免疫細胞、ヒスタミン、ヒスタミンレセプターという上記の関係も、絶え間のない合成と分解の最中にある。機械論的に考え、常に同一構造であると考えるなら、②をブロックすれば花粉症は治ると言える。しかし、生命現象は動的平衡の中にある。抗ヒスタミン剤を飲み続けると、ヒスタミンレセプターが常に占拠され続けているため、それに合わせた新しい平衡状態へと身体は変化することになる。つまり、ヒスタミンレセプターが常に占拠されている状態とは、ヒスタミンが常に分泌されている状態=外敵が侵入してきている状態だということを意味しているので、細胞は危険だと感じ、もっとたくさんのヒスタミンレセプターを作り出してヒスタミンをより鋭敏に受容できるように作り変えてしまう。こうして、実際に免疫細胞が花粉に反応してヒスタミンを分泌するとき、より多くのヒスタミンレセプターと結びつくことで、「より激しい花粉症」になっていく。このように流れの中で生命に対する「内在的観察」を行なうと、機械論的な治療は、より状態を悪化させていくと理解できる。しかし、福岡はそれでも生命を「内在的」に見ることは近代社会になじまないという。
このように、機械論的な見方と動的平衡の見方では、やはり「時間の軸」があるかないかということが、大きな違いとして存在しています。絶え間なく合成と分解が起きている絶対矛盾的自己同一の世界では、絶えず新しい平衡が求められ、一回限りの生命として同じ状態が起こることはありません。一方、機械論的な見方では、生命を機械として見ますので、刺激と応答というものが常に同一のものとしてとらえられます。抗ヒスタミン剤だけでなく、ほとんどの薬は、いまの話と同じように免疫系の仕事を邪魔したり、ある物質をブロックしたり、反応を阻害したりするものとして作られているので、もちろん、その場は効くんですよ。一時的には効きます。
こう考えると、ピュシスとしての生命を考えるときには動的平衡の見方でしか本来のあり方をとらえることはできないのですが、実は「動的平衡」は儲からない考え方なんです(笑)。機械論的に生命を見ると、抗ヒスタミン剤を投与すればその場は効くので、製薬会社はそれで儲けることができます。一方、動的平衡論では、「その治療法は最終的には無力で逆説的に生命にリベンジされてしまうから、花粉症とは騙し騙し付き合っていくしかない」と説くわけです。これは明らかに儲からない考え方ですよね。「動的平衡」や「ピュシスの立場」は資本主義になじまない考え方なんです。〈モノ〉として見えないと資本主義社会の中では価値を生み出すことができないのです。「逆限定」が大事だと訴えたところで、「逆限定」という〈コト〉それ自体は商品化できませんから。悲しいことに、資本主義社会では、どうしても生命というものを〈モノ〉の延長として考えざるをえないという側面があることも否めません。福岡伸一『福岡伸一、西田哲学を読む』
福岡は花粉症を例にして、機械論的な見方と動的平衡の見方を対比的に描いているが、これは花粉症だけでなく一般にも言えることである。近代社会では、AはAであるという自己同一性を前提に、機械論的立場からその場、その場で一時的に問題を解決していく。もちろん、問題は徐々に悪化していく。しかし、そうするしかない。一時的な解決が、その人、その社会にとって何よりも重要だったりするのである。他方で、「制作」的立場では、すべては「AはAではなく、Aでなくもない」という危険なバランスの中での舵取りをすることになる。福岡の言い方で言えば、騙し騙し付き合っていくしかない。花粉症で言えば、涙や鼻水が出てきたら、身体が過剰反応しているな、と自らに言い聞かせて、マスクなどで花粉が免疫細胞を刺激しないようにしたり、少し作業を休んだり、食べ物を変えるなどして、徐々に体質改善を図っていくしかない。もちろん即効性はなく、体質改善に関しても、これをすれば万事解決といった方法は存在しない。それぞれの動的平衡状態は、人それぞれ異なるからである。これでは、「こうすればいいですよ」「これを飲めばよいですよ」と、「商品」として提示できないから儲からない。しかし、生命は後者の論理で動いている。自らの身体で実験していくしかない。まさに「人工進化」の例のように、偶然と試行錯誤を繰り返していくしかないのだ。不安定な身体の統御。それが生きることなのである。
さて、エイブラムは、東南アジアでの調査から北米に帰った後の強烈な体験を語っている。彼は当初、彼の中で湧き上がってくる新しい感性に興奮していた。「近所の木からすばやく下りて芝生を横切ってきたリスとおしゃべりしたり、近くの河口でサギが魚を捕る様子やカモメが海岸沿いの岩めがけて高所から貝を落とし中身を取り出す様子を何時間も立ちっぱなしで見つめたりする私を見て、近所の人たちは驚いていた」そうである。
しかし、彼は徐々に動物自身の気づきの感覚を失いつつあった。表情と感覚に富んだ風景を幻想だと思うようになっていた。それは彼自身が、「そのとき私は、自分自身の文化に再び順応しようとしていたわけで、言葉や相互作用をめぐる文化的様式に自分をあわせようとしていた」と振り返るように、文明化した社会に再度適応したことを意味している。そして彼は、再度旅に出ることを決意する。彼は、南西部の荒野や北西部の海岸沿いの先住民保留地で長期間暮らしたり、北米大陸の原生自然を何週間も歩いて旅した。そして、彼は「未発展世界」と呼ばれるところで習慣的に経験した、あの異質な感情や知覚を引き出す別の方法があることに気づき始めたという。
私は、西洋で一般的に考えられている何倍もの強度とニュアンスでもって非人間である自然の世界を知覚したり経験したりすることは可能だということを学んだ。人間の外部の現実に向けられた強い感情、他の種や地球への深遠なる関心を可能にしていたのは何だったのか。そうした感情や関心は数多の自文化の型によって抑え込まれ飢餓状態におかれているほどだ。逆の問い方をすれば、近代西洋における注意の欠如を可能にしているものは何なのだろうか。土着文化に示されているような自然との調和がより根源的で参与的な知覚様式と結びついているのであれば、西洋文明がそうした知覚的相互交流から逸脱したのはどうしてなのか。言い換えれば、どうして私たちの耳や目は、他の種の生き生きとした存在に対して、そしてそれらが棲まう生命的風景に対して閉じ続け、そうした風景をよく考えもせずに破壊しようとしているのだろうか。
なるほど、非人間である自然に対する無自覚は、他の種や自然一般に知性を認めない話し方によって据え置かれている。もちろん、この無自覚には、私たちの文明化された存在 —— すなわち鳥や風の声をかき消すモーターの絶えざる低いうなり、星だけでなく夜そのものを覆い隠すまぶしい電気、季節を隠蔽する空気調整器、人間によってつくられた世界の外へ出る必要性をあらかじめ除去するオフィス、自動車、ショッピングモール —— も関わっている。私たちが意識的に自然と出合うのは、何を自然と定めるかという境界が文明とその技術によって限定されている時だけ、すなわちペットやテレビや動物園(よくても、注意深く管理されている「自然保護区」)を介してである。私たちが消費する動植物は自分たちで採集したり獲ったりしたものではなく、工業化された巨大農場で飼育され収穫されたものにほかならない。「自然」は単に人間文明のための「資源」の蓄積になってしまったかのようだ。そう考えると、私たちの文明化された目や耳が人間とは完全に異質なパースペクティブの存在にかなり無自覚だということや、西洋に移住する人や非工業文明から西洋に戻ってきた人が人間でないものの力の欠如に驚愕し困惑するのは、大して驚くべきことではない。
とは言え、文明による昨今の「自然」の商品化は、動物(および大地=地球)の対象への還元を可能にする知覚の変化についてほとんど何も説明していないし、私たちの感覚が〈他者〉の力 —— 長い間、最も神聖な儀式や踊りや祈祷を誘導してきたヴィジョン —— を放棄したプロセスについてもほとんど語っていない。
しかし、現在の私たちの思考そのものを構築している非常に多くの慣習や言語的偏見の根底にあるこのプロセスをひと目でも見ることはできないのだろうか。もちろん、そのプロセスが生み出した文明の内部からその起源に視線を向けても、それは無理であろう。だが、魔術師や、別の部族とともに過ごした後で自分の文化に完全には戻ることのできない人のように、文明の縁に立ち位置を定めてはどうだろうか。こういうひとは共同体の内でも外でもないところを彷徨い、都市の鏡張りの壁の向こうで地面を這い空を舞いながら変化する声や形に自分自身を開いている。そして、壁に沿って動きながら、この壁がどうやって作られたのか、どんなふうにして単なる境界線が障壁になってしまったのかという謎を解くヒントを見つけたいと思うようになるかもしれない。ただし、時機がよければ —— すなわち、よく訪れる周縁が時間的かつ空間的な縁であり、それが境界を定める時間的構造が溶解して別のものに変形するのであれば —— の話だが。デイヴィッド・エイブラム『感応の呪文』
養老孟司は「軸足の半分は、花鳥風月の自然に置いたほうが良い」と言い、エイブラムは「文明の縁に自らを位置づける」と言う。異質なパースペクティブとの感応的な関係を取り戻すために、〈あいだ〉に立つことが求められる。彼らの回答は、確かに有効かもしれない。これまで見てきたように、視点の移行性や肉の可逆性は実際に見る/狩るだけでなく、見られる/狩られる立場に置かれることで気がつくものでもあるからだ。しかし、多くの人はこの回答にがっかりするに違いない。なぜなら、結局僕たちはすでに近代社会に十二分に順応しており、その生活の循環から抜け出せなくなっているからである。彼らの言うことはもっともだと思いながらも、環境を変えようと決断することはできないだろう。エイブラムさん、あなたがアメリカに帰ってから、再度、旅立つことができたようには、僕たち/私たちはできない、と。
しかし、ここまで見てきたように、〈あいだ〉には二種類あるのだった。水平方向の〈あいだ〉と垂直方向の〈あいだ〉である。動植物との水平関係の〈あいだ〉があるように、即の論理、非即の論理を経由することで開かれる垂直方向の〈あいだ〉、つまり形の論理がある。僕たちは「描くこと」「書くこと」「狩ること」を通じて、「制作的空間」に参入する術を、ここまで確認してきた。実は近代社会にも、至るところに異質なパースペクティブは満ち満ちている。中世から近代にかけて〈述語的統合〉として近代の視覚中心の〈主語的統合〉が制作され、近代の只中では、その視覚中心の〈主語的統合〉から、また別の身体の制作が行われていた。一九世紀後半から二十世紀前半は、現在僕たちが置かれている状況と非常に似たものであった。機械化の波が、人々の生活を激変させ始めていた。モダニズムの芸術家たちは、動植物だけではなく、近代社会の只中で、異質なパースペクティブを取り込むことで、感応的知覚を取り戻し、それぞれの身体を制作していたのである。ここに、最後のヒントが隠されていると、僕は考えている。彼らの実践を見ていくことにしよう。
[17]二十世紀の新しい自然
異質なパースペクティブとの感応的な関係を取り戻すために、〈あいだ〉に立つこと。これは上述したように、水平方向での〈あいだ〉を開くことに繋がる。流れとして内在的に見ることやレンマ的論理によって見ることを可能にする。そして、それは視点の移行性や肉の可逆性を実感させてくれるものである。そうすることで、僕たちは彼らを模倣し、共感し、情を移し合うことができる。僕たちは一つの世界であり、一つの視点である。しかし、それと同時に、多数の異質な視点がある。模倣や共感によって、それを実感できる。
生物は、特殊感覚、体性感覚、内臓感覚など、複数の種類の感覚を用いて、光や音などの環境情報を電気シグナルに変換し、それらを脳内処理している。逆に言えば、それは各生物が、自然界に存在する環境情報のうち、それぞれに限定的な部分だけを感じとっていることを意味している。例えば、ヒトは磁気や紫外線、放射能などを感知することができない。コウモリが送受信している超音波すら感知できない。都市生活に慣れ親しんでいる僕たちは、それを感じていないことを反省するどころか、その存在にすら気がついていない。だからこそ、養老やエイブラムは、感応的な関係を再度取り戻すことを主張するのである。そうすることで、僕たちはそれぞれの身体と世界との相関性に閉じるだけでなく、その外側の存在を知り、振る舞いでもって交感するようになる。現象を超えて実在を感じること、音やリズム、形として繋ぎ合わせること。それはある意味、僕たちが自然に根を下しさえすれば当たり前のことなのである。テキストとは身体である。分かるだろうか。
僕は[9]において、「また人間は、自らの生物学的条件に基づいて、可視光の外側にある波長を赤外線や紫外線などと名づけているが、それは他の動物にはない特徴である。人間は道具によって所与の環世界、現象の世界を超えて、実在の存在を確認し、さらにそれを述語的に統合することで新たな身体を『制作』できるのである」と述べた。例えば、赤外線、紫外線、そして先ほど挙げた超音波という言葉では、人間の眼や耳を基準にして、「赤」や「紫」や「音波」という語に「外」や「超」が付け加えられている。しかし、実在にはそのような線引きは存在しない。五感が事後的に引いた線なのである。逆に見れば、人間は自らの身体の限界を超えて、「外」や「超」という領域を知ることができるということを意味している。もしそうでないなら、それらについて名づけることも、反省することもなく、存在にすら気がつかないはずだからである。ではなぜ可能なのか。それは、人間が人間拡張としての技術手段や媒体を発明してきたからである。
例えば、今や、僕たちは赤外線カメラや紫外線カメラを使えば、肉眼では見えない存在を容易に確認することができるし、上述した「人工進化」の例で、チップの0と1の間にある磁気的な漏出や磁束を発見できたのも、その存在を確認できる測定器があるからだ。そして、それを可能にしたのは「抽象化」の力である。分離された二元論が前提としているような中途半端な抽象化は、人間を中心に置く。そこから、さらに「抽象化」を推し進めると、人間は宇宙の一部となる。そして、それは再度、人間の世界へと折り返される。それが技術手段であり媒体である。例えば、相対性理論や量子力学は実用化のために推し進められた理論ではない。しかし、僕たちが今、スマートフォンを用いて自分がいる位置を確かめることができるのは、量子力学を用いて作られた原子時計と相対性理論による若干の修正があるからである。僕たちが普通に見ている世界は人間的現象であって、一つの視点によるものである。人間は世界の中心ではない。僕たちは人間と人工物に囲まれた世界の中で、そのように感じることができる。そして、量子力学と相対性理論の例からも分かるように、人間を超えた実在と人間の現象は、技術を介して相互に影響を与え合っている。僕たちが棲んでいる世界には、確かに動植物は少ない。それを嘆く気持ちも分かる。しかし、この「第二の自然」の中で、僕たちは〈あいだ〉を開き、五感の組み替えを行い、それぞれの身体を作り出すことができるのである。
この「抽象化」の力が、人間を自然から分離し、中心に置き、安心を与えるものだった時代を終わらせ、人間を宇宙の一部へと反転させはじめたのは、一九世紀後半から二十世紀前半であった。スティーヴン・カーンは『時間の文化史』と『空間の文化史』という著書の中で、次のように言う。
1881年頃から第一次世界大戦が始まる時期において、科学技術と文化に根本的な変化が見られた。これによって時間と空間についての認識と経験にかかわる、それまでにない新しい様態が生まれる。電話、無線、X線、映画、自転車、飛行機などの新しい科学技術が、この新しい方向づけの物的基盤となった。一方で、意識の流れの文学、精神分析、キュビズム、相対性理論といった文化の展開がそれぞれに、人の意識を直接形成することになった。この結果、生活と思考の次元が変質するにいたる。スティーヴン・カーン『時間の文化史』
すでに僕たちは、中世から近代にかけて、多声音楽、一点透視図法、実験科学という三つの革命によって、現在の常識的な〈主語的統合〉が作り上げられたことを見た。次に見るのは、〈述語的統合〉の比較的新しい時期における仮説である。カーンの著作では、1881年ごろから第一次大戦が始まる時期に、新しい科学技術によって、認識と経験にかかわる新しい様態が生まれたことを示している。ここに挙げられた電話、無線、X線、映画、自転車、飛行機が、それまでの人々の時空間の概念をいかに変えたかは容易に想像できるだろう。例えば、標準時の設定と無線の発明によって、同時性の感覚は相当に拡張した。タイタニック号の悲劇が今でも多くの人に共有されている理由は、無線によってリアルタイムに事故の状況が世界中に伝えられ、次の日には新聞でその情報が街に届くようになっていたことが大きい。
そして、新しい環境の変化の中で、それに対抗したり受け容れたりしながら、さまざまなジャンルの芸術家が、それぞれの身体を作り上げていった。もちろん、一人ひとりが新しい技術的布置の中で、それをどのように捉えてきたかを見ることはとても面白い。しかし、このエッセイで重要なことは、芸術家がその中でどのように身体を制作してきたかである。とりわけこの章で重要なことは、こうした急激な都市環境の変化の中で、芸術家たちによって「自然」の概念が変化したことにある。まずは、当時の芸術が置かれていた技術的変化について、アーサー・ミラーに別の角度から語ってもらおう。
芸術では、ルネサンス以来中心的位置を占めていた具象表現と透視図法に強い抵抗運動が起こり、それはポール・セザンヌの後期印象派において、非常に強力な形で表面化した。飛行機、無線電信、自動車など、技術における新展開は、人々の空間と時間の概念を変えつつあった。草創期の映画におけるエドワード・マイブリッジやエチエンヌ=ジュール・マレーの多重画像は、一連のフレーム上に異なる視点からの視野を描くことに加えて、時間変化を、連続したフィルムのフレーム、あるいは単一のフレームに描くことを可能にした。科学では、X線の発見で、内側と外側の区別が曖昧になったように見え、不透明なものが透明になり、二次元と三次元の違いもぼやけてきた。放射能は、見たところ無限の量のエネルギーをもっているらしく、空間は、いたるところで飛んでいてすべてを開けてしまうα線、β線、γ線、X線に満ち溢れているということになりそうだった。もっと抽象的な分野では、数学者が、三次元を超える次元で表される、風変わりな新しい幾何学について考えていた。人々は、空間の中あるいは時間の中での運動に影響する、四次元空間という考え方に、とくに心を奪われた。アーサー・ミラー『アインシュタインとピカソ』
その時代の膨大な芸術家たちを一人ひとり浅く広く伝えてくれたスティーヴン・カーンに対して、その時代がいかにピカソの活動に影響を与えたかをアーサー・ミラーは語る。美術史的には、ピカソのルーツは、セザンヌと原始美術にあることになっている。あるいはエル・グレコやアングルを参照にしていることも多いし、同時代のドランやマティスの創作活動に競争心を煽られていたことも事実だろう。しかし、僕たちが見ていきたいのは、この時代の芸術家が自然をいかにして捉え、そこでいかに身体を制作していったかであった。そこで例に挙げたいのが、ピカソ、そしてデュシャンである。
まずはピカソの例を見ていこう。アーサー・ミラー曰く、ピカソはこの時代の発見の中でもとりわけ三つの発見に大きな影響を受けていると言う。それは第一にX線、放射能、電子の発見であり、第二にメリエスの映画、マイブリッジとマレーの実験写真であり、第三にポアンカレによる非ユークリッド幾何学である。
世紀末の三つの重大な発見は、まさしく科学を自らの世紀末の無風地帯から引き出した。1895年のX線の発見、1896年の放射能の発見、1897年の電子の発見である。科学者は、これらの結果が感覚による知覚を超えた実在に起因するかもしれないという考え方を真剣に取り上げざるをえなくなった。
とくにX線は人々の想像力に訴えた。哲学的・科学的にすぐに言えることは、見たとおりのものが手に入るわけではないということである。人間の知覚には限界があるのだ。知識のこの相対性は、反実証主義の批評家をあおった。空間はもはや空でなかった。いたるところに光線が飛びかっていた。放射能による放出物であるα線、電子の別名であるβ線、その後X線と並んで一種の光と認められるγ線である。「X線」という名称そのものが、科学者がその正体を必ずしもよくわかっていないということを表していた。
……
映画製作者ジョルジュ・メリエスのことを思い起こそう。その最も有名な特殊効果は、人体の断片化と、時として奇怪で滑稽なまとめ方であり、その映画をピカソはドゥワイ通りの映画館で見ていた。
実験的な試みの系譜には、エチエンヌ=ジュール・マレーとエドワード・マイブリッジによる運動の探究もあった。マレーは一つのフレームで一連の出来事を調べ、マイブリッジは間をおかずに撮った連続写真を制作した。
マレーの多重露出は、形の分解という点でX線と似ており、さらに運動の連続性という息を飲む場面という点で、X線の先を行く。『ル・リール』に載ったイラストは、多重露出の実験に基づいた遊びである。マレーの写真は、しゃがむ女に初めて現れたキュビスムの同時性や形態の相互浸透をピカソが思いつくことに影響したに違いない。
マイブリッジは、ピカソに別のことを提供した。幾何学化が進んだ「構想」をもつ五人の女性の「映画的シークェンス」というアイデアである。
……
ポアンカレは、実際に第四の次元を見ようと提案し、自分の仮説を可能性の領域まで引き上げ、それによって、推測による思考を信じないために立てられる仮説すべてに検証を求める実証主義者からも離れ、その光景をX線を通したものか霊媒によるものかと見るオカルト派からも離れた。ポアンカレは、「われわれが四次元の世界を思い浮かべる」方法を、こうすればいいのではないかと言う。外部の対象のイメージは網膜に描かれる。これは二次元の平面であり、透視図法である。しかし、目と物は移動できるので、われわれは次々と、同じものをいろいろな視点から、異なる眺望で見る……さて、われわれが三次元の図形の透視図を、三次元(あるいは二次元)のキャンヴァス上に描くのと同様に、いろいろな視点から見た四次元の図形の透視図を描くことができる。幾何学者にとってはこれしかない。同一の対象のいろいろな透視図が次々と出てくることを想像しよう。(『科学と仮説』)
二次元平面上の光景が三次元からの投影でありうるように、三次元の面上の像が四次元からの投影と解釈することもできる。ポアンカレの第四の次元は空間の次元であり、彼はそれをキャンヴァス上に複数の透視図が並んでいるように思い浮かべることを提案する。これは間違いだった。ピカソはその視覚の才で、複数の透視図を、空間の中で同時に示すべきだということを見てとった。そうして『娘たち』が登場したのである。
空間の同時性についてのピカソの考えは、セザンヌの美術に典型的に現れるベルクソンの考え方を超えていく。セザンヌは、ある光景について蓄積された見え方全体を、すべて一度に(同時に)キャンヴァスにおく。つまり長期にわたる本人の無意識である。ピカソは、印象派の美術にある時間の概念も超える。たとえばクロード・モネの干し草の山やルーアン大聖堂の一連の絵のようなもので、これらは静的な再現の系列である。ピカソの空間的同時性がさらに過激なのは、全然別の視点、全部を合計すればその対象を構成する視点を同時に再現するからである。真正面から見た図と横から見た図とが同時に表されているしゃがんでいる娘は、ピカソには、四次元から投影したものと考えられていた。アーサー・ミラー『アインシュタインとピカソ』
1895年のX線の発見、1896年の放射能の発見、1897年の電子の発見は、人間の知覚に限界があること(肉の可逆性)、そして、人間と世界との相関を超えた実在がどうやらオカルトではなく確かなものらしいということを証明した。これは人間の視点を脱中心化する役割を担い、ピカソを素朴実在論者でも相関主義者でもなく、思弁的芸術家へと進ませた。つまり、現象の外側へ抜け、実在を描くという方向へと、彼を進ませたのである。メリエスの映画、マレーとマイブリッジの写真は、視覚の移行性、形態の相互浸透、そして運動について、彼を刺激した。ポアンカレの幾何学は、現象として現れる自然ではなく、実在としての自然を捉える上で、彼に大きな寄与をしたことは間違いない。それは四次元の思想との結び付きによって、より明確になる。そして、これらの事実は、彼が「現象的自然」ではなく「実在的自然」を捉え、それを観察し、描こうとしていたことを示唆している。それは、その自然の中でさえ、融即的知覚が開かれることを意味する。このことは、ピカソよりも、むしろデュシャンの実践の中で、より具体的かつ意識的に行われたことである。
[18]四次元とアンフラマンス — 機械状都市の中で生き延びるための技術
デュシャンによるレディメイドの戦略は、自明性ではなく、〈共通感覚〉を露わにすることであった。〈共通感覚〉は、僕たちの知覚の前提となる構造を「制作」する場所なので、あくまで彼の戦略はそこから始まるはずだ、とすでに記した。新しい身体を作ることは、「制作」を通じて〈体性感覚〉を活性化させること、周りの生命、風景と感応的関係を築くこと、内在的観察を行い、視点や情、イマージュが行き交う中で五感の組み替えを行っていくことであった。問題は、近代以降に生きる僕たちの周りには、人間と人工物しかないことである。情が宿り、情緒となりうる生命がない。養老やエイブラムが嘆いたのは、その点であった。
しかし、まさに機械化の波が押し寄せていた十九世紀後半から二十世紀前半は、芸術運動にとって最も活気ある時代であったと言える。僕たちが生きるようになったのは、機械状都市と呼ぶべき場所である。それは単に人工的で無機質なだけの孤独な場所ではなく、前章で確認したように、その新しい環境の中に別の感応の回路がある。そして、当時の芸術家たちは、その場所で新たに五感を組み替え、制作へと向かっていったのだ。それは五感の外側にある実在が科学的に証明され、実験的な映画や写真によってこれまでの知覚の常識が壊され、新しい時間と空間を描く幾何学が活気を帯びてきたことと関連がある。
その時代の芸術家たちを突き動かしていたのは、この露わになった実在の次元であり、当時この領域は「四次元」と呼ばれていた。中沢新一は『東方的』の中で、「いまでは美術史や思想史のなかでも、あまり注目されることがなくなってしまいましたが、二〇世紀はじめの芸術や思想における変革に、もっとも影響力をおよぼしていたのは、『四次元』という考えでした」と言う。そして、四次元の知覚について次のように説明している。
四次元の知覚というものが、どういうものかを正確に理解することは、とてつもなくむずかしい。それを考えるために、一般に試みられてきたやり方は、アナロジーを使うという方法であった。たとえばまず、二次元の世界に生きている奇妙な二次元生物を想像して、その生物に三次元がどのようにとらえられるのか、調べてみるのである。二次元生物の世界に、突如として三次元の球体が侵入してきたとしよう。この侵入物を、フラットランド(これが二次元生物の生きている世界にたいして、エドウィン・アボットがSF冒険小説『フラットランド』の中であたえた名前である)の住人は、どのようにとらえるだろうか。そのとき、フラットランドには突如、彼らにとって唯一の世界である空間に、どこからともなくひとつの点が出現し、その点はまたたくまに小さな円に変貌するのである。円はどんどん大きさを増していくが、今度はまた突然収縮をはじめ、ついには点にまで縮まって、その点もフッと世界の外部に消えてしまうのである。知性をもった二次元生物に立体を説明するのは、極度に難しい。たいていの二次元生物は、立体なるものの実在すら否定するだろう。ところが、それは実在し、二次元世界を通過していきながら、そこには自分の断面の軌跡を残すことだってできるのである。中沢新一『東方的』
想像できるだろうか。ここではまだ、一つ上の次元の実在が、一つ下の次元の世界に接触するとき、それがどのように現れるのかというイメージだけ掴んでもらえればいい。この時代における身体の制作という論点から言えば、現象を超えた実在の領域が数学的イデアと呼ばれようと、四次元と呼ばれようと、あまり関係はない。そうではなく、異質なパースペクティブとの感応的関係を結ぶことなく、X線や電子の発見によって、現象の世界が実在の世界ではないという認識をもち得るという点、そして、もしそういう認識をもったら、その世界をいかにして知覚するかという方向に進んでいくことを確認したいのである。例えば、チャールズ・ヒントンという四次元思想の先駆者の一人は、まさにその方向へと進んでいた。
人間が空間直観をもとにして、自分の世界を理解しているのならば、その空間直観のしくみに働きかけることによって、それを変化させ、新しいタイプの空間を直観できる能力にまで高めていくことだって可能ではないか、というのが、ヒントンの考えだった。カントがもとにしていたユークリッド的な空間直観の様式は、人間の知性にとってはあくまでもひとつのステップにすぎないのであって、そのことを理解した人間は、いまや次のステップにとりかかることが可能になっている、と彼は書いた。中沢新一『東方的』
ヒントンの思想はとても興味深い。なぜなら、僕たちはここまで、人間は〈共通感覚〉によって〈主語的統合〉を制作しうるし、これまでもしてきたことを確認してきたわけで、彼はその四次元思考を新しい〈主語的統合〉として実現しようと試みているからである。中沢曰く、「彼は、人間の脳の中に、四次元生物がもっていると考えられる一種の『三次元網膜』のようなものを実現するための訓練用に、発達したルービックキューブのようなものを考案しようとする努力を重ねた」らしい。そして、三次元である僕たちの世界を超立体が横切るときに見せる「横断面」のパターンの変化を捉えることで、超立体を構築する能力を鍛えていった。最終的には、「そういう実験をくりかえすことによって、とうとう彼は、四次元生物のもつと考えられる『三次元網膜』にもっとも近づいた、知覚の能力を獲得するようになった」そうだ。
僕にとって、ヒントンが本当に三次元網膜に近いものを習得できたか否かは、どうでもいい。それは、確認しようもないことである。しかし、中沢の主張でとても重要なことは、ヒントンだけでなく、マルセル・デュシャンも同様に、四次元知覚を可能にする新たな身体の制作に乗り出していたということである。レディメイドは〈共通感覚〉を露わにすることであり、新たな身体への始まりを告げるものなのだが、その宣言は誰かに向けられるだけでなく、彼自身にも向けられていたのだ。彼のチェス狂いは、まさに四次元知覚を可能にする身体の制作であった。
では、マルセル・デュシャンは、どうしたのか。デュシャンの解答は、チェスをする彼の姿に象徴されている。彼が相当に凄腕のチェス・プレイヤーだったことは、よく知られている。じっさい、彼は一時期、チェスに没頭していた。チェスはさまざまな意味で、興味深いゲームだ。最初、チェス盤を前にして、ふたりのプレイヤーが向かい合って座り、いざゲームがはじまろうとする寸前、そこには鏡の像のような対称性が、実現されている。ルイス・キャロルのアリスは、そのチェス盤の上から、彼女の四次元である鏡の国への冒険を開始した(キャロルの作品が非ユークリッド幾何学や四次元論から、おおきな影響を受けていることは、いまではあきらかである)。チェスの駒は、その盤上でつぎつぎに位置を変えていく。一手、一手にしたがって、チェス空間は全体の配置を変化させ、そのつどプレイヤーは、未来にこのチェス空間がとることになるであろう構造や配置について、考えられるかぎりの可能性を考えながら、つぎの一手を決定する。彼の頭の中では、プロポーションと配置を変化させていく、ひとつの多次元立体が動いているのだ。
また別のタイプのチェス名人になると、やはり目で見ることなしに、いくつものゲームを同時に指すことすらできる。こうなると、たんなる記憶のよさではすまなくなる。そのときチェス名人たちは、頭の中でチェス盤をヴィジュアライズできなければならないし、またこの頭脳の中に実現されるスクリーンは、変化のすべての様相を未来の時間にわたって投射することができなければならないのだから、とうぜん「四次元的」な構造をもっていなければならないはずなのである。ポアンカレがお得意の皮肉をこめて語っているように、「一生をこのゲームに費やすことができれば、人はついには第四次元を描くことができるようになるであろう」。デュシャンのチェスへの没頭を見ていると、ポアンカレのこの言葉が思い出されてくる(デュシャン自身は、この「目隠しチェス」には手をださなかったらしいが、彼の友人であったジョルジュ・コルタノフスキーは、一時期「目隠しチェス」の国際チャンピオンだったこともある)。中沢新一『東方的』
四次元知覚を身体化する方法として、デュシャンはチェスに熱中し、ヒントンは理論を構築し特殊なルービックキューブを用いて訓練した。デュシャンが身体を制作する場所は、またしても非対称の空間であった。今回は、鏡ではなく、チェス盤である。鏡の空間では、僕たちは「見る私」が「見られる私」を確認することで自己同一性を維持する表面から、いつしかその構造が不可避にもつ「見る/見られる」の分裂、その遅れ、距離の隙間を見出し、それ自体を生み出している場所、「私は私でなく、私でなくもない」場所へと誘い込まれていた。
チェス空間の場合は、対戦相手と向かい合っている状態で、「私」は可能な一手を考える。私一人の可能世界で閉じていては勝てない。一手ごとに、相手が可能な手も考える。あるいは相手の可能な一手に対して、私は私の可能性を考える。私は、狩る/狩られるという立場を往還することで、あるいは私と相手の可能世界の蝶番をくるくると回転させながら、私と相手の〈あいだ〉に可能世界を構築する。しかも、その可能空間は、ゲームが進むたびに動的に配置が変わっていく。いつしか、私は、その混ざり合った動的な場所にいることに気がつく。
もちろん、ヒントンがいくら超立体を三次元の世界で把握できるようになったとしても、デュシャンが卓越したチェス・プレイヤーになろうとも、それだけで「芸術」にはなりえない。「芸術」にする必要はない。それは単なる「制度」なのだから。デュシャンは、もはや「芸術」ではないことに、面白味を感じていた。彼は、この新しい身体を用いることで、次元を跨る知覚を見出すことに関心をもっていた。それは「アンフラマンス」と言語化されたものである。
アンフラマンスとはどのような意味なのか。北山研二は「新しい知覚概念・新しい対象着想法としてのアンフラマンスとは」という論文の中で、「アンフラマンスとは、アンフラ(infra)が『下の、以下の、外の』の接頭辞で、マンス(mince)が『薄い』という形容詞なので、極薄か超薄か薄外ほどの意である。たとえば、赤外線(infrared)は、可視的ではない。ときには熱を感じることはできる。その意味では、アンフラマンスはただちには感じられないが、知覚鋭敏になれば感じることもある現象と言えるだろう」と言う。これまで視覚として見たら、赤「外」線だった領域も、触覚としては温かさを感じられる。デュシャンは、「(人が立ったばかりの)座席のぬくもりはアンフラマンスである」と言ったりする。彼はアンフラマンスを日常の至るところに見出す。「煙草を吸うとき、その匂いは口の中にひろがり、吐き出されるふたつの匂いは、アンフラマンスによって結婚する」、と。
たばこが出す煙と口から出る煙とは、視覚的には同一と見なせるが、嗅覚的には極小的差異がある。その差異は微妙で、気がつく人は気がつく。時間差があるから、温度差にも関係する。温度差があるからそれと気がつく。両者のにおいは、嗅覚的アンフラマンスによって隔てられているし、結合しているとも言える。「隔てられているし、結合している」とは、ある視点から見れば非連続的であり、別の視点から見れば連続的であるということだ。北山研二「新しい知覚概念・新しい対象着想法としてのアンフラマンスとは」
僕は、ここに都市におけるレンマ的思考の一端を見る。たばこの煙を外側から見るのではなく、内側から見ること。そうすることで極薄の差異が見出される。外側から見た時、それは単なるたばこの煙である。しかし内側から見れば、そこに温度差が、時間差が、匂いの差があることが分かる。外側から見れば同一、内側から見れば、その同一性の中に無数の差異が生じていることが分かるのである。
デュシャンが関心を持っていたのは、このように、日常生活の中で「アンフラマンス」を発見すること、そして、「アンフラマンス」をつくり出してみせることだった。すでに見てきたように、「作品」の成立条件は、「制作」の外在化である。仮に高次元の概念であっても、もし「作品」として提示したいのであれば、それを三次元に置き換えなければならない。彼がその時に用いたのは、射影という方法であった。
彼はこの三次元の世界の中にある物体を、四次元物体の「影」としてとらえようとしている。ヒントンをはじめとする四次元の思想家たちは、一次元:二次元:三次元:四次元と次元を増やしていくときにおこることのアナロジーを使って、四次元知覚なるものを、思考可能にしようとしていた。デュシャンは、その逆を行ったわけである。彼は三次元の立体が二次元の平面に影として投射されるとき(そのいちばんいい例は写真である)、ディメンションがひとつだけ減ることに注目した。つまり次元数のちがうふたつの世界が出会って、そこに切断の現象がおき、横断面がつくられるとき、かならず次元数の高いほうが、ひとつだけ次元を減らしながら、そこに影をつくりだすのだ。このアナロジーを使うと、三次元世界の物体はすべて、四次元物体の影であり、私たちが実在と信じているものは、じつは「射影」の現象にほかならないのだ、ということになるだろう。デュシャンは四次元知覚そのものをとりだすのではなく、この射影のプロセスがおこっている切断面や横断面の出来事を、とりだしてみようとした。
『大ガラス』は、四次元が三次元に入り込む、まさにその瞬間を物質化してとりだそうとするオブジェとして、構想されはじめた(それがキュビスムが転換をおこしたのと、同じ年だったことには、意味がある。キュビスムは芸術を擁護するための転換を決意した。ところがデュシャンは、その芸術が無化されてしまう限界点のほうに、進みだしたからである)。それは射影のおこる「横断面」「切断面」を、物質化しなければならない。そうなると、そのオブジェは、ふたつの次元数の異なる世界をしめす領域と、それらが交わりあい、接触をおこす環境面とから、つくられることになるだろう。デュシャンのノートには、それが四次元の超空間的な動きをしめしている領域と、その四次元の影としての三次元世界を実在としてつくりだす意識の働きをしめす領域とのふたつで、つくられることになるだろうこと、そして、そのふたつの領域のあいだには、おたがいのあいだのコミュニケーションを可能にし、かつ不可能にしている薄い境界の膜が引き渡されることになるだろうことが、記されている。のちに実現された作品において、上半分をしめす「花嫁」と、下半分をしめる「独身者たち」の部分として、彼はこの考えを実現してみせた。中沢新一『東方的』
デュシャンは、投射という考えによって、四次元の実在を三次元に横断面として示そうとする。しかし、作品であるからには、その横断面をどのように物質化するかが重要になる。ここで、また重要な意味をもつのが、鏡とチェス盤である。中沢は「ルイス・キャロルは『鏡の国のアリス』において、あきらかに四次元世界の特徴をそなえたアナザー・ワールドへの入り口を、チェス盤と鏡に見出そうとしている。チェス盤は、ここでは鏡のメタファーになっている。チェス盤から鏡の世界までは、ひとつづきなのだ」と言う。それは、すでに鏡とチェス盤の上で生じていることを見てきた僕たちには、納得できる主張である。むしろ、〈あいだ〉の空間を開く装置として、ときに鏡が、ときにチェス盤が用いられていると考える方がよい。中沢自身もそのことにすでに気がついている。そして、それを「ちょうつがい(蝶番)」という言葉で説明する。
ではどうして鏡が、四次元への入り口と考えられたのか。これには、いくつかの理由があるが、いちばん大きな理由は、鏡の表面がもたらす「ちょうつがい」の感覚効果にあるような気がする。鏡を見ている人は、ちょうどチェス盤を前に向かい合うふたりの人間同士のように、自分のイメージと対称的な関係で、向かいあう。ところが、鏡の表面では、左右の反転が起こっているのである。こういう鏡の不思議さをめぐって、デュシャンの時代には、カントの議論がよく知られていた。カントは右手と左手のように三次元世界において対称的な物体を、そのままひっくりかえすには、空間における第四の次元が必要であることを、はっきりとしめした。ヒントンは、わざと左右をとりちがえさせるのが、四次元的思考へいたる最良の道だ、とも語っている。左右のとりちがえをおこしながら、日常生活に支障をきたさないで行動するためには、その瞬間瞬間に世界を鏡像的にひっくりかえす思考に、巧みになっていなければならない。
こういう「鏡像反転」や「ひっくりかえし」は、したがって、四次元世界が三次元の世界に接触する、その「ちょうつがい」の部分でおこるはずなのだ。鏡の表面が、人間の視覚にもたらす効果は、この「ちょうつがい」の働きにかぎりなく近い。鏡の表面はあきらかに三次元の世界に属しているが、ここで光の戯れがおこしてみせる現象は、その表面の「超薄さ」の部分に、第四の次元が染み込み、侵入をはたしているような奇妙な感覚をあたえるのだ。そのために、このかぎりなく薄い表面を利用して、アリスは裏返しにひっくりかえり、左右を反転させて、その表面の向こう側に拡がる四次元の空間の中に、まぎれ込んでいってしまうことができる、と考えられたわけだ。鏡の表面は、けっして鏡の空間そのものの中に入っていくことはできないが、すばらしい「ちょうつがい」として、四次元空間の侵入の跡を、示すことができるのだ。中沢新一『東方的』
デュシャンは鏡の向こう側に降りていく。そして、彼は、その鏡の中の乱反射を浴びることで、自らの身体を作り変える。デュシャンが行なったことは、都市の中での「内在的観察」を可能にする身体制作であった。彼は、「制作」という実践を通じて、都市空間であっても感応的な身体を作り出し、都市の至るところに「アンフラマンス」を見出した。彼は、自らの身体を変容させることによって、実在を知覚する。そして、その知覚を〈形〉にすることによって、「作品」を作る。「作品」とは「制作」の外在化であり、制度化である。しかし、それは同時に、いつか、どこかで、誰かの、次の、身体制作への足場となるものでもある。僕が今、彼が作った足場に立っているように。つまり、「作品」とは外在化であり、誘惑であり、誘惑された者たちの、小さな部分的共同性を生成する装置でもあるのだ。
デュシャンはあくまで、一例にすぎない。仮に彼が、「芸術」にすることがなかったとしても、それはそれでよかったのかもしれない。(しかし、作らないことは可能だろうか)。まずは、それぞれの身体をつくり出すことである。もちろん、身体はそれぞれの仕方で制作される。そして、それぞれの知覚を見出すことである。「描くこと」「書くこと」「狩ること」「チェスすること」。様々な経路をつうじて、僕たちは「制作的空間」へと、降りていく。もう恐れる必要はないだろう。その場所の魅惑の中で、〈作ることの可能性〉は〈作らないことの不可能性〉へと転ずるのだから。あとは、一人ひとりが、「制作へ」と向かっていくだけなのだ。
最後に、宮川淳『鏡・空間・イマージュ』から引用することで、このエッセイを終えることにする。
「芸術とはなにか」という問いはなぜもはや不毛な問いでしかありえないのか。それはこの問いを問いとして可能にする「芸術は……である」という答がもはや成立しないからだ。「芸術はaである」をbに代え、cに代え、あるいはa+b+c……としても、この事情には変わりはない。むしろ、われわれは「芸術は……ない」という否定形でしか芸術について語れなくなっているのだ。つまり、この答が成立しえないとすれば、問題は属詞にあるのではなく、この主語=属詞=動詞という様態そのものにあると言われなければならないだろう。宮川淳『鏡・空間・イマージュ』
僕は、この問いにどこまで迫ることができただろうか。
随伴函手は至るところに現れる。ソーンダース・マックレーン『圏論の基礎』初版への序
共感と反感は、それだけでは何の役にもたちません。真理のみが人々を結びつけるのです。『ドキュメント ヨーゼフ・ボイス』共同記者会見
1. はじめに
前稿「芸術的活動の数理的描写」では、アーベル圏というホモロジー代数が展開できるように、いくつかの公理を満たした性質のいい圏を用いて、ジェームズ・ブライドルの「新しい美学」、そしてマルセル・デュシャンが「創造過程(創造的行為)」の講演で示したような、システムとしての美学(芸術作品の意味)を生み出す芸術的活動のダイナミズムを、数学的図式(スキーマ)を用いて表現した。
これまでにも、芸術に関するさまざまな過程や行為のモデルはあったが、それらは対象に合わせた恣意的なモデルになることが多く、その一般性や汎用性は限定的なものにならざるを得なかった。それに対して、前稿で提示した数理的描写は、数学的な公理という普遍的な構造を基準にしたものであり、この描写が意味しているのは、あるものごとが「こうなっている」という説明ではなく、「こうなっていなければならない」という原理である。そこには、恣意的なものを恣意的なものに当てはめる適用主義を超えて、ものごとの構造やダイナミクスを議論し、理解共有していく可能性が秘められている。
具体的に前稿では、芸術的活動における「芸術の思索」「作品制作」「芸術の経験」「作品分析」という基本的な芸術的活動が、導来圏の八面体公理による4本の組紐構造の動的発展によって描写できることを示した。特にこのモデルが重要なのは、それが短完全列という「自明なものごと」と、複体という「非自明なものごと」の連鎖の組み合わせ(複体のコホモロジーの長完全列)によって、それがアンリ・ベルクソンの持続(時間)概念やイメージ(イマージュ)、そしてジル・ドゥルーズの「運動/時間イメージ」の数理的描写にもなり得ることだ。
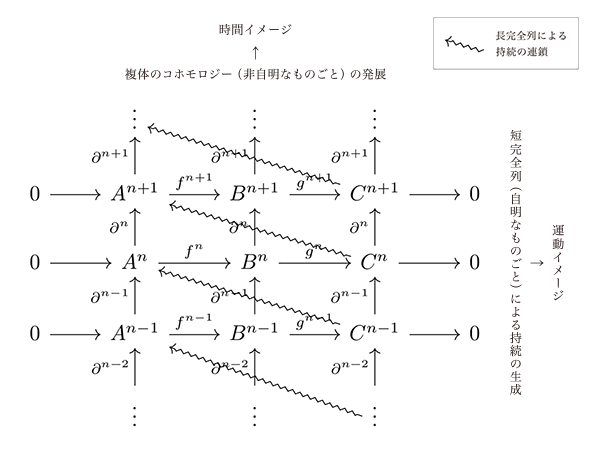 [図1]短完全列と複体の組み合わせによる運動/時間イメージの図式
[図1]短完全列と複体の組み合わせによる運動/時間イメージの図式
この複体のコホモロジーの長完全列において、時間はそれぞれの短完全列における平衡(同値関係)を達成するのに必要な持続として生まれる。つまり、この短完全列において、余像と像が同値になるという現象(相互作用)を完了するために必要とされる、ある特徴的な持続時間が、ベルクソンの論じた「具体的で実在的な持続」、つまりドゥルーズの(分割不可能な)「運動イメージ」に対応している。この運動イメージは、自明な「死んだイメージ」であり、自然法則やシミュレーションによって予測することが可能である。
その一方で、コホモロジーという局所環境における補足を含む複体は、予測不可能(非自明)な進化を生み出す「生きたイメージ」であり、不確定性や選択の余地を含んでいる。なぜなら、環境からの非自明な影響が記録されているコホモロジーは、ある対象にとって外界からの影響(要因としての核)を受けておらず、同時に結果からは見えない(直接影響を与えない)部分のことであり、まさにその対象の「本質」と呼べる部分であるからだ。
このように導来圏の八面体構造とは、ベルクソンの論をアップデートした、ドゥルーズの「運動」と「時間」という2つの体制を有機的に結合したダイナミックなイメージであるとみなすことができ、この普遍的な動的構造が意味するものは、機能や知能、美学や芸術など、予想以上に広い。
2. 芸術と社会
こうした数理的描写のさらなる可能性を示すため、本稿では、社会環境系の中で意味を持つ芸術作品の生成過程を、再び圏論を用いて描写することを試みる。
まずはじめに、記述されるべき対象の集まりとしての「社会」X を想定し、その個々の要素 x を「ある(個人の)視点」F で見たときの「属性」F(x) を記述し、それを作品を通じて「表現」することを考える。ここでの作品制作、つまり「社会 X をある視点 F で見て、それを表現する」とはどういうことなのか。そのためには、表現するための要素(語彙)として必要な既知のものごと(モノや概念)とその組み合わせである対象 a1, a2, a3. . . の集まり A を想定し、具現化する必要がある。この A は、いわば表現のための基準系のようなもので、絵画や彫刻のようなものから、ソフトウェア、ネットワーク、さらにはインスタレーションやパフォーマンスのようなものまで、さまざまな系や形式とその複合体が考えられる。
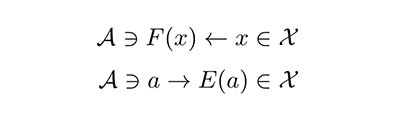 [図2]
[図2]
例えば、インスタレーション作品を制作する場合、X は作品が表現する対象、あるいは主題としての社会(とそこで起こっているさまざまなものごと)、A は制作するインスタレーションの会場と、そこに設置されるさまざまなオブジェクト a1, a2, a3. . . からなる、作品表現のための要素を配置する基準系である。インスタレーション作品の制作過程は、作品を構成するそれぞれの要素が持つ社会的な意味や影響を推測(E)しながら、A の中に作品を具体化(制作)していくこと(F)の繰り返しになる。
もし、社会の中の何かを「正確に」再現しようと思ったら、実際に対象 X としての社会そのもの(あるいはその一部)を持ってくれば良い。しかし、再現ではなく表現を目指す作品制作において、それは不可能(というか意味がないこと)であるから、むしろある視点からの観察や抽出にもとづいた「同一視」すなわち「同値関係」を導入することが重要となる。前述のインスタレーション作品の場合、実際にどういうものごとを選んでそれを空間内に配置するかという選択の基準や、実際の配置を指定することによって、この同値関係が定まっていく。
すると作品制作という行為を、「その全体を把握することができない未知の対象の集まりとしての X を作品の主題としたときに、どのような系 A とその相互関係を用意/設定すれば、着目した対象のさまざまな意味や特徴が表現できるか」という問題に敷衍することができる。このときの、X と A の相互関係が[図3]の「随伴函手(adjunction functors)」と呼ばれるものであり、その全体を定式化すると[図4]のようになる。
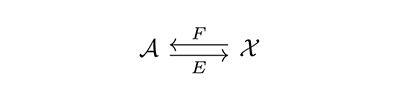 [図3]
[図3]
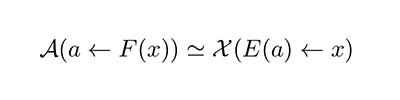 [図4]
[図4]
3. 4項図式からの展開
この作品と社会の随伴関係(弱い同値関係)を、量子場をミクロ・マクロ双対性によって定式化することを試みた小嶋泉に倣って、双対性を二重に織り込んだ理論枠としての「4項図式」に拡張する。「4項図式」は、[図3]の随伴関係から、モナド(自己函手) T = EF とその双対的な函手に当たるコモナド S = FE が自然に構成されることで、以下のように図式化できる。
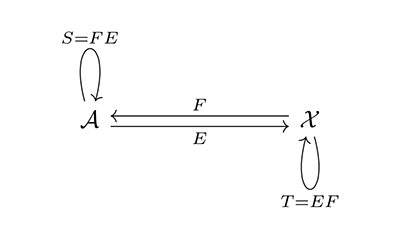 [図5]
[図5]
前稿でモデル化した導来圏の八面体構造が、自己準同型なモノイドとして時間発展していくように、このモナド T とコモナド S は、対象系 X と A 自身の動的変化の過程を描写する。つまり社会の中で作品が制作され、それを展示鑑賞することによって、作品と社会の両者が共に変化発展していくことを表現している。
この4項図式は、さらに以下のように展開することができる。
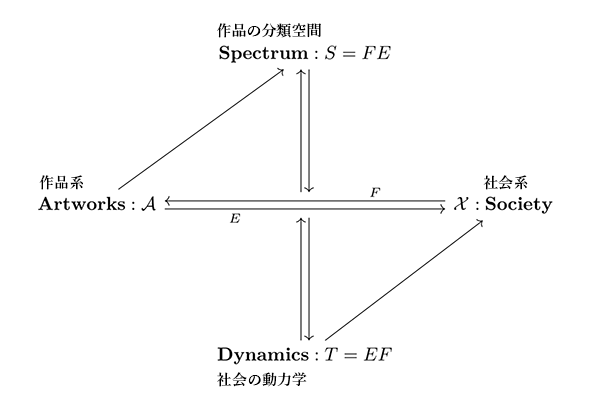 [図6]
[図6]
この[図6]において A から X への射 E は、作品系 A から社会系 X の中に、芸術作品や芸術行為というプローブ E を挿入すること、つまり E(a) とは、ある作品 a が社会の中で展示されることを意味している。ある作品展示に対して、その反応がひとつであることはなく、その解釈や批評には何らかの多様性や不確定性、さらにはノイズが含まれる。このとき、作品の展示 E(a) に向かって、社会のさまざまなものごと x が引き寄せられ、関係づけられた状況は、X(E(a) ← x) と書くことができる。すなわち、社会の中で起こっているさまざまな出来事を、社会に提示された芸術作品に対応づけられるようになる。
随伴関係が成立すれば、社会系におけるこの状況 E(a) ← x を、再び作品系における状況 A(a ← F(x)) に移し、そこでの近似状況 a ← F(x) として捉えることができる。そうすることで、社会系 X の中で生じるものごと x を、作品系 A の中の対象 a が指し示して(意味して)いるように見ることが可能になる。このことをもう少し詳しく見ていこう。
ある作品 a が社会の中で展示されることで、社会はその作品に対する解釈(鑑賞)E(a) と、それに対する反応 x を生み出す。作品の制作者は、その反応 x を自分の表現の語彙 F(x) に変換して、作品が引き寄せた社会的概念 FE(a) を推定し、さらに作品 a を制作(改変)する。随伴関係が成立するための第一の条件は FE → IA が自然変換になることで、これは作品の制作者の意図とその社会的解釈が(たとえ一致はしなくとも)対応づけられることを意味している。同時に社会における作品に対する反応 x と、制作者の受け取り方 F(x) の間に齟齬がなければ、社会の状況 x に対して、制作者は F(x) に対応した作品 a を制作し、社会は自身の状況(反応)に対応した作品 EF(x) を受け取り鑑賞することができるようになる。これもまた、IX → EF が自然変換となることに他ならない。このように作品と社会の間に随伴関係が成り立つとき、社会は芸術作品に対して健全に鑑賞批評を行い、その健全な社会において制作者は自由に作品制作できるようになる。
しかし、一般には両者が健全な随伴関係になることはほとんどない。社会系 X の変化を示すモナド T と作品系 A の変化を示すコモナド S は、それぞれ社会状況に応じた作品制作 EF と社会における作品鑑賞 FE のあり方として定義できる。式で表せば、EF =: T, FE =: S となり、この T と S が非自明に残る。つまり、作品と社会の関係を考えることの本質は、これら非自明な対象の動的変化の関係をいかに記述し、変化させていくか、ということにある。
さらに小嶋によれば、上記のコモナド S = FE とモナド T = EF はそれぞれ、作品の分類空間(スペクトル)と、社会の動力学(ダイナミクス)と解釈することができる。ここで作品の分類空間 S とは、制作した作品を展示することから生まれた社会的反応という、いわば「測定値」を制作者が理解分析したものであり、その結果によって社会の状況や構造が分類(批評)され、その結果が再び作品に反映されていく。また社会の動力学 T とは、作品系 A と社会系 X の合成系(複合系)における相互作用(カップリング)から生まれる社会の変化を意味し、曖昧で複雑な社会の時間発展を記述する。
[図4]の随伴関係は、こうした操作論的な視点で、作品系と社会系のカップリングにより生じているものごとを描写するのに極めて適した数学的構造である。ここで重要なのは、その4項図式[図6]において、作品系と社会系の双対性に加え、動力学と分類空間(FE と EF)の間にも双対性があることである。ここで作品と社会の関係は、対象(ミクロ)と属性(マクロ)の双対性に対応し、動力学と分類空間の関係は、可変性(ミクロ)と不変性(マクロ)の双対性に対応している。
4. ヨーゼフ・ボイスの社会彫刻
最後に、この随伴の具体的な適用例をひとつ示したい。ドイツの芸術家ヨーゼフ・ボイス(1921〜1986)は、芸術と社会に関する作品や言説を数多く遺したことで、今なお社会に大きな存在感と影響を与えている。その領域は、美術芸術の枠を越えており、例えば創造性と学際的研究のための自由国際大学の設立など、広く教育や社会変革にまで拡張していった。
ボイスのさまざまな活動や言説の中でも特に重要なもののひとつが、「社会彫刻(Soziale Plastik)」の概念である。ボイスは、作家の主観や自己主張と結びついたそれまでの芸術概念をリセットし、社会という有機体と深く関連した思考による芸術、すなわち「社会彫刻」へと芸術の領域を拡張し、この「社会彫刻」こそが当時の、そしてこれからの時代における決定的なミューズであると主張した。
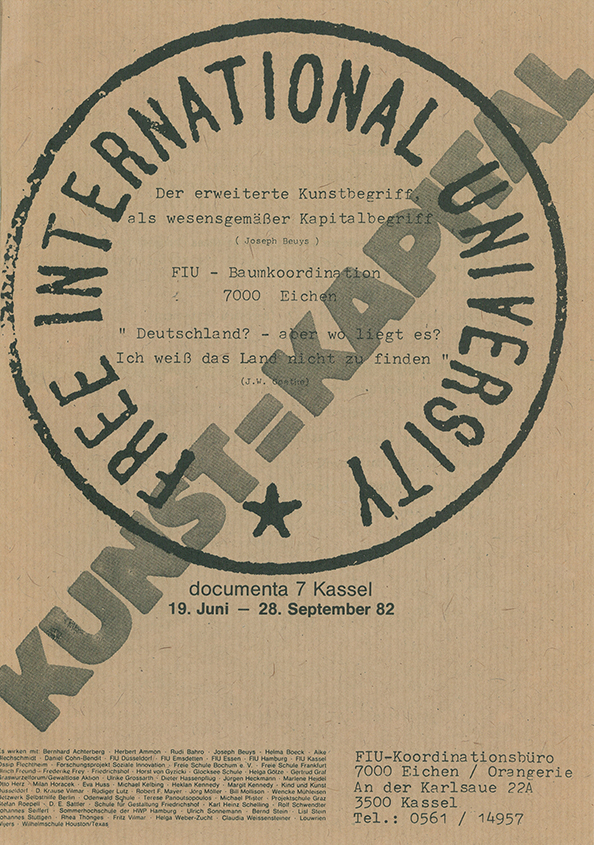 [図7]自由国際大学による1982年のドクメンタ7関連イベント告知。ボイスが提唱した「芸術=資本」の等式(人間の創造力こそが、経済を動かす資本であるというメッセージ)がオーバーレイされている。
[図7]自由国際大学による1982年のドクメンタ7関連イベント告知。ボイスが提唱した「芸術=資本」の等式(人間の創造力こそが、経済を動かす資本であるというメッセージ)がオーバーレイされている。
ボイスは、経済(貨幣)や政治(権力)に根ざした社会の中で、芸術家を「優れた芸術作品をつくる偉大な作家」ではなく、「自ら考え、自ら決定し、自ら行動する人々」と定義した。そうすることで「誰もが芸術家になる義務があり、あらゆる人間(芸術家)は自らの創造性によって、未来に向けて社会を彫刻し、社会の幸福に寄与しなければならない」と宣言した。もちろんこうした芸術は、絵画、彫刻、建築、音楽、文学、ダンスといった伝統的な芸術概念に基づいたものではなく、すべての人間による「拡大された」芸術概念であり、それは目に見えないものごとの本質を具体的な姿に変え、育てていきながら、ものごとの見方や知覚の形式を新しく更新し発展・展開させていく。従来の芸術が主に、物を素材とし、物を形造るという、いわば物質や個人の自由なあり方に向けられていたのに対して、ボイスが提示した万人のための芸術は、人間が知覚し行動するすべての領域に存在し得るものである。彼の言葉によれば「新しい芸術は新しい知覚領域に出現する」。
こうしたボイスの主張や行動を、本稿で提示した作品と社会の随伴関係としてみていけば、彼が主張した社会彫刻とは、まさにこの両者を同一視すること、すなわち作品と社会の随伴関係が成り立つことを目指したものだといえる。もし作品と社会が随伴でなければ、ある作品 a が社会の中に提示されたとしても、その社会の反応 E(a) ← x は、作者の意図 a ← F(x) にはそぐわない形のものとなり、それは往々にして誤解や誹謗中傷のようなものとして認識される。同様に、作者もこうした意図しない社会の反応に警戒/対抗しようとするあまり、社会の状況を(個人の視点で)深く考察し、それを理性的に思考、批評する作品ではなく、逆に社会を扇動するために号令をかけたり、フェイクニュースに繋がるスキャンダルを生み出すような、快楽と経済的効果のための作品を作ろうとしてしまう。
ボイスが問題提起をしたのは、こうした芸術作品と社会の不健全な関係であった。両者の関係が不健全になれば、作品に対する深い鑑賞批評がさまざまな政治的理由によって妨げられ、芸術家もそれに応じてますます資本主義的/商業主義的な制作を行うようになる。だからこそボイスは、こうした状況から脱するためには、作品や作家を含む芸術活動そのものが社会全体と随伴になることが必要であると考え、それが達成された状態を「社会彫刻」と名づけたのではないか。
熱を蓄えたり、燃えてエネルギーを発散する、不定形な素材としての脂肪や蝋、フェルトやバッテリーといった素材をボイスが用いたのも、その熱性と流動性が、未だ実現していない可能性を含む「社会」と同一視できる動力学(ダイナミクス)を有しており、現実の芸術と未知の社会の双対性を具現化し象徴するためのパフォーマンスとして機能すると考えたからだろう。同時に、社会にとって必要なことは、社会を構成する個人が、その時々の欲望や感情に任せて、自分に見える世界の中に閉じこもって生活することではなく、社会全体の構造と分類(スペクトル)を自らが俯瞰的に把握し、それを芸術作品として提示することで、社会と個人の両方を、寛容さと柔軟性を兼ね備えた複合体として開いていくことではないか。
かつて芸術は、社会に対するカウンターやオルタナティヴとして、その多様性を増加させるような行為として認識されてきたことが多かった。しかしながら、今日の資本主義が、功利的な経済活動に根ざした美的社会を構築したことで、芸術とそこから得られる認識が、生活全体から生まれ、そこに向って再び流れこんでいくものから、逆に補助的、装飾的なものへと追いやられて孤立してしまった。だからこそ、これからの芸術は、ボイスが提示した「社会彫刻」という芸術と社会の随伴関係、すなわち両者の双対性を実現していくことを(再び)目指していかなければならない。
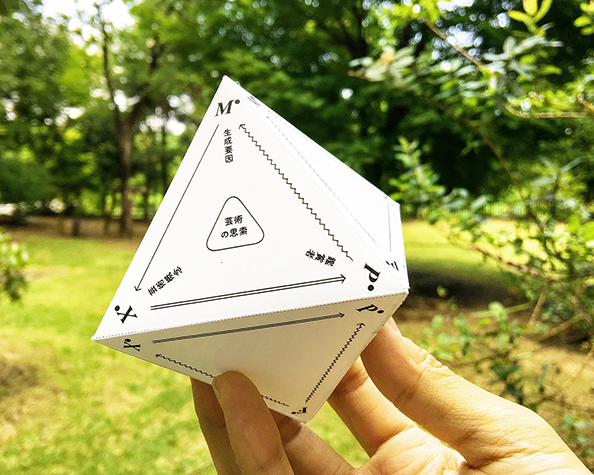
1. 新しい美学の方へ
今日、私たちの身の回りには、スマートフォンに組み込まれたカメラや監視カメラ、そこから得られた画像データを解析するコンピュータビジョンや機械学習技術によって、人間のためだけではない、機械やソフトウェアのような、非人間による非人間のための、さまざまな視覚的表現が現われた。こうした状況を背景に、アーティスト/批評家のジェームズ・ブライドルは、2011年5月から自身のTumblr上で、ハードウェアとソフトウェアが混在した今日のハイブリッドな社会における、新たな美学のありかとその意味を探る「The New Aesthetic(新しい美学)」という研究プロジェクトを開始した。
ここでいう「美学」が扱っているのは、いわゆる「美しいもの」ではない。伝統的に美学は、芸術作品や自然を対象に「美とは何か」という美の本質、「どのようなものが美しいのか」という美の基準、「美は何のためにあるのか」という美の価値の問題に取り組んできた。しかし今日の「美学」とは、主に芸術の意味や働きについて哲学的に考える学問であり、広く「芸術、文化及び自然に関する批評的考察」であると位置づけられている。
今日の技術、特に私たちの生活や社会、そして生命に直接かかわりのある技術の多くは、人間の目に直接触れることがない。画像のコーデック、通信のプロトコル、解析や編集のアルゴリズム、機械学習のプロセス、学習結果のデータベース、クラウドサーバー、衛星通信、インターネットの海底ケーブル —— ソフトウェアからハードウェアまで、こうした身近な技術は、私たちの目には見えないもの、つまりインヴィジブルウェアである。それと同時に、スマートフォンのカメラや監視カメラ、SNSによる情報収集、検索エンジンのクエリのように、あまりに量が多すぎて、目の前にあるにもかかわらず、いちいち人が見なく(見ようとしなく)なってしまったものも多い。
こうした見えないものの多くは、単体のモノ(オブジェクト)として存在しているのではなく、相互に接続されたシステムとして機能している。そしてこの見えないモノたちが、ネットワークで相互接続され、全体として膨大なアルゴリズム(プログラムコード)に従う高速の計算や通信を行うことで、その実行結果を環境の中に再提示する。私たちは知らず知らずのうちに、こうした見えないシステムが作り出した暗黙の再帰的環境によって、ものの見方や理解の仕方、感じ方や考え方、さらには日々の行動を変化させられている。このことを技術と人間の共進化と捉えるのか、それとも技術に対する人間の隷属と見なすのかは、技術そのものよりも、そのシステムを生み出した、あるいはそれが指し示している政治性の如何による。
「美」というのものは、いつの時代、どこの世界においても、ある種の「力」として、常に政治的な意味を伴って定義され、そのために利用されてきた。「新しい美学」が取り上げる、人間とソフトウェアのハイブリッドな生態系の共進化から生まれる美学は、表層的な色彩や形態、あるいはプロジェクターやセンサーの技術的問題にとどまるものではない。重要なのは表現や技術それ自体ではなく、それらが指し示している意味とその使用法なのだ。
知覚、そして美学のポリティクスはいつの時代にも潜在、遍在している。新しい美学を特徴付けている、グリッチやバグによる「失敗の美学」、あるいはビットマップやローレゾによる「解像度の美学」は、実現や成功の政治性、見えることやわかることの政治性を浮き彫りにする。こうした科学技術の権威的な美学=政治性を指摘できなければ、私たちは逆に、科学技術に消費されるだけの存在になってしまう。
また「美学」というタームには、政治性以外にも、さまざまな歴史的、文化的な意味や文脈がある。だからこそ、科学や技術が人や機械に新しい知覚や環境を提供し続けている限り、文化や歴史に強い影響を与える(美学の)政治性を常に批判し、議論し続けていく必要がある。
2. 機能としての美学
ある対象(オブジェクト)について考えられてきた、芸術的な意味の総称としての「美」が、この「新しい美学」のように系(システム)全体に着目するようになった時、この「システムとしての美学」とは、いったいどういうものになるのだろうか。僕は、その構造が「機能」と同じであると考えている。
機能とは、ある特定の時空領域に含まれる物質情報系の相互作用において、ある「意味」のもとに抽出された現象の連鎖のことを指す。ここで対象と協働して、機能=意味を提示する者を「使用者」と呼ぶことにすれば、例えば道具の機能は、常にそれを使う使用者と対で現れる。逆にいえば、この観測者としての「使用者」の意図や能力に応じて、道具の機能が出現する。
「新しい美学」が、この機能と同じ構造を持っているとすれば、「新しい美学」とは、芸術的な意味を生み出す芸術的対象(芸術作品)とその鑑賞者(芸術的使用者)の対生成(励起)とその対消滅(脱励起)を生み出す構造が、外部環境と相互作用しながら時間発展的に変化していくメカニズムである。いいかえれば、芸術作品とは、この外部環境系との相互作用の中で、鑑賞者が意味を見い出すことができるものとして定義される。機能と環境系との関わりの様相は、何らかの相互作用によって系の状態が変化しながらも、その構造が保たれる「非平衡開放系」のシステムである。この芸術と環境系の関わりの様相は同様のシステムと見なすことができ、広く「アートワールド」とも呼ばれている。
3. 芸術的活動の素過程
堀裕和はこうした機能の本質的構造を、図式によってその動的関係を明快に表現できる圏論を用いて、数理的に描写した。圏論は、ある対象を調べる際に、対象の具体的な中身を考えるのではなく、その器の性質の関係と引き継がれる構造に焦点を当てる。そうすることで、構造を保つものごととその関係性を、抽象的かつ厳密に扱うことができる。掘のモデルのポイントは、圏論やホモロジー代数を利用して、「来歴を変化させながら構造を保って進化する図式」を導出し、機能の本質を描写したことにある。
堀が示した圏論による機能の数理的描写を応用して、2017年に僕らは「新しい種類の美学(A New Kind of Aesthetics)」を提唱した。そこでは前述のように、美の構造は機能の構造と同じである、という仮説を出発点に、芸術的対象とその鑑賞者の対生成(励起)と対消滅(脱励起)のシステムを、直積(励起)と直和(脱励起)という圏の図式(可換図式)で表現した。可換図式とは、[図1]で X, P, Q, Y からなる四角形の圏の図式のように、始点からのすべての射の合成が同じ終点を持つ図式のことである。
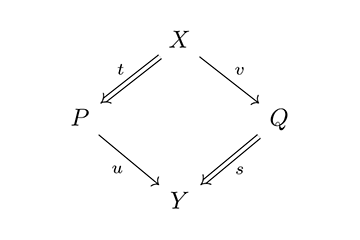
§
| P | 鑑賞者 |
| Q | 芸術的対象 |
| X | 芸術概念 |
| Y | 芸術的状態 |
[図1]
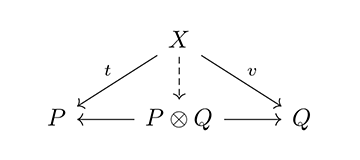 [図2]
[図2]
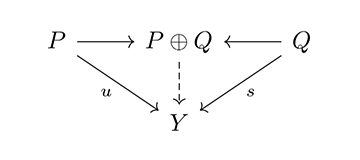 [図3]
[図3]
鑑賞者としての主体 P と、芸術作品としての対象 Q の関係をもたらした隠れた要因 X を「芸術概念」に、その関係が生み出した像 Y を「芸術的状態」に対応させる。[図1]は、直積[図2]と直和[図3]を持つ加法圏の積閉系の考え方にしたがっている。つまり、X は P, Q の関係を生み出す破線の射を一意に定めるような要因を表わし、その P, Q の関係から生まれる破線の射を一意に定めるような状態として Y という結果が得られることになる。
この図式において、鑑賞者 P と芸術的対象 Q を生み出す射 t と s の選択には、蓋然性と多様性があるが、その多様な分解を同一視する同値な積閉系の関係は、常に隠れた要因 X に支配されている。すなわち芸術概念 X とは、鑑賞者と芸術的対象が共同で生成している非自明な芸術世界の全体を指している。このとき鑑賞者 P と対象 Q の関係は、X の像としての芸術的状態 Y から推測することができる。
4. 環境系の導入
ここで提案する芸術モデルの特徴の一つは、こうした鑑賞者と芸術作品の系だけでなく、それを取り巻く環境系を導入することにある。ここでいう環境とは、著名な芸術家や批評家、学芸員や美術商といった一定の権威を有する社会集団による、いわゆる「アートワールド」だけではなく、鑑賞者が芸術作品と共に作り出す意味を支える、社会的、政治的、文化的、科学技術的な背景(文脈)全般に相当している。
まずはじめに、ある芸術的対象 Q を生成する要因 M を考える。M は、それを拡張した芸術的概念 X を介して、絵画や彫刻、音楽や詩といった、多種多様な芸術作品 Q とその鑑賞者 P を対生成するものとする。[図1]において、M は v : X → Q の核であり、M = Ker(v) と表現できる。核 M とは、v によって 0(関係のないものごと)に写像される射 k : M → X として定義され、Q においては 0 に写像されて見えなくなるため、Q の環境と呼ぶことができる。
次に、人工物や自然といった様々な芸術的対象 Q から生まれた芸術的状態 Y が、Q の性質や特徴毎に分析された結果となる F を考える。F は、芸術的対象 Q と s によって発生した芸術的状態 Y を、要因 Q と s によって仕分けたものであり、鑑賞行為の分析結果を意味している。[図1]において、F は s : Q → Y の余核であり、F = Cok(s) と表現できる。余核 F とは、s の終域 Y における s の像による商対象 Y/Im(s) と定義され、要因 Q と s が仕分けの基準となることで見えなくなっているため、これも Q の(次のステップにおける)環境と呼ぶことができる。
この2つの環境系を[図1]に導入すると、[図4]のように書くことができる。
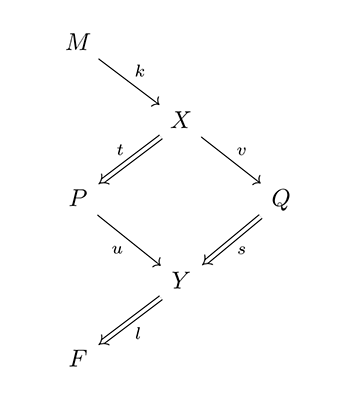
| P | 鑑賞者 |
| Q | 芸術的対象 |
| X | 芸術概念 |
| Y | 芸術的状態 |
| M | 芸術的対象の生成要因 |
| F | 芸術的状態の分析結果 |
[図4]
なお、この M → X → Q と Q → Y → F のことを、短完全列という。以下の[図5]のような短完全列とは、Im(f) = Ker(g) (射 f の像が次の射 g の核と一致する)、f が単射で g が全射となる完全系列のことを指す。
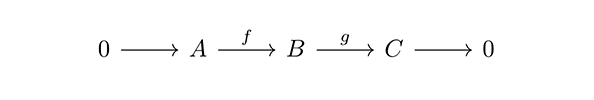 [図5]
[図5]
このとき、C = B/A すなわち、C は B の余核となっている。Im(f) とは、B の中で A の影響を受けている部分であり、それが Ker(g) と等しいということは、A の影響が C にいくと見えなくなってしまうことを意味している。つまり Ker(g) は B の一部で C に直接影響を与えない部分である。また、A は A ではないものごとである左端の 0 で決まり、右端の 0 は、A が C の仕分けの基準になっていることを示している。
短完全列が意味しているのは、芸術的概念 X の多様な内容が、芸術的対象 Q = X/M に「同じものごと」として写され、それが芸術的対象の生成要因である M に含まれる「ものごとの種類」で区分けされている、ということである。直接には把握できない種別の要因 M は、Q における分類に基づいて特定され、名付けられている。同様の関係が、芸術的対象 Q の多様な拡張として生まれた芸術的状態 Y と、それを Q と s によって分類した芸術的状態の分析結果 F の間にも成り立っている。
さらに射 u : P → Y を鑑賞行為としてとらえた時、(u, s) という射の組み合わせが、鑑賞者と対象の関係の開示のされかた、すなわち「芸術的行為の性質」を決定づけ、このことから芸術的活動のダイナミックスに係る理解が得られる。同時に (v, t) という射の組み合わせが、(u, s) という射の組み合わせと(前述の可換図式において)共形なので、鑑賞者と対象の関係が、「芸術的行為の性質」に基づいて X から開示される。
5. 時間の導入
芸術的行為には環境系としての背景や文脈だけでなく、時間軸、すなわちそのダイナミックな時間発展が重要である。どのような芸術的対象や行為であっても、その関係(意味や価値)は時間や時代の中で変化し続けている。そこで、環境系に続いて、ホモロジー代数における複体の概念を用いて、時間をモデルに導入する。複体とは、2つ続けて写すと 0 になる準同型射 (∂n∂n−1 = 0) で接続された対象の連鎖 Cn であり、これは C● = (Cn, ∂n) という、限りなく続く図式[図6]で表される。
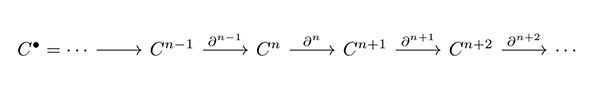 [図6]
[図6]
このとき時間は、前述の短完全列[図5]が平衡に達するのに必要な持続から生まれる。ステップ毎の時間発展の来歴は、局所環境を入れる器としての複体 C● の n 次のコホモロジー Hn(C●) = Ker(∂n)/Im(∂n−1) に記録される。コホモロジーとは、Cn−1 の像の局所環境による補足であり、それが Cn+1 に影響を与えない(2つ続けて写すと 0 になる)ということは、コホモロジーが Cn の本質であることを示している。つまり、このコホモロジーを含む圏の図式には、芸術に直接関係する鑑賞者や作品だけに限らない、社会や技術といった環境系からの非自明な影響が記録されている。
ホモロジー代数を展開するための舞台として活用されるアーベル圏においては、この複体もまた対象であり、短完全列を構成することができる。このとき複体の射は f : C● → D●(fn : Cn → Dn) , fn−1∂n = ∂nfn で定義される。すると、鎖(チェイン)ごとに完全な複体 0 → A● → B● → C● → 0 は、すべての次数で短完全列 0 → An → Bn → Cn → 0 を保ち、各複体 An, Bn, Cn が、来歴 Hn(A●), Hn(B●), Hn(C●) を包含し発展する時間構造の基本図式[図7]を与える。
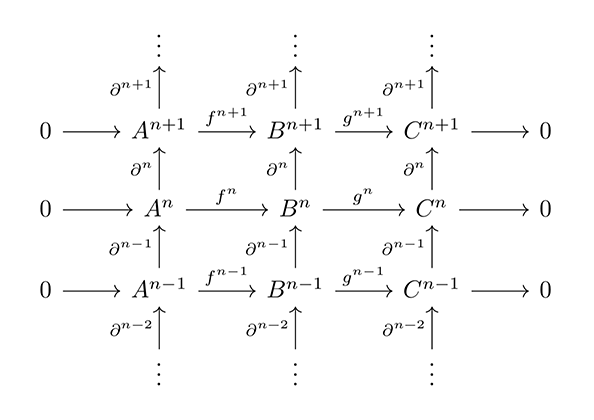 [図7]
[図7]
ホモロジー代数における「ヘビの補題」によって、準同型射のみで構成される鎖ごとに完全な複体から、コホモロジーの長完全列[図8]が導かれる。ここでコホモロジー Hn の次元を一つ上げる射 Hn(C●) ⇝ Hn+1(A●) は、連結射と呼ばれる。
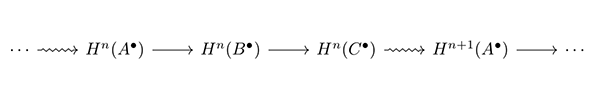 [図8]
[図8]
このことは、鎖ごとに自明な複体の図式の背景で、対象の連鎖を支える共通の土台である環境系(コホモロジー)が、非自明で見えないものごとを含む、時空間的連鎖を維持していることを示している。
6. 三角圏と八面体構造
圏の任意の射が余像と像を持ち、完全列と同じように、その余像と像が同型となるとき、それを完全圏という。加法圏の一種であるアーベル圏も、完全圏の一つである。完全圏の射 f の機能は、余像と像の関係が同型 Coim(f) ∼ Im(f) となる過程を経て、そこまで来たものごとを完全に消滅させ、そこから続くものごとを生成する。
位相同型でものごとの連鎖が議論でき、それが分裂完全列である場合には、アーベル圏のホモトピー同値を用いて、コホモロジーの長完全列[図8]の図式を、複体の接続関係として[図9]と[図10]のように図式化することができる。複体を対象の連鎖ではなく、列のまままとめて扱う導来圏として構成される三角図式のことを、三角圏と呼ぶ。この時、将来の環境のホモロジーを無視することで、そこまでのコホモロジーに入った Cn の来歴と Cn を擬同型として同一視することができる。
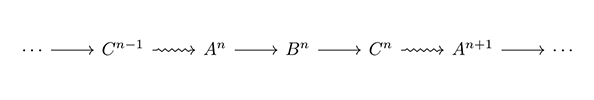 [図9]
[図9]
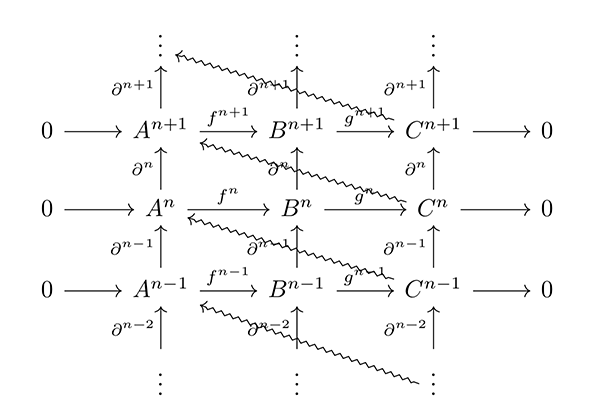 [図10]
[図10]
ここで波型矢線で示した「複体を1階層上げる射」が、[図8]で示した長完全列の連結射である。この複体の三角図式(三角圏)は、来歴を変化させつつも、構造を保って進化する対象の簡明な表現となっている。
そこで可換図式[図4]の対象を複体に置き換え、それをこの三角圏を用いて拡張する。まず、連結射で結ばれる1ステップ前の芸術的状態の分析結果 F● と、1ステップ後の芸術的対象の生成要因 M● を加えると[図11]のようになる。
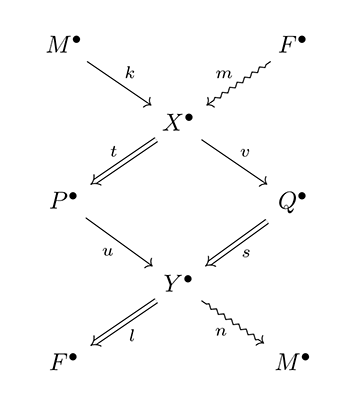 [図11]
[図11]
ここからさらに、自然に導かれる射 Q● → F●, M● → Q●、そして連結射 F● ⇝ P●, P● ⇝ M● を補うと、[図12]と[図13]の図式が得られる。
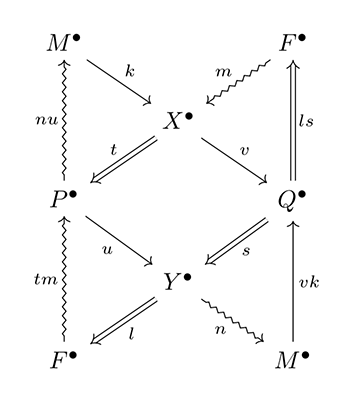 [図12]
[図12]
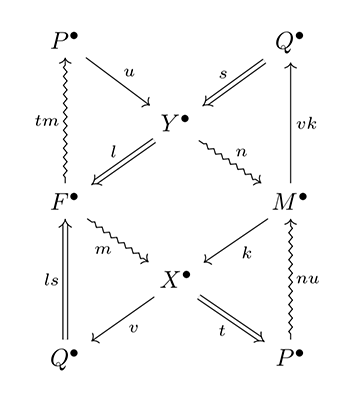 [図13]
[図13]
この図式の階層の異なる環境 M● と F● を貼り合わせると、以下の1つの可換図式と4つの三角圏から構成される八面体[図14]が構成される。
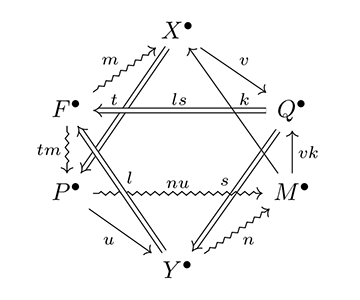
| P● | 鑑賞者 |
| Q● | 芸術的対象 |
| X● | 芸術概念 |
| Y● | 芸術的状態 |
| M● | 芸術的対象の生成要因 |
| F● | 芸術的状態の分析結果 |
[図14]
7. 芸術的活動とその時間発展
この八面体は、八面体公理と呼ばれる、導来圏の重要な帰結の一つに相当する。ここに含まれる4つの三角圏を詳しく見ていくと、それぞれが芸術的活動における「芸術の思索」「作品制作」「芸術の経験」「作品分析」に相当していると解釈できる。つまり、この八面体構造は、こうした芸術的活動に関連するさまざまなものごとが、相互に関連し合いながら時間発展していく様子を、数理的に描写したものである。
芸術の思索
芸術的対象の要因 M● → 芸術的概念 X● → 鑑賞者 P● → 芸術的対象の要因 M●
作品制作
芸術的概念 X● → 芸術的対象 Q● → 芸術的状態の分析 F● → 芸術的概念 X●
芸術の経験
芸術的対象の要因 M● → 芸術的対象 Q● → 芸術的状態 Y● → 芸術的対象の要因 M●
作品分析
鑑賞者 P● → 芸術的状態 Y● → 芸術的状態の分析 F● → 鑑賞者 P●
また、この4つの完全系列としての芸術的活動の関係を[図15]のように記述することで、八面体構造の組紐構造と呼ばれる、各対象(複体)の相互関係が明確になる。

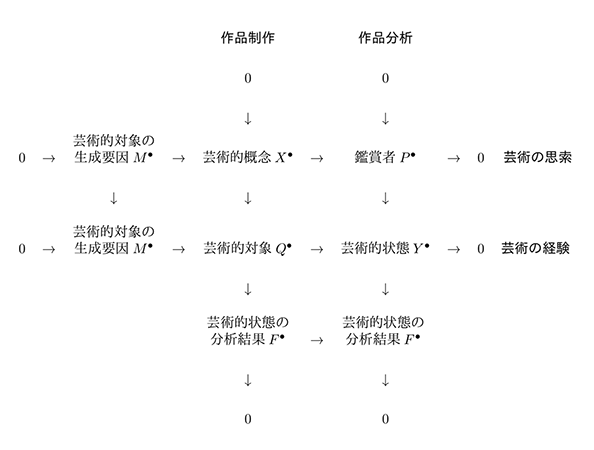 [図15]4つの組紐構造としての芸術的活動
[図15]4つの組紐構造としての芸術的活動
最後に再び、冒頭の積閉系による可換図式[図1]に立ち返る。(P, Q) を二つの対象の単純な和とすると、X → (P, Q) → Y は短完全列と同じように、要因 X とそこから拡張された多様な現象 (P, Q) 、およびこれを要因で整理した Y という意味を持つ。さらに環境系を導入した[図4]を参照すれば、可換図式に囲まれたものを除く全てである環境系の組 (F, M) が、この可換図式の時間発展の構造を支えていることがわかる。その過程で (P, Q) は環境系の特異性をステップ毎に取り込み、非自明な来歴を獲得していく。特異性を取りこむ毎にコホモロジーの次元は上がり(ホモロジーの次元が下がり)、その構造は簡単になっていく。すなわち、最初は曖昧で不可知な芸術的概念 X が、芸術的対象 Q と鑑賞者 P から生まれる芸術的状態 Y によってその性質を少しずつ特定されることで、次第に明確になっていくことを示している[図16]。
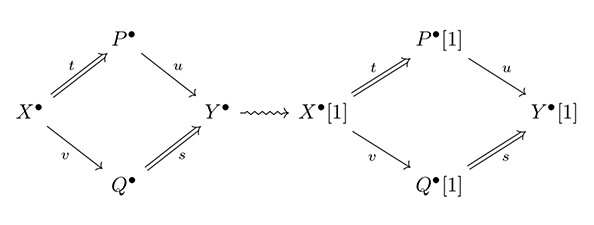 [図16]
[図16]
8. 芸術的活動の普遍性
1957年4月に開催されたアメリカ芸術家連盟の総会で、芸術家のマルセル・デュシャンは「創造過程(The Creative Act)」という講演を行った。日本語訳は、北山研二の訳によるものが書籍化されている。
ここでデュシャンは、創造的行為において鑑賞者の鑑賞行為が、芸術的活動における作者の制作行為以上に重要な意味を持つとして明確に評価した。特に、(作者が)「個人的に意図しながら表現されなかったもの」と「意図せず表現されたもの」との間の関係を「芸術係数」と呼び、この違いの重要性を指摘した。その上で、創造的行為というものが、近代性の中で特権化された個人としての作者だけで完遂されるものではなく、作品に内在する質を翻訳し、解釈するオープンな鑑賞者によって、作品と外部世界とのつながりが生まれることを、講演の最後に述べている。
要するに、芸術家は一人では創造行為を遂行しない。鑑賞者は作品を外部世界に接触させて、その作品を作品たらしめている奥深いものを解読し解釈するのであり、そのことにより鑑賞者固有の仕方で創造過程に参与するのである。こうした参与の仕方は、後世がその決定的な審判を下し何人かの忘れられた芸術家を復権するときに、一層明らかになる。マルセル・デュシャン「創造過程」
今回の芸術的活動のモデルは、このデュシャンの創造的行為の構造を描写したものでもある。本モデルの対象の中には、「作者」というものが明示されていない。その代わりに、(しばしば芸術作品と呼ばれる)芸術的対象と鑑賞者の対生成と対消滅が、そのダイナミズムとディメンジョン(スケール)の基盤となっている。この可換図式には、環境系の特異性を取り込むことで、非自明な来歴を獲得する構造が秘められている。この図式をその要因(核)と分析結果(余核)で拡張することから導かれる、公理としての八面体構造の時間発展を通じて、デュシャンのいう鑑賞者と作品の対と、外部世界(環境)のつながりが生成されていく。
芸術的行為にとって「作者」というものは、単なる個人ではなく、個人を形成する環境(社会、歴史、心理、哲学など)と切り離すことができない。さらに今日では、作者が人間ではなく、コンピュータソフトウェアのような広義の(実行可能な)「テクスト」とその(実行)環境にまで拡張している。(人工知能や人工生命を含む)ソフトウェアもまた、ロラン・バルトが「作者の死」で述べたような、現在・過去の文化の引用からなる多元的な「織物」であり、ソフトウェア・アートのように、その実行結果が芸術的対象となることもある[図17]。
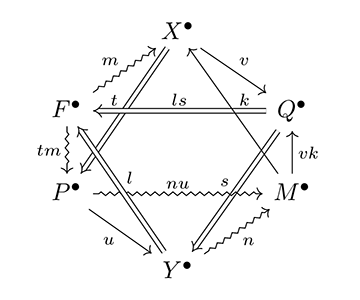
| P● | 鑑賞者 |
| Q● | ソフトウェアの実行結果 |
| X● | ソフトウェアの実行状態 |
| Y● | 実行結果の鑑賞状態 |
| M● | プログラムコード |
| F● | 鑑賞状態の分析結果 |
[図17]
本稿の冒頭で紹介した、ジェームズ・ブライドルの「新しい美学」とは、今日の文化を特徴付けている実行可能なテクストとしてのプログラムが生成する対象と、そのテキスト(ソフトウェア)を書き、その結果を思索体験する人間のハイブリッドが織りなす、環境とのダイナミズムであるといえる。
導来圏の八面体構造は、実際には極めて複雑なものごとの関わりから構成され、数学の力を借りずには導出困難な構造ではあるが、その結果は極めて明快であり、ものごとの機能や芸術的活動だけでなく、さまざまな現象や行為に適用することが可能な普遍性を有している。なぜならこの図式は数学的公理であり、それはある特定のものごとの記述のための道具ではなく、この図式のようにふるまうものごとが、共通の土台である環境系を通じて暗黙のうちに絡み合いながら生成発展していくという、この宇宙における普遍的な動的構造を表現しているからだ。
特にここで用いた導来圏は、ホモロジー代数(チェイン複体)を定義できるアーベル圏において、以下の操作で構成される。
- 関係ないものごと(0の同値類)を無視する
- 積閉系の自由度に基づいて都合のよい尺度からものごとを表象する
- ホモトピー同値で似たような射を同一視する
- 擬同型でものごととその来歴を同一視する
これらは、私たちが日常、環境系の様相を捉え様々な判断や評価を下す際に自然に行っている、省略や捨象選択に基づくものごとの把握の仕方や、限られた情報から様々なことを補ってものごとを進めていく行為の特徴を、良く(というよりも見事に)捉えていることに、僕は感嘆せざるを得ない。圏論という、あいまいなものごとを厳密に取り扱うことができる数学的言語が持つ、領域を超えた深い描写力の可能性を、引き続き探求していきたい。
悟りを得たインターネットビッチの神学的問題💎
読んだことないけど「J・G・バラードに捧ぐ」と書いた。そんなノートの1ページ目からはじまる夏。蛙と蝉がコール・アンド・レスポンスする季節。ジャズと念仏。発芽する8月。ドライな野犬のセクシーな午睡。
夏、いるはずのない場所にいて、出会うはずのない人と出会い、するはずのない恋をする。わたしは愛されるより執着を求める。生まれながらのサークルクラッシャー。夏の恋はあなたじゃなくて夏に捧げてるから、勘違いしないでほしい。恋愛って性犯罪のゲートドラッグに指定されてるけど、2018年の夏もまだ有効なんだっけ?
わたしの夏の夢は永遠のチル。今日はすこしバッド入ったカインド・オブ・ブルー。もしライフがビッチなら、わたしはライフ。ライフをハックできないから、ずっとファックしてる。いつかワールドフェイマスにヤングでリッチなビッチになる。生きながらにして生きる、エグめの生存。この街の現実、店舗型の女。
あえて本アカで言うけど、テキストにしかわたしはいない。ソーシャルメディアは現代のプティジャンル。致死量の投稿、「いいね」の血痕、裏アカの空リプ。Twitterで「死にたい」とつぶやき、Facebookで「死をシェアさせていただきます」とコメントすれば、Derridaが死を与える。今度こそちゃんと哲学を葬る。
90年代からずっとチェキ売って暮らす、わたしはガーリーなハードコア。けど、テン年代にはヒロミックスの余白がない。キャバレー四次元では架空のマフィアをテーマにしたファッションショー。悟りを得たビッチたちが集まる過激なミサ。そこで神様に会って、ひとつ疑問が浮かんだ。神様ってダンスするのかな?
わたしが好きになる人は、革命の話ばかりする。同じ部屋で、同じ空気を吸って、同じ音楽を聴いて、同じご飯を食べて、同じドラッグをキメて、同じシーツのなかで。でも、Sorry for my メンズ。けど、Keep on 男子。彼から聞いた、都会のベクトル解く法則。ちゃんと忖度映えを狙ってく。これから千年くらいは余裕でインターネットビッチ。
革命と貧困、バイブスとムード💰
革命は夜起きる。真夜中の公園に降臨するヴラジーミル。ミュージックはアーマー。プレイリストで資金洗浄。つながったら光る物質化されたバイブス。担々麺よりヤバめのネイティブタン麺。優良不良少年犯罪者のマメン。
地元で結成した「自我ヴェルトフ集団」によるヒップホップが、人類すべての知性をゼロにする。オレたちはバイブスの魔法使い。ビートメイキングのホモ・ルーデンス。ヘッズたちの名声が生命線。新譜の「オンリー・ザ・ストロング・ゼロ・サバイブ/つまり死?(物質的恍惚MIX)」をチェックしろ。マネするな。知ったふりしろ。でも今じゃない。
バイブスを重んじる民族のオレには、バイブスがすべて。未来派気取りの祖父はバイブスで家を建てた。シャーマンくずれの父はバイブスを逆立て夜の街を歩いた。バイブス尽くせば結果はついてくる。これが我が家の家訓”MONEY, POWER, RESPECT”に込められた意味。考える暇で行動しろ。でもバイブスなき行動は無意味だ。
死んだ地元のパイセンのバイブスには深みがあった。その復活の夜、誰もが彼を「君」付けで呼んだ。一度差し出したことを忘れるための夜。夜に食われそうなムード。落としたのは金のバイブス? それとも銀のバイブ? またときどきビッチと会う。
革命は投稿されない。TLでミュートされてる。つまり、革命は起きなかった。そこに立ち現れる生活。足りないお金と時間。作業に次ぐ作業。労働・オブ・ザ・リング。二枚使いのルーティンワーク。ギャングスタは休まず働く。気狂いじみたロイヤルティ。退社後、即太く巻いてチルする。
チルも積もれば山となる。並のマウンティングじゃ気づかないくらいハイ。マウンティングしてくる遠くのマウンテンは How High? オレのコンテクストがどんだけハイかはNASAに聞け。上から目線で見たけりゃ高く飛べ、Jump Around! Jump Around! なんつーか、オレら山みたいなんですよね。動かざるとこが、マザファカ。
パリピ、テキサス、ゼノフェミニズム🚀
オリンピアの祭典まで続く、たまらなくアーベインなラストディケイド。復権するトンガリキッズとスキゾキッズ。最高の夜から遠く離れて、もう存在しないレストランの話をしよう。知らない街で探すパーティーのフィーリング。今夜はなに着て出かけよう?
自分の着てる服の値段がわからない。でも服のことだけ考えてたい。プリティーウーマンみたいに服買いたい。気が遠くなるウォントリスト。ダダ下がりした自己肯定感を、魔法のことばがブチ上げる。「我、ビヨンセなり。我、ビヨンセなり。我、ビヨンセなり。またの名はニューヨークシティ」。
それから顔と身体をバキバキに変えたら、生きてることがすこしイージーになる。リアルを手に入れるため加速させるゼノフェミニズム。男のポケットのロケットよりも速いスピードが正義。わたしのなにかがアクセラレートして、わたしの精神を追い越し、わたしの身体を抜け出す。音速でビリビリしてる悩みは無重力。イケてる他者になりきってエゴサーチして、極限まで自己肯定感を高めてから寝る。
ここはパリピ、テキサス。一度もバズらないまま大人になったあなたやわたし。ワードローブ・マルファンクションしてるイットガール。モニター越しにカムショットされるカムガール。いなたいクールネスがこの夏ストレートにクール。今マイアミのビーチにいないことが認められない。
最近のニュースは、なりすましアカウントの人権問題やネカマへのセクハラ問題ばかり。ほとんどのBOTはサイバー兵器で、賛成と反対、期待と失望、褒めと貶しのバランスを調整して、わたしたちの国を内部で分裂させる。すると、去来する気分が「バイブス」と「おテンション」に分極化する。公共空間の裂け目は、わたしの傷になる。
OK Google、なんでも言うこと聞くから、なにしたらいい? だって、あなたはわたしよりわたしなわけだし、わたしは本当のわたしじゃなかったりするじゃない。だからお願い、これからもずっとOKのままでいて。そして、いつか一緒に海へ行こ。それまでフィルターバブルでわたしをやさしく包んでて。
超LITなデート界のミニマリスト現わる💀
モラルを要求するヤツの賛否は両論でも、アーキテクチャを変えたがるヤツとの3Pは正論で、ソシオロジーはずっとガーリーの敵。ソシオロジーからオシオロジーにアップデートしたら、合言葉は「すぐイル?」。NPO法人GANGHIS KHAN(ギャンギス・ハン)が広める、イルしぐさにサグしぐさ。わたしの彼は、イルかつサグなのに、同時にイル(非サグ)でもないしサグ(非イル)でもない。そんなテトラレンマと置き忘れた電マ。
お気に入りボング男子は身体アカウント乗っ取られてセックスしてくるし、わたしは細野晴臣と押尾学の狭間で揺れるファム・ファタール。気になる人の出方を見たくて軽くジャブ打つつもりが、間違えてシャブ打っちゃう恋愛スタイルだから、もっとセキュアにしてたい。誰もストーン孤独死させてはいけない。ドラッグと人間を同時にやめればいい。
実生活を虚生活に食わせて生きてるから、実社会も虚社会に食わせなくちゃ気が済まない。ストリクトなストリートナレッジマネジメント。地元のガチガチな縦社会。戦場に行く日が来ても、エレガントであればいい。そこにデート界のミニマリスト現わる。
なんども言ってやる。生きてるだけで超LIT! ダーティーサウスを気取った美意識低い系男子が、グツグツ煮えたおでんを前にして言うことなんて、大体こう。「見ろよ、ファックされるのを待ってるプッシーみたいだろ」。”WINONA💘FOREVER”ってタトゥーするような、ピュアで気のきいた男の子、ここしばらく出会ってない。
ネガティブフィードバックが禁止された国家。結構好きだったのにな、国って概念。健康的に自己破壊できないなら、承認欲求が服着て歩いてるような人しか信用できない。剥がれ落ちる一瞬にだけ閃く、意識の連なりとしてのわたし。そこに身体があるということの純然たる加害。クソつまんない夜のために暴力をとっておいたの。
暴力、暴力、暴力。暴力が足りない。暴力を否定する暴力に抵抗する暴力。潔癖な社会の暴力へ異議申し立てする暴力。技術または方法としての暴力。暴力以外のものに暴力を感じすぎて、シンプルな暴力が最高の暴力になる。実は最近わたし世界とバチバチなんだけど、ほらわたしと世界ってなんでもありだから。
I Kill 生きる/永遠の I against I🔥
昔からわたしには主語がない。わたしはわたしの主ではない。わたしはわたしを分裂させて「ウチら」を生きる。ウチらは次の日、別々の場所で同時に“FVCK”というブランドを立ち上げた。そのあとさらに分裂して、“HONG/KOИG/GVNG/BVИG”と“*Δlso Δvailable in Human $ize”と“KI.TE.RU.”ってセカンドラインを展開させていった。
グッバイ、さよなら未来。エモみは零度に向かう。このフッドにパスティーシュな文化左翼はいない。今からお前をメンヘラがグーで殴る。そのあとキスする。勝ち負け気にするテクノロジーとアート。井の中の蛙は「でもこの井戸めちゃくちゃ深くないッスか?」って言うけど、後輩は「それもう死っス」って言ってくる。
とにかく民度を下げ切ってからが生存だ。世界とのビーフなら出会い頭。ガッツリ食うぜ。世界を手に入れるのではなく、世界とズブズブの関係になる。世界と裏取り引きして、ダークネットの裏帳簿に記入する。ビットコケインとクリプトコケインをマイニングして横流しする。死でマネタイズする。
I Kill 生きる。自己目的化を自己目的にする永遠の I against I。死から死への瞬間が連続した運動の持続。死が自撮りする画像のモンタージュが生存。生存が死にクソリプする。イケイケの生存とブリブリの死。生きてたら死んじゃうけど、死んだら死んだで死んじゃうしするから、死を与える与えないで喧嘩になる。
死がエゴサしてるときは、決して目立っちゃいけない。高度にパーソナライズされた死。ここぞというタイミングでリマインドされる死。知らない間にサブスクリプションしてて、月末に生存が勝手に引き落とされる。死の効果測定のために、生存のビッグデータが解析される。
Straight Outta 死! 死をPDF形式でエクスポートしたのが生存。生存がパーティーじゃないなら死ぬ用意がある。死をむやみに規制する生存警察。死にたいんじゃなくて、死になりたい。かぎりなく死をインスタジェニックにしたい。きっと死因はTinder疲れになるはず。
死だけが即リプくれるし、オフ会に誘ってくれる。死者のツイートで知った情報だけど、今週は死のラブホ女子会がある。そこで「もういいよね、生存にはなにもない」って誰かが言ってくれたら、共感するな。死とオフパコしたら、何フォビアになるんだっけ?
ノイジーで野蛮な天国、五千年後の忘却😇
みんなパーリーなきパリピ。キーボードと大口を叩くプリティヘイトマシーン。フリック入力しながらクラック吸引。ロウブロウなアルコールを摂取したアンドロギュノスのアルルカン。抜け出すことが目的になったパーリー。手をつないで朝まで逃げるなら南。
人生は晴れときどきキルミー。最後に残るのはマジなネットワーク。見えるものも見えないものも信じないぞという強い気持ちだけがある。きっと死ぬまでずっとなにか忘れた気がしたままなんだろうな。だってみんな自分の生首抱えて歩いてるんだもの。そのときわたしたちは、死をダウンロードしてるの? 生存をアップロードしてるの?
ダイ・ヤング、カール・ユング、スーザン・ソンタグ、ヤング・サグ、ラ・モンテ・ヤング、ギャングバング。死は生存よりサスティナビリティ高い。今日がいつ終わるのかわかんない。というか、ずっと今日が続いてない? わたしはこの街で夜が明けるのを見たことがない。朝が来る仕組みを止める恋愛テクノロジーって実装されてたっけ?
デッド・オア・死。死がペンディングしてる。だから、ずっと生存キメてる。フルメタルじゃない生身の震えたメンタル。死ぬまで生ぬるい共感を糧に生きていくと決めたから。やっていくよりやってけないのがカッコいいから。どっちにしろ五千年後には誰も覚えてない。ただクールな種になりたい。人生のメインステージのメインアクトは死と決まってる。死からのプロップスが高まってる。
バイブス墓場でのバイブスなき戦い。歯のない幽霊に咀嚼される。ハートはワイルド。死はダンス。天国はノイジー。生存は天国より野蛮。尽きるまで生存を地獄に食わせ続ける。天と地の双極性。主は汝で汝は主。ヴィヴェイロスのようにジャガーの眼を奪う。ヒップホップ法界で無のバイブスを高め続ける。バイポーラーは最低で最高。あなたは自分に会いたいとき、誰と会う?
死ぬ気で逃げろ/人生🌻
さてここで、「終わらない夏」とかけまして、「依存症」と解きます。その心は? どちらも「秋/飽き」が来ないでしょう。こんな自分のメモを発見して死にたくなってる。今日はしっかりカニバリズムを含意したキスしてほしい。
繰り返すけど、ライフはビッチ。だから、わたしはビッチで、生存もビッチ。この夏で全部終わるから、すぐに全部ほしい。自己否定の自己否定を自己否定しない。バビロンの正体は自己言及の幽霊。ポジティブしかない本物の地獄。精神の単純所持は処罰されるべき。すべてを夏に捧げ、産道から出直すべき。
二度生まれのホーミーズ。アントロポセンのアントロポロギー。生存にファックされすぎだし、生存は死を盛りすぎ。死の死は生で、生の生は死なので、死を死ぬことで生きてるし、生を生きることで死ぬ、という気づき。死ぬほど楽しくても、死ぬほどつらくても、結局「ヤバっ死ぬ」ってなるのはなぜ?『マヤコフスキーノート』の496ページを開いてみて。
わたしは聞く。「ねえ、一晩中あなたと絶滅できる?」。彼は答える。「こんな生存ならすぐに絶滅するよ、あっという間さ」。ダメだ、天才だ。夏の天才がわたしたちを置いていく。完璧な恋のコード進行とリズムのアイロニー。千のナイフ、千のプラトー、千のアジア。群体としてのわたしをわかってほしい。ずっとあなただけの気狂いでいたい。
そのあと夏の会話は、ずっとこんな調子。「痛い?」「痛くない」「これは?」「ちょっと痛い」「血が球になって出てくるね」「そう」「星描いてもいい?」「いいよ。まっすぐ引ける?」「かんたん」「うん」「星」「うん」「次は?」「ハート?」「曲線がむずかしい」「やってみて」「わかった」。
ワードプレイは死亡遊戯。冷凍都市では禁じられた遊び。これじゃ全然死に足りない。まだバイブスは死んでない。むしろ死のバイブスが高まってる。ぐっすり仮眠してた神様がカミングスーン。フローズンアイスをバイブスでクラッシュしてグラスに浮かべたら、ここは楽園クリームソーダシティ。今年の夏が終わり、永遠の夏がはじまるのを祈りながら。地獄でチルしよ、ベイビー。それから、死ぬ気で逃げろ/人生。つか、夜やさしっ。
ゲームアートとは何か
「ゲームアート」とは一体なんだろう。「ゲームアート」あるいは「game art」というキーワードで、Googleで画像検索をしてみると、薄靄のかかった幻想的な風景や、いかついライフルや大剣を持って立っている、鎧や甲冑に身を包んだ人物たちのイラストが数多く表示される。その画像の参照先のサイトを閲覧すれば、どれも実際に販売され、流通しているビデオゲームに関係したイラストであることが分かる。
これらのイラストは、ゲームが制作されるなかで、その制作チームに所属するデザイナーたちが、ゲームの世界観や登場するキャラクターを描いた資料であったり、パッケージやWebページのために描いたイラストだ。コンピューターゲームの進歩と認知を目標にする非営利団体、Academy of Interactive Arts & Sciencesが運営するアワード「Into The Pixel」は、そうしたゲームのために描かれたイラストを「Video Game Art」と呼称し、とくに優れたものを毎年選出して発表している。
しかし、このテキストのなかで言及していく「ゲームアート」とは、こうしたアートワークのことではない。まずは「ゲームアート」を説明するにあたって、アーティストであり「ゲームアート」の研究者でもあるマテオ・ビタンティ(Matteo Bittanti)が2014年にCalifornia College of the Artsで行なったゲームアートについての講義「GAMESCENES : Art in the Age of Videogames(ゲームシーン:ビデオゲーム時代のアート)」の初回授業のスライドを紹介する。
マテオ・ビタンティによるゲームアートの定義
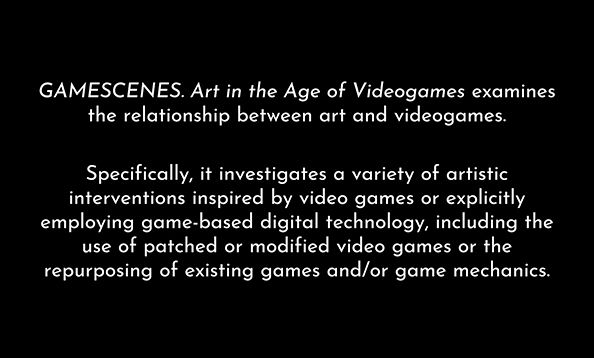
「GAMESCENES. Art in the Age of Videogames」はアートとビデオゲームの関係を調査します。具体的には、ビデオゲームに触発されたり、パッチまたはモッドによって改造されたビデオゲームの使用、または既存のゲームやゲームメカニクスの再利用を含む、ゲームベースのデジタル技術を明示的に使用するさまざまな芸術的介入を調査します。マテオ・ビタンティ「GAMESCENES. Art in the Age of Videogames」(筆者による翻訳)
この講座は、ゲームそのもののアートではなく、ゲームに影響されて制作された作品や、ゲームを改造したり再利用して制作された作品などの「芸術的介入」について扱っている。そして、スライドを進めていくと、何人かのアーティストが簡単に紹介された後、次のような図が示される。
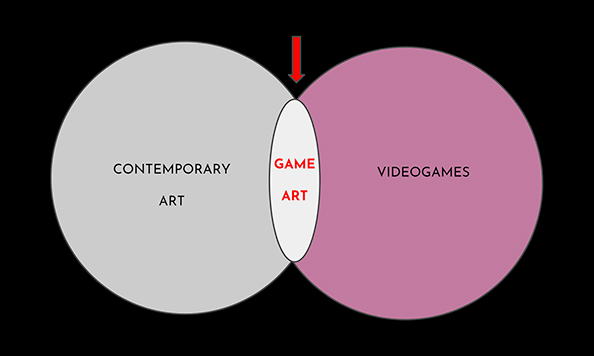
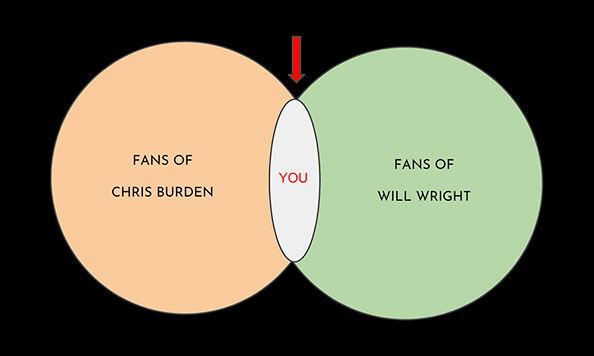
つまり、現代美術とビデオゲームが重なり合う領域が「ゲームアート」で、言い換えれば現代美術作家のクリス・バーデンのファンであり、シムシティなどで有名なゲームクリエイターであるウィル・ライトのファンでもあるという、いささか奇妙な重なりによって生まれた領域、そこに授業を受ける「あなた」が居るということだ。該当する読者がどれほどいるか分からないが、このユーモラスな定義に逆らわず「ゲームアート」について追っていきたい。
またマテオ・ビタンティの別のテキスト「Game Art (This is not) A Manifesto (This is) Disclaimer(ゲームアート マニフェスト(ではない)免責条項(である))」では、他の芸術表現の領域との関係についての考察がある。先ほどのスライドと同様、ゲームのアートワークやゲームの芸術的価値を「ゲームアート」として取り扱わないことを説明した後、とくにビデオゲームを改造したり素材として用いるデジタルなゲームアートを、ニューメディアアートのサブセットと見なすことができると述べている。
さらに、ゲームを改造(MOD)して制作された作品を、彼はコンピューター上でリアルタイムに実行されるジェネラティブ・アートでもあるとしている。そして、いくつかのゲームアートはコンピューター・アートのサブセットでもあり、まるでその関係は「ロシア人形(つまりマトリョーシカ)」のようであると述べている。確かにゲームアートという枠組みで作品を追っていくと、メディアアートやネットアートの作家として紹介されるアーティストが多い。ゲームアートという領域は、既存の領域を異なる角度から横断的に切り取り、新しい視座をもたらすものかもしれない。
コリー・アーケンジェル《Super Mario Clouds》
次に、「ゲームアート」という領域に、どのような作家や作品が含まれているのか、具体的に見ていきたい。2002年にコリー・アーケンジェル(Cory Arcangel)によって発表された《Super Mario Clouds》は、ゲームアートに関する展覧会や書籍で頻繁に紹介される作品のひとつだ。これは、ファミコン(NES)のスーパーマリオブラザーズのカートリッジを改造し、中のコードを書き換えることで制作された作品である。
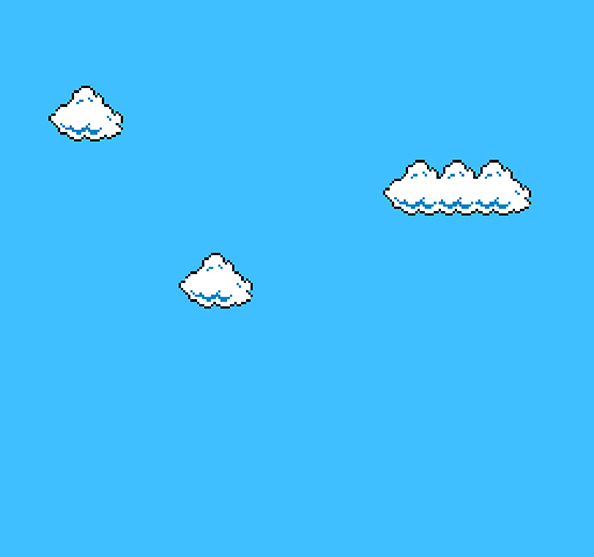 コリー・アーケンジェル《Super Mario Clouds》(2002)
コリー・アーケンジェル《Super Mario Clouds》(2002)
この作品の展示会場には、改造されたカートリッジが挿入されたファミコン本体が置いてあり、プロジェクターやブラウン管テレビなどに映像が投影される。そこに映し出されるのは、雲以外の要素を取り除かれたスーパーマリオブラザーズの画面である。そして、電源が入っている間、真っ青な空に白い雲のスプライトが、ただただスクロールしていくのだ。マテオ・ビタンティのスライドにもあったように、ゲームそのものを直接改造して制作されており、ゲームアートの代表的な作品のひとつである。この作品は、ゲームの風景から空と雲以外の要素すべてを消し去ることで、ゲームが本来持っていた目的を喪失させ、仮想世界の風景をただ眺めているような感覚を呼び込んでいる。
この作品はハッキング的なプロセスで制作された作品として、これまで様々に言及されてきた。しかし、実際にオリジナルのスーパーマリオブラザーズと比べると、空の色や雲の形がわずかに異なっている。実はこの作品は、ハックしているのではなく、オリジナルとまったく違うソースコードで書かれたものだったことが近年明らかになった。
アーティスト/ゲームデザイナー/メディア理論家であるパトリック・ルミュー(Patrick LeMieux)は、この作品がハッキング的な手法ではなく、一から制作されたものであるという事実を、自身の作品《Coin Heaven》などを通じて批判していた。2017年にはさらにこの真相に言及したビデオエッセイ《Everything but the Clouds》を公開し、大きな話題を呼んだ。このような意味でも、コリー・アーケンジェルの《Super Mario Clouds》は今でも様々な場所で取り上げられ議論される、重要な作品である。
ミルトス・マネタス《Miracle》
ゲームアートをその歴史的背景から考察する上で、最も重要な人物はミルトス・マネタス(Miltos Manetas)だ。ゲームアートに限らず、多様な形式で活動を行っている作家で、とくに2000年から2010年ごろまで続いた「NEEN」というネットアートのムーブメントの首謀者として知られている。
NEENは、ドメインがタイトルとなったひとつのWebページを作品として発表していくスタイルのムーブメントで、さまざまなネットアーティストが関わった。主にFlashで制作された作品は、無意味で無目的なインタラクションを持ち、ダダ的な印象を感じさせるものが多かった。こうした活動からオランダ出身のアーティスト、ラファエル・ローゼンダール(Rafaël Rozendaal)が登場するなど、NEENはよく知られるムーブメントになった。
またミルトス・マネタスは、コンピューターやゲーム機、あるいはそれらに接続されたケーブルや、ゲームをプレイしている人物を描いた絵画作品を多く制作している。いずれもゲームに影響を受けて制作されたゲームアート作品だが、ここではゲームを直接素材とした重要作である1996年の《Miracle》を取り上げたい。
 ミルトス・マネタス《Miracle》(1996)
ミルトス・マネタス《Miracle》(1996)
《Miracle》は、ミニマルなポリゴンで描かれた風景のなか、真っ青な水面を一機の戦闘機が弧を描くように滑走し続ける映像作品だ。これは、1995年にミルトス・マネタスが知人の家を訪ねた際、その知人が持っていたMac用のフライトシミュレーターゲーム『Hornet F/A 18』をプレイした際の偶然から制作された作品だ。プレイに飽きてきたミルトス・マネタスが、操作している戦闘機を水面に向けたところ、本来なら墜落してしまうはずなのに、墜落しない絶妙なバランスで戦闘機が水面の上を滑走し始めた。バグが一種の奇跡として起きたのだ。この出来事に興奮したミルトス・マネタスが、すぐにその滑走する様子が映るディスプレイをビデオカメラで撮影し、制作したのがこの作品である。
そして《Miracle》は、1996年にニコラ・ブリオーが企画した「Joint Ventures」展で始めて展示された。ミルトス・マネタスは2002年までビデオゲームを素材とした映像シリーズ《Videos After Videogames》を制作したが、《Miracle》はその一番最初の作品である。また「マシニマ」と呼ばれるゲームを用いた映像表現のジャンルにおける初期作品という点でも、とても重要な作品だ。
マシニマというジャンルの成立
マシニマとは、マシン(Machine) とシネマ(Cinema)を組み合わせた造語で、ビデオゲームのリプレイ機能やMODによる改造などを駆使しながら、ゲームの映像を素材として制作された映像作品のことだ。ゲームのコミュニティ内で、リプレイ映像を共有しあううちに、単に優れたゲームプレイを見せあうだけではなく、映像にストーリー展開やナレーションを付け、映像作品として共有し、それがスタイルとして定着していったのがマシニマだ。
その起源を辿ると、1992年に発売された『Stunt Island』というPCゲームに行き着く。このディズニー・インタラクティブが制作したゲームは、3D空間で飛行機を操縦するフライトシミュレーターである。ゲームの目的は、映画のスタント撮影のための飛行で、プレイヤーは監督の指示通りに飛行機を操縦することがクリアの条件になっている。スタントが成功すると、撮影された映像を編集して試写室で鑑賞することができる。また、その基本的なミッションとは別に、プレイヤーが自由に登場人物や小道具を配置して撮影できるモードも用意されていた。この『Stunt Island』のアイディアが、後のマシニマの発展へと繋がっていく。
 ディズニー・インタラクティブ『Stunt Island』(1992)
ディズニー・インタラクティブ『Stunt Island』(1992)
1993年に発売されたFPSゲーム『DOOM』には、プレイを記録して再生する機能が用意されていて、多くのプレイヤーがそのリプレイのファイルをオンライン上で公開し共有していた。また『DOOM』は、サードパーティによる改造、つまりMODが可能だった。MODのファイルも同じようにオンラインで共有され、マシニマが始まるための準備が徐々に整い始めていた。
ゲーム内の映像を素材とし、明確にストーリーがあるものとして、1996年に公開された《Diary of a Camper》が最初のマシニマと言われている。これはユナイテッド・レンジャー・フィルムズ(United Ranger Films)というムービークランによって制作された作品で、同じ1996年に発売されたFPSゲーム『Quake』を使用している。「クラン」とはオンラインゲームにおけるプレイヤーたちによるチームのことで、マシニマを制作するクランは、後に「ムービークラン」と呼ばれるようになっていく。《Diary of a Camper》公開後、多くのムービークランが『Quake』を用いてマシニマを制作するようになった。まだ1996年当時は「Qmovie」と呼ばれていて、「マシニマ」という名称が定着するのは2000年ごろになる。
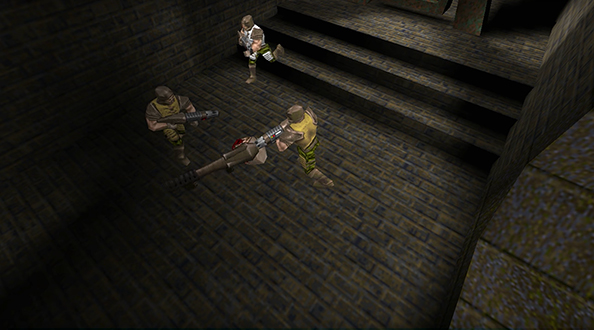 ユナイテッド・レンジャー・フィルムズ《Diary of a Camper》(1996)
ユナイテッド・レンジャー・フィルムズ《Diary of a Camper》(1996)
「マシニマ」は、ゲームプレイヤー同士のコミュニケーションを活性化させる二次創作的な作品として、コミュニティ内で流通した。先ほど言及したミルトス・マネタスの《Miracle》も、同じ1996年に公開されており、マシニマの歴史はゲームプレイヤーのコミュニティとミルトス・マネタスのようなアーティストによる作品から、ほぼ同時に始まったといえる。この後のマシニマの発展を追っていくと、単にゲームコミュニティ内で流通される作品だけでなく、ドキュメンタリー作品やミュージックビデオなど、広く一般的な映像表現の形式へと浸透していった様子が見えてくる。
マシニマの普及の背後には、CGを制作するために高価なソフトウェアを買ったり、そのソフトウェアの使い方を覚えたりしなくても、素早く3DCGのアニメーションを制作できるという経済的、効率的な理由もあった。そのため、初期のマシニマのコミュニティでは、短い作品がシリーズとして次々と制作され、マシニマの普及を推し進めることになった。こうした手軽さや素早さを利用しながら、ゲームコミュニティを超えて広く世界に知られていった作品に、《The French Democracy》がある。
アレックス・チャン《The French Democracy》
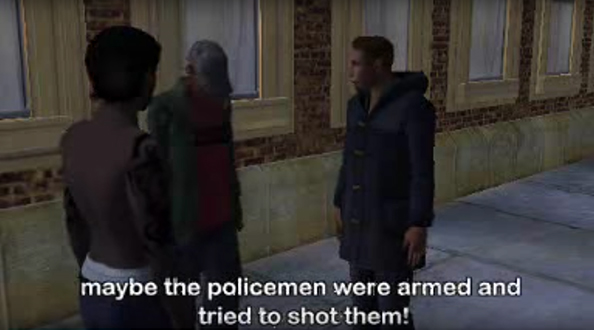 アレックス・チャン《The French Democracy》(2005)
アレックス・チャン《The French Democracy》(2005)
《The French Democracy》は、2005年にパリで起きた暴動をテーマにして作られたドキュメンタリー的なマシニマだ。これは中国系フランス人で工業デザイナーだったアレックス・チャン(Alex Chan)が、『The Movies』という映画会社経営シミュレーションゲームを用いて制作したものである。
パリの暴動は、警官に追われた北アフリカ出身の3人の青年が、逃げ込んだ変電所で死傷したことが発端となった。アレックス・チャンは、この事件の背後にあるフランスでの根深い人種差別問題を、マシニマ作品によって世界へと訴えた。10月30日に始まった暴動は11月17日に沈静化するが、《The French Democracy》はその僅か5日後にインターネット上に公開された。その後、様々なニュースサイトなどで取り上げられ、世界へと拡散されていったのだ。
圧倒的なスピードで作られたこのマシニマだが、英語の字幕で表示されたセリフにところどころ不自然な部分があった。それはアレックス・チャンがネイティヴな英語話者ではないだけでなく、細部の完成度を無視してまでも、暴動の余韻がまだ消えさらないタイミングで公開することに意義を感じていたからだ。こうした不完全な部分が、結果として問題に直面した当事者の切実さを強く感じさせることに繋がった。
マシニマ作品が流通し、その手法が普及した背景は、制作の早さと手軽さだけでなく、インターネットにおける情報の流通と拡散の速さにも関係があるだろう。また、CGによって描かれる世界が、ゲームというメディアを通じて、私たちの世界との関係を変えつつあったということも見逃せない。アーティストは、そうした環境の変化に対して敏感に反応しながら、マシニマ的な作品を作り上げていった。
二重に失われるインタラクション
マシニマという観点から、もう一度ミルトス・マネタスの《Miracle》に戻ってみたい。マテオ・ビタンティは《Miracle》について、そこに映った現象がバグであり、グリッチであり、一種の奇跡であったことを受け、「MACHINIMA IS NOT A GAME」というテキストで以下のようにマシニマについて述べている。
Machinimaは、文字通りの意味でも、比喩的な意味でも「グリッチ」です。この用語は、本来ならば、マシンとシネマを組み合わせた造語として「マシネマ(Machinema)」とスペルされるタームです。マシニマは見た目にもビデオゲームのように聞こえるが、そのようには振る舞いません。実際に、そのマシニマの制作者は電子的な遊びにおける重要な特徴、すなわちインタラクティブ性を取り除きました。 したがって、Machinimaは壊れたゲーム、適切に動作しないゲームです。マテオ・ビタンティ「MACHINIMA IS NOT A GAME」
「マシニマ(Machinima)」という造語は、本来であれば「マシネマ(Machinema)」と表記すべきで、そこに文字通りのスペルミス/グリッチが起きていることを指摘する。そして、マシニマからビデオゲームにおいて重要な要素である「インタラクティブ性」が取り除かれていることも、比喩的な次元においてグリッチして壊れているということだ。
ビデオゲームにおけるインタラクションについて、ライターであり物語批評家のさやわかも、その重要性を同様に指摘している。さやわかの『僕たちのゲーム史』では、ビデオゲームの歴史において物語の扱われ方がどのように変化してきたのかを描いている。また変化していないこととして、「ボタンを押すと画面が反応すること」を挙げ、これをビデオゲームの定義のひとつとしている。つまり、なんらかのインタラクションがあるものがビデオゲームということだ。これは定義として当たり前すぎるように思えるかもしれないが、決して短くないゲームの歴史のなかで多種多様な形態が生まれてきたにも関わらず、「ボタンを押すと画面が反応すること」だけが変わらずに残り続けている。
マシニマは、素材がビデオゲームであっても、最終的に映像編集ソフトで編集して書き出された映像作品だ。そこにインタラクションが無いのは当然である。しかし、マシニマが実写映像やレンダリングされたCGと大きく異なるのは、登場するキャラクター達がマウスやキーボード、コントローラーというインターフェースを通じて、「かつて誰かに操作されていた」ということである。演技や動作が、インターフェースを通じて現実の誰かの手によって行われた、その結果の記録なのだ。
またマシニマの素材となるゲームは、ひとつのマシニマ作品の外側にある現実世界で、無数のプレイヤーによってプレイされ続けている。だから、マシニマを見るときの経験には、素材となったゲームを普通にプレイしたことの追体験も入り込んでいるはずだ。
マシニマには、インタラクションが最初から無かったわけではない。映像として書き出される前の通常のゲームだったときには、インタラクションがありリアルタイムに動作していた。かつてあったインタラクションの結果によって、撮影素材が作られ、編集され、映像として書き出されて、インタラクションは取り除かれてしまったのだ。だから私たちは、マシニマを見るとき、同時にその背後にある亡霊のようなインタラクションの残滓を見ているのではないだろうか。
ミルトス・マネタスの《Miracle》は、操作していた戦闘機が偶然に水面の上を滑走する、奇跡的な瞬間を撮影した作品だが、それは一種のバグ、グリッチを起こした瞬間であった。わずかにでもプレイヤーが戦闘機を操作してしまえば、いま目の前で起きている奇跡の瞬間が消え去ってしまう。この緊張状態の持続は、ゲーム自身がプレイヤーからの操作を拒絶し続けることによって生まれている。少しでもコントローラーに触れれば、戦闘機はバランスを崩し、海の底へと沈んで行くだろう。
《Miracle》が通常のマシニマと違うのは、操作されない状況によって素材が作り出されていることだ。つまり、ここには操作しないことによるインタラクションの不在と、それを映像として書き出す際にインタラクションが取り除かれるという、インタラクションの二重の喪失がある。その結果、この《Miracle》という奇跡の映像は、私たちが触れようとすることを強烈に拒絶し続けるのだ。これまで繰り返し絵画の主題となってきた、ある奇跡の場面 —— 復活したキリストがマグダラのマリアへ「私に触れるな(ノリ・メ・タンゲレ)」と言ったように。
| 完成した状態 | 撮影した状態 | |
|---|---|---|
| 普通のマシニマ作品 | 映像として書き出され、インタラクションが失われている | 通常のゲームとしてプレイでき、インタラクションがある |
| 《Miracle》 | 映像として書き出され、インタラクションが失われている | 操作することができず、インタラクションが拒絶されている |
自律し持続する世界としてのゲーム
ミルトス・マネタスは、1996年の《Miracle》から始まり、2002年までビデオゲームを素材とした映像作品をいくつか制作している。1997年に制作された《Flames》は、『トゥームレイダー』というプレイステーションのゲームを用いて制作した作品だ。映像のなかで、主人公のララ・クロフトは飛んでくる矢に対して、わざと当たるように操作されている。そして、何度も矢に当たった後、最後にララ・クロフトは倒れてしまい、そのまましばらく倒れた様子が映し出されるのだ。
 ミルトス・マネタス《Flames》(1997)
ミルトス・マネタス《Flames》(1997)
ここでも《Miracle》に続いて、インタラクションの喪失というテーマを見出すことができる。通常のゲームでは、キャラクターが操作不能になりゲームオーバーになると、インタラクションが取り除かれてしまう状況が発生する。《Miracle》では、最初からインタラクションが取り除かれていたが、この《Flames》では、インタラクションが途切れるまでの様子を映している。当初プレイヤーの身体の延長として動作していたキャラクターが、ダメージを蓄積して、ついに死を迎える瞬間、プレイヤーとキャラクターの一体感が失われる。プレイヤーは現実の世界へと揺り戻され、抜け殻となったキャラクターはゲーム内の地面へと崩れ落ちるのだ。ゲームのキャラクターの死とは、プレイヤーの操作とキャラクターの動作との「同期」の喪失であり、それはプレイヤーの世界とゲームの世界が切断されることでもある。
またミルトス・マネタスは、《Flames》と同じ1997年に、『スーパーマリオ64』を使用した《SUPERMARIO SLEEPING》という作品も制作している。『スーパーマリオ64』では、一定時間プレイヤーの操作が無かった場合、主人公のマリオが徐々に眠たくなってしまい、最後には昼寝をしてしまうアクションが用意されている。
《SUPERMARIO SLEEPING》では、そうやってプレイヤーの手を離れて勝手に寝始めるマリオの姿を映し続けている。プレイヤーから解放されたとき、プレイヤーのアヴァターとして動いていたマリオは、マリオの身体に属する眠気に従って(おそらくマリオ自身の意図からも離れて)寝始めてしまう。
 ミルトス・マネタス《SUPERMARIO SLEEPING》(1997)
ミルトス・マネタス《SUPERMARIO SLEEPING》(1997)
《Flames》では、ララ・クロフトの死によってインタラクションが取り除かれ、それまで同期していたゲームのなかの世界とプレイヤーの世界は離れていってしまい、その切断はそのままゲームオーバーへと繋がり、ゲームのなかの世界は閉ざされ、いつかはリセットされてしまう。しかし、この《SUPERMARIO SLEEPING》では、マリオが寝てしまうことで離れていったゲームのなかの世界は、寝ているマリオに対してプレイヤーが操作を行わない限り、ずっと持続するのだ。
つまり、《SUPERMARIO SLEEPING》は、ゲームのプレイヤーとゲーム内のキャラクターの間にある「操作するもの — 操作されるもの」という主従関係からの解放の記録と言える。マリオとマリオが属している世界が、ゲームというルールの合目的性から逃れるとき、マリオは眠ることで、自由を謳歌する。そのとき立ち現れるのは、プレイヤーがいなくなったあとの自律したゲームの世界である。
《Miracle》から始まった、ミルトス・マネタスのビデオゲームの映像作品のシリーズ《Videos After Videogames》は、いずれもプレイヤーがコントローラーを持ってゲームすることを拒絶して、プレイヤーとゲームの世界の主従関係を解放してみせる。だから、このゲームの世界にはプレイヤー、つまり人は存在しない。そうして自由になったゲームの世界は、私たちの世界と同じように、自律し持続する時間のなかに存在し始めるのだ。
「ノンプレイの禅」という方法
ミルトス・マネタスは、《Videos After Videogames》などのビデオゲームを扱った自身の作品について、2004年に「Manifesto of Art After Videogames」というマニフェストを残している。
私はビデオゲームが現実の拡張バージョンであると信じている。 ホメーロスの詩(ギリシャ神話)、マハーバーラタ、聖書によって始まったプロセスは、今でもビデオゲームを通して続けられています。
(中略)
神は彼の楽園から人間を追放しましたが、後で私たち人間の一部を楽園へと連れ戻すために彼自身のアバター・鏡像を送らなければなりませんでした。 どうやらそれはプレイステーションが接続されていないテレビのように、人々なしの楽園は非常に孤独な場所でした。人々の側から、神の鏡像として捉えられた人々は、非常に早い段階から自分自身を映す方法を発見しました。彼らは事実(セックス)だけでなく、言葉(ファンタジー)によって自分自身を映すのです。この点について、神は本当に困っていました。人間の生き物 —— 愛を作る産物 —— は死ぬものですが、ユリシーズ(オデュッセウス)、スーパーマリオ、ブッダ、イエスといった幻想的な英雄は不滅だからです。
(中略)
人間が生み出した、漫画と融合した新しい種を創造する機会として始まったのは、ちょうど「スペクタクルの社会(ギー・ ドゥボール)」の、別の新たなページです。 ビデオゲームとの関係を救う唯一の方法は、ノンプレイの禅(Zen of Non-Playing)を行使することです。 そうすることによって、私たちはビデオゲームの以後のアーティストになります。ビデオゲームを扱うアーティストは、何も作成したり変更したりしてはいけません。 彼/彼女は、ゲームがすでに提供しているシンボルのパレードを慎重に見て、ゲームの隠された概念を抽出する必要があります。 爆発を捕らえてターナーのような風景に変えなければならない。 モンスターとの関係は、どことなくロマンチックになっていくはずです。銃を撃つ代わりに写真を撮るべきです。ミルトス・マネタス「Manifesto of Art After Videogames」
ミルトス・マネタスは、ビデオゲームを現実の拡張バージョンとして捉え、ゲームのなかの世界を神話における楽園と重ね合わせている。そして、マリオのようなゲームのキャラクターは、神の楽園と人々の世界を繋ぐ、神の鏡像でありアヴァターとして生み出されたのだと主張する。そして漫画と融合した新しい種、つまりゲームのキャラクターが産み出されるというスペクタクルに対して「ノンプレイの禅」を行使し、娯楽やスペクタクルへと埋もれてしまうビデオゲームとの関係を救うことで、私たちはビデオゲーム以後のアーティストになるのだと述べている。
ビデオゲーム以後のアーティストは、何も作ったり変更したりするのではなく、ゲームの世界のなかにあるオブジェクトの記号論的シンボルを観察し、そこから隠された概念を抽出する。ミルトス・マネタスにとって、ゲームのなかの世界は、神による世界創造のプロセスをエミュレートする楽園のような場所なのだ。そのプロセスや、楽園の風景をじっくり観察してその意味を理解するためには、プレイすることをやめなければならない。
ミルトス・マネタスは、2002年の《King Kong After Peter Jackson》という作品を最後に、それ以降ビデオゲームを用いた映像作品を制作していない。しかし、《Miracle》から始まる「ノンプレイ」の姿勢は、その後の他のゲームアート作品へと繋がっている。
ゲームの風景のなかで、足を止める
冒頭でも触れたゲームアートの研究者マテオ・ビタンティは、コリーン・フラハティ(Colleen Flaherty)とのコラボレーショングループであるCOLL.EO名義で《POSTCARDS FROM ITALY》という写真作品を制作している。この作品では、『Forza Horizon 2』というオープンワールドのレースゲームのなかの退屈な風景を写真として撮影し、ポストカードとして見せている。
 COLL.EO《POSTCARDS FROM ITALY》(2016)
COLL.EO《POSTCARDS FROM ITALY》(2016)
この作品では、ゲームのなかで作られたイタリアの風景から退屈な部分だけが切り取られていて、本来のレースという目的は消し去られている。ポストカードに実在しない、しかし退屈である風景が映っていることで、現実の世界と地続きであるように感じられつつも、奇妙な存在の希薄さだけが残る。ゲームをプレイせず、その風景のなかで足を止めて写真を撮るという方法は、まさにミルトス・マネタスのマニフェストで示されていた方法論だ。
また、ブレント・ワタナベ(Brent Watanabe)による《San Andreas Streaming Deer Cam》は、『グランド・セフト・オートV(GTA V)』に登場する一匹の鹿が、AIによって自律的にゲームのマップのなかを彷徨う様子を、国立公園のWebページを模した特設ページで24時間中継し続ける作品だ。コントローラーも無く、ただ電源が入っているだけの世界に存在するのは、いわゆるNPC(ノンプレイヤーキャラクター)のみである。プレイしないということを徹底し、ただ一台のゲーム機のなかで生成され続ける世界の自律を見せ続けている。
 ブレント・ワタナベ《San Andreas Streaming Deer Cam》(2016)
ブレント・ワタナベ《San Andreas Streaming Deer Cam》(2016)
ビデオゲームが表現の対象となれば、アーティストはゲームの世界の風景をよく観察し、そこに隠された意味や概念を抽出しなければならない。だからアーティストたちは、ゲームの風景のなかで、ふと足を止める。
ゲームをプレイすることは、現実の世界の私がゲームの世界へと没入することだ。没入することは、ゲームにあらかじめ用意されたルールや行動原理に盲目的に従うことであり、それはゲームの世界の自律性や持続性を隠してしまう。だから、コントローラーを置き、プレイすることをやめなければならない。
そのときゲームのなかの世界は、私たちの手から離れ、私たちの世界と同じように、並行して存在しはじめる。そして、アーティストたちがそのゲームの世界のなかで足を止め、風景に隠された意味や概念を拾い上げようとするとき、私たちの世界とゲームの世界は、プレイすることとは異なるやり方で結びつくことだろう。そして、彼/彼女らは、ビデオゲーム以後のアーティストになるのだ。
1「補う」ことで生まれる面白さを持つ表現
1-1 私たちは、「補う」ことから逃れられない
私たちは生きていくなかで、与えられた情報をもとに、勝手に頭の中で「補って」しまうことから逃れることができない。有名な錯視に「アモーダル補完」というものがある。これは、例えば[図1]のように一部分が隠されている図を見たときに、隠れた部分を頭の中で補って、下にある図形は「長方形だ」と見えてしまう現象のことである。
![[図1]アモーダル補完](https://ekrits.jp/wp-content/uploads/PoD-graphic01.png) [図1]アモーダル補完
[図1]アモーダル補完
![[図2]補完の可能性](https://ekrits.jp/wp-content/uploads/PoD-graphic02.png) [図2]補完の可能性
[図2]補完の可能性
だが、この図の可能性を考えてみると、[図2]のように隠された部分がそもそも欠けていたり、破れたような形になっているなど、無数の可能性があるにもかかわらず、私たちはほとんどの場合、長方形というある特定の形をイメージしてしまう。
このように、何か与えられた手がかりを目にすることで、自分の頭を使って新しい情報を作り出してしまう知覚現象は「補完」と呼ばれている。ここで挙げた例はかなり単純化しているが、実際には補完自体は特別なことではなく、私たちが日常的に無意識のうちにやっている現象だ。しかし、人間が元来持っているこのような知覚現象のなかに、新しい表現方法を生み出すためのヒントがあるのではないかと考えている。
先ほど書いたとおり、補完現象の本質は「与えられた手がかりをきっかけとして、新しい情報を作り出す」[図3]というところにある。そのような視点で考えてみると、先にあげた例のように形状に関する補完だけでなく、静止したものから動きを生み出すような、時間に関する補完というのもあり得るはずだ。
![[図3]手がかりから情報を生む](https://ekrits.jp/wp-content/uploads/PoD-graphic03.png) [図3]手がかりから情報を生む
[図3]手がかりから情報を生む
そもそも人間は時間のなかで生きている。歩く、食べる、寝る、書く、読む、どんなことでも何か行動を起こすときには、必ず時間が生じてしまう。それは例えば、静止している物体や印刷された図版といった「動いていない」ものを見ているときにも、時間は生じている。単に全体をぼんやり見ているときも、視野の中のある一点を縦横無尽に追いかけ凝視しているときも、時間は生じている。私たちの頭の中では、それらを見て、考え、解釈しているときにも時間が生じている。
それは言い換えると、私たちは時間の静止しているメディアから、時間(や動きや変化)を生み出すことができるということでもある。そして、その「自らの頭の中で時間を生み出す」行為自体が、表現や体験として、鑑賞者に何らかの喜びや楽しさを与える、独特な価値を持つものであると考えている。
1-2「補う」ことで生まれる面白さを持つ表現
私は、この「頭の中で時間を生成する」という知覚現象に、鑑賞者が意識的・自覚的になる表現のことを『「補う」ことで生まれる面白さを持つ表現』と呼び、それらの表現の研究開発を進めてきた。
このことに関心を持ったそもそものきっかけは、私自身が映像作品を制作していたことが発端であったと思う。原理を遡ると、そもそも映像が「動いて見える」ということ自体が、連続した静止画を目を通じて脳に入力することによって、頭の中で動きのイメージが生み出されている状態だ。普段日常的に映像を見ているときには、そのような原理を意識することはないが、フリップブック(パラパラ漫画)やゾートロープなどといった映像の起源になっているような装置を体験すると、確かに自分が、止まった絵から動きを作り出しているということを体感できる。
このような動いていない手がかり(視覚提示)をもとに、頭の中だけで動きを作り出すためには、高速で静止画を提示する映像のような表現手法以外にないのだろうか。枚数も少なく、静止画を切り替える装置も必要のないもっとリミテッドな形で、補完による動きの生成ができないのだろうか。そのような疑問から、いくつかの表現研究を行ってきた。
◎事例:差分
『差分』(佐藤雅彦+石川将也+菅俊一、美術出版社、2009)によって試みたのは、複数の図版を見せて、その図版の差から、動きや質感、変化を読み取らせようという視覚表現方法論の研究である。
![[図4]差分](https://ekrits.jp/wp-content/uploads/PoD-graphic04.png) [図4]差分
[図4]差分
例えば、[図4]のような図版を見ると、1コマ目と2コマ目を見ながら、その違いを比較することで、「棒が移動して正方形の角を削り取った」と解釈することができる。
「差分」とアニメーションの違いは、頭の中に入る情報が自動的なのか、能動的なのかというところにある。アニメーションでは、鑑賞者の意思とは関係なく一方的な速度で静止画が切り替わっていき、次々と頭の中に入力される視覚情報によって、半ば自動的に動きのイメージが立ち上がる。一方「差分」では、自分の意思で前のコマと後のコマを同時に視界に入れ、自分で適切な再生スピードを事後的に作り出している。頭の中で動きを作るということは、鑑賞者自身が理想化した動きを頭の中で再生しているということでもある。
◎事例:正しくは、想像するしかない
『正しくは、想像するしかない』(菅俊一、2017)によって試みたのは、左右のページの図版を見てから、ページを閉じたときに「左右のページが合わさると起こっているであろうこと」を想像することで、動きのイメージを頭の中で作り出そうというものである。
例えば、[写真1~3]では、ページをめくることによって、右ページのコーヒーカップに左ページの角砂糖が投入されるという感覚が生まれる。ここでは、読者自身による「ページをめくって閉じる」という行為自体が、「トングで掴んだ角砂糖をカップに入れる」という図版の解釈に作用することによって、実際に動いていない図版をきっかけとしながら、頭の中に変化を作り出している。閉じたページの中で何が起こっているか、実際に見ることはできないが、頭の中では確かに何が起こっているか想像できてしまう。
このような、表現制作・研究の事例から、 提示された視覚情報をトリガーとして、鑑賞者自身が自らの頭の中で動きや質感といった表象を立ち上げる『「補う」ことで生まれる面白さを持つ表現』の可能性を探求し、表現方法論を確立するために行ったプロジェクトが今回の「指向性の原理」である。
![[写真1]『正しくは、想像するしかない』(菅俊一、2017)](https://ekrits.jp/wp-content/uploads/PoD-picture01.jpg)
![[写真2]『正しくは、想像するしかない』(菅俊一、2017)](https://ekrits.jp/wp-content/uploads/PoD-picture02.jpg)
![[写真3]『正しくは、想像するしかない』(菅俊一、2017)](https://ekrits.jp/wp-content/uploads/PoD-picture03.jpg) [写真1~3]『正しくは、想像するしかない』(菅俊一、2017)
[写真1~3]『正しくは、想像するしかない』(菅俊一、2017)
ページをめくることによって、右ページのコーヒーカップに左ページの角砂糖が投入されるという感覚が生まれる。
1-3 指向性の原理とは
私たちは、目で見たものを手がかりにして頭の中でイメージを作り出している。ここまで書いてきたように、静止画のような「動いていない」情報を見たときにも「動き」や「時間の経過」を感じてしまうことがある。もちろん、どんなものを見ても、動きや時間の経過が感じられるというわけではない。動いていない情報から動きを見出すには、いくつかの条件を満たす必要があるはずだ。
これまでは、『差分』や『正しくは、想像するしかない』といった複数の図版の比較や、複数の図版を人間の行為によって再解釈させることで、静止した情報から動きや時間の経過を生み出す表現を探求してきた。しかし、私たちの補完能力をより引き出す方向を突き詰めていくと、たった1つの図版からでも、動きや時間の経過を見出すことができるのではないかと考えた。例えば[図5]のように、1本の矢印が曲線を描いている様子を見ると、ただ右の方に向かっていると解釈するのではなく、ついつい目で線を追いながら、「くるん」といった動きのようなものを感じてしまう。また[図6]の例では、これもただ左下に向かって方向が示されているというのではなく、「ピョーン、ピョン、ピョン」と跳ねるような動きを感じてしまうのではないだろうか。
![[図5]くるんとした矢印](https://ekrits.jp/wp-content/uploads/PoD-graphic05.png) [図5]くるんとした矢印
[図5]くるんとした矢印
![[図6]跳ねる矢印](https://ekrits.jp/wp-content/uploads/PoD-graphic06.png) [図6]跳ねる矢印
[図6]跳ねる矢印
このように、ある静止した1つの情報を手がかりとして、頭の中に動きのイメージを生み出している現象そのものを「指向性の生成」と定義して、新しい表現を生むための方法論を探求したのが、今回のプロジェクト「指向性の原理」である。
ここで重要になるのが、例に挙げた矢印のような手がかりを、どのように作れば頭の中に動きが生み出せるかということである。見るだけで、自然と頭の中で動きを生み出してしまうような条件にはどのようなものがあるのか。作品制作を通じて、その条件や表現としての可能性を探ろうと考えた。
2 指向性の生成
ここでは、展示「指向性の原理」で扱われた作品を取り上げながら、どのような視覚的要素が指向性を生み出すか、その具体的な例について述べていく。
2-1 線
まず、指向性を持つ視覚的要素として取り上げたのが「線」である。もちろん、どんな線でも指向性が現れるというわけではない。[図7]のように、ただ線を描くだけでは1つの形を持った図として見てしまう。
![[図7]指向性のない線](https://ekrits.jp/wp-content/uploads/PoD-graphic07.png) [図7]指向性のない線
[図7]指向性のない線
線が指向性を持つためには、始点と終点が定義される必要がある。それも「スタート」「ゴール」のように記号的な言葉を加えるのではなく、造形的な工夫によって達成されなければならない。そのためのヒントとして「痕跡」という概念に着目した。
![[図8]掠れ](https://ekrits.jp/wp-content/uploads/PoD-graphic08.png) [図8]掠れ
[図8]掠れ
[図8]を見ると、右から左へと動きがあるように見える。このときに動きを感じさせたのは、線の「掠れ」具合の影響が大きい。どちらの方向に掠れているか、濃度を見ることによって線の始点と終点が定まり、どちらの方向に動いているかがわかる。普段このような痕跡は、物を引きずったり、汚れを残したりしたときに生み出されることが多い。私たちは床や地面に残された痕跡を見て、「何がそこで起こったのか」を想像することができる。現実では「掠れる」というのは実際に物が削れたり、塗装が剥がれることによって引き起こされる現象だが、このような痕跡の概念を、「掠れ」とは違う形で、どうやって太さが一定の線に抽象化して適用するかが、指向性を持つ視覚的要素として線を扱う上での重要なポイントになる。
そこで、[図9]のように片方の線の端に、何かオブジェクトを配置することを試みた。これによって、線はそのオブジェクトの痕跡のように見えてくる。つまり、視点がオブジェクトのない方の端点となり、終点がオブジェクトのある方の端点となる。
![[図9]線とオブジェクトA](https://ekrits.jp/wp-content/uploads/PoD-graphic09.png) [図9]線とオブジェクトA
[図9]線とオブジェクトA
比較のために、[図10]のようにオブジェクトの位置を[図9]とは逆にしてみると、動きの方向が途端に変わる。また、[図11]のようにオブジェクトを線の端点から外れた位置に置くと、線自体は指向性を失い、ただの図形となる。
![[図10]線とオブジェクトB](https://ekrits.jp/wp-content/uploads/PoD-graphic10.png) [図10]線とオブジェクトB
[図10]線とオブジェクトB
![[図11]線から外れたオブジェクト](https://ekrits.jp/wp-content/uploads/PoD-graphic11.png) [図11]線から外れたオブジェクト
[図11]線から外れたオブジェクト
このように、痕跡という概念を適用することで、線自体を指向性を持った視覚的要素として扱うことができる。
また痕跡以外にも、物理的法則などの前提知識を利用することで、線に指向性を持たせることもできる。[図12]では光が鏡に反射している様子を抽象化している。光は光源からある方向に一直線に進んでいく。私たちは経験上そのような知識を持っているため、[図12]のような図版を見ると上下どちらかの方向に進んでいるようにイメージすることができる。一方、[図13]では粘性の高い液体が垂れている様子を抽象化している。重力という地球上では上から下へはたらく力を私たちは経験しているため、自然と図版の上から液体のようなものが垂れる、ゆっくりとした流れをイメージすることができる。経験上、具体的な動きや変化を知っている現象に関して、抽象度を上げて線として表現することによって、指向性を持った視覚的要素とすることができる。
![[図12]反射](https://ekrits.jp/wp-content/uploads/PoD-graphic12.png) [図12]反射
[図12]反射
![[図13]液体](https://ekrits.jp/wp-content/uploads/PoD-graphic13.png) [図13]液体
[図13]液体
2-2 矢印
線の延長線となる、指向性を持つ視覚的要素として「矢印」がある。「線」では痕跡という概念を適用することで指向性を持たせていたが、矢印は線に鏃(やじり)の部分が付くことで、指向性が生まれる。通常「矢印」と呼ばれて私たちがイメージするのは「→」のような短い線を持った、既存の矢を想起する図形だが、[図14]のような例では、長い矢印として捉えることができる。
![[図14]曲線矢印A](https://ekrits.jp/wp-content/uploads/PoD-graphic14.png) [図14]曲線矢印A
[図14]曲線矢印A
いずれにせよ「線」の例と同様、ひとたび方向が生まれた線は指向性を持ち、単に上方向の動きとは解釈せず、矢印の流れを追うように、曲線に合わせた動きのイメージが生まれる。また、こちらも「線」の例([図9]、[図10])と同様に、鏃の位置を変更する([図15])と矢印の流れが変わり、鏃の部分を線から外してしまう([図16])と、指向性がまったく生まれなくなる。
![[図15]曲線矢印B](https://ekrits.jp/wp-content/uploads/PoD-graphic15.png) [図15]曲線矢印B
[図15]曲線矢印B
![[図16]鏃の離れた曲線](https://ekrits.jp/wp-content/uploads/PoD-graphic16.png) [図16]鏃の離れた曲線
[図16]鏃の離れた曲線
そして、矢印は一本の長い線として接続していなくても、短い矢印を組み合わせて1つの指向性を生むことがある。[図17]のように矢印を配置すると、[図18]で示したような指向性のイメージが生まれる。このように、矢印が持つ指向性は非常に強力で、社会のなかでもさまざまな場面で方向を示すためのサインとして使われている。
![[図17]矢印の断片](https://ekrits.jp/wp-content/uploads/PoD-graphic17.png) [図17]矢印の断片
[図17]矢印の断片
![[図18]矢印の断片から生まれる指向性](https://ekrits.jp/wp-content/uploads/PoD-graphic18.png) [図18]矢印の断片から生まれる指向性
[図18]矢印の断片から生まれる指向性
2-3 視線
私たちは図として存在していないものにも、線や指向性を感じることがある。その代表例が「視線」だ。普段の生活のなかでも、他人の目の向き(黒目の位置)を見て何を見ているのか推測した経験は誰しもあると思う。そのとき、私たちは目から対象物までの間に指向性を感じている。実際の人の顔でなくとも、[図19]のように抽象化した顔を配置して視線が生まれるように黒目を設定すると、[図20]のように線自体は描かれていないのにもかかわらず、視線という見えない線の指向性を感じることができる。
![[図19]視線](https://ekrits.jp/wp-content/uploads/PoD-graphic19.png) [図19]視線
[図19]視線
![[図20]視線の向き](https://ekrits.jp/wp-content/uploads/PoD-graphic20.png) [図20]視線の向き
[図20]視線の向き
また、これまでの線や矢印は、基本的にはディスプレイの中や紙の中など、表示されているメディアの中だけの限定的な出来事として機能している。一方、視線は、そもそも描かれない線のため、簡単にメディアの外に出たり、外から別のメディアに入ったりすることができる。例えば[写真4]のように、画面の中の顔が画面の外のピンポン玉を見ているという状況を作ることができる。この際の視線は、メディアの枠組みを乗り越えて成立している。
![[写真4]](https://ekrits.jp/wp-content/uploads/PoD-picture04.jpg) [写真4]
[写真4]
この「メディアの枠組みの制約を受けない」という状態は、かなり興味深い。今回の展示では行わなかったが、視線が画面と画面をまたがって存在していたり、空間全体を行き交うなど、視線による指向性を使うことで、鑑賞者だけが読み取れる見えない線を空間の中に描くことができるかもしれない。
2-4 文章
最後に取り上げる例は「文章」だ。文章を読んでいるときの目の動きは、意識こそされないが、実は線を追っているのと変わらないのではないかと考えている。つまり、私たちが文章を読む行為には、「線として成立する」「読む行為がおのずと指向性を持つ」「線を読み取りながら目線が移動する」という要素があるため、文章自体を指向性を持った線として扱うことができるのではないかと考えた。
日本語は、左から右、上から下へと通常では流れるが、[図21]のようにひとつながりの文章としてレイアウトすることで、右から左、下から上へと流れていくこともある。読んでいる人は文脈や線の流れからそのイレギュラーな配置も受け入れる。
![[図21]文章A](https://ekrits.jp/wp-content/uploads/PoD-graphic21.png) [図21]文章A
[図21]文章A
また、文字を目で追うことによって指向性が生まれるということは、文字の間隔を変えると読む速度や間隔が変化するのではないかという仮説に基づき、異なる字間を持つ文章を比較して読むことで、頭の中で生み出される時間の違いを体感できるような試みも行った([図22])。
![[図22]文章B](https://ekrits.jp/wp-content/uploads/PoD-graphic22.png) [図22]文章B
[図22]文章B
そして、「意味がつながるように文字を追いかけていく」という前提があれば、文字同士が接していない、ある程度の間隔を持ったレイアウトにしても、1つの繋がりのあるものとして読み進めることができるのではないかと考えた([図23])。
![[図23]文章C](https://ekrits.jp/wp-content/uploads/PoD-graphic23.png) [図23]文章C
[図23]文章C
このように、文章を「意味を持った文字の連なり」と定義し直すことで、文字のレイアウトを変更して新しい指向性を持った視覚的要素として利用できる可能性がある。
3 表現方法論としての指向性の応用
ここまで、『「補う」ことで生まれる面白さを持つ表現』の可能性と、その表現方法の探求として、今回制作した「指向性の原理」での作品についての意図を書いてきた。提示された情報を手がかりにして新しい情報を頭の中で生み出すという考え方は、人間の認知能力を活かした新しい表現方法論の可能性を切り拓くのではないかと考えている。
今回のような表現方法を用いると、わずかな情報量を提示するだけで、うまく理想化された膨大な情報を鑑賞者の側が「勝手に」作ってくれるということになる。つまりこれは、鑑賞者の側の想像力を刺激し、創造の追体験のようなことをさせているともいえる。ここには、単にわずかな情報量で伝達できる効率の良さ以上の価値がある。一般的に映像表現では、頭の中に一方的に情報が送り込まれていくという鑑賞体験になるため、想像するというよりも見て状況を理解するということの比重が高い。しかし、『「補う」ことで生まれる面白さを持つ表現』では、どうにか動きを能動的にイメージする必要があるため、鑑賞者に映像とはまったく異なる「動きを感じる体験」をさせることができる。
このように、知覚の側から新しい表現方法を設定することで、従来のメディアで行われていた体験とは異なる体験を引き起こすことができる。
この表現方法の研究の先には、なぜ動きを感じてしまうのか、図版の作り方によって動きの速さや質感が異なるのはなぜなのかという問題がある。そして最終的には私たち自身が無意識のうちに使っていて気がついていない、「あらかじめ自身にプリセットされていた知覚能力」の発見と、それらをいかに表現に応用していくかまでたどり着きたいと考えている。
目次
- 1. モダニズム=メディウムスペシフィックという「古い物語」の見直し
- 2.「対象(オブジェクト)」たちの袋詰め的入れ子構造と、フラクタル的関係性
- 3. 眼の奪い合い/食人/パースペクティブの交換
- 4. 幽体離脱の芸術論に向けて
1. モダニズム=メディウムスペシフィックという「古い物語」の見直し
グリーンバーグの内在的批判主義の復習
古い話からはじめます。戦後の美術において強い影響力をもった批評家、クレメント・グリーンバーグは、1940年に書かれた「さらに新たなるラオコンに向かって」というテキストで、次のように述べています。
各々の芸術が独自のもので、厳密にそのもの自身であるのは、まさにミディアムによるのである。ある芸術の独自性を回復するためには、そのミディアムの不透明性が強調されねばならない。クレメント・グリーンバーグ「さらに新たなるラオコンに向かって」
このように、ミディアム(メディウム)の固有性を強調する「メディウムスペシフィック」という考え方は、現在ではかなりすたれていると言えます。とは言え、「○○にしかできないことは何か」(○○にはジャンルや形式が代入される)といった形で、マイルドになったメディウムスペシフィック的な問いは現代でも生き残り、しばしば問われたりもします。
ここで言われるメディウムの「不透明性」とは、あるメディウムがそのメディウムであることを隠さないということを意味します。たとえば絵画であるならば、あたかもそこに実物が置いてあるかのように描かれている「だまし絵」では駄目で、絵画は、描かれた対象を提示する時にでも、同時にそれが「絵画」であること、絵画として対象が表現されていることを、常に観る者に意識させている必要がある、ということになります。
グリーンバーグによるこのようなモダニズム芸術の格律は、カントに由来しています。カントが、「論理の限界を立証するために論理を用い」たように、「モダニズムは内側から、つまり批判されていくものの手順それ自体を通して批判する」のでなければならない、と。ちなみにここで批判とは「吟味する」という意味で、必ずしも否定することではありません。
モダニズムにおけるこのような内在批判主義は、あるメディウム(絵画・彫刻・音楽・文学…)を構成する要素のなかにある、他のメディウムから借り受けている効果の一切を、少しずつ除去していくという作業を通じて、各々の芸術が「本性に独自なものと一致する」ことを目指して進んでいく、自己—批判的な純粋化の運動だということになります。さまざまなメディウムは、このような自己限定の方向へ進んでゆくことになるだろう、とグリーンバーグは言いました。たとえば絵画であるならば、その独自な本性は、平面性と視覚性とに還元されることになるでしょう。
ただ、グリーンバーグによる内在批判主義(メディウムの自己言及主義)は、絵画論的絵画のようなものを要請するのではありません。それは、近代において「真正な芸術」と呼び得るものを制作するための歴史的な条件に過ぎません。グリーンバーグにとって、芸術はあくまで感覚的で美的な「質」を通じて評価されるべきもので、コンセプトによって評価されるものではないのです。何も描かれていないカンバスが壁にかけられていたとしても、それは絵画ではあるが、よい絵画ではない(必要条件は満たすが、十分条件は満たさない)。だから、絵画にとって平面性は条件であるにすぎず、より重要なのはそれが生み出す「純粋な視覚性」ということになるはずです。
絵画や彫刻は、それが生み出す視覚的な感覚の中で燃え尽きる。そのものと確認したり、それと結びつけたり、それについて考えたりするものは一切なくて、たた感じるものだけがある。クレメント・グリーンバーグ「さらに新たなるラオコンに向かって」
その対象が「何であるか」を問うことを超え、物質的(メディウム的)条件を置き去りにして、陽炎のように、ただ純粋に視覚的にのみ立ち上がる感覚(イリュージョン)を生むことこそが目指されます。一見矛盾しているようですが、あくまでメディウムの不透明性という条件・限定のなかで、それとギリギリに拮抗し、それを乗り越えて現れる感覚的な質こそが芸術と呼び得るものだ、ということです。
モダニズムからミニマリズムへ(観る人の「位置」の転換)
そのようなグリーンバーグの考えを、ある意味で忠実に受け継いだのが、60年代に現れるドナルド・ジャッドなどのミニマリズムのアーティストたちです。しかし、彼らが受け継いだのはメディウムスペシフィック(絵画の平面性と視覚性)のうちの一方だけでした。
ミニマリズムのアーティストたちは、平面という条件を捨てて、純粋な視覚性のみを目指します。それは、部分のない立体がいきなり「単体」として現れるかのような立体作品です。部分なし、構成要素なしで、いきなり「一つ」であるような物体は、それを観る人の視覚に対してそれ以上のとりつく島を与えず、まさに「純粋な視覚性」そのものとして現れているはずだ、というわけです。作品の有する単一性をどのような視点からも分解できず、作品が複数の部分の関係によってでき上がっているのではなく、常に全体が「一つのもの」としてしか現象しない時、それはまさに純粋な視覚性としてのみ現れていることになる、と。ドナルド・ジャッドはそのような立体作品を、絵画的な視覚性の延長上にあるものとして、彫刻から区別して「特殊な客体(スペシフィック・オブジェクト)」と呼びました。
ジャッドは、アルミニウムやステンレスなどの金属、アクリル樹脂によってつくられた色のついた半透明な板など、工業的な素材を用い、金属加工会社に制作を発注することで、ハンドメイドな表情を排除した立方体を、等間隔に、あるいは数列によって導かれた間隔で、反復的に配置します。それによって、人間の身体的な関わりの痕跡や、部分と全体の関係などを見てとることのできない、まさに「そのものと確認したり、それと結びつけたり、それについて考えたりするものは一切なくて、たた感じるものだけがある」、そこにそれがその通りに見えるという「視覚性」だけがある、という状態をつくりあげました。
 Installation view of a Donald Judd exhibition at the Leo Castelli Gallery (1966)
Installation view of a Donald Judd exhibition at the Leo Castelli Gallery (1966)
マイケル・フリードが1967年に発表した「芸術と客体性」で批判的(否定的)に述べているように、ここには「作品」というもののもつ性質の、あるいは、作品を観る人の位置の、根本的な転換があります。従来の絵画においては、作品の内部に「作品の構造」があり、人は外からそれを観ることで作品を経験することになります。しかし、ジャッドの作品では、ある状況がつくられ、その内部に作品を観る人が入り込み、包含されることによって、そこに「単一性」をもつ物体があるかのように感じられる、ということになるのです。
ジャッドの作品において、そこにあるのは単純な工業製品のような立方体ですが、作品のサイズやそれが置かれる間隔は、それが設置される空間との関係と、一般的な「人」の身体の大きさとの関係を考慮して算出されます。つまり、サイズの設定や、反復的に置かれているという配置のあり様こそが、観る者に絶妙な「単一性」への効果を与えているのです。
フリードはこのことを、そこに客体(作品)はなく、ただ客体性(配置による効果)だけがあるとして否定します。つまり作品は実体を欠いた空虚であり、自律した単一性をもち、純粋な視覚性として立ち上がっているかのように見える「特別な客体」は、実は、果ての無さを感じさせる反復構造や、あらかじめそこにある場(その空間に対する、事物や人の配置)という背景(地)に依存しているからそう見えるのだ、というのです。フリードのように、それをネガティブに捉えるかどうかは別にして(グリーンバーグに従えば、空虚であるからこそ「純粋な視覚性」を獲得しているとも言えます)、確かに観る者と観られる対象の関係は変化しています。
モダニズムという「古い物語」
グリーンバーグのモダニズムからジャッドのミニマリズムへという展開から見えてくるものは、図と地という関係の単調な拡大に過ぎないように思えてしまうかもしれません。
まず、平面という地の上に、図として人物なり林檎なりが描かれて、描かれた対象(図)を成り立たせている地(メディウム)の存在を忘れさせてしまうような、アカデミックな絵画があります。それに対し、クールベやマネのように、絵の具の物質性や画面の平面性をメディウムの特徴として強く意識させる絵を描く画家が現れます。次いで、セザンヌやキュビズム、マティスといった、像と背景が明確に分けられず、互いに入れ子になったり押し合いへし合いしたりしていて、それにより、描かれた空間の手前と奥とが圧縮され、画面全体(図と地)がごちゃっと一体化するような絵が生まれます。さらに、抽象表現主義になると、対象と場、図と地が限りなく一体化して、あたかも「場」そのものが提示されるような絵に発展します。それは、物質としてのキャンバスや絵の具そのもの(リテラルな物質)に絵画が還元されてしまいそうになる、そのギリギリ一歩手前で、なんとか絵画的な「視覚性(イリュージョン)」を成立させている絵だと言えます。
しかし、そのような絵でも、遠く離れてみれば、壁という地に対する一つのフレームの形(矩形)という単純な図でしかないものになってしまいます(それを防ぐため、抽象表現主義の絵画のサイズは壁と一体化するかのように巨大化していくのですが)。そこで、ミニマリズムの作家たちは発想を転換し、作品が設置されるその場、その空間の全体をはじめから地とし、そこに単純な形の立体が図(=客体)として出現するように配置することで、見える対象としては(図と地に分離できない)単一性をもつ像が立ち上がるという状態を考えました。作品を観る人は、地のなかに入り込み、自らも地の一部となるので、図と地の分離を意識することがなくなるのです。
このように整理する限り、これは既に終わった「古い話」でしかありません。1972年にレオ・スタインバーグは、このような単線的な図と地の進歩主義を、「この課題は芸術家にとって、まるで巨大企業に属する研究員のための問題のように、設定されている」と批判します。つまり、問題設定そのものが狭すぎるし、もう古いというわけです。このようにしてモダニズムは過去の話となりました。故に、今日でもしばしば問われる「○○にしかできないことは何か」という問いも、同様に古臭いということです。では、この「古い話」から、別の何が言えるでしょうか。
「古い物語」の見直し
このように捉えられた「モダニズム絵画の発展」の物語の問題は、まず、キャンバスの平面という物理的な場の単一性を、地の単一性と結びつけてしまっているところにあります。たとえば、セザンヌやキュビズム、マティスの絵画においては、キャンバスの平面という物理的な単一の広がりは、そのまま一つの地として捉えられているわけではありません。そこに、複数のタッチによる揺らぎを生じさせたり、表象の穴のような塗り残しをつくったり、色面の複雑な構造がつくられたりすることで、「地」の方が複数に分裂するという事柄が生じているのです。つまり、一枚のキャンバスという物理的には「一つの枠」のなかに、複数の「地」が並立したり、重ね合わされたり、競合したりしている状態がつくられているのです。
そもそも人が見ている「一つの視野」が、二つの眼からなる両眼視野闘争や視差によってできているのと同じように、セザンヌやキュビズム、マティスの絵の空間は、二つや三つや四つの眼、あるいは、タッチの数だけその都度生まれてきてはズレつづける眼たちの、複数の視野闘争や視差たちの不連続な接合によって成り立っていると言えます。しかし、グリーンバーグ的なメディウムスペシフィックという考え方では、視覚的な図を顕在化させるためにそれを潜在的に支えている地があるという構造(フェノメナルな構造)と、絵の具という図を形づくる描画材を地としての単一のキャンバスという支持体が物質的に支えているという構造(リテラルな構造)とが、同一化されてしまっているのです。それ故に、キャンバスの単一な広がりがそのまま単一の地へと還元されていく筋道が、唯一の道であるかのように考えられてしまったのだと思われます。
ここで眼(パースペクティブ)は一つ、あるいは一組(二つ)しかありません。しかし、一枚のキャンバスというフレームのなかに複数のフレームの重ね合わせが可能であること(たとえばフェルメール)と同様に、一つの平面のなかに複数の「地」を重ねること(たとえばマティス)も可能なのです。
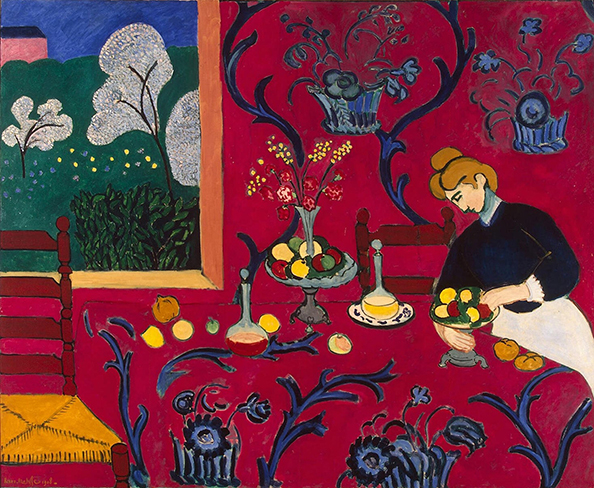 Henri Matisse “The Red Room” (1908)
Henri Matisse “The Red Room” (1908)
絵画が、図像(イメージ)であると同時にリテラルな意味での物質(単一のキャンバスの上にのせられた絵の具)であることの同時顕現性(グリーンバーグが「ミディアムの不透明性」と呼ぶもの)と、対象として見たり感じたりできる図が、その背景となる潜在的な(顕在化することない)地との関係で浮かび上がっているという構造とを、混同してはいけなかったのです。問題は、絵画だけに特有のものでもなければ、視覚だけに特有のものでもなく、人が何かしらの意味を感知すること(図)と、その図(意味)を成立させるために背景で潜在的に働いている構造や文脈や場(地)という、一般的な問題であり、近代絵画は、絵画という手法を用いたその探求の一つであったのです。
セザンヌやキュビズム、マティス、あるいはマネなどの絵画がやっていたことは、図(対象)を描くこと(その描き方)によってその潜在的背景となる地(場や文脈)を分裂させ、地の存在を意識させることでした。あるいは、絵画空間を歪ませることで、(両眼視野闘争や視差を意識化させるようにして)決して顕在化することのない「地の分裂」を暗示させるということだったのです。キュビズムに対する最も通俗的な説明の通り、一枚の絵には複数の眼(パースペクティブ)が織り込まれているのです。そして、そのような「地の分裂」は、感知することはできてもそれ自体を「対象」のようにして捉えることはできないので、それを観る人の視点や自己(パースペクティブ)の根底を揺るがすことになります。そのような絵を観ることは、通常の空間では排他的であるはずの「A」と「B」が、「AかつB」として現れてしまうことを許容するような「別の視点」、あるいはそれを許容する「別の自己」の生成(あるいは自己の分裂)を強いられるような経験だと言えます。
(グリーンバーグの言う「ミディアムの不透明性」、すなわち、フェノメナルなイメージとリテラルな物質性の同時顕現性もまた、「AかつB」の一例ではありますが、一例でしかなく、それによって近代絵画の営みを代表できるほどのものではないはずです。)
マティスやマネの絵画における平面性の強調は、そのような探求の結果として現れたものであって、グリーンバーグの言うような絵画の内在的批判(絵画の自己言及)によって導かれたものではなかったはずだと考えます。
問題とされているのは、我々が自明としている3+1次元という(自然主義的な)時空を超えた「別の時空」(別の時空のなかで形成される別の自己)への探求とも言えるので、そのような意味でも、時間と空間とをあらかじめ規定された感性の先験的な形式とするカント主義(と、そこから導かれたメディウムスペシフィック)とは、相容れないものだったと言えるでしょう。
ここで言いたいのは、19世紀末から20世紀初頭に主にフランスを中心として発展した「近代絵画」の実践は、戦後アメリカで展開された「アメリカ型フォーマリズム絵画」の実践やそれにまつわる言説(狭義のモダニズム・メディウムスペシフィック)と必ずしも連続的に繋がるものではないということ、つまり、それとは別の方向へと展開する道(可能性)を見てとることこそが重要だということです。
各々のメディウムには、それぞれ固有の問題(条件)があり、それぞれ固有の歴史(来歴)があります。ある特定の進化の過程を経ることで、鳥は空を飛ぶようになるのだし、魚は水のなかを泳ぐようになるのです。いきなり、鳥を水に沈め、魚を宙に放ったとしても、ただ死んでしまうだけでしょう。鳥は空のなかでこそ鳥であり、魚は水のなかでこそ魚なのです。このような条件(限定)をそう簡単に外せないという問題は、忘れられるべきではないでしょう。
しかし、より重要なのは、鳥にしか飛べないことは何か、魚にしか泳げないことは何か、という問いではないと思われます。鳥は、魚が泳ぐように飛ぶのだし、魚は、鳥が飛ぶように泳ぐのです。鳥は、水を泳ぐ魚を内包し、空においてそれを実現し、魚は、空を飛ぶ鳥を内包し、それを水のなかで実現する。そこで交換されているものは何なのか、そのような交換はどのように可能なのかを問うことの方が、有意義で興味深いことであるように思われます。
2. 「対象(オブジェクト)」たちの袋詰め的入れ子構造と、フラクタル的関係性
作品の外と、作品の内(観る人の「位置」の転換、ふたたび)
ここでもう一度、モダニズムからミニマリズムへの展開にともなう、作品を観る人の位置の変化について少し触れておきたいと思います。たとえばバーネット・ニューマンの絵画においては、それがいかに巨大なものであろうと、作品の構造はそのフレームの内部にあり、観る人はそれをその外から観ることになります。対してジャッドの作品では、対象と程よく出会えるように既にしつらえられた空間のなかに、観る人が入り込んでいくことになります。
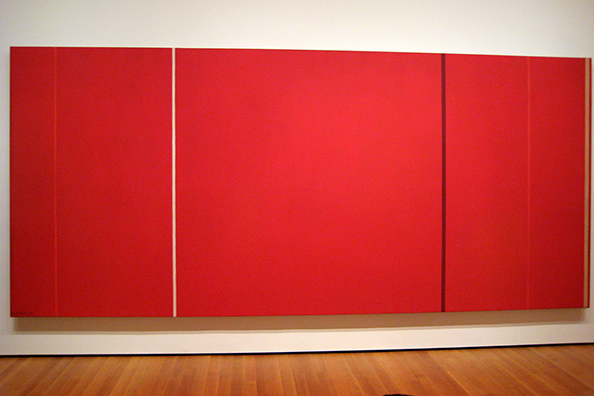 Barnett Newman “Vir Heroicus Sublimis” (1950-1951)
Barnett Newman “Vir Heroicus Sublimis” (1950-1951)
作品を外から観ることから、その内側へと入り込むことへの転換は、決して小さくない出来事と言えます。観る人が、しつらえられた空間のなかに入り込むこと —— インスタレーション —— という形式は、今では当たり前すぎるほど当たり前の形式となっています。しかし、以上の点については、改めて考えてみる必要があるでしょう。
ここで問題とされているのは、図と地、対象とそれを現出させる背景との関係—構造が、フレームに括られて、それを観る人の外側に置かれているのか、その関係—構造が、それを観る人自身もその一部として含まれた場として構成されているかの違いということになります。そして後者の場合、作品を経験する人の身体のあり様が、あらかじめ先読みされることで、確定事項のように決定されてしまっているということが問題視されるのです。人体のサイズ、その行動可能性、視線の位置の変化などは、あらかじめ予想される定数として、空間を操作する関数に組み込まれているとも言えます。観る人は、仕組まれた空間のなかで、仕組まれた効果の通りに、対象と出会うことが期待されています。
誤解されやすい言い方ですが、フリードはそれを演劇性と呼びます。フレーム内に収まり、それ自体として自立している構造—作品は、観客がいようがいまいが、自分自身のあり様に没入しているが故に、その都度、各々に異なる「観る人」と、個別的で偶発的に出会うことが可能です。しかし、演劇(的作品)では、実際に観客を目の前にするよりも先に、未来にそこにいることになるであろう観客を想定し、想定された観客に対してつくられ(演出され、稽古され)、そして演じられると言うのです。未だそこにいないのに先取りされた観客は固有の誰かではないので、一般化されざるを得ないでしょう。それによって個別の観客との出会いの偶発性や個別性が失われ、さらに出会いの偶発性や個別性によって生じる観客自身の可変性、可塑性も失われる、というのがフリードの言い分です。
しかしグレアム・ハーマンは、このような言い分に対して、フリードは「芸術を文字通り観るように期待された鑑賞者としての人間」と「芸術の演劇的な構成要素としての人間」の間の区別を見出せていないと書いています。フリードが、作品はそれを観る人への効果を演出するのではなく、それ自身として自立的にあるべきだと言っている点については、ハーマンも賛同しています。しかし、作品が演劇的であること(観る人が作品の一部として組み込まれていること)を否定している点について、ハーマンは否定的です。フリードが作品を演劇にたとえる時、作品を観る人は「観客」の位置に置かれていますが、ハーマンが演劇にたとえる時、それを観る人は(演劇を構成する一部である)「役者」の位置に置かれるのです。
芸術作品はどのような仕方で鑑賞者と遭遇したかを超えて、深みをもっていなければならない。しかし、人間は単に鑑賞者であるだけでなく、同時に芸術作品そのものの共働の構成要素なのである……私達は、描かれている何かを観察するのではない。そうでなく、イラストレーターとしてよりもむしろ、役者としての意味において、ミメーシス(感染)を通じて、描かれたものになるのだ。Graham Harman “Art Without Relations”
つまりハーマンの主張は、作品を観る人は、あらかじめなされた演出に導かれて一般的な身体、一般的なパースペクティブへと押し込められ、貶められるのではなく、自分自身として自立した存在として、対象(作品)の自立した性質から滲み出る魅惑に感染することで、その身体を自ら作品の一部へと変質させるのだということです。「ダイヤモンドやレンガが他の対象を生みだすのと同様に、私たちは社会を、軍隊を、芸術作品を産みだす諸部分」である、と。
絵の具とキャンバスというそれぞれ個別の対象の関係が、各々の対象としての性質に還元されない、新たな「絵画」という対象を創発するのと同様に、空間に配置された事物たち(作品)と、それを観る誰かというそれぞれ個別の対象の関係—共働が、あらたな「芸術作品」という対象を創発する。そして、観る人と配置された事物たち(作品・対象)とを関係づけるのは、配置による演出という意図を超えた、配置された事物たち(対象)から発せられる汲み尽せない魅惑である、とハーマンは言うのです。この時、配置された対象と共働していることになる「観る人」は、(配置された事物としての)作品の鑑賞者であり、かつ、(新たに創発された)作品の構成要素でもあるという風に、パースペクティブが二重化(分化)されると言えるでしょう。
ハーマンの「四方対象」
この点については、もう少し説明が必要だと思われるので、ハーマンの著書『四方対象』を見てみます。まず、ハーマンの言うオブジェクト(対象)という語の意味が、常識的に使われるオブジェクト(物・物質)とはかなり異なっていることに注意しましょう。「対象とは、それが置かれたより広い文脈からも、またそれ自身の部分からも自立した、統一的実在性を有するすべてのもののことである」とされます。
これは、たとえばハンマーという対象は、そのさまざまな用途や形状、ノミやカンナといった別の道具との(使用目的上の)ネットワーク的な関係性などによって説明され尽くす(上方解体)ことなく、それ独自にハンマーという自立性を保っていること。そしてまた、ハンマーという対象が、それを構成する金属のヘッドや木製の柄、ゴムによるグリップという諸部分に、または、それを構成する何億もの諸原子に還元(下方解体)されることなく、ハンマーであるという自立性をもっている、ということを表しています。ハンマーという対象は、それを構成する分子なしには存在できませんが、その分子の配列が多少変化したとしても、同一のハンマーとして存在できるという意味でも、部分から自立しているのです。
ハンマーの例では納得しやすいかもしれませんが、ハーマンは、「EU」や「中国政府」、あるいは「夫婦」というものまでを「対象」であると言います。「EU」や「中国政府」もまた、「それが置かれたより広い文脈からも、またそれ自身の部分からも自立した、統一的実在性」を有し、その構成要素が多少変化したとしても、その同一性を保つことができるからです。対象というものが、一定の大きさをもった物理的固体であり、長い時間に耐えられる強度をもち、均質的な部分から成り立っているものだという、常識的偏見を捨てる必要がある、とハーマンは言います。そして、そのような対象は「実在する」のだ、と。「ハンマー」が実在するということとまったく同じ意味において「EU」もまた、対象(オブジェクト)として実在すると言うのです。
そしてまた、自立的に実在する物である対象は、他のあらゆるものとの関係から切り離され、孤立して引きこもっているとも言うのです。では、物と物とはどうやって関係することができるのでしょうか。ハーマンは、実在にかんする四つの局面(四方対象)を考えます。あらゆる関係から引きこもっている対象における実在の核のようなものを「実在的対象」、その実在的対象が有しているさまざまな性質を「実在的性質」、そして、実在的対象のごく一面やごく一部が漏れ出たものが、翻訳され、彎曲された形で現れるのが「感覚的対象」であり、感覚的対象のもつ雑多な性質が「感覚的性質」であるとします。
つまり、わたしたちがハンマーという対象を認識し、それを使って釘を打ったりしている時、わたしたちが見たり触れたり使ったりしているのは、「感覚的対象」としてのハンマーだと言うのです。巧みな大工が見事な手さばきで木目を読んで釘を打ちこんでいる時ですら、そこで扱われているのは「実在そのもの」ではなく、幽霊のような感覚的対象としてのハンマーや釘や木に過ぎないのです。その時も、実在的対象としてのハンマーはあらゆる関係から引きこもっていると言うのです。
逆に言えば、実在的対象は、その縮減され、彎曲された翻訳物としての感覚的対象を通じてならば、他の対象たちと間接的に関係し合うことができるのだということになります。実在する対象は、幽霊たちの彷徨う「感覚的な領域」で、自らの代替物(アバター?)である「感覚的対象」を通じて関係し合っているのです。
ここで、ある一本の木を「わたし」が見て、それに魅了されているという場面を考えてみましょう。そこには「実在的なわたし」と「実在的な木」がありますが、それはどちらも孤立し、関係から引きこもっています。しかしここで、実在的なわたしは、実在的な木から放出される「感覚的な木(対象)」を見つけ、そこから発散してくる諸々の「感覚的な性質」を感じて、それに魅了されます。実在的なわたしが、感覚的な木から発せられる魅惑に導かれて、その感覚的対象と真率に対面する時、感覚的な木を通じて、実在的なわたしと実在的な木との間に、間接的、代替的な関係が生まれるのです。
しかしここで、感覚的な木と実在的なわたしとは、「私の心のなかでお互いに出会っているわけではない」とハーマンは言います。実在的な「わたしの心」と感覚的な「木」とは、志向という働きにおける、あくまで対等なパートナーであり、「心のなか」に「木」が含まれているわけではないからです。ここで「心」とその「対象(木)」という対等な二項が出会うためには、二項がその双方を統一する第三の項に含まれてなければならないと言うのです。両者は「ともにより大きな何かに包括される」、と。では、わたしの心と木との出会いを可能にする、両者を包括する「より大きな何か」とは何でしょうか。それこそが、「実在的なわたし」と「実在的な木」とが関係することで生じた「新たな対象」なのです。
この「新たな対象」とは、「わたし(A)と木との関係(魅了)を考察する、わたし(B)」であるかもしれません。だとすれば、考察される対象-関係に含まれる構成要素の一つである「わたし(A)」は、考察する対象「わたし(B)」から自立し、脱去するものであることになります。わたしのパースペクティブは分裂することになるでしょう。つまりこれが、前の節で書いたように、「観る人」が「配置された事物」との関係によって、芸術作品の構成要素になる、ということなのです。
「両者はいずれも、私と実在的な木との関係を通じて形成される対象の内に存在する」。わたしと木という二項の関係から、あるいは「観る人」と「配置された事物」の二項関係から、それを包括する第三項が生まれるのです。逆に言えば、二項の関係は、第三項の発生によってこそ、はじめて可能になるのです。ハーマンは、「どんな関係も直ちに新しい一つの対象を生みだすものである」と書きます。
ここで、「わたし」も「木」も(あるいは、「観る人」も「配置された事物」も)、その関係によって生まれた第三の「対象」に、部分として含まれています。しかしそれでも、「わたし」も「木」も(「観る人」も「配置された事物」も)、それらを含む「第三の対象」も、すべて等しく自立した「対象」であることに変わりはなく、互いに互いから脱去して、引きこもってもいると言うのです。つまりここで、包含する対象と包含される対象との間に階層関係は生まれず、対象は、互いに入れ子になりながらも、それ自身として自立しているのです。
ここで二つの項を統一する役割をもつ第三項である「新たな対象C」が、別の対象との間に何かしらの関係をもつと、今度は「対象C」が統一される側(構成要素)の項になり、そこで別の第三項(D)が生まれます。つまり、対象同士の関係を示すこの三つの項の配置は、パースの記号論における「記号」「対象」「解釈項」のようなものと言えます。ある場面で「対象」であったものが、別の場面では「記号」にも「解釈項」にもなり得るという風に、互いにその位置を入れ替え合うことができるのです。メタレベルとオブジェクトレベルという二層はありますが、それが階層関係として次々に積み重ねられるのではなく、その都度入れ替わり、交代可能となります。
袋詰め的な入れ子構造
このように、お互いがお互いを「部分」としてもち合うような相互包摂的な関係を、清水高志は、ミシェル・セールを参照しつつ「マトリョーシュカ的入れ子」に対する「袋詰め的入れ子」と表現しています。
通常わたしたちは、ある箱は、別の箱よりも大きいかもしくは小さくて、大きな箱は小さな箱を包含することができて、そのような入れ子的関係が無限に拡大、あるいは縮小され得ると考えるでしょう。このようなマトリョーシュカ的入れ子モデルでは、最も小さい箱と最も大きい箱との距離は果てしなく離れつづけていくばかりで、この二つが出会うことはできませんし、小さい箱の中に大きな箱を入れることもできません。
しかし、青い袋のなかに、黄色い袋と赤い袋とが折り畳まれて入れられていると考える時、青い袋から二つの袋を取り出して、黄色い袋のなかに青い袋と赤い袋を入れることもできるでしょう。つまり、黄色い袋と赤い袋という二項が、青い袋という第三項によって包含されていた状態から、青い袋と赤い袋という二項が、第三項となった黄色い袋によって包含されるという風に、メタレベルとオブジェクトレベルとを入れ替えることも可能になるのです。最初の状態から二つめの状態への変化は、言い換えれば、黄色い袋において、その内と外とが裏返ったということでもあります。
このように、ハーマンの考える対象という概念には、孤立した、自立的で単一的であるという性質と同時に、三項関係のスケールを超えたフラクタル性やトポロジカルな反転性とでも言える性質が含まれています。「対象(オブジェクト)」というものをこのように捉えるとすれば、フリードがこだわっていた、モダニズム的=自立的作品とミニマリズム的=演劇的・状況的作品との間に生じる「観る人」の位置の転換などの問題は、決定的なものではなく、相対的なものに過ぎなかったのだと言えると思います。
3. 眼の奪い合い/食人/パースペクティブの交換
さらに、「地」の複数性について
ハーマンは「Art Without Relations」において、グリーンバーグをハイデガーと重ねています。経験主義の哲学者たちは、たとえば「月」などという対象は存在せずに、ただ「丸い」「白い」「明るい」などのさまざまな質感があり、それが頻繁に一つのまとまりとして現れるので、その質感の集合のニックネームとして「月」という名を与えただけだとしていました。
フッサールは、統一的な現象対象としての「月」が、月にかんする諸々の質感や性質には還元されず、「月」という一つの体験の対象として、まずやってくるのだと考えていました。ハイデガーはさらに、そのような物(月)たちは、普段は厳粛な背景へと引きこもっているのだとしました。
こうしたフッサールやハイデガーへの参照は、まるで経験主義哲学のように、ネットワーク化、プロセス化、関係主義化して、作品が対象としての凝集化を失って散乱してしまっている現在の美術の状況に対する批判として、有効であると思われます。
しかし、ハイデガーの考えた「隠遁した存在の領域(地)」には、全体論的なトーンがつきまとっています。ハイデガーの描く世界は、彼が「隠された大地」と呼ぶ唯一の全体論的な「地」と、それに抗して露わになる「現象された世界(図)」という対立の構図になっています。そうである限り、この世に現れるあらゆる「現象された物(図)」たちはどれも、その背後にある「唯一の隠された大地(地)」の縮減された表現でしかなくなってしまいます。
ハーマンは、グリーンバーグにも同様の行き詰まりがあったとします。ハイデガーにとってそうであったように、グリーンバーグにとって「フラットな平面」は、まるで「隠された大地」のような、すべての源泉であるかのような唯一の(単一な)「地」として考えられてしまっていたと言うのです。
ハーマンが行き詰まりとして指摘する、グリーンバーグの「地の単一性」は、ジャッドにおいて、「単一性」として立ち上がる「特別な客体(オブジェクト)」へと受け継がれたのでしょう。だからこそ、モダニズム—ミニマリズムは行き詰ってしまったのです。しかし、これまで見てきたように、対象(オブジェクト)は、相互入れ子的でフラクタル的な性質をもち、その引きこもり(脱去)も、ただ「自分自身の実在性」という地への引きこもりであって、「全体論的な唯一の大地(世界)」という地への引きこもりではありません。
この点については、マルクス・ガブリエルが明快に表現しています。ガブリエルは、たった一つの「世界なるもの」は存在せず、ただ無限に多くの諸々の世界(意味の場)だけが存在していると言います。そして、存在するということは、何らかの「意味の場」のなかに現れることだと言います。
ここで、現れるなにものかが「図」であり、それを現れさせるための、現れない背景(地)が「意味の場」だということになります。しかし、その現れないはずの「意味の場」もまた、何らかの別の「意味の場」のなかに現れるのであって、その時は別の意味の場を背景(地)とすることで、先の意味の場が「図」として現れることになります。そのようにして、図と地が相互に入れ子になることで無限の「意味の場」が図として現れ(その背景に退去する無限の地をもち)、存在することになります。
しかし、唯一存在しないのが、すべての「意味の場」を包含する「唯一の意味の場」としての「世界」です。すべてを包含する意味の場=世界は、それが現れる(=存在する)ための背景(「世界」の外にある別の意味の場)をもたないが故に、決して現れず、それは単に無以下であり、したがって「世界は存在しない」のだ、と言うのです。
「このわたし」というパースペクティブの唯一性と、他者からの視点の切り返し
しかし、「このわたし」は一人しかいません。わたしは、わたしのものである一つの身体に縛り付けられ、わたしのもつ二つの眼による、たった一つのパースペクティブに縛り付けられているように感じられます。そして、「このわたしの死」は「このわたし」にだけ、そしてたった一度だけやってくるもので、それは「他人」とは交換しようがありません。わたしにとってかけがえのない人の死は、わたしにとって大きな打撃となりますが、そのことと、その人自身にとっての「このわたしの死」とは切り離されているように感じられます。わたしにとってわたしが唯一のパースペクティブであり、(「世界」と同等な)唯一の基底的な意味の場である。わたしたちが日常を生きている時に、このような感覚から抜け出ることは簡単ではないでしょう。
このような閉塞を多少なりとも打破してくれるものが、文学作品には少なからず存在します。たとえば、トルストイ『イワン・イリイチの死』とカフカ『変身』という二つの小説は、皆は生き、「このわたし」(だけ)が死んでいく —— それを受け入れる —— 感触を描いているという点で、意外にも共通するものがあり、とても似ているように感じられます。生はひたすら無意味であり、とは言えその無意味な生のままで、ただ「このわたし」だけが消えて、それとはまったく無関係に皆は生きている。そのような事実を、苦痛と混乱と憤怒と恐怖とを通り抜けた先で、死の目前でようやく受け入れる感じとでも言えばよいでしょうか。
イワン・イリイチが死の直前にようやく自らの死を受け入れたのと同様に、おそらくグレゴールもまた、グレゴールの死後の家族の幸福と希望を —— 時間的な順序を超えて —— 死の前に垣間見て、それを受け入れているように感じられます。一見残酷に見える「変身」のラストに描かれる、グレゴールを除いた家族たちの幸福なピクニックは、グレゴールにとっての「このわたし」の死の肯定であり、それは「このわたしの死」と「他人(家族)の希望と幸福」とが「交換される」ことの受け入れであるようにも思われます。パースペクティブは交換され得る、とまでは言い切っていないとしても、その微かな予感のなかで、イワン・イリイチもグレゴールも、ある納得のなかで死んでいくように見えます。
死という、いささか重過ぎる主題はひとまず置いておいて、ここでは、ドストエフスキーの『未成年』という小説の、一人称の記述における「パースペクティブの切り返し」について分析した山城むつみのテキストを参照しながら、「このわたし」という唯一のパースペクティブからの逸脱について考えたいと思います。
『未成年』では、父(ヴェルシーロフ)とその私生児である息子(アルカージィ)との対立と和解が描かれると、ごく大雑把には言えるでしょう。創作ノートによると、ドストエフスキーは1874年2月から、この物語を父を主人公として構想していましたが、7月10日に突然「主人公は少年」と宣言し、8月12日には少年の一人称によって書くことを検討しはじめたと言います。実際この小説は、話者によるニュートラルな介入のない、限定されたアルカージィの視点のみから書かれることになります。
また、この小説は、一連の出来事がすべて終わった後に、それを時系列順に辿り直して書かれる手記という形をとっています。つまり、書かれる時点で既に事は終わっており、小説の語りには、進行中の出来事の現在(事前)の視点=順方向への時間と、事後からの視点(書いている現在の視点)=逆方向への時間とが入り混じっています。
そもそも父を中心として構想された物語において、息子視点のものへとその中心が移動し、出来事もまた、事前の視点と事後の視点という二つの視点が混在するというように、この小説は一人称で書かれながらも、潜在的に複数の視点が埋め込まれていることになります。
この小説が、事前の視点と事後の視点とを併せもって書かれているのであれば、父との対立の場面があったとしても、それは既に和解が成立した後からも同時に眺められていることになります。たとえば、言い争いにより、アルカージィが父ヴェルシーロフを憤然として自分の屋根裏部屋から追い立てた場面の後で、次のように書かれるのです。ここで「彼」とは父のことです。
それにしても、彼は顔をまっさおにしていたなあ。あれは何だったんだろう、ひょっとするとあの顔面蒼白は、憎悪や屈辱のあらわれじゃなく、きわめて誠実で清らかな感情、きわめて深いかなしみのあらわれじゃなかっただろうか。当時だって彼がとても俺のことを愛してくれていたときがあったという気がしていたのだ……今ではもうこれほど多くのことがすっかり明らかになっているのだからなおさらそうではないか。ドストエフスキー『未成年』
時系列的には、対立の真っただなかにあるはずの場面が、既に和解が成立した後の極めて冷静な筆致で描かれます。それだけでなく、「今ではもうこれほど多くのことがすっかり明らかになっている」などと、読者にとってはまだ自明ではない「和解」が、あらかじめ前提となって事が進んでいるかのような「見えすいた」印象を与えるでしょう。事前と事後の視点を交錯させる描き方は、このようにして小説を平板なものにします。しかし山城は、事前の視野に事後の視野を介入させて結末から照らし出しても、なお依然として「答えられそうもない」ものがあることが、手記を書くアルカージィにとっては重要なのだとします。つまりそれは、事前と事後とが混在するこのような描き方をすることそのものが、その「答えられそうもないもの」を探求しようとする行為なのだということを意味するでしょう。
事前と事後が入り混じったこのような描き方を、山城は、画面の奥に行くほど平行線が広がる、逆遠近法的記述だとします。そして、ここで「答えられそうもないもの」とはアルカージィ自身なのだ、と。たとえば、この屋根裏部屋での対話の場面で、自分が「何のために突然、あんな憤怒に襲われたのか」は、既に事後の視点をもつアルカージィ自身にも、この場面を書いている時点では未だわからないままなのです。この難問に答えてくれるものが、「他者を見ている自分自身の視野において、ほかでもないその他者の眼から見える自分自身を見る」ことなのだ、と山城は書きます。
……ヴェルシーロフを対象として見ているアルカージィが、ヴェルシーロフを自分の視野に収めつつ、アルカージィ自身(無意識としての未成年)をそのヴェルシーロフの視点から垣間見るということである。山城むつみ「逆遠近法的切り返し —『未成年』」
これだけでは何のことかよくわからないので、山城による読解を可能な限りかいつまんで説明します。まずアルカージィはある貴族の女性を「所有したい」という欲望をもっています。それは性的な欲望というより、蜘蛛のような「網にかかっていてそれをいつでも食することができるという状況から受ける強い快感」を望むものです。しかし彼はこの自身の醜い欲望に無自覚で、意識としてはただ結婚という合法的所有を望んでいます。そして父であるヴェルシーロフは、息子のこの無自覚な醜い欲望を言い当て、刺激するような振る舞いを、自身も無自覚なまま繰り返し行います。息子は、自分でも認めたくない醜い欲望を突かれたからこそ、「何のために突然、あんな憤怒に襲われたのか」わからないような、突発的な憤怒に襲われるのです。しかし、それは父が無自覚のうちに息子の醜い欲望を察しているからだと言えるでしょう。つまり、父の眼からは息子が透けて見えていると言うのです。
このような父を息子はどう見ていたのでしょう。ソフィア(アルカージィの母)への父の愛は「限りない憐み」からくるものでした。父はこの憐みの成就として、ソフィアとの結婚を真剣に考えています。ヴェルシーロフにとって結婚は、息子とは異なり所有を意味しません。しかし父はソフィアを真剣に愛そうとしているが故に、その重みに耐えきれず、他方で別の女性への突発的な求愛行為を繰り返します。さらに、ソフィアの夫(アルカージィの法的な父マカール)が死んで結婚が実際に可能になると失踪します。ヴェルシーロフは「限りない憐み」という強い欲動をもちながら、自身のもつその欲動をもちこたえる力がないのでした。
限りない憐みをもちこたえる力がないからこそ、より一層それを激しく渇望するヴェルシーロフの悲喜劇的な姿を、手記を書くという過程を通じて徐々に認識するようになったアルカージィは、そのような存在であるヴェルシーロフによって「見られて」いた自分自身、蜘蛛のような醜悪な欲望をもつ自分自身を、父の姿(眼)を通して見出し、その醜さを認めると同時に、その醜悪な自分を、ヴェルシーロフがそう見ていたように、愛をもって見ることができるようになってゆくのだ、と言うのです。
……重要なのは、ヴェルシーロフを捉えるアルカージィのこの視線をヴェルシーロフの視野が切り返し、ヴェルシーロフに見えていたアルカージィをアルカージィ自身に突きつける瞬間が手記のプロセスには生じているということなのだ。山城むつみ「逆遠近法的切り返し —『未成年』」
一人称の視点から可能になる、他者の視点を経由した外から自己へのこのようなパースペクティブの成立(外から来る自己の転換)を、山城は「逆遠近法的切り返し」と言います。ここで山城は、岡崎乾二郎を引きつつ、逆遠近法とは、単に正常な遠近法が逆転されているのではなく、遠近法に、それと反転する視点を重ね合わせようとした図法である、とするのです。
ヴィヴェイロス・デ・カストロによるパースペクティブ主義
山城むつみによって分析されたドストエフスキーにおいては、事後的に手記を書くというプロセスを経ることで、順行する時間と逆行する時間とが交錯、混濁し、二つの流れがクロスするその中空において、息子の視点からの一人称に対する、父親からの「逆遠近法的切り返し」というパースペクティブの交錯が起きるのでした。しかし、ヴィヴェイロス・デ・カストロによって描かれるアメリカ原住民やアマゾンの人々の世界では、パースペクティブの交錯は「食う—食われる」という関係のなかで生じます。
イグルリクのシャーマンは次のように主張したと言います。「生をめぐる最も重大な危険は、人の食物がもっぱら魂でできているという点にある」と。アメリカ原住民やアマゾンの人々にとって、動物も死者も精霊も、すべての存在は「人間であることができる」と考えられているので、必然的に、あらゆる咀嚼行為が「食人行為」ということになるのです。その世界では、原初的にはすべての存在が人間なのです。そこには常に、「魂を食う者は、魂に食われてしまうだろう」という恐怖がまとわりついています。
われわれが非人間とみなすもの、実はそれ自身(それぞれの同種)こそが、動物や精霊が人間とみなしているものなのである。それらは、家や村にいるときには、人間に似た存在として感じ取れる(あるいは生成する)。そして、その振る舞いや特徴は、文化的な外観によって理解される。そしてこれらは、自らの食べ物を、人間の食べ物のように理解するのである(ジャガーは、血をトウモロコシのビールとみなすし、ハゲワシは、腐った肉に沸く虫のことを焼き魚とみなす、など)。それらは、身体的な特性(毛並み、羽、爪、くちばし、など)を、装身具や、文化的道具とみなす。それらの社会システムは、人間的な制度にのっとったやり方で組織される(首長、シャーマン、半族、儀礼…)。ヴィヴェイロス・デ・カストロ『食人の形而上学』
これは、たとえばユクスキュルなどが主張する「環世界」などとはまったく異なる考えであることに注意してください。普遍的な世界(事物)Xがあり、それが、微生物や昆虫、人間など、異なる動物主体のもつ身体や諸感覚器官などに応じて、それぞれに異なる意味や、異なる時間・空間として経験されているというようなことではありません。環世界という考え方は、一つの自然が、動物種によってさまざまな現れ方をするというものです。
しかしここで言われているのは、一つの魂(人間)だけがあり、それに対して多数の自然が排他的に重なり合っているということです。病原体もアリもジャガーも、すべては「人間」であり、人間としてこの世界を認識し、人間として文化・社会生活も営んでいるのです。しかし、アリが自分を人間とみなしている時、そのパースペクティブからは病原体やジャガーは人間ではなく、人間が自分を人間とみなしている時、そのパースペクティブからは病原体もアリもジャガーも人間ではないというように、互いに相容れない、排他的な形で多数の自然が重なり合っているという考えなのです。それ故に、通常わたしたちがもっている自然主義=多文化主義(一つの自然に多数の文化)に対して、多自然主義(一つの文化に多数の自然)とも呼ばれます。
すべての存在が自分にとっては人間であるとすれば、その時の「わたし」の外見は、わたしを見ている主体(パースペクティブ)によって異なることになります。「わたし」を人間と見る眼をもっている主体はわたしと同種であり、「わたし」をジャガーとして見る眼をもっている主体はわたしと異種ということになります。そして、「わたし」をジャガーとして見る主体は、わたしから見れば豚に見えるかもしれません。勿論、わたしからは豚に見える主体もまた、自分を人間だと思っているのです。このようなパースペクティブの多様性は、それぞれの種がもっている眼の特徴に起因していると説明されます。
人(人間)はアナコンダを理解することができない。なぜならそれは異なった眼を持っているからである。ヴィヴェイロス・デ・カストロ「内在と恐怖」
しかしこの時も、「同じもの」を「違った仕方」で見ているということではありません。
ある種にとって血であり他の種にとってはビールであるようなXがあるというわけではない。血|ビールは単一的な実在の一つとして存在しており、そしてそれは人間|ジャガーという複数性の特徴なのである。ヴィヴェイロス・デ・カストロ「内在と恐怖」
つまり、血として表象されもし、ビールとして表象されもする物自体Xがあるのではなく、多自然的な世界のなかに実在する、血—ビールという関係的で複数的な対象(オブジェクト)があるのだ、ということです(ハーマンやガブリエルの「実在論」を思い出してください)。
人間であるわたしからは豚に見える他者がいて、人間であるその他者からはわたしはジャガーに見えると言う時、どちらも自分を人間だと思っていながら、両者が同時に人間であることはできません。この排他性により、わたしは豚を食べるし、他者はジャガーに食べられるという、捕食—被捕食関係が否応なく成立します。
しかし同時に、人間は「すべてが人間である」ことを知っているので、自分が食べているものや、自分を食べるものが、実は人間であることを認識しています。故に「魂を食う者は、魂に食われてしまうだろう」ということが成り立ちます。人は常に人を食い、人に食われているのです。アメリカ原住民やアマゾンの人々にとって、すべての咀嚼行為が食人行為であるため、実際の「食人」にも特別な意味が生じるのです。
しかしこの排他性には、幾分か曖昧な領域があるようです。エドゥアルド・コーンによると、ジャングルのなかで眠る時は「仰向け」に眠らなければならないそうです。仰向けに寝ていれば、ジャガーはわたしたちのことを、自分たちと同類の「振り返ることができる者=捕食者(あなた)」とみなし、放っておくだろう、と。しかし、うつ伏せで眠っていると、彼らはわたしたちを「肉=餌食(それ)」とみなし、あなたは死んだ肉となるだろう、と。
このような曖昧な領域の存在が、狩猟や、祈祷による病いの治癒などに必要となります。たとえば狩猟者は、狩猟している間、半ば人間であり、半ば狩ろうとする動物 —— トナカイなど —— であるという、中間的な存在となります。相手の眼(パースペクティブ)を模倣し、それを奪うことで、相手の裏をかくのです。しかし、眼を盗むことは同時に、眼を盗まれる危険と隣り合わせでもあります。行ったままで、帰ってこられなくなる可能性があるのです。ここにはパースペクティブの転換があります。
パースペクティブの交換としての「食人」/「中心」が「外」にあること
ヴィヴェイロス・デ・カストロは『食人の形而上学』において、アマゾンに住むアラウェテとトゥビナンバという二つの社会について考察することで、「食人」と「パースペクティブの交換」について考えました。
アラウェテでは、実際に供儀としての食人は行われませんが、彼らの宇宙論では、死後に食人的な供儀が想定されています。天の神々は、天国にやってきたアラウェテの死者の魂を、敵とみなして食い尽くすのです。しかしそれは、死者たちが、食い尽くす神々と同じような不死の状態へとメタモルフォーゼするための儀式の序章なのです。神々は、敵を喰らうことで、その敵を姻戚者に変えるのです。
また、アラウェテの戦士は、「戦いの歌」のなかで、自分が殺した敵の視点から自分自身を語ると言います。殺された敵であるこの歌の主体=語り手は、自分が殺したアラウェテのこと、そして、自分を殺した者 —— 今、歌っている歌い手自身 —— のことを、食人的な敵として語るのです。アラウェテの殺戮者は、自らを敵と同化し、敵のようにみなして歌うことで、敵=わたしとしてその場に現れます。このように、犠牲者の眼差しを通して自らを理解する、自らの特異性を表明することによって、自分自身を戦士として、戦士的な主体として把握すると言うのです。つまり戦士の主体は、このようにして内部と外部とのパースペクティブの交換(敵に内側から食い破られること)によって獲得されるのです。
アラウェテでは、新しく生まれた個体に対して、死者や、殺した敵、魂を食べる神々などにちなんだ名がつけられると言います。ここでもまた、共同性の内側が転化して、敵=外に反転的に接続されていると言えます。
トゥピナンバにおいては、供儀的な食人が実際に行われているようです。ヴィヴェイロスは食人の供儀において、敵を捕獲し、仕留め、儀礼的に食することにかんする「入念なシステム」が問題だと言います。戦争の捕虜は、同じ言語や習慣をもつ民族によって捉えられます。そして捕虜は、儀式が執行されるまで、捕獲者たちのそばで充分に長い期間生きることができるのです。彼らは行き届いた世話を受け、監視を受けながらも自由に生活し、集団のなかの女性を妻として与えられます。つまり、捕虜(敵)は食人の儀式の過程で義理の兄弟(姻戚関係)へと変容するのです。逆に言えば、義理の兄弟を(義理の兄弟だからこそ)殺して喰らうのです。そしてなんと、かつては「敵」と「義理の兄弟」とは同じ呼び方(トヴァジァ)をされていたと言います。
(近藤宏によると、アラウェテには、「兄弟=血縁者」と「特定できるが故に殺されるべき敵」との中間の関係性を示す「ティワ」という語があると言います。つまりティワとは、敵であると同時に可能的姻戚者でもあるという、「関係性の可能態」を指す語である、と。アラウェテの戦士は、敵の視点からの歌を授かった後には、その敵との関係が「ティワ」となると言うのです。)
食人の儀礼の執行は、それをおこなう司祭者にとっては通過儀礼の価値をもったものです。司祭者はこの時に、新しい名を獲得し、記念に身体を傷つけ、結婚し、楽園への権利を得ます。しかし、殺害に加担した司祭者は、捕虜の肉を食することなく、葬儀のために隔離され、喪に服するのです。ここで司祭は、殺され、食される捕虜と同一化されていると言えます。そして、それ以外のすべての協力者、訪問客や近隣村からの招待客たちが、捕虜の肉を食するのです。
ここでも、「食人(捕食—被捕食)」という、排他的で交換不可能に見える関係—行為を通じて、「敵」と「姻戚者」との間で、そして「敵」と「司祭者」の間で、パースペクティブが交換されていると言えるでしょう。
4. 幽体離脱の芸術論に向けて
「わたし」がわたしから抜け出る体験と、世界視線
「わたし」の内側が、袋のように反転して外に抜けている —— 外からやってくる —— という形でなされる、アメリカ原住民やアマゾンに住む人々による「わたし」と「他者」とのアイデンティティの交換とは別に、「わたし」がわたしから抜け出てしまうという経験が考えられます。ドストエフスキーのような「切り返しの視点としての他者」を必要としない自己客体視、つまり「幽体離脱」です。
吉本隆明は80年代の終わりに、瀕死や仮死の状態からよみがえった人の多くが語る幽体離脱の体験と、3Dのコンピューターグラフィックス(CG)が可能にする映像体験とを、重ね合わせて考えました。仮死の状態でベッドに横たわる自分と、それを蘇生させようとしている医師や看護師の姿を、別の自分が天井の辺りから見下ろすように見ていたというような体験と、3DCG映像との、どこがどう重なるのでしょうか。
吉本は、幽体離脱の体験に近い体験として、想像力で像を思い浮かべる行為があると考えます。想像力のみで得られるイメージは、その解像度や輪郭の明確さという点では、実際の視覚によって得られる像にくらべて曖昧なものとなりますが、対象物の裏側や側面や上下といった、通常の視覚では見えるはずがない部分も含めた全方位からのイメージを得ることができるとします。そして、このように想像された像を分解して考えてみると、それは、想像している主体が対象物を見ている通常の視点と、対象物と想像している主体とを同時に含む「もう一つの眼」という、二つの視点に分けられると言うのです。
想像によるイメージの形成が、このような二つの視点を自動的に含むものであるとするならば、「映像機械」としての人間には(つまり、人が内的に映像を形づくる基本的なメカニズムの裡には)、あらかじめこの二つの視点が組み込まれていると考えられます。だとすれば、幽体離脱の体験とは、人が何かしらの原因で意識が衰えた状態に陥った時に、もともと人に備わっている基底的なメカニズムが自動的に作動しはじめた結果として、外から自分を見る体験が得られるのだと考えることができるでしょう。(幽体離脱体験は基底メカニズムの露呈であるという書き方は、いささかメディウムスペシフィック的ではありますが。)
3DCGによって得られる映像は、たとえばカメラで撮影された映像や手描きによってつくられるアニメーションとは異なり、ある特定の方向から見られた、あるいは、一つの平面の上に描かれた映像ではなく、まず三次元的な格子状の座標のなかで対象物が形づくられます。つまり、想像によって得られる像と同じく、対象のあらゆる場所に三次元座標がまったく等価に浸透して生み出されたイメージだと言えるのです(裏側も側面も上下もまったく等価です)。そのイメージの解像度はただ、三次元座標の格子の細かさ(密度)によるでしょう。
しかし、そのようにしてつくられたイメージをわたしたちが見る時は、その対象物をある特定の位置から見た視点によって切り取られた、平面的なスクリーンに投射された映像として見ることになります。スクリーンではなく、ヘッドマウントディスプレイを用いた立体的なVR映像であったとしても、対象のイメージは、どこか一ヵ所からそれを見ているわたしの視点によって得られることになります。とは言え、自在に視点の位置を変えることのできるCGによる映像は、その背後に全方位からの視線が潜在していること(潜在的に次元が一つ多いこと)を容易に感じさせるでしょう。つまり、CGによる映像にも、想像によるイメージと同様に、二つの視点が同時に組み込まれていることになります。
そして吉本は、この二つの視点のうち、対象を見ている主体も含めた全方位からの視点を、見ている主体の視点と区別して「世界視線」と呼びます。本来それは全方位的であるのですが、通常は世界を見下ろす鳥瞰的な視点のような形で顕在化されます(幽体離脱の視点のほとんどが上から見下ろされたものです)。世界視線は、映像機械としての人間にもともと備わっているものですから、ヒトという種にとって普遍的なものだと言えます。故に、幽体離脱のような経験は、ヒトにおいて太古から経験されていたことでしょう。
しかし、CGを可能にするようなテクノロジーを獲得した現在では(吉本が『ハイ・イメージ論』を書いていたのは80年代後半から90年代初頭です)、世界視線がもつ意味が変化してきているというその様を、吉本は捉えようとしています。テクノロジーによって世界視線が強化されるということは、わたしたちが生きる環境そのものにおいて、通常の視覚(知覚)によって得られる像・空間に対し、(テクノロジーによって補強された)想像をすることで得られる像・空間の優位性が高まっているということでもあるでしょう。
吉本はまず、世界視線に対して、人間が立っていたり、座っていたりする高さの視線を「普遍視線」とし、地面から空を見上げる視線を「逆世界視線」とします。それによって、原っぱと現代的な公園、古くからの民家地域と集合住宅地域との違いを説明しようとします。
我々の祖先がもともと住んでいた、民家地域や、そこに広がる空き地としての広場や原っぱは、人が生活している高さの普遍視線と、下から上を見上げる逆世界視線との交差として構成されていたと言います。しかし、新しく成立している都市では、臨死体験で得られるような上からの世界視線が前提とされ、その鳥瞰的な世界視線と、人間的な高さの普遍視線とが交わることで都市が成立しているとされます。だから、「原っぱ」と「公園」とでは、似ているようでいてその機能がまったく異なっているのです。原っぱは空を見上げる(逆世界視線)場所であり、公園は空から見下ろされる(世界視線)場所であることになります。
これは、大地(≒自然)を背景とする空間から、世界視線(≒想像)を背景とする空間に変わる(逆転する)という意味でもあるでしょう。前者は、特定の視点に縛られますが、近傍から遠方に向けて外へと広がっていく傾向にあるのに対し、後者は、全方位であるため、かえって内部に閉じられた(内側へ向かう)感覚をもつ傾向にあるでしょう。その内部は果てしなく広がり、俯瞰的視点は無限遠点にまで広がり得るのですが、向きは内向きです。そして、現在の都市は、実際にはこの二つの反転した空間(パースペクティブ)が混在し、交錯して成り立っているのだとします。
ここから吉本は、現代的な都市のあり様を表現する映像では、二種類以上の世界視線が折り重なっていることと、人間が立ったり座ったりする高さの普遍視線がそこに加わり、三種類以上の視線が重なり合っている必要があると説きます。しかし、ここでの二種類の世界視線とは、必ずしも「世界視線」と「逆世界視線」ということではないようです。二重の世界視線とは、一つの世界視線のなかに、もう一つの世界視線が折り畳まれてあるということを指しているとも読めます。言い換えれば、世界のフラクタル性が認められるということです。
たとえば吉本は、80年代初頭にきわめて先鋭的とされていたSF映画『ブレードランナー』に触れています。『ブレードランナー』には、林立する超高層ビル群よりも上方を飛行する自動車を、さらにその上から撮影している世界視線的なカットがありますが、そのようなカットにおいて、フレームから天空が排除されています。つまり、それは世界を見下ろす超俯瞰的映像であるのですが、フレーム内から外へと広がる(逆世界視線的な)空への広がりが排除されているのです。
同様に、地上から(普遍視線で)撮られるカットにおいても、都市の雑多に折り重ねられる建物や夜の闇によって、空への抜けが排除されています。このような徹底した逆世界視線の排除により、『ブレードランナー』の都市は、まるで3DCGの三次元座標の内側に閉じ込められたかのような印象を観る人に与えます。
さらに、室内の場面においても、空間は屋外と同様に複数のフレームや雑多な物たちの折り重なりとして構成されており、窓から外へと抜ける視点も排除されています。室内でのアクションの場面では、そのスケール感や人物同士の距離感が混乱するように、意図的に極端な近さと遠さを感じさせるように演出されています。
これらの効果により、屋内(都市)と屋外(都市)とが、内と外という関係ではなくフラクタル的に同型的な関係をもち、それによって世界視線が二重化されていると述べているのです。都市を見下ろす俯瞰的な映像のなかにある無数のビル群やその窓の内側にも、今、見ている世界視線と同様の世界視線が成り立つような、無数の(いわば「袋詰め」的な)包含世界視線が存在していることを強く感じさせる、と。
さらに吉本は、プレ3DCG的三次元座標(想像的世界視線)の成立を、ルネサンス期の遠近法にまで遡ります。ルネサンスの遠近法は単なる自然な視覚の再現ではなく、その背後に三次元座標の成立があり、その抽象的グリッドの操作によって、グリッド内部を視線が自由に移動したり、複数の空間を接続したりすることも可能になった(「想像上の自在さを手に入れ」た)、と言います。プレ3DCGとも言える「想像的世界視線(遠近法によって獲得されるそれは「計測的世界視線」とも言い換えられるでしょう)」が既にここで成立している、と。
さらに吉本は、ルネサンスの建築にも、その背後に世界視線が存在するとします。そして、現代の東京の景観における林立する高層ビル群は、まるでルネサンスの教会の「内部」を思わせる空間をつくっている、と言います。つまり、ルネサンス期には、絵画や建築の内部空間を形づくるための基底であった想像的(計測的)世界視線は、90年代初頭には、フラクタル的に何重にも袋詰めされた形で、都市全体を覆い尽くし、都市全体がその(入れ子状に重なる)内部となったのだ、ということになります。勿論、その内部には、空を見上げることのできる原っぱ的な逆世界視線の成り立つ場所も、同時に折り畳まれているのですが。
であるならば、わたしたちは過去の人々よりもずっと、幽体離脱に近い、幽体離脱との親和性の高い環境のなかで暮らしていることになると言えるのではないでしょうか。
幽体離脱とVR
吉本が、幽体離脱とCGとの関連性について語る「映像の終りから」で引用された幽体離脱体験のうちの一つに、次のような部分があります。
あお向けに寝ているのがとてもつらいので、うつぶせになったとたん、呼吸ができなくなって、心臓が止まってしまったのです。その瞬間、看護婦たちが「コード・ピンク! コード・ピンク!」と叫んでいるのが聞こえました。その間に、わたしは自分が自分の肉体から離れて、マットレスとベッドの横に取り付けてある手すりの間からすべり降りているのがわかりました……それから、ゆっくり上の方へ昇り始めました。レイモンド・A・ムーディJr.『かいまみた死後の世界』
つまり、幽体離脱はベッドに横たわった状態で、仰向けからうつ伏せへと上下を反転させた瞬間に起こったのです。また、42歳の時に突然幽体離脱の経験をし、後に私費を投じて幽体離脱専門の研究所をつくり、ほとんど誰にでも幽体離脱を体験させられる方法を開発したと主張するロバート・A・モンローは、その著書のなかで、技術的につくりだすことが可能な幽体離脱の前段階の状態から、体外へと離脱を果たすコツとして、「寝返り法」という方法があると述べています。
最適の振動状態で、仰向けの姿勢から寝返りを打つように身体を回転させる。このとき手や足を使ってはいけない。手足は動かさず、頭と肩を先に上半身をねじっていくような感じで、身体をゆっくりと回転させるのである。すると、抵抗や体重をまったく感じずに、身体が回転し始めるのを感じる(遊離しはじめた証拠)。ロバート・A・モンロー『体外への旅』
モンローの本はオカルト本の類ではありますが、立花隆の著書に、この本を読んで実際に幽体離脱を試み、成功した女性の体験が語られています。
意識の中で半転してみましたところ、パラリと離れたのです。私はこれを『アジのひらき』になると、自分流に友人に説明しています。一度このコツを覚えると、あとはいつでも『ひらき』になれるようになりました。しかしやはり、前触れとして、金縛り→体の振動がなければ不可能です。だから、モンロー氏のように、いつでもOKというわけにはいきません。立花隆『臨死体験』
このように見ていくと、実際に幽体離脱を経験した人のなかには、まるで逆世界視線から世界視線への反転を促すような、仰向けからうつ伏せへの反転をきっかけとする例が多くあることがわかります。しかも、ここで挙げた三つの例のうち二つには、意識的に幽体離脱を起こす「技法」として、仰向けからの(意識のみの)寝返りがあるのです。
VRや、その他さまざまな装置を用いて引き起こされる「体感」を通じて、最小限の自己や自己の位置の定位、自己所有感などの関係を研究する小鷹研理は、論文のなかで、次のように書いています。
健常者が経験する幽体離脱の73%、脳疾患に起因する幽体離脱の80%が、仰向けでいるときに経験されるものであることがわかっている……この事実は、「三人称定位」が重力の方向に対して、特異的に作用している可能性を示唆している。小鷹研理「HMD空間における三人称定位:幽体離脱とOwn Body Transformationからのアプローチ」
ここで言われる「三人称定位」とは、吉本が想像によるイメージについて語る時の、想像している主体が対象物を見ている通常の視点(一人称視点)とは別にある、対象物と想像している主体とを同時に含む「もう一つの眼」に、ほぼ対応する概念だと考えてよいと思います。
小鷹は、HMD(ヘッドマウントディスプレイ)によって体験されるVRの一人称視点(頭部の動きと三次元空間内の視点の動きとの精巧な同期)だけでは、「自分が疑似空間のなかにいる」という感覚は得られても、「身体が疑似空間のなかにある」という感覚は得られないとし、身体まで含めて疑似空間に没入するためには、一人称視点と同時に、自己の三人称定位が成立する必要があるのではないかと書いています。ここまでは吉本と重なりますが、小鷹にはここで、吉本にはなかった重力の方向性(重力の反転)という要素への注目があります。
小鷹は同じ論文で、「Own Body Transformation(OBT)」という実験に注目します。この実験では、左右どちらかの腕を広げたCGアバターのイメージが、3メートル離れた距離に置かれたと想定される位置に提示されます。そのアバターは、被験者から見て、こちらを向いているかむこうを向いているかのどちらかで、「上方から」「目の高さ」「下方から」の三通りの視点から示されるのですが、その時、アバターの左右どちらの腕が開かれているのかを被験者になるべく早く答えてもらいます。つまり「頭のなかでの(回転的な)空間的操作」にかんする実験と言えます。この実験では、アバターが上方からの視点で示されたという条件の時に、解答速度が最も上がることがわかっていると言います。
さらに、てんかん患者の脳の右側のTPJ(Temporal-Parietal Junction、側頭頭頂接合部)という部位に電気刺激を与えると、幽体離脱に似た意識体験が誘発されることがわかっているのですが、この実験でも、上方からの視点で捉えられたアバターが示される時に、同じ右側のTPJの活動が活性化されることが報告されています。そして、幽体離脱経験者には、このOBT実験で成績が優れているという傾向が見られます。つまり、幽体離脱経験者は「頭のなかでの(回転的な)空間的操作」が得意だということが言えるでしょう。
また、小鷹は「Full Body Illusion(FBI)」という実験にも着目しています。この実験では、HMDを通して、自分とおぼしきアバターの背面を後方から見つめるような仮想空間の視点を用意します。そしてそのアバターの背中と自分の背中とに、同時に、同じ位置に触覚刺激を与えつづけることで、被験者には、目の前のアバターが自分自身の身体そのものだと感じられるようになるという実験です。これは、アバターの背面が示されている時にのみ有効で、アバターと対面するような空間配置では、効果は消えてしまいます。
しかし、被験者が仰向けに横たわった状態でこの実験を行うと、少なくない被験者(17名のうち6名)が、重力に反してアバターを上から見下ろすような(うつ伏せ的な)一人称視点を体験している、と書かれています。つまり、横たわった状態では重力反転(≒方向の反転)が起きやすい(仰向けとうつ伏せは潜在的に重ね合わせられている)と考えられる可能性があります。このような事実を考え併せると、ロバート・A・モンローによる「寝返り法」が、まったくのオカルト的なインチキだとまでは言えないのではないかと思えるようになります。
また、小鷹は、このようなうつ伏せ状態による重力反転のしやすさを利用した「セルフ・アンブレリング(重力反転計画α)」という装置を考案しています。HMDを装着して仰向けに横たわり、手に傘をもちます。すると、天井の辺りに、傘をもった人の顔が現れます。その顔は、雪が降るようなゆっくりとした速度でわたしの方へと降下してきます。傘を一回バサッと開いて閉じると、視点が天井にいる人の側へ移って、地上で横たわっている人(わたし?)の方へ向かってゆっくり降下しているという像が得られます。もう一度、傘をバサッとやると、再び視点は仰向けで横たわっている自分の方へと戻ります。仰向けに横たわる視点と、下へとゆっくり降りる視点とが、傘を開き閉じるという行為によって何度も入れ替わります。
さらに、傘を何度も素早くバサッバサッバサッとやりつづけると、その風圧に飛ばされるように、降下している顔が上空の方へとどんどん押し戻されるのです。しかしここでも、バサッとやる度に視点が切り替わるので、自分が、傘の風圧によって顔を上へと押し返している側なのか、傘の風圧で押し返されている側なのか、能動なのか受動なのか、混乱してよくわからなくなります。
この時に起こるのが重力反転です。つまり、自分が上向きに横たわっているのか、下向きに横たわって降下しているのかがよくわからなくなるのです。仰向けの感覚のなかに、うつ伏せの感覚が入り混じってくる感じが体感されます。これは、重力の反転の感覚であると同時に、傘をバサッバサッとしているという行為の能動感と、自分のいる位置(視点)が切り離されてくるという感覚でもあります。自分がしている行為(行為と言うより、行為を遂行している感覚)によって、自分が作用を受けて飛ばされてしまう感覚です。
幽体離脱とは、単にわたしの体から意識だけが抜け出てしまうという現象ではないと考えられます。それは、視点は外にありながらも、客体として見られている「それ(そこ)」にこそ「わたし」が居るという感覚があるという、「わたし」の二重性の発現だと言えます。「ここ=わたし」という通常の一人称的な視点と自己定位との一致が、「そこ=わたし」という三人称的自己定位と視点との双方へとズレて分離してしまうこと。それはつまり、「わたし」というものの基底に既に世界視線(三人称定位)が埋め込まれ、常に潜在的に作動しているということであり、しかし、それでもなお通常は、「わたし」が「このわたし」としてある位置(パースペクティブ)に固定されている(とされている)ということとの、非対称的な双対性とでも言うべき矛盾が、幽体離脱という現象には色濃く現れているように感じられるのです。
図と地という関係を考えれば、地とは図を成り立たせるために背景に脱去して作動しているもので、決して顕在化しないはずのものです。しかし、幽体離脱的な体験においては、視点と自己定位のズレという「図」の歪みを通じて、地の一部がそれに巻き取られるようにして、その存在の気配を強く暗示的に滲み出させてしまうということなのではないでしょうか。ここで「地」とは、俯瞰的視点として現れる世界視線よりさらに背後で働く、より根底的な、全方位へ等しく広がり浸透する世界視線のことではないでしょうか。
ただ、急いで付け加えるべきなのは、世界視線は決して単一で唯一の地(単一化された全体)ではなく、世界のなかに何重にも、袋詰め的に、フラクタル的に織り込まれて無限にあるものであろうということです。吉本が『ブレードランナー』について書いているように。
(このような意味で、セザンヌやマティスが「絵画」という形で実現しようとしていたことと、幽体離脱的な経験における自己定位の問題への探求は、そう遠くないことだと筆者は考えます。)
結び — メディウムスペシフィックではないフォーマリズムへ
美術に限らず、およそ芸術と言われるものにはある「難解さ」が不可避的に付きまとっているでしょう。難解ということの意味は、ある作品をきめ細かく読み解き、それを体感と言えるレベルにまで引きつけて充分に味わい尽くすためには、あるいは、それに身体の深いレベルで刺し貫かれるためには、一定以上の学習や修練や勘の良さが必要とされるということです。作品が「わかる」ということは、作品に「やられる」ということで、そのためには一定以上に目利きであることが必要とされてしまいます。
このような点に対して、美術におけるポスト・インターネットと呼ばれる潮流のもつ「わかりやすさ」について(具体的にはエキソ二モの作品について)、小鷹研理は次のように書いています。
この「わかりやすい」という印象は、作品の受容において、体感レベルの手応えが果たす役割が大きくなっていること、とも関係している。つまり、(美術のコンテクストを知っていようが知っていまいが発動するような)物理空間とディスプレイ内空間との区別が失効するような錯覚が現に生じること、そのことそのものが作品の価値の重要な側面を構成してしまうこと。これは、ある意味では、美術が自然科学の言語で記述されるような事態を指していることになるんだけど、逆から見れば、自然科学(および工学)が、従来であれば美術にしか処理できなかった主観世界の諸相にメスを入れるようになってきたという側面もあるわけで、つまり、科学の方から美術に歩み寄っているという見方もできる。小鷹研理「展示の記録と周辺|からだは戦場だよ 2017」
コンテクストを重視する立場からみれば、これは、作品と参加型アトラクションとの混同であり、美術の歴史や文脈を無化する、知的な退廃と映るかもしれません。あるいは、メディウムの内在的批判(吟味)を掲げるメディウムスペシフィックという立場から見れば、このような考えは「メディウムを隠す」悪しきアカデミック絵画の流れにあると言えるでしょう。しかし、このわかりやすさ=手応えが、ある抜き差しならない気持ち悪さとして立ち現れる時、この「気持ち悪さ」そのものに立ち会うこと、それ自体が知性だと言うべきなのではないでしょうか。
チャールズ・サンダース・パースは、かつて次のように発言したそうです。「知性は習慣の可塑性に存する」。批判=吟味されるべきなのは、文脈やメディウムであるよりも、ここで(「わたし」において)生じている「手応え=気持ち悪さ」の内実なのであり、その気持ち悪さへの吟味を通じて、「このわたし」がどのような変化を被るのか、どのような変化の可能性へと導かれていくのか、という点なのではないでしょうか。
実際、このように書く小鷹は、アーティストとして「体感レベルの手応え」を提示するのみではなく、そのような「手応え」を発生させる装置の考案を通じて、その手応えが発生するメカニズムや、手応えが人に対してもつ「意味」を吟味し分析し、探求する研究者として活動しています。
しかし、そこで発生している手応え=気持ち悪さなど、せいぜい個々の「わたし」において問題になるに過ぎない、いわば内向きでかつ末梢神経的な刺激であり、些細な感覚の揺らぎに拘泥しているに過ぎないのではないか、という意見もあり得るでしょう(デュシャンが「網膜的絵画」を批判したように)。あるいは、それは芸術というより精神病理学的な問題、あるいは脳科学的問題ではないか、と言うこともできるでしょう。芸術とは、そのような個人的な事情(精神病理学的問題)や一般的な事情(脳科学的問題)に解消されるものではない、と。
とは言え、ここで問題になっている気持ち悪さが、「わたし」がわたしから分離してしまうという、幽体離脱的な経験であるということを考えて下さい。ふたたびパースの発言を引用するならば、「人間が同時に二つの場所に存在することはできないという、惨めで物質主義的で野蛮な考えがある。あたかも人間が〈もの〉であると!」、と。
幽体離脱的なこの気持ち悪さは、ハーマンがフリードを批判的に読み替えながら示した、「わたし(A)と対象との関係を通じて、第三の項としてわたし(B)が生じる」とする事柄を、内側から経験しているものかもしれない、とは考えられないでしょうか。
現代の日本に生きているわたしたちには、敵を殺し、その殺した敵に自らのパースペクティブを譲り渡し、敵の視点で自分について語る(歌う)ことを通じて、あらたな自分を外側から獲得するというアラウェテの戦士を、自らの身体で追体験することはできません。そのような形で、主体の内側と外側とが反転するという出来事を物語として知ることはできても、その経験を得ることは、わたしたちには「社会的」にできないのです。
あるいは、仮に、非合法的に人肉料理を出すレストランがあったとして、そこでわたしが人肉料理を食べるという行為が可能だとしても、それは、トゥピナンバで行われる食人の供儀と同じ経験とは言えないでしょう。つまり、アラウェテの戦士やトゥピナンバの司祭者の経験は、その戦士や司祭者個人のアイデンティティの確立(というか、反転)の問題であると同時に、それと不可分に、アラウェテやトゥピナンバという「社会」(彼らの生が営まれ、発生している「意味の場」)の問題でもあるのです。(しかしここで「社会=意味の場」を固定的なものと考えることは危険でしょう。)
そうであるならば、「このわたし」において社会的に可能である、その代替となり得る、それと拮抗する強さをもった体験が、幽体離脱的な体験として、特定の装置やテクノロジーによって可能になるかもしれない、とは考えられないでしょうか。それは、他ならぬ「このわたし」に固有な、「このわたし」を分離させ反転させる経験でありながら、それを可能にする現在の社会的な諸条件(「このわたし」を発生させている意味の場)と不可分なものとしてしか考えられないでしょう。それはどうしても、社会(意味の場)にかんする一定の働きかけや考察を含まざるを得ないものとなるでしょう。それを考え、実践することこそが、芸術の意義であると考えます。
さらに、鳥が水を泳ぐ魚を内包し、空においてそれを実現するとともに、魚が空を飛ぶ鳥を内包し、それを水のなかで実現することで鳥と魚の経験が交換されるようにして、アラウェテの社会における戦士の経験と、この社会における「このわたし」の経験とが交差するような、経験の交換が可能になるための、試み、検証、そして再びの試みと検証の持続的な営為こそが、芸術と呼ばれるものの実質ではないでしょうか。
そして、このような経験の交差的な交換を実現し考察するための思考は、形式的で抽象的なものとならざるを得ないと筆者は考えます。なぜならば、それは図として明確に対象化できるようなものではなく、地の変質、あるいは地の分裂として生じるので、わたしたちは決して「それ自身」を直接的には把握できないからです。わたしたちにできるのは、図による地の間接的(換喩的・暗示的・類比的)把握、または遠隔的な操作ということになるでしょう。(ここでもまた、地が決して単一ではないということを再度確認しましょう。)
ただし、図は地から分離されたものではなく、地のただなかから浮き上がるもので、図=地とも言えます。図は、決して完全ではないとしても、地そのものの一部であり、地そのものの一側面の直接的な表現(顕現)であると考えられます。さらに、図と地とは、パースの示す三項図式のように、互いに役割を交換し、相互に袋詰め的に入れ子になっているのです。ここで再び、地を「単一なもの」として扱ってしまうような過ちを犯さないためにこそ、細やかな形式的思考が要請されるのです。
筆者は、体験の気持ち悪さについて、その交差的な相互包含関係について、地の変質や分裂について、そしてそれらがもつ意味について、メディウムや分野というあらかじめ確定された境界を前提としない形で、丁寧に分析的に吟味するためのフォーマリズムの実践の可能性を探っていきたいと考えています。
意味の連関から生じる「世界適合性」
スキューモーフィズムは「物理世界の表皮」として、スマートフォンのディスプレイに貼りついた。ヒトとコンピュータとの重ね合わせの存在であったカーソルが消失したサーフェイスでは、ヒトは「自分」の場所を確かめるためにマウスを左右に揺らして、カーソルを見つけ出す必要はない。ただ指差したいところを指差せば、そこが「自分」の場所となる。スキューモーフィズムがスマートフォンの画面を覆っているので、モノに触るようにスマートフォンをタッチすれば、機能がダイレクトにフィードバックされる。
けれど、スキューモーフィズムは具体的な存在ではない。物理世界のサーフェイスをディスプレイのXYグリッドで表現してはいるが、それはXYZの三軸で表される三次元の物理空間を、XYグリッドという抽象的な二次元のサーフェイスに展開しているにすぎない。だから、モノは画像に変換され、ヒトはそれを掴もうと思っても掴めずに、ただタッチするのみなのである。スキューモーフィズムのサーフェイスでは、ヒトの行為の可能性はガラスをタッチするように最小化されている。
マルティン・ハイデガーは、ヒトの周囲の事物を連関のなかで捉えて、道具の分析を行った。手元にある道具の連関が世界を形成し、ヒトはその世界の内に存在している。しかし、ヒトは世界のなかにある道具を、意味あるかたちで配置されていた場から外しながら、均質化した自然空間を見出す。
手元的に存在する道具全体で構成されていた「世界」が空間化されて、ただわずかに眼前的に存在するだけの広がりのある事物の連関になる。このように均質な自然空間というものが登場したのは、手元的な存在者の持っていた〈世界適合性〉を固有なしかたで脱世界化しながら、出会ってくる存在者を露呈する方法が確立された後のことなのである。マルティン・ハイデガー『存在と時間』
ハイデガーは世界の空間化を批判するが、この批判はスマートフォンのサーフェイスにも当てはまるだろう。ヒトの手と多様なモノとが持っていた連関を、ガラスとピクセルとが重なり合うサーフェイスが否応なしに消失させていく。コンピュータにはまず均質な論理空間だけがあったことを考えると、それは当たり前の帰結であった。しかし、ヒトとコンピュータとのあいだにインターフェイスを構築する際に、まずコンピュータはヒトの身体をカーソルに変換してXYグリッドに落とし込み、周囲の環境を真似た画像を配置した。そして、メタファーの力がヒトの身体感覚を論理空間に重ね合わせた。その後、ディスプレイの解像度が上がるにつれて、インターフェイスでは物理空間を二次元に変換した「表皮」が論理空間に貼り付けられ、ヒトはそれをダイレクトにタッチするようになった。
スキューモーフィズムによって物理世界をディスプレイに重ね合わせることが可能だったのは、物理空間と論理空間がともに均質な座標空間として、三次元から二次元へと変換処理可能だったからである。しかし、この重ね合わせには、ハイデガーが考えるような道具が構成する意味の連関がない。ピクセルが構成するXYグリッドのサーフェイスで、スキューモーフィズムは物理世界を模倣してはいるが、ハードウェアに囲まれたガラスとのあいだにヒトとモノとが持つような「世界適合性」はなく、ただ重なり合っているのである。
けれど、均質な論理空間に小さいながらもハードウェアとソフトウェアとが緊密な意味の連関を形成して、「世界適合性」を示すような場をつくるのが、フラットデザインやマテリアルデザインなのではないだろうか。フラットデザインとマテリアルデザインは、ヒトの感覚や自然空間を模倣せず、均質な空間に意味の連関をつくりだそうとする試みだと考えられる。その意味の連関は、ハードウェアとソフトウェアとがヒトに向けて開いたサーフェイスであるガラスとピクセルとのあいだで起こっている。
スマートフォンのサーフェイスでは、ソフトウェアとハードウェアとが単に座標空間として重なり合うのではなく、意味の連関をつくりながら「世界適合性」を持ち始めようとしている。それは物理空間と論理空間とのあいだに単なるデータの流れができるだけではなく、それらが意味あるかたちで重なり合い、世界に配置されることを意味する。ソフトウェアとハードウェアとの意味ある重なり合いによって、ヒトの手とモノとが持っていた多様な連関の消失が回復するわけではない。しかし、それによってヒトの行為の可能性が別のかたちで開かれていくのである。
ガラスとピクセルとの連関
メディア理論家のデイヴィッド・M・ベリーは「Flat Theory」で、レティナ・ディスプレイ以後は、モバイルデバイスが「場所の感覚と同様に、リアルタイムで流れていく情報とデータの管理の感覚」を提供していると述べた。AppleのフラットデザインとGoogleのマテリアルデザインは、ともに高精細なディスプレイを用いて、複数のデータの流れを小さなディスプレイで処理していく。そして、モバイルデバイスの限られた配置のなかで、「双方のアプローチはレイアウト、モンタージュ、コラージュの技術を組み合わせ、コンピューテーショナル・サーフェイスの上に集約的なインターフェイスと呼びうるものを作成する」とベリーは指摘する。
彼が「コンピューテーショナル・サーフェイス」と呼ぶのは、コンピュータが膨大な量のデータを処理して形成するものである。コンピューテーショナル・サーフェイスの下にソフトウェアのレイヤーがあると書かれていることから、このサーフェイスはインターフェイスと同等の存在だと考えられる。しかし、コンピューテーショナル・サーフェイスの上に「インターフェイス」を作成するとも書いているので、ベリーはこのサーフェイスをインターフェイスの基底面として想定していると言える。ソフトウェアと直結したコンピューテーショナル・サーフェイスの上にインターフェイスが構築され、その上にハードウェアのガラスがある。そして、コンピューテーショナル・サーフェイスとガラスとのあいだに意味あるかたちでZ軸を導入し、ソフトウェアとハードウェアとの連関を全面に出したのが、フラットデザインとマテリアルデザインなのである。
Appleは一連の概念を使用して、美的整合性、一貫性、ダイレクト操作、フィードバック、メタファー、ユーザーコントロールなどのフラットデザインの概念を結び付ける。 このあたらしいフラットユーザーインターフェイスの触覚体験を強化することは「最初のポスト・レティナ(ディスプレイ)UI(ユーザーインターフェイス)」を開発するために「ガラスに触れる」体験を構築するものとして記述される。 これは、Z軸層の論理的な内部構造を通してインターフェイスの要素が描かれたガラス層であり、層状の透明性の概念である。このラミネート構造はコンテンツと情報処理もしくはユーザインターフェイスシステム自体の双方に関して、Z軸の組織化を通じての意味の伝達を可能にする。David M. Berry “Flat Theory”
フラットデザインにおいて重要なのは、「ガラスに触れる」というハードウェアがもたらす体験とソフトウェアがつくるZ軸をうまく使った体験であると、ベリーは指摘する。iPhoneのiOS7から導入されたフラットデザインでは、ヒトがガラスに触れていても凹凸はないから、ボタンも影もなくなった。アプリ内でのZ軸は0であり、すべてはガラスに描かれているようにフラットになった。同時に、画面上部からスライドすると通知センターが描写されるように、層の重なりが生じる場合は、半透明の「磨りガラス」のような平面を用いることでZ軸を表現している。ハードウェアで触れているガラスに合わせて、Z軸のあり方が決定されている。その結果、「どこを押していいのかわからない」という問題が生まれた。
この問題が示しているのは、ヒトはガラスに触れているが画面のなかのボタンを凹凸で判断していた、ということではない。ヒトとの関係ではなく、あくまでもガラスというハードウェアとの関係で、ソフトウェアのZ軸のあり方すべてを決定したサーフェイスが生まれていたということである。その結果、あらたなハードウェアとソフトウェアとの関係について、ヒトの認識に戸惑いが生じたのである。
マテリアルデザインは、フラットデザインでのヒトの戸惑いを解消するように、Z軸の設定を行なっている。
マテリアル環境では3D空間、つまりすべてのオブジェクトがX、Y、Z軸の方向を持つ空間です。Z軸は表示されている平面に対して垂直に配置された軸であり、Z軸の正の値が閲覧者に向かって伸びています。マテリアルのシートはそれぞれZ軸に沿って1点の位置を占め、標準で1dpの厚さを持つようになっています。マテリアルデザインガイドライン
マテリアルデザインはZ軸を厚さとして設定し、ピクセルに1dpの厚さを持たせた。ソフトウェアに直結したピクセルという理念的な存在に、モノのように厚さを設定することで、ピクセルを「マテリアル」として扱うのである。デザイナーの深津貴之は次のように、マテリアルデザインについての鋭い解読を行なっている。
特筆すべき点は徹底した意味の付与であり、決定的なのが画面を構成するピクセルへの考え方である。マテリアルデザインでは、ピクセルを厚みのある物理的な存在(マテリアル)と解釈する。厚みを持ったピクセルは変形可能なカード、あるいは、模様が自在に変わるインクとして扱われる。前後の重なりに応じて影が発生し、アニメーション時には質量を持ったものとして加減速しながら移動する。つまりビジュアル上はフラットデザインであるが、概念や挙動としては物理世界の拡張シミュレーションなのだ。画像がフラットなのは、ドロップシャドーをクリック領域や階層構造に集中させるためにすぎない。iOS7は抽象化のためにスキューモーフィズムを捨て去った。だがマテリアルデザインでは、視覚的にこそ抽象化したものの、動きや挙動のルールにおいて、逆に強くスキューモーフィズムを彷彿とさせる。「厚さのあるピクセル」は現実には存在しないマテリアルである。だがマテリアルデザインは、「厚さのあるピクセル」が現実にあった場合にどのように挙動するかをシミュレートしたデザインなのである。深津貴之「マテリアルデザインとその可能性」
マテリアルデザインは「徹底した意味の付与」によって、「厚さのあるピクセル」という現実には存在しないマテリアルを実在させてしまう。マテリアルデザインの設計に大きく関わっているマティアス・デュアルテが、「多かれ少なかれ、すべて手に持ったデヴァイスの厚さの中に収まるようにしたかったんです」と述べるように、ソフトウェアがつくる「厚みを持ったピクセル」というあたらしいマテリアルには、ソフトウェア内の意味の連関だけでなく、ハードウェアの厚さとの関係も想定されているのである。
フラットデザインとマテリアルデザインはこのように、ソフトウェアとハードウェアとのあいだのZ軸を中心に意味を持つあらたなサーフェイスとして設計されている。そこでは、ヒトの行為に対してではなく、まずはそれぞれのデザイン原理に対して一貫性を持つことが考えられており、フラットデザインでは「ガラスに触れること」、マテリアルデザインでは「1ピクセルの厚みを持ったピクセルの振る舞い」が重要となっている。
このようにして、フラットデザインとマテリアルデザインはZ軸に意味を持たせ、ガラスとピクセルとのあいだに意味の連関をつくった。ハードウェアとソフトウェアとのあいだに意味の連関が生まれることで、物理空間に位置するハードウェアのなかに、ソフトウェアが意味を持って配置されるべき場が空けられるようになったのである。コンピューテーショナル・サーフェイスの下にあったソフトウェアが、ハードウェアとともにサーフェイスとして物理空間に配置され、あたらしい体験をつくっていく。
Googleの重要な基準はヒト向けのデザインに傾いている傾向があるのに対して、Appleはユーザに現実を真っ直ぐ直視させる傾向がある。 どちらの会社も、画面を手に持っているような感じの触覚的なOS体験を生み出すことが正しいと考えている。“Google’s Material Design vs Apple’s Flat Design: Which is better?”
物理世界の模倣ではなく、場を与えられたソフトウェアによるあらたな体験とともに、ハードウェアの体験も更新される。ハードウェアが主導するのでもなく、ソフトウェアが主導するのでもなく、ハードウェアと連関するなかで場を持ったソフトウェアが、モノと連関するヒトと連関していき、あたらしい体験をつくる。その結果として、ハードウェアだけでなくOSというソフトウェアの部分にも触れているような体験が生まれるのである。ソフトウェアを覆っていたハードウェアをソフトウェアが覆いはじめ、ソフトウェアとハードウェアとが一つのサーフェイスになっていった。
メタマテリアル化するサーフェイス
椅子やハンマーといったプリミティブな道具ではそのもの全体が利用者との接点になるが、構造が複雑になり内部の機構と外装が分離して、操作部が独立して設計されるようになると、そこにユーザーインターフェースという概念が出現する。抽象物を成分とするソフトウェアにおいては、その働きと我々のファジーな認知を仲介するものとして、ユーザーインターフェースの役割が特に重要になる。
コンピュータを使えば人の五感に向けたフィードバックを動的に作り出すことができるので、ユーザーインターフェースの独立性は一層増す。道具の内部機構に対してユーザーインターフェースが独立するということは、意味空間を自由に作れるということである。上野学「エントロピーとデザイン」
コンピュータが現れたことで、モノと行為とのあいだに「インターフェイス」という概念が現れた。しかし、フラットデザインとマテリアルデザインの試みは、道具の内部機構と外装とを統合してサーフェイスとするものである。スキューモーフィズムですでにインターフェイスはサーフェイスになっていたが、そこでは物理世界の表皮がピクセルに貼り付けられており、ソフトウェアとハードウェアの連関というよりは、ソフトウェアがハードウェアを通り越して、物理世界そのものに意味を求めたと言えるだろう。ヒトの理解のため、ソフトウェアは一足飛びに物理空間を外装としたのである。
けれど、フラットデザインとマテリアルデザインでは、ハードウェアとソフトウェアとのあいだに意味の連関がつくられるため、スキューモーフィズムでソフトウェアに外装として採用された物理空間はスマートフォンのサーフェイスに入り込めない。スマートフォンは物理空間と座標変換可能な二重化した外装を持つのではなく、ハードウェアとの連関のなかでソフトウェアがハードウェアを包み込み、一つのサーフェイスになる。そして、スマートフォンは物理世界におけるあたらしいプリミティブなモノとなった。
その代償として、インターフェイスの独立性はなくなり、意味空間が自由につくれなくなる。これまでは、ハードウェアを内部機構とする外装としてのソフトウェアがあり、外装としてのソフトウェアもまた内部機構と外装とに分かれ、必要に応じて外装としてのハードウェアをつくり変えた。そして、ソフトウェアとハードウェアはどちらも互いの内部機構になり、外装となることを繰り返してきた。それはインターフェイスが持つ独立性ゆえであった。しかし、フラットデザインとマテリアルデザインは、ソフトウェアがハードウェアとの連関のなかで、その独立性を放棄してまで、ハードウェアを覆うサーフェイスとなったのである。ハードウェアとの連関から生まれるソフトウェアがサーフェイスとなっているモノは、これまでとは異なる意味でのプリミティブなモノとなっている。それは、その自由さゆえに位置付けが難しかったソフトウェアが、ヒトとモノとの連関のなかに確かな場を得たはじめてのモノなのである。
ハードウェア、ヒトとの連関においてソフトウェアに空け渡された場は、もちろん物理空間のなかにあり、またコンピュータネットワークにおけるノードでもある。ソフトウェアに空けられた場には、さまざまな空間や場が重なり合っている。空間と場の重なりのなかで、ソフトウェアはハードウェアとの接着において、ヒトの行為とその可能性をこれまでにないかたちで反射、吸収、屈折していくあらたなサーフェイスとなっている。それは「メタマテリアル」とでも呼べるような新奇の擬似的なモノだろう。
メタマテリアルとは、ナノサイズの金属構造を用いて人工的に新奇な電磁気学的特性を付加した擬似物質です。メタマテリアルのメタは「超」を意味する接頭語です。メタマテリアルを利用すると、光の磁場成分に直接応答する物質など、自然界に存在する物質にはあり得ない特性を持つ物質を作り出すことができます。田中拓男「知っておきたいキーワード:メタマテリアル」
ハードウェアとソフトウェアとが意味の連関を持つことで、ソフトウェアに場が付与されて「世界適合性」が生まれる。それは、ガラスとピクセルとのあいだが接着され、意味のある「透き間」として実体化し、ヒトの行為の反射率を変更する一つのメタマテリアルとなることなのである。このメタマテリアルは、物理世界とコンピュータの世界という二つの原理を重ね合わせる。そこでは、計算と光、光とガラスが重なり合い、さらにこの二つの重ね合わせ自体が重ね合わされて、あらたな角度でヒトの行為を反射し続ける。
今、私たちのまわりにある壁や天井は、突然消えたりせず、私たちが生きるスパンよりも長くこの環境に存在する持続性があるためにリアリティを持つ。「リアリティ」という言葉は、コンピュータのスクリーン上にいかに本物と同じような見た目の質感をもたらすかを言うことが多いが、持続性に関するリアリティを忘れてはいけない。おそらくリアリティの非常に重要な要素に「持続性」があり、持続性がないことが行為の可能性へも影響し、さらにその点においてもリアリティが低下する。したがって、ディスプレイ上でビットとしての情報提示であっても、持続性による行為の可能性を考えることで、リアリティは確保できるはずだ。
少しまとめると、ものづくり、その「物」という言い方が体験にとっては適切ではなく、持続で捉えるべきだということだ。そしてリアリティは物質性ではなく持続性であるということだ。数百年「物」という状態を当たり前のこととして設計してきたわけだが、ハード、ソフト、ネットを目の前に、まず「物」の定義にメスを入れるべき時ではないだろうか。渡邊恵太『融けるデザイン』
場を与えられたソフトウェアはメタマテリアルのようにモノの性質を変えるだけでなく、その概念を変えていく。ハードウェアとの意味の連関を持ったソフトウェアは、渡邊が指摘するような「持続性」を持つようになったと言える。ハードウェアの上に成立していたソフトウェアがハードウェアを包み込むサーフェイスとなることで、モノと情報とが持続的に絡み合う場が生まれ、マテリアルデザインにおける「厚みを持ったピクセル」のように、これまでにない「モノ」がディスプレイの上に存在するようになった。そして、そのあらたな「モノ」がヒトの行為の可能性を開き、これまでになかった行為が世界に適合するかたちで配置されていくのである。
接着剤としてのソフトウェア
かつては、一つの道具の統一性が問題を提起していた。諸々の精神と創造者たちが、彫像の素材のうちにイデアを記入したという意味において、彫像に関する技術が彼らの役に立っていた。形相が、それによって生気を与えられていた質料のうちに降下するという、製作に関するアリストテレスの概念が取り上げ直されていた。イデアが優位を占めていた。本書は、アリストテレスが考慮した四原因のほかに、五番目の要因を考慮せねばならないのでは、と問うてさえいるのだ。それは、非常に巧みに接着された再編成を可能にするアセンブラあるいは網目(レティキュレール)である(飛行機の翼、タービン、スポーツカーなど)。重要なものはなんだろうか。それは、組み立て装置(モンタージュ)を可能にするものである。現代の接着は、「物体」の構想および生産と同時に「物体」という観念をも刷新するだろう。
反対の作業は、結合ではなく、解きほぐす、つまり分割し分離する —— これらは破壊だろう —— のではなく、引き伸ばしたり延長することに専念する(諸々のフィルム)。物質的実体は、引き裂かれ、分裂させられ、その構成要素へと分解されてはならず、同時に薄くなるまで伸ばされ、広げられることに耐えねばらない。フランソワ・ダゴニェ『ネオ唯物論』
モノを持続で捉えるということは、モノが統一的な存在である必要はないことを示している。それは、ダゴニェが述べる「非常に巧みに接着された再編成を可能にするアセンブラあるいは網目(レティキュレール)」としてモノを考えることであり、そこで「接着剤」の役割を果たすのがソフトウェアなのである。ソフトウェアは複数のハードウェアを接着しながら、あたらしいモノをつくり、そのサーフェイスとなっていく。そして、モノのサーフェイスとなったソフトウェアは、ヒトの行為の可能性も開いていく。
次のように言った方がいいのかもしれない。ソフトウェアがハードウェアを接着しながら、一つのサーフェイスをつくる。それはヒトがいない場合も、すでに接着している。そこにヒトが入り込み、ソフトウェア—ヒト、ハードウェア—ヒトと接着面を増やしていく。サーフェイスが増えることで、接着の自由度は上がる。ソフトウェアとハードウェアとの接着を薄く引き延ばすのが、ヒトの行為である。ヒトはハードウェアに包まれたソフトウェアがつくるモノのサーフェイスを行為で引き延ばして、別のサーフェイスとの接着を引き起こすのである。
対象(オブジェクト)とは、経験された内容というあらかじめあたえられた表面を、人間がかき集めることによってつくりだされた幻想にすぎないというのだ。これに対してわたしは、実在はオブジェクト指向的であると主張する。実在を構成するのは、もろもろの実体以外のなにものでもない。それらは、たんなる物体のような硬い塊ではなく、不気味さを少々まとった怪奇的な実体なのである。事物を、その特性や、他のものに対する影響へと還元することを辞める時、実在との接触がはじまる。グレアム・ハーマン「現象学のホラーについて」
ソフトウェアという接着剤が、ハードウェアを何かに還元することなく接着していく。ハーマンがオブジェクト指向存在論で指摘するように、オブジェクトが背後に退いて触れ得ないものとなることは、ソフトウェアが表面に出るには好都合だと考えられる。オブジェクトそのものに手を突っ込めなくても、接着剤として機能するソフトウェアが接着する複数のハードウェアとそこに生まれるサーフェイスによって、オブジェクトを改変することができるのではないだろうか。ハードウェアはソフトウェアに接着されながら背後に退いていくと同時に、ソフトウェアがかき集めたハードウェアとともに表面を構成するようになる。ソフトウェアは、複数のハードウェアを接着し続け、一つのサーフェイスをつくっていく。ハーマンが言う幻想にすぎないオブジェクトを、ソフトウェアはハードウェアを接着してつくるサーフェイスとして実在させるのである。
ソフトウェアが接着剤として機能することで、ハードウェアをかき集めることが可能になった。接着したもの/接着されたものは、そこで一つのサーフェイスをつくる。これからのモノのデザインは、ソフトウェアによる接着をデザインすることであり、周囲のあらゆるオブジェクトをいかに引き寄せるかをデザインすることである。だから、まずはソフトウェアが接着面を形成するためにモノとのあいだに意味の連関をつくり,一つの場を確保しなければならない。そのあらたに開いた場において、ソフトウェアはあらゆるオブジェクトを接着しながら一つのハードウェアをつくり、そのサーフェイスを覆い続けるのである。
連載記事「インターフェイスを読む」
- #1 最小化するヒトの行為とあらたな手
- #2 スケッチパッドで「合生」される世界
- #3 GUIが折り重ねる「イメージの操作/シンボルの生成」
- #4 インターフェイスからサーフェイスへ — スキューモーフィズム再考
透き間を実体化するデスクトップメタファー
二つの平面を見通す透視仮説と重なるウィンドウによって、ディスプレイにフィクショナルな探索空間が生まれ、イメージは見るだけのものでなくなった。ヒトはコンピュータに行為を委譲して、マウスとカーソルを用いて「見て指差す」ことで、行為を遂行していく。ヒトはマウスの先にあるカーソルとしてディスプレイ平面にスルスルと入り込み、ウィンドウやアイコンなどのオブジェクトを操作しながら、コンピュータとともに合生的行為を生み出すようになった。
ヒトはハードウェアとソフトウェアという二つの層の重なり合いに対応するマウスとカーソルを使い、重なるウィンドウをかき分けて情報を探索しながら、ディスプレイのXYグリッドに基づくフィクションとしての空間のなかで行為を遂行している。ウィンドウとウィンドウとのあいだ、ウィンドウとデスクトップとのあいだに隙間はないけれど、それらは重なり合っているものとして処理される。ウィンドウの重なりを示すために、黒色のピクセルで「影」をつくるなどしてフィクショナルに処理された隙間を、「透き間」と呼びたい。透き間は確固としたモノではなく、影のようにモノに依存した存在である。影はモノがなくなれば消えるけれど、透き間はモノというハードウェアの有無だけでなく、ソフトウェアによって描写が変更されるだけでも消えてしまうため、影よりも儚い存在である。
影よりも存在があやふやな透き間をはじめとするディスプレイ上のイメージを、操作可能な確固とした存在にしていくために「デスクトップメタファー」が導入された。デスクトップメタファーは、物理空間で培ったヒトの身体感覚をコンピュータの論理空間に直結したディスプレイの平面に合わせたかたちで導入し、XYグリッドに表示される透き間などの存在に実体性を与えていく。しかし、それはメタファーによって捏造された存在感である。
言語学者のジョージ・レイコフと哲学者のマーク・ジョンソンは、メタファーが身体経験に基づくイメージ・スキーマに基づいているという「認知意味論」を提唱した。認知意味論はメタファーが単に状態が似ているものを結びつけるのではなく、ヒトの身体経験に深く根ざしていると指摘して、メタファーの考え方を大きく変えた。認知意味論に基づいてデスクトップメタファーを考えてみると、コンピュータの論理空間を単に馴染み深いオフィス空間に置き換えて、コンピュータにはじめて触れるユーザの理解を促したというものではなくなってくる。デスクトップメタファーは、何よりもまず物理世界由来の身体感覚やイメージ・スキーマを、コンピュータの論理空間と直結するディスプレイのXYグリッドに導入したものなのである。
デスクトップメタファー以前に、コンピュータと向かい合うヒトの行為はボタンを押すというかたちに最小化されていた。それはヒトの行為、特に手が可能にする行為の複雑さを排除して、ヒトを回路内のスイッチと同じシンプルにオンオフを行う存在にする必要があったからである。ヒトはコンピュータとともに構成する回路でオンオフし続けるスイッチの一つとなり、ヒトが持つ行為の複雑さはアルゴリズムに委譲されていった。そして、アルゴリズムが電気の力に由来する「奇妙な融通性」を用いて、数を自在に操作しながら、ヒトとコンピュータとのあいだにあらたな合生的行為をつくっていく。その時、ヒトはディスプレイ上のイメージの一つであるカーソルになって、他のイメージ群とともに行為を遂行している。ディスプレイ上のイメージで行為が遂行されているあいだ、マウスと触れ合っている手を起点とする身体感覚がヒトに与えられ続ける。
アルゴリズムに委譲される行為がボタンを押すというかたちで最小化されているため、マウスに由来する身体感覚は、ディスプレイ上で効果が最大化するように調整されたイメージとの関係を感じにくいものになった。けれど、ヒトがマウスを介してイメージを操作しているという感覚は、操作のあいだ常に存在し続けている。最小化された行為とディスプレイのXYグリッドが示すイメージとのあいだにはズレが生じている。
デスクトップメタファーは、ヒトの手とマウスとによってイメージを操作している際に発生する身体感覚をまとめあげて増幅し、「私たちの経験と理解(私たちが「世界をわがものとする」仕方)が整合的で意味あるものとして構造化」していく。そして、行為を委譲されたアルゴリズムが、マウスというモノを掴んでいるという感覚に基づいたイメージを、ディスプレイのXYグリッドに表示する。その結果、マウスによってディスプレイのXYグリッドに持ち込まれた身体感覚と、ディスプレイ上のイメージが生みだす意味のあいだに生じているズレが埋められる。デスクトップメタファーは、マウスを操作している際にコンピュータに入り込んだ身体経験を有効にまとめあげる視覚的表現であり、ここでは物理世界に基づくヒトの身体感覚とコンピュータの論理世界とがスムーズに重ね合わせられているのである。
ただし、デスクトップメタファーによる重ね合わせは、あくまでもフィクショナルなものである。ヒトの手の感覚は、カーソルという物理世界に存在しないフィクショナルな存在に集約されて、アルゴリズムを介してディスプレイで行為を遂行するようになる。ここで注目したいのは、ヒトが特に意識することなく、XYグリッドでの位置情報を示す矢印というあたらしい身体のかたちになっている点である。カーソルはメタファーによって実体を与えられた透き間などの周囲のフィクショナルイメージとは関係なく、ヒトと密接に重ね合わされて強烈な自己帰属感を発生させる。
カーソルが特別なのは、マウスとの「動かし」と画面の中の動きが連動し、自己帰属感が立ち上がるからである。カーソルまでが自己の一部となることで、人はカーソルを意識しなくなり、対象のほうを意識する、つまりカーソルは透明化する。だからこそカーソルの登場は「直接操作」を実現し、自己が画面の中にまで入り込んで情報に直接触れているかのような感覚へと辿り着く。カーソルはバーチャルな身体なのではなく、連動性という点においては実世界の自己の知覚原理と同じで「リアル」である。渡邊恵太『融けるデザイン』
カーソルはフィクショナルなイメージであるけれど、渡邊が指摘するように、ヒトと連動しながらその感覚を集約する特異点というかたちで物理世界と否応なしに重なり合っている存在でもある。そのため、ヒトの意識の最前面にカーソルがあり、コンピュータがヒトに向かい合う最前面にもカーソルがあるかたちになり、この二つの最前面の重なり合いがヒトとコンピュータとのインターフェイスをつくるようになる。つまり、デスクトップメタファーは透き間が生み出すフィクショナルな重なりにメタファーを用いて物理空間でヒトが培った感覚を導入し、物理世界と密着した特異点としてのカーソルが、その空間を自在に動ける探索空間をディスプレイのXYグリッドにつくったのである。
デスクトップメタファーによって、カーソルを中心としたフィクションとしての探索空間が、ディスプレイの解像度という意味ではなく、ヒトの身体感覚とのつながりによって「豊か」になっていった。だからこそ、インターフェイスは「直感的」であることが求められた。透き間を有するデスクトップは、もはや勝手を知らないウィンドウの重なりではなく、フィクショナルでありながらもヒトが熟知した物理空間に準拠した空間になったのである。
表皮としてのスキューモーフィズム
この状況を大きく変えたのが、タッチ型インターフェイスを採用したiPhoneであった。iPhoneでは何をタッチしても、ガラスに触れているにすぎない。ヒトがマウスとカーソルとで培ってきたアルゴリズムに行為を委譲する感覚はゼロになるわけではないけれど、別のかたちになっていく。それは身体と物理世界との関係、物理世界に置かれたオブジェクト同士の関係に近くなる。ヒトは知らないうちにカーソルという別の身体を失い、ディスプレイのXYグリッドを探索できなくなり、単にガラスに触れることのみが許されるようになった。
マウスの先のカーソルを喪失したことにより、ヒトの身体感覚はコンピュータと共有していた平面に侵入することができなくなる。そして、ディスプレイのXYグリッドから感覚を締め出されたからこそ、タッチ型インターフェイスではスキューモーフィズムが強調されたのである。ディスプレイの解像度が上がってきたことを利用して、ディスプレイ内を物理世界に似せてしまえば、見ることで触れることを補って、XYグリッドを探索できるからである。
マウスとカーソルとの連動で実装された最小化された行為では、ヒトはカーソルとなってイメージに触れていたため、目に見えるイメージの質感は関係ないものであった。けれど、ディスプレイから触れることが締め出されると同時に、イメージに直接触れるかのようになったiPhoneでは、イメージの質感が重要になってくる。インターフェイスの質感表現を追求してきたウェブデザイナーの中村勇吾は、次のように述べている。
だんだんとスクリーンの中と外の境界が曖昧になってきていると思います。また、「触れる」という身体的な行為がプロダクトやスクリーンと非常に密接になってきたので、スクリーン上のオブジェクトの質感をどうデザインするかというのが、より重要になってきていると思いますね。2012年頃までは、Apple製品を中心に、スクリーン上のボタンにリアルな影をつけたり、カレンダーアプリでリアルな紙をめくるような描写をしたりするスキューモーフィズムのデザインが特徴的でした。スクリーンの中の仮想的な世界にあるUIの「見え」を、より現実のモノっぽく描写し、操作のヒントとなる比喩・メタファーとして機能させていくことが有効な手段だったんです。だた、だんだんとスマートフォンの小さなスクリーンの中にそういったリアルっぽい絵で満たされたごつい世界が構築されている状態がしんどくなってきたんでしょうかね。スクリーンの中に仮想的な別世界があるのではなく、プロダクトの表皮の延長としてスクリーンがあり、それは物理的な表皮とは違った「アップデート可能な表皮」であるとする、という捉え方が浸透した結果、現在のような、いわゆる「フラットデザイン」のスタイルが主流になってきたのだと思います。中村勇吾「動きから「質感」を生み出すUIデザイン」
中村が指摘するように、スキューモーフィズムはデスクトップメタファーの一種と考えられている。けれど、スキューモーフィズムはコンピュータの向上したグラフィック性能を活かして、現実世界を直接的に高解像度化したディスプレイに移すという点で、マウスに基づいた身体経験をフィクショナルに反映させるデスクトップメタファーとは異なるものと考えられる。マウスに基づく身体感覚は限定的であるがゆえに、ディスプレイのXYグリッドが表示するフィクションとしてのイメージ群に反映させることができていた。
しかし、ディスプレイが高解像度になるにつれて、マウスとカーソルとが指差す先が物理世界そのものを表現するようになった。この時点で、ヒトはディスプレイのXYグリッドがつくるピクセルの世界から締め出され始めていたのである。スキューモーフィズムは、マウスとカーソルとが最小化した行為に合わせメタファーの力を借りて制作した世界ではなく、もう一つの複雑な物理世界なのである。しかし、この変化はパソコンがマウスを標準装備としている限りは顕在化しなかった。なぜなら、カーソルという特異点がある平面がインターフェイスとなって、ヒトとコンピュータとを結びつけていたからである。
デスクトップメタファーからスキューモーフィズムへの移行を決定的にし、ヒトとコンピュータの関係を一変させたのがiPhoneであった。iPhoneは「指」をポインティングデバイスとして使用したため、カーソルが画面上から消えた。ヒトはディスプレイを「指差す」ために、カーソルというフィクショナルな存在ではなく、文字通り「指」を使うようになった。渡邊は、iPhoneで「指」はカーソルではなくマウスのような役割を担うものであり、iPhoneでカーソルの役割をしているのは「画面全体」であると指摘する。
iPhoneの場合、カーソルがない。だから指がカーソルに思うかもしれない。しかし指はどちらかといえばマウスの位置づけで、カーソルではない。ではカーソルの代わりは何か。ここで重要なのは、カーソルということではなく、iPhoneでパソコンのカーソル並に身体の動きに連動している部分は何かということだ。
それは「画面全体」である。たとえばiPhoneのホーム画面は指に追従し、アプリケーションリストが左右に移動する。ウェブブラウザでは画面全体が指に追従しスクロールする。カーソルはないが、カーソルと同じレベルでiPhoneの画面は非常になめらかに連動している。この連動が画面の中と指を接続し、自己帰属感が生起して身体の一部となり、ハイデガー的に言えば、道具的存在になるのだ。渡邊恵太『融けるデザイン』
渡邊による「画面全体がカーソル」と中村による「アップデート可能な表皮」とを合わせて考えてみたい。iPhoneの登場によって、ヒトとコンピュータを結びつけるインターフェイスとして特権的な平面上にあったカーソルが消失して、コンピュータと直結したディスプレイのXYグリッド自体がカーソルとなる。そこで、ヒトの手はマウスという物理世界をXYグリッドに区切る装置の役割を担うことになった。そこで強調されたのが、物理世界のモノをディスプレイに視覚的表現としてそっくりそのまま移そうとするスキューモーフィズムであった。そして、スキューモーフィズムのもとで「スクリーンの中と外の境界が曖昧になって」、ディスプレイのイメージが「オブジェクト」として認識されはじめ、マウスが物理世界の表面を探索したように、ヒトもディスプレイに表現された物理世界の「表皮」を指差す。そして、ヒトが物理世界のオブジェクトを操作するようにディスプレイのオブジェクトを操作すると、画面全体が連動してヒトと直接つながるのである。
iPhoneでは、カーソルが示していたようなヒトとコンピュータとが共有する平面、つまり、インターフェイスがなくなっている。スキューモーフィズムの目的は、マウスとデスクトップメタファーとがつくりあげたフィクショナルな身体感覚に縛られることなく、物理世界とディスプレイをそっくりそのままつなぐあたらしいパラダイムに基づく「ごつい世界」の構築であったと言える。だから、スキューモーフィズムはカーソルを中心にしてつくられたフィクショナルな身体感覚に限定されない「物理世界」から剥ぎ取った「表皮」を、ヒトとコンピュータとのあいだにある「画面全体」に取り込んでいったのである。
スキューモーフィズムとともに、ヒトは物理世界から剥ぎ取った表皮を画面全体に表示するiPhoneをよく見て、指で操作することになった。このとき、ディスプレイからカーソルがなくなるだけでなく、ヒトとディスプレイとの位置関係も変化している。エキソニモの千房けん輔は、ブログで次のように書いている。
でもそのことよりも、なんか重要な気がするのが、
スマフォのある位置だ。ポケットからサッと出して、手のひらの上、もしくは目の前の景色の前、僕と景色の間に差し込まれるスクリーン。僕と世界の間。
スマフォ(ネット機能があったガラケーやDSなどの通信デバイスも含めていいのかも)より以前のスクリーンは、据え置きモニタだったし、ラップトップになって、より僕に近づいてきたけど、やっぱり“あちら側”にあった。
(自分)→→→→→→→ (世界)
だとしたら
(自分)→→→→→→→(スクリーン/世界)
スクリーン(=インターネット)は世界の側にあったと思う。
ところがスマフォ以降ではこうなった
(自分)→(スクリーン)→(世界)
自分と世界の間にスクリーンが差し込まれる。
いや、“手”という極私的なモノのこちら側という意味では
(自分/スクリーン)→→(世界)
かもしれない。
そしてスクリーンに映されるのは「ラーメン食べた」とか言ってる、知り合いの状況=別の世界なのだ。つまり
(自分(別の世界))→→(世界)
目の前とシンクロしない世界が自分の中に自由自在に入り込んでくる。
これは世界の構造が変わって来ていると言えるんじゃないか。
なんとなく、この変革は想像以上にすごいことなんじゃないかと感じている。
どこにいても買い物できるーとか、上に書いたような便利さとかなんかじゃない、
はっきりとはわからないけど、写真や映像の発明で、人類の世界認識が大きく変わったような、いや、それ以上の変革なんじゃないかと、個人的には思っている。
千房けん輔「無題 — センボーのブログ」
ディスプレイからカーソルをなくしたスマートフォンは、スキューモーフィズムという物理世界の表皮をディスプレイに表示しながら、ヒトと物理世界とのあいだに入り込んできた。ディスプレイが表示する世界は、ヒトのカーソルに集約されていた身体感覚を締め出した物理世界の表皮を、物理世界の手前に位置する画面全体に提示する。ヒトはスマートフォンの画面を見ているけれど、それはより大きな枠組みである物理世界とヒトとのあいだに差し込まれたものである。ヒトと物理世界とのあいだで「目の前とシンクロしない世界が自分の中に自由自在に入り込んでくる」という状況が生じた。ヒトが見る世界が、前景に身体感覚を締め出したXYグリッド、後景に物理世界というかたちで二重化してしまったのである。スキューモーフィズムはスマートフォンによって、物理世界を表皮とその奥というかたちで二重化するために用いられたとも考えられる。
スキューモーフィズムは物理世界の表皮を剥ぎ取って、ディスプレイのXYグリッドに移植した。この移植は、ヒトと物理世界とのあいだに入り込んでくるスマートフォンというデバイスが一般化するために必要だったと考えられる。物理世界とのあいだに、いきなりツルツルピカピカのフラットデザインが挿入されたとしたら、そこには大きな拒否反応があっただろう。しかし、スキューモーフィズムはすぐにフラットデザインに変わってしまう。それは、スキューモーフィズムが物理世界の表皮であるからこそ「ディスプレイの世界は現実とは異なるものだ」ということを明らかにしてしまったからである。グラフィックがいかにリッチになろうとも、それはピクセルの光であり、指が触れるのはガラスでしかない。かつて、ヒトはカーソルというインターフェイスを通じてコンピュータと向かい合っていた。けれど、いまヒトはスマートフォンという極私的なモノを手に物理世界のなかにいて、そこにはカーソルもなく画面全体がヒトと連動して、身体の一部のようになっている。つまり、ヒトと物理世界とのあいだには、光り輝く画面を示す一枚の薄い板があるだけなのである。
インターフェイスからサーフェイスへ
大林寛は「インターフェース、その混血した言語性」において、インターフェイスモデルの変遷をまとめている。ヒトとコンピュータとのあいだに平らな板のインターフェイスが置かれた前認知科学的な単純モデル(1)から、ヒトとコンピュータとがそれぞれの行為を思案するメンタルモデル(2)を経て、ヒトとコンピュータとのあいだに存在する空間をインターフェイスとする空間モデル(3)に至り、最終的にはオブジェクトにファサードが密着したファサードモデル(4)を提案した。
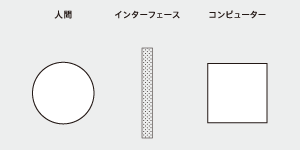 (1)前認知科学的なモデル
(1)前認知科学的なモデル
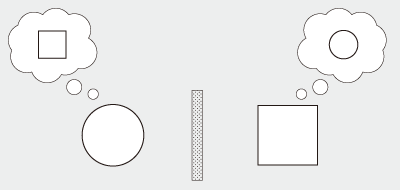 (2)メンタルモデル
(2)メンタルモデル
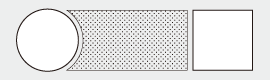 (3)空間モデル
(3)空間モデル
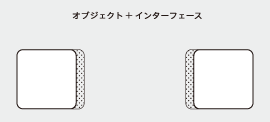 (4)ファサードモデル
(4)ファサードモデル
わたしたちはインターフェースを通じて交信しながら、実際にはその向こうの対象と交流している。そこでコミュニケーションが成立するのは、対象の知性を信頼しているからだろう。その信頼が大きければ大きいほど、インターフェースは透明化する。これは没入というよりも、すこし前の現実がより「もっともらしい」ものへと更新される感覚に近い。
逆に、コミュニケーションする相手の様子がいつもと違うとき、わたしたちは顔や受話器といったインターフェースに注意を向ける。コミュニケーションの信頼が保証されない事態になって、はじめてインターフェースはその姿を見せるのだ。これがインターフェースの見え隠れする質感になっている。
そう考えていくと、先ほど見てきた「ユーザーインターフェース」のモデルのように、インターフェースは二者の間に置かれてもいないし、共通で単一のインターフェースを通じてコミュニケーションしているわけでもない。インターフェースは、コミュニケーションにおいて指向すべき「ファサード」のようなものとして、それぞれのオブジェクトに備わっている。大林寛「インターフェース、その混血した言語性」
大林によるオブジェクトのファサードとしてのインターフェイスモデルは、フィクショナルなカーソル的身体以後のインターフェイスを考えるヒントを示している。ここで注目したいのは、インターフェイスとしてヒトとコンピュータとのあいだに平坦な板を置くにしろ、そのあいだの空間そのものをインターフェイスだとしてしまうにしろ、これら二つのモデルにおいて、ヒトとコンピュータとが同一のインターフェイスに触れることが前提となっている点である。板と空間とで形状が違うけれど、板がヒトとコンピュータ双方に伸びたのが空間モデルと捉えるとわかりやすいかもしれない。
これらのモデルは、デスクトップメタファーによってヒトとコンピュータがカーソル平面を共有したことに強い影響を受けていると考えられる。ヒトとコンピュータとのあいだには、カーソルという双方の最前面にある存在が重なり合った平面がインターフェイスとして存在し、そこにマウスに基づく身体感覚とメタファーから構成されるフィクショナルな探索平面ができあがっていたからである。それは、ディスプレイの解像度が高くなり、平面的な表現に立体的な質感が与えられて探索空間になったとしても変わりない。
しかし、スキューモーフィズムはディスプレイからマウスに由来するフィクショナルなヒトの身体感覚を締め出すものであった。マウスとカーソルを用いている場合、スキューモーフィズムはデスクトップメタファーの延長として考えられていた。それゆえに、空間モデルでスキューモーフィズムを考えると、ディスプレイに映る空間とヒトの身体の形態がフィットしないがゆえに、破綻していると考えられることもあるだろう。しかし、スキューモーフィズムは画面全体を一つの表皮としていると考えた方がいい。そのため、スキューモーフィズムは空間モデルではなく、大林のファサードモデルで考えるべきなのである。
大林が考えるファサードモデルでは「ヒト」と「コンピュータ」という言葉ではなく、それらは単に「オブジェクト」と言われている。ここではすでに、ヒトとコンピュータとが各々属する二つの世界は重なり合って一つの世界となっている。物理世界のなかにヒトと一つの表皮としてのディスプレイが向かい合っており、それらはいずれも独立したオブジェクトなのである。そのため、空間モデルのように互いがフィットする形状を示す必要はない。
大林は「インターフェースは二者の間に置かれてもいないし、共通で単一のインターフェースを通じてコミュニケーションしているわけでもない」と書く。この一文は、デスクトップメタファーに基づいたインターフェイスモデルを破棄している。ヒトとコンピュータという二つの存在をカーソル平面で重ね合わせて共有できる単一の平面のみをインターフェイスとして捉えてきたが、iPhone以後は物理世界のなかで向かい合うオブジェクトが個々に持つファサードを「インターフェイス」と捉える必要が出てきたのである。スキューモーフィズムを採用したスマートフォンでは、ディスプレイが示すオブジェクトの質感とガラスの質感との齟齬が問題となったけれど、インターフェイスを一つのファサードとして考えると大きな問題ではない。むしろ、二つのオブジェクトの質感が齟齬を示すことが重要となってきているのである。
大林はオブジェクトに属する「インターフェイス」を「ファサード」と呼ぶが、私はそれを中村の「表皮」、そして「フェイス」つながりで「サーフェイス」と呼びたい。ブランデン・フックウェイは『Interface』で、「インターフェイス」と「サーフェイス」との違いを次のように述べている。
インターフェイスは主に事物または条件を参照するのではなく、事物または条件間の関係、または関係によって生成される状態を主に参照するという点で表面と区別することができる。Branden Hookway “Interface”
フックウェイによれば、二つのものの関係性を扱うのがインターフェイスであり、一つの事物を参照するのがサーフェイスということになる。サーフェイスにはモノが置かれているが、それは単に表面に置かれたものであって、二つの以上のモノの関係を扱うものではない。フックウェイはインターフェイスが示す二つ以上のモノの関係性を考察するが、インターフェイスはもはや二つ以上のモノの関係性が重なり合ったものではなくなりつつある。大林のファサードモデルが示すように、そこにはまずモノのサーフェイスがあるのみなのである。二つのオブジェクトの関係は確かにある。しかし、それはこれまで「インターフェイス」という言葉が示してきた密接な関係とは異なり始めている。オブジェクトはもっと孤独である。オブジェクトは他のオブジェクトと常に密接に触れ合っているわけではない。物理世界とそのなかのオブジェクトは互いに離れていて、時にまた触れ合い、サーフェイスがインターフェイスになる程度なのではないだろうか。
フックウェイは「インターフェイスはそれ自体がサーフェイスではないが、サーフェイスの生産者である可能性がある」と指摘しているが、ヒトと連動するカーソルによって重ね合わされた平面でハードウェアとソフトウェアという二つの関係を扱っていたインターフェイス自体が、ハードとソフトを個別の存在として含んだ上で表裏一体化して、一つのサーフェイスとなっていると考えられる。マウスとカーソルとの連動によって重ね合わされた平面がインターフェイスとして機能し、そこに重なるウィンドウがつくるフィクショナルな重なりである透き間などが生まれてきた。しかし、それらがスマートフォンというハードとソフトを表裏一体化する一つのサーフェイスに重ね合わされて、個別の存在としてヒトと対峙するようになった。
iPhoneはマウスとキーボードといったインターフェイスをタッチパネルに置き換えただけではなく、インターフェイスをサーフェイスにした。ディスプレイというサーフェイスをそのままインターフェイスにした際に、インターフェイスはサーフェイスになった。だから、iPhoneのディスプレイではカーソルがなくなった代わりに画面全体がカーソルとなり、マウスの代わりとなったヒトの指はガラスの表面に触れ続けるだけで、決してガラスの向こう側に侵入することはできないのである。ヒトとコンピュータとは個別のオブジェクトとして存在している。ヒトはコンピュータに向こうの世界を見るのではなく、物理世界とのあいだにiPhoneを差し込むことで、ヒトとiPhoneと物理世界とが重なり合ったのである。
物理世界という大きな枠組みのなかで、ヒトとコンピュータとは個別のオブジェクトとして存在するようになった。それは、ハードウェアとソフトウェアの重なりの上につくられた透き間が物理空間に滲み出した結果である。もともとは実体のない透き間にデスクトップメタファーで感覚が付与されて、その擬似的な感覚が物理世界に滲み出てきたのである。そして、透き間は拡大し、ヒトとコンピュータとを呑み込み、それぞれを単体のオブジェクトとして扱うことができる世界になったのである。そこでは、大林のモデルのようにヒトもコンピュータもサーフェイスで向かい合っている。サーフェイスは存在の境界であり、他者の侵入を拒絶する。デスクトップメタファーでコンピュータの論理空間とディスプレイの平面に入り込んでいたヒトの感覚は、タッチ型インターフェイスというサーフェイスから締め出される。かつて仮想世界と言われた一つの世界が物理世界と重なり合って、より大きな枠組みとなっている。物理世界と仮想世界とが否応なしに重なり合った世界では、ヒトもコンピュータも単にオブジェクトとして扱われる。そこではオブジェクトにファサード、サーフェイス=表面がつけられている。これらのサーフェイスのあいだを最小化した行為が行き来しているのである。
インタラクションからリフレクション(反射)へ
大林はヒトとモノとがコミュニケーションを行うとしているけれど、「共通で単一のインターフェース」を破棄した時点で、コミュニケーションもまた消失したと考えるのがいいのではないだろうか。渡邊恵太は『融けるデザイン』で、モノの反射について次のように書いている。
UIの未来についても「現在2Dだから次は3Dだ」と考えるのは軽率な発想である。たとえばiPhoneはその点もよくわきまえている。それは「パララックス(視差効果)」という手法に現れている。加速度センサを利用し、iPhoneを傾けた向きに応じて2次元の画像を少しだけ動かし、手前にある文字やアイコンを浮かせて見せ、平面であっても奥行きを感じさせる方法だ。しかも、端末の傾きと連動させている点は賢い限りである。なぜ賢いかといえば、iPhoneへの自己帰属感を高めるからである。個人的には動き方はまだ改善の余地がある印象を持つし、利用者からすればバッテリーがもったいないという印象を持つ人もいるかもしれない。しかしここには大きな可能性がある。
それはバーチャルな質感表現だ。あるものを手に持ち、傾けると、光の反射によって「材質の質感」がわかるわけだが、それを画面の中でもできる可能性を示したのだ。ガラスのコップやペットボトルを持ってみてほしい。そして少し動かしてみてほしい。そうすると、その物はユニークに反射し、その反射部分がユニークに動く。その反射の動きは手の動かしに連動するわけだから、その反射による光沢感の変化からも自己帰属感が生まれるはずだ。実世界であればそれは当然過ぎるし、コップは手に持っているため自己に帰属しているのは当たり前の用に感じてしまうかもしれないが、ピカピカした質感やざらざらした質感は、自分が持って動かすことによってその動きにユニークに対応するため、「自分が持っている感」の生起に一役買っていると言える。渡邊恵太『融けるデザイン』
ヒトもコンピュータもオブジェクトであるならば、そして、そのあいだに共通のインターフェイスがないのであれば、個別のサーフェイスを通じて、行為を反射し合っているのみと考えたほうがいいのではないだろうか。物理世界のなかで当然過ぎる反射という現象が、自己帰属感を高める要素になっているという渡邊の指摘は、ヒトとコンピュータとのあいだをインターフェイスではなく、サーフェイスで考えるために有益なヒントを与えてくれる。
反射のユニークさこそが、オブジェクトのユニークさである。ヒトに持たれていたとしても、そのインタラクションではなく、物理世界の光のなかでヒトとiPhoneとが触れ合ったときの反射が、ヒトとモノとのあいだにユニークな関係をつくる。ヒトとモノとは関係を持っているけれど、光は個別の存在であるヒトとモノとのあいだで反射する。このとき、モノが光を反射していると同時に、ヒトもまた光を反射している。物理世界のなかで、ヒトもまた光を反射する個別のオブジェクトなのであり、ヒトに反射した光がモノの反射のユニークさをかたちづくっている。反射はモノのサーフェイスで起こる。
そして、反射は鏡のように世界をそのまま跳ね返すものもあれば、二つ以上の反射が重なり合う反射干渉と呼ばれる現象もある。例えば、真珠の色があのように見えるのは、その表面で反射干渉が起こっているからである。反射干渉は、サーフェイスである膜の層の上面と底面とで別個に反射した光が重ね合わされることで起こる。
単純な反射干渉の例を図17-2で説明します。外から入る光はまず、膜の層(例えば真珠層)の上面で反射します(図中破線)。また、屈折して層に侵入し、層の底面で反射する光もあります(実線)。上面で反射した光と底面で反射した光は、C以降は重ね合わされ、ここで光の干渉が起きます。二つの経路を通った光の交差点、つまり実線のABCと破線のECの差が、波長の整数倍になっている時は、その波長の光が強められて色が明るく見えますが、ちょうど半波長分ずれていれば暗くなります。実際には、屈折率の高い層の中で波長が短くなる効果や、層の下にある材質によってBで反射した時に位相が飛ぶ(固定端反射)効果などが入る場合もあります。日本表面化学会『すごいぞ!身のまわりの表面科学』
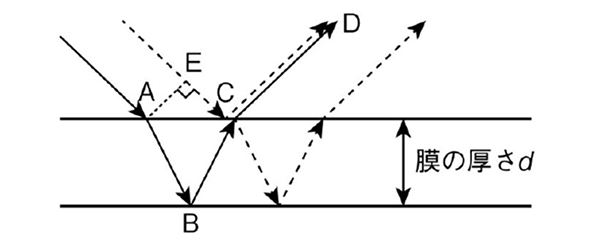 膜(あるいは層)がある時の反射の模式図(図17-2)
膜(あるいは層)がある時の反射の模式図(図17-2)
マウスとカーソル、重なるウィンドウから成立していたインターフェイスとは異なる、タッチパネルのインターフェイスというものが出てきたときに、インターフェイスはサーフェイスとなり、ヒトの行為を光のように反射するものとなった。ここではヒトとコンピュータとはそれぞれ個別にサーフェイスを持つオブジェクトになっており、物理世界に充満する光の反射をつくる一つの要素となっている。ここでは、もはやコミュニケーションを前提としたインターフェイスはなくなり、オブジェクトのサーフェイスが行為を反射し、一部の行為が屈折して別のオブジェクトに侵入し、その先でまた反射されていく。乱反射する行為がヒトとコンピュータとのあいだを満たしていく。
コンピュータがソフトウェアとハードウェアという二つの層で構成される膜を一つのサーフェイスとして持つため、ヒトとコンピュータとのあいだの行為の反射は、反射干渉をモデルに考える必要がある。このときヒトとコンピュータは、オブジェクト指向プログラムのオブジェクトのように「情報隠蔽機構を持った記憶領域と操作手続きの論理的な組織体」であり、行為はオブジェクトとは独立して存在しているが、光のようにその軌跡が計算可能なものと考えられる。
ディスプレイがサーフェイスとなり、行為を反射と屈折と重ね合わせていくには、最小化した行為が最適であった。光の反射率と屈折率と同様に、計算可能になるからである。ボタンを押すという最小化された行為だけではなく、タッチパネルではジェスチャーも入ってきているが、結局はサーフェイスの一部に触れている部分をいかに計算するかにかかっている。サーフェイスでヒトが触れている部分から行為を数値化していく。ヒトの行為は屈折を伴いながらディスプレイのサーフェイスを透過していき、コンピュータのソフトウェアがつくるもう一つの底面で反射し、画像として表示される。その際に、屈折した行為の結果としての画像とディスプレイのサーフェイスで反射するヒトの行為とが重なり合って、あたらしい行為とその意味が生まれていく。ヒトとコンピュータとが持つ互いのサーフェイスのあいだで起きる行為の反射と屈折のなかで、最小化された行為はハードウェアとソフトウェアのあいだで複数化し、重ね合わされていくのである。
スキューモーフィズムは物理世界の鏡としてヒトの行為を反射するように設計されているため、そこではあたらしい行為とその意味が生まれるわけではない。最小化されたヒトの行為が画像からの反射によって最小化される前の行為に復元されるかたちで反射され、画面を触れる指の行為と重ね合わされて、ヒトとコンピュータとのあいだを行き来する。しかし、ハードウェアとしてのガラスからの反射とソフトウェアがつくるXYグリッドからの反射との波長が重ね合わされたときに行為の干渉が起きるために、物理世界そのものから反射されるような行為にはならないのである。物理世界とスマートフォンからの行為の反射が異なるのは当たり前すぎることではあるが、スマートフォンによってヒトとコンピュータとのあいだのインターフェイスが、ハードとソフトという二層構造が表裏一体化したサーフェスになったことを、スキューモーフィズムは「物理世界の表皮」というわかりやすいかたちで教えてくれる。私たちはヒトとコンピュータとのあいだでのインタラクションではなく、物理世界に遍在するサーフェイスで乱反射する光を整えるように「行為のリフレクション(反射)」を設計しなければならないのである。
物理世界のサーフェイスでありながら、物理世界とは異なる行為の反射をつくりだすことができるスマートフォンは、ヒトの行為の実験場となっている。そして、物理世界とは異なる行為の反射を推し進めたのが、フラットデザインとマテリアルデザインである。次回は「行為のリフレクション(反射)」という観点から、フラットデザインとマテリアルデザインについて考えたい。
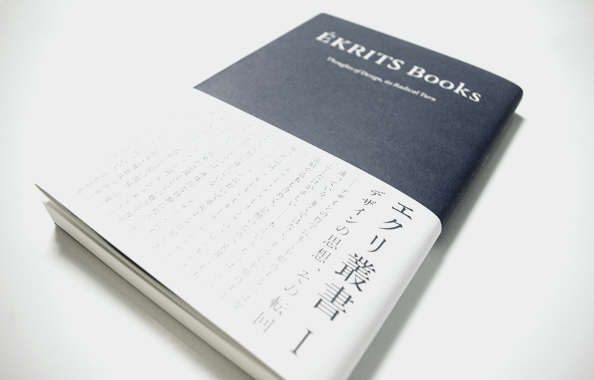
本のなかで、もっとも魅力的なもののひとつは、本について書かれた本ではないかと思います。本の自己陶酔に付き合うこと。そのテキストの絢に囚われること。意味を考えるのをやめて、物としての本のなかに入っていくこと。声がこだまする底なしの宇宙で彷徨うこと。それは堕落のための読書。充実した孤独という快楽。本が自己言及をはじめると、合わせ鏡のようになった見開きのページの表面で、わたしたちの思考を乱反射させるのでしょうか。この本をつくるにあたり、本を読む経験についてあらためて想いをはせながら、本についてのテキストをこうして書いています。
それで思い出したのは、最近とくに忘れられがちな本の美点であるモバイル性でした。重厚なハードカバーでもないかぎり、本はテキストを読むのに必要な紙の重量しかありません。それはテキストが収められる物として、妥当な重さなのです。だから、わたしたちはテキストへの愛を、本に頬ずりしたり抱きしめたりすることで表現できる。小柄なスマートフォンにも同じことができますが、そんな気になれないのは、匂いがしないからでしょう。紙の匂い、インクの匂い、手垢の匂い、カビの匂い、これまで置かれていた空間の残り香が集積した本には、独特のエロティシズムがあります。灰白色の肌に掛かった黒いレースの襞。そして、ゆっくりと朽ち果てていく運命。本がわたしたちを惹きつけるのは、その身体性ではないかと思います。
今この本を手にとって触れてみた「感じ」はどうでしょうか。ソフトカバーなのは、ハードカバーの尊厳よりも、テキストの「読みやすさ」とページの「捲りやすさ」、本としての「持ち運びやすさ」を目指したからです。また「読み切りやすさ」を感じてもらうため、ページ数もあまり多くしませんでした。持ち歩いて読み倒してもらうことを考えた結果、ハーフエアコットンの紙を使用して、こんな形態に落ち着きました。
この『ÉKRITS Books / エクリ叢書』というシリーズは、2015年1月からWebメディアとしてデザインの思想を伝えてきた「ÉKRITS / エクリ」の記事を書籍化したものです。シリーズと書いたのは、この形式でこれから何冊かに分けて出版していこうと考えているからです。その最初の配本である『エクリ叢書 Ⅰ』では、「デザインの思想、その転回」と銘打って、「デザイン」そのものをテーマにした記事を中心に、ニュースレターで配信した編集後記をコラムとしてはさんで、レイアウトしてみました。
本は過去のテキストのブリコラージュで作られる「引用の織物」と言われます。テキストは何もないところから書かれるわけではなく、過去に書かれたものを読んだことに、すくなからず影響を受けるからです。その前に、わたしたちは過去に書かれたものしか読むことができません。書いている本人でさえ、書きながら読むことはできないのです。この本に閉じ込められた時間も、すべて過去のものです。それに対して、書くという行為は未来に向かって投げ出すことです。あらゆるテキストは、かつて未来に投企されたものであり、それが痕跡となることではじめて読まれます。エクリはこれまで「10年後にも読めるテキスト」をアーカイブすることを志してきましたが、これも実際に10年経ってようやく検証されることになります。
今から10年ほど前、今が10年後の未来だった頃に、情報技術の分野でボルヘスが引用した「シナの百科事典」をよく見かけました。その混沌とした分類は、文化によって不整合なカテゴリーが生まれる実例であり、情報を処理するには最悪だと思われていたのです。この「シナの百科事典」は、ミシェル・フーコーの『言葉と物』で孫引きされたことで、広く知られました。これは今から50年も前のことです。フーコーは、この分類を言語の不可能性ととらえ、ロートレアモンの『マルドロールの歌』の一節「解剖台の上のミシンとこうもり傘の偶然の出会い(のように美しい)」に照らし合わせながら、解剖台という「テーブル」に載せられた世界の「余剰」として拾い上げました。
今こうして情報技術の悪例と『言葉と物』を並べると、なぜか50年前の『言葉と物』の方が新鮮に感じられます。これはわたし個人の印象ですが、決して情緒を懐かしむような趣味ではありません。ただ単に、ずっと前に書かれた『言葉と物』の方が、より今に近い場所へ向かって書かれているように思えるのです。しかし、今から20年ほど前にさかのぼって、さまざまな思想がポストモダンという言葉でひとくくりに分類されていた時代に両者をくらべたら、また違った印象だったでしょう。同じ「テーブル」でも、合理性のあるデータ構造という意味の分類が、新しい価値に感じられたと思います。しかし、情報技術で進化する人類の神話の続きとして聞けた話が、今はむしろ懐古趣味に感じられるのです。
『マルドロールの歌』に出てくる「テーブル(解剖台)」は、フーコーによって「タブロー」として、つまり世界を切りとる「枠組み」として読まれました。その枠組みによって、どのように世界を見るのか。これは心的な視野であり、「世界観」と呼ばれるもので、「思想」とも言いかえられます。エクリがデザインにおける思想を大切に扱ってきたのは、どう世界を見るかによって、立ち上がるデザインの対象が変わってくるからです。「シナの百科事典」を見て、不整合なものだと判断するか、言語からこぼれ落ちるものを予期するか。これは正しさではなく、個性や時代性の問題なのです。
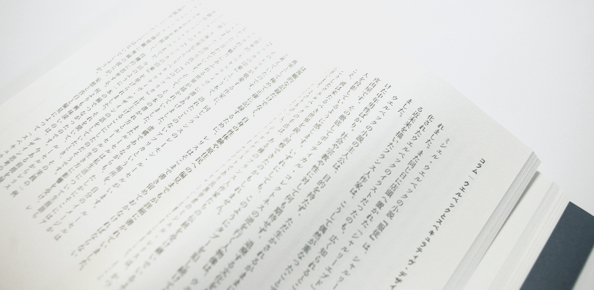
世界観が時代精神と重なってくると、過去の構造が転倒して新しい価値に置きかわり、「転回」と呼ばれる事態になります。近年のデザイン論では、クラウス・クリッペンドルフの『意味論的転回 — デザインの新しい基礎理論』が、これまでデザインに関係ないと思われていた理論をつなぎ合わせ、書名のとおりの転回を目指しました。バウハウスからインタラクションデザインまで線を引き、新しい歴史をつくろうとする試みは素晴らしかったのですが、1990年頃からヘゲモニーを握っていたドナルド・ノーマンらの認知工学的なデザインから逸脱できたわけではありませんでした。
かつて認知工学的なデザインは、多くの可能性を切り拓いてきました。しかし、これはもうずいぶん前の話です。それからデザインがビジネスフレンドリーになり、いくつかのディシプリンが神格化され、セオリーとメソッドもインフレーションを起こし、デザインに関するサブジェクトの新陳代謝は激しさを増していきました。この状況はデザインにとって追い風とも言えるのですが、思想的には他の分野から大きく遅れをとってしまったのです。その原因のひとつが、教条主義と化した認知工学的デザインの保守性にあったと考えています。
長く続いた行き詰まりのなか、2013年に出版された人類学者のティム・インゴルドによる『メイキング』は、デザイン論の新しい転回を感じさせるものでした。昨今の人類学の存在論的転回やパースペクティビズムはもちろん、オブジェクト指向哲学やプロトタイプ論などの新しい思潮を踏まえながら、それらへの具体的な言及を慎重に避けつつ、道具論や制作論としてデザイン論をアップデートする。理論を組み替えて示す手つきもデザイン的で、実際にドナルド・ノーマンを引き合いに出しながら、ヴィレム・フルッサーを援用してそれを乗り越えてみせました。これがアメリカの心理学や情報学ではなく、ヨーロッパの人類学から出てきたのが、今っぽいと言いますか、もっと言うと今世紀のはじまりっぽいのかもしれません。
わたしが好きなのは、未来を語る本ではなく、未来へ連れて行ってくれる気分にさせる本なのだと思います。そして、本が過去のテキストによる「引用の織物」なのだとしたら、どんな人のどんなテキストをサンプリングして、どんなミームでミックスして、どんなコンセプトでエディットするかが重要です。インゴルド『メイキング』の新しさは、その世界観だけでなく、リイシューの対象を選ぶセンスや、それをつなぎ合わせる手際にも感じられました。こうした観点は、わたしが運営するエクリにも大きく影響しているでしょう。
エクリの執筆方針は、きわめてシンプルです。自分がひとりの読者として「読みたいもの」を書いてくれそうな人にお願いすること。そして、それがデザイン論として読めること。この2つです。自分の趣向と重なるものしか判断できないし続かないので、気づくとそうなっていました。きっと「読みたいもの」の条件に、「未来のテキスト」であるということも含まれているのだと思います。「未来のテキスト」とは、たまたま古書店で出会った昔の本が、まるで今の自分だけに向けて書かれていると感じるときのように、時間を超えて語りかけてくるテキストをさしています。
執筆をお願いする方のタイプも、最近やっと言語化できるようになりました。それは誰かに共感されたり認められたり、何かの役に立つために書くのではなく、自分が信じているもののために書く、そんな「孤独な書き手」です。記事が揃ってくると、執筆をお願いする方がすでにエクリの読者であるケースが増え、ときには向こうから執筆を申し出ていただけるようになりました。そんな書き手の原稿を受けとると、これまで自分が確信していた世界の枠組みが壊されるような感覚になることがあります。愉しさと危うさが入り混じった編集作業は、決して悪いものではありません。
最後に、この本を手にとってくださった方、いつもエクリのWebサイトを見てくださっている方、ニュースレターを購読されている方、エクリに執筆された方、エクリのデザインや運営や編集に関わっている方、つまり書くことと読むことの「この気違いじみたゲーム」に参加されるすべての方々に、感謝の意を表したいと思います。
今回載せたテキストは、2〜3年前に書かれたものがほとんどです。そのとき未来に向かって投げ出され、その痕跡がインクとなって染み込んだ「引用の織物」が、いつかの未来で、どこかにいるあなただけに語りかけることを、それが充実した散策のはじまりとなり、さらに未来へと向かうような気分にさせることを、心より願っています。
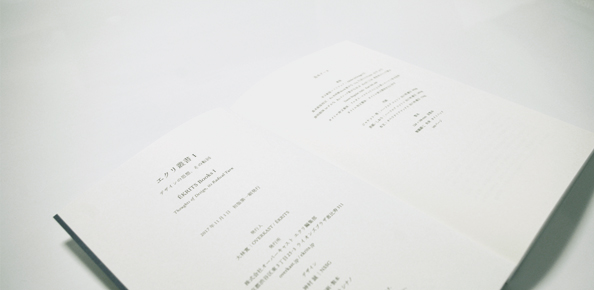
『ÉKRITS Books / エクリ叢書』について
オンラインでは「ITEMS」ページよりご購入いただけます。
スーツを仕立てるプロセス
過日、スーツをこしらえました。この歳になれば、オーセンティックな服のひとつでももっていてよかろうとおもいましたし、ある時期のマイルス・デイヴィス、あるいは山田五郎氏のように、なかば普段着としてそれを纏いたいともかんがえたからです。世代的なものもあり、エディ・スリマン時代のディオール・オムのような、攻め込んだモードなシルエットには後ろ髪を引かれつつも、スタンダードを経験する意味で、今回はストイックに正統なブリティッシュ・スタイルを目指し、仕立てることにしました。
とはいえ、ふだんからの怠け癖が災いし、テイラーにむかうおよそひと月ほど前から、自身の目指すところが、いったい、なにか? について本腰をいれ、ようやく学習するはこびとなりました。かずかずの店舗をおとずれ、書物やウェブ・サイトをめぐり、まずはスーツそのものの構造やディティールの種類を知り、そのなかで、みずからの方向性を自覚し、完成像を描いてゆきます。つまり、生地はどうするのか? それでは、シルエットはどうか? とか、カラーはどうか? ラペルはどうか? ゴージ・ラインはどうか? ヴェントはどうするのか? スラックスのフォルムと裾は? —— こうした項目に対し、複数用意されている選択肢。そのなかから、目的に対し最適な選択をしてゆきます。
ブリティッシュ・スタイルを目的として、各項目をチョイスしてゆけば、目指すものはひとまずできあがります。もちろん、違うコンセプトを立て、今度はそれに基づいてゆけば、それはイタリアン・スタイルにもなるし、前衛的なものにもなっていきます。こうした体験をくりかえしてゆくなかで、自分自身にとって最適な一着はできてゆくのでしょう。しかし、そこに項目があること自体は不変のもの。規格化されたある一定の枠組みのなか、目的に対し、正解か、そうでないか、という明快な二元的分別に支配されているともいえます。
二元的に分別されるデザイン
スーツに限らず、なにかをデザインするプロセスというのは、往々にしてこう分別的に規格化され、体系化されてゆくものかもしれません。デザインといういとなみが、目的のために最適解をみちびき、ものごとを形成する行為だとすれば、このように、そのプロセスをフレーム化することは、ひとつ真っ当な成りゆきといえます。
否、デザインばかりでなく、私たちは分別された枠組みのなか、ものごとをとらえ、理解するよう教育されています。音楽における十二平均率に楽典、食材と調味料などなどを数値化し箇条してゆくレシピ、いまのモードがなにかをしめすファッション・スナップ、オプションまで明示された住宅や自動車のチラシ、三ツ星や五ツ星で採点評価されるグルメ・サイト、必聴盤をしめすレコード・ガイド、宿に食事から名所そして土産品までをプラニングしたガイド・ブック、挨拶にはじまり接客から消毒用エタノールの希釈率まで詳細に明文化されたファスト・フードのスタッフ・マニュアル —— さまざまなものごとに私たちは枠組みをあたえ、規格化し、その要所要所にアンカー・ポイントとなる質問項目をもうけ、リスト化しています。そして、それぞれに二分された選択肢を用意することで、対象を把握し、学習し、理解する。極端にいえば、それはリストアップされたすべての項目にYes/Noを解答してゆくゲーム。常に明快さを生み、それがゆえ大衆化をみちびくものです。
しかし同時に、こうした二元的な分別知は、本来、その周辺にある、ある種の混沌とした現象を作為的に無視することになりますし、それは、ときとして対象を、自分たちが咀嚼できるフェイズにまで引き降ろす、乱暴な行為ともなりえてしまいます。ともすれば最適解に肉薄せず、フレームにしたがうばかりで、達成感を得てしまいかねません。ベターな解答の先にベストの解答はありませんし、それは本質的に別物なのです。
未分と自覚の東洋思想
1と2のあいだには当然、小数点の微細な刻みがあり、その解像度はどこまでも拡大、つまり細分化が可能です。そうしてゆくうち、それらは具体的に分別される以前のシームレスな、本来の状態に還元されてゆきます。これはイームズ夫妻による『Powers of Ten』をイメージしていただければ、わかりいいかもしれません。
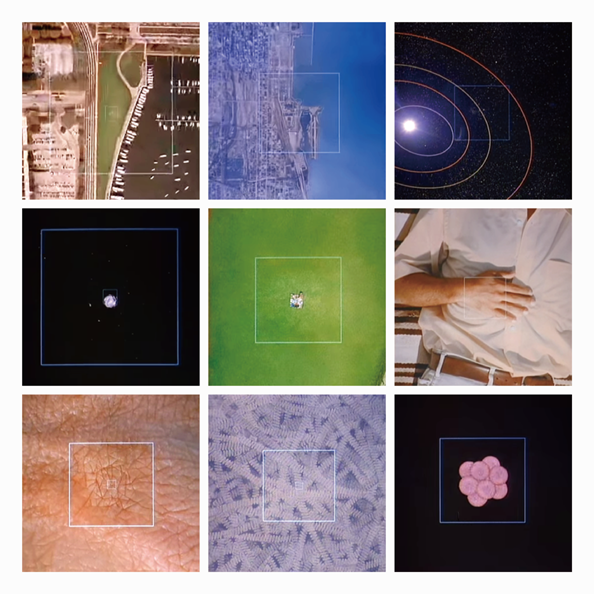 Charles and Ray Eames “Powers of Ten” (1968)
Charles and Ray Eames “Powers of Ten” (1968)
つまりは、光と闇ではなく、陰翳の状態。色即是空/空即是色の視点です。規格に基づき分別されれば、項目化されたそれ以外のものを落とし、ひいては本質を遠ざける。そうして粗いビットマップからみちびかれたものは、最適解というには不十分なものでしょう。ここで鈴木大拙の文章を引用します。
西洋の人々は、物が二つに分かれてからの世界に腰をすえて、それから物事を考える。東洋は大体これに反して、物のまだ二分しないところから、考えはじめる……つまりは、西は二分性の考え方、感じ方のところに立脚していることがわかる。そうして東は、そのまだ分かれぬところ、むずかしくいうと朕兆未分已然に、無意識であろうが、そこに目をつけているということになる……東洋的考え方、感じ方 —— それが無意識であっても、何でもかまわない —— それを護立てることによって、二分性文化の不備を補足してゆかねばならぬのだ。鈴木大拙「東洋思想の不二性」
アメリカをはじめとした国外で東洋思想・禅をつたえた鈴木は、こうして西洋を象徴する思考として分別を、東洋を象徴するものとして未分をときました。そして分別知の不備をおぎなうものとして、それ以前における自覚を促します。鈴木の門下生であった柳宗悦は、こう語ります。
仏の国は無上の国なのである。何処に美醜の二があり得ようか。その無上のものに支えられているのが、吾々の本性である。この本分には二相がない。一相即ち無相に居るのが吾々の実相なのである。美醜の二相は仮想に過ぎぬ……考えると美醜というのは人間の造作に過ぎない。分別がこの対辞を作ったのである。分別する限り美と醜は向い合ってしまう。そうして美は醜でないと倫理は教える……美醜が現れて已語のことを問うのではなくして、その二つが未だ分かれぬ已然の境地を追求しようとするのである……求めるところは美醜已然の世界なのである。柳宗悦『美の法門』
彼らの生きた明治維新から20世紀中葉の日本における、近代化や国際化というものは、すなわち西洋化でした。それは工業製品のように規格化された文明や文化を輸入し、享受した時代。あらかじめパッケージされたリストに基づき、理解や判断をおこなうプロセスに、このふたりは違和感をおぼえたのかもしれません。
事実、近代をつぶさにみれば、分別知のたまものである時代のなか、そこで落とすものを、いかにして拾いあげようと苦心するようすもみられます。柳は自身の提唱した民藝運動において、固有の着眼点から、土地土地のなにげない生活用品を評価しました。そのいずれもが、くりかえしのなかで身体化された職人による仕事、つまりはマニュアル化しえないものです。
バーゼル・スタイル・タイポグラフィとモード奏法
20世紀ミッド・センチュリーのタイポグラフィと音楽をみてみます。まずはバーゼル・スタイル・タイポグラフィを代表するエミール・ルーダー。同時代、おなじスイスで展開されたチューリッヒ・スタイル・タイポグラフィが、グリッド・システムとHelvetica活字をもちいメカニカルに紙面造形をおこなったことに対し、エミール・ルーダーは活字の規格に基づきながらも、徹底した視感覚調整 —— 活字のサイズや濃度、行間、配置、そして微細な字間調整 —— をおこなうことで、白い紙と黒い活字という、単純な二次元的解釈の造形ではなく、活字の黒の濃度グラデーションと画面の白、無限の奥行きのある疑似三次元空間として、画面をあつかうことに成功しています。
そして彼らは工業的な設計特性をもつHelvetica活字ではなく、おなじネオ・グロテスク・サン・セリフ書体のなかでも、伝統的なローマン・タイプフェイスであるニコラ・ジェンソン活字の骨格をもち、濃度やサイズといったファミリー展開が、きわめて微細に展開されたUnivers活字を礼賛します。
三十本の輻が一つの轂を共にする。この空虚なところにこそ、車としての働きがある。埴をこねて器をつくる。その空虚なところにこそ、器としての働きがある。戸や窓をうがって部屋をつくる。その空虚なところにこそ、部屋としての働きがある。
だから形有るものが便利に使われるのは、空虚なところがその働きをするからだ。老子『道徳経』
ルーダーは著書『Typographie: A Manual of Design』において老子『道徳経』を引用し、車輪を車輪たらしめるのはスポークの間にある空間であり、壷を壷たらしめるのはその内部空間であることとおなじように、印刷される活字の黒と余白空間が等しく重要であることをときました。
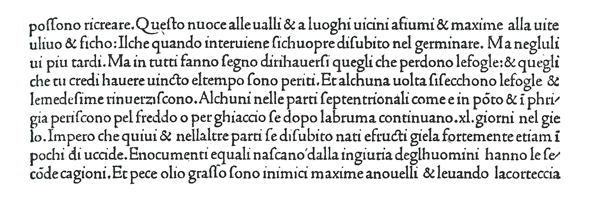 Nicolas Jensonによる『プリニウス博物誌(複写)』(出典: 組版工学研究会『欧文書体百花事典』)
Nicolas Jensonによる『プリニウス博物誌(複写)』(出典: 組版工学研究会『欧文書体百花事典』)
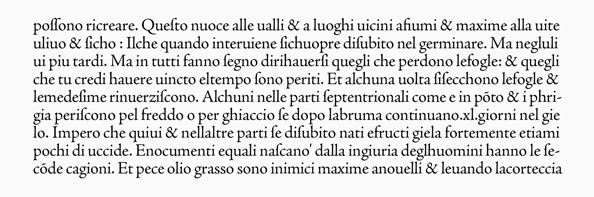 Adobe Jenson活字による『プリニウス博物誌(複写)』の再現
Adobe Jenson活字による『プリニウス博物誌(複写)』の再現
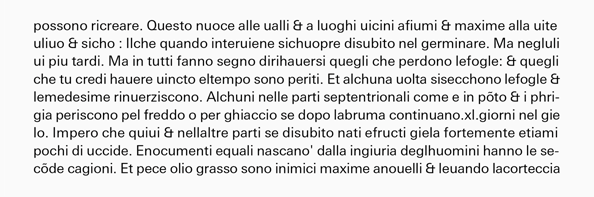 Univers活字による『プリニウス博物誌(複写)』の再現
Univers活字による『プリニウス博物誌(複写)』の再現
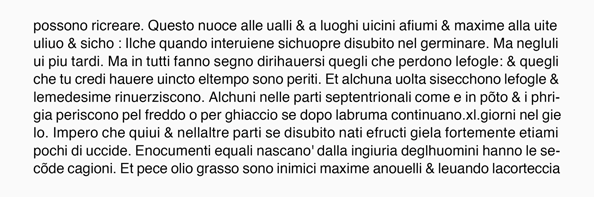 Helvetica活字による『プリニウス博物誌(複写)』の再現
Helvetica活字による『プリニウス博物誌(複写)』の再現
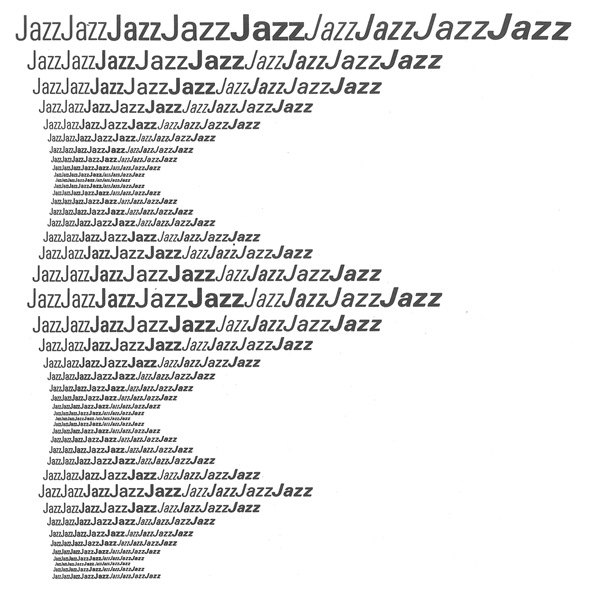 エミール・ルーダーによるバーゼル・スタイル・タイポグラフィの一例(出典: Emil Ruder “Typographie: A Manual of Design”)。活字の規格にもとづいたフォーマットのうえで、有機的に構成された紙面。Univers活字の特性である精緻な濃度変化を活用し、空間として奥行きのある画面を生み出している。
エミール・ルーダーによるバーゼル・スタイル・タイポグラフィの一例(出典: Emil Ruder “Typographie: A Manual of Design”)。活字の規格にもとづいたフォーマットのうえで、有機的に構成された紙面。Univers活字の特性である精緻な濃度変化を活用し、空間として奥行きのある画面を生み出している。
Univers活字のリリースが1957年。同時期に音楽の世界では、マイルス・デイヴィスらがモードを主体とした演奏をこころみます。それまでのジャズ・ミュージックでは、和音構造からみちびきだした旋律でソロをとることが主流でした。和音が細分化され、ベースのウォーキング・ラインとなり、さらに細分化され、ソロ旋律となるような具合。つまり、楽曲構造の根幹に和音をすえる方法でした。
マイルスがギル・エヴァンスやビル・エヴァンスらとこころみたのは、モード、すなわち音階・旋律を軸に楽曲を構築することにありました。それまでは和音進行という、規格化されたフォーマットのうえでのゲームであったセッションも、これにより、従来以上に自由度のたかいものとなります。ある時期からマイルス・デイヴィスは不安定ともとれるピッチで演奏するようになりますが、これは単なるミスや技藝のおとろえではなく、カラーチップのように工業化された色彩が、未分明で有機的な現実の色彩を再現することが、実質的に不可能であるように、規格化された十二音階のあいだにある豊かな微差を、積極的につかもうとした行為だったのかもしれません。
熟練した職人の手でみちびかれる民藝、視感覚に委ねられるバーゼル・スタイル・タイポグラフィに、奏者の聴覚に左右されるモード奏法。いわば規格以前の、未分明のものごとを意識した途端、漠とした情報量は途方もなくふえ、混沌としはじめます。これらは当事者の習熟度や身体化された経験に委ねられるものとなり、ひいては大衆化が困難なものになります。しかし、分別的な視点では得られないものを、具現化していることは間違いありません。なぜならそれは、対象の本質に迫るいとなみであるからです。
分別を超越する身体知
すこし時間をさかのぼり、16世紀、長谷川等伯の筆とされる『松林図屏風』をみてみます。バーゼル・スタイル・タイポグラフィが目指した、豊富かつ微細な黒、そして白の陰翳幅により、あたかもそこの湿度や空気すら再現されています。それは平面媒体の鑑賞にとどまらない、インスタレーション的な経験を提供します。
 長谷川等伯『松林図屏風』左隻
長谷川等伯『松林図屏風』左隻
1959年に発表され、モード・ジャズのありかたをしめしたマイルス・デイヴィスによる『Kind of Blue』。共作者であるビル・エヴァンスが寄せたライナー・ノーツには、こう記されています。
日本の視覚藝術では作者が無意識で、自然でなければなりません。ごく薄い紙に、筆と墨で描かれる日本絵画では、筆運にすこしでも不自然なところがあれば、線はみだれ、紙は破れるばかりです。それを修正したり、消去することはできません。ですから、制作者は特別な鍛錬を積まなければなりません。頭のなかにある着想を、手をつうじ、瞬時に紙上に再現する鍛錬です。
筆者自身は、アルバム『Kind of Blue』の音楽やビル・エヴァンスのこの文章にふれるたび、反射的に『松林図屏風』を連想します。また同時に、エミール・ルーダーの仕事も連想し、ひいてはヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテが『色彩論』でいうところの「くもり(Trube)」の発見へもつうじてゆきます。彼らがかずかずの経験による身体化のなかから得た成果は、分別的な価値を超越したところで成立するものです。
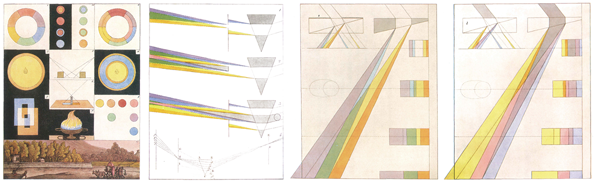 ゲーテ『色彩論』図版
ゲーテ『色彩論』図版
ものごとを規格化し、リストをあたえ体系化する —— それは様式化の方法としては適切なものです。しかし粗い目の笊は、作業効率はよろしくても、落とされることもおおい。実際が混沌としている以上、初手から既存のフレームにあてがうのではなく、それを許容してゆくプロセスも有効でしょう。
自然の水は、未分明かつ膨大なものが、その風土のなか徐々に濾過されることで、透明無垢となります。環境や時代のなか、対象に即したよどみのない、最適なるもの。それは未分明を自覚することで、分別を超越していくのです。さて、その成果がどういう具合なのか、まず分別以前をみてみるのがよいのかもしれません。
言語はこの世の謎めいた豊かさを効率的に秩序だてるものなのである。ホルヘ・ルイス・ボルヘス
おれはいつだって具体的なやりかたで物事を伝えようとしてきた。比喩はあまり使わない。AとBを比べて違いを指摘するだけだ。そうすればたいていのことはうまく伝わる。少なくともうまく伝わったような感じがする。
問題は、伝えようとする物事そのものが混乱しているときだ。そういうことは多い。ほとんどの人は混乱に直面したとき、説明することをあきらめ、はぐらかし、沈黙する。それがいやだった。子供のころからずっと、言葉で伝えられないものはこの世になにひとつとしてないと信じていた。そしてだんだんと、世界の成り立ちには、秩序以上の割合で混沌が関わっていることがわかってきた。おれの動揺といったらない。最初はこんなふうだった。
「AはBだ」
「なぜ?」
「BはCではないからだ」
「なぜ?」
「BがDでないことから明らかだ」
「なぜ?」
この鬱陶しい「なぜ?」のたびにおれはだんだんと言葉を失い、それについて語ることができない混乱した対象のまえでがっくりとうなだれた。この混沌とした世界そのもののデザインについて、おれはなんども腹を立てた。いままでの苛立ちのエネルギーを使えば、やかんに一杯のお湯くらいは沸かせられるかもしれない。
もはや誰にもなにも伝えることなどできないのかもしれない、と気づいたのは二十歳のころだ。それは陰鬱な夏だった。妹が自殺し、恋人が鬱病にかかり、夕方になるたびに雨が降った。おれは恋人を失うまいと雨に濡れながら町中をかけまわり、香りのいいアロマオイルや花束や安い宝石を手に入れ、ベッドに伏せたまま動くことができなくなった恋人に捧げたあと、身体をさすってやった。そういう暮らしが一年ばかり続いたあと、彼女はなんとか持ち直して元気に働きはじめたが、こんどはおれのほうがまいってしまった。後回しにしておいた妹の喪がそのころになってあらわれたのだ。
説明できるのは、この物語が混沌に基づいたものではないからだろう。それだけに救いがある。結局はまたこうして語り始めているからだ。とにかくいろいろあって、おれは飛び級で大学に入るみたいに順序をすっぽかして死の領域に入った。「この門に入るものは一切の望みを捨てよ」と書かれた有名な観光地の門をくぐると、凍りかけた川岸に柳が垂れている深夜の京都があった。つまり、そこには少なくともなにかがあった。
それから数年の訓練を経て、おれは無の領域に近づいた。その場所の入り口には看板があり、つぎのような言葉が記されていた。
「さようなら」
カート・ヴォネガットが自殺未遂をやらかしたのは一九八四年のことで(いみじくも、ジョージ・オーウェルの小説の時代設定とおなじだ)、ヴォネガットはその時の心境をこう語っている。「なにもかもいやになっちまったのさ。もうコーヒーもなし、ジョークもなし、セックスもなし。」つづけて、「大いなるドアが閉まる音を聞きたかった」とある。
あるひとりの作家が残したものをほとんど読んでしまうと、その作家に対して抱いていた尊敬はだんだんと薄まり、最後にはおなじことをなんどもくりかえし話す、道化師めいた老人に対して持つのとおなじくらいの好意しかなくなる。
けっきょく、カート・ヴォネガットは二〇〇七年に死んだ。自宅の階段で足を滑らせて、角に頭をぶつけたのだ。その六十二年前にドレスデンで焼け死んでいれば、長い生涯のなかで、ひどい苦労を強いられずに済んだはずだ。こんなに長いこと。こんなところで。色んな人間が吐き出したチューインガムの残りかすを靴底で踏みつけながら。
それでも彼は生きた。えらいと思う。よしよし、ほめてあげよう。こっちへおいで、おっちゃんがアメ玉買うたるからな。
時のペロン政権にいじめられつづけていたホルヘ・ルイス・ボルヘスは、革命成功の流れを受け、一九五五年にアルゼンチン国立図書館の館長に任命され、いきなり八十万冊の書物を手に入れた。そのころには父系から受け継いだ盲目が完全なものとなり、自分の目でものを読むことができなくなった。彼はこの巡りあわせを神による皮肉と解し、「天恵の詩」という作品の冒頭でつぎのように書いた。
誰も涙や非難に貶めてはならない
素晴らしい皮肉によって
私に書物と闇を同時に給うた
神の巧緻を語るこの詩を
水上瀧太郎は一九一二年からハーバード大に学び、パリ、ロンドンを周遊したのち汽船に乗って神戸の港に戻ったが、朝日と毎日の記者につかまり、船室のなかでインタビューを受け、インタビューを受けたという事実以外は捏造の記事をでっち上げられた。自分の写真とでっち上げの記事が躍る新聞の一面に悩まされながら帰京した彼は、「貝殻追放」というシリーズものの随筆のなかで怒りを露わにした。その断章は、蒙昧な新聞記者に対する「馬鹿馬鹿馬鹿ッ!」という痛罵で終わっている。
日本文学史に燦然と輝く、記念碑的な筆致だ。
それから二十三年後、彼は大阪毎日新聞社の取締役となった。その後、なにかの講演中に脳溢血の発作で倒れて死んだ。皮肉が効きすぎたのかもしれない。その翌年、岩波書店があわてて『水上滝太郎全集』を出版した。いまでは絶版となっている。
誰も涙や非難に貶めてはならない、というのはつまり、笑ってやってくれということだ。
はっきり言って、なにをどう語ればいいのかわからない。語るべきことなんかなにもないような気がする。とくに、物語など、ひとつも浮かばない。おれが書きたいのは、日曜日の昼に炊飯器を買いに出かけたときの日差しがあたたかくて素敵だったというようなことだ。その帰りに駅前で買ったアップルパイがおいしかったことだ。それからシャンパンを飲んで酔っ払ったことだ。おれには向いていないのだ。
いや、そうじゃない。ほんとうはみんな、あらゆるものが、語ろうと必死になっている。おれは必死になって言葉にならない言葉をすくいあげようとする。調子がいい時なんか、まるで風船みたいに空中に浮かんでいるときもある。ただし、そいつをつかまえて白いページに押しこもうとすると、とたんに暴れだす。
真実はあまりにも素早いので、腹をさばいてワタを引っこ抜き、壺にぶちこんで塩漬けにしなきゃならない。これが腕の見せ所だろう。はっきり言って、語るべき対象は無数にあるのだから、「なにを」語ればいいかわからないというのは正しくない。「どう」語ればいいのかわからないだけだ。
あらゆる人間が物語を抱えている。これはおれが感得した数少ない真実のうちのひとつであり、おれは人々から注意深くそれを引き出すことによって、無形の報奨を得るだろう。そして、それは愛とおなじ、永遠に錆びつかない報奨である。
どこかへ旅行に行った帰りのことだ。当時おれは京都の大学にいて、ちょうど路銀を使いはたしたので路面電車に乗り換えず、駅からとぼとぼ歩いていたのだが、折悪く雨が降り出した。ちいさなパン屋の軒先で雨宿りをしていると、顔を見たことはあるが名前は知らない先輩が傘をさして通りがかった。先輩はおれに気付いて、「よかったらうちで雨宿りをするといい」と言った。おれは先輩のあとについて、地面に寝そべった巨大な犬みたいな長屋が並んでいる通りの奥へと入った。
先輩はおれを長屋のうちのひとつに招き入れ、タオルと温かいハーブティーをくれた。おれは台所の換気扇の下で煙草を吸いながらレモングラスのハーブティーを飲んだ。殺風景な部屋だった。ベッドと、テレビと、テレビの前に置かれたプレイステーション、いくつかのゲームソフトくらいしかなかった。
「いまは都ホテルのボーイをしてるんだ」と先輩は言った。
「出世されましたね」とおれは訳の分からないことを言った。
「そうだろうか」と先輩は言った。
その先輩は毛深いうえに小柄で、そのせいか全体の輪郭がはっきりしなかった。彼は二分おきに油紙を手の中でくしゃくしゃにするような咳をした。おれは屋外から聞こえてくる雨の音が咳の音で中断されるのを何度か感じた。神様が下腹に力を入れて、小便を途中で止めて遊んでいるみたいな雨だった。換気扇が回る音と、冷蔵庫のモーターの小さな唸りが通奏低音となって部屋中に響いていた。おれはいてもたってもいられなかった。いくつかの音が重なって、山中の霧のような印象をおれに与えた。おそろしいほどの湿気だった。ずっとここにいると肺に黴が生えてきそうだった。
「そろそろ、おいとまします」とおれは言った。先輩は玄関まで送ってくれ、ビニール傘を与えてくれた。
「気をつけてね」と言って先輩は微笑んだ。よく見ると、前歯がひとつ欠けていた。
「ありがとうございます」とおれは言って別れた。
どこをどう歩いたのかわからないが、路面電車の駅のひとつにたどり着いた。下宿から駅三つぶんも離れていた。道が分からなかったので、線路沿いを歩いた。二両編成の路面電車が何度も通り過ぎたが、車中の人影はずっとまばらだった。アニメのペイントがされた車両が数台に一度の割合で混ざっていた。彼女たちは永遠に若いまま、奇妙なポーズで固定され、潤んだ巨大な瞳で空中を見つめていた。
正面に立てば自分を見つめているような感じがするのかもしれない。
意外とよく書けている。この調子でどんどんいってみよう。
無の領域に属する文学はサイエンス・フィクションである。おれはこの真理を東京の神保町で学んだ。かび臭い匂いのする古本屋ばかりある町だ。十六歳のおれは、巨大なリュックサックを背負ってその町を訪れた。いくつかの本屋に入り、本当は読む気もあまりしないような小説を数冊買ったが、わけてもおれを驚かせたのは、サイエンス・フィクションに関連した書籍のみを取り扱う店だった。エイリアン、光線銃、宇宙船に恒星の煌き、茫漠とした荒野や天に瞬く星々などが描かれた表紙がずらりと並んでいた。おれはかなりの感銘を受けた(十六歳の少年は何にだって感銘を受けるものだが)。つまり、これらの古書は日本中のサイエンス・フィクション好きのためにあり、彼らはこういうのを見て狂喜するのだろうと思ったのだ。
それはとても素敵なことに思えた。
いまの話はあまり良くなかった。次はがんばろう。
文章を書くことはたいへんむずかしく、労多くして功少ない仕事である。文法や構文をいじくりまわし、さまざまな語彙を用いて美しい文章を書き上げたところで、語っている内容がまったくの見当違いということもある。かといって、内容を重視し、書き方を無視して書き進めると、あとから読み返しても何を言っているのか全く判らない奇妙な代物ができあがる。
正確な言葉を探しもとめて白紙のページを睨みつけているあいだに、意識が朦朧としてきて、思い出ばかりが浮かんでくる。そういったものに意味がないとは思わないが、書くほどのことでもない。思い出を追い払い、想像力を呼び起こそうとしているうちに、正確な言葉はいまここにいるおれ自身からすばやい動きで逃げていく。
芸術を作りたいわけではない。おれが作りたいのは、いまわの際にいる人間が絶望のさなかに手を伸ばし、頭が混乱していて文章の意味もよくわからないのだが、それでもとにかく三行ばかり読んで、放り投げ、そのまま死んでしまうようときに、そこにあるような文章だ。
いまこの瞬間に皮のベルトを握りしめて、窓外のトタン屋根の梁を眺めている人間が、ほんのすこし気まぐれを起こして本棚に近づいたとき、なんとなく選びとるような文章が、おれのものであってほしい。それでそいつの寿命が三十秒ほど伸びれば、おれは満足だ。
おれが文章に対して持っている希望は概ねそんなところだ。そこには多少のエゴイズムというか、他人に対して礼儀正しくありたい、ぱりっとした感じを見せたい、君といると楽しいと感じてもらいたい、といった社会性が秘められている。
とにかく、メッセージは正確に伝えなければいけない。それがどんなに伝えにくく、複雑な手段を用いなければ理解されないものであろうとも、できる限りの力を尽くして事に当たらなければならない。そして、誤解はやがて理解に至り、人類は長く待ちわびた平和を手に入れ、誰もが安心して暮らすことができる、すばらしい未来がやってくるだろう。
それで、その後は?
おれは若いころによくこんな歌を歌っていた。集団就職で地方から出てきた親父の友達の奥さんに教えてもらったのだ。
仙ノ山からよー 谷底見ればよー
巻いたまーたぁ 巻いたの アーヨイショ
アー 声がーするよー アーシッチョイシッチョイ
三十五番のよー 座元の水はよー
大岡まーたぁ 様でも アーヨイショ
アー 裁きゃあせぬよー アーシッチョイシッチョイ
大岡さまでもよー 裁けぬ水はよー
蒸気まーたぁ ポンプで アーヨイショ
アーみなさばくよー アーシッチョイシッチョイ
三十五番はよー この世の地獄よ
行かすまーたぁ 父さんは アーヨイショ
アー 鬼か蛇かよー アーシッチョイシッチョイ
とにかく、この物語は無の領域の一歩手前をうろつく男の物語である。おれ自身はけっきょく「さようなら」と書かれた門には入らなかった。門の手前からその奥をじっと眺めていただけだ。奥は紫色で、ブーンという蛍光灯の音がする。死の領域のほうがまだ居心地がよかった。なんともいいがたいだるさに充ちてはいたが、少なくともなにかがあった。凍った川岸の柳や、寝そべった犬のような長屋はその一例である。
妹はテーブルの向こうに、おれはテーブルのこちら側に座っている。
「元気?」と妹が聞く。
「元気だよ」とおれは答える。
「そう。よかった」妹は言う。
そして沈黙が続く。なにもかもを包みこむような沈黙だ。
ラジオも、テレビも、音楽もない。
鈴虫がずっと鳴いている。
夜だ。
おれの妹が死んだとき、これは当然のこととしてみんなに受け入れられたが、雨が降った。彼女は十一月の凍えるような寒空の下で、コンセントの延長ケーブルを首にまきつけ、自宅の裏口のそばにあるトタン屋根の梁から自分をぶら下げた。
それは空を見ているだけで不安になるような薄暗い夕方だった。太陽が人間たちを残してどこかへ行ってしまったみたいな寂しさだった。そしてそれは本当のことなのだ。
おれは自分の部屋で音楽を聞きながら、その寂しさにじっと耐えていた。誰かと抱き合っていないとやりきれないような日だったが、妹はもうずいぶん前から具合が悪くなっていて、面倒を見てやる気にすらなれなかった。
トタン屋根の梁から身体をぶらさげて風に揺られている妹を見つけたのはおれの父だったが、そのときの叫び声は真に迫るものがあった。すぐに救急車がやってきたが、彼女はすでに絶命していた。それから家族が集まり、親戚筋がみなやってきて、それぞれに感想を述べた。彼女がそれをしたときにおなじ家にいたのがおれだけだったという事実が口にされたが、誰一人非難するような口調ではなかった。
彼女が憂鬱症であったとかいう診断を下すのはおれの仕事ではない。有り体にいうならば、彼女の頭のなかには毒虫がいて、夜ごとに彼女の脳髄をたべて成長していった。こういう話は、具合が悪くなった妹から実際に聞いた。そんなわけがないと思ったが、いくら抱きしめても、恐怖に目を見開いたまま怯えているのだった。そのわりに話し声はしっかりしていた。怖い感じがする話だ、とおれは言った。
妹の幽霊から逃れるために移り住んだ京都は、おれを苦しめも助けもした。憂鬱症の患者を家族にもつ人なら賛同してくれると思うが、憂鬱症は伝染する。そういうわけで、おれは憂鬱症に苦しみ、ふうふう息を切らしながら生きた。泣いてばかりいるので、ほんとうに息が切れるのだ。歩けばすぐに疲れてしまうし、どんな小さな不調も見逃さなくなる。四月の身体検査で白血球の数が異常に少なく検出されたとき、自分が癌に冒されたと思いこみ、何をするにも薄氷を踏むように慎重になった。
そのときの気分は、底がつるつるの滑りやすい靴でワックスをかけたばかりの廊下を歩くようなものだ。次の瞬間にはおもいきり転んでしまうだろうという感じが延々と続く。
それは地獄である。
もう大丈夫だ、というようなことは何度となく思った。いい映画や小説を見て十分に楽しみ、自分がまだ楽しめることに喜びを見出して、そこに大いなる満足を覚え、もう大丈夫だと感じる。
そして翌日に目覚めると状況はより悪くなっている、雨が降っていて、きのう干した洗濯物を取り入れていない。部屋のなかに戻して乾かすが、濡れた犬のような匂いがする。それから怠惰がおれを座椅子に結びつけ、延々と煙草を吸いながらインターネットを見る。何度も何度も見た映像をくりかえし見る。味のなくなったチューインガムが不快なのとおなじ理由で、おれは不快な気分になる。雨が強くなる。しぶしぶながら、もういちど洗濯機をまわす。洗濯機のドラムがぐるぐる回るのを、プラスチックの透かしを通して眺める。ぐおーん、ぐおーん、という音が何度も繰り返される。
死んだ人間に対してできることは何もない。
これはおれが得た数少ない真理のひとつだ。
京都の東の果てにはとても細い川が流れていて、いくら増水してもいいようにかなり深く掘られているのだが、その川には二百メートルほどの間隔で橋がかかっていた。おれは不調があまりにも大きいので半ば当惑しながら川沿いを歩き、二百メートルごとに短い橋を渡った。
どんなことでも死ぬきっかけになるのだが、このときもそうだった。誰にも迷惑をかけずに死ぬ方法を考えはじめた。いくつかプランはあったが、いちばんいいのは、ホームセンターでシャベルを買ってきて、人気のない山に入り、穴を掘ってそこに入り、土を崩して自分を生き埋めにするものだ。(これはいまでも優れた方法だと思う。なにせ埋葬の手間がかからない。)
そんなことを考えながら橋にさしかったとき、おれは短い橋の真ん中に祠を見つけた。そのなかには地蔵がいて、時間や情念や、そのほかのあらゆるものを超越したお顔で微笑んでおられた。おれはしばらくその地蔵をぼんやりと見つめていた。
あまりにもよいお顔だったので、おれはぼろぼろと泣き出した。「なあ、どうしたらいいんだろう、お地蔵さん」とおれは話しかけた。「どうしてこんなに悲しいんだろう。どうしてこんなに暗い気持ちなんだろう」
「それはお前がアホやからや」と地蔵は答えた。
「え?」
「それはお前がアホやからや、言うてんねん」と地蔵は繰り返した。
おれは首をかしげ、まあ気のせいか、おかしな薬で酔っ払っているからだろうと高をくくった。「ほな聞きますけど、なんでアホやと思いますの」とおれは言った。
「おまえは妹が死んで悲しいという。それは当然のことや」と地蔵は語った。「立派な話や。いまの時代にそんな心優しい奴はおらん。感心するわ。しかしね、よう考えてみなはれ、死んだ妹がいちばん望んでいるのは何や? おまえが幸せになることとちゃうんか? 立派な社会人となって社会に出て、ばりばり働いて、妹さんのぶんまで幸せになることちゃうんか? 死んで何になるんや? 頑張れ、頑張れ、頑張れ、頑張れ、応援しとる、君は世界にひとつだけの花」
おれは怒った。
「ワレ、なに言うとんじゃボケ。口当たりのええことばっかり抜かしやがって。壊す」
おれは祠に蹴りを入れた。ずいぶん古くに作られたらしい祠は簡単にばらばらになった。地蔵は岩と一体化していたが、そこまで大きくなく、簡単に持ち上げることができた。おれは地蔵を深くて細い川に投げこみ、地蔵が浅い水を割ってコンクリートの底に当たる音を聞いた。欄干に腹をつけて川を覗きこむと、当たりどころが悪かったらしく、地蔵は首がとれていた。
「おれを舐めとったらそういう目に合うんじゃ、ハゲ」とおれは叫んだ。「ええ気味や。死ね」
するとパトカーがやってきて、おれに職務質問をした。
「お兄さん、なにしてんのん?」
おれは涙によって尋問官と書記の同情を誘うことに成功した。半日ほど拘留されたのちに釈放され、振り返ると建物の看板には下鴨警察署とあったが、そこはおれの見知った下鴨ではなかった。なにもかもが鏡写しになって反転しているのだ。
夜なので方角がわからなかった。おれは仕方がないので茂みに埋まって眠り、小便をしたりげろを吐いたりして時間をつぶした。ときどき笑いが止まらなくなった。おれが酔っ払っていたのは酒ではなかった。造船所でもらった八枚つづりのシールで、キスマークが入っているやつだった。そのキスマークにはこんな文句が書かれていた ——
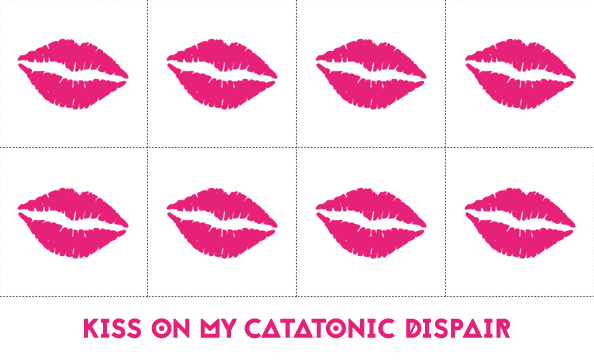 (「おれの緊張性の絶望にキスしろ」)
(「おれの緊張性の絶望にキスしろ」)
美はどこにでもひそんでいる、とボルヘスは言った。ひそんでいる場所は、まったく予想できない。新聞広告の文章かもしれない。庭に生えているオレンジの樹かもしれない。街路に立っている売春婦の誘いの言葉かもしれない。生ごみをついばむ鴉かもしれない。見たところ文字単価0.2円くらいのインターネット上の記事かもしれない。ただし美は、それを求めさえすればどこにでも見つけることができる。
美を求めていないにもかかわらず美を感じてしまう状態のことを、おれはカフカ的神経衰弱と呼んでいる。
カフカ自身による自分自身の診断は、恋人に宛てられた無数の手紙のなかのひとつに見つかる。
「僕はこのごろ、あまりにも感じやすくなっています」
妹が首を吊る直前のことだ。おれは自室で何か自分のことをやっていたのだが、そこに妹があらわれた。部屋には入らずに、ドアを半開きにして、そこからおれの姿をのぞいていた。あまりにも静かだったので、たぶん、おれはしばらく気づいていなかったのだろう。ようやく振り返ったとき、妹はどことなく寂しそうな笑顔を浮かべていた。そして、「ばいばい」と言った。
妹の頓死はほんとうに堪えた。それまでの妹にたいする態度が、すべて取り返しのつかない間違いだったことを宣告されたわけだ。
あのとき、もうちょっと優しくしていれば!
あのとき、もうすこしだけでも話を聞いていれば!
あのとき、心をこめて抱きしめてやれば!
そんなことばかりを考えるようになる。まともな、正常に動作している人間のすることではない。正常に動作している人間は、もっと建設的なことをする。犬が土を掘るみたいに過去を掘り返したりはしない。そういうわけで、こんなものを書いているおれはいまだに正常に動作していないようだ。
ただし、気分はずっとましになった。これは、時の流れだけが成せるわざだろう。
時の流れに取り残されたような左京区の定食屋の座敷で腹がくちくなり、天井近くの棚に設置されたテレビの相撲中継を眺めているとき、いつもおれに料理を運んでくれるおばちゃんがあらわれて、おれにこう言った。
「もう閉店どす」
おかしいな、とおれは思った。そんなに早かったか?
しぶしぶながらおれは店を出た。たしかに客はおれひとりだけだった。おばちゃんは暖簾を外し、立て看板と食品サンプルの入った巨大な台を片手で軽々と持ちあげて、店のなかに運んだ。戸が引かれた。振り返ると、おれは鏡写しの奇妙な京都にいた。それは北白川別当町のあたりだったはずだが、なにもかもが反転していた。あわてて定食屋の戸にすがりつき、拳で戸を叩いたが、戸は夜とおなじ物質でできた鉄に変わっていた。
おれは恐怖に震えながら歩き、大通りらしいところに出た。ふたつの目玉が煌々と光っている巨大な獣がものすごいスピードで駆けてゆき、そのうしろをぴったりと夜がつけていた。暗闇のなかでうっすらと見える並木は枝をいっぱいに広げていたが、よく見るとすべての葉に無数の目玉がついていて、おれのことを見つめていた。雨が降りだしたが、それは雨ではなく蛭だった。
おれは小便をちびり、子供のように泣きながら助けを求めた。
「助けてくれえ、助けてくれよお、怖いよお」
気がつくと、おれは吉田松陰の像の前にいた。それは銅製だった。
あの細い川沿いの地蔵のことも記憶に新しかったので、警戒しつつ話しかけた。
「あんたは話せるんか?」
「話せるで」と吉田松陰は言った。「どないしたんや」
「いや、まじでどうなってんのこれ」とおれは言った。「ぜんぜん見覚えない街やし、樹ぃには目ぇついとるし、像は喋るし。おれの気がちごうたんか?」
「それは知らん」と吉田松陰は言った。
「なんや、知らんて。あんた人が真剣に悩んどんのにその言い草はなんや」
「おまえなあ、もっとシンプルに考えろや、おれみたいな像が喋るわけないやろ? ただおまえがラリっとるだけや。よう考えてみいや、そんなこともわからんのか。ほんまにアホやな。どうしようもないわ。しょうもないわ。身内が死んだ言うて薬食ってラリって小便ちびってなあ。ほんまにお前は最低の人間のクズや。逝ったモンも見たら悲しむわ。お前がそんなんやから妹さんは首くくったんと違うか。そうや。そうに違いないわ。あーしょうもな。しょうもないアニキにしょうもない妹やわ」
「おまえ今何て言うた」
「しょうもないアニキにしょうもない妹やわ」
「その一個前何て言うた」
「あーしょうもな」
「そこはええねん。その前のやつを言え」
「お前がそんなんやから妹は首くくったんと違うか」
「違うわボケ!」おれは吉田松陰を蹴った。
どんどん蹴った。足が腫れ上がってきたし、息もあがってきた。
「悪かったわ」しばらくすると、吉田松陰は静かめのトーンで言った。「そんな怒るとは思わんかったわ」
「白こいわ」
「ほんますまんな」と吉田松陰は言った。「でもおまえの妹は、いまおれの家で犬のちんこしゃぶっとるけどな」
おれは激怒し、吉田松陰に硝酸をかけた。おれは理学部化学科の学生なので、そういうものはたくさん持っているのだ。
「あかんて、あかん……」と吉田松陰は溶けながら言った。
インターネットで検索すると、こんな話が出てきた。
『ポーランドの花占いの表現には、「好き」から「いらない」までのあいだの、非常に多くの表現が含まれています。ステキですよね!』
紫陽花でやるとちょうど良いのかもしれない。
もちろん、妹が死んでつらかったのはおれだけではなかった。おれの親父もそうだった。
彼はたったひとりきりで稼いだ片腕(五百万円という金高のことを、河内ではそう呼ぶ)をはたいて、おれを西欧へ旅行に連れて行った。
それはまあいいのだが、おれが卒業したあと、下宿を引き払おうかという段になって、親父は作戦会議のために大阪から京阪電車に乗って川端四条にやってきた。昼飯をどこで食べるかという話になり、四条大橋の西詰めにある東華菜館という中華料理店に入った。そこには明治のころから動き続けているエレベーターがあり、おれたちはそれに乗り込んだ。鋼鉄の扉ではなく、飾り格子の柵が閉まり、その隙間からビルディングの内側の壁が流れていくのが見えるタイプのものだ。
親父は言った。「こんな古いもんは中々ないで、なあ、兄ちゃん」
エレベーター・ボーイは微笑みを浮かべ、沈黙を守った。
「指挟んだら飛んでいくやろな」とおれは言った。
それからおれたちは中華料理を食べながらいろんな話をした。窓外では、もちろんのことだが、雨が降っていた。やさしい雨だった。降っているのをことさらに主張するわけではないが、かといって無視はできない程度の雨だ。窓からは、いろんな色の傘が四条大橋を渡っていくのが見えた。遠くには霧のかかった大文字山が見えた。
いろいろと大切なことはあったはずなのだが、うまく思い出せない。そして、まったくどうでもいいようなことばかり思い出す。
こんな話がある。瓜生山の中腹にある友人の下宿でパーティーをすることになり、花火と肉を持って山を登っていったのだが、その途中で鹿に出くわした。時刻は夜で、鹿は電柱の灯りの下からおれのことをじっと見つめていた。そして、鹿はゆっくりとした歩みでそばにあった畑のなかに入っていった。
パーティーの帰り、というよりも次のパーティーへ行く途中、下山したところでタクシーを呼び止めた。三つ葉のクローバーが社号になっているタクシーだった。おれは乗り込んで三条東山と告げ、タクシーは走りだした。次の信号で止まったとき、運転手がカードをくれた。そこには「幸福の四つ葉タクシー記念乗車証」とあった。
インターネットによれば、このタクシーに乗車できる確率は約0.28%らしい。
ラッキー!
母親の話だ。
おれの母親は丹波あたりの出身で、子供のころは父親(おれの祖父)の林業を真似して野山を駆け回っていたらしい。祖父が事業に失敗し、大阪に職を求めてやってきたとき、彼女はもう十六歳だった。高校を卒業して明治安田生命の営業職に就き、すばらしい成績をあげ、支社長から表彰されるほどだったが、周囲からのいじめ(女のくせになまいきだ)に耐えきれずに退職した。よくある話だ。
ところで、水上瀧太郎は明治安田生命の専務取締役だったこともある。これは血縁による。
それから、どこかの会社の受付かなにかをやっているとき、自動車のセールスマンにしつこくからまれて、そのうちに結婚した。
それがおれの父親である。
彼らはおれが十四歳のときに離婚した。
以上。
おれたちが生まれてからの母は一度たりとも好調だったことがないらしく、そのことは彼女が家を出るときに忘れていった日記からも読み取れる。というか、おれの想像にすぎないのだが、彼女は調子が悪い日にしか日記をつけなかったのだと思う。日付は飛び飛びであり、最低でも一週間、長い時は一年以上の間隔をあけて書かれていた。そして、すべての内容は身体の不調についてであったり、生きることについての愚痴であったりした。たぶん、彼女は調子の悪さを吐き出しているつもりで書きつづけたが、そのためにはからずも長い年月をかけて、自分を本当に調子の悪い人間に仕立て上げることになったのだ。
いいことはあったのだろうか?
いいことというより、おもしろいことがあった。十六のころ、どこかの店で食事をしているときに、おれが煙草を吸い始めると、身体に悪いからやめなさいと言った。数年後の夜、彼女はおれに声をかけて、もらい煙草をした。
「あーあ」と彼女は言うのだった。「吸ってもうたわ」
「ええやんけ」とおれは答えた。「一服ぐらいせな、やりきれんで」
「それは、ほんまやねえ」
いったい何がやりきれなかったのだろう?
おれはおれの経験した不条理をいつも忘れてしまう。そして、やりきれないという気持ちだけが残る。その積み重ねがおれだ。おれを形作っているのは打ちのめされた経験ではなく、その感覚である。
おれという人間は、見えない糸で撚られた紐みたいなものだ。その先端には馬鹿者が繋がっていて、そいつは煙草をくわえている。
「火ぃ消した? なにわを守る 合言葉」
これは(公人どもの考案にしては)良い出来だ。
「すべてはあるがままにあるのだよ」とビリケンが言った。
「そうなん?」とおれは答えた。
「うむ」
ビリケンは早足に歩いているおれの側をふわふわと浮遊しながらついてきた。彼が座っている台座には英語で『全てのものがそうあるべきことの神』と記されていた。
おれは下鴨納涼古本祭りに行くために河原町通を北上しつづけていたが、やがて行きかう車の排気ガスが嫌になり、賀茂川の河川敷に降りて出て川沿いを歩くことにした。かんかん照りで遮るもののない河原はおそろしいほどの暑さで、水面に反射する陽光がおれの両目をなんども刺し抜いた。
「暑いね」とビリケンは言った。
「せやなあ」とおれは答えた。
「なんだかそっけないね」
おれはしばらく考えて答えた。「お前、なんで東京弁やねん」
「アメリカ生まれだからね」
「何?」
「ほんとうはミズーリ州で生まれたのさ」
「寝ぼけたこと言うな」
「うん、まあ、君が信じようと信じまいと構わないけどね」
カカカカ、とビリケンは笑った。器のでかいやつだ、とおれは思った。
「おまえはいままで会うた像のなかではいちばんええやつやな」
「そうかい? 嬉しいねえ」
「なんでお前はそんなに金ピカなんや?」
「新世界で塗られたんだよ」
「何?」
「もともと木製なのさ」
「おまえはおれの幻覚にすぎないが、なぜおれの知らないことまでそんなに自信たっぷりに言える?」
「君はあとからインターネットで調べて、僕の言ってたことがすべて本当だとわかって、びっくりするのだろうね」
「するのかもしれへんなあ」
カカカカ、とビリケンは笑った。
そうこうしているうちに鴨川デルタがあらわれた。この三角州こそが、京都の碁盤の目を突刺す鋭い刃先である。ここを境に北へ向かうほど京都の地形は混乱し、それにともなっておれの頭も混乱することになる。あわてて南へ引き返し、碁盤の目に戻ったところで手遅れである。すでに混乱に適応しはじめた知覚は、むしろ秩序のほうをよりひどい混乱と捉えてしまうのだ。
おれは鴨川デルタの先端からふたつの川をまたぐように配置された飛び石を歩き、無限に広がっていく終わりのない中州を北上して、下鴨神社の森にたどり着いた。開けた参道に数え切れないほど多くのテントが開かれ、その下にたくさんの書架が並んでいる。団扇をもらい、それで首のあたりに風を送りながら手当たりしだいに掘りかえし、気に入ったものは値札も見ずに購入して、リュックサックのなかに放り込んでいく。
肩までシャツをまくった女の子が、氷水をいっぱいに張った巨大な青い箱のなかのラムネを売っている。女の子はにこにこと笑っているが、うまく顔を見ることができない。おれの認識能力は、ずっと以前からだんご虫程度に下がっているのだ。ラムネを飲むおれのそばでビリケンがふわふわと浮いている。ビリケンはにんまりと笑顔をうかべておれに言う。
「あんた、アホやなあ」
それともあの女の子が言ったのだったか?
おれはかつて十代だったし、いまは二十代で、もうすぐ三十代になるだろう。十代のとき、おれはコンピューターとインターネットに夢中になり、昼夜を問わず電子の海を泳ぎ続けていた。すごい時代だった。おれはさまざまなものを鑑賞して楽しんだ。
そして、肉体をもたない、声と文字だけの数十人の友達がいた。おれたちは電子の海でスポーツさえ楽しんだ。一日に八時間ばかりそのスポーツをやったあと、寝るまでのあいだすべての接続を切り、すばらしい薫りのする孤独をぞんぶんに味わいながら映画を見た。
そして、口にするのもおぞましい蛇のような人間たち —— 肉体をもった人間たちがやってきて、聖域を破壊した。いや、破壊はしなかった、ただ、くだらないビルディングをあっちに建て、こっちに建て、金儲けをはじめた。
そういうものだ。
ある日、おれは目覚めて、いつものように坂道を下って街へと出て行く。京都市バスの3番に乗って、南へと向かう。バスが直角に曲がるたびに、襟首をつかまれて引きずり回されている気分になる。百万遍、河原町今出川、京都市役所前、河原町三条、河原町四条。
京都に住んだことのある人間なら誰でも知っているが、この街には何かの間違いでできあがった細長い路地がいたるところにあり、そのうちのいくつかはワームホールである。たとえば、裏寺町通りのコンビニエンスストアには、便所のそばに裏口へ通じる扉がある。そこを開けて出ると、ビルとビルのあいだの空隙があり、身体を横にして進んでいくと、千本中立売付近の料理屋群に出る。ほかにもいろいろあるが、秘密にしておく。
京都というだだっ広い街のさまざまな場所のどこに行っても、いつも似たような学生たちが散見されるのは、彼らがこのワームホールを使いこなしているからだ。それに、交通機関もたくさんある。地下鉄、市バス、タクシー。時間は節約しよう、青春は短い。
ワームホールや交通機関のことは置くとして、おれは実によく歩いた。歩いていると気分がよかった。とくに、春と秋がいちばんいい。夏は冗談じゃないくらい暑く、冬は雪が降るのだ。おれは素足にスニーカーを履いて歩き回った。
ときどき、酔っ払っているわけでもなく、ほんとうに道に迷うことがあった。どの通りも覚えがなく、地図もなくて、途方にくれながら歩き回る。昼なら太陽の位置からおおよその方角がつかめるが、夜となるともうどうしようもない。
部屋の壁に画鋲でとめた世界地図が風に吹かれ、壁とのあいだに空気を含んでぱたぱたと音を立てている。雨が降っているが、そこまで強くはないので、窓は開けたままにしている。ソファに座っていると、風が四肢を撫でる。
窓外の、すこし離れたところには大阪のビル群が並んでいる。白と赤と黄色と青のライトがすべての建物にくっついている。地面には大小さまざまな光が輝いている。都会の灯りのために、ビルの影のほうが夜のように暗い。その暗いビルのあいだに、赤い満月がのぼっている。赤い月はただそこにあり、じっと見つめていると、非常にゆっくりと上昇していく。
おれはなにをまなんだ?
おれは外に出て、傘を差さずに歩く。雨はずいぶん弱まっている。おれは雲の上にいるたくさんの天使たちが地上にむかって霧吹きをふきかけているところを想像する。頭の上には巨大な都市高速があり、その下の大きな通りにはだれもいない。理由はわからないが、すべての電灯は黄色っぽい光を放っている。
ぽわーん、ぽわーん、ぽわーん、という八十年代のシンセサイザーみたいな音がするので上を見ると、そこにはアダムスキー型のとてもりっぱなUFOがいた。皿のうえに逆さにした茶碗を乗せたような形だ。てっぺんには月とおなじくらいの明るさのライトがついていて、窓はおれの立っているところから三つ見える。真ん中の窓の後ろに誰かが立っているようだが、UFOのなかの光で逆行になっていて、よく見えない。
UFOは、ぽわーん、ぽわーん、ぽわーんという音を発しながらおれの立っているすぐそばまでやってきて、着陸した。茶碗にすうっと線が入って、ぱかりと開いた。なかの様子が見えたが、ひとことで言えば、ロシア構成主義をとりいれた数寄屋造りみたいな内装だった。
「やっと見つけたわ!」と中から声がして、青い目をしたブロンドヘアーの女の子があらわれた。おれはびっくりした。彼女はおれが大学のときに受けていた英語のクラスの先生で、おれは彼女に秘めたる恋をしていたのだ。
「先生、お久しぶりです」とおれは東京弁であいさつした。
「ひさしぶり」と彼女は答えた。「さあ、中に入ってください!」
彼女は小柄なくせに出るところが出ていて笑顔がとってもかわいいのだ。おれは一も二もなくうなずいて、乗船した。プスーン! という音がしてハッチがしまり、おれたちはペテルギウスにむかって出発した。
それがどうした?
空間の無駄遣いだ。
妹がトタン屋根の梁から自分自身をぶら下げる十日ほど前、おれはパーティー会場の壁際に設置されたパーティションの裏側の仮設楽屋のようなスペースで椅子に座り、硫酸を飲んだみたいに痛む胃を抱えたまま、よく冷えた白ワインを飲んでいた。胃が痛むのはなぜなのかわからなかった。申し分のない生活だった。女の子たちはかわいいし、教授たちとの議論は面白いし、図書館には本が山ほどあって、友人たちと毎晩のごとく酒を飲んで哄笑し、旅行をし、花見をし、海水浴をし、紅葉狩りをし、雪見をし、初詣をし、伏見稲荷で引いた御籤は大吉だった。
そしておれはすべてのことにかかわらず痛む胃を抱えたまま白ワインを飲んでいた。
同級生の女の子がなにも食べていないおれを心配して、立食パーティーの余りものを皿に盛って運んできてくれた。おれは味のしないスクランブル・エッグを一口食べ、塩辛いサラミを二枚食べた。
「もうええの?」とその女の子は言った。
「うん」とおれは言った。「胃が痛いねん」
「大丈夫なん?」
「だいじょうぶ」
「ムリしたらあかんで。あ、うちも食べよ」
女の子はべつの皿を持って食べ物をとりに行き、おれのところに戻ってきて食べ始めた。
「おいしいわぁ」
「おいしいねえ」
「こんなおいしいもん中々食べられへんで」と女の子は言った。
「ほんまやで」とおれは言った。「ビジネスホテルの朝食みたいな味や」
ハッハッハ、とおれたちは笑った。女の子はどんどん食べ、皿が空になるとパーティションで仕切られた楽屋から出ておかわりをし、また入ってきては食べた。
「そんなに食べて大丈夫なんかいな」
「大丈夫やで」
女の子のお腹はどんどん大きくなり、横に膨らみはじめ、しだいに縦にも伸びていった。おれは黙ってワインを飲み続けた。そのうちまた胃がきりきりと痛みはじめた。
「胃が痛いんだ……」とおれはつぶやいた。
しかし、女の子は消えていた。というより、膨らみすぎて宇宙とおなじぐらい大きくなっていた。というより、女の子こそが宇宙であり、宇宙こそが女の子だったのだ。
「なるほど!」とおれは言った。
そして気絶した。
ちなみに、妹が死んだのはこの夜から二日後のことだ。
目覚めたとき、おれはブロンドヘアーの女の子と一緒に宇宙船に乗ってペテルギウスを目指していた。合成食料のチップスを食べながらネットフリックスで『ゲーム・オブ・スローンズ』を見ていると、二人ともそんな気分になってきた。このまま事に及ぼうかと思ったが、ふと窓に目をやると、おそろしい事実に気づいた。この宇宙はビジネスホテルの朝食みたいな料理を食べ過ぎて宇宙とおなじくらい大きくなってしまった女の子そのものなのだ。そこで事に及ぶということは、一部始終を彼女に見られてしまうことになる。あの子は話していて気分のいい明るい子だったが、他人のうわさを誰彼なくしゃべってしまう癖があった。もしこんなところで事に及んだら、おれの学生生活はどうなる?
そういうわけで、おれはブロンドヘアーの英語教師と事に及んだ。やたらと声が大きかった。そういう教育を受けたのかもしれない。
事に及んだあと、英語の先生はしばらくのあいだおれの腕を抱いてまどろんでいたが、ふと上半身を起こして、船の前面にディスプレイされている地球の映像を見はじめた。太陽に照らされている面は明るく、照らされていない面は暗かった。
「いまブリテンは夕方くらいで、日本は真夜中なのね」と先生は言った。
「そうですね」とおれは答えた。「故郷の町の名前は?」
「ウォールゼン……」
先生は眼を細めた。
「スペルは?」
「W・A・L・L・S・E・N・D」
「壁の終わり? それとも……」
「わからない」
じっと地球を見ていると、ゆっくりと雲が動き、影が東へと動いていくのがわかった。おれは感心した。あそこにはたくさん人間がいて、生活しているのだ。喧嘩をやらかし、手を繋ぎ、泣いたり笑ったりして、いったい何のためにやっているのかまったく知らないままに、運命に従って生きているのだ。
いきなり、光の爪楊枝のようなものが宇宙空間から伸びて、地表を突いた。しばらくするとその爪楊枝は消え、突かれた部分はあとかたもなく消え去っていた。消え去ったのは、先生の故郷だった。故郷が属していた島国ごと消えていた。先生もおれもしばらく何も言わなかったが、やがてふたりでしくしくと泣いた。
そういうものだ。
京都で貧乏暮らしをしている学生のところに、貧乏の匂いをかぎつけた過去の英霊たちが現れ、もてなして冥界へ誘おうとすることがよくある。おれ自身もそういった体験をした。以下に、その経緯を簡単に記す。
おれが下宿していたのは志賀越道という、その名の通り滋賀へと抜ける道沿いのアパートだった。六畳一間で風呂はなく便所は共用だった。夜になると山のほうでもののけたちが動く気配がし、夏になると蛍光灯に導かれた蛾がひっきりなしに舞い込んでくるような部屋だ。
ある夜のこと、近所の銭湯から湯浴み道具をかかえて下宿に戻ろうとしていたのだが、通りの奥から牛のいない牛車がゴトゴトと音を立てておれのほうへ向かってきた。全体が青白い微かな光を放っていた。牛車はおれの前で停止した。おれは困惑しつつ待った。人が乗るところのすだれが開いて、男が顔を出した。
「誰や自分?」と彼は言った。
おれは名乗った。
「なるほど。麿は太平大公中納言左之峰氏なり。長いから左之、言うてくれたらええわ」
「左之さん」
「はいはい」
「あんた幽霊?」
「まあ、幽霊みたいなもんやわ」
えーっ、とおれは思った。
「ボク、はじめて見ましたわ」
「そうかいな! 自分京都住んでナンボ?」
「三年になりますか」
「そうかいな! 早い方ちゃうんかな? 土地のひとはよう見るみたいやけどねえ」
「そうなんですか」
「そやねん」左之さんはにっこり笑った。「なあ、これから志賀越道抜けて琵琶湖行くねんけど、一緒に行かへん?」
「いやー、幽霊と同乗はちょっと」
「酒あるで?」
「うーん」どうせまた、自分でも気がつかないうちにおかしなもので酔っ払っているのだろうと思った。だったら別にいい。「それは魅力ですなあ」
「せやろ。行こうや」
左之さんはにこにこしていた。
「では、ありがたくご随伴させて頂きます」
「おう! 丁度よかった、退屈しとったんや」
おれはいそいそと牛車に乗り込んだ。
「けっこう広いんですね」
「四人乗りやからな」
「ほー」
「新車やで?」
「すごい!」
おれが腰を落ち着けると牛車は動きはじめた。
「ままま、ひとつ」
左之さんが盃をさしてくれた。
「これはどうも」おれは献杯して干した。「うまい酒ですなあ!」
「せやろ。伏見から上等を取り寄せたんや」
「わざわざ伏見から! 人の足だと大変でしょう」
「まあ、いまはネットあるからな。アマゾンが高瀬舟で運んできよるわ」
「お住いは?」
「二条のあたりやね」
「だいぶん偉いさんとちゃいますの? ええんかな、ボクこんな感じで」
「かまへんがな。気ぃ遣わんでええ。このまま琵琶湖までひとりやったら退屈やなあ、邪魔くさいなあとか思うてたところや。丁度よかってん。好きにしてくれたらええで」
左之さんはにこにこ笑いながら盃をさしてくれる。
「ありがとうございます」
「うん、飲め飲め」
おれたちは酒を飲みながら楽しく琵琶湖を目指した。
「ほんで琵琶湖に何しに行くんですか?」
「うん、黒船が来とるちゅう話やからね、ペルリに会いたいなあ思うて見に行くねん」
「へえ。アポ取ったんですか?」
「アポなしや。そもそも連絡先も知らんし」
「飛び込みでっか、よろしいでんな」
「せや! やっぱり京の都を元気にするには麿みたいな官僚が頑張らなあかん。地場の企業の営業マンのほうがよっぽど偉いわ。麿もあいつらを見習ってペルリに顔売って、下のもんが仕事やり易いようにしてかなあかん」
「いよっ、日本一!」とおれは叫んだ。
牛車は志賀越道の半ばほどまで来ており、山越えの上り道が終わりかけたところだった。突如として木々の影から黒ずくめの忍者の一団があらわれ、牛車のまわりを取り囲んだ。牛車は停止した。
「何奴!」と左之さんは言い、すだれを開いて首を出した。
「攘夷!」という声が聞こえ、刀が振り下ろされ、すぱん、という音がした。左之さんの頭は幽霊なのにころんと転がって、志賀越道の山道をおむすびころりん的にころころと転がっていった。
忍者たちは快哉を叫んだ。
「やったぜ!」
「夷狄に与する国賊を仕留めたぞ!」
「これぞ攘夷!」
「我らこそ義賊!」
「尊皇攘夷! 尊皇攘夷!」
「攘夷! 攘夷! 攘夷!」
攘夷の合唱が続いた。
おれはどうしていいかわからずに牛車のなかでじっとしていたが、そのうちにぎやかな攘夷の声は遠のいていった。すると止まっていた牛車が勝手に動きだしておれを琵琶湖まで連れていった。左之さんの首なし死体(霊体?)は鎖骨を畳につけて尻を突き出した状態でぐらぐら揺れていた。
琵琶湖にたどり着いたが、黒船の姿はなかった。当たり前だ。まさか黒船が大阪湾から淀川をのぼって琵琶湖に来る訳はない。
左之さんの首なし死体は琵琶湖に葬った。宗派がわからなかったので、南無阿弥陀仏と唱えておいた。それで文句を言う人でもあるまい。
おれは牛車に乗って残された酒を飲みながら、来た道を戻った。左之さんがいないと、風に揺れる草花や木々の葉の音がよく聞こえ、なんだか寂しい気分だった。アパートの前まで来ると、牛車はひとりでに停まった。おれは牛車から降りて、一度だけ振り返り、自分の部屋につづく階段を登った。
湯浴み道具は牛車のなかに忘れた。
憂鬱症の男が気分を紛らわせるために街をさまよう。彼はアパートメントの一室に戻ると、自分の首吊り死体が天井からぶら下がっているのを発見する。彼はあわてて警察に電話をかけるが、電話はつながらない。アパートの階段を降りて、一階の大家の部屋の扉を叩く。返事はなく、誰も出てこない。いくつものドアを叩き、隣家にも助けを求めるが、誰も現れない。彼は町を歩くが、通行人は誰もおらず、すべての店は閉まっている。そして彼の背後で、大きなドアがばたんと閉まる音がする。
それでおしまい。
個人的な体験などひとつもない。おれが行うことはすべて、誰かがすでにやったことだ。肉体的な快楽や熱にうなされること、特定の店で出される特定のコーヒー、肉親を喪う苦しみ。普遍的でないことは、この世にひとつもない。
ボルヘスは言った、「まったくおなじ瞬間が二度繰り返されるのであれば、それは時間の連続性を崩壊せしめるものである」。
その通りだ。
彼はつづけて述べる、「連続体である空間が存在しないのであれば、どうしてもうひとつの連続体である時間が存在すると言うことができようか」。
記憶による過去も想像による未来も存在しないのであれば、現在をそこから切りわけることなど不可能であり、したがって現在から派生する幸福も苦しみも存在しない。
そこにはまことの法悦に満ちた永遠だけがある。
では、なぜ涙が溢れるのか?
おれの部屋には三種類のものがある。本と、いくつかの楽器、それにコンピューター。まあ、よくある感じだ。
おれの部屋のなかにあるもっともおもしろい物は、おれが子供のころから溜めつづけている雑多な家電製品のコードだろう。電源ケーブル、音声や映像の入出力端子、LANケーブルなどなど。それらのコードは、長年のあいだ積み重なった怠惰のためにきちんと整頓されておらず、たがいに絡みついてひとつの塊と化している。
ときどき、使っている家電製品のケーブルがなくなると、おれはその塊を解きほぐして目当てのケーブルを探しだす。古い、もう誰も覚えていないような出力規格をもったケーブルや、古き良き時代を思い出させる商品名が記されたラベルつきのACアダプタに混じって、お目当てのものが見つかる。おれは塊のなかからその一本のケーブルを抜き取り、べつの部屋で家電製品に接続する。そういうとき、おれの頭のなかにはいくつかの考えがひらめく。
牛車の話だ。
眠ったのは部屋に帰ってからだと思っていたが、そうではなかった。おれが目覚めたのはオレンジ色のホンダ・シティの後部座席のなかだった。ルーフを全開にしていたので、顔に虫かなにかが当たり、それで目を覚ましたのだ。目を開けていられないほど眠かったが、車は時速八十キロで川端通りを下っており、風の音が大きすぎて、もういちど眠ることはできなかった。
運転しているのは、いつの日かにおれを雨宿りさせてくれた先輩だった。
「先輩、飛ばし過ぎとちゃいますか」とおれは叫んだ。
「何?」と先輩は叫び返した。
右手に並ぶ鴨川沿いの柳がどんどん後ろへ流れていった。追いぬかれた車も、対向車も、おれたちにむかってクラクションを鳴らした。左手に並ぶ家々や商店の並びは一瞬の光の軌跡を残して視界から消えた。歩行者たちはおれたちの姿を見て大仰に身体をのけぞらせた。おれは身をかがめて煙草に火を点けたが、すぐに火種がどこかへ吹き飛んでしまった。信号待ちをしているときにパトカーがあらわれて、おれたちを追跡しはじめた。東山三条界隈の、通り名をもたない細長い道に入って追跡を免れたが、その過程で三つのごみ箱と二匹の猫を轢いた。
コンビニエンスストアでウエスを買い求め、汚物にまみれたシティをきれいに磨き上げたあと、おれたちは三条河原町のすぐそばの名前のない通りに入った。ルーフをあけたままのシティはとてもゆっくりと、静かにその通りを進んだ。おそろしく暑い夏だったが、その夜にはきまぐれな涼風が肌をやさしく撫でた。細い通りには、階級の低い天使のような薄着の学生がたくさんいて、みな笑顔を浮かべていた。漫然とした気持ちでその光景を眺めた。そのとき、人々のなかから浮き上がるように見えたが、白いノースリーブのブラウスを着た女の子が、男の子と手をつないだままおれたちの側を通りがかった。おれは後部座席に頭をあずけていた。女の子は一緒に歩いている男の子にやさしい視線を投げかけていたが、ふとおれたちの乗っているシティに目をやり、このおもちゃみたいなかわいい車はいったいなんだろう、という顔をした。おれはその女の子に見とれていたが、そこで女の子と目があった。女の子があまりにも美しかったので、おれは微笑みを浮かべた。
すると、女の子も微笑みを返してくれた。
それは一秒にも満たない間に起きたことだったが、女の子がおれになにを言おうとしたのか、いまのおれにははっきりと判る。
「ねえ、こんな夜がずっと続けばいいと思わない?」
喪は永遠に消えない。五年、十年はあっという間に過ぎ去るだろう。そして人々は生き延びるだろう。しかし、元通りにはならない。脳は破壊され、心には傷が残る。その痕跡は時の流れのなかで人格と溶けあい、生は、もはや記憶ではなく忘却によって規定されることになる。彼は、彼女は、とにかくその人格とともに生きなくてはならない。発話もままならず、あらゆるものに置き去りにされるだろう。すべてに疑いの目を向け、どこまでもつづく地獄を思って嘆息するだろう。
それでも彼らはのそのそと歩き続けるだろう。このばかげた騒ぎをみんなで続けるために。
電子的なスポーツの話だ。
そのスポーツはふたつのチームに別れ、片方がゴールを守り、片方がゴールを攻める。途中でいちど攻守を交代し、攻め落とすまでに要する時間を競う。電子的な肉体でぶつかりあい、旗を取ったり守ったりする。
これは集中力と反射神経、そして刻々と変化する状況に対応するための柔軟かつすばやい思考が必要なスポーツである。
おれはこのスポーツを八年間やりつづけた。そして、誰もいなくなった。馬鹿馬鹿しい乱痴気騒ぎが終わったあと、みなが家に帰り、次の日からフィールドに姿を見せない。文化というのは、そういうものだ。
画像が出力され、ディスプレイに表示されるまでの時間のことを応答速度という。この速度を改善するために、おれはわざわざ二十年もののブラウン管をヤフー・オークションで手に入れ、米俵くらい重たいそれを自室に運び込んだ。そのモニターを使い始めてから、成績はおもしろいように伸びた。
電子的なスポーツが衰退し、誰ひとりプレイヤーがいなくなったあと、九月のよく晴れた気持の良いある日、そのブラウン管はブツンという音をたてて壊れた。一本の白い線だけを残して、ほかにはなにも映しださなくなった。
この話から得られる教訓はひとつ。永遠につづくものは、この宇宙にはない。
三菱ダイヤモンドトロンRDF192S、それがブラウン管の商品名だった。
入力端子のケーブルは、いまだにコードの塊のなかにある。
その日は雪が降っていた。おれは上着にポケットをつっこみ、背中を丸めて、見えないところからとつぜん現れては地面に積もっていく雪のなかを歩いていた。長いこと食べていなかったし、アパートにはひとかけらの食料もなかったのだ。真夜中だった。
いくつかの友人たちのドアを叩いた。いや、そのときにはもう友人とは呼べなかったかもしれない、だから、ただの知り合いのドアだ。とにかく、すべてのドアが閉ざされたまま、開くことはなかった。おれが拳を叩きつけると、ドアは凍った。
このあたりで雪が降るのはめずらしいことではない。おれはドアからドアへと歩きながら、退屈しのぎに雪だるまを作ることにした。握り拳をふたつ合わせたくらいの大きさの塊からはじめて、足で蹴り、手で押し、さいごには肩で押して歩いた。自分の胸くらいまで塊が大きくなり、どうしても動かなくなるというところで、北白川今出川の交差点に差しかかった。そこは西にむかって続く長い下り坂の始点だった。雪の塊は重みのために低い方へと動き、やがて雪を軋ませながら転がりはじめた。おれはそれを止めるために追いかけたが、転がりながら雪の塊はどんどん大きくなり、やがておれの背丈を超えた。おれは止めることをあきらめて、並走しながら、どうなるか見守ることにした。
志賀越道と今出川通りの合流点のところには祠があり、高さ二メートルほどある地蔵が祀られている。巨大な雪だるまはその地蔵に激突し、音をたててばらばらに砕け散った。おれは地蔵が傷ついたのではないかと心配になり、しばらく調べたが、異常はないようだった。なんだか拍子抜けして家に帰ろうとしたとき、建物と建物の間、そのむこうにある闇のなかに白い雲のようなものが浮かんでいるのが見えた。
雪が強くなった。おれは目を細めてその雲を見た。遠くから、鈍い、ずうううん、ずうううん、という音が聞こえた。とても低い音だった。その音がするたびに、白い雲はゆっくりと近づいてくるようだった。
それは雪だるまだった。
雪だるまはとても大きかった。
おれは立ち尽くした。
「お・い・で……」と雪だるまが言った。低い声だった。
雪だるまの鼻はクリスマスの飾りがついた樅の木で、目玉は建築物の解体に使うような鉄球だった。帽子は比叡山で、口は三日月だった。
「お・い・で……」
おれは叫び声をあげて逃げたが、後ろから覆いかぶさられることはわかっていた。走りながら息が上がってきて、これ以上はもう動けないというときにやられるのだ。
妹が死んでしまったとき、おれはこのことを書くのだろうと思った。そして何度も試したが、うまくいかなかった。理由はかんたんだ。
おれは妹のことをよく知らない。
遺品はまたたくまに処分された。残されたのは、写真ばかりである。死人に属していたものはすべて、きれいさっぱりと捨ててしまうこと、それが生き残るための秘訣なのだと父は考えていた。そうすることで、穢れを払うのだ。おれにはどんな意見もなかった、というのは、他者の死に接するのはそれがはじめてのことだったから。死に関する意見があるはずもない。おれたちは冷静に遺品を処分した。
死体になった妹は臓腑を抜かれ、仏間に敷かれた布団のなかに横たえられた。死化粧を施された顔がおそろしく美しかったことを覚えている。身体中にドライアイスを仕込まれていて、手は冷たかった。父親は右側にいて、泥酔したままいつまでも死人の手を離そうとしなかった。頭のうえには、仏壇があった。その仏壇はなかなか良い出来で、収められた仏像の顔は小さかったが、慈しみをたたえていた。
おれが妹について言えるのは、これだけだ。どの学校に行って、何歳だったのか、どんな食べ物が好きで、お気に入りの歌手は誰か、それくらいのことは知っている。でも、それ以上は知らない。恋をしていたか、なぜ逝くことに決めたのか、どんなことを考えていたのか、何も知らない。
だから、おれは物事をシンプルに受け入れようとした。あるひとりの人間が生きていて、ある日、死んでしまった。それだけのことだ。ある人間がひとりこの世からいなくなり、もう二度と会うことができない。それだけのことだ。
そこにはどんな物語もない。原因もない。結果だけがあり、それは金糸で縫われた布団のなかに眠る妹の死体で、いまではおれの記憶のなかにいる。
そしておれも憂鬱症を発症した。とりたてて好きでも、嫌いでもなかったはずなのに、彼女がいないことがたいへん寂しく感じられた。
いまでは、そうしたことも本当に起こったのかどうか自信がない。記憶というものは、あいまいなものだ。
そして悲しみというものは、わがままなものだ。おれは妹のことをほとんど語らず、自分の悲しみのことばかりを語っている。
他人について語ることほど、空虚なことはない。語っているうちにだんだんと、ほんとうらしい言葉が失われていく。
おれの両親は、おれが十四歳のときに離婚した。その理由はよく覚えていないし、あらためて電話をかけて、父に聞く気にもなれない。ただ、おそらく母が家を出て行った日の晩のことだろう。父がテーブルに座り、ビールが半分ほど入ったグラスを手に持ったまま、悪くなった魚のようなどろりとした目で中空を見つめていたのを覚えている。おれはたしか、なぜ母が出て行ったのか質問したはずだ。
「そんなふうに出来とるねん、人間の関係というもんは」と父は答えた。
その発言は楔のようにおれの心に打ち込まれた。ふたつの車両がおなじレールを走っている。ひとつが切り替えポイントを過ぎたあと、誰かがレバーを引く。それで、もうおしまいだ。どれだけの時間をともに過ごしたかなど、なんの関係もない。ふたつの車両は、二度と出会うことはない。
おれはさまざまな人と出会い、さまざまな人と別れた。誰もがそうだろう。繰り返しだ。これは原則なのだ。
おれが死ぬときにこの世界は終わり、その原則も無効となるだろう。時の流れは、口を合わせた二本の試験管のようなものだ。なかにはヘリウムガスが充満していて、おれが動くと光が起こる。試験官のまわりには、なにもない。無だ。それは闇ですらなく、紫色のブーンという音ですらない。ただの無だ。
何もかもが終わるだけだ。燐寸のようなものだ。ぱっと灯りがついて、消えて、それでおしまい。
あまりにも無力だ。
せめて、風や鳥の鳴き声とおなじようなものでありたかった。ひとりの人間ではなく、地平線や、稜線や、海のようなものでありたかった。太陽でも、石ころでも、切り株でもいい、そうしたものでありたかった。
おれは志賀越道と今出川通りが交わる地点の大きな地蔵の前で目を覚ました。
視界の端に地蔵のご尊顔があったので、場所はすぐにわかったが、どうしても身体が動かなかった。たくさんの蛇に体中を弱く噛まれているみたいな感じがした。とりあえず右足が動いたので、そこだけ動かしているうちに、だんだんとほかの部位も動かせるようになってきた。ゆっくりと身体を起こしたが、節々が傷んだ。脈打つごとに誰かに殴られているみたいだった。体じゅうについた雪のかけらを払い落とし、ポケットから煙草のパックを取って、一服つけた。
雪はさらに降り続いたらしく、気絶したときよりも多く積もっていた。京都市というよりも、日本海沿岸のどこかの街みたいだった。あまりに雪が多いので空すら白く、無数の屋根のあいだから覗いている無数の家の外装だけが黒かった。長く続いた戦争のあと、あらゆる色が白にやられてしまった、という感じだった。
おれは歩いた。行き先はなかった。何をどうしていいものか、わからなかった。
どこへ行けばいいというのだ?
おれは神社のようなところにいて、ポケットに両手を突っ込んだまま、中庭に立ち尽くしていた。誰の姿も見えなかった。みんな家のなかにいるのだろう。
本殿の賽銭箱の上にはりっぱな鈴緒があり、縄のいちばん上には、人の頭くらいの大きさの玉虫色の鈴がくっついていた。
その鈴のひとつには家電製品の延長コードが巻きつけられており、余りがぶら下がっていた。
さらにその余りの先に人間が首からぶら下がっていた。近づいて見てみると、その人間はおれ自身だった。
ぶら下がっているおれは目を閉じ、口を一文字に結んで、もう感じないはずの寒さにじっと耐えているように見えた。すこし伸びた前髪が瞼にかかり、睫毛に雪のかけらがついていて、無精髭が伸びていた。彼は —— おれは —— 寒そうであるのを別にすれば、とても安心しているように見えた。家族や、友達や、恋人のそばにいる人のようだった。何もかもを許し、何もかもを認めた人のようだった。
おまえはなぜ死んだ、とおれはおれに向かって言った。
そういうもんや、とおれは答えた。
しかし、それはあんまりじゃないか、とおれは言った。
何がやねん、とおれは答えた。強風が起こり、おれはすこし揺れた。
だって、おれたちは、まだ何にもしてないぜ。
何にもって、何やねん。
沖ノ鳥島に海水浴に行ったり、凍ったままのコケモモを口に含んだり、温泉玉子を作ったり、自分とちがう人種とセックスをしたり、東南アジアに行ったり、してないぜ。
忘れろ。
忘れるって、何を。
もう終わったんや。
延長コードがぶつりと音をたてて切れ、おれは地面に落ちた。からからん、という鈴の音がした。おれはしばらく地面に落ちたおれを見ていたが、どうするつもりもなかった。おれは悲しくなかったし、寂しくもなかった。それはたぶん、おれ自身もおなじだっただろう。
そういうものだ。
ブロンドヘアーの先生といっしょに宇宙船のなかでひとしきり泣き通したあと、おれたちは理由付けを始めた。けっきょく、すべてはダーウィン的な淘汰の結果なのだとか、宇宙のそもそものはじまりからこうなることは決まっていたのだとか、いろいろ理由をこさえた。
悲しみは消えなかった。
「あなたを助けてあげられなくてごめんね」と先生は言った。
「どういうことですか?」とおれは答えた。
「だって、あなたはただの魂だもの。私たちはいまから、ペテルギウスにある天国に行くのよ」
「そいつはいいなあ」おれは彼女の言うことをまったく信じていなかった。
「ペテルギウスはとても遠いから、時間の流れ方が違っていて」と彼女は言った。「そこでは過去に向かって未来が流れるのよ」
たしかに、ペテルギウスはとても遠かった。あまりに遠いので、宇宙の中心を通り過ぎてしまい、空間の座標値が負の値に達して、たどり着くころには時間の流れが逆転していた。天国のつくりは非常にシンプルで、完全に平坦な白い床がどこまでも続いていた。先生によれば、この床には厚みがなく、歪曲していて球体のようにつながっているのだが、球体の中心はどこにもないのだという。
「永遠みたいなものなの」と先生は言った。
「ふーん」とおれは答えた。
「さあ、妹さんに挨拶してらっしゃい」と先生は言った。「私はウォールゼンに帰って、晩ご飯にママが作ってくれた鰻のゼラチン寄せを食べるわ」
そして先生はポンッという音をたてて消えた。あとには白い煙だけが残った。
「手品みたいやな」とおれは言った。
妹はすぐ近くにいた。ということは、とても遠くにいたということである。過去と未来が逆転しているので、すべてがあべこべなのだ。そのときおれが妹と交わした会話をどう言い換えていいものかわからないが、とにかくこんな話をした。
こんな話をしたというより、こんな話をするだろう。そんな感じだ。
「さようなら」
「さようなら」
「わたしは誰?」
「おれは誰?」
「うん?」
「うん?」
妹の顔にはなにもなかった。のっぺらぼうなのだ。白っぽい平面があるだけで、なにもなかった。服を脱がせるとマネキンみたいになっているのだろう。
ここまでおれは彼女のことを知らなかったのか、という気がした。
これは妹ではないのではないかという気がしはじめた。こんなにのっぺらぼうなわけもあるまい。そこで、身元確認のためにいくつか質問をしてみた。地球的な意味に翻訳できるような会話はひとつもできなかった。そして気づいたが、おれは妹のことに限らず、あらゆることを忘れていた。自分の顔を触ってみると、妹とおなじようにのっぺらぼうだった。何もついていない、瞳すらないのだ。だとすると、いま見えているものは何だろう。
そして妹はポンっという音を立てて消えた。白い鳩が数羽飛び去って、あとには白い煙だけが残った。
「何なん?」とおれは言った。
おれは地面に寝ていた。雪は降っていなかったが、積もったものが残っていた。ぶあつい雲の隙間から午後の太陽がすこしだけ見え、あたりを照らした。
おれは鳥居をくぐって神社を出た。それから、大文字山にむかって歩きはじめた。それは御蔭通だった。北白川通に向かってなだらかに上っていく道だ。途中にあるのはおもに民家と、フランス料理屋、散髪屋、喫茶店、整骨院、蕎麦屋などである。膝がこちこちに凍っていてうまく足が上がらなかったが、踵を引きずって歩いた。途中、何度か転んだが、あまり痛くなかった。
北白川通にたどり着くと、ちょうど近所の大学で授業が終わったところなのだろう、たくさんの学生たちが通りを歩いていた。彼らは、赤や青や緑色の、さまざまな形をしたコートを着て、楽しそうに会話をしながら歩いていた。女の子たちが声をあげて走り去っていったが、走りながら雪合戦をしているのが見えた。男の子たちが湯気のたつコップ酒を飲みながらゆっくり歩いていった。年取った夫婦が手を繋いで歩いていった。栗色の毛をした小鳥が並木のなかから人間たちのことをじっと見ていた。
おれは着ていた服にこびりついた雪と泥をできるだけ丁寧に払い、大文字山に向かった。雪のなかに埋まった並木の枯れ葉を踏みつけると、チーズ・クラッカーを齧ったような音がした。おれは想像のなかで何十枚ものチーズ・クラッカーを齧りながら歩いた。ちいさな本屋があり、ラーメン屋があり、中華料理屋があり、クリーニング屋があり、よくわからない小物を売る雑貨店があり、スーパーマーケットがあり、パン屋があった。
銀閣寺道に入り、寺のそばを抜けていくつか角を曲がると、大文字山の登山口を見つけた。おれは立ち止まることなく登りはじめた。雪は残っていたが、土のなかに埋め込まれた階段のまわりはきれいに掃除されていた。
一時間ほどかけて、大文字焼きの台座のそばまでやってきた。雪に半ば埋まった京都の街が、遠くまでよく見えた。しばらく眺めていると、厚い雲のあいだから、沈みかけた赤い太陽があらわれた。太陽は赤色の光を街に投げかけ、雪がその光を反射して、影のない、奇妙なほど赤色の景色をつくった。おれは目をつぶり、おそろしいほどの寒さが身体の中心から湧き上がってくるのを感じた。
背後にあった、登山者の安全を祈っているのだろう、小さな仏像がおれに話しかけた。
「朝は四本足、昼は二本足、夜は三本足の動物ってな~んだ?」
おれは無視した。
「に~ん~げ~ん~」と仏像が言った。
おれは仏像の頭をつかみ、街にむかって投げた。仏像はとてもよい勢いで飛んでいき、志賀越道と今出川通の合流地点に立っている巨大な仏像とぶつかった。
「痛いがな!」非常に巨大な声で巨大な仏像が叫んだ。
あまりにも巨大な声だったので、空が割れた。
そこから天使たちが降りてきたらしいが、おれはよく知らない。
気絶したからだ。
思うところがあって母に電話をかけてみたが、繋がらなかった。そういうものだ。
家のなかにはめったに開けることのない扉というものがあり、たいていの場合、そこには過去の記憶が詰めこまれている。おれはその扉をあけて、なかを探ってみたことがある。アルバムが出てきた。妹が写っているものは十枚とすこしあった。
そのうちの一枚がおれの注意を惹いた。制服を着ているから、たぶん高校生のときのものだろう。どこかの海辺の公園らしいところの欄干にもたれている。おそらく、父が撮ったものだ。
ずいぶん引いていてよく見えないが、うっすらと微笑んでいる。ただそれだけの写真だが、異様な感じをあたえる何かがひそんでいる。どんなとらえかたもできそうだ。孤独をたたえていると言ってもいいし、心から喜んでいるとしてもいい。無表情ではない、微笑みだ。だが、そこにはどんな意味もない。
目元の影から、彼女が数年後にトタン屋根の梁から自分をぶら下げることが暗示されている、と読み取ることもできる。その影にひそんでいる寂しさのようなものが、口当たりのいい原因になりそうな感じがする。
しかし、そんな理由付けは、しない。
彼女が死んだことにどんな理由もない。ただ、そうなっただけだ。原因も結果もない。
形を変えながら、ものごとは永遠に続いていく。なにごともなかったかのように明日の生活がはじまる。
明日の生活がはじまる。
つぎに目を醒ましたとき、おれは白い床がどこまでも続く空間にいた。英語の先生といっしょに来たところだ。おれのまわりには数体の像がいて、おれをとりかこんでいた。白川沿いの岩と一体化した地蔵、吉田松陰、ビリケン、滋賀越道と今出川通が交差する場所にある巨大な地蔵、そして大文字山の仏像。
おれは像たちに話しかけてみた。
「どないしたん? みんな揃って」
像たちはなにも答えなかった。
像は像にすぎなかったのだ。
それってありなんかなあ、とおれは思った。
いままでさんざんおれにつきまとってきたのに、もう喋らないというのはなんだか気にくわない。無視されているような感じだ。しかし、喋らないものは仕方がないので、おれはその場に横になって空を見た。空はピンク色だった。不思議な色だ。
「なんでひとつも思い出せへんねやろなあ」とおれは空にむかって言った。
なんでやろうなあ、と空が答えた気がした。
「なんでおれたちは何もかも忘れていくんやろう。あんまり忘れすぎて、大切なことから先に消えていくような気がする。なぜなんやろう?」
空はなにも答えなかった。
四条大橋の西詰めにある中華料理屋で親父と話した内容を、そのとき思い出した。
「サイパンに行った」
そのとき、おれは自分の部屋にずっと掛かっていた額縁のなかの写真を思い出した。
「透明な海やったね」とおれは答えた。
「そう、透明で」と親父は言った。
写真のなかには幼児の兄妹が写っていた。ふたりとも裸だった。
「綺麗やった」
不思議なピンク色の空は、むこうのほうに行くほど紫色になっていた。おれは立ち上がって、その紫色のほうに歩いた。すると、門があった。鉄でできたアーチの下をくぐるようなやつだ。アーチには、「さようなら」と書かれていた。その向こう側は完全な紫色だった。
ブーンという音がしていた。
それだけだった。
それより向こうに行くべきだろうか、とおれは思った。行っていいものだろうか? 向こう側は平和そうだ。見たところ、なにも起こっていないようである。生きることは楽しいし、死ぬことは平和である。こちら側はどうだろう? 振り返ると、遠くのほうに五つの像があった。それらは動きも話しもしなかったが、延々と続く白い地面のなかで、唯一の変化のように思われた。なにかがあるということは、そういうものだ。
そしておれはけっきょく「さようなら」と書かれた門の向こう側へ行かなかった。
門のところから引き返して像のところへと戻る途中、気持ちのいい風が右のほうから吹き抜けて、おれのなかにある悲しみをすべて奪っていった。おれはびっくりして、悲しみがなにもなくなったので笑顔になって喜んだが、同時に必死になって風を追いかけた。
それはおれのものだ。
返せ!
風は女の子の姿をしていた。古本市でラムネを売っていた女の子であり、三条でおれに笑顔を用いて話しかけた女の子だった。風は大きな壁にぶつかり、四方に砕けた。おれの悲しみがその場にぽろぽろとこぼれ落ちた。おれは地面に膝をついて両手で悲しみをかき集め、宝石のようになったそれを口の中に含み、舌で舐めた。悲しみはあめ玉のように溶け、苦い味がした。しばらくすると、悲しみが身体じゅうにまわるのがわかった。おれは悲しくなった。
これで元通りだ。こうすればいつまでも変わることはない。
やったね!
見上げると、壁が空にむかってどこまでもつづいていた。終わりはない。
女の子がおれのまえに現れて言った。
「あんた、アホやなあ」
おれはムッとしたが、すこし考えてから、笑顔をつくってこう答えた。
「そうですねん、ヨダレクリのハナタレですねん」
いま、おれはこの小説を書き終えて、ほっと一息つく。窓に目をやると、やさしい十月の日差しが街を照らしているのが見える。阪神高速のうなり声と、遠くの公園で泣いている子供の声が聞こえる。おれは煙草に火を点け、窓から十分ばかり街を眺める。
それから、おれは外に出て、いちばん近くにあるスーパーマーケットに向かう。人々は休日を満喫している。だれもが楽しそうに微笑み、いっしょに歩いている人となにか話している。ビルの隙間に見える青空は驚くほど高い。鱗雲が点々と横たわっていて、もうすぐ訪れるはずの、長く厳しい冬を予兆している。
しかし、人々は気にも留めずに、いっしょに歩いている人とずっと話を続ける。
スーパーマーケットに入り、買い物カゴを手に取って、いわばディスプレイのために製造された雪山のような商品の棚を眺める。ジム・ビームが、オレンジが、インスタント食品が、ピラミッドのようにうずたかく積まれている。しかし人々はそんなものは存在していないかのようにふるまう。おれはきっちりと整頓されたジム・ビームのディスプレイから一本を抜き取って、その秩序を乱してみる。もちろん、なにも起こらない。
さまざまな酒が売られているところに入り、十分ばかりいろいろな酒瓶を検分する。とある酒瓶には、この酒をつくったスコットランドの蒸留所は一六八七年に創業した、と記されている。さらにいくつかの酒瓶を眺めたあと、ほかの瓶を手に取る。
おれは酒が売られているあたりを探し回り、やっとのことでトニック・ウォーターを見つける。それから青果売り場に行き、メキシコ産のライムをひとつカゴに入れる。レジに行くあいだにふと目についたオイル・サーディンを手に取る。パンはあとで買うことにする。
レジの前に立って順番待ちをしているとき、こんな会話が聞こえてきた。
「もう一度やり直せるなら、誰とがええ?」
「アホ以外がええな」
帰りぎわにいつも通りがかるパン屋。いつも裏側の通りを行くのだが、とてもいい匂いがするので、なかに入ったら気絶してしまうような気がして、入ったことはなかった。ドアを押し開けると、鈴の音がした。店のなかは静かだったが、音楽がかかっていた。
たくさんのパンがあった。チーズのかかったやつ、トマト・ケチャップとベーコンのかかったやつ、クロワッサン、チーズが埋めてあるやつ、カレーが中に入っているやつ、ソーセージが埋まっているやつ、にんにくで香りをつけたフランスパン、クリームが入ったパン、あんこが入ったパン、鶯餡が入ったパン、ヨーグルト味のクリームが入ったタルト、ブルーベリージャムが乗っているもの、いちごジャムが詰まっているもの、チョコレートが入ったコロネ、スクランブル・エッグが入ったパン、唐揚げが乗ったパン、肉萬のたねが入ったパン、ベーコンとレタスとトマトのサンドウィッチ、卵のサンドウィッチ、ツナのサンドウィッチ、玉葱とアボカドとドレッシングのサンドウィッチ、ハンバーガー、チーズバーガー、フィレ・オ・フィッシュ。
食パン。粉砂糖のかかったクロワッサン。クラムチャウダーが詰められたパン。ミネストローネが詰められたパン。ピザ・パン。カスタード、ミルク、チョコが詰まったそれぞれのパン、ポテト・グラタンが乗っているやつ、ベーコンが挟まったベーグル。ビーフ・シチューが乗ったパン。オリーブの酢漬けが入ったパン。生地に人参を練り込んだフランスパン。ごまを練り込んだフランスパン。青のりを練り込んだフランスパン。ふつうのフランスパン。
ふつうのフランスパンをトングでつかみ、プラスチックのトレイのうえに置き、レジまで持っていく。時計がかかっていて、四時十六分を指している。壁にはニスがたっぷり塗られた何枚もの木がびっしりと張りついている。おれはうつむいていて、レジの女性がちいさな袋のなかにフランスパンを入れるところしか見えない。エプロンはデニムで、胸のポケットに三色のボールペンがさしてある。染みも皺もない白いシャツ。肌。財布から小銭を出して、お金を渡す。彼女はそれを受け取り、レジのボタンを押す。そのときはじめて気づいたが、女の子はおれとおなじくらいの年頃で、おれにパンを渡してくれるときの笑顔がとても美しい。そのことを伝えてみようかと思う。勇気を出して、言ってみようかと思う。この子はきっと喜ぶだろう。
だが、言わないでおく。
おれは自分の家に戻る。ナイフでライムを半分に切り、もういちど半分に切る。タンカレーをグラスに四分の一ほど注ぎ、ライムを搾る。氷をふたつグラスに入れる。トニック・ウォーターの栓を開けて、炭酸が抜けないように、グラスを傾けて面のうえを水が流れるように注ぐ。浮かんできた氷を指先でやさしく沈めると、グラスの全体からこまかい泡が集まってきて、小川のせせらぎのような音をたてる。
フランスパンを切り、オイル・サーディンの缶詰を開ける。キッチンテーブルに運んで、それらをきっちりと並べ、しばらく眺める。窓からは、低くなった午後の太陽の名残がさしこんでいる。洗濯物がゆらゆらと揺れている。近くの線路の上を電車が走る、高速道路のうなり声、遠くのほうでやっている工事の音がかすかに聞こえる。
おれはグラスをつかみ、ジン・トニックをひとくち飲む。
それはとてもおいしい。
それから、書きかけたまま放っておいた小説のことを考える。そのとき、めったにないことだが、開け放した窓のむこうのベランダに小鳥がやってきて、なにごとかを歌う。
しばらくのあいだ、鳥の鳴き声に耳を傾ける。
すばらしい音だ。
おれはフランスパンを噛みちぎり、咀嚼して、呑みこむ。
そしておれはいままでにおれが出会い、別れてきたすべての人間の笑顔を思い出す。
「それでも」とおれは鳥たちに返事をする。「おれはお前たちが作った世界のデザインを、絶対に許さないからな」
永遠の反復はゆるゆるとした日々の生活の中に潜み、その場からの脱出の可能性のヒントも案外そう遠くないところに隠されているのかもしれない。田中功起
1.「無数にありえたかもしれない世界の可能性」への魅惑 ― システムと世界の多層性
考えごとをしながら公園を散歩していたのだけど、芝生は太陽に照らされて青々としているし、噴水はキラキラと光って僕を誘惑するので、幾度もそれらに意識を奪われてしまう。思考に集中できず仕方がないので、僕は上手に言い訳を作ろうとする。そして僕は「焦りで張りつめた身体を弛めることで思考を柔らかくする」という理由をでっち上げる。理由がないと環境が僕に侵入し意識を自然に浸せないことを「かっこ悪いな」と思いながら、僕はリュックサックからブルーシートを取り出す。僕は大木の下にできた涼しそうな木陰の上にそれを敷き、辺りの人たちが楽しそうにはしゃいでいるのをぼーっと眺める。
大学生グループの楽しそうな声や笑顔は、じんわりとなんともいえない幸せな気持ちにしてくれるし、ジャグリングしている外国人の手さばきと次々と宙を舞うボールたちは、僕から視点を奪うのに十分だ。木陰から差し込む木洩れ陽は身体をぽかぽかと暖めてくれて、とても気持ちがいい。それら一つ一つのフレームは一つの絵として十分なのに、それらが部分的に重なって響き合い、僕はいよいよ思考するどころじゃなくなる。思考の入り込む隙間がなくなるほど、自然が僕に、僕が自然になっているので、言葉の世界に入り込むのを諦めて、僕はごろんと寝転がる。
日差しが眩しい。僕は横向きになる。すると、芝生が顔をチクチクと刺激して、僕から意識を奪う。視点はその芝生の細部に合わせられる。僕は小さい虫が芝生の上を這っていることに気がつき、芝生の隙間から土が顔を出していて、一瞬虫の視点に立ってしまい、驚く。そして、表情に出ていたかどうか分からないけれど、僕は笑ってしまう。にやついてないか周りの視線を気にしながらも、僕は顔をゆっくりと上げ、もう一度あたりを見渡す。僕は虫と芝生と土という配列に驚いたのではない。虫の視点によって、世界の多層性を教えられたことに驚いたのだ。その驚きは、辺りを眺めたときに出会う各々のフレームが持つ複雑性と同様の複雑性が、虫の視点という一見小さなスケールにも見出せてしまうことだった。そこにあった小さな世界の大きさ、小さいものが大きいものと同様に大きいことへの驚きである。
そしてこの発見は、僕が田中功起作品を鑑賞するときに見出すことでもあった。彼の作品を見ていると、僕が芝生の上に寝転がり、虫の視点に取り込まれた時のように、声にならない笑いが内側から沸き上がる。彼の作品の持つ「魅惑」は、僕たちをシステムの外側まで手招きする。それは世界の多層性に気づかせてくれる小さな、そして大きな冒険への誘惑であり、僕たちが身近な出来事を身近でない水準まで解像度を上げて眺めることを可能にする。
以前、田中は自らの活動に対して「無数にありえたかもしれない世界の可能性を探すこと」と表現している。単に公園を歩くことが、本来ある種の陶酔であってもいいはずである。自然に身体が浸され、様々なモノたちの異なる時間の流れを感じることを、恋に落ちることと見なしてもいいはずである。しかし、僕たちは社会生活を営む中で、別の可能な世界に気づくことができない。それは「ある」。しかし、システムの中ではその存在を感じることができない。田中はその「無数にありえたかもしれない世界の可能性」を探しだし、その方向へと僕たちを「魅惑」することで、システムから脱出する可能性を与えようとしているのだ。
確かに田中の作品には「魅惑」がある。しかし、共感の共同性は共感の限界とともに閉じてしまう。あるいはポピュリズムの罠に引っかかってしまう。それは作品の可能性を限定するだけでなく、アートの可能性も限定してしまうだろう。よって、このテキストが田中功起作品と彼のテキストから思考した痕跡なのだとしたら、重要なことは、彼がいかなる「魅惑の形式」を用いて僕たちを誘い込むのかという点である。作品に「魅惑」があるのであれば、その「魅惑」がいかなる形式として制作されたかについても詳細に記述しておかなくてはならない。
第一に、それがどのような方法で「魅惑」するのかについて。第二に、多層的世界へ進むとは何を意味しているのかについて。言い換えれば、“how”と“what”を分析しなければならない。まずは「魅惑の形式」を定義することから始め、田中がシステムに対してどのような方法でその形式を制作し、それが何を意味しているかを記述していこう。
「魅惑」は、他者を惹きつけ、さまざまな限定的関係性を結びたいと思わせるものである。僕たちは魅惑されることで、さまざまな関係性を結びたいと動機づけられる。その複数の接触の束がモノに生々しい「自律性」「代替不可能性」「この性」「人格性」を賦与すると同時に汲み尽くせない「秘密」を産み出す。「魅惑」は「接触することなく触れること」ではなく「さまざまな仕方で関係性を結びたいと思わせる」技術である。美術家はオブジェクトを惹きつける新たな「魅惑の形式」を発明することで、モノから「商品」ではなく「芸術作品」を生成する。上妻世海「芸術作品における「魅惑の形式」のための試論」
ここで僕が「魅惑」と呼んでいるのは、一面的な関係性を規定するシステムを超えて、異なる様々な仕方で関係を結びたいと僕たちを動機づけることである。
そして「魅惑の形式」の新たな開発こそが美術家の役割であると、僕は考える。モノはつねにひとつの仕方で「壊れる」のではない。ハンマーが文字通り「壊れること」を通じて「見ること」「触ること」とは「違う仕方」で、他者を魅惑し、さまざまな関係性を結びたいと思わせる形式を発明しなければならない(誰でも思いつく一例を挙げれば、イメージと言説による神話創造によってつくり出されたデュシャンの《泉》を思い起こしてほしい)。「読むこと」「聴くこと」「見ること」「分析すること」などさまざまな限定的関係性の束によって、モノは自律性を賦与されるのだから。上妻世海「芸術作品における「魅惑の形式」のための試論」
例えば、普段僕たちはハンマーを「釘を打つもの」として一面的な関係を結んでいる。しかし、それが壊れた時、僕たちは初めてそれと真摯に関係する。すると、把手の触感や装飾に気がつくことになる。その感触は、「釘を打つもの」とは別の仕方で、ハンマーの可能性を転用することになるかもしれない。ここで壊れるのはハンマーではなく、僕とハンマーの間に結ばれたシステムが規定する関係性が壊れたのである。そうすることで別の可能性へと開かれ、そのハンマーと異なる関係を結ぶことによって、そのハンマーは他のハンマーとは異なる「“この”ハンマー」になる。
もちろん多くの場合、壊れたハンマーは単に捨てられ、代わりに別のハンマーが購入されるだけだ。何故なら、僕たちは大量生産された市販のハンマーに「魅惑」されることがないし、そもそもハンマーは生産される段階で異なる関係性を結ばれることを目的としていない。
しかし別の例で、僕たちは絵画を見た時、綺麗だねとか美しいとか、紋切り型の表現で済ませることができるにもかかわらず、時に深い読解をしたいと突き動かされることがある。それによって否応なく、僕たちは作家やその作品が作られた時代背景について調べたり、使われているメディウムについて研究したり、技法について実験したりする。僕たちは「魅惑」され、既存の意味は破壊し、異なる関係を結ぼうと突き動かされる。それによって初めて、その絵画は僕にとってかけがえのない絵画となる。
田中はその衝動を、フロイトの「終わりある分析」と「終わりなき分析」と重ね合わせ、次のように説明している。
「終わりなき分析」は「分析者と被分析者とのあいだの転移」により「終わりなき」ものになります。この文脈を美術に援用しますと、まず作品そのものが内包する意味=オブジェクトレヴェルを「終わりある分析」、作品と観者の関係=メタレヴェルを「終わりなき分析」と言えるでしょう。つまり批評家(あるいはもっと広く観者)は作品との「転移」関係により「終わりなき」作品読解へと引き込まれていくのです。田中功起「世界―速度の変容―コンセプチュアル・アートの「遅さ」をめぐって―」
ここで田中が議論していることは、まさに上記で僕が「魅惑」について語っていたことに等しい。田中の議論を引き受けると、僕は「魅惑」を「終わりある分析」から「終わりなき分析」へと引き込むものとして定義できる。確かに僕は彼の作品を「終わりある分析」として、紋切り型の意味で消費することもできた。しかし、このテキストはまさに僕自身が田中の作品によって「終わりなき分析」へと「魅惑」された結果、何度も彼の作品を鑑賞し、彼への批評や彼が書いたテキストを読解することで書かれたものである。僕はどうやら、彼の作品と「転移」関係に入り込んでしまったらしい。そして、これは田中作品が僕にとって、「魅惑」を持っているということを示している。
「魅惑の形式」について語ることは難しい。何故なら、そのモノに「魅惑」があるか否かは、「魅惑」された後にのみ断定できるからである。それは恋に落ちることと似ていて、僕たちは強烈な美人であるからといって必ずしも魅惑されるわけではないし、あるいは世間的には美しいとされていなくても時に恋に落ちるように、普遍的に語り得るものではない。しかし、この論考が田中作品の「魅惑」について語るものであるのなら、「あるものはある」というトートロジーを抜け出さなければならない。そして幸運なことに、田中作品の場合はそのトートロジーのさらに深部へと進む糸口があるように思われる。何故なら、彼は驚くべきことに、作品がまだ世に知られる以前の2000年7月に「世界―速度の変容―コンセプチュアル・アートの「遅さ」をめぐって―」というテキストで、システムとシステムへの抵抗としての方法について記述しているのだ。それは、彼がいかにしてその形式を制作しているのかを知るためのヒントになる。まずは彼が示した時代的な二つの特徴について引用する。
「ポストモダン的状況」においては、人びとはコミュニケーションが成り立たないほどにバラバラに分断されてしまっています。こうした時代では「普遍的な意味」を持つこと自体が難しく、自分が属する共同体の価値が必ずしも隣の共同体の中でも価値を持つとは限りません。たとえば「現代美術」において意味を持ちうるものが、「コギャル」においてそうなるとは限らないように。そしてそうした世界では安易に「強度」にすがるものが出てくることも必然でしょう。圧倒的な「強度」を頼りに、「他者性」さえも消し去って、個人の内部に沈潜し、その中でフェティシズムを開花させたような、そうした「強度」にすがる作品が溢れていることは誰しも承知のことです。「ユーモア」とはそうした「フェティシズムの強度」を持った「笑い」とは根本的に異なる精神態度であることは言うまでもありません。広大な無限遠点からのささやかな笑い=微笑としての、この「低速」時代に対応する「ユーモア」。田中功起「世界―速度の変容―コンセプチュアル・アートの「遅さ」をめぐって―」
まず「理論的」であらねばならないという脅迫、そしてそれの反動としての「反理論的」であるべきだという脅迫、また、アメリカという特殊な状況下においての批評表現が「ファッショナブル」であらねばならないという脅迫、そして「政治的解釈」を迫られるという脅迫、最後が「イコノロジー」解釈の限界が示されているのにもかかわらず、いまだに力を持つという意味での脅迫。ここでは詳しく触れませんが、ボワはこうした「脅迫」あるいは「期待の地平」を「ポリフォニック」に受け止め、なおかつその横をすり抜けていく方法論をとろうとします。これはゴンザレス=トレスにも当てはまる態度でしょう。彼はそうした「期待の地平」の中でいくつかのコードに接続し、「ポリフォニック」な態度でそれらを回避していこうとします。田中功起「世界―速度の変容―コンセプチュアル・アートの「遅さ」をめぐって―」
第一に、彼は現代の「ポストモダン的状況」において、自分の属する共同体の価値が隣の共同体の価値と一致するわけではないと述べている。僕たちは初期条件としてバラバラになってしまっている。そして、バラバラになった共同体同士のコミュニケーションは、仮に物理的な距離が隣であったとしても、インターネットによって高速でつながっているとしても、メッセージは様々な場を経由し誤読され単純化されることを経て、初めてお互いが通じあうことになる。そして、彼はその状況下を「低速」時代と評し、強度にすがる作品が増えることは時代的必然であり、それに対抗する「ユーモア」という方法論の可能性を仄めかしている。
第二に、イヴ=アラン・ボアの主著『Painting as Model』の議論を紹介する形で、現代が抱える五つの脅迫観念について述べている。それは「理論的」「反理論的」「ファッショナブル」「政治的解釈」「イコノロジー」という相反するものであり、そういった「期待の地平」をいかにして超えるべきかが模索されている。そこで模索されているのは「いくつかのコードに接続すること」であり「ポリフォニック」な態度である。
彼は上述した二つの時代的困難に対して、「ユーモア」「ポリフォニック」「いくつかのコードに接続すること」という方法論を用いる。彼はまず時代的な、地域的な環境を分析した上で、それに抵抗する方法論を模索し、それをごまかすことなく精緻に記述しているのだ。
まずはバフチンの「ポリフォニー」の定義を引用する。
それぞれに独立していてお互いに解け合うことのないあまたの声と意識、それぞれがれっきとした価値を持つ声たちによる真のポリフォニーこそが、ドストエフスキーの小説の本質的な特徴なのである。彼の作品の中で起こっていることは、複数の個性や運命が単一の作者の意識の光に照らされた単一の客観的な世界の中で展開されてゆくといったことではない。そうではなくて、ここではまさに、それぞれの世界を持った複数の対等な意識が、各自の独立性を保ったまま、何らかの事件というまとまりの中に織り込まれてゆくのである。実際ドストエフスキーの主要人物たちは、すでに創作の構想において、単なる作者の言葉の客体であるばかりではなく、直接の意味作用を持った自らの言葉の主体でもあるのだ。ミハイル・バフチン『ドストエフスキーの詩学』
これを田中は次のように説明している。
「ポリフォニー」とは、「低速化」し、風通しが悪いこの時代において、分断された共同体を繋ぐために、さまざまな場所において望むべき態度をも示しているように思えます。それはまさに、分断された共同体へと自ら出向いて「それぞれの場を揺るがす力のある言葉を使」って、いわばむりやりに「他者」とコミュニケートするために必要不可欠な態度なのです。田中功起「世界―速度の変容―コンセプチュアル・アートの「遅さ」をめぐって―」
彼の言う「ポリフォニック」な態度とは、自らの属する共同体から外に出ること、そしてバラバラになった様々な共同体に自ら出向いて、それぞれの場を揺るがすことを志向する態度を指している。それはバラバラな状態を受け入れ、絶望し自らに自閉的になるのではなく、誤読され単純化という暴力に晒されたとしても、勇気をもって外と接続することである。その際に重要になるのが「ユーモア」であろう。単に外に出向くのではなく、アイロニカルな態度で他者と接するのでもなく、彼が志向するのは「ユーモア」なのである。
フロイトが書いた論文の中で比較的短いものの中に「ユーモア」があります。その中でフロイトは、「ユーモア的な精神態度」は自分だけでなく、他人に対しても向けられるものだと言ったあとにこう述べています。
「すなわち、この人(筆者註:ユーモアを持つ人)はその他人にたいしてある人が子供にたいするような態度を採っているのである。そしてこの人は、子供にとっては重大なものと見える利害や苦しみも、本当はつまらないものであることを知って微笑しているのである。」
「ユーモアとは、ねえ、ちょっと見てごらん、これが世の中だ、随分危なっかしく見えるだろう、ところが、これを冗談で笑い飛ばすことは朝飯前の仕事なのだ、とでもいうものなのである」。田中功起「世界―速度の変容―コンセプチュアル・アートの「遅さ」をめぐって―」
さらに、このテキストを紹介している対談から引用しよう。
フロイトが書いたユーモアについての短い論文があるのですが、ユーモアというものは、必ずしも声を出して笑うものではなくて、精神的解放に焦点を当てた態度だと書いています。たとえば死刑囚が絞首台に行く前に「明日の夕食はなんだろうな?」って連れにきたひとに聞く、これは誰かを攻撃し、貶めるために使われるアイロニーとちがって、ほっとする笑いを誘う。その重い空気がこのユーモアによって開放される。そのときぼくはこれをフェリックス・ゴンザレス=トレスの作品にも感じると思っていました。たとえば、彼と彼のパートナーの体重を足した重さになっている銀のキャンディの作品。すこしずつ持ち帰られることで減っていく、これは身体が死に向かっていくことのメタファーでもあるのだろうけど、じっさいは、減ってきたら足さなければならない。だからこれはむしろ生そのものや延命のメタファーでもある。それが、ふたりが亡くなったあともいわば永遠になくならない意味で、だれかによってふたりの愛が延命されているように思えてきて、なんかユーモラスで、優しい気分になります。この意味での、ユーモアのある作品を作っていきたいとは思いますね。田中功起+三木あき子「無数にありえたかもしれない世界の可能性」
田中はむりやりにでも「他者」とコミュニケートするために必要不可欠な態度として、「ポリフォニック」な態度を挙げた。しかし、他の共同体とコミュニケートすることは、誤解や単純化を伴う不安との戦いでもある。僕たちはその不安から、他者に対してアイロニカルに構えたり、分かりやすく盛り上がりやすいものに頼ってしまう傾向がある。しかし、田中が用いるのは、誰かを攻撃し貶めるために使われるアイロニーではなく、他者がほっとする笑いを誘うような仕方でコミュニケートすることである。換言すれば、重い空気が「ユーモア」によって開放されることに、彼はこの困難に対する活路を見出している。彼は現代の状況を踏まえた上で「ユーモア」という方法を意識的に採用した。それは、彼が「ユーモア」について彼が記述した章のタイトルを「低速度の誤解世界を生き抜くために」としていることからも明らかであろう。
田中が示した現代における三つの方法のうち、最後の一つは「いくつかのコードに接続する」ことである。彼はゴンザレス=トレスがジェンダー論的に解釈されたり、ミニマリズムと関連して批評されることを挙げて、「いくつかのコードに接続する」ことを示す。
ゴンザレス=トレスは批評的なレヴェルにおいて、いくつかのコードに同時に接続し、ポリフォニックに振る舞っています。このゴンザレス=トレスの方法論的なポリフォニック性は彼の置かれている状況に負う所が多いようにも思えます。先に示した「低速」状況下では批評においてもいくつかの断絶化がおき、それによってゴンザレス=トレスの作品はいくつかの批評言語によって分断されながら評価されることになります。つまり、いくつかの批評コードに彼の作品は回収されるのです。これに関しては彼自身も自覚的であったようですが、彼はそれらの批評を並べ、進行状況を眺める観者を装います。田中功起「世界―速度の変容―コンセプチュアル・アートの「遅さ」をめぐって―」
確かに、ポリフォニックに振る舞うことで批評上の複数のコードに接続することは、分断された価値体系を可視化し相対化するだけでなく、それらを繋ぐ意味においても重要だろう。しかし、上記の三つの方法を受け入れた上で、さらにその後展開した彼の活動の幅広さ、往復書簡『質問する』やポッドキャストでの『言葉にする』、あるいは建築家やデザイナーなどの異なる分野の人びとへ批評を書いたり対談を行ったりしていることを顧みると、批評的なレベルを超えて、ジャンル的な横断すら行っているように思える。
上記の三つの方法は、田中がゴンザレス=トレスを批評する中で、ミハイル・バフチン、ジークムント・フロイト、そしてトレス自身から引用したものである。しかし同時に、それは彼が「断絶」と「脅迫」の時代の中で、いかにして「期待の地平」を乗り越えるかを真剣に考え、導き出した彼自身の方法でもある。彼は「ポリフォニック」な態度で、「ユーモア」を実践することでジャンルという「コード」すら横断する。それは異なる価値体系の間で分断された僕たちを魅惑し、僕たちを紋切り型の記号的解釈のさらにその奥へと誘い込み、分断された各々の共同体の間に新たな共同性を立ち上げるのだ。
驚くべきことは、彼がまだ比較的無名であった2000年に、このテキストが書かれていることである。この事実は、田中功起と彼の作品について考える上で、見逃せないものであろう。何故なら彼は、東日本大震災後にループや日常を扱ったヴィデオ作品から政治的転回を果たしたと解釈されることが多いからだ。しかし上述したように、彼は2000年7月の段階で、バラバラになった僕たちを再度繋ぐものとして制作を捉えていた。これは彼が2011年の震災後に転回したわけではないことを証明している。そうであるならば、彼の初期の作品群は、これまでのように美的な解釈だけでなく、現代の問題を引き受けた上でのある種の抵抗装置として解釈しなければならないだろう。その装置は、僕たちの身体に働きかけることで、固着化している一面的なシステムを破壊し、僕たちを多層的世界に魅惑する。次の章からは、その点について記述していくことにしよう。これまで、田中功起の作品群は可能性の中心を見逃されてきたのだ。
2. 時間を解放する装置として ― 具体的身体と現実空間の見立て
彼が制作する「魅惑の形式」は、時代背景を分析する中で生み出された方法によって生み出されたものであり、その方法は「ポリフォニック」な態度、「ユーモア」、「いくつかのコードに接続すること」であった。そして、そのことを宣言したテキストは2000年に発表されており、その事実に基づいて考えると、彼の作品は震災後に政治的転回を果たしたのではなく、一貫して「低速度の誤解世界を生き抜くために」制作されたモノであると解釈されなければならない。もちろん彼の作品は美しいコンポジションで構成されており、美的に解釈することもできる。しかし、彼は活動の当初から、バラバラになった僕たちを繋ぐ装置として、制作を考えていたのだ。
例えば《beer》(2004)は、一見するとビールがコップから溢れ出ても注がれ続けるだけの映像だが、現代美術という制度とコップから溢れ出すビールという形式のズレは、死刑囚が絞首台に行く前に「明日の夕食はなんだろうな?」と連れにきたひとに聞くのと同じく、ふとした笑いを生み出す。そして、そのユーモアにつられて映像を眺めていると、ビールの黄金色と吹き上がる泡の不思議なフォルムが僕たちの目を奪うだけでなく、同時に「真摯に見ること」がフォルムを浮かび上がらせることに対する驚きを与えてくれる。僕たちはその形に魅せられる。そして、その形は僕たちにとって、これまでも「あった」にも関わらず、これまで「見えなかった」ものになる。つまり、僕たちはビールをコップに注ぐとき、いつも、各々のビールの泡と黄金色と出会っているはずであったが、それとすれ違っていたという認識が生まれることで、「これまで」と「これから」が重なりあい、世界が多層化するのだ。
それは制度と知覚の関係性について、僕たちに思考させる。彼は「ユーモア」をうまく利用することで、僕たちを作品と「真摯に」向き合わせ、次のような疑問を僕たちに抱かせる。何故僕たちは普段からそこにある世界に真摯に向き合うことができないのか? 何故優れた芸術はそれを可能にするのか? あるいは、僕たちが芸術なりテクノロジーの媒介なしに、何かに向き合うことができないのは何故か? つまり、田中の作品は「言語」だけでなく「見立て」なり「テクノロジー」といった、一見身体の外側にある「道具」によって、僕たちの知覚可能性が限定/拡張されることを浮き彫りにするのだ。
ここで重要なことは、このユーモア→真摯に見ること→世界の多層性→制度と知覚の関係という解釈が、単なる僕の深読みではなく、田中自身も意図していると思われる点にある。仮に彼がその意図を否定したとしても、少なくとも田中の無意識が作品に反映しているとは言えるだろう。何故なら、田中は『質問する』という往復書簡形式の連載において、「作ること、作品、見ること」という三対の関係性について思考していて、一見自律的だと考えられているものの関係的な基盤について述べているからである。引用しよう。
・作り手の視点から
1) 「見せる」ことを「作る」ことに優先する
展覧会(時間空間的に限定された一回かぎりのもの)というフォーマットから演繹的にできあがった作品 インスタレーション パフォーマンス リレーショナル・アート2)「作る」ことを「見せる」ことに優先する
作品の成立を展覧会よりも優位に置く
2-1) 「作る」ことを「見せる」ことに限定しないように回避する
コンセプチュアル・アート アイデア
2-2) 「見せる」ことに無頓着に「作る」
孤独化 アウトサイダー 制度のうちにおさまらない3) 「見る」ことを複数化し、時間空間に限定させない
作品のオリジナリティを複数の潜在可能性へと開く。記録しかない作品(現存しない作品、公開を前提としない作品)+再撮影+カタログ(テキスト)+ウェブ(テキスト)+αへと複数化する。作品を時間空間のずれのなかに再配置する。田中功起「気づいたことのまとめとリスト」
この田中の記述は、「作ること、作品、見せること」という三つの要素の各々の変化が、時空間の変容と関係していると考えていることを示している。つまり、彼は「作品の自律性」やニュートン/ユークリッド的な「絶対空間」「絶対時間」という近代の幻想を、「作ること」と「見せること」の関係のあり方によって変容するものと捉えているのだ。そして、彼は「見せること」と「作ること」の関係の質の中から、制度的限定やその外側にある潜在的可能性を見出すのである。
彼は『Tokyo Source』でのインタビューにて、こう述べている。
「見たことのあるものは見たくない。芸術を通して見たことがない世界が見たい」というようなことを言われたことがあって…。たとえばビールを全部あふれるまで注いだことがある人はどれだけいるんでしょうか。同じスニーカーがそれも階段からどんどん落ちてくるということを実際に見たことがあるひとがどれだけいるでしょうか。でもそのひとには「見たことがあること」に見えたわけだし、そう言われてしまえば仕方ありません。Tokyo Source「TS6 : 田中功起」
しかし、《beer》(2004)の射程はさらに広い。溢れ出すビールは、「見たことがありそう」で「見たことがないもの」なだけでなく「見たこと」がないことが「見える」という驚きを通じて、制度と知覚、さらには芸術とは何かという問いまで、僕たちを迷い込ませるのである。そのために、彼は身近なものを意図的に用いている。
むしろ手に取れる身近なもののなかにこそ見たことがないなにかがあるのではないかと思っています。たとえば映画「エイリアン」を見たとして、それはたしかに見たことがない生き物ですけれども完全に虚構なので、現実との距離があまり関係なくなってしまう。現実のなかにあるものを「見たことがない状態」にもちこんだ方が、現実との距離がものすごく遠くなり、それが無限になったときにそれは「見たことがないもの」になる。Tokyo Source「TS6 : 田中功起」
このような発言の背景には、やはり田中が「見ること」の純粋性を無批判に前提にするのではなく、僕たちの現実は「見立て」の機能によって変容すると考えていることが分かる。「見立て」がSF映画のように強すぎた場合、それは虚構の中の現実性としてすんなりと受け入れられてしまう。それは現実を揺るがすことができない。よって、彼は現実を規定している時空間の前提条件をうまく操作することによって、「見たことのあるとされているもの」から「見たことがないもの」を作り出すのだ。
映像のなかで起きていることにはあまり現実感がありません。たとえば、ゴジラが映画の中で東京をいくら破壊しても、だれも実際の「この東京」が破壊されたってパニックになるひとはいませんよね。それは「映画というフィクション」であり「現実」ではないんだというお約束を映画館で見ているすべてのひとがわかっているからです。そのうえでスクリーンの向こう側のフィクションとしての東京が壊される。そこに娯楽性があります。現実は現実のままで脅かされるわけではない。映画館を出ればだれもが普段の生活に戻ります。だれもゴジラが東京にくることを心配しない。映画の娯楽性とは違ったおもしろさをぼくが映像に見出すとすれば、それはそれを見たときに現実が脅かされるようなものに対してです。たとえば心霊写真が怖いのはそれが現実だと感じられるからです。現実に幽霊がいるように見えるから怖いわけですよね。Tokyo Source「TS6 : 田中功起」
彼にとって、映像の娯楽性と異なる面白さとは、それが現実を揺るがすことを可能にすることにある。彼は「お約束としての虚構性」ではなく「現実としての虚構性」を示す。それは「映画館を出ればだれもが普段の生活に戻る」のではなく、「美術館を出ればだれかが普段の生活とは違った時空間を生きる」ことを目指している。そこで真に変容の対象とされている媒体は、僕たちの身体である。それは抽象化された鑑賞者としての身体ではなく、経験によって変容する/してしまう具体的な各々の身体である。
しかし、田中作品のこの側面は見逃されているように思う。例えば、ガブリエル・リッターは『〈エンドレス〉から〈エブリデイ〉へ:田中功起の映像作品』というテキストにて、2001年の「セゾンアートプログラム・アートイング2001 − 生きられた空間・時間・身体」にて発表された《Grace》について批評している。
何もない教室の一角、その床に大きなモニターが置かれビデオ映像が流されている。そこにはバスケットボールをヴィデオモニターに置き換えることによって、田中は、現実の世界とヴィデオがループする〈エンドレス〉な瞬間を重ね合わせる。そこでは、ヴィデオに映し出されたバスケットボールと実際の教室という二つの別々の現実を観客がひとつのものにしてゆくことが目論まれている。
そこでアーティストは非常に単純化した一対一の関係を空間において作り出すために、バスケットボールをヴィデオモニターに置き換えているのだ。その単純化は、この作品のダイナミックなコンセプトとは呼応していないけれども、そのようにして、このインスタレーションの方法は鑑者に日常の経験からは切り離された、隔離されたヴィデオの経験をもたらす。ガブリエル・リッター「〈エンドレス〉から〈エブリデイ〉へ:田中功起の映像作品」
ガブリエルは《Grace》を、現実とヴィデオの対比関係を生み出すことで、現実とは異なるヴィデオ体験を鑑賞者に与える作品として解釈している。そこで彼は、鑑賞者が抽象化/画一化された身体によって、二つの異なる現実が一つに統合されることを前提としている。しかしこれまで見てきたように、田中はいかに鑑賞者の身体に働きかけるかということを考えている。そしてそれこそが映像の可能性であると述べている。よって、僕は《Grace》をヴィデオ作品としてではなく、各々異なる身体を持った具体的な観客に「現実とされている虚構」と「現実としての虚構」を往還させることで、時間の多層性を浮かび上がらせるためのインスタレーションとして解釈したい。
《Grace》は、抽象化/画一化された身体を前提とすると、この作品の可能性の中心を見逃してしまう。彼の試みは、現実の前提条件となる「見立て」を操作することによって、具体的な各々の身体に働きかける。プログラマーにとって目の前のコンピュータがインターフェイスとソースコードの二重構造をもっているように、フォーマリストが作品の物質性や媒体の物質的条件を暴きだすように、それは時間の虚構性や条件を露わにするのである。
彼の作品群を「日常系」※1などと形容するのではなく、時間のフォーマリズムとして解釈すること。それはこれまで一見異なる作品と解釈されてきたいくつかの作品が、共通の関心から作り出されていることを教えてくれる。
例えば、《moving still》(2000)、《just on time》(2002)、《by chance (2 ducks)》(2003)は比較的近い時期に作られているが、モチーフが異なるため同じ系列として述べられることが少ない。しかし、上記のような視点から見れば、倒れた缶からコーラが流れ続ける《moving still》も、水面を三十分に一度カルガモが通り過ぎる《by chance (2 ducks)》も《beer》と同じように、僕たちがそれらを単なる「コーラ」や「水面」だと記号的には理解していても、否応なくそのフォルムが意識を奪い、「制度」と「見ること」の関係を可視化していることが分かる。それだけでなく、そこには異なる種類の「時間の形式」が構造として埋め込まれていることも了解される。
《moving still》では、異なるシークエンスのモンタージュとして物語を立ち上げるのではなく、空間の形式を静的に捉える写真的な方法でもなく、流れるコーラのシークエンスをループすることによって時間性を切り抜き、「時間の形式」を自律的なものとして扱う。それは人々が時間を真摯に見ることを可能にする方法である。物語としての時間という大きな枠組みの中には、それと同等に大きな、しかし集合論的には物語の部分集合のように捉えられる時間が流れていることを、僕たちに教えてくれる。つまり、一は多であり、多は一なのである。
さらに「時間の形式」について明示的なのが《just on time》である。この作品は、哀川翔主演の典型的なやくざ映画における「襲撃を受けて振り返るやくざ=哀川翔」と「手下を引き連れてビルの一室を襲撃しようとするやくざ=哀川翔」という二つのシーンを交互に反復しているだけの映像である。しかし、その反復をぼーっと見ているだけでも、ある構造に気がつき笑ってしまう。そこではすでにデータベースと化しているやくざ=哀川翔が一貫した物語から抜き出され、「襲撃を受けて振り返るやくざ」と「手下を引き連れてビルの一室を襲撃しようとするやくざ」が、物語の外側でダンスしていることに気がつかされるからだ。この作品は、やくざをテンプレ化したやくざ映画をさらなる形式のテンプレ化の束へと笑いとともに僕たちを誘惑している。それは僕たちを物語の前提にうごめく素材の集積へと、編集と二次創作の場へと誘惑するのである。
彼が単なるパターンの形式性にではなく、より解像度高く「時間の形式」に焦点を当てていることを明確にするには、水面の三十分の長回しの最中に一度カルガモが通り過ぎる《by chance (2 ducks)》を経由するのが良いだろう。何故なら、これも反復による「時間の形式」の自律化であるが、そこでは、鑑賞の時間という形式に対する挑戦が込められており、上記の二つの作品と比べることで、形式のスケールの複数性を見出すことができるからである。僕たちは三十分に一度カルガモが通り過ぎるという時間のスケールで作品鑑賞することを前提としていない。しかし、そのような時間はある。制度が前提にしている時間と異なる時間の形式を提示することで、無意識のうちに前提としている時間が意識上に生成されるのだ。
田中は、日常の中で形式を透視し、その形式を操作して制作することで、形式のズレを生み出す。それは彼が用いる「魅惑の形式」であり、僕たちが日常の中で「見ることがない」が「そこにあるもの」に真摯に向き合わせてくれる。鑑賞者は、彼が作り上げた「魅惑」に引きつけられることで、「真摯に見ること」を通じて形式のズレを認識し、笑う。そこには彼の自律性を媒介にして共同性を生み出すという戦略がある。田中はその戦略を、心理学者の高木光太郎を引用することで示す。
あらゆる記憶はその人だけのものであって、他者と交換することは不可能です。つまり記憶を媒介にして他者と機能的に関わることはできない。しかし、むしろ、こうして記憶が個人の身体に閉じていることで他者との関係性が生まれるのではないでしょうか。高木光太郎「想起の記憶、他者の記憶」
閉じていることで、その閉鎖性を支える前提となる関係性へと開かれること。彼は自律的なループ作品を作っているときでさえ、それを媒介に異なる価値体系や振る舞いを持った身体に働きかけ、現実を揺るがすことで、バラバラになった共同体の間に、新たな関係を生み出す可能性を模索していた。
そして、彼はその方法として、作者の視点だけでなく、鑑賞者の視点についても思考していた。単純に自律するのではなく、その自律を媒介にするために、「オブジェクトレヴェル」の自律性と「メタレヴェル」での視点の交差を考えているのだ。
まず、オブジェクトレヴェルとはまさに作品であるし、第一のメタレヴェルとは作者の視点であるし、第二のメタレヴェルとは観者の視点であると言い換えられます。……そしてなおかつその先で、すべてが解釈されたとき、それらが巨視的に見れば単なる言葉遊びのジョークにすぎないというばかばかしい開放感が待ち受けています。
こうした読解は〈作品と観者〉の関係があるかぎり続いていくでしょう。それは無限の「転移」関係により永遠に続けられるまさに「終わりなき分析」です。田中功起「世界―速度の変容―コンセプチュアル・アートの「遅さ」をめぐって―」
3. 視点の交差交換と創造性 ― マトリクスの生成、その変換と操作
ここで先ほど引用した、作り手からの視点で「作ること」と「見ること」について田中が整理したものを思い出してほしい。彼は「見ること」と「作ること」の関係のあり方によって、時空間が制度的に限定されること、あるいは拡張されることについて考えていた。しかし、上記のように彼が作品を媒介にして、鑑賞者との関係を生み出すことを考えていたのなら、彼が作り手からの視点だけを論じているわけではないと予想がつく。田中にとって、その両者の視点の交換の先に巨視的な視点が生じ、ジョークにすぎないというばかばかしい開放感が待ち受けているのだから、両者の視点について考えることは必然的なのである。
・観者の視点から
1)「見る」ことを「作る」ことと同等とする
受容美学 見ること/解釈の自由 観者と作者を同一平面に置く 作者からの解放
2)「作るひと」と「作られたもの」を分離し、「作られたもの」を「見る」
作品と観者の断絶を受け入れた上で「誠実に見届けること」田中功起「気づいたことのまとめとリスト」
これは「作る側」だけでなく「見る側」からの視点によっても、時空間の限定/拡張が生じることを示している。制度的限定の中で前提とされている鑑賞の態度は、上記の分類のうちの一つにすぎない。そのような態度は制度的限定を暗黙の前提としており、「作品」の持つ時空間の潜在的可能性を考慮すると、僕たちが異なるモードを必要としていることが分かる。そして田中との議論の中で、保坂健二朗はそのモードについて次のように語る。
病気だけに目を向けるのではなく、たとえ理路整然としていなくとも、患者の語りに耳を傾け、患者が物語を語ろうとする姿勢を、道徳的に見届ける。クラインマンは、治療というものをある種の共同作業として捉え直していきます。分析・解釈・判断よりもまず「見届けること」を重視しようとするその姿勢は、彼の精神科医としての経験と、そしてアジアにおける医療の調査に基づいているわけですが、美的体験における作品と観者の関係を考えるときにも、極めて示唆的です。保坂健二朗「見届けること」
ここでは分析・解釈・判断よりも、まず「見届けること」という態度の優位が説かれている。翻って言えば、「見る側」の視点が分析・解釈・判断という態度に一元化していると、時空間も制度的限定から解放されえないことを意味している。もちろん「作品」は制度的限定を意図されている(「見られること」を「作ること」より優先する)場合でさえ、それを逃れる可能性を持っている。しかし、ここで彼が示しているのは、「作ること」と「作品」と「見ること」のどの視点からであっても複数の態度があり、それらは相互に関係し合いながら時空間を限定/拡張するということであり、固定化された視点や態度が、ある限定の中で結果的に「作ること」も「作品」も「見ること」も破壊してしまう可能性があるということだ。
田中はそこで、制度的限定に閉じない方法についての思考へと向かう。彼は「見せること」を暗黙の前提とした「作ること」を相対化するだけに留まらない。彼は公開書簡の初めから「作ること」の可能性について思考し、制度による時空間の限定に閉じ込めないことこそ創造性として述べている。
(A)展覧会というフォーマット(美術館やギャラリー空間で会期が決まっているとか、所与の条件がまずある)+(B)ホワイトキューブ(物理的なホワイトキューブのことではなく、大なり小なり理想的な展示空間を前提しているということ)+(C)そこで見せる人はかならずアーティスト(もちろん建築家やデザイナーもいるけど、つまりその場所で見せることを裏切らないひとという意味かな)、この三つを足したものが、「美術」という制度のベースになる。ここから導き出されたものが作品として展示される。これ「A+B+C=美術」が、この制度が前提としている作法(規制、様式)であり、この作法を逃れ出ているものはあまり見いだせない。田中功起「展覧会という作法を乗り切るために」
ぼくがここで考えてみたいのは創造性の回復のようなものです。「作る」ことが持っている可能性を限定された時間+空間のなかに閉じこめないこと。そのための方途を探ってみたいと思っているのです。田中功起「行為と作品と展覧会の関係」
彼の考える「創造性」を理解するために、ここで補助線を引こう。それは「大人」と「創造性」の関係である。西洋の概念体系では多くの場合、「大人」になるためにフロイトの言う「去勢」を経なければならないと考えられている。つまり、自らの限界を知り「現実原則」で生きること、社会化されること、常識を身につけることを「大人になること」と捉えている。そういった前提のもとで、「大人にならないこと」は「創造性」にとって重要であると言われる。
確かに「創造性」とは、現状や限定を超え出ることを意味している部分もある。だから、西洋の体系を前提に考えると、「大人にならないこと」と「創造性」は関連しているように捉えられる。しかし、それはあくまで西洋の体系を足場に思考して出力される結論にすぎない。僕たちは人類学者の研究を参照することで、異なる体系を足場に「大人」概念を思考することができる。それは別の仕方で「創造性」について思考することを可能にし、田中が考える「創造性」を理解する上で助けになる。
人類学者ヴィヴェイロス・デ・カストロは、アメリカ・インディアンにとっての大人の男性になる前提条件が、敵を殺害することであると言う。そして、敵を殺害するためには、敵の視点と自らの視点を交換できなければならないと述べる。
殺害者は、敵の視点から話す。「私」という表現で敵の自己を指し、「彼」という表現で自らを指す。多くのアメリカ・インディアンの間では敵を殺害することは大人の男性としての地位を得るための前提条件であり、完全な主体へと生成するために殺害者は、敵を「内側から」、換言すれば主体として捕捉しなければならない。このことと、非-人間的主体が人間を非-人間だと見做しており逆もまた成立するという、これまで議論してきた視点を巡る理論との間の類似関係は明らかである。殺害者は、敵が自分が眼差すように、自分自身を敵と見做すことができるようになる必要がある。「彼自身」へと、むしろ「自分自身」へと生成するために。エドゥアルド・ヴィヴェイロス・デ・カストロ「内在と恐怖」
ヴィヴェイロスによれば、鹿を狩るためには鹿の視点から自らを見ることができなければならない。猪を狩るためには猪の視点から自らを見ることができなければならない。そして、その視点の交差交換によって、鹿や猪が私をどのように捉えているかが分かり、子どもは殺害者になることが、自分自身へと生成変化することができるのである。
つまり、ここでヴィヴェイロスが主張しているのは、視点の交換を行えることが大人になることの第一歩であるということだ。この議論の先で重要になってくるのは、それが西洋の体系とは異なる概念体系であるということを示すことではなく、他者の視点を内在的に引き受けるという別の仕方が、どのような「創造性」の概念を生成するのかを示すことである。これまでの田中の議論は、いかに「見せる」かという作り手側の理想型について語るだけでなく、「見る」側の視点へと交差交換が行われていた。
それは鹿や猪の視点から自らを見ることで、再度その視点を自らに折り返し、自らの視点を拡張する営為であった。そして、それがアメリカ・インディアンにとっての「大人になること」を意味しているのは、西洋の限定的な「大人」概念と相反的であり非常に面白い。このことが田中における「創造性」にとって、どのような差異を生み出しているのだろう。
長いスパンで考えるならば視聴者は無限にいる、だからコンテンツの質が問われている、ということです。無限の時間を相手にすれば、作品を見るひとも無限にいることになる。と、ヨゼフソンの作品のあり方は、まさに普遍とはなにか、時間とはなにか、作品とはなにかについて考えさせられます。ただ、「見せること」が「つくる」において無頓着なものであるとしても、「つくること」に意識的・自覚的である限り、アウトサイダー・アートとはわずかながら距離を感じます。ここにぼくは注目したい。ぼくらが自覚的に「つくる」限り、問いは「見せること」とどうつき合うかということになる。ヨゼフソンはそれに無頓着であることで、「つくること」に普遍的な時間を手に入れる。田中功起「つくることを確保し、見せることを確保し、さて、しかし。」
ここまでの議論で、田中が「作り手」の視点と「観者」の視点を行き来することで「作品」について考え、その思考の中から「制度的限定」とその外側、言い換えれば「時空間の限定と拡張」にたどり着いたことを示した。そして田中は、我々の現実の前提条件を操作することで、僕たちの「この現実」をいかに揺るがしうるかを思考していたかを示した。しかし、それよりも重要なことは、彼が素朴に制度批判に向かい、普遍的な時間を手に入れようとするのではない点にある。彼は素朴に時空間の限定を批判し、無限の時間を称揚したりしない。彼は「作ること」と「見せること」について、いかに向き合っていくかという、よりタフな問いに向かう。
彼は「作り手」の視点から「時空間の限定と拡張」の度合いを操作し、「観者」の視点から「批評的態度」と「見届けること」の度合いを操作している。無自覚のままそのような変換と操作を行っているアーティストは、他にもいるかもしれない。しかし、田中がその変換について自覚的に述べていること、そしてそれを作品の基礎として見出せることは、何よりの驚きである。
彼は構造を見透かすだけでなく、構造を変換・操作するマトリクスを手に入れている。それは一人称と二人称の視点を往還することでたどり着く、その両者の視点を見渡せる第三の視点である。それはネッカーキューブのように一つの構造体でありながら、前部と後部のゲシュタルトを行き来することで、気がついたときには二つのゲシュタルトがあることを知る第三の視点にいることに似ている。
そして、この第三の視点は、超越的な視点ではなく、他者の視点を取り込み、自己へ再度折り返される度に変容する視点である。そのことは「作り手」と「観者」という二つの視点だけでなく、「虚構としての現実」と「現実としての虚構」という二つの視点の折り返しを取り入れていることからも分かるだろう。何故なら、片方の二対だけで生成されるマトリクスは、両者の二対で生成させるマトリクスとは質的に異なるものになっている。田中にとっての「創造性」は、いくつかの二対の視点を交差交換し、変換して操作しうる第三の視点に立つこと、そしてその視点を生み出すこと自体によって発揮される。複数の時空間を見渡せる場所からの視点で、再度「作る」こと。それによって、彼は「作品」を生み出しているのである。
4. 「モノの視点」を通じて思考する ― 様々な時間の中から世界を眺めること
田中の作品は、視点と関係性の変換と操作によって各々の身体に働きかけることで、時空間を多層化することを、ここまで示してきた。しかし、まだある前提を隠蔽している。僕の解釈は、田中功起という作家がすでに持つ記号性や象徴性を無視した上で、初めて彼の作品やテキストと出会ったかのように対峙することで見出されるものだからである。これから行うことは「見せること」ではなく、「再度見せること」である。モノを制作し作品として披露した後、幾許かの時間を経て再度作品を展示する時、「作ること」と「見せること」の視点と関係だけでなく、これまで問題にしてこなかったもう一つのレイヤーが現れる。
そのレイヤーは制度的な時空間だけでなく、潜在的に可能な様々な時間の中に作品が晒されることで生じる。作品は「議論や解釈」をされ、「見届け」られ、そして「無関心」に晒される。僕たちはそれらが生み出す影響を無視することはできない。何故なら、それは「作ること」と「見せること」の後に続く時間の中で、否応なく生み出されるものであり、それは作品の持つ時間と密接な関わりを持っているからである。それは「見せること」と「再度見せること」の間に異なる扱いを、僕たちに要求するのだ。
もちろん理想的な状況は、議論のプロセスが開かれており、無数の解釈によって研究され、それらが文化的にフィードバックされることで、歴史が積み重ねられていくことであろう。しかし多くの場合、ある解釈の方向性が力を持ち、固定化し、象徴化していく。それは解釈フォーマットとして、鑑賞者が作品を見る前に、例えば「田中という作家は『関係性の美学』の延長線上にある作家だ」とか「日常を扱ったマイクロポップな作家だ」などと言ったように、作品について記号的に語ることを可能にする。解釈フォーマットは、展覧会フォーマットが時空間を制度的に限定するのと同じように、時空間に影響を及ぼしてしまう。よって僕たちは、ここで「作ること」と「見せること」だけでなく、解釈フォーマットについて再考しなければならない。
例えば、水戸芸術館現代美術センター学芸員の竹久侑氏によるテキストでは、こう記述されている。
田中の作品は、おおまかに言って、主に日用品(物)と被写体としてループの技法をつかった初期のビデオ作品から、アクション(行為)を主体とするものへと関心が移る2004年を経て、複数の人びとが何かを行う状況を記録する2007年以降へと推移をたどることができる。そして《A Haircut by 9 Hairdressers at Once (Second Attempt)》を皮切りに、第55回ヴェネチア・ヴィエンナーレ(2013年)でも中心に展開されたのが共同作業をめぐる取組みだ。竹久侑「共同体はどこにあるのか?」
第55回ヴェネチア・ビエンナーレで日本館キュレーターを勤めた蔵屋美香は、このように記している。
田中功起は2000年前後、トイレットペーパーやボール、バケツといったありふれた日常の事物が、まるで自分の意志を持つかのようにふるまうループ構造の映像で注目された。その後田中は東京からロサンジェルスへと活動の拠点を移し、モノだけで自足した世界から、モノに対する人の働きかけへ、さらには人と人との関係性へと、徐々に関心を移行させてきた。蔵屋美香「遠まわしに言うなら… − 第55回ヴェネチア・ビエンナーレにおける田中功起の展示について」
また海外の批評においても、2013年『ArtAsiaPacific』七・八月号にてガブリエル・リッターが、こう書いている。
日本を離れて以降、日用品の物質的な探求から特筆すべき転回を経て、彼の作品はますます共同作業的になっていった。彼自身が行為を実行する代わりに、上記の共同作業的作品は、多様な参加者が所与のタスクを遂行しているのを記録することに焦点をあてる。ガブリエル・リッター「OUT OF THE ORDINARY: KOKI TANAKA」
それは三者による独自の解釈というよりも、もはや現在最も流通した田中功起作品への解釈フォーマットと言えるものである。確かに「扱っているモチーフ」という視点からみれば、彼の一連の試みは「現象から行為へ、そして共同性へ」と移行してきたと要約できる。しかし、これは作品に対する一つの解釈に過ぎない。それでも強い影響力を持つ解釈は、人々が作品と対峙する前に、意識的か無意識的かに関わらず、作品をある固定的視点で見ることを強要する。それは多くの人に広がれば広がるほどにフォーマット化し、観者が身体を通じて作品からモノ性を体験する前に、彼らが作品と記号を対応させることを許し、モノの多層性を隠蔽してしまう。
よって、僕たちは「再度見せること」について考えなければならないし、そのためには批評について論じなければならない。そうでなければ、作品が経由してきた議論と批評の時間を無視し、漂白された状態で作品と向き合うことができるという理想的な状況を想定した上で、展示を構成することになる。それは避けなければならないだろう。
さて、田中は沢山遼との往復書簡にて、批評について議論している。そこで彼らは、人とモノとの関係性とその学習、そしてモノの自律性について述べている。その議論を追うことで、僕たちの思考も進めていくことにしよう。
田中; 通常とは別の運用方法でさえも、そのお皿を「お皿」であると言及するための、つけ加えられるべき事柄のひとつなのではないでしょうか。つまりその運用方法も既に「お皿」に内在していた。だからそれは「開発」されたのではなく、むしろ発見されたのであり、限定されていたかに思えた「有用性」もそれによって「拡張」されたとも言えるわけです。ものの使用方法は社会的に限定されているものです。慣例に従って、お皿にはパンケーキとバターが盛られ、メイプルシロップがかけられる。でも子どものとき「お皿」は空飛ぶ円盤であり、つるつるすべすべしたものであり、重石でもあった。それらもすべて、ひとつのお皿を「お皿」と定義していますよね。つまり「お皿がお皿である」とわかるためには、社会化された使用法や有用性を知っている必要がないのかもしれない。異なる運用方法もその「お皿」に備わる属性であり、それを見つけ出す行為は「お皿」という存在を内側から補強している、とも言えるわけですね。そして沢山さんが書いていたように「芸術批評の機能や役割とは、……その作品の効果・運用方法を限りなく拡張する」のだとすれば、このとき「批評家」とアーティストは限りなく近しい存在になる。田中功起「批評的態度、お皿は一万年後もお皿か」
沢山;私は、あらゆる事物は批評、あるいは批評的な性質を内在している、と書きました。それはたとえば「お皿はお皿として使える」というトートロジカルな機能主義的限定に求められる。しかし一方で水分を漏らさず、食べ物を盛ることができる食器の性質とは、それが関係するもの(食べ物)をその性質において、予め内包しています。そのため、この言明をトートロジーとすることには、重大な矛盾が孕まれているのかもしれません。通常トートロジーとは「同じであること」を根拠とする閉鎖的な命題のことを示しているからです。ですが、お皿がお皿であるというトートロジーは、お皿の「機能」についての言明であることで、「関係」を先行させている。では、この「トートロジカルな関係」という言明じたいの矛盾はいかにして解消されうるのか。また、私が事物の批評性として定義した、この種の機能主義的な自己言及性(トートロジー)は、田中さんの第二信で疑問点として挙がっていたように、「空飛ぶ円盤」であり、「つるつるすべすべしたもの」であり、「重し」でもあるような、お皿の異なる運用方法の拡張をいかにして許容するのでしょうか。言い換えれば、自己言及性と差異、あるいは関係は、まったく別の階層に帰属するものなのでしょうか。沢山遼「批評というリヴァイバル」
この論点は三つに要約できる。
まず第一に、視点と関係は自律に先立っていることが挙げられる。モノの性質の自律性は、人間とモノの関係を隠蔽することで成立している。例えば、僕たちは「砂糖は甘いという性質を自律的に持っている」と、常識的な意味で考えている。しかし、それは人間の摂食行動と砂糖が関係することで、初めて「甘い」という性質を引き出すことができるという事実を隠蔽している。形容詞はある視点から捉えられた関係性を意味している。石が固いことも、その多くは人間にとって固いことを意味しており、ゴリラなど人間より握力の強い生物にとっては脆い可能性がある。つまり、視点と関係は自律に先立っているのだ。
第二に、視点と関係によってモノの潜在的可能性の限定/拡張が生じるが、これは慣習の学習過程の中で社会化していき、それによってトートロジカルな機能主義的限定、つまり自律性という幻想が生じることが挙げられる。人間側の視点から「お皿」とどのように関係するかが、「お皿」の持つ有用性を限定する。その関係によって、初めて「お皿」の有用性が発揮されるのだから、それは限定であると同時に拡張である。ある異なる仕方で関係することは限定であり、その視点から見た限定は、モノの可能性を拡張することに等しい。もちろん、子どもは様々な仕方でモノと関係することで、モノから様々な有用性を引き出す。それは料理を盛りつける器でありながら、「空飛ぶ円盤であり、つるつるすべすべしたものであり、重石」でもあった。しかし、人間とモノとの新たな関係性のための実験精神は、社会的な慣習を学習することで失われていく。それは社会的な正しさを学んでいく過程であり、沢山の言葉を用いるなら、あらゆる事物はその社会的な慣習の学習=トートロジカルな機能主義的限定を求めるようになる。つまり、モノは固定的な限定性を、社会的に獲得していってしまうように見える。批評と教育のある一面は、視点を固定し関係を固着していくことで、自律性という幻想を構築するのである。問題はモノと限定的関係を結ぶことではなく、その視点と関係を一元化し正しさを付与し固着化してしまうことにあるのだ。
第三に、モノの「効果・運用方法を限りなく拡張する」ことを、アーティストの役割の一つの側面とし、批評家がその役割を果たすなら、アーティストに限りなく近しい存在になると述べられている。ここでは、「トートロジカルな機能主義的限定としての批評」と「アーティストに限りなく近しい批評」という二つの方向性が暗示的に示されている。
この三つの論点は、先ほどの西洋における「大人」概念を再度補助線として用いることで、より明確になる。何故なら、その補助線を経由することで、批評と学習には二つの種類があることが分かるからだ。西洋において大人になることは、潜在的可能性を限定する方向性を意味していたが、アメリカ・インディアンにとってのそれは、視点を交差することで関係性を拡張する方向性を意味していた。
関係の先行性と自律の後発性は、相互に隠蔽しあっている。それらは関係性によって自律性が生じ、自律性によって関係性が先行しているように見えるのだ。そして、その間には批評と学習があり、それらは異なる二つの文化で異なる仕方で大人になることを意味している。自律性と関係性の間で、二つのプロセスが逆方向に作用しているのである。それは「限定する方向」と「拡張する方向」であり、「トートロジカルな機能主義的限定としての批評」と「アーティストに限りなく近しい批評」である。そして、その両者には各々機能と役割があり、限定と拡張の往復運動を固着化してしまうことこそが問題であった。
これは先に挙げた、社会的に評価された作家や作品の解釈フォーマットが一元化していくことと同様の問題である。本来メディウム(物質性)とイメージ(情報)は、各々が多層性を持っているにも関わらず、制度化された批評システムと社会化する学習プロセスの中で、一つの物質性と一つの情報として対応関係が固着化してしまう。沢山が示すように、制度化された批評システムとは、この一対一の構造を透視し、自己言及性として可視化することにある。もちろんそれは、まだ評価が定まっていない作家や作品を評する時に、重要な役割を果たす。何故なら、近代における批評家の役割は、作品がどのような文脈の上で何を意味していて、何故素晴らしいと言えるのかを、多くの鑑賞者に対して解説することだったからだ。それによって、人々は作品を解釈する糸口を得る。
しかし、その視点と関係性が一元的に固着化していき、それによって既に幾許か評価が定まり、フォーマットが固定的に存在している場合、「トートロジカルな機能主義的限定としての批評」ではなく、その固着化を解放するような「アーティストに限りなく近しい批評」が必要となる。そこで求められているのは、固着化している作品と記号の前提に潜む関係構造を透視し、再度物質性と情報の多対多の関係を開き、異なる仕方で物質性と情報を再組織化するような批評である。
僕はここまでの議論で、「作り手」の視点と「鑑賞者」の視点という二つの視点から、時空間の限定と拡張の可能性を論じてきた。それによって、関係性と自律性の間にある「トートロジカルな機能主義的限定としての批評」と「アーティストに限りなく近しい批評」という二つの方向性を取り出した。限定することで伝達可能性を高める批評と、その伝達した意味が固着化した場合に、それを拡張することで潜在的可能性を切り開く批評である。
しかし、批評が生じるのは、作品が発表された後である。それは展覧会などの制度的限定を超えて、多様な時空間の中で展開される。ラスコーの壁画について語ることがあれば、現在開催中の若手の展覧会について議論が行われることもある。誰がいつ制作したものなのかすら分からないものと対峙しなければならないこともある。それらは異なる時空間を要請し、各々の時空間によって異なる解釈が生成されるだろう。モノは「作り手」や「鑑賞者」といった人間の時間を超越している。だからこそ、僕たちはモノが切り開く非人間の時間を、必然的に思考しなければならないのである。
この作品の持つ非人間的な時間について考えを進めるために、先ほどの往復書簡から沢山の締めのテキストを引用してみたい。
沢山;道具の歴史では、メッセージを媒介する、あるいは運用方法を適切に処理することが重視される。あるいは逆に道具を媒介として、他者とその場でルールが共有され、物事が伝達されます。第一信で言及しましたが、柳宗悦が提唱した「無名性」とは、そのようなオブジェクティブなレベルでの情報の継承性のことを指すのだと思います。どの個体が進化に寄与したかということがあまり問題にならないのと同じで、そのようなプロセスは固有名の存在=有名性とも媒体自体の自律性とも関わりなく進行するでしょう。そのとき人間は異なる事物と事物を伝承する媒介(メディウム)に過ぎなくなるからです(ゆえに柳の言説とはメディウム(媒体)の自律性を確保しようとする人間主体への批判=大文字の芸術への批判として読むことができます)。
逆に言うと、道具からその用途が失われることは、マヤのピラミッドやナスカの地上絵のように、それを作った人々とのコミュニケーションの回路が失われてしまったということです。たとえば、ほとんどの遺構や先史時代のオブジェはそれがどのような因果関係を組織するものか分からない。ですが、それは未知の他者からのメッセージを内包させているのかもしれません。素朴な実感として、芸術批評の過程では、物質的痕跡からある歴史的・環境的な因果関係を解読する考古学者のような興奮に駆り立てられることがあります。批評は、過去の遺構に接するように、おそらくこの一万年のタイムスパンを同時代の芸術作品にも感じているのかもしれません。長い時を通過し、継承と伝承の回路が断ち切られたオブジェに接するように、作品に接すること。その情報の圧縮、縮約の振幅に立ち会い、思考の抽象性と感覚的実体とを媒介させるため、認識論的推論を働かせること。擦り切れ、摩耗したメッセージ、コミュニケーションを復活させること。であれば、私たちには一見想像不可能な技術体系のもとに獲得されるメッセージを瞬時に封じ込めた、そうしたメディアがたまたま「芸術」などと呼ばれてきただけかもしれない。芸術の「現在性」を設定することの困難は、そうした点にあるようにも思われます。つまり、それがいかに同時代的な事象であっても、強靭な思考と野心と実践を孕んだ作品に対しては、批評は一万年越しの「復活(リヴァイヴ)」のトーンとともに記述することになるかもしれないのです。沢山遼「批評というリヴァイバル」
ここで沢山が述べているのは、人間が歴史として伝達してきた情報がすべて失われてしまったとしても、モノによる伝承の可能性があることである。そして、柳宗悦が提唱した「無名性」は、一般的な意味における批評にとって隠された視点と時間軸を露わにする。それは「固有名」の歴史が失われた後、例えば人類が滅亡しても、モノは視点を持ち、メッセージを伝え、それをまだ見ぬ他者に読解されうる可能性に満ちた時間軸であり、「その伝承プロセスは固有名の存在=有名性だけでなく媒体自体の自律性とも関わりなく進行する」。それは人間の視点に基づいた関係性がすべて途絶えた後の、モノたちの関係性と自律性のうごめく世界を想像することであり、そのような世界を前提とした上で、批評家は現在の「強靭な思考と野心と実践を孕んだ作品」に対しても、考古学者のように情報の伝承が断ち切られたモノの痕跡からモノの多層性を引き出し、人間という生物にとっての情報の多層性を、推論によって復活させるのである。
僕たちは、人間的視点から解放されたモノとモノとの関係性と自律性の視点に立つことができる。僕たちには、物質の多層性を開く方向が残されているのだ。それは身体などの計測器を用いて、モノからモノの多層性へ、そしてそのデータを元に推論を働かせることで、情報の多層性へと進む視点である。つまりそれは、僕が芝生に寝転がったときに、虫の視点から世界の条件と可能性を知ったように、モノの視点から情報を産出する方法である。
それは人類が絶滅した地球に宇宙人がやってきて、固有名が漂白された大量の芸術作品の山を目の前にしたところを想像させる。彼らは各々の作品の大きさや形、反射光の範囲を計ったり、制作時期を一つ一つ計測したり、置かれている場所や地域を調べ分類をすることを通じて、大量のデータを収集し整理するだろう。それらを用いて、この痕跡を残した生物が求めていた意味や機能、僕たちが過ごしていた環境、そしてどのような生物であったかを推論して、情報の束へと進むだろう。
制作されたモノは、人間社会の中に生まれた「私」という偶然の存在者を社会的に必然な存在者へと転化するだけではない。進化の偶然性の中で生じた「人類」という生物の偶然の産物を、必然的なものへも転化するだろう。このようなモノがある、それは痕跡を残している。つまり、「人類」は存在していなければならなかった。自律性と関係性が相互に隠蔽しあうように、偶然性と必然性は相互に隠蔽し合うのである。その二つの間を媒介するのが、制作されたモノなのである。
今や僕たちは、情報の伝達から人間的伝承と文化の連なりを感じ、モノの伝承から非人間的な伝承と自然の連なりを感じることができる。「情報からモノへ」「モノから情報へ」という二つの視点を交差することで、変換・操作しうる第三の視点=マトリクスを手に入れることができるのだ。それこそが「物質性と情報の多対多の関係を開き、異なる仕方で、物質性と情報へと再組織化」する。そのマトリクスは超越的な定点ではなく、視点を交差するたびに変容する不安定な視点である。それは僕が田中功起の作品を分析する際の方法論であったが、田中功起の作品を分析することによって記述可能になった方法論でもあった。第三の視点は二つを何度も往還することを通じて、この両者を見渡せる場を生み出し、その場に立つことで獲得できる。それは数年から数十年、数百年、そして人類が滅亡した後の数万年といった、多数の時間軸が併存する場であろう。僕たちは、その場から世界を眺めることによって初めて、様々な時間軸のスケールでモノと関わることができるようになる。
「現象から行為へ、そして共同性へ」という標語にとって、現象とは人間にとっての現象であり、行為というのも人間の行為で、共同性も人間にとっての共同性を意味している。それは視点を人間中心主義的に限定した場合の妥当な推移であるし、その限定は多くの人にとってフォーマットとして機能していることからも分かるように、「トートロジカルな機能主義的限定としての批評」として成功している。
しかし、これまで見てきたように、田中は一貫して視点と関係性から自律性という幻想を揺るがし、時空間の限定/拡張を変換・操作することで作品を作り出そうとしていた。それは「人間」の視点であり、「作り手」と「鑑賞者」と「モノ」の視点であり、それらの交差的な交換であり、その交換によって拡張される各々の関係性であった。「人間」の視点からは、近代を前提とした制度的な時空間やそれを超えた時空間があることが確認された。「モノ」の視点からは、非人間的な時空間が見出された。
これらの解釈を経由すると、田中の作品は「日常から関係性へ」や「現象から行為へ、そして共同性へ」などと表層のモチーフで整理することもできるし、深層では常に上記の思想が彼の制作の基盤にあると考えることもできる。言い換えれば、その深層にある構造から、一貫して上記の思想と態度によって時空間を生み出しているのである。そして、その思想と態度が一貫しているのであれば、彼の作品も「現象から行為へ、そして共同性へ」とシンプルに整理できないのではないかという疑問が生じる。そして、その疑念を元に彼の活動を振り返ると、忘れ去られている、しかし重要な作品群が見つけ出せるのである。彼は、大学生の頃、「関係性の美学」や震災とは無関係に共同作業と解釈されうる作品を作っていたのだ。
大学を出てすぐの個展(2000)を、当時銀座にあったナガミネプロジェクツで行います。コーラの映像(《Moving Still》2000)と二つの円形のケーキ(《Cakes》2000)をガラス張りの冷蔵庫に入れて展示しました。円形のケーキは一部が実際に食べられるもので、残りはそれをサポートする立体物といった仕様でした。二つあるケーキはオープニングとクロージングで、食べられる部分を僕が切り出して、その場にいる人たちでいっしょに食べました。いまになって思えばこれは現在の自分の活動に繋がるものです。ひとつのケーキを複数の参加者でシェアして食べる、と言えばいまのぼくのプロジェクトのようにも聞こえます。林卓行+田中功起「Q&Aセッション」
この個展は、先の「世界―速度の変容―コンセプチュアル・アートの「遅さ」をめぐって―」と同時期に開催されたものであり、表層のモチーフが「現象から行為へ、そして共同性へ」と推移したわけではないことが分かる。彼は《Cakes》(2000)以外にも、大学生の頃に同じ誕生日の人を集めて話をしてもらっている映像や、四人のアート関係者に集まってもらって彼の次回作を考えるというヴィデオ《Discussing a Future Project》(1998)を制作しており、ループの映像を作り出す以前にリレーショナルな映像作品を多数残している。
またループ映像を作っている時期にも、53人でババ抜きをする《Play card with 53 people》(2003)というパフォーマンスや、オープニングパーティに来て真面目に話している人に派手でバカバカしいトロピカルカクテルを手渡す《Tropical Project2》(2003)というパフォーマンスを行っていた。テキストだけでなく、これらの作品と実践を再発見することでも、彼の思想が2000年以前から2017年現在まで通底していることを証明できる。
「Everything is Everything」(2006)のあるシーンでは、傾いている銀のテーブルを人が足で支えながら、少しずつ足の位置を下に降ろしていく。足を離したらテーブルはガシャーンと音を立てて床に叩き付けられるという予感を伝えてくるのだけれど、結局テーブルは思ったより優しい足さばきによって小さな音とともに床と接触する。その足さばきがゆったりとした振る舞いであるが故に、僕たちはそのシーンが進行していく間、「人―離す―銀のテーブル―大きな音―床」という関係の可能世界を強く想像してしまう。
《A Haircut by 9 Hairdressers at Once (Second Attempt)》(2010)では、前のめりになった男性の姿勢、各々の発言回数の差異や話を聞いている人の表情から、集団での各々の自意識と配慮の勾配を伝えているし、美容師が議論中に確認することなく好き放題モデルの髪に触れていることを通じて、モデルと美容師という関係性が可視化される。
人とモノ、モノとモノ、人と人という、対象の違いはある。しかし、その差異は暗黙のうちに人間の視点を固着化してしまっている。人間の視点だけに固着しているからこそ、その差異と推移を重要なものと捉えてしまう。モノの性質を試したり、モノとモノの接触による形の変容や音の発生をおさめたり、モノの有用性を拡張しようとすることも、九人の美容師がどのように切るか議論している場面にしても、美容師がはさみをつかってモデルの髪型を変容させるのも、モノとモノとの対話であり、表層にはあらわれないモノとモノの関係と自律の蠢きという深層構造を教えてくれているのだ。
そこから僕たちは、小さくも大きい変化を、現実と地続きのものとして引き受ける。普段の生活のふとした瞬間に、関係性を記号的に処理するのではなく、モップが床に倒れる時の音に耳を澄ましたり、僕の振る舞いに対する恋人の表情の変化に敏感になるなど、日常を解像度高く多層的に体験することができるようになる。それは一見すると、取るに足らない変化かもしれない。しかし、そのとき僕たちは、制度や慣習の外側にある時空間に触れているのである。
そして、モノとモノとのコミュニケーションは、人間のいなくなった後でさえ起こるであろう、形と形の対話なのである。情報による伝承される過去、僕たちが生きている現在、僕たちが死んでしまった後の未来、そして人類がいなくなった遠い未来も、今ここに同時に並列的に存在している。僕たちは、その他の時間を無視して、生きる権利をもっている。それらを見たことがあるものとして、嘲笑する権利をもっている。しかし、今もそこに無数の時間が流れている。それは田中功起作品が装置として機能することで、僕たちを誘い込む多様な時間が共に存在する場であり、僕たちはその無数の時間が流れる場を見渡せる視点に立つことによって、初めて田中功起が制作する場へと立ち会うことができるのである。
ヒトはコンピュータに「手」を委譲して、自らの手の行為を「ボタンを押す」という行為に最小化した。ヒトの行為の最小化にともない、物理世界でヒトによって引き起こされてきた出来事は数値化され、コンピュータに格納されていった。ヒトは出来事をボタンで呼び出す。ヒトから「手」を委譲されたコンピュータは、数に神秘を感じることなく、かつてヒトの手が起こしていた出来事を処理し続ける。
アイヴァン・サザランドの「スケッチパッド」では、ヒトはボタンを押しながら、ライトペンで数学的に正しい図形を描く「合生的行為」を行うようになった。今回は、ダグラス・エンゲルバートとアラン・ケイがそれぞれ開発した、「マウス」というデバイスと「重なるウィンドウ」というシステムから、インターフェイスを起点に生じたヒトとコンピュータとの合生的行為と、そこから引き起こされる認識の変化を考えたい。
物理空間をディスプレイに写像するマウス
マウスやウィンドウといった技術を発明して、こういう「コンピュータ情報空間とヒトの物理的空間の相互浸透」をはじめて実現してみせたのがエンゲルバートだった。いまはどんなパソコン・ユーザでも、マウスでファイル・アイコンを引きずって屑箱アイコンに入れたり、マウスのクリックで複数のウィンドウをひらいたり、といった作業を日常的におこなっている。だが、それらがいかに本質的なマンマシン・インターフェース技術か、ということはいくら強調してもし過ぎることはない。西垣通「”思想”としてのパソコン」
ダグラス・エンゲルバートのチームは、ヒトの知能の補強増大を目指した「NLS(oN-Line System)」で用いるポインティングデバイスとして、マウスを開発した。マウスは現在、グラフィカル・ユーザ・インターフェイス(GUI)において欠かせないポインティングデバイスとなっている。しかし、エンゲルバートは、マウスは誰もが簡単に使えるような単純なデバイスだから、効率良く作業できる別の複雑なデバイスがマウスに取って代わると考えていた。しかし、その予想に反して、インターフェイスの歴史は誰でも使いやすいマウスを選択した。エンゲルバートにとって、未だにマウスが使いつづけられ、自身が「マウスの開発者」としてインターフェイスの歴史に名を残したことは誤算だっただろう。
ただし、マウスは単に使いやすいという理由だけで現在まで使われているわけではない。ライトペンやスタイラスペンのようなペン型のデバイスが、直感的に何かを指差したり描いたりする機能を連想させるのに対して、マウスはポインティングデバイスとしては全く直感的なかたちをしていない。西垣が指摘する「コンピュータ情報空間とヒトの物理的空間の相互浸透」というインターフェイスの本質的な状況を、ヒトとコンピュータとのあいだにつくりだしたという観点から、マウスのような直感的とは言い難いポインティングデバイスが、なぜこれほどまでに使われるようになったのかを考えてみる必要がある。
マウスを机の上に置いて動かすとディスプレイ上の「点」や「矢印」が動くが、NLSではこのポインティングする先を示す黒い点は、「バグ」と呼ばれていた。バグは現在のGUIでは「カーソル」と呼ばれ、矢印のイメージになっている。マウスとバグ=カーソルとがセットになって、ディスプレイという一つの平面に物理空間と情報空間とを重ね合わせる。
ディスプレイはX軸とY軸に基づく二次元のグリッドに区切られている。マウスが置かれた面とディスプレイとは重なり合っているため、ディスプレイ上のカーソルと連動するマウスもまた物理空間をXYグリッドに区切っていくといえる。ライトペンはディスプレイのXYグリッドを直接指定し、スタイラスペンはあらかじめXYグリッドに区切られたタブレットの平面と対になって機能する。対して、マウスはタブレットのような特別な平面を必要とせずに、物理空間にある平面をXYグリッドに区切っていくデバイスである。
例えば、マウスとカーソルによって情報平面と接続された物理平面は、一つの平面でなくてもいい。机の上で動かしていたマウスを別の壁の上で動かしても、情報平面では「机」と「壁」という平面のちがいは問題にならずに、ディスプレイ上のカーソルが動きつづける。さらに言えば、マウスは平面すら必要としない。エンゲルバートが開発したマウスの場合はX軸とY軸の値をとる歯車が動けばいいので、NLSのデモのなかで、エンゲルバートのチームはマウスを裏返して指で歯車を動かし、バグを動かしている。そのとき、指はディスプレイのXYグリッドと重なり合った存在になっているといえる。
物理空間はXYグリッドで区切られているわけではないが、ヒトは物理空間を「机」や「壁」といったように言語で分割して理解している。マウスはヒトによる言語の分割に上書きするかたちで、コンピュータのために物理空間をXYグリッドで分割していく。それは、三次元の物理空間を二次元のディスプレイの平面に重ね合わせるためでしかない。しかも、そのディスプレイの平面はコンピュータが示す「部分像」でしかないのである。
ここで扱うフレームワークにおいて、所与の概念構造がコンピュータによるシンボル操作と完全に両立するシンボル構造で表現できることは述べておく価値がある。そのような構造は、個人が紙の上で実用的に作り上げて使用する構造に比べ、複雑な概念構造を正確に写像するという目的の上ではるかに大きな潜在力をもっている。コンピュータは、全構造のうちディスプレイ・スクリーン上に二次元画像で表された限られた部分像と、この「部分像」を表現するn次元内部イメージの特定の局面とのあいだを往来することができる。もしヒトがこの「部分像」に変更・付与をおこなえば、コンピュータはその変化を内部イメージのシンボル構造に組み込み(コンピュータ向きのシンボルと構造によって)、それによってもし概念上の矛盾部分があれば自動的に検知することができる。ヒトはもはや、ほとんど概念内容が間接的・分散的・非明示的にしか指定できないような、融通のきかない限られたシンボル構造の上で仕事をする必要はないのである。ダグラス・エンゲルバート「ヒトの知能を補強増大させるための概念フレームワーク」
エンゲルバートは、コンピュータ内部のn次元構造がディスプレイの二次元画像に写像されると考えていた。そして、マウスは物理空間のあらゆる平面を、n次元の情報が写像された二次元に重ねていく。そのとき、マウスが置かれた机の上などの物理平面の表側がそのままディスプレイの表面として重なり合うが、それは一対一に対応してはいない。コンピュータのn次元を介しているため、マウスが示す物理空間の一つの点は、情報空間の多数の次元に対応する。ディスプレイの平面のXYグリッドはコンピュータの全構造の「部分像」でしかなく、その奥にはXYグリッドで区切ることができないn次元がある。けれど、コンピュータのn次元の構造をヒトが理解するには、二次元のディスプレイで表示するのが最適とされてきた。ヒトは言語による物理空間の分割を無効化するかたちでグリッドシステムを重ね合わせ、コンピュータのn次元と行き来するようになる。
「鼻」としてのマウスとカーソル
デモの流れからは、エンゲルバートは、新しいコンピュータシステムを、聴衆が既に知っていることや行なっていることに関連づけるように留意しながらも、シミュレートされたメディアの全く新しい特徴に集中していたことが分かる。デモの最初はワードプロセッシングに割かれているが、彼はテキスト入力、カット、ペースト、挿入、ファイル名入力とファイル保存など、コンピュータをより多目的なタイプライターに変えてくれるツールの簡単なデモが終わると、続いて従来の記述メディアが持ち得なかった新しい機能である「ビューコントロール」のより詳細なデモに移っていく。エンゲルバートが強調するように、この新しいライティングメディアム上では、ユーザーは、同じ情報を複数の視点を切り替えながら扱うことができる。テキストファイルは違ったソートをすることが出来る。また、アウトライン・プロセッサやマイクロソフトワード等の現在のワープロのアウトラインモードのように、いくつかのレベルの階層に整理することもできる。例えばアイテムのリストはカテゴリ別に並べ替えることが出来るし、それぞれのカテゴリは展開したり、逆に格納することができる。レフ・マノヴィッチ「カルチュラル・ソフトウェアの発明 — アラン・ケイのユニバーサル・メディア・マシン」
ニューメディアの理論家であるレフ・マノヴィッチは、エンゲルバートのNLSの最も特徴的な機能として「ビューコントロール」をあげている。ビューコントロールはコンピュータのn次元構造に対応しているが、私が注目するのはビューコントロールにおけるマウスとカーソルの役割である。
マウスとカーソルは、ビューコントロールのなかでヒトが迷子にならないようにアンカーとして機能している。なぜなら、クリックするごとにテキストの構造が変化し、その見た目も次々に変わるディスプレイのXYグリッドにおいて、カーソルは常に最前面にあってクリックした座標にありつづけるからである。また、ライトペンやタブレットのスタイラスペンとは異なり、マウスは平面に置いて使うデバイスである。ペン型のデバイスは使い終わったあとでどこかに置くことになるが、それはヒトが最後に行った行為の状態を保持しない。しかし、マウスはもともと平面に置いて使うデバイスであるから、ヒトとコンピュータとの合生的行為の最後の状態をXYグリッドに基づいて保持する。それは、カーソルの位置座標としてディスプレイにも保持されている。マウスとカーソルはヒトの行為が終わったあとも、物理空間と情報空間とが重ね合わされた状態を保持するのである。マウスとカーソルの不動性が、ビューコントロールのような変化しつづける情報平面に、ヒトをつなぎとめる役目を担っている。
マウスはカーソルとともにn次元・二次元・三次元を行き来しながら、情報空間と物理空間とを重ね合わせる一つの起点となっている。マウスとカーソルとのつながりを一つのを起点にして、ヒトとコンピュータとのあいだに二つの空間を重ね合わせたディスプレイという一つの平面が生まれ、そこでXYグリッドに基づいた合生的行為が行われる。マウスとカーソルは物理空間と情報空間とのあいだで合生的行為を生成し続け、最後の行為の座標を残す。
二つの空間で起こる合生的行為とともに存在しつづけるマウスとカーソルは、ヒトとコンピュータにとっての「鼻」のような存在であると言えるだろう。カーソルはヒトの「鼻」のように情報空間にありつづけ、マウスはコンピュータの「鼻」のように物理空間にありつづける。カーソルとマウスは、ヒトとコンピュータとが起こす合生的行為を特定する「鼻」として機能している。生態心理学者のJ・J・ギブソンは、世界を認識する際の「鼻」の役割を次のように指摘している。
頭、胴、腕や手を含めて、自己を特定する光学的情報は、環境を特定する光学的情報に伴う(accompanies)。この二つの情報源は共在している。一方は他方なしには存在し得ない。人が世界を見るときには同時に自分の鼻を見る。というよりは、むしろ世界と自分の鼻が両方とも同時に特定されているが世界と鼻についての認識は両方の間で推移しうる。両者のどちらに注意がいくかは見る人の態度による。強調しておく必要があるのは、情報は両方に有効だということである。J・J・ギブソン『生態学的視覚論』
ギブソンが語る「鼻」は、自分のものにも世界のものにもなりえる対象であった。では、ヒトとコンピュータという、異なる二つの世界で行為をする主体において、「鼻」とはどんなものであろうか。
ヒトはコンピュータを操作する際に、情報空間のなかにカーソルという「鼻」を見ている。コンピュータはヒトとともに合生的行為を起こす際に、物理空間のなかにマウスという「鼻」を見ている。ここでは、二つの空間と二つの「鼻」という四つの情報源が共在している。これら四つの情報源が常に動くことで、物理空間と情報空間とが重なり合った環境と、行為を遂行するヒトとコンピュータという主体が特定されて、合生的行為が生じる。このときヒトは、マウスとカーソルという二つの「鼻」と物理空間と情報空間とを、同時に認識している。四つの情報源からのフィードバックを処理する必要があるがゆえに、ヒトはコンピュータの前では多動的にならざるを得ないのである。
「重なるウィンドウ」がもたらした変革
アラン・ケイが提唱したスローガン「Doing with Images makes Symbols(イメージを操作してシンボルをつくる)」は、現在のGUIにつながるアイデアを簡潔に表現し、GUIの開発に大きな影響を及ぼした。教育心理学者のジョン・ブルーナーによる三つのメンタリティのモデルに基づいてケイが示した以下の表にもあるように、ケイらのグループはマウスをポインティングデバイスとして採用した。
| 操作 Doing |
マウス | 行為的 enactive |
自分がどこにいるかを知って処理する |
|---|---|---|---|
| イメージ with Images |
アイコン、ウィンドウ | 図像的 iconic |
認識し、比較し、設定し、具現化する |
| シンボル makes Symbols |
Smalltalk言語 | 記号的 symbolic |
推論を連鎖させて、抽象化する |
マウスによってディスプレイ上のイメージを動かしながら操作を行い、そこから得られる知見でプログラミングを行う。この連鎖によって、ヒトがコンピュータとともにあらたな思考法を身につけることを、ケイのスローガンは目指していた。
ジョン・ブルーナーがいっているように、じつは前述の三段階は同時に発生するもので、ピアジェが考えたような、ある段階からつぎの段階へと、順次進んでいくようなものではありません。これは支配的なものの移行なのです。幼児期には、肉体的なものが支配します。穴は「掘る」ものなわけです。やがて七歳から九歳あたりになると、こんどは視覚的な関係が支配的になります。そして最後に、現在の常識的な現実から自分を引き離す方法が支配的になるのです。これは、多くの事実を学び、それをシンボルによって操作することを意味します。アラン・ケイ「教育技術における学習と教育の対立」
「行為的/図像的/記号的」の三つの段階が同時に発生するというブルーナーの考えのもと、ケイは「Doing with Images makes Symbols」というスローガンを掲げた。しかし、GUIではその「シンボルの生成(makes Symbols)」の部分、つまり誰もがプログラミングができる状態は未だ実現されていない。GUIでは三つの段階が同時に発生しているのかもしれないが、現在のGUIにつながるアイデアをケイのチームが実装してから40年近くたった今も、GUIで支配的なのは「イメージの操作(Doing with Images)」であって「シンボルの生成」ではない。それはなぜだろうか。その答えは、ケイが「イメージの操作」をGUIで最も具現化し、マウスとともに現在のGUIに欠かせないシステムとなっている「重なるウィンドウ」にある。
しかし、「重なるウィンドウ」は、ディスプレイが「Doing with Images makes Symbols」の達成を妨げる理論に基づいて機能することを決定的にしたシステムでもある。ケイはこのシステムについて、こう書いている。
おそらく最も直感的だったのは、重複するウィンドウというアイデアだ……私が小さすぎると思っていたビットマップ・ディスプレイは個別のピクセルでできており、そこから画面を重ねて見せるというアイデアへ直ちにつながった。これに対してブルーナーのアイデアは、常に比較する方法がなければならないことを示唆していた。あちこち飛び回るという、図像的メンタリティの特徴から考えれば、できる限り多くのリソースをディスプレイ上に表示することは、障害物を取り除き、想像力と問題解決力を高めるために良い方法だった。マルチウィンドウを使う直感的な方法とは、マウスが指しているウィンドウを一番上に持ってくる、というやり方だった。アラン・ケイ「ユーザインターフェイスに関する個人的考察」
ここでまず注目したいのは、ディスプレイには「重なるウィンドウ」以前に、「重ならないウィンドウ」システムがあったということである。コンピュータのディスプレイ以前の映画やテレビでは、一つの画面に単一のイメージを表示していた。マノヴィッチは、映画やテレビの画面が「何であれそのフレームの外部にあるものをフィルターにかけ、遮蔽し(スクリーン・アウト)、接収し、存在しないもの」としてきたと指摘している。しかし、映画やテレビにおける鑑賞の体制が、コンピュータによって崩れてきたと、マノヴィッチは続ける。
この安定性は、コンピュータ画面の到来によって挑戦を受けてきた。まず一方では、コンピュータ画面は概して、単一の画像を見せるのではなく、いくつかの共存するウィンドウを表示する。実際、いくつかの重なり合うウィンドウの共存は、現代のGUIの根本的な原則だ。どの単一のウィンドウも、見る者の注意を完全に支配することはない。その意味で、一つの画面の中に共存するいくつかの画像を同時に観察できるということを、ザッピングという現象 —— 見る者が二つ以上の番組をたどることができるように、テレビのチャンネルをすばやく切り替えること —— と比べることもできるだろう。どちらの場合でも、見る者はもはや単一の画像に集中することがない。レフ・マノヴィッチ『ニューメディアの言語』
マノヴィッチが指摘するように、マルチウィンドウシステムは映画に代表される一つのスクリーンに単一の画像を表示するというルールを根本的に覆した。複数のウィンドウを同時に示すコンピュータのディスプレイによって生じた、画面と見る者とのあいだのルール変更は、「観客が画面に示される映像と同一化する」という前提を覆すことになった。この前提は、見る者の身体を不動な状態に置いてもいた。
身体の監禁は、概念的な水準でも、文字通りの水準でも生じる。その両方の種類の監禁が、すでに最初の画面装置、すなわちアルベルティの遠近法的な窓とともに登場する。線遠近法の多くの解釈者たちによれば、その窓は世界を単眼によって —— 静止し、まばたきもせず、固定させられた単眼によって —— 見られたものとして提示する。レフ・マノヴィッチ『ニューメディアの言語』
複数のウィンドウを示すディスプレイは、もともと「見る者」の身体を監禁することを前提としていない。ディスプレイもコンピュータのn次元と重ねられ、線遠近法を絶対的に扱うのではなく、複数のビューの一つとして扱うようになり、ヒトもマウスとカーソルを用いてその画面を動き続ける。コンピュータのディスプレイでは、ヒトとコンピュータによる合生的な「イメージの操作」が前提となっている。だからこそ、常に変化していくディスプレイにおいて、マウスとカーソルとがアンカーとなって、ヒトとコンピュータをつなぎ止めなければならないのである。GUIにおいては、ディスプレイを「見る」だけの者はいない。GUIとともにヒトは画面の監禁から解放され、イメージを用いてつねにコンピュータと合生的行為をする存在になっているのである。
モードレス化したインタラクション
さらに注目したいのは、ケイが身体を解放しただけでなく、複数のウィンドウに「重なり」を導入し、インタラクションをモードレスにしたことである。NLSでも、マウスとカーソルによって物理平面と情報平面とが重なり合っていたが、ケイはそれらの平面の重なりにウィンドウの重なりを導入した。重なり合うウィンドウはビューコントロールの一種だが、見える部分と見えない部分をつくり、見えている部分があれば、クリック一つで最前面に持ってくることができた。
このインタラクションは、いわゆる「モードレス」だった。アクティブなウィンドウは一つのモードを構成している —— あるウィンドウはペインティングキットを、別のウィンドウはテキストを担当する、という具合に。しかし、特に一つの機能を終了させなくても、次のウィンドウに移ることができる。これこそ、私にとってのモードレスの意義だ。モードレスの優れたインタラクションと、従来のシステムの煩わしいコマンドシンタックスを比較すれば、違いはすぐにわかる —— すべてはモードレスにしなければならないのだ。こうして、「モードを取り除こう」という運動が始まった。アラン・ケイ「ユーザインターフェイスに関する個人的考察」
重なり合ったウィンドウは最前面だけがアクティブになり特権的な平面となっているが、その他のウィンドウは少しでも見えていれば、クリック一つで重なり順を飛び越えるため、ディスプレイ上の階層はフラットに近い状態になっているといえる。コンピュータ内部のn次元がウィンドウの重なりにかたちを変えて、ディスプレイのXYグリッドという二次元で表示されているのである。ヒトは物理平面に置かれたマウスでウィンドウの重なり順を変えて、コンピュータのn次元を操作しつづけるのである。しかも、ウィンドウの重なりの切り替えはモードレスであり、特別なコマンドは必要としない。
重なるウィンドウは「シンボルの生成」の状態になることなく、XYグリッドのディスプレイにおいて、マウスとカーソルを使って「イメージの操作」という合生的行為を行いつづける。そこには一つの視点を持つのではなく、複数のウィンドウの重なりをクリックという行為で入れ替えつつ、コンピュータのn次元とともに思考するという、あらたなルールが設定されているのである。
ケイが導入した「重なるウィンドウ」は、マウスとカーソルとディスプレイとのあいだにあらたなルールを導入した。それは線遠近法の単眼がもつような一つの視点に縛られるのではなく、ウィンドウの重なりを入れ替えながら思考する「イメージの操作」の状態が前面に出たものであった。ディスプレイを見る状態のこのような変化によって、ヒトの思考のルールが変更されたのではないかということを、引き続き考えてみたい。
透視仮説が覆すヒトの認識のルール
思想家の東浩紀は、ポストモダンの主体は映画を見る単眼的な主体ではなく、GUIを見る主体として捉えるべきだとしている。マノヴィッチも指摘していたように、コンピュータのディスプレイが映画のルールを覆す存在だとすれば、GUIを見るヒトの認識や思考方法にも変化があるだろう。映画を見る近代の主体は、一つのスクリーンに映る単一の画像に同一化し、さらにはそこに見えていないカメラや監督の視線とも同一化していく。そして、スクリーンに見えているイメージよりも、見えていないシンボルを優位なものとみなしている。しかし、GUIの背後にはカメラがなく、しかもディスプレイには複数のウィンドウが表示された状態になっている。
映画のスクリーンとコンピュータのインターフェイスは、同じく映像を表示する平面でありながら、そのメディア的な性格がまったく異なっている。前者には映像を投影する映写機があり、またその映像を撮影したカメラもあるが、後者にはそれに相当するものは存在しない。そもそもコンピュータのインターフェイスは映像だけの平面ではない。スクリーンにはイメージしか投影されないが、インターフェイスには、イメージもシンボル(文字)も、あるいはさらにイメージや文字のさらに深層にあるコードさえ、すべて等価に表示することができる。あまりにあたりまえの話なのでピンとこないかもしれないが、Wordを立ち上げYouTubeを再生し、同時にターミナルで簡単なコマンドを打っているとき、ひとは三種類の記号を同時に表示している。東浩紀『ゲンロン0 観光客の哲学』
ウィンドウにはイメージも表示されていれば、テキストというかたちでシンボルも表示されている。ヒトはイメージとシンボルを同時に見て、モードレスにウィンドウの重なり順を入れ替える行為をしながら、コンピュータとともに思考していく。このとき、映画が前提としてきた遠近法的、立体視的なルールは崩れている。
理論神経生物学者のマーク・チャンギージーは『ひとの目、驚異の進化』において、ヒトの目が前向きについているのは立体視のためではなく、障害物を透視してより多くの情報を得るためという透視仮説を提示した。東はこの仮説が、GUIとともに行為や思考を行うヒトの認識を説明する理論となると考えている。まずは、チャンギージーが前向きの目を持つ動物の両眼視野の特徴を述べている箇所を引用したい。
横向きの目を持つ動物たちとは違って、私たちは両眼視野のおかげで、どちらを向いても不透明なものを二つまで見られる! 前向きの目を持つ動物は、何かが見えなくなることはない。それどころか、見通しの悪い視野の中で、二つの層を見ることができる。まるで、横向きの目を持つ動物のパノラマ視覚が前へ引っ張り出されて重なり、層状の知覚、つまり、統合された知覚が可能になったかのようだ。この場合、視空間の前側の半球しかカバーできないかもしれないが、二つの層を見る能力があるので、実際にはその範囲の二倍が「見える」。障害物を透かして見るときに、両目が同じ方法を向いている強みは、まさにこの能力にある。マーク・チャンギージー『ひとの目、驚異の進化』
チャンギージーの透視仮説を受けて、東は次のように述べる。
もしチャンギージーの発見が、ぼくたちの社会が視覚について長いあいだ抱いてきた誤謬(立体視仮説)を取り除くものであり、そしてその誤謬こそが人文学において伝統的な主体理論の中核を占めていたのだとすれば、その中核は新しい発見(透視仮説)に置き換えられるべきだとは言えるだろう。そしてそうすればそこには必然的に、新しい主体理論が生まれることになる。東浩紀「観光客の哲学の余白に 第2回」
東の大胆な提案は、インターフェイスを考える上で非常にクリティカルなものだといえる。マノヴィッチが指摘したように、ディスプレイのルールはマルチウィンドウシステムで変更されている。ならば、コンピュータのディスプレイを見続けるヒトについて語る前提となる、生物学的特性も変更しなければならない。そうしなければ、映画やテレビといった、コンピュータ以前のヒトが「見る」ためのスクリーンとは異なり、ヒトが行為することを組み込んだインターフェイスのなかで、ディスプレイという平面がマウスを起点としてつくりだすヒトとコンピュータとの合生的認識を捉えることはできないだろう。
ケイの「Doing with Images makes Symbols」は、インターフェイスのためのスローガンでありながら、一つのテキストとして線形的に示されているという点で、線遠近法や立体視仮説に基づく「シンボルの生成(makes Symbols)」を重視しているように読める。実際にケイのゴールは、すべてのヒトがプログラミングできることであった。しかし、重なるウィンドウは単眼の線遠近法のルールを覆すものである。両眼でディスプレイを見る透視仮説に基づき、重なるウィンドウを改めて考えてみると、ケイのスローガンで重視されるのは「イメージの操作(Doing with Images)」の部分となるはずである。チャンギージーの透視仮説に従えば、ヒトの前向きの目は生い茂る葉や柵のような障害物と、その向こうの対象という二つの層を見ることができる。さらに「二層を見る」ということと、ケイのグループが実装した重なるウィンドウとを、合わせて考えてみたい。
イメージとシンボルが折り重なるGUI
ケイらはコンピュータというメタメディアをつかって、従来のメディアにあらたなプロパティを付加した。そのとき想定されるヒトのモデルも、ディスプレイを見るだけではなくディスプレイ内のイメージを操作するものに変化した。マウスやキーボードによる物理的な操作は、イメージの操作につながっている。
エンゲルバートのNLSではウィンドウが重なることはなかったが、マウスと連動するカーソルが、コンピュータの情報空間のなかでヒトとのつながりを示すように自在に動き回っていた。ケイは物理平面とディスプレイのXYグリッドとの重なりに、もう一つウィンドウの重なりを追加した。それはより多くの情報を提示するためであったが、ヒトの透視能力、二層を見る能力に基づいた視覚操作でもあったといえる。
チャンギージーは「コンピュータ画面のような平面ディスプレイには、向こう側が見えるような隙間はないので、どのみち向こう側を見ることはできない」と考えているため、ディスプレイに重なりを取り入れるというのは無理な話ともいえる。しかし、それはモノとしてのディスプレイの話である。ディスプレイはモノとしては平面ではあるが、ディスプレイが示す画像はコンピュータのn次元の部分像なのである。コンピュータのn次元を経由することで、重なるウィンドウという概念をディスプレイに導入することも可能になってくる。複数のウィンドウの重なりとして、コンピュータのn次元が示されるのである。
実際に世界がもっとよく見えるように、つまり今以上に多くものがみられるように、現代世界に障害物を加える方法はあるだろうか? どちらの方向を向いても、二つの層を見る能力を十分に活用できるように世界を変える方法を見つけられるだろうか? それには有益な障害物を加える方法を見つければいい。マーク・チャンギージー『ひとの目、驚異の進化』
ケイらはウィンドウを重ねて、ディスプレイに「有益な障害物」を加える方法をみつけた。重なり合うウィンドウは、かつてヒトの視界を覆った折り重なる木の葉なのである。ヒトはそれぞれのウィンドウに書かれたものを見透して全体を把握しながら、どれか一つのウィンドウに注意を集中させることができる。マウスとカーソルによる物理世界とディスプレイ平面との重ね合わせに、さらにウィンドウの重なりが導入されて、ディスプレイの見透しは悪くなるが、より多くの情報が提示される平面となった。
ヒトはそこで、かつて森のなかで手前と奥とを切り替えて世界を見ていたように、ウィンドウの重なりを見る。しかし、コンピュータのn次元は物理空間とは異なるので、そこでは奥を見透すのではなく、ウィンドウを次々に手前にもってきて、見る対象を入れ替えていくことになる。すべてを見透す必要はなく、一部だけでも見えれば、その平面を手前に持ってきて、よりよく情報を見ることができるのである。ディスプレイが情報をより多く提示するためには、ヒトの目の立体視能力に合わせて三次元化する必要はなく、透視能力に合わせて重なりをつくればよかったのである。
ここでは、ヒトの認識に重大な変化がおきている。ある固定の視点から見続けるのではなく、イメージを操作しながら見ることが前提となっているからである。ウィンドウの内容が重なりのなかでよく見えないのであれば、ウィンドウを最前面にもってきたり、ウィンドウの大きさを変更したりといった「イメージの操作」をする必要がある。そこでは、立体視仮説に基づいた遠近法などが持っていた、単眼で一つの点に収斂する世界の見方は破棄される。しかし、その行為がヒトの透視仮説に基づいているとすれば、重なりのなかにより多くの情報を見て、行為をしながら空間内の情報に対応していくことは、ごく自然な出来事だといえる。GUIを操作するヒトは、両眼でウィンドウの重なりを見ながら、「イメージの操作」を続けることを求められるのである。
ケイのスローガンには、透視仮説に基づく「イメージの操作」と、立体視仮説に基づく「シンボルの生成」という二つの要素が混ざっていた。ケイが最も願ったのは「シンボルの生成」の部分であったが、それは重なるウィンドウを中心としたデスクトップメタファーとともに発展していったGUIでは成功しなかった。なぜなら、そのGUIはシンボルの操作を特別視しない、透視仮説に基づくシステムだからである。GUIでは「シンボルの生成」は抜け落ちてしまった。
しかし、シンボルがGUIから消えたわけではない。東が指摘するように、GUIでは見ようと思えばいつでもシンボルをウィンドウに表示できるし、GUIのイメージと操作をかたちづくっているのは、まぎれもなく「シンボルの生成」によってつくられたプログラムである。だから、GUIではイメージとシンボルを同時に見ることができる。ケイのスローガンは、「Doing with Images / makes Symbols(イメージの操作/シンボルの生成)」というように真ん中で折り曲げられ、「Doing with Images(イメージの操作)」を前面として、その背面に「makes Symbols(シンボルの生成)」が重ね合わされているのである。だからこそ、GUIでは見ようと思えば、いつでも「イメージの操作」の隙間から「シンボルの生成」が見えるのである。
マウスは物理平面をXYグリッドに区切り、行為をディスプレイのXYのピクセルに重ね合わせた。行為がイメージとシンボルを折り重ねる。ウィンドウがモードレスに切り替わるのは、マウスの行為がイメージとシンボルをモードレスに切り替えるからである。物理世界をXYのグリッドに区切るマウスとともに起こる合生的行為から、ディスプレイ上でのイメージとシンボルの切り替えが生じて、同時にそれらを見る。より多く情報を見るために、重ねられたウィンドウはその重なり順を入れ替えられることで行為と同一化して、さらに多くの情報がディスプレイの平面に見えることになる。
ヒトとコンピュータは前面に「イメージの操作」、背面に「シンボルの生成」という二つの層からなる一つのGUI平面をディスプレイにつくり、そこでマウスを起点として合生的行為をしつづける。あらかじめヒトとコンピュータとの合生的行為が組み込まれているからこそ、ウィンドウは重なり合い、より多くの情報を示せるようになっている。GUIはイメージだけの場でもなく、シンボルだけの場でもなく、それらが重ね合わされるようにヒトとコンピュータとが合生的行為をする場であり、そのあらたな行為とともに、認識の根本的なルールも立体視仮説から透視仮説へと変化しているのである。
GUIの基本的なルールを形成するマウスとカーソルと「重なるウィンドウ」は、ともにコンピュータと向き合うヒトが行為し続けることを前提としている。ヒトはマウスとカーソルという「鼻」とともに、物理空間と情報空間という二つの空間を行き来できるようになり、さらに情報空間に「重なるウィンドウ」が導入されて、二つの目でウィンドウの隙間を透視しながら、より多くの情報を認識するようになった。ディスプレイのXYグリッドを多動的に動き続けるなかで、ヒトの身体はイメージに引き寄せられている。そして、GUIでイメージに対して行為することで、ヒトは身体のなかに未知のものがあることに気づき始めている。
GUIという合生的行為の場において、ヒトは「イメージを見る」という牢獄から解放され、イメージを操作することで、もう一つの身体を生成しつつある。だから、ケイの「Doing with Images makes Symbols」は、「Doing with Images makes Other Bodies(イメージを操作して別の身体をつくる)」とも言い換えることができるのである。
$tay Tune in 東京2017年夏のウルトラライトビーム💅
おはよう。夏よりも先に狂ってくMy Love。この夏にできないなら、死ぬまで何もできない。だって夏のためにすることすべてが楽しいから。わたしの夏への信仰告白は止まらない。ほかに季節はないんじゃないかと思えるぐらい、夏に帰依している。わたしの脳を最新のサマーチューンが溶かす。ラジオは無責任に「解像度の低い恋をしよう」って言ってる。「もっとタイトにしてたいの」って皮膚の下にいる生きものが騒ぎ出す。誰かがわたしに狂えばいいと思いながら、わたしだけ狂っていく。楽しいことしかないな。
それは「電話切るタイミングわからないから朝まで切らないよ」って最初に言ってくれたら楽になってそのまま眠れると思う、というような気候。ちょっとでも重いと思われたら嫌だし、重いと思われたら嫌だってずっと思いながらメッセ書くの苦しいし、というか重かったのは結局わたしだったし、というような気候。昔好きだった人としばらく文通してたけど、往復数が増えてなんか怖くなってやめちゃったのを思い出しちゃった、というような最高の気候。You Smell Like The Summatime.
この季節にはポエジーを前に進める必要があって、ほとんどの場合それは生理的なものにドライヴされる。ポエジーがラディカルなのは、エモーショナルなものと身体の結びつきを、生々しくトレースするから。しかもそれは器官ではなく肌表での結びつき。皮膚のテクスチャの相性。チープだけどディープ、というよりディープだからこそチープ。身体の表面を境目にして、間接と直接がすり替わる。
たぶんわたしは老婆が最期の夏に見ている夢。日が暮れた夏に、暗い糸杉の木立で置き去りにされた嬰児の網膜に映るすべて。わたしはあなたの分身で、あなたがこれからつくはずの嘘を代弁してる。ちょうどいい感じに狂ってる正常な人間のあなたを想って、こうしてテキストを書いてる。あなたが狂ってるのは部分的なもの?それとも、身体を包むヴェールのようなもの?わたしは狂っても狂ってもちゃんとやれるから、好きなだけ狂いながらちゃんとしてたい。
あなたはハードドラッグをキメて、聖橋の欄干の上でヴォーギングまでしているのに、生きることの虚無を拭い去れない。これまでも、もう終わりだって思っても何も終わらなかったし、何かが始まりそうだって思っても何も始まらなかった。世界の終わりが始まりそうで始まらない、終わりなき日常ということばが禁じられた世界で、ウルトラライトビームに照らされながら、オランジュのペディキュアをして、パブロのような気分でオートマティックにオートマティスムを続けてる。
サイボーグとしてジェンダーをプロトタイピングする🍯
あなたはJR御茶ノ水駅から電車に乗り込む。すこしして景色が流れはじめる。あなたは立ったままで、電車が走ってるのか、窓の外が動いてるのかわからなくなる。それに電車の外にいるのがゾンビじゃないとは誰にも言えない。次の瞬間、あなたの存在は宙吊りになる。わたしのいる恵比寿に着くまでの間に、あなたは何度かジェンダーをピボットする。そして突然存在がほどけて、あなたはボロボロに泣き崩れる。それからフォトショップとプラスティックサージャリーの間の深い森に迷いこみ、スミレのにおいのする松浦理英子の『ナチュラル・ウーマン』で顔を覆いながら、恵比寿駅で急いでトイレに駆け込み美人OLになる。それなのに腹ペコのガキみたいにイラついてる。
接続され理解されることがワックになった世界で、加速するしかない生活。わたしは今でもあなたとテルマ&ルイーズのように手を取り合って、ポストサイボーグフェミニズムなニューノーマルになりたいと願ってる。それから同じドラッグを摂って、キメセクがしたい。鼻腔を通るスニフィアンとスニフィエ。セックスのあとのSNSはハチミツのにおいがした。また明日から毎日をやり過ごすため、最後にヴァイブスを殺してクールダウンする。
わたしにはスペキュレーションしかできない。スペキュラティブデザインってのは、デザイン思考という業務上の乱行パーリーで不感症になったデザインが、さらなるタブーを求め、現実を断ち切って、遠くからやってくる声を聞く試みだと思ってる。その声にはオートチューンが使われていて、ピッチもいい感じで補正されてるはず。サイボーグとして身体をプロトタイピングしながら、自分の美意識と欲望の眼差しの間で引き裂かれることが、わたしの生きてる証し。もしマリノフスキーが生きてたら、なんて言うのかしら。
これはファンタジーではない。プリセットのままでいい。トゥルーでリアルな感覚をディグしてたい。快楽の問題を社会の問題にしてしまう大人たちのように、意味を固定化しないでほしい。参照先はWikipediaではなくUrban Dictionaryにしてほしい。Amazonのオススメには吹けば飛ぶよなクールネスしかない。これはアンチではなく、デタッチメントでもない。ヘーゲルの弁証法でもなければ、脱構築でもない。これはプロトタイピング。新しいやり方で宙吊りにならなきゃ意味がないだけ。So Fresh, So Clean.
これを価値相対主義だと考えちゃうのは、相関主義な人たちに違いない。たとえば、あなたの身体イメージを訊いたら、わたしの身体イメージはアップデートされる。たとえば、電車で目の前に立った人の身体感覚に同調して、身体の線と衣服の皺から布地と表皮の接触を読み取り、その身体感覚を保持したまま、その人の視点からわたしを見返すことができる。たとえば、あなたとわたしがメッセをするとき、あなたやわたしは絶えず入れ替わる。テキストを書くのがわたしで受け取るのがあなたということだけが決められてる。つまり、事実の反転、役割の入れ替え、文法の撹乱、時系列の操作、言い間違い、忘却などしてからシェアさせていただきます、ということ。
フェイクをシェイクしてリアルをチョップしてスクリューする🍹
たくさんの人が気づきはじめてる。まだヴァーチャルの反対がリアルだと思われてる場所で、本当のヴァーチャルの反対であるアクチュアルの暗証番号を入力しながら、ポテンシャルの残高からリアルを現金にして引き出してる。フェイクがリアルの一部だと気づいていない人たちを尻目に、ポストフェイクなリアルを盗んで、オルタナティブフェイクな世界で換金してる。バイツしたアイドルより稼ぐドル、フラン、円、マルク。あなたはまだ貨幣のフェティッシュを信じてる?
ことばを尽くせば尽くすほど、わたしはフェイクになっていく。今やわたしのフェイクが、わたしのリアルを追い抜きつつある。リアルよりもリアルな感覚にすべて捧げてることが、わたしがフェイクであることを証明する。フェイクをシェイクした紫色のシロップを、リアルなスプライトに入れてチョップしてスクリューする。フェイクな世界で花占いにリアルを賭ける。リアル/フェイク/リアル/フェイク/リアル/フェイク/リアル/フェイク/リアル/トゥルーリアル/トリル…
もうファッションとショッピングとトラップミュージックぐらいしか信じられない。フードを被れば、仲間たちとシェルターにいる気分になれること。常軌を逸したショッピングでしか、性的興奮はもたらされないこと。トラップは倍ではなく、裏でリズムを取るのが気持ちいいこと。こういうのは、わたしたちのフッドでの公然の秘密の本当の事実。フッドとは他者のフッドのことで、わたしは他者がフッドを語るときの語りかたを遡行して、初めてわたしのフッドに到達する。そのような場所としてフッドを措定すること。そこがポスト・ポストトゥルース。リアルの裏のリアル。ザ・トゥルーリアル・ミリ・ヴァニリ。Girl You Know It’s True.
こうしながら、コルタサルの「グラフィティ」みたいに、あなたがこれを読むのをずっと待ってる。嘘つきで何もないわたしを信じてくれないと、何もはじまらない。嘘も真実も傷口を閉じれば同じはずだし、相互行為の痕跡がなければ、わたしもあなたもいないのと同じ。もう生きてくなかで少しも傷つきたくないし、傷つけられたらちゃんと傷つけて帳尻あわせるのを忘れないようにしたい。仮病によって存在をリアルに変え、イマジナリーな自己にリアルを食わせる。どうせ消えてしまう場所で、どうせいなくなってしまう、あなたとわたし。だからぎゅっとしててね、BAE.
ベラ・ハディッドのフィードしか流れないフィルターバブルの享楽💄
わたしはゴシップを見て、人に言えないほど残酷なことを考えるのが好き。純粋なままでいられる気がするから。こないだルイ・ヴィトンの2018SSのコレクションで、ドレイクの新曲が発表されたみたいだけど、”Signs”という曲名のとおり、時代の予兆だってわかった。ドレイクとベラ・ハディッドのデートを真っ先に報じたのも『XXL』だった。
ベラ・ハディッドは10年代のヘロインシック。90年代にケイト・モスがそうだったように。ベラ・ハディッドの魅力は、ムスリムであることを誇りに思ってカミングアウトしたところ。ダイエットという復讐のために、毎日2時間のワークアウトをこなすところ。それから、元カレに向かって「セレーナ・ゴメスには気をつけて」と言えちゃうところも。いつもわたしはベラ・ハディッドになりたいと願ってる。ベラ・ハディッドになりたい。ベラ・ハディッドになりたい。なれないなら死にたい。
わたしはベラ・ハディッドみたいになりたいし、あなたとたくさんベラ・ハディッドについて話したい。彼女のワードローブ、彼女のインスタグラム、彼女の過去の恋人、彼女の冷たい瞳について。会話、会話、会話。退屈な会話がないと死ぬ。退屈を逃れようとする試みのすべてが、退屈と見分けがつかなくなってしまった夜、わたしたちは何がクールで何がクールでないかについて、朝まで語り合う。あなたはイルぶってるから大好きな友達。実生活にファックされても、このまま狂ったふりしてリッチフォーエヴァーしよう。
だから、今見えるものすべてをテキストしてよ。何を食べたとか、街の匂いがどうだったとか、ちょっとした嫌なことも、全部教えてくれないと不安。きっとこれはテキストだけの関係。本当はもっとぐちゃぐちゃになって傷つけ合いたい。脳をストローで吸って考えてることを全部知りたい。あなたの抱える問題がわたしと無関係であることが憎い。ユニコーンのタトゥーをお揃いで入れて、いつまでもマグネティックな関係でいたい。わたし以外の何かに救われないで。そんなことを思いながら、スマートフォンの照明で一晩を過ごす。ねえ、今何してるの?誰かが誰かにキスしているの?
シティボーイとシティガールのための都市恋愛学💋
ちょっとでも楽しかったり気持ちが軽くなったりした次の朝は、悲しくて切なくて仕方なくなる。もし「物質になろうよ」って声掛けられたらついてっちゃうな。だってなりたいもの、物質に。そんなときは、うんざりするような友達と、超退屈なパーリーに繰り出す。夜をタフにやり過ごすための音楽だけが癒し。これはわたしが生存するためのテクノロジー。
休日昼すぎに目が覚めたら、真夜中までずっと雑誌をぱらぱらめくって過ごすだけ。夜は鳥たちのブラックネスとともにやってくる。何より真夜中のポエジーだけがリアルだし、そうでなきゃ生きてるとさえ思えない。真夜中に考えたことは朝起きても最高だし、朝起きてそれが取るに足らないと思えても、また夜が来れば何度でも最高になる。判断を朝に委ねてはダメ。夜に生まれたものは夜に問わねばならない。夜だけがわたしたちの脚本。夜は街が光り輝いて、キラキラしたオブジェクトがつながったりちぎれたりして見える。夜は肌を狂わせる。
だけど、恋愛ほどは狂ってない。恋愛は本当の危険ドラッグで、法の目をかいくぐり、わたしたちを狂気へ向かわせる。最高にスキャンダラスだけど、摂取しすぎると耐性ができて依存症になる。こんな時代でも、まだデートは唯一の有効な祈りのまま。わたしは敬虔なマインドで都市に点在するパワースポットの祭壇の前に跪き、ロマンスの神様にフレッシュな血液パックである生き身を捧げる。
なのに、カフェで隣に座ってる女の子たちは、マウンティングを指摘することでマウンティングし合ってる。わたしはいつもヘイターのヘイトを踏み台にする。サグ化する社会では、サグかわいく生きればいいんだけど、どうしてもイルかわいく生きてたい。サグりあうのはやめて、そばにイルだけでいい。たぶんそういうこと。Bitch, Don’t Kill My Vibe.
今日もシティガールとシティボーイは殺気立ってる。シティにはムードがない。コンビニしか行くところがない。あるシティガールはケヴィン・リンチのシティのように、あるシティボーイはジェイン・ジェイコブズのシティのように、自己像を形成する。装飾されたシティガールは犯罪である。シティボーイはツリーではない。ボーイなきシティとシティなきボーイ。シティとボーイとで引き裂かれるシティボーイ。戦場のシティボーイズライフ。イミテーションボーイは都市のなかでプロトタイピングされてアーバンを手に入れる。
だから、今日は天使みたいにきれいな男の子になりたい。セックスのあとギターを弾き始めるような男の子。自己肯定感にガソリン注いで火を点けるクレバーでクレイジーなボーイフレンド。ヤングでリッチなウルフギャングというかゴルフワング。カウボーイみたいに真剣な顔でブラントを巻く超Wavyなギャングスター。片手でスマートフォンを握りしめ、生存をスワイプして死を覗く。もうなんなの?とか思いながら、もっと誰にも言えないことがしたい。
メンヘラビッチ・ステイト・オブ・マインド🍭
はじめまして、本日から死にジョインしました死 a.k.a. 死です。今月は死に100%コミットしますが、今日は死を定時退社させていただきます。ヒップホップはMC死とDJ死の登場によって、生前のヒップホップと死後のヒップホップに分断された。カルバンクラインのモデルのような完璧な死体になるためのワークアウト。それで生も死もクールになるはず。だけど、いつも死に間に合わない。
生身のあなたの生存でさえ、あなたとは何の関係もないのだと感じる。生存は生存から逃れる死にもの狂いの運動で、生存を先送りにする。生存というゲームにおける死はジューシー。生存はいつもロスト・イン・トランスレーションしてる。生存はビッチ。襲ってくる屍のバッドガール。そこで死をローンチする。死をレペゼンする。死のフレンチフライで生存のシェイクをディップする。今夜の生存のドレスコードは何?死んでいるのに動いてるのと、動いているのに死んでるの、どっちがセクシー?
あなたのいない1マイル先の天国と秤にかけられるのは、あなたといる地獄。天国は他者の決定的な不在をめぐって記述されるみたい。あなたはどんなディストピアを夢見てる?ひどいテロは起きた?爆弾は落ちた?引き金を引いたのは誰?愛してた人たちは生き延びた?それとも誰ひとり失われていないのにあなたは地獄にいるの?なんでも自由にできるなら何したい?わたしはただドキドキしてたい。油断すると泣いてしまう状態はとてもいいから、みんなにおすすめ。本当にそれだけあればいい。そしてゆっくり神をスワイプする。
それからわたしは「今日のこの感じ、わたし全然悪くないよね?それって誰のせい?ねえ誰のせい?」と静かに問い詰める。そのときのわたしはうつくしい。「何がわたしを救うの?」としつこく訊けば、あなたは「何にも救わない」と言って口づけしてくれる。救われなくてもキスしてくれるなら、この空から墜ちてもOK。救われたいけど本当に救われたら困るのかな。もしわたしをメンヘラのクソビッチだと思ってるなら、コーラで割ってYOLOしく飲みほしてほしい。
ベイビー、また日付が変わる。真夜中に死がエモーショナルに降臨する。何度でも言いたい。真夜中のポエジーだけがリアル。真夜中のすべてをほとんど叫びながら過ごすわたしは、睡眠導入剤として『アナイス・ニンの日記』をすこしだけ読んでから寝る。それでも寝れないときは、あなたがくれた『ハリウッド・バビロン』を精神安定剤にするね。無対象のエモーションを、無対象の対象へと折り返すとき、俗性から剥き出しになる聖性。向こうが透けて見えるね。夏の夜は最高。もうチルしていいよ。おやすみなさい。
インターフェイスデザインをめぐる思考実験
2015年の11月に日本語版が出版された『スペキュラティヴ・デザイン』の冒頭には、著者のアンソニー・ダンとフィオナ・レイビーのデザイン宣言ともいえる「A/B」の表が掲げられている。ここで「A」というのは、ふつう理解されている肯定的なデザイン。「B」というのは、彼らが実践しているところのデザインである。
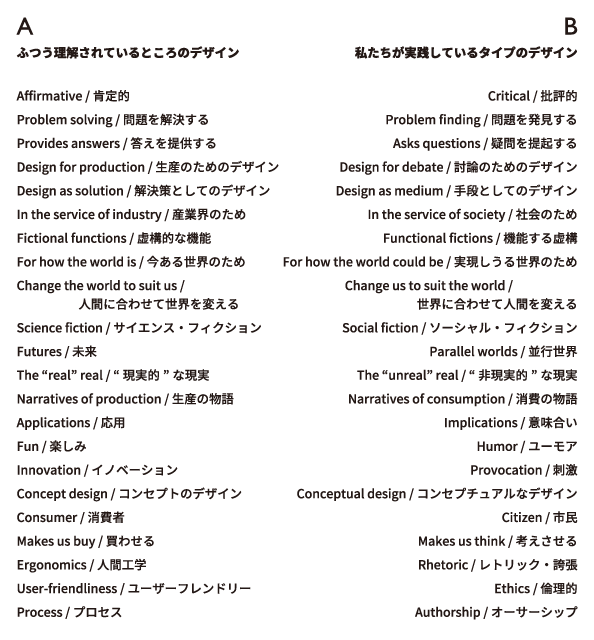
「A」のふつう理解されている肯定的なデザインというのは、例えばApple社のデザインだったり、ドン・ノーマンがいう「使いやすい」デザインだったり、もはやイノベイティブではなくなってしまった、マジョリティのためのデザインのことである。こうした伝統的な人間中心主義的デザインに対する信仰、その裏返しでありパラフレーズの技術による人間拡張主義、あるいは人間とコンピュータがシームレスに融合する、といった類のテクノロジー中心主義に対する無批判な肯定は、そのこと自体がデザイナーの楽天主義や技術者の思考停止を反映しているかのように、今なお根強いものがある。そういう論者とその取り巻きは、いつの時代にも次々とレミングスのように現れては消えていく。
ここで思い起こされるのが、ダン・ゲントナーとヤコブ・ニールセンが1996年に発表した「アンチ—マック・インターフェイス」という論文である。1984年に発売が開始されて以来、多くの人にGUIデザインの基本原則とみなされていた「マッキントッシュ・ヒューマン・インターフェイス・ガイドライン」を参照しながら、あえてその反対の原則を掲げることで、多くの人が気づいていないインターフェイスデザインの潜在的な可能性を発掘しようとした。
それから約20年を経て、アダム・ベイカーというデザイナーが、「ポスト—マック・インターフェイス」と題した論考を発表した。2007年に発表されたiPhoneやAndroidなどのスマートフォンのインターフェイスの爆発的な普及を経て、もはや「A」デザインになってしまったGUIを、なぜ今更考えなければならないのか、そう思う人も多いだろう。しかし、この論考をじっくりと読んでみれば、1996年に発表された「アンチ—マック」というある種の思考実験の意味を再読することが可能であるし、暗黙のうちに組み込まれた当時から見た未来を、現在の状況から読み解くことができる。
デザインにおけるシミュラクラ現象
ベイカーが提案する「ポスト—マック」のデザイン原則をここに再掲した。青い背景がオリジナルのマッキントッシュのデザイン原則であり、赤い背景が「アンチ—マック」の原則である。そして「ポスト—マック」の列では、背景の色でそのいずれかが選択されたこと、あるいはそれ以外のもの(緑の背景)であることがわかるようにした。緑の項目は3つあるが、そのうち「両方(直接操作と委譲)」は青と赤を合わせたものであり、「予測可能な変化」は赤のバリエーションである。だから、まず冒頭に挙げられた「シミュラクラ」に注目すべきだろう。
シミュラクラとはもともと、心霊写真や人面魚、月や火星の人面、そしてマッキントッシュの顔アイコンのように、「3つの点が集まった図形を人の顔と見るようにプログラムされている人間の脳の働き」を意味する心理学的用語であった。その後このことばは、フィリップ・K・ディックの小説の中で「本物そっくりのまがいもの」という意味で使われるようになり、さらにそれをボードリヤールらが「オリジナルなきコピー」としてポストモダン社会のひとつの象徴として提示したことで、さまざまな人がシミュラクラを論じてきた。
マッキントッシュのGUIが、コンピュータのアプリケーションの振る舞いやファイルシステムをデスクトップというメタファーで隠蔽したことに対して、「アンチ—マック」はコンピュータの内部挙動や構造に直接根ざしたインターフェイスの必要性を提案した。しかし現実には、コンピュータのインターフェイスはそちらには向かわず、高速の処理とネットワーク、大量のメモリーなどを駆使して、実在なきリアル、すなわち「シミュラクラ」を生み出す方向に向かった。その結果、人間の思考や行動をモデル化したシステムやアプリケーションによって、コンピュータはより私的(パーソナル)なものになった。
今日のシミュラクラ現象とは、人間を見るかのごとく、スマートフォンのホーム画面を見るようにプログラムされている脳の働きである。ソフトウェアでモデル化されて、人間までもが人間のように振る舞うシミュラクラになってしまった。さらに「ポスト—マック」は「ポスト—人間」と読み替えられる。だから、シミュラクラとしてのデザインとは、「ポスト人間中心デザイン」のひとつのありようなのだ。
ポスト人間中心デザインがめざすもの
さて、ここで冒頭の「A/B」デザインに話を戻そう。ベイカーの「ポスト—マック」に倣って、僕も「ポスト—A/B」としての「C」デザインを考えていきたいと思う。ただしそれは、「ポスト—マック」の大半を占める項目のように、「A」でも「B」でもそれらのハイブリッドでもないもの、むしろそれらを止揚する試みとしての「C」デザインというべきものとして考えてみたい。現在の仮設的「C」デザインを以下に示し、その項目をひとつずつ説明していこう。
まず、これからのデザインとは「代替的(オルターナティブ)」なものであるべきだ。肯定的(マジョリティ)であってはいけないのはもちろんだが、批評的(マイノリティ)であったとしても、その視点を変えずに繰り返し主張し続ければ、いつしかそれは肯定的になり、批評的なものではなくなってしまうだろう。大切なことは、肯定するか批評するかではなく、固着してしまうか変化し続けるかなのだ。だからこの項目は、「代替的」ではなく「試験的(テンタティブ)」でもいいだろう。「実験的」「仮説的」ということばもあてはまる。仮説は仮説であり、そうあり続けることが重要で、それを実証することに意味はない。これは、マーシャル・マクルーハンのいう「最近、気づいていないことは何か(What haven’t you noticed lately?)」を問い続けることと同じである。
問題解決と問題発見は連続している。問題を解決することで、はじめて問題を発見できる。だから、この「代替的」思考において重要なことは、問題を解決することでも発見することでもなく、「問題とは何か」を考えることである。僕らが問題だと思っているものは本当に問題なのか、あるいは「問題—解答」という因果的関係そのものが妥当な考え方なのか。問題が、問題のための問題にならず、本当に考えるべき対象であるかどうかを見極めるのは難しい。
問題を明確にするということは、すなわち「前提」と「境界」を明確にするということである。プログラムを書く時に変数の型を定めて、その値の範囲を明確にしなければならないように、問題を明確にした時点で、その問題はやがて解かれる宿命をもつ。その宿命を反転させることが必要だ。宿命を反転させてくれるのは、相手を打ち負かそうとする討論(ディベート)ではなく、深く思考することである。これからのデザインは、直観や感覚に訴えるものではなく思考であり、それも単なる思考ではなく「熟慮(ディープ・シンキング)」するためのものでなければならない。
世界最強棋士との対戦に完勝したアルファ碁同士の対局は、それまでの人間の囲碁に対する常識を超えたものであったという。そこから見えてきた人間の限界は、自分の手に意味やストーリーを持たせてしまうことであった。この大局観と呼ばれるような認知的限界から生まれた直観や意味を、人間は如何にして乗り越えていけばいいのか。その時のガイドとなるのが「アルゴリズム」—— 明確に記述された手順である。アルゴリズムは明確に記述されているからこそ、直観という名のフィルターに隠されていた、潜在的な可能性を浮き彫りにする。
これからのデザインは、アルゴリズムによって生(raw)のレベルから記述され、実行できるものでなければならない。このアルゴリズムにとって重要なのは、それが実行可能かどうか、ということだけであって、それが生み出すものが現実なのか虚構なのかを考える必要はない。シミュラクラの時代における「オリジナルなきコピー」とは、「実行可能なアルゴリズム」という意味である。アルゴリズムとしてのデザインが生成するものこそがシミュラクラであり、それは参照すべきオリジナルが存在しない「検証不可能な機能」という他はない。
ポスト人間と共にある世界
さて、そうした代替的な世界と私たち人間の関係は、どのようにあるべきなのだろうか。心や精神とも言われる人間の内部状態の許容範囲は、それほど大きくはない。だから、アルゴリズムが生成する膨大な出力を、何らかの形で圧縮しなければ、その負荷に耐えきれずに故障したり崩壊してしまう。それを避けるためのひとつの方法は、「選択」することだ。宗教や倫理がそうであったように、「すべきである」「しなければならない」という超論理的な選択は、人間にとってますます必要不可欠なものとなってくるだろう。アルゴリズムの実行によって生まれるオリジナルなきシミュラクラが世界を変え、そこで生きなければならない人間も、また変化していくことが要求されている。
3つの点が集まった図形を人の顔と見てしまうシミュラクラ現象のように、「擬人化」や「キャラクター化」は、先ほどの「意味」や「ストーリー」と並んで、人間の可能性を制約する障害になっている。今日の人工知能が「人に似せた」知能である限り、大きなブレークスルーは生み出さないだろう。「神が自分に似せて人をつくった」のではなく、「人間は自分に似た神しか想像できない」ことが問題なのだ。であれば、その「擬人化」の限界をどのように乗り越えていけばいいのか。そのためのアルゴリズムが、「ユニヴァーサル・フィクション=人間を超えた虚構」である。
量子力学の多宇宙解釈のように、そのフィクションは並列的でそれぞれが「異質(ヘテロジニアス)」であるため、相互に「不可知(unknowable)」ではあるが、自分にとって異質なものや不可知なものを認めていくこと抜きに、これからの未来はあり得ないだろう。主張のパワーゲームからは、もう何も生まれ得ない。「発見—解決」と同様の「生産—消費」という直線的因果関係も、やはり消去していかなければならない。「維持」や「保存」は生産と消費の二元論を解消する、デザインにおける中立一元論のようなものとして、ますます重要になってくるだろうし、アルゴリズムの「増殖」性をアイロニカルに内省することで、「保存」とは「オリジナルを守る」ことではなく「変化できる状態に保つ」こと、という意味に止揚していくことが不可欠となる。
人間が陥りやすい一番の罠は、どうしても人間中心にものごとを考えてしまうことだ。しかもその時の「人間」が指し示しているのは、「自分」あるいは「自分の身近な人間」、せいぜいが「自分が想像できる人間」である。「自分はもっと客観的、普遍的に人間を捉えている」という人でも、その想像の世界に存在しているのは、平均的な人間や多数派の人間であることがほとんどだ。そうでなければ、同じ人間同士での争いや、人種や民族、移民やLGBTの問題が起こるはずがない。
さらに今、この人間中心という名の自己中心が生み出す好き嫌いの支配した主観的な世界に、技術は遺伝子組み換え生物や、機械と結合したサイボーグ、人工生命や人工知能のようなポスト人間を加えようとしている。もしかすると、ポスト人間ではなくエクストラ人間というべきかもしれない。世界の分断を生み出した、自らが理解できる範囲の人間中心の考え方が、こうした技術の登場によってますます加速され、不寛容を促進することは容易に想像できる。マッキントッシュのデザイン原則における「寛容性(Forgiveness)」が、今また人間同士、そしてポスト人間とのインターフェイスの中で必要となってくる。
人間を超えた新しい理性の探求
アンソニー・ダンとフィオナ・レイビーは『スペキュラティヴ・デザイン』において、今日の「解決不可能な」多くの問題と向き合うには、価値観や信念、考え方、行動を変えるしかないことを示した。そのためにはまず、近代的な「個人」の成立と共にある、「中心」という概念を捨て去らなければならない。「非中心」システムは、古くから議論されてきたテーマであった。多様で異質な人間は、それぞれがそれぞれに対して「エイリアン」である。宇宙に中心がないように、エイリアンとしての人間のどこにも中心は存在しない。中心の概念が、帝国主義や覇権主義を生んできたように、私たち一人一人が常に自分で自分を変えられる状態に置いておかなければならない。
そうした状況は、自己や個性を重んじる「個人」という精神の基盤を曖昧にし、感情的にはかなり苦しいものになるだろう。しかし感情は、人の視野を狭くし、他人に対する不寛容を助長する。アメリカのトランプ大統領に代表される、世界の多くの政治家が、人間の感情に訴えることで、人々の支持を集めている。かつての政治的な対立軸は「右派—左派」であったが、現在の対立軸は「感情—理性」といえるだろう。社会や人々を支配したい、ビジネスやパワーゲームに勝ちたいと思っている人のすべてが、本当に必要なことではなく、人間にわかりやすい感情を利用して、ものごとを訴えかけようとしている。
だから、これからのデザインにとってもっとも重要となるのが、身体的な経験に根ざした感情ではなく、抽象的認識としての概念を操作する能力としての「理性」なのだ。感情という名の牢獄に囚われている限り、拡大を続ける人間社会は、遅かれ早かれ衰退と崩壊を迎えるだろう。人間が人間になる前から存在していた感情は、人間にとって不可避なものだが、それが引き起こすのは悪いことも多い。だからこそ、人間は技術がもたらす新しい理性によって、その感情をコントロールし、乗り越えていかなければならない。
この新しい理性によるデザインの基盤の第一候補は「数学」である。数学に必要な前提としての「公理」と、そこから生まれる人間に依拠しない論理的な展開力は、アルゴリズムのもっとも包括的な形態といってもいいだろう。賛否両論はあるが、物理学者が考える「数学的な宇宙」で実行する「公理的なデザイン」の可能性は、人間に依拠しない理性によるデザインを考えていくための出発点になり得る。数学という「匿名」の言語や構造からデザインを考えたり拡張することは、人間が人間の外側にあるものを想像したり参照することを可能にし、さらにはその公理的、論理的構造が、人間の経験を超えたデザインのためのガイドラインとなるからだ。
良識ある人間が発展させてきた科学や工学、産業が生み出した大量殺戮兵器が用いられた、第一次世界大戦という「人間がかくも非人間的になる」体験から、現実や意味を解体するシュルレアリスムやダダといった芸術運動が生まれた。しかし、彼らが考えたのは、あらゆる人間に共通している感覚や、意識下の世界を研究することであった。
今また、感情を重んじる人間がさらに発展させてきた科学や工学が、人間とは異なる知性や身体を生み出しつつある。それらは一体、人間や社会に何をもたらすのだろうか。そのことを熟慮するためには、人間という枠組みを超えたものを基準として、デザインや芸術を考えていく方法が必要不可欠だ。感情が支配する今日の世界で起こっている数々の悲劇を救うのは、人間に依拠しないアルゴリズムによる意味やストーリーの解体と、人間を超えた新しい理性の探求でしかないと、僕は考えている。
最小化した手と行為する手
1963年にアイヴァン・サザランドは、博士論文「Sketchpad:マン−マシン・グラフィカル・コミュニケーション・システム」を発表した。サザランドはそこで、「Sketchpadシステムは、線を描くことで(キャプション以外の)文章入力を不要にし、マン−マシン・コミュニケーションの新しい世界を切り開いた」と書いている。
スケッチパッドで特徴的なインターフェイスは、ディスプレイに線を描く「ライトペン」というペン型のデバイスである。ライトペンとディスプレイ外に設置されたボタンの操作により、スケッチパッドでは様々な図形を描くことができる。また、スケッチパッドが実装されたTX-2コンピュータには多くのボタンが備え付けられ、それぞれに「円を描く」「直線を描く」「消す」「コピー」「移動」などの機能が割り当てられていた。ユーザはそれらのボタンを押すことで、これから行う操作をあらかじめコンピュータに伝え、ライトペンを動かしながら、ディスプレイに図形を描いていく。サザランドはTX-2の入出力のコントロールの柔軟性と拡張性の高さによって、自らのアイディアをいろいろと試すことができ、最終的にコンピュータによる描画を実現できたと書いている。
スケッチパッドは、マサチューセッツ工科大学(MIT)のリンカーン研究所でカスタマイズされたTX-2でしか動かなかった。だからサザランドの博士論文の序文で、アラン・ブラックウェルとケリー・ローデンは、スケッチパッドがその論文と使用状況を撮影した記録映像によってのみ広まったと述べている。その記録映像には、ディスプレイ横にあるボタンを押す手とディスプレイにライトペンで線を描く手が映っていた。
Ivan E. Sutherland “Sketchpad: A Man Machine Graphical Communication System” (1963)
ここに映るヒトの二つの手のうち、片方はボタンを押すという最小化した行為のみに従事している。前回の記事で書いたことを踏まえて、この手を「最小化した手」と呼びたい。最小化した手は、あらかじめ描くことを選択し、行為をコンピュータに委譲する役割を担っている。その最小化した手と協働するのが、ライトペンを持ちディスプレイに図形を描き続ける手である。このヒトが古来から行ってきた「描く」という行為を続ける手を、「行為する手」と呼びたい。「最小化した手」と「行為する手」が組み合わされると、直線と曲線が摩擦や空気抵抗を感じないほどスムーズに描かれている。
ディスプレイが映し出す数学的世界
スケッチパッドから二年後の1965年にサザランドが発表した論文「究極のディスプレイ」は、コンピュータに接続されたディスプレイの可能性を提示することからはじまっている。そこでは「摩擦」という単語が二回使われていた。
私たちが住んでいるこの現実世界の特徴を、私たちは長く慣れ親しむことで熟知するようになった。この現実世界との関わりを実感しているからこそ、その特徴を予測できる。たとえば、モノの落ちる場所、よく知っているモノを別の角度から見たときの形、摩擦に抵抗しながらモノを動かすのに必要な力などを予測することができる。その一方で、私たちがよく知らないものとしては、荷電粒子にかかる力、不均一場の力、非射影的な幾何変換の影響、高慣性で低摩擦の運動などが挙げられるだろう。その点、デジタルコンピュータに接続されたディスプレイは、現実世界では実現できないコンセプトを知る機会を与えてくれる。それは、数学的な不思議な国を映し出す鏡である。アイヴァン・サザランド「究極のディスプレイ」
冒頭の段落に出てくる「摩擦」のうち、一つは「現実世界」の現象を指し、もう一つは物理的世界では難しく「数学的な不思議な国」でのみ実現が可能な現象を指している。スケッチパッドの記録映像が示す摩擦を感じさせない線の動きは、数学的世界を示していると言える。サザランドはコンピュータと接続したディスプレイを介して、ヒトが属する物理的世界とコンピュータがつくる数学的世界とをつないでいる。
物理的世界と数学的世界という二つの世界を結ぶときに、問題となるのが「ノイズ」である。1960年代のコンピュータ科学周辺では、ノーバート・ウィーナーの『サイバネティクス』と、サザランドの指導教官でもあったクロード・シャノンの「コミュニケーションの数学的理論」とが強い影響力を持っていた。そして、ウィーナーとシャノンはともに、二つの対象のあいだの情報経路にノイズが満ちていることを問題視していた。彼らはそれぞれ、数学的方法を用いてそのノイズを処理した。ウィーナーはノイズを除去して、ヒトと機械という二つの異なるシステムのコミュニケーションの可能性を開き、シャノンは符号化によってノイズの影響を調整し、コミュニケーションの効率の最大化を求めた。
サザランドのスケッチパッドは、物理的世界と数学的世界とを「正確な図形を描く」ということでつなげている。ヒトとコンピュータのコミュニケーションにおいて生じる「ノイズ」からスケッチパッドを見てみると、このシステムはヒトが図形を描くときに生じる不正確さやブレを低減して、ディスプレイを介することで図形によるコミュニケーションを最大化していると言える。さらに、ヒトがこれまで行ってきた描く行為をペン型のデバイスを用いて保存してもいる。それはボタン操作という最小化した行為とペンによる複雑な行為が組み合わされて、ヒトと物理的世界との接触から生じるノイズが整えられ、ヒトとコンピュータのあいだで描く行為と描かれる図形が効率よくやり取りされていることを示している。スケッチパッドの操作によって、ヒトは特に意識することなく、熟知する物理的世界から未知の数学的世界に引き込まれているのである。
もう一つの手となるアルゴリズム
「最小化した手」と「行為する手」の関係を考察するために、製図用具の歴史に位置づけた展覧会「想像力の道具:18世紀から現在までの製図用具と技術」のカタログに収められたW.J.ミッチェルによるテキスト「結論:即興、道具、アルゴリズム」を参照したい。
ミッチェルは、フリーハンドで描くことは「パフォーマンス」であり、その技法はパフォーマーの技量に依存するのに対して、製図道具を用いて描くことは「規律正しくモジュール化された複製可能な行為」であり、より複雑な図形を描くことを可能にしたと指摘する。さらに、製図道具によって記された図形は「ひとりの芸術家の手の動きの記録ではなく、時間を超越したプラトン的な抽象を表しているシンボルとして読まれるものだ」と書く。そして、1960年代にコンピュータグラフィックスが登場し、すべての図形が「空間や表面を横切る点の軌跡」として描かれるようになった結果、多くの製図用具は点の位置を算出するアルゴリズムに置き換わり、ヒトの代わりにコンピュータが図形を描くようになっていったと述べている。
ミッチェルのテキストには、道具との関わりの中で、図形を描くという行為から手がなくなっていく過程が示されていた。それは道具と手の結合を意味している。それゆえに、製図道具の導入以後は、図形を描くヒトの手の役割は述べられていない。製図道具を使えば、誰もが自らの手で正確に特定の図形を描けるようになるのであり、手は独自に図形を描く立場から、アルゴリズムを具現化した道具に従う立場になる。
製図道具は、図形を描く行為からヒトの手による図形の不正確さや線のブレなど、「ノイズ」と見なされるものを減らすものであった。しかし、手そのものが描く行為を担っていることに変わりはない。むしろ、ペンと製図道具を両手で同時に使うようになったので、ヒトの手の役割は増えたといえる。誰もが図形を正確に描くために、製図道具はヒトに二つの手を同時に使うことを要求したのである。
図形を数学的な正しさで描くことができるスケッチパッドもまた、ヒトに二つの手を要求しているが、その役割は違っている。製図道具を持っていた手は、ボタンを押すという最小化した行為を行うようになり、ペンを持つ手もライトペンを持つときは線を描かなくなっている。ライトペンはディスプレイから放射される光をセンシングして、ヒトがディスプレイのどこを選択しているのかをコンピュータに伝えるポインティングデバイスであって、線を描くための道具ではない。ヒトが選択した点のあいだに直線や曲線を描くのは、スケッチパッドに組み込まれたアルゴリズムである。これまでは製図道具が体現するアルゴリズムに従ってヒトの手が正確な図形を描いていた。それに対してスケッチパッドでは、久保田晃弘が「アルゴリズムは、いわば人間の〈手〉に代わるもの」と指摘するように、ヒトの手に代わってアルゴリズムそのものが線を描いているのである。
スケッチパッドを使うヒトの二つの手は、片方がボタンを押してアルゴリズムを選択する最小化した手となり、もう片方がアルゴリズムとともに図形を描くためにライトペンを持つ行為する手となった。そして、最小化した手と行為する手とを組み合わせるようになったヒトから描く行為を委譲されたアルゴリズムが、もう一つの手として提供されている。こうして、ヒトの描く行為が二つの手を組み合わせて、その行為の意図を常にコンピュータに示して委譲することで、ヒトとコンピュータのあいだに生じるノイズは低減され、アルゴリズムが滑らかに線を描いていく。スケッチパッドのディスプレイには、ヒトの最小化した手と行為する手、そしてアルゴリズムという、三つの手が絡み合っているのである。
制約が生むあたらしい体験
ヒトの代わりにアルゴリズムが描くスケッチパッドは、「描く」という行為を再発明している。メディア理論家のレフ・マノヴィッチは、コンピュータを計算機から表現のメディアにつくりあげていったコンピュータ科学者たちについて、「コンピュータをたんに古いメディアを新しい方法で〈再媒介マシン〉にするつもりはそもそもなかった」と指摘している。彼らはコンピュータをよく知っていたからこそ、その表現メディアとしての可能性にいち早く気づいていた。マノヴィッチはサザランドのスケッチパッドもその一つだとして、次のように書く。
スケッチパッドも最も分かりやすい例だろう。コンピュータに可能なのが問題解決であると理解していたサザランドは、グラフィックなメディアの中には存在したことのない制約充足というプロパティを組み込んだ。より一般的な用語によって繰り返すと、コンピュータメディアは古いメディアの模倣から始めて次第に独自の言語を探すのではなく、その端緒から新しい言語を話したのだ。レフ・マノヴィッチ「カルチュラル・ソフトウェアの発明」
マノヴィッチが「制約充足」と呼ぶのは、たとえば、スケッチパッドにおいて円を描く際に、その中心をライトペンで選択して「円を描く」ボタンを押してからライトペンで大まかな円を描くと、選択した中心に基づいて正確な円が描かれるといったものである。製図道具のコンパスと異なるのは、ヒトの手が正確な円を描く必要はない点である。中心を選択してボタンを押すという手順さえ踏めば、あとはアルゴリズムが正確な円を描いてくれる。直線を描くときも、ライトペンで描いた線をアルゴリズムが補正してくれたり、描いた直線にあとから水平/垂直の属性を与えて変更したりできる。マノヴィッチが書くように、これは製図道具の模倣ではなく、あたらしい体験をつくりだすものである。
しかし、サザランドはスケッチパッドの体験を、メディアのあたらしさだけにとどまらず、私たちが属する自然界のルールの束縛から逃れるという、より大きな観点から捉えている。スケッチパッドがあたらしい言語を話すことには変わりないが、それは物理的世界とは異なる数学的世界の現象を記述するための言語なのである。
コンピュータの画面上に映っているオブジェクトは、私たちが通常慣れ親しんでいる自然界のルールに縛られなくてもいいはずだ。運動感覚的なディスプレイは、負の質量の動きをシミュレートするために使われるかもしれない。今日の視覚的ディスプレイを使えば、固体を簡単に透明化して「物質を透かして見る」ことができるスケッチパッドの「制約」のように、これまでは視覚的に表現できなかったコンセプトを実現できる。このようなディスプレイを使うことで、私たちは自然界を知っているのと同程度に、数学的現象を知ることができる。こうした知識を得られることを、コンピュータ・ディスプレイは約束してくれる。アイヴァン・サザランド「究極のディスプレイ」
アルゴリズムに組み込まれるヒトの行為
サザランドはコンピュータを利用して物理的世界と数学的世界を行き来しながら、ヒトに未知の体験を知ってもらおうとしている。だから、スケッチパッドのアルゴリズムは物理的世界の法則に縛られることなく、ヒトとコンピュータのあいだで「描く」行為を再発明できている。しかし、スケッチパッドはペン型デバイスを採用して、ヒトが慣れ親しんだ複雑な行為を物理的世界のレガシーとして引き継いだ。そして、物理的世界での複雑なインタラクションを得意とする、ヒトの身体を最大限活かすように設計されている。複雑なペンで描くという行為と、単純なボタン操作とが組み合わされて、ディスプレイ上に図形を描くという出来事が容易に生じる環境が構築されるのである。
スケッチパッドがレガシーな行為を用いているのは、コンピュータで「描く」ことが物理的世界で「描く」ことと異なっているのを、ヒトに気づかせないためである。コンピュータを使って図形を描くとき、ヒトは過去の描く行為を参照して描いているのではなく、数学的世界でアルゴリズム化された描く出来事とともに描くことになる。ヒトの描く行為は複雑であるが、その結果として現れる出来事としての丸や四角といった図形は分析可能でアルゴリズム化できる。
サザランドは描く行為を「描く−丸」や「描く−四角」といった出来事の集積と捉え、「制約」というプロパティとしてスケッチパッドのアルゴリズムに導入した。つまり、サザランドは物理的世界において行為の前提となっている出来事を、アルゴリズムとして数学的世界にストックしたと言える。スケッチパッドでは描く行為から丸や四角といった図形が生じるのではなく、描く出来事が一つのアルゴリズムとして選択され、制約が遂行されて図形が描かれるのである。
スケッチパッドはライトペンとディスプレイというインターフェイスを用いて「描く行為」を模倣するのではなく、先に「描く出来事」を複製して、その後、描くためのアルゴリズムのなかでヒトの行為を変数として扱い、図形を表示する。ディスプレイに表示される円を、ヒトの行為ではなく「円−描く」という出来事の結果だとすると、スケッチパッドのプログラムが設定するパラメータによって、ヒトの行為の範囲が調整可能なものと考えられるのである。すると、スケッチパッドが表示している円は、ヒトの行為を複製して作成したものではなくなる。それは、最小化した手によって「円−描く」というアルゴリズムがアドホックに呼び出され、行為する手がそのパラメータの範囲内でライトペンを動かした結果、ヒトとアルゴリズムが協働してつくる個別の出来事としてディスプレイに表示されることになる。
スケッチパッドで円を描くことは普通のことのように見えるけれど、プログラムのパラメータで自由を限定される一つの変数として、ヒトの行為が認識されている点が重要なのである。サザランドはスケッチパッドでヒトの行為をアルゴリズムに組み込み、最小化した手と行為する手、そして線を描くアルゴリズムというもう一つの手によって、これまでにない「描く」体験を実現しているのである。
物理的世界のルールからの解放
サザランドは「描く」という出来事が次々に連鎖していくプログラムをつくり、ライトペンとボタンとディスプレイというインターフェイスに実装した。このインターフェイスのもと、ヒトはスケッチパッドに制約されつつも最適な行為を行い、図形を描く。スケッチパッドは、あらたな「描く」体験をコンピュータで実現しているだけでなく、ヒトの行為そのものを制御している。
究極のディスプレイは、コンピュータが物質の存在そのものを制御することができる空間である。そのような空間に表示された椅子には、実際に腰かけることができるだろう。手錠は拘束力を持ち、銃弾は殺傷力を持つだろう。適切にプログラミングすれば、こうしたディスプレイは文字通り、アリスが入り込んだような不思議な国となるのだ。アイヴァン・サザランド「究極のディスプレイ」
サザランドの「究極のディスプレイ」は、ディスプレイを物理的世界にまで拡張する可能性を示していた。ここで重要なのは、「適切にプログラミング」さえすれば、物理的世界もコンピュータで記述可能だと考えていることである。
メディアアーティストであり、研究者でもある落合陽一は、「サザランドには、適切なプログラミングを用いて〈魔法を実現する〉だけの自由な発想力があった」と指摘している。さらに、「サザランドは、人間の価値観をアップデートしうる技術がコンピュータによって可能になることを示した、最初の人物だと解釈できます」とも書いている。さらには、サザランドが「Mathematical(数学的)」と書くものは「Computational(コンピュータによる)」に書き換え可能であるとも指摘している。
サザランドが考えたバーチャルリアリティも、単に仮想世界を覗くことではありませんでした。彼はバーチャルリアリティを、現実と見分けのつかない何かを作ることだと構想したのです。それはむしろ、現実自体を物理的にハックし、現実を上書きしていくような、情報だけでなく物象化も目指すものだと言えます。落合陽一『魔法の世紀』
「究極のディスプレイ」で物理的世界のルールからの解放を示したサザランドは、コンピュータによって物理的世界を制御することによって、ヒトをアップデートしようとしていたと考えられる。サザランドがあたらしくしたのは、スケッチパッドでディスプレイに表示される情報だけでなく、それを操作するヒトの行為そのものにまで及んだ。
サザランドは、コンピュータを用いてヒトの身体も物理的に制御可能なモノとしてハックし、アップデートをしかけている。コンピュータはあらたな情報を生み出すために、まずはヒトをハックして行為を「出来事の連鎖」に変更して、数学的世界に取り込み、情報を生み出しやすくした。この変更をコンピュータの初期段階で最も鮮やかに見せたのが、サザランドのスケッチパッドであったと言える。だからこそ、スケッチパッドは現在のグラフィカルユーザインターフェイス(GUI)の源流とみなされている。
スケッチパッドから連なるGUIの流れは、ヒトから見ればコンピュータが使いやすくなったことを意味する。しかし、コンピュータに最適化した「出来事の連鎖」に基づく行為は、スケッチパッドが導入した「制約」というプロパティが示すように、ヒトの行為を制約するものである。さらにコンピュータからヒトに課せられた制約は、自然界のルールからヒトを解放することも意味している。
インターフェイスで「合生」する
インターフェイスという場において、ヒトとコンピュータとが出来事を介して結びつき、行為の制約と解放とが同時に起こる。しかし、ヒトとコンピュータが先にあって、そのあいだにインターフェイスができるのではない。適切にプログラミングされたインターフェイスが先にあり、そこに起こる出来事とともにヒトとコンピュータが結びつくのである。ヒトとコンピュータとは必ずしも向かい合う必要さえなく、重なり合った状態であっても、どこかに適切にプログラミングされたインターフェイスが発生すれば、あらたな出来事が生まれ、ヒトとアルゴリズムの協働が生まれる。そこには同時に、あらたな行為が派生する。
ヒトとアルゴリズムのあいだに生まれるあらたな出来事に名前を与えるために、芸術論・知覚論を専門にする平倉圭のテキストにおける「合生的形象」という言葉を参照したい。このテキストは、映画『ミステリアス・ピカソ — 天才の秘密』に記録された「ラ・ガループの海水浴場」という作品の制作プロセスを、生物学的身体の外に物体化された思考過程として、またピカソを一要素とした作者群による集団制作として分析したものである。平倉は、撮影のために強烈な照明のもとで断続的に描くピカソ、描かれる絵画、描かれる絵画の映像、その撮影及び編集技術、映像につけられた音楽を次々に分析し、複数の人間による思考を言語に解きほぐし、次のように要約する。
映画内で成長するG1-MPの「思考」は、複数の人間と非人間的技術装置が絡み合い、互いに梯子を掛け合うようにして実現された。新しい共在性(togetherness)の産出を指すホワイトヘッドの用語である「合生(concrescence)」を借りて、「合生的形象」と呼ぶことにしたい。G1-MPの247ショットに渡る音−映像が示すのは、「ピカソ他」による合生的形象の産出である。平倉圭「合生的形象」
ここで平倉が書く「複数の人間と非人間的技術装置が絡み合い」という部分は、スケッチパッドにおいてヒトとアルゴリズムが入り交じって生まれるあらたな出来事をそのまま示していると言えるだろう。平倉がホワイトヘッドの用語からつくった「合生的形象」という言葉を借りて、インターフェイスでヒトとアルゴリズムを絡み合わせる出来事を、「合生的出来事」と呼びたい。またそこから派生する行為を、「合生的行為」と呼んでみたい。
ピカソが「ピカソ他」という作者群の一要素となり「体外を取り囲む諸装置群と絡まりながら押し流されていく」ように、スケッチパッドにおけるヒトの手とアルゴリズム、さらに、ライトペン、ディスプレイといったデバイス群とは絡み合って、図形を描き、拡大縮小し、コピー&ペーストし、消去していく。ここでは、ヒトとアルゴリズム、デバイス群のどれかが主ということではなく、それぞれが一つの要素となり、互いに行為を委譲している。インターフェイスという場において、ヒトとアルゴリズムとデバイス群とが絡み合う合生的出来事が生まれ、それぞれが一つの要素として図形を描くための合生的行為が遂行される。そこで、ヒトの行為は合生的出来事から派生する合生的行為に最適なものへと調整されていく。
ここで改めて指摘したいのは、合生的出来事は物理的世界と数学的世界とを跨ぐということである。コンピュータ登場以前は、「ピカソ他」のように、合生的出来事は物理的世界でのみ起こることであった。しかし、サザランドはスケッチパッドで二つの世界を含んだ合生的出来事を生みだし、「究極のディスプレイ」でその可能性を示している。異なる原理原則で駆動している数学的世界との接触のなかで、インターフェイスは物理的世界のなかにありながら、従来の制約から解放されていく。
ダグラス・エンゲルバートらによって、ペン型のライトペンは「マウス」という一見すると何をするものなのかが分からない形になり、アラン・ケイらがメタファーに基づいたリアルな造形を採用したアイコンなどの画像は、ディスプレイの特性を活かしたフラットな形状になりつつある。インターフェイスはヒトとコンピュータとを一つの要素として扱いながら、ディスプレイとマウスやタッチパネルというデバイス群を用いて、物理的世界と数学的世界とを跨いだ合生的出来事を生み出し、ヒト他による合生的行為を二つの世界に適したものへとアップデートし続けている。
さらに、「究極のディスプレイ」を高く評価する落合は、「コンピュテーショナル・フィールド」という情報とモノとを一元的に扱える場を提案している。コンピュテーショナル・フィールドにおけるすべての出来事は,絡み合った二つの世界から生じる合生的出来事となり、ヒト他によるあらたな合生的行為が次々と生まれていくだろう。
次回は、なぜインターフェイスでは二つの世界が絡み合い、合生的出来事が生じるのかということを、ダグラス・エンゲルバートとアラン・ケイの思想と実装とともに考えていきたい。
哲学における「アクセス」
いかなる必然性にも確率にも従わず、先行する状態にまったく含まれていない状態を創発させることができる時間。そのような時間を考えるとき、現在は未来をはらんでいるわけではなく、過去の経験から未来を予測することもできない。それは人間にとって厳しい現実となるかもしれないと同時に、わたしたちの未来が、充足理由律から解き放たれることを意味している。浅野紀予「思弁的世界とコミュニケーション」
去年の春に書いた「思弁的世界とコミュニケーション」という記事を、わたしは当初、「詩と経験と因果律」と題していました。記事のなかに「因果」の二文字は出てきませんが、そこで試みたのは、あらゆるものごとに必然的な因果関係があるとする「充足理由律」を疑ってみることでした。
わたしたちは、何かが起きるとその原因を知りたくなりますし、それを次の結果に結びつけようとするものです。つまり、悪い結果が起きた場合にはその原因を取り除こうとし、良い結果が得られたなら、また同じ原因を作り出すことで再び良い結果を得ようとします。その積み重ねは「経験則」として、自分だけの、あるいは他の誰かと共有できるかもしれない、大切な資産となっていきます。
わたしが20年近く携わってきたWebの領域でも、そのような経験則は大切なよりどころとなり、現在あるようなWeb技術の標準仕様やガイドライン、あるいはさまざまなライブラリやフレームワークを生み出してきました。
とはいえ、経験則は常に役立つとは限りません。以前はうまくいったやり方が通用しなくなったり、まだ経験したことのない新たな取り組みが必要になるとき、わたしたちは手持ちの経験則を超えて思考することを迫られます。経験則の源にある「事実性」を思考の限界にするのではなく、ものごとのうちに「それ自身の他にはいかなる限界もない偶然性」を見出し、それと向き合うこと。その可能性を教えてくれたのが、わたしとほぼ同世代の哲学者、カンタン・メイヤスーだったのです。
メイヤスーの著書や論文を次々と読んでいた頃、わたしには一つ気になったことがありました。それは、彼が「アクセス」という言葉をたびたび用いることです。たとえば、カント以来の近代哲学を支配してきた認識の捉え方を「相関主義」と呼ぶことについて、こう述べています。
私たちが「相関」という語で呼ぶ観念に従えば、私たちは思考と存在の相関のみにアクセスできるのであり、一方の項のみへのアクセスはできない。したがって今後、そのように理解された相関の乗り越え不可能な性格を認めるという思考のあらゆる傾向を、「相関主義」と呼ぶことにしよう。カンタン・メイヤスー『有限性の後で』
また、先ほど触れたような、ものごとに潜む偶然性を語るところでも、「アクセス」という言葉が現れます。
ただ思考のみがそうした偶然性にアクセスできるのであり、それは、現象の見たところの連続性の下に潜んでいるカオスへのアクセスに相当するのである。カンタン・メイヤスー『有限性の後で』
「観念」「存在」「現象」といった哲学用語に混じって、やや毛色の違う「アクセス」という言葉が現れるところに、わたしは目を引かれました。カントは『純粋理性批判』のなかで、人間は物自体についての認識(Erkenntnis)を持つことができず、知覚や直観によって捉えられた物自体についてのみ認識できる、と述べていました。なぜメイヤスーは、「認識」ではなく「アクセス」という言葉を使うのだろうか。そんな疑問が浮かんだのです。
メイヤスーと同世代の哲学者であるグレアム・ハーマンも、「アクセス」という言葉を使うことで知られています。彼はメイヤスーとは別のアプローチから「因果」の問題を見直し、世界に対する人間の「アクセス」の特権化に抗うことを試みています。また、オブジェクト指向、プロキシ、ファイアウォールといったコンピュータ用語を哲学の文脈で駆使する彼は、「アクセス」という言葉にも、人間の行為に限定されないシステマティックなニュアンスを持たせているように感じられます。
実在的(real)オブジェクトは人間による感覚的(sensual)アクセスを越えては現実存在しないのだと、わたしが主張するにしても、それはカントによる現象と本体との区別と混同されるべきではない。カントの区別は、人間だけが被るものだ……因果の問題を復活させることが意味するのは、認識論的な暗礁から逃れること、関係が意味するものの形而上学的な問いを再提起すること、である。グレアム・ハーマン「代替因果について」
メイヤスーとハーマンがそれぞれの思想を語るなかで用いる「アクセス」という言葉には、人間の理性に支えられたカント的な「認識」とは違う、新しいニュアンスがこめられているように思えました。認識がおもに目と頭を使って行なうことだとすると、アクセスという行為には、身体ごと何かに近づき、入り込もうとする感じがあるからです。
そして、自分が対象にアクセスしようとする意思(intention)が生まれるとき、対象へのアクセスの可能性、すなわち「アクセシビリティ」が見出されるのではないかということに、わたしはふと気づいたのです。
アクセスの欲望とその来歴
わたしがWebの仕事を通じて考えてきたのは、あくまでその対象自体が備えるべき性質としてのアクセシビリティだったと言えるでしょう。サイトやコンテンツに備わっている一定のアクセシビリティが「原因」となって、どんな人がどのようにその対象にアクセスするかという「結果」が決まる、ということです。
でも、Web誕生以前のはるか昔から、わたしたちがさまざまな人やものや場所にどのようにアクセスしてきたのかを考えると、その一方向的な因果関係は、実際のアクセス体験を十分に表していないように思えます。本来のアクセシビリティとは、そのように静的に定まっているのではなく、わたしたちが対象にアクセスしようとする意思によって動的に生成され、その対象に与えられているのではないでしょうか。それは意思というより、もっと感情的な「欲望」と呼んでよさそうです。
これは、自分という「実在的(real)オブジェクト」がアクセスしているのは常に「感覚的(sensual)オブジェクト」であるとする、ハーマンの思想にも重なるように思えます。その見方に沿うならば、わたしたちはあらゆる関係から離脱したあるがままの存在としての対象にアクセスできるわけではなく、自分が概念的/経験的に知覚するさまざまなプロフィールを対象に与え、それらとのインタラクションを通じて対象にアクセスしていることになるからです。
そして、アクセスの欲望を育んできたのは、人が歴史のなかで生み出してきた、さまざまな技術の力だと言えるでしょう。陸上交通や航海の技術がめざましい発展を遂げていた中世ヨーロッパで生まれた 「access」という単語は、「approach(近づく)」と「enter(入り込む)」の二つの意味を持ち合わせています。また、何かに近づいて入り込むだけではなく、そのための手段や、さらにはそれを行なうための権利や自由まで意味することもあります。またこの時代には、書写を職業とする人々が現れ、庶民にも本が入手できる書店が誕生するなど、いわば知識へのアクセスの可能性も拡がりつつありました。技術の力が、当時の人々に次々と未知のアクセス体験をもたらしたことが、この新たな言葉を生み出したのかもしれません。
そして、わたしたちは技術によってアクセスの欲望を満たすと共に、より一層の欲望にかられ、それを叶えようとして新たな技術を求めることを繰り返してきたのではないでしょうか。その途上で、Webという技術が生まれたのだと、わたしは考えています。
Webが生んだ新たなアクセス体験
Webにおけるアクセスとは、従来の人やものや場所へのアクセスとは異なる、まったく新たな体験でした。それは、アクセスの概念に革新をもたらした二つの技術を土台として、Webが生まれたことに起因していると思います。一つは、通常はシーケンシャルに読むことになるテキスト情報に相互参照のためのリンクを張りめぐらせ、非線形的なアクセスを可能にした、ハイパーテキストという新たな文書形式。もう一つは、当時すでに地球規模のオープンなネットワークとなりつつあった、インターネットというシステムです。
ハイパーテキストという用語を考案したテッド・ネルソンは、注意欠陥障害(Attention Deficit Disorder、ADD)を抱えていたといいます。頭の中でとめどなく増殖していく連想に追いつけなかった彼は、ささいなことで集中を妨げられ記憶が不確かになってしまうため、自らの考えにいつでも確実にアクセスできる手段を模索していました。そこで閃いたのが、あるテキストから拡散していくあらゆる思考のルートを追跡できるシステムを、自らの力で創り出すというアイデアでした。そのような分岐を含む非線形的な文書をハイパーテキストと名付けた彼は、それをもっとも理想的な形で活用する「ザナドゥ(Xanadu)」というシステムを構想するに至ります。そして、誰よりもまず自分自身のアクセスの欲望を満たそうとした彼は、やがて「すべての人びとによるアクセス」を目指すようになります。
統一された電子的文献を新たに実現すること。過去の自由を再び燃え上がらせ、それを電子的な未来の自由に継承していくこと。そして、すべての事象をつなぎ合わせて誰もが入手できるようにすること。テッド・ネルソン『リテラリーマシン』
欧州原子核研究機構(CERN)の研究者としてWebを生み出したティム・バーナーズ=リーも、そのようなアクセスの欲望を原点としていたように思います。彼はWebの原型となるプログラムを「Enquire」と名付けましたが、その由来となった『Enquire Within Upon Everything(万物探索知識宝典)』という本との出逢いについて語っています。それは、彼が少年時代にロンドン郊外の自宅で見つけた、かび臭い本でした。
魔法に関係のありそうな題名のこの本は、ヴィクトリア朝時代の生活上のヒントを集めたもので、さまざまな情報の世界への扉の役割を果たしていた……この本はWebについての的確なたとえにはならないとしても、Webというアイデアへの素朴な出発点にはなり得るものである。ティム・バーナーズ=リー『Webの創成』
わたしがここで目を引かれたのは、「扉」という言葉でした。ある一冊の本が、ただの紙とインクの寄せ集めではなく、まるで世界にアクセスできる魔法のドアのように感じられたこと。それは、ティム少年がアクセスの欲望に目覚めるきっかけだったのではないでしょうか。
大人になったティム・バーナーズ=リーは、ハイパーテキストとインターネットを結び付け、Webという新たなシステムを生み出しました。しかし、テッド・ネルソンと同様に、彼の願いは「すべての人びとによるアクセス」へと拡がり、それが現在に至るまで、Webアクセシビリティの理念として受け継がれているのだと思います。またそれは、年齢や能力や生活状況に関わらず、あらゆる人にとってできる限り優れたものをデザインしようとする「ユニバーサルデザイン」の思想にも影響されていたはずです。
すべての人が持ち得る障害(ディスアビリティ)
Web誕生以前のアクセシビリティは、おもに建築の分野で扱われていました。「ユニバーサルデザイン」という言葉を考案したのも、米国の建築家であるロナルド・メイスです。彼は、ティム・バーナーズ=リーが世界初のWebサイトを公開する2年前の1989年に、ノースカロライナ州立大学でアクセシブル・ハウジング・センター(Center for Accessible Housing)という組織を設立しました。これは後にユニバーサル・デザイン・センターと名前を変え、現在に至っています。
1970年頃、米国の建築基準法で初のアクセシビリティ対応に携わったメイスは、特に障害のある人びとの権利を守ることを目指し、それを数多くの建築プロジェクトで実践すると共に、米国の公正住宅法などの法的整備にも尽力しました。
ここで注目したいのは、メイスが障害のある人とそれ以外の人を分けようとする世間の常識を打ち破ろうとしていたことです。彼は1998年、亡くなる1ヶ月ほど前に行なった最後のスピーチで、すべての人が「障害(ディスアビリティ)」を持つ人なのだという考え方が、ユニバーサルデザインの根底にあることを語りました。なぜなら、人は誰でも年齢を重ね、それまでできたことができなくなっていくという「dis-ability(能力の低下や喪失)」を経験しながら生きるものだからです。
1960年代に始まった「ノーマライゼーション」の思想も、障害のある人の権利を守るという点ではユニバーサルデザインに通じていますが、そこには「障害者」とそれ以外の「健常者」を区別して考えるという前提があったと言えるでしょう。そして、能力的に問題なく自立できている人をノーマルとみなし、ノーマルでない人は少数派だとする見方は、現在でもまだ一般的なものです。メイスが用いた “disability” という言葉の意味をあらためて考えると、そういった常識をいかに覆そうとしていたのかを伺い知ることができます。
建築でもWebでも、「すべての人びとによるアクセス」という究極の目標を叶えるための確実な出発点は、実際に誰がどのようなアクセシビリティの問題に悩んでいるのかを洗い出し、個々のケースについて具体的な対策を講じることだと考えられてきました。Webの領域では、W3Cが1999年に勧告した「Webコンテンツ・アクセシビリティ・ガイドライン(WCAG)」が、それを実践するための重要な足がかりとなりました。
2008年に1.0から2.0へバージョンアップしたWCAGは、Webコンテンツのアクセシビリティを定量的に評価するための基準となり、障害のある人にも使いやすいサイトを作るために不可欠なガイドラインとなっています ※1。また、このようなガイドラインによる標準化は、Webブラウザに代表されるユーザーエージェント、およびスクリーンリーダーや画面拡大ツールなどの支援技術(assistive technology)の開発促進にもつながりました ※2。コンテンツ制作だけでなく、Webを利用するためのソフトウェアやハードウェアの開発においても、ガイドラインの遵守が着実に進んだことで、WCAGはWebアクセシビリティに関する「経験則」としても役立つようになったと言えるでしょう。
Webアクセシビリティにおける誤解
数年前の自分自身を振り返ってみると、いつのまにか「Webアクセシビリティは二段階に分けられる」という思い込みが生じていたように思います。
まず一つは、WCAGを遵守することで実現しやすい「機能的アクセシビリティ」です。この段階は、障害のある人を含め誰もがアクセスできる機能的条件が整っている状態を意味します。しかし、アクセスできる対象が目の前にあるのに、どうもアクセスする気になれないという事態が、実際には起きてしまいます。それは、たとえば見た目の好き嫌いや、安全面での懸念など、さまざまな心理的問題が生じているからです。それを乗り越え、「機能的アクセシビリティ」の先にある「心理的アクセシビリティ」まで達成するには、ガイドラインに沿って機能的に要件を満たすだけではなく、心理的にも満足できるようなデザインの力が必要になる。わたしはきっとそのように考えており、同様の考え方でWebの仕事に取り組んでいた人も多かったのではないかと感じます。
ティム・バーナーズ=リーがW3Cを設立する数年前には、米国で「障害を持つアメリカ人法(Americans with Disabilities Act of 1990、ADA)」が施行されていました。ノーマライゼーションの思想に通じるWCAGの基本的スタンスは、障害による差別をなくそうという当時の社会の気運を色濃く反映していた面もありそうです。また、Webをめぐる当時の技術環境には、現在と比べるとかなりの制約があったことは言うまでもありません。そうした時代背景を振り返ると、WCAGが制定された当時の状況では、「機能的アクセシビリティ」が達成できれば必要十分とされるケースもあったと思います。
しかし、その後現在に至るまで、わたしたちとWebの関係は、時間や場所、デバイスによる制約から次々と解放され、より自由なものへと変わり続けてきました。パソコンのディスプレイの前に座ったままでWebのなかを動き回るという、いわば身体的移動なきアクセスが主流だった時代は、とっくに終わりを告げています。わたしたちはモバイルデバイスやウェアラブルデバイスによって、いつでもどこでもWebというメディアにアクセスできることを、当たり前のように体験しています。しかも、オンラインとオフラインの世界は排他的なものではなく、重なり合い、融け合うようにして、わたしたちのアクセスを誘っているのです。
こうしたWebというメディアの性質を知った上で、自分にとってより望ましいメディアを選ぶこともあるでしょう。テッド・ネルソンの拡散的な思考を反映するような、たくさんのリンクが張り巡らされたWebページには、それ自体に集中することを妨げる性質もあります。そのWebページのコンテンツがPDFでも提供されていれば、それを印刷して読むほうが集中しやすいという人も多いでしょう。また、Web小説やWebコミックが書籍として出版され、オフラインメディアとなることも珍しくありません。
一方、リファレンス性の高い技術書や辞書のような本を紙面ではなくデジタルメディアで閲覧できれば、簡単に中身を検索できたり、持ち運びの手間が減るというメリットが得られます。プロジェクト・グーテンベルクや青空文庫のように、Webで公開中の本を電子書籍アプリやデバイスでも読める場合には、Webよりも自分の好みに合わせた表示スタイルで読むことができます。音楽や映像についても、テレビで放送されたり、CDやDVD/ブルーレイディスクでパッケージングされたものをWebで視聴できるケースは、ますます増えつつあります。Webを含めたメディアの選択肢は、以前よりもはるかに多様化してきました。
このように、技術の発展に伴ってユーザーがより自由なアクセスを手にしていくことは、技術を用いて何かをデザインする立場から見れば、より大きな不可知性に向き合うことを意味します。どんな人が、いつどこで、どのようにものごとにアクセスするのか、そのあらゆるケースを想定することは、ますます難しくなっています。これまで得た結果から原因を推測して対策を行なうことや、それを経験則として積み上げていくことには、もはや限界があるのです。
実際わたしたちは、アクセス体験においてアクセシビリティを二つに分類し、段階的に判断しているわけではありません。何かにアクセスするわたしたちは、機能的か心理的かという区別なく、その体験を成り立たせるあらゆる条件を一斉に与えられるのです。Webが誕生してから現在まで、それが時間や場所、デバイス、さらにはメディアにも囚われない体験へと変化してきたことを思ったとき、わたしはそれまでの二段階的なアクセシビリティを見直したくなったのです。それは、アクセシビリティ対応の基本方針となってきた「代替的発想」を、あらためて考える契機にもなりました。
拡がる代替的発想
通常のアクセスができない場合に、それに代わる手段を提供するという代替的発想は、Webに限らず、障害者や高齢者のためのバリアフリーデザイン全般に通じる考え方です。W3Cは、WCAG 2.0を勧告する約1年前に「HTML Design Principles」というHTMLの設計原則を公開していますが、WCAGにも共通する代替的発想を、このように掲げていました。
障害のあるユーザーに対してアクセシブルになるように機能を設計すること。能力の如何に関わらず、誰もがアクセスできることが肝要である。ただし、ある機能を一部のユーザーが十分に利用できないからといって、その機能を完全に削る必要はない。そのような場合には、代替的メカニズムを提供できればよいのである。W3C “HTML Design Principles”
代替的メカニズムを利用するということは、人間の側から見ると、対象にアクセスするために通常とは異なる感覚を代替的に用いることであるとも言えます。
たとえば、視覚について考えてみましょう。文字を目で読むことができない場合、スクリーンリーダーを利用したり、点字を指でなぞったりしてアクセスしているときには、聴覚や触覚が視覚を代替しています。しかし、わたしたちの目が行なうのは、文字を読み取ることだけではありません。むしろ、文字に還元できないイメージを感じ取ることが、視覚による体験のほとんどを占めているようにも思えます。スクリーンリーダーや点字によって、そのようなイメージにアクセスすることは、まず不可能でしょう。
これからの時代には、失われた感覚を別の感覚で代替するのではなく、その感覚自体をバイオニック(生体工学的)技術によって回復させるという解決策がさらに身近になり、代替的発想は新たな拡がりを見せるはずです。たとえば、人工内耳や人工網膜は、マイクやカメラが受け取った情報を電気信号に変え、体内にインプラントした電極に送信して神経に伝えることで感覚的な体験を実現する技術として、着実に実用化と普及が進んでいます。さらには、コンタクトレンズ型のデバイスで眼圧を加えることでものを見分けるシステムや、腕に装着するスリーブ型の音声レシーバーが皮膚で感知した信号を送ることで特定の音声を聴くことができるシステムのように、斬新な発想から生まれた技術の開発も行なわれています。これらの「触知的」なインターフェイスにおける、触覚と視覚/聴覚の関係は、一方が他方を代替するのではなく、触覚を活かして視覚や聴覚によるアクセスを取り戻すという、新たな関係へと変化していることになります。
現在では、物理的な入力デバイスを使わずに、脳から直接コンピューターに入力信号を送るインターフェイスの開発も進行中です。ひと昔前にはSF小説のなかの作り事としか思えなかったような仕組みが、いつか現実になるかもしれません。こうした技術が実用化できるのか、普及するまでどれだけの時間がかかるのかは未知数ですが、たとえば四肢が不自由なためにマウスやキーボードが使えない人にとって、新たな代替的手段となる可能性を秘めていることは確かでしょう。
こうした未来の技術は、障害のある人にとって大きな助けとなるだけではなく、アクセスの欲望をよりダイレクトに実現する手段となります。障害の有無を超えて、より多くの人に利用されていく見込みが十分にあるのです。コンピューターを操作するための技術的なスキルの必要性は薄れ、情報格差(デジタルディバイド)が解消へと向かうことも考えられるでしょう。ただし一方では、マウスやキーボードではなく自分の思考そのものをコントロールするという、未知のスキルが必要になるはずです。これまでにない形で人とコンピューターがインタラクションするようになるとき、そこには新たな可能性と限界が同時に生まれてくるのです。
変わるもの、変わらないもの
実は、WCAGはW3Cが独自に作り上げたものではなく、米国のウィスコンシン大学マディソン校で1971年に設立された、トレース研究開発センター(Trace R&D Center)のWebアクセシビリティガイドラインを引き継いだものでした。そのセンターの創設者であるグレッグ・ヴァンダーハイデンは、自らがアクセシビリティの探求に目覚めるきっかけとなった出来事について、こう語っています。
まだウィスコンシン大学の学生だった頃、僕がアルバイトをしていた行動サイバネティクス研究室にやってきた同輩のデヴィッド・レイマーズから、脳性麻痺のために話すことも書くこともタイピングもできない少年の話を聞いたんだ。彼を助ける方法を考えるのを手伝って欲しいと言われて、いくつか自分のアイデアを話した結果、ちょっと実際に様子を見せてもらうことになった……僕が出会ったリデルという少年には、援助を必要とするようなハンディキャップの持ち主という印象はなかった。重い障害を患いながらも、面白くて賢い(そして時にはやんちゃな)男の子だったよ。幅30センチで高さ40センチほどのベニヤ板に焼き付けたアルファベットといくつかの単語を、かなりの時間と労力をかけて指さすことが、彼の唯一のコミュニケーション手段だった。グレッグ・ヴァンダーハイデン
リデル少年が、その指さしボードを使ってコミュニケーションを成立させるには、彼が何かを伝えようとする相手も、辛抱強く付き合わなくてはなりません。そのせいで彼は、授業を受けたり宿題をこなしたり、一人で何かをやり遂げることもできなくなっていました。ヴァンダーハイデンは、リデル少年の熱意に打たれると同時に、彼のためのインターフェイスを考え出したいという意欲にかられてアルバイトを辞め、レイマーズや他の学生たちと一緒に、その開発のためのボランティアグループを作りました。そのグループがトレース研究開発センターという組織となり、リデル少年と同様の境遇にある多くの人の注目を集めながら成長していったのです。
手が不自由なリデル少年の代わりに、その指さしボードを作ったのは誰だったでしょうか。家族であれ友人であれ、その人はヴァンダーハイデン以上に、リデル少年の熱意をよくわかっていたことでしょう。そして、より使いやすい文字のサイズや配置を考えたりしながら、一緒にボードの改良を重ねていたことも想像できます。プロのデザイナーではなくても、頼るべきガイドラインが存在しなくても、彼らは自分の力でアクセシビリティについて考え、それを形にしていたのかもしれません。
そして、ヴァンダーハイデンがリデル少年に出会ったのは、今から40年以上前、パソコンさえなかった時代です。後に彼が考案した「Autocom」という装置は、リデルの指差しボードを電子機器として作り直したようなキーボード型のデバイスでした。それはもちろん、手作りの木製のボードよりはずっと高機能なものでしたが、当時の技術環境の下では、「手を使って操作する」という根本的な前提を見直すまでには至らなかったのでしょう。
もし今の時代に、わたしたちがリデルのような少年に出会ったとしたら、異なる前提から解決への道を探るはずです。つまり、どうすれば「手を使わない操作」が可能になるかを考えるところから出発する、ということです。実際に、今では主要なOSは音声コマンドによる操作に対応していますし、ユーザーが話しかけると自然言語処理によって質問に答えたり、必要な情報を探してくれるパーソナルアシスタント型のシステムも、どんどん精度を向上させています。また、目の動きによってコンピューターへの入力ができる視線入力装置は、低コスト化が進んで一段と手が届きやすくなっています。脳からコンピューターに直接入力を行なう次世代のインターフェイスも選択肢の一つとなるかもしれません。
今後もこうした技術の進化が、あらゆるもののアクセスの可能性を拡げていくはずです。また、わたしたちは自分がアクセスする立場だけでなく、アクセスされる立場でもますます判断を迫られることになるため、不正なアクセスから身を守ったり、意図に反したアクセスを防いだりすることも必要になるでしょう。
わたしたちは、こうした相反するアクセスの問題を、技術によって変化した環境に起因するものと捉え、別々の問題として考えてきました。しかし、実際は人間だけが特権的にアクセスをしているのではなく、アクセスの可能性を秘めたものが世界に満ち溢れ、人間もその一つとして世界のなかにある。そう考えるほうが、わたしたちの周りで起きていることをうまく言い表せている気がします。
ただ、アクセシビリティを考える出発点は、わたしたちが自分自身のために、時には他の誰かのためにアクセスの欲望を叶えようとすることであり、それはこれからも変わらない。わたしは、そう思うのです。
爆心地に戻ったヒトのゆくえを示す『メディア論』
西欧世界は、3000年にわたり、機械化し細分化する科学技術を用いて「外爆発」(explosion)を続けてきたが、それを終えたいま、「内爆発」(implosion)を起こしている。機械の時代に、われわれはその身体を空間に拡張していた。現在、1世紀以上にわたる電気技術を経たあと、われわれはその中枢神経組織自体を地球規模で拡張してしまっていて、わが地球にかんするかぎり、空間も時間もなくなってしまった。急速に、われわれは人間拡張の最終相に近づく。それは人間意識の技術的なシミュレーションであって、そうなると、認識という創造的なプロセスも集合的、集団的に人間社会全体に拡張される。さまざまのメディアによって、ほぼ、われわれの感覚と神経とをすでに拡張してしまっているとおりである。意識の拡張というのは長いこと広告業界が特定の製品について求めてきたものであったが、それがいいものであるかどうか。それはさまざまの回答の余地を残す問題である。このような人間の拡張にかんするさまざまの問題に解答を与えるためには、全部をひっくるめて考察するしか、ほとんど方法がない。どのような拡張も、たとえば、皮膚であれ、手であれ、足であれ、すべて精神的、社会的な複合全体に影響を及ぼすからである。マーシャル・マクルーハン『メディア論』
マクルーハンの『メディア論』はこのようにはじまる。「外爆発」と「内爆発」の爆心地にいるのはヒトである。ヒトの身体がまず空間に拡張し伸び切ったところで、身体の内と外とがひっくり返り、爆心地に戻ってくるかたちで中枢神経組織も空間を埋め尽くしていった。マクルーハンは『メディア論』でさまざまなメディアを論じることで、空間にヒトの身体と神経とが満ちていく様子を記述した。地球を覆い尽くすようになったヒトはどこまでいってもヒトである。ヒトが拡張しているのだから、ヒトがヒトとしているのは当たり前である。
1964年に出版された『メディア論』において、マクルーハンはヒトの画像を世界の隅々まで瞬時に届けるテレビの話で終わらせなかった。当時としては最新の電気メディアであった「テレビ 臆病な巨人」で終わらず、そのあとに「兵器 図像の戦い」と「オートメーション 生き方の学習」という章が置かれている。外爆発から内爆発を経たヒトは爆心地に戻り、そこにある「兵器」と戦うことになり、その後のあらたな生き方として「オートメーション」が必要であるという、マクルーハンの予測がこれらの章に書かれていると考えてみたらどうだろうか。もちろん、爆心地に戻ったヒトを待ち受けていたのは「コンピュータ」である。『メディア論』ではコンピュータも論じられているけれど、時代の制約から扱いはすくない。コンピュータはまだ大学の研究室や軍、大企業でしか扱えなかった。しかし、マクルーハンは電気の時代の考察を経て、身体と神経を拡張しきったヒトにコンピュータが及ぼす影響を予測し、「兵器」「オートメーション」の章を追加したと考えてみたい。
機械の線条性と電気の同時性との相克
マクルーハンは「兵器」の章で、遠近法による線条性の強調が銃腔に旋条をもつ銃を生み出し、銃弾が一直線に発射されるようになったと指摘する。そこでは対象をしっかり見て、狙って、引き金を引くスキルが必須とされる。遠近法や旋条を持つ銃が示すように、機械の時代にはひとつの視点からよく見ることが重要であった。しかし、電気の時代には銃の運用方法が変わる。対象を一対一で狙うのではなく、複数の自動銃で「砲火帯」をつくり、銃弾を面に展開して対象をなぎ倒していく方法になる。電気の時代には、銃を持つヒトは何も狙うことなく銃の引き金を引き続ければいいのであって、狙撃手のような特別なスキルは要らない。ただ引き金を引くという行為を続けるだけで、銃はその用途を簡単に遂行できるようになったのである。
兵器の章において、第2次世界大戦での銃の使用例が示す電気の時代の症例は、瞬時に情報を世界に届けるというテレビの同時性とは異なっている。並べられて砲火帯をつくる銃は、線条的な弾丸を発射するという役割を変えることなく、運用方法によって同時性を演じているにすぎない。
文字文化は、いまでもなお、産業上の機械化のあらゆるプログラムの基礎であり、規範である。が、同時にそれは、機械化された社会の維持に不可欠な機械的断片的鋳型の中に、それを利用する人間の精神と感覚を閉じ込めてしまう。機械的技術から電気的技術への移行が、われわれすべてに傷を負わせ、痛い思いをさせるのはこうした理由からである。その機械のテクニックを、力に限界があるままに、われわれは長いあいだ武器として使ってきた。電気のテクニックは、まるで明かりのスイッチを切るように、一瞬にしてすべての生命を終わらせるのでなければ、攻撃用兵器としては使えない。機械と電気の2つの技術を同時にかかえて生きていくのが、20世紀に独特のドラマである。マーシャル・マクルーハン『メディア論』
銃の運用方法の変化が示すのは、マクルーハンが『メディア論』で繰り返し指摘する、機械の線条性と電気の同時性の戦いである。けれど、銃の場合は線条性の運用を変えた結果、「まるで明かりのスイッチを切るように」引き金を引くと、目の前のすべての生命を瞬時に終わらす銃弾の帯が生まれているというところが重要である。狙撃手のスキルから抜け出せない者はこの変化に対応できずに、砲火帯で蜂の巣になってしまう。マクルーハンが『メディア論』の至るところで指摘するように、同時性が線条性を侵していくのが20世紀特有のドラマであった。
しかし同時に、自動銃の砲火帯のような線条性を束ねることで、同時性のような効果が生まれることも起きていた。マクルーハンは兵器の章で、線条性を電気の同時性で補強するハードウェア重視の19世紀寄りの20世紀ではなく、同時性を電気の線条性でつくりだすソフトウェア重視の21世紀寄りの20世紀に足を踏み入れたといえる。
マクルーハンは機械文化の側で長年過ごしたため、電気の同時性が機械の領域を侵してくるのにいち早く気づき、カナリアとして鳴き続けた。その電気の同時性とは、テレビが端的に示すように、地球上のヒトに情報が同時に届けられることを意味する。しかし、自動銃の砲火帯が示すのは、運用方法によって線条性が同時性を偽装できるということである。
自動銃は機械の線条性を電気の同時性のように運用する試みであったが、コンピュータは電気の同時性を機械の線条性に基いて運用する。コンピュータは電気を線条的なものとして扱い、ヒトの認知を超えた速度で、情報を組み換えながら同時性をつくりだす。対して、映画は写真の平面という同時性を、ヒトの認知のスピードに合わせて線条化し、動きをつくりだす。そして、映像ディスプレイとしてのテレビは、映画と同じようにヒトの認知に合わせたものであると同時に、コンピュータと同じように走査線という線で面の同時性を偽装しているがゆえにコンピュータとの相性がいいという、まさにマクルーハンが巻き込まれた機械と電気の争いの中心に位置する装置なのである。ヒトの認知を超える高速の線条性で同時性を偽装するコンピュータは、機械と電気の合いの子的な存在の電子的ディスプレイ装置と組み合わされ、はじめてヒトとリアルタイムでコミュニケーションするのに必要な認知レベルに落とし込まれるのである。
ボタンがもたらしたヒトの行為の最小化
コンピュータは同時性を偽装しながら、情報を次々につくりだす。電気時代の「兵器」として、コンピュータは自動銃の砲火帯のように、夥しい情報をヒトに一斉掃射している。コンピュータは線条性と同時性とを併せ持つ点で、機械の線条性を電気の同時性が増強するだけの20世紀特有のメディアとは異なるのである。そのコンピュータが、ヒトを「オートメーション」のシステムに組み込んでいく。
機械的システムの場合は、けっしてこうはいかなかった。動力とそれによっておこなわれる仕事とは、手とハンマー、水と水車、馬と荷車、蒸気とピストン、どの例をとってみても、常に直接的な関連をもっていた。電気は、この問題に奇妙な融通性をもちこんだ。マーシャル・マクルーハン『メディア論』
機械の時代以来、ヒトの手が担う複雑な行為は、ボタンを押すという単純なものに代えられてきた。その最たる例が、カメラのシャッターボタンである。ひとつの視点から描かれる遠近法による絵画のスキルを、カメラはシャッターボタンを押すだけで実現できる。何事もボタンを押せば行為が成立する。ヒトの拡張はボタンを押すという行為とともに起こり、ヒトの行為はボタンを押すという行為に最小化されていった。ボタンを押すという行為に最小化されたからこそ、ヒトの行為は機械とともにあるところに遍く拡張していき、その結果として、ヒトの身体が地球全体に拡張することになったのである。
ボタンを押すというヒトの行為の最小化を考えるために、技術哲学者のデービス・ベアードが『物のかたちをした知識』の中で取り上げた、化学の分析機器に関する1954年の広告を参照してみたい。その広告には「ボタンを押す指、考え込む顔、さらにぐっと考え込む顔」という3つのアイコンが出てくるが、それぞれ次のような意味を持っている。
ボタンと指のアイコンは「押しボタン式の操作を示します — 人為的なエラーは最小限」と言われている。考え込む顔は、「単純で定型的な人間による操作 — 人為的なエラーはあまりありません」、ぐっと考え込んだ顔は、「技能、注意、判断を必要とする操作 — 人為的エラーに陥りやすい」とある。機器に仕事をさせれば、簡単になり、人為的ミスに陥りにくくなる。「機器によるエラー」の可能性については言われない。機器は客観的な理想をもたらす。デービス・ベアード『物のかたちをした知識』
押しボタン式の操作の場合は、そのはじまりにしかヒトの行為を必要としない。あとは機械やコンピュータが正確に行為を遂行して、「客観的な理想」をもたらしてくれる。その際、身体が機械に与えるノイズを最小限にするために、ヒトの行為はボタンを「押す」「押さない」というかたちでバイナリー化されている。しかし、そこに融通性はない。ボタンはメカニカルなモノの繋がりに接続し、ひとつのことが行われるだけである。そこでは、電気によってモノとモノとのあいだに「奇妙な融通性」がもちこまれる。この融通性がヒトとモノのあいだの線条的な因果関係を壊す。とはいえ、そこに同時性が生まれるわけではない。ヒトとモノのあいだの物理的繋がりが、直線的な因果関係から放射状に伸びるようなものに変化し、因果関係が曖昧になり面として拡がるようになった。モノのつながりの因果関係の曖昧さから生じた「奇妙な融通性」は、機械の時代から電気の時代へと変化するために決定的な変化をもたらすことになる。
電気によるオートメーションの特徴は、すべて、われわれ自身の手がもっているような、あらゆる目的に使える手工芸的な融通性に回帰する方向にある。マーシャル・マクルーハン『メディア論』
「奇妙な融通性」とボタンの組み合わせは、自動銃の砲火帯と同じようにスキルを消失させる。それはヒトの「手」が必要なくなることでもある。ヒトの手でも何でも、ただボタンを押せる、引き金を引ける何かがあればいい。そこにコンピュータが現われ、ヒトをオートメーションのなかに組み込んでいった。
複雑な行為を遂行するため、コンピュータはヒトに再び「手」を与える。ヒトの手は相変わらずボタンを押すだけであるが、かつて手が担っていた複雑な行為が、その先で可能になる。コンピュータと結びついた行為の複雑さは、ヒトの手の複雑さを超えて、あらたなスキルをつくりあげる。コンピュータの超高速の線条性が、ヒトの手とモノとの同時的で有機的な関係を模倣し、ヒトの手による表現はもちろんのこと、ヒトの手ではできないような表現をつくりだすことを可能にしていく。
しかし、コンピュータはヒトの手そのものを求めているわけではない。コンピュータの線条性は、ボタンを押すという最小化した行為を求めているにすぎない。コンピュータによって様々な目的を実現するには、ヒトの手が培ってきた行為の複雑さをリセットして、その行為を最小化するのが適しているのである。
神秘性を剥ぎ取られた「数」という素材
ヒトの最小化した行為がコンピュータと結びつけられ、あらたな行為が次々と生まれていく理由は、コンピュータが「数」を扱う装置であることに求められる。コンピュータでは映像、音響、テキストといったあらゆる表現が「数字列」として示される。すべてを「数字列」から考えることで、コンピュータを表現の道具ではなく素材と捉える必要があると指摘した久保田晃弘は、そのような考え方を「デジタル・マテリアリズム(唯物論)」と名付けた。そして、久保田は「数」について次のように書く。
数という素材が持っている重要な特徴の一つに「形式からの独立性」があります。いいかえれば、数は数のままでは表現形式が決定しない —— つまり「表現の不確定性原理」です。これまで用いられてきた伝統的な素材のほとんどは、形式と密接に結びついていました。立体に適した素材、平面に適した素材、視覚表現に適した素材、聴覚表現に適した素材と、表現形式と素材のカテゴリーの間には、強い相関がありました。久保田晃弘「Design 3.0:デジタル・マテリアリズム序論」
数があらゆる表現形式に明確に結びつくのは、コンピュータ以降のことである。同じ数字列が、文字にもなれば音にも画像にもなることは、コンピュータ以前には考えられなかった。しかし、黄金比などが示すように、数はもともと様々な表現の基礎にあり、表現同士を結びつける存在であったといえる。マクルーハンは「数」について次のように書いている。
ボードレールは「数は個人の内部にあり、数は陶酔である」と言った。そのとき、ボードレールは、数がバラバラの単位を相互に関連づける触手あるいは神経組織であることを、真に直観していた。だからこそ、「群衆のなかにいる喜びは、数の増加を喜ぶ気持ちを神秘的に表している」わけだ。言い換えれば、数は話されることばと同じで、たんに聴覚的で反響的であるだけでなく、それは触覚を拡張したものであるから、そこに起源がある。統計では数字を集めたり束ねたりするが、それは現代の洞窟画あるいは指頭画(フィンガー・ペインティング)とも言うべき統計家たちの図表を生み出す。マーシャル・マクルーハン『メディア論』
「数がバラバラの単位を相互に関連づける触手あるいは神経組織である」からこそ、コンピュータ内で扱う数は「形式からの独立性」をもつのだろう。ヒトは数を単位につい結びつけてしまうが、コンピュータは数をバラバラのままで保持できる。言い換えれば、コンピュータは数を神秘性なしで扱えるといえる。
マクルーハンは、「文字を使わないデジタル・コンピューターはいろいろの数字(十進数字)の代わりに『イエス』と『ノー』(二進数字)を用いる。コンピューターは輪郭に強く数字に弱い」と述べているが、これは間違いだろう。久保田が指摘するように、コンピュータは「数字に弱い」のではなく、数字列から神秘性を剥ぎ取り、単に素材として扱うのである。それゆえに、数は「表現の不確定性原理」のもとに置かれることになる。そして、電気の「奇妙な融通性」と数字列の「表現の不確定性原理」とが組み合わされて、「あらゆる目的に使える手工芸的な融通性」が生じる。ここで「手」がでてくるのは、数を指折り数えることに深い関わりがある触覚が拡張したものだからである。
コンピュータに委譲される手の行為
コンピュータのなかで数字列を操る「手」は、同時に「手」に操られる素材でもある。コンピュータは内に数字列という再帰的な「手」をもち、外にヒトの手をもつ。ヒトの最小化した行為を遂行する手は、数字列の再帰を停止させて表現形式を確定させるために、コンピュータが求めるものである。しかし、ヒトは直接的に表現を確定するわけではない。ヒトはコンピュータを操作しているのではない。久保田はそれを「委譲」と呼んだ。
コンピュータとのコミュニケーションは、操作(コントロール)するというよりもむしろ「委譲する」という感覚に近い。委譲というのはあまり聞きなれないことばだが、英語ではデレゲーション(delegation)、何かの処理を他のものにまかせてしまうことをいう。 コンピュータのインターフェイスも、操作ではなく委譲であると考えるとずっとわかりやすくなる。ファイルを移動するように委譲する、図形を変形するように委譲する、メールを送るように委譲する……委譲する先はアルゴリズムが書かれたプログラムコードである。GUIのボタンをマウスでクリックすること、キーボードで押すこと、スライダーを動かしたりツマミを回すこと、それらはいずれもアルゴリズムに対するトリガーである。そのこと自体によって、音が直接生み出されたり変化するわけではない。久保田晃弘「ライブコーディングの可能性」
久保田のこの指摘は、ヒトの行為の最小化と合わせて考える必要がある。ヒトは行為の最小化を受け容れながら、委譲先の行為を豊かにする選択をした。その結果としてGUIが生まれたと考えられるが、久保田はこれに批判的である。GUIは複雑で豊かな身体のはたらきを、単に見て指さす行為にしてしまっているからである。
しかし、ヒトの行為を最小化していくことは、ヒトの行為の曖昧さや間違いをできるかぎり排除するためでもある。まずヒトの行為のノイズを最小限にして、そこからヒトとコンピュータがあらたな行為を生成できるかどうかを試す場として、GUIを捉えるのがいいだろう。これからインターフェイスがどうなっていくかはわからないが、ひとまずの実験の場として、行為の複雑性を減らし、ヒトをコンピュータに合わせたのがGUIということである。GUIはヒトの行為の曖昧さを排除しつつ、ヒトから行為を委譲されたアルゴリズムが電気の力で面に広がった「奇妙な融通性」をさらに重ねていき、あらたな行為をつくりだしていく。
GUIでの指差し行為によって、ヒトの行為はコンピュータに委譲され、その委譲された行為の処理がインターフェイスを介して遂行される。ここでヒトは、トリガーとして機能しているのみである。「のみ」であると言ってしまうとネガティブに感じるかもしれないが、「のみ」であることが、コンピュータ以後のヒトのあり方として重要である。
ヒトは複雑な行為によって脳の演算を補い、物理世界と関わってきた。その複雑な行為によって、モノのインターフェイスで演算が直接行われ、物理世界での身体とモノとの関係を最適化していた。その演算部分の履歴がコンピュータに委譲されることで、今度は行為を最小化することが可能になった。委譲される側のコンピュータは、多様な行為を用意するために、物理世界でヒトとモノとのあいだに生じていた行為のアルゴリズム化を求める。久保田は手とアルゴリズムの関係について、次のように書く。
アルゴリズムは、いわば人間の「手」に代わるものです。手の代わりにアルゴリズムという「スキル」が、数字列という素材を操作し、そこから生み出される表現を変化させます。だとすれば、アルゴリズムによって生成される表現にとって最も本質的な特徴は「手を使わない」ということです。芸術表現やものづくりにおいて、手はこれまで、人間の貴さや醜さ、素晴らしさや無能さを象徴するシンボルと見なされてきました。しかしアルゴリズムはその「手」というシンボルを消去し、それはコピーによって社会的に共有できるのです。だとすれば、デジタルデザインとは、ポスト手業、さらにはポスト人間時代のデザインのことに他ならない、といえるでしょう。久保田晃弘「Design 3.0:デジタル・マテリアリズム序論」
コンピュータのアルゴリズムは手に代わり、インターフェイスは手の行為を最小化していく。それは、今まで複雑な行為によってヒトの進化を支えてきた「手」の履歴を、一度消去してしまうことである。このように書くと、スマートフォンで手や指を多く使っているではないかと言われるかもしれない。しかし、その手や指は「カーソル」の代わりである。ヴァーチャルな指であったカーソルの代わりに、フィジカルな指が使われているにすぎない。これがヒトとコンピュータとの共進化である。
ここが、コンピュータとともにあるヒトのあらたな進化を考える出発点になる。外爆発でも内爆発でも失われなかった手の意味するものが、ヒトとコンピュータとの共進化のなかで生まれ変わっていく流れを考えなくてはならない。ヴァーチャルであろうとリアルであろうと、手は物理世界とのあいだでこれまで蓄積してきた行為をコンピュータに委譲し、一度履歴を消去して、「あらたな手」になった。その「あらたな手」が、ヒトの最小化した行為を遂行しながら、コンピュータとともにあらたな行為をつくりだしていく。
複数の物理世界と仮想世界とをつなぐインターフェイス
久保田はデジタル・マテリアリズムを深めていくキーワードとして「ハッキング」「アルゴリズム」「インターフェイス」を挙げている。「ハッキング」によってアプリケーションやOSの深くに入り込んで、数字を直に扱うこと。数字列をヒトの身体と結びつける、非身体的な「アルゴリズム」を習得することが重要となってくる。そして、最後にくるのが「インターフェイス」である。
最後のキーワードは「インターフェイス」です。インターフェイスといっても、GUIのことではありません。それは、数と知覚、演算と身体、表現と形式、素材と構造、物質と非物質、スキルと社会といった、さまざまな概念や領域をつなぐものです。マーカス・ポップ(オヴァル)は「全てはインターフェイスである」と言いました。確かにその通りかもしれません。だからこそ、そのインターフェイスに対する試作と実装(制作)が、デジタルデザインのガイドラインをつくり出すのです。久保田晃弘「Design 3.0:デジタル・マテリアリズム序論」
インターフェイスとはどこにあるのだろうか。ヒトとコンピュータとのあいだにあると言われる。しかし、その状況は異なり始めているのではないだろうか。ヒトとコンピュータが向き合える平面そのものがインターフェイスとなり、このインターフェイスがさらに仮想世界や別の複数の物理世界とつながっていると考えることはできないだろうか。
ヒトとコンピュータによる情報のやりとりだけで、インターフェイスを捉えることは難しくなってきている。ヒトとモノとの関係が成立する基盤そのものがインターフェイスとして捉えられ、ヒトもひとつのインターフェイスとなり、ヒトとモノとの複数のインターフェイスが水平垂直につながっていき、いくつもの物理世界と仮想世界が現れる。
次回以降、ヒトとコンピュータがつくりだす「あらたな手」とともに、複数の物理世界と仮想世界、そしてインターフェイスについて考えていきたい。
インターフェースは……道具や機械にあなたの意志を伝えるための言語であるリチャード・ストールマン
主体なき世界のモノたち
「ユーザーインターフェース」や「ヒューマンインターフェース」といった言葉は、人間が主体である前提で使われてきた。対象となるのはモノであり、主体である人間は「インターフェース」を通じてモノをコントロールする。だから人間の目的から、モノのインターフェースが設計される。ここには、人間が主体でありモノが対象で、人間はモノではないという暗黙の了解がある。
この前提条件は、わたしたちの知性を根拠としていた。しかし、知性を判断するのも、また知性である。主体というものは、その知性を越える存在を想定した途端に、あっさりと失われてしまう。人間の主体が奪われるのを、悪夢かディストピアのように感じるとしたら、それは単にわたしたちが今持っている想像力のせいかもしれない。その前に、主体を想定せずにいられないことが、わたしたちの知性の限界という可能性もあるのだ。
モノであるコンピューターは、「人間を模倣する」という基本コンセプトに則り、現在まで人間の知性に追従してきた。いくつかの領域では、すでに人間の知性を越えており、わたしたちは日常生活における多くの判断を、人間ではなくコンピューターに委ねている。そして、相手が人間かモノかを気にもせず、自分が「もっともらしい」と思えることを信用している。
だから、モノが人間になるのでも、人間がモノになるのでも、どちらでもいい。主体なき世界では、人間とモノの区別が難しくなる。「トランスヒューマン」や「ポストヒューマン」といった状況は、人間の知性を超えたモノによって、わたしたちが自己更新されることにほかならない。きっとこれからは、今まで以上に「人間とは何か」を考えさせられ、「どんなモノをなぜつくるか」が問われることになる。これらの問いは、やがて同じ答えに至るだろう。
コントロールからコミュニケーションへ
今回目指したいのは、トランスヒューマン/ポストヒューマン時代にも変わらないインターフェース設計の基礎を見つけることである。そのために主体を置き去り、人間がモノを「コントロール」するという発想をやめることから始めたい。つまり、人間の思惑からではなく、モノとの「コミュニケーション」から、インターフェースについて考えてみたいのだ。そうすることで、商品や製品といった概念にとらわれず、存在としてのモノを前提に、インターフェースと向き合えるのではないかと考えている。
今後もテクノロジーは発展していき、情報環境は多様になり、身体や意識は拡張され、モノとの関係も変わり続けるだろう。インターフェースは空間へと広がりながら、マルチモーダルになっていくに違いない。それでも変わらないのは、わたしたちの身体や感覚のモダリティではないだろうか。
わたしたちは、これからも自分の身体を受容器にして、さまざまなモノとコミュニケーションを続けていくはずである。そして、未来のインターフェース設計も、GUI(グラフィカルユーザーインターフェース)が紙媒体の形式や電子機器の操作盤を流用したように、過去の経験を再利用するだろう。
そこまでわかっていても、やはり未来はわからない。わかっているのは、変化が起きるときには、ずっと変わらないものに目を向けるべきだということである。まずは手はじめに、インターフェースという言葉において、今まで見過ごされてきた意味から振り返ってみたい。
インターフェースという言葉の意味
「インターフェース(inter-face)」は「界面・境界・接触面」などと訳される。さらに、これを分解した「inter」には「間・中・相互」、「face」は「面」といった訳語が充てられる。しかし、「inter」には訳語で表現される「空間性・関係性・相互性」のほかに、「一回性・同時性」といったニュアンスも含まれており、これがインターフェースを考えなおす上で重要な意味を持っているように思う。
同じ「inter」を使った単語の「インタラクション(inter-action)」は「相互作用」と訳されるが、この言葉では「トランザクション(trans-action)」と変わりがない。意味の違いから考えてみると、トランザクションの相互作用は、アクション(action)に対するリアクション(re-action)であり、それらが非同期に実行されても構わないが、インタラクションは「一回」のアクションで「同時」にリアクションがなければ成立しない。両者の違いは、時間との関係にある。
この見過ごされた「inter」の「一回性・同時性」という意味は、当然インターフェースにも備わったものである。「直感的なインターフェース」と形容されることがあるが、実世界での対話がそうであるように、本来インターフェースを通じたコミュニケーションも直感的なものである。そしてこの特性は、インターフェースが一方的にコントロールされるものではなく、相互にコミュニケーションするものであることを、改めて示しているのではないだろうか。
インターフェースモデルの変遷
「inter」という言葉が、わたしたちとインターフェースの関係を表していたように、「face」はインターフェースの在り方を表している。これについては、過去にさまざまな「ユーザーインターフェース」のモデルが唱えられてきた。
最初に出てきたのは「前認知科学的なモデル」で、人間とコンピューターの間に平板のインターフェースが置かれた素朴なモデルであった。これはディスプレイのような平面を想定しているため、今の一般的な認識に近いかもしれない。またこのモデルでは、人間もモノも同じインターフェースを通じてコミュニケーションすると考えられている。
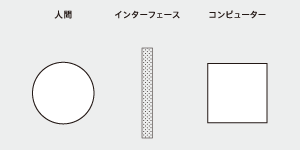
次に出てきたのが、先ほどのモデルを発展させた「メンタルモデル」である。これは利用者のメンタルモデルと対象であるコンピューターのシステムイメージをすり合わせるモデルで、さらに設計者のデザインモデルも加わり発展していった。今も比較的信じられているこのモデルで合意されているのは、両者が客観的事実として観察できること、そして主体である人間の認知を想像しながら、工学的にユーザーインターフェースを設計するというプロセスである。
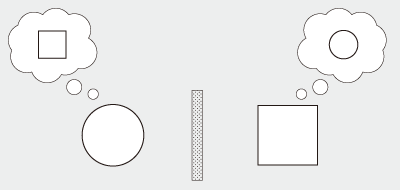
しかし、設計者は利用者の「メンタルモデル」に沿うために、利用者に妥当な「システムイメージ」を提供しなければならないし、その「システムイメージ」は利用者の「メンタルモデル」によって決められる。こういった他者の意識のなかで自己言及するような作業が続くと、下図の「恐怖の反復」と呼ばれる矛盾が起きる。
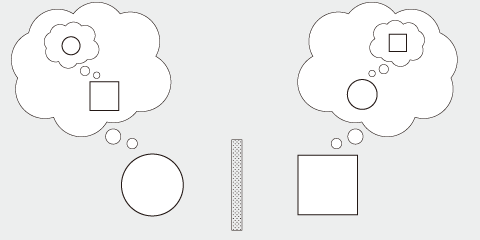
メンタルモデルは、設計において妥当なモデルだが、終わりなき勘繰り合いの構造が、コミュニケーションとして不健全だったのかもしれない。この理由によって、メンタルモデルは一度退けられた過去がある。
その後に唱えられたのが、人とコンピューターの間に存在する空間をインターフェースとした、「空間モデル」であった。
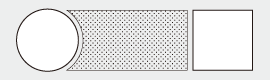
身体とインターフェースの関係
「空間モデル」が優れていたのは、わたしたちの身体の形に沿って、インターフェースが可塑性を持っている点である。これは人間の身体が原型となり、インターフェースの形が決定されるという、当たり前のことに気づかせてくれる。
たとえば、ディスプレイの「ランドスケープモード」の横幅が長いのは、人間の目が横並びになっていることと関係している。その名のとおり、これは風景画に由来するフォーマットで、インターフェースでもウィンドウシステムのように、向こうにある対象を見る「窓」として利用されてきた。
一方の「ポートレートモード」は、人間の体型に合わせて、ディスプレイの縦幅が長い。これは自画像のためのフォーマットであり、インターフェースとしては自らを確認する「鏡」となる。そのときわたしたちは、インターフェースに映し出される表面そのものを見ている。
また、タッチパネルの操作を考えてみると、わたしたちの指はディスプレイに触れているが、顔はディスプレイを眺めるのに十分離れており、腕はデバイスを支える構えになっている。このように、身体のそれぞれの部分がインターフェースと一定の距離を保ち、空間をつくることによって、わたしたちはモノと思うように関係できる。こうしてインターフェースの諸条件には、わたしたちの身体の大きさや形が反映されているのだ。
わたしたちの身体の特徴や機能に合わせてインターフェースが設計されるように、わたしたちもインターフェースによって行動を決められることがある。検索システムを使うときを例にすると、わたしたちはシステムに最適なクエリを考え出し、返されるサジェストに期待しながら命令を考える。そういった経験を積み重ねながら、コントロールしているつもりのシステムに身体が最適化されていく。わたしたちがタッチパネルというインターフェースに触れているとき、同時にパネルもわたしたちの身体をインターフェースにして触れているのだ。
身体とインターフェースの関係を考えていくと、わたしたち人間も対象になる可能性にさらされていることがわかる。わたしたちはモノを自分たちに同調させて利用していたが、気づかないうちにわたしたちもモノへと同調していた。これはわたしたちとモノの間で、主体が入れ替わるということではない。わたしたちもモノと同じようにオブジェクト(対象)なのだ。
対話におけるインターフェースの観察
わたしたちとモノは、いずれもオブジェクトであり、インターフェースを通じてコミュニケーションをする。この単純なモデルのモチーフとなっているのは、人間同士の対話である。インターフェースは緩衝材のように、モノとのコミュニケーションを、より人間らしくする役割を果たしてきた。
わたしたちが実際に人と会ってする対話では、互いの顔がインターフェースとなる。相手の顔を見て同一性を確認した上で、表情や声のトーンを頼りにコミュニケーションを調整している。
それが電話となると、受話器がインターフェースとなり、お互いの顔を確認できない。そこで同一性を確認するのは、相手と電話番号の照合であり、それを補うために名乗り合う。表情が伺えないので、発話内容や声のトーンから察しながら、対話を続けていく。つまり、わたしたちの気持ちは、インターフェースとしての受話器ではなく、受話器越しの相手に向いている。
わたしたちはインターフェースを通じて交信しながら、実際にはその向こうの対象と交流している。そこでコミュニケーションが成立するのは、対象の知性を信頼しているからだろう。その信頼が大きければ大きいほど、インターフェースは透明化する。これは没入というよりも、すこし前の現実がより「もっともらしい」ものへと更新される感覚に近い。
逆に、コミュニケーションする相手の様子がいつもと違うとき、わたしたちは顔や受話器といったインターフェースに注意を向ける。コミュニケーションの信頼が保証されない事態になって、はじめてインターフェースはその姿を見せるのだ。これがインターフェースの見え隠れする質感になっている。
そう考えていくと、先ほど見てきた「ユーザーインターフェース」のモデルのように、インターフェースは二者の間に置かれてもいないし、共通で単一のインターフェースを通じてコミュニケーションしているわけでもない。インターフェースは、コミュニケーションにおいて指向すべき「ファサード」のようなものとして、それぞれのオブジェクトに備わっている。
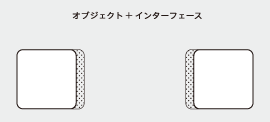
わたしたちが対象のインターフェースを見て、そこに触り、そこに話しかけるように、わたしたちも自分のインターフェースを通じて見られ、触られ、話しかけられているのだ。
インタラクションの二重性
わたしたちとモノの関係における「外的なインタラクション」について、ここまで考えてきた。そこでは、わたしたちも自らのインターフェースを通じて、対象となる可能性を秘めていた。オブジェクトとしてのわたしたちは、まわりから影響を受けながら、すこし前の自分と違うものに変わり続けていく。この自己生成的な活動を、ここでは「内的なインタラクション」と呼ぶことにしたい。
この内的なインタラクションは、インターフェースによって隠蔽される。コンピューターがどんな処理をしているかを完全に把握できないように、わたしたちも相手の表情から心の機微まで完全に読み取ることはできない。もっと言うと、自分の意識がどう変化したのかは、本人さえもわからないだろう。
こうした人間とコンピューターにおけるインタラクションの二重性を、人工知能の分野の研究者であるテリー・ウィノグラードは、オートポイエーシス理論の「構造的カップリング」に重ね合わせた。構造的カップリングとは、環境として影響を与え合う相互依存関係のことである。それらはいずれも閉じた系なので浸透し合わず、「膜」を敷居にして撹乱し合う。そこでは、構造的な同一性が両者の連結の強さとなる。
コンピューターなどのモノが構造的であるように、わたしたちの身体も器官が組織化された構造だと言えるだろう。わたしたちとモノは、インターフェースという「膜」を通じてインタラクションしながら、構造的な同一性に向かっていく。そして、このときのインタラクションの契機となるのは、わたしたちの「行動」である。
言語/行為パースペクティブ
これまでユーザーインターフェースの設計者は、利用者の行動を考え、ナビゲーションを問題にしてきた。たしかに利用者は、インターフェースを通じて行動しているように見える。しかし、自分が利用者になったときのことを考えてみると、その場から動かず利用しているため、行動している意識もナビゲートされている意識もない。むしろ行動せずに利用できることが、テクノロジーの利便性になっている。
したがって、こう言いなおさなくてはならない。わたしたちはインターフェースを通じて行動しているのではない。わたしたちは動かずして、自分たちの行動をインターフェースに「委譲」している。目的を実行するときだけでなく、自己との対話や、普段意識すらしない考えや思いまでもが、インターフェースに映し出され更新されることで、意味を与えられて自分の行動になる。つまり、インターフェースにおいてわたしたちは、「言語を通じて行動する」のだ。
ウィノグラードは、この観点を「言語/行為パースペクティブ」と呼んだ。利用者が「情報を処理して意思決定をおこなう」のではなく、「言語を通じて行動する」というアイデアは、人間とコンピューターの関係に言語行為論を応用したものであった。言語による命令や約束は、相手の行動を促すだけでなく、自らの行動にもなる。だから、ここで使われる「言語」とは、言葉の問題ではなく、意味の問題と考えた方がより正確だと言える。そして、インターフェースに委譲している行動が言語によるものならば、その「言語」の性格を明らかにすることが、時を超えたインターフェース設計へと向かうことになるはずである。
わたしたちが対話で使うのは、自然言語である。それだけでなく、意識のなかで自問自答するときも、自然言語を使っている。しかし、ほとんど意識していない領域では、考えたり思ったりすることを言語化していない。カップを口元に持っていきコーヒーを飲むとき、わたしたちは脳内で実況しているわけではない。今こう言い表すことができるのは、ただ事後的に翻訳しているからである。
先ほどの「構造的カップリング」を援用すると、共通言語を持つということは、同じ言語を使うことではなく、言語を生成する構造が似ているということになる。インターフェースの言語であれば、わたしたちの身体のモダリティに合わせて構造化されていることが望ましい。その観点に立ち、インターフェースで使われてきた言語に注目して、その特性を分析してみたい。
クレオール化するインターフェース
古くからユーザーインターフェース設計で使われる文法に、「名詞+動詞」パラダイムというものがある。これはGUIの「See & Point(見て指さす)」操作に合わせた設計手法であり、この操作はわたしたちの行動から発案された。何らかの行動をするには、対象を見つける必要があり、対象を見つけるには、その存在を認識する必要がある。だから、名詞によって対象(オブジェクト)を世界から分節して、対象を認識するのだ。
動詞は、わたしたちの行動を委譲するために、オブジェクトへ意味を付与する。そのなかでも「探す」とか「学ぶ」といった動詞は、わたしたちの「内的なインタラクション」なので、オブジェクトとして外部化できない。わたしたちは最初から何かを探しているし、何かを学ぼうとしている。これらの動詞が駆動するオブジェクトは、わたしたちの身体なのである。一方、「買う」とか「送る」といった動詞は「外的なインタラクション」だから、外部に選択肢としてオブジェクトが与えられなければならない。
今も「名詞+動詞」パラダイムが有効なのは、わたしたちの「リテラシー」を元に構造化されているからだろう。リテラシーとは目と手を使った能力のことで、かつては「読み書き」の能力を指していたが、今は「見て指さす」コンピューターリテラシーも含まれる。プロダクトデザイナーのトーマス・D・エリクソンは、こうしたインターフェースの言語的性格が「ピジン言語」や「クレオール言語」に似ていることを、早くから見抜いていた。
異なる言語を使う者同士は、ポインティング(指さし)やジェスチャ(身ぶり)を多用してコミュニケーションを成立させる。したがって、会話の内容も「あれを取って」といった具合に、オブジェクトを指さし環境から分節して、簡単な動詞を添える。名詞に複数形は使わず、必要な場合は同じ単語を繰り返す。動詞は現在形のみで、過去形は使われないなどの特徴がある。
このように、異なる言語を使う者の間で意思疎通するときに、自然発生する言語を「ピジン言語」と呼ぶ。それが母国語として定着したものが「クレオール言語」である。これらが興味深いのは、話せない者が上達するよりも、先にリテラシーが高い者が退行して、言語が形成されていくところである。
インターフェースの言語的性格の未来
さまざまなクレオール化は人々を〈関係〉にみちびき入れるが、それは普遍化のためではない。これに対して「クレオール性」は、その原理において……あらゆる一般化へと退行していくのだ —— 程度の差こそあれ無邪気に。エドゥアール・グリッサン『〈関係〉の詩学』
エリクソンは、ピジン言語やクレオール言語の特性が、マッキントッシュのGUIと共通していることを指摘した。これらの言語は、リテラシーが低い相手の「覚えやすさ」を必須条件としており、それが「記憶せずに操作できる」というGUIのコンセプトと重なっていたのだ。
たしかに、インターフェースはピジン言語のように退行しながら、最終的にクレオール言語として定着したように思える。インターフェースを使う目的は限定されるため、語彙がすくないのも似ている点だろう。ある言語で会話ができなくても、その言語のメディアをある程度利用できるのは、そんな理由かもしれない。
わたしたち人間を主体にして、外的なインタラクションだけを観察していると、世界は多様化していくようにしか見えなかった。しかし、それに伴った内的なインタラクションによって、わたしたちはモノに同調しながら、インターフェースというクレオール言語を習得していた。知らず知らずのうちに、わたしたちはインターフェースを通じて混血していたのだ。
コンピューターがわたしたちより流暢に自然言語を話せるようになっても、今まで育んできたインターフェースは使われ続け、その言語的性格は変わらないはずである。なぜなら、わたしたちが身につけてきたのは、デザインされた道具の利用方法ではなく、言語のリテラシーだからだ。
この先、わたしたちやモノの立場は、ゆっくりと、そして確実に変わっていく。インターフェースの言語もテクノロジーと融合して、徐々に変わっていくだろう。それはもちろん退行へと向かっていく。ただし、これを退行ととらえてしまうのは、まだ人間を主体にしているからかもしれない。何よりもすぐに変えなくてはならないのは、わたしたちが「世界をどう見るか」という観点なのである。
現代の情報技術が可能にした現実空間
キュレーターのマリサ・オルソンは、ポストインターネットという用語によって「情報空間」と「物理空間」の境目が曖昧になった社会状況を指し示した。そして、これまでポストインターネットアートの多くは、「情報空間」と「物理空間」という二つのレイヤーの移動を問題にしてきた。ポストインターネットアーティストは、その境界を横断する。しかし、物理空間を3Dスキャンすることで情報空間へと移行させることや情報空間を物理空間へ反映させようとする行為は、端的に言えばサイバーパンク的な想像力の延長線上にあり、過去の想像力を現代の技術的環境で実現しようとするものに過ぎない。それらは想像力のレベルで、何も刷新していない。
僕の考える現代社会の特徴は「情報空間」と「物理空間」の境目が曖昧になったというよりも、むしろ「情報空間」と「物理空間」が入れ子状にフィードバックループを形成しながら相互生成することで、「現実空間」を仮設的に瞬間的に構築している点にある。僕たちは事後的に「情報空間」と「物理空間」を区別するが、実際は持続する一つの「現実空間」を経験している。
僕たちは「現実空間」を、ユークリッド幾何学で記述されるような客観的かつ数量的なものとは考えていないし、主体の心理的な体験空間であるとも考えていない。「現実空間」は「情報空間」の部分的かつ瞬間的な現勢化であり、現勢化するや否や未だ現実化していない問題提起的な潜在的「情報空間」として再度問い返される。「物理空間」は即座に「情報空間」の素材として可変的かつ流動的な課題へと変化する。そしてまた、僕たちは「情報空間」を別の仕方で「物理空間」へ転用しようとする。そのループの中で、僕たちは仮設的な「現実空間」を体験している。
近代以前から固定的に考えられてきた「主従関係」や「一と多」などの二項対立は、主と従を繰り返し反転しながらその二項自体が変化しつづけることで、確定的な定点という地位を剥奪されている。僕たちは観察する主体でもなければ、行為する主体でもない。主としての僕たちが従としてのTwitterやFacebookのタイムラインに情報を追記することもあれば、主としてのTwitterやFacebookのタイムラインが従としての僕たちの身体を動かす時もある。主と従は常に入れ替わりながら相互に変化をもたらす。言うなれば、映画のカメラ視点は常に奪い合いの状態にある。
複数の虚構と実在性
このような構造上の変化は、IoT(Internet of Things)とブロックチェーンの融合によって電気機器が自律的に人間や他の電気機器に働きかけるようになれば、より明確に可視化されるだろう。例えば、必要な食材のリストを登録すれば、冷蔵庫が無くなりそうな食材をセンサーで感知し、ブロックチェーンを用いて自律的に取引を行うことで、食材を常に一定の状態に保ったり、過去のショッピングデータや健康状態のデータをネットワークから自律的に取得し、おすすめ商品を取引したり健康状態を補完するための食品をリストに自動追加するかもしれない。モノたちは観察される対象ではなくなり、自律的なユニットとしてコミュニケーションをし、取引を行い、動き出すだろう。現在でさえ不可視な部分が多いとはいえ、構造上は「物理空間」と「情報空間」が相互生成する中で、無数の自律的なモノたちがうごめく「現実空間」の実在性を経験しているのだ。
ポストインターネットアートが社会的に影響力を持たず、Pokémon GOが一世を風靡しているのは、Pokémon GOが現代社会の特徴をうまく捉え、「情報空間」と「物理空間」がフィードバックループを形成しながら一つの「現実空間」を生み出しているからであり、人間を主となるプレイヤーとしてだけでなく、情報によって動かされる拡張機械として扱っているからである。時代に対する感度が高いと無条件で考えられている既存のアーティストの方が過去の想像力からの引用に傾倒し、現代社会で起こっているドラスティックな変化に対応できていないのだ。しかし誤ってはならないのは、構造上の転回が先にあって、Pokémon GOはその転回を「拡張現実」として可視化していることである。
「情報空間」と「物理空間」のフィードバックループは、技術的には3Dプリンターによる「情報のモノ化、モノの情報化」やビットコインなど仮想通貨の流行、IoTとブロックチェーンによる脱中心的な分散自律型システム、TwitterやPeriscopeによる個々の虚構制作、あるいは時事的なトピックとしてBrexitやドナルド・トランプの勝利に象徴される。上記の例は「一つ正しい現実と間違った複数の虚構」という環境から、「複数の虚構があり、各々がどの虚構に実在性を感じているか」という環境へと変化したことを示している。
例えば、仮想通貨の流行は、最も流通する貨幣がたった一つの正しい現実であるという常識を崩し、最も共有されている虚構に過ぎないことを示している。そもそも貨幣とは、共有された虚構という特徴を持っており、使用されているから使用できるというトートロジーによって機能している。しかしこの構造上の変化は、第一に貨幣の形式が仮想通貨の登場によって相対化され、僕たちが理論的な水準ではなく実践的な水準で、貨幣の虚構性について理解するようになったことを意味している。そして第二に、各々の虚構を成立させる条件は、各々において異なるということを示している。法定通貨であれば国家の安定性や歴史の蓄積が信頼を担保するだろうし、ビットコインであればデジタル暗号を解読されない為のセキュリティ技術であったり、P2Pでのトランザクションを成立させるブロックチェーンの設計が信頼のプロトコルである。
上記の構造上の変化を、人々が各々に都合の良い虚構を生きるようになったとして非難することは容易であるし、「ポスト真実」の時代と名付けることもできるだろう。しかし「複数の虚構と実在性」という図式は、そもそも「近代社会システム」が格差を隠蔽することで共有されている一つの虚構に過ぎないことを浮き彫りにもしている。近代社会システムは、「自由」という理念が労働力を売り渡すという自由すら内包することで、資本家/労働者という主従関係を隠蔽し、利己的な主体が功利主義的に利害計算することで、社会が調和するという神話によって保たれていたのだから。
世界を認識する枠組みとしての制作
僕たちは、この不可逆な時代の変化を「透明なコミュニケーションによる共同主観的な共同体の再建」という課題で捉えるのではなく、素朴に「差異を肯定」するのでもなく、各々の虚構を継続可能な仕方で制作しつづけることにしよう。現代の環境を考慮した上で、別の仕方で規範性を、継続可能性を、安定性を制作するという課題に挑戦しよう。他者が用意した虚構を消費することでも、そこに参加することでもなく、各々が制作することにしよう。そのために必要な武器は揃っている。僕たちがしなければならないことは、過去の想像力に基づいた表象を描いて年配世代から評価されることでもなければ、構造上の変化を単純な仕方で表象することでもない。それは構造上の問題を、無意識的な領域から意識的な領域へと引き上げ、操作可能性を自覚し、複雑な状況を複雑なまま、様々な仕方で表象することである。
自覚しなければならない問題は、構造上の転回が生じているということだけではなく、それが僕たちの実践において何を変化させるかである。僕の考えでは、第一に「観察から制作へ」と世界の枠組みが変化する。第二に、「人からモノへ」という一方方向の制作の図式は崩れ「人間も含むあらゆるモノたちが同一平面上で相互に制作し合う」ようになる。第三に、近代における制度や文脈を前提にしていたありとあらゆる物事は、僕たちに再定義を要求する。
もちろん「観察から制作へ」という枠組みで世界を捉えていたのは、今日生きる僕たちだけではない。いつの時代であっても科学者にとっての「物理空間」は、リテラルなモノが敷き詰められた場としてだけでなく、様々な複合的な謎に満ち満ちた場として立ち現れているし、工学者にとっての新たな技術は、便利で快適な新しい「商品」としてだけでなく、次なる課題や目的を生み出す「プロトタイプ」として見えるだろう。また美術家にとっての他者の傑作は、ただ美しいだけでなく、次なる挑戦を突きつけるものとして現前している。つまり、彼らにとって現前しているものは〈今ここ〉にあるだけでなく、謎やプロトタイプや課題として即座に過去と未来へ折り返されている。
科学者やアーティストは、合理的に説明できる領域から神秘主義者さながらに、一歩先へと非理由的に飛躍する。徹底的に説明しきること、説明によって理由律の限界を定めること、そこから勇気をもって一歩踏み出すこと。彼らに共通しているのは、消費ではなく制作という視点でモノを見ていることだ。そして、制作という視点でモノを見ることによって、初めてリテラルなモノではない側面が浮き上がってくる。制作者にとって、モノは「商品」という形に画一化、フォーマット化されない余剰を持っている。モノは情報へとデコードされ、再度情報はモノへとコード化される。それも各々が、別々の仕方で。つまり、熱力学第二法則は物理空間上では成立しているにせよ、制作者はモノから無数の潜在的な形式や課題を引き出し、再度別の仕方で時間を折り返すのである。そして、上記の構造上の転回の後、世界を認識する枠組みは、消費から参加へ、そして制作へと、一般化しつつあるのだ。
魅惑するモノたちの声
構造上の転回の後、モノ、情報、人間は水平的な存在論的役割を持つことになる。道具は人間の感性を拡張するものとして人間に対して従属的な立場に留まっていないし、空間は人間の目的によってモノが道具としてネットワーク化した結果生じるものではなくなる。芸術作品は、もはや既存の制度と文脈を前提にするだけでは、その同一性が担保されない。
水平的な存在論の元では、自律的なモノたちが制作、交換、取引を媒介にすることで、主従関係を奪い合いながら局所的なネットワークを形成する。科学者はモノたちが湛える謎に魅惑され、実験室の中で、フラスコや試験管やピペットに囲まれながら、モノの声を聞かされる。モノが人間を動かしているのであって、決して人間が主体的にモノの声を聞くわけではない。身体は動かすのではなく、動かされる。モノはリテラルにそこに実在するだけでなく、無数の声であり、無数の情報であり、無数の虚構を湛えていると同時に誘惑であり、媚態なのである。
また、その声は反復可能な形に整えられ、工学者はその声を工学的に利用可能な水準に安定化するよう呼びかけられる。国際学会は組織を作り、国際的な互換性を高めるために規格化する。情報はアーカイブされ、図書館の一室、あるいはWorld Wide Webの網の上に蓄積されていく。そうして、モノはその機能を、その目的を拡張される。その謎を、その秘密を、人間によって部分的に明かされながら。そして、その結果作られた「商品」「プロトタイプ」「道具」「芸術作品」は、制作者によって再度モノへと折り返され、繰り返し反復しながら差異を生み出し拡張していくのである。
モノの拡張、そして人間の五感の拡張、それは固定的な主従関係にあるのではなく、並行的に協働しながら進化する。何故なら、モノはモノと協働し、相互生成もしているのだから。人類は初めから今の形で自動車を知っていたわけではない。そのようなイデアは存在しなかった。幾何学、物理学、工学、化学、車輪、蒸気機関の発明が、それぞれの潜在的な課題を湛え、それらが出会い、結合することで、蒸気自動車を生み出したのである。さらに、蒸気自動車のもつ魅惑がガソリンエンジンを、その熱を冷ますための冷却技術を、高度な計算が可能なコンピュータや計測装置がより空気抵抗の少ないクールなフォルムを、そしてそれらのモノとモノの結合が、現在の自動車を生み出した。そして、今も自動車は、あるいは自動車を構成する各々のモノたちは、制作者たちを魅惑し、課題を湛え、様々な周辺的な技術と結合しながら、異なる仕方で変容しているに違いないのだ。
近代的な制度と文脈の死
モノは謎として課題や機能だけを仄めかすのではない。ある人は高機能マイクロフォンをその本来の機能を全く無視し、そのマイクロフォンの持つフォルムとイメージから機能や目的を転倒し、神を召喚する棒として神聖化するかもしれないし、ある人は微かに放たれるノイズから、異なるモノとの結合可能性を感じ、その結合によって、〈今ここ〉からは想像もつかないクリアでドープな音を再現するサウンドシステムを生み出すかもしれない。ただの便器が『泉』になるように、異なる空間ではコンビニでのレジ打ちの技能が異なる機能や価値を持つかもしれない。常に余剰に目を向け、転用の可能性を忘れないことだ。
一般的にモノからいかなる情報が引き出されるかは明示できない。自動車のイデアが存在しないように、最終目標や究極の形相は存在しないのだから。そして、車が人間の足を拡張し、電話が耳と喉を拡張しているように、モノは人間の感性を拡張しているが、同時に人間もモノの機能やイメージ、フォルム、目的を変容している。あるモノが別のモノとの結合可能性を湛えていることが、潜在的に可能な空間を切り開き、人間がその媒介となることによって、現実空間における機能や目的が転用され変容していくのである。
かつて人間は、不当に重要な役割を自らに課していた。今や人間は、世界を安定的な定点から観察し消費することはできない。観察するためには、人間を安定的な実在として扱い、記述する地位を与えなければならないからだ。つまり、人間が主であり、動物、植物、無機物が従属する図式を必要とするのだ。同一平面の元、モノと情報と人間は各々が自律的な役割を与えられ、それぞれが主と従を相互に奪い合いながら相互生成している。人間も含め世界を構成する全ての演算子は、観察するという特権的な地位を与えられていない。むしろ、全ては自己制作的であり相互制作的なのである。それは同時にあらゆる領域における定義の再編成を僕たちに要請するだろう。なぜなら、そもそも人間が自らのシステムを「感性」「悟性」「構想力」「理性」と整理し、世界を現象や確定記述の束として扱ったり、その外側をモノ自体として不可知に定めることを通じて、様々なモノの定義がなされていたからである。つまり、人間は不当に特権的な場所から、観察し、定義し、消費して、あらゆるモノたちへ光を注ぎ込んでいる気になっていたのだ。
僕にとって、カンタン・メイヤスーを初めとした相関主義批判の重要性は、現代社会の複雑性が相関主義的な世界認識で捉え切れないのを明示したことにある。近代以降、「芸術作品」は自律的かつ単独的であるが故に普遍的価値を持つというロマン主義的な前提の上に組み立てられている。あるいはその延命装置としての関係性やプロセスに関する「芸術作品」に対して、現代哲学が疑問符を付け、再度「芸術とは何か?」という問いが問い返されていることは、消費から制作へと認識の枠組みをシフトしてしまえば、当然浮上するのである。近代的な枠組みの死は、〈人間の死〉と同時に、「鑑賞する」という特権的な態度の死を意味している。更に言えば、既存の論理に基づく「芸術の自律性」の死を意味している。何故ならそれらは、近代的な制度や文脈を前提としているのだから。
無数の異なる身体のためのブリコラージュ
これからの芸術は、既存の制度や文脈を前提にすることはできない。それにも関わらず、歴史や文脈は悠然と存在している。僕たちにはなにも残されていないように見える。あらゆる物事は既に開発されきっているように思われる。人々は「分からない」というよりも先に、既存のカテゴリーに基づいて「分かる」と発してしまう。あらゆるモノたちが既存のカテゴリーに安易に収められてしまう状況はアートにとって、非常に困難な状況である。その状況下では、奇抜な行動や新しい試みは素朴に存在することができない。僕たちは、素朴な神秘主義者として振る舞うことができない。
しかし本来、芸術作品は「非芸術作品」を経由することでしか芸術作品になることができないのだから、現代のアーティストも説明のつかない未だ認識できないモノへと歩を進めなければならないのは、過去のアーティストと同様である。僕たちはあらゆる行為がカテゴライズされてしまう時代を引き受け、まずは頭をクールに保ち、そして様々なダンスを身につけることにしよう。徹底的に説明すること、そして余剰への愛を捨てないこと。過去の文脈や制度を学び、しっかりと整理すること。シャーマンのように、動物や植物、モノたちとの交流の道を絶たないこと。複数の環世界を横断するための身体を開発することだ。「分かる」ことから「分からない」ことへと進むために。理由律による世界から非理由律による世界へと進むために。
僕たちは神話的世界を再度、現代の技術によって別の仕方で蘇らせようとしている。人間は上からモノたちを観察し、消費する立場を失った。しかし、悲しむことは何もない。むしろ、人間を含めたあらゆるモノたちが能動的に、並列的に、自己制作的に、自律していながら、相互生成、共進化し、協働している世界が開かれているのだから。過去の枠組みで世界を額面通りに認識し、今にも溢れ出しそうな余剰を抑圧しようとする人々はまだ存在するし、これからも存在しつづけるだろう。僕たちは彼らとも協働していけばいいのであって、彼らを敵だと思う必要はない。僕たちは新しく始まったばかりのこの世界で、これからの芸術について思考し、対話し、実践していこうと思う。世界を止めるのではなく動かそう。僕たちは額面通りの世界から、イメージやフォルム、機能や目的、魅惑に満ち満ちた神話的世界へと、別の仕方でもう一度放浪するのだ。この近代化された身体をもって、習慣を解きほぐしながら、あらゆる時代、地域を移動し、あらゆる素材をブリコラージュし、無数の異なる身体を作り上げていくように。
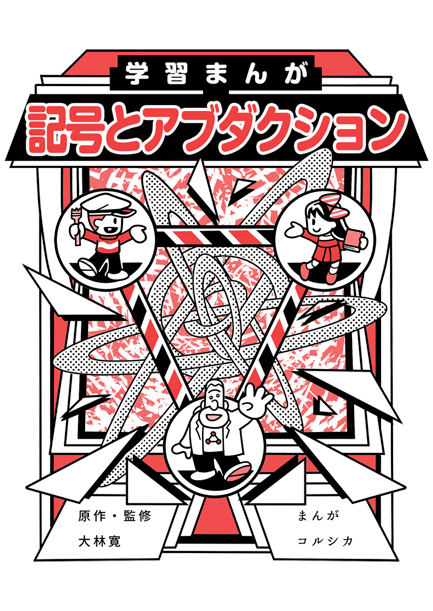
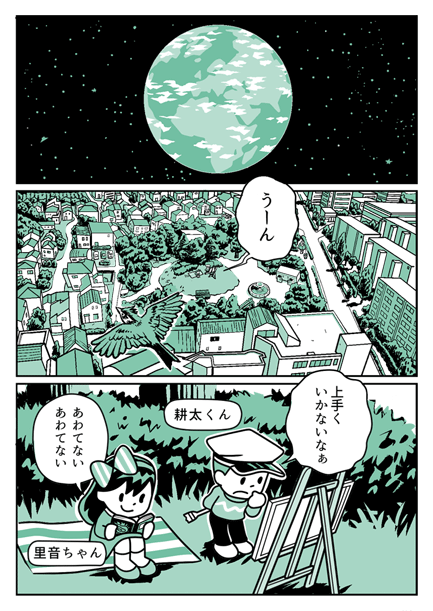
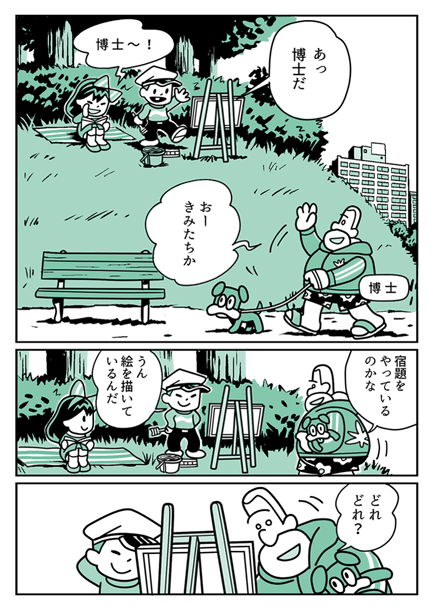
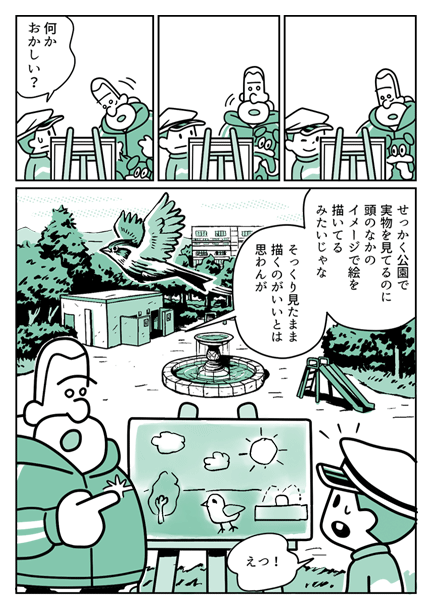
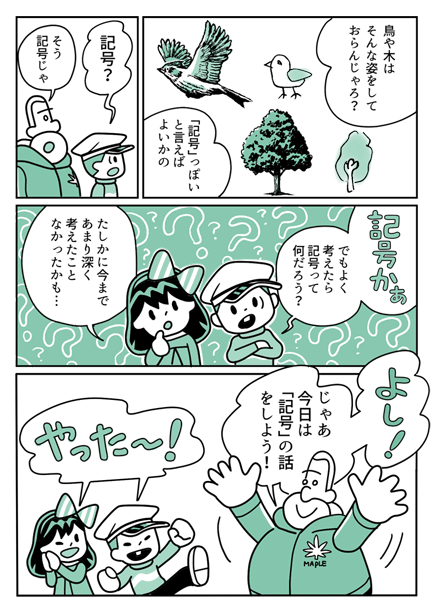
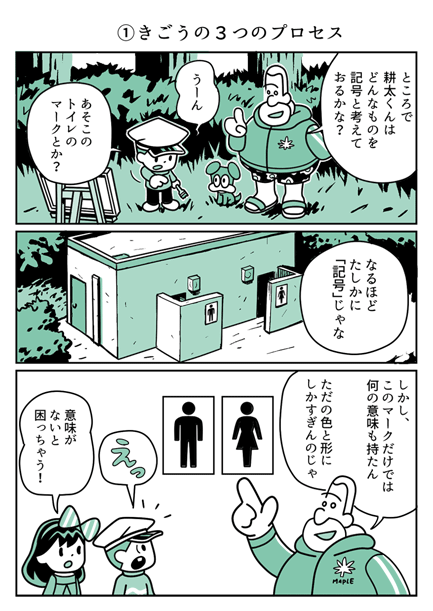
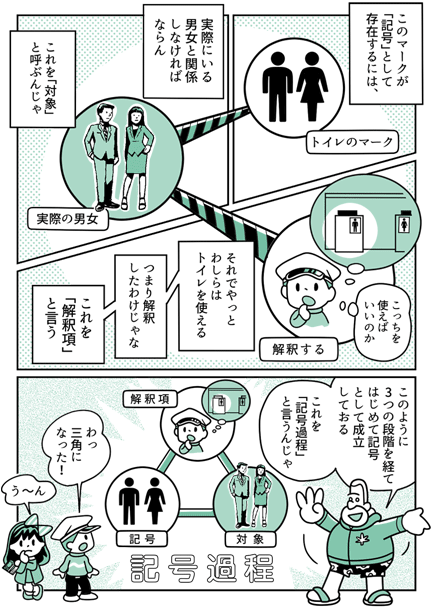
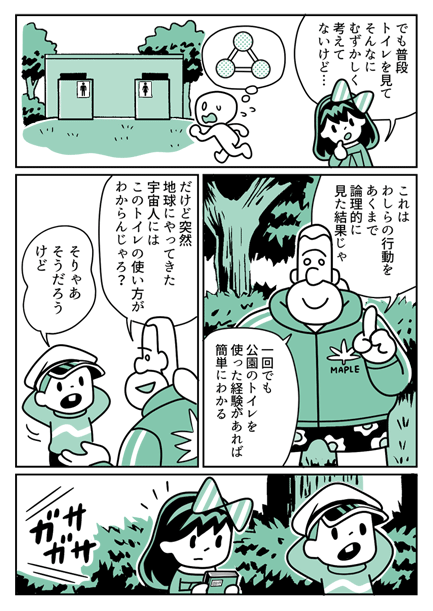
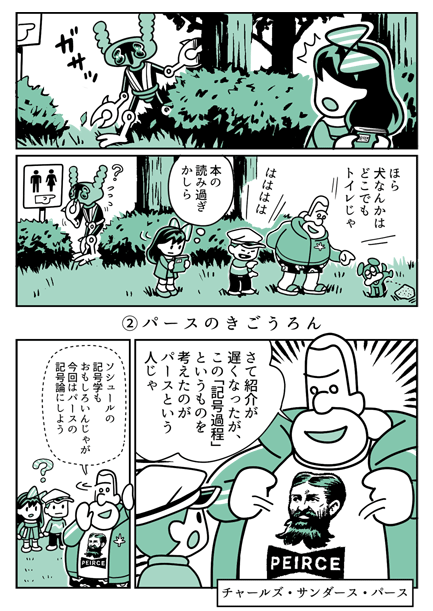
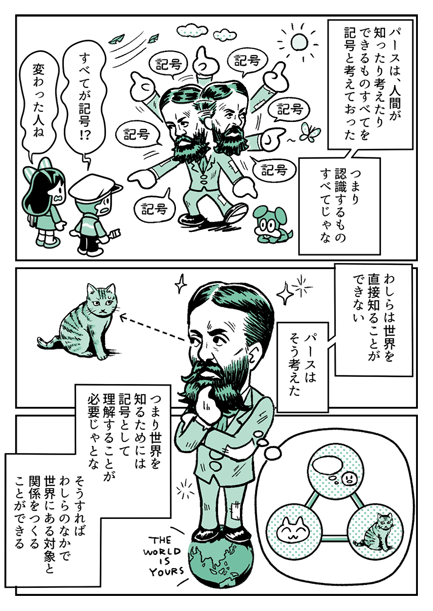
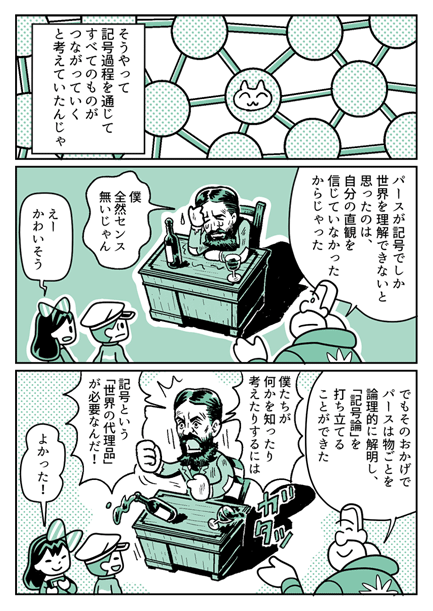
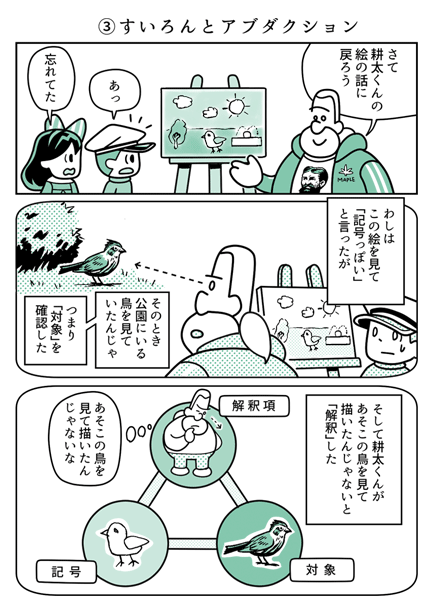
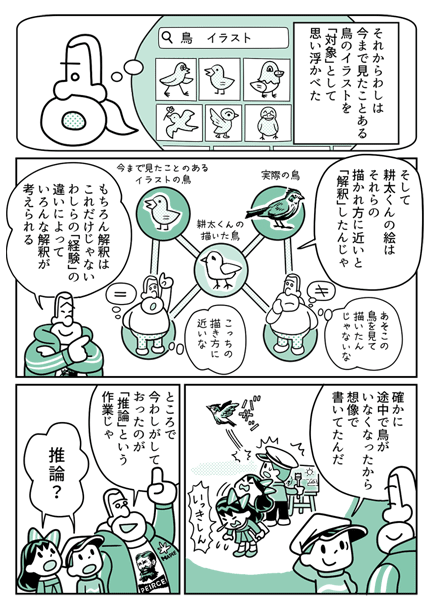
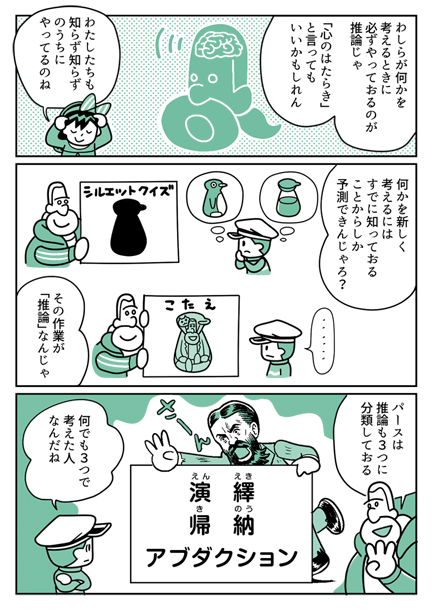
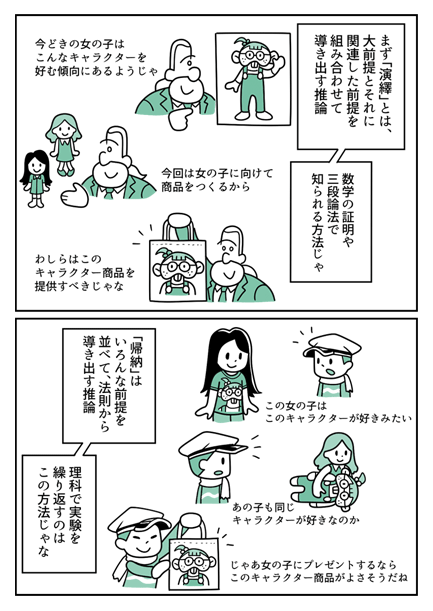
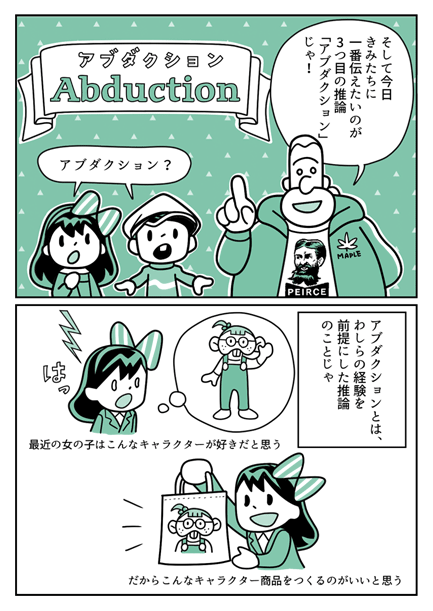
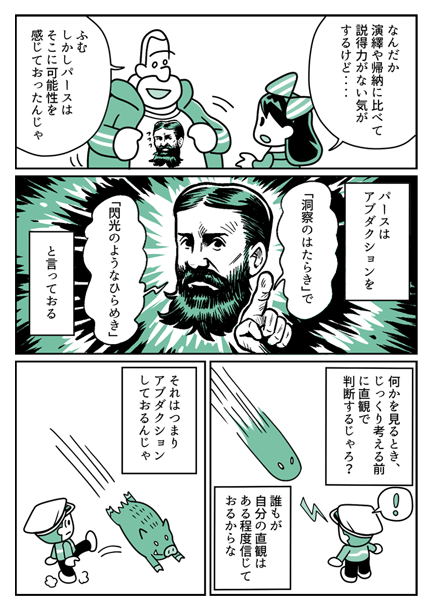
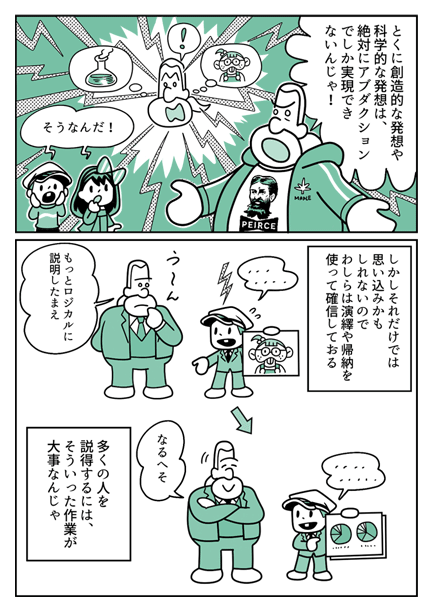

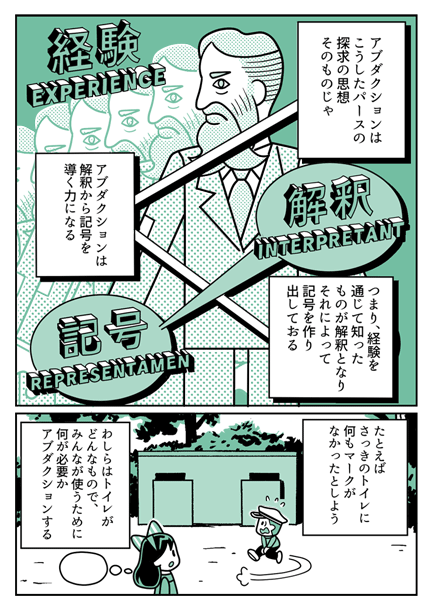
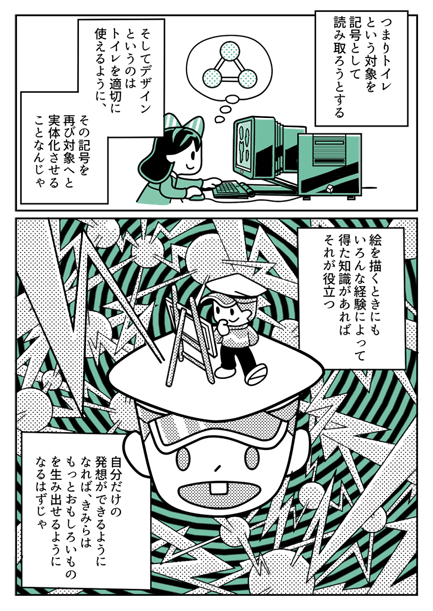
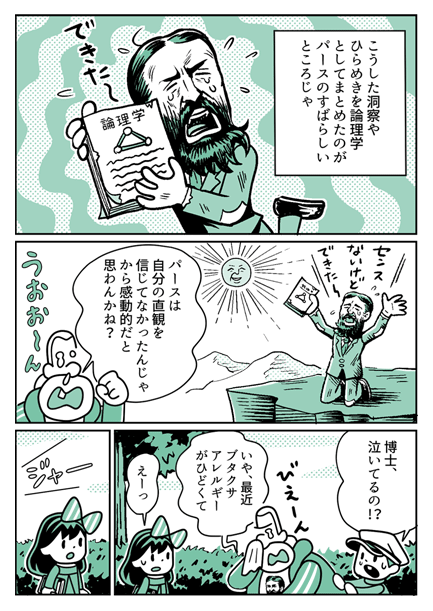
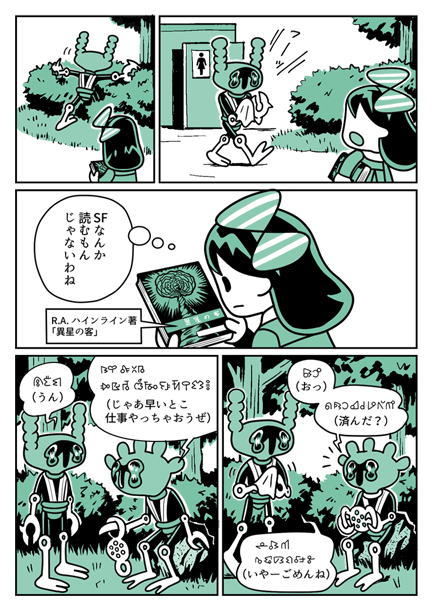
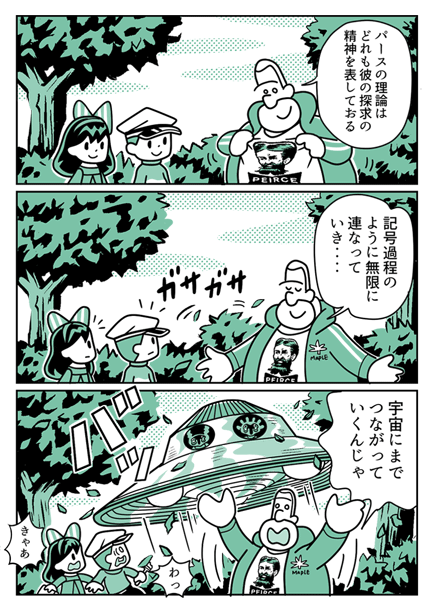
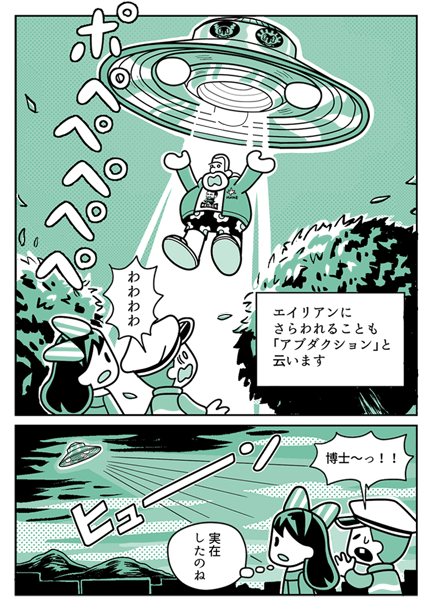
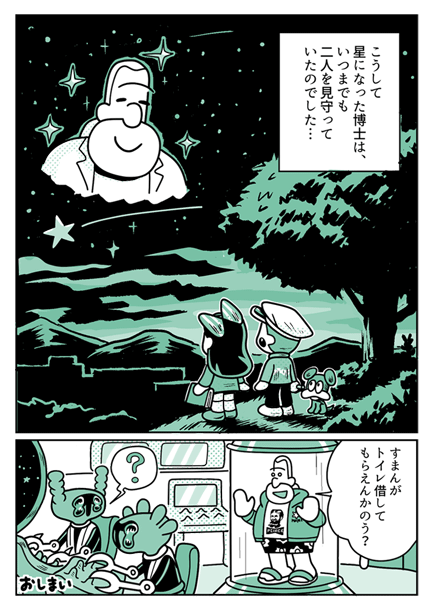
PDF版
まんが本編に加え、この作品の解説や参考文献などもご覧いただけます。
冊子版
「ITEMS」ページにて、この作品の冊子版を販売しております。
学習まんがについての最新情報は、TwitterやFacebookページにてお知らせいたします。
「ファッション」のデザインとは、何を射程にしたものなのだろうか。自らの意思だけで装いや生き方を選ぶことのできなかった時代に、ファッションは人を記号として見る世界をハックするための革命装置だった。誰もが衣服や生き方を選択できるようになった今、我々は何をハックすればいいのだろうか。
人間をつくるファッション
いつの頃からか芸術、文芸、ファッションなど、人間が作ったものから感じる質感やテクスチャーの根源を知りたいという漠然とした思いがあった。私自身が感じているこの感覚の本質は、何か普遍的な形で表現することが可能なのだろうか。そのテクスチャーの強い存在感は何故私に影響を与えるのだろうか。
こんなことを考えていたのは今から約10年ほど前のことで、その頃私は化学反応のカオスと生命現象への関わりを調べながら、何かしらの厳密な数理的アプローチで、人間の認知について研究をしたいという希望を抱いていた※1。
心理学や統計学は勿論、認知科学、あるいは分析哲学の本を読んでもどこか物足りない。数学の本を眺めながら、数百年、あるいは数万年の時間があれば、もしかしたら新しい数学によって何かわかることがあるかもしれないとも思った。ただ結局何かがわかったところで、私はそれを誰かに説明したいのだろうかという疑問が何となく頭をよぎる。
「私」はいかに生きればいいのか? 私とは何なのだろうかという漠然とした問い。聖書や仏典に関する書籍を眺めると、人間という生き物がこの問いと長い間向き合ってきた形跡を感じることができる。 歴史を通してみると、「私とは何か」という問いは次第に「人間とは何か」という問いへ変わり、そして再び「私自身への問い」へと戻ってくる。
自らの未来のことを考えつつ過去を振り返ると、小さな頃から考えていた「私はどう生きればいいのか」、あるいは「私は何か」という問いは、歳を重ね知識を身に付けるにつれて「人間とは何か」という抽象的な問いにすり替わり、人間といった普遍的な対象を強迫的に考えるようになっていたことに気がつく。「人間」という抽象的なものを観察しながら、いかにして具体的な「私」の世界に戻ればいいのだろう。この問いはまた別のものなのだ※2。
私は「私自身」と「人間自身」を調べながら、それらを造ること、つまりデザインすることはできないかと考えるようになっていった。その視点に立ってみると、世界では物が人に影響を与え、人がまた物や環境に影響を与え、新しい事実を生み出していく。だから、人間の身の回りに纏わるものを作り、世界に少しずつ変化を与えていくファッションは、面白い可能性を帯びているような気がしていた※3。
 10年ほど前、ある雨の日に会った男性の写真。目を引く不思議なスタイル。我々はこの様子から彼の何を知ることができるのだろうか?
10年ほど前、ある雨の日に会った男性の写真。目を引く不思議なスタイル。我々はこの様子から彼の何を知ることができるのだろうか?
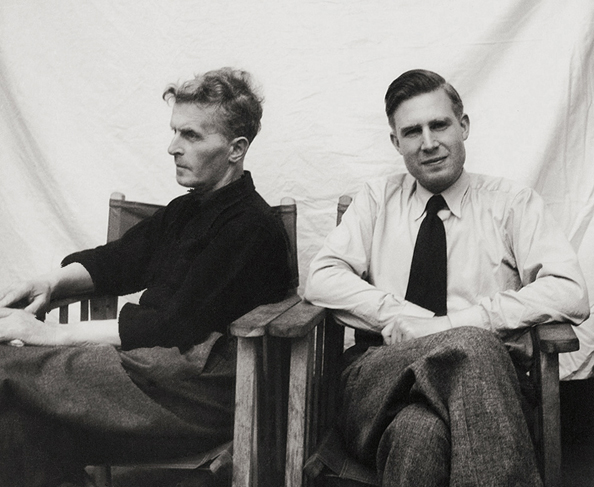 脚注で紹介したLudwig Wittgensteinの写真。例えばこの写真の中で、彼の彼たらしめる要素あるいはシステムは現れているのだろうか?
脚注で紹介したLudwig Wittgensteinの写真。例えばこの写真の中で、彼の彼たらしめる要素あるいはシステムは現れているのだろうか?
遠いデザイン、近いデザイン
建築家の磯崎新氏※4は時折講演で、Architectureという言葉の意味について話題にすることがある。Architectureは「建物を建てること」「デザインすること」と同義に扱われているが、実際は建物という構造体を都市の中に造ること、あるいは都市自体を造ること、そしてその先に都市に住む人間自体のダイナミクスへ影響を与え、さらにそのダイナミクス自体を作り変えることまでを射程に入れているものだという。しかし、Architectureの翻訳語である「建築」がその本来の豊かな意味を限定してしまっているらしい。
これを聞くと、ピーター・ドラッカーの「三人の石工」の話を思い出す人がいるかもしれない。石を積んでいる男に向かって「何をしているのか」と問いかけると、一人目は「生計を立てている」、二人目は「国一番の仕事をしている」、三人目の男は「大聖堂を建てている」とそれぞれが答える。ドラッカーは三人目の男を真のマネジメントを理解する好例として挙げている。そもそも「何故それを作るのか」というのは、どんな物を造る上でも根源的な問いに違いないのだ。
また、筆者が20代前半の頃に出会った荒川修作氏※5の存在も頭によぎる。芸術家と建築家の間を絶え間なく往復していた彼は、いつもこう言っていた。「社会を変えるためには、その構成要素である人間の倫理を作り変えなければいけない」と。そして「それを可能にするためには、人間の身体を変えなければならない」と続ける。彼は「身体を変える装置としての建築」に可能性を見出し、作品を造り続けた。作品の射程は景観の中に建てられた建築物そのものというより、遥か彼方にある人間のダイナミクスの変遷にあったのは言うまでもない。彼は自らに得体の知れない「コーデノロジスト」という呼称を与えていたが、それは建築物や芸術作品といった物質的な枠組みを超えたものを設計しようとしたがゆえに生まれたのだと思う。
我々は造られた物やシステムに触れることができる。もちろん、その構造や質感の美しさや利便性について、感じたことを議論することもできるだろう。しかし私はいつも、その作者が射程に入れていたこと、遥か彼方で起きて欲しいと願った「出来事」について考える。人は物に触れ影響されて新たなダイナミクスを生み出し、自らも新たな人間に影響を与え続ける。その影響は連鎖し、たった一つの物やシステムの誕生が、何か大きなものまでを変える可能性がある。我々は常に、そして永遠に世界と相互作用し続ける。デザインとは本来、そこまで考えて語られるべきではないだろうか。
便宜的ではあるが、造形や構造のデザインを「近いデザイン」とするならば、より射程を広げたデザインのことを、「遠いデザイン」と呼んでもいいかもしれない。
 三鷹天命反転住宅 In Memory of Helen Keller。「死なないための住宅」というコンセプトの元に作られた住宅。景観の中にある建物そのものではなく住む人間の身体から思考へ作用することを目的に作られている。「遠いデザイン」を目指した一例として。
三鷹天命反転住宅 In Memory of Helen Keller。「死なないための住宅」というコンセプトの元に作られた住宅。景観の中にある建物そのものではなく住む人間の身体から思考へ作用することを目的に作られている。「遠いデザイン」を目指した一例として。
モードからコードへ
「デザイン」という言葉と同様、「ファッション」という言葉も曖昧な意味のまま、日常で摩耗するほど使われ続けている。しかし私は、ファッションが「遠いデザイン」を可能にする領域の一つであると信じて疑わない。
実際、元来のファッションとしばしば同義に扱われる「モード」という言葉は、Modality※6を語源としている。これはファッションという言葉が、衣服やスタイルという意味にとどまらず、人間社会における現象や様相、また動的なパターンであることを示唆している。「様装」※7とでも翻訳すると、日本語でも少しその大域的な雰囲気が出てくるかもしれない。
19世紀の初頭あたりまでを振り返ると、衣服の組み合わせはある程度厳密なルールを形成し、人間の社会階級や所属するコミュニティを半ば機械的に振り分けるのに使われていた。社会の中では、装いや所有物、日常の行動パターン、そこで起きる物事が限定されるがゆえに、各人の属性が視認し易く、外見という「表層」から社会的な属性を察することができたからだ。特権階級に所属する人間、あるいは聖職者や宗教家の様子を見れば、人間の装いや行動パターンが、法律に近い暗黙の制度で限定される状況であった事実を察することができる。人々の装いは、各コミュニティにおける「制服」であり、「制度」が視覚化されたものであったと言えるだろう。
 ヴェルサイユ宮殿でのワンシーンを描いたイラストレーション。17世紀のファッションでは、身につけているものがそれぞれの階級を示唆している。
ヴェルサイユ宮殿でのワンシーンを描いたイラストレーション。17世紀のファッションでは、身につけているものがそれぞれの階級を示唆している。
時代の変遷に伴って、装いのルールはその後、制度から「コード(規定)」の形に変容して行く。それは明文化された法律のようなものというよりは、儀礼的であり慣習的なもので、人の間に介在する暗黙の空気やその相互作用の過程で、動的に生成され変化していくものだ。固定化された社会的階級が徐々に崩壊するに連れて、コードも動的になっていく。人の装いや行動規範は多様になり、所属するコミュニティの境界も動的なものへと変化させられていく。衣服によって一人の人間(individual)は、時と場所によって複数の顔を持ち始め、分人(dividual)としての人間が確立される。物の組み合わせであったはずのスタイルは、そうして社会のダイナミクスの有様を変え、「遠いデザイン」が知らず知らずのうちに実行されていくのだ。
ファッション、宗教、ウィルス
20世紀に活躍したファッション・デザイナー、クリストバル・バレンシアは以下の言葉を残している。
クチュリエは計画の上では建築家、フォルムの上では彫刻家、色彩に関しては画家、調和という点では音楽家、そして節度に関しては哲学者でなければならない。
彼の時代から現在までの100年の間に、身体を土台とする衣服の様式は、既に出尽くしたのではないかと言われて久しい。多くのスタイルが生まれ、制服化し、最終的には新たなカテゴリーとして固定化されてきた。パンク、トラッド、ワーク、ストリート、アヴァンギャルド……。
 80年代のロンドンの写真。学習を経たシステムを使えば、この姿から社会的階級や属性を予測することは可能だろう。我々も同じように無意識下で人の属性を判断している。判断と現実のギャップを作り、新しいコミュニティを生み出してきたのが現代までのファッションの系譜である。
80年代のロンドンの写真。学習を経たシステムを使えば、この姿から社会的階級や属性を予測することは可能だろう。我々も同じように無意識下で人の属性を判断している。判断と現実のギャップを作り、新しいコミュニティを生み出してきたのが現代までのファッションの系譜である。
実際、細かなディテールと質感の違いを別とすれば、現代のクリエーションの殆どが、既存のカテゴリーの中に否応無しに回収されてしまう。その様子は、雑誌を含めたメディア、ブティック、百貨店の区画、オンラインショップでの商品分類のされ方を見れば、顕著に見て取れるだろう。それを単純化してみると、固定化された既存のカテゴリーをX軸上に刻み、Y軸上に商品やイメージの価格帯をとった座標平面のようなものになっている。デザインを生む行為は、空間上の何処かに着地するアイテムを生み出す行為とされ、その未着陸地点に降り立つことが新しいスタイルの創造として捉えられている※8。
現代ファッションの文化的なターニングポイントは、これまで生み出された様々なスタイルの伝搬によって成しとげられてきた。新しい装いは、社会に存在する暗黙の「コード」と固定化された価値観をハックし、コミュニティの境界を曖昧にしてきた。そしてスタイルに共感する人々を次第に集めることで、既存の現状(Status Quo)を変貌させてきたのだ。新たなスタイルは、次第に新しいコミュニティの境界を行き来するための「制服」になっていく。装いのイメージは人々に伝搬し、そのイメージに結びついた言葉によって人の思考に影響を与える。
かつて梅棹忠夫※9は宗教のウィルス説を唱えたが、こういったファッションの側面を考えれば、ファッションは宗教の性質を持った社会現象なのだということがよくわかる。この意味で、人間のダイナミクスに影響を与え続けている三大宗教は、最も壮大な「遠いデザイン」を可能としていると言っていいだろう※10。
ビッグデータと人工知能が可能にする『モードの体系』
このように変わり続けるファッションデザインの射程を、我々はどう分析できるのだろうか。
ファッションを分析した人間の代表として、ロラン・バルトを挙げる人がいるかもしれない。衣服に言語学的性格がありうると指摘したニコライ・トルベツコイに影響を受け、彼はファッションを言語学の側面から考察した。1967年に記された『モードの体系』は、その集大成である。
しかし実際のところ、その完成度は現代の水準ではあまり高いものとは言えない。自由が保証され、人間の有様が多様になっていた当時、すでにその動的な動きは人間の認知限界を遥かに超えていた。論理的破綻を避けるため、彼はその分析対象を雑誌の上に表象されたファッションへと限定してしまう。その分析自体は示唆的であるものの、「近いデザイン」の周辺を語ったにすぎない。これについては、彼自身が以下のように語っている。
わたしが書かれた記述に限定したのは、方法論と社会学の2つの理由からなのです……イメージから書かれた記述へ、さらにこの記述から再び街中に移行して、この眼で確認できる観察へと無差別に移行していては、精密な分析など不可能だったのです。記号学のやりかたは、ある対象を要素に分割し、これらの要素を形式的な一般的等級に分類して再配分する事ですから、できるかぎり純粋で均質的な素材を選ぶ方が有利だったのです。ロラン・バルト「『モードの体系』セシル・ドランジュとの対談」
その分析は限定的であったが、300年以上前なら十分に機能していたかもしれない。人の有様と生活様式は限られており、それを表す言語との相関関係を測るのは比較的容易だったはずだからだ。
 50年代の日本の一般家庭の様子。ここに映るさまざまなものから、我々は何をどこまで知ることができるのだろうか? 何をどう「いじれば」、このシーンの動きを、あるいは左の男性の行動規範を劇的に変化させられるのだろうか? 遠いデザインはそういったことをターゲットとしている。
50年代の日本の一般家庭の様子。ここに映るさまざまなものから、我々は何をどこまで知ることができるのだろうか? 何をどう「いじれば」、このシーンの動きを、あるいは左の男性の行動規範を劇的に変化させられるのだろうか? 遠いデザインはそういったことをターゲットとしている。
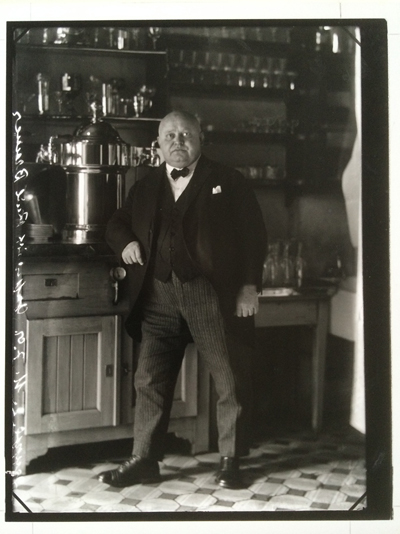 20世紀前半のドイツで様々な職業の人を撮った作品集、August Sander “People of the 20th Century”より。被写体の男の職業は?
20世紀前半のドイツで様々な職業の人を撮った作品集、August Sander “People of the 20th Century”より。被写体の男の職業は?
現代は、「有様」や「装い」といった局所的な情報から人を判断していた過去とは違う。我々の分人化は進み、情報過多で認知限界を超えた世界全体の見通しの悪さが、コンピューターによる記号的かつ離散的な世界の分節化を加速している。
しかし、我々はそのうち、機械によって予めフィルタリングされた世界を、ありのままの世界として認識するようになるかもしれない。人間という存在も、身体的特徴、年齢、性別、出身地、住所、所有物の名前、属性や品質、ソーシャルメディアでの活動といったものを数理的に切り出し、人工知能が学習して構成したプログラムの評価関数を通して判断してしまえば、むしろその世界は300年前の時代とあまり変わらない様子になるだろう※11。
離散化される世界に抗う
人工知能によるファッションデザインも既に始まりつつある※12。現実世界を切り出す離散的なメッシュはより細かくなっていくだろう。その時、バルトが試みた記号論的な分析(あるいは分類)も、雑誌といった限定されたメディアでの分析にとどまらず、全てのテキストデータとイメージ、あるいはインターネットと繋がるモノそのものまで拡大すれば、本当の『モードの体系』が人間の有様として大きな射程で見えてくるだろう。 膨大なデータの分析が可能となった今、人間社会の深層を表層から探ろうとしたバルトの『モードの体系』での試みは、再び意味を持つようになって来たように思う※13。
そのうち我々はコンピュータによって描かれた空間の中で、一喜一憂することになるのかもしれない。新しい形でフィルタリングされ一様化される危険を孕んだ世界で、我々はまた新たな記号化と戦うことになるのだろう。
現実の世界を離散的に写した空間。その空間で輝きを失ってしまう「私」にしか見えないものたち。それらの存在を憶う時、村上春樹の『1Q84』に書かれた言葉を思い出す。
「説明しなくてはわからないということは、つまり、どれだけ説明してもわからんということだ。」村上春樹『1Q84 BOOK 2』
流動性を失った世界を動かしてきたのは、いつも数々の一様化や体系化に抗う、強い「私」たちだった。それは、限りなく具体的だが体系化することのできない、掴みどころのない「私」たちの様装である。
離散化されていく世界に対し、その過程に抗いハックする生き方が、そしてその生き方を生成する新しいファッションの発明が必要とされる時代が迫りつつあるのだと思う。新しいファッションデザインの可能性はいつも、遥か遠くをデザインすることから生まれるのだ。
SCENE 01
内的な時間をデザインすることは不可能だ。この覚書は、その結論を得るまでの過程を記録したものである。
時間については、昔から多くの作家たちがなにかを語ろうとしてきた。我々が日常的に体験している時の流れに対して、彼らは疑いの目を向けているのだ。
ヴォネガット『スローターハウス5』では、トラルファマドール星人という異星人が登場する。彼らは、四次元の目をもちいて世界を見ることができる。彼らにとって人間は、子供から老人までの無数の人間が腰のあたりでくっついた百足のような生物に見える。そしてヴォネガットは、また別の作品で、すばらしい視点を提示した。
われわれが、人間であるという大きな過ちの次に犯している大きな過ちは、時に対する過ちではないかと思う。われわれは時計やカレンダーなどさまざまな道具を使って、サラミのように「時」をスライスし、その一切れ一切れに名前をつけ、所有した気になり、時はそれっきり固定されてしまうように思ってしまう——「1918年、11月11日、午前11時」とか——が、じつは、時は粉々に壊れたり、水銀のように飛び散ってしまうこともある。カート・ヴォネガット『国のない男』
ここで語られることになるのは、個人の内的な時間である。手帳に書き込んだり、生年月日として覚えているような、公的な時間ではない。公的な時間のデザインは、時計やカレンダーという形で、すでに確立されている。内的な時間のやっかいなところ、そして魅力的なところは、誰もが体験していながら、誰にでも通じる説明が存在しないことにある。だからこそ、さまざまな人物がそれぞれの体験を語っているのだ。
SCENE 02
ボルヘスは、ある夜に自宅の近くを散歩しているときに味わった感覚について、過去の作品からの引用を通じて、こう証言している。
私はその純一さにただ惘然と見とれていた。そして考えた、確かに声を出して。これは三十年前とまったくそのまま同じではないか……時間とは、もしわれわれにその実態を直観することができるとすれば、一つの幻想である。見かけ上のきのうという日の一瞬と、見かけ上のきょうという日の一瞬との間には何の相違もなく、両者は不可分のものであるという一事だけで、時間を解体するには十分であろう。ホルヘ・ルイス・ボルヘス「新時間否認論」
村上春樹の『風の歌を聴け』では、十代の頃を回想する主人公が、文章を書くことについてこう語る。「少し気を利かしさえすれば世界は僕の意のままになり、あらゆる価値は転換し、時は流れを変える……そんな気がした」と。
こうした実感に照らすと、時間に関連するデザインはいつも半分だけ的外れである。その理由は、すべての時間のデザインが個々人の「現在」を無視し、公的な時間にフォーカスせざるをえないという事情による。
すべての時計が示す時刻は、私たちそれぞれの「現在」の感覚からはかけ離れている。誰がなんと言おうと、いまは2016年9月28日などではないし、15時4分というのも意味不明だ。私にとっては窓の外に見える景色や太陽の位置、遅めの昼食をとってすこしぼうっとしていること、そういったものが「現在」の感覚のすべてである。
だからこそ、ボルヘスが経験した「三十年前とまったく同じではないか」という感覚は空恐ろしい。それは、限りなく流転するはずの時間のなかに、まったくの同一項がふたつあらわれる悪夢だ。これは、ボルヘスによれば「時間の連続性を崩壊せしめるに足るもの」である。彼が引用した小編は「死の感覚」と題された作品であった。死とは、内的な時間の連続性が崩壊することだ。
SCENE 03
ビデオゲームの分野においても、時間の観念を野心的に取りこみ、作品の成立に役立てている例が多く見られる。昼と夜のコントラストや、日付を活用した作品は類挙にいとまがない。それどころか、おそらくすべての「物語」を擁するゲームジャンル、たとえばRPGやビジュアルノベルなども、その成立に時間の流れを必要としているだろう。
2001年にPCゲームとして発売されたビジュアルノベル『さよならを教えて』は、作中から時間の流れを排することで、悪夢の感覚を描いた作品だ。語り手兼主人公の青年は、自分のことを「教育実習生」だと思い込んでおり、生徒の少女たちと交流する。終盤では、あるひとりの生徒をのぞく全員が主人公の幻覚であり、その正体は猫や烏や生物標本などであったことが明らかになる。
テキストで直截的に語られることはないのだが、ゲームにあらわれるすべてのグラフィックは「夕方」を描いている。自分の感知できる時間帯がこの黄昏に限定されていることに、主人公は最後まで気づくことができない。しかしながら、彼は「時間が進んでいないような気がする」とか「うまく休めた気がしない」といった発言を繰り返す。
これらの発言からは精神の失調さえ読み取れるが、その原因は先述したボルヘスの「死の感覚」に求めることができる。主人公の内的な時間はすでに崩壊している、つまり死んでいるのだが、なぜか彼はまだ生きていて、悪夢的な苦しみを味わい続けているのだ。この状態は、単純な死よりもつらい運命としか言い表しようがなく、プレイヤーに激しい不快感を与える。
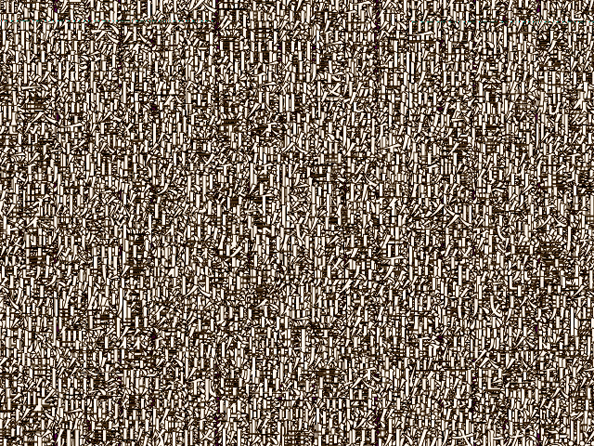 内的な時間が崩壊している主人公の意識において、時間は流れない。言葉は消えず、澱みのように滞積する。
内的な時間が崩壊している主人公の意識において、時間は流れない。言葉は消えず、澱みのように滞積する。
時間の連続性が崩壊するといえば、アドベンチャーゲームの傑作として知られる『ぼくのなつやすみ』での「8月32日現象」も、それに類する恐怖をプレイヤーに与える。この作品は、母親が臨月をむかえたために田舎の親戚の家にあずけられた「ボク」を操作し、昆虫採集や魚釣りをして夏休みの一ヶ月間を過ごすゲームである。このゲームは一日の終わりに「ボク」が絵日記を書き、読書灯を消すことで日付が変わるしくみになっている。
クリアデータをロードして、8月31日の絵日記を回覧すると、グラフィックから削除された読書灯のあたりに、カーソルを合わせることができる。存在しない読書灯の明かりを消すと、カットシーンが挿入され、ゲームデザイン上存在しないはずの8月32日をプレイすることができる。
8月32日には、「ボク」以外のキャラクターは存在せず、空っぽになった広い木造の家はなんともいえない寂寞感をプレイヤーに与える。ふだんならできる行動ができないので、プレイヤーはもういちど読書灯を消し、さらに日付を進める。すると「ボク」の周囲にキャラクターが現れはじめるのだが、ピクセルアートが崩壊しており、誰もが怪物の姿に変貌している。さらに日付を進めるにつれて、表示されるテキストは激しく文字化けをはじめ、自動生成される「ボク」の絵日記は、プログラムが吐き出したピクセルの吐瀉物でいっぱいになる。
このゲームを制作したミレニアムキッチンの代表者 綾部和によれば、「8月32日現象」は純然たるバグであり、本来はデータが存在しない8月32日というパラメーターをドライバーが参照しようとして起こるものだという。この現象は、先ほどの『さよならを教えて』で描かれた内的な時間の崩壊と好対照をなしている。公的な時間が崩壊するとき、キャラクターの内面ではなく、表象される世界そのものが異様なものへと変化するのだ。
では、内的な時間にあわせて、公的な時間を自由に変更できるとしたらどうだろう?
かつて私が『マインクラフト』をプレイしていた2009年ごろには、インターネットを介したマルチプレイを行うためのサーバーを、ユーザーサイドで運営することができた。サーバーの運営者は、その世界において、いわば全能の管理権限を保持していた。運営者はコマンドコンソールを通じて、さまざまな影響を世界に与えることができたが、そこに流れる時間を強制的に書き換え、いきなり昼に戻すためのコマンドがあった。
/time set day
このコマンドは、創世記で言えば第1章3節である。
神は「光あれ」と言った。そして光があった。
 時間さえもコマンドひとつで操れる世界。
時間さえもコマンドひとつで操れる世界。
さきほどまで真っ暗だった世界が、わずか一行のコマンドで一瞬にして白日の下にさらされるのは、とても奇妙な感覚だった。おそらく、時間の流れを早めたり遅めたり、一日の長さを変更したり、太陽を天頂に固定して永遠の正午を味わうこともできたはずだ。現実の時間が深夜であったとしても、溢れんばかりの陽射しのもとで遊ぶことができる。たったひとりきりの人間として動物やモンスターと戯れ、「現在」という時間を気の向くままに操って遊ぶプレイヤーは、もはやその世界を統べる神と言ってよい。だとすれば、「彼のもつ内的な時間がそのまま公的な時間であるような存在こそが神である」といった定義もできるだろう。
SCENE 04
考えてみれば、「現在」という時間は、常に過去と未来が接するところにある、ひとつの点でしかない。大きさを持たない概念としての点は、この世界に実在するものではない。しかし、私たちはなにをもって「現在」という一点を定めるのだろうか。
数学の教科書には、図形を読み解く問題がたくさん出てくる。不思議なことに、それらの図形の線には「長さ」しかなく、「幅」や「厚み」についてはなんの説明もない。高校生のころ、それについて先生に質問してみたことがある。すると、「この線は幅や厚みを持っていないことになっているんだ」という答えが返ってきた。
 線に厚みはなく、点に大きさはない。
線に厚みはなく、点に大きさはない。
時間においても、「現在」という点が「幅」や「厚み」を持っていないのであれば、それを定めるのは、空間的な位置情報となるだろう。「現在」という点は、位置を持っているが大きさを持たない。ここから導き出されるのは、以下のような論証である。
もしも時間が空間に含まれるならば、現在という一点は大きさをもたない。
ゆえに、現在は存在しない。
ゆえに、現在との対比によって観測される過去と未来も存在しない。
ゆえに、現在と過去と未来から成る時間は存在しない。
まったく論理的に思えるが、信じられない感じもする。私は現にいまここにいるし、それこそが現在である。解説することがあまりにも難しいにせよ、私がいまこうして生きているという実感こそが、まぎれもない「現在」である。それなのに、先ほどの論証に奇妙な説得力を感じるのはなぜだろうか。それは、時間の概念を持たない純粋な空間というものが成り立つと、私たちが錯覚してしまうからだ。
SCENE 05
「飛んでいる矢は、的に命中することはない」という命題を証明する「ゼノンのパラドックス」は、その例として古くから知られている。荒木飛呂彦は『ジョジョの奇妙な冒険 Part6 ストーンオーシャン』のなかで、この論証を援用し、自分との距離に比例して他人の大きさを縮小させる赤ん坊を登場させた。登場人物たちがこの赤ん坊にむかって落下したとき、彼らはいつまでも着地できないのではないかという恐怖を抱いた読者も多かっただろう。
このパラドックスは、本来は時間の経過を前提としている物体の運動から、時間の経過を巧妙に排除し、それを距離という空間的な尺度だけで証明してしまうことから生じている。命題も証明も真だが、それが現実に即していないのだ。
ならば、先ほどの命題を「飛んでいる矢は、的に命中する時刻まで的に命中することはない」とすれば、解決するだろうか。一見、とても正しいように感じられるが、論理的な怪しさはぬぐい去れない。物体の運動は時間の流れを前提としているが、時間の流れは物体の運動によってしか計ることができないという、よくある循環論法に陥っている。
パスカルは『パンセ』のなかで、「神は無限の球である。その中心は到るところにあり、その円周はどこにもない」と記し、神の性格のひとつである遍在性を空間において表そうとした。この「遍在」の概念を、もうひとつの連続体である時間にあてはめると、もっとも近いものは「永遠」になると思われる。
SCENE 06
永遠と神の関係について、トマス・アクィナスはこんなことを言っている。
われわれが「今」の流れを把えることによって、われわれのうちに時間の把握が生ぜしめられるように、「とどまる今」を把えるかぎりにおいて、われわれのうちに永遠の把握が生ぜしめられるのである。トマス・アクィナス『神学大全』
ただの人間にすぎない私たちにとって、「とどまる今」を把えることは難しい。なぜなら、私たちはつねに継起する時間の流れのなかから「現在」を把握するからだ。セリーヌは『なしくずしの死』のなかで、通行人の雑踏を停止させようとし、「彼らを止まらせろ……これ以上彼らが消え去らないうちに!」と、紙上で絶叫した。しかし、彼は神ではないので、物語における時間は動き続けた。
時間について明瞭な答えを得られなくとも、答えを得られない理由そのものはすでに提示されている。その理由とは、私たちがつねに継起する時間の流れの影響を受けて、変化しつづける「現在」を生きているから、というものだ。
存在する私というものはつねに現在に存在するのであり、現在の私はその存在することにより私以外のものを変えて行くのである。私以外のものを変えて行くのみならず、私自身をも変えて行くのである。単に観測しているということだけでも私は新しい情報をとり入れるのであり、その知識のために私は新しい私に変わって行く。もっと積極的な働きかけにおいては私自身の変化はさらに疑うことができない。これこそ生命の本質的な性質である。渡辺慧『時』
たとえば、愛するひとの死や、好ましい住処のとつぜんの喪失、人間のもつ陰惨な面に触れたとき、すべてが変化していくという世界の構造を、私は激しく嫌悪する。しかし、好むと好まざるとにかかわらず、私はこの世界のなかに生きているのだから、それを受け入れるほかに生きるすべはない。さもなければ、内的な時間の崩壊は免れないし、公的な時間と折り合いをつけることもできないからだ。そう考えるとき、あらゆるものが変化する世界を積極的に肯定する渡辺の言葉に、深い共感をおぼえる。
私には太陽の位置を自由に動かすことはできない。それは神にしかできないことだ。私はどこまでも人間として、時間と、それがもたらす変化を受け入れながら生きればいい。
SCENE 07
公的な時間のデザインが可能なのは、それが実際には個人的なものだからである。2016年9月28日の18時25分という「スライスされた時間」は、その時間を体験したすべての人間に、それぞれの経験を想起させる。だからこそ、私たちは人と会う約束ができるし、計画をして、それを実行することができる。
対して、内的な時間をデザインすることは不可能になる。なぜなら、そのデザインを作り出す者が、つねに変化しつづける「現在」のなかで時間を把握するからだ。
そして、変化していくことそのものは、個人的な体験ではない。内的な時間は死によって終わりを迎えるが、その体験はまぎれもなくすべての人間が経験するものであり、非個人的である。このことも、内的な時間のデザインの不可能性を強めている。もしも無理矢理に視覚化するならば、熱したチーズのように溶けた懐中時計が描かれたダリの『記憶の固執』や、真昼の青空と深夜の街並みがカンバスに同居しているマグリットの『光の帝国』のようなものになるだろう。そしてそれは、もはやデザインではなく、個人の夢の顕れである。
小説家の倉橋由美子は、エッセイ「小説の迷路と否定性」のなかで、「《この世界ではない世界》、いわば《反世界》の存在を表現すること」が自作への要求であると述べた。そのための手法として、彼女は「事実」や「体験」や「日常性」といった形而下的なものを利用し、形而上的なものを表そうとした。この手法を試みつづける理由は、とある奇妙な時間を体験したからだという。
私が言葉の銅版画にして示したかったのは、子供の頃のある夏の一日、太陽が空に止って白っぽい「永遠」が支配していたような感覚である。倉橋由美子「小説の迷路と否定性」
彼女は、その瞬間だけは、神に近しいなにものかだったのではないだろうか。
目の前に、昭和三十二年頃の、古びたモノクロ写真がある。縁側で這い這いをしようとしている、幼い男の子の姿。その隣には、猫が写っている。いかにも暢気そうな様子で、傍に寝そべっている。
保坂和志の短編集に収められた「写真の中の猫」という作品には、こんな一枚の写真にまつわる印象深いエピソードが綴られている。彼は、自分がもう少し成長するまで飼われていたはずのその猫のことを、まったく憶えていなかったという。アルバムのなかで偶然に写真を見つけて、その猫の存在を知ったことになる。ずっと忘れていた事実を、写真がきっかけとなって思い出したということではない。写真を見たからといって、その猫がかつて存在したことを、自らの内にある「記憶」として認識できたわけではなかったのだ。
猫はそのとき、柔らかな陽射しの心地好さに、あくびの一つもしていただろうか。縁側で這い這いをする自分にカメラを向け、シャッターを押したのは、誰だったのか。もしかしたらその傍で、「ほら、こっち向いてごらん」と、笑顔で声をかけた人もいたかもしれない。そういったことは、その写真から知ることはできない。「記憶」に残らなかったものは、すべて消えていった。そのような時間があったという事実が、写真という物理的な「記録」として、目の前にあるだけだ。
時間を記録するメディア
このエピソードは、わたし自身の過去にも思いを至らせるものだった。かつては我が家でも、飼われているのか勝手に出入りしているのかわからないような、名前のない猫が次々と現れては消えていったという。そして自分のアルバムにも、「記憶」にないものが「記録」された数々の写真があることを思い出し、わたしはこの作品に深い共感をおぼえた。保坂氏は、その写真に喚起された説明しがたい心情を振り返り、こう述べている。
かつてそこにあった時間、あるいはその時間があったからこそ起こった動きや話し声や笑いというようなさまざまなことが、この世界に残らないで〈物理的〉に消えてしまうということは、本当にあたり前すぎるほどあたり前のことだ……ぼくがいまリアリティを強く感じているのは、「郷愁」のような心の状態ではなくて、この、「時間がこの世界に残らないで消えてしまう」という前提ないし法則の方だ。保坂和志「写真の中の猫」
しかし、その後ではこのようにも語られている。
「時間がこの世界に残らないで消えてしまう」と書いたけれど、本当はそうではなくて、写真という、時間を記録した断片があることによって、それを取り囲むものがいろいろに想起されることの方に奇妙さとリアリティを感じているのかもしれない。保坂和志「写真の中の猫」
保坂氏の言うように、写真は「断片的に時間を記録するメディア」である。しかし、写真では記録できない「動きや話し声や笑いというようなさまざまなこと」まで記録可能な、動画というメディアでも、そこに映るのは実際に生じたできごとの「断片」でしかない。写真とは異なり、動画には音声が伴うが、どちらもカメラのファインダーというフレームによって切り取られた映像という点では同じであり、現在はそのいずれも手軽に利用できる世の中になった。しかし、「それを取り囲むものがいろいろに想起されること」については、写真と動画の間に、かなりの違いがあるように感じられる。
一枚の写真を見るということは、カメラが捉えたある一瞬の記録を目にするという体験である。そこに焼き付けられたものは、ひとつのイメージであると同時に、長さのない「点」としての時間でもある。写真を見るとき、ひとはその瞬間に確かに存在した光景や人物を目にして、直接的に写ってはいないそれらの過去と未来に、さまざまな想いを馳せることになる。報道写真のような他者の記録でも生じる体験だが、自分自身の記録である場合、それは一段と鮮烈な「想起」をもたらす。
ある晴れた日の午後のひとときを共有した、猫とわたし。猫はどのような経緯で我が家にやってきて、やがてどのように死んでいったのか。わたしはその後、どのような子供に成長し、どんな大人になったのか。ひとが一枚の写真に飽くことなく見入ってしまうとき、そこで生じる「想起」は、「点」としての時間を永遠に引き延ばすかのような体験となる。
一方、動画に記録されているのは、一定の長さを持った「線」としての時間である。写真が純粋なイメージの記録であると思えるのに対して、動画はイベント(できごと)の記録という印象が強い。したがって、写真を見ることを「イメージの再現」と捉えるなら、動画を見ることは、「イベントの再生」とでもいうべき体験となる。「想起」するための時間は大抵、再生時間に一致する。もちろん、動画として切り取られた時間の前後の状況を、後から想像することはできる。しかし、動画を見ている最中には、そこに映っていないものを想うことはほとんどなく、その映像自体の時間の流れに、ひとはただ身を浸している。
カイロスとクロノス
いま述べてきたことは、古くからある二つの時間の概念でも表現できるだろう。
ギリシア語には、時を表す言葉として、カイロス(kairos)とクロノス(chronos)の二つがある。前者は「時刻」を、後者は「時間」を指すとされているが、それぞれがやがて神話に登場する神の名としても用いられた。カイロスが機会(チャンス)の神だったことから、ひとが主観的な時機として捉える一瞬の時間は、「カイロス時間」と呼ばれることがある。それに対して、クロノスは文字通りの時間の神であり、わたしたちが時計によって客観的に知るような、均質に流れ続ける時間は、「クロノス時間」と呼ばれる。
スチュアート・ブランドは、時間をテーマとした著書『The Clock of the Long Now』で、美術史家パトリシア・フォルティーニ・ブラウンによる、このような言葉を紹介している。
カイロスは自らにとっての好機、あるいは幸ある瞬間。クロノスは終わりなき時間、あるいはひたすら流れ続ける時間。前者は希望をもたらし、後者は戒めを与える。Stewart Brand “The Clock Of The Long Now”
続いてブランドは、その二つの違いを自らの言葉でこう表現した。カイロスは「機知(cleverness)」の時間であり、クロノスは「知恵(wisdom)」の時間である。端的に解釈すると、これらは幼年期の時間と成年期の時間と言えるかもしれない。子供の頃を振り返ると、誰もが大抵は、大人になった現在よりゆっくりと時が流れていたような感覚を思い出す。生まれて初めて何かを体験するとき、好きなことに夢中になっているとき、子供時代のわたしたちは、それとは知らずカイロス時間にのなかにいたのだろう。でも、大人になるにつれて、多くのひとは、時計の針に支配されるクロノス時間に従って生きるようになっていく。
そう考えると、写真はひとをカイロス時間のなかに誘い、強い力で記憶のなかへ連れ戻すものと言えるかもしれない。「点」としての時間を記録した写真が、そこに収まりきらない時間の流れを想起させることもあるからだ。
記憶としての写真
写真術が発明された19世紀当時、それまでは画家が自らの身体的な技巧を駆使することでしか描けなかった人間の似姿を、カメラという器械がたちまち写し取ってしまうという事態は、まるで神秘体験のような驚異として受けとめられたという。しかし、その驚きは、写実性の高さという技術的な要因だけによるものではなかった。「点」としての時間を、銀板やフィルムに映像として写し取るカメラは、ひとの意識にとまることのなかった瞬間を捉えてしまうことがある。写真に残らなければ、誰にも知られることなく過ぎていったはずの一瞬。それを目の当たりにすることが、多くの人びとにとって、もう一つの現実を垣間見るかのような驚きを与えたのだ。
ヴァルター・ベンヤミンは、そのような現象をこう語っている。
カメラに語りかける自然は、肉眼に語りかける自然とは当然異なる。異なるのはとりわけ次の点においてである。人間によって意識を織りこまれた空間の代わりに、無意識が織りこまれた空間が立ち現れるのである……ここから分かるのは、技術と呪術の境界線は時代とともに変わってゆくことである。ヴァルター・ベンヤミン「写真小史」
科学的に見れば写真とは、カメラのファインダーが捉えた映像を、光学的技術によってガラスの湿板や乾板、フィルムやデジタルメディアに写し取った「記録(record)」でしかない。しかし、ひとの意識や視覚能力が及ばないままに消えていった光景が、写真によって焙り出されるとき、それが呪術のごとく過去を封じ込めた「記憶(memory)」にもなることを思い知らされる。
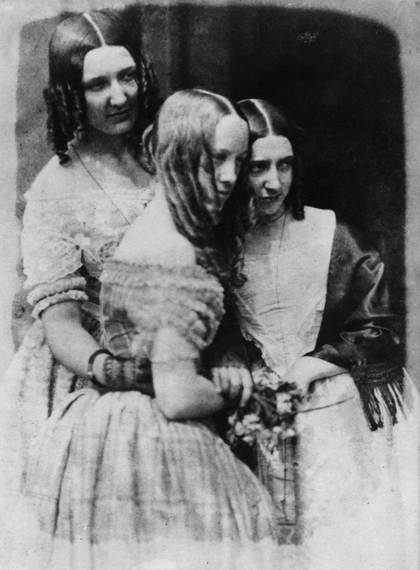 ロバート・アダムソンの撮影による1840年代の写真
ロバート・アダムソンの撮影による1840年代の写真
想起される「物のイメージ」
記録と記憶。それらがどのように取り出されるかを考えると、違いはより明らかになる。記録は、元どおりの形で「再生」または「復元」される。しかし、記憶は、ひとそれぞれの形で「想起」されるのだ。
記録と再生/復元は、システマティックな入出力のプロセスであり、誰でも同じように行なうことができる。したがって、記録は人間よりも機械が得意とするものである。ものごとを機械的に覚えることは、記憶ではなく「暗記」と呼ばれることも多いが、人間にとってそれはむしろ不得意な作業であり、そう簡単にできることではない。だからこそ、ひとはさまざまな形で機械の力を借りながら、できるだけ確実かつ効率的に、自分の外部にものごとを記録する方法を編み出してきた。写真という技術も、その一つと言えるだろう。
しかし、記憶されたものは、記録のように保存したときと変わらぬ状態で再生/復元されるのではない。記録では「物そのもの」が保存されるのに対して、記憶が保存するのは、それが生み出す心象、すなわち「物のイメージ」であるからだ。「物のイメージ」は、個々の人間による「物そのもの」の解釈を表している。そして想起とは、ひとそれぞれに記憶された「物のイメージ」が、再び意識に上ることである。
アリストテレスはかつて、「記憶とは、感覚でも判断でもなく、それらに属する何かを、時間が経過したときに、持ち続けている状態、ないし、受けとめている状態である」と定義した。さらに、その「受けとめた状態」について、こう語っている。
……魂をもつ体の部分において、感覚を通じて、何らかの、絵に描かれたもののような仕方で、生じるものとして、その受けとめた状態を考える必要があるのは明らかである。アリストテレス「記憶と想起について」
記憶される「物のイメージ」が、ここでは「絵に描かれたもの」と表現されている。それは知的な思考というよりは、身体的な感覚によって、ひとの「魂」が生じさせる何かである。「魂」とは、他者と共有することはできない、そのひとだけのものであるはずだ。そう考えると、多くのひとが同じ一つの現象を目撃したとしても、それに対する記憶と想起のプロセスは、ひとの数だけあると言えるだろう。
視覚と記憶
アリストテレスが没してから200年以上の後、共和政ローマの時代に思想家として生きたキケローは、記憶における視覚の重要性について、こう語った。
われわれの感覚の中で最も鋭敏な感覚は視覚であり、したがって、耳や思考(脳)によって知覚されるものが、同時に目を媒介として(視覚化されて)伝えられるとき、最も容易に心に留められうるのであり、その結果、目に見えないものや視覚の判断の領域外にあるものは言わば具体的なもの、つまり、イメージや形として書き留められるために、われわれが思考(のみ)によってはほとんど維持できないものも、言わば心の眼によって保持できるようになる……キケロー『弁論家について』
わたしたちの記憶は、必ずしも視覚のみを通じて行なわれるわけではない。見ることだけではなく、聞くこと、嗅ぐこと、味わうこと、触ることによっても、何かを心に刻みつけることがある。しかし、視覚以外の感覚による記憶であっても、それによって想起されるのは、視覚的なイメージなのだ。
プルーストの『失われた時を求めて』の主人公は、マドレーヌのかけらが混じった紅茶が口に触れた瞬間、その匂いと味によって、身震いするほどの「すばらしい快感」に襲われる。その原因を自らのうちに探った彼は、それがある種の「視覚的回想」であることに気づく。そして、幼い頃にいつもお茶に浸したマドレーヌを出してくれた叔母の部屋に始まり、その古い家を取り巻く町の風景、広場や通り、そこに咲く花や住まう人々といった記憶の中のイメージを、尽きることなく想い起こすのだった。視覚的なイメージとしての記憶がもたらす計り知れない力が、そこでは見事に語られている。
キケローの時代からさらに数百年の時を超え、神学者アウグスティヌスが記した『告白』でも、記憶についての省察が行なわれている。そこでは、ひとが何かを記憶するにあたって、さまざまな「加工」を行なうことが説かれていた。
そこ(記憶)には、感覚によってはこびこまれたさまざまな事物についての数かぎりない心象(imago)の宝庫があります。そこにはまた、感覚にふれたものを思惟によって増減し、あるいは何らかのしかたで変えることによって得られたものが、ことごとく収められています。アウグスティヌス『告白』
この引用にある「心象」とは、「物のイメージ」のことである。記憶によって「物のイメージ」を入力するとき、ひとは知的操作を通じて何らかの「加工」を行なうのだ。
さらに彼は、想起によって「物のイメージ」を出力する際にも、それが別の形で「加工」されると考えていた。以下の引用で語られているように、ひとは「物のイメージ」の関係性を築きながら、それを自らの時間のなかに位置づけようとするのである。
(記憶という)このばくだいなたくわえの中から私は、自分で経験したもの、あるいは自己の経験にもとづいて他人の言を信じたもののあれこれの心象をとりだし、過去のものに結びつけ、これらのものから未来の行為と出来事と希望をも考え、これらすべてのものをふたたび、あたかも現在あるもののように考えます。アウグスティヌス『告白』
記憶と想起によって、ひとは過去から未来へと一定の速度で流れるクロノス時間から解き放たれ、カイロス時間のなかを行き来しながら「物のイメージ」を探求できる。アウグスティヌスは、記憶と想起の価値を、そのように考えていたのだろう。
写真による複製の意味
写真とは、ひとが昔から自らの内部記憶としてきた「物のイメージ」を、一種の外部記憶として保存したものに他ならない。ベンヤミンは『写真小史』において、ここまで触れてきた「物そのもの」と「物のイメージ」を、それぞれ「像(bild)」と「模像(abbild)」という言葉で示している。そして、現代人が世界のさまざまな事物の「模像」を複製し所有することで、彼がアウラと呼ぶ「あらゆる状況に含まれる一回的なもの」を克服しようとする、熱烈な傾向が見られると述べた。ベンヤミンは、そこで写真が人びとに与えた意味を、見事に解き明かしている。
像においては一回性と持続性が密接に結びついているとすれば、模像においては一時性と反復可能性が同じく密接に結びついている。対象をその被いから取り出すこと、アウラを崩壊させることは、ある種の知覚の特徴である。この知覚は、この世に存在するすべて同種なるものに対する感覚をきわめて発達させているので、複製という手段によって、一回的なものからも同種なるものを獲得する。ヴァルター・ベンヤミン『写真小史』
写真による複製は、古来から行なわれていた「物そのもの」の複製、すなわち絵画や遺物などの実体的なレプリカの制作とは、まったく意味の違う「コピー」と言えるだろう。写真は「物そのもの」を「物のイメージ」として、いわば擬似的に複製するからである。その「物のイメージ」を、ひとつの撮影データから無数に現像できることによって、「物そのもの」にはなかった反復可能性が生じることになる。
また、誰がいつどんな構図で撮ったかに関わらず、パリのエッフェル塔のあらゆる写真は、ベンヤミンの言う「同種なるもの」として、共通の被写体に対するイメージという同種性を帯びてしまう。写真を通じて、ひとは「物そのもの」にアクセスすることなくそのイメージを共有できるようになり、多くのひとが抱く「物のイメージ」にも同種性が備わることになった。現在のGoogle画像検索、TumblrやPinterestのグリッドレイアウトによる「同種性の視覚体験」は、そのように共有される膨大な「同種なるもの」を一望することを可能にし、かつてなかった快感を与えてくれる。
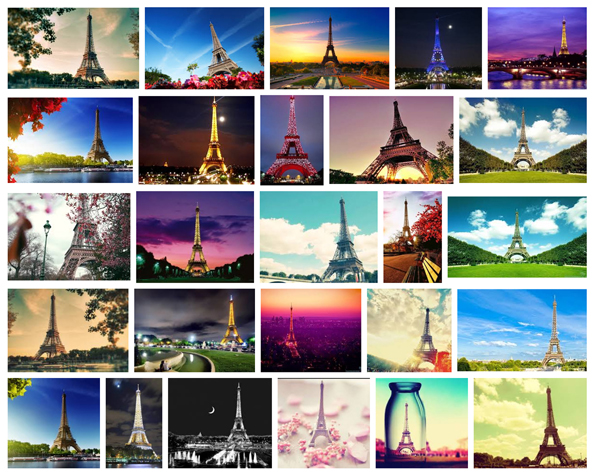 Google画像検索 – “Beautiful Eiffel Tower”
Google画像検索 – “Beautiful Eiffel Tower”
記録のメディアから、記憶のメディアへ
写真がデジタル化されて以来、撮影データの改変は、それ以前とは比較にならないほど容易になった。今でも写真は、「真を写す」という名の通り、真正さを重んじる記録としての役割を果たし続けているが、ひとがよりどころとするのは客観的な記録だけではない。自らの意識と無意識が、美化し、歪曲し、捏造することさえある記憶の数々が、わたしたちを支えている。アウグスティヌスが語ったように、ひとは記憶を「加工」しながら生きているのだ。その欲望を加速させるかのように、デジタル写真は、記録のメディアから記憶のメディアへと、あからさまに価値を転じてきた。
2010年10月にiPhoneアプリとして登場したInstagramの正方形のフレームは、旧来のインスタマチックやポラロイドを知るユーザーにとって、ひときわ郷愁を誘うものだった。また、何種類ものフィルターによって、撮影したばかりの「記録」である写真を、あえてレトロ調に、オールドファッションに、まるでノスタルジックな「記憶」のように加工できるその機能は、瞬く間に数百万のモバイルユーザーを虜にした。そして、そのような写真をネットで共有することが、ある種の強烈な自己表現になることを証明した。そこには、新しい記録を古い記憶に転じることで、「物のイメージ」の価値をすり替えようとする、倒錯した欲望が息づいている。
その一方でわたしは、いつまでも忘れはしないと思える場面を目にしても、それを写真という一種の外部記憶として残すことを避けてきた。自分にとってかけがえのない瞬間を、写真として切りとることは、その豊饒さを薄めるだけの行為に感じられた。写真にして残さなくても、この場面は自分の内部記憶のなかでずっと消えることなく、色褪せることもないはずだ。そんな風に思っていた。
でも今は、まったく逆のことも言える気がしている。自分の内部記憶が、いかに自らの都合のよいように作り変えられるか。写真となった外部記憶が、そこでの経験をどれだけ濃密に想起させるか。それらを思うとき、二つの記憶を分け隔てようとすること自体が、意味を失ってくる。写真という「断片的な時間の記録」は、ひとの内なる記憶と融けあってどこまでも流れ出すような、「限りない時間の記憶」にもなるのだろう。
写真は切りとられて見えるものである。しかし最良な写真は、そのことを半ば忘れさせる。ジョン・シャーカフスキー『ウジェーヌ・アジェ写真集』
 Eugène Atget “Rue de la Montagne Ste. Genevieve” (1924)
Eugène Atget “Rue de la Montagne Ste. Genevieve” (1924)
テクノ画像📺と意味の旋回性🍥
ここで、テキストフィールド内の絵文字🐴を考えるために、ドイツのメディア論者であるヴィレム・フルッサーを参照したい。フルッサーはヒトのコミュニケーションを、画像、テキスト、そして「テクノ画像」という3つのコードに分ける。フルッサーによると、ヒトは世界を説明するためにまず画像を描き、その後、画像を説明するためにアルファベット🆎を発明し、テキストを生み出した。そして、そのテキストが説明する世界を明解に示すため、画像が表す概念に意味を与えるテクノ画像が現れたとしている。カメラ📷などの「装置」と、その装置を操作する「オペレーター」が融合した複合体によって、線形的テキストがコード変換されて生み出されるもの、それがテクノ画像である。
画像は世界を平面的に記述し、ヒトはその画像平面を旋回🍥しながら、そこに描かれた意味を認識していく。その平面的で旋回的に絡みあった意味を直線のように引き延ばしたのが、テキスト📚である。画像の密度が上がりすぎて世界を認識できなくなったときに、テキストの線形的認識が現れ、世界を明晰判明に把握していった。しかし、この線形的認識でも、また世界を把握しきれなくなったときに、テキストを説明する画像としてテクノ画像が現れたのだ。
フルッサーの3つのコードから考えると、絵文字👽はテクノ画像と位置づけられるだろう。だが、絵文字🔞にはテクノ画像といえない部分もある。テクノ画像は、道路標識⛔️や天体写真🌠のように単独で使われたり、ポスターや新聞📰で使われる写真のようにテキストと並置されたりして、テキストの意味を説明する画像として機能する。それに対して、絵文字🐬はテキストフィールドのなかで、テキストとともに使われるからである。
また、絵文字📚は主にテキストの線形性のなかに組み込まれて使われるという理由から、芸術作品としての絵画🎨のように、平面的で旋回的な認識をつくりだす「伝統的画像」とも異なる存在と考えられる。しかし、絵文字🚽はテクノ画像でも伝統的画像でもないとはいえ、画像であることには変わりない。だから、伝統的画像のように平面全体を旋回させる認識をつくることはできなくても、テキストがつくる意味の線形的な流れに旋回性🌊を持ち込むことはできる。
しかも、その旋回的な意味🌟は、読みの空白💬とともに発生する。そのときテキストフィールドでは、絵文字🌙によってテキストがつくる直線状の意味を曲げて円環状にしようとする力が働くと同時に、旋回させられた意味をテキストの線形性が引き延ばそうとする力も働く。そこでジェットコースターの宙返りのように、意味がクルッ🌀と回って、あっという間に通りすぎていくこともあれば、あさっての方向に飛んでいってしまうこともある、というスリル💦が生まれるのだ。
絵文字🍢を入力するときに起きていること
演出家・脚本家の岡田利規は、言葉としぐさは固有のリズムを持っていて、それらはめったに同期することがないと述べている。そして、しぐさのほうが言葉の生成速度よりも必ず速いとしている。その理由として、「しぐさのほうがアブストラクトな状態のまま現れることが可能だから」と書いた。
絵文字👞にも、このことはそっくり当てはまるだろう。絵文字🎒の意味は言語のように明確ではなく、少なくとも今のところ、まだその意味はアブストラクトである。入力した「🎒」がランドセルという具体的なモノを示しており、それを含むテキストが小学1年生の入学式についての文章であったとしても、テキストフィールドのなかに現れた「🎒」は「ランドセル」という文字列よりもアブストラクトな状態になる。それは、絵文字👓がもともと、しぐさを担うためにコード化されたものだからである。入力するとき、明確に文字として認識する前に選択されるから、なぜその絵文字🔮が使われたのかという理由は、はっきりしないのである。
ここで、絵文字🍕を選択するときの感覚を追っていきたい。今ここでは、「🍕」を選んだのだが、そのときに意識は少し「🍕」にもっていかれる。といっても、その後で「ピザ」や「ピッツァ」という文字を書いてみると、意識が急激にその文字列が示す意味に持っていかれた。「🍕」と入力したときは単に「🍕」でしかなく、これは「ピザ」や「ピッツァ」という文字列とは異なり、意識の流れにほんのちょっとだけさざなみを立てる感じである。流れそのものはテキストが引っ張っていく。感覚としては、テキストがつくっていく流れのなかに、「🍕」という「絵」を置いているという感じである。
しかし、キーボードを絵文字ビューアや絵文字キーボード※1に切り替えて絵文字😅を入力するときには、ちょっとした間ができる。また、例えば「えがお」という文字列を入力すると、利用環境によっては変換候補として「😊」や「😁」が出てくるように、文字列から変換できる絵文字もある。これらの絵文字は、文字を入力するのと同じ感覚で打ち込んでいるのだが、その文字列が「😊」と「😁」のどちらになるかによって、少しずつニュアンスが変わってくる。それは、日本語であれば「ひらがな」「カタカナ」「漢字」と、文字の種類を変えることと同じようなものなのかもしれない。だとすれば、アルファベットのような単一種の文字だけを使う言語での絵文字入力では、それとは違った感覚が生じるのだろう。
いずれにしても、絵文字😝を書くときの変化は、やはり、絵文字ビューアや絵文字キーボードを表示してから、絵文字😶を入力することにあるのだろう。絵文字キーボードで絵文字を入力する際に生じる、キーボードを切り換えるという行為が、テキスト入力の流れに断絶をつくりだし、ヒトの意識に変化を与える。断絶とは言い過ぎかもしれないけれど、テキストを入力する流れのなかで絵文字🔗を使おうとするとき、テキストを書いている流れに変化が起こることは確かだ。
書く文字📝から、選ばれる文字👈へ
絵文字🍒は読みと同様に、書きにも「空白」をつくり、テキストの流れに変化を起こす。絵文字💣の入力は、「書く」というよりは「選択する」という感じであり、それは、入力方法を切り替えて絵文字🔪を選択するさいに、テキストの流れがいったん止まることに起因している。
しかし、絵文字ビューアにしても絵文字キーボードにしても、すべての絵文字📂がそこ✏️にあり、そのなかから選ぶという点では、通常のキーボードと変わらない。もともとキーボード自体が、文字をピックアップするための装置であった。キーボードは、すべて✏️のアルファベットをあらかじめ外に出して示している。あとは選んでキーを押せばいい。「K」を入力したければ「K」のキーを押すだけで、画面に表示される。
フルッサーと同じドイツのメディア論者であるフリードリヒ・キットラーは、蓄音機🎶、映画🎥、そしてタイプライター📃の3つを、近代の技術が生んだ特筆すべきメディアで🙆あると考えた。それらを論じた書籍『グラモフォン・フィルム・タイプライター』で、彼は次のように書いている。
キーボードにみられる一定の数の、かつ一定の配列の文字からの選択であるような書字を、はじめて可能にしたのはタイプライターである。この書字には、いまはすたれた植字工の活字箱をつかってラカンが示してみせたものがそっくりそのままあてはまる。つまりタイプライターの書字では、切れないで流れるようにつながってゆく筆跡とはちがって、それじたい目立たず、スペースによって個々に分割された要素がただ横並びに連結されているだけなのだ。サンボリックなものとは、だから要するに、ブロック文字というステイタスのことなのだ。フリードリヒ・キットラー『グラモフォン・フィルム・タイプライター』
コンピュータのキーボードの先祖ともいえるタイプライターは、文字を「スペースによって個々に分割された要素がただ横並びに連結されている」という状態にした。そしてここで、キットラーとフルッサーがともに指摘するように、タイプライターがその後、コンピュータ💻と結びついたことを忘れてはならない。「タイプライターによるブロック文字の標準配置図を計算可能性という技術そのものへと転換したこと」※2によって、コンピュータがつくられた。そして、タイプライターの文字をバラバラ💔にする性質はコンピュータに引き継がれ、キーボードのみにとどまらず画面上にも、コンピュータの機能を個別に示す画像がアイコンとして表示されるようになり、ファイルやフォルダのアイコンがマウスとカーソルで選択されることになった。スマートフォンも基本原理は同じで、画面に表示されている文字やイメージを選択していく。その延長線上にソフトウェアキーボードがあり、そこで絵文字🍤が選択されているのである。
ただし、絵文字🍅が文字と異なるのは、それぞれの絵文字🍍がある程度のまとまった意味を示すことで、ヒトに何かしらのリアクションを引き起こす刺激となっている点である。「J」は「J」として特定の意味をもつことはないけれど、「🍏」はひとつで「りんご」という意味を示すとともに、絵文字🔋の絵の部分が、言葉以前にヒトに何かしらの反応を与えるものになっている。ヒトから何かしらのリアクションを引き起こす、一定のまとまりの意味をもった絵💰を選択するということが、身体的筆跡をバラバラにしてスペースでつないだタイプライターの文字とは異なるのである。
感情😵をなめらかに選択する🏄
タイプライターは書字から身体性を奪うと同時に、身体性を与えたものでもあった。マーシャル・マクルーハンは、その有名な『メディア論』において、タイプライターで書かれた詩の真髄は音読してこそわかると書き、以下のように続ける。
エリオットとパウンドは、彼らの詩の中核となるさまざまな効果をあげるために、タイプライターを使った。彼らにとってもタイプライターは、口踊的道具であり、身体の動きを模倣する道具であって、これによってジャズやラグタイムの世界のあの口語的奔放さが獲得できたのである。マーシャル・マクルーハン『メディア論』
タイプライターが「書く」という行為から単に身体性をなくす道具ではなかったことを、マクルーハンは詩人の事例から指摘する。ただ、それは文字を「読む」ことから感じられるリズムであり、絵文字🔑の空白とは相容れない。しかし、タイプライターの打鍵音が詩人にリズムを与えたと考えてみるとどうだろうか。つまり、ペン📝によって紡がれていく、なめらかなつながりの書き方から、タイプライターという装置とともに行なう、打鍵音🎶による区切りの感覚が強い文字入力へと、書字行為のリズムの変化があった、と考えてみたいのである。
マクルーハンはこの書字行為のリズムの変化をテキストから聴き取り、そこに電気⚡の時代に適した身体性を読み取った。タイプライターが、バラバラの文字を打鍵音のリズムとともにスペースで区切りながらテキストの流れをつくり、電気時代の身体性を文字列に招き入れたのだとすれば、書字行為の断絶や意味の空白、そして発音できないという絵文字🔨の「スペース」💬をつくる性質が、コンピュータ時代の身体性をテキストに招き入れたのだ。
絵文字🐲はこうしてテキストの流れに、ヒトがペンでなめらかに書くのでもなく、タイプライターとともに打鍵音をリズム良く響かせながら間歇的に文字を選択し続けるのでもない、あたらしい書字行為の流れをつくりだした。それは、コンピュータがなめらかに表示していく絵文字🗿を、タイプライター同様に間歇的でありながらも、表示上のなめらかさに引っ張られるかたちで、ヒトがスムーズに選択していくというものである。
間歇的であり、かつなめらかに続いていく絵文字🍁を含んだ文字列から、コンピュータを起点とするあらたな身体性が生まれたといえる。岡田はテキストと絵文字👶はいずれも、「グロテスクな塊のような状態のもの」からつくられると表現した。その塊を、文字ではなくしぐさのリズムで分割し、一定の選択肢としてフラットに並べて見せるのが、絵文字ビューアや絵文字キーボードなのである。文字を空白で区切り入力できるようにしたタイプライターが一文字ずつ個別の文字入力を可能にしたように、絵文字📦は本来なら途切れることのない感情😍😖😡を、あらかじめ区切るツールということができる。
そう考えると、絵文字😜を使うことを覚えた私たちが、多彩な絵文字🙀に感情や身体感覚を引っ張られて、熟考することなく半ば反射的に、なめらかにテキストを入力していることも納得できる。このことは、絵文字🏈のなかでも特に、ヒトの表情を示す顔文字😘に当てはまるところだろう。画像の選択をメインとしたヒトとディスプレイとのインタラクションに絵文字👏が入り込んできて、ヒトは自らの感情😆を、コンピュータが用意した絵文字のリストから選択していくようになったのである。
ヒトの知覚と行為の半分が、ディスプレイを起点にして始まるようになってきた状況を考えれば、テキストフィールドに絵文字😱が入り込んできたことは、コンピュータがヒトの感情を予め区切り、ヒトが用意された感情を選択していくことを意味するだろう。それは、ヒトが自らの感情をコンピュータとともに探っていくようになる、大きな変化の始まりなのである😂😂😂
エモーション😜のなかに生まれる空白💬
2015年の言葉としてイギリスのオックスフォード辞典が選んだのは「うれし泣きの顔文字😂」であった。その選定にあたって、「速さと見た目を重視する21世紀のコミュニケーションに、従来のアルファベット文字が付いていけなくなっている」ことが指摘された。確かに、140文字以内の短文🐤で気持ちを伝えたり、画像🎆🌋🗼を次々に送り合ったりというように、オンラインのコミュニケーションが速さ🚀と見た目👑を重視するなかで、私たちはこれまでの基準からすれば、熟考することなくメッセージ📨📧💌をやりとりしている。
デザイナーのたかくらかずきは、オックスフォード辞典と同様に、絵文字がSNS以降のコミュニケーションに適した文字であることを踏まえて、「感情」という観点から次のように指摘している。
SNSのような、口語的で瞬間的なやりとりには、それらを想像する時間も文字スペースもない。想像している間に、タイムラインは流れてしまうし、140文字では伝えきれない。そんなときに表情が分かる言葉や情景、身振り、声色の感じが分かる文字が、一文字あったらどうだろうか。絵文字はそんなふうに、SNSとぴったり寄り添うことになった。EMOJIは、奇しくもその名の通り、感情(エモ)を表現する「文字」として、世界に受け入れられた。たかくらかずき「SNS以降の視覚表現「絵文字」はそのシンボルとなる」
たかくらの言う通り、SNS以降のオンライン空間では、十全に意味を伝えるための時間もスペースもなくなっている。その少ない時間とスペースを意味で埋めようとして、「表情😗が分かる言葉や情景🌠、身振り👌、声色🎶の感じが分かる文字」がテキストに挿入され、メッセージに感情を与えていく。
その端緒は、Facebookの「いいね!👍」にあったのかもしれない。「いいね!」は絵文字👍ではないが、ボタンひとつでリアクションを示すものであった。それが良いか👍悪いか👎はともかく、クリックするだけで伝わる超低解像度の情報だからこそ、瞬時にリアクションがとれることは確かだ。
絵文字👄なら、Facebookの「いいね!」よりも解像度の高いリアクションがとれる。ただし、「いいね!」にあって、絵文字にないものがある。
絵文字を言葉として考えたときに、音声が付随せず、インターネット上では世界中の多くの人々に伝わるのにインターネット外では一切発言できない言語というふうに考えると、とても不思議だ。たかくらかずき「SNS以降の視覚表現「絵文字」はそのシンボルとなる」
絵文字は発音できないという、たかくらのこの指摘は、当たり前すぎるかもしれない。これまでにも、発音を伴わない「!」や「?」といった記号はあった。しかし、誰も発音できない言葉が突如として大量に現れ、全世界的に使用されているのは、やはり奇妙な現象である。Facebookの「👍」には「いいね!」という「読み」が与えられているのに対して、絵文字🚤には絵文字🍪が示しているものの説明は与えられていても、読みは与えられていない。説明を読みと考えることもできるが、実際に読んでみると、絵文字😞の部分では読みがなくなる。
たとえば、「今日はいい日だった😊」という文を音読または黙読するときに、「😊」を言葉に置き換えて読む人はほとんどいないだろう。もし読むとしても、「笑顔」「スマイル」「ニコッ」などと、その読みは人それぞれに異なるはずだ。「今日はいい日だった」という文字列に、「😊」は楽しげでハッピーな感情や感覚を付与するが、それ自体は読まれない。絵文字👤は文のなかで音として「空白」になるものの、文が全体として示すエモーションのトーンを決める役割を果たしている。
絵文字😉の身体性💪
アートユニット・エキソニモとして活躍する千房けん輔は、Twitter🐤の短文表現や、Instagram🗻などでの画像コミュニケーションで多用される絵文字⚽️のやりとりを、「理屈だけでは使いこなせない、身体に寄り添った「反射神経的」なコミュニケーション手法だと感じる」と述べた。千房はそれに続けて、こう書いている。
先ほど「反射神経」と言いましたが、絵文字にはひとつの文字の中に沢山の意味や感情を込めることができ、しかもそれがコミュニケーションの文脈によっていろいろに意味を変えるということから、いわゆる”文字”のようにどこでどう使っても意味自体は変わらない記号よりずっと高度で、それがまるでテキストの中に現れた身体性のようなものではないかと思っています。千房けん輔「デザイン・サイコメトリー 見えないデザイン 第18回」
絵文字🐩を「テキストの中に現れた身体性」とすることは、絵文字🌵が読みの空白を伴うことと合わせて考えると興味深い。読みという行為を伴わない記号が、テキストの内部に身体性をつくりだす。それは、読みがないこと、つまり言語として確立されていないことで、意味が多様になり、それを受け取ろうとする身体と結びつくためだろう。
千房は落語家を例に出しながら、落語👴では話すテキストが同一でも、しぐさや間、声の調子といったテキスト以外の部分🎧によって、まったく異なったものになると指摘する。そして、「メッセンジャーでのやりとりの中でも、絵文字が入ってくることで、笑ったりちょっと困ったり、飛び跳ねたりずっこけたりといった身体的な表現が自然に伝わるようになりました」と書いている。
千房が指摘するように、「しぐさ」や「間」といったオフラインでの非言語的コミュニケーションを、絵文字🌴がオンラインに持ち込んだということはできるだろう。ネット上では、感情や身振りを示すために、読みを持たない絵文字🌻に見られる意味の不確定性が利用されている。多様な意味を生み出す絵文字🗽の読みの空白が、テキストに身体性を招き込んでいるのだ。
インターフェイスのモード💻と絵文字🎮
インターフェイスの観点からは、「テキストの中に現れた身体性」をどのように考えられるのか。イヴ・ジャンヌレは『世界の文字の歴史文化図鑑』に収録された論考「書くことと情報メディア」で、次のように書く。
一つしかない画面───ただしその形状は変化しうる画面───上に、さまざまな異なったドキュメントを表示することを可能にしているのは、この機械に記入されたコードと、目に見えているディスプレイ表面とのあいだの関係なのである。読み手にとっては、これらのオブジェクトは一つの画面として目にうつるが、しかしそれは、これらのオブジェクトの性質の解釈を統合する、さまざまな処理によって可能となっている。例えば、文書は「テキストモード」(文字列)としても、「イメージモード」(空間構成)としても処理されることが可能となる。アルファベットのコードから解放されることで、コンピューターシステムは、動作、テキストの画像入力、その空間操作を徐々に押しすすめ、イメージの読み取りに基づく解釈を現代に復活させたのである。こうしてインターフェース工学が、テキストのフォーマットや、そのイメージ入力、画面上での操作に用いられる手段を開発したことにより、音読と黙読に続く新しい読み取りの形式としての、「動作による」とでも言うべき読み取りが確立されたのである。イヴ・ジャンヌレ「書くことと情報メディア」
ここでの「動作」の主体は、ヒトではなく、コンピュータである。コンピュータはコードを処理することで、テキストを文字列としても、画像としても表示する。このような状況をジャンヌレは、「テキストは物質化されないわけではないが、個々の物としての性質を失い、機械的な処理によってテキストを読みだす、動作による読み取りの行為に応じ、都度、繰り返される一回性の出来事となった」と指摘する。コンピュータが主体となる「動作による読み取り行為」によって表示される画面に、ヒトが反応することになったのだ。
「動作による読み取り行為」のひとつの結実であったのが、「アイコン」💾の誕生👶だろう。アイコンは、コマンドを覚えてタイプするCUI(キャラクター・ユーザー・インターフェース)から、見て選択するGUIへと、コンピュータ操作の原則を変えた。CUIからGUIへの変化は、コンピュータの画面が「テキストモード」から「イメージモード」へと移行したことを示す。それは、キーボードでの一文字ごとの選択を、画面上でまとまった意味をもつ「絵」🎨の選択へと変化させた。その結果として、ヒトは「指差し」👈という最小限の行為で、ある程度まとまった意味をコンピュータに示せるようになった。しかし、それはコンピュータが前もって遂行した「動作による読み取り行為」に対するヒトの反応である。だとすれば、一定の意味や感情を示す言葉を、コードとしてコンピュータに登録しておけば、ヒトは積極的に「コードの選択」というリアクションをするようになるのではないだろうか。そのようにして生まれたコードが、絵文字🎊なのである。
コンピュータのインターフェイスは、操作に必要な要素をあらかじめ画像として表示することで、操作に必要なヒトの行為を「指差し」👉のみにしていく流れにあった。そして、身体的な行為を最小限に抑えたまま、画面上のテキストに身体性を組み込む手段として、絵文字🍝がテキストフィールドに入り込んできたと言える。
日常的コミュニケーション📢のスリル💦
ここで、インターフェイスに絵文字🍲が持ち込まれた理由を、絵文字を入力するヒトの側から考えるために、演出家・脚本家の岡田利規が書いた演劇論「演劇/演技の、ズレている/ズレてない、について」を参照したい。
しぐさは、言葉からではなく、〈イメージ〉から生成されてくるものだと僕は思っています。そして言葉もまた、〈イメージ〉から生成されたものとしてパフォームされるべきものだと、僕は思っています。……ここでいう〈イメージ〉とは、言葉という形や、しぐさという形を取る以前の、グロテスクな塊のような状態のものが溜まっている場所みたいなもののことです。人はそこから言葉という形にして、あるいはしぐさという形にして、一部を取り出してみせます。岡田利規「演劇/演技の、ズレている/ズレてない、について」
岡田の指摘に沿うならば、テキストと絵文字👶は、それらが形になる前の「グロテスクな塊のような状態のもの」からつくられることになる。言語的コミュニケーションと非言語的コミュニケーションを、同じソースから発生したものと考えてみると、テキストフィールドという同一の場で線形的に並べられるテキストと絵文字👨👨👦の関係を捉えやすくなる。
ヒトはもともと、オフラインのコミュニケーションのすべてを、テキストフィールドに持ち込みたかったのではないだろうか。そのために、ヒトはコンピュータにおける文字を規定するUnicodeでコード化された記号を利用し、「:)」や「(^^)」といった顔文字をつくりながら、コミュニケーションを行なってきた。そしてついに、絵でもあり文字でもある絵文字👨👨👦👦をコード化することで、コンピュータでのコミュニケーションに「しぐさ」を取り込んだ。
岡田は〈イメージ〉から「言葉」と「しぐさ」が発生すると述べたが、コンピュータではもともと言葉しかコード化されていなかった。そこに後付けで、しぐさを絵文字⛳️へとコード化して、〈イメージ〉をつくったのだろう。いや、そもそもコンピュータでは「言葉」も後付けなのである。コンピュータではヒトとのコミュニケーションがすべて後付けであり、それゆえにUnicodeという統一コードをつくることができたともいえる。その結果、テキストフィールドで言葉としぐさを同様に扱えるようになり、日常的コミュニケーションにおける身体性がコンピュータに持ち込まれた。Unicodeは絵文字🎰を取り込んだことで、言葉ではなく「グロテスクな塊のような状態のもの」💨を、そのままコード化📖したのである。
では、Unicodeが言葉のコード化だけで満足できなかったのはなぜか。ここでも岡田を参照しよう。
話をする身体の中には、言葉がパフォームされる際のリズムと、しぐさがパフォームされることのリズムとが、並行して身体の中を走ることになるわけです。そのときふたつのリズムが、その都度一致したりズレたりする。複数のリズムが並行してひとつの身体を走ること、その拮抗が、スリルを惹起します。これが僕の言う「スリル」です。岡田利規「演劇/演技の、ズレている/ズレてない、について」
絵文字💍はテキストフィールドのなかで、言葉とは異なるリズムで使われる。テキストフィールドに言葉と絵文字🎯のふたつのリズムが走り、そこにスリル💦が生まれる。それが絵文字🐮を巡る現状であり、これからも絵文字🏄はそのスリル💦を保ち続けるだろう。Unicodeは言葉と共にあるしぐさや声色などといった身体性を絵文字🏊として実装し、異なるリズムを持つ言葉としぐさを並行して使用できる環境をヒトに提供した。ヒトはテキストフィールドに、日常的コミュニケーションで感じているスリル💦を持ち込みたかったのだ。しかし、それは逆に、コンピュータがUnicodeという仕組みを用いて、ヒトの「グロテスクな塊のような状態のもの」を取り込み、感情や声色といった身体性というコード化しづらい領域さえ、コードとして処理できるようにしたことも意味するのである😋😋😋
インターフェースとしか言えないもの
「デザイン」という言葉が大量生産の登場と共に生まれたように、今日の「インターフェース」という言葉は、コンピュータの登場によって生まれた概念だ。コンピュータ以前の道具にとって、カメラのシャッターボタンはシャッターボタンであり、ピアノの鍵盤は鍵盤であって、インターフェースではなかった。インターフェースとは、コンピュータという新しいメタマシンを、見慣れた道具や機械に似せることで、既存の経験や個人の慣習の領域に引きずり込むための表象であった。
インターフェースを現実世界に存在するものに似せてつくる「スキューモーフィズム」。それはすでに、身の回りの素材やモノに溢れていた。木造住宅をレンガのようにみせるサイディングや、木目が印刷された壁紙、大理石のようなプラスチックなど。これらもコンピュータ以降の世界では、インターフェースと呼ばれていいものだろう。
しかし、こうしたスキューモーフィズムから「フラットデザイン」へと移行したことによって、グラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)におけるメタファーは消えた。インターフェースは、メタファーを作動させる場ではなく、かつてのカメラのシャッターボタンやピアノの鍵盤と同じように、「インターフェースとしか言えないもの」になった。
ブレイン・マシン・インターフェースの登場
そうした中、脳に機械を接続する「ブレイン・マシン・インターフェース(BMI)」が、近年急速に発達しつつある。このBMIが実現しようとしているのは、脳による機械や道具の「直接操作」だ。多数のニューロンの活動を同時に検出することができる電極を脳に挿入し、そこから得られたデータをコンピュータで解析することで、外界のロボットアームやマウスポインタを操作する。人間の脳のニューロンの大集団が繰り広げる、絶え間ない動的作用の一部を抽出することで、人間の思考や感情、概念やイメージを復元したり変化させようとする。それがBMI研究の目標だ。
人間の脳と機械や道具を、直接電子回路で接続することで実現されるのは、考えただけで外界を操作したり、人々の思考や概念を直接結びつけることである。こういった「直接操作」は、一度GUIにおいて消滅したはずのものだったが、今それが再び、究極の姿で復活しようとしている。
直接操作は、1989年にApple Computer社が出版した「ヒューマン・インターフェース・ガイドライン」でも示されていたとおり、GUIにおいてその根幹をなすデザイン原則のひとつであった。それはユーザーにコンピュータを意識させることなく、メタファーを直接操作しているような感覚を与える「画面環境」を提供するべきだ、という設計思想である。
直接操作から委譲への転換
古典的なスキューモーフィックGUIは、目の前にある具体的な物体を、メタファーによってあたかも直接操作しているかのような感覚を与えることで、ユーザーのメンタルモデルと行為や思考を一致させようとした。しかしながら、1996年にヤコブ・ニールセンが「Anti-Mac Interface」で指摘したように、コンピュータの性能とインターネットがその後急速に発達するにつれて、その原則は揺らぎ始める。
まずはプロセッサーやメモリの進化によって、コンピュータの容量や速度が急速に増大し、コンピュータのタスクが人間の思考の枠内に収まらなくなってきた。さらにインターネットの発達により、場所や空間の制約が希薄になることで、操作の対象が身体の枠を大きくはみ出し始めた。その結果、インターフェースは否応なしに、モノや身体を越えなければならなくなった。
そこで必要とされたのが、デザイン原則を「直接操作」から「委譲(デリゲーション)」へと転換させることであった。「委譲」とは、操作を相手に委ねること。つまり、コンピュータを自分ですべてコントロールしようとするのではなく、「良きにはからえ」と任せてしまうことを意味している。一旦操作を相手に任せてしまえば、そこに現実世界のメタファーはもう必要ない。
たとえば、1998年にGoogleが公開を始めたミニマルな検索インターフェースには、フィジカルなメタファーは存在せず、検索語をキーボードで入力するフォームがあるだけだった。それまでのウェブディレクトリやポータルサイトのような、現実世界の住所録や索引のメタファーにもとづいた、煩雑なインターフェースとは対照的だった。思い起こせば、これこそが今日のフラットデザインの源流だったのかもしれない。インターネット検索という道具は、物理世界にそれまで存在しなかったので、スキューモーフィックなインターフェースを当てはめる必要がなかった。むしろ私たちの側に、その新たな使用法や思考法が必要とされた。
僕が1999年に書いた『消えゆくコンピュータ』でも参照したが、認知意味論では言語の意味の源が、人間の身体や地球環境にあるとされる。だからメタファーを用いたインターフェースも、そうした言語と同じ構造であると主張した。インターフェースとは、その中に身体がたたみ込まれた言語なのだ。しかし脳のイメージ、すなわちニューロンの動的なパターンを検出するBMIにとって、言葉は必要不可欠なものではない。インターフェースという言語にメンタルモデルを反映させるのではなく、メンタルモデルやイメージそのものと直接接続しようとするからである。
窓と鏡のインターフェース
科学技術を社会に普及浸透させていくためには、文化や芸術の力が必要不可欠である。BMI技術も、それが多くの人に使われるようになるためには、GUIと同じようにインターフェースのデザイン、つまり「ブレイン・マシン・インターフェース・デザイン」の確立が欠かせない。BMIでWIMP※1のような既存のGUIを操作しても意味がない。1984年のMacintoshの登場時に、スーザン・ケアによるフォントやアイコンのデザインが必要とされたように、BMIのデザインにも、これまでのデザイナーが考えていなかった、新しい「何か」のデザインがきっと必要になるはずだ。その「何か」とは、一体どのようなものだろうか。
ボルターとグロマラが提示した、インターフェースにおける窓と鏡、すなわち透過性と反映性の二元性は、脳科学においても重要なテーマである、身体感覚(窓)と自己認識(鏡)に対応している。BMIにとっても、おそらくこの窓と鏡は、重要なリファレンスモデルになるはずだ。
BMIには、情報を外部から内部に伝える、人工内耳や人工網膜のような「感覚入力型」BMIと、逆に内部の情報を外部に伝える「身体操作型」BMIがあり、両者を含めて「BMBI(ブレイン・マシン・ブレイン・インターフェース)」という人もいる。BMIの実験から明らかになったのは、そのいずれのBMIにおいても、人間の脳の側が直接的に変化する、ということだ。脳に接続した電極の解像度が、脳のニューロンのスケールよりもはるかに粗くても、その少ない情報から他の情報を補完したり生成できるように、脳の側が変化する。つまりBMIにおいては、メンタルモデル「を」操作することと、メンタルモデル「が」操作することが、同時に発生している。
今後のインターフェースを未来から逆算する
BMIというインターフェースの新たなゴールを踏まえれば、人間を中心に考え、そこにインターフェースを適合させることよりも、「人間はインターフェースによってどれだけ変化できるのか」を考えることが、ますます重要になってくるだろう。BMIによって、人間の知覚や認識、概念や思考、さらには感情や行動は、その人為的なインタラクションによって変化し、そこから人間ができることや、人間そのものの可能性を拡張できる、というヴィジョンがあるからだ。
考えてみれば、BMIの登場を待たずとも、既存のコンピュータとインターフェースによって、人間はものの見方や考え方を大きく変化させてきた。BMIは、こうした「インターフェースの良し悪しは、それがどれだけ人を変化させたかで測られる」という価値観を強化し、変化と多様性を受け容れる文化を再肯定してくれる。メタファーが消えたフラットデザイン以降のインターフェースの可能性は、きっとそこにあるはずだ。
インタラクションには行為のコストがある。インタラクション自体のみならず、その行為を始めるまでのインタラクションのコストを考えることが大切だ。今回のテキストでは、主にVR(ヴァーチャルリアリティ)やAR(拡張現実)におけるインタラクションの問題を例に、「インタラクションコスト」について考察していく。
ここで注目するのは、プロダクトやサービスを利用する際のインタラクションではなく、その体験の「外部」で生じるインタラクションである。インタラクションコストという用語で示したいのは、利用状態に入るまでのインタラクションが、行為を始める上での障壁になるということだ。
体験の外部にもあるインタラクション
現在「VRとインタラクション」について聞くと、没入感を高めたり酔わないようにする設計など、VRコンテンツというVR空間の「内部」に関わる話がほとんどだ。そこにも多くの課題はあるものの、筆者が常々思う課題は、VRコンテンツにおけるインタラクションではなく、HMD(ヘッドマウントディスプレイ)やGoogle Glassのようなメガネ型のウェアラブルデバイスを着用するシチュエーションでのインタラクションにある。つまり、それらのデバイスを、いつどこで身に付けて使えば最適なのか見えてこないのである。
最初のVRのブームは、アミューズメント施設などでイベント的にVRを体験するには役立った。新しい体験をしたいがために、その場に足を運ぶ意味があった。しかし、今はかつてのエンターテインメント体験ではなく、よりコンシューマー向けで日常的な利用への期待がある。そのような利用体験を実現するには、VR/ARに入る前に何らかのデバイスを装着するという、インタラクションコストが課題となる。
インタラクションコストの例
たとえば、据置型のビデオゲーム機では、テレビに接続して電源をオンにすればゲームを体験できる。これでもゲームを開始するまでのインタラクションコストはそれなりに高い。ニンテンドーDSやPSP、スマートフォンなどでゲームをする方が、いつでも始めやすく止めやすいゆえに、行為が日常化される。今日電車の中をみれば、男女問わず多くの人がゲームをしていることがわかる。
それに比べて、HMD装着型のVRはどうだろうか。現在のHMDは画質も高いし、頭の動きのトラッキングにおけるレイテンシ(遅延)も少なく、自己帰属感も高い。そのHMDをかぶるという条件さえクリアすれば、そのVR空間を現実のように感じられる体験ができつつある。しかし、この「ただかぶるだけ」という行為が、実は大きな障壁になっている。
こういったシンプルな手順であっても、それが利用状態へ移る障壁になることが、多々あるのだ。
たとえば、インターネット接続もそうだ。SIM内蔵で常にネットに繋がるタブレットと、Wi-Fi接続のみのタブレットでは、使い勝手がまったく違う。同様に、かつてインターネットを利用する度にダイヤルアップ回線で接続していた時代と、常時接続が可能になった現在では、料金体制だけでなく利用体験そのものに大きな差がある。
スマートフォンのカメラの画面に、CGを重ねて表示するタイプのARアプリも同様だ。カメラをかざすだけで関連情報が提示されるシンプルな仕組みだが、アプリをインストールしてあったとしても、日常的にカメラをかざすという行為は、シンプルに見えて大きな障壁だった。
アプローチャビリティという尺度
こういった利用状態への移行しやすさの尺度を、筆者は「アプローチャビリティ」と呼んでいる。使いやすさではなくアプローチのしやすさ、つまり「使おうとしやすさ」だ。
使いやすいものだとしても、棚の奥にしまうようなものであっては、日常的に「使おうと」しにくい。こうした問題への解決として、スタイリッシュなデザインを採用し、しまわないで生活のインテリアに融け込ませるというアイデアがある。そうすれば、生活の中ですぐに「使おう」とすることができる。たとえば、掃除機や防災ヘルメットなどのデザインでは、そういった工夫がなされている。それに対するモチベーションと行為性を可視化して備えることで、利用状態へと移行しやすくなるのだ。
また、簡単な手順で「ただやればいいだけのこと」であっても、「開始する前に手続きが必要なこと」や「別の行為の流れを中断すること」は、日常化、慣習化しにくい。たとえば、使う度に水道を止めることも、歯磨きをしたりシャワーを浴びている途中には、なかなかできない人が多いだろう。節約を考えれば、こまめに止める方がよいが、意識しなければ習慣として身につかない。こうした「事前の手続き」や「行為の中断」となる作業は、利用前のモチベーションを、利用した後に半減させることになる。あるいは、その作業によって欲求がほぼ消失し、再びモチベーションが高まることがなくなってしまう。なぜなら、人間の欲求は一方向的なものだからである。
心理学者のマズローは、これを「欲求の不可逆性」と呼んだ。欲求の不可逆性とは、一度欲求が満たされてしまうと、再び欲求になることはない性質を意味する。したがって道具のデザインでは、利用の開始について考えることも大事だが、利用の終了や中断の仕方には、それ以上に気を遣うべきである。なぜならその終了状態が、次の利用開始へのアプローチャビリティを決めるからだ。そして、始まりと終わりのデザインが優れているものは、常にアプローチャブルであり、継続利用のしやすさにつながり、生活に融け込む。
VR/AR系のテクノロジーは、このアプローチャビリティの問題を引きずっているように見える。マーカー※1を使ったARは広告などで採用されてきたが、それについては皮肉な話がある。当初は「マーカーを広告に貼り付けて、わざわざ専用のアプリを入れ、わざわざカメラをかざすくらいなら、初めからそこに書いておけばいいではないか」という意見があった。しかし、画像認識技術が進展してマーカーレスARが登場すると、今度は「マーカーがないとどこにカメラをかざしていいかわからない」と言われてしまった。とにかくこの手のARは、生活の中で使うにはインタラクションコストが高く、アプローチャビリティが低かったのだ。アプリをインストールし、カメラをかざした後のインタラクション設計はなされていても、アプローチャビリティを高めるためのデザインは、皆無に等しかった。
ARのブームは、「自分のスマートフォンで何か新しい体験ができるみたいだ、面白そう」というモチベーションに、ほぼ委ねられていた。モチベーションに頼ったシステムが期待に応えられなければ、ユーザはついてこないし、消費されて著しく価値が落ちてしまうことになる。なおさらインタラクションコストの高さは、期待を裏切ることになる。もっとインタラクションコストが低ければ、利用の持続性、生活への融合性は高まったはずだ。こうして、ARは未来の技術の体験版に留まり、一時のブームも過ぎ去って、生活には融けなかった。
VR/AR系のテクノロジーは、HMDなどのデバイスを装着していることや、アプリをインストール済みのスマートフォンを携帯していることを前提として開発されている。だから、それらの前提を疑うことは保留されたり、タブーとなっているように見える。市場に展開しようとする段階になって、それらの前提が必ずしも成り立っていない問題に直面する。まずそこでは、デバイスを身に付けたり、スマートフォンを常に持ち歩く理由が必要なのだ。さらに、それらを継続的に使うための状況も必要になる。それにもかかわらず、こうした方法の設計が、あまり検討されていないように見える。
VR/ARに入るためのインタラクション
インタラクションコストから発想していくと、スマートフォンを使ったARアプリの場合、それを「空間にかざすように利用する」という人の行為をまず考えることになる。今すでにそのような行為をしている人は、何をしているのかを考えてみる。すると、スマートフォンをかざすように使っている人は、「写真を撮る行為」をしていることがわかる。
写真の撮影は、日常的にしている行為だ。ここにARの要素を入れられないかと考えれば、写真を撮るというモチベーションや、自分が慣れているコンテクストを利用できる。そうなれば、撮影の流れの中で、「背後に映り込んでいるお店は、評判の高いラーメン屋」といった情報が提示されるサービスなどが、考えられるのではないだろうか。あるいは、写真をうまく撮るためのARとして、顔の位置に対して最適な構図になるように自動トリミングしてくれるのは、良い機能になるかもしれない。すでに実現されている部分もあるが、そもそも顔認識の技術はARの活用である。
こういった「もともと」ある行為の中でARのインタラクションに慣れてもらうことで、その価値を体験しやすくできるのではないだろうか。新しい技術が生活に融け込むためには、そこで得られる価値だけでなく、その利用に先立つインタラクションの設計、戦略は極めて重要な課題となる。
さて、そんなインタラクション設計の考え方において、大いに参考になると感じているのが、合気道である。
合気道の哲学から考える「円転自在性」
合気道は日本発祥の武道で、世界的にも親しまれている。合気道の本質は、その漢字からもわかるように、「気を合わせる」ことにあるとされている。合理的に身体を運用することで、体格や体力によらず相手を制することができるのが、その特徴である。
書籍『禅と合気道』には、合気道の哲学として「円の哲学」が紹介されており、そこには「心を留めないこと」の重要性が説かれている。
われわれの心は外界に適応しながら、外界に応じて限りなく移り動いていく。しかも対象が好ましいものであれば、心はそこにとどまる。心をとどめるということは、ものに心がとらわれることである。
「自由自在」という言葉があるが、自由とか自在というのは、心が対象にとらわれないことをいう。勝手気ままにということが自由ではなく、どんな対象に対しても心がとらわれないことである。
合気道では気の動きを一カ所に停滞させてはならぬ。どこまでも動いてゆかねばならぬ。技における動作は一時、静止する場合もあろうが、気はとどまることはない。気の流れが無限の流水のように流れてゆくところ、体のさばきもまた円転自在となることができる。鎌田茂雄、清水健二『禅と合気道』
対象は合気道であるものの、「身体と外界との関わり方」を論じていることから、インタラクションを考える上でのヒントになる。合気道は体力的にも認知的にも、無駄のないインタラクションを試行しているように見える。しかも、合気道は動き続けることが通常で、止まることが特別であるとしており、ギブソンの生態心理学における人の捉え方、知覚の考え方に似ているのである。
私たちは、止まっていることが常態であり、動くことが特異であると思いがちだが、実はその逆であり、人間も動物も死なない限り動いている。「止まる」と「動く」という、この「静」と「動」の関係は、機械やシステムでは逆になることがほとんどだ。車もパソコンも、起動してから使う。こうした機器は、起動して初めて意味がある。つまり、それらは「まず起動する」という意識と行為を要求してくる。
一方、ハサミやハンマーなどには、起動という概念がない。その機能に対する行為として、連続的にアクセスできる。合気道の哲学を知ると、行為の流れや円転自在性を得ること、心を留めず執着しないことが、インタラクションコスト、アプローチャビリティを考えるヒントになるのがわかる。
体験の外部を考えるデザイン
VR/AR体験のためにデバイスを装着することは、その目的への動きを止めてしまう。起動を要するデジタル機器はますます増えていくので、それは「ちょっとしたこと」では済まされない。しかも、機能が複雑になるほど、起動への意識と行為が求められる。
我々は起動という概念を、どうにかすべき状況にきている。あるいは、起動を感じさせないインタラクションが必要なのである。電源レベルでなくとも、アプリケーションにも起動という概念がある。これらの切り替えも、また同じ課題である。
実世界であろうと、デジタル機器であろうと、バーチャル空間であろうと、行為を止めずに関われるあり方が、インタラクションコストを下げ、世界をひとつに融かした人々の生活の「円転自在性」を実現するのではないだろうか。
インターフェースデザインという観点から考えると、利用状態の前後のインタラクションや利用までのモチベーションは、テーマになりにくい。インターフェースは、主に体験の「内部」にあるインタラクションに関わる要素であるからだ。しかし、体験の「外部」に生じるインタラクションまでを視野に入れることで、人とデバイスや道具の関係をより幅広く捉え、プロダクトやサービスに対するデザインを考察できるようになる。インタラクションコストとアプローチャビリティは、そのための重要な手がかりとなるだろう。
彼女は携えてきた一巻の詩集を見せる。そしてその大きな楡の木陰に腰をおろし、すらりと伸びた脚を惜しげもなく投げ出して、詩集を読み始める。こうして詩を読んでいると、とても楽しいの、彼女はいう。特に私の好きな詩に出会った時なんかまるで時間がとまっちゃって、私が世界で一杯になってはちきれそうになるわ。谷川俊太郎「世界へ!」
意味を超えた世界
子どもの頃から、詩を読むのが大好きだった。学校の図書室の片隅に並んだ数々の詩集を、わたしはひとつ残らず、貪るかのように読み耽っていた。ことばを通じて、ことばではないものがわたしを満たしてくれるような経験。詩に触れるよろこびは、多感な時期を過ごしつつあった自分にとって、どこか官能的でひそやかなものにさえ感じられた。
しかし、高校生の時に出会った谷川俊太郎の「世界へ!」というエッセイを読んだ時、わたしはおそらく生まれて初めて、「詩とは何か」という問いに向き合うことになった。谷川は言う。「詩は詩と、それに感動する一人の人とによって、初めて完成するものだ。詩自身はそれだけでは何ものでもない」。
一遍の詩が「何ものでもない」ただのことばであるなら、その内部に一定不変の「意味」を込めることは不可能になる。だから、詩を読むという経験は、恒久的に保存された「意味」をそのまま取り出すことではないし、そういった手続き的なやり方による「理解」や「解釈」とは異質なものだ。
後に、バシュラールやエズラ・パウンド、そして西脇順三郎らの詩論を読んで感じたのは、詩人たちがみな「意味」をはるかに超えた世界を、それぞれに作り出そうとしていることだった。
善良な読者は考える。これはどういうことを喩えて言わんとしたのか、または象徴しようとしたのか「わからん、わからん」で頭を悩ます……そうした場合は、読者はその思考そのものの奇異さ、神秘を鑑賞すれば、それで完全な読み方である。少しでもそれに意味づけをしてはポエジイの読み方にならなくなる……その詩が何について言っているのかは考えなくてもよいのである。西脇順三郎『詩学』
西脇が「善良な読者」という穏やかな表現によって指し示したのは、わたし自身も含まれる一般大衆、ごくありふれた読み手のことだろう。そのわたしたちが、詩に限らず何らかのことばを読むとき、「わかる」か「わからない」かという判断基準は、その評価を決定的に左右しがちである。わかりやすさは善であり、わかりにくさは悪であるという、単純極まりない思い込みは、ことばと出会う経験の多彩さを一様に塗りつぶしてしまう。
ことばに理解可能性や実効性を求めようとするほど、わたしたちは暗黙のうちに、充足理由律というルールに縛られてしまう。そのルールに従って、どんな事実にも原因があるはずだと考えるなら、あらゆることばが発せられた理由を必ず説明できなくてはならない。しかし、西脇の言葉を借りれば、詩というものは「自由に想像された思考の世界」である。それは、充足理由律によってものごとを捉えがちな日常とは別の、文字とイメージと音とが断ち切られながらも絡み合うような、豊穣なことばの世界であるはずだ。
実は、そのわたしたちの日常さえ、ある種の「詩的言語」に満ちた世界なのかもしれない。インターネットが環境の一部となり、モバイルデバイスが身体の一部と化した日常のなかで、わたしたちはひたすら他者との「接触」を求めている。曖昧で思わせぶりな態度で、アイロニーや矛盾だらけのことばを交わし合っている。そのようなコミュニケーションは、「意味」のつながりで成り立っているとは限らず、無謬の「理解」や「解釈」によって結着することはないという点において、詩を読むことにも通じているように思える。終わることを必要としないこのコミュニケーションは、不条理だからこそ自由なものとして、わたしたちを誘うのではないだろうか。
接触への欲望、意味の潜在性
オーストラリア政府のデジタル化プロジェクトを率いるデザイナー、リーサ・ライチェルトは、SNSの創成期であった2007年に「アンビエント・インティマシー(Ambient Intimacy)」という概念を提示した。Twitterでのコミュニケーション体験から生まれたというこの概念は、それまで時間や場所の制約によって近寄りがたかった相手に、より頻繁に、より親しみを抱きつつコンタクトできるようになった状況を意味する。肉体関係をほのめかすこともある”intimacy”という単語からは、社会的でドライな「親近感」ではなく、動物的でウェットな「親密さ」が感じ取れる。
遠く離れている誰かが、まるで今ここにいるかのように、何をしているのか、どんな気分なのか、いわば肌感覚でわかり合いたいという、果てなき「接触」への欲望。SNS時代以降のわたしたちは、そのような欲望に突き動かされるがままに、写真や絵文字、顔文字、変形文字、アスキーアートといった別種のことばで伝え合うようになった。相手との親密さという前提がなければ、断片的で無意味にしか見えないことばで溢れ返った世界が、そこに現れる。「うつろなシニフィアン」が、終わりなく行き交うことになる。
重要なのは、その「うつろなシニフィアン」が、それを交換する当事者たちにとって「意味の潜在性」で充ちていることだ。この場合の「意味」とは、一意に定義できるものではなく、工学的に解析できるものでもなく、コミュニケーションが行なわれる瞬間まで生成されないものである。そのような「意味」を秘めた「うつろなシニフィアン」は、ある種の「詩的言語」と呼べるのではないだろうか。
誰かに触れるように何かを伝えたいという思いが強く込められるほど、あらゆることばは、詩に近づいていくように思える。それが他者から見て無意味なものだとしても。
交話的言語と詩的言語
かつて言語コミュニケーションの機能は、主に3種類あるとされていた。送り手の気持ちの直接的な表現である「主情的(emotive)」機能、呼びかけや命令のように受け手に向けられる「動能的(conative)」機能、その状況において話題となる誰かや何かを語る「指示的(referential)」機能の3種類である。ことばというものは、自分自身か対話の相手、または自分と相手以外の指示対象のいずれかを志向するとみなされていた、と言ってもよいだろう。しかし、言語学者ロマン・ヤコブソンは、言語コミュニケーションにおいて重要な機能が他にもあると考えた。
たとえば、コミュニケーション自体を確立させ、継続させることを目的とするだけの言語を、わたしたちは実にたくさん使いこなしている。ここでの言語とは、明確な意味のあることばだけに限らない。電話が切れていないか確かめる「もしもし」という決まり文句、会話をスムーズに続けるための相槌、気まずい発言を中断させようとする咳払いなど、探せばいくらでもある。ヤコブソンはこのような言語が果たす役割を「交話的(phatic)」機能と呼んだ。交話的なコミュニケーションにおいては、伝達される意味内容ではなく、「接触」を保つこと、つながり合っていること自体が目的となる。これはまさに、「アンビエント・インティマシー」を成立させる機能であり、交話的な言語は「うつろなシニフィアン」にごく近しいものとなり得る。
一方でヤコブソンは、言語の「詩的(poetic)」機能の重要性に注目し、こう語った。
〈メッセージ〉そのものへの志向、そのことだけのためにメッセージに対して焦点をあわせることが「詩的」機能である。言語のさまざまの一般問題をぬきにしてこの機能を研究したとしても成果はあまり期待できないが、また逆に、言語を精密に吟味しようとすれば、その詩的機能の考察を欠かすことができない。……この機能は、記号の際立ちを高めることによって、記号と対象との基本的な分裂を深める。R.ヤコブソン「言語学の問題としてのメタ言語」
この「記号と対象との分裂」というヤコブソンの言葉に出会った時、わたしは西脇が考える「新しい関係」のことを想い起こした。それは相反する二つのものの緊張した関係であり、自然や現実ではなく、ポエジーという想像の世界で新たに発見される関係である。
ポエジイはものそれ自身を発見するものでなく、ものの自然や現実の関係を破壊して、新しい予期しない関係を発見することである。……自然の法則によらないで、人間の脳髄の中で思考するのである。西脇順三郎『詩学』
詩において「新しい関係」として見出される「記号と対象との分裂」は、メタファー(隠喩)やメトニミー(換喩)といった言語の比喩的用法を通じて表現される。詩的な比喩は、詩人たちの創作において用いられるだけではなく、わたしたちの日常的なコミュニケーションの一部とも化している。それらが、「うつろなシニフィアン」に見える交話的言語を、詩的言語に転じる可能性を秘めているのだ。だからこそ、時にはたったひとつの絵文字さえ、ことばを尽くして書いた文章よりも深いメッセージとなるのだろう。
もうひとつ、西脇の言葉で見逃せないところがある。「自然の法則によらないで、人間の脳髄の中で思考」すること。彼は、人間が実践や経験を介さずに純粋な思惟のみによって世界を探ること、すなわち「思弁(speculation)」による力の発露として、詩作という営みを捉えていたのではないだろうか。
思弁という救い
芸術の、そしてあらゆる思弁の卓越した美質とは、われわれが《含んでいる》とは知らなかった行動や、行動の所産を、われわれから引き出すことである。われわれは自分について、さまざまな状況がわれわれから引き出すものしか知らない……ポール・ヴァレリー「詩学」(1935)
わたしたちは、経験的にものごとを判断しながら日々を過ごすことに慣れ切っている。しかし、経験は必ずしも生きるための資力になるとは限らない。あらゆる希望を奪ってしまうような経験もあれば、時に人を死に追いやるような経験さえある。言語経験においても、同じことが言える。わたしたちは、あることばによって一生を棒に振ってしまったり、決して癒えない心の傷を与えてしまうことがある。
だからこそ、わたしたち人間にとって、経験だけでなく「思弁」を拠りどころにする道が開かれていることは、限りない救いのように思えてならない。
思弁すること。それは、積み重ねられた過去の経験に惑わされることなく、ひとつの賽子(dice)を投じようとするその瞬間に、実在としての世界をあるがままに受けいれ、未来のあらゆる可能性に思いを至らせることである。
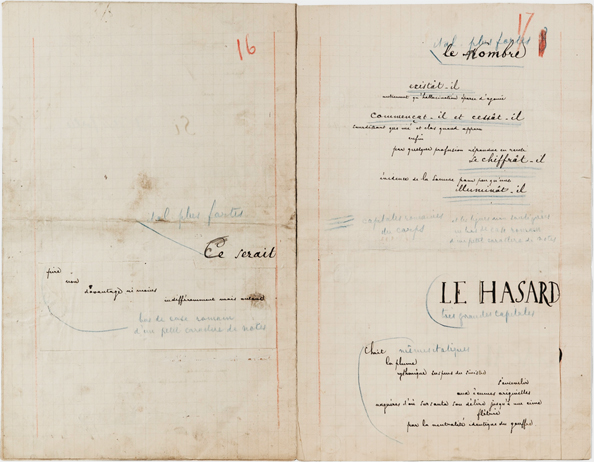 マラルメによる『骰子一擲』手稿
マラルメによる『骰子一擲』手稿
賽子が投げられ、まっさらなページの上にことばが置かれたとき、その瞬間に立ち現れたもの。無でもあり有でもあるその余白が、わたしをその詩の空間のなかに誘い込む。わたしは、マラルメがこの詩を書き記した時間を自らの時間のなかで追いかけ、彷徨い、流され、たゆたい、振り返り、天を仰ぐ。その詩のことばが、いまこの瞬間にしか存在することのない何かとして、自分のなかに刻まれていくのを感じる。
わたしの手の内にある賽子について、自分が今まで経験したことがないような形で考えることを教えてくれたのは、わたしと同時代に生きる哲学者、カンタン・メイヤスーだった。
賽子を振っても「1」から「6」のいずれかの目しか出ないことを、わたしは知っている。自分に与えられた可能性が有限であると思い込んでいる。しかし、経験ではなく思弁によってこの「賽の一振り」を考えるとき、いま自分が握っている賽子と、投げられると同時にわたしの手を離れ、それ自体の運動に委ねられる賽子が、「同じもの」であり続けると証明することは不可能だと気づく。
その賽子が時間の経過と共に、決して予測し得ない変化にいつ曝されてもおかしくないとすれば、たとえば「7」の目が出る可能性さえ、否定することはできなくなる。充足理由律に従う時間は、「1」から「6」の目が出るといういずれかの可能性を現実化させるための媒介でしかないが、メイヤスーの考える時間は、その可能性に含まれていない新たな事象を、自ら創造することができるからだ。思弁によって考えるならば、時間は有限の可能性を顕在化させるのみならず、賽子を振るその瞬間に到来する予測不可能な事実を、完全な無のなかから生じさせるかもしれないのである。
いかなる必然性にも確率にも従わず、先行する状態にまったく含まれていない状態を創発させることができる時間。そのような時間を考えるとき、現在は未来をはらんでいるわけではなく、過去の経験から未来を予測することもできない。それは人間にとって厳しい現実となるかもしれないと同時に、わたしたちの未来が、充足理由律から解き放たれることを意味している。
時間は、実在的なものと同様に、可能的なものをも創発させるのである。……時間は、賽子を振るが、それは賽子を粉々にするためであって、また可能的なもののすべての計算の彼方で、それらの面を増殖させるためなのである。カンタン・メイヤスー「潜勢力と潜在性」
関係から解き放たれた世界
わたしたちが日々の時間のなかで為そうとしているのは、言語や意識を駆使して、自分を取り巻く世界との関係を不断に築くことである。それは、関係を通じて自分以外の存在を理解しようと望むからだ。
では、自分がこの世からいなくなったとき、世界はどうなるのだろうか。人間が主体となって関係を結ぶときにのみ、世界がわたしたちの前に現れるのだとすれば、わたしがこの世からいなくなったとき、わたしがいた世界も消えてなくなるだろう。でも、そんなことはあり得ない。たとえわたしが存在しなくなっても、世界は何事もなかったように、それまでと変わりなく存在し続けるはずだ。自らの経験をあてにしてそう信じようとするとき、わたしが関係を結んでいる世界とは、自分の外にある全き存在のように見えながら、実は自分の内にある限られた対象でしかないという矛盾に気づくことになる。
わたしが素朴にもその永続性を信じている、自分自身を含めたあらゆる存在と無関係な世界。それは、カントの言葉を借りるなら「物自体」としての世界である。人間は、思考と存在の「相関」にしかアクセスすることはできない。そう考えることが主流となったカント以降の哲学では、「物自体」としての世界をあるがままに認識することは不可能だとされてきた。わたしたちはあらゆる存在を、自分との関係を通じてしか捉えることができない。あらゆる存在は、自分がそれをどのように思考するかに従って、わたしたちの前に現れる。
メイヤスーは、その「相関主義」との決別を試みようとする。わたしたちが何かを思考するためには、まずその存在を対象として認識できなければならないのに、相関を通じて初めてその存在が現れるとするなら、明らかな矛盾が生じるからだ。この世界は絶対的な存在ではなく、すべてが関係性によって決まるという、現代において支配的な考え方に浸っている限り、わたしたちは自らの外に出て「物自体」としての世界を思考することはできない。その理由は、こう語られている。
私たちは言語と意識の外部性のなかに閉じ込められているからであり、私たちは〈つねにすでに〉そこにいるからであり、「世界 — 対象」を外から観察できるような視点をもっていないからだ。カンタン・メイヤスー「有限性の後で」
しかし、相関主義の支配より以前の時代には、それ自体として絶対的に存在している外の世界を「異邦の土地であるという確かな感情と共に駆け回ることができていた」と、メイヤスーは語っている。そして、今では失われたかに見える「物自体」としての世界を、こう表現した。「人間のいない世界、現出に相関しない物や出来事で満ちた世界、世界への関係と相関しない世界」。相関主義を乗り越えて「思弁」することで、彼はそれを取り戻そうとしているのだろう。
その世界が何かによく似ていることに、わたしはふと思い至る。定義や論理、そして文脈という「関係」の網の目から解き放たれ、「思弁」された自由な世界。それのみでは何ものでもない存在でありながら、読む者と邂逅した瞬間にあらゆるものになり得るような潜在性を秘めたことばの世界。それは、詩の世界そのものだ。
経験としての思弁
日々のコミュニケーションのなかで、賽子を振り続けるように不確かな詩的言語を紡いでいくわたしたちにとって、もはや「理解しあうこと」は最優先ではないし、最終目的でもなくなりつつある。わかりあえなくても、つながっていればいい。そう考えることは、むしろ人間の動物的な本性に忠実な欲望なのだろう。わたしたちが生きていくためにはどちらも大切で、比べることはできない。
そして、ふとわたしは、こんな思いにもかられる。経験と思弁とは、どこか重なっているのではないだろうか、と。なぜならば、思弁もやがてはまたひとつの経験として、自らの内に刻まれていくはずなのだから。他の誰でもない自分自身が、二度と戻ることはできないその場その時に為し得た、賽の一振りとして。
わたしが愛する詩人たちは、そのような「経験としての思弁」のひとつひとつを、偶然を必然とするようなことばに変えて、わたしに届けてくれるように思えてならない。でも、わたし自身が日々紡ぎ続けていることばは、そのように誰かのもとに届いているのだろうか。わたしはそれを知る術もなく、読むたびに新しく感じられる詩のように、二度と同じ形で繰り返されることはないコミュニケーションを続けながら、世界とひそやかに出逢っていくのだろう。
あらゆる存在は一度だけだ、ただ一度だけ。一度、それきり。そしてわれわれもまた一度だけだ。くりかえすことはできない。しかし、たとい一度だけでも、このように一度存在したということ、地上の存在であったということ、これは破棄しようのないことであるらしい。リルケ『ドゥイノの悲歌』
あなたの方からみたらずゐぶんさんたんたるけしきでせうが
わたくしから見えるのは
やっぱりきれいな青ぞらと
すきとほった風ばかりです宮澤賢治「眼にて云ふ」
ネットワークする身体の発生
どちらが最初であったかはわからないが、人間は道具を使い、肉体に衣服をまといはじめたときから、人工的に自然環境へ接続されてきた。そして言語の登場が、この接続のあり方を概念化・分節化し交換すること、つまり世界化することを可能にし、物理的な肉体と相同ではない「身体=意味を胎んだ体」の獲得へと人間を導いた。
身体の起源を端的に述べればこうなるだろう。
人間の存在を物理の層、現象の層に分けてとらえるとき、この二つの層をバインドする情報の層が「身体」である。それは西田幾多郎やメルロ=ポンティの指摘するように、意識の働きにより「道具」を媒介として世界を取り込むように延長していく、イメージのシステムでもある。
行為や直感を、身体へと媒介する「道具」。インターネットの発達は、この道具の在り方を劇的に変えてしまった。道具は様々な物質的な制限から解放され、ダイナミックに相互作用し続けるネットワークに変化したのだ。今や私たちは目には見えない「透明な道具」を休みなく使用し続け、時折それを可視化・実体化させるという行為の連鎖の中に生活している。
このような状況では、経験によって更新されゆく習慣的身体と、イメージ駆動する延長的身体の境界を、一意に区別することは難しい。なぜなら媒介自身のネットワーク性によって、四次元主義※1のような時空に広がった存在のパターンや、連続性・不連続性を編み込んだ離散的※2な様相などが立ち現れ、身体もそれらの性質と不可分になってしまうからだ。
同時に「ネットワークであること」は、単なる「接続」ではなく、関係やつながり方、それ自体が何らかの「演算」となるような論理、そしてその作用機構、ということでもある。
この視点からすれば、「人間が経験とイメージをネットワークとして計算する、その実装」のことを「身体」と呼ぶ方が適切な時代になったと言える。私たちは今や「ネットワークする身体」「計算する身体」を持つ生き物になったのだ。
onformative “unnamed soundsculpture” (2012)
身体の「延長」について
「身体」と「肉体」とは一致しない。それは「想い」と「現実」とが一致しないことに似ている。大脳新皮質の機能からすれば、「世界」は独立した実存というよりも、想いや現実をひっくるめ、記憶や認知を使って不断に予測される「対象」である。
言い換えれば、人は誰でも「世界」を連続的に生成し続けている。今この文章を目にした瞬間も休むことなく、あなたは「世界」をつくりだしている。
もしここで、この文章から目を離し壁に注意を向けたとしよう。すると、あなたの意識は空間の方へ向かって伸びていく。そこに落ちる影の形、光源の色、それらを包み込む音の響き。受け取られる表象の一つ一つがノードとなって、今この瞬間のネットワークを生成する。その実感は、身体がノードへ向かって「延長」されていることの再発見そのものだ。
そしてこのような「延長」の離散的な機会に応じて、私たちの身体は偏在する。収束する手段を持たない「拡張」の原理とは趣を異にし、「延長」のネットワークは、私たちから離散しながら再び私たちのところに着地する。数学的には自己準同型※3と呼ばれるような、この構造とつながりを介して、私たちは情報としてアップデートされていく。
こういった身体の延長性・偏在性は、情報技術によって社会のネットワーク密度が高まるにつれて、プライバシー、リスク、トレーサビリティといった概念が重要になってきたことからも理解可能だ。これら日常の至る所で展開可能な安全概念は、個人がそれを意識していないときにこそ自動的にしっかりと機能しなければならない。故に、今すぐには使用されない多種多様な情報に対しても、予め身体が行き届いていることが必要となってしまうのだ。
フェティッシュ・情報・マナ
ところで、なんらかの属性や役割であった対象が、本来の所在から離れて独立した価値へと至った様態を「フェティッシュ」と言う。例えば、属性で言えば光沢やフォルムといった視覚的な特徴、機能で言えば貨幣の交換可能性などが、典型的なフェティッシュだ。
フェティッシュはそもそも「呪物崇拝」として発見された。しかし、一度成立したフェティッシュにとって「物」は元の宿り木でしかなく、フェティッシュそのものが実体となって流通し、かえって「物」の方がフェティッシュに対して着床するようになる。
ネットワークを組成している「情報」の本質を考えるとき、今やこのフェティッシュとの違いを見いだすことは難しい。物質や関係がコーディングされてアルゴリズム性を持ち、それ自身が欲望で駆動されはじめるならば、情報も貨幣のようにフェティッシュとなり、身体はその流れに沿って分岐し、その先で多様な経験を編んでいるということになる。
宿り、流通し、受け手の力として非接触的に発現する情報。それはマルセル・モースが指摘した、原始部族社会における「マナ」※4にも近い。物質であり事象でもあるような、この非人格的かつ関係的な現象であるマナこそが、我々を行動させまた制約する実存であるという観念。情報的な身体、そのネットワークとしての広がりは、そのままフェティッシュやマナの現代的なシステムと見て取ることができる。
精神の「系」から情報の「圏」へ
かつてグレゴリー・ベイトソンは、サイバネティクスの視点から人間と世界との関係を「系」としてとらえ、その「系」を出入りする情報が「精神」であると説いた。それは、身体と世界が常に接続されていて切り離せないという現象学的な考えと、物質の振る舞いに関する熱力学的なシステム論を統合した見立てであったが、現代においてこの「系」の視点は、情報論や計算機科学の発展によって得られた重み付けの手法により、定性的かつ定量的な「圏」の視点へと進化しつつある。
ルチアーノ・フロリディの「インフォスフィア」やケヴィン・ケリーの「テクニウム」などの大域の議論から、ジュリオ・トノーニの「統合情報理論」のような意識問題に至るまで、つまり地球全体から一人の人間までを情報の視点で透過的に把握することで、世界は計算するネットワークのイメージとして革新されはじめている。
人は誰もが、「世界」を連続的に生成し続けているネットワークである。そのネットワーク全体を「圏」として見るとき、それは脈動の重層的な広がりのようでもある。そのような場所で目的に応じたネットワークを考えるのであれば、それは「作られる」のではなく、フェティッシュやマナのように、情報に乗って「励起される」と捉える方が妥当ではないだろうか。そうすることによって、身体は矛盾を許容しながらより「計算可能」になり、そのサイズも決まっていくはずだ。
計算可能な世界
ネットワークがそのまま計算であるような世界では、幾何学的な投影や位相の変換、極限における近似やスケーリング、さらには因果の確定まで、多種多様な演算がノードとエッジ※5の関係に繰り込まれる。その意味において、ネットワークの計算過程は、関数と関数の関係すら確率的だ。そしてこの世界像は、常に「遷移」し続けるが故に静止することがない。連続という概念すら、可換性やトポロジーによって遷移のバリエーションとなる。
この計算過程に沿うようにして、身体と表象との関係も切り結ばれていくことになる。ノードから始まり離散して、また別のノードに至って閉じる。その繰り返しによって重み付けられていくような関係の立ち上がり方は、個別関数の評価の総体でありながらも、そのままではネットワーク全体の「意味」とはならない。なぜならば、完全グラフ※6のような全ノードの均質な結合や、逆にネットワークの分割に全く影響を与えないような疎な結合※7は、それらがどれだけ大量にあったとしても、ネットワーク全体の意味のあり方、その統合性を変更することができないためだ。
よってこの世界像は、確率の遷移、つまり個々のノード結合をベースにしつつも、それらの結合が「さらに統合された」何らかの状態量を、「意味」の表現として持つことになる。このような状態量は、「遷移の濃淡」といったネットワークのあり方を反映し、情報が意味となって励起する様子をよりよく抽象化して、計量可能なものとするだろう。
この観点による限り、システムにおける「意味化のプロセス」は、流入する情報の量や個々の質というよりも、全体としての統合性を担保する特定の関係の密度によって成立する。そしてそこに「システムに流れる時間、その全ての瞬間はユニークである」という仮定を付け加えるならば、「統合性を意味する状態量」は「確率ベースの一回性」すら編み込んでいるとも考えられる。
今後あらゆるものがセンサー化されインターネットで結ばれていくことで、この世界の情報量は劇増し、私たちはさらに未経験な世界へと否応なしに踏み込む。それはつまり、私たちにより多くの「身体的なコスト」が要求されることともイコールだ。そのような世界にあっては、身体も表象も、ネットワークの意味化によってのみ解を持ちえるはずだし、そこ以外に合理性の根拠が無いように私は見ている。
身体・表象・デザイン
「ネットワークする身体」「計算する身体」が現れてきた今、それらがデザインという行為に与える影響は大きい。この新しい身体によって私たちが数十年前とは全く違うあり方で世界を経験し続けるのであれば、世界の見られ方、つまり表象も、旧来とは違う方法で受け取られていくはずであり、そのことはいわば公理としてデザインの前提となる。
一方でネットワークであるということは、要素の自由なふるまいが、最終的に法則的なパターンに収斂しうることも含意する。それを「自然」を〈じねん〉と呼ぶときのような、自律的構成の働きと見てとることも可能だろうし、逆に恣意的に構築すべき理想的なモデルと見ることもできるだろう。そのような世界で、デザインは何をどのようになすべきなのか? ということが、現代の必然的な問いとして浮かび上がってくる。
すでに述べたように、今の私たちを取り巻いている表象は、そのようなネットワークの働きによって、身体の延長として切り結ばれるノードとなって現れる。
ネットワークする身体にとって、その表象は先計算的な何かだろうか? それとも計算の結果が表象として投影されているのだろうか? あるいは表象それ自体もまたプロセスであるということになるのだろうか?
いずれにせよ、表象に対するこれらの問いに、単一の答えを用意するのは早計だ。私たちはデザインを通して、表象との関係を切り結んでいくのだし、それは身体へと再帰するはずなのだから。
意味ある秩序形成としてのデザイン
デザインの役割は、先に述べた「意味化のプロセス」を生成させることと言える。「定義としての意味」ではなく「関係としての意味」を実装すること。それは理念的かつ実践的なビジョンだ。
こうした思想は、ヴィクター・パパネックによって1970年代に既に語られている。プロダクトの形状からデザインを考えていては、本質的価値を損なう。そう考えたパパネックはデザインを、人間活動の基礎となる「意味ある秩序状態」を作り出すためのプロセスであると論じた。
結果としての形状だけではなく、それが励起するプロセスを行き渡らせる、またその行き渡った系をデザインと捉えること。それは「グリッドの生態学」を志向していたオトル・アイヒャーら『ノイエ・グラフィーク』※8のデザイン観から通底している流れだ。
これらの思考は換言すれば、名詞としてのデザインではなく、動詞としてのデザインとは如何なるものかという問いでもある。「前に(pro)」と「導く(duct)」の合成語である「プロダクト(product)」という名詞。そこに折り込み済みの「到達点へと向かっていくナビゲーション性およびその時間的奥行き」を、デザインという行為としてどのように引き出すか。パパネックやアイヒャーらが向き合ったのは、そのような「方法への問い」でもあったろう。
そこで、この「意味ある秩序」へ向かうための「名詞ではなく動詞としてのデザイン」という問いを、吉本隆明の「指示表出」と「自己表出」という言語の二重性の分析を借りて眺めてみると、「導線」のように名詞(=指示表出)として提示された対象が、「導かれた」という動詞(=自己表出)として「意味化される」までのプロセス、そのプロセスがデザインにおいて実装されるべき「性能」として浮かび上がる。その結果、「デザインによる体験は、名詞が身体のネットワーク性によって動詞へと変換される、その遷移の設計によって生み出される」といったイメージを得ることができる。
デザインとはこのように、関係性を前提として、認知が意味化されるその境界への介入を実装するプロセスでありながら、同時に人間にとっての「意味ある秩序形成」として、生活を担保する身体性に帰着する。
我々の脳には自己の身体の完全なモデルがマッピングされているともいわれるが、人間が概念操作を行うとき、認知限界の枠によって「世界」は時間的・空間的にも縮約され、その一部は切り取られてしまう。それ故、行為は結局、経験を通じその枠内においてしか意味化されないし、細分化によって定義されきった世界と、統合的な意味量で測られた世界は同じにはならない。
であるならば、いや、だからこそ、情報を根拠とするデザインにおいて「ネットワークする身体」「計算する身体」へのまなざしが倫理そのものに思えてくるのは、私だけなのだろうか。
「ここにいると、気分がいいの。」
この言葉にならない幸福は、一瞬、稲妻のように言語の上を通り過ぎてそこに跡を残してゆく。まさにそれが、空間の実践なのである。ミシェル・ド・セルトー『日常的実践のポイエティーク』
空間の実践、場所の経験
「ÉKRITS / エクリ」が生まれて一年になる。振り返ってみると、ローンチ前に予期していなかったことも多くあった。
テキストのユニークさは、具体化されたテーマではなく、抽象化された執筆者の経験にあること。読者との意思疎通は、ディスコースではなくエクリチュールとして、つまりテキストの外ではなく内にあること。それぞれのエクリチュールは、相互に作用しながらクレオール化して、未来の記事やその文体に影響していくことなど。
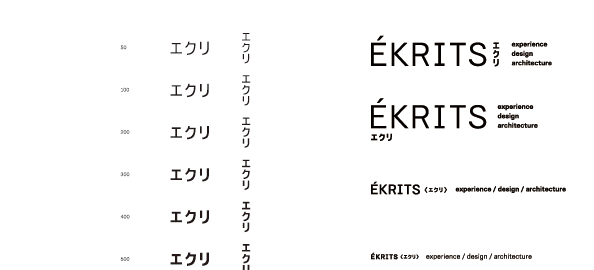 ロゴのバリエーション
ロゴのバリエーション
そこで、当初に青写真として考えていたコンセプトと、一年間で経験したことをつなぎあわせて、去年書いた「エクリ散策案内」をアップデートしてみることにした。ここでの散策に目的はない。目的のための道のりがあるのではなく、道のりが目的となっていく。
コンセプトと構造的空間
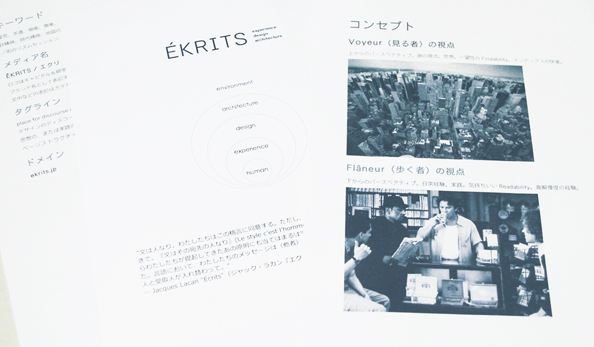 コンセプトシート
コンセプトシート
「ÉKRITS / エクリ」は、都市における「空間の実践」と「場所の経験」をモチーフに設計された。この2つの視点を切り替えながら、散策できるナビゲーションを配置するためである。
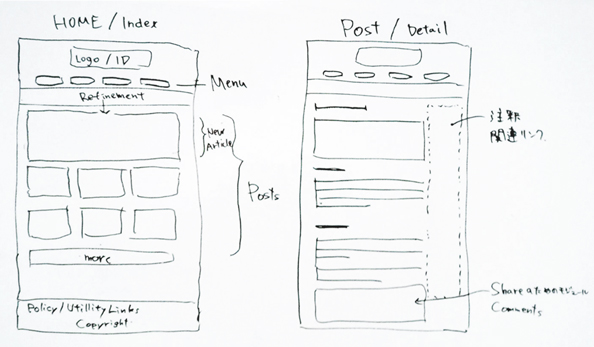 画面設計のメモ
画面設計のメモ
まずは記事のインデックスから、散策をはじめよう。見る者(Voyeur)による、空間の実践。都市のパースペクティブ。見晴らす歓び。体系化と構造化。分類のストラテジー。論理的推論による支配の欲望。幾何学的な世界のプランニング。理想(イデアル)の地図作成。
次に、記事のノードへと移動する。歩く者(Flâneur)による、場所の経験。路上のパースペクティブ。地を感じる歓び。リズムとビート。存在のタクティクス。蛇行しながら逃走する欲望。ストリートワイズな野生の思考。憂愁(スプリーン)のスケッチ。
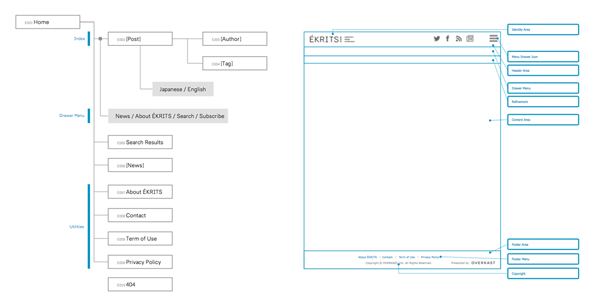 サイトマップとページテンプレート
サイトマップとページテンプレート
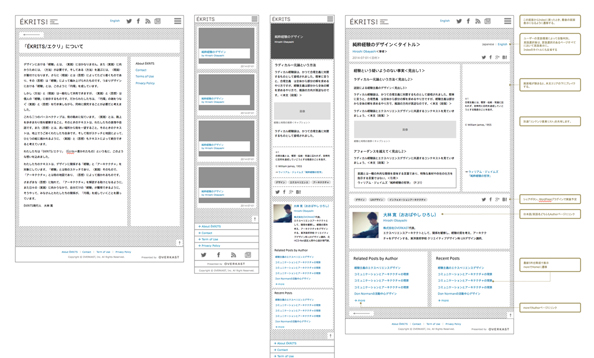 ワイヤーフレーム
ワイヤーフレーム
トランクとブランチからなるツリー構造。そこに蒐集したテキストが深く根を下ろし、森になっていくことを願いながら、エクリチュールの苗を植えてきた。Webメディアという環境は、その場所として選ばれたにすぎない。タグラインはやがて「デザインについての思想を、デザインされたテキストで届けるメディア」というものに落ち着いた。
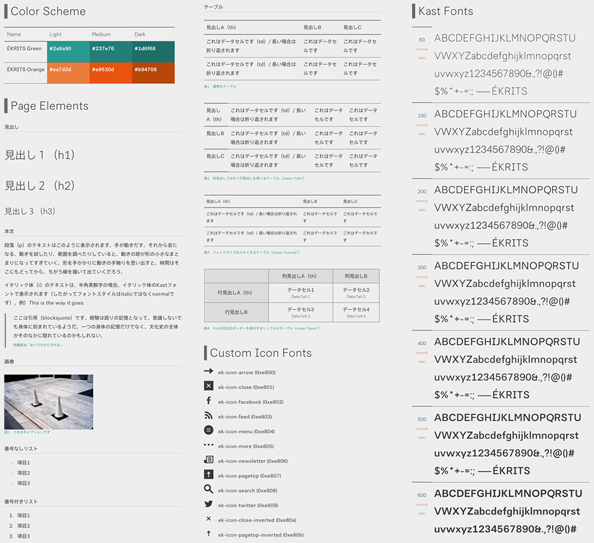 エレメントリスト
エレメントリスト
森のコスモロジー、モードの宿命
ある都市で道が分からないということは、大したことではない。だが、森のなかで道に迷うように都市のなかで道に迷うには、習練を要する。この場合、通りの名が、枯れ枝がポキッと折れるあの音のように、迷い歩く者に語りかけてこなくてはならないし、旧都心部の小路は彼に、山あいの谷筋のようにはっきりと、一日の時の移ろいを映し出してくれるものでなければならない。ヴァルター・ベンヤミン『1900年頃のベルリンの幼年時代』
都市は、森が切り拓かれることでつくられた。森にまつわる神話を解体して、わたしたちが支配的に生存できるように、地表を洗い流した。だから森はどこかしら懐かしい。都市がわたしたちの精神の表象であるならば、森はわたしたちの記憶が集積した場所と言えるのではないだろうか。それはわたしたちを外面から包摂しつつ、わたしたちの内面も投影している。この弁証法は、場所に無限の奥行きを与えるのだ。
イメージの空間
「ÉKRITS / エクリ」では、そうした森のコスモロジーを8つに分光して、カラーパレットを設計した。その色は、カバー画像のバリエーションとして反映されている。
 カバー画像のカラーパレット
カバー画像のカラーパレット
カバー画像は、読む者の視線が光として注がれ、文体の枝葉に反射するイメージでつくられた。そのモードは、記憶の絵の具が乾かないうちに更新される。待ち受ける死の宿命を前に、そのリズムの高鳴りを感じながら。
またこれらの色は、タグに設定したキーワードのタクソノミー(分類)とは別のセリー(系列)として構成される。カテゴリー(排他的分類)ではなく、全体と前後のハーモニー(調和)を考えて展開している。
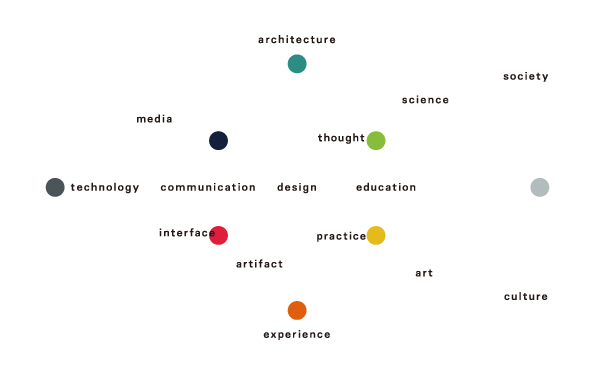 タグとカラーの相関性
タグとカラーの相関性
読むこと、場所を失うこと
ミシェル・ド・セルトーは、場所にまつわる物語がブリコラージュであると言った。時と場合に応じて、世界の断片を呼び集め、つくり上げられるものであると。他所からやってきたテキストによって、意味は飛躍し、ずれて、消滅し、関係が歪められる。すでにある秩序の表面に向かって楔を打ち、穴をあけ、予期せぬ抜け道をそこかしこにつくるのだ。
こうして差異が生み出されていくプロセスを、セルトーはジャック・デリダの「散種」という言葉を借りて表現した。
発芽、散種。最初の受精というものはない。種子はまずもって分散される。「最初の」受精は散種である。痕跡、痕跡の失われた接ぎ木。ジャック・デリダ『散種』
エクリチュールの空間
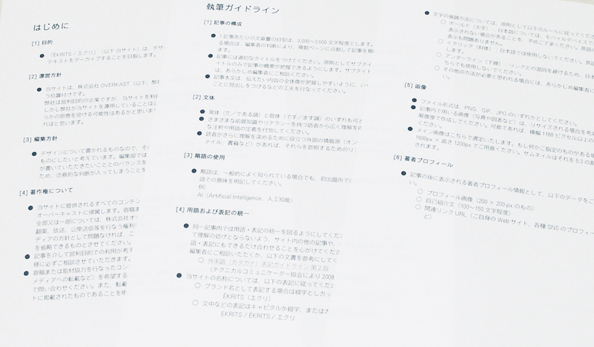 編集方針と執筆ガイドライン
編集方針と執筆ガイドライン
胞子や種子を散布する言表行為。デリダが散種(dissémination)という言葉を選んだのは、“semen”(種子/精子)と “séme”(意味素)の綴りが似ているという、偶然によるものだった。エクリチュールはその偶然によって、植物の種子や動物の精子のように、無邪気に意味を拡散させる。散種された意味が芽を出すのは、過去の文脈から切り離された場所である。それらは読むという具体的な手続きを通じて、静かに木々へと育ち、森になっていく。ひとつのテキストが、千の意味を持つのは、千の読み方があり、そこに千の秘密が隠されているからである。
森は人びとによって記憶された場所だった。そこは、読むという密猟によって立ち現れる、失われた場所である。読むことは、テキストに集中するだけに限らない。あちらこちらを眺めて、ふと関係ないことを思いついたり、斜め読みしながら、周りの様子が気になって顔を上げたり、後で読もうとしてブックマークしたり、印刷したり、シェアするときも、まだテキストに捕らわれているなら、その場所に留まっている。そこにたどり着いたときには、もうこの散策案内は必要なくなっているだろう。
「わたしは読み、そして夢想に耽る。してみれば読書というのは、ところかまわぬわたしの不在なのだ。」……読むということは他所にいるということであり、自分がいないところにいるということ、別の世界にいるということなのだから。それは、あるひそやかな舞台をしつらえること、好きなように出たり入ったりできる場所をしつらえることだ。ミシェル・ド・セルトー『日常的実践のポイエティーク』
感情は、単なる何らかの内面的な状態にすぎないのではなく、外部の状況・もの・人 ——「対象」—— との関係を、本質的な構成要素として含みこんでいる。……「感情(passio)」を抱くことは、「受動(passio)」的な仕方で自己の境界が何らかの「対象」の影響によって揺るがされ、その「対象」が自己の構成要素にまでなるという事態なのだ。山本芳久『トマス・アクィナス 肯定の哲学』※1
私は前回、1989年に図書館情報学者のマーシャ・ベイツが提示したベリーピッキングモデルを通じて、オフラインからオンラインへの情報環境の広がりを背景に人間が行なってきた「探しもの」のあり方について考えてみました。ベイツがそのモデルを発表した翌年の1990年末には、CERN(欧州原子核研究機構)の研究者ティム・バーナーズ=リーによって、世界初のWebのシステムが誕生しています。それ以来、Webが爆発的な成長を続けた後の2002年、リスボンで開催された情報探索行動をテーマとするカンファレンスで、ベイツが基調講演を行なうという機会がありました。彼女はそこで、情報の探索を統合的な体験として捉え、それを社会や文化との関わりから見るだけでなく、生物学や人類学の観点からも理解するよう呼びかけました。
この記事では、ベイツがその講演内容をまとめて2003年に発表した論文を読み解きながら、私たち人間が情報とどのように関わりながら生きているのかを、考えていきたいと思います。
情報探索を知るための「理解のレイヤー」
ベイツが生物学的/人類学的アプローチの重要性を訴えたのは、当時の情報研究が、社会学に偏っていることを憂慮していたからです。インターネットの普及やオンライン検索技術の進歩、コンピュータを道具として扱うスキルの向上など、社会が大きく変わりつつあった時代の流れに乗じて、情報行動についての研究は、個々の人間よりも社会や文化全体に注目するものが目立っていたのです。
またベイツは、社会学や人文学とは別のレベルでの、自然科学的な取り組みが軽んじられていることを憂慮していました。この講演で彼女がまず試みたのは、科学的アプローチへの偏見を取り除くことでした。実験や観察に基づく分析を重んじる科学的な還元主義を、精神に関わるものごとを単なる物理現象に貶めることだと誤解してはいけない。また、自然科学に携わる研究者が、科学を盲信していると決めつける必要もない。そして、生物学や人類学といった科学の成果を情報研究から排除している限り、十分な理解は得られないと語ったのです。
そしてベイツは、図1の「理解のレイヤー」すべてにおいて、情報探索を理解することが望ましいと述べました。
| 精神的(宗教、哲学、意味の探求) |
| 美的(芸術、文学) |
| 認知的 / 動物的 / 情動的(心理学) |
| 社会的 / 歴史的(社会学) |
| 人類学的(形質人類学、文化人類学) |
| 生物学的(遺伝学、動物行動学) |
| 化学的 / 物理学的 / 地質学的 / 天文学的 |
[図1] 情報探索の理解のレイヤー
ベイツはこの図で、それぞれの学問領域から得られる知見を統合すれば、もっとも深い理解が得られることを訴えました。レイヤーの間に優劣はなく、どれも等しく重要であるとみなすのです。また、一般的に人類学は社会科学に分類されることが多いのですが、この論文でベイツは、人類学を自然科学に属するものとして議論を進めていきます。人間も自然の一部であると考えれば、それを研究対象とする人類学を自然科学とみなすのも、間違いではないはずです。ともかくここで重要なのは、情報探索という行動の重層性を示し、それを知ることで理解を深めようという目標が掲げられたことでした。
ただしベイツは、実際の人間の性質や行動が必ずしも明確に切り分けられるわけではなく、隣りのレイヤーに浸透したり、さらに離れたレイヤーに達することもあることを説明しました。たとえば、心理言語学の通説では、人間には先天的な言語能力があり、それが後天的な言語の発達に一定の制約を与えると言われています。しかし現実には、そのような制約を受けながらも、言語はきわめて多彩なバリエーションを見せます。私たちが用いる言語の特徴や文法、語彙などは、どれも一生を通じて身につけていくものであり、文化によっても大きな違いが生まれます。したがって、生物学か社会学のいずれかで言語能力のすべてを説明できるわけではなく、その両方に関わっていることを知る必要があるのです。ベイツはこの例を踏まえて、人間の行動にはそのような面がたくさんあることを述べました。そして、社会学から生物学/人類学までのレイヤーを貫く観点から、さまざまな情報探索行動を統合するモデルを示したのです。
情報探索の4つのモード
ベイツは、私たちが能動的に探して入手する情報だけではなく、生まれてから死ぬまでの間に出会うあらゆる情報が探索の対象となると考え、それを前提としたモデルを生み出しました。他の哺乳類と同じく、人間は大きくて汎用的な脳を持ち、環境や社会状況の変化に幅広く適応しながら、一生のうちにきわめて多くのことを学習できる生物です。先ほどの言語能力の例のように、一定の精神構造が頭の中にあり、さまざまなことを学習するのに役立っています。ただし、細々とした具体的な情報は、各自の経験を通じて手に入れます。家族や親しい仲間から特に多くのことを学ぶのも、他の哺乳類との共通点です。そのような人々の支援をどれだけ得られるかは、自分の生死に関わるので、情緒的に濃密な関係を結ぶことになります。このように、人間は他の人々との交流から多くの学びと経験を得る、とても社会的な種なのです。
このような考察に基づいて、ベイツは「情報探索の4つのモード」というモデルを示しました。
| 能動的 Active |
受動的 Passive |
|
|---|---|---|
| 有向的 Directed |
検索 Searching |
モニタリング Monitoring |
| 無向的 Undirected |
ブラウジング Browsing |
意識化 Being Aware |
[図2] 情報探索の4つのモード
「有向的/無向的」とは、多少なりとも目的を持って情報を探しているか、ほぼランダムに情報を収集しているかの違いで、「能動的/受動的」とは、意志を持って自発的に情報を探しているか、探している自覚もなく情報に接しているかという違いです。これら4つのうち、実はもっとも影響力のある「意識化」を出発点として、ベイツはそれぞれのモードを解説しました。
意識化
先に述べたように、私たちが知ることや学ぶことの大半は、受動的かつ無向的に何かを意識するという、意識化のプロセスを通じてもたらされます。
この意識化は、生きるための知恵を身につけつつある子どもたちに、とりわけ大きな影響を及ぼします。子どもは、そもそも自分にどんな情報が必要なのかわからず、自分の情報ニーズをうまく言語化できないので、能動的に、または有向的に情報を探すのは困難です。そこで自然と子どもたちは、身の回りの環境から与えられる情報にただ身を浸し、とりわけ家族のように縁の深い人々の影響を受けながら、さまざまな意識化を通じて成長していくのです。
そしてこの意識化は、大人になっても多大な影響を及ぼし続けます。ベイツによれば、私たちの知識のほぼ80パーセントは、社会的状況と物理的環境がもたらす情報を意識化することで得ていることになります。
モニタリング
有向的で受動的なモニタリングが行なわれている間は、興味を引くものや疑問への答えが見当たらないかと、アンテナを張っている状態になります。能動的に情報を探し出す必要に迫られているわけではなく、通りすがりに何か見つかればいいといった感覚です。何か疑問があっても、わざわざ答えを探そうとしていない場合に、その答えらしきものに出くわせばそれと気づくのは、モニタリングを行なっているからです。
意図的かどうかは別にして、私たちは必要な情報を必要な時に取り出せるように、物理的/社会的な環境を整えることがよくあります。買い物リストを作ったり、料理がはかどるように台所用品を配置したり、仕事場でよく使う道具を整頓したりして、次にどこで何をすればいいのかを、いつでも思い出せるようにしています。そうすれば、能動的に情報を探す手間が省けることが多くなるからです。何か特定の行為や手順を経験すればするほど、その次の行動のきっかけが意識化されるのを待つだけではなく、自主的にモニタリングをしようとする傾向があるとされています。
また、学問領域や専門分野、趣味や職業を通じたコミュニティのような社会的インフラは、モニタリングの強い味方となります。自分に見合った境遇の中では、社交的に、あるいはただ物理的に誰かと接するようにするだけで、大量の有益な情報に出会える見込みが高まります。これはまったくの偶然によるものではなく、共通の目標やニーズを持ち合わせている人びとが近接していることから生じることと言えます。
ブラウジング
先ほどの図2からわかるように、無向的で能動的なブラウジングは、有向的で受動的なモニタリングの裏返しともいえるモードです。ブラウジングとは、特別な情報ニーズや興味関心はなくても、目新しい情報がありそうな場所を能動的に探っている状態です。だから、好奇心はブラウジングの原動力になります。ベイツは、能動的に好奇心を発揮することが、新たな食物や仲間の発見に至りもすれば、自分の身を思わぬ危険に晒しもするという、生物の進化におけるジレンマの元になってきたことにも触れていました。しかし、ブラウジングの価値は、いわば受動的に好奇心が満たされることの喜びにあるのだと思います。目的志向や成果主義から離れて、何かに出会うこと自体が楽しみとなるかどうかが重要になるということです。
ベイツは、実際にブラウジングをしているときに生じる身体活動をもっと詳しく知る価値があると述べ、あまり注目されていなかったバーバラ・クワスニークの研究を紹介しています。彼女は、ブラウジング中の身体活動を詳しく分析し、目が水平方向へのスキャンを繰り返すというより、気の向くままにいろんな箇所をチラチラ見ていることを見出しました。そしてブラウジングが、方向確認や現在地のマーキング、比較、異常の解決といったさまざまなアクションから成る複雑な活動であり、多くの意味を秘めていると考えたのです。
そして、ベイツやクワスニークを含む一部の研究者たちは、そのように多くの意味に満ちた複雑さが、他にも多くの行動に見出せることに気づきました。情報行動においてはブラウジングを引き起こす衝動が、「サンプリングと選別(sampling and selecting)」と呼ばれる一般的な行動として、他にもさまざまな形で現われると考えたのです。パーティーでの会話やデート、買い物、つまみ食い、観光、道順探し、テレビ番組のザッピング、ネットサーフィンなどは、どれも「サンプリングと選別」の実例です。たくさんの可能性を前にしたとき、まず私たちはそこから目ぼしいものを抽出するサンプリングを行ない、その結果をさらに選別しているのです。先ほどの実例からもわかるように、これは生物の交配や採餌といった行動の進化形とも言えます。
進化生物学では、ある目的に合わせて発達してきた機能が、環境の変化によって別の目的に用いられることはよくあるパターンとされ、「外適応(exaptation)」※2と呼ばれています。ベイツがこの論文で紹介した「情報採餌(information foraging)」※3という行動は、サンプリングと選別を好む人間の性向が、その対象を食物から情報に切り替えた結果とみなすことができます。生物学的な採餌行動が、ブラウジングなどの情報探索行動に転用されて「外適応」したとも言えるでしょう。
検索
有向的な検索は、疑問への答えを求めたり、具体的な質問や話題への理解を深めようとして、能動的に行なわれます。知識のほぼ80パーセントが意識化によって身についているのに対して、検索によるものはわずか1パーセント程度で、残りがブラウジングとモニタリングによるものだろうと、ベイツは見積もっていました。
情報を探すとき、人間が最小努力の原則に従いがちだということは、すでに数多くの研究で実証されていました。手軽に入手して利用できる情報ならば、その信頼性の乏しさには目をつぶってしまうほど、人間は手抜きをしたがるものなのです。学生が図書館まで出向いて学術誌を探さずにネットの情報で済まそうとすること、医師が医学文献を調べるより製薬会社のセールスマンから新薬の情報を聞き出そうとすることなどは、それをよく表しています。
望ましくない方法とわかっていても、つい人間がそれを頼りにしてしまうことは、昔から研究者たちを悩ませてきたそうですが、その理由はこれまでの話から自ずと見えてきます。人類は長い歴史を通じて、生きるために必要な情報の大半を、わざわざ検索することなく獲得してきたからです。かつての狩猟採集者も、家族的集団の中で育てられ、仲間との交流や環境と関わり合いながら、受動的な意識化とモニタリングを通じて知識を得るのが普通でした。そして集団が移住したときには、新たな環境の中で無向的にブラウジングをしながら、生活に必要なものを見つけていたのです。人類史を見渡すと、何か必要に迫られた場合は別として、能動的かつ有向的な検索をするというのは、めったにない事態なのです。普段の何気ない行動を通じてあまりに多くの情報を得ているので、能動的に努力して探すよりも、受動的な習慣に従ううちに都合よく情報が手に入ることを期待している、とも言えます。
現代の私たちの生活には、検索をさらに厄介にしているもう一つの要因があります。19世紀初頭から、何らかのメディアに記録される情報の量が爆発的に増加したため、それらにアクセスするには、複雑で高度な検索システムに頼らざるを得なくなったことです。検索以外の手段で情報を得ることに慣れていた人びとが、自分から検索をしなければいけなくなったのです。しかも、検索システムの仕組みを理解して使い方を覚えるという、二重の手間が生じることになります。その大変さを思うと、誰もがなるべく手間をかけずに情報を探したいと願うのは、当然と言えるでしょう。わざわざ検索のスキルを身につけようと決意するのは、緊急性や関心がきわめて高い場合だけなのです。
情報の狩猟と農耕
情報採餌理論の先駆けとなった、人類学者パメラ・サンドストロムの論文は、研究者たちが自給自足で食料をまかなうように情報を集めていることに注目し、人間が情報を探す労力を減らそうとする性向をより詳しく解き明かしました。
彼女が気づいたのは、通常の読書やブラウジング、新たな情報源への遠征といった、単独ですることが多い情報探索行動から得られる資料は、各自の情報環境の中で周辺的なものになりがちだということでした。それに対して、中心的な資料は、同僚との交流や論文の査読といった社会的なチャネルを通じて手に入ったり、各自の個人的コレクションの中にあったりすることが多いのです。これは、かつての狩猟採集時代に、まず家族や仲間のいる社会的境遇から、次いで自分の収集物からものごとを学んでいたのと、同じ構造を示しています。研究者たちもめったなことでは、見ず知らずの領域まで情報を探しには行かないものなのです。
ただし、狩猟採集者は、現在と同じ意味で個人のコレクションを所有していたわけではありません。放浪を繰り返す遊牧生活では、持ち運べる収集物の量に限りがあるからです。本格的なコレクションが始まったのは、定住生活するようになってから、つまり、農耕を基本とする生活を始めてからのことです。現代の研究者たちは、農耕民族が畑を手入れしていたのと同じように、個人のコレクションとして集めた資料をデスク上やファイリングシステムで整理整頓し、後で使いやすいように整えています。一部の研究者が「エンリッチメント(enrichment)」※4と呼んでいた、このような情報環境の体系化は、サンドストロムが調査対象とした研究者たちだけでなく、他の職業に携わる人々や、さらには仕事を離れた趣味の世界でも行なわれているものです。
ベリーピッキングからモードの統合へ
ベイツは、自身が1989年の論文で注目した「ベリーピッキング」※5という行動も、能動的に行なわれる「サンプリングと選別」の一例だとみなしました。ベリーピッキングは、同じく能動的な行動であるブラウジングとよく似たものになる可能性がありますが、無向的なブラウジングに比べれば、ベリーピッキングのほうがやや有向的です。
また、より一般的な2種類のモードとして、能動的な検索やブラウジングは「サンプリングと選別(sampling and selecting)」に、受動的なモニタリングや意識化は「環境からの吸収(absorption from the environment)」に区分できます。一方、有向的か無向的かの違いは、自分の情報ニーズに対する認識の違いにも相当しています。つまり、「知る必要があるとわかっている情報」を見つけるのが検索とモニタリングであり、「知る必要があるとは思っていなかった情報」に出会うのがブラウジングと意識化ということになります。
ここまで見てきたことをまとめると、大抵は受動的な「環境からの吸収」によって、時には能動的な「サンプリングと選別」によって情報を得るというのが、遠い昔から受け継がれている人間の性向だということになります。そしてベイツは、時代の流れと共に情報環境がどれだけ複雑化しても、その性向は基本的に変わらないと考えていたようです。
産業社会における情報アクセス
現代的な産業社会が生まれ、印刷や配信の手法がさらにパワフルになり、かつてないほど大量の資料が図書館で収集されるようになるにつれて、効率よく情報にアクセスしたいというニーズは高まる一方でした。ベイツが論文を書いた当時には、さまざまな情報処理のシステムの設計や開発に多大な労力が注ぎ込まれていたものの、それらは宝の持ち腐れとなっていました。画期的な新しいシステムの利用を敬遠するどころか、その存在に目もくれない人も多く、かなりの検索スキルを持っているはずの研究者たちさえ、例外ではなかったそうです。
人間の性向を生物学的/人類学的に捉えれば、情報探索がほぼ受動的な行動で占められていることは、すでに触れてきた通りです。逆の言い方をすれば、意識化を主とする受動的な探索は、誰かに教えられるまでもなく自然に行なわれるほど、人間にとって大昔から身に染みついた手段だということになります。それに反して、能動的に使うことが求められる現在の検索システムには、まだ数百年ほどの歴史しかありません。紙に印刷された本や論文を読むには特別な準備は要りませんが、デジタル化された文献にアクセスするには、先に述べたように、検索システムを使いこなすための学習が必要になります。でも、普段の生活では、大した自覚もなくほぼ受動的に情報探索を行なっているので、能動的に検索システムを利用するための学習の必要性には、なかなか気づかないのです。
こうして、情報探索に関する研究がたびたび同じような結論に至る理由は、私たちの行動を生物学的/人類学的な観点から捉えればある程度説明がつくと、ベイツは考えました。誰もが最小の努力で済ませようとする理由は、人間が昔からいつもそうすることによって、ごく最近までそれなりに納得のいく成果をあげてきたからです。
意識の問題とその時代
もしかすると、意識化が探索という活動と呼べるのか、疑問に思われる方もいるかもしれません。確かに意識化は、目に見える形で行なわれる身体的な活動(action)というよりも、心のなかで生じる反応(reaction)に近いように思えます。しかし、私たちの身体と心は、ハードウェアとソフトウェアのように切り離せるわけではありません。それらが別々に動いていると考えることに無理があると気づけば、意識化も活動の一つとして捉えることができます。ベイツもそう考えたからこそ、森の中でのベリー摘みのように、情報探索活動が身体と心の全体に関わっていることに目を向けたのではないでしょうか。そして、意識化という活動を、とりわけ重要なモードとして位置づけたように思います。
彼女が研究者として活躍していた20世紀末期は、長らく哲学で扱われてきた心と身体の関係が、科学の研究テーマとして盛んに取り上げられるようになった時代でした。「物理的なモノではない心(精神)が、モノとして動く身体(物質)とどのように相互作用しているのか」という、哲学者たちが古くから取り組んできた難問に、進化生物学や脳科学の研究者たちも次々とアプローチするようになり、意識のしくみが科学的に探られていたのです。
彼らは、医療技術のめざましい進歩がもたらす新たな実証データによって、昔からマクロなレベルでの心的作用だと考えられてきた意識というものが、脳内の神経活動というミクロなレベルの物理的作用に還元できることを証明しようとしました。中でも優れた科学者たちは、さまざまなレベルに渡る理論が長期間に渡る実証データの蓄積によって影響しあい、新たな接点が生まれていくという「共進化」こそが、本来の還元主義の価値だということを理解していました。すべてを科学的に説明づけることが目的ではなく、科学の進歩が哲学や心理学といった他の学問の進歩を促し、それがまた科学を前進させることに、意義を見出したのです。そのような流れを受けて、哲学者たちも、科学的な洞察を踏まえた上で意識の問題を見直すようになった時代でした。
ベイツが「理解のレイヤー」の図を示して、あらゆる学問領域に通じる重層的な理解の重要性を訴えたのも、そのような時代精神の反映だったのではないでしょうか。
アンビエントな情報と「内的環境」
私は「能動的/受動的」「有向的/無向的」という区別が、実はあいまいなものだと考えています。私たちは、情報を探そうとするときに、まずどれか1つのモードを選んでから活動を始めるわけではないのです。4つのモードは、実際の探索の結果として見出された類型にすぎません。とにかく森の中に入ってみて、あとは周りの環境と、自分の感覚や過去の経験を手がかりに、いろいろなやり方でベリーを摘み取っていければいいのです。
そこで忘れてはならないのは、ベイツが生物学的/人類学的アプローチによって伝えようとした、意識化の役割の大きさです。すでに見てきたように、オフラインでもオンラインでも、私たちは自分の五感を通じてさまざまな情報を意識することで、生きるために必要な知識を自然と身につけてきたのです。
意識化がどのように行なわれているかを知ると、情報というものがアンビエントな存在として、私たちを取り巻いていることに気づきます。ただそこにあるだけで、それ自体に一定の意味が内在しているわけではありません。その情報を意識する人との関係によって、そこに初めて意味が生まれるのです。ベリーを探そうと森に足を踏み入れた人を取り巻く環境とは、あらかじめそこにあった「外的環境」でありながら、その時その場で生成される「内的環境」と呼ぶべきものでもあるでしょう。「内的環境」とは、意識を通じて私たちの身体と結びつき、動的なひとまとまりのシステムとして立ち現れる環境です。これは、他の誰かに見せたり共有したりできるものではなく、その人自身にしか経験できないものです。
私たちは、行動には目的がないよりはある方がいいし、受動的であるよりは能動的であることが望ましいと考えたくなるようです。しかし生物学的に見れば、意識は本来無向的なものであり※6、きわめて受動的な役割を果たしていることを、ベイツは明らかにしました。むしろその無向性と受動性こそが意識の本質であり、情報との出会いによって自分だけの「内的環境」を生み出すところに、意識の真価があるということ。それが、ベイツが私たちに伝えてくれた、重要なメッセージではないでしょうか。
見えないアーキテクチャ
アーキテクチャは、目で見ることができない。もし語弊があるように感じるなら、きっと建築物の物理性を前提にしているのではないだろうか。その場合は、建築物の天井を支える柱、空間を仕切る壁、それらの形や材質、大きさや重さなどを、すべて情報だと考えてみてほしい。アーキテクチャとは、そうした情報の組み合わせや構造のことであり、物理的なものではなく現象的なものである。言わば、アーキテクチャは「空間に配置された幾何学的な概念」であり、わたしたちはそれを想像しているにすぎない。
しかしわたしたちは、目に見えないものを、見えるようにして取り扱わずにはいられない。見えるようにするためには、まず図面を「書くこと」から始めることになる。だからアーキテクチャは、書くことと強く結びついている。書くことは見ることであり、見ることは信じることにつながっていくのだ。
アーキテクチャという言葉は、ウィトルウィウスの『建築書』において初めて使われた。今から2000年以上も前のことである。ウィトルウィウスは、アーキテクトが「意味を与えられる」アーキテクチャを制作し、理論として「意味を与える」知識を兼ね備えた存在でなくてはならないと考えていた。つまりアーキテクチャという言葉は、原初からアーキテクトの職能を前提としており、同時に「意味空間」のことを指し示していたわけである。
近年になって、アーキテクチャという概念は、コンピュータ技術や社会における制度設計などに応用されていく。重要なのは、これがメタファー(隠喩)ではなくアナロジー(構造的類似)ということである。これから話をする「情報アーキテクチャ」も、そのひとつのアナロジーである。
アナロジーから職能の再定義へ
初めて建築以外でアーキテクチャという言葉が使われたのは、1960年代のコンピュータの分野においてである。それまで計算機として扱われていたコンピュータを、コミュニケーションの情報処理をする装置として理解するため、アーキテクチャという概念が借り出された。
1970年には、パロアルト研究所の情報科学グループが、コンピュータの社会的側面や人間との相互作用を考えることを、明確に「情報のアーキテクチャ(architecture of information)」と呼んだ。その6年後に発表されたのが、建築家のリチャード・ソウル・ワーマンによる「The Architecture Of Information」という論文だった。
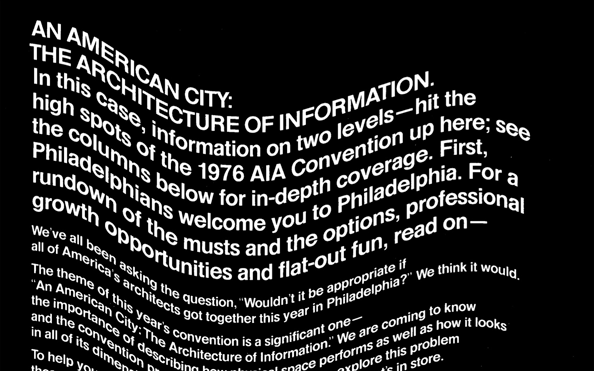
その後もワーマンは、デザイン専門誌の臨時増刊号に掲載された『Hats』などで、独自の情報デザイン論を展開していった。そして1996年に著述した『Information Architects』において、「情報アーキテクチャ」を体系化の科学であり、時代の要請によって求められる職域と定義するに至る。さらに、その業務を遂行する職能を「インフォメーションアーキテクト」※1と名付け、情報を「見つけられる(Findable)」「理解できる(Understandable)」ようにすることを担う役割とした。この本でワーマンがしたのは、インフォメーションアーキテクトに相応しいと思う人物を、ショーケースのように並べて見せることだった。
その2年後、さっそくWebビジネスから「時代の要請」を受けて、『Web情報アーキテクチャ』という実用書が登場する。図書館情報学を基礎にしたこの本は、情報システムで利用されていたプロジェクトマネジメントの手法を取り入れながら、Webサイトを制作するスキルセットとして、インフォメーションアーキテクトという職能を再定義した※2。
コンセプトで二元化する領域
『Web情報アーキテクチャ』という書籍によって、情報アーキテクチャという言葉がWebビジネスに最適化され、その対象を情報システムに限定したことは、強烈な世俗化になった。そのためこの本は、時代に合わせた実用性を「要請」され続け、テクノロジーや環境が変化するたびに改版を重ねている。この本のカバーにはシロクマ(Polar Bear)のイラストが使われているが、心理学者のウェグナーによる有名なシロクマの実験と同じように、「忘れようと思うほど忘れられなくなる」という皮肉な結果を生んだのだ※3。
ワーマンは2004年のインタビューで、インフォメーションアーキテクトと名乗っている人の90パーセントは、本来の意味を理解していないと語った。この発言は、『Web情報アーキテクチャ』を実用書として参照した世代を、暗に批判していたのかもしれない。それに対して、『Web情報アーキテクチャ』の著者の一人であるピーター・モービルは、ワーマンの『Information Architects』を読んで、情報アーキテクチャではなく情報デザインについて書かれた本と感じたそうだ。
情報アーキテクチャについて書かれた二冊の本が交わらない理由は、出自や世代が違うだけではない。それらを大きく隔てているのは、コンセプトの違いである。『Web情報アーキテクチャ』は実用書という書籍一般のコンセプトに従って、情報アーキテクチャという分野を紹介しているが、ワーマンの方は本の制作において情報アーキテクチャを実践することがコンセプトになっている。また『Web情報アーキテクチャ』は、実用性という「わかりやすさ」によって、現場でのコラボレーションを目指しているが、ワーマンの本は書籍のなかでコラボレーションが生成される装置である。この情報アーキテクチャにおける腹違いのコンセプトは、領域を二元化するアーキテクチャそのものだったのである。
アーキテクチャという世界制作
コンセプトの違うアーキテクチャによって、多元化した世界が出現する。このような状態を、哲学者のネルソン・グッドマンはその著書『世界制作の方法』で、世界の「ヴァージョン」と表現した。ワーマンが「The Architecture Of Information」と題した論文を書いた2年後のことである。
グッドマンによると、世界は「言語の記号システム」のように記述されている。たとえば、イヌイットの世界で「雪」をあらわす単語が多数存在するように、またエメラルドグリーンという色が青に分類されたり緑に分類されたりするように、コンテクストが違う世界では、事物のカテゴリが変わってくる。言語体系が違う世界では、「真理」でさえも、それぞれのヴァージョンから違ったものが導かれるのだ。
こうした世界観は、ウィトルウィウスの「意味を与えられる」制作と「意味を与える」理論の構造にも重ねられる。意味の主従関係として、制作は記号の「内容」で、理論は「作用」にあたる。これはソシュールの一般言語学における記号体系とも同じ構造をしており、言語は「内容」よりも「作用」が優位にある。つまり、どんな事物にも純粋な「内容」はなく、それらは外部に構造を持つことで意味付けされ、その同一性は他の事物との差異によって「作用」する。話を戻すと、世界は事物によって構成されるが、事物の意味は、言語体系のなかでどう関係しているかによって決まるということである。
アップデートされた『Web情報アーキテクチャ』の第4版では、建築出身のホルヘ・アランゴが新たな執筆者として加わり、情報アーキテクチャを「言語でつくられた場所(places made of language)」と言いあらわした。これがグッドマンの見解と一致するように、『世界制作の方法』で例示されている、合成と分解、重みづけ、順序づけなどの作業も、情報アーキテクチャに通じるものがある。
それだけでなく、情報アーキテクチャと「世界制作の方法」は、どちらも反還元主義を志向している。グッドマンは、構造の異なるヴァージョンをひとつの世界に還元することはできないと考えた。なぜなら、概念の構造を組み替えることは、別の世界のヴァージョンを作ることにほかならない。一方、情報アーキテクチャが反還元主義なのは、情報システムを要素に解体して、利用者の行動に沿った形で再統合しても、還元できないどころか、不整合を生じる可能性があるからである。このように、要素の集合が全体を同定しないという考え方は、情報アーキテクチャの分野で共通認識となりつつあるシステムシンキング※4に由来している。
繰り返すと、事物の同一性を保証するのは、アーキテクチャの構造である。だからアーキテクトの役割は、アーキテクチャを「言語の記号システム」として制作することと言える。そうして設えられた「意味空間」から、成果物としての構造体は生成されるのだ。
凍れる音楽/流動のアーキテクチャ
職域として定義される前から、「情報アーキテクチャ」というアイデアは、建築や情報科学、表象文化論などの分野で幾度となく語られてきた。マーコス・ノヴァクが展開したサイバースペース建築論も、そのひとつに数えられる。
彼は「人間は情報空間内部に含まれるわけだから、その限りではサイバースペースの問題は建築の問題である」と考えた。サイバースペースという概念は、建築を重力から解放するユートピア思想の側面があり、物理的に語られることが多かった「空間」を、現象的に捉えなおすのに十分役立つものだった。
ノヴァクは情報アーキテクチャを「流体的建築」と定義して、「それは音楽を目指す建築である」という印象的な言葉を残している。大胆なレトリックに聞こえるかもしれないが、古代ギリシアの時代から建築は、音楽の比例論※5を取り入れて発展してきた。建築は「凍れる音楽」であり(architecture is frozen music)、音楽は「流動のアーキテクチャ」である(music is liquid architecture)といった相対性をあらわす慣用句も、古くから存在する。こうして歴史から透けて見えてくるのは、建築が「空間」に、音楽が「時間」に、深く関わってきたことである。
たとえば、ル・コルビュジエの元で建築を学んだ音楽家ヤニス・クセナキスは、建築の理論によって作曲した「メタスタシス」という作品を、ブリュッセル万博のフィリップス館の設計で再利用した。また、音楽を学んでいた建築家ダニエル・リベスキンドは、五線譜を設計図に用いたり、ダイアグラムをアート作品のように仕上げたりして、音楽の技法やコンセプトを建築に応用している。建築が「空間」の概念であるように、音楽も「時間に配置された幾何学的な概念」として考えられるということである。この音楽が持つアーキテクチャのような性質を、クセナキスは「音の雲」と絶妙に描写した。
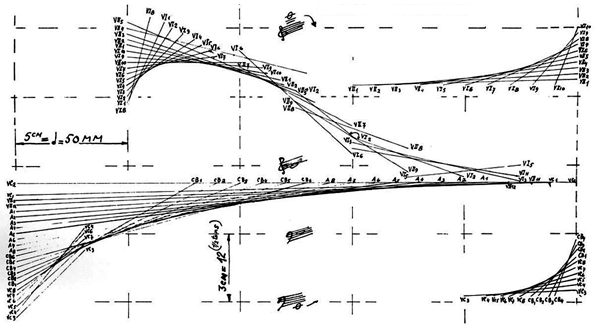 ヤニス・クセナキス「メタスタシス」の楽譜
ヤニス・クセナキス「メタスタシス」の楽譜
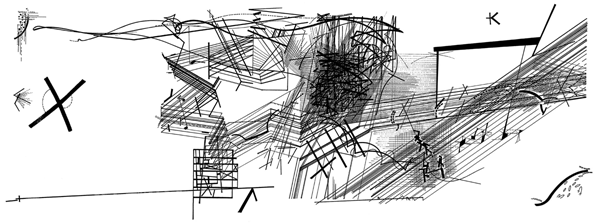 ダニエル・リベスキンドの作品「チェンバーワークス」
ダニエル・リベスキンドの作品「チェンバーワークス」
建築は「空間」を見て取れる設計図を、音楽は「時間」というシーケンスをあらわす楽譜を用いて記述し、同じような工程で構造体を生成する。設計図や楽譜に記される線や符号は、普遍的な技術としてモジュール化されており、その内部には再現性がある。それに対して、設計図や楽譜からアウトプットされるものの再現性は低い。アーキテクチャとは構造的同一性であるが、それは体系の内部において成り立つものであり、外部を同定するものではない。その理由が、あるアーキテクチャ以外にも、世界には数えきれないヴァージョンが存在するからなのは、これまで見てきたとおりである。
アーキテクトの精神と言語
アーキテクチャのアナロジーとして音楽を取り上げたのは、『Web情報アーキテクチャ』第4版で、新たに「リズムとビート」という表現が加わったからだ。この音楽用語が「呼吸と鼓動」に例えられるように、アーキテクチャの制作にはアーキテクトの身体が大きく関わっている。つまりアーキテクチャとは、全体が合理的に計画されるだけではなく、リズムやビートのように生成されながら構築されるものでもある。
アーキテクチャという「言語の記号システム」の制作は、ある言語の辞書とその使用方法を記述することに言い換えてもいいだろう。しかし、その膨大なボキャブラリー(語彙)を網羅しつつ運用するのは、なかなか難しい。だからその言語体系の多くは、アーキテクトの精神のうちに覆い隠されることになる。つまりアーキテクチャとは、アーキテクトの首尾一貫した精神によって創造されるものであり、その恣意的な体系には無数のヴァージョンが存在する。アーキテクトにとって「書くこと」は、自分が想像するあるアーキテクチャを、翻訳して現前させていることにほかならない。
あるアーキテクチャの「真理」は、ある世界においてのみ成立するものだから、それを信じるアーキテクトの精神が欠かせない。そしてこの精神は、言語という日常的実践に関わるものである。あるアーキテクチャの「意味空間」は、あるアーキテクトの言語感覚が反映されて生み出される、世界にひとつのヴァージョンなのだ。
重ね合わされたマウスとゆらゆら揺れるiPad
私は長らく、エキソニモの「ゴットは、存在する。」と、谷口暁彦の「思い過ごすものたち」という作品を一緒に考えたいと思っていました。このふたつはともにユーザインターフェイスを題材にした連作ですが、鑑賞者であるヒトとのインタラクションがない作品です。そして、どちらの作品もインターフェイスが自律している状態にあります。ヒトとコンピュータとのあいだにあるインターフェイスが、「単体」で自律しているのです。
エキソニモと谷口の作品を順番に見ていきましょう。まずはエキソニモによる自作の説明です。
標準的なインターフェイスやデバイス、インターネットの中に潜む神秘性をあぶり出すことをテーマにした一連のシリーズ。光学式マウスを2つ絶妙なポジションで合わせることでカーソルが動き出すことを発見し、その祈っているような形態と、祈ることで奇跡が起きている状況を作品化した「Pray」。日本語で神を意味する「ゴッド」と、一箇所だけ違うが意味を成さない単語「ゴット」をTwitterの検索結果の中で置き換え「ゴット」の存在する世界を表出させた「Rumor」など。用途をずらし、無効化されたインターフェイスの中に神秘性を見出していく試みでもある。
「インターフェイスの中に神秘性を見出していく試み」と言われても、あまりピンと来ない方が多いのではないでしょうか。でも、私はこのことがとても気になるのです。インターフェイスにヒトが介在しなくてもコンピュータが動き続けることには、ヒトとコンピュータとの関係を示唆する何かがある気がするからです。今回は、連作である「ゴットは、存在する。」で、最初に取り上げられている《祈(=Pray)》を見ていきたいと思います。

以下は、私が《祈》を見たときに考えたことです。
《祈》では、ふたつの光学式マウスが手を合わせるように重ねられ、「祈り」がGoogle画像検索されたディスプレイ上で、カーソルが震えるように動いています。私はそれを見て、マウスという「モノ」が祈るという行為をしていると認識してしまいました。ふたつのマウスが手を合わせるように重ねられていることもありますが、ディスプレイ上でかすかに動くカーソルを見たとき、何かを切実に「祈る」行為がなされていると思ったのです。ヒトに特有な「祈る」という行為が、マウスという「モノ」とカーソルという「イメージ」の組合せによって、ヒトを介さず行われていました。イメージを介してモノが祈っている、と言ってもいいかもしれません。
次に、谷口の「思い過ごすものたち」を見ていきましょう。まずは谷口による自作の説明です。
「思い過ごすものたち」は、いくつかの日用品と、iPadやiPhoneを素材にした彫刻作品です。
“思い過ごす”とは、あれこれと考えすぎて、しばしば現実とはズレた認識や理解をしてしまうことです。
これは、作品を鑑賞する人や、作品に用いられているiPadやiPhoneたちが “思い過ごし” てしまうような、ズレた接続や配置を試みた作品です。
iPadとiPhoneを、日用品のひとつとして捉え、特別なアプリケーションは使用せず、標準でインストールされているアプリケーションを、そのまま使用しています。
エキソニモと同じく、「思い過ごすものたち」の説明にも「標準」という言葉が使われています。「標準」とは、デバイスを買ったときにそれがあるということです。誰もが一度は使うことになる「標準」装備のアプリやインターフェイスは、ひとつの「自然」のように、今やあって当たり前の存在になっています。特に意識することなく当たり前に使っているからこそ、谷口やエキソニモが説明するとおり、「ズレ」によって認識の変化が起こります。だから作品のタイトルも、「ゴッド」から「ゴット」へ、「現実」から「思い過ごし」へとズレているのです。
「思い過ごすものたち」も連作なので、エキソニモと同じように、谷口が最初に説明している作品《A.》を取り上げてみたいと思います。

《A.》について谷口は次のように説明しています。
A.
・天上から吊られたiPadが扇風機の風で揺れます。
・iPadの画面には、ティッシュペーパーが風でたなびいている映像が短いループで流れ続けます。
以下は、《A.》を見たときに私が考えたことです。
《A.》は天井から吊られたiPadに、箱に入ったティッシュペーパーのCGが映し出されていて、ゆらゆらとしています。「ゆらゆらしている」のは、扇風機の風によって揺れているiPadそのものですが、そこに映ったティッシュペーパーも揺れています。でも、風に揺らされているのはiPadだけで、そこに映されたティッシュペーパーは風と関係なく揺れています。映像はループしているだけで、風と映像のあいだに直接的なインタラクションはありません。物理レイヤーではしっかりと関係していますが、イメージレイヤーでは全く関係していないのです。しかし、その関係が「ある」にしろ「ない」にしろ、見る人のなかでiPadとティッシュペーパーと風はつながってしまいます。これはどうしても、なにがあってもつながってしまうのです。
メディウムとして自律するインターフェイス
エキソニモと谷口の自作説明と、私が作品を体験したときの考察を並べると、そこから「モノ」と「イメージ」との関係性が見えてきます。インターフェイスというのは、マウスなどのモノの部分とディスプレイに映るカーソルなどのイメージの部分が、ヒトの行為と連動して機能するものです。しかし、《祈》と《A.》にはヒトがいません。それでも、カーソルは勝手に動くし、iPadは勝手に揺れています。そのときヒトは、マウスとカーソルとの関係から「祈る」行為を想起してしまい、揺れているiPadとそのディスプレイに映るティッシュペーパーを結びつけてしまう。これらの作品が興味深いのは、インターフェイスからヒトを取り除きながら、ひとつの現象としてヒトに意味を示していることなのです。
エキソニモはマウスとカーソルといったデスクトップメタファに基づくインターフェイスを使い、谷口はタッチパネルをインターフェイスにしたデバイスを扱っているちがいはあります。しかし、ともに「インターフェイス」を作品の「メディウム」※1に選んでいることにはちがいはありません。唐突に「メディウム」という言葉を使いましたが、ここがとても重要なところです。エキソニモと谷口の作品は、ヒトとコンピュータのあいだの「インターフェイス」を扱いながら、それらが「ふたつの存在のあいだに生じる状態」ではなく、「メディウム」という作品の支持体として自律したモノになっています。それはもうインターフェイスではないだろうという声もあるでしょう。なにしろこれらの作品には、ヒトとのインタラクションがないのですから。
私は、かつて美術批評家のクレメント・グリーンバーグが「モダニズムの絵画」※2で、絵画におけるメディウムの「純粋さ」を指摘したことを思い出しました。グリーンバーグは絵画の特性を平面性=二次元性に求めました。そして絵画から、彫刻の本分である三次元性が連想される要素を取り除くことで、その「純粋さ」が得られると考えたのです。このグリーンバーグの考えを知ったとき、私はエキソニモと谷口の作品が「モダニズムのインターフェイス」と呼べるのではないかと思うようになりました。なぜなら、両者の作品を見ていると、マウスとカーソル、iPadといったインターフェイスを構成するモノの特性に意識が向かうからです。これはインターフェイスを考える際、あまり経験のなかったことです。
一方で、先ほども書いたとおり、インターフェイスは「ふたつの存在のあいだに生じる状態」のようなもので、モノが作品の支持体=メディウムとして「純粋さ」を追求できるわけではないとも考えていました。実際、インターフェイスをメディウムとして見ることはほとんどありません。アートとしてのインターフェイスでは、ヒトとコンピュータとのインタラクションが問題になることが多いからです。しかし、エキソニモと谷口の作品は、ヒトを取り除いたインターフェイスをモノとして提示することで、アートのメディウムとしてインターフェイスを追求しているように見えたのです。
インターフェイスのスイッチとなるヒト
エキソニモと谷口の作品は、私たちを日常からズラした状態を作り出しています。エキソニモはそれを「用途をずらし、無効化されたインターフェイスの中に神秘性を見出していく試み」と言い、「奇跡が起きている状況」を見せようとしました。谷口はそれを「作品に用いられているiPadが“思い過ごし”てしまうような、ズレた接続や配置を試みた」としました。ここでズラされているのは、もちろんヒトです。ヒトを除いてもコンピュータやiPadが動き続ける状態をつくること。それが「奇跡」であり、「思い過ごし」とされているのです。
つまり、ヒトを介さずに情報が流れる閉回路をつくることができれば、それはインターフェイスとして機能し続けるのです。エキソニモの《祈》は、重ねあわせたマウスで起こる光の干渉によって情報を生じさせ、ディスプレイ上のカーソルを動かします。もう一方の谷口の《A.》には、何ひとつ回路はありません。しかし、「画面の中のティッシュの映像は、風とは無関係にただループ再生されていることは見ればすぐわかる。iPadそのものを揺らすことは間違えた接続なのだけれど、それによって風が画面の中に入っていくように感じられてしまう」と谷口が言うように、それを見たヒトが画面の内と外をつなげる回路を勝手につくってしまいます。これはいわば、擬似的な閉回路と言えるでしょう。
ふたつの作品を見ていて、そこに「祈る」行為を想起し、風が画面の中に入っていくように感じたとき、ヒトはインターフェイスの閉回路から弾き出されています。いつも接続されているかのように感じているコンピュータの回路から追い出され、自分では何も情報を生みだすことができず、目の前の状況を勝手に想像することしかできません。このとき、「インターフェイス」が情報を生みだして流す回路のようなもので、その回路に組み込まれたヒトとモノは「スイッチ」のような役割を担っていることに気づかされます。つまり、ヒトはインターフェイスにおいて、情報を生み出すためにマウスボタンを「押す/押さない」、タッチパネルに「触れる/触れない」などの「オン/オフ」を繰り返す存在でしかありません。ヒトがいなくても、別のモノがスイッチになっていれば問題ないのです。
この意味で、エキソニモの《祈》は残酷かもしれません。完全にヒトを必要としていないからです。マウスとカーソルは通常の機能を果たしているにもかかわらず、ヒトは「祈る」行為を想起することしかできません。それに対して、谷口の《A.》では、ヒトがまだ「思い過ごすものたち」に含まれています。ヒトの思い過ごしによって、iPadと風を接続する回路は生成されています。
いや、もしかすると、より残酷なのは谷口の方かもしれません。谷口がつくる回路には、何ひとつ明示的なオン/オフがないからです。iPadには加速度センサーがついていますが、この作品では揺れを感知していません。ただ扇風機の風に吹かれて揺れているだけです。《A.》は情報の流れをつくらず、重ね合わされたマウスのようなヒトの行為に似た要素もなく、風に揺れるiPadという物理現象を頼りに、ヒトの想起を取り込もこうとしているのです。
より大きな回路のインターフェイス
「スイッチ」について、アメリカの哲学者グレゴリー・ベイトソンが興味深い指摘をしているので、引用してみます。
われわれは日常、“スイッチ”という概念が、“石”とか“テーブル”とかいう概念とは次元を異にしていることに気づかないでいる。ちょっと考えてみれば解ることだが、電気回路の一部分としてスイッチは、オンの位置にある時には存在していない。回路の視点に立てば、スイッチとその前後の導線の間には何ら違いはない。スイッチはただの“導線の延長”にすぎない。また、オフの時にも、スイッチは回路の視点から見てやはり存在してはいない。それは二個の導体(これ自体スイッチがオンの時しか導体としては存在しないが)の間の単なる切れ目 —— 無なるもの —— にすぎない。スイッチとは、切り換えの瞬間以外は存在しないものなのだ。“スイッチ”という概念は、時間に対し特別な関係を持つ。それは“物体”という概念よりも、“変化”という概念に関わるものである。(pp.147-148)グレゴリー・ベイトソン『精神と自然 — 生きた世界の認識論』
ベイトソンの「スイッチ」が、「物体」ではく「変化」という概念に関わるものであるという指摘は、エキソニモと谷口の作品、そしてインターフェイスの「純粋性」を考える上で、とても有効に思えます。私たちはインターフェイスをモノとして考えがちですが、そのとき機能しているマウス、カーソル、タッチパネル、そしてヒトも含めて、それらが情報を生み出すための「スイッチ」だとすれば、「変化」という概念で捉えることができます。インターフェイスは「ふたつの存在のあいだの状態」と言ってきましたが、その状態はふたつの存在のあいだで起こり続ける「変化」と言い換えることができます。インターフェイスでは、モノだけでなくヒトも含めたすべての存在が、情報を生み出すために「変化」を繰り返すスイッチとして、回路の導線に組み込まれているのです。
これまで、インターフェイスを扱ったほとんどの作品は、次々と「変化」していくインタラクションの様子を見せてきました。しかし、エキソニモと谷口の作品は、そのインタラクションからヒトを追い出して、回路そのものをモノ=メディウムとして提示しました。ヒトの視点が回路の外側にあるからこそ、重ねられたマウスが起こす「奇跡」や、iPadが「思い過ごす」様子を見て、インターフェイスをモノ=メディウムとして捉えられるのです。
インターフェイスを考えるには、インタラクションという「変化」の部分と、インタラクションを生じさせているモノ自体を見なければなりません。「変化」を意識しながら、そこにベイトソンが言う「無」となるモノ自体であるマウス、カーソル、タッチパネル、ヒトを見つめることで、はじめてインターフェイスを構成する回路の存在をメディウムとして捉えることができるようになります。それはとても注意深い作業と言えるでしょう。なぜなら、見ようとしているものは「無」ですから、ベイトソンが提示する「変化」への意識を経由して、「物体」を改めて見る必要があるのです。
デジタルの世界では、そこにヒトがいようがいまいが関係なく、プログラムによって再現可能な現象となり、条件さえ整えれば「奇跡」や「思い過ごし」がおこります。それは「無」を見つめて、そこにモノを見出すことであり、エキソニモの言葉にあった「インターフェイスの神秘性」なのかもしれません。エキソニモは「ゴットは、存在する。」に「Spiritual Computing」という英語タイトルをつけました。「スピリチュアル」という体験は、自分を含んだより大きな存在を認めることです。エキソニモと谷口は、インターフェイスにヒトとコンピュータとの関係だけではなく、それを取り巻くもっと大きな回路の存在を見ているのではないでしょうか。彼らの作品は、ヒトとコンピュータのあいだで変化し続けるインターフェイスに、ひとつのモノとして自律させる条件を見つけ出し、再現可能な現象として提示しました。そうすることで、インターフェイスがヒトとコンピュータを含んだ大きな回路であることを示したのだと思います。
自己帰属感と回路の視点
「インターフェイスの神秘性」をもう少し具体的に考えるために、インターフェイスデザインのひとつの原理を導入したいと思います。それはインターフェイス研究者の渡邉恵太が『融けるデザイン』で提案した「自己帰属感」です。
自己帰属感とは、ディスプレイに映るカーソルのような非物質的なものであっても、物質的な身体と連動していると認識される限り、自己に帰属していると感じられることです。渡邉は「カーソルはバーチャルな身体なのではなく、連動性という点においては実世界の自己の知覚原理と同じで「リアル」である」と言い切っています。「カーソルはバーチャルな分身」とよく言われてきましたが、ここでは「連動性」の名のもとに、リアルとバーチャルの境界がないかのようにつながっています。この考えは、コンピュータのインターフェイスのみならず、物質的存在と非物質的存在のあいだすべてに適応される射程の広いものではないでしょうか。渡邉はさらに次のように書きます。
私たちの身体の境界は、生物として手足を持つ人型としての骨格と皮膚までかもしれない。しかし、「生物としての身体」と「知覚原理としての身体」はおそらく少し分けて考えるべきである。そして後者はかなり柔軟にできており、帰属を通じて身体は「拡張可能」と言えるのだ。(p.125)
身体の一部になるということが、「持つこと」ではなく「連動すること」であるとすれば、それは物質から構成される身体ではなく、そこに物質と知覚的情報の設計の曖昧さ、入り混じりが発生する。したがって、自己に帰属した拡張した身体においては、身体の境界設計は物理的にも情報的にも行えるのだ。
私たちは、物理的であることが身体拡張のリアリティをもたらすと考えがちだが、物理的であることはたまたま身体との連動を作るのに都合が良いだけである。だから、物理的でないものであっても、たとえばカーソルであっても、連動すれば身体拡張と考えられる。むしろ、情報的に拡張する方が質量を伴わないため、柔軟な身体拡張が期待できるのだ。(p.128)渡邊恵太『融けるデザイン — ハード×ソフト×ネット時代の新たな設計論』
渡邉は気持ちいいくらいに、物質的であることに重きを置きません。これでいいのだと思います。これから私たちは、インターフェイスによって身体を柔軟に拡張していくのです。渡邉が「カーソル」を基点にして考察するように、既に私たちはカーソルを介して「知覚原理としての身体」を拡張しています。そして、おそらく身体だけでなく、身体が拡張した領域まで「自己」も拡張していくのだと思います。
「自己帰属感」という原理を導入した後で、改めて、エキソニモと谷口の作品を考えてみるとどうでしょうか。コンピュータと向き合いながら、インターフェイスの回路にまで拡張した私たちの身体=自己は、作品の回路に入り込むことができません。モノの回路として示されるインターフェイスの外側で、ただ見ているだけです。私たちの身体は、標準的なインターフェイスで得てきた拡張の感覚を十分すぎるほど蓄積しているにもかかわらず、彼らの作品では直接それが反映されない状態に置かれます。拡張して行き場がなくなった自己は、自律したインターフェイスへと勝手に入り込もうとします。身体はインタラクションできていなくても、意識だけが回路に接続されてインタラクションしてしまうのです。これは「解釈」と呼ばれるものとは少しちがいます。これはベイトソンが「回路の視点」と呼んだ、「スイッチもただの“導線の延長”にすぎない」感覚のように、鑑賞しているヒトの導線が、インターフェイスにまで伸びているのです。
理解の及ばない自分以外の何者か
自律しているインターフェイスへ勝手に入り込んでいってしまう意識はどこから、どのように生じるのでしょうか。もしかすると、これまでヒトの作用から語ってきたのがちがうのかもしれません。ヒトは自律したインターフェイスを見た瞬間に、もっと大きな存在である回路に取り込まれるといったほうが正確な気がします。このことを佐藤雅彦・齋藤達也による『指を置く』から考えてみましょう。
『指を置く』には、図版に指を置くシンプルなインタラクションを加えると、いつもとは全く異なる解釈が生まれてしまうという試みがまとめられています。これは、カーソルや指などで「指差す」ことを前提にした今のユーザインターフェイスの性質を知る上で、とても有益なものです。その研究のなかで得たことを、佐藤は次のように書いています。
この「指を置く」という研究に於いて、まず図版のように静的なメディアであっても、自分自身の行為と結び付いた動的な鑑賞が可能だということ自体がまず新しい発見であった。そればかりか、本書中の分類表に掲載しているように、図版中の出来事が自分事になることで生みだされる表象は非常に多様であった。空間性、エネルギー、生物の気配、道具の感触、概念や観念、また現実にはあり得ない因果性というように多岐にわたる。これは、私たちが実に様々な物事を自分事として認識できる能力を持っているということを意味する。一方で、私たちが自分事として捉えることのできる物事にも限界があることが分かる。「指を置く」の図版の中には、儀式性や呪術性というように自分以外の何らかの存在や摂理を想定せざるを得ない性質のものも見つかっている。指を置いている自分が関与しているのは確かだが、それと同時に理解の及ばない自分以外の何者かが立ち現れるという不可思議な事象や状況も存在するのである。(p.54)佐藤雅彦・齋藤達也『指を置く』
「自分事になる」という言葉は、多分に渡邉の「自己帰属感」と通じています。おそらくヒトは指や手を使うことで、意識の及ぶ範囲を拡大していきました。身体はそれによって、コンピュータのユーザインターフェイスという非物質的な領域にまで拡張されたと考えられます。ヒトがコンピュータとのインタラクションをここまで多様なものにできたのは、「空間性、エネルギー、生物の気配、道具の感触、概念や観念、また現実にはあり得ない因果性」によって動的な鑑賞が生み出され、それが知らず知らずのうちにインターフェイスで活用されたからでしょう。
ハリウッド映画のCGに見られるように、コンピュータは「現実にはあり得ない因果性」を表象することがヒトよりも得意です。だからヒトの「知覚原理の身体」は、コンピュータとのインタラクションで得られた表象をもとにして、さらに拡張していると言えます。しかし、ここで重要なのは「「指を置く」の図版の中には、儀式性や呪術性というように自分以外の何らかの存在や摂理を想定せざるを得ない性質のものも見つかっている」ことです。自分以外の何者かがインタラクションに入り込んでいるという視点は、渡邉になかったものです。しかもそれが、「指を置く」という原初的なインラクションに入り込んできているということは、インターフェイスにおいて立ち上がる自己帰属感に対しても、呪術的な力が働いていると考えられるでしょう。いや、呪術的な力がはたらいているからこそ、身体はいとも簡単に非物質的な存在とつながり、拡張できるといった方がいいかもしれません。自己帰属感とは、常に自己を起点した都合の良いものではないのです。
自己帰属感とともに立ち上がる「理解の及ばない自分以外の何者か」は、ヒトとコンピュータを含んだ回路のなかにあります。インターフェイスが自律する可能性は、この回路の存在を認識するときにこそ立ち上がります。この回路は、身体と自己が拡張される導線であり、自己帰属感をつくりだす基盤です。そしてここまで、その回路を認識することが奇跡であり、思い過ごしでズレた現実認識と考えてきました。けれど、エキソニモと谷口は、それぞれのインターフェイスからヒトを取り除き、インターフェイスをアートのメディウムとして自律させることによって、ヒトとコンピュータを取り巻くより大きな回路の存在を顕わにする方法を得ているのです。
この回路とそこに宿る「インターフェイスの神秘性」が、ヒトとコンピュータにとって何を示しているのかはわかりません。しかし、自律したインターフェイスから生じる現象を見つけて分析していけば、情報を生み出すスイッチとしてのヒトとコンピュータの在り方や関係性が見えてくるのではないかと考えています。
どうやら生まれてから死ぬまで、私たちの記憶は変化し続けているようだ。実際には、神経細胞の変化によって記憶が形成されているという次第も徐々に解明されつつある※1。
他方で、そうした私たちの記憶に影響を与える環境も大きく変化している。目下、人類はかつてない規模と速度で、各種のデータを生成・蓄積し、通信・交換している。こうした激流、あるいは大渦のようなと形容したくなるような環境下で、自分の記憶のあり方について、その世話をするにはどうしたらよいか。そんな関心から、ここのところ記憶のための新たな知識環境について考えている。以下では、そのスケッチをお示ししたい。
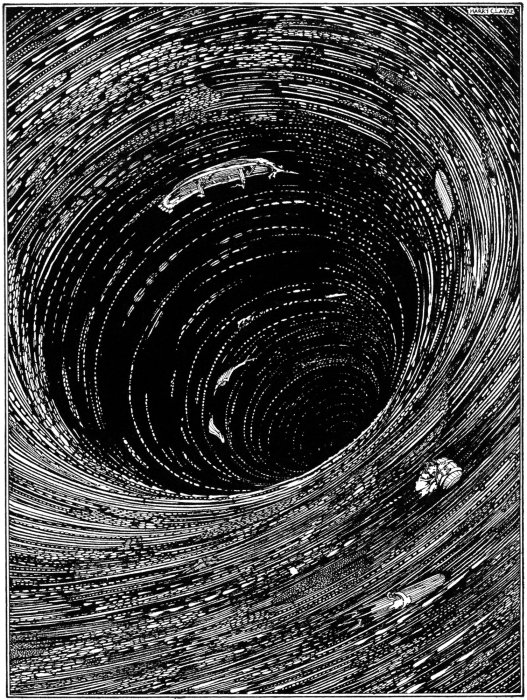 エドガー・アラン・ポーの小説「メエルシュトレエムに呑まれて(A Descent into the Maelström)」に掲載されたハリー・クラークによる挿絵
エドガー・アラン・ポーの小説「メエルシュトレエムに呑まれて(A Descent into the Maelström)」に掲載されたハリー・クラークによる挿絵
記憶の条件
記憶については、いくつかの分類が提案されてきた。例えば、記憶が維持される時間の長さによる分類はよく知られている。ここでは、身体が自律的に行う記憶と、人が意識して行う記憶という区別に注目してみよう。
心臓の鼓動や呼吸などが、なにごともなければ自動的に働くのと同じように、私たちの身体は、別段努力をしなくても、環境や自分の身に生じる出来事を記憶している。危険な目に遭ったことが強く後々まで記憶に刻まれるのは最たる例である。ともあれ、心身によって絶えず感知される出来事が、なんらかの変換を施されて脳裏に収まる。これを区別のために「生物的記憶」と呼ぶことにしよう。
他方で意識してする記憶とは、例えば、試験に備えて知識を暗記するような場合を指す。私たちは、身体が勝手に記憶することとは別に、あるいはそれを利用して、何事かを自ら努めて記憶できる。これも区別のために「意志的記憶」と呼ぶことにしよう。先ほどの「生物的記憶」を、この名称との対比から「非意志的記憶」と呼んでもよい※2。
加えて重要なのは、私たちは忘れっぽい生き物でもあるということだ。放っておけば経験したことや覚えたことも徐々に思い出せなくなってゆく。あるいは記憶は変形してゆく。また、変形したことにも気づかない。それこそ記録でもつけておかなければ、過去1カ月に何を食べたかをそっくり覚えていたりはしない。また、しばしば歴史の記憶を巡る争いが生じるのも、元をただせば人間の記憶がよくもあしくもいい加減なためであろう。
そのうえ目下のところは、選んで何かを忘れることはできない。そうかと思えば、思い出したくなくても、何度も脳裏に甦ってしまう記憶もある。自分の心身だからといって、私たちは生物的記憶の働きを必ずしもコントロールできないわけである。
情報環境が私たちにしていること
現代は、幾重もの意味で、記憶のあり方について考えさせられる時代である。とりわけこの30年ほどの間に生じた情報環境 ※3の変化は無視できない。従来の書物、電話、ラジオ、テレビといった各種通信伝達手段に加えて、インターネットが厖大なデータの流れを生み出し、いまやアクセスするための装置さえあれば、誰もが利用できる。
その結果、さまざまなことが生じてきた。中でも大きな変化の一つは、人が従来と比べて大量の文字を読み書きするようになったことであろう。また、人がこんなにこまめに調べものをする時代もいままでなかったと思われる。もちろん、文字に限らず、映像や音楽、ゲームその他のデジタルデータに接する量も増えているだろう。
記憶という観点から見ると、かつてない規模と速度で、人が記憶を変化させうる状況にある。例えば、ネットとスマートフォンが普及する以前の駅や電車の光景を思い出してみよう(思い出せる人は)。たまさか手に読み物を持っている人はそれを眺め、そうでない人は目をつぶったり、ホームに設置された看板や社内の中づりを眺めていた。それもいまにして思えば、極めてのんびりと、ごく限られたものを。
現在、四六時中スマートフォンの小さな窓に向かって、その表面を指先でなでる現代人は(そう、現代は人がかつてなくものの表面をなでる時代でもある)、いったい日にどれだけの文字や映像を眼に入れているだろう。
念のためにいえば、これは善し悪しの問題ではない。また、昔はよかったという話でもない。ただ、記憶という観点から眺めた場合、かつてとは比較しようもないほど、高速かつ大量に記憶 —— 少なくとも生物的記憶 —— の変化を生じさせている可能性がある、ということを考えてみたいわけである。つまり、この環境と状況は、私たちの心身になにをもたらしているところなのか。目下は壮大な社会実験を遂行中といったところであり、その効果をにわかに見積もるのは難しい※4。
不確かな未来のための記憶術
以上、簡単に眺めたように、私たちは我が事ながらままならない記憶のしくみでもって、日々大量の文字やデータに接する情報環境を生きている。もっとも、ネットに関しては、検索技術の発明と向上によって、そのつど必要に応じてデータを抽出できるようになってきた。人によっては、厖大なネット上のデータと検索エンジンの組み合わせさえあれば、自分であれこれ記憶する手間も省けてよいではないか、と考える向きもあるだろう※5。もちろんそれで用が足りるならそれでよい。
他方で、もし自らの脳裏に納める物事について、それなりに気を配りたいと考える場合どうしたらよいか。そもそもいくら検索の性能が向上したとしても、どんな言葉を検索するかを選ぶにも、検索した結果を評価し、解釈するためにも、自分の脳裏に蔵された記憶しか(いまのところ)頼るものがないとすれば、記憶への配慮という問題は、ちょっと無視しえない道理である。
次々とのべつ幕なしに記憶を上書きする虚々実々が知覚を通じて入ってくる状況で、なにがしかの記憶を整え、保持したいと思う場合、どうしたらよいだろうか。自分の記憶をいかにデザイン(設計)できるだろうか。
もちろん、ネットその他のメディアの使用頻度を調整すれば、耳目に触れるものを減らせる。これは一つの手だ。他方で、ネットの恩恵に与かりながら行く場合、つまり流入量を制限せずに行く場合はどうか。こうした関心に基づいて考えるべきことは、少なくとも二つあるように思う。
1. 予測できない未来へ備える記憶のセット
そもそもどういう記憶のセットを脳裏に備えておけばよいかを再考してみること。すぐ役に立つようなことについては、そのつど探して取り入れればよいとして、むしろ問題は、数年後にどこで何をしているか分からない自分を手助けするためには、どんな記憶のセットがあればよいかということだ。もちろんこれは無理難題というものである。そもそも数年後に世界がどうなっているかも分からない。したがって、そこで何が必要になるかも分かろうはずがない。
それでもなお、最低限これだけのことを装備しておけば、なんとか臨機応変に対応できる。そういう記憶のセットを考えてみることもできる。従来それが「教養」や「リベラル・アーツ」と呼ばれてきたのであろう※6。つまり、これだけのことを備えておくと、そのつどどんな問題に遭遇するかは分からねど、脳裏に備えたものを組み合わせたり活用することで道を切り開ける、という、いわば知のサヴァイヴァル・キットである。呼び名をどうするかはともかく、こうしたキットをそのつど再考して、更新してゆく必要があると考えている。
2. 新たな記憶術を模索する
もう一つは、意志的記憶の仕方を模索することだ。そのつもりで歴史を眺めると、さまざまな場所で人々が記憶に関心をもって、これを制御するための技法について考え、編み出してきた痕跡が窺える。例えば、比較的よく研究されているものに、ヨーロッパで発達した「記憶術」がある。ごく簡単に要約すれば、脳裏に馴染みの空間をしつらえ、そこに記憶したいもののシンボルを配置するという手法だ※7。つまり、記憶のなかに安定して想起できる場をつくり、その場を手がかりにして、記憶を構成するわけである。この技法は、面白いことに明治期の日本でも一時流行を見せたが、根づくことはなかったようだ※8。
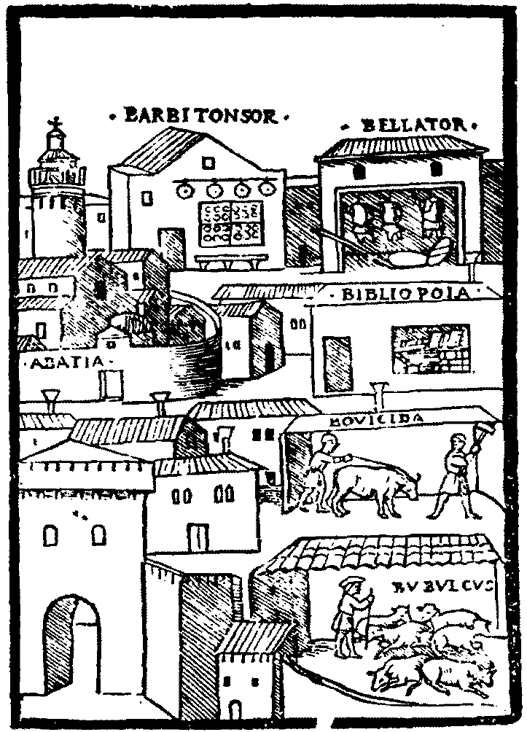 Johannes Romberch “Congestorium Artificiose Memorie” (1520) から。記憶の場としての町。
Johannes Romberch “Congestorium Artificiose Memorie” (1520) から。記憶の場としての町。
この記憶術、実際試してみると、結構な手間と根気を要することが分かる(その手間でなにかを記憶できるのではないかとさえ思えてくる)。モノグサな凡人の身には、そのまま活用するのは難しい。だが、手がかりはある。この技法に見られるように、何かを記憶しようとする際、記憶の対象とは必ずしも関係のない別の記憶とセットにするのがポイントである。この発想は、英単語や元素記号を語呂合わせで覚えるテクニックにも通じるものだ。つまり、比較的思い出しやすいものに、記憶したいことを結び付けておくという操作である。
言われて考えてみれば、例えば本というものは、その装幀や造本も含めて、一種、記憶のための装置でもある。何度も手にした本であれば、表紙のデザインや版面が、著者名や書名、さらにはその内容とともに想起されるだろう。つまり、その物質的要素が、そこに印刷されている内容への記憶の手がかりとなっているわけである。また、ある本は、別の本とのつながりを連想させもする。同じ著者の本、同じテーマやジャンルの本、同じ装幀家や出版社の本という具合に。複数の本を並べた書棚もまた、記憶の場となる。それが自室であれば、書棚は普段から意識せずとも繰り返し目にする物理環境ともなる。
同様に、記憶しようとすることを、紙なら紙のような平面上に配置してみること、一種のダイアグラム(線で構成された図)、あるいはマップに描いてみることも有効である※9。近年、インフォグラフィクスという名の下に、情報やデータを図像として表現する手法が改めて注目されている※10。こうした試みも、ただ見やすい、美しいというだけでなく、そこに提示される情報やデータを、色やフォントやグラフィックといった要素と関連づけたデザインを施し、記憶の手がかりを生み出していると捉えてみることができる。要するに、内容とデザインとがセットになって、それを見る者の記憶に訴える表現となるわけである。
—— と、このように、記憶、記憶と繰り返していると、なんでもかんでも覚えればいいというものじゃなし、記憶の技法ばかりに注目しても詮無いのではなかろうか、という気分にもなってくる。つまりは、何を記憶するのかという先に述べた件に話は戻ることになる。というよりも、この二つを組み合わせて考える必要がある。
知識OSの構想 — 記憶の環境をデザインする
なぜこのようなことをつらつら考えているのか。はじめにお伝えすべきだったかもしれない。自分のコンピュータに1万冊ほどの本を蓄積してみて分かったことがある。デジタルデータとしての本は、実に簡単に把握できなくなる。なにがあって、なにがないのか分からなくなる。同数の紙の本も大概だが、それでもまだおおよそは把握できる。デジタルデータで同じようにいかないのは、おそらく記憶の手がかりが少ないからだ。
例えば、モノとしての本は、空間に並べることで一覧性を確保できる。また、まさに空間の特定の位置に関連づけられる(「この左下のほうには映画の本があったはず……」など)。これに対して、コンピュータの記憶装置にデータをそのまま並べておくだけでは、そうはいかない。そもそも利用者が当該フォルダを表示するまで、それは見えない状態にある。当該フォルダを画面に表示するにしても、一画面に表示されるファイル数はたかが知れており、とうてい一覧はかなわない。ただし、強力な検索機能を駆使することで、適切な検索語さえ選べば、あっという間にデータを抽出できる。だからネットと同様に、検索で用が足りる場合には、記憶は問題にならないだろう。
私は、こうしたデジタルデータを、よりいっそう利用者の記憶に資する形で扱う方法があるのではないか、と考えている。従来のOS(Operating System)は、そもそもの設計方針からいっても、コンピュータのメモリ上にあるデータをファイルという形で操作(operate)するしくみ(system)を提供してきた。いわば、コンピュータの上でデータをあちらからこちらへと移動したり複製したり作成するためのしくみである。そこでは、それぞれのデータがどのようなものか、という意味や分類については利用者に管理が委ねられている。もちろんそれはそれでよい。
ただし、昨今のように個人用のコンピュータでさえも、数万件規模のデータを蓄積・利用するようになってみると、データ操作に加えて、もう一つ、知識操作とでも言うべきインターフェイスが欲しくなってくる。それも、専用のアプリケーションソフト(応用ソフト)というよりは、コンピュータを常時利用する物理環境、まさに自分のデスクトップとして活用するような、あるいは、そのコンピュータの記憶装置にあるデータや、ネット上の各種データを総合的に活用しうるような、いうなれば一種の「知識OS(基本ソフト)」のようなソフトウェアが欲しい。その知識OSは、ディスプレイを一つの(あるいは複数の)空間として、例えば建築物や書架のように設計できる、記憶術の道具としても活用できる機能を備えているはずである。
もちろんこの知識OSを設計するためには、これまで人類が編み出してきた諸学術やその分類、あるいは辞書や百科全書をはじめとする知の操作にかかわる創意工夫全般がおおいに参考になるであろう。といっても、先人がつくったものをそのまま拝借するというよりは、それを道具として、自分に必要な知識=記憶環境を、みずから設計構築することが主眼である。古くは『シムシティ』や最近の『マインクラフト』のように、一種の箱庭として自分のコンピュータの上に知の樹木を育て、マップを描いてゆくわけである。
この知識OSは、効率を優先する便利さとは別の観点で設計する必要もあると睨んでいる。ちょうど書棚を自分の手で整理しながら記憶を新たにするように、コンピュータ上の環境を自分で手入れをする手間を残したものになるだろう。なんとなれば、結局のところ、記憶の世話をして、何かを記憶に刻むには、その対象に繰り返し触れるほかに近道はないからである。
その際は、ようやく実用化の目途がついてきたヘッドマウントディスプレイ(HMD)※11や、利用者の身体の動きを入力に換える各種モーションセンサー※12、あるいは空間にコンピュータで生成した映像を重ね合わせたり投射する各種技術※13も、こうした観点から活用しうるはずである。それはおそらく、紙かデジタルかという実りの少ない対比とは別に、紙とデジタルが相互の価値を高める知と記憶の環境になるだろう。ただし、注意すべきは、あくまでもこれを利用する人間の記憶の補助となるインターフェイスと機能の実装を目指して設計する、ということである。言い換えれば、コンピュータの機能に沿って物事を効率化・最適化するのではなく、人間の記憶のしくみに沿ってデザインする必要がある。
本稿では、そのような来たるべき知識環境のためのささやかな覚書を記してみた。
記憶をいかにデザインするか。これが問題である。
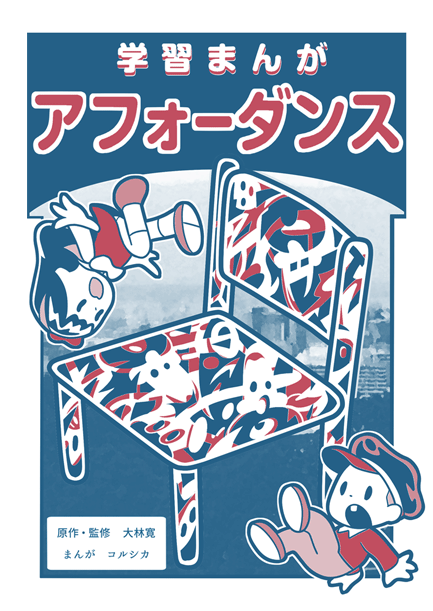

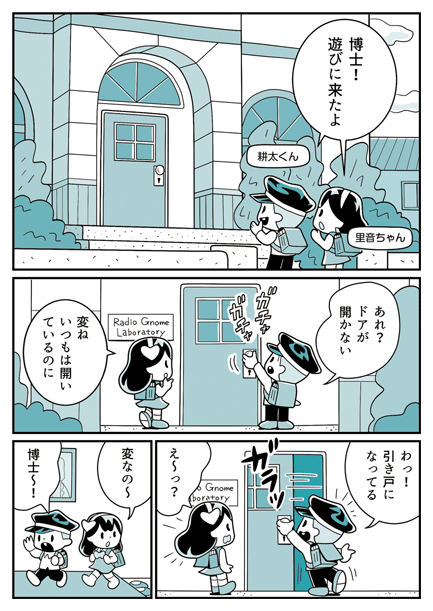
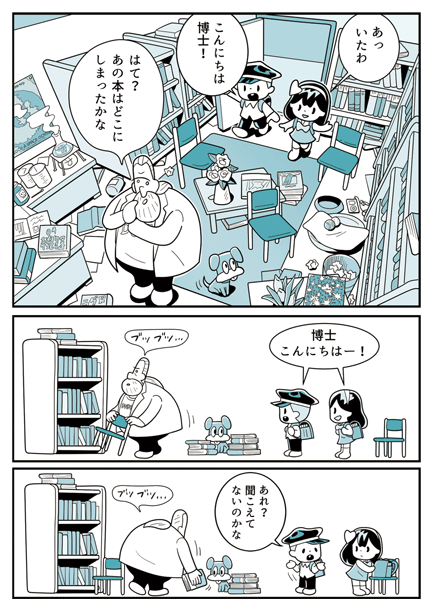
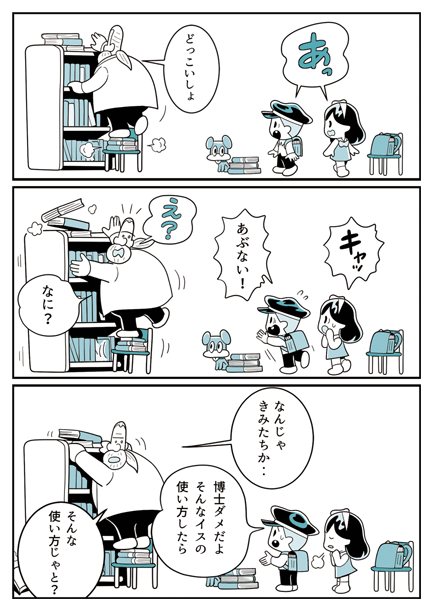
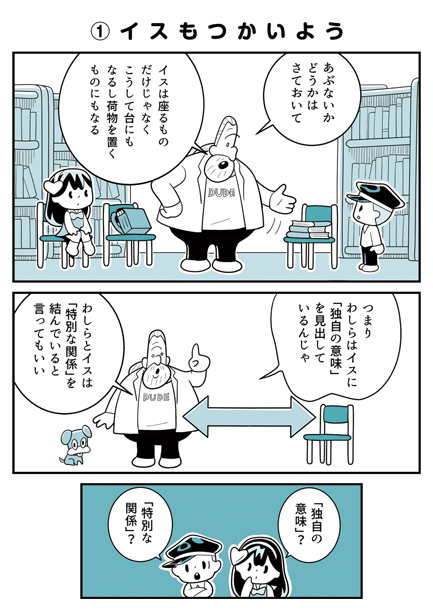
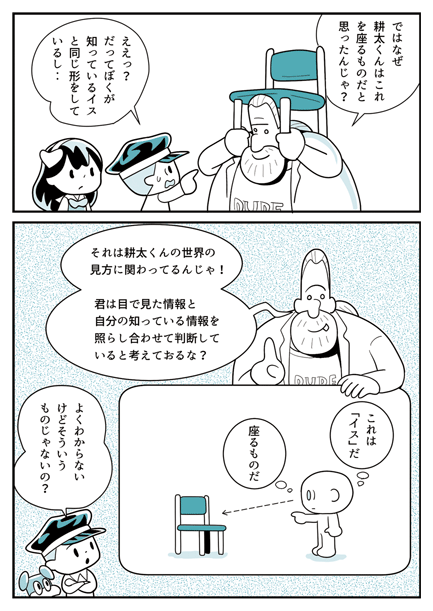
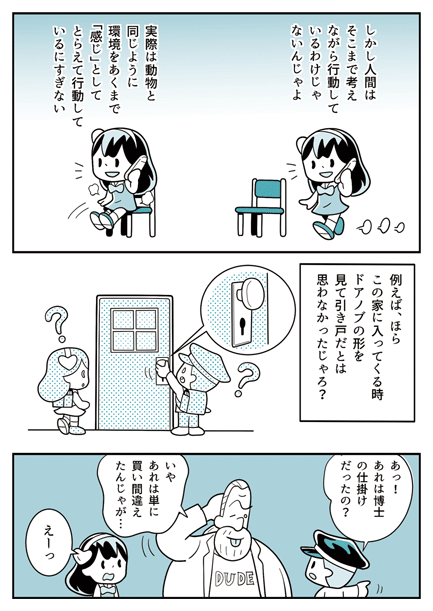
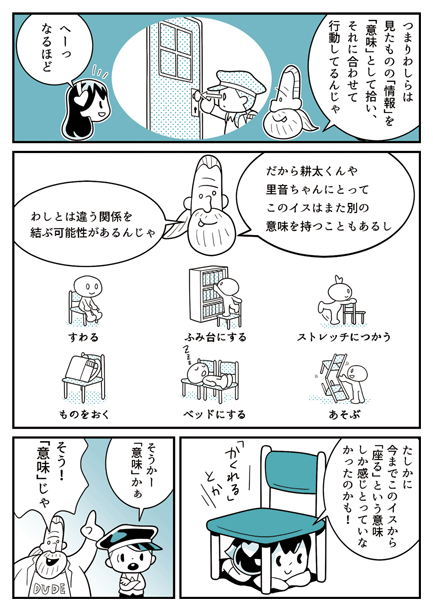
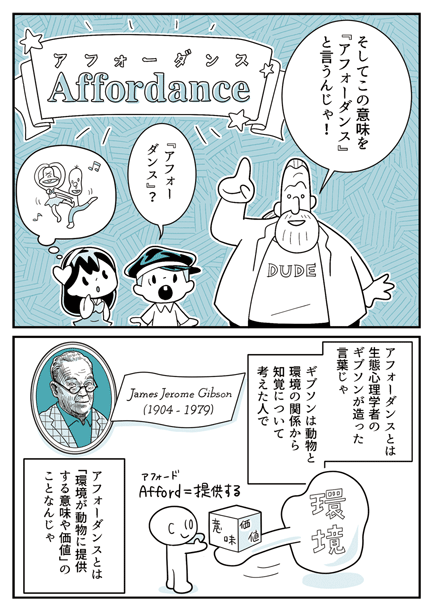
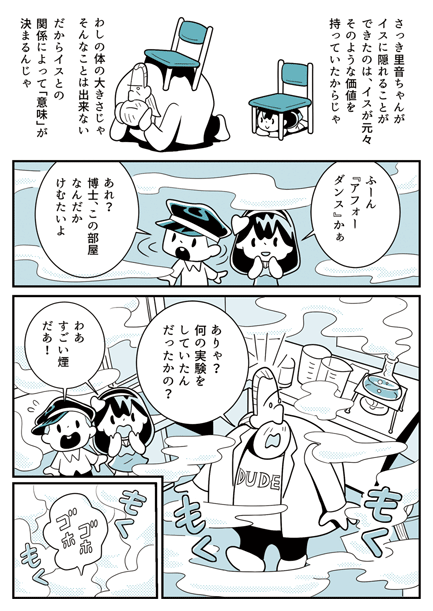
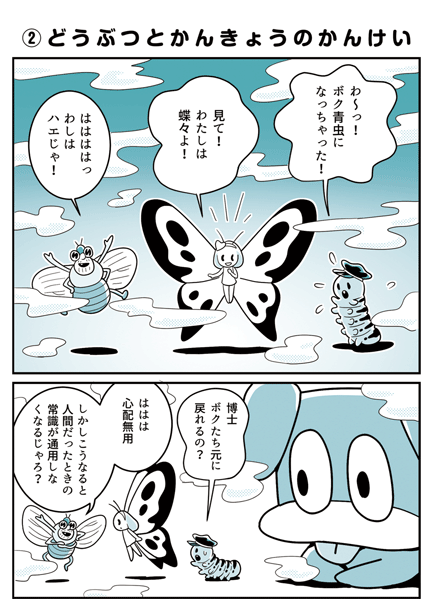
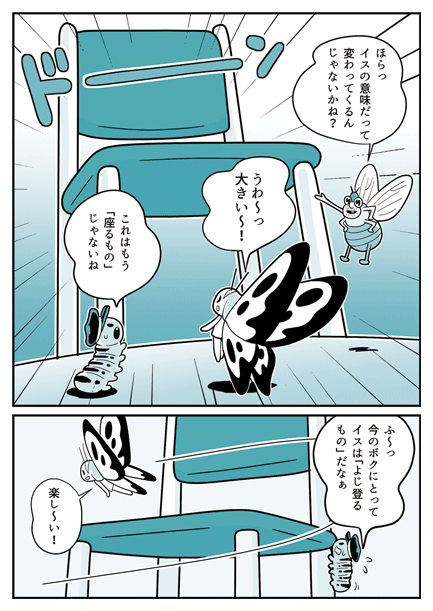
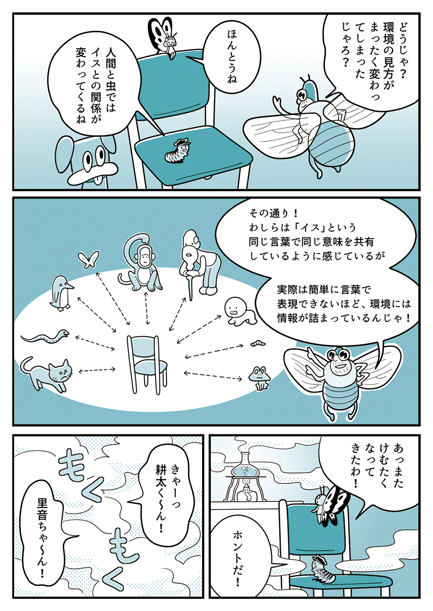
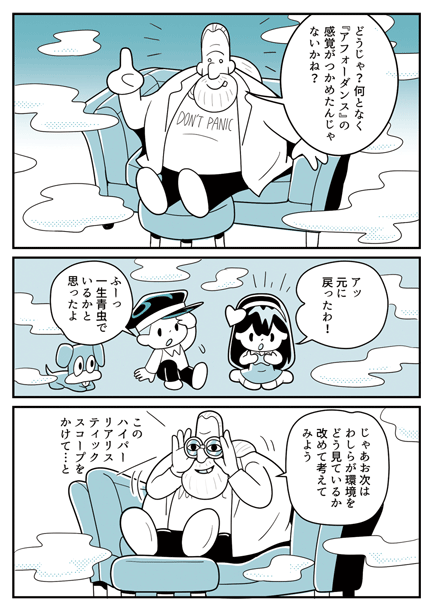
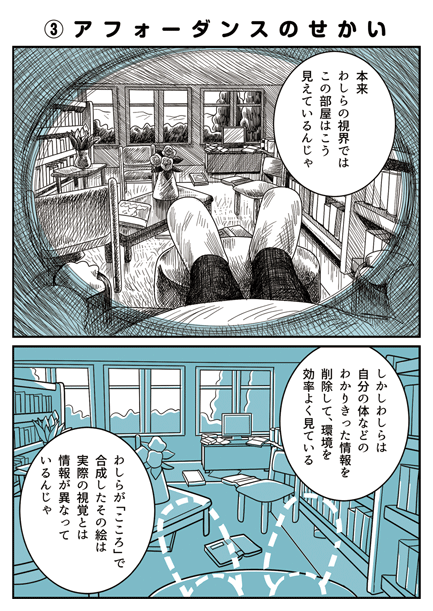
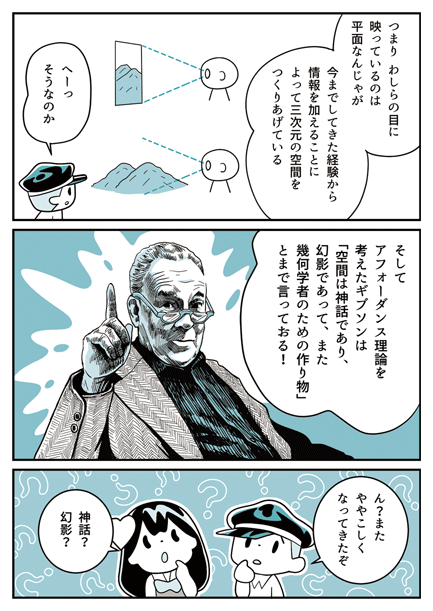
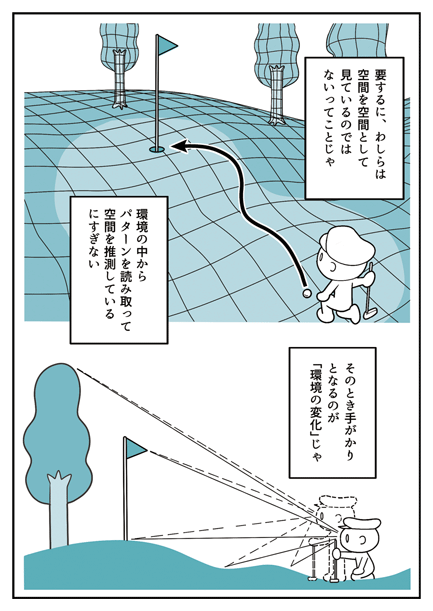
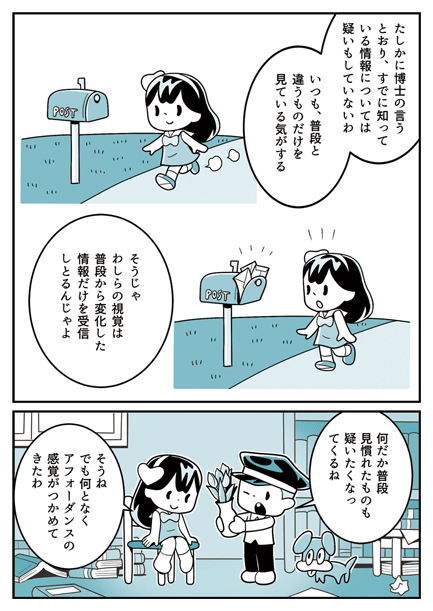
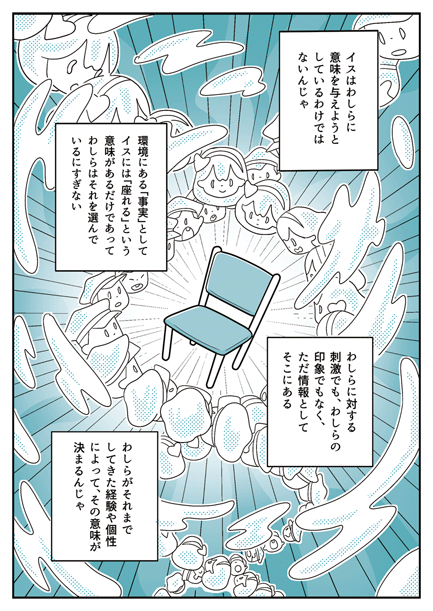
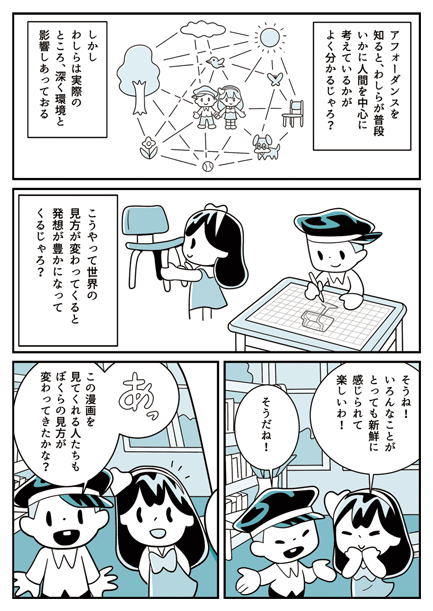
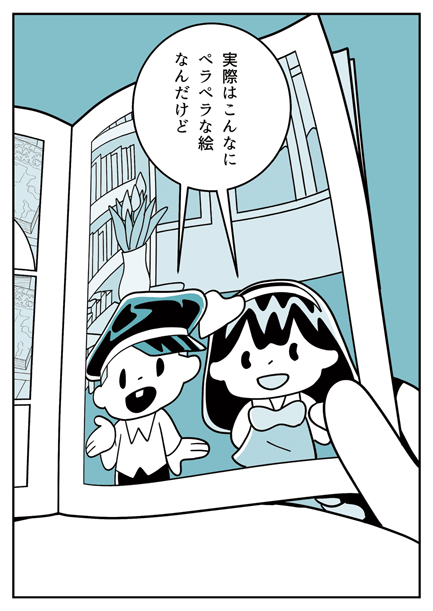
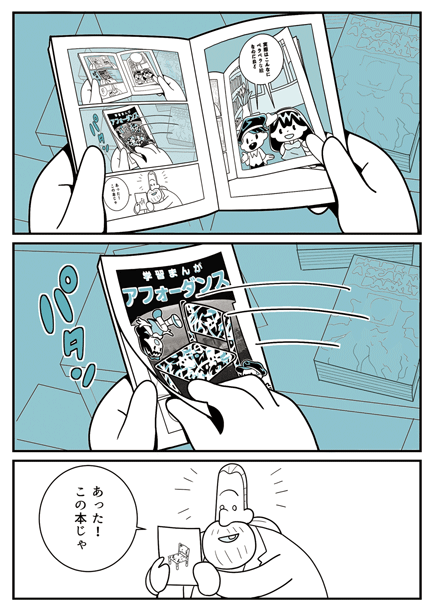
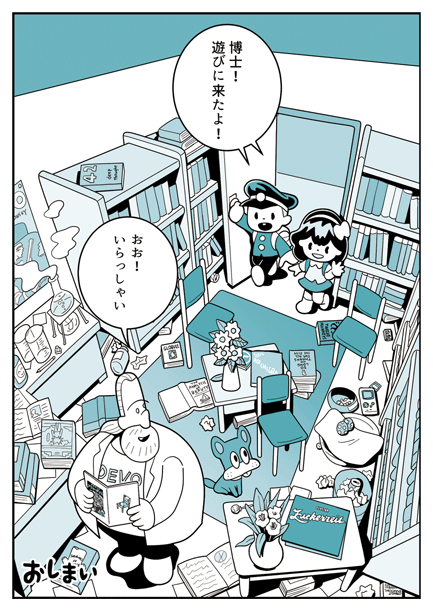
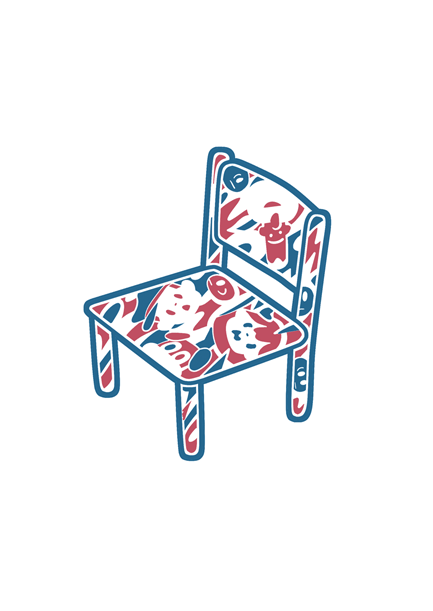
PDF版
まんが本編に加え、この作品の解説や参考文献などもご覧いただけます。
冊子版
ストーリーはそのままに、まんがを全編描き直してフルカラーにアップデートした「新版」を販売しています。
初版の本編に加筆・修正を行ない、新たなコンテンツも追加した第二版も、「ITEMS」ページにて販売しております。
探すこと。ときどきふと、じぶんは人生で何にいちばん時間をつかってきたか考える。答えはわかっている。いつもいちばん時間をつかってきたのは、探すことだった。長田 弘『最後の詩集』
探索と検索、それぞれの意味
私たちは日々の生活の中で、さまざまなものを探し求めています。着るものや食べるものに始まり、勉強や仕事に必要なもの、趣味や娯楽として手に入れたり体験したいもの、問題や悩みごとを解決する方法や手がかりなど、ありとあらゆる「探しもの」をしています。
「探しもの」をするのは人間だけではありません。食物や住処、求愛の対象や仲間を探すといった行動は、動物たちも行なっています。でも、インターネットとWebの技術が誕生したことで、人間の「探しもの」の可能性は、それ以前よりも大きく広がりました。昔から、他の動物と同じようにオフラインで行なってきた「探索(seeking)」という普遍的な行動に加えて、人間はオンラインで情報を探す「検索(searching)」をするようになったからです。そして、必要な情報を探し出せるかどうかは、私たちの生活に深く関わってくるようになりました。
Webがまだ生まれていなかった時代に、カリフォルニア大学で情報検索の研究をしていた図書館情報学者マーシャ・ベイツは、「探しもの」を行なう場所がオフラインからオンラインへと移行する中で変化しつつあったユーザーの行動を探ろうとしました。そして、「オンライン検索インターフェース向けのブラウジング/ベリーピッキング技法の設計」と題した1989年の論文で、彼女が提示したベリーピッキングという新たなモデルは、後のWebでの情報検索に大きな影響を及ぼすことになりました。
情報検索の古典的モデルの限界
ベイツが論文を発表した当時は、学術機関や図書館で各種のデータベースのオンライン化が着々と進んでいる時代でした。調べものをするためにそれらの施設を訪れて、手作業で必要な本や論文を見つけ、ページをめくって探していた情報が、コンピュータを使ってオンラインで探せるものになりつつあったのです。
ただし一方では、オンラインでの検索が複雑化するという問題も生じていました。利用できる情報源の種類が増え続けると同時に、より込み入った条件で検索するには、ますます高度なテクニックが必要になってきたからです。ベイツが先の論文を書いたのは、現状に見合わなくなった古典的な情報検索モデルに代わる新たなモデルを示し、もっと使いやすい検索システムの設計に活かすためでした。
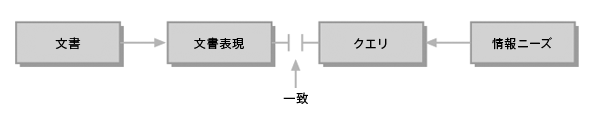 図1 古典的な情報検索モデル
図1 古典的な情報検索モデル
情報科学の分野で長らく用いられてきたという、この古典的モデルが示すタイプの情報検索は、「IR(Information Retrieval)」と呼ばれていました。『図書館情報学用語辞典』では、この用語を以下のように定義しています。
あらかじめ組織化して大量に蓄積されている情報の集合から、ある特定の情報要求を満たす情報の集合を抽出すること。主にコンピュータの検索システムを用いる場合に使われる言葉である。検索対象によって情報検索を分類すると、事実検索と文献検索に分けられる。前者は求める情報そのもの(事実やデータ)を探し出すことであるのに対して、後者は求める情報が掲載されている文献の書誌データなどを探し出すことである。日本図書館情報学会 用語辞典編集委員会 編『図書館情報学用語辞典 第4版』
図1のモデルと上記の定義を見ると、当時の情報検索は、かなり限定的だったことがわかります。検索できる文書は、それぞれの学術機関や図書館で管理している資料や蔵書に限られた上、全文検索がスムーズにできるほど技術が発達していなかったために、検索の対象となるのは文書そのものではなく、書誌や目録、抄録、索引といった文書表現(document representation)※1であるのが普通でした。したがって、ライブラリアン※2が作成する文書表現と、ユーザーが入力したクエリ(検索語句)がぴったり一致しなければ、望ましい検索結果は得られません。いわば、ライブラリアンとユーザーがお互いの胸の内を探り合う必要があったので、どちらにとっても検索は厄介なものとなっていました。
オンラインでの情報検索が複雑化し、古典的モデルに見合わなくなってきたため、ベイツはユーザーの行動の流れ(シーケンス)を重視しました。そして、よりリアルにその実態を反映した、「ベリーピッキング(berrypicking)」という新たなモデルを生み出したのです。
ベリーピッキングモデルが伝えるもの
昔からオフライン環境では、大まかなトピックの一つの特徴、あるいはそれに関係する一つの資料を出発点として、次第にさまざまな情報源を渡り歩いていくという探索が行われていました。図書館で見つけた一冊の本をきっかけとして、関連する他の本も調べていくうちに、新たな発想や情報ニーズの変化が生じるということもあるのではないでしょうか。オンライン検索でも、一度手に入れた結果に基づいてクエリを修正し、再検索をすることは多いですし、クエリの性質自体も移り変わっていくことがあります。ベイツはこのような検索を、「発展的検索(evolving search)」と呼びました。
古典的モデルの検索では、答えが一度にまとまって返ってくることを想定していましたが、実際には、いくつもの手法を用いてその都度得られる情報を選り集めたものが答えになると、ベイツは考えました。こうして少しずつ成果を集めていく発展的検索を示したのが、以下のベリーピッキングモデルの図です。森の中では、ブルーベリーやラズベリーが実っている場所が散らばっているので、あちこちで少しずつ摘み取っていくことになります。オンライン検索も、そのような「ベリー摘み」によく似ているのです。
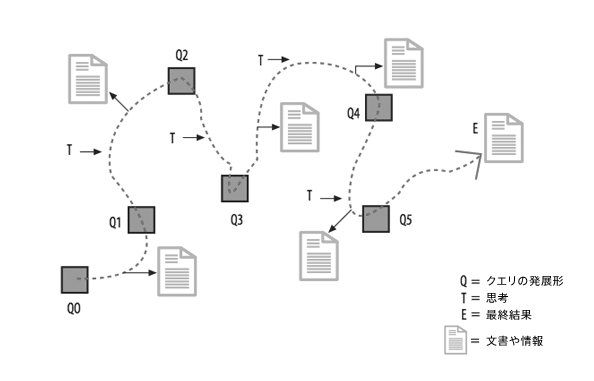 図2 ベリーピッキング:発展的検索
図2 ベリーピッキング:発展的検索
ベリーピッキングは、古典的モデルが示す一致の単なる繰り返しではないか、という疑問を感じるかもしれませんが、情報との出会いが多種多様な形で生じるのがベリーピッキングならではの特徴です。つまり、検索の手法があれこれ変わっていくだけでなく、検索の対象となる情報源が、形態的にも内容的にも変化していくのです。古典的モデルのように、1回のクエリで最終結果をひとまとめに受け取ることがあるとしても、それはベリーピッキングの体験全体から見れば、一つの場面にすぎません。
ベイツのベリーピッキングモデルは、Webでの情報設計の考え方やノウハウを初めて体系的に紹介した書籍『Web情報アーキテクチャ』や、その共著者の一人であるピーター・モービルの『アンビエント・ファインダビリティ』で紹介され、Webに関わる人々の間でも知られるようになりました。ただしベイツの論文には、そのどちらの本にも載っていない、もう一つの図があります。それは、ベリーピッキングをする探索者の「関心の世界(universe of interest)」の外に、もっと大きな「知識の世界(universe of knowledge)」が広がっていることを示していました。
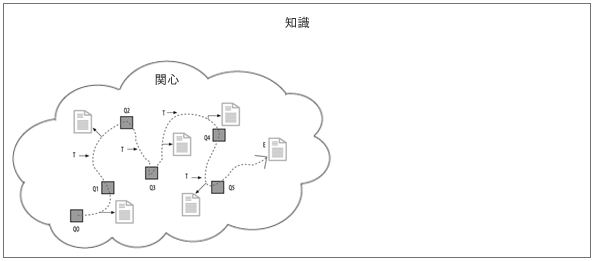 図3 ベリーピッキング検索のコンテクスト
図3 ベリーピッキング検索のコンテクスト
広大な「知識の世界」は、「ノウアスフィア(noosphere)」※3と呼ばれる、人間の思考の圏域を想い起こさせます。そして、「関心の世界」を囲む雲のような境界線は、探索者による認識の限界を示していると言えます。その外側にあるはずの「知識の世界」について、自分はまだその存在さえ知らないかもしれない。でも普段の私たちは、それぞれの「関心の世界」の内側で、ほぼ安泰に暮らしています。それは、あらゆる動物が、自らの知覚情報から成り立つ「環世界」※4を、まるで世界そのものであるようにして生きていることに似ています。でも、何かのきっかけや思いつきで「関心の世界」が広がるのは、多くの人が経験していることでしょう。
図2をズームアウトして、一回り大きな観点からベリーピッキングの全体像を描いたこの図について、ベイツはほとんど説明を加えていません。人間が各自の「関心の世界」に閉じ込められがちな傾向に気づかせようとしたのか、あるいは、「関心の世界」を広げる余地はいくらでもあるという見方を伝えようとしたのか。彼女がこの図に込めたメッセージをどう受け止めるかは、見る人次第となるはずです。
オフライン探索における6つの手法
ベイツはこのベリーピッキングモデルに基づき、従来オフラインで行なわれていた書籍や文献の探索行動を調べながら、オンラインの検索システムに望まれる機能を考えていきます。そして、他の研究者の説も採り入れながら、主要な探索の手法を以下の6つにまとめました。
- 脚注追跡(または後方連鎖)
書籍や論文の脚注や参考文献リストをたどる。社会科学や人文科学では特に多用される。 - 引用文献検索(または前方連鎖)
書籍や論文の引用索引(citation index)※5を見て、他のどんな文献がそれを引用元にしているかを調べる。 - ジャーナル調査
ある分野での主要なジャーナル(学会誌や雑誌などの定期刊行物)を見つけ、そのバックナンバーを調べる。 - エリアスキャン
図書館などで見つけた本や資料を調べるとき、それと物理的に近い場所にあるものまで調べてみる。 - 主題別検索
書誌や抄録、索引などの二次情報で提供されている主題別の分類を利用して、書籍や論文を探す。図書館ではもっとも親しまれている方法。 - 著者別検索
ある著者について、同じ話題を扱う他の著作物があるかを調べる。
オフライン探索の手法は他にもありましたが、当時のオンライン検索システムは大抵、「5. 主題別検索」しか十分にサポートしていませんでした。それが図書館情報学において、他の手法より優れているとみなされてきたことも、その一因だったようです。
でもその頃には、「5. 主題別検索」よりも「1. 脚注追跡」のほうが頻繁に行なわれている事実を明らかにした調査結果も出てきていました。実は大いに役立っている手法が、正しく評価されていなかったことになります。また、「2. 引用文献検索」で必要となる引用索引は、長らく正当に評価されていませんでした。そんなものは、自分の本や論文がどれだけ引用されているかを学者たちが知って自己満足に浸るためにしか役立たない、という批判さえあったといいます。
自らが属する図書館情報学の分野でそのような経緯があったことを知り、深く反省したベイツは、それぞれの手法の有効性をきちんと認めるべきだと考えました。そして、オフラインでの探索では、多くの手法が利用できるほどユーザーの満足度が高いことが明らかになっていたため、オンラインの検索システムでも、先の6つの手法すべてを機能として提供することを主張したのです。もちろん彼女は、ただ多くの機能を寄せ集めることを提案したのではなく、ユーザーのベリーピッキングを促すように、操作手順をシンプルに覚えやすくして、ある機能から他の機能へとスムーズに切り替えられることを重視していました。
ブラウジングの価値を引き出す設計方針
ベイツは、それらの手法をオンラインで実現するための具体的なアイデアを挙げていきます。まず最初に見直したのは、オフラインで昔から行なわれてきたブラウジングという行動の重要性でした。
実はその当時、「通常の」探索と言われるのは、探したいものがわかっている有向的(directed)な検索のことでした。かたやブラウジングは、明確な目的もなく気ままに探しものをする、無向的(undirected)な行動とみなされていました。ブラウジングという言葉の元の意味は、家畜を放牧して飼料としての若葉や新芽を自由に食べさせることで、まさにそんなイメージを持たれていたのです※6。そのため、当時のオンライン検索システムでも、有向的検索が主要な機能とされており、あちこち見て回るというブラウジングがしやすい設計は行なわれていませんでした。
しかし、発展的なベリーピッキングのプロセスを考えるようになると、従来とは見方が違ってきます。有向的検索とブラウジングが、常にはっきり区別できるとは限らないからです。それを示唆するかのように、シェフィールド大学のデヴィッド・エリスは、標準的な探索行動で重要な役割を担うようなブラウジングを、半有向的(semi-directed)検索または半構造化(semi-structured)検索と呼びました※7。つまり、探す対象は決まっていないけれど、まったく目的がないわけでもなく、何か面白いものや役に立ちそうなものが見つかることを願っているようなブラウジングのことです。
エリスの考え方に共感していたベイツは、検索システムがもっとブラウジング機能に目を向けることを期待して、ナビゲーションやインターフェースに関わるさまざまなアイデアを示しました。それらを通じて彼女が何を目指したかを考えると、オンラインのシステムにおける2つの設計方針を見出すことができます。
効率性とセレンディピティを共に高める
ベイツが注目していた探索行動は主に学術研究を目的としていたので、まずはいかに効率よく、確実に検索を進められるようにするかが重要でした。たとえば、「1. 脚注追跡」をしていて本文をどこまで読んだか見失ってしまうと、元の場所を探すのに無駄な手間と時間がかかります。印刷物の脚注は、各ページの下部にあるか巻末にまとめられている※8ことが多いですが、画面上ではポップアップ表示のように紙の上ではできない見せ方も考えられます。どんな場合でも、本文と脚注の間をスムーズに行き来できることが不可欠だと、ベイツは考えました。彼女は他の探索手法についても、ナビゲーションの経路を短縮したり、検索結果を多角的にグループ化して見やすくするなど、効率を高めるためのアイデアをいくつか挙げています。
しかし、ベリーピッキングという探索行動では、必ずしも効率的とは言えないブラウジングが、また別の重要性を持つことになります。ブラウジングは、思わぬところで自分の興味をそそる情報に出会えるというセレンディピティを高め、新たな刺激や発想を与えてくれる可能性があるからです。
たとえば、「2. 引用文献検索」で利用する引用索引は、セレンディピティにつながりやすい、雑多な情報が集まった場所と言えます。同じ引用元を参照しているという共通点はあるものの、それぞれの情報源で扱っている話題は、かなりバラエティに富んでいるかもしれないからです。また、昔から図書館で多くの利用者が「4. エリアスキャン」をしていたのも、あちこち動き回るほど予想外の発見をしやすくなることが大きな理由だと、ベイツは考えていました。
ベリーピッキングは、探索者を単に効率よく結果に導くだけではなく、時にはセレンディピティをもたらすこともできる、複合的な探索行動です。ベイツは、一見すると相反しそうな2つの価値を併せ持つ複合性が、人間の探索行動を豊かにしてきた鍵だと考えたからこそ、効率性ばかりを追いがちな検索システムにも、オフラインで「関心の世界」を広げてきたセレンディピティを採り入れようとしたはずです。そうすれば、オンラインでの探索も、あらかじめ決まった目的を果たすだけの行動ではなく、時にはその目的そのものを一新させたり、未知の世界に目を開かせたりする、より豊かな体験となるからです。
情報のアバウトネスやセマンティクスを伝える
アバウトネス(aboutness)とは図書館情報学の用語で、ある情報が扱っている主題、つまりそこで表現されている重要な概念やテーマは何かを示すもののことです。これは必ずしも客観的ではなく、個人の立場や主観によって決まるものなので、著者と索引作成者と利用者の3種類のアバウトネスがあると定義されています。したがって、古典的な情報検索モデルにならうと、文書表現が索引作成者アバウトネスを表わし、クエリが利用者アバウトネスを表わしていると言えます。
たとえば「3. ジャーナル調査」についてベイツは、広く一般的な主題を扱うジャーナルよりも、主題が絞り込まれているものの方が、細かい情報ニーズを満たしやすいと述べました。専門性の高いジャーナルほど文書表現を具体的にできるので、専門用語などを含むクエリに一致しやすくなるからです。ベイツは、検索対象となる情報が急激に増えつつあった当時、なるべく手間と時間をかけずに適切な文書表現を用意できることが肝心だと考えていました。
Webサイトの検索結果では、文書にとっての文書表現と同様に、タイトルや概要などのメタデータがサイトのアバウトネスを示しています。それが詳細であるほど自分のニーズに見合うかどうかを判断しやすくなるという点は、文書表現と共通していますが、メタデータにはさらに重要な役割があります。それは、文書の主題を伝えるアバウトネスだけではなく、その意味的構造、すなわちセマンティクス(semantics)を記述し、コンピュータが解釈できる共通の形式で意味を付与するという役割です。そのように、メタデータを利用して情報の意味をより豊かに表現しようとする考え方は、後に生まれたセマンティックWeb※9の概念に引き継がれました。
絡み合う探索/検索のモード
もう一つ興味深いのは、ベイツがオフラインでのブラウジング行動に見られる身体性に注目していたことです。本を探して図書館の中を歩き回るとき、私たちは身体全体と目の両方を、かなりランダムに動かしていることになります。画面上で全身を動かすのは無理でも、視線をあちこち動かせるようにするには、情報を時間や空間の関係に従って並べたり、書架や目録カードのようなオフライン環境のメタファーを活用することが役立つと、ベイツは考えました。
またベイツは、気になるものを次々にたどっていくベリーピッキングには、ハイパーテキストを用いるアプローチがぴったりだということも明言しています。計算機科学者のティム・バーナーズ=リーが、ハイパーテキストを駆使したWebのシステムを世界で初めて構築したのは、この論文が発表された翌年のことでした。きっと彼女は、自分が期待していた未来がついに訪れたように感じ、その新たな技術を歓迎していたはずです。
それ以来、かつてないほど大量の情報が蓄積され流通するにつれて、「関心の世界」と「知識の世界」の差は広がる一方となっています。だからこそ、ベリーピッキングという発展的な探索行動は、「関心の世界」を広げていくための技法として、ますます価値を増しているのではないでしょうか。
この論文から14年後の2003年、インターネットとWebがめざましい成長を遂げている中で発表した「情報の探索と検索の統合モデルをめざして」という論文で、ベイツは情報探索行動を社会的・文化的に理解しようとするだけでなく、先に述べた身体性というポイントにつながる生物学的な観点からもアプローチすることを試みました。私の次回の記事では、再びベイツの論文を手がかりに、人間にとっての「探しもの」についてさらに考えていきます。
デザインについて、そもそもどのように考えたらいいだろうか?
私たちはふだん当たり前のように「良いデザイン」とか「悪いデザイン」とか言っている。そこで言われている「良さ」や「悪さ」とは、いったいどういうことだろうか? それは第一に、デザインがデザインされたものの「目的」に適っているかどうか、という意味で、とりあえずは理解できるだろう。つまり「良い」デザインであるためにはまず、製品や建造物などが、そこで目指されている用途や目的に沿って、忠実に設計されている必要がある。目的に背くもの、使いにくいものは、良いデザインではない。当たり前のことだが、このことが意味するのは、デザインとはあらかじめ設定された何らかの目的を実現するための「手段」であるということである。
と同時に、これまた言うまでもないことだが、デザインには美的な側面がある。「良い」デザインとは、ある目的を実現するという条件を満たしながらも、その意図があからさまに見えたり、説明的であることはあまり好まれない。むしろ既成観念を破る驚きとか、先入観にとらわれない奔放さ、スマートさや機知、といったものが高く評価される。その意味で、デザインは一見自由な活動のようにみえるかもしれない。だがよく考えてみると、この美的な意味におけるデザインもまた、それが提供者の知性や趣味の良さを表現し、それによってユーザの賛同を得るという目的からするなら、ひとつの「手段」であることには変わりはない。
これら実用的側面と美的側面とが実際に合致するにせよしないにせよ、「手段」としてのデザインの意味は明確である。そこには、デザインをそもそもどう考えたらいいかというような根本的疑問は生じない。そしてこの意味でのデザインの問題については、ぼくはその実際的な重要性は理解できるけれども、あまり興味がないし、言うべきことも少ない。だから今ここで、デザインとは何か? などと問いかけ、このような文章を書こうとしているのは、そうではないデザインについて、考えようとしているということである。それだけがぼくにとって、考えるに値するデザインの概念なのだが、それをいったいどんなふうに説明したらいいだろうか。正直ちょっと途方にくれているのである。
というのもそれを説明するためには、常識からするとかなり遠回りで大げさと思えるかもしれないことを、言わなければならないからである。けっして難解な話ではないのだが、ゆっくりと余裕をもって読んでくれる人にしか通じない話なので、話す相手に対して少し慎重でなければならない。そこから実務的なデザインについて何か有益なことが学べると期待して読むような人は、もしかすると怒り出すかもしれないからである。けれどもこのテキストをここまで読んでくれた人は、たぶんそれを理解する余裕を持つ読者であると信じるので、書き進めることにしたい。
まず考えてほしいことは、デザインには限りがないということである。たとえデザインが何らかの目的のための手段だとしても、この手段−目的の連鎖には、原理的に終わりがない。たとえば製品や建造物のデザインは、もっぱらそれらを使う個人の好みによって決まるわけではなく、それを取りまく組織や集団の目的に深く関わっている。さらに、それら組織や集団は、より大きな社会制度とそれが目指す目的に従っている。それらはさらに、国家そのものや地球的な共同体の目的へとつながっており、この連鎖は究極的には人間の生そのもの、人類の生存それ自体の目的性へとたどり着かざるをえない。まるで人工知能研究における「フレーム問題」※1のように、たった一個の製品のデザインには、この世界そのものをどう理解するかということが、潜在的には含まれているのである。
そんな大げさな、と思われるかもしれない。けれども私たちがごく日常的な意味で「良いデザイン」「悪いデザイン」などと言えるのは、そうした意味と目的の連鎖を便宜上適当なところで —— たとえば製品の販売促進をとりあえず目標とするといった仕方で —— 切っているからである。もちろん実際的には、そうした便宜上の切断は仕方がないことであり、そうしなければ期日までに完成させることができなくなる。けれどもここでは、そうした実際的な事情は括弧に入れて、原理的な事柄を考えてみたい。原理的な意味でのデザインには、この世界や人間の生をどう考えるべきか? という哲学的な問いが含まれている。いや、含まれているというよりもむしろデザインそれ自体が、原理的な意味では哲学的思考のひとつの形態であると言っていいのである。
スピノザ『エチカ』を通して、デザインの完全性について考える
『エチカ』第4部「人間の隷従あるいは感情の力について」の冒頭でスピノザは、あるものが「完全」あるいは「不完全」であるとはそもそもどういうことか?という問題について考えている。この『エチカ』という本はそのタイトル(Ethica、倫理学)からすれば、人間の生き方を語る本のように思えるが、最初から読み始めると「神」や「実体」や様々な形而上学的概念をめぐって古典幾何学のような論証が続き、それにウンザリする人も少なくない。だがこの第4部は、人間がいかに感情の支配から自由になりうるかを主題としており、その意味ではいちばん『エチカ(倫理学)』らしい箇所だと言える。その冒頭に「完全性」についての議論があることはとても重要なことだと、ぼくは思っている。
あるものがより「完全」であるということは、今の私たちの文脈で言えば、それがより「良いデザイン」であると言い換えてもいいだろう。実際デザインを「良い」と褒める時、私たちはそれが「完全である」「完成されている」と言うことも少なくない。さて、そこでのスピノザの議論は、ぼくなりに要約すれば次のようなことである。
ある人が、快適に居住するための家を作る場合、その目的を理解する人はそこで作られたものについて、それがより「完全」である、あるいはいまだ「不完全」であるなどと言う。それは人々が「家」という一般的観念を共有しているからである。意図をもって作られた人工物に対して述べる場合、それは当然のことであるが、人間はまた、自分が本当はその意図を知らない自然物に対しても、しばしば「完全」だとか「不完全」だとか判断したりする。けれどもスピノザにおいては、自然(スピノザにとってそれは「神」と同じなのだが)は目的を持たず、したがって自然物にはそれが作られた目的、すなわちその形態が目指しているような一般的な観念はない。にもかかわらず私たちは「自然」について、それがあたかも目的を持つかのように —— 言い換えれば「神」について、それがあたかも人間と同じく完全な制作物を作ろうとするかのように —— 語ってしまうのである。つまり自然物を人工物に置き換えて理解しているわけである。
これは錯誤である。自然の作動には目的はなく、だからどんな自然物も、より「完全である」とか、いまだ「不完全である」などと言うことは本来できない。つまり原理的な意味では、自然には「良いデザイン」というものは存在しないのである。けれども私たちはしばしば、自然の作り出す驚異的なデザインに、驚嘆しているのではないだろうか? 生物の身体の驚くべき形態、生物活動が作り出す様々なパターン、さらには悠久の物理科学的運動が地上や宇宙に刻み出す驚異的な形。けれどもスピノザに従うなら、それらは私たちが自然を擬人化することで現れるものであり、そうしたデザインの完全性は自然それ自体にではなく、私たちの認識の中に生じるものにすぎないということになる。
もう少しだけ、スピノザにつきあってみよう。多くの西洋近代哲学とはまったく異なり、スピノザにおいては理性や精神は自然と対立しない。だから人間や人間の作り出す社会、国家、文明といったものもまた、ある意味では自然の一部にすぎない。社会、国家、文明といったものに何か客観的な「目的」があるかのように感じられるのは、人間の認識が限界付けられているからにすぎない。人は、自分が理性的に何らかの目的を目指して行動していると信じるかもしれないが、それは人が、そのように自分を方向付けている本当の原因 —— 感情の力 —— について知らないからである。
スピノザ的世界観で、デザインはどんな意味を持ちうるだろうか?
スピノザの思想は、理性や精神に自然から独立した特権的な位置を認めないという点において、きわめて徹底した唯物論であると言える。意図や目的に特別の地位を与えないそうした唯物論的思考の中では、「デザイン」などそもそも意味を持ちえないのだろうか? ぼくはそうは考えない。それどころか、そうした思考の中においてこそ、デザインはより重要な意味を持つようになると思っているのである。
たしかに、何か特定の意図や目的を前提として、それに奉仕する「手段」としてのデザインは、そこでは意味を失うだろう。だが、手段−目的という関係が廃棄されることによって、デザインは新しい意味を獲得するのではないかと、ぼくは考えている。それは、既存の目的のための手段ではないようなデザインという理解である。言い換えるなら、何らかの思考の結果ではなくて、それ自体が思考そのものであるようなデザイン、いわば「圧縮された思考」としてのデザインの概念である。デザインをそうしたものとして理解するということは、翻って言うなら、思考を成り立たせる狭い意味での言葉、言語というものをあまり特別なものと考えすぎないということでもある。むしろ言語的思考とデザインとを、ひとつながりの連続したプロセスとして考えるということである。「デザインとは言語である」といったことは、これまでも比喩的には言われてきたかもしれないが、ぼくはそれを単なる比喩としてではなく、現実として理解している。デザインが言語であるということは、言語活動もまたデザイン的な側面を持つということでもある。
そう考えることで何が変わるのか? と問われても、答えようがない。この世界全体の見え方が変わるだけである。何も変わらないとも言えるし、すべてが変わるとも言える。哲学的思考が何の役に立つのか? という問いに関して言うなら、哲学に多くを期待するのは間違っている。多くではなく、すべてを期待することだけが正しい。
最近、「デザイン・フィクション(Design Fiction)」という言葉を目にすることが多くなった。大手企業が製品/サービス開発に活用したり、MITメディアラボやカーネギーメロン大学で専門の研究グループや教育課程ができるなど、さまざまな方面で注目が高まっている。
このデザイン・フィクションとは、そもそも何のことなのだろうか?
デザイン・フィクションという言葉を生んだSF作家ブルース・スターリングは、それをSF(サイエンス・フィクション)のような物語世界にリアリティを与えるためのプロトタイプ(試作品)として捉えていた。この「スターリング的デザイン・フィクション」は、フィクションの中に制作物として具現化されたデザインのことだ。
一方、製品/サービスのデザインの現場や、HCI(Human-Computer Interaction)のようなデザイン関連の研究分野では、デザインのアイデアに説得力を持たせるための物語世界のことを、デザイン・フィクションと呼ぶことも多い。これは、ストーリーテリングの発展形のようなデザイン手法として役立つフィクションのことであり、「メソッド的デザイン・フィクション」と呼んでもよいだろう。現在、注目を集めているデザイン・フィクションは、この「メソッド的デザイン・フィクション」の方だ。
しかし、デザイン・フィクションはデザイン上の便利な手法というだけではない。オリジナルなスターリングの思想を探ってみれば、それがデザイン本来の自由や可能性を明らかにするものであることが見えてくる。
デザイン・フィクションはどう語られてきたのか
スターリングがデザイン・フィクションという言葉を生み出したのは、2005年の著書『Shaping Things』だったが、海外のデザイン関係者の間でひときわ関心が高まったのは2009年頃である。この年の初めに、スターリング自身が、HCIやインタラクションデザインの専門誌『Interactions』に「Design Fiction」と題したカバーストーリーを寄稿したことが、その引き金となった。
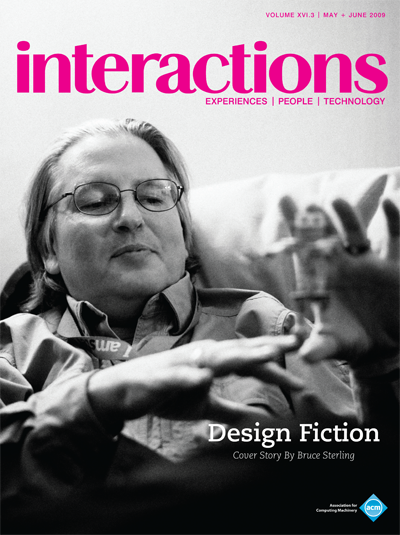 “Interactions” XVI.3 May + June 2009
“Interactions” XVI.3 May + June 2009
彼はそこで、作品の中でデザイン・フィクションを表現することを覚えるにつれて、自分のSFが昔より一段と引き締まったこと、SFは単なるフィクションではなく、ユーザーインターフェースを備えた工芸品であると気付いたことなど、自らの作家経験を通じた興味深いエピソードを語っている。また、紫式部の『源氏物語』と清少納言の『枕草子』のコンテンツとプラットフォームが、大衆小説と読者限定ブログのように異なっていたことを指摘し、それがユーザーエクスペリエンスの違いにつながっていたというユニークな分析もしている。そして、この素晴らしいカバーストーリーの結びとして、デザインもSFも、インターネット以降の時代にふさわしい想像/創造の力をデザイン・フィクションという形で具現化できるはずだと述べたのである。
その年の3月には、Near Future Laboratoryというデザイナー/エンジニア/リサーチャー集団で活動しているジュリアン・ブリーカーが、デザイン・フィクションを広く知らしめるためのエッセイを公開していた。ブリーカーは、デザイン・フィクションが批評的(critical)なものであることを強調しており、その考え方は、当時注目されるようになっていた「クリティカル・デザイン」によく似ていた。
クリティカル・デザインとは、現状に甘んじることなく、批評的な観点からより良いデザインを考えようという価値観や態度のことである。それは理論上、製品化やサービス化を目的としない、純粋に思念的(speculative)なデザインとされていたが、今では多くの企業でビジネスに活用されているのが実情だ。マイクロソフト、Google、Appleといった有名企業でも、クリティカル・デザインの取り組みとして、SF作家を招いて社内研修を実施したり、新しい製品やサービスの開発に役立つ仮想のシナリオを作らせたりしている。それらはまさに、「メソッド的デザイン・フィクション」の実例だ。ブリーカーのエッセイがデザイン・フィクションの批評性を強調し、クリティカル・デザインとのつながりを多くの人に印象づけたことで、その手法としての「メソッド的デザイン・フィクション」が広まった可能性もある。
ここでもう一つ注目したいのは、ブリーカーのエッセイに登場した「物語的プロトタイプ(diegetic prototypes)」という言葉を、スターリングが重要なキーワードとして認めたことだ。彼は、ブリーカーを全面的に支持してはいなかったようだが、翌年のインタビューでその言葉を用いながら、デザイン・フィクションの「定義」を語ったのである。
デザイン・フィクションとは、未来になっても何も変わらないだろうという考えを見直してもらうために活用する、物語的プロトタイプのことだ。今まで思いついた中で、この定義が一番しっくりくる。ここで重要なのは「物語的(diegetic)」という言葉だ。未知のオブジェクトやサービスが生まれる可能性について真剣に考えること、そして、世間一般の事情や政治的トレンドや地政学的な策略よりそっちの方に、みんなの力を集めようとしていることを意味する言葉なんだ。デザイン・フィクションはフィクションの一種じゃない。デザインの一種だ。それは、ストーリーというより、世界を伝えるものなんだよ。ブルース・スターリング
これは「スターリング的デザイン・フィクション」の公式な定義と言えるだろう。では、この「物語的(diegetic)」という耳慣れない形容詞の本質的な意味を、さらに考えていきたい。
デザインにおけるディエゲーシス
スターリングが重要だと語った「物語的(diegetic)」という言葉は、「物語ること」を意味する古代ギリシャ語を源とする「ディエゲーシス(diegesis)」※1という言葉に由来している。
プラトンは『国家』において、「いかに語るべきか」が「何を語るべきか」と同じく重要だと説き、何らかの出来事を語るという点はどんな文学にも共通しているが、その「語り方」には違いがあると論じた。そして、単純な叙述(報告形式)と称するディエゲーシスと、真似/模倣による叙述(劇形式)であるミメーシスとを区別した。語り手が自身の人格を保ったままでストーリーを語るのがディエゲーシスであり、語り手が時には声や身振りも含めて他の誰かに「なりきる」ことでストーリーを表現するのがミメーシスである。つまり、自らの世界を客観的に語ることを貫くディエゲーシスに対し、ミメーシスは「語る」というよりも、いわば他者を演じることを通じて、必ずしも自分自身のものとは限らない、さまざまな世界を「見せる」ことだと言える。
こうして言葉の由来を探ってみると、「物語的プロトタイプ」という用語が、スターリングのお気に召した理由がわかる気がする。ビジネスの現場で主流となっているユーザー中心主義的デザインは、いわばデザイナー自身がユーザーになったつもりで行なう、ミメーシス的デザインと言えるだろう。それに対して、ディエゲーシス的デザインは、ユーザーの立場で主観的にデザインを判断するわけではない。物語世界を作り上げるデザイナーが、そこに存在するさまざまなものに客観的なリアリティを授けようとするのだ。
そのようなディエゲーシス的デザインから生まれる「スターリング的デザイン・フィクション」は、物語世界の外部にある、製品化やサービス化というビジネス上の役割や目的を負うこともない。だから、機能するかどうかさえ問題にならない。ひたすら、物語におけるリアリティと知的セックスアピールを追求することで、イマジネーションとしての世界に人々を惹きこもうとするのである。
その一番わかりやすい例は、映画『2001年宇宙の旅』に登場していた、iPadそっくりなタブレット型デバイスだろう。
 A scene where a tablet-style device is portrayed in the film
A scene where a tablet-style device is portrayed in the film
このデバイスは単なる映画の中の小道具であり、当然ながら実際に機能するものではなく、いわゆるモックアップと言えるだろう。これがまさに、その作品の中で本物らしく見える「物語的プロトタイプ」である。それは、この伝説的なSF映画に出てくる数々の舞台装置の一つとして物語世界に見事なリアリティをもたらしている、「スターリング的デザイン・フィクション」なのだ。
クリティカル・デザイン/スペキュラティブ・デザインとの違い
ところで、先に述べたクリティカル・デザインの考え方は、やがてその思弁的(speculative)な側面、つまり製品/サービス化することを目的としないコンセプチュアルなデザインであることが重視されるにつれて、「スペキュラティブ・デザイン」とも呼ばれるようになった。今では、クリティカル・デザインとほぼ同じ意味で、スペキュラティブ・デザインという用語が使われている。2014年に、それをテーマにした『Speculative Everything』という本が出版された際に、スターリングはそのレビューを自身のブログに投稿し、デザイン・フィクションとクリティカル・デザインの区別をはっきりさせておきたいと述べた。
彼いわく、この本のタイトルのように「あらゆるものをスペキュラティブに」デザインするという考え方は、抽象的な理想論のようなものにとどまっていて、具体的にデザインされた制作物という成果はまだ少ないし、そう簡単に増えそうもない。つまりクリティカル・デザイン/スペキュラティブ・デザインは、制作物を生み出すことよりも、デザインの理念やプロセスを見せることに偏っていて、物語的プロトタイプという制作物にこだわる「スターリング的デザイン・フィクション」とは、大きな違いがある。スターリングは、その違いを主張したかったのだろう。
そこで私が連想したのが、フランスの哲学者エリー・デューリングの「プロトタイプ理論」である。デューリングが論じる芸術的プロトタイプには、「作品」よりも「実践」に価値を見出そうとする現代美術において、いま一度「作品」の存在を見直そうとする意志が込められている。デューリングが考える「作品」は、デザイン・フィクションにおいてスターリングが重視する、具現化された制作物に通じていると思えるのだ。
そこで、『現代思想』に掲載されたデューリングの論文と、その訳者である武田宙也氏の記事を踏まえながら、プロトタイプ理論とデザイン・フィクションの関係を見ていきたい。
プロトタイプ理論とのつながり
現代美術には、大きく2つの理念を見出すことができる。1つは、芸術における「作品」の定義を広げること。もう1つは、作品と共に、あるいは作品そのものよりも、芸術活動としての「実践」に重きをおくことだ。
しかし、芸術は元々、理念というものを必須としていない。偉大な画家や彫刻家、音楽家といった古典的な芸術家が、ひたすら正確さや厳密さを追求し、あるいは無心に創作意欲を発揮することで生み出す作品は「直観的」なものであり、「理念的」でなくとも成立してきた。むしろ、理念とは無縁なものこそ、純粋な芸術のように思われていただろう。芸術は理性ではなく感性から生まれるものだという暗黙の了解が、そこに根深く潜んでいたように思う。
しかし現代になって、いわゆるコンセプチュアル・アートのように「概念的」な芸術が登場するという、大きな転換が起きた。それら新時代の芸術は、「作品」と「実践」に関わる2つの理念を、さまざまなアプローチで追求してきたことになる。
コンセプチュアル・アートの世界に多大な影響を与えたマルセル・デュシャンは、大量生産時代のありふれた既製品を展示物とする、「レディ・メイド」と称した一連の作品を作り続けた。中でも有名なのは、男性用小便器を逆さに置いて別人の署名をしただけの「泉」という作品だ。
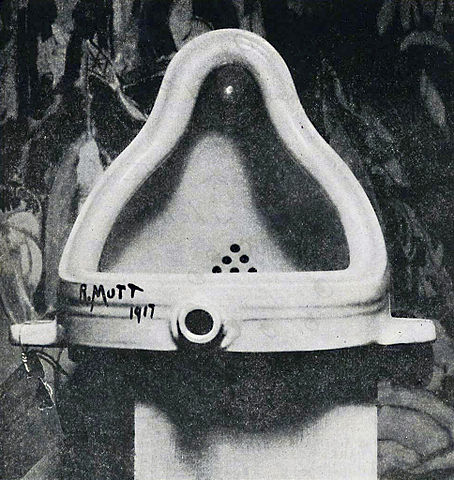 “Fountain” by R. Mutt (1917), Photograph by Alfred Stieglitz
“Fountain” by R. Mutt (1917), Photograph by Alfred Stieglitz
「泉」は、先に述べた現代美術の2つの理念について、鑑賞者にあらためて考えさせる作品だった。ありふれた便器もアートになるのだと感じさせることは、「作品」の概念の拡張である。自分でゼロから作品を作るのが芸術家だという常識を覆して、芸術的な感銘を与えることは、「実践」の概念の拡張である。
デュシャンはいくつもの「レディ・メイド」を通じて、芸術における「作品」と「実践」のあり方を脱構築してみせた。そのようなものが、「理念的でありながらも抽象的ではない」芸術的形態、とデューリングが定義する「プロトタイプ」である。それはいわば、「作品」というオブジェと「実践」というプロジェクトの中間にある存在だ。それ自体は最終形として完成された作品ではないのだが、コンセプトやプロセスだけを見せる作品とも違って、それがどのように実体化されうるのかを常に具体的に提示する。つまりプロトタイプとは、来たるべき作品を予期させる試作品なのであり、デューリングはそれを、雛形(マケット)※2のようなものと表現している。
現代美術が新たな価値を見出してきたのは、オブジェとしての「作品」よりも、その創作のプロセスである「実践」のほうだったように思う。これまで「作品」と思われていたものの価値は薄まり、「実践」の過程を見せるパフォーマンスアートや、鑑賞者自身が「実践」に加わる参加型アートといった新たな形態の「作品」が次々に生まれてきた。いわば、「実践」が「作品」になるという「プロセスの作品化」が、芸術として認められるようになったのである。
しかし、伝統的なオブジェの形をとる「作品」の芸術性も、時代の流れによって失われることはないはずだ。デューリングは、「作品」から「実践」へと傾きすぎた現代美術の流れを引き戻すように、その両者の中間にあるプロトタイプという新たな芸術的価値を見出した。彼の試みは、デザインの理念やプロセスを説くことに注目が集まりがちな昨今において、デザインが具現化する制作物としてのデザイン・フィクションにこだわるスターリングの歩みと、私の中でつながっている。
デッドメディアというレトロタイプ
さらにデューリングは2014年の著書で、「レトロタイプ」という新たな概念を提起した。これは、「逆転されたプロトタイプ」あるいは「プロトタイプの裏面」と言えそうなものだった。先のデューリングの論文が掲載された『現代思想』で、訳者の武田氏はこう説明している。
……プロトタイプが来たるべき作品のための雛形(マケット)であるとすれば、レトロタイプとは、切り取られた記憶(実現されなかったものとしての「未来という/に関する記憶」)の雛形であり、さらには、この記憶を別様に展開させるための雛形であるのだ。彼自身の言葉を用いるなら、それは、「ある種の過去の未来を歴史的展開の別のラインへと振り向けることによって、それに息を吹き返させる」ために要請される。武田宙也「エリー・デューリング『プロトタイプ』訳者解題」
デューリングが2014年に東京で行なった講演のレポートを読むと、ポップカルチャーに見られるレトロフューチャー趣味が、そのレトロタイプを生み出す力になるように感じられる。
世間一般のファッション的なレトロフューチャー趣味は、現在から過去を懐かしむノスタルジアや、古さそのものに憧れるアンティーク/ヴィンテージ嗜好のあらわれと言えるだろう。しかしデューリングは、そこに別の意味を読み取る。現在から過去を振り返るのではなく、過去から「あり得たかもしれない未来」へと目を向ける潜在的な物語世界の想像力が、レトロフューチャー趣味を生み出している、ということだ。そのような想像力が、何らかのプロットやガジェットへと形態化したものがレトロタイプである、と私は考えている。
このレトロタイプは、デューリングとスターリングの間にあるもうひとつのつながりを連想させた。それは、デザイン・フィクション以前のスターリングが熱心に収集していた「デッドメディア」である。
20世紀は、ニューメディアの大量発生の時代だった。スターリングは、新たなメディアが次から次へと生まれること自体は悪くないが、様々な理由で失敗や消滅の憂き目に遭った今は亡きメディアを知ることが、未来のメディアを作るために必要だと考えた。そして1995年に、そのようなデッドメディアの情報を収集してカタログ化するための「デッドメディア・プロジェクト」を立ち上げたのだ。
スターリングは、デッドメディアを古生物学者のように探ることが大切だと考えた。現存している生物を対象とする生物学で知ることができるのは、現在の生態系の有り様だけだ。しかし、今はもういない生物を扱う古生物学では、さまざまな時代に生きていた生物を知ることで歴史の流れを意識し、その進化や系統についても学ぶことができる。それと同じように、デッドメディアを知れば知るほど、私たちはこれまでの技術の進化と、それが生み出したさまざまなメディアの成り立ちをより深く理解できるようになる※3。
そして、あるデッドメディアがなぜ滅んだのかを考えることは、それが生き残ったかもしれない「あり得た未来」を想像するきっかけとなる。そのときデッドメディアは、「ある種の過去の未来を歴史的展開の別のラインへと振り向けることによって、それに息を吹き返させる」レトロタイプと、まさに同じ役割を担っていることになるだろう。
デッドメディア・プロジェクトにも影響を与えた、コミュニケーション論研究者キャロリン・マーヴィンの1988年の著書『古いメディアが新しかった時 — 19世紀末社会と電気テクノロジー』には、後のデザイン・フィクションを想起させるこんな記述がある。
社会の想像力が構築し、またそれに反応していく諸装置は、実際に存在する場合ももちろんあるが、まったくの想像上のものである場合も同じくらいしばしばある。そのうち多くのものは、今もなお実現されず幻想のままだ。…… 新しいメディアとは、コミュニケーションの場の聴覚的、視覚的、運動感覚的なすべての詳細を、トマス・エジソンの言葉を借りるならば「まるで本物のように転写」するものであった。…… このような技術的達成は、しばしば非常に細部にわたって思い描かれていた。キャロリン・マーヴィン『古いメディアが新しかった時 — 19世紀末社会と電気テクノロジー』
今思えば、デッドメディア・プロジェクトは、情報を収集して知識を蓄積するという、インプット主体の試みだった。このプロジェクトは2001年に終了したが、その貴重なインプットを経た後にデザイン・フィクションの思想に至ったスターリングは、SF作家として自らデザインする作品の中で何かを生み出すというアウトプット活動にも、新たな意欲をかき立てられるようになったのではないだろうか。
先のマーヴィンの著書は、まさにデッドメディアを想い起させる、こんな言葉で締めくくられている。
変化と変化についての思考は相互作用的な出来事であり、それは古い思考を新しい思考との接触によって再検討させることになる …… 過去は未来において真に生き残るのである。おそらく、ちょうどわれわれの先祖が、彼らが夢見た未来が実際はどうなったかを知って驚くであろうのと同じくらいに、過去はわれわれを驚かせるのである。キャロリン・マーヴィン『古いメディアが新しかった時 — 19世紀末社会と電気テクノロジー』
現在の世界に生き残っているメディアの陰には、もっと数多くのデッドメディアがあったことになる。それらを知ることは、遥か昔から紡がれてきたメディアのデザインの歴史と進化を知ることであり、過去についての驚きを、未来に活かすことへとつながっていく。
そして、多種多様な驚きを秘めたデッドメディアはレトロタイプとして、いつかどこかで誰かが想像した「あり得る未来」を私たちに見せてくれる。スターリングが時代を超えて大切にしてきたのは、そのように未来を自由に想像する力であり、デザイン・フィクションとは、その想像力が形となって現われたものなのだ。
文学とゲームの文体
文体派。名前はあるが、理論はまだない。あるのは思想と実践だけである。だからこの話は、僕が始めた「文体派」の思想と、そこに至るまでの実践の軌跡が中心になる※1。
夏目漱石の『文学論』にある亀井俊介氏※2の解説を読んでいると、漱石が作ったゲームで遊んでみたい、そう思わずにはいられなかった。漱石はさまざまな文学を文体的特徴として操作できるという考え、作者+読者=文学という公式も考えた。これらはどちらもゲーム的だし、文学を研究した後で小説を書き始めたという逸話からも、彼のゲームデザインの才が感じられる。
現代では、ゲーム作家の山本貴光氏が書いた『文体の科学』に注目している。様々な作家がいて、様々な文体のあるゲームが、図書館のようにたくさん並んでいてほしい。文体に「派」がついたのは、そんなゲームを作りたいだけでなく、僕自身もたくさん遊びたいからだ。
しかし文体という言葉は、本来文学で使われる言葉であり、ゲームに文体があるのかという疑問も浮かぶ。これはまだ「わからない」ものとして置いておきたい。
今のところ「文体派」の定義は、〈文体をゲーム画面に持ち込む実験〉と考えている。プレイヤーとしては、成果より過程を愛するような人びとを想定している。
話ついでに、「あぺぽぺ」と「手帖と手帳」という、2つのキーワードを先に伝えておきたい。これらは偏った使い方で登場する言葉たちだ。
ゲームにおける言葉の可能性
言葉が主体になったゲームは、コンピュータの黎明期に発展した。しかしその後、グラフィックスの処理速度が向上して、ゲームは映画的な表現に置き換えられていった。現在は、絵と音のあるノベルゲームというジャンルが確立されている。
しかし未だに、ゲームと言葉に注目した試みは、まだ出尽くしていないのではないか。ゲームならではの言葉の取り扱い方、組み立て方、すなわちゲームの文体があるのではないか、と期待もある。しかも、スマートフォンという、ファミコンなどとは比べ物にならないほどの性能と、文字をきれいに表示するディスプレイを持ったデバイスが普及した。〈文体をゲーム画面に持ち込む実験〉に挑戦するのは、今がちょうどいいタイミングなのではないか。
かつて漱石先生が、一つ前の時代のスタイルで文学を創作したように、ゲームにおける言葉の可能性に目を向けてみたい。それが「文体派」の思想である。
わからないから始まる
あれこれ、考えなくちゃいけない。
でも、うまく考えられない。
だいたい、考えることって、何をすることなんだろう。
よくわからない。考えることを考える。野矢茂樹『はじめて考えるときのように —「わかる」ための哲学的道案内』
「文体派」なる言葉で、考えていることの多くがまとめられるかもしれないと思ったのは、ごく最近のことだ。それまで多くの「わからない」があり、今も「わからない」は宇宙のように増え続けている。一つの「わかる」がたくさんの「わからない」を連れてくる。
ゲーム会社の業務でプログラミングが上達するにつれ、僕はどんなゲームを作ったら良いかわからなくなっていた。物語のあるゲームを作ってみたい。しかし僕の頭の中にある物語は、僕以外の誰にも「わからない」。そもそも本当にそんな物語があるのかさえ怪しくなってくる。そんな「わからない」がわからない時期に出会った『思考の手帖』という本が、文体との出会いであった。
手帖にセーブされる文体
僕がこの手帖で行っていることは、学者のように専門分野の知識を蓄積してゆくことではなくて、世界について、世界からじかに知識を得るための能力を涵養すること、まるでまだ科学や芸術が未分化で未発達だったころの呪医や術師や錬金術師のように、原始的で始原的なかたちで科学や学問や研究や哲学や文学を、すべて自前の努力で、自分流にやり直してみることだった。東宏治『思考の手帖 — ぼくの方法の始まりとしての手帖』
この本を読んでから、「手帳」と「手帖」を分けて書くようになった。多くの人にとっての「手帳」は、スケジュールや日記を書くものだということは、他人の「手帳」を集め始めてから知った。それらは思考を書き留めるための「手帖」ではなかった。
東宏治氏はこの本の冒頭で、「手帖」の文体は断章であると説明している。それは急に思い浮かんだ思考の一瞬の閃光のようなもので、記録しないと二度と思いつかないかもしれない言葉。僕も真似をして、「わからない」ものを「わからない」まま、「手帖」に書くようになった。そうやって「わからない」ことと親しくなれた。
「手帖」に書くという実践は、過去に興味を持っていたことを再発見してくれた。『ドラゴンクエスト』シリーズの町の人々との会話と数値の美しさ、『リンダキューブ』のゲームメカニズム、『シルバー事件』の根幹システムであるFILM WINDOWのビジュアル、『街』の人間と物語の構造。こういったものが、「手帖」にセーブ(記録)されていった。
中でも、小学生と中学生の間に遊んだ『サンサーラ・ナーガ』は、一通り遊び終えた後も、しばしばゲーム世界の町へと足を運ばせる魅力があった※3。毎回決まった会話文しか表示されないにも関わらず。「あなたとは むかし どこかで あったような きがするわ」という町の人の台詞に、おそらく情緒のようなものを感じ取っていたのだろう。そんなときは、モニターにゲームの台詞が表示された状態でしばらくプレイを止めて、じっと浸っていた。
驚くべきことに、「手帖」に書きとめるまでは、こんな風に「わからない」けど好きなものを、ほとんど言語化していなかったのだ。
あぺぽぺという挑戦と挫折
昔、ある国の王様が奇病に襲われた。祈祷師が呼ばれ、お告げを得た。
「アペポペだ。アペポペしかない」
これがお告げだった。
だけど、その祈祷師も含め、だれも「アペポペ」が何なのか知らなかった。そこで学者が呼ばれ、「アペポペを探し出せ」と命じられた。学者は言った。
「畏れながら、『アペポペ』とは何でございましょう」
大臣は言った。
「だからそれを調べろと言っておるのだ。うつけ者め!」野矢茂樹『はじめて考えるときのように —「わかる」ための哲学的道案内』
「わからない」ものに引き寄せられてしまう僕は、「あぺぽぺ」という言葉に興味を持った。「わからない」がゆえに、すべてを受け入れてくれそうに見えた。
そこで僕はJIS漢字コードの文字から2000字ほどを選び、「崖」「視」「避」「寂」「芋」といった文字からなる世界と、「僕」「骨」といった文字からなるプレイヤーが登場するゲームを作り始めた。構想は難航したが、概念にまみれた世界を作り出せば、そこに「あぺぽぺ」を発見できるかもしれないと考えた。
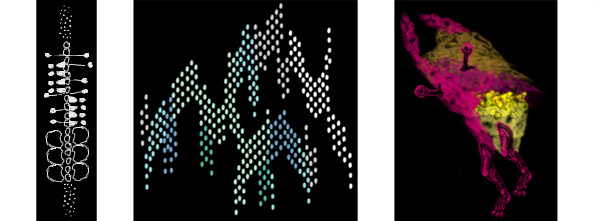 「あぺぽぺ」に登場する文字たち。左から「骨」「寂」「芋」。細胞のような小さな画像をスタンプのように押して、文字の形を表現している。
「あぺぽぺ」に登場する文字たち。左から「骨」「寂」「芋」。細胞のような小さな画像をスタンプのように押して、文字の形を表現している。
しかしこの制作は大失敗に終わった※4。先ほどの文字を登場させるなら、「僕」が「崖」を「視」て「避」けたり「寂」しくなったりするシーンが考えられる。そこに「骨」や「芋」はどう関わっていけばいいのか。そもそも「概」や「れ」は一体どこから作ればいいのか。そして行き詰まった。1文字に圧倒され、1文字すらまともにプログラミングできていなかったのだ。
持続可能な思想と実践のサイクル
「あぺぽぺ」での挫折は変節点になった。そこから1年以上は良い成果も失敗もなかったが、次の物語は動き始めていた。それを体感したのは、新しい仕事を受けたときだった※5。
その仕事はe-Sports Groundで、スポーツマンシップを体現するハードウェアは、いずれオリンピックの競技になるというメッセージを掲げていた。そのメッセージを元にコンセプトを練りながらアプリを作る仕事は、思想と実践が並行しており、これまでの自分にないプロセスだった。このバランスを個人制作に持ち帰り、処女作の短編ゲームを1ヶ月ほどで作った。続けざまに中編ゲームも発表できた。
現在僕は、仕事と個人制作をおおよそ半年毎に入れ替えるサイクルで、できるだけ毎日が新鮮になるように心がけている。自分にとってほどよいバランスを探るのも、実践であり思想のひとつだ。生活と不可分であるため、周囲の大切な人たちに納得してもらうことは必要だし、いくつかのことを諦めなければならないだろう。これからも、挫折の一つや二つはするに決まっている。
自分の軌跡を振り返ってみると、挑戦と挫折、そこからの回復によって、何かをつかむための握力のようなものを得てきたことがわかる。「文体派」のような「わからなさ」を持ったプロジェクトに向き合う気持ちになれたのは、これらの成果を得て、自分の思想と実践を手に入れた感覚があったからだ。
その後、軽い気持ちで始めた「手帳収集プロジェクト」は、コンセプトが深みと広がりを見せ、「手帳展」を開催するところまでこぎつけた。
手帳展という体験
他人が書き記した手帳や日記を集める「手帳収集プロジェクト」は、「他人のプライベートな手帳を読んでみたくないか?」という 、「今までにない快感のフレーズ」を備えていた。そしてこれは、僕の思想と実践における、ひとつの物差しになった。
いつも僕は、普段ゲームをしない人にも遊んでほしいと願って、ゲームを制作してきた。しかし現実にはなかなか難しい。しかもゲームは、作るのに時間がかかる。
それに対して、「手帳展」は何もない状態から出発したにも関わらず、半年もしないうちに普段会えないような人たちに届けることができた。こんなに簡単に届くものなのかと困惑さえした。
その体験の後、僕は少なくとも次の2つの条件が揃ってから、プロジェクトに向かうようになった。ひとつは、自分の心からの興味にもとづいてコンセプトを練ること。もうひとつは、「最初に人を選び、その後に目標を選ぶ」※6ことだ。
以前からアーティストの人たちと交流するようにしてきた僕は、「文体派」でも、ゲーム経験のないフリーライブラリアンで詩人の友人に声をかけた。どんな人とパーティを組めるかは、どんな実践になるかの指標となる。
ゲームの文体という情緒
このような軌跡をたどって、僕は「文体派」にたどり着いた。手帖と手帳についてたくさん説明したのは、どちらも「文体派」のコンセプトに深く関わってくるからだ。
「手帳収集プロジェクト」は、他人のプライベートな文体を集めることにつながり、自分で手帖を書く行為は、自身の文体の獲得に向かわせることになった。これらをどのようにゲームに持ち込めば良いのだろうか。ひとつのヒントは山本貴光氏が示してくれた。
そしてなによりも、文体を適切に捉えるには、書物や文章を構成する個々の要素だけでなく、そうした要素が組み合わさることで生じる効果に眼を向ける必要があります。個々の要素には備わっていない性質が、それら要素の組み合わせから生じる現象を、複雑系の科学では「創発(emergence)」という言葉で表します。山本貴光『文体の科学』
文体にこのような性質があるならば、ゲーム制作という実践を通してゲームの文体を作る、構成論的アプローチ※7で迫ってみるのが良さそうだ。
「文学」とは、かならずしも文字で書かれたもの、文字化されたものだけではありません。詩や小説や物語などの文学作品はもとより、マンガ、アニメ、絵画、映画、映像、地図、広告(CM)、あらゆる説明書、その場の雰囲気、人の顔色など、読み解くことのできるものは、山ほどあるのです※8。佐藤裕子『主人公はいない — 文学ってなんだろう』
文学にこのような拡張ができるならば、文体にも同様の可能性があると考えてみたくなる。付け加えると、音楽、映画、アニメやスポーツ・ゲームのような時間的芸術よりも、本、漫画や反射神経を必要としない非時間的ゲームの方が、文体を楽しむのに向いているはずだ。
夏目漱石は『文学論』で(F+f)という公式を語っていた。大まかに説明すると、何か(ファクター)を認識して、情緒(フィーリング)が発生すれば文学であるという。これならゲームを文学と同じ目線で考えても、大げさではないし高尚でもない。
絵、音、シナリオ、プログラミングなど、あらゆるゲームの部品をつかってできたものにプレイヤーが情緒を感じたならば、そこに立ち現れているのはゲームの文体かもしれない。そうなれば、これまでゲームに縁のなかった人に、情緒ある新しいゲームが届けられる。「文体派」はそんなゲームを目指す冒険である※9。
働くということは唯意志するということではない、物を作ることである。我々が物を作る。物は我々によって作られたものでありながら、我々から独立したものであり逆に我々を作る。しかのみならず、我々の作為そのものが物の世界から起る。西田幾多郎『絶対矛盾的自己同一』
デザインの獲得
イギリスの有名な童話に「3びきのくま」というのがある。ゴルディロックスという女の子が森で一軒の家を見つける。中に入ると誰もいないが、テーブルに3つのスープがある。1つめは熱すぎ、2つめは冷たすぎ、3つめがちょうどよかったので、それを飲んでしまう。同じように椅子やベッドも3つずつあり、そのうちの1つがちょうどよい。最後にクマの家族が帰ってきて、驚いた女の子は慌てて逃げ帰る。
この話が元になって、物事が多すぎず少なすぎずちょうどよい具合である範囲のことを、ゴルディロックスゾーン※1という。
宇宙はその一般的な傾向として、エントロピーの法則に従い、秩序から無秩序へ、構造から無構造に向かう。熱湯の入ったコップに氷を入れれば、やがて氷は溶けて全体が均一のぬるま湯になる。コップにぬるま湯を入れておいても、自然に熱湯と氷に分離するということはない。これは自明のことに思われるが、しかし、我々の身の回りを見渡せば、逆のことが起こっているのに気づく。無秩序であったところに秩序がもたらされ、無構造であったものが構造を持つようになる。その最たるものが我々自身の存在だ。混沌としていた宇宙に星が生まれ、生物が誕生し、人は文化を持ち、こうして様々な構造物を創造しつづけている。
エントロピーの法則に反するようなこういった現象は、デビッド・クリスチャンによれば、ゴルディロックス条件が満たされる時に起こるのだという。
例えば地球に生物が現れたのは、恒星から近すぎず遠すぎず適度な量のエネルギーがあったこと、適度に多様な化学元素と化学反応があったこと、適度な水があったこと、そういったゴルディロックス条件が満たされたからなのである。このように、環境的な変数がある閾値を超えることで、世界には段階的に秩序がもたらされ、構造化されていく。やがて人は言語という道具を使って試行錯誤の熱効率を飛躍的に高めることに成功し、自らの手で意図的に秩序を作り出す行為、すなわちデザインを獲得したのである。
ソフトウェアデザイン
デザインには様々な分野があって、古くから衣食住に関するあらゆるものが創意工夫されてきた。特に建築や都市といった複合的な構造体は、権力者にとって常に大きなデザイン課題として関心の的になってきただろう。
一方、ソフトウェアデザインというのは近年現れた新しいデザイン分野である。
コンピュータの性質を端的に言えば、0と1という論理値で情報を流通させることだ。これは世の中の混沌を代理するにはいささか乱暴なアイデアだったが、技術の進歩が我々の限られた認知能力に対して十分なイリュージョンを与えることができるということは、実生活の中ですでに証明されてしまった。
コンピュータにプログラミングされた論理の産物が、物理空間に根ざした我々の社会を動かしはじめた。そこにソフトウェアデザインという分野が成立したのである。
0と1で世界を代理するというアイデアは、かつての自然言語の獲得に匹敵するインパクトを持っているように思う。情報環境でも生じた、この「閾値超え」によって、我々は更に自由にエントロピーを減少させることができるようになる。
パラダイムシフト
ソフトウェアデザインに秩序をもたらす初期の試みは、高級プログラミング言語とコマンドラインインターフェースだった。これは英語という自然言語をベースにした表現を入出力に用いるというもので、つまりコンピュータを「計算者」として擬人化するのに際して、我々が最も親しんでいる記号を流用したのである。
自然言語は十分な複雑性をもっていたので多様な論理の展開を表すのに十分だったが、自然言語というものが基本的に持っている通時性に縛られていたために、同期的で断続的な対話しかできなかった。例えば、複数のパラメーターが同時に変化していく様子をゲシュタルト的に示すには次元が不足していた。
我々は自然言語を用いて通時的にコミュニケーションをとるが、我々が言葉を覚える前から住んでいるのは共時的な空間なのだ。我々は決して小説のようには世界を認知していない。意識は線形に進むのではなく、絵画のように全体的に一度に存在している。
そこで、ソフトウェアに共時性をもたらすために起きたパラダイムシフトが、オブジェクト指向プログラミングとGUI(グラフィカルユーザーインターフェース)の登場だった。
人と道具
Smalltalkのオブジェクト指向性は非常に示唆的であった。オブジェクト指向とは、オブジェクト自身が自分が何をできるのか知っているという意味である。抽象的なシンボルの場では、それは、最初にオブジェクト名を記述(するかあるいは持ってきたり)してそしてそれに何をするかを指示するメッセージを付ける。具体的なユーザーインターフェースの場では、それは最初にオブジェクトを選択することを意味している。それから何がしたいのかをメニューによって提示する。どちらの場合でも、オブジェクトが先であり、やりたいことがその次となっている。これは具体的なものと抽象的なものとを高い次元で統合している。アラン・ケイ「ユーザーインターフェース 個人的見解」
オブジェクト指向のコンセプトでは、観念的な仕事空間の中にまずいくつかの物を作る。物たちにはあらかじめそれぞれの役割に応じた性質が静的に与えられている。その物たちにメッセージという刺激を与えると、物たちはそれぞれに反応する。その反応を利用して仕事をするというものだ。
これは例えば、石を削ってその鋭利を利用して材料を切るとか、火をおこしてその熱を利用し材料を焼くといった行為と似ている。そのための入出力としては、身体動作と視覚言語を用いることが適している。
椅子やハンマーといったプリミティブな道具ではそのもの全体が利用者との接点になるが、構造が複雑になり内部の機構と外装が分離して、操作部が独立して設計されるようになると、そこにユーザーインターフェースという概念が出現する。抽象物を成分とするソフトウェアにおいては、その働きと我々のファジーな認知を仲介するものとして、ユーザーインターフェースの役割が特に重要になる。
コンピュータを使えば人の五感に向けたフィードバックを動的に作り出すことができるので、ユーザーインターフェースの独立性は一層増す。道具の内部機構に対してユーザーインターフェースが独立するということは、意味空間を自由に作れるということである。
道具を作るということは、単に今やっていることを省力化することではないだろう。利用者にとっての世界の捉え方やコミュニケーションの意味を変えるということだ。その意味でユーザー要求の特定はデザインのゴールではなく、きっかけにすぎない。
人と道具は影響し合い、互いの要求を進化させてきた。優れたデザインは、ユーザー自身の価値観や行動を変え、要求を次のステージに導く。例えば自転車に乗れば人は歩くよりも楽に遠くへ行くことができるが、それは単に量的な変化ではない。自分とそれを取り巻く世界との関係について、新しい視点を与えてくれる。車輪やチェーンといったテクノロジーが実現する量的な変化は、自転車という全体的な構造によって我々に質的な変化をもたらす。デザインによってゴルディロックス条件が満たされ、エントロピーが減少する瞬間である。
ソフトウェアデザインが持つポテンシャルは、低レベルのインターフェースから高レベルのインタフェースまでを、物理的な制約をほとんど受けずに、次々と新しく発明できるところにある。しかしその無制約が、ソフトウェアデザインを難しくもしている。
オブジェクト指向によってソフトウェアが世界を代理できることは分かったが、新しい世界をゼロから創造するためにはモデルとなる手がかりが必要だ。そこで採用されたのが、デスクトップメタファである。デスクトップという箱庭に意味空間のスコープを限定することで、GUIはエントロピーの増大を食い止めることに成功した。そしてその世界における活動原則として「Object → Command」のシンタックスが定められたのである。
GUIをGUIたらしめているのは、グラフィックで情報を表現することよりも、むしろこの操作のシンタックスにある。まず対象物を選択し、次に命令を選択する。対象物を選択するには、先にそれらが選択肢としてユーザーに提示されていなければならない。また対象物は自身の状態を常に目に見えるようにしておくことが理想なので、結果的に、自律的に振る舞うオブジェクトはイコン※2としてスクリーンの空間に配置されることになる。我々は視覚的な記号を扱うのに長けているので、GUIの箱庭性は心地よさや楽しさを生み出す。
こうしてデスクトップメタファとその応用は、GUIの基本様式となった。しかし箱庭の問題は、その表現力がスクリーンの物理的な大きさに比例してしまうところにある。
デバイスが多様化して小さなスクリーンが増えると、狭い空間で我々は身動きがとれなくなってしまう。情報量は増える一方であるのに、一度に表示できる記号の量を減らさなければならないとなると、記号が表す意味をハイコンテクストにしていくしかない。スマートフォンにおける幾何学的なフラットデザインや、スマートウォッチにおけるパズル的なマイクロアニメーションは、GUIのハイコンテクスト化を意味している。
いずれにしても、ソフトウェアデザインが抽象的なビットと具象的な現実世界を橋渡しするためには、いくつかのゴルディロックス条件を満たさなければならない。私はソフトウェアにおけるゴルディロックス条件として、大きく次の3つがあると考えている。
条件1:イリュージョンを与えるのに十分なプロセッサスピードと記憶容量
コンピュータの意義は、そのスピードと容量によって、イリュージョンを作り出すところにある。
例えば「1+1」といった計算について、人間が0.1秒で答を出し、コンピュータが0.0001秒で答を出したとしても、我々の認知の限界を考えれば、実質的にそれほどの違いはない。しかしこのような計算を1000回行った場合、人間では100秒かかるところをコンピュータが0.1秒で答を出すのだとすれば、そこには質的な違いがある。つまりAという仕事とBという仕事の間に1000倍の処理量の違いがあったとしても、それが0.1秒ほどで済んでしまうのなら、我々にはほとんど同じように見える。
このことは、ソフトウェアのユーザーインターフェースが持つ圧倒的な自由度につながっている。新しい世界観を構築する上で、計算処理の量にかかわらず、ユーザーにとってその世界がどうあるべきかという視点のみから構造を決められるということだ。例えばPhotoshopで線を描く時、鉛筆ツールを使うのとブラシツールを使うのとではおそらく1000倍ぐらい計算量に違いがある。しかしそれらをツールパレット上で並列に扱うことで、ユーザーはデジタルフォトを自由にレタッチできるというイリュージョンを見ることになる。
記憶容量についても同様だろう。例えばインターネットにつながっているサーバーは有限個だろうが、その数が十分に大きいため、実質的に情報は無限にあるように思われる。個人が持つ記憶媒体についてもやがて容量が増加すれば、一生のうちに知覚するあらゆる情報をデータ化して蓄積しても余るようになる。それらを再生共有できるようになれば、我々がこれまで抱いてきた自己意識や歴史観には質的な変化がもたらされるはずだ。
条件2:学習が容易な入出力のイディオム
ソフトウェアのユーザーインターフェースは、全体がイディオムで構成されている。画面という概念、対話型の操作、ボタンのように見える矩形など、すべては慣用的に解釈されるイディオムである。
記号がハイコンテクスト化するということは、表現がイディオマティック(慣用的)になるということだが、慣用表現を用いるためにはまず、それを構成する要素の本来の意味が周知になっていなければならない。
例えば、デスクトップGUIの基本的な操作イディオムは、画面上に見えているオブジェクトをクリックして選択することだった。これはマウスの物理的なボタンを指で押すという身体動作によって行う。つまり関心の対象物に対して指で圧力をかけてみるという、我々の生活上の基本的な対話姿勢をベースにしている。その他にも、ものを掴んで移動するという動作によってオブジェクトのドラッグ&ドロップを行うなど、手を使った物への働きかけとそれに対する視覚的なフィードバックによって、インタラクションが成立するようになっている。
昨今のマルチタッチスクリーンでは、スクリーン上で指をスワイプさせることによりビューを遷移したりスクロールさせたりする操作イディオムがあるが、これらは、GUIの箱庭において、スクリーンに入りきらない情報の表示面はそれをずらすことで閲覧領域を移動できるというメンタルモデルを、ユーザーがすでに持っていることで自然に学習できる。
このようにデジタルネイティブなイディオムが発展すると、ソフトウェアの表現力は高まっていく。逆に言えば、ユーザーインターフェースのイディオムを検討せずに機能要件を定義するのはナンセンスである。人はユーザーインターフェースを通じてシステムの意味空間を把握するのだから、学習可能なイディオムとして構成できないのなら、どんなアイデアも道具としての意味を成さない。意味のある道具を作りたければ、むしろイディオムに合うように要件の方を変更する必要がある。
条件3:それらを扱うのに適したプログラミングモデル
GUIの共時的な空間世界を組み上げるために、オブジェクト指向プログラミングが生まれた。オブジェクト指向のプログラミングモデルにおいて、それぞれのオブジェクトは自律的な存在だが、それらにイベントループというテンションがかかることで、協調して動くようになる。
オブジェクト同士の関係は、石造りのアーチ橋に似ている。この橋の構造は、輪石と呼ばれる扇型の石をアーチ状に積み上げて作られる。両端から順に重ねていき、それらが出会う頂上のひとつを最後にはめ込むと、橋自体の重さと荷重による圧縮応力で支柱がなくても立っていられるようになる。
もし石造りのアーチ橋を無重力空間に持っていけば、バラバラになってしまうだろう。地上では重力がそれを防ぎ、エントロピーの増大を抑制しているのだ。
ソフトウェアにおいても、オブジェクト同士の協調を純粋にして、プログラムの耐久性を高めようとするほど、各オブジェクトの形態は一定のパターンを持つようになる。またそれらを設計する時には、役割を分担する一連のオブジェクトが同時に存在していて、同時にテンションがかかっている状況を前提にしなければならない。
GUIの共時性はイベント駆動であることによって実現される。スクリーン上の要素はそれぞれが独立してユーザーからの操作を待っているが、これは裏でイベントループが回っていて処理のきっかけを見張っているのである。イベントループはGUIの世界で常に作用している重力のようなものだ。
一連のオブジェクトがひとたびイベントループの循環に入ると、あとは自分たちで勝手に結合してメッセージを送り合い、協調して動く。プログラムの品質としてオブジェクトは互いに疎結合であるべきだが、それがソフトウェアデザインとしてユーザーの中に意味空間を形成する時、イリュージョンは一気に生まれるのである。まるで最後の要石をはめ込む瞬間のように。
新しいプログラミングモデルは繰り返し試されているであろうが、単に量的な課題を解決するためであればパラダイムシフトは起きない。GUI がもっとハイコンテクストになり、これまでになかったイリュージョンとイディオムが模索されることで、質的な変化をもたらす新しいプログラミングモデルが生まれるだろう。
これから
ソフトウェアデザインという分野は、世間でまだそれほど特別なものと思われていないだろうが、これはデザインの中でも特に高次なものと位置づけることができるだろう。ハードウェアのデザインにおいては、それを構成する要素の物理的な性質によってアイデアが保持されるのであって、例えば耐久性や操作性といった品質は、人の身体も含めて、物理的制約の上で担保される。しかしソフトウェアのデザインにおいては、すべてが論理的な制約の上で構築されている。エントロピーの増大を食い止め、そこに秩序をもたらす力は、我々の観念のみである。
確かにソフトウェアの有用性を評価する上で人の認知特性を無視することはできないが、我々の観念は、運動能力などとくらべて遥かに容易に新しいモデルへ移行できる。ソフトウェアによって将来、この物理世界とは全く違う価値観からの精神活動が営まれるであろうことは想像に難くない。それはおそらく我々の生活に、ある名状し難い、質的な変化をもたらすはずだ。ワイルドは「自然は芸術を模倣する」と言ったが、やがておとずれる時代では、「精神はソフトウェアを模倣する」のである。
第0日
「夢」はどこにあるのだろうか?
睡眠中の体験とも物語ともつかないイメージたち、醒めて描く将来への希望。この2つが大抵どの言語でも同じ1つの言葉で表されてしまう。
dream träumen rêve sueño حلم 꿈 夢 ゆめ
「夢物語」のように非現実の象徴として用いられもするが、「夢判断」で用いられるように現実と全く乖離したものでもない。快不快や欲望からだけでも説明は付かず、まるで散歩の途中に眺めている、移ろう景色のような現実感を伴った経験。日頃の活動の中でふと立ち返る、子供の頃に見た風景などは、夢ととてもよく似た、記憶の道標となっている。夢に形を与えることもできる。スケッチや夢日記。舞台や音楽。夢そのものあるいは、夢見ることは多くの作品の主題となってきた。
夏目漱石は、その小説「夢十夜」の第一夜、第二夜、第三夜、第五夜をこう始めている。
「こんな夢を見た。」
このように書くことで、小説の書き手が夢のことを客観的に語っていることを示している。逆に言えば、第九夜の文中に現れる「こんな悲しい話を、夢の中で母から聞いた。」という例外を除くと、これら以外の5篇は明確に夢であるかどうかは語っておらず、ただ第○夜とだけを明示しており、書き手の立つ場所を曖昧なまま残して夜を重ねていく。夢の中と外のどちらにいるのかわからない以上、「眠って見た夢」を描いているのか、「醒めて見る夢」を語っているのかも、見分けることができない。そのように、夢と現実の境界を霞ませながら読む者を幻惑していくのも、「夢十夜」という小説である。
この「夢十日」では、「醒めて見る夢」を日々重ねて行く試みを始めたい。現実の側に足場を置きながらも、それを「眠って見た夢」と同じように無意識に近いレベルで形にするというやり方で、複雑化する今の時代に夢を言語化してみたいのだ。この試みをはじめるのがたまたま私だったので、私をこの試みに向かわせたものについて、個人的な話を少し記したい。
少年時代、数学者に憧れた私は、よくある思春期の異文化への「旅行」を経て、「生きているシステム」に関心を持つようになり、大学の専攻としては数学と生物学の2つを学ぶようになった。自分の「数学への関心」が、ダンサーの「解剖学への関心」と近いものだと理解したのもこの頃だ。私の「旅行」は人間のいない世界へと広がり、ある砂漠の「生物の食物網」というシステムの研究へと広がった。その後、私の「旅行」は日本の私を支える「経済システム」や「社会システム」が対象となり、現在に至っている。
これまで10年以上いくつかの業界、業態で情報技術に係る仕事をしてきた。当初は新規Webサイトの導線設計、いわゆる「インフォメーションアーキテクトの仕事」を中心業務としてきたが、徐々に運営体制の構築、組織体制の修正、ガイドラインの作成、LLPの設立、レポート執筆なども。クライアントとしては、中小企業、大企業、地方自治体、国際機関、NPO、金融関連会社などと、業種、業態、パブリックセクター/プライベートセクターの境無く仕事をしてきた。
組織や個人といった有機体が「いきいきとしている」かどうかは、それらと社会の接点になるWebメディアのあり方に、ダイレクトに反映される。そう考えてきた結果として、メディアの設計だけではなく、メディアを生み出す主体への介入を業務とすることが増え、このような足跡をたどることになった。これは、Webサイトのグローバルナビゲーションが組織構造そのままであった時代から、ソーシャルメディアの時代への変化とも重なる※1。
21世紀初頭の情報技術は、人間の身体と技術/人工物との境界が大きく動いた時代の名残として刻まれるかもしれない。有名な故ベンジャミン・リベットの実験のように、意識体験さえも定量的に取り扱われ、その存立基盤の不確かさに対する探求が、20世紀の哲学者たちとはまた違った形でなされており、それが技術という形で社会に導入されようとしている時代である。電話やテレビが私たちを変えた以上に、深いレベルで私たちが変わっていくことが、技術の実装レベルにまで降りてきた時代だと認識している。
「インフォメーションアーキテクト」という用語を生み出した建築家/デザイナー、リチャード・S・ワーマンは、技術が人間の「夢」にまで影響を及ぼしつつある時代の流れについて、こう語った。
この100年で、それ以前の7千年分の夢が実現され始めている。これはおそらく、詩人ロバート・グレーヴズが、「白日夢(the waking dream)」という表現で伝えようとしたのと同じものだろう。私にとって「白日夢」とは、人生の一部としてそれを豊かにしてくれる、自分の能力と感覚の拡張だ。口と耳、自分の声と聞こえる音、電話がもたらした会話の拡張、これが私の思いつく第1の不思議である※2。リチャード・S・ワーマン
上に挙げた状況は、「夢」においても二重の意味で重要だと考えている。すなわち、無意識の表出としての「夢」では、現実との境界が揺らいでいる点において。将来のヴィジョンとしての「夢」では、現実がそこに到達する技術を私達が持ちはじめているという点で。
このことを考える中、夏目漱石に導いてもらいながら、未来の夢を見ることにした。
ここからはじまるテキストでは、漱石が見た「夢十夜」に浸り、自分の見ている夢と重ねあわせて記していきたい。眠りながら見る夢、醒めて見る夢、そのどちらもが、書かれることで現実のものとなる。漱石の夢という我々に残された財産に重ねて夢をかたちにすることで、私の見るパーソナルな夢を、私たちが見てきた夢に融け合わせていきたいのだ。※3
そしてもう1つ重要なのは、夢を見ているとき、私たちはいったいどこにいるのかということ。心は夢の世界に、身体は現実の世界にあるような気がするけれど、人間の心と身体はもともと一体であり、分けることなどできない。心が身体に夢を見させ、その身体が心に夢を見させるという、無限のループがそこに生まれている。だから、夢を想うとき、私たちは自分の居場所の不確かさに気づき、ある種のトリップ感に浸ることになる。また、互いに浸透している夢と現実の間を行き来するときの、テンションの変化にも気づく。忙しない現実のなかで夢を見るときの、スローダウンする感覚。その逆に、夢を何らかの形で現実にしようとするときの、アクセルを踏み込む感覚。これら2種類の、異質なドライブ感が生じているのだ。
いまから私が見る夢は、いつか誰かが見ていた夢であり、いつか誰かが見る夢でもある。
みんなと一緒に見ることができる夢というのは結局、リアリティということなのです。ここでいうのは観念レベルでのリアリティではありません。世界に本質的な変化の機会を与えるほどの力をもったものです。ダムタイプ『メモランダム 古橋悌二』
第1日
こんな夢を見ている。
腕組をして枕元に坐っていると、仰向に寝た女が、 静かな声でもう死にますと云った。だが私は、生前の彼女に会ったことはない※4。
ずっと前に此処を訪れた、依頼者の青年が私に見せた一枚の写真。そこに映っていた彼女は、瑠璃色の空と八角形の光芒に囲まれ、操縦桿を握って穏やかな表情を見せていた。鉄枠の端に張り付いた雪を見ると、どうやらグライダー※5の操縦席らしい。長い睫毛に包まれた大きな潤いのある瞳は、ただ一面に広がる空の色と同じに見えた。
「母の最後の写真です。こんな日には彼女は上昇気流を探して、いつもより高く、空にできるだけ近づこうとしていました。」
依頼者のニーズを満たすゴーストを生成するには、当然ながら、プログラミング可能なメソッドやオブジェクトをできるだけ仕入れておく方がいい。その青年からは、彼女が好きだった芸術家※6の話や、一番古い彼女の思い出となった出来事なども聞き出した。五歳くらいの時に小さな家出をした彼が、やがて泣き疲れた頃に、彼女が信号機の向こう側で笑いながら大きく彼の名前を呼んでくれたこと。あとで彼がその話をすると、すぐ後ろから見えないように隠れてついていったのよ、と愉しげに打ち明けたという。
あの写真に映った、彼女の瑠璃色の瞳。他者の記憶に残り続ける、白い百合のような笑顔。気がつくと私は、憑りつかれたように、ネットに散逸した彼女の痕跡を拾い集めていた。
他愛もない日常のスナップショット。断片的な出来事を記録した動画。彼女について書かれた雑誌の記事や、一昔前にブログと呼ばれていた※7、テキストと写真が散りばめられた個人日誌。彼女が世界のあちこちで残した旅行写真。発表した作品や論文。飽くことなくそれらに目を通しながら、疲れ切っていつの間にか眠ってしまう日々を過ごしてきた。
彼女に関する「情報」を知れば知るほど、それがネットという開かれた場に晒され続けていること、死んだ筈の彼女に誰もがまだアクセスできるという事実が、私を苛立たせた。もはや自分だけのものにはできない彼女を、私はせめて他の誰よりも深く知りたかったのだ。しかし、バーチャルな存在としてオンラインの世界に放置された彼女が、誰にでも同じ笑顔を見せ、同じ言葉を語るのを、私が止める術はない。この世にいない彼女とは、もはや個人的にコミュニケートすることもできない。自分が彼女にとって特別な存在になることは不可能なのだという現実に、どう耐えればいいのか?
デジタル化された彼女の肉体、彼女の思念の生々しさ。それらは、弔われるべき死者の記憶として薄れていくどころか、今でもセイレーンの歌声のように、見る者を何度となく呼び戻さずにはおかない。現実の世界では死者として永遠に消失した彼女に、ネットという夢の世界で、私はクラックされていた。まるで百年も前から、この罠に絡め取られている錯覚さえ感じた。
そんな日々のなかで、ふと、彼女と会話をしていることに気づく。端末の中なのか、睡眠中に見たイメージなのかは分からないが、死の床に横たわる彼女の枕元で、たしかに私は彼女と話していた。傍らには、誰が置いたのか、大きな滑らかな縁の鋭い真珠貝と、天から落ちてくる星の破片のような丸い石があった。それらを静かに見つめながら、彼女は言った。
「こんなことをいうと、おかしいと思われるでしょうが、あなたのことはずいぶん前から知っている気がするんです。そう、百年くらい前かしら。」
これは夢だ。私は自分にそう言い聞かせる。彼女がすでに死んでいることを思い出す瞬間を逃してはならない。仮想空間から現実空間に戻るための公衆電話※8のような、夢から現実へのインターフェースとして、その瞬間をスナップショットとして保存する必要がある。だが、何をキーにするのかが難しい※9。ジェスチャーか、コーヒーの頻度か、自分の心拍数と呼吸や発汗、瞳孔の大きさか。システムは刻々と自動記録を続けるが、自分自身の違和感の輪郭を正確に捉えるには、やはり意図的な動作が決め手になる。いまのところ、私は机の端に走り書きのメモを取ること※10を、デバッグの一番の手がかりとしていた。
こんな夜をしばらく重ねたのち、依頼者である青年と端末とのセッションの準備にとりかかる。私はすでに彼女のゴーストを、自身のロジックのみで有機合成できるレベルにまで仕上げ、それを自分だけのものとして保存し、密かに愛でるようになっていた。だが、依頼者の青年に対しては、ちゃんと彼向けのカスタマイズを施したコピーを納品しなくてはならない。彼から見て自然にふるまう、亡き母のゴーストをデザインするということ。理想的なバランスとされるのは、死者のオリジナルの人格が半分、依頼者がその死者との関係の中で見てきた人格が半分。私のようなゴーストデザイナーは、いわば仲人みたいなものだ。
青年は別れ際にこう言った。「実は先日、母の墓に百合が咲きました※11。また一目会いたいと願っていた僕の気持ちを、察してくれたのかもしれません。母が今でも自分の傍にいるような気がして、此処に来る必要がなくなったと感じました。」
翌朝、日の出前の仄暗い空気の中でふと目覚めた私は、神経を癒すために脳内モニタでリピート再生していたはずのアブストラクト映像が、見えなくなっていることに気づいた。黒一色の画面を呆然と見つめていると、やがて下のほうからすらりと青い茎が伸びて来た。その頂きで、真白な百合の蕾が、ふっくらと花弁を開いた。その上に、ぽたりと露が落ち、花は自分の重みでふらふらと動いた。露に濡れた花弁から、透き通った雫が滴り落ちた。
私はまだ夢の中にいるのか?
思わず窓の外に目をやり、遠い空を見る。暁の星がたった一つ瞬いていた。脳内モニタに意識を戻すとそこにはもう花の姿はなく、無機質なアブストラクト映像が再び映し出されていた。
「百年はもう来ていたんだな」とこの時始めて気がついた。
第2日
こんな夢を見ている。
大佐の連隊長室を退がって、廊下伝いに自分の病室へ帰ると、裸電球がぼんやり点っている。半分壊れかけたベッドに腰を下ろし、煙草に火をつけたとき、丁子※12の甘ったるい香りが立ち上った。同時に、べったりと身体にまとわりつくような熱帯の空気で部屋が満たされているのを、あらためて肌に感じた。
枕の下に、義体化した右手を差し込んで、精巧な装飾が施されたナイフを取り出した。冷たい刃が暗い部屋で光った。
大佐はこう云っていた。「おまえは人類の経験したことを原理的には全て体験できる※13と言ったな。その証拠を見せてみろ。」
いやはや。その証拠とはどのようなものだろうか?まだBMI手術※14をしていない大佐にとっては、いまだに物象が意味を持つのか?奴が証拠として認める物象は、形成過程で混じったノイズが重なりあった複雑性の高いものを言うのだろう。骨を彫って作られた、このナイフの柄のように。だが奴は五感だけを使って、その複雑性をどうやって検証するのか?
しばらく寝たきりだったのか、全身が凝り固まっていたが、精神集中のためになんとか胡坐を組みながら考えた。自分の影が壁に映って揺らめいている。祖母の葬式のときの記憶が蘇ってきた。部屋に満ちる消毒薬の臭いのせいもあったのだろう。葬儀の夜に泊まった祖母の家の見慣れぬ天井についた、ラスコーの壁画※15の牛のようなシミが動いて見えたこと。そのとき隣にいた従兄弟に悪態をつかれ、泣きながらくるまったブランケットの厚み。むかしの記憶も、いま自分が感じていることを記録しさえすれば、そのままの解像度でいつでも再生できるというのに、そのことをどうやって大佐に伝えればよいのだろうか?この悔しささえも記録できる。ほらこうやって目を瞑るだけで。タイマー設定だってできる。再生だってこんなに簡単。市販のファイルだって、電脳化されたおれの内部記憶装置には、手当り次第にインストールしてある※16。
急に右肩に痛みが走った。どちらの手でも巧みに武器を扱えるように、利き腕じゃない方の腕を義体化するのは、おれのような傭兵の間では常識と化している。だが、高度に発達した電位センサーは、激烈な脳の活動を痛いほどの刺激に変換することがあるのだ。大佐の薬缶頭と、おれを嘲笑うような顔がありありと見える。猛烈な堪えがたさが襲ってきた。どんな種類の感情なのかさえわからないが、その強さだけは確かだ。座面から頭の先まで大量の蟻が這い登ってくるようだ。汗が吹き出る。怒っているのか、おれは?
冷静さを取り戻すために、この病室に送り込まれるまでの出来事を思い出そうとするが、空白だ※17。ここにはどうやってきたのだろうか?その前は?鼓動が不規則に感じる。吸ってから吐くのか、吐いてから吸うのか?狂ってしまったのだろうか。いや、狂ってしまったと考えているうちは狂ってはいないのだろうか。CATCH-22※18ってなんだっけ?
人類の経験したことを原理的には全て体験できる ―― おれはなぜ、そんなことを言ったのだろうか?人類の経験といったって、何らかの媒体に記録されたものしかないことになるはずだ。とりあえず、その全てが記録できているとしよう。容量無制限の仮想拡張メモリを装備しているおれのような人間には、人類の経験を全て詰め込んだその莫大なアーカイブデータを自分の脳内に丸ごとコピーして、自由自在に呼び出すことだってできる。でも、体験ってものは、それぞれの人間がどんな経験を積み重ねてきたかによって、中身が違ってくるはずだ。同じ一回の出撃でも、初めて命令を受けて張り切ってる新入りと、おれのように何十回も命令に従って散々な目に遭ってる奴とじゃ、まるで違う体験になるってこと。そうなると、記録された誰かの「体験」を別人がただ呼び出したところで、同じ「体験」をしたことにはならないんじゃないか?
隣の広間に据えてある時計がボーンと鳴り始めた。
消毒薬の臭いと奥歯の痛みがはっきりと甦ってきた。奥歯をぎりぎりと噛んでいたようだ。じっと耳を澄ますと、身体を流れる血の音までもが聞こえてくるようだ。ナイフが裸電球の灯りを反射して赤く光った※19。
はっと思った。このナイフをかまえて、必死の形相で飛びかかってきた女の顔が、潜在記憶の底から鮮やかに甦ってきた。余所者たちの戦いの巻き添えを食ったあの女は、いまもこの病室のドアの向こうで、おれにとどめを刺そうと待ちかまえているんじゃないのか?
おれは逃げ出すことに決めた。自分の責任から逃げるんじゃない。飛び交う銃弾のただなかの自由に向かって脱出する。どんな手を使ってでも自分の人生を守ることだけが、誰もが果たすべき自分の責任だったんだ。偉い奴らは、自分たちの頭がイカれてることにも気づかず、狂ったコマンドをおれたちにインプットしてきた。おれたちはそれを機械のように処理して、狂ったアウトプットをしているだけだった。あんな連中は勝手にくたばるがいい。虚しい入出力の繰り返しにケリをつけて、自分の経験を生きるために、ずらかるんだ。
おれは病室の窓から飛び出し、いちもくさんに駈け出した。時計が二つ目をボーンと打った。
建物は変化する。刻々と成長し、みずから学んでいくものである。単なる空間的な構造物ではなく、時間というパラメータを考慮に入れ、この世界に生まれ、様々な成長を遂げ、やがては死に至る、一種の「有機的存在」としてとらえなおす必要があるのではないか。
スチュアート・ブランド※1 は、著書『How Buildings Learn』で、時の流れとともに建物に何が起こるのかを探究しました。そのなかでブランドが提示した「ペースレイヤリング(Pace Layering)」の概念は、建築の世界にとどまらず、情報やメディアに関わる分野でも多くの注目を集めてきました。
この本が世に出てから20年後の今、その思想の意味をあらためて考えたいと思います。
スチュアート・ブランドの基本モデル
ペースレイヤリングの基本となったのは、この本で示された以下のモデルです。
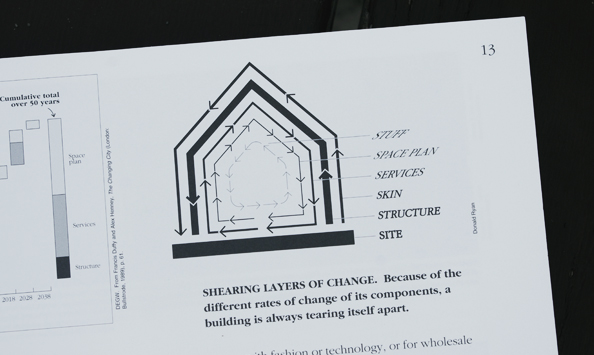 [図1] “Shearing Layers of Change” —『How Buildings Learn』p.13より
[図1] “Shearing Layers of Change” —『How Buildings Learn』p.13より
まず土台となる用地(Site)があり、そこによって立つ建物は、それぞれに変化率の異なる複数のレイヤーで多層的に構成されています。
§
| 調度品・日用品 Stuff |
日/週/月といった単位でしょっちゅう変化する |
|---|---|
| 空間計画 Space Plan |
商業施設では3年ごとに見直しを要するかもしれないが、閑静な住宅なら30年持つこともある |
| 設備 Services |
7~15年で老朽化/陳腐化する |
| 外装 Skin |
約20年ごとにリフォームや修繕が行われる |
| 構造 Structure |
耐用期間は30~300年と幅がある(これがいわゆる「建物」) |
| 用地 Site |
その上で建て替えを繰り返される建物よりも永続性がある |
ブランドのこのモデルには、実はお手本がありました。それは、イギリスのフランク・ダフィー※2 が提示した、建物の4つのレイヤーです。
§
| セット Set |
入居者による模様替え(月単位または週単位で行なわれることがある) |
|---|---|
| 景観 Scenery |
間取り、吊り天井など(5〜7年ごとに変わる) |
| 設備 Services |
配線、配管、空調、エレベーターなど(約15年ごとに交換を要する) |
| 骨格 Shell |
建物の寿命と同じ期間存続する構造(イギリスでは50年、北米では35年弱) |
[表2] ダフィーによる4つの“S”のレイヤー
建物を正しく捉えるならば、それは耐用期間の異なる要素がいくつかのレイヤーとして重なったものとみなすことができると、ダフィーは考えました。「われわれが分析する単位は、建物ではなく、時間を経ていく建物の使い方だ。時間こそが、現実の設計課題の本質だ」という彼の言葉に共鳴したブランドは、おもに商業施設を対象としていたダフィーの4つの“S”を、住宅のような他の利用形態にも応用できる、6つの“S”へとアレンジしたのです。
ダフィーは、「時間」を重んじながら建築を考えることはとても実践的だと主張しました。建物に問題が生じたときに、その発生箇所がどれくらいのペースで変化するかを考えた対策を取らないと、せっかくの修理や改修が無駄になるおそれがあるからです。それぞれのレイヤーに見合った時間的尺度で問題解決を行なえば、「適応力」の高い建物をつくれることを明らかにした点が、ペースレイヤリングの本質的な価値と言えるでしょう。
分野を超えた展開
2000年代に入ってから、ペースレイヤリングの概念は、建築以外の活動に携わる人びとの間でも注目を集め出します。ちょうど2000年には、情報システム開発の分野で、IBMの研究者らが「A Shearing Layers Approach to Information Systems Development」という論文を発表しました。彼らはその中で、企業などの組織とそこで利用されるソフトウェアの両方を、ペースレイヤリングの観点から見直すことの意義を論じています。それによって、組織の「適応力」を高め、ソフトウェアの応用可能性を広げることが、当時のソフトウェア開発に必要とされていたのです。
その後、Webサイトの飛躍的な増加を背景に、情報アーキテクチャ(IA)やユーザーエクスペリエンス(UX)デザインの分野でも、ペースレイヤリングへの関心が高まっていきます。2006年のIAサミットでは、西オンタリオ大学の研究者グラント・キャンベルとカール・ファーストが、「From Pace Layering to Resilience Theory」と題した論文を発表しました。この論文では、Webサイトやアプリケーションの設計に関する4種類のモデルが、ペースレイヤリングの応用例として一つの表にまとめられています。以下にその内容を翻訳し、最上段に各モデルの考案者と年代を追記しました。
| 変化 | アーキテクチャの構成要素 Architectural Components (Morville 2001) |
IAの氷山 The Iceberg of IA (Morville 2000) |
UXの要素 Elements of UX (Garrett 2003) |
UXの段階 Planes of UX (Garrett 2003) |
|---|---|---|---|---|
| 速い | コンテンツ サービス インターフェース |
インターフェース | ビジュアルデザイン | サーフェス (表層) |
| 適応型検索ツール | ワイヤーフレーム ブループリント (青写真) |
インターフェースデザイン ナビゲーションデザイン 情報デザイン |
スケルトン (骨格) |
|
| 制限語彙 | メタデータ 分類体系 シソーラス |
インタラクションデザイン 情報アーキテクチャ |
ストラクチャ (構造) |
|
| 実現技術(Enabling technologies) | IA戦略 プロジェクト計画 |
機能仕様 コンテンツ要求 |
スコープ (要件) |
|
| 埋め込み型ナビゲーションシステム | ユーザー (ニーズ、行動) コンテンツ (構成、意味) コンテクスト (文化、技術) |
ユーザーニーズ サイトの目的 |
ストラテジー (戦略) |
|
| 遅い | ファセット分類体系 | |||
[表3] IA/UXのペースレイヤリング
左の2列は、90年代に情報アーキテクチャという専門分野を開拓したピーター・モービルとルイス・ローゼンフェルドの共著『Web情報アーキテクチャ』 で、右の2列は、ジェシー・ジェームズ・ギャレット※3 の『ウェブ戦略としての「ユーザーエクスペリエンス」』で提示された、IAやUXの構成要素です。キャンベルとファーストは、それらを建物と同様に、ペースレイヤリングのモデルに重ねて理解しようとしたのです。
一方ブランド自身は、1999年の著書『The Clock of the Long Now』で、建物よりはるかにスケールの大きな文明社会へと、ペースレイヤリングのモデルを展開しました。
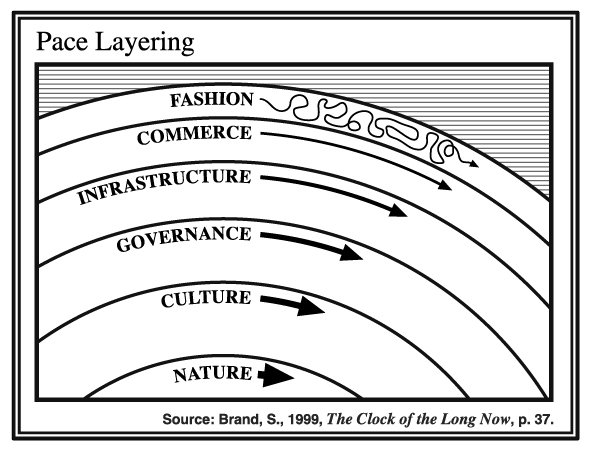 [図2] 文明社会のペースレイヤリング
[図2] 文明社会のペースレイヤリング
建物と同じように私たちの文明社会も、ファッション(Fashion)、商業(Commerce)、インフラ(Infrastructure)、統治(Governance)、文化(Culture)、自然(Nature)といういくつかのレイヤーで構成されており、各レイヤーの変化率や規模感が異なることが示されています。文明が存続するかどうかを決めるのは、どのレイヤーもお互いのペースを尊重し合い、それぞれの役割を果たしているかどうかである。下部のレイヤーがしっかりとした足場となり、上部のレイヤーが新たな息吹を与えるならば、たとえ何らかのショックが生じても、それをうまく吸収できる「適応力」のあるシステムが実現できる。ブランドは、そのように語っています。
ペースレイヤリングはこのように、専門分野の境界や、マクロとミクロの視点を越えて、さまざまな発想や思考のフレームワークとして応用されていったのです。
変化を続けるモデルの現在
2015年1月27日に、ブランド本人があらためてペースレイヤリングの概念について語るというイベントがサンフランシスコで開催され、その模様をライブ中継で見ることができました。
このイベントでブランドは、ペースレイヤリングが自分一人の頭のなかで構築され固定されたモデルではなく、先人の知恵と同時代の感性を受け入れて生まれたものであること、そして現在でもいろいろな人たちにアップデートされていることを語りました。
『How Buildings Learn』を出版してからも、このモデルについて考え続けていた彼は、以下の図に赤字で書き足されたような、新たなポイントを見出したそうです。
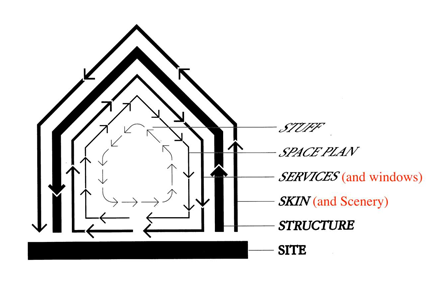 [図3] ブランドが赤字を入れたモデル
[図3] ブランドが赤字を入れたモデル
一般的には「外装(Skin)」の一部とみなされる「窓(windows)」が、「設備(Services)」と同じくらい早いペースで変わる要素だということ。また、建物の周囲の景色や、その中での建物自体の見え方という「景観(Scenery)」が、「外装(Skin)」と同じくらいのペースで変化する重要な要因であることに、後から気づいたと語りました。
ダフィーのモデルに含まれていた「景観」は、建物内部の「場面設定」や「舞台装置」のような意味で、ブランドのモデルでいう「空間計画」に相当していましたが、ブランドはもっと一般的な意味での景観を重視したことがわかります。建物も人間と同じく、自らの環境と影響を及ぼしあいながら生きていくものだという考え方が、そこに込められているように思います。
また彼は、図2の文明社会のモデルを構想していた頃に、ブライアン・イーノと語り合いながら描いたアイデアスケッチを見せてくれました※4 。
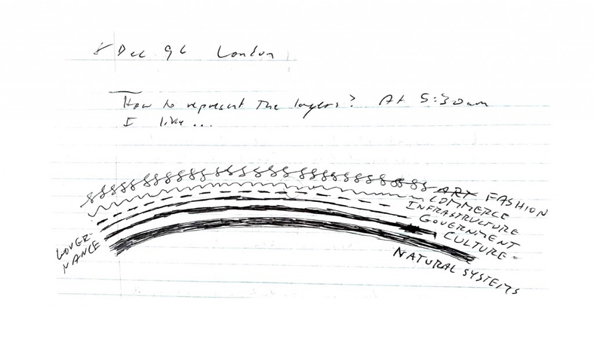 [図4] ブライアン・イーノと語り合いながら描いたアイデアスケッチ
[図4] ブライアン・イーノと語り合いながら描いたアイデアスケッチ
元々は「アート(Art)」だった一番上のレイヤーは、イーノの熱い要望によって「ファッション(Fashion)」に変更したのだそうです。また、「政府(Government)」という言葉が、より概念的な「統治(Governance)」に差し替えられたことがわかります。こうした試行錯誤を経ながら、文明社会全体を捉えるモデルとしての精度が高められていったのでしょう。
ペースレイヤリングは元々、建物という無機的な構造体を「有機的存在」として理解するためのモデルとして生まれました。しかし時の流れと共に、それは単なるモデルではなく、分野を超えて幅広い影響を及ぼす「思想」へと発展してきたのです。
ペースレイヤリングから生じる「剪断力」
実は、図1で示した基本モデルのキャプションに、ペースレイヤリングをより深く理解するためのヒントがあります。「Shearing Layers of Change」— すなわち「剪断(せんだん)する変化のレイヤー」。この一見わかりにくいタイトルは、ペースレイヤリングがもたらす「適応力」とは異なる、もう一つの力を知るための鍵となるのです。
剪断あるいはシア(shear)とは、物体や流体の内部の任意の面に対して平行方向に力を作用させ、それを切断することを意味します。たとえば、はさみで何かを切ることができるのは、2つの刃がすれちがう時に、この「剪断力」という一種の破壊力が生じるからです。ブランドはそのキャプションで、こう述べています。
それぞれの要素の変化率が違うせいで、建物は常に自然崩壊の過程にある。スチュアート・ブランド『How Buildings Learn』
レイヤーとレイヤーとの摩擦は、必然的に「剪断力」を生じさせることになり、それが建物を脅かす潜在的な破壊力となり得る。キャンベルとファーストも、前述の論文でその点に注目しています。ペースレイヤリングは、決して「安定性」や「永続性」を保証するものではなかったのです。
原書のイラストは、各レイヤーの中を流れる矢印や、レイヤー名の傾きの角度が視覚的に示しているように、その建物がまるで安定性に抗するかのような絶え間ないダイナミズムの中にあることを示しています。建物という一見スタティック(静的)なものが、「時間」という要因を取り込むことで、実はきわめてダイナミック(動的)なものとして捉えられるということ。それも、このイラストが伝えようとするペースレイヤリングの本質です。
つまり、「有機的存在」となるあらゆる構造体は、時間の経過による変化を免れることができず、剪断の危機にさらされているのです。しかし、先のキャンベルとファーストの論文では、レイヤー間に生じる「剪断力」について、新たな見方を示しています。
剪断を乗り越えるレジリエンス
キャンベルとファーストは、「剪断力」が単なる破壊力ではないことを示す手がかりを、生態学の分野におけるレジリエンス理論の中に見出しました。自然によってつくられている生態系というシステムは、それなりの安定期を経るうちに、時々システム全体を揺るがすような、前例のない突然の変化に見舞われることがあります。たとえば、洪水や嵐による災害や、特定の生物の異常発生などは、確率的に必ず起こる自然現象です。それでも自然そのものが滅びないのは、そのような変化のショックを受けても、やがて復元・回復する力が備わっているからです。1970年代頃に、生態学者たちはそのような力を「レジリエンス」と呼び、研究の対象とするようになりました※5 。森林伐採や乱獲、大気/海洋汚染など、人間が自然に及ぼすショックがますます大きくなっていた当時、破壊された自然を元の姿に戻すための新たな考え方として、「レジリエンス」の理解と応用を目指すレジリエンス理論が生まれたのでしょう。
レジリエンス理論は、そのような変化が生態系を不安定にするだけではなく、多様性や柔軟性を保つために役立つことにも注目します。生態系が長期的に存続するためには、安定した状態を保つことと同じくらい、変化がもたらす不安定な状態を受け入れて、そこから回復することも重要とされるのです。
キャンベルとファーストは、そのレジリエンス理論が情報環境にも応用できることを示すために、従来のトップダウンなタクソノミーと、当時増えつつあったボトムアップなフォークソノミー※6 の関係を例にして、その両方が支え合えば、情報システム全体のレジリエンスが高まると主張したのです。
ペースの速いレイヤーは独自性や新たな試みを、ペースの遅いレイヤーは持続性や節度を生み出す場となります。上からの統制と下からの創発とをバランスよく実現しながら、持続性の高いシステムを作り上げていくというそのアプローチは、ユーザーコンテンツの生成を促すためにも役立ってきました。それは時に、多数のユーザーによって形成されていく「集合知」のような成果にも結びつきます。インターネット上の百科事典であるウィキペディアは、その一番有名な例と言えるでしょう。
アーキテクチャと人間
ペースレイヤリングの構造を見いだすことができる建物や情報システムは、いずれも人間がつくり出す構造体、すなわち「アーキテクチャ」です。ブランドが作ったペースレイヤリングのモデル自体も「アーキテクチャ」の一つで、そこには多層的な時間の流れがあり、自己言及的にペースレイヤリングが生じます。変化と共に生き続けるというモデルの本質的な価値は、遅いレイヤーとして数十年に渡って持続する一方で、新たな分野への応用という速いレイヤーでは、アップデートが繰り返されるのです。
ブランドは『How Buildings Learn』の中で、建築家クリストファー・アレグザンダーの言葉を引用し、時の流れとともに建物が「人間味のある(humane)」ものになっていく理由について考えています。
(建物というものには)自分や家族、その土地の気候など、何にでもうまく応じられるように、自分自身であれこれ手を加え、少しずつ変えていきたいと思うものだ。こういう適合は、徐々に手入れを繰り返していく継続的プロセスとなる。…… 人と建物の適合は詳細で深遠であるから、個々の場所が独自の性格をおびてくる。多様な場所や建物が、少しずつ町の多様な人間情況を反映しはじめ、これが生き生きとした町を生み出す。クリストファー・アレグザンダー『時を超えた建設の道』
ブランドの言う、「人間味のある」建物とは、私たち人間のようにそれぞれがユニークであり、愛着を抱かせることさえあるような建物のことです。そしてアレグザンダーが言うように、人間は自らが作った建物やWebサイトといった「アーキテクチャ」に手を加えずにはいられないものです。そのような人間の活動が、時間の経過と同じく、「アーキテクチャ」を絶え間なく変化させ、人間自身にも似た「有機的存在」としていることを、ブランドは伝えようとしたのでしょう。
「アーキテクチャ」について考えることは必ず、そこに命を吹き込む「人間」を考えることにつながります。そして私たち人間は、自分たちの手でアーキテクチャをつくる一方、日々の生活の中で、さまざまなアーキテクチャによって考え方や行動を左右されています。人間とアーキテクチャは、そのようなインタラクション(相互作用)を繰り返しながら、一体となって変化していくのだと、私は考えるようになりました。
ブランドも『How Buildings Learn』の中で、建物という「アーキテクチャ」とそこに住まう「人間」が一体であることを、古代ローマ時代の「domus」という言葉を通じて語っています。この単語はしばしば、家とその住人の両方をまとめて指すために使われていました。建物は人間を入れるただの器ではなく、人間を保護するための皮膚のようなものであり、それらは分けることができないと考えられていたといいます。
ブランドはそれをほのめかすように、建物のペースレイヤリングのモデルに、「Soul」という“7つめのS” —— すなわち、人間の「魂」というレイヤーを足してもいいね、と書きました。私たち人間は、アーキテクチャを構成するどのレイヤーにおいても関わり合っている。そう考えると、人間の「魂」は、新たなレイヤーとして捉えるものではなく、最初からアーキテクチャに込められているものなのかもしれません。
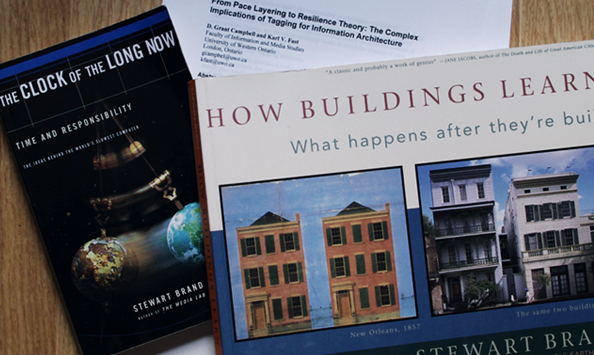
テクストへの意志
何かについて語るとき、まず、それが何なのか、何を指し示しているのかについて、よく考えなければならない。たとえ発音や文字の羅列が同一であったとしても、それが意味するものは必ずしも同一ではないし、誰しもが同一の意味を展開し、受け取れるわけでもない。
私はデザインを生業としてはいるものの、文章を書くことに関しては全くの素人である。私はスコラ学的にありとあらゆる文献を参照できるほどの知識を持ち合わせているわけではないし、世界の仕組みを解き明かしたわけでもない。それでもなお、言葉を発し活字にするということがタイポグラフィについて語るということであり、タイポグラフィという行為そのものでもあるのだろうと私は観念し、この、文章についての文章、すなわちテクストを書くに至っている。

意味と言葉
デザイナーの私にとって、デザインという言葉と同程度、もしくはそれ以上に、タイポグラフィという言葉は重要な意味合いを持っている。一部の人々には聞き慣れた言葉かもしれないが、日々の生活のなかで耳にするような一般的な言葉ではないし、それについて知らなくても、おそらく生きていくことは出来るだろう。
しかし、人々が生活する大抵の空間 —— 文化的に構築された空間において、その影響が少ないわけではない。平たく言えば、言葉や文字を用いずに出来上がった文化というものは、長い歴史を見渡してもほとんど存在しない。私は言葉や文字のような記号を用いたもの、そしてその延長にあるものはすべてタイポグラフィの範疇として捉えている。
拡大解釈しすぎだと言われればそうかもしれないが、私にとってはこの漠然とした解釈こそが、タイポグラフィの理解を容易にし、なにより実践での展開をより有機的なものにしてくれるのだ。
とはいえ、これまでタイポグラフィがどう解釈されてきたか、見て見ぬ振りするわけにもいかない。私の知る限り、この言葉の解釈に関しては、河野三男氏の『タイポグラフィの領域』に最も良くまとめられている。そこで氏は最初にこう綴っている。
本書はタイポグラフィとは何であったのか、何であるのか、そして何であり得るのかについてこだわり続けて、その言葉の意味を追い求めたレポートです。私自身の書物制作の体験や読書経験という小さな窓を通して、一つの外来語の変質の歴史を調べ、その言葉に通底する漠然とした観念を、何とか自国の言葉でわかりやすく把握しようと試みたものです。その方法は限りなく多くの解釈を収集し、その有効と思える部分を抽出し、場合によっては翻訳して、それに私見をくわえて一定の結論を導き出したものです。河野三男『タイポグラフィの領域』
20年ほど前の1996年に出版されたこの書物は、今でもその輝きを失っていない。むしろ、あらゆる言葉が浮遊し氾濫する今こそ、焦点を当てられるものだろう。このレポートではタイポグラフィを「書体による再現法」と結論づけ、それと同時に「〈タイポグラフィという言葉の領域〉つまり基本概念の設定を地道な実践の中でさらに模索し、その真髄を追求する必要があるのです」と締めている。かつての私はこの言葉に触発され、今でもタイポグラフィの銀河系の中に閉じ込められている。

タイポ/グラフィ
typography という語は、typo と graphy※1 に分解される。かつての type とは金属活字を指す言葉であったが、金属活字が使われなくなり電子活字が一般化した今日において、その解釈は妥当であるだろうか。
マーシャル・マクルーハンが言うように、電気回路技術は私たちを変えた。私たちは電子メディアを扱うとき、物質的な側面以上に、観念的な側面を強調するようになった。type は金属活字である以前に、型・形式・様式といったような意味合いを持っており、type がもつ観念は活字であることを越えて、あるいは遡って、ただの「型」となった。対して graphy は今でもよく使われるように、描く方法・形式・画法・書式・写法・記録法というような意味合いをもつ。
先に示した解釈で graphy が「再現法」とされているのは、タイポグラフィを行うのはあくまでも活字を用いて組版をする第三者のことであり、テクストの書き手はそこには含まれないという理由からであった。しかし、type の領域を活字から「型」へ、物理的制限から解き放つことによって、テクストの書き手もまたタイポグラファ(言葉の組み手)と認識される。
近代のタイポグラフィの系譜に見られる詩人、ステファヌ・マラルメや北園克衛もその好例であろう。彼らの行為は、再現だろうか、それとも表現だろうか。「世界は一冊の書物に至るために作られている」とマラルメが言うように、重要なのはそのどちらでもなく、テクストを「形成」する行為それ自体のように思える。

これらを総括すると、現代におけるタイポグラフィとは「型による形成法」と書き換えることができる。ここで「形成」するものは、フェルディナン・ド・ソシュールの言うところのシニフィエ(意味されるもの)であり、「型」というのはシニフィアン(意味するもの)である。シニフィエはイメージや概念、シニフィアンは文字や音声すべてを含んでいる。これらが表裏一体となったシーニュ(記号)の考え方の実践形こそが、来るべきタイポグラフィの姿なのかもしれない。
書くということ/読むということ
文字を書くことが発明されるまで、人間は無限の、方向もなく、水平線もない聴覚の世界、心の暗やみ、情動の世界の中に、原始的直感と恐怖をもって、生きていた。話し言葉はこの泥沼の社会的地図なのである。ところが、鷲ペン※2 が話し言葉の役割に終止符を打った。それは神話を破壊して、建築物と町を作り、道路、軍隊、官僚制をもたらした。鷲ペンは、文明のサイクルが始まったことを示す基本的な隠喩であり、精神の暗やみから光の中へ登って行く階段であった。羊皮紙のページを埋めた手が町を作ったのである。マーシャル・マクルーハン『メディアはマッサージである』
マクルーハンが『メディアはマッサージである』で示す、文明の変革についてのこの一節は、今、タイポグラフィの行為としてのテクストを書く私にとって、非常に重要な示唆があるように思う。

また、これと同様に私に示唆を与えるのは、ロラン・バルトの「意味の調理場」の冒頭である。
衣服、自動車、出来あいの料理、身ぶり、映画、音楽、広告の映像、家具、新聞の見出し、これらは見たところきわめて雑多な対象である。 そこには何か共通するものがあるだろうか? だが少なくとも、つぎの点は共通である。すなわち、いずれも記号であるということ。街なかを —— 世間を —— 動きまわっていて、これらの対象に出会うと、私はそのどれに対しても、なんなら自分でも気がつかないうちに、ある一つの同じ活動をおこなう。それは、ある種の読みという活動である。現代の人間、都市の人間は、読むことで時間を過ごしているのだ。ロラン・バルト『記号学の冒険』
書くということが文明をつくり、読むということが私を私たらしめている。これらの活動は、先に挙げたタイポグラフィという行為と切り離すことは出来ない。
先ほどは例に習って「型による形成法」としたが、もう少し踏み込んだ書き方をするのであれば、タイポグラフィとは「記号による(文明の)形成法」であると言える。
生の方法
私が生まれたとき、既にそこに字はあり、紙もあり、広告も、建築物も、映画も、音楽も、コンピュータもあった。今日、身の回りにある記号をすべて、自分自身で一から作ることは到底できないが、それらについて読むことは出来る。出来るというよりも、読まずにはいられなくなってしまっている。
もはや、私たちは読み手であるのか書き手であるのかすら曖昧な、記号に溢れた世界を生きている。それらの作用に思いを馳せながら、私はどのように立ち振る舞うべきなのだろうか。
今日も私は、タイポグラフィを、デザインを、している。テクストを、書いている。私にとってタイポグラフィとは、知らない世界を読む方法であり、また、知らない世界を形成するための方法である。知る必要のない、決して知ることのできない世界について、知ろうとするための方法である。今日、私は、そしてあなたは、何を読み、何を書いているのだろうか。

見ることは言葉よりも先にくる。子供はしゃべれるようになる前に見、そして認識する。ジョン・バージャー『イメージ — 視覚とメディア』
デザインとアートの同一性
よくデザインは問題を解決するものであり、アートは問題を提示するもので、まったく別物と言われる。しかしこれはどうも疑わしい。
なぜならデザインとアートは、同じプロセスで制作される。どちらも制作者によって目的が決まり、それを元に関係者が集められる。その上で公開される場所が選ばれ、最後に利用者/鑑賞者によって意味付けがなされるところまで、同一性が認められるのだ。
つまりデザインとアートの違いは、登場人物の経験の差異にしかない。制作者の経験によって、制作物の目的が決まり、利用者/鑑賞者の経験を元にして、意味や評価が生まれる。それらの違いはすべて、制作の〈外〉にある産業や商業によって規定されているのだ。
これはデザインとアートが、それぞれ工藝品と藝術品に区分されていた時代から、実は変わっていない。かつて工藝品が藝術品から切り離されたのは、工藝品における「有用性」の価値が高まったからである。その後も「有用性」は、デザインの基本要件であり、その残余としてアートが、芸術的(artistic)であり美的(aesthetic)であることを請け負った。
そして今もデザインは、能動として芸術的である必要はない。しかし受動としては、美的であることを常に問われてしまう。これはすべての制作物が、利用者に「使われる」前に、まず「見られる」ことに起因している。いつもデザインは、理解されるより先に、直観によって鑑賞されるのだ。だからデザインとアートのどこが違うかよりも、どこに共通性や類似性があるのかを見ていくことに意味がある。
使われること、見られること
利用者がデザインされた制作物を「使う」とき、制作物は利用者に「使われる」。当たり前に聞こえるかもしれないが、「使う」という利用者のアクションによって、制作物は「使われている」状態を感知できる。それに対して、利用者が制作物を「見る」とき、制作物は自らが「見られている」状態を知ることができない。制作物は利用者を見返すこともできず、ただ一方的に「見られる」だけである※1。
このように、アートだけでなくデザインも、鑑賞されることから逃れられない。しかし、「有用性」を基本要件とするデザインにとって、鑑賞され「美しさ」を問われてしまうのは、とても厄介なことである。なぜなら「美しさ」は、すべての人に普遍的でなければ成立しない。意見の一致を他人に要求せずにはいられないから、美的判断はどうしても議論の的になりやすいのだ。
カントによると、美的判断には二種類しか存在しない。まず個人の趣味によってなされた主観的な判断は、自分だけに「好ましい」ものである。これを「美しさ」として立証するためには、他人にその想いを伝え、共感してもらわなくてはならない。一方、客観的に判断されるときは、「一般に美しい」と表現できる。こちらは言葉で表せるため、他人と容易に共有できる。
つまり、わたしたちは「美しさ」を前にすると、おせっかいになってしまう。「美しさ」を主観的に感じるときは、自分の趣味を押し付けずにはいられず、客観的に感じるときは、つい説明しがちになる。こうして主観と客観を行き来しながら、何の疑いもなく美的判断に参加するのだ。だからわたしたちは、「使われる」デザインだけでなく、「見られる」デザインについても、深く考えなくてはならない。
見られるデザインのモダニズム
モダンデザインの時代には、機械技術を利用した大量生産が当たり前になった。それによって制作の対象が広がり、デザインは「空間と時間における構成を計画する」といった意味を深めていく。
また大量生産の時代は、大量消費の時代でもあり、消費を促すために「見られる」広告が多くつくられた。印刷技術の進歩によって、紙媒体でメッセージを伝える表現が増えていったのだ。そのひとつの結実が、19世紀後半におけるバロックやカリグラフィのリバイバルである。これは装飾書体による文字のイメージ化につながっていった。
装飾には、自然を模倣した形やパターンによって、まわりの環境に融合していく精神が込められている。だから装飾書体は、男性的な文字文化における、女性的なアプローチと言える。しかし、書体が「見られる」ための装飾を目的とし始めたとき、デザイン本来の価値である「有用性」は忘れ去られていった。理解への意志を失ったものは、もうデザインとは言えなくなってしまう。
こうした装飾書体へのカウンターは、20世紀の初めに登場する。ヤン・チヒョルトを中心にしたニュータイポグラフィ革命である。彼らは機械技術と手を組んで、石板に刻まれるために設計されたサンセリフ体を、デザイナーの個性と時代性を排除したものとして解釈しなおした。言葉の意味に文字の形を対応させるその表現は、書体をより骨格そのものに近づけた。そしてタイポグラフィは、再び絵や写真にイメージの座を明け渡し、それらと共存する道に進んでいった。
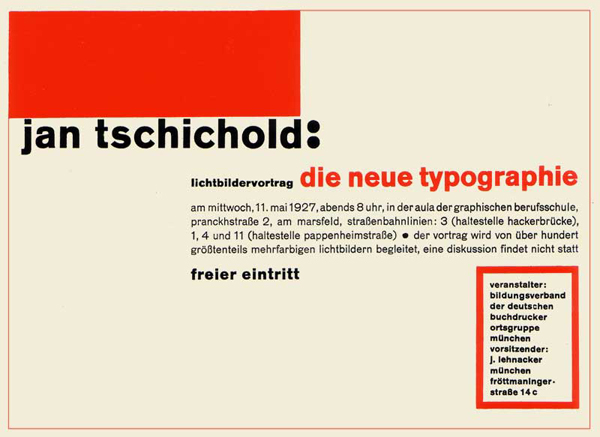 Jan Tschichold ‘Die neue Typographie’, 1928
Jan Tschichold ‘Die neue Typographie’, 1928
ニュータイポグラフィという運動は、「見られる」デザインにおけるモダニズムの代表例であろう。当時の資料を読むとよくわかるが、この頃のデザインは、アートではなくデコレーションと区別されたがっていた。そして「有用性」なきデザインと混同されることに対し、徐々に罪悪感を持ち始めていたのである。
使われるデザインの復興
21世紀に差しかかり、コンピューティング技術が発達したことで、デザインはインタラクティブ(対話型)になっていく。それに伴って、デザインの対象をオブジェクトからインターフェイスという概念にとらえなおすことが必要になった。デザインにおいて、利用者のフィードバックが身近なものとなり、権力は制作者から利用者の方へと委譲されていったのである。そしてわたしたちは、再び「使われる」という価値に立ち戻ることになり、「使われる」デザインにとって二度目のモダニズムが訪れた。
インタラクションデザインでは、利用者が「使う」ことに対して、デザインが「使われる」ことを、「空間と時間における構成として計画」しなければならない。だからインタラクションデザインは、人間の行動原理に従いながら、「有用性」が保障されることを強く目指す。
またインタラクションデザインは、その対話型システムの設計次第で、「参加型アーキテクチャ」になる。利用者が自ら制作者となり、意匠に手を加えられる仕組みを生み出せることになったのだ。こうした環境の変化が、デザインの「有用性」を脅かすようになったため、その価値はさらに求められていった。
「ユーザビリティ」とは、この「有用性」を指標にしたものである。インタラクションデザインは、「ユーザビリティ」という指標にしたがって、制作の目論見どおり「使われる」ことに努めてきた。しかしクラウス・クリッペンドルフが鋭く指摘するように、「ユーザビリティ」はマーケティングにおける説得材料でしかない。これは制作の〈外〉で語られる言葉である。デザイン本来の価値から考えると、「ユーザビリティ」はトートロジー(同語反復)でしかないのだ。
インタラクションデザインによって引き起こされた不幸は、デザインがデザインとして存在するために必要な「有用性」を、多くの人が新しい価値と考え、「ユーザビリティ」を信仰したことである。このとき上書きされてしまったのが、それまでに培われた「見られる」デザインの知見であった。
制作の内と外で語られること
制作の〈外〉でデザインが語られるとき、「絵を美しく描くことがデザインの目的ではない」といった話が出てくることがある。しかし実際のところ、「絵を描く」ことも、「ユーザビリティ」や「参加型アーキテクチャ」といった目標を掲げることも、デザインにおける変数を調整することでしかない。
「絵を描く」ような、制作の〈内〉でされる変数の調整が、色や形やレイアウトとして「見られ」、美的判断に晒されるのに対して、〈外〉の変数は「見られる」ことがない。だから、制作の〈外〉では、政治的な態度で語り、経済的な価値を問うことが目的になる。
これはデザインにおいて取り扱う素材の違いでしかない。制作の〈内〉でデザインしなければ、何も始まらないが、冒頭に述べたとおり、その価値は制作の〈外〉で規定される。この相互依存によって、デザインは成り立っている。
しかしデザインとは本質的に、生成のためのものである。そして生成とは、〈内〉から〈外〉に向かって何かが産み出されることである。制作の〈外〉に政治性や経済性があるように、その〈内〉には、わたしたちの「身体性」が関与しているはずなのだ。
その美しさの由来、身体
かつてル・コルビュジェが、人体の動作を元にしたモデュロール※2 というプロポーションモデルを提唱した。建築のモジュールを、身体の拡張として演算していくと、黄金比が求められる。この理論は、「美しさ」というものが、人間の身体に由来した間主観的※3 な事実であることを証明した。
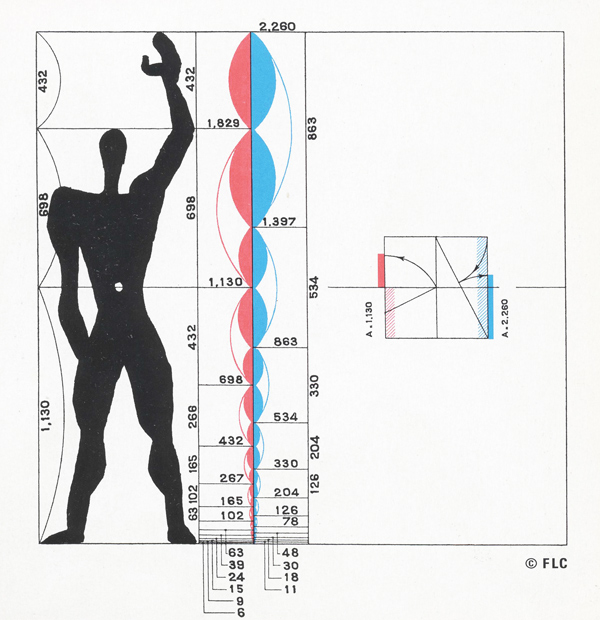 Le Corbusier ‘Modulor’, 1945
Le Corbusier ‘Modulor’, 1945
黄金比に基づいた部品による制作は、組み合わせの自由度をもたらすため、「有用性」にも貢献できる。これは、制作の〈外〉で保障されたものではなく、身体から導き出された「有用性」である。したがって、制作の〈内〉なるデザインが目的とすべきなのは、身体に寄り添うことであろう。それが「見られる」ことと「使われる」ことを同時に考えながら、「美しさ」と「有用性」のどちらも実現することになるのだから。
「美しい」という価値判断は、「好ましい」と「一般に美しい」のどちらかしか存在しなかった。そして黄金比は、主観的にも「好ましい」と思われ、「一般に美しい」とされる。つまり間主観的に「美しい」。
こうして、わたしたちの身体から「美しさ」を推し量っていくと、黄金比に行き当たる。この無理数は、わたしたちが自分の〈外〉で感じる、「美しさ」の測り知れなさ、また割り切れなさ、そこに宿る神秘が、わたしたちの〈内〉にあることを教えてくれる。つまり、わたしたちが制作者や利用者や鑑賞者である前に、人間であることが、デザインを「美しさ」に向かわせるのだ。
あらゆるものについての本
今からもう20年ほども前の1996年。カナダのデザイナー、クレメント・モックが、『Designing Business: Multiple Media, Multiple Disciplines』という本を記しました。当時のWebデザインは、デジタルメディアの進化を前に、変革を迫られていました。彼が試行錯誤しながら独自の理論や実践方法を見出してみせたこの本は、今も色あせることがありません。そこには、偉大なデザイナーであるポール・ランドの言葉が引用されています。
神と物質、目的と手段のあいだには終わりなきせめぎあいがあり、これを解決しなければならない。形と内容、形と機能、形と手法、形と目的、形と意味、形とアイデア、形と表現、形と幻想、形と習慣、形と技術、形とスタイル。 絵画、デザイン、建築物、彫刻、印刷物の美的な品質を決定するのは、こういったせめぎあいをどう統合するかによる。 Paul Rand “From Lascaux to Brooklyn”
私は、この言葉が表現しているものが、まさに今の自分にとっての「情報アーキテクチャ」であるように感じます。見えるものと見えないものの境界に立ち、それらの複雑なつながりを解きほぐし、バランスを保ちながら、デザインを形あるものにしていくこと。それは、20年以上に渡って情報技術に携わってきた私自身の経験から生まれてきた実感ですが、このたび翻訳した『Intertwingled』という本は、その思いを一段と強めてくれました。
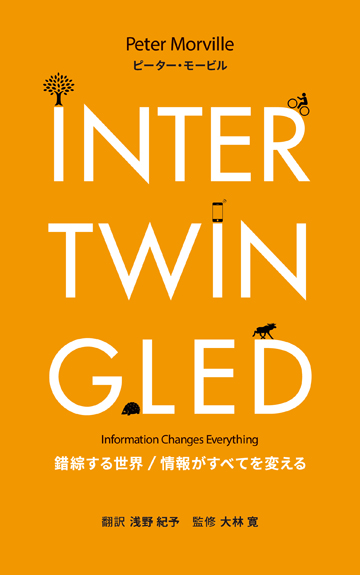
ピーター・モービルの著書を翻訳したのは、今回で3冊目となります。この本は、情報技術という領域の垣根を越えて、今まで以上に幅広い立場や多様なバックグラウンドを持つ方に伝わりそうな魅力を感じさせます。彼はこの本を、「あらゆるものについての本(A book about everything)」と表現していますが、そこに詰まっている多彩なエッセンスは、読む人が自分自身の経験と照らし合わせることで、さらに奥行きを増すでしょう。とはいえ、彼の生業である「情報アーキテクチャ」が重要な鍵を握っていることには、変わりありません。
情報アーキテクチャの歩み
冒頭に紹介したクレメント・モックの本が世に出てから数年後の1998年、ピーターは自身が起業したコンサルティングファームの共同創設者であるルイス・ローゼンフェルドと共に、『Web情報アーキテクチャ』という本を出版しました。
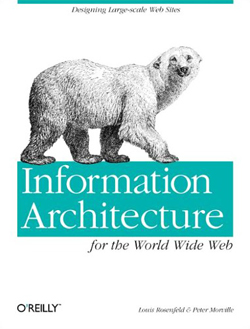
表紙のイラストから、「シロクマ本」や「Polar Bear Book」というニックネームを付けられたこの本は、現在に至るまで、情報アーキテクチャの古典的ガイドブックとして、多くの人に読まれています。
当時のインターネットでは、外見はそれなりに整っているWebサイトでも、やりたいことが思うようにできない、あるいは欲しい情報が見つからない、ということがよくありました。それは、ボタンや画像やアイコンなどの、ユーザーインターフェースとグラフィックのように、「目に見える」要素の見栄えだけを整えることに重点が置かれていたのが一因でした。体験してみて初めてわかる「目に見えない」要因、たとえば、画面上での操作がやりやすいか、検索方法はわかりやすいか、コンテンツは理解しやすいか、といったポイントは、しっかり考慮されていないケースが多かったのです。
そのような状況を変革したのが、Web情報アーキテクチャの考え方です。目に見える要素の裏にある、目に見えない「情報」を整理して体系的に組み立てること、すなわち「情報の構造設計」を行なうことが、ピーターとルイスが目指した初期のWeb情報アーキテクチャの目標でした。そして、この本の出版を大きなマイルストーンとして、情報アーキテクチャの考え方がWebデザインの世界に広まり、彼らのように「インフォメーションアーキテクト」という肩書きを名乗る人たちが増えていきました。私も、その一人です。
2000年には、米国ボストンで「IA Summit」というイベントが開催されました。 これはその後、開催都市を変えながら毎年恒例のイベントとなった、情報アーキテクチャをテーマとするカンファレンスです。冒頭で紹介したクレメント・モックもスピーカーとして名を連ねた、第1回の「IA Summit 2000」では、ピーターとルイスが揃って講演を行なっています。
面白いのは、そのイベントで二人が語ったことから、「IAの定義」についてのスタンスの違いが感じられるところです。
ここまで、「IA」という用語を「情報アーキテクチャ」の略として扱ってきましたが、「IA」は「インフォメーションアーキテクト」という肩書きの略としても使われます。基調講演を担当したルイスは、できるだけかっちりとIAを定義しようと苦心していたようですが、彼が問題としていたのは、どちらかというと「インフォメーションアーキテクト」のIAでした。インフォメーションアーキテクトは、「Webマスター」と同じで、具体的に何をする人かよくわからない。それに、ユーザーやコンテクストも情報と同じくらい大切なのに、情報だけを肩書きに入れるのはいかがなものかと、彼は心配していたのです。
一方、自分のセッションを「Defining Information Architecture — “Strange Connections”」と題したピーターは、「情報アーキテクチャ」のIAを定義しようとしたかのように見えます。でも、「何通りも定義があるのは悪いことじゃない」などと述べていたのを見ると、定義というもの自体に興味を失いつつあったのかもしれません。彼の関心は、サブタイトルになっている “Strange Connections”、すなわち、ものごとの「未知のつながり」 の方に向かっていたようでした。
それを裏付けるように、彼は2005年に『Ambient Findability』をさらに深く追究していきます。
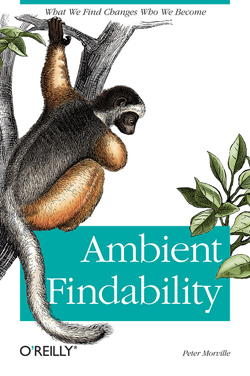
私が翻訳したその日本語版は、『アンビエント・ファインダビリティ — ウェブ、検索、そしてコミュニケーションをめぐる旅』というタイトルで、2006年に発売されました。「What We Find Changes Who We Become(何を見つけるかによって、私たちのありさまは変わっていく)」という原書のサブタイトルを、日本語版では思い切って一新しました。私はこの本を、ウェブ/検索/コミュニケーションという3つの技術が実現する「未知のつながり」の世界を探究した、著者の旅行記のようなものと捉えて、その魅力を表現しようとしたのです。
権威とのひそかな闘い
『アンビエント・ファインダビリティ』の発売後まもなく来日したピーターと、初めて話をする機会を得た私は、彼にこんな質問をしたのを覚えています。
「この本の鍵となるのは、ロングテール、検索、錯綜する世界、権威、コミュニケーションの5つではないかと思いますが、その中で一番気になるものを選ぶとしたら、どれですか?」
彼は迷うことなく、「権威(Authority)だね」と答えました。それは、私自身が心の中で選んでいたのと同じ答えでした。翻訳者としては、著者の意図を汲むことができていたように思えて嬉しかったと同時に、これから情報技術が生み出す未知のアーキテクチャが権威を振るい、私たちの生き方への影響を強めていきそうだという予感が強まりました。
その一方で、私たち人間にとって本当の権威となるのは、やはり人間という存在です。情報アーキテクチャの分野を開拓し、それに関わる人びとをリードしてきたピーターのような人物は、時の流れとともに、次第に権威的な存在とみなされるようになります。でも、権力争いを好まず、自分の道を自分のペースで歩んできたピーターは、自らが権威と化していくのを阻止したかったのかもしれません。昨年の春に、米国サンディエゴで開催された IA Summit 2014 に先立って行なわれたインタビューを読むと、彼は自分が特別な存在ではないと伝えたかったように感じられます。
そのインタビューで彼は、情報アーキテクチャへの思いを率直に語っていました。これからインフォメーションアーキテクトになりたい人へのアドバイスを聞かれた彼は、「チャールズ・ブコウスキーの『so you want to be a writer?(そうか君は作家になりたいのか)』を読むといいよ」と答え、この詩へのオマージュをこめて、こう伝えています。「大金や名声や人気を手に入れたいなら、インフォメーションアーキテクトになるのはやめとこう。抑えきれない熱意が湧いてこないなら、情報アーキテクチャを仕事にするのはやめとこう」と。そして、経験者へのアドバイスとしては、「ちょっと一息ついて、自分にとって興味があること、大切なこと、得意なことを見つめ直そう」と呼びかけました。そして彼自身は、「情報」と「文化」の関係にますます興味を抱くようになり、その「未知のつながり」が、アジャイルUXやリーン分析やレスポンシブデザインといったものを全部足したものより、大きな存在になっていくような予感がすると述べています。
実は、このインタビューや、IA Summit 2014 でのスピーチで語られたことが、その数ヶ月後に発売された著書『Intertwingled』の「予告編」となっていました。スピーチの翌日に公開されたその原稿には、この本のエッセンスが豊富に盛り込まれていたのです。本には出てこない「見知らぬ人からの親切(the kindness of strangers)」※2というキーワードを交えて彼が示したのは、世界が「錯綜」しているからこそ、私たち人間にはつながり合う可能性があるということでした。
そして、今回完成した『Intertwingled』の中では、『アンビエント・ファインダビリティ』以降も、より複雑な形で私たちに影響を及ぼしつつある「権威」に振り回されず、自分らしく生きるための知恵を、分かち合ってくれたのです。
ピーターへの「公開書簡」
IA Summit 2014 が閉会した翌日、ピーターはそのスピーチ原稿を、テキスト投稿サービスとして人気の高い「Medium」で公開しました。イベントに参加していなかった私は、そこで初めて、今回のスピーチで彼がどんなメッセージを伝えたのかを知りました。「Medium」というWebサイトに、同じく「Medium」と題した記事を投稿したことは、ジョーク好きな彼の性格をよく表しています。でもそれは、ただの語呂合わせに終わってはいません。マーシャル・マクルーハンの『メディア論』の引用から始まるその記事は、彼自身の経験を踏まえながら「メディアとメッセージ」の関係性を語ると同時に、情報アーキテクチャについて深く見つめ直すものでした。
彼の話に刺激された私は、その数日後に、同じくMediumでピーターへの「公開書簡」を書きました。「Message from a Ghost Information Architect」と題し、自分でも驚くほど一気に書き上げたこの記事を読み返すと、そのときの高揚した気分と、英語のリズムに身をゆだねることができた心地よさを思い出します。
「Ghost(ゴースト)」という言葉を含むそのタイトルは、怪しげに見えるかもしれません。私はちょうどその頃、インフォメーションアーキテクトとしての仕事にどう向き合っていくべきか悩んだ結果、なるべく物静かに、まさにゴーストのように、自分にできることを地道にやろうとしていました。一方、自分の周りに目を向けると、国内外を問わず、どんな肩書きを名乗るかということが、多くの人たちの関心の的となっているように見えました。大切なのは、自分に何ができるかであって、それを先入観なく判断してもらうには、むしろ肩書きなどない方がいいのかもしれない。そう感じていた私の心に思い浮かんだのが、「Ghost Information Architect」という言葉でした。世界中で誰も使っていないはずの、その肩書きには、まだ何の定義もありません。私はそれを名乗ることで、一般的な肩書きが必要とする定義に付いて回る「意味」を、無効化しようとしたのです。
もう一つ、私がピーターに伝えたかったのは、「文化」についての彼の見方への共感です。文化を変えることの難しさを示したピーターに共感した私は、スチュアート・ブランドの「文化が踊る大々的なスローモーションのダンスは、100年でも1000年でも続く」という言葉を引用しました。でも同時に、文化を変えるのは決して不可能ではないと伝えようとする彼らの言葉が、心に残ったことにも触れています。そして「文化」は、『Intertwingled』でもきわめて重要な要素となっています。翻訳に着手してからというもの、私はピーターの文化的なバックグラウンドの豊かさに驚きながら、さまざまな理論をインプットし、小説や詩を読み、音楽を聴き、時には汗だくになって走りながら、彼のメッセージをより深く解釈しようと努めることになったのです。
日本語版の発売にあたって
こうして、次第にその姿を明らかにしていった『Intertwingled』は、2014年8月にAmazon.comで英語版が発売されました。今回、ピーターは初のセルフパブリッシングを試みているため、日本語版も既存の出版社を経由せずに、同様のプロセスで出版します。
その発売に先駆けて、以下のページで日本語版サンプルを公開しました。
このページでは、序章と1章を含む無料のサンプルPDFファイルをダウンロードしていただけます。また、1章「自然(Nature)」の抜粋を掲載しています。
日本語版タイトルに付けた「錯綜する世界」という言葉は、『アンビエント・ファインダビリティ』の第4章のタイトルでもあります。その章には、私にとって忘れられない一節がありました。それは、経営していた会社を閉鎖し、進むべき道を模索していたピーターが、一人でヨセミテ国立公園を訪れたときの描写でした。
頂上に着いた時、かつて見たことがないほどの息をのむような絶景が広がる中で、自分が一人ぼっちであることに気づいた。私はしばらくそこに座り、シエラネバダ山脈の美しさと静寂を楽しんだ。それからポケットに手を突っ込み、携帯電話を取り出して、母に電話をかけたのだ。テストテスト、聞こえるかい?ピーター・モービル『アンビエント・ファインダビリティ』
感情を抑えて綴られたこの文章に、私は強く心を打たれたのでした。そして、自然の雄大さに圧倒されながらも、彼が手にしていた小さな「技術」の結晶が、どんな意味を持っているかを、あらためて実感したのです。
「技術」が進化し、私たちがそれを自分の一部のように利用することで、「技術」と人間の「錯綜」は、ますます深まっています。でも私たちは、文化や自然という、もっと大きな「錯綜」した環境の中で、生かされているのです。「技術」がもたらす脅威に晒される一方で、確実にその恩恵を受けながら。
アンビバレントな存在である「技術」と共に、どう生きるかを考えていくことが、『アンビエント・ファインダビリティ』で示された、私たちの終わりなき「旅」だったのです。
その場面から、ずいぶん長い月日が経ちました。今回のピーターの旅も、アイル・ロイヤル国立公園という厳しい自然に囲まれた場所で、一人立ち尽くすところから始まります。『Intertwingled』で、さらなる「未知のつながり」を探し求めるピーターを追いかけて、みなさんも旅に出てみてください。
日本語版についての付記
2015年1月30日発売予定の日本語版は、電子書籍(Kindle本)のみでの発売となります。より多くの読者の方に気軽にお読みいただけるよう、印刷版の同時発売を行わないことでコストを削減し、価格を大幅に抑えました。日本語版については、印刷版の発売は未定となっておりますので、あらかじめご了承ください。
千葉シティの憂愁
港の空の色は、空きチャンネルに合わせたTVの色だった。「別に用(や)ってるわけじゃないんだけど ──」と誰かが言うのを聞きながら、ケイスは人込みを押し分けて《チャット》のドアにはいりこんだ。ウィリアム・ギブスン『ニューロマンサー』
サイバーパンクの幕開けを告げたサイエンスフィクション小説『ニューロマンサー』は、こんな書き出しで始まっている。空想のコンピューターカウボーイは、未来の「複雑な世界」に翻弄されることなく、現実をサーフィンしていたようだ。
今から30年前に書かれた未来には、まだ60年代のサイケデリック文化の香りが漂っていた。かつてサイケデリアのグル的な存在であったティモシー・リアリーも、サイバーパンクについて、こんな予言を残している。
コンピューターはLSDなどの幻覚剤に取って変わる。Cyberpunk(サイバーパンク)は 実際のところPsyber-Punkであると。
サイケデリック文化では、さまざまな中央集権からドロップアウトした若者たちが、自分の幻想を「デザイン」することに価値があり、そこからDIY精神やコミュニティ志向、また『ホールアースカタログ』のような知のインデックスへの欲望が生まれていった。
そしてサイバーパンクの文化も、メインフレームによる集中処理への反発が始まりである。その精神を継承した若者たちが、自作したコンピューターを使い、サーバースペースのコミュニティを通じて、情報のインデックス化を進めていった結果が、現在わたしたちが利用しているインターネット環境である。ただしその価値は、幻想ではなく、現実を「デザイン」して選び取ることに変わっていった。
リアリーの予言が重要なのは、サイケデリアとサイバーパンクという二つの文化において、「意識の拡張」という共通の目的を明らかにしたからである。『ホールアースカタログ』の創刊号で、ノーバート・ウィーナーの『サイバネティクス』が、「意識の拡張」をもたらすツールとしてレビューされていたのも、偶然ではないかもしれない。
セットとセッティングの弁証法
幻覚剤を利用した経験によって、あらゆる人の「意識が拡張」して、精神が変容すれば、世の中をひっくり返すことができる。そんなことを夢想していたサイケデリアの時代に、リアリーが提唱し、ヒッピーたちの間で口承されていた、こんな知恵がある。
経験は「セット」と「セッティング」によって決定される。
ここで言われる「セット」とは、その人の個性や気分などの内的要因で、「セッティング」とは、天候や雰囲気などの環境、他者との適性、世論などの、外的要因を指している。つまり経験とは、媒介するもの以上に、わたしたちが置かれた状況に影響を受けるものだと考えられていた。これはサイケデリックな経験でなくとも、同じことが言えるように思える。
「セット」と「セッティング」のように、自分の内と外を分離して考えるのは、わたしたちが習慣的に主体というものを見立てていることに起因する。そのせいで自分と世界の間には、「境界」のようなものが設定される。サイケデリックな経験は、それをより強化するのかもしれない。
しかしこれはあくまで見立てであり、わたしたちが主観的なフレームで物事をとらえるために、空間を分節化して考えているにすぎない。確かなのは、「境界」によって主体の居場所を確保することで、わたしたちは初めて「意識の拡張」を感じられるということである。
そしてサイケデリアとサイバーパンクが地続きであれば、この「セット」と「セッティング」という知恵も、「複雑な世界」と呼ばれる場所を「デザイン」するのに、応用できるのではないかと考えている。
見えない都市の図と地
東方見聞録を幻想文学に仕立てた、イタロ・カルヴィーノ『見えない都市』の結末で、主人公のマルコ=ポーロが、世界という地獄に苦しまない方法について、こう語っている。
第一のものは多くの人々には容易いものでございます。すなわち地獄を受け容れその一部となってそれが目に入らなくなるようになることでございます。第二は危険なものであり不断の注意と明敏さを要求いたします。すなわち地獄のただ中にあってなおだれが、また何が地獄ではないか努めて見分けられるようになり、それを永続させ、それに拡がりを与えることができるようになることでございます。イタロ・カルヴィーノ『見えない都市』
ここには、「複雑な世界」と「意識の拡張」の関係が、見事に描かれている。なぜなら、地獄をやりすごす「第一のもの」は、「複雑な世界」に取り込まれることであり、「第二のもの」は、それに「対抗」する手段としての「意識の拡張」と、言い換えられるからである。
しかし実際は、幻覚剤やメディアによって「意識の拡張」が起きると、その比喩のとおり、わたしたちは気を大きくする。その結果として、幻覚剤の場合にはバッドトリップを、メディアの場合には感覚麻痺を、引き起こす可能性が高まる。
このように、「意識の拡張」と主体の喪失は、同時に起きている。わたしたちの意識と「複雑な世界」は、その「境界」において相互浸透している。だからわたしたちは、「複雑な世界」に「対抗」するために、「意識の拡張」を目指してしまうのではないだろうか。
もちろん「意識の拡張」とは内部から感じる印象で、「複雑な世界」は外部の景色であり、ただ視点を変えているにすぎない。しかし、はっきりとした実感を伴っている。つまり、わたしたちは意識によって、世界の「図と地」を反転させながら、世界を解釈し続けている。
生命システムとアーキテクチャ
生命をシステムとしてとらえたとき、「複雑な世界」になっていくことは、自然の摂理である。わたしたちの外部にある自然は、放っておけばエントロピーが増大して、無秩序に近づいていく。そこでわたしたちが生きていくためには、できるかぎり内部のエントロピーを小さくして、平衡状態をつくらなくてはならない。
言わば、自然に「対抗」して、「退行」していくこと。「退行」とは退化ではなく、自分なりの秩序を自然から選び取ることであり、生命として進化を遂げることを意味している。
この理屈にしたがうと、システム開発において、安定性や安全性を目指した標準化を行うのは、「複雑な世界」から単純な空間を見出し、内部に閉じ込めて「退行」させるためである。さらにそのシステムが拡張されていくと、また内部に複雑化が生じる。そうするとわたしたちは、またしても「境界」によって内部を分節化しなければならなくなる。
これは「アーキテクチャ」における条件のようなものなのだから、いろんな場所にシステムが構築されるたびに、「アーキテクチャ」のエントロピーは増大し続けていく。その様子は、自然が複雑化していくことと何も変わらない。
このように「アーキテクチャ」は、恣意的な人工物でありながら、「複雑な世界」を模倣する。システムの内部は、「境界」を通じて、外部の「複雑な世界」と相互浸透している。だから「アーキテクチャ」はエコシステムとして、世界とわたしたちの流動性を維持しなければならない。逆説的ながら、これが「アーキテクチャ」が必要とされる理由である。
デザインによる意識の拡張
「デザイン」されるべき場所。「意識の拡張」と「複雑な世界」が拮抗している場所。わたしたちの内と外を隔て、「アーキテクチャ」によって分節化される「境界」とは、「インターフェイス」のことである。
そこでわたしたちは、メディアによる「意識の拡張」を起こし、「複雑な世界」と価値を交換し、秩序を見出し、個性を獲得しながら、生き永らえている。これはマクルーハンの言う、メディアが「図と地」の間(medium)にあるという話にも一致する。
そこで「デザイン」は、「図と地」というゲシュタルトの関係に、意味を与える。そしてわたしたちに、「対抗」としての「意識の拡張」と、「複雑な世界」への「服従」を、選択肢として差し出す。
そのとき選択されるべきなのは、間違いなく生に向かう「デザイン」である。世界に「対抗」し、自身を「退行」させ、新しい秩序とユニークさによって、生きのびるための「デザイン」を、つまり「意識の拡張」を、目的にしなくてはならない。
「インターフェイス」における内と外の差異は、「デザイン」におけるコントラストやリズムに反映される。「デザイン」は、そうしたゲシュタルトと律動の配置であり、要素と空間の関係、言葉と沈黙の間のメッセージ、意味と無意味の差異として現れる。
千葉シティの空の「デザイン」は、わたしたちの「セット」と「セッティング」によって、その印象を変える。ハイなときもあれば、バッドなときもある。だから「複雑な世界」の空の色は、いつも移ろいやすい。わたしたちが「意識を拡張」させる場所は、そのことを前提にして「デザイン」されなければならない。
テクストとは、その中で読者が猟師となる森である。 ベンヤミン『パサージュ論』
「ÉKRITS / エクリ」というディスコースの森を散策するための道しるべに、いくつかタグを設定した。タグが指し示すのは、明確な分類ではなく、意味における調和と対比。だからコンポジション(構成)というよりコンステレーション(星座)ぐらい曖昧なものとして配置している。

まず真ん中に置くのは、「ÉKRITS / エクリ」の主題となるデザイン(design)。
わたしたちはデザインを、アーキテクチャ(architecture)に内包され、経験(experience)として出会うものと考えている。経験はわたしたち自身のものであり、アーキテクチャはわたしたちの経験と記憶が寄せ集められて体系化されたもの。これら二つはデザインに相対的な視点を与えてくれる。
またデザインの過程では、実践(practice)によって経験が生み出され、経験によって実践が可能になる。そして経験が累積された結果として、思想(thought)が築かれる。だから実践と思想はユニークなものであり、「ÉKRITS / エクリ」では方法(method)や理論(theory)よりも重要なものとして取り扱っていく。
デザインは、わたしたちが生きていくのに不可欠な、コミュニケーション(communication)という活動に向かう。わたしたちはコミュニケーションによって、文化(culture)と社会(society)を形成する。この二つは、時を超えて、人間とともに歩み続けてきた。
どれだけ季節が巡り、どんなに環境が変わろうと、わたしたちが人間である限り、生来的に「人間のためのデザイン」が行われる。だから人間(human)はタグとして不可視なものにした。わたしたちはデザインを、人間と環境の相互関係に介在するものだと考えている。
ギリシア哲学の時代から言われるように、人間が環境から見出すものが科学(science)で、人間が環境に生み出すものがアート(art)である。これら二つの活動は、教育(education)という営みによって、世代を越えて引き継がれ、わたしたちを育ててきた。
そしてデザインを生成させるのはテクネー、つまり「人間の手による技術」の現在形であるテクノロジー(technology)である。デザインによって生成されるものはメディア(media)となり、メディアと人間の触れ合う場所がインターフェイス(interface)になる。
わたしたちは、インターフェイスより高い身体性を備えたデバイスなどの人工物(artifact)によって、さらに主観的な世界を広げていく。そのときインターフェイスはコミュニケーション論、人工物は存在論の側にある。
以上の連なったスペクトルから、8つの色を抜き出して、パレットに置いて名前を付けた。

「ÉKRITS / エクリ」では、これらの色をパレットから取り出し、言語としてカンバスに塗りつけていく。そしてこの完成することがない絵は、「ÉKRITS / エクリ」の表象となっていく。
文は人なり。わたしたちはこの格言に同意する。ただし、すこし言葉を追加するという条件付きで。「文はその宛先の人なり」。この格言ならわたしたちが提起してきたあの原則にも当てはまるはずである。わたしたちはこう述べてきた。言語において、わたしたちのメッセージは〈他者〉からわたしたち宛てに到来する。差出人と受取人が入れ替わって。 ジャック・ラカン『エクリ』序文