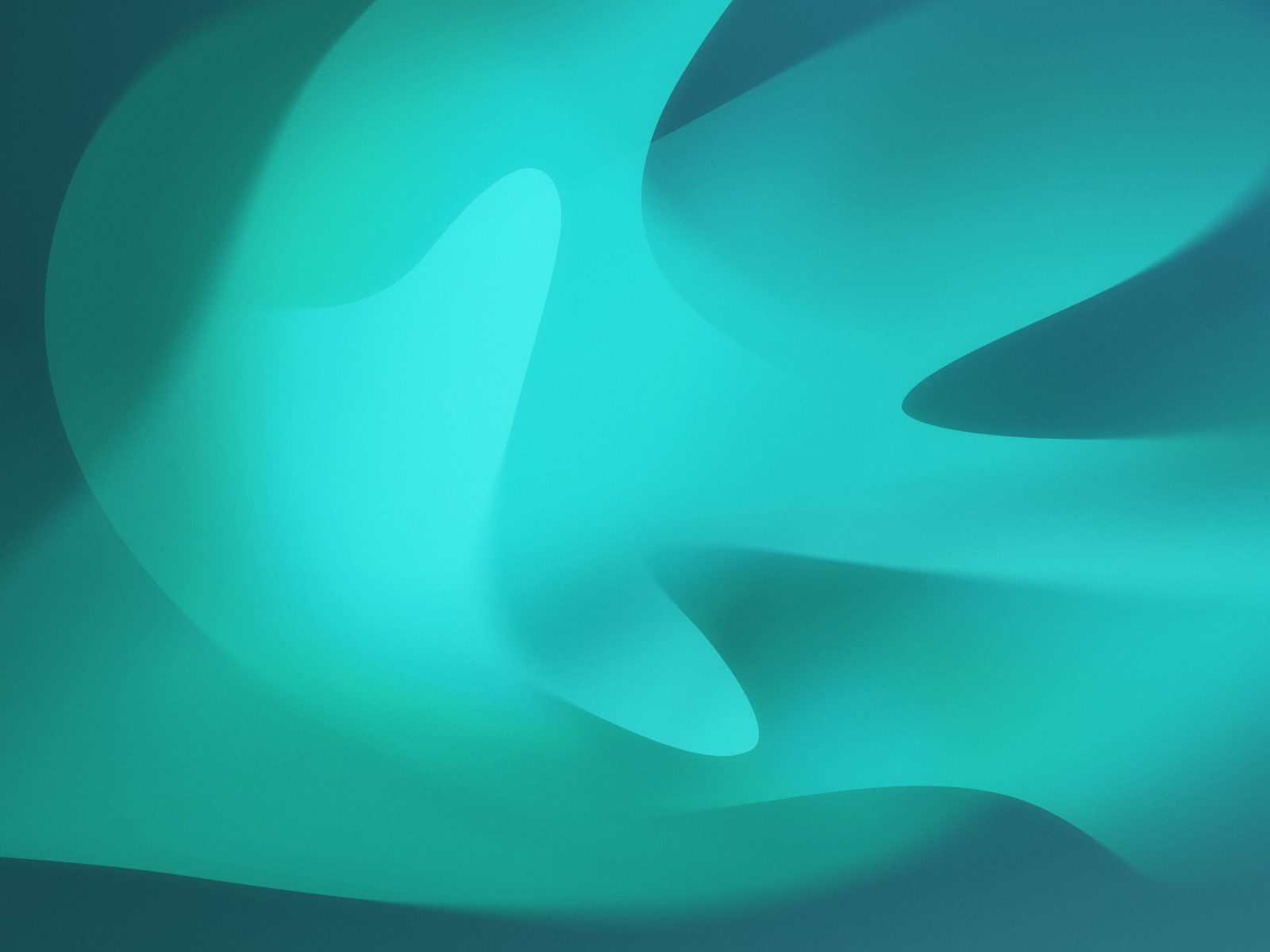デザインについて、そもそもどのように考えたらいいだろうか?
私たちはふだん当たり前のように「良いデザイン」とか「悪いデザイン」とか言っている。そこで言われている「良さ」や「悪さ」とは、いったいどういうことだろうか? それは第一に、デザインがデザインされたものの「目的」に適っているかどうか、という意味で、とりあえずは理解できるだろう。つまり「良い」デザインであるためにはまず、製品や建造物などが、そこで目指されている用途や目的に沿って、忠実に設計されている必要がある。目的に背くもの、使いにくいものは、良いデザインではない。当たり前のことだが、このことが意味するのは、デザインとはあらかじめ設定された何らかの目的を実現するための「手段」であるということである。
と同時に、これまた言うまでもないことだが、デザインには美的な側面がある。「良い」デザインとは、ある目的を実現するという条件を満たしながらも、その意図があからさまに見えたり、説明的であることはあまり好まれない。むしろ既成観念を破る驚きとか、先入観にとらわれない奔放さ、スマートさや機知、といったものが高く評価される。その意味で、デザインは一見自由な活動のようにみえるかもしれない。だがよく考えてみると、この美的な意味におけるデザインもまた、それが提供者の知性や趣味の良さを表現し、それによってユーザの賛同を得るという目的からするなら、ひとつの「手段」であることには変わりはない。
これら実用的側面と美的側面とが実際に合致するにせよしないにせよ、「手段」としてのデザインの意味は明確である。そこには、デザインをそもそもどう考えたらいいかというような根本的疑問は生じない。そしてこの意味でのデザインの問題については、ぼくはその実際的な重要性は理解できるけれども、あまり興味がないし、言うべきことも少ない。だから今ここで、デザインとは何か? などと問いかけ、このような文章を書こうとしているのは、そうではないデザインについて、考えようとしているということである。それだけがぼくにとって、考えるに値するデザインの概念なのだが、それをいったいどんなふうに説明したらいいだろうか。正直ちょっと途方にくれているのである。
というのもそれを説明するためには、常識からするとかなり遠回りで大げさと思えるかもしれないことを、言わなければならないからである。けっして難解な話ではないのだが、ゆっくりと余裕をもって読んでくれる人にしか通じない話なので、話す相手に対して少し慎重でなければならない。そこから実務的なデザインについて何か有益なことが学べると期待して読むような人は、もしかすると怒り出すかもしれないからである。けれどもこのテキストをここまで読んでくれた人は、たぶんそれを理解する余裕を持つ読者であると信じるので、書き進めることにしたい。
まず考えてほしいことは、デザインには限りがないということである。たとえデザインが何らかの目的のための手段だとしても、この手段−目的の連鎖には、原理的に終わりがない。たとえば製品や建造物のデザインは、もっぱらそれらを使う個人の好みによって決まるわけではなく、それを取りまく組織や集団の目的に深く関わっている。さらに、それら組織や集団は、より大きな社会制度とそれが目指す目的に従っている。それらはさらに、国家そのものや地球的な共同体の目的へとつながっており、この連鎖は究極的には人間の生そのもの、人類の生存それ自体の目的性へとたどり着かざるをえない。まるで人工知能研究における「フレーム問題」※1のように、たった一個の製品のデザインには、この世界そのものをどう理解するかということが、潜在的には含まれているのである。
そんな大げさな、と思われるかもしれない。けれども私たちがごく日常的な意味で「良いデザイン」「悪いデザイン」などと言えるのは、そうした意味と目的の連鎖を便宜上適当なところで —— たとえば製品の販売促進をとりあえず目標とするといった仕方で —— 切っているからである。もちろん実際的には、そうした便宜上の切断は仕方がないことであり、そうしなければ期日までに完成させることができなくなる。けれどもここでは、そうした実際的な事情は括弧に入れて、原理的な事柄を考えてみたい。原理的な意味でのデザインには、この世界や人間の生をどう考えるべきか? という哲学的な問いが含まれている。いや、含まれているというよりもむしろデザインそれ自体が、原理的な意味では哲学的思考のひとつの形態であると言っていいのである。
スピノザ『エチカ』を通して、デザインの完全性について考える
『エチカ』第4部「人間の隷従あるいは感情の力について」の冒頭でスピノザは、あるものが「完全」あるいは「不完全」であるとはそもそもどういうことか?という問題について考えている。この『エチカ』という本はそのタイトル(Ethica、倫理学)からすれば、人間の生き方を語る本のように思えるが、最初から読み始めると「神」や「実体」や様々な形而上学的概念をめぐって古典幾何学のような論証が続き、それにウンザリする人も少なくない。だがこの第4部は、人間がいかに感情の支配から自由になりうるかを主題としており、その意味ではいちばん『エチカ(倫理学)』らしい箇所だと言える。その冒頭に「完全性」についての議論があることはとても重要なことだと、ぼくは思っている。
あるものがより「完全」であるということは、今の私たちの文脈で言えば、それがより「良いデザイン」であると言い換えてもいいだろう。実際デザインを「良い」と褒める時、私たちはそれが「完全である」「完成されている」と言うことも少なくない。さて、そこでのスピノザの議論は、ぼくなりに要約すれば次のようなことである。
ある人が、快適に居住するための家を作る場合、その目的を理解する人はそこで作られたものについて、それがより「完全」である、あるいはいまだ「不完全」であるなどと言う。それは人々が「家」という一般的観念を共有しているからである。意図をもって作られた人工物に対して述べる場合、それは当然のことであるが、人間はまた、自分が本当はその意図を知らない自然物に対しても、しばしば「完全」だとか「不完全」だとか判断したりする。けれどもスピノザにおいては、自然(スピノザにとってそれは「神」と同じなのだが)は目的を持たず、したがって自然物にはそれが作られた目的、すなわちその形態が目指しているような一般的な観念はない。にもかかわらず私たちは「自然」について、それがあたかも目的を持つかのように —— 言い換えれば「神」について、それがあたかも人間と同じく完全な制作物を作ろうとするかのように —— 語ってしまうのである。つまり自然物を人工物に置き換えて理解しているわけである。
これは錯誤である。自然の作動には目的はなく、だからどんな自然物も、より「完全である」とか、いまだ「不完全である」などと言うことは本来できない。つまり原理的な意味では、自然には「良いデザイン」というものは存在しないのである。けれども私たちはしばしば、自然の作り出す驚異的なデザインに、驚嘆しているのではないだろうか? 生物の身体の驚くべき形態、生物活動が作り出す様々なパターン、さらには悠久の物理科学的運動が地上や宇宙に刻み出す驚異的な形。けれどもスピノザに従うなら、それらは私たちが自然を擬人化することで現れるものであり、そうしたデザインの完全性は自然それ自体にではなく、私たちの認識の中に生じるものにすぎないということになる。
もう少しだけ、スピノザにつきあってみよう。多くの西洋近代哲学とはまったく異なり、スピノザにおいては理性や精神は自然と対立しない。だから人間や人間の作り出す社会、国家、文明といったものもまた、ある意味では自然の一部にすぎない。社会、国家、文明といったものに何か客観的な「目的」があるかのように感じられるのは、人間の認識が限界付けられているからにすぎない。人は、自分が理性的に何らかの目的を目指して行動していると信じるかもしれないが、それは人が、そのように自分を方向付けている本当の原因 —— 感情の力 —— について知らないからである。
スピノザ的世界観で、デザインはどんな意味を持ちうるだろうか?
スピノザの思想は、理性や精神に自然から独立した特権的な位置を認めないという点において、きわめて徹底した唯物論であると言える。意図や目的に特別の地位を与えないそうした唯物論的思考の中では、「デザイン」などそもそも意味を持ちえないのだろうか? ぼくはそうは考えない。それどころか、そうした思考の中においてこそ、デザインはより重要な意味を持つようになると思っているのである。
たしかに、何か特定の意図や目的を前提として、それに奉仕する「手段」としてのデザインは、そこでは意味を失うだろう。だが、手段−目的という関係が廃棄されることによって、デザインは新しい意味を獲得するのではないかと、ぼくは考えている。それは、既存の目的のための手段ではないようなデザインという理解である。言い換えるなら、何らかの思考の結果ではなくて、それ自体が思考そのものであるようなデザイン、いわば「圧縮された思考」としてのデザインの概念である。デザインをそうしたものとして理解するということは、翻って言うなら、思考を成り立たせる狭い意味での言葉、言語というものをあまり特別なものと考えすぎないということでもある。むしろ言語的思考とデザインとを、ひとつながりの連続したプロセスとして考えるということである。「デザインとは言語である」といったことは、これまでも比喩的には言われてきたかもしれないが、ぼくはそれを単なる比喩としてではなく、現実として理解している。デザインが言語であるということは、言語活動もまたデザイン的な側面を持つということでもある。
そう考えることで何が変わるのか? と問われても、答えようがない。この世界全体の見え方が変わるだけである。何も変わらないとも言えるし、すべてが変わるとも言える。哲学的思考が何の役に立つのか? という問いに関して言うなら、哲学に多くを期待するのは間違っている。多くではなく、すべてを期待することだけが正しい。