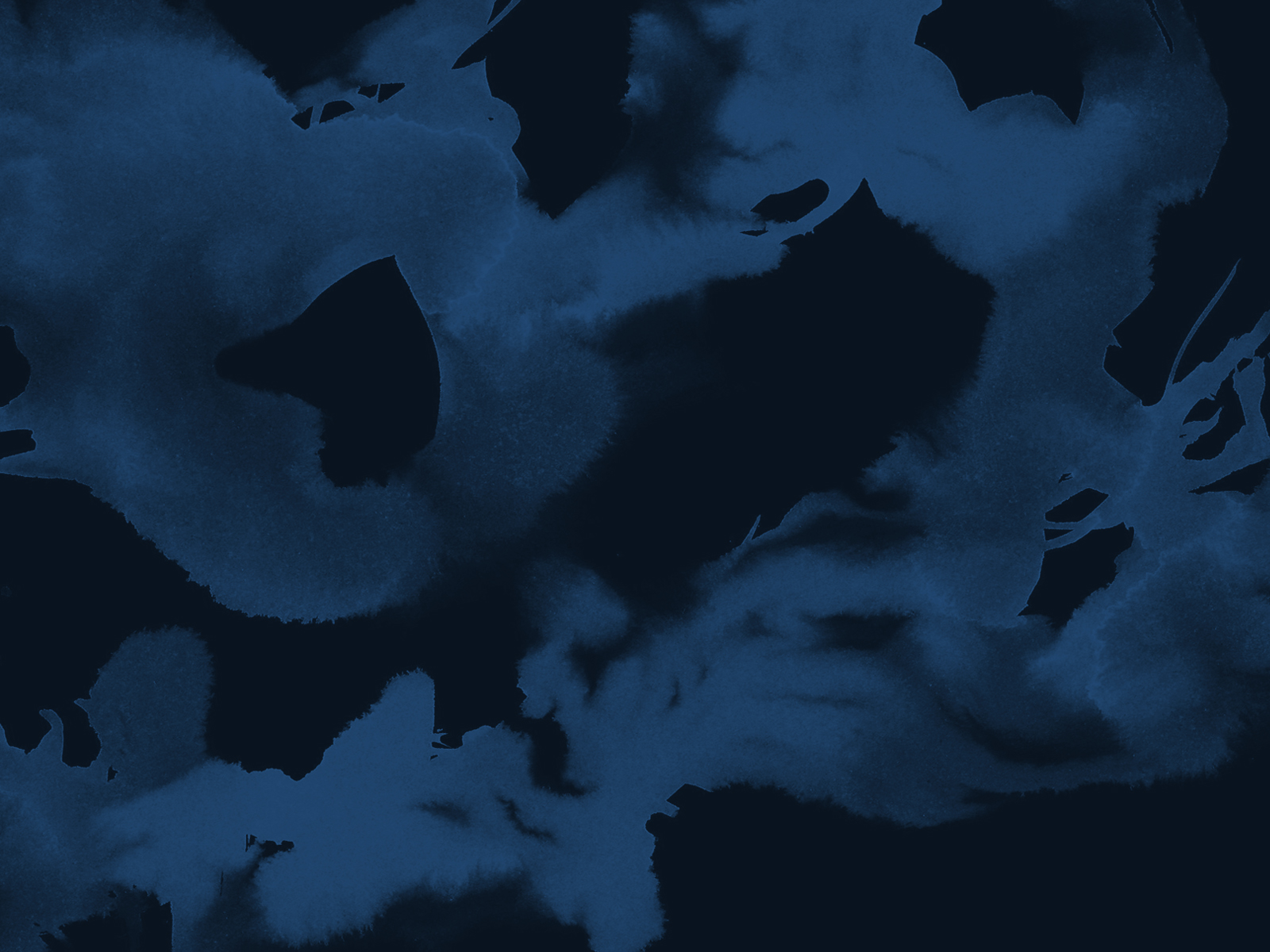唐澤太輔:
今日は神話研究を中心にして、人間と非-人間とのあり方を深く思索されている石倉敏明さんに、改めて現在の研究内容やアートとの接続などについてお伺いしたいと思います。以前、明治大学の野生の科学研究所で行われた公開研究会「可食性の人類学※1」にまつわる非常に興味深いお話をされていました。今一度この「外臓」という概念について簡単に教えていただけますでしょうか。
石倉敏明:
「外臓」という言葉を初めてお話ししたのは、ご指摘いただいた「ホモ・エデンス 可食性の人類学」という研究会の最終回です。この発表に至るまでに、実は二つの体験的なルーツがあるんですね。一つは2011年の東日本大震災の後に、写真家の田附勝さんと一緒に約1年かけて日本列島各地を旅した12回の旅の経験があります。
§
唐澤:
その旅というのは『野生めぐり:列島神話の源流に触れる12の旅※2』に載っている旅のことでしょうか。
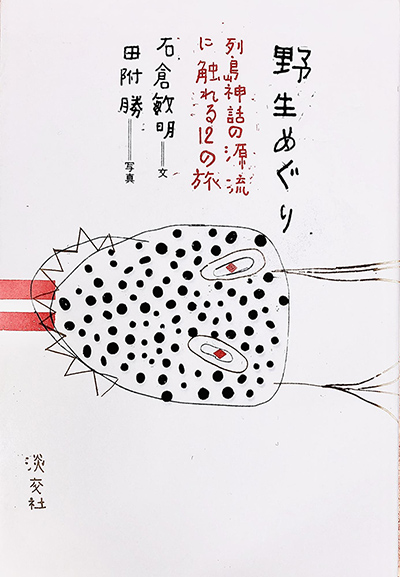

石倉:
そうです。田附さんと東北から九州まで一年間かけて旅をするなかで、各地で神々に捧げられた神饌だとか、死者や祖先の供養のためのお供物と何度も出会ってきました。そのとき、各地の農作物やお酒や味噌・醤油などの発酵食品、魚や動物の肉のような「海の幸」や「山の幸」をいただくことが、各地の神仏に対する信仰と不可分であることに改めて気づかされました。各地の食文化の背景を知る体験から、私たちの活動のエネルギーを支え、個々の身体を構成している「自然からの贈与」に対して敏感にならざるを得なかったのです。
なぜなら、東日本大震災の原発事故や放射能汚染の体験があったからです。当時は放射能汚染によって、東北では採集されていた山菜や魚が食べられない状況にあり、農作物や海産物に対する出荷制限もかなり残っていました。こうした経験と並行して、水俣病の発生現場でも同じような例が発生していたことを、結城正美さんの石牟礼道子論※3を通して知りました。郷土食の料理を、海や大地からの贈与としていただくという非常に古い時代から伝えられた感覚と、その贈与物が人間の社会経済活動の拡張に由来する放射能や水銀によって汚染されるという矛盾。そういった非対称の状況から自らの身体を取り戻すには、どう想像力を駆使すればいいのかを、一年間旅をしながら考えていたんです。つまり、食を通して自分の体と環境との関係をもう一度見直してみたかったんですね。
ちょうど東京から秋田に移住する時期でもありました。秋田の自宅からさほど遠くない田んぼの一角を借りて、子供たちと一緒に農作業をしたり、沢水で遊んだり、里山から山菜を採ったりするような経験も重ねていました。不耕起農法の稲作をやってらっしゃる菊地晃生さん※4が農場の一部を共有地として解放していて、市民が週末にやってきて農作業をするコミュニティをつくっていたんですね。
ある休日、お借りしている田んぼで無心に草取りをしながら、ふと一息ついて周囲の里山を見渡したときに、まるで自分の身体感覚が切れ目なく、目の前の空間や田んぼとつながっているイメージが湧き出してきました。近くの畑では山から降りてきたカモシカが歩いていて、田んぼのなかにはタニシやカエル、ザリガニなどの無数の生物が食べたり食べられたりしています。人間が食べ物として育てている作物もそこにあれば、その田んぼには無数の小動物や昆虫や植物、そして膨大な微生物が存在する。そういう多くの生物が混在するなかで、自分の身体の内側に広がる領域が外界の現実とつながっているのではないか、という思考実験をしてみたんですね。
考えてみたら、自分の体の内臓は、口と肛門を通して一つのチューブのように外部に開かれています。その内臓を、手袋をひっくり返すように拡張してみたときに、食料や他の生物とつながっている目の前の風景は、自分自身の内臓と地続きの空間と捉えられる。自分の目の前にある風景は、自分の内臓を外側にひっくり返した身体の延長として捉えることが可能なんじゃないか。「外臓」という概念を思いついたときに、そんな具体的なイメージが浮かんできました。
こうして、震災後の旅の経験と田んぼでの体験から、僕はこの地上の有限な空間の一部分が身体の内部と深く連絡しているという感覚を得ることができました。僕は大学院時代に人類学者の中沢新一先生から「対称性人類学※5」という、非常にユニークな理論を学んでいましたが、それを自分なりに理解する手がかりを掴めたように感じたのです。
この理論は、人間の思考のなかで世界の全体性を把握するような「対称性の論理」と、事物を分節して時系列に配置する「非対称性の論理」が複合的に生起している、という思想です。つまり人間の心は、時間と空間を超えていく「無意識的思考」と、世界を合理的に把握しようとする「意識的な思考」という二つの論理体系が「複論理(bi-logic)」として並行的に影響を及ぼしあっている。そうした論理が、「外臓」という言葉を通して、自分の身体的な実感として実を結んだように感じました。
自分の身体を貫く消化器系のチューブが、実は外部空間と無限に開かれた絡まり合うループを形成している。このループを「外臓」として概念化することによって、個々の身体を外界とつなぎながら、食べるものと食べられるものが共生している世界を理解するような回路が開かれるのではないか。そう思ったわけなんです。
里山や里川といった環世界の現実を、われわれ人間は皮膚や骨格といった身体の外部に広がる単位だと理解している。これを「非対称性の論理」だとすると、他方には、外的な環境のなかに存在している生物が、食べ物として身体をとおり抜けていくような「対称性の論理」が並存している。つまり自分が何かを消化して、それをエネルギーに変えていったりするような食の体験は、根本的には外臓と内臓との一種の連続した絡まり合いとして理解できる。別の視点からみれば自分の身体も、他者にとっては、外臓の一部であるかもしれない。そうやって鏡のようにイメージを映し合い、エネルギーが移行するループとして、内臓と外臓を捉え返してみたいというのが最初のアイディアでした。
§
唐澤:
自分の内臓を裏返した姿が自然なのですね。自分の身体が外界にも延長しているという感じですね。
石倉:
自分の内的自然と外的自然というものがあるとしたら、それを結んでいる様々な知覚的なインターフェースがあると思うんですね。たとえば五感を構成している様々な感覚器官は、すべて内臓という目に見えない無意識のレベルの身体につながっています。この感覚の回路は、内側に深く潜っていけばいくほど、外の空間とつながっている。この身体的な内と外との絡まり合いを意識化するような光景を「外臓」と名付けているわけです。
§
唐澤:
なるほど。内側が外に、他者につながっている。内即外、クローズ即オープンという感じで、その区別が曖昧になるところがインターフェースなのですね。
内が外になり、外が内になるとすれば、極端な話を言うと、人間が何か物を食べるってことは、結局自分の延長でもある自分自身を食べているとか、同種を食べているっていうことにもなるようにも思えます。それは一種の「カニバリズム」とも言えますか。
石倉:
はい。「外臓」という概念は、内臓的な体験を、皮膚を超えて外の環境へとつなげるときに出てくる概念です。つまり、僕らは山を見ても、山というリアルな空間を「自然」というカッコに括っている。一種の認識の閉域に入れてしまっている。でも、その山を具体的に見ていくと、様々な生き物が刻々と生を営んでいて、食べたり食べられたりするような、リアルな世界がそこには生成されています。
別の言い方をすると、様々な記号次元がそこで生起しているわけですね。人間的な記号はもちろん、それを超えたエドゥアルド・コーンが『森は考える※6』で伝えたような、様々な自己の生態系が、そこにひしめいている。そこで生きているものたちを食べるということは、実は人間を食べることと他の生き物を食べるということがフラットに同じような意味を持ってしまう危険とつながっています。喉元過ぎてしまえば、それは人間の肉であるか牛の肉であるか、それが何であるかっていうのは意識できなくなってしまう。そういう無意識の体験を自分の体の内側に抱えていて、常にカニバリズムと近いところにいる。
しかし、実生活においては、そこから理性的に遠ざかる、遠ざかっていられるかのように、自分たちを社会的な空間のなかで島のように限定された領域として囲っています。それが一種の共同体だとすると、共同体を超える流動的なエネルギーや知覚の絡まり合う次元に常に接しているはずなのではないかっていうことを、内臓の外側にあるリアリティとして掴んでみたいのです。
§
唐澤:
「島のように限定された領域として囲っている」という表現をされましたけれど、それは私たちが対象を理性的に遠ざけてしまっていて、本来的につながっているっていう事態に、分割線を引いてしまっているということでしょうか。
石倉:
そのとおりです。たとえば哲学者のデカルトは「我考える故に我あり」って言いましたけれども、たとえば芸術的な創作活動も、「我描く故に我あり」「我つくる故に我あり」を前提としてしまっている。つまり、ヨーロッパから始まった芸術のモデルで言うと、そもそもの起点となる主体はデカルト的な思考のモデルから抜け出せていない。僕はその「考える我」を、分割線以前に引き戻す作業が必要だと感じています。
「考える我」あるいは「つくる我」や「創作する我」も、無意識的にいつも何かを食べているはずです。僕らは理性的に身体的な次元を囲い混んでいるように見えるんだけど、何かを食べることによって、自分自身を外界に開き、同時に変容している。あのデカルトの「懐疑し、考える我」も、思考のエネルギーが働くためには、何か食べているはずです。食というインターフェースは、実は非常に大きなトランスフォーメーションの体験に隣接している。
§
唐澤:
非常によくわかります。「我考える故に我あり」に対して、石倉さんは「我食べる故に我あり」と「複数種世界で食べること※7でもおっしゃっていましたね。人は「我考える」という思考のエネルギーのためにも食べているわけで、その意味で「食」というのが最も基盤的なものとしてあると石倉さんは考えてるのだと思いました。
たとえば、仏教の捨身飼虎や神道の大宜都比売もそうなのですが、「食」にまつわる話が出てくる場面って、その宗教において非常に大事なことを伝えているケースが多いですよね。キリスト教のアダムとエヴァも、禁断の木の実を食べる話が極めて重要ですが、これは仏教と神道とすこし位相が違うという感じもします。
捨身飼虎や大宜都比売の話は、贈与という側面がとても強いように感じます。つまり、自分自身を純粋に捧げるという側面がすごく強いと思うんです。一方で、キリスト教の創世記における禁断の木の実を食べる行為は、人間による能動性の強さみたいなものが垣間見られる。キリスト教圏における「食」と、それ以外の場所における「食」の違いみたいなものについては、何かお考えはありますか。
石倉:
一神教の背景には、旧約聖書と新約聖書っていう二つの神話のシステムが絡み合って、そこで生まれている食の世界観がありますよね。ヘブライズムの考え方では、まさに知恵の実を食べることによって、純粋なイデアルな世界から追放されて、身体性を獲得していく。人間は、純粋に精神的な世界から追放されて、性や食といった、動物性と人間性の絡まり合う「肉」の次元、あるいは「堕落した世界」に落ちていく。しかし、こうした世界観の前提を神話学的に遡ると、エヴァをそそのかした蛇という存在は、実は古代的な知恵の象徴でもある。これはヘブライズムの神話以前の新石器時代的な、もっと古い神話につながっているわけです。
同様に日常食についての規定も聖書に由来しています。たとえば、イヴォンヌ・ヴェルディエの『料理民俗学入門※8』を読むと、やはり神が7日間で世界を創ったという神話が、フランスの農村の食事の思想として構造化されている様子が見えてきます。休息日である日曜日に人々が食べるメニューや食材の調理法、皿の数、テーブルマナーと、『創世記※9』で神が世界を創造していたとされる平日の日常食とは、区別されていて食べ方も違うんです。食材となる動物の種類も、神によってあらかじめ定められている。
だからキリスト教では、食事の前にまず創造主である一神教の神へ感謝をしてから食べ物をいただきます。それは食材となっている動物や野菜に対する感謝というよりは、それを与えてくれた神様の恩寵への感謝という意味を持っている。「一者に対する感謝」という前提があると思うんですね。つまり、食材は多様だけど、感謝すべき対象、食材を創った存在は唯一者であるっていう考え方があります。これは「一つの自然と多様な文化」という、人類学者フィリップ・デスコラが言うナチュラリズムの論理構造と同型ではないかと思うんです。
一方で、ヨーロッパ的な世界観の背景には、そうしたヘブライの神話に対して、ギリシャ・ローマの多神教的世界で生まれた別の世界観が組み込まれているようです。ギリシャ・ローマ的な古い神話は、一神教の表舞台からは姿を隠していますが、芸術的な想像力の世界では盛んに表象され、あるいは地中海のアルテミス神殿がのちにマリア信仰の拠点になったように、神話的な翻訳を経て、一神教の世界における聖母子像や聖者信仰、天使信仰といった形に偽装されていきます。実はこうした一種の神話的な異文化の翻訳システムのなかから、ヨーロッパの芸術や哲学が生まれていく。
自然は一つであるが、文化は多様である。これは言ってみれば、一神教的なヘブライズムの思想と多様な現れとしてのギリシャ・ローマの思想が折衷されている。人類学的な整理によれば、単一自然主義と多文化主義と言い換えられるでしょう。ニーチェが言ったように、近代という時代に「神は死んだ」かもしれない。しかし、その後にはヘブライズムの神が、フィジックスを支える「一者」として居座り続ける。それに対して多様な表象、多元的な価値のシステムとして「文化」が現れてきた。ニヒリズムというのは、この交代と分割以外の何ものでもありません。多文化主義とは、まさにギリシャ・ローマ的な仮象の世界として「多様性と虚構」を結びつけてきたわけです。つまり、自然と文化という二元論を背景としながら、一者と多者が結合しているヨーロッパ的なコスモロジーの体系があって、そのなかで実は「食」という体験の持っている多元性が矮小化されてきたのではないか。
僕は、こうしたヨーロッパ中心主義に対して、本当に食を多元論として語るためには、単一の自然という前提を、多自然主義的に解放していく必要があると考えています。そうすると、日本人のように「いただきます」と言って食事する習慣も、その対象は森羅万象の働きや個々の食材となっている生物群、食を提供してくれた生産者や料理人に至るまで、実は多様なものであることが見えてきます。
「食べられているもの」と「食べているわれわれ」が対峙することができるポイントは、もちろん創造主を絶対的な他者と考える神話とは別のシステムです。われわれが食べているものと、食べているものが生まれてくる環境と、われわれ食べている主体がどのようにつながっているのかということをたどっていくとき、このように思考を脱植民地化して、自然と人間の関係を別のしかたで編み直す可能性が見えてくると思うんです。
§
唐澤:
実は人間も食べられる存在であるというわけですね。だけど、私たち人間は往々にして、人間こそが最高捕食者であって、他のものが人間に食べられるということだけしか考えてない。それこそ動物園に囲われてしまっている動物は、人間によって見られる対象となっています。根本にある、人間が食べる方あるいは見る方、動物は食べられる方あるいは見られる方といった非対称な構造を問い直す必要がありますね。人間がそういう他種から食べられる可能性ということを、真剣に意識したときに、何が開けてくるのでしょうか。
石倉:
「我食べる故に我あり」という存在論的な起点からはじめると、一歩進んで「われわれもまた食べられる可能性がある」という推論が導き出されます。つまり、われわれのような肉を持った存在が、他者の「外臓」のなかで食べられる存在としてあるということから、「我食べられる故に世界あり」っていうことも反転して言える。
「食べる我」の内臓的視点からは「世界がある」ということは説明できない。なぜなら、その食べ物は、すでに世界のなかで与えられてしまっているからです。しかし、外臓的に「我食べられる」と言ったときに、複数種の次元が現れる。初めて食べられるものがたくさんひしめくモノの世界、物象の世界が見えてくる。ここが世界の世界性、食の世界性を担保している外臓の根拠であり、身体の外在性や相互性を支えている物質的次元の根拠でもある。
しかもこの物質的次元は、常に数多くの分解者という存在によって支えられている。生態学の理論のなかでは、生産者と消費者、そして分解者っていうふうに三層に分かれて論じられます。たとえば森のなかに入ってみると、直接食べる・食べられる関係にあるという生き物はごく一部で、圧倒的多数は食べられずに朽ちていく。つまり、運良く食べられて、他者のエネルギーとして活用されてもらったのはごく一部であって、食べられることなく朽ちていくものが圧倒的多数なんです。だけど、その朽ちていくものたちがどうなるのかというと、実は菌類や粘菌といった目に見えないものたち、あるいは目につきにくい小動物や昆虫に食べられる。この「食べられることの多数性」に、循環という次元の深みがあると思います。
「食べること」「食べられること」は決して「対関係」じゃないんですよね。われわれは「食べること」を、常に恋愛や性愛関係のように、二者の関係としてモデル化しがちです。しかし、これは実は「一対多」の関係を孕んでいます。しかも、この場合「多」に対峙するのは「一」を含むような生態系全体の集合としてイメージできると思います。「私はわれわれに食べられる」とでも言えるような「多数者に食べられている」という感覚。常に地球に食べられているというか、自然に食べられているというか、自分を取り囲む外臓全体に還元されていく。それによって朽ちて、自分も、大きなものがエネルギーの一部になることができる。
つまり開かれた全体性に対して、自分が食べ物になるということは、誰かと特別な関係を結ぶというよりは、もしかしたら「無駄死に」のような体験に見えるのかもしれない。しかし、もちろんそれは無駄ではあり得ないのです。ですから、菌とかウィルスとかと共生するっていう次元を真剣に考えるならば、捕食者・被捕食者の対関係を超えたところまで、食の思想を拡張しなければならないと思います。
§
唐澤:
まさにそうだと思います。朽ちていくっていうのも、実は食べられているんですよ。僕は死んだら粘菌に食べられたいと思っているんですけど、粘菌とかバクテリアが食べることによって朽ちていくんですよね。だから、人間というのは、ある特定の一者だけに食べられるだけじゃなく、食べられた後、糞尿になって排出された後は、バクテリアとか粘菌にも捕食されていく。そうやって、他の生命を、あるいは世界を支えていくっていうことだと思うんです。
そういった意味でも、捕食者と被捕食者は、一対一ではありません。一対多なんですよね。そのように、自分が食べられることが世界を支えていることにつながることを意識したり実感することが、現在は少なくなってきている。その原因は一体どういったところにあるんでしょうか。
石倉:
都市化、文明化の進展によって、われわれが直接土に還元されなくてすむようなシステムが構築されてきました。その環境では、土とつながっているという実感すら忘れてしまいがちです。これを乗り越えて、自然の循環系と人間の文明圏の循環系を接続するためには、おそらく「自己」や「身体」という概念を更新する必要があります。
グレゴリー・ベイトソンが言っているように、森のなかの生物の「自己」は皮膚を超えて存在している。その自己は、複数の身体に渡って分散することもあれば、自分の身体の内部にある様々な、たとえば細胞の一つ一つといった次元まで、実は自己が縮尺されたり拡散している。このことを踏まえて、エドゥアルド・コーンが「諸自己の生態学」という視点を出したことは、非常に革命的なことだと思っています。
この思想は、食べられる経験とも関係しています。実は自分が多数者に食べられるということは、自己が身体の皮膚のような境界では区切られないし、時間的にも個体の一世代では決して終わらないっていうことですよね。だから「複数の自己」によるアニミズムが可能になる。食べる・食べられる関係のなかで捉えられる二者の次元を超えて、実は多数者に食べられ、解体され、朽ちて土に還って、次世代の再生を準備するという次元から、「諸自己の生態学」を担保するような別の現実性が見えてくる。
しかし、アニミズムを一神教よりも遅れた原始的段階にある素朴な宗教思想であるという思想モデルを、19世紀の人類学はつくってしまっていた。こうした人類学がつくってきた前提によって、私たちはおよそ100年間ものあいだ思考を停滞させてきたのかもしれません。そのことにはっきり気づいていたのは、南方熊楠くらいではないでしょうか。今や文明圏における循環と自然界における循環を接続することによって、新しいアニミズムというか、より適切なアニミズムのモデルを提示することが可能になってきました。それをやらなければいけない時期に差し掛かって来ている、と考えています。
§
唐澤:
文明圏における循環システムと自然界における循環システム、それらをどう接続していくかは難しい問題だと思うんですけど、何か重なり合う部分ってありますか。
石倉:
本来はあらゆるシステムが重なり合っていると思います。文明圏の人工物と、自然の次元は常に重なり合っている。このことを、ネパールのサンクという町で出会ったネワールの友人は、「この世界のなかには、女神の身体と関係ないものはどこにも存在しない」と言っていました。つまり、人工物と自然物を分割しない、非二元論的な思考がネワール仏教の女神信仰を支えているわけです。このような知恵は、ネワールだけでなく世界中の先住民社会に伝えられています。ここから、自然資源に対するエコロジカルな配慮や生命倫理の感覚も継承されてきました。
ところが、私たちは資本主義が前提とする「自然の植民地化」によって、無限につながる女神の身体を人間の有限な所有物であるかのように、そして地球上の限られた資源を無限に開発できるかのように取り違えるようになってしまった。人間の文明圏を中心とするモデルに縛られてしまって、都市を取り巻くものを軽く見たり、自然を開発したり、環境を棄損してきたわけです。これが「人新世」と言われる時代の非常に大きな問題をつくってしまった。形而上学的な問題と社会的・経済的な問題のあいだに、解消しがたい大きな亀裂が生じています。ここに生じているのは有限と無限の大きなズレなのです。
§
唐澤:
人間界における人工物というのは、実はすべて自然からできているわけですもんね。だから、それぞれの人工物には、すでに自然のすべてが含まれていると言ってもいいかもしれない。これは如来蔵思想の考え方にもつながってくるものがあって、それぞれ個々の存在として生きているが、実はそれらのなかにすべての如来なる種みたいなものが含まれている。今のお話を聞いていて、そのようなことを想像しました。
また先ほどから説明されている「食べるもの」「食べられるもの」の関係に真摯に向かい合いつつ、我と汝、我と世界との関係を考えていくという話にもつながりそうです。石倉さんがイメージされている日本の歴史と仏教、あるいはそれを背景にした「共生の思想」について、もうすこし教えていただけますか。
石倉:
如来蔵思想の日本的展開を考えてみるとき、「ヒジリ」という存在が重要な役割を担っていたと思います。最初期のヒジリには二つのタイプがある。一つは行基菩薩のように、社会的な空間に介入していくタイプのヒジリ。つまり、たとえば治水や土木工事、大仏建立といった社会事業を通して、人間のために環境をよくするような、一種の人間的利他だと思うんです。同時に、自然智宗や道教の山林修行者や伝説上の役小角や蜂子皇子のように、修行のために山林に入っていく別のタイプのヒジリがいて、彼らは人間界から離れたエコロジカルな現実に触れることによって、「人間を超える」立場から利他を完成させようとします。どちらも人間と非人間の根源に、分割することのできない「如来」を胎児のように抱えている。平安時代には、その前の時代の律令仏教と山林仏教の分岐を背景に、この二つの流れがダイナミックに交わることによって、都市と山岳を結ぶ新しい思想が生まれてきました。いわゆる「本覚思想」の展開も、人間と非人間の双方に「如来」を宿すという如来蔵思想の読み替えから生まれています。
つまり、多くの人口が集まる文明的な生活圏と、山岳のアジールを背景とする修行道場とを結び、人間的利他と超人間的利他をつなぐ。これが日本仏教のプロトタイプだと思います。しかし、都市の政治権力と山岳の宗教的権力が拡大してしまうと、人間的世界と宗教的世界が分離していきます。すると、多くの祖師が比叡山から下りて、鎌倉仏教という宗教的なルネッサンスを発生させる。このように日本仏教は常に里と山の関係を背景にしていて、多様な宗派や修験道の行者たちがその媒介役を担っていた。そういう形で、如来蔵思想は日本列島に一つの大きな思想史をつくってきたのではないでしょうか。
日本列島の歴史では、こういった仏教的な利他思想の系譜と、古くから継承されているような神話の神々の世界が集合することで、いわゆる「神仏習合」という人・生物・自然・神仏の共生関係が思想化されてきたと思います。この共生関係をベースに人間と非人間の関係を見ようとすると、最初から人間だけに限定された世界が形成されいく「共同体」といったイメージで、社会を捉えることが難しくなってきます。
僕は「共異体」という概念が必要になってくると思っています。つまり、同一的な共同性が担保された純粋な社会共同体以上のモデルとしての「共異体」です。人間を取りまく世界が常に「人間以上(more than human)」であるように、日本列島の各地に形成されてきた社会は常に「共同体以上(more than community)」であったのではないでしょうか。
§
唐澤:
「共異体」という概念を最初に使ったのは、小倉紀蔵さんでしたよね。
石倉:
そうです。哲学者の小倉紀蔵さんは「共異体」という概念を、中国と朝鮮半島、極東の日本列島といった東アジア諸地域の広域共同体として概念化しました※10。かつて民主党の鳩山政権が「東アジア共同体」という理念を掲げたときにも、それに対する一種のオルタナティブとして、互いの差異を尊重する「東アジア共異体」を提起されていたわけです。
僕は2017年に、中国返還後20周年を迎える転換期の香港で「神話・歴史・アイデンティティ」について考えるアートプロジェクトで香港に滞在したとき、韓国語と日本語の通訳者からこの概念を教えていただきました。この概念を知って、僕は大きな衝撃を受けたんですが、同時にこの概念を本来の文脈から大幅に拡張してみたいという誘惑に駆られました。つまり、この概念を、歴史と神話の関係、複数種の共生圏、身体と環境世界の関係など、これまで「同一性」の枠内で語られてきた物語をハイブリッドなものに書き換えるための概念につくり変えてみたい。そう思ったんです。
§
唐澤:
「共異体」は華厳思想的という気がします。「共同体」は、同じ種のなかで、さらに同じ理念みたいなものを共有している集まりという印象ですが、「共異体」は、異種間同士の対称的なあり方、個々を単純に無化しない形での異種間の共存のあり方、つながり合いみたいなものを目指していると感じます。華厳でいう「事事無礙法界」的なものを感じるんですが、石倉さんは「共異体」と華厳とで、何かつながりを考えられてたりするのでしょうか。
石倉:
「共異体」というモデルは、個々の差異を解消することなしに、むしろ差異によってこそ個々の生命存在をつなぐことができるのではないか、という発想に基づいています。そして、そこには異なる存在論の接続を通じて、人類が蓄積してきた多種多様な科学の成果を排除せずに、どんなふうに各集団の神話やコスモロジーからも多元的な知恵を継承するか、という課題が含まれています。
人間の共同体を中心に科学を語ろうとすると、そこに一神教の遺産である「絶対的な一者」の残滓として「単一の世界」という近代的前提を抱え込まざるを得なくなってしまいます。これは人類学者のジョン・ロー※11やアルトゥーロ・エスコバル※12が「単一世界の世界(One-World World)」という形で批判してきたように、地球を人間活動の背景として一元化し、植民地主義的な開発経済の枠組みを形成してしまう。
これに対して「野生の科学」というものがあるとすれば、その視点には人間の人間性を相対化するような、多次元性の政治が関与してきます。人間の共同体が宇宙の中心にあって、人間がすべてを俯瞰して自然をつくり変えていくのではない。そういった人間中心主義的な視点から離脱して、一種の共通世界を再発見していくときに、仏教が説いている非二元論や多元論が再発見されることになります。
その内実に深く入り込んでいくためには、仏教の思想だけでなく、神話的思考や先住民のコスモロジーのように、科学的なロゴスの枠組みでは捉えきれない、「レンマ」の思考による「多元的宇宙(pluriverse)」の次元が現れてくる。このようにロゴスの物語で捉え切れないものをどう想像し、世界化のモデルとして実現していくのか。唐澤さんが一貫して取り組まれている南方熊楠研究や中沢先生の『レンマ学※13』のように、華厳思想を現代的に再発見していくことは「共異体」の現代的な問いに直結すると思います。
人類学者の大杉高司さんが「非同一性による共同体※14」、あるいは非本質主義的な「無為のクレオール」ということを提案されています。これは仏教が説いている「空の論理」や「縁起の法」といった、インドの古代宗教に対する、ブッダによる本質主義批判の問題と重なってくるのではないか、と昔から考えてきました。つまり、クレオールやハイブリッドの実相を見ていこうとする人類学的な同一性批判は、仏教的なロジックと親和性が高いと思えるのです。
このような「非同一性」が担保されないまま、人間と非人間の集合体が実体化されてしまうなら、コーンの「森は考える」という議論は森全体を実体化して「森の神」という偶像の思考を想定することになってしまう。ところが、そうならないような仕組みが先住民社会にはあって、常に複数種が多元的に拮抗しながら、「開かれた全体性」が維持されるような状況が生まれている。ここにも「非同一性による共同体」あるいは「共異体」が生成しているのだと思います。
§
唐澤:
なるほど、今仏教を複数種の問題と関連付けられていましたが、僕は「種」と関係しているのではないかと思いました。要するに、日本という神道の土壌に蒔かれた「種」で、それが土壌のエネルギーを吸い上げつつ、花を咲かせている。それがいわゆる神仏習合だとも言えるし、日本的な仏教を展開していく手法だと思っています。日本に仏教が入ってきて、どう花を咲かせていったのか。その手法を見ていく必要もありそうです。
石倉:
たしかに仏教を複数の「種」と考えるのは、とても魅力的ですね。僕は、仏教は地中に根茎をめぐらす植物のようなもので、そこからアジア各地の芸能や建築などが展開してきたのではないか、と考えたことがあります。
僕は学生時代に北インドでフィールドワークをしていて、手持ちの金銭が尽き、大きな壁にぶち当たった時期に、仏教聖地のブッダガヤで行われていた仏教の祭礼に参加して、しばらく頭を冷やしていました。そんなぽっかりと空白が開いてしまったような体験をしていて、ふと気がついたことがあります。
ゴータマ・シッダールタが悟りを開いたというブッダガヤの聖地には、大菩提寺という寺院の伽藍がありますよね。ご存知のとおり、その中心部には簡素な金剛座というブッダ成道のモニュメントがあって、その後ろに一本の菩提樹が生えています。もちろん、この樹は何代も植え替えられてきているのですが、それを見たとき僕は「仏教とは、一本の樹なんだ」と理解しました。
ゴータマは、シャーキャ族の王子として城内で暮らしていたときも、想像を絶する苦行に取り組んでいたときも、結局悟りを開くことはできなかった。しかし、彼は苦行をやめて山から降り、この菩提樹の前に座ったときにようやく、世界を貫いている縁起の法則を発見した、と言われていますよね。この有名な説話は、この地に生えていた菩提樹という植物をなくしては、決して語ることができないのです。
ゴータマは、個人の心理的な葛藤を超えて、この一本の樹の下で世界のリアリティを悟った。僕はそのことに大きな意味があると思っています。僕が菩提樹の前で、茫然自失としていたとき、周囲ではチベットやモンゴル、ネパール、中国、タイ、韓国、日本といった様々な地域から聖地を訪れた仏教徒たちが、それぞれ全然違うスタイルでお祈りをしていました。キリスト教やイスラム教の世界ではありえない光景ですが、それはまさに唐澤さんがおっしゃったように、仏教という種を各地の民衆が自分たちの思想や表現の大地に移植して、それぞれ異なる果実を育てているように見えたのです。
このように、仏教世界の多様性というのは実に大きなもので、ブッダガヤにある各国の寺院は全て建築様式が異なっているし、礼拝のしかたも微妙に異なります。そもそも経典も、多様な言語に翻訳されていますし、五体投地の作法も違う。しかし、お祈りをしている人たちは、同じように一本の樹の方を向いています。そこには、仏像も神像もなくて、一本の菩提樹が生えているだけだった。
もちろん菩提樹の前には、金剛坐という簡素な「場所」があります。そこに一本の樹があり、人が座れる場所があるということ。つまり、「場所」と「植物」の関係から、全ての歴史が始まっているということだと思うのです。神々からではなく、聖書から始まっているわけでもない。土地に先住する「植物」と、人が座る「場所」だけがある。ブッダという存在は人間と地続きで、理論上は万人に開かれた「覚者」としての理想像です。このことは、誰もがこの菩提樹の下に座る権利と可能性を有している、という開かれたビジョンにつながってくる。
そう考えると唐澤さんがおっしゃったように、仏教という「種」を、あるいは菩提という「種子」を運んで、離れた土地に根付かせて、花を咲かせ果実を実らせていくという、魂の歴史が見えてきます。仏教が移植される大地は、古い時代から続く各地の神話と地続きです。ある土地から別の土地へと種を運ぶことや根を生やすこと。そこに育つこと。そして知恵の花を咲かせ、慈悲の実をならせること。世代を継いでいくこと。仏教からこういう可動的な植物の生態モデルが得られるのではないかと思っています。
§
唐澤:
言葉も違う、お祈りのしかたも違う人たちがいて、真ん中に仏像ではなく菩提樹だけというのおもしろいですね。強力な中心ではない柔らかな中心が、逆に共異体的に人々をつなぎ合わせるものとして機能しているように思いました。「共異体」に関しては、〈Cosmo-Eggs|宇宙の卵※15〉(第58回ヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展日本館展示)でも重要なテーマだったと思うんですが、これは作品内でどう実現されたと思いますか。
石倉:
そのように〈Cosmo-Eggs|宇宙の卵〉というプロジェクトを読み込んでもらえて嬉しいです。「共異体」というものが実現されなかったことは、これまで一度もないと思っています。常にそこにあるものだという言い方もできると思います。かといって、それを実体化したときに、大きなものを失ってしまうかもしれない。「共異体」とは、架空の集合体であって、そこに創造の可能性がある、と理解するべきかもしれません。僕たちが「卵」というモデルにこだわったのは、そこにまだ生まれていない世界像を込めたかったからです。
同時に、僕たちは沖縄の八重山諸島や宮古諸島に散在している「津波石」という小さな場所を手掛かりにしながら、人新世という時代に通用するような、具体的な共生と共存のイメージを共有したいと考えてきました。そもそも共同制作のきっかけになったのは、美術家の下道基行さんが沖縄の離島で撮影してきた「津波石」の映像作品のシリーズでした。
ご存知のとおり、「津波石」とは、かつて海の底にあった巨石が、大きな地震や津波の衝撃を通じて移動し、地表にもたらされたものです。つまり、この石は過去の大きな災害のモニュメントになっています。同時に、その津波石を撮影した下道さんの作品には、アジサシという渡り鳥が営巣している姿や、小さな生物が岩のうえを這っている姿、岩に生えている苔や植物、農機具を使ってサトウキビを収穫する島民の姿、石の前で記念撮影する子どもたちの姿も写っています。つまり、津波石とは異なるものの集合体、あるいは「共異体」という開かれた全体性のモデルを示すのにうってつけなミクロコスモスだったのです。
科学的な視点から見れば、津波石の多くはもともと海中に沈んでいたサンゴ石灰岩で、海中の生物が化石化して付着しています。そもそもサンゴは褐虫藻という藻類と共生する生物で、津波の後に打ち上げられた陸上でも、多くの動植物と共生領域を形成していました。つまり、石の上に木々や植物が生い茂っていたり、様々な鳥類の生息地になってもいます。

津波石は聖地として信仰されていたり、特別な埋葬場所とされたこともあります。そうかと思えば、児童が遊ぶ公園の遊具になっているし、多良間島には津波石を壁面に、手づくりの住居をつくって住んでいる方もいました。〈Cosmo-Eggs|宇宙の卵〉というプロジェクトでは、服部浩之さんのキュレーションによって、そういった多種多様な存在へとつながっていく津波石のあり方を、人間と非人間の共生モデルの表現として提示しています※16。
こういった津波石の多様性を発見し、映像作品としてシリーズ化していた下道さんの活動への応答として、作曲家の安野太郎さんは現地で再録した鳥の声をもとに、卵生神話を彷彿とさせるような曲を作曲し、機械制御されたリコーダーで音楽が自動生成される装置を制作しました。建築家の能作文徳さんは、中心部が筒抜けになっている日本館という歴史的な建築物に対して、参加した作家たちのそれぞれのアプローチを丁寧に共存させるような、現代のエコロジー思想を体現する建築を制作しています。下道さんの作品を映す可動式のスクリーンやマップケースなどの什器、安野さんの音楽を生成するバルーンや空間内のリコーダーの配置も、すべて能作さんと作家たちとの共同制作です。

僕は、宮古・八重山諸島や台湾でのフィールドワークから津波神話や卵生神話を収集し、そこから子宮からではなく卵という空間から新しい人類が生まれるという創作神話を作り、他の作家たちがそれを日本館の壁に刻んでくれました。こうして日本の最南端の島々で行われた津波石のフィールドワークを通して、美術家・建築家・作曲家・人類学者がヴェネチアでの展示プロジェクトを構築するのは、これまであまり行われたことがない、実験的な取り組みだったと思います※17。
§
唐澤:
「共異体」は常にダイナミックな動きで、ある意味プロセスそのものですよね。先日見たアーティゾン美術館での帰国展でも、プロセスが生き生きと描かれていたのが印象的でした。壁に〈Cosmo-Eggs |宇宙の卵〉が展示されるまでのプロセス・タイムラインがずっと書いてあって、共異体的だと思いました。
〈Cosmo-Eggs |宇宙の卵〉がすごくおもしろいのは、常に変化していくところです。真ん中のバルーンに人が座ったときの空気が管を通ってリコーダーへ運ばれる。そしてそれぞれのリコーダーが反応し合って、常に違う音が出る。あれは動的な様態を示唆的に表現されていると思いました。それから、スクリーンに付いている車輪、あれは動かさないのに動くという可能性を見せてるところがすごくおもしろい。止まっているけども動く可能性を示しているっていう意味で、静と動の共存、それは静止状態のなかにダイナミックな動きを想像させ、とても共異体的な装置だと感じました。
異なる専門性を持つ者同士が理解・制作・実践を共有する共異体的協働の方法を模索するなかで、石倉さんは創作神話をお作りになったわけですが、そこには「共異体」の概念はどのように反映されているのですか。

石倉:
このプロジェクトの特徴は、集中的なフィールドワークだけではなくて、日本の各地に分散して住んでいるメンバーが、オンライン上のコミュニケーションを利用して打ち合わせを続けてきたことにも現れていると思います。つまりその後、新型コロナウイルスで一般化したオンライン会議のような仕組みを多用して意思疎通を図ってきた、ということです。初回の打ち合わせも、僕は秋田からオンラインで参加しましたが、そのとき、二十年ほど前に宮古諸島を旅行したときに聞いた「卵生神話」のことを思い出しました。
この打ち合わせのときに決まった「宇宙の卵」と言うタイトルは、もちろん神話学上の「宇宙卵(Cosmic Egg)」を参照していますが、その背景にはこの「卵生神話」があります。池間島のウハルズ御嶽という場所と関連する日光感精説話で、少女が太陽を浴びて卵を生むという伝説ですね。創作神話のなかでは、同じ宮古諸島や近くの八重山諸島に伝わる津波伝承神話と一緒に取り上げられますが、その理由は、前者の「卵生神話」が世界の始まりを、後者の「津波神話」が世界の終わりを伝える神話だからです。
下道さんの映像作品も、安野さんの作曲した音楽の生成装置も、実は反復構造という共通点を持っています。僕が調査した「津波神話」と「卵生神話」は、それぞれ別の系統で一緒になることはないのですが、実はこの二つを連続的に扱うことで、この地域に長い時間をかけて反復している地震や津波という災害、そしてそれを超えて生存し続けてきた人間とそれ以外の生物の歴史を喚起してみたい、と考えました。その後、少女が12個の卵を産むという話が、偶然安野さんが展示空間内に設置した12個のリコーダー装置と呼応したり、日本館の天井から差し込む陽光や卵の黄身のようなバルーンといった卵の隠喩的な視覚的要素がつながって、徐々に無意識の必然性や共同性を獲得していくことになりました。
それでも、「津波神話」と「卵生神話」をつなぐミッシングリンクは、結局2019年の1月に台湾を訪れるまではうまく発見することができませんでした。創作神話をつくる期限が迫っていたこの時期、沖縄から国境をこえて台湾原住民の神話を現地で調査するなかで、偶然この二つの話型をつなぐ神話が見つかりました。台湾の台東地域には、海岸部に転がる大きな石から先祖が生まれてきたとか、洪水の後に生き残った祖先が卵を産んだという格好のモチーフがあったんです。それは、まるで卵のように孵化する雛鳥のように、海の近くにある鉱物から祖先が現れるという神話群です。こうした台湾に伝わるいくつもの神話を見つけたときに、ようやく創作神話の全体像が浮かんできました。
僕は、自分が物語作者となって神話を書くというよりは、日本の南限に当たる先島諸島や国境を超えた台湾の神話を集めることによって、これまで国家単位で語られてきた神話を、島々のコスモロジーの感覚から再構築したいと思っていました。この作業は、最後に台湾で「石の卵」の神話を見つけたことによって、一気に進んで完成に向かいました。
できあがった創作神話には、いわゆる民間伝承ばかりでなく、自分自身の個人的な想像やイメージが含まれていますし、今回関わったメンバーや現地の人々から聞いた出来事の断片が織り込まれています。また、東アジアの日光感精説話が男性や女性の同性集団の結社と関係してきたことも、大きな意味を持っています。結果的に、今回は男性のメンバーばかりが集まったので、あえて子宮からではなく、卵から先祖が生まれたという話型に集中し、人間を超えた次元での誕生や生命について考えるという展開になっていきました。
§
唐澤:
たしかに〈Cosmo-Eggs |宇宙の卵〉のメンバーは男性だけですね。あえて同性集団で、異性性を考えるのは大事だと思いますが、もしメンバーに女性がいたら、また作品もすこし違う感じになっていたかもしれません。
「太陽を浴びた少女が卵を産む」と言う展開も、いろんな重要なエレメントが隠されているようで、おもしろいと思いました。太陽からの光という贈与によって、大人ではない少女が爬虫類のように卵を産む。これは人間の生理を優に超えている。贈与を起点にしながら、人間と非-人間、大人と子供など、共異体的在り方を表現しているとも思えます。そこに大きなヒントを得て、石倉さんは創作神話をつくったのだと思います。人類学者が神話を創作するのは、なかなか勇気がいることだと思ったんですが、他の人類学者から何かコメントはありましたでしょうか。
石倉:
生産的な批評はいくつもありましたが、非難の類は一切無かったですね。今の日本の人類学は、従来の制度から発展して表現方法を多元化・豊穣化していこうとしています。ですから、僕たちの仕事も、アートと人類学の協働を探ろうとしている一連の実験的な流れの一部として受容されているのかもしれません。
もちろんこうした実験の先駆けとして、中沢新一先生がアーティストのマシュー・バーニーに向けた創作のユーカラ※18をはじめとする、批評的な考察と詩的実践のあいだに位置付けられるような、一連のテキストが存在しているはずです。上橋菜穂子さんみたいに小説や物語を書いたりするような人類学者もいらっしゃるし、人類学者シオドーラ・クローバーとアルフレッド・クローバーの娘であるアーシュラ・K. ル=グウィンの『ゲド戦記※19』にも、神話的な要素はふんだんに盛り込まれています。そういう創作的なテキストと、人類学的な記録としての民族誌をつないでいくような回路が、「表象の危機」以後に数々の苦闘を通じて獲得されてきました。20世紀後半から21世紀の頭にかけて、人類学・歴史学・神話学・考古学・社会学・精神分析学・芸術学などが再構築の時代に入ってきて、そこで生まれてきた一つの可能性として、創作実践があるはずです。
§
唐澤:
石倉さんより前に、中沢先生も創作テキストを発表されていたんですね。よく考えたら「四次元の賢治※20」も、それに近い表現な気がします。中沢先生は、いち早く宮沢賢治や南方熊楠に可能性を見出し、再評価するテキストを発表し続けているのだと思います。
石倉:
そのとおりです。そして中沢先生も、多くの先人からその精神を受け継いできたのだと思います。たとえば民俗学の方でも、柳田國男と佐々木喜善の『遠野物語※19』から折口信夫の『死者の書※22』まで、ストーリーテリングを組み込んだ学問の系譜がつくられてきましたし、フランスの人類学ではレヴィ=ストロースやフィリップ・デスコラが、非常に詩的な創造をテキストに組み込む方法に挑戦してきました。ルーマニア出身のミルチャ・エリアーデ のように、学術と文学の両輪から研究を深めていった宗教学者もいます。そう考えると、ストーリーテリングをもう一度見直してみるのも、芸術人類学の一つの重要な課題と言っていいと思います。
また、複数の種との関係や視覚的な媒体以外の表現方法、音楽や演劇、現代芸術や環境デザインなどの領域と人類学的実践の協働も、これから大きく発展していく見込みがあると思っています。そのためには、人類学を知的生産に閉じ込めるのではなく、他の学問領域とアートを架橋するような、越境的インターフェイスとして鍛えていく必要があると考えています。
§
唐澤:
僕が研究している南方熊楠という存在との接点も、そのあたりに隠されているように感じます。ストーリーテリングの可能性は、南方熊楠が膨大な書簡や記録を通して実現してきた、まだ未開拓な知の領域にも含まれているように思えるのです。また熊楠が粘菌研究をとおして生命のロジックを掴み取っていったように、科学と様々なアートの領域を結んでいくような視点も、これから大事になっていく予感がしますね。今日はありがとうございました。