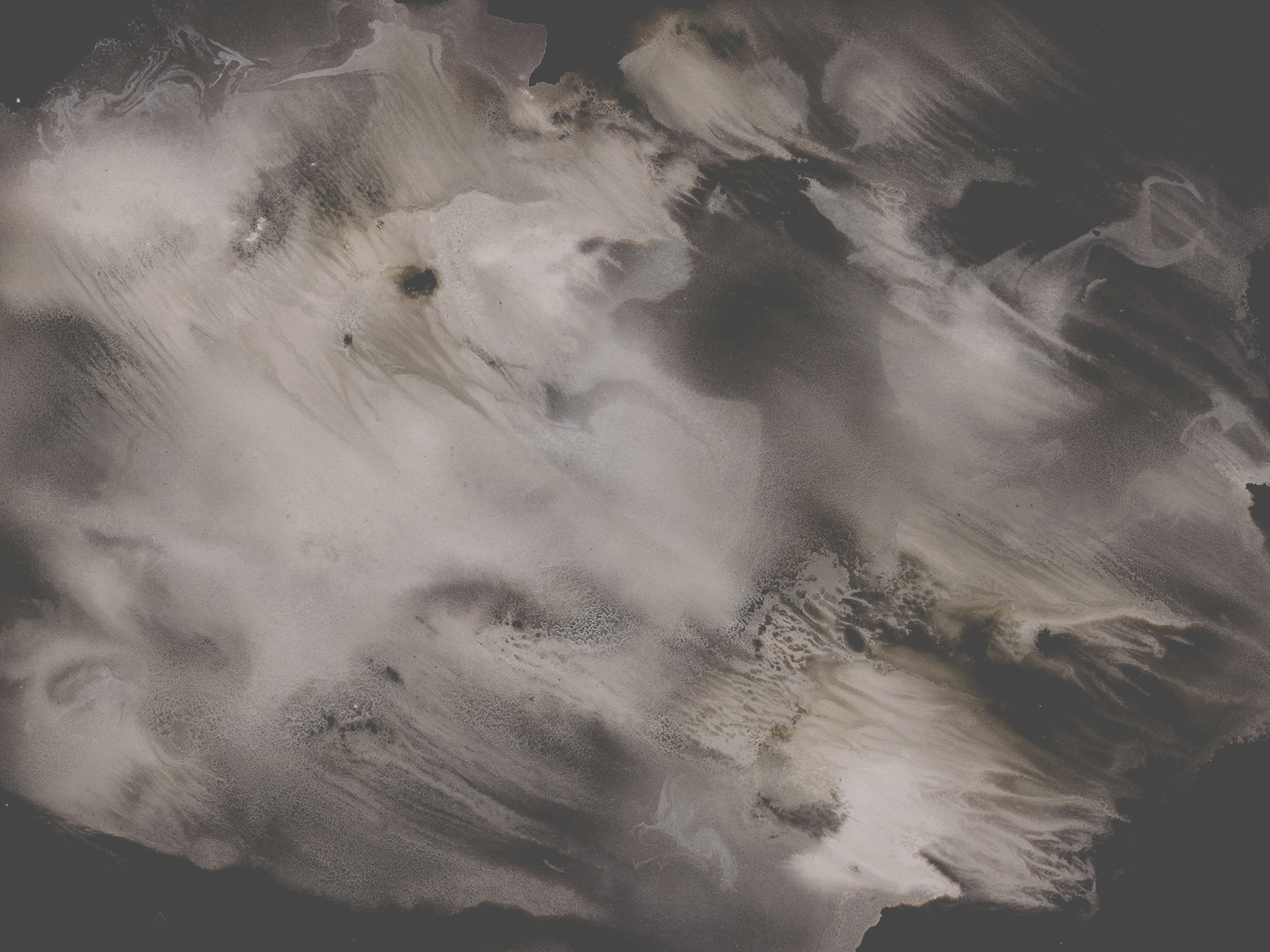運動共感の撓(たわ)み
三好:
ぼくはデザインにおける運動共感を研究してきたのですが、平井さんの『世界は時間でできている※1』のなかにも運動共感について書かれていると感じる部分がありました。実際にぼくが展開したような動きとデザインの話が、平井さんの理論の中でどういう位置づけになるのか、とても興味があります。またその話を踏まえて、自分のこれまでの研究が、デザイン哲学や方法論として、今後どのように展開し得るかというのは、楽しみなところです。
ぼくは最初、フランスの美学者であるフランク・ポッパーの『Origins and Development of Kinetic Art※2』を読んで、ベルクソンを知りました。これはぼくがキネティックアートを勉強した本で、文献の輪を広げるきっかけにもなったものです。たとえばこの本をハブにして辿り着いたポール・スリオは、おそらく動きの描写的な美学を探求した最初の人物なんですが、彼の『運動の美学※3』という本にも何度もベルクソンが登場します。
フランク・ポッパーは、1910年代あたりから始まったキネティックアートが当時重要な作品を多く残しているのは、同時期に時間哲学に関するテキストが生まれたこともきっかけとしてあるのだろうと書いています。その時間哲学のひとつとしてベルクソンが出てきます。1910年代というと、デュシャンの「自転車の車輪(Bicycle Wheel)」が出てきた時代です。ぼくが博士の学生として運動共感の研究をしていたときは、そこまでベルクソンの存在を意識できていなかったのですが、平井さんの本を読んで感銘を受けて振り返ったときに、自分自身の研究の原点にも関わるような実感がありました。
動きの芸術性について、ベルクソンはどのような言説や問題意識を持っていたのでしょうか。
平井:
芸術論としてまとまった形ではないのですが、芸術についての言及は、ベルクソンのほぼすべての著作に散りばめられています。テクストの分量が少ない代わりに、印象的なところで使っていると思います。その中でも動きに関わるもので思いつくのは四つぐらいあります。
ひとつは彼の処女作である『意識に直接与えられたものについての試論※4』の冒頭で美的感覚というものに触れているところです。芸術が運動共感による催眠を用いて印象づけを行うのだ、という話をしています。三好さんの著書『動きそのもののデザイン※5』で引かれているレイノルズとリーズンの著書※6にアメリア・ジョーンズが巻頭言を寄せていて、そこでもちょうどこの箇所が引用されていましたね。このくだりでベルクソンは、芸術は感情を“express(表現)”するのではなくて、“impress(印象付ける)”すると言っています。そこで運動共感を使うというんです。人はつい頭で見てしまうから、まずは頭を眠らせるために、身体的な共感を使って一種の昏睡状態に持っていくのだと。すると精神は一旦フラットになって敏感になるから、アイデアをくどくど表現せずとも、ほんのすこし示唆するだけで一気に感化されるというわけです。数行ぐらいですが、そんなテクニカルな話が書いてあります。
二つ目として、『試論』の中では「優美さ」についても話していました。これも実は運動と時間の中で美的なものを説明するという話になっています。例えばバレエダンサーの動きの優美さとは、運動によって未来を先取りすることでわれわれの身体が動かされるようになることだ、という具合に時間で捉えることができるんです。『試論』は1889年に刊行された彼の処女作ですが、こういった話を特段の説明なしに、息をするようにしているので、運動共感のアイデアは前提としてあったように思います。
三つ目に、別のところでダ・ヴィンチの絵画論※7を参照しながら、蛇のくねりみたいな動きがアートにとって大事なんだということも言っています。これはコレージュ・ド・フランス講義でも言っていました。
そしてもっとも重要な四つ目は「キネステジック(kinésthesique)/キネステティク(kinesthetic)」という言葉の使用ですね。この言葉の生みの親はチャールストン・バスティアンという人なんですが※8、そのバスティアンを引用して議論しているのが『精神のエネルギー※9』という1919年に出た論文集です。この本にある「知的努力」という論文の中で、たとえばワルツのような複雑な運動を習得するときに「キネステティク・イメージ」からつくっていくという話を、バスティアンに言及しながらしています。
ちょっとそれが出てくる文脈のお話をしておくと、“le schéma dynamique”という、ベルクソンの哲学全体にとっても枢要な概念があって、今だと「力動的図式」と訳されているのですが、ぼくはこのschémaは「構想」と訳した方が適切かなと考えています。なぜならこれはアクチュアライズされた運動ではなくて、「動き」をクリエーションするその背後にあって、それを参照しつつ、それによって突き動かされながらも、それ自体は背後に留まり続けているような、そういった潜在的な動きの「種」みたいなもの。それを“le schéma dynamique”と名づけて、論文を通じて概念を彫琢しています。
“le schéma dynamique”には、ギリシャ語の“dynamis”、「力」という意味の単語が入っています。だから単に「動的」だけではなく「潜勢的」という意味合いが含まれています。アリストテレスの言う潜勢態のような意味で、「潜勢的な力」です。だから現実化されている運動ではなく、背後にあって「動き」を「動き」たらしめる「動き」と考えています。こう聞くと形而上学的な概念に感じられるかもしれませんが、それを心理学的な文脈で議論していたというのが、今見ると逆に新鮮でおもしろい。
この論文は「知的努力」というタイトルの通り、われわれがなにか知的な発明をするときに、その現象の核になる概念を指すアイデアになります。知的努力における動的図式の概念をつくる前のひとつの参照項として、バスティアンのキネステティク・イメージという概念が出てくるのです。
この「キネステティク」というのは、大事な概念のひとつです。1960年ぐらいの哲学心理辞典に遡ると、バスティアンが語源という話は書かれているんですけど、同じ頃にウィリアム・ジェームズとかも出てきていて、彼は“kinesthetic sensation(運動感覚)”において “immediate”なものと“remote”なものを区別しています。immediateは自分の身体の自己受容感覚みたいなもののことで、もうひとつのremoteというのは、三好さんが問題にしているような、視覚や聴覚を経由して外にあるものから間接的・遠隔的に惹起される運動感覚のことです。そして、非常に重要なことに、そうした動きの感覚の「記憶」があるという議論をしているんですね。それのことをキネステティク・イメージ(kinesthetic image)というんです。運動記憶とその記憶が重要だということは、当時よく議論されていたけど、現代ではそこまで注目されていないかもしれないですね。
自分が何かをするとき、最初にしたい「動き」のイメージがあって、それが筋肉運動によって模倣されて実現するわけです。子供が発声を獲得する場合などが例に挙げられますが、そもそもどうやったら狙った声が出るのかという文脈で、キネステティク・イメージが導入されたみたいで、哲学的に豊穣なポテンシャルを持った概念だと思います。こんな感じで、ベルクソンのアートに関する言及には今も埋もれていて、あまり主題化されていない論点がまだまだありますね。
ついでに言ってしまうと、全部は調べきれていないんですが、もう少し掘っていくと“innervation”という単語も見つかります。“nerve”という単語が入っていて、中枢から運動系への、遠心的な方向の神経発火を伴うような感覚のことを指して用いられていました。これがキネステティクの系譜を遡ったところにあるようです。
三好:
ありがとうございます。つまり「感覚が芽生える可能性がある」みたいな状態ですかね。
平井:
そうですね。三好さんの話は、リモートな“kinesthetic sensation”にあたると思うんですけど、リモートに作用されるためには、こちら側にある種の雛形が必要になります。手持ちのカードがない見知らぬ動きには、どうやっても共感しようがないわけです。
ベルクソンは、キネステティク・イメージという要素について「撓(たわ)める」という言い方をしています。新しい動きを学ぶとき、相手の動きそのものは手持ちにはないけれど、既に持っている歩行やつま先立ちのキネステティク・イメージを素材として持ち込んで、それを撓めて、新しい形の方に沿わせていって動きを学ぶという話をしています。なので、“kinesthetic sensation”の前後には記憶があって、そこでつながってくるんだと思います。
三好:
たしかに、人が物の動きに共感するときは「撓みまくっている」と思います。他の人の動きを真似るときには、もちろん自分の運動感覚を撓めなければいけませんが、人間と同じ身体すら持たないものの感覚を想像するときには余計に撓ませる必要があるわけです。だけど、それをいとも簡単にやれてしまうときがあるのが運動共感の不思議なところだと思っています。
撓ませようと思って撓めるのではなく、勝手に撓んでいるんですよね。能動でも受動でもなく反射的にすることもあるわけです。さらに不思議なのが、意識的に運動共感をしてみようと思えば、想像力を駆使して能動的に自分をその対象物に入れ込むということもできるんですよ。一口に運動共感と言っても、色々なレベルのものがあると思っています。
平井:
運動共感が中動態的に発生するという点には、ぼくも関心があります。ぼくの今回の本の話で言うと、もう「水路づけ」ができあがっていて回路が流れるだけの「未完了相(〜しつつある)」の場合は、ゾンビ的というか反射的な反応になっていますよね。
時間アスペクトとしては「アオリスト相(点的・完結的に捉えられた動作)」のように閉じてしまう。これに対して撓める、つまり新しい組織化が必要なときには、リアルタイムで改変していかなければいけません。そうすると、この状態で生じる時間相は、前後がまだ決まっていない「未完了相」という特殊な時間相が開いて、そのときにキネステティクな感覚成分が、とくに意識として体験される側面が際立つんじゃないかと整理しています。「水路づけ」というベースラインと、それがどれぐらい未完了方向に撓むかによって、ベルクソン的な枠組みの中に運動共感の生じる様態みたいなものが、すこし整理できると思っています。
この辺りは三好さんがどう思われるのか気になるところで、せっかくなので引用してみます。訳の中で「図式」というのは「シェマ」、つまり「構想」のことです。
この図式が完成したと見なされて、その図式の中に模範が見いだされる運動を、体が連続的に生み出すようになったそのときに、私たちは踊りはじめることができる。言い換えればこの図式、すなわちおこなうべき運動をだんだん抽象的に示すようになるこの表象は、おこなわれる運動に対応するすべての運動感覚で満たされていなければならないということである。それができるのは、そうした運動感覚のイメージ、バスティアンの言葉を借りれば全体の運動を構成する部分的要素的な運動の「運動感覚的写像(キネステティク・イメージ)」を、つぎつぎに呼び起こすことによってだけだ。それら運動感覚の記憶は、呼び起こされるにつれて現実の運動感覚に、つまり実際の運動に変わっていく。
アンリ・ベルクソン『精神のエネルギー』
このあと具体的に、たとえばワルツを覚えるときには、そのまま既存の運動感覚を用いるわけにはいかないという話が続いていきます。
それらを多少なりとも変化させてワルツの一般的な運動の方向へ撓め、とりわけそれらを新しく組み合わせなければならない。すなわち、一方には新しい全体的な運動の図式的な表象があり、他方にはその全体的な運動を分析して得られる要素的な運動と同一な、または類似した古い運動のキネステティク・イメージがある。ワルツの習得とは、そうした古い諸々のキネステティク・イメージを図式の中へ一緒に入りこめるように新しく組織づけてやることである。
アンリ・ベルクソン『精神のエネルギー』
古い要素のキネステティク・イメージを新しい体制に入れると、そのままではいられないから、それぞれが撓んでお互い掣肘し合いつつ調整してすり合わせて、ひとつの全体的な新しい運動が獲得される。これが「未完了相」と記述できるわけです。
三好:
「未完了相」という概念を使っていたら、ぼくの博論ももうすこし簡単に書けていたかもしれませんね。ここで「未完了相」のことを「生まれつつある」状態とまでいってしまうと、多分もう既に「生まれてしまっている」んだと思いますが、どちらかといえば「生まれようとすればいつでも生まれそうだけどまだ待機している」という状態ですよね。この「待機中」というのは、未来にならないと存在しないわけではなくて、現にそれがその人の中にあるという状態じゃないか思います。人工物と空間と人の関係の中で、この状態をどう書き表せばいいのか難しくて悩んでいました。ぼくの研究の場合は、簡単にいえばまず対象の動きがあって、それに共感するということです。
マルチタイムスケールの中で起きていること
三好:
ところで、その動きを見ずとも共感が芽生えるみたいなことすらあるといったときに、これをどう解釈すればいいのでしょうか。
ぼくの本の後半で事例として、「カーリング・ベッドランプ」という作品を紹介しました。夜になるとランプシェードがねじれることで光を遮断して、だんだん暗くなるというものです。これを細かく時間を切って考えると、ランプシェードがまず動く、そしてその動きを見て運動共感を感じた結果、同じような身体感覚が芽生えたというような時系列のように思えます。だけど、何回か使っていくうちに、おそらくこのランプを見なくても、音を聞いただけでそういった感覚を得るでしょうし、そろそろこのランプが動くんじゃないかなという予測だけで運動共感が芽生えることもあるんだと思います。
このときに、抽象的な時間で区切れないような、何かが起こる可能性と、実際に起こったイベントがネバネバとひとまとめに存在していて、実際に起こった/起こらないといった前後関係すらも緩い状態があるように感じます。平井さんが本で触れられていたマルチタイムスケールの中にある遅延の概念が、事後的な方向だけでなく、同様に未来方向にも延びているのではないかというのが、研究の実践を通じて掴んだ感覚でした。
平井:
まさにマルチタイムスケールの話だと思います。ベルクソンは、可能性という概念すらも時間でつくっているんです。一般的に考えられている時間は現在−過去−未来があって、様相はそうしたタイムラインが何本もある、つまり次元数をひとつ上げるようなイメージだと思うんです。だから様相というのは時間超越的と考えられるんですよ。でもベルクソンはその様相概念も、ぼくが今回取り出した拡張記憶と運動記憶のかけ合わせの中でつくっていくと考えているんです。
たとえば、実際に生物が空間を運動記憶でなぞっていく中で、運動可能な水路ができていくと言っています。これはデイヴィッド・ルイスが言う可能世界のようにこの現実と別個に実在しているものでもなければ、単に観念的だったり抽象的なものでもない。この世界にグラウンディングしていて、どこに道があってどこに道がないかという具体的な感覚で、空間がデザインされているという話をしています。それは過去の反復によってそうなるわけなんです。こうして可能性というのも時間によって世界内に実装することができて、そうすると可能性の変化みたいなものが語れるようになるわけです。
先ほどのベッドランプが家に来るまでは、そんなエコロジーは自分の家にはなかったわけじゃないですか。だけど、それが導入されることによって、可能性空間が変わってくる。この可能性空間も理念的なものではなくて、実際に空間を行動することで身体の形が変わるということです。それを毎回の運動のスケールで見ると、ただカサカサと音を立てる動きだったりするけれど、それは運動記憶によって折り畳まれるし、拡張記憶によって凝縮されるし、そのダイナミクスの中で予感を感じながら接しているということが起こってくるわけです。
三好さんが紹介されている作品群はどれもおもしろくて、ベルクソンだったらどう考えるのか解きなさいと問いかけてくる例題集のように、想像を刺激されながら本を読んでいました。
三好:
運動記憶のところで、一見するとその遅延の中で過去に伸びるような水路づけがされるというのも、何か起こったあとでその人や動物の中でつくられるということですけど、それが同時にその未来方向への行動の可能性をつくっている。実は両方向に延びているということなんですね。
平井:
本では「システムの時間」というところで言いたかったことなんですけど、一定以上のスケールの生物であれば感覚運動入力には幅があるわけです。それがひとつの単位となって反復されて、つまり折り畳まれるので、そのひとつ分が空間になっていて、空間の中にある幅が埋め込まれています。これを時系列でプロットすると、未来という言い方になりますが、正確に言うと「もう感じ取っている」ので、未来ではなくて現在なんです。折り畳んで空間をつくって、その空間の中に先取りされた未来と言いたくなるものに撓みがあるからこそ、ぼくたちは豊かな感情を抱けると思うんです。
運動についての三好さんの考えと共鳴するなと思う点は、まさに運動に寄り添う形でオンタイムで生じるクオリア的なものへの眼差しがあるという点ですね。認知科学でも現象的な質や内的なものをすべて還元していくやり方があるわけなんですけど、一方で見落とされているものもあると思います。運動はすごく懐が深くて、繰り返しによって人間をゾンビ化するというか、パターン化すると思うんです。そういうタナトス的な側面を持つと同時に、その都度新しいくねりや撓みによって、ぼくたちを逆方向にも持っていってくれる。その動きの振れ幅がわれわれのクリエイティブな活動を支えているというのは、ベルクソンの思想の根幹に通底するテーマだと思います。
ベルクソンの記憶の逆円錐図はまさにそれを言っていて、上に行くだけだとただ夢を見ている人になってしまうし、下の先端に行くとただ反射している人になるから、その中間を動きながらしなやかな感受に開かれた知性をつくっていくという話なんです。
三好さんの本では、その態度がそこかしこで表明されている気がして、繊細に見てらっしゃる方という印象を持ちました。とくにおもしろかったのは、アレグサンダーの「名のないクオリティ(無名の質)」を挙げていたり、アフォーダンスだけじゃないみたいな話をされていたところで、改札機の痛みを感じるという話もありましたね。
三好:
ありがとうございます。デザインの中でアフォーダンスは市民権をやや得すぎているともいえて、それはいいことでもある反面、すこし過剰に感じるところもあります。アフォーダンスから見ると、簡単にいえば、自分の身体と改札機がどう接し得るか、そしてそのときどんな身体感覚が生じるかという側面しか記述できない。だけど、改札機の痛みを、共感的に自分の痛みとして知るというチャンネルもあるわけで、本ではアフォーダンスをオントゥ(onto)、運動共感をイントゥ(into)というように整理しました。
デザインのなかで身体性について初期に語られていたのは、おそらくエルゴノミクスの理論あたりですけど、たとえばパソコンの画面は顔のどの高さにあるといいとか、この身長の人にはこれくらいの椅子の高さがいいといったような、直接的かつ機能的な意味での身体性だったと思います。アフォーダンスも、「物を触る」とか「ボタンを押す」といった実用的なレベルでの身体の話になるじゃないですか。それに対して運動共感は、機能性や実用性というよりは、何をどう感じるか、という高い次元の話ができる議題だと考えています。
なので、リアルタイムに生まれつつある運動感覚の中にもチャンネルが違うものが複数混ざっていて、そこにはアフォーダンスだけでは読み解けないものもあるんだということを、今回の本では書く必要があると思っていました。
平井:
ベルクソンも進化論を踏まえて哲学をつくり、知覚論もつくった人です。われわれが文化的に活動できるのは、純粋に思弁的な認識で世界をコピーしているからではなくて、有用性による古いフィルタリングに余剰が入ってくるからです。反復によって機能的な知覚システムがつくられていくんですが、そうした自動運転だけでは意識にならない。われわれはそこに拡張をかましているから、余計なものをいろいろと感じてしまうんです。
そういった経験は役に立つから起きるわけではなくて、余剰なんです。そして自然はそうした余剰をまた刈り取っていくんだと思うんですよ。やがて有用性に回収される日が来て、回収されないものは単に回収されないわけなんですけど、その間、まだ役に立つか立たないかがわかっていない狭間に、われわれの意識というのはあるんじゃないかと考えています。
ぼくの本の第6章「創造する知性」では、意識が発生する部分だけではなくて、意識が終わっていないことも問題だと書いたんですね。有用性に収斂して、反復による運動がすべてを機能的に回収していくなら、理論的に考えて、われわれの意識はなくなっていくはずなんです。そうならないでいられるのは、改札機の痛みに共感してしまうような、現時点では進化的に何の有用性も持っていない、溢れかえった自然の豊穣さをわれわれがまだ抱えているからで、その限りにおいて意識が遅延し続けているという感覚があります。
広大な身体とその水路
三好:
なぜ運動共感するのかについては、ミラーニューロンに関する研究などを見ると、模倣学習や社会形成のために必要だったのではないかという話もあります。それだけだと、やや機能的なというか、機械的な説明にしかなっていませんが、おそらくそれとは異なる解釈や説明の仕方もあるだろうと思います。
運動の反復の中で、もう意識しなくてもいいものとして無意識下に捨てられそうだけど、まだずっと残っている感覚を持って人は生きているんだと思いますが、これは進化が追いついていないという感じなんでしょうか。
平井:
そうですね。「まだ遊んでていいよ」と言われているのかなと思います。その意味で、人ではないものへの運動共感というテーマ自体が、すごく大事だと思うんです。人に対する共感は当然必要にして有用だけど、実際は人に対しても必要以上のものがあるはずなんです。改札機の痛みのような有用性がないとされるものへの共感がが起こっていることにこそ意味があると思いますし、その理論を組み立てられていくことで、翻ってわれわれが人間に対する共感についても深く考えられるようになってくると思います。
三好:
平井さんの本の中では、ベルクソンが環境に拡がる知覚システムとして定義した「広大な身体」に触れていましたが、そこにもつながる話だと感じました。身体が広大になって知覚が空間全体に及ぶというのは、身体が空間と「同一化する」と捉えることもできるし、また「同一化」というよりはあくまで「同伴している」と捉えることもできるのではないかと思います。これは運動共感を考える際にもとても重要な視点です。この「広大な身体」を平井さんがどのように考えて書かれたのかをお聞きしてみたいです。
平井:
「広大な身体」のところは、身体を張り巡らせている知覚システムの話で、有用性に従って水路が掘られるというより、むしろできあがった水路が有用性を定義することになります。運動の繰り返しによって知覚空間を掘り進めて水路があるランドスケープを開く。それが生物の知覚になるという話だったんですけど、お話を聞きながら考え直してみて、やっぱりそこにもずれはあるわけですよね。
もし完全に盲目的に、つまり没入的に「広大な身体」を生きている生物だとすると、それは既にリモートとは言えないじゃないですか。だから、「距離はあるが分割されない」※10空間というのは、通常の意味での身体と「広大な身体」にギャップがあって、それがぼくたちの時間スケールのギャップに対応していて、この身体を使って運動階層もつくられている。進化レベルで繰り返されているものだけじゃなくて、その都度の撓みがあるということですよね。
ギターを何度も弾くという行為を例にすると、新しく聴いたことのないフレーズを生み出すには、手ぐせを土台としつつもそれを撓めることが必要なわけですよね。「広大な身体」は、これから広がる音空間に対するセンシングとして必要なので使われるけど、それをただ擦(なぞ)っているのではない。これまで培ってきた「広大な身体」があるからこそ、運動を新しい方向に水路づけていくことができる。そのギタープレイヤーは、初めて新しく挑戦するプレイに対して、「まだ踏んでないけど踏めばそこにある」という感覚を持っていると思います。進化は、基本的には数撃ちゃ当たる戦法でランダムにやっていって結果が絞ってくれるという話です。それに対してわれわれが限られた時間の中で、こんなにもクリエイティビティを発揮できるのは、方向づけの感触を持てるからではないかと思います。
第3章あたりに書いた、記憶の中の色合いやニュアンス、時間徴表などにも通じそうな話です。まだやっていないけどなんとなくこっちの方がいい気がするとか、まだ思い出していないけど記憶がこの辺にあるみたいなことが、「方向づけ」としてわかることがありますよね。記憶を思い出すときに、まだ思い出していないけどこっちの方にあった気がすると探っていく、オリエンテーションの感覚があるわけです。盲目的にやっているわけでもないし、神秘的に直観したわけでもない。ちゃんと根拠があって、さまざまな体験質のネットワークが持っている関係自体が質に織り込まれているから、それを頼りに探ることができる。その探索のヒントになるものがそこにあるから、われわれは無目的にランダムに無限回繰り返さなくても、学習しながら新しいことができてしまうんだと思います。
三好:
記憶の質を頼りに時間を見つけていくときのように、クリエイションにおいてもオリエンテーション感覚があって、構造としてほぼ同じようなことが起こっているわけですね。
平井:
ベルクソンは、冒頭で話した“le schéma dynamique”の発動ケースを三つ紹介していて、そのひとつ目が「想起」になります。そのときにオリエンテーションを使うわけです。そのあとに「解釈」とか、実際のアイデアを「発明」する例も出てきて、彼の中では地続きになっていると思います。
三好:
空間の中で運動共感の研究をしたとき、明らかな法則としてあったのが、自分の身体に近すぎるものに対しては、運動共感をする余裕が持てずに、アフォーダンス的なチャンネルになるということだったんです。たとえば、まさに今改札機を通ろうとする人にとっては、改札機自体の痛みよりも自分がそれに当たったときに感じるであろう痛みの方が当然重要なわけです。そこを左右するのは空間的な近接なんですね。逆に遠いと運動共感への余裕ができる。遠くを飛んでいる鷹を見て、「ああやって飛べたらこんな感じかな」と想像することはできますが、目の前に鷹がいるときには、その余裕はありません。
だから、われわれと対象物の距離によって、チャンネルが変わるんじゃないかと思います。アフォーダンス的な知覚と運動共感的な知覚で、記憶の方に行くか想像の方に行くかが違うというのは、先ほどの「広大な身体」のトピックにも通じそうです。
平井:
どうしてチャンネルが変わるんですかね。
三好:
自分の身体を守らなくてはいけないという、かなり基礎的な本能によるものだと思います。逆にそこが緩い人は、目の前を通り過ぎる鷹にも運動共感ができるのかもしれないですけど。ただおそらく、どちらかではなく両方があって、そのバランスなのかなとは思います。
平井:
おもしろいですね。ベルクソンは想起できるための条件として、「無用なものに価値を与えることができないといけない」と言っているんです。裏返すと、過去を現在に役立てることに想起は必要ないということなんですね。
たとえば、過去にある動物がこのルートを通ってヒヤリ体験をしたから、ここではなくてこっちを通りたいというときに、われわれは何らかの感情移入して、そいつが想起したからその判断をしたと思ってしまいますが、もっとインパルス的なものでもいいわけですよね。過去の体験自体をイメージとして想起するといった高度なことは必要なくて、とにかく結果だけわかればいいから、今何をすべきなのかというファンクショナル(機能的)な答えだけがあればいい。フェノメナル(現象的)な想起体験は、むしろ余剰なんですよね。有用性に切り詰められた生の状態では、どんどんフェノメナルなものは削られていって、ファンクショナルな答えを出せるものだけが残っていくんでしょうね。
三好:
運動共感について考える前は、どんなマテリアルを使ってどういったリズムにすれば美的な動きは可能なのだろうかと考えていました。つまり、どんな方程式があるんだろうと考えていたんですね。しかし、それでは解くことができず、問いそのものの破綻に直面してしまいました。そこで、ふと一段階ステップバックして、なぜ自分はこの動きの感覚を得ることができるんだろうと考えたときに、自分の運動感覚があるからだということに気づいたんです。
クオリアの材料を物理的に見つけようとしても見つからないけど、魔法のランプがあるわけでもなくて、そこで時間を見なかったからクオリアの現出を説明できなかったと平井さんが書かれていたところを読んだときに、その運動共感の研究をしていたときの自分と通じるものを感じました。クオリアに関する話は、ベルクソンの言説の中でどんな位置づけなのかについてお聞きしたいです。
平井:
ベルクソンが使う「凝縮」という用語があって、フランス語では“contraction”と言うんですが、これ自体が彼のクオリアを説明するときに道具立てとなる理解は、教科書的にシェアされています。問題は「凝縮」の中身なんですよ。彼が表面上で言っていることは読めばわかるんですが、これを理論的に解剖して実際に「それが何をやっているのか」という部分には、あまり理解が進んでいませんでした。
僕個人の「凝縮」の理解は、むしろ現代の科学における発見からヒントをもらいました。実際に脳内の時間がマルチスケールになっているとかですね。そうやって何本も凝縮を扱った論文を書いて少しずつブラッシュアップしてきたのですが、今回の本で決め手となった識別可能性空間の変形の話は、ぼくの貢献にあたるものです。もちろん多様体概念に基づいているので外から持ってきたわけではありません。それでも、凝縮においてなぜ量が質になるのかが一番のミッシングリンクで、ここをつなげられた人は今までいませんでした。
ハードプロブレムというのは解けない問題とされていますよね。そこをベルクソンが時間によって打開しようとした。でもそれは、哲学者による鍵括弧つきのメタフィジカルな「学説」ではないんですよ。むしろ解決に向けて検討可能な素案、構想を提示してくれていると思うので、それを今回の本ではできるだけフラットな表現で示そうと意識していました。こんなアイデアがあるんだと感じてもらえて、さらにそこからアイデアが派生したりバージョンアップできるきっかけになればいいと思います。
静止物の時間と動き
平井:
キネステティクな運動共感の話が、鑑賞者が対象に対して持っているものと考えられてしまうように、どうしても認識論として二元論的に乖離しがちですが、時間についても同じようなことが起こっていると思います。まず客観的な時間というのがあって、それを長く感じたり短く感じる経験が主観であるといったようなモデル化がされてきました。
三好さんの本でも、最初の方で二階のサイバネティクスの話をされてましたよね。感じているものも主体の一部で、それはインタラクションによって起きているわけだから、どう感じるかも含めて記述の中に入れてあげるべきなんです。そうすると作品のような対象とその鑑賞者自体を含めたインタラクション自体を同じゾーンで観測することができて、そのスケールで物事を語れるようになるんだと思います。ぼくの本ではこういった話を序論に書いてますけど、三好さんも同じように意識されている印象を受けました。
ある対象の使い勝手を感性工学的にデザインするだけではなくて、エージェントも含めたデザインを考えられるのは、理論に対するスタンスが違うからではないかと思います。主観やクオリアみたいなものを前提にするやり方では、それらを世界の外に特権化してしまうということになります。もちろんそういった記述によって得られるものはあります。でも逆に、すべてをグラウンディングするなら、身体だけではなく記憶もグラウンディングさせて、スケールが違うところまで視野に入れれば、すべて世界に与えられている道具立てでできます。
その意味で、世界は神秘的なものでもないし、理解できるはずだと考えられるようになります。だから、そこまで視野に入れて見せてあげる。それがぼくだとマルチスケールの組み立てだったわけで、三好さんの場合は運動共感によるデザインというアイデアになったのではないかと思いました。
三好:
そうですね。「私自身」という要素を含めてメタな系として捉えないと、そもそも運動共感の研究プロセスが説明できないと考えていました。感性工学では、正面から見た車をどう感じるかというのを、質的な評価だけじゃなくて、脳波などで量的なところも見ようとしていますよね。これから発展していくアプローチではあると思います。一方で、学生時代に聞いた感性工学の講義のなかで、車を見たときの人の脳波を分析すれば、みんながかっこいいと思う車がデザインできるようになるという話をしていたんですけど、脳がそう言っていても、本当にその人がかっこいいと思っているかというのは、かならずしもそうは言えないんじゃないか、と感じたのを覚えています。
平井:
それだと迎合的なデザインにしかならないし、新しい水路をつくっていく方がクリエイティブですよね。ただ他方で、量的な尺度が入ることも大事だと思うんですよね。ベルクソンの『試論』の段階では量を敵視している論調が見えます。でも『物質と記憶※11』ではそうした考えをアップデートして、量と質の間を真面目にブリッジさせようと考えた結果、記憶の議論になって、さらにマルチスケールの議論になったわけです。
ただ主観的な流れの時間があるというので終わりではない。その先があって、われわれが流れる時間を感じているのも身体の感覚運動が実際に持っている0.5秒から3秒というスケールの回路があるからで、これは実際に計測できるものです。ただしそこに計測できるところだけではなく、計測できない面もあるわけで、その間の相互作用を捉えてあげることが必要になります。なぜなら、ぼくらの識別可能性空間は、その両方がないと変形にならないので、その意味では質か量かの片方だと出てこない論点だと感じます。そう考えられれば、感性工学もベルクソン的におもしろい成熟の方向があるかもしれません。
三好:
運動共感もそのまま物体や空間のデザインに応用できるまでには至っていないと思います。動きの研究で言うと、最初にロバート・フィッシャーが運動共感の原石みたいなものを昔の哲学的なスタイルでつくって、それを受けてかはわからないですけど、ポール・スリオが動物の歩行をストロボ写真で撮ったりしながら、科学的な分析と合わさった美学というものをつくろうとしました。その頃からサイエンティフィックなアプローチとフィロソフィカルなアプローチが一体になった流れができてきたんだと思います。
ディー・レイノルズが運動共感を論じる頃には、ミラーニューロンの理論を参照しつつも、それに縛られない形で、アーティスティックなリサーチを独自に組み立てていきました。さらに昔の生態心理学でも、人間の知覚を物理学的に対応づけして、感覚的な部分と科学的な部分を結びづけようとしていたと思います。
本を読んで平井さんが大切にされていると感じたのも、そういった点でした。哲学書ではあるけども、スピリチュアルに展開されていくわけではなくて、最近の科学的な文献を参照したり、その一方で盲視の話が出てきたりするところが、読みやすいと同時に説得力がありました。
平井:
ありがとうございます。運動共感の話で、人だけではなく物も含めると言いましたけど、動かないものへの運動共感はかなり大事だと思っています。ぼくの本の4章で「運動図式」という概念を説明しているんですが、この運動図式は通常の意識的認知で用いられるものなので、対象が動いていなくてもその輪郭をたどり、動きとして捉えるんですね。静止物にも動きがあるというのは、ある人々にとってかなり自明なことです。だけど、説明してもなかなかピンと来てもらえないことも意外と多い。
ぼくは美大出身なんですが、最初デッサンを習っていたときに、ここの動きが描けていないというフィードバックをもらうことがよくありました。対象はずっと静止しているのに、その動きを捉えろと言われるんですね。自分の中ではそのときにアップデートされて自明なものになったのかもしれません。逆にそういう訓練を受けていない人にとっては、動きという言葉ではピンとこないのかもしれないですね。
三好:
デッサンの練習を繰り返す中で、静止物の中に動きが入っていないと思うことができない知覚になっているのかもしれませんね。
平井:
三好さんの本の中でも動きの“aesthetic”の部分が大事だと書かれていましたよね。実際に動いているかどうか、つまり計測量的に対象物が動いているかどうかではなくて、動いていなくても、動きの感じというのは起こりうる。これは僕の本の序章で述べた「静止にも時間がある」という論点につながります。対象世界からそれを観察している自分を外に出してしまえば、あたかも絶対静止みたいなことが言えそうになるんですが、実際には「さっきから止まっている」ことを経験しているので、止まっているという状態が成り立つためには時間が絶対必要になります。それはエージェントが対象と相互作用しているから可能になるので、それも埋め込まないとできません。むしろそれを埋め込み忘れると主体が虚焦点みたいになってしまうんです。
だからこれは根本的にベルクソン的なアイデアだと思うんですよね。世界が動いていると言っているのは、ヘラクレイトスのようにすべては流動であるみたいな意味ではないんです。時間はマルチスケールの中でその形をとるので、その時間のギャップを外に出して、同質的な時間だけで何かが運動しているという状態を生み出せると思ったら大間違いなんですよ。
三好:
ぼくが静止を動きのエレメントのひとつと捉えたのも同じで、静止を観測しているオブザーバーの存在を入れると、そこにも時間が流れているからでした。
平井さんの本では、何か決断するのに時間がかかるのではなくて、決断できる状態になるのに時間がかかることについて、「時間を稼ぐ」という言葉で説明していましたよね。あとは瞬間的に反応する物質のレベルじゃなくて、人間の中に入力があったときの反応にすこし遅れがあるのは、入力に対する反応や選択肢をつくるためのラグがあるからだという話もありました。
Research through Designという実践を通した研究でも、「時間稼ぎ」をしている部分が大いにあるんですよね。自分が作っているものがどういうものなのか、そのときには理解しきれなかったとしても、つくり出しながら研究を進めているときがあります。そうしていると、最初につくったものが、あとになって時間差で効いてくることがあったりします。
自分の本では、ラナルフ・グランヴィルという人を何度か引用したんですけど、彼が中心的な役割を果たしたデザイン・サイバネティクスの領域に“willfull unknowing”という言葉があります。「意図的に知らない」という意味なんですけど、先ほどの決断に時間がかかるのは決断できるようになるための時間を要しているからだという話に通じると思いました。個人的にも、静止に運動共感があるということはわかっていたけど、そこでわかったことにせず、ちゃんとわかるまで待つということをしていたんじゃないかと思います。
平井:
それは本当に大事ですね。ぼくも「答えで蓋をするな」という言い方をするんですが、情報が溢れていて答えがいくらでも手に入る世界だと、それを取り入れすぎてしまって、すべてが俯瞰的になって受動的になるんですよね。ぼくはそれを恐れているんです。問いのアンテナが立つのは、それがオープンな間、解けていない間だけじゃないですか。だから、遅延された問いが開いている状態こそ、われわれの感受性が一番敏感な状態じゃないかと思います。
「美大にいたのに今なぜ哲学をしているのか」とよく聞かれるんですけど、そこまで変わったことをしているつもりはないんです。でも基本的には何をしている人でも同じじゃないかと思います。自分が世界と出会う中でいろんな問いが起こる。デザイナーやアーティストも、それを形にする作業をしていて、哲学では論文や本のような道具で形にしている。だけど、それはいずれの活動においても、いつも暫定解なんですよ。
あえて妥協して答えにする必要はないし、むしろこれぞファイナルアンサーと思って出しても、結果として暫定解にならざるを得ないことばかりです。それは問いというものが、こちらが手を抜けるほど簡単なものではないということなんですよね。むしろ安心して全力の答えを出せばいい。問いはまたその答えを超えてくるから。その時間スケールギャップを楽しめるようになってくると、どんなこともおもしろく取り組めるようになる気がします。