近藤宏:
私自身も日本語版の翻訳に関わったのですが、2013年に英語で発表されて世界中で大きな反響のあった“How Forests Think(邦題:『森は考える※1』2016年刊行)”の著者であるエドゥアルド・コーンさんに、本日は主に三つのテーマについてお伺いしたいと思っています。ひとつ目は、『森は考える』についてお尋ねしたいと思います。つぎに、民族誌的現実について分析し、考える方法について。そして、最後に、『森は考える』以後に、どのようなことをなされてきたのかについてお聞きしたいと思っています。まずは、この刺激的で挑発的なタイトルの著作『森は考える』で、何を目指されていたかを振り返りっていただけますか。
『森は考える』はどのように作られたのか
エドゥアルド・コーン:
『森は考える』は民族誌なので、人々と共に暮らし、その人たちがなすことに耳を傾けるなかで出来上がりました。わたしがフィールドワークを行なった地域では、人は人のあいだでのみ暮らしている訳ではありません。彼らは森のなかで、人と人以外の様々な存在に囲まれて暮らしていました。そのため「民族誌を行なって(doing ethnography)」、様々な存在に「耳を傾け」ました。そこには「人びとの声を聞くこと」以上の意味があったのです。私は、人ではない存在たちの声にも耳を傾けていたのです。わたしは、人々がこうした「他なる存在」と交流する様子を傾聴していました。
そのうち、人々が森にいる存在とコミュニケーションをとるときには、言語がふつうとは少し変わったかたちで使用されているのに気付いたのです。そのようにして、人々が何をしているのかを理解するには、わたしがもともと考えていた人類学自体についても変えていかなければならないことに気付いたのです。森のなかで様々なたぐいの存在と関わり合う人々と真の意味で一緒に過ごすこと。それがこのプロジェクトの根本にあります。

近藤:
コーンさんが、そのような発見を一冊の本にまとめる際に、最も難しかったことは何でしょうか。
コーン:
いろいろな段階で多くの困難に出くわしました。私は、本書の基になる調査を行なったエクアドルでは四年間を過ごしました。現地のフィールドワークも、その段階のひとつです。そのフィールドワークは博士論文のプロジェクトの一部だったのですが、ともかく、本当に長い時間をそこで過ごしたのです。「ああ、全く何も起こらないな、退屈だ」と感じたこともありました。しかし、物ごとが急にひとつに結びついて、ひらめく瞬間もあって、後から振り返ってみると、本書にあげた最も刺激的な発見のいくつかは、ほんの数秒の間に起こったことだったのです。
そうした発見については、その後かなりの時間を割いて執筆することになりました。時間性というのは、面白いものですね。とくに何もしないことに多くの時間を費やすこともあれば、瞬く間にことが起こる状況が突然訪れたりもします。そんなふうになるには、自分がその場に居続けることが必要だったのです。いずれにせよ、この本では森が考えるとはどのようなことであるのかを説明しようとしています。そして「なぜそんなことが言えるのか」「人類学の枠組みでもそんなことが言えるか」といったことを、本書を読んだ人たちが話題にできるように、揺さぶりをかけることが狙いなのです。
わたしはこれまで、人類学が多くのことを伝える術を持たないことに歯痒い思いを抱いてきました。人類学者が決まって言うのは、この人たちはこう考え、あの人たちはこう考えている、といったことです。わたしには、そんなことをやっていたのでは、誰かが言った何ごとかを記述する以上に先に進んでいくことができないように思えたのです。
人が他なる存在と関わり合っているという事実があったため、わたしは、研究のやり方は他にもあるのではないかと考えたのです。その結果、本書で扱った研究に結びつきました。というのは、彼らは、森のなかで事を成し遂げるためには、社会的現実や文化的現実 —— 人類学者が日ごろ研究対象としているようなたぐいの現実 —— とは異なる現実へと踏み込んでいく必要があったからです。人々は、他なる存在とは異なる水準で交流しています。話し方や考え方を変えざるを得ないほどに異なる水準においてなのです。わたしはこうした点にとても興味を抱きました。
こうしたことをひとたび理解し、その跡を追うようになれば、その現実が見えてくるようになる、そしてもしその現実にきちんと目に向けるならば、読者が人類学であると考えていることを問わずにはいられなくなる。そうしたことを本書では示そうとしました。人類学は、もはや文化について語るだけではなくなっています。人間であるとはいったい何を意味するのかを考え直すよう、読者は促されるからです。こうしたことすべてにわたって書かれているのが本書です。
§
近藤:
『森は考える』でコーンさんは、人類学者として、現実の新たな捉え方を探っていたのですね。人類学者は、現実を文化的現実として描写することに慣れていて、「ある人たち」だけにとっての現実、つまり他の誰かの現実として理解しています。それに対して、コーンさんが行なったのは、このような現実を、他なる存在の現実、そしてわれわれの現実にまで広げる方法を探すということだったということですね。つまり、「他者の現実」を二つの方向に広げることだと理解しました。
コーン:
まさにそれこそ、わたしが試みたことだったのです。このように現実について語ることができるという事実を示したいと考えました。だからこそ「いかに森は考えるのか」という問いが浮かび上がってきたのです。 わたしは、そこにこそ問題があると指摘したのです。それは、人文科学や社会科学、人類学にある真の問題、これまではなかなか取り組みえなかった問題です。人間を超え、人間が世界をどう見ているのかは超えていくことなどできやしないと考えているのです。
跳ね返ってきた『森は考える』のインパクト
近藤:
なるほど。『森は考える』には、様々な反響が寄せられました。もし気になった反響があれば、教えていただけますか。好意的な反響のなかで、意外だったものはありましたか。
コーン:
学術的な反響は、概ね好意的なものだったと思います。それらは興味深いもので、今でもたまに思い返しています。なかには、わたしの意図を理解していると感じるものもありましたが、その他にはどうなのか分からないものもありました。わたしの意図を十分に理解できていないと感じる表面的な反響もありました。しかし、あまり期待はしていなかったのでその分とても刺激的に感じたのが、専門の人類学外からの反響でした。とくに音楽や芸術の分野で重要視されたことでした。これはとても刺激になりました。
§
近藤:
どのような反響だったのですか。
コーン:
リザ・リムという音楽家がいます。彼女は、中国系オーストラリア人で、現代クラシック音楽のすばらしい作曲家です。彼女は、「How Forests Think」という曲名の交響曲を作曲しました。
これには本当に感動しました。彼女はこの曲を12種類の楽器のアンサンブルとして書きましたが、そのなかには中国の楽器である簫が含まれています。この楽器は、彼女がこの交響曲を演奏する際にはいつも使用されています。簫は、一人の演奏者が演奏します。中国の音楽家がこの楽器を使用するレパートリーを作ったのですが、息を吐いたり吸ったりして音を出すので、とても有機的です。それを演奏するプロセス、さらに、演奏者同士が調子を合わせようとする様子がとても面白いと感じました。作曲にわたしは全く関わっていませんが、わたしの本『森は考える』がインスピレーションとなってこの曲ができたと聞いて、とても興奮しました。
当たり前ですが、珍しいことですね。専門書の議論を参考に音楽に置き換えるなど、普通なら考えられません。この本はわたしの手を離れて歩き出したのです。何が起こっているのか、わたしには理解できませんでしたが、後になって、われわれは連絡を取り合うようになり、カナダ南部にあるバンフという町の芸術センターで、音楽コース、つまり夏期の音楽コースを共に教えました。それ以来、われわれは一緒に活動をしています。わたしにとって、このコラボレーションはとても刺激的なものです。
§
近藤:
音楽家としての彼女の反応が、今では新たなコラボレーションへと発展したのですね。他のアーティストは、いかがでしょうか。
コーン:
本当に新しいことが起きているのは、アートの分野ではないかと思います。アーティストたちはアイデアを求めており、気候変動に関心を強く持っています。アーティストたちは、拙著から、気候変動について表現する方法を見出しました。
また、アートにおける問題には、表象に関するものがたくさんあります。本書では、生ある世界と私たちの関係性を本当に理解するには、表象について理解せねばならないということを強調しました。私たちはいかに事物を表象するのか、また他者がいかに事物を表象するのか。そういったことを理解しなければならないのです。
§
近藤:
日本では、ある美学の専門家が『かたちは思考する』という本を執筆しています※2。このタイトルには、『森は考える』の影響が見られます。内容は、芸術家や画家の創作過程を通して、図形やかたちそのものがどのように考え始めるのかというものです。あなたと彼の著書は、どこか似たような考えに基づいているようです。
コーン:
そうですか。ぜひ彼と連絡をとってみたいですね。
§
近藤:
わたしの知る限りでは、日本でも、人類学以外の分野からも創造的な反響がありましたよ。
一流の人類学者とは民族誌的思想家のことである
近藤:
では、つぎのテーマに移りたいと思います。翻訳者として感じる本書の魅力のひとつは、フィールドワークの経験で得られた民族誌的現実を独特な仕方で読み解いていくところにあると思います。あなたが現代人類学を論じたレビュー論文※3のなかで、一流の人類学者を「民族誌学的思想家」だと表現していますね。民族誌的現実が人類学独特の広い視点をもたらしていると述べているように思われる、喚起的な表現だと思います。民族誌的現実をめぐる考え方や、民族誌的現実を通した考え方というのは、いったいどういうものだと思いますか。
コーン:
人類学という分野が非常にユニークである点として、観念とその歴史に高い関心を持っていることも挙げられるでしょうけれど、結局のところ、方法論が重要なのです。民族誌とは、個人的な思い込みを少しでも取り除いて、事物に対する考えを変えるような何かと向き合う方法を見つけるための手法です。
民族誌がそうした手続きの中心にあるのも、それが、あらゆることを考え直さざるを得ない場のようなものだからなのです。事物に対する思い込みを思い切って捨てなければなりません。そして、それがまさに廃れることのない、変わることのない形式なのです。形式というよりも、変わらず進行しつづける、そのようなものだと言ってもいいかもしれません。人類学のなかでも優れたもののひとつは、方法にあると思います。それは、自らの道具立てや思い込みの全てを問い直すようなものとしての、耳の傾け方なのです。
§
近藤:
『森は考える』では、数秒から1分ちょっとの間に起こったことを詳細に描写し、そこにいかに民族誌的に深い意味があるのかを説明していましたね。民族誌的現実について考えることが、われわれの考えの前提を再考する機会となるという点は、多くの人類学者が同意すると思います。ただ、本書にはそれ以上のもの、現実の豊かさを伝える方法のようなものがあるように思えます。
コーン:
はい、そうした現実にはいくつかのことが含まれていると思います。まず、本書を執筆するときにとても助けになったのは、会話や、起きた出来ごとに対する非常に丁寧な描写の録音データがあったことでした。些細な事柄に対する豊かさは、ここから生み出されています。また現実の細部は、言わばいくつもの層をなしているのだと受け止めまることができました。そして、その点に留まることにも時間をかけたのです。そのようにすることで、物ごとを様々なレイヤーから比べることが可能になったのです。
現地の民族生物学というレイヤーではできる限りの動植物の調査を行ない、さらには民族誌的なレイヤー、歴史的知識のレイヤーへと踏み込みました。これらの事柄全てによって、様々な事物を探り当て、関連づけることが可能になったのです。そしてもちろんのこと、それらの多くは、書いているあいだにやって来たものだったのです。
わたしは、書くこと自体が、関連性や物ごとを把握する方法であると考えています。なので、別の事柄をコツコツと探り当てるために、立ち戻っては別の道のりを探るという方法を取ったのです。本書を書いていたときに行なっていたことのひとつがそれです。
本書は博士学位論文を再考し、完全に書き換したものです。学位論文にある文章は、本書には一文も入っていないかもしれません。しかしそれでも、土台にあるプロジェクトは同じでものですよ。扱われているのは同じ素材です。
学位論文と本書の文章は全く異なりますが、同時に全く同じものです。ただこの研究においてとくに刺激的だったのは、たくさんのフィールドノートを手にしていたときです。ノートはすべてタイプされていました。すべてコンピュータに収められたのです。研究期間も終わりに近づいており、これらのノートをすべて手に取って丁寧に読み込み、そのノートに対してさらにノートを作ったのです。フィールドノートにある大きなテーマはそれぞれ何だったのか、ノートを取ろうとしたのです。
わたしは最終的に約125ページの長さの文章を書き上げました。これらはフィールドノートに対するノートなのです。それはこれまでになく興奮した時間でした。自説を立証し要点を示さねばならないとき、すべてが関連している様子を示さなければならないとき、そうした考えを書くことは難しいように思われました。ですが、パターンだけを見ているとき、物ごとを見ているとき、洞察力が発揮されているときには、すべてをありのまま残したいと思う気持ちによって、書くことに対する情熱が続いたのだと思います。そうできるよう、深く注意を払っていました。こうして本書が出来上がったのです。
パターンを見つける、森を録音する、森の思考が人間の言語を変える
近藤:
おっしゃってることに、とてもワクワクします。それが、『森は考える』のなかでも述べられている、パターンを見つけるための方法だったのですね。
コーン:
そうなんです。まさに、パターンを見つけることだったんですよ。類似性について、ともいえるでしょう。森はいかに考えるかが本書のテーマであり、森の考え方が、全体像として繋がりを持ち始めたのです。そのような思考を自分の創造的思考においても養おうと努めたのです。そして、そのために文章を書くことがどれだけ助けになったことか、ひとたび物ごとが分かり始めて並行して見えてくるものがあるのは面白いですよね。非常に興奮します。
実は、わたしは文章を書くのが上手ではありません。明解な文章を書くのが苦手なのです。すごく長い時間をかけて書いています。数段落を分かるようにするために数週間をかけることさえあります。そのような文章が説得力を持つようになるのは、こういった文章に対して「この文は何だ?わたしはあまり好きになれない。何てつまらないんだ!」といった自分の心の反応を大切にするのです。そして、より良い文章が書けるよう、できる限りの努力を続けています。
§
近藤:
あなたが思考する上で、パターンや類似性を見つけることが非常に重要であるとおっしゃっいましたね。著書では、類似性やパターンを見つけようとするのは生命特有の考え方だというベイトソンの研究について触れていましたよね※4。ベイトソンの議論を見つける前に、なんとあなたはすでに彼が述べていたこと、つまりフィールドノートからパターンを見つけ始めていたのですね。生命が考えるように、あなた自ら考え始めていた。
コーン:
レヴィ=ストロースは、数学、音楽、人類学が、真の天命(vocation)であるという素晴らしい発言をしています※5。なぜなら、それらの分野は、自分自身によって、あるいは、自分自身のうちに、すっかりと見出すことができる天命だからです。自分のなかから引き出すことができるのです。
そして、自分の発見が、フィールドとの関わりが、考えるためのツールを与えてくれるという意味において、まさしくその通りだと思います。そして、深く考えているときは、その考えが他の人の深い考えと合致するということは十分にあり得る話なのです。もちろん、ベイトソンとわたしは同じ考えにたどり着くかもしれませんが、それはその考えが本当はわれわれの考えではないからなのです。それは、われわれが耳を傾けた世界から示されたものなのです。
§
近藤:
日本で行なったプレゼンテーションでは、森での録音を使って、木が倒れる音を聴衆に聴かせていましたね※6。わたしも人類学者としてフィールドワークを行なうのですが、わたしは木の倒れる音を録音するために森にレコーダーを持って行くという考えは全くありませんでした。レコーダーをわざわざ持って森のなかを歩こうということは、どのように思いついたのでしょうか。
コーン:
わたしが用いる方法のひとつは、インタビューではなく、自然のなかや、自然に囲まれて起こっている物ごととして、人々が普段どおりの文脈で話している様子を捉えようとするのです。そのために、テープレコーダーを森に持って行なったのです。
§
近藤:
フィールドワーク中はいつもテープレコーダーを持っていて、どこでも録音を始めていたということですね。
コーン:
森に入るときは、たくさんの物を持って行くのですが、何も使わないときもありました。今、どうやっていたかを思い出します。わたしは本当に興味深い会話を録音したときもありますが、いつも上手くいくとは限らず、結果的にはどうということのない録音もたくさん残っています。

近藤:
『森は考える』で、コーンさんはイメージで考えるという表現を使って、人類学者の考えに特有の感性を表わしているように思われます。そして、著書のなかの写真はとても美しく、とても示唆に富んだものになっているように思います。 イメージで考えるというアイデアは、どのように思いついたのでしょうか。とくに刺激を受けた経験や研究、議論などはあったのでしょうか。
コーン:
わたしがフィールドワークを行なった地域の人々は、数百年前はどの言語を話していたかあまり分かっていないような人びとです。どのようなことばを話していたか、誰も知らないのです。
数百年前から現在にかけては、ペルー由来のケチュア語族のひとつであるキチュア語を話しています。この言語は、インカ文明と共に北方に広がり、アンデス系諸語と密接に関係しています。アマゾンで話されていることには、アンデスで話されていることと密接に関連するものがあります。しかし、興味深い例外もあります。そのひとつが、アマゾンの方言には、アンデスにおける同じ言語には存在しない「擬音語」が、ひとつのクラスと呼べるほど多く生まれているということです。
わたしはそのことに注意を向けるようになりました。わたしは、これが別の考え方への小さな入り口のようなものだということに気づいたのです。そうした擬音語は、いろいろな事を為すことばです。森のイメージを創造することで、森のことを語っているのです。音のイメージ、行動のイメージ、行動が展開されてゆくイメージ。普通のことばの使い方とは、全く異なるものです。そのことばはどれも、本当に写象主義的(imagestic)なのです。それらのことばを調べ、なぜ使われているのか、なぜ森のなかでなのか、なぜアンデスでは使われずにこの場所では使われているのかについて分かろうとしました。
そうしたことがわたしの関心を引くようになり、イメージを考えることへの足掛かりができたのです。そしてわたしが考えるには、つまるところその考えによって、人が森のなかで考えることが可能になるのです。それが「森の思考」にとても似ているからなのです。つまり、言語で用いられているような象徴、つまり恣意的な記号を伴わない思考のかたちであるような、森にいるあらゆる存在の思考にとても似ているのです。
非常に興味深いのは、それがどれほど模倣されるのかによって言語が変わってくる、という点です。また、そうした模倣による部分は言語そのものにうまく収まらないことが多いという点も、興味深く思っています。イメージは全体で、たとえば活用変化させることはできないからです。そして、他の言語にもこのようなイメージ的な部分があるのも面白いところです。日本語にも多いのではないでしょうか。
真の思想家であるアマゾンの人たちとともに、倫理的なプロジェクトへ
近藤:
なるほど、すごく面白いですね。ところで、三つ目の話題に話を移したいと思います。ここからは、「森は考える」以降のプロジェクトについてお尋ねします。現在進められている、「Forests for Trees」というプロジェクトについて教えてください※7。そこでは、アニミズム的概念を実際の環境政策に生かし、関連づけようとするエクアドルの人びとのネットワークと協力されていますね。彼らはどのような活動を行なっているのでしょうか。また、彼らとどのように仕事をしており、そこから何を学びましたか。このようなコラボレーションを通して感じることはありますか。
コーン:
『森は考える』という本は、様々な意味で存在論的な本でした。その本では、世界における物ごとのあり方をテーマにしています。どちらかと言うと学者向けに、世界は現在考えられているものではないことを述べた本でした。もしそうなら、哲学的・概念的な枠組みを超えて、もっと世界に対して正確なものにしていかなければなりません。とくに世界をめぐる議論としては、われわれはみな何らかの仕方で考える森に暮らしているということがあります。それはひとつの実在です。だから、そのことについて書いてみたのです。すると、新しいプロジェクトがかたちになり始めました。
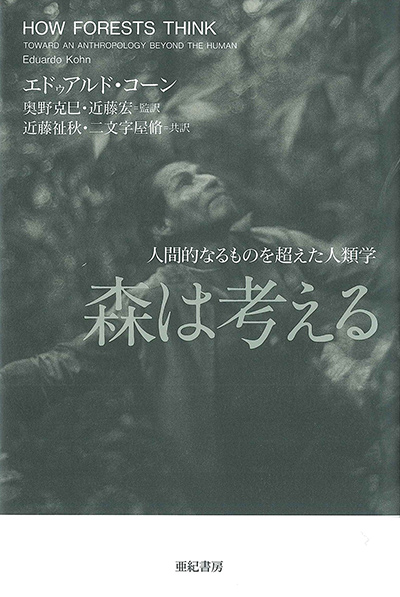
『森は考える』の刊行後に、わたしは「待てよ、考える森というのは実在するだけではなく、良いものでもあるんだ」と考え始めたのです。それには価値があります。そして価値があるならば、その価値が壊されないようにするために、そして世界にそうしたものを増やすために、われわれができることは何かを考え始めました。こうして、わたしの研究がより倫理的なプロジェクトに繋がったのです。存在論的なプロジェクトは、倫理的なプロジェクトに変わっていきました。
そうして、わたしはエクアドルに戻りました。わたしは、2015年から16年にかけて、研究休暇期間をエクアドルで過ごしました。その期間に成し遂げたかったのは、アマゾンにある他のコミュニティと共に活動することでした。これらのコミュニティとは、こうしたたぐいの倫理的プロジェクトを分かち合うことができました。そのプロジェクトは、われわれの生き方やなすことではなく、本当に守るべき良いものなのです。そのことを、わたしたちは人々に伝えています。こうしてわたしは、アマゾニアにある森を石油会社や道路工事から守っている人びとと同盟を結び、世界の人々に伝えようとしています。そうした人びとと共に活動するようになることで、わたしの研究もとても刺激的なものとなりました。
「Forests For The Trees」のという本についてのアイデアですが、タイトルは英語のことわざから来ていて、日本語に相当するものがあるかどうかわかりませんが、英語では「木を見て森を見ず(you can’t see the forest for the trees)」と言います。この表現は通常、細部ばかりに気を取られて全体を見失うことを意味しています。一般性が見えていないのです。つまりこの表現について考えられるのはたいてい、人間には抽象化する能力が特別に備わっているということです。本当にしっかりと考えているときは、適切な抽象化を行なっています。わたしもこの表現について考えていますが、同じ比喩を、文字通りに、また比喩的に考えています。
何が言いたいかというと、森のようなものが存在するということです。森は、われわれがつくりあげる、単なる抽象化されたものではありません。森とは、単なる木々の集まりではないのです。それは創発的な特性ですから、それを構成する諸要素に還元できるものではないのです。ひとつの森という事物が存在し、その森には木々にとって良いものを言い表すための何かがあるのです。比喩的に言えば、われわれはその木々なのです。
つまり、わたしは今では、森とは何かを語るのではなく、気候変動や恐ろしい生態学的危機に直面しているわれわれを、森がどのように導いてくれるのかを問うているのです。今までの人間中心の倫理観が通用しなくなっていることは明らかです。われわれを導いてくれる、より大きな世界の声に耳を傾ける方法を見つけなければなりません。しかし、どうしたらいいのかがあまりよくわかっていないのです。
森のなかに導きを見つけるというのは、実際にはどういうことなのか。アマゾンに暮らす人びとは、その方法について素晴らしい答えを持っていました。そのため、わたしは真の思想家である、アマゾンの思想家、精神的なリーダーたち、物ごとを探求する方法や問いかける方法、関わり合う方法を絶えず問い直すこの人びとと共に活動をしています。彼らと共に事をなすのはとても刺激的で知的な旅ですが、いつでもその目標は、気候変動に対する具体的な方法を考え出すことにありました。
§
近藤:
最近、エクアドルの原油流出事故について、他の著者と共著でアルジャジーラに短い記事を寄稿していましたね※8。この記事も、ネットワークのメンバーとのコラボレーションの産物なのでしょうか。
コーン:
はい、彼女もメンバーです。 わたしは仕事の幅を広げています。以前、アヴィラで仕事をしていた頃の仕事は、わたしと、コミュニティと森だけでした。今ではいろいろな人と共に活動をしています。そのひとつに、サラヤクとサパラという2つの先住民族のコミュニティとのコラボレーションがあります。わたしはどちらとも共に仕事をしていますが、なかには密接な共同作業になるものがあります。わたしは、彼らのアニミズムを政治的声明文書に翻訳する作業を手伝っています。
これは新しいからこそ非常に面白く、魅力的な仕事です。わたしは、教えながら、ある種の翻訳を彼らが行なうことを手伝っています。このことは、その場所で起こっていることを描写する機会を与えてくれるだけではなく、描写することが物ごとに対する考え方といか関係しているかを教えてくれます。こうして、彼らがそうしたことを行なうのを、手伝ってきたのです。さらに、共に執筆もしています。
そうしていると、彼らの夢やビジョンを見る仕方が重要なものになったために、書くことに対する私たちの考え方が変わりました。ことばに対する感情面での応答が、大切になってきたのです。コミュニティとの共同作業の他にも、アーティストとの共同作業もあります。ミュージアムを作ろうとしています。パズルのもうひとつのピースは、弁護士や森の保護に興味のある人たちとのコラボレーションです。
なので、アルジャジーラの記事は、活動家であり学者でもあるマヌエラ・ピークとのコラボレーションから生まれたものです。彼女とわたしは、法廷で争われることになった原油流出事故の証人の友人です。そのため、それに関する記事を書いたのです。
§
近藤:
先住民のコミュニティと書いた文章は公開されたのでしょうか。
コーン:
はい。なかでもとくに面白いのが最初の一本で、それが理由でこのような仕事をするようになりました。サラヤクのコミュニティが執筆し、完成させました※9。つまり、わたしは書いていないのです。編集作業を手伝い、よりまとまったものにしただけです。
文章は、初めからよく練りこまれたものでした。キチュア語で「Kwak Sacha」と呼ばれる、生きている森を意味する概念はすでに出来上がっていました。「生きている森」は、パリで開催されたCOP 21気候サミットで、彼らが発表した宣言です。わたしはサラヤクの人びとからこの宣言を発表できるように、編集する手伝いをしてほしいと頼まれました。そして、それを各国の首脳の前で発表したのです。多くの人の前で発表を行ないました。
文章はアニミズムに関するもので、人類学者にとってはそれほど驚くべきものではありません。このようなアニミズムは、アマゾンの先住民の考え方として重要な部分を占めます。しかし、この文書が他と一線を画するのは、彼らが理解しそれに従い生きているアニミズムを取り上げて、「もし、わたしたちこそが法律を作ることができたら、どうなるだろうか。それによって、法律や財産、主権や権利に対する理解は、どう変わるだろうか」と言っているところにあります。
彼らはアニミズムの考えを政治の領域に持ち込み、どうしたら押し戻すことができるのかを示しています。まずこの作業が終わると、他のコミュニティ、サパラがわれわれの活動を聞いて、森との関係についての知と彼らのメッセージを世界に伝えるために、いくつかの法的な活動を行ないたいと考えるようになりました。これはとても面白いプロセスです。というのも、森の声を聞く様々な方法を見つけながら、そうした文章を書ことになったからです。とても深められています。今までに二本の文書を仕上げ、三本目に取り掛かっています。
世界に耳を傾け、イメージ的な地図制作をせよ
近藤:
コーンさんは、ある論文で、「時代が求める倫理的実践の一環として森の考え方を育てていく」という決意を表明していましたね※10。人類学は、現代にどのような倫理的プロセスを提供できるのでしょうか。あなたは、われわれの今をどう捉えて、現代における喫緊の課題とは何なのでしょうか、人類学は現代にどのような貢献ができるとお考えですか。
コーン:
現代の大きな問題は、気候変動という危機だと思います。皮肉めいて面白いのは、この気候変動は、人間が原因のものだという点です。それは人間のあり方に対する理解を変えてしまいます。実際にこのような影響を与えているのが人類の文化であるならば、それを理解した上で、人間とは何かを考え直さなければならないのではないでしょうか。
また、われわれが生きるこの時代は、地質学的には人間の時代である「人新世」としばしば考えられています。それを考え直す際に、人類学が関わってくるのは、ごく自然なことだと思います。批判としてだけではありません。単に人間は間違ってしまったと言うだけでなく、これから何が可能なのかを提言する立場として。そう、これは創造的なプロジェクトなのです。
§
近藤:
森と同盟を結ぶ新たな方法を考えだす必要があるのですね。
コーン:
はい、その方法を見つけなければなりません。人類学的な問いとして興味深いのが、その解決策が耳を傾けることから生まれるというところです。それを成し遂げるには、いかになされてきたのかに耳を傾け、習得することが必要になるのです。こうした倫理的アプローチを面白いと思うのは、あることが良いとか悪いとか、あるいは道徳的規範を学ぶための異なる場所が見つけられる、と述べている訳ではないからです。その倫理的アプローチは、あなた自身が答えを見つけられると伝える、世界に耳を傾ける特別な方法で、耳を傾ける様式は、生ある世界にある様々なダイナミクスの一部として既に存在しうる、ということを言っているのです。
ここにもある種の並行性、つまり物ごとをめぐるわれわれの考え方との間にあるイメージ的な地図制作(imagestic mapping)が、改めて存在するということです。その地図を通して、そのかたちを、世界に事物が到来するプロセスを通して、事物を考えることを学ぶのです。
§
近藤:
今日はインタヴューに答えていただきまして、ありがとうございました。エクアドルの人々とコラボレーションした文章を読むのが楽しみです。人類学者だけでなく、気候変動や環境災害の問題を真剣に考えるすべての人にとって、非常に重要なことではないでしょうか。
コーン:
今後、もっと一緒に何かができるといいですね。



