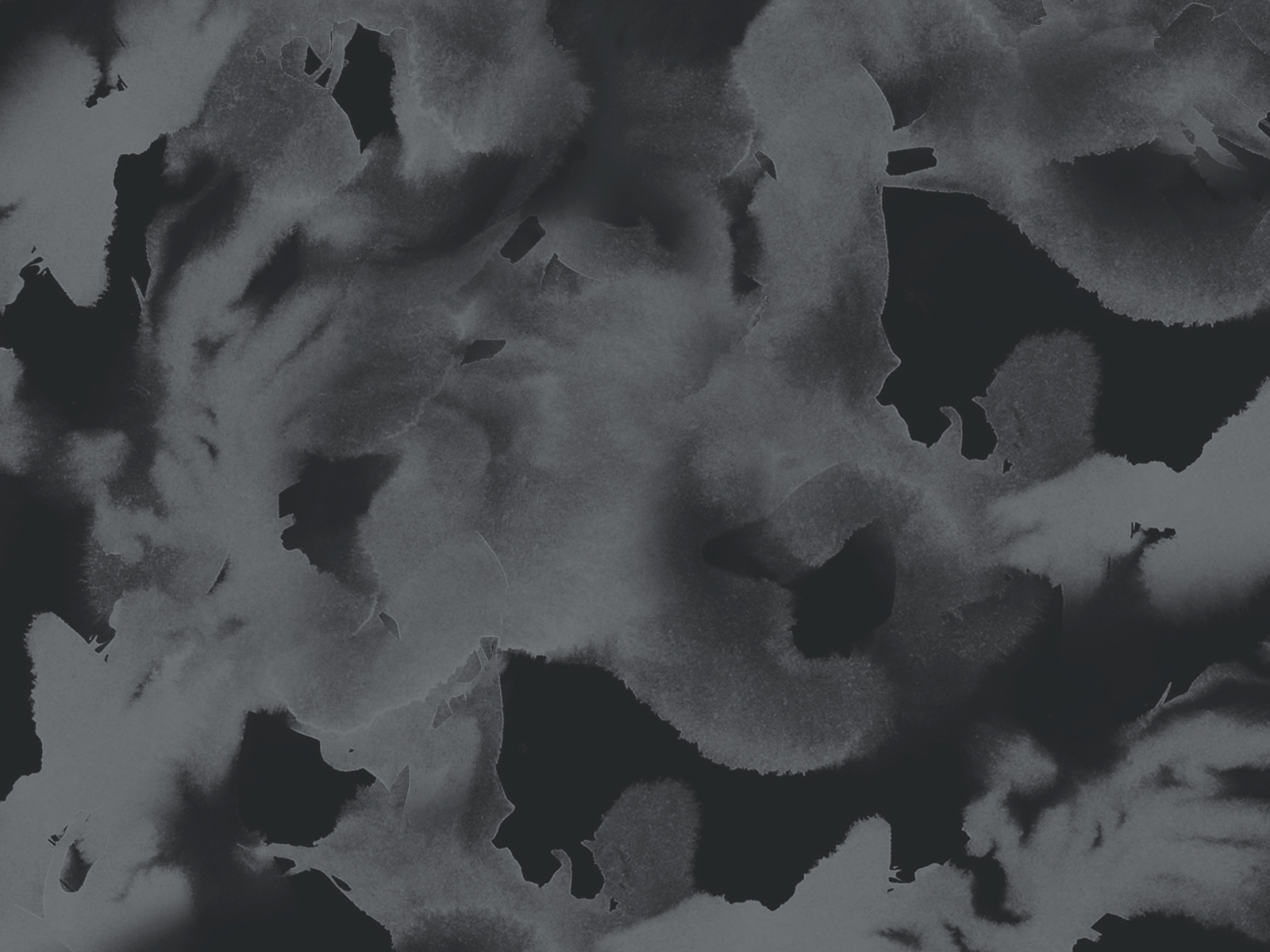人類学を複数化し、問題の裏の不在に共感する
奥野克巳:
第2部では、「More-Than-Human」シリーズ※1に掲載された、ファインさん、コーンさん、パンディアンさんのインタビュー記事を取り上げていきます。引き続き、広島大学大学院博士課程後期文化人類学専攻の大石友子さん※2と東京大学大学院博士後期課程フランス文學専攻の中江太一さん※3に話をうかがいながら、近藤祉秋さんと私で整理していきたいと思います。
村津蘭さんによるインタビューの中でナターシャ・ファインさんが注目するのが、モンゴルの医療です※4。モンゴルの人々が、げっ歯類のマーモットを狩って珍味として食べるのは、その肉に強力な治療性があるとされているからです。他方で、マーモットは、毎年若者に死をもたらすペスト菌の保有動物です。モンゴル人はそのことをよく知っていて、自然の中の観察を通じて、マーモットの動きが鈍いと、ペストが潜んでいることを知る民俗知を持っていると言います。
モンゴルにおける動物由来の感染症に関する観察行動から、一体何が言えるのでしょうか。ファインさんは、ウイルス源を特定して責任の所在を配分するのではなく、ウイルスの異種間の移動に着目することもできるはずだと言います。そのような見方を発達させてきたモンゴルの牧畜民の社会では、「ワンヘルス」に先立って、古くから人の医療と動物の医療を区別してこなかったため、「予防法」的な医療の仕組みが発達しています。モンゴル医療では、土地の状態と人や家畜の健康が相関するという視点で捉えてきたという点も示唆的です。
ファインさんへのインタビューの後半では、人類学の表象の問題が取り上げられていました。彼女は映像人類学の方法として、映像を見る観客が、映し出される対象と一緒にいて、自分たちが全体の一部であるかのように感じられる「観察映画」を採用しています。映画がゆっくりとしたテンポで始まれば、全体がゆっくりとしたテンポで進むことを観客に想像させます。ファインさんにとって、この映像手法は、人類学が向き合うフィールドの現実、声のトーンや物の手触りなど、フィールドワークを人類学に導入したマリノフスキーが大事だと唱えた「実生活の不可量部分(imponderbilia)」を伝えるのに適したものだと言います。
また、この手法は動物に関して観客に伝えたいことのあり方に適したものでもあります。映像だけでなく、例えばGoProカメラを動物に取りつけるなど、多様なメディア環境を駆使することで、単に論述のスタイルだけではないマルチモーダルな人類学が、彼女の次なる課題だと言います。
ファインさんは、マルチスピーシーズを通じて、動物に対する人間の関わり方はひとつではないと認識することができると述べています。マルチモードを用いて実生活の不可量部分にどのように接近するのかという問題意識も彼女にはあります。インタビューを通じて彼女は、マルチスピーシーズ、マルチモーダルによって、マルチプルな人類学の展望を示してくれたのだと言えるでしょう。
続いては、『森は考える※5』の著者エドゥアルド・コーンさんへの近藤宏さんによるインタビューです※6。このインタビューでは「人類学とは何か」という問いに対する彼なりの答えの模索が感じられました。
前半では『森は考える』がどのように作られたのかが述べられていますが、彼はエクアドル東部のフィールドでさまざまな存在に耳を傾けたと言います。それには、人々の声を聞くこと以上に意味がありました。そうするうちに、森の中で人々がコミュニケーションをするときには、言語のあり方が普段と違っていることに気づいたのです。そのことから、彼が元々考えていた人類学について考え直さなければならないと思うようになった。同時に、人類学は実は多くのことを伝える術を持っていないのではないかということにも気づいたと言っています。
コーンさんは、人類学が、この人はこう言い、あの人たちはこう言っているという記述以上に進めていないことと、社会的・文化的な現実だけを相手にすることはパラレルなものだと見ています。そして、人々が森の中でさまざまなことをおこなうように、異なる現実の中に踏み込んでいかなければならないと考えるようになったと述べているのは、とても印象的でした。
また彼は、個人的な思いを排除して、事物に対する考えを変えるような何かと向き合う方法を見つけるための手法が民族誌なのだと言っています。そのようにしながら、『森は考える』のサブタイトルにもなっている「人間的なるものを超えた人類学」という人類学の新たな展望に、コーンさんはたどり着いたのではないでしょうか。
意外なことに、コーンさんは文章が上手ではないそうで、すごく時間をかけて執筆に取り組んでいる。そのこと自体がまた、関連性や物事を把握する方法にもなるのだと述べていました。
コーンさんのフィールドワークは、レコーダーを森の中に持ち込んで、録音しながらおこなう聴覚的なものだったことについても触れていました。そうした態度は、彼が、擬音語が多い言語体系の存在に気づくことにもつながったようです。擬音語とは音響イメージでもあり、人が森の中で考えるならば、“sylvian thinking”つまり「森の思考」は人間に大きな影響を受けるのです。
哲学的であり概念的な書物である『森は考える』の刊行後に、コーンさんは、森とはよいものであると気づいたと言います。そのことによって、森の価値が破壊されないために、存在論的な思考をすることから、倫理的なプロジェクトに関わるようになりました。コーンさんにとって、森は私たちを導いてくれるものであり、現在彼は、世界の声に耳を傾ける方法を、アマゾニアの思想家である精神的なリーダーたちとともに探ろうとしています。
人新世に関しては、人間が間違ってしまったということを、その概念が示しているというだけでなく、人新世という概念を手に入れることで、これから一体何ができるのかを考える機会にもなりうるし、その際に私たちは、世界に耳を傾けることが大切だと結んでいました。
コーンさんと同じように、人類学がどうあるべきなのかという角度から考えているのが、次の山田祥子さんによっておこなわれたアナンド・パンディアンさんのインタビューです※7。
彼の人類学への出発点は、環境問題を勉強する中で、見捨てられた環境でさえ、現地の人たちにとっては価値があり、重要なのだと気づいたことにありました。そこから、人は間違うこともあるが、環境マネジメントのように間違いを修正すべきという点から出発するのではなく、人がどうして特定の行動を取るのかを理解することこそが大事であると考え、人類学の世界に飛び込みました。
パンディアンさんの人類学は、とても現実的でかつ前向きです。何か問題があるということは、同時に他のやり方で物事をおこなう可能性があることを示している。つまり、何らかの問題は、別の根本的なあり方を想像することにつながるというわけです。
パンディアンさんにとって民族誌とは、ある種の変わった環境論的な方法論です。他者世界への没入を伴う民族誌を通じて、想定外の事態や困難に向き合う開放性や感受性を養い、予測しなかった状況を学ぶのが人類学であると捉えています。
インタビュー記事からは、パンディアンさんの人類学に対する強い肯定的な価値観が伝わってきます。彼にとって「人間性」というのは、他者に共感する同朋意識のことです。そして、それが人類学的な問いを突き動かすのです。人類学者は、目の前に何かを喚起してくれるという点において、映像作家や文化人とさほど違いはないとも言います。
そのことを踏まえて、人類学が果たす役割とは、西洋を独善的なものにした人種主義や帝国主義の遺産に対して効果的に立ち向かうことで、その延長線上に、人間と非人間の境界を越えた人間性も主題化しうるはずだと見ています。そのことによって、西洋の自然・文化の二項対立の奇妙な反復ではない、より強度のある環境概念を、人類学の歴史から見ていくことができるのだと言うのです。
コーンさんが森の中で音響イメージに着目したように、パンディアンさんも思考の物質的な基質として働くさまざまなイメージの重要性を指摘しています。思考は、世界から離れた場所ではなく、世界そのものに属している。人類学者は、そうしたイメージを、自らを通して表象するチャネラーだというわけです。パンディアンさんの言っていることは、コーンさんの「記号過程」的です。そして、それぞれの驚きやアイデアに向き合うことにより、思考や存在の質感を変容させてくれる絶え間ないプロセスこそが、人類学の経験の手法だと述べていました。
人新世については、その概念を用いた現在の状況が現われてきた中で、アジア・アフリカの人たちの役割は小さかったため、非ヨーロッパの営みの側から人新世について想像してみることで、別の可能性が見えてくるとも語っていました。存在感があるものの裏側では、ある犠牲のもとで何かが不在になっていることを、人類学者は考えてみるべきだと。
不在になってるように見える、他の考えの存在感に焦点をあてることで、潜在的な変革へと歩んでいくことができる。近代性とは、他のものが排除されたことによって成立したものであり、失われたものを回復させることもまた、人類学にとって重要なのだと、パンディアンさんは考えていました。
以上、第2部の3つのインタビューの概要でした。
ナターシャ・ファイン:動物をめぐる知を探り、人々の声やモノの質感を現前させる
大石友子:
第2部では、それぞれの方が人類学者として、フィールドで人間以上の関係に巻き込まれながら調査をおこない、その研究成果を民族誌として描き出して世に出すだけに留まらず、創造的なプロジェクトに関与していることが印象的でした。
マルチスピーシーズ民族誌を実践している人類学者の中には、先住民運動などに、コーンさんがおっしゃってるような通訳的、つまり概念の翻訳的な立場で関わっている方が多くいるように感じます。それはおそらく、先ほど近藤さんもおっしゃっていたように、この分野が科学技術の人類学の潮流を汲みつつも、例えばヴィヴェイロス・デ・カストロの多自然主義(multinaturalism)であったり、デ・ラ・カデナの多元的宇宙(pluriverse)※8のような、単一の世界と複数の文化ではなく複数の世界という視座を提示した、先住民の人間と自然の関係性についての議論の潮流を汲んでいることもつながっているように思います。
その中で気になったのは、日本のマルチスピーシーズ人類学においてはアートや文学、哲学などとの協働は見られますが、海外のような積極的な運動との結びつきがこれまであまりなかったように感じられることです。海外と日本の運動のあり方が異なるのかもしれないのですが、この第2部のインタビューで触れられている海外でのアクティヴな活動は、とても刺激的でした。
こうした視点からインタビューを見ていくと、ファインさんは2つの積極的な活動をおこなっています。ひとつは、モンゴルの医療に関するフィールドワークをベースにしながら、民族誌映画などのマルチモーダルなコミュニケーションを通じて、一般の人々にも動物や土地との関係性を自分たちとは異なる認識方法から理解してもらうことを目指す活動。もうひとつは、モンゴルの医療と知識の伝達について研究する国際チームで、生物医療の技術と牧畜コミュニティが持つ病に関する知識の統合に向けて、異なるパースペクティヴを健康という観点で結びつけようとする活動です。
どちらの活動も、異なるパースペクティヴを持った人々が他者と結ぶ関係性を別のあり様から捉える可能性とともに、その異なったパースペクティブが重なる地点を作り出すことで新たな可能性も拓いていくという、重層的かつ創造的な活動として捉えることができると思います。こうした活動は、人類学者がフィールドワークで、自分のホームである慣れ親しんだ世界とフィールドという異なる世界を行き来して、双方の世界における現実の不可量部分へと接近できるからこそ可能になっているのだろうと感じました。
パンディアンさんの議論にも関わるのですが、モンゴルの伝統的医療のようなものは、時代遅れとみなされて、合理化されていくシステムに反映されず、衰退する可能性もあるかと思います。そう考えると、ファインさんの国際チームでの活動は、衰退していく可能性もある伝統的なものの中に未来性を見出していくものだと感じます。そして、このような活動は、人類学者が得意としていることなのではないでしょうか。
奥野:
マルチスピーシーズ研究の誕生には、複数の世界への視点が人類学の中にもたらされたことも一役買っているのではないかということですね。その指摘はなかなか興味深いです。
では中江さんからもお願いできますか。
中江太一:
はい。ファインさんの話を読んで最初に思ったのは、コロナ禍でインタビューがおこなわれ、この「More-Than-Human」シリーズがWebサイトとして制作されたことの意味です。パンデミックに見舞われた世界において、モア・ザン・ヒューマン的な発想がどのような点で有効なのかを考える契機になったと思います。
ファインさんのインタビューでは、マーモットが取り上げられます。この動物にある種の薬のような効果があると信じているモンゴルの人々の風習と、実はペストを媒介する動物であるという医学的な側面のせめぎ合いが語られていて、非常に興味深く感じました。
また、畜産業についてのブランシェットさんのインタビューでも、人間社会は「豚の感染症を貯め込む貯蔵庫の中核」になっているということが指摘されていました。ウイルスや細菌を前にしては、人間と動物というのは同じ立場に置かれています。マルチスピーシーズという新しい人類学の見取り図によって、この人獣共通感染症が明瞭に見えてくることがよくわかるのではないでしょうか。
この点を補足する意味で、最近再注目されているカミュの『ペスト※9』でも、ペストに最初に感染したのは人間ではなく、ネズミだったことを思い出しました。それから人類学の分野では、フレデリック・ケックの『流感世界ーパンデミックは神話か?※10』がありますが、マルチスピーシーズ人類学の視点からすれば、どちらの本も物足りなく映ります。
カミュの『ペスト』においては、ネズミはオランという地域の人々を襲うペスト禍を予兆する一種の印、記号にしか過ぎません。ケックの『流感世界』についても、鳥インフルエンザに襲われた社会の生政治分析が中心となっていて、人間と動物を問い直す発想は欠けているように思いました。
コロナに関する文学としては、体験記的なものやコロナ禍の人間を描いた作品が次々と出版されていますが※11、今後はマルチスピーシーズ的な発想も求められると思います。今現在、ウイルスをめぐる新しい人類学があるのでしょうか。
奥野:
その指摘は、種を超えて広がるウイルスや細菌などの病原体を、人間と動物種を扱うマルチスピーシーズ民族誌が取り上げる余地があるのではないかということですね。コロナを含め、ウイルスをめぐる人類学がありうるのかという大きな問いも出ましたが、これは後に残しておきましょう。
エドゥアルド・コーン:森の知的興奮を聞き、人間の言語世界に還す
大石:
コーンさんの『森を考える』は、すべての生き物が記号過程にいるということを描き出しており、日本でも広く読まれている著書だと思います。その著名な本を書かれているコーンさん自身が、インタビューでは「人類学が多くのことを伝える術を持たないことに歯がゆい思いを抱いていた」と述べているのが印象的でした。
ここでは、ファインさんがマルチモーダルなコミュニケーションを用いて不可量部分を伝えようとしていたように、人類学において従来とは異なる方法が探求されるようになった背景には、フィールドワークと民族誌を書くことの間にあるギャップが強く認識されるようになったことがあるとわかります。
そうした中で、ナイトさんのインタビューでも指摘されたように、人間の視点や語りだけから、他なる存在との関わりを描くことの先へと進むために、コーンさんは、森で録音データを収集したり、多様なレイヤーを用いて、人々が他なる存在と交流する様子に耳を傾けながら執筆をおこなったという経緯がおもしろいです。フィールドワークやデータ分析の方法としても参考になりました。
先ほど近藤さんから、パースペクティヴィズムは視覚に寄りすぎているという指摘がありましたが、実は私もそう感じていました。なので、最近は視覚に加えて、聴覚や嗅覚にも注目をしています。
クアイの人々が、象のことを理解することは絶対にできないと言っていることに触れましたが、それは人間同士の親密な関係、例えば親友や配偶者であったとしても、その人のことを完璧に理解するのが難しいという事実がベースとなっています。そして、理解することはできないと彼らが言う際には、絶対に理解できると言い切ってしまうことで生じる権力性を持ち込まないという意図が込められているように感じます。
ただし、クアイの人たちが象の視点を完璧に理解することはできないからといって、理解しようとしていないわけではありません。実際に象と向き合う場では、コーンさんが聴覚に注目したように、象の発する声や身体を用いて出す音に耳を傾けることが重要になります。さらに、クアイの人々と象の関係は、匂いを交換することから始まります。コーンさんが用いたレコーダーでの録音のエピソードからは、そういった聴覚や嗅覚を使いながらおこなわれる人間以上の存在との相互交渉の実践を、いかに記録することが可能なのか考えさせられました。
また、『森を考える』が著者の手を離れて、作曲家などのアーティストへと影響を与えたり、コーンさんが「倫理学的なプロジェクト」と呼んでいる活動において、実践的な活動、とくにアニミズムの考えを政治の領域に持ち込むといった共同作業をおこなっていることには、ファインさんの活動とも通じるものがあると思いました。
アニミズムを政治的な場に持ち込むということは、人類学が現地の人々と共同しながらできることのひとつとして、重要なことだと感じています。例えば、クアイの人々もアニミズム的な見方を参照しながら象との親密な関係を築いており、象を家族の一員として語ります。しかし、近代的な見方においては、動物との親密な関係は嘘や虚構として捉えられ、クアイの人々はむしろ象を搾取し酷使する人々として批難されてきました。さらに、彼らの持つ象の所有権を取り上げようとする動きも過去にはありました。
第1部の最後の議論と重なりますが、動物の視点を理解することはありえないという不可知論を前提としつつ、近代的な存在論では、人間中心主義的な視点から象を被害者として捉える見方が一般化しているため、なかなか象との親密な関係自体を社会に受け入れてもらえない状況があります。アニミズム的な視点を村の中に留めておくのではなく、いかに彼らの地位の向上や社会の構築へとつなげていくことができるのかを考えさせられました。
奥野:
アニミズムを現代政治の場に持ち込むというのは、「森は考える」と考えてみることから始めようと唱えて『森は考える』を書いた、コーンさんならではのインスピレーションに溢れる着想だと思いました。これを手がかりに、何か考えていくことができそうですね。隅々まで概念と言葉によって覆い尽くされ、それへの黙従によって人々が囚われの身となることの根源にある、悟性からなる政治の舞台が、直観に基づくアニミズムの景色に変えられてしまうのは、想像しただけでワクワクします。
中江さんの方からも、コーンさんのインタビューに関してコメントをお願いします。
中江:
『森は考える』を読んだ印象は、非常に重厚で難解な作品というものでした。なので、このインタビューは導入として好適なのではないかと思います。思考というのは人間の特権的な行為ではなく、人間以外の存在にもありえる。つまり、森が思考するという着想に至るまでのプロセスで、コーンさんが味わった知的興奮がリアルに伝わってきました。
彼は、フィールドワークが無意味に感じられたり、退屈であったりするかと思えば、物事が突然ひとつに結びついて、ひらめく瞬間が訪れるとも言っています。後から振り返ってみると、本書に生かされた最も刺激的な発見のいくつかは、ほんの数秒の間に起こったことだったと言うのです。
コーンさんが述べている研究や調査における時間の問題は、文学研究をやっている私にも共感できるものです。ひらめきの瞬間性が語られている一方で、それを言葉にすることの難しさも述べられていました。「私は文章を書くのが上手ではない」という率直な告白には、そのことが端的に表れていたのでしょう。コーンさんは、言葉を用いていかに説得力を持たせられるのか腐心していて、それが言語の模倣性やオノマトペに対する関心にもつながったのではないかと思いました。
それから、大石さんも触れられていたところで、人類学研究が芸術活動を触発していることにも興味を持ちました。リザ・リムさんの音楽が『森は考える』から着想されていましたが、他にも人類学の影響を受けて別の分野が刺激される例があれば知りたいです。文学の領域においても、人類学的な知を取り入れようという動きがありますし、例えばハラウェイが現代美術界に大きなインパクトを与えていることは知られていると思います。
奥野:
たしかにメイキング・オブ・『森は考える』といった趣のある刺激的なインタビューでしたね。人がその一部でもある森というフィールドへの入り方を考えさせられました。また、コーンさんが『森は考える』後に、倫理的なプロジェクトに関わるようになって、「森の思考」を持ち込みながら、アクチュアルな問題に自然な成行きで加わっていったという点も、おもしろいところです。
アナンド・パンディアン:ひとつの経験から質的統合性を引き出す
大石:
この第2部のインタビューには重なる部分が多くあり、かつ相互補完的になっていると思います。その中でもとくにパンディアンさんのインタビューは、人類学やその研究手法が持つ可能性とおもしろさがふんだんに述べられており、希望の溢れるものだと感じました。
とりわけ、人類学的思考は、エスノグラフィーという手法によって、身体をもって感じ、考え、この世界の可能性と実際性に向き合うことから生じているものであると位置づけ、人類学者は、映画作家や文化人と同様に、出会う者の心を揺り動かそうとしているのだと指摘されているのが印象的でした。
これはファインさんが民族誌映画を制作したり、コーンさんがレコーダーを用いて耳を傾ける中で、民族誌を書くだけでなく、さまざまな人を巻き込んだり、巻き込まれたりする事態が発生していることとも関わっているように思います。こうした視点から、人類学や人類学者の役割をチャネルやメディアだと考えていくと、民族誌映画や実験的民族誌のような取り組みや、さらには環境人文学におけるフィクション的な記述が持つ可能性に注目していく必要があると感じました。
また、そのためにもフィールドワークの中で、身体で感じ、考える。コーンさんの言葉で言えば「人類学者が日ごろ研究対象としているようなたぐいの現実とは異なる現実へと踏み込んでいく」ことが重要なのだと、改めて確認できました。
中江:
パンディアンさんのインタビューは、人類学についての再帰的な問いのようなものが多く、なかなか理解できない部分も多かったのですが、一番興味を惹かれたのは、デューイを引いて人類学のフィールドワークについて話しているところでした。
パンディアンさんは、一般的な意味での“experience”と一回性の“an experience”を分け、後者には質的統合性というものがあると言っています。ここには、フィールドワークという一回性の具体的な行為の中から現実についての深い認識が生まれてくるという、基本的な価値観が提示されているように思いました。
以上の解釈が誤っていないとすれば、文学と人類学の研究にも共通点があるのではないかと思います。文学あるいは文学の研究というのは、ひとりの作家、ひとつの作品という個別的なものから、普遍的な問いを引き出すことに存しているからです。
奥野:
なるほど。パンディアンさんが一回性の経験を大事にしているというのは、非常に興味深いですね。
パンディアンさんを含め、この3人のインタビュー記事を読んで、とりわけ強く印象に残ったのは、人類学者が「人類学とは何か」を問わざるをえないという意味で、再帰的な問いを自らのうちに抱え込みながら、フィールドに往っては還り、還ってはまた往く研究者だという点です。
人間世界にはさまざまな問題が蔓延っていますが、それは事が成し遂げられた別の可能性があったことを示していると、パンディアンさんは言っています。そして、別の可能性を想像する人類学を構想していると。それは中心にどっしりあって存在感を放っているものではなく、周縁に見捨てられていたものたちの方から世界を眺めることであり、学問の実践の中で身体化してきた人類学に染みついた見方であるように感じました。
パンディアンさんには、現代の人類学の改革者であるティム・インゴルドが哲学に向かうのと似た感性があるように思います。インゴルドは『人類学とは何か※12』の中で、人類学とは人々「について」の学ではなくて、人々「とともに」人間の生を学ぶ学だと再規定しました。これまで人類学者がフィールドで長らくやって来たことを正直に述べ直すことによって、学問の制度の中で一般化されたデータを取るためのフィールドワークという見方をひっくり返したのです。
パンディアンさんのアイデアには、インゴルドに比肩しうる「騒めき」のようなものがあるのではないでしょうか。この「More-Than-Human」シリーズの中でも、彼にとっての「ヒューマン」とは人類学のことで、彼のインタビューは、人類学以上、あるいは人類学を超えていくという趣がありました。その意味で、パンディアンさんの人類学が今後どんな成長を遂げていくのか、また彼がコロナをどう捉えるのか、とても楽しみです。
マリノフスキーから100年後の人類学
近藤祉秋:
まず、大石さんがお話しされていた、英語圏と日本語圏の違いについてお答えします。実はこの「More-Than-Human」シリーズを企画した理由のひとつが、英語圏と日本語圏の人類学の間にある違いを伝えるということだったんです。これだけグローバル化した世界で、コロナ禍以前はアカデミアの国際交流も盛んでしたが、それぞれの国や言語圏ごとに人類学の動向も異なるという状況があります。この企画では、海外の状況を伝えつつ、日本からの発信もおこなうというのが狙いでした。なので、大石さんがファインさんの記事を読み、海外の動向に触れて刺激を受けたというのは、個人的にはとてもうれしかったです。
中江さんからは「コロナ禍を受けてどのような新しい試みがありうるのか」という問いをいただいていましたので、いくつか事例を挙げてみます。私自身はデジタル民族誌やデジタル人類学という分野を学び始めて、フェイスブックなどのSNSを使った調査方法を試行しています※13。私の調査地は、80人くらいの小さな村ですが、古老でもフェイスブックのアカウントを持っているところなんです。Twitterのアカウントを使って、調査している方の話も聞きました。SNSを使った調査方法はおそらく今後多くの事例が出てくるのではないかと思います。
また別のおもしろい動きとして、オートエスノグラフィーの手法を応用したものもあります。オートエスノグラフィーとは、自分で自分の生活を民族誌として記録することを意味するのですが、知り合いにコロナ禍での日々の生活を文字や音声で記録してもらい、それを集めて分析するという調査方法を試している人もいます※14。
人類学のスタイルとしては、ひとりの人間がひとつの村やコミュニティに行き、長期間住み込むというのが定番です。しかし、それがコロナ渦でできなくなった今、さまざまな新しい試みが生まれています。今おこなわれている試みの多くは、コロナが終息したら顧みられることはないかもしれません。それでも、新しい方法を模索してみることは、人類学の未来を考える上で有益かもしれないと思っています。
ちょうど100年ほど前にマリノフスキーが『西太平洋の遠洋航海者※15』を出版したことにより、アームチェア人類学からフィールドワークをベースとした人類学へと変化が起こりました。現在、コロナ禍により生じている変化がどの程度続くのかもわからないですし、その後に影響を与えるような変化をもたらすのかも不透明な情勢ではありますが、マリノフスキー革命が起きてからほぼ100年後に人類学のフィールドワークをめぐる状況が揺れているのは、興味深いことだと感じています。
最後に、人類学とアートの関係性に関しても短めにコメントをさせてください。そもそも「マルチスピーシーズ民族誌」という言葉が生まれる背景として、「マルチスピーシーズサロン」というアート展がありました。第1部でも名前が出てた「マルチスピーシーズ民族誌」の特集を組織したカークセイは、バイオアートに関心を持っていました。彼が中心となって、人間と生き物の関係、とくにテクノロジーを介したような生き物との関係を表現したアートを集めた展覧会がアメリカ人類学会で企画されました※16。カークセイが組織した特集の序文※17では、この「マルチスピーシーズ・サロン」で出品された作品も紹介されていて、このことからして現在の人類学とアートの近しい関係性をうかがうこともできるかもしれません。