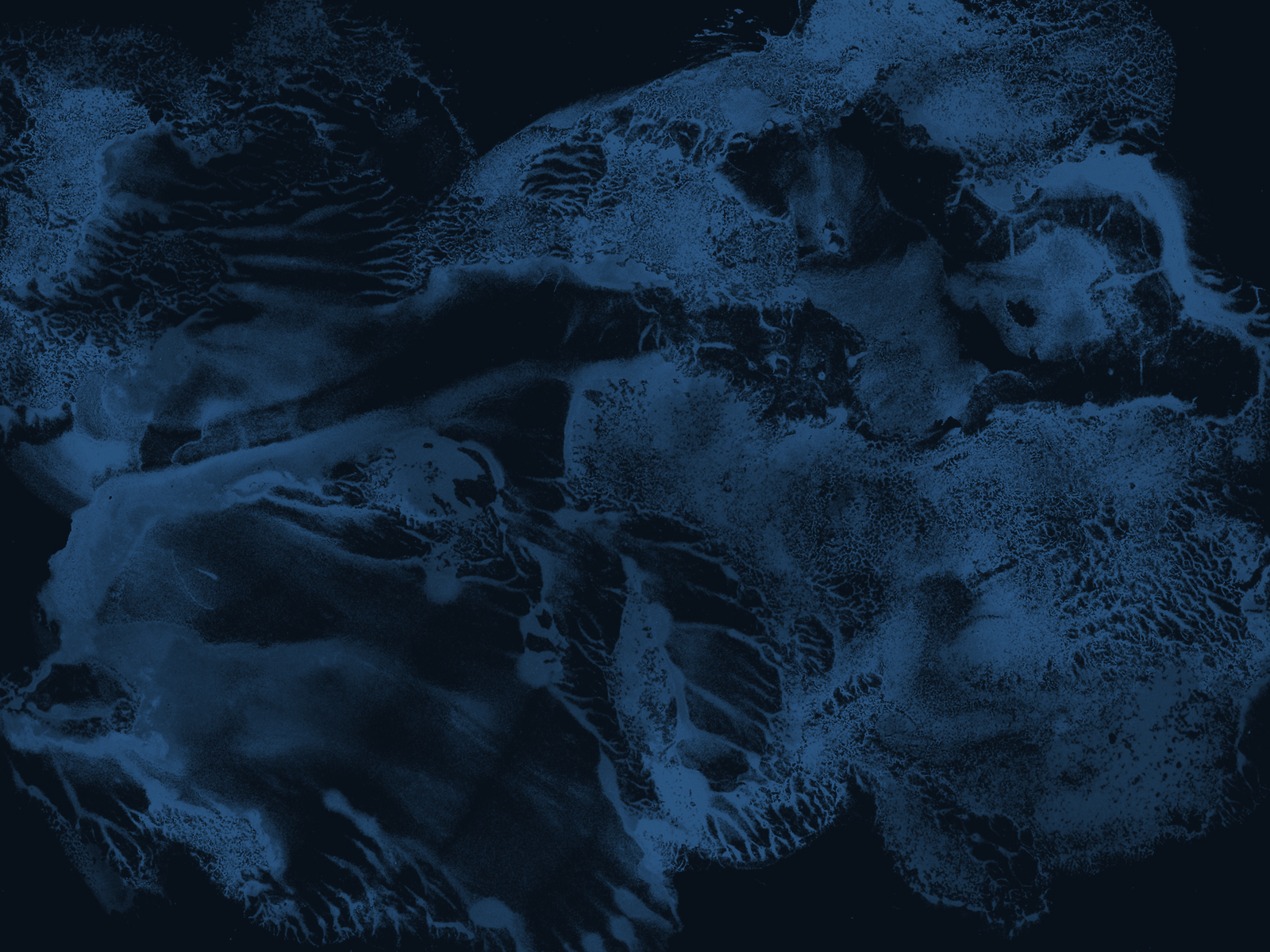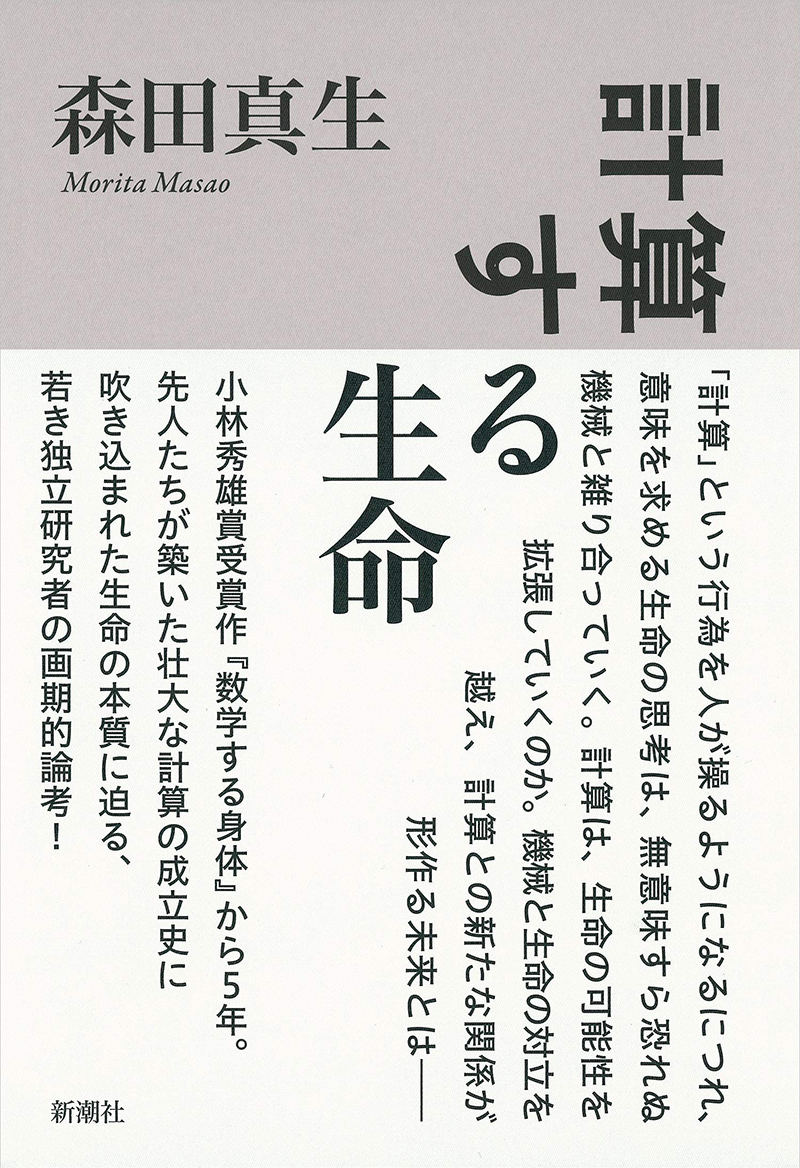
§
——— まず『計算する生命※1』の第一章「「わかる」と「操る」」に書かれているのは、前著の『数学する身体※2』から引き継がれた内容です。計算という他律的なプロセスに身を委ねることによって、自分が直観的にわからないものにアプローチできるというのが、いろんな事例を踏まえて書かれています。つまり、操作しながらある対象にアプローチし続けていると、事後的にわかるというフェーズがやってくると。それは自然にやってくるのではなくて、何かしらの操作に対するイメージを誰かが創造していくような段取りであり、そのようにしながら数学が進化してきたということが書かれていると思います。
この「操る」という部分はよくわかるんですが、なぜ操っているうちに「わかる」というフェーズが出てくるのか。その創造性について、森田さんはどのようにお考えになっているんでしょうか。
森田:
その部分が数学という学問のおもしろくて不思議なところなんです。「操る」という他律的なプロセスに身を委ねていたら、思わぬ意味が染み出してきてしまう。それがなぜなのかという問題は本書を貫く主題のひとつでもあります。
僕もこの問題に対してはっきりした答えを持っているわけではないのですが、ひとつだけたしかなことは、「意味が染み出してくるまで付き合う」必要があるということです。意味がわかるようになったときは、自分も生まれ変わっている。だから、生まれ変わるまで「まだ意味のわからない」ものと付き合ってみることが必要なんです。
§
——— 「意味が染み出す」という表現は、仏教用語の「熏習(くんじゅう)」のように、行為を繰り返していると、それが後天的に自分の性質として固定されてくるというのにも近い感覚かもしれません。
数学は、人間の生得的な神経回路のなかに組み込まれているものではなくて、何かしらの神経回路を流用して文化的に学習される機能だと思います。言語も同じですが、そういった人工性のあるものと付き合い続けることは、人間にとってどういった意味があるのか。それを考えさせられたのが、この本を読んでいて一貫して興味深かったところです。
数学で言うと、計算行為を繰り返していくことによって、後天的に「こうすると意味としてて成立するんじゃないか」というイメージ、もしくはメンタルモデルみたいなものができてくるわけですよね。このあたりの仕組みやデザインが、非常におもしろいなと思いました。
森田:
この本の最初の方に粘土の話が出てきます※3。僕は必ずしもそうは見てはいないんですが、すごく素朴に、心というレイヤーの下に生命、その下にモノというレイヤーがあるという見方がありますよね。数学は、「心」という一番上のレイヤーでやっているイメージが強いかもしれないですが、実際には心も生命もないモノである粘土が、数学的思考の可能性を拡張する上で大切な役割を果たしているわけです。粘土のように、心があるわけでも生きているわけでもないモノと付き合っていく過程のなかで、新たなメンタルモデルが獲得されてきた。
僕たちは「頭」で考えているだけではなくて、自分たちの外にある粘土とかにいわば「学ばせてもらっている」わけです。頭だけで考えているときは、たとえば7と8が曖昧に混ざってしまっているんだけど、粘土や石は分かれたままでいてくれる。そうやってモノの性質に頼ることで、僕たちは7と8を区別する能力を獲得してきた。ある意味では、「モノが人間を賢くしてきた」という言い方もできるかもしれません。心も生命もないからという理由で、モノは不当に低く評価されてしまいがちですが。
実際のところ、モノの方が人間よりクリエイティブなことがあるし、機械が人間を驚かせることもある。意識も生命もない時代に、細胞よりも小さな時空が一千億を超える銀河を生み出してきたわけですから、人間のような意識や生命を持たないとされる事物に対して、僕たちはもっと謙虚にならないといけないと思います。
この本の物語を、天才数学者からではなく、粘土から始めたいと思ったのは、僕なりのモノに対する敬意の表明でもありました。
§
——— 7と8が生得的な頭だけでははっきりと区別できなくて、ぼんやりした量的なものとしてしか把握できない。生得的なものというのは、カントの言うアプリオリなものだと思うんですけど、それはおそらく進化的に獲得してきた神経回路ですよね。進化的に獲得してきた世界以外に、人間は文化領域を持っている。その文化領域の特徴は何なのかと考えると、それはモノとのハイブリットとして存在しているということなんじゃないかと思います。
類人猿は幼少期から成長していくときに、母と子のような二者関係のなかで精神を育んでいくわけですけど、人間の発達学の本を読むと、人間はそれだけでなく、母と子のなかに第三項としてのオブジェクトが必ずあるみたいなんですよね。そのオブジェクトを含めた三者関係で、精神が発達していくというふうにプリセットされている。モノと人間との関わりは、かなり本質的な問題だと思うので、『計算する生命』がそこから始められたのも、非常にわかりやすかったですし、今の話を聞いて納得できました。
森田:
一般的には心や生命を持たないとされる粘土や石、天体や光、あるいは時空そのものに僕は深い敬意を抱いています。できれば、人間だけでなく、こうしたモノたちが主役となるような歴史を描いてみたいという思いがあります。ただ、心という島のなかで生きている人間が、本当にモノの境地まで降りていこうとすれば、かなり厳しい道になるだろうと思います。
§
——— 人間の脳はいろんなものを結合構造で考えますよね。要するに、アナロジックに考えていく。数学のわかりにくさも、脳がデフォルトとしてはアナロジックに考えるように出来ているところにある気がします。
数学は、互いが互いを干渉しない離散的な単位で成立するわけですよね。それを外在的なロジックでつなげていく仕組みを持っていると思うんですけど、人間の脳の使い方から考えると無理やりなことをやってるイメージがあります。だけど、そうやって無理やりなことをしないと、人間の心の島を出てモノの領域に入っていけないのかもしれないですね。
森田:
そうですよね。138億年前の宇宙について、緻密な推論ができるようになったのは最近のことですけど、すごいことですよね。そうやって人間が身体的に存在し得ない世界についてすら正確に思考することを可能にしてくれるのが数学のすごいところです。
§
——— たとえば物理学は、基本的に数学で記述されるじゃないですか。当然ながら、あらゆる数学的な財産を物理学が使っているわけではなく、物理学の体系のなかで使い勝手のいい数学を引っ張ってきて隠喩的に使っているのだとは思います。
それにしても、人間が心という次元で創意した数学という体系が、モノとモノとの関係性を記述する物理学に、なぜ有効なのか。その相関性については、どのようにお考えですか。
森田:
人間はモノに育まれてきたわけですよね。さらに言えば、人間の精神は地球生命圏に抱かれていて、その物理的な構造のなかで進化してきた。数学的な思考が、人間が生きてきた物理的な環境条件にどこまで規定されているのかというのは興味深い問題です。
数学は人間が耐えられるギリギリの線まで意味の世界を拡張しようとしてきた営みだと思うんですけど、今は物理環境がいまだかつてない速度で変化しはじめています。完新世と呼ばれる時代の、これまでの気候パターンや生態系の秩序が崩れようとしている。そうなると、人間は考え方や見方をかなりラディカルに変えざるを得ない。
考えてみれば、数学の歴史はいまのところ完新世のなかにしかないわけです。数学の歴史は、比較的安定した地球環境のなかで、あえて人間の思考の環境を撹乱し続けてきたとも言えます。ところが今度は、物理的な環境そのものが動揺しはじめてしまったわけです。これが果たして僕たちの思考にどう作用するのか。物理環境の変化が、これまで暗黙のうちに人間の思考を制約してきた条件にどう作用していくのか。この点に僕はとても興味があります。
僕がティモシー・モートンに惹かれるのは、彼が「まだ意味のない方」に僕たちの認識を引っ張り出していく力として、環境の変動を読み解こうとしているからです。「まだ意味のない方」に圧倒的な力で人間の認識を引っ張り出していく学問として、僕は数学に惹かれてきたんですけど、モートンはそれをやるのはこれからは人間じゃないと言ってるんです。『Hyperobjects※4』という本のなかで彼は、「まだ意味のない方」に僕たちを強烈に引っ張り出しているのは、いまや気候とか放射性廃棄物とかウイルスとかではないのか、と言うんですね。
§
——— 当然ながら、人間はもともと自然環境のなかに存在してきているわけですよね。一方で、人間が「ここは人間の世界です」と境界線を引いて、そこで完結した意味の世界も作ってきた歴史があります。今の話を聞いて、人間が境界線を引けない、あるいは境界線を超えて考えられるところまで、われわれの知性が進化してきているとも思いました。
森田:
その通りですね。両方の側面があって、物理環境の変化と認識の変化は分かちがたく混ざり合っているわけです。実際、100年後の気候についてシミュレートする技術がなければ、地球温暖化を危機として認識することはいまだにできていなかったかもしれません。
その意味では、数学や人工知能そのものというよりは、数学や人工知能と混ざり合った物理環境の変化が、人間の認識を激しく揺さぶっている時代ですよね。
この本にも書いたように、少なくとも19世紀までは、「まだ意味のない世界」の最前線を開拓していたのは、数学だったと思います。本書では、19世紀まで数学の歴史を描いていたのに、20世紀から認知科学や人工知能の話になり、最後は地球環境の話になりますが、これは、「数学の歴史」を描こうとしたというよりも、「まだ意味のない世界」が開けていく歴史を描こうとしたことの、自分にとっては必然的な帰結でした。
§
——— 自然環境は、人間が完全に抱握することができない不確実なものとして、われわれを取り囲んできています。では、なぜそれを人間が理解できるかというと、脳自体が自然でありモノなわけですよね。なので、「モノがモノを認識する」という意味で話を聞くと、大きな歴史の展開の仕方としてわかる気がします。
そういう意味で、数学は「digit」というものを対照させる。一番わかりやすいのは指ですけど、この離散的な観念をいかにマニピュレートするかという発想が大元にあります。モノに対する認識と数学的な進化は、道具の進化に近いんじゃないかなと思いました。道具の進化と考えれば、AIと認知科学とか、その先の環境の問題もつながってきます。
人間の環境と言うとき、当然ながら人間ありきの環境になっているわけですが、そもそもこれを人間がメタレベルで操作するのは可能なのか。可能であれば、どう可能なのかといったあたりが、一番おもしろい論点かもしれません。
森田:
道具という観点だと、すこし不十分かもしれません。まず数学は何よりも「おもしろい」んですよね。つまり、喜びとか快楽みたいなものがあって、これこそが肝心です。道具性や生産性みたいなものはあくまで副産物であって、まだ意味のないところで遊戯的に思考していることのおもしろさが核心だと思います。結果的に概念が生まれたり、新しい装置が生まれたりする。
生命の歴史もそうかもしれない。戯れたり、触れ合ったりすることが気持ちよくて、副産物としてDNAが残ってしまう。性行為の目的がDNAを残すことだというのは、見方のスケールがすこし狭いかもしれない。
僕は農家の友人が多いんですけど、彼らは育てること自体を楽しんでるんですよね。もちろん生きていくためにやっているので、ちゃんと野菜が売れないといけないんだけど、売るためだけに作っているわけではない。むしろ植物との交感関係に深い喜びを感じていて、結果的においしい野菜ができてしまっているという感じなんですね。
だから、数学の歴史についても、道具性という観点だけになってしまうと、すこし偏ってしまう気がするんです。
「モノがモノである」というのは根本的に「playful」なことではないかと、今年出版されたティモシー・モートンと文化人類学者のボイヤーの共著『Hyposubjects: on becoming human※5』に書かれていました。彼らは「playful」であることの方が「accurate」だというおもしろい言い方をしています。遊戯的である方が、現実の認識として緻密であり正確なんだと。
生真面目に生産性を追求している方が、現実の大雑把すぎる認識の帰結かもしれない。物質でさえplayfulに動き回っているじゃないかと彼らは語ります。何しろ、あらゆる物質は量子のスケールでは、じっとせず動き続けている。
物質でさえ遊戯的なのだとしたら、遊戯的な姿勢で生きている方が正確なのではないか。彼らが語るのは「正しさ」ではなく「accuracy(精緻さ)」です。遊び心を持つ方が正しいんだとか正義なんだとは決して言わない。ただ、そっちの方が精緻ではないか、と。
数学の最大の魅力はその圧倒的な遊戯性にあって、まだ意味のない領域に踏み込んでいくからこそ、人は遊戯的にならざるを得ない。遊びというのは、既知の意味に回帰するのではなく、新たな意味が見つかるまで現実と付き合うことです。だから、まだ意味のない状況では、遊戯的なモードに入る方が現実的であって、さも意味があるかのように生真面目に振る舞うのは、かえって的外れになる可能性がある。
§
——— ÉKRITSから上妻世海の『制作へ※6』という本が出版されているんですけど、表題の「制作へ※7」という論考があって、そこに書かれている制作行為というのが、今話にあったplayfulであるということだったんですね。つまり、モノを存在論的な「be」で考えるのではなくて、生成的な「become」で考えるモードに入っていくことを、彼は制作モードと言ってるんです。
あらゆる分野で、何かを発見したり発明するようなことは、きっとそういうモードにいなければいけないわけですよね。それは、正義のためとか、あるいは確定記述的に存在している何かのためにやるわけではなくて、まだ意味がない状態に対して意味をクリエイトしている。その界面が、制作モードでありplayfulなモードじゃないかと感じました。
数学も同じように、数学者の先端的な研究において、非常にクリエイティブな分野ですけど、数学に苦手意識がある人にとって、数学は確定記述の連鎖というイメージですよね。確定記述の連鎖は、他律的なマニピュレートをずっとやっていくイメージです。前著の『数学する身体』もそうですけど、今回の『計算する生命』はいろんな人が読んでいて、そのなかには数学が苦手な人もいると思いますし、そういった人が読んでもよくわかるように書かれていると思います。
しかし、今の時代には、数学が苦手でも、他律的にロジカルに考えないとたどり着けない問題が山ほどあります。モートンのハイパーオブジェクトもそうですけど、これまで自分の役割を演じていれば済んでいたものが、そうもいかなくなっている。人間関係のミクロなところでも、前はたとえば父親をやっていればよかったのが、自分で自分の人間関係のポジションをクリエイトしていかないといけない。そういった問題が、拡張性の高い議論に落とし込まれていることも、森田さんの本を読む人の動機としてあるのかなと思いました。
森田:
まだ意味のない世界で遊戯的に生きるモデルを示してくれているのは子供たちだと思うんです。子供と大人が何人かで同じ場所にいると、大人が強権を発動しない限り、場を支配するのは子供たちなんですよね。そのとき大人は、意味を主宰しているのは自分たちだと思っているわけです。
たとえば、スプーンはこうやって使うものですとか、本は丁寧に扱いましょうといった感じで、意味をコントロールする側に立っていると思っているんです。それに対して子供たちは、スプーンを投げたり叩いたり、本を破ったりして、あらゆるものをまだ意味のないものとして使いはじめる。なぜ弱いはずの子供たちの方が、意味を支配している大人たちを翻弄できるのか。
別に子供たちは大人に対してレジスタンスを起こすわけではないんですよね。自分たちの正義みたいなものを論じているわけでもない。大人が生きている世界を否定するのでも乗り越えようとするのでもなく、大人が生きている世界を、その世界の配置のまま、あらゆる構成要素を違う意味で使いはじめていくわけです。
大人が設定した世界の配置をすこしも変えずに、それらの構成要素の意味を改変していく遊戯性によって、子供たちは結果的にその場を支配していく。子供という近代的な概念が作られたとき、この世界の事物の意味を正しく理解している大人こそが完全な人間であり、子供はそこに到達していない未熟な存在としてカテゴライズされたと思うんです。だけど今は、固着した意味に執着している大人の方がむしろ危うい立場で、子供の遊び心を持つことの方が現実的になってきている。そういった図と地の反転みたいなことが、いろんなところで起きている気がします。
§
——— おもしろいですね。今のお話を聞いていて、現象学系の哲学者であるミゲル・シカールが書いた遊戯論『プレイ・マターズ※8』を思い出しました。遊戯論の系譜には、ホイジンガやカイヨワがいますけど、シカールは「遊び心」というものを中心に考えているところがおもしろくて。彼の考える遊び心とは、「既存のものの流用行為」なんですね。それが遊びの基本要素であり、それ自体の定義だというわけです。
近代的なスタイルである強い主体同士の争いは、システムを正しく構築する戦いになります。それに対して、『プレイ・マターズ』に書かれているのは、たとえばデモをするときに、「反対」と言って徒党を組むのではなく、バリケードのなかで鬼ごっこみたいなひとつのゲームを始める手法でした。参加している人たちは、鬼ごっこをして遊んでいるわけなので楽しいんですよ。
そうやって、既存のシステムやスタイルを流用して、自分の内面的な快楽へと介入させていく。これはシステムの革命ではなく、存在様式の革命だというわけです。だけど、考えてみると、そもそも流用という行為が結構すごいと感じます。
森田:
この本の冒頭が子供の指の話なのは、遊戯性から認識の拡張の歴史を捉えていきたいという思いもあったからなんですが、指で数えるのも流用から始まってますもんね。
モートンの『Realist Magic※9』という本のなかで、数ページ使って、蛙の大群が鳴くシーンが描かれる場面があるんですが、とても印象的な描写です。カエルの鳴く声がモートンの頭のなかではオノマトペに翻訳され、メスの蛙には誘惑の声として翻訳され、湖水の表面には振動として翻訳され、といった具合で、さまざまなエージェントが、カエルの鳴き声を全然違った仕方で「translate」していくんですね。
モートンはtranslationという言葉を使いますが、要するに、同じものがさまざまな主体のなかでまったく違うことを引き起こしていく。彼はこの世界を壮大な翻訳の網として見ているわけです。
ある意味では、モノとモノとが互いの存在を「流用」しているということですよね。たとえば、僕が落ち葉を踏んで秋だと思うのは、落ち葉の流用じゃないですか。土中の虫たちは落ち葉によって栄養が供給され、雨にとっては地面に衝突する前の障壁になっている。思わぬ仕方で相互に存在を流用し合う網としてこの世界を見るというのはおもしろい視点です。
§
——— エドゥアルド・コーンという人類学者が『森は考える※10』で書いている話にも似てますね。コーンは記号というひとつの象徴次元を前提にしているので、もしかするとモートンの哲学からすると旧来のパラダイムを引きずっているところはあるかもしれませんが。
つまり、誰もが生態系が連環していることを漠然とイメージしているけど、どうやって連環しているのか突き詰めていくと、モートンのように「内即外」みたいなことを想定しないと成立しないと思うんですよね。だけど、「内即外」にたどり着くには、一旦内と外を分けて、外というものを外在化して経由しないといけない。規律的な記号操作にもかかわらず、数学が拡張性を持っているのも、そういった段取りを踏まないと、人間の認識はそこに到達できないからかもしれません。
森田:
モートンは、カント的な内と外という境界を解消するのではなく、みんな持っているものだと言うんですよ。石も雨も川もトカゲも持っている。要するに、カント的な内と外の境界を持つ権利を白人男性だけではなくて、みんなに解放しようというわけですね。
§
——— おもしろいですね。今の森田さんの興味は、生態的なもののなかにそもそも原型として存在している知性の働きみたいなところに向いているんですかね。
森田:
今はとにかく、天動説から地動説への転回に匹敵するような認識の転回が始まっていると思います。「エコロジカル・ターン」と言ってもいいと思いますが、強い主体である人間のまわりを、弱いオブジェクトたちが回っているんではなくて、生態学的なモノの賑わいのなかに、僕たちの弱い主体が生成しているというイメージです。昔からそういう見方はあったと思いますが、今は膨大な科学的データの裏付けもあって、エコロジカルに自画像を描写し直していくことが不可避になってきている状況ではないでしょうか。
最近、この意味でいろいろなおもしろい思考が実験的に試みられていますが、哲学者のエマヌエーレ・コッチャが近著『Metamorphoses※11』で、生命の歴史全体を「変態」の歴史として見てはどうかという大胆な提案をしています。変態、特に昆虫の完全変態が驚くべきなのは、イモムシから蝶へという見事なまでの形態の変化を成し遂げるということ以上に、どう見ても違うイモムシと蝶に、子供ですら連続性を見出すことができることです。コッチャは「二つの身体、しかし同じ生命」という書き方をしていますが、解剖学的にどれほど異なる身体でも、小さな子でさえ「この蝶はあのイモムシだ」とわかる。だが、「異なる身体を同じ生命が貫く」という「metamorphosis」の構造は、イモムシと蝶の間だけでなく、あらゆる生き物の間で成り立つ原理ではないかとコッチャは言うんですね。生命は、この数十億年間、変態に変態を重ねてきた。だが、すべてを貫いているのはあくまで「同じ生命」であると。
§
——— コッチャは『植物の生の哲学※12』を書いた人ですね。エコロジーも強いサブジェクトによる対象へのアプローチとイメージされてしまうようなところがあります。たとえばディープエコロジーと言われているような分野も、根本の転回を認識してないとおもしろくない話になっちゃいそうですよね。
森田:
環境問題は同時に精神問題でもあるというのが、モートンの認識の根底にはあると思います。内と外が通じているとすれば、環境が崩れていくことは心が壊れていくということでもあって、心の崩壊をどう防ぐかが環境問題の最前線だと思うんです。木を植えることも大事なんだけど、それ以上に心が壊れないことも大事ですよね。
ひとつのわかりやすい戦略は「もう何も感じないことにする」ということで、感性を閉ざせば心は壊れない。モートンはそれに対して、感性を開いたままでも発狂しない道を探ろうとしているわけです。そのためには、この世界を受け止める概念の枠組みそのものを変えなければいけない。今まで通りの春が来ないとか、当たり前の食事ができなくなるとか、風景が変わったりパンデミックがあったり、そんななかで心を平穏に保つためには自己像をかなり変えなければいけないと思います。
「強い主体」というヴィジョンに囚われたままだと、遅かれ早かれ心がもたなくなっていくと思うんですよね。モートンと同じくらい、僕はリチャード・パワーズという小説家にも影響を受けているんですけど、彼の書いた『オーバーストーリー※13』は樹木が主人公の作品なんです。人間活動による環境破壊から樹木を救おうと立ち上がる8組の人間たちの物語を通して、これまで自分が囚われていた認識の枠組みを解きほぐしてくれるような素晴らしい小説です。
そのパワーズが、今年の9月に『Bewilderment※14』という新作を出版する予定なんですけど、これは親子の物語らしいんです。息子が小学校3年生で、繊細でひょうきんで知的で優しい子なんですね。舞台はおそらく生態系がティッピングポイントを超えてしまった世界で、30年前まで存在もしなかった種類の精神疾患が子どもたちのあいだで広がっている。そんななか、息子がその精神病に患ってしまうんだけど、父親は抗精神薬を飲ませる以外の方法で救えないか考えるんですね。父親は、息子の精神を守る方法として、ひとつは違う惑星に行くこと、もうひとつは若くして亡くなった母親の記録しておいた脳波を注入して安らぎを思い出させてあげるというやり方を考えるんですね。
父親は地球外の惑星を研究している科学者で、現代のテクノロジーを象徴するような存在です。彼は、息子を生き延びさせるために、ここではないどこかに行こうとする。それに対して、息子はあくまでこの星に留まろうする。だけど、この星にいようとする彼は、抗精神薬を飲まされたり、学校を退学させられたり、とにかく社会から「異常」として排除されそうになる。社会のなかに留まろうとしたら、さっき言った「感じない人間」にならないといけないわけです。そんな設定からしてすごく刺激的なんですけど、まだこの本は出版されていないので、今はペンギンブックスに載っていた紹介文から、勝手にいろいろ妄想してるだけですが(笑)
いずれにしても、感じることをやめずに狂わない生き方をしようと考えたとき、playfulにエコロジカルな転回を遂げていくことが、ひとつの道じゃないかと僕は思っているんです。
§
——— カール・ロジャーズや彼に師事した哲学者のユージン・ジェンドリンとか、カウンセリングの系譜で「傾聴」について広めた思想家たちがいますよね。「傾聴」というただ人の話を聴くスタンスが、なぜ治癒効果をもたらすのかというと、頭で考えている状態を停止して、体が今何を感じているかに意識を集中するからだそうです。一歩間違うとマインドフルネスの俗流みたいに思えるんですけど、今のお話を聞いていて、どちらも体のよくわからなさについての話に感じて、思い出しました。
ジェンドリンは『体験過程と意味の創造※15』という本で、体はそもそも生態バランスを取るように思考している存在だと言っています。その生態バランスが崩れた状態は、社会のなかでの精神の偏りであり、それによって何かしらの病をもたらすことになる。なので、体が偏る思考スタイルを解除するのに、体という生態の秩序を一回ヒアリングするんだそうです。だから、傾聴とは人の話を聴くことではなくて、体の声を聴くという行為すべてを肯定してくれる第三者がいることによって、自分が治癒していくというプロセスなんです。
今は何か共通の危機感のようなものがあって、このままだと狂うんじゃないかという漠然とした感覚も共有されているのかもしれません。どうしたら自分のなかの秩序を回復していけるのかを探っている状態と言いますか。つまり、生態系秩序という観点で見ると、エコロジカルターンとカウンセリングはリンクしているのかもしれないと思いました。
森田:
モートンも「attunement」とよく言っていて、これは他者に耳を澄ませながら、波長を聴いてなじませていくことなんですけど、「傾聴」は大事ですよね。attunementは、単に波長を合わせることではないんですね。同じ波長で束になると、ファシズムになってしまう。
僕はattunementを象徴している存在として、『セロ弾きのゴーシュ※16』のゴーシュを思い浮かべます。いろんな動物が彼の水車小屋には来るんだけど、全然噛み合わない。「噛み合わないけど付き合ってみる」というところがゴーシュの優しさです。豊かな生態系も、ひとつひとつの生き物たちのせめぎあいを見てたら、必ずしも噛み合っていないですよね。お互いの領域を侵犯し合いながらも、互いの存在を感じ、呼応し合う。みんなが同じ波長で一体化してしまっているわけではないわけです。
§
——— カール・ロジャーズも、傾聴しても同意してはいけないと言ってますね。特に人間同士の場合、同意してしまうと、無意識に相手がその同意に対してチューニングしてくる。そうすると、お互いにチューニングし合って空気を読み合うという状態になる。これはおそらく社会的動物としての人間の根本になるもので、だからこそ社会が作れるとも言えるんですけど、心を病んだ人がそれをやってしまうと、その闇から抜け出せなくなってしまうと話していました。
これまでは、いかに人間関係においてチューニングするかが主軸だったと思います。だけど、今は異質なまま共鳴するというのがどういうことなのかを考えることが、エコロジカルターンのあとに出てくるひとつのテーマになってくる気がします。
森田:
たとえば宇宙から地球に交信しているときに「Can you hear me?」って確認するじゃないですか。その声が切れたときに、本当にいきなり孤独になる。「あなたの声が聴こえています」と応えることが、存在を確認する最もプリミティブなところにあるんだと思います。
僕は人間以外のものも含めて、一緒に生きているのはダンスみたいなものだと思うんです。でも、たとえば二酸化炭素の排出量の数値だけをみて、木を何本植えようとかってやるアプローチはハイパーサブジェクト的ですよね。環境を「問題」にして、それを「解決」するために合理的な方法で介入していくだけになってしまっては、これもまた新たな暴力だと思うんですよ。
人間が自分の言葉を通して自分を取り戻していくカウンセリングの話もそうですけど、庭でも動物でもそうで、まずはしっかり相手に耳を澄ましてみるだけでも、相手が元気になるというのはあると思います。
§
——— 人間同士の傾聴も、一番最初にすることはまず言葉で考えてしまうオートマティックな回路を遮断することだと言いますもんね。体の声を聴くってことは、その対象が言葉ではなく、あくまで「感じ」だということです。ただ人間は言葉が根絡みになっている存在なので、「感じ」から言葉が浮かんでくるのを待つというスタンスなんですけど。
自然は人間的な言語を持っているわけではないですが、「感じ」というのは浮かんでくると思うんですよね。それを詩的な言語ではなく、システム的な言語で話すというのは、エコロジカルターンのなかでできそうな感じがしますね。
森田:
藤原辰史さんが『現代思想』の「気候変動」特集で「「規則正しいレイプ」と地球の危機※17」という論考を書かれていたんですけど、地球のエコロジカルな危機の核心は二酸化炭素の排出量だとか温暖化そのものにあるわけではなくて、化石燃料による「高速ピストン」と「高速回転」によって、人間と環境の関係があまりに貧困になっていることではないかと指摘しています。環境に耳を傾けることなく、こちらが決めたペースを一方的に相手に押し付け続けることによって、地球が「凍てついた空気で満たされている」ことこそ「最近の地球の住み心地悪さ」ではないかというんです。
§
——— パンデミックなんかを考えると、人間は自然の動きを把握しているつもりでも予測できていないわけだから、傾聴せざるを得ないという気もしますね。
森田:
傾聴せざるを得ないので、早めに傾聴しはじめた方が被害がすくなくなるんじゃないかと思います。
§
——— 今回の本では、フレーゲの次にウィトゲンシュタインを取り上げられていて、脚注のなかで古田徹也さんの本も載っていました。今の自然を傾聴していない話と、古田さんの『言葉の魂の哲学※18』に書かれていた、内包している情報がすくない状態でステレオタイプのコピペみたいな言語を使う状態は、わりと似たようなことを言っている気がしています。それで文学的な打破という方向も重要なのかもしれないと思いました。
森田:
そうですね。パワーズの小説も、植物についての研究がベースになっていて、自然科学が文学的な想像力を広げていっている側面は間違いなくあると思います。いろんな技を組み合わせながらやっているという意味では、文学的な表現も数学的な認識も科学的な方法も、人間が得意としている方法での世界の翻訳の仕方ですよね。モートンは、トカゲが地面を舐めることも人間が数学することも、それほど違わないんじゃないかと言ってます。どれもこの地球上で生きるという経験のtranslationなわけです。
§
——— 今多くの人が、translateするときの基本的なプロトコルに興味が向いているという感じがします。つまり、実務的ではなく原理的に考えないと、ブレイクスルーできないのがわかってきていると言いますか。森田さんの今回の本が求められているのも、それを専門的な方向ではなくリーダブルな形で、作品としてテキストにまとめられているからじゃないかと思います。
森田:
この世界は不公正とか憎しみや悲しみに溢れていますよね。もしかすると、希望なんてないのかもしれない。でも同時に、人間のスケールを離れて見ると、この宇宙は圧倒的な遊戯性と生産性と創造性を発揮していることに気づかされます。
僕たちがまだ理解できていないところに、何かとても肯定的なことが広がっているのではないかという感覚が僕にはいつもあります。自分が何者なのかという理解がラディカルに更新されていった先で、心が壊れていくのに任せるだけじゃなく、新しい存在の安らぎと喜びを見出していける可能性があるんじゃないかと思っているんですよね。環境の変動や生態系の変化は、そっちの方向に僕たちを引っ張り出していく力のひとつになるかもしれません。
§
——— たしかに、局所的なものがあって、さらに広いものがあるというわけではなく、より大きな秩序が局所性の内部でも入れ子構造になっているんですもんね。
森田:
僕は小さいときに「永遠」という概念にすごく恐怖を感じたんですよ。自分は有限の存在で、どこかで終わりが来るのに、形而上学的な永遠のなかにはそれがないというのがすごく怖かった。でも今はちょっと違う考え方をしています。
たしかに有限の側からは無限にアクセスできない。でも逆に、無限の側から見ると、すべての有限がゼロに潰れてしまう。つまり、無限の側から見ると、有限の差異を見ることができない。僕たちは有限の側にいるから、無限性に戦慄したりすることができるわけです。局所的なスケールでしか見えないものがあって、それは全体から俯瞰しようとすると消えてしまう。どちらが優位というわけでもないですよね。有限は無限にたどり着けない。だけど、無限は有限をすくい取れない。
§
——— そうですね。有限と無限が相互包摂している状態を認知できて、われわれはどちらにもアクセスできる。無限という概念をわれわれがつかんでいることに、人間の可能性を感じておもしろいなと思います。行き詰まった空気というのは、局所的に固着しているから感じるわけですし。
森田さんの本に解放感があって、playfulなところに引っ張られる感じがするのは、今言った有限と無限が相互包摂しているような人間の可能性に開かれるからかもしれません。たとえ人類が滅んだとしても、知性の可能性はすごいというところに拓けてくるので。
森田:
最後の章に「計算と生命のハイブリッドとしての私たちの本領が試されている※19」と書いていますけど、ここは「人間の本領が試されている」とも言えました。むしろそっちの方がリズムはいい。でも、別に「人間」じゃなくていいよねと思っているんです。自分が人間という仕方で存在しているという認識自体から、少しずつ思い込みを解きほぐしていきたい。
§
——— ライプニッツが「多様性」と言ってますが、これは生物多様性といった意味ではなくて、パースペクティブが増えれば増えるほど神の世界に近づくといった意味です。このパースペクティブが増えれば増えるほどというのは、translateが増えれば増えるほど完全な世界に近づくとも言い換えられそうです。誰かが主体になって全体を把握しようするよりも、translateの機会が増えていく方が、知性がある種の完全な世界に近づいていく。そんなことを、今のお話を聞いて感じました。
森田:
僕が僕であるという「自己同一性(identity)」は絶えず未来によって壊され続けるもので、それ自体はそこまで重要ではないんですよね。僕は別の人にもなれる。というか、自分が自分でないものに変わり続けるという生命の流れこそ、誰にも止めることができないものです。
§
——— じゃあ自覚ということ自体は、そこまで重要じゃないんですかね。自覚できるという意識の問題よりも、意識に先行する生態システムというか、全体の知性が大事というか。たとえば、いかに人間が生態的な知性をシンクロできるか、あるいは利用できるか、translateできるか、アクセスできるか。そんなところが、一番おもしろい部分なのかもしれません。
森田:
そうですね。自覚することは、新しく行動を起こすことでもないし、イノベーションを起こすことでもない。どこか違うところに行かないと救われないとか、今いないところに技術の力でたどり着かないと希望が拓けないということはない。もうすべて必要なものは揃っている。このことに気づくこと、気づくことを自分に対して許していくことが大事だと思います。
つまり、すでにしてしまっているとてつもないこと、そのとてつもなさに目覚めていくこと。その蓋をちゃんと開けて感じる。そうしたらすでに自分たちは十分救われていたことが発見されるのではないか。僕はそう考えています。
§
2021年5月13日 インタビュアー: +M(@freakscafe)