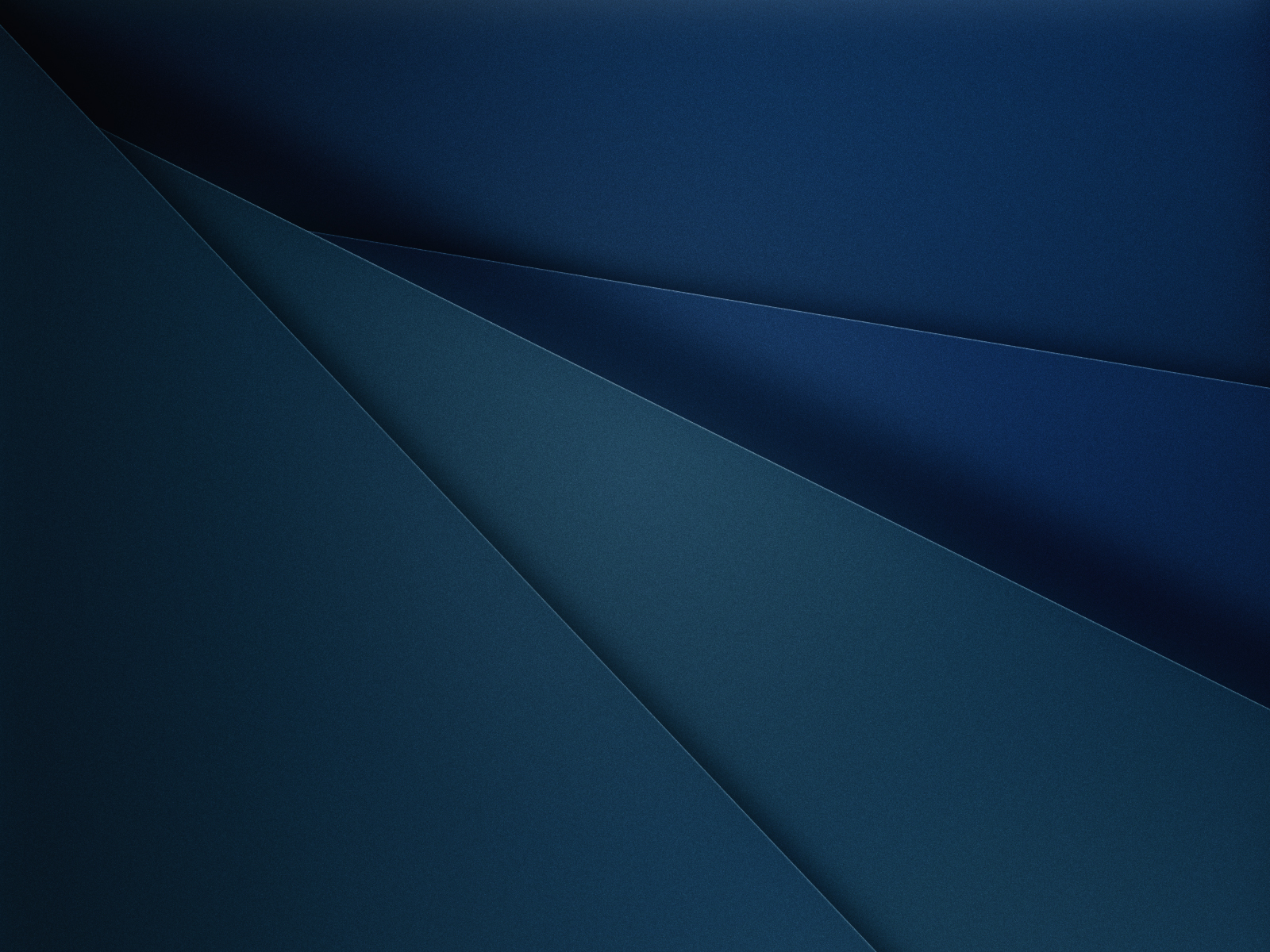SCENE 01
内的な時間をデザインすることは不可能だ。この覚書は、その結論を得るまでの過程を記録したものである。
時間については、昔から多くの作家たちがなにかを語ろうとしてきた。我々が日常的に体験している時の流れに対して、彼らは疑いの目を向けているのだ。
ヴォネガット『スローターハウス5』では、トラルファマドール星人という異星人が登場する。彼らは、四次元の目をもちいて世界を見ることができる。彼らにとって人間は、子供から老人までの無数の人間が腰のあたりでくっついた百足のような生物に見える。そしてヴォネガットは、また別の作品で、すばらしい視点を提示した。
われわれが、人間であるという大きな過ちの次に犯している大きな過ちは、時に対する過ちではないかと思う。われわれは時計やカレンダーなどさまざまな道具を使って、サラミのように「時」をスライスし、その一切れ一切れに名前をつけ、所有した気になり、時はそれっきり固定されてしまうように思ってしまう——「1918年、11月11日、午前11時」とか——が、じつは、時は粉々に壊れたり、水銀のように飛び散ってしまうこともある。カート・ヴォネガット『国のない男』
ここで語られることになるのは、個人の内的な時間である。手帳に書き込んだり、生年月日として覚えているような、公的な時間ではない。公的な時間のデザインは、時計やカレンダーという形で、すでに確立されている。内的な時間のやっかいなところ、そして魅力的なところは、誰もが体験していながら、誰にでも通じる説明が存在しないことにある。だからこそ、さまざまな人物がそれぞれの体験を語っているのだ。
SCENE 02
ボルヘスは、ある夜に自宅の近くを散歩しているときに味わった感覚について、過去の作品からの引用を通じて、こう証言している。
私はその純一さにただ惘然と見とれていた。そして考えた、確かに声を出して。これは三十年前とまったくそのまま同じではないか……時間とは、もしわれわれにその実態を直観することができるとすれば、一つの幻想である。見かけ上のきのうという日の一瞬と、見かけ上のきょうという日の一瞬との間には何の相違もなく、両者は不可分のものであるという一事だけで、時間を解体するには十分であろう。ホルヘ・ルイス・ボルヘス「新時間否認論」
村上春樹の『風の歌を聴け』では、十代の頃を回想する主人公が、文章を書くことについてこう語る。「少し気を利かしさえすれば世界は僕の意のままになり、あらゆる価値は転換し、時は流れを変える……そんな気がした」と。
こうした実感に照らすと、時間に関連するデザインはいつも半分だけ的外れである。その理由は、すべての時間のデザインが個々人の「現在」を無視し、公的な時間にフォーカスせざるをえないという事情による。
すべての時計が示す時刻は、私たちそれぞれの「現在」の感覚からはかけ離れている。誰がなんと言おうと、いまは2016年9月28日などではないし、15時4分というのも意味不明だ。私にとっては窓の外に見える景色や太陽の位置、遅めの昼食をとってすこしぼうっとしていること、そういったものが「現在」の感覚のすべてである。
だからこそ、ボルヘスが経験した「三十年前とまったく同じではないか」という感覚は空恐ろしい。それは、限りなく流転するはずの時間のなかに、まったくの同一項がふたつあらわれる悪夢だ。これは、ボルヘスによれば「時間の連続性を崩壊せしめるに足るもの」である。彼が引用した小編は「死の感覚」と題された作品であった。死とは、内的な時間の連続性が崩壊することだ。
SCENE 03
ビデオゲームの分野においても、時間の観念を野心的に取りこみ、作品の成立に役立てている例が多く見られる。昼と夜のコントラストや、日付を活用した作品は類挙にいとまがない。それどころか、おそらくすべての「物語」を擁するゲームジャンル、たとえばRPGやビジュアルノベルなども、その成立に時間の流れを必要としているだろう。
2001年にPCゲームとして発売されたビジュアルノベル『さよならを教えて』は、作中から時間の流れを排することで、悪夢の感覚を描いた作品だ。語り手兼主人公の青年は、自分のことを「教育実習生」だと思い込んでおり、生徒の少女たちと交流する。終盤では、あるひとりの生徒をのぞく全員が主人公の幻覚であり、その正体は猫や烏や生物標本などであったことが明らかになる。
テキストで直截的に語られることはないのだが、ゲームにあらわれるすべてのグラフィックは「夕方」を描いている。自分の感知できる時間帯がこの黄昏に限定されていることに、主人公は最後まで気づくことができない。しかしながら、彼は「時間が進んでいないような気がする」とか「うまく休めた気がしない」といった発言を繰り返す。
これらの発言からは精神の失調さえ読み取れるが、その原因は先述したボルヘスの「死の感覚」に求めることができる。主人公の内的な時間はすでに崩壊している、つまり死んでいるのだが、なぜか彼はまだ生きていて、悪夢的な苦しみを味わい続けているのだ。この状態は、単純な死よりもつらい運命としか言い表しようがなく、プレイヤーに激しい不快感を与える。
 内的な時間が崩壊している主人公の意識において、時間は流れない。言葉は消えず、澱みのように滞積する。
内的な時間が崩壊している主人公の意識において、時間は流れない。言葉は消えず、澱みのように滞積する。
時間の連続性が崩壊するといえば、アドベンチャーゲームの傑作として知られる『ぼくのなつやすみ』での「8月32日現象」も、それに類する恐怖をプレイヤーに与える。この作品は、母親が臨月をむかえたために田舎の親戚の家にあずけられた「ボク」を操作し、昆虫採集や魚釣りをして夏休みの一ヶ月間を過ごすゲームである。このゲームは一日の終わりに「ボク」が絵日記を書き、読書灯を消すことで日付が変わるしくみになっている。
クリアデータをロードして、8月31日の絵日記を回覧すると、グラフィックから削除された読書灯のあたりに、カーソルを合わせることができる。存在しない読書灯の明かりを消すと、カットシーンが挿入され、ゲームデザイン上存在しないはずの8月32日をプレイすることができる。
8月32日には、「ボク」以外のキャラクターは存在せず、空っぽになった広い木造の家はなんともいえない寂寞感をプレイヤーに与える。ふだんならできる行動ができないので、プレイヤーはもういちど読書灯を消し、さらに日付を進める。すると「ボク」の周囲にキャラクターが現れはじめるのだが、ピクセルアートが崩壊しており、誰もが怪物の姿に変貌している。さらに日付を進めるにつれて、表示されるテキストは激しく文字化けをはじめ、自動生成される「ボク」の絵日記は、プログラムが吐き出したピクセルの吐瀉物でいっぱいになる。
このゲームを制作したミレニアムキッチンの代表者 綾部和によれば、「8月32日現象」は純然たるバグであり、本来はデータが存在しない8月32日というパラメーターをドライバーが参照しようとして起こるものだという。この現象は、先ほどの『さよならを教えて』で描かれた内的な時間の崩壊と好対照をなしている。公的な時間が崩壊するとき、キャラクターの内面ではなく、表象される世界そのものが異様なものへと変化するのだ。
では、内的な時間にあわせて、公的な時間を自由に変更できるとしたらどうだろう?
かつて私が『マインクラフト』をプレイしていた2009年ごろには、インターネットを介したマルチプレイを行うためのサーバーを、ユーザーサイドで運営することができた。サーバーの運営者は、その世界において、いわば全能の管理権限を保持していた。運営者はコマンドコンソールを通じて、さまざまな影響を世界に与えることができたが、そこに流れる時間を強制的に書き換え、いきなり昼に戻すためのコマンドがあった。
/time set day
このコマンドは、創世記で言えば第1章3節である。
神は「光あれ」と言った。そして光があった。
 時間さえもコマンドひとつで操れる世界。
時間さえもコマンドひとつで操れる世界。
さきほどまで真っ暗だった世界が、わずか一行のコマンドで一瞬にして白日の下にさらされるのは、とても奇妙な感覚だった。おそらく、時間の流れを早めたり遅めたり、一日の長さを変更したり、太陽を天頂に固定して永遠の正午を味わうこともできたはずだ。現実の時間が深夜であったとしても、溢れんばかりの陽射しのもとで遊ぶことができる。たったひとりきりの人間として動物やモンスターと戯れ、「現在」という時間を気の向くままに操って遊ぶプレイヤーは、もはやその世界を統べる神と言ってよい。だとすれば、「彼のもつ内的な時間がそのまま公的な時間であるような存在こそが神である」といった定義もできるだろう。
SCENE 04
考えてみれば、「現在」という時間は、常に過去と未来が接するところにある、ひとつの点でしかない。大きさを持たない概念としての点は、この世界に実在するものではない。しかし、私たちはなにをもって「現在」という一点を定めるのだろうか。
数学の教科書には、図形を読み解く問題がたくさん出てくる。不思議なことに、それらの図形の線には「長さ」しかなく、「幅」や「厚み」についてはなんの説明もない。高校生のころ、それについて先生に質問してみたことがある。すると、「この線は幅や厚みを持っていないことになっているんだ」という答えが返ってきた。
 線に厚みはなく、点に大きさはない。
線に厚みはなく、点に大きさはない。
時間においても、「現在」という点が「幅」や「厚み」を持っていないのであれば、それを定めるのは、空間的な位置情報となるだろう。「現在」という点は、位置を持っているが大きさを持たない。ここから導き出されるのは、以下のような論証である。
もしも時間が空間に含まれるならば、現在という一点は大きさをもたない。
ゆえに、現在は存在しない。
ゆえに、現在との対比によって観測される過去と未来も存在しない。
ゆえに、現在と過去と未来から成る時間は存在しない。
まったく論理的に思えるが、信じられない感じもする。私は現にいまここにいるし、それこそが現在である。解説することがあまりにも難しいにせよ、私がいまこうして生きているという実感こそが、まぎれもない「現在」である。それなのに、先ほどの論証に奇妙な説得力を感じるのはなぜだろうか。それは、時間の概念を持たない純粋な空間というものが成り立つと、私たちが錯覚してしまうからだ。
SCENE 05
「飛んでいる矢は、的に命中することはない」という命題を証明する「ゼノンのパラドックス」は、その例として古くから知られている。荒木飛呂彦は『ジョジョの奇妙な冒険 Part6 ストーンオーシャン』のなかで、この論証を援用し、自分との距離に比例して他人の大きさを縮小させる赤ん坊を登場させた。登場人物たちがこの赤ん坊にむかって落下したとき、彼らはいつまでも着地できないのではないかという恐怖を抱いた読者も多かっただろう。
このパラドックスは、本来は時間の経過を前提としている物体の運動から、時間の経過を巧妙に排除し、それを距離という空間的な尺度だけで証明してしまうことから生じている。命題も証明も真だが、それが現実に即していないのだ。
ならば、先ほどの命題を「飛んでいる矢は、的に命中する時刻まで的に命中することはない」とすれば、解決するだろうか。一見、とても正しいように感じられるが、論理的な怪しさはぬぐい去れない。物体の運動は時間の流れを前提としているが、時間の流れは物体の運動によってしか計ることができないという、よくある循環論法に陥っている。
パスカルは『パンセ』のなかで、「神は無限の球である。その中心は到るところにあり、その円周はどこにもない」と記し、神の性格のひとつである遍在性を空間において表そうとした。この「遍在」の概念を、もうひとつの連続体である時間にあてはめると、もっとも近いものは「永遠」になると思われる。
SCENE 06
永遠と神の関係について、トマス・アクィナスはこんなことを言っている。
われわれが「今」の流れを把えることによって、われわれのうちに時間の把握が生ぜしめられるように、「とどまる今」を把えるかぎりにおいて、われわれのうちに永遠の把握が生ぜしめられるのである。トマス・アクィナス『神学大全』
ただの人間にすぎない私たちにとって、「とどまる今」を把えることは難しい。なぜなら、私たちはつねに継起する時間の流れのなかから「現在」を把握するからだ。セリーヌは『なしくずしの死』のなかで、通行人の雑踏を停止させようとし、「彼らを止まらせろ……これ以上彼らが消え去らないうちに!」と、紙上で絶叫した。しかし、彼は神ではないので、物語における時間は動き続けた。
時間について明瞭な答えを得られなくとも、答えを得られない理由そのものはすでに提示されている。その理由とは、私たちがつねに継起する時間の流れの影響を受けて、変化しつづける「現在」を生きているから、というものだ。
存在する私というものはつねに現在に存在するのであり、現在の私はその存在することにより私以外のものを変えて行くのである。私以外のものを変えて行くのみならず、私自身をも変えて行くのである。単に観測しているということだけでも私は新しい情報をとり入れるのであり、その知識のために私は新しい私に変わって行く。もっと積極的な働きかけにおいては私自身の変化はさらに疑うことができない。これこそ生命の本質的な性質である。渡辺慧『時』
たとえば、愛するひとの死や、好ましい住処のとつぜんの喪失、人間のもつ陰惨な面に触れたとき、すべてが変化していくという世界の構造を、私は激しく嫌悪する。しかし、好むと好まざるとにかかわらず、私はこの世界のなかに生きているのだから、それを受け入れるほかに生きるすべはない。さもなければ、内的な時間の崩壊は免れないし、公的な時間と折り合いをつけることもできないからだ。そう考えるとき、あらゆるものが変化する世界を積極的に肯定する渡辺の言葉に、深い共感をおぼえる。
私には太陽の位置を自由に動かすことはできない。それは神にしかできないことだ。私はどこまでも人間として、時間と、それがもたらす変化を受け入れながら生きればいい。
SCENE 07
公的な時間のデザインが可能なのは、それが実際には個人的なものだからである。2016年9月28日の18時25分という「スライスされた時間」は、その時間を体験したすべての人間に、それぞれの経験を想起させる。だからこそ、私たちは人と会う約束ができるし、計画をして、それを実行することができる。
対して、内的な時間をデザインすることは不可能になる。なぜなら、そのデザインを作り出す者が、つねに変化しつづける「現在」のなかで時間を把握するからだ。
そして、変化していくことそのものは、個人的な体験ではない。内的な時間は死によって終わりを迎えるが、その体験はまぎれもなくすべての人間が経験するものであり、非個人的である。このことも、内的な時間のデザインの不可能性を強めている。もしも無理矢理に視覚化するならば、熱したチーズのように溶けた懐中時計が描かれたダリの『記憶の固執』や、真昼の青空と深夜の街並みがカンバスに同居しているマグリットの『光の帝国』のようなものになるだろう。そしてそれは、もはやデザインではなく、個人の夢の顕れである。
小説家の倉橋由美子は、エッセイ「小説の迷路と否定性」のなかで、「《この世界ではない世界》、いわば《反世界》の存在を表現すること」が自作への要求であると述べた。そのための手法として、彼女は「事実」や「体験」や「日常性」といった形而下的なものを利用し、形而上的なものを表そうとした。この手法を試みつづける理由は、とある奇妙な時間を体験したからだという。
私が言葉の銅版画にして示したかったのは、子供の頃のある夏の一日、太陽が空に止って白っぽい「永遠」が支配していたような感覚である。倉橋由美子「小説の迷路と否定性」
彼女は、その瞬間だけは、神に近しいなにものかだったのではないだろうか。