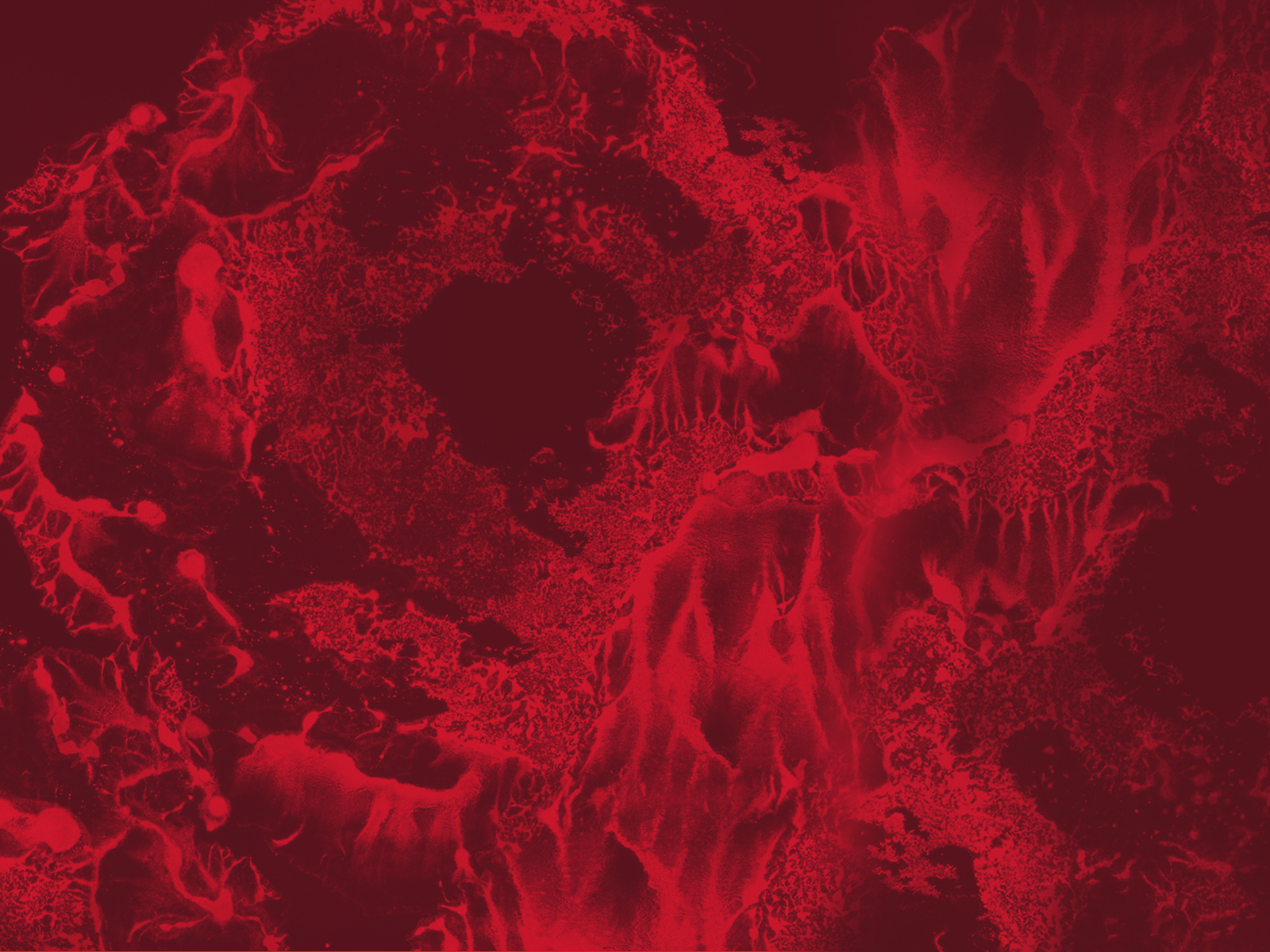ノスタルジーではないアナログ回帰
ピークだった1976年の「2億」から、2009年に「10万」まで落ち込んでいたものが、2017年には急に「100万」まで回復。一体何の数字かと思うだろうが、これはどこかの会社の株価総額の乱高下ではなく、国内のレコードの年間生産枚数だ。
ピークと底値が2000倍も違うとは極端な話だが、CDからネット配信に移った音楽業界で市場規模は小さいものの、ここ10年で10倍も伸びた商品もそうはないだろう。タワーレコードのようにレコード専門フロアを新設する店も現れ、ブックオフなどでも扱う店舗数が激増し、人気のアーティストが新曲のリリースにレコードを加えるようになり、昨年からのコロナ禍の間にアメリカではCDの売り上げを抜いたことがニュースになった。
1970年代末までは音楽消費はアナログ方式のレコードやカセットテープが主流だったが、1980年代に入ってCDが登場し、デジタル方式が席巻しはじめた。折しもパソコンが世に出はじめた頃で、ファミコンが発売されてゲームのBGMに電子音が取り入れられYMOが流行した時代だった。2000年代にはブロードバンド化したネットの普及でダウンロードやストリーミングが主流になり、音楽はパッケージを持たないただのラベルを貼られたデータファイルになっていった。
こうしたレコードの復活劇を横目に見ながら『アナログの逆襲※1』というタイトルの本も見かけるようになり、生まれた時からデジタルが普通のZ世代が物珍しそうにLPやカセットテープを手にする姿が報じられ、「カセットカルチャー」なる言葉も生まれたと聞くと複雑な心境になる。
ノイズが多く、音質も悪く、ウォークマンのようなポータブルプレーヤーにも馴染まず、かさばって場所を取ると敬遠された古いメディアに若い世代が目覚めるのも不思議な気がするが、手に触れられないデジタル信号ではなく、インテリアにも使えそうなサイズのジャケットもいいのだろう。やはりメディアというものは、器としての身体性や物質性が肝要ではないかと、改めて感じている。
デジタル化の普及とその加速
ここ数十年のデジタル化の潮流は、従来のメディアの持つ手法を数値化・アルゴリズム化し、コンピューターを介することで精緻化し分類し精度を向上させてきた。コンピューターはまず文字や記号を論理として扱っていたが、1960年代にはCGの研究が始まってCADのような図面を扱うことから絵画的なアートの表現にも応用されるようになり、次には文字のフォントをアウトライン化し組版をグラフィック化して、画面で見たままをそのまま印刷媒体にも出力できるWYSIWYGを可能にした。
通信の世界では、もともと電信が文字をコード化してデジタル信号のような方式で送っていたが、音声を伝える電話を含めたデジタル化が局の間を結ぶ基幹回線で始まり、1980年代にはそれが一般家庭に届く回線にまで及び、1990年代のインターネットの普及で全デジタル化が加速した。同時にテレビ放送の電波にも、当初不可能と言われてきたデジタル方式の研究が進み、いまでは有線から無線を含めたすべてのインフラやコンテンツに及び、これまで蓄積された人類のあらゆる文物がデジタル情報に変換され、AIの導入によりコンピューターという機械によって読まれ処理される世界がやってきた。
写真の世界では当初、デジタルカメラは精度や表現力で従来のフィルム方式に及ばないと言われてきたが、2年程度で性能の倍化が進むというムーアの法則によって、いまではほぼ完全に市場を独占するまでになっている。スマホに常備されたカメラ機能とネットによって、ありとあらゆる画像や映像までもが自由に流通する世界がやってきた。さらにデジタル化された情報は自由に操作したり加工したり検索したりすることが可能になり、歴史的文物をデジタルでスキャンしてアーカイブしたり、現実世界のモデルを作ってナビゲーションをする「ミラーワールド」や「デジタルダブル」などと呼ばれるVR環境を作ったり、モデル化されたモノを3Dプリンターなどで実体化することまで行われるようになってきており、世界の全デジタル化の流れは止まりそうにない。
しかし、こうした流れが見えるようになってからの時間は40年ほどでしかない。1980年代にパソコンが出現した頃には、「アナログ対デジタル」という二項対立的な図式はまだ成立しておらず、これはその分野の研究者やビジネス、秋葉原に群がりオタクと呼ばれた若者の趣味の問題として、つまりサブカル的なトレンドとしてしか認識されていなかった。新聞や一般雑誌でデジタル関係の話題を扱う場合も、「OS」や「RAM」や「パソコン通信」といった言葉に、毎回注釈を付けなくては通じなかった。
ところが1990年代になってパソコンが大型コンピューターを名実ともに凌駕し、1995年のWindows95発売以降にインターネットが注目されるようになると、従来は特殊な世界の隠語のように扱われていたデジタル世界の用語が日常会話でも頻繁に使われるようになり、「最新のバージョンのアプリをダウンロードしてバグを解消する」などといった話が、ほとんどの場面で通じるようになった。
こうして、ありとあらゆる機器がネットにつながり、教科書からショッピング、ワクチン接種予約から友人との付き合いや国の行政までもがすべてデジタル化される時代には、それに追いつけない旧来の方式や世代が可視化されるようになった。パソコンやスマホを使いこなせない人は、自らを「アナログ人間」と言い訳するようになった。デジタルリテラシーなる言葉も飛び出し、こうした新しい読み書きソロバンに対応できないマイノリティーをどうにかしないと社会が機能不全に陥ると心配する声も聞かれる。それは中世の時代に、グーテンベルクの活版印刷が出現して、それまで口伝えだった物語や決め事がすべて印刷された本に収められるようになり、文字の読み書きができる人の世界観が大きく変わった一方で、そういうリテラシーも持たない人々が取り残されていった姿とも重なる。
こうした印刷革命による中世から近世への転換は、その効果が社会全体に及ぶのに百年単位の時間がかかったものの、それが宗教改革や科学革命の引き金を引き、確実に世界を変えていった。現在のデジタル化もその革命と同じように、世界の人々のコミュニケーション能力を飛躍的に向上させ、アラブの春やSNSによる世界的スターの出現など、前の時代の枠組みを超えた変化を起こしている。その変化の速度は、印刷革命の比ではないほど急激だ。
テクノロジーは普及率が10%を超えたあたりから顕著になり、25%程度になると一気に100%へ向けた加速が始まる。この25%に達するまでの時間は大ざっぱに見積もって、電話は40年、テレビは25年、パソコンは15年だったが、近年の携帯は10年、インターネットは5年と、普及の速度自体が加速している。これから出現するさまざまなメディアやサービスはさらにその傾向を強めると思われ、誰もが追い付いていくのに苦労することになるだろう。
デジタルとアナログの再定義
そうなると、デジタルに対応できないアナログ旧世代は絶滅危惧種になってしまう。そう考えてしまう人も多いのではないだろうか。しかし、デジタルとアナログを二分して、テクノロジーが引き起こす世代間格差に読み替えるのは、この問題の本質を捉えてはいない。現在は、コンピューターやデジタル機器を操作できることがデジタルで、それに追いつけないのがそれ以前のアナログという対立構造とされるが、人間の文明や知はこうした二項対立の優劣でできているわけではない。本質はもっと違うところにある。
そもそもデジタルという言葉はラテン語の「指(digitus)」から来ており、指で数を数える行為によって何かを区切って数値化することを言う。つまり、離散的な値に量子化するところから名付けられたものだ。そして、アナログはギリシア語の「比例(αναλογία)」を語源としている。これは連続した量を表す言葉から来ており、比例の他に「類推・類比・比論」などと訳される。似た物を比較して共通する傾向や法則を導くアナロジーも、これと同じ語源である。
最近のトレンドは、こうした本来数えられない何かの比を無理やり数値化してデジタルの数値に換算して処理しているだけで、われわれは生活の中で通常どちらが大きいかという判断に、わざわざ面積や体積を計ってはおらず、目視や秤を使っても分からないときに初めて数値化しているに過ぎない。そのためには、ある人為的な基準になるメートルとかグラムとか言われる単位を設定して、対象とのアナログ的な比較で閾値を定めて切って数値化するしかない。
もともとデジタルの元になった数えるという行為は、分かれているものの個々を一体と見なして数えるか、数えられないものを無理やり等量に分けて、それに数のラベル付けて数えているに過ぎない。しかし、この数えるときに使われる自然数の考え方は、連続する音声を切って文字に変換する書き言葉の延長線上にある言語的な行為の一環で、数字にひとつずつ加えて序数として順番を付けて並べ、後の方に来るものほど大きいとみなす行為だ。
リベラルアーツと数学
人類が最初に数と真剣に向き合うようになったのは、古代のギリシャ・ローマ時代だろう。現在は大学の教養科目を「リベラルアーツ」とも呼ぶが、これはもともとこの時代の学問体系から派生した「自由七科」(septem artes liberales)が元になっており、この中に数学が位置付けられていた。この七科は言語に関する三科(trivium)と数学に関わる四科(quadrivium)に分かれ、三科は「文法・修辞学・弁証法(論理学)」、四科は「算術・幾何・天文・音楽」から構成され、それらを統合する上位の学として哲学、さらには神学が控えている。
この四科を詳細に見ていくと、「算術」は人や物の数を数えることを基礎とした数論で、幾何は測量から派生した空間の測定から派生した学問としてユークリッドなどが体系化したものだ。算術はまさにデジタルのようにすべてを数値化し、それを演算して大小を決めたり取引に使ったりするためのもので、1次元的な世界を対象にする。
「幾何」はもともとナイル川の氾濫により土地を再区分することから発達したが、2次元の面の量を対象としたものだ。面積は周囲の長さを測量して求めることもできるが、面積を比較する際には分数のように自然数同士を対比することで、自然数では記述できない、いわゆる数えることのできない有理数が必要になる。比で表された数は割り切れることもあるが、自然数ではカバーされない有限や無限の小数になる。さらにはこうした比で表せる有理数ではない、平方根やπのような無理数も生じてくる。こうした量としての体系が有理数と無理数を合わせた実数で、その有理数の中のごく一部に自然数に負の数を加えた整数があり、その中の負の数を除いた数えられものに対応した自然数が包含されている。
ここで数学の理論を問題にしたいのではなく、むしろ自然の中で個々に数えられるものは例外的なもので、数えられないものの方がはるかに多いという事に注目してほしい。すべてを数の体系で表記できるが、それを数えることはできず、大小が比較できるだけの無限に数え続ける数としての量なのだ。
四科の他の学にはさらに「天文」があるが、これは星の動きを3次元的に記述して追うもので、残った「音楽」は数で表される音の周波数同士の調和を時間的な展開の中で測るので、4次元的なものになる。いくぶん乱暴な解釈になるかもしれないが、四科の「算術・幾何・天文・音楽」は数学の次元を高めていく体系なのだ。三科の「文法・修辞学・弁証法」は文系の学ではあるが、言語論理としての基礎体系であり、これらを自然体系に次元別に展開したのが四科だと考えるなら、リベラルアーツ全体の体系が見えてくるだろう。
こうした学問や知の体系は、13世紀にヨーロッパで大学が作られたときに法学、医学などの専門応用分野や神学が加わった際に、これらの基礎学問体系として採用され、その後はスコラ学などの洗礼を受け、その後の科学革命や啓蒙主義による新しい学の基底にあった。その後、独立を果たしたアメリカの教育で意識的に取り上げられるようになり、現在はまたさまざまな学問や知の体系の基礎として日本の大学でもリベラルアーツの重要性を説くようになってきている。
コンピューターは数論から幾何学へ進化した
このいわば知の原型(アーキタイプ)とも言えるリベラルアーツに、最近の情報科学を対照して眺めてみると、現在のコンピューターはアルゴリズムとしての三学をもとに、徹底的にすべてを数値化して演算することから始めるもので、まず四学のうちの「算術」を拡張したものと考えられる。
ところが自然数を基本に置いた四則演算を高速に行うことで発達したコンピューターは、科学計算や給与計算、経済予測などには有効だったものの、人間なら子どもでもできる人の顔を区別したり、アルゴリズムを特定できない事物には無力だった。そのため数値計算でカバーできない対象を、アナログ的にパターンとして比較分類するパターン認識と言う分野の研究が始まった。つまり、直線的な数値演算ではなく、二次元的な量や形の比較によって分類や処理を行う方式だ。
コンピューターは脳の働きをモデル化したものとされるが、チューリング・マシンと呼ばれる数学者アラン・チューリングの計算モデルは、言語的思考の記号演算を基本にした論理モデルだった。しかし実際の脳にはコンピューターのような演算回路や素子に該当するものはなく、ニューロンが絡み合っているだけだ。そこでニューロンのモデルをそのまま回路化して、つまり脳神経をアナログ的に類比して作られた「ニューラル・ネットワーク」というモデルが存在する。
このモデルは最初、1957年にフランク・ローゼンブラットがパーセプトロンとしてモデル化し、多くの事例やデータを与えることでニューロン間の結合を最適化するように学習し、人間が論理でなく経験からパターンを学んでいく方式を応用する道を拓き、これがチューリングの論理方式と等価な演算を行えることも確認された。そして、何度かニューラル・ネットワークのブームが訪れたが、複雑なニューロンに大量に学習データを与えてニューロン間の結合を調整するための計算を、論理方式の現在のコンピューターで個々に分解して行うと、膨大な計算が生じて、なかなか実用的な成果が出なかった。
ところが近年になって、ゲーム機などで使われる並列画像処理の演算チップを使うことにより、この計算を桁違いに早く行わせることが可能になり、複雑なニューロンのモデルを構築して実験してみると、猫や犬の写真を見分けることから始まって、ついには専門家が経験で判断していた画像の分類などを人間を上回る精度でこなすようになってきた。この新しいニューラル・ネットワークは、非常に高度だと思われてきた将棋や囲碁などの盤面ゲームにも応用され、論理計算では突破できなかった人間を上回る能力を発揮するようになり、グーグルに買収されたディープマインド社が開発した囲碁プログラムのアルファ碁は2015年にプロ囲碁棋士を破り、2年後には世界チャンピオンを破るまでになった。
当初の人工知能(AI)の開発は、論理計算で人間の能力を真似して知的な処理を行うもので、言葉による論理を論理式で演算する、いわば数論の証明のような処理を行ってきたため、言語化できない対象や、論理やアルゴリズムが解明できない対象には非力だった。ところがニューラル・ネットワークのような直線的な論理ではなく、並列的に情報を比較して分類する方式は、まさに情報を幾何学的に扱い、量としての比較を通して解答に至ろうとする方式で、論理やアルゴリズムが解明されていない対象に対しても有効だ。
アルファ碁がプロ囲碁棋士を打ち負かしているのは、膨大な可能性をひとつひとつ論理演算しているではなく、人間が経験から学んだ直感的に勝てるパターンを使って勝負をする方式を踏襲し、それを人間の脳より早く、より多くの可能性を試すことができるせいだ。そう考えるなら、第三次AIブームとして再び注目されている現在のトレンドは、まさにニューラル・ネットワークにより、コンピューターが数論から幾何学へ進化した、つまり、デジタルからアナログへと進化、もしくは深化したものと考えられなくもない。
アナログは数や論理を言語的に追う作法ではなく、面的に量を比較検討していくことだと考えるなら、アナログがデジタルに劣った何か低次元の話だと考えるのは、はなはだしい誤解である。つまり、現在注目が高まるAIブームは、われわれが信じるところのデジタル万能主義の拡張系と言うよりも、アナログへの回帰によるコンピューティングの新次元への進化と考えるべきなのだ。
現在はデジタル方式のコンピューターの全盛時代で、ニューラル・ネットワークの学習過程を計算で支えているのは、ニューラルをモデル化したデジタル方式のマシンだ。それはアナログ的なネットワークモデルの中を通るデータを、従来のようにひとつひとつデジタル化して分解して処理しているのでデジタル方式に見えるが、全体の構成や処理方式がアナログ的な方式なのだ。
アナログコンピューターとボルヘスの悪夢
1946年に発表された、初の全電子方式のデジタル計算機ENIACは、巨大な電子式ソロバンのようなものだったが、実はそれに先立ってアナログ・コンピューターが研究されていた。
これは、計算モデルを逐一計算するのではなく、基本的に対象のメカニズムをそのまま真似したモデルを、電気回路や歯車を組み合わせた機械を作り、こうしたミニモデルで対象の全体を模倣するものだった。いちいち手間のかかる数値計算をすることなく、瞬時に結果を得ることができるが、電気部品のバラツキや歯車の精度に制約を受け、大まかな比や動きとしての大局を把握することには有用だが、最終的な精度を数値演算的な方法のように高めることに限界があり、結局はデジタル方式のコンピューターが実用化されると表舞台から消えていった。
最も古いアナログ・コンピューターで有名なのは、太陽系儀オーラリーだ。これは古代に作られた太陽や月の動きを模して作られた太陽系のミニモデルで、太陽と月と地球の規則的な動きを歯車で組み合わせて、その日時に地球の模型を動かすと、太陽や月が連動して動いて実際の位置を割り出してくれるもので、ギリシア時代からあったとされるが、18世紀初頭にオーラリー伯爵の名前から取られて、この呼び方になった。
これはまさに、ラテン文学の巨匠ルイス・ボルヘスが『創造者※2』の中で書いた、ある皇帝と地図師の話を彷彿とする。皇帝は正確な地図を目指して地図師に詳細な現実の世界の地図を作らせるのだが、それがあまりに忠実なモデルとなってしまい、最後には現実の帝国と入れ替わってしまうという話だ。
インターネットの次の姿として、現在注目を浴びているミラーワールドは、現実の都市を忠実に再現したシミュレーションモデルで、例えばその中でデジタル化した自動運転車を走行させて訓練を重ね、さまざまなシチュエーションの場面から学習させることもできる。まるで現実を生き写しにした鏡が、現実の代わりに動いて現実を支配してしまうという、ボルヘスの描いた悪夢そのままの構図もそこには見える。
ウェブと検索サービスが支配するインターネットは、もともとは数値計算する計算機を電信のようなネットワークを用いて相互に接続して、それぞれの計算機が手紙をやり取りして同じ計算を分担して行うような共同作業のためのものだった。また当初はデータベースという図書館のような大量のデータの集積所にアクセスして、書物を閲覧する道具のように使われた。それが90年代のウェブの導入によって誰でもが簡単に使えるようになり、コンピューター同士の通信が、コンピューターと人の通信に移行し、ついにはコンピューターのネットワークの周辺に位置していた人と人を中心につなぐようになってきて、それがウェブ2.0とかソーシャルメディアと呼ばれるようになった。
この時代にはグーグルのように、インターネットの集合体としてのクラウドの中にある情報をキーワードで検索して選び出すというばかりではなく、キーワードという言葉で名指しできない、何かのトレンドやマクロな傾向を感覚的に把握することも必要になってくる。いまでは、人々の集めた文字化されたデータをキーワードで探るばかりか、利用者がどういう情報と、もしくはどういう対象や他者とコミュニケーションをしているかという行動パターンやコンテクストが重要になっている。アマゾンが利用者の購買パターンから商品と消費者、もしくは消費者同士の情報交換からリコメンドを提示してくるように、情報パターンをアナログ的に処理することが社会全体のミニモデルとして成立しており、インターネットはまさにミラーワールドとして機能しはじめている。
来たるべきアナログ時代のデザイン
こうした時代にデザインするという行為は、まさにこの不特定で論理の分からない自然現象や社会現象に対して、その環境で学んだ人間もその中の一部となって、全体像を模索する作業になる。緻密な論理計算を必要とする局面もあるかもしれないが、まだ海の物とも山の物とも分からない対象に、経験や直感から生まれたヴィジョンを重ね合わせ、対象のあるべき姿に対してのヴィジョンを実現してくことになる。
リベラルアーツは、こうした人間の知の仕組みを、言語の論理で定式化し、自然や社会と言う対象に関しては、まずは言語的な数論的思考で攻め、次に幾何学的に量を比較しながらバランスを整え、さらにはそれを天文学的に立体的に調和した形に組み上げ、全体を時間軸の中で音楽を奏でるように演奏する手法を提唱している。現在のコンピューターは基本的な計画の構造や工程を論理的に整備することに威力を発揮するが、それに加えてパターン的直観的なもっと空間的な広がりのあるデザインという行為をサポートしようとしている。
そう考えるなら、現在の時代に遅れたアナログと、次世代を先導するデジタルという二分法は、まるでナンセンスになってしまう。現在のインフラとしてのコンピューターは土台部分を数値計算によって精密化して強化しているが、いくらAIを導入して人間より早く高度な問題に解を導き出してくれるとしても、どういう問題を解かなくてはいけないか、いままで問題にされなかった疑問を導き出すということに関しては脆弱だ。
デジタル方式の算術型のコンピューターが、限定された問題領域で成果を上げているのを見てその延長線上に、コンピューターの知的能力が人類を上回るとするシンギュラリティーの論議がまことしやかに取り上げられ、「AIが人類を滅ぼすのか」といった類の本が出ているが、これもデジタルとアナログの優劣を論じるのと同じく意味はない。
現在は人間の脳を中心にした能力の一部を、デジタル方式で拡張している最中だが、コンピューターの進化の次のステップとしては、個々に数値処理した対象同士の相互の集合的なパターンを幾何学的アナログ的に処理することが求められており、それこそまさに人間が経験や直感から判断する「デザイン的思考」に近いものなのだ。脳に特化したように見えるコンピューターを人間全体の機械化ともっと広く捉えるなら、もともとは肢体を機械化したものとして捉えられてきた車やさまざまな工具を高度化して人間の似姿にしたロボットこそ、こうしたトレンドの行く先にあるものかもしれない。
人間を機械という他者、もしくは人間以外の何かで代替するという流れで見るなら、現在のコンピューターによるAIは、脳髄の言語機能にだけに特化した拡張で、AIが外界の情報をそのまま得て、外界にそのまま作用するには、それによって駆動される肢体が必要になる。その典型的な応用例として、現在よく話題になる自動運転車が典型的事例になるだろう。利用者が意志を持って身体的移動をするために、目的地をイメージし指令すればそれを地図情報やその時点の交通パターンに対応して判断し、道路のいま現在の状況にリアルタイムで対処しながら安全に目的地に到着するというモバイルマシンこそ、人間の脳と身体を拡張したパートナーの雛形だ。
アンドロイドや外骨格としての人間型もしくは人間のパートナーとしての広い意味でのロボットやアンドロイドは、何も機械の身体を持たなくてはならないというものではない。すでに人類の半数以上が常時接続されている集合体としてのインターネットは、地球全体をニューラル・ネットワーク化した身体のような存在で、ソフトや情報で直接的・間接的に人類をひとつの人間のようにまとめている。
こうした世界では、利用者である個人の生活空間や精神世界とネット全体の集合的実体が、まるでフラクタルのような相似形としてアナログな関係にあり、個人の主張や情報発信が全世界でリアルタイムに共有されていく。そんな時代の人生観や世界観は、いままでのメディアの発達の中で得られた知見を理解し、さらに違うステージの問題として考えていかなくては論議できない。そこにこそ未来のデザインの可能性がある。