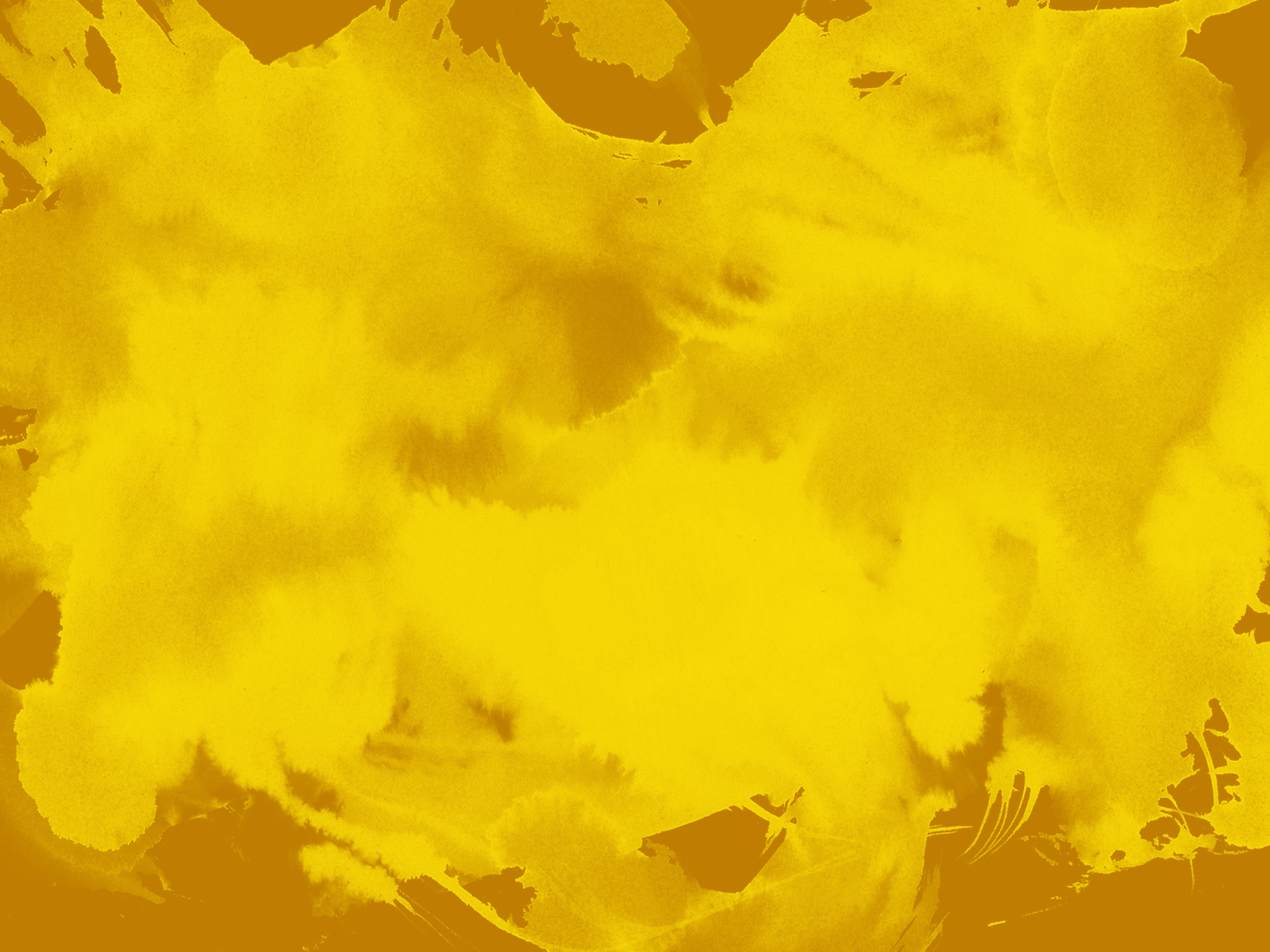宮本万里:
ご著書 “Animal Intimacies: Interspecies Relatedness in India’s Central Himalayas※1”に対するアメリカ人類学会の2019年のベイトソン賞の受賞おめでとうございます。今日は、この本の中身を中心にインタヴューを行ないたいと思います。
本書のなかでは、ヤギ、ウシ、サル、ブタ、クマという5種類の動物を主に取り上げていますね。これらの動物のうち、サルやクマは明らかに家畜化された動物ではありません。家庭で飼育されている家畜と野生動物とでは、村の人々と動物との関係性は全く異なると想像しますが、この5種類の動物に関する物語を1冊の本にまとめようと考えた理由は何だったのでしょうか。また、これらの複数の動物の関係性を通して何を伝えたいと考えたのでしょうか。
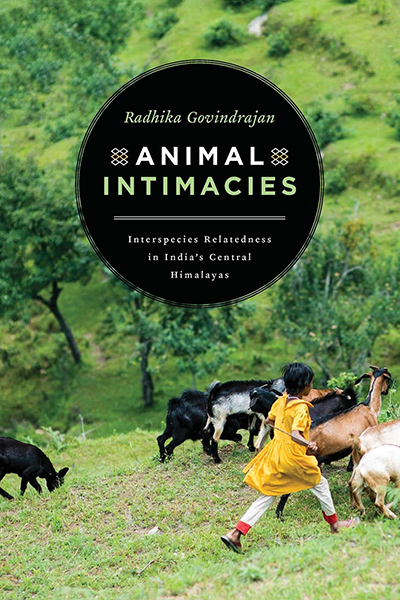
ラディカ・ゴヴィンドラジャン:
私は、修士号を南アジア近代史で取り、修士課程では、同地域における植民地時代の野生動物保護に関する研究を行いました。その後、博士課程の研究として、そのテーマでフィールドワークを行いました。私が博士課程を開始した当初は、野生動物の保護に焦点を当てつつ、それを現代にまで拡大していこうと考えていました。しかし、私はすぐに、野生動物と家畜動物といった分類は歴史的背景に左右され変化するものであって、その境界は常に曖昧であることに気がつきました。例えば、ヒョウが村をうろついて人を襲うのは、神々が「バリ」、つまりは家畜の生贄を望んでいることを示しています。ゆえにヒョウは神々にとっては家畜化された動物なのだ、と村人が私に言ったことがありました。こうした分類における流動性が、様々な動物がどのように異なる場所に出入りしているのか、もっと深く考えてみたいと思うきっかけです。それによって、「野生動物」という自明で不変の分類に違和感を覚え、人間と人間以外の動物が日常的に遭遇していくなかで、このような分類が、いつどうして意味を持つようになったのかを考えるようになりました。
なぜこの5種類の動物なのかという問いについては、これらの動物が、それぞれが全く異なる状況に置かれていると考えるからです。本書における重要なポイントのひとつは、個々の動物やその集団の歴史・性質・行動が、特定の社会的関係や社会を構築する上で欠かせないものだという点です。
血縁関係の一形態としての生贄に関する章は、ヤギの物質性とその性癖、そして人間とヤギとの関係性について扱っています。ウシの保護に関する問題や、国家の開発プロジェクトが「外来種」のウシを飼うのか「在来種」のウシを飼うのかというジレンマをどのように生み出してきたかという問題などがあります。それらについては、様々なウシの特性を実際に知ることによってのみ解決することができるのだと思います。外来種のウシへの懸念や、そのことが文化的アイデンティティに与える影響については、平地の都市部から山村に置き去りにされたサルの話を通して探ることができます。私がヤギを通してこうした話を語ったとしても、同じものとはならなかったでしょう。なぜなら、帰属に関するこのような話が可能になったのも、外来種のサルの行動があったからです。セクシュアリティと家父長制に関する問題は、クマの話を中心にしています。
はじめにこのような大きなテーマに興味を持ち、そのテーマが特定の動物によって具現化されていることに気づいたのです。最初に本書を執筆しようと考えたとき、各章で異なる動物を取り上げることになるとは思ってもいませんでした。各章は「生贄について」「宗教と保護政策について」「所有と移動・移住について」、そして「セクシュアリティについて」の章になると考えていました。しかし、執筆を進めるうちに、「なるほど、それぞれのテーマは、これら5種類の動物と、人間・神・国家・人間以外のその他動物との間にある状況化された関係性によって明確に説明できるのだ」と思うようになりました。ですので、異なる動物を中心に各章を構成したいとはじめから考えていたわけではなく、こうした経緯を通して本書の構成が自然と出来上がりました。
人間の代わりに犠牲となるヤギ
宮本:
第2章はヤギの生贄についてでしたが、そこでは、生贄として捧げる動物を世話する村の女性たちの労働とその価値について書かれています。
南アジアにおいて女性と「自然」との関係性や愛着を説明する際、ヴァンダナ・シヴァ※2などが主張するエコフェミニズム等の既存の理論を通して説明されることが多いですが、あなたは女性の労働に焦点を当てることで既存の理論を全く異なる方向へ導いており、その分析視角は非常に新鮮でした。
ゴヴィンドラジャン:
そうですね、ある種のエコフェミニズムの文献は、このような本質化された範疇で議論される傾向にありますが、それは、たとえそのような主張が善意に行われたのとしても、本当に問題だと思っています。とはいえ、いくつかの研究は、自然に対する女性の親和性を示す例としてエコフェミニストたちが支持しているチプコ運動などについて議論しながら、これらの主張を見事に複雑化させています。例えば、ハリプリヤ・ランガンは、女性が「生まれながらの」環境保護主義者であるというエコフェミニストの主張は、実際には女性たちが抱く経済開発への願望を不可視化することになっていると指摘しています※3。
そもそも彼女らが抗議を行う理由のひとつは、このような状況で生きていくことの難しさに注目してもらうことにあります。私にとって、カースト・資本・ジェンダーといった政治経済的問題について考えることは非常に重要であり、女性の自然への親和性を生来的なものとして崇拝することに対する重要な対抗手段となります。私は、広範囲の構造的な要素によって形作られる労働の特定のやり方から、どのようにして感情的な愛着や葛藤が生まれてくるのかを探ることに興味があります。生贄を扱った章では、このように、母性的な愛着というジェンダー化された言説が、動物の世話において、女性が全責任を背負うという家父長的な労働体制によって、どのように形作られているのかを考えています。

宮本:
人々の労働の軽重が神々によって計測され、その労働だけがヤギを貴重な生贄として価値あるものにするという考えは、刺激的であり興味深いと思います。他方で、あなたの主張の中では、野生動物を生贄にするという習慣の有無やその価値については、全く触れられていないようです。狩猟を通した野生動物の供儀のような習慣は、あなたのフィールドとする山間部にはもともと存在しないのでしょうか。あるいは、現在のように家畜を生贄とする風習は、実際には平野部の人々によって持ちこまれたものである可能性はあるでしょうか。
ゴヴィンダラジャン:
興味深い質問ですね。ヴィーナ・ダスといった研究者は、ヴェーダ時代までさかのぼれば、人間も生贄となる5種類の存在のうちのひとつであったのだと主張しています※4。私たちが野生動物と呼ぶ動物も含め、さまざまな種類の生物が生贄として供されてきました。しかしながら、私のフィールドワークの対象地域では、生贄とされているのは家畜だけです。この地域の生贄の歴史が示すように、本来の生贄は人間でしたが、悲しみにくれた両親の嘆願の末、神々は人間の代わりに動物を生贄にすることを許しました。しかし、その代替の生贄を失うことは、痛みと悲しみをもたらさなければなりません。簡単に別れられるなら、本来、犠牲とはならないからです。
狩猟に関して述べると、この地域において植民地時代と植民地後の野生動物保護の歴史が長く、法的な規制の結果、狩猟はほとんど行われなくなりました。この地域の人々は、「密猟」により、国から罰金や投獄という罰則が与えられることを恐れました。時折ジャングルの鳥を殺したり、イノシシを殺す話をする人もいますが、野生動物の狩猟は決して一般的なものではありません。私が話を聞いた人々のなかで、野生動物を生贄として捧げたと記憶している者はいませんでした。
そうは言っても、この地域のある特定の寺院では、生贄となる動物やその方法について、今述べたことと違う部分もあります。デヴィドゥラ(Devidhura)という寺院で聞いた話によると、女神は、人々が人間の代わりに動物を生贄として受け入れて欲しいと懇願した際、こう言ったそうです。「よろしい、では動物の生贄を受け入れるが、人間の血も捧げるように」と。ラクシャー・バンダンの日にこの寺院で何が行われるかというと、寺院の世話を任されている4つの氏族が寺院に集まり、10分間互いに石をぶつけ合うのです。そして、戦いの後に地面に十分な人間の血がこぼれていれば、女神の人間の血に対する要求は満たされた、と考えることにしたのです。そしてご想像の通り、この種の儀式は、多くの活動家や第三者の不安の種となっています。なぜなら、儀式的な投石が例証したように、これには「近代性」が欠けているとして受け取られたためです。
しかし、この場はたしかに「近代的」な空間であり、祭はすくなくともこれまで数回は(携帯電話会社の)ボーダフォンがスポンサーとなっていました。このイベントの見物者には、携帯電話のSIMカードが配布されることもあったのです。これらの祭りは、しばしば地方公務員らによって開催されていました。活動家がどのように生贄というテーマに取り組むかを決定づける、伝統と近代性の言説を考えるためには、この場は本当に魅力的な空間だと思います。
在来のウシと外来のウシ、ウシ保護論者とヒンドゥー・ナショナリズム
宮本:
第3章では「パハリ牛」と呼ばれる在来牛に対する人々の愛着・執着が描かれています。パハリ牛あるいは在来牛というカテゴリーは、「商用牛」や「近代牛」と呼ばれる外来種のジャージー牛と比較するなかでその特徴が明確化します。本を読んで、牧畜村の発展のために政府がジャージー牛を導入したブータンの事例が思い起こされました。私が調査を行っているブータンの村の村民は仏教徒です。ウシにはヒンドゥー教のような宗教的価値はありませんが、外来種のウシが季節的な移牧の妨げになることが懸念されており、人々は交雑が進むことを心配していました。あなたがフィールドワークを行った地域では、在来牛がジャージー牛と交配した場合、生まれた雑種はジャージー牛とみなされるのでしょうか。また在来牛だけが持つ宗教的な力を認める一方で、地域の人々は、この2種類のウシの境界をどこに定めているのでしょうか。
ゴヴィンドラジャン:
これらのウシを交雑させた場合、通常は「ドガラ(dogalla)」と呼ばれ、2つの品種の中間に位置づけられます。それは、もう「純粋な」在来牛とはみなされません。
ヒンドゥー教至上主義者の言説の中でも、在来性が特に重要視されています。現在、多くの牛舎では「うちは在来牛しか飼っていないよ。外国産の牛は要らないね」と言うでしょう。そして、本書にもある通り、確かハリヤーナー州だったと思いますが、ある政治指導者は、ジャージー牛の牛乳を飲むと、ジャージー牛自身が犯罪者の性質を持っているため、犯罪者になってしまうという類のことを言っていました。その言説の中には、非常に強い排外主義的な歪みがあります。「在来牛の繁殖のみを推奨すべきだ」と国に提言するウシ保護論者も出てきています。そして、国はある在来品種の再現プロジェクトにも投資しています。

しかし、酪農を農村開発の原動力にしようとするのであれば、ジャージー牛よりも乳量がすくない「パハリ」種を奨励するのが難しいという事実は変わりません。乳量が多いとの理由から、サヒワール種や平地系の在来品種を勧める人もいますが、このような地形では飼育はより困難です。つまり、酪農とウシの保護を同時に推進するというこのプロジェクトの核心には、軋轢が存在するのです。私が本書で述べたなかでの最大の葛藤のひとつは、「ジャージー牛をどうすべきか?」という問題で、ヒンドゥー教至上主義者と地元の人々の双方を悩ませています。ウシ保護論者は、外来種のウシは純粋でなく、犯罪者で、愛情や世話をするに値しないと思っていても、「ああ、このジャージー牛は外来種だから殺しても良いのだ」とは言いたくないのです。結局のところ、これらのウシもまたウシなのですから。そして、この認識が行き詰まりを生み、彼らが現在、解決しようとしている難問を生み出しています。彼らの多くは、現実にはそこまで多くのウシを育てることができないこと、そして国によって酪農がこれほどまでに推進されている限り、雄牛や老齢牛を見捨てざるを得ないことを認識しているからです。
ケイティ・ガレスピー※5やヤミニ・ナラヤナン※6ようなフェミニスト研究者が指摘するように、乳牛の理にかなった末路は牛肉なのです。この点は、右翼のウシ保護論者の多くが考え抜こうとしている問題だと思います。本書では、世界ヒンドゥー協会(VHP)のある指導者が、ヒンドゥー教徒はウシを捨てても非難されるべきではなく、ウシを捨てず手放さないよう人を説得する方法を考える責任は、ウシ保護論者にあると主張したことについて述べています。彼らは、「どうすれば酪農にも焦点を当てつつ、在来牛を推進できるのか」と問いかけています。そして、それが時々、興味深い意味で国家との対立点となって現れるのです。
§
宮本:
現在のインドにおけるウシ保護を取り巻く環境について知ることができ、とても興味深く感じました。ウシをめぐる分類はすでに重層的なものとなっていますが、あなたが在来牛に関して説明された側面は、ヒマラヤ地域を含む多くの地域で、一層重要なものになってきていると思います。近年では、女性たちは、在来牛以上に、ジャージー牛の飼育により多くの労力を投入する必要に迫らせているようです。もしも、投入された労働量を考慮すれば、将来的には、ジャージー牛が神々への最良の贈り物になりうるでしょうか。それとも、ジャージー牛は、宗教的価値という点から在来牛の代わりになることは決してないと考えますか。
ゴヴィンドラジャン:
いいえ、人々はジャージー牛が宗教的に重要なウシになる可能性があるという考えも受け入れています。本書のなかでも触れた、私が興味深いと感じた疑問のひとつに「どの時点でジャージー牛が山地のウシになるか」というものがあります。「品種」自体も存在論的には不変の分類という訳ではありませんが、必ずしも「品種」の変容という意味ではなく、これらのウシが食べる食べ物、飲む水、従属する神々、山で過ごした世代の長さなど、山に対する様々な実質的な関連性や交流という面での話です。すくなくとも私がフィールドワークを行った地域では、農村部の家庭で「純粋な」在来牛を見つけることがより困難になっていることから、多くの人がジャージー牛しか手に入らないかもしれないという考えで揉めていたように思います。
人々はジャージー牛の糞尿で間に合わせの儀式を行うようになっています。一部の人々は、このような儀式は最終的にジャージー牛の異なる物質性に順応していくのではと推測しています。ジャージー牛が「商用」牛となると同時に、「儀式用」牛となることへの寛容性もありました。これが、これらの農家が持つウシの分類についての見解と、右派ヒンドゥー教徒の無節操な排外主義とを区別している点だと考えます。これらの村でも、外来牛や在来牛といった分類を使っていましたが、ジャージー牛に深い愛情を注いでいないという訳ではありませんでした。その点については、本書の中で詳しく記しています。村人たちは、ジャージー牛がある種の儀式には不向きなウシであると言いつつも、自分たちが育てているウシに強い愛情と尊敬の念を抱いていました。これは特に、これらのウシの飼育に関する労働の大部分を担っていた女性に当てはまりました。
外来のサル、在来のサル、排除するか、帰属させるか
宮本:
続く第4章では、都市部に住むよそ者が新たに連れてきたサルと地域の人々の関係性を、サルに対する人々の振る舞いや態度から描き出そうとしています。(都市から山岳部へサルを移動させるという)この現象の背景には、ハヌマーン(ヒンドゥー教の神猿)の崇拝もあるとお考えですか。つまり、ヒンドゥー教を信仰する人々が、ハヌマーン神の眷属は聖域にいるべきだと考え、都市に住むサルを山へと移動させようとしているのでしょうか。
ゴヴィンドラジャン:
それもありますが、サルが野生動物保護法で保護されているからです。間引きに反対する宗教的な議論は確かにありますが、動物愛護活動家が主張する、サルを殺すことは法律に違反するという議論もあります。隣のヒマーチャル・プラデーシュ州では、農家に凶暴化するサルを銃で撃つ免状を与えると発表しました。それが発表された時、様々な選挙区で大騒ぎになりました。動物愛護団体は、これは残虐行為だと言い、野生動物保護活動家は、インドの野生動物の遺産の大規模な破壊への扉を開くきっかけとなることを懸念し、ヒンドゥー・ナショナリズム団体は、サルはハヌマーンを体現した存在であるため殺してはならないと主張しました。多くの森林警備隊員は、この問題がどれほど多くの議論を生んでいるかを考えると、どうしたらいいのか本当にわからないと私に話してくれました。
しかし、農村の生活への被害は現実のものです。複数の組織やNGOがこの問題に取り組んでいます。このような状況では、人は農業を続けることができません。これは深刻な問題で、さまざまな解決策が提案されています。不妊手術を行うという選択肢もあります。それが成功しなかったのは、特に動物愛護活動家から、人道的に実施できるかどうかについて懸念が出たからです。間引きという解決策も、まだあまり好意的に受け止められていません。
宗教の問題は、多くの山地の民にとって複雑なものでした。サルを殺すのは罪深いと考える傾向にある一方で、果樹園を荒らしていたサルに毒を盛るという話もよく聞きます。ある男性は、かつて私に、自身の土地で、死んだアカゲザルを見つけたと言いました。彼はあまり多く説明しませんでしたが、私は彼が多くの収穫物を失ったことへの悔しさから、畑に毒を撒いたのではないかと推察しました。死んだサルを見て罪悪感と恐怖を感じた彼は、贖罪としてラングールに餌を与えていました。このように、こうした都会からきたサルをどう扱うかについては、倫理的・宗教的に深いジレンマがあり、それに対応するために様々な解決策が生まれました。

§
宮本:
現在、村にはあなたが描くように都市部から来た外来のサルがいますが、それ以前から同地域には在来のサルが生息していましたよね。その在来のサルと外来のサルを比較してみると、当然のことながら、人々は現在は在来のサルに対して自分の身内のような愛着を持っており、都会のサルが彼らにとっていかに異質な存在であるかを語るでしょう。しかし、都会のサルが来てから、在来のサルに対する認識が寛容になったということは考えられるように思います。在来のサルと村人との以前の関係性はどのようなものだったのでしょうか。地域の共同体の一部となりうるような、親しみのある存在としてのみ認識されていたのでしょうか。それとも、駆除されるべき害獣として認識されていたのでしょうか。
ゴヴィンドラジャン:
その地域に生息するあらゆる動物が、害獣・友人・仲間という異なるカテゴリーの間を浮動する存在だ、という強い感覚が、私の中に間違いなくあります。在来のサルも、間違いなく時には「害獣」となる可能性があります。しかし、人々は、在来のサルの「略奪」には対処できるという感覚があり、それは外来のサルとの共存に関連してよく表現される言葉「アアタンク(aatank)」、つまり恐怖、の感覚はありませんでした。人々が私に言うには、たいていの場合、在来のサルが果樹園に来るのは数日で、その後は森に戻るのだそうです。彼らにとっては、森で十分だったからです。彼らは時々森から出てきましたが、村に住むことはありませんでした。このこともまた、現在の状況の特異性を強調するための、懐古の念を含んだ過去の恣意的な解釈である可能性もあります。しかし、それは広く主張されており、私たちは真摯に受け止めなければならないと思います。
また、人々はそれとは異なったことも述べます。一つには、略奪の性質の違いが挙げられます。在来の森のサルはたまに果実を盗んだり、農作物を食べたりすることはあっても、外来のサルのように家の中まで入ってくることはありませんでした。そこには、恐怖感と不安感が蔓延していたのです。「これら外来のサルは、すぐに家の中まで入ってきます。人が家の中で座っていても、ただ入ってきて人の食べ物を奪うのです。もしあなたが何かを言えば、噛み付いてくるでしょう」と。人々はこの行為を、在来のサルにはない「大胆な犯罪性」のようなものとして語っています。在来のサルと外来のサルを区別する際に人々が指摘するのは、この完全なる恐怖心の欠如と村の「乗っ取り」ともいえる行為でした。
「家畜-野生動物」としての野生化したブタ
宮本:
何重もの意味も込められているという点で、逃走した雌ブタの話は非常に読みごたえがありました。私が調査しているブータンでも、昔はブタの飼育が一般的で、ご存じの通りトイレの下でブタを飼うこともありました。ただ、宗教に関係しているとはいえ、ブタの飼育をやめた理由は両者でかなり異なるように思います。
この章では、実験農場の家畜化されたブタが脱走して野生化していくストーリーをベースにしながら、インドで法的には否定され禁止されているカーストによる差別や抑圧について、その重層的な構造が巧みに描かれていますね。
ゴヴィンドラジャン:
カーストに基づく抑圧は、インド全土と同様にこの地域でも存在し、今でも力を持っています。私は、蔓延するカーストの暴力と、この抑圧や暴力に対する最下層のダリット(不可触民)の抵抗や拒絶が、日常的な人間関係の中でどのように行われていたのかを理解することに興味を持っていました。
ブタはこの疑問に対し、重要な取っ掛かりを提供してくれました。ブタと、ブタを飼育するダリットカーストを「不浄」とみなすことは、B.R. アンベードカル博士が言うところのカーストの「段階的不平等※7」を維持するために、支配的なカーストの人々が日常的にカーストの暴力を行使するための方法となったのです。フランツ・ファノンが力強く指摘しているように、抑圧者の言説は根本的に動物学的なものであり、抑圧された者に動物性を与えることで、彼らに対する植民地的な暴力を正当化する方法として使われているのです。私は、ベネディクト・ボワスロンが「連結性※8」と呼ぶような、カーストと動物化の交点についてはやるべき重要な研究が残っており、人間と人間以外の動物との関係性を研究することにより、こうした関係性への洞察が得られるだろうと考えています。
しかし、この交点をどう捉え、どう表現するかということにも気を配らなければなりません。ザッキヤ・イマン・ジャクソンが指摘するように、「人間」を超越して、人間-動物間の区別を元に戻そうとする急激な動きは、人間が決して不変の分類ではなかったという事実を見落とすだけでなく、解放的なヒューマニズムを求める様々な被抑圧集団の葛藤を根底から覆すこととなります※9。
私にとって特に重要だったのは、支配的なカーストによるカースト暴力の全容を明かさず、その暴力が向けられた人々にとって異論のない形で示されることにありました。私は、ダリットの村人たちがどのようにして支配的なカーストによるこうした抑圧に立ち向かい、それを覆してきたかを、脱走した雌ブタの話を交えながら強調したかったのです。
本書でも触れていますが、ダリットの村人数名がよく言っていたのは、森にいるイノシシはおそらく脱走した雌ブタの子孫であり、本当は野生のイノシシではないということでした。このことは、豚肉の消費を不浄であり「最下層カースト」の地位を示すものだと非難する支配カーストが、せいぜい暴力的な偽善者でしかないことを意味しているのだと、彼らは言うのです。私は、これらのカースト支配に対する批判は、野生化したブタの歴史、特にその話で示されているような、野生の流動的な性質に基づいていることを主張します。私にとって、これらの論争は、カーストと動物性の関係が偶発的で予期せぬものであり、民族学的に理解されなければならないことを思い起こさせてくれます。
§
宮本:
非常に刺激的な議論ですね。ザッキヤ・イマン・ジャクソンが示す論点は、検討に値するものだと思います。階層や差別と動物性の関係を論じるためには、前提として理解しておくべき論点が非常にたくさんあるように思います。
この章の中で、もしかしたら重要な点ではないかもしれませんが、脱走した雌ブタの牙の大きさについて人々が話している箇所が気になりました。村人たちは、脱走した雌ブタの子孫はより大きい牙を持っていると語っていたそうですが、その話をすることで、彼らはいったい何を示唆したかったのでしょうか。動物を危険な存在に変えるという意味で、遺伝子操作を恐れているということでしょうか。論点として私はそこは興味深いと思ったのですが、結局その話題は全体的な議論に再び包摂されることはありませんでした。この一連の会話を通して何を伝えたかったのか、もし可能であれば教えていただけますか。
ゴヴィンドラジャン:
この章では、ブタの凶暴性についての様々な証言を、互いの会話の中に入れてみました。多くの野生生物学者は、ブタが「野性化」した場合、迅速な形態学的な変化が起こる可能性を示唆しています。豚の形態は、数世代という非常に短い期間で変化することができます。私にとって、これらの知見は、人々が私に話してくれた、脱走した雌ブタの歴史や、その子孫が簡単に「ジュングリ(jungli)」つまり野生化した話と非常に一致していました。
私が本書を執筆する際、ある男性は、イノシシを「パルトゥ・ジュングリ(paltu-jungli)」つまり「家畜-野生動物」と呼びましたが、それはブタが両者のカテゴリー間をいかに簡単、迅速に移動することができるかを言い表しています。私にとっては、野性の偶発性について、人々が主張の根拠として挙げた証拠に重点を置くことが大切なことでした。私はこれらを、故意に証拠と呼んでいます。彼らは、非常に長い間動物と共に暮らし、動物に関する観察的・経験的知識を豊富に蓄えている人々です。私は、このような異なる種類の状況化された知識のいずれかを使って他方の真実性を確認すると言うよりも、これらの知識を積み重ねることに関心を抱いていました。言い換えれば、私はクマオニの人々が私に話してくれたことを、「科学的証拠」によって裏付けしたり証明しなければならない、ある種の「ローカル・ナレッジ(土着の知)」として主張したくはなかったのです。私は、彼ら自身の証拠を元にして考え、野生生物学者の状況化された知識と合わせることで、会話にまとめたいと思ったのです。
クマとのセックスを語る女性たち
宮本:
ご著書の最後の章は、クマについての話でしたね。この章は、インスピレーションを与えてくれる内容でした。ここで登場するクマは、この本に書いてあった他の動物とは全く異なる姿をしているように思えます。クマと女性の物語を通して、男女の(不)平等性や再生産能力、家庭内暴力など、女性を取り巻く問題の存在を示唆していますが、この本の最後の章としてこの物語を挿入した動機はどのようなものだったのでしょうか。そうしたジェンダー不平等に対する意識が、女性たちの全ての会話の底流に常に存在していることを示唆したかったのでしょうか。そして、彼女たちが抱くひそかな不満や希望を抽出して表現するには、このクマの話が最適だったということでしょうか。そんなことを聞いてみたいと思います。
ゴヴィンドラジャン:
興味深い質問ですね。私は、ヤギやサル、さらにはイノシシやヒョウと比べて、クマがこの風景にいかに「存在しない」かについて悩んでいました。しかし、後になって気がついたのですが、クマは物質的・象徴的風景の中に、私が考慮に入れるべき重要な仕方で、存在していたのです。同僚のジュノ・パレーニャス※10の研究は、この点を考える上で非常に参考になりました。特に彼女の「物質的痕跡」という考え方は、存在していないように見えるものの中で存在を示すものです。トウモロコシ畑が平らになっていて夜間に食べた跡があったり、クマに襲われた女性の顔の傷跡があったりと、いたるところにクマの「物理的痕跡」は存在していました。
女性たちがクマについて極めて性的な話をすることで、多くの根源的な禁止事項や二項対立が露わになってしまったのではないかと考えています。例えば、人間とクマが恋人同士だったという考えです。親密性の持つ本来の寛容性を強調することで、女性の性的快楽に対するカースト家父長的な支配に立ち向かっていたのです。ある女性は、夫が疲れすぎてセックスできないと言った時に、夫を叱責したという話を私たちにしていました。彼女は夫に、クマならセックスしても疲れないだろうと言いました。このクマの話を通して自身の性欲を主張する姿には、本当に心を打たれました。確かに、女性がクマとのセックスの話をすることで得られる快感については、私も考え抜いてみたいものでした。単に、この話を戦略的に使って家父長制へ挑戦していただけではありません。そこにはクマとのセックスがどのようなものであるのか想像することへの、純粋な好奇心と興奮がありました。
私にとっての課題は、これが、いかに親密で具体化された関係であるかを考えることでした。それは、人間と動物、血族と他人といった分類がどのように理解され、経験されるかを形作る上で、女性が飼育しているヤギとの関係性とは全く異なる一方で、それに劣らず意味のあることでした。私にとってこの章は、人間以外の動物との多様な関係性、そして前述のように、それらの関係性の状況化された明示に対して民族学的な注意を払うことの重要性について述べることにありました。
§
宮本:
なるほど、確かにこの章は他の一連の章と表面的には全く異なるように思えますが、クマの話は、人々と動物との関係性に対する我々の想像力を刺激しながら、この本のすべての章を繋げる役割を果たしているようにもみえます。そして、おっしゃるように、人間が多様な他の生物種との境界線を越えることで快楽を経験すると考えることは、他章を含む本の全体を包括的に理解するヒントをくれるように思います。
マルチスピーシーズ民族誌の展望
宮本:
本書を含むあなたの研究が多様な研究領域を横断している点は承知していますが、インタビューの最後に、特にマルチスピーシーズ民族誌という分野の将来的な展望について、ご意見を伺ってもよろしいでしょうか。
ゴヴィンドラジャン:
私がマルチスピーシーズ民族誌の分野でとても刺激的だと思うのは、その知的な幅広さであり、それが実際に広い範囲に渡って関心を持ち、取り組んでいるという点です。
私が思う、マルチスピーシーズ民族誌として分類される研究の多様性をゆるやかに結びつけているものは、ステファン・ヘルムライヒとエベン・カークセイが、人間以外の動物や物質の持つ特有の歴史や伝記と表現したものを辿ることへの関心です。それ以上に、この分野のすべての仕事で力を発揮しているのは、寛容性であり、創造的な探求と思考への献身だと考えます。自分自身の研究において、私はこうしたことを、批判的な擬人観であり、他の人の立場にある自己を想像しようとする意思であり、すべてのリスクや消去にもかかわらず自己を超越した運動を生ぜしめる姿勢であり、より公正でより自己陶酔的ではない未来の可能性を開くような行為、として捉えてきました。
私は、マルチスピーシーズ民族誌を、多様で異なる問題に洞察を与えてくれる分析レンズのようなものだと捉えており、それは必ずしも人間と人間以外との関係性が中心であるとは限りません。エミリー・イエーツ・ドーア※11、ナタリー・ポーター※12、アレックス・ネイディング※13のように、健康や病気を理解するための方法としてマルチスピーシーズ民族誌を研究している人たちもいます。アレックス・ブランシェット※14、ケイティ・ガレスピー、ソフィー・ツァオ※15のように、屠殺場や酪農場、ヤシ農園など、産業資本の現場においてマルチスピーシーズ民族誌を研究している人たちもいます。ジュノ・パレーニャス、ハーラン・ウィーバー※16、アンヌ・ジャレ※17、ベネディクト・ボワスロン、ザッキヤ・イマン・ジャクソン、マリア=エレナ・ガルシア※18のように、人種、ジェンダー、帝国主義、宗教に関する問題を不可欠と考え、中心的な課題とした研究もあります。
私が考える限りにおいて、マルチスピーシーズ民族誌は、より広い学問分野との対話を模索し、人間以外と人間との関係性がどのように形成されているのかを考察し、数多くのその他の構造的要素のなかで、人種、人種差別、ジェンダー、セクシュアリティ、医療や資本の言説や実践を形づくる際に、最も力を発揮するでしょう。ある意味、この分野は本当に爆発的に発展しており、その包括的な理論的枠組みを特定のアプローチや学派に絞るのが難しいところまで来ていると思います。それは素晴らしいことです。
私の考えでは、マルチスピーシーズ民族誌は、さまざまな存在の異なる作用や働きによってさまざまな社会がどのように構成されているかについて、多様な方法で探求するときに、最盛期を迎えると思います。そして私は、この流動性と寛大性が、今後もこの分野の特徴であり続けることを期待しています。
§
宮本:
マルチスピーシーズ民族誌に関して、とても豊かな示唆をいただき、ありがとうございました。