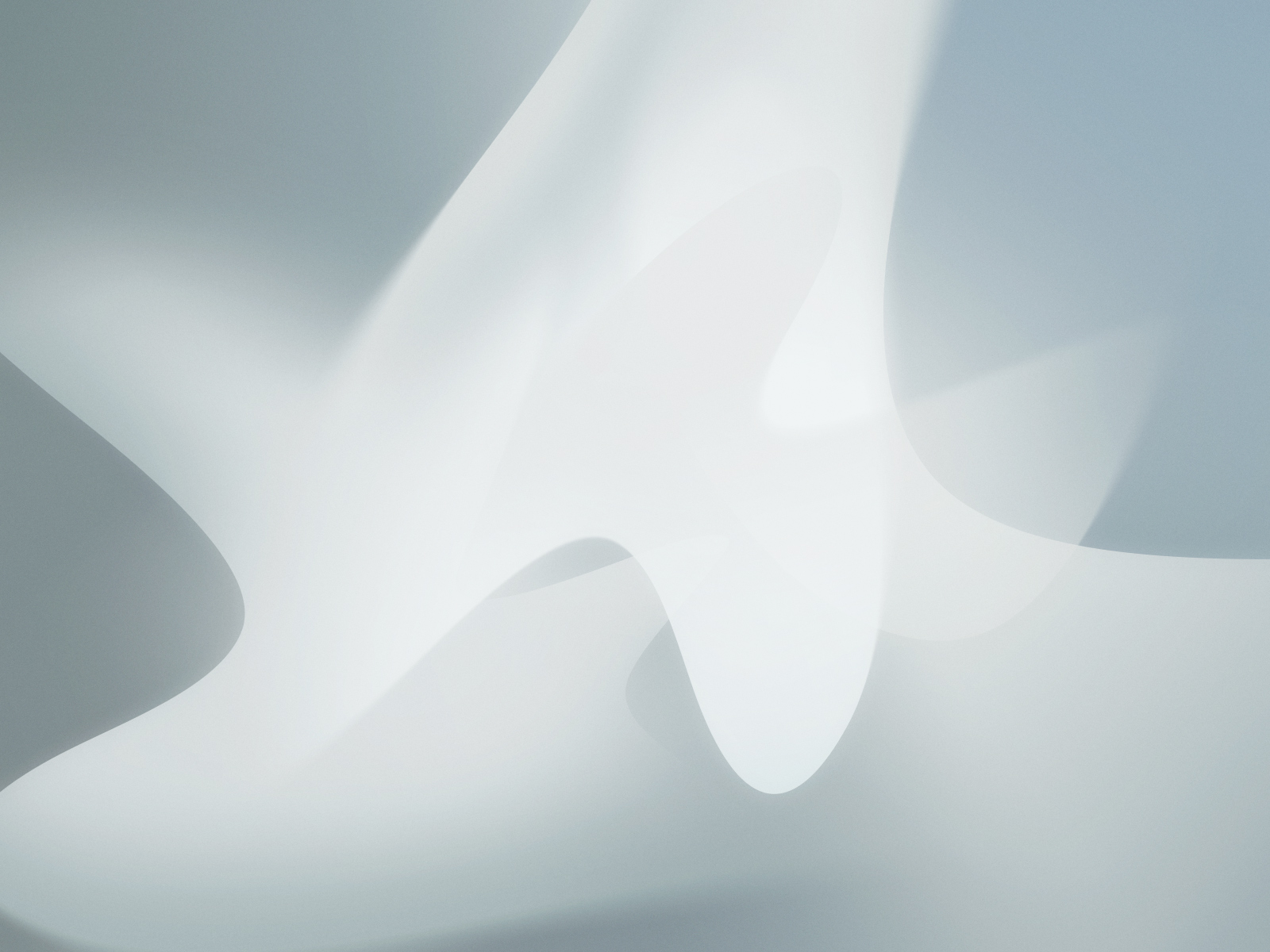感情は、単なる何らかの内面的な状態にすぎないのではなく、外部の状況・もの・人 ——「対象」—— との関係を、本質的な構成要素として含みこんでいる。……「感情(passio)」を抱くことは、「受動(passio)」的な仕方で自己の境界が何らかの「対象」の影響によって揺るがされ、その「対象」が自己の構成要素にまでなるという事態なのだ。山本芳久『トマス・アクィナス 肯定の哲学』※1
私は前回、1989年に図書館情報学者のマーシャ・ベイツが提示したベリーピッキングモデルを通じて、オフラインからオンラインへの情報環境の広がりを背景に人間が行なってきた「探しもの」のあり方について考えてみました。ベイツがそのモデルを発表した翌年の1990年末には、CERN(欧州原子核研究機構)の研究者ティム・バーナーズ=リーによって、世界初のWebのシステムが誕生しています。それ以来、Webが爆発的な成長を続けた後の2002年、リスボンで開催された情報探索行動をテーマとするカンファレンスで、ベイツが基調講演を行なうという機会がありました。彼女はそこで、情報の探索を統合的な体験として捉え、それを社会や文化との関わりから見るだけでなく、生物学や人類学の観点からも理解するよう呼びかけました。
この記事では、ベイツがその講演内容をまとめて2003年に発表した論文を読み解きながら、私たち人間が情報とどのように関わりながら生きているのかを、考えていきたいと思います。
情報探索を知るための「理解のレイヤー」
ベイツが生物学的/人類学的アプローチの重要性を訴えたのは、当時の情報研究が、社会学に偏っていることを憂慮していたからです。インターネットの普及やオンライン検索技術の進歩、コンピュータを道具として扱うスキルの向上など、社会が大きく変わりつつあった時代の流れに乗じて、情報行動についての研究は、個々の人間よりも社会や文化全体に注目するものが目立っていたのです。
またベイツは、社会学や人文学とは別のレベルでの、自然科学的な取り組みが軽んじられていることを憂慮していました。この講演で彼女がまず試みたのは、科学的アプローチへの偏見を取り除くことでした。実験や観察に基づく分析を重んじる科学的な還元主義を、精神に関わるものごとを単なる物理現象に貶めることだと誤解してはいけない。また、自然科学に携わる研究者が、科学を盲信していると決めつける必要もない。そして、生物学や人類学といった科学の成果を情報研究から排除している限り、十分な理解は得られないと語ったのです。
そしてベイツは、図1の「理解のレイヤー」すべてにおいて、情報探索を理解することが望ましいと述べました。
| 精神的(宗教、哲学、意味の探求) |
| 美的(芸術、文学) |
| 認知的 / 動物的 / 情動的(心理学) |
| 社会的 / 歴史的(社会学) |
| 人類学的(形質人類学、文化人類学) |
| 生物学的(遺伝学、動物行動学) |
| 化学的 / 物理学的 / 地質学的 / 天文学的 |
[図1] 情報探索の理解のレイヤー
ベイツはこの図で、それぞれの学問領域から得られる知見を統合すれば、もっとも深い理解が得られることを訴えました。レイヤーの間に優劣はなく、どれも等しく重要であるとみなすのです。また、一般的に人類学は社会科学に分類されることが多いのですが、この論文でベイツは、人類学を自然科学に属するものとして議論を進めていきます。人間も自然の一部であると考えれば、それを研究対象とする人類学を自然科学とみなすのも、間違いではないはずです。ともかくここで重要なのは、情報探索という行動の重層性を示し、それを知ることで理解を深めようという目標が掲げられたことでした。
ただしベイツは、実際の人間の性質や行動が必ずしも明確に切り分けられるわけではなく、隣りのレイヤーに浸透したり、さらに離れたレイヤーに達することもあることを説明しました。たとえば、心理言語学の通説では、人間には先天的な言語能力があり、それが後天的な言語の発達に一定の制約を与えると言われています。しかし現実には、そのような制約を受けながらも、言語はきわめて多彩なバリエーションを見せます。私たちが用いる言語の特徴や文法、語彙などは、どれも一生を通じて身につけていくものであり、文化によっても大きな違いが生まれます。したがって、生物学か社会学のいずれかで言語能力のすべてを説明できるわけではなく、その両方に関わっていることを知る必要があるのです。ベイツはこの例を踏まえて、人間の行動にはそのような面がたくさんあることを述べました。そして、社会学から生物学/人類学までのレイヤーを貫く観点から、さまざまな情報探索行動を統合するモデルを示したのです。
情報探索の4つのモード
ベイツは、私たちが能動的に探して入手する情報だけではなく、生まれてから死ぬまでの間に出会うあらゆる情報が探索の対象となると考え、それを前提としたモデルを生み出しました。他の哺乳類と同じく、人間は大きくて汎用的な脳を持ち、環境や社会状況の変化に幅広く適応しながら、一生のうちにきわめて多くのことを学習できる生物です。先ほどの言語能力の例のように、一定の精神構造が頭の中にあり、さまざまなことを学習するのに役立っています。ただし、細々とした具体的な情報は、各自の経験を通じて手に入れます。家族や親しい仲間から特に多くのことを学ぶのも、他の哺乳類との共通点です。そのような人々の支援をどれだけ得られるかは、自分の生死に関わるので、情緒的に濃密な関係を結ぶことになります。このように、人間は他の人々との交流から多くの学びと経験を得る、とても社会的な種なのです。
このような考察に基づいて、ベイツは「情報探索の4つのモード」というモデルを示しました。
| 能動的 Active |
受動的 Passive |
|
|---|---|---|
| 有向的 Directed |
検索 Searching |
モニタリング Monitoring |
| 無向的 Undirected |
ブラウジング Browsing |
意識化 Being Aware |
[図2] 情報探索の4つのモード
「有向的/無向的」とは、多少なりとも目的を持って情報を探しているか、ほぼランダムに情報を収集しているかの違いで、「能動的/受動的」とは、意志を持って自発的に情報を探しているか、探している自覚もなく情報に接しているかという違いです。これら4つのうち、実はもっとも影響力のある「意識化」を出発点として、ベイツはそれぞれのモードを解説しました。
意識化
先に述べたように、私たちが知ることや学ぶことの大半は、受動的かつ無向的に何かを意識するという、意識化のプロセスを通じてもたらされます。
この意識化は、生きるための知恵を身につけつつある子どもたちに、とりわけ大きな影響を及ぼします。子どもは、そもそも自分にどんな情報が必要なのかわからず、自分の情報ニーズをうまく言語化できないので、能動的に、または有向的に情報を探すのは困難です。そこで自然と子どもたちは、身の回りの環境から与えられる情報にただ身を浸し、とりわけ家族のように縁の深い人々の影響を受けながら、さまざまな意識化を通じて成長していくのです。
そしてこの意識化は、大人になっても多大な影響を及ぼし続けます。ベイツによれば、私たちの知識のほぼ80パーセントは、社会的状況と物理的環境がもたらす情報を意識化することで得ていることになります。
モニタリング
有向的で受動的なモニタリングが行なわれている間は、興味を引くものや疑問への答えが見当たらないかと、アンテナを張っている状態になります。能動的に情報を探し出す必要に迫られているわけではなく、通りすがりに何か見つかればいいといった感覚です。何か疑問があっても、わざわざ答えを探そうとしていない場合に、その答えらしきものに出くわせばそれと気づくのは、モニタリングを行なっているからです。
意図的かどうかは別にして、私たちは必要な情報を必要な時に取り出せるように、物理的/社会的な環境を整えることがよくあります。買い物リストを作ったり、料理がはかどるように台所用品を配置したり、仕事場でよく使う道具を整頓したりして、次にどこで何をすればいいのかを、いつでも思い出せるようにしています。そうすれば、能動的に情報を探す手間が省けることが多くなるからです。何か特定の行為や手順を経験すればするほど、その次の行動のきっかけが意識化されるのを待つだけではなく、自主的にモニタリングをしようとする傾向があるとされています。
また、学問領域や専門分野、趣味や職業を通じたコミュニティのような社会的インフラは、モニタリングの強い味方となります。自分に見合った境遇の中では、社交的に、あるいはただ物理的に誰かと接するようにするだけで、大量の有益な情報に出会える見込みが高まります。これはまったくの偶然によるものではなく、共通の目標やニーズを持ち合わせている人びとが近接していることから生じることと言えます。
ブラウジング
先ほどの図2からわかるように、無向的で能動的なブラウジングは、有向的で受動的なモニタリングの裏返しともいえるモードです。ブラウジングとは、特別な情報ニーズや興味関心はなくても、目新しい情報がありそうな場所を能動的に探っている状態です。だから、好奇心はブラウジングの原動力になります。ベイツは、能動的に好奇心を発揮することが、新たな食物や仲間の発見に至りもすれば、自分の身を思わぬ危険に晒しもするという、生物の進化におけるジレンマの元になってきたことにも触れていました。しかし、ブラウジングの価値は、いわば受動的に好奇心が満たされることの喜びにあるのだと思います。目的志向や成果主義から離れて、何かに出会うこと自体が楽しみとなるかどうかが重要になるということです。
ベイツは、実際にブラウジングをしているときに生じる身体活動をもっと詳しく知る価値があると述べ、あまり注目されていなかったバーバラ・クワスニークの研究を紹介しています。彼女は、ブラウジング中の身体活動を詳しく分析し、目が水平方向へのスキャンを繰り返すというより、気の向くままにいろんな箇所をチラチラ見ていることを見出しました。そしてブラウジングが、方向確認や現在地のマーキング、比較、異常の解決といったさまざまなアクションから成る複雑な活動であり、多くの意味を秘めていると考えたのです。
そして、ベイツやクワスニークを含む一部の研究者たちは、そのように多くの意味に満ちた複雑さが、他にも多くの行動に見出せることに気づきました。情報行動においてはブラウジングを引き起こす衝動が、「サンプリングと選別(sampling and selecting)」と呼ばれる一般的な行動として、他にもさまざまな形で現われると考えたのです。パーティーでの会話やデート、買い物、つまみ食い、観光、道順探し、テレビ番組のザッピング、ネットサーフィンなどは、どれも「サンプリングと選別」の実例です。たくさんの可能性を前にしたとき、まず私たちはそこから目ぼしいものを抽出するサンプリングを行ない、その結果をさらに選別しているのです。先ほどの実例からもわかるように、これは生物の交配や採餌といった行動の進化形とも言えます。
進化生物学では、ある目的に合わせて発達してきた機能が、環境の変化によって別の目的に用いられることはよくあるパターンとされ、「外適応(exaptation)」※2と呼ばれています。ベイツがこの論文で紹介した「情報採餌(information foraging)」※3という行動は、サンプリングと選別を好む人間の性向が、その対象を食物から情報に切り替えた結果とみなすことができます。生物学的な採餌行動が、ブラウジングなどの情報探索行動に転用されて「外適応」したとも言えるでしょう。
検索
有向的な検索は、疑問への答えを求めたり、具体的な質問や話題への理解を深めようとして、能動的に行なわれます。知識のほぼ80パーセントが意識化によって身についているのに対して、検索によるものはわずか1パーセント程度で、残りがブラウジングとモニタリングによるものだろうと、ベイツは見積もっていました。
情報を探すとき、人間が最小努力の原則に従いがちだということは、すでに数多くの研究で実証されていました。手軽に入手して利用できる情報ならば、その信頼性の乏しさには目をつぶってしまうほど、人間は手抜きをしたがるものなのです。学生が図書館まで出向いて学術誌を探さずにネットの情報で済まそうとすること、医師が医学文献を調べるより製薬会社のセールスマンから新薬の情報を聞き出そうとすることなどは、それをよく表しています。
望ましくない方法とわかっていても、つい人間がそれを頼りにしてしまうことは、昔から研究者たちを悩ませてきたそうですが、その理由はこれまでの話から自ずと見えてきます。人類は長い歴史を通じて、生きるために必要な情報の大半を、わざわざ検索することなく獲得してきたからです。かつての狩猟採集者も、家族的集団の中で育てられ、仲間との交流や環境と関わり合いながら、受動的な意識化とモニタリングを通じて知識を得るのが普通でした。そして集団が移住したときには、新たな環境の中で無向的にブラウジングをしながら、生活に必要なものを見つけていたのです。人類史を見渡すと、何か必要に迫られた場合は別として、能動的かつ有向的な検索をするというのは、めったにない事態なのです。普段の何気ない行動を通じてあまりに多くの情報を得ているので、能動的に努力して探すよりも、受動的な習慣に従ううちに都合よく情報が手に入ることを期待している、とも言えます。
現代の私たちの生活には、検索をさらに厄介にしているもう一つの要因があります。19世紀初頭から、何らかのメディアに記録される情報の量が爆発的に増加したため、それらにアクセスするには、複雑で高度な検索システムに頼らざるを得なくなったことです。検索以外の手段で情報を得ることに慣れていた人びとが、自分から検索をしなければいけなくなったのです。しかも、検索システムの仕組みを理解して使い方を覚えるという、二重の手間が生じることになります。その大変さを思うと、誰もがなるべく手間をかけずに情報を探したいと願うのは、当然と言えるでしょう。わざわざ検索のスキルを身につけようと決意するのは、緊急性や関心がきわめて高い場合だけなのです。
情報の狩猟と農耕
情報採餌理論の先駆けとなった、人類学者パメラ・サンドストロムの論文は、研究者たちが自給自足で食料をまかなうように情報を集めていることに注目し、人間が情報を探す労力を減らそうとする性向をより詳しく解き明かしました。
彼女が気づいたのは、通常の読書やブラウジング、新たな情報源への遠征といった、単独ですることが多い情報探索行動から得られる資料は、各自の情報環境の中で周辺的なものになりがちだということでした。それに対して、中心的な資料は、同僚との交流や論文の査読といった社会的なチャネルを通じて手に入ったり、各自の個人的コレクションの中にあったりすることが多いのです。これは、かつての狩猟採集時代に、まず家族や仲間のいる社会的境遇から、次いで自分の収集物からものごとを学んでいたのと、同じ構造を示しています。研究者たちもめったなことでは、見ず知らずの領域まで情報を探しには行かないものなのです。
ただし、狩猟採集者は、現在と同じ意味で個人のコレクションを所有していたわけではありません。放浪を繰り返す遊牧生活では、持ち運べる収集物の量に限りがあるからです。本格的なコレクションが始まったのは、定住生活するようになってから、つまり、農耕を基本とする生活を始めてからのことです。現代の研究者たちは、農耕民族が畑を手入れしていたのと同じように、個人のコレクションとして集めた資料をデスク上やファイリングシステムで整理整頓し、後で使いやすいように整えています。一部の研究者が「エンリッチメント(enrichment)」※4と呼んでいた、このような情報環境の体系化は、サンドストロムが調査対象とした研究者たちだけでなく、他の職業に携わる人々や、さらには仕事を離れた趣味の世界でも行なわれているものです。
ベリーピッキングからモードの統合へ
ベイツは、自身が1989年の論文で注目した「ベリーピッキング」※5という行動も、能動的に行なわれる「サンプリングと選別」の一例だとみなしました。ベリーピッキングは、同じく能動的な行動であるブラウジングとよく似たものになる可能性がありますが、無向的なブラウジングに比べれば、ベリーピッキングのほうがやや有向的です。
また、より一般的な2種類のモードとして、能動的な検索やブラウジングは「サンプリングと選別(sampling and selecting)」に、受動的なモニタリングや意識化は「環境からの吸収(absorption from the environment)」に区分できます。一方、有向的か無向的かの違いは、自分の情報ニーズに対する認識の違いにも相当しています。つまり、「知る必要があるとわかっている情報」を見つけるのが検索とモニタリングであり、「知る必要があるとは思っていなかった情報」に出会うのがブラウジングと意識化ということになります。
ここまで見てきたことをまとめると、大抵は受動的な「環境からの吸収」によって、時には能動的な「サンプリングと選別」によって情報を得るというのが、遠い昔から受け継がれている人間の性向だということになります。そしてベイツは、時代の流れと共に情報環境がどれだけ複雑化しても、その性向は基本的に変わらないと考えていたようです。
産業社会における情報アクセス
現代的な産業社会が生まれ、印刷や配信の手法がさらにパワフルになり、かつてないほど大量の資料が図書館で収集されるようになるにつれて、効率よく情報にアクセスしたいというニーズは高まる一方でした。ベイツが論文を書いた当時には、さまざまな情報処理のシステムの設計や開発に多大な労力が注ぎ込まれていたものの、それらは宝の持ち腐れとなっていました。画期的な新しいシステムの利用を敬遠するどころか、その存在に目もくれない人も多く、かなりの検索スキルを持っているはずの研究者たちさえ、例外ではなかったそうです。
人間の性向を生物学的/人類学的に捉えれば、情報探索がほぼ受動的な行動で占められていることは、すでに触れてきた通りです。逆の言い方をすれば、意識化を主とする受動的な探索は、誰かに教えられるまでもなく自然に行なわれるほど、人間にとって大昔から身に染みついた手段だということになります。それに反して、能動的に使うことが求められる現在の検索システムには、まだ数百年ほどの歴史しかありません。紙に印刷された本や論文を読むには特別な準備は要りませんが、デジタル化された文献にアクセスするには、先に述べたように、検索システムを使いこなすための学習が必要になります。でも、普段の生活では、大した自覚もなくほぼ受動的に情報探索を行なっているので、能動的に検索システムを利用するための学習の必要性には、なかなか気づかないのです。
こうして、情報探索に関する研究がたびたび同じような結論に至る理由は、私たちの行動を生物学的/人類学的な観点から捉えればある程度説明がつくと、ベイツは考えました。誰もが最小の努力で済ませようとする理由は、人間が昔からいつもそうすることによって、ごく最近までそれなりに納得のいく成果をあげてきたからです。
意識の問題とその時代
もしかすると、意識化が探索という活動と呼べるのか、疑問に思われる方もいるかもしれません。確かに意識化は、目に見える形で行なわれる身体的な活動(action)というよりも、心のなかで生じる反応(reaction)に近いように思えます。しかし、私たちの身体と心は、ハードウェアとソフトウェアのように切り離せるわけではありません。それらが別々に動いていると考えることに無理があると気づけば、意識化も活動の一つとして捉えることができます。ベイツもそう考えたからこそ、森の中でのベリー摘みのように、情報探索活動が身体と心の全体に関わっていることに目を向けたのではないでしょうか。そして、意識化という活動を、とりわけ重要なモードとして位置づけたように思います。
彼女が研究者として活躍していた20世紀末期は、長らく哲学で扱われてきた心と身体の関係が、科学の研究テーマとして盛んに取り上げられるようになった時代でした。「物理的なモノではない心(精神)が、モノとして動く身体(物質)とどのように相互作用しているのか」という、哲学者たちが古くから取り組んできた難問に、進化生物学や脳科学の研究者たちも次々とアプローチするようになり、意識のしくみが科学的に探られていたのです。
彼らは、医療技術のめざましい進歩がもたらす新たな実証データによって、昔からマクロなレベルでの心的作用だと考えられてきた意識というものが、脳内の神経活動というミクロなレベルの物理的作用に還元できることを証明しようとしました。中でも優れた科学者たちは、さまざまなレベルに渡る理論が長期間に渡る実証データの蓄積によって影響しあい、新たな接点が生まれていくという「共進化」こそが、本来の還元主義の価値だということを理解していました。すべてを科学的に説明づけることが目的ではなく、科学の進歩が哲学や心理学といった他の学問の進歩を促し、それがまた科学を前進させることに、意義を見出したのです。そのような流れを受けて、哲学者たちも、科学的な洞察を踏まえた上で意識の問題を見直すようになった時代でした。
ベイツが「理解のレイヤー」の図を示して、あらゆる学問領域に通じる重層的な理解の重要性を訴えたのも、そのような時代精神の反映だったのではないでしょうか。
アンビエントな情報と「内的環境」
私は「能動的/受動的」「有向的/無向的」という区別が、実はあいまいなものだと考えています。私たちは、情報を探そうとするときに、まずどれか1つのモードを選んでから活動を始めるわけではないのです。4つのモードは、実際の探索の結果として見出された類型にすぎません。とにかく森の中に入ってみて、あとは周りの環境と、自分の感覚や過去の経験を手がかりに、いろいろなやり方でベリーを摘み取っていければいいのです。
そこで忘れてはならないのは、ベイツが生物学的/人類学的アプローチによって伝えようとした、意識化の役割の大きさです。すでに見てきたように、オフラインでもオンラインでも、私たちは自分の五感を通じてさまざまな情報を意識することで、生きるために必要な知識を自然と身につけてきたのです。
意識化がどのように行なわれているかを知ると、情報というものがアンビエントな存在として、私たちを取り巻いていることに気づきます。ただそこにあるだけで、それ自体に一定の意味が内在しているわけではありません。その情報を意識する人との関係によって、そこに初めて意味が生まれるのです。ベリーを探そうと森に足を踏み入れた人を取り巻く環境とは、あらかじめそこにあった「外的環境」でありながら、その時その場で生成される「内的環境」と呼ぶべきものでもあるでしょう。「内的環境」とは、意識を通じて私たちの身体と結びつき、動的なひとまとまりのシステムとして立ち現れる環境です。これは、他の誰かに見せたり共有したりできるものではなく、その人自身にしか経験できないものです。
私たちは、行動には目的がないよりはある方がいいし、受動的であるよりは能動的であることが望ましいと考えたくなるようです。しかし生物学的に見れば、意識は本来無向的なものであり※6、きわめて受動的な役割を果たしていることを、ベイツは明らかにしました。むしろその無向性と受動性こそが意識の本質であり、情報との出会いによって自分だけの「内的環境」を生み出すところに、意識の真価があるということ。それが、ベイツが私たちに伝えてくれた、重要なメッセージではないでしょうか。