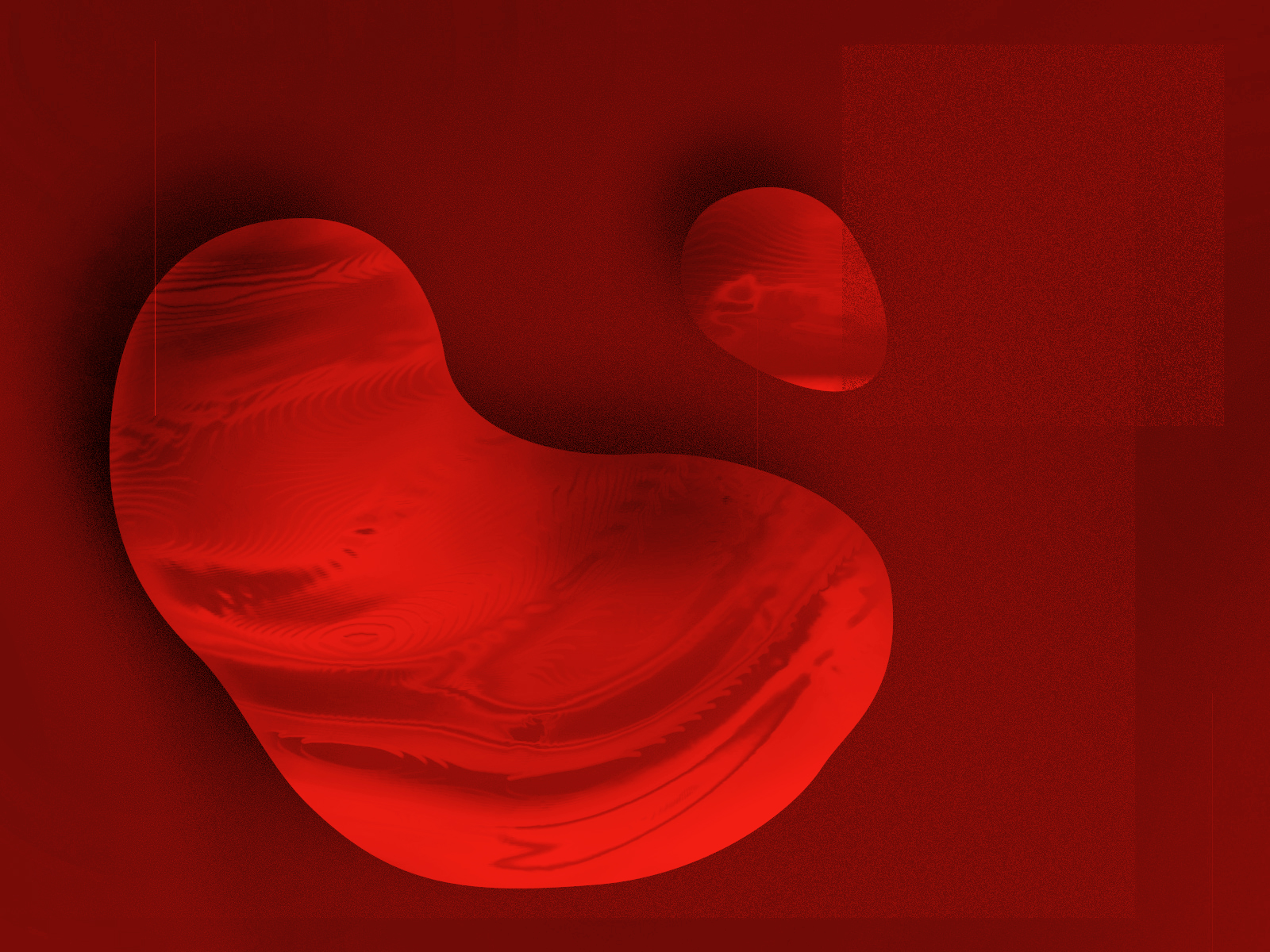個人の時代に代わるもの、それは、しばしば素朴に信じられがちなように、集団の時代なのではない。そうではなく、ある非人称の時代。なぜなら、個人の時代が終わったとすれば、問題は、主体=客体という二元論と、そして認識 → 伝達(現実の主体的な再現)という二重過程との上に成立してきた近代の古典的な認識論そのものの崩壊にほかならないであろうからだ。そして、このコギトの消滅のうちにあらわれるもの、それはそれ自体の存在における言語であり、イマージュであり、コミュニケーションでなくて、なんだろうか。宮川淳『鏡・空間・イマージュ』
[0]はじめに
このエッセイは、「制作」という概念を制作することを目標としている。「制作」とは捉えどころのない、奇妙な概念で、「制作」を介して、常識とされている知覚や行為の様態が変化することを伴う。だから、これまで人々は、芸術家の発言を過度に神秘化したり、あるいは、過度に単純化したりしてきた。彼らの発言は、真剣に受け取られることがなかった。
僕はときどき、宮川淳が、アルベルト・ジャコメッティの「似ている、見えるとおりに」という発言に導かれる仕方で、イマージュの存在論に迫る姿を思い浮かべる。彼を駆動しているのは、僕と同様の問いであるように思えた。つまり、「見たまま書いている、描いている。彼らはそう言う。にもかかわらず、なぜそのような表現になるのか」、これである。見たまま、書くこと。この〈見たまま〉が意味することには、「制作」を考える上で、重要な鍵が隠されているように思えた。まずは、宮川淳の『鏡・空間・イマージュ』を検討するところから議論を始めることにしよう。
[1]描くこと、書くことを通じて
ポール・エリュアールは書く。
そして、ぼくはぼくの鏡のなかに降りる
死者がその開かれた墓に降りてゆくようにコクトオのオルフェもまた鏡をとおりぬけて冥府に降りてゆく。そして、なによりもわれわれは鏡のなかに落ちることをおそれるのだ宮川淳『鏡・空間・イマージュ』
宮川は「鏡について」というテキストを上記の一文から始める。僕たちはなぜ〈鏡のなか〉へと降りていくことを恐れるのだろう。
まずは宮川がここで鏡という言葉で表現していること、そして彼が、〈鏡のなか〉(そして、鏡の表面)という言葉を用いていることについて考えたい。宮川は、鏡とは何かということを考える上で距離という視点から思考しはじめる。「距離が見ることの可能性であるならば、〈見ないことの不可能性〉(モーリス・ブランショ)、それが鏡であり、その魅惑なのだ。なぜなら魅惑とはまさしくわれわれから見ることをやめる可能性を奪い去るものにほかならないのだから」と彼は言う。距離は、僕が対象を見るとき不可避に存在するように思われる。そして、距離は見ることの可能性であり、見ないことも可能にするものである。僕が焦点を合わせた対象とそれを可能にする距離という構造は、知覚の基礎的構造として一般化できるように思う。
しかし、そうではない、と宮川は言う。彼は、アルベルト・ジャコメッティの絵画とその絵画へのサルトルの批評に対する反論を元に、「絵画は、イマージュの危険な魅惑、見ないことの不可能性を見ることの可能性に馴化することによって、はじめて絵画として制度化されてきたのではないか(その典型的な例は透視法だろう。透視法が決して視覚の真実ではなかったことはすでに明らかだが、さらに、それはおそらく、この不透明な空虚を、測量可能な距離に還元することによって透明で機能的な空虚と化す、もっとも体系的な方法ではなかっただろうか。)」と言い、画家としてのジャコメッティの課題は、逆に、見ることの可能性を、見ないことの不可能性へと解放することであった、と言う。つまりこういうことになる。鏡、眼をそらすことを奪う魅惑、見ないことの不可能性が先にあり、それを馴化・制度化する形で絵画が成立しており、ジャコメッティの目的は、この一度馴化されてしまった〈見ないことの不可能性〉、鏡とその魅惑を再度取り戻すことにあるのだと。
〈見ないことの不可能性〉と〈見ることの可能性〉、〈鏡のなか〉と〈鏡の表面〉。見ること、そして鏡にはそれぞれ二つの重なった様態があるらしい。その二つの側面は、宮川だけでなく、精神病理学の中でもしばしば言及される。例えば木村敏は、『空間と時間の病理』での野矢啓一との対談で、「鏡で自分の姿を見るというときに、私が、あるいは自分が、自分を能動的に見るのでもあるし、自分が自分によって受動的に見られるのでもあるんだけれども、もう一つね、自分が自分にとって見えている、という中動態的な経験でもあるわけでしょう。自分という場所で、その場所自身が経験されているという。自己とか自我とかいった主語的あるいは客語的な存在ではなくて、自分が自分に見えるという述語的・与格的な主体の確認、これが大きいんじゃないか、という気がするんですよ」と語っている。鏡を見ることは一般的に、主体としての私が対象としての私を見ることを意味している、と考えられているが、それだけでなく、主体と対象という二元論的知覚そのものを成立させる場所を見るという経験でもある、と言うのだ。そしてその場所こそ、宮川が「鏡の中に降りていく」と表現している場所なのである。ここに二つの「見る」がある。私が対象を見るという仕方、私が私と非—私を成立させる基体そのものを見るという仕方。鏡の表面と、その中。
しかし、ここには反論が考えられる。例えば、鏡の経験は、単に私が私のイマージュを見るだけのことであり、宮川が言うような大層なことではない、と。もしあなたがそう反論したくなるとしたら、あなたはイマージュとその魅惑を捉え損ねているのかもしれない。宮川は次のように言う。「イマージュはつねに対象の再現であることが自明の前提となっている」。イマージュの問題は、それがそのイマージュである「元の事物」、言いかえれば、イマージュとして意識に与えられた対象の存在に、そしてそれのみに還元されてしまうことにある。しかし、「イマージュがそこにある」(ガストン・バシュラール)ということが真の問題なのである。イマージュは、根源的に、ここ、イマージュが現わす対象の存在ではなく、いわばイマージュそのものの現前、なにものかの再現ではなく、単純に似ていることなのである。
似ていること、それは単にあるものがほかのものに似ていることにすぎないのではないのだから。というか、むしろこの事実を通じて、しかし、より深く、つぎのようなことなのだ —— 同じものであり、しかも同時にほかのものであること、それがあることとは別のところでそれ自体であること、それゆえに、ある〈中間的な〉空間、「表と裏、夜と昼 —— というよりも蝶番のように表と夜、裏と昼、そのどちらでもなく、しかも同時にその両者であるもの」、いわばこの非人称的な〈と〉の空間そのものの浸透であり、それがすべての自己同一性(「彼が彼と自分の肉体を占有しており、彼と彼の大きさを占めており —— 道のほこりにまみれてそこにある二本の足 —— 時間と空間のすべてを占めており、それをかんづかれることなく離れようとする彼の努力にもかかわらず、ついに逃れうるものでもなく……」)をむしばむのだ。なによりもこのわたしとわたしとのあいだのずれ —— 「もう一度映像が僕を見つめる、その映像の目。そしてもう一度およそ想像を絶する空間が僕たちのあいだに形作られる。もっと近く、もっと遠く。僕は右腕をあげる、とただちに左腕が答える……」宮川淳『鏡・空間・イマージュ』
似ているものを模倣先の対象に還元することは、常にAはAであると盲目的に信じていることを意味している。僕は鏡を見る、右腕をあげる、とただちに左腕が答える。鏡に映る僕のイマージュは、僕にとても似ている。しかし、それは僕である。鏡の表面を見ることは、「私は私である」と確認することである。確認することで、僕は安心する。やはり私は私であった、と。「私が私であること」は、見ることの可能性である。それを前提にすることなく、「私は対象を見た」という一文を書くことなどできるだろうか。しかし、僕たちは油断することはできない。なぜなら〈見ることの可能性〉は、いつだって〈見ないことの不可能性〉へと転換する危険性を持っているのだから。
じっと鏡を見つめてはならない。そこには僕たちを引き込む魅惑があるのだ。鏡を見ることは私を見ることであるわけだが、そこで私は、「見ている私」と「見られている私」という、二人の私に分裂している。そしてこの分裂を通して、「見ている私」が「見られる私」との同一性を確認する。この同一性の確認は、時間の中で、常に流れ去った私を後から確認することでしかない。流れ去った時間、それは〈見ることの可能性〉であり、宮川がいう〈距離〉のことである。「見ている私」と「見られている私」の間の距離。僕たちが自己同一性として安心しているものの構造はこのようになっている。分裂しつつ同一であることを確認すること。もう、その分裂の裂け目、距離が、〈見ないことの不可能性〉へと転換する一歩手前である。その裂け目からは、この再帰的運動を可能にする場所が、あなたを覗き込んでいるのだから。あなたは鏡の中へ誘い込まれていく……。
鏡の中は「私は私でなく、私でなくもない」という二重否定の眩暈、自己同一性の裂け目、木村敏のいう述語的・与格的主体の横溢、危険な香りと魅惑に満ちた〈あいだ〉の空間を開くことである。宮川が鏡という言葉を用いて「見ること」を考える理由は、ここにある。なぜ僕たちは「鏡の中に降りていく」のを恐れるのか。そして、それと同時に、なぜこれほどまでに惹きつけられるのか。僕たちは「私は私である」という同一性に安心を覚える。他方で、この同一性に嫌気がさしている。宮川は「この鏡の空間、この二重化の体験、この自己同一性の裂け目、それは《彼》が、たえず、そしてたとえば、車を全速力で疾走させることによって空しく期待していたものにほかならないだろう」と言う。僕たちは安心を求めるだけでなく、それを退屈だと思う。そして危険な香り漂う眩暈の中へ、誘い込まれる。
宮川は鏡の空間を描き出す上で、さらに興味深い論点へと進む。彼は言う。「それはまたすぐれて〈本〉の空間ではないだろうか」と。ここまで「見ること」と「見られること」によって語っていたことを、「書く行為」と「読む行為」という二項を用いて、再度、そして別の仕方で、彼はこう語る。
書く行為は読む行為によって二重化されなければならないのだ、そのときに成立する〈中間的な〉空間、すなわち〈本〉(だが作品ではなく)。作家が、あるいは作品が —— あの自己表現が重要なのではもはやない。作家はなにごとかを伝えるために書くのではなく、そしてコミュニケーションとは作家が読者に伝えることではない。重要なのはこの本の空間であり、この本の成立そのものこそがコミュニケーションにほかならないのだ。そこでは書く行為と読む行為とが同時的・相互的なものとして理解されるこの〈彎曲した空間〉……そしてもう一度およそ想像を絶する空間が僕たちのあいだに形作られる、もっと近く、もっと遠く。僕は右腕をあげる、とただちに左腕が答える……このすぐれて鏡の空間であるもの、一冊の〈本〉。
……
《ぼく》の存在そのものの曖昧性はここから生まれる。それは決してあのいわゆる自我の非連続、不確実性を意味しているのではない。それは書くことの根源的な体験 —— 鏡の体験、二重化の体験であり、多かれ少なかれ、一人称の小説、いやすべての小説に内在する曖昧性なのだ。というより、フィクションとはおそらく、この二重化の危険な体験のいわば制度化によるエグゾルシスムではなかっただろうか。それによって、作家はおしゃべりの不毛な空間、この鏡のなかからのがれ出ることを、一方、読者は物語、この無意味なおしゃべりの背後に意味を求めることを許されるのだろう。
……
しかし、制度(たとえば三人称単数)であるよりも前に、フィクションとは言語の根源的な体験なのだ。文学言語のではなく、われわれの言語そのものの。なぜなら、日常言語があり、文学言語があるのではないのだから。そうではなく、文学とはわれわれの言語の根源的な体験なのだ —— 語るというそれ自体の運動における言語そのものの現前、それゆえに、すでにそれ自体のうちにおいて、非人称的な〈書く行為〉と〈読む行為〉とによってたえず二重化されなければならないこの鏡の空間。この二極が外在化され、人称化されるとき、われわれはそれを作家と呼び、読者と呼ぶのだ。宮川淳『鏡・空間・イマージュ』
繰り返しになるので、簡単にまとめる。ここで宮川が言っていることは、「見ること」と「見られること」の二重化と並行的な関係にある。そして、この「書く行為」と「読む行為」という二重化の中を〈本〉と呼ぶのである。彼が絵画を〈見ないことの不可能性〉を〈見ることの可能性〉へと変容させる制度であるというように、ここでは作品が絵画に相当する。根源的体験とは、作家が作品を読者に届けることではなく、この非人称的な〈書く行為〉と〈読む行為〉に二重化されることなのである。作家、読者、作品は、あくまでその外在化、制度化として成立している。宮川はジャコメッティを評して、彼は見ることの可能性を再度見ないことの不可能性へと開こうとしていると言った。同様に、書くことの可能性を書かないことの不可能性へと再度解放すること。それこそが求められているのだ。
宮川は〈描くこと≒見ること〉あるいは〈書くこと≒読むこと〉という制作の循環構造の中に、魅惑的かつ危険な非人称性を見出す。なぜ危険か。それは制作的実践によって、安定的なコギトが分裂し、その奥にある基底が見え隠れするからである。近代化とはこの同一性を確保することでなければ何なのだろう。「私が私であること」を保証するために作り上げてきた一連の制度を、近代制と呼んでもよいくらいだ。絵画という制度、作品という制度は、まさにそれらを象徴していると言えよう。鏡≒本の空間は、非人称の二重化が可能になる場のことを指している。そして、僕はこれから、レーン・ウィラースレフの『ソウル・ハンターズ』を参照しながら、鏡≒本の二重化を生きること —— 森の中では、それがミメーシスの実践として現れるのだが —— が、いかに不安定な生と死のあいだの統御であるかを示すつもりである。しかし、その前に宮川がここまでに示した「制作」に焦点を当てることにしよう。
宮川が言うように、「制作」とは二重化の体験である。描くことは見ることであり、書くことは読むことである。それは媒体との技術的対話である。作り手は素材に働きかけ、そこから何らかの応えを得る。そして、それに導かれながら、あるいはそれを裏切りながら、書く、そして読む、書く、その循環。もちろん構想はあるだろうが、すべて計画した上でそれを投影するわけではない。媒体との対話・抵抗の中で出てきた偶然性と向き合いながら、良いか悪いか試行錯誤しながら、修正したり、加筆したり、行ったり、来たりするのである。
アランは『芸術の体系』の中で、「アイディアが制作に先だち、それを規制するのは工業である。制作とは、制作の只中でアイディアが湧いてくること」だと言い、保坂和志は『小説の自由』の中で、「書かれた文章は書き手のイメージの写しではなくて、書き手は半分は書かれた文章からその先を書くヒントを得る」と言う。旧約聖書「創世記」の冒頭は「光あれ」「神は光を見てよしとされた」である。神ですら〈形〉にするまで光の良し悪しを判断できなかったのだ。「生産」が、決められた設計図通りに同じものを作ることを意味するとしたら、「制作」とはその只中でまた別のアイディアが湧き、それによって行き来する往還運動なのである。
そこでは、安定的な自己同一性を保つことはできない。なぜなら、あらかじめ構想していた安定的な私は、書くこと、描くことによって、そのたびに別の私として作られるのだから。ロラン・バルトが『言語のざわめき』の中で、「書くということにおいて、主体はエクリチュールと/から直接に同時的なものとして構成される、エクリチュールを介して実現され、影響をこうむる」と言っているように、である。「作品」や「作者」「読者」という概念は、制作の過程の中で「これでよし」と切断し〈形〉として外在化した結果、生じるものにすぎない。ここには過去から現在、そして未来へ、という時間の流れでは捉え切れない往還運動が存在する。つまり、偶然誤って引いてしまった線によって、作り手がそれに導かれることで〈形〉ができ上がったとき、その偶然性は「作品」にとっての必然性へと変化する。過去は変えられないものではなく、「制作」では頻繁に変わり続けるのだ。そして、「作品」として外在化されること、あるいはそれを引き受け「作者」となることで、主体もまたさらに変化していく。リチャード・セネットが『クラフツマン』の中で語るように、「制作」の中で、つまり物質性との対話の只中で、作り手は作ることへの責任や技術や精神の自己規律を醸成していくのだから。
[2]狩猟を通じて
ベンヤミンはミメーシスにひとつの理論ではなく、ひとつの「能力」を見出すのであり、それは身体のように人間の条件から切り離せないものである。この能力は、近代において、諸々のイメージとシミュラークルが横溢し、ゆえに現実的と感じるものが何もない世界をもたらした。だが、ベンヤミンが論じるには、ミメーシスの根源はまねることによって世界や他者との間に類似性を育もうとする原始的な衝動にまでさかのぼることができる。「自然は類似性を作り出す。擬態のことを考えるだけでわかるだろう。だが、類似性を生み出すための最も高い素質は、人類のものである。類似性を見出す才能は、他の何者かになったり、そのようにふるまったりしようとする、往時の力強い衝動の痕跡に他ならない。おそらく、人間の高次の機能のうち、模倣する能力が決定的な役割を担わないものはないだろう」。レーン・ウィラースレフ『ソウル・ハンターズ』
ここまで宮川淳の『鏡・空間・イマージュ』を元に、「制作」によって二重化の空間が開かれることを示してきたわけだが、ここからは予告していたように、レーン・ウィラースレフの『ソウル・ハンターズ』を参照しながら「非人称の二重化の経験」をより詳細に思考していきたい。この二重化の経験が、近代的な「見る私が見える私を確認するという自己同一性の在り方」と対照的な関係にあることは分かったし、それが「描くこと」「見ること」と「書くこと」「読むこと」の往還運動の中で見出されることも確認したが、それが近代的自我とは別の「私」であるとするならば、この「非人称の二重化」を生きるとは何なのか、より具体的に考える必要がある。宮川は鏡≒本の空間を理論として描き出した。しかし、「鏡の中に降りていく」ことは、鏡があるから可能になるわけではなく、そもそもそれを可能にする能力が僕たちにあるから可能なのだ。それは一般に、ミメーシス(模倣)と呼ばれる力である。
『ソウル・ハンターズ』は、シベリアの先住民ユカギールの元で行なった通算18か月のフィールド調査 —— ウィラースレフはある事件をきっかけに森の中での逃亡生活を余儀なくされ、現地民と狩猟生活を共にしながら多くの時間を過ごすことになるのだが —— をまとめた民族誌である。『ソウル・ハンターズ』の感想でしばしば聞かれるように、確かに一読しただけでは、本書は僕たちとまったく異なる枠組みを用いる〈狩猟民の哲学〉を詳細に記述し、僕たちに彼らの身体の在り方≒模倣様態を教えてくれるものとも読める。「彼は境界領域的な性質を有していた。彼はエルクではなかったが、エルクではないというわけでもなかった。彼は、人間と非人間のアイデンティティの間にある奇妙な場を占めていたのだ」という記述が、そのことを象徴的に示している。エルクというのはユカギールではよく狩猟されているシカ科の動物であり、この描写はウィラースレフが狩猟を共にしていたスピリドン爺さんが実際にエルクを狩るときの描写である。
僕たちは生活する上で狩りをすることはないので、この本が描いている様態が僕たちのものとは異なると、考えてしまうことも無理はない。しかし、すでに宮川の「鏡」についての議論を経た僕たちは、ここに書かれている境界領域的な場所を自分たちと無関係であるとは考えないだろう。宮川の「私は私ではなく、私でなくもない」と、ウィラースレフの「私はエルクではなかったが、エルクではないというわけでもなかった」は、私が見ているのが鏡であるか、エルクであるかの違いでしかないのである。
模倣行為の最中に狩猟者が持つ人間のパースペクティブ —— つまり、世界についての自らの主体的な観点を有する、自意識を持つ人間としての自覚 —— は、それ自体を超えて、エルクに対して外側から投影されるようになる。それゆえエルクは、狩猟者が持つ人間のパースペクティブを帯びたものとして経験される。同時に狩猟者は、脱人間化を経験する。つまり狩猟者は、自らの模倣演技を鏡写しにするエルクのふるまいを観察することを通じて、外側から、すなわち主体としての他者の観点から、自らを客体として見るようになる。結果として狩猟者の人間としての自己同一性は、自らのうちにではなく、模倣的な生き写しのうちに宿ることになる。狩猟者はもっぱらエルクのうちに自らを見出すことができる。そのためエルクは、狩猟者が本当はいったい何者であるのかの「秘密」を握ることになる。そういうわけで、逆説的なことに、狩猟者は容易にエルクの人格性を否定することができないのである。なぜなら、このことが実質的に彼自身の人格性を否定することを意味するからである。換言すればエルクが意志、意識、情動性などの力を持たない純粋な世界=内=客体に過ぎないのだと考えようとすれば、狩猟者は自らに対してもそのような諸性質を否定することになり、ある意味で、「自己を欠いた」まま置き去りにされてしまう。それゆえ、狩猟者の心理的な安定、つまり人格としての自己意識は、人格としての動物にこそ依存している。
それだけではなお、狩猟者によって経験されているエルクの「人間化」は完全ではない。エルクの身体は外部から認識される。そのことは、それが外にあるもので、それゆえ、狩猟者にとってはいくらか異質なものであることを意味する。狩猟者は、エルクと自分自身がまったく同じではないことを知っている、むしろ、知っている必要がある。もしそうでなければ、彼は(主体である)エルクのパースペクティブだけに文字通り身を委ねて、変身してしまったことであろう。だから、エルクは狩猟者自身と似てはいるが、まったく同一のものではないと認識される。
換言すれば、私たちが扱っているのは、「私」と「私=ではない」が「私=ではない=のではない」になるような、奇妙な融合もしくは統合である。私はエルクではないが、エルクでないわけでもない。同じように、エルクは人間ではないが、人間でないわけでもない。他者と似ているが、同時に異なっているという、この根源的な曖昧さは、動物と人間がお互いの身体をまといながら、なりすました種に似ているが、まったく同じというのではないやり方でふるまうという、ユカギールの語りの中に私たちが見出すものに他ならない。さらに、模倣の文脈で狩猟者が出会うのは、独自の個的な自己としての動物ではなく、人格の原型としての動物である。つまり、動物は自己=充足的な人格としてではなく、むしろ人格性の鏡、媒介物、もしくは仲介路として経験される。だからユカギールの神話では、繰り返し、彼以外の何ものでもない固有名を持つ特定の狩猟者が、種の原型的な名前に総称的な接尾辞である「男」あるいは「女」を加えた名前を持つ動物と出会うのである。レーン・ウィラースレフ『ソウル・ハンターズ』
ここに、宮川が「鏡の中」として描き出した「非人称の二重化」としての私が、より一般性のある仕方で描き出されていると、僕は考える。鏡を見るとき、私は私を見る、見る私と見られる私の間隙に、「非人称の二重化」「私は私ではなく、私でなくはない」が現れる。しかし、それはミメーシス(模倣)によって、より一般的な経験として捉え返すことができる。私はあなたを見る。私はあなたでなく、あなたでなくもない。そしてあなたは私でなく、私でなくもない。ユカギールにおいて、動物は鏡として、媒介物として、あるいは仲介路として経験される。そうであるとすれば、近代人が対象として見ていると思い込んでいる他者も、そうでないとどうして言えるだろうか。そして、だからこそ、僕たちは他者に対して人格性を付与できるのである。私とあなたが分離された認識論を前提にしていたら、僕はあなたに人格性があることを見出すことはできない。その認識論を前提にすれば、あなたがタンパク質でできたアンドロイドであることを、僕は否定できない。しかし、そうではなく、ミメーシスを前提にすれば、僕があなたの人格性を否定することは、僕の人格性を否定することになる。僕はあなたではなく、あなたでないのでもないのだから。僕はあなたを通じて僕を部分的に知るのである。そして、それはユカギールが動物に人格性を付与していることと同じなのだ。
ウィラースレフによれば、実践とはデカルト—デュルケム主義における「分離された二元論」でも、ハイデガー—インゴルドにおける「世界との完全な一致」でも汲み尽くせないものである。換言すれば、実践とは「私が対象を見る」といった、私と対象が切り離された認識の在り方でもなければ、私と対象が完全に同化すること、「私はエルクである」でもなく、その間を揺らぎながら「私はエルクではなく、エルクでなくもない」を維持することなのである。その制御に失敗することは、彼らにとって死を意味する。模倣とは魅惑と危険に満ちたものなのだ。獲物を誘惑することについての彼らの実践を、その一例として引用しておこう。
誘惑は基本的にはゲームである。そこでは、誘惑者が彼の犠牲者の自己愛的な傾向に付け込むことによって、彼女が興奮の頂点に達するところを探り、それによって彼女がすべてを、その命さえも、彼のために犠牲にしてもいいと思うようになる。しかし、誘惑者である彼自身は、感情面で抜き差しならない状態になるに違いない。犠牲者に対して共鳴や愛情を示すことが必要なのだけれども、彼には彼女と恋に落ちることは許されない。愛とは変身のようなものである。それは自分から他者への移譲、すなわち自分を譲り渡すことである。ゲバウアーとウルフは、「愛の終着点」とは、「自分自身を拡張して、相手に同化すること」であると述べている。この意味で、愛は誘惑とはかなり異なる。誘惑とは、少なくとも理念的には、誘惑する側には偽りの愛が、誘惑される側には虚栄があるだけだ。それにもかかわらず、誘惑と愛の境界線ははっきりしない。誘惑のゲームは、二者の間に本当の愛情が芽生えるという危険を常に抱えている。狩猟者たちは、自分が殺す動物に対して、いかに同情や愛さえ感じるようになるのかを語る。しかし彼らは、そうした感情が危険で払いのけられるべきものであることを常に強調したのである。それでもなお彼らは、狩猟者がエルクを観察していてある種の魅力的な特性や行動に惹き込まれ、差し迫った自分の仕事のことを忘れてしまって、気がつけばすでに手遅れで、動物が手の届かない場所に行ってしまうことが、ときどき起こると語る。こうした失敗を、彼らは狩猟者が獲物と恋に落ちたと表現する。この愛に夢中になると、他になにも考えられなくなり、食欲を失くして、しばらくすると死に至る。レーン・ウィラースレフ『ソウル・ハンターズ』
生きることは、僕たちを世界に接触させつつそこから切り離す存在様態≒二重のパースペクティブであり、狩猟のモードでは動物への/からの模倣を通じて人間と動物の間を揺らぐ「愛と誘惑の駆け引き」であり、人間集団の中では先祖のアイビ(魂)を引き継ぎつつ「木煙の匂い」や「語り」を通じて自己のアイデンティティを保ちつつ生きることである。繰り返すが、実践的生とは、動物と人間と魂のどこか一極に偏ることを防ぎながら、その不安定さを乗りこなすこと=生きることである。
その生を、ウィラースレフは、具体的な事例を用いて描き出すことに成功している。そして、実践に重きを置く=二重のパースペクティブを生きるが故に、アイビ(魂)はあらかじめ与えられた二元論(精神と身体)に基づくものではなく、文脈と関係性によって動物にも人間にも「人格」を付与すると説明する。彼は「アイビは同じ理性的能力を人間と非人間に付与するのであって、それらの人格が別様に考えるのは、それぞれの種が特定の身体的存在であり、世界に対する志向性をもたらす独自の肉体的自然 —— メルロ・ポンティの言葉を使うならば、特定の『身体意識』 —— を持つためである」と述べる。
『ソウル・ハンターズ』の読者の中には、ヴィヴェイロス・デ・カストロのパースペクティヴィズムとの近さを感じる人がいるかもしれない。ウィラースレフ自身は、パースペクティヴィズムの理論的成果を多分に認めつつも、理論的でしかないことへの疑念を発している。彼が描き出すのは「実践によって開かれるモード」である。それは「世界観」という概念が前提としているような、「全体性をもった構造や地図のような形」で実在しているわけではない。だからこそ、彼は具体的な事例と共に、人々がどのように「不安定な魂の制御」を行っているのかを記述する必要があったのである。それは「動物やモノの人格性は、狩猟の最中のような、綿密で実践的な没入が生じる特定の状況下において立ち現れるものだ。こうした特定の状況を離れたとき、ユカギール人は、私たち同様、必ずしもモノを人格として見ているわけではなく、代わりに人間の主体と非人間の客体の区別がはるかにたやすくなされるような、ありふれた客体からなる世界を生きている」という記述を見れば明らかであろう。これは宮川が「描くこと」や「書くこと」を通じて、鏡の中へ、そして本の中へと降りていくことと同様である。画家であろうと、作家であろうと、綿密で実践的な没入が生じているとき以外は、コンビニで買い物をしたり、テレビを見たりして過ごすこともあるに違いない。彼らも、実践的モード以外の時は、私と対象を二分する日常的な認識論を生きているのである。
僕にとってユカギールの実践哲学は、それだけで魅力的なものだ。しかし、僕が『ソウル・ハンターズ』を読んでいて最も震撼させられた点は、ウィラースレフが実践的揺らぎの中で「実在」を見出す際に、精霊とコンピュータを並列的に例示していることにある。彼は、ユカギールの人々が精霊を実践的道具として扱っているが故に全体的な理論的説明を必要としていないことを、ハイデガーの道具連関を用いて示す。他方で同様に、僕たちがコンピュータを用いる際に、上手くいっているときは情報工学やコンピュータの機能的連関について知る必要がないことを挙げている。あらかじめ与えられた抽象的な「実在と虚構」の二元論がなければ、ユカギール人の「住まわれる視点」(インゴルド)から、実践の中で必要に応じて精霊が生成されるのであり、それは僕たちの日常生活の中で必要に応じてコンピュータが生成されていることと同義なのである。換言すれば、共同体を維持していく上で必要であるから精霊が要請されているのであって、それが上手くいっている限りは、精霊がどのような姿をしているのか、どんな機能をもっているか、などと考える必要はないのである。それは今、僕がコンピュータでこのエッセイを書く上で何の不都合もないが故に、コンピュータとは何かとか、なぜコンピュータで文字を打てるのかなどと考えないことと同義である。
それは、「知覚とは概念表象や認知の問題だとする伝統的視点を留保し、その代わりに事物が人々の日常的な活動の流れの中で立ち現れるやり方によって進められる。換言すれば私が提起するのは、いわば分析の順序を逆転させることである。つまり、人々と事物との実践的なかかわりの方こそが決定的な基礎であり、それが『知的文化』すなわち抽象的な認知や概念表象にとって不可欠の前提になっているという仮定からはじめるのである」というウィラースレフの宣言からも、読み取ることができる。「我々にとって事物の根源的な価値とは抽象的な思考の対象としてではなく、実践的使用のための道具的なモノであるということだ。コンピュータにせよ精霊にせよ、それは何かがなされるために用いられるのであり、それゆえ具体的な目標を成就するために事務的に淡々と用いられる『道具』として立ち現れる」のである。
つまり、ウィラースレフの隠されたもう一つの主張は、遠くのどこかに住む「他者」の存在様態を描くことではなく、僕たちが抽象的二元論を暗黙の裡に基礎として据えているが故に、自身の実践的様態をまるで解明できていないということであり、またアニミズムや模倣様態は近代社会の中でも強く生き延びているということである。ユカギール人は、文化的な質が近代文明に比べて低いから、動物に人格性があると考えているわけではない。復習になるが、なぜ彼らがそのように考えるかというと、それはミメーシスによって「私はエルクではなく、エルクでなくもない」「エルクは私でなく、私でなくもない」という状態を経験するからである。エルクの中に私を見出さざるをえないので、エルクの人格性を否定することは私の人格性をも否定することに繋がるのである。そして、それは、僕たち近代人が「私はあなたではなくあなたでなくもない」という状態を経験することによって、他者の人格性を捉えることと同義なのだ。あなたの人格性を否定することは、私の人格性を否定することに繋がる。鏡の経験、ミメーシスの経験がなければ、僕たちは機械論的な無機質なものとして世界を捉えざるをえないのである。そして、この主張は、分離的な二元論の象徴的な思考法であるデカルト—デュルケム主義の延長線上にある文化相対主義が、他文化を見ることで自文化を相対化するというよりも、その基礎に他者を当てはめるが故に、自らの枠組みを自ら強化することになっている、という記述によってより強く述べられる。
まさにこの文化相対主義の主張には問題がある。すべての文化がそれ独自の構築された意味の枠組みに閉じ込められ、そうした枠組みはその文化に関連する基準でのみ測ることができると主張するということは、人類学者はある特定の文化の成員であるにもかかわらず、すべての文化についての文化=超越的な解釈を提示していることになる。これは論理的に矛盾している。相対主義的な言明を非相対主義的な一般主張としておこなっているからである。それゆえに相対主義的立場は、あらゆる他者の生がその中で形作られているとされる文化の諸世界から、人類学者だけは一歩抜け出していることを必然的に含意する。なぜなら、「文化を超えた観察の地点によってのみ、〔土着の〕理解を……ある独立した現実の……ひとつの可能な構築に過ぎないと見なすことができる」(インゴルド)からである。換言すれば人類学的な文化相対主義の主張は、西洋の認識論が土着の理解に対して持つ優位性の基盤を掘り崩すのではなく、実際にはむしろ改めて強化するのである。レーン・ウィラースレフ『ソウル・ハンターズ』
これは、単に他文化を解釈するときだけでなく、自文化を解釈するときに対する警告でもある。二元論的分離の元で何を解釈したとしても、基礎であるその二元論を当てはめ強化するだけになり、都合の悪い問題は隠喩的/象徴的な意味しかなく、実在ではないと処理し続けることになるのだから。ウィラースレフは、これまで隠喩としての地位しか与えられなかった「実在と実践の関係」について、真摯に向き合おうとしているのだ。そして、彼は本書の最後の段落で次のように言う。
私が主張しているのは、ミメーシスはアニミズム的な象徴世界を制作するための前提にして不可欠の条件であるということだ。日常生活におけるミメーシス的実践なしには、アニミズムの象徴世界は生きられた経験との間にいかなる類似も生まず、まったくのところ宇宙論的な抽象概念以外の何ものでもなくなるだろう。したがってミメーシスはアニミズムの実践的側面であり、その世界製作の仕組みそのものである。現代世界ではミメーシスが重要性を持つというベンヤミンの発見それ自体が、我々の大衆文化の中でアニミズム的な形のつながりが表面化していることの証左である。実際のところ現代におけるアニミズムの広範な役割についてはかなり多くのことを語ることができるものの、それは別な本の主題としなければならない。レーン・ウィラースレフ『ソウル・ハンターズ』
現代におけるアニミズムの役割に関するウィラースレフの本は、未だ出版されていないようだが、本書だけでも十二分にその可能性は伝えられている。本書の表向きの目的は、アニミズムを〈真剣に受け取る〉ための枠組みを提示することである。そして、そのために抽象的な枠組みから現象をトップダウンに当てはめるのではなく、実践的に文脈と関係性の網目の中へ再参入する必要性を論じる。しかし、ベンヤミンが言うように、人間こそがミメーシスを最大限に用いることができるのであれば、その原理はまさに僕たち自身の隠蔽された原理でもあるのだ。宮川が「描くこと」「書くこと」を通じて鏡の空間へ、本の空間へと僕たちを誘うように、ウィラースレフは「狩ること」を通じて、「愛と誘惑の危険な場所」へと僕たちを誘う。
その場所は鏡による死と誘惑の乱反射、私と非—私がせめぎ合う場所である。「私は彼/女ではなく、彼/女でなくもない」。だからこそ、僕たちは途切れなくメディアを経由して届くニュースに模倣的共感を示すのだ。なぜ、テレビやSNSを通じて届く有名人の浮気や不倫に対して、怒ったり嫉妬したりする人がいるのか。ミメーシスは、未だ僕たちの実践的知覚の基礎的な原理なのである。もはや僕たちは、「発達した人間は象徴的に統合されることで単一の〈私〉を形成し、その外部として〈他者〉と向き合う」という枠組みを疑わなければならない。これは発達過程としての〈鏡像段階〉ではない。僕たちの中にある危険な魅惑と向き合わなければならない。ユカギール人が、サウナに入り人間の匂いを落とし、森の中でヒトの言葉を控え、模倣を通じて部分的に非人間化し、キャンプに帰還した後は仲間に出来事を語り、木煙とタバコの煙の中で部分的に人間化するように、僕たちも僕たち自身の方法で、誘惑と変身の世界に再参入しなければならない。もうそれを否認することはできない。
ここまでで二つの存在様態があることを示してきた。一つには安定した自己同一性が対象を認識するという常識的な在り方、一人称単数小説のような私小説的コギトである。第二に、鏡の空間、イマージュとミメーシスによる魅惑の世界では、「私は私ではなく、私でなくもない」といった二重否定を伴った不安定な〈私〉が取り出された。そして、宮川にもウィラースレフにも共通するのが、特殊な二つの様態を示しているわけではなく、それが描くことや書くこと、あるいは狩猟をすることといった実践や儀礼を通じて切り替えられる様態であるということであった。一流の画家であろうと、日常生活においては社会に共有される〈常識〉を踏まえてコンビニやスーパーマーケットで買い物をするだろうし、狩人もキャンプに帰ると、二元論的な認知の元、仲間と語り、木煙やタバコの煙の中で人間化するのである。
僕はここで、描くこと、書くこと、狩ることを通じて僕たちが降りていく、あるいは落ちていく空間を「制作的空間」と名づけたい。なぜなら、これまでの宮川やウィラースレフについての議論は、二つの空間が記述され、AからBへの移行が無媒介に示されてしまうのが常だったからだ。僕がここまでの議論で強調してきたのは「描くこと、書くこと、狩ること」を経由するということである。僕たちは、制作という媒介によって、「制作的空間」に入る。制作するためには制作を介さなければならない。この一歩、降りていく経路、落ちていくまでの経路を無視してはならない。「制作的空間」には、世界観が前提とするような全体性は客観的に存在しないのである。鏡≒本の空間や、狩りの空間が制作的であるという側面だけでなく、表と裏を繋ぐ制作という契機を強調する意味でも、このように名づけたいと思っているのだ。
[3]制作的空間への二重拘束的方法
西田幾多郎は「場所」という論文の有名な箇所で、「我とは主語的統一でなくして、述語的統一でなければならぬ、一つの点ではなくして一つの円でなければならぬ、物ではなく場所でなければならぬ」と述べている。僕は、これから「制作的空間」が主語的統一ではなく述語的統一であるということ、一つの点ではなく一つの円であるような私であることについて記述したいと思っている。しかし、上記のように、それはAからBへという単純な移行として示すことが難しい。なぜか。それはウィラースレフの言うように、それがデカルト—デュルケム主義的な二元論でもなく、ハイデガー—インゴルド的な「世界との完全な一致」でもない、〈あいだ〉の場所だからであり、「制作」という契機を必要としているからである。二元論でも一元論でもダメだというのは、美術史的に言えば、僕たちがモダニズムを経由した現在を生きていることとも関連している。すでに僕たちは、分離的な二元論も、同化的な一元論も、共に否定された歴史の上に生きているのである。
例えば、岡崎乾二郎は『絵画の準備を!』の中で、こう述べている。
レディメイドといういい方には二重の意味が読みとれます。実はデュシャンが絵画の網膜性を批判するといった場合、その網膜性とは、むしろ視覚のレディメイド性をこそ批判していると思うんです。通常の自然主義的な絵画もしくは芸術というのは、つねに受動的であって、受動的であるかぎり、そこで得られた視覚はぜんぜん自然ではなく、むしろレディメイドの社会化されたものとしてしかありえないというのが、実はデュシャンの根本的な批判にはあった。なおかつ純粋な経験ないし純粋な知覚、あるいは松浦さんのいい方でいえば、ある種の純粋なイメージというものを自律させようとするならば、むしろそれを成り立たせていると自明視されているところの当の物体なり場というものをすり替える必要がある。網膜が受動的にあてにしている対象、それをあらかじめ社会化されたオブジェとして置きかえてしまうことによって、ずれを発生させ、視覚=網膜と対象を結びつけていた自明なつながりを切断し、どこにも属さない経験を確保しようとする作戦が、簡単にいえばデュシャンのレディメイドにはあると思います。つまり、「網膜の受動性」の批判がデュシャンにはある。社会的、歴史的に規定される対象と結びついた自明性を破壊することによって、もしくは遅延させることによって、いかなる対象にも結びつかない経験の自律性が得られる、と。……おそらく、モダニズムの根本には、純粋知覚に対する断念みたいなものがあって、なおかつ、それを仮に成り立たせるとすればどういうかたちがありうるか、という二重拘束的な方法論があったのではないか。岡崎乾二郎 / 松浦寿夫『絵画の準備を!』
ここで言われているレディメイドの戦略とは、簡単に言えば、対象によって文脈をずらすことで前提として隠れていた視覚的自明性を露わにする、というよく知られたものである。しかし、岡崎が指摘するのは、その戦略の意図が自明性を露わにすることによって、既存の認知フレームを使いまわすことのできない経験=純粋経験を炙り出すことだと言うのである。そして、レディメイドの戦略に見られるように、モダニズムの根本には純粋知覚に対する断念があり、単純に制度的な知覚から純粋知覚への移行という戦略は取れないのである。デュシャンの場合、それはレディメイドという制作であった。そして、そこにはもちろん、歴史も絡んでいる。
岡崎 ― そうですね。ヨハネス・イッテンや宮沢賢治の教え方というのは限界としての個人を探求するわけです。都会文化や都会人のあらぬ表現に憧れ、自分の能力を省みず、やらなくてもいい勉強をしたり、ひとの色使いを真似したりしないで、自分の限界に気づいてそれをプラスに生かしなさいとやる。それは素材に対する教え方にも反映している。
松浦 ― だけど、それは結局、あらゆる現状の社会的矛盾をありのままに維持しろということになる。
岡崎 ― まさにそう機能する可能性がある。だけどそのモラルが、バウハウス以降のというか二十世紀の教育モデルにはあるわけですね。素材を生かしなさいというのと、素材としての自分の特性を見つけなさいというのは同じことでしょ。紙で鉄や木の真似をするな、紙自身の限界を楽しめ、破れやすい紙であることを生かして表現しろと。そういう意味でヨハネス・イッテンだとか宮沢賢治自身は媒介者でしかないわけです。だけどその媒介者がむしろ芸術家として突出し、実際の個々の表現者、生産者は媒介者によって組織されるための素材そのものになってしまう恐れがある。もちろん、芸術家という代表、特権的な主体を排除できないと考えられてしまうとすればですが。反対に、こうした特権的な主観を先験的構造の中に位置づけ、解消しようとしたと見れば、イッテンや賢治は、その認識も、その存在もとても大きかったことになると言えますね。つまり構造主義につながる視点がそこにあった。
松浦 ― たしかに二十世紀のある種の芸術家のイメージは、能産的に何かを無数に産出する天才というよりも、媒介者という位置、ないしメタファーがもっとも的確なような気はします。たとえばシュルレアリストの場合でも、霊媒者への自己同一化というか、それこそ闇の領域の言葉を自分の身体を通過させることによって、それを昼間の言葉に置きかえるような、媒介者の位置の確保への意志が見られます。あるいはクレー自身の用いた言葉の中にも、媒介者としての「木の幹」という比喩があるね。岡崎乾二郎 / 松浦寿夫『絵画の準備を!』
このように、純粋知覚—純粋受動性の戦略というのは、二十世紀の美術史の中に散見されるが、ここで二人が行なっている批判は、ウィラースレフが行なったハイデガー—インゴルド的な「世界への完全な一致」という戦略への批判と同質の関係にある。単純に同化する一元論的な神秘主義に居座ることはできない。もちろん分離的な二元論を肯定することなど不可能である。二元論でも一元論でもない不安定な場所を維持することが求められているのだ。作りつつ、作られ、作られつつ、作ること。宮川が鏡≒本として、あるいはウィラースレフが二重のパースペクティブ、不安定な魂の統御と言った、その魅惑と危険に満ち満ちた場所に立ち続ける技術である。
[4]常識と共通感覚
二重拘束的方法論というとき、一つの疑問が湧いてくる。主体—対象—属性的な日常的視覚でもなければ、自己を媒体とする一者への同化でもない〈あいだ〉の場所。単に日常的な知覚に居座るのでもなく、霊媒者としての芸術家の位置を獲得するのでもなく、その間の揺らぎの中を、生と死の揺らぎを生きなければならないということは分かった。そして、先に挙げたデュシャンのレディメイドの戦略は、岡崎曰く、自明性を露わにすることを媒介に、僕たちを純粋知覚へと進ませるものであった。しかし、自明性を露わにすることは、即、純粋知覚へと飛躍可能なのだろうか。私と非—私の裂け目から見える、それを可能にする場所、それ自体が問われなければならない。
ここからは、中村雄二郎の『共通感覚論』の議論を検討していきたい。中村は、〈コモン・センス〉という言葉がもともと持っていた二つの意味を検討することを通じて、自明性が露わになった場所に辿りついているように思う。
常識とは、私たちの間の共通の日常経験の上に立った知であるとともに、一定の社会や文化という共通の意味場のなかでの、わかりきったもの、自明になったものを含んだ知である。ところが、このわかりきったもの、自明になったものは、そのなんたるかが、なかなか気づきにくい。常識の持つ曖昧さ、わかりにくさもそこにある。その点で、さきにふれたデュシャンとケージの企てが、〈芸術作品〉の通念(約束事)の底を突き破り、そこに芸術の分野で、日常化された経験の底にある自明性をはっきり露呈させたことは、甚だ興味深い。この場合、日常経験の自明性が前提とされ、信じられていなければ、その二つの企ては共にもともと根拠を失い、〈作品〉として成り立たないだろう。しかしながら二人の作品の場合、そのような日常経験の自明性は、もはや単に信じられているのではない。信じられていると同時に、実は宙吊りにされ、問われているのである。中村雄二郎『共通感覚論』
このように、中村もマルセル・デュシャンについて注釈を加えることから議論を始めている。まずは彼が示す〈コモン・センス〉についての二つの側面を見てみることにしたい。
日常経験は、多くのわかりきったこと、自明なことの上に成り立っている。そのために、もっとも身近なものでありながら、かえってありのままにはとらえにくい。あまりにも身近で、多面的で、錯綜しているために、距離をとって一定の視点からとらえることができない。ここで要求されるのは、なによりも総合的で全体的な把握、それも理論化される以前の総合的な知覚である。その点からいうと〈常識〉は、現在ではあまりその知覚的側面が顧みられないでいるが、まさに総合的で全体的な感得力としての側面を持っている。常識とは〈コモン・センス〉なのであるから。というより、ふつういう常識とは、この〈コモン・センス〉の一面をあらわしたものにすぎない。たしかにコモン・センスには、社会的な常識、つまり社会のなかで人々が共通(コモン)に持つ、まっとうな判断力(センス)という意味があり、現在ではもっぱらこの意味に解されている。けれどももともと〈コモン・センス〉とは、諸感覚(センス)に相わたって共通(コモン)で、しかもそれらを統合する感覚、私たち人間のいわゆる五感(視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚)に相わたりつつそれらを統合して働く総合的で全体的な感得力、つまり〈共通感覚〉のことだったのである。
この共通感覚のあらわれをいちばんわかりやすいかたちで示しているのは、たとえばその白いとか甘いとかいう形容詞が、視覚上の色や味覚上の味の範囲をはるかにこえて言われていることである。すなわち甘いについていえば、においに関して〈ばらの甘い香〉だとか、刃物の刃先の鈍いのを〈刃先が甘い〉とか、マンドリンの音に関して〈甘い音色〉だとか、さらに世の中のきびしさを知らない考えのことを〈甘い考え〉だとか、など。またアリストテレスでは、共通感覚は、異なった個別感覚の間の識別や比較のほかに、感覚作用そのものを感じるだけでなく、いかなる個別感覚によってもとらええない運動、静止、形、大きさ、数、一(統一)などを知覚することができるとされている。その上、想像力とは共通感覚のパトス(受動)を再現する働きであるともされている。さらにすすんで、共通感覚は感性と理性とを結びつけるものとしてもとらえられている。中村雄二郎『共通感覚論』
彼は、ここで〈コモン・センス〉が本来持っていた二つの意味、〈常識〉と〈共通感覚〉を取り出している。〈共通感覚〉は、アリストテレスが用いていたように、五感を跨りそれを統合する感得力であり、感性と理性を結びつけ、想像力を司る場所であると言われる。そして、そこから広く一般に、人々に共有され制度化された判断が常識と言われるものになったのである。つまり、共通感覚とは一種の統合作用であり、それは生成を司るものである。そして、それが静的に固定化されたものが常識なのだ。つまり、デュシャンの例で中村が露わにしたのは、表層を覆う〈常識〉を剥ぎ取った先に見える〈共通感覚〉である。
『共通感覚論』の素晴らしいところは、この〈共通感覚〉という場を見出すだけでなく、それがどのようなものなのかという問いへと、さらに突き進んでいくことにある。例えば、先のデュシャンのレディメイドについて、僕は自明性を剥ぎ取ることが純粋経験へと繋がるのか、という問いを投げかけておいた。中村は、「〈社会通念としての常識〉は、多面性を持った豊かな現実、変化する生きた現実を十分に捉ええないものとして問われ、打破されねばならない。けれども、だからといってまったく無用なものであるどころか、私たちにとって社会生活上なくてはならないものであって、むしろ〈豊かな知恵としての常識〉へと自己脱皮するための前提となっている」と言う。どういうことだろう。
中村はここで、精神病理学者ブランケンブルクの論文「〈コモン・センス〉の精神病理学序説」と著書『自明性の喪失』を参照しながら、議論を深める。ブランケンブルクの患者であるアンネ・ラウは、「私に欠けているのは、きっと自然な自明さということなのでしょう」「私に欠けているのは何なんでしょう。ほんのちょっとしたこと、ほんとにおかしなこと、大切なこと、それがなければ生きていけないようなこと」と言う。アンネの症状は寡症状性分裂病の症例として、とくにその自己陳述として完璧に近いものだとされている。彼女の意見を元に考える限り、アンネの病状は、自明性を欠いていることにある。しかし問題は、自明性を欠いた先にあるのが、活き活きとした現在としての純粋経験などではなく、現実と生命的接触を欠いた(ミンコフスキー)生だということである。つまり、常識や自明性を剥ぎ取ることは、直接的に純粋経験へと辿りついたりしないのである。ここでアンネが失ったのは、本当に自明性なのだろうか。中村はそうではないと結論づける。
この問題を考える上で、中村が〈コモン・センス〉を、静態的な社会〈常識〉としての側面と、それすら含め五感を貫通し統合する理性と感性を繋ぎ、想像力を司る場所としての〈共通感覚〉とに分けていたことが重要になる。彼は次のように言う。
アリストテレスが〈共通感覚〉として名づけたこの基本的な感受性は、人間と世界とを根源的に経路づけ、僕たちがそもそも〈世界〉といわれうるものを現前させる働きをもっているのだ。そしてこの感受性が欠けるとき、〈世界〉は単なる〈感覚刺激の束〉としてただ僕たちの感覚表面につきささってくるカオスにすぎなくなる。われわれの方からそれを積極的に〈世界〉として構成することがどうしてもできなくなる。すでにアリストテレスは〈共通感覚〉を〈構想の能力〉と見なしたが、この〈構想〉とは単なる想像や空想の意味をこえて、現勢的な構成的知覚に際していつでも一緒に働いているものなのだ。中村雄二郎『共通感覚論』
アンネが喪失したものは〈常識〉としての自明性ではない。〈常識〉をそのたびに構成している〈共通感覚〉を喪失しているのである。僕たちの議論に合わせて整理すれば、私—対象—属性という〈常識〉的な認知の在り方は毎回同じように〈共通感覚〉が構成してくれるから、その事実を忘却している限りにおいて〈常識〉なのである。〈共通感覚〉の部分集合として〈常識〉があるのだ。
デュシャンがレディメイドの戦略で露わにしているのは、自明性の基盤ではない。それが僕たちに開示しているのは自明性を生成する〈共通感覚〉の場であり、異なる知覚への可能性の中心なのである。そして、お分かりの通り、これは僕が宮川やウィラースレフを経由することで定義した「制作的空間」と同じ場所である。ここまでの中村の議論では、〈コモン・センス〉の二つの側面、〈常識〉と〈共通感覚〉、静態的な枠組みとそれを含めて生成する動態的な機能が示されただけであり、そこへの経路、つまり「制作」という側面はまだ見えてこない。しかし後に、中村もその経路について示すことになる。先に進めよう。
[5]〈共通感覚〉から五感の組み替えの歴史へ
カール・マルクスは『経済学・哲学草稿』の中で、「五感の形成は、現在に至るまでの全世界史の一つの労作である」と言った。僕は、この言葉に「制作」を考える上での二つのヒントが隠されていると思う。一つには、五感は形成されたものであるという点。そしてもう一つには、全世界史の〈一つ〉の労作であるという点である。あえて記述される〈一つの〉という言葉には、〈別の〉という暗示が込められている。中村雄二郎『共通感覚論』は、上記の〈共通感覚〉の発見から、五感の組み替えという議論へと進む。それは別の身体の制作へと繋がる重要な論点である。
中村は「五感の形成は歴史のなかで行われ、感性は歴史的なものであるという考え方は、これを私たちの観点から、つまり知覚を共通感覚の働きとして捉えなおすとき、もっと別のかたちで展開することができるのではないだろうか。……人間感覚の歴史的な形成と変化とを、知覚の深層の歴史として捉える視点が得られるだろう。五感そのものの洗練と組み替えによる、緩慢で非連続な人間の知覚の深層の歴史、としてである」と言う。そして、その具体的な例として、近代の初めに行われた〈五感の階層秩序の再編成〉を紹介する。
ヨーロッパ中世世界では、もっとも洗練された感覚は、すぐれて知覚的な感覚、世界のもっとも豊かな接触をうち立てる感覚とは、なにかといえば、それは聴覚であった。そこでは視覚は、触覚のあとに第三番目の位置を占めていたにすぎない。つまり五感の序列は、聴覚、触覚、そして視覚の順であった。ところが近代のはじめになって、そこに転倒が起こり、眼が知覚の最大の器官になった。見られるものの芸術であるバロックが、そのことをよく示している。では、中世世界ではなぜ聴覚が優位を占め、視覚が劣位におかれていたのであろうか。それは一方で、キリスト教会がその権威をことばという基盤の上においており、信仰とは聴くことであるとしていたからである。聴覚の優位は十六世紀においても、神学に保障されてまだ強かった。《神ノ言葉ヲ聴クコト、ソレガ信仰デアル》、《耳、耳だけが〈キリスト教徒〉の器官である》とルターも言っている。それだけではない。それとともに他方で、視覚は触覚の代理として官能の欲望に容易に結びつくものと考えられたからである。スペインの聖者フアン・デ・ラ・クルスの先駆者たちの一人は、自分の眼で見るものをなんと五歩以内のものに限り、それを越えてはものを眺めてはならない、としていた。イメージにはなにか自然のままのもの、つまり規律的な道徳を破るところがあると考えられていたのであった(ロラン・バルト『サド、フーリエ、ロヨラ』)。
ルネサンスの〈五感の階層秩序〉のなかで聴覚と視覚の位置が逆転し、視覚が優位化したことは、たしかに自然的な感性としての官能が解放されたことと結びついている。ところが、近代文明は、触覚と結びついたかたちでの視覚優位の方向では発展せずに、むしろ触覚と切りはなされたかたちでの視覚優位の方向で展開された。近代文明にあっては、ものや自然との間に距離がとられ、視覚が優位に立ってそれらを対象化する方向に進んだのである。近代透視画法の幾何学的遠近法や近代物理学の機械論的自然観、それに近代印刷術は、その方向の代表的な産物である。と同時に、その方向を強力におしすすめたものであると言えよう。そうしたなかで、時間も空間もすべて量的に計りうるものだと考えられるようになり、その結果、人間の時間も空間も宇宙論的な意味を奪われ、非聖化された。また、遠近法にもとづく錯覚が利用されて、一般に視覚上或る一点が固定され、そこに収斂するように描き出されたものこそが眼に見える、秩序だった、永続的なものであるという幻想がつくり出された。中村雄二郎『共通感覚論』
この引用で覚えておいてほしいのは、中世から近代にかけて、聴覚中心の五感の秩序が視覚中心の秩序へと変化したことと、その視覚の在り方が、触覚と結びついた形で発展したのではなく、切り離される形で進んだということである。これは、主体—対象—属性という認知の在り方が近代において成立したことを意味している。中世から近代にかけて五感の組み替えがあったことについては、中村雄二郎だけでなくさまざまな論者がそれぞれの視点から論じている。その中で最も示唆的であったのは、理論物理学者ゲーザ・サモシが『時間と空間の誕生』という本の中で論じていることである。
重要で新しい種類のシンボルによる時間と空間と、それによる新しい人間の宇宙像は、十七世紀の実験科学の誕生とともに展開した。科学革命である。最初の実験科学は時間や空間の中の世界を数学による数量というシンボルで記述し、これらの数が興味深い実験と観測によって見い出されうると考えた。「実験的方法」は、よく知られるようになっているように、人間の感覚が正しく用いられれば外界から信頼に足る情報を得ることができ、数学と言語はシンボルによる時間や空間の一般法則を数式化するために用いられうるという考えに基づいている。この考え方は類まれなるもので、それ以前には似たようなことが系統だてて行われたことはなかった。
感覚を時間や空間での数量的な法則、秩序を見出すために用いるという発想が諸科学を生んだのである。しかしその発想そのものは科学から生まれたわけではなく、むしろ芸術に源を発している。物理学における実験という方法が生まれるよりも約四世紀前に、多声音楽が西欧で発展し、それとともに音楽のリズムをそろえるための記譜法がもたらされた。この方法は歴史上初の数に基づく、周囲とは独立した、正確なシンボルによる時間の測定を可能にしたのである。これがうまく行ったことで、正確で信頼しうる方法で短い時間間隔を数えれば数を用いて時間の経過を記述することが可能だということがはっきりわかったのである。このように、科学で計測されるあるいは数学的な時間が用いられるようになるはるか以前に、音楽家によってそれは発明され、定義され、用いられ、研究されていたわけである。
他方、視覚芸術の方は、空間の知覚を表す法則の発見という形で役に立った。科学で実験という方法が確立する二世紀ばかり前に、人間の最も重要な空間感覚である視覚に関する洗練された数量的規則が立てられたのである。イタリア・ルネサンスの画家たちは、幾何学法則を視覚の法則にあてはめ、それにより歴史上初めて、高度にリアルな絵の創造が可能になったのである。この結果は、人間の空間や空間にかかわる性質の知覚においては、視覚が数学法則に正確に従っているということを強く示したのである。
西洋文明が扱う文化史家がこぞって認めると思われることは少ないが、そのうちの一つは、三つの重要な発展が西洋文明にのみ発生し、根づき、花開いたという点である。その三つは多くの面で西洋の文明の特徴となっている。その三つが、多声音楽、透視図法による絵画、実験科学である。めったに気にとめられないことではあるが、この三つがいずれも、基本的には同じ技術上の問題と取り組むことで生まれてきたというのは特筆すべきことである。その問題とは、時間間隔、空間的な隔たり、それらの様々な関係について、信頼しうる尺度を見出すための感覚の使い方ということである。つまり、知覚される世界を、いかにして数学的秩序に従わせるかということである。また、これもめったに気づかれないことだが、この決定的な企てに関しては、芸術の方が実験科学に先んじているという点も特筆すべきことである。
この西洋の芸術と科学での問題は、おおよそ十三世紀の半ば(多声音楽の始まり)から、十七世紀末のアイザック・ニュートンの時代(科学革命の仕上げ)にかけて、徐々にではあるが着実に解決されていった。この新しい発展は、シンボルによる時間や空間の新しく強力な体系を生み出し、それが世界の新しい知覚のしかた、理解のしかたにつながったのである。先にも触れたように、この新しい宇宙像は、人々が意識して自分の五感を信頼し、直接の感覚印象が性質についての主な情報源になるのと並行して展開した。これがこの時期に、知られる限りでは歴史上初めて、しかもただ一度起こったのである。ゲーザ・サモシ『時間と空間の誕生』
重要な箇所なので長い引用になったが、今では近代主義とされている特徴が中世、ルネサンス期に準備されたことだけでなく、その五感の組み替えが芸術によって率先して行われたことが、ここで示されている。繰り返し言うように、デュシャンの戦略は〈共通感覚〉という隠された生成の場を開示することであった。そして〈共通感覚〉は、僕たちが前提としている自明性を生み出すものであるが(その場合には〈常識〉と呼ばれる)、他方で新たな五感の秩序をも生み出すものである。要するに「制作」とは、この〈共通感覚〉という暗闇へと降りていき、新たな五感の秩序を形成すること、それぞれの身体を独自の身体として生成することにあるのだ。
事前にある「私」を「私と非—私」へ切り裂き、その裂け目へと降りていくこと。「私が私ではなく、私でなくはない」場所で、媒体と対話する中で偶然と戯れ、よろめきながら往還運動を続けること。その危険と魅惑に満ち満ちた不安定な場所で生き抜き、新しい私を立ち上げ続けること。中世から近代にかけて開発された多声音楽と透視図法による絵画は、まさにこの新たな感覚、新たな身体の制作によって/と共に制作されたのであった。そして、ここまでで、僕たちは、デュシャンのレディメイドの戦略が、彼の制作の終わりではなく、始まりにすぎなかったことを理解できる。なぜなら、〈常識〉を解除し〈共通感覚〉の場を開示すること、それはそこから新たな身体の制作が始まることなのだから。
[6]諸感覚の新しい配分比率
中村は「近代世界での視覚の独走と専制支配に対して、触覚や聴覚の回復を図ること、その方向で五感の組み替えを行なうことの必要性は増している」と言う。なぜか。それは、現代が、次々と新たに現れるテクノロジーによって、五感の組み替えを強制する時代だからである。しかし、この事実は自然への回帰を推奨するものではない。そうではなく、このようなテクノロジー環境こそが僕たちにとっての自然なのであり、〈共通感覚〉を麻痺させるのではなく、〈共通感覚〉を活性化し、それぞれの五感の組み替えを制作することが推奨されるのである。
レオナルド・ダ・ヴィンチが自然を観察することを何よりも重視したように、僕たちはこの「第二の自然」(タウシグ)の生成を観察することを重視しなければならない。テクノロジーを嫌悪したり忌避したりしている場合ではないのである。1979年に『共通感覚論』を刊行した中村が存命なら、2018年現在のテクノロジーに対する熱狂を見て何と言うだろう。現在は、彼が危惧していた時代よりもさらに増して、それぞれが諸感覚の新しい配分比率を制作する必要性が高まっていると言えるのではないか。
ここにおいて必要なことは、人間拡張としての技術手段あるいは媒体のひき起こす感覚の〈麻痺〉や〈閉鎖〉をこえて、五感を組み換え、諸感覚の新しい配分比率を発見することである。新しい技術の衝撃によって、変化を蒙るのは、部分ではなく全体としての組織である。すなわち、ラジオの影響は視覚に及び、写真の影響は聴覚に及ぶ。新しい衝撃が加わるごとに、感覚全体の配分比率が変化する。今日われわれが求めているのは、心理的、社会的見地から感覚の配分比率の変化をいかに統御するかという方法である。あるいは、そのような変化をすべていかに避けるかという方法である。ここにおいて、物事を全体的に把握する人間として、芸術家の存在が重要な意味を持ってくる。
新たな技術の打撃でわれわれの意識の働きが麻痺してしまうまえに、芸術家は感覚の配分を調整することができる。彼らは、麻痺と識域下の動きや反応がはじまるまえに、感覚を正すことができるのである。事実、芸術家たちは、すでに百年以上もまえから、〈諸感覚を統合する〉神経組織の役割を触覚に与え、それによって電気時代の挑戦に応えようとしてきた。とくにセザンヌ以来、触覚は、芸術作品に一種の神経組織あるいは有機的統一を与えるものとして、芸術家の心をとらえてきた。その後、触覚の働きが美術において持つ重要性は、バウハウスの感覚教育のプログラムをはじめ、パウル・クレーやワルター・グロピウスその他、1920年代のドイツの多くの芸術家たちの仕事によって、広く一般に知られるようになった。そして、そのような電気時代への応戦は、逆説的にも〈抽象芸術〉によって、つまり古い絵画的イメージの因襲的な形骸ではなく中枢神経組織を作品にもたらす抽象芸術によって、はじめて成就された。人々はいまや、人間という統合的存在によって、触覚がこれまでよりもいっそう必要であることを感じてきている。宇宙船のカプセル中で無重力状態におかれた乗務員は、この統合的な働きをもつ触覚を保つためにたいへんな努力をしなければならない。おそらく触覚とは、ものとの皮膚接触にとどまるものではなく、精神のなかで、ものが持つ生命そのものと触れ合うことではないだろうか。古代ギリシャ人は、一つの感覚を他の感覚に変換し、人間に意識を与える共感覚あるいは〈共通感覚〉の能力を想定していた。と、このようにマクルーハンは言っている。中村雄二郎『共通感覚論』
ここにおいて、なぜ僕が鏡≒本の空間、〈共通感覚〉の場を「制作的空間」と名づけ直すかを、より明確にできる。中世において芸術家によって準備された身体は、近代において一般化され、常識となった。それはまた〈共通感覚〉を覆い隠す〈常識〉になったのだ。しかし、さらにそこから、近代はそれに対して新たな身体を作り出していた。中村は「セザンヌ以降、触覚は芸術作品に一種の神経組織あるいは有機的統一を与えるものとして、芸術家の心をとらえてきた。〈抽象芸術〉によって、つまり古い絵画的イメージの因襲的な形骸ではなく中枢神経組織を作品にもたらす抽象芸術によって、はじめて成就された」と言う。
芸術家とは「作品」を作る人を指すのではない。上記のように、「作品」は、あくまで「制作」という媒体との対話を通じて、私と非—私が不安定に循環し、私と対象それ自体を生成し、その中で〈あいだ〉に生じるものが〈形〉として外在化されることで、外側から見たときに「作品」と呼ばれるだけのことなのだ。それは同時に「作者」と「読者」を生む。しかし、それは副次的なことである。重要なことはそれぞれの諸感覚を再構成すること、それぞれの身体を制作することである。毎月のように発表される新たなテクノロジー、そして変わっていく環境。それは僕たちのコントロールを超えている。僕たちの身体は次々と無意識のうちに変更される。
僕たちは今、自覚的に、この諸感覚の配分比率へ介入することを求められている。中村はその役割を芸術家に与える。しかし、僕はそれを、皆がもつべき技術であると思っている。これは皆が制度的な意味で芸術家であるべきだと言っているのではない。非制度的な意味で芸術家であるべきだと言っているのだ。環境によって身体を作られるな。作られつつ、作ること、作りつつ、作られること。受動的な状態から往還的な状態へ移行すること。能動的な状態ではない。それは幻想にすぎない。自分勝手な幻想を媒体に投影するな。媒体には媒体に固有の特性がある。媒体と対話することで私と対象の双方が生成される。事前にすべてを把握する主体は存在しない。だからこそ僕はこのエッセイを通じて、「制作的空間」とは何かを詳細に記述したいのだ。そして皆を誘惑したい。自己同一性が分裂する危険な場所へ、魅惑的な場所へ。何よりも僕自身の新たな身体への足場として機能させるために。そして、それがいつか、どこかで、誰かの足場として機能することを祈って。
[7]諸感覚の〈体性感覚〉的統合
先の中村の記述について、僕が意図的にまだ語っていない部分がある。それは、中村が触覚を特権的に扱っている点である。彼は近代世界の中で視覚の絶対的優位に疑問を投げかけた人物として、ジョージ・バークリーとコンディヤックを挙げる。そして、「距離そのものは見られない。遠くにある物体との距離の見積もりは感覚ではなくて、むしろ経験にもとづいた判断の働きである」というバークリーの言葉や、「視覚だけによっては、ひとは空間についての観念も位置についての観念も大きさや運動観念も持ちえず、眼にそれらを見ることを教え込めるのは触覚だけである」というコンディヤックの言葉を引用しながら、視覚を基礎づけるものとしての触覚という論点が、近代の只中にも生じていたことを示す。
また、コリングウッドの「そこへセザンヌがやってきて、あたかも盲目の人のように描くことをはじめた。彼の天才のなんたるかをよく示している静物画のデッサンは、あたかも両手で探りまわされた物体のようである」という記述を引用し、「セザンヌにあるのは絵画における〈触覚〉の回復」であり「運動する〈触覚〉である」と言う。そしてセザンヌ以降、「普通考えられているよりもはるかに大きく触覚的なものの重視の上で近代絵画が成り立っている」と言う。中世の聴覚中心の身体から、近代にかけて芸術家が制作してきた身体を視覚中心のものとするなら、近代のまさに中ほどで哲学者や画家たちが取り組んできたのは、視覚から触覚優位への身体の編成であったということを、中村は言いたいのである。
もちろん、この視点は一面的であり、近代美術史に詳しい人であれば、反論や反例を示すことは容易かもしれない。しかし、最後まで彼の議論を追ってみることにしよう。そうすることで、彼がなぜ触覚優位の五感編成を推奨しているのか、その理由が分かるはずである。そのために、これまでの議論よりも五感について解像度を上げなければならない。僕は、ここまで無批判に五感という用語を用いてきたが、現在最も広く近代生理学で用いられている分類は、もう少し入り組んだものになっているようである。
現在最も広く用いられている感覚の分類(勝木保次)によると、諸感覚は特殊感覚(視覚、聴覚、嗅覚、味覚、平衡感覚)、体性感覚(触覚、圧覚、温覚、冷覚、痛覚、運動感覚)、内臓感覚(臓器感覚、内臓痛覚)という三つに分けられる。そして、第一のグループの特殊感覚とは、脳神経によって信号の伝達されるもの、つまり脳神経連絡の諸感覚であり、次に第二のグループの体性感覚とは、体性脊髄神経によって伝達されるもの、つまり脊髄連絡の諸感覚であり、最後に第三のグループの内臓感覚とは、内臓神経によって伝達されるもの、つまり内臓連絡の諸感覚であった。
このような三つのグループの伝達・連絡経路をみると、第一のグループの特殊感覚が純脳型で直接に大脳に伝えられるのに対して、第二のグループの体性感覚が四肢へと広がる脊髄神経をとおして大脳に伝えられることが示されている。また、第三のグループの内臓感覚は、体性感覚が脊髄神経系の内部知覚であるのに対して、自律神経系の内部知覚であるということになる。自律神経も脳から出て内臓に分布している。けれども、その脳の部分というのは、大脳皮質ではなくて脳幹と呼ばれるところなのである。この自律神経系の内部知覚は、視覚や聴覚などの特殊感覚にくらべてはもちろんのこと、体性感覚にくらべても漠然として曖昧である。それというのも、この場合、内臓感覚神経からの情報が間接的に、拡散したかたちでしか脳幹を含む皮質下中枢に伝えられないからである。そして体性感覚は、すでに述べたように、無意識のまとまりと結びついた諸感覚の遠心的な統合の働きを持っている。けれども、体性感覚がその働きを十分に発揮するためには、このもっと無意識的で暗い内臓感覚に根を下ろす必要があるのだろう。
昔からただ触覚といわれたものは、単に皮膚の接触感覚にとどまらない体性感覚の一つであり、それは、同じく体性感覚に属する筋肉感覚や運動感覚と密接に結びついて働くものであった。かつて触覚とされたものを、このように体性感覚として捉えなおしたのは、もとより狭い意味での触覚までも体性感覚に還元するためではない。そうではなくて、狭義の触覚も、体性感覚の一つとしてその基盤の上に、筋肉感覚や運動感覚と結びついてはじめて、具体的な触覚として働くことを明らかにするためであった。このようなわけで、触覚を以て昔からよく五感を総合するものといわれてきたけれども、それはいわゆる触覚、ふつういう意味での触覚のことではなくて、実は、触覚に代表された体性感覚のことだったのである。中村雄二郎『共通感覚論』
彼は〈触覚的〉という概念を、上記のように近代生理学の成果を用いて再定義する。中村は、セザンヌを「絵画における〈触覚〉の回復」と言い、彼の絵画には「運動する〈触覚〉」があると言った。しかし、彼は今や〈触覚〉を〈体性感覚〉と、〈運動する触覚〉を〈運動する体性感覚〉と言い換える。そして、「風景を分解する印象派の外光描写をこえて、セザンヌは体性感覚を重視し、〈盲目の人のように〉静物や風景を描いたのであった。それというのも、印象派の外光描写によっては自然のもつ生命そのものに触れえないことに気がついたからである」 と言ってのける。彼が〈触覚〉を〈体性感覚〉と再定義した理由は、〈体性感覚〉が〈触覚〉という表層との接触だけでなく、内(筋肉感覚や運動感覚)と外(触覚)を繋ぐものであること、そして筋肉感覚や運動感覚に代表されるような動態的な感覚であることを強調するためである。それは、中村による「この風景を分割する印象派の外光描写」と「セザンヌの自然のもつ生命そのものに触れるような運動する体性感覚」という対比に示されている。そして中村は、「自然のもつ生命そのものに触れる」ことが、体性感覚を優位にすること、あるいは活性化することによって可能になると考えているのである。
[8]一つの点ではなく一つの円であるような私について — 主語的統合と述語的統合
[2]において、僕は西田幾多郎の「場所」という論文を引用することで、次のように宣言していた。主語的統一ではなく述語的統一へ、一つの点ではなく一つの円であるような私について記述したいと思っていると。そして、ようやくここで、僕は「点ではなく円である私」の輪郭を示すことができる。
中村が〈触覚〉を特権的に扱う理由は、彼が〈触覚〉を〈体性感覚〉という筋肉感覚や運動感覚を含めたものとして考えていることを配慮しなければ分からない。〈体性感覚〉は〈触覚〉という表層感覚であると共に、〈筋肉感覚〉や〈運動感覚〉は深層感覚でもあるので、一方では〈視覚〉、〈聴覚〉、〈嗅覚〉、〈味覚〉などと結びついて外部世界に開かれており、他方では〈内臓感覚〉と結びついて暗い内部世界への通路を持っている。〈体性感覚〉は、このように外部世界と内部世界を繋ぐ〈あいだ〉の場所である。知覚を〈五感〉による外界からの感覚刺激だとすれば、知覚は受動的であると考えざるをえないが、現実の知覚は言うまでもなく空間の中での運動を伴っている。対象を触ったり、振ったり、押したり、叩いたりすることで、その対象から情報を引き出している。
佐々木正人は『知性はどこに生まれるか』という著書で、アメリカの心理学者ジェームス・ギブソンのアフォーダンス理論について解説している。そこで説明されるのは運動の中での知覚である。これまでの知覚理論が不動の定点から五感に基づいた受動的な知覚を扱ってきたとすると、ギブソンが扱うのは双方がバラバラに運動する中での知覚である。例えば、眼の前にアルミニウムの1メートルの棒があるとする。これまでの知覚理論であれば、定点から頭も首も固定した状態で観察することが求められ、「この棒はだいたい1メートルである」とか「この棒は、つるつるとしていて硬そうである」とか、五感のどれかに基づいた情報を引き出すことを期待された。しかし、それは僕たちの通常行っている知覚の在り方とは大きく異なる。なぜなら、見るとき、僕たちは身体や首や頭の向きを動かしたりしながら見ているからである。僕たちは眼で見るのと同様の記述情報(長さや硬さ)を、棒を振ったり、押したり、叩いたりすることで、眼をつむっていても引き出すことができる。このように動かすことで、変化の流れの中で変化にもかかわらず、モノの変わらない性質(不変項)を見出すことを、アフォーダンス理論ではダイナミック・タッチと呼ぶ。
ダイナミック・タッチにおいて、環境自体が持続と変化をもったものとして扱われる。その持続と変化の中で、僕たち自身も運動しながら、「変形」と「不変」を受け取ることで情報を得る。先ほどの棒の例で言えば、僕たちは、実際にさまざまな仕方で振ってみることで、その棒を曲げたり折ったりしなくても、どのくらいの力で、どのくらいの遠心で振ると、この棒が曲がるのか折れるのかという、より具体的かつ実践的な情報を掴むことができる。もちろん、そこで得られる情報の質と量は、動かす主体の経験値によって左右される。普段からアルミニウムの棒を扱う仕事をしている人と、初めて触る人では、ダイナミック・タッチから得られる情報に差がある。初めて陶芸をしてみる人と、熟達した陶芸家とでは、泥に触れるときの腕の動きとそれに伴う泥の変化と不変をまったく異なる質で受け取っていることは、実際に陶芸家に会ったことがなくても想像できるはずである。そして、得られる情報は身体との循環構造を作り出す。流れの中で得られた情報によって、身体が制御され、その制御によって、また異なる情報が流れの中から得られるのである。佐々木は次のように言う。
行為の未来をつくりだすことは、行為がじょじょに露わにする環境の変化の中にあるというわけだ。未来、ただし探索する行為がなければ存在しない未来であるが、それは進行している行為が露わにする環境の変化に知覚されている。つまり行為はこれから起こることを「予期する情報」をつくりだしている。行為はそれが探索し、これから発見することになることによって創造されている。佐々木正人『知性はどこに生まれるか』
「制作」とは、実際にやってみることで「未来の情報」を生み出しながら、その次へと進んでいく、あるいは引き返していく往還運動なのである。あらかじめすべての情報が客観的にあるわけではない。未来がある。ただし、探索する行為がなければ存在しない未来なのである。未来は、経験と行為によってそれぞれに創造される。まずは「制作」してみること、そうすることで僕たちは「制作的空間」へと入り込んでいくのだ。
『共通感覚論』が出版された当時、まだジェームス・ギブソンの議論は日本にほとんど紹介されていなかったので、ここでギブソンが参照されることはなかっただろう。にもかかわらず、僕が佐々木の議論を紹介したのは、動きの中での知覚を別の視点からも捉えるためであった。中村はギブソンと同様、身体運動にも焦点を当てはするのだが、これから説明するように、彼の関心の中心は、運動感覚がいかに知覚そのものを生み出す基体として機能しているかという点にある。しかし、「制作」というこのエッセイの目的から言えば、「諸感覚の基体的統合」だけでなく「行為によるそれぞれの未来の創造」という論点は、是非とも紹介する必要があった。視覚中心の知覚ではなく、身体中心の知覚を理解する上で、この二つの側面は外せなかった。一つは「行為によるそれぞれの未来の創造」という点が、「制作」を媒介として「制作的空間」へ入って行くという議論を裏づけるものであり、もう一つは「諸感覚の基体的統合」という点が、「制作的空間」の内部を記述する上で必要だったからだ。
中村はギブソンではなく、ベルクソンの「運動図式」とメルロ=ポンティの「身体図式」の考え方を元に思考する。これまでの議論と「身体図式」の考えを組み合わせることで、「諸感覚の基体的統合」の役割を身体に持たせているのだ。まず「運動図式」とは、「人間の身体は、生の有用性のために組織され習慣化された〈感覚—運動機構〉として捉えることができる。それは、生理学的な意味で、求心性の感覚神経回路と遠心性の体性つまり運動神経回路との連動機構であるにとどまらない。そうではなくて、主体の行動への身構え、つまり能動的な意味賦与の作用、とのかかわりで働くものとしての、そのような二つの回路の連動機構」である。このように「運動図式」を、これまでの五感に基づいた受動的な知覚概念とは異なり、体性感覚とくに運動感覚の全体化の働きのうちに、内部世界の無意識に根ざした、行動への意味と方向を賦与したものであると評価する。他方で、それはまだ人間の身体のもつ受動的かつ能動的という両義性を捉え切れていないと考える。そして、運動感覚をただ単に運動感覚としてではなく、深層の内部知覚として捉え直すために、「運動図式」に加え、メルロ=ポンティの「身体図式」を持ち出すのだ。
「身体図式」は、〈運動感覚〉を表層における外部とのかかわりとしてだけでなく、深層の内部知覚としても捉えるものである。通常、身体の内部知覚は意識の表層には現れない。しかし、それは実存的な身体の本質的基盤であり、しかも外部知覚と連続している。無意識の苛立ちや内臓の機能不全が気分に影響を与え、それが知覚や行動に影響を与えることは、日常的に理解できるものである。「身体図式」は、〈体性感覚〉としての〈運動感覚〉を、外部世界に行為として表層的に関連づけるだけでなく、気分として潜在的にかかわらせている、主体的で可能的な身構えのことを指す。
このようにして、中村は内部感覚としての〈体性感覚〉という点から「身体図式」に着目することで、〈体性感覚〉が知覚あるいは五感の統合の基体であることを示す。〈体性感覚〉は、〈触覚〉、〈運動感覚〉、〈筋肉感覚〉が、すなわち内側と外側が交差的に入り組んだ場所である。そして、その場所は、表層である特殊感覚(視覚、聴覚、嗅覚、味覚、平衡感覚)と深層である特殊感覚(臓器感覚、内臓痛覚)を相渡る場所であり、だからこそ中村は諸感覚(特殊感覚)の体性的統合を〈基体的〉統合とも〈述語的〉統合とも呼ぶのである。
それが〈基体的〉統合だけでなく〈述語的〉統合と呼ばれる理由は、お察しの通り、諸感覚の〈主語的〉統合と言うべきものがあるからだ。これは〈共通感覚〉と〈常識〉の対概念に相当するものである。つまり、僕たちが暗黙の裡に用いている知覚の構造、近代図式、主体—対象—属性という構造が、〈主語的〉統合と呼ばれるもの、そして〈常識〉にあたる。それはもちろん、時代、地域、そして、芸術家の例で見ても分かるように、人によっても異なる。〈常識〉が通じないことがしばしばあるのを思い出せば分かるだろう。そして、〈述語的〉統合は、鏡≒本の空間、デュシャンが切り開いた場所、〈共通感覚〉、そして「制作的空間」のことを指している。〈主語的〉統合が、時代、地域、そして人によって異なるのは、この〈述語的〉統合が別の〈主語的〉統合を「制作」する潜勢力を持っているからである。
私たち人間の諸感覚の統合は、基体的、述語的な統合の上に成り立つ主体的、主語的な統合として考えることができる。そして、主体的、主語的統合は、基体的、述語的統合の基礎の上に成り立つとはいえ、それと同時にひとたび成り立つと、基体的、述語的統合を拘束する働きを持っている。後者を潜在的な基盤として前者が現れる一方、前者によって後者は導かれ、方向づけられる。まさにそのようなものとして、後者は基体的、述語的統合なのであり、前者は主体的、主語的統合なのである。諸感覚の体性感覚的統合が基体的、述語的統合であり、主体的、主語的統合を代表するのが視覚的統合であることはすでに述べたとおりである。中村雄二郎『共通感覚論』
重要な点は、主語的統合は述語的統合の上に成り立つとは言え、ひとたび成り立つと述語的統合を方向づけるようになるということである。つまり、主語的統合が強烈に優位になると、述語的統合が異なる身体を「制作」することを抑制するようになる。人と違うからとか、常識的ではないという理由で、違和感や差異を無視したことは誰にでもあるだろう。
しかし、ここまでの議論で、知覚の在り方そのものを「制作」する場所を、ある程度明らかにできた。僕たちは、西田的に言えば、点でもあり円でもあるのだ。ここから先は、さらに議論を進め、中村が「この風景を分割する印象派の外光描写」と「セザンヌの自然のもつ生命そのものに触れるような運動する体性感覚」という対比で示していること、つまり述語的統合を活性化させることで、「自然のもつ生命そのものに触れる」ということを考えていきたい。
[9]「ロゴス的立場」と「形式論理」が捉えられないもの — 生命、進化、偶然性
ここまで、分離する二元論と同化する一元論という二つの〈あいだ〉の場所について語ってきた。分離する二元論は、自然や生命を記述する際に区分することで、〈あいだ〉をノイズとして切り捨ててしまうし、同化する一元論は、体験によって自然や生命と同化することで「分かる」というプロセスを経るため、その体験を言葉では汲み尽くせないものとして神秘化してしまう。
ここまで僕は、どちらかの立場に偏ることではなく、その〈あいだ〉を維持することを説いてきた。もちろんその立場は変わらないが、今度は中村雄二郎がセザンヌを評して発した「生命そのものに触れる」ということを別の角度から考え直すために、生命を記述する方法や技法について考えていきたい。中村が言うように、〈共通感覚〉の活性化によって、生命そのものに触れる言語が、つまり生命の記述が可能になるなら、その可能性について考えていきたいのである。
しかし、繰り返すようだが、もう僕たちは単に純粋経験を称揚することはできない。一なる者との同化、世界との完全な一致は、今や神秘主義的とかファシズム的と形容されるものの象徴でもある。同様に、分離された二元論の問題も至るところに噴出している。僕たちはピュシス(自然)をロゴスで切り分けるのではなく、別の仕方で捉える技法を必要としている。ここから見ていきたいのはロゴスとピュシスの差異、そして形式論理とレンマ的論理という二つの論理である。
福岡伸一は『福岡伸一、西田哲学を読む』の中で、ロゴスとピュシスの差異について、「ロゴスは、自然を切り分け、分節化し、分類し、そこに仮説やモデルやメカニズムを打ち立てようとする言葉の力、もしくは論理の力である。イデアやメタファーを作り出す力である。一方、ピュシスとは、切り分け、分節化し、分類される以前の、ありのままの、不合理で、重畳で、無駄が多く、混沌に満ち溢れ、あやういバランスの上にかろうじて成り立つ動的なものとしての自然である」と言う。
また、木岡伸夫は『〈あいだ〉を開く』の中で、形式論理とレンマ的論理の違いについて、「Aと非Aの関係は、形式論理における矛盾律と排中律を前提としている。両者にとって〈中間〉は存在しない。これに対して、AとBの関係は、Aがある程度までBと共通する存在であることを容認する。この関係における両者の区別は曖昧であって、両者は分断されることなく、つながりをもつ。この意味において、差異は中間的なものを予想し、異なるものとものの〈あいだ〉が開かれている。このように、レンマ的論理では、世界をどこまでも非対立的で差異的なものの表れとして見る姿勢、すなわちあらゆる存在をさまざまな〈あいだ〉において見ようとする理論的態度が、前提されていると言わなければならない」と言う。
二人がピュシスとレンマ的論理への回帰を必要だと考える理由は、共通している。それは、切り分け、分類する思考法や、矛盾律、排中律を絶対的公理としてしまうことで、二項が互いに作られつつ/作る〈あいだ〉の場所、活き活きとした生命の生成、流れや循環を歪めて解釈してしまう、あるいは思考不可能なものへ変えてしまうと考えているからである。しかし、切り分けることでは捉えられない生命の領域と言われても、何を言っているんだ、と驚く人がいるに違いない。そこで、まずはこの領域が、僕たちの現実的な実践に深くかかわる話であることを示す必要がある。
森田真生は『数学する身体』の中で、「人工進化」という分野での興味深い話を紹介している。人工進化とは、人間が理論的に一から構成したアルゴリズムではなく、偶然性と試行錯誤という進化の仕組みを元に作られたアルゴリズムのことである。例えば、何かしらの最適化問題を解く場合、進化アルゴリズムは初めにランダムな解の候補を大量にコンピュータの中で生成し、目標に照らして相対的に優秀な解の候補をいくつか選び出す。次に、それらの比較的優秀な解の候補を元にして、さらに「次世代」の解を生成する。そして、その操作を繰り返す。つまり、各世代の「次世代」を「変異」させながら、次々と自己複製をさせていくだけなのだが、最初はランダムに選ばれた候補群であっても、上記の操作を繰り返していくと、より目標を達成できるものへ「進化」させることができる。
森田が紹介しているのは、人工進化の研究の中でも少し変わっている、イギリスのエイドリアン・トンプソンとサセックス大学の研究グループによる「進化電子工学」の研究である。通常の人工進化が、コンピュータの中の仮想的なエージェントを進化させるのに対して、彼らは物理世界の中で動くハードウェアそのものを進化させることを試みる。
課題は、異なる音程の二つのブザーを聞き分けるチップを作ることである。人間がチップを設計する場合、これはさほど難しい仕事ではない。チップ上の数百の単純な回路を使って、実現できる。ところが彼らはこのチップの設計プロセスそのものを、人間の手を介さずに、人工進化の方法だけでやろうとしたのだ。
結果として、およそ四千世代の「進化」の後に、無事タスクをこなすチップが得られた。決して難度の高いタスクではないので、それ自体さほど驚くべきことではないかもしれない。が、最終的に生き残ったチップを調べてみると、奇妙な点があった。そのチップは百ある論理ブロックのうち、三十七個しか使っていなかったのだ。これは人間が設計した場合に最低限必要とされる論理ブロックの数を下回る数で、普通に考えると機能するはずがない。
さらに不思議なことに、たった三十七個しか使われていない論理ブロックのうち、五つは他の論理ブロックと繋がっていないことがわかった。繋がっていない孤立した論理ブロックは、機能的にはどんな役割も果たしていないはずである。ところが驚くべきことに、これら五つの論理ブロックのどれ一つ取り除いても、回路は働かなくなってしまったのである。
トンプソンらは、この奇妙なチップを詳細に調べた。すると、次第に興味深い事実が浮かび上がってきた。実は、この回路は磁気的な漏出や磁束を巧みに利用していたのである。普通はノイズとして、エンジニアの手によって慎重に排除されるこうした漏出が、回路基板を通じてチップからチップへ伝わり、タスクをこなすための機能的な役割を果たしていたのだ。チップは回路間のデジタルな情報のやりとりでだけでなく、いわばアナログの情報伝達を、進化的に獲得していたのである。
人間が人工物を設計するときには、あらかじめどこまでがリソースでどこからがノイズかをはっきりと決めるものである。この回路の例で言えば、一つ一つの論理ブロックは問題解決のためのリソースだが、磁気的な漏れや磁束はノイズとして、極力除くようにするだろう。だが、それはあくまで設計者の視点である。設計者のいない、ボトムアップの進化の過程では、使えるものは、見境なくなんでも使われる。結果として、リソースは身体や環境に散らばり、ノイズとの区別が曖昧になる。どこまでが問題解決をしている主体で、どこからがその環境なのかということが、判然としないまま雑じりあう。森田真生『数学する身体』
僕がこの話を引用した理由は三つある。
第一に、それがチップ上の回路という人工的なものであっても、実在の世界は連続的であり、0と1に切り分ける二値論理からトップダウンで判断することによって見逃されてしまう領域が生じることである。自然は連続的で人工物は非連続であると聞くが、そうではない。デジタルに機能するように作られたチップでさえ、連続的なのである。生命はこの連続性の中で、偶然性と試行錯誤によって生成を行なう。しかし、僕たちは視覚中心のロゴスによって「Aと非A」に切り分けてしまう。生命は切り分けることができるわけではなく、余剰部分をノイズとして処理することで、人間にとっての「生命」を「機械」的かつ効率的に捉えているだけのことである。つまり、人工物もふくめてすべては連続的で、それを切り分けて捉える視点と連続的に捉える視点が二つあるだけなのだ。この問題については、後ほど「外在的観察」と「内在的観察」という議論として、改めて取り上げたい。
第二に、トンプソンらがこの奇妙なチップを詳細に調べることで、0と1の外側に置かれていた磁気的な漏出や磁束の機能を見出したことである。この事実は、人間がロゴスや知覚原理の外側を発見できることを示している。もしロゴスに切り分けられた認識の外側にアクセスできないのだとしたら、なぜ37個の論理ブロックだけで機能するのか、僕たちは永遠に解明できない。しかし世界には、現在その人が用いている知覚原理で現象される「強い属性」だけでなく、潜在的な「弱い属性」が満ち満ちており、注意する範囲を変えたり、カメラやレントゲンなどの装置によって知覚範囲を拡張したりすることで、その実在を確認できる。それは、人間が主語的統合だけでなく述語的統合から、別の主語的統合を「制作」することができるという事実を示している。また人間は、自らの生物学的条件に基づいて、可視光の外側にある波長を赤外線や紫外線などと名づけているが、それは他の動物にはない特徴である。人間は道具によって所与の環世界、現象の世界を超えて、実在の存在を確認し、さらにそれを述語的に統合することで新たな身体を「制作」できるのである。
第三に、ロゴスによって切り分けられた世界でのトップダウンの構築よりも、連続性の中での偶然性と試行錯誤によるボトムアップの進化の論理の方が、より最適な解を導き出すことを具体的に例示したかったのである。
[10]ピュシスへの回帰 —「外在的観察」と「内在的観察」
先ほどは、連続性を切り分けることで理解する方法、ロゴスや形式論理では捉えられない領域があることを示した。それは、生命や進化や偶然性として扱われている領域なのだが、他方で僕たちの常識とは異なり、チップなどの人工的だと思われている世界も、実は連続性の世界の只中にあるということを示した。そして部分的ながら、人間がその連続性を捉え記述できる可能性についても示してきた。では、福岡の言う「ピュシスへの回帰」や木岡の言う「レンマ的論理」は、どのような仕方でそれを捉えるのだろうか。
まず、福岡伸一は前出の書で、「生命を定義する時、生命とは細胞をもつもの、遺伝子(DNAもしくはRNA)をもつもの、代謝を行うものというように、属性を列記することでは、本質の廻りを堂々巡りするだけで生命たりえる条件に辿りつかない」と言う。例えば、「ウイルスは、DNA(もしくはRNAを)をもつが、それ自体では細胞をもたないし、代謝も行わない。こんなウイルスは生命といえるのか。それは生命をどの属性で定義するかに関わってくる」と。それは、それぞれの研究者が自らの専門に基づいて複数の属性の中のいくつかを特権化することを意味し、相対主義的な混乱をもたらすことになる。
僕はこのような「主体—対象—属性構造」に基づいた記述スタイルを、「外在的観察」と定義する。これまでの議論からすると、これは主語的統合の近代バージョンである視覚を中心化した認知の在り方と同義である。同書において、福岡と対談している池田善昭も、上記のような議論は「生命を外部の視点(立脚点、着眼点)から存在として見ている」だけだと批判し、より正確に判断しようとするなら、生命の内側から生命自体になりきってなされなければならないと述べる。そして、それが実在として生命を捉える方法であると言う。
この「生命になりきって内側から捉える」という表現には、どこか同化的な一元論の匂いがする。しかし、ここでの「内側から見る」というのは、構造でもあり流れでもある状態を捉える方法を指しており、福岡はそれを「動的平衡」という概念で提示している。「動的平衡」とはルドルフ・シェーンハイマーが名づけた言葉であるが、福岡は「福岡伸一の生命浮遊」という連載の中で、このように語っている。
シェーンハイマーは、同位体を使って生体物質の動きを可視化し、私たち生物が食べものを摂取することの意味を問い直した。一般に、生物にとって食べものとは、自動車にとってのガソリンと同じ。つまりエネルギー源だと考えられていた(今もそう捉えている人は多い)。
しかし実はそうではない。確かに食物(主に炭水化物)はエネルギー源として燃やされる部分もあるが、タンパク質は違う。私たちが毎日、タンパク質を食物として摂取しなければならないのは、自分自身の身体を日々、作りなおすためである。シェーンハイマーはこの事実を鮮やかな実験で初めて示した。
たとえば私たちの消化管の細胞はたった2、3日で作り替えられている。1年も経つと、昨年、私を形作っていた物質はほとんどが入れ替えられ、現在の私は物質的には別人となっているのだ。つまり、生命は絶え間のない分子と原子の流れの中に、危ういバランスとしてある。私が自らの生命論のキーワードとしている「動的平衡」である。それまで静的なものとして捉えられてきた生命観に、シェーンハイマーは、新しいパラダイムシフトをもたらしたのだ。
動的平衡の流れを作り出すためには、作る以上に壊すことが必要である。それゆえ細胞は一心不乱に物質を分解している。福岡伸一「福岡伸一の生命浮遊」
福岡は、生命は「この流れの中の危ういバランス」としてある、と言う。ここでいう流れとは、作るために壊すことであり、壊すことで作ることである。僕がここで、食べることを中心に「動的平衡」を説明した部分を引用した理由は、食べることという日常的な行為の意味が、不動のAという個体にエネルギーを外部から加えることから、Aが常に非Aへと変化しながらAであることを保つことへと、意味が転回するからである。ここで福岡が「危ういバランス」と言うのは、Aは非AになりつつAであるということが、非AになりつつAでないものになる可能性を常に孕んでいるからである。食べることという、とても日常的な行為でさえ、危ういバランスの中でなんとか自己同一性を維持している、非常に危険な行為なのである。
福岡は『生物と無生物のあいだ』で、「もし、やがては崩壊する構成成分をあえて先回りして分解し、このような乱雑さが蓄積する速度よりも早く、常に再構築を行うことができれば、結果的にその仕組みは、増大するエントロピーを系の外部に捨てているということになる」と言い、「流れこそが、生物の内部に必然的に発生するエントロピーを排出する機能を担っていることになるのだ」と書く。そして、「生命がエントロピー増大の法則に抗う唯一の方法とは、生命システムの耐久性と構造を強化することではなく、むしろ、そうした仕組み自体をエントロピーの流れの中に置くだけのことだった」と述べるに至る。
なぜか僕たちは、明日も、明後日も、明々後日も、同じ身体をもち、自己同一性を保ち続けることができると信じている。しかし、物質的には1年も経つと、僕は僕ではない。僕は自らを分解することで自らを構築し、自らを構築することで自らを分解する「流れ」である。そして、この「流れ」の中で構造を維持するためには、「私は私である」という自己同一性の耐久性や構造を強くするのではなく、エントロピー増大の法則による乱雑さが構造の維持を不可能にしてしまう前に、先回り的にその同一性を部分的に分解し、そして構築する必要があるように、「私は私でなく」(分解)、「私は私でなくもない」(構築)という「流れ」の中に身を置くことになる。こう言うと、言いすぎだろうか。生命は、物理的な法則を先回り的に捉え、分解と構築のリズムによって、その流れに乗ることで自らを維持している。それは、過去から現在へ、そして未来へと流れる線的な時間(エントロピー増大の法則)を内側に取り込むことで、未来から現在へと流れる時間を生み出すことであろう。なぜなら、乱雑さが増大する時間の流れを先回り的に捉えて、つまり未来を捉えて、現在において分解と構築を行っているのだから。
池田善昭は『福岡伸一、西田哲学を読む』の中で、「時間というものは過去から未来へと線的に流れるだけじゃなくて、向こう(未来)から(回って)くる時間もある」と言う。そして、このような生命の捉え方を、福岡は「内側から見る」と言っている。外側から、生命をAであるとかBであるとか切り分けることで静態的に定義するのではなく、外側の流れ(エントロピー増大の法則)と内側の流れ(分解と構築のリズム)が相互に包摂し合いながら、Aは常に非AになりながらAであるという不安定な状態を保つ構造体として、生命を捉えること。同一性ではなく、変形と流れの中で、つまり時間の中で生命を捉えること。このエッセイでは、このように流れに身を置くことで内側から生命を捉える方法を、「内在的観察」として定義する。
[11]〈あいだ〉を切り捨てず、〈あいだ〉を捉えること — レンマ的論理について
「中間」、〈あいだ〉を考えようとするレンマ的論理と、中間的なものを認めないロゴス的論理の対蹠点は、〈生〉をいかにとらえるかにある。生(ないし生命)の領域は、形式論理の同一律および矛盾律にもとづく弁別・分別を受け付けにくい独特の性格を帯びている。無生物の世界に妥当する、Aか非Aかの二者択一に対して、Aでも非Aでもないといった中間的で曖昧な様相を呈するのが、生きたものの世界だからである。木岡伸夫『〈あいだ〉を開く』
僕がレンマ的論理に注目する理由は、ロゴスによって捉えられない生命の領域を、純粋経験によってではなく、その体験を媒介に、別の言語によって捉える方法を考えるためである。流れに内在化するというのは、そのための第一歩なのだ。中村雄二郎は〈体性感覚〉の活性化を推奨したが、〈体性感覚〉が活性化した後、どのような言語がそこに現れるのか、僕はそれを考えたいと思っている。ヒントになるのは、ロゴス的論理に代えて、木岡伸夫がレンマ的論理としてまとめる山内得立の思想である。ここにはまさに、鏡≒本の空間、「制作的空間」を記述するための論理が隠されているように思えるからだ。
山内がテトラレンマの形に仕上げたのは、大乗仏教を代表する龍樹(ナーガールジュナ Nāgārjuna)による『中論』(Madhyamaka-kārikā)の根本思想である。後に詳しく見ることになるが、『中論』の核心的主張は排中律の逆転にある。
これらは「AでもなくĀでもない」という仕方での二重否定をつうじて、独特な「中」の境域を開く論理を表している。しかし、排中律の逆転だけなら、伝統的なインドの四論(四句分別)にも見られる。それは、①A、②非A、③A亦非A、④非A亦非非A、の順に立てられ、第三レンマが二重否定を表し、第四レンマが二重否定の形をとる。
これに対して山内は、四句の配列を変えるべきであり、両非(④)が両是(③)に先立つ形式こそ、レンマ的論理体系でなければならないと主張する。なぜなら、龍樹が革新的であったのは、素材としては古代インドの論理形式にほかならない四論を解体して、「AでもĀでもない」両非の第三レンマを柱とする新たなテトラレンマを構築した点にある、と解釈されるからである。
一 A(肯定)
二 Ā(否定)
三 AでもなくĀでもない(両非)
四 AでもありĀでもある(両是)龍樹の立場は、「AでもなくĀでもない」第三レンマを中心とする否定の論理である。それは、肯定を否定し、その否定をまた否定することによって肯定に還る、という意味の二重否定ではない。肯定も否定もともに否定することによって、〈肯定—否定〉の対立そのものを否定するという「絶対否定」である。木岡伸夫『〈あいだ〉を開く』
ここで木岡は「AでもなくĀでもない」両非こそが、テトラレンマを一つの論理とするための鍵を握ると言う。「論理とするために」という言葉が重要である。なぜか。それは山内が、「AでもĀでもある」という両是が先行する四論の形式は一種の直観知ではあっても、それを「論理」と呼ぶことはできない、と考えたからだ。山内はこのように考えることで、鈴木大拙が説くような、非AであることがそのままAであるとする類の「般若即非の論理」を、非論理として一刀両断に斥ける。それは、僕がここまで展開してきた議論で言えば、純粋経験をそのまま称揚するような仕方を退け、二元論と一元論の〈あいだ〉になんとか留まり、そしてその場を記述するという危険なサーフィンを続けることなのだと思う。
しかし、僕は、この龍樹のテトラレンマを組み替える形で作られた山内版テトラレンマには弱点があるように思う。ここまでの議論で、僕が「制作的空間」に入るには「制作」を媒介にするしかない、と言っていたことと同じなのであるが、山内のテトラレンマでは、一度純粋経験へと降りていく媒介が存在しないように思えるのだ。サーフィンをするためには、まず海に入らないといけない。陸サーファーが言葉の上で、「サーフィンというのはねー」といくらでも言葉を紡ぐことはできるが、形式的なことは言えても制作的なことは何も語れないだろう。まずは海に入ること、そしてそこから、ボードの上で初めて波との対話が始まるのである。
では、そもそも山内版テトラレンマではなく、その元である龍樹のテトラレンマとはどのようなものなのだろうか。清水高志は『実在への殺到』の中で、カンタン・メイヤスーの〈素朴実在論者〉、〈弱い相関主義者〉、〈強い相関主義者〉、〈思弁的哲学者〉という四項を説明する上で、龍樹の『中論』におけるテトラレンマを用いている。
『中論』の第十八偈に現れる典型的なテトラレンマ(四句分別)では、最初に①「すべては真実(如)であるという命題が語られ、次に②「すべては真実でない」という命題が述べられる。①は素朴に現実の世界を信じる者の見方であり、②は現象はすべて一刹那の後には変化するという洞察をもったものの見解である。そして三番目に③「すべては真実であり、かつすべては真実でない」という命題が述べられる。つまり、①のような素朴なものにとっては真実であり、修行をして②のような見解をもったものには真実でない、というのである。
しかしこれらは、ある刹那の次の刹那に起こることにいずれも依存したものなので、第四の命題④「すべては真実であるのではなく、かつすべては真実でないのではない」が説かれなければならない。仏教ではなにか対象を否定するとき、次の対象が浮かんでくるような否定、対象のあり方にその都度左右される否定を相対否定と呼び、そうでない否定を絶対否定と呼ぶ。「空」が理解されるのはこの絶対否定によるとされるが、③まではいずれも否定対象の状況に依存した、相対否定によるものである。それゆえ④では、③そのものが否定され、何らかの対象に依存しない(無自性な)かたちで、③の不可知論自体がさらに転倒されねばならない。④の命題は、なんらかの対象について語られるわけではないが、すべての対象について真実なことが述べており、「空」の立場からこうした否定を行う何者かも、また確かなのである(真如の確立)。清水高志『実在への殺到』
ここまで繰り返し出てきた鏡とミメーシスの論理、「Aでなく、Aでなくもない」という二重否定を、仏教では絶対否定と呼ぶ。木岡はそれを、一種の直観知であっても論理とは呼べないと言った。単に体験をベースにした「制作的空間」を上位のものとし、「日常的知覚」を下位のものとするような言葉では、確かに論理と呼べないだろう。しかし、清水がこの後に、「メイヤスーが、現実世界の法則の安定性への疑念だけを語っていると考えるのは、ナーガールジュナの空論が虚無ばかりを語ったものだと考えることと等しい。彼らの思想は、むしろ大いなる肯定の思想へと繋がるものなのだ」と書くように、この絶対否定、二重化の運動、制作的空間は、体験による暗き底へと降りていくときの危険で不安定なリズムを、サーフボードで波に乗るように乗りこなすことなのである。つまり、絶対否定自体を肯定するのではなく、その不安定さを乗りこなすこと、それこそが絶対否定が肯定だと言う意味であり、清水の挙げた①の素朴実在論者でいることが肯定的なのではない。また、相対否定の中でポジショントークを繰り広げるスキルを磨くことが、肯定に繋がるわけでもない。それは現状維持的であり、制度肯定的なのであって、一つ一つの生命を肯定するわけではないのだ。
ここまでの議論を整理すると、素朴な肯定から相対否定へ、そして絶対否定へと降りていった後に、それを一種の直観知で終わらせず、一つの論理とするためにレンマ的論理があると再定義できるように思う。つまり、まずは龍樹—清水テトラレンマで絶対否定に辿りついた後に、龍樹—山内テトラレンマによって、直観を論理へと記述しなければならないのである。
実際、『ロゴスとレンマ』が参照する『中論』の核心的主張は、排中律を逆転する〈中の論理〉にある。そして、『中論』に具体化された〈中の論理〉の核心は、龍樹—山内テトラレンマの第三レンマ(二重否定)から第四レンマ(二重肯定)への転換であり、それを山内は「即の論理」と呼んでいる。一見、山内の議論の問題は、四項に収めなければならないという強迫観念ではないかとさえ思う。そもそも「即の論理」さえあれば、龍樹—清水テトラレンマでも二重否定から、即、二重肯定へと転換することになっているので、安直に第五レンマとして、二重肯定を設定すればいいと考えてしまいそうになる。あるいは、第五レンマなど必要ではなく、二重否定即二重肯定なのだと、直観的に分かればいいとも言いたくなる。しかし、山内の悩みは、まさにこの「即の論理」がはたして論理と呼べるものなのだろうかということに端を発しているのである。
山内を悩ませたのが「即の論理」であったことは間違いない。繰り返すと、なぜなら彼は、直観知ではなく論理を示すことを目標としていたが、「即の論理」における否定は弁証法のような媒介作用ではなく、もちろん前提から演繹できるような推論でもないからだ。二重否定から二重肯定への移行は、即時に成立する直接的な体験、直観的で具体的な事実としか考えられないのである。もちろんこれまで見てきたように、このような二重否定から二重肯定へという「即の論理」は、描くこと、書くこと、そして狩ることなど多くの場面で見られる経験である。しかし、そこに成り立つ直接的な知は、はたして「論理」の名に値すると言えるのだろうか。
山内は『ロゴスとレンマ』の中で、「即とは分かたれたものが同時にあり、分かたれてあるままに一であることである」と言う。木岡伸夫は前出の書で、この発言を元に、ロゴス的論理とレンマ的論理が前提とする論理空間の違いについて次のように述べる。
弁証法における媒介が時間の作用として考えられているのに対して、否定と肯定の両立は一つの空間を必要とする。対立する二項を、時間における矛盾ではなく空間における差異として見るとき、上の第三・第四レンマのあいだに不即不離の関係が生じる、と考えて不都合はないだろう。矛盾律・排中律は、生成を時間の相のもとにとらえるという大前提において、存在理由をもつ。それとは反対に、空間的な観点に立つことによって、時間的見地からは両立しがたいものの並立が可能となる。たがいに矛盾対立するものの両立する論理空間が、そこに成立することによって、「即の論理」は〈中間を開く〉と考えられる。
ロゴス的論理は、存在と存在の根拠としての原因、つまり別の存在を区別する。物の存在を根拠づけるとされるのは、ふつうの物ではない特別な存在、つまりは神である。したがって、存在と非存在が同列に立つなどということはありえない。これに対してレンマ的論理は、存在の根拠を無とすることによって、存在と非存在、有と無を、不即不離の関係においてとらえる。これは、存在を「物」ではなく「事」として考える立場である。AとĀが区別されつつ同時に成り立つ根拠が考えられ、それは「非」と呼ばれる。「即」が成り立つのは「非」によってであるから、「即の論理」は「即非の論理」でなければならない。
西洋起源の形式論理が、排中律によって中間的なものを否定するのに対し、「空の論理」は対立する二者の中間を容認する。しかしその立場は、存在を無からとらえる存在否定の立場であり、それも単に有を否定する無にとどまらず、その否定をも否定する「絶対否定」の立場である。木岡伸夫『〈あいだ〉を開く』
ここで木岡が言っていることは、「即の論理」を論理として捉えられないのは、矛盾するものが並置している空間を前提にしていないからであるということだ。鈴木大拙に頻繁に見られる「Aは非AであるからこそAである」という般若思想を、山内が反論理的と厳しく指弾したことは、すでに記述しておいた。山内は、このような逆説が成り立つ根拠について、「般若の思想において存在と非存在とが同一視せられるのは決して論理的にではなく、むしろ場所的に近接しているからである……存在することは決して存在しないことを原因とするのではなく、存在と非存在とが直観的に近接しているところから両者が結合するのである」と言う。つまり、「場所的に近接している」ことが直観的に把握されるが故に、存在と非存在とが同一であるとされているだけであり、論理的ではないと言うのである。
しかし、山内はそれを直観ではなく論理として扱う術を見出す。そこには絶対否定が関係する。これは相対否定にとどまらず、肯否の区別がそこから生ずる根源的な無、「絶対無」である。この点に注目しよう。山内は「レンマ的無はロゴス的有無を超越して、それらを共にその中に成立せしめる」と言う。これは非常に興味深い指摘である。僕たちは〈常識〉を生成するものとしての〈共通感覚〉、〈主語的統合〉を制作する〈述語的統合〉をすでに見てきた。つまり、ここで山内が言っているのは、有無の区別によって成り立つための根拠がレンマ的無であり、それは「否」や「不」ではなく「非」であるということだ。山内は「非は肯否の合一であるのではなく、むしろ、肯否の区別がそれ(「非」)から発源するか、または少なくとも、それ(=「非」)を根拠とするか、そのいずれかのものでなければならない」と言う。
ここまで僕たちが議論してきたことと重ねて解釈すれば、絶対否定の場所とはまさに「非」であり、鏡≒本の空間であり、〈共通感覚〉であり、それらをまとめて僕が「制作的空間」と名づけた場所であった。山内はここで、鈴木大拙が言い表したような般若思想の直接経験の賛美を超えて、「非」を肯否の区別の根拠として位置づけている。彼が言う論理性は、ロゴス的論理ではなく、この「非」の場所における論理なのである。
さて、ここで木岡が言う時間的見地というのは、因果律にもとづいた単線的時間概念であり、福岡がピュシスとして捉えた流れとは異なるわけだが(なぜなら、生命はこの因果律を先回り的に捉えて分解と構築を行なう)、その時間的見地では、Aは何かの結果であり原因である。A → B → Cと因果律に基づいて連鎖していくことが前提とされている。そして、その始まりとして神がある。しかし、存在と非存在、有と無が並立する空間を前提に思考すれば、即の論理は論理として扱うことができるのだ。もちろん「即の論理」さえ、即、「非即の論理」であるわけだが。
とは言え、この違いをこれだけで理解するのは難しいため、補助線を引くことにする。例えば、岩田慶治は『アニミズム時代』の中で、この二つの考え方を「因果性」と「同時性」と定義している。「因果性」とは、今言ったように、原因と結果の連鎖として世界を捉える立場である。そこでは対象はすべてバラバラになっており、有と無は同時に存在しえない。そして「同時性」とは、「A即非A、非A即A」として捉える立場である。ここで岩田が「同時性」として描いたものは「即の論理」に違いないのだが、興味深いことに、自然科学者である福岡伸一が言っていた生命の時間も、まさにこの「同時性」の時間のことなのである。
生命は、上述したように、エントロピー増大の法則が生命構造を維持不可能にする前に、先回り的に自らを分解し、そして構築する。そこで起こっているのは、分解即構築、構築即分解という絶え間ない流れである。食べ物の例で説明したように、AがAであることを維持するという意味で食べることを捉えると、Aが動けることの原因であり、Aが動けることはその結果である。しかし、実際に起こっていることは、Aを構成している要素を絶え間なく分解し、それを絶え間なく構成する流れである。食べることは、この流れの中で起こる要素の入れ替えなのであって、それは「因果性」ではなく「同時性」として考えなければ捉えられない。言い換えれば、僕たちは「死につつ、生き、生きつつ、死んでいる」のである。そして、それこそが生きることなのだ。福岡は、それを自然科学の中で、「同時性」の論理、「即の論理」として捉えたのである。中村元と紀野一義が翻訳した『般若心経・金剛般若経』には、こんな一節がある。
かれらは生きているものでもなければ、生きているものでないものでもない。それはなぜかというと、スブーティよ、「〈生きているもの〉というものは、すべて生きているものでないということだ」と如来が説かれているからだ。それだからこそ、〈生きているもの〉と言われるのだ。『般若心経・金剛般若経』
[12]「即の論理」と「中の論理」にまたがる縁起思想
木岡伸夫は、「空の論理」が縁起の構造と結びつくことによって、初めて〈中の論理〉がその実質を備えると言うが、これはすでに、このエッセイで鏡の空間における人格性というテーマで論じたこととかかわっている。つまり、「私はあなたではなく、あなたでなくはない」という二重否定によって、私はあなたの中に私を部分的に見出す。それ故に、私はあなたの人格性を否定できない。これはあなたがエルクであろうが、熊であろうが同様である。文化的水準が低いから、ユカギール人が動物に魂や人格性を賦与するのではなく、ミメーシスによって「鏡の中に降りていく」が故にそうなのであった。では、山内にとって、空の論理と縁起思想はどのように結びつくのだろう。
すべての事物が縁起的関係においてあるということは、それ自体としての本質(自性)をもたない、すなわち空であるということだ。山内は『ロゴスとレンマ』にて、「一つの事物がそこに存在するのはそれ自らによってではなく、他に依って、他を持って、他との関係に於て存在すると考えるのが中論の立場であった」と説明する。そして、その縁起的関係と無自性を理解する上で、木岡は『ロゴスとレンマ』の第十章「火と薪との考察」(「燃焼可焼品第十」)を取り上げて、説明する。
火と薪の関係は、同一でもなく別異でもない。もしこの二つが同一なら、薪に点火する必要はなく、火は絶えず燃え続けるであろう。しかし、火と薪がまったく別のものであるなら、どうして火を薪に点じることができるだろうか。火と薪は同一でもなく、異なったものでもないからこそ、火が薪に点じて燃えるということが起こりうる。
火が現に燃えつつあるとは、どういうことか。薪が薪として燃えることはなく、火は単に火として燃えることもない。火が薪に点じられることによってはじめて燃えるということは、それぞれがたがいに他を待って、他に依って、自己の存在を表すこと(相依相待)を意味する。しかし、両者が相待的である関係において、火と薪は別々のものでなければならない。火は火として、薪は薪として、それぞれの自性をもたなければならない。しかし、そうした自性にとどまるかぎり、両者は独立であって燃えることは生じない。火と薪は自性を有しながら、また自性を失わなければならない。自性をもつと同時に自性を失うことによって、すなわち火が火として、薪が薪としての同一性を保つとともに、その同一性を失うことによって、はじめて両者の関係 —— 燃焼の事実 —— が成立する。
燃焼の事実において、火と薪はそれぞれの独自性を失って結合し、一体化する。火と薪は相互に依存しつつ、相互肯定的な関係にある。しかるに、火が燃えていくとは薪を減少させていくことであり、逆に火が消えかかっていくとは薪の減少が否定されることである。つまり、火の肯定は薪の否定を、火の否定は薪の二重否定つまり肯定を意味する。これは、最初の相互肯定とは異なり、一方の肯定が他方の否定につうじるという反対の関係、矛盾的対立というべきあり方を示している。
さらに、火がいっそう燃え盛っていった場合、薪は小さくなる。火の肯定、薪の否定が進行して、ついに薪が燃え尽きたとき、薪は完全に否定される。しかしそれは、火の肯定ではなく、火の消滅を意味する。これは、火の側からすれば、自の肯定、他の否定が、自己否定にゆきつくということにほかならない。その反対に、火勢が弱まり消えかかっていくならば、火の否定が薪の肯定につながることになる。しかし、もし火が消えてしまい、火の否定が成就したならば、そこには薪もまた存在せず、ただ木片が転がっているに過ぎない。こうして自己否定の極にゆきついたなら、それと同時に、矛盾対立の関係にあった他も滅び去る結果となる。
この例を見れば分かるように、対立する二者の肯定—否定の関係は複雑である。単純な二値論理の世界では、一方の肯定は他方の否定であり、他方の肯定は一方の否定である。ところが、一方が自己の肯定(他方の否定)を強行したとき、それが他方の消滅を生じさせることによって、自己も消滅せざるをえない結果を生む。逆に、自己の否定がゆきつくところは、他者の全面肯定のようでいて、他者否定の結果を生む。「相互対立における両者は、対立を残していないかぎり、自ら自己を滅ぼしてしまう結果を招く」(『ロゴスとレンマ』)ことになる。木岡伸夫『〈あいだ〉を開く』
ここまで読むと、なぜ僕が論を進めるにあたって、レンマ的論理を紹介しているのかが理解できるだろう。ロゴス的論理は外側から事物を眺め、AであるとかBであるとかCであるとか定義することで切り分け、原因と結果の連鎖によって、必然的な関係の中に整理してしまう。薪と火の関係であれば、木に火をつける(原因)、すると燃焼が生じる(結果)。しかし、レンマ的論理は、その只中で起こっていることについて「内在的観察」を行なう。薪と火の関係は相互依存的であり、薪でありつつ火であるという状態を維持しなければ、相互に消滅する危ういバランスの中にある。そして生命とは、そのような相互依存的なバランスの中での流れであった。だから、それを捉える「内在的観察」の技法、そして「レンマ的論理」が今求められているのである。
ここに、前出の森田真生『数学する身体』で紹介されていた例がある。とある大学で、マグロロボットを作るというプロジェクトが立ち上がった。実際のマグロは驚くべきスピードで泳ぐので、そのマグロの「泳法」の秘密を解明して、潜水艦や船の設計に活かそうという目的だ。科学者たちがマグロの泳法を調べる過程で、ある興味深い仮説が浮かび上がった。マグロは自らの尾ひれで周囲に大小の渦や水圧の勾配を作り出し、その水の流れの変化を活かして推進力を得ているというものだ。ロゴス的論理で作られた船や潜水艦にとって、海水はあくまで克服すべき障害物である。そこには海水があり船があるという切り分けの論理が働いている。しかし、マグロは周囲の水を、泳ぐという行為を実現するためのリソースとして積極的に活かしている。燃焼が薪と木の〈あいだ〉のバランスによって生じる現象であるとすれば、遊泳は海水と動きの〈あいだ〉のバランスによって生じていたのである。
ロゴス的論理ではAとBは別のものとされ対立し、克服すべきものと捉えられるが、生命は環境との相互作用の上で生きている。マグロにとって周囲の水の流れは、運動のためのリソースであって障害ではない。森田は次のように言う。「生物は機械と違い、環境の中を生き残ってきた進化の来歴を背負っている。ロボットにとって環境はあくまで『解決すべき問題』かもしれないが、生命の方は、環境を『問題』と片づけてしまうにはあまりにもそれと深く交わっている」と。すべての事物は、本質あるいは実体として切り分けられるわけではない。あるいは切り分けて考えてしまうと、本質を掴み損ねる。泳ぐという行為一つを取ってみても、切り分ける思考だけでは捉えられないのだ。
仏教では、完全に独立した自己存在をもたず、他のすべてと関係し合う在り方が、そのものの無自性、すなわち空を意味する。そのように相互依存的かつ相互排除的な両面をもった「相依相待」の関係が、縁起の構造である。ロゴス的論理によって捉えられないものを、西欧では生命を内側から見ることで捉えようとしている。マグロの泳法は、その一例である。しかし、東洋はもともとレンマ的論理を持っていたはずであり、「内在的観察」を得意としていたはずだ。今、レンマ的論理が求められているというのは、「外在的観察」と「内在的観察」という二つの様態があるという哲学的関心からの主張ではなく、実践的に有効であると考えているからなのだ。
[13]形の論理と二種の〈あいだ〉— 垂直的と水平的
ここまでの議論を、「因って」(原因)、「依って」(縁起)、「由って」(理由)という三種の「よって」を通じて、整理することができる。自然科学の因果関係と「主語的統合」は、物事の「原因」と「結果」を追究し、「私が対象を見る」という記述を可能にし、「私は私である」という自己同一性を強化することで、第一の「因って」を保っている。大乗仏教の空観、鏡≒本の空間、狩りの様態、「述語的統合」、すなわち「制作的空間」では、第二の「依って」が表す一と他の相依相待、つまり「縁起」の関係、私の二重化、ミメーシスの眩暈、「私は私でなく、私でなくもない」という私と非—私の不安定な統御、そして五感の組み替えによって、「主語的統合」を可能にする場が示された。第三の「由って」が表すのは、存在の根拠が存在でも非存在でもなく、それらの根源たる「非」、絶対無にあることが明らかにされた。そして、その「非」の場所から、肯定と否定が現れるのであった。それは、これまであまり指摘されることのなかった「制作的空間」への媒介、つまり一歩目の「制作」という側面である。まず、この「由って」を経ることで、僕たちは肯定と否定が現れる場所、主語的統合を生み出す場所、常識が生成される場所、そして身体が新たに編成される場所に立つことができるのである。
しかし現代において、最後の「由って」からはファシズムの香りがしなくもない。事実、木岡も「絶対無という言葉で飾ってはいるものの一なるものへの回帰なのではないかという疑問が頭をよぎる」と言っている。山内は「存在が無根拠であることによって、自由が成立し、存在の自覚が生まれる」と、ハイデガー風のことを言ってしまうので、なおさらである。この垂直上の〈あいだ〉、存在と存在の根拠の〈あいだ〉を、山内はどのように捉えていたのか。木岡は「存在論的な水準を異にする二者を結ぶ中間者は考えられるのか」と言う。そして、山内が最後に辿りついた〈形〉の論理について、「この問いに対する彼の答えは、中間者は〈存在〉ではなく〈形〉であり、形の世界において〈一〉と〈多〉の統一が実現する —— そこに働く論理は存在の論理ではなく表現の論理である」と言うのだ。
〈型〉はそれ自体、存在と非存在の領域にまたがることを含む概念である。それは、多様なものの〈形〉の中から、統一的な意味として浮かび上がる、そのかぎりで具体的な存在性をもつ。それを現実化しようとすれば、存在するいずれかの〈形〉によって表現されるほかない。そのさい〈型〉は、そこに存在する〈形〉とは異なるものの、その〈形〉をつうじてのみ窺い知られる根源的な何か、つまりは表現する働きを意味している。
いま「表現する働き」と言ったが、それは〈もの〉ではない。ものに具わる〈形〉を透かしてその背後を窺うがゆえに、われわれはそこに実体的な〈もの〉を見ようとする。しかしそこにあるのは、働きとしての〈こと〉、つまり表現作用のみである。存在の根拠を存在に見立てようとするこうした思考に対して、現れるのは存在ではなくその幻に過ぎないということを、まさに〈型〉(かた=痕跡)という語が示している。
〈形の論理〉を構成する〈形〉と〈型〉の関係において、二者はいずれもが他方から規定されるとともに、自己から他を規定するという、相反する二重の面をもつ。〈型〉は〈形〉を生み出し、つねに〈形〉に先んじて存在する。しかし〈形〉は〈型〉によって規定されるばかりでなく、自己を創造し、かつそれをつうじて〈型〉をつくってゆく自由を有する。このことを縁起思想に則って、〈型〉と〈形〉の相依相待と呼んでもよいだろう。
つまり、西洋哲学の根本前提である「存在するものは、すべてその根拠である存在(神)から生まれた」という存在論的命題を換骨奪胎しているのである。木岡伸夫『〈あいだ〉を開く』
驚くべきことに、ここで言われている〈型〉と〈形〉の論理は、すでに「制作的空間」として述べたような、〈型〉という〈常識〉と〈形〉という〈共通感覚〉の相互包摂関係にほかならない。ここでも「制作」は、やはり存在と存在の〈あいだ〉で行われる。僕たちは、そこで作りつつ、作られ、作られつつ、作る。ますます確信をもって、僕は恐怖に打ち勝つことができそうだ。僕たちは、まず一歩を踏み出し、降りていかなければならない。今、僕たちが絶対的だと思っている視覚中心の「主語的統合」という〈型〉は、中世においては聴覚中心の「主語的統合」であった。それは近代以前の芸術家たちが作り上げた身体が一般化したものにすぎない。降りていかなければならない。その場所は、魅惑と危険に満ち満ちた鏡と模倣の空間である。そこで再度、僕は僕の身体を作り上げる。もう一度、身体の内へと進もう。〈体性感覚〉を活性化しなければならないのだ。
[14]芭蕉、道元、岡潔の身体へ
ここで森田真生が紹介する松尾芭蕉と道元、そして彼らについてコメントしている岡潔について語っていきたい。それによって、本論を再び整理する。そして、体性感覚を活性化させる方法について、再度考えていきたいのである。まずは簡単に、森田の議論を通じて、僕のこれまでの議論を振り返ることにしよう。
芭蕉の句は「生きた自然の一片がそのままとらえられている」ような気がする、と彼は言う。
たとえば、
ほろほろと山吹散るか滝の音
という句があるが、これなどは「無障害の生きた自然の流れる早い意識を、手早くとらえて、識域下に映像を結んだ」ためにできたのだろう、と岡はエッセイの中で書いている。
「ものの見えたる光いまだ心に消えざるうちにいいとむべし」とも言った。芭蕉の方法には「もの二つ三つ組み合わせて作る」アルゴリズムはない。芭蕉の句は、ただ芭蕉の全生涯を挙げて「黄金を打ちのべたるやうに」して導出される。その「計算速度」は、まさに電光石火の如きである。
芭蕉の意識の流れが常人よりも遥かに速いのは、彼の境地が「自他の別」「時空の框」という二つの峠を超えているからだと、岡は考えた。過去を悔いたり、未来を憂いたり、人と比べて自分を見たり、時間や空間、あるいは自他の区別に拘っていては、それが意識の流れをせき止める障害となる。逆に、そうした区別にとらわれなければ、自然の意識が「無障害」のまま流れ込んでくるというのである。
生きた自然の一片をとらえてそれをそのまま五・七・五の句形に結晶させるということに関して、芭蕉の存在そのもの以上に優れた「計算手続き」はない。水滴の正確な運動が、水を実際に流してみることによってしかわからないのと同じように、芭蕉の句は、芭蕉の境地において、芭蕉の生涯が生きられることによってのみ導出可能な何かである。森田真生『数学する身体』
ここで語られる、芭蕉の「自他の別」「時空の框」という二つの峠を超えているという状況は、まさに「AはAである」という状況から「AはAではなく、Aでなくもない」という状態への移行を指す。狩人は森の中でヒトの言葉を話さない。なぜなら、それはミメーシスを通じて鏡の空間に入るための重要な儀礼だからだ。自己同一性を外す技術は多数ある。画家は「描くこと」「見ること」を通じて、鏡の中へ降りていく。作家は「書くこと」「読むこと」を通じて、降りていく。芭蕉も、自己同一性の区別を外す。そうすることで、生きた自然の一片を捉えて、そのまま五・七・五の句形に結晶させる。そこで用いられるのは、ロゴス的論理ではなくレンマ的論理であり、「内在的観察」である。これは単に、自他の区別が無い状態を作ればよいということではない。彼の身体が、その結晶化の基体なのである。〈述語的統合〉を活性化すること、それぞれの身体を作ること、それが「制作」であるというのは、まさにこういうことなのだ。芭蕉は俳句という〈形〉を制作することを通じて〈型〉を作る。とは言え、最初は芭蕉も〈型〉の元にあったのである。作りつつ、作られること。まさに「制作的空間」の中で。
道元禅師は次のような歌を詠んでいる。
聞くままにまた心なき身にしあらば己なりけり軒の玉水
外で雨が降っている。禅師は自分を忘れて、その雨水の音に聞き入っている。このとき自分というものがないから、雨は少しも意識にのぼらない。ところがあるとき、ふと我に返る。その刹那、「さっきまで自分は雨だった」と気づく。これが本当の「わかる」という経験である。岡は好んでこの歌を引きながら、そのように解説をする。
自分がそのものになる。なりきっているときは「無心」である。ところがふと「有心」に還る。その瞬間、さっきまで自分がなりきっていたものが、よくわかる。「有心」のままではわからないが、「無心」のままでもわからない。「無心」から「有心」に還る。その刹那に「わかる」。これが岡が道元や芭蕉から継承し、数学において実践した方法である。森田真生『数学する身体』
ここでも芭蕉と同様に、「無心」であることが唱えられる。「無心」から「有心」へと還るときに「わかる」のだと。しかし、なぜ、それによって「わかる」のか。森田は岡潔の言葉を引き、「それは自他を超えて、通じ合う情があるからだ。人は理でわかるばかりでなく、情を通わせ合ってわかることができる。他の喜びも、季節の移り変わりも、どれも通い合う情によって『わかる』のだ」と言う。
「情緒」は「情」の「緒」(いとぐち)と書く。「情」という日本語には独特のニュアンスがある。情が移る、情が湧く、あるいは情が通い合う。情はいとも容易く「私」の手元を離れてしまう。「私(ego)」に固着した「心(mind)」とは違い、それは自在に、自他の壁をすり抜けていく。しかも環境の至るところに「情」の動きの契機となる「緒」がある。そんな「情」と「緒」の連関としての「情緒」を、日本人は歌や句の中に読み込んできた。
うちなびく春来るらし山の際の遠き木ぬれの咲き行く見れば
(『万葉集 巻第八』一四二二 尾張連の歌)遠くの山に、桜がぱぁっと咲いている。すると、その姿がそのまま自分の喜びになる。花の咲く姿を「緒」として、人の「情」が動き出す。
「情」と「情緒」という表現で言えば、岡はある時期からこれを、意識的に使い分けるようになる。一口に「情」と言っても様々なスケールがあって、「大宇宙としての情」もあれば、「森羅万象の一つ一つの情」もあるというのだ。それを使い分けるために岡は、前者を「情」と言って、後者を「情緒」と呼び分けるようになる。
自他の間を行き交う「情」が、個々の人や物の上に宿ったとき、それが「情緒」となるというのである。森田真生『数学する身体』
これまでの議論で、鏡の空間では、あなたにもエルクにも人格性が与えられると言った。それはイマージュ、あるいはミメーシスの作用であった。「私はエルクでなく、エルクでなくもない」が、同様に「エルクは私でなく、私でなくもない」。僕はエルクの人格性を否定できない。なぜなら、僕はエルクの中に「私」を部分的に見出すのだから。岡の場合は、「情」が行き交い、人や物に宿った「情緒」がある。もちろん表現は異なるが、「創造性」についてのさまざまな議論を読めば読むほど、同様の論理が潜んでいるとしか思えない。「自他」の区別のない状態に自己を持っていくと、「情」や「イマージュ」や「縁起」が飛び交う場所が開かれる。詩人はその場所において、「無心」であるだけでなく「有心」に戻らなければならない。僕たちはすでに知っている。あちら側に完全に移行することは危険なのだ。その危険なバランスを生きること。そうすることで「わかる」のである。
ここまででイマージュや情緒の行き交い、ミメーシスの眩暈が体感的統合の領域において生じることを確認してきた。さらにそれを裏づけるものとして、カッシーラーが『シンボル形式の哲学』の中で表情 —— 魅惑的であったり威嚇的であったり馴染み深い感じを与えたり心和ませたりするもの —— こそが、知覚に「実在性の根源的色調を与え」、それによってこそ、知覚が「実在についての知覚」になっていると述べていることを挙げておこう。さらに、木村敏の『自分ということ』によると、離人症患者は客観的に「近い/遠い、重い/軽い、熱い/冷たい」を理解できる —— どちらが重いだろうか、どちらが軽いだろうかと質問されれば、数字を頭の中で介して、難なく答えることができる —— が、彼の患者が「温度の高低はわかりますが、暑い寒いといった感じはどうもピンときません」と答えるように、その「実在性」を掴むことができない。
これまでの議論を踏まえると、彼らは主体的統合—視覚的統合として、また「対象」として、つまり自分とは切り離されたモノとして、今日が暑いのか寒いのかは理解できるが、〈私〉—〈対象〉構造を支える基体、述語的統合=体感的統合が機能していない状態のため、自らの身体との繋がり、「実在性」を持てない。やはり、体感的統合は情動やイマージュ、表情といったエモーションの行き来の前提となる基底なのである。
[15]体性感覚を活性化することとは
すでに取り上げたように、森田真生は「芭蕉の句は、芭蕉の境地において、芭蕉の生涯が生きられることによってのみ導出可能な何かである」と述べていた。僕たちに最後に残されている問いは、それぞれの身体を作り上げるとは何かということである。芭蕉は、芭蕉の身体を作り上げた。それによってのみ、芭蕉の句は導出可能である。確かにそうだろう。しかし、〈共通感覚〉に根を下すこと、〈体性感覚〉を活性化することを可能にする原理を明らかにしなければ、身体性という一点において神秘化するだけのことになってしまう。ここまで示してきたように、〈共通感覚〉は体性感覚であり、感覚と理性の変換点であり、想像力の場所であった。中村雄二郎は『共通感覚論』で、次のように言う。
その働きは身体を基礎として身体的なもの、感覚的なもの、イメージ的なものを含みつつ、それをことばつまり理のうちに統合することである。また、サブ言語としての身体言語からいわゆる言葉への通路を開くことでもある。私たちの感性は、共通感覚をとおして活性化され、整えられ、秩序立てられなければならず、また理性は共通感覚にしっかり根をおろすことが必要である。感性のいたずらな放散と理性の不毛な形式化を免れるためには、共通感覚をいきいきと働かせることが大いに役立つはずである。このようなものとして共通感覚を、またその十全な意味を捉えなおす上で、統合関係と連合(範列)関係、あるいは結合関係と選択軸という二つの関係軸の直覚的な交叉から成る言語活動ほど、好都合な手がかりは少ない。なぜなら、語の自由な選択と結合とによる自由な言語活動は、デカルトやチョムスキーのいう理性や良識よりも、共通感覚の覚醒によってはじめてなされるからである。中村雄二郎『共通感覚論』
言語と身体は、分離された異なる領域と考えられがちである。しかし、「身体性」を考える上で、言語を起点にすることは重要である。身体が理性と感性、そして想像力を司る場所だとするなら、傾きとして理性的な言語、そして感性的、想像的な言語もある。また、このエッセイでここまで忌避してきた、ロゴスと結びつく形式化された言語ではなく、身体に根を下ろした生きた言語について考えることは、マジックワードとして曖昧に扱われがちな「身体性」という概念の解像度を上げることに寄与するからである。
そして、ここから僕は、この身体と環境と言語という問いについて、環境人文学に大きな影響を与えてきたデイヴィッド・エイブラムの『感応の呪文』という書籍を元に考えていくことにする。エイブラムはその中で、レヴィ=ブリュールやメルロ=ポンティを元に、身体と知覚と言語の関係を次のように要約している。
①知覚という出来事は、経験的に考えると、本来相互作用的で参与=融即的な出来事であり、言い換えれば、知覚するものとされるものの相互交流にほかならない。
②知覚される事物は知覚する身体との遭遇において、生命ある生ける力となって積極的に私たちを関係の中へ引き入れる。自発的で前概念的な経験は現象を二元論的に、生命あるものと「無生命」のものに分け隔てることはせず、せいぜい生命あるものの多様な形における相関的区別を認める程度である。
③感覚する身体と、表情に富む生ける風景との知覚的相互交流は、他者とのより意識的で言語的な相互交流を生みもし支えもする。私たちが「言語」と呼ぶ複雑な相互作用は、私たちの肉体と世界の肉との間で常にすでに展開している非言語的な交流に根ざしているのである。
④したがって、人間の言語は、人間の身体や共同体の構造によってのみ特徴づけられているのではなく、人間以上の大地の喚起力に富む地形や型の影響も受けている。経験的に考えれば、言語が人間という有機体の特別な所有物でないことは、言語が私たちを包み込む生命ある大地の表現であるということと同じである。デイヴィッド・エイブラム『感応の呪文』
融即とは、主語的統合のように主体と対象が分離された状態での知覚ではなく、主体と客体が未分化の状態で相互に影響を与え合う知覚を意味している。もともとは、哲学者レヴィ=ブリュールが『未開社会の思惟』の中で提示した未開人の知覚に関する概念であったが、後に文化人類学の調査によって論争が起こり、撤回されたものである。エイブラムはこう言う。
メルロ=ポンティの著作では、融即が知覚それ自体を定義する特性であることが示唆されている。現象学的にみて知覚は本来融即的であると主張することは、最も親密な次元において、融即が常に、知覚する身体とそれが知覚するものとの活動的な相互作用あるいは連結をめぐる経験であることを意味している。あらゆる言語的反省以前の、世界との自発的で感覚的な関わりの次元において、私たちはみなアニミストなのである。デイヴィッド・エイブラム『感応の呪文』
これは僕たちがこれまで見てきたように、ミメーシスによって動物やモノに人格性が付与されることと同じであり、他者に人格性が付与されるのも、同様の論理によるものであった。僕たちは近代人であってアニミストではないと主張することは、他者に人格性を賦与することを否定するに等しい。
さらに融即を詳しく見ていくと、四つの特徴によって語られている。その四つとは、移行性、可逆性、共感性、共感覚性である。まずは移行性と可逆性について、エイブラムの書籍から見ていこう。
実際、マウンテンライオンと出会った時、私はより強烈に自分が感覚する主体であるだけでなく、他者の目(と鼻)からすれば感覚される客体であり食べられる対象ですらあることを思い知らされる。私の腕を這っている蟻、目と肌が知覚しているこの蟻でさえ、私の動きや気分の化学変化に即座に反応して蟻自身の感受性を示している。蟻との関係において私は自分自身が高密度で物質的なものであり、うねる大地と同じように自分の行動が気まぐれなものだと感じる。最後に問うが、なぜこの主体と客体の「可逆性」は私が経験するすべての存在に及ばないのだろうか。私の感受性ないし主観性が、他者にとって目に見えて肌で感じられる形態はどれも、周りの存在そして私に対しても敏感で反応の早い、経験する主体であると考えるほかないと思うに至った。
知覚の移行性や肉の可逆性というのは、突如として木が私たちを見ていると感じること —— 自分が剥き出しにされ、視線にさらされ、観察されているように感じること —— なのである。デイヴィッド・エイブラム『感応の呪文』
視覚の移行性や肉の可逆性は、マウンテンライオンやジャガーといった、人間を食べる生き物との遭遇によって強く印象づけられる。確かに、ヴィヴェイロス・デ・カストロも同様のことを言っている。彼は「アメリカ大陸先住民のパースペクティヴィズムと多自然主義」という論文で、「パースペクティブの転置に際しての基礎的な次元であり、同じく構成的であるだろう次元は、捕食者や獲物という相対的で関係的な状態に関連している」と述べている。もちろん、そうなのかもしれないが、この狩る/狩られる、見る/見られるという相対的で関係的な状態は、都市生活を行なう僕たちにも想像することはできるはずである。
次に、共感性と共感覚性は、エイブラムの著書で次のように定義されている。
「知覚」という語が意味するのは、すべての身体的感覚がともにはたらき活発化しながら協調しておこなう活動にほかならない。実際、刻々と変化する周りの風景をめぐる非言語的経験に注意を払うと、いわゆる別々の感覚といわれるものが融合していることがわかる。距離をおいて目や耳や肌の関わりを個別に考えることができるのは、経験の後でしかない。ある感覚の役割を他の感覚の役割と区別しようとしたとたん、私の感覚する身体の感応的世界への全的な融即を絶たざるをえなくなる。
これは、感覚が別々の様相であることを否定するものではない。ここで主張したいのは、感覚が、単一の統一された生ける身体の様々な様相であり、それらの複合的な相互依存において展開する相補的な力であるということである。それぞれの感覚はこの身体の存在の独特の様相なのだが、知覚という活動においては、様々な種類の感覚が交わり重なりあう。そういうわけで、遠くの空を舞っている大鴉は、私にとって単なる視覚的イメージではない。目でその姿を追いながら、私は大鴉が羽を伸ばしたり曲げたりするのを自分の筋肉で感じるし、すぐ近くの木に向かって舞い降りてくれば、それは視覚に訴えると同時に内臓にも訴える経験にほかならない。大鴉のおおきなしわがれ声は頭上で方向転換する時も厳密な意味で聴域内に限定されているわけではない。その声は、見えるものを通じて響いているのであり、その漆黒の姿にふさわしい向こうみずなスタイルや気分で、目に見える風景を生き生きとさせているのである。デイヴィッド・エイブラム『感応の呪文』
まずエイブラムは、言語以前の経験においては、五感という分節化を経ないことを示唆している。次に、統一された生ける身体では、複合的な相互依存においてさまざまな種類の感覚が交わり重なりあうと主張する。見ることを通じて、〈運動感覚〉や〈内臓感覚〉が共鳴し、声が見ることを通じて響くと表現されている。言語以前の経験とは、これまでの議論では〈共通感覚〉〈述語的統合〉〈体性的統合〉などと言われてきたものである。そこは、理性と感性を繋ぐ場所であり、情動やイマージュが飛び交い、想像力を司る場所であった。
エイブラムは自らが体験したことを元に、民族誌や哲学書を使って概念を構築していくタイプの論者なので、テキストは詩的で喚起力があるが、フィクションの印象を回避できないのも確かである。なので、ここではヴィラヤヌル・ラマチャンドランによる共感性と共感覚性の定義も引いて、エイブラムの主張がある程度妥当性のあるものであることを補完しておきたい。まずは、共感性に関するラマチャンドランの有名な実験を紹介したい。それは彼が『脳の中の幽霊』で取り上げた実験である。
ラマチャンドランはミラーニューロンを応用した実験を行なった。ミラーニューロンとは、イタリアのジャコモ・リゾラッティらがサルの実験で発見した、脳の模倣を司る機能を指している。例えば、サルがものを持ち上げる動作をする。すると、該当する脳の一部分も当然のことながら活動している。さらに彼らは、他のサルが何かを持ち上げる動作を見ているだけでも、脳の同じ部分が活動していることを発見した。模倣機能が存在するということは、視覚芸術や文学ではしばしば言われていたことだが、彼らはこの運動と脳の対応を元に、実際に自分が運動しているときだけでなく、他者の運動を見ているときにさえ、さも自分がその運動をしているかのように脳が活動することを発見したのだ。ミラーニューロンは他者の運動だけでなく、他者の痛みや感覚も模倣する。例えば、目の前の人の手が金槌で思い切り叩かれるところを見たら、こちらまで思わず手を引っ込めてしまうだろう。脳は活動しているが、本当に痛いわけではない。これはどういうことであろう。ラマチャンドランの疑問は、そこに端を発している。
ラマチャンドランは、他者の痛みや感覚を見ると、その痛みや感覚に対応する脳の一部分は活動するが、同時に、実際の手の皮膚や関節にある受容体から「私は触れられていない」というフィードバック信号が出て、ミラーニューロンからの信号をキャンセルしていると考えた。そして、そのアイディアを検証するために、湾岸戦争で片腕を失ったハンフリーという幻肢患者に協力を依頼した。一般に幻肢患者は、腕がないにもかかわらず、まだそこに腕があるという幻想を抱いている。ハンフリーの場合は戦争で腕を失っていたのに、顔を触れられるたびに失った手の感覚を感じていた。ラマチャンドランはそんなハンフリーに、学生の一人を見てもらいながら、そのジュリーという学生の手を撫でたり叩いたりしてみせた。すると、ハンフリーは驚いた様子で、ジュリーの手がされていることを自分の幻肢に感じる、と叫んだ。ラマチャンドランの予想通りの結果だった。ハンフリーのミラーニューロンは正常に活性化されたが、それを打ち消す手からのフィードバック信号がないので、ミラーニューロンの活動が、そのまま意識体験として現れてしまったのである。
ラマチャンドランが「獲得性過共感」と名づけたこの現象は、幻肢患者だけでなく、簡単な操作を加えることで健常者にも再現できることがわかった。例えば、ラバーハンド実験と呼ばれるものでは、被験者の目の前に置いた作り物の手と、被験者の手に同様の刺激を10分間与えて、作り物を自分の手と錯覚させ、今度は作り物の手の上に室温のプラスチックを置いて取り除いた後に氷を置き、温度の変化をどう感じたかを調査した。本物の手には温度変化がなかったにもかかわらず、20人中15人が「自分の手が冷たく感じた」と回答した。さらに、氷の後にプラスチックを置くと、18人が「温度が上がった」と答えた。あるいは、麻酔によって皮膚からの感覚入力を遮断すると、誰もが文字通り、目の前の人と痛みを共有してしまうこともわかった。これらの例が意味するのは、皮膚からのフィードバックがなければ、自己と他者の運動や感覚を区別する術がないことである。
次に、共感覚性に関するラマチャンドランの発表を見ていきたい。ラマチャンドランが「数字に色を見る人たち」という論考で言うには、共感覚とは、二つ以上の感覚が混ざり合ってしまうことだが、それ以外は極めて正常な状態にある。何十年にも渡り、共感覚で起こる現象はインチキだとか、単に記憶によるものとか言われ、あまり真剣に受け止められることはなかった。しかし最近、これが実際に起こっていることが科学的に証明された。おそらくこの現象は交差活性化、つまり通常は別個に働く脳の二つの領域が互いに活性化し合うために起こるとされる。また、共感覚のメカニズムを探求するうちに、脳がどのように感覚情報を処理し、それを使って一見無関係なものを抽象的に結びつけるかもわかってきたそうだ。彼は共感覚を研究することで、それが共感覚者と呼ばれる一部の人に見られる特性ではなく、概念をつくるということを可能にする一般的な性質であると主張するに至った。少し長くなるが、見てみよう。
共感覚の仕組みを神経学的に理解することによって、画家や詩人、小説家の創造力を多少は説明できるかもしれない。ある研究によると、このようなクリエイティブな職業に携わる人々では、共感覚者の割合は一般の8倍にのぼるという。
創造的な人々の多くに共通する才能のひとつが、隠喩的表現の巧みさだ(たとえば、シェイクスピアの戯曲の台詞「あの窓が東の空ならば、ジュリエットは太陽」のように)。彼らの脳は、太陽と美少女のように一見無関係な領域どうしがリンクするようにできているかのようだ。つまり、共感覚が一見無関係な知覚的要素(色や数字など)を勝手に結びつけてしまう状態だとすれば、隠喩は一見無関係な概念的領域を結びつけてしまうことだといえる。おそらく、これは単なる偶然ではないだろう。
多数の高次概念がおそらく特定の脳領域(マップ)につながっているのだろう。考えてみれば、数字以上に抽象的なものはないのに、先ほど説明したように、脳の比較的小さい領域(角回)で処理されているのだ。私たちは突然変異によって異なる脳マップ間で過剰な交信が起こるために共感覚が引き起こされると考えている。
ここでいうマップとは皮膚の小領域のことで、そこでは特定の知覚的要素、たとえば、形の直線性や曲線性、そして色合いなどが表される。共感覚を生み出す遺伝子が脳のどこで、どのくらいの広がりで発現するかによって、共感覚や、一見無関係な概念をリンクさせる傾向(つまりは創造性)が生まれるのだろう。こう考えれば、あまり役に立つとは思えない共感覚の遺伝子が生き延びてきたこともうなずける。
私たちの研究は、芸術家には共感覚者が多い理由を明らかにするだけでなく、一般の人も実は共感覚の能力を持っていて、そうした形質が抽象概念を進化させてきたのではないかということを示唆している。抽象概念をつくることに関して、ヒトは抜きん出た能力を示す。抽象概念に関係するTPOとその内部にある角回は、通常、異種感覚情報の統合(クロスモダル統合)にかかわっている。
この脳領域には、触覚、聴覚、視覚からの情報が一緒に流れこみ、ここで高次の知覚が作り出されていると考えられている。たとえば、猫はふわふわしていて(触覚)、ニャーと鳴いたり、喉をごろごろ鳴らし(聴覚)、ある決まった外見(視覚)とにおい(嗅覚)をしている。猫を思い浮かべたり、「猫」という言葉を聞いただけで、これらの感覚がいっぺんに喚起される。
ヒトでは角回が類人猿やサルと比べて不釣り合いに大きい。それは角回が最初は異種感覚情報の関連づけのために進化したものの、しだいに隠喩などのより抽象的な機能が勝るようになっていったからなのだろう。
心理学者のケーラー(Wolfgang Köhler)が考案した2つの絵を見てみよう(詳しく知りたい方はブーバ・キキ効果で検索してみてほしい)。ひとつはインクの染みのように見えるが、もうひとつは割れたガラスの尖った破片のように見える。「どっちが『ブーバ』でどっちが『キキ』に見えるか」と尋ねられると、98%の人がインクの染みがブーバで、ガラス破片をキキと答える。アメーバのようなやわらかい曲線が、脳の聴覚中枢で優しい波動として処理される「ブーバ」という音にぴったりくるのだろう。そして「ブーバ」と発音するときに唇をゆっくりとすぼめる感じともよく合うのだろう。一方、「キキ」という音の波形と、それを発音するときに舌が口蓋に鋭くあたる感じは、この尖った形に見られる突然の変化によく表れている。
この2つに共通するのは、形から連想される抽象的特徴だけだ。そうした抽象的概念はTPO近辺、おそらく角回で生まれるのだろう(最近、私たちは角回が傷ついた人々ではこのブーバ・キキ効果が失われることを発見した。彼らは、2つの形を適切な音に結びつけることができない)。ある意味で、私たちは誰もが“隠れ共感覚者”なのかもしれない。
つまり、角回は非常に初歩的な抽象概念を作り出している。似ても似つかないものから共通する特徴を引き出しているのだ。角回がどの程度正確にこの仕事をするのかはわからない。しかし、クロスモダル抽象概念をつくれるようになったことで、もっと複雑な種類の抽象概念に進むことができるようになったのだろう。異なる機能のために別の機能が乗っ取られてしまうのは進化ではよく見られることだ。クロスモダルによる抽象概念構築は、隠喩や抽象的思考だけでなく、言語のもとにもなったかもしれない。ヴィラヤヌル・ラマチャンドラン「数字に色を見る人たち」
これによって、エイブラムが主張していたように、知覚とは分離された二元論ではなく、移行性、可逆性、共感性、共感覚性を伴った未分化の相互浸透であることが、ある程度証明されたのではないかと思う。それだけでも、『感応の呪文』は十二分に重要な書籍なのだが、さらにこの四つの知覚の前提を受け入れることで、現在の言語理論に対して別の道を示していくことになる。
少なくとも科学革命以降に一般化し、また今日でもほとんどの言語学者が最も一般的なものと仮定している言語観によれば、あらゆる言語は恣意的ではあるが慣習的に合意を得ている言葉ないし「記号」の連なりであり、統語的および文法的規則に備わる純粋に形式的なシステムによってつながっている。このような見解のもとでは、言語はコードの様相を呈する。言い換えれば、言語は知覚世界における現実の物や出来事の表象=再現前の方法であって、世界との内在的で非恣意的な結合がなく、したがって世界から切り離すことが可能だということになる。デイヴィッド・エイブラム『感応の呪文』
さらにエイブラムは、「そうした言語観は、意味を新たに創造してゆく行為が廃れ、『われわれから真の表現の努力といえるものを少しも要求せず、聞き手がそれを了解するためにも何ら努力を必要としないような』慣習的かつ既成の様式にならって人びとが話をする時、すなわち意味というものが貧弱になってゆく時にのみ生じうる」と続ける。彼は、科学革命以降の最も一般的な言語観(ソシュール以後) —— 世界と分離された慣習的かつ恣意的な記号システム —— では、意味を新たに創造していく行為が廃れると警鐘を鳴らしている。なぜなら彼は、言語が世界と分離されたものではなく、世界が奏でる音、形、そしてリズムと切り離すことができないと考えているからである。
よく知られている一章「表現としての身体と言語」(『知覚の現象学』)では、言語が身ぶりに由来するということ、すなわち、伝達指向的な意味はまず身ぶりに宿り、この身ぶりによって身体が自発的に感情を表したり感情の変化に対応する過程を詳細に論じている。身ぶりは自発的かつ直接的であり、心の中で特定の感情と結びつけられてしまうような恣意的な記号ではない。むしろ、身ぶりこそ私たちの感情が具体化したもの、明確に見て取れる形をとった喜びや怒りという感情なのである。そうした自発的な身ぶりに遭遇したとき、私たちはまずその身ぶりを意味のない態度として受け取り、次に心の中で特定の内容や意味と結びつけて理解するということはしない。身体的身ぶりは私たち自身の身体に直接話しかけるのであり、内的にあれこれ考えることなく理解されるものなのである。
活動的な生きた語りはまさに身ぶりであり、言葉の意味をその言葉の音、形、リズムと切り離すことのできないような音声的身ぶりである。伝達指向的な意味は根底において常に感情に訴える。すなわち、他の身体ないし風景全体と共鳴することができるという元来身体に備わっている能力から生み出され、経験をめぐる感覚的な次元に根ざしているのである。言語的意味は、物理的な音や意味に恣意的に当てはめられて「外的」世界に投げ出されるような観念や身体のない本質といったものではなく、感覚的な世界の深奥から、すなわち出会い、遭遇、参与=融即という行為のさなかから生まれてくるのである。デイヴィッド・エイブラム『感応の呪文』
エイブラムはこのように、言語とは世界と分離した恣意的かつ慣習的な記号システムではないと繰り返す。融即を前提とした身振りによって、僕たちは世界と共鳴し合い、音、形、リズムと絡まり合いながら意味を生成している。また彼は、「慣習的な意味から成るこの二番目の層を、口頭の表現に備わる音の調子、リズム、共鳴によって成立している意義、感じることのできる意義から切り離してはじめて、言語をコードとして —— 純粋に形式的な規則によって結びつけられている恣意的な記号から成る確定的で写像可能な構造として —— 捉えることが可能になる。そして、言語を真に抽象的な現象であると考えることによってのみ、言語が人間だけの所有物である」と言うのだ。
確かに、エイブラムの主張は非常に興味深く、僕に限って言うと、かなり実感に近いものがあるので納得できる。しかし、身振りが言語の起源であるという仮説に対して、言語学の主流は懐疑的なので、再びラマチャンドランに登場してもらい、先ほどの議論を説得的に示しておきたい。
言語を発明しようとしている原始人のグループを想像してみよう。みんなはリーダーを見つめている。「よし、今日からこれをバナナと呼ぶ。さあ、みんなで言ってみよう。バ・ナ・ナ」—— いやいや、こんなふうではなかったことは確かだ。
そのグループには、すでに体系的な言語コミュニケーションのための下地ができていたはずだ。私たちは共感覚の神経生物学的基盤を研究したことにより、隠喩の発達(つまり外見上は似てもいないし、関連つけようもないものどうしに深いつながりを見つけられるようになったこと)が、タネとなって、そこから言語が芽生えたのではないかと考えるようになった。
人間には、ある特定の形にある種の音を結びつけるという生まれながらの傾向がある。これは、原始人が共通する語彙を使いはじめるときに重要だったはずだ。さらに、物体の視覚的形態、文字や数字、そして単語を処理する特定の脳領域は、共感覚者でない人でも相互に活性化される。つまり、ぎざぎざの形態には鋭い発音の名前をつけたくなるのだ。
さらに、2種類の異なるタイプの神経連絡が私たちの考えを裏付ける。第一に、視覚的形態と聴覚のための知覚野は脳の後ろ側にあるが、ここと、脳の前方にある発話に関係する特定の運動領域の間には交差活性化が起こる。とがった形や耳触りな音は、発話に関係する運動制限領域を誘発して、目や耳から入ってきたぎざぎざの情報に合うような破裂音が出るように舌と口蓋を動かす。
「ちょっぴり」「ちょっと」などを意味するdiminutiveやteeny-weeny、フランス語のun peuの発音をするときに、私たちは口をすぼめるが、これは物の小ささをジェスチャーで示しているのだ。脳は、見たことや聞いたことを、その入力情報にあった口の動きに翻訳するルールをもともと持っているらしい。
第二の証拠は、手と口の動きに必要な一連の筋肉の動きを調整している2つの近接する運動野間で、シグナルの溢れ出しのような現象が起こることだ。私たちは、この効果を協調運動と呼んでいる。ダーウィンが指摘したように、はさみで紙を切るとき、私たちは無意識のうちに歯をくいしばったり弛めたりしている。まるで手の動きを口に反映させているかのようだ。言語学者の多くは、手の動きが声の言語の基礎になったという説には異論を唱えているが、協調運動は「手の動き・言語説」の裏付けになると私たちは考えている。
私たちの太古の先祖が、主として唸りや喚きや悲鳴などの感情的な声でコミュニケーションをとっていたとしよう。それらの声は右半球と感情に関係する前頭葉によって生み出されるということがわかっている。後に、身振りによる初歩的なコミュニケーションシステムをつくりあげ、それが徐々にもっと精巧で洗練されたものになっていった。
何かを自分の方に引っ張る手の動きが、「こちらへ来い」という手招きへと発達したという仮説には無理がない。そのような身振りが協調運動によって、口と顔の筋肉の動きに変換され、それから、のどから出てくる感情的な声がこれらの口や舌の動きを通して伝え、その結果として、最初の発話が生まれたと考えることもできる。
では、この説にシンタックス(言語において単語やフレーズを用いる規則)はどのようにはめ込まれるのだろうか。道具の発明が、これに重要な役割を果たしたかもしれないと私たちは考えている。たとえば、まずハンマーの頭部を作り、次に柄を付け、それから肉を叩き切るといったふうに、道具作りには順序がある。これは大きな文の中に節を組み込むのと似ている。カリフォルニア大学ロサンゼルス校のグリーンフィールド(Patricia Greenfield)に続いて、私たちも、道具の使用における下位部品の組み立てのために発達した前頭葉の領域が、のちに単語を節や文章につなぎ合わせるという完全に新しい機能にとって代わられたのかもしれないという説を提案する。ヴィラヤヌル・ラマチャンドラン「数字に色を見る人たち」
エイブラムとラマチャンドランによると、言葉の意味は本来表情に富み、身振り的であり、かつ詩的なのである。僕たちにはもともと、異なる感覚を繋ぎ合わせる能力が備わっている。これを隠喩的と呼んでもよいし、詩的と言ってもよいだろう。そして、ここまでロゴス的論理と言ってきた慣習的で指示的な言語は、本質的に二次的で派生的なのだ。もし言語が純粋に理性的で恣意的なコードではなく、「肉的相互交流と参与=融即から生まれる感覚的で身体的な現象」であるならば、私たちの言語は人間という種以外のものの身振り、音、リズムからも影響を受けていると言えるだろう。それはウィラースレフのミメーシスの理論からでも、エイブラムによる融即理論からでも示すことができるはずだ。そうなれば、もはや「言語」は人間だけの所有物ではない。言語が、常にその根底において身体的、感情的に共鳴するのであれば、鳥が奏でる歌の疑いようもない表現の豊かさや、深夜に響きわたる狼の遠吠えから、完全には分け隔てられない。実際、もし人間の言葉が身体と世界との絶えざる相互作用から生ずるのであれば、エイブラムの言うように、「この言語は私たちに『属して』いるように生命的風景にも『属して』いる」のではないだろうか。
ここまでで、言語とは何かを見ていくことを通じて、身体を活性化させること、あるいは体性感覚から主語的統合を作り出すための基礎を描き出せたのではないだろうか。円としての私は、眼によって分離された対象を表象するのではなく流れの中に内在し、視点が移行し、さまざまな情やイマージュ、音や形が飛び交う中で、リズムを感じ、自らの身体で振る舞い、それらを隠喩的に接合していく。そして、それは身体が自然に根を下ろした状態なのである。そうでなければ、言語は死んでしまうのだ。主語的統合を作り変え続けなければならない。それが身体を制作するということなのである。
もし僕たちが融即としての知覚を、ミメーシスとイマージュの力を再度手に入れるならば、それは可能である。確かに、単純に推奨することはできない。そこは、「私は私でなく、私でなくもない」という危険なバランスが求められる場所なのだから。宮川が言うように、僕たちは「鏡の中へ降りていく」ことを何より恐れる。しかし、恣意的で無機質なシステムの中で鬱々としながら、自己同一性の檻の中に入っているくらいなら、「制作」を介して、その世界へ降りていくことを選ぶ方がいいのではないだろうか。
エイブラムは言う。「人間の作った複雑な技術をすべて放棄しなければならないということを意味するのだろうか。いや、そうではない。だが、感応的世界としっかり付き合えるようにならねばならない、ということは含意されている」と。なぜか。それは「身体的世界の肌理、リズム、味わいを知り、人間の発明品との違いを容易に見分けることができなければならない。直接的で感応的な現実だけが人間以上の神秘において唯一の試金石であり続け、電子的に生産される眺望や遺伝子工学で作られた快楽にあふれた昨今の経験世界を判断する確固たる試金石になる。身体的に感じることのできる大地や空との日常的な接触を通してのみ、私たちは、私たちを支配する多次元において自分の位置を確かめ航海する術を学ぶ」からである。僕は今を生き延びるためにこそ、むしろエイブラムにならい、そして勇気をもって、「制作へ」と言うのだ。
[16]ロゴス的環境と資本主義の論理
自殺した女の子の日記を見ると人、人、人……人物しか出てこない
犬はいなかったのか? 猫は? 鳥は? 花は?
コンクリート塗れの人工物に囲まれた閉塞空間の中ではどうしても
人間関係の比重が重くなってしまう
軸足の半分は、花鳥風月の自然に置いたほうが良い養老孟司『ホンネ日和』
これは2011年9月25日(日)にTBSで放送された『ホンネ日和』という番組で、養老孟司が語った言葉である。僕はこの言葉を聞いたとき、まさにエイブラムの融即についての四つの特徴を思い出していた。とりわけ、移行性と可逆性の部分である。僕たちは見るものであり、見られるものであること。あるいは食べるものであり、食べられるものであること。これは確かに、ジャガーやマウンテンライオンと遭遇した場面を想像すれば、容易に理解できる。鳥やエルクがいる。木があり、花が咲いている。ヒトとは異なる生命がいることは、ヒトというものが一つの視点に過ぎないことを理解させてくれる。人間関係に疲れることは多々あるだろう。しかし、そのとき自然に根を下し、感応的に身体が動きさえすれば、そこには動物や植物との声と、形と、リズムによるコミュニケーションがある。そして、そこで制作すればよい。身体を、言語を、それぞれの仕方で作り上げればよい。確かにそうだ。
理論として理解できても、身体を開くのは、難しい。そう思う読者がいてもおかしくないと思う。僕たちは人、人、人、そして人工物に囲まれている。養老孟司が言うことは確かに正しい。軸足の半分は、花鳥風月の自然に置いた方がいい。しかし、どうすればいいのだろうか。この章では、芸術、狩猟、宗教、そして脳科学の一部などで、ここまで論じてきたような身体の在り方が幅広く見られるにもかかわらず、なぜ分離する二元論的な見方が近代世界を覆い尽くしているのかを考えてみたい。そして、これまで記述してきた「制作」の概念によって、最終的に近代世界を生き延びる技法として示せればと思う。
木岡伸夫は、二元論が広く一般化している理由をこう述べている。
デカルト的な世界認識の方法・構図が、古い見方に取って代わったということは、それが正しいからというよりも、その見方に付随する実践の成果が、人々に受け容れられ、支持されたということに過ぎない。つまりそれは、新たに確立された機械論的な自然観が、それまでに不可能であったような能動的で積極的な生き方、人間の世界に対する技術的な支配を可能にしたということである。それは、世界認識の「正しさ」ではなく、実践に結びつく有用性が人々によって受け容れられたということを意味する。〈あいだ〉に関して言えば、〈もの〉と〈こころ〉には中間が存在しないというのが「正しい」ということではなく、そういう中間的なものを考えない態度が、技術的実践に必要不可欠であったというだけのことである。〈あいだ〉を考えるよりも、考えないことの方に有益さがある。このことが、哲学的二元論のロゴスを近代科学の原理たらしめた根本的理由である。レンマ的論理が、ロゴス的論理に対するオルタナティヴとしての地位を失い、忘却の彼方に退くことになったのは、それが認識の原理として不適切で誤りである、というようなことではなく、社会が期待する実生活に有用な論理ではなかったからにほかならない。木岡伸夫『〈あいだ〉を開く』
確かに木岡の言うように、これまでの技術的水準であれば、ロゴス的論理を用いて、要素を外在的に組み合わせることで十分に必要な需要は賄えたのかもしれない。しかし、木岡が『〈あいだ〉を開く』を書く動機として、生命を捉える論理が必要とされてきていると言うように、分離された二元論で世界を捉えることには限界が来ているように思う。それは環境汚染などの問題だけではない。僕がここまで、「人工進化」や「マグロロボット」の例など、実際に「内在的観察」が社会実装の水準で必要とされてきている事実を示してきたこと、あるいは養老孟司の言葉からも察することができるように、今やますます画一化と自己同一性を強める現代社会において、このエッセイで記述してきた技法は、技術の面でも実存の面でも必要不可欠の知識であると、僕は考えている。とは言え、まだ答えを急がず、別の視点からの論点も眺めてみよう。
福岡伸一は『福岡伸一、西田哲学を読む』で、木岡とは別の視点から、「内在的観察」が排除されてきた論理を語っている。彼がその典型的な例として挙げるのは、花粉症である。そもそも花粉症は病気ではなく、免疫システムの暴走であると言う。清潔になりすぎた近代社会では排除するべきウイルスや雑菌が少なく、花粉に害があるわけではないにもかかわらず、免疫システムはそれを過剰に洗い流そうとしてしまう。これは、「①ある免疫細胞が花粉に反応してヒスタミンという物質をばらまく。②別の免疫細胞の表面にあるアンテナのような分子(ヒスタミンレセプター)がヒスタミンをキャッチし、外敵が襲来してきていることを察知する。③この免疫細胞が涙や鼻水のような分泌液をたくさん出させて、花粉を体内から洗い流そうとする」と形式化できる。この状態を、僕たちの社会は花粉症と名づけているのである。
こうした暴走を機械論的に見て治そうとすると、僕たちは抗ヒスタミン剤という薬を服用することになる。抗ヒスタミン剤とは、ヒスタミンとしての機能(外敵が襲来してきたことを知らせる信号)は持たないが、ヒスタミンレセプターを占拠することができるように、ヒスタミンに似た化学構造をもった物質のことである。免疫系は、前述した三段階の作用によって花粉症の状態を作り出しているので、先ほどの②の段階を防ぐことで、涙や鼻水など人間が不快と感じる反応が生じないようにするのである。
しかし、すでに見てきたように、僕たちの身体は同一性の構造ではなく、常に分解と構築を続ける不安定な流れである。免疫細胞、ヒスタミン、ヒスタミンレセプターという上記の関係も、絶え間のない合成と分解の最中にある。機械論的に考え、常に同一構造であると考えるなら、②をブロックすれば花粉症は治ると言える。しかし、生命現象は動的平衡の中にある。抗ヒスタミン剤を飲み続けると、ヒスタミンレセプターが常に占拠され続けているため、それに合わせた新しい平衡状態へと身体は変化することになる。つまり、ヒスタミンレセプターが常に占拠されている状態とは、ヒスタミンが常に分泌されている状態=外敵が侵入してきている状態だということを意味しているので、細胞は危険だと感じ、もっとたくさんのヒスタミンレセプターを作り出してヒスタミンをより鋭敏に受容できるように作り変えてしまう。こうして、実際に免疫細胞が花粉に反応してヒスタミンを分泌するとき、より多くのヒスタミンレセプターと結びつくことで、「より激しい花粉症」になっていく。このように流れの中で生命に対する「内在的観察」を行なうと、機械論的な治療は、より状態を悪化させていくと理解できる。しかし、福岡はそれでも生命を「内在的」に見ることは近代社会になじまないという。
このように、機械論的な見方と動的平衡の見方では、やはり「時間の軸」があるかないかということが、大きな違いとして存在しています。絶え間なく合成と分解が起きている絶対矛盾的自己同一の世界では、絶えず新しい平衡が求められ、一回限りの生命として同じ状態が起こることはありません。一方、機械論的な見方では、生命を機械として見ますので、刺激と応答というものが常に同一のものとしてとらえられます。抗ヒスタミン剤だけでなく、ほとんどの薬は、いまの話と同じように免疫系の仕事を邪魔したり、ある物質をブロックしたり、反応を阻害したりするものとして作られているので、もちろん、その場は効くんですよ。一時的には効きます。
こう考えると、ピュシスとしての生命を考えるときには動的平衡の見方でしか本来のあり方をとらえることはできないのですが、実は「動的平衡」は儲からない考え方なんです(笑)。機械論的に生命を見ると、抗ヒスタミン剤を投与すればその場は効くので、製薬会社はそれで儲けることができます。一方、動的平衡論では、「その治療法は最終的には無力で逆説的に生命にリベンジされてしまうから、花粉症とは騙し騙し付き合っていくしかない」と説くわけです。これは明らかに儲からない考え方ですよね。「動的平衡」や「ピュシスの立場」は資本主義になじまない考え方なんです。〈モノ〉として見えないと資本主義社会の中では価値を生み出すことができないのです。「逆限定」が大事だと訴えたところで、「逆限定」という〈コト〉それ自体は商品化できませんから。悲しいことに、資本主義社会では、どうしても生命というものを〈モノ〉の延長として考えざるをえないという側面があることも否めません。福岡伸一『福岡伸一、西田哲学を読む』
福岡は花粉症を例にして、機械論的な見方と動的平衡の見方を対比的に描いているが、これは花粉症だけでなく一般にも言えることである。近代社会では、AはAであるという自己同一性を前提に、機械論的立場からその場、その場で一時的に問題を解決していく。もちろん、問題は徐々に悪化していく。しかし、そうするしかない。一時的な解決が、その人、その社会にとって何よりも重要だったりするのである。他方で、「制作」的立場では、すべては「AはAではなく、Aでなくもない」という危険なバランスの中での舵取りをすることになる。福岡の言い方で言えば、騙し騙し付き合っていくしかない。花粉症で言えば、涙や鼻水が出てきたら、身体が過剰反応しているな、と自らに言い聞かせて、マスクなどで花粉が免疫細胞を刺激しないようにしたり、少し作業を休んだり、食べ物を変えるなどして、徐々に体質改善を図っていくしかない。もちろん即効性はなく、体質改善に関しても、これをすれば万事解決といった方法は存在しない。それぞれの動的平衡状態は、人それぞれ異なるからである。これでは、「こうすればいいですよ」「これを飲めばよいですよ」と、「商品」として提示できないから儲からない。しかし、生命は後者の論理で動いている。自らの身体で実験していくしかない。まさに「人工進化」の例のように、偶然と試行錯誤を繰り返していくしかないのだ。不安定な身体の統御。それが生きることなのである。
さて、エイブラムは、東南アジアでの調査から北米に帰った後の強烈な体験を語っている。彼は当初、彼の中で湧き上がってくる新しい感性に興奮していた。「近所の木からすばやく下りて芝生を横切ってきたリスとおしゃべりしたり、近くの河口でサギが魚を捕る様子やカモメが海岸沿いの岩めがけて高所から貝を落とし中身を取り出す様子を何時間も立ちっぱなしで見つめたりする私を見て、近所の人たちは驚いていた」そうである。
しかし、彼は徐々に動物自身の気づきの感覚を失いつつあった。表情と感覚に富んだ風景を幻想だと思うようになっていた。それは彼自身が、「そのとき私は、自分自身の文化に再び順応しようとしていたわけで、言葉や相互作用をめぐる文化的様式に自分をあわせようとしていた」と振り返るように、文明化した社会に再度適応したことを意味している。そして彼は、再度旅に出ることを決意する。彼は、南西部の荒野や北西部の海岸沿いの先住民保留地で長期間暮らしたり、北米大陸の原生自然を何週間も歩いて旅した。そして、彼は「未発展世界」と呼ばれるところで習慣的に経験した、あの異質な感情や知覚を引き出す別の方法があることに気づき始めたという。
私は、西洋で一般的に考えられている何倍もの強度とニュアンスでもって非人間である自然の世界を知覚したり経験したりすることは可能だということを学んだ。人間の外部の現実に向けられた強い感情、他の種や地球への深遠なる関心を可能にしていたのは何だったのか。そうした感情や関心は数多の自文化の型によって抑え込まれ飢餓状態におかれているほどだ。逆の問い方をすれば、近代西洋における注意の欠如を可能にしているものは何なのだろうか。土着文化に示されているような自然との調和がより根源的で参与的な知覚様式と結びついているのであれば、西洋文明がそうした知覚的相互交流から逸脱したのはどうしてなのか。言い換えれば、どうして私たちの耳や目は、他の種の生き生きとした存在に対して、そしてそれらが棲まう生命的風景に対して閉じ続け、そうした風景をよく考えもせずに破壊しようとしているのだろうか。
なるほど、非人間である自然に対する無自覚は、他の種や自然一般に知性を認めない話し方によって据え置かれている。もちろん、この無自覚には、私たちの文明化された存在 —— すなわち鳥や風の声をかき消すモーターの絶えざる低いうなり、星だけでなく夜そのものを覆い隠すまぶしい電気、季節を隠蔽する空気調整器、人間によってつくられた世界の外へ出る必要性をあらかじめ除去するオフィス、自動車、ショッピングモール —— も関わっている。私たちが意識的に自然と出合うのは、何を自然と定めるかという境界が文明とその技術によって限定されている時だけ、すなわちペットやテレビや動物園(よくても、注意深く管理されている「自然保護区」)を介してである。私たちが消費する動植物は自分たちで採集したり獲ったりしたものではなく、工業化された巨大農場で飼育され収穫されたものにほかならない。「自然」は単に人間文明のための「資源」の蓄積になってしまったかのようだ。そう考えると、私たちの文明化された目や耳が人間とは完全に異質なパースペクティブの存在にかなり無自覚だということや、西洋に移住する人や非工業文明から西洋に戻ってきた人が人間でないものの力の欠如に驚愕し困惑するのは、大して驚くべきことではない。
とは言え、文明による昨今の「自然」の商品化は、動物(および大地=地球)の対象への還元を可能にする知覚の変化についてほとんど何も説明していないし、私たちの感覚が〈他者〉の力 —— 長い間、最も神聖な儀式や踊りや祈祷を誘導してきたヴィジョン —— を放棄したプロセスについてもほとんど語っていない。
しかし、現在の私たちの思考そのものを構築している非常に多くの慣習や言語的偏見の根底にあるこのプロセスをひと目でも見ることはできないのだろうか。もちろん、そのプロセスが生み出した文明の内部からその起源に視線を向けても、それは無理であろう。だが、魔術師や、別の部族とともに過ごした後で自分の文化に完全には戻ることのできない人のように、文明の縁に立ち位置を定めてはどうだろうか。こういうひとは共同体の内でも外でもないところを彷徨い、都市の鏡張りの壁の向こうで地面を這い空を舞いながら変化する声や形に自分自身を開いている。そして、壁に沿って動きながら、この壁がどうやって作られたのか、どんなふうにして単なる境界線が障壁になってしまったのかという謎を解くヒントを見つけたいと思うようになるかもしれない。ただし、時機がよければ —— すなわち、よく訪れる周縁が時間的かつ空間的な縁であり、それが境界を定める時間的構造が溶解して別のものに変形するのであれば —— の話だが。デイヴィッド・エイブラム『感応の呪文』
養老孟司は「軸足の半分は、花鳥風月の自然に置いたほうが良い」と言い、エイブラムは「文明の縁に自らを位置づける」と言う。異質なパースペクティブとの感応的な関係を取り戻すために、〈あいだ〉に立つことが求められる。彼らの回答は、確かに有効かもしれない。これまで見てきたように、視点の移行性や肉の可逆性は実際に見る/狩るだけでなく、見られる/狩られる立場に置かれることで気がつくものでもあるからだ。しかし、多くの人はこの回答にがっかりするに違いない。なぜなら、結局僕たちはすでに近代社会に十二分に順応しており、その生活の循環から抜け出せなくなっているからである。彼らの言うことはもっともだと思いながらも、環境を変えようと決断することはできないだろう。エイブラムさん、あなたがアメリカに帰ってから、再度、旅立つことができたようには、僕たち/私たちはできない、と。
しかし、ここまで見てきたように、〈あいだ〉には二種類あるのだった。水平方向の〈あいだ〉と垂直方向の〈あいだ〉である。動植物との水平関係の〈あいだ〉があるように、即の論理、非即の論理を経由することで開かれる垂直方向の〈あいだ〉、つまり形の論理がある。僕たちは「描くこと」「書くこと」「狩ること」を通じて、「制作的空間」に参入する術を、ここまで確認してきた。実は近代社会にも、至るところに異質なパースペクティブは満ち満ちている。中世から近代にかけて〈述語的統合〉として近代の視覚中心の〈主語的統合〉が制作され、近代の只中では、その視覚中心の〈主語的統合〉から、また別の身体の制作が行われていた。一九世紀後半から二十世紀前半は、現在僕たちが置かれている状況と非常に似たものであった。機械化の波が、人々の生活を激変させ始めていた。モダニズムの芸術家たちは、動植物だけではなく、近代社会の只中で、異質なパースペクティブを取り込むことで、感応的知覚を取り戻し、それぞれの身体を制作していたのである。ここに、最後のヒントが隠されていると、僕は考えている。彼らの実践を見ていくことにしよう。
[17]二十世紀の新しい自然
異質なパースペクティブとの感応的な関係を取り戻すために、〈あいだ〉に立つこと。これは上述したように、水平方向での〈あいだ〉を開くことに繋がる。流れとして内在的に見ることやレンマ的論理によって見ることを可能にする。そして、それは視点の移行性や肉の可逆性を実感させてくれるものである。そうすることで、僕たちは彼らを模倣し、共感し、情を移し合うことができる。僕たちは一つの世界であり、一つの視点である。しかし、それと同時に、多数の異質な視点がある。模倣や共感によって、それを実感できる。
生物は、特殊感覚、体性感覚、内臓感覚など、複数の種類の感覚を用いて、光や音などの環境情報を電気シグナルに変換し、それらを脳内処理している。逆に言えば、それは各生物が、自然界に存在する環境情報のうち、それぞれに限定的な部分だけを感じとっていることを意味している。例えば、ヒトは磁気や紫外線、放射能などを感知することができない。コウモリが送受信している超音波すら感知できない。都市生活に慣れ親しんでいる僕たちは、それを感じていないことを反省するどころか、その存在にすら気がついていない。だからこそ、養老やエイブラムは、感応的な関係を再度取り戻すことを主張するのである。そうすることで、僕たちはそれぞれの身体と世界との相関性に閉じるだけでなく、その外側の存在を知り、振る舞いでもって交感するようになる。現象を超えて実在を感じること、音やリズム、形として繋ぎ合わせること。それはある意味、僕たちが自然に根を下しさえすれば当たり前のことなのである。テキストとは身体である。分かるだろうか。
僕は[9]において、「また人間は、自らの生物学的条件に基づいて、可視光の外側にある波長を赤外線や紫外線などと名づけているが、それは他の動物にはない特徴である。人間は道具によって所与の環世界、現象の世界を超えて、実在の存在を確認し、さらにそれを述語的に統合することで新たな身体を『制作』できるのである」と述べた。例えば、赤外線、紫外線、そして先ほど挙げた超音波という言葉では、人間の眼や耳を基準にして、「赤」や「紫」や「音波」という語に「外」や「超」が付け加えられている。しかし、実在にはそのような線引きは存在しない。五感が事後的に引いた線なのである。逆に見れば、人間は自らの身体の限界を超えて、「外」や「超」という領域を知ることができるということを意味している。もしそうでないなら、それらについて名づけることも、反省することもなく、存在にすら気がつかないはずだからである。ではなぜ可能なのか。それは、人間が人間拡張としての技術手段や媒体を発明してきたからである。
例えば、今や、僕たちは赤外線カメラや紫外線カメラを使えば、肉眼では見えない存在を容易に確認することができるし、上述した「人工進化」の例で、チップの0と1の間にある磁気的な漏出や磁束を発見できたのも、その存在を確認できる測定器があるからだ。そして、それを可能にしたのは「抽象化」の力である。分離された二元論が前提としているような中途半端な抽象化は、人間を中心に置く。そこから、さらに「抽象化」を推し進めると、人間は宇宙の一部となる。そして、それは再度、人間の世界へと折り返される。それが技術手段であり媒体である。例えば、相対性理論や量子力学は実用化のために推し進められた理論ではない。しかし、僕たちが今、スマートフォンを用いて自分がいる位置を確かめることができるのは、量子力学を用いて作られた原子時計と相対性理論による若干の修正があるからである。僕たちが普通に見ている世界は人間的現象であって、一つの視点によるものである。人間は世界の中心ではない。僕たちは人間と人工物に囲まれた世界の中で、そのように感じることができる。そして、量子力学と相対性理論の例からも分かるように、人間を超えた実在と人間の現象は、技術を介して相互に影響を与え合っている。僕たちが棲んでいる世界には、確かに動植物は少ない。それを嘆く気持ちも分かる。しかし、この「第二の自然」の中で、僕たちは〈あいだ〉を開き、五感の組み替えを行い、それぞれの身体を作り出すことができるのである。
この「抽象化」の力が、人間を自然から分離し、中心に置き、安心を与えるものだった時代を終わらせ、人間を宇宙の一部へと反転させはじめたのは、一九世紀後半から二十世紀前半であった。スティーヴン・カーンは『時間の文化史』と『空間の文化史』という著書の中で、次のように言う。
1881年頃から第一次世界大戦が始まる時期において、科学技術と文化に根本的な変化が見られた。これによって時間と空間についての認識と経験にかかわる、それまでにない新しい様態が生まれる。電話、無線、X線、映画、自転車、飛行機などの新しい科学技術が、この新しい方向づけの物的基盤となった。一方で、意識の流れの文学、精神分析、キュビズム、相対性理論といった文化の展開がそれぞれに、人の意識を直接形成することになった。この結果、生活と思考の次元が変質するにいたる。スティーヴン・カーン『時間の文化史』
すでに僕たちは、中世から近代にかけて、多声音楽、一点透視図法、実験科学という三つの革命によって、現在の常識的な〈主語的統合〉が作り上げられたことを見た。次に見るのは、〈述語的統合〉の比較的新しい時期における仮説である。カーンの著作では、1881年ごろから第一次大戦が始まる時期に、新しい科学技術によって、認識と経験にかかわる新しい様態が生まれたことを示している。ここに挙げられた電話、無線、X線、映画、自転車、飛行機が、それまでの人々の時空間の概念をいかに変えたかは容易に想像できるだろう。例えば、標準時の設定と無線の発明によって、同時性の感覚は相当に拡張した。タイタニック号の悲劇が今でも多くの人に共有されている理由は、無線によってリアルタイムに事故の状況が世界中に伝えられ、次の日には新聞でその情報が街に届くようになっていたことが大きい。
そして、新しい環境の変化の中で、それに対抗したり受け容れたりしながら、さまざまなジャンルの芸術家が、それぞれの身体を作り上げていった。もちろん、一人ひとりが新しい技術的布置の中で、それをどのように捉えてきたかを見ることはとても面白い。しかし、このエッセイで重要なことは、芸術家がその中でどのように身体を制作してきたかである。とりわけこの章で重要なことは、こうした急激な都市環境の変化の中で、芸術家たちによって「自然」の概念が変化したことにある。まずは、当時の芸術が置かれていた技術的変化について、アーサー・ミラーに別の角度から語ってもらおう。
芸術では、ルネサンス以来中心的位置を占めていた具象表現と透視図法に強い抵抗運動が起こり、それはポール・セザンヌの後期印象派において、非常に強力な形で表面化した。飛行機、無線電信、自動車など、技術における新展開は、人々の空間と時間の概念を変えつつあった。草創期の映画におけるエドワード・マイブリッジやエチエンヌ=ジュール・マレーの多重画像は、一連のフレーム上に異なる視点からの視野を描くことに加えて、時間変化を、連続したフィルムのフレーム、あるいは単一のフレームに描くことを可能にした。科学では、X線の発見で、内側と外側の区別が曖昧になったように見え、不透明なものが透明になり、二次元と三次元の違いもぼやけてきた。放射能は、見たところ無限の量のエネルギーをもっているらしく、空間は、いたるところで飛んでいてすべてを開けてしまうα線、β線、γ線、X線に満ち溢れているということになりそうだった。もっと抽象的な分野では、数学者が、三次元を超える次元で表される、風変わりな新しい幾何学について考えていた。人々は、空間の中あるいは時間の中での運動に影響する、四次元空間という考え方に、とくに心を奪われた。アーサー・ミラー『アインシュタインとピカソ』
その時代の膨大な芸術家たちを一人ひとり浅く広く伝えてくれたスティーヴン・カーンに対して、その時代がいかにピカソの活動に影響を与えたかをアーサー・ミラーは語る。美術史的には、ピカソのルーツは、セザンヌと原始美術にあることになっている。あるいはエル・グレコやアングルを参照にしていることも多いし、同時代のドランやマティスの創作活動に競争心を煽られていたことも事実だろう。しかし、僕たちが見ていきたいのは、この時代の芸術家が自然をいかにして捉え、そこでいかに身体を制作していったかであった。そこで例に挙げたいのが、ピカソ、そしてデュシャンである。
まずはピカソの例を見ていこう。アーサー・ミラー曰く、ピカソはこの時代の発見の中でもとりわけ三つの発見に大きな影響を受けていると言う。それは第一にX線、放射能、電子の発見であり、第二にメリエスの映画、マイブリッジとマレーの実験写真であり、第三にポアンカレによる非ユークリッド幾何学である。
世紀末の三つの重大な発見は、まさしく科学を自らの世紀末の無風地帯から引き出した。1895年のX線の発見、1896年の放射能の発見、1897年の電子の発見である。科学者は、これらの結果が感覚による知覚を超えた実在に起因するかもしれないという考え方を真剣に取り上げざるをえなくなった。
とくにX線は人々の想像力に訴えた。哲学的・科学的にすぐに言えることは、見たとおりのものが手に入るわけではないということである。人間の知覚には限界があるのだ。知識のこの相対性は、反実証主義の批評家をあおった。空間はもはや空でなかった。いたるところに光線が飛びかっていた。放射能による放出物であるα線、電子の別名であるβ線、その後X線と並んで一種の光と認められるγ線である。「X線」という名称そのものが、科学者がその正体を必ずしもよくわかっていないということを表していた。
……
映画製作者ジョルジュ・メリエスのことを思い起こそう。その最も有名な特殊効果は、人体の断片化と、時として奇怪で滑稽なまとめ方であり、その映画をピカソはドゥワイ通りの映画館で見ていた。
実験的な試みの系譜には、エチエンヌ=ジュール・マレーとエドワード・マイブリッジによる運動の探究もあった。マレーは一つのフレームで一連の出来事を調べ、マイブリッジは間をおかずに撮った連続写真を制作した。
マレーの多重露出は、形の分解という点でX線と似ており、さらに運動の連続性という息を飲む場面という点で、X線の先を行く。『ル・リール』に載ったイラストは、多重露出の実験に基づいた遊びである。マレーの写真は、しゃがむ女に初めて現れたキュビスムの同時性や形態の相互浸透をピカソが思いつくことに影響したに違いない。
マイブリッジは、ピカソに別のことを提供した。幾何学化が進んだ「構想」をもつ五人の女性の「映画的シークェンス」というアイデアである。
……
ポアンカレは、実際に第四の次元を見ようと提案し、自分の仮説を可能性の領域まで引き上げ、それによって、推測による思考を信じないために立てられる仮説すべてに検証を求める実証主義者からも離れ、その光景をX線を通したものか霊媒によるものかと見るオカルト派からも離れた。ポアンカレは、「われわれが四次元の世界を思い浮かべる」方法を、こうすればいいのではないかと言う。外部の対象のイメージは網膜に描かれる。これは二次元の平面であり、透視図法である。しかし、目と物は移動できるので、われわれは次々と、同じものをいろいろな視点から、異なる眺望で見る……さて、われわれが三次元の図形の透視図を、三次元(あるいは二次元)のキャンヴァス上に描くのと同様に、いろいろな視点から見た四次元の図形の透視図を描くことができる。幾何学者にとってはこれしかない。同一の対象のいろいろな透視図が次々と出てくることを想像しよう。(『科学と仮説』)
二次元平面上の光景が三次元からの投影でありうるように、三次元の面上の像が四次元からの投影と解釈することもできる。ポアンカレの第四の次元は空間の次元であり、彼はそれをキャンヴァス上に複数の透視図が並んでいるように思い浮かべることを提案する。これは間違いだった。ピカソはその視覚の才で、複数の透視図を、空間の中で同時に示すべきだということを見てとった。そうして『娘たち』が登場したのである。
空間の同時性についてのピカソの考えは、セザンヌの美術に典型的に現れるベルクソンの考え方を超えていく。セザンヌは、ある光景について蓄積された見え方全体を、すべて一度に(同時に)キャンヴァスにおく。つまり長期にわたる本人の無意識である。ピカソは、印象派の美術にある時間の概念も超える。たとえばクロード・モネの干し草の山やルーアン大聖堂の一連の絵のようなもので、これらは静的な再現の系列である。ピカソの空間的同時性がさらに過激なのは、全然別の視点、全部を合計すればその対象を構成する視点を同時に再現するからである。真正面から見た図と横から見た図とが同時に表されているしゃがんでいる娘は、ピカソには、四次元から投影したものと考えられていた。アーサー・ミラー『アインシュタインとピカソ』
1895年のX線の発見、1896年の放射能の発見、1897年の電子の発見は、人間の知覚に限界があること(肉の可逆性)、そして、人間と世界との相関を超えた実在がどうやらオカルトではなく確かなものらしいということを証明した。これは人間の視点を脱中心化する役割を担い、ピカソを素朴実在論者でも相関主義者でもなく、思弁的芸術家へと進ませた。つまり、現象の外側へ抜け、実在を描くという方向へと、彼を進ませたのである。メリエスの映画、マレーとマイブリッジの写真は、視覚の移行性、形態の相互浸透、そして運動について、彼を刺激した。ポアンカレの幾何学は、現象として現れる自然ではなく、実在としての自然を捉える上で、彼に大きな寄与をしたことは間違いない。それは四次元の思想との結び付きによって、より明確になる。そして、これらの事実は、彼が「現象的自然」ではなく「実在的自然」を捉え、それを観察し、描こうとしていたことを示唆している。それは、その自然の中でさえ、融即的知覚が開かれることを意味する。このことは、ピカソよりも、むしろデュシャンの実践の中で、より具体的かつ意識的に行われたことである。
[18]四次元とアンフラマンス — 機械状都市の中で生き延びるための技術
デュシャンによるレディメイドの戦略は、自明性ではなく、〈共通感覚〉を露わにすることであった。〈共通感覚〉は、僕たちの知覚の前提となる構造を「制作」する場所なので、あくまで彼の戦略はそこから始まるはずだ、とすでに記した。新しい身体を作ることは、「制作」を通じて〈体性感覚〉を活性化させること、周りの生命、風景と感応的関係を築くこと、内在的観察を行い、視点や情、イマージュが行き交う中で五感の組み替えを行っていくことであった。問題は、近代以降に生きる僕たちの周りには、人間と人工物しかないことである。情が宿り、情緒となりうる生命がない。養老やエイブラムが嘆いたのは、その点であった。
しかし、まさに機械化の波が押し寄せていた十九世紀後半から二十世紀前半は、芸術運動にとって最も活気ある時代であったと言える。僕たちが生きるようになったのは、機械状都市と呼ぶべき場所である。それは単に人工的で無機質なだけの孤独な場所ではなく、前章で確認したように、その新しい環境の中に別の感応の回路がある。そして、当時の芸術家たちは、その場所で新たに五感を組み替え、制作へと向かっていったのだ。それは五感の外側にある実在が科学的に証明され、実験的な映画や写真によってこれまでの知覚の常識が壊され、新しい時間と空間を描く幾何学が活気を帯びてきたことと関連がある。
その時代の芸術家たちを突き動かしていたのは、この露わになった実在の次元であり、当時この領域は「四次元」と呼ばれていた。中沢新一は『東方的』の中で、「いまでは美術史や思想史のなかでも、あまり注目されることがなくなってしまいましたが、二〇世紀はじめの芸術や思想における変革に、もっとも影響力をおよぼしていたのは、『四次元』という考えでした」と言う。そして、四次元の知覚について次のように説明している。
四次元の知覚というものが、どういうものかを正確に理解することは、とてつもなくむずかしい。それを考えるために、一般に試みられてきたやり方は、アナロジーを使うという方法であった。たとえばまず、二次元の世界に生きている奇妙な二次元生物を想像して、その生物に三次元がどのようにとらえられるのか、調べてみるのである。二次元生物の世界に、突如として三次元の球体が侵入してきたとしよう。この侵入物を、フラットランド(これが二次元生物の生きている世界にたいして、エドウィン・アボットがSF冒険小説『フラットランド』の中であたえた名前である)の住人は、どのようにとらえるだろうか。そのとき、フラットランドには突如、彼らにとって唯一の世界である空間に、どこからともなくひとつの点が出現し、その点はまたたくまに小さな円に変貌するのである。円はどんどん大きさを増していくが、今度はまた突然収縮をはじめ、ついには点にまで縮まって、その点もフッと世界の外部に消えてしまうのである。知性をもった二次元生物に立体を説明するのは、極度に難しい。たいていの二次元生物は、立体なるものの実在すら否定するだろう。ところが、それは実在し、二次元世界を通過していきながら、そこには自分の断面の軌跡を残すことだってできるのである。中沢新一『東方的』
想像できるだろうか。ここではまだ、一つ上の次元の実在が、一つ下の次元の世界に接触するとき、それがどのように現れるのかというイメージだけ掴んでもらえればいい。この時代における身体の制作という論点から言えば、現象を超えた実在の領域が数学的イデアと呼ばれようと、四次元と呼ばれようと、あまり関係はない。そうではなく、異質なパースペクティブとの感応的関係を結ぶことなく、X線や電子の発見によって、現象の世界が実在の世界ではないという認識をもち得るという点、そして、もしそういう認識をもったら、その世界をいかにして知覚するかという方向に進んでいくことを確認したいのである。例えば、チャールズ・ヒントンという四次元思想の先駆者の一人は、まさにその方向へと進んでいた。
人間が空間直観をもとにして、自分の世界を理解しているのならば、その空間直観のしくみに働きかけることによって、それを変化させ、新しいタイプの空間を直観できる能力にまで高めていくことだって可能ではないか、というのが、ヒントンの考えだった。カントがもとにしていたユークリッド的な空間直観の様式は、人間の知性にとってはあくまでもひとつのステップにすぎないのであって、そのことを理解した人間は、いまや次のステップにとりかかることが可能になっている、と彼は書いた。中沢新一『東方的』
ヒントンの思想はとても興味深い。なぜなら、僕たちはここまで、人間は〈共通感覚〉によって〈主語的統合〉を制作しうるし、これまでもしてきたことを確認してきたわけで、彼はその四次元思考を新しい〈主語的統合〉として実現しようと試みているからである。中沢曰く、「彼は、人間の脳の中に、四次元生物がもっていると考えられる一種の『三次元網膜』のようなものを実現するための訓練用に、発達したルービックキューブのようなものを考案しようとする努力を重ねた」らしい。そして、三次元である僕たちの世界を超立体が横切るときに見せる「横断面」のパターンの変化を捉えることで、超立体を構築する能力を鍛えていった。最終的には、「そういう実験をくりかえすことによって、とうとう彼は、四次元生物のもつと考えられる『三次元網膜』にもっとも近づいた、知覚の能力を獲得するようになった」そうだ。
僕にとって、ヒントンが本当に三次元網膜に近いものを習得できたか否かは、どうでもいい。それは、確認しようもないことである。しかし、中沢の主張でとても重要なことは、ヒントンだけでなく、マルセル・デュシャンも同様に、四次元知覚を可能にする新たな身体の制作に乗り出していたということである。レディメイドは〈共通感覚〉を露わにすることであり、新たな身体への始まりを告げるものなのだが、その宣言は誰かに向けられるだけでなく、彼自身にも向けられていたのだ。彼のチェス狂いは、まさに四次元知覚を可能にする身体の制作であった。
では、マルセル・デュシャンは、どうしたのか。デュシャンの解答は、チェスをする彼の姿に象徴されている。彼が相当に凄腕のチェス・プレイヤーだったことは、よく知られている。じっさい、彼は一時期、チェスに没頭していた。チェスはさまざまな意味で、興味深いゲームだ。最初、チェス盤を前にして、ふたりのプレイヤーが向かい合って座り、いざゲームがはじまろうとする寸前、そこには鏡の像のような対称性が、実現されている。ルイス・キャロルのアリスは、そのチェス盤の上から、彼女の四次元である鏡の国への冒険を開始した(キャロルの作品が非ユークリッド幾何学や四次元論から、おおきな影響を受けていることは、いまではあきらかである)。チェスの駒は、その盤上でつぎつぎに位置を変えていく。一手、一手にしたがって、チェス空間は全体の配置を変化させ、そのつどプレイヤーは、未来にこのチェス空間がとることになるであろう構造や配置について、考えられるかぎりの可能性を考えながら、つぎの一手を決定する。彼の頭の中では、プロポーションと配置を変化させていく、ひとつの多次元立体が動いているのだ。
また別のタイプのチェス名人になると、やはり目で見ることなしに、いくつものゲームを同時に指すことすらできる。こうなると、たんなる記憶のよさではすまなくなる。そのときチェス名人たちは、頭の中でチェス盤をヴィジュアライズできなければならないし、またこの頭脳の中に実現されるスクリーンは、変化のすべての様相を未来の時間にわたって投射することができなければならないのだから、とうぜん「四次元的」な構造をもっていなければならないはずなのである。ポアンカレがお得意の皮肉をこめて語っているように、「一生をこのゲームに費やすことができれば、人はついには第四次元を描くことができるようになるであろう」。デュシャンのチェスへの没頭を見ていると、ポアンカレのこの言葉が思い出されてくる(デュシャン自身は、この「目隠しチェス」には手をださなかったらしいが、彼の友人であったジョルジュ・コルタノフスキーは、一時期「目隠しチェス」の国際チャンピオンだったこともある)。中沢新一『東方的』
四次元知覚を身体化する方法として、デュシャンはチェスに熱中し、ヒントンは理論を構築し特殊なルービックキューブを用いて訓練した。デュシャンが身体を制作する場所は、またしても非対称の空間であった。今回は、鏡ではなく、チェス盤である。鏡の空間では、僕たちは「見る私」が「見られる私」を確認することで自己同一性を維持する表面から、いつしかその構造が不可避にもつ「見る/見られる」の分裂、その遅れ、距離の隙間を見出し、それ自体を生み出している場所、「私は私でなく、私でなくもない」場所へと誘い込まれていた。
チェス空間の場合は、対戦相手と向かい合っている状態で、「私」は可能な一手を考える。私一人の可能世界で閉じていては勝てない。一手ごとに、相手が可能な手も考える。あるいは相手の可能な一手に対して、私は私の可能性を考える。私は、狩る/狩られるという立場を往還することで、あるいは私と相手の可能世界の蝶番をくるくると回転させながら、私と相手の〈あいだ〉に可能世界を構築する。しかも、その可能空間は、ゲームが進むたびに動的に配置が変わっていく。いつしか、私は、その混ざり合った動的な場所にいることに気がつく。
もちろん、ヒントンがいくら超立体を三次元の世界で把握できるようになったとしても、デュシャンが卓越したチェス・プレイヤーになろうとも、それだけで「芸術」にはなりえない。「芸術」にする必要はない。それは単なる「制度」なのだから。デュシャンは、もはや「芸術」ではないことに、面白味を感じていた。彼は、この新しい身体を用いることで、次元を跨る知覚を見出すことに関心をもっていた。それは「アンフラマンス」と言語化されたものである。
アンフラマンスとはどのような意味なのか。北山研二は「新しい知覚概念・新しい対象着想法としてのアンフラマンスとは」という論文の中で、「アンフラマンスとは、アンフラ(infra)が『下の、以下の、外の』の接頭辞で、マンス(mince)が『薄い』という形容詞なので、極薄か超薄か薄外ほどの意である。たとえば、赤外線(infrared)は、可視的ではない。ときには熱を感じることはできる。その意味では、アンフラマンスはただちには感じられないが、知覚鋭敏になれば感じることもある現象と言えるだろう」と言う。これまで視覚として見たら、赤「外」線だった領域も、触覚としては温かさを感じられる。デュシャンは、「(人が立ったばかりの)座席のぬくもりはアンフラマンスである」と言ったりする。彼はアンフラマンスを日常の至るところに見出す。「煙草を吸うとき、その匂いは口の中にひろがり、吐き出されるふたつの匂いは、アンフラマンスによって結婚する」、と。
たばこが出す煙と口から出る煙とは、視覚的には同一と見なせるが、嗅覚的には極小的差異がある。その差異は微妙で、気がつく人は気がつく。時間差があるから、温度差にも関係する。温度差があるからそれと気がつく。両者のにおいは、嗅覚的アンフラマンスによって隔てられているし、結合しているとも言える。「隔てられているし、結合している」とは、ある視点から見れば非連続的であり、別の視点から見れば連続的であるということだ。北山研二「新しい知覚概念・新しい対象着想法としてのアンフラマンスとは」
僕は、ここに都市におけるレンマ的思考の一端を見る。たばこの煙を外側から見るのではなく、内側から見ること。そうすることで極薄の差異が見出される。外側から見た時、それは単なるたばこの煙である。しかし内側から見れば、そこに温度差が、時間差が、匂いの差があることが分かる。外側から見れば同一、内側から見れば、その同一性の中に無数の差異が生じていることが分かるのである。
デュシャンが関心を持っていたのは、このように、日常生活の中で「アンフラマンス」を発見すること、そして、「アンフラマンス」をつくり出してみせることだった。すでに見てきたように、「作品」の成立条件は、「制作」の外在化である。仮に高次元の概念であっても、もし「作品」として提示したいのであれば、それを三次元に置き換えなければならない。彼がその時に用いたのは、射影という方法であった。
彼はこの三次元の世界の中にある物体を、四次元物体の「影」としてとらえようとしている。ヒントンをはじめとする四次元の思想家たちは、一次元:二次元:三次元:四次元と次元を増やしていくときにおこることのアナロジーを使って、四次元知覚なるものを、思考可能にしようとしていた。デュシャンは、その逆を行ったわけである。彼は三次元の立体が二次元の平面に影として投射されるとき(そのいちばんいい例は写真である)、ディメンションがひとつだけ減ることに注目した。つまり次元数のちがうふたつの世界が出会って、そこに切断の現象がおき、横断面がつくられるとき、かならず次元数の高いほうが、ひとつだけ次元を減らしながら、そこに影をつくりだすのだ。このアナロジーを使うと、三次元世界の物体はすべて、四次元物体の影であり、私たちが実在と信じているものは、じつは「射影」の現象にほかならないのだ、ということになるだろう。デュシャンは四次元知覚そのものをとりだすのではなく、この射影のプロセスがおこっている切断面や横断面の出来事を、とりだしてみようとした。
『大ガラス』は、四次元が三次元に入り込む、まさにその瞬間を物質化してとりだそうとするオブジェとして、構想されはじめた(それがキュビスムが転換をおこしたのと、同じ年だったことには、意味がある。キュビスムは芸術を擁護するための転換を決意した。ところがデュシャンは、その芸術が無化されてしまう限界点のほうに、進みだしたからである)。それは射影のおこる「横断面」「切断面」を、物質化しなければならない。そうなると、そのオブジェは、ふたつの次元数の異なる世界をしめす領域と、それらが交わりあい、接触をおこす環境面とから、つくられることになるだろう。デュシャンのノートには、それが四次元の超空間的な動きをしめしている領域と、その四次元の影としての三次元世界を実在としてつくりだす意識の働きをしめす領域とのふたつで、つくられることになるだろうこと、そして、そのふたつの領域のあいだには、おたがいのあいだのコミュニケーションを可能にし、かつ不可能にしている薄い境界の膜が引き渡されることになるだろうことが、記されている。のちに実現された作品において、上半分をしめす「花嫁」と、下半分をしめる「独身者たち」の部分として、彼はこの考えを実現してみせた。中沢新一『東方的』
デュシャンは、投射という考えによって、四次元の実在を三次元に横断面として示そうとする。しかし、作品であるからには、その横断面をどのように物質化するかが重要になる。ここで、また重要な意味をもつのが、鏡とチェス盤である。中沢は「ルイス・キャロルは『鏡の国のアリス』において、あきらかに四次元世界の特徴をそなえたアナザー・ワールドへの入り口を、チェス盤と鏡に見出そうとしている。チェス盤は、ここでは鏡のメタファーになっている。チェス盤から鏡の世界までは、ひとつづきなのだ」と言う。それは、すでに鏡とチェス盤の上で生じていることを見てきた僕たちには、納得できる主張である。むしろ、〈あいだ〉の空間を開く装置として、ときに鏡が、ときにチェス盤が用いられていると考える方がよい。中沢自身もそのことにすでに気がついている。そして、それを「ちょうつがい(蝶番)」という言葉で説明する。
ではどうして鏡が、四次元への入り口と考えられたのか。これには、いくつかの理由があるが、いちばん大きな理由は、鏡の表面がもたらす「ちょうつがい」の感覚効果にあるような気がする。鏡を見ている人は、ちょうどチェス盤を前に向かい合うふたりの人間同士のように、自分のイメージと対称的な関係で、向かいあう。ところが、鏡の表面では、左右の反転が起こっているのである。こういう鏡の不思議さをめぐって、デュシャンの時代には、カントの議論がよく知られていた。カントは右手と左手のように三次元世界において対称的な物体を、そのままひっくりかえすには、空間における第四の次元が必要であることを、はっきりとしめした。ヒントンは、わざと左右をとりちがえさせるのが、四次元的思考へいたる最良の道だ、とも語っている。左右のとりちがえをおこしながら、日常生活に支障をきたさないで行動するためには、その瞬間瞬間に世界を鏡像的にひっくりかえす思考に、巧みになっていなければならない。
こういう「鏡像反転」や「ひっくりかえし」は、したがって、四次元世界が三次元の世界に接触する、その「ちょうつがい」の部分でおこるはずなのだ。鏡の表面が、人間の視覚にもたらす効果は、この「ちょうつがい」の働きにかぎりなく近い。鏡の表面はあきらかに三次元の世界に属しているが、ここで光の戯れがおこしてみせる現象は、その表面の「超薄さ」の部分に、第四の次元が染み込み、侵入をはたしているような奇妙な感覚をあたえるのだ。そのために、このかぎりなく薄い表面を利用して、アリスは裏返しにひっくりかえり、左右を反転させて、その表面の向こう側に拡がる四次元の空間の中に、まぎれ込んでいってしまうことができる、と考えられたわけだ。鏡の表面は、けっして鏡の空間そのものの中に入っていくことはできないが、すばらしい「ちょうつがい」として、四次元空間の侵入の跡を、示すことができるのだ。中沢新一『東方的』
デュシャンは鏡の向こう側に降りていく。そして、彼は、その鏡の中の乱反射を浴びることで、自らの身体を作り変える。デュシャンが行なったことは、都市の中での「内在的観察」を可能にする身体制作であった。彼は、「制作」という実践を通じて、都市空間であっても感応的な身体を作り出し、都市の至るところに「アンフラマンス」を見出した。彼は、自らの身体を変容させることによって、実在を知覚する。そして、その知覚を〈形〉にすることによって、「作品」を作る。「作品」とは「制作」の外在化であり、制度化である。しかし、それは同時に、いつか、どこかで、誰かの、次の、身体制作への足場となるものでもある。僕が今、彼が作った足場に立っているように。つまり、「作品」とは外在化であり、誘惑であり、誘惑された者たちの、小さな部分的共同性を生成する装置でもあるのだ。
デュシャンはあくまで、一例にすぎない。仮に彼が、「芸術」にすることがなかったとしても、それはそれでよかったのかもしれない。(しかし、作らないことは可能だろうか)。まずは、それぞれの身体をつくり出すことである。もちろん、身体はそれぞれの仕方で制作される。そして、それぞれの知覚を見出すことである。「描くこと」「書くこと」「狩ること」「チェスすること」。様々な経路をつうじて、僕たちは「制作的空間」へと、降りていく。もう恐れる必要はないだろう。その場所の魅惑の中で、〈作ることの可能性〉は〈作らないことの不可能性〉へと転ずるのだから。あとは、一人ひとりが、「制作へ」と向かっていくだけなのだ。
最後に、宮川淳『鏡・空間・イマージュ』から引用することで、このエッセイを終えることにする。
「芸術とはなにか」という問いはなぜもはや不毛な問いでしかありえないのか。それはこの問いを問いとして可能にする「芸術は……である」という答がもはや成立しないからだ。「芸術はaである」をbに代え、cに代え、あるいはa+b+c……としても、この事情には変わりはない。むしろ、われわれは「芸術は……ない」という否定形でしか芸術について語れなくなっているのだ。つまり、この答が成立しえないとすれば、問題は属詞にあるのではなく、この主語=属詞=動詞という様態そのものにあると言われなければならないだろう。宮川淳『鏡・空間・イマージュ』
僕は、この問いにどこまで迫ることができただろうか。