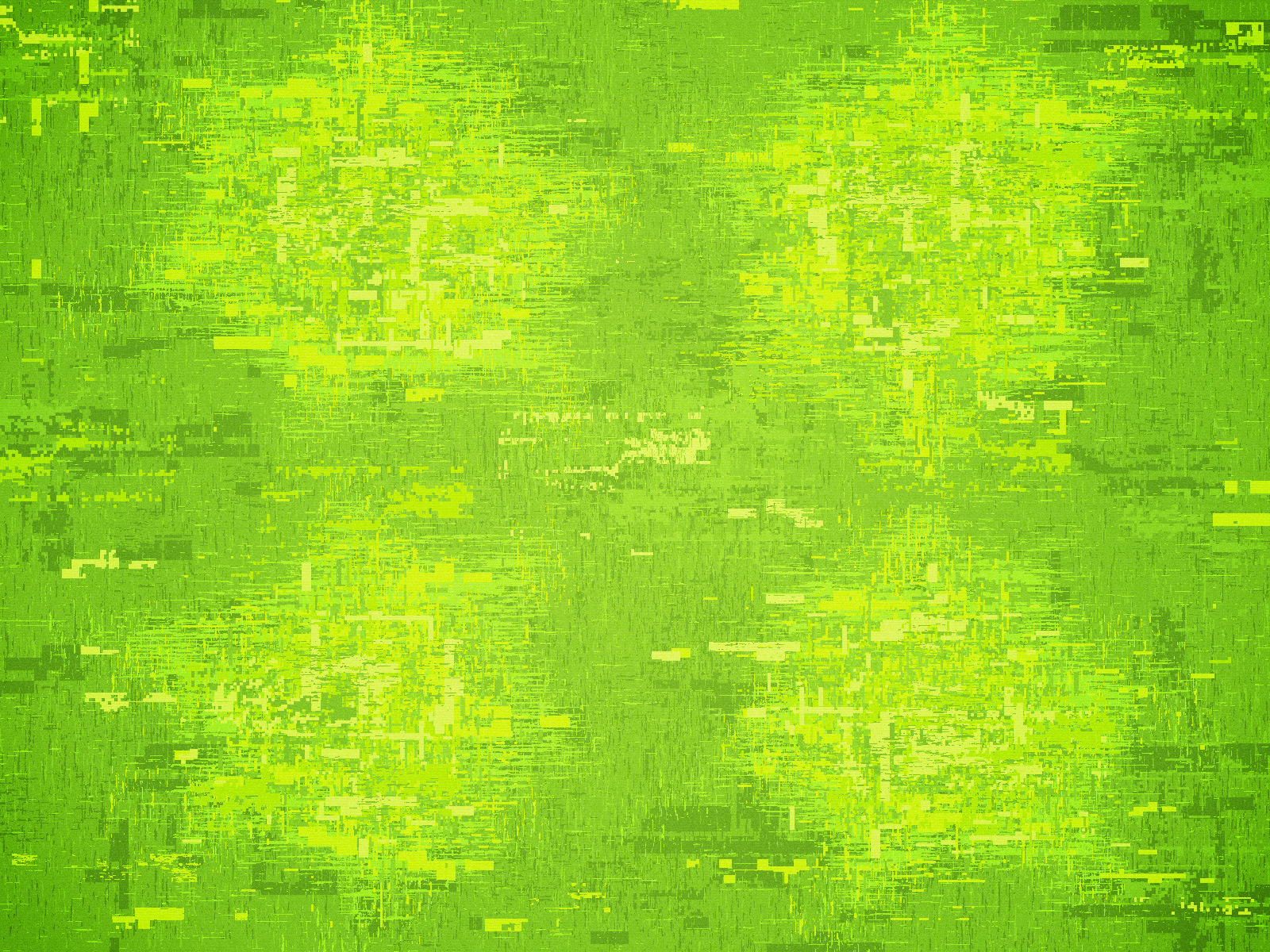言語はこの世の謎めいた豊かさを効率的に秩序だてるものなのである。ホルヘ・ルイス・ボルヘス
おれはいつだって具体的なやりかたで物事を伝えようとしてきた。比喩はあまり使わない。AとBを比べて違いを指摘するだけだ。そうすればたいていのことはうまく伝わる。少なくともうまく伝わったような感じがする。
問題は、伝えようとする物事そのものが混乱しているときだ。そういうことは多い。ほとんどの人は混乱に直面したとき、説明することをあきらめ、はぐらかし、沈黙する。それがいやだった。子供のころからずっと、言葉で伝えられないものはこの世になにひとつとしてないと信じていた。そしてだんだんと、世界の成り立ちには、秩序以上の割合で混沌が関わっていることがわかってきた。おれの動揺といったらない。最初はこんなふうだった。
「AはBだ」
「なぜ?」
「BはCではないからだ」
「なぜ?」
「BがDでないことから明らかだ」
「なぜ?」
この鬱陶しい「なぜ?」のたびにおれはだんだんと言葉を失い、それについて語ることができない混乱した対象のまえでがっくりとうなだれた。この混沌とした世界そのもののデザインについて、おれはなんども腹を立てた。いままでの苛立ちのエネルギーを使えば、やかんに一杯のお湯くらいは沸かせられるかもしれない。
もはや誰にもなにも伝えることなどできないのかもしれない、と気づいたのは二十歳のころだ。それは陰鬱な夏だった。妹が自殺し、恋人が鬱病にかかり、夕方になるたびに雨が降った。おれは恋人を失うまいと雨に濡れながら町中をかけまわり、香りのいいアロマオイルや花束や安い宝石を手に入れ、ベッドに伏せたまま動くことができなくなった恋人に捧げたあと、身体をさすってやった。そういう暮らしが一年ばかり続いたあと、彼女はなんとか持ち直して元気に働きはじめたが、こんどはおれのほうがまいってしまった。後回しにしておいた妹の喪がそのころになってあらわれたのだ。
説明できるのは、この物語が混沌に基づいたものではないからだろう。それだけに救いがある。結局はまたこうして語り始めているからだ。とにかくいろいろあって、おれは飛び級で大学に入るみたいに順序をすっぽかして死の領域に入った。「この門に入るものは一切の望みを捨てよ」と書かれた有名な観光地の門をくぐると、凍りかけた川岸に柳が垂れている深夜の京都があった。つまり、そこには少なくともなにかがあった。
それから数年の訓練を経て、おれは無の領域に近づいた。その場所の入り口には看板があり、つぎのような言葉が記されていた。
「さようなら」
カート・ヴォネガットが自殺未遂をやらかしたのは一九八四年のことで(いみじくも、ジョージ・オーウェルの小説の時代設定とおなじだ)、ヴォネガットはその時の心境をこう語っている。「なにもかもいやになっちまったのさ。もうコーヒーもなし、ジョークもなし、セックスもなし。」つづけて、「大いなるドアが閉まる音を聞きたかった」とある。
あるひとりの作家が残したものをほとんど読んでしまうと、その作家に対して抱いていた尊敬はだんだんと薄まり、最後にはおなじことをなんどもくりかえし話す、道化師めいた老人に対して持つのとおなじくらいの好意しかなくなる。
けっきょく、カート・ヴォネガットは二〇〇七年に死んだ。自宅の階段で足を滑らせて、角に頭をぶつけたのだ。その六十二年前にドレスデンで焼け死んでいれば、長い生涯のなかで、ひどい苦労を強いられずに済んだはずだ。こんなに長いこと。こんなところで。色んな人間が吐き出したチューインガムの残りかすを靴底で踏みつけながら。
それでも彼は生きた。えらいと思う。よしよし、ほめてあげよう。こっちへおいで、おっちゃんがアメ玉買うたるからな。
時のペロン政権にいじめられつづけていたホルヘ・ルイス・ボルヘスは、革命成功の流れを受け、一九五五年にアルゼンチン国立図書館の館長に任命され、いきなり八十万冊の書物を手に入れた。そのころには父系から受け継いだ盲目が完全なものとなり、自分の目でものを読むことができなくなった。彼はこの巡りあわせを神による皮肉と解し、「天恵の詩」という作品の冒頭でつぎのように書いた。
誰も涙や非難に貶めてはならない
素晴らしい皮肉によって
私に書物と闇を同時に給うた
神の巧緻を語るこの詩を
水上瀧太郎は一九一二年からハーバード大に学び、パリ、ロンドンを周遊したのち汽船に乗って神戸の港に戻ったが、朝日と毎日の記者につかまり、船室のなかでインタビューを受け、インタビューを受けたという事実以外は捏造の記事をでっち上げられた。自分の写真とでっち上げの記事が躍る新聞の一面に悩まされながら帰京した彼は、「貝殻追放」というシリーズものの随筆のなかで怒りを露わにした。その断章は、蒙昧な新聞記者に対する「馬鹿馬鹿馬鹿ッ!」という痛罵で終わっている。
日本文学史に燦然と輝く、記念碑的な筆致だ。
それから二十三年後、彼は大阪毎日新聞社の取締役となった。その後、なにかの講演中に脳溢血の発作で倒れて死んだ。皮肉が効きすぎたのかもしれない。その翌年、岩波書店があわてて『水上滝太郎全集』を出版した。いまでは絶版となっている。
誰も涙や非難に貶めてはならない、というのはつまり、笑ってやってくれということだ。
はっきり言って、なにをどう語ればいいのかわからない。語るべきことなんかなにもないような気がする。とくに、物語など、ひとつも浮かばない。おれが書きたいのは、日曜日の昼に炊飯器を買いに出かけたときの日差しがあたたかくて素敵だったというようなことだ。その帰りに駅前で買ったアップルパイがおいしかったことだ。それからシャンパンを飲んで酔っ払ったことだ。おれには向いていないのだ。
いや、そうじゃない。ほんとうはみんな、あらゆるものが、語ろうと必死になっている。おれは必死になって言葉にならない言葉をすくいあげようとする。調子がいい時なんか、まるで風船みたいに空中に浮かんでいるときもある。ただし、そいつをつかまえて白いページに押しこもうとすると、とたんに暴れだす。
真実はあまりにも素早いので、腹をさばいてワタを引っこ抜き、壺にぶちこんで塩漬けにしなきゃならない。これが腕の見せ所だろう。はっきり言って、語るべき対象は無数にあるのだから、「なにを」語ればいいかわからないというのは正しくない。「どう」語ればいいのかわからないだけだ。
あらゆる人間が物語を抱えている。これはおれが感得した数少ない真実のうちのひとつであり、おれは人々から注意深くそれを引き出すことによって、無形の報奨を得るだろう。そして、それは愛とおなじ、永遠に錆びつかない報奨である。
どこかへ旅行に行った帰りのことだ。当時おれは京都の大学にいて、ちょうど路銀を使いはたしたので路面電車に乗り換えず、駅からとぼとぼ歩いていたのだが、折悪く雨が降り出した。ちいさなパン屋の軒先で雨宿りをしていると、顔を見たことはあるが名前は知らない先輩が傘をさして通りがかった。先輩はおれに気付いて、「よかったらうちで雨宿りをするといい」と言った。おれは先輩のあとについて、地面に寝そべった巨大な犬みたいな長屋が並んでいる通りの奥へと入った。
先輩はおれを長屋のうちのひとつに招き入れ、タオルと温かいハーブティーをくれた。おれは台所の換気扇の下で煙草を吸いながらレモングラスのハーブティーを飲んだ。殺風景な部屋だった。ベッドと、テレビと、テレビの前に置かれたプレイステーション、いくつかのゲームソフトくらいしかなかった。
「いまは都ホテルのボーイをしてるんだ」と先輩は言った。
「出世されましたね」とおれは訳の分からないことを言った。
「そうだろうか」と先輩は言った。
その先輩は毛深いうえに小柄で、そのせいか全体の輪郭がはっきりしなかった。彼は二分おきに油紙を手の中でくしゃくしゃにするような咳をした。おれは屋外から聞こえてくる雨の音が咳の音で中断されるのを何度か感じた。神様が下腹に力を入れて、小便を途中で止めて遊んでいるみたいな雨だった。換気扇が回る音と、冷蔵庫のモーターの小さな唸りが通奏低音となって部屋中に響いていた。おれはいてもたってもいられなかった。いくつかの音が重なって、山中の霧のような印象をおれに与えた。おそろしいほどの湿気だった。ずっとここにいると肺に黴が生えてきそうだった。
「そろそろ、おいとまします」とおれは言った。先輩は玄関まで送ってくれ、ビニール傘を与えてくれた。
「気をつけてね」と言って先輩は微笑んだ。よく見ると、前歯がひとつ欠けていた。
「ありがとうございます」とおれは言って別れた。
どこをどう歩いたのかわからないが、路面電車の駅のひとつにたどり着いた。下宿から駅三つぶんも離れていた。道が分からなかったので、線路沿いを歩いた。二両編成の路面電車が何度も通り過ぎたが、車中の人影はずっとまばらだった。アニメのペイントがされた車両が数台に一度の割合で混ざっていた。彼女たちは永遠に若いまま、奇妙なポーズで固定され、潤んだ巨大な瞳で空中を見つめていた。
正面に立てば自分を見つめているような感じがするのかもしれない。
意外とよく書けている。この調子でどんどんいってみよう。
無の領域に属する文学はサイエンス・フィクションである。おれはこの真理を東京の神保町で学んだ。かび臭い匂いのする古本屋ばかりある町だ。十六歳のおれは、巨大なリュックサックを背負ってその町を訪れた。いくつかの本屋に入り、本当は読む気もあまりしないような小説を数冊買ったが、わけてもおれを驚かせたのは、サイエンス・フィクションに関連した書籍のみを取り扱う店だった。エイリアン、光線銃、宇宙船に恒星の煌き、茫漠とした荒野や天に瞬く星々などが描かれた表紙がずらりと並んでいた。おれはかなりの感銘を受けた(十六歳の少年は何にだって感銘を受けるものだが)。つまり、これらの古書は日本中のサイエンス・フィクション好きのためにあり、彼らはこういうのを見て狂喜するのだろうと思ったのだ。
それはとても素敵なことに思えた。
いまの話はあまり良くなかった。次はがんばろう。
文章を書くことはたいへんむずかしく、労多くして功少ない仕事である。文法や構文をいじくりまわし、さまざまな語彙を用いて美しい文章を書き上げたところで、語っている内容がまったくの見当違いということもある。かといって、内容を重視し、書き方を無視して書き進めると、あとから読み返しても何を言っているのか全く判らない奇妙な代物ができあがる。
正確な言葉を探しもとめて白紙のページを睨みつけているあいだに、意識が朦朧としてきて、思い出ばかりが浮かんでくる。そういったものに意味がないとは思わないが、書くほどのことでもない。思い出を追い払い、想像力を呼び起こそうとしているうちに、正確な言葉はいまここにいるおれ自身からすばやい動きで逃げていく。
芸術を作りたいわけではない。おれが作りたいのは、いまわの際にいる人間が絶望のさなかに手を伸ばし、頭が混乱していて文章の意味もよくわからないのだが、それでもとにかく三行ばかり読んで、放り投げ、そのまま死んでしまうようときに、そこにあるような文章だ。
いまこの瞬間に皮のベルトを握りしめて、窓外のトタン屋根の梁を眺めている人間が、ほんのすこし気まぐれを起こして本棚に近づいたとき、なんとなく選びとるような文章が、おれのものであってほしい。それでそいつの寿命が三十秒ほど伸びれば、おれは満足だ。
おれが文章に対して持っている希望は概ねそんなところだ。そこには多少のエゴイズムというか、他人に対して礼儀正しくありたい、ぱりっとした感じを見せたい、君といると楽しいと感じてもらいたい、といった社会性が秘められている。
とにかく、メッセージは正確に伝えなければいけない。それがどんなに伝えにくく、複雑な手段を用いなければ理解されないものであろうとも、できる限りの力を尽くして事に当たらなければならない。そして、誤解はやがて理解に至り、人類は長く待ちわびた平和を手に入れ、誰もが安心して暮らすことができる、すばらしい未来がやってくるだろう。
それで、その後は?
おれは若いころによくこんな歌を歌っていた。集団就職で地方から出てきた親父の友達の奥さんに教えてもらったのだ。
仙ノ山からよー 谷底見ればよー
巻いたまーたぁ 巻いたの アーヨイショ
アー 声がーするよー アーシッチョイシッチョイ
三十五番のよー 座元の水はよー
大岡まーたぁ 様でも アーヨイショ
アー 裁きゃあせぬよー アーシッチョイシッチョイ
大岡さまでもよー 裁けぬ水はよー
蒸気まーたぁ ポンプで アーヨイショ
アーみなさばくよー アーシッチョイシッチョイ
三十五番はよー この世の地獄よ
行かすまーたぁ 父さんは アーヨイショ
アー 鬼か蛇かよー アーシッチョイシッチョイ
とにかく、この物語は無の領域の一歩手前をうろつく男の物語である。おれ自身はけっきょく「さようなら」と書かれた門には入らなかった。門の手前からその奥をじっと眺めていただけだ。奥は紫色で、ブーンという蛍光灯の音がする。死の領域のほうがまだ居心地がよかった。なんともいいがたいだるさに充ちてはいたが、少なくともなにかがあった。凍った川岸の柳や、寝そべった犬のような長屋はその一例である。
妹はテーブルの向こうに、おれはテーブルのこちら側に座っている。
「元気?」と妹が聞く。
「元気だよ」とおれは答える。
「そう。よかった」妹は言う。
そして沈黙が続く。なにもかもを包みこむような沈黙だ。
ラジオも、テレビも、音楽もない。
鈴虫がずっと鳴いている。
夜だ。
おれの妹が死んだとき、これは当然のこととしてみんなに受け入れられたが、雨が降った。彼女は十一月の凍えるような寒空の下で、コンセントの延長ケーブルを首にまきつけ、自宅の裏口のそばにあるトタン屋根の梁から自分をぶら下げた。
それは空を見ているだけで不安になるような薄暗い夕方だった。太陽が人間たちを残してどこかへ行ってしまったみたいな寂しさだった。そしてそれは本当のことなのだ。
おれは自分の部屋で音楽を聞きながら、その寂しさにじっと耐えていた。誰かと抱き合っていないとやりきれないような日だったが、妹はもうずいぶん前から具合が悪くなっていて、面倒を見てやる気にすらなれなかった。
トタン屋根の梁から身体をぶらさげて風に揺られている妹を見つけたのはおれの父だったが、そのときの叫び声は真に迫るものがあった。すぐに救急車がやってきたが、彼女はすでに絶命していた。それから家族が集まり、親戚筋がみなやってきて、それぞれに感想を述べた。彼女がそれをしたときにおなじ家にいたのがおれだけだったという事実が口にされたが、誰一人非難するような口調ではなかった。
彼女が憂鬱症であったとかいう診断を下すのはおれの仕事ではない。有り体にいうならば、彼女の頭のなかには毒虫がいて、夜ごとに彼女の脳髄をたべて成長していった。こういう話は、具合が悪くなった妹から実際に聞いた。そんなわけがないと思ったが、いくら抱きしめても、恐怖に目を見開いたまま怯えているのだった。そのわりに話し声はしっかりしていた。怖い感じがする話だ、とおれは言った。
妹の幽霊から逃れるために移り住んだ京都は、おれを苦しめも助けもした。憂鬱症の患者を家族にもつ人なら賛同してくれると思うが、憂鬱症は伝染する。そういうわけで、おれは憂鬱症に苦しみ、ふうふう息を切らしながら生きた。泣いてばかりいるので、ほんとうに息が切れるのだ。歩けばすぐに疲れてしまうし、どんな小さな不調も見逃さなくなる。四月の身体検査で白血球の数が異常に少なく検出されたとき、自分が癌に冒されたと思いこみ、何をするにも薄氷を踏むように慎重になった。
そのときの気分は、底がつるつるの滑りやすい靴でワックスをかけたばかりの廊下を歩くようなものだ。次の瞬間にはおもいきり転んでしまうだろうという感じが延々と続く。
それは地獄である。
もう大丈夫だ、というようなことは何度となく思った。いい映画や小説を見て十分に楽しみ、自分がまだ楽しめることに喜びを見出して、そこに大いなる満足を覚え、もう大丈夫だと感じる。
そして翌日に目覚めると状況はより悪くなっている、雨が降っていて、きのう干した洗濯物を取り入れていない。部屋のなかに戻して乾かすが、濡れた犬のような匂いがする。それから怠惰がおれを座椅子に結びつけ、延々と煙草を吸いながらインターネットを見る。何度も何度も見た映像をくりかえし見る。味のなくなったチューインガムが不快なのとおなじ理由で、おれは不快な気分になる。雨が強くなる。しぶしぶながら、もういちど洗濯機をまわす。洗濯機のドラムがぐるぐる回るのを、プラスチックの透かしを通して眺める。ぐおーん、ぐおーん、という音が何度も繰り返される。
死んだ人間に対してできることは何もない。
これはおれが得た数少ない真理のひとつだ。
京都の東の果てにはとても細い川が流れていて、いくら増水してもいいようにかなり深く掘られているのだが、その川には二百メートルほどの間隔で橋がかかっていた。おれは不調があまりにも大きいので半ば当惑しながら川沿いを歩き、二百メートルごとに短い橋を渡った。
どんなことでも死ぬきっかけになるのだが、このときもそうだった。誰にも迷惑をかけずに死ぬ方法を考えはじめた。いくつかプランはあったが、いちばんいいのは、ホームセンターでシャベルを買ってきて、人気のない山に入り、穴を掘ってそこに入り、土を崩して自分を生き埋めにするものだ。(これはいまでも優れた方法だと思う。なにせ埋葬の手間がかからない。)
そんなことを考えながら橋にさしかったとき、おれは短い橋の真ん中に祠を見つけた。そのなかには地蔵がいて、時間や情念や、そのほかのあらゆるものを超越したお顔で微笑んでおられた。おれはしばらくその地蔵をぼんやりと見つめていた。
あまりにもよいお顔だったので、おれはぼろぼろと泣き出した。「なあ、どうしたらいいんだろう、お地蔵さん」とおれは話しかけた。「どうしてこんなに悲しいんだろう。どうしてこんなに暗い気持ちなんだろう」
「それはお前がアホやからや」と地蔵は答えた。
「え?」
「それはお前がアホやからや、言うてんねん」と地蔵は繰り返した。
おれは首をかしげ、まあ気のせいか、おかしな薬で酔っ払っているからだろうと高をくくった。「ほな聞きますけど、なんでアホやと思いますの」とおれは言った。
「おまえは妹が死んで悲しいという。それは当然のことや」と地蔵は語った。「立派な話や。いまの時代にそんな心優しい奴はおらん。感心するわ。しかしね、よう考えてみなはれ、死んだ妹がいちばん望んでいるのは何や? おまえが幸せになることとちゃうんか? 立派な社会人となって社会に出て、ばりばり働いて、妹さんのぶんまで幸せになることちゃうんか? 死んで何になるんや? 頑張れ、頑張れ、頑張れ、頑張れ、応援しとる、君は世界にひとつだけの花」
おれは怒った。
「ワレ、なに言うとんじゃボケ。口当たりのええことばっかり抜かしやがって。壊す」
おれは祠に蹴りを入れた。ずいぶん古くに作られたらしい祠は簡単にばらばらになった。地蔵は岩と一体化していたが、そこまで大きくなく、簡単に持ち上げることができた。おれは地蔵を深くて細い川に投げこみ、地蔵が浅い水を割ってコンクリートの底に当たる音を聞いた。欄干に腹をつけて川を覗きこむと、当たりどころが悪かったらしく、地蔵は首がとれていた。
「おれを舐めとったらそういう目に合うんじゃ、ハゲ」とおれは叫んだ。「ええ気味や。死ね」
するとパトカーがやってきて、おれに職務質問をした。
「お兄さん、なにしてんのん?」
おれは涙によって尋問官と書記の同情を誘うことに成功した。半日ほど拘留されたのちに釈放され、振り返ると建物の看板には下鴨警察署とあったが、そこはおれの見知った下鴨ではなかった。なにもかもが鏡写しになって反転しているのだ。
夜なので方角がわからなかった。おれは仕方がないので茂みに埋まって眠り、小便をしたりげろを吐いたりして時間をつぶした。ときどき笑いが止まらなくなった。おれが酔っ払っていたのは酒ではなかった。造船所でもらった八枚つづりのシールで、キスマークが入っているやつだった。そのキスマークにはこんな文句が書かれていた ——
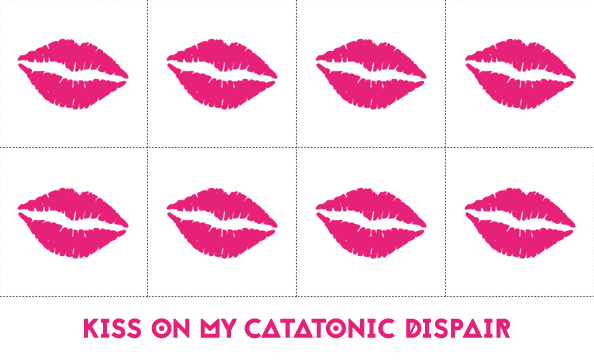 (「おれの緊張性の絶望にキスしろ」)
(「おれの緊張性の絶望にキスしろ」)
美はどこにでもひそんでいる、とボルヘスは言った。ひそんでいる場所は、まったく予想できない。新聞広告の文章かもしれない。庭に生えているオレンジの樹かもしれない。街路に立っている売春婦の誘いの言葉かもしれない。生ごみをついばむ鴉かもしれない。見たところ文字単価0.2円くらいのインターネット上の記事かもしれない。ただし美は、それを求めさえすればどこにでも見つけることができる。
美を求めていないにもかかわらず美を感じてしまう状態のことを、おれはカフカ的神経衰弱と呼んでいる。
カフカ自身による自分自身の診断は、恋人に宛てられた無数の手紙のなかのひとつに見つかる。
「僕はこのごろ、あまりにも感じやすくなっています」
妹が首を吊る直前のことだ。おれは自室で何か自分のことをやっていたのだが、そこに妹があらわれた。部屋には入らずに、ドアを半開きにして、そこからおれの姿をのぞいていた。あまりにも静かだったので、たぶん、おれはしばらく気づいていなかったのだろう。ようやく振り返ったとき、妹はどことなく寂しそうな笑顔を浮かべていた。そして、「ばいばい」と言った。
妹の頓死はほんとうに堪えた。それまでの妹にたいする態度が、すべて取り返しのつかない間違いだったことを宣告されたわけだ。
あのとき、もうちょっと優しくしていれば!
あのとき、もうすこしだけでも話を聞いていれば!
あのとき、心をこめて抱きしめてやれば!
そんなことばかりを考えるようになる。まともな、正常に動作している人間のすることではない。正常に動作している人間は、もっと建設的なことをする。犬が土を掘るみたいに過去を掘り返したりはしない。そういうわけで、こんなものを書いているおれはいまだに正常に動作していないようだ。
ただし、気分はずっとましになった。これは、時の流れだけが成せるわざだろう。
時の流れに取り残されたような左京区の定食屋の座敷で腹がくちくなり、天井近くの棚に設置されたテレビの相撲中継を眺めているとき、いつもおれに料理を運んでくれるおばちゃんがあらわれて、おれにこう言った。
「もう閉店どす」
おかしいな、とおれは思った。そんなに早かったか?
しぶしぶながらおれは店を出た。たしかに客はおれひとりだけだった。おばちゃんは暖簾を外し、立て看板と食品サンプルの入った巨大な台を片手で軽々と持ちあげて、店のなかに運んだ。戸が引かれた。振り返ると、おれは鏡写しの奇妙な京都にいた。それは北白川別当町のあたりだったはずだが、なにもかもが反転していた。あわてて定食屋の戸にすがりつき、拳で戸を叩いたが、戸は夜とおなじ物質でできた鉄に変わっていた。
おれは恐怖に震えながら歩き、大通りらしいところに出た。ふたつの目玉が煌々と光っている巨大な獣がものすごいスピードで駆けてゆき、そのうしろをぴったりと夜がつけていた。暗闇のなかでうっすらと見える並木は枝をいっぱいに広げていたが、よく見るとすべての葉に無数の目玉がついていて、おれのことを見つめていた。雨が降りだしたが、それは雨ではなく蛭だった。
おれは小便をちびり、子供のように泣きながら助けを求めた。
「助けてくれえ、助けてくれよお、怖いよお」
気がつくと、おれは吉田松陰の像の前にいた。それは銅製だった。
あの細い川沿いの地蔵のことも記憶に新しかったので、警戒しつつ話しかけた。
「あんたは話せるんか?」
「話せるで」と吉田松陰は言った。「どないしたんや」
「いや、まじでどうなってんのこれ」とおれは言った。「ぜんぜん見覚えない街やし、樹ぃには目ぇついとるし、像は喋るし。おれの気がちごうたんか?」
「それは知らん」と吉田松陰は言った。
「なんや、知らんて。あんた人が真剣に悩んどんのにその言い草はなんや」
「おまえなあ、もっとシンプルに考えろや、おれみたいな像が喋るわけないやろ? ただおまえがラリっとるだけや。よう考えてみいや、そんなこともわからんのか。ほんまにアホやな。どうしようもないわ。しょうもないわ。身内が死んだ言うて薬食ってラリって小便ちびってなあ。ほんまにお前は最低の人間のクズや。逝ったモンも見たら悲しむわ。お前がそんなんやから妹さんは首くくったんと違うか。そうや。そうに違いないわ。あーしょうもな。しょうもないアニキにしょうもない妹やわ」
「おまえ今何て言うた」
「しょうもないアニキにしょうもない妹やわ」
「その一個前何て言うた」
「あーしょうもな」
「そこはええねん。その前のやつを言え」
「お前がそんなんやから妹は首くくったんと違うか」
「違うわボケ!」おれは吉田松陰を蹴った。
どんどん蹴った。足が腫れ上がってきたし、息もあがってきた。
「悪かったわ」しばらくすると、吉田松陰は静かめのトーンで言った。「そんな怒るとは思わんかったわ」
「白こいわ」
「ほんますまんな」と吉田松陰は言った。「でもおまえの妹は、いまおれの家で犬のちんこしゃぶっとるけどな」
おれは激怒し、吉田松陰に硝酸をかけた。おれは理学部化学科の学生なので、そういうものはたくさん持っているのだ。
「あかんて、あかん……」と吉田松陰は溶けながら言った。
インターネットで検索すると、こんな話が出てきた。
『ポーランドの花占いの表現には、「好き」から「いらない」までのあいだの、非常に多くの表現が含まれています。ステキですよね!』
紫陽花でやるとちょうど良いのかもしれない。
もちろん、妹が死んでつらかったのはおれだけではなかった。おれの親父もそうだった。
彼はたったひとりきりで稼いだ片腕(五百万円という金高のことを、河内ではそう呼ぶ)をはたいて、おれを西欧へ旅行に連れて行った。
それはまあいいのだが、おれが卒業したあと、下宿を引き払おうかという段になって、親父は作戦会議のために大阪から京阪電車に乗って川端四条にやってきた。昼飯をどこで食べるかという話になり、四条大橋の西詰めにある東華菜館という中華料理店に入った。そこには明治のころから動き続けているエレベーターがあり、おれたちはそれに乗り込んだ。鋼鉄の扉ではなく、飾り格子の柵が閉まり、その隙間からビルディングの内側の壁が流れていくのが見えるタイプのものだ。
親父は言った。「こんな古いもんは中々ないで、なあ、兄ちゃん」
エレベーター・ボーイは微笑みを浮かべ、沈黙を守った。
「指挟んだら飛んでいくやろな」とおれは言った。
それからおれたちは中華料理を食べながらいろんな話をした。窓外では、もちろんのことだが、雨が降っていた。やさしい雨だった。降っているのをことさらに主張するわけではないが、かといって無視はできない程度の雨だ。窓からは、いろんな色の傘が四条大橋を渡っていくのが見えた。遠くには霧のかかった大文字山が見えた。
いろいろと大切なことはあったはずなのだが、うまく思い出せない。そして、まったくどうでもいいようなことばかり思い出す。
こんな話がある。瓜生山の中腹にある友人の下宿でパーティーをすることになり、花火と肉を持って山を登っていったのだが、その途中で鹿に出くわした。時刻は夜で、鹿は電柱の灯りの下からおれのことをじっと見つめていた。そして、鹿はゆっくりとした歩みでそばにあった畑のなかに入っていった。
パーティーの帰り、というよりも次のパーティーへ行く途中、下山したところでタクシーを呼び止めた。三つ葉のクローバーが社号になっているタクシーだった。おれは乗り込んで三条東山と告げ、タクシーは走りだした。次の信号で止まったとき、運転手がカードをくれた。そこには「幸福の四つ葉タクシー記念乗車証」とあった。
インターネットによれば、このタクシーに乗車できる確率は約0.28%らしい。
ラッキー!
母親の話だ。
おれの母親は丹波あたりの出身で、子供のころは父親(おれの祖父)の林業を真似して野山を駆け回っていたらしい。祖父が事業に失敗し、大阪に職を求めてやってきたとき、彼女はもう十六歳だった。高校を卒業して明治安田生命の営業職に就き、すばらしい成績をあげ、支社長から表彰されるほどだったが、周囲からのいじめ(女のくせになまいきだ)に耐えきれずに退職した。よくある話だ。
ところで、水上瀧太郎は明治安田生命の専務取締役だったこともある。これは血縁による。
それから、どこかの会社の受付かなにかをやっているとき、自動車のセールスマンにしつこくからまれて、そのうちに結婚した。
それがおれの父親である。
彼らはおれが十四歳のときに離婚した。
以上。
おれたちが生まれてからの母は一度たりとも好調だったことがないらしく、そのことは彼女が家を出るときに忘れていった日記からも読み取れる。というか、おれの想像にすぎないのだが、彼女は調子が悪い日にしか日記をつけなかったのだと思う。日付は飛び飛びであり、最低でも一週間、長い時は一年以上の間隔をあけて書かれていた。そして、すべての内容は身体の不調についてであったり、生きることについての愚痴であったりした。たぶん、彼女は調子の悪さを吐き出しているつもりで書きつづけたが、そのためにはからずも長い年月をかけて、自分を本当に調子の悪い人間に仕立て上げることになったのだ。
いいことはあったのだろうか?
いいことというより、おもしろいことがあった。十六のころ、どこかの店で食事をしているときに、おれが煙草を吸い始めると、身体に悪いからやめなさいと言った。数年後の夜、彼女はおれに声をかけて、もらい煙草をした。
「あーあ」と彼女は言うのだった。「吸ってもうたわ」
「ええやんけ」とおれは答えた。「一服ぐらいせな、やりきれんで」
「それは、ほんまやねえ」
いったい何がやりきれなかったのだろう?
おれはおれの経験した不条理をいつも忘れてしまう。そして、やりきれないという気持ちだけが残る。その積み重ねがおれだ。おれを形作っているのは打ちのめされた経験ではなく、その感覚である。
おれという人間は、見えない糸で撚られた紐みたいなものだ。その先端には馬鹿者が繋がっていて、そいつは煙草をくわえている。
「火ぃ消した? なにわを守る 合言葉」
これは(公人どもの考案にしては)良い出来だ。
「すべてはあるがままにあるのだよ」とビリケンが言った。
「そうなん?」とおれは答えた。
「うむ」
ビリケンは早足に歩いているおれの側をふわふわと浮遊しながらついてきた。彼が座っている台座には英語で『全てのものがそうあるべきことの神』と記されていた。
おれは下鴨納涼古本祭りに行くために河原町通を北上しつづけていたが、やがて行きかう車の排気ガスが嫌になり、賀茂川の河川敷に降りて出て川沿いを歩くことにした。かんかん照りで遮るもののない河原はおそろしいほどの暑さで、水面に反射する陽光がおれの両目をなんども刺し抜いた。
「暑いね」とビリケンは言った。
「せやなあ」とおれは答えた。
「なんだかそっけないね」
おれはしばらく考えて答えた。「お前、なんで東京弁やねん」
「アメリカ生まれだからね」
「何?」
「ほんとうはミズーリ州で生まれたのさ」
「寝ぼけたこと言うな」
「うん、まあ、君が信じようと信じまいと構わないけどね」
カカカカ、とビリケンは笑った。器のでかいやつだ、とおれは思った。
「おまえはいままで会うた像のなかではいちばんええやつやな」
「そうかい? 嬉しいねえ」
「なんでお前はそんなに金ピカなんや?」
「新世界で塗られたんだよ」
「何?」
「もともと木製なのさ」
「おまえはおれの幻覚にすぎないが、なぜおれの知らないことまでそんなに自信たっぷりに言える?」
「君はあとからインターネットで調べて、僕の言ってたことがすべて本当だとわかって、びっくりするのだろうね」
「するのかもしれへんなあ」
カカカカ、とビリケンは笑った。
そうこうしているうちに鴨川デルタがあらわれた。この三角州こそが、京都の碁盤の目を突刺す鋭い刃先である。ここを境に北へ向かうほど京都の地形は混乱し、それにともなっておれの頭も混乱することになる。あわてて南へ引き返し、碁盤の目に戻ったところで手遅れである。すでに混乱に適応しはじめた知覚は、むしろ秩序のほうをよりひどい混乱と捉えてしまうのだ。
おれは鴨川デルタの先端からふたつの川をまたぐように配置された飛び石を歩き、無限に広がっていく終わりのない中州を北上して、下鴨神社の森にたどり着いた。開けた参道に数え切れないほど多くのテントが開かれ、その下にたくさんの書架が並んでいる。団扇をもらい、それで首のあたりに風を送りながら手当たりしだいに掘りかえし、気に入ったものは値札も見ずに購入して、リュックサックのなかに放り込んでいく。
肩までシャツをまくった女の子が、氷水をいっぱいに張った巨大な青い箱のなかのラムネを売っている。女の子はにこにこと笑っているが、うまく顔を見ることができない。おれの認識能力は、ずっと以前からだんご虫程度に下がっているのだ。ラムネを飲むおれのそばでビリケンがふわふわと浮いている。ビリケンはにんまりと笑顔をうかべておれに言う。
「あんた、アホやなあ」
それともあの女の子が言ったのだったか?
おれはかつて十代だったし、いまは二十代で、もうすぐ三十代になるだろう。十代のとき、おれはコンピューターとインターネットに夢中になり、昼夜を問わず電子の海を泳ぎ続けていた。すごい時代だった。おれはさまざまなものを鑑賞して楽しんだ。
そして、肉体をもたない、声と文字だけの数十人の友達がいた。おれたちは電子の海でスポーツさえ楽しんだ。一日に八時間ばかりそのスポーツをやったあと、寝るまでのあいだすべての接続を切り、すばらしい薫りのする孤独をぞんぶんに味わいながら映画を見た。
そして、口にするのもおぞましい蛇のような人間たち —— 肉体をもった人間たちがやってきて、聖域を破壊した。いや、破壊はしなかった、ただ、くだらないビルディングをあっちに建て、こっちに建て、金儲けをはじめた。
そういうものだ。
ある日、おれは目覚めて、いつものように坂道を下って街へと出て行く。京都市バスの3番に乗って、南へと向かう。バスが直角に曲がるたびに、襟首をつかまれて引きずり回されている気分になる。百万遍、河原町今出川、京都市役所前、河原町三条、河原町四条。
京都に住んだことのある人間なら誰でも知っているが、この街には何かの間違いでできあがった細長い路地がいたるところにあり、そのうちのいくつかはワームホールである。たとえば、裏寺町通りのコンビニエンスストアには、便所のそばに裏口へ通じる扉がある。そこを開けて出ると、ビルとビルのあいだの空隙があり、身体を横にして進んでいくと、千本中立売付近の料理屋群に出る。ほかにもいろいろあるが、秘密にしておく。
京都というだだっ広い街のさまざまな場所のどこに行っても、いつも似たような学生たちが散見されるのは、彼らがこのワームホールを使いこなしているからだ。それに、交通機関もたくさんある。地下鉄、市バス、タクシー。時間は節約しよう、青春は短い。
ワームホールや交通機関のことは置くとして、おれは実によく歩いた。歩いていると気分がよかった。とくに、春と秋がいちばんいい。夏は冗談じゃないくらい暑く、冬は雪が降るのだ。おれは素足にスニーカーを履いて歩き回った。
ときどき、酔っ払っているわけでもなく、ほんとうに道に迷うことがあった。どの通りも覚えがなく、地図もなくて、途方にくれながら歩き回る。昼なら太陽の位置からおおよその方角がつかめるが、夜となるともうどうしようもない。
部屋の壁に画鋲でとめた世界地図が風に吹かれ、壁とのあいだに空気を含んでぱたぱたと音を立てている。雨が降っているが、そこまで強くはないので、窓は開けたままにしている。ソファに座っていると、風が四肢を撫でる。
窓外の、すこし離れたところには大阪のビル群が並んでいる。白と赤と黄色と青のライトがすべての建物にくっついている。地面には大小さまざまな光が輝いている。都会の灯りのために、ビルの影のほうが夜のように暗い。その暗いビルのあいだに、赤い満月がのぼっている。赤い月はただそこにあり、じっと見つめていると、非常にゆっくりと上昇していく。
おれはなにをまなんだ?
おれは外に出て、傘を差さずに歩く。雨はずいぶん弱まっている。おれは雲の上にいるたくさんの天使たちが地上にむかって霧吹きをふきかけているところを想像する。頭の上には巨大な都市高速があり、その下の大きな通りにはだれもいない。理由はわからないが、すべての電灯は黄色っぽい光を放っている。
ぽわーん、ぽわーん、ぽわーん、という八十年代のシンセサイザーみたいな音がするので上を見ると、そこにはアダムスキー型のとてもりっぱなUFOがいた。皿のうえに逆さにした茶碗を乗せたような形だ。てっぺんには月とおなじくらいの明るさのライトがついていて、窓はおれの立っているところから三つ見える。真ん中の窓の後ろに誰かが立っているようだが、UFOのなかの光で逆行になっていて、よく見えない。
UFOは、ぽわーん、ぽわーん、ぽわーんという音を発しながらおれの立っているすぐそばまでやってきて、着陸した。茶碗にすうっと線が入って、ぱかりと開いた。なかの様子が見えたが、ひとことで言えば、ロシア構成主義をとりいれた数寄屋造りみたいな内装だった。
「やっと見つけたわ!」と中から声がして、青い目をしたブロンドヘアーの女の子があらわれた。おれはびっくりした。彼女はおれが大学のときに受けていた英語のクラスの先生で、おれは彼女に秘めたる恋をしていたのだ。
「先生、お久しぶりです」とおれは東京弁であいさつした。
「ひさしぶり」と彼女は答えた。「さあ、中に入ってください!」
彼女は小柄なくせに出るところが出ていて笑顔がとってもかわいいのだ。おれは一も二もなくうなずいて、乗船した。プスーン! という音がしてハッチがしまり、おれたちはペテルギウスにむかって出発した。
それがどうした?
空間の無駄遣いだ。
妹がトタン屋根の梁から自分自身をぶら下げる十日ほど前、おれはパーティー会場の壁際に設置されたパーティションの裏側の仮設楽屋のようなスペースで椅子に座り、硫酸を飲んだみたいに痛む胃を抱えたまま、よく冷えた白ワインを飲んでいた。胃が痛むのはなぜなのかわからなかった。申し分のない生活だった。女の子たちはかわいいし、教授たちとの議論は面白いし、図書館には本が山ほどあって、友人たちと毎晩のごとく酒を飲んで哄笑し、旅行をし、花見をし、海水浴をし、紅葉狩りをし、雪見をし、初詣をし、伏見稲荷で引いた御籤は大吉だった。
そしておれはすべてのことにかかわらず痛む胃を抱えたまま白ワインを飲んでいた。
同級生の女の子がなにも食べていないおれを心配して、立食パーティーの余りものを皿に盛って運んできてくれた。おれは味のしないスクランブル・エッグを一口食べ、塩辛いサラミを二枚食べた。
「もうええの?」とその女の子は言った。
「うん」とおれは言った。「胃が痛いねん」
「大丈夫なん?」
「だいじょうぶ」
「ムリしたらあかんで。あ、うちも食べよ」
女の子はべつの皿を持って食べ物をとりに行き、おれのところに戻ってきて食べ始めた。
「おいしいわぁ」
「おいしいねえ」
「こんなおいしいもん中々食べられへんで」と女の子は言った。
「ほんまやで」とおれは言った。「ビジネスホテルの朝食みたいな味や」
ハッハッハ、とおれたちは笑った。女の子はどんどん食べ、皿が空になるとパーティションで仕切られた楽屋から出ておかわりをし、また入ってきては食べた。
「そんなに食べて大丈夫なんかいな」
「大丈夫やで」
女の子のお腹はどんどん大きくなり、横に膨らみはじめ、しだいに縦にも伸びていった。おれは黙ってワインを飲み続けた。そのうちまた胃がきりきりと痛みはじめた。
「胃が痛いんだ……」とおれはつぶやいた。
しかし、女の子は消えていた。というより、膨らみすぎて宇宙とおなじぐらい大きくなっていた。というより、女の子こそが宇宙であり、宇宙こそが女の子だったのだ。
「なるほど!」とおれは言った。
そして気絶した。
ちなみに、妹が死んだのはこの夜から二日後のことだ。
目覚めたとき、おれはブロンドヘアーの女の子と一緒に宇宙船に乗ってペテルギウスを目指していた。合成食料のチップスを食べながらネットフリックスで『ゲーム・オブ・スローンズ』を見ていると、二人ともそんな気分になってきた。このまま事に及ぼうかと思ったが、ふと窓に目をやると、おそろしい事実に気づいた。この宇宙はビジネスホテルの朝食みたいな料理を食べ過ぎて宇宙とおなじくらい大きくなってしまった女の子そのものなのだ。そこで事に及ぶということは、一部始終を彼女に見られてしまうことになる。あの子は話していて気分のいい明るい子だったが、他人のうわさを誰彼なくしゃべってしまう癖があった。もしこんなところで事に及んだら、おれの学生生活はどうなる?
そういうわけで、おれはブロンドヘアーの英語教師と事に及んだ。やたらと声が大きかった。そういう教育を受けたのかもしれない。
事に及んだあと、英語の先生はしばらくのあいだおれの腕を抱いてまどろんでいたが、ふと上半身を起こして、船の前面にディスプレイされている地球の映像を見はじめた。太陽に照らされている面は明るく、照らされていない面は暗かった。
「いまブリテンは夕方くらいで、日本は真夜中なのね」と先生は言った。
「そうですね」とおれは答えた。「故郷の町の名前は?」
「ウォールゼン……」
先生は眼を細めた。
「スペルは?」
「W・A・L・L・S・E・N・D」
「壁の終わり? それとも……」
「わからない」
じっと地球を見ていると、ゆっくりと雲が動き、影が東へと動いていくのがわかった。おれは感心した。あそこにはたくさん人間がいて、生活しているのだ。喧嘩をやらかし、手を繋ぎ、泣いたり笑ったりして、いったい何のためにやっているのかまったく知らないままに、運命に従って生きているのだ。
いきなり、光の爪楊枝のようなものが宇宙空間から伸びて、地表を突いた。しばらくするとその爪楊枝は消え、突かれた部分はあとかたもなく消え去っていた。消え去ったのは、先生の故郷だった。故郷が属していた島国ごと消えていた。先生もおれもしばらく何も言わなかったが、やがてふたりでしくしくと泣いた。
そういうものだ。
京都で貧乏暮らしをしている学生のところに、貧乏の匂いをかぎつけた過去の英霊たちが現れ、もてなして冥界へ誘おうとすることがよくある。おれ自身もそういった体験をした。以下に、その経緯を簡単に記す。
おれが下宿していたのは志賀越道という、その名の通り滋賀へと抜ける道沿いのアパートだった。六畳一間で風呂はなく便所は共用だった。夜になると山のほうでもののけたちが動く気配がし、夏になると蛍光灯に導かれた蛾がひっきりなしに舞い込んでくるような部屋だ。
ある夜のこと、近所の銭湯から湯浴み道具をかかえて下宿に戻ろうとしていたのだが、通りの奥から牛のいない牛車がゴトゴトと音を立てておれのほうへ向かってきた。全体が青白い微かな光を放っていた。牛車はおれの前で停止した。おれは困惑しつつ待った。人が乗るところのすだれが開いて、男が顔を出した。
「誰や自分?」と彼は言った。
おれは名乗った。
「なるほど。麿は太平大公中納言左之峰氏なり。長いから左之、言うてくれたらええわ」
「左之さん」
「はいはい」
「あんた幽霊?」
「まあ、幽霊みたいなもんやわ」
えーっ、とおれは思った。
「ボク、はじめて見ましたわ」
「そうかいな! 自分京都住んでナンボ?」
「三年になりますか」
「そうかいな! 早い方ちゃうんかな? 土地のひとはよう見るみたいやけどねえ」
「そうなんですか」
「そやねん」左之さんはにっこり笑った。「なあ、これから志賀越道抜けて琵琶湖行くねんけど、一緒に行かへん?」
「いやー、幽霊と同乗はちょっと」
「酒あるで?」
「うーん」どうせまた、自分でも気がつかないうちにおかしなもので酔っ払っているのだろうと思った。だったら別にいい。「それは魅力ですなあ」
「せやろ。行こうや」
左之さんはにこにこしていた。
「では、ありがたくご随伴させて頂きます」
「おう! 丁度よかった、退屈しとったんや」
おれはいそいそと牛車に乗り込んだ。
「けっこう広いんですね」
「四人乗りやからな」
「ほー」
「新車やで?」
「すごい!」
おれが腰を落ち着けると牛車は動きはじめた。
「ままま、ひとつ」
左之さんが盃をさしてくれた。
「これはどうも」おれは献杯して干した。「うまい酒ですなあ!」
「せやろ。伏見から上等を取り寄せたんや」
「わざわざ伏見から! 人の足だと大変でしょう」
「まあ、いまはネットあるからな。アマゾンが高瀬舟で運んできよるわ」
「お住いは?」
「二条のあたりやね」
「だいぶん偉いさんとちゃいますの? ええんかな、ボクこんな感じで」
「かまへんがな。気ぃ遣わんでええ。このまま琵琶湖までひとりやったら退屈やなあ、邪魔くさいなあとか思うてたところや。丁度よかってん。好きにしてくれたらええで」
左之さんはにこにこ笑いながら盃をさしてくれる。
「ありがとうございます」
「うん、飲め飲め」
おれたちは酒を飲みながら楽しく琵琶湖を目指した。
「ほんで琵琶湖に何しに行くんですか?」
「うん、黒船が来とるちゅう話やからね、ペルリに会いたいなあ思うて見に行くねん」
「へえ。アポ取ったんですか?」
「アポなしや。そもそも連絡先も知らんし」
「飛び込みでっか、よろしいでんな」
「せや! やっぱり京の都を元気にするには麿みたいな官僚が頑張らなあかん。地場の企業の営業マンのほうがよっぽど偉いわ。麿もあいつらを見習ってペルリに顔売って、下のもんが仕事やり易いようにしてかなあかん」
「いよっ、日本一!」とおれは叫んだ。
牛車は志賀越道の半ばほどまで来ており、山越えの上り道が終わりかけたところだった。突如として木々の影から黒ずくめの忍者の一団があらわれ、牛車のまわりを取り囲んだ。牛車は停止した。
「何奴!」と左之さんは言い、すだれを開いて首を出した。
「攘夷!」という声が聞こえ、刀が振り下ろされ、すぱん、という音がした。左之さんの頭は幽霊なのにころんと転がって、志賀越道の山道をおむすびころりん的にころころと転がっていった。
忍者たちは快哉を叫んだ。
「やったぜ!」
「夷狄に与する国賊を仕留めたぞ!」
「これぞ攘夷!」
「我らこそ義賊!」
「尊皇攘夷! 尊皇攘夷!」
「攘夷! 攘夷! 攘夷!」
攘夷の合唱が続いた。
おれはどうしていいかわからずに牛車のなかでじっとしていたが、そのうちにぎやかな攘夷の声は遠のいていった。すると止まっていた牛車が勝手に動きだしておれを琵琶湖まで連れていった。左之さんの首なし死体(霊体?)は鎖骨を畳につけて尻を突き出した状態でぐらぐら揺れていた。
琵琶湖にたどり着いたが、黒船の姿はなかった。当たり前だ。まさか黒船が大阪湾から淀川をのぼって琵琶湖に来る訳はない。
左之さんの首なし死体は琵琶湖に葬った。宗派がわからなかったので、南無阿弥陀仏と唱えておいた。それで文句を言う人でもあるまい。
おれは牛車に乗って残された酒を飲みながら、来た道を戻った。左之さんがいないと、風に揺れる草花や木々の葉の音がよく聞こえ、なんだか寂しい気分だった。アパートの前まで来ると、牛車はひとりでに停まった。おれは牛車から降りて、一度だけ振り返り、自分の部屋につづく階段を登った。
湯浴み道具は牛車のなかに忘れた。
憂鬱症の男が気分を紛らわせるために街をさまよう。彼はアパートメントの一室に戻ると、自分の首吊り死体が天井からぶら下がっているのを発見する。彼はあわてて警察に電話をかけるが、電話はつながらない。アパートの階段を降りて、一階の大家の部屋の扉を叩く。返事はなく、誰も出てこない。いくつものドアを叩き、隣家にも助けを求めるが、誰も現れない。彼は町を歩くが、通行人は誰もおらず、すべての店は閉まっている。そして彼の背後で、大きなドアがばたんと閉まる音がする。
それでおしまい。
個人的な体験などひとつもない。おれが行うことはすべて、誰かがすでにやったことだ。肉体的な快楽や熱にうなされること、特定の店で出される特定のコーヒー、肉親を喪う苦しみ。普遍的でないことは、この世にひとつもない。
ボルヘスは言った、「まったくおなじ瞬間が二度繰り返されるのであれば、それは時間の連続性を崩壊せしめるものである」。
その通りだ。
彼はつづけて述べる、「連続体である空間が存在しないのであれば、どうしてもうひとつの連続体である時間が存在すると言うことができようか」。
記憶による過去も想像による未来も存在しないのであれば、現在をそこから切りわけることなど不可能であり、したがって現在から派生する幸福も苦しみも存在しない。
そこにはまことの法悦に満ちた永遠だけがある。
では、なぜ涙が溢れるのか?
おれの部屋には三種類のものがある。本と、いくつかの楽器、それにコンピューター。まあ、よくある感じだ。
おれの部屋のなかにあるもっともおもしろい物は、おれが子供のころから溜めつづけている雑多な家電製品のコードだろう。電源ケーブル、音声や映像の入出力端子、LANケーブルなどなど。それらのコードは、長年のあいだ積み重なった怠惰のためにきちんと整頓されておらず、たがいに絡みついてひとつの塊と化している。
ときどき、使っている家電製品のケーブルがなくなると、おれはその塊を解きほぐして目当てのケーブルを探しだす。古い、もう誰も覚えていないような出力規格をもったケーブルや、古き良き時代を思い出させる商品名が記されたラベルつきのACアダプタに混じって、お目当てのものが見つかる。おれは塊のなかからその一本のケーブルを抜き取り、べつの部屋で家電製品に接続する。そういうとき、おれの頭のなかにはいくつかの考えがひらめく。
牛車の話だ。
眠ったのは部屋に帰ってからだと思っていたが、そうではなかった。おれが目覚めたのはオレンジ色のホンダ・シティの後部座席のなかだった。ルーフを全開にしていたので、顔に虫かなにかが当たり、それで目を覚ましたのだ。目を開けていられないほど眠かったが、車は時速八十キロで川端通りを下っており、風の音が大きすぎて、もういちど眠ることはできなかった。
運転しているのは、いつの日かにおれを雨宿りさせてくれた先輩だった。
「先輩、飛ばし過ぎとちゃいますか」とおれは叫んだ。
「何?」と先輩は叫び返した。
右手に並ぶ鴨川沿いの柳がどんどん後ろへ流れていった。追いぬかれた車も、対向車も、おれたちにむかってクラクションを鳴らした。左手に並ぶ家々や商店の並びは一瞬の光の軌跡を残して視界から消えた。歩行者たちはおれたちの姿を見て大仰に身体をのけぞらせた。おれは身をかがめて煙草に火を点けたが、すぐに火種がどこかへ吹き飛んでしまった。信号待ちをしているときにパトカーがあらわれて、おれたちを追跡しはじめた。東山三条界隈の、通り名をもたない細長い道に入って追跡を免れたが、その過程で三つのごみ箱と二匹の猫を轢いた。
コンビニエンスストアでウエスを買い求め、汚物にまみれたシティをきれいに磨き上げたあと、おれたちは三条河原町のすぐそばの名前のない通りに入った。ルーフをあけたままのシティはとてもゆっくりと、静かにその通りを進んだ。おそろしく暑い夏だったが、その夜にはきまぐれな涼風が肌をやさしく撫でた。細い通りには、階級の低い天使のような薄着の学生がたくさんいて、みな笑顔を浮かべていた。漫然とした気持ちでその光景を眺めた。そのとき、人々のなかから浮き上がるように見えたが、白いノースリーブのブラウスを着た女の子が、男の子と手をつないだままおれたちの側を通りがかった。おれは後部座席に頭をあずけていた。女の子は一緒に歩いている男の子にやさしい視線を投げかけていたが、ふとおれたちの乗っているシティに目をやり、このおもちゃみたいなかわいい車はいったいなんだろう、という顔をした。おれはその女の子に見とれていたが、そこで女の子と目があった。女の子があまりにも美しかったので、おれは微笑みを浮かべた。
すると、女の子も微笑みを返してくれた。
それは一秒にも満たない間に起きたことだったが、女の子がおれになにを言おうとしたのか、いまのおれにははっきりと判る。
「ねえ、こんな夜がずっと続けばいいと思わない?」
喪は永遠に消えない。五年、十年はあっという間に過ぎ去るだろう。そして人々は生き延びるだろう。しかし、元通りにはならない。脳は破壊され、心には傷が残る。その痕跡は時の流れのなかで人格と溶けあい、生は、もはや記憶ではなく忘却によって規定されることになる。彼は、彼女は、とにかくその人格とともに生きなくてはならない。発話もままならず、あらゆるものに置き去りにされるだろう。すべてに疑いの目を向け、どこまでもつづく地獄を思って嘆息するだろう。
それでも彼らはのそのそと歩き続けるだろう。このばかげた騒ぎをみんなで続けるために。
電子的なスポーツの話だ。
そのスポーツはふたつのチームに別れ、片方がゴールを守り、片方がゴールを攻める。途中でいちど攻守を交代し、攻め落とすまでに要する時間を競う。電子的な肉体でぶつかりあい、旗を取ったり守ったりする。
これは集中力と反射神経、そして刻々と変化する状況に対応するための柔軟かつすばやい思考が必要なスポーツである。
おれはこのスポーツを八年間やりつづけた。そして、誰もいなくなった。馬鹿馬鹿しい乱痴気騒ぎが終わったあと、みなが家に帰り、次の日からフィールドに姿を見せない。文化というのは、そういうものだ。
画像が出力され、ディスプレイに表示されるまでの時間のことを応答速度という。この速度を改善するために、おれはわざわざ二十年もののブラウン管をヤフー・オークションで手に入れ、米俵くらい重たいそれを自室に運び込んだ。そのモニターを使い始めてから、成績はおもしろいように伸びた。
電子的なスポーツが衰退し、誰ひとりプレイヤーがいなくなったあと、九月のよく晴れた気持の良いある日、そのブラウン管はブツンという音をたてて壊れた。一本の白い線だけを残して、ほかにはなにも映しださなくなった。
この話から得られる教訓はひとつ。永遠につづくものは、この宇宙にはない。
三菱ダイヤモンドトロンRDF192S、それがブラウン管の商品名だった。
入力端子のケーブルは、いまだにコードの塊のなかにある。
その日は雪が降っていた。おれは上着にポケットをつっこみ、背中を丸めて、見えないところからとつぜん現れては地面に積もっていく雪のなかを歩いていた。長いこと食べていなかったし、アパートにはひとかけらの食料もなかったのだ。真夜中だった。
いくつかの友人たちのドアを叩いた。いや、そのときにはもう友人とは呼べなかったかもしれない、だから、ただの知り合いのドアだ。とにかく、すべてのドアが閉ざされたまま、開くことはなかった。おれが拳を叩きつけると、ドアは凍った。
このあたりで雪が降るのはめずらしいことではない。おれはドアからドアへと歩きながら、退屈しのぎに雪だるまを作ることにした。握り拳をふたつ合わせたくらいの大きさの塊からはじめて、足で蹴り、手で押し、さいごには肩で押して歩いた。自分の胸くらいまで塊が大きくなり、どうしても動かなくなるというところで、北白川今出川の交差点に差しかかった。そこは西にむかって続く長い下り坂の始点だった。雪の塊は重みのために低い方へと動き、やがて雪を軋ませながら転がりはじめた。おれはそれを止めるために追いかけたが、転がりながら雪の塊はどんどん大きくなり、やがておれの背丈を超えた。おれは止めることをあきらめて、並走しながら、どうなるか見守ることにした。
志賀越道と今出川通りの合流点のところには祠があり、高さ二メートルほどある地蔵が祀られている。巨大な雪だるまはその地蔵に激突し、音をたててばらばらに砕け散った。おれは地蔵が傷ついたのではないかと心配になり、しばらく調べたが、異常はないようだった。なんだか拍子抜けして家に帰ろうとしたとき、建物と建物の間、そのむこうにある闇のなかに白い雲のようなものが浮かんでいるのが見えた。
雪が強くなった。おれは目を細めてその雲を見た。遠くから、鈍い、ずうううん、ずうううん、という音が聞こえた。とても低い音だった。その音がするたびに、白い雲はゆっくりと近づいてくるようだった。
それは雪だるまだった。
雪だるまはとても大きかった。
おれは立ち尽くした。
「お・い・で……」と雪だるまが言った。低い声だった。
雪だるまの鼻はクリスマスの飾りがついた樅の木で、目玉は建築物の解体に使うような鉄球だった。帽子は比叡山で、口は三日月だった。
「お・い・で……」
おれは叫び声をあげて逃げたが、後ろから覆いかぶさられることはわかっていた。走りながら息が上がってきて、これ以上はもう動けないというときにやられるのだ。
妹が死んでしまったとき、おれはこのことを書くのだろうと思った。そして何度も試したが、うまくいかなかった。理由はかんたんだ。
おれは妹のことをよく知らない。
遺品はまたたくまに処分された。残されたのは、写真ばかりである。死人に属していたものはすべて、きれいさっぱりと捨ててしまうこと、それが生き残るための秘訣なのだと父は考えていた。そうすることで、穢れを払うのだ。おれにはどんな意見もなかった、というのは、他者の死に接するのはそれがはじめてのことだったから。死に関する意見があるはずもない。おれたちは冷静に遺品を処分した。
死体になった妹は臓腑を抜かれ、仏間に敷かれた布団のなかに横たえられた。死化粧を施された顔がおそろしく美しかったことを覚えている。身体中にドライアイスを仕込まれていて、手は冷たかった。父親は右側にいて、泥酔したままいつまでも死人の手を離そうとしなかった。頭のうえには、仏壇があった。その仏壇はなかなか良い出来で、収められた仏像の顔は小さかったが、慈しみをたたえていた。
おれが妹について言えるのは、これだけだ。どの学校に行って、何歳だったのか、どんな食べ物が好きで、お気に入りの歌手は誰か、それくらいのことは知っている。でも、それ以上は知らない。恋をしていたか、なぜ逝くことに決めたのか、どんなことを考えていたのか、何も知らない。
だから、おれは物事をシンプルに受け入れようとした。あるひとりの人間が生きていて、ある日、死んでしまった。それだけのことだ。ある人間がひとりこの世からいなくなり、もう二度と会うことができない。それだけのことだ。
そこにはどんな物語もない。原因もない。結果だけがあり、それは金糸で縫われた布団のなかに眠る妹の死体で、いまではおれの記憶のなかにいる。
そしておれも憂鬱症を発症した。とりたてて好きでも、嫌いでもなかったはずなのに、彼女がいないことがたいへん寂しく感じられた。
いまでは、そうしたことも本当に起こったのかどうか自信がない。記憶というものは、あいまいなものだ。
そして悲しみというものは、わがままなものだ。おれは妹のことをほとんど語らず、自分の悲しみのことばかりを語っている。
他人について語ることほど、空虚なことはない。語っているうちにだんだんと、ほんとうらしい言葉が失われていく。
おれの両親は、おれが十四歳のときに離婚した。その理由はよく覚えていないし、あらためて電話をかけて、父に聞く気にもなれない。ただ、おそらく母が家を出て行った日の晩のことだろう。父がテーブルに座り、ビールが半分ほど入ったグラスを手に持ったまま、悪くなった魚のようなどろりとした目で中空を見つめていたのを覚えている。おれはたしか、なぜ母が出て行ったのか質問したはずだ。
「そんなふうに出来とるねん、人間の関係というもんは」と父は答えた。
その発言は楔のようにおれの心に打ち込まれた。ふたつの車両がおなじレールを走っている。ひとつが切り替えポイントを過ぎたあと、誰かがレバーを引く。それで、もうおしまいだ。どれだけの時間をともに過ごしたかなど、なんの関係もない。ふたつの車両は、二度と出会うことはない。
おれはさまざまな人と出会い、さまざまな人と別れた。誰もがそうだろう。繰り返しだ。これは原則なのだ。
おれが死ぬときにこの世界は終わり、その原則も無効となるだろう。時の流れは、口を合わせた二本の試験管のようなものだ。なかにはヘリウムガスが充満していて、おれが動くと光が起こる。試験官のまわりには、なにもない。無だ。それは闇ですらなく、紫色のブーンという音ですらない。ただの無だ。
何もかもが終わるだけだ。燐寸のようなものだ。ぱっと灯りがついて、消えて、それでおしまい。
あまりにも無力だ。
せめて、風や鳥の鳴き声とおなじようなものでありたかった。ひとりの人間ではなく、地平線や、稜線や、海のようなものでありたかった。太陽でも、石ころでも、切り株でもいい、そうしたものでありたかった。
おれは志賀越道と今出川通りが交わる地点の大きな地蔵の前で目を覚ました。
視界の端に地蔵のご尊顔があったので、場所はすぐにわかったが、どうしても身体が動かなかった。たくさんの蛇に体中を弱く噛まれているみたいな感じがした。とりあえず右足が動いたので、そこだけ動かしているうちに、だんだんとほかの部位も動かせるようになってきた。ゆっくりと身体を起こしたが、節々が傷んだ。脈打つごとに誰かに殴られているみたいだった。体じゅうについた雪のかけらを払い落とし、ポケットから煙草のパックを取って、一服つけた。
雪はさらに降り続いたらしく、気絶したときよりも多く積もっていた。京都市というよりも、日本海沿岸のどこかの街みたいだった。あまりに雪が多いので空すら白く、無数の屋根のあいだから覗いている無数の家の外装だけが黒かった。長く続いた戦争のあと、あらゆる色が白にやられてしまった、という感じだった。
おれは歩いた。行き先はなかった。何をどうしていいものか、わからなかった。
どこへ行けばいいというのだ?
おれは神社のようなところにいて、ポケットに両手を突っ込んだまま、中庭に立ち尽くしていた。誰の姿も見えなかった。みんな家のなかにいるのだろう。
本殿の賽銭箱の上にはりっぱな鈴緒があり、縄のいちばん上には、人の頭くらいの大きさの玉虫色の鈴がくっついていた。
その鈴のひとつには家電製品の延長コードが巻きつけられており、余りがぶら下がっていた。
さらにその余りの先に人間が首からぶら下がっていた。近づいて見てみると、その人間はおれ自身だった。
ぶら下がっているおれは目を閉じ、口を一文字に結んで、もう感じないはずの寒さにじっと耐えているように見えた。すこし伸びた前髪が瞼にかかり、睫毛に雪のかけらがついていて、無精髭が伸びていた。彼は —— おれは —— 寒そうであるのを別にすれば、とても安心しているように見えた。家族や、友達や、恋人のそばにいる人のようだった。何もかもを許し、何もかもを認めた人のようだった。
おまえはなぜ死んだ、とおれはおれに向かって言った。
そういうもんや、とおれは答えた。
しかし、それはあんまりじゃないか、とおれは言った。
何がやねん、とおれは答えた。強風が起こり、おれはすこし揺れた。
だって、おれたちは、まだ何にもしてないぜ。
何にもって、何やねん。
沖ノ鳥島に海水浴に行ったり、凍ったままのコケモモを口に含んだり、温泉玉子を作ったり、自分とちがう人種とセックスをしたり、東南アジアに行ったり、してないぜ。
忘れろ。
忘れるって、何を。
もう終わったんや。
延長コードがぶつりと音をたてて切れ、おれは地面に落ちた。からからん、という鈴の音がした。おれはしばらく地面に落ちたおれを見ていたが、どうするつもりもなかった。おれは悲しくなかったし、寂しくもなかった。それはたぶん、おれ自身もおなじだっただろう。
そういうものだ。
ブロンドヘアーの先生といっしょに宇宙船のなかでひとしきり泣き通したあと、おれたちは理由付けを始めた。けっきょく、すべてはダーウィン的な淘汰の結果なのだとか、宇宙のそもそものはじまりからこうなることは決まっていたのだとか、いろいろ理由をこさえた。
悲しみは消えなかった。
「あなたを助けてあげられなくてごめんね」と先生は言った。
「どういうことですか?」とおれは答えた。
「だって、あなたはただの魂だもの。私たちはいまから、ペテルギウスにある天国に行くのよ」
「そいつはいいなあ」おれは彼女の言うことをまったく信じていなかった。
「ペテルギウスはとても遠いから、時間の流れ方が違っていて」と彼女は言った。「そこでは過去に向かって未来が流れるのよ」
たしかに、ペテルギウスはとても遠かった。あまりに遠いので、宇宙の中心を通り過ぎてしまい、空間の座標値が負の値に達して、たどり着くころには時間の流れが逆転していた。天国のつくりは非常にシンプルで、完全に平坦な白い床がどこまでも続いていた。先生によれば、この床には厚みがなく、歪曲していて球体のようにつながっているのだが、球体の中心はどこにもないのだという。
「永遠みたいなものなの」と先生は言った。
「ふーん」とおれは答えた。
「さあ、妹さんに挨拶してらっしゃい」と先生は言った。「私はウォールゼンに帰って、晩ご飯にママが作ってくれた鰻のゼラチン寄せを食べるわ」
そして先生はポンッという音をたてて消えた。あとには白い煙だけが残った。
「手品みたいやな」とおれは言った。
妹はすぐ近くにいた。ということは、とても遠くにいたということである。過去と未来が逆転しているので、すべてがあべこべなのだ。そのときおれが妹と交わした会話をどう言い換えていいものかわからないが、とにかくこんな話をした。
こんな話をしたというより、こんな話をするだろう。そんな感じだ。
「さようなら」
「さようなら」
「わたしは誰?」
「おれは誰?」
「うん?」
「うん?」
妹の顔にはなにもなかった。のっぺらぼうなのだ。白っぽい平面があるだけで、なにもなかった。服を脱がせるとマネキンみたいになっているのだろう。
ここまでおれは彼女のことを知らなかったのか、という気がした。
これは妹ではないのではないかという気がしはじめた。こんなにのっぺらぼうなわけもあるまい。そこで、身元確認のためにいくつか質問をしてみた。地球的な意味に翻訳できるような会話はひとつもできなかった。そして気づいたが、おれは妹のことに限らず、あらゆることを忘れていた。自分の顔を触ってみると、妹とおなじようにのっぺらぼうだった。何もついていない、瞳すらないのだ。だとすると、いま見えているものは何だろう。
そして妹はポンっという音を立てて消えた。白い鳩が数羽飛び去って、あとには白い煙だけが残った。
「何なん?」とおれは言った。
おれは地面に寝ていた。雪は降っていなかったが、積もったものが残っていた。ぶあつい雲の隙間から午後の太陽がすこしだけ見え、あたりを照らした。
おれは鳥居をくぐって神社を出た。それから、大文字山にむかって歩きはじめた。それは御蔭通だった。北白川通に向かってなだらかに上っていく道だ。途中にあるのはおもに民家と、フランス料理屋、散髪屋、喫茶店、整骨院、蕎麦屋などである。膝がこちこちに凍っていてうまく足が上がらなかったが、踵を引きずって歩いた。途中、何度か転んだが、あまり痛くなかった。
北白川通にたどり着くと、ちょうど近所の大学で授業が終わったところなのだろう、たくさんの学生たちが通りを歩いていた。彼らは、赤や青や緑色の、さまざまな形をしたコートを着て、楽しそうに会話をしながら歩いていた。女の子たちが声をあげて走り去っていったが、走りながら雪合戦をしているのが見えた。男の子たちが湯気のたつコップ酒を飲みながらゆっくり歩いていった。年取った夫婦が手を繋いで歩いていった。栗色の毛をした小鳥が並木のなかから人間たちのことをじっと見ていた。
おれは着ていた服にこびりついた雪と泥をできるだけ丁寧に払い、大文字山に向かった。雪のなかに埋まった並木の枯れ葉を踏みつけると、チーズ・クラッカーを齧ったような音がした。おれは想像のなかで何十枚ものチーズ・クラッカーを齧りながら歩いた。ちいさな本屋があり、ラーメン屋があり、中華料理屋があり、クリーニング屋があり、よくわからない小物を売る雑貨店があり、スーパーマーケットがあり、パン屋があった。
銀閣寺道に入り、寺のそばを抜けていくつか角を曲がると、大文字山の登山口を見つけた。おれは立ち止まることなく登りはじめた。雪は残っていたが、土のなかに埋め込まれた階段のまわりはきれいに掃除されていた。
一時間ほどかけて、大文字焼きの台座のそばまでやってきた。雪に半ば埋まった京都の街が、遠くまでよく見えた。しばらく眺めていると、厚い雲のあいだから、沈みかけた赤い太陽があらわれた。太陽は赤色の光を街に投げかけ、雪がその光を反射して、影のない、奇妙なほど赤色の景色をつくった。おれは目をつぶり、おそろしいほどの寒さが身体の中心から湧き上がってくるのを感じた。
背後にあった、登山者の安全を祈っているのだろう、小さな仏像がおれに話しかけた。
「朝は四本足、昼は二本足、夜は三本足の動物ってな~んだ?」
おれは無視した。
「に~ん~げ~ん~」と仏像が言った。
おれは仏像の頭をつかみ、街にむかって投げた。仏像はとてもよい勢いで飛んでいき、志賀越道と今出川通の合流地点に立っている巨大な仏像とぶつかった。
「痛いがな!」非常に巨大な声で巨大な仏像が叫んだ。
あまりにも巨大な声だったので、空が割れた。
そこから天使たちが降りてきたらしいが、おれはよく知らない。
気絶したからだ。
思うところがあって母に電話をかけてみたが、繋がらなかった。そういうものだ。
家のなかにはめったに開けることのない扉というものがあり、たいていの場合、そこには過去の記憶が詰めこまれている。おれはその扉をあけて、なかを探ってみたことがある。アルバムが出てきた。妹が写っているものは十枚とすこしあった。
そのうちの一枚がおれの注意を惹いた。制服を着ているから、たぶん高校生のときのものだろう。どこかの海辺の公園らしいところの欄干にもたれている。おそらく、父が撮ったものだ。
ずいぶん引いていてよく見えないが、うっすらと微笑んでいる。ただそれだけの写真だが、異様な感じをあたえる何かがひそんでいる。どんなとらえかたもできそうだ。孤独をたたえていると言ってもいいし、心から喜んでいるとしてもいい。無表情ではない、微笑みだ。だが、そこにはどんな意味もない。
目元の影から、彼女が数年後にトタン屋根の梁から自分をぶら下げることが暗示されている、と読み取ることもできる。その影にひそんでいる寂しさのようなものが、口当たりのいい原因になりそうな感じがする。
しかし、そんな理由付けは、しない。
彼女が死んだことにどんな理由もない。ただ、そうなっただけだ。原因も結果もない。
形を変えながら、ものごとは永遠に続いていく。なにごともなかったかのように明日の生活がはじまる。
明日の生活がはじまる。
つぎに目を醒ましたとき、おれは白い床がどこまでも続く空間にいた。英語の先生といっしょに来たところだ。おれのまわりには数体の像がいて、おれをとりかこんでいた。白川沿いの岩と一体化した地蔵、吉田松陰、ビリケン、滋賀越道と今出川通が交差する場所にある巨大な地蔵、そして大文字山の仏像。
おれは像たちに話しかけてみた。
「どないしたん? みんな揃って」
像たちはなにも答えなかった。
像は像にすぎなかったのだ。
それってありなんかなあ、とおれは思った。
いままでさんざんおれにつきまとってきたのに、もう喋らないというのはなんだか気にくわない。無視されているような感じだ。しかし、喋らないものは仕方がないので、おれはその場に横になって空を見た。空はピンク色だった。不思議な色だ。
「なんでひとつも思い出せへんねやろなあ」とおれは空にむかって言った。
なんでやろうなあ、と空が答えた気がした。
「なんでおれたちは何もかも忘れていくんやろう。あんまり忘れすぎて、大切なことから先に消えていくような気がする。なぜなんやろう?」
空はなにも答えなかった。
四条大橋の西詰めにある中華料理屋で親父と話した内容を、そのとき思い出した。
「サイパンに行った」
そのとき、おれは自分の部屋にずっと掛かっていた額縁のなかの写真を思い出した。
「透明な海やったね」とおれは答えた。
「そう、透明で」と親父は言った。
写真のなかには幼児の兄妹が写っていた。ふたりとも裸だった。
「綺麗やった」
不思議なピンク色の空は、むこうのほうに行くほど紫色になっていた。おれは立ち上がって、その紫色のほうに歩いた。すると、門があった。鉄でできたアーチの下をくぐるようなやつだ。アーチには、「さようなら」と書かれていた。その向こう側は完全な紫色だった。
ブーンという音がしていた。
それだけだった。
それより向こうに行くべきだろうか、とおれは思った。行っていいものだろうか? 向こう側は平和そうだ。見たところ、なにも起こっていないようである。生きることは楽しいし、死ぬことは平和である。こちら側はどうだろう? 振り返ると、遠くのほうに五つの像があった。それらは動きも話しもしなかったが、延々と続く白い地面のなかで、唯一の変化のように思われた。なにかがあるということは、そういうものだ。
そしておれはけっきょく「さようなら」と書かれた門の向こう側へ行かなかった。
門のところから引き返して像のところへと戻る途中、気持ちのいい風が右のほうから吹き抜けて、おれのなかにある悲しみをすべて奪っていった。おれはびっくりして、悲しみがなにもなくなったので笑顔になって喜んだが、同時に必死になって風を追いかけた。
それはおれのものだ。
返せ!
風は女の子の姿をしていた。古本市でラムネを売っていた女の子であり、三条でおれに笑顔を用いて話しかけた女の子だった。風は大きな壁にぶつかり、四方に砕けた。おれの悲しみがその場にぽろぽろとこぼれ落ちた。おれは地面に膝をついて両手で悲しみをかき集め、宝石のようになったそれを口の中に含み、舌で舐めた。悲しみはあめ玉のように溶け、苦い味がした。しばらくすると、悲しみが身体じゅうにまわるのがわかった。おれは悲しくなった。
これで元通りだ。こうすればいつまでも変わることはない。
やったね!
見上げると、壁が空にむかってどこまでもつづいていた。終わりはない。
女の子がおれのまえに現れて言った。
「あんた、アホやなあ」
おれはムッとしたが、すこし考えてから、笑顔をつくってこう答えた。
「そうですねん、ヨダレクリのハナタレですねん」
いま、おれはこの小説を書き終えて、ほっと一息つく。窓に目をやると、やさしい十月の日差しが街を照らしているのが見える。阪神高速のうなり声と、遠くの公園で泣いている子供の声が聞こえる。おれは煙草に火を点け、窓から十分ばかり街を眺める。
それから、おれは外に出て、いちばん近くにあるスーパーマーケットに向かう。人々は休日を満喫している。だれもが楽しそうに微笑み、いっしょに歩いている人となにか話している。ビルの隙間に見える青空は驚くほど高い。鱗雲が点々と横たわっていて、もうすぐ訪れるはずの、長く厳しい冬を予兆している。
しかし、人々は気にも留めずに、いっしょに歩いている人とずっと話を続ける。
スーパーマーケットに入り、買い物カゴを手に取って、いわばディスプレイのために製造された雪山のような商品の棚を眺める。ジム・ビームが、オレンジが、インスタント食品が、ピラミッドのようにうずたかく積まれている。しかし人々はそんなものは存在していないかのようにふるまう。おれはきっちりと整頓されたジム・ビームのディスプレイから一本を抜き取って、その秩序を乱してみる。もちろん、なにも起こらない。
さまざまな酒が売られているところに入り、十分ばかりいろいろな酒瓶を検分する。とある酒瓶には、この酒をつくったスコットランドの蒸留所は一六八七年に創業した、と記されている。さらにいくつかの酒瓶を眺めたあと、ほかの瓶を手に取る。
おれは酒が売られているあたりを探し回り、やっとのことでトニック・ウォーターを見つける。それから青果売り場に行き、メキシコ産のライムをひとつカゴに入れる。レジに行くあいだにふと目についたオイル・サーディンを手に取る。パンはあとで買うことにする。
レジの前に立って順番待ちをしているとき、こんな会話が聞こえてきた。
「もう一度やり直せるなら、誰とがええ?」
「アホ以外がええな」
帰りぎわにいつも通りがかるパン屋。いつも裏側の通りを行くのだが、とてもいい匂いがするので、なかに入ったら気絶してしまうような気がして、入ったことはなかった。ドアを押し開けると、鈴の音がした。店のなかは静かだったが、音楽がかかっていた。
たくさんのパンがあった。チーズのかかったやつ、トマト・ケチャップとベーコンのかかったやつ、クロワッサン、チーズが埋めてあるやつ、カレーが中に入っているやつ、ソーセージが埋まっているやつ、にんにくで香りをつけたフランスパン、クリームが入ったパン、あんこが入ったパン、鶯餡が入ったパン、ヨーグルト味のクリームが入ったタルト、ブルーベリージャムが乗っているもの、いちごジャムが詰まっているもの、チョコレートが入ったコロネ、スクランブル・エッグが入ったパン、唐揚げが乗ったパン、肉萬のたねが入ったパン、ベーコンとレタスとトマトのサンドウィッチ、卵のサンドウィッチ、ツナのサンドウィッチ、玉葱とアボカドとドレッシングのサンドウィッチ、ハンバーガー、チーズバーガー、フィレ・オ・フィッシュ。
食パン。粉砂糖のかかったクロワッサン。クラムチャウダーが詰められたパン。ミネストローネが詰められたパン。ピザ・パン。カスタード、ミルク、チョコが詰まったそれぞれのパン、ポテト・グラタンが乗っているやつ、ベーコンが挟まったベーグル。ビーフ・シチューが乗ったパン。オリーブの酢漬けが入ったパン。生地に人参を練り込んだフランスパン。ごまを練り込んだフランスパン。青のりを練り込んだフランスパン。ふつうのフランスパン。
ふつうのフランスパンをトングでつかみ、プラスチックのトレイのうえに置き、レジまで持っていく。時計がかかっていて、四時十六分を指している。壁にはニスがたっぷり塗られた何枚もの木がびっしりと張りついている。おれはうつむいていて、レジの女性がちいさな袋のなかにフランスパンを入れるところしか見えない。エプロンはデニムで、胸のポケットに三色のボールペンがさしてある。染みも皺もない白いシャツ。肌。財布から小銭を出して、お金を渡す。彼女はそれを受け取り、レジのボタンを押す。そのときはじめて気づいたが、女の子はおれとおなじくらいの年頃で、おれにパンを渡してくれるときの笑顔がとても美しい。そのことを伝えてみようかと思う。勇気を出して、言ってみようかと思う。この子はきっと喜ぶだろう。
だが、言わないでおく。
おれは自分の家に戻る。ナイフでライムを半分に切り、もういちど半分に切る。タンカレーをグラスに四分の一ほど注ぎ、ライムを搾る。氷をふたつグラスに入れる。トニック・ウォーターの栓を開けて、炭酸が抜けないように、グラスを傾けて面のうえを水が流れるように注ぐ。浮かんできた氷を指先でやさしく沈めると、グラスの全体からこまかい泡が集まってきて、小川のせせらぎのような音をたてる。
フランスパンを切り、オイル・サーディンの缶詰を開ける。キッチンテーブルに運んで、それらをきっちりと並べ、しばらく眺める。窓からは、低くなった午後の太陽の名残がさしこんでいる。洗濯物がゆらゆらと揺れている。近くの線路の上を電車が走る、高速道路のうなり声、遠くのほうでやっている工事の音がかすかに聞こえる。
おれはグラスをつかみ、ジン・トニックをひとくち飲む。
それはとてもおいしい。
それから、書きかけたまま放っておいた小説のことを考える。そのとき、めったにないことだが、開け放した窓のむこうのベランダに小鳥がやってきて、なにごとかを歌う。
しばらくのあいだ、鳥の鳴き声に耳を傾ける。
すばらしい音だ。
おれはフランスパンを噛みちぎり、咀嚼して、呑みこむ。
そしておれはいままでにおれが出会い、別れてきたすべての人間の笑顔を思い出す。
「それでも」とおれは鳥たちに返事をする。「おれはお前たちが作った世界のデザインを、絶対に許さないからな」