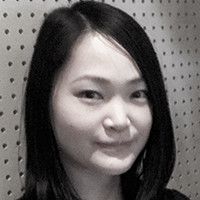江川あゆみ:
「エコクリティシズム」と呼ばれる文学研究の、日本における牽引者のお一人である結城正美さんに、エコクリティシズムとは何か、また日本でのエコクリティシズムの状況、ご自身の研究について伺っていきたいと思います。
まずは、エコクリティシズムがどのような文学研究か。それが成立した背景や、これまでどんな展開を見せてきたのかをお聞かせください。
結城正美:
包括的に言えば、「エコクリティシズム」は人間と環境との関係をめぐる文学研究です。研究が組織的に始まったのは1990年前後です。1960~70年代に、それまでの白人男性作家中心の文学研究が見直され、人種やジェンダーの問題に目が向けられる修正主義的な動きがありました。そして、環境の時代が世界的に幕を開けた1970年代から、今エコクリティシズムと言われているような研究が個人レベルでは存在しはじめていました。しかし、個人レベルでは相互参照は難しく、学会がなければ共同研究や研究交流もなかなかできません。
エコクリティシズムはいくつかの変化を経てきました。これは波のメタファーで語られることが多く、「第一波」からはじまって、現在を「第四波」だと言う人もいます。最初期の第一波では、人間と環境の関係と言うとき、環境という言葉は主に自然環境、とくに野生の環境を指していました。研究者も白人研究者が中心でした。
その後、エコクリティシズムの内部から、自然環境に焦点を当てることを批判的にとらえる動きが出てきます。社会環境を視野に入れて、人種やジェンダーの問題も環境問題に結びついているという認識が共有されていきました。それとともに、研究者も人種やジェンダーの点で多様化し、国や地域も脱アメリカ中心的な広がりをみせます。なので、エコクリティシズムは非常に多様化している文学研究だと言えるでしょう。
エコクリティシズムには、文学研究における「キャノン(正典)」の問題も含まれています。文学研究と言うと小説が批評の対象に据えられることが多い。しかし、エコクリティシズムでは英語でいう“literature”(書かれたもの一般)が批評対象である点が大きな特徴です。
初期の頃に注目されたのは、「ネイチャーライティング」と呼ばれる自然環境についての一人称ノンフィクションエッセイでした。ノンフィクションエッセイは、文学研究でほとんど取り上げられてこなかったのですが、エコクリティシズムでは一人称ノンフィクションエッセイにこそ、人と環境との関係をめぐる深い思索が織り込まれていると考えられてきました。ほかにも、映画や漫画、アニメなどの文学表象に関わるものまで、広くエコクリティシズムの検討題材になっています。
私が今お話ししていることのほとんどは、この文学研究を組織的に生んだ研究者の一人であるシェリル・グロトフェルティの共編著“The Ecocriticism Reader※1”のイントロダクションに書かれています。彼女は、エコクリティシズムの特徴として、“open and suggestive”であることを挙げています。端的に言えば、間口が広い、ということです。そのため、エコクリティシズムという言葉自体に縛りがあるとして、「文学・環境」(literature and the environment)と言われることもあります。
オープンであることは、他分野との関連を重視する姿勢を含んでいますので、学際的なアプローチをとることもエコクリティシズムの特徴です。また、オープンであるとは、研究者だけで議論するのではないという意識の現れです。環境の問題に関わるわけですから、研究者以外の幅広い層の人たちと交流することが重要になる。一方、それが裏目に出て、文学批評理論として洗練されていないという批判が、エコクリティシズム内部からあったのも事実です。
21世紀に入り、国や地域を超えたトランスナショナルな視点が出てきました。人種問題が環境問題に関わっていると認識した上で、人種を超えて共通する問題に目を向ける研究が見られるようになりました。国や地域を超えたグローバルな地球環境問題への関心の高まりと、軌を一にしていると思います。
エコクリティシズムや「環境人文学」(Environmental Humanities)で醸成されている概念や切り口が持つ可能性として、私は、従来論じられていたことを新たにとらえ直して議論を活性化するはたらきに注目しています。
たとえば、奥野克巳さんを中心に日本で進められているマルチスピーシーズ研究。「マルチスピーシーズ」は、日本の環境文学の代表的作家である石牟礼道子さんの作品を論じる際にも「使える」概念だと思います。石牟礼作品では、人間とノンヒューマンの存在の交流が描かれています。
石牟礼作品はこれまで「アニミズム」や「共生」、あるいは水俣病の問題では「共苦」といった概念で、文学だけではなく社会学など多分野で議論されてきました。同時に、そうした議論は前近代を理想化していると批判する向きがあります。しかし、これらを「マルチスピーシーズ」という枠組みでとらえ直すと、批評的距離が生まれます。対話のプラットフォームが開けてくるのです。「共生」として語られてきた石牟礼作品のある一面を「マルチスピーシーズ」の見地から語ることで、より広い分野や世代の人たちと話ができる印象があります。
この「マルチスピーシーズ」という概念が提起する問題について、すこしお話をさせてください。まだ勉強中ですが、「マルチスピーシーズ」というのは「種」という概念自体を問い直す動きであると理解しています。
「人新世」(the Anthropocene)の問題は、現在エコクリティシズムでも環境人文学でも議論されています。その根底にあるのは、人類というとき「この人類とは誰のことか」(Who is this “we”?)という問いです。歴史家のディペシュ・チャクラバルティが言っていますが、現代に生きているわたしたちは、これまで一度も人間を「種」ととらえてきたことはないのではないか。人新世を「種」としての人間が“geological force”(地質学的に強い存在)になった時代ととらえるシナリオに対して、マルチスピーシーズ研究がどう切り込んでいくのか関心があります。
人間を「ひとつの種」として見るという問題を考えるとき、やはり石牟礼道子を参照したくなるんです。石牟礼作品には虐げられている人々が多く描かれます。社会的に差別を受けている人々、たとえば水俣病患者であったり、狂人だと思われている人は、他者を同じ人間として見ているところがあります。少なくとも石牟礼作品ではそう描かれています。
たとえば、水俣病患者がチッソ※2の社長に「同じ人間として自分たちのことを考えてもらいたい」とか、「同じ人間としてこの苦しみを一緒に考えてもらいたい」と言います。同じ人間としてチッソの社長や役員と向き合っているわけです。ですが、チッソの社長たちは彼らを人間扱いしていなかった。だから、平気で有毒物質を垂れ流していたわけです。被差別者が他者と「同じ人間」として向き合うとき、そこには「ひとつの種」と言える広い人間のとらえ方がある。そして石牟礼の描くそういう人々の世界には、蛸や狐や馬酔木との交流があり、マルチスピーシーズの関係が描かれている。
ですから、科学的な「種」の再考を含めて、人間をひとつの種としてとらえることを学ぶ上でも、石牟礼作品は示唆的だと思います。人類が“geological force”となった人新世の議論をするときに、自分たちが「ひとつの種であるとはどういうことなのか」という問題についても考えなくてはいけない。そのときにエコクリティシズムが重要な役割を果たすと思っています。
§
江川:
結城さんご自身がエコクリティシズムを始めたきっかけはどういったものなのでしょうか。
結城:
私はもともと田舎の育ちです。川や原っぱ、山など、自然豊かなところで毎日遊んでいました。今思えば、非常に恵まれた子ども時代だったと思います。家のぐるりに小魚が泳ぐ小川があって、祖母はそこで洗濯をしていたし、母は鍋を洗っていた。小川といっても生活に必要な水を引く用水路ですが、側面に苔が生え、タニシがくっついているような、本当に楽しい小川でした。家の敷地内を流れるその小川で、裸になって遊んでいました。
ですが、小学高学年の頃に、そこがコンクリートで三面張りにされてしまいました。小魚は姿を消し、時期になると湧いて出ていたホタルもいなくなりました。それには衝撃を受けましたし、怒りも感じました。なんでこんなことをするんだと。小学生の私は、建設会社が工事する現場を見ていて、言葉にならないモヤモヤしたものを感じていました。しかし、どうすることもできず、とくに行動を起こすわけでもなく、そのモヤモヤをずっと抱えることになりました。
大学に入り、師匠である野田研一さんの授業がきっかけで、アメリカ文学を専攻するようになり、修士課程に進みました。修士論文を書いているとき、シェリル・グロトフェルティと共にエコクリティシズムの生みの親の一人である、スコット・スロヴィックの集中講義がありました。そこで環境文学作品をたくさん読んで衝撃を受けました。「これも文学なのか」と、私の文学観が音を立てて崩れました。
でも、それらを読みながら、幼少期に感じた「なんできれいな小川をこんな風にするんだろう」というモヤモヤにつながったんです。そして気づいたらこの道に入っていました。ですから、自分の経験と学問としてのエコクリティシズムは分離していない。後付けかもしれませんが、分離していないところに魅力を感じたのかもしれません。
エコクリティックには、プライベートな生活と研究者としての自分を分けていない人が少なくありません。環境の問題は人間の問題であり、ローカルであると同時にグローバルであり、パーソナルなものとプロフェッショナルなものが絡み合っている。そのスタンスに惹かれて、気づいたらそっちに進んでいたという感じです。
§
江川:
結城さんは博士論文をサウンドスケープについて書かれ、そこから関心が多岐に広がっていかれたように思います。もし関心が広がるきっかけになった人や作品との出会い、あるいはご経験などがあれば、お聞かせください。
結城:
最初にサウンドスケープやアコースティックエコロジーに関心を持ったのは、修士課程でランドスケープについて学んだことと関係していると思います。指導教授の野田研一さんが「文学におけるランドスケープ」の問題を専門としていて、風景論についての講義を受けてきたからです。そのときに「なぜ見ることばかりなんだろう」と疑問に思ったのが出発点かもしれません。視覚中心主義は差別の問題とも関わります。ですので、視覚とは別の感覚経験から文学研究ができないかと考えていたように思います。
ちょうどその頃、テリー・テンペスト・ウィリアムスという作家の作品を読んでいたことも聴覚的経験に関心を持った理由だと思います。この作家は先住民文化に造詣が深く、彼女の作品を読みながら、先住民の口承文化や、「耳を傾ける」という心構えや態度に、非常に関心を持ちました。また留学先のネヴァダには先住民が多く、アジア系の私は親近感を持ってもらえたのか、部族の集まりにも参加させてもらえました。先住民文化に関心を持ち、そういう出会いもあって、サウンドスケープの問題に行き着いたように思います。
日本に帰ってきてからは、アメリカの環境文学ばかり研究していても、なんだか机上の空論という感じがしたんです。環境の問題はローカルな問題でもありますから、日本のことにも目を向けないといけないんじゃないかと思ったわけです。そこから、日本文学とアメリカ文学とを比較研究的に見るスタンスにシフトしていきました。それで石牟礼道子や森崎和江の作品を研究するようになりました。
§
江川:
結城さんはデイヴィッド・エイブラムの『感応の呪文※3』(原題 “The Spell of the Sensuous”)を翻訳出版されています。訳者あとがきでは、この本が“more-than-human”(人間以上)という言葉を学術的に用いた最初の著作だと書かれていましたが、この“more-than-human”という概念についてお話しいただけますか。
結城:
“more-than-human”は、おそらくマルチスピーシーズと非常に近い概念、インターチェンジャブルに使えるものだと思います。とはいえ、まったく同じではありません。マルチスピーシーズでは、種という概念の見直しも含めて、人間もひとつの種と考えることが根底にあります。“more-than-human”は、人間がいて、しかし人間だけではなく、それ以上の存在がいるということでしょうか。指しているのはそれほど違わないのですが、開かれ方がすこし違うイメージだと思います。
『感応の呪文』の章のひとつは、1998年に出版された『緑の文学批評※4』という、エコクリティシズムの主要論文のアンソロジーに入っています。私はこの翻訳を担当し、非常に優れた研究書だと感じていました。そのうちいろんな人の書くものに“more-than-human”という言葉が出てきたのですが、ほとんどエイブラムへの言及がない。それほど一般的な用語として流通しはじめたということです。
しかし、日本ではまだほとんど使われていませんでした。なぜ日本で“more-than-human”という概念が使われないのか考えたとき、エイブラムの翻訳がないからだと気づいたんです。重要な概念は、研究書が翻訳されているから広く使われるわけなので、これは自分で翻訳しようと思いました。
『感応の呪文』は、エコクリティシズムの「ナラティブ・スカラシップ」に相似したスタイルで書かれているのが、面白いところです。ナラティブ・スカラシップとは、従来の学術スタイルとは異なり、作品に描かれている場所に研究者が身をおき、文学テクストとそのテクストに影響を与えている場所というふたつのフィールドで分析をおこない、そのときの経験や思考の揺れをテクスト分析に織り込む研究手法です。ですから、そこにはパーソナルな思索が含まれています。
ナラティブ・スカラシップは、現在ではエコクリティシズムで一般的になりつつありますが、『感応の呪文』が出版された1996年当時はめずらしかった。この本は、エイブラムが博士論文を発展させたものだと思いますが、博士論文は学術的に書くことが求められています。しかし、その後に発展された『感応の呪文』を読むと、執筆スタイルがかなり工夫されていることがわかります。
まずイントロダクションが、学術的なイントロダクションとナラティブ・スカラシップ的なパーソナルなイントロダクションに分かれています。各章も学術的な章とパーソナルな章が交互に配置してあります。学術的に書こうとすると漏れてしまう思索の部分を取り込もうとしている。その試み自体が“more-than-human”への接近に必要な手続きだったのでしょう。従来の学術的方法では、おそらく“more-than-human”に接近することができない。つまり、あの本のスタイル自体が“more-than-human”なるものへのアプローチを示すひとつのかたちなのだろうと思います。
日本だと、管啓次郎さんの論考は初期の頃からナラティブ・スカラシップですね。
§
江川:
結城さんは今まで単著を2冊出版されていますが、2冊目の『他火のほうへ※5』では、食や汚染に関する論考と作家のインタビューが並べられています。その構成は、食を描いた文学テクストとの対話と、そのテクストを生み出した作家の身体的環境との対話を重視したものだと書かれていますね。ここには“academic”の言葉の語義とされる「研究のことばかり考えて外の世界を忘れてしまう」研究スタンスではなく、研究者による批評的モノローグにならないよう、他者に対して開かれた研究者の姿があるように思います。
対象へ身体的に参与していくこうした批評のスタンスから、文学から見た食の問題、汚染の問題、核・原発の問題へのアプローチなど、これまで取り組んでこられたことについてお聞かせいただけますか。
結城:
食の問題と汚染の問題はつながっています。これもきっかけは石牟礼文学でした。とくに『苦海浄土※6』の「水俣病わかめといえど春の味覚」という、忘れがたいフレーズ。なぜ有機水銀で汚染されているとわかっているのに、あの人たちはわかめを食べたのかと、不思議で不思議で仕方がなかった。その疑問が食と汚染の問題への関心につながりました。
食と汚染に関する議論では、食の安全性やリスクに焦点が当てられますが、水俣病わかめの問題は、それからことごとく外れます。社会的に非常に影響が大きく、読み手の心を揺さぶる石牟礼さんの文学世界に描かれている「水俣病わかめといえど春の味覚」というのは、どういう食の風景なんだろうと思い、食と汚染について考え始めました。これが私の食をめぐるエコクリティシズムの原点です。
汚染への関心はそこからさらに膨らんで、今取り組んでいるのは放射性物質による汚染の問題です。これには文学研究だけでなく、対話活動からもアプローチしています。エコクリティシズムの研究者の間では、「エコクリティシズムとは何か」(What is ecocriticism?)だけでなく、「エコクリティシズムは何をするのか」(What does ecocriticism do?)ということが、初期の頃から問われています。いろいろなタイプのエコクリティックがいますが、私自身は“doing”の方にいく傾向がある。専門として文学研究に従事していますが、それが行動につながるような機会には積極的に参加してきました。
そのひとつが高レベル放射性廃棄物の地層処分の問題です。高レベル放射性廃棄物は地上に貯蔵しておくわけにいかない。テロなどで狙われると大変なことになります。今すぐにでも処理しなくてはいけない。地下500メートルくらいのところに安全な形で隔離する地層処分が国の方針として選択されましたが、場所の選定は進んでいません。埋める場所を決める上で多くの人との対話が必要ですが、その対話が成り立たない。
高レベル放射性廃棄物は「原発のごみ」とも言われます。地層処分は、原発の問題ではなく、ごみの問題なのですが、やはり原発と関わるために、賛成・反対という対立軸が持ち込まれます。対立の場になってしまうと、当然ながら対話は進まない。でも地層処分をめぐる対話は絶対に必要なので、今はこの対話活動に関わっています。
この対話活動の一環として、2019年の秋に福井県鯖江市で開催された、原発のごみを考えるシンポジウムに参加しました。福井は原発銀座と呼ばれるほど原発が集中しています。ですから、登壇者はみんな結構ピリピリしていて、そのパネラーの一人がNUMO(原子力発電環境整備機構)という地層処分を進める組織の方でした。
NUMOの方たちは、日本各地で地層処分に関する対話型説明会をおこなっています。「非常に安全な技術で埋めますから、どうぞご安心ください」と説得するスタンスです。司会は作家の田口ランディさん。私はランディさんと一緒に何度か対話活動に参加していますが、彼女は分かりやすい言葉で重要なことをお話しになるので適任でした。そして、私は文学研究でこういった問題に関わる立場から、パネラーの一人として参加していました。
そのときに、上品に話をしても対話にならないと思ったので、私がすこし誘導尋問みたいなことをしたんです。「ウランの身になって考える」ということを説明するために、アメリカのネイチャーライターであるアルド・レオポルドの“Thinking Like a Mountain※7”(山の身になって考える)というエッセイを引き合いに出したんですね。このエッセイは、生態系という大局的な見地に立ったときに、人間のおこないがどう見えてくるかということを主題にしています。
それで私は「原発のごみを安全な形で埋めるといっても、埋められるウランの残りかすにしてみれば、人間のために徹底的に搾り取られた後に、ごみとして埋められるって、やってられないんじゃないですか」と言いました。驚いたことに、そうするとNUMOの方が「自分がウランだったら、これだけ人間に貢献したのにごみとして捨てられるって、ふざけんじゃねーって言いたい」って答えたんです。そのときに初めて、NUMOの方と通じ合った感触を得ました。対話の場が開けるかもしれないと感じたんです。
地層処分の対話の場をつくるのに、文学が有効な手段になりうると思いました。批判的な物言いだと喧嘩になってしまうので、文学を媒介に「こういうふうに語っているエッセイがあります」と言ってみる。対話を進めるためのコモングラウンドを形成するときに、文学が果たす役割は小さくないと思いました。このように、今はエコクリティックという立場で作品分析をしながら、そこで培ってきた考え方をアクチュアルな問題につなげることを試みています。
§
江川:
最後に「環境人文学」についても聞かせてください。環境人文学は21世紀に入ってから始まった人文・社会科学分野の協働の動きで、環境をめぐる文化的・哲学的枠組みを学際的アプローチから探ろうとするものですが、結城さんも里山についての協働的研究を実践され、その成果を共編著『里山という物語※8』として出版されています。この取り組みについても聞かせください。
結城:
『里山という物語』は、歴史学者の黒田智さんとの共編著書で、他の分野の研究者にも関わっていただきました。環境人文学という協働の取り組みはオーストラリア、北欧、北米でかなり盛んですが、それぞれ地域ごとに特定のトピックで議論されています。たとえば、オーストラリアでしたら先住民アボリジニの問題がかなりフォーカスされていますし、北欧ですと寒冷地特有の問題と気候変動、北米でもロサンゼルスならアーバンネイチャーなど、その地域特有の環境に関わるトピックが扱われています。
当時勤務していた金沢大学は、キャンパスが里山にあり、里山研究も活発でしたので、この問題は金沢でやるべきだろうと問題意識を共有する研究者が集まって取り組みました。共生のシナリオだけで進んでしまうのは危険だという共通認識があり、里山を言説や歴史の観点からきちんと分析をしなければと考えたのです。その成果をまとめたのが『里山という物語』です。
環境人文学は研究分野ではなくプラットフォームです。問題意識を共有する研究者が集まって協働しながら研究を深めていく場なので、問題意識が共有されていないと成り立ちません。専門知を深めて共有することと、実際に起きている問題への理解が、協働には必要です。
そこでいう問題はローカルなものもあれば、グローバルな気候変動や、先ほどお話しした放射性廃棄物の地層処分のような問題もあるわけですが、里山は金沢という場所にあったテーマでした。いずれも、アクチュアルな問題に向けた研究であり、対話のコモングラウンドを探る環境人文学的プロジェクトなのです。
§
江川:
文学的想像力を対話の場に用いていくということですね。それは文学的想像力が社会に対してなにができるかという問いへのひとつの答えかもしれません。本日は大変興味深い話をお聞かせいただき、ありがとうございました。