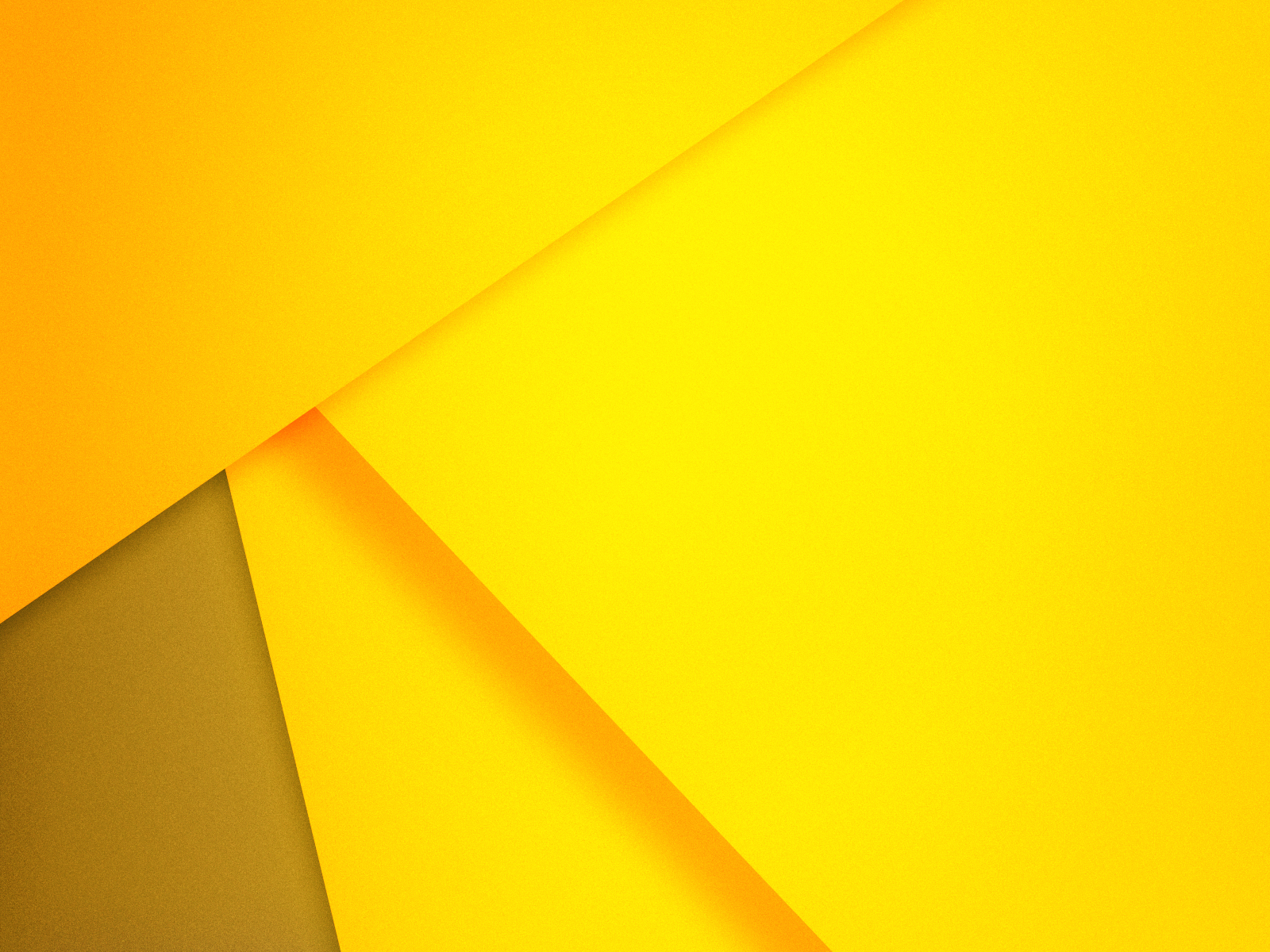目の前に、昭和三十二年頃の、古びたモノクロ写真がある。縁側で這い這いをしようとしている、幼い男の子の姿。その隣には、猫が写っている。いかにも暢気そうな様子で、傍に寝そべっている。
保坂和志の短編集に収められた「写真の中の猫」という作品には、こんな一枚の写真にまつわる印象深いエピソードが綴られている。彼は、自分がもう少し成長するまで飼われていたはずのその猫のことを、まったく憶えていなかったという。アルバムのなかで偶然に写真を見つけて、その猫の存在を知ったことになる。ずっと忘れていた事実を、写真がきっかけとなって思い出したということではない。写真を見たからといって、その猫がかつて存在したことを、自らの内にある「記憶」として認識できたわけではなかったのだ。
猫はそのとき、柔らかな陽射しの心地好さに、あくびの一つもしていただろうか。縁側で這い這いをする自分にカメラを向け、シャッターを押したのは、誰だったのか。もしかしたらその傍で、「ほら、こっち向いてごらん」と、笑顔で声をかけた人もいたかもしれない。そういったことは、その写真から知ることはできない。「記憶」に残らなかったものは、すべて消えていった。そのような時間があったという事実が、写真という物理的な「記録」として、目の前にあるだけだ。
時間を記録するメディア
このエピソードは、わたし自身の過去にも思いを至らせるものだった。かつては我が家でも、飼われているのか勝手に出入りしているのかわからないような、名前のない猫が次々と現れては消えていったという。そして自分のアルバムにも、「記憶」にないものが「記録」された数々の写真があることを思い出し、わたしはこの作品に深い共感をおぼえた。保坂氏は、その写真に喚起された説明しがたい心情を振り返り、こう述べている。
かつてそこにあった時間、あるいはその時間があったからこそ起こった動きや話し声や笑いというようなさまざまなことが、この世界に残らないで〈物理的〉に消えてしまうということは、本当にあたり前すぎるほどあたり前のことだ……ぼくがいまリアリティを強く感じているのは、「郷愁」のような心の状態ではなくて、この、「時間がこの世界に残らないで消えてしまう」という前提ないし法則の方だ。保坂和志「写真の中の猫」
しかし、その後ではこのようにも語られている。
「時間がこの世界に残らないで消えてしまう」と書いたけれど、本当はそうではなくて、写真という、時間を記録した断片があることによって、それを取り囲むものがいろいろに想起されることの方に奇妙さとリアリティを感じているのかもしれない。保坂和志「写真の中の猫」
保坂氏の言うように、写真は「断片的に時間を記録するメディア」である。しかし、写真では記録できない「動きや話し声や笑いというようなさまざまなこと」まで記録可能な、動画というメディアでも、そこに映るのは実際に生じたできごとの「断片」でしかない。写真とは異なり、動画には音声が伴うが、どちらもカメラのファインダーというフレームによって切り取られた映像という点では同じであり、現在はそのいずれも手軽に利用できる世の中になった。しかし、「それを取り囲むものがいろいろに想起されること」については、写真と動画の間に、かなりの違いがあるように感じられる。
一枚の写真を見るということは、カメラが捉えたある一瞬の記録を目にするという体験である。そこに焼き付けられたものは、ひとつのイメージであると同時に、長さのない「点」としての時間でもある。写真を見るとき、ひとはその瞬間に確かに存在した光景や人物を目にして、直接的に写ってはいないそれらの過去と未来に、さまざまな想いを馳せることになる。報道写真のような他者の記録でも生じる体験だが、自分自身の記録である場合、それは一段と鮮烈な「想起」をもたらす。
ある晴れた日の午後のひとときを共有した、猫とわたし。猫はどのような経緯で我が家にやってきて、やがてどのように死んでいったのか。わたしはその後、どのような子供に成長し、どんな大人になったのか。ひとが一枚の写真に飽くことなく見入ってしまうとき、そこで生じる「想起」は、「点」としての時間を永遠に引き延ばすかのような体験となる。
一方、動画に記録されているのは、一定の長さを持った「線」としての時間である。写真が純粋なイメージの記録であると思えるのに対して、動画はイベント(できごと)の記録という印象が強い。したがって、写真を見ることを「イメージの再現」と捉えるなら、動画を見ることは、「イベントの再生」とでもいうべき体験となる。「想起」するための時間は大抵、再生時間に一致する。もちろん、動画として切り取られた時間の前後の状況を、後から想像することはできる。しかし、動画を見ている最中には、そこに映っていないものを想うことはほとんどなく、その映像自体の時間の流れに、ひとはただ身を浸している。
カイロスとクロノス
いま述べてきたことは、古くからある二つの時間の概念でも表現できるだろう。
ギリシア語には、時を表す言葉として、カイロス(kairos)とクロノス(chronos)の二つがある。前者は「時刻」を、後者は「時間」を指すとされているが、それぞれがやがて神話に登場する神の名としても用いられた。カイロスが機会(チャンス)の神だったことから、ひとが主観的な時機として捉える一瞬の時間は、「カイロス時間」と呼ばれることがある。それに対して、クロノスは文字通りの時間の神であり、わたしたちが時計によって客観的に知るような、均質に流れ続ける時間は、「クロノス時間」と呼ばれる。
スチュアート・ブランドは、時間をテーマとした著書『The Clock of the Long Now』で、美術史家パトリシア・フォルティーニ・ブラウンによる、このような言葉を紹介している。
カイロスは自らにとっての好機、あるいは幸ある瞬間。クロノスは終わりなき時間、あるいはひたすら流れ続ける時間。前者は希望をもたらし、後者は戒めを与える。Stewart Brand “The Clock Of The Long Now”
続いてブランドは、その二つの違いを自らの言葉でこう表現した。カイロスは「機知(cleverness)」の時間であり、クロノスは「知恵(wisdom)」の時間である。端的に解釈すると、これらは幼年期の時間と成年期の時間と言えるかもしれない。子供の頃を振り返ると、誰もが大抵は、大人になった現在よりゆっくりと時が流れていたような感覚を思い出す。生まれて初めて何かを体験するとき、好きなことに夢中になっているとき、子供時代のわたしたちは、それとは知らずカイロス時間にのなかにいたのだろう。でも、大人になるにつれて、多くのひとは、時計の針に支配されるクロノス時間に従って生きるようになっていく。
そう考えると、写真はひとをカイロス時間のなかに誘い、強い力で記憶のなかへ連れ戻すものと言えるかもしれない。「点」としての時間を記録した写真が、そこに収まりきらない時間の流れを想起させることもあるからだ。
記憶としての写真
写真術が発明された19世紀当時、それまでは画家が自らの身体的な技巧を駆使することでしか描けなかった人間の似姿を、カメラという器械がたちまち写し取ってしまうという事態は、まるで神秘体験のような驚異として受けとめられたという。しかし、その驚きは、写実性の高さという技術的な要因だけによるものではなかった。「点」としての時間を、銀板やフィルムに映像として写し取るカメラは、ひとの意識にとまることのなかった瞬間を捉えてしまうことがある。写真に残らなければ、誰にも知られることなく過ぎていったはずの一瞬。それを目の当たりにすることが、多くの人びとにとって、もう一つの現実を垣間見るかのような驚きを与えたのだ。
ヴァルター・ベンヤミンは、そのような現象をこう語っている。
カメラに語りかける自然は、肉眼に語りかける自然とは当然異なる。異なるのはとりわけ次の点においてである。人間によって意識を織りこまれた空間の代わりに、無意識が織りこまれた空間が立ち現れるのである……ここから分かるのは、技術と呪術の境界線は時代とともに変わってゆくことである。ヴァルター・ベンヤミン「写真小史」
科学的に見れば写真とは、カメラのファインダーが捉えた映像を、光学的技術によってガラスの湿板や乾板、フィルムやデジタルメディアに写し取った「記録(record)」でしかない。しかし、ひとの意識や視覚能力が及ばないままに消えていった光景が、写真によって焙り出されるとき、それが呪術のごとく過去を封じ込めた「記憶(memory)」にもなることを思い知らされる。
 ロバート・アダムソンの撮影による1840年代の写真
ロバート・アダムソンの撮影による1840年代の写真
想起される「物のイメージ」
記録と記憶。それらがどのように取り出されるかを考えると、違いはより明らかになる。記録は、元どおりの形で「再生」または「復元」される。しかし、記憶は、ひとそれぞれの形で「想起」されるのだ。
記録と再生/復元は、システマティックな入出力のプロセスであり、誰でも同じように行なうことができる。したがって、記録は人間よりも機械が得意とするものである。ものごとを機械的に覚えることは、記憶ではなく「暗記」と呼ばれることも多いが、人間にとってそれはむしろ不得意な作業であり、そう簡単にできることではない。だからこそ、ひとはさまざまな形で機械の力を借りながら、できるだけ確実かつ効率的に、自分の外部にものごとを記録する方法を編み出してきた。写真という技術も、その一つと言えるだろう。
しかし、記憶されたものは、記録のように保存したときと変わらぬ状態で再生/復元されるのではない。記録では「物そのもの」が保存されるのに対して、記憶が保存するのは、それが生み出す心象、すなわち「物のイメージ」であるからだ。「物のイメージ」は、個々の人間による「物そのもの」の解釈を表している。そして想起とは、ひとそれぞれに記憶された「物のイメージ」が、再び意識に上ることである。
アリストテレスはかつて、「記憶とは、感覚でも判断でもなく、それらに属する何かを、時間が経過したときに、持ち続けている状態、ないし、受けとめている状態である」と定義した。さらに、その「受けとめた状態」について、こう語っている。
……魂をもつ体の部分において、感覚を通じて、何らかの、絵に描かれたもののような仕方で、生じるものとして、その受けとめた状態を考える必要があるのは明らかである。アリストテレス「記憶と想起について」
記憶される「物のイメージ」が、ここでは「絵に描かれたもの」と表現されている。それは知的な思考というよりは、身体的な感覚によって、ひとの「魂」が生じさせる何かである。「魂」とは、他者と共有することはできない、そのひとだけのものであるはずだ。そう考えると、多くのひとが同じ一つの現象を目撃したとしても、それに対する記憶と想起のプロセスは、ひとの数だけあると言えるだろう。
視覚と記憶
アリストテレスが没してから200年以上の後、共和政ローマの時代に思想家として生きたキケローは、記憶における視覚の重要性について、こう語った。
われわれの感覚の中で最も鋭敏な感覚は視覚であり、したがって、耳や思考(脳)によって知覚されるものが、同時に目を媒介として(視覚化されて)伝えられるとき、最も容易に心に留められうるのであり、その結果、目に見えないものや視覚の判断の領域外にあるものは言わば具体的なもの、つまり、イメージや形として書き留められるために、われわれが思考(のみ)によってはほとんど維持できないものも、言わば心の眼によって保持できるようになる……キケロー『弁論家について』
わたしたちの記憶は、必ずしも視覚のみを通じて行なわれるわけではない。見ることだけではなく、聞くこと、嗅ぐこと、味わうこと、触ることによっても、何かを心に刻みつけることがある。しかし、視覚以外の感覚による記憶であっても、それによって想起されるのは、視覚的なイメージなのだ。
プルーストの『失われた時を求めて』の主人公は、マドレーヌのかけらが混じった紅茶が口に触れた瞬間、その匂いと味によって、身震いするほどの「すばらしい快感」に襲われる。その原因を自らのうちに探った彼は、それがある種の「視覚的回想」であることに気づく。そして、幼い頃にいつもお茶に浸したマドレーヌを出してくれた叔母の部屋に始まり、その古い家を取り巻く町の風景、広場や通り、そこに咲く花や住まう人々といった記憶の中のイメージを、尽きることなく想い起こすのだった。視覚的なイメージとしての記憶がもたらす計り知れない力が、そこでは見事に語られている。
キケローの時代からさらに数百年の時を超え、神学者アウグスティヌスが記した『告白』でも、記憶についての省察が行なわれている。そこでは、ひとが何かを記憶するにあたって、さまざまな「加工」を行なうことが説かれていた。
そこ(記憶)には、感覚によってはこびこまれたさまざまな事物についての数かぎりない心象(imago)の宝庫があります。そこにはまた、感覚にふれたものを思惟によって増減し、あるいは何らかのしかたで変えることによって得られたものが、ことごとく収められています。アウグスティヌス『告白』
この引用にある「心象」とは、「物のイメージ」のことである。記憶によって「物のイメージ」を入力するとき、ひとは知的操作を通じて何らかの「加工」を行なうのだ。
さらに彼は、想起によって「物のイメージ」を出力する際にも、それが別の形で「加工」されると考えていた。以下の引用で語られているように、ひとは「物のイメージ」の関係性を築きながら、それを自らの時間のなかに位置づけようとするのである。
(記憶という)このばくだいなたくわえの中から私は、自分で経験したもの、あるいは自己の経験にもとづいて他人の言を信じたもののあれこれの心象をとりだし、過去のものに結びつけ、これらのものから未来の行為と出来事と希望をも考え、これらすべてのものをふたたび、あたかも現在あるもののように考えます。アウグスティヌス『告白』
記憶と想起によって、ひとは過去から未来へと一定の速度で流れるクロノス時間から解き放たれ、カイロス時間のなかを行き来しながら「物のイメージ」を探求できる。アウグスティヌスは、記憶と想起の価値を、そのように考えていたのだろう。
写真による複製の意味
写真とは、ひとが昔から自らの内部記憶としてきた「物のイメージ」を、一種の外部記憶として保存したものに他ならない。ベンヤミンは『写真小史』において、ここまで触れてきた「物そのもの」と「物のイメージ」を、それぞれ「像(bild)」と「模像(abbild)」という言葉で示している。そして、現代人が世界のさまざまな事物の「模像」を複製し所有することで、彼がアウラと呼ぶ「あらゆる状況に含まれる一回的なもの」を克服しようとする、熱烈な傾向が見られると述べた。ベンヤミンは、そこで写真が人びとに与えた意味を、見事に解き明かしている。
像においては一回性と持続性が密接に結びついているとすれば、模像においては一時性と反復可能性が同じく密接に結びついている。対象をその被いから取り出すこと、アウラを崩壊させることは、ある種の知覚の特徴である。この知覚は、この世に存在するすべて同種なるものに対する感覚をきわめて発達させているので、複製という手段によって、一回的なものからも同種なるものを獲得する。ヴァルター・ベンヤミン『写真小史』
写真による複製は、古来から行なわれていた「物そのもの」の複製、すなわち絵画や遺物などの実体的なレプリカの制作とは、まったく意味の違う「コピー」と言えるだろう。写真は「物そのもの」を「物のイメージ」として、いわば擬似的に複製するからである。その「物のイメージ」を、ひとつの撮影データから無数に現像できることによって、「物そのもの」にはなかった反復可能性が生じることになる。
また、誰がいつどんな構図で撮ったかに関わらず、パリのエッフェル塔のあらゆる写真は、ベンヤミンの言う「同種なるもの」として、共通の被写体に対するイメージという同種性を帯びてしまう。写真を通じて、ひとは「物そのもの」にアクセスすることなくそのイメージを共有できるようになり、多くのひとが抱く「物のイメージ」にも同種性が備わることになった。現在のGoogle画像検索、TumblrやPinterestのグリッドレイアウトによる「同種性の視覚体験」は、そのように共有される膨大な「同種なるもの」を一望することを可能にし、かつてなかった快感を与えてくれる。
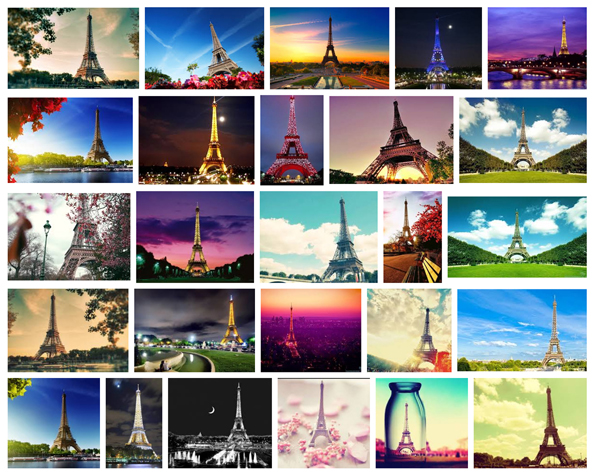 Google画像検索 – “Beautiful Eiffel Tower”
Google画像検索 – “Beautiful Eiffel Tower”
記録のメディアから、記憶のメディアへ
写真がデジタル化されて以来、撮影データの改変は、それ以前とは比較にならないほど容易になった。今でも写真は、「真を写す」という名の通り、真正さを重んじる記録としての役割を果たし続けているが、ひとがよりどころとするのは客観的な記録だけではない。自らの意識と無意識が、美化し、歪曲し、捏造することさえある記憶の数々が、わたしたちを支えている。アウグスティヌスが語ったように、ひとは記憶を「加工」しながら生きているのだ。その欲望を加速させるかのように、デジタル写真は、記録のメディアから記憶のメディアへと、あからさまに価値を転じてきた。
2010年10月にiPhoneアプリとして登場したInstagramの正方形のフレームは、旧来のインスタマチックやポラロイドを知るユーザーにとって、ひときわ郷愁を誘うものだった。また、何種類ものフィルターによって、撮影したばかりの「記録」である写真を、あえてレトロ調に、オールドファッションに、まるでノスタルジックな「記憶」のように加工できるその機能は、瞬く間に数百万のモバイルユーザーを虜にした。そして、そのような写真をネットで共有することが、ある種の強烈な自己表現になることを証明した。そこには、新しい記録を古い記憶に転じることで、「物のイメージ」の価値をすり替えようとする、倒錯した欲望が息づいている。
その一方でわたしは、いつまでも忘れはしないと思える場面を目にしても、それを写真という一種の外部記憶として残すことを避けてきた。自分にとってかけがえのない瞬間を、写真として切りとることは、その豊饒さを薄めるだけの行為に感じられた。写真にして残さなくても、この場面は自分の内部記憶のなかでずっと消えることなく、色褪せることもないはずだ。そんな風に思っていた。
でも今は、まったく逆のことも言える気がしている。自分の内部記憶が、いかに自らの都合のよいように作り変えられるか。写真となった外部記憶が、そこでの経験をどれだけ濃密に想起させるか。それらを思うとき、二つの記憶を分け隔てようとすること自体が、意味を失ってくる。写真という「断片的な時間の記録」は、ひとの内なる記憶と融けあってどこまでも流れ出すような、「限りない時間の記憶」にもなるのだろう。
写真は切りとられて見えるものである。しかし最良な写真は、そのことを半ば忘れさせる。ジョン・シャーカフスキー『ウジェーヌ・アジェ写真集』
 Eugène Atget “Rue de la Montagne Ste. Genevieve” (1924)
Eugène Atget “Rue de la Montagne Ste. Genevieve” (1924)