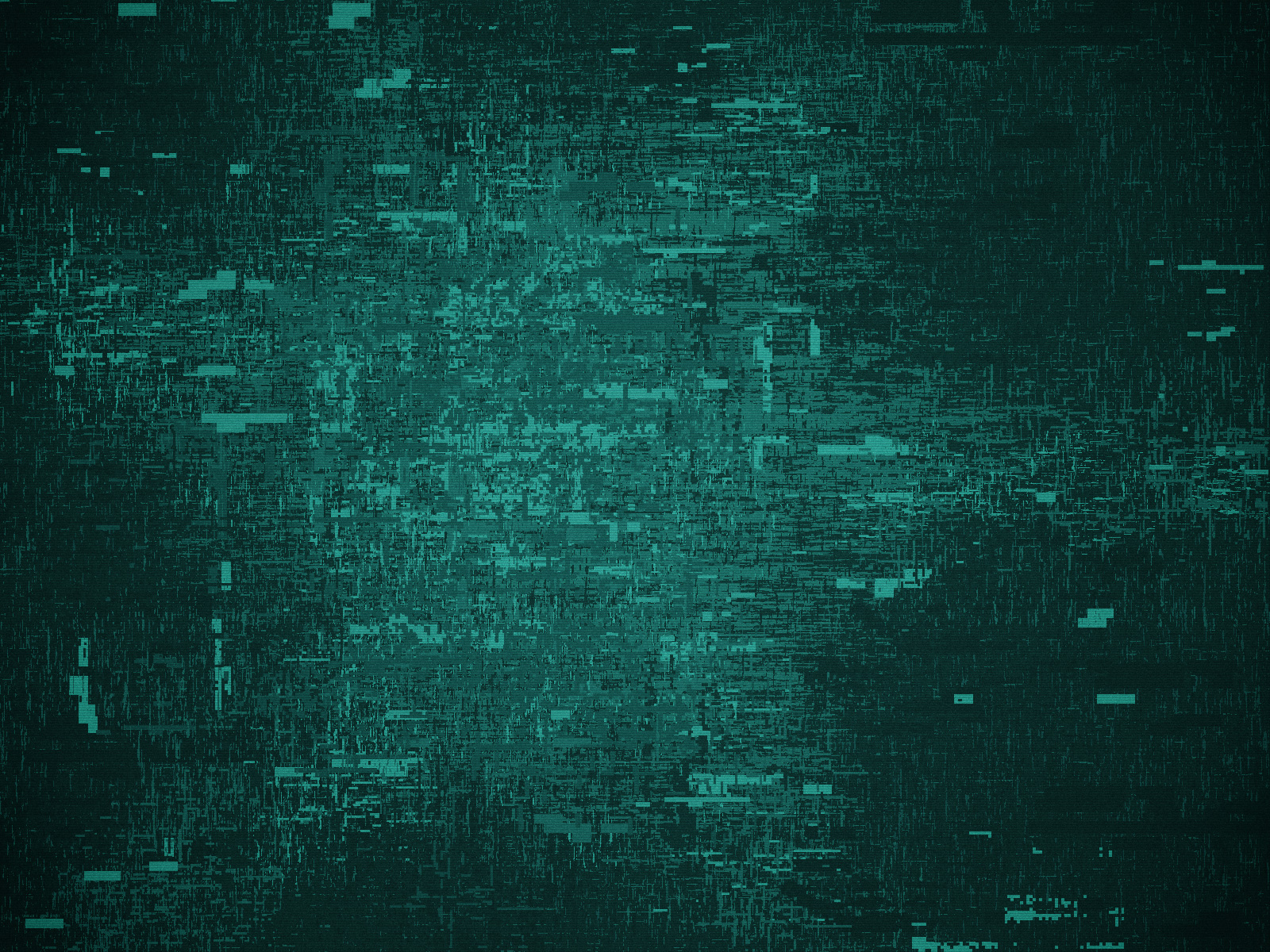爆心地に戻ったヒトのゆくえを示す『メディア論』
西欧世界は、3000年にわたり、機械化し細分化する科学技術を用いて「外爆発」(explosion)を続けてきたが、それを終えたいま、「内爆発」(implosion)を起こしている。機械の時代に、われわれはその身体を空間に拡張していた。現在、1世紀以上にわたる電気技術を経たあと、われわれはその中枢神経組織自体を地球規模で拡張してしまっていて、わが地球にかんするかぎり、空間も時間もなくなってしまった。急速に、われわれは人間拡張の最終相に近づく。それは人間意識の技術的なシミュレーションであって、そうなると、認識という創造的なプロセスも集合的、集団的に人間社会全体に拡張される。さまざまのメディアによって、ほぼ、われわれの感覚と神経とをすでに拡張してしまっているとおりである。意識の拡張というのは長いこと広告業界が特定の製品について求めてきたものであったが、それがいいものであるかどうか。それはさまざまの回答の余地を残す問題である。このような人間の拡張にかんするさまざまの問題に解答を与えるためには、全部をひっくるめて考察するしか、ほとんど方法がない。どのような拡張も、たとえば、皮膚であれ、手であれ、足であれ、すべて精神的、社会的な複合全体に影響を及ぼすからである。マーシャル・マクルーハン『メディア論』
マクルーハンの『メディア論』はこのようにはじまる。「外爆発」と「内爆発」の爆心地にいるのはヒトである。ヒトの身体がまず空間に拡張し伸び切ったところで、身体の内と外とがひっくり返り、爆心地に戻ってくるかたちで中枢神経組織も空間を埋め尽くしていった。マクルーハンは『メディア論』でさまざまなメディアを論じることで、空間にヒトの身体と神経とが満ちていく様子を記述した。地球を覆い尽くすようになったヒトはどこまでいってもヒトである。ヒトが拡張しているのだから、ヒトがヒトとしているのは当たり前である。
1964年に出版された『メディア論』において、マクルーハンはヒトの画像を世界の隅々まで瞬時に届けるテレビの話で終わらせなかった。当時としては最新の電気メディアであった「テレビ 臆病な巨人」で終わらず、そのあとに「兵器 図像の戦い」と「オートメーション 生き方の学習」という章が置かれている。外爆発から内爆発を経たヒトは爆心地に戻り、そこにある「兵器」と戦うことになり、その後のあらたな生き方として「オートメーション」が必要であるという、マクルーハンの予測がこれらの章に書かれていると考えてみたらどうだろうか。もちろん、爆心地に戻ったヒトを待ち受けていたのは「コンピュータ」である。『メディア論』ではコンピュータも論じられているけれど、時代の制約から扱いはすくない。コンピュータはまだ大学の研究室や軍、大企業でしか扱えなかった。しかし、マクルーハンは電気の時代の考察を経て、身体と神経を拡張しきったヒトにコンピュータが及ぼす影響を予測し、「兵器」「オートメーション」の章を追加したと考えてみたい。
機械の線条性と電気の同時性との相克
マクルーハンは「兵器」の章で、遠近法による線条性の強調が銃腔に旋条をもつ銃を生み出し、銃弾が一直線に発射されるようになったと指摘する。そこでは対象をしっかり見て、狙って、引き金を引くスキルが必須とされる。遠近法や旋条を持つ銃が示すように、機械の時代にはひとつの視点からよく見ることが重要であった。しかし、電気の時代には銃の運用方法が変わる。対象を一対一で狙うのではなく、複数の自動銃で「砲火帯」をつくり、銃弾を面に展開して対象をなぎ倒していく方法になる。電気の時代には、銃を持つヒトは何も狙うことなく銃の引き金を引き続ければいいのであって、狙撃手のような特別なスキルは要らない。ただ引き金を引くという行為を続けるだけで、銃はその用途を簡単に遂行できるようになったのである。
兵器の章において、第2次世界大戦での銃の使用例が示す電気の時代の症例は、瞬時に情報を世界に届けるというテレビの同時性とは異なっている。並べられて砲火帯をつくる銃は、線条的な弾丸を発射するという役割を変えることなく、運用方法によって同時性を演じているにすぎない。
文字文化は、いまでもなお、産業上の機械化のあらゆるプログラムの基礎であり、規範である。が、同時にそれは、機械化された社会の維持に不可欠な機械的断片的鋳型の中に、それを利用する人間の精神と感覚を閉じ込めてしまう。機械的技術から電気的技術への移行が、われわれすべてに傷を負わせ、痛い思いをさせるのはこうした理由からである。その機械のテクニックを、力に限界があるままに、われわれは長いあいだ武器として使ってきた。電気のテクニックは、まるで明かりのスイッチを切るように、一瞬にしてすべての生命を終わらせるのでなければ、攻撃用兵器としては使えない。機械と電気の2つの技術を同時にかかえて生きていくのが、20世紀に独特のドラマである。マーシャル・マクルーハン『メディア論』
銃の運用方法の変化が示すのは、マクルーハンが『メディア論』で繰り返し指摘する、機械の線条性と電気の同時性の戦いである。けれど、銃の場合は線条性の運用を変えた結果、「まるで明かりのスイッチを切るように」引き金を引くと、目の前のすべての生命を瞬時に終わらす銃弾の帯が生まれているというところが重要である。狙撃手のスキルから抜け出せない者はこの変化に対応できずに、砲火帯で蜂の巣になってしまう。マクルーハンが『メディア論』の至るところで指摘するように、同時性が線条性を侵していくのが20世紀特有のドラマであった。
しかし同時に、自動銃の砲火帯のような線条性を束ねることで、同時性のような効果が生まれることも起きていた。マクルーハンは兵器の章で、線条性を電気の同時性で補強するハードウェア重視の19世紀寄りの20世紀ではなく、同時性を電気の線条性でつくりだすソフトウェア重視の21世紀寄りの20世紀に足を踏み入れたといえる。
マクルーハンは機械文化の側で長年過ごしたため、電気の同時性が機械の領域を侵してくるのにいち早く気づき、カナリアとして鳴き続けた。その電気の同時性とは、テレビが端的に示すように、地球上のヒトに情報が同時に届けられることを意味する。しかし、自動銃の砲火帯が示すのは、運用方法によって線条性が同時性を偽装できるということである。
自動銃は機械の線条性を電気の同時性のように運用する試みであったが、コンピュータは電気の同時性を機械の線条性に基いて運用する。コンピュータは電気を線条的なものとして扱い、ヒトの認知を超えた速度で、情報を組み換えながら同時性をつくりだす。対して、映画は写真の平面という同時性を、ヒトの認知のスピードに合わせて線条化し、動きをつくりだす。そして、映像ディスプレイとしてのテレビは、映画と同じようにヒトの認知に合わせたものであると同時に、コンピュータと同じように走査線という線で面の同時性を偽装しているがゆえにコンピュータとの相性がいいという、まさにマクルーハンが巻き込まれた機械と電気の争いの中心に位置する装置なのである。ヒトの認知を超える高速の線条性で同時性を偽装するコンピュータは、機械と電気の合いの子的な存在の電子的ディスプレイ装置と組み合わされ、はじめてヒトとリアルタイムでコミュニケーションするのに必要な認知レベルに落とし込まれるのである。
ボタンがもたらしたヒトの行為の最小化
コンピュータは同時性を偽装しながら、情報を次々につくりだす。電気時代の「兵器」として、コンピュータは自動銃の砲火帯のように、夥しい情報をヒトに一斉掃射している。コンピュータは線条性と同時性とを併せ持つ点で、機械の線条性を電気の同時性が増強するだけの20世紀特有のメディアとは異なるのである。そのコンピュータが、ヒトを「オートメーション」のシステムに組み込んでいく。
機械的システムの場合は、けっしてこうはいかなかった。動力とそれによっておこなわれる仕事とは、手とハンマー、水と水車、馬と荷車、蒸気とピストン、どの例をとってみても、常に直接的な関連をもっていた。電気は、この問題に奇妙な融通性をもちこんだ。マーシャル・マクルーハン『メディア論』
機械の時代以来、ヒトの手が担う複雑な行為は、ボタンを押すという単純なものに代えられてきた。その最たる例が、カメラのシャッターボタンである。ひとつの視点から描かれる遠近法による絵画のスキルを、カメラはシャッターボタンを押すだけで実現できる。何事もボタンを押せば行為が成立する。ヒトの拡張はボタンを押すという行為とともに起こり、ヒトの行為はボタンを押すという行為に最小化されていった。ボタンを押すという行為に最小化されたからこそ、ヒトの行為は機械とともにあるところに遍く拡張していき、その結果として、ヒトの身体が地球全体に拡張することになったのである。
ボタンを押すというヒトの行為の最小化を考えるために、技術哲学者のデービス・ベアードが『物のかたちをした知識』の中で取り上げた、化学の分析機器に関する1954年の広告を参照してみたい。その広告には「ボタンを押す指、考え込む顔、さらにぐっと考え込む顔」という3つのアイコンが出てくるが、それぞれ次のような意味を持っている。
ボタンと指のアイコンは「押しボタン式の操作を示します — 人為的なエラーは最小限」と言われている。考え込む顔は、「単純で定型的な人間による操作 — 人為的なエラーはあまりありません」、ぐっと考え込んだ顔は、「技能、注意、判断を必要とする操作 — 人為的エラーに陥りやすい」とある。機器に仕事をさせれば、簡単になり、人為的ミスに陥りにくくなる。「機器によるエラー」の可能性については言われない。機器は客観的な理想をもたらす。デービス・ベアード『物のかたちをした知識』
押しボタン式の操作の場合は、そのはじまりにしかヒトの行為を必要としない。あとは機械やコンピュータが正確に行為を遂行して、「客観的な理想」をもたらしてくれる。その際、身体が機械に与えるノイズを最小限にするために、ヒトの行為はボタンを「押す」「押さない」というかたちでバイナリー化されている。しかし、そこに融通性はない。ボタンはメカニカルなモノの繋がりに接続し、ひとつのことが行われるだけである。そこでは、電気によってモノとモノとのあいだに「奇妙な融通性」がもちこまれる。この融通性がヒトとモノのあいだの線条的な因果関係を壊す。とはいえ、そこに同時性が生まれるわけではない。ヒトとモノのあいだの物理的繋がりが、直線的な因果関係から放射状に伸びるようなものに変化し、因果関係が曖昧になり面として拡がるようになった。モノのつながりの因果関係の曖昧さから生じた「奇妙な融通性」は、機械の時代から電気の時代へと変化するために決定的な変化をもたらすことになる。
電気によるオートメーションの特徴は、すべて、われわれ自身の手がもっているような、あらゆる目的に使える手工芸的な融通性に回帰する方向にある。マーシャル・マクルーハン『メディア論』
「奇妙な融通性」とボタンの組み合わせは、自動銃の砲火帯と同じようにスキルを消失させる。それはヒトの「手」が必要なくなることでもある。ヒトの手でも何でも、ただボタンを押せる、引き金を引ける何かがあればいい。そこにコンピュータが現われ、ヒトをオートメーションのなかに組み込んでいった。
複雑な行為を遂行するため、コンピュータはヒトに再び「手」を与える。ヒトの手は相変わらずボタンを押すだけであるが、かつて手が担っていた複雑な行為が、その先で可能になる。コンピュータと結びついた行為の複雑さは、ヒトの手の複雑さを超えて、あらたなスキルをつくりあげる。コンピュータの超高速の線条性が、ヒトの手とモノとの同時的で有機的な関係を模倣し、ヒトの手による表現はもちろんのこと、ヒトの手ではできないような表現をつくりだすことを可能にしていく。
しかし、コンピュータはヒトの手そのものを求めているわけではない。コンピュータの線条性は、ボタンを押すという最小化した行為を求めているにすぎない。コンピュータによって様々な目的を実現するには、ヒトの手が培ってきた行為の複雑さをリセットして、その行為を最小化するのが適しているのである。
神秘性を剥ぎ取られた「数」という素材
ヒトの最小化した行為がコンピュータと結びつけられ、あらたな行為が次々と生まれていく理由は、コンピュータが「数」を扱う装置であることに求められる。コンピュータでは映像、音響、テキストといったあらゆる表現が「数字列」として示される。すべてを「数字列」から考えることで、コンピュータを表現の道具ではなく素材と捉える必要があると指摘した久保田晃弘は、そのような考え方を「デジタル・マテリアリズム(唯物論)」と名付けた。そして、久保田は「数」について次のように書く。
数という素材が持っている重要な特徴の一つに「形式からの独立性」があります。いいかえれば、数は数のままでは表現形式が決定しない —— つまり「表現の不確定性原理」です。これまで用いられてきた伝統的な素材のほとんどは、形式と密接に結びついていました。立体に適した素材、平面に適した素材、視覚表現に適した素材、聴覚表現に適した素材と、表現形式と素材のカテゴリーの間には、強い相関がありました。久保田晃弘「Design 3.0:デジタル・マテリアリズム序論」
数があらゆる表現形式に明確に結びつくのは、コンピュータ以降のことである。同じ数字列が、文字にもなれば音にも画像にもなることは、コンピュータ以前には考えられなかった。しかし、黄金比などが示すように、数はもともと様々な表現の基礎にあり、表現同士を結びつける存在であったといえる。マクルーハンは「数」について次のように書いている。
ボードレールは「数は個人の内部にあり、数は陶酔である」と言った。そのとき、ボードレールは、数がバラバラの単位を相互に関連づける触手あるいは神経組織であることを、真に直観していた。だからこそ、「群衆のなかにいる喜びは、数の増加を喜ぶ気持ちを神秘的に表している」わけだ。言い換えれば、数は話されることばと同じで、たんに聴覚的で反響的であるだけでなく、それは触覚を拡張したものであるから、そこに起源がある。統計では数字を集めたり束ねたりするが、それは現代の洞窟画あるいは指頭画(フィンガー・ペインティング)とも言うべき統計家たちの図表を生み出す。マーシャル・マクルーハン『メディア論』
「数がバラバラの単位を相互に関連づける触手あるいは神経組織である」からこそ、コンピュータ内で扱う数は「形式からの独立性」をもつのだろう。ヒトは数を単位につい結びつけてしまうが、コンピュータは数をバラバラのままで保持できる。言い換えれば、コンピュータは数を神秘性なしで扱えるといえる。
マクルーハンは、「文字を使わないデジタル・コンピューターはいろいろの数字(十進数字)の代わりに『イエス』と『ノー』(二進数字)を用いる。コンピューターは輪郭に強く数字に弱い」と述べているが、これは間違いだろう。久保田が指摘するように、コンピュータは「数字に弱い」のではなく、数字列から神秘性を剥ぎ取り、単に素材として扱うのである。それゆえに、数は「表現の不確定性原理」のもとに置かれることになる。そして、電気の「奇妙な融通性」と数字列の「表現の不確定性原理」とが組み合わされて、「あらゆる目的に使える手工芸的な融通性」が生じる。ここで「手」がでてくるのは、数を指折り数えることに深い関わりがある触覚が拡張したものだからである。
コンピュータに委譲される手の行為
コンピュータのなかで数字列を操る「手」は、同時に「手」に操られる素材でもある。コンピュータは内に数字列という再帰的な「手」をもち、外にヒトの手をもつ。ヒトの最小化した行為を遂行する手は、数字列の再帰を停止させて表現形式を確定させるために、コンピュータが求めるものである。しかし、ヒトは直接的に表現を確定するわけではない。ヒトはコンピュータを操作しているのではない。久保田はそれを「委譲」と呼んだ。
コンピュータとのコミュニケーションは、操作(コントロール)するというよりもむしろ「委譲する」という感覚に近い。委譲というのはあまり聞きなれないことばだが、英語ではデレゲーション(delegation)、何かの処理を他のものにまかせてしまうことをいう。 コンピュータのインターフェイスも、操作ではなく委譲であると考えるとずっとわかりやすくなる。ファイルを移動するように委譲する、図形を変形するように委譲する、メールを送るように委譲する……委譲する先はアルゴリズムが書かれたプログラムコードである。GUIのボタンをマウスでクリックすること、キーボードで押すこと、スライダーを動かしたりツマミを回すこと、それらはいずれもアルゴリズムに対するトリガーである。そのこと自体によって、音が直接生み出されたり変化するわけではない。久保田晃弘「ライブコーディングの可能性」
久保田のこの指摘は、ヒトの行為の最小化と合わせて考える必要がある。ヒトは行為の最小化を受け容れながら、委譲先の行為を豊かにする選択をした。その結果としてGUIが生まれたと考えられるが、久保田はこれに批判的である。GUIは複雑で豊かな身体のはたらきを、単に見て指さす行為にしてしまっているからである。
しかし、ヒトの行為を最小化していくことは、ヒトの行為の曖昧さや間違いをできるかぎり排除するためでもある。まずヒトの行為のノイズを最小限にして、そこからヒトとコンピュータがあらたな行為を生成できるかどうかを試す場として、GUIを捉えるのがいいだろう。これからインターフェイスがどうなっていくかはわからないが、ひとまずの実験の場として、行為の複雑性を減らし、ヒトをコンピュータに合わせたのがGUIということである。GUIはヒトの行為の曖昧さを排除しつつ、ヒトから行為を委譲されたアルゴリズムが電気の力で面に広がった「奇妙な融通性」をさらに重ねていき、あらたな行為をつくりだしていく。
GUIでの指差し行為によって、ヒトの行為はコンピュータに委譲され、その委譲された行為の処理がインターフェイスを介して遂行される。ここでヒトは、トリガーとして機能しているのみである。「のみ」であると言ってしまうとネガティブに感じるかもしれないが、「のみ」であることが、コンピュータ以後のヒトのあり方として重要である。
ヒトは複雑な行為によって脳の演算を補い、物理世界と関わってきた。その複雑な行為によって、モノのインターフェイスで演算が直接行われ、物理世界での身体とモノとの関係を最適化していた。その演算部分の履歴がコンピュータに委譲されることで、今度は行為を最小化することが可能になった。委譲される側のコンピュータは、多様な行為を用意するために、物理世界でヒトとモノとのあいだに生じていた行為のアルゴリズム化を求める。久保田は手とアルゴリズムの関係について、次のように書く。
アルゴリズムは、いわば人間の「手」に代わるものです。手の代わりにアルゴリズムという「スキル」が、数字列という素材を操作し、そこから生み出される表現を変化させます。だとすれば、アルゴリズムによって生成される表現にとって最も本質的な特徴は「手を使わない」ということです。芸術表現やものづくりにおいて、手はこれまで、人間の貴さや醜さ、素晴らしさや無能さを象徴するシンボルと見なされてきました。しかしアルゴリズムはその「手」というシンボルを消去し、それはコピーによって社会的に共有できるのです。だとすれば、デジタルデザインとは、ポスト手業、さらにはポスト人間時代のデザインのことに他ならない、といえるでしょう。久保田晃弘「Design 3.0:デジタル・マテリアリズム序論」
コンピュータのアルゴリズムは手に代わり、インターフェイスは手の行為を最小化していく。それは、今まで複雑な行為によってヒトの進化を支えてきた「手」の履歴を、一度消去してしまうことである。このように書くと、スマートフォンで手や指を多く使っているではないかと言われるかもしれない。しかし、その手や指は「カーソル」の代わりである。ヴァーチャルな指であったカーソルの代わりに、フィジカルな指が使われているにすぎない。これがヒトとコンピュータとの共進化である。
ここが、コンピュータとともにあるヒトのあらたな進化を考える出発点になる。外爆発でも内爆発でも失われなかった手の意味するものが、ヒトとコンピュータとの共進化のなかで生まれ変わっていく流れを考えなくてはならない。ヴァーチャルであろうとリアルであろうと、手は物理世界とのあいだでこれまで蓄積してきた行為をコンピュータに委譲し、一度履歴を消去して、「あらたな手」になった。その「あらたな手」が、ヒトの最小化した行為を遂行しながら、コンピュータとともにあらたな行為をつくりだしていく。
複数の物理世界と仮想世界とをつなぐインターフェイス
久保田はデジタル・マテリアリズムを深めていくキーワードとして「ハッキング」「アルゴリズム」「インターフェイス」を挙げている。「ハッキング」によってアプリケーションやOSの深くに入り込んで、数字を直に扱うこと。数字列をヒトの身体と結びつける、非身体的な「アルゴリズム」を習得することが重要となってくる。そして、最後にくるのが「インターフェイス」である。
最後のキーワードは「インターフェイス」です。インターフェイスといっても、GUIのことではありません。それは、数と知覚、演算と身体、表現と形式、素材と構造、物質と非物質、スキルと社会といった、さまざまな概念や領域をつなぐものです。マーカス・ポップ(オヴァル)は「全てはインターフェイスである」と言いました。確かにその通りかもしれません。だからこそ、そのインターフェイスに対する試作と実装(制作)が、デジタルデザインのガイドラインをつくり出すのです。久保田晃弘「Design 3.0:デジタル・マテリアリズム序論」
インターフェイスとはどこにあるのだろうか。ヒトとコンピュータとのあいだにあると言われる。しかし、その状況は異なり始めているのではないだろうか。ヒトとコンピュータが向き合える平面そのものがインターフェイスとなり、このインターフェイスがさらに仮想世界や別の複数の物理世界とつながっていると考えることはできないだろうか。
ヒトとコンピュータによる情報のやりとりだけで、インターフェイスを捉えることは難しくなってきている。ヒトとモノとの関係が成立する基盤そのものがインターフェイスとして捉えられ、ヒトもひとつのインターフェイスとなり、ヒトとモノとの複数のインターフェイスが水平垂直につながっていき、いくつもの物理世界と仮想世界が現れる。
次回以降、ヒトとコンピュータがつくりだす「あらたな手」とともに、複数の物理世界と仮想世界、そしてインターフェイスについて考えていきたい。