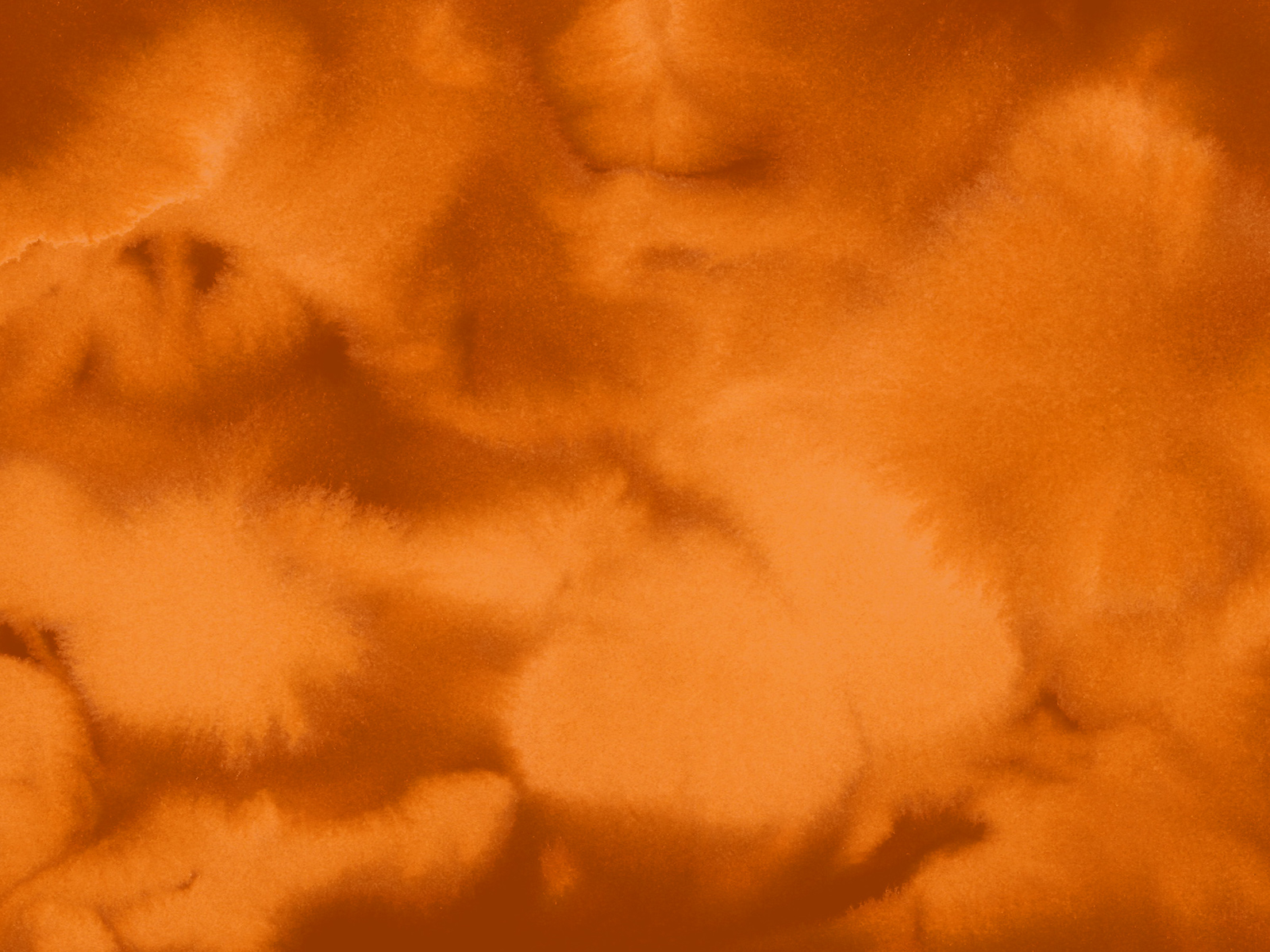村津蘭:
ナターシャさんは2016年からモンゴルのマルチスピーシーズ医療について調査されていると伺っています。まずその観点からコロナウイルスについてのご意見をお聞かせいただけますか。
ナターシャ・ファイン:
私は現在、モンゴルの医療と知識の伝達について研究する国際チームで活動していて、その一部は「ワンヘルス※1」という概念の枠組みに関係しています。ワンヘルスとは、人間への医療と動物に対する医療、そして環境的な要因を組み合わせる、比較的新しい医療的な枠組みです。この種を超えた学際的なアプローチは、人文学や社会科学の中では今まであまり探求されてきませんでした。
私たちのプロジェクトのひとつの課題は、フィールドワークを通して、ローカルの文脈の中で用いられてきたモンゴル医療を、どう文化横断的に見ていくかということです。ちょうどマルチスピーシーズ的なつながりに焦点をあてたマーモットとペストについての論文を2本書き上げたばかりなのですが、そのひとつはマーモットと(ウイルスの媒介動物である)蚤、ペスト菌、その他の種が、どのように相互接続的な社会生態の一部であるかについて注目したものでした。モンゴルの牧夫はマーモットを狩って、珍味として食します。マーモットに強力な治療性があると感じているのです。モンゴルでは毎年数件、マーモットを狩った若い男性がペストで亡くなるケースがあるにも関わらず、マーモットに対する古くからの文化的な伝承やコスモロジーにおける知覚は、ペストへの恐怖に勝る傾向があると言えます。
コロナウイルスもまた種を超えた病で、最近はウイルスがどこから来たのか、それが潜んでいるのは蝙蝠か鳥なのか、その媒介体となるのは何か、センザンコウなのかジャコウネコなのかなどの議論がされています。しかし、このように素早く変異するウイルスは、種の間の差によって可鍛性が高くなるため、出所を特定するのが困難です。私は、このようなウイルスの発生源に着目して、場所を明確に特定して責任を配分しようとするのではなく、ウイルスが異なる種の間を移動するあり方や、私たちにとって採用可能な予防措置に焦点をあてる必要があるというエベン・カークセイ※2の意見に賛成します。
コロナウイルスを国内に入れないように、モンゴルはよくやっているといえます。その理由のひとつは、遊牧を主な生業とする国家として、しばしばペストのような動物由来感染症の病気や、ブルセラ病や口蹄疫、炭疽病のような人獣共通感染症に対処しなければならなかったからだと思います。本来彼らは、生物科学の医者や獣医が、人獣共通感染症に対抗するためには種を跨ぐ病に注目することが最良な方法だと言い始めるずっと前から、何千年もワンヘルスの枠組みに沿ってやってきたのです。
モンゴルでは、病に対する検疫や隔離に長い伝統があります。例えば去年の2019年5月初旬に、薬として生のマーモットの肉を食べて亡くなった夫婦がいましたが、彼らがいた地元の町では即座に隔離が宣言されました。モンゴル人はこのような対策に慣れているのです。しかし、牧畜コミュニティにおいて、病の予兆に気づいたときの対応は、どちらかというと予防法に関するものです。例えば、馬が鼻水を出していたり躓いたりするのは、馬インフルエンザのサインかもしれなかったり、見張り役のマーモットが警告音を出すことに失敗し鈍い動きをしているのは、マーモットの群居地にペストが潜んでいるサインかもしれないといったことです。ですから、政府はワクチンなどの生物医療の技術と、牧畜コミュニティが持つ病の前兆や予防実践に関する知識を統合するべきなのです。
§
村津:
私たちの医療や健康の考え方に、コロナウイルスはどう影響を与えたと考えますか。
ナターシャ:
コロナウイルスは、人間の身体と健康だけに着目するような、人間中心的やり方ではいけないという、私たちの認識を高めたと考えています。生物医療や西洋医学の枠組みはとても細分化されています。アネマリー・モル※3は『多としての身体』を出版し、医療システムが異なる存在論としてどのように分断されているのかを手際よく示しました。また、彼女とジョン・ローはカンブリアの羊について書いています※4。彼らは、農夫たちの羊に対するある見方に対して、獣医はまた異なる見方で見ていること、さらに疫学者もまた異なるスケールで見ていることを指摘しました。人類学者や社会科学者として私たちがしなければならないのは、これらすべての異なるパースペクティヴを、健康という観点でどのように結び付けられるのか考えることです。
モンゴルの医療はより包括的なものであって、さまざまな側面を別々の領域的なカテゴリーにただ振り分けるものではありません。治療師(healer)は、特定の薬用植物を、出産した後の牛にも腎臓に問題を抱えた人にも、処方する場合があります。違う分量で、おそらく他の特定の材料と混ぜたりする形で。ここで問題なのは、新しく変異した毒性のある病に対抗するには、どうしてもワクチンに頼る必要があるために、伝統的医療で対処できないことです。このように素早く広がる病とどう向き合うかについては、何世紀にもわたって蓄積された知識がないのです。
しかし、モンゴルの医療が得意なのは、免疫力を高めて健康を維持し、周囲の土地(ノタック)を見守りながらバランスを保って、このような病を初期段階で予防する方法を考えることです。この性質は、日本や中国、チベット、アーユルヴェーダのような、多くの異なる伝統医療のアプローチにも共通していると思います。モンゴルの医療はあまり知られておらず、もともと多元的で、他の「伝統的な」医療技術を受け入れていますが、モンゴル高原に特有の長年の実践も多くあるのです。

村津:
調査について言えば、ナターシャさんはテクストを基盤とする従来の民族誌(ethnography)だけではなく、民族誌映画(ethnographic film)も作成していますね。今世紀に入って、映像の技術的な発展と人類学におけるパラダイムシフト、特に象徴的な構造から実践や感覚に力点が移る中で、民族誌的調査を構成するものとして、映画制作に対する関心が高まっています。今日、映像人類学者は実験的なものからフィクション映画まで、さまざまな映画制作のスタイルを使っていますが、その中でも「観察映画(observational film)」は主要な位置を占め続けています。ナターシャさんも制作方法として採用している「観察映画」は、1960年代の移動可能な音声同録システムと軽量カメラの発達によって可能になった、ダイレクト・シネマやシネマ・ヴェリテ※5を含めた一群のドキュメンタリー映画です。ナターシャさんが「観察映画」という映像制作のスタイルに辿りついた経緯と、調査方法としてどんな特色があるのかを教えていただけますか。
ナターシャ:
私の学問的背景には動物行動学があり、以前はナチュラル・ヒストリー的な映画制作をしていました。ですが、2004年に初めてオーストラリア国立大学(ANU)に来て、博士号取得のための調査を実施したときに、民族誌的な映画制作が人類学的な調査の一部として認められていることを知りました。それで映画制作を自分のフィールド調査の方法として取り入れることができたのです。デイヴィッド・マクドゥーガルとジュディス・マクドゥーガル※6が私の大学を拠点としていたのは幸運でした。
観察映画は、観客がまるで対象と一緒にいて、自分たちが全体の一部かのように感じさせるように、異なるコンテキストで彼らを夢中にさせます。それは、時間や空間がごた混ぜに短いカットが編集され、必然的に没入しにくいものとは違うものでありたいのです。ANUに所属していたもう一人の有名映像作家のゲリー・キルディアは、全知の存在のような外部のナレーションで観客を動揺させるのではなく、いかにドキュメンタリーの「夢の中に」没頭させるべきかについて語っています。
観察映画制作は、スタイルとしても倫理的にも、自分が動物に関して伝えたいことと一致するように感じました。なぜなら、ナチュラル・ヒストリー的な映画制作は演出されることが多く、現実よりもドキュメンタリードラマのようだからです。観察映画は、フィールドの人々が展開する出来事を実際に記録するプロセスであり、用意されたスクリプトや計画に沿うものではありません。つまり、観察映画はコンセプトやアイディアに関しての方向性は持っていますが、フィールドに根付くことで影響を受けていく、現在進行形のプロセスなのだと言えます。
§
村津:
観察映画はあからさまなナレーションや演出を含めず、フィールドの実践に焦点をあてることで、物語の対象の方が映画制作者の計画よりも重要だと示しているのですね。この態度は人類学的な関わり方と一致していて、それが人類学的な映画制作として支持される理由かもしれません。デイヴィッド・マクドゥーガルといえば、彼は「観察映画が世界には見るべき価値があることが起こっているという前提に基づいている。そして、対象の持つ特有の空間的、時間的なあり方は、その見るべきもののひとつである※7」と述べています。ナターシャさんの制作した映画「ヨルング・ホームランド」は、場所のもつ時間やテンポを感じさせることに成功していると思いますが、このような効果をもたらすために考えたことを聞かせていただけますか
ナターシャ:
テンポとコンテキストを築くことは、デイヴィッド・マクドゥーガルから学んだ重要な観点で、私はそれをこの「ヨルング・ホームランド※8」の中で実践しました。私は自分が運営に携わっていた修士課程の民族誌映画制作コースにデイヴィッドをゲスト講師として招いたのですが、彼は映画の最初の5分間でテンポを描き、残りがどのように進むかを示すのだと話していました。つまり、ゆったりとしたテンポで始めたならば、その後の映画が同じようなテンポで進むことを観客は受け入れるのです。だから「ヨルングの時間」のゆったりとしたテンポを表現するために、映画の冒頭は静かな朝のシーンから始めました。町から離れたアボリジニーのコミュニティの中にいるということが、どう感じられるかも伝えたかったのです。大抵の場合は静かで、物事がゆっくり起こりますが、太陽が降り注ぐと、急に多くの活動が始まることもあります。
村津:
民族誌映画はマリノフスキーが言った、声のトーンや物の手触りなど、日常の数えられない質である「不可量部分(imponderabilia)」を伝える方法だと思います。不可量部分は民族誌家が調査するべき要素のひとつとされますが、社会的構造やナラティブと違い、テクストだけで表現することが難しいものです。ナターシャさんの映画「ヨルング・ホームランド」で、特に不可量部分的なものを感じたのは、海辺で一人の女性が、獲った魚を分け与えなかったことで海鷲になってしまった男の子の民話を語るシーンでした。このシーンを作ろうと思った背景を教えていただけますか。
ナターシャ:
その民話を取り上げることにしたのは、ヨルングの老人が語っていたからです。それは、私たちが捕らえた海の食料を調理していたら、ちょうど近くで海鷲が数匹のカラスから巣を守ろうとして騒いでいたときのことでした。彼女は私に実際の海鷲とコスモロジーの間のつながりを感じてほしかったのだと思います。この民話はよく知られたもので、ヨルング・ホームランドの学校教育のために英語で書かれていました。本で読むこともできますが、私はこの民話がどんなやり方で語ることを目指されていたのかを、田舎で物語られる正しい文脈の中で示したかったのです。これは子どもたちのための物語ですが、海鷲が頭上で鳴いている場所で座って聞く必要があるのです。そうすることで、物語の中の鷲と空を飛び回る本物の鷲のつながりを作ることができて、まったく文脈から外れた教室の本の中にある物語より、ずっと心に訴えるものになります。
この鷲は多層的な意味を持っています。海岸にいる実際の鷲であるというだけではなく、物語を聞いている子どもたちと直接的にもつながっている存在です。物語の中で、人間、つまり子どもたちの先祖が鷲に変身したことで、海鷲が彼らのトーテム動物かもしれないという点で、彼ら自身も鷲の一部であると考えられるからです。この動物は人間と鷲の間を変身することができるので、物語を聞くヨルングの子どもたちにとって意味深いものです。それはヨルングの人々が鷲のパースペクティヴで考えることを促すのです。
§
村津:
民話の的な側面だけではなく、ナターシャさんのおっしゃる「多としての存在(multiple being)※9」という概念も伝えているわけですね。このような不可量部分的な側面を伝える方法は、映画だけに限定されているわけではありません。近年、アメリカを中心として「マルチモーダル人類学(multimodal anthropology)」という概念が、映像人類学に代わるものとして提唱されています。この動向は、フィールドにおいても、人類学者が属する社会においても、さまざまなメディア環境が急速に発展してきたことを反映しています。このマルチモーダルという発想は、メディア関連の実践だけにとどまらず、感覚的・身体的を巻き込む民族誌にも広げられるのではないでしょうか※10。マルチモーダル人類学について、ナターシャさんのご意見をお伺いできますか。
ナターシャ:
私はさまざまな種類のメディアを用いた、マルチモーダルなコミュニケーションに賛成です。ポッドキャストの新たな動向や、調査を追究するためにオーディオを使うこともとても良いと思っています。学者たちはいまだに本というメディアによって自己規定する傾向がありますが、他の要素も取り入れていくことは重要だと思います。私は限られたアカデミックの聴衆だけではなく、一般の人々にもアイディアやコンセプトを伝えたいのです。アカデミアという枠を超えて、自分の研究に関心を持ってくれる人々に届けたいと常々思っていました。
私はさまざまなコミュニケーションのモードを試してみるのが好きで、ひとつひとつのプロジェクトにおいて、どのように伝えるのが一番いいのか考えてきました。2017年に私は「二つの季節 ~モンゴルのマルチスピーシーズ医療~※11」という観察映画を撮ったのですが、そこで多くの馬の瀉血(医療の目的で実践者が、さまざまな箇所に針を刺し血を抜くこと)の事例を撮影しました。また、ある作品は、医学歴史家が主催した、流動体に関するカンファレンスに出席したことに刺激を受けて始めたものです※12。私たちはそれを、新聞や雑誌で探査ジャーナリズム的なものを伝えるのによく使われる「Shorthand」というツールを用いて作りました。ページをスクロールしていくと、それに合わせてイメージが変化するのです。多様な静止画があることで、ストップモーションアニメーションのようになる。最終的に、3つの独立部からなるフォトエッセイになったのですが、瀉血についての調査を伝える新しい道具として「Shorthand」を使うことは、非常に楽しいことでした。
近年は、別の存在のパースペクティヴを得るために、GoProカメラも使っています。ちょうど今年の初め、コロナウイルスが私たちの生活に影響を与える前に、さまざまな聴衆に対して多様な方法でコミュニケートするためのひとつの試みとして、パートナーと他のアーティストと一緒に展示会を共同キュレートしました。その展示会は「モア・ザン・ヒューマン:人新世時代における動物※13」というタイトルです。ここで私が展示した映像は、気候変動に直面する人間と馬の経験に関わるために、馬に乗る若いモンゴル人の牧夫のヘルメットにGoProをつけて撮ったものでした。馬と牧夫は、残りの群れの馬を見つけるために、雪嵐の中を探索しなければいけない中で、人間と馬がひとつの存在としてどのようにランドスケープと関わっているかがわかる、素晴らしいフッテージになったと思っています。
また去年には、私が住んでいるところの周辺、オーストラリアの首都キャンベラから1時間ほど離れたところで、ひどい山火事があったんです。そこで私は火事で全焼した直後に、馬とその騎手が黒く焦げてしまった森林を横切るところを記録しました。モンゴルの凄まじい雪嵐から、オーストラリアの夏に火事を引き起こす異常な熱波まで、気候変動が環境に対して全く異なる方法でどのように影響しているのかを示したかったのです。私はこの展示で、2つの対照的なシナリオを、ひとつは白を中心に、もうひとつは黒をを中心とした映像として並べ、馬と騎手が変化しゆく彼らの世界を案内するというかたちで展示しました。

最終的には、人々に、自分自身が他の動物や土地との関わりを異なる方法で認識できるということを理解してもらうことが目的です。彼らの中には、家畜が道具になったり、消費される生産物になることを恐れて、肉を食べることを心配する人がいます。しかし、私は他の文化にいる動物へのさまざまなパースペクティヴや存在論を示すことで、彼らにそのような問題を超えて考えたり、動物と関わり合う方法がいかに異なっているかについて知ってほしいと思うのです。
私は奥野教授が代表をしているマルチスピーシーズ人類学に関する科研費プロジェクト※14の一員です。そのプロジェクトの一環で、日本で騎射のフィールドワークをして、2018年9月には東京の流鏑馬祭と京都の笠懸神事を観ました。また、二つの異なる文脈における人間と馬の感覚的エスノグラフィや社会文化的な関与を比較するために、去年9月にモンゴルのウランバートルで国際騎射フェスティバルを調査しました。更にこのプロジェクトの一部として実施されている連続セミナーの中で発表し、マルチスピーシーズ研究における私のアプローチを博士課程の学生に教えるために、東京へも行きました。この複数年のプロジェクトの一端を担い、マルチスピーシーズ人類学にフォーカスしている日本の研究者と関わる機会が与えられているのは、素晴らしいことだと感じています。
§
村津:
ナターシャさんがおこなっている、一般の人々へのアウトリーチの仕方や人類学的な参与のスタイルを広げていくアプローチはとても興味深く、刺激的だと感じました。人類学的な実践が多様な方法で実施されているという意味で、私たちが目指しているのは、ナターシャさんが提示する概念を借りて言うならば、「マルチプルな人類学」と言えるものかもしれませんね。今日はコロナウイルスやマルチスピーシーズ、そして今日の人類学的な取り組みについて示唆的な考えを聞かせていただき、本当にありがとうございました。