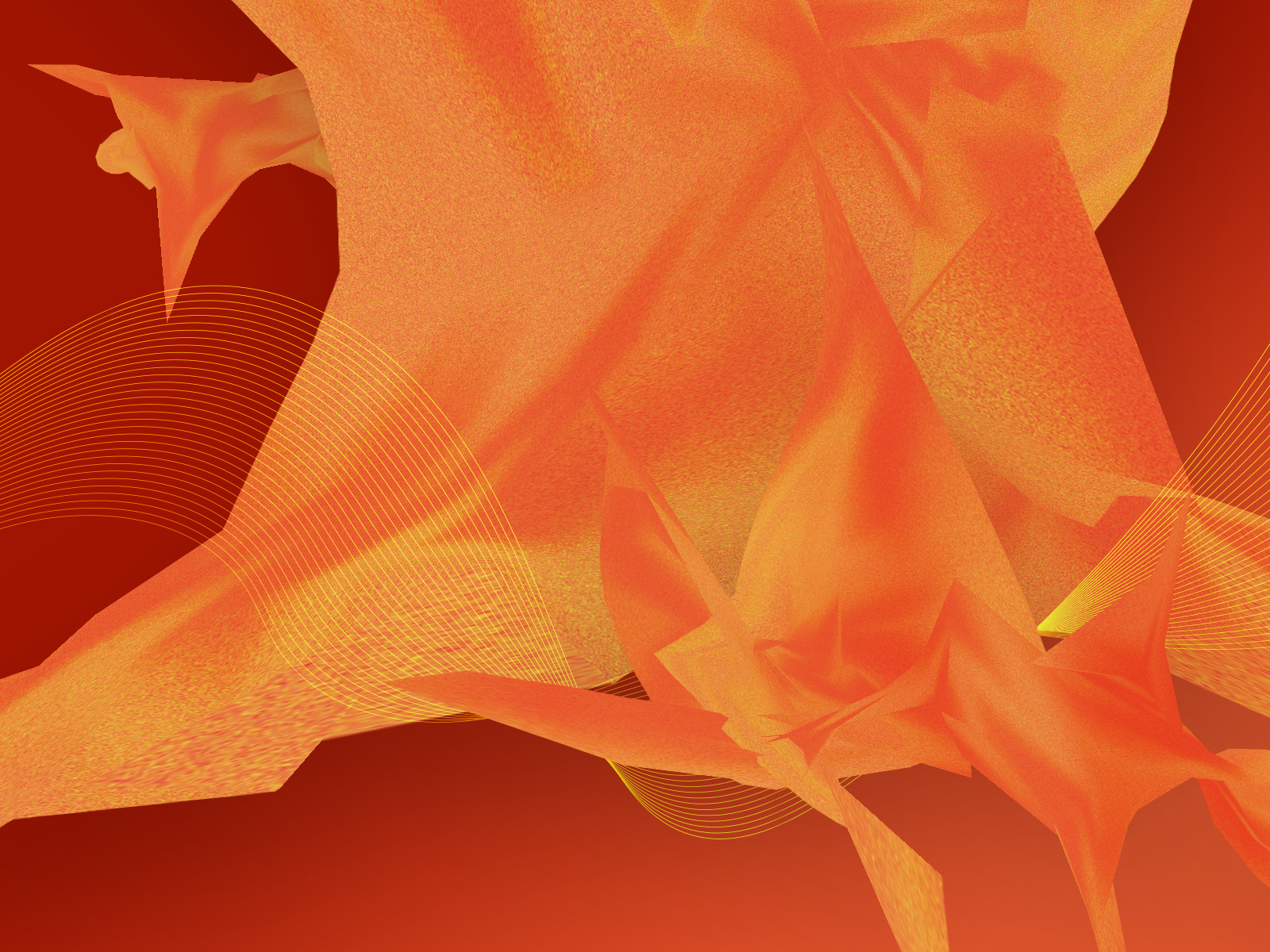1. 人間的なるものを超えて
気がつくと、人類学はその名前が示すとおり、人間のことだけを探究する学問になっていたと言ったら、奇妙に響くだろうか。
人類学は長らく、人間が生み出し、営んでいる制度や慣習などを「文化」と呼び、その記述を「民族誌」と称して、人間の文化の記述と考察に浸った末に、記述のしかたや学問を成り立たせている仕組み、その権力配分にまで気を配りながら、どうしたらそのような再帰的な課題を乗り越えて正統な学問たり得るのかを考えるのに頭を悩ませてきた。
そのことは、形質人類学、考古学、言語人類学、文化人類学という4部門から成る総合学を目指した、20世紀初頭のボアズ流のアメリカの人類学の「後退」であり、フィールドワークを学問の中心に位置づけ、民族誌を制度化した、マリノフスキー由来のイギリスの人類学の「前進」の結果だった。世界に広がった、民族誌を重要視するイギリス流の人類学は、アメリカで巻き起こったポストモダン的な自己反省モードの投入によって内向きの議論を重ね、前世紀末から今世紀初頭にかけて隘路を歩むことになったのである。
そうした前進と後退の歩みの陰に、もう一つの人類学の流れがあった。レヴィ=ストロースの人類学である。1938年にブラジル調査に出かけたレヴィ=ストロースのフィールドワークは、一つの社会で局地的な調査をおこない、輝かしい成果を出し始めていたマリノフスキーのそれとは異なり、集団間の「断面」の比較を通じて変異の多様性と共通性をあぶり出し、様々な変形によって一定の原理が広汎に見出されることを示すものだった。その手法はその後、レヴィ=ストロースの研究に通奏低音として鳴り響きながら、「音韻論の社会構造への応用」(『親族の基本構造※1』)から「異種との交換(交歓)」(『神話論理※2』)という主題へと次第に高められていったのである※3。
デスコラやヴィヴェイロス・デ・カストロなど、レヴィ=ストロースの思想を継承した人類学者たちは、人間と他の生物種との関係へと踏み込むことで、「アニミズム」「パースペクティヴィズム」「多自然主義」など、人類学だけに留まらないより包括的な人文学の新たなトピックを見出したのである。人類学は21世紀を迎えると、人間のみでなく、人間を含みつつ人間を超えて、より大きな研究枠組みの中で思考するようになった。コーンの「人間的なるものを超えた人類学」は、そうした流れの中から生まれた一つの果実である。
森が考えているということで、いったい何が言われようとしているのかをよく考えてみたい。つまり、(全ての思考の基礎を形成する)表象の諸過程と生ある存在のつながりを、人間的なるものを超えて広がるものに民族誌的に注意を向けることを通じてそれがあきらかになるにつれて、つかみだすことにしよう。そこで表象の本性について私たちが抱く前提を再考するに至った見識を用いることで、それが私たちの人類学的な概念を変えるのかを探ってみるのがよいだろう。このアプローチを「人間的なるものを超えた人類学」と名づけようではないか。
エドゥアルド・コーン『森は考える — 人間的なるものを超えた人類学※4』
コーンは、パースの記号過程を用いて、人間を含め、あらゆる生ある存在がいかに思考するのかという問いを立てる。そうすることによって、人間のみを扱う人類学を超えて、哲学とも深く交差しつつ、ノンヒューマンとヒューマンを同じ地平に眺める人類学の新たな領野を切り拓いたのである。
2. マルチスピーシーズ民族誌/人類学
「マルチスピーシーズ(複数種)民族誌」も、その流れに位置する。それは、異種間の創発的な出会いを取り上げ、人間を超えた領域へと人類学を拡張しようとする。
その成立の経緯は、概ね以下のように説明される。レヴィ=ストロースが動物を「考えるのに適している」と捉えたのに対し、ハリスは、それらは「食べるのに適している」と捉えた。しかし、動物を含む他の生物種は、人間にとって、たんに象徴的および唯物的な関心対象というだけではない。他種は、人間や別の種と関わりながら絡まりあってきた。ハラウェイが言うように、他種は人間にとって「ともに生きる」存在でもある。マルチスピーシーズ民族誌は、この「ともに生きる」というアイデアを重視する。それは、複数種を取り上げることによって、動植物を人間主体にとっての対象としか捉えようとしてこなかった人類学が抱える人間中心主義的な傾向に挑戦しようとする※5 ※6 ※7。
オグデンらによれば、マルチスピーシーズ民族誌とは、行為主体である存在者の絶え間なく変化するアッサンブラージュの内部における、生命の創発に通じた民族誌調査および記述である※8。それは、複数の有機体との関係において、人間的なるものが創発する仕方を理解しようとする。ヴァン・ドゥーレンらによれば、マルチスピーシーズ人類学は、他種をたんなる象徴、資源、人間の暮らしの背景と見ることを超えて、種間および複数種間で構成される経験世界や存在様式、他の生物種の生物文化的条件に関する分厚い記述を目指す※9。マルチスピーシーズ民族誌/人類学は、人間を静的な「人間–存在(human beings)」ではなく、動的な「人間–生成(human becomings)」と捉える。
インドでは年間何百万という牛が死ぬが、神聖視されているため食べられることはない。牛は死にかけると、遺体ごみ置き場に連れて行かれる。ハゲワシはそれを30分できれいに解体する。しかし今日、牛を食べることがハゲワシを殺す。というのは、貧困層が牛を使って作業を続けるために、また牛の足の病気、乳腺炎、出産困難などを処置するために、安価な非ステロイド系抗炎症薬ディフロフェナクが牛に投与されるが、それがハゲワシに腎障害をもたらすからである。インドでは現在、ハゲワシの減少に反比例してイヌが増えている。イヌは、ハゲワシのようなスピードと完璧さで死骸を片付けはしない。イヌは町をうろついて人を襲い、狂犬病などをもたらす。ハゲワシがいないと、人や動物の健康に重篤な影響がある。このようにして個体は絡まりあって生きており、生と死を含む複数種の文脈では、他者の苦しみへの純粋な反応を考慮しなければならない。
ツィンによれば、マツ、マツタケ、菌根菌、農家の人たちが絡まりあって生存可能性を生み出している。痩せた土地でマツと菌根菌は共存しており、菌根菌が育つとマツタケになる。農家の人たちは、燃料や肥料を求めてマツ林に入り、生態系に介入する。そのことで、マツは排除されることを免れ、マツにとって程よく攪乱された状況がつくり出される。マツ、菌根菌、農家の人という異種の偶然の遭遇によりマツタケが育つ。また日本では、高品質のマツタケは高価な贈り物として、特定の小売に卸され、人間関係の構築のために用いられる。マツタケはいったん自然から切り離されるが、人間と自然が絡まりあったものとして、人間社会にもたらされる※10 ※11。
ドメスティケーションを再考する過程で、ステパノフらは「飼育する/飼育される」という古典的な二項図式に代えて、ヒューマンとノンヒューマンが入り乱れ、それらが長期にわたって根を張るハビタット(生息地、なわばり)である「ドムス(domus、家)」を変容させるような、相互行為的な動態による三項的な図式を提起している。コミュニティとはこれまでは、生物学では自然環境の中で種が相互作用する場であり、社会科学では人間の集団を意味したが、ステパノフらはレステルの概念を拡張して「ハイブリッド・コミュニティ」という包括的な概念を創出する。それは、「共有されたハビタットの周りの人間、植物と動物の間の長期にわたるマルチスピーシーズ的な連携の形式」のことである。南シベリアのトゥバの「アアル・コダン(生きる場所)」というハイブリッド・コミュニティでは、家族と家畜がともに暮らしている。そこでは、すべての要素が相互に依存しあっていて、人間の過ちが家畜に病気をもたらし、ヤクの供犠はアアル・コダン全体に繁栄と健康をもたらすとされる※12。
マルチスピーシーズ民族誌/人類学は、人間と人間以外の存在という二元論の土台の上で繰り広げられる、人間と特定の他種との二者間の関係ではなく、人間を含む複数種の3+n者の「絡まりあい」とともに、複数種が「ともに生きる」ことを強調する。人間主体に現れる範囲のみで他種は捉えられるべきではない。それはたんに象徴的・唯物的な対象ではないとされる。
こうしたマルチスピーシーズ人類学※13の特性をより鮮やかに理解するために、哲学の課題を一瞥することは有用だと思われる。現代のモノの哲学は、マルチスピーシーズ人類学と同根の主題を孕んでおり、人類学の近年の研究成果を取り入れて交差し、拡張されているからである。
3. 種を記述する技法
カント以降の哲学では、人間がモノに対してつねに特権的な位置を保ってきた。対象世界が差異や多様性に満ちているにしても、あくまでも人間主体から見た剰余や外部とされてきたのである。ハイデガーにとっても、世界は何らかの目的をもった道具が連関してできており、その連関に不確定さを持ち込むのはつねに人間であった。モノが人間に現れる範囲でしか捉えられてこなかった「相関主義」を批判して、近年ハーマンは、モノとモノが能動的であり受動的である役割を演じながら独立的に作用することを強調する※14。
哲学者・清水高志は、近年の人類学の議論を積極的に援用しながら、擬人化される傾向にあるハーマンの「オブジェクト指向哲学」に挑んでいる※15。清水は、モノとモノが互いに移動し相互包摂する往還運動を強調する。マルチスピーシーズ人類学もまた他の生物種を人間に現れる範囲でのみ扱うのではなく、相関主義を超えて種と種の関係性それ自体へと踏み込んでいるのだとすれば、両者の課題は共通している。
ところで、ここでいうモノには非生命だけでなく、生命も含まれる。マルチスピーシーズ人類学が扱う「種」とは、主に生命である。以下では、生命記述の技法について、モノの哲学の議論の延長線上で手短に触れておきたい。
清水を継承しつつ上妻世海は、「ありのままの、不合理で、重畳で、無駄が多く、混沌に満ち溢れた、あやうい可能性の上にかろうじて成り立つ動的なものとしての自然である※16」〈ピュシス〉や、「あらゆる存在を様々な〈あいだ〉において見ようとする理論的態度※17」としての〈レンマ的論理〉を骨組みとして、生命記述の技法を検討している※18。上妻は福岡の「動的平衡」論を導きとしながら、以下のように述べる。
なぜか僕たちは、明日も、明後日も、明々後日も、同じ身体をもち、自己同一性を保ち続けることができると信じている。しかし、物質的には1年も経つと、僕は僕でない。僕は自らを分解することで自らを構築し、自らを構築することで自らを分解する「流れ」である。そして、この「流れ」の中で構造を維持するためには、「私は私である」という自己同一性の耐久性や構造を強くするのではない。エントロピー増大の法則による乱雑さが構造の維持を不可能にしてしまう前に、先回り的にその同一性を部分的に分解し、そして構築する必要があるように、「私は私でなく」(分解)、「私は私でなくもない」(構築)という「流れ」の中に身を置くことになる。
上妻世海「制作へ」
生命は変形と流れの中で、つまり時間の中で分解と構築を孕むものとして捉えなければならない。言い換えれば、「僕たちは『死につつ、生き、生きつつ、死んでいる』」のだ。
上妻はこの議論をさらに進めて、生命記述の技法を、事物がそこに存在するのはそれ自らによってではなく、他に依って他との関係においてであるとする龍樹(ナーガルジュナ)の『中論』に求めている。生命は「相依相待」により、生命たり得ている。生命の本質とは、事物の存在が「他との関係に縁よってある」という「縁起」に他ならない。
種が生命のことであるならば、「種」を自律的で安定的なものと捉えることには慎重でなければならない理由がここにある。種に出入りする他種によって種が相依相待的に生まれつつ死に、死につつ生まれるのだとすれば、「マルチスピーシーズ(複数種)」が喚起する、自律し安定した「種」のイメージは問題含みであることになる。それゆえに、種と種の絡まりあいに迫ろうとするマルチスピーシーズ人類学は、「種」とは何であるのかという問いを疎かにすべきではないということを、ここでは確認しておきたい※19。
4. 制作論的転回のほうへ
マルチスピーシーズ人類学が、人類学自体を反省的に捉え返した「再帰人類学」の先に、「人間とは何か」をふたたび問い始めた21世紀の人類学によって生み落とされた一つの嬰児であるならば、それは、既存の人類学の装いを必ずしも纏っている必要はない。先述したように、マリノフスキーの流れを汲む民族誌の積み重ねがあったからこそ人類学は発展したのであるが、他方で、人間に現れる範囲でしか他の生物種を取り上げることがない、人間しか対象にしない多文化主義的(文化相対主義的)な人類学を生産し続けてきたのであり、その延長線上で、再帰人類学においては民族誌を書くことそれ自体が問われたに過ぎなかったのである。では、「既存の人類学の装いを必ずしも纏わない」人類学は今日、いかにして可能なのだろうか。その解の一つは、いわゆる「人類学の存在論的転回」を超え出ていくところにある※20。
そしてその手がかりは、ふたたび上妻の制作論に求めることができる。上妻の説く「消費から参加へ、そして制作へ」という図式は、「他者」の真っただ中で暮らし、民族誌を書いて人類学を生産し続けた、マリノフスキー以降の〈消費〉、文化を書く自己を反省し社会実践に向かうとともに、民族誌を「他者」の参加へと開いた、再帰人類学の〈参加〉、そして、そうした多文化主義の所産を経て、今日、複数種の「制作的空間」へと降り立って、〈制作〉へと踏み出し始めた、多自然主義的な人類学の流れにそのまま当てはめることができよう。
上妻が示唆するように、「制作的空間」に降りていく時、異質なパースペクティヴとの感応的な関係を取り戻すためには、言語、とりわけ人間の「言語」を用いているだけでは十分ではない。そこでは、「現象を超えて実在を感じること、音やリズム、形として繋ぎ合わせること」が要請される。「制作的空間」におけるテキストとは、身体に他ならないのだ。鏡の向こう(「制作的空間」)に降りて、鏡の中で乱反射を浴びることで、自らの身体を作り替えなければならない。
「制作」とは、実際にやってみることで「未来の情報」を生み出しながら、その次へと進んでいく、あるいは引き返していく往還運動である(中略)まずは「制作」してみること、そうすることで僕たちは「制作的空間」へと入り込んでいく。
上妻世海「制作へ」
なすべきは、多文化主義的な土台の上でなされる〈消費〉と〈参加〉を超えて〈制作〉することである。「制作的空間」は、自己/他者、人間/自然に分割された人間の自己同一性を前提とせず、動植物を含む雑多な他者との不安定な運動の中に自己の変容を促すという意味において、多自然主義的な場へと向かう。マルチスピーシーズ人類学の「制作的空間」には、異種間の交歓からなる多自然主義的風景が開かれているのだ。
『マルチスピーシーズ・サロン』の中でシムンが試みるのは「人間のチーズ」の〈制作〉である。人間のミルクから作られたチーズを問題なく食べた人がいた一方で、ミルクの提供者が何を食べたのか分からないという理由で食べるのを拒否した人もいた。しかし、人間のミルクは人間にとって生まれて最初の栄養である。乳の分泌によって汚染は取り除かれるため、疫学上の問題はない。乳首を刺激していれば、年齢に関わらずミルクが出る。性腺刺激ホルモン注射によって男性が授乳することも可能であり、自ら授乳して子を育てた男性の報告もある。人間のミルクには凝乳させる乾酪素が欠如しているため塊にならないので、シムンは山羊のミルクを混ぜてチーズを作る。それは蜂蜜をかけてクラッカーの上に乗せて食べるとおいしいという。だが、人間のチーズにはどこか場違いの感覚がある。逆に、牛や羊などの他種から作られるチーズこそが「人間的」なのだ※21。私たちは、「内なる他者としての人間のミルク」から作られるチーズから乱反射を浴びることになる。
カークセイは、ザレツキーによる〈制作〉を取り上げている。彼はホモ・サピエンス代表としてコンテナの中で、ショウジョウバエ、酵母菌、大腸菌、アフリカツノガエル、カラシナなどと1週間過ごした。作業中に(頭からアンテナではなく足が伸びている)「アンテナペディア異常」のショウジョウバエを逃がしてしまったことがある(そのハエは食べても無害だという)。逃げたハエをめぐるメールのやり取りの最中に、ザレツキーは遺伝子が組み換えられた虫がすでにたくさん放たれていることを知る。他方、人間の管理の下で展示されたネズミがその後どうなったかが示されていないと、PETA(動物の倫理的取り扱いを求める人々の会)のローズはザレツキーに噛みついた。ザレツキーは5、60匹のネズミのうち展示後10匹が持ち帰られ、その他は廃橋の下に逃がされて死んだか食べられたのだろうと応答するとともに、「マルチスピーシーズ・ハウジングの倫理とは何か?」「生き物は人間の管轄下で生きることが許されるべきか?」という問いを発した。そしてザレツキーは、冷たいケージで病みやつれ孤独に苦しむ動物たちは自由に動き回りたがっていると説くPETAに従って、ケージの扉を開いて生き物たちを解き放ったのである。そのことでザレツキーは、人間の管理下に出現した「新しい野生」と、動物たちが長らく自由に動き回っていた「古い野生」の間の境目を曖昧にした。カークセイによれば、ザレツキーは狂った市民科学者を装って運動家や行政官たちの不安と戯れながら、「責任」についての問題提起をし、生物学的汚染に対する恐怖のイメージを喚起したのである※22。ザレツキーの「制作的空間」で、人間は他種との間で、自己の身体をじわじわと変容させていく。
身体の変容を伴う〈制作〉は、本源的には、日々のマルチスピーシーズ的な実践の中に埋め込まれている。雑誌『つち式』には、奈良県で数年前から農業に従事する東千茅が身体的に経験し、その目に映る農の風景が綴られている。東は、脱穀した籾の山に鼻を近づけて青い匂いを嗅ぎ、自らの生身を作ってくれる稲籾「ほなみちゃん」を慈しむ。退治した蝮の肉を鶏と分かち合い、鶏はかわいくかつうまそうだと語る。鶏種をニックと名づけて飼うが、時々鶏に飼われていると感じるともいう。
生きるとは、なによりもまず、他の生き物たちと生きかわすことなのだ。それは、多種多様な生成子たちの、それぞれの個体への作用とそれぞれの個体の外部の作用の、複雑にからみあい織りなす布の一糸となることである。
東千茅『つち式 二〇一七※23』
個体中心主義的なドグマから翻訳された日本語である「遺伝子」に代えて、「生成子」という日本語を案出した真木悠介(見田宗介)の生命論と交差しながら、東は「土を耕さない」日々の農業の実践をつうじて、他種との間でなされる自己の変容を言葉として紡ぎだす※24。
「本来生きることは、他人との関わり以前に、他種との関わりの次元の話である」。「現行の社会では、こうした異種との話が語られることはほとんどなく、人間間の話ばかりが氾濫している(中略)そこには不思議なくらい異種との話が見られない。あったとしてもそれらは、異種との関係を嗜好品的なものに限定するような、あるいは、異種との関係をあくまで同種との関係の手段や代償とするような、人間関係中心主義的な諸相である」。『つち式』は、マルチスピーシーズ人類学が取り組むべき今後の実践的な制作論的課題の一つの方向性を示している。
5. はじまりに向けて
マルチスピーシーズ民族誌としてはじまった試みは同時にマルチスピーシーズ人類学へと拡張され、その後またたく間に、アートやパフォーマンスなどを含む様々な実践と連携しながら、新たな知の領域を形成しつつある。マルチスピーシーズ研究は、人類学の下位部門というよりも、人間を単一の統合された存在として見るのではなく、それらがないと人間が存在しなくなる他の種と絡まりあいを視野に入れながら、人間中心主義的な既存の人文学とその周辺領域を脱中心化する、新たな「思想」となりつつある※25。人間と他種という二者間の関係ではなく、人間を含みながら複数種という3+n者の絡まりあいを。人間に現れる範囲での種ではなく、ともに生きる種たちのダイナミズムを。人間–存在ではなく、人間–生成を。安定的で自律的な「種」ではなく、相依相待によりそのつど作られる「たぐい※26」を。民族誌を著わすだけではなく、多様なメディアをつうじて制作を。
人間は、身体外部の環境の中の種を体内に取り込みながら生命を繋ぐだけでなく、身体内部に住む1千兆個に及ぶとされるヒト常在細菌の複数のコミュニティーとのマルチスピーシーズ的な関係の中で生きる人間–生成である。ストレプトコッカス・ミュータンスという細菌は、農業により穀物を摂取し、糖分が豊富になった人間の体中で「家畜化」されるようになった。それは糖分を好み、歯周病や虫歯を引き起こす原因となる※27。あらゆる生命はまた、複数種との関係だけでなく、非生命との絡まりあいの中にも生きている※28。マルチスピーシーズ研究はすでに石と人の関係をも研究の俎上に載せてきており※29、研究対象をモノやコトなどを含む、非生命にまで拡張する兆しがある。人間が生み出した「情報」が逆に人間の思考や行動に影響を与える状況は、科学情報革命の進展によって、とりわけ、モノのインターネット(IoT)の広がりにより顕著なものとなりつつある。
最後に、人類には世界の歴史を超えるより大きな歴史があるという考えに基づいて、138億年前の宇宙創成にまで遡って、そこから宇宙、地球、生命、人類へと複雑化する現象を探る「ビッグヒストリー」という新しい学問の動きがある※30。私たちの経験からは遠いながらも、宇宙の事象をいかにマルチスピーシーズ研究の射程に収めるかは、宇宙という壮大な外部を想定することで人類や文化を強烈に意識すること目指す「宇宙人類学」の試みとも重なる※31 ※32。
民族誌だけでなく、アートやパフォーマンスや種々の実践とも連携し、さらにミクロ、生命以外、マクロを取り入れながら、マルチスピーシーズ人類学は今後その研究と活動をいったいどこまで拡張していくのだろうか。マルチスピーシーズ人類学は、いまその歩みをはじめたばかりである。いや、はじまりに向けてその準備の緒についたばかりなのかもしれない。『たぐい vol.1』に掲載されるのは、種と種の絡まりあいの考察を今後一層深めていくための起点となる論考である。