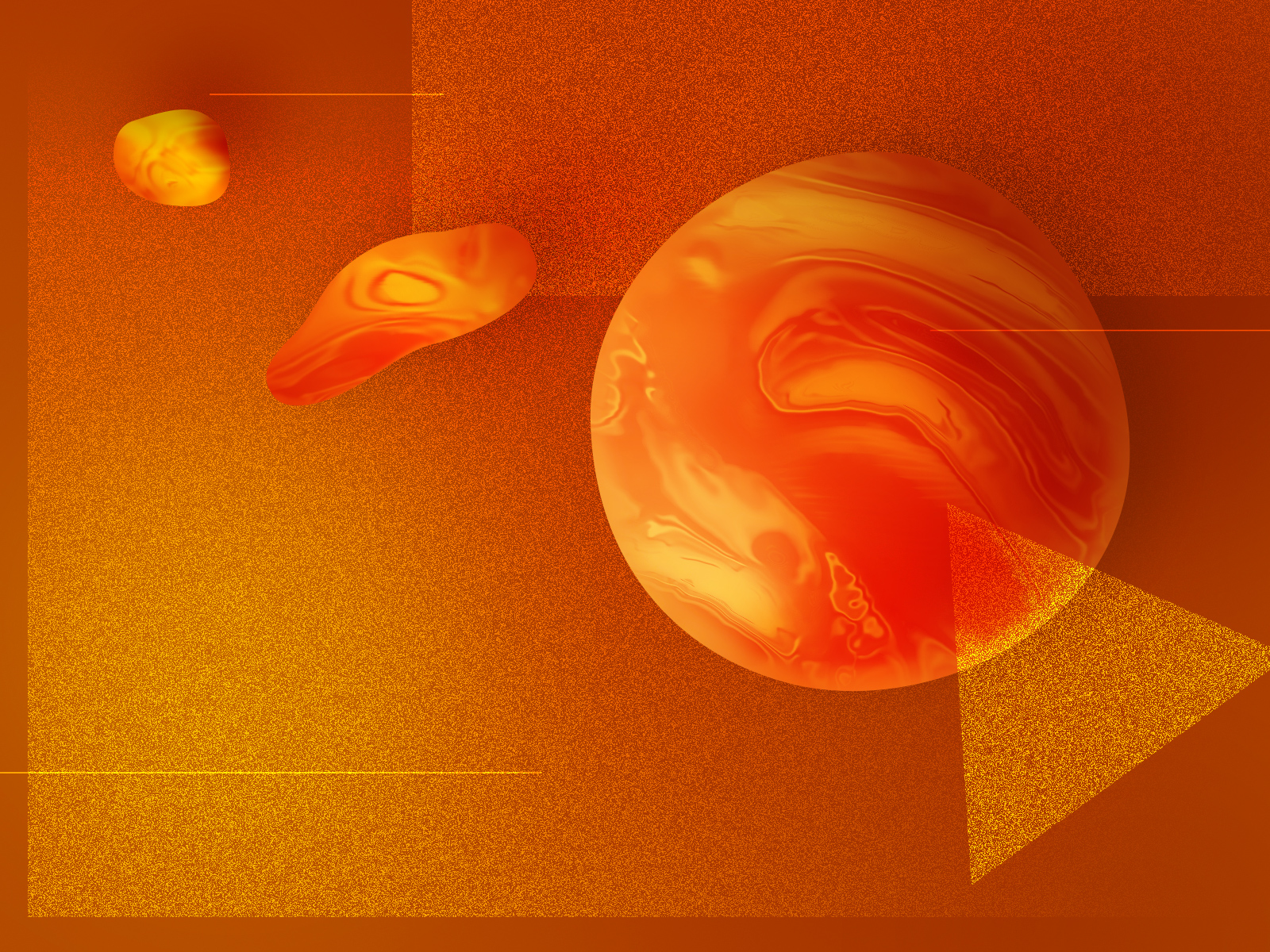1「補う」ことで生まれる面白さを持つ表現
1-1 私たちは、「補う」ことから逃れられない
私たちは生きていくなかで、与えられた情報をもとに、勝手に頭の中で「補って」しまうことから逃れることができない。有名な錯視に「アモーダル補完」というものがある。これは、例えば[図1]のように一部分が隠されている図を見たときに、隠れた部分を頭の中で補って、下にある図形は「長方形だ」と見えてしまう現象のことである。
![[図1]アモーダル補完](https://ekrits.jp/wp-content/uploads/PoD-graphic01.png) [図1]アモーダル補完
[図1]アモーダル補完
![[図2]補完の可能性](https://ekrits.jp/wp-content/uploads/PoD-graphic02.png) [図2]補完の可能性
[図2]補完の可能性
だが、この図の可能性を考えてみると、[図2]のように隠された部分がそもそも欠けていたり、破れたような形になっているなど、無数の可能性があるにもかかわらず、私たちはほとんどの場合、長方形というある特定の形をイメージしてしまう。
このように、何か与えられた手がかりを目にすることで、自分の頭を使って新しい情報を作り出してしまう知覚現象は「補完」と呼ばれている。ここで挙げた例はかなり単純化しているが、実際には補完自体は特別なことではなく、私たちが日常的に無意識のうちにやっている現象だ。しかし、人間が元来持っているこのような知覚現象のなかに、新しい表現方法を生み出すためのヒントがあるのではないかと考えている。
先ほど書いたとおり、補完現象の本質は「与えられた手がかりをきっかけとして、新しい情報を作り出す」[図3]というところにある。そのような視点で考えてみると、先にあげた例のように形状に関する補完だけでなく、静止したものから動きを生み出すような、時間に関する補完というのもあり得るはずだ。
![[図3]手がかりから情報を生む](https://ekrits.jp/wp-content/uploads/PoD-graphic03.png) [図3]手がかりから情報を生む
[図3]手がかりから情報を生む
そもそも人間は時間のなかで生きている。歩く、食べる、寝る、書く、読む、どんなことでも何か行動を起こすときには、必ず時間が生じてしまう。それは例えば、静止している物体や印刷された図版といった「動いていない」ものを見ているときにも、時間は生じている。単に全体をぼんやり見ているときも、視野の中のある一点を縦横無尽に追いかけ凝視しているときも、時間は生じている。私たちの頭の中では、それらを見て、考え、解釈しているときにも時間が生じている。
それは言い換えると、私たちは時間の静止しているメディアから、時間(や動きや変化)を生み出すことができるということでもある。そして、その「自らの頭の中で時間を生み出す」行為自体が、表現や体験として、鑑賞者に何らかの喜びや楽しさを与える、独特な価値を持つものであると考えている。
1-2「補う」ことで生まれる面白さを持つ表現
私は、この「頭の中で時間を生成する」という知覚現象に、鑑賞者が意識的・自覚的になる表現のことを『「補う」ことで生まれる面白さを持つ表現』と呼び、それらの表現の研究開発を進めてきた。
このことに関心を持ったそもそものきっかけは、私自身が映像作品を制作していたことが発端であったと思う。原理を遡ると、そもそも映像が「動いて見える」ということ自体が、連続した静止画を目を通じて脳に入力することによって、頭の中で動きのイメージが生み出されている状態だ。普段日常的に映像を見ているときには、そのような原理を意識することはないが、フリップブック(パラパラ漫画)やゾートロープなどといった映像の起源になっているような装置を体験すると、確かに自分が、止まった絵から動きを作り出しているということを体感できる。
このような動いていない手がかり(視覚提示)をもとに、頭の中だけで動きを作り出すためには、高速で静止画を提示する映像のような表現手法以外にないのだろうか。枚数も少なく、静止画を切り替える装置も必要のないもっとリミテッドな形で、補完による動きの生成ができないのだろうか。そのような疑問から、いくつかの表現研究を行ってきた。
◎事例:差分
『差分』(佐藤雅彦+石川将也+菅俊一、美術出版社、2009)によって試みたのは、複数の図版を見せて、その図版の差から、動きや質感、変化を読み取らせようという視覚表現方法論の研究である。
![[図4]差分](https://ekrits.jp/wp-content/uploads/PoD-graphic04.png) [図4]差分
[図4]差分
例えば、[図4]のような図版を見ると、1コマ目と2コマ目を見ながら、その違いを比較することで、「棒が移動して正方形の角を削り取った」と解釈することができる。
「差分」とアニメーションの違いは、頭の中に入る情報が自動的なのか、能動的なのかというところにある。アニメーションでは、鑑賞者の意思とは関係なく一方的な速度で静止画が切り替わっていき、次々と頭の中に入力される視覚情報によって、半ば自動的に動きのイメージが立ち上がる。一方「差分」では、自分の意思で前のコマと後のコマを同時に視界に入れ、自分で適切な再生スピードを事後的に作り出している。頭の中で動きを作るということは、鑑賞者自身が理想化した動きを頭の中で再生しているということでもある。
◎事例:正しくは、想像するしかない
『正しくは、想像するしかない』(菅俊一、2017)によって試みたのは、左右のページの図版を見てから、ページを閉じたときに「左右のページが合わさると起こっているであろうこと」を想像することで、動きのイメージを頭の中で作り出そうというものである。
例えば、[写真1~3]では、ページをめくることによって、右ページのコーヒーカップに左ページの角砂糖が投入されるという感覚が生まれる。ここでは、読者自身による「ページをめくって閉じる」という行為自体が、「トングで掴んだ角砂糖をカップに入れる」という図版の解釈に作用することによって、実際に動いていない図版をきっかけとしながら、頭の中に変化を作り出している。閉じたページの中で何が起こっているか、実際に見ることはできないが、頭の中では確かに何が起こっているか想像できてしまう。
このような、表現制作・研究の事例から、 提示された視覚情報をトリガーとして、鑑賞者自身が自らの頭の中で動きや質感といった表象を立ち上げる『「補う」ことで生まれる面白さを持つ表現』の可能性を探求し、表現方法論を確立するために行ったプロジェクトが今回の「指向性の原理」である。
![[写真1]『正しくは、想像するしかない』(菅俊一、2017)](https://ekrits.jp/wp-content/uploads/PoD-picture01.jpg)
![[写真2]『正しくは、想像するしかない』(菅俊一、2017)](https://ekrits.jp/wp-content/uploads/PoD-picture02.jpg)
![[写真3]『正しくは、想像するしかない』(菅俊一、2017)](https://ekrits.jp/wp-content/uploads/PoD-picture03.jpg) [写真1~3]『正しくは、想像するしかない』(菅俊一、2017)
[写真1~3]『正しくは、想像するしかない』(菅俊一、2017)
ページをめくることによって、右ページのコーヒーカップに左ページの角砂糖が投入されるという感覚が生まれる。
1-3 指向性の原理とは
私たちは、目で見たものを手がかりにして頭の中でイメージを作り出している。ここまで書いてきたように、静止画のような「動いていない」情報を見たときにも「動き」や「時間の経過」を感じてしまうことがある。もちろん、どんなものを見ても、動きや時間の経過が感じられるというわけではない。動いていない情報から動きを見出すには、いくつかの条件を満たす必要があるはずだ。
これまでは、『差分』や『正しくは、想像するしかない』といった複数の図版の比較や、複数の図版を人間の行為によって再解釈させることで、静止した情報から動きや時間の経過を生み出す表現を探求してきた。しかし、私たちの補完能力をより引き出す方向を突き詰めていくと、たった1つの図版からでも、動きや時間の経過を見出すことができるのではないかと考えた。例えば[図5]のように、1本の矢印が曲線を描いている様子を見ると、ただ右の方に向かっていると解釈するのではなく、ついつい目で線を追いながら、「くるん」といった動きのようなものを感じてしまう。また[図6]の例では、これもただ左下に向かって方向が示されているというのではなく、「ピョーン、ピョン、ピョン」と跳ねるような動きを感じてしまうのではないだろうか。
![[図5]くるんとした矢印](https://ekrits.jp/wp-content/uploads/PoD-graphic05.png) [図5]くるんとした矢印
[図5]くるんとした矢印
![[図6]跳ねる矢印](https://ekrits.jp/wp-content/uploads/PoD-graphic06.png) [図6]跳ねる矢印
[図6]跳ねる矢印
このように、ある静止した1つの情報を手がかりとして、頭の中に動きのイメージを生み出している現象そのものを「指向性の生成」と定義して、新しい表現を生むための方法論を探求したのが、今回のプロジェクト「指向性の原理」である。
ここで重要になるのが、例に挙げた矢印のような手がかりを、どのように作れば頭の中に動きが生み出せるかということである。見るだけで、自然と頭の中で動きを生み出してしまうような条件にはどのようなものがあるのか。作品制作を通じて、その条件や表現としての可能性を探ろうと考えた。
2 指向性の生成
ここでは、展示「指向性の原理」で扱われた作品を取り上げながら、どのような視覚的要素が指向性を生み出すか、その具体的な例について述べていく。
2-1 線
まず、指向性を持つ視覚的要素として取り上げたのが「線」である。もちろん、どんな線でも指向性が現れるというわけではない。[図7]のように、ただ線を描くだけでは1つの形を持った図として見てしまう。
![[図7]指向性のない線](https://ekrits.jp/wp-content/uploads/PoD-graphic07.png) [図7]指向性のない線
[図7]指向性のない線
線が指向性を持つためには、始点と終点が定義される必要がある。それも「スタート」「ゴール」のように記号的な言葉を加えるのではなく、造形的な工夫によって達成されなければならない。そのためのヒントとして「痕跡」という概念に着目した。
![[図8]掠れ](https://ekrits.jp/wp-content/uploads/PoD-graphic08.png) [図8]掠れ
[図8]掠れ
[図8]を見ると、右から左へと動きがあるように見える。このときに動きを感じさせたのは、線の「掠れ」具合の影響が大きい。どちらの方向に掠れているか、濃度を見ることによって線の始点と終点が定まり、どちらの方向に動いているかがわかる。普段このような痕跡は、物を引きずったり、汚れを残したりしたときに生み出されることが多い。私たちは床や地面に残された痕跡を見て、「何がそこで起こったのか」を想像することができる。現実では「掠れる」というのは実際に物が削れたり、塗装が剥がれることによって引き起こされる現象だが、このような痕跡の概念を、「掠れ」とは違う形で、どうやって太さが一定の線に抽象化して適用するかが、指向性を持つ視覚的要素として線を扱う上での重要なポイントになる。
そこで、[図9]のように片方の線の端に、何かオブジェクトを配置することを試みた。これによって、線はそのオブジェクトの痕跡のように見えてくる。つまり、視点がオブジェクトのない方の端点となり、終点がオブジェクトのある方の端点となる。
![[図9]線とオブジェクトA](https://ekrits.jp/wp-content/uploads/PoD-graphic09.png) [図9]線とオブジェクトA
[図9]線とオブジェクトA
比較のために、[図10]のようにオブジェクトの位置を[図9]とは逆にしてみると、動きの方向が途端に変わる。また、[図11]のようにオブジェクトを線の端点から外れた位置に置くと、線自体は指向性を失い、ただの図形となる。
![[図10]線とオブジェクトB](https://ekrits.jp/wp-content/uploads/PoD-graphic10.png) [図10]線とオブジェクトB
[図10]線とオブジェクトB
![[図11]線から外れたオブジェクト](https://ekrits.jp/wp-content/uploads/PoD-graphic11.png) [図11]線から外れたオブジェクト
[図11]線から外れたオブジェクト
このように、痕跡という概念を適用することで、線自体を指向性を持った視覚的要素として扱うことができる。
また痕跡以外にも、物理的法則などの前提知識を利用することで、線に指向性を持たせることもできる。[図12]では光が鏡に反射している様子を抽象化している。光は光源からある方向に一直線に進んでいく。私たちは経験上そのような知識を持っているため、[図12]のような図版を見ると上下どちらかの方向に進んでいるようにイメージすることができる。一方、[図13]では粘性の高い液体が垂れている様子を抽象化している。重力という地球上では上から下へはたらく力を私たちは経験しているため、自然と図版の上から液体のようなものが垂れる、ゆっくりとした流れをイメージすることができる。経験上、具体的な動きや変化を知っている現象に関して、抽象度を上げて線として表現することによって、指向性を持った視覚的要素とすることができる。
![[図12]反射](https://ekrits.jp/wp-content/uploads/PoD-graphic12.png) [図12]反射
[図12]反射
![[図13]液体](https://ekrits.jp/wp-content/uploads/PoD-graphic13.png) [図13]液体
[図13]液体
2-2 矢印
線の延長線となる、指向性を持つ視覚的要素として「矢印」がある。「線」では痕跡という概念を適用することで指向性を持たせていたが、矢印は線に鏃(やじり)の部分が付くことで、指向性が生まれる。通常「矢印」と呼ばれて私たちがイメージするのは「→」のような短い線を持った、既存の矢を想起する図形だが、[図14]のような例では、長い矢印として捉えることができる。
![[図14]曲線矢印A](https://ekrits.jp/wp-content/uploads/PoD-graphic14.png) [図14]曲線矢印A
[図14]曲線矢印A
いずれにせよ「線」の例と同様、ひとたび方向が生まれた線は指向性を持ち、単に上方向の動きとは解釈せず、矢印の流れを追うように、曲線に合わせた動きのイメージが生まれる。また、こちらも「線」の例([図9]、[図10])と同様に、鏃の位置を変更する([図15])と矢印の流れが変わり、鏃の部分を線から外してしまう([図16])と、指向性がまったく生まれなくなる。
![[図15]曲線矢印B](https://ekrits.jp/wp-content/uploads/PoD-graphic15.png) [図15]曲線矢印B
[図15]曲線矢印B
![[図16]鏃の離れた曲線](https://ekrits.jp/wp-content/uploads/PoD-graphic16.png) [図16]鏃の離れた曲線
[図16]鏃の離れた曲線
そして、矢印は一本の長い線として接続していなくても、短い矢印を組み合わせて1つの指向性を生むことがある。[図17]のように矢印を配置すると、[図18]で示したような指向性のイメージが生まれる。このように、矢印が持つ指向性は非常に強力で、社会のなかでもさまざまな場面で方向を示すためのサインとして使われている。
![[図17]矢印の断片](https://ekrits.jp/wp-content/uploads/PoD-graphic17.png) [図17]矢印の断片
[図17]矢印の断片
![[図18]矢印の断片から生まれる指向性](https://ekrits.jp/wp-content/uploads/PoD-graphic18.png) [図18]矢印の断片から生まれる指向性
[図18]矢印の断片から生まれる指向性
2-3 視線
私たちは図として存在していないものにも、線や指向性を感じることがある。その代表例が「視線」だ。普段の生活のなかでも、他人の目の向き(黒目の位置)を見て何を見ているのか推測した経験は誰しもあると思う。そのとき、私たちは目から対象物までの間に指向性を感じている。実際の人の顔でなくとも、[図19]のように抽象化した顔を配置して視線が生まれるように黒目を設定すると、[図20]のように線自体は描かれていないのにもかかわらず、視線という見えない線の指向性を感じることができる。
![[図19]視線](https://ekrits.jp/wp-content/uploads/PoD-graphic19.png) [図19]視線
[図19]視線
![[図20]視線の向き](https://ekrits.jp/wp-content/uploads/PoD-graphic20.png) [図20]視線の向き
[図20]視線の向き
また、これまでの線や矢印は、基本的にはディスプレイの中や紙の中など、表示されているメディアの中だけの限定的な出来事として機能している。一方、視線は、そもそも描かれない線のため、簡単にメディアの外に出たり、外から別のメディアに入ったりすることができる。例えば[写真4]のように、画面の中の顔が画面の外のピンポン玉を見ているという状況を作ることができる。この際の視線は、メディアの枠組みを乗り越えて成立している。
![[写真4]](https://ekrits.jp/wp-content/uploads/PoD-picture04.jpg) [写真4]
[写真4]
この「メディアの枠組みの制約を受けない」という状態は、かなり興味深い。今回の展示では行わなかったが、視線が画面と画面をまたがって存在していたり、空間全体を行き交うなど、視線による指向性を使うことで、鑑賞者だけが読み取れる見えない線を空間の中に描くことができるかもしれない。
2-4 文章
最後に取り上げる例は「文章」だ。文章を読んでいるときの目の動きは、意識こそされないが、実は線を追っているのと変わらないのではないかと考えている。つまり、私たちが文章を読む行為には、「線として成立する」「読む行為がおのずと指向性を持つ」「線を読み取りながら目線が移動する」という要素があるため、文章自体を指向性を持った線として扱うことができるのではないかと考えた。
日本語は、左から右、上から下へと通常では流れるが、[図21]のようにひとつながりの文章としてレイアウトすることで、右から左、下から上へと流れていくこともある。読んでいる人は文脈や線の流れからそのイレギュラーな配置も受け入れる。
![[図21]文章A](https://ekrits.jp/wp-content/uploads/PoD-graphic21.png) [図21]文章A
[図21]文章A
また、文字を目で追うことによって指向性が生まれるということは、文字の間隔を変えると読む速度や間隔が変化するのではないかという仮説に基づき、異なる字間を持つ文章を比較して読むことで、頭の中で生み出される時間の違いを体感できるような試みも行った([図22])。
![[図22]文章B](https://ekrits.jp/wp-content/uploads/PoD-graphic22.png) [図22]文章B
[図22]文章B
そして、「意味がつながるように文字を追いかけていく」という前提があれば、文字同士が接していない、ある程度の間隔を持ったレイアウトにしても、1つの繋がりのあるものとして読み進めることができるのではないかと考えた([図23])。
![[図23]文章C](https://ekrits.jp/wp-content/uploads/PoD-graphic23.png) [図23]文章C
[図23]文章C
このように、文章を「意味を持った文字の連なり」と定義し直すことで、文字のレイアウトを変更して新しい指向性を持った視覚的要素として利用できる可能性がある。
3 表現方法論としての指向性の応用
ここまで、『「補う」ことで生まれる面白さを持つ表現』の可能性と、その表現方法の探求として、今回制作した「指向性の原理」での作品についての意図を書いてきた。提示された情報を手がかりにして新しい情報を頭の中で生み出すという考え方は、人間の認知能力を活かした新しい表現方法論の可能性を切り拓くのではないかと考えている。
今回のような表現方法を用いると、わずかな情報量を提示するだけで、うまく理想化された膨大な情報を鑑賞者の側が「勝手に」作ってくれるということになる。つまりこれは、鑑賞者の側の想像力を刺激し、創造の追体験のようなことをさせているともいえる。ここには、単にわずかな情報量で伝達できる効率の良さ以上の価値がある。一般的に映像表現では、頭の中に一方的に情報が送り込まれていくという鑑賞体験になるため、想像するというよりも見て状況を理解するということの比重が高い。しかし、『「補う」ことで生まれる面白さを持つ表現』では、どうにか動きを能動的にイメージする必要があるため、鑑賞者に映像とはまったく異なる「動きを感じる体験」をさせることができる。
このように、知覚の側から新しい表現方法を設定することで、従来のメディアで行われていた体験とは異なる体験を引き起こすことができる。
この表現方法の研究の先には、なぜ動きを感じてしまうのか、図版の作り方によって動きの速さや質感が異なるのはなぜなのかという問題がある。そして最終的には私たち自身が無意識のうちに使っていて気がついていない、「あらかじめ自身にプリセットされていた知覚能力」の発見と、それらをいかに表現に応用していくかまでたどり着きたいと考えている。