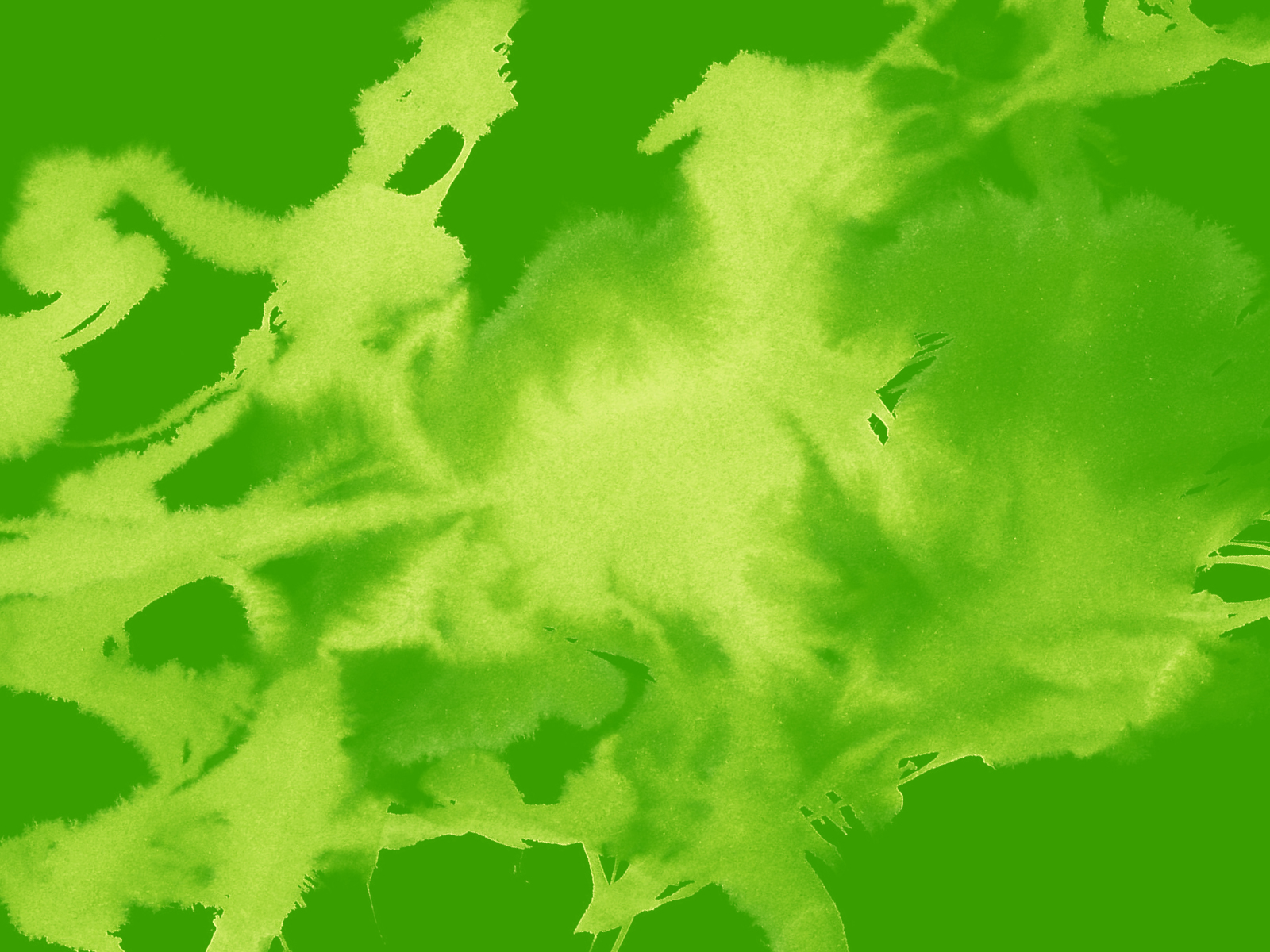合原織部:
ナイトさんは、社会人類学者として、日本の紀伊半島の山村を対象にした数多くのフィールド調査をされてきました。扱ってきたトピックは、狩猟、農業、林業、そして人間と野生動物とのコンフリクトなど、広範囲にわたります。近年の研究は、日本のモンキーパークにおける人間とサル(ニホンザル)の関係性をワイルドライフ・ツーリズムの場として考察するものです。これまでの研究では、今日の日本における人間と動物の関係性のダイナミクスが主なテーマとなっていたように思うのですが、どのような経緯でこれらのトピックに関心を持ったのでしょうか。また、調査対象として日本の山村を選んだ理由はありますか。私自身、宮崎県の山村で人間と野生動物とのコンフリクトに関する調査をおこなっていて、このようなトピックに関心があります。
ジョン・ナイト:
1980年代に博士課程の学生として日本を訪れ、和歌山の本宮町で山村での過疎化について研究していました。本宮には約3年間滞在して、町の外へと移住し、お盆や正月に故郷へと帰省する人々といった、とくに人間の移動に注目していました。最終的に博士論文では、観光客(本宮には有名な温泉があるため)や「Iターン」と呼ばれる移住者や、外に移住していく人々を扱いましたが、私の主な関心は、人々が地元を離れる理由や、そのような移住が残された村へ与える影響にありました。
これが私の日本での研究における第一ステージだったと思います。このとき村が動物が住む森に囲まれていたこともあって、研究の背景程度ですが、動物への関心もありました。1990年代に追加調査で本宮に戻ったとき、森の動物にも強い興味が湧き、それらの動物と、耕作を諦めたり村を出たりしていく人々、また村に侵入して農作物を荒らす動物との関係性などにも関心を持つようになりました。
はじめてモンキーパークに関心を持つようになったのは、1990年代後半に本宮出身の人と和歌山の伊勢ケ谷モンキーパークを訪問したときのことでした。そのパークがある椿エリアを訪れたのは、その周辺で深刻な猿害があると聞いたからだったのですが、それがモンキーパークに関心を持つきっかけになりました。
猿害の温床となる可能性があるにしても、モンキーパークは魅力的な場所です。伊勢ヶ谷にはじめて訪れてから、機会があるたびに伊勢ヶ谷や、他の地域にあるモンキーパークを訪問しました。結果的にこの経験は、日本の人間とサルとの関係性に関する私の視野を広げてくれました。村で生じている人間と動物のコンフリクトだけではなく、日本での人間と動物の関係性について、もうひとつの側面であるワイルドライフ・ツーリズムについて学ぶことも有意義だと考えるようになりました。それは野生動物を、害獣としてだけではなく、観光の資源としても捉えるということです。
モンキーパークの研究を通じて、私のテーマは人間とサルのコンフリクトから、サルが人間の魅力を受け取ることへと移っていきました。2000年代には日本中のモンキーパークを訪れましたが、なかでも特に深く関わったのが、小豆島の銚子渓自然動物公園でした。そこは他のパークとは違い、来園者が屋外で自由にサルにエサを与えることが許されていました。スタッフと知り合いにもなり、今ではそこが一番よく知っているモンキーパークです。
銚子渓自然動物公園は、私のモンキーパークに関する研究のメインの調査地となり、2018年までの間、機会があるたびに訪問しました。しかし、私のモンキーパークに関する調査は、もともと和歌山の山村でおこなっていたような長期滞在型のフィールドワークとはやり方が異なります。私は本宮に3年近く滞在しましたが、モンキーパークの調査は、短期間で複数回おこなった結果を元にしていました。小豆島でさえ、滞在期間は数週間を超えたことがありません。
動物の人間観とは何か
合原:
現代日本の人間と野生動物の関係性を考えるとき、近年の自然・社会環境の変容、特に農山村が経験してきたことを考慮するのが重要です。あなたの編著である『Natural Enemies※1(天敵)』と『Waiting for Wolves※2(狼を待ちながら)』では、現代日本の山村状況について論じています。それによれば、山村で過疎が起こるのは、人々が仕事を求めて都市に移住した結果だと言います。そして山村に人がいない状況は林業や農業の活動を低下させ、それが森林の野生動物の圧力に抵抗する人々の力を弱めることにつながると論じていて、このような人間と野生動物の衝突が生まれるプロセスは、日本の農山村に特有のものであると指摘しています。日本の人間と動物の関係性が持つ特異性について、もう少し説明していただけますか。
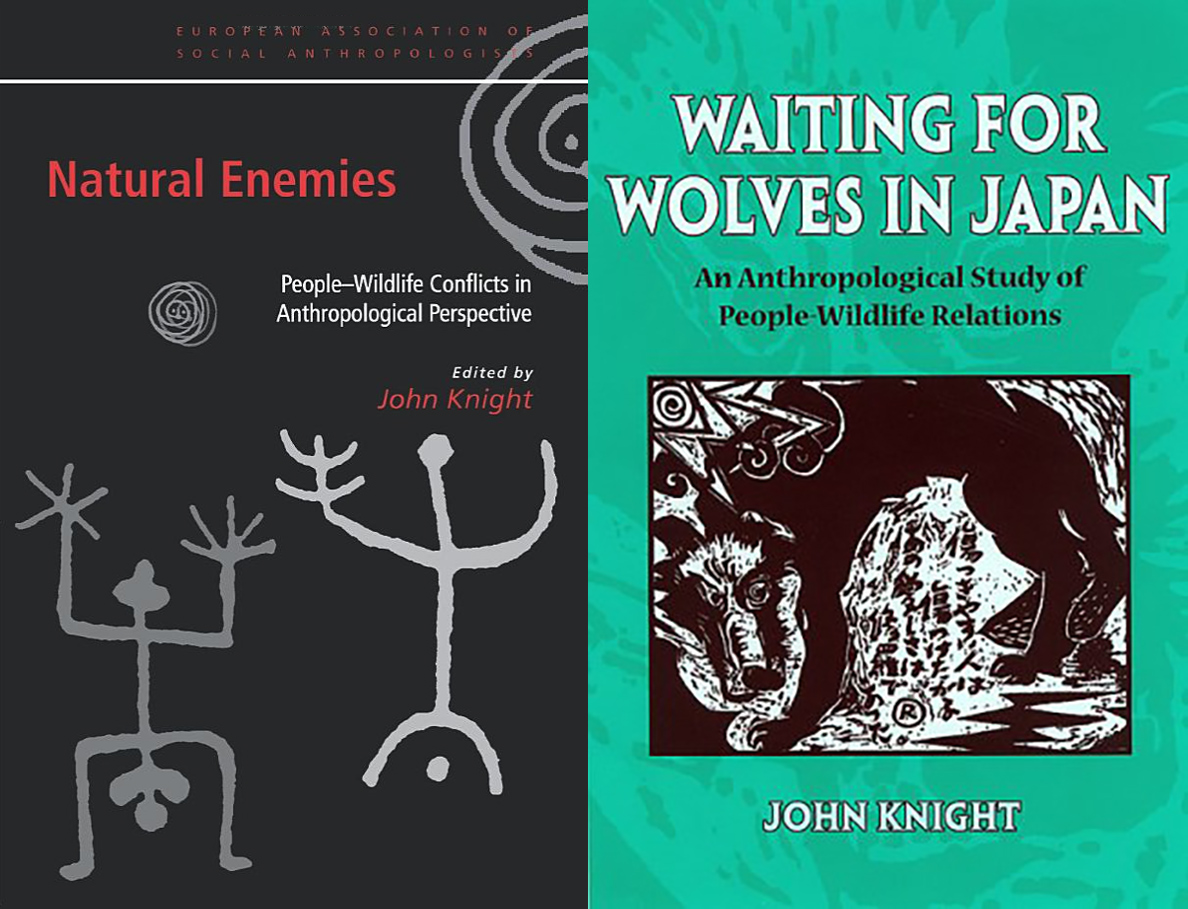
また今日の日本において、地方と都市の分離や、過疎化、人間と野生動物の衝突の問題は、以前にも増して深刻です。あなたは人間と野生動物の関係性について、このような変化をどのように捉えていますか。
ナイト:
人間が都市に流出し、野生動物が農山村に侵入することを、英語では”encroachment”という語で表します。社会人類学者として、私のアプローチは、山村の住民がその「侵略」という状況をいかに理解するのかや、それをいかに彼らの生活における大きな変容として捉えるのかを理解することにあります。彼らにとって、村と山林の境界は非常に重要なのです。
§
合原:
そうですね。彼らはそれを区別していますね。
ナイト:
動物が村のはずれに住んでいるときでさえ、動物が村に入ってくることは、村人たちにとってはある意味無秩序で異常な経験なのだと思います。それはどのような無秩序なのか。これに答えるためには、日本の山村住民の事例のように、ある場所に私たち人間が独占的に居住するのではなく、他の様々な存在とも重なり合っているという前提から始めるべきかもしれません。そして、このような場所での暮らしには、活動的な人間の存在が必要です。
この考え方は、過疎化に対する私の理解を次第に変えていきました。はじめのうちは、過疎化を単に数値の問題として捉えがちでした。役場の職員が人口減少についての話で取り上げる数値と似ているかもしれません。人々は過疎について、単純に人口減少によって生じる量的で数値的な問題という印象を持つ傾向にあります。ですが、私は過疎は量的かつ質的な問題であり、山村の生活空間における人々の活動の減少と連関していると確信しています。
簡単に言うと、山村で効率よく暮らすには、人々はそこで「活動的」に住まなくてはならないということです。逆に、過疎は環境に関わる活動が失われた状態だとも理解できます。単に人口だけでなく、残された人々の活動が減り、農作業や草むしり、植生除去もしなくなり、村のなかや近くの森を動き回ることも少なくなります。つまり、農山村の過疎化は「環境の不活性化」であり、このような人間の活動の減少が森の動物が侵入する状況を作り出すと考えられます。これが、農山村の過疎化と野生動物の侵入が同時に生じるひとつのあり方だと思います。
農山村と都市の乖離と、人間と野生動物の関係性の変容との関係についても質問されていましたが、私は動物がどのように人間を見るのかについて知りたいと思っていました。日本の民俗学者らは、ときどき「人間の動物観」という概念を使います。人間が動物をどう見るかというのは、魅力的な研究対象です。しかし、その言葉の逆、動物が人間をどう見るかという「動物の人間観」と呼べるようなものも、とても興味深いと考えています。
日本の農山村では、動物が人間に対する恐怖心を失ってより大胆にふるまうことが、今日大きな問題になっています。このことが逆に人間を刺激し、彼らが様々な方法で動物を追い払ったり怖がらせたりして、動物の人間に対する恐怖心を回復させることになります。それは「修復的に向き合い方を習慣づけること」と呼べるかもしれません。
もちろん、これはワイルドライフ・ツーリズムで生じていることとは対照的です。モンキーパークは、サルが人間への恐怖を失うことでのみ存在することができます。モンキーパークの人々は、そこを「野生のモンキーパーク」と呼びますが、「懐いたモンキーパーク」と呼ぶほうがより適切かもしれません。「懐く」という言葉には「慣れる」という意味も含まれますが、パークのサルは「極度に飼い慣らされている」と言えそうです。人間はサルを飼い慣らすためにエサを与え、人間に対する恐怖心を減らすことで、近寄ってくる観光客に慣れさせてきました。サルの大胆さは農民にとって問題ですが、モンキーパークが機能する前提でもあるのです。
日本のモンキーパークでサルに接触する人間
合原:
先ほど話したように、人間と野生動物の衝突は、人間の領域と野生動物の領域の境界に関する問題と深く関わっています。このような居住域の移動や、異種間の関係といった問題は、現在世界で広がっているコロナウイルスの状況下においても明らかと言えるのでしょうか。
森林伐採とコウモリの居住域の破壊が、人間とコウモリの接触を増やし、それによってウイルスがコウモリから人間へと伝染したと言われています。また、世界中でのロックダウンが、自然環境に予想外の利益をもたらしているという報告もされています。人々が一定期間家に閉じこもることで、空気や水はきれいになり、動物の生息数が増加したと言われます。あなたはウイルスと人間の関係や、それらの境界の問題について、どうお考えですか。
ナイト:
とても興味深い質問ですが、正直に言うとあまりよく知っているわけではありません。この数か月間、日本に行ってこの時期のモンキーパークを訪問したいと願っていました。コロナ禍がパークにもたらす変化を観察するのは、興味深いことだと思います。先に指摘していたように、コロナウイルスの起源は明らかに野生動物であるため、パークのサルなどを含めて野生動物と関わることに、人々がより神経質になるであろうことは想像できます。この状況が、パークにおける観光客とサルとの接触にどのような違いをもたらすのか知りたいと思っています。
この状況によって、パークが来園者にサルとの接触、特にサルへのエサやりを制限するようになるかもしれません。来園者にサルのエサやりを禁じているパークがある一方で、エサやりを許可しているパークもあります。そこでは人々が手でサルにエサをやることも許されていますが、その状況が変わるかもしれないと考えています。「ソーシャル・ディスタンス」が、パーク内の人間同士の接触だけではなく、人間とサルの接触にも適用されるかもしれないのです。
私は、人間による動物へのエサやりにとても関心があります。サルにエサを手渡しするのは、とても密な接触をともなう方法なので、よりセンシティブな対応になると予測しています。これまで通り来園者にサルへのエサやりを許可するパークもあるかもしれませんが、手渡しではなくエサを投げるように求めるかもしれません。コロナ禍は、人間と野生動物との接触により広い範囲の影響を与えるので、ワイルドライフ・ツーリズムにとっても特別な意味合いを持つと思います。
§
合原:
コロナウイルスの世界的流行が、人間同士だけではなく、人間とサルの「ソーシャル・ディスタンス」にも影響する可能性があるという考え方は興味深いですね。
人間と動物の関わり合いをどう見るか
合原:
続いて、人間と動物の関係を分析する際の、あなたの理論的視座について聞かせていただけますか。和歌山での野生動物による農作物被害に関する研究では、山村の人々の生活における動物の捉え方を示すために、動物のイメージや象徴的な意味を分析されています。これらの研究は、主に人間と動物の間のコンフリクトに関わるものである一方で、あなたの著作の『Animals in person※3(親しい動物たち)』では種間の親密性に着目して、いかに人々が動物に人間的な感情や知性を見るかについて検討されています。あなたの研究は、動物の人格に最も早い段階で着目した人類学研究なのではないでしょうか。
ナイト:
先にも述べたように、私の人間と動物の関係へのアプローチは農作物被害をめぐる山村住民と森の動物との間のコンフリクトに着目することから始まり、のちに動物に対する人間の魅力に関心を持つようになりました。それが話に出た『Natural Enemies』と『Animals in Person』の二冊につながっていきます。
『Animals in Person』は、人間と動物の関係の異なる側面に光を当てようと試みたもので、動物が人間に対して感じている魅力を検討しようとしたものです。そして、私はこの視点が、人間に匹敵するある種の感情や知性を持つ、人間と似た動物たちへの関心を引くと思います。私たちがコミュニケーション可能な相手としての動物です。
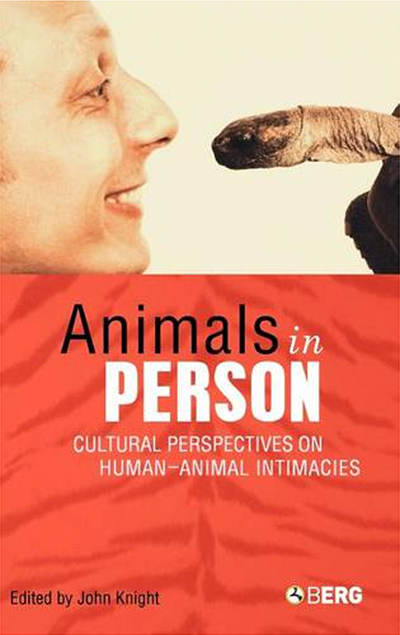
動物との衝突に関する理論に関して、私はある時期、人類学の理論である構造主義に基づいた「アノマリー(変則)」理論を用いていたことがありました。境界づけられたカテゴリーに収まらないものは、問題含みなものや無秩序、「アノマリー」として見られます。これを動物に当てはめると、私たちにとってある動物が文化的カテゴリーに当てはまらないと見える場合、それは変則的な動物とされ、特別で文化的な着目の対象になります。そのため、サルや大型類人猿を含む他の霊長類は、「アノマリー」として見られます。なぜなら、解剖学的、行動学的、認知学的など様々な点において、動物と人間のカテゴリーの間にあり、私たちと似ているけれども異なる、どっちつかずな存在だからです。
森から村へ移動して農作物を荒らし、また森へと戻っていく動物は、重要な空間の境界線を違反していると言えるので、この「境界侵犯」の考え方が適用できます。これが『Natural Enemies』で扱ったテーマであり、貢献した点でした。
最近は、人間による動物の表象よりも、人間と動物の関わり合いについて深い関心を持っています。ひとつモンキーパークで魅力的に思うのは、それが人間とサルの相互交渉を考察するのに適した場所であるということです。
§
合原:
人間と動物の関わり合いについて、何か具体的な理論を採用していますか。というのも、先の変則的動物についての説明を聞いて、メアリー・ダグラスのことを思い出したからです。そのような動物たちの関わり合いについて考察するときに参考にする特定の理論があるのではないかと思いました。
ナイト:
おそらくアーヴィン・ゴッフマンのような人でしょうか。ゴッフマンは、一対一や一対多を問わず、人間同士の相互交渉について強い関心があるので、さまざまなインスピレーションを与えてくれます。間違いなく霊長類学は、サルでも特にニホンザルの階層的な社会性など、サル同士の相互交渉のしかたについて多くのことを教えてくれます。そしてその型は、サルと人間との関わり合いについて理解するためにも使えます。
また、私たち人間が他者とどのように関わるかについての考察から派生して、サルを人や子どものように扱いながら、擬人的にサルと関わり合う方法を学んでもよいでしょう。ですが、実際の人間とサルの相互交渉は違ったものかもしれません。私のアプローチは、実際の交渉を観察して、何が起こっているのかを明らかにしようとするものです。
§
合原:
フィリップ・デスコラとジズリ・パルソンが編集した1998年刊行の『Nature and Society※4(自然と社会)』のなかの、あなたが執筆した章に関しても質問があります。あなたが執筆した章や、自然と動物に関して、デスコラらとはどのような議論をされたのでしょうか。
ナイト:
『Nature and Society』の主なテーマは、自然と社会の二元論に挑戦するものです。それは、非二元論または一元論的な視座から人間と自然の関わりに着目しています。私の章では、日本の材木プランテーションとそれが軽視されている状況を扱いながら、そのテーマに貢献しようと試みました。私の考えは、過疎というのは村だけではなく、特に放置された人工林などの森林にも起こっているのではないかというものです。例えば人工の針葉樹に人の手が入らなくなったり、人間と木の標準的なつながりが壊れたりしたときです。このことは、先に話したこととも関連しますが、人間の活動は、人間と環境との関係を作るのに役立っていて、日本の山村住民にはその感覚が強く根付いているように感じます。今もまだこのテーマに関心がありますが、それを針葉樹のプランテーションだけでなく、より一般的な形で日本の山村の環境にも適用しています。
最近の論文で、「環境下での行動のズレ※5という概念を使いました。その論文では、日本の山村における様々な「環境下での行動のズレ」を明らかにし、それらを埋める試みや、人間と土地との関わりを復活させて環境の秩序を回復させる試みについて説明しました。これらの環境下での行動のズレを埋める試みには、村人がサルや他の動物を追い払う「追い払い活動」があります。村の縁の植物を切り払ったり、木を切り倒したりすることで、動物の侵入を防ぎます。このような人間の活動の対象となる環境と、それがされない環境では大きな違いがあります。
複数の場所でフィールドワークをする
合原:
近年、フィールドワークをおこなう際の方法論として、マルチサイテッド・アプローチを用いるのが流行になりつつあります。つまり、複数の場所で調査研究を行なうというものです。この方法は、マリノフスキーの参与観察のようなクラシックな人類学の調査法とはやや異なるように思われます。マルチサイテッド・アプローチは、人間と自然の関係性を考察するうえで、新たな視座を与えることができると考えますか。
また、この調査法を用いて、今の日本の自然環境と人間の関係性を考察して、マルチスピーシーズ民族誌を書く研究も増えつつあります。マルチスピーシーズ民族誌は、人間と非人間の関係性を考察するもうひとつの流れとなっています。あなたはこれらの方法論的、理論的トレンドをどのように見ていますか。
ナイト:
いくつかの場所で調査をおこなうマルチサイテッド・フィールドワークは効果的だと思います。もちろんトピックにもよるのですが。私が実施した本宮での調査は、数多くの集落が広範な地域に分散している自治体ではありましたが、基本的にひとつの場所でおこないました。マルチサイテッド・フィールドワークの重要性は、異なる場所でたくさんの事例を調査することではなく、その異なる場所それぞれが研究のトピックにおいて重要な要素を形作ることのなかにあるのだと考えています。農山村の過疎化について言えば、移住者がどこから来るかだけではなく、どこに移住するのかにも目を向けるということなのかもしれません。
このような調査に最も近い経験は、本宮から大阪に移住した人に会うために大阪を訪れ、和歌山出身の大阪在住者が集まる和歌山県人会のミーティングに行ったことです。そこで関心を持ったもうひとつのカテゴリーは、本宮町のふるさと会(文字通りふるさとをベースとした集まり)に参加する人々でした。ふるさと会は、本宮にゆかりのない都会の住民に地元の名産品を販売する事業で、都市部のメンバーは季節ごとに地元の食品が入った荷包みを受け取ります。これは本宮を彼らの第二の故郷にするアイデアです。この架空のふるさととのつながりを明らかにするため、本宮産の食べ物を受け取る消費者にインタビューしようと町を訪れました。これが、おそらく私の本宮での調査でおこなった、マルチサイテッドフィールドワークに一番近い経験です。
人間と動物の関係について、マルチサイテッドフィールドワークをおこなうことには可能性を感じています。例えば、肉と動物の関係というトピックでは、うまく機能しそうです。それは生産者や、おそらくハンター、中間業者、これらの製品を売る会社、そして町の消費者を考慮した、肉の流通に関するマルチサイテッド的な調査ができそうです。この種のフィールドワークが、いかにマルチサイテッドな研究になるかが想像できます。
§
合原:
肉と動物の関係の事例をあげているように、マルチサイテッドなアプローチは、サプライチェーンを追うのに適しているように思えます。例えば、アナ・チンの書籍で取り上げられたマツタケの場合では、どのようにこれらの製品が生産され、モノへと変えられ、最終的に消費者によって消費されるのかといったことが書かれています。チンは、マツタケを事例に、人間と非人間の関係を含むこれらのつながりを描くためにマルチサイテッドのアプローチを使ったのだと思います。
ナイト:
あなたの宮崎の猟師に関する調査では、マルチサイテッド・フィールドワークを採用することも考えているのですか。
§
合原:
はい。私は「ジビエ」と呼ばれる、宮崎の野生のシカとイノシシの肉の商業化についてマルチサイテッド・フィールドワークをおこなったことがあります※6。野生獣肉の商業化により、人間や猟犬の寄生虫感染について興味のある寄生虫学者などの新しいアクターが、地域社会に参加するようになったのがわかりました。この新しい展開によって、私たちは山村を超えて、実験室やレストラン、マーケティング・コンサルタントを訪れてみたりするようになりました。
日本のモンキーパーク、動物へのエサやり
合原:
近年の研究では、サルと人間の関係性に注目し、農作物被害、野生のモンキーパーク、観光へのサルの利用などを含む、幅広いトピックを扱っています。あなたは野生のモンキーパークを、霊長類学と観光の視座から考察しています。あなたは、サルと人間の関係性を考察するアプローチには霊長類学者の視点も取り入れているのですか。
ナイト:
私が教育を受けた伝統的な社会人類学は、人間に焦点があてられた人間中心的なものでした。動物が、人間環境の一部として取り扱われていたのです。
それに代えて今では、私たち人類学者は、動物を仲間の主体として見ることができます。動物たちの生きる空間は人間と重なり合いながら、共通の空間を、異なるしかたで経験している非人間の主体だといえます。人間とサル(霊長類の仲間)に関しては、世界を経験する方法や集団のメンバーとしてのふるまい方などに、似ているところや違うところが混ざっていると思われるのです。私のアプローチは、人間とサルの関係を見るのに、人間の視点だけでは十分ではないと考えています。サルの視点から人間-サル関係に着目するというやり方が重要だと考えていて、いまはそちらに移行しつつあります。
このアプローチを進めるためには、特にニホンザルの場合、日本の霊長類学者の研究にある程度精通している必要があります。霊長類学は、モンキーパークの出現に重要な役割を果たしましたが、もっと根本的なところでもサルのふるまいに対する理解を助けてくれます。そうでないとしたら、私の説明は、モンキーパークで働く従業員や観光客、またはサルから畑を守る村の人々といった、単に人間の視点からサルとの関係について描いたものでしかなくなるでしょう。
いかにして私たちがサルの視点を理解できるのかという質問がありましたね。どのようにサルの群れが機能するのかや、どのようにサルたちの間の階層や序列が機能するのか、サルがエサの周りでどのようにふるまうかを知ることは、おおむね可能です。私はエサに対するサル同士の競争に強い関心があります。ニホンザルがエサのために競争するとき、上下関係がとても重要です。これは、人がサルにエサをやるのを見たり、(私がときどきするように)エサやりをするときに明確になります。
エサやりは一対一でおこなわれるのではありません。なぜなら、近くでエサを狙う他のサルがいるためです。来園者がサルにエサをあげるとき、多くの場合は一対一の状況と考えますが、実は一対多なのです。サルは「エサを手に入れる」のを近くにいるサルとの競争として見ているのです。パークの来園者は、エサやりを通じた相互交渉について、あまりちゃんと理解していないようです。はじめは一対一の相互交渉のように見えるかもしれませんが、実際はより複雑です。霊長類学は、それを理解する手助けをしてくれます※7。
§
合原:
なるほど、人間からではなく、サルの視点からサル-人間を研究するというのは、言われてみればとても魅力的な研究方法ですね。最後に、あなたの研究の今後について聞かせていただけますか。
ナイト:
数年前にモンキーパークについての本を執筆し、モンキーパークの組織とその機能のしかたを考察しました。動物園に見られる飼育下の展示システム(captive system)と対比して、モンキーパークを展示における放し飼いシステム(open-range system)に見立てたのです※8。最近はパークの訪問者が娯楽として行うような、手渡しでのエサやりに関するの本を執筆しており、それが時間とともにどう展開してきたのか、そしていかにそれが間違った方向に進み問題となりかねないのかについて書いています。
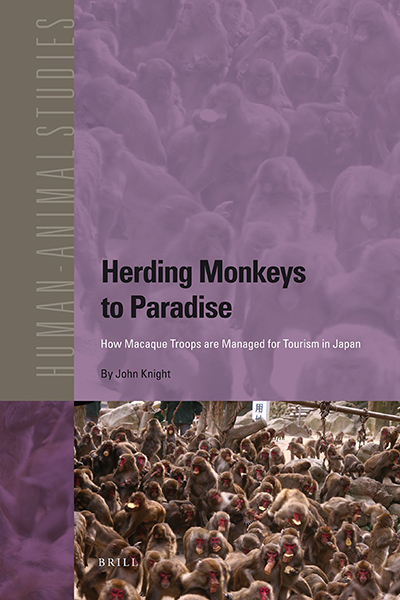
また最近は、日本における娯楽としての動物へのエサやり一般に興味があります。エサやりは日本で広くおこなわれており、道路端や庭や公園、駅前でハトや野良ネコへのエサやりが見られます。今年は日本を訪れることができていませんが、次に機会があればモンキーパークから離れ、他のさまざまな動物たちを対象にしながら、食物がやりとりされる場をより詳しく観察したいと考えています。
§
合原:
今日は、興味深い話をお聞かせいただき、ありがとうございました。