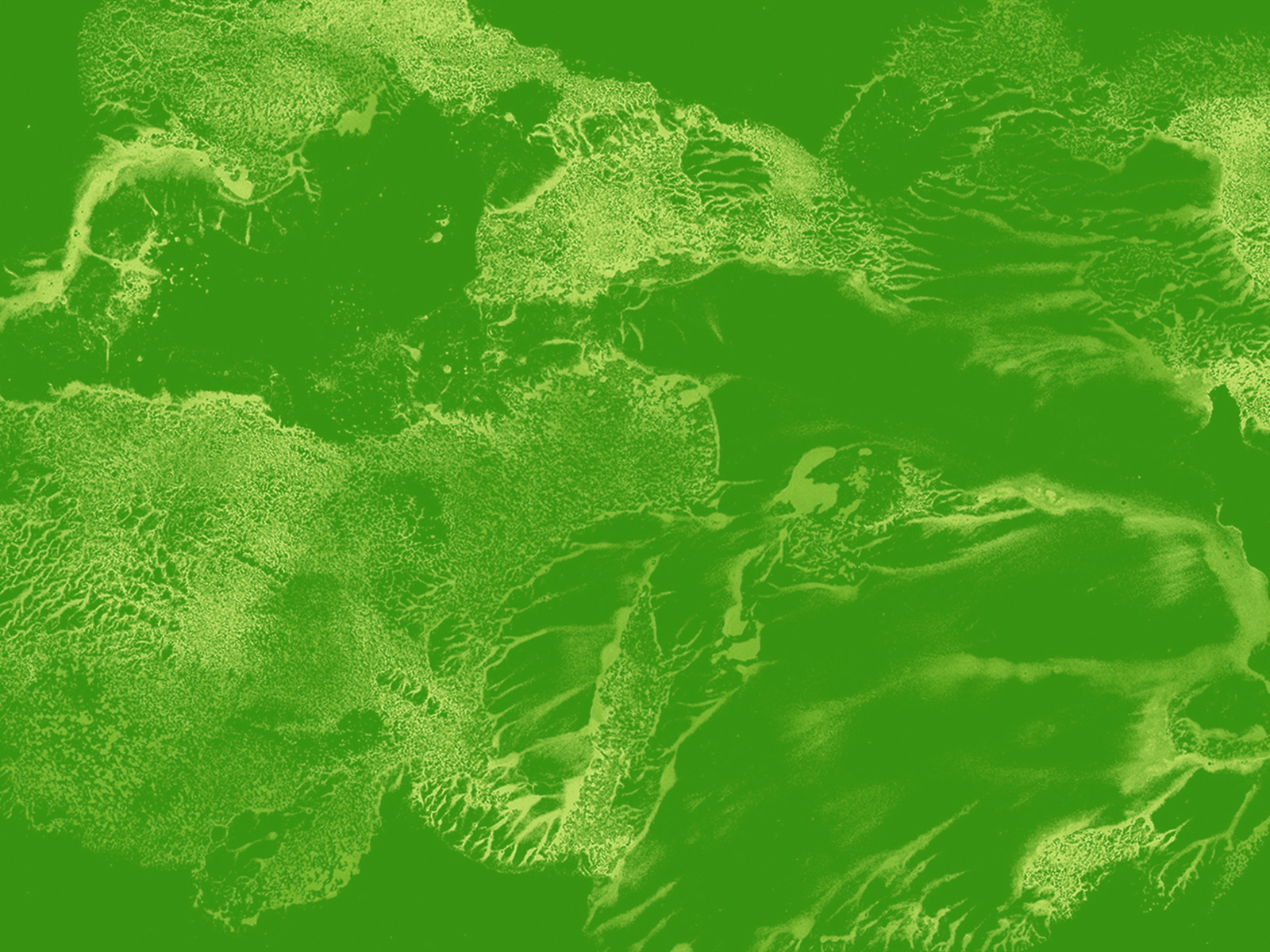伊藤亜紗『手の倫理』(2020)
伊藤亜紗『手の倫理』(2020)
——— 今回は、伊藤亜紗さんの『手の倫理※1』という著書を解題しながら、インタビューを進めていきたいと思います。
わたしたちが生きていく場面で意思決定をしないといけないときに、最近は社会通念にならって動けば間違いないということが通用しない状況になっていて、もっと創造性が重要視されているのを感じるようになりました。これまでの解題インタビュー※2の反応を見ると、通り一遍にことを済ませていくのではなくて、自分自身で状況を打開していきたいと考えるような方たちが読んでくださっているようです。今回の伊藤さんの著書は、まさにそうした方に響くのではないかと思い、もっとくわしく話をうかがってみたかったという経緯がありました。
わたしが伊藤さんのことを知ったのは、『ヴァレリーの芸術哲学、あるいは身体の解剖※3配ったりしたんです。それ以降のお仕事も一貫して、主体でも客体でもない第三項的な身体を、いろんな形で問題にされています。それを思弁的に論じるのではなく、視覚障害者の方や吃音を持つ方への取材を通して、フィールド科学的な手法で論じられている。その手法によって、思弁的には気づけないであろう内部からの多様な視点や論点が出てきている印象がありました。
今回の『手の倫理』は、フィールドワークでの経験を「触覚」という観点でまとめられていました。この方法論がおもしろいんですけど、人文科学では異質だと思います。このようなやりかたは、伊藤さんにとっては自然な感覚なのでしょうか。それとも、何かしらの戦略があってこういったお仕事をされているのでしょうか。
伊藤:
実感としては自然な流れなんですけど、背景に構造的な要因はあるんだと思います。大学院までは、カントが言ってることや、いろんな美学者や哲学者の言説を細かくテキスト分析するようなことだけをやっていました。ただ、これをずっとやることで美学史学はできるけれど、美学には永遠にたどり着かないことに気づいてしまいました。研究としてはすごくおもしろかったんですけど、感性や感覚を扱っているのに言語分析で終わってしまうので、ずっとしっくりこなかったんです。
そもそもわたしがあまり本を読むのが得意じゃないというのもあって、本を読んで理解することが自分の実感を深めてくれないというか、知識が増えることと感性が深まることが連動しない感覚があったんですね。それが決定的になったのは、自分が大学院のときに出産したときでした。出産は身体を持っている人間にはとても大きな経験だと思うんです。ところが、出産について分析した哲学書や美学関係の本がないことに衝撃を受けました。つまり、そこに書かれていることが普遍的だと謳っているわりに、実はまったく普遍的じゃなかったと気づいたんです。
つまり、白人男性の身体をベースにした哲学を、東洋人で違うジェンダーのわたしのような研究者がやっているということが、知識が増えても感覚が深まらないことの原因だったのではないかと考えたんです。従来の美学や哲学で語られていたことは、一種の人工物というか、フィクションの身体であって、もうすこし現実に落とさないと、研究としても閉鎖的な意味での美学史学になってしまうと感じました。その状況から外に出るためには、文献調査だけじゃなくて、現実の身体にアプローチする必要があるだろうと考えたんです。
とはいえ、現実の身体というのは全部違うわけですよね。そのひとつひとつの身体がわかればいいんですけど、いきなり個別に行くのは研究として怖くて、方法論がもわからなかったので、ものすごく抽象的な身体一般と個別の身体の中間として、類的なレベルだったら扱えるかもしれないと思いました。それで障害を持った方とか、特徴がわかりやすい身体であれば、美学的な研究としてフィールドワークができるのではないかと思ってやりはじめたんです。
§
——— なるほど、ありがとうございます。もう最初のヴァレリーの本の時点で、今のフィールドワークのベースになる視点がすでにあった気がするんですけど、ヴァレリー研究によって、現在の基本形のフレームを掴んでいったということなんでしょうか。
伊藤:
自分ではまったく変わっていないと思っていて、ヴァレリーが言っていたことをそのままやっているぐらいの感覚でいます。ヴァレリーは言葉を使って体を鍛えるみたいなことを考えていたと思うんです。わたしがそこに焦点を当てているだけでもあるのでしょうけど、自分が書いたものもそうであったらいいなと思っています。言説として体系を緻密にしていくのではなくて、その言葉と出会うことで体がどう変わるか。その体の変化の方がゴールであって、そこに向けて自分の文章を書いているという姿勢に影響を受けていて、そのままやっている感じがあります。
§
——— ヴァレリーの本のなかでは「装置」という言い方をされていたと思うんですけど、いわゆる記号体系を練り上げて一つの体系に集約していくのではなく、「装置」として身体に作用させていく思考が、どの本にも一貫してあるという印象を持っていました。なので、ハイコンテクストなことを踏まえないと読めない本にはなっていないと思うんです。たとえば哲学とか、それこそヴァレリーのような文学であるとか、そういったものにまったく触れたことがない人がいきなり読んでも、何かしらの示唆が得られるというつくりになっていて、非常に拡張性が高い印象があります。
最初に言ったように、わたしやÉKRITSの読者の多くが、そもそもアカデミズムの人間ではないので、自分の実践に役に立つ思想がほしいという向きが強い。前に解題した上妻世海の『制作へ』もそうですが、伊藤さんのヴァレリー論から『手の倫理』までの著作も、繰り返し参照できる実用性がある感覚です。
伊藤:
それはわたしの今の職場が文学部ではないことが大きいかもしれません。学生たちが理工系なので、ベースが全然違うんですね。わたしは大学院では芸術の教員ですけど、彼らのような美術にまったく興味もない人にどうわかってもらうかを考えると、もう人体改造をするレベルなんです。これは学生だけじゃなく教員もそうなので、まったくコンテクストが違う人たちとコミュニケーションしないといけない環境にいるんです。
§
——— それで言うと、単行本にまとめられたばかりの『見えないスポーツ図鑑※4』がありますよね。この本にはフェンシングの例が出てくるんですけど、われわれがフェンシングをする機会はなかなかない。でも伊藤さんの本を読んでいると、フェンシングの身体感覚が理解できる。これを一言で要約すると、「身体を通じた翻訳」という感じがしたんです。つまり、みんな身体を持っているからコンテクストいらないよねという感覚で書かれているような印象です。この発想は今の時代に受け入れられやすいし、ここまでラディカルに考えられたものじゃないと役に立ちにくい状況になっているとも思いました。
要するに、コンテクストを前提としてしまうと、そのコンテクストを精緻化していくしかない。論文を読んで論文を書くというのも役には立つけど、異分野まで拡張しようとすると相当なリテラシーがいるということになる。伊藤さんは研究をされつつも、そういったリテラシーを持っていて、それが翻訳をされて表現されているので、わたしたちが読んでも簡単にアクセスできる気がしています。
伊藤:
はい。そのとおりだと思います。
——— 本題の『手の倫理』についても、いくつか聞かせてください。まず第1章で、そもそも「倫理」とは何かということが議論されていますね。古田徹也さんの『それは私がしたことなのか: 行為の哲学入門※5』という本にある道徳(moral)と倫理(ethics)の対比を援用しながら、議論するという形になっている※6。
道徳が長い時間かけて定まった一般性の答えに沿って生きるのだとすれば、倫理は一般性を前提としない状況のなかで都度普遍性を問い直すという態度のことだといったことが書かれています。ここで重要だと思ったのは、道徳/倫理みたいな二極性が、いわゆる個別性/一般性という二項対立ではなくて、「一般性に準拠するか/その都度問い直すか」という態度の問題として設定されているところでした。
つまり、人はそもそも倫理的でないと創造的ではありえないのかなということが伝わってきたんです。当然クリエイターは今の社会のなかに生きていて、そこから何かしらの材料を持ってきてクリエイティブな活動をするわけですけど、そのときに倫理的な態度をとること自体がクリエイティビティの基本条件ではないかと受け取ったんです。この読み方がそもそも合っているのかお聞きしたいです。
伊藤:
倫理的であることは創造的であるというのは意識して書きました。それは、答えを自分で探していくという意味です。道徳の場合は、最初に答えがあって命令としてトップダウンで自分に突きつけられるわけですけど、倫理の場合は、状況によって自分で答えを探すわけで、自分なりに状況を発見して材料を集めてつくられる答えなわけです。だから、一般的に理想化された答えからすると、妥協案にも見えるんだけれど、この妥協こそが創造的で。この条件からどう答えを探すかというすり合わせが状況の観察だし、答えを探すというのが創造的だと思います。
でも、その逆のこと、つまり創造的であるためには倫理的でなければならないという発想は、自分で考えていませんでした。でもそうですよね。おもしろいと思える作品は、やっぱり倫理的なんですよ。最初の計画通りつくられたものって、芸術作品でもおもしろくないものですし。芸術作品つくるときに、自分で能動的につくっていくというよりも、できていくという言い方をしますよね。ミケランジェロが、自分は石像をつくっているのではなく、大理石のなかから取り出しているみたいなことを言う有名な話がありますけど、あの態度ってすごい倫理的だと思います。
大理石と自分の関係のなかからつくられるものは何だと考えていく。そして、自分の計画を強制しているわけではないというのが、すくなくとも本人の実感としてはある。そうやってちゃんと出会っているところは倫理的だし、結果としてやっぱりおもしろい。ミケランジェロの作品って未完成のものとかもあって、ああいうのはやっぱりつくっていくなかで出てきた絵画で、そこまでで一旦つくるのを中止するということだったと思うんですね。そう考えると、たしかに創造的であることのなかに倫理性は含まれているかもしれないです。
——— なるほど、ありがとうございます。一般的に倫理と道徳はよく一緒にされていますね。人間関係でも、正しいひとつの基準があって、その正しさを逸脱すると道徳的ではない。あるいは同じような意味合いで倫理的ではないと言われる。こうした用法が日常的なのかなと思います。ただ『手の倫理』を読むと、厳密に倫理的と道徳的は態度として違う。
人間関係で言うと、目の前にいる人には必ず目で見ることのできない側面があるという前提で人と接すると書かれていますけど、これを伊藤さんは「敬意」と表現しています。人を見ただけでは決めつけないという態度だと思うんですけど、これって人に限らず動物であっても、さっきのミケランジェロの大理石のようなマテリアルであっても、客体としてある性格を決めつけてしまうと、そこでの対話的なプロセスというのは一切発生してこないことになるわけです。そう読むと、倫理的であることは、やはりひとつの創造性の基本条件だと思いました。
これは、たとえば障害者の方たちへの福祉の話にも関わってくるんだと思います。トップダウンで決めて制約的に関わっていくのではなく、関わりのなかで協働的に場のコンセンサスをつくっていく態度。自分にはこう見えるが実際は違うかもしれない。それを「不意打ちの可能性」を手放さないと言われていますけど、仮説を立てて関わってみたら、仮説とは全然違う反応が返ってくるといったことを、フィールドワークで沢山体験されていると思うんです。
伊藤:
そうですね。毎回圧倒されるというか、負けた気分になるんですけど、それがやっぱり楽しいですよ。結局自分とその相手との差が見えてくるということなんだと思うんです。最初は自分の頭で想像している相手なので、まったく差はないんですけど、その差を探るような感じでコミュニケーションしていくと、最後はすごい差が見えてきて。お互いが情報交換しているだけじゃなくて、人間関係の変化が感覚としてわかるのがおもしろいですね。
——— 『手の倫理』では、とくに「触覚」について前景化されて、それを軸に議論されています。この部分を読んで思ったのが、われわれが人間関係を結ぶときには、距離を測ってる感覚があると思うんですね。つまり、日常的にも距離が近いとか遠いとか、相手との人間関係の基準として距離の概念を物差しとして使っている。しかし、視覚障害者の方には距離を測るという視覚的な基準がまず通用しないわけですよね。なので、まずは触れることからスタートするという感じなんですけれど、その近さ/遠さというアナロジーで考えているのが、実はまったく自明ではないという驚きが、いろんな事例から伝わってきました。
本の最初の方で、触覚的な関係においては、信頼して相手に預けた分だけ相手のことを知ることができると、ご自身の実体験を書かれています。そのことで愕然としたのがよく伝わってきました。要するに、自明性みたいなものが裏返るというか、世界が壊れるといった体験だったんだろうなと思ったんです。もちろんわたしからすれば、文章からの想像なんですけど、そもそも異質なものに出会っていくのが好きな方の文章だと感じました。
伊藤:
そうですね。自分でも簡単に自分が思っていたものが壊れると感じているんでしょうね。いつも自分が考えていることは大したことはないというか。今回触覚のことを考えるにしても、触覚を介すと一番自分が壊れやすいと感じるんです。触覚というもの自体が、視覚を基準にした社会の倫理とは違うものを提示するという意味で壊すのと、触覚自体が自分の輪郭を簡単に壊すという、二重の特性を持っている。
恋愛関係がわかりやすいですけど、成人してしまうと恋愛がほぼ唯一の身体的に濃厚な接触になってきます。そういう接触が自分の輪郭を壊す。たとえば子供と接していて、自分が触覚によって壊されやすいと感じることもあります。ちょっとした喧嘩ごっこのような、取っ組み合いをやるじゃないですか。そうすると、自分の暴力性がすごく掻き立てられちゃうんですよね。情けないんですけど、手加減できなくなくて、本気で怒っちゃったりして。でもこういうのが発端で、感情よりも先に触覚を通して自分の枠が壊されて、虐待が起きるんだと思うんです。
さっきお話にもあったように、身体的な接触で精神的な距離が測れなくなるという、危機的な状況でもあるわけです。その危機感を実感していた部分がありました。触覚の揺さぶってくる力がすごいので、自分の思い込みが壊れるのも簡単だろうなと。何かそういうご経験ってありますか。
——— 複雑な手続きなしで、瞬間的に壊れる感覚ですよね。自分の経験だと、時代背景もありますけど、僕が生まれ育ったところがかなり荒れている地域で、不良たちが跋扈していたんですよ。なので、殴り合いとか頻繁に起こるようなところで、フィジカルな接触は日常的でした。もちろん子供の頃というか、高校くらいまでですけど、『ビー・バップ・ハイスクール』みたいな世界観ですね。
僕はそこまでの不良ではなかったですが、喧嘩で殴り合いになる機会はよくあったんですね。その感覚は今でもどこかで覚えています。要するに、身体接触がまったくない状態と、胸ぐらをつかまれた状態って、一気に温度感が変わるんですよ。実際に殴られると、もう興奮してアドレナリンが回って、今度はほとんど痛くもないというアグレッシブなモードに入る。殴られても痛くないし、普段なら殴るのも躊躇するところを、平気で殴っちゃう(笑)つまり、暴力的なモードにスムーズに切り替わっていく感覚があります。
そういう経験がまったくないと、暴力的な人に見えるようなことだけど、そうじゃなくてそのシチュエーションによってスイッチが入っている。触覚によって、われわれが普段考えている秩序立った世界が、いかにフィクショナルなものであるかと露呈される。
伊藤:
おもしろいですね。胸ぐらをつかむのは、相手のモードを切り替えるためなんですね。
——— おそらくスイッチが入るんですよ。その前段階で、よくガンを飛ばすと言われる、にらみ合いの状態がありますけど、あのときは正直「もうここで引いてくれ」とお互いに願いながらやっていると思うんです。誰も喧嘩はしたくないので。だけど、どっちかが胸ぐらをつかむと、もうやるしかないという状態になる。こういうのが日常になってくると、その世界観の変わり方が自分のなかに記憶されるので、あんまりひどい状態には至らなくなる。今度は興奮しても、これ以上殴ったら後遺症になるという手前で止められたり、そういう制御が効かせられるようになるんです。
伊藤:
おもしろいですね。でも、だからこそ倫理だと思うんですよね。そうやってスイッチが入ってしまうことがあるからこそ、倫理的な感覚が生まれるし、自分も条件に含めた最善の選択を冷静に考えられる。わたしも地元が八王子なのでヤンキーだらけでした。中学のときに好きな人ができると、その人の名前を手首にカッターで書くみたいな世界です(笑)今思うとすごい触覚的な世界でした。
——— 言語というのはコードに基づいた記号的な世界観をつくっていきますが、触覚はもっと物質的で、あまりコード化されない情報がやり取りされる世界観って特徴があると思うんです。だけど、そこには内在された秩序みたいなものがある。まったく無分節の状態ではなくて、言語のようにコード化はされてないし、視覚的な秩序でもないけど、何か分節された摂理のようなものがある気がするんですね。それを逆にまたこうやって言語化していくと、ややこしい話にはなっていくんですけど。
つまり、直にそこにアクセスして、その世界のなかでいろんな情報をやり取りしようというひとつの前提が立てられると、いろんな問題が自ずと解きほぐれていくという印象を持ちました。伊藤さんの本でも、「信頼」と「安心」について社会心理学者の山岸俊男さんの論を援用して、安心を突き詰めていくと、たとえば事務作業が増えて煩雑になるというデメリットがあると書かれてました※7。
安心のために書類が煩雑になっていくと、いろんな不具合が出てきます。とくに大きい企業に勤められている方からは、書類を処理する時間が多すぎるという話をよく聞きます。つまり、社内で決められたフォーマットで情報を共有することに、実際の仕事以上にエネルギーを使わないといけない状況があって、要するに社員を信頼していないからそうなっていることに、多くの人が気づいている。
なので、いろんなものを信頼するというコミットの仕方が、触覚的な倫理におけるひとつの大きなファクターなのかなと気がしています。今はどちらかというと、できるだけ安心な状態を実現しましょうと考えてしまうことが多い。たとえば、公園で子供にとって危険なものを排除していこうとか、そういったことが社会的には主流と感じているんですけど、そこへの異議申し立てにもつながっていくのかなと思いながら読んでいました。
伊藤:
そうだと思うんですけど、実際にどうしたらいいのかは自分でもよくわかっていないんです。安心を追求することは、それはそれで大事だとは思うんですよね。さらにテクノロジーが高度になれば、より安心の方に行ってしまう。その結果、今実際そうなっていると思うんですけれど、ますます人を管理することになってしまう。それに対して「100%の安心はないんだよ」と言って、信頼に目を向けてもらうのに、どうしたらいいのかまではわかっていないんです。
信頼はそもそも根拠がないものなんですよね。誰かが最初に信頼すると、信頼された人がそれを受け取って、お互いに信頼モードみたいなものになり、それからまた人を信頼するようになるといったことはあると思うんですけど、社会全体というレベルで考えてしまうと、経済活動ともリンクしないので。
——— そうですね。個人の実感ですけど、たとえばビジネスの場合は、大きな取引になればなるほど、信頼のほうが大事になってくる感覚がありますね。
伊藤:
ああ、そうですね。それはなぜですかね。
——— たとえば大きな契約をして、億単位のお金が動くときは、安心を突き詰めてもどこかに裏があるかもしれない、穴があるかもしれないというリスクは、完全に潰すことができないんです。小さなアウトソーシングであれば、逆に安心を求めてるんですけど、大きな取引では対面で相手に会って、長い間話をして、ようやく契約にこぎつけるというプロセスを必ず取らないといけない状態になります。
そのプロセスで何をやっているか考えると、やはり相手に嘘をつかれてしまうと終わりなので、相手が信頼できるかどうかを見極めていく作業をしてるんだと思います。リスキーなことを潰していく。社会全体の設計が安全を志向するのは必然的な流れという気はするんですけど、安全をベースにした社会環境でも、個々の場面では信頼についての能力を鍛えていかないといけないという気はしますね。
伊藤:
それは能力を鍛えるという感覚があるんでしょうか。
——— 当然ながらビジネスは利益を追求する側面が大きいので、おいしい話にはとりあえず警戒するわけです。このおいしい話が、どういう経緯で回ってきたのか考えたりして、警戒モードになるわけです。この警戒モードになったときに、リスクを取るか、警戒して引くか判断する能力は、鍛えるって感覚が言葉としてしっくりきます。最終的に決めるときに、欲望に負けていないかとか、今このお金があったら自分に都合がいいみたいなところでバイアスがかかってないかとか、そういった内部検証のプロセスを経ているんですよ。
こういった、自分の情動がどう動くかをメタレベルでチェックしていく能力は、経験知が大きいと思いますね。ビジネスで大失敗する人の多くは、おいしい話に流されるパターンが多いですけど、情動に検証能力が負けてしまっているんじゃないかという気がします。
伊藤:
なるほど、自分の情動をちゃんと分析できるということなんですね。おもしろい。
——— 安心というのは、おそらく客観的に評価できると思うんです。でも信頼は、検証しても最終的に騙されることがありえるので、客観的な評価ができないんですよね。たしか山岸さん自身の本※8に書かれてたと思うんですけど、信頼というのはうまくいったり騙されたりした経験知を積み重ねて、どこに賭けると成功するパターンが多くて、どこに賭けると失敗するパターンが多いのかが確率論的にわかっていることが、信頼する能力なのかなという気がします。
伊藤:
これはかなり建設的な判断ですね。前に将棋の羽生善治さんとお話したことがあって、彼も若い頃は何十手も先まで読んで、こう打てばこうなるというのをわかって対局していたそうです。だけど、年齢を重ねていくと、そういった計算能力は若い人に敵わなくなってきて、大局観みたいなものに頼るようになってくるそうなんです。それは分析的なものではなく、経験知の積み重ねで、ひとつひとつ目を読むのではなく、将棋盤の感じみたいなものを読むことらしく。そういったことには、経験知を判断の根拠とする自分の能力もありますが、経験知がたまってくると必然的に意志決定の方法が変わるということもありそうです。年齢的なものだけではなく、信頼と安心もおそらく関係していると思います。
——— 信頼は属人的にならざるをえないですが、安心は誰にとってものことになると思うんですね。人を選ばないというか、たとえば幼児にとっても安心みたいな状態で、誰もが安心できるようにリスク要因を減らしていくわけです。触覚的な倫理も、ある程度ナレッジを蓄積していくことはできるんですが、最終的にはどうしても現場で人が感じるところに依存せざるをえない。なので、自分の感覚と相手の感覚を育てていかないといけません。この育てていくという感覚が、なかなかシステムには適合しないような気がします。
伊藤:
そうなんですよ。学生たちと「AIにできなくて人間にできることは何か」というお題でディスカッションしたことがあって、たぶん手加減はAIにできないんじゃないかと言っていて、おもしろいと思ったんですね。手加減というのは、自分の能力を完全に発揮しないということになります。
たとえば、子供と100m走で競争するときに、相手が自分より遅そうでも、その子がすごく怒りっぽかったら、自分が負けようかなと思うじゃないですか。そういった社会的な条件を要因にして、自分のアウトプットを調整していくのが、手加減なんだと思います。しかも、手加減したのが相手にわかってしまうとよくない場合が多いですよね。わかった方がいい場合もあるんだけど、そこも含めて感じ取って、自分の行動の調節をするというのが手加減なので、それはAIにはできないのではないかみたいな話になったんですよ。
——— ものすごく単純に言うと、コード化できるかできないかという話ですよね。みんながなんとなく気づいているのは、そのコード化できない領域をどう評価するかが重要だとということで、それが伊藤さんの本が求められていて、読んだときにインパクトを得ている人が多い理由じゃないかとも思います。
続けて、本の内容についてお聞きしていきます。第2章の「触覚」ですが、西洋哲学では距離がゼロであったり、持続性や対称性、それからヘルダーの彫塑論を援用しながら、触覚が内に入り込む感覚であると論じられています。内に入り込むときは、文字通り相手の内に入り込めるということなので、それが触り方によって引き出される情報が違ってくるという議論がされています。
ここを読んで、なんとなく医者の触診をイメージしたんですけど、触る側の身体化された想像力がかなり大きく関わっている気がしたんですね。つまり、医者が触ればどういう病変があるのか直観できるけど、素人が触っても全然わからない。このように身体を重要な情報源とすることが、いろんな現場であるんじゃないかと思いました。
伊藤:
そうですね。さまざまな身体知を持っている職人さんの技術もそうですよね。医療の話で言うと、東洋医学と西洋医学で触り方がかなり違うらしいです。西洋医学の場合は、先ほど言われたように触診なんですけど、東洋医学の場合は切診と言います。まったく観察する対象が違っていて、西洋医学の場合は要素還元主義なので、臓器を触診しようとするんです。対する東洋医学では、触ったときの患者さんの反応を見ている。たとえば、触ったときに患者さんがくすぐったがったとき、西洋医学では緊張されると臓器が触れないのでノイズととらえます。だけど、東洋医学の場合には、くすぐったがる体から、その人の緊張度や人に対する信頼感の持ちようとして反応を受け止め、そこから状態を診ていくらしいです。触るときも、東洋医学では手を温めるんですよね。サイエンティフィックに分割してパーツを見るのではなくて、対人間で見ていくのでかなり違う。
——— 東洋の知恵の系譜で気とか丹田とかありますね。これを東洋医学と言っていいのかわからないですが、そもそも丹田という臓器があるのではなく、体全体のバランスのなかのひとつの一点を指して丹田と呼んでいる。そのことが視覚的ではなく、触覚的だと思います。視覚だと、何かを分析可能な対象として見るのが前提になりますけど、東洋医学の体系全般が分析的ではなく、必ず関係的に見ていく気がしますね。こちらのアクションに引き出されたリアクションから、状態を解釈をしていくと言いますか。
伊藤:
そうですね。さっきは西洋と東洋という言い方をしましたけど、西洋医学も遡れば東洋に近いところがあります。四体液説の頃はもっとホリスティックだったと思いますが、顕微鏡の発明や解剖学の進化などによって、すごく視覚的なものになっていった経緯がおそらくあって、触っているようで実は見ているといった感覚が強いのかもしれません。
——— 西洋医学の体系は近代の体系で、すべてを要素還元的に見る目線を持っていて、それが知の体系になっている。医者はその知の体系を頭に入れつつ、臨床の現場で身体的な情報も組み合わせていると、何かで読んだことがあります。職人からアーティストまでが、記号的な知性だけでは対処できなくて、必ず現場では身体知みたいなものを使っているのが実際のところなんだと思います。
伊藤:
その読まれた本は佐藤友則さんの『身体的生活※9』ですかね。わたしも読んで、その箇所に感銘を受けました。数値は問題ないんだけど、この患者さんを今日このまま帰しちゃいけないという気がしたという話ですよね。
——— それですね。身体の情報から直観につながっていくんだけど、そこはコードを経由しているわけではないのかなと。
伊藤:
実際に話を聞くと、理系の研究者でもそういった部分はすごく大きいみたいなんですよね。理系の研究と言うと、数字で考えているイメージを持ってしまうけど、職人的な部分がどうしても残るみたいなんです。前に人工衛星の研究者から聞いたのは、小さい人工衛星を飛ばして宇宙空間で展開する構造を研究しているんですけど、宇宙空間での実験では展開の様子が見えないじゃないですか。数値として情報は入ってくるし、シミュレーションもできるんだけど、それだけではわかったことにならないんですって。最終的には展開しているのを自分の体で再現する能力がすごく大事なんだそうです。遠隔だから触れないけど、最後はむしろ触覚的にわかることが研究者としての能力にすごく重要で、分野ごとの身体知があることを強く感じます。
——— 本のなかでは、触覚について「さわる」と「ふれる」という二つの極を示されてますよね。ここで言われている「さわる」というのは、物を相手に、その性質や状態を確認することです。一方の「ふれる」は、相手に心というか内面がある前提で、こちらがふれることによって、相手もふれられているのを認識する。つまり、こちらのイマジネーションと分かちがたく結びついている触り方を指しています。だから、触ると同時に触られていて、能動と受動が曖昧になっていくような、双方向性があるのが「ふれる」だと思います。
先ほど例にした西洋医学の触り方は「さわる」のに近くて、東洋医学の触り方は「ふれる」のに近い。おもしろいのは、「ふれる」が双方向とは言っても、身体という物質が媒介としてあるところです。つまり、心という領域だけで起きてることではなくて、身体という自然に開かれたなかでの相互行為だと思うんです。倫理と言われると、どうしても心と心の関係みたいになるし、「ふれる」と「さわる」をカッチリした二分法で考えると、複雑に感じるんですけど、実感としてはまったく複雑ではありません。それは身体という自然に媒介されているからじゃないかという観点が、すごくおもしろくて広がりがあると感じました。
伊藤:
そこに注目していただけたのはすごく嬉しいです。こう書いてよかったと思いました。やっぱり「さわる」と「ふれる」を分けて書くと、「ふれる」という双方向性が重要なんだねってところで一見終わりがちなんです。でも先ほど話されたように、そもそも身体は人間的なものを超えている部分があって、そこへのアクセスでも触覚が開かれているんですよ。
本の最後の方で、看取る人たちが死にゆく体を「さわる」ことで納得するという話をしています※10。原始的な交流を超えて、この体が生命の先に行くことを納得するときは、一方的に受け止めるしかない。でもそこには納得感のある「さわる」がまたある。これも触覚のすごさだと感じます。
生と死の話では、そういったことがよく言われると思うんですけど、それ以外にも人間の体に対して「さわる」ことは結構あるんですよ。「あとがき」で書いたのは、母親に「さわられる」という経験なんです。母親との関係と言うと、「ふれる」ことで自分を大切にしてくれて、慈しまれた経験をよく聞きますよね。たとえば、痛いところを手当てされるとか。だけど、よくよく考えると「さわられた」ときの方が幸せだったという記憶もあるんです。母親が何も考えず、自分の体をただ気持ちよさそうに、母親自身の快楽のために触っているときに、ものすごく自己肯定感が高まっていた気がして。自分にもそういった感覚があったと、本を読んで話を聞かせてくださった方もいました。
つまり、「ふれる」方が必ずしもコミュニケーションとして人間的に深いわけでも、そこがゴールというわけでもない。その先に「さわってしまう」という感覚もあるんです。さわられてしまう。さわってしまう。「さわる」ことは、自分の想像を超えたものと出会うということでもある。自分が物質になり、物質として扱われるのが、実は深い肯定だったり、深い納得だったりするということすらもある。そこも大事にしたいと思うんです。
——— そうですね。結局のところ、双方向性の「ふれる」に関しても、そこに何かしら存在しないと「さわる」ことができない。何かを「さわる」上で、その「さわる」のひとつの特殊な形が「ふれる」と考える方が合っているのかなという気がしました。当然ながら、身体という物質がないと、そもそも「ふれる」ことすらできないわけなので。
心と心がふれあうといった言説は多いですけど、それは人間と人間だけのクローズドなサーキットに閉じていってしまう窮屈なものでもある。「ふれる」ということを否定的に考えているわけではないけど、「人間のふれあいって大事だよね」といった言説を聞くと、窮屈な印象も持ってしまう。この「さわる」ときの物質は、現実には物質をベースにした生命体なので、ただの物質というわけではなく、やはり生きている身体を触っている。このあたりを読みながら、そこで身体が返す反応によって、人間関係が開放的になっていくような感覚を持ちました。
伊藤:
生まれた環境のせいもありそうですけど、小学校から中学校くらいまでは、友達の体と接触する経験がそれなりにあったと思うんですよ。そうすると、友達それぞれの体が持っている生命体としての強度を理解することになります。たとえば、ある子とぶつかって、すごい弾力性が高い体だと知ったりとか。
そこで知ったのは、人格とは別の、生命体としての個性みたいなものだと思います。その基本情報が頭にあった上で、たとえばボールをパスするときの力を加減したりしてました。この子ならこれぐらいの速球でも大丈夫とか、そういったことが信頼関係にもつながっていた気がするんです。そういうレベルの情報も、人間関係のなかですごく重要だと思います。
——— モダンとプレモダンに二元化するとして、今おっしゃったような身体を互いに理解し合うことは、プレモダンの世界で構築されていたことじゃないかという気がします。たとえば、狩りをするとき、あいつは狩れるけど、あいつは狩れないみたいな区別だったり。変な表現になりますけど、それは触覚的に見ているという感覚ではないかと思います。距離をおいて視覚的に接するときも、なんか信頼できるなという感覚は、プリミティブな身体性から出てくるのではないでしょうか。こうしたプレモダン的な世界観がすべて正しいわけではありませんが、これを失いすぎると閉塞的な関係性になってしまうという気がします。
伊藤:
身体介助を受けている人は、さまざまな介助者と物理的に接触しているので、触覚的な人格をすごく重視しているんですよね。そうすると、パッと見の視覚的な情報と、実際が違うことが多いらしくて、この人は丁寧そうだと思っても、介助してもらうと適当だったりとか、堂々としていると思ったら、妙に慎重な手つきで触られたりとか。慎重に触られても、それはそれで面倒くさいと感じたりするらいんですけど。いずれにしても、視覚的に見えるその人と、その人そのものを、違う物差しで見て知っているわけですよね。
——— ヘッドスパを受けるみたいな日常的なケースでも、気持ちいい人と雑な人がいたりしますよね。
あと、おもしろいと感じた論点が、第6章の「不埒さ」と題されているところです。視覚的な秩序は、ひとつの対象をフレーム化してカテゴライズしていく種類の秩序だと思うんですけど、触覚はそもそも対象化やカテゴライズがしづらい感覚であると。AというフレームとBというフレームがあったとしても、触覚においては混ざり合ってしまう。本のなかでは、介護現場で介護している体感と、性愛のときの体感を混同してしまう例が上げられていました。つまり、性愛的な行為の場面で、つい介護のことを思い出してやる気をなくすとか、逆に介護の現場で性愛を連想して混乱してしまうといったことです。
このあたりの話を読んでいると、これは創造性という問題意識にも引きつけられるのがわかります。創造的な場面というのは、秩序立てられた客観的な情報、言わばキャビネットに入っているような情報を一旦机の上にばらまいて、それをいろんな形で結合させていく作業だと思うんですね。こういった作業も触覚的なんだと思います。
デザイナーやアーティストの作業現場を見ると、本当に手探りでやっている。これを秩序壊乱的とネガティブに評価することもできますが、この視覚的にカオティックな状態を経由しないとクリエイティビティにはならないという気もするんですよね。
伊藤:
そうですね。わたしがとても尊敬している東大の情報学環の暦本純一さんが、『妄想する頭 思考する手※11本を出版されるんですけど、タイトルがかっこいいなと思って、先に言われた感がありました。
手には考える力があって、この考える力というのは、先ほどおっしゃったように、手で触りながら違う枠組みに行ってしまうというか、想像していたのとは違う場所に横滑りしていくようなおもしろさがあるんです。
すこし前にご紹介してくださった『見えないスポーツ図鑑』も、ひたすら手で考える研究だったんですね。研究するときには、山のように百均のグッズを置いて、ノープランでどうするか考える。ただ大学でやる研究なので、先に研究計画書を出さないといけない。研究計画書を応募して、はじめて研究費がつくので、それ自体に創造性がないんですよ。答えがわかっていて実行するための枠が与えなければならないんです。だけど、研究はそんな風に結論が見えているわけではなくて、本当は何をやっているかよくわからないまま進めていくわけです。
いろんなものを触っていくうちに、『見えないスポーツ図鑑』というコンセプト自体ができてきたりとか、この種目ならこれを使って翻訳できるのではないかといったことが見えてくる。これは、そもそも人間の考えるという作業が、自分の頭のなかで完結しないもので、自分以外の材料が考えているみたいなところがあるんだってことなんです。それは常に意識して研究しています。
——— 頭で考えるというのは、一回記号化したものを組み合わせていくことだと思うんですけど、記号ありきで考えてしまうと、どうしても楽しくない思考になっていくのかもしれません。身体からまだコード化されていない情報を受け取って材料にせずに、頭だけで考えてしまうと、妄想的になっていくんだと思います。とくに手は自由に動くので、身体のなかでも思考に向いている器官という気がします。
手を使って試行錯誤していても、そもそも人間は生物として構造化されているので、分節機能が働くんだと思います。伊藤さんがされているのは、完全に混沌としたものを混沌としたままかき回しているわけではなく、人間の身体という分節構造で対象を構造化していく作業だから、そのまま思考と言えるのかなと感じました。
伊藤:
そうですね。その一方で、妄想も重要だと思うんです。妄想というか、言葉がつくり出すものは、常に無茶苦茶。わたしの今回の本では二項対立がたくさん出てくるんですが、これは体や認識に対してショックを与えたいと思って、意識的にやったんです。言葉だけで完結すると机上の空論だけど、それが体や認識と組み合わさったときはおもしろくて、そこから派生して変化が起きることがある。二項対立ってもの自体が、勝手に言い切るような言葉の使い方で、すごく妄想的なんだと思います。
そういう意味で、体は分節することで創造性を発揮するという面がありますが、混沌とした部分もあります。障害を持っている方が、どこかが痛いんだけど、それがどこなのかわからないときに、言葉を求めて痛みを分節化したいということがある。実際に分節化すると痛みが変質することがあって、よく体と言葉は対立的にとらえられるんですけど、対立するからこそお互いが材料や道具になるところがあって、そこが重要だと思うんですよね。
——— 『手の倫理』では二元論として書かれていましたけど、一方で哲学の系譜では心身一元論や汎神論みたいな世界観もあります。だけど、お話をうかがって、現実に創造的な拡張性が持てるのは、身体を他者と考えることじゃないかと感じました。
伊藤:
とにかく「体はすごい」みたいな身体論がありますよね。「体はすべてを知っている」みたいなの(笑)だけど、体があることで、しんどい面もたくさんある。体が勝手にやっていることがたくさんあって、それに巻き込まれて付き合わなきゃいけない。おっしゃるとおり、体はある種の他者というか、自分だけど自分ではないというのをメッセージとして突き付けてくる存在だと思います。これは自分の実感でもあるので、この先もそこを中心に考えていきたいと思っています。
2020年12月14日
インタビュアー: +M(@freakscafe)