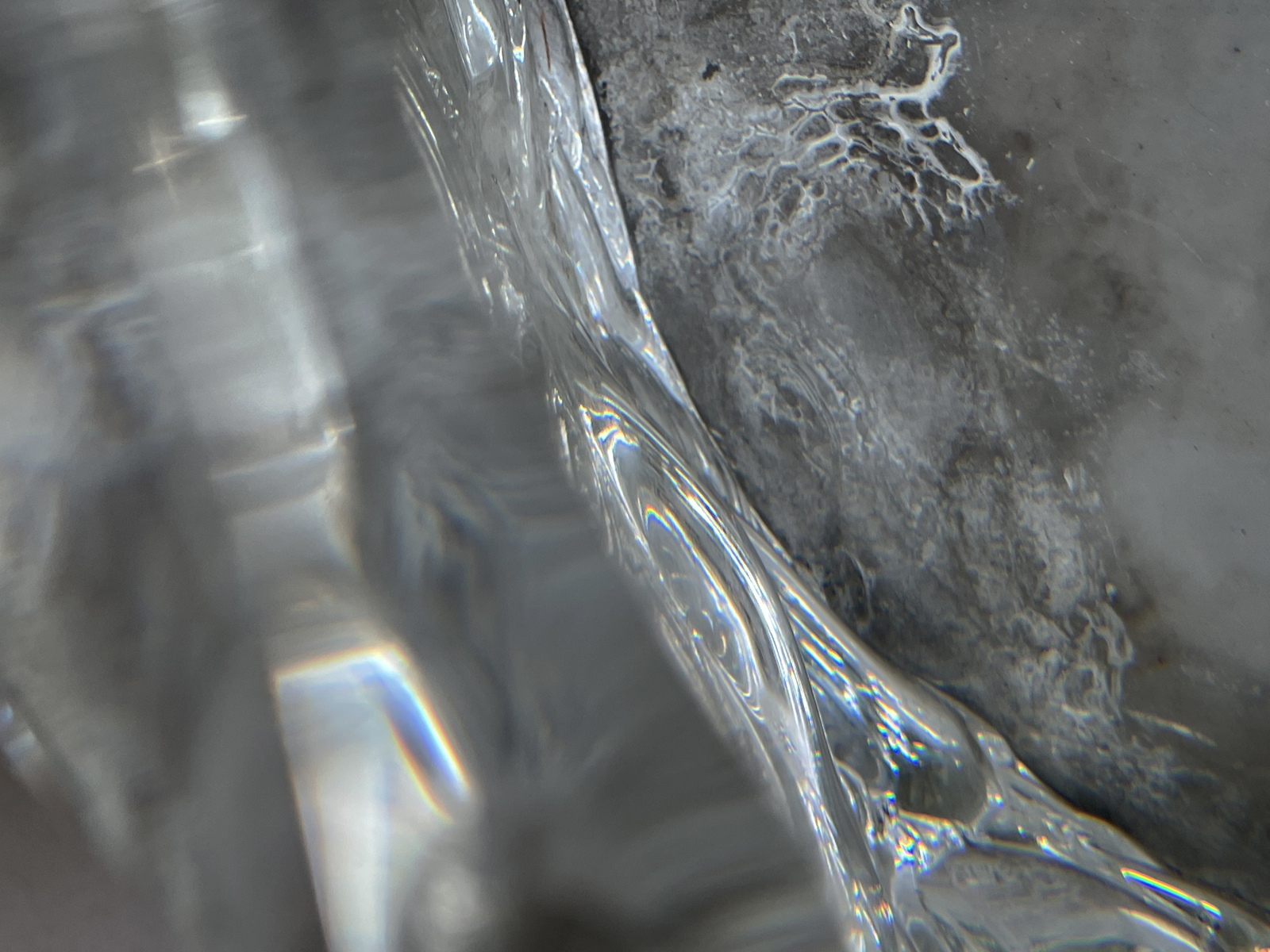ホーム画面をスワイプする体験の「わからなさ」
2007年にiPhoneが登場して以来、私たちは日常的に画面に直接触れるようになった。ディスプレイに表示されているアイコンをタップしてアプリを起動したり、写真をスワイプして次の写真を見たりしている。タップはマウスやトラックパッドのクリックを代替するものであり、特に違和感もなく受け入れた人が多いだろう。では、スワイプはどうだろうか。スワイプは「iPhoneユーザガイド」の「iPhoneの操作に使う基本的なジェスチャについて」で「画面の上で1本の指を素早く移動します。例えば、ホーム画面を左にスワイプすると、ほかのアプリが表示されます※1」と説明されている。こちらもほとんどの人があたらしい操作方法として受け入れただろう。しかし、私はiPhoneのホーム画面のスワイプに大きな違和感を持っていて、そのことを認知科学の研究者小鷹研理とメディアアーティストの谷口暁彦とのトークで話した。小鷹が私の話を次のようにまとめてくれている。
水野は、iPhoneでホーム画面をフリックする際にみられる、アプリのアイコンがグリッド状に並ぶレイヤ全体が面として左右に移動する映像を見せながら、この体験の「わからなさ」について説明された。とりわけ、ディスプレイに物理的に触れている一点の操作が全体の面に及ぶ変換の恣意性に対して、ある種の「不安」さえ覚えるという。一方で、この種のインタフェース体験は、多くのユーザにとって既に自明のもの、馴染みのあるものとなっていることも事実である。小鷹研理「「気持ちいい」と「気持ちわるい」の錯覚論、メディアアートとの対話※2※3」
今回※4、私が考えたいのは、ホーム画面の遷移を可能にするスワイプというジェスチャについてである。なぜ私はこのスワイプ体験に「わからなさ」を感じ、スワイプに慣れた今でもたまに違和感を感じ続けているのだろうか。スワイプ体験を考える準備として、まずはカーソル体験を「自己帰属感」を軸に考察し、その後、ラバーハンド錯覚とカーソル体験との比較を行う。最後に、スワイプが皮膚という「半自己」的存在をヒトとコンピュータとのあいだに入れる行為であるがゆえに、画面に対しての「自己帰属感」が曖昧になり、「画面帰属感」というあらたな感じが生まれていることを示す。
カーソルと「自己帰属感」
渡邊恵太の『融けるデザイン』は2015年に出版され、2022年末には10刷がなされたインターフェイスデザインの基本書となっている。その理由は、インターフェイスデザインに情報で体験をデザインする時代に適した「自己帰属感」というあたらしい軸を提示したからである。
動きの連動によって自己への帰属感が立ち上がってくる。つまり、私たちは普段カーソルを意識しないで対象を意識しているというカーソルの「透明性」の正体は、「動きの連動」がもたらした自己感、自己帰属の結果であったと言えるのではないだろうか。また、ハイデガーの事物的存在と道具的存在も、この連動が生み出す自己帰属で説明するのが良さそうだ。
つまり、私たちはユーザーインターフェイスの設計に「自己帰属(感)」という新しい設計の軸を手に入れたのだ。しかもこれはカーソルを利用したシステムはもちろんのこと、コンピュータにおけるさまざまな入力手法を考えるときの強力な設計指針となる可能性を持つのだ。
渡邊恵太『融けるデザイン※5』
渡邊が『融けるデザイン』で書いた「自己帰属感」は、実際にインターフェイス設計の「強力な設計指針」となっている。ここで私が考えたいのは、インターフェイスデザインにおける「自己帰属感」の有効性ではなく、渡邊が「sense of self-ownership」の訳語として「自己帰属感」を使っていることである。渡邊は次のように書いている。
もともとこうした「自己感」については脳科学や哲学の分野でも議論されており、そこでは自己感は2つに分類され紹介されている。それは、「自己帰属感[身体保持感](sense of self-ownership)」と、「運動主体感(sense of self-agency)」というものである。
渡邊恵太『融けるデザイン※6』
なぜ「sense of self-ownership」の訳語として「自己帰属感」が使用されているのを取り上げるのかというと、「錯覚」という観点からインターフェイス体験を考察するために読んだ小鷹の『からだの錯覚※7』では「自己帰属感」が「sense of agency」の訳語として使われていたからである。私は小鷹研究室が考案する錯覚を体験して以来、ディスプレイに表示されているアイコンや画像などのデータから構成される「デジタルオブジェクト」に「触れる」という体験を分析するには、錯覚が起こる身体の仕組みを利用する必要があると考えるようになっている。錯覚の強烈な体験が身体イメージそのものを変えてしまうように、インターフェイスは使い続けるなかで身体とデジタルオブジェクトとの関係を否応なく変えているのではないだろうか。このような考えで小鷹の本を読んだときに、渡邊と「自己帰属感」という訳語の使われ方が異なることは、錯覚とインターフェイスとを繋げて考えるきっかけになると考えたのである。
「sense of ownership」と「sense of agency」は哲学者のショーン・ギャラガーが「ミニマルセルフ」を構成する要素として提示したものである※8※9。「ミニマルセルフ」とは自己を構成する最小限の要素であり、物語や記憶から成立する「ナラティブセルフ」の対となっている。そして、「ミニマルセルフ」は「この身体はまさに自分のものである」と感じる「sense of ownership」と「この身体の運動を引き起こしたのはまさに自分自身である」という「sense of agency」から構成されている。ギャラガーが論文に書くように、自発的行為においては「sense of ownership」と「sense of agency」とは一致していて、区別がつけにくい状態にある。だとしても、「自己帰属感」という語が「sense of ownership」と「sense of agency」にそれぞれ使われているのは興味深い状況であり、ヒトとコンピュータとが向かい合うインターフェイスという場で形成されるミニマルセルフに独自性があるとすれば、ここにそのヒントがあると、私は考えている。
小鷹が「sense of agency」の訳語として「自己帰属感」を使っているところを確認したい。小鷹は遊びから発展していった「蟹の錯覚」の説明の延長で「自己帰属感」(sense of agency)を使っている※10。「蟹の錯覚」は以下のような手順で行う「即錯」の一つである。
基本レシピ
- 向かい合った二人が、一枚の厚紙を裏側で両手を交差して保持する。この際、それぞれの両手は、一方を手前側にもう一方を奥側に位置させる。
- お互いに指をわしゃわしゃしてみる。
小鷹研究室as「即錯23:18 – 蟹蟹の錯覚」
この錯覚を体験すると「多くの体験者は「自分の手が自分の意図に反して勝手に動いてしまう」というような、視覚と運動感覚の齟齬を経験する」と説明される。実際に「蟹の錯覚」を体験してみる相手の手を自分の手と感じるなどして、自分の手を動かしているのは自分ではないような奇妙な感じが生まれてくる。小鷹はこのこんがらがった感覚を次のように説明する。
「自分の身体であるにもかかわらず、自分の思い通りに動いてくれない」状況として、本書ではすでに、「腕の圧迫」と「エイリアンハンド・シンドローム」の事例を取り上げています。ところで、特殊な症例である後者が稀な事態であることはいうまでもありませんが、こうした事例でよく引き合いに出される「腕の圧迫」であってもそうそう日常的にお目にかかれるものではありません。実際、このタイプの「ねじれ」を、私たちが意図して作り出すことは至難の業です。私たちの日常は、自分の身体が思い通りに動くという鋼の囲いの中に、深刻なまでに閉じ込められているのです。筆者は、《蟹の錯覚》が、そうした鋼の囲いを溶解させるための一つの呪術のようなものと考えています。
さて、ここで問題とされている、自身の運動感覚を起点として対象を意図通りに制御できているときの感覚のことを、学術の用語では、特に「自己主体感」あるいは「自己帰属感」(sense of agency)と呼びます(以下、単に主体感と呼びます)。主体感とは、つまるところ、視覚や聴覚によって把握できる外在的なイベントが、自己の意図を基点にしている、という感覚にほかなりません。したがって、主体感は、形式的には、運動と(典型的には視覚などの)外在的な感覚とのマッチングによって担保されることになります。
ところで、日常的には経験することが極めて少ない「主体感なき所有感」に対して、これとは逆のねじれである「所有感なき主体感」は、「これを体験しない日などない」というほどに、私たち人間にとって極めてありふれた事象です。というのも、このねじれは、道具の利用において生じている自己の投射にほかならないからです。
小鷹研理『からだの錯覚※11』
小鷹は身体とカーソルとが連動している運動を視覚という外在的な感覚とマッチングさせて、物理的な延長としての道具ではなく、情報的に延長した道具としてカーソルを捉えて「自己帰属感-主体感」とするという見方をしている。そして、彼は「自己帰属感-主体感」を説明するために前後に「自分の身体であるにもかかわらず、自分の思い通りに動いてくれない」状況、「自分の身体が思い通りに動くという鋼の囲い」、「主体感なき所有感」、「所有感なき主体感」と興味深い多くの言葉が書かれている。これらを活かして、渡邊の「自己帰属感-所有感」との比較を行っていきたい。
その前に、小鷹が「sense of ownership」をどのように表記するかを書いたところを見ておこう。
本書で関心のある体の感覚とは、そのほぼ全てが、「それが自分のものである」と感じられるような、当人にとってのみ主観的にアクセス可能な自己所有の意識のことを指します。これは、実験心理学の世界では所有感(ownership)と呼ばれるものですが、筆者は、一般向けに説明する際には「からだ」という括弧付きの表記をすることとします。今後、本書の中で、文脈に応じて所有感と「からだ」のいずれかの用語が頻繁に登場しますが、特に説明が無い場合、「からだ」とは、そのような身体の所有に関わる主観的な意識および、その際の身体のイメージを指していると理解してください。
小鷹研理『からだの錯覚※12』
小鷹が「sense of ownership」に当てるのは「からだ」であり、その説明に渡邊の「自己帰属感-所有感」で重要な役割を果たす「連動」は出てこない。小鷹が考える身体所有感は何かと連動するわけでもなく、ある状況において、ヒトの主観に現れる身体のイメージとなっている。
小鷹の考えに基づくと、身体が思い通り動き、カーソルがその動きに連動することは所有感より主体感をヒトに与えるだろう。そのとき、ヒトとカーソルとの関係は、小鷹がペンを自在に使っている人であっても、ペンを自分の身体だと思う人はいないとした上で、「ペンで紙に何かを書いているとき、主体感はペン先に鋭く投射される一方で、所有感はあくまでも自分の手の領域の中に引きこもったままなのです」と指摘しているものになっている。それは「所有感なき主体感」が示す道具的存在としてカーソルを捉えることであり、思い通りに動く限りは「からだ」は自分の身体に引きこもっていて、意識されないのである。
対して、「連動」を重視する渡邊はカーソルを「からだ」ではなく、「自己(self)」との関係で考えていて、ヒトとカーソルとの連動によって「自己」を情報空間に引っぱり出していくことが目指されている。それゆえに、渡邊の「自己帰属感-所有感」はギャラガーの考えるミニマルセルフを構成する「sense of ownership」と「sense of agency」から逸脱した意味を示す。『融けるデザイン』は生態心理学者のJ・J・ギブソンの影響をもとで書かれており、認知と行為との連動が重要視されている。出版から5年経った2020年に渡邊が「自己帰属感」という言葉と出会ったのは、河野哲也の『「心」はからだの外にある』だったと書いている。そして、河野はギブソンの考えを追いながら「自己帰属感」について次のように書く。
私たちが移動し運動するときには、つねに環境の変化の知覚がともなっている。知覚風景の自己帰属感は、この環境知覚と自己知覚の相互依存性から生じてくる。したがって、知覚風景が自己に帰属しており、他人に帰属していないのは、私の目の前にある知覚風景の変化が自分によって引き起こされ、他人によって引き起こされたものではないからである。とするならば、私の知覚風景の変化とは、逆から言えば、私がある環境のなかを移動した、あるいは運動したという事態に他ならない。つまり、知覚の自己帰属感とは、単純に私が移動したということ、そしてその移動は、自分が随意的に行ったのであり、他人によって引き起こされたのではないことを、その裏側から述べたもの以上ではない。
河野哲也『「心」はからだの外にある※13』
ここでは身体が環境内を思い通りに動くことが前提となっていて、思い通りに環境内を動いたことで生じる自己と環境との連動が知覚風景の自己帰属感を生じさせるとされている。さらに、河野は「実際には、知覚風景の自己帰属は、自分が他人に邪魔されずにある環境のなかを移動・運動できたということにすぎない。そして、知覚風景を所有するということは、その環境に慣れ親しみ、適応的な習慣を獲得したということである※14」と書く。河野のテキストからも、渡邊にとって、そして何よりも、インターフェイスデザインにとって、「自分の身体であるにもかかわらず、自分の思い通りに動いてくれない」状況は避けるべき状態であり、コンピュータにおいてはこの状況はマウスとカーソルとの組み合わせによって解消されていたと言えるだろう。渡邊にとって「自己帰属感-所有感」とは「からだ」に対する意識であるよりも、自己と知覚風景とが連動するという動きのなかで、自身を取り囲む空間が自己に帰属していく感覚なのである。そこで渡邊は思い通りに動かせるカーソルに対して、ヒトの身体がラケットなどの物理的道具を思い通りに動かせる「自己帰属感-主体感」を情報的に拡張して適応させるのではなく、情報空間を自由に移動・運動できる自己という意味で「自己帰属感-所有感」を与えるのである。
カーソルが特別なのは、マウスとの「動かし」と画面の中の動きが連動し、自己帰属感が立ち上がるからである。カーソルまでが自己の一部となることで、人はカーソルを意識しなくなり、対象のほうを意識する、つまりカーソルは透明化する。だからこそカーソルの登場は「直接操作」を実現し、自己が画面の中にまで入り込んで情報に直接触れているかのような感覚へと辿り着く。カーソルはバーチャルな身体なのではなく、連動性という点においては実世界の自己の知覚原理と同じで「リアル」である。
渡邊恵太『融けるデザイン※15』
マウスとカーソルとが連動することで、ヒトはカーソルのみならず情報空間そのものとも連動して、あたらしい空間を自由に移動するようになる。渡邊がこの状況を「自己が画面の中にまで入り込んで情報に直接触れている」と書くとき、マウスを持つ「からだ」は身体のある物理空間に閉じ込められたまま、「自己」の一部がカーソルとなって情報空間に現れるということが起きる。カーソルは情報的に延長した道具として画面に現れているのではなく、カーソルはヒトの動きとの連動を示して、ヒトとコンピュータとのあいだに生じるミニマルセルフの情報的現れとして画面に現れているのである。
物理空間と情報空間とあいだを跨ぐ「自己」とカーソルとの強固な関係を渡邊に実感させたのが「マルチダミーカーソル実験※16」である。「マルチダミーカーソル実験」は、カーソルと見た目が同じダミーカーソルを画面上に複数配置して、自分のカーソルを発見できるかを調べたものである。「マルチダミーカーソル実験」の問いは「まずカーソルが身体であるかということ以前に、そもそもカーソルを人はどう認知しているのか?物理的につながっていないのに、どうして「自分で操作している」と感じるのか?なぜ画面のカーソルが「自分の」操作しているカーソルなのか?※17」であった。「カーソルが身体であるか以前」に「自分」を考えているところに注目したい。「マルチダミーカーソル実験」は物理空間と切り離された情報空間における「自己」を発見するための実験だと言える。画面上の動く複数のカーソルから、自分の動きと連動するカーソルを発見した瞬間、そのカーソルはミニマルセルフの情報的現れとして認識される。
30個ものダミーカーソルがあるにもかかわらず、どういうわけか、ほぼすぐにと言っていいほど自分のカーソルが特定できるのだ。しかも、一度特定してしまうとほとんど見逃すことがなく、混沌とした画面であっても明瞭に力強く、操作とカーソルが結びついた体験を得られたのであった。これには驚いた。しかも、自分でもどうやって見つけているのかわからないのだ。ただ動かすと「あー!いたいた!」という感じである。これは新しい体験というよりも、混沌の中からいつもの「当たり前」感覚が湧き上がる体験であった。
渡邊恵太『融けるデザイン※18』
ヒトとコンピュータとのあいだには、マウスとカーソルとの連動によって情報的に拡張されたミニマルセルフが現れる。ヒトは物理空間にいて、カーソルは情報空間にいるが、それらの連動が一度認められると、その連動は即座にヒトとカーソルとを含んだミニマルセルフを構成していく。私が「私」を探すという奇妙な状況ではあるが、連動を発見できない状態であっても、カーソルは情報空間にいる「私」として画面上にいることには変わらない。情報空間の「私」は物理世界の私に見つけてもらえていないだけなのである。しかし、そのときは、ミニマルセルフは情報的に拡張されはしない。そして、物理世界の「私」が動きの連動を認知すると「あー! いたいた!」と情報空間の「私」とのあいだに即座にミニマルセルフが成立する。何らかのきっかけで連動性を見失わない限り、その関係が解けてしまうことはない。物理空間と情報空間との断絶をまたぐミニマルセルフの発生は、身体とカーソルとがともに思い通りに動き、かつ、連動すれば成立する。その際に、「からだ」は身体に引きこもったままになっている。なぜなら、「自分の身体が思い通りに動くという鋼の囲い」が「からだ」を身体に閉じ込めているからである。カーソルはミニマルセルフの情報的現れではあるが、そこに私が持つ主観的な身体イメージである「からだ」はリンクしていない。渡邊の「自己帰属感-所有感」はカーソルは単なる道具的存在ではなく、カーソルは「自己」ではあるが「からだ」はないという奇妙な存在として画面を思い通りに移動していることを示しているのである。
カーソルとラバーハンド錯覚
この節では「錯覚」という観点からカーソル体験を考えていきたい。小鷹はからだの錯覚を研究していこうと彼自身に思わせた衝撃的な錯覚として「ラバーハンド錯覚」を挙げている。ラバーハンド錯覚とは、体験者の手を衝立で隠した状態で、体験者から見えるゴムの手と体験者からは見えない手の同じ部分に、同時に触覚刺激を与えると、ゴムの手が自分の手のように感じられるというものである。この錯覚自体は心理学の実験として有名なもので、インターフェイス研究とは一見関係ないものにみえるかもしれない。しかし、「ラバーハンドの遅い発見問題」という小鷹の問題意識は、ラバーハンド錯覚とインターフェイス研究とをリンクしてくれる。小鷹はこのシンプルな錯覚が学術的にはじめて発表されたのが1998年だったこと、そして、「ネイチャー」に発表されたにもかかわらず、その後10年はあまり注目もされなかったことに着目して、インターフェイス研究と関係する次の指摘をしている。
最初の疑問に戻ると、筆者の直感では、パーソナル・コンピュータの普及が、1990年代後半におけるラバーハンド錯覚の登場の後押しをした側面が指摘できるように思います。というのも、ラバーハンド錯覚は、身体を物理的な実体としてではなく、複数の感覚信号の組み合わせによる一種の情報的な効果として扱うものであるからです。
コンピュータの普及により、事物を情報的に処理する感受性が世界に浸透しつつあった1990年代後半に、「情報としての身体」を謳うラバーハンド錯覚が発表されたことは、単なる偶然であるとは思えないのです。
小鷹研理『からだの錯覚※19』
ラバーハンド錯覚が発見されるには、コンピュータの普及によって、身体を物理的なものから情報的なものとして扱うということが必要だったのではないかという、小鷹の指摘が本研究にとって重要である。ラバーハンド錯覚の発見と普及とパソコンやスマートフォンの普及とをパラレルな事象と見做してみると、インターフェイスは身体における「複数の感覚信号の組み合わせによる一種の情報的な効果」を試す場であり、「情報としての身体」をさまざまに変形させてきたと言えるだろう。その一つの例が、前節で扱った渡邊の「自己帰属感-所有感」が示すミニマルセルフの情報的現れとしてのカーソルと言えるだろう。ヒトとコンピュータとの連動に「複数の感覚信号の組み合わせによる一種の情報的な効果」を浸透させてあたらしい「自己」を形成するのである。
カーソルとラバーハンド錯覚の関係を探るために、まずはこの錯覚が起こる原理を確かめたい。ラバーハンド錯覚は自分の手の位置が偽の手へ移動して起こる。このときに関係するのが複数の関節の回転状態をもとに計算される固有感覚である。ラバーハンド錯覚では自分の手の位置を示す固有感覚が偽の手の位置へ移動している。この事象は「固有感覚のドリフト」と呼ばれている※20。では、「固有感覚のドリフト」はなぜ起こるのだろうか。それは偽の手を見ている視覚の確かさにある。小鷹は「私たちの認知システムは、視覚から得られる空間情報に対しては、解像度が十分な限り、絶対的な信頼性を与えています」と書いている。
対して、固有感覚から得られる位置情報は視覚ほど確かなものでない。普段は、位置情報に関して信頼性が高い視覚が固有感覚の曖昧な位置情報を補正しているのだが、ラバーハンド錯覚では曖昧な固有感覚の位置情報が視覚の確かな位置情報を上書きする。同時に与えられる触覚刺激によって、見えない自分の手の刺激が示す曖昧な位置情報が見えている偽の手に対する刺激に重ね合わされる。小鷹はこの状況を次のように書く。
位置に絶対的な信頼を有している視覚は、融通がきかずに相手に歩調を合わせることができないという側面があります。すなわち、固有感覚が本来的に宿している曖昧さこそが、ラバーハンド錯覚を享受できる「能力」を私たちに授けているということができるでしょう。
小鷹研理『からだの錯覚※21』
固有感覚は曖昧だから柔軟に視覚の正しさに融通をきかせて、位置情報を移動させることができてしまう。「物質としての身体」の位置は変わらないが、視覚と固有感覚が脳に送る信号が変調して、固有感覚が重ねられたラバーハンドが「物質としての身体」を情報的に拡張した「情報としての身体」の一部となる。「情報としての身体」を構成する視覚と固有感覚からの信号は、もともと「物質としての身体」から生じたものであるから、ラバーハンドにおいて「情報としての身体」と「物質としての身体」とが重なり合って、ゴムの手を自分の身体と感じるようになる。ラバーハンド錯覚で起きているのは、普段は重なり合っている「物質としての身体」と「情報としての身体」を特殊な状況において一度分離させて、別のかたちで統合するということであろう。
カーソルがラバーハンド錯覚と異なるのは、同時に与えられる触覚刺激がなく自分の手の動きがディスプレイに反映される点である。カーソルと同じような状況でもラバーハンド錯覚は起こり、「ムービング・ラバーハンド錯覚」というジャンルが形成されていて、主にVRを使った実験が行われている。そこでは、自分の手の動きで生じる固有感覚の曖昧な位置情報が、画面上に正確な位置情報として表示される。そして、画面を見て、再度、手を動かすという再帰運動で曖昧な位置情報と正確な位置情報との組み合わせが「情報としての身体」を変容させていく。その変容はカーソルというヒトと連動するデジタルオブジェクトが現れてきたからはじめて可能になったというわけではない。ラバーハンド錯覚が示すように固有感覚が示す曖昧な位置情報と視覚が示す正確な位置情報を元々処理していたからこそ、ヒトはカーソルを簡単に受け入れられたと言える。同時に、マウスによるカーソル操作によって、視覚が固有感覚をハッキングしていく手と目との情報的連動に慣れたからこそ、ヒトがラバーハンド錯覚が発生させる「複数の感覚信号の組み合わせによる一種の情報的な効果」に敏感になって、錯覚を発見できたとも言える。
カーソルとラバーハンド錯覚との相互作用を裏付けるまでとは言えないけれど、興味深い事象として、ラバーハンド錯覚が1989年に発見されて20年以上経った2010年代に様々なバリエーションの錯覚が報告されているということが挙げられる。このことは次のように2つの段階に分けて考えられるだろう。はじめに、私たちがマウスとカーソルをはじめとするインターフェイス体験をしていくなかで、ラバーハンド錯覚が示した感覚情報の組み合わせから生じる「物質としての身体」と「情報としての身体」と分離とその再統合とともに起こる「からだ」の変容に慣れていった。次の段階として、情報的に変容した「からだ」に対しての体験を設計し、「からだ」のさらなる変更可能性を探る試みが行われるようになった。小鷹がラバーハンド錯覚の原理を説明したのちに紹介している「軟体生物ハンド」と「マーブルハンド錯覚」は第二段階の試みにあたるだろう。
「軟体生物ハンド」は、小鷹研究室がラバーハンド錯覚をアレンジしたものである。金属の鍵でシリコンのラバーハンドの表面をなぞったり、ぐりぐりと押し込んでいるときに、被験者の手にも同じことを行う。すると、被験者は自分の手がシリコンのように「ぐにゃんぐにゃん」になってしまうのも否応もなく感じてしまう※22。ラバーハンド錯覚のように偽の手を自分の手と感じるだけでなく、その皮膚の質感が変わってしまうというところがラバーハンド錯覚の第2段階と言えるところである。私は小鷹研究室で「軟体生物ハンド」を体験したことがあり、今でも気持ち悪い感覚とともに体験を思い出せる。錯覚を体験中の私の手はいつにもなくぐにゃっとしたものであり、鍵がぐいっとラバーハンドを押し込んだ時には、自分の手の甲の皮膚が手を置いた机の表面に着いてしまったというとても奇妙な感じがあった。
また、「マーブルハンド錯覚」は次のような錯覚である。ヘッドフォンを装着した体験者の前に衝立を置き、自分の手首から先を見えない状態にして、実験者がその手をトンカチでトントンと叩いて、トンカチが手の甲にあたる瞬間に「コツン」という硬い石を叩いたような音をヘッドフォンから流す。この状態がしばらく続くと、体験者は自分の手が「自分の手の皮膚のマテリアルが、硬直した石のような感覚に変質していく」のを感じる※23。この二つの錯覚体験に対して、小鷹は次のように書いている。
これらは、私たちの認知システムが、皮膚の素材感覚をつくりだすうえで、触覚から得られる情報よりも、視覚や聴覚から得られる情報を重視していることを示しています。実のところ、触覚から得られる皮膚の素材に関する情報は、身体にとっての本来的にバーチャルな視聴覚情報によって書き換えられてしまう程度に、微々たるモノでしか無かったのです。つまり、私たちの皮膚のマテリアルに関する信念は、おそらくは、ほとんど視覚や言語による経験的なものに過ぎなかったと考えることができるのです。
小鷹研理『からだの錯覚※24』
この指摘は、ラバーハンド錯覚では皮膚が触覚刺激を偽の手と同時に受けることで「物質としての身体」を「情報としての身体」へと拡張したことを考えると意外である。しかし、ここで移動したのは皮膚感覚そのものではなく、身体の位置情報を示す固有感覚だったのであり、皮膚そのもののマテリアルは問題になっていない。皮膚のマテリアルを問わないままに、視覚と固有感覚とのあいだで情報の移動があり、「物質としての身体」から「情報としての身体」が分離し、再統合していった。「軟体生物ハンド」と「マーブルハンド錯覚」は、ラバーハンド錯覚で分離した「情報としての身体」に対して、感覚信号の組み替え可能性として視覚情報と聴覚情報を使ってあらたな介入を試みた結果として、「物質としての身体」を覆う皮膚のマテリアル感覚がほとんどないことが示された。さらに、触覚情報が書き換えられてしまうほど弱いということが重要である。視覚など他の感覚との関係によって、触覚が決まっていく。
錯覚体験から皮膚を考えると、カーソル体験で触覚を含めた皮膚は外界からの情報を単調化してしまうフィルターとしても機能すると言えるだろう。マウスとカーソルの関係のおいても、操作中にマウスを握る手が見えないか、見えたとしても周辺視にあり明確ではないことで、マウスを握る手の皮膚が外界からの情報を単調化することによって、手がマウスを握っているということは特に意識されなくなっている。皮膚からの感覚情報が意識されないほど単調化されているからこそカーソルという視覚情報と組み合わせることが容易になっていく。
インターフェイスにおける感覚情報の組み合わせ変更の試みの一つの例として、渡邊が開発した「Visual Haptics」が挙げられる。「Visual Haptics」はカーソルが可能にした「情報としての身体」に対するあらたな体験をつくっている。そこでは「情報としての身体」としてのカーソルとその先にある対象とのあいだで生じる感覚信号の組み替え可能性が試されている。「Visual Haptics」は以下のように説明されている。
カーソルで触れる対象の状態に応じてカーソルの動きや変形を利用することで、ユーザが実際に触っているような感覚を再現することが可能となる手触り感提示システムです。ざらざら感、ベタベタ感、立体感、奥行き、液体の抵抗感、風に流される抵抗感など、多様な感覚を再現します。
渡邊恵太「Visual Haptics※25」
身体とカーソルとの連動の変調によって、情報空間が自己に帰属する感じがズレ、特殊な感触が生まれる。私は「Visual Haptics」を体験していて、確かにさまざまな手触りを感じるのだが、それは「ガムテープ」「水」「蜂蜜」が示す物理世界の感触とも異なる独特な感触であった。その独特の感触はもちろん私が感じているのであるが、その発生源はマウスを持つ右手全体であった。右手がとにかく「重く」「鈍く」感じられるのである。この体験は、小鷹が書く「自分の身体であるにもかかわらず、自分の思い通りに動いてくれない」状況に陥ったモノであり、私がカーソルとの連動で、「自分の身体が思い通りに動くという鋼の囲い」の外に出された体験だったと言える。
渡邊は『融けるデザイン』で、「Visual Haptics」を「自己帰属感-所有感」で次のように分析している。
VisualHapticsでは、動きの連動に少しだけノイズ(位置のずらし、時間遅延、カーソルの変形)を適用したことによって、ある感触を発生させた。そして、自己帰属感は「動かし」の連動から発生していることについては述べた。マルチダミーカーソル実験によって、動きから自己を特定できることもわかった。つまりカーソルの自己感は動きの連動の結果である。この状態を、マウスとカーソルの連動 100%、自己帰属 100%とする。一方 VisualHapticsでは、それにノイズを発生させ、連動を乱している。だから連動は低下し、その結果、自己帰属感も低下、たとえば自己帰属 80%となる。
つまり感触の発生は、自己帰属感の低下によって生み出されると考えられるのではないだろうか。そしてより具体的には、感触の発生とは、その帰属が環境側に持っていかれることが、その環境の感触を生み出していると考えられるのではないだろうか。すなわち自己帰属率の配分が、インタラクション時の気持ち良さ/悪さ、また感触や質感の多寡になっているのではないだろうか。裏を返せば、私たち人間の実世界の環境認識についても、感触として感じていることが、自己帰属率の配分というようにも捉えられるのではないか。
渡邊恵太『融けるデザイン※26』
「Visual Haptics」の独自の感触は環境側に自己帰属率を持っていかれることから生じるという渡邊の主張を、自分の身体だと思っていたものが思った通りに動かなくなる「主体感なき所有感」の状況は「身体から所有感が剥がれていく」事態だとする、小鷹の指摘と合わせて考えてみたい。デジタル環境を制御しているコンピュータがカーソルというミニマルセルフの情報的現れを動きをイレギュラーにすることで、ヒトとカーソルとのあいだの自己帰属率を変化させる。そのとき、私から「自己帰属感-所有感」から剥がれていき、私の身体でありながら「この身体はまさに自分のものである」と言えないような状況が訪れる。それは皮膚が触覚にほとんど寄与せずに視覚的に引っ張られる特殊な状況である、その結果として、私とカーソルとの連動が私に独自の感触を与えるのである。このとき、私は私とカーソルとで形成したミニマルセルフの一部でもなく、私の身体でもなく、体験の瞬間まで全く知らなかった「異物」を自分とカーソルとのミニマルセルフに招き入れてしまっていたと言えるのではないだろうか。
この「異物」のことを「光学的身体」と呼んでみたい。「光学的身体」は渡邊が「Visual Haptics」を開発したときの説明で使っていた言葉である。渡邊自身はこの言葉を気に入ってはいたが「身体とは何であるか?」という問いが残り続けたとしている※27。その後の考察で身体は「自己帰属感-所有感」における「自己」と環境との連動という「知覚原理」に昇華していく。しかし、ヒトとコンピュータとがディスプレイを介して連動しつつもどこか思い通りにならずに独特の感触を示す状態を「光学的身体」と呼んで、カーソルと身体との関係を考えてみたい。なぜなら、「Visual Haptics」が示した自己帰属率の配分による感触の発生には、「からだ」が寄与していると考えられるからである。
小鷹はラバーハンド錯覚のバリエーションの最後として「インビジブルハンド」を紹介している。「インビジブルハンド」は、ラバーハンド錯覚のように自分の手を見えない位置に置き、ラバーハンドがあるべきところに何に置かない状態で、実験者が体験者の手と何もないところを同時に筆で撫でると、何もないところに「見えない手」が存在するように感じるというものである。小鷹は「インビジブルハンド」の感覚をはじめて身をもって体験したとき、「そこで目の当たりにしたのは、「なんとなく」などというような甘ったるいレベルでは決してなく、そこに「自分の手がある」としか言いようのない、確固たる実在の感覚だったのです」と述べている※28。そして、この体験について次のようにまとめている。
実際、この透明な「からだ」からは、三次元的な奥行きや膨らみが、ありありと感じられます。この錯覚体験から得られる何よりも重要な知見は、「からだ」が、少なくとも視覚的な水準では、物質的な実体を必要としないということにあるように思います。
小鷹研理『からだの錯覚※29』
さらに、「インビジブルハンド」は「体験者の無意識の中に眠る「からだ」を物理空間に引っ張り出してきている」と考えるべきだとしている。見えないながらも確かに感じられる実在の感覚というのは、インターフェイスを介して体験するデジタルオブジェクトに対する感覚を考える上で重要なものになっていくだろう。「インビジブルハンド」と同様に「VisualHaptics」も「「からだ」を物理空間に引っ張り出し」たと考えられる。物理空間に引っ張り出された「からだ」が即座に私とカーソルとの連動に重ねられて「光学的身体」となり、剥ぎ取られた「自己帰属感-所有感」を補うようにミニマルセルフに介入して、「重さ」や「鈍さ」という感触を情報的につくるのである。
最後にカーソルが情報的感触をつくるためには「↖」という抽象的なかたちが必要であることを確認していきたい。小鷹研究室出身の石原由貴は渡邊の「VisualHaptics」と対となるような試みを行っている。渡邊の「VisualHaptics」が「からだ」を利用しつつも、「重さ」や「鈍さ」をカーソルとの連動で情報的感触としてつくるのに対して、石原の研究「rubber hand pointer」は生々しい「からだ」そのものをカーソルに与えようとするものである。小鷹は「rubber hand pointer」について次のように書いている。
パソコンのディスプレイ空間内を意図通り移動する際の指示棒となる、あのおなじみのポインタ↖が、 文字通り「自分の指そのもの」であると感じられるためにはどうすればよいのか、という問題を考えた。とりわけ、ラバーハンド・イリュージョンの原理の一つ、「空間的整合性/antomical congruency」をディスプレイ空間に適用し、ポインタに身体所有感が投射されることによって、何かが変わることを期待したのだった。しかし、よくよく考えてみれば、インタフェースデザインにおけるポインタの本質は、各人の身体に固有の生々しさを排除し、華麗にディスプレイ空間を駆け廻る”匿名性”にあったはずであり、「手の形態との相似性」という制約によって、ユーザとの身体的なつながりを無理強いすることは、機能性の根幹に関わるところでポインタの首を締めることになる。
小鷹研究室as「小鷹研究室の各位●各論●身体論(カクイカクロンシンタイロン)※30」
小鷹研究室のカーソルの扱いはミニマルセルフの情報的現れではなく、ヒトが持つ「からだ」の投射先とするためにラバーハンド錯覚の原理の一つである「空間的整合性」を使って「手」のかたちを模したものになっている。石原と小鷹はカーソルを手に似せることで、手に引きこもっている「からだ」を情報空間に持ち込もうとした。しかし、小鷹が書くようにカーソルの本質は「華麗にディスプレイ空間を駆け廻る”匿名性”にあった」ので、この試みはうまくいかなかった。石原と小鷹の「rubber hand pointer」を経由することで、カーソルがミニマルセルフの情報的現れとして、「からだ」を捨象した「自己」になっていることが強調されるだろう。ラバーハンド錯覚を体験したときのような驚きなくしてカーソルをスムーズに受け入れてしまうのは。カーソルが「↖」という手から離れて、何かを指示するという機能を抽出した抽象的な形をしているからである。手という「からだ」を捨象したカーソルはヒトの固有感覚と視覚とが示す位置情報とリンクしたミニマルセルフを形成する情報的現れとして画面に存在している。だから、渡邊は「柔軟な身体拡張」について次のように書けるのである。
私たちは、物理的であることが身体拡張のリアリティをもたらすと考えがちだが、物理的であることはたまたま身体との連動を作るのに都合が良いだけである。だから、物理的でないものであっても、たとえばカーソルであっても、連動すれば身体拡張と考えられる。むしろ、情報的に拡張する方が質量を伴わないため、柔軟な身体拡張が期待できるのだ。
渡邊恵太『融けるデザイン※31』
「柔軟な身体拡張」を行うためには身体に閉じ込められている「からだ」をそのままにしておかなければならない。それは「自分の身体であるにもかかわらず、自分の思い通りに動いてくれない」とヒトが感じるような状況を回避するためである。その上で、身体とデジタルオブジェクトとの連動を「自分の身体が思い通りに動くという鋼の囲い」に入れてはじめて、「柔軟な身体拡張」が行われる。さらに、その鋼の囲いのなかでヒトとコンピュータとの連動で生じる「自己帰属感-所有感」の配分を上げ下げすることで、情報的で質量を伴わない「光学的身体」がヒトとデジタルオブジェクトの連動に介入して、デジタルオブジェクトに対する感触が生まれるのである。
スワイプと「皮膚としての身体」
これまでカーソルについて考えてきたが、カーソルは画面上に常に見えていて、ミニマルセルフを情報的に拡張可能にする媒介的存在だった。しかし、タッチパネルになるとカーソルは画面から消えてしまった。渡邊はiPhoneではカーソルがなくなったが、「自己帰属感-所有感」は引き続き残っているとしている。そして、カーソルの代わりにヒトと連動するようになったものとして「画面」を挙げている。
それは「画面全体」である。たとえばiPhoneのホーム画面は指に追従し、アプリケーションリストが左右に移動する。ウェブブラウザでは画面全体が指に追従しスクロールする。カーソルはないが、カーソルと同じレベルでiPhoneの画面は非常になめらかに連動している。この連動が画面の中と指を接続し、自己帰属感が生起して身体の一部となり、ハイデガー的に言えば、道具的存在になるのだ。
渡邊恵太『融けるデザイン※32』
確かにiPhoneの画面に表示されているデジタルオブジェクトは指によく連動している。しかし、私の手は「私の手」であってカーソルではないし、画面全体もまたカーソルではない。ミニマルセルフの情報的現れだったカーソルがなくなっているのだから、ヒトとコンピュータとのあいだに現れるミニマルセルフにも変化があるはずである。第一、iPhoneなどのタッチパネルに触れる手と画面との連動は、手とカーソルのような思い通りの連動ではない。手と連動してカーソルが情報空間を縦横無尽に動くのに対して、スマートフォンで手と連動する画面はその自在な動きの全てに連動するわけではない。
例えば、iPhoneのホーム画面に現れる指と画面との連動を記述してみよう。右にスワイプすると半透明なレイヤーに載ったかたちでウェジェットが現れ、左にスワイプするとアプリリストが移動する。さらに左にスワイプすると半透明なレイヤーと共にアプリライブラリが現れる。上から下にスワイプすると通知センターが現れるが、下から上にスワイプしても何も起きない。しかし、ディスプレイの下端から上にスワイプすると開いているアプリケーションが画面を埋めないかたちで現れて、左右にスワイプできる状態になる。スワイプの位置と方向とで何が起こるのかが変わってくる。何度かスワイプすれば何が起こるか把握できるが、マウスとカーソルとの連動のようなシンプルさはない。同じジェスチャが異なる状況を引き起こすこともある。ジェスチャに対する連動の決定権は、コンピュータ側にあると言わんばかりである。このことを後押しするかのように、画面から放射される光によって、画面に触れる指の影は消去されて、いつもとは異なる様相になっている。
さらに、スワイプという同一の行為で、画面全体を一つのデジタルオブジェクトとして移動できたり、画面の一部に現れているウィジェットの切り替えたり、アプリウィンドウを引き寄せたりできる。スワイプして移動するデジタルオブジェクトの大きさに関わらず、スワイプをしている行為の感触が変わらない。これは、渡邊が「情報的に拡張する方が質量を伴わないため、柔軟な身体拡張が期待できる」と書いていたことに関係するだろう。何をスワイプしても質量を感じないのである。私がスワイプに感じた不安の一つはここにあった。小鷹は私のスワイプに対する不安な感じを受けて「例えば、僕は8年前に初めてiPadを買ってマップで地表面をフリックしたときに無茶苦茶感動したのを覚えてるんだけど、あれは正に「質量ゼロの超弩級の球体を指一本で転がしてる」体感によるものだったと思う※33」というツイートをしている。いかなる大きさのデジタルオブジェクトであっても、指一本で常に同じ感触でフリックしたり、スワイプできてしまうということが「質量ゼロ」の感触をつくるのではないだろうか。
影を消去された指に対して画面全体が連動しはするけれどカーソルほどの連動性はなく、「質量ゼロ」という感触がありながら、スワイプはタッチパネル操作の必須のジェスチャとして受け入れられ、何十億の人たちが日常的に行うものになった。スワイプはカーソルの情報的に拡張されたミニマルセルフという感じではなく、指は指であり、画面が画面であるということ前提にして、多くの人に受け入れられている。だとすれば、スワイプはカーソルとは異なるかたちで「からだ」をうまく使って、ヒトとコンピュータとの連動をあらたにつくっていると考えられる。そこで、スワイプを分析するために、小鷹研究室が考案した「スライムハンド錯覚」を取り上げたい。「スライムハンド錯覚」から生じる皮膚に対する感覚の変化が、スワイプに影響を与えていると考えられるからである。小鷹はこの錯覚について次のように説明している。
スライムハンド錯覚は、一般的なラバーハンド錯覚と同様に、机に向かい合って座る(実験者と体験者の) 2人1組で体験することができます。体験者の前に置かれた鏡の手前側にスライムを、鏡の奥側に体験者の一方の手を添え、体験者は鏡に映るスライムを、ちょうど自分の奥側の手と重なるようにして直視します。この状態で、対面する実験者が、スライムと体験者の手の甲を同時に摘んだり引っ張ったりすると、体験者自身の手の素材感がまるでスライムのような伸縮性のある質感に劇的に変化します。スライムハンド錯覚は、なんといっても、筆者の経験した錯覚の中で最大級に衝撃的な体感を与えるものです。
小鷹研理『からだの錯覚※34』
ラバーハンド錯覚系の実験と同じ構成を持つ「スライムハンド錯覚」は、被験者のほとんどが錯覚を感じると報告されている。私自身も「スライムハンド錯覚」を体験したときに、手の甲の皮膚が思った以上に引っ張られているのを感じたし、鏡に映るスライムという視覚情報にいとも簡単に感覚が騙されてしまうのかと感じた。小鷹は「スライムハンド錯覚」を「人を選ばない錯覚」と呼び、その理由を皮膚にターゲットを絞っているいるからではないかと推測している。「従来のラバーハンド錯覚は、人間の身体を「骨格としての身体」として捉えていた一方で、スライムハンド錯覚は「皮膚としての身体」に照準を合わせます」と述べた上で、小鷹は次のように書く。
人間の身体の空間的な認知のための主要な材料を提供するのは、関節に受容器が存在する固有感覚の仕事でした。ところが、固有感覚は「骨格としての身体」の所在を同定するものの「皮膚としての身体」の所在に関しては、あくまでも無頓着です。この固有感覚の怠慢は特別に責め立てられるべきものではありません。というのも、人間の皮膚が身体の骨格にぴたりと張り付いている限り、皮膚の空間認知は、固有感覚からの情報で代替可能であるからです。
小鷹研理『からだの錯覚※35』
小鷹の指摘は、マウスとカーソルと組み合わせた体験とスワイプなどの指のジェスチャを組み合わせたタッチパネルの体験が、単にデバイスの違いだけでなく、デバイスを使う際に「情報としての身体」で生じる感覚情報の組み合わせも大きく変更されている可能性を示している。マウスとカーソルとの組み合わせでは、「骨格としての身体」が示す固有感覚の曖昧な位置情報と画面上のカーソルが示す正確な位置情報とが「情報としての身体」で重なり合うというものであった。ここで「皮膚としての身体」はマウスを持つ手というものであり、マウスの感触などは単調化されて意識に上がらないものになっていた。しかし、スワイプはカーソルのときには見えていなかったり、見えていたとしても周辺視にあった「骨格としての身体」が視界中央部の画面の上に現れることになる。「骨格としての身体」の固有感覚と視覚による位置情報が視界で重なり合うようになる。ここでは「情報としての身体」における感覚信号の組み合わせの変化は起こりようがない。ここで重要になっているのが「骨格としての身体」と画面上のデジタルオブジェクトのあいだに「皮膚としての身体」が挟まっているということである。「皮膚としての身体」はガラスに触れつつ、コンピュータのための位置情報を生成していく。
皮膚認知を有しながら、空間認知を持たない皮膚は、自己と非自己の中間にある、神経系にとっては半ば「モノ」のような存在であるといえます(筆者は、最近「半自己」という言葉を使っています)。
小鷹研理『からだの錯覚※36』
デジタルオブジェクトとのあいだに半ば「モノ」であり、「半自己」と言える皮膚がある。これらモノでも自己でもないないような中途半端な存在が、視界のなかでデジタルオブジェクトと絡み合うことで「質量ゼロ」のような情報的感触が生まれるのだろう。「皮膚としての身体」を介して生まれる「質量ゼロ」の感触は、「Visual Haptics」が「骨格としての身体」の位置情報と視覚情報とのズレによって、「重さ」や「鈍さ」という感触をつくり出すのとは対照的である。視覚情報と「骨格としての身体」からの固有情報は重なり合って正確な位置情報を意識に入力し続けているとき、「皮膚としての身体」は上記二つの情報から正確に位置を把握されつつ、同時に、タッチパネルに対しても位置情報を入力しながら、それ自体の位置感覚が希薄な状態にある。皮膚が視覚と固有感覚とデジタルオブジェクトとの位置関係を不安定な状態にしていく。この不安定な状態がデジタルオブジェクトに対する「質量ゼロ」の感触を生成すると考えられる。
小鷹は皮膚がつくる不安定な状態において、自己の境界の揺らぎが起こっていると次のように指摘している。
錯覚の個人差は一般に、「自分」に本来属していないものを「自分」として受け入れるか否かに関わる感受性の差異によって説明されています。ところが、皮膚は、そもそもが非自己としての性質を兼ねているため、皮膚を舞台に繰り広げられる奇怪な演出に対して、「それが自己のものか否か」を判定する審査が、ギリギリのところで免責されているのです。
小鷹研理『からだの錯覚※37』
デジタルオブジェクトと私という「自己」のあいだに皮膚という「非自己」があることで、指とデジタルオブジェクトの連動が「自己のものか否か」という判定が免責されていると考えてみるのは、とても興味深いことである。小鷹の皮膚に対する考えに基づいて、ホーム画面のスワイプに対しての「勝手な」連動や何をスワイプしても「重さ」や「感触」が同じで「質量ゼロ」を感じしまうことを改めて分析してみると、スワイプと画面との連動が自分に帰属しているのか、それともコンピュータに帰属しているのかを、皮膚が曖昧な状態のまま処理していると言えるだろう。
スワイプする指は影を失っているという不自然な状態ではあるが、常に見えていて、思い通りに動いている。しかし、指が連動するデジタルオブジェクトの動きは、「自己」とは関係なくコンピュータが決めていく。スワイプでは連動の主導権が曖昧になっているにもかかわらず、そこにあたかも「自己帰属感-所有感」があるかのように感じてしまう。それは、皮膚がスワイプという行為を「自己のものか否か」を決定することなく受け入れ、私も意図してしない連動を受け入れていくからである。スワイプはカーソルのように「皮膚としての身体」の存在を周辺に押しやり、皮膚の感覚を無効化していくのではなく、皮膚感覚の曖昧さを活かして「皮膚としての身体」を媒介として機能させる。その結果として、「情報としての身体」は「物質としての身体」だけでなく、コンピュータが制御する画面とも統合してしまうのである。このように考えると、私がiPhoneのホーム画面のスワイプに感じた違和感と不安は指と画面との連動から生じる「自己帰属感-所有感」が私に帰属するものなのか、コンピュータに帰属するものなのかが曖昧な状態なままで行為が行われ続けることにあったと言える。
ここで興味深いのは、インターフェイスデザインの側からスワイプを見てみると、スワイプによる意図しない連動はインターフェイスの操作感に「ヌルヌル」というあたらしい言葉をもたらしたかもしれないということである。渡邊は次のように書く。
さらに最近では、「ヌルヌル」といった操作感覚もネット上ではよく見かける。これもまた興味深い表現だ。「ヌルヌル動く」という表現は、サクサクより上の評価として使われることが多い。この表現はおそらく、動きの連動が高いことが前提のうえで、自分で操作しているのとは若干違う「すべり」を感じている様子と筆者は考えている。つまり、自己帰属感はあるのだけれど、自分が動かす以上に、より素晴らしく補正されたかのように動いてくれる感触表現ではないだろうか。
渡邊恵太『融けるデザイン※38』
「ヌルヌル」が示す「すべり」は「自分で操作しているのとは若干違う」とされている。自分とデジタルオブジェクトとのあいだに皮膚という自己でもあり、モノでもある存在を介在させることで、自分ではない異物としてのコンピュータを受け入れるための空白ができ「すべり」が生じる。皮膚がつくる「すべり」において、私がこれまで慣れ親しんだ「からだ」の感触と「皮膚としての身体」を利用してコンピュータの情報処理で補正される感触とが組み合わされていく。その結果として、「自己帰属感はあるのだけれど、自分が動かす以上に、より素晴らしく補正されたかのように動いてくれる感触表現」という奇妙な体験をすることになる。
渡邊は「自己帰属感はあるのだけれど」と書くが、スワイプでは主体感、所有感ともに「自己帰属感」がなくなっているのではないだろうか。スワイプでは「皮膚としての身体」がヒトと画面との連動に介入して、「情報としての身体」が画面を統合した瞬間に、連動の主導権の割合がヒトに100%割り当てられなくなり、画面を自在に動かすコンピュータ側にも割り当てられるようになる。だから、ヒトがそうしたいからというのもあるが、画面が「ヌルヌル」と動くから、スワイプを余計に速くしてしまったり、何を意図することもなく何回もしてしまったりするということが起こるようになる。つまり、スワイプは行為の始まりは「自己帰属感」から始まるけれど、知らないうちに「画面帰属感」からも生じるようになっているのである。
「画面帰属感」では連動の主導権がコンピュータに移り、私が行為を起こすから画面が変化するのではなく、画面が変化するから行為が起こるようになる。そして、この連動の主従関係の変化を曖昧にするのが皮膚という「半自己」である。カーソルとの連動とは異なり、画面が自己に帰属するのではなく、自己が画面に帰属するという大きな変化を皮膚という「自己のものか否か」の決定を免責された存在が連動の主導権の割り当ての変化を覆い隠してしまう。だから、ヒトはスワイプにあたかも「自己帰属感」があるかのように感じてしまう。
しかし、「ヌルヌル」と気持ちよく行為と画面が連動しているときに、そこで生じているのは「画面帰属感」であって、スワイプで生じる画面の動きがヒトとコンピュータとを構成要素とするミニマルセルフの輪郭をつくるということが起きている。思い通りに動く影なきヒトの指とコンピュータに制御された画面とのあいだに生じる同時多発的な連動が、自己を画面に帰属させたあたらしいミニマルセルフをつくるのである。