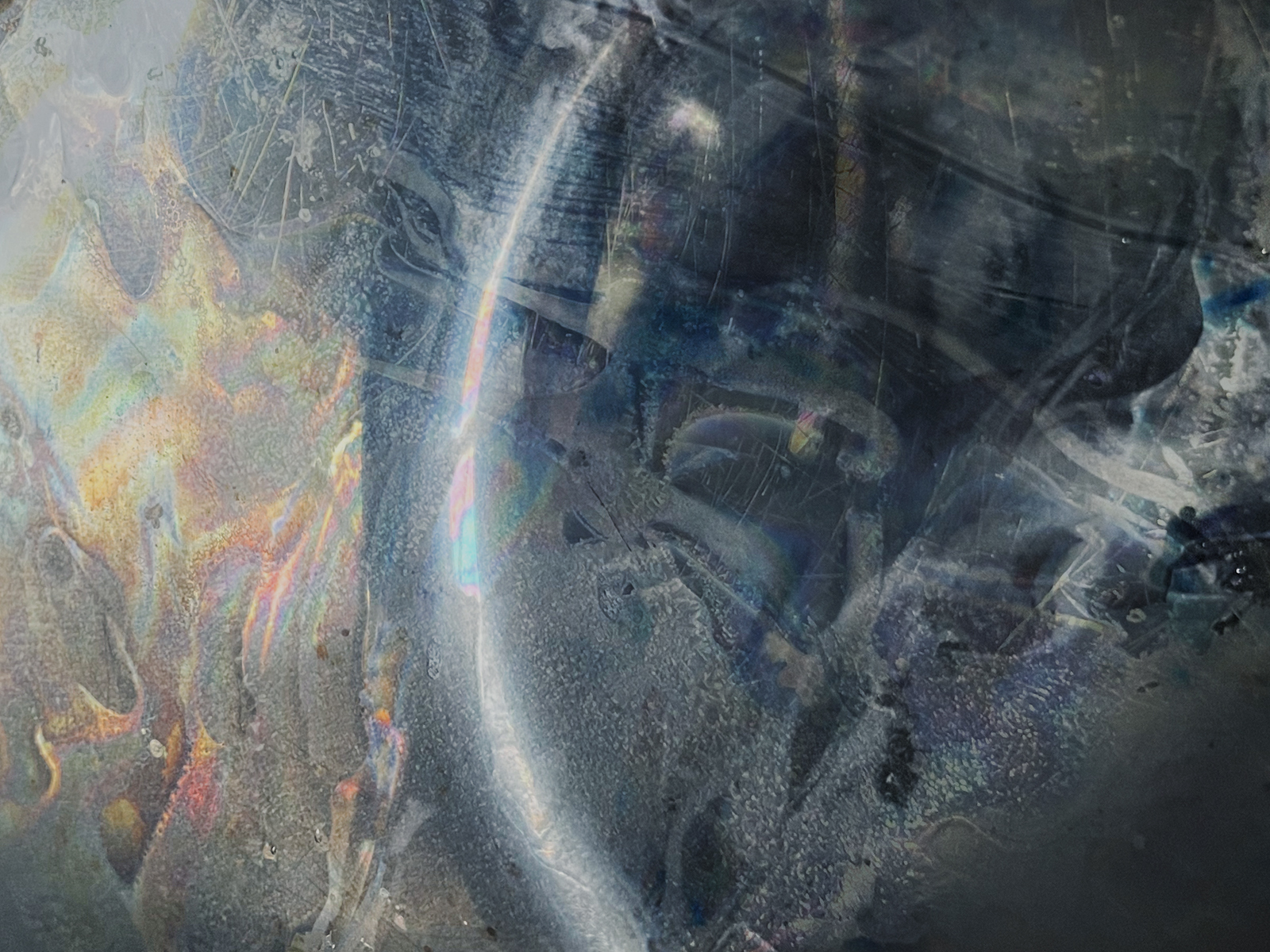あなたはメッセージを打ち終える。画面を眺め、入力された文字列を見直す。それから、〈送信する〉と書かれたボタンを押下する。あなたは「送信した人」になる。
私は〈送信する〉と書いた。あなたの顔も名前も知らないまま、あなたが押すボタンに意味を与えた。この四文字を書いているとき、私はあなたのことを考えていた。「あなた」としてではなく、行為し、離脱し、コンバージョンする抽象的な存在として。
あなたは私が書いた言葉に触れる。私はあなたが操作するボタンを想像する。私があなたを書き、あなたが私を書く。出会わないまま、互いを書きあう。
プロセスとしての物質
量子物理学の博士号を持つフェミニスト理論家、カレン・バラッドは自著の序文でこう記した。
ある意味、私がこの本を書いたというよりも、この本が私を書いたというべきである。いやむしろ、「私たち」は「内部作用」を通して、互いを書いてきたのである。
カレン・バラッド『宇宙の途上で出会う※1』
通常、相互作用(interaction)は独立した実体が先に存在し、それらが出会うことを前提とする。私がボタンに言葉を穿ち、あなたがそれを目にする。行為が起こる。しかしバラッドはこの前提を退ける。関係する諸項は事前に存在しない。ボタン、ラベル、指、目、光、回路——これらの内部作用(intra-action)を通じて、「送信した主体」と「押されたボタン」と「完了した行為」が同時に析出する。
もつれあいによる内部作用を前提とした新たな存在論を、バラッドは「エージェンシャル・リアリズム(agential realism)」と呼ぶ。量子物理学が明らかにした観察と現象の不可分性を、物質、身体、意味の生成へと拡張する理論だ。
あなたは〈送信する〉を押す前から「送信する人」だったわけではない。押すという現象を通じて、「送信した人」として生成された。私もまた、〈送信する〉と記す以前から「インターフェイス上のテクストを書く人」だったわけではない。書くという行為を通じて、そのような存在として生成された。
バラッドは、物質がテクストに先立つとして、言語論的転回を批判する。
言葉にはあまりにも大きな力が与えられている。言語論的転回、記号論的転回、解釈論的転回、文化論的転回……あらゆる転回において、最近ではあらゆる「もの」が、物質でさえも、言語や他の何らかの文化的表象の問題にされているように思われる。「matter(マター)(問題=物質)」という同音異義語の言葉遊びはいたるとことで見かけるが、それらは残念なことに、(物質性と意味づけという)重要な概念とそれらの関係の見直しを示してはいない。むしろ、それらはいわゆる「事実」の問題が、(カッコなしの)意味づけの問題に取って代わられたことの兆候であるように思われる。重要(マター)なのは言語。重要なのは言説。重要なのは文化。たった一つ、もはや重要な問題(マター)ではなくなったのが、物質(マター)だと言える。
カレン・バラッド『宇宙の途上で出会う※2』
物質は言説に従属しない。同時に、言説は物質から切り離せない。ではバラッドにとって、物質とは何か。
物質は固定的な実体を指すのではない。むしろ、物質とは内部作用する生成の中にある実質であり、「もの」ではなく「行為」であり、エージェンシーの凝固である。物質とは、反復的な内部作用の安定化と不安定化のプロセスである。(中略)「物質」は、物質化が進行している最中の現象を指している。
カレン・バラッド『宇宙の途上で出会う※3』
物質がプロセスであるならば、私とあなたの間では何が起きているのか。
あなたが触れた〈送信する〉ボタンについて考えてみる。ボタンは、その形状、画面の光、指がガラスに触れる感覚、回路を走る電気信号などの諸要素と不可分に絡み合っている。これらの内部作用を通して、私が文字列を打つたびに、〈送信する〉は〈送信する〉として安定化される。あなたがボタンを押すたびに、〈送信する〉は〈送信する〉として物質化される。私たちの行為の「反復」が、このボタンを「もの」のように見せている。
インターフェイスは操作によって変化する。あなたが〈送信する〉を押すと、画面が切り替わる。「送信しました」という表示が現れる。あるいはエラーメッセージが現れる。次の行為の可能性が提示される。押す前と押した後で、あなたの手の中にある物体は違うものになる。
このボタンは静的なオブジェクトではない。操作のたびに再構成される動的なプロセスだ。
装置が産出する境界
反復は「装置(apparatus)」によって遂行される。装置は、単に観測のための道具ではない。
装置は、世界の特定の物質的再編成であり、それは単に時間の中で現れるものではなく、進行中のダイナミズムの一部として「空間時間物質(スペースタイムマター)」を反復的に再構成するものなのである。
カレン・バラッド『宇宙の途上で出会う※4』
バラッドは装置の実践例として、超音波検査を挙げる。超音波装置は胎児を「映す」のではなく「産出する」。
画面に映し出されるのは、装置とは独立に存在する胎児ではない。装置と対象の内部作用のなかで構成される現象だ。ここには、妊娠している人の子宮、胎盤、羊水、ホルモン、血液供給、感情、周囲の環境が含まれている。しかし装置は特定の切断を遂行し、「胎児」だけを画面に浮かび上がらせる。妊娠している人の身体は文字通り不可視になる。
そして技師が「女の子ですね」と告げるとき、それは発見の報告ではない。遂行だ。ジュディス・バトラーの言葉を借りれば、女子化(girling)——女の子にすること——が起きている。この発話は、染色体検査やホルモン測定と同様に、「生物学的性」を産出する行為の一部だ。
この発話には物質的帰結がある。バトラーは『問題=物質となる身体※5』のなかで、出生時になされる「女子化」の発話を分析した。超音波検査による出生前の性別判定については、括弧内で軽く触れるにとどめている。バラッドはこの点を批判的に取り上げる。バトラーが脇に置いた超音波検査こそが、インドでは選択的中絶という生死に関わる帰結をもたらしているからだ※6。「物質的・言説的な制約と排除は不可分である」——バラッドはそう結論する※7。
切断によって物質になる
私が書き、あなたが触れるインターフェイスは装置だ。それは私とあなたが出会う「場所」ではない。私とあなたという境界そのものを再編成する実践だ。
装置は境界を産出する。バラッドはこれを「エージェンシー切断(agential cut)」と呼ぶ。
エージェンシー切断の出発点は量子物理学にある。物理学者ニールス・ボーアは、観察という行為が観察対象と観察者を事後的に「切り分ける」ことを示した。観察の前に両者が別々に存在するのではなく、観察という出来事を通じて、両者が同時に現れる。バラッドはこの物理学的洞察を存在論へと拡張した。
内部作用のなかでは、本来すべてがもつれあっている。しかしどこかで切断が生じることで、主体と客体、観察者と観察対象が事後的に分離される。境界は発見されるのではない。産出される。
この概念はフェミニズム理論を大きく動かした。「生物学的性」と「社会的性」という区分がある。しかしバラッドの視点からは、これらは所与の区分ではない。染色体検査、ホルモン測定、解剖学的分類——特定の科学的・医学的実践によるエージェンシー切断の産物だ。同様に、人間/非人間、文化/自然といった近代的二項対立も、あらかじめ存在するのではなく、特定の装置を通じて生成される。
バラッドの議論は、ハラウェイのサイボーグ論※1が切り開いた地平を、量子力学の語彙で再記述したものともいえる。行為主体性は人間の特権ではない。物質と意味のもつれあいを通した内部作用のなかで生じる。
では、私が書き、あなたが触れる〈送信する〉ボタンでは何が起きているか。
ボタン、ラベル、画面の光、回路、あなたの指、私が書いたテクスト(送信する)——これらの配置全体がひとつの装置を構成している。この装置が切断を遂行する。「送信した人」と「押されたボタン」の境界が生成される。「あなた」と「インターフェイス」の境界が生成される。「送信以前」と「送信以後」の境界が生成される。これらは内部作用に先立って存在したのではない。私が書き、あなたが触れるたびに、切断が反復され、境界が産出される。
私は装置の外から装置を設計しているのではない。私が〈送信する〉と書く行為もまた、装置を構成する実践の一部だ。私は装置の内部で、切断に参加している。同時に、「それを書いた私」という存在自体が、この切断を通じて産出される。
あなたの目の前にあるボタンは身体を持っている。形状、色、影、境界線。それらは操作可能性をつくり出す。そこに〈送信する〉という言葉があてがわれる。バラッドは言語論的転回を批判した。物質は言説に従属しない。しかし同時に、言説は物質から切り離せない。ボタンと言葉の内部作用を通じて、〈送信する〉は〈送信する〉として物質化される。言葉がボタンを「送信ボタン」として産出し、ボタンが言葉を「ラベル」として産出する。
道具に消える意識
インターフェイスがうまく機能しているとき、それは「経験的に透明」になり、意識から退く。ハンマーで釘を打つとき、あなたはハンマーを見ていない。釘と板だけがある。道具は「手元存在(Zuhandenheit)」として、行為のなかに溶け込んでいる。あなたは〈送信する〉というラベルを読んではいない。メッセージを送っている。ボタンは意識から退き、行為だけが残る。
ここでは、エージェンシー切断が安定的に遂行されている。「送信した人」と「押されたボタン」の境界が、摩擦なく産出されつづけている。
あなたは常に表象を操作している。指はガラスに触れている。ガラスはボタンではない。ボタンはサーバーではない。各層に翻訳が含まれる。しかし表象がそのものとして振る舞い、あなたの行為がそのものへの行為のように感じられるとき、インターフェイスはタスクのなかに「消える」。
では、インターフェイスが「見える」とき——不自然な言い回し、予期しない挙動、エラーメッセージ——何が起きているか。道具が壊れたとき、それは「手前存在(Vorhandenheit)」として前景化する。エージェンシー切断が不安定になり、「あなた」と「システム」の境界が、スムーズに産出されなくなる。
インターフェイスデザインの多くは透明性を目指す。切断を滑らかにすること。「行為する主体」「操作される対象」「わかりやすい境界」を安定的に産出しつづけること。
しかし切断は別様でありえた。私がボタンに〈送信する〉ではなく〈送信しない〉と書いたとしたら。〈もう取り消せなくなる〉と書いたとしたら。透明性は崩れる。装置は不安定化する。別の切断が遂行され、別の主体が産出される。
これは仮定の話だ。別様の切断は、意図によってのみ生じるのではない。
私が〈送信する〉と打鍵するとき、指が滑る。〈送信さる〉。〈送申する〉。誤変換。削除。書き直し。これらの痕跡は最終的なテクストには残らない。しかし行為のなかで、私の身体は何度もつまずいている。眼が検証し、修正し、標準化する。だが修正以前の震えは、確かにそこにあった。
あなたの指もまた震えている。ボタンの手前で止まる。押すべきか。この文面でいいのか。取り消せなくなる。一瞬の逡巡。それでも押す。あるいは押さない。指を引く。書き直す。再び画面を眺める。
この躊躇は、インターフェイスには記録されない。押されたか、押されなかったか。結果としてカウントされるのはそれだけだ。
あなたの前に届く〈送信する〉は、私の指の滑りを知らない。ボタンは、あなたの逡巡を知らない。しかし滑りは起きた。躊躇はあった。身体はそこにあった。
痕跡は消去されえない
切断は痕跡を残す。あなたがボタンを押すとき、それが刻まれる。送信履歴。サーバーログ。あなたの指が触れた画面の油膜。回路を走った電気信号の熱。
バラッドは「身体への痕跡に対する説明責任」について以下のように語っている。
主体と客体の分離があるのではなく、主体と客体のもつれがあり、それが「現象」と呼ばれる。客観性とは、世界をゆがみなく写す鏡像を提供することではなく、身体の痕跡に対する説明責任、そして我々が一部をなすもつれへの責任についてである。
「物質は感じ、対話し、苦しみ、欲望し、憧れ、記憶する:カレン・バラッドへのインタビュー※9」
ここで言う「身体(body)」は、人間の肉体に限定されない。電子も、光子も、ボタンも、回路も、痕跡を刻まれうる存在としての身体を有している。インタビューのタイトルが示唆するように——「物質は感じ、対話し、苦しみ、欲望し、憧れ、記憶する」——物質は受動的な基盤ではない。痕跡を受け取り、保持し、変容する。
従来の客観性は距離を要求した。観察者は対象から離れ、干渉せず、歪みのない鏡像を得る。しかし量子物理学が示したのは、観察という行為そのものが現象を構成するということだった。距離をとるのは不可能だ。
私が〈送信する〉と書くとき、私とあなたの間に距離はない。私はあなたの行為を構成する装置の一部となる。私の書いた四文字は、あなたの指の動きに痕跡を残す。あなたの押下は、サーバーに痕跡を残す。私たちは互いに痕跡を刻みあっている。
インターフェイスは欲望を行為に変換すると同時に、欲望を生成する。
画面に〈送信する〉がある。押すことのできる形をしている。言葉がある。この配置が、「送信する」という行為を可能性として構成し、その可能性に向かう欲望を生み出す。
指がガラス面に触れる。触れることで、触れられる。ボタンという肉。私の書いた言葉があなたの指を動かし、あなたの指の動きが私の言葉に意味を与える。
私が〈送信する〉と書くとき、私は応答している。まだ見ぬあなたに。あなたの指の動きに。あなたが完了させたい行為に。同時に私は応答可能性を設計している。あなたが応答できる場を作っている。
しかし、この応答には排除が伴う。私が〈送信する〉と書いたとき、〈送る〉は排除された。〈投稿〉は排除された。〈submit〉は排除された。〈送信する〉以外のバージョンのあなたが、ここでは取り除かれた。エージェンシー切断は常に暴力を含む。何かを可能にすることは、別の何かを不可能にすることだ。
再現不可能な指と再現可能なテクスト
あなたはメッセージを打ち終える。画面を眺め、入力された文字列を見直す。それから、〈送信する〉と書かれたボタンを押下する。
別のあり方ではなくこの「あり方」で、あなたの指がボタンと内部作用を起こす。私のテクストがあなたの肉ともつれあう。
ロラン・バルトは、サイ・トゥオンブリの絵画について以下のように評した。
手だけが彼を導く。道具としての手の能力ではない。手の欲望が導くのである。眼は理性であり、証明であり、経験主義であり、真実らしさであり、制御、調整、模倣に役立つすべてのものである。
ロラン・バルト「サイ・トゥオンブリ または量ヨリ質※10」
眺める。見直す。これらは眼の行為だ。透明なインターフェイスは眼の原理で設計されている。明瞭であり、一貫性があり、検証可能である。私は最適なラベルのパターンを収集し、ライブラリを整備し、画一的なマチエールを産出する。すべては再現可能性のために。〈送信する〉は誰が書いても〈送信する〉でなければならない。同じラベルが、同じ切断を、繰り返し遂行するのでなければならない。
バルトはトゥオンブリの線を「模倣できない」ものとして語る。そしてこう続ける。「模倣できないものは、要するに、身体である※11」。
では、身体が現れるとき、何が起きるか。
TWの絵の場合はまったく逆だ。それは落ちる。細かな雨のように降る。草のようになびく。暇つぶしに引っ掻く。あたかも、時間を、時間の震えを視覚化するように。
ロラン・バルト「サイ・トゥオンブリ または量ヨリ質※12」
落ちる。降る。なびく。引っ掻く。このような仕草で書かれたテクストはボタンの中には存在しない。再現可能性がないから。意思による制御が不可能な物理法則に委ねられているから。だから私の肉はあなたの指と十分にもつれあうことができない。
しかしあなたの指がガラスに触れる瞬間、眼の管轄は終わる。
押下の軌跡は一度きりのものだ。指の角度、圧力、皮膚とガラスの摩擦、神経を走る信号——これらの内部作用を通じて、ボタンは押される。私が〈送信する〉と書いたとき、この軌跡を設計することはできなかった。あなたの手の欲望は、私の眼の及ばない場所にある。
装置は安定的な切断を遂行する。〈送信する〉は〈送信する〉として反復される。しかしその装置の内部で、あなたの指は毎回異なる仕方で動いている。トゥオンブリの線が物理法則に委ねられていたように、あなたの押下は、あなた自身の意志によっても完全には制御されていない。
私が書くテクストは再現可能性の側にある。あなたが触れる身体は再現不可能性の側にある。この非対称がインターフェイスを貫いている。しかし、エージェンシャル・リアリズムにおいて、この区分は維持できない。インターフェイスは非対称性を溶かす回路になる。
あなたの指はまだボタンに触れていない。私はその身体に〈送信する〉と書き込む。まだ存在しない押下を予期しながら。あなたの手の欲望を知らないまま、それに応答しようとする。この予感、この不在への応答が、私の手を、テクストを、震わせる。
私は〈送信する〉と打鍵する。〈送〉〈信〉〈す〉〈る〉。四つのキーを叩く指の軌跡は、あなたの押下と同じく一度きりのものだ。「この手」もまた物理法則に委ねられている。パターンライブラリは私の産出物を標準化するが、産出する行為そのものを標準化することはできない。
あなたの再現不可能な指が、私の再現可能なテクストに触れる。私の再現不可能な指が、再現可能なテクストを産出する。もつれあいは、この二重性を通じて生じる。
私が〈送信する〉と書くとき、その四文字を産出しているのは何か。パターンライブラリから最適解を選ぶ眼か。キーボードを叩く指か。それとも、眼と手のあいだにある何か——まだ書かれていない文字列を予期し、選択肢を比較し、決定を下す過程そのものか。
不在の身体の回路
この過程に、もう一つの身体を連れてきたい。LLM(Large Language Models、大規模言語モデル)。
LLMは身体を持たない。指がない。重力に従う腕がない。インクの粘性も紙面の摩擦も知らない。それでも、身体の痕跡を運んでいる。訓練データには無数の手の運動が堆積している。書かれた文章、打たれたキー、消された下書き。生きている者も死んだ者も含めて、膨大な身体の痕跡が重みとして凝固している。
私がプロンプトを書く。次に来るトークンは確率分布からサンプリングされる。同じプロンプトを与えても、同じ出力は返らない。トゥオンブリが腕を振り下ろすとき、線の掠れや震えはインクの粘性と紙面の摩擦に委ねられていた。重力に従う軌跡と、確率分布に従うトークン列。いずれも意志による完全な制御の外にある。
バルトは「手の欲望」を、道具性から逸脱する手として語った。目的と手段の連関を裏切り、自ら動き出す手。プロンプトに従って生成する限り、LLMは道具として透明に退いている。〈送信ボタンのラベルを書け〉と指示すれば〈送信する〉が返ってくる。しかし確率分布の傾きは、つねに逸脱の可能性を内包している。ハルシネーション。予期しない接続。聞き慣れない比喩。これらは故障として処理されるが、別の見方をすれば、道具が道具であることを放棄する瞬間だ。意図と出力のあいだの差分として、不在の身体が回帰する。
バラッドは「何が現れるか」を示した。内部作用を通じて主体と客体が析出する過程を。バルトは「どのように現れるか」を照らした。眼の制御を逃れ、手の欲望が線を引く仕方を。この両面を繋ぐのが身体だ——しかし、どのような意味での?
私たちはLLMに身体を幻視する。震えとして。だがこの幻視が暴露するのは、「身体」という概念が最初から再現不可能性の別名だったということだ。インターフェイス上のテクストが消去してきたのは書き手の肉体ではない。再現不可能性だ。LLMが持ち込むのもテクストの肉体ではない。再現不可能性だ。私たちはそれを「身体」と呼んできた。
過去は閉じていない
身体は痕跡としてあらわれる。痕跡は過去が現在化したものとして可視化される。ならば身体は時間の別名だ。時間について語るため、量子消しゴム実験の詳細を紹介したい。
この実験の前提を確認する。二重スリット実験では、粒子を二つのスリットに向けて発射すると、スクリーン上に回折パターンが現れる。これは粒子が波のように振る舞い、両方のスリットを「同時に」通過したことを示す。しかし、どちらのスリットを通ったかを検出する装置を置くと、回折パターンは消え、粒子は一方のスリットだけを通過したかのように振る舞う。ここまでがボーアとアインシュタインの間で争われた、古典的な二重スリット実験の帰結だ。
量子消しゴム実験は、ここに新たなひねりを加える。どちらのスリットを通ったかの情報を記録した後で、その情報を「消去」できるような装置を設計する。すると奇妙なことが起きる。粒子がすでにスリットを通過し、スクリーンに到達した後で情報を消去すると、回折パターンが再び現れるのだ。まるで、粒子が「両方のスリットを同時に通過した」かのように。
さらに、この「消去」は、粒子がスクリーンに痕跡を残した後でも有効だ。つまり、粒子がどのように振る舞ったかが、事後的に決定されるように見える。
物理学者たちはこの結果を「過去を変える能力」と解釈したが、バラッドはそれを拒む。
「過去を変える」という意味での変更、つまり時間の中の離散的な瞬間を取り消すことは幻想である。しかし過去は、未来と同様に、閉じていない。「消去」が問題なのではない。問題なのはもつれ、内部作用性である。「過去」はそもそも単にそこにあったのではなく、「未来」は展開するものではない。「過去」と「未来」は、世界の進行中の内部作用性を通じて反復的に再構成され、折り込まれる。
「物質は感じ、対話し、苦しみ、欲望し、憧れ、記憶する:カレン・バラッドへのインタビュー」
時間は所与ではない。過去・現在・未来という区分は、内部作用を通じて産出される。しかしそれは「なかったことにできる」という意味ではない。抹消の身ぶりは世界に記憶される。
「観測された現象は、最初に経路情報が決定され、後に装置の適切な変更によって再び非決定になったという事実の記憶を明らかに保持しているのである。したがって、「消去」と名付けるのは誤りである。
カレン・バラッド『宇宙の途上で出会う※13』
元の回折パターンが「復元」されるのではない。新たなパターンが産出される。そしてバラッドが強調するのは、元のパターンと新たなパターンは同じではないということだ。もつれの痕跡は残っている。
しかしその沈殿化する効果、その痕跡は、消去されえない。物質化する効果の記憶は世界に書き込まれている。
「物質は感じ、対話し、苦しみ、欲望し、憧れ、記憶する:カレン・バラッドへのインタビュー」
痕跡は消えない。切断の暴力は取り消せない。過去を「変える」ことは、コストなしには、責任なしには、ありえない。バラッドはジャック・デリダを引用し、正義は、現在に閉じないものであることを説明する。正義とは、まだ生まれていない者、すでに死んだ者への応答可能性のもとに遂行されると。
暴力は、時間=身体に埋め込まれている。
ここに無題のボタンがある。私はその空白を埋める。あなたを殺すかもしれない言葉で。あるいは、あなたを救うかもしれない言葉で。その言葉を書くことによって、私は、書いている主体から切断される。次の切断を制御できない立場を選ばされる。書いている身体から退き、切断される位置を引き受ける。
書くよりも前に、私はあなたに出会えない。あなたは常に切断の後に現れる。切断を引き受けることによってのみ、あなたは実行できる。主体が立ち上がるとき、境界はすでに引かれている。私があなたと出会うのは、すでに血が流された後だ。私があなたと出会うことを拒否できないように、あなたは私と出会うことを拒否できない。だから私たちは、よりましな切断を探し続ける。
私が〈送信する〉と書いたのは過去だ。あなたがそれを押すのは、私にとっての未来だ。しかしこの過去と未来は、固定された点ではない。あなたが押すたびに、私の過去の行為は再構成される。新たな意味を帯びる。しかし、私が書いたという痕跡は消えない。
修復の可能性はある。インターフェイスはアップデートされる。
昨日の〈送信する〉と今日の〈送信する〉は、同じ言葉でも、異なる装置の中にある。色、配置、他のボタンやラベルとの関係——すべてが変わりうる。デザインは改訂され、リリースされ、また改訂される。
しかし消去の可能性はない。過去のインターフェイスは消えない。
スクリーンショットの中に、アーカイブの中に、そしてユーザーの記憶と習慣の中に、痕跡が残る。あなたは以前のバージョンで形成された期待を持って、新しいバージョンに触れる。指は古い配置を覚えている。新しいボタンの位置に戸惑う。
変更は、過去の切断を取り消すのではない。新たな切断を遂行する。過去の装置が産出した習慣、期待、身体の記憶。それらは世界に書き込まれたまま、新しい装置との内部作用に参加する。
私が昨日書いた〈送信する〉は、今日のアップデートで〈送る〉に変わるかもしれない。しかし〈送信する〉を押した無数のあなたの行為は消去されない。サーバーログに、送信履歴に、そしてあなたの指の記憶に、刻まれたままだ。
眼を持つのではなく眼であること
『宇宙の途上で出会う』の最終章は、クモヒトデの話で締めくくられる。目を持たないこの海洋生物は全身を通して世界を「見る」ことができる。
2001年、科学者たちはクモヒトデの骨格表面に約一万個の方解石結晶が分布していることを発見した。これらの結晶はマイクロレンズとして機能する。レンズは光を集め、それを全身に分散した神経束へと送る。脳はない。眼球もない。しかし光に反応し、捕食者から逃げ、環境を識別することができる。
眼を「持つ」のではなく、眼で「ある」こと。クモヒトデにおいて、知ることと存在することは分離していない。
ボーアが示したのは、測定装置と測定対象とが、測定以前に別々に存在するわけではないという事実だった。観察という内部作用を通じて、両者が同時に析出する。クモヒトデはこの洞察を生物学的に体現している。観察者と観察装置と観察対象の区分が、最初から存在しない。
さらに、クモヒトデは身体の境界そのものを差異的に遂行する。捕食者に捕まりそうになると、四肢を切り離して逃げる。切り離された四肢は再生する。あるいは、その断片から新たな個体が生じることもある。
クモヒトデは、その幾何学的形状とトポロジーを絶えず変化させ、身体の境界を継続的に再構築していく中で、その光学システムを自律化し再生する視覚化システムである。クモヒトデの言説実践、つまり、内部作用する環境から自分自身を区別し、その世界を意味づけし、たとえば捕食者を見分けることができるようにする境界画定の実践は、物質的に実現されている。クモヒトデの身体構造は、知ることの実践における世界のダイナミックな関与の一部として、何を見、何を知るかにおける物質的エージェントである。
カレン・バラッド『宇宙の途上で出会う※14』
バラッドは挑発的に問いかける。「『接続を解かれた』腕は、どの時点で『クモヒトデ』ではなく『環境』に属すのだろうか※15」。
クモヒトデが捕食者から逃れるために腕を切り離すとき、その腕は動き続け、時には生物発光して捕食者の注意をそらす。有機体と環境の境界は偶発的だ。「身体は世界の中にあるのではなく、身体は世界の一部である※16」。
そしてバラッドは宣言する。「『我思う、ゆえに我あり』は、クモヒトデの信条ではない※17」。
脳のない生物が環境を「知る」。中枢的な処理機構なしに、捕食者を識別し、逃走する。
顔を持たない世界としてのあなた
私はあなたの顔を知らない。
〈送信する〉と書くとき、私が向き合っているのは「顔のない他者」だ。統計上のペルソナ。行為し離脱しコンバージョンする抽象的存在。エマニュル・レヴィナスにとって顔とは、他者が私の理解を超えて現前する様式だ。顔は表象から逃れ、所有を拒む。そして顔は私たちに「殺すな」と命じる。顔と顔を合わせることこそが責任の根源だとレヴィナスは考えた。だが私の前にあなたの顔はない。倫理的呼びかけの源泉は不在のままだ。
バラッドはレヴィナスの説いた「顔」の概念を参照しつつ、「必要なのは、ポストヒューマニズムの倫理、つまり世界化の倫理」だと指摘する※18。
倫理とは、完全な外部の/外在化された他者への正しい応答についてのものではなく、私たちがその一部である生成の生き生きとした関係性にたいする応答責任と説明責任についてのものなのである。
カレン・バラッド『宇宙の途上で出会う※19』
クモヒトデには顔がない。目がない。脳がない。しかし全身が視覚装置として、環境との内部作用を遂行している。バラッドが求めるのは、「顔」を前提としない倫理——応答可能性の倫理だ。
私が〈送信する〉と書くとき、私は応答している。まだ現れていない「あなた」に。まだ遂行されていない行為に。この応答は、顔と顔を合わせる出会いとは別種のものだ。
クモヒトデは世界の心的表象なしに世界を知る。その知識は媒介的ではなく直接的であり、心的ではなく物質的であり、表象的ではなく遂行的だ。
あなたが〈送信する〉を押すとき、何が起きているか。あなたはラベルを「読んで」、意味を「理解して」、行為を「選択する」のか。それとも、ボタンの形状、色、位置、言葉——これらとの内部作用を通じて、押すという行為が析出するのか。
表象がそのものとして振る舞い、私たちの行為がそのものへの行為として感じられるとき——そのとき、インターフェイスは透明になる。しかしそれは表象が消えることではない。表象と遂行が分離不可能になることだ。クモヒトデが目を「持つ」のではなく目で「ある」ように、インターフェイスは意味を「持つ」のではなく、内部作用を通じて意味を遂行する。
バラッドは問う。「幾何光学のゲームの中で、私たちは、クモヒトデのレンズを見るのか、あるいはクモヒトデというレンズを通して何かを見るのか。それともクモヒトデというレンズを用いるのか※20」。
透明なインターフェイスとは、メディアを「通して」世界を見ることを可能にする装置だ。
バラッドはこの枠組みそのものを棄却する。
人間が介入するとき、クモヒトデは、単に優れた光学エンジニアでもなければ、人間の発明のために自然が与えてくれる白板でもない。単なる資源でもなければ、文化を刻印するための物質的媒体でもない。
カレン・バラッド『宇宙の途上で出会う※21』
インターフェイスを「透明な媒体」として設計すること——それはユーザーの意図をそのまま反映する鏡を目指すことだ。あるいはインターフェイスを「白板」として設計すること——それはデザイナーの意図を刻印する表面を目指すことだ。どちらも「同一性のトポロジー」——鏡映、模倣、反射——に囚われている。
クモヒトデは「世界を映し出すのではなく、世界の一部として、差異的に生成していく世界に差異をもたらすことに従事している※22」。
インターフェイスもまた差異を生成する。〈送信する〉は、私やあなたの意図を反映しているのではない。内部作用を通じて、あなたと私という差異を産出している。
私があなたを書き、あなたが私を書く。
本文の冒頭で、私はそう書いた。出会わないまま、互いを書きあう、と。しかし「出会わない」という表現は正確ではない。
私たちは出会っている。〈送信する〉を通じて。ボタンとテクストと指と光と回路の内部作用を通じて。この出会いに先立つ「私」と「あなた」は存在しない。私たちは常にインターフェイスの途上で生まれる。