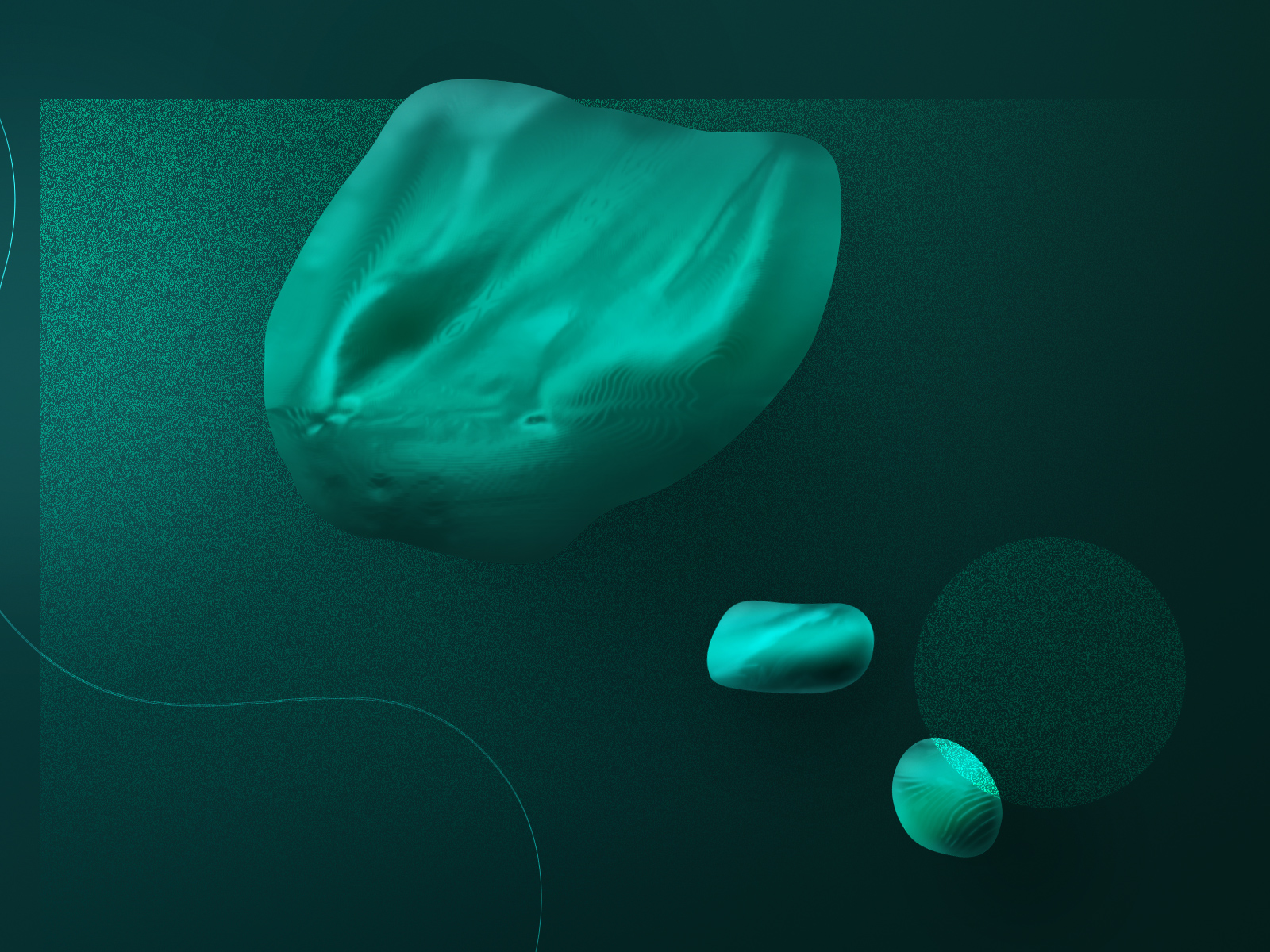意味の連関から生じる「世界適合性」
スキューモーフィズムは「物理世界の表皮」として、スマートフォンのディスプレイに貼りついた。ヒトとコンピュータとの重ね合わせの存在であったカーソルが消失したサーフェイスでは、ヒトは「自分」の場所を確かめるためにマウスを左右に揺らして、カーソルを見つけ出す必要はない。ただ指差したいところを指差せば、そこが「自分」の場所となる。スキューモーフィズムがスマートフォンの画面を覆っているので、モノに触るようにスマートフォンをタッチすれば、機能がダイレクトにフィードバックされる。
けれど、スキューモーフィズムは具体的な存在ではない。物理世界のサーフェイスをディスプレイのXYグリッドで表現してはいるが、それはXYZの三軸で表される三次元の物理空間を、XYグリッドという抽象的な二次元のサーフェイスに展開しているにすぎない。だから、モノは画像に変換され、ヒトはそれを掴もうと思っても掴めずに、ただタッチするのみなのである。スキューモーフィズムのサーフェイスでは、ヒトの行為の可能性はガラスをタッチするように最小化されている。
マルティン・ハイデガーは、ヒトの周囲の事物を連関のなかで捉えて、道具の分析を行った。手元にある道具の連関が世界を形成し、ヒトはその世界の内に存在している。しかし、ヒトは世界のなかにある道具を、意味あるかたちで配置されていた場から外しながら、均質化した自然空間を見出す。
手元的に存在する道具全体で構成されていた「世界」が空間化されて、ただわずかに眼前的に存在するだけの広がりのある事物の連関になる。このように均質な自然空間というものが登場したのは、手元的な存在者の持っていた〈世界適合性〉を固有なしかたで脱世界化しながら、出会ってくる存在者を露呈する方法が確立された後のことなのである。マルティン・ハイデガー『存在と時間』
ハイデガーは世界の空間化を批判するが、この批判はスマートフォンのサーフェイスにも当てはまるだろう。ヒトの手と多様なモノとが持っていた連関を、ガラスとピクセルとが重なり合うサーフェイスが否応なしに消失させていく。コンピュータにはまず均質な論理空間だけがあったことを考えると、それは当たり前の帰結であった。しかし、ヒトとコンピュータとのあいだにインターフェイスを構築する際に、まずコンピュータはヒトの身体をカーソルに変換してXYグリッドに落とし込み、周囲の環境を真似た画像を配置した。そして、メタファーの力がヒトの身体感覚を論理空間に重ね合わせた。その後、ディスプレイの解像度が上がるにつれて、インターフェイスでは物理空間を二次元に変換した「表皮」が論理空間に貼り付けられ、ヒトはそれをダイレクトにタッチするようになった。
スキューモーフィズムによって物理世界をディスプレイに重ね合わせることが可能だったのは、物理空間と論理空間がともに均質な座標空間として、三次元から二次元へと変換処理可能だったからである。しかし、この重ね合わせには、ハイデガーが考えるような道具が構成する意味の連関がない。ピクセルが構成するXYグリッドのサーフェイスで、スキューモーフィズムは物理世界を模倣してはいるが、ハードウェアに囲まれたガラスとのあいだにヒトとモノとが持つような「世界適合性」はなく、ただ重なり合っているのである。
けれど、均質な論理空間に小さいながらもハードウェアとソフトウェアとが緊密な意味の連関を形成して、「世界適合性」を示すような場をつくるのが、フラットデザインやマテリアルデザインなのではないだろうか。フラットデザインとマテリアルデザインは、ヒトの感覚や自然空間を模倣せず、均質な空間に意味の連関をつくりだそうとする試みだと考えられる。その意味の連関は、ハードウェアとソフトウェアとがヒトに向けて開いたサーフェイスであるガラスとピクセルとのあいだで起こっている。
スマートフォンのサーフェイスでは、ソフトウェアとハードウェアとが単に座標空間として重なり合うのではなく、意味の連関をつくりながら「世界適合性」を持ち始めようとしている。それは物理空間と論理空間とのあいだに単なるデータの流れができるだけではなく、それらが意味あるかたちで重なり合い、世界に配置されることを意味する。ソフトウェアとハードウェアとの意味ある重なり合いによって、ヒトの手とモノとが持っていた多様な連関の消失が回復するわけではない。しかし、それによってヒトの行為の可能性が別のかたちで開かれていくのである。
ガラスとピクセルとの連関
メディア理論家のデイヴィッド・M・ベリーは「Flat Theory」で、レティナ・ディスプレイ以後は、モバイルデバイスが「場所の感覚と同様に、リアルタイムで流れていく情報とデータの管理の感覚」を提供していると述べた。AppleのフラットデザインとGoogleのマテリアルデザインは、ともに高精細なディスプレイを用いて、複数のデータの流れを小さなディスプレイで処理していく。そして、モバイルデバイスの限られた配置のなかで、「双方のアプローチはレイアウト、モンタージュ、コラージュの技術を組み合わせ、コンピューテーショナル・サーフェイスの上に集約的なインターフェイスと呼びうるものを作成する」とベリーは指摘する。
彼が「コンピューテーショナル・サーフェイス」と呼ぶのは、コンピュータが膨大な量のデータを処理して形成するものである。コンピューテーショナル・サーフェイスの下にソフトウェアのレイヤーがあると書かれていることから、このサーフェイスはインターフェイスと同等の存在だと考えられる。しかし、コンピューテーショナル・サーフェイスの上に「インターフェイス」を作成するとも書いているので、ベリーはこのサーフェイスをインターフェイスの基底面として想定していると言える。ソフトウェアと直結したコンピューテーショナル・サーフェイスの上にインターフェイスが構築され、その上にハードウェアのガラスがある。そして、コンピューテーショナル・サーフェイスとガラスとのあいだに意味あるかたちでZ軸を導入し、ソフトウェアとハードウェアとの連関を全面に出したのが、フラットデザインとマテリアルデザインなのである。
Appleは一連の概念を使用して、美的整合性、一貫性、ダイレクト操作、フィードバック、メタファー、ユーザーコントロールなどのフラットデザインの概念を結び付ける。 このあたらしいフラットユーザーインターフェイスの触覚体験を強化することは「最初のポスト・レティナ(ディスプレイ)UI(ユーザーインターフェイス)」を開発するために「ガラスに触れる」体験を構築するものとして記述される。 これは、Z軸層の論理的な内部構造を通してインターフェイスの要素が描かれたガラス層であり、層状の透明性の概念である。このラミネート構造はコンテンツと情報処理もしくはユーザインターフェイスシステム自体の双方に関して、Z軸の組織化を通じての意味の伝達を可能にする。David M. Berry “Flat Theory”
フラットデザインにおいて重要なのは、「ガラスに触れる」というハードウェアがもたらす体験とソフトウェアがつくるZ軸をうまく使った体験であると、ベリーは指摘する。iPhoneのiOS7から導入されたフラットデザインでは、ヒトがガラスに触れていても凹凸はないから、ボタンも影もなくなった。アプリ内でのZ軸は0であり、すべてはガラスに描かれているようにフラットになった。同時に、画面上部からスライドすると通知センターが描写されるように、層の重なりが生じる場合は、半透明の「磨りガラス」のような平面を用いることでZ軸を表現している。ハードウェアで触れているガラスに合わせて、Z軸のあり方が決定されている。その結果、「どこを押していいのかわからない」という問題が生まれた。
この問題が示しているのは、ヒトはガラスに触れているが画面のなかのボタンを凹凸で判断していた、ということではない。ヒトとの関係ではなく、あくまでもガラスというハードウェアとの関係で、ソフトウェアのZ軸のあり方すべてを決定したサーフェイスが生まれていたということである。その結果、あらたなハードウェアとソフトウェアとの関係について、ヒトの認識に戸惑いが生じたのである。
マテリアルデザインは、フラットデザインでのヒトの戸惑いを解消するように、Z軸の設定を行なっている。
マテリアル環境では3D空間、つまりすべてのオブジェクトがX、Y、Z軸の方向を持つ空間です。Z軸は表示されている平面に対して垂直に配置された軸であり、Z軸の正の値が閲覧者に向かって伸びています。マテリアルのシートはそれぞれZ軸に沿って1点の位置を占め、標準で1dpの厚さを持つようになっています。マテリアルデザインガイドライン
マテリアルデザインはZ軸を厚さとして設定し、ピクセルに1dpの厚さを持たせた。ソフトウェアに直結したピクセルという理念的な存在に、モノのように厚さを設定することで、ピクセルを「マテリアル」として扱うのである。デザイナーの深津貴之は次のように、マテリアルデザインについての鋭い解読を行なっている。
特筆すべき点は徹底した意味の付与であり、決定的なのが画面を構成するピクセルへの考え方である。マテリアルデザインでは、ピクセルを厚みのある物理的な存在(マテリアル)と解釈する。厚みを持ったピクセルは変形可能なカード、あるいは、模様が自在に変わるインクとして扱われる。前後の重なりに応じて影が発生し、アニメーション時には質量を持ったものとして加減速しながら移動する。つまりビジュアル上はフラットデザインであるが、概念や挙動としては物理世界の拡張シミュレーションなのだ。画像がフラットなのは、ドロップシャドーをクリック領域や階層構造に集中させるためにすぎない。iOS7は抽象化のためにスキューモーフィズムを捨て去った。だがマテリアルデザインでは、視覚的にこそ抽象化したものの、動きや挙動のルールにおいて、逆に強くスキューモーフィズムを彷彿とさせる。「厚さのあるピクセル」は現実には存在しないマテリアルである。だがマテリアルデザインは、「厚さのあるピクセル」が現実にあった場合にどのように挙動するかをシミュレートしたデザインなのである。深津貴之「マテリアルデザインとその可能性」
マテリアルデザインは「徹底した意味の付与」によって、「厚さのあるピクセル」という現実には存在しないマテリアルを実在させてしまう。マテリアルデザインの設計に大きく関わっているマティアス・デュアルテが、「多かれ少なかれ、すべて手に持ったデヴァイスの厚さの中に収まるようにしたかったんです」と述べるように、ソフトウェアがつくる「厚みを持ったピクセル」というあたらしいマテリアルには、ソフトウェア内の意味の連関だけでなく、ハードウェアの厚さとの関係も想定されているのである。
フラットデザインとマテリアルデザインはこのように、ソフトウェアとハードウェアとのあいだのZ軸を中心に意味を持つあらたなサーフェイスとして設計されている。そこでは、ヒトの行為に対してではなく、まずはそれぞれのデザイン原理に対して一貫性を持つことが考えられており、フラットデザインでは「ガラスに触れること」、マテリアルデザインでは「1ピクセルの厚みを持ったピクセルの振る舞い」が重要となっている。
このようにして、フラットデザインとマテリアルデザインはZ軸に意味を持たせ、ガラスとピクセルとのあいだに意味の連関をつくった。ハードウェアとソフトウェアとのあいだに意味の連関が生まれることで、物理空間に位置するハードウェアのなかに、ソフトウェアが意味を持って配置されるべき場が空けられるようになったのである。コンピューテーショナル・サーフェイスの下にあったソフトウェアが、ハードウェアとともにサーフェイスとして物理空間に配置され、あたらしい体験をつくっていく。
Googleの重要な基準はヒト向けのデザインに傾いている傾向があるのに対して、Appleはユーザに現実を真っ直ぐ直視させる傾向がある。 どちらの会社も、画面を手に持っているような感じの触覚的なOS体験を生み出すことが正しいと考えている。“Google’s Material Design vs Apple’s Flat Design: Which is better?”
物理世界の模倣ではなく、場を与えられたソフトウェアによるあらたな体験とともに、ハードウェアの体験も更新される。ハードウェアが主導するのでもなく、ソフトウェアが主導するのでもなく、ハードウェアと連関するなかで場を持ったソフトウェアが、モノと連関するヒトと連関していき、あたらしい体験をつくる。その結果として、ハードウェアだけでなくOSというソフトウェアの部分にも触れているような体験が生まれるのである。ソフトウェアを覆っていたハードウェアをソフトウェアが覆いはじめ、ソフトウェアとハードウェアとが一つのサーフェイスになっていった。
メタマテリアル化するサーフェイス
椅子やハンマーといったプリミティブな道具ではそのもの全体が利用者との接点になるが、構造が複雑になり内部の機構と外装が分離して、操作部が独立して設計されるようになると、そこにユーザーインターフェースという概念が出現する。抽象物を成分とするソフトウェアにおいては、その働きと我々のファジーな認知を仲介するものとして、ユーザーインターフェースの役割が特に重要になる。
コンピュータを使えば人の五感に向けたフィードバックを動的に作り出すことができるので、ユーザーインターフェースの独立性は一層増す。道具の内部機構に対してユーザーインターフェースが独立するということは、意味空間を自由に作れるということである。上野学「エントロピーとデザイン」
コンピュータが現れたことで、モノと行為とのあいだに「インターフェイス」という概念が現れた。しかし、フラットデザインとマテリアルデザインの試みは、道具の内部機構と外装とを統合してサーフェイスとするものである。スキューモーフィズムですでにインターフェイスはサーフェイスになっていたが、そこでは物理世界の表皮がピクセルに貼り付けられており、ソフトウェアとハードウェアの連関というよりは、ソフトウェアがハードウェアを通り越して、物理世界そのものに意味を求めたと言えるだろう。ヒトの理解のため、ソフトウェアは一足飛びに物理空間を外装としたのである。
けれど、フラットデザインとマテリアルデザインでは、ハードウェアとソフトウェアとのあいだに意味の連関がつくられるため、スキューモーフィズムでソフトウェアに外装として採用された物理空間はスマートフォンのサーフェイスに入り込めない。スマートフォンは物理空間と座標変換可能な二重化した外装を持つのではなく、ハードウェアとの連関のなかでソフトウェアがハードウェアを包み込み、一つのサーフェイスになる。そして、スマートフォンは物理世界におけるあたらしいプリミティブなモノとなった。
その代償として、インターフェイスの独立性はなくなり、意味空間が自由につくれなくなる。これまでは、ハードウェアを内部機構とする外装としてのソフトウェアがあり、外装としてのソフトウェアもまた内部機構と外装とに分かれ、必要に応じて外装としてのハードウェアをつくり変えた。そして、ソフトウェアとハードウェアはどちらも互いの内部機構になり、外装となることを繰り返してきた。それはインターフェイスが持つ独立性ゆえであった。しかし、フラットデザインとマテリアルデザインは、ソフトウェアがハードウェアとの連関のなかで、その独立性を放棄してまで、ハードウェアを覆うサーフェイスとなったのである。ハードウェアとの連関から生まれるソフトウェアがサーフェイスとなっているモノは、これまでとは異なる意味でのプリミティブなモノとなっている。それは、その自由さゆえに位置付けが難しかったソフトウェアが、ヒトとモノとの連関のなかに確かな場を得たはじめてのモノなのである。
ハードウェア、ヒトとの連関においてソフトウェアに空け渡された場は、もちろん物理空間のなかにあり、またコンピュータネットワークにおけるノードでもある。ソフトウェアに空けられた場には、さまざまな空間や場が重なり合っている。空間と場の重なりのなかで、ソフトウェアはハードウェアとの接着において、ヒトの行為とその可能性をこれまでにないかたちで反射、吸収、屈折していくあらたなサーフェイスとなっている。それは「メタマテリアル」とでも呼べるような新奇の擬似的なモノだろう。
メタマテリアルとは、ナノサイズの金属構造を用いて人工的に新奇な電磁気学的特性を付加した擬似物質です。メタマテリアルのメタは「超」を意味する接頭語です。メタマテリアルを利用すると、光の磁場成分に直接応答する物質など、自然界に存在する物質にはあり得ない特性を持つ物質を作り出すことができます。田中拓男「知っておきたいキーワード:メタマテリアル」
ハードウェアとソフトウェアとが意味の連関を持つことで、ソフトウェアに場が付与されて「世界適合性」が生まれる。それは、ガラスとピクセルとのあいだが接着され、意味のある「透き間」として実体化し、ヒトの行為の反射率を変更する一つのメタマテリアルとなることなのである。このメタマテリアルは、物理世界とコンピュータの世界という二つの原理を重ね合わせる。そこでは、計算と光、光とガラスが重なり合い、さらにこの二つの重ね合わせ自体が重ね合わされて、あらたな角度でヒトの行為を反射し続ける。
今、私たちのまわりにある壁や天井は、突然消えたりせず、私たちが生きるスパンよりも長くこの環境に存在する持続性があるためにリアリティを持つ。「リアリティ」という言葉は、コンピュータのスクリーン上にいかに本物と同じような見た目の質感をもたらすかを言うことが多いが、持続性に関するリアリティを忘れてはいけない。おそらくリアリティの非常に重要な要素に「持続性」があり、持続性がないことが行為の可能性へも影響し、さらにその点においてもリアリティが低下する。したがって、ディスプレイ上でビットとしての情報提示であっても、持続性による行為の可能性を考えることで、リアリティは確保できるはずだ。
少しまとめると、ものづくり、その「物」という言い方が体験にとっては適切ではなく、持続で捉えるべきだということだ。そしてリアリティは物質性ではなく持続性であるということだ。数百年「物」という状態を当たり前のこととして設計してきたわけだが、ハード、ソフト、ネットを目の前に、まず「物」の定義にメスを入れるべき時ではないだろうか。渡邊恵太『融けるデザイン』
場を与えられたソフトウェアはメタマテリアルのようにモノの性質を変えるだけでなく、その概念を変えていく。ハードウェアとの意味の連関を持ったソフトウェアは、渡邊が指摘するような「持続性」を持つようになったと言える。ハードウェアの上に成立していたソフトウェアがハードウェアを包み込むサーフェイスとなることで、モノと情報とが持続的に絡み合う場が生まれ、マテリアルデザインにおける「厚みを持ったピクセル」のように、これまでにない「モノ」がディスプレイの上に存在するようになった。そして、そのあらたな「モノ」がヒトの行為の可能性を開き、これまでになかった行為が世界に適合するかたちで配置されていくのである。
接着剤としてのソフトウェア
かつては、一つの道具の統一性が問題を提起していた。諸々の精神と創造者たちが、彫像の素材のうちにイデアを記入したという意味において、彫像に関する技術が彼らの役に立っていた。形相が、それによって生気を与えられていた質料のうちに降下するという、製作に関するアリストテレスの概念が取り上げ直されていた。イデアが優位を占めていた。本書は、アリストテレスが考慮した四原因のほかに、五番目の要因を考慮せねばならないのでは、と問うてさえいるのだ。それは、非常に巧みに接着された再編成を可能にするアセンブラあるいは網目(レティキュレール)である(飛行機の翼、タービン、スポーツカーなど)。重要なものはなんだろうか。それは、組み立て装置(モンタージュ)を可能にするものである。現代の接着は、「物体」の構想および生産と同時に「物体」という観念をも刷新するだろう。
反対の作業は、結合ではなく、解きほぐす、つまり分割し分離する —— これらは破壊だろう —— のではなく、引き伸ばしたり延長することに専念する(諸々のフィルム)。物質的実体は、引き裂かれ、分裂させられ、その構成要素へと分解されてはならず、同時に薄くなるまで伸ばされ、広げられることに耐えねばらない。フランソワ・ダゴニェ『ネオ唯物論』
モノを持続で捉えるということは、モノが統一的な存在である必要はないことを示している。それは、ダゴニェが述べる「非常に巧みに接着された再編成を可能にするアセンブラあるいは網目(レティキュレール)」としてモノを考えることであり、そこで「接着剤」の役割を果たすのがソフトウェアなのである。ソフトウェアは複数のハードウェアを接着しながら、あたらしいモノをつくり、そのサーフェイスとなっていく。そして、モノのサーフェイスとなったソフトウェアは、ヒトの行為の可能性も開いていく。
次のように言った方がいいのかもしれない。ソフトウェアがハードウェアを接着しながら、一つのサーフェイスをつくる。それはヒトがいない場合も、すでに接着している。そこにヒトが入り込み、ソフトウェア—ヒト、ハードウェア—ヒトと接着面を増やしていく。サーフェイスが増えることで、接着の自由度は上がる。ソフトウェアとハードウェアとの接着を薄く引き延ばすのが、ヒトの行為である。ヒトはハードウェアに包まれたソフトウェアがつくるモノのサーフェイスを行為で引き延ばして、別のサーフェイスとの接着を引き起こすのである。
対象(オブジェクト)とは、経験された内容というあらかじめあたえられた表面を、人間がかき集めることによってつくりだされた幻想にすぎないというのだ。これに対してわたしは、実在はオブジェクト指向的であると主張する。実在を構成するのは、もろもろの実体以外のなにものでもない。それらは、たんなる物体のような硬い塊ではなく、不気味さを少々まとった怪奇的な実体なのである。事物を、その特性や、他のものに対する影響へと還元することを辞める時、実在との接触がはじまる。グレアム・ハーマン「現象学のホラーについて」
ソフトウェアという接着剤が、ハードウェアを何かに還元することなく接着していく。ハーマンがオブジェクト指向存在論で指摘するように、オブジェクトが背後に退いて触れ得ないものとなることは、ソフトウェアが表面に出るには好都合だと考えられる。オブジェクトそのものに手を突っ込めなくても、接着剤として機能するソフトウェアが接着する複数のハードウェアとそこに生まれるサーフェイスによって、オブジェクトを改変することができるのではないだろうか。ハードウェアはソフトウェアに接着されながら背後に退いていくと同時に、ソフトウェアがかき集めたハードウェアとともに表面を構成するようになる。ソフトウェアは、複数のハードウェアを接着し続け、一つのサーフェイスをつくっていく。ハーマンが言う幻想にすぎないオブジェクトを、ソフトウェアはハードウェアを接着してつくるサーフェイスとして実在させるのである。
ソフトウェアが接着剤として機能することで、ハードウェアをかき集めることが可能になった。接着したもの/接着されたものは、そこで一つのサーフェイスをつくる。これからのモノのデザインは、ソフトウェアによる接着をデザインすることであり、周囲のあらゆるオブジェクトをいかに引き寄せるかをデザインすることである。だから、まずはソフトウェアが接着面を形成するためにモノとのあいだに意味の連関をつくり,一つの場を確保しなければならない。そのあらたに開いた場において、ソフトウェアはあらゆるオブジェクトを接着しながら一つのハードウェアをつくり、そのサーフェイスを覆い続けるのである。