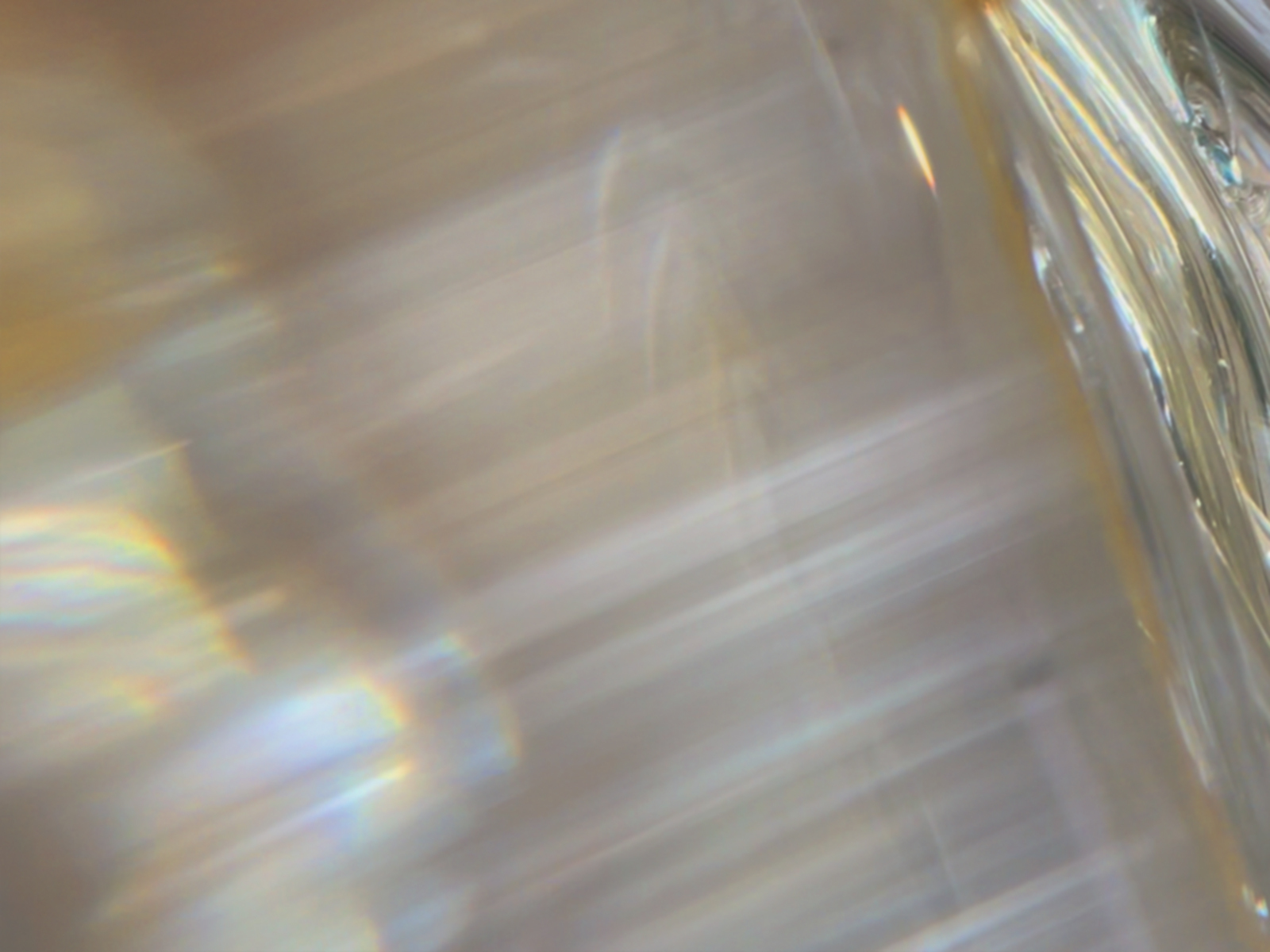日本で西洋哲学をするということ
小石祐介:
下西くんの『生成と消滅の精神史※1』を非常に興味深く読みました。ただ同時に結構考えさせられたというか、西洋哲学の範疇で何かを語ることについての限界も感じたんです。下西くんのような立場の独立研究者がこういう本を書くことの意義をとても強く感じる一方で、これをありがたがっている一部のインテリ層の振る舞いは、この本が心の底で射程にしているところと実は結構ずれているんじゃないかなという懐疑的なところがあります。
この本では、古代ギリシアのホメロスから議論をはじめることで、正当に西洋哲学史的な手続きを踏んだのだと思いました。本を読んでいると、ときどき書き手自身の気分が高揚して、表現が大袈裟になっているのが目につくことがありますよね。古い人の言葉をひたすらに振り回して、やたら説教臭かったり。今回の下西くんのように高揚を抑えながら、クールなトーンでこういった哲学の本が書かれたことが新しくて、とてもいいスタイルだと思ったんですね。
下西風澄:
僕の本を読んでそういう指摘をしたのは、小石くんぐらいでした。ただ実は、もうすこし込み入った事情があります。西洋哲学史を描くという「正当な」形式を借りながら、通常の手続きではソクラテスやイオニアの哲学からはじまるところを、あえて文学であるホメロスから出発させ、そこに歪な違和感を生じさせることを狙っていました。その意味で、僕は小石くんが言う、日本語をベースに日本で哲学をやっていることに対して、すごく自覚的でもあるんですよ。
昔から日本には優秀な哲学者がいたけど、なかなかグローバルに認知されることがなかった。それは哲学が西洋のものだという意識がかなり根深いからじゃないかと思います。たとえば哲学でも、分析哲学のような分野は英語をベースとして論じられ、自然言語の概念的な含意や歴史性よりも論理的な言葉を重視しますが、それでも実際は残酷なパワーゲームが働いている。哲学という学問そのものが、ヨーロッパの強い権威性のもとで成立しているということは、否定しがたい事実だと思います。
僕は最近とくに、哲学の内容というよりも、世界が概念によって構築されているという「形而上学」という考え方の形式そのものが、近代がすでにインストールしてしまった西洋思想のゲームの一部であると感じることが多くなりました。西洋の形而上学には、「このテクストに世界の真実が書かれている」という信念や、信仰と言ってもいいようなものがあると思うんです。僕のなかにもそういう気持ちはあるし、それこそがおそらく「高揚」の正体だろうと思います。西洋哲学は、いわばこの「形而上学的高揚」のなかで紡がれているし、それは近代哲学が中世神学との格闘や対抗から形成されてきたということとも無縁ではないと思います。そしてまたその高揚のなかには、「私たち(西洋)」が真理を紡ぐという特権意識があることも否定し難いと思う。
そういう状況を踏まえて、まったく違う東洋の歴史的言語と身体感覚を持ったこの国において「思考する」とはいったいどういうことなのか。また「思考の歴史を書く」とはなんなのか。おそらく、形而上学的高揚ではテクストをドライブできない。それとは別のリアリティや信念によって言葉と思考を紡いでいかなければならないだろう、そう思っていました。そこが本を書く上での出発点になっています。
そのような場所で何ができるか考えた結果、あえて日本でやっているというオリエンタリズムを毒牙として受け入れながら、ねじれた形での思考とその歴史を再提出するやり方しかないんだろうなというところに行き着きました。おそらく日本でも「批評」の系譜を意識しながら哲学をしている人は、どこかでこの問題を意識していると思います。そういった意味でいろいろやり方はあると思いますが、僕にとっては今回の本がひとつの答えでした。
小石:
昔、日本で結構有名な、とある哲学者の知人と話をしたときに、日本人がアメリカやヨーロッパで分析哲学の話をしても、なかなか真剣に取り合ってもらえないと言っていたんですよね。向こう側からすると、哲学はすなわち西洋哲学だし、分析哲学は現代の一丁目一番地みたいな意識があるから、東洋人が分析哲学をやっても二級市民扱いをされるんだと。これは仕方ない部分もあると思います。
でもこういったとき、アメリカとヨーロッパに対峙する日本人を含めたアジア系の人々の振る舞いのノルムって、大体似てしまうんですよね。特にある程度の立場になると、明らかな差別や不利な扱いを受けても、「差別された」とか「不公平だ」と明言すること自体が、業界のノルムに逆らって自らの評価を貶めることだからやらない。でもそれが海外じゃなくて、日本国内のコミュニティのなかでお互いに振る舞いを相互監視しあったりする状況がよく見られます。
この間、アカデミー賞の授賞式でミシェル・ヨーとキー・ホイ・クァンの一件があったじゃないですか。ミシェル・ヨーがオスカー像を持っていたのに、ジェニファー・ローレンスが横取りして渡したとか、キー・ホイ・クァンがオスカー像を渡そうとしたら、ロバート・ダウニー・ジュニアが無視してぶんどったというシーンがあって、Xで炎上しているのを見ました。燃やしているのは韓国人、いわゆるコリアンアメリカンなどのK−POPファンダムのような人たちだったんですけど。炎上がニュースになりはじめて、それを鎮火させたのはミシェルとクァンの当人たちだったんですよね。まったく関係ないのに、あれは差別だとか差別でないとか、欧米ではこうだとか、日本で議論してる人が多かったんですが、そういう議論じゃなくて、素直にああいうものに対してはファックユーと中指を立てる人がもっといてもいいと思いますね。
西側の土俵で西側のゲームをしていると、こういったことがあっても、飄々として数字で結果を出していくのがいいとされているんだと思います。一方で、定量的に評価できない領域の仕事では、土俵に立つのが誰か、というポジショニングの問題が常に重要になります。たとえば哲学だと、香港のユク・ホイが西洋哲学にも東洋哲学にも通暁していることで有名です。彼の力を考えると、香港ではなく欧州の中心にいてもおかしくないと勝手に思うのだけど、現実ではそういうわけではない。だからこそユニークな思想がそこにはあると思いますが。ただ基本的に人文社会科学はリベラルな立場だけど、西洋の土俵なので、西側社会のノルムで活動することが推奨されるし、それにおいてのみ評価されるという暗黙の了解があると思います。
今回の下西くんの哲学史は日本語で書かれているので、想定する読者も日本語話者だけれど、100年前の学者が書いた本と違って、幅広い層に読まれることを想定していると思うんです。カントが200年以上前に『純粋理性批判※2』を発表したときのように、一部のコミュニティを対象としているわけではないから、読者にはある程度の教養が求められますよね。昔の哲学者はいわば特権階級でフリーハンドでなんでもやれたのだと思うし、インターネットもないので、何をやって批判されようが知ったことかと言える立場でしたけど、下西くんはもっと社会的にフラジャイルな立場で本を書いている。自分自身の人生を変数に入れて、有限な時間や状況のなかで文章を書かないといけない。その試行錯誤の過程で、後半に自然と夏目漱石が出てきたのかなとも思ったし、その立場でこのアウトプットを生み出したのがいいと思いました。
下西:
漱石を入れたのもそうだけど、一見すると普通の西洋哲学史っぽく、もっと言うと教科書っぽく書いているところもあって、そこは結構自覚的です。実はこのあたりのスタイルは、浅田彰『構造と力※3』があえて「チャート式」で哲学史を書いたことを意識していたところもありました。あの本は、哲学が西洋のものであり、それを参考書のように勉強する日本人という図式をアイロニカルに体現しています。僕はそこに本質的な部分を感じていました。
アイロニーがいいかはさておき、少なくとも哲学や芸術というヨーロッパにおいて自明に成立している概念がない場所で、哲学や芸術をしようとすれば、それをそのまま実行するのではなく、それが成立し得る条件そのものから思考し実践することが必要なのではないかと思います。あるいは、場合によっては、むしろ条件を考えることのほうが重要な場合もあり、そこで哲学史を眺め直してみるという作業はひとつの方法なのだと思いました。
あの時代は、哲学がファッションになるほどの流行があり、まさに消費社会のなかでグッズやデバイスのように哲学が語られうる状況がありました。現在はそれとはだいぶ状況は違いますが、あらゆる情報がプロトコルとして流通しながら、それぞれの島宇宙で、それぞれにとって必要なものだけが求められる情報の消費社会になっています。そんななかで消費に抗うには、それぞれの読者にとってコンテンツとして興味が持てるパラグラフを作りながらも、同時にその部分的な関心から入ると、いつのまにか長大な物語につながっていくという構成になるのがおもしろいのではないか、というのも念頭にありました。もちろん一番大きいのは、自分の実存的な理由でがむしゃらに書いたことなんですけど。
もうひとつ意識していたのは、ラッセルの『西洋哲学史※4』ですね。ラッセルも、教科書的に哲学の歴史を整理しているように見せかけて、実は古代ギリシアの哲学がはじめから現代のラッセル自身がやっている言語哲学へと発展する必然的な流れを持っていたのだという風に、歴史を再構成して誘導しています。このあたりをひねって、歪な西洋哲学史を描きたかった。もうすこし正確に言うと、僕にとって自然な哲学を書こうとしたらこんな奇妙な形になって、そのことを成立させるために、いろいろな方法を取り込めないかと試行錯誤したということです。細かく見ていくと、たとえばデカルトのあとにロックやヒュームではなく、パスカルを経由することでカントの意味を見出すというような流れは、他ではなかなかないんですよね。でも僕はあえてそこに重点を置きたかった。そうしなければ書かれなかった歴史、拾われなかった意識のあり方があるだろうという強い気持ちがありました。
大哲学者であるフッサールやハイデガーのあとに、ほとんど知られていないヴァレラというチリのサイエンティストを入れたのも、普通に考えたらあり得ない哲学史観です。だけど、それをあたかもつながっているかのように偽装できるのが、西洋哲学の真っ只中で正史を書く立場じゃない人だからこそできる歴史の見せ方だと思うんです。そういう意味で、この本は、一見普通の哲学史のような組み立てをしながら、絶対に西洋人がやらないような流れを作っています。これはやりたかったことのひとつでした。
つまり一言で言うと、僕たちはいわば「奇形の歴史」を書くしかないのではないか、と思っていました。四書五経や李白や杜甫などの漢籍や仏典をすべての教養の基礎にしていて、ここ100年くらい前までソクラテスもカントも読んでいなかった日本人が、哲学をするということはどういうことなのか。一般化すれば、これは「近代」という、学問・言語・制度・価値観のすべてを、半ば一挙に入れ替えなければならかった国の、不自然で無理をした文化や眼差しをどう考えればいいのか、という問題です。
実際に現代の日本は、漫画やアニメが文化の中心にあり、先進国のなかでは自国の軍隊もうまく位置づけられていない奇妙で特異な国家でもあるけど、これらは急速な近代化と敗戦というふたつの傷を抱えていることの結果だと思っています。漱石のなかには、そういう歪さが詰まっています。ヴァレラというチリ出身で、辺境の地から西洋の哲学や科学を眺め直して異端となった人物を西洋篇の最後に持ってきたというのも、その違和感に共感できた部分があったからだと思います。
小石:
なるほど、おもしろいですね。ヴァレラが晩年に書いた『身体化された心※5』では、仏教についての言及が多数ありますが、これは彼のなかで研究という行為が行き詰まってたからなんでしょうか。
研究には常に自分の人生が変数として入ってきますよね。まず自分の寿命というものもあります。有限性のなかで、アウトプットの総和あるいは積分が、コミュニティに受け入れられた結果として、閾値を超えないと成果にならない。数学者の岡潔が「人間は死なない」と言ってたのは、多分そういうことを前提としていて、限界を自己認知しないで超克するためだったんじゃないかと思うんです。
死なないと思ってしまえば無限の時間で探求ができるし、有限時間内にやらなければという計画はいらない。そのリミッターを外して研究するのは実社会で生きる個人としてリスクだし、そのリスクに向き合う自分の煩悩によって研究の方向性も変わってくる。研究者は各個人で、時限的なマンハッタン計画みたいなものを抱えているわけですよね。建前上言わなくても、これまでにこのアウトプットくらいでやらないといけないというものが、普通はある。
岡潔がそうであったように、あるいはアンドリュー・ワイルズが『フェルマーの最終定理※6』の仕事をするときに、他の仕事を放棄して没頭したように、コミュニティ内で求められるノルムを放棄するようなことが、ヴァレラ自身に必要だったんじゃないでしょうか。荒川修作も「死なない」ということについて頻繁に言及をしていました。これも有限性との戦いみたいなものがあったんじゃないのかなと。
下西:
たしかにヴァレラにとって仏教は思想的な立脚点でもあるんだけど、それだけじゃないんです。彼は科学者でありながら、自らの人生の有限性を意識していた思想家でもあったと思います。実際にヴァレラの研究には、人生の問題がつねに関わっていました。彼はチリで生まれ、ハーバード大学でのちにノーベル生理学賞を獲ることになるトルステン・ウィーセルという人の研究室で博士号を修めて、1970年に一度チリに帰るんですね。
そのときチリではアジェンデ政権という社会主義政権が成立していたんですが、1973年にピノチェトによる軍事クーデターが勃発して、この政権はすぐに崩壊してしまいます。それでチリ国内は軍事の支配領域がコントロールできなくなって、住民が逃げ惑う悲惨な状況になりました。
当時のチリ大学にはウンベルト・マトゥラーナがいました。彼はアメリカの神経科学の最前線にいて、形式ニューロンのモデルを考えたウォーレン・マカロックとも一緒に研究したりしていました。マトゥラーナの貢献もあって、当時のチリ大学の科学研究レベルは高かったのだけど、チリの科学者たちはピノチェト政権によって世界中に亡命することになります。このクーデターは、奇しくも「911」に起こっていて「チリのディアスポラ」と言われていますが、ヴァレラはその歴史的な事件に大きなショックを受けてしまいます。
この話はあまりパブリッシュされていないけど、彼がアメリカに亡命したすぐあとの講演録では、そのときに相当傷ついたという話をしています。同じ国にいた人たちが、あるときからそれぞれ全然違う勢力に分かれていく現実を見て、「サイエンティストである自分の存在に何の意味があるんだろう」といったことを考えるようになった。
当時のヴァレラはG・スペンサー=ブラウンあたりにも関心があって、ロジックを使って生命や意識の秘密に迫れるんじゃないかと考えていました。だけど、人間の意識があっという間に変わってしまうという出来事を目の当たりにした。昨日まで味方だと思っていた人が敵になって、敵だと思っていたら味方になるみたいなことが一瞬で起こった。その末に、もしかするとサイエンスにはたくさんのスタンドポイントがあり、意識は普遍性みたいなものから遠いところにあって、一瞬で変容してしまうものなんじゃないかと悩むことになります。
そうして仲間たちと離れ離れになったヴァレラは、アメリカで初めての仏教大学であるコロラド州のナロパ大学※7を創設したチョギャム・トゥルンパに出会います。その周辺ではチベット仏教の偉い人たちが、当時のヒッピーカルチャーみたいなものと融合しながら仏教を普及しようとしていて、そのコミュニティに所属することになるんです。彼はそこで仏教を学び、瞑想をすることで傷を癒そうとしていたし、実際に救われているんですよね。
そのことをヴァレラはある種の実存的な問題として捉えて、サイエンスの研究と並行しながらマージしたいという気持ちがあったと思うんですよ。当時の政治や文化の状況も含めて、たぶん彼のなかにビジョンが生まれたんだと思います。
だから、彼はサイエンティストでもあるんだけど、同時にカルチュラルな人でもある。ある時代のアメリカの文化と思想の領域を横断するような機運をつかみながら、それをどう研究と思想に昇華することができるかを考えていたように思います。
小石:
ヴァレラはヨーロッパの人という印象があったんですけど、アメリカが長かったんでしたっけ。
下西:
たしかにヴァレラは、そのあとパリに行って、エコール・ポリテクニークの神経学研究所に長くいましたね。ただ、彼の研究や思想が発展していったのはやはりアメリカでした。
アメリカでは、たとえばラルフ・ワルド・エマーソンのような人たちが、自然を感じて癒やされてセルフリライアンスが可能になるといった流れもあって、それが現代のアメリカの自己啓発ブームにつながっていきます。それは、人間の意識と自然現象を接続するビジョンに導かれているし、またそこにはスピリチュアリティや東洋思想が常に関係してきます。こういったアメリカの系譜を考えると、おそらくヴァレラの思想はヨーロッパよりもアメリカの文化との相性がよかったんじゃないかなと思います。
小石:
ヘンリー・デイヴィッド・ソローの『ウォールデン 森の生活※8』じゃないけれど、一回自然に入って世捨て人体験をして、それから脱皮して戻ってくるスタイルってありますよね。それを感じますね。
領域を越える文化と宗教
下西:
サイエンスと文化の話の続きですが、ヴァレラは、アメリカでカルチャーの集合体が作られて展開されるムーブメントのなかにいたんです。
ヴァレラと『身体化した心』を一緒に書いた哲学者のエヴァン・トンプソンは、お父さんがウィリアム・トンプソンという思想家でヒッピー的な人物でした。彼はロックフェラー財団※9から資金提供を受けて、リンディスファーン協会というものを作ります。この協会は重要で、スチュアート・カウフマンやジェームズ・ラブロックらが参加し、グレゴリー・ベイトソンも滞在研究員をしていました。ベイトソンの『精神と自然※10』は、ウィリアム・トンプソンのリンディスファーン協会での講義録として出ているんです。
ここには研究者だけではなく、チベット仏教徒もいましたし、詩人やアーティストたちが訪れていて、謎の文化的な拠点にもなっていました。スチュアート・ブランドなどのカウンター・カルチャーの重要人物も初期のメンバーになっていて、スティーブ・ジョブズが影響を受けたことでも有名な『THE WHOLE EARTH CATALOG※11』を作ったスチュアート・ブランドは、そのあとに『CoEvolution Quarterly(季刊:共進化)※12』という雑誌を作りますけど、ヴァレラはここにも寄稿しています。その周辺に60年代から70年代のサイバネティクスとヒッピーカルチャーとIT関係のトピックが渾然一体となった母体ができて、そういったコミュニティにとって、仏教は重要な思想的な着想源になっていましたね。
小石:
なるほど、おもしろいですね。昔のファッションの動きに似たものを感じます。スチュアート・ブランドの『THE WHOLE EARTH CATALOG』はユニクロの柳井正さんが気に入ってる本らしいです。
カルチャーの話で思い出しましたが、実はかつてのアメリカで、フランスの哲学者のミシェル・フーコー、ロラン・バルトやジャック・デリダが流行ったのも、アメリカ人のオルタナティブカルチャーへの関心かららしいんですよね。このあたりはフランソワ・キュセの『フレンチ・セオリー※13』に書かれているんですが。おそらく、仏教もそうなんだと思います。これはすごくファッションっぽい動きだなと。
西洋社会で仏教への関心を象徴するカルチャーアイコンがダライ・ラマなんですが、彼への関心もファッション的な側面があります。実は、僕はダライ・ラマに会って握手してもらったことがあるんですけど、ヨーロッパ出張でファッション関係者とにこの話をするとかなりウケがいいんですよね。仏教の教典を読んでいるわけではないと思いますが、オルタナティブな文化にアンテナを張っている人が興味を持ちます。フランスの現代思想がファッション的に消費されているのは当時から今もまだ続いているけれど、東洋のカルチャー好きには仏教がファッションの一部として消費されています。自分はコミュニティのなかでまわりの人たちと違う、とメッセージングするための隠喩に使われている。
もっと古くは、サイエンスも元々は神学から来ていますよね。占星術も天体物理学だったわけで。科学史、思想史を見ているとオルタナティブへの関心とその変容がパラダイムに関係していると感じていて、それが僕にはファッションの動きに重なって見えるんですよね。既存のエスタブリッシュメントに対抗するという意識から自然と異質なオルタナティブな文化を混ぜていくのは王道だから。
下西:
日本で複雑系の受容があったときも、同じように仏教との関連性を見る動きがありました。どちらかと言うと、科学者よりも一部の哲学者たちにその傾向があったように思います。
科学が神学的な背景を持っているというのはそのとおりですね。ニュートンも晩年は熱心に聖書研究をしてたし、科学研究を推し進める個人的なモチベーションのなかにも、なんらかの信仰や世界観が入っていたと思います。その意味で、複雑系的なコスモロジーは日本・アジア的な世界観と相性がいいので、思想として惹かれるのもわかる気がします。また実際に、一神教的な世界観ではないコスモロジーが可能にする科学や思想があるなら、それもまた展開するに値するものではあると思います。ただその辺は織り込み済みで解毒しながら受け入れた方がいいと思っていて、それをどのようにできるのかは考えています。
小石:
そうですよね。乱暴な言い方をすると、科学や数学のトレンドや王道的なもの、数論や素粒子論などは、一神教的な世界観がどこかに存在すると思うんですよ。信仰のもとに研究されているようにさえ見える。世界の構造はこういう構造であるべきで、こうあってほしいという信仰が、人間の考える方向性をキックしている気がします。
ピタゴラス教団も振り返るとそうでした。そして、コペルニクスの地動説にも宇宙はもっと構造的に美しいはずという理念があったはずです。すると不思議とそうであってほしい方向に結果が出て、信仰心にポジティブ・フィードバックがかかっていく。
最近の数学ではラングランズ・プログラムという統一理論が話題ですが、そこで主要な貢献をしているローラン・ラフォルグは、かなり信心深い強いカトリックらしいですね。西洋的宗教観が身体化されている人の方がやりやすい研究っていうのはある気がします。最近流行のAGIの開発も、もしかするとそうなのかもしれない。そういう研究と日本の身体感覚は相性がどこまでいいのかはわかりません。
信仰心によって思考というか煩悩のノイズを減らして、人生の変数が少なくなるからこそできることってあると思うんです。たとえば本を書く行為には、その変数が如実に出るじゃないですか。時間のなかで自分自身へ反響するものを完全に無視して本が書ける人はそんなにいない。
話が戻りますが、そういう意味で、今回の下西くんの本は、下西くんがちゃんと独立して自身の生き方を試行錯誤する活動のなかから自然に出てきているから、リアルに感じたし、そこにオリジナリティを感じました。
過去の哲学書や文学作品でも、実際にこの人がどういう立場で書いたかを知って読まないと、本はちゃんと読めない。最近は間口を広げたあっさり目の教養本が売れているみたいですが、下西くんは本を書くために自分を犠牲にしているものがあって、そのリアルさから生まれる際どい緊張感が紙面に現れて、鬼気迫っている感じがよかった。
下西:
ありがとう。たしかに僕は、制度のなかで考えたり書いたりすることが苦手だったし、そこを出発点やゴールにしているつもりもなかった。だから、ただ自分の人生の時間を削りながら書かなければならない何かだけに向き合うというスタイルになったと思います。
実際のところ僕は、専門を超えて、哲学や文学や科学や、いろんな領域を超えてこんな無謀で勝手なことを書いたら、馬鹿だと思われるかもしれないと考えていたところもありました。その意味では、馬鹿だと思われてもいいから書きたいものを書こうとひらきなおって、アカデミアから離れるつもりで書いたとも言えるんだけど、逆に本を出してから学会や大学に呼ばれる機会が増えました。もしかすると最近のアカデミアの空気が変わりつつあって、僕のようにアカデミズムの外にあるスタイルの思想に対しても、好感を持ってもらったのかもしれません。
僕自身は、今はもうアカデミズムの内とか外とかそもそもそういうものを考えることもなく、ただ考えたり書いたりするだけですが、そういう感覚を共有できる人は大学でもその外側でも増えているように思います。
小石:
それはいいことですね。アカデミズムの陰の部分ではないですけど、日本のローカルな学会が昔のドイツの哲学者の研究をしていたとして、単純にドイツからかなり距離がある時点でリアルじゃないのに、日本のなかだけでタコツボ的に権威になりうるという状況があるじゃないですか。地理的にもグラフ的にも中心とは離れすぎていて現地に念力すら届きそうにもないのに、ローカルなしきたり警察みたいなものが生まれて、固有名詞を並べたり知り合いの名前をポケモンカードみたいに出してマウントを取り合ったりするようなことが起きていますよね。
ファッション業界でも似た構造があるけど、これは結構やばいなと。最近はNewJeansを追いかけている中年のファンがNewJeansおじさんと揶揄されているみたいですが、マルクスおじさん、フーコーおじさん、ドゥルーズおじさんとか、たくさんいるわけで、これが実は相当やばいんじゃないかって僕は思うんですよね。たまにカフェとかで海外リーグのサッカー談義を店内全体に聞こえるような大音量でしている人とかがいて、すこし暑苦しいなって感じがするんだけど、もしかするとモンティ・パイソンの哲学者サッカーはそこから来たのかもしれない。
下西:
前に小石くんはSNSで、今ラグジュアリーブランドが世界で強いのは、ヨーロッパの貴族文化や王族文化を煮詰めて継承したことをプレゼンテーションしているからじゃないかと話していましたね。
小石:
ラグジュアリーブランドっておもしろくて、なんだかんだその運用はフランスでしか成功していないんですよ。そのなかでも長期で本当にうまくいっているのはLVMH、エルメスとシャネル。でもよく考えたら、フランスの人たちって革命で王様を殺したわけじゃないですか。革命を起こして王族を捕まえてギロチンにかけて処刑したのにも関わらず、現代のフランス人は王族や貴族が愛したラグジュアリーを世界中で売りまくっている。
今も王族は残っているんだけど、そこまで影響力がない。その威光を引き継いでいるのは直系の王族ではなく、ルイ・ヴィトンとかエルメスのような記号になったブランドではないかというのが僕の考えです。フランスは王政が潰れて、その王の細胞がラグジュアリーブランドの経済活動に吸収されたんだと思います。そこがすごくおもしろい。
これが、なぜかイタリアとか、まだ王様がいるイギリスとか、他の国ではそこまでうまくいってないのか不思議なんですが、思いつく理由は2つあります。ひとつはラグジュアリーブランドのビジネスを作り上げたLVMHのベルナール・アルノーが天才だということだと思います。
2つ目の理由は、こちらの方が大きい要因だと思いますが、フランスという国自体が世界一の超大国であるアメリカにとって強い憧れの対象だからだと思うんですよね。最近だとNetflixのドラマで人気の『Emily in Paris※14』がわかりやすいですが、フランスはアメリカにとって特別なんですよ。文化の面で劣等感を感じてルックアップしている。
元から国内に移民が多くてある程度イメージが固定化しているイタリア、あるいはルーツがあるイギリスと比べて、フランスはある意味手付かずで言葉も違う。得体が知れないんだけどかっこいいという価値観が生まれやすいのかもしれません。フランスはアメリカの建国に貢献したという側面もありますが。
アメリカではフランスの現代思想も、知識人のファッションアイテムとして受容され流行りました。デリダやバルトが1966年にジョン・ホプキンス大学に呼ばれ、本国よりもアメリカの方で大きくバズった。フランスのことをよく知っているのが通であるというポジショニングが成立したんですね。アメリカの動きに呼応して、フランスでは逆輸入するような動きがありました。こんなところに、フランスだけがラグジュアリーで成功している理由と通じる部分があるんじゃないかと思います。
そして、アメリカに憧れる人たちは自動的にフランスにも目が行くわけです。憧れの方向とそのグラフ構造というのは重要だと思います※15。
下西:
第2次世界大戦でヨーロッパが荒廃したあとに、アメリカが経済力を持って学者やアーティストを自国に呼び集めたりすることで、アートの中心をパリからニューヨークに奪還する動きをしていましたね。これは歴史と伝統のない新興国アメリカがヨーロッパへのコンプレックスの埋め合わせとして絶えずやり続けなければならない仕事です。
つまり、「俺たちは単なる成金じゃないんだ」ということを言い続けなければいけない。そうでなければ、アメリカは暴力と欲望だけしかアイデンティティを持たない「動物」へと帰してしまう可能性があって、それを常に恐れている。だけど、それを逆にフランスも利用しているってことですよね。
フランスだけに限らないんだけど、今回の本で歴史について書きながら改めて感じたのは、ヨーロッパは歴史を偽装することに長けているということでした。
哲学でも、ニーチェは古代ギリシアとドイツの歴史的な連続性を神話的に語る傾向があったし、ハイデガーもドイツ語の源流をギリシア語に見出し、その連続性をマニアックに書き続けていました。それがナチスへの加担というような問題につながってくる。ソクラテスやプラトンといった哲学の起源がヨーロッパにあるという物語も怪しいところがあって、当時のギリシアがどこかというと、実は中東に近いですよね。
小石:
ソクラテスをはじめギリシア時代の彫刻を見ると、西欧のヨーロッパとは違って、地中海系というか明らかにアラブ系と見分けがつかない雰囲気がありますよね。アレキサンダー大王やキリストが中東系の顔をしていただろうというのは、今もたまに言われますが、宗教画だと白人になっている。確かに歴史の偽装は上手い。地続きの地中海まわりをそもそも何系といって区別するのも、当時のことを考えるとナンセンスな感じがします。実際、ヨーロッパ起源と思われているものの多くが、中東・アラビア文化の遺産だと言及したジクリト・フンケの研究※16があるんですが、英語で著作が手に入らないのが闇が深いですね。あまりそういう方向に大衆の関心が行ってほしくないという西欧の総意を感じなくはないです。
下西:
そうなんです。つまり、いかにもヨーロッパの起源がそこにあるように見せて、歴史をうまく編集してして物語を普及させてきたわけです。そして恐ろしいことに、一度作られた物語は市民の心のなかに常識として定着し、そのまま政治的行動として実現する。今のイスラエルの問題も、明らかにそうした物語の延長線上にある。ああいうものを見ると、ヨーロッパが掲げる「倫理」や「政治的正しさ」が、いったいどういう物語のもとに成立しているのかについては、相当慎重に考えたり受け入れたりしなければならない。
僕はヨーロッパが、現代の文化や思想や歴史を作ってきたことは、やはり偉大だと思っているし、その恩恵を強く受けてきました。しかし、これと同時に、その偉大さは植民地支配や特権的意識の愚かさのなかで形成されてきたこともまた事実です。ヨーロッパを称揚するのでもなく、非難するのでもなく、偉大さと愚かさをともに見つめながら、なぜそのようなことが生じているのかを冷静に思考することが重要だと思っています※17。
戦後の日本では、アメリカが米軍の駐屯基地を作ったときに、軍事的なコントロールだけでなく、キャンプの周辺でジャズやロックを流して、映画館を作っていた。石原慎太郎は、青年期に米兵に殴られたという傷を持っていたし、村上龍はロックとコカ・コーラでアメリカを知ったと話していました。戦後の直接的な統治という状況もあって、日本にとってのアメリカの威光はかなり身体的だったはずです。それに対してヨーロッパは、歴史的に教養とか文化という形で、知的な占領政策みたいなことを高度にやり続けてきたんだと思います。
今のSDGsもそういった物語の覇権性の先にある話だし、アメリカの軍事・経済的な強さに対して、ヨーロッパはナラティブの強さを持っているということなんでしょうね。
小石:
ヨーロッパの強さは、ナラティブの強さですよね。だから、パリで開催されるオリンピックの開会式で何をするのか楽しみにしています。かなり現代的なメッセージが出てくると思う。
駐屯地と言えば、実は僕は12歳まで米軍基地がある街で過ごしていました。だからアメリカと聞くと、西海岸のスタートアップとかニューヨーカーのイメージじゃなくて、一緒に遊んでくれた週末車いじりをしている短髪角刈りのガタイのいいアメリカ兵たちを思い出します。私にとって言葉の通じない角刈りのアメリカ兵達との共通言語はNBAや音楽といったポップカルチャーでした。
余談ですが、アメリカの強さって、反米国家にもそのカルチャーが浸透していたところだと思うんです。反米の北朝鮮で金正日が亡くなったときに用意された霊柩車はリンカーンでした。金正恩が黄金期のシカゴ・ブルズのファンでデニス・ロッドマンが大好きだというのは有名です。アメリカのカルチャーは反米国家にも浸透しているんです。
湾岸戦争のときにフセイン大統領がアメリカ軍に捕まって、その様子がインターネットに流れてたじゃないですか。彼が潜伏していた家の洗面台か何かを報道写真でみたんですが、そこにはアメリカブランドのシャンプーが置いてあったんです。その頃の僕もフセインと同じシャンプーを使っていて被っているのに笑いました。
憧れの話に戻ると、アメリカのインテリや文化人がヨーロッパに憧れる一方で、日本はアメリカに憧れてきたんですよね。アカデミックにも経済的にも文化的にも。日本人のなかにはアメリカに行くと、もともといた日本のコミュニティに対して優越感を持つ人がいますが、アメリカというのは受け入れた人に、そういう感情を抱かせる装置として機能しています。
アメリカのコモディティとカルチャーはどこにでも浸透している。それがアメリカの強さなんです。映画や音楽もそうでした。ただ最近のエンタメに関しては、テンプレになってつまらなくなっている気もするんですね。
この間驚いたのは、スーパーボウルのハーフタイムで出てきたアーティストがみんな年配だったということですね。スヌープ・ドッグ、エミネム、アッシャーとか、確かにスターですが、結構世代的には上の人たちがよく知っているプレイヤーです。だけど、僕がまだ高校生ぐらいのときは、10代や20代のアメリカのアーティストがいっぱいいました。同世代でここまでできるんだと、負い目のようなものも感じるほどでした。
今若い世代で世界のヒットチャートで目立っているのはビリー・アイリッシュぐらいでしょうか。上の世代だとファレル・ウィリアムスはルイ・ヴィトンのディレクションまで手掛けていてすばらしいし、カニエ・ウェストも僕は好きですが、もうベテランなんですよね。
そうやって見渡すと、群雄割拠の時代になったなと感じます。サスペンス、ミステリーの映像作品が好きでよく観るんですけど、昔ならアメリカの一強でお家芸だったこのジャンルで、最近はヨーロッパでもスペイン、ポーランド配信でおもしろい作品をよく見かけるようになりました。韓国も有名ですが、コロナのときは中国語の先生に教えてもらった86年生まれの紫金陈という作家の小説が原作の『隐秘的角落※18』という作品がおもしろくて、テンセントの爱奇艺で中国作品を物色しましたが大分シーンが変わったと感じます。
Netflixで日本のコンテンツが人気になって、ときどきニュースになっていますが、アメリカのコンテンツシェアが相対的に下がったからじゃないかと思います。そして、エンタメのシェアの低下が、もしかするとアメリカ覇権の綻びのはじまりなのかもしれないと思うんですよね。
音楽もファッションとの絡みを見ると世界からおもしろいアーティストがあちこちから出てきていますよね。リナ・サワヤマ、ベルギーのLous and The Yakuzaみたいな切り口は昔だったらもっとアメリカ発信だった気がします。
アメリカ一強ではなくなった原因のひとつは、アメリカが小さな島になりつつあることだと思うんですよね。その例のひとつが、アメリカ式のWoke問題かもしれません。ポリコレ的価値観は世界各地にあるわけですが、アメリカ式のポリコレカルチャーが世界すべてに自然に適用されるのは無理がある。ただその無理であるという事実と、アメリカこそ世界のルールを作るんだというリベラル層の自意識の歪みが、辻褄が合わないレベルになったのかなと思います。
昔のアメリカ映画を観ると、今だとアウトな表現が多いですが、コンテンツとして圧倒的におもしろいものも多い。ハリウッド作品には、聖書や神話が下敷きになった王道なものをよく見かけますが、使い古された起承転結を老若男女が楽しめるように複数のレイヤーにしている作品が多いんですよね。だからこそ、世界の人が楽しめたのかなと思います。今は過去に成功したものの焼き直しも多いし、コンテンツが作りにくくなっているように見えます。
さっき下西くんが話してたみたいに、日本が戦争で負けたときにはジャズやエルヴィスを聴いて、やっぱりアメリカはすごいと思っていたはずなんですよね。口では「日本人かくあるべし」みたいな勇ましいことを言っていた昭和の文化人も、アメリカンカルチャーにズブズブだった。あるいはアメリカを意識しているがゆえに、英国式に謎にこだわったりする人がいましたよね。同じように、アメリカがイラクで戦争をしているときでさえ、イラクでマイケル・ジャクソンを聞いていた人はいたと思うんです。それは本当にアメリカのポップカルチャーのシェアが独占的だったからだと思います。それが失われた結果、この先50年ぐらい経ったあとに何が起きるのか考えてしまいます。
今ビヨンセやリアーナ、テイラー・スウィフトがどれだけ世界的に影響力があるのかわかりませんが、グローバルのヒットチャートにいるビリー・アイリッシュのような若いアーティストが年齢を重ねるとどうなるんでしょうね。アメリカの記号が世界の大衆のなかから薄れていくのは、初めて経験する時代だし、国際秩序の乱れのはじまりかもしれない。
それは思想についても同じで、なんとなく無根拠にアメリカの大学がすごいと思えるのも、実はポップカルチャーがイメージを支えているのではないかというのが、僕の仮説です。多くの人は、イーロン・マスクやビル・ゲイツよりも、ケンドリック・ラマーやビリー・アイリッシュ、セレナ・ウィリアムスやレブロン・ジェームスらが取り巻く世界に憧れていると思うので。実際、スティーブ・ジョブズやイーロン・マスクが起業家として世界的に人気なのも、彼らがポップカルチャーに関心を持っていることを態度で表明しているからじゃないかと思います。
ファッションと文化のボキャブラリー
——— 小石さんはファッションという言葉をいい意味と悪い意味で使い分けていますが、それにはどんな意図があるんですか。
小石:
人間が身につけるものなら、教養や知識さえも装備品になると思っているんです。たとえば下西くんの本を、純粋におもしろいと思って読んでる人もいると思いますが、「読んだという事実を身につけたい」と思って読んでる人も多いはずです。この後者の読み方はファッション的ですよね。
——— 一方で、ゲームをおもしろくするといった意味でも、ファッションという言葉を使っていますよね。
小石:
そうですね。僕はファッションのことを普段から「様装」と言うようにしています※19。ファッションはそもそも現象であって、洋服とか流行といったことに限定されないという意図で使っています。
この間、友人の桑田光平さんがやっている東大の表象文化論の講義に、私とコイシミキがゲストで呼ばれて話したんです。そこで学生から「自分はファッションに興味がなくて、ユニクロとかしか着ないので、そんなにファッションについて語られても」みたいなおもしろい発言を聞きました。でも僕には、その態度がファッション的に思えるんです。自分はユニクロしか着ないけど、実際の美術や芸術が語られる場にいることには関心があるわけですよね。そんな彼が哲学書を読んでるとしたら、それってすごくファッション的じゃないですか。
だから、ファッションを「様装」、つまり人間の「様」と「装い」として考えると、服に限らず、人文書を読むとか、メディアについて語るといったこともファッションになるわけです。エディ・スリマンがデザインしたセリーヌを好んで着るという話とあまり変わらない。
ファッションの創造性や豊かさって、それが何の情報に結びついているかなんです。ひとつの服が意味できることは限られるから、どんな背景で成り立って結びついているかが重要になる。たとえばSDGsのような漠然としたコンセプトしかないと、環境と人に大事なものって結局なんなんだとなって、それで終わってしまいますよね。
さっき下西くんからラグジュアリーの話もあったので、今セリーヌのディレクターをしているエディ・スリマンの作っているものの話をします。彼のデザインソースは、アメリカやフランスの古着がベースです。半ばコピーと言ってもいいくらいそっくりなものを作っているんですけど、日本人のデザイナーがフランスのユーロヴィンテージをコピーするのとはまったく意味が違うんですよね。エディ・スリマンが自分のブランドを立ち上げて一人でやるのと、セリーヌでやるのでも意味が違うし、彼が前にディレクターをやっていたイヴ・サンローランでやったとしても、一着のアイテムが内包する意味がまったく変わってくる。
エディ・スリマンというデザイナーがおもしろいのは、そういったことを理解した上で仕事をしていることです。日本でもアメリカでもあまり話題になりませんが、彼はグランゼコールのパリ政治学院(シアンスポ)を出たエリートです。ちなみにクリスチャン・ディオール自身も同じシアンスポの出なんですよ。グランゼコール出身者が、いかにもグランゼコールの大学に通っている若者が着てそうな服を作っているのが、結構おもしろいところなんですよね。
ディオール本人含め、グランゼコールの界隈には、いろんな学者や政治家、LVMHの役員まで様々な人たちがいるわけです。そういう系譜にある人の作ったレザージャケットが、1960-70年の時代を引用して、そこにアメリカのエッセンスもすこし入っているといった背景があると意味が違ってきます。そして、そこに意味を見出す人たちも出てくるわけです。この服を着る人は、こんな本を読んでるかもしれないというような、アイテム一着が持つ固有名詞のネットワークグラフが豊かになっていくわけです。
グラフ構造の例で言うと、フランスやアメリカの60-70年代に生まれた音楽や映画のシーンなら、そのイメージ像が世界中にばらまかれているので、エディ・スリマンぐらいの世代だと説明がなくても伝わる。こういった情報のつながりまでを作ることが、ファッションのデザインだと思います。そういった意味では、世の中には服を一着も作らないファッションデザイナーもいると思いますし、そういう広い意味でファッションという言葉を使っています。
下西:
哲学も学問でありながら、さっきの『フレンチ・セオリー』じゃないけど、文化的な側面もありますね。つまり、学問もその時代のなんらかの情報と結びついた多層的な構築物であることからは逃れられません。だからこそ、学問がマーケットやカルチャーと結びつくときには、常に自己再生産的になっていく危険性があり、それに敏感である必要があります。
一方で、僕はアカデミズムの持つ専門性や権威性が非常に重要だとも思っています。時代の動きに左右されない、真理の探求や論争の蓄積が歴史を作っている面は大きい。しかし同時に、その閉鎖性をどう時代と結びつけていくのかという視点も大切です。そして、その相矛盾するようなふたつの視点は、大きな学問論やアウトリーチ論として考えるのではなく、一種の身体感覚のようなものとして捉えるのが重要なんじゃないかと思っています。どれだけ専門的でマニアックなことをやっていても、その現代的な意味をつかむ感覚は必要だと思うし、逆にどれだけ開かれて分かりやすいことを書いても、安易な形式的思考になってしまうこともある。
インターネットによって領域が分断されて、一方で各領域をプラットフォーマーがAIアルゴリズムによって縦横無尽に再編集していますが、他方ではSNSがそれぞれの個人をよくも悪くも経営的主体にしました。そうすると、自分の読者が誰なのか手に取るようにわかるようになる。年齢や性別のようなマーケティング的な層だけではなく、文体レベルにまで及ぶ具体的なフェティッシュが高解像度で見えてくるわけです。そのとき単に無視するのではなく、逆にネットに適応しすぎるのでもなく、そのフックを利用したり裏切ったりしながら、どうやってインターネットの速い思考とコミュニケーションを、長大で歴史的な時間感覚へと接続させていけるかが大事だと思います。
もしマーケットやカルチャーに免疫がないと、そこに向けた言葉だけを話して硬直化しちゃうと思うんですよ。そうすると結束力は強まるんだけれど、本来ネットワークが持っていた飛び地のようなものが失われてしまいます。
小石:
その図式は、ファッションで海外のマーケットを相手にするときに起きる現象でもあります。アジア人が欧米の人たちをオーディエンスにすると、たとえばコムデギャルソンだったり三宅一生、あるいは裏原宿の文脈にあるものを期待される側面があります。たまにアジア系の新進のデザイナーが、マーケットに合わせて次第にコムデギャルソンだったりヨウジヤマモトっぽいエッセンスを入れると、自称ファッション通が批判をすることがありますが、極東から西洋のオーディエンスに発信しているという条件、自分自身が日本人であるということを安易に批判している人たちは軽視しすぎだと思いますね。
日本というフィルターを通して、西洋から一番最初に見えるファッションの文脈はそこなんですよね。これはアートの世界で、漫画・キャラクター文化と村上隆が、日本というフィルターを通すことで自然に接続される状況と似ているかもしれません。これはタイプキャストなわけだけど、ある意味受け入れなければいけない側面でもある。今後も重要になるのは、海外のメジャーなオーディエンスが理解可能な文脈とボキャブラリーを、デザインによって増やして共有していくことだと考えています。
一方、アメリカとヨーロッパは、お互いの文化をうまく使い合ってきました。だけど、さっきのユーロヴィンテージのたとえのように、日本人がフランスのものをただ引用をしても、よそ者というか、ただの物好きとか、よく知っているオタクとして扱われる。西洋人が着物を羽織ったり、外国人が相撲で横綱になっても、そこに本流があるとはなかなか認められにくいのと同じ構図です。現代ファッションと洋服自体が西洋で生まれたものだから、ある程度の互換性がある形で文脈は共有されている。
建築では磯崎新が『Japan-ness in Architecture※20』という本を書きました。彼がキャリアを通してやろうとしていたのは、まさに日本で海外に発信するときに使用可能なボキャブラリーを残していくことだったと思うんです。そして、当時の日本のオーディエンスほど、海外に伝わっているかを気にする人たちもいなかった。
ファッションも同じように、「Japan-ness」のボキャブラリーを増やしていかなければいけないと思います。これまで高田賢三、三宅一生、川久保玲や山本耀司、あるいはNIGOが「Japan-ness」を提示してきて、そこが足場になっているからこそ、今の世代の人たちの仕事が海外でも読み解けるようになっている。逆に、受容する側が理解するための足場がまったくないものは、そこに新しさがあったとしてもパクり扱いになったりする。
足場がないところをわかってもらうためには、下西くんの本のように、漱石や『万葉集※21』を伝えるために、ホメロスから書いて文脈を作ることが必要になってくる。そうやってコミュニケーションからはじめないといけない状態になってしまうわけですよね。日本人が服を作るときに、コミュニケーションからはじめようとすると、現代のオリエンタリズムの目を避けられない。もうそういう構造なんだから、それを受け入れた上でボキャブラリーを増やしていくしかない。思想も同じだと思います。
新しいイメージの意味を支えるのは、社会に存在する記号のグラフネットワークのなかでノードの数が多いものたちです。ノードは足場です。ノードをどう引っ張ってつなげてどう作るかみたいなことが重要になってきます。その意味で、ボキャブラリーを増やさないといけないんですよね。
さっき「アメリカとはなにか」というイメージの話をしていましたが、それを支えるのはマリリン・モンローやオードリー・ヘップバーンとニューヨーク、ジョーダン、シュワルツェネッガーのターミネーターだったり、カニエ・ウェストやAppleのような固有名詞で、それがアメリカを支えるものになっていった。アメリカを語るための文法の固有名詞が増えていくと、自然と社会に備わっていくわけです。説明しなくてもそれはアメリカだとわかる。そういった語彙をどうやって豊かにしていくかが、ファッションの仕事にとって、もっと言うと東洋文化全体にとっての課題だと思います。
今は日本に外国人がたくさん来ているし、最近ではヴィム・ヴェンダースが『PERFECT DAYS』という日本を舞台にした映画を撮りました。そういった作品のなかに映るイメージの蓄積が、日本や東京から連想される意味に厚みを生み出します。これがものを作ることや本を書くことにもつながっていく行為だと感じます。何をやるとしても、毎度ホメロスとかプラトンから説明してカントを経由して書かないといけないのは、骨が折れるし時間切れになる。
下西:
僕の本では、日本の歴史についてもすこし書きましたが、日本のグローバルに馴染めない歪さみたいなものが、逆説的に世界に受け入れられるところにおもしろさを感じます。
日本のアイドルがよくも悪くも低身長と相性のいい幼児的身体をミームレベルにまで完成させているのに対して、韓国の文化は完全にグローバル対応に向かっていて、K-POPアイドルはアジア的身体さえ抹消するかのごとく、身体レベルで改造をしてパフォーマンスをグローバルにチューニングしています。映画でもポン・ジュノの『パラサイト』なんかは、ハリウッドやNetflix的な文法で作られていますよね。表現の形式をグローバルな基準に設定しながら、そのコンテンツをアジア的なものにする戦略は強いと思いながらも、本当は表現の形式や文法こそを輸出しなければ、文化としての強みは生まれないようにも感じます。
表現のフォーマットをグローバル対応しながら、アジア的なコンテンツをねじ込むという戦略は、アートの世界では村上隆やアイ・ウェイウェイがやってきた方法です。彼らは無理やりコンテンツをその表現に押し込むことで、半ばフォーマットそのものも変容させていくぐらいの力があったと思いますが、最近だとホー・ツーニェンなんかははじめからフォーマットを無視して、西洋にはない表現を追求しているように思えます。フォーマットの覇権は、国力レベルの要因が大きいので、こうした表現がどこまで世界で受け入れられるのかは興味深いと思っています。
一方で、日本のポップ・カルチャーはグローバル対応がうまくできているように見えません。日本の文化は国内に閉じこもって、歪な形のものをそのまま提示している印象があります。特に漫画やアニメなどは、いきなりネットを通じて日本の表現形式そのままに、世界へと届くという状況がある。最近だとアニメカルチャーや、それを生成したニコニコ動画的なプラットフォームが可能にした表現でもあるボカロ文化から派生した音楽も、海外でバズったりしています。
もちろんそこには国内需要で満足していることや、単に戦略の苦手意識などもあると思うけど、僕はその奇妙さが一周してアイデンティティになっている表現がおもしろいと感じます。今後はそこが参照点になっていく可能性もあると思うんですよ。その醜悪さも含めて、閉鎖性が生む奇形的な表現が、突如として普遍性を帯びるのはおもしろい。そういう意味で、グローバル対応することと閉じこもることが、そのまま外側と内側という対応関係ではなくなっているようにも感じます。
小石:
実際にソウルへ行ったり、韓国の人たちと仕事をしてみると、街のカルチャーがグローバル対応しているわけではなくて、ローカルなところもおもしろいと感じます。むしろ我々がよく目にしている外向きの部分は、かなり人工的に作られていると思います。
日本の場合、海外の1980〜90年代生まれの世代の人たちが、日本のことを勝手に学習して受け入れはじめてくれている部分があるから、海外のカルチャーの文脈に乗せて翻訳する手数が大分減ったかもしれません。鳥山明さんが最近亡くなりましたが、『ドラゴンボール』の悟空とかベジータは、海外の人にも知られているわけじゃないですか。そうすると、そこをインスピレーションにして新しいものを作っても説明なしに通じるということが起きる。30年前はこれは無理でした。受容されていないものをボキャブラリーとして使う時はそこに説明が必要になるし、だいたいにおいて説明が真剣に聞かれることはないので。
勝手にボキャブラリーが増えてくれているのが一番文化にとってありがたいんですよね。負い目を感じつつ苦手なことをやらなくても、そのままでいいところは、前に比べて増えていると思います。ホメロスから書かなくても、デカルトくらいからはじめても通じるし、料理番組でおにぎり作るのに、稲を植えて秋まで待つことはない。
下西:
最近だと「もの派」の再評価がありましたね。戦後の「もの派」は、その辺に落ちている石や木を使って作品を作っていましたが、一方でそこには禅思想などのステートメントがあり、他方では戦後の荒廃した風景や貧困者の自覚というテーマがありました。しかし最近になって、哲学で「モノ」そのものを思考する形而上学である思弁的実在論が流行ったり、それから人新世という文脈で大地やモノが再認識されたりして、まったく違うコンテクストで「もの派」が再評価されています。
変に対応して自らコンテンツを作るんじゃなくて、こっちでやってたことが全然違う文脈で発掘されることも可能になっていますね。もしかしたら、それは最近の海外で日本のシティ・ポップが再評価されているような現象にも近いかもしれません。
インターネットにあらゆる過去の作品がアーカイブされて簡単にアクセスできる状況において、当時の文脈とは別の文脈にいきなりつながってしまうことが起きるわけですよね。これは逆に、積み上がっていく歴史性が消去されて、すべてのコンテンツがフラットに消費されてしまうという危険性と表裏一体でもあると思いますが、あらゆる場所で文脈そのもののリミックスが可能になっているとも言える。だから、文脈に合わせて種を撒くことも大事だけど、コアなことをやっていれば、いつかどこかで拾われることもあるのかなと思います。
小石:
それはきっとどちらも必要ですね。もう7〜8年くらい前のことですが、友人が誘ってくれてDAZED創業者のジェファーソン・ハックと食事する機会があったんです。そのとき「古い日本の雑誌で何かおもしろいものはないか」と聞かれて、松岡正剛の『遊』を教えたんです。そうしたら興味を持ったみたいで、その場でいろいろ調べはじめて勝手に興奮してたんですよね。勘のいい人なら、そこに書いてある言葉がわからなくても、明らかにここには宝があるということを雰囲気でわかってもらえる。そういう感性の鋭い人たちは、自分で勝手に文脈を見つけてレビューして新しい意味付けをしてくれる。
「もの派」もそうかもしれないですけど、その人たちが解釈したい方向性のパーツとして、うまく文脈を作っていく。だけど同時に、磯崎新や村上隆のように、自分たちで文脈を作ったり意味付けすることもやらないといけないと思います。それが昔から今に至るまで日本人が苦手なのは、おそらく西洋を知っていることが知性の基準になっているからです。日本のインテリやアーティストの大半の人は、折口信夫よりもハイデガーやデリダの方が知的だと思っているはずです。
インテリの人たちはファッションに抵抗感がある人が多いけど、そういう人ほどファッションの感覚が必要だと思います。小難しいことを言っている東洋人というのは思いの外、世界から見るとコモディティになっていてオリジナリティはありません。本人たちは、身なりや素振りや言動より、思想で勝負と思っているかもしれませんが、小難しいことを言ってる東洋人は世界には意外とありふれてるんですよね。西洋文化について語っているならなおさらです。ジジェクなんかはスロベニア出身です。辺境の西洋人、ヨーロッパの二級市民であることを自覚してコミカルに振る舞うことで、自分のメッセージングに使っていますよね。ファッション的にキャラクターとして消費されることで思想を伝えていて、さすがだと思います。
下西:
たしかに、単に西洋で評価されることが重要であると考えるのと、西洋での評価を逆輸入して利用して価値を成立させることが重要であると考えるのは、似ているようで大きく違いますね。
そういう意味で、世界での評価と国内での人気にギャップがあるのが、夏目漱石のおもしろさでもあります。海外での評価が高い日本文学の作家は、三島由紀夫や川端康成あたりでしょうか。川端康成は日本ペンクラブの会長をやっていて、グローバルにも活動していました。それに比べると、漱石は全然人気がないんですよね。
だけど、漱石のようなヨーロッパのモダニズムとグローバリズムに対するアレルギー反応は、近代の非西洋圏のどこででも起きていた話です。そのとき人間の精神に何が起きたのかを克明に記録していたのが漱石です。だから本当は、世界史としても批評性が高いんだけど、その複雑に入り組んだところまでパッケージ化できないから難しい。そういうものが掘られて、もう一度評価されるということも今後はあるんじゃないかと思います。
小石:
この間、漱石のデビュー作『吾輩は猫である※22』を久々に再読したんです。改めて傑作だと思いました。途中何度も笑いましたが、特に印象的なのは金縁眼鏡の美学者の迷亭※23がアンドレア・デル・サルトの言葉を捏造して、主人公の苦沙弥先生※24に伝えると、苦沙弥先生が「へえアンドレア・デル・サルトがそんな事をいった事があるかい。ちっとも知らなかった。なるほどこりゃもっともだ。実にその通りだ」と頷くシーンがあるんです。近代化に伴って西洋に対する劣等感を抱えながら生きるキョロキョロした現代人を描いているわけですが、これは100年経過した今もあまり変わってないですよね。西洋を知っていることがインテリの証で、西洋に認められることが最高の栄誉であるというのは、構造的に変わっていない。
世界で圧倒的に認められたという意味で、ファッションでは川久保玲を挙げました。文芸においては、海外で最も知名度のある日本の作家は村上春樹でしょう。村上春樹も日本文学を理解するためのコンテクストになっていて、日本の作家が西洋に出たら、村上春樹からの距離を一旦指標として測られるようになっていると思います。今の中国では川端康成が流行っているらしいですが、中国人に漱石がたくさん読まれたら、欧米による中国研究の過程で、現代中国が見ていた夏目漱石という文脈ができて、漱石が西洋社会で受容されるという流れもあるかもしれません。マーティン・スコセッシやヴィム・ヴェンダースがやたら褒めるから、小津安二郎や黒澤明の映画を観るようになった外国人がいるみたいな感じで。
もしかするとそのきっかけは、中国になるのかもしれないとも感じます。中国というとアレルギー反応を起こす人も結構多くて、まわりの差別的発言だったり見下すような発言に閉口することも多いんですけど、僕は日本にとって中国がグローバルなブリッジとして重要な役割を担うと考えています。
まずひとつは、大陸本国もそうですが華僑社会の広大さからくるマーケットの広さです。そのマーケットが広さゆえに、世界が中国で人気なものを無視できないんです。たとえば、NIGOがKENZOのクリエイティブディレクターになりました。これは彼の実力でもありますが、LVMHが中国をはじめアジアでの人気がビジネス的に無視できなかったからだと思います。今では旧正月に世界のラグジュアリーブランドが月餅を作るようになったくらいですから。
もうひとつは、僕自身も仕事で必要になって中国語を勉強しているんですけど、中国語自体がおもしろい言語なんですね。芥川竜之介の『侏儒の言葉※25』も、中国語になると途端にかっこいいし、シャープになる。日本語から英語にすぐに翻訳できなかったものが、日本語から中国語に翻訳してから、さらに他の言語に翻訳すれば、意味を保存して伝えることができる可能性はあるんじゃないかと感じます。数学的な操作みたいな形で。なので、中国に視線が集まる過程で、日本が新たに発見されることもあるんじゃないかなと思っています。
アフタートーク
——— 下西さん、福田歓一さんの『政治学史※26』という本をご存知ですか。すこしマニアックかもしれませんけど、自分にとってはこの本が今まで読んだ哲学史のなかで一番おもしろかったんですね。
上手に俯瞰してまとめたような本は、役に立つけどおもしろいことは稀で、おもしろいと感じるのは、著者と一緒に歴史を旅する感覚が持てる本なんです。それがさっきの福田さんの本にはあって、下西さんの本にはさらに濃くあるように思えました。歴史上の人物一人ひとりにちゃんと会って、じっくり話し込んでから帰ってきているように感じたんです。
下西:
ありがとうございます。たしかに、『万葉集』や『古今和歌集※27』を読むときは、1ヶ月ぐらい籠もって読み続けていたので、万葉人になった気持ちになっていたと思います。
小石:
それはすごく大事なことですよね。どうしても昔の偉人を大きく見がちだけど、その人の等身大のサイズ感がわかってないと、理解できないこともあるので。
——— フィールドワークをしながら、気づくと憑依しているような感覚ですよね。
下西:
そうですね。『万葉集』は4500首ぐらいあるんですよ。それで、僕は1ヶ月くらい部屋に引きこもりながら『万葉集』をひとつずつ順番にすべて読んでいったんですが、その脳のまま『古今和歌集』を読むと、急激におしゃれになっているのがわかる。言葉が掛かっていたり、色が鮮やかになっていたり、知的になっているのが体感として明らかにわかるんです。
『万葉集』を読み続けたことで、『古今和歌集』の華やかさが感じられて、宮廷文化のなかで書かれた歌というリアリティがわかってくる。そういった感覚で学問をやるのは大事なんだと思いました。だから、今回の本もリアリティのあることしか書かないようにしました。
小石:
リアリティ重要ですね。そこがないと響かない。最近『方丈記※28』を読み直したんですが、結構おもしろいです。Xで張り付いて投稿連投してそうな元官僚のおじさんをイメージして、その人が書いているんだなと時代を変換して読むとかなり新しい発見がありました。結構こういう人はいただろうなというリアリティ。
今はまだ本を書いたあとで忙しいと思いますが、下西くんは今後どんなことをやろうとしているんですか。
下西:
いろいろありますが、ひとつは本で書き足りなかったことを追加で書こうと思っています。今回はわざと唐突にヴァレラを出してきたところがあるんだけど、彼の背景にあったサイバネティクスの思想をもうすこし掘り下げたいと思っています。
なぜアメリカという大地でコンピュータやインターネットのような科学技術が発展したのか。それは、新大陸にやってきたピューリタンが機械で自然を開拓するなかで生まれてきたのだというおおまかな仮説を持っているのですが、そのあたりの宗教と技術と意識の交雑する歴史の話をしたいです。
小石:
なるほど、それはおもしろそうですね。また適温な、クールなトーンで書いてほしいです。
下西:
いつだってやる気はないのですが、がんばります。
2024年5月2日 聞き手: 大林 寛